![]()
 [日本地図]
[日本地図]
 [ホームページ]
※携帯電話版は http://www.kgym.jp/i
[ホームページ]
※携帯電話版は http://www.kgym.jp/i
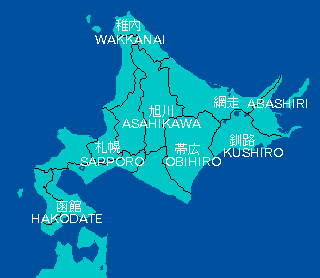
![]()
 東大沼野営場から駒ケ岳 Photo=29kb
東大沼野営場から駒ケ岳 Photo=29kb
![]()
 夕暮れ Photo=15kb
夕暮れ Photo=15kb
瀬石(せせき)と相泊の二つの露天風呂は羅臼から半島の奥へと入ります。海岸にまで迫った知床半島の脊梁山脈の縁を,海に落ちそうになりながら舗装路が相泊まで細々と続いています。どちらも道から見下ろした海岸にある開けっ広げな露天風呂です。瀬石温泉は個人が管理されているので,一声かけてからお湯をいただきます。潮が満ちてくれば海に沈んでしまうような,ただ岩で囲んだだけの湯船です。何も施設はありません。道路から見えないように岩蔭で着替えます。相泊温泉は男女別にバラックで囲まれていますが,海側には壁がなく,岩浜越しに海を眺めます。
昨年(95年)瀬石を訪れた時はTVの中継車が来ていました。露天風呂に入りながら先客のライダーに聞いた処では3時からの番組の中継だという話です。彼はTVに映りたいのでこのまま瀬石で待っているとか。相泊まで往復して戻って来るとちょうど撮影をしていました。
寿都
「すっつ」と読みます。松前・江差・瀬棚から岩内へと道南を日本海沿いに北上するルート(国道229号)は,あまり北海道らしい地域ではありませんが,交通量も少なく,海と鄙びた漁村の点在する風景の中をのんびりと流して行けます。岩内の南,積丹半島に向かって真北に突き出した岬が弁慶岬,この付近の義経伝説のひとつでもあります。岬の東の深い湾の奥が寿都の町です。国道を走るとそのまま通り抜けてしまいますが,町の中心部は北に平行する旧道沿いにあります。
 弁慶岬 Photo=21kb
弁慶岬 Photo=21kb
![]()
旭川方面
朱鞠内湖
雨竜貯水池。人造湖としては北海道最大。日本最寒の地で自動車メーカーの寒冷テストコースがあるらしい。
キャンプ場の売店でビールと焼肉セットと炊いたご飯を仕入れてお手軽な夕食ができます。売店が閉まってしまうと近くの集落まで走らないと買い出し出来ませんが,インスタントラーメンぐらいしかなかったです。展望台の看板にはサカナの絵が描いてあったので,キャンプ場で「釣ってもいいですか?」と聞いたのですが,「かまわないけど,サカナいないよ」と言われてしまい,実際釣れませんでした。湖のまわりを一周すると,ダートと高速ワインディングをつなぐ事になり変化にとんだ走りが楽しめます。
 夏空と雲とダート Photo=21kb
夏空と雲とダート Photo=21kb
名寄
歌登から道道120号を南へ下って来ると道道49号(ツーリングマップルでは255号)との交差点・仁宇布(美深町)でちょっと休憩。「羊乳」をいただきました。¥310だったかな。よく振って飲む事,との注意書きに従っていただきましたが,ちょっと酸味のきついモロモロの入った独特の味です。飲む前はヨーグルトみたいな味かなぁ,生臭くないだろうなぁ,と恐る恐るでしたが,ちょっと違いましたね。
美深市街には入らずに,手塩川右岸(R40の対岸)をピヤシリ山を目指して南に下りました。国道を一気に走らずこういう脇道に入ると結構地図に載っていない「見処」が道端にあらわれたりして,ちょくちょく一服することになります。道を間違えては「この先熊出没侵入禁止」の看板で引き返したり,手塩川の河原に出てしまったりと,そんな調子でのんびり走っていると,「日本一のヒマワリ畑」との道標が現れました。道標によると8月下旬前後が満開とか。まあ今は上旬だけどつぼみぐらいならついているだろうと,次々と現れる道標に従ってちょっときついダートを延々と登ります。いい加減うんざりした頃やっとたどり着きましたが,一面の葉っぱでした(^_^;)。うーん,これが咲いていれば見事だろうなぁ,と櫓の上で一服。中年夫婦の乗った4輪がやってきて,「咲いてませんね」とお互いに確認しました。
この日はどうもついていなくて,ピヤシリ山へも登りましたが,道は工事してるは,そのうちもうそろそろ山頂かなぁという按配になっても,何やら下りになってくるし,ゴロタ石のゴロゴロする道で,前輪押さえるのがやっとになってきて,なんか変だなぁ,と。道端で一服していると,KDX(←バイクの名前です)の男の子が跳んで来ました。お互い相談したところ,どうやら道を間違えたという結論に。KDXの彼はこのまま行って反対側へ抜けるそうですが,私は引き返す事にしました。
結局途中でみかけたロープで侵入禁止になっていた道が山頂への道でした。そろそろ夕方になってきたので,片道30分(だったっけ? 2時間だったような気も)の歩きはパスしてとりあえず証拠の写真をパチリ。ツーリングマップルにある「ハイマツの群生と360度の雄大な展望」は諦めて,名寄市街へ下りました。なにやら他にも道端で見かけましたが,あまり多くを語りたくない(笑)。このあとも風連町でテントを張るつもりが,雨がパラツキ出したので,R40を飛ばしてこの日は旭川東急イン泊まりでした。
 一面のヒマワリ(のつもり) Photo=36kb
一面のヒマワリ(のつもり) Photo=36kb
![]()
稚内方面
浜頓別
クッチャロ湖の湖岸に設備の整ったキャンプ場があります。広い芝生に樹木とベンチが散らばっています。売店・コインランドリーもあり市街地もすぐですので何の不便もありません。市街地が近いといってもキャンプ場の中からはわからず,前の湖岸と裏の林しか目に入らない静かな環境です。市街地からキャンプ場への入り口の両側に国民宿舎と温泉センターがあり,どちらでも入浴できます。温泉センターの方が新しく,街の人はこちらへ行くそうです。
湖岸を一周する道は,緩やかな起伏の牧場地帯の中を通り抜けます。バイクで走るとあっという間ですが,のんびりとレンタル自転車でまわるといかにも北海道らしい伸びやかな風景にどっぷりとつかり込むことになります。
市街地の中心あたりの路地の中程で,少し分かりにくいところに自転車屋さんがあります。このあたり(浜頓別と周辺の街)では,バイクを修理できるのはここだけだそうです。(update:Feb/1998)
 クッチャロ湖周辺 Photo=40kb
クッチャロ湖周辺 Photo=40kb
 安別駅(現在は廃線) Photo=46kb
安別駅(現在は廃線) Photo=46kb
歌登
オホーツク沿いの枝幸町から10数キロ山の中に入ります。町から更に南に10キロほどいくと歌登町健康回復センターがあり,いろいろな施設の中に温泉ホテル・キャンプ場があります。キャンプ場は尾根の上にありますが,自由に利用できる施設がそろっています。ログハウスにはガス湯沸かし器付きの流しや水洗トイレなども設置されていてノートに名前を書くだけで利用できます。下の新築(?)のホテルでは¥300(だったっけ?)で観光ホテルのような立派な温泉に入れます。買い出しは町まで降りないと駄目なようですが。
歌登を出て南へ道道120号を行くと,廃線跡のような「遺跡」が道沿いに現れてきました。鉄道マニアではないので詳しい事は分からないのですが,この辺りを国鉄が走っていたんでしょうか? 北海道はほんとに道路は立派だけど鉄道は迫害されていますねぇ。税金で作った道路と原則独立採算の鉄道が自由競争すれば負けるに決まっていますが。この辺の社会資本に金をかける余裕の無い「貧乏国」日本の象徴のような光景です。
 道端にて Photo=25kb
道端にて Photo=25kb
![]()
網走方面
雄武
オホーツク沿いの小さな町です。興浜南線の終着駅でした。興部から浜頓別へ出るにはここから興浜北線の北見枝幸までバスを乗り継がなければなりません。一昨年の夏,ある日の夕暮れ,北からR238を下って来た私は,町の入り口の国道沿いの食堂で夕食を取っていました。店のオヤジさんは話好きらしく,この魚は何でめずらしいんだ,とか色々と説明してくれます。
「昔ね。学生の頃,国鉄で来たんですよ。」
「そう」
オヤジさんは興味なさそうでした。町にはもう鉄道はありません。
中湧別
サロマ湖の西,オホーツク沿いの湧別と湧別川上流の上湧別との間,行政区画で言えば上湧別町です。国道247号から一ブロック入った所に道の駅「中湧別」があります。図書館などが入った文化センターとバスターミナルが合体したような施設ですが,文化センターTOMの中に「日本でも数少ない,北海道では唯一の」漫画美術館があります。いかにも新しい公共施設といった建物で,なかなか居心地の良い道の駅でした。
知床半島
やっぱり第一級の観光地ですね。見物したところをならべていくと観光ガイドになってしまいます。私は一度北海道に渡ると2・3週間うろうろするので全道を一周することが多いのですが,短い休みしか取れなくて初めての北海道なら,道東・釧路を基点に阿寒湖周辺と知床をまわればとりあえず後悔しないんではないでしょうか?
道東の夏は寒いです。冬は内陸部が冷え込むそうですが,夏,宗谷岬からオホーツク沿いに「南に」下って行くとだんだんと気温が下がってきます。根室・釧路あたりが一番涼しいようです。
知床半島は温泉地帯です。ウトロ・岩尾別・羅臼とあります。また露天風呂はカムイワッカ・熊の湯・瀬石・相泊などです。
半島のウトロ側,岩尾別温泉は一軒宿の温泉だそうですが,残念ながら私は岩尾別YHに泊まったのでしりません。学生時代泊まった時は,岩尾別YHのミーティングはランプの光の下でした。今でも岩尾別旅情を唄っているんでしょうか? さすがに中年になるとYHに泊まるのも気恥ずかしいで気になります。
カムイワッカ湯の滝は知床林道の奥にあるのですが4輪が渋滞しています。バイクなら楽に入れますが,道端で着替えるのはちょっと恥ずかしいですね。沢登りという感じで奥へ登るほど岩棚を流れる水が暖かくなって行きます。所々適当な湯船になる淵があります。好みの湯温のところでゆっくりと浸かって帰って来るので,まだ一番奥までいったことはありません。初めて登ったときはビーチサンダルで行ったのですが,岩登りしなければならない所などあって苦しい。翌年は入り口のところのレンタルワラジを利用しました。靴下の上にワラジを履いて登るのが正解のようです。
 カムイワッカ湯の滝 Photo=26kb
カムイワッカ湯の滝 Photo=26kb
 瀬石の露天風呂 Photo=22kb
瀬石の露天風呂 Photo=22kb
走っている最中,出会うライダーとの世間話によると羅臼の国設キャンプ場は一杯だとか。「写ルンです」のフィルムがなくなったので,羅臼の町のコンビニで「撮りっきりコニカ」を買って出て来ると,年配のライダーに声を掛けられました。
「どこ泊まるんです」
「熊の湯のところのキャンプ場は一杯だそうですね」
「うん。僕はこれから帰る処だから,よかったら場所を譲りましょうか」
と親切におっしゃって下さいました。ちょっと心が動いたんですが,混雑したキャンプ場では落ち着かないので,ありがとう,でもいいです,と断ってしまいました。
後で上まで走って行くと確かに大盛況です。ちょうど雨がぱらついて来たので,熊の湯には入らず,往路で下見していた市街地のそばの町立キャンプ場にテントを張りました。ここはちょっとした丘の上ですが,コンビニが近いのでビールの心配が要りません。
![]()
釧路方面
中標津 →地図
「シベツ」というのは確か「大きな河」という意味だと記憶しています。「ベツ」が「川」という意味なので,川沿いにある街で,上流の街は「上〜ベツ」・中流域の街は「中〜ベツ」・河口の街は「浜〜ベツ」,という地名をよく見かけますね,北海道では。
国鉄の駅名でいうと,標津川の河口にあるのが「根室標津」で,そこから上流に遡って「中標津」がありました。国鉄はもうなくなりましたが,中標津空港があるので時間距離は近い街です。
知床半島を南下しながら,雨の中をヘルメットのシールドについた水滴を拭いながら走っていると,(たぶん泥の微粒子でシールドが)傷だらけになって前が曇ってしまったので,バイク屋を探して中標津の街をうろうろしたのですが,見あたらないので通りがかりのカブのおじさんにをたづねました。街の中心から旧国道を東に少し行くとあるということで,「らいだーすさろんBUM金沢」(phone(01537)2-1749)というショップを見つけました。バイクグッズだけでなく,キャンピングガスのカセットなども置いてあり,オイルやフィルターの交換・チェーンの増締めなどに,翌年から毎年寄るようになりました。
中標津の町は,大きなスーパーや書店もありなかなか便利です。書店は,大阪などでも道路沿いによくある駐車場付きの郊外型店舗が,コミックの品揃えも良く便利です。またショットバーやインターネットのできる漫画喫茶など,都会にあるものは一通り揃っています。ツーリングマップルにある国道沿いの回転寿司は,毎夏,ライダーには一品のサービスを行っているようです。街から釧路・弟子屈方面に走ると国道沿いの左側に目立つ駐車場付の郊外型店舗です。
温泉は市街地に集中しています。マルエー温泉,湯トピア,東洋グランドホテル,町営保養所,ちょっとはずれにウィングイン,とあります。一番高いグランドホテルで¥600でした。マルエー温泉は,数年前にビジネスホテルに改装してきれいになりましたが,町で唯一の銭湯が閉業して以来,銭湯代わりに公的補助を受けていているそうで,銭湯料金で入れます。マルエー,湯トピア,保養所には,コインランドリーがあります。湯トピアは温泉の方のフロントで声をかけると,併設のライダーハウスのコインランドリーが利用できます。マルエーは,私は気がつきませんでしたが、あるそうです。他には年中閉まっている喫茶店(?)の裏に回るとコインランドリーがあります。なお開陽温泉は2000年現在休湯中です。(町が買い上げて整備するという噂があるそうです)
キャンプ場は,市街地のはずれの緑ケ丘森林公園の奥に町営が,空港のそばにライダーズハウスを兼ねた民営の「オートパーク族(うから)」があり,そして開陽台の展望台の裏,と3カ所あります。森林公園と族は有料・開陽台は無料です。
開陽台はずいぶんときれいになっていて,4輪も多く,観光スポットと化しつつありますが,「330度の展望」はそのままです。展望台の一階には,土産物屋と(前は駐車場の隅にあった)食堂が入り,裏のキャンプ場もきれいに整地されています。オフロードバイクなら駐車場脇からキャンプサイトまで入れます。4輪やビッグバイクは駐車場に停めて,サイトまで階段を昇り降りすることになりますが。
森林公園のキャンプ場も,開陽台のそれも,施設は立派なものが揃っています。森林公園は樹間なのでちょっと湿気が多く,開陽台は開けっぴろげなので悪天候のときは大丈夫かなぁ,という程度です。(update:Dec/2000)
 中標津駅にて Photo=38kb
中標津駅にて Photo=38kb
養老牛温泉
中標津(開陽台)から道道150号を西へ向かい適宜現れる道標に従って行くと養老牛温泉にでます。温泉街を抜けると道は細いダートに変わり,しばらく行くと道の右に露天風呂が見つかるでしょう。
からまつの湯は,細い渓流の岸に岩で囲んだ小さな湯船です。流れの水を引き込むことにより湯温を調整できるように工夫されています。バラックの更衣室が傍に男女別に2つ建っていますが,湯船自体は完全な露天が一つだけです。先客のライダーと挨拶を交わしながらお湯をいただいていると,カップルが4輪で現れたので,写真は遠慮して更衣室だけ写しました。
ダートをそのまま進むと再び道道150号に出,裏摩周方面に抜ける事ができます。
 からまつの湯 Photo=32kb
からまつの湯 Photo=32kb
![]()
帯広方面
然別湖
山の中の湖です。まわりの然別湖畔温泉は観光地,山田温泉は一軒宿,北の麓の糠平温泉は温泉場という印象でした。湖畔温泉から北に数分走ると山田温泉の手前に然別湖北岸野営場があります。ここは昨年(95年)の8月の北海道でキャンプした中では一番寒かったです。標高が意外とあるようです。トレーナーを着込んでスリーシーズンのシュラフにもぐりこみ,上にバイクジャケットを掛けても夜中に寒くて目が醒めました。
ここは静かなキャンプ場です。バイク・車は中に入れる事ができません。荷物の運搬にはリヤカーを貸してくれます。また夜二時に電源が落とされます。二時前でも湖岸まで降りると,キャンプ場のランタンの光も届かず,さすがに帯広方面は少し明るいですが,湖とそのまわりを囲む山々の上に満点の星空が広がっていました。
キャンプ場の管理人さんの話によると,湖畔温泉の観光ホテルでは入浴不可,山田温泉で入浴できるそうです。ビールは近くのホテル・旅館の中の自動販売機ぐらいのようです。私は20キロほど北の糠平温泉まで入浴に走りましたが,糠平温泉の集落には食料品店・酒屋・薬局・食堂などもあります。酒屋のオヤジさんは話好きな方で,この酒は冷えたのがあるとか,どこから来たんかとか,の最後にマケてくれました。最初に目についた旅館で入浴させて貰いましたが,露天風呂も渓流沿いでなかなかオツでした。キャンプ場がある(らしい)ので,こちらでキャンプするのも楽かも知れません。
翌日日高へ抜けるためにR274を走っていると鹿追で道端に駐屯地が。門の前にバイクを止め詰所で頼むと,若い兵隊さん一人がついてくれて,引退した(?)戦車に触らせてくれました。
 「うちのは最新型じゃないんです」74式と Photo=30kb
「うちのは最新型じゃないんです」74式と Photo=30kb
![]()
北海道へのアクセス
毎年6月初めに出る「アウトライダー」や「モーターサイクリスト」の7月号あたりで,「北海道特集」をやっているので,とりあえずはそれを見るのが確実ですが。
北海道へバイクを持って行くには,「自分で走って行く」「長距離フェリー」「バイク専用列車」「自動車陸送便」「航空貨物」などの方法があるようです。この順に体力や時間を節約できますが,その分,財布が消耗します(笑)。
「自分で走っていく」のは,大阪から青森まで,日本海まわりでも1500キロぐらいあるので,どうしても最低1泊は必要です。高速はまだ新潟までしか通じていないので,そこから先は以外と時間がかかります。青函フェリーは深夜も走っているので,夜行便で仮眠すると時間が節約できます(青函連絡船の夜行はゆっくり6時間かけて走っていましたが,フェリーは4時間でついてしまいますが。。)。大間からの便は数が少ないですが,大間の港のそばでキャンプできるので便利です。カウル付きの大型バイクだと,名神(名阪)→東名(中央)→東北道と高速を使うという手も使えますが,いずれにしてもしんどいでしょうね。以前,自動車で一度とバイクで一度往復したことがありますが,どちらも東北ツーリングを兼ねていたので,北海道だけが目的の場合はお勧めできません。
「長距離フェリー」が,一押しです。北海道へ渡る便は,舞鶴か敦賀を深夜に出て2泊して早朝小樽に着くという便利なダイヤになっています。乗る前は,2泊も船の中に閉じこめられるのはかなわんなぁ,という印象だったのですが,結構居心地も良いし退屈もしません。昨年(96年)は出発の予定が立たず舞鶴からの便の予約がとれず,新潟(直江津発もある)から小樽行に乗りましたが,夕方着の便だったのでちょっと不便でした(でも,このフェリーの売店で地元発行の北海道キャンプ情報の本を売っていたので,上陸してから重宝しました)。フェリーは日本海側と太平洋側を走ってますが,太平洋側の方が料金が割高な分,船の設備が良いですね。波は太平洋側の方が高いようです。ある年仙台から名古屋行のフェリーを利用しましたが,当日の飛び込みでも乗れました。翌年,苫小牧発仙台経由名古屋行を利用しましたが,30ベットある2等寝台の一室が,仙台で29人降りてしまって,一人部屋に。なるほど仙台からならいつでも乗れるなぁと。北海道行は比較的予約を取り易いですが,8月後半の帰りの便は20日前後に集中するので早めに予約を取った方が良いようです。
「バイク専用列車」は,大阪からは「モトとレール」,東京からは「モトトレイン」という企画が毎年あるようです。バイクのための貨物列車を連結していて一気に北海道へ上陸できます。料金も手頃なので人気があるようですが,その分すぐに予約が埋まってしまうので早めにプランを立てておいて,駅の旅行センターなり,時刻表でチェックを入れます。
「自動車陸送便」というは,運送会社のトラックで運んで貰うというものです。道路を走っていると良く見かけるように,乗用車の陸送はいくつもの会社がやっているようですが,「日産陸送」という会社ではバイクも運んでくれるそうです。各飛行場のそばにも営業所があるので,これでバイクだけ先に運んで貰い,自分は飛行機なり列車でのんびりと行きます。大きなバイクショップなどで,ツアーを募集してショップのトラックで運んでくれるという企画もあるようですが,これは日程が合わないと利用できませんね。似たような手段に,長距離フェリーでバイクだけ運んで,自分は飛行機か列車でいくというものがあるようですが,乗用車と違ってバイクの場合は自分で船への積み降ろしをしなければならないそうなので,船は絶対にイヤという場合以外は利用しにくいでしょうね。
「航空貨物」は,自分の乗る飛行機に専用パレットでバイクを積んで飛ぶというものですね。最低一泊は指定ホテルから選んで止まらなければいけないというパック旅行です。JALやANAでやっているようです。
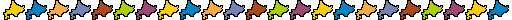
註釈
(50音順)
アウトライダー
ミリオン出版発行の月刊ツーリング情報誌。毎月始めに出る。バイク雑誌はいろいろとありますが,全国誌で,ツーリング専門誌はこれぐらいではないでしょうか。大阪では江坂の東急ハンズでバックナンバーが手に入りましたが,最近は誌面のバックナンバー常備店のリストに載っていませんね。東京では神保町の書泉ブックマートの地下に結構揃っていました。
お風呂・コインランドリー
長期ツアラーにはチョッチ切実な問題ですね。ユースホステル泊まりっていう場合はノープロブレムなんですが。
とりあえず,なんとかなります。
お風呂に関しては,各市町村に一つは「健康ランド」のような施設ができています。というより,温泉を探して走るっていうのが,北海道ツーリングの楽しみのようになっています。離島の場合でも島のどこかに一つは銭湯があるようです。ただし毎日開湯ではない場合もあるようですので,その辺だけ注意して下さい。リッチにシャンプー・リンスまで備え付けのところから,銭湯のようにすべて(石鹸・タオル)持参でなければならないところまでありますので,とりあえず初めてのところは入浴セット持参で行って下さい。プラスチックの洗面器が備えて付けていないお風呂というのは残念ながらまだ出会っていませんが。。
車と違い,ライダーの場合,貴重品をすべて持ち歩かなければならないのですが,ちょっとしたところでは,大抵貴重品ロッカーがあります。なければ番台のおばさんに預けるしかありませんが。この手のロッカーは大抵,100円入れて使い終わるとお金が戻ってくるタイプです。例外ですが,静内の温泉の場合,小さなロッカーは,50円入れて戻ってこないタイブなのでといって受付のおばさんが50円玉を両替して下さいました。でも大きな方のロッカーはお金がいらないから,空いていたらそっちを使いなっ,と教えて下さいました。
コインランドリーはありません。大きな町にはあるようですが,見つけるのが結構大変です。で,どうするか。まずライダーハウスを探して下さい。次に「健康ランド」のような温泉施設にも結構付属しています。あとは,キャンプ場の管理人さん・バイク屋さん・ガソリンスタンドの人に聞いて下さい。実は通りすがりの町の人に聞くのが一番確かだと
いう話も某キャンプ場で聞きましたが,コインランドリーなんって,本来フツーの堅気の人間には必要のないものですので,地元の人も結構知らないようです。
オンロード/オフロード・バイク
厳密な意味はちょっと違うかも知れませんが,フツー雑誌や仲間内で使う時は,舗装路を主に走るモーターサイクルがオンロード,未舗装路(ダート)も走れるのがオフロード,でしょうか?
オンロードはロードスポーツとか言ったりします(これも厳密には違うか)。レーサーレプリカとかネイキッドとかツアラーって,やつですね。このうちネイキッドには,カウリングがついていません。「単車」と言った場合にフツーの人が頭に思い浮かぶ形のフツーのバイクです。一番好きなんですが,高速は風圧が凄いし,ダートはちょっとしんどいし,と今は乗ってません。
オフロードって言っても,公道(道交法の適用されるフツーの道)を走れないバリバリの奴から,トレール・デュアルパーパスまで色々ありますよね。オフロードを直訳すれば「道じゃないところ」だから,たとえ未舗装路でも公道には違いないんだから,オン&オフと言った方がいいんでしょうが,フツー縮めてオフです。HONDAのカタログには「デュアルパーパス」と分類されています。高校生はこの手のバイクをひっくるめて「モトクロ」と呼んでいます。だいぶ外していると思うのですが,自分らの言い方も所詮は仲間内の用語法ですから,人のことは言えない。
カニ族
バックパッカー。リュックを担いでの旅行者。アタックザック(背嚢型)ではなく,昔風のリュックザックはサイドポケットが横に大きく張り出しているため,改札口などを横向きにカニ歩きして通り抜けるために命名されたらしい。今でも使うのかなぁ。二十年前は地元の人にこう呼ばれました。バックパッカーというと大きなフレーム付きのザックを担いだ外人さんのイメージですね。
ちなみに,バイクはミツバチ族,自転車はチャリダー・バイカー,歩きはトホダー・アシダー,とか一部ではいうらしい。
ツーリングマップル
噂によるとツーリングライダーの約8割が持っているという昭文社発行のライダー向け道路地図帳。オンロードバイクに乗っていた頃は開くとタンクバッグに丁度入ったので便利だったのですが,オフに乗り換えてからはウェストポーチに入れています。また道の状況や施設などいろいろ詳しいので,車で出かける時も愛用しています。
著者はいろいろ苦労なさってるんでしょうが,やはり道路は生き物。完全に信用していると,いきなり通行禁止だったり,キャンプ場がなくなっていたりと,酷い目に会う事も何回か。。
※という記述はずいぶん前に書いたのですが、そのあいだに名前もツーリングマップからツーリングマップルに変わり、版型も2度変わりました。2000年度版からは,無線綴じになり,使いやすくなっています。(update:Dec/2000)
バイク屋
北海道では小さな町にはバイク屋さんがありません。地方では,カブなどを扱っている自転車屋さんに駆け込むことになります。でも聞くところによると,バイクを扱える人が引退したりで,そういう自転車屋さんすらどんどん減っているそうです。トラブりそうなときは,早めに大きな街で手当てしておきましょう。
なお逆にツーリングライダーの多い地域のバイク屋さんには,夏のシーズン中は無休で営業したり,部品の在庫を持ったりしていて,親切なお店にあたると助かります。(new:Dec/2000)
ホクレン
ここでは北海道の農協経営のガソリンスタンド(GS)の事。毎年夏になるとライダーいらっしゃいのキャンペーンをやっていました。キャンペーン参加のGSで給油すると,地図や旗が貰えたりスタンプを押してくれたりします。ツーリング情報なども親切に教えて貰えます。キャンペーンに参加していないホクレンのGSも多いので注意。北海道に上陸したら,とりあえず「ライダー歓迎」の旗・立て看を探して給油して見ましょう。
なお小さな町のGSは,日曜定休の場合が多いので、マップでGSのマークを確認してギリギリで走っているとエライ目にあうことがあるので要注意。ロングツーリング中は曜日の感覚がなくなることがあるのでね。(update:Dec/2000)
北海道キャンピングガイド
\1800(97年版)とちょっと高いですが,お勧めです。「Rise」という北海道のアウトドア情報誌を出している札幌のギミックという会社から毎年4月頃にでているようです。各キャンプ場に「ライダー中心」「ファミリー中心」「オールマイティ」の評価が付けられていて,近くのGS・商店・お風呂その他の情報も親切で分かり易いと思います。
入手方法ですが,道内でも一般の書店では,置いているところが少ないような気がします。大阪では梅田の駅前第一ビルのIBS石井スポーツ(登山用品部の2階テント売り場),苫小牧では市街からフェリーターミナルへ向かう産業道路沿いのセイコーマート(コンビニ)で,また釧路では駅前の小さな書店で見かけました。新日本海・東日本海・東日本の各フェリー船内の売店でも扱っているようです。(ギミック・〒011 札幌市北区北33条西4丁目4-15 Fit334 2F / TEL(010)737-4344 / FAX(010)737-5138)
道の駅
元々は一般道にも高速道路のSA(サービスエリア)みたいな施設を作ろうという趣旨だったそうですが,観光物産館みたいになっていますね,大抵のところが。まあ広いパーキングに,きれいなトイレはあるし,食事も取れてお土産も買えるという点で重宝しています。走っていて見掛けるとつい寄ってしまいます。中には結構特色のある楽しい駅もあります。北海道の道の駅では,道路地図も無料で貰えるのが嬉しいです。なおこの「北海道 道の駅 SAFTY ROAD MAP」は置いている駅といない駅があります。置いている道の駅でも近年は平積みしてあるのを見かけないような。インフォメーションの人に「地図ありますかぁ」と聞いて,置いてあれば出してもらえます。全道が一枚で見渡せるのでプランを練るのに便利しています。高速のSAでもらえる地図は高速の範囲しか載っていないので。(update:Dec/2000)
ミツバチ族
バイクツーリングするライダー。エンジン音「ブンブン」から来るらしい。実際にこう呼ばれた事はありませんが。ライダーハウスなどのネーミングに使われているのは見かけました。
ライダーハウス
木賃宿。食堂やら銭湯やら民宿やらバイク屋さんあるいは個人が,ボランティアベースで開放している宿。無料あるいは心付け程度,で泊めて貰える。その食堂で食事をする事なんて条件のところもあります。寝袋を持参した方が良いです。あくまでボランティアなのに何か勘違いしているマナーの悪い利用者がしばしば問題になっているようです。
夕方雨が降り出して今日はキャンプはいやだなぁというときには探して見ましょう。ガソリンスタンド(特にキャンペーン参加のホクレンなど)で聞くと分かるかもしれません。「旅ツーリング」(正式名称が未だに分からない)という本などにある程度のリストが載っています。
といいつつ実は私はライダーハウスに泊まったことはありません,雨が降っていてもテントを張るっていう「あうとどあー」なやつだからです。でも,コインランドリーはちょくちょく利用させていただいています。一般のコインランドリーのないような小さな町でも,ライダーハウスに行けば宿泊者でなくても利用させていただけるからです。その印象ではライダーハウスの方々は親切な方ばかりでした。
 工事中です。データを増やして行きます。
工事中です。データを増やして行きます。見出し
本文
 画像 Photo=kb
画像 Photo=kb
Sojin Project / Masaaki 'Jack' KAGEYAMA