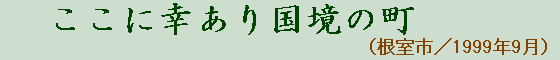
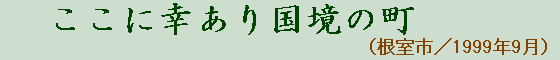
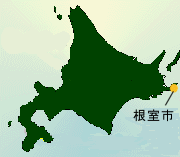 旅に出る前のこと。どこから北海道へ入ろうかということで、迷っていた。
旅に出る前のこと。どこから北海道へ入ろうかということで、迷っていた。
今回の旅はまったくのプライベートなのだ。どこから入ろうが、あるいはどこから出ようが、制約はまったくない。これがいつものように「出張ついでに足を延ばす旅」ならば、制約は多いが決まるのも早い。
9月になってようやく取ることができた9日間の夏休みだった。溜まりにたまったフラストレーション・・・当然のごとく旅に出ることに決めた。そしてこれも当然であるかのように、行き先は北海道と決めていた。
旅のスタイルはバックパッキングで行こうと考えた。「予定」というしがらみから完全に開放された旅をしたいと考えたからだ。
足の向くまま気の向くまま、何の制約も受けずに時間を過ごす・・・「出張ついで」の旅ではこうは行かない。まあ実際には行き帰りの足の確保だとか、それに伴う大雑把な旅程だとかは考えるわけだし、「完全に開放された旅」なんて、なかなか難しい話なんだけど・・・。
さて「バックパッキングで」ということまでは、すぐに決まったのだ。だが肝心の「じゃ、どこへ行こうか?」、これがなかなか決まらない。
比較的まとまった自由な時間がいざできてみると、「あそこへ行きたい」「いやいやこの機会に、どこそこへ行こう」などと、欲も出てしまう。
考えてみれば、たかだか9日間なんだよなぁ。そう思い返すと何やらミミッチく、そしてさらには寂しい気分にもなるのだが、やっぱり無駄にはしたくないと考えてしまうのだ。
さてそんなわけで、相変わらず目的地も決まらないまま、あれこれそんなことを考えながら過ごしていた、そんなある日のこと。
網走在住の知人に「北海道へ歩き旅に行く」ことを伝えたところ、「網走湖畔のキャンプ場で会いましょう!」という話がとんとん拍子に決まっていった。同時にこれであっさりと、今回の目的地が道東となることも決まったのだった。
あとはその知人と会うのを旅の最初にするか、最後にするかで、上陸地点を決めればよいだけ・・・実はその知人とは、まだ実際にお会いしたことがないのだ。それだけに旅のエピローグとしてお会いする方がインパクトもあるかも知れない。そうなると・・・
道東と呼ばれる地域は広い。その大部分は手付かずの原野であったり、湿原地帯であったり、地平線まで続く牧場地帯であったりする。
そんな中で自分が以前から「行ってみたい!」と思いながら、なかなか訪れる機会のなかった町をピックアップしてみることにした。そこで浮かんだ町が根室、そして別海という二つの町だった。
根室はご存知のとおり、日本本土最東端の町。そしてその先、本当に本土最東端に位置する納沙布岬からは、限りなく近く、だが訪れるにはあまりに遠い北方領土の島々を望むことができる。
別海をご存知の方は少ないかも知れないが、国策で開発された大規模牧場が広がる町。人の数の何倍もの牛がいる、そんな「広さ」の中に浸ってみようと思った。
どちらも私にとっては初めての町。そう思いはじめると、急速にイメージが膨らみ始め、旅のアウトラインのようなものが決まっていった。
今回は航空会社のマイレージポイントが貯まっていたので、そのマイレージポイントを利用しての無料航空券を使うつもりでいた。直前の変更ができない航空券なので何かと制約が多い(ほ〜らね、結局こんな具合に制約が増えて行くんだ)のが欠点だが、運賃が肩代わりできるのは嬉しい。
「帰りは網走に一番近い女満別空港に決めた。それじゃ、行きは根室に比較的近い釧路空港にしよう」
本当は中標津空港の方が根室に近い空港と言えるのだろうが、今回訪れようと思っている別海の町は、この中標津町と根室市の間に位置している町なのだ。だから一旦通り過ぎて根室まで行き、また戻ってくることになることが気に入らなかった。それに一度「花咲線」とも呼ばれるJR根室本線を走る列車に乗ってみたいとも思う。
というわけで、例によって長い前置きを終えて、今回の旅日記は釧路の町から始まる。
(今回特別に旅のアウトラインを長々と書いているには理由があるのです。今回の旅では、本編の根室に始まって、あちこちの町を気ままに歩いたわけですが、後日掲載する予定の、他地域の旅日記共通のプロローグ的な意味合いを持っているためなのであります。ご了解くださいませ)
 釧路駅前。もう何度か訪れたことがある町なので、大体の地理感覚はある。
釧路駅前。もう何度か訪れたことがある町なので、大体の地理感覚はある。
だが「とりあえずガスボンベ(登山などで使う携帯コンロ用のダルマ型ボンベのこと)を入手しよう」と思ったのだが、どこで買えるのかまではさすがに解らない。郊外のホームセンターなどへ行けば確実に入手できることは解っているのだが、そこまで行くのも大変だ。
そこで根室行きの列車の時刻を駅で確認してから、野外生活道具満載の重いバックパックを背に、交番へ向かうことにした。交番でガスボンベを入手できる店を尋ねようと思ったのだ。
「う・・・ん、ガスボンベねぇ・・・。どこにあるかなぁ・・・」
と、思案顔の年配のお巡りさんの横で若いお巡りさんが、「あそこだったらあるかもしれないなぁ。今地図に場所書いてあげるから待っててください」と言って、近くにある大きな釣具店を教えてくれた。確かに釣具店なら常備している可能性が高い。
釣具店で無事入手できて、再び駅に戻った。
戻る途中で交番に寄って「教えていただいた店、売ってましたよ。どうもぉ〜」と声をかけると「そりゃ良かった」と笑顔で答えてくれた。
旅に出るとなぜか必要以上に愛想が良くなる私だが、これはささやかながらも事が上手く進み、気持ちの良いスタートを切れたこともあって、素直な気持ちでお礼の言葉が出たためでもある。
根室行きの列車が出発するまでには、まだ時間があった。
この列車はJR根室本線を走る列車だが、「本線」と言う名前の割にはその雰囲気はローカル線。単線の線路を二両程度の編成のディーゼルカーが行き来している。
時間の効率を考えるなら都市間バスという手もある。待ち時間などを考えると、おそらくその方が早く根室に到着するだろうとは思うのだが、根室までは「鉄路」で行きたいと思っていた。バスが走るだろうルートは部分的にだが通ったことがあるし、この根室本線からの車窓風景が魅力的であると人から聞いたことがあったからなのだ。
というわけで、駅前でぼんやりと時間をつぶして過ごす。
目の前で一人女の子が自転車を組み始めた。輪行しながら旅をしているのだ。「輪行」とは、自転車を分解して袋の中に入れ、公共交通機関(別に公共じゃなくてもいいんだけど)を利用してで目的地まで移動するサイクリングのスタイルだ。目的の場所で再び自転車を組み上げて走り出す。
車やバイクで旅をしている人からすると、「自転車旅じゃかったるくて」と思うかもしれない。だが公共交通機関と自分の足(たまに、人の情け・・・つまりはヒッチハイクです)だけが頼りで旅をしている私などは、「自転車があればもっと行動範囲が広がるのに」と思うことの方が多い。
そんなわけで私も数年前に自転車ツーリングをもくろみ、輪行可能な結構な値段のMTBを購入したのだが、結局町乗り用の自転車と化してしまっている。ちょっともったいないなぁ・・・(にも関わらず、最近流行の「折り畳み自転車」を旅用に、などと考えたりしているのだから、困ったものだ)。
そんなことを思いながら過ごしているうちに、ようやく出発の時間となった。これから3時間、のんびりローカル線に揺られて最東端の町、根室を目指すことになる。
 根室に到着したのは、夕方近い時間だった。
根室に到着したのは、夕方近い時間だった。
せっかく「車窓風景を楽しもう!」と思っていた割には、ほとんどの時間を居眠りして過ごしてしまった。覚えているのは、厚岸湖のあたりの風景と、その付近の湿原風景くらい。これじゃ、とっとと高速バスで移動したほうが良かったかな?などとも思うのだが、これがいつもの旅らしいと言えば確かにそうなのだ。後悔の連続は人を逞しくしてくれるらしい(笑)。
終着駅根室の駅舎を写真に収め、釧路から電話で予約を入れたホテルへと向かう。
今日は根室市街地で過ごすことになるだろうし、それだけに遅い時間に到着してからテントの設営場所に悩むのが億劫な気がして、今日だけはホテルへ泊まろうと考えたのだ。
ホテルは、なんだか古ぼけた商人宿のような風情の小さなホテルだった。その割にはそこそこの料金を前払いで要求された。「眠れればどこでもいいや」ということで選んだホテルなので致し方ないのだが、札幌あたりのそこそこのホテルと同程度の料金だけに、「もうちょっと考えりゃ良かったかな?」と多少の後悔をしながらチェックインを済ませた。
バックパックは部屋に置いて、まずは街中を偵察に出ることにした。
今回は道東のあちこちを移動するつもりだったので、ツーリングマップル(昭文社刊)と言う名前の地図を購入し、そのままじゃ重いので、道東地域の必要と思われる部分だけをコピーして持ってきた。
名前のとおりバイク旅用の地図なので、普通の道路地図よりも旅の際に便利な情報が多い。例えば坂道などでは「比較的急な道」なんて注釈が付いていたりする。もっともバイクなら「比較的」でも、自転車なら「かなり」になるし、歩くとなると「とんでもなく」になるので、読み変える必要がある。
話を戻して、そんな便利な地図なのだが、街中を歩くには当然ながら役不足。普通の市街地図の方が便利なのは言うまでもない。
だがこの市街地図までは手が回らなかった。それでなくとも今回はバックパッキングスタイルだけに、とにかく装備が多いのだ。極力必須ではない装備を削った末、町歩き用地図は落選した。町歩き用地図は途中で入手できるであろう観光パンフレットと、人の善意に縋る(すなわち地元の方に尋ねるのだ)ことでカバーできると考えたからだ。
というわけで、今は手元に何の情報も持っていない(元々ガイドブックの類は持ち歩かないので)、やむを得ず勘を働かせて歩き始める。
闇雲に歩き始めてもどこかにたどり着くものだし、そこからとりあえずの目的地のようなものが自然に浮かんでくることも多い。

 歩いているうちに海に出た。北方領土の島影のようなものも見えるが、あれがどの島なのか、本当に島なのか、自信がなかった。まあ明日になれば納沙布岬に出かけるつもりでいるので、そのときに嫌でも(嫌じゃないけど)島の姿を見ることができるだろう。
歩いているうちに海に出た。北方領土の島影のようなものも見えるが、あれがどの島なのか、本当に島なのか、自信がなかった。まあ明日になれば納沙布岬に出かけるつもりでいるので、そのときに嫌でも(嫌じゃないけど)島の姿を見ることができるだろう。
そう思って海沿いの道から繁華街らしき道に入る。なんだか寂しい感じがするのだが、こんなものなのかなぁ。時間がまだ早いためかも知れないが・・・。
目に映る風景と見えている風景は、人の心のフィルターを通るためか、人によってそれぞれ違って見える。私は根室と言う町に対して「さいはての国境の町」というフィルターを持っているのかもしれない。だから寂しく映る・・・そんなことを感じながら歩いていたら、あっという間に繁華街を抜けてしまった。
繁華街を抜けてさらに続く商店街どんどんと歩いていると、ホームセンターの建物が見えた。
「特にさしあたって必要なものはないな」と思いつつも暇つぶしに中に入ってみると、「なぁ〜んだ、やっぱりあるじゃない!」。釧路で調達したガスボンベだが、しっかりこのホームセンターにも常備されていたのだ。わざわざ釧路で調達してくる必要もなかったわけだ(だが欲しいときに入手できないなんてこともおおいので、これはこれで正解なのだ)。
せっかく入ったのだからと店内を一周しているうちに、なんとなく電池式のシェーバーを購入してしまった。途中で身だしなみに気を付けようなんて気はさらさらないのだが、使い捨てのようなコンパクトなシェーバーだったので、つい手が伸びてしまったのだ(でも結局は一度も使わずに持ち帰る羽目になってしまった。余計な荷物を増やしただけというわけ・・・やれやれ)。
幹線道路を歩いて、市役所の前を通り掛かった。
市役所には「北方領土は日本の領土」の看板が掲げられていた。不確定な国境線を目の前にした町ならではという気もするが、これは根室に限った話ではなく、実は北海道ではそれほど珍しいことではない。
最近ではあまり耳にしなくなったのだが子供の頃、札幌あたりの町中で流れる街頭放送では、この「北方領土返還」の放送が流れていたことも覚えているし、今でも例えば北海道庁には同様の内容の垂れ幕が下がっていたりする。
市役所の門近くには「ここに幸あり」の歌碑が刻まれた石碑があった。
「この歌と根室になんの関係があるんだぁ?」と思ったのだが、後で知った話では、この有名な歌の作詞者(故高橋掬太郎氏)と作曲者(飯田三郎氏)が、共にこの根室の出身なのだった。市庁舎から決まった時刻になると流れるメロディも、この歌であるらしい。
いい歌だよなぁ。今でも古く感じない、名曲だよなぁ・・・などと思いながらも、この歌が流行していた時期はさすがに私の時代ではない。
久しぶりに見たような気がする夕焼け空の下、歌詞も節回しもいい加減なまま、この歌を口ずさみながらホテルへと戻ることにした。

 翌日は快晴。日頃の行いだろうか?(笑)。
翌日は快晴。日頃の行いだろうか?(笑)。
今日はこれから路線バスで納沙布岬へ向かう。納沙布岬からまた根室まで戻ってきて、別海町まで一気に移動しようと、昨夜ホテルの近くの店で夜食のラーメンをすすりつつ考えていたのだ。
駅前の観光インフォメーションセンターはバスターミナルを兼ねている。ここでパンフレットを入手したが、荷物がまたまた増えてしまうわけだ。昨日到着したときにこのパンフレットを入手していれば役立ったろうし、もう少し市街地歩きを楽しめただろうにと思ったが、「後悔先に立たず」というわけだ。
背中のバックパックをどうにかできないかと困って(コインロッカーには、とてもじゃないが収まりきらないのだ)、バスチケット売り場のお姉さんに相談してみたら、親切にも「また戻ってらっしゃるんでしたら、こちらで預かっておきましょうか?」と言ってくれた。
昨日から親切な人に恵まれて(昨日の交番の警察官は「職務」といっちゃえばそれまでなんだけど。でも仕事だってお互い気持ちよくなれる方が良いよね)、今日の天気のように良い気分が続く。
そう、昨日の夕焼け空が暗示していたとおり、今日は快晴なのだ。
納沙布岬行きのバスは空いていた。終点まで乗車したのは私を含めて数人のみ。
途中の風景は陳腐な言い回しだけど、日本離れした風景が続いていた。歩いた方が楽しそうだとも思ったのだが、やっぱり納沙布岬でゆっくり過ごしたいと思い返し、終点まで乗車したのだ。
周囲を見渡すと、そこそこ建物は建っているのだが全体的な印象としてはガランとした、"北海道らしい岬風景"が広がっている。
この風景の中に異質に感じられるほどの高さの「平和の塔」が建っている。そんな異質さ覚えるのは私だけだろうか?
この塔は国や市が建てた公共施設ではない。話に聞くところでは某団体が、北方領土を展望する目的で建てた塔なのだそうだが、この塔を実際に目にしてみると、このガランとした風景の中ではその飛びぬけた高さに、なんだか違和感を感じてしまったのだ。これだけの高さだと、島からもこの塔を見ることができるだろう。島から見えるこの塔は「平和の塔」に見えるのだろうか?
もちろんこの印象は、様々な立場や主義、あるいは経験と記憶によっても変わってくることだろう。だからこの印象を人に押し付けるつもりもないのだけど。
おそらく今日の天気なら、展望台のてっぺんからは北方領土全体が見渡せるのかも知れないと思ったのだが、結局登ってみることをしなかったので実際のところは解らない。
さてまずは、納沙布岬の先端が見える展望ポイントまで行き、写真を数枚撮影。
今回は荷物も多いしコンパクトカメラにしようか・・・などと思ったのだが、結局一眼レフカメラを持って来た。「よいカメラを持っているからと言って、よい写真が撮れるわけではない」ということは重々承知しているのだが。気分だけはプロカメラマン・・・というわけだ。それでも、少しでも軽量化しようと考え、レンズは標準ズームレンズを一本だけにした。

 続いて納沙布岬の先端へと向かう。
続いて納沙布岬の先端へと向かう。
昆布漁の船がたくさん出ていて収穫の真っ最中。陸の上で昆布干しの真っ最中。
この風景だけを見ていると、平和でのどかな北海道の漁村の一風景なのだが、思いのほか間近に、島が見えている。あれが水晶島だろうか。向こうに住む人々からは、こちらはどのように見えているのだろうか。見ている風景と見えている風景・・・立場が変わると、それもまた変わって見えるに違いない。
平和で、のどかで、明るい風景が見えているというのに、不安定で、厳しい、悲しい現実が写っている。曖昧なままの国境線が存在し、北方領土という未解決のままの問題が、ここからは展望できるのだ。
「島は奪われた」「北方領土を取り戻せ」。バスの車窓から眺めていると、この岬へ近付くに連れて道路脇のそんな看板が増えて行く。それが依然として北方領土問題の現実を示している。
北方領土と呼ばれるものが生まれ、異国の人がその島で暮らすようになって半世紀以上が過ぎている。彼の島々で暮らし始めた人たちも今では世代が代わり、その島々が生まれ故郷の人の方が多くなってしまったことだろう。
一方では、かつてその島々が生まれ故郷だった人たちは少しづつ減って行き、話の中や映像などを通してしか知らない人が増えて行く。
これだけの年月を掛けてなおかつ解決できない問題。時間が掛かれば掛かるほど、さらに解決までの道が遠くなる。
国と国のメンツの問題ではない。「そこ」に暮らす人々とかつて「そこ」に暮らしていた人々にとって、これからどうあることが一番幸せな選択なのか・・・。
問題が簡単に片付くようなものではないのは承知している。普段はそれほど関心を持ってもいない私ごときが、ここで偉そうに語るべきことではないとも思う。
だが、あまり触れたくない、あまり考えたくない、そう思いながらも、ここを訪れてみたらどうしても考えざるを得ない風景が目の前に広がっていた。

 岬の先端でも写真を数枚。
岬の先端でも写真を数枚。
岬近くには数軒の飲食などができる店が並んでいる。
寄ってビールの一杯でも・・・とも思ったが、あんまり北方領土の話をしたくないし、したくないけど、そんな話になってしまいそうだし・・・そんなことを勝手に想像していたら、なんとなく気乗りがしなく通り過ぎてしまった。
来た道を引き返し、バスの停車場へ戻ることにする。
バスの停車場近くには立派な駐在所があった。そもそも集落の言えるほどの集落でもないところにこんな駐在所があるのが不思議に思えるのだが、それは他の地域だったらと、但し書きが付く。ここはやっぱり国境が見え隠れする場所なのだ。何かを監視するためらしき塔が併設されている。
土産屋を何軒か覗いてみたが、これ以上バックパックを重くしたくないので、見るだけで済ませる。最初から買うつもりもなかったのだけど(ごめんなさい)。
 それにしても良い天気。快晴と言える。空が作り物のように青い。
それにしても良い天気。快晴と言える。空が作り物のように青い。
"ここに幸あり"のサビ部分の歌詞に「ここに幸あり 青い空」というフレーズがあるが、まさにそんな気分になる青い空だ(歌詞の意味はちょっと違うはずだけどね)。
バスの発車時間まではまだ時間があった。
だが運転手さんがドアを開けてくれたので、バスに乗り込んで出発を待つことにした。
再び根室駅前。預かってもらっていたバックパックを受け取る。
「あのぉ、料金は・・・」そう尋ねると、「いや、いいんですよ」との返事。この一言は嬉しかった。
コインロッカーを利用していたら有料なのだから、これは得をしたことになるのだが、タダで済んだことが嬉しいのではない。気軽に預かって頂いたことと、「お金なんていりません」と言ってもらった、その気持ちが嬉しいのだ。
でもこれはたまたま「コインロッカーに入らない荷物だった」ことによる偶然と「職員の方の好意」によるものなので、小銭を浮かせようと、なんでもかんでも預かってもらおうと考えないように。皆さん、コインロッカーを利用しましょうね(笑)。
 根室駅前にはカニの加工販売をしているお店が数軒並んでいる。
根室駅前にはカニの加工販売をしているお店が数軒並んでいる。
このうちの一軒で花咲カニを買った。今この場で食べようと思ったわけではなく、自宅に送るためだった。
花咲カニはタラバカニを小型にしたようなカニで、甲羅や手足にはタラバよりも鋭い刺があるカニだ。
このカニ、北海道でも厚岸から根室の根室半島周辺の海域でしか獲れないカニで(北海道以外ではサハリン、千島列島などで獲れる)、まさにこの根室ならではのカニということになる。小型な分だけもちろんボリュームはタラバに負けるが、味はタラバの味をギュッと濃厚にした感じで個人的には花咲カニの方が旨いと思っている。
札幌あたりでももちろん手に入るのだが、日持ちさせるため塩味がきつ過ぎたり、味が落ちていることも多い。
さてさてここで買ったこのカニに関して、私にとっては悲しい後日談がある。
旅を終えてこのカニを楽しみにしながら帰ってみたら、優しい我が家族はすべて味わい尽くした後で、私の口にはまるで入らなかったのだ(泣)。というわけで今回産地ならではの花咲カニの味は、結局試食した足の先っぽのみだった(やっぱり泣)。
駅に戻る。列車に乗って次の町、別海町へ移動だ。
駅周辺には高い建物が少ないせいか、また駅前が広々とした空間であるせいか、どことなく大陸的な印象を感じる。北海道の東のはずれの小さな半島の町なのに。
根室駅は終着駅。でもついうっかり忘れてしまいがちだが、重要なことに「終着駅は始発駅」でもあるということがある。そう言えば、そんな昔の歌があったっけ・・・なんだか「ここに幸あり」と言い、この歌と言い、「懐メロモード」だなぁ・・・。
JRらしいスムーズさのかけらもない発進の仕方で始発駅根室を列車は走り出した。相変わらず車内は空いている。
徐々に列車はスピードを増し、国境の町から離れて行く。
車窓風景を目にしながら、ぼんやりとこの根室の旅を振り返る。
「ここに幸あり国境の町」
キャッチフレーズのような言葉が浮かんだところで、根室の旅を終え、次への旅が始まろうとしていた。