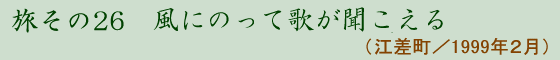
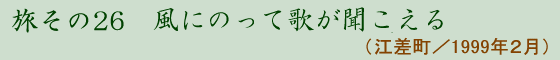
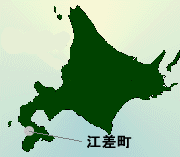 雪煙を上げて走る列車。雪煙の合間に見える風景は白い雪と樹林。
雪煙を上げて走る列車。雪煙の合間に見える風景は白い雪と樹林。
ここで汽笛でも鳴り響けば、まるで映画のワンシーンのようでなかなかロマンチックな情景かも知れないが、現実はそう都合良くは進まない。
車窓の風景も変わらず、車内の変化もなく、ただひたすらに退屈なだけの時間が流れている。
函館を出発した列車は途中の「木古内」で連結した車両の半分を切り離し、終点の江差の町に向かっていた。
退屈は眠り薬。次から次へと押し寄せる眠気の波状攻撃を受けながら、私は列車の中で過ごしていた。
私は昨日から函館に滞在していた。札幌からの長期出張の帰り。そのまま帰るのは惜しいので、例によって足を延ばしてのことだった。
札幌滞在中は「流氷を見にオホーツクへ行こう!」と思っていたのだが、最後の最後になって気が変わってしまった。今年は例年以上に寒い北海道。風邪気味だったこともあり、さらに厳しい冬を追いかけて旅することが、なんだか面倒になってしまったためだ。
函館は雪が少なく、北海道の中では比較的穏やかな気候の町。速度の一番早い特急列車を利用すれば、札幌から3時間程度。ビールでも飲んで、その後一眠りもすれば到着してしまう時間だ。そんなささやかな理由だけで、函館に向かうことにしたのだった。
昨日の昼に函館に到着してからは、自宅へ土産を送るつもりで朝市の何軒かの店を見て回ったり、函館山の夜景を見たりして過ごし、夜にはホテル近くの料理屋で酒を飲みながら過ごした。ただ風邪のためか、どうも調子が出てこない。「こりゃ大人しく帰ったほうが良かったかな?」と思ったりもして、そうなると酒も進まない。結局あっさりと切り上げて、ホテルに戻ったのだった。
「明日はどうしようか」と考えはじめたのはホテルに戻ってからだった。函館駅前のホテルには二泊の予約を入れていたので、明日は丸一日空いている。
ベッドに寝ころんで、時刻表をパラパラと捲りながら地名を拾って行く。
函館は何度も訪れているのだが(少なくとも1年に1回は函館を訪れていると思う)、函館周辺の町にはほとんど足を運んでいない。函館近くの森町に母の実家がある関係で、函館は札幌に次いで馴染み深い町ではある。だが函館とこの森町を結ぶ線上を行ったり来たりしているだけで、その線から外れたことがほとんど無いことに、あらためて気が付いた。
子供の頃に一、二度訪れた町もあるかも知れないが、記憶がなければ、それは知らないのも同じ。どこへ行っても「初めての町」を訪れることになる。
だが、それだけにどこへ行こうか迷うことになる。特別に行きたいところもないので、なかなか場所も決まらない。訪れるための「きっかけ」が無いのだ。無理にきっかけを作って出かけても、おそらくは退屈な旅になってしまう。
 そんなことを考えているときに、ふと目に留まったのが江差の地名だった。
そんなことを考えているときに、ふと目に留まったのが江差の地名だった。
もう二、三年前のことだが、「蝦夷共和国樹立」を夢見て函館五稜郭に立て籠もった、榎本武揚の本を読んだ。影響を受けやすい私は、一時期この榎本武揚を、尊敬する人の上位に置いていたことがある。その実務者的な発想、合理的な考え方・・・どれもが私に欠けている部分であり、だからこそ尊敬する人物だったのだ。もっとも「一時期」と書いたように、コロコロと尊敬する人が変わるような優柔不断さは私の持ち味なので(笑)、しばらく経ってみると忘れていた名前ではあったのだが。
さてその榎本武揚の本。その中で強く印象に残っていたのが、味方の援護に向かった当時最新鋭の軍艦・開陽丸が、嵐に翻弄されて座礁沈没するシーン。ストーリーの本筋ではないのだが、なぜか印象深く覚えていた。そして、その舞台となった町が江差の町だったことを思い出したのだ。
季節までは思い出せない。だが「荒れた日本海」というそのイメージが、今の季節にはピッタリという気がした。ついでに数年前にその開陽丸が引き上げ復元されたという話を耳にした(目にした?)ことを思い出した。
「寒風吹きすさぶ江差で開陽丸を見る」。
少々こじつけがましい「きっかけ」ではあるが(結局は無理にきっかけを作っているわけだよね)、都合良く目的のようなものも出来たので、この江差へと出かけることにしたのだった。
江差は民謡の町。「江差追分」と聞けば、ご存じの方も多いだろう。私も名前ぐらいは知っている。だが江差駅に着いて真っ先に「ムムム、この寒さは・・・」と思い、その駅前風景の寂しさに、続いて「向こうは寒風吹きすさぶ冬の日本海」などと思うと、想像力が退化しつつある私などは、民謡よりも演歌を想像してしまう。
市街地は駅から少々離れているらしい。そのせいか、寂しい駅前にはタクシーが何台も停車していた。だがここは雪道を歩くのが気分。そう、気分は演歌の世界なのだ。
鼻歌で「津軽海峡冬景色」などを口ずさんだりしているが、これは北海道の対岸、青森の歌だった。おまけにこの江差からは本州を目にすることはできない(たぶん)。
そもそもが歌詞を正確に知っているわけではないので、壊れたレコードプレーヤーのように同じフレーズばかりを繰り返している(例えが古いですねぇ。CDとかMDと言った方が良いのだろうけど。でもこっちの方がピンと来てしまうのだよなぁ)。
「"函館本線"の歌の方がピッタリかも」と途中で思ったが、こちらは題名だけで、歌詞はおろかメロディすら頭に浮かんでこない。「気分は演歌」などと言っていながら、所詮はこの程度の知識なのだ。
車道沿いに家が建ち並んでいるので、歩きながら海を眺めることはできない。雪が横から降き付けるような感じで降っていて、それだけに寒さを強く感じている。
坂道を少し下って、また少し上り返すと、「ここが江差の中心街」と思える地点に到着した。
中学生ぐらいの女の子数人が目の前を横切り、3階建て(?)のスーパーの中に入って行った。その元気の良さに、「さすがは風の子、江差の子」だと思う。フリースの上に、さらにダウンを着込んでいる私が、寒さに体を堅くして歩いているというのに・・・。
昼食にはまだ早い。それに腹もまだ空いていない。先に開陽丸を見ることにしよう。
そう思って、港へ続いているだろう、少々急な坂道を下って港を目指す。観光施設らしい姿が見えているので、そこへ向かうつもりでいる。
それにしても風が強い。"厳しい冬"を感じるのは、降雪よりも風に対して感じることが多い。日本海から吹き付ける風は容赦なく温もりを奪い、弱々しい冬の日差しなど問題にしていない。童話の「太陽と北風」の話を思い出したが、今の気分では圧倒的に北風に軍配があがる。もっとも今吹いている風は西からの季節風かな?
 さて開陽丸。まずは資料館に立ち寄ったが、考えてみれば開陽丸そのものに思い入れがあるわけでもなく、また幕末にロマンを感じていたり、興味を持っているわけでもない。
さて開陽丸。まずは資料館に立ち寄ったが、考えてみれば開陽丸そのものに思い入れがあるわけでもなく、また幕末にロマンを感じていたり、興味を持っているわけでもない。
だから様々な展示資料を見ても、正直に言ってしまうと特別な感慨は湧かないのだ。むしろ史実とはかけ離れたところで、「沈んでいた船を復元した」という事の方にロマンを感じてしまう。なんだか申し訳ないような感想なのだけれども。
ともあれ、こじつけのような「きっかけ」はあっさりと満たされた。実はすでに関心は今目の前に見えている「かもめ島」と呼ばれる陸続きの島に移っている。
 事前にガイドブックなり観光パンフレットなりで、見所やどんな土地なのかを知って置けば良いと思うのだが、いつも後手になる。そういった資料で紹介されている中で、自分が興味を持てそうな場所に真っ先に向かえば効率も良く、見忘れもないのだろうが、そのあたりがいつも「行き当たりばったり」。後になってから「うわぁ、こんなところがあったんだぁ。行けば良かったなぁ」と失敗を嘆くのだ(同じ場所を何度も訪れて、何度目かでようやくその町の魅力的な場所を見つけることなんて、しょっちゅうなのだ。自慢になるようなことじゃないけど)。
事前にガイドブックなり観光パンフレットなりで、見所やどんな土地なのかを知って置けば良いと思うのだが、いつも後手になる。そういった資料で紹介されている中で、自分が興味を持てそうな場所に真っ先に向かえば効率も良く、見忘れもないのだろうが、そのあたりがいつも「行き当たりばったり」。後になってから「うわぁ、こんなところがあったんだぁ。行けば良かったなぁ」と失敗を嘆くのだ(同じ場所を何度も訪れて、何度目かでようやくその町の魅力的な場所を見つけることなんて、しょっちゅうなのだ。自慢になるようなことじゃないけど)。
だから今目の前に見えている島についても事前に何の知識も無いのだが、なんだか面白そうだと、その「かもめ島」に向かうことにした。
土産屋のような建物がある。
夏場は賑わう場所なのだろうが、今は閉ざされている。確かに冬のこの時期に、多くの観光客を期待できないだろうと思う。雪の上に踏み跡が付けられてはいるが、さらにその上にはうっすらと雪が積もっている。江差についてから休み休みに降っている雪が、本格的に降り始めたらあっという間に消えてしまうだろう人の痕跡なのだ。
島の頂部へは階段を上る。その階段を上り切ると、そこは平坦な場所になっていた。
ここにも宿&土産屋のような建物があるが、同じように閉ざされている。やはりここもまた、冬期は休業中ということなんだろう。
新雪が新雪のまま、表面だけが強い風でザラメ状の中途半端な堅さを保っている。だから一歩前に進むたびに「ズボッ」と足首ぐらいまで埋もれてしまう。幸い防水性のあるハイカットのトレッキングシューズを履いているので、靴の中にまで雪が入り込むことはないのだが、気を許すと脹ら脛ぐらいまで埋もれてしまうので要注意。そろそろと歩を進めることになる。
 東屋風の展望台(と言っても、コンクリート製で立派)まで来た。
東屋風の展望台(と言っても、コンクリート製で立派)まで来た。
この展望台付近はさらに目一杯の季節風にさらされているので、雪面もかなり堅く、表面がひび割れるぐらいで埋もれることもない。
この展望台から日本海を眺める。
冬の日本海と言えば、ご想像通り。寒々しい灰色の海。白い波頭がさらに寒々しさを倍加させている。残念ながら雲は厚く、遠方の展望もない。「奥尻島でも見えるかな?」などと思っていたのだが、今は何も見えない。
音を立てて吹く風は、何かの歌のようにも聞こえるのだが、何の歌なのかは解らない。江差に到着した時に「演歌か民謡か」などと思ったためだろうか、なんでもかんでも歌に聞こえてしまうから困ったもんだ(笑)
「寒いよなぁ。夏来たら、いいとこなんだろうけど」そんな感想しか浮かんでこない。
この島ではキャンプもできるようだった。穏やかな季節ならば、きっと居心地の良い場所なのだろう。
「でも、今はそうは思えないよな、やっぱり」
今この季節にテントを張る酔狂な人は当然ながらいない。この寒さと風の強さは、たぶん冬の日本アルプス3千メートル級の稜線上にいるのと同じじゃないだろうか・・・。
トレッキングシューズは防水性があると言っても、防寒性があるわけではない。足の爪先が冷たくなってきた。
冷たさに足先がジンジンと痺れてきたところで、さすがに我慢できなくなって引き返すことにした。ようやく腹も空いてきた。昼飯を食べることにしよう。
 開陽丸の資料館が面した道を挟んで反対側は、漁港になっている。
開陽丸の資料館が面した道を挟んで反対側は、漁港になっている。
この漁港に隣接してフェリー乗り場もある。ここからは、あの北海道南西沖地震で不幸な災害に遭遇し、そして奇跡とも呼べる復興を果たした奥尻島に向かうフェリーが出ている。地震の前の奥尻を私は知らない。旅人の能天気な思いつきと言われればそれまでだが、いつかこの島を訪れてみたい・・・そんなことを思いつつ、港を通りすぎた。
車道に出て、そのまま歩き続けるとレストランを発見。「江差追分会館」なる立派な施設に隣接して建てられたレストランだ。ここで昼食を取ろうと考えた。
中に入ったが、広いレストランは閑散としている。観光シーズンではないためか。
「いらっしゃいませ。どうぞお好きなお席にお座りください」
一人で旅していると、つい遠慮して隅の席を選ぶことが多い。で、今回も無意識に窓際だが隅の席に座ってしまった。広い店内には他に客が一組いるだけだというのに・・・。私は慎み深い性格なのだなぁ、きっと(笑)。
迷った末、ありきたりのメニューを注文。海鮮風の塩ラーメン。もちろん、生ビールも忘れない。
さっきまで寒さに震えていたくせに、考えてみるとおかしな話だが、暖かい室内に入った途端に条件反射のように冷たいビールが飲みたくなる。もっとも北海道の冬は必要以上に室内が暖かいので、これが条件反射であったとしてもおかしくはない。
「お客さんは、どちらからいらっしゃったんですか」
「神奈川です」
お客さんがほとんどいない気楽さからか、そんなことをレストランの方に尋ねられる。
「そうですか。江差へは観光ですか?」
「ええ、そうなんです。札幌への出張帰りに函館に寄ることにしたんですけど、そのまま江差まで足を延ばしたというわけで・・・」と答えると、「今の季節は寂しいでしょ、この町は。寒いしね。夏はこれでも賑やかなんですよ」
母の実家が森町なので函館までは良く来るのだが、函館周辺の町はほとんど知らないこと、江差を訪れたのも今回が初めてであることなど、色々と話を続けて行くうちに今お話ししている方は、元々が東京でサラリーマンをされていた方だということを知った。
もう何年も前に江差に移り住んだらしいのだが(記憶が曖昧なのだが、ご本人か奥さんがこの町の出身であったとお聞きしたような。移ってきた理由もお聞きしたと思うのだが、覚えていない)。
さらに会話は続く。
「東京の景気はどうですか。あっちは不景気だと言っても、それなりに仕事はあるでしょう?」「ホントは向こうにまた戻りたいとも思うんですけどね。でもこの年になってから今更仕事を変えるのもねぇ・・・」。
若い頃を過ごした東京への思いと、江差の町で暮らすことを選択した決意のようなものが入り混じったような話しが、しばらく続けられた。
食事を終えて立ち上がろうとしたところで、「そうそう。こんなのがあるから持っていってください」と言いながら、観光パンフレットを手渡された。付近の見所なども教えて頂く。
支払いを済ませ、お礼を言って外に出る私に「どうぞ、お気を付けて」。
レストランの中の「暖かさ」をカイロ代わりに連れ出すような気分で、再び歩き出す。
 江差追分会館では、決められた曜日にイベントのようなものが開催されているらしい。今日は残念ながら何も催してはいない(本音は、あんまり残念という気はしていないのだが)と教えられたので、そのまま素通りし、これも教えられた古い商家(横山家−江戸時代に栄えた回船問屋/旧中村家−同じく江戸時代に栄えた仲買商など)に向かうことにする。
江差追分会館では、決められた曜日にイベントのようなものが開催されているらしい。今日は残念ながら何も催してはいない(本音は、あんまり残念という気はしていないのだが)と教えられたので、そのまま素通りし、これも教えられた古い商家(横山家−江戸時代に栄えた回船問屋/旧中村家−同じく江戸時代に栄えた仲買商など)に向かうことにする。
実は私、城を除けば歴史的建造物というものにあまり興味がない。正確に言えば、周りの建造物を含めた歴史的建造物の立地や景観(と回りくどい言い方をしたが、別に学術的な意味はこれっぽっちもない)、雰囲気には興味があるのだが、その建造物の中に陳列されている品々には興味が湧かないのだ。
「これが商家で使われていた由緒正しき算盤であるぅ」などと見せられても、思うことは「ふ〜ん」ということぐらいなのだ。だからいつもそうした建造物の前までは足を延ばすのだが、入場料のようなものを払って中まで入ろうとはあまり思わない。タダなら別だが・・・(なんだかんだ言って、結局はケチなだけ?)。
と言うわけで、それらの建物は外から眺め、写真を撮って十分満足したところで再び歩き出す。
 知らない町の知らない通りをブラブラ歩くことは楽しい。無目的で歩こうとも、なぜか楽しい。歩いていると些細なことにも関心が惹かれる。日常生活で歩くときは、これほど周りに関心を持って歩くことはない。だが旅先で歩くということは、何の変哲もない石垣に、あるいは表札の変わった名字に、「ほぉっ」と意識が留まるのだ。
知らない町の知らない通りをブラブラ歩くことは楽しい。無目的で歩こうとも、なぜか楽しい。歩いていると些細なことにも関心が惹かれる。日常生活で歩くときは、これほど周りに関心を持って歩くことはない。だが旅先で歩くということは、何の変哲もない石垣に、あるいは表札の変わった名字に、「ほぉっ」と意識が留まるのだ。
だがこれには「いつもだと」という但し書きが付く。
今日はこうして歩いていても、いつもと勝手が違うのだ。無理矢理にきっかけを作って江差を訪れたためだろうか、どうにも気分が乗らない。
「あそこへ行きたい!」「あそこへ行けば、何かあるかも知れない」。そういった、前へ進む気力のようなものが湧かないのだ。
だから今は、大失敗したような気分で黙々と歩いている。
当てずっぽうに歩いている内に、再び駅へと続く道に出た。
このまま駅に向けてのんびり歩けば、ちょうど良いタイミングで江差を出る列車があるはずだ。
「寒い」と言いながら、タクシーを利用しようと考えないのには、理由がある。何度も訪れる機会のある町ならば、タクシーでもなんでも利用してしまうのだが、そうでない場合、少しでもこの町の「空気感」を味わいたい・・・そんなことを思うからなのだ。「それでは、どんな空気感を感じましたか?」と訊かれると、答えようがないのだけれど・・・。そしてまた、そんなことを思いながらも、一向に楽しい気分になれないまま、歩き続けている。
歩いていて「もう一度、海を見ていこうか」と思った。闇雲に歩いていただけだったが、それでも1時間以上歩き続けていた。
車道からは海は見えない。港から比べて高い場所に付けられた道なので、おそらくここから見える海は断崖の向こう側。その断崖と車道の間には家が建ち並んでいる。
ちょっと横道に入って、もしかしたら私有地かもしれない場所から覗かせて貰おうと思ったのだが、優秀な番犬に盛大に吠えられて挫けてしまった。別にやましい気持ちはないのだが(でも人の家の敷地内に入り込むかも知れないのだから、十分やましい行為だね)、慌てて逃げ出してきてしまったのだ。
その場を離れても犬は吠え止まない。この寒さの中で散歩にも出られずに、暇を持て余しているのかも知れない。結局海を見ることは諦めて、寄り道をせずに、駅へ真っ直ぐと向かうことにした。
 駅に到着。
駅に到着。
この江差駅は江差線の終着駅。なぜこんなに町から離れたところに駅があるのか不思議な気もするのだが、町から離れている分だけ、余計に「終着駅らしい寂しさ」を感じる。
相変わらず風は強く、雪が舞っている。
ここでもまた風音が何かの歌のように聞こえていた。
そんなことを考えていたら、ふと今日一日の乗りきれない気分の理由が解るような気がしてきた。
風邪気味であったこと。強い風が吹き、寒さが肌身に染みたこと。そんなことがきっかけで、侘しさ、辛さ、寂しさ、そんな心の中に内在していて自分でも気が付かない感情、だがどんな時も実は常に離れることのない一人旅特有の感情が、今日は素直に顔を覗かせている・・・やれやれ、こんなところで自分の気持ちを分析してもしょうがないじゃないか・・・。
「江差追分って、どんな歌なんだろう。一度聞いてみないとな」
結局、一度も耳にしてはいないのだ。
「江差追分も演歌みたいな曲なのかなぁ」ふと、そんなことも思った。演歌のようにストレートに「情念」を歌ったものではないのかも知れないが。なぜかそんな気がする。
函館へ戻る列車が入線した。
いつもながらの勝手な想像が膨らんだところで、江差の旅を終えようとしていた。
<<江差追分(代表的なもの)>>
−前唄−
国をはなれて 蝦夷地が島へヤンサノェー
いくよねざめの 波まくら
朝なタなに聞こゆるものはネ〜
友呼ぶかもめと 波の音
−本唄−
かもめの なく音に ふと目をさまし
あれが蝦夷地の 山かいな
−後唄−
沖でかもめの なく声聞けばネ〜
船乗り稼業は やめられぬ
−前唄−
松前江差の 津花の浜で ヤンサノェー
すいた同志の なき別れ
ついていく気は やまやまなれどネ〜
女通さぬ 場所がある
−本唄−
忍路高島 およびもないが
せめて歌棄 磯谷まで
−後唄−
蝦夷地海路の おかもい様はネ〜
なぜに女の 足とめる