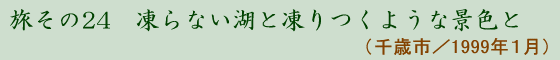
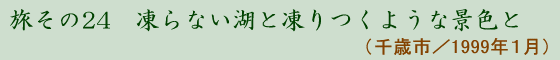
 北海道を訪れたことのある人にとって、「千歳」という地名は、馴染みの深い地名ではないだろうか。
北海道を訪れたことのある人にとって、「千歳」という地名は、馴染みの深い地名ではないだろうか。
北海道内には道外と北海道を直接結ぶ航空路線がいくつかあるが、その中でも新千歳空港を発着する便数はずば抜けて多い。たとえば東京(羽田)−札幌(新千歳)間は、30分に一本の過密ダイヤだ。 だからこの新千歳空港を玄関口として、北海道へ入った人も多いだろう。
だが私が千歳という町に対して抱くイメージは、この「表玄関の町・千歳」ということではない。私が真っ先にイメージし、そして思い出すことは、「坂の町」ということなのだ。実はこれには子供の頃の思い出が強く影響している。
千歳には近しい親戚がいる。子供の頃は家族揃ってよくその親戚の家を訪れていた。親戚の家の前には緩やかな坂道がある。その親戚の家を訪ねるたびに、子供の頃の私は最高の遊び場をみつけた気分で、その坂道で時間を過ごしていたのだ。
私の生まれ育った札幌東部は、見渡す限りの「真っ平らな土地」だった。住宅がまだそれほど建て込んでいない時代、2Km先の家が2階の窓から見ることができる、そんな平坦な土地に暮らしていた。それが理由で「坂道」というものに憧れを感じていたのかも知れない。
坂道を上っては、その上から周りの景色を眺めて過ごす。また下りては上ることを繰り返す。ただそれだけの時間がたまらなく楽しい一時だった。
その後も今回のように仕事で札幌滞在中などには時々寄ってはいるのだが、今あらためてその坂道を見ると、本当に緩やかなのんびりとした坂道でしかなかった。だが子供の頃見たその坂道は、別の景色を私に見せてくれる、魔法の道だったのだ。
さて最初から話が脱線したが(いつものことだけど)、今回はその私にとって思い入れの深い町、千歳を訪ねる旅。本格的な冬を迎えた1月にこの地を訪れた。
きっかけは、ホテルで朝食を摂っている際にたまたま新聞で見掛けた「支笏湖氷濤(ひょうとう)祭り」の記事。この祭りを見るために、久しぶりに支笏湖に足を延ばそうと考えたのだ。
 北海道は冬場に観光客が激減するらしい。「えっ!?、"スキー客"で結構多いんじゃない?」と思うかも知れないが(私もそう思っていた)、逆に一般観光客は極端に減少するらしい。スキー人口の何割かは、確かに北海道を訪れるかも知れない。だが一般観光の人の数と比べて考えれば、なるほど少ないというのもうなずける。
北海道は冬場に観光客が激減するらしい。「えっ!?、"スキー客"で結構多いんじゃない?」と思うかも知れないが(私もそう思っていた)、逆に一般観光客は極端に減少するらしい。スキー人口の何割かは、確かに北海道を訪れるかも知れない。だが一般観光の人の数と比べて考えれば、なるほど少ないというのもうなずける。
それにスキー客が訪れるのは札幌などの限られた都市部とスキー場だけ。その両方から外れる観光地は、この季節を乗り切るために、あの手この手で観光客誘致に知恵を絞ることになる。
北海道の冬と言えば「雪」と「氷」の世界。その天然の資源を有効活用しない手はない・・・と言うことで、この時期あちこちで「ミニ雪祭り」を始めたり、氷の器に蝋燭を灯してファンタジックな風景を演出したりするなどのイベントが開かれている。そしてこの、氷濤祭りもそんなイベントの一つなのだ(たぶん)。
さて、そんなわけで私は今、JR千歳駅前にいる。
駅前の交番で支笏湖行きのバス乗り場を確認し、バスの時刻を確認する。私が思っていた以上に便数があるようなので、ちょっと寄り道してから支笏湖に向かうことにした。
氷濤祭りは昼よりも夜。ライトアップされた氷の芸術を見るならば、夕方から夜に掛けての時間がベストの時間・・・そう思ったのだ。

 千歳の市街地の反対側には、ほとんど足を運んだことがない。
千歳の市街地の反対側には、ほとんど足を運んだことがない。
この反対側には千歳川を遡上するサケを観察したり、遡上するサケをインディアン水車と呼ばれる捕獲機で捕獲するところなどが見学できる「サケのふるさと館」という施設がある。だが今は遡上の季節をとっくに過ぎているので、なにが見学できるのかは解らない。
時間をつぶすにはちょうど手頃と思って、この施設を訪れることにした。
雪道は除雪もされているし、それほどの量でもない。元々千歳を含むこの地域は、北海道でも比較的雪の少ない地域なのだ(だから北海道の玄関口としての空港を作るのにも適している)。
そんな雪道をしばらく歩くと、サケのふるさと館が見えてきた。
入り口まで来たのだが、途中から気が変わっていた。「中に入らなくてもいいかぁ・・・」。
実は以前からここに来たら、「サケの遡上を見るんだもんね」と、ず〜っと思っていたのだ。今まで機会がなかったわけではないのだが、サケの遡上シーズンにはいつも外れていて、そのたびに「今度にしよう」と先延ばしにしてきた。で今回も、サケを見ることも出来ない今の時期に、一度館内を見てしまうと次回に訪れたときの楽しみが半減してしまうような、そんな貧乏性?のために途中で先送りするつもりになっていたのだ。ああ、情けなや・・・(笑)
館の裏手に回り、インディアン水車のところまで行ったのだが、この季節は水車も外されている。そう言えば、入り口のところに水車が展示されていたが、あれがそうだったのだ。
しばらく千歳川を眺めながら過ごしていたが、他にやることもない。じっと立っているだけでは寒いだけ・・・結局来た道を引き返し、駅まで戻ることにした。
駅前に戻ったところで、ちょうど良い時間になった。
再びバス停まで行き、支笏湖行きのバスを待つ。
すでに行列が出来ていて、そのほとんどは氷濤祭り目当ての人たちのようだった。
乗ったバスは新千歳空港始発のバスだった。すでに7割方の乗客が乗っていて、なんとか座るには座れたのだが、くつろげる感じではない。
ただでさえ窮屈な二人掛けシートに、いつも以上に防寒着を着込んでいる二人が座るのだから、体が固定されている状態と大して変わりがない。
市街地を抜けると、もうあたりは自然の真っ只中。そう言えば、千歳駅から支笏湖に向かうルートはほとんど経験がない。雪のない季節だと札幌から支笏湖方面への直通バスがあるし、5年ほど前に支笏湖を訪れたときも、レンタカーを借りて同じルートでドライブを楽しんでいる。だからこのルートは何やら新鮮な気分がしている。
蛇行する千歳川が、バスが走るこの道に、まとわりつくように流れていた。

 やがて1時間ほどで支笏湖に到着した。予想通り乗客のほとんどは観光客だったようだ。みんな、湖に向かって歩き出す。私も帰りのバスの時間をチェックしてから、他の乗客の後に付いて歩く。
やがて1時間ほどで支笏湖に到着した。予想通り乗客のほとんどは観光客だったようだ。みんな、湖に向かって歩き出す。私も帰りのバスの時間をチェックしてから、他の乗客の後に付いて歩く。
支笏湖は冬でも凍らない湖だ。確か不凍湖の北限が、この支笏湖だったと記憶している。
空気はキーンと冷たく、顔が痛いほどなのに、今目にしている湖はさざ波を打っている。
「こんな寒いのに、凍らないとはねぇ・・・。見ているこっちは凍っちゃいそうなのに」
そんなことを思いながら、支笏湖の写真を何枚か撮影し、氷濤祭りの会場へ足を進めた。
陽が完全に落ちるまでには、まだ1,2時間ほどの時間がある。

 会場内を一回りしたが、「本番はこれからよぉ〜」と言う感じ。想像通り、やはりライトアップされている方が魅力があるということなのだろうか。訪れている人の数も、まだそれほどでもない。
会場内を一回りしたが、「本番はこれからよぉ〜」と言う感じ。想像通り、やはりライトアップされている方が魅力があるということなのだろうか。訪れている人の数も、まだそれほどでもない。
ところでこの氷濤祭りの「氷のオブジェ」、どうやって作るのだろうか・・・そう思って見てみると、鉄パイプなどで矢倉を組み、その周りを松の葉などで覆った上に、氷が幾層にも張り付けられている。
この「土台」に、スプリンクラーなどで霧状の水を吹きかけることで、様々な形のオブジェを完成させるらしい。吹きかける水は支笏湖の湖水だそうで、支笏湖ならではの氷のオブジェの出来上がり・・・と言うわけだ。
ただしこうして説明してしまうと簡単なようにも思えるのだが、美しい氷のオブジェを作り維持するためには、安定した天候と凍てつくような低温が不可欠。作成者の気苦労も並大抵ではないそうだ(とまあ、すべて伝聞モードです。この場ではそんなこと、これぽっちも考えてはいなかったのだが)。

 日が暮れてからもう一度ゆっくり廻ることにして、湖畔を歩くことにした。
日が暮れてからもう一度ゆっくり廻ることにして、湖畔を歩くことにした。
会場脇の吊り橋を渡り、人のいない湖畔を歩く。
吊り橋は千歳川に掛けられている。支笏湖を源流にして流れる千歳川は、やがて石狩川と合流し、日本海に注ぐ。私のイメージ通り、千歳川は源流からしてゆったりと流れる川なのだ。
こんな季節に湖畔を散策する人などいないせいか、ところどころでは予想外に雪は深い。気を許すと、うっかり「ズボッ」と膝近くまで埋まってしまうことになる。
台形型の特徴的な山頂を持つ樽前山が、ここまで来るとハッキリと姿を現す。ここで写真を1枚。続けてもう1枚。
夕暮れ時の美しい、でも寂しい、そして厳しい風景を見ていたら、なぜか子供の頃過ごした「冬」の出来事が思い出された。そして脈絡もなく記憶は過去を彷徨いだす。この旅日記の冒頭の「坂道」の記憶もその一つ。凍らない湖と凍りつくような風景とノスタルジックな記憶。
「支笏湖はね、自殺者の死体が上がらない湖なんだ。湖の底にね、枯れた木がいっぱいあって、そこに引っかかってしまうんだね。だから湖の底にはいっぱい白骨があるんだ。昔は"死ぬ骨"って書いて、死骨湖って言ってたんだよ」
子供の頃に誰かに聞かされた話だ。偽物臭い怪談話のたぐいなのだが、ドキドキしながらその話を聞いていたことも思い出す。
美しさと寂しさと厳しさを見せる風景が、私を「思い出」の世界に誘い込んでいる。
雪の中に埋まっていたため、トレッキングブーツの中に雪が入ってしまった。ジンジンと痺れたような足の冷たさを感じて、ここで来た道を引き返すことにした。
 ようやく辺りを闇が包み出していた。それとともに氷のオブジェは幻想的な風景を作り出す。人の数もあきらかに増えている。
ようやく辺りを闇が包み出していた。それとともに氷のオブジェは幻想的な風景を作り出す。人の数もあきらかに増えている。
そばで見ると照明灯にセロハンを被せた「安っぽさ」のようなものが目に付くので、なんだか興ざめした気分にもなるのだが、遠くから眺めている分にはなかなか立派なものにも見える。
「これってレーザー光線を使ったり、テーマ性のある音楽なんかも流せば、もっと演出効果があがるのに...」などと勝手なことも思うのだが、正反対に、だからこその「手作り」の雰囲気が心地良いとも感じている。観光客は身勝手でわがままなもので、その中の一人に私も含まれている。
早足で一周。もう一度、今度はゆっくり立ち止まりながら一周して、会場を後にした。
さらに人の数は増えつつあるようだった。

 体が冷え切っていたのと、おなかが空いていたこともあり、バス乗り場に向かう途中で見つけたラーメン屋で体の外と中から暖を取ることにする。
体が冷え切っていたのと、おなかが空いていたこともあり、バス乗り場に向かう途中で見つけたラーメン屋で体の外と中から暖を取ることにする。
観光地で食べるラーメンで、旨いラーメンに遭遇する確率はかなり低いと思っているのだが、北海道の場合は必ずしもあてはまらない(と個人的には思っている)。
ここのラーメンもそれなりに満足できる味だった。もっとも「空腹に優るご馳走はない」という格言のような言葉も世にはあるけれど・・・。
バス乗り場の待合所でバスを待つ。他にも幾組かがバスを待っていた。
誰もが言葉少ななのは、寒さに口を開くのが億劫なためだろうか。もちろん待合所の中が寒いわけではない。それほど屋外の寒さが厳しいということなのだ。
バスは半分ほどの混み具合。今度は二人掛けの座席に一人で座ることができた。
氷濤祭りはまだまだこれからが本番。花火が打ち上げられる(土日祭日のみ)のもこれからという時間なので、帰る人もまだまだ少ない。
「花火が上がる時間までここにいようか」とも思ったのだが、札幌で知人と待ち合わせをしていたので、この時間に引き上げることにしたのだ。
寒さを我慢しながらずるずると遅くまで時間を過ごしていたら、きっと帰りは満員バス。ここに到着してからず〜っと感じている「ノスタルジックな気分」も、あっさりと褪めてしまうかも知れない。
来るときに車窓から見た千歳川の蛇行も、今は闇の中。何も見えず、ガラスは曇って自分の顔さえ写らない。ノスタルジックな気分のまま、ぼんやりと過ごすしかない時間が流れる。
バスの中は暖かすぎるほどの暖房が利いていた。眠りを誘う気持ちの良さ。
いつの間にかぐっすりと寝込んでしまった私の目が覚めたのは、千歳の市街に入ってからだった。