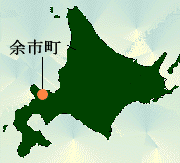 札幌の北西、小樽からさらに西に進むと余市という町がある。
札幌の北西、小樽からさらに西に進むと余市という町がある。
この町を称して「日本のスコットランド」と呼ぶ人がいる。
それはこの町が、スコッチウイスキーの故郷、スコットランドと気候風土が酷似していることによるものらしい。
ニッカウヰスキーの創業者「竹鶴政孝」もそう思った一人に違いない。そしてこの地にウイスキーの故郷を作ろうと思ったのだろう。1934年。ニッカウヰスキーの前身「大日本果汁株式会社」がこの地に設立された。
余市が果たしてスコットランドと同じ気候風土なのかは、正確なところは分からない。
だが余市を訪れると、なるほどここは「ウイスキーの地だ」と思ってしまう。そしてスコットランドも「きっとこんな気候風土なのだろうか」と想像してしまう。
今回はそんな日本のスコットランド、余市町を訪ねる旅。
今回の札幌出張は1泊2日という短期の出張だったため、最初から遠くへ出かけるつもりはなかった。ただ「せっかく訪れる北海道だ。短い時間でもちょっと足を延ばしてから帰りたい」と思っていた。
実は札幌へ来る前から「余市のウイスキー工場をまた訪れたいなぁ」と思っていたのだ。そして札幌へ向かう飛行機の中で「余市なら近いし、帰りに時間があったら寄って来よう」と考えていた。
つまり今回は、飛行機の中で旅の目的地が決まったというわけだ。
札幌から余市まではJRを利用するか、札幌駅前からの直通バスが利用できる。
だが駅まで行ってみると、余市まで行く列車がお昼までない。直通バスもかなりの時間待つことになりそうだ。
そこで「とりあえず小樽まで行こう。確か駅前のバスターミナルから余市や岩内、積丹方面のバスが出ていたはずだ」ということで、小樽まで快速列車で向かうことにした。
ちなみに今日は祭日(12月23日)なので「ニッカの工場見学が出来るのか?」ということが多少心配だった。せっかく余市まで行くのだし、せっかく日本のスコットランドを訪れると言うのに、ウイスキー工場なしではつまらない。
駅の本屋で立ち読みをして(スミマセン!)事前に調べた結果、「年末年始を除き、休祭日も見学が出来る」とのことだった。

小樽までの快速列車はほぼ満席。予定通り右側の座席に座って日本海を眺める(こちら側に座ると日本海を間近に見ることが出来る。これは旅日記"その3"でも触れています)。冬の日本海ということで、荒れた海を想像していたのだが、波は穏やかだ。
やがて小樽駅に到着。小樽に近づいた辺りから雪がちらついていた。札幌は快晴だったのだが、さすがに山を越えると天候も違う。
改札を抜け、バスターミナルへ。記憶していたとおりこのターミナルからバスが出ていた。
すぐにバスが来て乗車。ニセコバスの「岩内」行きだ。一部重複する区間を中央バスとこのニセコバスが走っている。
バスは空いていた。乗客は私を入れても6名。一番最後に乗り込んできた高校生風の二人連れは、手にスノーボードらしきものを持っている。このバスで行くとするとどこで滑るのだろう?
市街地を抜けると海が見えてきた。見ると、冬の日本海でサーフィンをしている人の姿が目に付いた。サーフボードを片手に海を見ている人の姿も見える。う〜ん、雪景色とサーフィン・・・あまり想像したことがない風景だよなぁ。バスの中では、スノーボード、バスの外ではサーフボード・・・。

バスは30分ほどで余市駅前に到着。まずはニッカウヰスキーの工場に向かうことにする。工場は余市駅から垂直に延びる道路の突き当たりにある。駅から歩いて2、3分の距離だ。
この工場、正式には「ニッカウヰスキー北海道余市原酒工場」と言う。この工場ではモルト原酒を製造している。
実はこの工場を訪れるのは今回が3回目になる。
1度目は秋の日の夕方にここを訪れた。だが見学時間も終わりに近い時間だったせいで、残念ながら中にはいることが出来なかった。窓越しに受付のお姉さんにジェスチャアで「入れませんか?」と尋ねると、窓口の向こうから同じように大きなジェスチャアで「バツ印」を笑顔で返されてしまったのだ。結局すごすごと引き返す羽目になってしまった。
2度目は同じく秋。札幌在住のK氏に車で連れてきて頂いた。この時は問題なく中に入れたのだが、社員旅行と思われる団体と一緒になって見学することとなった。なんとなく落ち着かない雰囲気の見学にはなってしまったが、それでもこの工場内の雰囲気がとても気に入った。
そして今回。今回は冬。季節が違うと、また違った雰囲気が感じられるかも知れない。
到着した時刻は昼の12時15分。正門には「見学は1時からです」という立て看板が置かれている。
一度はその看板を見て「周辺を散歩してから出直そう」と思って歩き出した。余市川まで歩き、「もう完全に雪景色だなぁ」などと思っている内に、段々と足の冷たさが辛くなってきた。
雪が舞っていてかなり寒い。感覚的には氷点下(実際に氷点下だったかもしれない)だ。出張帰りということで、靴も普通の革靴を履いているので、圧雪されていないところを歩いているうちに雪が靴の中に入ってしまった。このままでは工場を見学する前に足の冷たさに挫折してしまうかも知れない(笑・・・ちょっとオーバーだよね)。
そこで意を決して「中の待合所で待たせて貰おう」と思って、工場正門に戻ることにする。
「あのぉ〜見学したいんですけどぉ」
「はい。いらっしゃいませ。見学ですと、案内が付いての見学は1時からになっていますが、ご自由に見学されるのでしたら、今からでも結構ですよ。どちらにされますか?」
なんのことはない。自由見学なら、今すぐにでも入れたのだ。何も除雪していない道を雪漕ぎしながら歩いている必要など無かったのだ。
「あっ、じゃあ以前にも見学したこと有りますので、今回は自由見学で」と余計なことまで口走って、中にはいることにする。
入り口で記帳して、パンフレットを受け取った。
後で「構内を自由見学することは許可していない。案内に従って見学せよ」といった旨の案内板を見かけたので、もしかすると本当は自由見学は認めていないのかも知れない。何度も入り口の前を行ったり来たりする私を見るに見かねてなのかな?(笑)・・・私以外に自由見学の人たちを何人も見かけたので、見学者の少ないこの時期はいつもこのようになっているというのが、真相だろうけど。


構内の見学場所はコース化されているので、迷うことはない。
雪景色が前回訪れたときとはまた違った印象を与えてくれる。
歩く人が少ないため、道の上も新雪状態で、これは外を歩いているときとあまり変わらない。この季節にここを訪れるときは足周りに注意した方がいいだろう。
最初に見るのが、蒸留工場とブレンド工場。特に大きなポットスチルが印象的な蒸留工場が面白い。今日はポットスチルに火は入っていないが(見学用はいつも?)、ここのは「直火焚き」という直接ポットスチルを加熱する方法で蒸留している。温度に気を配りながら「微粉炭」と呼ばれる燃料を一杯一杯手作業でくべて蒸留をするそうで、そこには熟練した職人の技が生きているそうだ(と、もらったパンフレットに書いてあった)。
ただそう聞いただけで「手間暇がかかるのだ」ということはわかる。自動化によりチョイチョイと作られたものではないからこそ、その出来上がった製品に有り難みが出るのだろうなぁ。


続いて「竹鶴資料館」。この資料館ではこの地でのウイスキー造りの歴史などを詳しく知ることが出来る。奥には喫茶コーナーがあり、古いこの建物の中で「ティータイム」を楽しむのも雰囲気があっていいかもしれない。私はティーよりもウイスキーの方が好みなので、資料館の見学だけで満足したが。
雪道と樹林(白樺)とレンガ造りの建物。そしてさり気なく(でも演出として)積まれているウイスキーの樽などを見ていると、確かに見慣れた風景とは違う、外国にいるような気分になってくるから不思議だ。
そして観光客が少ないのもまたいい。案内の方に先導されて歩くのも、パンフレットでは知り得ない話なども聞けて良いのだが、前回のように団体に囲まれるのは私の好みではない。すれ違う人がほとんどいないせいか、構内はシーンと静まり返り、まったく別世界の雰囲気が漂う。
「ニッカ会館での試飲は1時15分からです」と言われていたので、試飲までにはまだ時間がある。その前にウイスキーの「貯蔵庫第1号」を覗こうと思ったのだが、これは扉が重く開かない。力を込めれば空きそうでもあるが、許可も無しに開けて良いかわからないので、一旦諦めることにした。
しょうがなく構内を適当に歩くことにする。コース外を歩こうとすると、雪が途端に深くなるため、結局同じようなところをグルグル歩き回ることになってしまった。でもそれだけでも楽しめるから不思議だ。歩き続けているせいで、足の冷たさを除けばそれほど寒さは感じない。


1時15分を過ぎたところで、ニッカ会館の展望台へ。この建物は観光用の施設で、お土産コーナーや売店、レストランなどが中にある。この施設の屋上階が展望コーナーになっているのだ。
それほど高い場所にある展望台ではないのだが、辺りに高層の建物が建っていないので見晴らしは良い。展望台からは余市の町並みと余市川が見える。もちろん、工場敷地内の風景も見ることが出来る。
どこがどうと言うわけでもないのだが、前回もこの景色を見て気に入った。そして、今回もまた満足できた。創業者の竹鶴さんは、この景色のどこにスコットランドを感じたのだろう・・・。
さて展望台を降りて、試飲コーナーへ。先客が4人ほどいる。私も早速一杯頂いたのだが、空きっ腹のせいか胃がキューと鳴る。体の中から火照ってくる感じだ。ウイスキーはやはり北国のお酒なのだなぁ。冬が似合う酒だという気もする。
続けざまにもう一杯・・・。
この試飲コーナーではお土産に、余市工場限定のウイスキーを購入する事が出来る。買って帰ろうかどうしようかしばらく迷ったのだが、帰りの荷物のこと(鞄に入るスペースがない)が頭にあり、結局断念してしまった。
他にもウイスキーを材料としたお菓子やチョコレートの類も売っている。


再び外に出る。
展望台から外を見ているときに、案内の方に先導された見学者が丁度、貯蔵庫のところにいるのが見えた。もしかすると今は扉が開いていて中に入ることが出来るかも知れない。
貯蔵庫のところまで来ると、期待していたとおり入り口の扉は開いていた。
中に入る。記憶にある「香り」が甦る。
熟成の過程で甘い香りが貯蔵庫内に広がる。果物の甘い香りに近い香りだ。ただ長時間その場に居ると酔ってしまいそうな感じでもある。この香りが強烈だったので、強く記憶に残っていたのだ。
入り口まで戻ってきたところで、受付で会釈をすると、にこやかに会釈を返してくれた。ここの工場の人はみんな愛想が良い。だからこっちもつい、愛想良くなってしまう。


さて、昼食を食べよう。
さっきウイスキーを入れたせいか、猛然とお腹が空いて来た。
通りを歩くおばさんに「どこか魚料理の美味しい店は?」と尋ねて教えて貰ったお店に入ることにする。
魚屋の2階にある「海鮮工房」というお店だ。
入ってみてビックリ。その値段の安さは「海の幸が安くて旨い」と言われる北海道でも群を抜いている。しかも階下の魚屋の直営店だそうだから、新鮮なことは間違いない。
ここでは"カニ丼定食"と"生ビール"、そして"宗八カレイの焼き物"を注文して、締めて1554円(税込み)。カニ丼定食のカニはずわい蟹の身がたっぷりは入っていて特に満足感が高い。お腹に余裕があればイカ焼き(ゲソ付き/250円)も追加注文したかったが、さすがにこれ以上は食べられない。
注文した品が来るまでの間、入ってくるお客さんを何気なく見ていると、手に「るるぶ北海道」を持っている人が2組もいた。うち一人は「ウニ丼食べたいんですけど、下で買ってくると調理してもらえるって・・・」と言っている。
このあと自宅に戻ってから、「るるぶ」を見てみると確かに書いてある。「下の魚屋で買ったウニを・・・」のくだりもちゃんと掲載されているのだ。「恐るべし、るるぶ。侮るべからず、るるぶ」なのだなぁ。


十分満足してお店を出た。
懐(ふところ)をあまり気にせずに、食べたい物をお腹一杯食べられたときに、私は幸せな気分になれる(これは私だけじゃないね)。雪はまだ降っているが、そんなことは気にもならない。「帰りは列車で帰ろう」と思って駅まで行ったが、次の列車まで1時間半も待つことがわかっても、寛大な気分でいられる(笑)。
ただ現実には、1時間半もここで時間を潰す気にもなれなくて、また帰りも路線バスを利用することにした。
スコットランドは海が近く、霧やもやが立ちこめる気候風土であるらしい。
そして清浄な空気と水。原料の大麦を乾燥させるための燃料となるピート(この時、ウイスキーに独特の香りが付く)に恵まれていること。これらの条件が揃うとウイスキー造りに最適な土地となるらしい。
余市の自然を見て「竹鶴政孝」は何を思ったのだろう。この地の何が「日本のスコットランド」と彼の目には見えたのだろう。
だがそれが分からなくとも、確かにこの地は日本のスコッチウイスキーの故郷であり、日本のスコットランドだった。
だから今日の私は「日本のスコットランドで舌鼓」というわけだ。
それにしても「旨い酒」があるところに「旨い食べ物」がある・・・世の中、うまく出来ているものです。
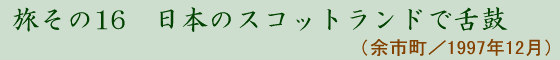
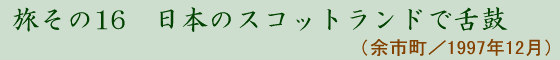
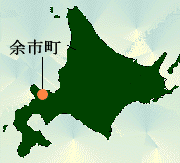 札幌の北西、小樽からさらに西に進むと余市という町がある。
札幌の北西、小樽からさらに西に進むと余市という町がある。 小樽までの快速列車はほぼ満席。予定通り右側の座席に座って日本海を眺める(こちら側に座ると日本海を間近に見ることが出来る。これは旅日記"その3"でも触れています)。冬の日本海ということで、荒れた海を想像していたのだが、波は穏やかだ。
小樽までの快速列車はほぼ満席。予定通り右側の座席に座って日本海を眺める(こちら側に座ると日本海を間近に見ることが出来る。これは旅日記"その3"でも触れています)。冬の日本海ということで、荒れた海を想像していたのだが、波は穏やかだ。 バスは30分ほどで余市駅前に到着。まずはニッカウヰスキーの工場に向かうことにする。工場は余市駅から垂直に延びる道路の突き当たりにある。駅から歩いて2、3分の距離だ。
バスは30分ほどで余市駅前に到着。まずはニッカウヰスキーの工場に向かうことにする。工場は余市駅から垂直に延びる道路の突き当たりにある。駅から歩いて2、3分の距離だ。
 構内の見学場所はコース化されているので、迷うことはない。
構内の見学場所はコース化されているので、迷うことはない。
 続いて「竹鶴資料館」。この資料館ではこの地でのウイスキー造りの歴史などを詳しく知ることが出来る。奥には喫茶コーナーがあり、古いこの建物の中で「ティータイム」を楽しむのも雰囲気があっていいかもしれない。私はティーよりもウイスキーの方が好みなので、資料館の見学だけで満足したが。
続いて「竹鶴資料館」。この資料館ではこの地でのウイスキー造りの歴史などを詳しく知ることが出来る。奥には喫茶コーナーがあり、古いこの建物の中で「ティータイム」を楽しむのも雰囲気があっていいかもしれない。私はティーよりもウイスキーの方が好みなので、資料館の見学だけで満足したが。
 1時15分を過ぎたところで、ニッカ会館の展望台へ。この建物は観光用の施設で、お土産コーナーや売店、レストランなどが中にある。この施設の屋上階が展望コーナーになっているのだ。
1時15分を過ぎたところで、ニッカ会館の展望台へ。この建物は観光用の施設で、お土産コーナーや売店、レストランなどが中にある。この施設の屋上階が展望コーナーになっているのだ。
 再び外に出る。
再び外に出る。
 さて、昼食を食べよう。
さて、昼食を食べよう。
 十分満足してお店を出た。
十分満足してお店を出た。