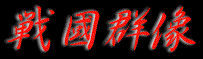163「検地―聖域なき構造改革―」
蜂屋頼隆(1534―1589)
兵庫頭、出羽守、侍従。美濃出身で、早くから隣国尾張の織田信長に仕え、黒幌衣衆のひとり。永禄十一年(一五六八)、信長の上洛に従う。以後、石山本願寺攻めをはじめ各地の一向衆との戦いに参加した。また、信長の命により、謀叛した荒木村重の一族を尼ヶ崎で処刑した。天正十年(一五八二)、本能寺の変後、羽柴秀吉に従い山崎の合戦で明智光秀を破った。豊臣政権下では敦賀四万石を与えられ、羽柴の姓を授けられ、敦賀侍従と呼ばれた。嗣子がなく断絶。室は丹羽長秀の妹。
◆サラリーマンの納税が天引きであることを「ガラス張り」と言われたりする。が、自己申告制のままであれば、十のうち七ぐらいを所得として申告し、その分の税を納め、あとの三はまるまる余禄とすることができる(余地がある)。検地はこうした隠された三の分までも摘発し、一定の税を安定的に徴収できるようにする目的がある。
◆かつて「検地」と呼ばれる「聖域なき構造改革」があった。ここでは特に太閤検地のことを指すものとするが、百姓が検地を嫌がるのは、年貢の基準が決められてしまうというのが要因のひとつである。「高」が決められると、その土地を領する大名も果たすべき軍役を把握されてしまう。太閤検地の弱点は、物成りのいい土地もそうでない土地にも一定の基準を適用していったところにあるであろう。
◆蜂屋頼隆は検地反対派だった。今風に言えば抵抗勢力か。ある時、秀吉を囲んだ夜話の際、機嫌がよさそうなところを見計らって、「検地お許し候ように」と箇条書きを差し出した。要旨は次の通り。
一.今度の検地で上下とも痛みが並大抵ではないこと。すべての痛みは積もっていっても、しまいには元へ戻るものであること。検地による痛みは元へ戻らない。
一.士民に限らず、老後の楽しみがなくなり、人の気味も年々卑しくなり、至誠の人物はいなくなってしまうでしょう。
一.それでも検地を進めるのであれば、せめて故郷の屋敷分だけでも除外してほしい。
◆すると、秀吉は表面上、ニコニコ笑いながら、
蜂屋出羽検地ゆるせとさしていへどそらうそぶひて聞ぬ関白
と詠んだ。当時検地が進められつつあった出羽の検地と蜂屋の官名を、さらに条書中の「痛み」という言葉と蜂屋の蜂にかけて「さして」をひっかけたシャレであろう。かつて「ハチの一刺し」という言葉が流行ったが、蜂屋頼隆の直諌は「一刺し」にはならなかったようである。◆この蜂屋頼隆は、常々、「五去七恐之図」という座右の銘を紙に書いて貼っておき、朝夕ながめて戒めとしていたという。「五去」とは「私心、闇君、邪欲、弐妻、雑学を去れ」ということで、身を守る要であるという。一方、「七恐」とは「主君、聖理、鬼人、位職、闇夜、水火、悪人を恐れよ」ということであった。主君、聖理、位職をあげるところなどは、頼隆の慎み深い性格を物語っている気もする。主君を恐れよということはイエスマンに徹することではない、というのは先の直諌でも知られよう。闇夜や水火を恐れることは、臆病になれということで、信長、秀吉に仕えて修羅場をくぐって来た者だからこそ、言える言葉であるかもしれない。信長も頼隆を信頼し、戦評定をする時には必ず彼を加えたという。
◆検地の話に戻る。
◆検地が推進された結果、武士は土地から切り離された。土地は一時の預りものとなり、勝手に売買できるようなものではなくなった。武士はお座敷で忠勤に励むしか生きる道がなくなり、自立性は失われ、官僚化していく。
◆明治維新の立役者に大名や上級の武士が皆無といっていい状況も、無理もあるまい。自主独立の気風は下級武士、軽輩の者の間で細々と命脈を保って来たのであろう。それならば、現代の政治、経済あらゆる分野の閉塞状況を打破できる者が、既存の政治家や官僚の中から出現することは望むべくもない、という見方もできる。
◆蜂屋氏は頼隆の没した後、嗣子がなく断絶となった。頼隆は遺物として金三十枚を秀吉に進上したが、返却されたという。形見の金は返し、改易に及ぶあたり、秀吉の頼隆に対する感情がほの見える思いである。頼隆の遺領敦賀には、大谷吉継が移って来る。出羽検地は大谷の主導で進められた。
 XFILE・MENU
XFILE・MENU