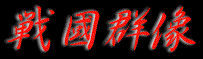

071「川よりも深く、ゆるやかに」
有吉立行(1558―1607)
四郎右衛門、武蔵守。細川藤孝・忠興に仕える。十三歳の折、不始末をおこした細川家の料理人を討ち、藤孝から賞賛される。天正元年(1573)、淀の城攻め以後、三十数度の合戦に出るという。慶長五年(1600)、細川忠興が上杉征伐に従軍すると、松井康之とともに豊後杵築城の留守を預かり、大友義統の軍を破った。慶長十二年十二月十四日、備後鞆の船中で病没。万歳山天聖寺に葬られる。
◆川を(あるいは橋を)渡る際の逸話というものは数多い。有名なところでは一休さんの「このはし渡るべからず」のエピソードがあるし、上杉景勝は輿が沈みそうになると無言で片手をあげるや、反射的に家臣団は全員川中へ飛び込んだという凄絶な逸話の持ち主だ。毛利元就は家臣に背負われて川を渡ろうとして家臣が転んだのを咎めなかった。小田原城攻めの際、断崖に接する細い橋を馬で渡る諸将の中でひとり徳川家康は下馬した上に、自らは徒歩の者に背負われて渡った。家康のエピソードなどは「石橋を叩いて渡る」の同工異曲であろう。「石橋」シリーズといえば「叩いて他人に渡らせる」とか「叩いても渡らない」など現在にいたるまでさまざまなバージョン(?)が再生産され続けている。これなどは言葉のリトマス試験紙といってもいい。
◆川あるいは橋は、そこにリスクがひそむ。これをいかに回避するかによってその人の器量が問われるのである。川や橋にちなんだ逸話が多くなったのは器量人をはかるモノサシとして簡便だったからだろう。あなたはご自分の「石橋」を持っているだろうか。
◆細川家の家臣にヌボーっとした男がいた。名前は有吉四郎右衛門。細川家の記録には「総じて若き時は鈍き生まれつきと諸人存じ候」とある。当時は十七、八歳ぐらいであったろう、このヌーボー四郎右衛門が幼少の頃の細川忠興の遊び相手。忠興を肩車に乗せて川を渡ろうとした時のことである。川が思ったより深く、四郎右衛門の身体はズブズブと沈んでしまった。川の真中あたりに来た頃には四郎右衛門の頭はとっくに水面下。「だいじょうぶか、四郎右衛門。応答せよ、応答せよ!」忠興の呼びかけに対しても、水中からはあぶくが立ち上るばかり。
◆それでも幼少の主君を肩車に乗せた四郎右衛門は川底を歩いて無事に向こう岸へたどりついた。ところが、忠興を下ろした途端、そのまま昏倒してしまった。「たいへんだ、四郎右衛門が死んだ」と大騒ぎする忠興の声を聞きつけた者たちが、足でもって四郎右衛門の腹を空気ポンプのように踏みつけ、たまった水を吐き出させてなんとか蘇生させた。家臣たちの乱暴な扱いを見ても四郎右衛門が軽んじられている様子が想像できる。
◆この時、肩車されていた細川忠興はおさなごころに「この者ただものにあらず」と思った、と『細川家記』は記している。人間空気ポンプと化している四郎右衛門を見て、忠興がどういう意味で「ただものにあらず」と言ったかはわからないが・・・。
◆この四郎右衛門、頭まで水に浸かったせいかどうかはわからないが、長じてなかなかの人物になったらしい。『細川家記』によれば、「次第にさかしく成り」とある。だんだん利口になってきたというのである。藤孝・忠興の二代に仕えて武功も数え切れず。
◆関ケ原の合戦で天下の大勢が決すると、武功の書き立てなどが流行った。有吉家でも嫡男康以と家宰の葛西惣右衛門の両人が相談してこれにならおうと考えた。そこで、四郎右衛門およびその父祖代々の武功聞書を作成するため、主人のところへインタビューにやってきた。すると四郎右衛門は「みっともないことをするな。そんなことは外様や新参のすることだ。譜代の家臣の働きぶりはご主君がみんなご存じだ。ただ細川家に有吉の名字が残っていればそれで十分なのだ。聞書などつくっているヒマがあったら、有吉の家が絶えないようにする工夫でも考えろ」と言った。四郎右衛門には聞書などが小賢しい「危機回避」に思えたのかもしれない。家を絶えないようにする工夫、すなわち「おまえも主君を背負って水に飛び込め」と言いたかったのだろう。
◆そういうわけで有吉四郎右衛門立行の覚書・聞書の類は遺されていない。もっとも寛永十六年(1639)に有吉の屋敷が火事に遭った。この時に古い書き付けなどが失われたという。四郎右衛門のインタビュー拒否の逸話がこの火事以後につくられたものだとしたら、「聞書・覚書」がない理由づけとしてはやせ我慢っぽくて面白いのだが。
 XFILE・MENU
XFILE・MENU
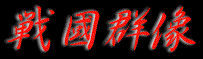

 XFILE・MENU
XFILE・MENU