新宿御苑 |
江戸時代に信州高遠藩内藤家の下屋敷のあった場所、日本式庭園の玉藻池付近が下屋敷時代のものを継承しています。かつては玉川園と呼ばれていて、屋敷東側を流れていた玉川上水よりの余り水や渋谷川の水を引いて、池や滝を作り、築山、谷の有る十の景勝地が作られていました。樹齢四百年を誇る巨木もあり興趣がつきない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
太宗寺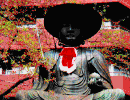 |
内藤新宿の仲町に位置し、寛文8年(1668)の創建、信州内藤家の菩提寺。六地蔵は正徳2年(1712)地蔵坊正元が10年がかりで江戸中からの浄財よって、旅人と江戸市民の安全を祈願して各街道口に建立した。銅造地蔵菩薩座像、六道(地獄道、飢餓道、畜生道、修羅道、人間道、天上道)をさまよう人々を救うのが地蔵菩薩です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
穴八幡神社 |
境内の穴から阿弥陀如来像が出てきたことから、穴八幡神社と言われる。流鏑馬は享保13年(1728)八代将軍吉宗が世嗣の疱瘡平癒祈願のため、穴八幡神社へ奉納したのに始まり、以来将軍家の祈願所として、若君誕生の祝いや厄除けに高田馬場で流鏑馬が奉納された。現在は都立戸山公園に会場を移して小笠原流流鏑馬として公開されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊野神社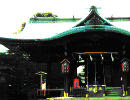 |
十二社の熊野神社は、室町時代の応永年間(1394〜1428)に中野長者と呼ばれた鈴木九朗が、故郷の紀州熊野権現を勧請したのに始まる。 鈴木家は熊野三山の祀官をつとめる家柄であったが、源義経に従ったため、奥州平泉より敗走し、九朗の代に中野に住むようになった。その後、鈴木家は家運が上昇し、応永10年(1403)には熊野三山の十二所権現を総て祀ったと言われています。 享保年間(1716〜35)に八代将軍吉宗が鷹狩りの機会に参拝し、滝や池を擁した風致は江戸西域の景勝地として賑わった。 氏子町は西新宿並びに新宿駅周辺及び歌舞伎町で新宿の総鎮守となっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 天竜寺 | 門を入って江戸時代の時の鐘があり、上野寛永寺、市ヶ谷八幡の鐘と共に江戸三名鐘と言われていた。この鐘はこの寺を菩提寺にした笠間城主牧野備前守が明和4年(1767)に作らせた物です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学習院旧正門 国重要文化財 |
明治10年(1877)に神田錦町にあった時の正門で鋳鉄製で透かしの唐草模様となっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||
副都心超高層ビル |
都庁展望台より新宿御苑を望む | ||||||||||||||||||||||||||||
花園神社 |
慶安元年(1648)に尾張公の別邸の花園に創建され、その後三光院が別当であったことから、三光稲荷または花園稲荷と呼ばれ、内藤新宿の鎮守として崇敬された。現在の社殿は昭和40年の再建です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
新宿山手七福神
|
|||||||||||||||||||||||||||||