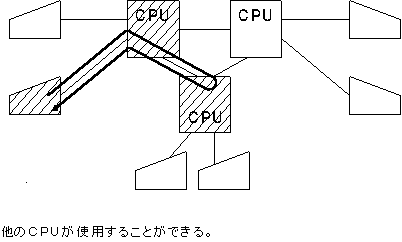カ
回線交換方式
通信を始める前に回線を確保してから情報の伝送を行う交換方式。この代表的な例が電話である。この方式では一度回線を確保してしまえば,
通信が終了するまでその回線を占有することになる。
回線使用率
その回線群が運んだ呼量の割合。回線使用率は、次式で表される。
回線使用率=総呼量/回線数×100[%]
回線制御プロセッサ
外線トランクの管理を行うプロセッサ。中央制御プロセッサの制御に基づいて動作する。回線制御プロセッサは、着信情報を検出して外線着信情報をデータ線等を通じて電話機制御プロセッサに伝達し、各ボタン電話機で着信表示を行うように依頼するほか、保留機能、内線回路等の管理・制御も行う。
回線保留時間
呼が発生してから終了するまでの回線を占有している時間。回線保留時間は次式で表される。
回線保留時間=呼ごとの保留時間の計/呼数
回転同期
走査速度を一致させる同期方式。回転同期は、ファクシミリの同期方式用いられている。
開リンク結線方式
空きリンクと空き出線を組み合わせて選択する結線方式。リンクがふくそうしていると、出線が空いていても出線選択範囲から除かれるので、出線は不完全群の扱いとなる。2段接続のフレームに多く用いられている。
回路C(制御:コントロール)
X.21の相互接続に用いられている回路の一つ。DTEからDCEを制御する。データ転送中はこの回路をON状態にしておく。
回路CD(受信キャリア検出)
X.21bisの相互接続に用いられている回路。交換設備から信号を伝送するための搬送波(キャリア)を検出するための回路である。
回路CDL(データセット回線接続)
X.21bisの相互接続に用いられている回路。DTEの動作準備の状態を示す回路である。
回路CS(送信可)
X.21bisの相互接続に用いられている回路。DCEが交換網に信号送出可能かどうかを示す回路である。
回路DR(データセットレディ)
X.21bisの相互接続に用いられている回路。DCEの動作準備の状態を示す回路である。
回路ER(データ端末レディ)
X.21bisの相互接続に用いられている回路。回路CDLと同様な機能がある。
回路G
X.20、X.21の相互接続に用いられている回路。信号用接地又は信号の帰線に使われる。
回路Ga
X.20の相互接続に用いられている回路。DTEとDCE間が不平衡複流回路の場合、この回路がDTEの共通帰線として使用される。
回路Gb
X.20の相互接続に用いられている回路。DTEとDCE間が不平衡複流回路の場合、この回路がDCEの共通帰線として使用される。
回路I(表示:インディケーション)
X.21の相互接続に用いられている回路。DCEの状態をDTEに知らせる。
回路R
X.20、X.21の相互接続に用いられている回路。データ信号の受信に使用される。
回路RD
X.21bisの相互接続に用いられている回路。データ信号の受信に使用される。
回路RS(送信要求)
X.21bisの相互接続に用いられている回路。DCEの送信機能を制御し、ONでDCEを送信モードにする。
回路RT(エレメントタイミング)
X.21bisの相互接続に用いられている回路。受信信号エレメントタイミング信号を提供する。
回路S(信号エレメントタイミング)
X.21の相互接続に用いられている回路。DCEからDTEに信号のタイミング情報を供給する。
回路SD
X.21bisの相互接続に用いられている回路。データ信号の送信に使用する。
回路ST2
X.21bisの相互接続に用いられている回路。送信信号エレメントタイミング信号を提供する。
回路T
X.20、X.21の相互接続に用いられている回路。データ信号の送信に使用される。
会話モード
基本モードの片方向伝送を拡張したモード。交互に会話的に情報メッセージを伝送するもので、一方が伝送終了符号を送信すると伝送方向を反転させて、他方が伝送を開始する方式である。
カウンタ
通話メモリに対しタイムスロット内の情報を若番地から順に記録させる制御を行う。また制御メモリへクロックを送出する。
架空ケーブル
架空配線に用いられるケーブル。CCPケーブルが用いられている。また、つり線の要らない自己支持形と、つり線にケーブルリングを用いて架渉する丸形ケーブルがある。
拡張モード
基本モードの機能を拡張したもの。会話モード、両方向同時伝送モード、複数従局セレクション、コードインデペンデントモードの4つのモードがある。
確認型情報転送手順
フレームに付与された順序番号により、受信側で順序誤りやエラーフレームの検出を行い、再送の通知を行う手順。
画素
送信原稿に光を当てて反射する光の量によって白・黒の判断を行う単位。
仮想チャネル識別子(VCI)
ATMヘッダ情報の一つ。1つの通信に対応して1つのVCを設定し、これを識別するたの割り当てられた識別子のこと。
画素密度
1mmの間に画素がいくつあるかを表す単位。
カッド
ケーブルの心線を2対4本に撚り合わせたもの。
過電圧保護(O)
過電圧保護回路
各種回路のLSI等を高電圧から保護する回路。
加入者回路
通話電流の供給、過電圧保護、呼出信号送出、直流ループ監視、符号化/複合化、2線/4線の相互変換、試験引き込みの各機能(ボルシット)を持った回路。
加入者線交換機
加入者回線を直接収容する交換機。
加入者線試験ループ
加入者線信号装置
PB信号受信、可聴信号音送出等の加入者線の信号処理を行う装置。
加入者線路設備
収容局のMDFからユーザ設備との分界点までの線路のこと。
加入者線路用ケーブル
地下ケーブルとしてはPECケーブル、地下配線ケーブルとしてはCCP−CJケーブル、架空ケーブルとしてはCCPケーブルが用いられている。
簡易形網制御装置
既存の電話機で発着信し、電話機とDTEを切り替える機能をのみを持つ装置。
簡易二重床
フリーアクセスのこと。
監視形式(Sフレーム)
Iフレームの受信確認、再送要求、一時送信休止要求など、データリンクの監視制御を行うために使用。また、Sフレームでは、情報フィールドの転送は行わない。
完全群
入線から出線のどの回線でも選択できるような接続。出線のうち1回線でも空いていれば必ず接続できるものを完全群という。
感熱記録方式
主走査1ラインの画素数に相当する熱ヘッドを1列に並べ、画信号に応じて電流を流しヘッドに熱を発生させることにより、記録紙上に塗布された発色剤を化学変化させて記録画を再現する方式である。
キ
き線ケーブル
収容局から固定配線区画までのケーブル。通常は地下化されており、PECケーブルが使用されている。
規定点
ユーザ・網インタフェースにおいて、端末と網側設備との接続状態をモデル化して、それを標準構成として規定した点。
機能群
ISDNユーザ・網インタフェースで使用される装置の機能を表したもの。機能群には、NT1、NT2、TE1、TE2、TAがある。
ISDNユーザ・網インタフェース構造の1つ。基本インタフェースは、2つのBチャネル(64Kbps)と1つのDチャネル(16Kbps)の2B+Dで構成される。また、1次側のケーブルには、メタルケーブルが使用されている。
基本形データ伝送制御手順
データ伝送、誤り制御等を伝送制御キャラクタを用いてブロック単位で伝送する方式。この伝送制御キャラクタには10種類あり、これによりデータの開始・終了や情報メッセージ形式を規定している。誤り検出の方式は、パリティチェックやCRC方式が用いられている。
基本モード
基本形データ伝送手順の一つ。メッセージの構成、データリンクの設定手順及び情報メッセージの転送等が規定されている。
逆方向
従属局から制御局又は従局から主局へ向かう方向。
キャラクタ
文字や記号のこと。
キャラクタダイヤル
データ端末のキーボードを用いて、英数字コードを伝送することにより行われる方式。キャラクタダイヤルを用いることにより相手端末への接続に要する時間を短くすることができる。
キャラクタチェック方式
チャラクタを用いた誤りチェック方式。キャラクタチェック方式には、パリティチェック方式、定マーク符号チェック方式、ハミング符号チェック方式がある。
キャラクタ(SYN)同期方式
特定符号(SYN:0110100又は01101000)を同期キャラクタとしてデータの前につけて同期をとる方式。この方式では、送信データがない場合SYN符号が送出されていないので同期はとれておらず、受信側では常時SYN符号のビットパターンを監視している。この場合、受信側でSYNを見落とさないよう、送信側で2つ以上のSYN符号を続けて送出し、受信側でSYNを受信すると、その後の8ビットずつ順番に取り出し、同期を取りながら符号を組み立てる。
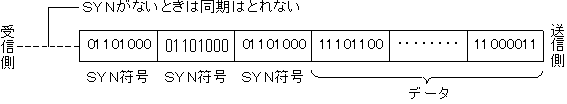
キャリアセンス
送信装置から電波を発射する場合に、空チャンネルを自動的に検出する機能。
キャンプオン
ボタン電話やPBXのサービス機能の一つ。相手が話中の場合、発呼者が呼出し状態のまま待機していれば、相手が終話した時点で自動的に呼び出す機能である。
キュー
順番待ちをする人などの列のこと。キューでは、到着順に処理される。
共通線信号装置
ITU−T勧告No.7による局間共通線信号の送受信等を行う装置のこと。
共通線信号方式
通信回線とは別に信号回線専用の回線を用いて、この信号回線を多数の通話回線が共通に使用する信号方式。
共通バッファ使用率オーバ
ふくそう制御を検出する方法の一つ。共通バッファ使用率オーバは、各パケット交換機及び各パケット多重化装置について、常時、単位時間当たりの共通バッファの使用個数を監視し、一定の基準値をオーバした場合にふくそうと判断する。
共通保留試験
PBXやボタン電話装置の試験の一つ。外線通話中に保留ボタンを押下することによって、通話を保留して、他の電話機で保留表示中の外線ボタンを押下することで応答ができることを確認する試験である。
極性整合ダイオード
DP信号送出回路のトランジスタ回路に対し、回線の極性が変化しても正しい極性を与えることができる。
極性反転検出回路(PC)
外線着信の際、外線の極性反転を検出し、着信予告の表示を行う回路。
局線市内自動発信
いわゆる「ゼロ発信」のこと。内線から「0」をダイヤルすることにより局線を掴みその後は通常の電話番号をダイヤルし発信できる機能である。
切替リレー
停電検出回路に使われているリレー。停電時又は停電復旧時に制御部からの指示に従いカットスルー(バイパス)又は復旧動作を行う。
記録変換
複合化した画信号を記録しに記録すること。ファクシミリの記録変換には、感熱記録方式と電子写真(レーザー)記録方式がある。
近端漏話
送信信号の伝送方向と逆方向に現れる漏話。
ク
空間分割スイッチ
クロスバスイッチに用いられている水平と垂直の交点の接点で動作するスイッチ。
クラッド
コアのまわりにあるシリカの層。クラッドは、光をコアの方に反射させることで、光がコアから漏れないようにしている。
グレージング方式
不完全群の結線方式。今では使用されていない、A形、H形の交換機の主として中間階梯で採用されていた。
クロスバスイッチ
クロスバスイッチでは、各水平路と各垂直路に置かれたバー、あるいはその交点に置いた継電器を動作させて交換する方式。また、クロスバスイッチのことを空間分割スイッチという。
クロスポイントスイッチ
電話機と外線との接続及び電話機相互間の接続を行うスイッチ。電子式ボタン電話装置等で採用されているスイッチである。
クロック同期方式
群計数チェック方式
ブロックチェック方式の一つ。伝送する符号のブロックごとに、ブロック内の符号を垂直に並べ、各ビットの水平方向の1の数を2進数で加算し、その結果を伝送ブロックの後に送信する方式である。この方式は、パリティチェック方式の欠点である偶数個の誤りに対処できる。
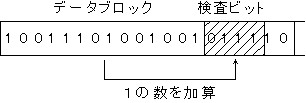
ケ
経路選択制御
ケースA
ISDNでのパケット交換サービスとしてITU−T勧告X.31で規定されているサービスの一つ。ケースAは、ISDN内にパケット交換機がなく、ISDNに接続されているパケット端末は、ISDNの回線交換機を経由して公衆パケット交換データ網内のパケット交換機にアクセスサービス形態である。この場合Bチャネルのみが使用可能である。
ケースB
ISDNでのパケット交換サービスとしてITU−T勧告X.31で規定されているサービスの一つ。ケースBは、ISDN内にパケット交換機がある場合のサービス形態である。この場合、BチャネルとDチャネルを用いることができる。
ケーブルパス
アンダーカーペット工法を用いる場合、ケーブルを立ち上げる箇所でフロアクリップと併用して用いるもの。床面から立ち上げたケーブルを機械的に保護する。
ケーブルラック
ビル内でケーブルを配線するためのラック。配管に比べて多くのケーブルを収容することができる。ケーブルラックには、垂直ラックと水平ラックがある。
コ
呼
利用者が通信を目的として、電話やパソコンなどで通信設備を占有することをいう。
コア
光ファイバの中心にある石英またはプラスチックでできたもの。コアは、温度や曲げなどの外力により、減衰量が大きく変化する。
高位レイヤ機能
OSI参照モデルのレイヤ4〜レイヤ7までに対応し、端末間の通信手順、情報の蓄積変換などの機能。高位レイヤ機能は、低位レイヤ機能のようにISDNに必ず必要とするものではなく、端末自体で持つことが多い。
交換プログラム
交換動作を進める基本的なプログラム。交換プログラムには、呼処理プログラム、障害管理プログラム、再開処理プログラム、運用保守プログラムがある。
交互充電方式
蓄電池設備を2組設置し、一定の周期で交互に放電・充電を行い設備を運転する方式。最近はあまり採用されていない。
光電変換
送信原稿に光を当て、反射光量を画素ごとに電気信号に変換すること。ファクシミリの光電変換には、CCDイメージセンサと密着形イメージセンサがある。
構内ケーブル
ビル内等で用いられるケーブル。心線の構成はCCPケーブルと同じである。屋内で使用されるので柔軟なPVC外皮でできているが、難燃性(FR)のケーブルもある。
コーデック
音声信号を符号化(coder)し、また、符号を音声に復元する復号化(decoder)を行うもの。これらの機能を合わせてコーデック(CODEC)という。
コードインデペンデントモード
基本形データ伝送制御手順の拡張モードの一つ。JIS7単位符号以外のビット構成を伝送することができるモードでる。データ部分に伝送制御キャラクタと同じビット構成が現れた場合は、その前にDLEキャラクタを挿入し、DLEキャラクタに続く符合はデータと見なす。
コードレス電話
自由に持ち運びながら通話ができる無線を使った電話。接続装置(親機)と電話機(子機)の構成。最近では電話機(子機)がPHS対応の製品もある。
コールウェイティング
通話中に着信があった場合に、通信中の相手を保留し、その着信に応答する機能。
コールトランスファ
通話中の内線電話機でフッキングとダイヤル番号等所定の操作をすることにより、通話中の相手を目的の相手に転送する機能。
コールパーク
通話中の内線電話機でフッキング等の所定の操作をし、通話中の呼を保留したとき、保留した呼に、他の内線電話機から特番をダイヤルすることにより応答できる機能。
コールバック
いったん接続された通話を切断し、着信側から発信側を呼び接続する方式。コールバックでは、着信側の課金になる。また、企業などのセキュリティ対策として用いられている。
コールピックアップ
あらかじめグループを設定しておき、グループ内の他内線への着信呼に対し、特番をダイヤルすることにより応答できる機能。代理応答とも呼ばれている。
コールプログレス信号
選択信号送出後、相手端末に対して回線が接続できない場合、網から発信端末に対して送出される信号。コールプログレス信号は、相手端末ビジー、着信拒否、網ふくそう、接続規制、選択信号伝送誤り等により、回線設定不可である理由がコードにより表示される。
国際ISDN番号計画
国際ISDNの番号は、ITU−T勧告E.164の中で規定されている。国を識別する国番号(CC)、国内の事業者を識別する国内宛先番号(NDC)、その事業者の加入者を識別する加入者番号(SN)より構成されている。
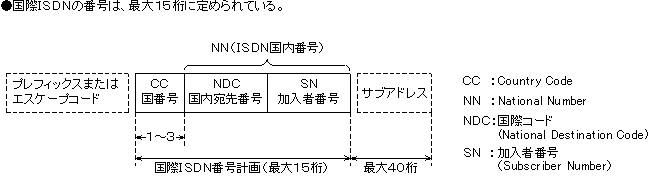
国際標準7単位符号
ISOで標準化されている「7ビット」の国際標準符号。この符号は、回線交換方式においてXシリーズインタフェースを有する端末の選択信号として用いられている。
呼処理プログラム
交換プログラムの一つ。正常運転時の呼接続動作を行うときにも用いられる。
呼損率
即時式の場合は接続過程で全話中(ふくそう)に遭遇した呼は接続されず、消滅するような呼を損失呼といい、その損失呼の発生する割合を呼損率という。呼損率をB、入線側に加わる呼量をaとし、そのうち運ばれた呼量をacとすれば、呼損率は次のようになる。
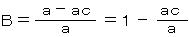
コネクション
通信経路のこと。
コネクション型
通信に先立って、仮想的な通信回線の確保と通信後の通信回線の開放が必要な通信方法。
コネクションレス型
仮想的な通信回線の確立を必要としない通信方法。
コネクタ接続
光ファイバを接続する方法の一つ。フェルールをピンとクリップを用いて接続する方法。分岐や切分けが必要な箇所に用いるが、融着接続法に比較して接続損失の点で劣る。
呼番号
特殊なメッセージを適用するユーザ・網インタフェースにおいて、呼またはファシリティの登録、解除、要求の識別に用いられる番号。
個別線信号方式
通信回線と信号回線を兼用して、対応する信号方式。
個別(自己)保留試験
PBXやボタン電話装置の試験の一つ。通話中に保留操作をした内線電話機のみが再応答できることを確認する試験である。
コマンド
コンピュータとコンピュータがネットワークを利用して通信するために決められた「約束ごと」という意味。プロトコルの国際的な標準として、ITU−T勧告や
ANSI 標準がある。
コマンド信号
同期式の接続制御手順等に用いられる接続制御信号の一つ。端末から網へ送出するもので、発呼要求や復旧要求を行う。
コマンドフレーム
受信側のアドレスを持つフレーム。
コモンモードチョークコイル
電磁妨害対策用として、線路の端末に挿入するコイル。このコイルは、縦電流に対して大きなインピーダンスを生じ、通話等の横電流に対してはインピーダンスを生じないように接続することにより、一種のローパスフィルタの役目する。
呼量
呼量の国際単位として、アーランを用いる。また、呼量は次式で表される。
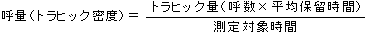
コンテンション方式
データ伝送を行う二つの局が対等であり、データを送信しようとする側がデータリンクを確立する方式。したがって、送信要求を先に行った局が主局となって送信権を得るいわゆる早い者勝ち方式である。
コンバータ
主直流電源の電圧・極性から異なる電圧・極性の直流を得るときに用いる装置。AC−DCコンバータ、DC−DCコンバータがある。
コンパンダ
集積回路の一つ。通話中における雑音レベルを下げるために用いられる。
コンピュータ間通信システム
遠隔地の異機種のコンピュータを対等の立場で結合し、これらコンピュータ群を多数のユーザで共同利用するシステム。
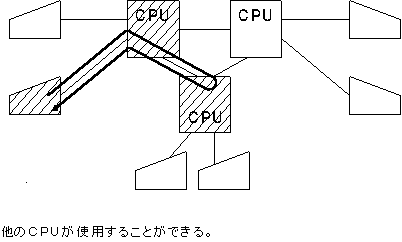
copyright(C) 1998 mori! all rights reserved.
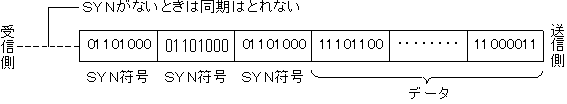
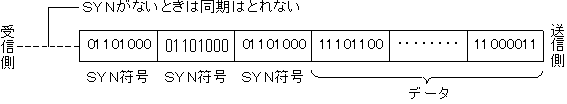
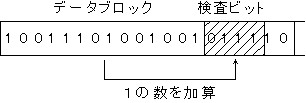
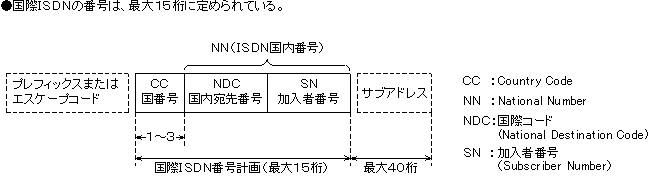
![]()
![]()