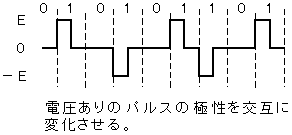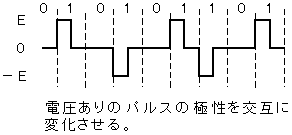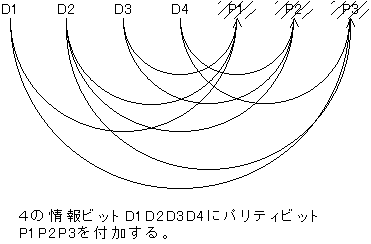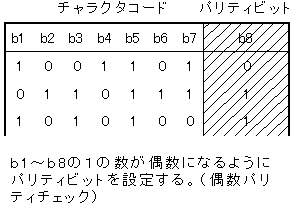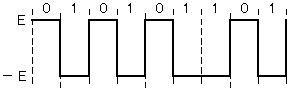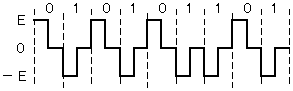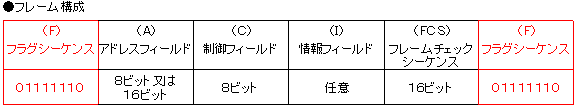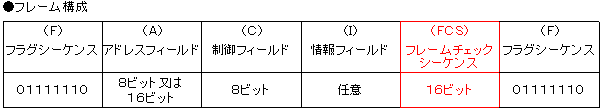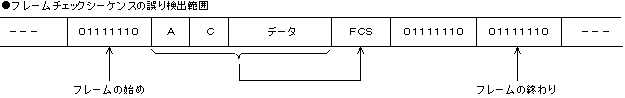ハ
ハイインピーダンス回路(HZ)
外線側と通話路との間のインピーダンスを整合させるための回路。
ハイウェイ
8bitのデジタル信号の通話用伝送路。送信ハイウェイと受信ハイウェイがある。また、タイムスロットはt0からt255までの256チャネルが多重化されている。
配線ケーブル
固定配線区画の加入者を収容するためのケーブル。架空配線ではCCPケーブルを、地下配線ではCCP−JFケーブルが用いられている。
媒体アクセス制御方式(MAC)
LANに必要な伝送制御技術で、ケーブルを複数ノードが円滑に共同利用するためのアクセス制御。OSI参照モデルのデータリンク層の下位副層に位置し、上位副層のLLCと共同動作することでデータリンク機能を実現する。バス型、トークンバス型、トークンリング型、無線LAN、FDDIなど各種LAN方式ごとに規定が存在する。
バイト
一般に、1バイトは8ビット。
バイナリコード手順
ITU−T勧告T.30で規定するG3ファクシミリに関するもの。伝送モードの標準は300ビット/秒の同期モードである。
2線−4線変換回路とも呼ばれ、外線からの2線を、送信用として2線、受信用として2線に分割して4線化する回路。デジタル信号の伝送には直流電流が用いられるため、アナログ信号のように1回線を送受信に兼用することは困難なので4線化する必要がある。
バイポーラ方式
単流方式の変形であって、単流方式の電圧ありのパルスを交互にプラス、マイナスの極性に変化させる方式。ISDNの基本インタフェースの伝送でAMI符号として利用されている。
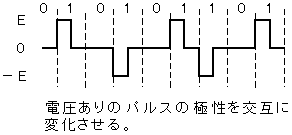
ハウラ(HOW)
受話器を外しっぱなしにしておくと、鳴る警報音。
パケット
ネットワーク上を流れるデータの固まり、またはデータの単位の呼び方。
パケット形態端末(PT)
パケットの組立て・分解機能を持っている端末。
パケット交換機(PS)
パケット多重化装置、パケット形態端末、他のパケット交換機との間でパケットの交換処理を行う交換機。また、交換処理のほかに、ルーティング制御、フロー制御なども行っている。
パケット交換方式
データを一定長のデータブロックに分割し、データブロックごとにあて先情報を含むヘッダを付加したパケットを組み立て、パケットごとに相手方に転送する方式。また、パケット交換機方式は、いったん記憶装置に蓄積させる蓄積交換方式を採用している。
パケット交換網
パケット形態端末(PT)、非パケット形態端末(NPT)、パケット多重化装置(PMX)、回線終端装置(DCE)、パケット交換機(PS)、から構成される。
パケットタイプ識別子
1オクテット(8ビット)で構成せれるが、最後のビットがデータパケットのときのみ0となり、それ以外のパケットでは1になっている識別子。データパケットの場合は、最後のビット0だけを確認すれば識別できるので、それ以外の7ビットは送信順序番号として利用される。
パケット多重
1本の回線で、同時に複数の相手と通信するために論理チャネルを設定する機能。
パケット多重化装置(PMX)
パケット形態端末及び非パケット形態端末を多数収容し、それぞれの端末からのデータをパケット化した後、高速回線に多重化しトラヒック集束を行う装置。
パケットレイヤプロトコル
X.25で規定されているレイヤ3のプロトコル。このプロトコルでは、相手端末までの論理チャネルの設定・解放を行う接続制御手順とパケットの送受信及び誤り制御を行うデータ転送手順が規定されている。
バス形
ネットワークを構成する各装置をバスと呼ばれる共通の伝送路に枝のように接続した構成。
パターンジッタ
タイミング回路の離調等に起因するジッタ。
発呼ユーザのアドレス情報フィールドの長さを表現するもの。発呼ユーザアドレス長は、ビット8〜5に2進数表示で挿入する。
発信音
ダイヤルトーン(DT)。電話機の受話器を上げたときに聞こえる、ツーーッという連続音のこと。
発信規制クラス
内線ごとに、発信を規制できる機能。超特甲、特甲、甲、乙などのクラスがある。
発信自動捕捉機能
発信時に送受器を上げるか、又はスピーカボタンを押下することにより、あらかじめ決められた外線を補足する機能。
バッチ処理
データをある程度まとめてからコンピュータで処理する方法。
パッド
ハイブリッド回路での4線化に伴うハウリングを防止するためのもの。
バッファ
転送データを一時的にためておくメモリ。
バッファ制御方式
フロー制御方式の一つ。端末ごとに受信用バッファに蓄えておくことのできるパケット数(契約バッファ)を定めておき、受信パケットの数が契約バッファの数を超えた場合に対して入力規制をRNRパケットで行うことができる。契約バッファ方式は、受信側の端末に設定されているすべての論理チャネルから入力するパケット数を規制している。
ハブ
スター形LANに使用される集線装置。ハブにモジュラジャックを差し込むだけで、簡単にLANを構築できるので、一般的によく用いられている。
ハミング符号チェック方式
キャラクタチェック方式の一つ。各情報ビットに数ビットの冗長ビットを付加し、一定の法則によるチェックを行うことにより、符号中に生じた1ビットの誤りを検出し、自己訂正を行う方式である。
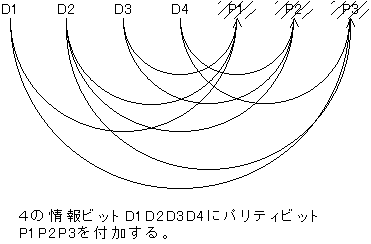
パラレルインタフェース
nビットずつ同時に転送するインタフェース。パラレルインタフェースには、SCSIなどがある。
パリティチェック方式
伝送する文字(キャラクタ)の中の1のビット数が偶数又は奇数となるよう冗長ビットを付加して伝送する方式。
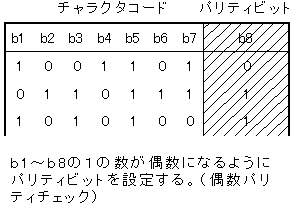
パリティビット
パリティチェック方式で、誤りを検出するために付加されるビット。
バルク伝送
複数のBチャネルを束ねて、より高速の伝送速度にする機能。
パワー給電回路
ボタン電話機の各表示器等に必要な電源を主装置からデータ線を通して供給する回路。
パワートランジスタ
一般にパワートランジスタは、コレクタ損失(Pc)1W以上のものを指す。小信号トランジスタに比べ最大コレクタ電流、最大コレクタ損失が大きく、発熱に対しても形状も大きく、金属でシールドされていたり、放熱フィン付きであったりする。
番号計画
回線交換網の番号計画は、ITU−T勧告X.121で規定されている。番号はデータ網識別番号DNICと網端末番号NTNからされている。
ハンズフリー
電話機に内蔵されたスピーカとマイクにより、送受話器を下ろしたままで相手と通話ができる機能。
ハンドオーバ
携帯電話やPHSなどで通話中に移動しても、通話を中断することなく無線基地局が切り替る機能。
ハントグループ
同じ電話番号を共有する論理チャネルのグループ。ハントグループに着信があると、順次空いているチャネルに着信させることができる。
半二重通信
双方向の通信はできますが、片方の端末が送信状態のときは他方の端末は受信状態になり、同時に双方向の通信ができない方式。
ヒ
非確認型情報転送
フレームの送達確認を行わない手順。非確認型情報転送は、放送型リンクに用いられている。この手順では、伝送エラーが検出されるとそのフレームは破棄され、エラー回復は行わない。
光合波器
送信側で波長の異なる複数の光信号を1本のファイバに合波する機能。
光ファイバケーブル
高純度のガラス繊維(パラスチック製の物もある。)できており、低損失、広帯域、無誘導、細径・軽量という特徴を持っているケーブル。
光分波器
受信側は1本のファイバを伝搬してきた波長の異なるとなる複数の光信号を各波長ごとに分波する機能。
引き上げケーブル
地下から架空に引き上げるときに用いられるケーブル。一般に、ガス隔壁(ガスダム)が付いている。
ビジートーン(BT)
ビット
コンピュータで扱うデータの最小単位。
データの最小単位のビットごとに同期をとる方式。
ビットレート
情報が授受されるときのビットの伝送速度。
ビデオテックス
電話回線を通じて文字や静止画を送受信する情報システムの規格。NTTが電電公社時代にCAPTAIN方式によるサービスを開始しましたが、ほとんど普及はしなかった。
不平衡型手順クラスのモード。2次局は1次局の許可なしにレスポンスを送信できる。
不平衡型手順クラスのモード。双方が複合局となり、相手の許可なしに互いにコマンド及びレスポンスを送信できる。
非パケット形態端末
非番号制形式(Uフレーム)
データリンクのモード設定要求又は、異常状態の報告などデータリンクの制御を行うフレーム。
ヒューズ
保安器に用いられており、電気通信回線に過大な電流が加わった場合瞬間的に溶断して端末設備を切り離すことができるもの。
10BASE−5で用いられるケーブル。Thickケーブル、イエローケーブルともいわれる。
標本化
時間的に連続しているアナログ信号の波形からその振幅値をある一定の間隔で標本値として採取すること。
標本化定理
原信号に含まれている最高周波数の2倍以上の周波数で標本化すれば原信号を完全に復元できるという定理。
避雷器
落雷による電流を大地に逃し、端末機器を守るためのもの。
ビルディングブロック方式
通信モジュールなどを箱状(ブロック)にし,モジュールをブロック単位で増設する方式。小規模から大規模まで同一製品で対応でき、また増設工事も容易にできるメリットがある。PBXやボタン電話装置等で一般的に用いられている。
ピンポン伝送方式
フ
ファーストセレクト
制御パケットに最大128オクテットのデータを付加することができる機能。この機能は着信側がファーストセレクト機能を契約するとともに、CRパケットにファーストセレクト機能を表示している場合のみ有効である。(ファーストセレクト機能を契約していない場合は、16バイトまでのユーザデータを付加することができる。)
ファクシミリ
公衆回線を使って画像を転送するシステム。G3ファクシミリ、G4ファクシミリなどがある。
ファシリティ長(FL)
付加サービスを通信ごとに要求する場合に用いる。ファシリティ長は、1オクテットであり、2進数表示で挿入する。
ファントム給電
カッド内の2つの側回線のうち、一方を往路、他方を復路とした回線での給電。
フィジカル層
ブースタ方式
電圧補償方式の一つ。DC/DCコンバータにより、数V程度の電圧を発生さし、負荷と直列にその電圧を挿入する方式である。この方式は中容量以上の電源設備に用いられている。
フェーズ1
回線の接続段階。回線交換を行うときに必要なフェーズである。
フェーズ2
論理的に送信側と受信側を結ぶ段階。この論理的に結ぶ動作のことを、データリンクの確立という。
フェーズ3
データ(メッセージ)を伝送する段階。
フェーズ4
データ伝送が終結し、データリンクが解放され、初期状態に戻る段階。
フェーズ5
回線を切断する段階。フェーズ1と同様に、回線交換を行うときに必要である。
フェルール
光ファイバの心線を接続するためのコネクタ。フェルールには、単心用とテープ用(4心、8心)がある。
フォールバック
回線状態が悪いときに、回線を切断しないで通信速度を自動的に低下させて、通信自体は続行できるようにする機能。モデムなどの通信機器に組み込まれている。
フォトグラフィック方式
図形等を画素で表示するもので、細部の表現が可能な方式。
負荷分散制御方式
同じ処理をする複数のプロセッサを、必要とする処理能力や信頼性に応じて配備し、制御する方式。
不完全群
任意の入回線に生起した呼が、出回線が空いているにもかかわらず損失呼となることがある交換線群。
デジタル伝送路より受け取ったパルスを受信側で元の信号に戻すこと。
複合局
1次局及び2次局の機能を合わせ持つ局。
複式配線方式
マルチ接続することでフロア相互間の需要が変動した場合に心線の融通が利く方式。
ふくそう
交換機において呼が集中して話中状態になること、又はネットワーク上においてトラヒックが増加し有効な通信ができない状態のこと。
副走査
主走査の後に次のラインのチェックに入ること。
ふくそう制御
網内でふくそうが生じた場合に、網を正常な状態に戻すための制御。
復調
変調された信号を受信側で元の信号へ戻すこと。
複流NRZ方式
0と1を電圧の極性の違いで表現し、また符号ビットのスロット長の時間幅でパルスを送出し、ビットスロットごとに電位ゼロに戻らない方式。
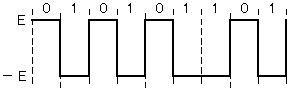
複流RZ方式
0と1を電圧の極性の違いで表現し、また符号ビットのスロットごとに必ずゼロに戻る方式。
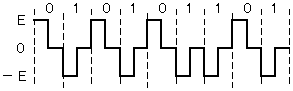
複流方式
0と1を電圧の極性の違いで表現する方式。
量子化されたパルスの値を8ビットの2進数に変換すること。これにより、伝送する波形はデジタル信号に変換され、この形式で受信側に伝送される。
符号分割多重接続(CDMA)
スペクトラム拡散技術を使った、携帯電話などの無線通信に使われる方式の一つ。この方式は、複数ユーザが同じ周波数帯を共有でき、ユーザを区別するのにユーザ通信チャネル固有のPN(擬似雑音)符号を使う。
復旧要求PADコマンド
標準無手順端末の通信シーケンスでの解放フェーズで用いられるもので、NTPから網に送出されるコマンド。
フッキング
フックスイッチを軽くたたくこと。
フックスイッチ
受話器の下にあるスイッチ。受話器を上げるとオフフックとなり、置くとオンフックとなる。
OSI参照モデルの第1層(レイヤ1)。コネクタの形状、電気特性、信号の種類等の物理的機能を規定している。
物理的条件
コネクタ等の形状、寸法、ピン配列の規格など。
物理レイヤプロトコル
X.25で規定されているレイヤ1のプロトコル。このプロトコルは、PTと網との間の接続コネクタの形状、ピン配列、電圧・電流等が規定されている。
浮動充電方式
負荷への電力を供給しながら蓄電池の充電を行う方式。
不平衡型手順クラス
1次局と2次局で構成されており、データリンクの制御は1次局が行い、2次局は1次局の指示し従って動作する。
不平衡複流相互接続回路
ITU−T勧告V.28で規定されている回路。20bit/s以下のデータ信号速度で動作する相互接続回路に適用され、使用できるケーブル長は極めて短く、20bit/sで15m程度である。
フラグシーケンス
フレームの同期をとるためのフィールド。「01111110」の特定のビットパターンが規定されている。フラグシーケンス以外の場所でこのビットパターンが現れると、フラグ同期がとれなくなるので、データ中に「1」が5個連続した場合、その後に送信側でダミーの「0」を挿入して送信し、受信側で「0」を削除することによってデータの透過性を実現している。
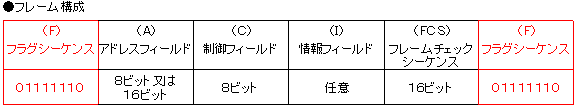
フラグ同期方式
データのブロックの区切りとして特定のフラグパターン(01111110)を送信して、送信側と受信側のタイミングを一致させる方式。
フラットプロテクタ
通信用フラットケーブルを床面に配線する場合に上面を覆い機械的に保護するもの。
プラプレート
壁からの電話線の取り出し口につけるプラスチック制のプレート。
フリーアクセス方式
通信線や電源が任意の場所から簡単に取り出せる二重床構造となっており、コンクリートと床面との空間に配線する方式。
フリーレット
フロアカバーのこと。
プルボックス
配管を中継するボックス。曲がり箇所や直線の長い箇所に使用する。
フレーム
OSI参照モデルのデータリンク層でデータを送信する信号の単位。
フレーム多重
1本の物理回線上にDLCIを用いて、複数の論理チャネルを設定すること。
フレームチェックシーケンス
誤り制御を行うためのフィールド。16ビットで構成され、サイクリックチェックコード(CRC)が使用されている。誤り制御の対象範囲は、アドレスフィールドから情報フィールドまでである。
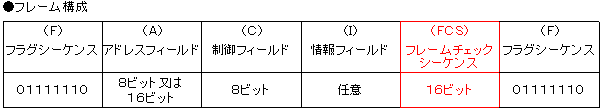
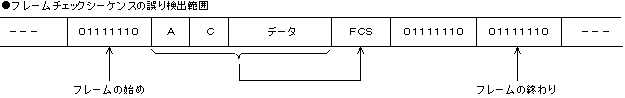
フレームリレー
X.25を簡略化し、高速化を図ったもの。具体的には、フレーム送信時シーケンス番号の付与、受信時のシーケンス番号のチェック、フレームの再送処理やフロー制御などを行わない。
OSI参照モデルの第6層(レイヤ6)。符号形式、データ構造、情報表現方法などの管理を行う。
フロアアウトレット
フロアにある屋内線やケーブルの取り出し口。フロアボックスともいう。
フロアカバー
フロアボックスから屋内線やケーブルを取り出すときに、フロアボックス、ケーブル等を機械的に保護する蓋のこと。
フロアクリップ
アンダーカーペット工法を用いる場合に、ケーブルを立ち上げる箇所でフロアクリップと併用して、床面から立ち上げたケーブルを機械的に保護するもの。
フロアダクト工法
断面が長方形または台形の鋼板製の配線用ダクトで、コンクリート内に埋め込んで使用する。電話用配線、コンセントに使用されている。
フロー制御
論理チャネルごとに流量を調節するウインドウ制御方式と端末ごとに流量を調節する契約バッファ方式がある。
ブロードバンド伝送
データ伝送などで、複数の変調した信号を異なる周波数帯域で同時に伝送する方式。
ブロック
ブロック同期方式で用いられるビット列の単位。
ブロックチェック方式
水平司直パリティチェック方式、群計数チェック方式、CRC(サイクリックチェック)方式がある。
ブロック同期方式
一定の長さのビット列を1つの単位としてブロックごとに同期をとる方式。ブロック同期方式には、調歩同期方式、キャラクタ同期方式、フラグ同期方式の3方式がある。
プロテクタサポート
フラットプロテクタを用いた配線の分岐箇所や曲がり箇所でのケーブル保護や立ち上げ部分におけるケーブルの固定に用いるもの。
プロトコル
データ通信を行うために必要な通信規約(約束ごと)のこと。
プロトコル識別子
ユーザ・網インタフェースのDチャネル上で転送される第3層のメッセージに必須の情報。プロトコル識別子は、このメッセージの情報がDチャネル・プロトコル第3層の呼制御メッセージなのか、X.25で用いられているパケットのような他のネットワーク層の情報かの識別に用いられる。
プロトコル変換
異なるプロトコル間でデータのやり取りを行う場合、一方のプロトコルを他のプロトコルに合わせる変換、または相互にプロトコルを合わせる変換。
分界点
第一種電気通信事業者側の設備(電気通信回線設備)とユーザ側の設備(端末設備または自営電気通信設備)の境界。通常、架空の場合は保安器、地下の場合はMDFが分界点となる。
分配段通話路
集線段と中継線、集線段相互、中継線相互を接続する時分割通話路であり、TSTの3段構成でできている。
ヘ
ベアラサービス
ユーザ・網インタフェースのS/T点相互間でレイヤ1〜3までの低位レイヤのみを提供するサービス。ベアラサービスでは、回線提供のみのサービスであり、端末の機能などの高位レイヤについては規定していない。
ベアラ速度
回線終端装置から伝送路に送出されたデータ信号が占有する伝送速度。ベアラ速度とデータ信号速度との関係は次のようになる。
ベアラ速度=データ信号速度×(8/6)×サンプリング数
閉域接続。端末グループ内のみの通信を可能とする機能。グループ外への発呼やグループ外からの着呼はできない。
平均サービス時間
単位トランザクションあたりのサービス時間。平均サービス時間は、次のような関係式にある。
平均サービス時間=1/平均サービス率
平均保留時間
回線を保留している時間の平均。平均保留時間は、次のような関係式にある。
平均保留時間=トラヒック量/呼数
平均待合せ時間
生起呼が待合わせる時間の平均。平均待合せ時間は、次のような関係式になる。
W=T/C
W:平均待合せ時間 T:延べ待合せ時間 C:生起呼数
平衡型手順クラス
2つの局の双方は対等で、それぞれ1次局と2次局の機能を持つ複合局として、データリンクの制御に関し責任を持つ手順クラス。
閉リンク結線方式
空き出線とそれぞれに接続するリンクを選択するのに、空き出線を一つ選んでから、これに至るリンクを試験し、整合がとれなければ直ちに話中処理を行うことを原則とする方式。
並列伝送方式
並列になっている各ビット列にそれぞれ通信回線を割り当て、同時に伝送する方式。
ページング
電話機の内臓スピーカや、外部スピーカを通して音声で呼び出す機能。
ベーシック手順
基本型データ伝送手順参照。
ページングトランスファ
外線からの着信呼を他の内線に転送したい場合に相手が離席中のとき、構内放送により呼び出した後、応答した内線へ外線からの着信呼を転送する機能。
ベースバンド伝送方式
送りたい信号の波形を、周波数帯域を変えずにそのままにして、電圧や光の強度に変換して伝送する方式。
ヘッダ
データ転送のためにデータをカプセル化する際に、データの前部に付加される制御情報。
変調
搬送波と呼ばれる正弦波の振幅、位相、周波数を変化させることによって、デジタルデータなどの情報を伝送すること。変調方式には、振幅変調、位相変調、周波数変調などがある。
変調速度
1秒間に信号が変調された回数(状態が変化した回数)を示すもので、単位はボー(Band)で表す。一般に1回の変調で伝送するビット数をnとすると変調速度は、次式のようになる。
変調速度=データ信号速度/n
変復調装置
ホ
保安器
電気通信回線設備に対する雷の誘導や電力線との接触事故等が起きた際に生じる異常電圧・電流から、端末設備と利用者の安全を確保する目的で設置するもの。ただし、地下配線の場合は必要はない。
保安用接地
PBX等の通信機器に用いられる保安用接地の主な目的は、漏電時の危険防止のため。装置内回路と筐体との絶縁が低下した場合、筐体に触れると感電の危険性があるため、筐体を接地する。
ボイスメール
人間の音声によるメッセージをファイルとして蓄えることにより、各種サービスを提供するシステム。
ポイント・ツー・ポイント通信
2地点間を1本の通信回線で結び、1対1の関係で通信する方式。
ポイント・ツー・マルチポイント通信
1本の通信回線を分岐して複数個の端末を接続し、1対nで通信する方式。
放電時間率
放電の速さを表す。例えば、全容量を10時間で放電させる場合の速度を10時間率という。
放電終止電圧
蓄電池において、反復使用が可能な最低の端子電圧。
ボー(Baud)
変調速度を表す単位。
ポーズ
ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルでセカンドダイヤルトーンの前に挿入する、タイミングをとるための遅延時間。
ポーリング
センタから各端末装置に対して送信の要求があるかどうかを聞いて、メッセージの勧誘を行うこと。
ポーリング/セレクティング方式
制御局と従属局をあらかじめ設定しておき、従属局は制御局の許可を得て送信権を獲得する方式。
捕そく試験
任意の内線から、PBXを構成する各種機器に、PBXを通じて、その全数に接続できることを確認する試験。
ボタン電話用屋内ケーブル
構内ケーブルの外形を細くしたようなもので、アナログ時代のボタン電話装置に使われていた。今では、フロア配線用のケーブルとして用いられている。
ホットライン
送受話器を上げるだけで、あらかじめ決められた特定の内線を呼び出すことができる機能。
ホトカプラ
発光ダイオードとその出力信号を受信するトランジスタで構成される半導体部品。電気信号を光信号に変換して信号を伝達するため、電気的絶縁が必要な回路に使用する。
ホトトランジスタ
光信号を電気信号に変換できる素子。
デジタル加入者線交換機にアナログ電話機を収容するために必要な内線回路に設けられる機能。ボルシット機能には、以下の七つの機能がある。
B: Battery feed 通話電流供給
O: Over voltage protection 過電流保護
R: Ringing signal sending 呼出信号送出
S: Supervisory 直流ループ監視
C: Coder-decoder 符号化/復号化
H: Hybrid 2線/4線変換
T: Testing 試験引き込み
copyright(C) 1998 mori! all rights reserved.