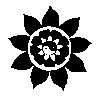
人知れず
闇に咲く花
黒蓮華(ヘイレンファ)
宇宙の理法に従って己れを開花しようとする場合、一体どういうことが必要となつて来るのか詰めてみよう。
ここでは、生命の持つ普遍的原理から、白蓮華に対して黒蓮華を設定する。
そしてこの黒蓮華を花開かしめんとするにあたり、聖者の道、即ち白蓮華(当為に従って咲く)に対して、聖性の道、即ち黒蓮華(道=タオに従って咲く)を説くことにする。
黒蓮華よ、智慧を積め。そして勇敢であれ。過去の己れ自身が歩んで来たように、未来の己れ自身が歩むであろうように、今の己れ自身も又、此の道を歩みつつある者であれ。
単なる偽善者としてあるよりも大悪人たらんとする者。教義・行為規範・道徳律等、一切の当為を、大人の深刻さと共に子供の無邪気さをもって破壊してしまう有罪者。−−我は彼を黒蓮華の人と呼ぼう。
「善」・「悪」の道徳観から自由であり、「善」のみだけでなく、「悪」をも平気で犯すことの出来る人間。「崇高さ」だけでなく、「醜さ」をも合わせ持つ混沌とした人間。−−我は彼を黒蓮華の人と呼ぼう。
己れの取りつつある道にハートがあるならその道に従い、然らずば、自己にとって最良の道を探し求めてゆく者。そのようにして自性に従い花開かんとする者。−−我は彼を黒蓮華の人と呼ぼう。
単なるヨーガ・禅的な発想では、生命の高次な展開は望めず、常に直接的な眠りの状態に止まるだけであることを知っている者。陰陽の両極に引き裂かれながら、その強大な力を背景にして、より高次な段階に己れの生命を展開させ開花させてゆく者。そのようにして虚空への道を歩む者。−−我は彼を黒蓮華の人と呼ぼう。
頼ろうとするから弱くなることを知っており、一切の依存関係を断つ者。その孤独の中で絶望的な、然し崖淵に立たされた者のみが持ち得る強大な力を得て、挑戦的な闘いを闘う者。−−我は彼を黒蓮華の人と呼ぼう。
社会の外見的な形態のみにこだわった、単なる権力の交替でしか過ぎない「革命」を、虚偽であると見抜いている者。真の革命は、正に己れの内なる生命に根差したものであることを知り、己れ自身を真正に発現させ花開かせようとしている者。そのようにして己れの意欲を満たしてゆく者。−−我は彼を黒蓮華の人と呼ぼう。
智慧の下で、己れは決して孤立した枠ではなく、己れの内に一切の宇宙を内包していることを知る者。「我か他者か」の幻影を打ち滅ぼし、一切の万有が即己れであり、一つの全体としての生命の諸現象であることを知る者。その智慧の下で、己れ即一切万有(衆生)の正に生きんとする意欲に依拠する者。−−我は彼を黒蓮華の人と呼ぼう。
このようにして宇宙の理法に従って花開いてゆく者。−−我は彼を黒蓮華の人と呼ぼう。
さて以降では、まず革命の実相を三つの異なった側面から論じ、次に、そこで得られた智慧の下で、地涌菩薩の末法末世における現代的役割を明らかにしてゆこう。
革命を何の様に把握するかに関して、最初に「我」という観点からすれば、先ず、己れ自身が楽しまねばならず、己れの意欲を満たしてゆくことが必要である。満たされた喜びを知らない魂にとって、生命の開花は不可能なままであるからである。
このように革命とは、ここでは己れ自身の生命の開花であり、即ち生きるということを意味するのでなければならない。
従って、己れ自身の身命等を犠牲にして衆生を助ける者に対して、己れの生命の開花・意欲を主張する者を貶めることは出来ず、却って革命の主体は後者にあると言わねばならないのである。
又、権力そのものによって最も恐れられているものは、具体的な諸権力同士の確執などでは決してなく、権力そのものの秩序を全く無視し打ち破らんとする者達、即ち正に、その革命の実践者達なのである。
それは、生存に窮し、それを満たさんとする者達であり、真に己れの徳から恋し求め合う者達であり、権力・権威を全く無視し超越して創造に打ち込んでいる者達であり、そして、己れを打ち滅ばし虚空を掴まんとしている者達である。
要するに、己れの徳から、一切の権力・権威・価値観・行為規範・道徳律等を無視し破壊せんとしている者達なのである。単なる権力同士の確執では、権力そのものの根本的な脅威とはなり得ないのである。
ところで、ここで前述の、「己れの身命等を犠牲にして衆生を助ける者」に関して少し調べてみることにしよう。
この場合、彼の行為が、外見的判断からして、自己犠牲として扱われることになるとしても、その犠牲者の内面に入って論ずる場合、それは「他者の為に己れの生命を無視した行為である」とは一概に断定出来なくなるのではないのか。
己れが生命を持たされ生きんとしている限り、己れの生を無視し、ないがしろにすることは決して出来ないであろう。自己犠牲と言われる場合でも、己れ自身はその他者を契機として、自身の生を生き切ろう(死に切ろう)としているのである。
従って、すべての者は、生きんとする限り、己れ自身の為に生き切ろう(死に切ろう)としているのであり、決して他者の為にではないと言わねばならない。
その為、未だ統一力の成す幻影に欺かれ、我と他者とを区別したまま己れの狭量な意欲のみに囚われている場合において、他者の為の自己犠牲を主張するのは単なる偽善に止まることになるであろう。単に頭の中で当為を述べているにしか過ぎないからである。
さてそれでは、何故ある者達において、己れの身命をも犠牲にしてまで他者を助け、その者の生命の開花を共に喜ぶ衝動が生じて来るのかが次に問題となる。
ここでは、他者との相互関係という観点から物事を論じなければならない。
表象能力が高く、此の世に対し常に虚しさを覚えている者達は、無機物をも含め、一切万有(衆生)の生命を、即ち一つの全体としての生命宇宙(統一力)が織り成す無数の渦や波の状態として感じ取り、又は自覚することが出来るのである。
そこでは、統一力の成す幻影は薄らぎ、我と他者との区別はさほど重要ではなくなるであろう。そして一切の魂(衆生)は、統一的生命力に支配された大小様々な無数の渦や波として、互いに支え・支えられる関係をどうしても持たされており、決して単独では生命を維持し発展させることは出来ないことが明らかとなるのである。
如何に己れ自身の生命を開花させようとしても、その生命の基盤を欠けば、どのように個人で努力しても、虚しいものに終らざるを得ないであろう。己れ自身の生命の発展・開花は、常に他のすべての者によって支えられているからである。
その為、すべての者(衆生)が関係を持たされて存在を余儀無くされている以上、己れ自身が真に生命を発展させ開花させようと欲するなら、どうしても他の者達の生命状態を高めてゆかねばならなくなる。
そして、時には、他者の為に己れを犠牲とせねばならなくなる場合も生じて来るのである。
最後に、一つの全体としての生命、即ち生命そのものの開花という観点から見れば、我と他者との区別は全くなし得なくなり、一切万有(衆生)は、その統一的生命の大きな渦・怒涛の中で、供物とならざるを得なくなるであろう。
従って、その怒涛の中では、「己れが他者の為に犠牲となる」という考えは消滅し、生命そのものは、己れ自身の為、己れ自身を花開かしめんとして、己れ自身を犠牲に供することになるのである。
己れの生きんとする意志は、一切万有に共有・通底されており、その為にこそ、我(即一切万有)の生き切ろうとする意欲は、一切万有の苦悩を己れ自身のものとして、喜んで自ら十字架を背負うことにもなるのである。
従って以上から、単に頭の中で当為としての自己犠牲を説くのは偽善に止まるとしか言えないのであるが、その犠牲の背後には、まず「我」という観点からすれば、切っ掛けは何であれ、己れの生を生き切ろう(死に切ろう)とする意欲が常に認められ、次に、他者との相互関係という観点からすれば、自身の生命をより展開させてゆくには、どうしても回りの者達を活性化してゆかねばならない暗黙の了解(知)が認められるのである。
そして最後に、生命そのものの開花という観点からすれば、我即一切万有の生命を花開かしめんとする意欲そのものが、その自己犠牲を強烈に要求していることが明らかとなるのである。
以上のようにして、己れ自身を開花させようとする意欲は、その支え・支えられる関係の中で、他の者達の生命の開花を強く求めることになり、その回りの者達の生命の状態が発展し開花するにつれ、自然に己れの生命も、又・更に花開いてゆくことになるのである。
このようにして、一つの全体としての生命は、正に宇宙の理法に従って、己れ自身を開花させようとしているのである。
さてところで、これに対して、統一力の成す幻影に欺かれたまま我と他者とを区別し、己れの囚われた意欲のみに従っている者は、その狭量な意欲の下で自己保存に汲々となる。
彼にはその狭量な意欲が一切であり、他のよりすばらしい自由性を予感することが出来ない。又・予感し得たとしても、その意欲に囚われている魂は、他の者達の生命の開花を嫉み妬む。
そして場合によっては、自らその開花を阻止しようとするに至るのである。
何故なら、彼は物欲が支配する法則の中で対象を奪い合い続けている為、より高次な生命状態が持つ法則を知り得ないまま、それを己れが住む最底辺の法則と同様に見なし扱うことしか出来ないからである。
然し、最底辺の法則では、奪うか・奪われるかのどちらかであるのに対して、より高次な生命状態にあっては、与えれば与えるほど与えられることになり、捨てれば捨てるほど得ることになるのである。
そこでは、奪うか・奪われるかの法則ではなく、生命そのものの開花の為に支え・支えられる関係を持たされ、ある者の開花は即己れ自身の開花となるのである。
さて、そのようにして他の者達の生命の開花を阻み貶めることは、正にその支え・支えられる関係の中で、己れ自身の生命の展開・開花の可能性を裏切り否定することにほかならず、すべての魂を、物欲というブラックホールに閉じ込めることにほかならないのである。
だが、そのようなことでは決して魂は満たされず、生命そのものは、開花することが出来ないまま腐り果ててしまうことにならざるを得ないのである。
この稿を結ぷにあたり、前述の所で得られた智慧を頼りに、我々の取り得る道を検討し直し、それを明確な光の下に晒してみることにしよう。
現代・末法末世の地獄図が描き出されているのであるが、ここでは、如何にしてこの囚われた社会(地獄図)を打ち砕いてゆくかが問題となる。
まず最初に生命そのものの開花という観点から光を投げかけるなら、己れ(即衆生)の生きんとする意欲を背後に持ちつつ、己れ(即衆生)の解放を求め闘い続けてゆくことが必要である。一切衆生の生命を糾合し、その力を生命そのものの解放へと向けさせることが必要である。
次に、他者との相互関係という観点から光を投げかけるならば、以下のようになるであろう。
即ち、その解放の過程においては、まず己れ自身が最初に変わってゆくことが必要である。己れ自身の変革の中で、他の者達の生命を高めてゆくことが必要である。
そしてそのようにして相互的に生命を高め合う相互変革の中で、共同体(組織)の祭りを挙行してゆくことが必要である。
最後に「我」という観点から光を投げかけるなら、己れ自身の生を生き切る(死に切る)ことが必要である。自身の魂を解放し、その高次な生命状態の中で純粋に遊ぶことが必要である。
以上の三つの側面を常に兼ね備えつつ、我々はこの地獄界から、己れ自身も含め、一切衆生を解放してゆくことが必要である。
我病む
我病む故に衆生病む
我即衆生病む
衆生病む
衆生病む故に我病む
衆生即我病む
衆生に病む〔個はすべての為に、すべては個の為に)
ところで、以上から得られた智慧を下敷にして、我々が今・具体的に実践すべきことは、そのような解放に自覚めつつある魂、あるいは覚醒すべき魂を目覚めさせることである。
社会を変革する主導者達を創り出してゆくことがどうしても必要である。
その為我々は、それらの者達が生まれ出る切っ掛けとしての場を痛切に待望し、微少ではあっても努力を積み重ねてゆく必要があるのである。
我々の対象が正に主導者に向けられ、絶対的少数者に向けられているのである以上、その成果は最初の内はほとんどないものと信じている。然し、次々と主導者達が現れ出し、回りの者達を変えてゆくにつれ、その成果は明確に認められて来ることになるであろう。
我々は今、信者・信仰者の群ではなく、超人(常に己を乗り越えていこうとする人)を待望する。
その為にこそ、我々自身が単なる信者・信仰者としてではなく、理法の実践者・行者とならねばならないのである。その実践の中で初めて、己れの内なる菩薩界も、無条件に涌出して来ることになるからである。
そして、たとえ前述の成果が刹那的で、直に消え去る程度のもので終るとしても、それらの超人達によって描き出される叡智的世界を、即ち黒蓮華を痛切に待望する。 その黒蓮華こそが、未法未世において咲く花なのであり、それこそが、私(即ち彼の一者)の〈夢〉なのである。
人知れず
闇に咲く花
黒蓮華(ヘイレンファ)
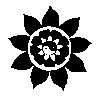
陽極まれば陰に転じ、陰極まれば陽に転ず。
白蓮華と黒蓮華とは、その生命原理によって相互に入れ替わる二現象である。
今、我々に必要なのは、遊びであり、祭りであり、そして生命の解放である。
黒蓮華の詩ーーおわり