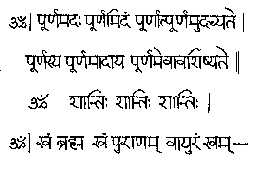
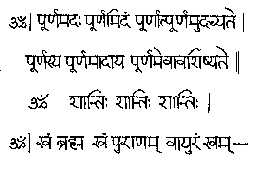
Om.彼のものは全体なり。此のものも全体なり。
(此の)全体は、(彼の)全体より生ず。
(此の)全体のすべてを取り去るも、
(彼の)全体は、実に、依然として有り。
Om.永遠なる喜び! 永遠なる喜び! 永遠なる喜び!
Om.梵は虚空なり。永遠なる虚空なり。
生命を吹き出す虚空なり ……。
今まで、統一され、表象内に表されるものを手掛かりとして、その根拠を統一面の中に求め調べてゆき、二つの異なった領域に就いて検討して来たのであるが、今度は、その統一面に関して得られた認識を元にして、統一力の実質的な反映とされる生成界に再び立ち戻り、統一力の働きかけに従って、忠実にその生成界を描き出すことにしよう。
然しながら、この生成界は、感覚を土台とする世界であり、如何に忠実な物質現象として描き出すとしても、それは、統一力の成す一側面上の影として〈存在〉するのでしかないことは前述の通りである。
その上、我々が成し得る経験の範囲も限られていることから、ここで描き出される生成界は、影としてありながら、しかも完全には描き出されることがないままであり、只我々は、その影に就いてありそうな話を作り出してゆくことしかできないのである。
ところで、我々万有が生成しつつある此の宇宙は、統一的一者の生命力によって支えられている一つの全体としてあるのであるが、我々の持つ直観形式によって、三次元の広がりの中における物体の生成・消滅という形で限定され、表されて来ることから、その〈存在〉する宇宙は、数多性の中での部分を持った「全体」として把握されてしまうことになるのである。
そして、そのような把握に従って、直観形式を適用しながら無限に時間・空間を歩き回り、その宇宙の「全体」に至ろうとするのであるが、然し、その形式の持つ性質上、決してその「全体」に至ることのないのは当然である。
宇宙は、その一者の統一的な生命力そのものによって支えられている以上、その力の中で宇宙全体を体現するに至らねばならない。その方向においてしか、明確に宇宙、即ち統一力を知ることは出来ないのである。
以下、そのことを中心に据えつつ、統一面から生成界のありそうな話を忠実に詰めてゆくことにする。
まず最初に、何故此の宇宙は、一つの全体としてしか認められず、複数の全体としてではないのか、という疑問に答える必要があるであろう。
此の物質現象として生成する宇宙を統一するものは単一性の中にあり、従って、その中の一者として有る何か或るものから吹き出されて来る全宇宙は、すべてその同じものに根拠を持つものとして、一つの生命力の中にあると言うべきである。
ところで、反省内では、複数の根拠(統一的一者)を仮定し、それに対応する複数の全体としての宇宙を別々に設定することが成され得るであろう。
然し、もし万が一そうであるとしても、それらが全く別々に切り離されてしまっている以上、我々には、その別な宇宙が存在することなど決して知り得ないであろう。
何故ならば、此の全宇宙における我々万有は、彼の一者の統一力の中でのみ生成・消滅を繰り返すしかなく、従って、その力に支配され、従属させられている以上、その統一力に基づく魂を保ちながら、その力の及ばない領域に超出すること自体矛盾であり、不可能であるからである。
そして、たとえ魂そのものとは多少懸け離れているものが、何らかの拍子にその領域に超出するとしても、今度は、別の宇宙の中にどのようにして入り込むことになるのかは、決して問題とは成り得ないのである。
即ち、その領域に超出するものは、決して魂を持ち続けることはなく、そのまま虚空の中に消え失せるだけであり、あるいは、また再び生成界の中に止まることになるとしても、その宇宙は、決して別のものとなるわけではなく、以前いた同じ生命力の中に、再び彼の一者によって吹き戻されることになるのである。
以上のことから、たとえその別な宇宙が存在するとしても、我々には決してそれを体現することも、写し出すことも、そして反省内で認識することも出来ないと言わねばならない。
我々は、此の一つの全体としての宇宙の中で、彼の一者につながれたままであり、その為、我々に云々し得るのは、彼の一者によって吹き出され統一される、一つの全体としての此の宇宙でなければならないのである。
そこで次に、この生成する宇宙を満たしている最も根本的なもの、即ち物質に就いて話を進めてみることにしよう。
まず、我々が物質と表現しているものの根拠を区別することから始めねばならない。
即ちそれは、表象機能において認められる直観形式(統一形式・空間形式)と、その背後にあってその両形式を満たす統一力そのものの働きかけとに区別され、この場合、前者を形式面、後者を実質面として扱うことにする。
ところで、物質は、空間形式の適用を俟って初めて成立する以上、それは触覚と視覚、両者のみにおいてその成立基盤を持つと言わねばならないであろう。
さて、そこで、その物質の直観形式のみからの表現は、「空間の中を運動する物体」と、このように言い表すことが出来、この形式面上の「物質」は、ア・プリオリに与えられることになる。その為、この「物質」は、「不生・不滅の物質」と言われたり、「物質の不滅性」として扱われて来たりもしたのである。
然し、だからと言って、実質面において満たされている必要のある物質が、不生・不滅であるとは言い切れないのであり、それはあくまでも、形式面上での表現にしか過ぎないのである。
その形式面を満たす実質面、即ち統一力の働きかけがあって、初めてその「物質」は、実質的な内容を満たされて、この実在的な世界に照し出され、物質として〈存在〉するようになるのである。
即ち、その〈存在〉する物質が、如何なる感覚的性質を持ち、如何なる位置において、如何なる形態を持ちながら、変化し、運動するのかは、単に形式面だけからでは説明し得ず、その内容を規定する統一力に、その実質的な根拠を求めねぱならないのである。
そして同様に、反省内で設定される因果関係も、その実質的な規定を、その背後にある同一の統一力によって持たされていると見なければならない。
その為、そこで把握される自然法則なるものは、形式的な必然性(空間内での運動)に対して、実質的な必然性(形而上からの統一力の働きかけ)が内容を満たすものとして表現され得るであろう。
そのことからその自然法則は、形式面が持つア・プリオリな確実性から、常に同一なる内容を持つ現象が発現し続けることを保証すると言うわけにはいかず、その実質面を規定する統一力によって、その法則は変更を求められることにもなるのである。
ところで、その統一力そのものが全く失せるような場合を想定すると、その力の具体的な表れである物質なるものは一切消滅してしまい、此の一つの全体としてある宇宙そのものも無に帰さねぱならなくなるであろう。
然しながら、そうではなくとも、その統一力の働きが「物質」の内容を満たすような性質のものではない場合には、如何に統一形式の下で空間形式を適用しても、それを満たす内容を欠く為、形式面・実質面両面を備えて初めて〈存在〉することになる物質など、決して表されて来ることはなく、只々虚なる空間が広がるばかりであろう。
だが、その場合には、何らかの統一力が働き続けている以上、此の宇宙は、表されることがないとしても、存在し続けると言わねばならないのである。
その為、物質は、全くの無から生成したり、全くの無へと消滅したりすることはあり得ないが、以上の通り、統一力の働きが形式面を満たすような性質のものではない為、そのまま虚なる空間に、物質として結実して表されることなく、何らかの力として満たされることになる領域もあるのであり、その虚としてしか表象し得ない空間から、統一力の働きかけによって物質が結実して生成し、表され、または、その虚なる空間へ、物質が消滅してゆくことは当然なされていることなのである。
そして、このようにして、形式的な「物質」が物質として表され、現象の基礎となるのは、その統一力の働き如何によるのであって見れば、此の〈存在〉する全宇宙が持つとされる物質の量的な減少や増加の有無は、この統一力の働きによって規定されていると言わねばならないのである。
さて次に、その統一力によって支えられている此の宇宙の、空間上の制限を調べてみることにしよう。
まず、実質的な内容を満たしながら〈存在〉する物質は、はたして無限に分割され得るような性質のものであるのかどうかが問題となるであろう。
この場合、確かに形式面のみにおいては、反省内で無限に空間形式を適用していって、物質を無限に分割してゆくことが表象され得るであろう。
然し、それは、全く形式面のみにおいて言えることであり、問題は、物質を結実させている統一力が、はたして実質的にそのことを許すかどうかということである。
何故なら、物質が結実し〈存在〉している場合に取るその大きさというものも、当然統一力によって規定されているからであり、その実質面を抜きにしては、物質の内容は何ら考えられることはできないからである。
従って、その統一力を全く無視して、形式面だけで「物質」を無限に分割し得るからといって、実在としてある物質までをもそうであると思いなすことはできないのである。
その大きさが統一力によって規定されるのである以上、そこで表され得る最小の大きさの物質も、当然その統一力によって規定されて来なければならない。そして、その統一力の下で最小の単位として見なされる物質は、その同一の統一力の中にあり続ける限り、その同一性を保ち、更により小さい単位へと分裂してゆくことはないとすぺきであろう。
ところが、その統一力は、決して同じ静的に一定した働きかけのみを成し続けることはなく、そのもの自身生命の動的な渦として様々に変化することは、それによって支えられている物質現象を調べるなら当然察することが出来るのであり、その為、その様々に変化する統一力の働きに応じて、その結実する最小単位の物質の大きさも変わり、場合によっては、無限に分割されてゆくような現象も認められて来ることになるのである。
然し、だからと言って、その統一力の無限なる変化に応じて、無限に分割されてゆく物質を表すことが確証されると言うわけではないであろう。
何故なら、我々に与えられる物質は、正に感覚的な表象である以上、その統一力の働きを物質として表すことの出来る範囲も、当然限られているのでなけれぱならないからである。
その範囲においてしか物質は生成して来ず、それ以外では、たとえ何らかの性質の働きかけがあろうとも、只虚なる空間が広がるばかりであろう。
そして、その虚なる空間を満たしている統一力の働きの変化に基づいて、物質が結実し、表象内に生成して来る時、初めて、それが最小のものか否かは決定し得ないとしても、最初の微小な物質が、実在的な〈存在〉として生成して来ることになるのである。
そしてまた、その〈存在〉が更に分割されるのを見届けようとしても、それは泡のように虚なる空間の中へと消滅してしまうことになるであろう。
次に、同様にして、この物質がはたして此の宇宙空間を無限に満たしてゆくのかどうかが問題となるであろう。
確かに、反省内で空間形式を無限に適用していって、宇宙を無限に広がりゆくものとして描き出すことが出来るのであるが、然し、それは、前述のものと同様、全く形式面のみによって描き出されるものであり、実質面による規定を無視したものである。
その為、まず我々は、その実質面としてある統一力そのものに、その問題の解決の鍵を求めねばならない。
即ち、問題は、その統一力の及ぶ範囲が中心となり、その範囲が、形式面としてある空間の中において、如何ように満たされて来ることになるのかが、此の宇宙の広がりに関する最も正当な把握の仕方となるのである。
何故なら、この統一力の下で初めて我々万有は、此の全宇宙の中で生成・消滅を繰り返すことになるのであって、その統一力を欠くものは、決して宇宙を構成し得ないからである。
そしてその場合、注意せねばならないことは、たとえ物質として結実せず、〈存在〉を表すことがなくとも、何らかの統一力の働きに満たされている限り、そこで表されるであろう虚なる空間も、宇宙空間を構成するということである。
従って、統一力が生命として及び得る範囲、それが宇宙空間の範囲を決定することになるのである。
ところで、その統一力が及び得る範囲から、無限なる宇宙の広がりが如実に示されて来るとは決して断言し得ないであろう。
宇宙には、やはり限界があるのではないか。その限界は、統一力に支配され、従属させられている我々万有には、決して超出することの出来ない性質のものであり、虚空に向かって超出しようとして、此の宇宙の果てから果てまで、たとえ駆け回ることができたとしても、結局は、元居た所で働いている同じ統一カの下ヘ、知らず知らずの内に押し戻されてしまうことになるのである。存立基盤としての統一力から切り離されてしまっては、我々万有は存立し得ないからである。
さて、今度は、その統一力によって支えられている此の宇宙の、時間上の制限に就いて調べてみることにしよう。
即ち、一切の物質がその中で生成・消滅を繰り返す此の宇宙は、はたして無限なる時間の中を満たしゆくことになるのかどうかが問題となるであろう。
そこでまず、その「無限なる時間」という表象が、一体何に根拠を得ているのか、それから調べてゆかねばならない。
ところで、時間というものが初めて意識されるのは、前述通り、統一主体によって照し出される点としての直覚が、二つ以上継起する時であるが、その統一主体が持つ統一形式、即ち継起の相互的な規定関係に基づいて、以前生成したもの、及びこれから生成するであろうものを、反省内で無限に継起させ、過去の方向においても、また未来の方向においても、無限に辿ってゆくことが出来、その為、無限の時間において生成し続けて来て、更に生成し続けてゆくであろう宇宙を表象することになるのである。そして、それと同時に、反省内で設定される因果関係の連鎖も、その表象内で無限に引き延ばされることにもなるであろう。
従って、この場合、宇宙が持たされることになる時間は、統一形式に従って表されたもの、及び表されるであろうものを貫通するものとして、反省内で描き出される無限に延長され得る一本の直線に喩えることが出来るのである。
然し、表象機能を働かせ、宇宙そのものを発現させる統一力が、統一形式に従って一切を統一するのである以上、その表象内で統一され、表されるに至るものは、常にその統一の先端においてであり、また、此の一つの全体としての宇宙の中で統一され、発現されるに至る一切の万有は、常にその統一の先端において吹き出されつつあるのでなければならない。
常に《今》において、生まれつつ、且つ死につつあるのでなければならないのである。
そして、統一力がたとえ物質として結実せず、〈存在〉として表されない場合であろうと、または、表象が一切否定されている場合であろうと、その統一力が働いている限り、常に《今》という点から、此の一つの全体としての宇宙は、生命を持って吹き出されつつあるのである。
ところで、この統一力が、もし己れの働きを一切停止する場合には、たとえ反省内で無限なる時間の流れを表象し得るとしても、実際には、その時点において、その流れは中断することになるであろう。
その為問題は、この統一力が常に働き、此の宇宙を常に支えているかどうかが中心となり、即ちそれは、彼の虚空に座す一者は、はたして常にその統一的な生命を吹き出し続け、此の一つの全体としての宇宙を常に支え続けるのかどうか、と言い換えることが出来るのである。
その生命の風としてある統一力を持ち続ける限り、此の宇宙は、その姿を変えながらも、無限なる時間の中を満たしてゆき、常にあったし、あるし、あるであろうことになるが、然し、その統一力をほんの僅かな間合においてでも失うようなことがあるとすれば、その無限なる時間の流れは中断され、その間、此の全宇宙は全くの虚空に帰すことになるのである。
そのいずれであるのか、今ここで答え得るような性質のものではないが、私自身としては後者を取りたい。それは、私の体験からする実感に基づいてそう判断するのである。
此の宇宙全体が破局に向かって進んでいることを信ずる。
その破局の中で、今までその統一力によって支配され、従属させられて来た一切のものが解放されねばならない。
それと同時に、彼の一者は、己れの持つ統一力によって欺かれ、隠されてしまった己れ自身の真の姿を取り戻さねばならない。
やがて、彼の一者によって新たな炎がその虚空に燈され、その新しい生命の息吹の中で、新しい宇宙が吹き出されて来ることになるであろう。ある一種の満たされた永遠なる喜びを持って。
風となって吹き出されるもの
それは彼の一者の夢
その風である私が表すもの
それは夢の又夢
死は覚醒の時
私の夢は表象と共に消え去り
彼の夢は万有と共に消え失せる
残るは虚無
弥勒の微笑み
満たされた喜び
以上、生成界全体のあり方を実質面から規定しようと試みて来たが、今度は、その生成界の中に投げ込まれる個々の魂は如何なる発現をしてゆくのか、を調べてみることにしよう。
その場合、魂は、ある限定された時間・空間の中に投げ込まれ、己れに持たされたイデアに従って、自身を発現することになるが、まず、その魂の発現のあり方を実質面から規定してゆかねばならない。
その為には、空間の中で照し出される知的な光の戯れを追うだけではなく、己れの内奥において与えられる情意を切っ掛けとして、魂自身が如何なる状態を満たしながら発現してゆくのかを、内的に知る必要があるのである。
まず最初に、その発現に際して、魂は己れの統一形式の中に、如何なる内容を満たしてゆくことになるのかが問題となるであろう。
即ち、内的な体験において、魂自身の状態が張り詰めている時や、魂の強い関心によって統一主体の注意が対外的に照し出される対象に注がれているような時には、他のものと比較して、そのもの自身が満たしている内容は色濃く、密度の高いものとなり、他のものの状態の変化に注意が向けられないことから、実際より「時間」が早く過ぎ去るように思われることであろう。したがって、ほんの僅かな間に、永遠の時間が流れたように思われる場合も生じてくるのである。
また、その魂自身の状態が散漫で、注意が様々な対象に向けられているような時には、前とは反対に、そのもの自身が満たしている内容は薄く、密度の低いものとなり、そこでの「時間」は、実際より遅く過ぎ去るように思われることになる。
このような内的現象は、決して単なる主観的な思いなしに止まるのではなく、魂そのものの働きに基づく実質的な内容の相違によるのである。
そして同様なことが、物質現象として表される此の生成界においても認められて来るのである。
即ち、この生成界の中で己れ自身を発現しようとする魂は、決してその統一形式を均等に満たしてゆくとは考えられず、その発現過程においては必ず、緊張・爆発・弛緩の各状態が認められることになるのである。
このようにして、個々の魂は、その発現過程において生じて来る様々な状態を体現しながら、起伏に富んだ実質的な内容を満たしてゆくことになるのである。
ところで、我々が日常使っている客観的な基準としての「時間」とは、便宜的な物指でしか過きず、それは、ある個別的な魂の物質現象を一定条件の下で観察し、その発現過程において認められる定期的な周期性を持って、他のものの現象に対する時間的長短の測定基準とすることから生じるのである。
然しながら、如何なる魂であれ、己れを均等に満たしてゆくことはあり得ず、また、一定の条件を保ち、定期的な周期性を導こうとしても、その条件を規定する統一力そのものが、常に変動しながら、《今》という点において生命の渦の中にある万有を廻転せしめつつあるのである以上、魂の発現過程において認められる周期性も、その実質面からの働きかけに応じて、たとえ同一なる魂と見なされるとしても、異なった周期性を示すようになることもあり得るのである。
その為、如何なる条件の下にあっても、一定の定まった周期性を持ち、均質な内容を満たしゆくような、絶対的な測定基準なるものは、此の生成界では決して与えられることがないと言わねばならないのである。
従って、この相対的な基準としての役割しか果せない「時間」は、異なった条件の下で持たされることになる己れの異なった基準の為に、ぽぽ一定の条件下で同様な周期性を持つ同様な現象に対して、異なった時間的長短を設定することになるであろうし、反対に、たとえその基準が一定の条件下で同じままであるとしても、その測定対象としてあり、同一と見なされている現象が、異なった条件下で異なった周期性を持たされる場合にも、やはり、その同一と見なされているものに対して、それぞれ異なった時間的長短を設定することにならざるを得ないであろう。
そして、以上のことから、同様な魂が、全く異なった条件下で異なった時間的長さの周期性を持たされ、場合によっては、ある領域の一昼夜が、ここでの人間界の法則の中では、八百年にも、千六百年にも相当することになるということも、決して非現実的な話ではないと言わねばならないのである。
このようにして、此の生成界における一切の魂は、均一な周期性の中で、均質に己れ自身を発現するのでは決してなく、生成界そのものを規定する統一力に従って、己れ自身に持たされる周期性の中で、収束・緊張・爆発・拡散を繰り返すのでなければならない。
そして、如何なる周期性の中で、如何なる内容を満たし、その発現を完結させるのかは謎であり、此の生成界を統一する彼の一者のみがそれを知っているのである。
そこで、次に、その統一的一者との関係の中で、選択的意志の働きを、その自由の有無という観点から調べてみることにしよう。
まず、この「自由」の意識が一体何に根拠を持つのであるか、調べてみる必要があるであろう。
それは、意識されるものである以上、当然表象能力が備わっていることが前提とされ、その上、己れの発現過程を変え得るものとして表象できるほどの、反省的な能力が必要となるのでなければならない。
そこにおいて、初めて「可能性」という領域が立ち表れ、過去、または未来におけるある原因の操作によって、異なった結果が得られたかもしれないと推測したり、またはある特定の結果が得られるかもしれないと推測したりすることができるようになるのである。
然しながら、既に生成したものも、生成するであろうものも、決して偶然に生成するわけではなく、常に形而上からの必然的な働きかけの下に生成するのであり、そこでの可能性の意識は、我々が持ち得る認識の絶対的な欠如を示すことにほかならないのである。
同様にして、この「自由」の意識は、己れの発現に際して与えられる様々な認識に対して、如何なるものにもとらわれることなく「自由」に選択して、働きかけることができると、反省内で表象することに基づくのであるが、然し、第一に、表象能力自体が魂の働きの一部としてある以上、その表象内に如何なる実在的な対象が照し出され、反省的な認識が成されるようになるのかは、その魂が持つ叡知的な領域にその実質的な根拠を求めねばならず、第二に、そこで表され、示されて来る対象なり認識なりが、如何なる意味を魂に与えることになるのかも、やはりその叡知的な領域によって規定されていると言わねばならないのである。
その為、上述のように、働きかける対象なり反省的な認識なりが、如何に広範囲で、「自由」な選択が成され得ると思われるにしても、そこで与えられるもの、及びそれが持たされる意味合は、決して自由と言われ得るような性質のものではなく、一切が、その実質的な根拠を、その叡知的な領域に負っているのである。※
ところで、我々万有が、その叡知的な領域によって規定され、それぞれ各自の舞台を務めねばならず、何らの自由も与えられてはいないのであれば、「生きる」ということ自体に一体如何なる意味があるのかが問題となって来るのかも知れない。
だが、この反省内での把握は、内的に与えられる生命力を抽捨してしまっているのである。
即ち、確かに反省内では、一切の情意、一切の実在的な世界、及び思考、そして一切の行為は、形而上からの必然性によって実質的に規定されていることを認識するが、然しそれらは、反省内で生命をほとんど抽捨されてしまった単なる脱け殺に過ぎないのである。
然し、これに対して、内奥において与えられる生命は、その情意に血を循環させ、実在的な世界に光を投げかけ、思考に実を稔らせ、そして行為を突き動かす。
実際、その生命の渦の中で生きるものは、その必然性を云々することなど成し得ないであろう。その渦の中で受け取ってゆくものの内にこそ、「生きる」ということの本当の意味を開示する鍵が隠されているのである。
※生成界のあり方は、物質現象間に設定される因果律によってではなく、一者から派生する形而上的な必然性によって決定される。一者そのものは、異なった宇宙を発現しうる実体として、気まぐれであり、自由性そのものなのかもしれない。
その叡知的世界に働きかけることによってのみ、我々は初めて真の自由を手に入れ、本来あるべき自己に向かって人生を切り開いていくことができるのである。
さて、次に、統一力に基づく魂の発現において、その魂が持たされるイデアが一体どのように機能することになるのか、調べてみる必要がある。
前述通り、我々は、個体の発現形式としてイデアを設定したが、それが、此の生成界に投げ込まれ、魂として生命を得、己れを発現しようとする場合、個々の魂は、己れに持たされたイデアに従って、本来あるべき己れ自身の姿を此の生成界に発現しようと欲するのである。
然し、統一力そのものが持つ自己確執の為、その意欲は様々な苦闘となつて、それぞれの魂の発現を特徴づけることになるであろう。
また、統一力そのものは、決して発現形式に還元されてしまうことはできず、そのイデアを通して己れの意志を満たすものとしてあり、その働きは、同一と見なされるイデアに対しても、異なった内容を満たしながら発現させることになるのである。
即ち、イデアが数の上で限定されている場合でも、統一力そのものの断えざる変化の中では、たとえ同一と見なされるものでも、様々に異なった内容の発現過程を持たされることになるのである。
その為、すべての魂は、何らかの点でそれぞれ異なった内容を持たされ、全く同じ内容の発現過程を繰り返すようなことはあり得ないと言うべきである。
然し、その反面、一切の魂は、己れの根拠をその統一力に持ち、その働きを体現していると言う点で、同じ内容を持ち得ると言うことも出来るのである。
次に、魂が、その統一力に基づき、如何なる欲求を持って己れ自身を発現することになるのか、イデアの持つ規則性に従いつつ調べてみることにしよう。
何故なら、如何なるイデアを持って発現することになるのかによって、その魂の欲求の内容も当然規定されて来る為、その欲求の分類は、イデア、特にその重層構造に従って成される必要があるからである。
ところで、そのイデアの性格的なものの方は、その諸欲求を性格づけ、特色づけるだけであるから、それ以上の説明は必要ないであろう。
そこで、前者の重層構造に従って、
(1)まず、無機物界においては、物質的な欲求が働き、上位に立つものを支える基盤となる。
この場合、ここで働くその欲求は、まず、此の生成界の無機物界に属する魂が、己れの内に物質を生成させようとする働きを内容とし、次に、そこで生成した物質を、今度は、魂同士が奪い合おうとする働きを内容とすることになる。
(2)次に、植物界においては、生存的な欲求が働き出し、有機体を養い、成長させようとする働きを内容とする。それは別に、養分と水の欲求と言い換えることが出来るであろう。
(3)そして、動物界においては、その上に、性的な欲求が重大な意義を持って働き、己れの種族を維持させようとする強い働きを内容とする。
(4)そして、頂上に立つ人間界においては、表象能力の充分な発達によって、その能力を満たそうとする知的な欲求が今までの下位的な諸欲求の他に生じて来る。
それは、その欲求が満たされる領域に従って、二つに区別される。即ち、直観内のものと、反省内のものとである。
前者は、愛撫などの触覚に訴えるもの、香などの嗅覚に訴えるもの、味などの味覚に訴えるもの、音楽などの聴覚に訴えるもの、そして、絵画などの視覚に訴えるものに区別される。
後者は、詩や哲学などの、言葉にその表現が託されているものが挙げられるであろう。
(5)最後に、人間界の中でも特に上部に立つ者においては、己れを打ち滅ぼし、一切の従属から解放されようとする欲求が強く働き出す。この欲求は、正にその性質から、神への欲求と言うことが出来るであろう。
以上のことから、魂の欲求は、底辺に常に認められる盲目的な切迫としての物質的欲求から、頂点における、一切の従属的な欲求から逃れ、虚空に至らんとする欲求まで、重層的に認められ、そのことを内的に把握するとすれば、闇の深淵の中で盲目的な切迫を受けている状態から、やがて、その深淵に漠然とした原始的な炎が生じ、そして、知性の光が燈されるようになり、後に、光の乱舞となつて、その極点において一切の欲求が断たれる時、その極度に高められた光の残照が、一瞬虚空を照射し、やがてその闇の中に消え去ってゆく、といったあり様が描き出されるであろう。
さて、以上のように、魂の欲求が重層構造の中で示されたのであるが、今度は、その最上位に立つ人間界において挙げられるあらゆる欲求が、その五つに区別された諸欲求の内のどのものに該当するのか調べてみることにしよう。
まず最初に、金銭欲と言われているものは、物質的欲求及び生存的欲求が、抽象物としての貨幣に向けられるものである。
また、権力欲は、物質的欲求そのものである。
権威欲・名誉欲は、その物質的な欲求が、他人の思念に向けられるものであり、前者は、その思念に対して、何らかの強制力を加え得る立場にあるものである。
以上のことから、金銭欲・権力欲・権威欲・名誉欲などは、共通の基盤を持ち、相互に取り換えられることにもなるであろう。然し、物質に対する直接的な支配に向かうことのない名誉欲というものは、単なる虚栄のみに止まると言えるのである。
ところで、人間界よりも下位に立つ世界では、その物質的欲求なり、生存的欲求なりは、当面の欲求が満たされるなら、それは止むのに、何故人間界においては、その物質的な欲求が強く発現されて来るのかが問題となるであろう。
一言で述べれば、それは、人間界において初めて備えられる反省的な能力によって、その当面の欲求が反復・増大され、果てしない範囲のものが欲求の対象と成り得るようになるからである。
即ち、本来の物質的欲求は、己れが存在することであるから、それは既に満たされているはずであり、また、生存的欲求も、当面の欲求が満たされるならそれで止むのに、表象能力が発達し、反省的な能力が備わると、その物質的な欲求は、まず、己れが存在する上での快楽・快適さを求め、次に、反省内で与えられる欲求の対象、即ち物質や思念等を飽くことなく求め、奪い合うことになるのである。
その為、当面の生存的欲求を満たすだけでは足りず、抽象化されて、蓄えることが出来、その上、他の下位的な諸欲求をも満たし得る欲求の対象として、貨幣を飽くことなく求めたり、また、当面必要なものだけでなく、反省内で時間・空間を満たし得る
限りの欲求の対象を認め、それを追い求めたりすることにもなるのである。
そして、その場合、欲求の対象とされるのは、直接己れの意欲を満たすことになる物質や思念だけではなく、その目的を達成するのに必要な手段としてあるものも、また、その対象として数えられて来ることになるであろう。
即ちそれは、有用なる手段として規定され、運用されることによって、初めて、目的としての貨幣なり、権力なり、権威や名誉なりを獲得することを可能ならしめ、容易ならしめるものとして、驚くべきほどの多様性を持って登場して来るのである。
その物質的欲求に基づいて、有用な手段として規定される対象の範囲は、万有の持つあらゆる働きにまで及ぶことになり、無機物・植物・動物だけに止まらず、人間の持つあらゆる働き・能力に対してまでも、恣意的に、有用な手段として規定し、己れの目的を達成する為に、あらゆる面で利用しようとすることになる。
また同様にして、「道具」の発明も、その生存的欲求に基づいて、究極的な目的を達成する為に、有用な手段として使用される物が登場することになるからであり、その目的を容易に導こうとする意欲によって、その「道具」も改良されてゆくことになるのであるが、しかし物質的な欲求の下で、高度に発達させられた「道具」は、既に我々の存在そのものを脅かすほどにまでなっているのである。
一切のものに対して、それをそのもの自体として知り、触れ合うのではなく、己れの囚われた欲求に基づき、一切を有用な手段として規定し、鎖の輪の中に縛りつけてしまうこの貧しい魂。
そして、それぞれ己れの因われた欲求に基づいて、他者を有用な手段として規定し、利用し合うこの貧しい社会。
その規定の網の中に止まる限り、我々は、己れの生を極つまらない偽善の中に閉じ込めてしまうことになるであろう。取り引きとは、己れの最も大切なものを、この正体の知れぬ悪魔に売り渡すことにほかならないのである。
さて、次に進んで、普通性的欲求と言われているものは、実際には本来のものより、物質的欲求に基づいて、性の対象を支配しようとしたり、己れの快適な存在を保証する物質的な条件を満たそうとしたりする場合がほとんどであろうし、また、生存的欲求を満たす為の手段となっている場合も多いであろう。
最後に、神への欲求とされるものは、此の生成界の一切の魂において認められるのであるが、この欲求が特に強くなって来るのは人間界で、それも、上部に立つ者にとっては、誰一の行動原理にまでなって来る。
そして、人間の共同体においては、「祭り」という形でその欲求は具現化されることになるのである。
その「祭り」の中で、人々は日常生活の連鎖から解き放たれ、今まで限定されて来た己れ自身の全体性を、その一切を巻き込む渦の中で確認し、それを他のすべてのものと共有するのである。
そして、己れ自身を掴み、満たされた中で、新たな生活がまた再び繰り返されてゆくのである。
ところで我々は、ここで、その「祭り」がどのようにして生じて来るのか、その発生を辿りながら調べてみることにしよう。ここで重大な役割を果すのが、「禁止」と「違反」である。
まず、人間界において、「禁止」というものが共同体のルールとして一番最初に登場するようになるのは、恐らく生と死に関してであるだろう。
何故ならば、生れる前の世界及び死後の世界は、此の世界とは全く隔てられている不可知な畏れの対象とされ、彼の世界から此の世界の事物や生活を守らねばならないからである。そしてそれ以降、彼の世界とは隔離された此の世界においては、日常の生活を守る為に、此の世界でのみ守られるべき共同体のルールが次々と産み出されて来ることになるのである。
然し、彼の世界は、我々がそこから生まれ、やがてそこへと死んでゆく世界として、此の世界と全く切り離されているわけではなく、それとの接点を何らかの仕方で此の世界の中に残しておかねばならず、それが、人間の共同体の中では、「祭り」という形を取って具現化されるに至るのである。
その「祭り」においては、日常生活にもたらされているすべてのルールは無効となり、それに取って代って、神的な混沌が産み出されるのである。その混沌とした渦の中に入り込むことによって、一切のルールは犯されることになるのである。
ところで、その周期的に繰り返される運動は、正に統一力の働きの中に配慮されており、それは、日常生活の連鎖に縛りつけられ衰弱してしまう魂を、その連鎖から解放し、新たな生命力を吹き込もうとするその働きに基づいていると言えるのである。
そして、その共同体の「祭り」そのものが儀式化してしまい、本来の形而上の目的を果たし得なくなる時、その配慮は、今度は、各個体の中で、己れ自身の「祭り」を催すよう促すことになるのである。
そして、そのような場合、そこで認められる運動は、前の周期的な円環運動とは異なり、己れ自身を掴まえようとする意欲の下でより先鋭化され、円錐の表面を螺旋状に辿りながら頂点に至らんとするのであり、そしてその頂点から跳躍して、一切の従属から解放され、虚空を掴まんとするのである。
さて、以上魂の持つ欲求に就いて調べて来たが、今度は、諸欲求を持って発現する魂そのものに就いて調べてみることにしよう。
まず、魂が様々な欲求を持ち得る時、ある一つの、または片寄った欲求が、他のものを抑圧し、犠牲にしているような場合には、その魂は、不健康で醜いと言うことができるであろう。
反対に、その様々な諸欲求が互いに抑圧し合うことなく、均斉を整えているような場合には、その魂は、健康で美しいと言うべきである。
従って、人間である以上、魂が物質的欲求や、生存的欲求のみに囚われている姿は醜いが、同様に、反省内における当為によって、生存的欲求や性的欲求などの、生理的な自然の欲求を無理に抑圧することも、不健康で醜いと言わねばならない。
当為による統制も、時には道を譲らざるを得ない場合があり、そのような時にこそ、我々の魂が本当に健康で美しいものであるかが証明されることになるのである。
そして、このように、健康で美しい魂が、真に心から欲する正にその状態こそが、魂の徳と呼ばれるべきものなのであり、その徳を積み重ねてゆくことによって、初めて魂の浄化が成され得るのである。
次に、魂の発現過程を、特に人間界において眺めておくことにしよう。
まず最初に、誕生から数年間は、生存的な欲求が強く発現され、此の世に生まれ出た以上、生きることを主張し、その間に、生きる為に必要な知性が訓練されることになる。
次に、子供時代においては、知性が生存的欲求よりも上回る為、知的な欲求が発現され、遊びに深く興じることが出来るようになる。
様々なものを切っ掛けとして、己れの空想の世界に入り込み、その世界と一体となる。そして、より表象能力の高い子供にあっては、直観的に此の世の本質を感じ取ることが出来、一種の哀しさ、虚しさを覚えるのである。
不安はこの時期に生じ、やがて発現されて来るものに対する予感が、ロマンチックな気がかりをもたらす。
そして、青年時代には、もう既に、生存的欲求に仕える為の知性は完備され、いよいよ様々な諸欲求が強力に発現されて来ることになり、その為、意識の内には様々な葛藤が引き起こされる。
この時期には、特に性的な欲求が強く発現されることになる。
また、子供時代のあの哀しさを湛えていた不安は、そのやがて来るべきものがこの時期に次々と発現され始め、その実質的な内容に直接触れることになる為、ほとんど消え去ってしまう。
そして、依然として知性が欲求よりも相対的に高い場合には、これから更に強く発現されて来るものに対して、強度な不安を包く。
成人となっては、欲求が頂点に到し、果てしない諸欲求が衝突し合うことになる。その為、矛盾と苦悩は一層大きなものとなる。それに反して、知性はそれらの下位的な諸欲求に仕えるのが精一杯で、不安や、それに伴う哀しさ・虚しさなどは、ほとんど覚えることができない。
生存的欲求・性的欲求とも頂点に立ち、その上、反省的な能力の介入により、物質的な欲求が特に強力に発現され、一切の欲求の中で支配的な地位を占めるようになる。そして、知的な欲求は、それらの中で影の薄いものとならざるを得ない。
ところで、そのような強い欲求に囚われ、閉塞されてしまった魂の、本来のあるべき姿を取り戻す為、形而上的な配慮が成されることにもなるであろう。それは、社会的なものであれ、個人的なものであれ、欲求そのものの否定、解消へと向かうのである。
最後に、体力が衰え、老人となる頃には、一切の欲求は相対的に衰えることになるが、然し、反省的な能力の介入によってもたらされる物質的な欲求は、体力にかかわらず衰えることはなく、却って、他の欲求がこの物質的欲求一色に塗りつぶされてしまうことにもなるのである。
さて最後に、この魂の発現を、対社会的な係わりの中で把握してゆかねばならない。
魂が他のものと共に此の生成界に投げ込まれている以上、個々の魂は、それぞれ回りのものと関係を持たされることになると言わねばならない。
その場合、その係わり合いは、無機物界や植物界においては、あの統一力の働きかけによってそのまま直接規定されることになるのであるが、然し、動物界や人間界においては、その係わり合いは、たとえ統一力の働きの下で規定されているとはいえ、表象を介して持たされることになるのである。
その為、表象能力が備わったものの、回りのものへの係わり合いは、その表象内で与えられる〈存在〉によって規定されて来ることになる為、ここでは、その規定の現状を、表象能力の程度に従って調べてゆくことにしよう。
そこで、まず、その訴えかけられる表象能力の領域に関しては、動物の場合には直観の領域内に止まるが、人間の場合には反省の領域に対しても成されることになり、そこでは、言葉が重要な地位を占めると言うことができるのである。
そして、そのような直観(経験)や言葉を介して、回りのものと係わり合いを持ちながら己れ自身を発現させることになるのであるが、それは取りも直さず、己れの属する集団社会の仕組や掟などを学ぶことをも意味するのでなければならない。
例えば、直観内に訴える場合では、親が子に餌の取り方を実践の中で示し、経験を積ませたり、また、集団の掟なり、社会の規則や道徳なりを、自身の行為によって子に示し、子がそれに反する時には、体罰で身体に覚え込ませたりするのである。そして、言葉に訴えることが出来る場合では、前者において経験されることを、言葉によって補いながら教え、説明するのである。
このように、集団社会そのものが教育の場を予定しているのであるが、特にこの人間界においては、その社会の持つ歪みの為、その中で認められるようになる教育の弊害にどうしても注目せざるを得なくなるであろう。
即ち、本来、個々の魂を健全で、美しいものとして発現させ、導かねばならない社会が、反対に、個々の魂の本来あるべき姿を歪め、充分な発現を抑圧してしまうものとして機能しているのである。
金銭・権力・権威・名誉などで動く社会は、取りも直さず物質的欲求にひどく囚われた社会であり、そのような社会の中で与えられる教育の場も、当然その物質的欲求に囚われたものとならざるを得ないであろう。
如何に教育の理念を説いても、社会の中で経験を通して与えられる教育の方が、はるかにしつこく心の内に働きかけるものである。
そして、そのような社会では、物質的欲求に対する配慮のみが成され、他の欲求に対しては何らの配慮も成されなくなるであろう。
まず、生存的欲求の対象としての食物・水に関しては、個々の魂が持つ素質に一番適した、健康に良いものを配慮するかわりに、金銭欲の為、魂の成育に害となるようなものを平気で使用し、混入する。その上、更に驚くべきことは、各個体のそのような配慮すらをも、金銭欲の為に、有用な手段として規定し、利用してしまう。
次に、性的な欲求に関しても、真に魂の徳から求めるよう配慮するかわりに、物質的欲求の下で取り引きの対象に貶められてしまう。
その場合、性の対象を物として支配しようとする場合だけでなく、己れの快適な存在を求め、生存的欲求を満たすだけのものとは認められないような場合にも、その物質的欲求が認められるのである。
そして、知的な欲求に関しては、表象能力のすべてがその物質的欲求に仕えることを要求されている為、その欲求が充分満たされ、その能力が開花されることはほとんどあり得ず、却って、その能力の開花は有害視されることになる。
また、能力が磨かれるとしても、それもまた、金銭や名誉などを獲得する為の手段としての地位しか持たない場合がほとんどであろう。
そして、稀に、手段としての地位に止まらず、その能力が無条件に開花するようなことがあっても、それもまた、金銭や名誉などが流れ込んで来ると、直にその能力は、それらを獲得する為の手段に貶められてしまうのである。
最後に、神への欲求に関しては、その物質的欲求そのものが持つ狭量な性質の為、その欲求に囚われている限り、決して己れ自身を解放することなど出来はしないのである。
ところで、このような物質的欲求に囚われた社会においても、壮健な魂は、その中で全く去勢されてしまわない限り、その歪められた状態を打ち破り、全的な幅を持って、己れ自身を発現しようとするのである。
一度、真に心から欲する状態を体現すれば、性的な欲求においてであれ、知的な欲求においてであれ、それからは、その徳を追い求めてゆくことになるのである。あの引き裂かれた愛を、あの純粋に無となり天翔けた天空を、と。
そして、その時魂を導くのは、対外的に表され、与えられるような教育ではなく、己れの内奥において一切を統一する、一者として控える何か或るものでなければならない。
Improvement makes strait roads, but the crooked roads without improvement are roads of Genius.
--The Marriage of Heaven and Hell (William Blake)
第三部 生成界 ーーおわり