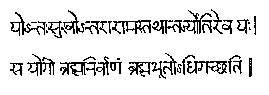
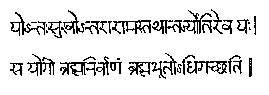
虚空に漂い、
喜びに満たされ、
(解放された喜びに)光り輝くもの、
その一身を供犠に捧げているものは、
梵としてその涅槃に入る。
さて、今まで統一面によって規定される物質現象としての生成界を調べて来たのであるが、ここでは、再び精神現象に戻り、生成界において魂の発現とされる状態を、主に内的に描き出して見ることにしよう。
対外的な世界に実在として表される〈存在〉は、知性の光の下に照し出される知的な光の戯れ、即ち影としての性質しか持ち得ないのであるが、然し、我々にはその領域における〈存在〉のみではなく、その領域の根底にあり、その領域内の〈存在〉を意味付ける、別の領域に属する〈存在〉も与えられており、それが、魂の状態の直接且つ内的な表れとされる情意であることは前述通りである。
この領域では、それは、統一主体によって主客合一の中で覚えられない時でも、意識されないまま、内なる深淵に広がる闇の海として魂の状態を体現しており、直観内であれ、反省内であれ、それは無意識の内にその表象全体に反映され、それらにおける〈存在〉に色合を持たせているのである。そして、魂が己れの状態を著しく変えるような時には、内的に、情意が〈存在〉として覚えられることにもなるのである。
そこで、ここでは以下の内的な情景が想い描かれるであろう。
即ち、まずこの始原としてある情意の海を統一主体が舵を操って航海しながら、その海の表面に、直観的な世界や反省的な世界を描き出し、それに見入っている。そして時には、己れを浮かべると同時に揺さぶり、直接意志を伝える情意の海に、注意を凝らし、その状態を窺うこともある。
また、夜中、海が凪ぐような時、統一主体は一切の気遣いから解き放たれ、その静まり返った海の天空に、無数の星を鏤め、その間を翔け回る。
以上の情景を舞台として、以降は、魂の状態を内的に、前述の諸欲求に従って見てゆくことにする。
(1)まず、物質的欲求において。
此の生成界に投げ込まれ、生成を繰り返している以上、一応その欲求は満たされており、その場合、その欲求の内的な現象は、深淵に広がる海の底に、只深く沈んだまま無闇に押し流されるものとして、この統一力に従属させられ、掻き廻されること自体が持つ存在の苦悩を湛えるのである。
そして、反省的な能力が備わることにより、その中で表される欲求の対象の獲得・喪失を切っ掛けとして、一喜一憂する情意の海の表面的な波の戯れが認められるようになって来るのである。
(2)次に、生存的欲求において。
統一主体は、その闇の海に知性の光を燈し、その照し出される実在的な世界の中に、己の欲求の対象としての水なり、食物なりを探し求めるのであるが、その場合、魂がその欲求を持っているのか否かによって、そこで照し出されて来るものの意味合は異なって来るのである。
即ち、魂が渇望している時には、その照し出される対象は、魂の注意を引き、魂を釘付けにする。内的な現象では、その照し出されるものは情意の渦の中で特別な色合を与えられ、統一主体はそれのみにかかずらうことになる。
そして、それを渇望しながらも手に入れることが出来ない時には、絶望のあまり表象機能そのものが一瞬停止し、情意の海がすべてを飲み込んでしまうであろう。そして、その後に表されるに至る〈存在〉は、その情意の色一色に塗り潰されることになる。
また、その渇望の対象を手に入れ、満たされてしまっている時には、新たに照し出されて来るものに対してもうほとんど興味を包くことはなく、そのまま光の戯れとして消えるにまかせることになる。たとえそれが如何に美味しいものとして照し出されるとしても、あまり重大な意味を持つことはないのである。
(3)そして、性的な欲求において。
上述の生存的欲求がある程度満たされ、魂を維持する以上の余力がある時に、その欲求が生じて来る。そしてそれは、種族の維持・繁栄を形而上の目的として持っている為、その性的な対象の選択もかなり厳しい。
一者の意向は、同じ魂同士を寄せ集めることに注がれているようであるが、人間界においては、思わくや打算が働き、そのような聖なる結びつきはあまり見受けられなくなる。
然し、二つの魂が、己れ自身の徳から真に求め合うような場合には、彼等の統一主体は、生存的欲求の時と優るとも決して劣ることのない激しい情意の波に打たれ、その目的を達するまでは、たとえ実在的な世界が照し出されていようとも、それは全くの光の戯れとしてしか思われず、また、何かを考えようとしても、その激しい情意の海の中から浮かび上がるのは、その対象のことばかりであろう。そして、極端な場合には、死を賭してでも契りを全うしようとするであろう。
以上の状態は、たとえ片思いであっても、己れの徳から真に欲する状態を体現している魂なら、誰でも持つことが出来るのである。
ところで、その求めている対象が結局手に入らないことが明らかとなる時、その欲求の激しさに応じて、そこで味わう絶望はより深いものとなって、情意の海を掻き廻すことになる。
そして、その欲求が完全に絶たれていない限りは、情意の海の奥深くで常にその対象に対する欲求が蠢き、その欲求の下で依然として求め続けようとして、今度は、その対象の代替物や、またはその対象の思い出を追い求めてゆくことになるのである。
また、その欲求の対象が手に入る時には、その正に対象が手元に入らんとする瞬間において、情意の海は激しく高まり、表象全体を飲み尽くし、統一主体はその激流の中で己れ自身を見失いながら、その激しい渦の中で生命そのものを謳歌する。
だが、その目的が達成され、その情意の海がすつかり凪いでしまった後で、その統一主体は、その手に入れることの出来た対象が以前とは異なった意来合を持たされていることに気が付かねばならなくなるのである。
何故なら、その性的欲求が満たされてしまった後では、その対象は、その欲求の下で与えられていた意味合を、もはや持ち続けることは出来ないからである。※(1)
そして、それを切っ掛けとして、たとえ共同生活につながれるとしても、それは、やがて生まれて来る子の生存的欲求を満たす為に必要な配慮が働くからであり、その形而上的な配慮の下で己れの種族を維持することになるのである。
この場合、人間においては、己れの果てしない物質的欲求を満たそうと打算が働き、その共同生活の形態を維持しようとする場合が多いのであるが、然し、一方において、その共同生活が打算によって維持されるのではなく、その上、それが性的な欲求の下で結ぴつけられた時よりも一層緊密にされる、別の新しい関係がこの人間界においては生じて来るのである。
それが即ち、知的な欲求の下での精神的な結ぴつきなのである。
その精神的な絆によって、性的な欲求の下で成される刹那的な結びつきに優る強い結びつきが生じ、ここにおいて初めて、人間として生まれて来るものの本来至るべき世界が現出して来るのである。
※(1)己れの徳から相手を真に求めることがあるとしても、その対象は、その自由性を獲得する切っ掛けとしての役割しか与えられてはいず、その対象が即ち自由性であると言うことにはならないのである。
然し、その対象の影としての性質を自覚していない為、その対象そのものを何か自由性を持つ実体であると思いなし、それに執着するといった愚行が成されるものである。
(4)最後に、知的な欲求において。
表象能力が充分発達し、それが下位的な諸欲求に仕えることなく純粋に高められる時に、それを満たそうとするその欲求が生じて来る。その為、この知的な欲求は、知性の遊びという性質を持たされていると言えるであろう。
ところで、その遊びが、その表象能力の純粋な高まりによるのか、それとも性的な欲求に基づく表象能力の高まりによるのかは、別に問題とはならない。然しそれは、生存的欲求が当然ある程度満たされていることが条件となるであろう。それが満たされていない限り、知的な能力はすべてその欲求に回され、仕えねばならなくなるからである。
また、当面の生存的欲求が満たされていながらも、魂が不健康な為、飽くことのない物質的欲求に因われている場合にも、やはりその知的な能力全体はその欲求に従属し、仕えねばならない。
そのような状態では、情意の海に天空が懸かることはなく、反省内に表される己れの利得・損失に、只一喜一憂する表面的な波の戯れのみしか認めることが出来ないのである。そしてまた、高い知力によってその波を静めることが成されるとしても、その物質的な欲求に従属している限り、その知力は決して純粋に高まって知的な欲求を満たすということはないであろう。
さて、ところで、知的な欲求は、音楽・絵・詩・小説など、様々な形を取って満たされることにもなるのであるが、その内のかなりのものが、恋愛などの性的な欲求に切っ掛けを持っていることが認められるであろう。
それは、性的欲求の持つ形而上的な目的と、知的な欲求における表象能力の高まりとは、決して対立するもの同士ではなく、却って、性的欲求の激しさが表象能力をいやが上でも高めてしまうからである。
その為、ここではまず、性的欲求を切っ掛けとする表象能力の高まりから見てゆくことにしよう。
まず、その性的欲求に基づき高められた統一生体は、翼を得て情意の海から舞い上がり、天空を天翔ける。そして、その飛翔の中で、情意の海に働きかけている力をそのまま写し出すのである。
その力は正に性的な欲求をもたらす形而上のもの、即ちエロスであり、それを内奥に体現し始めながら、統一主体はその力の本質を写し出し、やがて発現されて来る己れの焼尽・破滅を予感する。そのエロスの働きは、徐々に激しさを増し、その為、表象能力もいやが上にも高まる。
彼は、その情意の慌れ狂う渦の上を天空高く飛翔し、その中で写し出されるものを何らかの形にして残しながら、もう既にそこにやって来ている己れの破滅を予見し、それを願う。
そして、エロスの働きが極度に高まり、情意の海が怒涛となつて己れの天空すべてを飲み尺くさんとする時、乱気流の中で最後まで持ちこたえていた統一主体は、その天空の至高の高みにおいて己れに迫った破滅を目前にし、乱調の極点に至る。
ここでは、形として残されるようなものはすべて錯乱しており、眩暈や吐気、それに一つの呻きが、以前の芸術作品に取って代って、それ自体最高な芸術性を示すことになる。
そして、その怒涛が天空すべてを飲み尺くした時、彼はその渦の中に引き込まれ、眩暈の中で己れを見失いながらその激しい生命の渦に身を委ねる。
やがてその海が静まり返る時、彼は砂浜に打ち上げられている己れ自身の姿を見出すことになるのである。
さて、次に、知的な欲求として認められるもう一つの場合、即ち純粋に表象能力が高まる場合を見てゆくことにしよう。
この場合には、表象能力が高い状態に置かれている為、何らかの切っ掛けから直に統一主体は翼を得て、その静まり返っている情意の海の天空に舞い上る。その内奥に懸けられた天空に、無数の星を鏤め、翔け回る。そして、その星の間を天翔けながら、それらが囁きかけて来るものを写し出すのである。
その為、何らかの感覚が無理やり彼をその内奥の天空から連れ出し、対外的な世界の中に投げ込もうとする時、たちまちその天空は砕かれて、消え去り、彼は驚いてその世界に注意を向けることになる。
ところで、この知的な欲求は、前述通り、下位的な欲求に必要である以上の高められた表象能力が備わる為に、それが何らかの働きかけによって直に刺激され、統一主体は自由に飛翔し、戯れ、遊び回ろうとすることから生じて来るのであるが、然し、一般的には、表象能力は下位的な諸欲求を満たす為の手段程度のものしか与えられず、また、その表象能力が充分高い場合でも、飽くことのない物質的欲求を満たす為の手段となってしまう為、それが必要以上に高まって、純粋に飛翔するということは稀で、只子供の頃にそのような内的現象が認められるだけであろう。
何枚ならば、その時期においては、未だ魂の意欲は無垢なものとしてまどろんでいるが、それに比較して表象能力は急速に発達するからであり、その為、子供というものは、如何なる境遇にあっても、何らかの遊びに耽ることの出来る無邪気さを持つものである。
その時、統一主体の飛翔は、その相対的に高い表象能力の中で純粋なものとなり、己れの内に懸かる天空を天翔ける。そしてその天空は、全く凪いで休らっている無垢な情意の海を反映して、何らの曇りもない輝きを放つ。
然し、やがて、子供から青年、そして大人へと成長するにつれて、魂があの無垢な状態から己れの意欲を強烈に発現し出すと、その相対的に高かった表象能力は、諸欲求の手段として仕えることになり、それまでは天空を天翔けることの出来た統一主体の翼は、もがれてしまうことになるのである。
即ち、それに応じて、その情意の海も徐々に渦を巻き始め、たとえ何らかの切っ掛けから統一主体が翼を得て、己れの内なる天空を彷徨い歩く場合があるとしても、その天空は、もはや魂の無垢な状態を反映した全く晴れ渡った天真爛漫なものではなく、それは俄に黒雲に蔽われ出し、やがて雷雨を伴って、その統一主体の飛翔を限られたものにしてしまうのである。
そして、その飛翔の中で写し出されるものは、個体性に因われた魂の姿そのものでしかなく、存在そのものが持つ苦悩を基底に湛え、苦しみ、呻き、悶えるその情意の海の渦そのものでしかない。
それは、もはや生じては消えるといった表面的な波の戯れとしてではなく、様々な欲求を持たされ、海底の奥深くまでうねりを湛えた根深いものとして、己れの内なる深淵に広がっているのである。
ところで、己れの徳から真に対象を恋し、または天空を飛翔することの出来ない魂は、己れの満たされぬ思いを、情意の海を掻き回し、濁らすことで隠そうとするであろう。己れの徳から真に欲することが出来ず、只欲しようとすることを欲するだけであろう。
その為、その情意の海の深みも、魂が解放されない限り、不透明なもの、泥水状のものとなり、その表面に生じていた天衣無縫な波の戯れを抹殺してしまうことになる。その深みの中で、一度も真に満たされることなく、己れ自身の本来の姿を押し潰してしまう。
そして、己れの魂を腐らせてしまい、その腐臭を何か重大な意義があるかの如く示し、他の汚れなき魂にそれを強要することにもなるのである。
さて、芸術家として生まれて来る魂は、異常な表象能力の高まりの中で、たとえ情意の海が慌れ、その天空が黒雲に蔽われてしまっても、それを突き抜け、天空の果てを飛翔することも出来るのである。
その時統一主体が写し出すのは、万有すべてが持つ存在の苦しみから滲み出る、無限に透明な濃青の天空である。
それは、子供の頃写し出されたような、太陽の輝きに満ちた明るい青ではなく、すべての光を透過させて、無限の闇の中に滑り込んでゆく透明な青でなければならない。
また彼は、その黒雲を超え出た所で、時代の背後に渦巻く統一力を写し出し、描き出すのかもしれない。それは、個々の魂を包み込み、一切を渦の中の飛沫と化してしまうほどの強大なものとして、否応なくすべての魂の注意を向けさせることであろう。そして、それらは、この慌れ狂う大海のパノラマを前にして、眩暈を覚えることであろう。
然し、その統一主体が、厚く、時には雷雨を伴った黒雲の中で彷徨い続ける限り、その中で写し出されるものは、己れ自身の個体性に囚われた姿でしかない。
だが、個体性に囚われながらも芸術家というものは、その最も深い所を写し出し、描き出すことが出来るのである。
ところで、刻々と変わる情意の表面的な波の戯れを内容とする己れの姿とは、己れ自身の発現過程に伴って生じては消え失せてゆく泡沫でしか過きず、その姿を写し出し、描き出したものとは、更に儚い幻のようなものでしかないであろう。
その上更に非道いことには、全くの知的な光の戯れでしかない洗練された感覚的な訴えが、上述のものすべてに取って代って、「芸術性」を与えられているのである。
そこで、次の所では少し寄り道をして、作品を介して行われる伝達の構造を調べてみることにする。
さて、ここでは、表象内に与えられる〈存在〉としての作品が、伝達の媒体となるのであるが、その場合、人間のみにかかわらず、すべての魂が、創作の主体として、たとえ己れ自身の身体そのものであれ、または他のものであれ、何らかの形で作品を表し、示すことになるとすぺきである。
その為まず、無機物界及ぴ植物界におけるものは、己れの魂の状態を、そのまま我々の表象内に身体として示すのであり、従って、その感覚を土台とする知的な光の戯れは、その背後にある魂の状態と表裏一体のものとして、我々はその影から、その魂の状態を察することが出来るのである。
同様にして、表象能力を備えながらも、それがほとんど己れの意欲に仕えねばならない動物界においても、その表象能力は己れの発現の切っ掛けとしてしか機能せず、魂はやはり己れの状態を、そのまま我々の表象内に身体として示すだけである。
ところが人間界に至ると、その表象能力の発達の為、知的な欲求の下で身体以外の様々な形で作品が残されることになり、その場合、それらは上述通り、作者の魂の状態を反映し、それも、人間界でのみ持ち得る精神的な状態までをも反映することが成されるのである。
然しながら、それと同時に、その表象能力の発達の為、感覚を土台とする知的な光の戯れが、その魂の状態と切り離されたまま興味の対象となり、知性は、その戯れの洗練された姿を追い求めることにもなる。
即ち、統一主体が作品を創り出す時には、情意の海がそのまま彼に反映している為、その情意的なものが、感覚的な諸性質や形態、そして言葉という形を取って定着されることになるのであるが、然し一方で、それらの形が持つ知的な面が、その情意的なものから切り離され、知性の関心の下で、その洗練された知的な光の戯れが追い求められることにもなり、その為、そのままそれのみを内容とする作品が創り出されることにもなるのである。
然し、そのようなものは、感覚であれ、言葉であれ、単なる知的な光の戯れとしての意味合しか持ち得ないことは当然であろう。単に知性の光のみに基づいて創り出されるようなものには、決して魂が入らず、他の魂を心底から掴まえることなど出来はしないのである。
さて次に、受け手は、表された〈存在〉に反映されている情意的なものを、直覚の中で写し出し、その背後にある魂の状態を瞬間の内に把握するのでなければならない。
然し、その場合、その反映されている情意的なものと同質な魂の状態を体現したことのない者には、その表されて来るものに対して実感を持って共鳴することは出来ず、只、やがて己れにも発現されて来るであろうものに対する不安や引っ掛かりとして、魂の内奥に刻み込まれるに止まるだけであろう。
また同様に、受け手の魂が様々な渦の中で鍛練を積んで来ていない場合には、些細な感情のみに囚われ、ややもすると、表面に漂う知的な光の戯れのみを追い掛けることにもなる。
そして、受け手が己れの意欲に因われている場合には、その表されて来るものから、その背後にある魂の状態を、純粋な鏡となつて写し出すことなど出来はしないであろう。
その表され、意味付けられたものは、正にその意欲に囚はれた、己れ自身の歪んだ姿にほかならないからである。
ところが、受け手の表象能力が非常に高い場合には、その表されて来るものから、その背後にある魂の状態だけでなく、そのものの持つイデアや、その背後に働く統一力までをも写し出し、更には、万有が支配されているその統一力の本質そのものにまで、その直覚的な把握は及ぶのである。
次に、その表象能力の高さに根拠を持つ、副次的な産物を取り扱うことにする。即ち「不安」に就いてである。
ところで、我々がその「不安」を問題とする場合、その感情の根拠を、あの不可知な深淵に求めることが出来、それを「不安」として一つの本質的な相の下に総観するのであるが、ここでは、その相を自然的な性質に従って区分し、二種類のものを設定し、吟味してゆくことにする。
即ち、実在的な世界に働きかけて己れ自身を発現させる際に覚える不安と、反省内における構築物の崩壊に対する不安の両者である。
それでは最初に、前者から調べてみよう。
l 発現過程に伴う不安
まず、この場合の不安の源泉から述べてゆこう。
即ちそれは、表象能力の高まりの中で、統一主体がやがてきたるべく発現されて来るものを予感し、その明確な規定を成し得ないものに対して恐れを包くことをその内容としているのである。
従って、不安は、表象能力が高い状態において初めて覚えられる感情であり、その感情の切っ掛けとしてあるものは、やがて発現されて来るであろうものの漠然とした表象だけである。然し、未だそのものを内奥において体現していない為、その感情が続くことになるのである。そしてその不安が持つ性質は、その魂の発現過程に応じて異なってゆくことになるであろう。
即ち、子供時代においては、その相対的な表象能力の高さによって、己れの人生においてやがて発現されて来るであろうものを予感するが、そのものをまだ何も体現してはいず、そのものの実質的な知を持ち得ないままである為、その予感は、子供の頃に特有な甘い襖悩として覚えられる。
また、より高い表象能力を備えた子供は、己れの個体性を超出した所で働く統一力を写し出し、此の世の万有の本質を感じ取ることができ、それが哀しさ、虚しさとして覚えられることになる。
然し、魂の意欲が強く発現し、表象能力が諸欲求に仕えるようになると、そのような不安は消滅し、予感はほとんど成されることがなくなる。
そこでは、諸欲求の対象として限定されるもののみが不安を呼ぶだけであり、この場合の不安は、ある欲求の実現のみに根差しそれに先行する為、その実現によってその不安は解消されることになる。
ところが、高い表象能力を備える者達は、その欲求の対象として表されるに至ったものの背後に、一切を飲み尽くす深淵を予感し、時には、激しい欲求の中で高められた統一主体は、その対象の背後にある深淵の中ヘ己れが墜落し、破滅するであろうことも予見し得るのである。
そのような時、意欲の体現に際して統一主体は、間近に控える未知なる深淵を目前にして、引き裂かれるような不安を覚える。そして、その深淵が、一切の〈存在〉を飲み尽くし、己れをも破滅させるものとして、死の影を帯びている為、不安は極度に高まり、その死から逃避しようとする働きと、その死の中で己れ自身を解放しようとする働きとの迫間で、強烈に引き裂かれ続け、その烈傷の中で身悶えすることになる。だが、その不安の極点において、吐気と眩暈の内に崩れ落ち、その深淵の激しい渦に身を委ねることによって、その不安は解消するのである。
さて、そのように、己れ自身の徳から己れを破滅させ、己れ自身を解放した魂は、それ以降、己れ自身の発現に伴って生じて来る不安に対して、進んで突ぴ込んでゆき、それを消えるにまかせるようになる。
然し、反対に、その死から逃避し、一度も己れ自身を解放することの出来ないものは、その不安を決して解消させることは出来ず、それは、そのまま奥深く沈殿し、満たされないまま欝積し、やがて腐り出して来ることになる。
そして、その腐り出した悪魔的なものは、己れの満たされぬ思いを隠し、己れを欺こうとして、対外的な世界に表される対象を飽くことなく追い求め、支配しようとすることにもなるのである。
然し、如何に支配の手を広げようとも、そのままでは決して己れ自身を解放することなど出来はせず、却って、己れの不満を募らせるだけであろう。
そのようにして、満たされぬまま欝積した不安は、魂そのものを少しずつ蝕み、最後には、もはや取り返しのつかない完全なる腐敗に、魂を手渡すことになるのである。
その為、真に己れの徳からする欲求は、決して罪悪ではないと言わねばならない。もし罪悪が云々されるのなら、そのような徳を抑えて、死から逃避し、そして真には欲していないものを欲しようとして、本来あるべき己れ自身の発現を歪め、腐らせてしまうことの方が、よほど罪悪なのである。
一度徳を体現し、満たされた喜びを知った魂は、それ以降己れの徳を追い求めてゆくことになる。その徳の為になされる反抗・否定は、正に己れの影をも打ち砕くにまでなる。そのようにして、満たされた喜びを知った魂は、その喜びを常に心に持ち続け、徳を求めて己れ自身を真正に発現しようと苦闘し、その中で己れ自身を浄化してゆくのである。
そして、そのような時、己れを発現しようとする際に覚えられるその不安は、正に、本来あるべき己れ自身の姿を発現させ、導く、神的な呼びかけとなるであろう。
その呼びかけに従いつつ、苦闘の中で己れ自身を浄化してゆくことによって、初めて、その情意の海は、透明な深い輝きを持って、人の目に眩暈を覚えさせるにまでなるであろう。
ところで、生涯において高い表象能力を持ち続ける極稀な人々は、対外的に照し出されるこの実在的な世界から、その背後にある統一力の働きを写し出し、そのものの本質を予感する。永劫に亘って万有が負わされている苦悩を写し出し、此の世に対する哀しさ、虚しさを懐くのである。
そして、その予感の中で常に漂っていた負い目が、何らかの切っ掛けからはっきりと自覚され、意欲そのものの虚しい本質を知るに至る時、万有の一切の苦悩を己れ自身のものとして背負い込むのである。
一切のものの苦悩を己れ自身のものとして、一切のものの解放を願いながら、己れ自身の闘いを始めるのである。
2 構築物崩壊に対する不要
今度は、反省内における構築物の崩壊に対する不安の感情に就いて調べてみることにしよう。
この場合の不安も、前者のものと本質的には同じで、あの不可知な深淵にその根拠を持つのであるが、前者のものが、統一形式に従う発現過程の中で認められるのに対して、ここでは、その深淵の上に築き上げられる反省的な構築物と、深淵の中に潜む物自体とのずれにおいて認められて来るのである。そして、この反省的な構築物とは、反省内での思考作用によって認識されるものすべてである。
さて、我々は言葉の発明によって、認識されたものを伝達し、蓄積することが容易にできる為、人間の歴史が進むにつれて、我々が所有し得る知識の量も膨大なものとなり得るのである。
然し、それが己れ自身の思考によって実質的な内容を持たされ、体系付けられるのではない以上、そのような知識で作り上げられる構築物は、たとえ巨大なものであるとしても、ほとんど実質的な内容を欠いた空虚な認識のみをその支えとして持たざるを得なくなるのである。
そして、その空虚な構築物を何か実体であると見なし、その中に安住してしまうことから、一切の〈存在〉を支えているあの不可知の深淵などには注意が及ばなくなり、また、以前持っていたその深淵に対する直観的な察知能力も、徐々に退化してしまうことになるのである。
ところで、表象能力の高い状態を持つ子供時代においては、未だその反省的な構築物は充分なものではないとしても、その表象能力の高さによって物事の本質を直観的に察知することが出来、その不可知の領域を常に感じ取っているのであり、同様に、大人になっても、意欲に対して比較的高い表象能力を保ち続ける者は、己れの反省内で描き出される構築物に対して、常に不安を覚えているのである。
何故なら、その構築物が如何に立派で、高い認識に基づいて実質づけられ、体系づけられるとしても、その本性は現象であり、その背後には、我々には何ら規定し得ないあの深淵が控え、一切の構築物をすべて飲み込もうとしているからである。
そして、特に、己れの囚われた意欲に基づく構築物は、直にでもぐらつき出し、統一主体はその崩壊を予見することになるであろう。
即ち、そのような時彼は、己れ自身の囚われた意欲に仕えようとしている為、そこで築き上げられた構築物を必死になって守ろうとするが、然し、彼自身その構築物が幻であることを既に予感しており、その為、それを断乎守り通すことは出来ず、押し迫って来る深淵に強い不安を包きながら、その崩壊を待つことになる。
また、その構築物が己れの意欲を反映している為に、その崩壊は己れの死を帯び、その死から逃れようと様々な構築物をそれに代えて作り上げることになるが、然し、同じ囚われた意欲に基づくものである以上、それらは実は同じものでしか過きず、そのようなことによってでは、決してその死を克服することなど出来はしないのである。
真にその死を克服するには、進んでその死を迎え入れねばならない。己れの囚われた意欲に基づく一切の構築物を崩れるにまかせねばならない。己れの因われた意欲そのものが打ち砕かれ、己れの魂が解放されねばならないのである。
その時、情意の海が全く消え失せた内奥で、その統一主体は一体何を見ることになるのであろうか。
ところで、内的に見て、その不可知の深淵に燈される知性の光の消滅は、一切の〈存在〉の世界の消滅である。
確かにその知性の光の下では、己れの消滅後も依然として全宇宙は生成し続けることを、そして、その背後には常に統一的な何か或るものが有ることを、その上、その万有を統一する一者が、本当には己れの内奥に控え、この一切の〈存在〉の世界を統一しつつあることをも、描き出すことが出来るであろう。
然し、その知性の下で描き出される一者は、そのもの自体の影でしかない。その〈存在〉の世界から、その無としてしか規定し得ない不可知の深淵を覗き込むことでしかなく、積極的にその深淵の中に飛び込んで、そこに控える一者そのものを掴まえることではないのである。
その〈存在〉の世界に止まる限り、如何にその無としてしか規定し得ない領域がすべてであることを認識するとしても、その認識は、実質的な内容を欠き、全く虚しいものとしてそのまま終らざるを得ないであろう。
如何に「絶対性」が与えられるとしても、その〈存在〉の世界に止まる限り、それは相対的な影でしか過きず、やがて己れの消滅の時が訪れると、一切の〈存在〉の世界の消滅と同時に、その表されている一者の影もまた消滅しなくてはならないのである。
そこで、ここでは、その統一的一者そのものが控える彼の虚空に至る道を探り出さねばならない。彼の虚空を掴まねばならないのである。
その為、以下では、そのものに至るには如何なる道が与えられているのか調べてみることにする。
まず、反省的な認識の中では、前述通り、決してその統一しつつあるそのもの自体の姿に直接光を当て、それを掴まえることは出来ないと言わねばならない。
即ち、物質現象としての生成界では、その現象の背後に、一切を統一する抽象的な力を設定し得るに止まり、また、内的な精神現象では、直接内奥にて覚えられる情意や、直観的・反省的世界などの一切の〈存在〉を統一し表す、前者のものと同質な力を設定し得るに止まり、両者とも、それ以上のことは何ら積極的に規定し得ず、只無としてしか規定し得ない何か或るものがその深淵に控えていることぐらいしか表すことができないのである。
また、以前に我々は、様々な情意の波や渦を内奥において直接体現することによって、その万有を統一し発現させる一切の力を体現し、知ることができることを見て来たのであるが、然し、その知も、統一力そのものの体現に止まり、常に統一しつつあり、自身は決して統一されることのない彼の一者を体現し、掴まえることは出来ないままであると言わねばならない。
一切の魂は、彼の一者の吹き出す統一的な生命力の渦の中につながれ、その渦が形作る様々な波として、永劫に亙って泡沫の如く生じては消えてゆくしかないのであり、たとえ一切の統一力を体現するとしても、そこで知り得るものは、泡沫の如く刻々と変わりゆく魂の諸状態でしか過ぎないのである。
そしてまた、表象能力の高まりにおいて、天空を天翔けながら純粋な鏡となって、その働きかけて来るものを写し出す場合にしても、事は同様であると言わねばならないであろう。
その統一主体が魂の働きの一部として、一切を統一する彼の一者に支配され、従属を余儀無くされている限り、たとえ己れに働きかけて来るものを、全宇宙を翔け回って写し出すとしても、決して振り返ってその統一的一者の姿をそのまま写し出すことは出来ないのである。
天才が全宇宙を天翔けて、写し出し、描き出したものと言えども、それは、その一者そのものに対する暗示に止まるしかないのである。
従って、以上のことから、我々には決して彼のものに反省的な光を当てることも、またそのものを体現することも、そしてまた、そのものを写し出すことも出来ないと言わねばならず、結局如何なる方法によっても、そのもの自体を掴まえることは出来ないと言わねぱならないのであろうか。
ここにおいて我々は、形而上学の極点に立つ。
「統一主体の最内奥に有る虚空に超越者として座し、一切を統一しつつあるもの、それは一体何か。」
そこでもう一度、そのものに至る得る条件を、反省内で詰めながら調べてみることにしよう。
この場合の判断を成す究極的な指標は、一切の統一力の支配から己れの内容を保ちながら逃れ得るものの存否である。
まず、統一力によって統一され、意欲を持たされている魂そのものは、己れが存在しながら、しかもその統一力から逃れ出るようなことは出来ない。従って、そのようなものは、無闇な切迫の中で押し流されるだけで、決して虚空に至ることはないであろう。内的な現象においては、その魂の状態として表される情意の海は常に認められることになる。
次に、表象能力の整備によって生じる統一主体においても、それが魂そのものの働きの一部として、直観的・反省的世界を描き出す場合には、彼は依然としてその背後にある力によって統一され、それに従属し続ける。
また、表象能力の高まりの中で、統一主体が天翔けながらその働きかけて来るものを写し出す場合でも、それを統一するのは統一力でなければならず、従って、その飛翔も全く自由なわけではない。
そして、夢においては、統一主体は、様々な働きかけの中で、全宇宙を居乍らにして観ることが出来るとしても、それもやはり、あの統一力がそれらの様々な劇を上演させるのであり、彼は、己れの知性の光を消すまでは、その劇に縛りつけられたままなのである。
そして、やがてその光が消される時には、もはや彼は己れに働きかけて来るものを観ることはなくなるが、やはり統一力に支配されたまま、闇の深淵に休らい、漂うのである。
最後に、死においては、個体として発現して来た魂は、確かに己れの個体性を解消し、そこで持たさせられて来た一切の意欲から解放されることになるが、然し、だからと言って、彼の虚空にそのまま帰るというわけではないのである。
その「死」として表され、示されるものも、統一力の成す単なる幻でしか過きず、解消する魂は、統一力そのものが形作る全体としての大きな渦の中に、個体性から切り離されて投げ込まれ、その渦と一体となるのである。
従って、その場合の「死」とは、統一力が持つ生命の渦の一つの波の状態でしか過ぎず、その波の変化によって、再び魂は個体性を取り戻して、己れの発現を繰り返さねばならなくなるのである。その為、我々万有とは、決して《死ぬ》ことの出来ない不幸な存在であると言うこともできるのである。
また一方、統一主体は、その死の中で、統一力の支配から逃れ得る可能性を持つことになるのであるが、己れ自身が魂そのものの働きの一部である以上、その魂の解消と同時に己れも消滅しなくてはならず、従って、やっと統一力の支配から逃れるとしても、そのまま知性の光を保つことは出来ず、振り返ってその深淵に控える一者そのものの姿を写し出すことができないまま、闇の深淵の中に無となつて消え去るだけであろう。
以上のことから、この生命の渦の中に存在する一切のものは、統一力によって常に統一・支配され続け、決して彼の虚空を掴まえることなどできはしないと、このようにやはり断言せねばならないのであろうか。我々にはそのものに至る一切の道が閉ざされていると、このように断言せねばならないのであろうか。
このようにして、虚空を掴まんとしながらも、結局は残念せねばならなかった人々もいるのである。
然し、我々はここで、最後に述べた死の中でのあの可能性に就いてもっと調べてみる必要があるであろう。その中でしか可能性はなかったからである。
さてそこで、我々はあの時、通常の魂の解消としての死を想定していたのであるが、はたして死はそれのみに限定されるものなのであろうか。
そのまま魂が己れの個体性を解消してしまわなくとも、それと似たような現象として、魂の発現に伴う意欲がある瞬間途断えてしまうような場合にも、死の影を認めることができるのではないのか。
セックスの後に訪れるあの意欲の急激な減退も、また、目的のものを手に入れることができなかった時に味合う気落ちなども、すべてその死を連想させるのである。
そして、強烈に意欲するものほど、その意欲が打ち砕かれた時に味合うその死の影は、より大きなものとなるのである。
然し、意欲が依然として残っている限り、統一主体は再びその同じ意欲に基づいて世界を描き出してゆくであろう。手に入れることのできなかったものに対して合理化し、別の新たな意欲の対象や目的を作りだして、それらを追い求めてゆくであろう。
ところで一切の意欲が打ち砕かれる場合には、一体彼はどうなるのであろうか。
その時こそ初めて彼は、一切の意欲から切り離され、あの統一力の支配から逃れ出て、虚空に漂うのでなければならない。
その時こそ我々は、此の世の一切の輪廻に終止符を打つことの出来るあの《死》を手に入れるのでなければならない。
恐らく彼は、強烈な意欲を持って物質的欲求を発現させているのかもしれない。
その欲求の対象を飽くことなく追い求めて、その障害となるものはすべて否定し、利用できるものはすべて利用して来たのかもしれない。
然し、やがて、その欲求の対象が影としての性質しか持たないことを知る時が来るのだ。
その時、その盲目的な切迫の中で意欲が打ち砕かれ、初めて統一主体は一切の支配から解き放たれ、虚空に漂い、彼の一者そのものの姿を写し出すのだ。
その時、今まで情意の海を激しく掻き立て、濁らせていた意欲が打ち砕かれると、正にその刹那、それまで黒雲と雷雨によって飛翔を妨げられていた統一主体は、そのまま、激しい情意の海も、黒雲も、雷雨も、すべて消え失せた全くの真空の真只中に、只一人ぽつんと残されるのだ。
そして、その中に漂いながら、全く血の気の失せた光で一切の事物の本質を写し出し、意欲そのものの持つ虚しい性質をはっきりと自覚するのだ。
また彼は、強烈な意欲を持って性的欲求を発現させているのかもしれない。その欲求の対象を、死を賭してまで恋い求めているのかもしれない。
その時、激しく慌れ狂う情意の海の天空を、統一主体は夫翔け、己れの破滅を予見し、それを願いながら対象を求める。
そして、その対象が正に手に入らんとし、情意の海が怒涛となってその天空すべてを飲み尺くそうとする時、その欲求の対象が己れの影としての性質を告げ、その意欲すべてを打ち枠いてしまうと、その情意の海が怒涛となつて統一主体を至高の高みに押し上げ、正に飲み込まんとするその刹那、その怒涛は全く粉々に打ち砕け、そのまま虚無の中に消え失せてしまい、その時点において至高の高みに押し上げられていた統一主体は、高められた光を保ちながら、そのまま全くの真空の中に超出し、その中に漂うのである。
その残照が放たれた虚空の中で、その刹那、全く純粋な鏡となって彼の一者そのものの姿を写し出すのである。
強烈な意欲を持つ魂は、此の世の一切のものを手に入れようとする。その意欲の下で、己れがすべてであることを主張する。
然し、此の世の一切のものが影として己れの元から消え失せ、己れの一切の意欲が打ち砕かれてしまう時、その時こそ、初めて彼は、統一力の成せる此の世の輪廻の鎖から解き放たれ、虚空に漂い、その決して統一されることのない全く風の止む真空の中で、解放された永遠なる喜びに満たされるのである。
そして、また再び、その統一力によって此の世に吹き戻され、その輪廻の鎖の中につながれることになるとしても、今度は、その虚空の中で心眼となつて開示され、燈されるに至った霊光を頼りに、此の世の一切のものを無と見なし、それまでは無としてしか思われなかったその虚空を常に見据え、掴もうと追い求めてゆくのである。
ところで、高い表象能力を持ちながらも、魂の脆弱なものは、己れの内に照し出されて来る実在的な世界に対してのみならず、己れが生命を持って様々な魂の状態を発現してゆくこと自体に対しても、虚しさを常に持ち、何らかのちょっとした切っ掛けから一切の欲求を否定して、世俗から離れた所で己れの生を全うしようとすることであろうし、極端な場合には、自ら死を選ぶこともあるであろう。
然し、そのような死を選んでも、決して《死》に切れることはあり得ず、統一力による輪廻の波に弄ばれることになるだけである。
然るに一方、壮健で、強烈な魂は、たとえ一切のものの虚しさを知ったとしても、やはり己れの生を肯定せざるを得ず、どうしてもこの苦悩の世界に愛執せざるを得ないのである。やがて、意欲に基づく様々な激情の状態が、己れの意向にかかわらず発現されて来るのである。
それにもかかわらず、己れの意向としての諦観を固持しようとするのは、反省内での当為によって、己れの内に根差す生命力を絞殺することにほかならず、そのまま生ける屍となることである。
然し、彼は、すべての虚しさを知りつつも、此の世界を愛さざるを得ず、己れ自身を愛さざるを得ないのだ。
否、却ってこの苦悩の極点において、己れ自身を解放することを、虚空を掴むことを願っているのだ。
その瞬間においてしか己れを満たすことができず、他のものでは如何なるものによっても満たされることのないほど、それほどまで絶対的な自由性を心の内に燈されているのである。
それ以降、その虚空を見据え、此の世の一切のものの虚しい性質を知りながらも、新たな意欲の下でその対象を追い求め、己れ自身を賭けてゆくのである。然し、今度は、その影としての対象に因われることなく消えるにまかせるのである。運命として示される彼の一者の統一力に支配されながらも、軽やかに己れ自身の舞踏を踊り、一者の一切の意志を体現するのである。
彼にはもはや、何らの希望も目的もないであろうし、また、執着すべき何らの対象も持つことはないであろう。只、己れ自身の舞踏を軽やかに踊り切ること、その舞踏の中で、一者の叡知的な世界を無限に透明なものとして体現してゆくこと、そのことのみを願うだけである。
その時、彼の内奥に秘められたあの情意の海は、底無しと思われるほど深まり、苦悩の色を湛えながらも無限に透明な輝きを持ち、その表面には、あの子供の頃に生じていた無邪気な波の戯れが再び生じて来て、その海の深いふところに支えられながら、縦横無尽な舞踏を繰り返すことであろう。
第四部 内奥における情意の海と天空ーーーおわり