1.はじめに
関東以西の平野部の普通種採集派の方々にとっては、今や河川敷におけるヒラタ採集の季節の真っ只中ですね。 ところが、なかなか思うようにいかないのが、幼虫の同定。汗を流しながら割り出した幼虫が、ヒラタなのかコクワなのか、 はたまたノコなのか、判別できないとなると、フラストレーションが溜まる一方です。 とりわけ、ヒラタと信じていた幼虫が後でコクワに蛹化・羽化したとなると、やるせない思いでいっぱいになってしまいます。 3月にもなると、東海地方以西の地域ではヒラタ幼虫はそれなりに成長するので、大きさからだいたい判別できるようですが、 関東地方ではなかなかそうはいきません。なにせ、ヒラタ♂の成虫といえども、30-40mm台が普通サイズなのですから、 コクワとさほど変わらないのです。
幼虫の同定といえば、この「クワ馬鹿」において顔面の接写写真による図鑑がcoelacanthさんによって既に掲載されています( →全国共通指名手配犯人顔写真)。 また、あ~さんの採集記をはじめ、さまざまな方々のHPにて幼虫の顔の写真をアップで観察することが出来ます。 しかし、こうした先達による役に立つ画像を見つめて勉強を重ねても、パソコンもない野外で出くわした幼虫を自信をもって同定することは、 なかなか難しいというのが現実ではないでしょうか。
そこで、特にヒラタ狙いの採集向けに、平野部の地中の材によく見られるヒラタ、コクワ、ノコ幼虫の同定について、 特にヒラタとコクワの識別を中心に、独断と偏見に溢れる手引きの作成に挑んでみました。 同定の対象は、3令幼虫で、特に頭幅が7~8mmくらいの大きめのコクワ幼虫サイズを念頭に置きました。 そのくらいの大きさの幼虫が最も同定に悩みやすいと思われたからです。
できるだけ実践的な手引きとすることを心がけたつもりです。しかしながら、まだまだ勘違いなどがあるかもしれません。 また、他にも決定的な要素があることを、見落としているようにも思います。ご意見をお寄せいただければ、 今後、どんどん改良していきたいと考えております。
まずは、それぞれのクワガタ幼虫の顔面写真と、手描きの下手な図ですが、顔面イメージ図を並べたものをご覧下さい。
| ヒラタの頭 (画像撮影&提供:モグどん氏) | |
 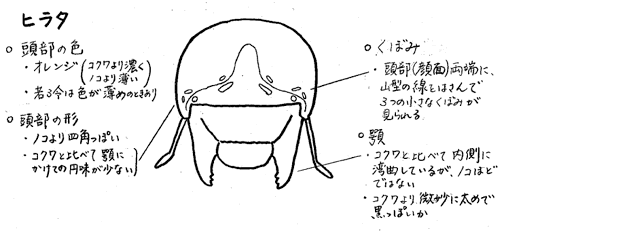 |
|
| コクワの頭 (画像撮影&提供:モグどん氏) | |
 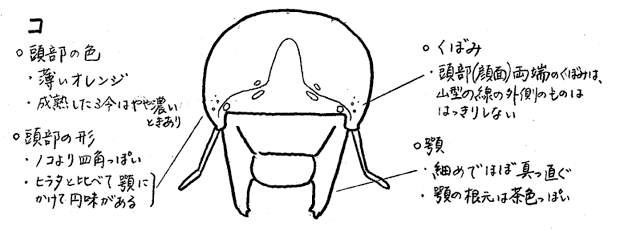 |
|
| ノコの頭 (画像撮影&提供:石井孝親氏) | |
 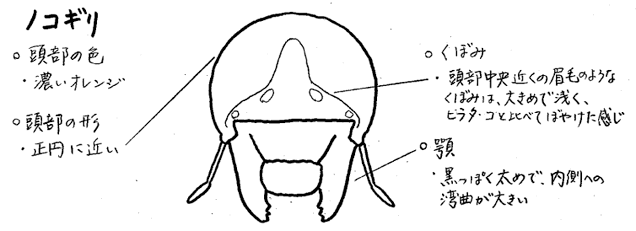 |
|
頭部(顔面)の特徴については、実は上記の図でほとんど語り尽くされているのですが、重複部分も含めて、以下、解説を試みます。
2. 頭部(顔面)の特徴
(1) 頭部の色
ヒラタ幼虫の頭部の色は、コクワより濃く、ノコ(オオクワ)より薄いオレンジ色であることは、ご存じのとおりと思います(注1)。 ただし、ヒラタの3令初期の頭部の色は薄めで、成熟するにしたがって濃くなるように感じられます。 したがって、ヒラタ若3令とコクワ成熟3令とでは、大きさだけでなく頭部の色にもさほど差がないことに注意する必要があります。
一方、ノコの頭部の色は、赤に近いくらい濃いオレンジ色です。
![[ヒとコ]](020126hirata_ko2.jpg)
左がヒラタ、右がコ。写真では色の違いは判りにくいですね
- (注1)
- 実は、わたしが奈良県で初めて採集したヒラタ幼虫は10gを優に超えようかという大きな3令幼虫でしたが、 その頭部はコクワ幼虫のように薄いオレンジ色でした(結局この幼虫は61mmの漆黒の♂に羽化)。 他の同定ポイントにも共通することでしょうが、何事にも例外がありうるということに、常に注意が必要だと思います。
(2) 頭部の形状
ヒラタ幼虫の頭部の形状は、ノコよりもやや四角っぽいのですが、コクワの頭部とはなかなか見分けがつかないほど似ていると思います。 しかし、下の写真をよくご覧いただくとお分かりになりますでしょうか、大顎の根元にかけての頭部の側線の丸みが、 ヒラタの場合はコクワより若干少ないように見えます。ただし、たいへん微妙な差であり、わたしがそう見えるだけなのかもしれませんので、 これのみをもって幼虫を識別することはちょっと難しいでしょう。
![[ヒの顔面]](mogu_hirata1.jpg) | ![[コの顔面]](mogu_ko1.jpg) |
| ヒラタの頭 | コクワの頭 |
| 画像撮影&提供:モグどん氏(再掲) | |
一方、ノコの頭部は正円に近い形状をしており、ヒラタやコクワと見分ける上で大きなポイントとなると思われます。
![[ノコの顔面]](noko_ishii.jpg)
ノコの頭はほぼ正円ですね
画像撮影&提供:石井孝親氏(再掲)
(3) 頭部(顔面)のくぼみ
このポイントが当記事のハイライトです。わたしはヒラタ幼虫とコクワ幼虫を、主に頭部の「くぼみ」(ディンプル)の違いを頼りに、 識別に努めているところです。そのくぼみとは、頭部中央あたりに凸型の線を挟んで二対ずつある眉毛模様のくぼみではなく、 顔面両端の口元近くにあるくぼみです。上の顔面イメージ比較図をご覧いただくのが最も早いのですが、ヒラタの場合は、 顔面両端の大顎の根元近くに、3つのくぼみ(凸型の線の内側に1つ、外側に2つ(注2))が見られます。 これに対して、コクワの場合は、凸型の線の内側に1つ明らかなくぼみが見られる一方で、 凸型の線の外側のくぼみはヒラタほどはっきりしておらず、いくつかの小さな点刻の集まりのように観察されます(下の写真参照)。 この違いは、例えば野外で採集した時においても、ルーペなどを使って注意深く観察すれば、識別可能だと思います (もちろんルーペがなくても観察可能です)。
なお、ノコ幼虫については、頭部中央の眉毛模様のくぼみは、ヒラタやコクワと比べると大きくややぼやけたような感じに見えます。 顔面両端のくぼみは、凸型線の外側のものは冒頭イメージ図では描かれていませんが、コクワに似て、いくつかの浅い小さな点刻が観察されます。
- (注2)
- ヒラタの凸型線の外側の2つのくぼみは、下の写真のとおり、「ハ」の形をしている場合が多いように見られます。 ただし、若3令幼虫の場合には、必ずしも「ハ」に見えない場合もあるようです。
 |  |
- (注3)
- こうしたヒラタのくぼみの特徴は、累代飼育中のヒラタ幼虫の顔面を何度も観察して見つけたものですが、 この方法でヒラタと同定した野外採集幼虫の一つ(東京23区内産)が、このほどヒラタ♂に蛹化しました。 今後、他の採集幼虫の蛹化・羽化によって、同定の実証事例が積み重なっていくことを期待しています。
![[コのエクボ]](020310ko_ekubo.jpg) |  |
![[コの顔面]](ko_ishii.jpg) |  |
(画像撮影&提供:石井孝親氏)
![[ノコのエクボ]](020316noko_ekubo.jpg) |  |
 | ![[オオの顔面]](oo_ishii2.jpg) |
(画像撮影&提供:石井孝親氏)
(4) 大顎の形状
ヒラタ幼虫の大顎は、コクワのそれと比べて、やや太くて黒く、先端の内側への湾曲があるように観察されます。この特徴は、成熟した3令幼虫ではかなり明らかであると思います。 しかし、小さめの幼虫の場合には相当に微妙であり、とくに野外の採集時においては、なかなか同定の決め手とはなりにくいように感じています。
![[ヒとコ]](020126hirata_ko1.jpg)
中央がヒラタ、その両側がコクワです。小さめの幼虫では、大顎の違いは実に微妙です
![[ヒの顔面2]](mogu_hirata2.jpg)
ヒラタ幼虫は、成熟すると大顎が黒く目立ってきます
(画像撮影&提供:モグどん氏)
一方、ノコ幼虫の大顎は、ヒラタよりさらに太くて黒く、大顎全体の内側への湾曲が見られるため、 注意深く観察すれば識別が可能と思われます。
![[ノコの顔面]](020130noko_kao.jpg)
ノコの太い大顎
(5) 凸型の縫合線
顔面に走る凸型の縫合線(?)の形状が、ヒラタの場合はコクワに比べやや平たいのではないか、との見方があります。 上の写真などで比較すると、たいへん微妙ながらそのような特徴が見てとれるように思います。
3. 気門の特徴
気門の形状は、ヒラタ(コクワ)とノコとを識別する大事なポイントの一つとなりうると思います。下の写真のように、 ヒラタの気門は"C"の形に近いのに比べ、ノコの気門は"["または"「"のような形をしています。 (ただし、ヒラタがまだ若い3令幼虫の場合には、"C"が縦長に見えて同定に迷うこともあります。)
一方、ヒラタとコクワの気門の差については、残念ながら今のところ有意な違いを見出していません。 ヒラタとコクワでは、気門の色が違う、という見方もあるようです。
![[ヒの気門]](hirata_kimon.jpg) | ![[ノコヒの気門]](noko_kimon.jpg) |
| ヒラタの気門 | ノコの気門 |
4. その他の特徴
(1) 白斑
ヒラタ幼虫は、♀だけでなく♂でも尻から3節目に白斑が見られる場合が多いと観察されます。 したがって、♂と思われるような頭幅の大きめの幼虫で、白斑が確認できる場合は、ヒラタである可能性が高いのではないでしょうか。 仮にその個体が♂でなくとも、大きい♀であれば、ヒラタへの期待が高まります。
(2) 腹部内の色
冬期採集においては、腹部や尻の中が透明な液体で満たされている幼虫個体をよく見かけます。 これは、不凍液によって体内の凍結を避けているためであると、どこかで読んだことがあります。 これまでの乏しい野外観察を踏まえれば、このように腹の中が透明な幼虫は、少なくとも関東平野部では、令を問わず、 おおむねコクワではないかと思っています。また、コクワは、食べ物が詰まっていても、腹の中の色に微妙な透明感があるように思われます。
これに対して、ヒラタは、食べている材にもよるでしょうが、冬期においても、 「ピンクや紫に染まった乳白色」(リュージョン氏によれば、薄皮饅頭のような色)とでも言うような腹の色をしているように観察されます。 コクワのような透明感をもった腹の色が観察されたことはありません。 ただし、ヒラタ幼虫も腹の中を不凍液で満たして越冬する場合もあると聞いており、この点はさらに検討していく必要があると考えています。
(3) すわりダコ(尻の形状)
俗に言う「すわりダコ」(尻の形状)がヒラタとコクワで違った特徴を持っているという見方があるようですが、 詳しくは未だ観察できていません。この点も、よいご意見があれば、加筆していきたいと思っています。
(4) その他
ヒラタ幼虫は、手でいじったりして刺激すると、茶黒い液を吐き出すことが多いとの見方がありますが、 これも同定の上での補助的なポイントとなるかもしれません。その他、頭部の毛穴、尻の毛穴なども同定の要素となりうる、とのご意見を伺っていますが、 自分自身未だ勉強不足です。何か判れば加筆したいと思います。
5.まとめ
以上が、わたしが経験不足ながら現時点で提示できる、ヒラタを中心とする幼虫同定のための要点です。 繰り返しになりますが、ヒラタ幼虫とコクワ幼虫の識別については、 頭部の色や大顎の形状などに加えて、頭部口元両端の「くぼみ」(いわば「エクボ」)の違いが「使える」ポイントではないかと考えています。 ノコ幼虫については、頭部の色や大顎・気門の形状などが、同定上の主なポイントとなるのではないでしょうか。
6.おわりに
いろいろグダグダと書いてきましたが、なんと言っても同定においてまず第一に重要なことは、 幼虫の姿を見たときの第一感(直感)なのでしょう。瞬時の総合判断と言い換えることができるかもしれません。 大きさ、体色、動き、それらすべてを合わせた全体的な様子を直感的に感じ取るのです。 そして、この直感の力を養うためには、コクワ幼虫ばかり沢山割り出してしまうという、誰しも一度は必ずする経験が、 実はたいへん役に立つように思います。そのような経験の積み重ねの結果としてはじめて、コクワ以外の幼虫に出会ったときに、 「あ、コクワではない」という直感が働くのであり、そうした直感というのは、誤らないことが多いのだと思います。 上に掲げた同定の要点というのは、あくまでもそうした直感を事後的に確認するためのものにほかならない、と考えています。
![[ヒラタとノコとコ×2]](020310hirata_ko.jpg)
左上がノコ、左下がヒラタ、右2頭がコクワ
これから春が深まるにつれて、材の中の幼虫が成熟度を増し、①ヒラタ幼虫がコクワ幼虫と見分けが付くほど十分大きく育っている、 ②ヒラタ幼虫の頭部の色がコクワ幼虫と見分けが付くほど十分濃くなっている、といった可能性がますます高まるので、 ヒラタ幼虫同定の苦労は冬期ほどではなくなるかもしれません。しかしながら、上記の手引きが、 皆さんの採集時に少しでもお役に立てば、たいへん嬉しく思います。
なお、この記事を書くにあたり、石井孝親氏(プロ写真家)、モグどん氏から幼虫頭部の接写写真の提供を、ピーコ氏、リュージョン氏、 コダック氏、えりー氏をはじめ、多くの方々からヒラタ幼虫の同定についての貴重なコメントを頂戴いたしました。 また、記事の編集に、ピーコ氏と爆発栄螺氏より多大なご協力をいただきました。厚く感謝申し上げます。
誤りや追加的な情報があれば、随時訂正・加筆していくつもりです。ご意見をお寄せいただければ幸いです。