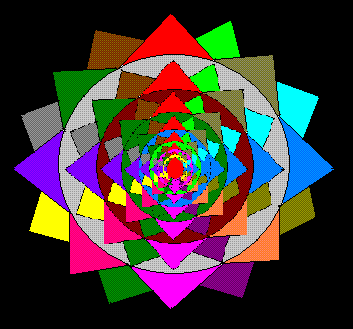
気功の穴
象気功
気功入門
|
タントウコウ さてさてさて、「タントウコウ」である。 あたしが、ここでゆー「タントウコウ」は「三円式」あるいは「三円功立禅」である。 「意拳」なんかでゆーところのいわゆる「立禅」である。 つまり立って「禅」をするわけである。 最近では比較的一般化して、けっこう格闘技の世界ではやる人が多いのであるが、これでなんで格闘技が強くなるかということは後半で解説するので、まあ、とにかくその方法を説明するわけである。 1、足を肩幅に開いて立つ。 足先はだいたい並行がいいのである。 平行というのは足先を内側に向ける外旋である。 立ち方には足先を外向きにする内旋と、足先を内向きにする外旋があるのであるが、外旋は武道にある立ち方で、空手のサンチンや太極拳などもこの立ち方であるのである。 2、足裏の親指の付け根から小指の付け根までの前足部に体重を置く。 3.ひざを緩める。 要するにひざを軽く曲げて立つのである。 まあ、どのくらい曲げるかとゆーと、らくーな程度とゆー人もいるし、高い椅子に腰掛けるようにとゆー人もいるし、もっと深くとゆー人もいるのであるが、あたしはまあ、できるだけリラックスできる範囲内とゆーのが妥当じゃないかと思うのである。 4、肩を緩めて手の平を胸の前で輪を作り、手のひらは丹田方向に向けるようにする。 指先は30センチぐらい開く。 まあ、この指先の広さについても、体の大きさによって違うのは当然なので、20センチでも30センチでもいいのであるが、胸の前で大きな風船を持っているとゆー感じの開き具合である。 5、手は指の間をらくに開いて太い樹木を抱くか、大きな風船を持っている感覚を持つ。 これが、タントウコウの氣を作る主軸をなす要素をなるのである。 手からの氣で体内の氣道を開くのである。 6、丹田に意識を置き全身を緩めてそのまま立ち続ける。 まあ、緩めるのと力を抜くのは本来は違うのである。 力を抜くのは文字通り力を抜くわけであるが、緩めるというのは「氣道」を開くということであるのである。 全身の氣道の管の空洞管を実感することであるのである。 その管をより太くし、全身の血行血流を改善し、体調を改善し、さらには脳のちょーしを改善しようてなことが気功法の目的であるのである。 以上である。 写真か絵を載せないとまるっきりの素人には何がなにやらさっぱりわからないとは思うが、象気功はめんどくさいので例によって絶対に図解なんかしてやらないのである。 タントウコウのやり方なんてもんはべつにあたしが唾を飛ばして説明せんでも世間には知ったかぶりがいくらでもいるので、誰も解説していないその先を解説するのが象気功の象気功たるゆえんなのである。 ううむ、なにを言いたいのはわからんがそーゆーことであるのである。 それで、まあ、何はともあれどのくらい立ち続けるかとゆーと、「お好きなだけ」である。 あたしの友人は毎日これを3時間やっている。 その上、 「タントウコウは瞑想であるので、やっているときは心を沈めて、断じてテレビを見ながらやったりラジオを聴きながらやったりしてはいけない」 とゆーのでたーだ毎日3時間立っているのである。 あたしゃまっぴらごめんである。 短い人生でほかにいくらでも面白いことがあるのに、たーだ立ってるのは馬鹿丸出しである。 まあ、それはともかく、これを毎日定期的に続けていると、氣道が太くなって、あるいは氣道の詰まりや締りが改善されて、毛細血管が開き、身体の隅々まで血液が行き渡り、酸素・栄養素が運ばれて、身体も脳も快調になるわけである。 これは要するに毛細血管が開いて血行がよくなっているということなんである。 タントウコウは前に輪を描いた手からの氣で氣道を際限なく開くわけである。 まあ、効率は悪いのであるが、立つだけであるので、数時間でも可能であるので、時間をかけて氣を養う、つまり、氣道を広げることができるわけである。 氣道が広がれば氣は高まり強くなるのである。 その先には怒涛の氣の放出もあるわけである。 それが発勁であり空勁であるわである。 それはともかく、氣に関しては、「手」が重要なのである。 たいていの人は氣を一番最初に「手」から認識するのである。 人間の脳の発達はこの「手」を使うことから始まったわけである。 実に脳の運動野の60%が「手」で締められているそうである。 だから、「手」は神経がものすごく張り巡らされているので、ものすごく敏感にいろいろな感覚を感じることができるのである。 この手の氣に対する感覚がわかってくると、「手」を通して太陽神経そうや他の臓器へ気が通じているのがわかるようになるのである。 それで、タントウコウを続けていると、発生した氣で氣道が広がり、細くなったり通りにくかったりする部位に氣が集まってそこを通ろうとするので、ちょうど気功師が治療で氣を送ったときのように、勝手に手足が動いたり跳ね回ったりする人もいるのであるが、あまり激しく動くときは止めて様子をみた方がいいのである。 続く。 |
Copyright (C) Zoukikou All Rights Reserved 無断転用転載厳禁 プライバシーポリシー Contact