�@
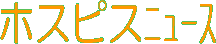 �@
�@�@�@�v�@�� �| �� ��
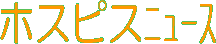 �@
�@| �@�z�|��>��w�g�s�b�N�X>�z�X�s�X�j���|�X>�o�b�N�i���o�|�ƭ->�v���|���� |
| ���҂̂��a�́C���C����������Ō�t�ɂ�镡���I�ȉ���ɂ���ĉ��P���� |
|---|
| �@���҂��C�}����s���������Ƃ͈�ʓI�ł��邪�C���̈ꕔ�͂��a�Ɛf�f����郌�x���ɒB����ꍇ�������B�������C���҂̂��a�́C�C�t����Ȃ��܂܌��߂����ꂽ��C���Â���Ȃ��܂܌o�߂��邱�Ƃ������ł���B �@����C���҂̂��a���Âɂ��ẴG�r�f���X�͖R�����C�L���Ȏ��Ö@�ɂ��Ă̌����͂قƂ�ǂȂ���Ă��Ȃ������B�p����Strong��́C����Z���^�[�ɒʂ����҂�ΏۂɁC�Ō�t�����{���邤�a�ւ̕����I�Ȏ��É���̌��ʂ��������B �@�Ō�t�ɂ����ʂȉ���ɂ���āC���҂����a�ł��邱�Ƃ����o���C�Ώ��Z�\��g�ɕt���C��t�Ƃ��a�ɂ��ẴR�~���j�P�[�V������}�邱�ƂŁC���a�ɑ��ēK�Ȏ��Â��{����C���҂̗}���C�s���C���ӊ��̏Ǐy�����ꂽ�B �@����̌����ł́C�ʏ펡�Âɂ����Ă��S����ɂ��a�ł��邱�Ƃ�����Ă���C���̌��ʂƂ��āC���߂�����Ă������a�ɑ��鎡�Â��J�n���ꂽ�\��������B���������āC����ɂ����ʂ́C���ۂ̌���ł͂���ɍ�����������Ȃ��B �@�{�����ł́C���҂ɑ�����ʂȉ�����C�����^���w���X�̐��Ƃł͂Ȃ��C������Ō�t�����{���Ă���_�͒��ڂ��ׂ��ł���B����f�ÂɃ����^���w���X�̐��Ƃ��펞�������������邱�Ƃ͖]�܂����̂�������Ȃ����C�l�I�������Ìo�ϓI�Ȋϓ_���炷��ƁC���ۂɂ͂��̂��߂̃n�[�h���͂��Ȃ荂���B �@�ނ���C����̌����ōs��ꂽ�悤�ɁC����f�Âɕ��i�g����Ă���X�^�b�t���P�����C�����̈�Î��������p���Ȃ��炤�a���Â̌��ʂ��I�ɍ��߂Ă������Ƃ̂ق��������I�ł��낤�B�����������f���́C���҂ɂ����邤�a���Â݂̂Ȃ炸�C���̑��̂�����g�̎����ɍ������邤�a���Âɂ��K�p�ł���\��������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N7��10�� |
| ��13����{�ɘa��Êw��@�Ǐ�ɘa�̂��߂̍ŐV�̋Z�Ƃ��̊��p�@��T�� |
| �@����ɔ����S�g�̋�ɂɑ���ɘa��Â̗����x�ꂪ�w�E����Ă���B�É��s�ŊJ���ꂽ��13����{�ɘa��Êw��̃��[�N�V���b�v1�u�W�w�I�I���R���W�[�F�Ǐ�ɘa�ɂ�����ŐV�̋Z�v�ł́C�ɘa��ÃX�^�b�t�Ƃ��Ēm���Ă�������"�ŐV�̋Z"�̊T�����Љ�ꂽ�B �����Ǒ�@�܂������N�����Ă��邩�𖾂炩�ɂ���w�͂� �@�ɘa��Â��銳�҂ɋN���銴���ǂ͈��������Ȃǂɍ���������̂������C�s�������Ƃ͗l�����قȂ�B�É������É�����Z���^�[�����ljȂ̑�ȋM�v�����́C�ɘa��Âɂ����銴���ǂ̂������ɑΏ��ɒ��ӂ�v������̂Ƃ��ăJ�e�[�e���֘A���������ǁC�P���w���y�X�ɂ��S���E�畆�����ǁCC. difficile�֘A�����Ȃǂ������C���̋�̓I�ȑΏ��@����������B�܂��������́C�ɘa��Âɂ����銴���ǂɂ��܂��Ώ����邽�߂̕��@�Ƃ��ẮC�u�܂��C�����N�����Ă��邩�𖾂炩�ɂ���w�͂����߂���v�Əq�ׂ��B �K�Ȑf�f�Ǝ��ÂŏǏ��P����Ǘ�͑��� �@�ɘa��Â̌���ł́C���҂��ˑR�C�����s���̔��M���N�������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B��ȕ����́u���̌����Ƃ��Č����Ƃ��ꂪ���Ȃ��̂ɃJ�e�[�e���֘A���������ǂ�����v�ƌ����B����̓J�e�[�e���̗��u���ʂ����S�Ö����������ɂ�����炸���ǂ���B���M�C������ɂ����ŋǏ������ɖR�������Ƃ��������C�t�Ɍ����C�Ǐ������ɖR�������M�ł̓J�e�[�e�������ǂ��^���ׂ����ƌ�����B�����Ȍ����������Ƃ��Ă̓��`�V�����ϐ����F�u�h�E���ہiMRSA�j�Ȃǂ̃O�����z���ہC�Δ^�ۂȂǂ̃O�����A���ۂ���������B�f�f�͌��t�|�{�ɂ��m�肷��B���Â̓J�e�[�e���̔��������ŁC�R�ۖ�Ƃ��Ă̓o���R�}�C�V���ɃZ�t�F���n��Ȃǂp����B �@�ɘa��Â̌���Ŕ�������P���w���y�X�����ǂɂ́C�Ɖu�}����X�g���X�̉e���Ȃǂ���C����߂ďd�ĂȂ��̂������B���������Ċɘa��Âɏ]�������t�́C�����납�炱�̂��Ƃɗ��ӂ��C���������d�ĂȃP�[�X�ɑ������Ă������ɑΏ����邱�Ƃ����߂���B �@�ɘa��Âɂ�����@�����ǂ̉����̍ő�̌�����C. difficile�����ł���B�f�f��C. difficile�g�L�V�������ɂ�邪�C���ꂪ�A���ł�C. difficile������ے�ł��Ȃ��m���͍����B���������āCC. difficile������z�肵���f�f�I���Â��e�F����Ă���B���Âɂ̓��g���j�_�]�[����o���R�}�C�V���̓��������������B �@��������́C����܂łɊɘa��Â̌��ꂩ�犴���ljȂɊ�ꂽ�R���T���e�[�V�����̗��R�͂��C�ɘa��Âɂ����銴���ǐf�Âʼn������ƂȂ��Ă��邩���������C���̐��тɂ��ďЉ���B �@����ɂ��ƁC���v105���̃R���T���e�[�V�����̂����R�ۖg�p���53���C�R�ۖ�g�p���52���ł������B�R�ۖg�p��̂���36���́u�����ǂ��ǂ����킩��Ȃ��v�Ƃ������̂ŁC17���́u�K�Ȏ��Â��킩��Ȃ��v�Ƃ������́B�R�ۖ�g�p��̂���43���́u���Â��������P���Ȃ��v�Ƃ������̂ŁC9���́u���Ò��ɐV���Ȗ�肪���������v�Ƃ������̂ł������B�܂�C�R���T���e�[�V�����̂����̂��Ȃ�̕������C�u�����N�����Ă���̂��킩��Ȃ��v�Ƃ������R�Ő�߂��Ă��邱�ƂɂȂ�B �@���Ȃ݂ɁC�����ljȂւ̃R���T���^���g���105���̏Ǐ�̕ω�������ƁC64���ɉ��P���F�߂�ꂽ�B���Ȃ킿�C�����ǂƐf�f���t���C�K�Ȏ��Â��s���C�����̏Ǘ�ŏǏ��P���邱�Ƃ������ꂽ�B �@�ȏ�̐��т����āC�������́u�ɘa��Âɂ����銴���ǂɂ��܂��Ώ����邽�߂ɂ́C���̑���E�������肷��C���炩���ߌX����m���Ă����ȂNJ����ǐf�Â̊�{�Ƃ������ׂ��w�͂�����ɋ��߂���v�Əq�ׂ��B�܂��C�������́C�����Ǘ\�h�ɂ͉@����������d�v�ł���ƕt���������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N11��6�� |
| �]��ᇂɔ������ɂ͑��߂̑Ή����@���ɁE�Ă�l����E����� |
| �@�]��ᇊ��҂̑����ł͍����I���Â����݂����C���҂̗]���͒Z�����Ƃ������B�P������w�ɘa��ÉȂ�Heidrun Golla���m��́u�]��ᇂł͓��W���Ƃ�������ꂽ�X�y�[�X�Ŕ]����������邽�߁C�Ǐ�͂���߂ďd���C�����i�K����ɘa�P�A�̎��{���������ׂ��ł���v�Ɣ��\�����B �X�e���C�h�̓K�������I�Ɋm�F �@�������]��ᇂ܂��͓]�ڐ��]��ᇂ̊��҂ł́C���ɁC���S�C�q�f�C�Ă�l����C��ჁC���o��Q�Ȃǂ̐g�̏Ǐ�ɉ����C�l�i�̕ω��C�F�m��Q�C�ӎ���Q�C����ςȂǂ̏d�����_�Ǐ����������B �@�g�̏Ǐ�ɂ��ẮC�]��ᇊ��҂̖�50���ŋْ��^���ɗl�̓��ɂ���������B��ᇂ̑��B�C����C�܂��͐��t�̏z��Q�ɂ���Ĕ]�����㏸����ɂ�Ēɂ݂���������B��ᇂɂ��]����͌��ǐ�����ł���C��ʂɃX�e���C�h��i��@�f�L�T���^�]��4mg/���j���t������B�������C����p���X�N�����ߐT�d�ɓ��^���C�K���ɂ��Ă͒���I�Ɋm�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�X�e���C�h���^������ɂ��\���Ɍy�����Ȃ���ΐ��E�ی��@�ցiWHO�j������i�K�I���@�ɏ]�����u�Ɋɘa�����݂�B �@�����̔]��ᇊ��҂ł́C�����̌o�ߒ��ɂĂ�l������邪�C��ᇂ̑��B���x���ɂ₩�Ȃق����}���ɑ��B����ꍇ�����C������̔����p�x�͍����Ȃ�B �@���삪�A�����Ĕ�������ꍇ��Ă�d�Ϗǂ�����ꍇ�͓��Ö@�̓K���ƂȂ�B�W�A�[�p���C�����[�p���C�N���i�[�p���̌��ʂ͂قړ��������C�����[�p���̂ق������ʂ̎������Ԃ��������߁C�d�Ϗǂ̎��Âɂ͓K���Ă���B �@�x���]�W�A�[�s���n����J��Ԃ����^���Ă��\���Ȍ��ʂ������Ȃ��ꍇ�́C�t�F�j�g�C���܂��̓o���v���_�̋}���O�a����������B�܂��C���߂ĂĂ�l���삪�������]��ᇊ��҂ɂ́C�R�z�����\�h�I�ɓ��^����B �@�]��ᇊ��҂ō��p�x�ɍ������鐸�_�����ɂ́C���a�C�s���C����ς���������B����ςɑ���Ö@�ł̓x���]�W�A�[�s���n��ƍR���_�a��p����B��҂ɂ�������I���̓n���y���h�[���ł���B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N4��23,30�� |
| ���҂ւ̃G���X���|�G�`�����^�̐�����l����@�X�C�X�ōs��ꂽ���^��͂��� ���D�y�a�@���@���E���w�Ö@�Z���^�[���@���R�@�א� |
| ���̍l�@�F�G���X���|�G�`�����^�͗��v�Ƃ̃o�����X�ɂ����čl�����ׂ� �@���҂̕n������ь��ӊ��ɑ��C�킪���ł͊T��Hb 8g/dL�ȏ��ۂ��x�ɗA�����s���邱�Ƃ��������C���Ăł͂��̊ȕ��C���S���C�Տ������ŗ��t�����ꂽ���ӊ��ւ̌��ʂɂ��Hb 12g/dL��ڕW�ɃG���X���|�G�`�����܂����^����邱�Ƃ������B �@Bohlius��͏�L�^��ɑ��C53 �̃����_������r���������^��͂��C�m���ɃG���X���|�G�`�����^�Ŏ��S���������グ�Ă��邱�Ƃ��������B �@�ΏƌQ�ɑ��G���X���|�G�`�����^�Q�ŁC�Ȃ����S�����������ʂɂȂ������͕s���ł��邵�C���w�Ö@���{�s�������҂ʼne�������Ȃ����R���s���ł���B �@�e�Ǘ�̎�������͂���悢�Ǝv���邩������Ȃ��B�������C�I�������҂̏ꍇ�C�}�ς����ɂ���������ƑS�g��Ԃ����������ɂ���C���S�����ꍇ�͌�������肷��w�͂͂����u����ɂ�鎀�S�v�Ɛf�f����̂���ʓI�ł���B���̌X���́C�킪���ł��ɘa�P�A�a���Ō����ł��邪�C���ۂ̎����͊����ǁC�S�����i����������ѕs�����j�C�d����Ǔ��Ìŏnj�Q�ɂ��o���C�e�파���ǂȂǂ������Ǝv����B �@�����̕a�Ԃ���肵�Ă��������Ԃ����QOL���P�ɂȂ��邱�Ƃ͋H�ł���̂ŁC���Ƃ��Ă��I�������҂ɐϋɓI�Ɋe�팟�����s�����Ƃ͔�����ׂ����ƍl����B �@���̂悤�Ȕw�i����C�G���X���|�G�`�����^�ɂ�鎀�S�������̌����͓��肳��Ă��Ȃ����C�G���X���|�G�`���ɂ���ᇑ��B�⌌���ǂ̑����Ȃǂ���������Ă���B �@�{�����̌��ʂ���C�����Hb 12g/dL��ڕW�ɃG���X���|�G�`�����^�𐄏����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ������C�S�������̈����͂킸���ł��邱�Ƃ���C�_���̌��_�ɂ�����悤�ɁC�G���X���|�G�`�����^�͌��ӊ��̉��P�Ɨ��v�Ƃ̃o�����X�ɂ����čl�����邱�ƂɂȂ낤�B �@�킪���ɂ����Ă͌��ӊ��������n���̂��҂ɂ͎�Ƃ��ĐԌ����A��������Ƃ�������̑Ή��̂܂܂ł悢�Ǝv����B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N5��19�� |
| �x�����̒����C������@�e�[�p�[�^�X�p�C����Z�X�e���g���L�p |
| �@�i�s�x����ȂǂŒ����C������𗈂��C�d�ǂ̌ċz�����悵���Ǘ�ւ̑Ώ��Ƃ��āC�C�ǎx����p�����C���X�e���g���u�p���s���Ă���B���{��w���n�����u�a�@���Ȃ̍א�F�������́C�e�[�p�[�^�X�p�C����Z�X�e���g�iTSZS�j��}������25��̗Տ����т������C���̕��@���x�����̒����C�������ɂ�����ً}���I�Ȓ�����������łȂ��CQOL�̉��P�ɂ��L�p�ł���ƕ����B �Z���Ԃŗ��u�\�ŁC�����Ɍ��� �@TSZS�̓X�p�C�����`��ɂ���ċ��ȕ��ւ̗��u���\�ł���C���a����ׂ肵���e�[�p�[�`��ɂ���ċC�ǂ����C�ǎx�ɂ����Ă̗��u���\�ȋ����X�e���g�ł���B�א싳���́C����1��TSZS���C�lj������獶�E�����ꂩ�̎�C�ǎx�ɂ����đ}������25��i�j��17��C����8��C���ϔN��66.2�C51�`88�j�ɂ��Đ��т��܂Ƃ߂��B �@�Ώۂ͂�������_�f�z�����C���x�̌ċz�����悵�ė��@�������҂ŁC�������͔x����23��C�H������i�p��j1��C�咰����̔x�]��1��ł������B �@�X�e���g���u��ɂ��Â��ł����Ǘ��25�ᒆ10��݂̂ŁC���w�Ö@�݂̂�9��C���w�Ö@�ƕ��ː��Ö@��1��B�ȏォ��C�����̔x���҂������ȑΏۂƌ�����B15��ł͋C�ǂ��獶�E�����ꂩ�̎�C�ǎx�ɂ�����1��TSZS��}�����C10��ł͂��̂ق��ɑΑ���C�ǎx�ɂ��Z���X�p�C����Z�X�e���g��}�����āC�Ɍ^���u�܂��͐l���^���u�Ƃ����B �@���ʂƂ��āC13��Ŏ_�f�z���𒆎~�ł��C6�Ⴊ���ʁC4�Ⴊ�p���܂��͑����ł������B�ċz����x��\��Hugh-Jones���ނ́C�X�e���g�}���O�ɑS�Ⴊ�ł��d��V�x�ȏ�ł��������C�}����� I �x9��CII�x5��CIV�x11��Ɖ��P���F�߂�ꂽ�B16�Ⴊ�މ@���C9��͑މ@�Ɏ���Ȃ��������C�މ@�\�ł����Ă����Җ{�l�̊�]�ɂ����@�𑱂�������������Ƃ����B23�Ⴊ���Ɏ��S���Ă���C�����͈��t��9��C����3��C���̗���10��C�x��1��ł������B���������͕���105.5���i7�`528���j�B �@��������TSZS�̒����Ƃ��āC(1)�d���C�ǎx����S�g�����̕K�v���Ȃ�(2)�Z���Ԃŗ��u���ł��C�����Ɍ��ʂ�������(3)�p�Ȃ��\�ŁC�C�ǎx���}��ǂ��Ȃ�(4)���u��ɕ��啨��p��ɋz������K�v���Ȃ��\���Ƃ��������B�������C�S��Ƀ}�N�����C�h�̏��ʒ������^���s���Ă���Ƃ����B �@����C�Z���Ƃ��ẮC(1)���u��Ɉʒu�̏C�����ł��Ȃ��i���Ă͂����Ȃ��j(2)�X�e���g���ɍċ���𗈂����Ƃ�����(3)����������i�����̕K�v�̂Ȃ���ɓK�p����j�\���Ƃ��w�E�����B �@�����25��ł�TSZS�̑}���E���u�ɔ����d��ȍ����ǂ͑S�������Ȃ��������Ƃ���C�������́u���������̏I�����ŋC������𗈂�����ɑ��钂������C�����QOL�̖ʂ��猩���ꍇ�CTSZS�͗L�p��airway stent�ƌ�����v�ƌ��_�t�����B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N7��16�� |
| ��������߁A�Ăё̓��ց@���nj^�Ŗڋl�܂���� |
| �@���������Ȃǂ̂��߁A����זE�����o�ɍL���萅�����܂��������̎��ÂɁA�������Ă�߂��A�h�{����Ɖu�����͑̂ɖ߂��u������ߔZ�k�ĐÒ��@�v�i�b�`�q�s�j�����ڂ���Ă���B���u�̖ڋl�܂肪���������]���̕��������ǁB���҂͕����̒���⑧�ꂵ�������P�����B�u�����͔����Ƒ̂����v�Ƃ̍l�������������A�J���҂�́u�������猳�C�ɂȂ�v�ƌĂт����Ă���B ���h�{���̊O�� �@����̕����́A�݂���◑������Ȃǂɂ�邪�������̂ق��̍d�ςł������A���Ȃ����ς�ς�ɖc��đ��ꂵ���Ȃ�����H�������Ȃ��Ȃ����肷��B �@�����≖���̐����A���A�ܓ��^�̂ق��A���o�ɐj���h�����������Â��s���Ă������A���ʂ͂P�T�Ԓ��x�ƒZ���B�h�{������a�Z���^�[ �i�R�����h�{�s�j���������̏���\�S��t�́u�h�{��ԂɊW����A���u�~���A�Ɖu�ɊW����O���u�������ꏏ�Ɏ̂ĂĂ��܂����߁A����ɕ��������܂�₷���Ȃ�A�J��Ԃ����тɑS�g��Ԃ��}���Ɉ�������v�Ɛ�������B �@���̌��_��₤�̂��b�`�q�s�B���������������Ȗ��ɒʂ��A������A�g�̂ɗL�Q�Ȃ���זE�A�ۂȂǂ���߂��ď����������A�A���u�~����O���u�����͉�����A��P�O���̂P�̗ʂɔZ�k���ĐÖ����犳�҂ɖ߂��B�P�X�W�P�N�ɕی����K�p���ꂽ�B ���O������ �@�������̕��@�́u�̍d�ςȂ���Ȃ����A���������̕����ł́A����זE�┒�����Ȃǂ̍זE�������������ߖ����ڋl�܂肵�A���~����P�[�X�����Ȃ��Ȃ������v�ƁA���肳��B �@���肳��͂Q�O�O�P�N�����Ë@�탁�[�J�[�Ƌ����ʼn��ǂɒ���B���������q�������̃|���X���z���Ȃǂłł��������̃t�B���^�[���g���A�������������O���ɉ����o���Ă�߂���]���̕��@���A�O����������ɂ�߂��ċl�܂�ɂ�����������ɕς����B �@��N�Ď��_�łS�O�l�̊��҂Ɍv�P�R�O����{�B�P��ɔ��������͂R��`�V��~�����b�g���ŁA�ł����������̍d�ρE�̂���̒j�����҂ɂ́A�R�N�R�J���̊ԂɂQ�W�Â��s�����B�A���u�~����₤���t���܂͈�x���g�킸�ɉh�{��Ԃ͏��X�ɉ��P�A���{�Ԋu�������Ȃ����B �@���肳��́u����̕����̏ꍇ�A�����q�l�Ȃnj��ʂ̍������ɖ�ł������̒������������y������Ȃ��ꍇ���������A�b�`�q�s�Ȃ�ċz����Ȃǂ��܂߂����o�Ǐ�͂��݂₩�ɉ��P���A��ɂ���菜����v�Ɛ����B �@���҂͐H�~�������čs���͈͂��L����B����p�Ƃ��Čy�����M�Ȃǂ�������ꍇ�����邪�A�V���b�N�Ȃǂ̏d���Ǐ�͂���܂łɂȂ��Ƃ����B ���ϋɎ��� �@���肳��͍�N�A�����̈�Ë@�ւɂ���A�t�|���v�Ȃǂ��g������y�Ȃb�`�q�s�V�X�e�����J�������B���ÑO�̏������P�O���قǂōς݁A���������̌����������A���̖ڋl�܂����������@�\�ŔS�t�̑�����������Ȃǂɂ��g����悤�ɂȂ����B �@���݁A������̃O���[�v�ɋ��͂��Đi�߂Ă���̂��A�݂���ɂ�邪���������҂̕��o���ɍR����܂𓊗^���鎡�ÂƁA�b�`�q�s�Ƃ̕��p�B����܂ŁA�R����ܓ��^�O�ɔ����������͂��ׂĎ̂ĂĂ������u�V�J���̂b�`�q�s��g�ݍ��킹�A�����悭�h�{�A�Ɖu������������Č��Ǔ��ɖ߂��A��莡�Ì��ʂ����܂�̂ł́v�Ə��肳��B �@���N�S���ɂ͂b�`�q�s�̕��y�Ȃǂ�ړI�ɂ�����������ݗ����ꂽ�B���肳��́u�]���͊ɘa�P�A�̈�Ƃ��Ăق��ڂ��s���邱�Ƃ����������b�`�q�s���A���������ɑ���ϋɓI�Ȏ��Âƈʒu�Â��A�W�����Â̘e���Ɉ�Ă����v�Ƙb���Ă���B ������Ì��N�j���[�X�@2009�N7��21�� |
| �A���}�Ŋɘa�P�A�@��ˎs���a�@ |
| �@��ˎs���a�@�i��ˎs���l�S���ځj���A���҂̊ɘa�P�A�Ƃ��ăA���}�̍�����g�����F������}�b�T�[�W�Ɏ��g��ł���B�@���̊O����t��e�a���ɂ̓A���}�����v���o��B�I�����W��x���_�[�Ȃǂ̍���ɂ��ӂ�A���҂���́u�a�@�Ɠ��̂ɂ����ƈ���Ă��ꂵ���v�ƍD�]���B �@�A���}�Ɏ��g�ނ̂́A��t���t�A�Ō�t���Q�O�l�ł���u�A���}�Z���s�[�ψ���v�B�S���̌����a�@�ł͏��߂Đݒu���ꂽ�Ƃ��������Ȉψ���B �@��ˎs���a�@���A���}�Z���s�[�ɒ��ڂ��n�߂��̂͂O�U�N�B���҂̃X�g���X���ɂ�a�炰�邽�߁A�ɘa�P�A�`�[���́u��֕⊮�Ö@�ψ��v�Ƃ��Ċ������n�߂��̂��͂��܂肾�����B �@���̌�A�E����ΏۂɎ葫�̃}�b�T�[�W�̕�����d�ˁA�O�W�N�P���ɂ��҂₻�̉Ƒ���ΏۂɃA���}�}�b�T�[�W���B���̔N�̂V���ɂ́A�e�a����O���v�P�T�J���ŃA���}�����v���g�����F�������n�߂��B �@�a���Ń}�b�T�[�W���邪�҂̂Ȃ��ɂ͖����Ă��܂��l�������A���̃����b�N�X���ʂ��\��Ă���Ƃ����B���N�R���ɂ́A��ˎs��t��̈�t���Q�����āu��˃A���}�Z���s�[���c��v��ݗ�����\�肾�B���c�ǐM�ψ����́u����͑S�a���Ŋɘa�P�A�̈�Ƃ��ă}�b�T�[�W�����Ă��������v�Ƙb���Ă���B �A�T�q�E�R���@2009�N09��21�� |
| ���_��ᇈオ���X�L���̋��L���@�T�C�R�I���R���W�X�g�̉�����Â�����|��22����{�T�C�R�I���R���W�[�w�� |
| �@��22����{�T�C�R�I���R���W�[�w���P�A�Q�̗����A�L�����̃����p���N�g�h�q�n�r�g�h�l�`�ŊJ���ꂽ�B����e�[�}�́u�����Âɂ�����S�̃P�A�̊g����v�B���҂̑����X�����������ŁA���_�I�ȃP�A��S���T�C�R�I���R���W�X�g�̖����ɂ��Ă̋c�_���s��ꂽ�B �@ �w��Q���ڂ̃V���|�W�E���u�ɘa�P�A�`�[���ɂ�����T�C�R�I���R���W�X�g�̖����v�ł́A��ᇓ��Ȉ�A�ɘa�P�A�a����Ȃǂ��A���ꂼ��̗��ꂩ��u���_��ᇈ�v�ɋ��߂�@�\�A�A�g�݂̍���Ȃǂɂ��Ă̌������q�ׂ��B ���߂��鐸�_��ᇈ�ɂ��A�h�o�C�X �@��������Z���^�[�����a�@�̒_�X���Ȃ̐X����펁�͎�ᇓ��Ȉ�̗��ꂩ��A���_��ᇈ�ɋ��߂�������ɂ��ĉ�������B����҂ƌ��������ۂɂ́A���_�I���ʂ̃T�|�[�g�̏d�v����Ɋ������ʂ������Ǝw�E�B���_��ᇈオ���R�ɉ���ł�����Â����A���_��ᇈオ���R�~���j�P�[�V�����X�L�����w�ԏd�v�������������B �@�X���������_��ᇈ�ɋ��߂�_�Ƃ��ċ������̂́A�@���_�Ȏ�f�ɑ���S���I���⊴�̌y���A�R�~���j�P�[�V�����X�L������̂��߂̐��_��ᇈ�̎��_���猩���A�h�o�C�X�B���_��ᇈ㓯�m�̘A�g��_��ᇈ�̒n��݂̐����C���҂̉Ƒ��ւ̐��_�I�T�|�[�g�\�̂S�_�B �@���_�ȓI����ɂ��ẮA�Ό����R���������҂��������ƂɐG��A��R�����������Ɏ�f�ł��鑶�݂Ƃ��ĔF�m���Ă��炤�K�v������Ƃ����B���̂P�̎��g�݂Ƃ��āA���_�Ȃ���f���邱�Ƃ̕��̃C���[�W���y�����邱�Ƃ��ӎ������u�X�����v���Љ���B�Q���҂���́u���_�Ȃ̐搶�ɂ����k�ł��邱�Ƃ��S�����Ɗ������v�u������������钆�ŁA�������m�����������邽�߂ɂ��������𗧂��Ă���v�Ȃǂ̐������A���_�Ȉ����f���₷�����Â���̈�Ƃ��ċ@�\���͂��߂Ă���Ƃ����B �@�܂��A��ᇓ��Ȉ�́A���҂ɂƂ��Ĉ����������m������Ȃ��P�[�X���������Ƃ��w�E�����B�����A�u���������ł����ɖ{�l�̉��l�ρA���f�͂�ۂ����邩�B�������ꂽ�����������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��d�v�v�Əq�ׁA���_��ᇈ�̎��_����̃A�h�o�C�X�Ȃǂ��Ȃ���A�R�~���j�P�[�V�����X�L�����K�v������Ƃ����B �@�܂��A��w�a�@�₪����a�@�ł͐��_��ᇉȓ��m�̘A�g���\�ł���Ƃ������A�ݑ�P�A�A�z�X�s�X�ւ̓]�@�Ȃǂ̒i�K�ł́u���_��ᇈ�̉���������I�Ɍp���ł��Ȃ��ꍇ������v�Ƌ��������B�]�@���ɂ͐��_��ᇈ�̈�ØA�g�����߂���ق��A���_��ᇈ�̒n��݂��������邽�߂̐��_��ᇈ�̈琬���ۑ�ɋ������B���҉Ƒ��̃P�A�̏d�v�������܂��Ă���Ƃ��A�u���҂̎��Ò������łȂ��A��������_�I�T�|�[�g���K�v�v�Əq�ׂ��B ���_��ᇈ�u���X�̃R���T���ɉ����邱�Ƃ������̑b�v �@���É��s����a�@�ɘa�P�A���̉��R�O���͐��_��ᇈ�̗��ꂩ��u�����A����̎{�݂̏��Љ�Ȃ��琸�_��ᇈ�݂̍���ɂ��ĉ�������B������{�@����ȍ~�A�u�����̕a�@�Ő��_��ᇈオ���҂̐S�̃P�A�����悤�ɂȂ��Ă��Ă���v�Ƃ̔F����\���B���߂�������Ƃ��ẮA���҂�Ƒ��̐��_�����A�S���v���Z�X�ւ̎x���Ȃǁu���܂��܂ȋ@�\�����邪�A���X�̃R���T���e�[�V�����ɒ��J�ɑΉ����邱�Ƃ����ׂĂ̊����̃x�[�X�v�Əq�ׁA��Ã`�[����A���ҁE�Ƒ��̃j�[�Y��S�[����c�����邱�Ƃ��ۑ�ɋ������B �@�܂��A���m���ł́u���_��ᇊw���C�v��W�J���A�����T�C�R�I���R���W�X�g�̋ςĂ�i�߂Ă��邱�Ƃ�����B�ɘa�P�A�`�[����A�ɘa�P�A�a�������a�@�́u���_�Ȉ�v�u�S�Ó��Ȉ�v��ΏۂƂ��Ĕ����̃��[�N�V���b�v�ŋc�_������́B���C��ł̓��[�����O���X�g���쐬����Ȃnj𗬂�[�߂��ɂȂ��Ă���A����͂��������l�b�g���[�N�������ɐ������Ă��������ۑ�ɂȂ�Ƃ����B �@�ɘa�P�A�a���̓����Ƃ��āA�@���a�A����ςȂǂ̐��_�����̕p�x�������A��Ɋɘa�̍���ǗႪ�����X�^�b�t�����͊�������P�[�X�������B���S�މ@�������⑰�P�A���ۑ�\�Ȃǂɂ����y�B���̏�Łu���҂̈��J���ŗD�悷��ȂǁA�a���ŗL�̉��l�ςɔz�����ׂ��v�Ƃ����B �ɘa�P�A�a���@���_��ᇈ�̃t�H���[������Q�{ �@��������Z���^�[���a�@�ɘa��ÉȂ̏��{���v���́A�ɘa�P�A�a����̗��ꂩ��A���_��ᇈ�Ƃ̘A�g�̌���ɂ��ĕ����B�ɘa�P�A�a���ł́A��ʕa���ɔ�ׂĐ��_��ᇈ�̃t�H���[������Q�{��18.4���ŁA����ς�傤�a�̐f�f�������A�u�Ǐ�ɘa�ɓ�a����P�[�X�v�����_��ᇈ�ɏЉ���X��������Ƃ����B �@�ɘa��È�ƁA���_��ᇈ�Ƃ̘A�g�����߂�d�g�݂Ƃ��ẮA�T�Q��̒��J���t�@�����X���^�p���Ă��邱�Ƃ������B�Ǘጟ����A����Ƃ�����������ʂ��āA�u���݂��ɘb���₷���W�����ł��Ă���v�Əq�ׂ��B�܂��A�ɘa�P�A�a�����ł̋���ɂ����_��ᇈ�Ɋ֗^���Ă��炤�K�v�������������B �u������v�̋�Ɍy���ɔz���������n�r�����@�㏞�I���n�r���̗L������ �@�É������É�����Z���^�[�̓c�K���q���͂Q���̃V���|�W�E���ŁA�u���n�r���X�^�b�t����̂��҂̐��_�S���I���ʂւ̃A�v���[�`�v���e�[�}�ɍu�������B���n�r���̖ړI�Ƃ��āA���a�⎡�ÂŐ����������̒��Łu�g�̓I�A�Љ�I�A�S���I�A�E�ƓI�ɍő���̋@�\��������ׂ��������邱�Ɓv�Ǝw�E�B�r������S�̋�ɂ̌y���ȂǁA�u�w������x�ɔz���������n�r���A�w������x�ɉe�����y�ڂ������ɃA�v���[�`���邱�Ƃ��]�܂��v�Ƃ̌������������B �@�g�̓I�r�����Ȃǂɑ���A�v���[�`�̎���Ȃǂ��Љ���B�Ⴆ�A�]��ᇂɂ��㉺���^���A���o��ჂȂǂ̋@�\��Q�ȂǁA�a���ŏI������Âł̊ɘa��ÂɃV�t�g�����߂���P�[�X�ɐG��u���̎����ɋ@�\���P�ړI�̃��n�r�����s�����Ƃ́A���ʂƂ��ē��삪�ł��Ȃ��Ȃ錻���ɒ��ʂ����Ă��܂��\��������v�Ƃ̌�����\���B�Ώ��@�Ƃ��ẮA����ꂽ�@�\���̂̉�ڎw���̂ł͂Ȃ��A�ق��̂��̂����p���Č����Ă���@�\��₤�Ƃ����g�㏞�I���n�r���e�[�V�����h�̕K�v�����������B �@�S���I���ʂɔz���������n�r�����s���ۂɂ́A���ꂼ��̊��҂́u�Љ�I�w�i�A�Љ�I�����A�d�����ȂNJ������ɔz�����A��Ɗ�����I������v���Ƃ̏d�v�����w�E�����B���҂̗v�]��ӎu�d����ق��A���a�₹��ςȂǂ̏Ǐ���P�[�X�ł́u���_�A�S���I���ʂ̐��m�Ȕ��f�v�����߂���Ƃ����B m3.com�@2009�N11��17�� |
|
��12����{�ݑ��w�� �牺�A�t�͊Ǘ��E���S�ʂ���S�g��Ԃ̉��P�ɗL�� |
| �@�ʏ�C�A�t�͌o�Ö��I�ɍs���邪�C�ݑ�×{���҂ł͐Ö�����̓��^������ȏꍇ������B����C�牺�A�t�͔�r�I��Z���ȕւŁC�Ƒ��ł��Ǘ����\�Ƃ��������_������B��Ö@�l���`�����q��ՃN���j�b�N�i�_�ސ쌧�j�̍����o����́C�ݑ�×{���҂ɑ��Ĕ牺�A�t���{�s�����Ǘ�������B�u�牺�A�t�ɂ��E���ȂǑS�g��Ԃ̉��P�������C�Ǘ�����ш��S�ʂ��l������ƍݑ��Âɂ����ėL���Ȏ��Î�i�ł���v�Əq�ׂ��B �������҂ł͊Ŏ��̏������\�� �@�Ώۂ͍ݑ�Ŕ牺�A�t���{�s����25��i�j��12��C����13��C���ϔN��85.9�j�B��b�����͂������ҁi�x�C�݁C�咰�C�X�C�]��ᇁC�畆�C�A���j��13��C�ҁi�������C�]�[�ǁC�p�[�L���\���a�C�����ǐ��x�����C�̍d�ρC�����S�s�S�j��12��ł������B �@�A�t���{�s���������ȗ��R�́C�i1�j�o���ێ�ʒቺ�ɂ��E���̕�i2�j�ӎ���Q�ɂ��o���ێ换��i3�j�x���܂��̓C���E�X�̎��Ái4�j���ÖړI�i5�j�Ƒ��̊�]�\�Ȃǂł������B�܂��C�牺�A�t��I���������R�́C�i1�j�z���Ԃ��s����i2�j�Ö��m�ۂ�����i3�j���Ȃ܂��͎��̔��j�̊댯���������i4�j�Ƒ��哱�̓_�H�Ǘ��\�Ȃǂł������B �@�牺�A�t�{�s���͔N�X�㏸���C��N��11��Ɏ{�s����Ă����B�牺�A�t�̓��^�����͕���11.6���C���^�ʂ͕���607.9mL/���ł������B �@���S��16��C���P��9��ł���C������������҂Ɣ҂ƂŔ�r����ƁC�������҂ł͎��S10��C���P3��ł������̂ɑ��C�҂ł͂��ꂼ��6��C6���50���ɉ��P���F�߂�ꂽ�B���^�����Ⓤ�^�ʂɂ������҂Ɣ҂Ŗ��炩�ȍ��͔F�߂��Ȃ������B �@�牺�A�t�𒆎~�������R�́C�i1�j�S�g��Ԃ̉��P�i2�j���S�i3�j�Ǐ��̋z����Q�ɂ�镂��i4�j�h�����̔畆���ԁi5�j�Ƒ��̊�]�\�ł������B �@�牺�A�t�̗��_�Ƃ��ẮC�i1�j�҂ł͗L���i50�������P�j�i2�j��������ɏ��Ȃ��ߏz���Ԃւ̉e�������Ȃ��i3�j�������҂ł͖{�l��Ƒ��������}����܂ł̋C���̐����C�S�̏��������鎞�Ԃ��ł���\�Ȃǂ��l����ꂽ�B����C���_�Ƃ��Ă͕���̑�����h�����ɔ畆���Ԃ��F�߂��邱�Ƃ�����C���̏ꍇ�͒��~����K�v������B�Ȃ��C�d�x�̊����ǂ͔F�߂��Ȃ������B �@���䎁�́u�牺�A�t���{�s���邱�ƂŁC�ݑ�I�����̊��҂�Ƒ��Ɏ����}����܂ł̎��Ԃ����邱�Ƃ��ł����v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N4��1�� |
| ��107����{���Ȋw��@�I�������҂ւ̌��t�|�{���{�͐T�d�ɍs���ׂ� |
| �@�ɘa��Â���I�������҂ւ̍R�ۖ^�͎��o�Ǐ���ɘa������Ƃ̕����邪�C�x�d�Ȃ錟����_�H�Ŋ��҂̋�ɂ������\�������O�����B�T�c�����a�@�i��t���j�ɘa�P�A�Ȃ̜A���Ҏ��́C��ʕa�@�ɂ����铯���҂ւ̊����ǎ��Â̌����c�����C���t�|�{�̕K�v���𒆐S�Ɍ����B�������߂��Ɨ\�������ꍇ�́C���t�|�{�̓K���͐T�d�ɔ��f���ׂ��Ƃ̌������������B ���S���O�ł͏Ǐ�ɘa�Ɋ�^���Ȃ� �@�Ώۂ́C2009�N1�`9���ɓ��@�ɘa�P�A�ȂɈ˗��̂������@�����S��̂����C���w�Ö@�Ȃǂ̐ϋɓI���ÏI����Ɍo�Ö��I�R�ۖ^���s����78 ��i�j��39��C����39��j�B�������C�R�ۖ�̎�ށC���t�|�{�̗L������ь��ʁC�Ǐ���P�̗L���ɂ��Č�����I�ɉ�͂����B �@���̌��ʁC37��i47.7���j�C43��i�d������j�ōR�ۖ^�J�n���ώ@���ꂽ�B�������̓���́C�ċz��n37.2���C������n32.6���C�A�H14���C�畆��g�D�Ȃ�16.2���B�����͗Δ^�ۂ��J�o�[����L��ȍR�ۖp�����Ă����B �@�R�ۖ^�J�n�G�s�\�[�h�̂���33��i76.7���j�Ō��t�|�{�����{����Ă����BPalliative Prognostic Index�ł͗\��3�T�Ԉȓ���\���ł��邱�Ƃ���C�A�����͎��S����3�T�ԈȑO�i19��j��3�T�Ԉȓ��i14��j�ɕ����Č����B���̌��ʁC��҂̂���4 ��͎��S3���ȓ��Ɍ��t�|�{���s���Ă���C�������̌��ʂ��������邱��Ɏ��S���Ă����B�܂��C���t�|�{�Ȃ��ł͏Ǐ�ɘa�������Ȃ��P�[�X�͌����Ȃ������B �@����ɁC3�T�ԈȑO�Q�ł�7���ȏ�Ŏ��o�Ǐ�̊ɘa������ꂽ�̂ɑ��C3�T�Ԉȓ��Q�ł�14�ᒆ5��ɂƂǂ܂����B����5��̌��t�|�{�͎��S2 �T�ԈȑO�ɍs���Ă���C���S���O�̌��t�|�{�͏Ǐ���P�Ɋ�^���Ȃ��\���������ꂽ�B�܂��C�c��9��̌o�߂͈����̈�r�����ǂ��Ă����Ƃ����B �@�����́u�K�ȍR�ۖ^�ɂ��C�I�������҂ł����o�Ǐ�̊ɘa�����҂ł���B�Տ�����ł́C�o���I�ȍR�ۖ�̑I���͂�ނ����Ȃ����C�������߂��Ɨ\�������ꍇ�ɂ͌��t�|�{�̎{�s�͐T�d�ɔ��f����ׂ����v�ƌ��_�B���ȂƊɘa�P�A�Ԃŋc�_�����ۑ�͑����C�����̌����𑱂��Ă����Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N5��20�� |
|
�I�������҂ւ̎_�f�z���͎����C�z���Ɣ�ׂđ�����P�ɍ����Ȃ� �I�[�X�g�����A�C�č��C�p��������RCT |
| �@�I�����̊��҂ɑ��C����̉��P�ړI�ł����Ύg�p�����_�f�z���B�ăf���[�N��w��Amy P. Abernethy����́C�I�������҂ɕ@�J�j���[���ɂ��_�f�z�����s���Ă������C�z���Ɣ�r���đ�����P�ɍ����Ȃ����Ƃ�Lancet9��4���I�����C���łɕ����B NR�X�P�[���Ōċz��]�� �@Abernethy����ɂ��Ɗɘa�P�A��70���̈�t����������҂Ɏ_�f�z�����s���Ă���Ƃ����B�������C�_�f�z�������ɂ��Ă̖��炩�ȃG�r�f���X�͂Ȃ����Ƃ���C�������3���������œ�d�ӌ������_������r�����iRCT�j���s���C�I�������҂ւ̎_�f�z���̌��ʂ����������B �@�Ώۂ́C�I�[�X�g�����A�C�č��C�p���̌v9�{�݂̔x�����C�ɘa�P�A�C����C�v���C�}���P�A�Ȃǂ̊O���f�ÉȂɒʉ@���̐�������1�����Ɣ��肳�ꂽ�I��������239��k18�Έȏ�C�������_�f�����iPaO2�j��7.3kPa�CMedical Research Council�iMRC�jdyspnea�X�P�[��3�ȏ�l�B�n���i�w���O���r����100g/L�j�C���Y�_���ǁiPaO2��6.7kPa�j�C�F�m�@�\��Q�kMini-Mental State Examination�iMMSE�j�X�R�A��24�l�C�i��������C���߂�7���ԂŌċz��܂��͐S�C�x���g���ǂ͏��O�����B �@�����̊��҂����Âɂ���Ԃ����肳������C�@�J�j���[���ɂ��2L/���̎_�f�����Ȃ��Ƃ�15����/���z������_�f�z���Q�i120��C�j�� 76��C���ϔN��73�j�ƁC�@�J�j���[���Ŏ����C���z�������鎺���C�z���Q�i119��C�j��71��C���ϔN��74�j�ɕ����C7���ԁCNumeric Rating�iNR�j�X�P�[����p���Ē��[�̑���̒��x��10�i�K�ŕ]�������B �@�Ȃ��C�����ǐ��x�����iCOPD�j�C�����x����͎_�f�z���Q�ł��ꂼ��59���C15���C�����C�z���Q�ł͂��ꂼ��68���C13���Ɍ���ꂽ�B QOL���P�C����p�����͓��� �@�x�[�X���C������6����̌v7���ԕ]���ł����̂́C�_�f�z���Q120�ᒆ112��i93���j�C�����C�z���Q119�ᒆ99��i83���j�ł������B�����̊��҂ɂ����钩�̕���NR�X�P�[���́C�x�[�X���C���ɔ�ׂĎ_�f�z���Q�ł�4.5����0.9�ቺ�i���Εω����|20���C95��CI�|1.3�`�|0.5�j�C�����C�z���Q�ł�4.6����0.7�ቺ�i���|15���C�|1.2�`�|0.2�j�������C���Q�ԂɗL�Ӎ��͌����Ȃ������iP��0.504�j�B����C�[���̕���NR�X�P�[���́C�_�f�z���Q��4.7����0.3�ቺ���i���|7���C�|0.7�`0.1�j�C�����C�z���Q�ł� 4.7����0.5�ቺ�i���|11���C�|0.9�`�|0.21�j�������C���l�ɗ��Q�ԂɗL�Ӎ��͔F�߂��Ȃ������iP��0.554�j�B �@���Q�ɂ�����QOL���P����ѕ���p�����ɍ��͂Ȃ��������C�ɓx�̖��C�͎_�f�z���Q10���C�����C�z���Q13���C�@�̉��ǂ͂��ꂼ��2���C6������ꂽ�B�_�f�z���Q�ł͕@����̖��ȏo����1�ᔭ�����Ă����B �@�����I����C�S��Ɏ_�f�z���ɂ��Ď��₵���Ƃ���C43��i18���j���_�f�z����]�܂Ȃ��ƉB���̂ق��ɁC������Ă����b�������Ȃ��Ɖ����̂�63��i26���j�C�����I����Ɏ_�f�z������]�����ۂɓ��������̂�41��i17���j�C�_�f�z������]���������ۂɂ͓������Ȃ������̂�74��i31���j�C�c���18��i8���j�͖��ł������B �@�J�j���[���ɂ��@�ւ̎_�f�z���́C�����C�z���Ɣ�ׂđ���̉��P���ʂɍ����Ȃ��������Ƃ���CAbernethy����͊��҂̗\����l�������S�����Ȃ����Â��s���ׂ��ł���Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N9��9�� |
| �i�s�����҂ɂ͑����i�K�ŏI������Âɂ��Ęb���K�v������ |
| �@�u�i�s�����҂́A���������ɏI������Â̑I�����ɂ��Ĉ�t�Ƙb�������ׂ��ł���v�Ƃ���č��Տ���ᇊw��̐V�������j���������\���ꂽ�B�����̒��҂ł���ăf���[�N��w�i�m�[�X�J�����C�i�B�j���f�B�J���Z���^�[�y����Jeffrey
M. Peppercorn���m�́A�u�����Âɂ����Ė��\�ȕ��@�͂Ȃ����A���҂Ɍ�����^���A�����ɒ��ړI�ɑΏ����鎡�ÁA�Ǐ�Ǘ���ړI�Ƃ����ɘa�Ö@�A�Տ������ւ̎Q���Ȃǂ̑I���������邱�Ƃ�m���Ă��炤�K�v������v�Ǝw�E���Ă���B �@���݁A�����鎡�ÑI�����ɂ��Č����Șb�����������Ă�������҂�10�l���S�l�ɖ����Ȃ��Ɛ��肳��Ă���A���҂̎��̒��O�i�����O���琔�T�ԑO�j�ɂȂ��ď��߂Ęb���������s����P�[�X������Ƃ����B�������A���̂悤�Șb�͂����Ƒ��������ɍs���ׂ��ł���Ƃ����B�܂��A���ړI�Ȏ������Âɉ����Ďx���E�ɘa�P�A���s�����Ƃɂ���āA�����̎��iQOL�j�����シ�邾���łȂ��A�]�����������邱�Ƃ������G�r�f���X�i�Ȋw�I�����j������Ɠ����͕t�������Ă���B �@����̐����ł͎�Ɉȉ��̂��Ƃ���������Ă���F * �i�s�����Âɂ����邷�ׂĂ̒i�K�ɂ����āA�����̎���D�悷��K�v������B * �ŏ��ɐi�s���Ɛf�f�������_�ŁA��t�͂����Ɋ��҂̗\�エ��ю��ÑI�����ɂ��Ċ��҂Ƙb�������K�v������B * ���҂́A�Տ������ɎQ������@���^������ׂ��ł���B �@Peppercorn���́u���҂����Â��牽�����Ɩ]��ł��邩�A��������Ă��邩����t���������邱�Ƃ��d�v�ł���v�Əq�ׂĂ���B�܂��A��t�͕s�m���ȓ_���܂߂Ċ��҂̗\��ɂ��Ė��炩�ɂ���K�v������B���̎�̓��ݍ��b������������ɂ͎��Ԃ���ǂƂȂ邱�Ƃ����邪�A�u��x�ɒ�����ʂ���яڍׂɂ��ẮA�ʓI�ɑΏ�����K�v������v�Ɠ����͎w�E���Ă���B�܂��A����̐����ł́A�ɘa�P�A���܂߂Đi�s���̎��Ìv��̘b�������ɗv�����p��ی��K�p�̑ΏۂƂ��邱�Ƃ𐄏����Ă���B �@�ă����e�t�B�I�[��-�A�C���V���^�C��Montefiore-Einstein�����ÃZ���^�[�i�j���[���[�N�j��Steven Libutti���m�́u���҂�Ƒ������̂悤�Șb�����鏀�����ł��Ă��邩�ǂ��������ɂ߂邱�Ƃ��d�v�ł���v�Əq�ׂ�ƂƂ��ɁA�u�����̈�t�͎��Â���߂邱�Ƃ�����A�ŏ��Ɍ����������̂͊��Ҏ��g�ł���ꍇ�������v�Ǝw�E���Ă���B �@Peppercorn���́u�i�s�����҂ɑ��A��t���炱�̂悤�ȗ����Șb���Ȃ��ꍇ�́A���҂̕�����q�˂�ׂ��ł���v�Əq�ׂĂ���B NIKKEI NET �����������N�@2011�N2��2�� |
| �����咰����������ɕ��S�Ȃ����Â��邩�H ���̕��@�Ƃ� |
| �@�����̐؏�����ȑ咰����̒�����ɂ́A�]���l�H���̑��݂��s�Ȃ���B�������A�S�g�����ɂ��J����p���K�v�Ȃ��߁A���ɖ�������̊��҂ɂ͐S�g�̕��S���傫���B�����ŋ�����ʂ����߂ɁA�咰�ɃX�e���g�𗯒u���鎡�Â��������ꂽ�B�J����p�����Ȃ��̂Ŋ��҂̕��S�����Ȃ��A�����ŐH�����ł���ȂǁAQOL�i�����̎��j�����P�ł���ɘa�P�A�̈�Ƃ��Ċ��҂���Ă���B �@ �@�咰����₻�̑��̂���̂��߁A�咰���������ꋷ�N����ƕ��ɂ∳�����ȂǂŁA�g�̓I�A���_�I��ɂ�������B����̐؏����s�\�ȏꍇ�A�]���͐l�H���݂��邱�Ƃ������B�������A�l�H���͑S�g�����ɂ��J����p�������ɁA�g�p�Ɋ����K�v������ȂǁA���ɖ������҂ɂƂ��Ă͐S�g�Ƃ��ɕ��S���傫���B�����ŋߔN�A�咰�̒��ɃX�e���g�𗯒u���邱�Ƃŋ�������P���鎡�Â����{�����悤�ɂȂ��Ă���B �@2005�N����2010�N�܂łɑ咰�X�e���g�𗯒u�������Ì��ʂ\�����A�s���L���a�@�i���{�L���s�j���������NJO�Ȃ̔��i��t�ɘb�����B �u����͍����p���s�\�ȁA�咰�ɕǂ������������ҁi�݂����q�{�������̏ꍇ���܂ށj19���ɑ��āA�咰�X�e���g�𗯒u���܂����B�X�e���g�͈ٕ��Ȃ̂Œ����Ԓu���ƕ��Q�����邽�߁A�]�����N�ŋ�������̎�p������A�������͐l�H�����X�e���g��������]���銳�҂�ΏۂƂ��Ă��܂��B���u����Ƌ����P����A�y�ɂȂ邾���łȂ��A�H�����ł���悤�ɂȂ�A�މ@���ĉƂʼn߂�����悤�ɂȂ����l�����܂��v NEWS�|�X�g�Z�u���@2011�N2��19�� |
| �݂낤�@�I�������ǂ��}���邩 |
| �@�N���Ƃ��đ̂����ƁA������H�ׂ��Ȃ��Ȃ�A�₪�ĐÂ��ɑ����������|�B���Ă͂��������V�������������Ȃ������B �@���܂͐H�ׂ��Ȃ��Ȃ��Ă������Ȃ���i������B���̑�\�i���u��ᑁi�낤�j�v�ł���B���Ȃ��̕ǂɖ��ߍ��ǂ��璼�ځA�݂ɗ����H������B �@�I�������}��������҂Ɉ�ᑂ�����ׂ����ۂ����߂���A��Ì���̊����͐[���B���{�V�N��w��̒����ł́A�F�m�ǂ̖����ŐH�������Ȃ��Ȃ����l�ɑ��A��ᑂ�_�H�ʼnh�{�Ɛ�����⋋���邩�ǂ����̌��f������|�ƈ�t�̂��悻�X�����l���Ă���B �@�K�v���͌X�̊��҂̏�Ԃɂ���ĈقȂ�A��T�ɘ_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����A���ՂɈ�ᑂ����邱�Ƃ́A�I�����ɂ���l���ꂵ�߂邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B �@�I�����̈�ᑂɂ��āA�ɂ₩�ȃ��[�������߂���B���܂��܂Ȋp�x����_�c��[�߂����B �@��ᑂ͗L�����̍����h�{�⋋�̕��@���B���ہA�̗͂����Č�������̂�H�ׂ���悤�ɂȂ�A���銳�҂�����B �@���́A�������߂��A�{�l�̈ӎv�m�F���ł��Ȃ��P�[�X���B��t�����Ă���āA�Y�މƑ������Ȃ��Ȃ��B �@�V���̏ꍇ�A�l�H�I�ȉh�{�̓��^�͖����ȉ����ɂȂ���A���炩�ȍŊ���D�����ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B����A��ᑂ�����Ȃ���A���s�����Ȃ������ƌ�ʼn���ނ�������Ȃ��B�ǂ����I��ł������͏����Ȃ��B �@�{�l�̈ӎv���u������ɂ����P�[�X������B�މ@��Ɏ{�݂�ݑ�ł̐H������y�ɂȂ�悤�A��ᑂ�������Ԃ�����B �@�O�����f������B���܂̌Y�@�ł́A���Â̍����T���⒆�~�͈�t���߂ɖ����\��������B�@�I�A�ϗ��I�ۑ�����A���̎Љ�I���ӂ�}�肽���B �@���ʗ{��V�l�z�[���ł݂Ƃ���d�˂Ă�����t�A�Δ�K�O����̈ӌ����Q�l�ɂȂ�B�����u�w�������x�̂����߁v�ŁA��ᑂ�����ۂ̒��ӓ_�������Ă���B �@�{�l�̗��v�����ł���A������H�ׂ��Ȃ��Ƃ������肪�Ȋw�I�ɂȂ���邱�ƁB��t����ᑂ̃����b�g�ƃf�����b�g�̗��ʂ�{�l�ƉƑ��ɐ���������ŁA�����I�ȓ��ӂ邱�Ƃ��K�v���B �@�������s����Ȃ�A�Ȃ�ׂ��ꂵ�܂��Ɏ��R�ȍŊ����}�������|�B�����]�ސl�͑������낤�B �@��������̂�H�ׂ��Ȃ��Ȃ�����A�ǂ����邩�B�{�l�̈ӎv���o���_�ɂȂ�B���C�Ȃ�������l���A�Ƒ��Ƙb�������Ă��������B �M��web�@2011�N3��4�� |
| �u����҂ƉƑ��̉�v������J�� |
| �@���}�h�̍���c���őg�D����c�A�A�u����҂ƉƑ��̉�v��8��4���A������J�Â��A2012�N�x�̗\�Z�T�Z�v���Ȃǂɂ��ċc�_�����B �@��\���b�l�߂鎩���}�̔��ҏG�v���́A����̖`���A�u�����̓M�A�����ւ��鎞�ɗ��Ă���B����܂ł̓��[�M�A�ł���Ă����B����͂���܂ʼn������Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B������{�@���ł��A���҂��������A��������i���c��������A�������Z���^�[�Ȃǂ��a�������B�����������������������A���悢���i�ƍ����̃M�A�ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����͂��̍���c�v�ƈ��A�B �@����ɂ́A�l�X�Ȋ��҉�o�ȁB�����J���Ȃ̂�������i���c��ψ��ŁANPO �@�l�O���[�v�E�l�N�T�X�������̓V��T��́A���҂̐g�̓I�ɂ݂�_�I�Ȓɂ݂̌y���ɂ͈��̎��g�݂��s���Ă������̂́A���҂̌o�ώx���ƏA�J�x���͎��c���ꂽ�̈�ł���Ǝw�E�B�u���̐�ڂ����̐�ځv�ɂȂ�Ȃ��悤�A���z�×{��x�̕��S����z�������ɉ����Čy������ق��A�u���҂̓��������i�쐧�x�v�̊m���Ȃǂ����߂��B �@�����Ȋw�R�c����i�����x������������ψ��ŁA��������̌��҂̉�X�}�C���[��\�̕Жؔ��䎁�́A�����F��K���O�Ȃǂő����̊��҂�����g�����A�����Ă��錻����Љ�A�h���b�O�E���O������v�]�B����ɁA�R����܂̕���p��Q�~�ϐ��x�ɂ��Č��J�Ȃ̌�����Ō��c�_����Ă��邱�Ƃ܂��A�u�~�ό���A���҂��A���i���J�����������Ƃ⎡�Âɓ���������t���i���錠���͎c��B����ɂ��A��Â��ޏk���邱�Ƃ��Ȃ��悤�A�T�d�ɐ��x�v����K�v������v�Ƌ��߂��B �@���̂ق��A�u�V�[�Y����x�b�h�T�C�h�܂ŁA�V�[�����X�Ȃ����̐��̊m���v�A�u���k�x���Z���^�[�̏[���Ȃǂɂ��A���E���k�̐��̏[���v�A�u�������_�a�@��A����������Z���^�[�̐����v�Ȃǂ̗v�]���オ�����B �@����ł́A���J�ȁA�����Ȋw�ȁA�o�ώY�ƏȂ̎O�Ȃ��A2010�N�x�̗\�Z�Ǝ��s��2011�N�x�\�Z������B���J�Ȃ̏ꍇ�A2010�N�x�̂�����\�Z�z316���~�ɑ��A���s�z��314���~�ł���_����Ҏ��͎w�E�B�s���{���̎��Ƃɑ���A���̕⏕�I�Ȑ��i�̗\�Z�ł��邱�Ƃ���A�u�����ł������Ȃ��\�Z���Ȃ����ׂĎ��s���Ȃ��̂��B�����ꐶ�����ɂȂ�A�s���{���������v�Ƃ��A���Ȃ̑Ή��𑣂���ʂ��������B �@���}�h�c�A�A�u����҂ƉƑ��̉�v��8��4���̑���ɂ́A20�l��̍���c���A��30�l�̋c���鏑���o�Ȃ����B���c�A�͖�55�l�̍���c�����琬��B �u���̊��҂̗v�]�́A�X�R�̈�p�v�A��c�� �@����ł́A��������i���c��ł̌������Љ�ꂽ�B �@�����c���ŁA���{��w���̖�c��l���́A�������߂��錻��F�����A�u���҂̗v�]�́A�����A����̐���s���̂ق��A��Õs�M�A��Êi���Ȃǂ̖��Ƃ��Č��݉����Ă��邪�A�\�ʂɏo�Ă���͕̂X�R�̈�p�B������{���I�ɉ������邽�߂ɂ́A���̒�ɒ���ł���l�X�Ȗ����������Ă����K�v������v�Ɛ����B �@���������ɂ́A�܂������I����ɗ�������{�v��𗧂āA���E�Z���I�v������肵�Ă����K�v�����w�E�B���ɏd�v�ۑ�Ƃ��āA�i1)������v�i�����ւ̕a�C�ƌ��N�A����A�\�h�A�����f�f�⎀���ςȂǂ̋���j�A�i2�j��Ò̐��̉��v�i�{�݊����^����n�抮���^�ւ̈ڍs�Ȃǁj�A�i3�j��Ãf�[�^�o�^���x�i����o�^�j�̊m���i���ғo�^����S�����̓o�^���x�ɂ��A���f���炪��̎��Ð��т܂ŁA�S���K�͂œo�^�j��3�_���������B �@�����c��̎O�̐��ψ����́A�\�Z�T�Z�v���̗v�]�ɓ������āA�d�����ׂ����삪�Љ�ꂽ�B ���������ψ��� �@�i1�j����Տ����������x���@�\�̐ݗ��A�i2�j�A�J�f�~�A�n��̎x�������Ƒn��x���@�\�̐ݗ��A�i3�j����o�C�I�o���N�̐ݗ��ƃQ�m���E�G�s�Q�m����͋��_�̐��� ���ɘa�P�A���ψ��� �@�i1�j�f�Ñ̐��ƘA�g�̐��A�i2�j�×{�Ɋւ��鑊�k�x���A�i3�j���猤�C�A�i4�j�n��ɘa�P�A�Ɋւ��鎿�I�ȕ]�� ������������ψ��� �@�i1�j����������Z���^�[�̐ݒu�A�i2�j�������_�a�@�̐ݒu�A�i3�j��������p��܂̊�ƒm���̐��i�@ m3.com�@2011�N8��4�� |
|
�����Љ�ی���Ë��c�� �����A���ː����Â̏[���Ƒ����ɘa�P�A���� |
| �@�����J���Ȃ̒����Љ�ی���Ë��c���i��F�X�c�N�E������w��w�@�@�w�����w�����ȋ����j��10��27���J����A�����A�����K���a��A�����Ǒ���e�[�}�ɋc�_�i�����́A���J�Ȃ̃z�[���y�[�W�Ɍf�ځj�B �@�����ł́A���ː����ÂƊɘa�P�A���œ_�B���J�Ȃ́A���ː����Âɂ��ẮA���Ґ����L�тɔ䂵�ĕ��ː����Èオ���Ȃ����Ƃ���A���ː��Ǝ˂̂��тɕ��ː����Èオ�f�@����u����f�@�v�̂ق��ɁA�u��I�Ȑf�@�v�̃p�^�[�����z�肵�A���ː����Èオ��I�w���̉��A�`�[���Őf�Âɓ�����Ă�B����ɂ��A�Ⴆ�A���ː����È�̐f�@�͏T1��ȏ�ȂǂɌ��炷�ȂǁA���S���y������B �@�ɘa�P�A�́A�����ł͂Ȃ��f�f����������{����ƂƂ��ɁA�g�̂����łȂ����_�ʂł̃P�A�������ɍs�������ۑ�B�܂��A�ɘa�P�A�a�����A�Ŏ�肾���łȂ��A�O����ݑ�ւ̉~���Ȉڍs���x��������g�݂̕]����ڎw���B���̂ق��A��×p����ɂ�14���̏������������邪�A30���ɉ������邱�Ƃ������ۑ�B �@�����K���a��̒��ł̏d�_�ۑ肪�A���A�a�B���͓����̌������ɂ����ē��A�a���t�ǂ�4���ȏ���߂錻��܂��A�O���ŁA��t��Ō�t�A�ی��t�ȂǑ��E�킪�A�g���ďd�_�I�Ɉ�w�Ǘ����s�����f�Õ�V��ŕ]��������j�B �@������́A�����S�ʋ։������{���Ă���a�@�͖�64���ɂƂǂ܂��Ă��邽�߁A�����K���a���ҁA�����E�ċz�펾�����҂Ȃǂ̎w���Ǘ����s���a�@�ɂ��ẮA�����Ƃ��ĉ����S�ʋ։���i�߂邽�߂̕�������B �@�����Ǒ�̃��[���́A���j�B���O���Ɣ�r����ƁA���{�͌��j�́u���܂��v�B���̈���A���ܑϐ����Ĕ���ő����_�ł��邽�߁ADOTS�i���ڊĎ����Z�����w�Ö@�j���O���Ő��i����B�܂����j�ł͑މ@�����������Ă��邱�Ƃ���A�މ@��Ɋւ���K����߂�悤�i�߂�ق��A���j�ȊO�̍����ǂ������҂ւ̑Ή��̐�������B ���A�a�̃`�[���ł̈�w�Ǘ���]�� �@���������Z���^�[�������̉ÎR�F�����́A���{�̕��ː����Â̒x���F�߁A�u���ː����Èゾ�������҂�f�Ă���킯�͂Ȃ��A���Ȃ̈�t���f�Ă���B���ː����Èオ�������Ȃ�������Ȃ��Ƃ�������O���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ǝw�E�B��×p����̏������Ԃ̉������x���B���̂ق��A����o�^���i�ւ̃C���Z���e�B�u��ݒ肷��ق��A��w�����m�̕]���Ȃǂ����߂��B �@���{�o�ϒc�̘A����Љ�ۏ�ψ����É��v�����㗝�̖k�����ꎁ�́A�u�ݑ�×{�̒��ł����Ɋɘa�P�A��i�߂邩�A���̃V�X�e�����ǂ��l���A���グ�Ă����ׂ������悭�����Ȃ��B���̓_�ɂ��Ă��������Ă��炢�����v�ƃR�����g�B���̑����̈ψ����A�ɘa�P�A�̐��i��]�������B �@���{����햱�����̊����v���́A�ɘa�P�A�a�����@�܂ł̑ҋ@���Ԃ́A����f�ØA�g���_�a�@�̖�35����2�T�Ԉȏ�Ƃ����f�[�^�ɂ��āA�u�����Ɛ[���B�ɘa�P�A�Ƃ����I�����ɒH����܂łɎ��Ԃ��������Ă���A�ɘa�P�A�a�����@�Ɏ���܂ł̎��Ԃ͂����艽�{�������v�Ǝw�E�A����ɁA�u��������̊ɘa�P�A�����{����Ȃ�A��葽���̊ɘa�P�A�a�����K�v�v�ƃR�����g�B����ɑ��A�ÎR���́A��ጃP�A�ȂǂƓ��l�ɁA�u�ɘa�P�A�a���v���Ȃ��Ă��A�ɘa�P�A�`�[�������A�e�a�������̐����\���Ƃ����B �@���̂ق��A���A�a�ւ̈�w�I�Ǘ��₽����A���j��ɂ��Ă��A�l�X�ȋc�_���o�����A��{�I�ɂ͈ψ��̎x��������ꂽ�B���ɓ��A�a��ɂ��ẮA�`�[����Â̏d�v�����������ꂽ�B m3.com�@2011�N10��26�� |
| �I�����݂낤�u���Í����T�����v�c�V�N��w�� |
| �@���{�V�N��w��i�������E����ы`(�₷�悵)���勳���j�͂Q�W���A����҂̏I�����ɂ�����݂낤�Ȃǂ̐l�H�I�����E�h�{�⋋�ɂ��āA�u���Â̍����T����P�ނ��I�����v�Ƃ̌������������B �@�I������Âɑ��铯�w��̊�{�I�ȍl�����������u����\���v�̉����łɐ��荞�܂�A�����̗�����ŏ��F���ꂽ�B �@�u����\���v��2001�N�ɍ��肳�ꂽ���A���̌�̎��Ԃɑ��������̂ɂ��邽�߁A10�N�Ԃ�ɉ������ꂽ�B�ߔN�A������H�ׂ��Ȃ�����҂Ɉ݂Ɋǂ��� �Ȃ��ʼnh�{�𑗂�݂낤�����y�B�a��̗͉̑ȂǂɌ��ʂ��グ�锽�ʁA���Ăł͈�ʓI�łȂ��A�F�m�ǖ����̐Q�����芳�҂Ȃǂɂ��L����������A���̐��� ���c�_�ɂȂ��Ă���B �@�����łł́A�݂낤�Ȃǂ̌o�ljh�{��l�H�ċz��̑����ɑ��錩�������߂Đ��荞�܂ꂽ�B����҂ɍőP�̈�Â�ۏႷ��ϓ_������A�u���Җ{�l�̑����� ���Ȃ�����A��ɂ傳�����肷��\��������Ƃ��ɂ́A���Â̍����T����P�ނ��I�����v�Ƃ��A�u���҂̈ӎv����薾�m�ɂ��邽�߂ɁA���O�w�����Ȃǂ� �������������ׂ��v�Ƃ����B YOMIURI ONLINE�@2012�N1��29�� |
| �傫�ȓ]�������}�������{�̐��㐧�x�@��49����{�����Êw�� |
| �@���{�̐��㐧�x���傫���ς�낤�Ƃ��Ă���B�w��P�ʂ̐���F�肩��C�����I��O�ҋ@�ւɂ��F��֓]������悤�Ƃ��Ă��邽�߂��B���É��s�ŊJ��
�ꂽ��49����{�����Êw��̓��ʊ��V���|�W�E���u���{�̐��㐧�x�F�傫���ς��R���Z�v�g�ƐV���ȕ������v�ł́C�킪���̐��㐧�x�̕��݂ƌv�悳
��Ă���V���x�̊T�v�C���×̈�̐��㐧�x�̌����ꂽ�B �@���{���㐧�]���E�F��@�\�̐��㐧�x������ψ���Ƒ�O�ҋ@�����ψ���̈ψ����߂��i��̂�����L���a�@�i�����s�j�E��c��l�@���́C�킪���̐��㐧�x�̂���܂ł̌o�܂��Љ�C�u��啪���v����u�����v�ւ̓]���̕K�v�����w�E�����B �@�킪���̐��㐧�x��1962�N�̖����w���㐧�x����n�܂�C���̌�C�����̊w����㐧�x�������B81�N�ɁC�w��Ƃ̐��㐧�x�̐�������} ��ړI�Ŋw��F��㐧���c��i�w�F���j�������B86�N�ɂ͊w�F���C���{��w��C���{��t��ɂ��1��ڂ̎O�ҍ��k��J����C�X�̊w��ł͂Ȃ��C���̎O �҂ɂ���Đ����F�肷������ւ̖͍����n�܂����B �@�O�҂̍l�����̈Ⴂ���玞�Ԃ͂����������C1993�N�Ɋ�{�I�̈�f�É�13�w��̐���̎O�ҔF�肪���ӂɒB�����B�܂��C99�N�ɂ͓��{�w�p��c����C���㐧�x�̐����Ƒ�O�ғI�Ȑ��㎑�i�F��@�\�̐ݒu�����ꂽ�B �ɘa��Ð��㐧�x�@�V���x�ւ̑Ή��͊w��Ō��� �@���{�ɘa��Êw������ő���w��w�@�ɘa��Êw�̍P���ŋ����́C�u�ɘa��Ð��㐧�x�v�̌���ɂ��ĊT�������B �@���{�ɘa��Êw��̐ݗ���1996�N�B����⑼�̎�������Ȏ����̑S�o�߂ɂ����Đl�X��QOL�̌����ڎw���C�ɘa��ÂW�����邽�߂̊w�ۓI���w�p�I�����𑣐i���C���̎��H�Ƌ����ʂ��ĎЉ�ɍv�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B �@�č��Տ���ᇊw��iASCO�j�ƕč����������iNCI�j���J�������ɘa�P�A�̌n���I����v���O�����iEPEC-O�j����{��ʼn����C2005�N���� ���̃v���O�����Ɋ�Â��g���[�i�[�Y���[�N�V���b�v���J�Â����B�܂��C2007�N����͂���f�ÂɌg����t��ΏۂƂ����ɘa�P�A���C���S���ŊJ�ÁB�� ��܂łɖ�2��6,000�l����u�����Ƃ����B �@2009�N�Ɏb��w����ƌ��C�{�݂̔F����s���C2010�N����ɘa��Ð���̔F�莎�����J�n�����B���݁C�b��w�����619�l�C�F�茤�C�{�݂�445�{�݁C�ɘa��Ð����24�l�ƂȂ��Ă���B �@�ɘa��Ð���̗v���Ƃ��āC���I�m���ƋZ�p�Ɋ�Â��Տ����H�E�R���T���e�[�V���������E����w���ƁC���I�m���Ɋ�Â��Տ��������������Ă���B �܂��C���C�J���L�������ɂ́C�i1�j�Ǐ�}�l�W�����g�i2�j��ᇊw�i3�j�S���Љ�I���ʁi4�j���g����уX�^�b�t�̐S���I�P�A�i5�j�X�s���`���A���ȑ��� �i6�j�ϗ��I���ʁi7�j�`�[�����[�N�ƃ}�l�W�����g�i8�j�����Ƌ���`�̑傫��8�̒�������B �@���݁C����p�̋��ȏ����쐬���ŁC����C����{���̂��߂̃Z�~�i�[�C����̐��U�w�K�Z�~�i�[���v�悵�Ă����\��Ƃ����B �@�V�������㐧�x�ɂ��āC�������́u�ǂ̂悤�ɑΉ����Ă������C�w��Ō������ł���v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N2��2�� |
| ��14����{�A���}�Z���s�[�w�� �A���}�Z���s�[�⊿����������ÁC�ɘa��Âɍv�� |
| �@����C������L�����p���C���a��\�h����ɂ͓�����Â��K�v�ƂȂ�B�����s�ŊJ���ꂽ��14����{�A���}�Z���s�[�w��i��������x�@�a�@���`�O�ȁE��
�L�������j�̃V���|�W�E���u������Âւ̃A�v���[�`�v�i���������a��w����U�w�����E���c�����C����w��w�@���̋@�\�⊮��w�u���E�ɓ���L��
���j�ł́C�A���}�Z���s�[�͌��N�E���e�₪�҂�QOL���P�ŁC�����͂��ÂŁC����͂����u�Ɏ��Âœ�����Â�ɘa��Âɍv������ƕ��ꂽ�B �`�G�R��Âɂ�����A���}�Z���s�[�`�Z���t�P�A�Ō��N�E���e��B�� �`�ɘa�P�A�ɂ�����A���}�Z���s�[�`���҂�QOL�����P �`���Á`���m��w�{�����̓�����Êm�����}�� �`�����u�ɂƊɘa��Á`�u�ɑ��݉��ł͖���ւ̐��_�ˑ����}�� �`�G�R��Âɂ�����A���}�Z���s�[�` �Z���t�P�A�Ō��N�E���e��B�� �@���{������Êw��̈����a�F�������́C�G�R��Âɂ�����A���}�Z���s�[�̖����ɂ��Č������C����̌��N�C�����C���e�͕a�C�̗\�h�ƃZ���t�P�A�ɂ��B������鎞��ɂȂ邪�C�A���}�Z���s�[�͌��N�E���e�ʂōv������Ƃ̌������������B ��t���S���犳�Ғ��S�̈�Â� �@���݁C���܂��܂Ȗʂœ����������ՓˁE�Z��������B�܂��C���E�I�Ȏ����͊��ɂ��L�����p�E�z�����������K�v�ł���C�Q�m���f�f��Đ���Â̔��B�� ��Â͎��Â̎��ォ��\�h�̎���ɓ������B�����ɑΉ������Â͕K�R�I�ɓ�����ÂɂȂ�C�ƈ����������͎w�E�����B �@���m��w�͏��w�I�C���v�w�I�ł���C���\���l�̃f�[�^���W�ߗ��_�I�Ɍ��_���o�����ƂŐf�f�E���Â��s�����C�ʓI��O�ɑ��ē������o���Ȃ��B���̂� ���Ȍl�̈�Â������ɂ͓`����w���܂ޑ���E��ֈ�ÁiCAM�j���L���ł���C���҂����邱�ƂŊ��Ғ��S�̈�Â�ڎw���̂�������Âł���B �@������Â̒�`�ɂ��ē��������́C�i1�j���Ғ��S�̈�Ái2�j�g�́E���_�i�S���j�C�Љ�i���j�C�쐫�i���j���܂߂��S�l�I��Ái3�j���Â����łȂ� ���a�\�h�C���N�ێ��C�����i�R����j�̂��߂̈�Á`��3�������C�u����܂ł̈�Â͈�t���S�̈�Â��������C����͊��Ғ��S�̈�Âɕς��Ă����Ȃ���� �Ȃ�Ȃ��v�Ƌ��������B �@����ɓ��������́C�����{��k�Ђł̓��C�t���C�������f����ď]���̐��m��w���s���Ȃ��Ȃ������ʁC�C���t�������܂�K�v�Ƃ��Ȃ������C�I���C���K�C �}�b�T�[�W�C�A���}�Z���s�[�Ȃǂ̃G�R��Â��𗧂��C��Ў҂�������ƕ]���B�܂������{��k�Ќ�Ɂi1�j�G�l���M�[������Ȃ��G�R��Âցi2�j���Ò��S ����\�h�E���N���S�ցi3�j�����̌��N�͎����Ŏ��Z���t�P�A�ց`�ω������Ǝw�E�����B �@�Ō�ɁC���������́u����̌��N�C�����C���e�͎��a�\�h�ƃZ���t�P�A�ɂ��B������邪�C�P�Ȃ钷���łȂ��C���N�Ŕ����������łȂ���Ȃ�Ȃ��B���Ɍ��N�E���e�ʂł̓A���}�Z���s�[���傫���v�����邾�낤�v�ƒ��߂��������B �`�ɘa�P�A�ɂ�����A���}�Z���s�[�` ���҂�QOL�����P �@�a�@�⊳�Ҏ���ւ̖K��A���}�Z���s�[���s�����f�B�J���A���}�����t��Tori�i�_�ސ쌧�j��\�Ńi�[�X�Z���s�X�g�̏��V���Âݎ��́C�A���}�Z���s�[�Ɗɘa�P�A�ɂ��Ď��g�̌o������Ɍ������C�A���}�Z���s�[�͂��҂�QOL�����P�ł���Ö@��1�Əq�ׂ��B ���҂��ł����y�Ȏp����S������ �@�z�X�s�X��ɘa�P�A�a���ł͌��݁C�{�����e�B�A�̃A���}�Z���s�X�g������I�Ɏ{�p���s���Ă��邪�C��̃A���}�Z���s�X�g������{�݂͏��Ȃ��B�a�@�Ō� �t���A���}�Z���s�[�̍u�K��ŕ����C���҂Ɏ{�p���Ă���{�݂������Ă��邪�C�A���}�I�C���w���̖��Ȃǂł��܂蕁�y���Ă��Ȃ��B �@�����̌���܂��ď��V���́C�ɘa�P�A�ł̃A���}�g���[�g�����g�̗v�_�Ƃ��āi1�j����������ɂȂ����Ƃ��ɉ������Ăق��������l����i2�j���҂� �Ƒ��̘b���悭�����i3�j���҂̒ɂ݂������ł��������悤�Ƃ����C���������i4�j�S�����߂ċC�����悳��^����{�p������i5�j�S�g�̃����b�N�X�ƏǏ� �ɘa�ɓ����`�Ȃǂ��������B�܂��C�ɘa�P�A�ł̃A���}�g���[�g�����g�ł́C���҂��ł����y�ȑ̈ʂŎ{�p���邱�Ƃ��d�v�ł���C���̎p�����{���Ɋy���ǂ��� ���m�F����K�v������Ƃ����B �@�A���}�g���[�g�����g�̌��ʂɂ́i1�j�����̎{�p�Ƒ��̃}�b�T�[�W�ɂ�镠���̉��P�i2�j�ア���܂ƕ����̎{�p�ɂ��֔�̉����i3�j�A���}�}�b�T�[�W�ɂ�鍂�x�����ѓ��퐶������iADL�j�̉��P�@�Ȃǂ�����B �@�ɘa�P�A�Ƃ��ẴA���}�g���[�g�����g���s���ۂ̊�{�p���Ƃ��ẮC�i1�j�{�p�҂̐��_�I����i2�j���҂̓����⌾����ǂݎ��C�S�����߂��{�p���s�� �i3�j���̐l�炵���������̂���`��������p���i4�j�Ƒ��̘b���X�����C���̋C�����𗝉�����p���i5�j�l���̏I���ɂ������Ӗ��������C�Â��Ȃ炸���� ���ƃ��[���A��Y��Ȃ��i6�j�`�[����ÂŃT�|�[�g����@�Ȃǂ��K�v�ł���B �@�Ō�ɓ����́C�A���}�Z���s�[�́C2002�N�ɐ��E�ی��@�ցiWHO�j���甭�\���ꂽ�ɘa�P�A�̒�`�ł���uQOL�����P���悤�Ƃ���A�v���[�`�v��1�ɂȂ���ƌ��B �`���Á` ���m��w�{�����̓�����Êm�����}�� �@���L���a�@�i�����s�j������Z���^�[���Ȃ̐��율�Õv�����́C���@�Ɋ����T�|�[�g�O�����J�݂��C�����̐i�s���҂ɒ��N�������Â��s���Ă����B�� �����́u����20�N�ȓ��ɁC����ɑ��鐼�m��w�Ɗ����ɂ�铝����Â��m�����邱�Ƃ��C�킪���̂����ÂɂƂ��ĕK�{�v�Ƌ��������B �u����v���P�ɗL���ȕ�� �@����͑S�g�����ł��邽�߁C�S�g�S�̂��ł��銿�����𗧂B���암����2006�N�t�ɊJ�݂��������T�|�[�g�O���̖ړI�́C������ɂ�邪�҂� �i1�j���Ǐ�̊ɘa�i2�j���C��QOL����i3�j����p�y���ɂ��v��ʂ�̂��Â̐��s�i4�j�������ʂƍR��ᇌ��ʁ`�Ȃǂ̌����ł������B �@�������́C�i�s���҂��悷���{�a�Ԃ��u����v�ƌĂ�ł���B���҂́C���̂ɂ���ɂɉ����C���Âɂ�镛��p����ǁC����ɖƉu�זE������o�����T�C�g�J�C���̉e���ɂ���āC�C�́E�̗͂��ቺ�����C���Ȃ��B �@����ɗL���Ȋ�����́u��܁v�ł���C�⒆�v�C���C�\�S��ⓒ�C�l�Q�{�h���̎O���܂����҂̏�ԁi�j�ɉ����Ďg��������B�܂��C�قڑS��ɑ��� ���s�����P����u�삨���܁v��C�����̐����G�l���M�[��~����u�t�v��₤�u��t�܁v�����p�����B�O�҂ɂ͌j�}䨗�ہC��҂ɂ͋��Ԑt�C�ۂȂǂ�����B �@�������͂���܂łɁC���ː��畆���ɑ��鎇�_�p�C�咰����̓]�ڗ�̏p��̕s�S�ɑ���u䟂����䓒�{�ܗ�U�v�C�����_�o��Q�ɑ����t�܁C������ �̃z�������Ö@�ɂ��z�b�g�t���b�V���ɑ���u�ČӍ܁{�삨���܁v�C���x�i�s����ւ̍R�����Ɗ�����̕��p�Ȃǂ����������Ǘ���o�������B �@�Ō�ɁC�u���҂����Â����t�́C���҂Ɋɘa�P�A�����߂邾���łȂ��C����̂��ÂɊ���������C����ɑ���V���ȓ�����w�����܂��v�ƌ��_�����B �`�����u�ɂƊɘa��Á` �u�ɑ��݉��ł͖���ւ̐��_�ˑ����}�� �@����ȑ�w��i�Ő��w�����̗�ؕ����́C�����u�ɂ̃��J�j�Y���Ɗɘa��Âɂ��čl�@�B�u�킪���ł͖����ɖ�i����j�ɑ������E�Ό����������C�u�ɑ��݉��ł͐��_�ˑ��͋N���炸�C�֔�C���S�E�q�f�C���C���\���Ώ��\�v�Ƃ����B ����g�p�ʂ͊؍������Ⴂ �@WHO�͊ɘa�P�A���u������ړI�Ƃ������Âɔ������Ȃ��Ȃ��������������҂ɑ��čs����ϋɓI�őS�l�I�ȃP�A�v�Ƃ��Ă���B �@�܂��C���R��̕��ނł͂����u�ɂ����̌�������i1�j���̂��������u�Ɂi2�j���ÂɊ֘A�����u�Ɂi3�j�S�g����Ɋ֘A�����u�Ɂi��ጁC�֔�Ȃǁj�i4�j���̂ɂ����Âɂ��W���Ȃ��u�Ɂi�ؓ��ɂȂǁj�`��4�ɕ����Ă���B �@WHO�̂����u�Ɏ��Â̍l�����ł́C��i�A�X�s�����Ȃǁj�C�㖃��i�R�f�C���Ȃǁj�C������i�����q�l�Ȃǁj��ɂ݂̋����ɉ�����3�i�K�Ɏg���� ���iWHO�O�i�K���Ƀ��_�[�j�C�u�ɂ̕]���ɂ���Ă͓�������̖���g�p���������Ă��邪�C�킪���ł͖���ɑ��������������C�Ɨ�؋����͏q�ׂ��B�� ���C�e���̖���g�p�ʂ�����ƁC���{�͊؍������Ⴍ�C�����͉p�����x�̎g�p�ʂ�ڈ��ɂ��ׂ��Ǝw�E�����B �@��������͉��ǐ�����ѐ_�o��Q���u�Ƀ��f����p���Ė���̐��_�ˑ����������������ʁC������̏ꍇ���u�ɑ��݉��ł͐��_�ˑ����}�����ꂽ�B����ɁC�� ���ł̌����Ń����q�l�̒��ɗp�ʂ�1�Ƃ����ꍇ�C������Ⴂ�p�ʂł����S�E�q�f�C�֔�͋N���邪�C���C��2.6�{�C�ċz�}����10.4�{�ȏ�̗p�ʂł� ���ƋN����Ȃ������B�u�����3�啛��p�֔̕�C���S�E�q�f�C���C�̂����֔�ɂ͉��܂�p���C���S�E�q�f��1�C2�T�Ԃőϐ����ł���B�܂��C���C�͑����� ���ɑϐ����ł���̂ŗp�ʒ��߂ɂ��C�قƂ�ǂ͏����v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N2��16�� |
| ��30����{�F�m�NJw�� �p�[�L���\���a���Ö�EACE�j�Q��Ś����@�\������ |
| �@�A���c�n�C�}�[�a�iAD�j���\�Ƃ���ϐ����F�m�ǂł́C�I�����ɚ�����Q�₱��ɋN������뚋���x�����d�v�Ȗ��ƂȂ�B�Q�n��w�ی��w�����ȃ��n�r
���e�[�V�����w�u���̎R�����ۋ����́C�I�����ł��o���ێ�ł�����Ԃ��ł��邾���������߂ɁC�Ö@�Ś����@�\�����߂���@�������B�p�[�L���\���a
�iPD�j���Ö�EACE�j�Q��Ś����@�\������ł���ƕ����B �I�����̌o�ljh�{����� �@�F�m�ǂ̏I�����ɁC�o��I�������I��ᑑ��ݏp�iPEG�j�Ȃǂ̌o�ljh�{�ւ̈ڍs���ł��邾��������邽�߂ɂ́C�뚋�̗\�h�ƐH�~�̑��i��}��K�v���� ��B�R�������́C�I�����̔F�m�NJ��҂ɁC�����@�\�ɐ[���֗^����_�o�`�B�����T�u�X�^���XP�iSP�j�𑝂₷���ʂ̂����܂�p���āC���̗L���������� ���B �@��̓I�ɂ́C���ǂ���10�N�ȏ�o�߂����F�m�ǏI�����Ŕ���E�\��Ȃ��Ȃ�C�H�������̒��ɂ��ߍ��ށC�ނ���Ȃǂ̖�20��ɑ��C�i1�jSP�̕��� �����߂�A�}���^�W���i�`150mg�j��L-DOPA���܁i�`300mg�j�i2�jSP�̕�����h��ACE�j�Q��i3�j�O����������ňݔr�o���i�E�H�~���i ��p�������Z�N�q���`��K�X�g�ݍ��킹�ē��^�����Ƃ���C�����ȏ�Ś����@�\�����サ�Ăނ����݂��������������łȂ��C�Ί��\��߂�C1�`2����x�� ����ȂǁC��⌾��ʂł̉��P���ʂ�����ꂽ�Ƃ����B �@�������́u�I�����̈��ՂȌo�ljh�{�ڍs�͗\�h���ׂ��ł���B�����@�\�����������܂����łȂ��C�������n�r���e�[�V������D�����\�t�g�H�C�~�L�T�[�H�ȂǐH�ׂ₷���`�Œ��邱�Ƃ�����v�Ƌ��������B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N3��1�� |
| �f�f������̊ɘa�P�A��-����J�� |
| �@��������i��{�v����āA�ɘa�P�A�Ɋւ����̓I�{����c�_���邽�߂́u�ɘa�P�A���i������v�̏����25���ɊJ���ꂽ�B��ł́A���f�f����
��ɘa�P�A����邱�Ƃ̏d�v�����A�����̈ψ�����w�E���ꂽ�B�c�_�̃X�P�W���[���ł́A�Z���I�Ȏ{��ɂ��Ă͗��N�x�\�Z�Ăɔ��f�����A�ɘa�P�A�`�[
���̔z�u�⋳��Ȃǒ������I�ȉۑ�́A�f�Õ�V�⋒�_�a�@�̂�����Ȃǂ��������ċc�_�����邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�����ɂ͉ԉ���Y���i�i�q���������a�@���_
�@���j���I�o���ꂽ�B �@�����҂Ƃ��̉Ƒ����ł�����莿�̍��������𑗂邽�߂ɂ́A�f�f������̊ɘa�P�A��A�f�f�A���ÁA�ݑ��Â̊e��ʂł̐�ڂȂ��ɘa�P�A���{���� �߂���B����œ��{�ł͖����A�u�Ɋɘa�ɗp�������×p����̏���ʂ͏��Ȃ��A�����݂̂Ȃ炸��ÊW�҂̊Ԃł��A�ɘa�P�A�ɑ��鐳�����������i�� �ł��Ȃ��̂����B �@���������w�i���Č�����ł͍���̘_�_�Ƃ��āA���f�Ñ̐����f�Â̎�������̐�--�����ɋc�_��i�߂邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�f�Ñ̐��ł͊ɘa�P�A �ւ̃A�N�Z�X�̉��P����̂�����A�ɘa�P�A�`�[���ȂNJe�E��̓K���z�u��A�g�ɂ��ċc�_����B�f�Â̎��ł́A�����҂̐S��ւ̔z�����f�Âւ̊ɘa �P�A�̑g�ݓ�������g�̓I��Ɋɘa�̂��߂̖�g�p�����_�I��ɂ��܂߂���Ɋɘa--�Ȃǂ����荞�܂ꂽ�B �@�f�B�X�J�b�V�����ł́A�f�Ñ��A���ґ�\�o���̈ψ�����u���̐f�f������̊ɘa�P�A�̕K�v���v���������ꂽ�B����ɑ��Ă����E���N���i�ۂ̗� ����ے��⍲���u�f�f������ѐf�f�v���Z�X�̒i�K����A�����Ɋ��ҕ��S���y�����邩�́A������{�@�̗��@���_�ɂ��܂܂��L�[���[�h���B���Ђ������� ��ŋc�_���Ăق����v�Ɖ������B �@����J���ψ��i���l�s�암�a�@��ܕ����j�́u�ݑ��Âɂ������×p����̓K���g�p���l����ƁA���ЂƂ��ی���ǂ��������A�g�̂�������c�_�ɉ����Ăق����v�Ɨv�������B �@�c�_�S�̂̃X�P�W���[���Ɋւ������ǂ́A�u���N�x���Ɏ��{�ł����Ă͂ǂ�ǂ��Ă��Ăق����v�Ɨv�]���A���N�x�\�Z�ɔ��f��������Z���I�ȋc�_�ƁA�Q�N��̐f�Õ�V�⍡��̋���Ȃǒ������I�Ɏ��g�ގ{��ƕ����ċc�_��i�߂邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B �@����ȍ~�̉�c�ł́A�P�c��R��ł̊��������h�Ƀq�A�����O�Ȃǂ����{���A��̓I�{��̒ɂȂ��Ă����B m3.com�@2012�N4��27�� |
| ���E���Ԃ̕��i �݂낤�̐���ɂ��ā\����҂́u���R�Ȏ��v�����߂��ɂ́\ |
| ���� ���@�_�ސ쌧���E�����ߊ}�f�Ï��i���{��s�j�����^���_�ސ쌧���z��ċz��a�Z���^�[���� �@���͒��N�C�_�ސ쌧���a�@�ŐS�����NJO�Ȉ�Ƃ��ċΖ����C��N�ސE��C���ʗ{��V�l�z�[����V�l�ی��{�݂Ȃǂ̘V�l�����{�݂ŁC�ӔC�҂Ƃ��č���҂̌� �N�Ǘ��Ɍg����Ă��܂����B�V�l�{�݂Œ�����҂̎��Ɋԋ߂ɐڂ���悤�ɂȂ��ĕ��������̂́C�s���R�Ȏ��ɕ������Ă��鍂��҂����Ȃ��Ȃ��Ƃ������Ƃł� ���B �@�{�݂ł͍���҂��V���Ŏ��ɂ����ɂȂ����Ƃ��C�Ŏ�邱�Ƃ͂����C�������ɕa�@�֑���܂��B��������ƕa�@�ł́u�H�ׂ��Ȃ��a�l�v�Ƃ��Ĉ����C���� ���肾�Ă��g���Ė����Ƃ�Ƃ߂悤�Ƃ��܂��B��t�͔N��ɊW�Ȃ������ł������������̂��`�����ƍl���Ă��邩��ł��B �@�������ߔN�C�u�݂낤�v�Ƃ����u�H�ׂ��Ȃ��a�l�����Â���v��y�ȕ��@���J������܂����B�������ň�Â̌���ł́u�H�ׂ��Ȃ��Ȃ��Ă��邩��C�݂낤�����܂��傤�v�ƁC���Ƃ��ȒP�Ɉ݂낤�̑��݂����߂��Ă���̂ł��B�����ɖ{�l�̈ӎv�̉�݂͂ق�̋͂��ł��B �@�����Ŗ���2����܂��B�ЂƂ́C����҂́u�V�����v�Ƃ͂ǂ��������̂��C�u���R���v�Ƃ͂ǂ��������̂��C��Ï]���҂ł����悭�������Ă��Ȃ��Ƃ� �����Ƃł��B���ЂƂ́C�ЂƂ��ш݂낤�݂���ƒ��~�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���͐[�����Ǝv���܂��B����҂��a�C�ł͂Ȃ��V���ŖS���Ȃ�Ƃ́C�� ��H�ׂ��Ȃ��Ȃ��āC�͂��悤�Ɏ���ł������Ƃł��B���̎��R�Ȏ����}���悤�Ƃ��Ă���Ƃ��ɁC�݂낤�݂���Ƃǂ��Ȃ邩�B�Q������Ŕ��ꂪ �Ȃ��C�葫���d�k���A����ԂƂȂ��Ă��C�ݒ�����v�ł���ΐ������ꑱ���邱�ƂɂȂ�̂ł��B �@�t�����X�ɒ����؍݂��Ă������̒킪�C�t�����X�̈�t���炱��ȑ䎌���܂����B�u�V�l��Â̊�{�́C�{�l�����͂ŐH�����ł��Ȃ��Ȃ�����C��t�̎d���͂��̎��_�ŏI���B���Ƃ͖q�t�̎d���ł��v�B �@���������݂낤�����߂ėՏ��ɉ��p���ꂽ�̂�1979�N�B�A�����J�ł̐_�o�����ɂ�隋����Q�̎q�����Ώۂł����B���ݓ��{�ł́C�������H�ׂ��Ȃ��I �����̍���҂̉����̂��߂Ɏg���Ă��܂��B������������ɑ��āCPEG�i�݂낤�j���J�����������O�Ȉ�̃K�E�_���[��t�́C�K�����ڂ݂Ȃ�����҂ւ� �ߏ�{�s�Ƃ����CPEG�̊J�������͈Ӑ}���Ȃ��������Ԃ�J���Ă���Ƃ����܂��B���݁C�݂낤�̊��҂�40������50���l�ɂ��̂ڂ�Ƃ����Ă��܂��B �@�ʂ����č���Җ{�l�́C�݂낤�ɂ�鉄����]��ł���̂ł��傤���B�����s���N������ÃZ���^�[�̊O�������562����Ώۂɍs�Ȃ�������������܂��i1999�N�j�B �@�F�m�ǂ��i�s���C�H���̐ێ换��C�Q������C�����̈ӎv��\���ł��Ȃ���ԂɊׂ������Ƃ�z�肵���ꍇ�C�݂낤����]���邩�ǂ��������₵�܂����B���ʂ́C�݂낤�̊�]�҂�2.7���C�o�@�݊ǂ�6���C�_�H��3.9���C�������Ȃ����ł�����42���ł����B �@�����������I�ɂ́C�݂낤���������u�Ƃ��Ď{�s����Ă���Ƃ����ł��B�܂�����C���̒����̂��ߎQ�����Ă������PEG���݂����Ă����t30�� �ɁC���������҂̗���Ȃ�݂낤�ł̉�����]�ނ��Ƃ�������ɑ��C21���͔ے�I�ȉł����B�F�m�ǖ����́C���{�l���܂߂������̌����҂��C�o�ljh�{ �@�̓K���łȂ��Əq�ׂĂ��܂��B �@PEG�̗ǂ��K���́C�]���Ǐ�Q��y�x�̔F�m�ǂŁC������Q�����������̂̈ӎ���Ԃ������Ȃ��Ǘ��C���̊O���ňꎞ��������H�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��ǗႾ�Ǝv���܂��B �@��Â̖ړI�́C�{���C���҂����悭�����邽�߂ɖ𗧂��̂łȂ���Ȃ�܂���B���݂̈낤�Ƃ��������ێ��̋Z�p���C���҂́u�����̎��v�iQOL�j�����߂��Ŗ𗧂��̂łȂ���C�g�����Ƃ�����������Ȃ��Ǝv���܂��B �@���́C�݂낤�̎�p��������t�����̑������C�݂낤�݂��ꂽ���N���݂̂��߂Ȗ��H���ڂ����͒m��Ȃ����Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B�l�Ԃ͒N�����C�� ��܂Ől�Ƃ��ĈӖ��̂���l���𑗂肽���Ɗ肤���̂ł��B����������ł́C�{�l���Ƒ����]�܂Ȃ����̂����̉������C�N���~�߂邱�Ƃ��ł��܂���B �@���N��1���C���{�V�N��w��C�u����҂̏I�����ɂ́C�݂낤���݂��܂ތo�ljh�{�Ȃǂ͐T�d�Ɍ��������ׂ��ł���C���Â̍����T���⎡�Â���̓P�� �i���Ȃ킿���~�j���I�����Ƃ��čl������K�v������v�Ƃ��܂����B�}����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́C�݂낤������E���Ȃ������߂�V���������邱�Ƃ�C�� �҂̈ӎ��������߂�Ȃ��ƕ����������_�ŁC�݂낤�𒆎~����@�I�Ȋ�����߂邱�Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N8��23,30�� |
| �����҂�QOL���P QOL�ቺ�ɂȂ��錑�ӊ������߂����Ȃ����Ƃ��d�v |
| �@���݁C�h�C�c�̂����҂�320���l�ɏ��B�h�C�c�����Z���^�[�i�n�C�f���x���N�j��Volker
Arndt���m�́u����̗\�オ���P�������Ƃ���C����C�����҂̐��͂���ɑ����邱�Ƃ��\�������B�������������҂�60����65�Έȏ�̍���
�҂���߂Ă��邪�C�����ɂ킽��QOL���Ⴂ���Ƃ����ƂȂ��Ă���v�ƃh�C�c����w��̑�30���c�ŕ����B �Љ�A�͈ˑR���� �@�����҂����ʂ���̂́C���̂��̂₪��̎��Âɒ��ڊ֘A�����肾���ł͂Ȃ��B��������[���Ȃ̂́C�����Ɋւ�閝���̎���������Ă��邱�Ƃ��痈��s���ŁC����͂������a��F�m�@�\�̒ቺ�ɂȂ���B �@�Љ�A���傫�Ȗ��ƂȂ��Ă���B1�N��ɍďA�J���Ă������҂͖��ɂ������C50�Έȏ�̊��҂ł�3����1�ɂƂǂ܂�B �@�������C�I�����_�ōs��ꂽ�����ł́C�ďA�J�̏͂���̎�ނɂ�肩�Ȃ�قȂ邱�Ƃ�������Ă���B�Ⴆ�C1�N��ɍďA�J���Ă������҂̊����́C�畆�܂��͐��B��̂���ł͍ő��80���ł���̂ɑ��C���t�̂����x����ł͋ɂ߂ĒႩ�����B �@�܂��C�h�C�c�n�悪��o�^����iGEKID�j���U�[�������g�B�ɋ��Z��������҂�Ώۂɐf�f��10�N�Ԃ�QOL������VERDI�����ł́C���� �҂�QOL�͑S�̓I�ɂ͌��N�l�ɋ߂����̂́C���ɂ͎Љ���@�\����퓮��C����I�@�\�C�F�m�@�\���������ቺ���Ă���P�[�X������ꂽ�B �@QOL��ቺ������ɂ߂đ傫�ȗv���Ƃ��Č��ӊ����������邪�CArndt���m�́u���ӊ��ɂ��ẮC�q�ϓI�ɕ]������ړx���Ȃ����ߌ��߂�����邱�Ƃ������v�Ǝw�E�B���̑��C������Q�C�H�~�s�U�C�u�ɁC�ċz����C�ݒ���Q�Ȃǂ������ԑ����Ɗ��҂Ɉ��e�����y�ڂ��B ���ǂ��������g�����ߒ������������ɂȂ�ꍇ�� �@���̈���ŁCArndt���m�́u���a�����������ɁC�������g�����ߒ������҂����Ȃ��Ȃ��v�Əq�ׂ��B����͊O���㐬���iPosttraumatic growth�GPTG�j�Ƃ��Ēm���Ă���C�S�I�O���������炷�o���ɂ���Y����C���Ȍ`���⑼�҂Ƃ̊W�C�l���ɑ���l�����Ƀ|�W�e�B�u�ȕω����N ���邱�Ƃ�����Ƃ������́B�����m�́u�����̂����҂�QOL�ɂ��ẮC�܂��s���ȓ_�����ɑ����B���҂̃A�t�^�[�P�A��{���I�ɉ��P���Ă����� �́C�����҂Ɏ��₷�邾���ł͕s�\���ŁC���̕���ł̌������������Ă����K�v������v�Ƌ��������B �@���x���g�E�R�b�z�������i�x�������j��Benjamin Barnes���m�ɂ��ƁC�U�[�������g�B�C�n���u���N�s�C�~�����X�^�[�s�Ŏ��W���ꂽ����o�^�f�[�^�̉�͂̌��ʁC�����҂�5�N�������͖�80���� ���邱�Ƃ��������Ă���B�������C�����������҂̎��S���X�N�͓��N��̌��N�l�Ɣ�ׂāC�����ɂ킽�荂�����Ƃ��������Ă���B����C������������� �����蒷�����Â��t������\�����������C�������҂̎��S���X�N�́C�f�f����8�`10�N��ł����N�l�Ƃقړ����ł���Ƃ����B �@�܂��C���������������a���҂̐��������f�f����͒������ቺ������̂́C���N�o�߂���ƌ��N�l�Ƃقڕς��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���������Ă���B�������C���������p�������a�̏ꍇ�́C���N�l�Ɣ�ׁC�����҂Ŏ��S���X�N�����炩�ɍ����܂܂ł���Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N11��22,29�� |