�@
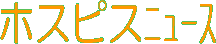 �@
�@�@�@�v�@�� �| �S�̃P�A
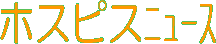 �@
�@| �@�z�|�� >��w�g�s�b�N�X>�z�X�s�X�j���|�X>�o�b�N�i���o�|�ƭ->�v���|�S�̃P�A |
| �y�T�C�R�I���R���W�[�ƃ����^���P�A�z�@�O���[�v�Ö@ | ||||
|---|---|---|---|---|
| �ۍ◲�@���C��w��w�������E���_��w �@�T�C�R�I���R���W�[�̗̈�̒��ŁC���҂���ւ̐S���Љ�I��������ڂ���Ă��܂��B �X�s�[�Q���E���f���̏W�c���_�Ö@ �@�X�^���t�H�[�h��w�̃X�s�[�Q���iSpiegel D�j��́C���u�]�ڂ��N�����������҂���𐔖����̃O���[�v�ɕ����C�u�W�c���_�Ö@�v���s���܂����B�����90���Ԃ̃v���O�����T1��C1�N�Ԃɂ킽��s�������̂ŁC�t�@�V���e�[�^�[�i�i�s���j�͐��_�Ȉ�C�\�[�V�������[�J�[�Ȃǂ����߂Ă��܂��B10�N�̒ǐՂ̌��ʁC����Q�ł͕��ϐ������Ԃ�36.6�����ƁC�ΏƌQ��18.9�����ɔ�ׁC��2�{�̉������݂��܂����B �t�@�E�W�[�E���f���̍\�������ꂽ��� �@UCLA�̃t�@�E�W�[�iFawzy FI�j��́C�����̈������F��̊��҂���𐔖����̃O���[�v�ɕ����C�S6��̏W�c������s���܂����B����́C���ł����R�ɘb���Ƃ����̂ł͂Ȃ��C���߂�ꂽ�e�[�}�̘b������C�����N�Z�[�V�����̕��@���w�ԂƂ������̂ŁC���ɁC�O�����ŐϋɓI�ȃR�[�s���O�i�Ώ��l���j���l�����邱�Ƃ�ڕW��1�ɂ��Ă��܂����B���̌��ʁC 6�T�Ԃ̉���v���O�����I������ł́C����O�Ɣ�r���C���Ԃ̉��P�C�Ɖu�@�\�̑������݂��C6�N��ł͍Ĕ����Ȃ�тɎ��S���ɗL�Ӎ��������܂����B ���C�厮�u�����҂���ւ̍\�������ꂽ����v �@40���̌����̌��ʁC�����ł͉���O�ɔ�r���āC���ԂɗL�ӂȉ��P���݂��܂����B�����6������̃t�H���[�A�b�v�����ł́C�Q���҂�2/3�́C������I�����Ă��������I�ɉ������C�����������肷��ȂǁC���̊��҂���ƘA������荇���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B����͑�5��ŐG�ꂽ�C����̌o�߂ɂ悢�e����^����u�\�[�V�����T�|�[�g�v�C�܂��́u�\�[�V�����l�b�g���[�N�v�����邱�ƂɂȂ�܂��B�܂�C���̂悤�ȉ���́u�\�[�V�����l�b�g���[�N������v�Ƃ��Ă̈Ӌ`�������ƂɂȂ�̂ł��B �@�W�c�ʼn�����s���ƁC�����a�C�����������҂��m�Ŏx�����������Ƃ��\�ɂȂ�܂��B���̂��߁C���҂���̌Ǘ����̌y����C��̓I�Ȗ�����������̂ɂ����ɖ𗧂��������\�ɂȂ�����C����ɂ͈�Î҂̐l�I�E���ԓI���������߂邱�Ƃɂ��Ȃ�����@�ł���Ǝv���܂��B �@���̂悤�ȉ�����C�������x���łȂ��C����̂���f�Â̏�ł�������O�̂悤�Ɏ��Õ��j�̒��ɑg�ݍ��܂�Ă������Ƃ����҂��Ă��܂��B cancercareonline�@2008�N1��24�� |
||||
| �v���C�}���P�A�オ�z�X�s�X�P�A��\���I�ɓ������� | ||||
| �@�wAmerican Family Physician�x3��15���̑����ŁA�z�X�s�X���҂̏Љ�Ǝ��Âɂ�����v���C�}���P�A��̖������q�ׂ�ꂽ�B�z�X�s�X�P�A�́A�ɘa���Â�]�ޖ����������҂̒N�ɂł����p�ł�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B �@�u�ƒ��́A�l���̏I���ɋ߂Â��Ă��銳�҂̃P�A�ɂ����Ă��������̂Ȃ��������ʂ������Ƃ��ł���v�ƃA�C�I����w�a�@�i�A�C�I���V�e�B�j��Michelle T. Weckmann���m���L�q���Ă���B �@�u�p�����ăP�A���s���A�e�E�q�E���ɂ킽���Đl�ԊW�������Ă��āA���҂̉��l�ρA�Ƒ��̖��A�R�~���j�P�[�V�����̃X�^�C���ȂǑ��҂ɂ͕�����Ȃ��m�����������ƒ�ゾ���炱���A���҂ƉƑ����z�X�s�X�Љ�̃v���Z�X�ɓ�����B�v���C�}���P�A��͐f�Ă��銳�҂Ɛe�����W�ɂ��邱�Ƃ������̂ŁA�z�X�s�X�P�A�����߂�̂��K�v�Ȏ��������Ȃ̂��f�ł���ȂǁA�I������Âɑ��ēƎ��̖�����S�����Ƃ��ł���B�v �@�u�z�X�s�X�P�A�Ɋւ��Đ����������҂̉��҂ƉƑ��̑唼�̎҂��A���҂��I�����Ɛf�f���ꂽ���Ƀv���C�}���P�A�ォ��z�X�s�X�ɂ��Ă̏��������ƕ������������Ɠ����Ă���v�ƁAWeckmann���m�͋L���Ă���B �@�u�z�X�s�X�͏I�����ɂ��銳�҂����悭�x�����A�D�ꂽ�P�A������i�ɂȂ肤�邱�ƁA�����āA�v���C�}���P�A�オ���҂̎��܂ŃP�A�S�̂̎w�����Ƃ葱���Ă���Ɗ��҂ւ̃P�A����������邱�Ƃ��A�����Ŏ�����Ă���c�c�܂��z�X�s�X�́A��ܓ��^�A�Ǐ�̊Ǘ��A���҂Ƃ��̉Ƒ��Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̍ۂɂ͈�t�ɂƂ��Ă��������̂Ȃ����\�[�X�ɂȂ�B�v �@�Տ��ɂ������X�̐����͈ȉ��̒ʂ�ł���B �@* ���Ɗ��ȊO�̐f�f���Ă��銳�҂́A�z�X�s�X�T�[�r�X�Ńx�l�t�B�b�g�邱�Ƃ��ł��A�\�オ2�J���ȏ�ł���z�X�s�X�ɏЉ�ׂ��ł���B�����Ƃ��L���ȃz�X�s�X�������Ԃɂ��Ă͋c�_���c����Ă��邪�A�قƂ�ǂ̎��Z���ŒZ��2�`3�J���Ԃł���B�ɒ[�ɒZ�������́A�ނ�����҂̑̒�������A���ɂȂ���B �@* �ł��邾�����������Ƀz�X�s�X�P�A�ɂ��Ċ��҂���щƑ��Ƙb�������ׂ��ł���A������P�A�ڕW�̑I�������L����ϓ_����Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�x������Љ�́A�T�[�r�X�Ɋւ���Ƒ��̖����x���Ⴍ�Ȃ�A���҂̑̒�������B�����ɂ��ƁA�z�X�s�X�ւ̏Љ�x�������Ɗ����Ă���Ƒ���11%����18%����B �@* NYHA���ރN���XIV�̐S�s�S�i���Î��Ɏ��o�Ǐ�j�ŁA���K���Âł��Ǐɉ����Ȃ����҂ɂ́A�z�X�s�X�ւ̏Љ�K���Ă���B �@* ���퐶���̂��ׂĂ̊����ɉ�삪�K�v�ŁA�ӎv�a�ʂ����͂�ł��Ȃ��悤�ȔF�m�NJ��҂ɂ́A�z�X�s�X�ւ̏Љ�K���Ă���B m3.com 2008�N3��27�� |
||||
| �I������Âɂ����銳�ҁE�Ƒ��ɂƂ��Ă̍őP���T�� | ||||
| �@��13����{�ɘa��Êw��̃V���|�W�E���u�I������Âɂ�����Տ��ϗ��F����Ȏ��ǂ��l����H�v �@�����͍�������掦���ꂽ���z�Ǘ������C�I�����ɂ����ėA�t�E���Â��ǂ����ׂ����ɂ��Ċe����̐��Ƃ����c���J��L�����B �y�Ǘ�1�z�Ƒ��̈ӌ����قȂ�ꍇ�C�A�t���ǂ����邩 �@2�N�O�ɗ�������ɂč��Փ����S�E�o�p���s����50�Α㏗���B���w�Ö@�{�s�������������i�s���C3�����O����T�u�C���E�X���J��Ԃ��C�ۑ��I���Ái�ꎞ�I��H�E�A�t�j�ʼn��P���Ă������C2�T�ԑO����͌o���ێ�𐧌��C�A�t1,000mL/���ł������C1�T�ԑO���畠���������C�ӎ������̂��ߖ��m�Ȉӎv�\�����ł��Ȃ��Ȃ����i�ċz����͂Ȃ��j�B��Î҂́C�A�t�p���ɂ�镠���E�ċz����̈��������O���C�Ƒ��ɗA�t���ʂ̑��k�������Ƃ���C���E���q�i�p����]�j�ƕv�i���~��]�j�̈ӌ��̈�v�������Ȃ��B �K�v�\���Ȉ�w�I���̒� �@�r�i���V����L���X�g���a�@�z�X�s�X���́C�v���q���������̊�]�Ƌ�Ɋɘa�̂Ȃ��Ŋ������Ă���͓̂����B1,000mL�ȏ�̗A�t�ŕ��������������O�����ώ@�����̌��ʂ���C���Ǘ�ōł������ł��Ȃ��Ή��́u�A�t�̑��ʁv���Ǝw�E�B�t�ɐ������ׂ��Ή��́C�ӎ��������ɂ��銳�҂̈ӎv�𐄒肵�C�Ƒ��Ԃ̊�]�����C�Ƒ��ɂł��邱�Ƃ��ꏏ�ɍl���Ă����Ȃ���C���ҏ�Ԃ��J��Ԃ��]�����āC�A�t�ʂ⎡�Ó��e���������Ă������Ƃ��Ƃ̍l�����������B �@�T�q(��)���C�t�E�v�����j���O�E�Z���^�[�s�[�X�n�E�X�a�@�E�Ō암�����C��Î҂Ƃ��Č����c�����C�a��̔��f�ƌ��ʂ���������邱�Ƃ�����Ƃ��C�P�A�̍ۂɂ́C(1)�Ƒ������o�[�e�l�̊��҂ɑ���v����(2)���҂Ȃ�ǂ����ė~�����Ǝv������(3)�\�ł���ΉƑ����ꏏ�ɃP�A������\���Ƃ��d�v�ŁC�Ƒ������炱���m�肦�銳�҂̍D�݂ɍ��������ɐ������邱�Ƃ�P�A��ʂ��ĉƑ����̗̂l�q��m�邱�Ƃ��l�����ׂ����Ƃ����B ���ҁE�Ƒ��̗�����ӌ������p������� �@���q���j���É��s����w��w�@�y���� �́C���Ǘ�ɂ��āu�A�t�̌��ʂ������\��Ɉ��e�����y�ڂ��̂ł͂Ȃ����ȂǁC���q����̕a��F���Ɍ��������\��������B��Ñ����犳�ґ��ɓ`������ɂ��Ă��C�A�t���]���̗ʂŌp�������琶�����ۂĂ�̂��C�����E�ċz����������鋰��͂ǂ��Ȃ̂��C���ʁE���~������ǂ��Ȃ̂����C���ׂĊ��ҁE�Ƒ��ɂ킩��悤�ɓ��탌�x���̌��t�Ő������ē`���C���ҁE�Ƒ��̗�����ӌ�����邱�Ƃ��d�v�ɂȂ�v�Əq�ׂ��B �y�Ǘ�2�z���_�I��ɂɑ�����Â��ǂ����邩 �@2�N�O�ɐt����Őt�E�o�p���s����50�Α�j���B3�����O�ɋ��œ]�ڂƐf�f���ꂽ�B1�����O���玩��ł̉�삪����ƂȂ�C�ɘa�P�A�a���ɓ��@�B���҂́u�����鉿�l�Ǝv���Ă����d�����ł����C�Ƒ��ɕ��S�������Ă���B���c�������Ƃ͂Ȃ��C���y�������ė~�����B�����Ȃ炸���Ɩ��点�ė~�����v�Ɨv������B �͕t���C�x���C�E�C�t����P�A �@�r�i�z�X�s�X���́C��Ɋɘa�͈ӎ�������g�̋@�\�ɗ^����e�����ł����Ȃ����@��D�悷�ׂ��ł���C��ʓI�ɂ͊Ԍ��I���ɂ���ɂ�D�悵�C�\���Ȍ��ʂ������Ȃ��ꍇ�Ɏ����I�E�[�����ɂ��l������Ƃ����p�����������B �@���ہC���Ǘ�̂悤��"�S���Љ�I�ȋ��"�ɑ���킪���̒��Â̌�����C�ɘa�P�A�a����ɒ����������ʂɂ��ƁC�����I�Ȑ[�����ɂ��s�������҂ŁC�S���Љ�I��ɂ����Â̗��R�ƂȂ����҂�1���ɂ����Ȃ��B�����I���ɂ͑啔���������\��1�T�Ԗ����̊��҂ɑ��čs���Ă���B �@�Ō암���́C�掦���ꂽ�͈͂ł͉Ƒ��̈ӌ����s�������C�u���ҁE�Ƒ��̕a�ɔ����r���̃v���Z�X�ƔߒQ��m��C���҂ƉƑ��̊W���₻�ꂼ�ꂪ���҂��ɂ������Ǝv���Ă��邱�Ƃ��l�����ׂ��B�������C��Ⴢɔ����s�����⍇���ǂɑ��郊�X�N���ŏ����ɂ���P�A���d�v�v�Ƃ̌������������B ���a���z�肷�ׂ� �@���q�y�����́C�u�����Ɩ��点�ė~�����v�Ƃ����i�����Ӗ����邱�Ƃ����Ҏ��g�ƂƂ��Ɍ������ׂ����Ǝw�E�B�u�{���͏��������߂Ă���̂�������Ȃ����C���҂��F�����Ă����w�I�͐��m�łȂ���������Ȃ��B�Ƒ����d�ׂɊ����Ă���͎̂v���߂����̉\�����������C�⌾��V�̏����̂��Ƃ��w�E�����炷�܂��Ă����ׂ����ƂɋC�t����������Ȃ��v�ƌ����B �@���Ǘ�̏ꍇ�C�����I�Ȓ��Â��s�����Ƃ��i��ɂ���͉������邪�C����܂��\���\�Ǝv����l�ԂƂ��Ă̐������ł��Ȃ��Ȃ�j�C�Ԍ��I���Â��������Ƃ��i�����̊ԋ�ɂ���������C�o�����ɍĂё����C���ɂȂ�\��������B���ʁC�����̊Ԃł��ӎ��̂��鎞����������邱�ƂɂȂ�j�C���_�I��ɂɑ���ʏ�P�A�����������Ƃ��i�l�ԓI�����𑱂��Ȃ���Ŋ��̂Ƃ����߂����邪�C���ʂ��o�Ȃ������ꍇ�C�炢�����𑗂邱�ƂɂȂ�j�̂��܂��܂ȃ����b�g�E�f�����b�g����������Ƃ��납��n�߁C���Җ{�l����і��炩�ɂ���Ă��Ȃ��Ƒ��̗����ƈӌ����m�F����K�v������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N9��18�� |
||||
| ��63��QOL������@��Õ���j�~��QOL�̊ϓ_�ōl�@ | ||||
| �@�����s�ŊJ���ꂽ��63��QOL������ł́C���ʍu���̏o���҂�Q���҂炪QOL�̊ϓ_�����Õ���̗\�h���l�@�����B �u���������v�Ȃ�4�̌������ �@���H�����ەa�@�̓��쌴�d���������́C����QOL�ƈ�Ê����\�z���C����������菇�ɂ��ču�������B���������́CQOL�ɂ�(1)�Љ���̔\��(2)�����E�m�����ۂ����(3)�ꂵ�݂̊ɘa(4)���������\��4�̌���������ƑO�u�������B�����āu�l�͎���������^�����Ă���C�����̖����L�p�Ɏg���Ă���Ǝ����ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ڕW�i�S�[���j�ւ̒B�����ȂǁC�炭�Ă����������������ď��z���邱�ƂŐ�����������v�ƁC�I�����̊��҂ɂƂ��Ă͐����������������d�v�ł��邱�Ƃ����������B ��t�͌��t�������E�l�ł��� �@���쌴�������͕č��Ɠ��{�̊ɘa�P�A�a���̈Ⴂ����C�I�����ɑ��鑨������_�����B���{�ł͊��҂Ɍ���p�ӂ��邪�C�č���4�`5�l�̑��������嗬�ł���Ƃ����B���̂��߁u�č��ł͕����ɂ���ł�����C�Ϗ܂��y���߂�������Ԃ��ȒP�ɒu����B���҂��ǓƂȂ܂��Ȃ��Ȃ��悤�ɂ��Ă���v�Əq�ׂ��B�܂��C�č��̊ɘa�P�A�ɂ�����ی��f�Â͂����鎾���ɑΉ����Ă��邪�C���{�͖@���ł���ȂLjꕔ�����Ɍ����Ă���_���������ׂ��ۑ�Ƃ����B �@��w�҃E�C���A���E�I�X���[�́u��w�̓T�C�G���X�ł͂Ȃ��C�A�[�g�ł���v�Ƃ������t���Ɂu�a���Ȃǂ����m���邱�Ƃ��C����Ӗ��ł̓A�[�g�ł���v�Ǝ咣�����B���������́u�w�]����1�T�ԁx���Ƃ��ȒP�Ɍ����Ⴂ��t�����邪�C��t�͌��t�������E�l�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�ǂ��܂Ō����ׂ����C�����ׂ��ł͂Ȃ����ȂǁC�����̂Ȃ��ŏ������ςݏグ�Ȃ��犳�҂̐S�������ق������Ƃ��̗v�v�Ƒi�����B �@�Ō��QOL�̌���ɂ͑��҂̖������Ƃ����p�����s���ł���C�u��t���������a�̈ێ������ɂ��ׂ�����ɂ���B�Љ�I��QOL����ɂ͖����������i���Ȃ���Ȃ炸�C������ǂ��q�������ɓ`���邩���l���ė~�����v�ƌĂт������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N12��4�� |
||||
| �I�������ҁ@��t�Ƃ̑Θb�Ŏ��S���O��QOL���� | ||||
| �@�_�i�E�t�@�[�o�[�������i�{�X�g���j��Alexi A. Wright���m��́C��t�ƑΘb�������I�������҂ł́C�Θb�����Ȃ��������҂Ɣ�ׂĐ��_�I��ɂ𖡂키���Ƃ����Ȃ��C���O�̍Ō�̏T�ɐϋɓI���Â͍s���Ȃ��X��������CQOL�������X���ɂ���Ɣ��\�����B �@�I�����ɂ�����Θb����C���҂͎������]�ގ��Â݂̍����C���̃S�[���m�ɂ���@�������B�������C���̂悤�ȑΘb�Ŋ��҂͈�Â̌��E�Ɛl���ɂ͌��肪����Ƃ��������ɒ��ʂ��邱�ƂɂȂ邽�߁C�S���I��Y�̌����Ƃ��Ȃ肤��B �@����܂ł̌����ł́C��t�Ɗ��҂͎��ɂ��Č�邱�Ƃ����߂炤���Ƃ������X�������炩�ɂ���Ă���B�������C���ۂɂ��̂悤�ȑΘb���C���҂̐S���I��Y����і����̎��Ó��e�Ɗ֘A���Ă��邩�ۂ��ɂ��Č������������͂Ȃ������B �@�����ŁCWright���m��́C�������҂�ΏۂɁC�I�����ɂ������t�Ƃ̑Θb�����S�O�Ɏ鎡�Ó��e�Ɗ֘A���邩�ۂ������������B����C�i�s���̂��҂Ƃ��̐e���̉���332�g���ΏۂƂ��C���҂�o�^�����玀�S�܂ŒǐՂ����B�ǐՊ��Ԃ̒����l��4.4�����ŁC���S����6.5������i�����l�j�ɂ͉��҂̐��_������QOL��]�������B�Ώۊ���332�ᒆ123��i37.0���j�����ۂɈ�t�ƏI�����Θb���s�����B �@�����̑Θb�́C��t�ƑΘb�����Ȃ��������҂ɔ�ׂāC�l�H�ċz�i1.6����11.0���j�C�h���p�{�s�i0.8����6.7���j�CICU���@�i4.1����12.4���j�̉��L�ӂɏ��Ȃ��C���S�O�̐ϋɓI�Ȉ�É�����L�ӂɌ������Ă����B �@�܂��C�I�����Θb���s�������҂ł́C��葁���Ƀz�X�s�X�{�݂ɓ��@���Ă����i65.6����44.5���j�B�z�X�s�X���@�����̑����͊��҂�QOL���P�Ɗ֘A���C�ϋɓI�Ȉ�É���̑����͊��҂�QOL�ቺ�Ɗ֘A���Ă����B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N12��18�� |
||||
| ������w�����F����Ɓu�������܂ł��������v�ӎ��@���҂ƈ�t�ɊJ�� | ||||
| �@������w�̌����O���[�v�ɂ��u�����ρv�Ɓu�]�܂������v�Ɋւ���A���P�[�g�ŁC���炪��������ɂȂ����ꍇ�Ɂu�������܂ŕa�C�Ƃ��������v�Ɠ��������҂̊�����81���ŁC��t��19���Ƒ傫�ȊJ�������邱�Ƃ��킩�����B�Ŋ��܂łӂ���ʂ�Ɏ����炵�����������Ɗ肤���҂̎v���ƁC���l���̎����Ŏ���Ă�����t�̍l�����e�����Ă���悤���B ���҂́u�����炵���v���d�� �@���A���P�[�g�͍�N1�`10���ɁC����w�a�@�ɘa�P�A�f�Õ����ŕ��ː��Ȃ̒���b��y�����Ɠ���w��w�@���N�Ȋw�E�Ō�w��U�ɘa�P�A�Ō�w����̋{�����ߍu�t�炪�C��Ï]���҂₪�҂̎��ɑ���ӎ��̔c����ړI�ɍs�����B�����ː��ȊO����f���̂���310�l�i�j��59���j�Ƒw����i�K����ג��o������ʎs��353�l�i��38���j�C���@�ł���f�ÂɌg����t109�l�i��88���j�ƊŌ�t366�l�i��4���j����̉��W�v�B���҂�75�������Â��݂ŁC20�������Ò��ł������B �@�]�܂������Ɋւ���u�������܂ŕa�C�Ƃ��������v�Ƃ̖�ɂ́C����81���Ǝs��66�����u��ɕK�v�v�C�u�K�v�v�C�u���K�v�v�Ƃ����B��t��19���C�Ō�t��30���ɂƂǂ܂����B���҂�s������t�ƊŌ�t���d���������ڂ́u��邾���̎��Â͂����Ǝv����v�i����92���j�C�u���邳�����킸�ɉ߂����v�i��95���j�C�u�����ӎ������ɁC�ӂ���Ɠ����悤�ɖ����𑗂��v�i��88���j�Ȃǂł���B ��Ï]���҂́u���ɔ�����v�X�� �@�t�ɁC��Ï]���҂����҂�s�����d�������̂́u�c���ꂽ���Ԃ�m���Ă����v�i��t89���j�C�u������l�ɉ���Ă����v�i�Ō�t92���j�Ȃǂł������B���҂�s���������ӎ������ɉ߂����čŊ����}�������ƍl�������C��t��Ō�t�͗]����c�����邱�ƂŎ����}���鏀���𐮂������Ƃ���X���ɂ������B �@�ǂ̉҂������x�d�����Ă����̂́u�̂ɋ�ɂ������Ȃ��v�C�u�����a�@�ȂǁC�������]�ޏꏊ�ʼn߂����v�C�u�M���ł����t�ɐf�Ă��炦��v�Ȃǂł������B �@�{���u�t�͖]�܂������ɑ���F���̊J���ɂ��āC�u���a���C���҂͂���������Ȃ�����O�����ɖ������߂������Ƃƍl���C��Ï]���҂͉��w�Ö@�Ȃǂ̐ϋɓI�Ȏ��Â��I�����ɂȂ��Ă������邱�ƂƑ����Ă���̂�������Ȃ��v�ƕ��́B�u�����܂ł���Ï]���Ҍl�̍l���ł���C�����Ċ��҂̋C���ɑ��閳�����⎡�Îp���̕\��ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ��B���̂����Łu��Ï]���҂͊��҂Ƃ̃M���b�v�܂��C�X�̊��҂��d�����邱�Ƃ��ꏏ�ɍl���ďI�����×{���x����K�v������v�Ƃ܂Ƃ߂��B �u���ւ̋��|�v�͈�t������ �@�����ςɂ��āu����̐��E�͂���v�C�u��₽����͂���v�̖���m�肵�����҂�2�����ŁC��ʎs������10�|�C���g���Ȃ������B�Ō�t�͂������4���ȏ�ł������B�S�̓I�ɁC�j�������������`���I�Ȏ���̐��E�ς�L����X���ɂ������B�^���_�I�Ȍ����ɂ��Ắu�����͌��܂��Ă���v�C�u�����͉^���ȂǂŌ��܂�v�Ƃ������҂�35�����ŁC4�Q�ōł����������B �@����y�����́u���҂͎���̐��E��썰�ȂǓ`���I�����ς��������C�^���_�I�ȌX����������v�Ǝw�E�����B �@�u�����|���v�Ɠ�������t��64���ŁC���҂�51���ƈ�ʎs����56�����������B�ގ�����u���͋��낵���v�Ƃ̖�ł��C�Ƃ���37���ł��������҂�s�������C��t�̂ق���48���Ƒ��������B���y�����́u��Î҂́w�����w�I�Ɏ��͖��ƂȂ�x�ȂǁC�����Ȋw�I�ɑ�����ӎ������邩��ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N2��26�� |
||||
| �ɘa�P�A�`�[���̉ۑ�ɏœ_�@�I�������҂ւ̑Ή����b��� | ||||
| �@��14����{�ɘa��Êw��w�p��19�A20���̂Q���Ԃɂ킽��A���s�ŊJ���ꂽ�B�����̃e�[�}�́u�ɘa��Á|���_������H�ց|�v�B�ɘa�P�A�`�[���̉ۑ�����グ�����������ق��A�m�a�l�iNarrative
Based Medicine�j�̊ϓ_����ɘa��Â݂̍�����l����V���|�W�E�����g�܂ꂽ�B�I�������҂ւ̑Ή����b��ƂȂ����B
�@�w��Q���ڂɂ́u���҂̐S�Ɋ��Y���`�ɘa��Âɂ�����m�a�l�̊ϓ_�`�v���e�[�}�ɃV���|�W�E�����J���ꂽ�B���s���w���t���a�@����T�|�[�g�`�[���̊ݖ{���j���́A�a�����҂̐l���̒��œW�J����P�́u����v�ƂƂ炦��m�a�l�ɂ��āA���҂���̕���̕����o�����d������l�����Љ�B�x�R��ی��Ǘ��Z���^�[���V�����́A��Â̌���łm�a�l���d�a�l�iEvidence Based Medicine�j��������Ƃ̎��_��W�J�����B �@ �ݖ{���ɂ��ƁA�m�a�l�Ƃ͕a�����҂̐l���̒��œW�J����P�́u����v�ƂƂ炦�A���҂�̌���Ƃ��đ��d�����@�B�����ɁA��w�I�Ȏ����T�O�⎡�Ö@���u��Îґ��̕���v�ƂƂ炦�A���҂̕�������荇�킹�āu�V��������v�����o���v���Z�X�����Âƈʒu�t����B �@�ݖ{���́u�ɂ݂��߂��镨��v�Ƒ肵�āA�A�ǂ��҂̃G�s�\�[�h���Љ���B���҂̓I�s�I�C�h�Śq�C���������o������A�ɂ݂��䖝���Ăł��I�L�V�R�h���̎g�p�����ۂ������Ă����B�������m�a�l�Ɋ�Â����A�v���[�`�ɂ���āA�ŏI�I�ɃI�L�V�R�h���̓��^�����ꂽ�Ƃ����B �@�V���� �́A�ݖ{���͊��҂ƈ�t�Ƃ̋�̓I�Ȃ����̒�����A���҂̕���i���a�j���܂������o�����Ƃ��|�C���g�Ƃ��Ďw�E�B���̃P�[�X�ł́g�ɂ݂����������h�Ƃ����͈̂�Îґ��̕���ł���A���̂��Ƃɉe������߂���ƁA�u�i���҂̕�������āj�ɂ݂�����C�Ɋ|���長�����ɂȂ��Ă��܂��v�ƒ��ӂ𑣂����B �@�܂��A���ɗ��҂̕��ꂪ����Ă��Ă��A�C�荇�킹�ĐV������������o�����Ƃ͉\�ł���Ƃ̌�����B��������ɂ́A���҂̈Ⴂ��A�C�荇�킹�̕K�v�������o���Ă������Ƃ��s���ł���Ƃ����B �@�V�����͂m�a�l�Ƃd�a�l�̊W�ɂ��āA�Η��I�ȗ������嗬�ł���Ɛ����B���̏�ŁA���҂̐��E�ς͈قȂ���̂́A���҂ƈ�t�Ƃ̑Θb�̌���ɂ����āA�m�a�l�͂d�a�l���E����������Ƃ̍l�������������B �u�m�a�l�ɃG�r�f���X��荞�߂�v �@�m�a�l�̎�@�����܂��@�\����A��Î҂Ɗ��҂Ƃ̊ԂőΘb���i�݁A���̌��ʁA���ÂɊւ��鋤�L�̕��ꂪ���o�����B���̕�����\�z����O������̗v�f�Ƃ��āA�G�r�f���X���m�a�l�̒��Ɏ�荞�܂��Ƃ����B �@�V�����̓G�r�f���X�̋�̗�Ƃ��āA�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�Ȃǂ�B�u�m�a�l�̍\���̒��ɃG�r�f���X�͏\���Ɏ�荞�ނ��Ƃ��ł���v�Ɨ͐������B m3.com�@2009�N7��17�� |
||||
| �s�����J�u���F����Ƃ̌����������@�z�X�s�X��E�R�肳�u�� | ||||
| �@�������a�u�������v�̗]�T�� �@����Ƃ̌����������ɂ��čl����s�����J�u�������̂قǁA�b��s�������̂����������s���z�[���ŊJ���ꂽ�B�����s�́u�P�A�^�E�������N���j�b�N�v�@���ŁA�ɘa�P�A�̐��ƂƂ��Ēm����R��͘Y�@�����u�t�Ƃ��ď�����A�u����ƌ��������`�n��Ŏx����v���e�[�}�ɍu�������B �@�R�莁�͂X�P�N����A�z�X�s�X��Ƃ��Ă��҂Ƃ�������Ă���B��������������A��\��́u�ڂ��̃z�X�s�X�P�Q�O�O���v�u�z�X�s�X�錾�v�ȂǁB �@�u���ŎR�莁�́A�������a�ƌ����錻���w�i�ɁA�u�i����ɂȂ��Ă��j�w���Ŏ����c�c�x�ł͂Ȃ��w����ς莄�����x�ƃ����N�b�V�����u���ĂƂ炦�������ǂ��v�ƁA�]�T�̂���S�\���̏d�v��������B���̏�Łu��l�̈�t�����łȂ��A�Z�J���h�I�s�j�I���A�T�[�h�I�s�j�I�����A�[���������Ö@��I�����ׂ����v�Ƙb�����B �@�܂��A�z�X�s�X��̌o������w���ƂƂ��āA��ɏǏ�ɘa�̑�����C���t�H�[���h�E�R���Z���g�i�����Ɠ��Ӂj�̑����������Ӗ������������l�ւ̃P�A--�Ȃǂ������A���ɃC���t�H�[���h�E�R���Z���g�ɂ��āu���҂̐l���͊��Ԍ���B���̒��Łw�l�Ԃ炵���x�w�����炵���x������ɂ́A�����ōl���A���f���邱�Ƃ��d�v�B��t�����m�ŃE�\�����A���̐l�̐l���Ȃ����ƂɂȂ�v�Ƙb�����B m3.com�@2009�N9��30�� |
||||
| ������F���������L�����y�[���@��Q�T����{��������w��E�����V���| �@���P�O��̎��A�Y�ݐ[���@�ǂ����������A�x���邩 |
||||
| �@��Q�T����{��������w��Q�O�O�X�N�P�P���Q�V�`�Q�X���A��t���Y���s�̓����x�C�z�e�����}�ŊJ���ꂽ�B��������⌌�t�����̊��҂��K���ɁA���C��
�Ȃ��Ăق����Ƃ����肢�����߂��u�N�̏Ί�@�݂�Ȃ̖��v���e�[�}�ɁA���{�������t�w�����{��������Ō�w��Ɠ����J�Â��ꂽ�B���ł͂V�������鏬����
���A���ǂ⎡����̎����ȂǑ����̖�肪�c����Ă���B����ŁA�������]�߂Ȃ��q�ǂ�������̂��������B���Җ{�ʂ̈�Â̂������A�x���Ɍ�������
�t��Ō�t�A�\�[�V�������[�J�[�̔����Ȃǂ��Љ��B �@�w����Ԓ��A���Ҏx���c�́u����̎q��������v�Ɠ��{��������Ō�w��J�����A�����V���|�W�E���u�P�O�㊳�҂̎����߂�����v�B������ӎv���肪 �\�ȂP�O�㊳�҂̃P�A�ɂ��āA��t��Ō�t�A�`���C���h�E���C�t�E�X�y�V�����X�g�i�b�k�r�j�Ȃǂ��܂��܂ȗ��ꂩ��A�ӌ����o���ꂽ�B �@���ꐫ�ƕ������K�v�|�|��t�E������a���� �@�P�O��̊��҂́A��l��f�Ă���l�ɂ͗������ɂ���������������������Ă��鐢��B�������m�����Ă������W�r��̎����ŁA�ƂĂ��s����ȏɒu����� ����B���̕s����Ȏ����ɁA���Ǝ��𗝉����悤�Ƃ������Ƃ́A����ɕs���肳��������ނƂ������Ƃ܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�h�ꓮ���ނ����������~�߂āA�u���v���v�Ǝx����ꐫ�ƁA�����Ɍ��������悤�����������K�v���Ǝv���B���̊T�O�̔��B�́A�P�O����Ƃق� ���l�Ɠ������炢�ɂȂ�Ƃ����邪�A�q�ǂ��ɂ���ĕ�������B�q�ǂ����ǂꂮ�炢�����l���Ă��邩���X�Ɍ��ɂ߂ĉ�b���A�ނ炪���߂Ă������`�� �Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�M���W���y��ƂȂ�A���Ǝ��Ƃ����s����ő傫�Ȗ���ނ�͎����̒��ɉ��Ƃ�������āA�����}���Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�� �Ă���B �@�������̓x�b�h�T�C�h�Ɂ|�|�Ō�t�E�c���b������ �@�q�ǂ��́A�������g�Œɂ݂��ɂ�i���ɂ����Ƃ��낪����B���Ɏv�t���͐S�g���ɐ��l�ֈڍs���l�ԊW���`�����Ă��������ł���A�����g����������� ���Ă���B �@�G���h�I�u���C�t�̂Ȃ��ŁA�Ō�t�Ƃ��Ăǂ��x���Ă������ƍl�����Ƃ��A���̎q�ƌ����������Ɓ����ɂ��邱�Ɓ��Ō�t�Ƃ��Ď����̎����Ă���͂��ő�� �o�����Ɓ�������͂��x���邱�Ɓ���]�����������邱�Ɓ����d���邱�Ɓ|�|�Ȃǂ��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B��������Î҂́A���҂Ȃǂɉ��������邩���� �炸�s���ɂȂ������A�x�b�h�T�C�h�ɍs���Â炢�Ƃ������Ƃ��o������B�Ō�̐��E�Ƃ��Ď��������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɩ��������́u�K�������̓x�b�h �T�C�h�ɂ���v�ƐM���A���ƌ��������鎩���ł��肽���Ǝv���Ă���B �@�������̎q�ǂ��̎��ւ̑Ή��|�|�b�k�r�E���c�T�q���� �@�a���Ŏq�ǂ����S���Ȃ������A�N��ɂ�����炸�c���ꂽ�q�ǂ����e�����܂��܂Ȕ����������B���[���Ȃǂ̕��y�ɂ��A���h�͕a�������ł͂Ȃ��O����K�� �w���ɂ��L����B���������Ƒ��̔������A��Î҂��ǂ��T�|�[�g����̂��l����K�v������B����ŁA�q�ǂ���S�������e�̍l�����ɔz�����邱�Ƃ�����B �@�����̎q�ǂ��̎��ɁA�c���ꂽ�q�ǂ������͂��܂��܂ȑr�������������B�A���o�����������肷�邱�ƂŁA�C���������A�S�̒��ɖS���Ȃ����q�ǂ����� �z�u���邱�Ƃ̎肪����ɂ��Ȃ�B����m�����ɂ���v�t���̎q�ǂ��ւ̃O���[�t�P�A�i�ߒQ�ւ̎x���j�́A�F�l�̎���`����^�C�~���O�̔z����A�`������� �S���A�Љ�I�w�i���l���������E��ɂ�鐸�_�I�ȃT�|�[�g���K�v���B �@���Z�J���h�I�s�j�I���̑��k�����|�|�\�[�V�������[�J�[�E������q���� �@��N�x�̑��k�����́A���ז�P���W�O�O�O���ŁA�����͕�e����̑��k�����A�ŋ߂ł͖{�l����̑��k�������Ă���B���Ò�����{�l�̑��k����P�[�X�� ���邪�A����͂P�O��̊��҂����S�ɂȂ��Ă���B �@�������Ƃ�����Ȃ��Ă����i�K�ɂȂ�ƁA�Z�J���h�I�s�j�I���̑��k�������B�u�����������Ƃ�����Ȃ����v�Ƃ����̂��ǂ��`���邩�Ƃ����������A��� �]���҂ɗ������Ă��炢�����Ǝv���Ƒ��������B �@�݂�Ȃ����݂��̂��Ƃ��v������Ċ撣�肷���邩�炱���A���Ԃ����ݍ���Ȃ��Ƃ������Ƃ��P�O��̊��҂̏ꍇ�ɂ͑����Ǝv���B�\�[�V�������[�J�[�́A�Z ���e�̎x�������A�Ƒ����ǂ����҂��x���Ă��������ꏏ�ɍl���闧��ɂ���B��������҉Ƒ��ƈꏏ�ɁA�G���h�I�u���C�t�̋ǖʂ��l���Ă��������Ǝv���B �@���q�ǂ��̎������ꂸ�|�|���҉Ƒ��E�����m�q���� �@���͏��w�T�N�Ŕ����a�a���A�U�N���̓��a�̊ԂɂT��̍Ĕ����J��Ԃ����B�T��ڂ̍Ĕ��̎��́A�����ƈႤ�Ɗ����Ă����B �@��t�Ɂu����ȏ㑱����Ɩ{�l�ɂƂ��ċ�ɂł����Ȃ��v�ƌ���ꂽ���A���Â��~�߂邱�Ƃ͎��������Ă��邱�Ƃ��Ƌ��|���������B�o��͂��������肾 ���A�ڂ̑O�Ɏ����̎q�ǂ��̎�������Ƃ������Ƃ��A�ǂ����Ă�������Ȃ������B�]����鍐�������ƂŁA���̋C�͂��Ȃ��Ȃ�����Ǝv���ƕ|�������B �@��t��Ō�t�͍őP��s�����Ă��ꂽ�Ǝv�����A���̎��͂��ꂪ������Ȃ��قǐ��_�I�ɕs���肾�����B�q�ǂ��ƈꏏ�Ɏ��ƌ����������Ęb�������A�������� �����Ă�Ƒ��͂���Ǝv���B����ŁA���_�I�ɕs���ɂȂ��Ęb���E�C���Ȃ��������̂悤�Ȑe������B�Ƒ��̂��Ƃ��l���ăT�|�[�g���Ă��炢�����Ǝv���B �@���^�[�~�i�����̃P�A�u�K�C�h���C���v�������|�|���[�N�V���b�v �@�u����̎q��������v�̃��[�N�V���b�v�ł́A�u�^�[�~�i���P�A�̃K�C�h���C������낤�v���e�[�}�Ɉӌ����������ꂽ�B �@��������̎����������サ�A�q�ǂ�����������ŖS���Ȃ邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ��Ă������A�^�[�~�i�����̃P�A�ւ̈ӎ����Ê��̐����͏\���Ƃ͂����Ȃ��B�� ���œ���ł́A���N�̔��s��ڎw���Č�����i�߂Ă����B �@����́A�K�C�h���C���̂����u�q�ǂ��̐S�Ɋ��Y���āv�Ɓu�^�[�~�i�����̉߂������v�̍��ڂɂ��ĕ��͂�B�u���m���O��ɂȂ��Ă���̂ł́v�u�� �a�P�A�́A�v��������Βʂ���̂ł͂Ȃ����v�u�w�`���Ă�����x�Ƃ������t�͂ǂ����v�|�|�ȂǂƎq�ǂ���S�������Ƒ����t�A�Ō�t�炪���܂��܂Ȉӌ��� �q�ׂ��B �@�K�C�h���C���쐬�ψ���̍גJ�������H�����ەa�@���@���́u�K�C�h���C�����ł��邱�ƂŁA�����Ă����q�ǂ������̐e�ł��A����Ȃ������q�ǂ������̂��� ���l���Ă��炦��v�Ƙb�����B �@���v���͂����H�@����̎q�ǂ��G��W �@��D���ȉƑ����̉��̃T�b�J�[�{�[���A�������Ȃ��Ă����N�W���|�|�B���P�K�ł͏�������̎q�ǂ������̊G��W���J���ꂽ�B�S������W�߂�ꂽ�S�V �_���W������A�͋����G�Ɍ�����l�������₦�Ȃ������B �@�|�X�^�[�ɂ��Ȃ����u���ł��������傾��v�́A�����s��c��̈�c�T���N���A�Q�U�J���̎��ɕ`������i���B�T���N�̏����Ȏ�`�ŁA�����̂��Ƃɂ��� ���́u���ꂳ��v��\���A�u�q�ǂ������v���w�ŕ\�������B�T���N�͂R�V�J���ŖS���Ȃ����B���e�́A��i�Ɂu���̂ɂ�Ƃ肳��ƂЂ悱�����̂悤 �ɁA���ł��ꏏ����v�ƃ��b�Z�[�W���Ă���B �@�{�����e�B�A�ŊG��W�ɎQ�������A��̐�������i�R�V�j�́A�u�T�����c���Ă����Ă��ꂽ���̂��A���������`�œ`���Ă�������v�Ƙb���Ă����B �����V���@2009�N12��12�� |
||||
| ��22����{�����a�@���_��w�� ���g�ݐi�ނ��҂̐S�̃P�A�Ɋ��� |
||||
| �@����f�ØA�g���_�a�@�ɂ�����ɘa�P�A�`�[���̐ݒu���K�{�ƂȂ�C�ɘa�P�A�ƕ����"�S�̃P�A�i���_��ᇊw�j"�����ڂ����悤�ɂȂ��Ă����B���s�ŊJ���ꂽ��22����{�����a�@���_��w��̃V���|�W�E���u�ɘa�P�A�Ɛ��_��ᇊw�̖ڎw�����́v�ł́C���҂��悷�邳�܂��܂Ȑ��_�Ǐ��S����Ԃɂ��āC�����Â̌���̍őO���ŐS�̃P�A�Ɍg��鐸�_�Ȉォ��̕��s��ꂽ�B �S���Љ�I����@�̊J�����i�� �@����Տ��ɂ����邳�܂��܂ȐS�����ʂ̖��ɂ��Č��y�������É��s����w��w�@���_�E�F�m�E�s����w�̖��q���j�y�����́C���҂ł͂����鎞���ɑ��ʂȐ��_�Ǐ��S����Ԃ��F�߂���ƊT���B�����������҂̌X�̐��_�Ǐ��S����Ԃɑ��āC�Ȃ�炩�̉�����K�v�ƂȂ��Ă��Ă���C���݂͐S���Љ�I����@�̊J�����i��ł��邱�Ƃ�����B �@���q�y�����ɂ��ƁC���_��w�I�f�f�̊ϓ_����́C���҂͑S�a���ɂ����Ė��ɂȂ�炩�̐��_�Ǐ����C���ɕs���C�}���̕p�x���������Ƃ�������Ă���B����Ƌ������Ȃ��琶����u����T�o�C�o�[�v�ɂ����Ă��C�Ĕ��E�]�ڂ̕s���C���Ȃ킿"�Ĕ��s��"�̕p�x�͍����B �@�܂������̉u�w�����ɂ����āC���҂͈�ʐl���ɔ�ׂĎ��E������2�{���x�C�L�ӂɍ����C���ɐi�s����̊��҂Őf�f�㐔�����ȓ��̎��E���ł��������Ƃ����ʂ��Ď�����Ă���B�ŋ߂̊ɘa��Â̌���ł́C�I�������҂ɂ����đ����F�߂���u�����I��ɁiPsycho-existential suffering�j�v�i���Ȃ̑��݂ƈӖ��̏��łɋN�����Đ������Ɂj�ɊS�������C���̌������i��ł���B �@�܂����y�����́C�R����^�Ɋ֘A���Ĕ����������Țq�C�E�q�f�Ƃ��āC�Óf��p�̋����R�������J��Ԃ����^����Ă��銳�҂ł́u�\�����S�E�q�f�v����30���ɔF�߂���ƕB�_�H���ɓ�������C�_�H�{�g����������C���˂̑O�ɃA���R�[�����ł����ꂽ�����ň��S�C�q�f�𗈂����Ƃ�����Ƃ����B �@�����������҂̍Ĕ��s��������I��ɂȂǂɑ��ẮC���ۓI�ɂ��W�����Ö@���m������Ă���킯�ł͂Ȃ��B���݂킪���ł́C���Ɍ����J���Ȃ̌����ǂ����S�ƂȂ�C�Ĕ��s���ɑ��Ắu�������Ö@�v�C�����I��ɂɑ��Ắu�f�B�O�j�e�B�Z���s�[�v�̊J�����i�߂��Ă���Ƃ����B �@�������Ö@�́C��肪��������ΐ��_�Ǐ��P����Ƃ����V���v���ȃ��f���ŁC�u�������Z�@�i5�X�e�b�v�j�v�őΉ��\�Ƃ����l���̂��ƂɎ��Ã}�j���A�����쐬����Ă���C���ۂɏp��̓����҂ɑ��ēK�p�������ʁC���_�Ǐ��P�������Ƃ�������Ă���B �@�f�B�O�j�e�B�Z���s�[�́C�i�s�E�I�������҂̎����I��ɂ��ɘa���C���҂̌Ƃ��Ă̑������ێ����邽�߂̎��ÂŁC9�̎���v���g�R���Ɋ�Â��ʐځi30�`60����3�C4��j��^����C���������������Ŋ��҂Ƌ�����ƂŕҏW���s���B �@���y�����́C�����������҂ɑ��邳�܂��܂Ȑ��_�Ǐ�C�S����Ԃɑ��ĐV���ȐS���Љ�I����@�̊J�����]�܂�Ă��邱�Ƃ��w�E�����B �����Âɐ��ʂ������_�Ȉオ�K�v �@���҂͂��܂��܂Ȑ��_�Ǐ��悷�邱�Ƃ������B��ʈ�ȑ�w���ۈ�ÃZ���^�[���_��ᇉȂ̑吼�G�������́C���҂̐��_�Ǐ�͎��Â���ѓ��퐶���̂��܂��܂Ȗʂɕ��̉e�����y�ڂ����Ƃ��w�E���C�����Â₪�҂���т��̉Ƒ��̐S���Ȃǂɐ��ʂ������_�Ȉ�̐f�Â̕K�v�������������B �o�^���_��ᇈ㐧�x���X�^�[�g �@�吼�����́C���҂ɂƂ��Đ��_�Ǐ��"���"�ł���Ǝw�E���C�u���҂́C���w�Ö@�����C���a�̂ق����ꂵ���ƌ����v�Əq�ׂ��B�܂��C���҂̖�9���͏p�㉻�w�Ö@���Ă��邪�C�}���Ǐ��悷�邪�҂ł́C��5�������p�㉻�w�Ö@���Ă��Ȃ��Ȃǂ̕�����C�ӎv�����Q��QOL�̒ቺ�C����ɉƑ��̐��_�I��ɂ⎩�E�ȂǁC���܂��܂Ȃ����Âɋy�ڂ����_�Ǐ�̕��̉e��������ƊT�������B �@���̂����œ������́C�����Â₪�҂̐S���C���_��w�I�Ȗ��ɐ��ʂ������_�Ȉ�ɂ��f�Â̕K�v�������������B �@�܂��C���҂̉Ƒ��͎����̋�Y��i���Ă͂����Ȃ��ƍl���C�Ƒ��̋�Y�͉ߏ��]�������X�������邪�C���҂̉Ƒ���"��2�̊���"�ƌ����Ă���C���ÂƃP�A�̑Ώۂł���Ǝw�E�B�����Âɏ]�����鐸�_�Ȉ�́C���҂̉Ƒ��̐S���ɂ����ʂ���K�v������Ƃ����B �@���������g�͊��ɁC�����̂��ҁC�Ƒ��̐f�Â��s���Ă��邪�C��������̐f�Â��s���Ȃ��Ō����Ă�����̂�����C������Ҍ����邱�ƂŁC���_��ÑS�̂̔��W�Ɋ�^�ł���ƍl���Ă���Ƃ����B �@�ŋ߂ɂȂ�C"�T�C�R�I���R���W�[�i���_��ᇊw�j"�Ƃ����w�₪���ڂ����悤�ɂȂ����B���{�T�C�R�I���R���W�[�w��ł́C�{�N�x����u�o�^���_��ᇈ�v���x���J�n���C�z�[���y�[�W�ihttp://jpos-society.org/�j��œo�^���_��ᇈオ���J�����\��ł���B�������́C�����Âɂ����鐸�_��ᇈ�̕K�v�������������B �i�s���҂̑傤�a�ɑ���Ö@�A���S���Y�����T�� �@���҂ɍ������邤�a�ƓK����Q�́C��ʐl���ɔ�ׂėL�a���������C���Âɓ������Ă͂���̕a��C���Â��l�������Ή����K�v�ɂȂ�B��������Z���^�[�����a�@�i�����s�j���_��ᇉȂ̐��������́C���҂ɍ������邤�a�C�K����Q�̐f�f�C�����C����@�̎��ۂȂǂɂ��ĊT�������B ��Ã`�[���̘A�g�����Ή����d�v �@�������ɂ��ƁC���@�ł͂��҂̂��a�̐f�f�ɂ��ẮC���ʂȐf�f����p�����Ă���킯�ł͂Ȃ��C�č����_��w��ɂ�鐸�_�����̕��ނƐf�f�̎������4�ŁiDSM-IV�j���p�����Ă���B�������C���f�f��ɂ���u������Q�v�C�u�H�~�ቺ�v�C�u�v�l�E�W���͒ቺ�v�C�u���ӊ��v�Ƃ������Ǐ�͂���ɂ��Ǐ�Ƃ̋�ʂ�����B�Ⴆ�C�݂��i�s����ƁC����̏Ǐ�Ƃ��ĐH�~�ቺ�������邱�Ƃ�����B�����́u���a�̐f�f��Ɋ܂܂�邱���̏Ǐ���ǂ̂悤�ɕ]�����Ă������́C����ꂪ��ɔY�ނƂ��낾�v�Əq�ׂ��B �@���̂��߁C���҂̂��a�f�f�@�Ƃ��āCDSM-IV�̐f�f��݂̂ɕ߂���Ȃ���I�f�f�i����̏Ǐ�ɂ��\���������Ă������j�C���O�I�f�f�i����̏Ǐ�ɂ��\��������Ǐ�͊����O���j�C��֓I�f�f�i����̏Ǐ�Ɋ֘A����\��������ꍇ�͑�֊���̗p����j�Ȃǂ������̃A�v���[�`�@����������Ă���B�ǂ̃A�v���[�`�@����ΓI�ɐ������Ƃ������̂ł͂Ȃ����C���݂́u�ߑ�]��������ߏ��]�����Ă��a���������Ă��܂����Ƃ̃f�����b�g�̂ق����傫���v�Ƃ����̂��Տ��łقړ����Ă���R���Z���T�X�ł���C��I�f�f���p�����邱�Ƃ������Ƃ����B �@�܂��C���a�ɑ���Ö@���s���ꍇ�ɂ́C���҂Ɋ��ɏo�����Ă���Ǐ�Ȃǂ��l���Ȃ���C�R����̑I�����s���K�v������B�����́C���Z���^�[�ł͐i�s���҂̑傤�a�ɑ���Ö@�̃A���S���Y�����쐬���Ă���ƕ����B�傤�a�̏d�Ǔx�]���Œ����x����d�ǁC���邢�͌y�ǂł��x���]�W�A�[�s���n�R�s����̃A���v���]�������^�Ŗ����ȏꍇ�ɂ́C��ʓI�ȍR���p�����邪�C���҂̌X�̕���p�v���t�B�[���ɂ���Ďg���������Ă���B�Ⴆ�C�R�����𓊗^���Ă��ēf���C�ŋꂵ��ł��邪�҂ɁC����ɓf���C�̃��X�N�̂���I��I�Z���g�j���Ď�荞�ݑj�Q��iSSRI�j��Z���g�j���E�m���A�h���i�����Ď�荞�ݑj�Q��iSNRI�j�𓊗^���邱�Ƃ̓��X�N�������ƍl�����Ă���B �@�܂�������́C���@���_��ᇉȂɏЉ��CDSM-IV�ɂ��傤�a�Ɛf�f���ꂽ�Ǘ�̂����C���_�ȏЉ��3�����ȓ��Ɏ��S���m�F���ꂽ20���ΏۂɁC�I�������҂̂��a�ɑ��鐸�_�ȉ���̗L������\���I�Ɍ��������B���̌��ʁC�\��1�����ȓ��ł�����9�ᒆ8��́C�R���^�ɂ��Ǐ���P�͔F�߂��Ȃ������B�����́u�\��1�����ȓ��̂��҂ɍR����𓊗^���郁���b�g������̂��B�ނ��땛��p��������ɏo�Ă��܂��̂ł͂Ȃ����v�Ǝw�E�B�I�������҂̂��a�ɂ��ẮC�����čR����͓��^�����C���ӊ��ɂ��Ă̓X�e���C�h�𓊗^����ȂǁC�����ɏǏ���ɘa���邱�ƂőΉ����Ă����̂��悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ����B �@����ɓ����́C���҂̂��a�̓����Ƃ��āC�u�ɂȂǂ̐g�̏Ǐ�̊ɘa��Љ�I���i�Ƒ��̃T�|�[�g�̒ቺ�Ȃǁj�C�����I��ɂ��֘A���Ă���Ƃ���Ă���Ǝw�E�B�����̊֘A�v�����܂߂��g�[�^���ȃP�A���K�v�ł���C��Ã`�[���̘A�g�����Ή����d�v�ł���Ƌ��������B ����ώ��Â͂���늳�̓����𗝉������x���I�P�A�� �@����ς́C���҂��ɘa�P�A�a���ɓ��@���鎞�_�Ŗ��C���̒��O�ɂ͖�8���Ɍ�����B���É��s����w��w�@���_�E�F�m�E�s����w�̉��R�O�u�t�́C���҂ɂ����邹��ώ��Âɂ��āC����ψȊO�ɂ����܂��܂ȋ�ɂ�L���Ă��邱�Ƃ�z�����C�x���I�ȑΉ����K�v�ł��邱�Ƃ��w�E�����B �I�s�I�C�h�֘A�̂���ςւ̑Ή��ɂ��K�n�� �@���R�u�t�́C���҂ɂ����邹��ώ��Âł͂܂��C����늳�̓������悭�������ăP�A�ɓ����邱�Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ����������B���Ȃ킿�C����̌o�߁C�Ƒ��\���C�������C�a��������e�Ȃǂ̏\���Ȕc�����K�v�ł���C����ς̎��Â����łȂ��C���ҁC�Ƒ��ւ̎x���I�ȃP�A���K�v�ł��邱�Ƃ��w�E�����B �@�܂�����ς́C�u�Ɏ��Âɑ��ĕp�p�����I�s�I�C�h�Ɋ֘A���Đ����邱�Ƃ��������C�ɂ݂Ƃ���ς̊ɘa�̗����͓�����Ƃ������B����ςƂȂ邱�Ƃ��u�ɕ]��������ɂȂ邱�Ƃ�����C������f�������邱�Ƃ��������߁C���_�Ȉ���ɂ݂̎��ÁC�I�s�I�C�h�̎g�����Ɋւ����{�I�m�����K������K�v������Ƃ����B �@�I�������҂ɂ����邹��ς͕p�x�����������ɁC��t�I�Ŏ��Ô������ɖR�������Ƃ������B��ÂƂ��ẴS�[�����s���ĂȂ��Ƃ������C�ǂ̎��_�ł���ς̎��Â���[�������I���ÂɈڍs����̂��Ƃ�����������B���u�t�́u�g�̓I���ʂ⊳�҂���т��̉Ƒ��̈ӌ���O���ɁC��ÂƂ��Ă̍őP�̃S�[�����l���C��I�Ȏ��_����P�A�ɓ�����K�v������v�Əq�ׁC��Ã`�[���Ə��C��ẪS�[���C���̗D�揇�ʂȂǂ����L���C�A�g���邱�Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ����������B ��I�P�A�������ɘa�P�A�`�[���̈琬�� �@����f�ØA�g���_�a�@�i�ȉ��C���_�a�@�j�ɂ�����ɘa�P�A�`�[���̐ݒu���C2007�N4���ɋ`�������ꂽ�B��������Z���^�[���a�@�i��t���j�Տ��J���Z���^�[���_��ᇊw�J�����̏��쒩�������́C�ɘa�P�A�`�[���ɂ����Đ��_�Ȉ�́C���_�Ǐ�ƐS���Љ�I�������킹���]���Ǝ��Â��s�����Ƃ����߂��Ă��邱�Ƃ���C��I�ȃP�A�������I�ɘa�P�A�`�[���̈琬�̕K�v�������������B �����Âɂ����鐸�_�ی����Ƃ��x������̐��� �@���쎺���́C�R���T���e�[�V�����E���G�]�����_��Ái�Տ��e�ȂŌ����鐸�_�Ǐ�̐f�Áj�ɂ����鐸�_�Ȉ�̖����ƁC���I�ɘa�P�A�`�[���ɂ����鐸�_��ᇈ�Ƃ��Ă̖����ɂ��Ĕ�r���C�O�҂ł͐��_�Ǐ�̊ɘa�����߂���̂ɑ��C��҂ł͕�I�ȏǏ�̊ɘa�C���Ȃ킿���_�Ǐ��łȂ���ÃX�^�b�t�C�Ƒ����܂߂��Ή������߂���Ǝw�E�B�܂��R���T���e�[�V�����E���G�]�����_��Âł́C���ÂɊւ��Ď��Ԃ̑����͏��Ȃ��C������x�g�̎��ÂƓƗ������Ή�����{�I�ɂȂ���邪�C���I�ɘa�P�A�`�[���ł́C���Â̒i�K�܂����Ή����K�v�Ŏ��Ԃ̐���������C���ʂ��𗧂Ă��Ή������߂���Əq�ׂ��B �@���{�ɘa��Êw�2008�N�ɍs�����u����f�ØA�g���_�a�@�̊ɘa�P�A�y�ё��k�x���Z���^�[�Ɋւ��钲���v�̌��ʂɂ��ƁC���_�a�@�ł̊ɘa�P�A�`�[���̕��ψ˗�������1�����Ԃŕ���4.5���C35���̎{�݂�3�����Ԃň˗�������10�������ł������B�܂����{�ɘa��Êw��ɏ������Ă����t�� 76���ŁC���{�T�C�R�I���R���W�[�w��ɏ������Ă����t��28���C�Ō�t���F��܂��͐��Ō�t�ł������̂�57���ł������B �@�������́C�킪���ɂ�����ɘa�P�A�`�[������������_�Ƃ��āC�����o�[�̂قƂ�ǂ����C�ŁC�Ζ����ԓ��̊������m�ۂ���Ă��Ȃ��i�l�̃{�����e�B�A�j���ߌ��C�@��s�����Ă���C�ߓx�Ɍl�̔\�́E�ӗ~�Ɉˑ����Ă���ʂ����邱�Ƃ��w�E�B�܂��g�D���̈ʒu�t�����s���m�ŁC�������̌n������Ă��Ȃ����ƂȂǂ��������B �@���_��ᇊw�͔�r�I�V�����w��ł���C�킪���̐��_��ᇈ�͂܂����ɏ��Ȃ��B���Z�Ȍ���ŗՏ��̍őO���ɗ����_�Ȉ�ɂƂ��āC�]���̋Ɩ��ɉ����Ċɘa�P�A�`�[���̉^�c�ɉ���镉�S�͑傫���B�������́C��ʐf�Âɂ����Ă͐��_�Ǐ�̑Ή����قƂ�ǂȂ���Ă��炸�C�Ō�t�C��Ã\�[�V�������[�J�[�C�S���E�ւ̐��_��w�I������قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ��ȂǁC����ł̉ۑ�͑����Ƃ��āC�����Âɂ����鐸�_�ی����Ƃ��x������̐���琬�̕K�v���C�܂����_�ی����Ƃƃv���C�}���P�A�E�`�[���̘A�g�V�X�e���̍\�z�̕K�v���Ȃǂ�����B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N1��28�� |
||||
| �r�f�I�Ŕ]��ᇂ̎��Ö@�I���ɕω��@������͉������Ìh���ECPR���ۂ� | ||||
| �@�}�T�`���[�Z�b�c�����a�@�i�{�X�g���j���Ȃ�Angelo Volandes���m��́C�]��ᇊ��҂ɖ������҂̊e�펡�Â̗l�q���B�e�����r�f�I�f�������������C���̌�̎��Ö@�̑I�����ǂ̂悤�ɕω����邩�ׂ��B���̌��ʁC�r�f�I������͊ɘa�P�A�݂̂�I�����C�S�x�h���iCPR�j�����ۂ���X�����F�߂�ꂽ�B �@ �l���̍Ō��Â��ɉ߂����I�� �@�r�f�I�ɂ�3�ʂ�̏I������Â̗l�q�����^����Ă���B���̉f���������������҂́C���Ö@�̑I�����ɂ��Č����Ő������������̊��҂ɔ�ׁC�������l���̍Ō��Â��ɉ߂��������Ɩ]�ތX�����������Ƃ��킩�����B���ہC�r�f�I�������������ґS�����u�]��ᇂ��i�s���Ă��������Â��邱�Ƃ�]�܂Ȃ��v�Ɠ������̂ɑ��C�r�f�I���������Ȃ��������҂ł͔����ɂƂǂ܂����B �@Volandes���m��́CMGH����Z���^�[�ň����_�o�P��̎��Â��Ă��銳��50���Ώۂɒ������s�����B�܂�CPR���s��ꂽ���҂�l�H�ċz��ɂȂ��ꂽ���҂��ǂ̂悤�Ȍo�߂����ǂ邩�Ȃǂ��܂߁C�I������ÂɊւ���m���ɂ��Ċ��҂Ɏ��₵���B�܂��C�]��ᇂ������Ɏ������ꍇ�� CPR���邩�ۂ����������B �ɘa�P�A���{�I���Â̌��i���f�� �@���҂͌����݂̂ł̐�������Q�i�ΏƌQ�j�ƁC�����ł̐����ƃr�f�I�����̗�������Q�i�r�f�I�����Q�j�Ƀ����_���Ɋ���t����ꂽ�B�ΏƌQ�ɂ́C�i1�j�����iCPR��@�B�I�l�H�ċz���܂ށj�i2�j��{�I���@���Ái�R�ۖ��A�t���^���܂ށj�i3�j�ɘa�P�A�̂݁\��3�i�K�Ɋւ��Č����Ő������s�����B�r�f�I�����Q�ɂ͏�L�̐����̌�C���̐������e��⊮����6���Ԃ̃r�f�I�f�����������B �@�r�f�I�ɂ�CPR�̖͗l��W�����Î��ł̐l�H�ċz��ɂ�鉄�����Ẩf���C���@���_�H�ōR�ۖ�𓊗^����Ă����{�I���Â̗l�q�̂ق��C�����z�X�s�X�ŕ��ʂɐH�����Ȃ���_�f�Ö@�Ȃǂ̊ɘa�P�A���Ă�����i���f���o���ꂽ�B���̌�C�]��ᇂ��i�s�����ꍇ��3�i�K�̎��Â̂����ǂ̃��x����I�Ԃ��C������CPR���邱�Ƃ�]�ނ��ۂ����₵���B�܂������ɁC���Ҏ��g���]�I�����ɂǂ�قNJm�M�������Ă��邩���]�����C�r�f�I�����Q�ł̓r�f�I�̓��e�ɑ��銴�z���������B ���������ɘa�P�A�� �@���̌��ʁC�r�f�I�����Q�ł�23�ᒆ21�Ⴊ�ɘa�P�A�݂̂��C1��͊�{�I���Â�I�������B�c���1��͌��f��ۗ����C�������Â�I�������҂͂��Ȃ������B�ΏƌQ�ł͖��i27�ᒆ14��j����{�I���Â�I�����C6�Ⴊ�ɘa�P�A���C7�Ⴊ�������Â�I�BCPR���邩�ۂ��Ɋւ��Ă͗��Q�Ƃ���������O�ł͍����Ȃ��C�������u�Ȃ��v�C3����1���u��v�C�c�肪�u�킩��Ȃ��v�������B�������C�r�f�I�����Q�͐����E�r�f�I�����̌�ł́C2�������21�ႪCPR��]�܂Ȃ������B����C�ΏƌQ�ł͐����O�ƂقƂ�Ǖω����Ȃ������B �@Volandes���m�́u�r�f�I�����Q�ł́C�ɘa�P�A��I�����闦���啝�ɑ������������łȂ��C�������邱�Ƃň��S�ł����Ƙb���Ă����B�r�f�I�ɂ���Ĉ�t�Ɗ��҂̘b���������i�݁C���҂��m�M�������Ď��Ö@��I���ł���悤�ɂȂ�B���コ�܂��܂Ȃ��҂�ΏۂɁC�r�f�I���ǂ�قǖ��ɗ��̂��ׂ���肾�v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N2��11�� |
||||
| ���ҁF�{���A�m���ā@�߂��݁A�炳�c�̌���銈���L���� | ||||
| ����Ì���̎Q�l�Ɂ^���Z�Ŏ��ƁA���k�狤�� �@�����̌������l�������A���܂��܂ȏ�Ŗ{�������n�߂��B�������҂�Ƒ��A�Ⴂ����ɂ��A�����Ɨ������Â��ɍL�����Ă���B �@����������邾���ł����܂��������B�q�ǂ��Ɏ����ł��Ȃ��̂��߂����A�v�w�����ł��v�ɐ\����Ȃ��C�����ɂȂ遄 �@���T�̑��q�ɂ����`�����B���X�u�}�}��Y��Ȃ��łˁv�ƌ����ẮA�v�ɓ{��ꔽ�Ȃ��遄 �@�m�o�n�@�l�u���N�ƕa���̌��@�f�B�y�b�N�X�E�W���p���v�i�����s������A�d�b�O�T�O�E�R�S�T�X�E�Q�O�T�X�j�͍�N�P�Q������A�z�[���y�[�W�ihttp://www.dipex-j.org�j�łQ�O-�V�O��̓�����̌��҂S�R�l�́u���v���A���������Á��Ĕ��E�]�ځ��������f�f���̔N��--�̂T���ڂɕ����Č��J���Ă���B �@�o�ꂷ��l�����͑S�������ŁA�ꕔ�͉����╶�݂͂̂����A�唼�͊���o���Č���Ă���B�p�I�b�N�X�t�H�[�h��̎��g�݂����f���Ƃ������̂ŁA�����J���Ȋw������̏��������B�O���B����̑̌��҂ɂ��b���Ă���A�߂��ꕔ���J����\�肾�B �@�u����T�|�[�g�������܁v��\�̎O�D������i�R�S�j�����������F������s���͂V�N�O�ɓ���������A���[��؏��B�m�l�ɂ��̊������������u�����̑̌����𗧂Ȃ�v�ƂO�W�N�āA�C���^�r���[�����B�u���Řb�������Ƃ͂��������A���炢������̂͏��߂āB�b���Ȃ��玩�R�Ɨ܂����ӂꂽ�B�u�߂��݂�炳��f���o�����Ƃ��ł����B���҂̘b���������蕷�����Ԃ̂Ȃ���t���w�����ɂ����Ăق����v�Ƃ����B �@�C���^�r���A�[�̓I�b�N�X�t�H�[�h��Ō��C�����Տ��S���m���w�u�t�珗���S�l���S�������B���̈�l�A�ˏ�T�q����i�S�U�j�́A���g������̌��҂��B�����s���̊Ō��ł���̊ɘa�P�A�Ȃǂ������Ă����O�U�N�Q���A���������������B���Ì�A�����ɖ{�i�I�ɉ����A���҂����̘b�����B�u�����{���ɂ炢���Ƃ͈�t��Ƒ��ɂ��������A���a�̗F�l�����肾�����B�T�C�g�����āA�P�l����Ȃ��Ɗ����Ăق����v�Ƙb���B �@�f�B�y�b�N�X�E�W���p���̍��v�Ԃ肩�����ǒ��i�T�O�j�́u���낢��ȗ���̐l�̌�肩��A�����������ł���P�[�X�����T����͂��v�Ɗ��҂���B�F�m�NJ��҂Ƃ��̉Ƒ��A���f�A���Ȃǂ̃f�[�^�x�[�X�������������B �@���҂̍���Ȃ��݂���i�S�R�j�������s�L���恁�͍�N�P�P�����{�A�Q�n���ɐ���s�̌����ɐ��苻�z����K��A������e�[�}�Ɏ��Ƃ������B�{���A�ځu�������v�ŏЉ�ꂽ���䂳��ɁA���k���������z���𑗂����̂����������B���Z����P�W�O�l���^���Ɏ����X�����B �@���䂳��͂R�V�̎��A�������������B��p�⎡�Â̌��ǂœ����̋Ζ����ސE���A�ďA�E�B��N���ɂ��҂̏A�J���x�������Ђ�ݗ������B �@���Ƃł͕����E��ÐE���u���R�N�����O�ɁA���҂̑������ȑO�̐E��ւ̕��A��]�݂Ȃ���]�E��]�V�Ȃ�����Ă��錻���A�Ȃ���Ђ�ݗ������̂��ɂ��Đ����B�u����ɂȂ������Ƃɉ����Ӗ�������͂��B�}�C�i�X�̌o���ɉ��l�����������A�������ɐ����Ă������Ǝv���Ă��܂��v�ƌ�����B �@���Ƃ������V�a�炳��i�P�V�j�́u�h���}�ȂǂŌ��邪�҂̃C���[�W�ƈႢ�A�͋����O�����Ȑ��������S�Ɏc�����v�B�S���̒��R���m�q���@�i�S�R�j�́u���k����������̖������g�߂ɍl���邫�������ɂȂ�v�Ɗ��҂���B �@���䂳��́u���z����ǂނƁA�b����������~�߂Ă��ꂽ�悤�ň��S�����B���ȏ��̒m�������łȂ��A���̑̌��k�����Ƃ͑厖�B�������Đl���ƂłȂ��Ɗ����Ă��炦���炤�ꂵ���v�Ƙb���Ă���B m3.com�@2010�N3��15�� |
||||
| ���҂̎��͂̑��҂��C�u�������̂��߂ɐ����Ă��Ăق����v�Ɗ肢�C ���̐����Ō�܂ōm�肵�Ă����̂́C������O�̂��� |
||||
| ����L���q���ɕ��� �@��41����s��m���t�B�N�V�����܁i���{���w�U�����Áj�ɁC��w���@���w�����Ȃ��g�́\�\ALS �I�������x���I�o���ꂽ�B��т��߂��ʒ��҂̐���L���q���ɁC��܍�ɑ��������b�Z�[�W���a���̌���Ɏv�����ƁC���ꂩ����g�݂������Ƃ��f�����B �\�\��܁C���߂łƂ��������܂��B ����@���肪�Ƃ��������܂��B���̂悤�ȑ傫�ȏ܂����������Ƃ͂܂������l���Ă����Ȃ������̂ŁC�Ƃɂ��������܂����B���܂��ɋ����������Ă��āC���͂ǂ��ɂ����Ă��܂��̂��낤�C�Ƃ����C�����ł��i�j�B �@�{�����������Ƃ͉Ƒ��ɂ͓����ɂ��Ă����̂ŁC��܂ɂ���Ēm���Ă��܂������C�ǂ�����������������̂��B�Ƒ����C���������̂��Ƃ�������Ă���{���������Đ��ɏo�Ă���킯�ł�����C���X���G�Ȗʎ����ł����B �\�\�R�����̖��c�M�j����̍u�]���������ɂȂ��āC�������ł������B ����@�����̌��t�����ꂵ�������ł��B���c�����g���]����Ԃ̑��q������Ŏ�������e�Ƃ��āC���Ǝ��̋��Ԃł̊������w�]���i�T�N���t�@�C�X�j�\�\�킪���q�E�]����11���x�i���Y�t�H�j�ɏ�����Ă������Ƃ�����C�����g�̉ߋ���U��Ԃ�w�����Ȃ��g�́x��ǂ�ł����������̂�������Ȃ��C�Ə���ɐ������Ă��܂��܂����B �@�܂��C�����䂭�g�̂̃P�A�ɂ����Č��ꉻ����Ă��Ȃ����Ƃ����X����C�����w�ɂ������Ƃ�]�����Ă����������̂��C���肪���������ł��B �a�l�̓A�X���[�g�C���҂̓g���[�i�[ �\�\ALS���̋L�^�Ƃ����ƁC�����I�ȁu���a�L�v�Ǝ���邩������܂��C����Ƃ͂܂������ʂ̂��̂ł���ˁB�u�A���I�Ȑ��v���m�肵�C�A������Ă邪���Ƃ��P�A������B�������������܂��B ����@ALS�̊��҂���͕����Ղ�ʂ��āC�u��w�ɂ������Ă��鏬�w��������Ƃ��������āv�Ƃ������~���P�ʂ̗v�������Ă��܂��B�u���H �w�̈ʒu�����������́H�v�ƌ����ƁC�p�`�b�Ƃ܂������Ԃ��Ă���B��������ʒu�̒������n�߂āC�܂��܂�����OK���o��܂ŁC���x���J��Ԃ��̂ł����ւ�Ȏ��Ԃ�������܂��B �@1��24���ԁC�Ƒ��ƃw���p�[����ւł��������g�̂̔������������ƌJ��Ԃ��Ă���̂��CALS�̉��B�Ԃߍ����Ă���ɂ�����܂���B �\�\�����ɐZ���Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��ƁB ����@�����B���҂���͐_�o���������܂��Đg�̂ɋɗ͏W�����C�x�X�g�ȑ̒��ɃR���g���[�����Ă��炨���Ƃ��܂��B�u�����͐������4����3�ɍ���ĉ����Ɉ��܂��āv�u�����͋C�������܂�悭�Ȃ�����C�ċz��������Ɨ��Ƃ��āC�ċC�̗ʂ�450����475�ɂ��āv�ȂǂƎ��ɍׂ����w�肵�Ă���������܂��B�����������������X�Ƒ����Ă���ƁC�ǂ��̒��͊F�ō��Ƃ����C�T�����܂�Ă��āC�a�l�Ƃ����ǂ��I�����s�b�N�̃A�X���[�g�̂悤�ɂȂ��Ă����ł���B���҂́C���̉��Ŏx����g���[�i�[�̋C���ł��B �\�\����́C���҂��������M�ł��Ȃ���ԁiTLS : Total1y Locked-in State�j�ɂȂ��Ă������Ȃ̂ł����B ����@�ˑR���̏�ԂɂȂ�킯�ł͂Ȃ��̂ŁC���̃X�^���X�͕ς��Ȃ��ł���B����܂ł��o���̐ςݏd�˂��������ăP�A�����Ă��Ă���C���҂���̊�����āC�������������̂����������ǂݎ���Ă��Ă��܂����ˁB������̌ċz�ł��B�������ĖS���Ȃ�u�Ԃ܂ŁC���҂̈ӎv�����ݎ�낤�Ƃ��Đg�̂��ƂĂ��厖�ɂ������܂��B �@�ł�����C����Ȑg�̉������Ă����l�ɂƂ��ẮC���b����g�̂�r�������Ƃ������Ȃ̂ł��B����������߂��������̂́C��̂����ɓB��ł��̂Ƃ��ł����B�ċz�킪�O���ꂽ����g�̂����݂��Ă���Ԃ͗�Âł����܂������C�Α���̃{�C���[���_�������u�Ԃ��ł��炩�����ł��ˁB �@����Ȃӂ��ɁC�g�̂�S��ӎ��Ɠ����ɑ�Ȃ��̂Ƃ��Ĉ������Ƃ�S�g�ꌳ�_�ƌĂт܂����C��⑼��ALS�̉��̗l�q����C�����������_�͎��R�ɐg�ɕt�����Ǝv���܂��B �\�\���{�ɂ͐̂���C���������l����������܂���ˁB ����@�ނ���ǂ��̍��ɂ��C�����I�ȐS�g�ꌳ�_�͂���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ł͎嗬�łȂ������ł��B �@�����ł́u��C�v���䂦�ɉ䂠��̃f�J���g�I�ȐS�g�_�Ɋ�Â��������ϗ��ς��嗬�ŁC�܂������ȍ����v�l����]���d�v������Ă��邽�߁C���Ȍ��肪�ł��Ȃ��Ȃ����琶���Ă��Ă��Ӗ����Ȃ��ƍl����ꂪ���ł��B �@���������v�l��ALS�̈�Âɂ����f����Ă��܂���B�Ⴆ�C�p���ł͗D�ꂽ�ɘa�P�A�̃v���Z�X������܂����C�����l�H�ċz��̑����� QOL�̒ቺ�ł���Ƃ��āC�I�Ȃ��悤������܂��B���Ȍ���ł��Ȃ��Ȃ�̂����玩���ł��Ȃ��Ȃ�B������ċz���I�Ȃ��Ƃ����l�������嗬�ł��B�I�[�X�g�����A�̊��҉�ł�ALS���҉Ƒ���ΏۂɁC���₩�Ȏ����}���邽�߂̍u�K��s���Ă��܂��B �u����ł����������v�ւ̋��� �\�\�ċz��̑I���ɂ��ẮC�{�l�̈ӎv���d�v���Ƃ��āC���O�w������r���O�E�B���������Ă����ׂ��Ƃ��镗�����C���{�ł����܂��Ă��܂��ˁB ����@������C�����I�ȐS�g�_�Ɋ�Â����̂ł��傤�B���{�͐����ɔ�ׂĒx��Ă���ƌ����܂����C�u���Ȃ��͐����������C���������Ȃ����v�Ƃ����₢���̂��̂��C���������Ƃ����c�_������܂��B �@�S�̒��ł͐��������Ɗ���Ă��銳�҂���ł��C��X�ɕs������������C�����������Ă��邱�ƂʼnƑ����ꂵ�ނƎv���ƁC���̐��������C������\�o���邱�Ƃ͓���B�����̖��u�ċz��𒅂��Ȃ��v�I�������Ă��܂����Ƃ�����܂��B���{�͌��݂̂Ƃ���ċz���I�Ԃ��Ƃ��ł��鍑�ł����CALS����8000�l���̂����C�ċz��𒅂��Ă��Ȃ�7���̒��ɂ��C������������璅�����Ȃ����͂��Ȃ肢�܂��B�������ɋ߂��������Ő����̑I���𔗂��� ALS���҂̔߂��݂��C���͓����납��Ђ��Ђ��Ɗ����Ă��܂��B �@�l�Ԃ͌ǓƂł����C�Ƃ�ڂ����Ő����Ă���킯�ł͂Ȃ��C���҂Ƃ̊W���Ő��������l�������ω����Ă����܂��B�N���ɍD����]�܂����ꂵ�����C������Ɣ߂����B�ł�����u���ɂ����v�Ƃ����҂ɑ��ĉƑ��C�F�l�C���l�Ȃǂ̑��҂��u�������̂��߂ɂ��������Ă��Ăق����v�Ɗ肢�C���̐����y�邱�ƂȂ��m�肵�Ă����̂́C������O���Ǝv���̂ł��B�������C���������������R�Ȋ��o���CALS���߂����Â���̓X�|�b�Ɣ��������Ă���悤�Ɋ����܂��B �\�\�u�@�B�Ɉ͂܂�Đ�������Ă��āC���킢�����v�Ƃ�������������܂��B ����@��ʓI�ɂ́C��Ë@��ɗ���Ȃ��ŁC�u�Ŋ��܂Ŏ����炵���v�u���R�Ɂv�S���Ȃ邱�Ƃ��ǂ����Ƃ��ƍl�����Ă��邩������܂���B�ł��������́C���Ƃ��܂������̂������Ȃ��Ȃ��Ă��C�ċz��𒅂��C�o�ljh�{�ɂȂ��Ă��C�����炵�������킸�ɖ��邭�����Ă���l��m���Ă��܂���ˁB���̓_�͂�������Ɠ`���Ă��������ł��ˁB �\�\�w�����Ȃ��g�́x�ɂ́C�f�Ï��̒����m��搶���C�ċz��𒅂��Đ����邱�ƂɈӖ�������Ɨ�܂������Ă��ꂽ���Ƃ�������Ă��܂����B ����@������Ӗ����������ĔY�ꂵ��ł����ɑ��āC�u����ł������Ă�������ˁv�Ƌ������Ă����l�͖{���ɏ��Ȃ������̂ł����C�����搶�͈�т��āu�n���Ẫp�C�I�j�A�ɂȂ���Č�������ˁv�ƕ�����C�Â��Ă��������Ă��܂����B �@�搶�́C�ꂪ�u���ɂ����v�Ȃǂƌ����Ă��C�u���x�͂�����֍s���܂��傤���v�Ȃ�Ď���������ł��i�j�B����ƕ���C�u���[��c ���Ⴀ�C�����~���Ɂv�Ɓi�j�B�x������l�͊��҂̔߂��݂͎~�߂Ă���荞�܂ꂸ�ɋ������肽�����̂ł��B�������C��ɂ������Ă���ƍm�肵�āC�u��������ɐ����Ă��������v�ƌ����Ă����Ă��������B ���ׂĂ����H���琶�܂ꂽ �\�\�u���̕a���́C�����邱�Ƃ�̌�����w�тȂ����@���^���Ă����v�ip. 160�j�Ƃ���܂����C�l�H�ċz���o�ljh�{���ϔO�I�ȋc�_�ɌŎ������C���H���J��Ԃ������Ƃœ���ꂽ���̂��ƂĂ��傫���悤�Ɋ����܂����B ����@���͂���܂ň�Â���������Ƃ��܂������Ȃ��C�ˑR��̉�쌻��ɑ��ݓ��ꂽ��ł��B �@������C����܂ʼnƑ��͑S���������т�H�ׂĂ����̂ɁC��ᑂɂ����Ƃ���ꂾ�����}�ɐH�ׂ镨���ς��Ȃ�Ă��Ƃ͔O���ɂȂ������B����o�ljh�{�܂ɂ͓f���C���Â��Ă����̂ŁC�ɗ̓~�L�T�[�H�������Čo�ǂň݂ɗ����Ė����Ȃ��܂����B�ǂ��l�܂点���ɒ���������@���H�v���C�J�����[�v�Z�����I���W�i���̌o�ljh�{��������肵�܂����B���̑��̃P�A�ɂ��������Ė쐫�I�ȉ������Ă����̂ł����C����ł����12�N�Ԍ��C�ɐ�����ꂽ�̂ŁC����ł悩�����C�Ƃ����m�M�������܂����B �\�\��Î҂̂ق����ӊO�ɂ��C�l�H�ċz���o�ljh�{�ɔے�I�ȏꍇ��������������܂���B ����@����͈�Â��W��������Ă��܂��āC��Έ�̐l�ԊW��������Ă����Ȃ�����ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���҂ƈ�Έ�̊W�ł̊��҂���͗B�ꖳ��̑��݂ł�����C�ł��邱�Ƃ͕Ђ��[���玎���Ă݂����Ȃ�͓̂��R�ł��B�����̉��҂��˘f���������n�߂�̂́C�������̂���ɂł���Ƃ��C���҂̂����ŋ�ɂ������Ă���ȂǂƑ��l�Ɍ���ꂽ�Ƃ�����ł��B�܂��C�����Ă��Ă��d�����Ȃ��Ƃ������ƌ�������Ă��܂����҂����Ȃ��炸�����ł����ǂˁB �N�ł���삪�ł���Љ�� �\�\12�N��ALS�̉����o������āC��a���̌���⍡��ɂ��āC�ǂ��l���Ă����܂����B ����@���C�a�C�ɂȂ��Ď��Â��Ă�����Ȃ����Ƃ��킩��ƁC�ꑫ��тɎ��ʘb�ɂȂ��Ă��܂��C���́g�ԁh�̂��ƁC�u�P�A�v���X�|���Ɣ����Ă���悤�Ɋ����܂��B�ł�����Ō�ɂ���Ă��́g�ԁh�͖��߂��邵�C���C�Ȃ�������L���Ȑl�����߂����Ă���l�����܂��B �@���������g�ԁh�̃P�A�̑���͎��H�̌o�����炵���w�ׂ܂���̂ŁC�N�ł���{�I�ȉ��\�\�g�̂��s���R�Ȑl�̎Ԉ֎q�ւ̈ڏ��O�o�̉�C�g�C���������\�\���ł���Ƃ����ȂƎv���܂��BNPO�@�l�������ł��C���̖��o���Ҍ�����20���Ԃ̍u�K����s���Ă��܂��B�g�̂̉�Ȃǂ͌���Ŏ��Ԃ������ė��K����ΐg�ɕt���̂ŁC���̍u�K��ł͎�Ɉӎv�`�B������ȏd�x��Q�҂ɑ���x���̗��O�ɂ��ċ����Ă���C����܂łɖ�900�l�̃w���p�[��{�����Ă��܂��B �@�F����Q�ɑ��Đ������l������g�ɕt����C��Q�̂���l�ւ̕Ό����Ȃ��Ȃ�ł��傤�B����ɕ��s���ĉ���L�������āC�Ƒ��ȊO�ɂ������˗����₷��������C�A���o�C�g�ʼn�����`������ł���ƁC���̏�Q�Ҏ{��ɂ����Ă��܂��B �\�\�Ƒ������ŕ�������ł��܂�Ȃ����Ƃ���Ȃ̂ł��ˁB ����@�Ƒ������őΏ����悤�Ƃ���ƁC����ɉ��₨���̍H�ʂɔ��ʂĂāC�`���b�Ɓu���Ȃ��Ȃ�Ίy�ɂȂ�v�Ƃ����l���������ԁB�₪�đ��݂̔ے肪�n�܂�܂��B�ł�����Ō�܂ł��̐����m�肵�Ŏ�邽�߂ɁC���ꂱ���u�P�A���Ђ炢�āv�C���l�Ƒ����Ƃ���͑���C�Ƒ��͈����v���o�̋��L�Ƃ������Ƒ��ł����ł��Ȃ��x����������ׂ����ƁC�o������w�т܂����B �u�v�ł͂Ȃ��u�W�v���l�ԑ��݂̍Œ���� �\�\�w�����Ȃ��g�́x�ł͏�������Ȃ��������Ƃ�����̂ł��傤���B ����@���ɂ����Ƃ����l�Ɂu������v�Ɨ�܂��̂͘������Ɣᔻ����邱�Ƃ�����܂��B�u�炢�v�u���ɂ����v�Ƃ����v���ɋ������Ċy�Ɏ��˂�悤�Ɏx�����邱�Ƃ��d�v���ƁB�Ȃ������������҂���ɁC���邢�͊��ғ��m���u���Ȃ��ɂ́g������`���h������v�ƌ����Ă���̂��C���̖{�ɂ͏\���ɂ͏�������Ȃ������ł��B �@���̓����́C���́C���܂��܂Ȉ�É�쐧�x������Ă���ALS�����҂̐������܂ɒ[�I�Ɍ����Ă��܂�����C�ނ�̂��Ƃ͂����ǂ����ɏ��������ł��B���̕�̕���͕��w�I�Ń��}���`�b�N�ł�������܂����C����Ƃ͈Ⴂ�C�d�x��Q�҂����̔j�V�r�Ȑ�������G��ȃA�N�e�B�r�X�g�Ƃ��Ă̊���L�������e�ɂȂ�ł��傤�B �@�Ⴆ���{���iALS�����ҁ^���{ALS�����j����́C���Z�����l�����āC���܂ꂽ�Ƃ����玊���s������ŗv���x5�������Ƃ����l�Łi�j�C�l�́u������ӎv�v�����ł͐������Ȃ����Ƃ��C�悭�킩���Ă���l�ł��B�l�͌��q�̂悤�Ɂu�v�Ƃ��đ��݂���̂ł͂Ȃ��C�u�W�v�𑶍݂̏����ƒm���Ă���B�{�l�͎��o���Ă��Ȃ���������܂��i�j�B �\�\�V���̂��̂Ȃ̂ł��傤�ˁB ����@���Ƌ��{����́C�悭�R���r��g��ō��̉�c�ȂǂŔ������܂����C�ޏ��͖{���ɒZ�����t���������܂���B����������c��܂��Đ������Ă��邩��C�ǂ����Ă����̍l�������u�����h����Ă��܂��āC���{����̎v���Ƃ́C��������Ă��邱�Ƃ�����܂��B�ł����{����́C����ł������ƒB�ς��Ă���B�ޏ��̑��҂�M����́C�l�����˔\���C�ޏ��̗×{���x���Ă���Ǝv���܂��B �\�\���ꂩ�炱�̖{����Ɏ������ɁC�Ђƌ����肢���܂��B ����@�ǂޕ��ɂ���Ă͂Ƃ�����Ǝ��̒ɂ��L�q�����邩������Ȃ��̂ł����C���̌o�����Ă������Ƃ�f���ɏ���������ł��BALS�����҂̉Ƒ�����́C�{��ǂ�Łu����������Ă������Ƃ��Ԉ���Ă��Ȃ������v�u�ق��Ƃ����v�Ƃ������܂��̂ŁC���������Ă�������������邩������܂���B �@�Ƒ��̉������Ă�����C�ݑ���̍őO���ŔY��ł���Ō�t����E�w���p�[�����ɁC�Ђ炩�ꂽ�P�A�Ő��̊�]���Ȃ������̑̌���͂���ꂽ�炤�ꂵ���ł��B �\�\���肪�Ƃ��������܂����B �T����w�E�V�� ��2881���@2010�N05��31�� |
||||
| �y�b�g�Ŗ��₵�A�z�X�s�X�ɘa�P�A�L���� | ||||
| �@��������Ȃǂ̊��҂��P�A����u�z�X�s�X�E�ɘa�P�A�a���v�ŁA�y�b�g�̎������݂�������a�@���S���I�ɑ����Ă���B����܂ŕa�@�ł́A�����ǂ̋��ꂪ����Ƃ���A�y�b�g�͂��@�x���������A���_�I�Ȗ��₵��X�g���X��a�炰���w�I�Ȍ��ʂ̑傫���ɒ��ځB�ɘa�P�A�ł͊��҂₻�̉Ƒ����T�i���j��ԂɊׂ邱�Ƃ�����A���҂�͂Â���g�Ƒ��h�Ƃ��Ă̖������y�b�g���S���Ă���B �@�x�m�R����]�ł���R���������s�̋ʕ�ӂꂠ���f�Ï��B�Y��Ȏ��R�̂��Ƃŗ×{�����𑗂肽���Ƒ���ޗǂȂǂ�������҂����Ă���B �@�U�O��̕v�Ȃ͖�S�J���ԁA�����̃`�����ƈꏏ�ɕa���ŗ×{�����𑗂����B �@�ӂ����炵�̕v�Ȃ��`�������Ƒ��Ɍ}��������ɍȂ̕a�C�����������B�v�i�U�R�j�́u�a�@�Ƀy�b�g�Ȃ�ă_�����Ǝv������A�����Ƃ����̂ŋ������B�Ȃ�����ŖS���Ȃ�Ŋ��܂ŋC���������肵���Ǝv���܂��v�ƌ��B �@���a�S�W�N�A���I�Ƀz�X�s�X���J�Ƃ�������L���X�g���a�@�i���s�j�ł͓���������̗����������Ă����B�z�X�s�X�͓Ɨ����łȂ����߁A�������y�b�g�̓P�[�W�ɓ���Ď������݁A�傫�ȃy�b�g�͌��ւł̖ʉ�Ƃ��Ă���B�z�X�s�X���a�@�u�s�[�X�n�E�X�a�@�v�i�_�ސ쌧�j�ł́A�����̋��Ȋ��҂ɔz�����Č��������͗��p�ł��Ȃ����A��^���Ȃǂ��e�������ʂ����둤�̃h�A����o����ł���悤�H�v����B �@�܂��挎�P�W���ɃI�[�v���������{�a��s���a�@�̊ɘa�P�A�a���ł��y�b�g�̖ʉ���������Ă���Ƃ����B���a�@����Z���^�[���̕���������t�́u���������a���������銳�҂�Ƒ��̋C�������ǂ��ɘa����̂�����Î҂̏d�v�Ȏd���v�Ƃ��Ă���B �@�����������ۂ̓y�b�g�̎���l�����������Ă���̂����R�����A�y�b�g�̈�w�I���p�ɂ����ڂ���Ă���B �@���҂͕a�C�̐i�s�ɔ����A�ӎ������⌶�o�Ȃǐ��_�Ǐ���u����ρv���N����B�\�h�ɂ͕a��������̊��ɋ߂���Ԃ����邱�Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ��ŋ߂̌����Ŗ��炩�ɂȂ�A�ɘa�P�A�ł̃y�b�g�̈ʒu�Â�������ɏd�v�ɂȂ��Ă���B �@����������x�ȚM���i�قɂイ�j�ނƂ̐G�ꍇ���͐l�Ԃɓ��݂���X�g���X���y����������ʂ��l�����A��Â̕⏕���ÂƂ��ċߔN���E�ŗp�����Ă���B �@���̂��߂X���Ɋɘa�P�A�a���z�I�[�v�������a�̎R���c�ӎs�̓�a�̎R��ÃZ���^�[�ł́A����܂ł̃y�b�g�̖ʉ�ɉ����A�߂��A�j�}���Z���s�[�����{����\�肾�B �@���҂�Ƒ��̐��_�I�P�A����ɂ����ʈ�ȑ�̑吼�G�������i���_��ᇉȁj�́u�l�Ԃ͌܊����h������Ɛ��_�I�Ɉ��肷��B����̓��a�́A�Ƒ��̐��_�I���S���傫���T�a�Ȃǂ̐f�f�������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���҂����₩�ɉ߂�����A���̉Ƒ��̐��_�I�P�A�ɂƂ��Ă����ʂ͑傫���A�y�b�g�̎������݂ɂ͑傫�ȈӖ�������B������y�b�g�ɗ����̂���a�@�͑����邾�낤�v�Ƙb���Ă���B MSN�Y�o�j���[�X�@2010�N11��6�� |
||||
| �R�N�O�ɍ��m���c�������ۂ����a�c�ׂ���A����́H | ||||
| �@�����P�S���A�H����炪��̂��߁A�W�O�Ŏ����������m�g�j�̖����f�B���N�^�[�A�a�c�ׂ���B��R�N�O�ɁA���m�������A��p����ʂȉ������Â���]�����A�a�@����s���̃P�A�n�E�X�Ŋɘa���Â��Ă����悤���B���������A����Ƃ̌����������ɂ��āA����͂ǂ����Ă���̂��B �@�Ղ̖�a�@�O�ȕ����E�����m���t�́u�a�c�����ׂĂ̎��Â����ۂ����̂��A���邢�͍R������Â��������ۂ��ĕ��ː����ÂȂǂ͎Ă����̂����킩��Ȃ��̂ŁA�͂����肵�����Ƃ͌����Ȃ��v�Ƃ�����ŁA�������B �u�����O�҂ł���Ύc�O���B�H������ɂ͕��ː��ƍR������Â̑g�ݍ��킹�Ŏ�p�Ɠ����̎��Ì��ʂ�������P�[�X���������Ȃ��B���́g���ʁh�����N�̉����Ȃ̂��A���邢�͐��N�ɋy�Ԑ������Ԃ̉����Ȃ̂��͌l���������Ĉ�T�ɂ͌����Ȃ��B�܂��R����܂��g�����Ƃŕ���p��������̂����������A��������������v�f���l�����킹�������ŁA�ŏI�I�ɂǂ����ׂ��������߂�̂͊��҂��g�B��Ȃ̂́A���҂����̑I�����ɂ��Ă悭�������邱�Ƃ��Ǝv���v �@�ŋ߁A�T�����ȂǂŁu�R����܂͌����Ȃ��v�Ƃ������_�����A�����邪�c�B �u�ꕔ�͔[���ł��镔�������邵�A�c�_�ނ��Ƃ͂������Ƃ����A�����Ă����g�ɘ_�h�B��t������I�Ɋ��҂ɉ����t����̂́A���҂̕s���v�ɂȂ��肩�˂Ȃ��v�ƍ�����t�B �u�m���ɕW�����Âł̍R����܂̎g�����ɂ͖��_�͂���v�ƌ��̂́A���ۈ�Õ�����w���w�Ö@�����������a�@�����E�����L��t�B �u���ʂ╛��p�̏o���ɂ͌l�����傫���A����p�̃��X�N���l�����ɁA�N�ɑ��Ă��ꗥ�Ƀh�J���Ǝg���Ă���A���ƂŒ������Ă����|�Ƃ����l�����͊��Җ{�ʂ̈�Âł͂Ȃ����A���ׂ��ł͂Ȃ��B����p�ŋꂵ�܂Ȃ��M���M���̐��ŁA�ʂ̓��^�ʂ�����߂Ă����ׂ₩�Ȕz�������ׂ����v �@�����A������t���A�ŋ߂́u�R����܂͌����Ȃ��v�Ƃ����ꕔ�̘_���ɂ͔ے�I���B �u���܂ǂ��w�R����܂������Ȃ��x�ȂǂƂ�����t�����邱�Ƃɋ������ւ����Ȃ��B�܂��Ƀi���Z���X���v �@�ǂ��܂ł̎��Â���]���邩�́A���҂̐l���ς������B�����āA�a�c����̈��炩�Ȏ���ے肷����̂ł͂Ȃ����A�R����܂Ɋ�]��������������������̂��B ZAKZAK�@2011�N1��25�� |
||||
| �q��Ă������@�a�@�̎q�ɏ����@�����t�̑哏�k��� | ||||
| �@������̓T�[�J�X��V���n�̃V���[�Ńp�t�H�[�}���X���铹���t�i�N���E���j���A�a�@�ɓ��@���̎q�ǂ�������K�₷��u�z�X�s�^���E�N���E���v�B���{�ł͂܂�����݂̔������������A���Ă̕a�@�ł͎��Â̈�тƂ��Ē蒅���A�Ɖu�͂����߂���̌��p�ɂ��Ă̌������i��ł���Ƃ����B����ȃz�X�s�^���E�N���E���̓��{�ł̕��y��ڎw�������t�̑哏�k���i�S�P�j�����É��s���́u�a�Ɠ����q�ǂ��������A�q�ǂ��炵�������߂���`�����������v�Ƙb���Ă���B �@�������̃T���^ �u�����[�N���X�}�X�I�v�\�B�Q�O�P�P�N�P���P���A���É��s���S���ɂ��閼�É����ԏ\���a�@�B�l���̂Ȃ������a���ɁA���邢�����������B�P�W�O�Z���`�̒��g��N�₩�ȃI�����W�F�̂Ȃ��ɕ�݁A�傫��������F�̌C�ɐԂ��@�B�����āA�T���^�N���[�X�̈ߑ��B�啔���̃J�[�e���z���Ɂu�����[�N���X�}�X���āc������������I�v�Ƃ������q�ǂ������̕\��ɂ́A���Ɋ��҂Ɗ�т����ӂ�Ă����B �u�����̕a�@�́A��t�A�Ō�t�����Ȃ����A�O���ł��銳�҂͉ƂɋA��̂ŁA�������₵���Ȃ��ł��B������A���N�����͕K���a�@�̎q�ǂ������ɉ�ɗ��܂��B�N�ɂƂ��Ă������͑厖�B�����ɃT���^���āA�e�L�g�[�Ȋ��������āA�Ȃ����ł���H�v �u���\�͂Ŗ��O���Ă悤���H�v�u������ɏ����Ă���̓ǂ�ł���I�v�u�͂��A���̎��v�A�v���[���g�v�u���A����A�ڂ��́I���̊ԂɎ�����́H�v�\�B�▭�ȃ{�P�ŏ���U������́A��i�̂悤�ȕ��D�A�[�g���I�B���Â̕���p�ő����̔��������������q���A�N�₩�Ȏ���ɖڂ��P�����A�x�b�h�̏�Ŕ�ђ��˂�悤�ɂ��Ď��L���Ă����B �u���ߐ��������̑��̌��Ԃ���V�N�ȕ�������悤�ɁA�q�ǂ��������a�@�̒���l�߂���C�̒��łӂ��Ƒ������鎞�Ԃ������Ă��������B�����̊Ԃł��A�炢���Â�Y��āA�q�ǂ��炵�������߂��u�Ԃ�����̂��������ł��v �@���a�C�Ɍ������E�C�� �@�z�X�s�^���E�N���E���ɂ��Ēm�����̂́A���Ƀv���̓����t�Ƃ��Ė{�i�I�Ɋ������Ă����O�R�N�B�č��ŊJ���ꂽ�����t�̋Z�p���������ŋ�_�����l�����������A���Œm�荇�������Ԃ̕a�@�K��ɓ��s�����̂����������������B �u�K���͏I����100+ ���̊��҂����@����z�X�s�X�B����ڑO�ɂ����l������O�ɁA���|����Ȃ�����A���{�ł���������Ȃ����Ⴂ���Ȃ��Ǝv���܂����v �@�č��ł̊����͑�l���Ώۂ��������A�^����ɓ��ɕ����̂́A�w�Z�ɒʂ����Ƃ��ł����A���Âɑς���q�ǂ������̎p�������B�����Ɏ��痦���铹���t�`�[���̃����o�[�ɂ��Ăъ|���ď�����i�߁A���O�S�N�ɂ͖��É����ԏ\���a�@�ł̊������X�^�[�g�B�K��͌������Q��B�T�[�J�X��V���[�ɏo�����鍇�Ԃ�D���Ẵ{�����e�B�A�������B �u���߂͕s��������܂������A�q�ǂ����������ł�����������y�����B���N�ȏ㌾�t�������Ă����q���w���肪�Ƃ��x�ƌ����Ă��ꂽ���Ƃ�����܂����B�l�����ɂ͕a�C���������Ƃ͂ł��Ȃ�����ǁA�a�C�ɗ����������E�C�͂������邩������Ȃ��Ɗ����Ă��܂��v �@���̕a�@������v�]������悤�ɂȂ�A�O�U�N�ɂ͂m�o�n�@�l�z�X�s�^���E�N���E�������ݗ��B���݂̊����́A����K�₾���őS����T�O�a�@�ɍL�����Ă���B�ŋ߂́A�T�[�r�X�Ƃ𒆐S�ɁA�����t���L�̃R�~���j�P�[�V�����p�ɂ��Ă̍u���𗊂܂�邱�Ƃ������Ƃ����B �u�����t�̖����́A����̈������Ė��B����̉��ɐ��荞�ނ悤�ɂ��Ď����Ă�����̂������o���e�N�j�b�N�́A�a�@��T�[�J�X�����łȂ��A�q�ǂ��̋���Ɍg��邷�ׂĂ̐l�ɎQ�l�ɂȂ�Ǝv���܂��v �@�����̕a�@�K��̒��߂�����́A�P��̂��N�ʁB�������A�܂̒��g�́A�C�O�̌����悩�玝���A�����O�݂��B�u�Ȃɂ���A�g���Ȃ������v�Ƃڂ₫�A�������ւ̑z����c��܂���q�ǂ������̏Ί��w�ɁA�Ԃ��@�̃T���^�́A���̕a�@�K��Ɍ������Ă������B 47NEWS�@2011�N1��30�� |
||||
| ����͈��Ɏア�c�����������ȁA�v�Ɩ��}���\�� | ||||
| �@���������2�N�O�Ɉ�t����u�]��3�����v�Ɛ鍐���ꂽ���ꌧ���l�s�̌��Ō�t�E��݂ǂ肳��i26�j���A�a���ɕ������Ɏ��Âƃg���[�j���O���d�ˁA��N���Ƀz�m�����}���\���i42�E195�L���j�Ŋ������ʂ������B �@�S�g�Ƃ��Ɏx�����̂́A�鍐��Ɍ��������v�̍_������i26�j���B2�l��5���A���s�����̘Z�������قŖ�120�l��O�Ɂq��l�O�r�r��2�N�Ԃ�U��Ԃ�A�u�����悤�Ǝv�����Ƃ��厖�B��Ȑl�̈��������v�킹�A���C�����ꂽ�v�ƌ�����B �@���s���̕a�@�̊Ō�t��������́A�̒��Ɉٕς�������2009�N1���Ɏ�f���A�݂���ƍ�����ꂽ�B�Ƒ��̑O�ł͋B�R�Ƃ��Ă������A�����A���ۂ��Ă����_������u�݂ǂ�͖̑̂l�̑̂ł�����B�ꏏ�ɏ��z���悤�v�ƌ����A���߂ė܂𗬂����B �@���N2���A�Ƒ���_������́u�]��3�����A�����Ă��N���z���Ȃ��v�ƈ�t���獐����ꂽ���A��ɂ͓`�����Ȃ������B�s�����������������A�]���ȊO�����₷��ƍ_���������Ă���A�u�����̗]���͎����Ō��߂�B���������Ǝv������A�͉̂����Ă����v�ƍl������悤�ɂȂ����B �@�R����܂ɂ�鎡�Â𑱂������A�u�a�C�����炱�����������A�ł��邱�Ƃ��Ƃ��Ƃ��낤�v�ƁA1000�̖����������ށu���m�[�g�v��������B�������ȓX�ŐH������A���s�ɍs���c�c�ƂÂ����B �@�_������̉����ŁA2�l�Ŏ��X�Ɩ��������ɕς��Ă������B���N4���ɂ́u�������悤�v�Ƃ����_������̐\���o���A��̈ӎu�ō����͂͏o�����ɁA��̒a�����Ɏs���̃z�e���Ō��������������B �@���N7�����ɂ͏Ǐ��P�������A2�x�ڂ̎�p�ň݂�3����2��E�o�B��́A�u�����v�������������_������̎v�����������悤�ɂȂ�A10�N4���ɍ����͂��o�����B �@�z�m�����}���\���o������m�[�g�ɂ͋L���Ă������A���̍������̓I�ɍl����悤�ɁB2�l�ŃW���ɒʂ��ȂǗ��K��ς݁A���N12��12���A�_������ƈꏏ�ɁA�t���}���\�����8���Ԃő��肫�����B �@��͍����A�ʉ@���Â𑱂���B�u�w����͈��Ɏア�x�͖{���������I�@��������̕����v�Ƒ肵���u����ŁA�_������́u���Ƃ����u�Ԃ�ڂ����ς������������A�Ȃ��狳���܂����v�Ƙb���A��́u�傫�ȈÈłɕ��蓊����ꂽ�����ł������A�����͏\���K�����Ǝ������A�l�������Z�b�g�ł��܂����B�v��x���ĉ�����l�Ɋ��ӂ��Ă��܂��v�Ƙb�����B m3.com�@2011�N2��8�� |
||||
| �u�Տ��m�̉�E�T�[���v��ݗ� | ||||
| �@���@���҂̐S�̃P�A��ݑ���ɏ]������m�����u�Տ��m�v�Ɩ��t���Ĉ琬���Ă������ƁA�m���ň�t�̑Ζ{�@�P����i56�j�炪2��16���A�u�Տ��m�̉�E�T�[���v�����s�E�������s�����_�ɐݗ�����B �@�S���I�ɂ����������g�݂ŁA�Ζ{����́u���V�a���̋ꂵ�݂⋰�|�ƌ��������l�Ɋ��Y�����Ƃɂ����@���҂̖���������͂��v�ƁA�^���҂̍L����Ɋ��҂��Ă���B �@���Q���̎��ɐ��܂ꂽ�Ζ{����͋���œN�w���w��A�V�����i�E����j�ŏC�s���A38�ŗՍϏ@�Œʎ��h�ǒ��ɏA�C�B���e��M�҂��Ŏ�����o������A����ɏI�����P�A����ϗ��ւ̊S�����܂����B �@��O���N���Ď����n�߁A2000�N�A�鋞���w���ɓ��w�B�ǒ������C���ĕw�ɑł����B06�N�Ɉ�t���i�����A���C�����a�@�ł̋Ζ����d�˂钆�Ō����Â̌��E���ڂ̓�����ɂ����B �@��t�s���ɂ��ߍ��ȋΖ��B�u�a�C��f�Ċ��҂�f�Ȃ��v�ƌ�����悤�ɁA������a�̊��҂����ʂ��Ă��鎀�ւ̋��|��a�炰�邷�ׂ��\���ɂ͎������킹�Ă��Ȃ��B���Ƃ����āA�@���Ƃ��a�@�ɏo���肷��u���N�ł��Ȃ��v�Ɣ����ڂŌ�����B �@���Ă̕a�@�ɂ́A�Տ���������u�`���v�����v�ƌĂ�鐹�E�҂�����B������Q�l�ɁA�u�m���̖����v��ǂ����߂ē�������邱�Ƃɂ����B �@����ł́A��Ã\�[�V�������[�J�[��z�[���w���p�[�Ȃǂ̎��i���擾�����m���Ɍ��C���s���������Łu�Տ��m�v�ɔF��B��P�T�Ԃ̕a�@���K���s������A�a�@��ݑ�ł̖@�b�⑊�k�A������ړ��̉�Ȃǂɏ]�����Ă��炤�B�^������m���͂��łɖ�20�l����A����A��ƂȂ�a�@����Ǝ҂���Ƃ����B �@12���ɊJ������t��Ō�t�A�m�o�n�W�҂�Ƃ̈ӌ�������ł́A�u���y���⑸�����͈�t�����̖��ł͂Ȃ��v�u�m��������ɂȂ��ނɂ͏\���ȃJ���L���������K�v�v�Ȃǂ̐����オ�����B����Ӗ�E���s��O�Ȍ𗬃Z���^�[�������́u�����Â͐S�̖�肪��ɂȂ��Ă���A�Ƃ��ɍl���鎞�����v�Ƙb�����B �@16���ɂ͎Q������m���炪�獇�킹���A��X�^�[�g���B���݂͉p���ŗՏ��w���w�сA���{�Ƃ��s�������Ă���Ζ{����́u���҂Ɂw�l�͎���ǂ��ɍs���̂��x�Ɩ��ꂽ��A�@���҂Ƃ��ĂȂ��荇����B�@�h���Ċ������L���Ă��������v�Ƙb���B �@�₢���킹�͓���i�O�V�T�E�X�T�S�E�P�O�O�T�j�ցB m3.com�@2011�N2��15�� |
||||
|
�����댳�C�m �ɘa��È�E��ÏG�ꂳ��C���^�r���[�@�c���ꂽ���ԂŁA�ǂ����������� |
||||
| �@�\�\��Â���̒����u���ʂƂ��Ɍ�����邱�ƂQ�T�v�ɁA���_���͊w�҃t�����N���́u�ǂꂾ���������������͂ǂ��ł��������ƂŁA�l���̎���Ӗ��ɂ͊W�Ȃ��v�Ƃ�����|�̌��t��������Ă��܂��B��������������̌��͂���܂����B �@����@�����A����܂��B�P�O��A�Q�O��ł��A���������炩�Ȋ�ŁA�u�搶�A�����l���ł����v�ƌ����Đ������������܂��B�u�l�͍K���ł��B����͂���܂���v�ƌ����c���Ă������Q�T�̐N�����܂����B�l�Ԃ̒�m��Ȃ������������܂��B����ŁA����ɂȂ��Ă��u�l���A�s�K���肾�����v�ƌ����ĖS���Ȃ�������܂��B �@�\�\�u���̒��̂��Ȃ��v�Ƃ����m�悪����܂��B�����a�̖����~�����ƁA�ޏ��ɍ������邽�߂ɂ�����l�A�����Y��e�̘b�ł��B�P�O��ɂȂ�����̖��́A������̍��������ۂ��āA疗y�Ƃ��Ď�������܂��B�P�O��ł����̂悤�ȐS���ɂȂ��̂��A�ƈ�ۂɎc��܂����B �@����@���܂�Ȃ���ɓ�a�̑��_�NJg���ǂ�����A�Q�O�㔼�Ŗ����̒_�ǂ���ɂȂ����N�����܂����B�l����������ɂ́A�z�X�s�X�ŒW�X�Ɛ������Ă����B�u�O�̕a�@�ł͎��Â̘A���ŋꂵ����������ǁA�����ł݂͂�ȗD�������Ă���čK���ł��v�ƌ����̂ł��B�Ŋ��̓��܂ň��炩�ł����B�N�����[���l���⎀�ɂ��čl�����̂łȂ��ł��傤���B �@������̂��߂P�S�ŖS���Ȃ������n������́A���O�٘̕_���Łu�a�C�ɂȂ��āA�����邱�Ƃ���Ȃ��̂��Ƃ킩��܂����v�ƃX�s�[�`���Ă��܂����B�ޏ��́u���X�[�p�[�f���b�N�X�v�Ƃ������a�L���o���Ă��܂��B�ނ�ޏ������̂悤�ɁA���Ǝ��ɖ{�C�Ō��������A�����Ă��邱�Ƃ��ǂꂾ���K���Ȃ̂��ɋC�����܂��B �@���������S���ɂ��ǂ蒅���邩�ǂ����́A�N��ɊW�Ȃ��B�ł��邾�����������āA��������̐l�Ɉ͂܂�Ď��ɂ����ƍl�������ł����A����̐l�ɕ���������Ă���ŁA�Ƒ��͂�������̂ɒN�����ɍۂɗ��Ă���Ȃ������A�Ƃ����������܂��B �@�u���肪�Ƃ��v�ƌ����c���ĖS���Ȃ��Ă������Ⴂ�q�����̂P�O���̂P�ł��͂�����A�l���ւ̊��ӂ̓x�����͑����邵�A�p�n�k�����܂�Ǝv���܂��B�����āA���������͖͂{���N���������Ă�����̂Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���܂��B �@�\�\�����l����ƁA�������ʂ�����������x�̍R������Â�A���܂��܂ȉ������ẤA�ނȂ������������܂��ˁB �@����@�R����܂ō�������\�������锒���a�Ȃǂ�ʂɂ��āA�����������Â��邱�Ǝ��̂ł́A�l���̖����x�͕ς��Ȃ��Ǝv���܂��B����͖{���ł͂Ȃ��ł��傤�B�c���ꂽ���Ԃłǂ���������������ŁA�قƂ�ǂ̕��ɂƂ��Ė{���A������ړI�͂��������������Ƃł͂Ȃ��͂��ł��B�R����܂��g���āA���̊Ԃɂ������s�ɍs�����A�Ƒ��ƈꏏ�̎��Ԃ��Ȃ�ׂ��߂������A�����������ɂƂ��čR����܂͗L�v�Ȃ��̂ł��B����ǂ��A�u���邱�Ɓv�������ړI���ƁA����͂قڗ����܂��̂ŁA���ǖ�������邱�Ƃ͓���B�R����܂̕���p�ŁA�������Đh���ڂɂ������̂ł͂Ȃ����A�ƌ���������������܂��B �@���������Â���Ӗ��͉����A�����������Ƃ�b�������A�u���͂��ꂪ����������܂����������v�Ƃ��A�u���̎����ɂƂ��āA���Â͂�������قǏd�v�ł͂Ȃ��v�Ƃ������ɘb����悤�ɂȂ�A�~����l�������Ȃ�ł��傤�B �@�������Ď���ł������Ǝ��̂ɑP���͂���܂���B��Î҂₲�Ƒ��̈ꕔ������K�v�ȏ�Ƀ^�u�[�����Ă��邱�Ƃ��A���҂���̌ǓƂ������Ă���Ǝv���܂��B�F���}���鎀�̓^�u�[�ł����ł�����܂���B�ނ��뎄�����͂悫�l���̂��߂ɁA�^�u�[�����Ȃ��Řb�������ׂ�������}���Ă���̂��Ǝv���܂��B���ꂪ���E�ō���Љ�����[�h���A�Q�O�S�O�N�ɂ͔N�ԂP�V�O���l���S���Ȃ�i���݂͂P�P�S���l�j�v���̑卑�v������{�����悵�čs���A�͂������Ă����ׂ����̂ł��傤�B �@�P�T�N�O�ɁA����̍��m�̓^�u�[�ł������A���͍��m���邱�Ƃ�������O�ɂȂ��Ă��܂��B����Ɠ����悤�ɁA���͎����^�u�[�ł��A���̒��͕ς���Ă����Ǝv���܂��B YOMIURI ONLINE�@2011�N3��1�� |
||||
|
�����m����̏����Ɏ��ȑr���̋��� 3�i�K�̏����ߒ����o�Ď���ɍ��� |
||||
| �@�j���[���[�N�B����w�Ō�w����Robin Lally�������́C�����҂��C��������m����Ă���C����ł��邱�Ƃ������悤�ɂȂ�܂ł̐S�̓����Ɋւ��錤�����ʂ\�����B �@�������ł́C���m�������҂́C���߂Ă̏C�m��Ȃ��ꏊ�C�����Ȃ�Ȃ����t�₳�܂��܂ȐE��̐l�Ƃ̏o��ȂǁC����܂ł͖��W�������V���Ȑ��E�Ɏ��g�����������Ȃ���f�f���ʂ�����Ă����ߒ������炩�ɂȂ����B ���m����̐S���ω��͍l������Ȃ����Ƃ����� �u���Ȃ��͓�����ł��v�ƍ��m���ꂽ�Ƃ��C���Y�����̐S�ɂ͉����悬��̂��B���݁C�č��ł͏�����8�l��1�l���l���̂����ꂩ�̎��_�œ�����ɂȂ�Ƃ���Ă���ɂ�������炸�C����������������m����Ă��玡�Â��p���J�n�����܂ł̊ԂɋN�����A�̐S���ߒ��ɂ��Ă͂��܂茤������Ă��Ȃ������B�������C���Â��J�n�����܂ł̊��ԁC���҂͑����ȃX�g���X��������Ɨ\�z����C�����̃X�g���X���K�ɉ�������Ȃ��ƁC�����^���w���X�ɉe�����y�ڂ����˂Ȃ��B �@Lally�������́C���̂悤�ȏɂ��āu�f�f����C��Ï]���҂̈ӎ��͊��҂̐g�̂ւ̉e���⎡�ÂɌ����Ă���C���m�����҂̎��ȊT�O�ɗ^����e���͍l������Ȃ����Ƃ������v�Ǝw�E���Ă���B �@�����œ��������͍���C�č��������̓�����Z���^�[�ŃX�e�[�W0�`�U�Ɛf�f���ꂽ������18��i37�`87�j�ɑ��C�f�f����6�`21����ɖʐڂ����{�B���҂ɓ�����̍��m�������̂��Ƃ���z�����C���̂Ƃ��̌o����b���Ă�������B �@���̌��ʁC�唼�̏������g�����ҁh���邢�́g�������ҁh�Ƃ��������������ߒ��ɂ����āu���Ȃ̑r�����v�C�܂�C�M���Ă������ȑ������������s���������Ă��邱�Ƃ����������B�܂��C���l�̖ڂ��C�ɂ���C����ǂ������������g�̍s���̂����ɂ���Ȃǂɂ���Ă����ȊT�O���h�炢���B �@�܂����������́C���҂�������������܂łɂ́C�i1�j�̊m�F�i2�j�s�����N�����i3�j�����@���琬��3�i�K�̏����ߒ������ǂ�Ƃ��闝�_��W�J���Ă���B �唼�̏����͕ω������� �@Lally�������ɂ��ƁC���m���������͊�{�I�ɁC�������g�Ǝ��͂̐l�X�ɂǂ̂悤�ɉe������̂��Ƃ������Ȃ銋�����������C�ے�I�Ȏv�l��}���ċC���]����}�邱�ƂŌ��ݒu����Ă�����R���g���[������悤�ɂȂ�C�ŏI�I�ɂ͂����l���̈ꕔ�Ƃ��Ď���ď��������߂�悤�ɂȂ�B �@�����C����̌����ł͑����̏��������g�̕ω�������C�g������̍��m�h�ɂ���āC�l���Ǝ��͂̐l�X�ւ̊��ӂ̐S���Ċm�F�ł����Əq�ׂĂ���B�܂��C�唼�̏����͑O�����Ɏ~�߁C����������ł���ƍl���Ă���B �@���������́u������̍��m���������́C�������������̂悤�Ɋ�����̂ł͂Ȃ����ƁC���m�����̎v�l�͌����Ĉُ�ł͂Ȃ��C�ق��̐l�������悤�ɍl���Ă��邱�Ƃ�m��ׂ����v�Ƌ����B����ɁC�u�����҂ł��邱�Ƃ𗝗R�ɎЉ�ƐE��Œ��ʂ���s�����ȏ�ʂ��玩�g����邽�߁C����ł��邱�Ƃ�����C���g�̒u���ꂽ���R���g���[������ۂɔ������銳�҂̐��_�I�G�l���M�[�̑傫���ɋ������v�ƕt�������Ă���B �@�܂�����̒m���ɂ��āC���m��1�`2�T�Ԃ̑����i�K�œ����҂��S�ɂǂ̂悤�Ȋ�����L���Ă��邩�𗝉����C�����҂ɑ��鑁���S���T�|�[�g�̈Ӌ`���l����ۂɖ𗧂ƌ��_�t���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N3��31�� |
||||
| �a���Ŋ�������̍Ō�̊肢�@�������̗͂���đ��q�́g���Ǝ��h���{ | ||||
| �@�������������s���悤�Ƃ�����e��O�ɂ��āA�Ō�̊肢�������Ă��������Ǝv���͉̂Ƒ��ɂƂ��ē��R�̐S�����낤�B�ăt�����_�B�ł��܁A�x����Ɠ����A������ԂɊׂ��Ă��鏗��������B�Ƒ��͗\�ߕ����Ă����ޏ��̊肢�������邽�߂ɖz�����A���N���Z�𑲋Ɨ\��̖����q�̑��Ǝ����A���̗͂͂���ĕa���Ō��s�����B �@�ĕ�����WJXT-TV�Ȃǂɂ��ƁA���̏����̓t�����_�B�W���N�\���r���̃z�X�s�X�ɓ��@���Ă��郁�A���[�E���B���b�g����B�c�O�Ȃ���A���܁u�x����Ƃ̓����ɕ����Ă���v�iWJXT-TV���j��ԂɊׂ����ޏ��́A�ŋ߂͉Ƒ��ɑ��锽���������Ȃ��Ȃ��Ă����B6�l�̎q�ǂ����Y�݁A7�l�̑������Ɏ������̑�ȕ�ƁA���悢��i���̕ʂꂪ�߂Â��ė������Ƃ�������Ƒ��́A�\�ߕ����Ă�����]�̂�����2��������ׂ��A�������ɂ킽�菀����i�߂Ă��������B������4��21���A�g�������ł��Ȃ����A���[����̂��ƂɁA�e���▖���q�̃u���C�N����̓������炪�W�܂�A��̊�]��������C�x���g���s��ꂽ�B �@���A���[����̑̒����l�����āA��t�����������Ԃ́u45�������v�i�ĕ�����CBS�n��WTEV-TV���j�B�܂��ŏ��ɍs��ꂽ�̂́A�v���[���[����Ƃ�20�N�ڂ̌����̐����������B�������������u���C�N����́u�����A������������Ɍ������v�iWJXT-TV���j�ƌ��A���S�[�������悤�B���߂ĕv�w�̈����m���ߍ��������e�̎p������ƁA���x��2�ڂ̊�]��������ׂ��u���C�N������ƂȂ�A��̕a���ɃK�E���Ɗp�X���������������������������ƁA�ގ��g�̓��ʂȑ��Ǝ����n�߂��B �@�u���C�N����̑��Ƃ����͂������Ƃ����A2�ڂ̊�]��������ꂽ���A���[����B�{���A�č��̍��Z�ł͉ċx�ݑO��5�����ɑ��Ǝ����s����̂���ʓI�����A�u�x�߂��đ҂ĂȂ��v�iWTEV-TV���j�Ƃ̔��f�ɂ��A�a���ł́g���Ǝ��h���s�����Ƃɂ����������B���͂��ďW�܂������������������̐����𒅂ĉ��o���A�u���C�N����ɂ͗p�ӂ������̑��Ə؏�����n���ꂽ�B �@���̂Ƃ��̏́A�o�}���f�B�[�E�Z�N���X�g����ɂ���ē���ŎB�e����Ă���A�u���C�N����̑��Ƃ����������������グ�Ė��邭���C�ɏj���Ă����l�q�B����Ȏq�ǂ������̃p���[�ɐG�����ꂽ�̂��A���A���[����́u���Ə؏��������v�Ɛ�����������ƁA���L���������������Ƃ����B����ɂ́u����3���Ԃŕꂪ�������B��̔����v�ƁA�}���f�B�[������������悤���B �@���͂̑傫�ȋ��͂������āA���A���[����̊肢��������ꂽ�ƁA���ʼn��낷�Ƒ������B�u���C�N����́A�����̓��������W�܂��Ă��ꂽ���Ƃ��u�S���������o���v�Ɗ��ӂ̋C�����ł����ς����Ƃ����B �i���i���h�b�g�R���@2011�N4��28�� |
||||
| ���҂̂��a�͉ߑ�]���@�L�a���͈�ʐl���Ɠ��� | ||||
| �@���҂̂��a�L�a���ɂ��Ă͖�莋����Ă�����̂́C���Ȃ��s���ȕ����������B���X�^�[��w�i�p�j��Alex
J. Mitchell���m��̍��ی����`�[���́C���҂̋C����Q���������������̃��^��͂����{�B�u���҂̂��a�L�a���͂���܂ʼnߑ�]������Ă����\��������v��Lancet
Oncology�i2011; 12: 160-174�j�ɔ��\�����B �������Ԃɂ��e�����邤�a �@����̉�͌��ʂɂ��ƁC���҂̂����C���a���������Ă��銄���͖�6����1�ŁC�C����Q�S�̂��܂߂Ă���3����1�ł���B�������C�����҂��������钆�C���a�������Â̂܂܌�������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��CMitchell���m��́u���a�����łȂ��C�s����Q��K����Q�Ƃ������֘A�C����Q�irelated mood disorders�j�ɂ��œ_�����킹���̌n�I�ȃX�N���[�j���O�v���O�������K�v�ł���v�Ƃ��Ă���B �@���a�͂��҂ɂƂ��ďd��ȍ����ǂ�1�ŁC���ɐ[���ȉe�����y�ڂ��B���a�ɂ��C���Âɑ���R���v���C�A���X���ቺ���C���@���Ԃ���������B�܂��������Ԃɂ��e�����y�ڂ��B����ɂ��Ă̌����͂���܂ő������s���Ă�����̂́C���҂ɂ����邤�a�⑼�̐��_�����̐��m�ȗL�a���͕s���ł������B �@�����œ����m��͍���C���܂��܂ȕa�@���ŁC���҂̂��a�C�K����Q�C�s����Q�Ȃǂ̗L�a�����������邽�߂Ƀ��^��͂����{�����B����┒���a�Ȃǂ̐�厡�Î{�݁i�������҈ȊO�ɂ��C���܂��܂ȕa���̊��҂��܂܂��j�Ŏ��{���ꂽ24�����i�v4,007��j�Ɗɘa�P�A�{�݁i�ӊ���i�s���҂��܂܂��j�Ŏ��{���ꂽ70�����i�v1��71��j�𒊏o�B�����̎����͂�������C�P�����������҂��Ï]���҂��ʒk�ɂ�肤�a�f�f���s�������̍��������ł���B�������C�قƂ�ǂ͊��҂�����Ɛf�f����Ă����5�N�ȓ��̃f�[�^�ł������B ���a�ȊO�̋C����Q�ɂ����� �@��͂̌��ʁC����┒���a�Ȃǂ̐�厡�Î{�݂ōs��ꂽ24�����ł́C���a�C�y�x���a�C�K����Q�C�s����Q�̗L�a���́C���ꂼ��14.3���C9.6���C9.8���C15.5���ł������B�ɘa�P�A�̎{�݂ōs��ꂽ70�����ł́C���ꂼ��14.9���C19.2���C19.4���C10.3���ł������B �@�܂������̏�Q�����邱�Ƃ������C�O�҂̎����ł͌y�x���a���܂߂����a�S�́C������ѓK����Q�C�s����Q���܂߂��C����Q�S�̗̂L�a���͂��ꂼ��24.6���C24.7���C29���B��҂̎����ł͂��ꂼ��20.7���C31.6���C38.2���ł������B �@Mitchell���m�́u�����̐��l�͂��܂荂���Ȃ����C�����Čy���͂ł��Ȃ��B����S�̗̂L�a�����㏸���C�����������܂��Ă��邱�Ƃ���C�傤�a�Ƃ���̍�����͉p����34���l�C�č��ł�200���l�Ɛ��v�����i����L�a���~���a�̗L�a���Ōv�Z�j�v�Ƌ����B�܂��C�u����̌����ł́C�ɘa�P�A�{�݂Ƃ���ȊO�̕a�@�ŁC���a�L�a�����邢�͕s����Q�L�a���ɗL�Ӎ��͔F�߂��Ȃ������B���̂��Ƃ���C���Î{�݂�a���̈Ⴂ�͂���قlje�����Ȃ����Ƃ��������ꂽ�v�ƕt�������Ă���B����ɁC�N���Ȃǂ��a�̊댯���q�����Ă��C�傫�ȕω��͌����Ȃ������B �@�����m��́u��t�����ږʒk�������̍�����������͂������ʁC����a�@�Ȃǂɂ����邤�a�݂̗̂L�a���́C����܂ōl�����Ă����قǍ����Ȃ��C6�l��1�l���x�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B���̐��l�́C�v���C�}���P�A�ɂ����銄���Ɠ����ł���v�Ƃ�����ŁC�u���a�ȊO�̋C����Q���������Ă������܂߂�ƗL�a����30�`40���ł������B���̂��Ƃ����t�́C���a�����Ɍ��炸�s����Q�C�K����Q�Ȃǂ̋C����Q�ɂ��Ă����ӂ��K�v������v�ƌ��_�t���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N7��7�� |
||||
|
�I�������҂Ɂgdignity therapy�h�͗L�� ���̃����_������r�����Ŗ��炩�� |
||||
| �@�}�j�g�o��w�i�J�i�_�j��Harvey Max Chochinov������́u���҂̑������d�������V�������_�Ö@�ł���gdignity
therapy�h�i���Ȃ��̑�Ȃ��̂��Ȑl�ɓ`����v���O�����j�́C�W���I�Ȋɘa�Ö@�⊳�Ғ��S�̗Ö@�iclient-centered
care�j�Ɣ�ׁC�I�������҂�QOL���P�Ƒ����ێ��C����ɉƑ��̕��S�y���̓_�ŗL�ӂɗD��Ă����v�Ƃ̃����_������r�����iRCT�j�̌��ʂ�Lancet
Oncology�i2011; 12: 753-762�j�ɔ��\�����B����̌��ʂ́C���̗Ö@�����ׂĂ̏I�������҂ɕ��L�������ׂ����Ƃ��������Ă���B QOL�Ȃǂ��܂��܂Ȏ�ϓI���ڂŌ��� �@�I�������҂̃P�A�́C�g�̓I���S�y���̖ʂŋߔN�傫���i�������B�������C���҂̏�I�C�Љ�I�C���_�I�j�[�Y�ɉ����邽�߂̉����i�͂قƂ�NJJ������Ă��炸�C�������̂܂܂ł���B �@Chochinov�������Ǝ��ɊJ�������ʉ����_�Ö@�ł���dignity therapy�́C���҂��ł��m���Ă��炢�����C�܂��͖Y��Ȃ��łق����Ǝv�����Ƃɂ��āC�����ɏ������߂���C�l�ɓ`���邱�Ƃɂ�芳�҂̋�ɂ��y�����C�I�����̐l����L���ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B�ȑO�ɍs��ꂽ��T�������ł́C�قڂ��ׂĂ̊��҂ɗL���ł��邱�Ƃ���������Ă����B �@��������͍���C���ۂ�dignity therapy�����҂̐��_�I��ɂ��y�����C�I�����̐l����L���ɂ��邩�ۂ����������邽�߁C���̗Ö@�Ɋւ��鏉�߂Ă�RCT�����{�B�J�i�_�C�č��C�I�[�X�g�����A�̕a�@�܂��͒n��{�݁i�z�X�s�X�܂��͎���j�Ŋɘa�P�A���Ă���18�Έȏ�̏I��������326����Cdignity therapy�i108��j�C���Ғ��S�Ö@�i107��j�C�W���ɘa�P�A�i111��j�̂����ꂩ�Ƀ����_���Ɋ���t�����B�����J�n���ƏI�����ɁC���_�I�L�����C�����C����ԁCQOL�𑪒肷��e�ړx�̃X�R�A���B�܂������I����C���҂̏I�����o���ɂ��Ď��L�������[��p���Ē��������B �@�����̌��ʁCdignity therapy�Q�ł́i1�j���Â͗L���������i2�j�i���Âɂ���ājQOL�����P�����i3�j�������ۂ���Ă��銴�o�����債���i4�j�Ƒ��̎����ւ̌����⑸�d�̎d�����ω������i5�j�Ƒ��ɂ����b��������?�ƕ������҂̊������C����2�Q�����L�ӂɍ��������B �@Dignity therapy�͂܂��C���_�I�L��������̖ʂŊ��Ғ��S�̗Ö@���L�ӂɗD��C�߂��݂Ƃ���Ԃ̌y���Ŋɘa�Ö@���L�ӂɗD��Ă��邱�Ƃ����������B�������C��ɂ̃��x���Ɋւ��Ă͗L�ӂȌQ�ԍ��͔F�߂��Ȃ������B �@��������́udignity therapy�����⎩�E��]�Ƃ����������ȋ�ɂ��y���ł��邩�ۂ��ɂ��Ă͈ˑR�����̗]�n�����邪�C���ȕɂ��I�����o���Ō��ʂ��F�߂�ꂽ���Ƃ���C���̗Ö@���I�������҂�ΏۂɗՏ��Ŏ��{���邱�Ƃ͗L�v�ƍl������v�ƌ��_�t���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N8��11�� |
||||
| ��Ì���ł����[���A�u�����߂��Ă��v�u��҂Ɗ��҂̕Ǖ����v | ||||
| �@�q����זE�@�������炢�́@�Q�ĕ�点�r �@���s�������̗���L���X�g���a�@�B��������̂T�O��j�����S���Ȃ�P�O���O�ɉr������B�������Âł͂Ȃ��A�g�̓I�ȋ�ɂ����A�c��̓��X�������ł��[�����ĉ߂����z�X�s�X�B���݂����ȋC���������[���A�Ő�Ԃ����Ƃ���v�����`����Ă���B �@���a�@���_�z�X�s�X���̔��ؓN�v����i�V�Q�j�́A���a�T�X�N�ɓ��{�łQ�Ԗڂ̃z�X�s�X�a���𗧂��グ�A����܂łQ�T�O�O�l�ȏ�̖����Ŏ���Ă����B�u�����߂��A�Ƃ������Ƃ����o���Đ�����̂́A�m���ɏ��Ƃ͂������ꂽ�ł��B�ł��A�K�������Ƃ��ł���B���͐l�Ԃ̖{�����Ǝv���܂��v�Ɗm�M����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�@�@�~�@�@�~ �@���@�����̒��ŁA���҂������y���݂ɂ��Ă��������̉�b�B �@���u�g�C�O���s�h�͂ǂ��ł������H�v �@���ҁu����ς�j���[���[�N�i�����j�͂����ł��˂��v �@���u�����ڂ��i�̒��j�́H�v �@���ҁu���������t���t�����܂����A�Q�A�R���o�ĂΑ��v�v �@�Ǐ������������҂��ꎞ�މ@����ۂ́A�u���v�B���۔������܂���v�ƌ����āA�u���۔��v�̕��������傫�ȓ������q���h�J���Ɗ��҂̐g�̂ɉ����B���ː����Â��撣�������҂���ɂ́A�u�\����v�悷��B �@����Ƃ��A�H������̒��N�������A�H���̋���i���傤�����j�ŕ����H�ׂ��Ȃ��Ȃ����B�[���ȏ��Ŕ�����́u�Ō`���H�ׂ�����ˁB�g�����炢��������g���g�����Ɠ��邩������Ȃ��ˁv�B������ď����́u�����g���g���Q�ĂȂ��ŁA�g���ɂł����킵�悤������H�v�B�ŕa�ő��ɂ����v�����������u�g��������ł����A�g�����炢�Ȃ甃���ɍs���܂���v�B����ƁA�{���ɂQ��̃g���̎h�g���g���g���ƐH�ׂ�ꂽ�Ƃ����B �@�����ȘA�g�v���[�Ɂu�I�`�v�܂ł��B��҂����҂��v���S���A���l�B���̃z�X�s�X�Ȃ�ł͂̌��i��������Ȃ��B �@�������A����͒P�Ȃ�_�W�����̂��Ƃ�ł͂Ȃ��B�݂���[���v�����S�����邩�炱���A�܂����낪�ʂ������A���[���A�����[���A�ށB�����āu������́v�����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�@�@�~�@�@�~ �@��Ì���ŏ����Ƃ͕s�ސT���A�Ƃ����������邩������Ȃ��B�������v�z�ƁA���c������́A�a�@�Ƃ����ǂ����ْ����̂����Ԃł́A���̏�����߂���Ȃ��܂����肷����ʂ�����A�Ǝw�E����B�u�܂��n�߂ɏ�������ƁA�s�v�c�Ƃ��݂��̌ċz�������Ă���B����̓R�~���j�P�[�V�����̑O�i�K�v�Ƃ����B �@�����Ƃŏk�܂鑊��Ƃ̋����B�������킹�邱�Ƃ́A���܂�e�����Ȃ��ғ��m�����g�������킹��`���[�j���O�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��낤�B�u���̌��p�ő���ɑ��銴�x���オ��ƁA���t�ɕ\���ȏ�̐^�ӂ��`���̂ł͂Ȃ����v�Ɠ��c����͂����B �@������́u��҂Ɗ��҂Ƃ�������̕ǂ�������߂ɂ����͕K�v�v�Ƌ�������B���Â����t�ƁA���Â���銳�҂̊Ԃɂ́A�㉺�W�������₷���B�����u�����Ƃŋ����������Ək�܂�A�M���W�����܂��B�Ŋ��̏ꂾ���炱���A�Γ��̗���̃R�~���j�P�[�V�����͑�v�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�@�@�~�@�@�~ �@�����������⍢��ȋǖʂɗ�������Ă��A�l�͂Ȃ������Ƃ��ł���̂��B �@�u����ڑO�ɂ������ɓI�ȏŏ���Ƃ������Ƃ́A����Ԃ��A����������A�����ō����w������Ƃ����S�\�����ł��Ă���Ƃ������Ƃł��傤�B����͐l�ԂƂ��Ă̐��n�x�ɂ��Ȃ����Ă���̂ł́v�Ɠ��c����B �@�Ŏ�鑤�A�Ŏ���鑤�A���݂��̂炳��������Ƃ������ɒu���A�v������܂���������Ƃ肷��B������́u�w�`�ɂ�������炸���x�Ƃ��A���̎��{���̗͂��A�ő���ɔ��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�B MSNJapan�Y�o�j���[�X�@2011�N8��15�� |
||||
| ���ґ����猩�����z�I�Ȃ��������̍�@ | ||||
| �@���������̍ہA�ǂ�ȕi�������҂Ɋ��邩-�B����Ȃǂœ��މ@���J��Ԃ����s�̉������b�q�i���Ƃ��E�肦���j����i�S�Q�j���A�����i�̏Љ�E�̔���a���K��}�i�[�̏��M����C���^�[�l�b�g�T�C�g���J�݂����B���ґ����猩�����z�I�Ȃ��������̍�@���f�ځB�u���҂ƋC�������Ȃ��鏕�����ł�����ꂵ���v�Ƙb���Ă���B �@��������͎q�ǂ��̂���A�オ��ƈ��������p��ǁB�����Əo�Y�̌�ɂ͗�����ᇁi����悤�j���E�o���A���Ẩe���Ŕ��������̎�p�����B���͗Γ��������A���@�͌v�P�Q��ɋy�ԁB �@�a���������A��Ћ߂����Ă����R�O�㔼�Ɂu�����闝�R��ړI������̂��v�Ƌ^����o���u���@�o�������Ď����ɂ����ł��Ȃ����Ƃ��������v�ƍ�N�A�܂��̓u���O���J�݁B������ق��̓��@���҂����������ň���J����p���v�������Ƃ����B �@���N�W���ɂ̓T�C�g���Ƀl�b�g�V���b�v���J�X�B�x�b�h�ɐQ�]��Ŗ{��ǂނ��߂̖���Ԃ�����p�̍��z�c...�B���҂̗��ꂩ�猵�I�A�����������i����ׂĂ���B �u�`���I�Ȃ��������́A���҂ɂ͂���������v�Ƙb���B���z�́u���҂���u�ł��Ί�ɂȂ邨�������v�ŁA���̂��߂ɂ͑���̕a��C�������l���邱�Ƃ��厖���Ƃ����B �@�u���O�R�[�i�[�ł́u�咰����͓��@��Q�T�Ԃ��炢�����������̃^�C�~���O�B�i�����i�́j�H�ו��ȊO���v�ƁA�a�C�⊳�҂̓������Ƃɂ��������̍�@���������B �@���ǂ̕s�����c��A������f���������Ȃ���������B������u���������R���V�F���W���v�Ɩ��t���A���҂̏Ί�ɂȂ����Ă𑱂��Ă���B �@�T�C�g�̃A�h���X��http://cocoro-sakura.jp/�@ m3.com�@2011�N10��21�� |
||||
| �ՏI�ԋ߂̊��҂̊肢�c�ЂƂ߉��������Ƃ́H | ||||
| �@����ڑO�ɂ������҂̑������Ŋ��Ɋ肤���Ƃ́A�u������y�b�g�ɂЂƂ߉���Ɓv�Ƃ����B�u�f�C���[�E�e���O���t�v�������B �@���҂̏I�����P�A���s���z�X�s�X���x�����鎜�P�c�́u�w���v�E�U�E�z�X�s�X�v���A�z�X�s�X�E����Ώۂɍs����������蒲���ɂ��ƁA�����ԋ߂ɔ��������҂���u�y�b�g�ɉ�킹�ė~�����v�Ɨ��܂ꂽ���Ƃ�����E���́A�S�̂�60���ɏ�����Ƃ����B �@���ɑ��������w�肢���Ɓx�́A�u��������f�[�g�Ȃǃ��}���`�b�N�ȋ@������V���Ă��ė~�����v�i57���j�A�u���j����p�[�e�B�[������Ăق����v�i50���j�ȂǁB �u�w���v�E�U�E�z�X�s�X�v�̂փU�[�E���`���[�h�\������́A�u�l���̍Ŋ���ڑO�ɍT�����Ƃ��A�����Ȃ��ƂŁA�傫�ȈႢ�����܂����́B�Ⴆ�A�F�l�ƈ���A�Ƒ��̒a������ɏo�Ȃ�����A������y�b�g�ɉ�����肷��l������B���̈���ŁA��������̒n�ɗ�������A������l�ƌ���������ƁA�Ȃɂ��B�����̂���傫�Ȃ��Ƃ����߂�l������v�Ƙb���Ă���B �W���[�j�[Online 2011�N10��31�� |
||||
| ���҂�5���ɂ��a�������C�j�[�Y���܂鐸�_��ᇊw�̖��� ���������Z���^�[���_��ᇉȁE���������ɕ��� |
||||
| �@����Ƃ����d��ȃ��C�t�C�x���g���^���鐸�_�I�Ռ��͐r��ł���C���a�Ȃǂ̐��_�Ǐ��悷�邪�҂͏��Ȃ��Ȃ��Ƃ����B���{�̂���f�[�^�ɂ��ƁC���҂̖�5�������a�Ɛf�f����C�K����Q���܂߂�Ɩ�20�������_�I��������Ă���Ƃ����B �@���̂悤�Ȕw�i����C���҂₻�̉Ƒ��ɑ��鐸�_��w�I�A�v���[�`����Ƃ��鐸�_��ᇉȂ̃j�[�Y�����܂��Ă���B���������Z���^�[�ł� 1992�N�ɐ��_�ȁi2008�N�ɐ��_��ᇉȂɖ��̕ύX�j��ݒu�C���҂Ƃ��̉Ƒ��ւ̐��_��Â�ɘa�P�A�Ɏ��g��ł���B���Z���^�[���_��ᇉȕ��� ���̐��������ɁC���_��ᇊw�̌���Ɖۑ�C���_�����ɜ늳�������҂ւ̖��ÂŒ��ӂ��ׂ��_����ʓI�Ȑ��_�Ö@�Ȃǂ����B ��ʂ̐��_�����Ƃ͈قȂ邪�ғ��L�̋ꂵ�݂��P�A �\�\���_��ᇊw�Ƃ́B �@�č���1970�N��ɔ��˂����C����Ɛ��_����Ƃ���w��ł���B�p��ł�psycho-oncology�Ƃ�������ŌĂ�Ă���B�č��ł͓����C���m����ʉ����Ă���C���m��̃����^���w���X�P�A�ɑ���Տ�����ł̎��v�����܂������Ƃ��w�i�ɂ������悤���B �@1986�N�ɍ��ۃT�C�R�I���R���W�[�w��iIPOS�j���n�݂���C���N�ɓ��{�x���Ƃ��ē��{�Տ����_��ᇊw��iJPOS�j���ݒu���ꂽ�B���{�T�C�R�I�� �R���W�[�w��̑O�g�ł���B����C�����Â���Ƃ��铖�@�ɂ����ẮC1992�N�ɐ��_�Ȃ̕W�Ԃ��f�����B�Ƃ��낪�C��ʂ̐��_�Ȃ���f���Ă�����̋� ���݂𗝉����Ă��炦�Ȃ��Ƒi���銳�҂��u���_��ᇉȁv�̕W�Ԃ�T���ė��@����悤�ɂȂ�C���@�ł�2008�N�ɐ��_��ᇉȂɕW�Ԃ����߂��B �@���_��ᇊw�̎�Ȍ����̈�́C�����늳�����Ƃ��̃X�g���X���^���鐸�_�I���ƁC���_��Ԃ�����̕a�Ԃ�i�s�ɗ^������ł���B���̑��C���Җ{�l�ȊO��ΏۂƂ������҉Ƒ��ɑ���X�g���X�P�A��C�����Î҂̐��_�I���܂Ŏ�舵���Ă���B ���҂͐g�̓I�E�Љ�I�E�S���I�v���ɂ�肤�a�ǂ��� �\�\���_��ᇉȂ̖����Ƃ́B �@���݁C�킪���ł͖��N���悻50���l������ɜ늳���Ă���B���҂̖�5���ɂ��a���������C�y�ǂ̂���Ԃł���K����Q�܂Ŋ܂߂�Ɩ�20������ �_�I��������Ă���Ƃ����f�[�^������C���_�Ǐ��L���邪�҂͖�10���l�ɒB����Ƃ����Ă���B���_��ᇉȂł́C���̂悤�Ȑ��_�I��������� ���҂ւ̎��É�����s���Ă���B �@���҂̂��a�Ɋւ��ẮC����ɜ늳����ȑO�ɂ��a���o������P�[�X�����邪�C����Ƃ����d��ȃ��C�t�C�x���g�ɂ��C����܂ł͐��_�I�ȓK���ɖ�肪�Ȃ������ɂ�������炸�C���߂Ă��a�ǂ���P�[�X�������F�߂���B �@����ɔ����X�g���X�Ƃ����Ă����܂��܂��B��̓I�ɂ́C�܂��C����ɂ��ɂ݂≻�w�Ö@�Ȃǂɂ��̂̂��邳�Ȃǂ̐g�̓I�v���B���ɁC�����늳������ �ƂŎd�����ł��Ȃ��Ȃ�����C���Ô�����Ȃǂ̌o�ϓI�ȋꂵ�݂�������肷��Љ�I�v���B����ɁC�]���鍐������C�q�ǂ���z��҂ȂǑ�Ȑl�� �̕ʂ���o�債���肷�邱�Ƃɂ��S���I�v����3������B �@���������l�����ɑ��Đ��_��w�I���ꂩ���Â���邱�Ƃ��傫�Ȗ����ł���B���@�̐��_��ᇉȂɂ͌��݁C��t5�l�i���2�l�C������Ƃ̕��C1 �l�C����2�l�j�C�Տ��S���m3�l�i���1�l�C����2�l�j������C���@���̖�600�l�̂��҂̂���40�`50�l���x�̐f�Âɓ������Ă���B�����āC ����15�`20�l�̊O�����҂ɂ��Ή����Ă���B ���ʂ�������p�ɔz���������҂̂��a�Ö@ �\�\���_��ᇉȂɂ����鎡�Â̎��ۂ́B �@���a�̔��ǂ͂���늳�����ڂɂ�������Ă���B���̂��߁C��q�����ʂ�C���E��A�g���d�v�ɂȂ��Ă���B�Ⴆ�C���҂̋ꂵ�݂��g�̓I�Ȓɂ݂ɗR ��������̂Ɣ��f�����ꍇ�C�ɂ݂̎��Â���Ƃ���f�ÉȂƘA�g���čs���K�v�����邾�낤�B���邢�́C�Љ�I�Ȗ��ɂ����̂Ȃ�C�\�[�V�������[�J�[�� �̘A�g���]�܂������낤�B���@�ł͊��҂̂��߂Ɉ�Î҂��A�g��}��Ƃ������O�����L���Ă���C���_��ᇉȑ���������Ȃ⑼�̐E��ւ��܂��ӎv�`�B������H �v�����Ă���B���ꂼ��̐�含��������ØA�g�����߂��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B �@�Ö@�Ɋւ��āC���ۂ̎��Âɂ������ʂ̂��a���҂Ƃ̑傫�ȈႢ�́C���ʂ�������p�ɑ��ĐT�d�������߂���_���B�Ⴆ�C���ɉ��w�Ö@�œf ���C�ɋꂵ��ł��銳�҂ɑ��C����p�Ƃ��ēf���C���F�߂��Ă���I��I�Z���g�j���Ď�荞�ݑj�Q��iSSRI�j���������邱�Ƃ͔�����ׂ����B �@�܂��C�R�����ƍR����Ƃ̑��ݍ�p�ɂ��z�����K�v���B��ʂ̂��a���҂Ɠ��l�ɁC�R����͗L���ł͂��邪�C�}���Ō��ʂ��o�����Ɛ��}�Ɏg�p����̂ł͂Ȃ��C����p�ɑ��ĐT�d�Ȗ�ܑI���Ⓤ�^���@���K�v�ł���B �@����C���_�Ö@�Ƃ��ẮC��͂�ł���{�I�Ȏx���I���_�Ö@�iSPT�j��p���邱�Ƃ���ʓI�ł���BSPT�́C��Î҂����҂̔Y�݂�s���ɂ悭�����X ���C�����◝���������Ċ��҂��x������Z�@���B���̑��C�\�������ꂽ�������Ö@�iPST�j������C���@�ł��������Ă���B�Ⴆ�C������̍Ĕ��ɑ��� �s���ɂƂ���Ă��邤�a���҂ɑ��āC�Ǝ��Ȃlj����ɖv�����鎞�Ԃ����悤�ɑ������肷��B ���҂̂��a���߂������t�s���̉����Ɍ������g�ݐi�� �\�\���_��ᇉȂɂ�����ۑ�Ǝ��g�݂ɂ��āB �@���@�ł̐��_��ᇉȐf�Âł́C�����Ԃɂ��銳�҂Ȃ琔���Őf�@�\�ł��邪�C�ꍇ�ɂ���Ă�30���`1���Ԃقǂ�v���邱�Ƃ�����B��ʂ̐��_�Ȑf�� �Ɣ�׃J�E���Z�����O�ɂ��d�_��u�����Ƃ����_��ᇉȂ̓�����1���B�����C���_��ᇉȂ̈�t�����Őf�Âɓ�����ɂ͈�t�̐��Ɍ��E������B �@���|�I�Ȉ�t�s���̉����Ɍ����āC���{�T�C�R�I���R���W�[�w��ł͗Տ��o���̈����������t��F�肷��o�^���_��ᇈ㐧�x����N�i2010�N�j ����݂��Ă���B�܂����x���n�܂��ē����C�܂�9�l�̓o�^�㐔�ɂƂǂ܂��Ă���B�F�������Ă��Ă����o�^�̈�t�������C����C�o�^�����t�� ���͑����邾�낤�B�܂��C���w��ł͌��݁C�����ψ����ݒu���Đ��㐧�x�̓������������Ă���B���_��ᇉȂ���Ƃ��Ċ������鐸�_�Ȉ�͂܂����\�l�� ���Ȃ����߁C���_��ᇉȂ̈Ӌ`������C�j�[�Y�̍����𗝉����āC����͂�葽���̐��_�ȗ̈�̈�t�ɎQ�����Ăق����Ɗ���Ă���B �@����ł���ꂪ���g�߂�ŊJ���1�Ƃ��āC�Տ��S���m�̂ق��C�Ō�t�ȂǑ��E��Ƃ̘A�g����������B����ꂪ�s���������J���Ȋw�����̌��ʁC ���҂ɂ�����u��I���_�Ǐ�X�N���[�j���O����v���O�����v���L�p�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����iPsychooncology 2010; 19: 718-725�j�B �@��q�������҂�5�������a�ł���Ƃ�������ɂ��Ă����C���͌��߂�����Ă���P�[�X�������B�����ŁC�Ō�t�ƘA�g���C���҂ɑ��鐸�_�Ǐ� �̃X�N���[�j���O��������{���邱�Ƃ��d�v�ł���B���ɓ��@�ł͎��H���Ă��邪�C�S���̂���f�ØA�g���_�a�@�ł̕��y��ڎw���C���݂͂��̃v���O�����̐� �x����荂�߂邽�߂̉���������s���Ă���B �@�܂��C���@�ł͕ʂ̌����O���[�v���s���Ă����t�����v���O�����Ɋւ��錤��������B�厡�オ�ǂ̂悤�ɂ��m���s���Ɗ��҂̐��_�I�V���b�N�������� ���a�炰�邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ����ϓ_�ɗ����C�厡������̋���v���O�����C�R�~���j�P�[�V�����E�X�L���E�v���O�����iCST�j�̍\�z��ڎw���Ă���B���� 2007�N����N5�`6��C�R�~���j�P�[�V�����Z�p���C��Ƒ肵�Č��C����{����Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N12��12�� |
||||
| �i�[�X���������u���ʑO�Ɍ�������v�g�b�v5 | ||||
| �@�����������l���Ō�̓���������A���Ȃ��͌�������ɂ��܂����B����͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����B �@�l���Ō�̎����߂������҂����̊ɘa�P�A�ɐ��N�g������A�I�[�X�g�����A�� Bronnie Ware ����B�ޏ��ɂ��ƁA���̊ԍۂɐl�Ԃ͂�������l����U��Ԃ�̂������ł��B�܂��A���҂�����������ɂ͓������̂��ƂĂ������Ƃ������Ƃł����A���Ɏ� ���ԋ߂ɍT�����l�X�����ɂ�������̒��ő����������̃g�b�v5�͈ȉ��̂悤�ɂȂ邻���ł��B �@ 1. �u�������g�ɒ����ɐ�����Ηǂ������v �@�u���l�ɖ]�܂��悤�Ɂv�ł͂Ȃ��A�u�����炵��������Ηǂ������v�Ƃ�������BWare ����ɂ��ƁA���ꂪ�����Ƃ����������ł��B�l���̏I���ɁA�B���ł��Ȃ����������������������ƂɊ��҂����͋C�Â��̂������B�������Ă����悩�����A�Ƃ����C������������܂ܐ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɁA�l�͋������O��������悤�ł��B �@ 2. �u����ȂɈꐶ���������Ȃ��Ă��ǂ������v �@�j���̑��������̌��������Ƃ̂��ƁB�d���Ɏ��Ԃ��₵�������A�����ƉƑ��ƈꏏ�ɉ߂����Ηǂ������A�Ɗ�����̂������ł��B 3. �u�����Ǝ����̋C������\���E�C�����ĂΗǂ������v �@���Ԃł��܂�����Ă������߂Ɋ�����E���Ă������ʁA���Ȃ��s���Ȃ����݂ŏI����Ă��܂����A�Ƃ������O���Ō�ɖK���悤�ł��B �@ 4. �u�F�l�W�𑱂��Ă���Ηǂ������v �@�l���Ō�̐��T�ԂɁA�l�͗F�l�̖{���̂��肪�����ɋC�����̂������ł��B�����āA�A�����r�₦�Ă��܂������Ă̗F�B�ɑz����y����̂��Ƃ��B�����ƗF�B�Ƃ̊W���ɂ��Ă����ׂ��������A�Ƃ���������o����悤�ł��B �@ 5. �u�����������ƍK���ɂ��Ă�����悩�����v �@�u�K���͎����őI�Ԃ��́v���ƋC�Â��Ă��Ȃ��l���ƂĂ������A�� Ware ����͎w�E���܂��B���K��p�^�[���ɗ��߂Ƃ�ꂽ�l�����u���K�v�Ǝv���Ă��܂������ƁB�ω��ӎ��ɋ���u�I���v������Ă����l���ɋC�Â��A��������� ���܂ܐ��������Ă����l�������悤�ł��B �@ �@�ȏ�A�ǂ���d���������e�ł����B�����ǂ�ŁA���Ȃ��͖�������ǂ��߂����܂����B Pouch�m�|�[�`�n 2012�N2��5�� |
||||
| ���悭�����邽�߂Ɂ@�������߂邱�Ƃ̑���@�L����m�̑̌n�u�����w�v | ||||
| �@���悭�����邽�߂Ɏ������߁A�����Ȃ�̎����ς��`�����čŊ��ɗՂށB���̎x���ƂȂ�V�����m�̑̌n�u�����w�v���L������݂��Ă���B �@�u�Ƒ��ɒm�点�Ă��Ȃ����͂���܂��H�v�B���O�̏��������x���͂������B�}�C�N������̂́A�A���t�H���X�E�f�[�P����q�喼�_�����B�s���ŊJ���ꂽ�u�����E���Ǝ����l�����v���J�Z�~�i�[�ł̍u�����B �@���ʂƃO���[�t�i�ߒQ�j�P�A���e�[�}�����A���[�����X�Ȍ��荞�݂A���ʑ̌��҂ɐڂ���ۂɔz�����ׂ��_�A�z��҂��������̔����ɂ��Ęb��i�߂��B �@�P�X�R�Q�N�h�C�c���܂�B�T�X�N�ɗ����A��q��Łu���̓N�w�v�N�u���A��ʂ̐l�X�ɂ��u���ւ̏�������v�̑��������Ă����B�����^�u�[�����镗�����������{�Łu�����w�v���J���Ă����������I���݂��B �@�����w�B�f�[�P�����_�����́u���Ɋւ��̂���e�[�}�ɑ��Ċw�ۓI�Ɏ��g�ފw��v�ƒ�`�t����B��w��N�w�A�S���w�Ȃǂ��܂��܂Ȋw���p���A���ƌ��������m�̑̌n�B�z�X�s�X�^���Ɛ[���ւ��������A���{�ł͂V�O�N�ォ�玀���w�Ƃ������t���p������悤�ɂȂ����B �������� �@�����w���i���̈�l�A�����i�i���܂��́E�����ށj���勳���ɂ��ƁA���̐V�����w�▼�ɒʂ���u�����ρv�Ƃ������t��"����"���ꂽ�͓̂��I�푈�O��B ���̌��t�ɑ����Ď��Ɏv�����͂��A�Ŋ��Ɋւ���l�����܂Ƃ߂Ă������Ƃ���v�z�╶�w����̍�i�Q���`�����Ă���Ƃ����B���������`���̒��A���{�ɂ��� �鎀���w�́A�����ϗ���V�A�ԗ�Ȃǂ̌����Ƃ����ѕt���Ȃ��畝�L���̈���\�����Ă����Ɠ��������͘b���B �u�w���{�l�̎����ς��ĉ����낤�x�Ƃ̖₢�́w���{�l���ĉ��x�ɂȂ���A����̕�����₢�����ǂ�����ɂȂ�v �@�s���̊S�������B�V���|�W�E���Ȃǂ̔����̑����ɋ��������Ƃ����B�w�i�ɁA��Â������ɂ������͈͂̊g��A����Љ�̐i�s������B��Ì��ꂩ��� �j�[�Y�������A�N�w��@���w�Ȃǂ̊w��I�~�ςf�����u�l���I�Ȓm�̌��݁v�̕K�v����Ɋ����Ă���A�Ɠ��������͘b�����B �����̂��ւ̊S �@�����w�͎��ƌ��������w�₾���A�K�v�Ƃ��Ă���͕̂K�������V�j�A���ゾ���ł͂Ȃ��B���w�@��l�ԕ����w���̓�����a�i�ӂ����E�݂�j�����������w�� ���Ƃ��n�߂��̂́A�X�X�N�H�B�ŏ��̎��ƂŁA�w���������̊O�ɂ��ӂ�Ă���̂ɋ������B�u�w������͉��̂��߂ɐ�����̂����l���鎞���B���̂��⎀�ɊS ������v �@����ɂ��������w�����S���Ȃ�ߒ�����L�`���ŒǑ̌����A��Ȃ��̂����������u���̋^���̌��v�ȂǁA����������������ƂŒ��ڂ��W�߂Ă����B����̎����w�E�X�s���`���A���e�B�����Z���^�[�������߂�B �@���g�A���ɒ��ʂ����o��������B�V���Ђŏ[�������������߂��������A�ˑR�S�g���܂Ђ���a�C�ɁB�ꖽ�͂Ƃ�Ƃ߂����̂́A�S�������Ȃ����X�B�����̊��҂����y�������肵�Ȃ���S���Ȃ�p�����Ďv�����B�u����ł����l�X�̂��߂ɉ����ł��Ȃ����̂��v �@���N�̓��@�A�Q�N���̃��n�r�����o�đ�w�Ɋw�m���w���A�Љ�����U�B���A�u���v�̉Ȗڂ��Ȃ��B�ŏI�I�ɕč��Ŋw��Ŕ��m�����擾�����B �@�����w�ւ̊S�����܂钆�A�̂��C�����Ȃ���������Ȋ�����W�J����B�M�S�ȃN���X�`�����ł���A���̂Ԃ�Ȃ��������̊j�ɂ͐M������B �@�u�����܂߁A�����邱�Ƃ��l����̂������w�v�Ɠ��䋳���B�u�����̖��͏����ł͖����B�l�ԂɊS�������A�Ⴂ��������w���̂��x�ɂ��čl���Ăق����v m3.com�@2012�N3��23�� |
||||
| ���S�O�A�S�Ђ̐e�E����u���}���v�c�S�����̌� | ||||
| �@����ł݂Ƃ�ꂽ���҂̖�S�����A�S���Ȃ�O�A���łɂ��Ȃ��e�̎p�������ƌ��ȂǁA������u���}���v�̌��������A���ꂪ���₩�Ȃ݂Ƃ�ɂȂ����Ă���Ƃ̒����������A�{�錧�Ȃǂōݑ��Â��s���Ă����t��̃O���[�v���܂Ƃ߂��B �@�ݑ�f�Â��s����t���w�����҂炪�Q�O�P�P�N�A�{�錧�T�����ƕ������P�����̐f�Ï��ɂ��K��f�ÂȂǂʼnƑ����݂Ƃ����⑰�P�P�X�P�l�ɃA���P�[�g�����B �@�u���҂��A���l�ɂ͌����Ȃ��l�̑��݂╗�i�ɂ��Č�����B���邢�́A�����Ă���A�������Ă���A�����Ă���悤�������v����q�˂��B�҂T�S�P�l�̂����A�Q�Q�U�l�i�S�Q���j���u�o�������v�Ɠ������B �@���҂������������ƌ�������e�́A�e�Ȃǁu���łɎ������Ă����l���v�i�T�P���j���ł����������B���̏�ɂ��Ȃ��͂��̐l�╧�A���Ȃǂ̓������������B �@�u���}���v��̌�������A���҂͎��ɑ���s�����a�炮�悤�Ɍ�����ꍇ�������A�{�l�ɂƂ��āu�ǂ������v�Ƃ̍m��I�]�����S�V���ƁA�ے�I�]���P�X�����������B �@�����́A�����Ȋw�Ȃ̌����������Ď��{�B�u���}���v�̌��͌o���I�ɂ͂悭����邪�A�w�p�I�ȕ͂���߂Ē������B �@���������o�[�ł���ݑ��Â̐���A�������E���k���w���Տ������́u�w���}���x�̌�����荇����Ƒ��́A���₩�Ȃ݂Ƃ肪�ł���B���Ƃ����o��ϑz�ł����Ă��A�{�l�ƉƑ�������������̌��ۂƂ��ĕ]������ׂ����v�Ƙb���Ă���B m3.com�@2012�N6��21�� |
||||
| �y���k��z���҂���́g���������h�v�������Ȃ���A�J�x���Ƃ� | ||||
| ���� �s���i�Ջ���ȑ�w�y�����E���O�q���w�j���i�� �ߓ� �������i����Љ�ی��J���m�E�ߓ��Љ�ی��J���m��������\�^��ʎВc�@�lCSR�v���W�F�N�g�����j �� �e�뎁�i����l���a�@���w�Ö@�ȁE�ɘa�P�A�`�[���j �a�c �k�����i�k����w��w���y�����E���O�q���w�j �@5�N������������54���܂ŏオ��C�����t�������a�C�ւƎp��ς����邪��B16�|65�܂ł̓�������ł́C���N�V���ɖ�22���l�̊��҂����܂� �Ă���B�{�N6���Ɍ��肳�ꂽ�C�����̂�������i��{�v��ɂ��A�J�x���̕K�v�������L�����ȂǁC���ÂƓ������ƂƂ̗������ۑ�ƂȂ�Ȃ��C��� �҂̗��ꂩ��͂ǂ̂悤�ȃT�|�[�g���ł���̂��낤���B�{���k��ł́C����̓����҂������炵�����������邽�߂́C�x���݂̍���ɂ��čl�@����B �u�������Ɓv�̈Ӌ`�Ƃ́H �����@�܂��u�������Ɓv���C���҂̕��ɂƂ��āC���邢�͂���̎��Â̏�łǂ̂悤�Ȉʒu�t���ɂ���̂��C����̌��҂ł���ߓ����炨�b�����������܂����B �ߓ��@���ɂƂ��ē������Ƃ́C�g�����̗Ɓh�ł�����܂����C�����g�����邱�� ���̂��̗̂Ɓh�Ƃ����Ӗ������������ł��B���ꂾ���ɁC�ςݏd�˂Ă������Ȏ����̉ߒ�������ɂ���ă��Z�b�g����C������Ƃ������Ă��܂����Ƃɋ�����R ��������܂��B�����l���̃C�x���g�̈�ƂƂ炦�C���̑O�����̌�������悤�ɓ������������ƍl����̂́C���҂ɂƂ��Ă������R�Ȃ��Ƃ��Ǝv���� ���B ���@�������ƂŎЉ�ɂ�������������������Ă��������C���������Ƃ����a�����������Ƃł��̖�����D����B����͂܂��ɁC�A�C�f���e�B�e�B�������͂������悤�ȋ�ɂł����C���̋�ɂ́C�S�g�ɑ傫�ȉe����^���܂��B �@����T�o�C�o�[�̂Ȃ��ŁC�A�Ƃ��Ă�����̂ق���QOL���悢�X���ɂ���Ƃ����������ʂ��k�Ă�A�W�A�ŕ���Ă��܂��B�������Ƃ����ÂɃv���X�̉e����^����_�ɂ��C���ڂ��ׂ����Ǝv���܂��B �a�c�@����l�̂��b�̒ʂ�C���҂���ɂƂ��āu�������Ɓv�́C�����⎡�Â� ��p���m�ۂ��邽�߂ɂ��C�g���C�t�h���[�������邽�߂ɂ��d�v�ȗv�f�ł��B�ł������Ï]���҂́C���Â��Ȃ��瓭���������҂����邱�Ƃ�F�����C���� ���Ŏd���̌p���ɍ���������Ă��������肷��K�v������܂��B�S�̂��猩��Ə��l����������܂��C�����Ă��鍢��̓����͐獷���ʂŁC���[����肪 ����ł���ꍇ������ƍl�����܂��B ���Â₻�̕���p�ɂ��A�J�p��������� �����@����ł͋�̓I�ɁC����̎��ÂƎd���Ƃ̗����̓���́C�ǂ��������_�ɂ���ƍl�����܂����B �ߓ��@�܂��C��p�����Â̑��I�����ɋ����邱�Ƃ������C���̂��߂̌�������@�ŁC�K���d�������f����܂��B�܂��C���w�Ö@�̂��߂̒ʉ@�������ԑ����C�X�P�W���[������������Ȃ邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B �����@2�N�O����n�܂����C���J�Ȍ��u����ƏA�J�v�i�}�j�̌����ǂɂ��l�b�g�����ł��C��p���̋}�Ȍ���C���w�Ö@�̗\��ύX�Ȃǎ��Ìv�悪�\�����ɂ����C�d���ɉe������Ƃ���������������܂����B 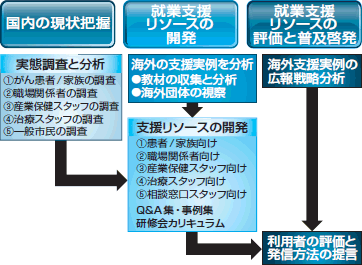 �@���Ƃ́C��͂艻�w�Ö@�̕���p�̖��ł��B����p�̒��x�ɂ͌l�������邽�߁C���̕s�m�肳�䂦�̔Y�݂�����悤�ł��B�S�g�Ɍ���錑�ӊ���W���͂� �ቺ�C������Ǐ�C�}���Ȃǂ��܂��܂ȕ���p�̏Ǐ�ɂ��C�v���悤�Ɏd�����ł����ɂ炳�������Ă�����́C���������܂��B ���@����p�ɂ��Ă͑�܂��ȑz��͉\�ł����C����ł��ڍׂȗ\���͂ł��� ���Ƃ����̂�����ł��B�����C���w�Ö@�̍ŏ���1�R�[�X���o�����邱�Ƃɂ���āC2�R�[�X�ڈȍ~�̂��������̊��o�����߂Ă��܂��B�ł����犳�҂���ɂ� �u1�R�[�X�ڂ̊Ԃ����͉��Ƃ����x�݂����炤���C�������ނł���悤�ȑԐ��𐮂��āC�ǂ�ȕ���p�����邩�C�l�q�����Ăق����v�Ƃ��b�����Ă��܂��B �����C���[�W��C�E������炭��g�����ɂ����h�� �ߓ��@����Ƃ��������ɑ��ĎЉ���C���[�W���C�A�J�ɉe�����Ă���Ǝv���܂��B�����g���ȑO�͂����ł������C����ƕ����ƂƂ����Ɂg���h��A�z���Ă��܂��B���R�u�d���̂��ƂȂ�ċC�ɂ��Ă���ꍇ����Ȃ���ˁv�ƍl�����������Ǝv���܂��B ���@�w�B�g�Ƃ��Ă̕a���x�i�X�[�U���E�\���^�O�C�݂������[�j�ł́g���Ă͌� �j�����̕a���������C���j����������Ă���́C�����̃C���[�W�Ɏ���đ������h�ƋL����Ă��܂��B���ꂾ�����������オ�������ł��C�K�v�ȏ�ɔߊ� �I�ȃC���[�W������Ƃ����a���ɔ킹���āC���܂��Ɉ�l�������Ă��銴�͂���܂��ˁB �����@���������C���[�W���ǂ��Ŕj���Ď��͂ɗ����Ă������C���̉ߒ��ŔY�܂����������ł��B �a�c�@�E��ŗ����Ɣz���邽�߂ɂ́C�a�C�̘b���u�ǂ��܂Łv�u�N�Ɂv���Ă� �����C���҂��g�����ɂ߂��Ƃ�v���܂��B���ɓ��������40�Ζ����ɑ��������̓������q�{����Ɋւ��ẮC�j����i�ɐ������ɂ����ȂǃW�F���_�[ �̖������݁C���Ԃ����G������\��������܂��B �@�ŋ߂ł́C��Ƃ̌�������ړI�Ƃ����l���팸��K�ٗp�҂̑����Ȃǂɂ��C�E��Ō݂��ɏ��������Ƃ�����������������܂��B���ɒ����K�͂̊� �Ƃ͐l�I�]�T�ɖR�����C�̒��s�ǂȂǂŐ�͂ɂȂ�Ȃ��l�ɂƂ��ẮC�K���������S�n�̂悢���ł͂Ȃ��B�����������C���҂���{�l�̊��������݁C���� �Ƃ��Ď��߂���Ȃ��Ȃ�P�[�X�����Ȃ��Ȃ��悤�ł��B �܂��́C�A�J�ɂ��Ęb���₷�����͋C����� ���@�ȑO�C���҂���̋ߐ�̎Y�ƈ�^�Ō�t����A�����������������Ƃ������� ���ŁC�d���Ǝ��Â̒������X���[�Y�ɐi�݁u�����܂œ����Ă����I�v�Ɗ��������o��������܂��B��������ƁC�ق��̊��҂���̃P�[�X�ł����낢�� ���肢���Ă݂����Ƃ����C�ɂȂ�u�E��ɎY�ƈ�̕��͂����܂����v�Ƃ������Ă��܂��̂ł����C��U�肪�����̂ł��i�j�B �a�c�@�Y�ƈ�̑I�C�`��������50�l�ȏ�̐E��́C���{�̑����Ə����̂킸�� 3���C�J���Ґ��ł݂Ă�4����ł��B����ɂ����̊�Ƃł��C�Y�ƈ�̖K�����1��ł�������C���邢�͒���K�₳���Ȃ��ꍇ������܂��B��̎Y�� ��ւ̃A�N�Z�X���m�ۂ���Ă����ƘJ���҂́C�S�̂̐������x�ł��傤�B �@���������������܂�����C�厡��̐搶�ɂ́C�����ł��Y�ƈ�I�Ȏ��_�������Ċ��҂���̏A�J�ɂ�������Ă�����������Ǝv���̂ł��B�u�E��̏�i�� �ǂ�Șb�����Ă��邩�v�u�d�ʕ��̉^���E�o���E�����ԘJ���ւ̔z�����K�v���v�Ƃ������b����o�����Ƃ��C�����������ɂȂ�܂��B ���@���҂���́C�a�@�ŏA�J�̑��k���ł���Ƃ͍l���Ă����܂��C�܂��͈�Î҂��C��z���āC�A�J�ɂ��Ęb���₷�����͋C����邱�Ƃ���ł��ˁB �����@�x���ɓ������ẮC�u����ƏA�J�v�����̈�ō쐬�����u����Ɋw�ԁ@���҂̏A�J�x���ɖ𗧂�5�̃|�C���g�v�i�\1�j���Q�l�ɁC�ł��邱�Ƃ��珇�Ɏ��݂Ă�����������Ǝv���܂��B
�a�c�@���ÂƏA�J�̗����̎x���ɔM�S�ȊO�Ȉ���ᇓ��Ȉ�ɃC���^�r���[���s���Ă܂Ƃ߂����̂ł����C���Z�Ȓ��ł����g��ł���������悤�ȁg�D����h���W�߂�����ł��B ���@�����g�C�u5�̃|�C���g�v���Q�l�ɁC���҂���ɖ₢���������Ă��܂��B����Ɓu���������Ǐ������ꍇ�C�ǂ������炢���ł����v�ȂǂƁC��̓I�ȑ��k���ł��C���i�Ή��ɂȂ��邱�Ƃ������ł��B �u�������S�v�����ݏo���_��Ȏ��Ñ̐� �����@���{�Տ���ᇊw��Ɠ��{���ÔF���@�\�̐搶���̂����͂Ď��{�� �ꂽ�����ł́u���ÃX�P�W���[�������҂���̎d���̓s���ɔz�����Č��߂��邩�v�Ƃ����ݖ�ɑ��C���ː��ɂ��Ă�28���C���w�Ö@�ɂ��Ă�42���� �u���߂���Ǝv���^�܂��v���v�Ɠ����Ă��܂��B���̐��l�ɂ͂悢�Ӗ��ŏ��X�����܂������C���搶�̎����Ƃ��Ă͂������ł����B ���@���w�Ö@�����ː����Â��C��{�I�Ɉ�t�̐f�@������K�v�ł�����C�Ζ��̐� �ȂǕa�@�^�c��̌��E������܂��B�������f�ÉȂ��Ƃɖ����S���āC��含�����߂�قǁC�Z�ʂ͗����₷���Ȃ�Ǝv���܂��B�����g�C�Ö@�͈�C���� �Ă������C�a���͊O�Ȃ̈�t�������Őf�Ă���Ă���C�O�����ɋ}�ςŌĂ�邱�Ƃ͂���܂���B���[�`���̌����Ɩ������܂�����Ă��炸�C��r�I�܂� �܂������Ԃ�����̂ŁC���҂���Ǝd���̘b���ł���킯�ł��B �����@�Ⴆ�ΏT��3�|4���O�����J���Ă���C���҂�����s���̂����j����I�����₷���Ȃ�܂��B������C�e�Ȃ̈�t�����̂��̖̂����ɐ�O�ł�����������Ă���C�������₷���Ƃ������Ƃł����B ���@�����ł��ˁB���̂��߂ɂ́C��������ᇓ��Ȉ���C�a�@�̒��Ŗ����������� �o�����炢�̋C�T�������Ď��Ìv��ɉ�����Ă����K�v������܂��B����ő���ʐ��Ȃ̐搶���ɂ��u��ᇓ��ȂɔC���Ă������v�Ƃ����F�������Ў����� �������������B�ŋ߂ł͑�������̊ɘa�P�A�̋C�^�����܂��Ă��܂�����C�`�[����Â̊ϓ_����C�A�J�̖��ւ̃R���T���g���u�Љ�I��ɂւ̃A�v���[�`�v �Ƃ����Ӑ}�Ŋɘa�P�A�`�[���ɂ��肢����Ƃ����̂��C��̕������ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���Ƃ���ł��B �a�c�@�u5�̃|�C���g�v�쐬�̉ߒ��ł��炽�߂ĔF�������̂́C��t�͕a�@�̒� �Œ�Ă��₷������ɂ���Ƃ������Ƃł��B�u�d���Ǝ��Â̗������x������v���Ƃ���j�Ƃ��ĕ\�����Ă��������C���̏�ŊŌ�t��MSW�Ȃǃ��f�B�J���X �^�b�t���܂߁C�ǂ�Ȏx���������S���邩��������B���ꂾ���ŁC�͂����Ԃ�ς��̂ł͂Ȃ����Ƃ������G�Ă��܂��B ���@�܂��͌���̐ӔC�҂��ӎ���ς��āC�������S�ƃ`�[����Â����ɂ������Ă����B���ꂪ�ς�邱�ƂŁC�a�@�S�̂ɂ��_������܂�C���ʂƂ��āC���������銳�҂���ɂ�莑����V�X�e�����ł��邩������Ȃ��C�Ǝv���Ă��܂��B �����@���҂���̈�ԋ߂��ł�����葱����厡��̕��X�ɂ́C�ނ�̐������̊� �]���ł�����蕷���Ă������������C�Ƃ����̂����̊肢�ł��B�u�Ĕ����āC���Ɣ��N������A�J�͍l���Ȃ��Ă�����ˁv�ł͂Ȃ��C���{�l�Ɂu���������v�Ƃ� ���v��������̂Ȃ�C�ŋ��̃T�|�[�^�[�Ƃ��āC��������Ȃ���x�������肢�������̂ł��B �@����������ǂƂ��āu�A�J�̖��ɔY�ފ��҂��C����ȍH�v�œ����₷���Ȃ����v�D����𑐂̍��I�Ɏ��W���C�Տ�����̕��X�Ƌ��L���Ă��������ƍl���Ă��܂��B ���k�ł����̏[���Ƃ����ɂȂ��郋�[�g�̐��� �����@�������N�ŁC����ƏA�J�ւ̊S�����������܂�C���҂����p�ł���c�[�������ɂ��������܂�Ă��܂��B����ߓ�����ɁC�\�ɂ܂Ƃ߂Ă��������܂����i�\2�j�B
�ߓ��@����ɓ����������̂͂܂��܂����Ȃ��̂ł����C���҂���ȊO�ɂ��C��Ƃ̕��C�����ďA�J�x���ɋ����������Ă����t�̕��ɂ��C�Q�l�ɂ��Ă���������Ǝv���܂��B �����@���������c�[���̊��p�𑣐i�������C���ꂾ���ł͉���������ꍇ�̂��߂ɁC�ʂɑ��k�ł��鑋���̏[�������߂���Ƃ���ł���ˁB �ߓ��@�u�ǂ��ɑ��k������悢���킩��Ȃ��v�Ƃ������͎��ۂɑ����ł��B �@����̎��ÂƎd���C��������x�ɑ��k�ł����͌���ł͖R���������C�n���[���[�N�C�N���������C�s�����C�����ۂȂǁC�����̋@�ւ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���_�͂��̗͂������Ă��銳�҂���ɂ́C�z���ȏ�ɑ�ςȂ��Ƃł��B �a�c�@�a�@�ɂ����āC�Љ�ی��J���m�i�ȉ��C�ИJ�m�j�̕��ƘA�g���C���҂���̑��k�ɑΉ��ł���悤�Ȏd�g�݂�����ł���Ƃ悢�ł��ˁB �ߓ��@����͎����C��Ò҂̕��X�ɂ��Ќ������Ă������������ƍl���Ă��邱�Ƃł��B �@���i��������Ă��Ȃ����҂���ɂ́C�a�@���ł̏���c�[���̏Љ�ŏ\���ł����C�s���Ɏ��߂�����ꂻ����������C�ی����t���Ȃ���邩�ۂ����� �ȃ��C���ɂ�����ȂǁC��͂���Ƃ�����������ق����悢�P�[�X������܂��B���͂ő��k�@�ւ�T���o���銳�҂������ł͂Ȃ��C�Ƃ����_���猾���� ���C��Ë@�ւ���̃��[�g����������邱�ƂŁC�~������͑����Ǝv���܂��B ���@�g�ИJ�m�h�Ƃ������݂�m��Ȃ��Տ�����C�܂����R�̂悤�ɂ���Ǝv���܂��B�܂��C�����������ɖ��邢�ИJ�m�̕����ǂ��ɂ���̂����C�a�@���ł͂Ȃ��Ȃ��킩��Ȃ����̂ł��B�Ⴆ�C�Љ�ی��J���m��Ȃǂňꊇ���ď����Ă���������ƁC���ɏ�����܂��B �ߓ��@���ł����C��Q�N���Ɋւ��ẮC�ИJ�m�ɂ��S���K�͂�NPO�@�l�ȂǑg�D�I�Ȏx�����\�ƂȂ��Ă��܂��B����ƏA�J�̖��ł����l�ɁC�m�����������ИJ�m�𑝂₷�ƂƂ��ɁC�g�D�I�Ȏx���̐��𐮂��Ă����K�v�����肻���ł��ˁB �����@�@���ɁC������x�A�J�̑��k�ɏ���m�E�n�E�������������邱�ƁB����ɕ��G�ȃP�[�X�Ɋւ��ẮC�ИJ�m�Ȃlj@�O�̐��ƂɃR���T���g�ł���̐������������C�x�X�g���Ƃ������Ƃł��ˁB ���@������C�@�O�ł��@���ł��悢�̂ł����C����T�o�C�o�[�̕��ɏA�J�Ɋւ� ��A�h�o�C�X�����肢�ł���V�X�e���̐������K�v�Ǝv���܂��B���҂�����u�搶�v���瑣�������C�����҂̏W�܂��A�h���H�J�V�[�O���[�v�Łu���҂Ƃ� �ā^�T�o�C�o�[�Ƃ��Ă����s�������v�Ƃ�������������Ă���������ƁC����D�ɗ����₷���ł��傤�B�W���̗v���́g����������h�ł��B��������Ďd ���𑱂���R�c�ȂǁC�����I�ȃm�E�n�E��`�����Ă��炦�邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B �ߓ��@�m���ɓ����ғ��m���u�������Ɓv�ɓ������Ęb�����́C�܂��܂����Ȃ��� ���B���Âł�������E����������C�ēx���E����ۂɕa�C��ʉ@�̂��Ƃ��ǂ��`���邩�C�Ƃ������Y�݂����������������܂��B�ďA�E�ɐ��������������̓I �ȃA�h�o�C�X�����炤���ƂŁC�傫�ȗ�݂ɂȂ�܂��B���������̌����V�F�A�����̕K�v���́C���������܂��ˁB ���҂���̂ƂȂ��Ė������ꉻ���Ă��� �����@�u���[�g���v��u�������S�v�Ƃ����L�[���[�h��̌�������̂Ƃ��āC�u����ƏA�J�v�����ǂł́C���Җ{�l�C�Y�ƈ�C�厡����Ȃ��u�A���蒠�v�̂悤�ȃc�[�����������Ă��܂��B�����ʓI�Ȋ��p�̂��߂ɂ́C�ǂ�Ȏ��_��������悢�ł��傤���B �ߓ��@�����܂Ŋ��҂���̂ł��邱�Ƃ��C����Ǝv���܂��B �@�Ⴆ�Ύ��́C���Ò��ɗ��p�ł���Г����x�ɂ��Ċm�F���Ă����������߂ɁC�u�A�ƋK���Łg�x�Ɂh��g�x�E�h�Ɋւ�����́C�Z���ԋΖ��Ȃǂ̋Ζ����x�Ɋ� ������ׂ̂�v�Ƃ�������Ƃ��C���k�҂̕��ɂ��肢���邱�Ƃ�����܂��B����������Ƃ��C�̐����◝���ɖ𗧂��Ă���悤�Ɋ����Ă��܂��B ���@����́C��ᇓ��ȁE�O�ȁE���ː��ȁC�����ďꍇ�ɂ���Ă̓��n�r���e�[�V�����ȂȂǁC���Â��ו�������C�厡�コ����サ�Ă����ꍇ������܂��B�Ȃ̂Ŋ��҂���̐��������ďA�J�̖��������ł���c�[�����ł��邱�Ƃ́C�傢�Ɋ��}�ł��B �a�c�@���ÂƎd���Ƃ̗����̂��߂ɒ������K�v�ȑ����̎����ɉ����C���Â̕s�m�萫��C�a�C�̒m���s���Ȃǂ̖�������B���������ŁC�ǂ�Ȕz�����ǂ̂��炢���߂Ă���̂��C���҂����猾�ꉻ�ł���悤�C�c�[���Ȃǂ�ʂ��Ďx�����Ă�����Ǝv���܂��B �o��l�����ꂼ��̗���ŁC�ł��邱�Ƃ��l���� �����@���ꂩ��̎x���݂̍���ɂ��āC�������ꌾ�����������܂����B �ߓ��@�����ИJ�m�ɂȂ����̂́C�����₷���E�ꂪ�����邱�ƂŁC���������Ɠ��� ��l�������C���F���K���ɂȂ��̂ł͂Ȃ����C�Ƃ����v������ł����B���܂��܂���ɂȂ�Ƃ����o���������̂ŁC���̌o�����Љ�ɊҌ�����Ӗ������� �āC�ИJ�m�Ƃ��ē����₷���E�����i�߂����ƍl���Ă��܂��B �a�c�@�u���������v�Ƃ����v���́C�Љ�ɎQ���������Ƃ����q�g�̍��{�I�ȗ~���� �������܂��B������i�݁C���݂�70�܂œ������Ƃ��ڕW�Ƃ��Ď������Ȃ��C��l�ł������̊��҂��u�����Ȃ��玡�Â��ł���悤�ɂȂ�v�Љ��� ���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ������ɂ���܂��B����Ƃ������������̑�\�ƂƂ炦�C���f���P�[�X���Ȃǂɂ���Ă���ɓW�J���ł���Ǝv���܂��B ���@��肻�̂��̂̔F�m�x�����@���x�̐����Ƃ������n�[�h�ʂ̉ۑ肪���낢�� ����܂����C��Ղ͐l�Ɛl�Ƃ̊W���Ǝv���܂��B�l�Ɛl�̊W�ł́C�g����������h�̃o�����X�̗ǂ��W����ۂC���^�̊W���ɐӔC�����Ƃ����w �߂�����܂��B���҂���ɂ͂��Зǂ��W���̃X�L����g�ɂ��Ă������������ł����C���������f�ÉȁC����ɂ͐E����Ǝ�����f�����W���������C�T �|�[�g���Ă��������ł��ˁB �����@�u����ƏA�J�v�̖��́C�o��l�����ƂĂ������̂ł����C���ꂼ��̗��� ����ł��邱�Ƃ�����Ə����������Ă�����������܂��B���N�x����n�܂������������i��{�v���5�N�Ԃ��I������Ƃ��Ɂu���҂���̏A�J�� �͂����܂ł悭�Ȃ����I�v�ƌ�����d�g�݂��C�F�ŘA�g���Ȃ������Ă��������Ǝv���Ă��܂��B�{���́C�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B �T����w�E�V�� ��2988�� 2012�N7��30�� |
||||
| �g�ђ[���ł��҂̃P�A�̎�������H ��V���Տ������̌��ʂ����\ E-MOSAIC�iSAKK 95/06�j���CESMO 2012 |
||||
| �@�ߔN�C�ڊo�܂��������ŕ��y���Ă���g�я��[���iPDA�j��X�}�[�g�t�H���́C��̂Ђ�T�C�Y�Ŏ����^�т��₷���C���܂��܂ȏ�
���f�������́E�����ł��邽�߁C�i�s���҂̃P�A�ւ̉��p����������Ă���B�X�C�X�̂���Տ������O���[�v�iSwiss
Group for Clinical Cancer
Research�j�́C�ɘa�P�A�̕K�v�Ȑi�s���Ҏ��g���Ǐ��PDA�Ŗ��T�L�^���邱�Ƃɂ��C���҂̏Ǐ���Î҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɕω�����
���邩�ɂ��āA���{�����N���X�^�[�����_������V���Տ����������{�B2012�N���B�Տ���ᇊw��N���w�p�W��iESMO
2012�G9��28���`10��2���C�E�B�[���j�ɂ����ē��O���[�v��Florian
Strasser�����C���̐��ʂ�����ꂽ���Ƃ����ꂽ�B �����̏Ǐ�C���p�����x���Ö@��ȂǂT�L�^ �@���O���[�v��Palm�Ђ�PDA�ŏǏ��h�{�ێ��ԁC���p�����x���Ö@��C�S�g��ԁiKarnofsly PS�j�C�̏d�Ȃǂ���͂ł���悤�ɂ��C���̃v���O������E-MOSAIC�Ɩ����B�]���̗p���L�^���Ɣ�r���āCE-MOSAIC������ QOL�iglobal quality of life�j�⊳�҂̏Ǐ�C���҂ƈ�t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɂǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ�����]�����邱�ƂƂ����B ��t�ɂ��o�^�K���u���Ìo���L���ŃR�~���j�P�[�V�����͂�L���c�v �@���҂̓o�^�K���́C�ɘa���Â��Ă���؏��s�\�i�s����ŁC�R������Â��O���ŎĂ���҂̑S�g��Ԃ̈����Ǘ�Ƃ����B��t�̓o�^�K���́C���Ìo ���L���ŃR�~���j�P�[�V�����͂�L���C�ɘa���Ö@�̌��茠��L����҂Ƃ��ꂽ�B��v�]�����ڂ́C�x�[�X���C����6�T�ڂɂ����鑍��QOL�̍��Ƃ��C�ړx�� ��EORTC-QLQ-C30�̍���29�C30���g�p�B2�Q�Ԃ�10�|�C���g�̍����F�߂�ꂽ�ۂɗՏ��I�Ӌ`��������̂Ɛݒ肵���B�����]�����ڂ��x�[�X ���C����6�T�ڂɂ�����Ǐ�̂炳�̕ω����G�h�����g���Ǐ�]���ړx�iESAS�j��p���ĕ]�������B�܂��C���҂ƈ�t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������邽 �߁C���҂̊������t�̗D���������o�I�A�i���O�X�P�[���iVAS�j�ŕ]�����邱�ƂƂ����B �p���L�^���Ɣ�ׂāC�Ǐy������t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������� �@�X�C�X������8�{�݂��Q�����C��t84�l�C����264�l���o�^���ꂽ�B���҂̐������Ԓ����l��5.8�J���iE-MOSAIC�Q6.3�J���C�p���L�^�Q 5.4�J���j�ł������B��͂́C�x�[�X���C���̑���QOL�₻�̑��̋��ϗʂŕ�����������ʃ��f���imixed effects model�j�ōs��ꂽ�B��v�]�����ڂł���x�[�X���C����6�T�ڂɂ����鑍��QOL��2�Q�Ԃ̍���6.84 �|�C���g�ƁC���v�w�I�L�Ӎ��͊m�F����Ȃ������iP��0.111�j�B����C�����]�����ڂł���Ǐ�̂炳�́CE-MOSAIC�Q�|4.9�i���P�j�C�p�� �L�^�Q2.0�i�����j�ł���CE-MOSAIC�Q�œ��v�w�I�L�ӂɉ��P���邱�Ƃ������ꂽ�iP��0.003�j�B�܂��C���҂̊������t�̗D������E- MOSAIC�Q�ŗL�ӂɌ��サ�����i��18.9�CP��0.014�j�C�p���L�^�Q�ł͑傫�ȕω��͌����Ȃ������i��4.7�CP��0.403�j�B �@�ȏォ��CStrasser���́u��v�]�����ڂ͒B������Ȃ��������CE-MOSAIC�̗��p���C�Ǐ�̂炳�⊳�҂ƈ�t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������� �P�����邱�Ƃ������ꂽ�v�Ƃ��A�u��������҃T�|�[�g�̂��߁C�c�[���̊J�����t�Ԃ̃l�b�g���[�N�\�z�ȂǁC����Ȃ���g�݂��K�v�v�Ƃ܂Ƃ߂��B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N2012�N10��5�� |
||||
| �������ҁ@��ɂ�j�[�Y�������C�K�ɕ]���C�Ή� | ||||
| ��41����{�����S�g��w�� �@�������҂́C�l�Ƃ��Ă܂������Ƃ��Ă��܂��܂ȋ�Y������Ă���B�����s�ŊJ���ꂽ��41����{�����S�g��w��i���������Ȏ��ȑ�w��w�@���B �@�\���֊w����E�v�ۓc�r�Y�����j�̃V���|�W�E���u�����̂���ƐS�̃P�A�v�k������������Ȏ��ȑ�w��w�@�S�ÁE�ɘa��Êw����E�����p����C�����a�@ �@�\�����a�@�ɘa�P�A�ȁE�i��p�����i�ċz����ȊO���f�Õ����j�l�ł́C���_��ᇈ�C��ᇓ��Ȉ�C�ɘa�P�A��炪��Y��������������҂̐S�̃P�A�ɂ� ���ĕB��ɂ�j�[�Y�������C�K�ɕ]���C�Ή����邱�Ƃ̏d�v����i�����B���̈ꕔ�����B �S�l�I��ɂւ̓K�ȕ]���E�Ή��� ��ᇓ��Ȉ�́u���ē����v �X�s���`���A���j�[�Y�������x���� �S�l�I��ɂւ̓K�ȕ]���E�Ή��� �@��ʈ�ȑ�w���ۈ�ÃZ���^�[ ���_��ᇉȂ̑吼�G�������͂��҂Ƃ��̉Ƒ��̐S��f�鐸�_��ᇈ�̗��ꂩ��C�u�����ɂ͊e�N��C�����ɉ������S�l�I��ɂ�����C�����K�ɕ]���E�Ή����邱�ƂōK���Ȑ������ł���悤�ɂȂ�v�Əq�ׂ��B ���҂̐��_��w�I�L�a��50�� �@���҂ɂƂ��āu����v���Ӗ�������̂́u���v�ł���C���S������1�ʁC���ÁC�d���C�Ƒ��̖��Ȃǂ��܂��܂ȃX�g���X������Ă���B �@���Ò��̂��҂ɂ͂���ԁC�K����Q�C���a�Ȃǂ����������C���_��w�I�L�a���͖�5���ƍ����B�I�����̊ɘa�P�A�a���ł͂���ρC�K����Q�Ȃǂ������F�߂���B �@�吼�����́C����̂��߂ɋ�ɂ��������������3��ɂ��ďЉ���B �@29�̏������҂͕s�D���Ò��Ɏq�{�̂���������C�q�{�S�E�ƂȂ�B�u�q�����Y�߂Ȃ��ł͉��l���Ȃ��B�������Ȃ��Ă͂����Ȃ��v�C�u�q��������Ă���l�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�Ȃǂ̑i������C�S�I�O����X�g���X��Q�iPTSD�j�Ɛf�f�����B �@7�̎q��������36�̏������҂͍���r���̍�����Ŏ�p�C���w�Ö@���s�����C�Ĕ��B���҂͒S����̍��r�ؒf�̒�Ă�I�������C�Ď�p�ɓq����B�������C�����ɓ]�ځB�ċz����i�s���C�ɘa�P�A�a���ɓ��@�B�u�q�����c���Ď��˂܂���v�Ƒi���C�������܂��S�����B �@72��?�S�����҂͂��܂��܂Ȏ��Â������I�����ƂȂ�C�ɘa�P�A�a���ɓ��@�B?�̂��珬���Ȍ����J���C���ꂪ���X�Ɋg�債�C��cm�̌��ƂȂ����B���S���钼�O�܂ŁC�����̂悤��?�̌������Œ��߂Ă����B �@��L�̊��҂�ʂ��āC�����ɂ͊e�N��C�����ɉ������g�́C���_�S���C�Љ�C�����ʂƑ���ɂ킽���Y�C�S�l�I��ɂ����邱�Ƃ�������B�����K�ɕ]�����C�Ή�����K�v������B �@��Y�C��ɂ�K�ɕ]���E�Ή����邱�Ƃɂ���Č��C�ɂȂ�C�K���Ȑ������ł���悤�ɂȂ�����Ƃ���63�̓����҂��Љ�B���̊��҂͓������p�� �ɂ��a�ǂ��C���w�Ö@����C�͂��Ȃ��������C���a�̎��Â��Ĉӗ~�����P���C���w�Ö@���邱�Ƃ��ł����B���̌�C�����{��k�Ќ�ɋ�Y ������Ă��镟�����̐l�����ɊG�莆�ʼn������b�Z�[�W�𑗂�܂łɂȂ����B ��ᇓ��Ȉ�́u���ē����v �@�Ղ̖�a�@�i�����s�j�Տ���ᇉȂ̍��엘�������́u��ᇓ��Ȉ�͂��҂́w���ē����x�ŁC�Ö@���s�������łȂ��C�l���E�����������n�����Ƃ��d ���B���҂������Ă��邱�Ƃ��������グ�đ���u���C���܂��܂ȐE��ƃ`�[����g��ň�Â��s���Ă����K�v������v�Əq�ׂ��B �l���̖ڕW���l�������Õ��j������ �@��ᇓ��Ȉ�̎�Ȗ����́C�R�����C���q�W�I��Ȃǂɂ��ϋɓI���Âɂ��čŐV�̃G�r�f���X�Ɋ�Â������Õ��j�����҂Ƙb�������Ȃ��猈��C�{�s ���Ă������Ƃł���B�܂��C����Ǐ�̊ɘa�C����p�̃R���g���[���C�S�g��Ԃ̊Ǘ��C�����ǂ̎��ÁC���_�I�T�|�[�g�̑��C�Տ������E�Տ��������s���C�V�� ���G�r�f���X���m�����邱�Ƃ��d�v�Ȗ����ł���B�����āC����1���߂���������C�����ẪR�[�f�B�l�[�g�ł���B����́C���ɖ��������Ȋ��҂́u�� �ē����v�߂�ƂƂ��ɁC�`�[����Ấu���������v�Ƃ��āC�S�̂����n���Ȃ���C���҂ɂƂ��čœK�Ȏ��Õ��j������B �@���҂́C������߂���u�炢���Âɂ�����]������v�C�u���Â���߂����]�����Ȃ��v�Ƌꂵ�݁C����������C���[�W�̂��߂Ɂu���Â��邱�Ɓv�� �̂��ړI�����C�Ȃ�̂��߂���������Ȃ��u���Â̂��߂̎��Áv���s���Ă���B�܂��u���ÖڕW�v�������Ƃ��d�v�ł���C���ÖڕW�̂��߂ɂ́u�R������ �g��Ȃ��v���Ƃ��K�ȑI���ł���ꍇ�������B �@���҂͂悭���Â��l���̑S�Ăł��邩�̂悤�Ɏv������ł��܂��B���Â͎����ւ̌����������̈ꕔ�ł���C�����͐l���̈ꕔ�ł����Ȃ��B���ÖڕW�́u�l�� �̖ڕW�v�̒��ɂ���͂��ŁC���҂̐l���̖ڕW�C���������l�����C�l�Ԑ��C���l�ς��d�����Ď��Õ��j�����߂Ă����K�v������B �@���҂͂���Ɛf�f����Ă��玀�S����܂łɁC����̍������Â��Ă���l�iCancer Patient�j�ƁC����ȊO�̐l���܂ޑS�āiCancer Survivor�j�ɕ�������BCancer Patient����Cancer Survivor�Ɉڍs����ۂɓ��ɖ����Ă��܂����Ƃ������̂ŁC���Ì����������g�̓I�C�S���I�C�Љ�I�Ή�Survivorship Care���K�v�ł���B �@���{�l�����Ŝ늳������������́C������C�咰����C�݂���ȂǁC���S���������̂͑咰����C�x����C�݂���C�X����C�x����C������ł���B���{�̓� �����萢��ł́C�j����菗���ł������C���ɓ�����Ǝq�{�����B��ʎВc�@�lCSR�iCancer Survivors Recruiting�j�v���W�F�N�g�ɂ������҂̐����j�[�Y��������C�ł����������ƂƂ��āu���_�I�ɕs����ɂȂ�v�C�u���Â���Ɋ֘A�����p �������ށv�C�u����ɍs�������Ƃ��s���Ȃ��v�����o���ꂽ�B�܂��p�[�g�i�[�̂��Ȃ��҂͔Y�݂��[���C���҂̏A�J�͏d�v�ȉۑ�ł������B �X�s���`���A���j�[�Y�������x���� �@���H�����ەa�@�i�����s�j�ɘa�P�A�Ȃ̗я͕q�����́C�������҂̊ɘa�P�A�ɂ��āu�X�s���`���A���ȃj�[�Y�������C���҂��X�s���`���A���y�C����������O�Ɏx���邱�Ƃ��d�v�v�Əq�ׂ��B ���ꂵ���C���₩���C�Ί炪�厖 �@���ÂƊɘa�P�A�ŏd�v�Ȃ͎̂����ɂ���ė��҂̔䗦��ς���̂ł͂Ȃ��C���҂̕K�v�ɉ����Ăǂ�����ł���̐��𐮂��C���̂悤�Ȉӎ��������� ���҂��x���邱�ƁC�����ꊳ�҂����ƌ����������Ƃ��ɐS�̓��h�Ɋ��Y���Ă������Ƃł���B�ɘa�P�A�ł́C�g�̓I�C���_�I�C�Љ�I�C�X�s���`���A���Ȏ��_ �ŁC���a�C���y�C���ꂵ���E���₩���C�[�����ɂ��Ȃ��犳�҂��x���Ă����K�v������B �@�����̂���ł́C��������u�ɊǗ��ɂ����镛��p�C���ǐ�������Ȃǂł̟��o�t�∫�L�C�����p����Ȃǂւ̓��ʂȑΉ�����[�؏���_�o��Q���u�ɂȂǂ� �����u�ɂ��܂߂��T�o�C�o�[�ւ̒��ɕ⏕���_�ʂł̃T�|�[�g���K�v�ɂȂ�B�w�l�Ȏ�ᇂł́C���Փ���ᇂɂ�鉺���g�̕���C�N��������Q�Ȃǂւ̑Ή� ���K�v�ƂȂ�B �@�l�Ƃ��Đ����Ă������炱�����߂���̂Ɉ��E�����C����E�����C���Ȏ��������邪�C�����S�Ă���������Ȃ��Ă���]�����邱�ƂŃX�s���`���A���Ȗʂ� ���ǂ���Ԃʼn߂����Ă������Ƃ��ł���B�������C����ɂȂ�ƁC���Ԃ������C�W���⎩��������Q����C�l�Ƃ��Ă̗~������������Ȃ��Ȃ�C�X�s�� �`���A���y�C����������B���i����X�s���`���A���ȃj�[�Y����������悤�Ɋւ���Ă������Ɓi�X�s���`���A���R�~���j�P�[�V�����j�ŁC���҂��X�s���`�� �A���y�C����������O�Ɏx���邱�Ƃ��ł���B���̐l�炵���₻�̐l�̗����F�߂邱�ƁC�C���������Ĉꏏ�ɍl���邱�ƁC�����ȊO�̂��Ƃ��悭�������� �Ȃǂ��X�s���`���A���P�A�ƂȂ�B �@�܂��C���ꂵ���Ƃ������o����X�̐����Ŏ����Ƃ��d�v�ł���C�������L�̃P�A��1�Ƀ��C�N������B���C�N�����邱�ƂŏΊ�����߂����Ƃ��ł���B �@�@���͊��҂������܂��܂ȍ߂̈ӎ��ɑ��鋖����^�����邱�Ƃ�����B �@�ߔN�C���X�ɘV�l�z�[������{�݂Ŏ��S����l�������Ă���C�����d�v�Ȏ��_�ƂȂ��Ă���B �@��ɁC�炳�C�Y�݂��y�����邱�Ƃ������ӎ������������C�m���C�Z�p�C�o����ς݂Ȃ���C�ǂ���������ł��炦�邩�C�S��a�܂����邩�C�Ί�������Ă��炦�邩�Ƃ����v�����̋C�����Ŋ��҂Ɛڂ��邱�Ƃ��厖�ł���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N10��18�� |