�@
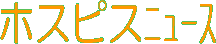 �@
�@�@�@�v�@�� �| �z�X�s�X�Ƃ�
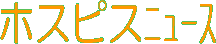 �@
�@| �@�z�|�� >��w�g�s�b�N�X>�z�X�s�X�j���|�X>�o�b�N�i���o�|�ƭ->�v���|�z�X�s�X�Ƃ� |
| �z�X�s�X��L���ɗ��p���Ȃ��č���t |
|---|
| �@�n�[�o�[�h��wBrigham and Women's�a�@�i�{�X�g���j��Gail Gazelle���m�́C�z�X�s�X�E�P�A�͑����̓_�ň�t�Ɗ��҂̑o�����������ꂽ�܂܂ł���Ƃ��錩����New
England Journal of Medicine�iNEJM 2007; 357: 321-324�j�ɔ��\�����B����͈�t�Ƀz�X�s�X�̗L���ȗ��p�@��������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B �z�X�s�X�E�P�A�̔����͊����� �@���̖��� 1 �́C�č���t�̑����́C�z�X�s�X�E�P�A�����ȊO�̊��҂ɍl�����Ȃ����Ƃł���B�č��ł́C�z�X�s�X�E�P�A�͊�����łȂ��A���c�n�C�}�[�a�C����^�C�v�̔x������S�����̊��҂ɂ��K�p�����B����ɁC���܂��܂Ȏ����ň����N������鐊��ł��z�X�s�X�E�P�A������B�Ⴆ�C�x���C�㕔�A�H�����ǁC�s���ǁC�i�s���̑̏d�����C������Q�C�i�s���Ő[�݂���ጐ���ᇂȂǂł���B �@�{�X�g���n��̃z�X�s�X�������̈�Ãf�B���N�^�[�����C���Ă���Gazelle���m�́u����ł��C�z�X�s�X���҂̔����߂��͖��������҂ł���B���̂ق��́C��40�����S�����̖������ҁC�F�m�ǖ������ҁC����ҁC�x�����C�]�������҂ł���v�Əq�ׂĂ���B �Z�����p���� �@���� 1 �̖��́C�č���t�̓z�X�s�X�E�P�A��]���������̊��҂ɍl�������C�]�������̊��҂����Ă͂܂�ƍl���Ă��邱�Ƃł���B�܂�C�����̊��҂͌��݂̊��K�I�Ȏ����������Ƒ����z�X�s�X�ɓ]�@�����ׂ��ł���B �@�z�X�s�X�ł� 6 �����Ԉȏ�̃P�A�����邪�C���҂̗��p���Ԃ̒����l��26���ԂŁC�č����̃z�X�s�X�ł͊��҂� 3 ���� 1 ���c��̐l���̍Ō�̏T�Ƀz�X�s�X�ɏЉ��C�]�@���Ă���B���̂��߁C2005�N�ɂ�120���l�ȏ�̊��҂��z�X�s�X�E�P�A�𗘗p�������̂́C���̑����͑Ó��Ȋ��Ԃ��Z�������B �@�z�X�s�X�ւ̓��@���x���Ȃ錴���ɂ́C�a�@�����s���̕a�̏I�������҂Ɏ����̂��߂̎��Â��s�����Ƃ���������B����ɁC�z�X�s�X�ɓ��銳�҂́C�h�����ۂ������҂łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�������������������� 1 �ł���BGazelle���m�́u�������C���@���x���ł��d��Ȍ����͈�t���g�̍l�����ł��낤�v�Ǝw�E���Ă���B �z�X�s�X�E�P�A�̔F���Ɍ�� �@�ł́C��t���g�̂ǂ̂悤�ȍl���������ƂȂ�̂��B�� 1 �ɁC�č���t�̑����́C���҂̎��͎��������̐f�Â̎��s�Ƃ݂Ȃ��Ă��邱�Ƃł���B�� 2 �ɁC�z�X�s�X�̂��Ƃ��o������C���҂̖]�݂��Ă��܂��Ƌ���邱�ƂŁC�����QOL�����コ�����萶�����Ԃ���������悤�ɓw�͂���̂��������ƈ�t���l���Ă��邽�߂ł���B�� 3 �ɂ́C�č���t�͖]�݂̂Ȃ���Ԃł��邱�Ƃ����҂ɓ`����ۂɎv�����̂���Ή������邽�߂̓K�ȌP�����Ă��Ȃ����Ƃł���B �@Gazelle���m�́C�� 4 �̓_���ł��d��Ƃ��C�u�z�X�s�X�E�P�A�͕s���̕a�̐i�s���ɒ��ʂ����Ƃ��ɁC�ł�����芳�҂����K�ɐ�������悤��������ړI�Ńf�U�C�����ꂽ�P�A�ł���̂ɁC�č��̈�t�̓z�X�s�X�E�P�A�͎����������Ƃ��̂��߂̍Ō�̎�i�ƍl���Ă��邱�Ƃ��v�Ǝw�E���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2007�N11��15�� |
| �I�������҂̉������Â̍����T���E���~�ɂǂ��Ή����邩 |
| �O�c ���� �i������w��w�@��È��S�Ǘ��w�y�����j �@�I������ÂɊւ�����I�w�j���Ȃ��Ȃ��ŁC��Ì��ꂪ�������Â̍����T���E���~�̖��ɓK�ɑΉ�����ɂ́C�ǂ̂悤�Ȓm�����K�v�Ȃ̂��B���Â̍����T���E���~�����e�����v���C���P���ׂ��葱���ɂ��āC��Ì��ꂪ���O�ɔc�����Ă������Ƃ��d�v���B �@�ł́C���Â̒��~�͈�ł��Ȃ��̂��ƌ����ƌ����Ă����ł͂Ȃ��B�����_�ł��C���Â̒��~�E�����T���͂Ȃ���Ă���B���Â̒��~�Ȃǂ����e����邽�߂ɂ́C(1)���Ò��~�����e�����(2)���P���ׂ��葱���\��2�_�ɂ��āC���̓��e�𐳊m�ɔc�����C�T�d�ɔ��f����ƂƂ��ɁC���̌��ʂ��L�^�Ɏc���Ă������Ƃ��d�v�ɂȂ�B �@���C��w�����C��苦���a�@�����A������̎����ɂ����Ă��C(1)���҂�������Ԃɂ��邩(2)���Ís�ׂ̒��~����]���銳�҂̈ӎv�����邩�����ƂȂ����B �@�I������Â̌���ł́C�Ƒ����瑁�����_�Ŏ��Â̒��~�����߂��邱�Ƃ�����B���҂̈ӎv���c���ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́C�ʏ�͉Ƒ��̂Ȃ��������҂�I�o���C����҂����ӂ�����Â����{����B�������C�������Â̒��~���ł��Ȃ��ꍇ�ł��C����҂����Â̒��~����]���邱�Ƃ�����B���̏ꍇ�C��Ë@�ւ͊��҂̍őP�̗��v�f���Ĉ�Â�i�߂邱�ƂɂȂ�B �@�`�[���ŏI������Â̐i�ߕ�����������ꍇ�C�e��Ï]���҂͐ϋɓI�ɔ������ׂ��ł���C�����łȂ���`�[����Â��������Ȃ��B�܂��C���Җ{�l�̈ӎv���s���ŁC�Ƒ������f�ł��Ȃ��ꍇ�C��Ã`�[����ϗ��ψ���Ŕ��f���ĉ������Â𒆎~�ł���Ƃ����B �@���{�~�}��w��́C��N10���ɋ~�}��Âɂ����ĉ������Â𒆎~����v����葱�����K�C�h���C���Ƃ��Ċw��x���ŏ��߂Ď������B�I�����ɂ��āC(1)�s�t�I�ȑS�]�@�\�s�S(2)�����ێ��ɕK�{�ȑ���̋@�\�s�S���s�t�I�ŁC�ڐA�Ȃǂ̑�֎�i���Ȃ�(3)�L���Ȏ��Ö@���Ȃ��C�����ȓ��Ɏ��S���\�������(4)�s�\�Ȏ��a�̖����ł��邱�Ƃ��C�ϋɓI�Ȏ��ÊJ�n��ɔ����\��4�ɕ����Ē�`�����B�����C�����V���Ђ��s�����A���P�[�g�̌��ʂł́C�~�}�~���Z���^�[�̑������w�j�̗̍p���������Ă���Ƃ����B �@�w�j�̓��e�����m�Ɉ�Ì���ɓ`����Ă��Ȃ��Ǝv���邽�߁C�w�j�̓��e�ɂ��Ċw��ɂ�����W�Ȃǂ�����C���m�ȗ����Ɋ�Â��������i�ނ̂ł͂Ȃ����Ǝv����B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N5��1�� |
| ��6����{�Տ���ᇊw��w�p�W����`�����Z�~�i�[�@Medical Oncologist���m���Ă��������ɘa�E�x���Ö@ |
| ���R �Y�l�i�����L���a�@ �ɘa�P�A�ȁj �@�]���C����̉��w�Ö@���s���ꍇ�͓��@���K�{�ł��������C�ߔN�C����p�̏��Ȃ��R����܂̊J���ɂ��C�O���ł̉��w�Ö@���\�ƂȂ����B���҂͎���ł̐����𑱂��Ȃ��玡�Â��s�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�CQOL�̌�������҂���Ă���B���̈���ŁC�O���Ŏ��Â�S�������t���u�ɊǗ��̌o�������Ȃ����߂ɁC���҂̒ɂ݂ɑ��ď\���Ȕz�����s���Ƃǂ��Ȃ����Ƃ�����B ����ɘa��Â͍R��ᇎ��Âƕ��s���čs���ׂ����́\��������̊ɘa�P�A�̓������\ �@����ɘa��ÁE�ɘa�P�A�Ɋւ��C�u�ɘa��Â͏I�����݂̂̈�Âł���v�Ƃ�������������҂݂̂Ȃ炸��Î҂̑��ɂ����܂��ɑ��݂���B���E�ی��@�ցiWHO�j�ɂ��C�ɘa�P�A�͏I���������ł͂Ȃ�������������R��ᇎ��Âƕ��s���ĊJ�n������̂Ƃ���Ă���B���ۂ̗Տ��ɂ����Ă��C��������̓K�Ȋɘa�P�A�ɂ���đމ@�≻�w�Ö@�̍ĊJ�Ɍ��т��ꍇ��C�t�ɍR��ᇎ��Â̌��ʂɂ���āC�Ⴆ�Β��ɖ�̌��ʂȂǁC�������ɂɑ��鎡�Â��y���ł���ꍇ������C���҂̓{�[�_���X�ȊW�ɂ���B �@�ɘa�P�A�ɂ����ĖÖ@�͏d�v�Ȉʒu���߂邱�Ƃ���C�w����Ö@����x�ɂƂ��Ă��C�ɂ݁C�ċz����C�����ǕǂȂǂɓK�ɑΏ����邱�Ƃ����߂���B �@�i�s�E�Ĕ����̂��҂ɍ�����������Ǖǂ́C�q�C�E�q�f�C�����c�����C���ɂȂǂ̏�����Ǐ���������C���҂�QOL�����ቺ������B���̂悤�ȏ����Ǖǂɑ��C�Ö@�Ƃ��Ă͏����Ǖ���}����p��L����R�R������i�L���u�`���X�R�|���~���Ȃǁj��X�e���C�h�C���f��p�̂���h�p�~����e�̝h�R��i�n���y���h�[���Ȃǁj���p�����Ă������C�ߔN�C�\�}�g�X�^�`���A�i���O���܂ł���I�N�g���I�`�h�̗L����������������C�{�M�ł�2004�N�Ɂu�i�s�E�Ĕ������҂̊ɘa��Âɂ���������Ǖǂɔ���������Ǐ�̉��P�v�ɂ��ĕی��K�������F���ꂽ�B �@�����Ǖǂ̎��Âɂ��āC�����ǕǂƐf�f���ꂽ�ꍇ�ɂ͑��������ɃI�N�g���I�`�h�ɂ��Ǐ�y����ϋɓI�Ɍ������C�����Ɏ�p�K���f����̂��]�܂����B �\���]�ڂ�L����ꍇ�ɂ́C�r�X�z�X�z�l�[�g����ː����Â��܂ޏW�w�I���Â��d�v�\ �@�����C�O���B���C�x���Ȃǂɂ����č��p�x�ɔF�߂��鍜�]�ڂ́C���������ɂ�a�I���܁C�Ґ������ɂ��_�o�Ǐ���Ƃ����B �@�ŋ߁C1�N�ȏ�̗\�オ���҂����Ǘ�ɑ��āC����QOL���ێ����\�Ȍ��肪��Ƌ������邽�߂̐헪���w���u�\�h�I����ɘa�P�A�iprotective cancer palliative care�j�v���d�v������Ă��Ă���B���̂悤�Ȋϓ_��������]�ڂɑ���W�w�I���Â̕K�v�������܂��Ă���B���]�ڂ�L���銳�҂ɑ��ẮCWHO���������u�Ɏ��Ö@�ɉ����C���ː����Â�r�X�z�X�z�l�[�g�̕��p�ȂǁC�ϋɓI�Ȏ��Â����߂��Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N5��22�� |
| ��49����{�_�o�w��@�؈ޏk�������d���ǁiALS�j���҂̎��Ì���v���Z�X�ɂ�����ϗ���T�� |
�`�I������ẪK�C�h���C���`�l�H�ċz��O���͊댯 �@��䉝�f�N���j�b�N�̐쓇�F��Y�@���́C�����J���Ȃ̏I������Â̌���v���Z�X�̂�����Ɋւ��錟����̈ψ��߂��o������C��N5���ɂ܂Ƃ߂��K�C�h���C���ɂ��āC�u���݂̖@���ł͎��ʌ����͔F�߂��Ȃ��v�Ȃǂ̏d�v���ڂ�����C��������̏I�������l���邤���ł̍���̉ۑ���������B �G�r�f���X�����c�_�� �@�쓇�@���́u�I������Â̌���v���Z�X�̂�����Ɋւ���K�C�h���C���v�ɂ��āu�����͂܂��n�܂�������Ō��_�ɂ͒B���Ă��Ȃ��v�Ƃ̔F���������������ŁC(1)���̂̌����ɂ͑��l��������̂ŁC�I���������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ�(2)�ɘa��Âł��ׂĂ̒ɂ݂͒��Â��܂߂Ċɘa�ł���̂ŁC�ϋɓI���y���͑ΏۂƂ��Ȃ�(3)�l�H�ċz����O�����Ƃ͕���s�ׂɓ�����댯�ł���(4)���ʌ����͌����Ƃ��ĔF�߂��Ȃ��\�Ȃǂ��d�v���ڂƂ��Ē����B �@���@���́C�e�d�v���ڂɂ��ċ�̓I�ȗ�������Ď��̂悤�ɉ�������B (1)�l�Ԃ̈ӎv�������ɏu�ԓI�ɕς�邩��Ꭶ�B�������܂Ԃ������z�����Ă��Ă��C�ڂ̑O���J���X������C��u�ɂ��ĕs�g�ȋC���ɕω�����B�܂��C�A����Ԃɂ���l�Ԃ����킢�������Ǝv���Ă��C�{�l�ɂƂ��Ă͐����Ă���Ƃ����u�d���v��100���s���Ă��鑶�݂ł���C�]����Ԃ̐l�ł��Ƒ��ɂ��Ă݂�C���݂��Ă��邾���ňӖ�������̂�������Ȃ��B�l�Ԃ͒��a�����S�̂̂Ȃ��Ő����Ă��鑶�݂Ȃ̂ŁC�I���������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B (2)���݂̓��{�ł͈�t�ɒm��������Β��Â��܂߁C���ׂĂ̒ɂ݂͊��S�Ɋɘa�ł��邱�Ƃ����҂ɓ`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���҂��₦����̓I��ɂ������Ƃ͂��肦�Ȃ��B (3)�l�H�ċz��͑��������Ƃ���C�S�g�Ɏ_�f�������������ȑ��݂ƂȂ�̂ŁC������O�����Ƃ͂��̑S�̂������s�ׂɓ�����B���������̂��O���Ƃ��������Z�����Z�I�l���������ׂ��ł͂Ȃ��B (4)���{�̖@���ɂ͐����錠���͂��邪���ʌ����͂Ȃ��B�������ʌ�����F�߂���C������]���Ă��Ȃ��l�ɑ��Ă����ʂ��Ƃ��������ꂽ��C��̓I�Ȏ��̕��@�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�Ȃǂ̊댯�������邽�߁C�T�d�ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���ׂĂ̎��Â��ɘa�P�A�Ɂ@QOL����̂��߂̃P�A���l���� �@(��)�����a�@�@�\�V���a�@�̒����F���@���́u�������Â������Ƃ����I���ł͂Ȃ��C���ׂĂ̎��Â͑S�l�I��ɂ̊ɘa�ł���Ƃ����ɘa�P�A�t���[���ɕς��Ă����K�v������v�Əq�ׁC����_�o�w��Ƃ��ėϗ��̖��ւ̋c�_��[�߂Ă����K�v����i�����B �����E�킪�`�[���� �@�������@���͂܂��C���Ö@���m�����Ă��Ȃ���a�́C�����ẨȊw���f���ł���EBM��N���e�B�J���p�X�݂̂Ă͂߂邱�Ƃ��s�\�ŁC��w�����f�Õ�V�̌n�̂Ȃ��ŏ\���Ɉ����Ă��Ȃ����Ƃ��w�E���C���҂��u�Ȃ���Ȃ��a�C�Ȃ琶���Ă����̂͂炢���C�Ӗ����Ȃ��v�ƍl�����Ƃ��C�{�l��Ƒ��C��Î҂��ǂ��Ή�������悢�̂��C���j�Ղ��Ȃ���Ԃł͈�Â𑱂����Ȃ��Ȃ�\��������Ɩ���N�����B �@���̂����ŁC�����@���́u���ʂȉ������Â��������鎀���v�Ƃ�����������߂���@�Ƃ��āC�ɘa�P�A���f���̗L�p�������������B�ɘa�P�A�T�O�̂Ȃ��ł́C�u���v����e����̂ł͂Ȃ��C���Ɏ���a�C�ƂƂ��ɐ����邱�Ƃ��m�肷��B���Â͐g�̓I��ɂ��Q�C�S���I��ɁC�Љ�I��ɂ���C��I��ɂ��܂߂��S�l�I�ȋ�ɂɑ���ɘa�Ö@�Ƃ��Ĉʒu�t����B�܂�C���Â̂�����߃C�R�[�����C���邢�͎��Â���^�[�~�i���P�A��180�x��ւ��ĉ������Â��s��Ȃ��Ƃ����l�����ł͂Ȃ��C�f�f���_����ɘa�P�A���n�܂�Ƃ����l�����ł���B���̃��f���ɏ]���C�K�v�Ȏ��Â�P�A�͖��ʂȉ������Âł͂Ȃ��Ȃ�C�s���������C��ɂ���������C���Ɏ���a�C���a�ƂƂ��ɐ����邱�Ƃ��m��ł���悤�ɂȂ�B �@���莾�����҂̐����̎��̌���Ɋւ��錤���ǂ�2007�N�x�ɂ܂Ƃ߂��uALS�̕�I�ċz�P�A�w�j�v�ł́C�ɘa�P�A�t���[���ւ̕ύX�m�Ɏ����Ă���B����ɂ��ƁCALS�̌ċz��P�A�͌ċz�푕�����������Âƍl����̂ł͂Ȃ��C�ɘa�Ö@�ƈʒu�t���C�ċz���w�Ö@�C�ېH�����T�|�[�g�C���w�Ö@�C��ƗÖ@�ɂ����퐶������iADL�j�̒����C�ɂ݂̃R���g���[���C�X�s�[�`�Z���s�[�ɂ��R�~���j�P�[�V�����T�|�[�g�C�S���Ö@�C�P�[�X���[�N�ȂǑ����E��P�A�Ƃ��ă`�[���ōs���Ă������j��������Ă���B �@���̂����ŁC�����@���́u�����ɍ������ɘa�P�A�Ɋւ��鎩�Ȍ���̓P�A�`�[���Ƃ̌𗬂̂Ȃ��ōs���C�a�Ԃ̕ω��C�P�A���e�C���Ԃ̕ω��ɂ���ē��e�͏�ɕω����Ă������́v�Ƃ����CQOL����̂��߂̐V�����C���t�H�[���h�E�R���Z���g�̍l������B�u��Â̂Ȃ��̖���ϗ����ɑւ���̂ł͂Ȃ��C�P�A��[�߂�c�_�����ׂ��v�Əq�ׁC�{���̊ɘa�P�A�T�O�𐳂������y���邱�ƂɐϋɓI�Ɏ��g��ł����p�����������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N8��7�� |
| �����\��s�ǂȐV�����́u�Ŏ��̈�Áv�@�u�����������ވ�Áv�ւ̔��z�]���� |
�D�� ���v �@����L���X�g���a�@�����ȕ��� �@�ŋ߁C�����\��s�ǂȐV�����̎��Õ��j�������āC�V������ÂɌg���a�@��8���ȏオ���Â̍����T���⒆�~���o�����Ă���Ƃ̒������ʂ�����Ă���C�킪���ł��u�ߏ�ȉ������Áv���������������L�������B����L���X�g���a�@�ł͐����\��s�ǂȏ�ԂɊׂ������̎��Îw�j�Ƃ��āC1998�N10���Ɂu�V�����̗ϗ��I�C��w�I�ӎv����̃K�C�h���C���v���쐬�����B���K�C�h���C���́C���ꂼ��̏Ǘ�ɑ����Ã`�[���̎��Õ��j�ƁC�Ƒ��Ƃ̘b�������̒��N�̒~�ς��琶�܂�C���@�ϗ��ψ���̏��F�č쐬���ꂽ�B �u��肷���̈�Áv�͔�ϗ��I �@1986�N�̒����V���Łu�����̂܂ܐV����2�N���v�Ƃ����L�����f�ڂ��ꂽ�B���̎��́C���@�ŏd�lj�����Ԃŏo����C�V�����W�����Î��iNICU�j�ł̎��Â̂��߂ɓ������������a�@�ɔ������ꂽ�B�������C���Â̂����Ȃ��ӎ����ċz���s�\�ȏ�Ԃ��������܂ܐl�H�ċz���2�N����������Ă���C����̎��̎��Â�����C���e�u���炩�ɐ������āv�E�a�@�u�O���ʐl�H�ċz��v�̊ԂŐ[���ȑΗ����������B���̎����́C����L���X�g���a�@�ɂ����Đ����\��s�ǂȐV�����̗ϗ��I�����l���钼�ڂ̌_�@�ƂȂ����B �@�D�˕����́u�ߔN�̈�ËZ�p�̋}���Ȕ��W�́C�]���~���s�\�ł������d�NJ��҂ɑ��Ă���w�I�ɉ�����C���Ɋ����ł���悤�ɂȂ����B����C�����\��s�ǂʼns�\�Ȗ������҂ɑ��Ă��@�B�I�ȉ������\�Ȏ���ɂȂ��Ă����B����1950�N�ォ��60�N��ɂ����ċ}���ɔ��W�����l�H�ċz����\�Ƃ��鐶���ێ����u�̊J���́C���������`�Ɋ�Â��������Âɑ傫�ȍv���������B�������C���̎����́C�����Ɋ��҂́w���Ǝ��x�����܂ł̂悤�Ɏ��R�Ȍ`�Ōo�߂�����̂ł͂Ȃ��C���B����������ËZ�p�ɂ���đ���ł���l�H�I�ȉߒ��ɕς���Ă��܂������Ƃ��Ӗ�����v�Ǝw�E����B����́C�V������Â̕������O�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B �ϗ��I���e�͈͂����� �@�D�˕�����́u���l�Ԃ炵����ÂƂ́H�v�Ƃ����ϓ_����C���@�̏�����ÂɌg���E��63�l�ɃA���P�[�g���s�����B���̌��ʂ����ƂɁC���̕a�@�ł͂ǂ̂悤�ȍl������m�邽�߁C���̐V�����f�Ñ��݉����V�X�e���iNMCS�j�ɑ�����30�{�݂̐E��427�l�ɃA���P�[�g���s�����B���̌��ʁC�u���������̎q���ł������Ȃ�ǂ����܂����v�Ƃ�����ɑ��ẮC���Â̒��~��167�l�ƍł������C�����ł킩��Ȃ���119�l�C�ɘa�I���Â�108�l�C�ϋɓI���Â�59�l�̏��ł������B �@�������q��ȑ�w��q������ÃZ���^�[�̐m�u�c���i������́C��w�I�ӎv����ɂ������̓I�Ȏ��Ís�ׂ̕��ނ��s�����BClass A�͂����鎡�Â�ϋɓI�ɍs���CClass B�͎�p�C���t���͂ȂǑ傫�ȕ��S�̂���������x�ȏ�̎��Â𐧌�����CClass C�͌��ݍs���Ă���ȏ�̎��Â͍s�킸�C��ʓI�{��ɓO����C�h���p�͎��s���Ȃ��CClass D�͐l�H�ċz����܂߂�����܂ł̂��ׂĂ̎��Â𒆎~����Ƃ������ނł���B�D�˕������Class A��ϋɓI��ÁCClass B�𐧌��I��ÁCClass C���ɘa�I��ÁCClass D���Ŏ��̈�ƒ�`���CNICU�ɂ������̓I�ȗϗ��I�C��w�I�ӎv����ɉ��p���Ă���B �ӎv�����̑Ή��ɔz���C�Ƒ����S�̊ɘa�P�A����� �@���K�C�h���C��������̕ω��ɂ��āC�D�˕����́u�Ŏ��̈�Â���������Ƃ����āC�K���������S���͑����Ă��炸�C�ނ��댸�����Ă���B�����ɍŊ��̂Ƃ��C���̍őP�̗��v����Ã`�[���ƉƑ��������ɘb�������悤�ɂȂ���Class A�i�ϋɓI��Áj�̓K���͏��X�Ɍ������CClass C�i�ɘa�I��Áj�܂���Class D�i�Ŏ��̈�Áj�������Ă����B�����ėϗ��I���e�͈͂̃K�C�h���C���쐬�i1998�N�j�Ȍ�́C�قƂ�ǂ�Class C�܂���D�ŖS���Ȃ��Ă���v�Ƃ��C�����Ɂu�Ō�͉Ƒ��C���ɕ�e�̋��Ŏ�������������闦���N�X�����Ă���B�ߏ�Ǝv����h����Â͍����T�����C�ق�100����e�̋��ŊŎ���Ă���v�ƕt��������B �@�ł́C����Class C��D��K�������ꍇ�C���̌�̑Ή����ǂ����邩�B�����ւ̔z���Ƃ��ẮC�ō��̊ɘa�P�A�C�ɂ݁C�s���CQOL�ȂǁC�Ƒ��ւ̔z���Ƃ��ẮC���̎�e�ɑ��鏀������C�ʉ�Ԃ���C�����X�L���V�b�v��P�A�ւ̎Q���Ȃǂ�������B�܂��C�Ŏ��ւ̔z���Ƃ��ẮC�ł���ΉƑ��S���̗�����C�Ō�͉Ƒ��C���ɕ�e�̋��̂Ȃ��ł̊Ŏ��C�Ƒ��̊�]�ɂ��M���ł���@���ƂȂǂ̗�����������C�u�����I�ɂ͉ƒ�ł̊Ŏ��Ƃ������Ƃ��ۑ�ƂȂ�v�Ɠ������B����ւ̔z���Ƃ��ẮC�\���Ȕ߂��݂̕\�o�C���㏈�u�ւ̎Q���C�L�O�B�e��`���̕i�C���ʂ��Ȃǂ�������B �َ��ɘa�P�A�̌������K�v�� �@����C�ŋ߁C�َ��f�f���傫���N���[�Y�A�b�v����Ă���B2004�N�ɕč���Leuthner SR�́C�َ��f�f��̐V�����I�����Ƃ��āC�u�َ��ɘa�P�A�v�̊T�O���Љ�Ă���B �@�D�˕����́u����َ��f�f������I�ɐi�����邱�Ƃ��\�z�����B�����Ȃ�ƁC�َ����Ẩ\����T������Ɠ����ɁCFetus as a patient�CFetus as a human�Ƃ��āC���̐l���Ƒ������ɂ���َ��ɘa�P�A�̑I�����̌������V���ȃe�[�}�ƂȂ��Ă��邾�낤�v�ƓW�]����B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N8��28�� |
| �I�[�X�g�����A�A�q�ǂ��z�X�s�X��K�˂� |
| �@�u�����w�v����Ƃ���A���t�H���X�E�f�[�P����q�喼�_�������X����{�A��ÊW�҂�̌��C�Ƃ��ăI�[�X�g�����A�̃z�X�s�X��K��A���{�ɂ͂Ȃ��q�ǂ����̃z�X�s�X�Q�{�݂����@�����B���s��ނ���A�q�ǂ��̏I������Âɂ��ăI�[�X�g�����A�̌�������B �@�q�ǂ��z�X�s�X�͉p�����N���ŁA�W�Q�N�ɃI�b�N�X�t�H�[�h�Ɂu�w�����E�_�O���X�E�n�E�X�v���ł����̂��n�܂�B�p���ɂ͂T�O�{�݈ȏ゠��Ƃ���A�I�[�X�g�����A�ɂ͂R�{�݂���B���@�����̂́A�ő�̓s�s�V�h�j�[�ɂ���u�x�A�E�R�e�[�W�v�ƁA�����{�����ɂ��鍑���ŌẤu�x���[�E�X�y�V�����E�L�b�Y�v�B �@�q�ǂ��z�X�s�X�̑Ώۂ́A����Ɍ��炸�A�������߂Ȃ����܂��܂ȕa�C�̎q�ǂ������B�t������ʼn�삷��Ƒ����x����B�Ŋ����}�����Ƃ��ė��p����P�[�X�͂ނ��돭�Ȃ��A���@��𗣂�Ēn��ɋA��A�ƒ�ōŊ����}���邽�߂̎菕��������̂���Ȗ������B�{�݂̖��̂�ŔɁu�z�X�s�X�v�̕����͂Ȃ��A�Â���ꂵ����A�z�����錾�t�͎g��Ȃ��B �@����1�A�V�h�j�[�k���̊C������ɋ߂��u�̏�ɂ���u�x�A�E�R�e�[�W�v�́A�V�h�j�[�̖��Ԏq�ǂ��a�@���O�P�N�ɊJ�݂����B�{�ݖ��ɂ́u�L�����v��̃R�e�[�W�̂悤�Ȋ��o�Ŋy����łق����v�Ƃ̊肢�����߂��A������ł͈����邵���召�̃N�}�̂ʂ�����݂��o�}����B�{�݂ŕ�炷���u�X�N�[�^�[�v���X�^�b�t�̈���Ƃ����B �@���シ������P�W�܂ł̎q�ǂ����؍݂��A���N�W���܂łɂR�S�V�l�����ꂽ�B�_�o�̓�a��_�o�؎������S�̂̂S�����ŁA���������]���܂ЂȂǂ̐�V����Q�������B�����ōŊ����}�����q�ǂ��͈ꕔ�ŁA�Ƒ��ŒZ���h������u���X�p�C�g�v��A�q�ǂ��Ǝ��ʂ����Ƒ����Ώۂ́u�ߒQ�P�A�v������B �@�I�����̑؍݊��Ԃɐ����͂Ȃ����A���X�p�C�g�ȂǂɎg���ꍇ�͍Œ��W���ԁB��삷��e�̐��_�I�E���̓I���S�̌y���ƁA�Ƒ��ʼn߂�������ꂽ���Ԃ��ɂ��邽�߁A�Ǝ��͂��ׂĐE����{�����e�B�A����s���A�Q�S���Ԏ蓖�Ă�_�P�A������B�q�ǂ��ɑ��ẮA�V�т�ʂ��ĕa�C���Q����C��������������悤���g�ށB�����a�C�����q�ǂ����W�߁A�{�����e�B�A���L�����v�ɘA��Ă������Ƃ�����B �@��Q�̉ƒ�Ƃ��ė��p���Ă��炤�̂����O�ŁA�h������H����Ȃǔ�p�͂��ׂĖ����B���ݔ��P�O���~�ƔN�Ԗ�P���V�O�O�O���~�̉^�c�����̂قƂ�ǂ͒n��Z����̊�t�Řd���A�s�����͎q�ǂ��a�@����Ă�B �@�{�݂ɂ́A�q�ǂ��̌��P�O�����ƁA�Ƒ����Q���܂�ł���Q����������B�����ł͈�Ís�ׂ͂����A���u�����g���B���p�X�y�[�X�ɂ̓e���r��c�u�c���y���ގ����o���A��������̑q�ɂ̂ق��A�������z���鏬�^�v�[���̂���u�X�p���[���v������B �@�X�p���[���ɂ͐��̂����炬�������A�u�n�C�h���Z���s�[�v�ƌĂ����₵�ɗ��p�����B�O�o������Ԃ����̎q�ǂ��ɂ́A�C���]���̌��ʂ�����Ƃ����B �@�ʓ��́u�N���C�G�b�g�E���[���v�ɂ̓v���C�o�V�[��ۂ��ߖh���ݔ�������A�e���v����{���߂��݂��Ԃ��A�吺�ŋ������Ƃ��ł���B�q�ǂ����e�Ɨ���ĂP�l�ŗV�Ԏ��ԂɎg�����Ƃ��ł���B�u�ߒQ�P�A�v�ɂ��K�v�Ƃ����B �@�V�h�j�[�x�O�ɏZ�ރw�����E�J�j���O�n������͂T�N�O����A�Q������̖��i�^���[����i�W�j�ƔN�S��قǗ��p���Ă���B�u�H�����������邱�Ƃ��炨�ނ����܂ŁA�f���炵�������Ă���B�o���R�j�[�Ŗ��߂鎞�Ԃ����Ă邱�ƂŐS�����炮�B�����q�ǂ����݂Ƃ�Ȃ�a�@�ł͂Ȃ��A�����������B���炩�ȋC�����ɂȂ��ł��傤�v�Ƙb�����B m3.com 2008�N10��20�� |
| ����O�Ƀ��r���O�E�E�C�������A�u�^���v�U��������@�]�����N�u�����v�P�� |
| �@�������������Ƃ��̎��Õ��j�����O�ɏ��ʂɎ����u���r���O�E�E�C���v�Ɏ^������l���U�����邱�Ƃ������J���Ȃ̃A���P�[�g�����ŕ��������B�������]�����N�ȓ��̖�����ԂɂȂ����Ƃ��A�������Â�]�ނ̂͂P�O�l�ɂP�l�������B �@�����͍��N�R���A��ʍ����T�O�O�O�l�ƈ�t���Ï]���҂X�O�O�O�l��ΏۂɎ��{�B�I������Â̂�������l���邽�߂ɂT�N���Ƃɍs���A����͂R��ڂŁA�S�̂̂S�U���������B �@����ɂ��ƁA���r���O�E�E�C���Ɂu�^������v�Ɖ�����ʂ͂U�P�E�X���ŁA�ߋ��̐��l�������������ŏ��̂X�W�N�ɔ�ׂP�S�E�R�|�C���g�������B��t�͂V�X�E�X�����^�������B���̂����A�u�@�������ׂ����v�Ɠ�������ʂ͂R�R�E�U���ɂƂǂ܂�A�u��t���Ƒ��Ƒ��k���A���̊�]�d����v�Ƃ̍l���͂U�Q�E�S���ɒB�����B�������A��t�ł͖@���������߂��̂��T�S�E�P���Ɖߔ����ɒB���Ă���B �@����A���������錩���݂��Ȃ��ƍ�����ꂽ�ꍇ�A�������Â�]�ނ͈̂�ʂ��P�P���A��t�͂V���B�Ƒ��̏ꍇ�ł́A��ʂłQ�S�E�U���A��t�łP�P�E�U���ƂȂ�A�����̂Q�{���x�ɑ������B m3.com 2008�N11��13�� |
| �u���y���v�̏u�Ԃ�����ց@�p�e���r�A���E�����Ɣᔻ |
| �@�p�e���r�ǂ��A���͂Ōċz���ł��Ȃ��Ȃ錴���s���̕a�������A2006�N�Ɂu���y���v�����p���l�j���̎��S�̏u�Ԃ����߂ĕ�������\�肾�Ɣ��\�A���E���������Ƃ̔ᔻ���Ă���B �@�X�J�C�j���[�Y�E�e���r��12��10���ߌ�9���i���{����11���ߑO6���j�����������B���y���͉p���ł͈�@�Ƃ���Ă���A�X�J�C���͔����y���̊����Ƃ�̔ᔻ�ɑ��u�j����������]�v�Ɣ��_���Ă���B �@�ԑg�͋c��ł����グ���A�u���E���p�́u�����Ȗ��ŕ����̋K�����ǂ����f����v�Ɠ��ق����B �@���̒j���������i�T�X�j����5�J���̓��a�̖��A���̏������ň��y����F�߂Ă���X�C�X�̕a�@�ŁA�Ȃ�����钆�A�^�C�}�[���g���Đl�H�ċz����~�߁u���E�v�����B m3.com 2008�N12��11�� |
| �e���r�Ɏ^�ۂ̈ӌ��������@�p���́u���y���v���� |
| �@�p�X�J�C�j���[�Y�E�e���r��12��10���A2006�N�Ɂu���y���v�����p���l�j���̎��S�̏u�Ԃ�\��ʂ���������B�����҂̊S�͍����A�^�ۂ��܂��܂Ȉӌ�����ꂽ�B �@�m��h����́u���N���ꂵ��ŖS���Ȃ����v���v���o�����B�ɂ���Ă͎��疽�����������ׂ����v�Ƃ̈ӌ�����ꂽ���A�u���y�����B�e���邱�Ƃɂ͓��ӂł��Ȃ��B�p��m��v�Ȃǂ̔ᔻ�I�Ȑ����オ�����B �@�p���ł͍ŋ߁A�������������O�r�[�I�肪���y�����邱�Ƃ�I�сA�������`�������e���@�I�ӔC�����Ȃ����ʂ��ƂȂ������Ƃŋc�_���ĂB���̒���Ƃ����āA���y���ɔ�����c�̂��u���������҂������Ȏ��݂��v�Ɣ��������߂Ă���B�e���r�Ǒ��́u�l�X���S�����߂Ă���e�[�}�ɂ��ċc�_���h������̂͏d�v���v�Ȃǂƕٖ������B m3.com 2008�N12��11�� |
| �������̖@������i����@���J�ȁE�I������Í��k��ŊW�c�̂��q�A�����O |
| �@12��15���C�����J���ȁi���J�ȁj�̑�2��I������Â̂�����Ɋւ��鍧�k��J����,���{����������Ȃ�5�c�̂���q�A�����O���s��ꂽ�B����������̈�`���O���́C�������̖@���������炽�߂đi�����B �@�����k��̖ړI�́C���҂̈ӎv�d�����]�܂����I������Â̂�������������邱�ƂŁC2��ڂ̍���͏I������ÂɊW�̐[��5�̈�ÁE���Ғc�̂̑�\�҂��Q�l�l�Ƃ��ď��v����C�ӌ����q�ׂ��B �@���{�����������1976�N�̔����ȗ��C���r���O�E�E�C���i�������̐鐾���j����Ď����̎��l�Ɋ֗^�ł��錠���C���R�Ɏ����}�����錠�����咣���Ă����B��`���͂��̂悤�Ȋ�����ʂ��āC�������͍����̊Ԃɏ�������������邱�Ƃ��w�E�B���J�Ȃ�2007�N�Ɍ��\�����u�I������Â̌���v���Z�X�Ɋւ���K�C�h���C���v�ł��C�{�l�̈ӎv���ő�����d���邱�Ƃ����荞�܂�Ă���B �@�������C�����ɂ��ƁC�K�C�h���C���ǂ���ɏI������Â����{����C�����[�u�̕s�J�n�⒆�~���I�����ꂽ��C����ł͈�t�̖@�I�ӔC�������\��������C�������̕��y��j��ł���B���̂悤�ȏɑ��āC�����́u�{�l�̈ӎv�ɔ����ĉ����[�u����������̂́C��O�҂̉��l�ς̋����Ől�����Ƃ��Ă��������ׂ��ł͂Ȃ��v�Ǝ咣�B��������@�������C���炩�Ȏ��̌����������Љ�̏d�v�������������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N12��16�� |
| ���ҁu����̐��E�v�u���܂�ς��v�M���銄���Ⴍ�@���傪�����ϒ��� |
| �@���҂͈�ʂ̐l�ɔ�ׂāA����̐��E��܂�ς��Ȃǂ�M���Ȃ��X�����������Ƃ��A������̑�K�͒����Ŗ��炩�ɂȂ����B�܂��u�]�܂������v���}���邽�߂ɕK�v�Ȃ��ƂƂ��āA���҂����N���ƕς��Ȃ�������]�̂ɑ��A��t��Ō�t����������҂��銄���͒Ⴍ�A�F���̍�����������ɂȂ����B �@�����́A���҂̎����ς�m�邽�ߓ�����̌����`�[������N�P������P�N�Ԃ����Ď��{�B����a�@���ː��ȂɎ�f�������銳�҂R�P�O�l�Ɠ��a�@�̈�t�P�O�X�l�A�Ō�t�R�U�U�l�A����ג��o������ʂ̓����s���R�T�R�l�̌v�P�P�R�W�l�����͂����B���҂͂V�T�������Íς݂ŁA���Ò��̐l�͂Q�O���������B �@�u����̐��E������v�ƍl����l�̊����͈�ʐl�̂R�S�E�U���ɑ����҂͂Q�V�E�X���A�u���܂�ς�肪����v�͈�ʐl�Q�X�E�V���A���҂Q�O�E�X���ŁA���҂̊������ڗ����ĒႩ�����B������ړI��g�������������͊��҂̕�����ʐl��荂���A�u�����̎����悭�l����v�Ƃ����l�����҂ɑ��������B �@�u�]�܂������v�Ɋւ��ẮA���҂̑��������N�Ȏ��Ɠ��l�̐����𗝑z�Ƃ��A�u�i���ʂ܂Łj�g�̉��̂��Ƃ������łł���v�i�X�R���j�u�ӎ����͂����肵�Ă���v�i�X�W���j--�Ȃǂ�]�B����A��ÊW�҂͂����ɂ��Ă̊��҂����ꂼ��R�O-�S�O�|�C���g�Ⴉ�����B�܂��A�u�������܂ŕa�C�Ƃ����������Ɓv��]�ފ��҂��W���ɒB�������A��t�͂Q���ɂƂǂ܂����B m3.com 2009�N1��14�� |
| �A����Ԃ̃C�^���A�l�������S�@������~��A�����ɏՌ� |
| �@17�N�O�̌�ʎ��̂ŐA����ԂƂȂ�A�Ƒ��̗v����2���A�����[�u���~���ꂽ�C�^���A�l�����A�G���A�i�E�G���O��������i�R�W�j��9���A�k�����E�f�B�l�ɂ�����@��̕a�@�Ŏ��S�����B������~���߂����ẮA���[�}�@�����i�o�`�J���j������铯���̐��_��2�����Ă��������ɍ����͏Ռ����Ă���B �@���@��̕a�@�͊��ɉh�{�⋋�ǂ���̉h�{�Ɛ����̕⋋���~�߂Ă����B���ڂ̎����͕s�������A������~���u���e�������Ƃ݂���B �@������~�����߂�Ƒ��̑i���͍�N�A�ō��قŔF�߂�ꂽ�B�����E�h�x�����X�R�[�j�����́A������̈��y���Ƃ��Ĕ�������o�`�J���Ȃǂ̈ӌ��ɔz�����A������~��j�~���邽�߂ً̋}���߂��t�c���肵���B �@�������A���h�o�g�̃i�|���^�[�m�哝�̂͐��߂ɏ������������ɂȂ������߁A�������͂��炽�߂ĉ�����~�j�~�̖@�Ă�����ɒ�o�A�R�c���n�܂��Ă����B �@�G���O��������̎���9���A�R�c���̏�@�Ŕ��\����A�c���炪�قƂ������B m3.com 2009�N2��10�� |
| �������C�ӎv����ɉe��������t������@�����͉\���@���r���O�E�E�B��������c�_ |
| �@4��14���C�����J���Ȃő�4��u�I������Â̂�����Ɋւ��鍧�k��v���J�Â��ꂽ�B �@�������ɂ́C����̈�Ï]���҂ɂƂ��ČY�����̃��X�N������ȏ�C�K�C�h���C���ƂƂ��ɖ@�����͕K�v�Ƃ��������������ŁC�@�����̕���p�Ƃ��āC���҂̈ӎv�����g�@�h�Ɋ�Â������_�ňӎv���肪���E�����뜜������B �@�܂��C�������̈ӎv����ōł��d�v�Ȃ̂́C���Җ{�l�̈ӎv�����C�c�_�̂Ȃ��ł͂��̈ӎv�m�F�̓���������ꂽ�B �@�I������Âɂ����鑸�����ɂ��Ă̋c�_�ł́C���݁C��t�C�@�w�҂����̃R���Z���T�X�Ɏ����Ă��Ȃ����B �@����C��Ì���ł́C���ҁE�Ƒ����瑸������]�ވӎv�����ۂɎ�����Ă���B �@���J�Ȃ�2007�N�Ɍ��\�����u�I������Â̌���v���Z�X�Ɋւ���K�C�h���C���v�ł́C�����������Җ{�l�̈ӎv���ő���ɑ��d���邱�Ƃ����Ƃ��Ă���C�{�l�C�Ƒ��C��ÃP�A�`�[���ȂǁC�O�ꂵ�����ӎ�`�̏d�v���������Ă���B �@�������C���ۂ̈�Ì���ł́C���r���O�E�E�B���⊳�҉Ƒ��Ƃ̘b�������ɂ�葸�����̈ӎv��������Ă��C���ۂɂǂ̂悤�ȍs�ׂ��Y�@�ɒ�G����̂����s���Ȃ��ƂŁC�j�[�Y�ɉ����邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ��w�E����Ă���B �@�����������Ƃ���C��Ï]���҂���́C�K�C�h���C���ɕ����C�������ɂ�������Ï]���҂���邽�߂̖@���������߂鐺���オ���Ă���B �č��̈ӊO�Ȏ����@�@�����͂Ȃ���Ă������ŁC�@����×ϗ��d �@���������Ȃ��C�u�����̑����̓��r���O�E�E�B���ɂ͎^���Ȃ̂ɁC�Ȃ����̖@�����ɂ͏��ɓI���H�v�Ƃ����^����悳��Ă���C������w��w�@�@�w�����w�����ȋ����̔���͗Y���́u�s���m�Ȗ@�̓`���閾�m�ȃ��b�Z�[�W�v�Ƒ肵�����\���s�����B �@�����́C�č��̖@����Ƃ��Ă���C���r���O�E�E�B���̖@�������s���Ă���č��ɂ�����C�������ɂ������@���߂̎���ɂ��ďЉ���B �@�܂��C�č��̃��[�X�N�[���̋��ނł���casebook�̂Ȃ�����C37�̔x�������҂���u���w�Ö@�ƃy�[�X���[�J���~�߂Ă���v�Ƃ����ӎv�������ꂽ��t����̑��k�ɂ��ďЉ�Bcasebook�ł́C�u�i�@���́j�ϗ��ψ���ő��k���Ȃ����v�Ə��������Ă���C���ꂪ�@���ƂƂ��Ă̍őP�̓����Ƃ��Ď�����Ă���C�u�����E�l�Ƃ����ނ̋L�q�ɂȂ����Ă��Ȃ��v�Ƃ����B �@�܂��C���l�ɕč��̈�t���Ǝ������̂Ȃ����玟�̂悤�Ȗ�����������B �@���̂ɑ������j�����C�l�H�ċz�������ďW�����Î��iICU�j�ɉ^�э��܂�C�]����ԂƔ��f���ꂽ�B�j���̓h�i�[�J�[�h���������Ă���C����̈ӎv�\������������Ă����B�������C����ڐA�`�[�����Ƒ��ɘA����������Ƃ���C����ɔ����ꂽ�B�ǂ����ׂ����H �@����ɑ��鐳���́u�Ƒ��̈ӎv�d���������߂�ׂ��ł���v�Ƃ������̂ŁC������́u�č��ł͖@����C�]�������Ƃ��Ă���C����͖{�l�i�����j�̈ӎv�ɂ��Ɩ��L����Ă��邪�C�i�č��ł́j�@�������ň�Â͓����Ă��Ȃ����Ƃ�������Ă���v�Ƃ����B �@�܂��C�č��ł́C�@�ƈ�Ái�ϗ��j�̖����͈قȂ�C��҂����d�v���ƍl�����Ă���Ƃ��C���r���O�E�E�B���@�̓K�p���Ȃ��Ă��C�i1�j���Җ{�l�̈ӎv�d�C�i2�j���a�⎩�E��]�̏ꍇ�͕ʁC�i3�j��肪����Ηϗ��ψ���ł����k?�Ƃ������_�ɏ]���Ĉ�Â̕��j�����܂�C�@�ɗ���ԓx�͎���Ă��Ȃ��Əq�ׂ��B �@����ɁC�č��ł́C���r���O�E�E�B��������l�͏����ŁC�����Ă���l�ł��K�p���O��������̂����Ԃ��Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N4��16�� |
| �I������Â��l����c�u�ǂ�������v��t�Ƙb�����@��Ã��l�T���X�@���t�H�[���� |
| �@�ǂ�����āA�����炵���Ŋ����}���邩�B�[���ł��闝�z�I�ȍŊ��Ƃ́\�\�B�u�I������Â��l����v���e�[�}�Ƃ����u��Ã��l�T���X���t�H�[�����v���T���Q�P���A���s�t��̓d�̓z�[���ŊJ���ꂽ�B�I������Â�ݑ�P�A�ɏڂ����R�l�̐��Ƃ��A����̎��g�݂�ӌ����Љ�Ȃ��甒�M�����c�_�����킵�A�W�܂����U�O�O�l�]��̎s���́A�^���Ȗʎ����ŕ����������B ���@�p�l���f�B�X�J�b�V�����@�� �p�l���X�g �@���É��w�|��w���A��`���O���� �@��䉝�f�N���j�b�N�@���@�쓇�F��Y���� �@��g�̋��N���j�b�N�E�[�l�����}�l�W���[�i�{�錧���s�j�@��Ώt������ �R�[�f�B�l�[�^�[ �@�O���Y�E�ǔ��V�������{�ЕҏW�ψ� ����Â̖��� �@�\�\���҂����̊ԍۂɖ���������Η��z�I�ł����A��Â͂ǂ�Ȗ������ʂ�����̂ł��傤���B �@��`�@�ɂ݂��������Ă��A����ǂ��Ȃ�̂��Ȃǂ̐��_�I�ȔY�݂͐s���܂���B���N������S�����āA���̐l�Ȃ�̈��炩�ȍŊ����}������悤�Ɏx����̂���Â̐Ӗ��ł��傤�B���ꂩ��̈�×ϗ��ɂ́A���������̐l�̍K���ɂȂ���̂��Ƃ������_���K�v�ł��B �@�\�\��Â��t�ɍŊ��̏u�Ԃ̖�����W���Ă���Ƃ���͂���܂��B �@��@�����́A�����̉^��������A�����̂Ȃ���������������ɂ���܂��B�ł��A��t��Ō�t�ɉ������āA�ӎv�\�����ł��Ȃ������Ƃ����b���悭�����܂��B���҂����̓���f���ɓ`���A�V���������⊴�����ł���悤�Ȋ���肪��ł��B �@�\�\���҂̊�]���������邽�߂ɁA�ǂ�ȓw�͂�S�����Ă��܂����B �@�쓇�@���̏u�Ԃ́A�����ł͒m�邱�Ƃ��ł��܂���B�܂薞���Ȑ��͌o���ł��Ă��A�����Ȏ����ǂ����͔��f�ł��Ȃ��B������A���҂ƕ��������Ĉꐶ�����b�������u�����悩�����v�Ƌ����ł��鐶������T���Ă����B���̐ςݏd�˂̒��ŁA������A�����K���ƍl���Ă��܂��B �@�\�\�u����ȍŊ����}�������v�Ǝ����Ă��銳�҂͂��܂����B �@��@���傤���ɂ݂����؈ޏk�i�����キ�j�������d���ǂ̍��X���ݎq����́A�l�H�ċz������Ȃ�����I�т܂����B�n���̒��w�Z�ōu�����A���̈Ӗ���₢������Ȃǒ���̓��X�𑱂��Ă��܂��B�ǂ����ʂ��ł͂Ȃ��A�ǂ������邩�B���̗E�C�Ɋ����������ł��B ���u�ݑ�v�x�� �@�\�\����ł̍Ŋ���]��ł��A�����ɂ́u��ނ��a�@�Łv�Ƃ������������̂ł́B �@��`�@����҂́A�Ŋ��͂�͂�Z�݊��ꂽ�Ƃ����]�݂܂��B���͂��������v�]�ɉ����邽�߁A�V�����^�C�v�̍���ҏZ��̏[���𐄐i���Ă��܂��B����ҏZ��͈�Âƕ������������A�Ŋ��܂Ŏ����炵���������T�|�[�g����B�݂��߂Ȏ����}����悤�Ȏ��Ԃ́A������Ȃ��Ȃ�͂��ł��B �@�\�\�ݑ��Ây�������ʼnۑ�́B �@�쓇�@���͂Q�O�O�U�N�Ɂu�ݑ�×{�x���f�Ï��v�Ƃ������x�����܂����B�������A���ۂɂ́A�ݑ��Âɂ��ǂ�����ɂ���l���啔���ł��B���̌����́A�����邱�Ƃ��\���ɐ������Ȃ���҂ɂ���܂��B�������s�\���Ȃ܂܁A���r���O�E�C�����쐬����͖̂{���]�|�ŁA���Ղɓ��ӂ��Ă͂����܂���B �@�\�\���{�̉ƒ�ł́A���͘b�肩�牓������ꂪ���ł��B�{���ɂ���ł����̂ł��傤���B �@��`�@���������ۂ���̂ł͂Ȃ��A�O�ꂵ�đ����Ăق����Ƃ����̂��A�܂����r���O�E�C���ł��B�d�v�Ȃ͖̂{�l�̈ӎv�d���邱�Ƃł��B�l�����ς��ΓP���ύX���ł��܂��B�݂Ȃ����N�Ȃ����ɁA�Ƒ��Ƃ��悭�b�������Ȃ���A���Ў����̎��ɂ��čl���Ă݂ĉ������B �ǔ��V���@2009�N6��18�� |
| ���y���͊ɘa�P�A�̏�Q�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��@�x���M�[�C���y���@�{�s��̒������� |
| �@�u�����b�Z�����R��w�I����������O���[�v�i�u�����b�Z���j��Lieve Van
den Block���m��́C2002�N�ɂ�����u���y���@�v�����肳�ꂽ�x���M�[�ł́C���@�̎{�s����ɘa�P�A���銳�҂͌������Ă��Ȃ����Ƃ������ꂽ��BMJ�i2009;
339: b2772�j�ɔ��\�����B ���y�������@�� �@����܂ł̌�������C�I�����ɂ͐����̒Z�k����w�I���f��������邱�Ƃ��������Ƃ����炩�ɂ���Ă���B�܂�C�v���I�Ȗ�܂̎g�p��C�p���I�Ȓ��Ö�̓��^�C�܂��͏Ǐ�ɘa�̂��߂̖�ܓ��^�̋����ȂǁC���ʓI�Ɏ����𑁂߂鏈�u���Ȃ���Ă���Ƃ������Ƃł���B �@�x���M�[�ł́C2002�N�Ɉ��y�������@�����ꂽ���C�ɘa�P�A�����{�����Ñ̐��̐������i��ł���BVan den Block���m��́C2005�`06�N�̃x���M�[�ɂ�����ˑR�����������S��2,000���͂����B����̌����́C�I�����̈ӎv����Ǝ��ۂɎ��I������Â̊W�����߂Ė��炩�ɂ�����K�͌����ł���B �@���҂̂���32����85�Έȏ�ŁC�j����͂قڔ������C������43���͂���ł������B���҂ł͑��̎����̊��҂ɔ�ׂāC���̛Ƃ��ĐH���␅���𓊗^�����ɒ��Ö�̏����ʂ𑝂₵�Ē��Ï�Ԃ��ێ�����邱�Ƃ������X���ɂ������B �@���̒��O��3�����ԂɃX�s���`���A���P�A�������҂́C�قƂ�ǂ܂��͑S���Ă��Ȃ����҂ɔ���y���܂��͈�t�ɂ�鎀�̛�I������X���ɂ��邱�Ƃ������ꂽ�B�����̒m���́C���y���Ɗɘa�P�A�͌����Ė���������̂ł͂Ȃ��C�݂��ɑ���̊W�ɂ��邱�Ƃ������Ă���B �@����ɏW�w�I�Ȋɘa�P�A�����l�قǁC�Ǐ�ɘa��ړI�Ƃ���������C�H���␅����ێ悹���ɒ��Ö�̏����ʂ𑝂₵�Ē��Ï�Ԃ�ۂ��ƂŎ����𑁂߂Ă����B�܂��C�����������҂ł͑����Ď����𑁂߂�I������Â����f����X����������ȂǁC�W�w�I�Ȋɘa�P�A�Ɛ������Ԃ�Z�k�����w�I�Ȉӎv����ɂ͊֘A���F�߂�ꂽ�B�����ɁC�I������Âɂ�����ӎv����Ɗɘa�P�A�͑������邱�ƂȂ��������邱�Ƃ������ꂽ�B �@�����������̒m���́C�x���M�[�ł͊ɘa�P�A���邱�Ƃ̂ł��Ȃ����҂��C���Ҏ��g�܂��͑�O�҂̈ӎv�ɂ���āC�ߓx�Ɉ��y���܂��͈�t�ɂ�鎀�̛�I�����Ă���Ƃ������O�����S�ɕ��@������̂ł͂Ȃ��B �@�����m�́u�����ł����l�̂��Ƃ������邩�ۂ��ɂ��Ă͂���Ɍ������K�v�����C���ʂ́C���ꂼ��̖@�I��ɘa�P�A�V�X�e���C�Տ�����ɂ�������y���݂̍����l�����Ȃǂɍ��E�����ƍl������v�Ǝw�E�������ŁC�u��t�ɂ�鎀�̛��e�F����Ă���ăI���S���B�ł́C��t�ɂ�鎀�̛�I�������l�̑������z�X�s�X�P�A���Ă����B�܂��C�@�����ɂ��z�X�s�X�ւ̏Љ�]�@���������C��t�ɑ���ɘa�P�A�g���[�j���O�����y�����ƕ���Ă���v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N10��1�� |
| �]�ށu�Ŋ��v�����߂ā@������ �S���� |
| �@�������ɂ��čl���錧���Ƃ̍��k��i����t���Áj���S���A�앗�����̌���t��قŊJ���ꂽ�B�u�������鐶�v�u�������鎀�v���l�����ɖ�R�T�O�l���W�܂�A�ꕔ�̒��O�����ɓ��肫��Ȃ��قNJS�̍������������킹���B �@���{������������Ȃ�̌��͌\��Y��\�A�����a�@�@�\����a�@�̐ΐ쐴�i�@���A�ߔe��ꎖ�����̉i�g�����ٌ�m�A�����܂�[�N���j�b�N�̎R�����i�@�����������A�ɘa�P�A�A�@���A�ݑ��Â̂��ꂼ��̗��ꂩ��I�����̖��ɂ��ču�������B���̐l�炵���Ŋ����}���邽�߂ɍs���A��ÁA�������g�����g�ނׂ����ƂȂǂ�b�����B �@��Î҂̗\�z��傫������Q���҂ɋ}����A�ʎ��Ƀ��j�^�[��݂��ĊJ�Â����B���^�����ł͏I������ÁA�ݑ���Ɋւ��鎿�₪������ꂽ�B�u�ɘa�P�A���������A�K������������ɓ���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��v�Ƃ�������ɑ��A���͑�\�́u�K���������̕K�v�͂Ȃ��B�厡��ɂ����Ƃ����Ƃ��͉�����f��Ƃ������Ƃ�\���o�Ă��������v�Ɠ������B �@�u�ݑ�ł݂̂Ƃ��i�߂�ɂ͉����K�v�Ȃ̂��v�Ƃ�������ɎR���@���́u���͍ݑ�𐄐i���邪�A��������L���V�l�z�[���ł݂͂Ƃ�̌o�����Ȃ��ȂǁA����͎���鏀���͂ł��Ă��Ȃ��B�v�挩�������K�v�v�Ƙb�����B�܂��u�Ƒ��̑��͍ݑ��]�܂Ȃ����Ƃ������v�Ƃ����w�E�ɑ��Ắu���Ȃ����͂ł��x���ł���d�g�݂�����悭�Ȃ�B�Ⴆ�Γ��������a����w�f�C�z�X�s�X�x�����邪�A�o�c�I�Ɍ������L����Ȃ��v�ȂǏI����������ʼn߂������߂̌����I�Ȏx�����K�v�Ƃ����B �@��ꂩ��́u����̏�Ől�Ԃ̖��ɂ��ċ�����K�v������v�u��Â̑��Ƙb�������@��K�v�v�Ȃǂ̗v�]���������B �����V��@2009�N10��5�� |
| �z�X�s�X�̐������Ă��Ȃ��������ґ����@��Ò҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����s������� |
| �@�n�[�o�[�h��w��Haiden A. Huskamp���m��́C�i�s���҂̑������f�f��4�`7�����̊ԂɃz�X�s�X�ɂ��Ĉ�t�ȂǂƘb�����������Ă��Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ�����Archives of Internal Medicine�i2009; 169: 954-962�j�ɔ��\�����B �b���������̂͂킸�������� �@�z�X�s�X���牶�b�銳�҂͏��Ȃ��Ȃ����C���̈���Ńz�X�s�X�Ɋւ���b��͊��҂̖����܂ŏo�Ȃ�������C�S���b�������Ȃ����Ƃ���������B�������C�i�s���҂ł͑����Ƀz�X�s�X����������̂͗L�v�ł��邱�Ƃ������ƍl������B �@�Ⴆ�C�z�X�s�X�ł͐N�P���̒Ⴂ���Â��s���邽�߁C���҂͂��悢QOL�邱�Ƃ��ł���B �@��t�����҂ɑ��ăz�X�s�X���Љ�邱�Ƃ͏d�v�ł���B������Huskamp���m�炪�č����̕����̒n��ŃX�e�[�WIV�̔x����1,517���ΏۂƂ��������ł́C�]�ڂ���Ɛf�f���ꂽ���҂̑����́C�f�f���4�`7�����ԂɈ�Ò҂ƃz�X�s�X�ɂ��Ęb�������Ă��Ȃ����Ƃ��킩�����B �@�����m��́u��t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����𑝂₷���ƂŁC�z�X�s�X�ւ̊��҂̔F���s����\��Ɋւ������ɑΉ��ł���v�ƍl���Ă���B�܂��C�X�e�[�WIV�̔x���҂̐������Ԓ����l�͐f�f�����4�`8�����ł��邽�߁C�z�X�s�X�ɂ��Ă̘b��������f�f��4�`7�����ȓ��ɍs�����Ƃ��K�Ƃ��Ă���B �@�f�f�̖�4�`7������Ɋ��҂܂��͊��҂̑㗝�l�ɃC���^�r���[���s�����Ƃ���C�C���^�r���[��2�����ȓ��Ɏ��S�������҂Ńz�X�s�X�ɂ��Ď厡��Ƙb���������s��ꂽ�̂͂킸��53���ŁC�������Ԃ���蒷�����҂ł͂��̊����͂���ɒႩ�����B �@�����ҁC�p�[�g�i�[�Ɠ����̊��ҁC���w�Ö@���Ă��銳�ҁC�n���ҁC�}�C�m���e�B�l��C�p�ꂪ�b���Ȃ����҂Ȃǂł́C��t�ƃz�X�s�X�Ɋւ���b�������������Ȃ��X��������ꂽ�B �\��̍l�������e�� �@�����̗]����2�N�����ƍl���Ă��銳�҂ł́C�]������蒷���ƍl���Ă��銳�҂Ɣ�ׁC�z�X�s�X�ɂ��Ęb���������Ƃ����Ȃ葽�����Ƃ��킩�����B���̌��ʂ���C��t�͊��҂Ɨ\��ɂ��ẴR�~���j�P�[�V������L���ɍs���Ă��Ȃ����Ƃ�C�\��̐������\���ɗ��������Ă��Ȃ����߁C���҂����g�̗\����y�ώ����Ă���\�����������ꂽ�B �@�u�ɂ܂��͌ċz�s�S���ł��d�x�̊��҂ƁC�d�Ǔx���Ⴂ���҂ł́C�z�X�s�X�ɂ��Ă̘b�������ɍ��ق͌����Ȃ������B �@�]���̉�������u�Ɋɘa����]�������҂�4����3���́C�z�X�s�X�ɂ��Ď厡��Ƙb�����������Ƃ���x���Ȃ������B�b�������̌��@�͊��҂Ɍ���������킯�ł͂Ȃ��悤�ŁC���҂�4����1���͑h���s�v�iDNR�j����]���Ă����ɂ�������炸�C��t�Ƙb�������@������Ȃ������B �@������ÂɊւ���b�������́C����I�ɂȂ�₷�����Ԃ�������B���̂����w�͂�����Ȃ��ȂǁC��t�ɂƂ��ėe�Ղł͂Ȃ��B�܂��C�b��������x�点����C�S���b�������ɉ����Ȃ����҂�����B �@�b������ꂽ�Ƃ��Ă��C�z�X�s�X�̂��ׂĂ̑��ʂ��\���ɐ����ł���킯�ł͂Ȃ��B��t��DNR�ɂ��Ă̘b���������������҂̂����C�z�X�s�X�ɂ��Ă��b�����������҂́C�킸��3����1�ł������B���̂��Ƃ���C���҂ƈ�t���b�������̃`�����X���킵�Ă��邱�Ƃ�����������B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N10��29�� |
| �z�X�s�X�͕s�v�̎���� |
| �@���s�k��̑����a�@�u�k��a�@�v�i���S�����j�̕��@���ŏ�����O�Ȉ�̔���M�O����i�T�S�j�́u�z�X�s�X�i�ɘa�P�A�a���j�������Ƃ��K�v���낤���v�ƈӕ\��˂����Ƃ��������B �@�킪���̃z�X�s�X�́A�f�Õ�V��̗D����������1990�N�㏉������S���ɍL�������B�z�X�s�X�̉ʂ����������͑傫���B�ȑO�͂����ȂǂŒɂ݂̂���͓̂��R�Ƃ���Ă������A�z�X�s�X�ł̈�×p����Ȃǂ̓K�Ȏg�p�ő����̏ꍇ�A�Ŋ��܂ŋꂵ�܂Ȃ��Ă��ނ悤�ɂȂ������炾�B �@�u���Î�i�������Ă���Ƃ��ɂ́A�����Ɋɘa�P�A�����邵���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�������Ö@�͂ǂ�ǂ��A���ÂƊɘa�P�A���ɍs������ɂ��Ă���v�Ɣ����t�B�u�ǂ�ȕa���ł����Ă��ɘa�P�A���K�ɍs��������킯�ł��v�Ƌ�������B �@�ŋ߂̂��Â͊e�f�ÉȂ̋�����ƂɂȂ��Ă����B���Â̑I�������L�������̂͂������A�S���オ�R���R�����邱�Ƃ�"���̂Ă�ꂽ"�ƕs����������҂������Ă����Ƃ����B �@�k��a�@�ł͊O�Ȉ�̔����t�炪��p��̊��҂ɂ��āA�K�v�ɉ����ĉ@���̊ɘa�P�A�`�[�����u�Ɋɘa�����Ă��炤���A�厡��Ƃ��Ă̐ӔC���Ō�܂ʼnʂ������j���т��A���҂̕s�������ɂ��w�߂Ă���B �@�ɘa�P�A���L�͂ɍs���A��ÃX�^�b�t�ɂ��x���̐����[�����A�z�X�s�X���s�v�ɂȂ�����҂��������B �����V���@2010�N1��6�� |
| ��t�́C���ɑ���"�S"�{���n��̎���ɍ�������ÁE���V�X�e���̍\�z�� |
| �V�t�Βk ���V�l�@�@�@�@���{��t�� �H�c���q���@1926�N���܂�D�t���[�̋L�^�f���� �@�V�t�ɓ�����C����́C�L�^�f��ēƂ��āC�w�s�𐫘V�l�̐��E�x�Ȃǂ̍�i��ʂ��āC����҈�Â�I������ÂȂǂɊւ��Ă��C���܂��܂Ȗ���N�����Ă���ꂽ�H�c���q�����}���C���E�ɗނ����Ȃ����q����Љ���}�������{�̈�ÁE���E��������������_�Ɛi�ނׂ����������ɂ��Č���Ă����������D �@���V�@�ߔN�C������i�݁C��Â���̕K�v�ȕ������������ŁC�Ŏ��ɂ��Ă���ÊE�̖�肩�Ǝv���Ă��܂��D���ǂ���ÒS���҂́C��w�E��p�̐i���ɂ���z������ËZ�p�Ƃ���"�Z"�������ĕ�d���邱�Ƃ��厖�ł����C�ŋ߁C�S�l�I�Ȉ�Â̕K�v���������Ă��܂��D �@�������C��Â��邢�͈�t������̏]���̍l�����ł͑Ή�������Ȃ������ǂ�����܂��D�����ŁC�H�c�搶���f���ʂ��Ď�����Ă���C��Â���ɂ��Ă̂��l�����f�������Ǝv���܂��D �@�H�c�@�ŏ��ɂ��f�肵�Ă��������̂ł����C���͈�w�E��Â̐��Ƃł͂Ȃ��C���ʂɕ�炵�Ă���l�ԂƂ��Ď���������������������C���̐��ł���f���ʂ��Ė���N���Ă��܂����D�ł�����C�S���f�l�̎��_�ł̘b�C����Ӗ��ŕ��ʂ̐l�Ԃ̗����Ȉӌ��Ƃ������Ƃł���������������Ǝv���܂��D �@ �@���V�@�͂��D�����������_���猾���Ă��������̂��厖���Ǝv���Ă��܂��D�Ƃ���ŁC������������Ƃ��낢��Ȃ��Ƃ��v���o���܂����C���͏��a17�N���܂�ł��̂ŁC�I����3�`4�������̂ł����C�搶�́C�����������̎v���o������܂����D �@�H�c�@���͑吳15�N�C�����B�̑�A���܂�ŁC����啪�N��Ȃ��̂ł�����C������ۂɎc���Ă���̂́C��O�̏��w�Z���珗�w�Z����C�Ƃ������ɂ��������̖L���Ȃ������̂��Ƃł��D�ꂪ���d�ɋl�߂���{�̂��ߗ����Ƃ͕ʂɁC�Ƃ̋߂��̒��������X�ɒ����������Ă��Ă��炤�C�傫�Ȃ��M�ɂ��낢��ȗ������Z�b�g���ꂽ�����������̂������������Ɉ�ۂɎc���Ă��܂��D����ɁC���Ƃ͈Ⴂ�C�m�荇����ߏ��ɂ��N�n�̂���������������Ƃ������K������܂����D �@�����́C���̎q�͒����𒅂����Ă����̂ł����C�ꂪ���\�n�C�J���Ȑl�ŁC�����Ē����������Ă��ꂸ�C�������͈�Ԃ����m���𒅂āC���q�l��������̂�҂��āC���������������������������̂��ƂĂ��y���݂ł����ˁD �@���V�@�m���ɁC�������ɂȂ�Ɛe�މ��҂�����t�������̂���l���W�܂��āC�ɂ��₩�ɉ߂��������オ����܂������C�ŋ߂́C�Ƒ������ŎO�������߂����ƒ낪�����Ȃ����悤�ł��ˁD�̂́C���N�ʂ����������c�c�D�J���^���╟���D�j�̎q�́C�����g���₷���낭�D �@�H�c�@�����C���N�ʂ����炢�C�J���^���₷���낭�C�H���������܂����ˁD �@���V�@���́C�������Ȃ�ł̗͂V�т╗�K���C���܂茩�����Ȃ��Ȃ�܂����D�������C�嗤�͏������ɓ���Ƒ�ςȊ��g�ɏP���邻���ł�����C���������ł��傤�ˁD �@�H�c�@��̕��ł�������C�g�����āC�������Ă��뉺10�x���炢�ł����D �@���V�@���C�Ŋ����Ȃ��삳��ł��炵���̂ł����D �@�H�c�@�����C���͂��܂��v�ł͂Ȃ��C�̑��Ƃ��X�|�[�c�͎����ċ��ŁC����قNJ����ł͂���܂���ł����D �@���V�@�w������́C���{�ʼn߂����ꂽ�̂ł��ˁD �@�H�c�@�����ł��D���R�w���ɓ���C�Ƃ���A�������̂ŁC3�N�ԗ��ɓ����Ă��܂����D �@���V�@�w��������g�f��ɓ���ꂽ���̎v���o�͉�������܂����D �@�H�c�@�w������͑����m�푈�^���������ŁC�s��̔N�̑��Ƃł��D���ł͐H�ו����قƂ�ǂȂ��C�Ђǂ����������Ă��܂����D�Ō�̈�N�Ԃ͊w�k�����Ƃ��Ē�����s�@���쏊�ŗ��̃G���W��������C���͐��ՍH�ł����D�s��̔N�̎O���C���Ǝ��ŋ�P������C�L�O�ʐ^���Ȃ�����ł����D���ƌ�C��A�̉Ƃ܂ŁC���ʂȂ�O���l���̂Ƃ�����\���ȏォ���āC����ƋA��܂����D �@�O�N�����Ĉ����g���āC�{�Вn�̐É��ŏo�ŎЂɋ߂��̂ł����C�����ɏo�����āC����c�����̂����e�ɂ�����GHQ�̃`���y���Z���^�[�ɋ߂܂����D���̎��C���R�w���̉��t�̉H�m���q�搶���C������g���X�Ɉ��������Ă��ꂽ�̂ł��D �@�����C���������ł͊�g���X���g�b�v�ł������C��g�ΗY���́u���ꂩ��͉f�������̎���ɓ���v�Ƃ�����u���Ă���ꂽ�C��̌����ŗL���Ȗk�C����w�̒��J�F�g�Y���m�̌������i��g�f�搻�쏊�̕�́j�ɁC�X�^�b�t�ɓ���Ȃ����Ɛ����|�������̂ł��D���́C�f��͂悭������Ȃ������̂ł��f�肵���̂ł����C�u�{�̕ҏW�͂ǂ��ł��傤�v�ƌ����C�w��g�ʐ^���Ɂx�̕ҏW�X�^�b�t�Ƃ��āC���J�F�g�Y�������ɓ������̂ł��D �@�������J�F�g�Y�������ɂ́C�ʐ^�̐��E�ł͔��ɗL������������m�V������g�ʐ^���ɕҏW���ŁC����ƁC����U���Ă����������H�m���q�搶�̑��q����ʼnf��ē̉H�m�i���C�f�����肽���Ƃ������Ƃœ����Ă����܂����D �@�ŏ��͕ҏW�����Ă����̂ł����C�f��̕������Z�����Ȃ�C������̃X�^�b�t�Ɉ��������C���o�����炨�����낢���̂ł�����C�f��̎d��������悤�ɂȂ����̂��C���̐��E�ɓ��������������ł��D �@���V�@�����f��̂��Ƃ͑S��������܂��C�f�������̂͑�ς��Ǝv���܂��D���́C���{�씪�ēC�݂ˎq��v�Ȃ́C���̐e�̊��҂������W�ŁC���ɐe�������Ă���āC���c�i�������j�̎���֍s���܂��ƁC����Ƃ��\�z�̓r���Ȃ̂���ςȂ���J������Ă���̂�������܂�������D �@�H�c�@���́C�h�L�������^���[�f��ŁC���{�씪����͌��f��ł�����C���낢��ȓ_�ňႢ������܂�����ǁC�f��Â���͊m���ɑ�ςł���ˁD ��t�{���̎g���ƏI������� �@���V�@�搶������ꂽ�f��C�w�s�𐫘V�l�̐��E�x�w���S���ĘV���邽�߂Ɂx�w�I���悯����ׂĂ悵�x�Ȃǂ́C������ÊE������l���Ă����ׂ��C���܂��܂Ȗ����N����Ă��܂��D�������C�����̖������z���Ă������Ƃ͔��ɓ���Ƃ������܂��D �@�I������Âł́C������Ƃ����ʂƂ������Ƃ́C���̐l�̖��Ȃ̂ł��傤���C��ÒS���҂Ƃ��ẮC���N�ɂȂ��āC������x���A���Ă������������Ƃ����̂��{���̎g���ł���C���̂��߂Ɏ����̎��Ă�m����Z�p�����킯�ł��D�������C���{�l�̍l�������C�g���������������Ă���Ă����̂́C���������ȂƂ������Ă���C���̓_�͌������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��D �@�����C�I������Âł��z�X�s�X��Âł��C���������铹�͂Ȃ��̂��ƓO��I�ɓw�͂���̂���t�̎g���ł���C�ŏ�����z�X�s�X��ÂƂ��I������ÂɐϋɓI�Ɏ��g�ނ��Ƃ́C�u��Õ����v�ȂǂƔᔻ�𗁂т��˂��C��t���Ƃ��ẮC�Ȃ��Ȃ����ݐ�Ȃ�����Ƃ��낪����܂��D �@�h�L�������^���[�f��́C���炭���͎����̂ł��傤���C�ڂ̑O�ɋN�����Ă��錻�����f�������Ă�����킯�ŁC���낢��Ȃ��̂����߂��Ă���͂��ł����C�����͉�������������炢���̂ł��傤�ˁD �@�H�c�@��������������炢�����Ƃ�������͍���܂��ˁD���̍�i���i���Ă��邱�Ƃ����ł����āC������Ƒi������C������Ɗ����Ă�������킯�ł�����C����͍�i�̖��ł����Č�����̖��ł͂Ȃ��ł���ˁD �@���V�@�m���Ɉ�ۂɎc��f���́C�S�����Ɏc���Ă��܂��ˁD�w�ԂЂ��x�Ƃ�����i���C�{���ƖY��Ă��܂��܂����C�f��̉f�������͏����܂���C�������ł���ˁD �@�H�c�@���������悤�ɉf���̗͔͂��ɋ����āC"�S���͈ꌩ�ɂ�����"�ƌ����܂����C�{�������ς��ǂނ����C�p�b�ƌ����f����ŕ������Ă��܂��D������C����Ӗ��ŁC�f�������Ƃ����̂͐ӔC������Ǝv���܂��D �@���܂ʼnf�搧��̂Ȃ��ŁC�ǂ̂��炢��Â̎d���ɂ�������Ă������v���Ԃ��Ă݂܂�����C��g�f�搻�쏊��1964�N�ɁC���{��t��̊��ŁC�wTV��w�����u���x�Ƃ����e���r�ԑg���������̂ł����C���̎��̉�͕������Y�搶�ł����D���́C�����C�䒃�m���̈�t��قɎf���āC�����搶�����̒��Ō����Ă���قǕ|���搶���Ƃ͒m�炸�ɂ��b�����Ă����̂ł��D �@�����������̂́C�u�]�o���v�u�_�o�ǁv�u����ǁv�Ȃǐ��{�ŁC���ꂪ��w�ɂ���������ŏ��ł��D1960�N��̌㔼�ŁC���{�̈�w�������������Ői�����C�܂��Ɉ�w�ɑ���M���������܂�Ƃ���ł����D �@���V�@���a30�N�ォ��́C���{�̌o�ς��������C��w���}���ɐi����������ł��ˁD �@�H�c�@��������w�̔ԑg������Ȃ���C�u�Ȃ�Ĉ�w�͂������̂��낤�v�ƁC�傫�ȐM�������������̂ł��D���ꂼ��̐�啪�삪���̂������i�����Ă����r���������Ǝv���܂��D �@���̌�C�S�R�Ⴄ�d���ɓ������̂ł����C���̈�w�ɑ��Ď�����{�I�ȋ^����������̂́C�\�N�������Ȃ�1972�N�C���̖�������ŖS���Ȃ������ł��D�������ʂ������ɂ���C���o���S�̂ɓ]�ڂ��Ă������Ƃ���U�ŕ�����܂������C���߂͂��������Ă��܂��C������������Ȃ������D���Ƃ������Ƃœ��@���C���J���ŖS���Ȃ����̂ł��D���̎��C�ŏI�I�ɒɂ݂����ɂЂǂ��Ȃ��āc�c�D �@���V�@�ɂ݂��Ђǂ������̂ł��ˁD �@�H�c�@�����D�����q�l��ł��Ă�������̂ł����C�����Ԃł܂��ɂ���̂ŁC�u���Ƃ����Ă��������v�Ƃ��肢����ƁC�u�̂Ɉ�����������łĂȂ��v�ƌ�����̂ł��D���͋����C�ɂ݂ɑΉ������Â��Ȃ����Ƃ�s�v�c�Ɏv���܂����D �@���ꂩ��C�Ō�ɁC�������߂��ȂƎv�������ɁC�������Ƒ��͕�������o����C����҂��x�b�h�ɔ�я���āC���̑̂��������Ă���D�����C�S���}�b�T�[�W���Ǝv���̂ł����C���炭���āC�u���Ƒ��̕��C�ǂ����v�ƌ����ē�������C���͎���ł��܂����D���́C���̎��C��Â͐l�������ƂɏW�����C�ǂ�����Ă������Ȃ��������ƂŏI���ɂȂ�v�z�����Ȃ��̂��Ǝv���܂����D �@�l�Ԃ͂ǂ�Ȃ��Ƃ����Ă����ʁD�����Ĉ�Â͍ł����ɑΉ����Ă���w��ł���C�Z�p�ł���킯�ł��D�������C���������Ă����߂������Ƃ������Ƃł��������l���Ă��Ȃ����ƂɁC���ɋ^��������܂����D �@�l�Ԃ����ʎ��ɁC�ł��g�߂ɑ��݂����҂����ɂ��ĉ����l���Ă��Ȃ��̂͂��������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����̂ł��D�ł��C����҂���́C���h���ׂ��C�����|�����݂ł�����C����Ȃ��Ƃ�������e��������҂�����g�߂ɂ��Ȃ������̂ŁC���͂�������ݍ��܂܁C���\�N���߂��Ă��܂����킯�ł��D �@���V�@����̖�����Âɂ��ẮC�������d�˂��C���{��t��ł��C�w������ÂɊւ���P�A�̃}�j���A���x�i�������N9��15�����s�j��w����ɘa�P�A�K�C�h�u�b�N�x�i����20�N3�����s�j���̍��q���쐬���C����ɔz�z����Ȃǂ��āC�����Â̐����̌����}���ēw�͂����Ă���Ƃ���ł��D ���E�����ɑΉ�����V�X�e���̏d�v�� �@�H�c�@���̌�C���܂��܂ȌX���̍�i�������Ă����Ȃ��ŁC�����Ăш�ÂɌ��������������ƂȂ����̂��C�w�s�𐫘V�l�̐��E�x�Ƃ�����i�ł����D �@���́u�F�m�ǁv�ƌ����܂����C1982�N�����́u�s���ǁv�ɂ͑Ή��������Ȃ���̓I�Ȏ��Õ��@���Ȃ��ŁC���鐻���Ђ���F�m�ǂɑ�����̂�������l����w�p�f������肽���Ƃ����b����g�f��ɗ����̂ł��D����������S�����邱�ƂɂȂ�C�ďC�҂ŁC�������}���A���i��ȑ�w�������������J��a�v�搶���C�u�F�m�ǂɑ��Ĕ��ɂ��炵���Ή������Ă��邩��v�ƏЉ�Ă����������̂��C�F�m�ǂ̕���50�l���炢���@���Ă���F�{��K�a�@�ł����D������10���C�B�e�Ŗ�1�J�������̂ł����C���́C�F�m�ǂ��ǂ�Ȃ��̂��S���m��Ȃ������̂ŁC�l�Ԃ�����Ȃӂ��ɂȂ��Ă��܂��ƒm��C�{���ɃV���b�N�ł����D�@���̎����N�m�搶�́C�u�m���ɔF�m�ǂ͎���Ȃ����C���̎d���ŏ�Ԃ͉��P�o����v�ƌ����C��������l�́C�����Ă����m�\�ł͂Ȃ��C�c���Ă��������đΉ����Ȃ����Ƃ����̂��匴���ł����D �@���Y�ꂪ�Ђǂ��Ȃ�C�����������������Y��Ă��܂����l�́C�u����������������Ȃ��́v�Ƃ��u�܂��������Ƃ������āv�ƁC�Ƃ̐l�Ɉ������Ƃ̎w�E�������ꂸ�C���x���{���āC���_�s���ɂȂ�C�ُ�s���������Ă���D����ŁC��ɕ����Ȃ��Ȃ��ĕa�@�ɂ���킯�ł����CK�a�@�ł́C����҂�����Ō�t������C���N��肪��������Ă���ɔے�I�Ȍ��t���g��Ȃ��̂ł��D �@�����ɂ���l�͉�������Ă������ē{���Ȃ��D�{���Ȃ��Ƃ������Ƃ́C�����̑��݂͔ے肳��Ă��Ȃ��Ƃ������ƂŁC���_�����������ĉ��₩�ɕ�点��悤�ɂȂ�D�ł�����C�m�\�͐����Ă��邯��ǁC���������ĐÂ��ȏI�����}���邱�Ƃ��o����킯�ł��D�����搶�́C�u�����ł͖�͂قƂ�ǎg���܂���D�������1�T�ԁC�x���Ă�1�J���C�撣���Ă��������Ή������Ă���C�݂�ȗ��������Ă��āC�Ǐ��P�����ꍇ������܂��v�ƌ����܂����D���ꂪ������悤�ȉf����B�肽���Ƃ������̂��C�w�s�𐫘V�l�̐��E�x�ł��D �@���́C���̉f������邨��҂���Ɍ��Ă������������ɁC�u��̂ǂ��̎{�݂ł����D�a�@�Ȃ̂ł����v�ƕ����ꂽ�̂ŁC�u�����C�a�@�ł��v�Ɠ�������C�u�a�@�Ȃ̂ɁC���̎��Â����Ă��Ȃ�����Ȃ����v�ƌ���ꂽ�̂ł��D���́C�n�b�Ƃ��܂����D�܂�C����҂���̈ӎ��̂Ȃ��ł́C��삪���ÂɌ��ѕt���Ă��Ȃ��D�Ȃ������d�v�����Ȃ��̂��낤�ƕs�R�Ɏv���C�܂��C�h��ŕ������܂܂ɂȂ�܂����D �@�����C���N����F�m�ǂ̕�������č����Ă���Ƒ��͂��������̂ł����C�ǂ����Ă����������炸�C���ԑ̂������āC�݂�Ȗق��Ă��܂����D��f��ɂ́C�Ƒ��ȂǁC�吨�̐l�����ɗ����܂����D�܂�C��������ĎЉ���ɂȂ��Ă��Ȃ������F�m�ǂ̖�肪�C���̉f��ɂ���ăI�[�v���ɂȂ��Ă������̂ł��D �@���́C�S���z�������Ă��Ȃ������̂ł����C��f����������ƂȂ��āC�u�����ꂪ�Ȃ邩������Ȃ��D���̎�����������삪�K�v�Ȃ�C�����̖��Ƃ��čl���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����b�������̏ꂪ�C���������ŋN���Ă����̂ł��D�t�Ɏ�����������������̂́C�F�m�ǂւ̑Ή��������邾���ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��C�܂�C�Ή��o���Ȃ��Ƒ����吨����Ƃ������Ƃł����D�ǂ��̒n��ł��C���ɑΉ��o����V�X�e�����v��ƒɊ����C�w���S���ĘV���邽�߂Ɂx�Ƃ����f������邱�ƂɂȂ����̂ł��D �@���́C�w�s�𐫘V�l�̐��E�x����������C���ʗ{��V�l�z�[���i���{�j�������ƕK�v���Ǝv�����̂ł����C�����ł͕K�����������`�����悤�ȑΉ������Ă��Ȃ��D�Љ�Ή��o����悤�ɂƍl���āC�ǂ��{�݂�T�������Č������̂��C���r�c���̃T���r���b�W�V�����ŁC�w���S���ĘV���邽�߂Ɂx�́C���ׂĒr�c���Ŏ�ނ��邱�ƂɂȂ�܂����D �@���̍��́C�ǂ��̓��{�������I�ŁC���ւ�F�m�ǂ̂��N��肪���鏊�͕K���܂��Ă���̂ł��D�߂�Ɖ��z�Ƃ������ƂŁC�V�����v�̓��{�̂Ȃ��ɂ́C�L�������邮�����悤�ɂȂ��Ă��āC�F�m�ǂ̂��N��肪��������1���������Ă���Ƃ����{�݂�����܂����D �@���V�@���݁C�����̒s��Ή��̕a���͊O�֏o��ꂸ�C���邮�����L�ɂȂ��Ă��܂��ˁD �@�H�c�@�����ł��D��������ĔߎS�ȋC�����ɂȂ�܂����D�Ƃ��낪�C�T���r���b�W�V�����ł́C���ւ��f�C���[���̃x�����_�̌˂��J���Ă��āC�F�m�ǂŜp��l�͏o�čs���Ă��܂��D����ƁC�p��l���Ƃ�"�p����p�[�g"�Ƃ����A���o�C�g�̒S���҂����āC�����ƈꏏ�ɕ����āC�����тꂽ���A���Ă���DK�a�@������i�Ή������Ă����̂ł��D �@����ɁC�����C�������i��ł���ƌ����Ă����C�A�����J��X�E�F�[�f���Ȃǂ̕�����i���ɍs�����ƍl���܂����D�A�����J�́C�V�l���Z�ނ��炵���n�悪�o���Ă����̂ł����C���̒n�悾���ł����̂ŁC���S�̂Ƃ��đΉ����Ă����X�E�F�[�f���ɍs���Ď�ނ����킯�ł��D �@���V�@������i���Ƃ��ẮC�k���̃X�E�F�[�f����f���}�[�N���L���ł��ˁD �@�H�c�@�����C�f���}�[�N�͔F�m�ǂ̐l�͕a�@�ɓ��@�����Ă���ł������C�X�E�F�[�f���ł̓��^���Ƃ������ŃO���[�v�z�[�������������Ƙb��ɂȂ��Ă��܂����D�f���œ��{�ɃO���[�v�z�[�����Љ�ꂽ�̂́C�w���S���ĘV���邽�߂Ɂx���ŏ����Ǝv���܂��D�܂����{�ł́C�u�O���[�v�z�[���v�Ƃ������t���Ȃ��C���͉f��̂Ȃ��Łu�O���[�v�n�E�X�v�ƌ����Ă��܂����D �@���́C�O���[�v�z�[������ނ��āC�ƂĂ����ꂵ�������̂ł��D�Ƃ����̂́CK�a�@�ł́C���ꂾ�����������Ă���̂ɁC�[���ɂȂ�ƁC�݂�ȁu���낻��ƂɋA��܂��v�ƌ����ăi�[�X�̏��ɗ���D�������Ƃɂ���Ƃ͂�����v���Ă��Ȃ��D�ǂ������炢���̂��낤�ƍl���Ă��܂����D �@���ꂪ�C���^���̃O���[�v�z�[���ł́C�݂�Ȏ����̉Ƃɂ���Ǝv���ė��������Ă���̂ł��D���{�Ƃ͂����Ⴂ�ɑ����X�^�b�t���Ƒ��Ƃ��đΉ����C�䏊�ŗ�������������C�݂�Ȃňꏏ�ɐH����������ƁC�ƒ�I�ȕ��͋C������グ�Ă��āC�F�m�ǂ̐l�ɂ͂��������Ή����K�v�Ȃ̂��Ƌ��������܂����D �@1990�N�Ɂw���S���ĘV���邽�߂Ɂx���������鐔�J���O�ɁC�����ȁi�����j���u����ҕی��������i�\�J�N�헪�i�S�[���h�v�����j�v�\���C����ƑO�シ��`�ł����̂ŁC�����̕������Ă��������܂����D �I������ÂŖ�����t��"�S" �@���V�@�F�m�ǂ̕��̉�삩��C�����V�X�e���̂�����ւƁC�u�V�����x����v�Ƃ����e�[�}�̍�i�������Ă���ꂽ�킯�ł��ˁD�����āC�w�I���悯��� ���ׂĂ悵�x������ꂽ�c�c�D �@�H�c�@�͂��D���̂����C�قƂ�ǂ̐l���I�����ɂ͕a�@�ɉ^��Ă������{�̃T���r���b�W�V�����ɁC�ɘa�P�A�ɑΉ��o�����t���풓����悤�ɂȂ��āC80���̐l���{�݂ōŊ����}����悤�ɂȂ�D�]���Ƃ����̂ł��D���̍��ɂ͊ɘa�P�A�a�����o���āC����̏I�����ɂ��Ă����ɂȂ��Ă��܂����D �@�����āC�x�R���̎ː��s���a�@�Ől�H�ċz����O�������߂Ɋ��҂��S���Ȃ����Ƃ������Ƃŕa�@�����Ӎ߉�������Ƃ̕����āC���������ƕ����Ă�����Âɑ���s�M���̂悤�Ȃ��̂��\�����Ė�莋����C�b�������Ă������͋C���o���Ă����ȂƊ����܂����D���ꂪ���������ł������̂��C�w�I���悯��� ���ׂĂ悵�x�ł��D����܂ł́C�l�Ԃ̎��ɂ��Ă��ꂱ�ꌾ���͙̂H�z�ł͂Ȃ����C�m�����Ȃ����C���̂������Ȃ��Ƃ��������ł������C����80���z��������C���������Ă������Ƃ����C�ɂȂ��Ă������̂ł��D �@��قǁC��̂��b���f���āC����҂���́C�ӔC�킳��C������������i�ׂ��N�������̂ł�����C����Ƃ���܂ł�낤�ƍl����͓̂��R�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����C��͂�C��w�C��Â������ǂ��Ƃ炦�邩�Ƃ������Ƃ��C���炵�Ȃ�������Ȃ��Ǝv���̂ł��D �@����͋��炾���ōςޖ��ł͂Ȃ��C����҂����l�ЂƂ�̌��ӂƂ������C�v�z�̖��ł��D�͂����肵���v�z��������Ǝ����Ă��邨��҂���ł���C���҂���͔[�����邵�C���Ƃ��i�ׂ��N�����Ƃ��Ă��C�Ή��o����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��D�����������Ƃ��l���ė~�����Ǝv���Ă������̂��C���̉f��Ȃ̂ł��D �@���V�@���̐搶�̂��b�ɁC����C���{�̈�ÁE���ɋ��߂��邱�Ƃ��S������Ă���悤�Ɏv���܂��D���̒��������Ȃ�������Ȃ��Ǝv���܂����C��t�ɂ́C��͂苳�炪�厖�Ȃ̂ł����C�ǂ��������Ă��܂��ˁD �@�z�X�s�X��ɘa�P�A�ȂǏI�����Ɉ�Ò�����ꍇ�́C�m���C�����C�N�w�C�ϗ������łȂ��C�@���Ȃlj����S���x������̂��Ȃ��Ɩ������낤�Ǝv���܂��D �@���ꂩ��́C������t�̐��c�̂Ƃ��Ă��C�������o���_�Ƃ��Đ������Ă��������Ǝv���܂��D�C���t���G���U�̃��N�`���ڎ�Ȃǂɂ�����"�u�[�X�^�[����"�ł͂���܂��C���ӂƂ��u�Ƃ��������̂��C�Ō�͐����̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��čL�܂�C�傫�ȗ͂ɂȂ��Ă����܂��D �@��Âɂ����ẮC�w����ËZ�p���厖������ǂ��C���ɑ���"�S"��|�����Ƃ̏d�v����搶�ɂ��w�E�����������悤�ȋC�����܂��D �@�H�c�@���Ȃǂ������͙̂H�z�ł�����ǂ��C�{���Ɉ�l�̊��҂Ƃ��āC����҂���Ɋ��҂��邱�Ƃł��D �@���V�@���̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��D�����C���N�ɔ]�O�ȁC8�N���炢�O�ɏ������2��̎�p���Ă��܂��D�ڂ݂Ď�������Â��銳�҂Ƃ�������ɂȂ�ƁC���G�Ȃ��̂�����܂��ˁD �@�������C�݂�Ȃ̋C������傫���������Ƃ����̂͑�ςȂ��Ƃł����C�f��́C�f�����C�������L���Ă����܂�����C���������_�͂����ł��ˁD �@�H�c�@�����ł��D�w�s�𐫘V�l�̐��E�x�����������̔��������āC�u�����C�f���̎d�������Ă��Ė{���ɂ悩�����v�Ǝv���܂����D �@���V�@���ꂩ��800���l�Ƃ�����c��̐��������҂Ƃ�����N��ɒB���C�Ŏ����삪�K�v�ƂȂ��Ă��܂��D����ɁC�F�m�ǂ̕����������Ă��܂�����C���̒����ǂ��Ή����Ă������͑傫�Ȗ��ł��D���������Ƃ����ǂ����̎���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��C�����̊F����ɂ����Ƃ��C�t���ė~�����̂ł��D �@���͂����C�u�n��̊F���C�t���Ď��g��ł���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ƙb���Ă���̂ł����C�܂��F�m�ǂƂ����_��Q�Ƃ��������X�ɑ��Ēn��Љ�̎v���͌����Ă��Ȃ��̂�����ł��ˁD �@�H�c�@�����ł��ˁD�ł��C�w�s�𐫘V�l�̐��E�x�������������猩����C�F�m�ǖ��ւ̔F���͔��ɍL�����Ă����悤�Ɏv���܂��D �@���ł́C�������ƌ����Ă��C�����s�v�c����Ȃ�����ɂȂ�܂�������ˁD �@���V�@�]���ǐ��̔F�m�ǂ͖h���邩���m��܂��C����͈�w�I�ȑ傫�Ȗ���ł��D �@�������C���ǂ��ꂽ�����ǂ����邩�Ƃ������Ƃ��厖�ŁC�F�m�ǂɌ��炸�C������Î҂��C�n��̈�t��𒆐S�ɂ��āC�����̃j�[�Y�ɉ�������悤�ȁC�n��̎���ɍ�������ÁE���V�X�e���̍\�z�𐄐i���Ă����ׂ����ƍl���Ă���̂ł��D �@��ÁE���E�����̕���ŁC�ǂ̂悤�Ȗ������ʂ����Ă������C���C����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��D �@�{���͖{���ɁC���肪�Ƃ��������܂����D ����j���[�X�@2010�N1��20�� |
| ���ɏꏊ�Ȃ�p������ԁA�p���� |
| �@�����}����̂ɍœK�ȍ��͉p���\�\�p���u�G�R�m�~�X�g�iEconomist�j�v�̒�������u�G�R�m�~�X�g�E�C���e���W�F���X�E���j�b�g�iEconomist Intelligence Unit�AEIU�j�v��14���A���̂悤�Ȓ������ʂ\�����B �@EIU�́A�o�ϋ��͊J���@�\�iOECD�j����30�����Ƃ��̑�10�����̈�t�E���ƂȂǂ�ΏۂɁA�I������Âɑ��鍑���ӎ��A�g���[�j���O�̗L���A���ɍ܂̎g�p�A��ҁE���ҊԂ̃R�~���j�P�[�V�����̓������Ȃǂ���Ƃ��A�u�N�I���e�B�[�E�I�u��f�X�iQOD�A���̎��j�v��]�������B �@�p���́A���{�ɂ��I������ÃT�|�[�g��A�z�X�s�X�Ԃ̃l�b�g���[�N���[�����Ă���_���]������A40�������g�b�v�ɗ������B2�ʂɂ̓I�[�X�g�����A�A3�ʂɂ̓j���[�W�[�����h�������N�C���B�A�C�������h�A�h�C�c�A�č��A�J�i�_���g�b�v10���肵���B �@�f���}�[�N22�ʁA�t�B�������h28�ʂȂǁA�x�T���Ƃ���鍑�̕����������L���O����20�ʂƒ�]�������ق��A���[�X�g10�ɂ̓|���g�K���A�؍��A���V�A���������B�ʼn��ʂ̓C���h�������B�i���{�͍��z�Ȉ�Ô�ƈ�Âɏ]������l���̕s����������A�Q�R�ʂƒႢ�]���������j ���x�T���ł̏I������Ð������}�� �@EIU�́A�u�Ő�[�̈�ÃV�X�e����L����x�T���v�ł���Ð��x�ɏI������Â�g�ݍ���ł��Ȃ����������Ǝw�E�B�l�̎��������сA����҂�����������Ȃ��A�����������X�ŏI������Â̎��v���}���ɍ��܂�Ƃ̌��ʂ����������B �@�܂��A�ɘa��Â͕a�@�����ōs����ׂ����̂ł͂Ȃ����ƁA����ł̎���I�Ԑl���������Ƃ������A������m�̈琬����������悤�E�߂Ă���B AFPBB News�@ 2010�N07��15�� |
|
�������Ò��~�̑Ó����́u�i�@�����Ō��_�o���ʁv ��苦���a�@����������V���| |
| �@�ō��ق̏㍐���p�ŏI��������苦���a�@�����ł́C�������Ò��~�̑Ó�����@��ōق����Ƃ̓�������炽�߂ĕ�������ɂ��ꂽ�B�s���ƈ�Â��l����V���|�W�E�����s�ψ���̃V���|�W�E���u��苦���a�@���������Ɩ@���l����v��7��18���C�����s���ŊJ����C�����̓����҂ƂȂ�����t�̉Ƒ���Ō�t�C�@���̐��ƂȂǂ���ÂƃV�X�e�����قȂ�i�@����Ís�ׂ̐�������_�t���邱�Ƃɖ���������ȂǂƂ���ӌ������B�l�Ƃ��Ď��ʂ��Ƃd����s�ׂ��u�ƍ߁v�ƌ��Ȃ���錻��ł́C��Ï]���҂̏d���Ƌ�Y�͌��E�ɗ��Ă���B �����ʼn������Ò��~�̓K�@��͎����ꂸ �@��苦���a�@�����́C1998�N11���ɓ��a�@�ɐS�x��~�ʼn^�ꂽ�b�����҂ւ̏��u�ɒ[����B���҂͑h�����l�H�ċz��͊O�ꂽ���̂̋C�Ǔ��`���[�u�͎c���ꂽ�܂܂ō�����Ԃ͑����C�d�NjC�ǎx���Ȃǂŗ\�f�������Ȃ��ƂȂ����B�厡��̐{�c�Z�c�q���͊��҉Ƒ��Ƃ̂��Ƃ���o�āC�������Ò��~�̂��ߋؒo�ɖ�𓊗^�����B���ꂩ��3�N��C������������E�l�e�^�œ������ߕ߁C�N�i����鎖���ɔ��W�����B �@��R�̉��l�n�ٔ����ł͎E�l�߂̐�����F�߁C����3�N�C���s�P�\5�N�������n�����B��R�̓������ٔ����ł͉������Â̒��~���Ƒ��̗v���Ō��f���ꂽ���̂ƔF�肵�Č��Y�������̂́C�L�߂͕ς��Ȃ������B�ō��ق܂ő���ꂽ����N�i2009�N�j12���ɏ㍐���p�B�������Â̒��~�������t���E�l�߂ɖ��ꂽ�����ōō��ق����f�������̃P�[�X�ƂȂ������C�������Â̒��~����������͎�����Ȃ������B �u���Ƃ��Y���ňЊd���Ă܂Ŏ�肽�����́v�Ƃ� �@�{�c�Z�c�q���̌Z��ŃV���|�W�X�g�߂��c��`�m��w��w�@�����E���������w�����̐{�c�N�����́u�ٔ����͗��O�I�C���z�I�ȍl���ōٔ��ɗՂ�ł���B���̓_�����������̎i�@���f���������v�ƐU��Ԃ����B �@�ٌ�m�ō��������Z���^�[�������Z���^�[���C��劯�̑��`��Y���́C�Y���i�ׂł́u���ۂɂ����������Ƒi��̎������قȂ��Ă��܂����߁C�i�@����Âɉ������ɂ͌��E������v�Ƃ̌������������B�����āu���Ƃ��Y���ňЊd���Ă܂Ŏ�肽�����v�͂Ȃ�Ȃ̂��B�I������ÂŎ����ׂ��́C���p�Ŏ����鐶���ł���v�Ƒi�����B �@�T�c�����a�@�i��t���j��A��Ȍږ�̏����G�����́C������Љ�ł͓������ɗގ������肪��������Ǝw�E���C�u���肬��̓w�͂������ɂ�����߂邱�Ƃɂ��������͂���̂ł͂Ȃ����v�ƒ�N�B��Ís�ׂ̑Ó����́u�@���̂悤�ɉ�㈓I�C�����I�ɍl����̂ł͂Ȃ��C�X�̏ɍ��킹�čl����ׂ��v�Ǝ咣�����B ���l�Ȋ��o�C��������錻���@�ŋK��ł��邩 �@�s���̕a�@�ɋΖ������t���_�؎�b���́C�����d��ŗ]���킸�����������҂̎�p��f�O����������Љ���B��p���������Ȃ��������Ƃ��S�Ɉ����������Ă������C�⑰����́u�Ŋ��̂��ʂꂪ�ł����v�Ɗ��ӂ��ꂽ�Ƃ����B�����͎ӎ��������Ƃ��ӊO�Ɋ��������̂́C��t�Ƃ��ċM�d�Ȍo��������ꂽ�Ƃ��C�u��Ì���ł����������Ȃ����o�⊴�����̂ɁC�@���ňꂭ����ɋK�肷�ׂ��łȂ��v�Ƌ��������B �@�R���f�B�J���̗��ꂩ����ӌ����������B�Ō�t�̍P������q���́C���銳�҂��Ō�t�ƃR�~���j�P�[�V���������Ă����Ƃ��ɉ������Â̋��ۂ����Ă������C�Ō�t����t�ɓ`���Ă���������Ă��炦�Ȃ������������������B�u�Ō�t�����҂̈ӎv���L�^���C��������ƂɈ�ÎҊԂ̈ӎv�����}��ׂ��łȂ����B�E����ŊŌ�t�������ł�����𐮂���K�v������v�Ƌ��߂��B �@�{�c�Z�c�q���̐f�Â��Ă������҂̉Ƒ��ł���֓����q���́C���҂ƈ�t�̊W�Ɍ��y�����B�����͐f�@�ɓ�����{�c���̎p���ɑ��銳�҂̐M���͌��������Ƃ��C�u��t�����҂̖ڐ��ɗ����C���҂̂��߂��v���Ă���̂��Ƃ������Ƃ����҂͕q���Ɋ�������Ă���B���ꂪ��������ΐM���W�͐��܂��v�Ƙb�����B �@�i���̎肪�ǂ��܂ň�Âɉ�����ׂ��Ȃ̂��Ƃ����c�_�́C���l�ȍl����s����Ȑ��ǂȂǂ̉e���ŋ�̍���u����ɂ͎����Ă��Ȃ��B��Ï]���҂����҂̂��߂��v���Đl�Ԃ炵�����˂�菕��������ΗL�߂ɂȂ鋰�ꂪ�����ȏ�C�����ɕK�v�Ȉ�Ís�ׂƎi�@���f�̕������𑁋}�Ɍ��o���Ȃ���C��Èޏk�̗���͎~�܂�Ȃ��B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N7��20�� |
|
�u�R���Â��I�����Ă���ɘa�P�A�v�̎���͏I����� ��RCT�ő�������̊ɘa�P�A���������ԉ����ɂ���^ |
| ���D�y�a�@���@���E���w�Ö@�Z���^�[���@���R �א� �����̔w�i�F�Ō`����ł͊ɘa�P�A�̏d�v�����F������Ă��Ă��� �@�����̎�p�s�\���邢�͍Ĕ��Ō`���҂́C�Ö@�ɂ�萔�����̉����͓�����ɂ���ŏI�I�ɂ͎��S����B���S����O�ɂ͒ʏ킪��͑傫���Ȃ��Ă���C����ɂ��e����̓I��ɂɔ������ƂƂ��ɁC���_�I��ɂ͐f�f�������т��đ����B�ꎞ�I�Ɂu����͏k�����܂�����v�ƌ�����Ƃ��͂���ɂ���C�S�̂�ʂ��Ă͑��傷�邱�Ƃ̂ق��������C�㔼�͂��܂��܂ȃo�b�h�j���[�X�������}���邱�ƂƂȂ�B����Ö@���Ă�����Ԃ́u�l���̍Ō�̐����v���̂��̂Ȃ̂ł���B �@�������������_�ɗ��ƁC�Ō`������Âɂ�����ɘa��Â̐�߂�ʒu�͏d�v�ł���C���j�𐬂��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B �@����C�x���҂Őf�f��������ɘa�P�A����������Q�̂ق���QOL�͗ǍD�ŁC�������Ԃ����������Ƃ̕č��̃����_������r�����iRCT�j�̌��ʂ����ꂽ�̂ŏЉ��iN Engl J Med2010; 363:733-742�j�B �����̃|�C���g�F��������̊ɘa�P�A�Q�ŗǍD��QOL����ѐ������Ԓ����l���� �@�V���ɓ]�ڐ��זE�x����Ɛf�f���ꂽ�O�����҂ɂ����āC�f�f��̑����̊ɘa�P�A�������C���Ó]�A�ƏI������Âɋy�ڂ��e�������������B �@�����̊��҂��C����̕W�����Âɑ����ɘa�P�A��g�ݍ��킹�čs���Q�ƁC�W�����Â݂̂��s���Q�̂����ꂩ�Ƀ����_���Ɋ���t�����B�x�[�X���C���� 12�T�ڂ�QOL�ƋC�����C���Â̋@�\�]���E�x�iFunctional Assessment of Cancer Therapy-Lung�GFACT-L�j�ړx�ƁC�a�@���ɂ�����s���Ɨ}���ړx�iHospital Anxiety and Depression Scale�j��p���ĕ]�������B��v�A�E�g�J���́C12�T�ڂɂ�����QOL�̕ω��Ƃ����B �@�����_�����̑ΏۂƂȂ���151��̂����C27�Ⴊ12�T�ڂ܂łɎ��S���C107��i�c��̊��҂�86���j���]�������������B�����ɘa�P�A�Q�̂ق����C�W�����ÌQ��� QOL ���ǍD�ł������kFACT-L�ړx�i0�`136�_�ŁC�X�R�A�������ق�QOL���ǍD�ł��邱�Ƃ������j�̕��σX�R�A98.0�_ vs. 91.5�_�CP��0.03�l�B�܂��C�����ɘa�P�A�Q�̂ق����C�}���Ǐ��悷�銳�҂����Ȃ������i16�� vs. 38���CP��0.01�j�B �@�I�����ɐϋɓI���Â������҂́C�����ɘa�P�A�Q�̂ق����W�����ÌQ��菭�Ȃ������ɂ�������炸�i33�� vs. 54���CP��0.05�j�C�������Ԃ̒����l�͑����ɘa�P�A�Q�̂ق������������i11.6���� �� 8.9�����CP��0.02�j�B ���̍l�@�F�ɘa�P�A�̕���ł��ϋɓI�ɗՏ������� �@�R���Â��I�����Ă���ɘa�P�A���s���Ƃ�������͏I������B���E�ی��@�ցiWHO�j��2002�N�ɔ��\�����ɘa�P�A�̒�`�́u�����������������ɂ����ɒ��ʂ��Ă��銳�҂₻�̉Ƒ��ɑ��Ď����̑������CQOL�����P���邱�Ƃł���i�ꕔ���j�v�Ƃ��đ�������̊ɘa�P�A�̕K�v����������Ă��邪�C���߂Ă��ꂪ�����ꂽ�B �@�{�����ɂ�����ɘa�P�A�̎��ۂ́uNCP Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care, Second Edition, 2009�v�Ɏ�����Ă��邪�C���{��t��́u����ɘa�P�A�K�C�h�u�b�N2008�N�x�Łv�Ɏ�����Ă���悤�Ȓʏ�̊ɘa�P�A�ɃJ�E���Z���[�ɂ�閧�ڂȐ��_�I�P�A����������悤�Ȃ��̂ł���B �@���_�I�T�|�[�g�ɂ�鐶�����Ԃ̉����͈ȑO�������Ă���iCancer2008; 113: 3450-3458�j�C�@���͖��炩�Ƃ͌����Ȃ����C�����Âɂ�����ɘa�P�A�̏d�v���́C�f�[�^�Ƃ��ďؖ��������B�G�r�f���X�̊m���ɕK�v�Ȃ̂͗Տ������ł���B �@������Â̕���ł́CRCT�̏d�v������t�ɏ\���F������C���{�ł̑�U���C��V���Տ������̎��{�����������Ă���̂͊�����B�������C�ɘa��Â̕���ł̓��{�̗Տ����������ɏ��Ȃ��̂��c�O�ł���B�ϗ��I�ȍ�������z���C�������v�w�҂ɑ��k���Ċe�푽�{��RCT����悵�Ă��炢�����B �@�e�[�}�͂�������B�Ⴆ�C���ӊ��̖Ö@�ɂ��Ă͓��ɁC���{�Ŕėp�����X�e���C�h�{���Ɍ��ӊ����P�ɗL���Ȃ̂��C�Ȃǂł���B�����i�G�r�f���X�j�ƌ�����ߋ��̘_�������Ă��G���h�|�C���g�͌��ӊ��ifatigue�j�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��̂ł���i�u����̌��ӊ��ɐ��_�h���L���v�Q�Ɓj�B �@����C��������̊ɘa�P�A���d�����邠�܂�C�����I���Â̏�Q�ƂȂ�悤�Ȃ��Ƃ͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����`���Łu�Ō`����v�ƌ��肵���͖̂łȂ��邱�Ƃ��܂��Ȃ�����ł���B �@��Ō`����C�Ⴆ�C���t��ᇂ⏬������ł͏��قȂ�B���������p��̍R����Âɂ������u�ɃR���g���[���̂��߂̃I�s�I�C�h�ʂ������߂ɕ֔�ƂȂ�r���N���X�`�������ʂ���������Ȃ��̂ł���C��t�́u�P�l�̊���������_�v�ł����Ȃ��B�����I���ÂɊւ��ẮC�u���ɂ͊��҂ɉ䖝��������K�v������v�̂���ނ����Ȃ��B��������̊ɘa�P�A�ɂ����ẮC���������������I���������l���ɓ��ꂽ�����I���f���K�v�Ƃ���邾�낤�B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N8��27�� |
|
���r���O�E�E�B���̕��y�E��Ì���ւ̐Z���Ȃǂ�� ���J�ȁE�I������Â̂�������k��A���Ď��܂Ƃ� |
| �@10��28���A�����J���ȁE�I������Â̂�����Ɋւ��鍧�k��i�����F�����E��q��w�@�w�����ȋ����j�́A���Ă����܂Ƃ߁A���e�ɑ�ō��ӂ����B����A����̕ύX�E�⑫�A���ڗ��Ă̒����Ȃǂ��s���A�����J����b�ɒ�o����\��B�I������Â̂�����ɂ��ẮA1987�N�ȗ��A5�N���Ɓi����̂�7�N�j�A4���ɓn���Ĉ�ʍ����E��Õ����]���҂ւ̈ӎ������ƁA����Ɋ�Â��������d�˂��Ă����B����̕��́A2008�N3���Ɏ��{���������i�q�̐��F1��4402�l�j�܂��Ă܂Ƃ߂����́B �@�������ʂ��A���k��́A(1)�I������ÂɊւ��銳�ҁE�Ƒ��A��Õ����]���҂̏��i���̉����A(2)�ɘa�P�A��ł����̊g��A�ɘa�P�A�Ɋւ���Õ����]���҂ɂ����鐳�����m���̕��y�A�u�ɘa�P�A�������}���邱�Ɓv�Ƃ̃C���[�W�̕��@�Ǝ��ÁE�ɘa�P�A�����s�ōs���u�p�������P�A�v�̐Z���A(3)���r���O�E�E�B���ƏI�����̂���������肷��ۂ̃v���Z�X�̏[���A(4)�Ƒ��P�A�E�O���[�t�P�A�̋c�_���i�A(5)���҂��ӎv��\���ł��Ȃ��A�܂��͔��f�ł��Ȃ��Ȃ����ɂ����锻�f��s�ғ��̂�����̌�����A�����̏I������Âɑ���S�̌���A�Ȃǂ̕K�v����B�����܂Ƃߌ���A�I������Â̂�����ɂ��Ĉ��������������s���A���ǂ��I������Â��������邽�߂̋�̓I�ȕ������̒���������悤�v�]�����B �@�������ʂ���́A�ȉ��̂悤�ȌX�������炩�ɂȂ����B �@ �I������Âɑ���S�͍����i80-96���j���A�������Âɂ��ĉƑ��Řb�����������Ƃ�����l�͔������x�i48-68���j�ł���A�\���ɘb�����������Ƃ�����l�͏��Ȃ��i3-7���j �A �������Âɂ��ĉƑ��Ƙb�����������Ă���l�̕����A�������Âɑ��ď��ɓI�ȌX���������� �B ���r���O�E�E�B���i���ʂɂ�鐶�O�̈ӎv�\���j�̖@�����ɂ��āA��ʍ����͖@�����ɔے�I�Ȉӌ���6���������A��t�E�Ō�E���͈ӌ������Ă��� �C �������ÂɊւ��āA51-67���̐l����t�Ɗ��҂̊Ԃŏ\���Șb���������s���Ă��Ȃ��ƍl���Ă��� �D ��Õ����]���҂̊ԂŁA�I������Ԃ̒�`�≄����Â̕s�J�n�A���~���Ɋւ���ꗥ�Ȕ��f��ɂ��ẮA�u�ڍׂȊ�����ׂ��v�Ƃ̈ӌ��Ɓu�ꗥ�Ȋ�ł͂Ȃ���ÁE�P�A�`�[�����\���Ɍ������ĕ��j�����肷��悢�v�Ƃ̈ӌ��œ��Ă��� �E �uWHO�������u�Ɏ��Ö@�v�ɂ��Ă悭�m���Ă����Õ����]���҂͏��Ȃ��i20-31���j�A�O���ɔ�ׂĂ�⌸�����Ă��� �@��c�̖`���A��J�וv�E�㐭�ǒ��́A�u�I������Âɂ��ẮA�����̊S�������A�l�̉��l�ς����l�����Ă���B�e�ՂɌ��_�邱�Ƃ̂ł��Ȃ������������A���J�ȂƂ��ẮA�d�v�Ȗ��Ƒ����A������I�����̂�����ɂ��āA�����̈ӎ��������s���Ȃ��猟�����d�˂Ă��������v�ƈ��A�B�r�㒼�ȁE�c��`�m��w��w����Ð���E�Ǘ��w���������́A�����u������ÂɊւ����ʎs���̈ӎ��ƈ⑰�̕]���v���o���A������ÂɊւ��A�a�@�Ŏ��S�������҂̈⑰�����̌��ʂƁA���n��ɂ������ʏZ���̈ӎ������̔�r���Љ�B�u��ʏZ�������҂̈⑰���A�Ƒ��̉�����Â̈ӌ���m���Ă����̂͑S�̂̔����ȉ��B������Âɂ��Ă͈⑰�̕����m��I�ł���A��t���ӌ����ƕ]�����銄�������������v�Ƃ��āA�u������Âɂ��Č�������ۂɂ́A��ʍ��������Ȃ��A�⑰�̑̌������Ƃ��d�v�v�Ǝw�E�����B �@����͗Y�E������w��w�@�@�w�����w�����ȋ����́A�u�I�����ɂ́A��G�c�ɕ����āA�~�}��Â̂悤�ɒZ���Ԃ̂��́A���Ȃǔ�r�I�����ɓn����́A����ɂ�鎾�a�Ȃǒ����ɓn����́A�Ƃ���3�敪������B���ꂼ��ɂ��Čʂ̋c�_���s���ƂƂ��ɁA���{��t�����{�~�}��w��E���{���w��E���{�V�N�a�w��ȂǁA�֘A����w��̃K�C�h���C�����r�������Ă͂ǂ����B�܂��A�ɘa�P�A�̏[���x�̎��Ԃ�A���i���̉����ɂ����ĕK�v�Ƃ���Ă�����̎�ށE�ʁA�O���[�t�P�A�̎���A�܂����r���O�E�E�B���ɂ��āA���ݎ��ۂɊ��҂ɋL�q���Ă�����Ă���a�@���ǂꂭ�炢����A�ǂ̂悤�Ȗ�肪���邩�A�ǂ̂悤�Ȍ`�Ŋ��p����Ă��邩�E���Ȃ����ȂǁA����ɂ������̓I����Ȃǂ����W���A�����ǂȂǂŋc�_��[�߂邱�Ƃ��]�܂����v�Ɨv�]�����B �@���̂ق��A�u�I������ÂɊւ�����i���̉����͏d�v�����A����ŁA��ÁE�Z�p�̍��x���E��剻�ɂ����i���̊g��͕K�R�B���ׂĂ̔��f�����Җ{�l�E�Ƒ��̑I���E����Ɉς˂��A���������悤�ɂȂ�ƁA���Ɋ�@�I�ɂ��銳�ҁE�Ƒ��ɁA�ߑ�ȕ��S�ɂȂ�͂��Ȃ����Ɗ뜜�����B���ނ̐\���E�葱���Ȃǂ����ł��c��Ȏ�ԂɂȂ邾�낤�v�i�ɓ����Ă��E���{��a�E���a�c�̋��c���\�j�A�u��������"�I����"�Ƃ������t�͓K�Ȃ̂��B�I�������Ȃ���������l�A��Q����������A����Ԃł����Ă����ɐ����Ă���l�͂��āA"�I����"�Ƃ������m�Ȏ��Ԃ�����킯�ł͂Ȃ��v�i�쓇�F��Y�E��䉝�f�N���j�b�N�@���j�A�Ȃǂ̈ӌ���������B m3.com�@2010�N10��28�� |
| �ɘa�P�A�l�ς��@�I�ׂ�H���A�A�Q�E�N�����Ԃ����R |
| �ɘa�P�A�l�ς��@�I�ׂ�H���A�A�Q�E�N�����Ԃ����R (1) �@�Ŏ�����ẪC���[�W�������ɘa�P�A���l�ς�肵�Ă���B�����P�W���ɃI�[�v���������{�̘a��s���a�@�E�ɘa�P�A�a���́u����Ɠ������҂���Ƀ����b�N�X���Ă��炤�������邱�Ƃ������v�ƁA�̒��ɂ���đI�ׂ鑽�l�ȐH����p�ӁB�N���E�A�Q���ԁA�Ƒ��̏o��������R�����A�y�b�g�̖ʉ���������Ă���Ƃ����B ����������l�b�g�� �@�ɘa�P�A�a���͋�a���̂Q�t���A�����z���A�P�U���ɂQ�Q�x�b�h��z�u�B�a�@�̃��j�z�[����W���s���N�F�ɐV�����A�e�������ԍ��ł͂Ȃ��Ԍ��t�ŋ�ʂ����B���������p�ӂ��A���C�͉Ƒ��Ɠ����悤�ɉƒ땗�C�ɋ߂��A�����������f�U�C�����B�C���^�[�l�b�g�����p�ł�����{������k�b���Ȃǂ��݂����B �@���Ɂu�H�ׂ邱�Ƃ�������͂ɂȂ�v�ƕa�@�H�ɗ͂����Ă���B�u�ɘa�P�A���ʐH�v�Ƃ��đ��a���̐H���ɔ�ׁA�e�i�����ʂɂ������ɁA�D���Ȃ��̂������ł��H�ׂ���悤�i����{�ɑ��₵���B���҂��H�ނ���������Œ������ł���B�u���Âɔ�ꂽ�Ƃ��ɐS�g�̏�Ԃ𐮂��Ă��炤���߁A���i�̐����ɋ߂Â���悤�S�����Ă���v�ƊŌ�t���̐�������݂���B���������A�C�f�A�ɂ͊��҂ւ̃A���P�[�g�����f����Ă���Ƃ����B �@�������͊Ŏ��Ƃ͂قږ������������Y�t�B�Y�Ȃő����̉Ƒ��Ɛڂ����l������̗ǂ��������A�u���҂����Ƒ��̋C�������ق����Ăق����v�ƕa�@���痊�܂ꂽ�Ƃ����B �@���a���ł͍R����܂̕���p�Ŗ��o���ς������A�オ���тꂽ�肷��ȂǐH�������ɂ����Ȃ������Ҍ����ɁA�������N���ڂ𗁂тĂ���u�P���H�i���w�Ö@�H�j�v��p�ӂ����B���҂ւ̃A���P�[�g����I�����Ă���c�q�A�T�C�_�[�A�݂��ȂǏ\����ނ�B���҂̑̒��ω��ɍ��킹���A���߂ׂ̍����T�[�r�X���s���Ă���B �ɘa�P�A�l�ς��@�I�ׂ�H���A�A�Q�E�N�����Ԃ����R (2) ���s����菜�� �@���������������҂��L���ɐ��������߂ɂ́u�Ǐ�R���g���[����_�I�ȕs������菜�����Ƃ��K�v�v�i���������E���a�@����Z���^�[���j�Ƃ��āA�R����܂Ȃǂ̕���p��ɘa�P�A�ɒʂ�����t��Ō�t�A�\�[�V�������[�J�[�炪�펞���k�ɂ������Ă���B �@���V����w��w���t�����V����@�̎R�����q�E���ÃZ���^�[�Ō�t���́u�ɘa�P�A�́A����̎��Â̐������ɐ��Ƃ���������ĕs������菜���Ƃ��납��n�܂�B�������A�Ƃ�����Ί��҂���͓��ɕ��������Ă��܂������ŁA�P�A������ɂ��Ă��܂��P�[�X������B�P�A�������Ǝv�킹�镵�͋C�Â���͏d�v���v�Ǝw�E����B �@���Ҏx���c�́u����Ƌ��ɐ������v�i���s�k��j�̕l�{���I����́u���҂̍s���𐧌����Ȃ��̂́A�Ǐ�R���g���[���Ɗ��҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����\�͂Ɏ��M������Ƃ������ƁB��Ɋ��҂̕��������Ă���Ă���Ƃ������S����������v�ƕ]�����Ă���B MSN�Y�o�j���[�X�@2010�N10��31�� |
|
ICU�̏I������Âɑ卷 �@���╶���C��t�̎p���Ȃǂ��e�� |
| �@���V���g����w�ċz����ȁE�~�}��w�Ȃ�J. Randall Curtis������́C�W�����Î��iICU�j�ɂ�����I������Â̍��ƁC��t�ƉƑ��̍l������p�����I������Âɋy�ڂ��e���ɂ��Č������C���̌��ʂ�Lancet�i2010:
376; 1347-1353�j�ɔ��\�����B��������́u��t�́g�^�ʂ�̎菇�h�ɂȂ肩�˂Ȃ������ێ����u�̎��O���̌���Ɋւ��ď\���ɒ��ӂ��ׂ����ƁC�܂��Տ���͐����ێ����u�̎��O���𔗂�{�݂���̈��͂��x�����C�����Ɋ��҂��]�܂Ȃ���Â��s�����Ƃ��Ȃ��悤���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��Ă���B �W�w�I�A�g�ɒx�� �@�~����Âɂ����Ċ��҂��ŐV�̐����ێ����Â���ꏊ��ICU�ł���B�~����Â͍��z�ő����̈�Î�����K�v�Ƃ��邪�C�d�Ăȑ�����s�S�������Ă��������ێ����邱�Ƃ��ł��闘�_������B�������C������ICU�̎��S�������͍����C�I������Â��p�ɂɍs����ꏊ�ł�����BICU�ł͐����ێ��ɏd�_��u�����߁C���̍����I������Â̒�����C�Տ���ɂƂ��ċ~���ƏI������Â̒��ɍs�����Ƃ͑傫�ȕ��S�ƂȂ��Ă���B �@ICU�̏I������Âɍ��������闝�R�Ƃ��Ă͏@���C�����CICU�̈�Ñ̐��C�I������Âɑ����t�̎p���C�����̏d�Ǔx�C�P�[�X�~�b�N�X���ށC�\��Ə�����QOL�Ɋւ����t�̗\���Ȃǂ̈Ⴂ����������B �@Lancet������Series of Critical Care�Ɍf�ڂ��ꂽ�_���ł́C�l���̍���ɂ��ICU�̏I������Â̎��v�͑��傷��Ƃ��Ă���B�č��ł͑S���S��5����1��ICU�Ŕ������Ă���C85�܂ł͔N��������Ă����̔䗦�͌������Ȃ��B���_���ł́u�Љ�ƍ��Ƃ͑��債���鍂��Ґl���C���ɐ���������������������L���鍂��҂ɓK�ȋ~�����Â����K�v������v�Əq�ׂĂ���B �@�I������Âƈ�Ã`�[���Ƃ̘A�g�ɂ͒n�捷������B�Ⴆ�C21�J���̏W�����Ð���1,961�l��Ώۂɍs��ꂽ�A���P�[�g�ł́C�u�Ƒ��̂��Ȃ����҂ɂ��ďI������Â̌����ɊŌ�t���܂߂�v�Ɠ�������t�͖k���ƒ�����62���ł������̂ɑ��C�쉢�ł�32���C���{�ł�39���C�u���W���ł�38���C�č��ł�29���ɂ����Ȃ������B�I������ÂɊւ��ďW�w�I�A�g���i��ł��Ȃ����Ƃ́CICU�œ����Տ���ɂ�����R���s���nj�Q�C���a�C�S�I�O����X�g���X�̑����Ɋ֘A���Ă���B �Ƒ��̊֗^�̒��x�ɂ��n�捷 �@���B17�J���C37��ICU�ōs��ꂽETHICUS�����ɂ��ƁC�I�����̈ӎv����Ɋւ���Ƒ��Ƃ̘b�������͓쉢�i47���j���k���i84���j�ƒ����i66���j�ň�ʉ����Ă����B�Ƒ��̊֗^�ɂ��Ă̓C���h��100���C���`��98���C���o�m����79���C�X�y�C����72������t�����X��44���܂ő傫�ȍ���������B �@Curtis������́u�I������ÂɊւ��āC��t�͌���Љ�ɂ����鑽�l���ƕ��G����F�����C�ɍ��킹�ăA�v���[�`����K�v������v�Əq�ׂĂ���B�������炪��Ă���ICU�ɂ�����ӎv����A�v���[�`�ł́C�܂���t���\���]������B���ɁC�Ƒ��̖�����]�����C����2�i�K�Ɋ�Â��čŏI�I�Ȏ��g�ݕ������߂�B��t�͊��҂�Ƒ��Ƌ����ňӎv������s�����C���̍ہC���҂̏�Ƒ��̍D�݂ɍ��킹�ďC�����ׂ��ł���B �@��������́CICU��Ã`�[���Ɗ��҉Ƒ��Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����𐬌�������v�f�Ƃ��āi1�j���I�Șb�������̏���m�ۂ���i2�j��t���Ƒ����玿�����i3�j���҂����̂ĂȂ����Ƃ��Ƒ��Ɋm��i4�j���Ҏ��g���D�ގ��ÂƉ��l�ς��d������?�Ƃ������_�������Ă���B �@�����\�������l�����łȂ��CICU�̊��ґS���ɂƂ��ăR�~���j�P�[�V�����͏d�v�ł���B��������ɂ��ƁC�t���I�ł͂��邪�C�������т����҂̉Ƒ��̕����C���S�������҉Ƒ����ICU�Տ���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɖ������Ă��Ȃ��Ƃ����B �@���ɂ��e�����傫�� �@�����ێ��̊J�n�ۗ��܂��͒�~�Ɋւ��āC��t�̊Ԃōl�������قȂ�B���錤�����ʂɂ��ƁC�k���ł͎��S��47���������ێ��ۗ̕��܂��͒�~��ł��������C�쉢�ł�18���݂̂ł������B �@�@���͗ՏI�Ǝ��S�C�I������Âɑ���l���������E����d�v�Ȍ�����q�ŁC���ҁC�Ƒ��C�Տ���̏@�����W����B�Ⴆ��ETHICUS�����̌��ʂł́C��t�����_�����i81���j�C�M���V�������i78���j�C�C�X�������i63���j�̏ꍇ�C���Â͒�~�������p������邱�Ƃ��������C��t���J�g���b�N�i53���j�C�v���e�X�^���g�i49���j���邢�͖��@���i47���j�̏ꍇ�͒�~����邱�Ƃ������B�@���͂܂��C�L��������Ă���Ƃ͂����C���ՓI�ł͂Ȃ��]���̎�e�����肷��d�v�ȗv���ł�����B �@Curtis������́uICU�Ŕ������鎀�S���͑���������C�����ێ��̊J�n�ۗ��܂��͒�~�Ɋւ���d�v�Ȍ�����s����ŁC�L�v�ȐM���ł���G�r�f���X��w�j�����@���Ă���v�Ƃ��C�u�����������Â̒�~�́C���̎菇�Ɠ��l�̗Տ��菇�ł���B���̂悤�Ȍ����ICU�œ����Տ���ɂƂ��ă��[�`���̎菇�ƂȂ肤�邽�߁C�Տ���͐����ێ��̒�~�����߂�{�݂���̈��͂��x�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ێ����u���~���錈��̗��_�I��������ËL�^�Ɏc���ׂ��ł���v�Əq�ׂĂ���B �@��������́u�I������ÂɊւ��ĉ\�Ȍ��萢�E�I�Ɉӌ�����v������ɂ́C�����̖������ۓI�ȃt�H�[�����ŃI�[�v���Ɍ������Ă����K�v������B������n��ɂ����āC�i�̍����~����Â���邽�߂ɂ͗ϗ��I�Ȉӎv����C�W�w�I�`�[���ɂ�����R�~���j�P�[�V�����ƘA�g�C���҂Ƃ��̉Ƒ��Ƃ̌��ʓI�ȃR�~���j�P�[�V�����C�`�[�����Ɗ��ҁE�Ƒ��Ƃ̑Η��_�̊m�F�Ɖ����ɏd�_��u�����P�����s���ł���v�ƌ��_�t���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N12��2�� |
| ��t�̏@���ς��I������Âɉe�� |
| �@�����h����w��Clive Seale�����́C�Տ���̏@���ς��I������Âɗ^����e�����������Ƃ���C���_�_�҂��邢�͕s�m�_�҂̈�t�ł́C�I�����̒��Î��ÂȂǖ������҂̎����𑁂߂鎡�Â��s���\�����C�[���M�S������t�ɔ�ׂĖ�2�{�������Ƃ����������B�ڍׂ�Journal
of Medical Ethics�i2010; �I�����C���Łj�ɔ��\���ꂽ�B�܂��C�M�S�̂�����t�́C���Ö���g�p�������Âɂ��Ċ��҂Ƙb���������Ƃ����Ȃ����Ƃ������ꂽ�B ���߂̎��S�Ǘ������ �@Seale������́C�p���̈�t8,857�l��ΏۂɗX���ɂ��A���P�[�g�����{�����B�ΏۂƂȂ�����t�̐��ɂ́C���ɏI������Â̈ӎv����Ɍg��邱�Ƃ̑����_�o�Ȉ�C����҃P�A�C�ɘa�P�A�C�W�����ÁC�a�@����C��ʓ��Ȉ�ȂǕ��L���̈悪�܂܂ꂽ�B �@�A���P�[�g�ł́C���߂̎��S�Ǘ�ɂ��āC�Ŋ��܂Œ��Ö�������I�Ɏg�p�������ǂ����C�܂��C���̎��Â�I�����邱�ƂŎ��������܂�\�������邱�Ƃ����҂Ƙb�����������ǂ�����q�˂��B�����ɁC���g�̐M�▯�����C��t�ɂ�鎀�̂ق����C���邢�͈��y���ɑ���l�����������B���悻4,000�l�����i��42���j�C����3,000�l�����S�Ǘ�̎��Âɂ��ĕ����B �@�҂̂��������𔒐l��t����߂Ă���C�����̈�t�ł͐M�S�[���Ɖ����������ł��Ⴉ�����B��t�̐��ƐM�̊W������ƁC����҈�Â̐���͑��̐���Ɣ�ׂăq���Y�[���k��C�X�������k�������C�ɘa�P�A�̐���ɂ͑��̐���ɔ�ׂăL���X�g���k�C���l�������ق��C�u�M�S�[���v�Ǝ��F���Ă����t�������X���ɂ������B ���y����ق������̎^�ۂɂ��e�� �@���𑁂߂邱�Ƃ�\���C�܂��͂�����x�Ӑ}�����ӎv��������邩�ۂ��́C��t�̐��ɑ傫���W���Ă����B���������ӎv������s���Ɖ�����t�́C�ɘa�P�A����ɔ�ׂĕa�@����łق�10�{�������B �@�܂��C���ɂ�����炸�u�M�S���قƂ�ǂȂ��v�܂��́u�M�S���ɂ߂Ĕ����v�Ǝ��F���Ă����t�ł́C�������������𑁂߂邱�Ƃ�\���C�܂��͂�����x�Ӑ}�����ӎv������s���Ɖ��������u�M�S���ɂ߂Ă����v�܂��́u�M�S�����Ȃ肠���v�Ǝ��F�����t�̂ق�2�{�ł������B �@�ł��M�S�[����t�ł́C�I������Â̈ӎv����ɂ��Ċ��҂Ƙb�����������Ƃ�����Ɖ����l���C���̈�t�ɔ�ׂĒ����ɏ��Ȃ������B �@���������p���͎��̂ق�������y���̖@�����ɑ���x���ɂ����f����Ă���C�ɘa�P�A����ƐM�S�[����t�́C���łȔ��̎p�����������B �@�A�W�A�n�Ɣ��l�̈�t�ł́C���̂ق�������y���̖@�����ɑ��锽�̎p�����C���̖����O���[�v�ɔ�ׂĊɂ₩�ł������B �@Seale������́u��t�̉��l�ςƗՏ��ɂ�����ӎv����Ƃ̊W�ɂ��āC�F����[�߂�K�v������v�ƌ��_�t���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N12��9�� |
| �q�݂̂Ƃ�A���������@�������Ҏx���c�́A�I�����P�A�̎�����쐬 |
| �@��������̂��ߗ]��������ꂽ�q�ǂ��̐e�ɕK�v�ȐS�\���Ȃǂ�������������u���̎q�̂��߂ɂł��邱�Ɓ@�ɘa�P�A�̃K�C�h���C���v�����Ҏx���c�̂��쐬�A12��19���ɑ��s�ŊJ�����V���|�W�E���Ŕ��\����B�����āu���v�ɓ��ݍ������ł͗�̂Ȃ����q�́A�q�ǂ����݂Ƃ����Ƒ����ÊW�҂�̌o���̌����Ƃ���������e�ƂȂ��Ă���B �@�u����̎q��������v�i�����s�j�𒆐S�ɁA�������Â�ɘa�P�A�Ɍg����t�E�Ō�t�A�\�[�V�������[�J�[�A�{�싳�@�A�q�ǂ���S�������Ƒ��炪���͂��č�����B�u�q�ǂ��ɂƂ��Ă̎��v�u�e��Ƒ����ł��邱�Ɓv�u�ɂ݂̌y���v�u�^�[�~�i���i�I���j���̉߂������v�ȂǂP�O���ڂ��A�a�T���P�U�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��B �@��������̎q�ǂ��������鋰�|���ɁA���Y�����ɂ͂��낢��Ȍ`������Ɛ������Ă���B�q�ǂ��̎v���d����̂��őP�Ƃ��A���̂��߂ɉƑ��E��Ã`�[���E�w�Z�̋��t�炪�悭�b�������ׂ����Ǝw�E����B�a�C�̎q�ǂ��̂��傤�����ւ̔z���⎀�ʌ�̔ߒQ�i�O���[�t�j�ւ̌������������l������e���B �@�q�ǂ��̊ɘa�P�A�ɂ��āA��w����̌��L�Ȃǂ͏o�ł���Ă��邪�A�Ƒ��ɂ���Î҂ɂ��ʂ���S�\������₷�����������͂���܂łȂ������B�N��������A�S���̐����ی����A���ʎx���w�Z�Ȃǂɔz�z����B�Ƒ��ɂ͎��ÊJ�n���ɑ��̏��ނƈꏏ�Ɉ�t�����n���ȂǁA�V���b�N�ɂȂ�Ȃ��`�Ŏ�ɓ������悤�H�v����Ƃ����B �@�쐬�Ɍg���������̃\�[�V�������[�J�[�A������q����́u�q�ǂ����S���Ȃ�\�����l���邾���ō߈������o����e������B�q�ǂ��̎v���Ɋ��Y�����߁A�e���ÊW�҂��悭�b�������Ăق����v�Ƙb���B �@�V���|�͂P�X���ߌ�R���A���s�k�撆�V���T�̑�㍑�ۉ�c��ŁB�₢���킹�͓���i�O�R�E�T�W�Q�T�E�U�R�P�P�j�B m3.com�@2010�N12��19�� |
| �d�a�̎q�����z�X�s�X���@�Ó�̐X�̌Ö��ƂŊJ�݂� |
| �@��������Ȃǂ̏d���a�C���Q�Ɠ����q�ǂ��������h���ł���"�q�ǂ��̃z�X�s�X"��_�ސ쌧��钬�ɂQ�O�P�Q�N�H�ɊJ�݂��悤�ƁA�����Ȉ��m�o�n�@�l�̃����o�[�炪������i�߂Ă���B �@�Ó�̊C����]�ł��鍂��̌Ö��Ƃ��ė��p�����{�݂̖��̂́u�C�݂̂���X�v�B���������{�݂͓��{���Ƃ����A�^�c������c�@�l�̗����b��T������i�S�P�j�́u�q�ǂ����������R�ɐG��A������͂�{����ꏊ�ɂ������v�Ƙb���Ă���B �@�b�コ��ɂ��ƁA�q�ǂ��̃z�X�s�X�͏d���a�C�̎q��ƉƑ������S���ċx�{���邽�߂̈�ÃP�A�t���h���{�݂ŁA�p������e���ɍL�܂����B�������̓��{�ł́A�ݑ�Ő��b������Ƒ��ً͋}���Ȃǂ̎q�ǂ��̗a���悪�Ȃ���A�S�g�Ƃ��ɋx�܂�Ƃ����Ȃ��Ƃ����B �@���������Ƒ��̕��S���y������u��Q�̉Ɓv�����낤�ƁA�����ɘa�P�A�Ɏ��g�ލגJ�������H�����ەa�@�i�����j���@���炪���āB���̑�����l������ƂȂǂ̊��������Ă��铌���̂m�o�n�@�l�������̍b�コ�A�S���`���̎c�����Ö��ƂR������A�O�X�N�Ɏ{�݂��^�c������c�@�l�����������B �@����ƃG�C�Y�̊��҂������@�ł��Ȃ����{�̊ɘa�P�A�a���i�z�X�s�X�j�Ƃ͈Ⴂ�A�C�݂̂���X�ł͏d�Ǔx�ɂ�����炸���܂��܂ȏ�Ԃ̎q�������B�J��͊Ō�t���풓���A���ʂ͐e�q�ŔN�V���Ԓ��x�A�h���ł���{�݂�ڎw���B �@�u���͔_�Ƃ⋙�t�Ȃǒn���̐l�����͓I�Ȃ̂ŁA�~�J������n�����Ԃ�̌�����@������肽���v�ƍb�コ��B�X�ł̖ؓo���A�߂��̊C�݂ň�V�т��ł���B �@���݂́A�e�q�Ŕ��܂��h�����Ȃǂ̃o���A�t���[�H�����������A�̌��h�������ꒆ�B �@��N�P�Q����{�A�S�g�������Ȃ��Ȃ��a�������������q�����i�W�j��A��đ̌��h��������t�����ˎs�̐��������i�S�S�j�́u�a�C�̎q�����Ƒ��͉Ƃɂ����肪���B���������{�݂𑝂₵�Ăق����v�Ɗ��҂����B m3.com�@2011�N1��7�� |
| �H�̊�тÂ炷�H�v |
| �@���ʗ{��V�l�z�[���A�u���[�o���C�̊Ǘ��h�{�m�̒����L���q���u��̃`�L���g�}�g�N���[���ςł��v�ƃX�v�[���Ōy�����������B��̃W�����ƃt�H�A�O���̃��[�X�A�X���[�N�T�[�����A���ʒ��̃��[�X���胍���C�����c�c�B �@��N�P�Q���P�P���A�N���X�}�X�c���[������ꂽ�_�˃|�[�g�s�A�z�e���i�_�ˎs������j�̍L�ԁB�P�O��̊ۃe�[�u�����Ƒ��A�ꂪ���ꂼ��͂݁A�t�����`�̃t���R�[�X���y����ł����B �@�ꌩ�A���ʂ̃p�[�e�B�[�B�Ⴂ�́A�V����a�C�A��ᇂȂǂł̂ݍ��ޔ\�͂��ቺ�����u������Q�v�̐l�����̚����H�Ƃ������Ƃ��B �@�P�Ȃ闬���H�Ƃ͏����Ⴄ�B�Ƃ�݂������胀�[�X��ɂ����肵�āA��炩�������̒��ł�����x�ł܂�ɂȂ��Ă̂ݍ��߂�悤�H�v����Ă���B �@���Ɉ�Ñ�̖�艀�q�������z�e���Ƌ��͂��ĂQ�O�O�X�N�����悵�A����łQ�x�ځB���҂���u���܂ɂ͊O�H���v�Ƃ̐��������Ƃ����������Ƃ����B���{�݂̓����҂��K�ꂽ�B �@�p�[�L���\���a�ɔ����뚋���x���ɋꂵ��ł����{��Òj����i�W�P�j�́A�Ȃ̍K�q����i�V�U�j�ƂQ�l�ŖK�ꂽ�B���i�͂��܂��̂ݍ��߂��A�H�����c�����Ƃ��������A���̓��͊��H�B �@�u�y���݂ŁA�O������l�N�^�C�I�тɔY��ł�����ł���v�Ɩڂ��ׂ߂�K�q����B���̉��ʼnÒj����́u�l�N�^�C�Ȃ�Ē��߂�́A�v���Ԃ肾����ˁv�ƏƂꂽ�B �� �@�����H�́A�ߔN�i���𐋂��Ă���B����̈�̓~�L�T�[���������H�ނ��v�����̂悤�Ɍł߂�Q�����܂��B �@�_�ˎs���J���Q���ڂɂ�����ʗ{��V�l�z�[���u�u���[�o���C�v�ŃR���\���X�[�v�������������B�ȑO�Ȃ�~�L�T�[�ɂ�����ꂽ��X�[�v�ƍ������Ă������A�j���W���ƃL���x�c���Q�����܂Ōł߂�ꂽ��Ԃœ����Ă����B�m���ɂ��ꂼ��̖��������B �@�Ǘ��h�{�m�߂钆���L���q����i�R�T�j�́u�����������̂͌뚋��h���v�����_�B���͋C�����������̗v�f�ƍl���A�s����G�߂��Ƃɓ��ʂȃ��j���[�̐H�������B �@���H�ɂ����o�C�L���O�������Ƃ��̂��ƁB���i�͚����H�����H�ׂȂ����p�҂��A�z�^�e�̈��肸���ɁA�����Ǝ��L�����B��������͋����킹�����m�ƋV�B���Ӑ[����������B��������̂ݍ��ނ̂����͂����B�u�D���Ȃ��̂Ȃ�H�ׂ������A�H�ׂ���v�B�����M���Ȃ����B �� �@��ނ̍Ō�ɁA�{���s�������̔����a�@�̊ɘa�P�A�ȁi�z�X�s�X�j��K�˂��B�v�Q�O���B�����̂��҂��A�c���ꂽ�l���̎��Ԃ��߂����B �@�����A�e�������Ǘ��h�{�m���܂��A�̒������A���̓��̒��H�Ɨ[�H�̊�]���Ƃ�B���j���[�ɂ͒��邻�ꂼ��Q�P�i�̎ʐ^�����ԁB�r�t�e�L�₤�ȏd�A�������H��C�N�̓��Ă��Ȃǃ��X�g�����畉���̓��e���ւ�B�ǂ��I��ł���H�̒l�i�i�Q�U�O�~�j�͕ς��Ȃ��B��Ԑl�C�͓�Ă����ǂ������B �@���a�@�̉h�{�Ǘ��ȋZ�t���̓n�ӑP������i�T�S�j�́u���j���[�ɍڂ��Ă��Ȃ��������ޗ��̓s�����t���悤��������Ή�����v�Ƙb���B �@�Ƃ�킯�l�C�ŁA���ʂȗ����́A���������тƂ����B�T�����l���ۂ�J���s���o�N�^�[�ɂ��H���ł̐S�z������A�a�@�ł̒͂���߂č���Ȑ����B�����a�@�ł��ɘa�P�A�ȈȊO�̕a���ł͏o���Ȃ��B�k�̏ォ��A���R�[�����ł�����ŁA�R�O���ȓ��ɐH�ׂĂ��炤�B �@���N�̏t��A�S���H�~���o���A�ӂ�������ł����V�O��̑咰���҂̒j���������B�u���������сA�H�ׂ܂��v�B�n�ӂ���̒�Ăɒj���̊�F���ς��Ɩ��邭�Ȃ����B�u���������v�ƐH�ׂ�p�ɁA�ȂƑ��q���܂��B�P�J����ɑ��E����ԍۂ܂ŁA�H�������y����ł����Ƃ����B �@�u�����������o�����H�����A���҂���̐l���̍Ō�̐H���ɂȂ�B�o�������̂��Ƃ��������B������Ȃ��悤�Ɂv �A�T�q�E�R���@2011�N1��7�� |
| ����ł݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ�!?�@��p�A��Ìn���w�Z�Ɂu���S�̌��J���L�������v���J�� |
| �@����ŏ��߂Ė��̑�����m��I�@��p�m������Ȋw�Z�i�ȉ��m�����j�͐��E�ŏ��߂Ď��S�̌��J���L���������J�݂��A12��8���Ɍ��J���\����s�����B�w���͎��ۂɈ⌾��������A�����A�o���A�������̎��S�̃v���Z�X��̌����邱�Ƃ��ł���B �@�ɂ��ƁA�m������2009�N�ɐE�Ɛ��N���X�Ƀ��C�t�P�A���Ɗw�Ȃ�ݒu���A2010�N�A��p���畔�i���ȏȂɑ����j����⏕��500����p�h���i��1400���~�j���A�u���V�������w�Z���^�[�v��ݗ������B�Z���^�[�ł̓O���[�t�P�A�A�I�����P�A�A�e��֏ꓙ�̐�勳���ȊO�ɁA10�̓����������ݒu����Ă��鎀�S�̌���������A�w���͊��S�Ȏ��S�̃v���Z�X��̌����邱�Ƃ��ł���B �@�m����ꃉ�C�t�P�A���Ɗw�ȏ�����緒B�\���ɂ��ƁA���S�̌��J���L�������͂܂��������瓱���Ƃ��āu���H�O����v���s���A���̌�A�w���͈⌾��������A���ɑ����ɒ��ւ��A��e���B�e���Ă��犻���ɓ���B�w�������̎w���ɂ��A���̂Ǝ����̐��U�ɕʂ�������A�{���̈�̂̂悤�ɑ��V�t�����g�̂��߂ɍs�������A�o���A�������̈�A�̃v���Z�X��̌�����B �@緒B�\���ɂ��ƁA�w�Z�����C�t�P�A���Ɗw�Ȃ�ݗ������ړI�́A�e���ʂŊ���ł��鑒�V�t�̈琬�ł���B�w���̊����̒��ł̑̌����Ԃ�10���قǂł����Ȃ����A�u�ԋ߂Ɏ��������A����̗���ɗ����čl���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�v�������B���҂�⑰���X�ɑ��d���v�����A���̉��l������̌����邱�ƂŁA���V�T�[�r�X�̌���ɂȂ����Ă����ƌ����B �@�w�������̗��ߎ��́A���S�̌��J���L�������͈�w�A�S���w�A�@���Ȃǂ̊p�x���玀�����߂邾���łȂ��A�u���̉��̈ӎ��v�Ƃ����ӎ��T�O�ɒB���邱�Ƃ��ł���ƌ����B���V�Ƃɏ]������҂͋V���������Ɏ���s�������łȂ��A�u���҂̊��o�v�d���邱�Ƃ��X�ɏd�v�Ȃ̂ł���B �@���S�̌��J���L�����������Ō�w�Ȃ̗т���́A�u�����ɓ��������̏u�ԁA��������̂��Ƃ��܂���萋���Ă��Ȃ����Ƃ��v���o���āA�������c�O�Ɏv�����v�ƌ��B�̌����I����āu�����v������A������1��1�b���ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv�����������B �@�܂��A�w�Z���́A�ډ��A���O�҂����S�̌��v���O�����ɎQ���ł���ƕ\�������A�����I�ɂ͒n��A�e��c�́A�X�ɂ͖��Ԋ�Ƃɂ܂ł��̑Ώۂ��L���A��葽���̐l�ɑ��Ƃ͈�����u���̂��̋���v���Ăق����Ƃ��Ă���B ���P�b�g�j���[�X24�i���j�@2011�N1��8�� |
| ���̂Ƃ����� |
| �@�u���R�Ȏ����v�ς��ӎ� �@�������߂��A�����߂��Ƃ킩������A�ǂ�Ȏ��Â�P�A���������B �@�����J���Ȃ��Q�O�O�W�N�A��ʂ̐l������ΏۂɎ��{���������ɂ��ƁA�������U�J���ȓ��ɔ����Ă���ꍇ�A�V�P���̐l��������Â��u�]�܂Ȃ��v�u�ǂ��炩�Ƃ����Ɩ]�܂Ȃ��v�Ɖ����B �@����Ŋ�]����̂́A�u��ɂ�a�炰��v���T�Q���ōő��B�u������Â𒆎~���āA���R�Ɏ������}��������v���Q�W���ŁA�����͂P�O�N�O�̓��l�̒�������{�������B �u���҂���@���̂܂܂Łv�ŏЉ����ӋI�q����́A�ǂɂ��h�{�⋋�Ƃ������[�u�����݁A���̉ƂŖS���Ȃ����B �@�X�O�N��ɂW�O���l�䂾���������̔N�Ԏ��S���́A�O�R�N�ɂP�O�O���l�����B�Q�O�Q�O�N��ɂ͂P�T�O���l��Ɛ��v����Ă���B �@��t�̑[�u�Ő������I��点��u���y���v��u�l�H�ċz����O���v�̎��Ⴊ�\�ʉ����A������I������Âɒ��ڂ��W�܂����B�ŋ߂́u���҂ɂƂ��āA�ǂ�ȍŊ����]�܂������v�ɏœ_���ڂ��Ă��Ă���B �u�I�����v�Ƃ͋�̓I�ɂǂ�ȏ�Ԃ������̂��A���͖��m�Ȓ�`�͂Ȃ��B�u�����v�ɂ��Ă��A���������ɂ�����̂��͂͂�����ƌ��܂��Ă��炸�A�l���̏I�����߂���c�_���{�i������̂͂��ꂩ��ɂȂ�B �@���J�Ȃ̐l�����ԓ��v�ɂ��ƁA���{�l���S���Ȃ�ꏊ�́A���Ă͈�Ë@�ւ�莩����������B���ꂪ�V�U�N�ȍ~�͋t�]�B�O�X�N�ɂ͈�Ë@�ւŖS���Ȃ����l���W�P���A����͂P�Q���������B���͂O�U�N�A�Q�S���ԑ̐��ʼn��f�����t�ւ̐f�Õ�V�����������u�ݑ�×{�x���f�Ï��v�̐��x�����A�ݑ�ւ̎x����i�߂Ă���B�����A�n��ɂ���Đf�Ï��̐��⎿�ɂ͂��������B �@�Ŋ����ƂŌ}���邽�߂̎x���̂����݂Ƃ��āA��t�̉��f��K��Ō�A�ꍇ�ɂ���Ă͉��ی��𗘗p�����K�������w���p�[�̃T�[�r�X�Ȃǂ�����B�I������ÂɊւ�����J���̍��k���N���ɂ܂Ƃ߂����́A��Âɉ����āA���҂̐������x���邵���݂��܂߂����̕��y���ۑ�ɂ������B �@���k������̒�����q�勳���́u�܂���Â╟���ɂ������l���A�I������Âɂ��Ă̐��m�Ȓm���������A�킩��₷���������邱�Ƃ��K�v�B��ʂ̐l���A�����ɂȂ��Ă���������ʼnƂʼn߂����邱�ƂȂǁA������[�߂Ăق����v�Ƙb���B �@�����I�����c�H�@�˘f���Ƒ� �@�E���̏Ǐ�łQ�O�P�O�N�P�O���ɎO�d�����̕a�@�ɓ��@�����W�V�̊}�Ԉ�j����́A������h�{�̕⋋�ł�����������悤�Ɍ����A�ꎞ�͑މ@�ւ̊��҂��������B�����A���@�S���ڂ̂P�V���ɂR�W�x���M���o���A���ꂩ��͘b���قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ����B �@����������̗ʂ́A�����łƂ��Ă�����肸���Ƒ��������B���̂��߈�j����͂�����݁A�z�����K�v�ɂȂ����B �u���͏I�����Ȃ̂��v �@���j�̖r����i�T�Q�j�́A�����Ă����B�ʏ�̒E���Ȃ�A�P�A�Q���̓_�H�ʼn���͂��B����͂����̒E���Ƃ͈Ⴄ���Ƃ��A��t�̖r����ɂ͂悭�킩���Ă����B �u�����������Ă���ꍇ�A�����[�u�͒f��v�B��j�����������O�w�����̎ʂ����A�S����ɓn���Ă����B�ł��A���܂����́u������f��v�����Ȃ̂��A�ǂ����B �@��j���w��������낤�Ǝv�������ڂ̂��������́A�O�X�N�V���A�Ȃƈꏏ�ɐX���̗F�l�v�Ȃ�K�˂��Ƃ��������B���N��̂��̒j���́A�]�[�ǂ̌��ǂłQ�N�ȏ�Q�����肾�����B�Ăт����Ă������͂Ȃ��A�@����ǂ�ʂ��ĉh�{�𑗂荞�܂�Ă����B �@��j����͂��̗����I���Ă����A�C���^�[�l�b�g�Œ��ׁA�w�������������B�����ɂƂ��Ă̍Ŋ��������ӎ������悤�������B �@�r����́A��j��������H�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��A�މ@���ĉƂŗ×{�ł���悤�A�݂Ɍ����J���ĉh�{�𑗂�u�݂낤�v���������Ă����B��j����̏�Ԃɍ��킹�A���ی��̕ύX�\���������B�u�Ŋ��͎���Łv���A��j����̊肢�������B �@�����A�e�͈̂��������B���@�U���ڂ̂P�O�N�P�O���P�X���A�����ُ�ɑ��܂�p�����o���B������������A�ӎ����͂����肵�Ȃ��Ȃ����B �@�r����̖����́A�����Ă����B �u�{���Ɂw�I���x�Ɣ[���ł����Ȃ�A���킸�w�����ɏ]���B�ł��A�w���������邱�ƂƁA�Ƒ����w�I�����x�ƔF�߂邱�Ƃ͕ʖ�肾�v�B�r����͂����l���Ă����B �u�v�������v �@�Q�P���ߑO�V������B�r�����̎U������Ƃɖ߂�ƁA���Ԃ̓d�b�������B�\�����ꂽ�����̎s�O�ǔԂ́A��j�����@����a�@�̂��̂������B �u�����A��������v �@�d�b���Ƃ�ƁA��͂��Ζ����̊Ō�t���炾�����B �@�ċz��~�̘A���@�Ŋ������� �@�Q�O�P�O�N�P�O���Q�P�����B�Îs�̊}�Ԗr����i�T�Q�j������̓d�b���Ƃ�ƁA�W�V�̕��A��j�����@����a�@�̊Ō�t���炾�����B �u��������̖������R�O���炢�ŁA�ċz���~�܂��Ă��܂��B���ꂳ��ɂ͘A�������Ȃ��̂ł����A�����ɗ��Ă��炦�܂����v �@�r����́u����͖������B����������Ȃ��v�B���̎����ԋ߂��ƁA���߂Ď��������B �@�������������߂����̑[�u�͈���Ȃ��B�r����́A��j����̊�]���L�������O�w�����̎ʂ���a�@�ɓn���Ă����B����ŁA�u�̉\��������Ȃ�A�l�H�ċz��𒅂��Ăق����v�Ɨ���ł������B �@���݂��̂ĂɎ��Ƃ̊O�ɏo�Ă��āA�a�@����̓d�b�ɏo���Ȃ�������i�W�T�j�̂Ƃ���ɁA�r���Ԃŗ������A�ꏏ�ɕa�@�ɍs�����ƂɂȂ����B���Ƃւ̓r���A�r����͂�������Ԃ��~�߂ĕ�ɓd�b���A���B �u�ċz��𒅂��邩�����Ȃ����A�a�@�Ŗ����Ă��邩���m��Ȃ��B���ԂȂ����Ԃɍ���ւ�A���ꂳ��̂ق�����w�{�l�̊�]������A�����Ȃ��Ă����x�Ɠ`���Ă����āv �@��ƍ������A�Q�l�ŕa�@�ցB���@����W���ڂ̒��������B�u���������ȁv�Ɩr�������ƁA��́u���������ˁv�Ɠ������B �@���Ƃ���T���قǂŁA�a�@�ɒ������B�����Ƃ������̃x�b�h�ŁA�ċz�ƐS�����~�܂�����j���Q�Ă����B�_�H�⓱�A�A�_�f�}�X�N�͂����܂܂������B�r�����̓������A��t�����S���m�F�����B �@�ߑO�W���P�O���B�����͔x���������B �@��́A��j����ƌ������ĂT�V�N�ڂ������B�v�ɂ͂����Ɛ����Ă��Ăق��������B�ł��A���@�̌㔼�͂�������A���o�āA�ꂵ�����������B���킢�����������B �@��t�̖r����́A�����Ɩ����������B�����A�w�������Ȃ�������\�\�B�����ƁA�ċz��𒅂��Ă������낤�B �@�����č���A�킩�������Ƃ�����B �@�Ƒ��Ƃ����̂́A�Ō�܂Ŋ�]���̂ĂȂ����̂ȂB�u�I�����v���Ǝ����ɂ́A���̎��Ԃ�������A�ƁB �@���g�̊��҂̉Ƒ��Ɉӌ����Ƃ��A�u������f�ł���ˁv�Ǝ��R�Ɍ��ɂł���悤�ɂȂ����B �@�����n���Ă��ꂽ���O�w�����́A���܂��r����̎茳�ɂ���B�����̂Ɏg�����p�\�R�����A���炭�͎��Ƃ̋��Ԃɂ��̂܂܁A�u���Ă������肾�B �@���i����b�������� �@�a�C�ʼn������߂��A�����������Ƃ��ɔ����āA���Âɂ��Ă̊�]�������Ă������ʂ����O�w�������B�u���r���O�E�C���v�i�k�v�j�Ƃ��Ă��B�l�����ς��A�o�^����߂��菑����������ł���B �@�悭�m���Ă���̂́A�P�X�V�U�N�ݗ��̓��{����������i�����ǁE�����j���n�߂��u�������̐錾���v�B������x�点�邽�߂̉����[�u��A������A����Ԃ����J���ȏ㑱�����ꍇ�̐����ێ���f����e�ŁA�{�l�������A�������{������ۊǂ��A�R�s�[���Ƒ���Ɏ����Ă��Ă��炤�B��P�Q���T��l���o�^���Ă���B���͔N�ԂQ��~�B �@���ۂ̈�Ì���ł́A�{�l���]�܂Ȃ��ߏ�Ȉ�Â�����A���Ăق������Â����Ȃ������肷�邱�Ƃ�����B���ʂ�����A����Ȏ��Ԃ��������\��������B �@��ʂ�Ώۂɂ��������J���Ȃ̂O�W�N�̈ӎ������ł́A�k�v������Ă������p����Ƃ����l���Ɏ^�������̂͂U�Q���B�P�O�N�O�̓��l�̒�������P�S�|�C���g���������O���t�B �@�Ǝ��̏�����p�ӂ���a�@���o�Ă����B �@�S���{�a�@����̏����̏ꍇ�A�A�t��o�ljh�{�ȂǘZ�̈�Ís�ׂɂ��āA��]����A���Ȃ���I�ԁB���������Q�Q�O�O�a�@�̎Q�l�ɂ��Ă��炤���߂ɍ�����B �@����������Ì����Z���^�[�i���m����{�s�j�̏����́A�{�l�����f�ł��Ȃ����Ɏ厡�オ���k���ׂ��u�㗝�l�v�L���A�I�������}�������ꏊ��I��ł��炤�̂��������B �@���H�����ەa�@�i�����s������j�̏����ł́A�u�l�H�ċz��A�i�S��~�������́j�S���}�b�T�[�W�ȂǍő���̎��Â���]����v�u�����⋋���s�킸�Ŋ����}�������v�Ȃǂ̌܂̒�����A�����̍l���ɍł��߂����ڂɃ}�������Ă��炤�B�ҍ����ɒu���Ă���B �@�����A�����͂��ꂼ��̕a�@�ɂ����銳�҂�Ώۂɂ��Ă��āA���ʂ��Ȃ��a�@�𗘗p���銳�҂͐ڂ���@��Ȃ��B���̂��߁A���݂���m��Ȃ��l�������B �@���ʂ͊��҂̎��Õ��j�ɂ��āA�Ƒ�����t�Ƙb�����������ɂ��Ȃ�B�Ƃ͂����A�{�l�̈ӎv���u���̎��v�ɓˑR������Ă��A�Ƒ��͌˘f�������m��Ȃ��B �@���H�����ەa�@�̂k�v��������я͕q�E�ɘa�P�A�Ȉ㒷�́u���ʂ͂����܂ŁA�{�l�̊�]��m�邽�߂̈��i�B�����ďI���A�ł͂Ȃ��A���i����Ƒ���Ɗ�]��b�������A�l����[�߂Ăق����v�Ƙb���B �A�T�q�E�R���@2011�N1��16,21,22,23�� |
| �q�ǂ��I������ÁF�{�l�̈ӎv���d�@�w��w�j�āA�u���Ò��~�����v���L |
| �@���{�����Ȋw��i�\������j�̗ϗ��ψ����ƕ���́A�d���a�C�₯���������q�ǂ��̏I������ÂɊւ���w�j�Ă��쐬�����B�N��ɂ�����炸�A�{�l�̋C������ӌ����ő�����d���邱�Ƃ������Ƃ��A���Ò��~�⍷���T�����������鎖�Ԃ�F�߂����A���j�����߂�ۂ̗��ӓ_��菇�������Ă���B �@�I������Â��߂����Ă͂O�V�N�Ɍ����J���Ȃ����Җ{�l�̈ӎv�������{�Ƃ���w�j�\�������A�q�ǂ��̃��[���͂Ȃ������B���w��͉�����ʂ̈ӌ�������ŔN���̐��������ڎw���B �@�w�j�ẮA��t��Ō�t��̈�Î҂��q�ǂ��ɕ�����₷���������A�q�ǂ��������̋C������ӌ������R�ɔ�������@����m�ۂ���ƂƂ��ɁA���e�i�ی�ҁj�͂��̈ӎv�d���Ď��Õ��j�����߂邱�Ƃ����߂Ă���B �@���Â̍����T����l�H�ċz��̎��O���Ȃǂ̎��Ò��~�ɂ��ẮA�q�ǂ��̍őP�̗��v�ɂ��Ȃ��ƍl������ꍇ�Ɂu��Ăł���v�Ɩ��L�����B�������A���e�ƈ�Î҂̔[�������܂ł̘b������������ߒ��ւ̑����̈�Î҂̎Q�������f�����̏��ʂւ̋L�^�|�|�Ȃǂ̓_�����ڂ�����B����ɋs�҂̗L���ɂ��āA�W�@�ւƋ��͂��Ċm�F����A�Ƃ��Ă���B �@�������A���Ò��~�E�����T���Ɣ��f�����́A�q�ǂ��̕a�C���Ԃ����҂ňႢ���傫�����Ƃ�w�i�ɁA���L����Ƌ@�B�I�Ȏ��Ò��~�̔��f���N�����˂Ȃ��Ƃ̗��R�Œ�߂Ȃ������B �@���w��͈�ʂ̈ӌ������߁A�Q���Q�U���ߌ�P�����A����c���[��L�O�z�[���i�����s�V�h��j�Ō��J���_����J���B�₢���킹�͊w����ǁi�O�R�E�R�W�P�W�E�O�O�X�P�j�B ���������������������������� �@����� �@���u�N��v�������������@����ɂ͍ٗʍL�� �@�x�R���ː��s�̕a�@�ŋN�����������҂̐l�H�ċz��O�����i�O�X�N�Ɉ�t�͕s�N�i�j���A�����J���Ȃ��O�V�N�ɂ܂Ƃ߂��I������Â̎w�j�́A��ɑ�l��ΏۂɌ������Ă����B����A�������߂Ȃ��܂܁A�W�����Î��ɂ���q�ǂ�������̂��������B�܂��A�O�W�N�ɍ��������ÃZ���^�[�i�����j�́A�Ƒ��̓��ӂĐS�x��~���\�z����鏬���R�O�l�̎��Ò��~�����{�����ƌ��\�B���������m�ۂ��郋�[�����K�v�ɂȂ��Ă����B �@���{�����Ȋw��͎q�ǂ��ɂƂ��āA�q�ϓI�ɂ��őP�Ƃ����鎡�Â̕ۏ��ڎw�����B�w�j�ẮA�q�ǂ��́u�C�����v�d���ĕ��j����̓����҂ɉ����A���e�A��Î҂��܂ފW�ґS�����b�������A�[���ł���ӌ��̈�v��ڎw���葱����_�����ڂ���Ă���B �@�q�ǂ��̈ӎv�̊m�F�@�́A�q�ǂ��̏I������Ẩۑ肾���A�w�j�Ă͔N��ɂ��Ă̐������͂��Ȃ������B�q�ǂ��̔��B��a��͈�l�ł͂Ȃ��A�ɉ����āu�P�[�X�E�o�C�E�P�[�X�v�ɑΉ����邱�Ƃ��q�ǂ��̍őP�̗��v�ɂȂ�Ƃ̔��f���炾�B�������R�ŁA�͂������Ƃ����q�ǂ��̎��Â̒��~�E�����T���̊����߂Ă��Ȃ��B���̌��ʁA�����̎d���Ȃnj���̍ٗʂɈς˂�ꂽ�_�������B �@�w�j�č쐬�̈Ӌ`�ɂ��āA�S���҂́u�q�ǂ��{�l�A���e�A��Î҂�������Ȃ��葱�����������v�Ƙb���B���w��w�j���ɏ��o�������Ƃ́A���肬��̔��f�𔗂��Ă�����Ì���ɂƂ��ĘN��ɂȂ�Ƃ݂��邪�A�����ɏ����Ȉ�̊Ԃɂ́u���ՂȎ��Ò��~�������炳�Ȃ��悤�ɂ��ׂ����v�Ƃ̐��͎c��B�w�j�Ă����������ɋc�_��[�߂邱�Ƃ����߂���B ����jp�@2011�N1��27�� |
|
�d�x�̔F�m�ǂɂ͊ɘa�P�A�� �u���I�A�V�X�v�ɉ������� |
| �@�d�x�̔F�m�NJ��҂͎����̏Ǐ���\���ɓ`���邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁C��t�����҂����҂̏�Ԃ�c�����ɂ����B�����ŁC�P������w�a�@�ɘa�P�A�Z���^�[�̘V�N���_�Ȉ�ł���Klaus Maria Perrar���m�́C�����������҂ɑ���P�A�ɂ��āu�����_�ł́C�F�m�ǂ͎����s�\�Ȏ����ł��邽�߁C�I�����ɂ͊ɘa�P�A���s���ׂ��ŁC���҂���ɂɊ����Ă���Ǐ�����ɂ߂āC���̏Ǐ��\�h�E�ɘa����ƂƂ��ɁC�s�v�Ȉ�w�I��������炷���Ƃ��ɂ߂ďd�v�ł���v�Ƒ�8��h�C�c�ɘa��Êw��c�Ŏw�E�����B �o�߂ƂƂ��Ɋ��҂̍l�����͕ς�� �@Perrar���m�ɂ��ƁC�F�m�NJ��҂́C�����̌o�߂ƂƂ��Ɏ��g�̕a�C�ɑ��銴�������ς���Ă���Ƃ����B�����i�K�ł͔]�@�\������ȂƂ�������C���̍ۂɎ��g�̒m�I�\�͂�����Ă��邱�ƂɋC�t���C�ꂵ�ފ��҂������B�������C�F�m�ǂ��i�s����ƁC�����̊��҂��K����������悤�ɂȂ�C���ɂ͔��ǑO�����������銳�҂�����B�܂�C�i�s����ɂ�C�����̊��҂��y�ϓI�ƂȂ�C���������N�Ŗ��͓I�ł���Ǝv���悤�ɂȂ�B�������C���̂悤�Ȍo�߂͏\���ȉ��Ԑ��������Ă���ꍇ�ɂ̂ݔF�߂���B �@�܂��C�����m�́u�i�s�ƂƂ��ɐV��������~�ςł��Ȃ��Ȃ�C���Ԃ̊T�O������Ă����B����ɔ����C���g�̐����̗L�����⎀�ɂ��Ă̒m��������Ɏ����Ă����v�Ɛ����B���ہC�����m�͂���܂łɁC�V�l�z�[���ɓ������Ă���d�x�̔F�m�NJ��҂��e�������e�̎��ɒ��ʂ�����ɁC�ꎞ�I�Ɏ�藐�����Ƃ͂����Ă��C�����Ɍ��̐����ɖ߂�l�q��ڂɂ��Ă���B �@�����m��́C����ɔ����d�v�����Ƃ��āu���҂����ǑO�Ƀ��r���O�E�B���Ȃǂ̌`�Ŏ������ӎv�\�����C����Ƃ����nj�ł��C������x���含���ۂ���Ă����Ԃł̈ӎv�\���̂ǂ���d���ׂ����v�Ƃ��������������Ă���B �@����C�u�F�m�ǂ����ׂē���Ɉ����̂͊ԈႢ�ł���v�Ƃ��w�E�B�F�m�ǂƂ����ƁC���Ǘ����ł������A���c�n�C�}�[�^�F�m�ǂ��v�������ׂ邪�C�炢�ϑz�⌶�o�Ȃǂ̐��_�Ǐ������Ƃ��郌���B���̌^�F�m�ǂȂǂ�����C���ꂼ��o�߂��قȂ�B�Ⴆ�C�A���c�n�C�}�[�^�ł͔F�m�\�͂����N�ɂ��킽�菙�X�ɒቺ���邪�C�܂�Ɍ�����N���C�c�t�F���g�E���R�u�a�ł͔F�m�ǂ͒��������C2�`3�N�Ŏ��Ɏ���B�܂��C�]���ǐ��̏ꍇ�́C�F�m�ǂ��i�K�I�Ɉ������C����������������Ƃ���������������C���̌^�ł͎��E���������Ƃ����B �@���݁C�F�m�ǂ̏I�����Ɋւ���f�[�^�͂قƂ�ǂȂ��B���Ҏ��g�̕a���Ɨ����������Ă������߁C��ɂ�������Ǐ�ɂ��Ēm�邱�Ƃ�����ŁC�܂������_�ł́C��ɂ̓x�����i�u�ɂ͕����邩������Ȃ����j�𑪒肷��L���ȋ@����Ȃ��C�������邵���Ȃ��B���̂��߁C�����m�́u����C�I�����O�ƏI�����ɂ�����F�m�ǂ̐f�f�@�����P����C����ɂ��\�オ���シ�邱�Ƃ��ɖ]�܂��v�Ƌ��������B �u���I�A�V�X�v�Ƃ��������� �@�h�C�c�ł͋ߔN�C�d�x�̔F�m�NJ��҂ɑ���V���ȃP�A�̌`�ԂƂ��āu���I�A�V�X�v�����݂��Ă���B�d�x�F�m�NJ��҂́C����ɂ��ӎv�a�ʂ��S���C���邢�͂قڕs�\�ŁC�Q������C�܂��͂قƂ�ǐg�̂������Ƃ��ł��Ȃ����߁C���x���ł������Ȃ�B�u���I�A�V�X�v�ł́C���������d�x�F�m�NJ��� 6�`8�l���J�[�e����ǂ̈ꕔ�Ŏd��ꂽ�啔���ŋ����������C�P�A�X�^�b�t��14���ԏ풓����B �@���݁C���̕]�����s���Ă��邪�C���ɔ��\���ꂽ�ɂ��ƁC���҂̒��ӗ͍͂��܂�C�h�{��Ԃ����P����C�؋ْ��Ɛ��_�I�ْ����ቺ����B���X�^�b�t�̖ڂ����҂ɓ͂��₷���C�ʏ�̎{�݂�薞�����������Ă����B�܂��C�Ƒ��͊��҂�a���邱�Ƃŕ��S���y���Ȃ����Ɗ����Ă���Ƃ����B����ɁC�����̒ǐՒ����ł́C���̂悤�Ȍ`�Ԃʼn��������҂̕������������邱�Ƃ��m�F����Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N1��27�� |
| �������Ò��~�V���̕a�@���o���@����Ȏq�ǂ��̊��� |
| �@�~���������������߂Ȃ��q�ǂ��̋~�}���҂ɁA����ʂ����炵����l�H�ċz���~�߂��肷��u�������Â̒��~�v���������Ƃ�����a�@�͂V���A����ʂ������葝�₳�Ȃ��Ȃǂ́u�����T���v�͂R�S�����o�������Ƃ̒������ʂ��A���T�ꍑ�������Ì����Z���^�[�����f�Õ�����̌����ǂ��Q�U���܂łɂ܂Ƃ߂��B �@���セ���������҂̉Ƒ��ɁA�I�����Ƃ��Ď��Ò��~�⍷���T���������\��������Ƃ�����t�́A�U�O���ȏゾ�����B �@�I�����̎q�ǂ��ɉ������Â𑱂���ƁA�q�ǂ��̑�����`���ꍇ������ƍl�����t������A�����ǂ́A���̈�[�����������錋�ʂƂ݂Ă���B �@�����ł́A���~�⍷���T���Ɋւ���@����w�j�Ȃǂ̌��I�V�X�e�����������߂鐺�������A���Â̑I���f�����Ì���̌˘f���������яオ�����B �@�����ǂ͂Q�O�O�X�N�A���{�����Ȋw��Ɠ��{�~�}��w��̖�X�T�O�̐��㌤�C�{�݂ɃA���P�[�g�B�S�X�W�{�݂�����������B �@�ߋ��R�N�ԂɁA�Տ��I�ɔ]���Ɣ��f�����P�T�Ζ����̎q�ǂ��������̂͂R�V���B�������Â̒��~�o���͂V���łT��ȏオ�T�{�݁A�����T���͂R�S���łP�O��ȏオ�Q�O�{�݂������B �����ƒm�肽���@�j���[�X�́u���t�v ���������i2007�N2��16���j�I�����̊��҂ɑ��A�l�H�ċz���l�H�S�x���u��������A�h�{�⋋������Ȃǐ����ێ��̂��߂̏��u���s�����ƁB���Â𒆎~����ۂ̔��f����Ë@�ւ̎葱�����߂��K�C�h���C���ɂ��āA�����J���Ȃ͍�N�X���^�i�P�j�^���҂̈ӎv���d����{�Ƃ���^�i�Q�j�^���Âɂ��Ċ��҂ƍ��ӂ������e��������^�i�R�j�^�厡�ゾ���łȂ����̈�t��Ō�t���܂ވ�Ã`�[�������Õ��j�����߂�\�Ȃǂ𒌂Ƃ������Ă����\�B���Ȃ̌�������Ă���ɋc�_�𑱂��Ă���B �������Ò��~�i2006�N6��15���j�l�H�ċz���h�{�⋋�Ȃǐ����ێ����u���܂߂����ׂĂ̎��Â��~�߂邱�ƂŁA�ŕ��̓��^�Ȃǂɂ��u�ϋɓI���y���v�Ƌ�ʂ��āu���ɓI���y���v�Ƃ�������B���R�Ȏ���]�ފ��҂������̈ӎv�Ŏ��Â����ۂ����ꍇ���u�������v�ƌĂԁB���C����y�������̉��l�n�ٔ����́u���錩���݂̂Ȃ��a�C�Ŏ���������A�Ƒ���ɂ�鐄����܂ߖ{�l�̈ӎv�����邱�Ɓv�Ȃǂ����e�����Ƃ��ċ��������A��Ì���ɂ͂���̓I�Ȏw�j�����߂鐺���o�Ă���B 47NEWS 2011�N2��25�� |
| ���{�݊��w��ŏI�����̊ɘa�P�A�ɂ��Č��� |
| ��ʈ��E�ޗǗю� �@�����Â̐i�W�͖ڊo�܂����C�V���Ȏ��Ö@�̓o�ꂾ���łȂ��ɘa�P�A�̗��O�����������y���C��Î҂̈ӎ������߂邱�ƂƂȂ����B����ŁC���Տ��ɂ����Ă̓X�^�b�t���̏[����V�X�e���̉��҂ȂnjX�̈�Ë@�ւɂ���Ă��������C���z�ƌ����Ƃ̊Ԃɑ傫�ȃM���b�v�����݂���B��83����{�݊��w���i3��3�`5���C�X���O��s�j�̓��ʊ��V���|�W�E���u���w�Ö@��̐�ڂȂ���Â̎��H�v�ł͂��������܂��C�ɘa��ÉȁC������O�ȁC���w�Ö@�ȁC���ꂼ��̐��I���ꂩ�痦���Ȉӌ������\���ꂽ�B���̒��ŁC��ʈ�ȑ�w���ۈ�ÃZ���^�[�ɘa��Éȋ����̓ޗǗю����́C����Ö@�Ɍg����ᇓ��Ȃ��o�Ċɘa�P�A�ɐ�]���Ă���o������C�u���w�Ö@��̈�ÂɃX���[�Y�Ɉڍs���邽�߂Ɂv�Ƒ肵�C�I�����̊ɘa�P�A�ɂ��Č������q�ׂ��B �I�����ւ̕s���\�u����ŊŎ��ꂽ���v��11�� �@�g�ɘa�P�A�́C����̐f�f������n�܂�h�Ƃ̗��O�͍L����Î҂ɕ��y���Ă������C�����ɂ͑����̂��҂����̉��b�ɂ�������Ă��Ȃ��B���ɁC�i�s����ł͂�����ϋɓI�Ȏ��Â��I������������Ȃ����������邪�C�����Őg�̒u������Ȃ����Ă��܂����҂����Ȃ��Ȃ��B�Ⴆ�u�]��6�J���ȓ��̖�����ԁv�Ƃ������ŁC�u�×{�ꏊ�v�Ƃ��Ď������]����҂�63.3���ɒB������C�u�Ŏ��̏�v�Ƃ��Ď������]����҂�10.9���Ɍ������邱�Ƃ�������Ă���i�����J����2007�N�x�����j�B �@���̎�ȗ��R�́u��삵�Ă����Ƒ��ɕ��S��������v�i79.5���j�C�u�a�}�ς����Ƃ��̑Ή����s���v�i54.1���j�ł���C�ɘa�P�A�ɂ������Î҂̎x�����s�\���ł��邱�Ƃ��������Ă���B �@�ޗǗю��́C���ÏI����̈�Â�ڂȂ��ڍs���邽�߂ɂ́C�܂��u���҂̕s�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƒi�����B �a�@�オ�������� �@��L�����ł����グ��ꂽ�悤�ɁC���ÏI����̈�ÁC���Ȃ킿�I�����̊ɘa�P�A������Ƃ��ẮC����C�n��̊ɘa�P�A�a���C�n��̕a�@�E�f�Ï��Ȃǂ�����B�ޗǗю��́C�����̎{�݂́u���҂���̏ɉ����ēK�ɑI�������ׂ��v�ł���ɂ�������炸�C����ł́g�I������h�ɂ͎����Ă��Ȃ��Ǝw�E���C���̗��R���������������B �@���҂̊�]�͈�l�ł͂Ȃ��B�u�Ō�܂Ŏ��Ìp���������v�Ƃ����l������C�u���S�Ȃ��Ƃʼn߂��������v�Ɗ�]����l������B���҂̊�]�ɉ������ɘa�P�A�̂��߂̃L�[�p�[�\���͕a�@��ł���Ƃ��C�����́u�i�����̈�ÐE�́j�������Ƃ��āC�a�@��̐s�͂��s���v�Ƌ��������B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N3��22�� |
| �z�X�s�X�F�����a�@�A�J�݂U�N�@�]���A���̐l�炵���@�������̊ɘa�P�A �@�X�^�b�t��ہA�S���₷ |
| �@���������a�@�i�{���s�������j�ɖ������҂�̐l���̍Ŋ����݂Ƃ�ɘa�P�A�a���i�z�X�s�X�j���J�݂���ĂU�N�B��t��Ō�t�A���w�Ö@�m�A��Ã\�[�V�������[�J�[�A��t�A�{�����e�B�A���`�[���ƂȂ��Ē�����킸�P�A�ɂ������Ă���B �@�u���҂ƉƑ��̐S����₷�̂��������̎d���v�Ɗ⍲���ގq�Ō�t���B�R������ÂȂǂ͂��Ȃ����A�ɂ݂�_�I�ȋ�ɂ���菜���A�]�����ł�����肻�̐l�炵���߂�����悤�x�����A�N�ԂP�Q�O�`�P�R�O�l�𑗂��Ă���B �@�u�Ō�t�̗͂������ł���悤�A��t�Ƙb���������d�˂܂��B�X�^�b�t���S����ɂ��Ċ��҂�������B�݂Ƃ����Ƒ��ƃX�^�b�t�̊W�͑����A�⑰���W�܂�N�P��̂�����ɂ͑����̐l���W�܂��Ďv���o����荇���܂��B��肪���͑傫���ł��v �@�����a�@�̃z�X�s�X�͑S���I�ɂ��������x���ɂ���B�{��z��@���́A��t���D���s�ŊJ���ꂽ�S���ɘa�P�A�w���ҍu�K�ɎQ�����A���̐����Ɂu�m�M�����Ă��v�Ƃ����B �@�U�N�ԁi�O�T�N�S���`�P�P�N�R�����j�Ŏ��ꂽ���҂͉��ׂQ�R�Q�R�T�l�B�u�J�ݓ����́g���ʏꏊ�h�Ǝv���Ă��܂������A�z�X�s�X���ǂ̂悤�ȏꏊ���������[�܂�A���҂��Ƒ����v�����ς���Ă��܂����v�Ƌ{��@���͘b���B �@�ŏ�K�̂P�P�K�ɍ����z�e���̂悤�ȃ��r�[����K�Ȍ��A�O�����h�s�A�m�̐����t����z�[���Ȃǂ�����A�H�����ʉ�����R�B�Â����͋C�݂͂�����Ȃ��B �@�O�X�N�X��������މ@���J��Ԃ��Ă��鏗���́u�̂�т�Ǝ��R�C�܂܂ɉ߂����Ă��܂��B������t��Ō�t�����Ă����̂ň��S���ĉ߂����܂��v�Ƙb���A����뉀�Ɏ������~�J����E�ݎ�����B ����jp�@2011�N4��18�� |
| �Ŋ���I�ԁ@�I������Â����O�w�� |
| �@�啪�s�ň�l��炵�̏����]����i�V�T�j�́A���N�����A��ⳂɃy���𑖂点��B�l���̍Ŋ����}�������ɂǂ�Ȉ�Â��������A���Â�̂��B �@�q�P�r���ʂȉ������Â͂��Ȃ��q�Q�r��ɂ̊ɘa�͍ő������Ăق����q�R�r�A����ԂɂȂ������̐����ێ����u���O���A�u�݂낤�v�i�����Ɍ����J���āA�݂Ƀ`���[�u�ʼnh�{�𑗂���@�j�͋��ۂ���\�\�B �@�S���������e���R�������A�P���͎����p�ɕۊǁA�Q���͋ߏ��ɏZ�ނQ�l�̑��q�ɓn���A�u���̎����������t�Ɍ����āv�Ɨ��ށB�������������́u���O�w�����v�ȂǂƌĂ��B �@�V�N�O�B��������̕v�́A�P�N���炸�̓��a�����̖��ɖS���Ȃ����B��������������˔�����A�Ђ��̒ɂ݂Ȃǂ�����A�Ŋ��̎����l����悤�ɂȂ����B �@�S�z�Ȃ̂��݂낤���B�ȑO�A�ߏ��̏������F�m�ǂŐH�ׂ��Ȃ��Ȃ�A�݂낤�ɂ��邩�ǂ����ʼnƑ��Ԃ̈ӌ��������ꂽ�A�ƕ������B �@�u�݂낤�ŕa�C���ǂ��Ȃ�Ȃ炢�����A�Q������ł����������Ă��邾���Ȃ�炢�B���R�Ȏ����}�������v�B����Ȏv���Ŏw�����������悤�ɂȂ����B �@�����s�`��̉�ЎВ����R�q(���Ƃ�)����i�T�S�j�̕�e�A�a�q����i���N�W�R�j�́A���A�a���������A��N�Q���ɉE����ؒf�����B�F�m�ǂ�����b�ňӎv�a�ʂł������߁A���R���a�C�̌��ʂ����������ƁA�u�����[�u�͖]�܂Ȃ��v�ƌ����B �@�U���ɕa�@�ň݂낤�����߂�ꂽ�ہA��̊�]��`���Ēf�������A��t�́u�������Ȃ��Ȃ�āA�]�ˎ��ザ�Ⴀ��܂����v�ƌ����A�������Ă��炦�Ȃ������B �@���ǁA��͈݂낤�̑���ɕ@����̃`���[�u�ʼnh�{�⋋�������A�ꂵ�����Ō��������B�₪�Ĕx���ɂȂ�A���V���ɖS���Ȃ����B �@���傤�ǂ��̂���A��Ã��l�T���X�u���������l����v�ŁA�u���̐������A���m�[�g�v��m�����B�I������ÂɊS������Î҂�ō��u�����炵���������ɂ��l�����v���A���R�L�q���̎��O�w�����Ƃ��čl�āA���͎s�̂���Ă���B �@���R����͂����ɂP�O�����w���A�F�l�ɂ��z�����B�����́u�����[�u�͖]�܂Ȃ��v�ȂǂƊ�]���������݁A�Ƒ��Ƃ�������b���������B �@�u�����Ƒ������������m�[�g������A��̎��ɖ𗧂Ă�ꂽ�̂Ɂv �@�I������Â̑傫�Ȗ��̈�́A�{�l�̊�]���s���ȏꍇ���唼���߂邱�Ƃ��B����Ȓ��A�Ŋ��̈�Â�����I�сA���͂ɓ`���Ă����u���O�w���v���A�������L�������B YOMIURI ONLINE�@2011�N5��23�� |
| �����P�Q�a�@���u�ɘa�P�A���C�v�@����t�ɋ`���� |
| �@���҂�̒ɂ݂Ɋ��Y�����t����Ă邽�߁A���Ɍ�������Z���^�[�i���Ύs�j�Ȃnj����S�P�Q�a�@�͖{�N�x����A���C���̎���t�Ɂu�ɘa�P�A���C�v��u���`���t�����B�`�����͑S�����Ƃ����B���ÂɌg����t�S���̎�u���������߂钆�A�ɘa�P�A�Z���Ɍ��������g�݂Ƃ��Ē��ڂ��ꂻ�����B �@�ɘa�P�A8 �����C�́A�����P�Q�a�@�Ŋw�ԗՏ����C��i����v�S�W�l�j�̏������C�Q�N�ڂ̕K�C�ȖڂƂ��A�{�N�x�͂R�V�l���A��������Z���^�[�ȂǂT�a�@�łU�����珇���J�����v���O�����ɎQ������B �@���C�ł́A��×p����̓��^��A�I�����Ɍ����Ǐ�ȂNJ�b�m�����w�Ԉ���A���҂̐��Ɏ����X�������������ł���悤�O���[�v���[�N���������B�܂��A������������m�����t���Ɗ��Җ���������u���[���v���[�v��ʂ��A���҂̗����̌�����B �@���͂Q�O�O�W�N�A��������i��{�v��Ɋ�Â��A�e�n�́u����f�ØA�g���_�a�@�v�Ɋɘa�P�A�̌��C��J�Â��`���t�����B�S���łP�O���l�Ƃ������邪��f�È�t�S���Ɏ�u���Ăъ|���邪�A����܂łɏC�������͖̂�Q���l�Ƃ����B �@��������Z���^�[�̐�������Y�@���́u���̓I�A���_�I�Ȓɂ݂������ł����t�́A����Ɍ��炸���҂��]�ވ�Â�ł���B��t�Ƃ��Ă̊�b���w�Ԏ����Ɍ��C����Ӌ`�͑傫���v�Ƃ��Ă���B �y�ɘa�P�A8 ���z�@���������������ƌ����������҂ƉƑ��́u�����̎��i�p�n�k�j�v���P��ڎw�����u�B���Ï���������s���Đi�߂�̂����z�Ƃ����B��ɂ��ɂ݂⌑�Ӂi�����j���̃R���g���[�������m��̔ߒQ�ւ̑Ώ����������}���鐸�_�I��ɂ̊ɘa�Ȃǂ��w���B �_�ːV��NEWS�@2011�N5��29�� |
|
�I�������҂̐ϋɓI���y���C��e�ł����ᇓ��Ȉ��10���ȉ� �؍��C��������Z���^�[�̌��� |
| �@����ȂǂŏI�������}���Ă���l���C�����ێ���ړI�Ƃ�����Ñ[�u�𒆎~���邩�C���邢�͂���ɓ��ݍ���ŐϋɓI���y����I�Ԃ��|����̈Ⴂ�ł��Ȃ蓚�����Ⴄ���Ƃ��\�z���������c�_����ɂ́C�܂����̈Ⴂ��F�����邱�Ƃ��d�v���B���̂��сC�؍�����3,000�l����ΏۂƂ����������ʂ��؍��E��������Z���^�[��Young Ho Yun����ɂ����ꂽ�B �@����ɂ��ƁC�u�����ێ���ړI�Ƃ������Áv�Ȃǂɑ��C��e�ł���Ɖ�����ᇓ��Ȉ�̊����͈�ʂ̐l�Ƃقړ������������C�u�ϋɓI���y���v�u��t�ɂ�鎩�E�v�́C10���ȉ��Ƃ��Ȃ�Ⴂ�����ɂƂǂ܂��Ă����B ���ҁC��ʎs���̖����ϋɓI���y�����u��e�ł���v �@Yun����ɂ��ƁC�؍��ł́C2009�N�ɍō��ق����������x�����锻���������܂ŁC�I������Â̂�����Ɋւ���Љ�S�̂ł̋c�_�͂��܂�s���Ă��Ȃ������Ƃ����B����C�a�@�Ŏ����}���邱�Ƃ������Ȃ��Ă���Ȃ��ŁC�I������ÂɊւ��錤���̂قƂ�ǂ͈��y���ieuthanasia�j���t�ɂ�鎩�E�iphysician-assisted suicide�j�������Ǝw�E�B �@�����ł��҂₻�̉Ƒ��ifamily caregiver�j�C��ᇓ��Ȉ�C��ʎs���炪�I�����̎��ɍۂ��C�ǂ̂悤�Ȉ�Â�{���ɕK�v�Ƃ��Ă��邩�C�ӎ��������s�����B �@����Z���^�[����ѓ�����16�̑����a�@�Őf�Â��Ă��邪�ҁi1,242�l�j�C���̉Ƒ��i1,289�l�j����ю�ᇓ��Ȉ�i303�l�j�C�������̓��v�K�C�h���C���Ɋ�Â����o���ꂽ��ʎs��1,006�l�������ΏۂƂȂ����B �@�����̌��ʁC�u���v�Ȑ����ێ����Â̒��~�v�u�ϋɓI���u�ɃR���g���[���v�ɂ��ẮC������̃O���[�v��90���O�オ��e�ł���Ɠ����Ă����B �@����C�u�ϋɓI���y���v����сu��t�ɂ�鎩�E�v�ɑ��Ă͂��Җ{�l�ƈ�ʎs���̖�����e�ł���Ɠ����Ă����̂ɑ��C���҉Ƒ��͂��ꂼ���40���ƒႭ�Ȃ�C��ᇓ��Ȉ�ł͂��ꂼ��10���ɓ͂��Ȃ����ʂƂȂ����B �@����̌��ʂɑ��C���y���ɑ����e���͉��Ăɔ��Ⴍ�C���̔w�i�ɂ͉��ĂƃA�W�A�̌l�C�Ƒ��Ԃ̈ӎv����V�X�e���̈Ⴂ������̂ł͂Ȃ����ƍl�@�B����C��ᇓ��Ȉオ���y���⎩�E�ɏ��ɓI�Ȃ̂́C���Ă̍��X�Ɠ��l�Ƃ��Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N5��31�� |
| �ɘa�P�A�̏[����ڎw���C����܂����c�_���|��83����{�݊��w�� |
| �@�����Â̐i�W�͖ڊo�܂����C�V���Ȏ��Ö@�̓o�ꂾ���łȂ��ɘa�P�A�̗��O�����������y���C��Î҂̈ӎ������߂邱�ƂƂȂ����B����ŁC���Տ��ɂ����Ă̓X�^�b�t���̏[����V�X�e���̉��҂ȂnjX�̈�Ë@�ւɂ���Ă��������C���z�ƌ����Ƃ̊Ԃɑ傫�ȃM���b�v�����݂���B�O��s�ŊJ���ꂽ��83����{�݊��w��k����O��s���a�@�i�X���j�E��c�D�@���l�̓��ʊ��V���|�W�E���u���w�Ö@��̐�ڂȂ���Â̎��H�v�k��������ʈ�ȑ�w���ۈ�ÃZ���^�[�ɘa��ÉȁE�ޗǗю������C����E�����ǃZ���^�[�s����a�@�E���X�؏�Y�@���l�ł͂��������܂��C�ɘa��ÉȁC������O�ȁC���w�Ö@�ȁC���ꂼ��̐��I���ꂩ�痦���Ȉӌ������\���ꂽ�B �`�ɘa��Éȁ` �I�����ɕs���\�u����ł݂Ƃ�ꂽ���v��11�� �g�ɘa�P�A�́C����̐f�f������n�܂�h�Ƃ̗��O�͍L����Î҂ɕ��y���Ă������C�����ɂ͑����̂��҂����̉��b�ɂ�������Ă��Ȃ��B�����̓ޗǗы����́C����Ö@�Ɍg����ᇓ��Ȃ��o�Ċɘa�P�A�ɐ�]���Ă���o������C�I�����̊ɘa�P�A�ɂ��āC���҂̕s�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ̌������q�ׂ��B �a�@�オ�������� �@�ߔN�ł́C����ɔ����g�̏Ǐ��_�Ǐ��a�炰�邽�߂̊ɘa�P�A�́C����̐f�f�����玡�Âƕ��s���čs���ׂ��Ƃ���Ă���B����ŁC���ɐi�s����ł͂�����ϋɓI�Ȏ��Â��I�����C�S�ʓI�Ȋɘa�P�A�ֈڍs����������Ȃ����������邪�C�ޗǗы����́C�����Őg�̒u������Ȃ����Ă��܂����҂����Ȃ��Ȃ��̂�����ł��邱�Ƃ��Љ���B �@�Ⴆ�u�]��6�J���ȓ��̖�����ԁv�Ƃ������ŁC�u�×{�ꏊ�v�Ƃ��Ď������]����҂�63.3���ɒB����ɂ�������炸�C�ŏI�I�ȁu�݂Ƃ�̏�v�Ƃ��Ď������]����҂�10.9���Ɍ������邱�Ƃ�������Ă���i�����J���ȕ���19�N�x�����j�B����ɁC���̎�ȗ��R�́u��삵�Ă����Ƒ��ɕ��S��������v�i79.5���j�C�u�a�}�ς����Ƃ��̑Ή����s���v�i54.1���j�ł���C�ϋɓI�Ȏ��Â��I��������C���Ȃ킿�I�����̊ɘa�P�A�ֈڍs���邽�߂̈�Î҂̎x�����s�\���ł��邱�Ƃ��������ꂽ�B �@�������́C�ɘa�P�A��ڂȂ��ڍs���邽�߂ɂ͂܂��C�u���҂̕s�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƒi�����B�I�����̊ɘa�P�A������Ƃ��ẮC�����n��̊ɘa�P�A�a���C�n��̕a�@�E�f�Ï��Ȃǂ�����Ƃ����_�ɐG��C�����̎{�݂͌X�̊��҂̏ɉ����ēK�ɑI�������ׂ��ł���ɂ�������炸�C����ł́g�I������h�ɂ͎����Ă��Ȃ����Ƃ��w�E�����B�������͂��̗��R�Ƃ��āC�u��t�i�a�@��j���C���ҁE�Ƒ��̈ӌ���c�����Ă��Ȃ��v�C�u��t�i���j���C�ݑ�łǂ̂悤�Ȉ�Â�ł���̂��𗝉����Ă��Ȃ��v�C�u��t�i���������j���C�R����ÏI����̊��҂̎���ɕK�������ϋɓI�ł͂Ȃ��v�Ȃǂ̖��_���������B �@���҂̒��ɂ͍Ō�܂Ŏ��Ìp���������Ƃ����l������C���S�Ȃ��Ƃʼn߂��������Ɗ�]����l������B�I�����ɂ����Ĉ�Âɋ��߂���̂͌X�̊��҂ɂ���ĈقȂ�B��Î҂ɂƂ��ďd�v�Ȃ��Ƃ́C���҂Ɏ��Ȍ���̋@���^���邱�ƂƁC���ꂼ��̊�]��c�����Ă������Ƃł���Ƃ����B �@�������́C���҂̊�]�ɉ������ɘa�P�A�̂��߂̃L�[�p�[�\���͕a�@��ł���Ƃ��C�u�Ĕ������Ƃ��C�R����Â��I������Ƃ��́C���҂̊�]���m�F����ǂ��@��v�Əq�ׁC�u�����̈�ÐE�̒������Ƃ��āC�a�@��̐s�͂��s���ł���v�Ƌ��������B �`������O�ȁ` �g���z�̊ɘa��Áh�ɐ^�̒S����� �@�킪���ł͂���f�Âɂ����ĊO�Ȉオ�O�Ȏ��ÈȊO�̋Ɩ����L���S���Ă����Ƃ����w�i������B��ʕa�@�∤�m������Z���^�[�ŏ�����O�Ȉ�Ƃ��đ����̂��Â��s���Ă������É���w������O�Ȃ̏����O�y�����́C���g�̌o���Ɨ����Ȍ����������āC������O�Ȉオ���݂����Â̏�łǂ̂悤�Ȗ������ʂ����Ă��邩���Љ���B �^�t�ȊO�Ȉ�ɂ����E�͂��� �@�����y�����͔��\�̖`���Łu���́C����Ȃ��Ƃ�b���ׂ��ł͂Ȃ��̂�������Ȃ��v�ƑO�u��������ŁC���܂��ɑS���̑����̕a�@�Łu�O�Ȉ�͎�p�ɉ����Đf�f�≻�w�Ö@��S���C�e�Ȃ̖�������~�}��M���̑Ή��܂ōL���S�����Ă���v�Ǝw�E�����B �@�Ⴆ�C���y�������Ζ����Ă����n�����j�s�s�̈�ʕa�@�ł́C���Ȃ̖��������Ȃ������K��1�l���������C�����ĒS�����҂݂̂Ƃ���s���Ă����Ƃ����B���R�C�x���̓����Ȃ��܂ܒʏ�Ζ��ɖ߂�@������Ȃ��Ȃ����߁C�p���Ɂu���삪�����ȁv�Ǝv������グ����O�Ȉオ2�l�C�������܂ܐQ�Ă������Ƃ��������Ƃ̂��Ƃł���B���҂��炷��u��p�����Ă��������t�ɁC�ɘa�P�A���܂߂čŌ�܂Őf�Ă��炢�����v�Ƃ����C���������邩������Ȃ����Ƃ�F�߂Ȃ�����C�u�O�Ȉ�ɂ���͂���E�͂���v�Əq�ׂ��B �@�܂��C���҂��݂Ƃ�����ɁC�O�Ȉ�͎厡��Ƃ��Ď��S�m�F�⎀�S�f�f���̍쐬�ȊO�ɁC����̏��u���̂̔����C�č��܂ōs�����C���Ґ��̑����ɔ����C�݂Ƃ�̌����������邽�ߕs���s�x�ŏA�J����������Ȃ������o�Ă���B�Ɩ��̎�̂ł���͂��̊O�Ȏ�p�ɉe�������˂Ȃ��ł���C���y�����́C���҂d�Ɍ����邱�Ƃ͐l�ԂƂ��ē��R�̍s�ׂ��Ǝv�����C�u�O�Ȉ�Ƃ��ėD�悷�ׂ����Ƃ͉����ƍl����悤�ɂȂ����v�Əq�ׂ��B �@��J�̓x�����ƊO�Ȏ�p�ɂ�����~�X�����ɂ́C�֘A����������Ă���B���y�����ɂ��ƁC�ߔN�ł͊��҂ւ̕��ׂ��Ⴂ���ߓ���������p�̌������}�����Ă��邪�C�J����p�Ɣ�ׂāu����ɏW���͂��K�v���v�ƌ����B�V�~�����[�^�[��p���������ł́C�����s���ɂ��G���[������ۑ�B���ɗv���鎞�Ԃ̉���������Ă���iLancet 1998; 352: 1191�j�C�O�Ȉオ�s���s�x�̂܂�p���s���f�����b�g�͊ʼn߂ł��Ȃ��Ƒi�����B �@���y�����͊ɘa�P�A�̗��O�ɂ��đ傢�Ɏ^������Ƃ�����ŁC�u���`�̊O�Ȉ�́C��͂��p�Ö@���ɂ߂�̂��ł��d�v�ȐӖ��v�Ǝw�E�B���̋Ɩ��ƕ��s���Ċ����ł���قǁC��p���I������Â��ȒP�ȓ��e�ł͂Ȃ��C�u���z�̊ɘa��Â̂��߂ɂ́C�^�̒S���肪�K�v�v�Ƃ��C�u�F���܂̕a�@�̊O�Ȉ���Ɂv�Ƃ܂Ƃ߂��B �`���w�Ö@�ȁ` �u�Ō�܂œ��a�������v�Ƃ������҂ɂ������� �@���݂̂���Ö@�́C�Տ������ɂ���ăG�r�f���X�̊m�����ꂽ���Ö@�������ƂȂ�C���҂����]���ɂ�����炸���ÏI���ƂȂ邱�Ƃ������B�����̍��X�؉@���́C����Ö@�̑����Ŋ��Ă����o������C���ݓ��{�ŏ��F����Ă��邪�Ö�����ɗp���邱�ƂŁu�Ō�܂Ŏ��Â𑱂���Ƃ����I���������肤��v�ƕ����B ���q�W�I���Ö�̈ێ����Âɉ\�� �@����E�����ǃZ���^�[�s����a�@�́C�����a�@�Ȃ���1975�N�ɉ��w�Ö@�Ȃ�ݒu�����a�@�ł���B���@�̉��w�Ö@�Ȃɂ́C�Z�J���h�I�s�j�I�������߂ė��@���銳�҂������Ƃ����B���X�؉@���́C2009�N�ɍs��ꂽ������w�a�@�ɂ�鎀���ϒ����ł��C�u�Ō�܂ŕa�C�Ɠ����v��I�����銄�����C���҂�81���ɑ��Ĉ�Î҂ł�19���ł��������ƂɐG��C��Î҂Ɗ��҂̎��_���قȂ邱�Ƃ͂��т��ю�������Ă���Ǝw�E�����B �@����ɁC���@���͂��̐��l�ɐG�ꂽ��ŁC���@�Z�J���h�I�s�j�I���O���ɂ�����ő�̎�f���R���C�u���Ò�R���ƌ���ꂽ�B�ɘa�������Ö@�͂Ȃ��̂��v�ƁC���Ö@�����߂Ă̗��@�ł��������Ƃ��Љ�k34���i219�ᒆ75��j�l�B����ɁC���̂���40���i75�ᒆ30��j�����ۂɂ͋~�����ÂƂ��ĕی��K�������w�Ö@���\�ł��������Ƃ���C�u��Î҂́C�W�����Â��Ȃ��Ȃ�ɘa�P�A�̂݁C�ƌ��_���Ă��܂��Ă悢�̂��v�Ƌ^��𓊂��������B �@���@���́C���q�W�I���Ö�̓o��ɂ��u�����߂��Ƃ��C��]���銳�҂ɂ͌p�����Ď��Â���L�p�����G�r�f���X�Ƃ��Đ�������\��������v�Ƃ��C�؏��s�\�咰���҂�Ώۂɍs��ꂽ2���̗Տ������iBRiTE�����CARIES�����j���Љ�B�������ł́C���Ƃ��������Ă����q�W�I���Ö���p�����^���邱�ƂŐ������Ԃ̉�����������\����������Ă���B�܂��C���@�ċz����Ȃōs�����x�����̌����ɂ����Ă����l�̌��ʂ�����ꂽ���Ƃ�����B �@���@���́u���w�Ö@���~�Ŕ[������銳�҂���͂���ł悢�B�������C�����ÂŎ���҂̂͂炢�Ƃ������҂��������̂��v�Ƃ��C�����������҂Ɏ�������L�ׂ�I�����Ƃ��ĕ��q�W�I���Ö�ւ̊��҂��q�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N6��16�� |
|
�u����҂̏I�����̈�Â���уP�A�v�Ɋւ���u����\���v�C�����Ă\ ���{�V�N��w��CQ��A��lj����ʃP�[�X�ɂ������^��ɓ����� |
| �@���{�V�N��w��́u����҂̏I�����̈�Â���уP�A�v�Ɋւ���g����\���h����10�N���o�����N�i2011�N�j�C���w���53��w�p�W��i6��15�`17���C�����s�j�̃V���|�W�E���u����҂̏I�����̈�Â���уP�A�F�w����\���x10���N�ɂ������āv�ʼn����Ă\�����B�V���Ȏ��݂Ƃ���Q��A��lj����C��Ì���Ő�����ʂ̃P�[�X�ɂ������^��ɓ����悤�Ƃ��Ă���B����C���w��̌����T�C�g��ʂ��Ċw�������R�����g���W���C�ŏI�Ă��܂Ƃ߂�Ƃ����B �u�őP�̈�Â���уP�A�v���錠����i��E���i���邽�߂�11�̗����\�� �@���w��ϗ��ψ���ψ����̔ѓ��ߎ��i�}�g��w��w�@�l�ԑ����Ȋw�����ȋ����j�ɂ��ƁC����̉����̈Ӑ}�́C����10�N�Ԃ̎Љ��̕ω���֘A�̈�̃K�C�h���C���̔��\���C������ɑ���������\���Ƃ��邱�Ƃł������B �@�����Ăł́C����\�����o���ړI���C���ׂĂ̐l���L����u�őP�̈�Â���уP�A�v���錠����i��E���i���邱�Ƃƒ�`�B���w���11�̗�������̂悤�ɋL���Ă���B ����1�D�N��ɂ�鍷�ʁi�G�C�W�Y���j�ɔ����� ����2�D�ƕ����d�����Â���уP�A ����3�D�{�l�̖��������� ����4�D�Ƒ��̃P�A���Ώۂ� ����5�D�`�[���ɂ���ÂƃP�A���K�{ ����6�D���̋����K�C�� ����7�D��Ë@�ւ�{�݂ł̌p���I�ȋc�_���K�v ����8�D�s�f�̐i���f������ ����9�D�ɘa��Â���уP�A�̕��y ����10�D��ÁE�������x�̃p���_�C���ϊ��� ����11. ���{�V�N��w��̖��� �@���ꂼ��̗���ɂ́u�_���v��������C�I������Â̎��Ԃɑ����đO��̗���\�����������ݍ����e�����荞�܂ꂽ�B����1�ł́C�u�őP�̈�Â���уP�A�v�������������ŁC��ᑑ��݂��܂ތo�ljh�{��C�ǐ؊J�C�l�H�ċz�푕���̓K���͐T�d�Ɍ��������ׂ��Ƃ��C���Â̍����T���⎡�Â���̓P�ނɂ����y���Ă���B �@�܂��C����6�u���̋����K�C�Ɂv�͍���̉����Ŗ��m�����ꂽ���ځB��ÁE�����E�҂ւ̋��炾���łȂ������ɑ���[�����K�v�ł���C�u�I�����ɂ�����őP�̈�Â���уP�A�v�ɂ��Ĕ��M���Ă������Ƃ́C���w��Љ�ɕ����u�ӔC�v�Ƃ��Ă���B Q��A�͊w��������W�C�����X�V���Ă��� �@�ѓ����ɂ��ƁC2001�N�ɔ��\���ꂽ����\���́u�I�����̒�`�v���}�X�R�~�ł��т��ш��p�����Ȃǘb����Ă��̂́C��̐����Ȃ��Ƃ����������̈ӌ������������Ƃ����B�����ō���̉����ł́C��Ì���Ő������Ï]���ҁC���ҁC�Ƒ��̋^��ɓ��{�V�N��w�����Q��A���lj�����邱�ƂɂȂ����B �@�����́C���̂悤�ȗ���������B �@�Ⴆ�C�������ֈ�Â��ے肷�邱�Ƃ́C���ҌX�̉��l�ς̑��d�Ɩ������Ȃ����Ƃ�������ɂ́C�u�i����2�̎�|�́j�I�����̈�Â�P�A�ł����Ă��C�P�Ɍo���Ȃǂɂ��ƂÂ��Ĝ��ӓI�ɑΉ����邱�Ƃ͋�����Ȃ��C�Ƃ�����Î҂̂���ׂ��p���������̂ł��B�ꍇ�ɂ���ẮC���҂�Ƒ��̐Ȃ�肢�����Ȃ��邽�߂ɑ�ֈ�Â������ꍇ������܂��v�ƉB �@�܂��C�{�l�����m��]��ł���̂ɁC�Ƒ������m��]�܂Ȃ��ꍇ�̑Ή��ɂ��Ắu�Ȃ��a����m�肽���̂��C�Ȃ��m�点�����Ȃ��̂������ꂼ�ꂩ�畷���o���K�v������܂��B�i�����j�a�����m�ɂ�����邲�Ƒ��̕s������菜���C�ŏI�I�ɂ͖{�l�̈ӂɓY����悤�w�͂���ׂ��ł��v�Ɠ����Ă���B �@����́C�����Ăw��̌����T�C�g�Ɍf�ڂ��C�w�������R�����g���W�B���̌��ʂ𗝎���Ɏ���C�ŏI�ł��܂Ƃ߂Č��\����BQ��A�ɂ��ẮC�w�������̎���𐏎���W���ėϗ��ψ���ŋc�_���C���ł����Ƃ��납�甭�\���Ă����\�肾�Ƃ����B �@�V���|�W�E���̍Ō�ɂ͎��^�������s��ꂽ�B��ꂩ��́u�őP�̈�ÂƊ��҂̈ӎv�͈قȂ�B����1�Ɨ���2���������ׂ邾���ł͕�����ɂ����v�C�u�ɘa��ÂɊւ��āC�ɂ݂̗\�h����ꂽ��ǂ����v�C�u��Ï��u�̌���ɂ������@���̖�肪����_�ɐG���ׂ��v�C�u���R�����܂߁C�l�̈ӎv�f�����Â������Ăق����B���_�̌��ǂ������邾���̗���\���ɂȂ�Ȃ��悤�Ɂv�Ȃǂ̈ӌ������X�ɏo���ꂽ�B �@�i��̐A���a�����i���É���w��w��������w����Z���^�[�����j�͂����������ӌ��ɑ��C�u�Ⴆ�C���R���ɂ͗ϗ��̖��łȂ��@�I��肪���݂��C���������X�e�[�g�����g�ł͂����Ȃ��B�w����̊F���܂ɂ͗~���s�����c�闧��\���ɂȂ邩������Ȃ��B���̂��߂ɂ��C�ʐ��̂��錻��̈�Â���^��_�������o���CQ��A��~�ς��C�����X�V���Ă������Ƃ��C�ۑ�̋��L�ɂȂ���̂ł͂Ȃ����v�ƒ�Ă����B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N6��23�� |
|
������Â��琶�����x�����Â� ��16����{�ɘa��Êw��J�� |
| �@��16���{�ɘa��Êw�7��29�|30���C�b��g�a���i�\�a�c�s�������a�@�j�̂��ƁC�����ۂ�|�p�����̊فi�D�y�s�j���ɂĊJ�Â��ꂽ�B�J�Ãe�[�}�́u���̂���������
���̂����Ȃ� �ɘa�P�A�\�\�a�@����n��ցv�B�܂��܂��������鍂��E�����Љ�̐i�W�̂Ȃ��ŁC��ÑS�̂��Ƃ炦�Ȃ����C�ɘa��Ẩʂ����ׂ��������l����ׂ����܂��܂ȃv���O�������p�ӂ��ꂽ�B QOL��ቺ������_�o��Q���u�ɂ̍������߂����� �@�����⒆���_�o�̒��ړI�ȑ����C������@�\�s�S�ɂ���Đ�����_�o��Q���u�ɂ́C�G�o�h���ŎܔM�ɂ�h���悤�Ȓɂ݁C�d���l�ɂȂnj���Ȓɂ݂�U������B�я��v�]��_�o�ɂⓜ�A�a���_�o�ǁC������ᇂ̐Ґ���_�o�p�ւ̐Z���Ȃǂ���\�I�����C�����q�l�ɂ��������ɂ�������̖����u�ɂł���C���҂�QOL�����ቺ�����邱�Ƃ���L���Ȏ��Ö@���͍�����Ă���B�V���|�W�E���u�_�o��Q���u�ɂ̃��J�j�Y������}�l�W�����g�܂Łv�i����������s���s���a�@�E�y���u�Y���C����ȑ�E��ؕ��j�ł́C�ߔN���炩�ɂȂ��Ă����_�o��Q���u�ɂ̃��J�j�Y����f�f�E���Âɂ��čŐV�̒m�������ꂽ�B �@�Óc�����i����w�@�j�́C�_�o��Q���u�ɂ̃��J�j�Y���ɂ��ĕ����B�_�o����Q�����ƃO���A�זE�̈�C�~�N���O���A������������C�זE�ԏ��`�B�����ł���P2X4��e�̂��ߏ�ɔ����B����ɂ��C�]�R���_�o�h�{���q�ł���BDNF�����o����C�Ɋo�j���[������Cl�|���ݏo���|���v�̔����ቺ�������N�����C�ʏ�}�����̐_�o�`�B�����ł���GABA���������Ƃ��č�p�B���̂悤�ȗ���ŐG�h�����u�ɂ������N�����Ƃ����B �@����Ɏ���́C�_�o��Q���u�ɂ̈ێ��ɏd�v�Ȗ������ʂ����A�X�g���T�C�g�̑��B�Ƀ~�N���O���A�̊��������֘A���Ă��邱�Ƃ��𖾁B����̑n��ɂ�����^�[�Q�b�g�ƂȂ�\�������������B�V���ȑn���i�߂����ŁC����͊����F��V�K��p���������������̗Տ��K�����߂����u�G�R�t�@�[�}�v��B���̈��Ƃ��āCSSRI�Ȃǂ̍R���_�o�����u�ɂ�}������Ƃ̌������ʂ��������B �@�Z�J���F���i����a�@�j�́C�_�o��Q���u�ɂ̐f�f�E�]���C�Ö@�ɂ��ĊT���B���́u�_�o��Q���u�Ɋ��҂͐l����7�����x�v�Ƃ����t�����X�̉u�w�������ʂ���C���{�ɂ����Ă����݊��҂�����\�������������B�Ö@�Ɋւ��ẮC���{�y�C���N���j�b�N�w��{�N7���ɔ��\���C�����쐬�ɂ���������u�_�o��Q���u�ɖÖ@�K�C�h���C���v���Љ�B�{�K�C�h���C���ł́C�_�o��Q���u�ɂ̑��I���ɂ͎O�n�̍R����ƃv���K�o�����i���i�� �����J�J�v�Z���j����������Ă���B���Ɍ��ʂ̍����I�s�I�C�h�͒����I���^�̈��S�����m�ۂ���Ă��Ȃ����߁C�����\�オ�����̊��҂ł͑�O�I���ƂȂ��Ă���B �@����Ɏ��́C�_�o��Q���u�ɂ��]�������q�l��R���Ƃ���Ă������Ƃɂ��Ă��G��C�I�s�I�C�h���L���ȏǗ������Ǝw�E�B���̏�ŁC�ڗp�������C�I�s�I�C�h�ƃv���K�o�����Ƃp����C�p��ȃX�N���[�j���O���s���ȂǁC�ˑ��̗\�h�ւ̏\���Ȕz�������߂��B �@����ߎq���iKKR�D�y��ÃZ���^�[�j�͊ɘa�P�A��̗��ꂩ��C�_�o��Q���u�ɂ̃}�l�W�����g�ɂ��Ĕ����B���́C�_�o��Q���u�ɂ̌����ɂ́C��p�≻�w�Ö@�C����̐Z���C����ɕ��������ȂǑ��ʓI�ȗv�f�����邽�߁C�������C�ɂ݂̕��ʁC�����C���x�Ȃǂ��x�b�h�T�C�h�ŏڍׂɒ��悵�C�o�ߊώ@��ӂ炸�C���E��ł������d�v�������������B����ɖÖ@�ɂ��ẮC���ՂȃI�s�I�C�h�̓��^�E���ʂɌx����炵�C���ɕ⏕��ƕ��p���Ȃ���T�d�ɊǗ����ׂ��Ɛ������B���ɕ⏕��ɂ��Ă�����p�͔������Ȃ����Ƃ���C�e��܂̃����b�g�E�f�����b�g���n�m���C���҂̔w�i�C�a�Ԃɉ��������^��S�����邱�Ƃ��Ăт������B �@��t�̍��쌳�F���i��ʈ�呍����ÃZ���^�[�j�́C�R�����ɂ�閖���_�o��Q�ɂ��āC�\�h�C���ÂƂ��ɗL���ȕ��@���m�����Ă��Ȃ����������B�������܂�1�ł���I�L�T���v���`���Ɋւ��ẮCCa/Mg���^�ɂ���Ė����_�o��Q�̔����p�x�̌��������҂���Ă�����̂́C�������������CONcePT trial�ł́u�咰�����FOLFOX�Ö@�̑t������ቺ������v�Ƃ̒��ԉ�͌��ʂɂ���Ď������~�ƂȂ�C���m�Ȍ��_�͏o�Ă��Ȃ��Əq�ׂ��B�܂����́C�]����Ƃ��ėp�����Ă���NCI-CTCAE��DEB-NTC�̈�v�����Ⴂ���ƁC�����_�o��Q�̔���������P���̕]���ɍ������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��C�]���ɓ������Ă͊��҂̎��o�Ǐ�̏d�v���������B��t�C�Ō�t�C��t�ɂ��J���t�@�����X�T�s���C�V�[�����X�Ȋɘa�P�A�ɓw�߂Ă���ƌ��B �����Љ�������ɏ��邩 �@�p�l���f�B�X�J�b�V�����u������E�����̎���ւ̏����v�i�������k�喼�_�����E�O�����j�ł́C���ꂩ��̎Љ�̕ω��Ɉ�Â��ǂ��Ή����C�]�����Ă������c�_���ꂽ�B �@�ݑ��Â̑������I���݂ł��鍕���v���i��Ö@�l�Вc�G�C��j�́C��������n���P�A�V�X�e�����C��ÁE���E�\�h�E�Z�܂��E�����x���T�[�r�X����ڂȂ������V�X�e���ƕ]���B�������x����24���ԃP�A�̐��ƁC�����a�@�E�L���f�Ï��E�����f�Ï��Ƃ̘A�g�������v�ƂȂ�Əq�ׂ��B����͈�Î҂̌��C�̏�C���E��̒��ԂÂ���̏�C�Z�������N�ɂ��Ċw�ԏ�Ƃ��āu�n���Ë����w�Z�v��ݗ��B�Z���ƈ�Ë@�ւ��o�����I�ɂ�����荇���V���ȃR�~���j�e�B�֊��Ҋ����������B �@���茪�����i������w�@��j�́C�l���\���̕ϗe����݂���Ð���̉ۑ���T���B���͂��ꂩ��̈�Â݂̍���Ƃ��āC�S�l�I�Ȉ�ÁC�������̂��̂��x�����ÁC��������Ŏ��̈�Âւ̓]�������߂��Ă���Ƌ����B����ɁC���҂̎��Ȍ���̏d�v�������܂��Ă��邱�ƂɐG��C���Ƃ̏�����x�����K�v���Ƃ��C��Â̐�ڂ��Ȃ�������S���ƒ��𐄐i���ׂ��ł͂Ȃ����ƒ�Ă����B �@�ғN�v���i����j�́C�s�s���ł̋}���ȍ���Ǝ��S�ґ������������C�ݑ��Â̕��y��B�����̈�t������ʐ���Ƃ��Ĉ���Ă��邱�ƁC��t1�l�ł͍ݑ��Â�S���Ȃ��Ƃ����F�������邱�ƁC�a�@�ƒn����Ȃ��K�ȃR�[�f�B�l�[�^�[�����Ȃ����ƁC���҂��a�@�ˑ��I�ł��邱�ƂȂǁC����̖��_���������B����܂��C���ݐ�t�����s�Ƌ����Ői�߂Ă��钴����Љ��̂܂��Â���v���W�F�N�g�i���v���W�F�N�g�j���Љ�B�ݑ��ÁE�Ō�E���T�[�r�X���_�̊J�݂�J�ƈ�ɑ���on the job�̌��C�v���O�����̊J���Ȃǂ��Љ���B �@�哇�L�ꎁ�i����������Ì����Z���^�[�j��"�a��ɑ��鋤��"�Ƃ����l�ԓI�ȉc�݂Ƃ��Ďn�܂�����ẤC�Z�p�̍��x���C�l���̊m���C�Љ�̋��剻�E���G���ɔ����Z�p�I�ȉc�݁C�Љ�I�c�݂ɕς���Ă������Ǝw�E�B������Љ���}�������C�ݑ��Â��j�ƂȂ�C��ÁE���E�������A�g����"�����C�x����"��Â����߂��Ă���ƁC��ÊE�̕ϊv�𑣂����B �T����w�E�V�� ��2941���@2011�N8��22�� |
|
�`�i�s�x����҂̏I������Á` �ĂƃJ�i�_�Ńp�^�[���قȂ� |
| �@�č����������iNCI�j�ی��Ȋw�E�o�ϊw�����Joan L. Warren���m��́u�č��̐i�s���x����̍���҂ł́C�J�i�_�E�I���^���I�B�̍���҂Ɣ�ׂĕa�@��~�}�f�Î��̎�f�͏��Ȃ����̂́C���w�Ö@���Ă��銄���͍����v�Ƃ��錤�����ʂ�Journal
of the National Cancer Institute�i2011; 103: 853-862�j�ɔ��\�����B �قȂ��Õی��V�X�e�� �@�č����J�i�_������҂�ΏۂƂ�����I��Õی����x����������Ă��邪�C�I������Â̕⏞�͈͈͂قȂ�B�č��ł͈��̊���������҂ɑ��Ă̓��f�B�P�A���z�X�s�X�P�A���J�o�[����B����C�J�i�_�ōł��l���̑����I���^���I�B�ł́C�č��̃z�X�s�X�ɑ�������v���O�����͂Ȃ����C�}�����̓��@�{�݂�O���C�ݑ��Âɂ��ɘa�P�A����Ă���B �@Warren���m��́C�č��̒n�悪��o�^�ł���SEER�iSurveillance�CEpidemiology and End Results�j�v���O�����ƃ��f�B�P�A�̃f�[�^�C�I���^���I�B�̂���o�^�f�[�^��p���ė����̏I������Â��r�����B �@1999�`2003�N�ɔזE�x����iNSCLC�j�Ŏ��S����65�Έȏ�̊��҂𒊏o���C���S�O5�J���Ԃ̕ی������f�[�^�́B���w�Ö@��~�}��Î��̎�f���C���@�C�f�f���玀�S�܂�6�J�������̒Z�����҂ƁC��6�J���ȏ�̒������҂̎x���Ö@���Ɋւ���f�[�^�����W�����B �@�����Ƃ��I������ÃT�[�r�X�̗��p���͍����C���S�O1�J���Ԃ̗��p���͓ˏo���Ă����B�I���^���I�B�̍���҂̓��@���Ƌ~�}�f�Î��̗��p���́C�č��̍���҂ɔ�ׂėL�ӂɍ��������B �J�i�_�ł͔������@�����S �@�I���^���I�B�ł́C�命���̒Z�����҂�����ōŊ����}�������Ɗ�]���Ă������C�ݑ����]����Z�����҂̂����C�@�����S����48.5���ƕč���20.4����2�{�ȏ㍂���Ƃ������ʂ������B �@���S�O��5�J���Ԃɉ��w�Ö@���Ă����č��̍���҂̊����́C�I���^���I�B�̍���҂ɔ�ׂėL�ӂɍ��������B �@�����O���[�v�́C���̒m���͕č��ł͈�t�͂��ϋɓI�Ȏ��Â��s���C���҂͂��W���I�Ȏ��Â��邱�Ƃ������Ƃ�������̌����𗠕t������̂��Ǝw�E���Ă���B �@�č��̍���҂ɂ̓z�X�s�X�T�[�r�X�𗘗p����Ƃ����I���������邪�C�I���^���I�B�̍���҂ɂ͂��ꂪ�Ȃ��BWarren���m��́u�I���^���I�B�ł̓z�X�s�X�T�[�r�X���Ȃ����Ƃ��C���@����~�}�f�Î��̎�f���Ɖ@�����S���̍����ɂȂ����Ă���\��������v�Ǝw�E���Ă���B �@����Ɂu�����̒m���́C��Ð������Ď҂�א��҂ɑ��ďI������Â̌�������ƂƂ��ɁC��ÃT�[�r�X��v���O�����݂̍���ɕϊv�𑣂����������ƂȂ邩������Ȃ��v�ƌ��_�t���Ă���B �ӎv����̎����オ���ʉۑ� �@�_�[�g�}�X��Ð���E�Տ��f�Ì������i�ăj���[�n���v�V���[�B���o�m���j��David Goodman���m�́C�����̕t���_�]�i2011; 103: 840-841�j�Łu�I������Â͕č��ƃJ�i�_�E�I���^���I�B�Ƃ̊Ԃ̈Ⴂ�����łȂ��C�č������邢�̓J�i�_�����ł��n��ɂ���ĈقȂ�v�Ɛ����B���̏�ŁC�u�d�v�Ȃ̂͊��҂����ꂼ��Ɍ����������l�Ȉ�Â���]���Ă������ŁC�����������͖����ꂪ�����Ƃ������Ƃ��B�Љ�S�ʂɂ����镽�ϓI�Ȋ��҂̊�]���C�X�̊��҂̊�]�ƃj�[�Y�����������̂��ƌ��ߕt���Ă��܂��ƁC�I������Â̎������コ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�v�ƃR�����g���Ă���B �@�����m�́u�ł��]�܂����`�̏I������ÂƂ́C���҂��ӎv����v���Z�X�ɎQ���ł���P�A���v�Ǝw�E�B�u��݂����Ƀz�X�s�X�P�A��ɘa�P�A�̗��p�������߂�悤�ȃV�X�e�����v��i�߂邱�Ƃ�������ł͂Ȃ��B�ϋɓI�Ȏ����I�P�A��x���Ö@�C�ɘa�P�A�Ȃnj��s�̃P�A�����҂��ǂ̂悤�Ɋ����Ă��邩�ɂ��ė�����[�߂�ƂƂ��ɁC���҂��\���Ȑ���������őI���ł���悤�ɁC�ӎv����̎������コ���邱�Ƃ��̗v�ł���v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N8��25�� |
|
�����g�����h��T�� �����w�@���E��A�g�ƍ��ӌ`���̎d�g�݂� |
| �@������Љ�̓������ڑO�ɔ����Ă���킪���ł́C����҂��߂����Ă��܂��܂Ȗ��ɒ��ʂ��Ă���C���}�ɑ��߂��Ă���B���n�r���e�[�V�����i�ȉ����n�r���j�̑Ή���މ@�܂ł̓���t���邱�ƁC�����Ċ�]����I�������}�������邽�߂̍��ӌ`���ȂǁC��Ï]���҂���Ƃ͂��ǂ���@���m�����ׂ��C����C���҂ւ̑Ή��ƌ����ɒǂ��Ă���B����́C����҂̖��ɏœ_�Ă��B�Ώ��@�̊m���╁�y���}����隋����Q�̃��n�r���Ɋւ���A�g�ƏI�����̑މ@�O�A�g�C���҂̈ӎv�\��������Ȃ����ۂ̍��ӌ`���ɂ��āC3�l�̐��Ƃɕ������B Transdisciplinaly Team Approach/������Q���n�r���ɂ������t�̖��� �� ���v �� �@����҂̔x���̑����͌뚋�̊֗^����������C������Q�ւ̑}����Ă���B����ȑ�w���n�r���e�[�V������w�̒����v�����́C������Q�̃��n�r���ɂ͈�t��Ō�t�C���w�Ö@�m�iPT�j�C��ƗÖ@�m�iOT�j�C���꒮�o�m�iST�j�Ȃǂ��܂��܂ȐE�킪�_�����z���ĘA�g����Transdisciplinaly Team Approach�iTTA�j���s���Ƒi����B��t�⎕�Ȉ�t��TTA�ł̂܂Ƃߖ��ɂȂ邩�C���[�_�[�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ă����̃X�^�b�t�̋Ɩ���K�ɕ]�����邱�Ƃ����߂���Ƃ��Ă���B �H�ׂ�s�ׂœ����閞���� �@������Q�̃��n�r���ɂ��ẮC����������w���ւ̋���@����Ȃ����߂ɁC�������̕������������Ȃ��B�Ⴆ�Ώd�x�̚�����Q���҂Ɉ�ᑂ��{�s������́C���n�r���ɐϋɓI�ł͂Ȃ���t�����Ȃ��Ȃ��Ƃ����B�������́u�h�{�����N���A�ł��Ă��C���n�r���ɂ���ĉ�����H�ׂ���悤�ɂȂ邩������Ȃ����C�����ł��H�ׂ�s�ׂ����������邱�Ƃ����҂̖������ɉe������͂��v�Ɛ����B �@������Q�̃��n�r���ł́C��t��Ō�t�ȊO�ɂ������̐��E�킪����I�ɂ�������Ă���B�������C�P�Ȃ錩����������𖧂ɍs���݂̂ł͕s�\���ŁC�������́u���E��Ԃő���Ȃ����Â�⊮������TTA���d�v�ɂȂ�v�Ƙb���B����ɁCTTA�̐��������Ƃ��āi1�j���ÖڕW�m�ɐݒ肷��i2�j�@�\�̋A���\�����\�ł���i3�j�e�\�����̖��������肳��đ��݂ɑ��d�������i4�j�K�i�ȃ��[�_�[������i5�j�m���ƋZ�\����̃V�X�e��������?���Ƃ�������B �@���@���҂̍ݑ����z�肵�ď�̏�ŕ����P���́C�ǂ̐E�킪�s���ׂ����Ƃ����^��Ɠ��l�ɁC������Q���Âɂ����E�����s���Ăȕ����͕K������B�ǂ̐E�킪�������邩�́C�ɉ����ă`�[�����Ō������邱�Ƃ��]�܂����B�������́CTTA�Ń��n�r��������ł���u���҂̏���ɉ������ŗǂ̎��Â��ł��C�`�[���\�����̔\�͂����サ������v�Ɛ�������B �@TTA�̗L�p���́C���{�ېH�E�������n�r���e�[�V�����w����{���������Ŏ����Ă���B������Q���F�߂���]���Ǐ�Q���҂�TTA�ɂ��ېH�@�\�Ö@�ʼn������124��i����Q�j�Ɣ����Q27���ΏۂɁC�ېH�����@�\�̕ω��������B �@����Q�Ōp�����Ē����ɎQ���ł���69���Տ��I�d�Ǔx���ނŌ���ƁC�����2.86�}1.13����ŏI��ɂ�4.62�}1.63�ւƗL�ӂɉ��P���Ă����B����C�����Q�͏���2.52�}1.29�C3�J����̕]���ł�2.81�}1.44�ƗL�ӂȕω��͂Ȃ������B�ېH���x���͉���Q������2.54�}1.41�C�ŏI��6.07�}2.42�ŗL�ӂɉ��P�����̂ɑ��C�����Q�͂��ꂼ��1.38�}0.86�C2.52�}2.27�ƗL�Ӎ��͔F�߂�ꂸ�CTTA�ɂ�����̗L���������炩�ƂȂ����B �@����w�ōs���Ă��郊�n�r�����҂ւ̋�̓I�ȉ����Ƃ��ẮC�������e�̕]���ɂ͒S�������ː��Z�t�����łȂ��CST��Ō�t�Ȃǂ�������Ă���B�������́C�w������̍s���͂��Ă���ST�̖����ɂ��āu��{�I�ɂ͚����@�\�̕]�����s������C�������ɂ����Ȃ��čׂ����w�����o�����肷�ׂ��v�ƍl���Ă���B�����P�����Ō�t��PT�COT�炪�⊮�������Ȃ�����H����BTTA�̍œK�Ȏ��{�̂��߂ɏd�v�ȃJ���t�@�����X��~�[�e�B���O��K�X�J�Â��Ă���B �v�Ɉʒu�����t�ɕK�v�Ȕ\�� �@���n�r���̂��߂ɂ��܂��܂ȐE�킪�Z������`�[���̒��ŁC��t�͂ǂ̂悤�Ȗ������ʂ����ׂ����B�������́u���ׂĂ���t�����炱�Ȃ��͓̂�����C�������s������C�X�^�b�t�Ɏw�����o�����肷��Ȃǃ��[�_�[�Ƃ��Ă̖������ʂ������ƂɂȂ�v�Ɛ�������B����ɁC�uTTA�ɂ�������t�⎕�Ȉ�t�͒P�ɑ��݂��邾���ł͈Ӗ����Ȃ��B�@�\�̋A���𐳊m�ɗ\���ł��C���Âɑ��閾�m�ȐӔC��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��t��������B �@������Q�̃��n�r������肴������n�߂Ă���C��������TTA�̏d�v���������Ă������C�X�^�b�t�̗�����̂͊ȒP�ł͂Ȃ������Ƃ����B�]���ɂȂ����@�_��p���邱�Ƃɑ���X�^�b�t�̔����͂�ނ����Ȃ����C�uTTA�����܂������Ȃ��v����1�ɂ́C��t�̎p��������v�Ǝw�E����B�������́u�w��t�Ƃ��̑��吨�x�Ƃ����ƑP�I�ȑԓx��ς��Ȃ���C�A�g�͂��܂������Ȃ��B��肪����Α����ɉ��P�_���w�E���邱�Ƃ͏d�v�����C�X�^�b�t�̍s�ׂ�ے肷�邾���łȂ��C������̏̎^���d�v�ł��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƍ����}�l�W�����g�ƃR�~���j�P�[�V�����\�͂����߂���Ƃ����B �@����C�������n�r���̐��オ���Ȃ��{�݂Ŕ��Ȃǂ̗���Ƃ���TTA�ɉ���炴������Ȃ���t�⎕�Ȉ�ɂ��ẮC�u�K���������[�_�[�Ƃ��Ă̗����S���K�v�͂Ȃ��v�Ƙb���B���̏ꍇ�́C�u�X�^�b�t�̈ӌ��Ɏ����X���Ă���w����^����Ƃ����X�^���X�ł������낤�v�Ƃ̌����������B�������C�u��t�̓X�^�b�t�Ɏ��Â�C����ɂ��Ă��C�悭������Ȃ�����ƚ����@�\�̕]�����K�ɂł��Ȃ��悤�ł́C�`�[���̓S�[�������������˂Ȃ��v�ƒ��ӂ𑣂��Ă���B �@�������ɂ��ƁC���n�r�����\���ɋ��炷���w���E��ȑ�w�́C����30�Z�قǂ����Ȃ��B������Љ�ڑO�ɔ��鍡�C������Q���͂��ߍ���҂ɓK�ȃ��n�r�����s�����t�̎��v���}���ɍ��܂��Ă���B���{�ېH�E�������n�r���e�[�V�����w�����{���n�r���e�[�V�����w��C�S�������n�r���e�[�V�����a���A�����c��ł̌��C�C�u���ȂǁC�w�Z�ȊO�ł��w�K�ł����݂͐����Ă���C���@��A�Ȉ����Ȉ�Ȃǂ̎Q���҂������Ă���B�������́u���n�r���Ȃ̈�t�̎�����́C���ȂƔ�ׂĂ������B�w�ׂ�@��͂�������̂ŁC��]�҂͂ł��邾���Q�����Ăق����v�ƌĂт����Ă���B ���z�̊Ŏ��́g�I�[�_�[���[�h�h�̔��z�� �ɘa�P�A�̎��Ⴉ��l���� �R�� ���q �� �@�ݑ��a�@�ȂNJŎ��̏ꏊ�͂��܂��܂��邪�C�킪���ł͈�ʓI�ȊŎ�肪���i����Ă��������ۂ߂Ȃ��B���V����w�Y���a�@����ɘa�P�A�Z���^�[�̎R�����q�Ō�t���́u���z�̊Ŏ��̓I�[�_�[���[�h�I�Ȕ��z�ōs���C����������ɂ͌o�ϓI�ȕ]���ƒn����̎��܂Ƃ߂��s���v�Ǝw�E����B�ɘa�P�A�̎��Ⴉ��C������Љ�ɔ������މ@�O�A�g�̃q���g��T�����B �ݑ�Ŏ��u�K�������ŗǂłȂ��v �@�R���t������N�܂ŋΖ����Ă�������w���V����@�ł́C�މ@�x���`�[���ƈ�ÃT�[�r�X�x���Z���^�[�C���ÃZ���^�[���X�N������g�݁C����҂₪�҂Ȃǂ̑މ@�x�����s���Ă���B�މ@�x���`�[���͌�1��a������f���C�S���X�^�b�t����މ@�����̑��k������C���ɂ͒��ڎx�����s�����肵�Ă���B����̓w�͂����ł͑Ή��ł��Ȃ��ɂ���C�@���̈�ØA�g�ψ���ʼn��P���@�Ȃǂ����B �@�a����f���̑��k������2009�N4���`10�N7����474������C����87�����Ǐ�̈�������s����Ȃǂ̗��R��1��̑��k��x���ł͉������Ȃ������B���@�ł͊��҂����@����ۂɁC�މ@�������������X�N���[�j���O���s���C�މ@�x���̌v���g�ݗ��ĂĂ���B2010�N2�`10���ɃX�N���[�j���O����1��966��ł͖�95���̊��҂��x����K�v�Ƃ����C��3���͕a����f�ÉȂł̑Ή��őމ@���C�`�[���̒��ڎx�����K�v�������̂�2�����x�������B �@���t�����`�[���ł̑މ@�x�����s���P�[�X�̑唼�͏I�����̊��҂ŁC�������̑��d���d������B���҂��a��𐳂����������C���g�ʼn߂��������l�����߂邱�Ƃ��ł���悤�C�ł��邾����������̏����s���Ă���B�܂��C�Ƒ��ɂ����l�ɓ��������C���҂ƉƑ�������̉߂�������b�������@�������悤���߂Ă���B���҂̑މ@�ɍۂ���Ɩ��A�g���n�߂�O�ɂ͊��҂�Ƒ����`���މ@��̉߂������Ƃ��̗��R���m�F���C�ݑ�P�A�ڍs����S�������Ë@�ւƏ��V�����Ƃ̘A�g�͌p������邱�Ƃ��`���C���҂�������s������菜���悤�ɂ��Ă���B �@�Ŏ��ɂ��āC���҂ƉƑ��̈ӌ����قȂ邱�Ƃ���������B���t���́u�ǂ����I�Ԃ��ƈӌ����킹��̂ł͂Ȃ��C�Ƒ������҂̎������d����C�����ɂȂ��悤����������v�Ƙb���B�����ē���ꂽ���҂ƉƑ��̊�]���@���̒S����ɓ`���Ęb�����킹�C���j����ւƓ����B�ݑ�ł̊Ŏ��͍���Ƃ��Đ������ꂽ���C���t���́u�K�������ݑ�ł̊Ŏ�肪�ŗǂ̑I�����ɂȂ�Ȃ����Ƃ�����v�ƍl���C�ݑ�肫�̐����͍s���Ă��Ȃ��B �@�ݑ�P�A�Ȃǂ��s����Ë@�ւƘA�g����a�@�̗���Ƃ��ẮC�u�A�g��̐��������Ɓg�S�[���h�̋��L���~�����v�Ƒi����B���ɍݑ�×{�x���f�Ï��̊Ŕ��f���Ă��Ă��C�������҂�����Ȃ��炷���ɕa�@�֓����Ԃ��{�݂����Ȃ��Ȃ��B �@�킪���̍ݑ�P�A�̌���ł́C�l�ނ̎����ɂ�炴������Ȃ����ʂ�����C�l�̈ٓ��Ŏ{�݂̗͗ʂ��傫�����E���ꂽ��C���҂̋��Z�悪2����Ì��O�ŏ��߂ĘA�g����{�݂��������肷��P�[�X������B���t���́u�A�g��̐��m�ȏ�W��Ă��Ȃ����ߎ{�݂܂��͒S���Ҍl�����ׂ邵���Ȃ��C����ł͂��܂�ɂ�������I�v�ƒQ���B �@���҂̑މ@�ɂ���Đf�ÁE�Ǘ��̃o�g���𑼎{�݂ɓn�����ƂɂȂ邪�C���҂̖]�݂͉��X�ɂ��ĕω�������̂ł���C�r���Ŋ�]���ς�邱�Ƃ�����B�u�o�g����n������Î҂ɂ͊��҂̊�]�͕ς����̂Ƃ����O��ŃS�[�����l���Ă����Ȃ��ƁC�S�[���̋��L�ɂ͌��ѕt���Ȃ��v�ƘA�g������i����B �@�ʂ̖��Ƃ��ẮC�Ƃ��炵�̏ꍇ�ɕa��Ǘ�����x���̐����m�F���邪�C�Ƒ������������C���_�����ǂ��Ă����肵���ꍇ�Ɉ�t��Ō�t�C�P�A�}�l�W���[�Ȃǂ��O���[�v�őΉ�����ݑ��Î{�݂̕�������ăT�[�r�X�̒��ł��邱�Ƃ���C�Ƒ��̎����I���S�����Ȃ��Ƃ����B���ҁE�Ƒ��ƒS����̈ӌ�����������P�[�X�����Ȃ��Ȃ��C�x���`�[���ɂ�鏕����x�����K�v�ƂȂ��Ă���B �I�[�_�[���[�h�I�ȃA�v���[�`�� �@���ꂼ��̊��ҁE�Ƒ��̃j�[�Y�ɉ������x���͌������Ȃ��B�a�@�Ɛf�Ï��ŗp����ݑ�p�̈�Ë@��i���j���قȂ�ꍇ�́C��������f�Ï��Ɉڂ��C�����Ŋ��̎�舵�����w��������ōݑ�Ɉڍs�����邱�Ƃ������B���҂�2����Ì��O�Ő�������Ȃ�C�o�b�N�x�b�h�̂��߂ɖK��f�Â��\�ȗL���f�Ï��Ɉ˗�����B��]�̊Ŏ�葜�͓����ł��C�Ŋ��ɂ��ǂ蒅���܂ł̓��̂�͐l�ɂ���đ傫���قȂ邱�Ƃ���C�R���t���́u�^�[�~�i���������I�[�_�[���[�h�I�ȃA�v���[�`�����߂���v�ƕ��͂���B �@�ݑ�ڍs�ɔ����A�g�͊ɘa�P�A�����łȂ��C����҈�Âł������̖����͂�ށB���t���́C�A�g�𐬌������邽�߂ɒS���ғ��m�̈ӎv�a�ʂ����ނ̂��Ƃ�ŏI��点���C�ł��邾���Ζʂ��d�b�ȂǂŒ��ژb���悤�ɂ��Ă���B�܂��u���҂�Ƒ��̎v���͏�ɕω�����Ƃ����O��Ŏ����X���C�A�g����ɐq�˂������Ƃ�����Η����ɕ����v���ƂŁC�s���̎��Ԃ𖢑R�ɖh���ł���Ƃ����B �@�^�[�~�i�����ɂ��銳�҂̍ݑ�ڍs�ɂ͏[�������x���̐����������Ȃ����C���������Ɩ��ɑ���]���͍����Ȃ��B���t���́u�A�g�Ɩ��ɔ�₷���Ԃ͒����C�Ō�T�}���[�ɐf�Õ�V�͕t���Ȃ��B�l�C���ł͂��܂ł��P�v�I�Ȏd�g�݂͂ł����C�o�ϓI�ȗ��t����K�v�Ƃ��Ă���v�Ƒi����B����ɁC�n��̘A�g���ׂ�����̏��ɂ͂��������C�u�����I�ɕK�v�ȏ������L����ɂ̓V�X�e�������K�v�v�Ƙb���B �����F�m�NJ��҂ւ�AHN�C��t9�����u����v ���c�^�̓��{�炵���I������Â� ��c �O�q �� �@�F�m�ǖ����Ōo���ێ悪����ƂȂ������҂ւ̐l�H�I�Ȑ����E�h�{�⋋�iArtificial Hydration and Nutrition�GAHN�j�����錈�f�ɂ��āC��t�����9��������Ɗ����Ă��邱�Ƃ��C���{�V�N��w��̒����ŕ��������B������S������������w��w�@�l���Љ�n�����ȃO���[�o��COE�u�����w�̓W�J�Ƒg�D���v���C�������̉�c�O�q���́C�p�Ď��̎������d�^�ł͂Ȃ��C���Ԃ������č��ӌ`���𐬂����{�炵���I������Â��K�v�Ǝw�E���Ă���B �u�K���Ȑl���̏I�����v�Ƃ����l�� �@��������2010�N�x�����J���ȘV�l�ی����N���i�����Ƃ̈�Ƃ��Ď��{�B��c���́u�w�����͉����ׂ����́x�ƍl����݂̂ł́C���҂͖{���ɖ]�ލŊ����}�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�ƍs���߂��������[�u�ɋ^��𓊂�������B�܂��C�������̕��������u�w������x�C�w�����Ȃ��x�̓_�ł͂Ȃ��C���Ƃ��������K���Ȑl���̏I�����ƂƂ炦�ċc�_���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƒi����B �@�����Ώۂ͓��{�V�N��w��̈�t���4,506�l�ŁC��N10�`11���ɗX���ɂ�閳�L���̎��L�����⎆�Ŏ��{���C�L����1,554�l�i����34.5���j�ł������B�҂̂����j����84���ŕ��ϔN���53.8�C���ϗՏ��o���N����27.2�N�B���Ȃ͑������Ɉ�ʓ��ȁC�V�N�ȁC�z����ȁC�_�o���ȁC�����f�ÉȂł������B�傽�錻�݂̋Ζ���͈�ʕa�@32���C��w�a�@18���C�f�Ï�17���C�×{�a��10���C�V�l�ی��{��6���������B �@�����̔F�m�NJ��҂Ƃ̂��������́C45��������I�ɂ���C36�����������Ƃ�������Ɠ������BAHN�����̈ӎv����ɂ���������o����68��������Ƃ����B���̌o���҂ɁC�ӎv����ɂǂ̒��x���������������q�˂��Ƃ���C�u���ɑ傫���v16���C�u������x�v46���C�u�����������v27���ŁC89�����Ȃ�炩�̓���������Ă��邱�Ƃ����������B �@����Ɗ����闝�R�i�����j�ɂ��ẮC�u�{�l�ӎv���s���Ȃ��Ɓv��73���ƍł����������B�����āC�o���ێ�̌p��������������̂́u�x���⒂���̊댯�����邽�߁v�Ƃ����̂�61���C�u�Ƒ��̈ӎv���s����ł���v��56���������B�܂��CAHN�������T���邱�Ƃɂ���51�����C�s�����Ƃ�33�����u�ϗ��I�ɖ�肪����v�Ɗ����C45�����u���f���������Ȃ��v���Ƃ��������B�����́uAHN�����ɍۂ��ẮC��͂荢��ȏ�ʂɒ��ʂ��Ă���Ƃ̗����Ȏv�����\��Ă���̂ł͂Ȃ����B������f�𔗂��Ă���Ƃ����̂��������낤�v�Ƃ̌����������C���f�ӔC�S�ʂ���t�ɋA���錻��Ɍx����炷�B �@�I�����̎����������Â̍����傫�����E���邪�C�ېH����Ȋ��҂̉Ƒ��Ɉ�ᑂ��u�قƂ�Ǐ�Ɏ����v�Ƃ�����t��53���ŁC�����_�H�����l�C�o�@�o�ǂ�44���������B����C�\�Ȍ���o���ێ�őΉ����CAHN�͍s��Ȃ��Ƃ����I�������قږ�����t��34���ŁC�ɉ����Ď����I������I�ԌX���ɂ������B �@��������AHN���������̂́C���~�Ɏ���P�[�X�����Ȃ��Ȃ��BAHN������̒��~�o����q�˂��Ƃ���C44�����u����v�Ɖ����B���̗��R�i�����j�ɂ́C������x���Ȃǂ̈�w�I���R��68���ƍő��ŁC43���͉Ƒ��̊�]�ɂ���Ē��~�����f�����o����L���Ă����B�ق��ɂ͈�t�Ƃ���AHN�p���͊��҂̋�ɂ������Ă��܂����Ƃ��璆�~�f�����̂�23���C��Ã`�[���Ƃ��Ă̔��f��21���������B�܂��CAHN�p�������҂̑�����N�Q����Ƃ��Ĉ�t�l�Œ��~�����߂��̂�14���C��Ã`�[���Ƃ��Ă�13���ɏ��CAHN����������҂̂��߂Ɋ������Ă������������ɂȂ����B �@�������AHN���~�ɑ��C�S�z�ޗ������Ȃ��Ȃ��B�o���҂�AHN���~�őz�肳������q�˂�ƁC33�����u�}�X�R�~�������v�Ɠ����C�����ɔ��W�����˂Ȃ������Ɍ��O�������Ă����B������29�����u�@�I�ɖ�肪����v�C21�����u�ϗ��I�ɖ�肪����v�ƍl���Ă����B ������AHN�����T���́u�ɘa�P�A�v �@AHN�͐H���̑�ւł��邽�߁C�����T���͉쎀�����邱�Ƃɑ�������ƍl�����Î҂�����B��������c���ɂ��ƁC�����̔F�m�NJ��҂�AHN�����Ȃ����Ƃ́C�����w�I�Ɋɘa�P�A�̍�p�������炷�Ǝw�E����_��������iPrintz 1988�CSullivan 1993�CAhronheim 1996�C�A�� 2000�j�B�����ɂ��ƁC���҂ɂƂ��ċ�ɂ̏��Ȃ��Ŋ��̂��߂ɂ́uAHN�͕s�v�v�ł���C�uAHN�̍����T���C���~�͗ϗ��I�ɑÓ��v�ł���B�����́uAHN��K�v�Ƃ��銳�҂̑唼�́C���Ԃ����قLjӎv�\����o���ێ悪�ł��Ȃ��Ȃ�B�����Ȃ�O�ɁC�l���̍Ŋ��̒i�K���ǂ̂悤�ɐ����������C���҂𒆐S�ɘb�������Ă������Ƃ���v�Ƙb���B �@�����́u���Җ{�l�ƉƑ����C�{�l�ɂƂ��čőP�̐l���̏I�������ɂ₩�ɓ����o����ӎv����̃K�C�h���C�����K�v�v�ƒ���B���ہC���{�V�N��w��̃��[�L���O�O���[�v�͊��Җ{�l�ƉƑ��̂��ǂ��I�����̑I�����菕������u�ӎv����v���Z�X�m�[�g�v�̎���ł��쐬���Ă���B�����́u��t�������ɍŊ��̑I����C���Ă��Ă͂����Ȃ��v�Əq�ׁC�I�����݂̍�����l�����Î҂̊w���ψ���ɁC���ґ���������ׂ��Ƃ̍l�����������B �@�I�����ɂ����鎩�����d�̎p���������č��ł́C��t�Ȃǐ��Ƃɂ͏������߂���x�ŁC���߂�͖̂{�l�����̑㗝�l�Ƃ����X��������Ƃ����B�������C�����́u���̕��@�͓��{�ɂ͂Ȃ��܂Ȃ��B���{�l�͈�Î҂ɂ��ꏏ�ɍl���Ă��炢�����Ƃ̎v�����������߁C���Ƃ��T�|�[�g����`�ō��c��i�߁C��������ƍ��ӂ��`������d�g�݂����߂���v�Ǝw�E���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N9��8�� |
| ��������Living Will�iLW�j�̕��y�^���͊��҂̐l�����d�̉^�� |
| ��c ���v�@�����a�@�@�\��B����Z���^�[�i�����s�j���_�@���^���{��������������� �@20���I�㔼�̈�w��Â̐i���͂߂��܂����C�l�H�ċz��C�l�H���́C���w�Ö@�C�h�{�⋋�Ȃǂ̉������Â��傢�ɔ��B���܂����B���̂��ߎ��錩���݂̎���ꂽ�I�����̊��҂��C���炩�Ɏ��R�����������Ƃ��������₩�Ȋ�]������������C�h�������[�u�ŋꂵ�ޏ������Ă��܂����B�u�ɑ�̐i���ɂ��C�������҂ł����̓I�ɂ݂̂��߂Ɉ��y�����l����K�v�͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�������{�̂��҂̈ꕔ���C���܂��ɒɂ݂ŋꂵ��ł��錻���͈�t�̑Ӗ��▢�n�ɂ����̂Ŕ߂������Ƃł��B �@�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�iIC�j���Ȃ��ƁC���������Â��ł��Ȃ���Ê��ƂȂ�C���y�������̔��������҂̎��Ȍ�����ŗD�悷������ɐi��ł���CLW��o�^������{����������̉����12��5��l�ɂȂ��Ă��܂��B����ł����{�����̐番��1�ɉ߂��܂���B �������Ƃ͉��ł����H �@�������Ƃ́C�s���Ŗ����̊��҂��{�l�̈ӎv�ɏ]���C�����ێ��[�u�ɂ�鉄�����Â�f��܂����C�ɂ݂̏����Ȃǂ̏\���Ȋɘa�P�A���C�l�Ƃ��Ă̑�����ۂ��C���炩�Ɏ��R���𐋂��邱�Ƃł��B���{����������́C���𑁂߂�ϋɓI���y���⎩�E�����Ƃ͍l���Ă��܂���B�l�H�ċz���l�H���͂Ȃǂ̉����[�u�̒��~�́C�ꌩ�����𑁂߂�s�ׂƂȂ蓾�邽�߁C��@�ƍl�����t�������C�������Ɍ����^���ł����Ă��C���~����̂����߂炤��t�͏��Ȃ�����܂���B������́C�����[�u�Ȃ��ɂ͐������Ȃ���Ԃ͏I�����ƍl���Ă���C�����[�u�̒��~�⍷���T���́C���҂ɑ�������]�̈ӎv��������C�E�l��ϋɓI���y���Ƃ͍��{�I�ɈقȂ�ƍl���܂��B �@���ɐA����Ԋ��҂ւ̑Ή������ł��B�����I�A����ԂƂ́C��w�I�ɂ͑J�����̈ӎ���Q�������C3�����ȏ�̎��Âɂ��S�炸�C�ӎv�̑a�ʁC���͉^���C���͐ېH���s�\�ŁC�A�ւ͎��֏�ԁC�ዅ�͓����Ă��ӎ��ł��Ȃ���Ԃɂ��邱�Ƃł����C���͔����Ă͂��Ȃ��������̂ł��B���{�ł́C�]������O���C��ʎ��́C���邢�͔]�̎�p��ȂǂɐA����ԂɊׂ�l�������C��a�@��3��l�C��ʈ�Î{�݂܂őS���I�ɂ݂��3���l�ʂ���Ɛ��肳��܂��B �@���{�w�p��c�����悤�Ȓ��������̐A����Ԋ��҂ɑ���Ή��́C��×ϗ���C�Љ�o�ϓI�ɂ������Ēʂ�ʏd�v�Ȗ��Ƃ��āC�u���ƈ�Ó��ʈψ���v��ݒu���Č������C1994�N�ɐA����Ԋ��҂̈�Ò��~��3�������o���܂����B�i1�j���҂��s�\�̏�Ԃɂ���C�i2�j�ӎ��̂��������ɁC���҂���������]�̈ӎv��\���C�i3�j�������Â̒��~�͒S���オ�s���C�ł����B�I������Â̑ΏۂɐA����Ԋ��҂�Ƃ肠���ė~�����̂ł��B���E��LW���݂Ă��C�w�ǂ��ׂĂ̍��łƂ肠���Ă��܂��B �������̖@�����^�� �@���{����������̍l�������߂��@���v�j�ẮC2003�N�̕�ɍ���͌����J����b�ɒ�o����܂����B���������@�ɂ́C���t��o�@�ĂƋc����o�@�Ă�2������C������͋c�����@���߂����܂����B���}�h�́u�������@�������l����c���A���v�i���R���Y�����j�������オ��܂����B�����ϗ������ޗ��@�́C�ϗ��ςɊ�Â��l����������ɂ킽��̂ŁC�����I���ӂ̌`������ł��B�c���A����2005�N���2007�N�܂�9��̋c������ŊW�c�̂���q�A�����O���s���܂����B���{��t��C���{�ٌ�m�A����C�S���{�a�@����C�e�@���c�́i�����C�L���X�g���C�_���Ȃǁj�C���{�~�}��w��Ȃǂ̏\���c�̂̑�\���o�Ȃ��đ��������@�Ɏ^�ۂ̈ӌ���q����܂����B �@�c���A�����S����c���Ɂu�������̑I���ɂ��āv�̃A���P�[�g���s���܂����B��111���ŁC�������u�����[�u�����Ȃ��I���v�C�u��t�̖ƐӁv��F�߂Ă��܂������C�Ƒ��̔��̏ꍇ�ɂ͓������O�����܂����B�����܂��ċc���A���́C2007�N�̋c�A����Łu�Վ���Ԃɂ����鉄���[�u���~�Ɋւ���@���v�j�v�Ă\���܂����B�A����Ԃɂ͐F�X��肪����̂ŊO����܂����B���̋c�A�̗Վ���Ԃł̖@���v�j�Ă̎�ȍ��q�́C�i1�j���҂̈ӎv�Ɋ�Â������[�u���~�̎葱�������K�肵�C���~���̓K�Ȏ��{�Ɏ�����C�i2�j���҂������[�u���~�̈ӎv���Ŏ����C2�l�ȏ�̈�t���u�Վ���ԁv�Ɣ��肷��C�h�{�E�����⋋���܂މ����[�u�𒆎~�ł���C�ł����B �@�������C���̋c�A�̗v�j�ẮC���{��t��Ɠ��٘A�̈ӌ����ŃX�g�b�v���܂����B���{��t��̈ӌ��́u�������@�����ɍ����I���ӂ������Ă��邩�͐r���^��B���̂悤�ȏł̖@�����͈�Ì���̍����������v�ł����B���{����������́C�������̏�����������Ă���C��t�͖Ɛӂ����悤�ɓw�͂��Ă���̂ł��B�ŋ߂̑傫�Ȉ��y�������͖w�Ǔ��������ɂ����̂ł��B�܂������̎咣�́C�I�����ɑ��������������ƍl����l�̌����E�咣������ė~���������ŁC�������Â��������҂͂ǂ����ő������悢�̂ł��B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N9��22�� |
| �����{��k�ЂŊ������g�䂪�݁h�����̈ꏕ�̂��߂� �I������ÂɊւ���{�l�̈ӎv�m�F�J�[�h�����܂��� |
| ���[�O��i�c���`�m��wSFC��������ȏ����i�K��j�A���_�ی������m�A�Љ���m�j �@�]�[�ǂȂǂł�����A����ԂƂȂ�A������ʂ܂܉�����銳�҂����O�ɂ��āA�u���̕��͉ʂ����č��̏�Ԃ�{���ɖ]��ł���̂��낤���v�ƁA�Տ���Ȃ�N������x�͎��₵�����Ƃ�����Ǝv���܂��B����̈ӎv�������Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɔ����āA���炩���߈�Âɑ��郊�N�G�X�g�𖾂炩�ɂ��Ă����Ăق����B���̕v�͋{�錧�̓������̂���a�@�ɋΖ����Ă���̂ł����A�����{��k�Ђ�̌����ĉ��߂Ă��̏d�v����Ɋ����܂����B �@�ЊQ���ɂ́A�����\�ɏo�Ȃ��g�䂪�݁h�����݉����܂��B���ɐg���Ă��������A�����⊵��Ȃ����̂��߂ɂ݂�݂�̒�������A�v�̋Ζ���ɂ����X�Ɣ�������Ă��܂������A���̑����́A�]�����̌��ǂ�F�m�ǂŐQ������ƂȂ�A�ӎv�̑a�ʂ��ł��Ȃ�����҂ł����B���̋~��ǂ���̏Љ��ɂ́u�Ôg�ň��9�l��������s���s���v�u�{�l�͂��̉ƂŗB��̐����ҁv�ȂǂƏ�����Ă���܂����B�����ɂ݂܂������A����荢�����̂́A�Ƒ������Ȃ��Ȃ������߂ɁA���҂��g�̊�]��ӎv�̏����ł��Ȃ��Ȃ��Ă������Ƃł��B �މ@���҂������Ȃ��a�@�A�Ƒ� �@���X�ɑ����Ă��銳�҂��������邽�߂ɂ́A��Ԃ��������������҂��珇�X�ɑމ@������K�v������܂��B�Ƃ����Ă��A�߂��̕a�@����{�݂͂ǂ�����Ў҂Ŗ����ł������A���܂��܌��������{�݂�����u�肪�����邩��݂낤�ɂ��āv�Ƃ��A�u�M�d�ȗ×{�a�������̂�����A���v���オ��悤�ɋC�ǐ؊J�⒆�S�Ö��h�{�Ȃǂň�Ë敪���������Ă��ꂽ���v�ȂǁA������������������邱�Ƃ��������̂ł��B�܂��A�v�̋Ζ���̎���ł͂���܂��A����̐k�Ќ�ɂ͉��L�̂悤�Șb���悭���ɂ��܂����B �i1�j�Ƒ��ƘA�����r�₦�� �@���{�݂��S�Ĕ������̂̐H����ۂ�Ȃ��Ȃ�A�̒�������ē��@�����A�F�m�ǂ̂�����̃P�[�X�ł��B�ӎv�̑a�ʂ��ł��Ȃ��̂ŁA�Ώ����j�𑊒k���邽�߂ɉƑ�������Ƃ̂��ƂŔ����B�������A�u���ő̒���������v�u�Ԃ�������Č�ʎ�i���Ȃ��v�ȂǂƁA�ʒk�̓������邸��Ɖ�������Ă��܂��܂����B�d�b�ŗ��@���Ñ������Ƃ���A�u���������������ÂȂ��̐l�͖]��ł��Ȃ��v�Ɠf���̂Ă�悤�Ɍ����ĉ��M�s�ʂɁB�ʂ����Ė{�l�̈ӎv�����̂Ƃ���Ȃ̂��m�F�ł��Ȃ��̂Ŏ��Â̒��~���ł����A�Ƒ��ƃR���^�N�g�ł��Ȃ����߂ɕa�@����̍s��������܂炸�A�������@��]�V�Ȃ�����Ă��܂��܂����B �i2�j��Ô�����Ȃ̂ŕa�@����������Ȃ� �@�a���肵�����������̊��҂���̘b�ł��B�u���@���Ĉ�Â���K�v�����Ȃ��Ȃ����̂őމ@�ł��v�Ɠ`�����Ƃ���A�{�l���Ƒ��ƕ�点�邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă��܂����B�������A�Ƒ����u�Ƃ��������Ԃ����̂ōs���ꂪ�Ȃ��B���{�݂��ƕa�@���݂̃P�A�����邩�S�z�B���̂܂ܓ��@�����Ăق����v�Ə���܂���B�Ƃ��낪�Ō�t�ɘb�����Ƃ���A�Ƒ��̖{���́w���z20���~�̏�Q�N���������Ă��邵�A�g�̏�Q��1���ň�Ô�͖����Ȃ̂ŁA�a�@�ɂ��̂܂ܓ���Ă����������ʓ|���Ȃ��x�Ƃ̂��ƁB����������Z���ɂƂǂ܂��Ă���A�Ƒ��͕��ʂɐ������Ă��邻���ł����B�{�l�̊�]�Ȃǂ��\���Ȃ��ł��B�މ@�������s���ɏI��������߁A���ǐ悪�����Ȃ��܂ܕa�@�ɂƂǂ܂邱�ƂɂȂ�A�{�l�͍ǂ�����ł��܂��܂����B �i3�j���ԑ̂���ƂɈ������Ȃ��Ƒ� �@�]�����킸���Ȋ��҂���ɂ��āA�u�Ŋ��͉Ƃʼn߂��������ƌ����Ă�������v�Ɖ�������ɘA��ċA�낤�Ƃ��܂����B�Ƃ��낪�삯�����e������u�ƂŎ��Ȃ����炲�ߏ��l�ɏ���v�u�a�@�Ő������Ă��̂��K�����v�u�ƂŖS���Ȃ��Č����ɂł��Ȃ�����x�@������B�p�g�J�[����܂��Ă�Ȃ�Ċi�D�����Ȃ��v�ȂǂƉ������Ēf�O������܂���ł����B�����u�ł̘b�Ȃ������������Ă���Ȃ��B�{�l�����ނŊ�]���c���Ă���Ă����������̂��ȁv�Ƃۂ�Ƃ��ڂ��������ł��B �I�����̈ӎv�\���̈ʒu�t���̂����܂��� �@����̐k�Ђ�ʂ��Ď������́A�u���肵��������˔@�Ƃ��ďI���v���Ƃ�g�������Ēm��܂����B�܂��A�ˑR�P���Ă��鎩�R�ЊQ�ɂ���Ĉ�Ë@�ւ�Ƒ����猩������Ă��܂��\�������邱�Ƃ����܂����B�����炱���A�u���Âɂ���ĉ������߂Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�����͂ǂ̂悤�Ɉ�Â��s���Ăق����̂��v�Ƃ����ӎv���A�`�Ƃ��Ďc���Ă����K�v����Ɋ������̂ł��B �h�i�[�J�[�h��͂����u�I������Èӎv�\���J�[�h�v�i�\�ʁj�B 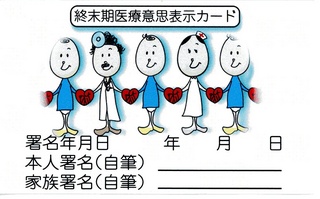 �@���z��`���Ə��邩������܂��A��Â͊��҂���̊�]�������邽�߂̂��̂��Ǝ������v�w�͍l���Ă��܂��B�����ňӎv�\�����ł��Ȃ��Ȃ������ɁA��Ë@�ւ���{�݁A�Ƒ��⑼�l�̓s���Ő�������邱�Ƃ�]�܂��A�u�����̍Ŋ����炢�͎����̈ӎv�Ō��߂����v�Ƃ������҂���̑z��������A���d�����ׂ��ł��傤�B �@���ʁB�×{�ꏊ�̂ق��A�����Ɋ֘A����9�_�ɂ��āA��]���L�ڂł���悤�ɂ����B�T�C�Y�͈�ʓI�Ȗ��h�Ɠ����B �@�������v�w�̂���Ȏv�����`�ɂ����̂��A����̈ӎv��\���h�i�[�J�[�h��͂����u�I������Èӎv�\���J�[�h�v�ł��B�������A�I������Âɂ��Ċ�]��`���邽�߂̏��ނ́A�l�b�g��T��������ł�������܂��B�����A�����ŊȒP�ɏ����A�g�тł���^�C�v�͔����ł��܂���ł����B���������J�[�h�Ȃ�A�T�C�������Ċۂ�t���邾���ōŒ���̈ӎv���\���ł��܂����A�C���ς�����炢�ł����������܂��B�����A����҂ɂƂ��Ă͎�����������������܂��A�����̊W�ŌX�̈�Ís�ׂɂ��Ă̐���������܂���B���e�ɂ��Ă��\�������Ă��Ȃ��ʂ�����܂����A�������̎��̂��Ƃ��Ƒ��ł悭�b�������Ă����������߂̑f�ނɂ͂Ȃ�Ǝv���܂��B ���o���f�B�J�� �I�����C���@2011�N11��8�� |
|
������Ȃ���̎����ρi�O�ҁj �u���v��m��Ȃ���t |
| �@���̎������҂��A�s�{�ӂɂ����X�ɖS���Ȃ��Ă����B�؈ޏk�������d���ǁiALS�j�Ől�H�ċz��̑�������]���Ȃ��������ҁA�p�[�L���\���a�ŏI�������}�������ҁA��N���A���c�n�C�}�[�a����Ɏ��E�������ҁA����Ă�ɒ_�X�����������d�퐫���Ǔ��Ìŏnj�Q�iDIC�j���������ҁc�B �@�i���ɐs���邱�Ƃ̂Ȃ��u���v�ɂ��āA��t�Ƃ��Đl�ԂƂ��ĉ��X�ƌJ��Ԃ��Ă��鎩�⎩���̈�[���Љ�����B �@������g�����ρh�ɁA�����͂������Ȃ��B100�l����100�ʂ�̉����邱�Ƃ��\�����m���Ă��邪�A���̂悤�Ȏd�������Ă���ƁA�X�́g�l�̎��h�Ƃ������̂ɐv���ɔ����������ŁA�ǂ̂悤�Ȏ������I�Ɉ��������Ȃ肪�����B�V�r�A�Ɏ������߂悤�Ƃ������ŁA���̒������Ōy���ɉ��߂��Ă��܂��B �@�����Ȃ��Ƃ������A���͂��̂悤�Ȏd���������Ƃ��Ă�����ɂ́A�����ǂ��������̂������܂��ɗ������Ă��Ȃ��B�p�����������Ƃ����A���̑Ώ��̎d����m��Ȃ��B �@��t�Ƃ��āA�����f���A���S�鍐�͂ł���B�������A�����u��҂ɑ��ĉ��������Ă������炢����������Ȃ����A�V�ɏ�����悤�Ƃ��Ă���l�ɉ������Ă������炢�����A�܂������v�l�͒ǂ����Ȃ��B �@�܂�A���́g�E�ƓI��p�t�h�Ƃ��������ł����āA���o�I�ɂ͎����������Ă���B�l�Ԃ̎��𗝉�������t�Ƃ����g�l�ԓI���p��h�i����Ɏ����n�������t�����j�Ƃ́A�قlj����B �@������O�����A�l�̐������u���v������B����A���͊m���ɁA�����đ啝�ɂ��̐��𑝂₵�A���݊����剻�����Ă����B�߂������A���{�l��2�l��1�l�͊��Ŏ��S����悤�ɂȂ�Ƃ����Ă���i�S�؍[�ǂ͂��̔����ŁA�]�����͔�����j�B �@���ꂪ�����Ӗ����邩�Ƃ����A�u�ɂ₩�Ɋm���ɐi�s����a���}�����A����ɔ����͂�����\���ł��鎀��������v�Ƃ������Ƃł���B����ɁA�]�������Ȃ�̐��x�ŎZ�o�\�ɂȂ�B�l�X�̐ؖ]���Ă���g���m�ȏ��h���A��Â̕���ɂ��Z�����Ă����㏞�ł���B �@��������t�́A�u�l�̑����̑��d�v�Ƃ������ڂ̉��A�����Ɂu�����Ă��Ȃ������v�Ƃ����g���u������̂��߁A���m��]���Ȃǂ̏��J���ɖ�N�ɂȂ��Ă���B�u����җl�ɂ��C���������܂��v�́u���җl�������߂��������v�ւƎ�q���ϊ����A�u���Ƃ����a�������������Ȃ������v���̂��A�u����5�N��������10%�ł��v�Ȃǂƍ�������悤�ɂȂ����B�����Č��ǁA�藧�Ă��Ȃ��Ȃ�A�u�����̂Ȃ��l�����߂����Ă����������߂ɁA�a�C�ƌ��������Ă��������v�ƌ������B �Ȋw�͎�����₳�Ȃ� �@������O�̂��ƂƂ��Ċ��Ⴂ���Ă����Ȃ��̂́A�u�ǂ�قljȊw���i���E���W���悤�Ƃ��A�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł���B �@��w�͉Ȋw���琬�藧���Ă��邪�A��ÂƂ����Z�p�͌o�������菊�Ƃ��������ł���B�u�ړI���Ⴄ�v�ƌ�����A���̒ʂ肩������Ȃ����A����ڐA��Đ���ÁA�Q�m�����̗��p�Ƃ�������[��Â��A�l�̎���ώ������邱�Ƃ͂Ȃ��B����Ɍ����Ȃ�A�����̔錍����������������������قǁA���ɒ��ʂ����Ƃ��̈����͓����ɂ����B �@�]�Ƃ�������́A���_������^���A�m�o���i��A���̂��Ƃ��L�����čĐ�����B�l�Ԃ̒m���Ɗ����͔]�ɂ���Ďx�z����Ă���B������A�������]�E�_�o���Ȉ�́u�]�͗B��ڐA�ł��Ȃ�����ł���v�ƌւ炵���Ɍ��B�������A����Ԃ��A����ł��܂��ΒN����������̂Ȃ��A�܂��Ă⑼�҂̒��Ő����邱�Ƃ��Ȃ�����Ƃ������Ƃł���B ���o���f�B�J�� �I�����C���@2011�N11��9�� |
| ��Â̖�������������100�̒� ���H�����ەa�@�@���쌴 �d�� ������ |
| �@��N10���ɖ�100�̒a�������}���C�Ȃ�������t�Ƃ��ėՏ�����ɗ����C�u���C���M�ȂǕ��L���W�������ł̊���Œm���鐹�H�����ەa�@�i�����s�j
�̓��쌴�d���������B���͐V����10�N��Ɍ������X�^�[�g���C���ɗ������S���Ƃ����B��������\�h��w�̏d�v��������C�u���l�a�v�ɑ���u�����K���a�v
�Ƃ����V�������t���āB�܂��C�^�[�~�i���P�A�̕��y�ɂ��s�͂���ȂǁC���{�̈�w�̔��W�Ɋ�^���Ă����B�����ŁC��������߂Ă����g�l���̒B�l�h�ɁC
����Љ�Ƃ̌����������C��Â̏������C�l���̓N�w���I������B �����E�`���̌p���ƈ�Ï��̗̒��ʂ���v�����ʂ��� ����������100���߂��������C�����̈�t�Ƃ��ăG�l���M�b�V���Ɋ����𑱂��Ă����܂��B����̏،��҂̗��ꂩ��C�L���ɘV���邱�Ƃ̈Ӗ��C�����E����Љ���}������{�̖������ɂ��Ă��b�����������܂����B �@���݁C���{�ɂ���100�Έȏ�̍���҂̐���3��9,000�l������܂��B�����I�O�́C��������100�l�ɂ������Ȃ������̂ɁC���ł͐��E�ōł����� �̐l�������B�S�̂�8������������߁C�j����2���ɂƂǂ܂��Ă���B�S�̂̔����͗v���҂ŁC�������ł��Ă��Ȃ��̂ł��ˁB����ł͍���܂�����C������ ���Ƃ�������҂��琬����K�v������B�����炸�؍����C���ɒ������l���̍���ɒ��ʂ��܂��B���������{�́C����Ɍ����ď��ɑΉ����Ȃ��Ă͂� ��܂���B ����̓I�ɂ͂ǂ̂悤�ȕ�����܂����B �@10�N�O�C(��)���C�t�E�v�����j���O�E�Z���^�[�ɐݗ������u�V�V�l�̉�v�́C75�Έȏ�̃V�j�A����C74�Έȉ��̃W���j�A����C20�`60�܂ł� �T�|�[�g��������킹�C1��1,000�l�̉������܂łɂȂ�܂����B������39�J���ɉ����C�n���C��L�V�R�ɂ��x���������āC����͓��{�̕����� �K���C�푈�̌������̐���ɓ`�������ŁC�g�S���ʂ̌��N������C��w�E��Â̐i���ɍv������w���X�E���T�[�`�E�{�����e�B�A�̖����������Ă� �܂��B������m�̕���C���X�|�[�c�̃T�[�N������������ŁC10��16���ɎO�d�ŊJ�Â����W�����{���[�ɂ�8,000�l���Q�����܂����B�����ł́C �킽����100�̒a�������j����150�l���̉�����t���_���X���I���Ă���܂����B �@��͂�C���낢��Ȋ�����ϋɓI�ɍs�����ƂŁC�K���������܂��āC���N��Ԃ��ǂ��Ȃ�Ǝv���܂��B�ł��邾�������̐l���K�����������ĕ�炵�Ăق������̂ł��B �u���̂��̎��Ɓv��ʂ��C���w�������ƃG�l���M�[�����Ƃ� ���f�ÁC�u���C���M�ȂǁC���Z�Ȑ����𑗂��Ă��܂����C���̌��C�̔錍�͂ǂ��ɂ���̂ł����B �@���������ʂ�C�킽����1���́C��c��ł����킹�C�ʒk�C�a����f�C�u���C���e���M�ȂǂŌߑO�������܂ŃX�P�W���[���͂����ς��ł��B�������C�킽 ���ɂ͔��Ƃ������C���ӊ����Ȃ��B���͑u�₩�ɖڊo�߂�B����ǂ��C100�ɂȂ����̂��@�ɁC�[��܂Ō��e�������̂���߁C12���ɂ͏��ɏA�����ƌ� �߂܂����B�܂��C�킽���͂���5�N�ق�10����1��̃y�[�X�Ŋe�n�̏��w�Z�ɏo�����C�u���̂��̎��Ɓv�Ɏ��g��ł��܂��B�q�������Ɂu�N�����̖��͂ǂ� �ɂ���́v�ƕ����ƁC�����Ă��͐S���Ɏ�Ă�B�S���͎_�f�Ɖh�{�����������t��]��葫������ɑ���|���v�ł����āC���ł͂Ȃ��B���͖ڂɌ����Ȃ��B �N�����������Ă��鎞�Ԃ��ڂɌ����Ȃ����C�G��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���ԂƖ��͎��Ă��āC�N�����ɂ͂��ꂪ�g����B�����������͎����̂��߂ɂ������Ԃ��g�� �Ă��悢����ǁC�傫���Ȃ����牽�Ɏg�����l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���������ӂ��Ɏ����̎��Ԃ��ǂ��g���Ă������Ƃ������Ƃ��C�����Ă���Ƃ������ƂȂ̂� �Ɛ�������ƁC�ނ�͂����Ɨ������Ă����̂ł��ˁB5�N�O�̒����w�\�̂��݂ց|��\�܍̂킽������x���p��C������ɖ�o����Ĉȗ��C�C�O�̎q�� ����������f���炵�������ɂ��ӂꂽ�莆���͂��悤�ɂȂ�܂����B���ꂩ���l�ɂȂ鐢�オ���̈Ӗ���m��C���E�ɕ��a�������炷���҂ɂȂ�C���ꂪ�� �����ɂƂ��ẴS�[���ł��B�킽���͋����Ŏq�������Ɛڂ��邱�Ƃɂ���āC�q���������炽������G�l���M�[��������Ă���킯�ł��B ��65�Έȏ�̔N��̂���̜늳���͍���2�l��1�l�Ƃ����Ă��܂��B�搶�͑�������^�[�~�i���P�A�̏d�v�����w�E���Ă����܂������B �@��w�̌��E��m��C�������炩�Ɍ}���邽�߂̈�Â��K�v���Ƃ����l���̉��C�^�[�~�i���P�A�ɗ͂����Ă��܂����B1993�N�ɕx�m�R��]�ސ_�ސ쌧���䒬�ɓ��{���̓Ɨ��^�z�X�s�X�Ƃ��ăs�[�X�n�E�X�a�@��ݗ����܂����B �@�^�[�~�i���P�A�́C�傫���ς��܂����ˁB�����O�܂ł͖����̂��҂̐g�̓I�Ȓɂ݂�ꂵ�݂���菜���C�C�����𗎂��������C�Â��ɐl���̏I�����} ���Ă��炨���Ƃ����l�������嗬�ł����B�������C�ŋ߂ł́C�Ő�[�̕��ː����ÂȂǂ��o�ꂵ�C���Ă͎��Ö@���Ȃ��S���Ȃ��Ă������҂���𐔃J���`�� �N�C������������P�[�X��������悤�ɂȂ��Ă��܂����B�Ⴆ�C����S���Ȃ����č��A�b�v���Ђ̑n�Ǝ҂�1�l�C�X�e�B�[�u�E�W���u�Y���ɂ��Ă��C�X�� ����̐؏���p����n�܂��Ċ̑����ڐA���C���ꂱ����s������8�N�Ԏ����������܂����B���ʓI�ȃ��\�b�h���g����̂ɁC���̗���ɔw�������闝�R�͂��� �܂���B�z�X�s�X�P�A�ł����Â�������߂��������ɁC�u���������@�͂���܂���C������g���܂��傤���v�ƒ�Ă���@������܂����B �i�[�X�v���N�e�B�V���i���[�������v���C�}���P�A�̐i�� �����{�̈�Â̏������ɂ��āC�ǂ̂悤�ȍl�����������ł����B �@��Ãe�N�m���W�[�����i���������̂́C��Ð��x�͂��̐��\�N�C�قƂ�ǐi�W���Ȃ��B�����ȁC�Y�ȁC�����Ȃ̈�t�s�������������C�z������܂���B��t �����ɋ����ꂽ�f�f�⎡�ÂƂ�������Ís�ׂ��i�[�X�ɂ��\�Ȃ�C���Ԃ͈�ς���͂��ł��B��t�̎d���ƃi�[�X�̎d����3����2���d�Ȃ荇���BX���Z�t�� �����Z�t�Ȃǂ̎d�������l�ł��B���������I�[�o�[���b�v�����d�����݂��ɕ��S���C���͂��Ȃ���Ή�����`�[����Â������]�܂����B�č���J�i�_��40�N�� �O�Ƀi�[�X�����t�iNurse Anesthetists�j������̊ē̉��C�Ɨ����Ė������s���̐��𐮂��Ă��āC���݂ł͕č��Ŏ��{������p�̂�����8���ł��̐l���������� ���܂��B�����ŁC���H���Ō��w��w�@�̏C�m�ے��ɂ���܂ł̏��Y�t�ɉ����C�����t�̗{���R�[�X��ݒu����v��𗧂Ă܂����B�܂��C50�N�O����w�E���� ���Ă����悤�ɁC���{�̃v���C�}���P�A�͊C�O�ɔ�ׁC���Ȃ�x��Ă���B���ɂւ��n�ł͌���ꂽ��Ë@�ւɊ��҂��W�����C�\���Ȉ�ÃT�[�r�X���ł��Ȃ� �Ȃ��Ă�����肩�C�z�����ꂽ��t�����N���o�����Č�サ�Ă��܂��B���̑ŊJ�Ɍ����C�Ȃ�ׂ����������Ƀv���C�}���P�A�ɏ]���ł���i�[�X�v���N�e�B �V���i�[�����肽���B�l��3���l���炢�̎����̂�ΏۂɁC�X�[�p�[�o�C�U�[���̈�t�Ƌ��͂��Ď��т�ςݏグ�Ă�������ł��B��w�E���͂��ߔ��͑� ���ł��傤����ǁC�n��Z���ɂ͖����ɂȂ��Ă��炦����̂Ɗm�M���Ă��܂��B �u��������������C�S�͂Ő�����v�����b�g�[�� �����N�C�x���ƂȂ��Ă���ꂽ���l�̔F�m�ǁC����ɋ}�ȕa�ɒ��ʂ��C��������邲�l�q���d�g�ɏ��C�����̋������Ăт܂����B���l�ւ̐ڂ����ŐS�����Ă���������_�������������������B �@�{���Ɏ��Ƃ������̂�g�߂Ɋ����܂����B�Ɠ��Ƃ�68�N�O�Ɍ������Ĉȗ��C�ǂ������ł���C3�l�̑��q����ďグ���ǂ���C�����Ă킽���̎d�����T�|�[ �g���Ă���錣�g�I�Ȕ鏑�ł����B����92�ɂȂ�܂����C20�N�O�ɉE�̔x�ɑ����̂��������Đ؏����Ă���B���̕��̔x���C���������������Ōċz �@�\���ቺ���Ă����B�]���_�f�s���Ɋׂ��ĔF�m�͂������C���t���o���Ȃ������̂ł��ˁB����ǂ��C�_�f��������R�~���j�P�[�V�������߂��Ă��܂����B 100��92�Ƃ�������̕v�w�ł����C���݂��̎��������邩��C�����ʂ�������Ȃ��Ɗo�債�C�^����ꂽ������S�͓������Đ����悤�C���ꂪ�킽�� �̐l���_�ł��B���������������ĂƂɂ�������t����Ă݂�B�u��������ĕ������v�Ƃ������̉̂��킽���͍D���ł��ˁB ���f�B�J���g���r���[���@2012�N1��5�� |
| �]��1�N�������҂ւ̖�܂̒v���ʏ�����C�p���E�ψ��� �@�߉����ߘg�g�݂�� |
| �@�p���̎��E�Ɋւ���ψ���Commision on Assisted Dying���C�]��1�N�����̖������҂�Ώۂɖ{�l����]�����ꍇ�ɂ͈�t����܂̒v���ʏ������\�ɂ�����s�����Ƃ��āCCMAJ��For
the record�������グ���iCMAJ 2012�N1��12���I�����C���Łj�B���ψ���͈��y���⎩�E�̍��@���̕K�v����i����ƂƂ��ɁC���m�Șg�g�݂���Ă���Ƃ����B �g�K�p���ҕ]���͈�t2�l�ȏ�Łh�g�ŏI��Ƃ͊��Җ{�l���h �@CMAJ�ɂ��ƁC����܂ł����т��ыc�_����Ă����������҂̈��y���⎩�E���߂�����ɑ��āC���ψ���̕��́u���Ȃ����E�́C����� ���߂�l��C���߂���\���ɑ��ăv���b�V���[�������Ă���l�ɂƂ��āC���S�u�����Ă��Ȃ��v�Ɩ�莋���C�u���s�̖@������ѐ���͖������҂� ��Î҂ɂƂ��ĕs���ł���v�Ɣᔻ�����B �@�����œ����ł́C�]��1�N�����̖������҂�ΏۂɁC���y������]����ꍇ�͈�t����܂̒v���ʏ�����������@�������肷�ׂ��Ǝ咣�B��Ɏ��̂悤�Ȏ��E�Ɋւ���@�߂̘g�g�݂�����B �@���m�ɒ�`���ꂽ���҂̓K�p���݂���i2�l�ȏ�̈ˑ��W�̂Ȃ���t���]���j �@�\�ł���Ί��҂��悭�m���Ă����t���������C���҂ƉƑ����T�|�[�g���� �@��܂̒v���ʏ�����, �s���g�p�ⓐ���\�Ȍ�����S�ɊǗ����� �@���E����]����͎̂��ÂɊւ���I�����̐����������҂Ƃ��� �@���E����]���銳�Җ{�l�����g�̖������߂̍ŏI��Ƃ��s�� �@2�l�ȏ�̈�t���]�����銳�҂̓K�p��ɂ��ẮC�i1�j�Ǐi�s���Ŏ����s�\�ł���C����12�J���ȓ��̎��S�������܂�閖����ԁC�i2�j���� ����̋��v�ł͂Ȃ��C���Җ{�l�̎����I�Ȉӎu�ɂ���]�ł��邱�Ƃ̏ؖ��C�i3�j���Җ{�l�����Ɋ�Â��I�����\�Ȑ��_��ԁ@���������B �@����ɁC��t�ɑ��āC���E����]���銳�҂����X�ɂ��Ȃ��������i�ŒZ2�T�ԁB�������C�]��1�J���ȓ��ł͍ŒZ6���j������悤�C�אS�̒��ӂ��Ȃ�����C�v���ɑΉ����ׂ��Ƃ��Ă���B �@�Ȃ��C�����ł́C�p�����Տ��]���������iNICE�j�����E�ɂ������܂̒v���ʏ����ɂ��Ď���������쐬���邱�Ƃ�v�����Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N1��16�� |
| �����Љ�ی���Ë��c�� �ɘa�P�A�a���A�u�]���@�\�v�̔F��Ȃ��Ă��� �`�[���ɂ��u�O�����ː��Ǝːf�×��v���V�� |
| �@�����Љ�ی���Ë��c���i��F�X�c�N�E������w��w�@�@�w�����w�����ȋ����j��1��30���ɊJ�Â���A1��27���ɑ����A�u�ʉ��荀�ڂɂ��āi����2�j�v���c�_�����i�����́A���J�Ȃ̃z�[���y�[�W�Ɍf�ځj�B �@30���̑���ŁA�ł������ȋc�_���W�J���ꂽ�̂��A�ɘa�P�A�a���̎{�݊�̌��������B���݂́u���ØA�g�̋��_�ƂȂ�a�@�������͂���ɏ�����a�@ �ł��邱�ƁA�܂��͍��c�@�l���{��Ë@�\�]���@�\�����s����Ë@�\�]�����Ă��邱�Ɓv�Ƃ����v�������邪�A������폜���A��t�̐l������͂��߁A�� �̎{�݊�����a���ł���A�u�ɘa�P�A�a�����@���v��u�ɘa�P�A�f�É��Z�v���Z��ł���Ă��������B�ɘa�P�A�̐��i���ړI���B �@�S���{�a�@�����̐��V���r���́A�u�ɘa�P�A�a���̑ΏۂƂȂ��Ë@�ւ𑝂₷���Ƃ͂������A��O�҂̕]���͑厖�Ȃ̂ŁA���炩�̌`�Ŏc���Ȃ����v�� ��āB�A����������ǒ��̉Ԉ�\�q���́A�u��O�ҋ@�\�̕]������v�����c���Ăق����B���{�̈�Â��q�ϓI�ɕ]�����Ă���̂́A���̋@�\�ł���A���҂� ��Ë@�ւ�T�����ɖ𗧂B�]�����邱�Ƃ��ނ��됄�i���闧��ɗ��ׂ��ł����āA�i�F��́j�n�[�h������������ƌ����č폜����̂́A���҂̎��_�� �����Ă���v�Əq�ׁA�v�����c���悤�������߂��B �@����A���������Z���^�[�������̉ÎR�F�����́A�u���{��Ë@�\�]���@�\������̂��Ƃ�]���ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��v�Ǝw�E�A�ɘa�P�A�a���̂���ȊO�̎{�݊�Ŏ��͒S�ۂł���Ƃ����B �@���̂ق��A�l�X�Ȉӌ������������A���J�ȕی��Lj�Éے��̗�؍N�T���́A�u�ɘa�P�A�a���̎{�݊�Ɍ��炸�A��O�ҕ]���͏d�v�����A�F��a�@���Ɍ��肵 �Ă��邱�Ƃ��A�ɘa�P�A�a���̐������肵�Ă���v���ɂȂ��Ă���v�Ɛ����A���ǁA�u�F��ɏ�����a�@�v�Ƃ̕\���������A�u���ØA�g�̋��_�ƂȂ�a�@�� �����͂���ɏ�����a�@�ł��邱�ƁA�܂��͍��c�@�l���{��Ë@�\�]���@�\�����s����Ë@�\�]�����Ă��邱�Ƃ������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�Ɓv�Ƃ� �����߂ɕ�����������\���ɗ����������B �@�ɘa�P�A���͂��߁A����f�Ê֘A�́A�u�[�������߂��镪��v�A�܂�_���̈����グ���\�肳��Ă��镪��B�O���ɘa�P�A���A���̈�t��z�u����ꍇ�̓_�����A�b�v����ق��A��×p�����4�܂ɂ��āA���������̐�����14������30���Ɋɘa����Ȃǂ̉�����s���B �@����ɁA���ː����Ð��i�̂��߁A�u�O�����ː��Ǝːf�×��v��n�݁B���ː����È�s���̌���܂��A��t������f�@���Ȃ��Ă��A��t�̎w���ŊŌ�t��f�Õ��ː��Z�t�����`�[���Ŗ���ώ@���邱�Ƃŕ��ː��Ǝ˂����{����̐��ɂ��āA�_����V�݂���B �@����֘A�̎�ȉ��荀�ڂ͈ȉ��̒ʂ�B ���ɘa�P�A�̐��i �E�ɘa�P�A�a������ъɘa�P�A�f�É��Z�̎{�݊�̕ύX�i�Z��Ώۂ́A�u���ØA�g�̋��_�ƂȂ�a�@�������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�ƁA�܂��͍��c�@�l���{��Ë@�\�]���@�\�����s����Ë@�\�]�����Ă��邱�Ƃ������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�Ɓv�Ɂj�B �E�����ɘa�P�A���i�̂��߁A�u�����u�Ɋɘa�w�����v�A�u�ɘa�P�A�f�É��Z�v�A�u�O���ɘa�P�A�Ǘ����v��V�݁B �E�u�����u�Ɋɘa�w���Ǘ����v�ɂ��āA�ɘa�P�A�̌o����L�����t���w���Ǘ����s�����ꍇ��V���ɕ]���B �E�R�f�C���i���p�j�A�W�q�h���R�f�C���i���p�j�A�t�F���^�j���i���ˍ܁j�A�t�F���^�j���i�o��z���^���܁j��4���܂̈�×p����ɂ��āA����������14������30���Ɋɘa�B�@ ������̐f�ØA�g�̏[�� �E�u����f�ØA�g���_�a�@���Z�v�́A���҂����łȂ��A�u����̋^���v�̊��҂̏Љ�̏ꍇ���Z��\�ɁB �E����f�ØA�g���_�a�@�ɂ����āA�Љ�҂����@�Ɏ��炸�A�O�����w�Ö@�������ꍇ�́u���ØA�g�Ǘ����v��V�݁B �E�u���ØA�g�v����藿�v�́A�u���@���ɍ���v�����ꍇ�ɎZ�肪�\���������A�u���@���܂��͑މ@����30���ȓ��v�ɍ��肵���ꍇ�A�u�v��̕ύX�v���s�����ꍇ�ł��Z��\�ɁB �E�u�����p����w���Ǘ����v�́A��p�����{������Ë@�ւ����łȂ��A����ȊO�̈�Ë@�ւ�2�x�ڂ̎w�������ꍇ���Z��\�ɁB �E�u���҃J�E���Z�����O���v�́A�]�@��������Ë@�ւł��Z��\�ɁB�@ ���u�O�����ː��Ǝːf�×��v�̐V�� �E�O�����ː��Ǝˎ��{�v��Ɋ�Â��A1�T�Ԃɂ����ނ�5���Ԃ̕��ː��Ǝ˂��銳�҂ɑ��A��t�̎w���ɂ��Ō�t��f�Õ��ː��Z�t���̃`�[���ɂ�閈��̊ώ@��]���B �E���ː����È�i���ː����Â̌o��5�N�ȏ�j���Ζ����Ă���A��]�̊Ō�t�Ɛf�Õ��ː��Z�t�����ꂼ��1�l�ȏ�Ζ����Ă��邱�ƂȂǂ��v���B ���������@��ÊǗ����ɂ�������ː����Â̕]�� �E�������@��ÊǗ����̕�͈͂���A���ː����Â����O�B m3.com�@2012�N1��30�� |
| �؍��́u�ՏI�̎��v�͐��E�R�Q�� |
| �@�c���k���i�L�����T���u�N�h�j�̃�������i�U�U�j�͍�N�P�����A�t������Ƃ����f�f�����B�\�E���̕a�@�ōR���Âƕ��ː����Â������A���ʂ�
�Ȃ������B�Ƒ��ƘA�����r�₦�ċv�����A��l�ŋ�J���Ȃ���߂����Ă������A�����Ȃ�n�߂���N�P�O���A�m�l�̏������Ď�s���̗×{�@�Ɉڂ����B�×{
�@���͒��ɍ܂�^���Ă��邪�A�������҂��Ǘ�������Ƃł͂Ȃ����߁A�ɂ݂߂���̂��e�ՂłȂ��B �@�Q�O�P�O�N�ɂ���Ŏ��S�����l�͂V���Q�O�S�U�l�B�������҂ɍł��K�v�ȃT�[�r�X�͒ɂ݂̒��߂��B�R���Â͂���قLjӖ����Ȃ��B�ɂ݂߂��Ȃ� ��l�������邱�Ƃ��d�v���B���Ƃ̑��k������A�ґz�E���K�ȂǂŐS���I�Ȉ�����ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������T�[�r�X���ɘa��Ái�z�X�s �X�j�Ƃ����B �@�������҂̂����ɘa��Â���l�͂X���ɂ����Ȃ��B��������̂悤�ɂ�����Ƃ�����ÃT�[�r�X�����Ȃ��l�͂R�Q�D�S���ɂ̂ڂ�B�S�O�D�V�� �͍���l�Q��L�m�R�ނȂǂ̐H���Ö@���ֈ�Âɗ����Ă���B��������Z���^�[�����S�҂̈⑰�P�U�U�S�l���A���P�[�g�����������ʂ��B �@��������ɘa��ÃT�[�r�X�͑S���S�S�@�ցi�V�Q�T�a���j�Œ��Ă���B��������Z���^�[�z�X�s�X�ɘa��Î��Ɖۂ̃`�F�E�W�������������́u�ɘa��Ð� �i���̉p���͐l���P�O�O���l������T�O�a����ۗL����v�Ƃ��u���̊��K�p����Ί؍��ł͂Q�T�O�O�a�����K�v�ƂȂ邪�A���݂͂܂��Q�X�������Ȃ��v�Ǝw �E�����B �@�\�E����a�@�̋�����i�z�E�e�\�N�j�����i���t��ᇓ��ȁj�́u�a�����s�����Ă��邤���A���݂��������Â��D�ޕ��͋C������A�e���̎��f��������v�Əq�� ���B�������҂̒ɂ݂̊Ǘ��ɂ͖����ɍ܂��g����B���E�ی��@�ցi�v�g�n�j�ɂ��ƁA�؍������P�l������̃����q�l�g�p�ʂ͂P�D�Q�~���O�����Ő� �E�U�Q�ʁB�P�ʂ̃I�[�X�g���A�͂P�T�R�D�S�~���O�������B�\�E����a�@�̋������́u�����ɍ܂͂قƂ�ǖ������҂��g�����A�g�p�ʂ����Ȃ��Ƃ����� �͊��҂����ꂾ����ɂ��ĖS���Ȃ��Ă���Ƃ������Ɓv�Ƙb�����B �@�V���K�|�[�����P�c�̂̃������c�ɂ��ƁA�؍��́u�ՏI�̎��v�͐��E�R�Q�ʂƂ����B�ی��������͍��N�A�S���S�S�J���̊ɘa��Ð��@�ւɂQ�R���E�H�� �i��P���V�O�O�O���~�j���x�����邱�Ƃɂ����B���F�i�A�W���j��a�@���lj����ꂽ�B���N�͈�ʕa�@���v�������Ζ������҂�ΏۂɊɘa��Â��ł��� �悤�f�Õ�V�_�����o���v�悾�B ��������@2012�N2��7�� |
| �I����Á\��t�ƈ�ʐl�͂Ȃ��I�����قȂ�̂� �P���E�}�[���C |
| �@���N���O�A���h���W�߂鐮�`�O�Ȉ�ł���A���̃����^�[�ł�����`���[���[�́A�݂Ɂu��v���������B�S�Ăōł��ǂ��O�Ȉ��1�l�́A������������K��
�Ɛf�f�����B���̊O�Ȉ�́A���҂̐����̎��͒ቺ������̂́A5�N��������3�{�\�\5������15���Ɂ\�\�Ɉ����グ�����p����|���Ă����B �ڂ������̂́A��t���鎡�Â̑����ł͂Ȃ��A���Ȃ��� �@�������A68�̃`���[���[�́A��p�ɂ͌����������Ȃ������B�����A�ނ͋A��A�f�Â���߁A�a�@�ɂ͓�x�Ƒ��ݓ���Ȃ������B�Ƒ��Ǝ��Ԃ��߂��� ���ƂɏW�������̂ł���B���J����A�ނ͉ƂŖS���Ȃ����B�ނ́A���w�Ö@�����ː����Â��O�Ȏ�p���Ȃ������B���f�B�P�A�i�č���Ҍ�����Õی����x�j �͔ނ̎��Ô�ɂقƂ�ǎg���Ȃ������B �@���������͂Ȃ����Ƃł͂��邪�A��҂����ʁB�����ł̔ނ�̓����́A�唼�̃A�����J�l���A�����ɑ����̎��Â��Ă��邩�ł͂Ȃ��A�����Ɂu���Ȃ� ���v�ł���B��҂́A�a�C�̐i�s�ɂ��Đ��m�ɗ������Ă���A�ǂ�ȑI����������̂���m��A�����Ǝv�����Â͂ǂ�Ȃ��̂ł������Ă�����B�� �����A�ǂ��炩�Ƃ����A��҂̍Ŋ��͐Â��ʼn��₩���B �@��҂��A��ʂ̐l�������Ɏ������Ȃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�������A�ނ�́A�ߑ��Â̌��E�ɂ��ĉƑ��Ə��������b���Ă���B���̎���������A��| ����Ȏ��Â͂��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��m�F�������̂��B���Ƃ��Δނ�́A�����Ŋ��Ƃ������ɁA�S�x�h���~�}�i�b�o�q�j���{����A�N���ɘ]����܂�ꂽ���͂Ȃ� �i�b�o�q�̐��������u�Ř]�����܂�邱�Ƃ͏\���ɂ���j�B �@��t���I�����̌��f�ʼn���]�ނ��ɂ��āA�W���[�t�E�i�E�K������́A2003�N�ɘ_���ɂ܂Ƃ߂��B�����ΏۂƂȂ�����t765�l�̂����A64�����A�� �����ċN�s�\�ƂȂ����ꍇ�A�~���̍ۂɎ��ׂ��[�u�Ǝ��Ȃ��[�u����̓I�Ɏw�����Ă����B��ʐl�̏ꍇ�A���������w�����s���l�̊����͂킸��20�����B �i���z���̒ʂ�A����̈�҂̕�����N�̈�҂������������u��茈�߁v������X���ɂ���B����́A�|�[���E���X�^�[����̒����Ɏ�����Ă���B�j �@��҂Ɗ��҂̌��f�ɂ́A�Ȃ����̂悤�ȑ傫�ȃM���b�v�����݂���̂��B������l���邤���ŁA�b�o�q�̃P�[�X�͎Q�l�ɂȂ�B�X�[�U���E�f�B�[������́A�e ���r�ԑg�ŕ`����Ă���b�o�q�ɂ��Ē������s�����B����ɂ��ƁA�e���r�ł͂b�o�q�̌�����75�����������A67���̊��҂��A��ł����B�������A������ ���E�ł́A2010�N�̒����ɂ��ƁA9��5000���ȏ�̂b�o�q�̂����A1�J���ȏ㐶���������҂�8���ɉ߂��Ȃ������B���̂����A�قڕ��ʂ̐����𑗂� ���Ƃ̂ł������҂͂킸��3���������B �@�̂̂悤�ɁA��҂��M����ɏ]���A���Â��s��������Ƃ͈قȂ�A���͊��҂̑I������{���B��t�́A���҂̈ӎu���ł��邩���葸�d���悤�Ƃ���B���A���� �Ɂu���Ȃ��Ȃ�ǂ����܂����v�ƕ������ƁA��t�͓�����̂�����Ă��܂����Ƃ��悭����B��X�́A��҂Ɉӌ������v�������Ȃ��B �@���̌��ʁA�ނȂ����u�~���v���Â���l�������A60�N�O��������ŖS���Ȃ�l���������B�Ō�w�̃J�����E�P�[�������́A�uMoving Toward Peace: An Analysis of the Concept of a Good Death�i���炬�ւ̓����F�ǂ����Ƃ����T�O�̕��́j�v�Ƃ����_���̂Ȃ��ŁA���������Ƃ������̂̏����������������A�Ȃ��ł��u�₷�炩�v�Łu�}���� �ꂽ���́v�ł���A�u�I�����}�����Ɗ����v�A�u���̐l�X��Ƒ����P�A�Ɋւ���Ă���v���Ƃ��d�v���Ǝw�E�����B����̕a�@�́A���������_���قƂ�ǖ� �����Ă��Ȃ��B �@���҂́A�I����Âɂ��ď����L�����Ƃɂ��A�u�ǂ����ʂ��v�ɂ��āA�͂邩�ɑ������R���g���[�����邱�Ƃ��\���B�唼�̐l�X�́A�ŋ����瓦��邱 �Ƃ͂ł��Ȃ����Ƃ͂킩���Ă��邪�A���͐ŋ����������Ɛh���B�A�����J�l�̈��|�I���������̓K�ȁu��茈�߁v���ł��Ȃ��ł���B �@�����A�����Ƃ�������Ȃ��B���N�O�A60�̎��̔N��̏]�Z�ł���g�[�`�i�ނ́A�����d���̌��������ɉƂŐ��܂ꂽ�j������ɏP��ꂽ�B���ǁA����� �x����ɂ����̂ŁA�����]�ɓ]�ڂ��Ă��邱�Ƃ����������B�T3�`5��A���w�Ö@�̂��߂̒ʉ@�ȂǁA�ϋɓI�Ȏ��Â��s���āA�]����4�J���Ƃ������Ƃ��� ���B �@�g�[�`�͈�҂ł͂Ȃ��B�������A�ނ́A�P�ɐ����钷���ł͂Ȃ��A�����̎������߂Ă����B�ŏI�I�ɁA�ނ͎��Â����ۂ��A�]�̎���}������p���邱�Ƃɂ����B�����Ĕނ͎��̂Ƃ���Ɉ����z���Ă����B �@���̌�8�J���ԁA����܂ł̐��\�N�ł͂Ȃ������Ǝv�����炢�A�y�������Ԃ��ꏏ�ɉ߂������B�ނɂƂ��Ă͏��߂Ẵf�B�Y�j�[�����h�ɍs�����B�Ƃł���� ��Ɖ߂������B�g�[�`�̓X�|�[�c�D���������̂ŁA�X�|�[�c�ԑg���ςĎ��̎藿����H�ׂ�̂���D���������B�ނ́A�������ɂ݂��Ȃ��A�͂�Ƃ��Ă����B �@������A�ނ͖ڂ��o�܂��Ȃ������B3���ԁA����Ԃ������A�����ĖS���Ȃ����B����8�J���Ԃ̔ނ̈�Ô�́A���p���Ă���1��ނ̖��ŁA20�h�����x�������B �@�����g�ɂ��Č����A�厡�オ���̑I�������L�^���Ă���B�������邱�Ƃ͊ȒP�Ȃ��Ƃ������B�����̈�t�ɂƂ��Ă��������낤�B��|����Ȏ��Â͂Ȃ��B�₷�炩�ɉi������B���̃����^�[�A�`���[���[��]�Z�̃g�[�`�̂悤�ɁB�܂��A�������̎��̈�Ғ��Ԃ̂悤�ɁB �i�M�҂̃P���E�}�[���C��t�́A��J���t�H���j�A��w�̉ƒ��w�̌��Տ��y�����B���̋L���́A�E�F�u�T�C�g�̃\�J���E�p�u���b�N�E�X�N�G�A�ɔ��\���ꂽ���̂�ҏW�����j �E�H�[���X�g���[�g�W���[�i�����{�Ł@2012�N2��27�� |
| ��56����{���n���V�����w�� �V������Á@�����ɍőP�̗��v�ƂȂ�I���� |
| �@�V������Âł́C�����őP�̗��v�ƂȂ�̂��������ɑ�����͂��ӎv���肷�邱�ƂɂȂ�C�ϗ��I�C�@�I�C�Љ�I�Ȗ��ɒ��ʂ��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B����
�s�ŊJ���ꂽ��56����{���n���V�����w��i����������q��ȑ�w��q������ÃZ���^�[�E��c�������j�̃��[�N�V���b�v�u�V�����̐��̑�َҁv�i������
����c��w��[�Ȋw�E���N��×Z�������@�\�E�͌����l�����@�y�����E��C�������C���É��s����w��w�@�V�����E������w����E������q���j�ł́C�Ƒ��x��
���s������̎厡��C�����̉Ƒ��C�㎖�@���̌����҂ȂǑ����ʂ���̔��\���s��ꂽ�B ��Ñ��Ɗ��ҁE�Ƒ��̋����ӎv����� �Ƒ��Q���^�̃`�[����Â��s�� �@�̉ߏ����͔�����ׂ� �q���ɂ͈�ÁC�e�ɂ͎q��Ďx���� ��Ñ��Ɗ��ҁE�Ƒ��̋����ӎv����� �@��q��������q�ی��Z���^�[����a�@�i�����s�j�V�����Ȃ̉�����F�����́C�V������Âɂ�����ӎv����݂̍���ɂ��ču���B�u��Ì���ł͈ˑR�� ���Ĉ�t���犳�҂ւ̈���I�ȃR�~���j�P�[�V�������s���Ă��邪�C�{���ɕK�v�Ȃ̂͑��݃R�~���j�P�[�V�����B�K�C�h���C����}�j���A���ň��ՂɌ��肪�} ����邱�Ƃ��Ȃ��悤�C�\���Șb�������Ɋ�Â������ӎv������s�����Ƃ��d�v�v�Ƒi�����B ���݃R�~���j�P�[�V�������d�v �@���������͂܂��C�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�ɂ��āi1�j��Ñ�����̓K�ȏ��̊J���i2�j���̊��҂ɂ�闝���i3�j���҂̎��Ȍ���\�͂̊m�F �i4�j���҂�������s���ۂ̎��R�ӎu�E�������̑��d�i5�j���҂̓��Ӂ`�̗��ꂪ�K�v�ł���Ɛ����B�u�C���t�H�[���h�E�R���Z���g���g���h�Ƃ����������� ����Ⴂ��t�⌤�C�オ�������C�{���̈Ӗ����\���ɗ������Ă��Ȃ����Ƃ�������B�R�~���j�P�[�V�����\�͂��s�\���Ȉ�ÃX�^�b�t�ƁC�͂�����ӎv�\������ ���Ȃ����҂Ƃ̊ԂŁC�V���ȁg���C����Áh���o�����Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ɩ���N�B����Ɂu����������₷���`���邾���łȂ��C��t�Ɗ��҂���� �����L���C���ݗ�����}�邱�Ƃ��s���v�Əq�ׂ��B �@�܂��C2004�N3���Ɍ����J���Ȑ����Èϑ������ǂ����\�����u�d�ĂȎ��������V�����̈�Â��߂���b�������̃K�C�h���C���v�Ɋւ��āC�u���E��� �Q����O�ʂɑł��o�����_������I�B�ӎv����̌��_�����v���Z�X�����L���邱�ƂɈӋ`�����邱�Ƃ���������Ă���v�Əq�ׂ��B �@����Ɉ�ÃX�^�b�t�Ɗ��҂����L������̒��ɂ́C��������Ï���łȂ��C��Ã~�X�Ȃǐf�Ó��e�ɂ�����鎖����s���̈����j���[�X�C�l���ς�� �����܂܂�邱�Ƃ��w�E�B�u�o�����̃R�~���j�P�[�V�����ɂ����̋��L�����ݗ����݁C��Õs�M�������傭����C�l��l�Ƃ��Ĉ��������Ȉ�Â������� ��B�K�C�h���C����}�j���A���ɗ�����ՂȈӎv������}���̂ł͂Ȃ��C����ł̘b���������x������Â��肪�d�v�v�Ƃ̌������������B �Ƒ��Q���^�̃`�[����Â��s�� �@���É��s����w��w�@�V�����E������w����̈ɓ��F�ꎁ�́C�d�ĂȎ����̑�\�I�ȑ��݂ł���18�g���\�~�[�ɂ��āC�ŋ�10�N�Ԃ̓��@�V�����W������ ���iNICU�j�ł̌o���ƁC�`�[����Âł̊ɘa��Â̎��H����u�\��s�ǂȎ����ł͉Ƒ��Q���^�̃`�[����Â��s���v�Əq�ׂ��B 18�g���\�~�[�Ŋɘa��Â�I�� �@�ɓ����́C18�g���\�~�[�̗\��ׂ邽�߁C2001�N1���`10�N12����10�N�Ԃɓ��@NICU�ɓ��@����18�g���\�~�[19��i�j��8��C���� 11��j��ΏۂɌ�����I�ɗՏ��o�߂����������B�Ώۂ̊T�v�́C���ύݑُT��36.2�T�C���Ϗo���̏d1,615.4g�C�鉤�؊J��68.4���C�@�O�o�� 36.8���C�o������̌��N�x������Apgar�X�R�A�̒����l��1��3�_�C5��6�_�B��p�{�s��6��B��������1�J��80���C6�J��20���C1�N10���B �����މ@����32���ł������B �@����ɓ����́C�ɘa��Â�I������18�g���\�~�[�ɑ��ē��@NICU�����g�`�[����Â̎��H�������B �@�Ǘ�͍ݑ�37�T�ŏo���̏����B29�T�ŗr���ߑ����w�E����C33�T�œ��@�Y�Ȃ��Љ�ꂽ�B�r���זE���F�̌�����18�g���\�~�[�Ɛf�f�C���e�C�c��C �V�����Ȉ�t�C�Y�Ȉ�t�Ƃ̘b�������̌��ʁC�u�O�ȓI�Ȏ��Â͖]�܂Ȃ������ȓI���Â̔͂��イ�Ŏ��Â���]����v�Ƃ̈ӌ��Ɋ�Â�37�T�Ōo�T���ʎ��R�� �ɂďo���B�o������ɕ�e�ɕ����ꂽ��C�C�Ǔ��}�ǂ���NICU�֓����C�ċz�Ǘ����J�n�����B�x�������C����79�Ŏ��S����܂ŁC��e�͂قږ����� ��ɖK��C�l�H�ċz�Ǘ����ŕ������⟔�����s�����B�ċz��Q���i�s���C�x�����������Č�������Ԃ̎����C�`�[���Řb�������C�a�@����뉀�ւ̎U�����āB �O���ɂ̓X�^�b�t�ƈꏏ�ɂĂ�Ă�V��������āC���V�̉��C��t�C�Ō�t���������ď��߂Ẳ��O�ւ̎U�������������B�Ƒ��͏I�n�Ί�Ŏʐ^��r�f�I�B�e ���s�����B�����S���Ȃ����̂́C����3����B�Ƒ��͌�����������~�߁C���Ƃ̂��������̂Ȃ����Ԃ��߂������Ƃ��ł����B �@�����́u�\��s�ǂȎ����̊����ɂ͉Ƒ��Q���^�̃`�[����Â��s���B�����ƉƑ������[���������Ԃ��߂������߂ɉ����ł��邩���ꏏ�ɍl���Ă������Ƃ��厖�v�Əq�ׂ��B �@�̉ߏ����͔�����ׂ� �@�@���Ƃ̗���Ŕ�����������c��w��w�@�@�������Ȃ̍b�㍎�������́C�����̏I������Âɂ��āu�q���̍őP�̗��v��������邽�߂̔��f�́C�P�[�X�o�C�P�[�X�őΉ�����������Ȃ��B���̗̈�Ŗ@���O�ʂɏo�߂���ׂ��ł͂Ȃ��v�Ƃ̍l�����������B �Ƒ����܂ރ`�[���Ŕ��f �@�b�㋳���͂������N�̏����̏I������Âɂ��Ă̌�������C���O���̎��g�݂ɂ��ĕ����B�č���t��̃��[���ł́i1�j���Â���������\�� �i2�j���Â̎��{����ѕs���{�Ɋւ��郊�X�N�i3�j���Â����������ꍇ�ɐ����������������x�i4�j���Âɕt������ɂ݁C�s�����i5�j���Î��{�̏ꍇ�ƕs ���{�̏ꍇ�ɗ\�z�����V������QOL�`��5���l�������ׂ����ڂƂ��ċ������Ă���B1989�N�ɍ��A����ō̑����ꂽ�����̌����Ɋւ�����i�� �{��1994�N�ɔ�y�j�ł́C�����̍őP�̗��v�̏d�v�����w�E����C�q���̍őP�̗��v�͉Ƒ��̍őP�̗��v����Ɨ��������̂Ƃ��Ĉʒu�t�����Ă���B���E ��t��I�^���錾�ł��C�q���̍őP�̗��v�����`�ɍl�������ׂ����ƂƂ���C�s�K�v�Ȑf�f�s�ׁC���u����ь������炷�ׂĂ̎q����i�삷�邱�ƂƂ���� ����B �@�����݂̂Ƃ���l�����ł́C�Ƒ��̖������d�v�ƂȂ�B����ɂ��āC�������́u���e�̔��f���q���ɒ������s���v��^����ꍇ�Ȃǖ@�I�K�����������������Ȃ��ꍇ�����邪�C���܂�@����������߂��Ȃ������悢�Ƃ���������Ƃ��Ă���v�Əq�ׂ��B �@�d�x��Q�V�����Ɖ������u�̍����T���C���~�Ɋւ��Ắu���ۂɂ̓P�[�X�o�C�P�[�X�Ŕ��f����������Ȃ��B�Ⴆ�Ύ��Â�i�߂Ă��������ɏ��ω����邱 �Ƃ͂�����ł�����B�l�H�ċz������C���̌�O������E�l�ɂȂ�Ƃ������@�B�I�Ȕ��f�͂��ׂ��ł͂Ȃ��B���Â𒆎~������Î҂ɌY���Ȃ����Ƃ͖@�̉� �����ɂȂ�Ǝv���v�Ƃ̍l�����������B �@����̓��{�ł̃��[���Â���ɂ��Ắu���e�𒆐S�ɁC��t�C�Ō�t�C�@���ƁC�����ϗ��Ȃǂ̐��Ƃ������C�`�[���ŐT�d�ɔ��f���Ă������Ƃ��厖�B�`�[�������肵�����Ƃ�@�͑��d����Ƃ����X�^���X���d�v�v�Əq�ׂ��B �q���ɂ͈�ÁC�e�ɂ͎q��Ďx���� �@���҉Ƒ��̗���ōu�������T��q�́C���Y���̃g���u������A����ԂɂȂ���������12�N�O��4�ŖS�������o������C�u���쌧�����ǂ��a�@�ł�4�N �ԁC��t�C�Ō�t�C�����̐l���`�[���ł킪�q�̖����x���C�킽��������e�Ƃ��Ĉ�ĂĂ��ꂽ�BNICU�͕����̏�ł�����B�q���ɂ͈�Â��C�e�ɂ͎q��� �x�����K�v�v�Əq�ׂ��B 1�l�̐l�ԂƂ��Ă��킢�����Ăق��� �@�T�䎁�̒����E�z�����́C���Y���̃g���u������ٕz���nj�Q�ɂ���_�f���������]�ǂƂȂ�C�o�����ォ��l�H�ċz����C�Ƒ��𒆐S�Ƃ����� �@�̃`�[���Ɏx�����4�N�Ԃ����B�T�䎁�͖����C������ĕ����͂��C�x�b�h�T�C�h�Ɋ��Y�����B�X�^�b�t�͗z�����������Ƃ��Ăł͂Ȃ��C1�l�� �l�ԂƂ��ĐS���炩�킢�������B �@�T�䎁�́u�M������X�^�b�t����������ꂵ�����ł��~�߂��C�e�Ƃ��ē����Ȃ���̐��̂��锻�f���ł����B�m����X�^�b�t�Ɏx�����čK�������� �Ǝv���v�Ɠ�����U��Ԃ����B�܂��C�d�ĂȐV�������P�A�����ÃX�^�b�t�ɑ��āu��e�́C���C�Ȏq���Y�߂��ɕ�e���i���Ƃ������ӂ̔O�ɂ����Ă��邱 �Ƃ�m���Ăق����B��e�Ƃ��ĉ������������Ƃ����C�����ɉ����Ăق����v�ƁC�e���`�[���̈���Ƃ��Ď�̓I�ɃP�A�ɂ��������Â���̕K�v���������B �u�킪�q�������Ă��邱�Ƃ����Ɋ�сC�������킢�����Ăق����BNICU�͕����̏�ł�����B�q���ɂ͈�Â��C�e�ɂ͎q��Ďx�����K�v�v�Əq�ׂ��B�� ���͗z�����̓��@���Ɏ������o�Y�C���݂�3�l�̖��Ɍb�܂�Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N3��1�� |
| ��30����{�h���w��@���ҍu�� �������Ò��~�̈�×ϗ��`�č��ł͊��҂̎��Ȍ��茠�͏I������Âɂ��K�p����� |
| �@�č��ł̓��[�`���̈�Ís�ׂƂ��Ē蒅���Ă���l�H�ċz���~�Ȃǂ̉������Â̒��~�����C�킪���ł͑傫�ȋc�_�ƂȂ�C��t�̌Y���ӔC��₤�����ɂ���
�W����B�R�����j�X�g�̗��[�[���i���n�[�o�[�h��w�������j�́C���w��̏��ҍu���Łu���{��35�N�ȏ�O�̕č��ƍ��������v�Ƃ��C�č��Ɍ��݂̃��[��
���m������܂ł̌o�܂��Љ���B �č��̗��j��ς���2�̍ٔ� �@1975�N10���C��ɕč���h�邪�����ƂɂȂ�ٔ����n�܂����B�J�����A����ԂƂȂ���21�̏����J�����E�N�B�������̗��e�����̐l�H�ċz����O�� �悤�C�i�ׂ��N�������̂��B�ٔ��́u�ċz��ɂȂ���Ă܂Ő������ꑱ�������Ȃ��v�Ƃ������C����������̖��̈ӎv�́C���@�ŕۏႳ�ꂽ�u���҂̎��Ȍ��� ���v���Ƃ��闼�e�ɑ��C�u�ċz��O���͎E�l�ň�×ϗ��ɂ�������B�ޏ��̌ċz����O�����Ƃ͈��y���̍��@���ɓ����J���v�Ƃ����厡�㑤�̋��ۂ̎p������ �_�ƂȂ����B�����͏،��ɗ�������t�������l�H�ċz��O���ɂ͂������Ĕ�����������B �@��R�����i�����ٔ����j�͈�t���̎咣��F�߂����C�T�i�̌��ʁC�B�ō��ق͗��j�I�ȍٌ����������i1976�N3���j�B�i1�j�������`���Ɗ��҂̎��Ȍ� �茠�̕ی�̗D��x�́C�N�P���x�Ɨ\��̃o�����X�ōl����ׂ��ł���C�̌����݂̂Ȃ����҂ɑ��āC�{�l�̈ӎv�ɔ�����N�P�̑傫�ȉ������u�𑱂��� �͕̂s�����i2�jincompetent�Ȋ��҂̎��Ȍ��茠���W������ׂ��łȂ��C�{�l���悭�m��Ƒ��ɂ��ӎv�̐���͍����I�`�Ƃ������R�̉��C7�l �̔����S����v�Łu���҂����Â����ۂ��錠���͌��@�ŕۏႳ��Ă���C�ċz����O���s�ׂ͎E�l�߂łȂ��v�Ƃ��������������C�����Ɉ�t��i�ǂ̋��|����� ��������u�ϗ��ψ���v��a�@���ɐݒu���邱�Ƃ𐄏������B �@����1�̑傫�ȍٔ���1988�N3���Ɏn�܂����N���[�U�������B��ʎ��̂̌��ǂŐA����ԂƂȂ����i���V�[�E�N���[�U���̉Ƒ������̌�4�N�ڂɁu�o �ljh�{�̒��~�v��a�@�ɐ\�����ꂽ�Ƃ���C�u�ċz��O���̗v���͎邪�C�o���h�{�͊O���Ȃ��v�ƍٔ��ƂȂ����B��̃N�B������������C�ċz��O���͑S�� �Ń��[�`���ƂȂ��Ă������C�a�@������~�Y�[���B�̏B�@�ł͌o�ljh�{�͈�Ís�ׂł͂Ȃ��C���~�͎��Ȍ��茠�̋y�Ȃ��u��@�v�ƒ�߂��Ă����ق��C���� ���~�̍����ƂȂ�{�l�̈ӎv�ɂ��Ă��m���ȏ؋������߂Ă����B �@�ŏI�I�ɘA�M�ō��قɎ������܂ꂽ���ٔ��́C�B�@�������Ƃ��C�Ƒ����̔s�i�ɏI��������C�����Ɂi1�j���҂����Â����ۂ��錠���͌��@���ۏႵ������ �i2�j�o�ljh�{����Ís�ׁ`�Ƃ�������I�ْ肪�s���C��̂�蒼���ٔ��ɂȂ������B������Ɂu�i���V�[�͐A����ԂɂȂ�ǂɂȂ��ꐶ�����ꂽ���Ȃ� �ƌ����Ă����v�Ƃ��������̏ؐl���o���������Ƃ��C�u���Ă��m�ł���؋��v�Ƃ��C1990�N12���C�B���F�ٔ����͌o�ljh�{���~�̖��߂������C�i�� �V�[�͂���2�T�Ԍ�C�▽�����B ���y���E�E�l�ƍ������閵�� �@�����͈ȏ���Љ����ŁC�u�č��ɂ�����c�_�́C�I������Âɂ����Ă����Ɋ��҂̌�������邩�ɐs����v�ƕ]���C���Ɍ�����1�̕���掦�����B�u�g���Áh���J�n���Ȃ�������C���~�����ꍇ�C�m���Ɏ��ʂƕ������Ă��Ă��C���҂ɂ́g���Áh�����ۂ��錠��������v �@1982�N8���C�ă��T���[���X�S�����ǂ��C�������Â𒆎~����2�l�̈�t���u�E�l�߁v�ō�������Ƃ����S�ď��̎��Ⴊ�������B2�퍐�͏p��C������� �ƂȂ������҂̉������Â��Ƒ��̗v���Ɠ��ӂ̉��ɒ��~����Ƃ����u�����n����t��Ɩ@���c�̂Ƃ̋��c�̏�ō쐬���ꂽ����̃K�C�h���C���ɏ]�������u�v ���s�����킯�����C��R���i���p�C��R�i�ǑÓ���̏B�T�i�R�i�O�R�j�́C���i�s���ْ̍���������B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N3��15�� |
| �����[�u�́u�s�J�n�v�ŁA��t��Ɛ�- ���}�h�c�A���@�Č��Ă�� |
| �@���}�h�̍���c���ł���u�������@�������l����c���A���v�i������q�P�F�E����}�Q�@�c���j��3��22���ɑ�����J���A15�Έȏ�̏I�������҂��A
�h�{�␅���̕⋋���܂މ����[�u�́u�s�J�n�v����]����ꍇ�A��t���[�u�����Ȃ��Ă��A���̖@�I�ӔC����Ȃ��Ƃ���u�I�����̈�Âɂ����銳�҂̈ӎv��
���d�Ɋւ���@���āv�i���́j�̌��Ă��������B���c�A��2005�N�ɔ������A����A�����A�����ȂǗ^��}�̍���c��112�l���Q�����Ă��邪�A���Ă��o��
���͍̂����߂āB �@���ẮA���ʂȂǂŊ��҂̈ӎv�\�������邱�Ƃ�O��ɁA2�l�ȏ�̈�t���A�u�s�����邷�ׂĂ̓K�Ȏ��Â����ꍇ�ł��A�̉\�����Ȃ��A������ �ԋ߁v�Ɣ��肵���ꍇ�Ɍ���A�S���オ�����[�u���s��Ȃ��Ă��\��Ȃ��Ɩ��L�B�I�������҂̏��a�̎��Â��u�ɂ̊ɘa�ɂ��ẮA�u�����[�u�v�̑ΏۊO�Ƃ� ���ق��A���ݍs���Ă��鉄���[�u�̒��~�͊܂܂�Ȃ��B �@��t�̖����A�Y���A�s����̐ӔC�͖��Ȃ��Ƃ������A�����[�u���n�߂Ȃ��ꍇ�A��t�͊��҂܂��͉Ƒ��ɐ������A������悤�w�߂�Ƃ����B ������A���٘A�Ȃǂ���T�d�_������ �@���̓��̑���ł́A���{��t��⊳�Ғc�́A���٘A�Ȃǂ���q�A�����O���s�������A�e�c�̂���͓��Ăւ̔��Έӌ���T�d�_�����������B �@����̓��쌪���C�����́A�u�i�����[�u�́j�����T��������@�������邱�Ƃ��A�{���ɈӖ�������̂��B���~�̖����܂߂āA��͂���ɋ��E������v �Ǝw�E�B���̏�ŁA�u�I�����œx�d�Ȃ�i�ׂ��N����̂͂Ƃ�ł��Ȃ��v�Ƃ̊�@���������A�T�d�ȋc�_�����߂��B �@�܂��A��Q�Ғc�́uDPI���{��c�v�̎O�V���c���́A�u�Ȃ����̂悤�Ȗ@�����K�v�Ȃ̂��B�N�̂��߂ɕK�v�Ȃ̂��v�Ɣ��̍l���������B���٘A�̐l���i�� �ψ����Õ���̕�����������A���Ăɔ��̗����\��������ŁA�u�ӎv�\���̓P��̕��@��A���̗L���̊m�F���܂߁A�ߋ��̈ӎv�̕\������A�����Ɍ��� �̖{�l�̈ӎv�f���Ă����̂��v�Ɩ���N�����B �@����A���{����������̕��������œ��Ȉ�̗�ؗT�玁�́A�u��w�̐i���ɂ���āA��t�哱�^�̍s���߂�����Â��i�v�Ƃ��A���҂�QOL�̊ϓ_����A ���x�̕K�v�����w�E�B�܂��A������̏�C�����ŁA��������t�̒����a�G���́A�u�������鐶���x���Ȃ�����A�����܂Ŋ��҂���̈ӎv�A��{�I�l���d���� ���v�Əq�ׂ��B �@���c�A�ł́A������ւ̖@�Ē�o��ڎw���Ă��邪�A���q��́u�ّ��ɖ@��������l���͑S���Ȃ��v�Ƃ��A�u���ꂼ��̐��}�ɂ������A�肢�������āA����ꂪ�o�����Ă�������������������ŁA�ŏI�I�Ȏ��܂Ƃ߂ɓ��肽���v�Əq�ׂ��B ��É��CB�j���[�X�@2012�N3��22�� |
| �S���a�������A�u�K�v�v�����F�m�x�Ⴍ �I�����K�C�h���C���A����ւ̕��y�i�܂� |
| �@�I�����K�C�h���C���͕K�v�����A�m���Ă�����̂����p���Ă�����̂��Ȃ��\�B�S���{�a�@����i�S���a�j���a�@�Ȃǂ�ΏۂɎ��{���������ŁA�I�����K�C�h���C�������y���Ă��Ȃ����Ԃ����炩�ɂȂ����B �@�S���a��2011�N�x�A�a�@����ی��{�݂Ȃǂ�ΏۂɃA���P�[�g�����{�B���̂����a�@�i427�J���j�A���V�l�����{�݁i325�J���j�A���V�l�ی� �{�݁i200�J���j�A���×{�^�V�l�ی��{�݁i32�J���j�A�O���[�v�z�[���i638�J���j�A�K��Ō�X�e�[�V�����i319�J���j�̍��v1941�J������� �����i�����27���j�B�����ɁA�e�{�݂ɏ�������E���i��t�A�Ō�t�A���m�Ȃǁj�A���҂̉Ƒ��ɑ��Ă��A���P�[�g���s���A�E��7869�l�A�Ƒ� 5215�l������i�������22���A15���j�B �@�I�����K�C�h���C���̕K�v���ɂ��Ď{�݂��Ƃɕ������Ƃ���A�u���������������v�Ɠ������̂́A�a�@�i409�J���j��62.8���A���ی��{�݁i546 �J���j��73.4���A�O���[�v�z�[���i625�J���j��71.4���A�K��Ō�X�e�[�V�����i318�J���j��67.6���B��Â���̌���ōL���I�����̃K�C �h���C�������߂��Ă�����Ԃ����炩�ɂȂ����B �@�ː��s���a�@�i�x�R���j�̌ċz��O���Ȃǂ����������ƂȂ�A�W�w���ђc�̂͑������ŏI�����K�C�h���C���������B06�N�ɂ͓��{�W�����È�w�� ���u�W�����Âɂ�����d�NJ��҂̖�����Â̂�����ɂ��Ă̊����v���A07�N�ɂ͌����J���Ȃ��u�I������Â̌���v���Z�X�Ɋւ���K�C�h���C���v�\�B ���̌�����{��t�����{�~�}��w��A�S���a�Ȃǂ��I�����ɂ��ăK�C�h���C�������肵���B �@�������A�����̃K�C�h���C������Â���̌���ɂ͕��y���Ă��Ȃ��B�����̏I�����K�C�h���C����m���Ă��邩�A�E���ɕ������Ƃ���A�u�m���Ă���K�C �h���C���͓��ɂȂ��v�Ɠ������̂́A�a�@�E���i1870�l�j��64.1���A���V�l�����{�ݐE���i1347�l�j��74.3���A���V�l�ی��{�ݐE�� �i812�l�j��75.5���A���×{�^�V���E���i149�l�j��75.6���A�O���[�v�z�[���E���i2348�l�j��79.9���A�K��Ō�X�e�[�V�����E�� �i1326�l�j��68.2���ɏ�����B���J�Ȃ̃K�C�h���C���̔F�m�x�͔�r�I�����������̂́A�u�m���Ă���v�͕̂a�@�E���i1870�l�j��19.6������ ���������B �@�I�����K�C�h���C���̗��p���Ԃ��ƁA�u���p���Ă�����̂͂Ȃ��v�Ɖ����̂́A�a�@�i408�J���j��66.7���A���ی��{�݁i536�J���j�� 47.2���A�O���[�v�z�[���i613�J���j��52.5���A�K��Ō�X�e�[�V�����i310�J���j��63.9���B�I�����K�C�h���C�������������Ă��A����ł� �F�m�͐i�܂��A���p������Ă��Ȃ����Ƃ������ꂽ�B �@�܂��A�I�����K�C�h���C���ɖ��L���ׂ�������E���i7852�l�j�ɕ������Ƃ���A�u�ӎv�m�F�ł��Ȃ��ꍇ�̑Ή��v��64.7���ƍł������A�����Łu�{�l �̈ӎv�m�F�̕��@�v�Ɠ��������̂�50.6���ɏ�����B�Ⴆ�Ό��J�Ȃ̃K�C�h���C���ł́A������̎����ɂ��Ă��G����Ă��邱�Ƃ���A���ݎ��̂̔F�m ���i�߂Ό���̃K�C�h���C�������p�����\��������B �@����s�S��x���Ȃǂ̔�������������҂ɂ��ẮA�{�ݑ��ƉƑ����̏I�����Ɋւ���F���̃Y�����傫�����Ƃ����炩�ɂȂ����B�{�݂ɓ����Ă��銳�҂� ���āA�{�݂ƉƑ����ꂼ��ɏI�������Ǝv�����ǂ��������Ƃ���A���ł́A�{�݂��I�������Ǝv���Ă��銳�ҁi120�l�j�̂����A�Ƒ����I�������Ǝv�� �Ă����̂�90.8���B����ɑ��Ĕ���ł́A�{�݂��I�������Ǝv���Ă��銳�ҁi148�l�j�̂����A�Ƒ����I�������Ǝv���Ă����̂�79.7���B����� �́A���ɔ�ׂďI�����̗\��\����������ƂȂǂ���A�F���̃Y�����傫���Ȃ����̂ł͂Ȃ����ƍl������B �@���̒��������́A���J�Ȃ�2011�N�x�V�l�ی����Ɛ��i��⏕���őS���a���s�����u�I�����̑Ή��Ɨ��z�̊Ŏ��Ɋւ�����Ԕc���y�уK�C�h���C�����̂�����̒��������v�B�ڍׂ͑S���{�a�@����̃E�F�u�T�C�g�Ō��J����Ă���B ���o���f�B�J���I�����C���@2012�N4��26�� |
| ��26��D�y�~�G����Z�~�i�[�@�q���������҂Ɏx���� |
| �@�ߔN�C�咰����������Ȃǂł�40�`60�Α�Ɣ�r�I��N�̜늳�҂��������Ă���B�`���C���h�E���C�t�E�X�y�V�����X�g�iCLS�j�ŁC�k�C����w�a�@
��ᇃZ���^�[�̓��䂠���ݎ��́C�q���������҂̎x�������ɂ��ĕB�u�q��Đ���̂��҂̑������C�q���ɂǂ�������������悢�̂��Y��ł�
��C���������e�q�o���ւ̎x�������߂��Ă���v�Əq�ׂ��B �m�炳��Ȃ��ƕs����X�g���X�� �@CLS�Ƃ́C�a�C�̎q���C�a�C�̐e�����q���_�E�S���Љ�I�ɉ�������l�ŁC1950�N��ɕč��Œa�������B���ݍ�����25�l�C�S���E�Ŗ� 4,000�l����������B���䎁�͓��@�̊ɘa�P�A�`�[���ɏ������C����̏������C���Ê��C�I������ʂ��āC�q���������҂���̑��k�ɉ����Ă���B �@�č��ł́C�e������ɂȂ����ꍇ�C�q���ɂƂ��ėL�v�ȏ��Ƃ��āC�i1�j�a�C�͂���Ƃ������O�iCancer�j�i2�j����͓`�����Ȃ��inot Catchy�j�i3�j����ɂȂ����̂͒N�̂����ł��Ȃ��inot Caused�j�`��3C���l�����Ă���BCLS�́C��@�I�ȏɂ����Ă��q�����u�͂̂��鑶�݁v�ƂƂ炦�C�q��������̗͂��ł���悤�x������� �����B �@�����ɂ��ƁC�e�ٕ̈ςɂ��āC���Ƃ��c���ł������������Ă���C���̎������~�߂�͂�����B�q���́C�m�炳��Ȃ��Ƃ̂��҂ɂ��ꂽ�Ɗ����C���� ���Ύ��ۈȏ�Ɉ������Ԃ�z�����C�����̂����Őe���a�C�ɂȂ����Ǝv���B�s����X�g���X���C�s���C�H�~�s�U�C�s�o�Z�Ƃ��ĕ\�ʉ����邱�Ƃ�����B �s�A�T�|�[�g�̃T��������2��J�� �@�e���q���ɕa�C�ɂ��Ęb���Ƃ��́C�q���̔N���ɉ����ė������₷�����t���g���C�w�����ȏ�ł͐g�̐}�Ȃǂ��Q�Ƃ���Ƃ悢�B���O�ɓ`���������e���������C���������Ęb����^�C�~���O�ƐÂ��ȏꏊ��I�ԁB�W���͂��r�ꂽ��x�e���C�q���������p���ɂȂ�܂ő҂B �@�q�������S�ł��邽�߂ɂ́C�w�����܂ł͐e�Ƃ̃X�L���V�b�v���d�v�ɂȂ�B�e�̓��@�Ȃǂ̕ω��������Ă��C���ɓ��c���ł́C�e���Ȃǂ��玙��Ǝ����s ���ē��퐶����������x�ۂ���邱�Ƃ��]�܂����B�v�t���ł́C�e�̕ω��Ɍ˘f���Ȃ�����e���C�������R�ƐU�镑���X��������C���������ɂ��钇�Ԃ̑��݂� ��������鏕���ɂȂ�B �@���䎁��͍�N5���ɁC�s�A�T�|�[�g�̈�Ƃ��āC�u�킩�J�t�F�v�Ƃ����q��Đ���̂��҂̂��߂̃T�������X�^�[�g�������B������2�E4���j���� �ߌ�2�`4���ɊJ�Â��C30�`50�Α�̏����𒆐S��7�`8�l�O��̎Q��������B�܂��C�e�̌������ɗ����q���̌ʃP�A�⓯�������̎q�����m���𗬂ł��� �������Ȃǂ̎x���������s���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N5��10�� |
| �č��z�X�s�X�{�����e�B�A�Ŋ��̂Ƃ��܂� |
| �����W�߂���⑰�̃P�A�܂� �@���������߂��ɂ���z�X�s�X�̌���B���{�ł͂܂������ꂽ�C���[�W�����邩������Ȃ��B�����A�z�X�s�X��i���A�����J�ł́A�����̎s�����{�����e�B�A�Ƃ��Ċւ���Ă���B �@�A�����J�A�G�b�O�n�[�o�[�^�E���ɂ���A�g�����e�B�z�X�s�X�ł́A�{�����e�B�A���d�v�Ȗ�����S���Ă���B �@�����̓��e�́A���҂̖K��A�N�ɐ���̃C�x���g�̏����A�����W�߂ȂǁB�܂����l���A�ߗׂ̈⑰�̂��Ƃ�K�ˁA�O���[�t�T�|�[�g������B�Q������{�����e�B�A�́A�O���[�v���Ƃɐ��I�Ȍ��C����B �@�挎�A�{�����e�B�A�̕\�������s���A����܂�3000���Ԉȏ㊈�����Ă���145�l�ɋL�O�i������ꂽ�B ��Ȃ̂͊��҂ւ̌h�ӂƖ��邳 �@�Ȃ��ł����҂̖K��ɂ͈�Ԃ�肪����������Ƃ����{�����e�B�A�������B10�N�ɓn�芈�����Ă����n���[�h����i81�j�͂����B �u�z�X�s�X�Ƃ����Ă��A�������ɂ��Ęb���Ă���킯�ł͂���܂���B���҂���Ɖ̂�����A�F������A�Ƒ��̂��Ƃ�b�����肵�Ă��܂��B����Ȏ��Ԃ��� �ꂵ���āA���̊Ԃɂ��A���̂ق������҂���ɉ�����Ă����ɒʂ��悤�ɂȂ��Ă��܂����B��Ȃ̂͊��҂���Ɍh�ӂ������āA�����Ă˂ɖ��邭�ڂ��� ���Ƃł��v�B �Ŋ��ɂЂƌ��������� �@�{�����e�B�A�����҂̎��ɗ��������P�[�X�������B�R�[�f�B�l�[�^�[�̃z�y����́A���̂Ƃ���������A�������犳�҂Ɍ��t�������Ăق����Ƙb���B �u���t����������A���҂���͍Ŋ��Ɏ����̂��Ƃ��C�ɂ����Đ��b�����Ă��ꂽ�l�������ɂ��邱�ƂɋC�Â��܂��B���ꂾ���̂��Ƃł���������A���炩�ɖ���ɂ����Ƃ��ł���̂ł��v�B �`�����e�B�j���[�X�@2012�N5��14�� |
| �����[�u�́u���~�v�ł���t�Ɛ� ���}�h�c�A�A�������@�Ăœ�Ă�� |
| �@���}�h�őg�D����u�������@�������l����c���A���v�i��E���q�P�F����}�Q�c�@�c���j��6��6���̑���ŁA�u�I�����̈�Âɂ����銳�҂̈ӎv�̑��d�Ɋւ���@���āi���́j�v�ɂ��āA��̈Ă����\�����B �@���ĂƂ��A�I�����ɂ��銳�҂̈ӎv�d���邽�߂ɁA�����[�u�Ɋւ���ӎv���肪�ł��邱�Ƃ�@���Œ�߂�ƂƂ��ɁA�@������߂�����ɍ��v�����Ή���������t��Ɛӂ��邱�Ƃ��ړI�B �@���Ă̑���͂��̑Ώۂɂ���B�����[�u�́A�i1�j�����[�u���J�n���Ȃ��ꍇ�i�s�J�n�j�A�i2�j�l�H�ċz��̎��O���ȂǁA���ɍs���Ă��鉄�����Â𒆎~ �����ꍇ�\�\���l������B���N3���Ɍ��\�������Ăł́A�O�҂Ɍ����Ă������A�i2�j���Ώۂɉ�����Ă��V���ɏo���ꂽ�B�܂�����ȊO�̕������A3���� ���Ă���ꕔ�C�����ꂽ�B �@6���̑���ł́A���{��t��Ɠ��{�ٌ�m�A����ւ̃q�A�����O���s��ꂽ���A������̒c�̂���������_�ł́A�������̖@�����ɂ��Ďx���͓����Ȃ������B �@���㕛��̉H���c�r���́A�u�����[�u�̕s�J�n������Ώۂɂ��邾���ł͕s�\���ł���A�����[�u�̒��~����������_�͐i�������v�Ƃ������̂́A�u������ ��@���ŋK�肷�邱�Ƃɂ��A��t�Ɗ��҂̐M���W�Ɋ�Â�����܂ł���Ă�������ɍ������������˂Ȃ��B�@������O�ꂽ�Ή��������ꍇ�ɁA�@���ɑ����� ���Ȃ��Ƃ���A��t���ӔC�Njy����邱�Ƃ��������Č��O�����v�Ƃ̍l�����������B����ɁA�����[�u�̒�`����Î҂̊Ԃł��K���������m�ł͂Ȃ���A���� �J���Ȃ�e�w��̏I������ÂɊւ���K�C�h���C�������y���Ă���Ƃ͌�������ƁA����Ŋ��ґ��ɂ����Ă����r���O�E�E�B�����Z�����Ă���Ƃ͌����Ȃ��� �Ƃ���A����ɐT�d�ȋc�_���K�v���Ƃ����B �@���٘A�l���i��ψ���ψ����̑��q�l�����́A�u�������̖@�����ɔ��v�Ɩ����B���̗��R�Ƃ��āA�u���҂̎��Ȍ��茠�́A�������Â̏�ʂő��d���� ��ׂ��ł���A�����I�����Ɍ�����̂ł͂Ȃ��B�������A���͊��ґS�ʂ̎��Ȍ��茠��ۏႷ��@���͂Ȃ��B�����ۏႷ��@�������A�I�����ɂ����鎩�� ���茠���������o���Ė@��������Ӗ��͂Ȃ��v�Əq�ׁA�u���҂̌����@�v�u��Ê�{�@�v�̂悤�Ȉ�ÑS�ʂɂ킽��@������邱�Ƃ��������߂���Ƃ����B �@�����c�ł́A��Q�Ҋ֘A�̒c�̂ɑ���q�A�����O���s�����A��Q�Ҋ֘A�c�̂��������̖@�����ɂ͔����Ă���A������c�_�̓�q���\�z�����B���q�� ���͍Ō�ɁA�u�ّ��͔����A�����I�ȗ�������ŁA�c�����@��ڎw�������v�ƈ��A�B��c��A�u�������������Ȃ���A������ւ̖@�Ē�o�͓���B �������A��������������A���߂č��̋c�A�̋c���̔C�������O�ɂ͖@�Ă��o�������v�ƃR�����g�A�܂�6���̓�Ă̂�������̗p���邩�́A����̋c �_����ł���Ƃ��Ă���B �u�I�����v��2�l�ȏ�̈�t�����f �@�������̖@�����́A���{����������Ȃǂ��x�����Ă�����̂��B6���Ɍ��\���ꂽ��ẮA�O�q�̂悤�ɖ@���̑Ώۂ��u�����[�u�̕s�J�n�v�݂̂Ƃ��邩�A�u�����[�u�̒��~�v�������邩�ňقȂ�B �@�ȉ��A���ʕ���������ƁA�u�I�����v�́A�u���҂��A���a�ɂ��čs�����邷�ׂĂ̓K�Ȉ�Ï�̑[�u�i�h�{�⋋�̏��u���̑��̐������ێ����邽�߂̑[�u���܂ށj�����ꍇ�ł����Ă��A�̉\�����Ȃ��A���������ԋ߂ł���Ɣ��肳�ꂽ��Ԃɂ�����ԁv�ƒ�`�B �@�I������ÂɊւ��銳�҂̈ӎv����͂����܂Łu�C�Ӂv�B��Q�Ғc�̂Ȃǂ��猜�O�̐����オ���Ă������Ƃ���A�u�������ێ����邽�߂̑[�u��K�v�Ƃ���� �Q�ғ��̑������Q���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɗ��ӂ��Ȃ�������Ȃ��v�Ɩ��L���Ă���B�܂��A����n�������c�̂ɑ��āA�I������ÂɊւ���[���ȂǂɕK�v�Ȏ{ ����u����悤���߂Ă���B �@�����[�u�́u�s�J�n�v���邢�́u���~�v���ł�������́A�i1�j���҂�����̈ӎv�����ʓ��ŕ\���A�i2�j�u�I�����v�̔���́A�厡����܂�2�l�ȏ�̈�t���s���\�\�ȂǁB�܂��u�s�J�n�v���邢�́u���~�v�̈ӎv�́A���ł��P��ł���Ƃ��Ă���B �@���̏��������A��t�������[�u�́u�s�J�n�v���邢�́u���~�v�̂����ꍇ�A�u������A�Y���エ��эs����̐ӔC�i�ߗ��ɌW����̂��܂ށj�͖���Ȃ����̂Ƃ���v�ƋK�肵�Ă���B �@6���̑���ł͏o�ȋc������A�u��t���Ɛӂ��������ɊY�����邩�ǂ������A�ォ�猾�������ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��̂��v�Ƃ̎��₪�o���ꂽ�B����ɑ��A�c �@�@���ǂ́A�u�ǂ�Ȗ@���ł��A���̗v���ɊY�����邩�ǂ����������邱�Ƃ͂��蓾��v�Ƃ��A����̖@���Ăł����l���Ƃ����B���㕛��̉H���c�����A�� �ɖ@�������肳���A�u�����I�ɂ́A�\���ɐ������āA���ӏ������A�Ή����Ă������ƂɂȂ邾�낤�v�Ƃ̍l�����q�ׂ��B m3.com�@2012�N6��7�� |
| �ɘa�P�A�@�u�����v����u�����邱�Ƃ��x����v�� |
| �R�����e�[�^�[ �\�a�c�s�������a�@ ���ƊǗ��� �b��g�a �� �@�����{�l�̎��S�����̑�1�ʂɂȂ����̂�1981�N�ł��邪�C����ȍ~������ɂ�鎀�S�Ґ��͑����̈�r�����ǂ��Ă���B���݁C���{�l��2�l��1�l �͂���ɜ늳���C3�l��1�l�͂���Ŏ��S����Ƃ����Ă���B����͔]������S�؍[�ǂ̂悤�ɋ}�����鎾���ł͂Ȃ��C�����͈����Ԃ��o�Ĉ������C���� �w�Ö@�Ȃǂ̗L���Ȏ��Î�i���s����I�������}���Ď��S����B���̂��߁C�u�ɂȂǂ̏Ǐ�̃R���g���[����ړI�Ƃ���I�����ɘa�P�A���ɂ߂ďd�v�ɂȂ�B�� �N�̃��C�t���[�N�Ƃ��Ă���̏I������ÂɎ��g��ł����\�a�c�s�������a�@�i�X���j���b��g�a���i�O�@���C�����ƊǗ��ҁj�ɁC�v���C�}���P�A�ɂ����� �ɘa�P�A�ɂ��ĕ������B �ɘa�P�A�̌��_�̓z�X�s�^���e�B�[ �@���҂��������Ă��邱�Ƃւ̑�Ƃ��āC2007�N�Ɍ����J���Ȃ́u������{�@�v���{�s���C���̒��Ŋɘa�P�A�̕��y�������ł��o�����B����� ����āC�S���e�n�̒n�悪��f�ØA�g���_�a�@�Ŋɘa�P�A���C��Ȃǂ�����Ɏ��{�����悤�ɂȂ�C�Q���������Ƃ̂���v���C�}���P�A������Ȃ��Ȃ��Ǝv�� ���B�������C����ɂ��ɘa�P�A�����y�����邩�Ƃ����ƁC�b�쎁�́u�܂��܂������͂����Ȃ��̂�����v�ƌ����B�u�u�ɃR���g���[���Ȃǂ̒m����Z�p �͑����g�ɕt�����Ƃ�����t�͑����̂��낤���C����͊ɘa�P�A�̕\�w�I�ȕ����B�ɘa�P�A��{���ɒ���̂ł���C�����Ɛ[�����O���w�Ԃ��Ƃ��厖�v�� �����͎w�E����B �@�m���Ɋɘa�P�A�Ƃ����ƁC��ʓI�ɃC���[�W�����̂��u�ɃR���g���[���ŁC�Ⴆ�Δ�I�s�I�C�h���ɖ��I�s�I�C�h�̎g�����Ƃ��������Ƃł���B������ ��C���������m����Z�p���K�v�ł��낤���C�������C�����g�ɕt���������ł͊ɘa�P�A���w���ƂɂȂ�Ȃ��C�Ɠ����͌����B�ł́C�������w�Ȃ���� ��Ȃ��Ƃ����ɘa�P�A�̗��O�Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��B�����́u�ɘa�P�A�̌��_�̓z�X�s�^���e�B�[�i�����݁C�v�����C�D�����C�����ĂȂ��C���Y���j�ł� ��C��Â̌��_���̂��̂ł���v�Ƃ��C���̊�{���O�Ƃ��āi1�j1�l1�l�̐l�Ԃ̐��������x����i2�j�y�ɐ����邱�Ƃ��x����i3�j�Ƒ�����҂��x���� �i4�j�`�[���Ŏx����|��4������Ƃ���B �����̎��̌����ړI�Ƃ�����Âւ̓]�� �u1�l1�l�̐l�Ԃ̐��������x����v�Ƃ́C����Ȃ炪��Ƃ����a�������ɖڂ�������̂ł͂Ȃ��C���̕a���������Ă���l���g���ҁh�ł͂Ȃ������Ɠ����g�l �ԁh�Ƃ��đΉ����C���̕a�������邱�ƂŋN���鐶����̕s�ւ��Ȃǂ��ł��邾�����Ȃ����邱�Ƃ��C��ÓI�Ȏ��_�ŁC�{�l�Ƃ̑��k�̏�őΉ����邱�Ƃ��Ӗ� ����B �u�y�ɐ����邱�Ƃ��x����v�Ƃ́C�ǂ̂悤�ȕa��ł���C�\�Ȍ��肳�܂��܂ȋ�ɂ���菜���C�y�ɐ���S���ł���悤�Ɏx�����邱�Ƃ��Ӗ�����B���̂� �߂ɂ́C�a��Ɋւ�����C�����Č������Ȃ����Ƃ�ۏ���̐��Â���C�ݑ�P�A�ɂ����鐶���x���̐��̐����Ȃǂ��d�v�ɂȂ��Ă���B �u�Ƒ�����҂��x����v�Ƃ́C���҂Ɠ��l�ɑ傫�ȕs���C��Y�C��ɂ������Ă���Ƒ����P�A���邱�Ƃ��Ӗ�����B�������ĉƑ��ƈꏏ�ɃP�A�����Ă����̐�����邱�ƂŁC�Ƒ��ɂ��łƂ���\�ɂ�����B �u�`�[���Ŏx����v�Ƃ́C��t�C�Ō�t�C��t�Ȃǂ̈�ÐE�C����уP�A�}�l�W���[�C�w���p�[�Ȃǂ̉��E���C���ꂼ��̎��_�Ŋ��Җ{�l��Ƒ��̃j�[�Y��c��������ŁC�A�g���ĕK�v�Ȏx������邱�Ƃ������B �@�b�쎁�ɂ��Ɓu����܂ł̓��{�̈�ẤC�������������Ƃ�ړI�ɁC���N��ڕW�Ƃ��āC�a�@���S�ɔ��B���Ă����v�B�������C���̍l�����ł́C����̏I�� ���̂悤�Ɏ��Î�i���s�����Ƃ���ł́C���͂�\���ȑΉ������Ȃ��Ȃ�B�����ŁC�����́u���ꂩ��͐����̎��̌����ړI�ɁC������ڕW�Ƃ��āC������ ��𒆐S�Ƃ�����Âɓ]�����Ă����K�v������v�ƌ����B �@�Ȃ��C�ȏ�̂悤�ȍl�����́C��������̏I�����ɂ������Ă͂܂�킯�ł͂Ȃ��B����Ƃ����͖̂���������1�ŁC�S�Ă̖��������́C�₪�Ă͎��Î�i�� �s����I�������}����B���Ƃ���C�ɘa�P�A�̗��O�̎���Ẫp���_�C���V�t�g�́C�S�Ă̖��������ɓ��Ă͂܂�ƌ����Ă悢���낤�B�u���ꂩ��܂��܂� ���{�̒�����Љ�͐i�W���Ă������C����͎���Ȃ����������l�������Ȃ��Ă�������Ƃ�����B���̂悤�Ȏ���Ɍ����ẮC�ǂ����Ă��������߂̈�Â��� �������x�����Âւ̕����]�����K�v�ŁC���ꂪ�ɘa�P�A�̗��O�ł���Ƃ�����v�Ɠ����B �ɘa�P�A�̒S����Ƃ��Ẵv���C�}���P�A �@�ɘa�P�A�������̏�𒆐S�Ƃ�����ÂłȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����C�v���C�}���P�A�͂܂��ɂ��̏�ł���Ƃ�����B�u����܂ł��C�ɘa�P�A�����܂������� �����́C�������̂���a�@�����C���ߍׂ����ݑ�P�A���s���Ă���v���C�}���P�A�ł��邱�Ƃ����������v���b�쎁�B�u���ꂩ��̊ɘa�P�A�̒S���� �Ƃ��ẮC�ނ���C�v���C�}���P�A����������ɂȂ�ׂ��v�Ƃ�����B �@����f�Â̒S����Ƃ��Ẵv���C�}���P�A��́C�a�@�Ζ���ɑ��āC����̃A�h�o���e�[�W�������Ă���B�܂��C�v���C�}���P�A��͓����납�犳�҂Ɛe �����ڂ��C���̐����K����E�ƁC�Ƒ����Ȃǂ�m���Ă��邽�߁C����̃��X�N�����ς���₷���B�����āC���X�N�������Ƃ��ɂ͌��f�E���������߂₷���C���� �ɂ�������₷���B�܂��C����ɜ늳�����ꍇ�ɍ��m����]���邩�ǂ����Ƃ������b���C�v���C�}���P�A��Ȃ�C�ǂ������������Ď��������邱�Ƃ��ł� ��B �@���҂ɂ��������ꂽ�ꍇ���C�����ǂ╹���ǂȂǂɂ��Ă悭�m���Ă���̂̓v���C�}���P�A��ł���B���������āC�u�v���C�}���P�A��͊��҂������ ����ɏЉ��ɂ��Ă��C�S�Ă��ς˂�̂ł͂Ȃ��C�ł��邾�������������悤�ɂ��ׂ��v�Ɠ����B�u�������ɂƂ��Ă��C�v���C�}���P�A�ォ��̏�� �͋M�d�v�ƌ����B �@�������̉��Ŏ��Â��s���Ă���Ԃ́C�ł��邾���o�߂�c�����C���҂Ɛ���Ƃ̋��n�����߂�B���҂Ɛ��ゾ�����ƁC���҂͐���ɉ������� �����������Ƃ������Ȃ��Ƃ������Ƃ����邪�C�v���C�}���P�A�����ĂȂ�C���ꂪ�ł���B�܂��C���҂̉Ƒ����v���C�}���P�A��ɂȂ�C�����Ƒ��k���₷ ���B�u���҂ƉƑ��ɂƂ��āC�ł��s����������C�܂��C���ꂪ��������Ȃ��ƈ�Õs�M�ɂ��ׂ点���˂Ȃ��̂��C��Âւ̃A�N�Z�X���r�₦�邱�ƁB�����h�� �Ӗ��ł̃v���C�}���P�A��̖����͑傫���v�Ɠ����B �ݑ�P�A�ɕK�{�̃`�[����� �@����̉��ł̂��Â��I�������́C�������v���C�}���P�A�オ��Â̒��S�ɂȂ邪�C���̍ۂ��u�ɂ��͂��ߌċz����C�q�C�E�q�f�̃R���g���[���ȂǁC�ɘa�P�A�̋�̓I�Ȓm����Z�p���K�v�ɂȂ��Ă���B �@�v���C�}���P�A�ł��҂̊ɘa�P�A���s���悤�ɂȂ�ƁC�ǂ����Ă��������Ȃ��̂��ݑ�P�A�ł���B�������C1�l�̃v���C�}���P�A��̍s����ݑ�P�A�� �͌��肪����B�����ŁC�Ō�t�C�P�[�X���[�J�[�C�P�A�}�l�W���[�C�w���p�[�ȂǂƂ̘A�g���d�v�ɂȂ�B�b�쎁�̌o���ł́u���Ɋɘa�P�A�ɏK�n�����Ō�t�C �P�A�}�l�W���[�ƃ^�b�O��g�ނ��Ƃ��ł���C��t�̕��S�͑傫���y�������v�ƌ����B �u�ɘa�P�A�ł́C�ŏI�I�ɂ͊��҂̎����łƂ邱�ƂɂȂ�̂ŁC�����炢���Ƃ��肪�C���[�W���ꂪ���B�������C���̈���ŁC�u���҂̐��������x�����v�� �����[����������C�܂��C���҂̐���������w�Ԃ��Ƃ������B���L���v���C�}���P�A�オ�C�{���̊ɘa�P�A��m��C���H���Ă���邱�Ƃ�]�݂����v�Ɠ����͌� �B SUMMARY �@�ɘa�P�A�̌��_�̓z�X�s�^���e�B�[�ł���C��Â̌��_�ł��� �@�ɘa�P�A�̊�{���O�Ƃ��āC�i1�j1�l1�l�̐l�Ԃ̐��������x����i2�j�y�ɐ����邱�Ƃ��x����i3�j�Ƒ�����҂��x����i4�j�`�[���Ŏx����|��4���������� �u������Áv����u�����邱�Ƃ��x�����Áv�ւ̓]���Ƃ����ɘa�P�A�̗��O�́C����̈�ÑS�ʂɕK�v�ȃp���_�C���V�t�g�ł����� �@�ɘa�P�A�̒S����̎���ɂȂ�ׂ��C�v���C�}���P�A��͂��܂��܂ȃA�h�o���e�[�W��L���Ă��� ���f�B�J���g���r���[���@2012�N6��28�� |
| �f�f�����玡�ÏI����������P�A ��17����{�ɘa��Êw��J�� |
| �@��17����{�ɘa��Êw�6��22�|23���C�_�ˍ��ۓW���ꑼ�ŊJ�Â��ꂽ�B�u��Î҂ɂł��邱�Ƃ́C���҂ɊS�������C���Y�������邱�Ɓv�ƍu��
�Ō���������������i���R���w�@�j�̂��ƁC�u�Ђ낭�@�ӂ����@�������v�Ƃ������e�[�}���f�����C�����̉��肪���\���ꂽ�B�{���ł́C�T�o�C�o�[
�V�b�v�ƁC��������̊ɘa�P�A���c�_���ꂽ�v���O�����̂��悤�����B ��������������̎��ォ�玟�̎���� ���������� �@���҂ƈ�Î҂������d��ɕ��p�l���f�B�X�J�b�V�����u�T�o�C�o�[�V�b�v�Ƃ����l�����\�\���Â��I���Ă�����@�Ђ낭�@�ӂ����@�������v�i�� �������H�����ەa�@�E�R���p�q���j�ł́C�܂�MD�A���_�[�\������Z���^�[��Lewis Foxhall�����C����T�o�C�o�[��QOL�����߂邽�߂ɓ��@�Ŏ��{���Ă���u�T�o�C�o�[�V�b�v�N���j�b�N�v�ɂ��Ĕ��\�����B�����ł́C�Ĕ��h�~�� �S�Ƃ������҂ւ̃P�A�����łȂ��C�v���C�}���E�P�A���Ō�t�C�\�[�V�������[�J�[�ւ̋�����s���Ă���B�܂��C���ǂ⎡�ÂɊւ��錤�������Ƃ� ���B���́C����T�o�C�o�[�V�b�v�͂���̎��Ð��т⊳�҂�QOL�����߂�V�����삾�Ƃ��C��w�̔��W�Ɋ��҂����B �@����T�o�C�o�[�̗��ꂩ��́C����Ȃ��ݎ��iNPO�@�lHOPE�v���W�F�N�g�j�Ə����C�ꎁ�iTBS�e���r�j���o�d�B�܂����䎁�͎��g�̌o������C���� �Ɛf�f���ꂽ���҂́C�a�ɂȂ�ȑO�ɂ��������܂��܂Ȗ�����r�����邱�Ƃɂ���āC���g�̍����I�ȑ��݂������X�s���`���A���Ȓɂ݂������Ă���Ɛ����B �Q�Ȃ�����Î҂Ɍ����āC���҂̐����������Ɏx�����Ăق����Ƒi�����B����ŁC���������ɂ݂͎����̐�����Ӗ���₢�Ȃ������߂̋M�d�ȃL�����T�[�M�t�g �ł�����ƁC�O�����Ȍ������������B �@�����Ĕ��������������́C����T�o�C�o�[�͈�Î҂ɂƂ��āg���������ȏ��h�ł���Ƌ����B���́C����̍Ĕ����^���Ď�f�����a�@�ŁC������摗��ɂ� ��C�����s���ƕs�M���������o������C���҂̕s���������ł���菜���ɂ͑������f�̌����E��p���d�v�Ƃ̍l�����������B�܂��C���҂̌o���k�ɂ͎��É��P�� �q���g����������Ǝ咣���C���҂̐��Ɏ����X����悤��Î҂ɋ��߂��B �@��Î҂̗��ꂩ��͎O�����o�d�B������Ǖa�@�̊Ō�t�ł���]���b�q���́C���@�Ŏ��g��ł���T�o�C�o�[�V�b�v�P�A�v���O�����ɂ��Ĕ��\�����B���ғ��m���݂��̑̌�����荇������C�a�⎡�Âɂ��Ċw�Ԃ��ƂŁC���S���Ď��ÂɑO�����ɗՂނ悤�ɂȂ����Əq�ׂ��B �@��t�̉��R���j���i�����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�j�́C���ɂ͊��҂������̉Ƒ��̂ق��������s��������Ă���ꍇ������Ǝw�E�B���Z���^�[���݂����s�A�T�|�[�^�[�ɂ�鑊�k���C���҂�Ƒ�����炤�T�����Ȃǂ̎��g�݂ɂ��ĕ����B �@�Ō�ɓ�����̐���ł���R�����́C�u���҂炵���ł͂Ȃ��C���Ȃ��炵���v�Ƃ������b�Z�[�W��`���C�G�r�f���X�����łȂ����҈�l�ЂƂ�̃i���e�B�u�Ɋ�Â������Â��s�����Ƃ��Ă����B �@���̌�̃f�B�X�J�b�V�����ł́C����T�o�C�o�[�ł����Î҂ł�����Q���҂���C�u��Î҂͂��܂��ɂ���T�o�C�o�[����Ís�ׂ̑ΏۂƂ������Ă��Ȃ��X ��������B��Î҂̍l����g�ǂ��g�g�݁h�Ɋ��҂���������ł͂��Ȃ����v�Ƃ�������N���Ȃ��ꂽ�B����ɑ��R�����́C����͈�Î҂Ɗ��҂Ƃ����� ���ł͂Ȃ��C�o�����ЂƂɂȂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��������C���̂��߂ɂ͈�Î҂����҂̏A�J���Ɋ֗^����ȂNj�̓I�ȃA�N�V�����v���������s ���Ă����K�v������Əq�ׂ��B ��������̊ɘa�P�A������ �@WHO�̐V��`�i2002�N�j�Łu��������̊ɘa�P�A�v��搂��Ă���10�N�C���̋@�^�����X�ɍ��܂����B2012�N�x����̐V���ȁu������� �i��{�v��v�ɂ����Ắu����Ɛf�f���ꂽ�Ƃ�����̊ɘa�P�A�̐��i�v���d�_�ۑ�̂ЂƂƂ���C�ɘa�P�A���C�̐��̌�������̐��̐�����}�邱�Ƃ� �ʖڕW�Ƃ��Ė��L���ꂽ�B �@�܂��C�O�ɂ����ẮC���҂�QOL�Ɋւ���_�����N�X�������Ă���B���ł��S���W�߂��̂́C�]�ڐ��זE�x�����҂ɑ��鑁���ɘa�P�A�����̌� �ʂ�������Jennifer S. Temel����̘_�����iN Engl J Med. 2010�mPMID: 20818875�n�j�B���w��ł́C�}�T�`���[�Z�b�c�����a�@����Z���^�[�ɂ�����Temel���ƂƂ��Ɏx���Ö@�����O���[�v�𗦂���William Pirl�������ق��C�u���ƃp�l���f�B�X�J�b�V��������悳�ꂽ�B �@�C���^�[�i�V���i�����N�`���[�u��������̊ɘa��Áv�ɂ�����Pirl���́C�u�ɘa��Â͐ϋɓI���Âƃz�X�s�X�̊Ԃ̃M���b�v���ǂ����߂�̂��H�v�Ɩ� ���N�B���f���P�[�X�Ƃ��āC�Ō�t�ɂ��d�b�J�E���Z�����O�ɂ��������̂�ENABLE�v���W�F�N�g�iJAMA.2009�mPMID: 19690306�n�j�̂ق��C�O�q�̘_���̌����f�U�C��������B���̌����ł́C�V���ɓ]�ڐ��זE�x���Ɛf�f���ꂽ����151�l���u���̕W�����Áv �Q�Ɓu���̕W�����Á{�����ɘa�P�A�v�Q�ɖ���ׂɐU�蕪���C�O�҂͊��ҁE�Ƒ����ᇓ��Ȉ�̗v�]���������ꍇ�̂݁C��҂͌��ɍŒ�1�x�͊ɘa�P�A�オ�� ���B���̌��ʁC�ꎟ�G���h�|�C���g�ł���12�T�ڂ�QOL�ω��ɂ����ẮC�����ɘa�P�A�Q�̂ق����L�ӂ�QOL���ǍD�������B�܂��G���h�|�C���g�Ƃ� �āC�����ɘa�P�A�Q�ɂ����ė}���Ǐ��P�����ق��C�������Ԃ̉����܂ł����F�߂�ꂽ�Ƃ����B �@���^�����ł́C�u�Ȃ������ɘa�P�A�ɂ���Đ������Ԃ����т��̂��v�Ƃ����_�Ɏ��₪�W�������BPirl���́u�i���̌����f�U�C���Łj���̗��R�܂ł͂킩 ��Ȃ��v�ƑO�u�����C�����ɘa�P�A�Q�ł͏I�����ɂ����ĉ��w�Ö@�𒆎~���鎞���������X���ɂ���C���̂��Ƃ��������Ԃ̉����Ɋ�^�����Ƃ���������� ���B�܂�����ŁC�����̌��ʂɂ���œ_�Ă�ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ��q�ׁCQOL���P���������d�v�Ȍ��ʂł���Ƌ��������B�Ȃ����ݑ��̓]�ڐ��x������� ����ɂ����ē��l�̌������i�s���Əq�ׁC����Ȃ�m���̏W�ςɊ��҂����B �@�����p�l���f�B�X�J�b�V�����u����Ɛf�f���ꂽ������̊ɘa�P�A�̎��H�̂��߂Ɂ\�\���ÂƊɘa�P�A�̗����v�i������JA���m�a�@�E�]���O�Y���C���R ���w�@�E�����r�`���j�ł́CPirl���Ɠ��{�̉���6�l�����{�݂ɂ����鑁���ɘa�P�A�̎��g�݂�BPirl������ᇓ��Ȉ�Ƃ̖��ڂȘA�g�ɂ��O ���ɘa�P�A�̎��݂��Љ���ق��C���{����͉@�O��ǂƂ̕����Ō�t�ɂ�鎿�⎆�X�N���[�j���O�Ȃǂ̎��g�݂����ꂽ�B �T����w�E�V�� ��2986�� 2012�N7��16�� |
| �s���{�����_�a�@�Ɂu�ɘa�P�A�Z���^�[�v�ݒu��--���J�ȁE������ |
| �@�ɘa�P�A���i�������7��11���A�����J���Ȃ��������u�ɘa�P�A�Z���^�[�\�z�v���ؗ��������B�e���_�a�@�Ɂu�ɘa�P�A�Z���^�[�v�����悤�Ƃ������̂ŁA�܂��͓s���{�����_�a�@�ł̐�����ڎw���B �@�ɘa�P�A�`�[���Ɗɘa�P�A�O���̘A�g�A�ɘa�P�A�f�Ï��̏W��E���͂ȂǁA�ɘa�P�A�ɂ��ĉ@�����f�I�Ȏ��g�݂�i�߂�̂��ړI�B m3.com 2012�N8��2�� |
| ��Íu���E�����w����@�����̂m�o�n���J�ÁA�Q���҂��W |
| �@�����{��k�Ђő����̐l�̖����D��ꂽ���Ƃ����������ɁA���ɂ��čl���悤�ƁA�����s�̂m�o�n�@�l�u���҂̌����I���u�Y�}���v�i�������E�r�i���ٌ�m�j�Ȃǂ́u��Íu���@�����w����v���J�Â���B�V�_�`�N���N�r���i������V�_�R�j�ȂǂőS�R��A�Q����͊e�T�O�O�~�B �@�u���͑�P��i�P�O���Q�V���j�������w�����҂ō�Ƃ̔g���]�L�q���u�t�́u���I���u���v����Q��i�P�Q���P���j�O�Ȉ�̓�m��ۊ삳��u�������� �߂Đ�����`�ݑ�z�X�s�X�̌��ꂩ��v����R��i���N�Q���Q�R���j���R�����w�������̒J�c���r����u���{�l�̎����ς̕ϑJ��U��Ԃ�v�B �@�₢���킹�͓��I���u�Y�}�������ǂO�X�Q�E�U�S�R�E�V�T�V�X�B m3.com 2012�N8��2�� |
| �������F��t�̏����ɂ�閖�����҂̎����A�ă}�T�`���[�Z�b�c�B�ō��@���� |
| �@�����̈ӎv�ƐM���Ɋ�Â��Đ����A�����Ď��ʂ��Ƃ͂����炭�A�l�Ԃ����ő�̎��R���낤�B�������A���̎��Ȍ��茠�ƈ��S�����A���Î҂Ƃ��Ă̈�t�̖�����A���ɓI�ɂ͐����̉��l�ƏՓ˂���Ƃ�����ǂ����낤���H �}�T�`���[�Z�b�c�B�ő����������@���̌��ʂ� �@�}�T�`���[�Z�b�c�B�̏Z���́A������11���A�������������l���邱�ƂɂȂ肻�����B�a���̐l�X�ɁA�����̖����I��点�邽�߂ɏ������ꂽ������ȓ��^���邱�Ƃ��\�ɂ���@�Ă̏Z�����[���s���邩�炾�B��������ΑS�Ă�3�Ԗڂ̏B�ƂȂ�B �u�������@�v���x������l�X�́A�����������銳�Ҏ��g�ȊO�̐l�����̖�𓊗^���邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł��邩��A���̍s�ׂ͈�t�����鎩�E�Ƃ͌Ăׂ� ���Ƒi����B�������A���Δh�̐l�X�́A�����̔���������҂�Ⴊ���ҁA�n�����l�X���A���Ô��}���邽�߂ɉƑ��⑊���l���爳�͂���\�����o�Ă��� ���O������A���������l�X�̖����댯�ɂ��炷���ƂɂȂ�Ǝ咣���Ă���B �������͈��y���� �@�I���S���B��1994�N�A�I�����ɂ��銳�҂������𑁂߂����������Ă��炤���Ƃ�F�߂��B���V���g���B��2008�N�ɂ���ɑ������B�}�T�`���[�Z�b�c �B�̏Z�����[�̓��V���g���B�̖@�Ǝ����㓯��ł���A�I���S���̖@�����~���ɂ��č���Ă���ƁA�u�}�T�`���[�Z�b�c�������A��(The Massachusetts Death with Dignity Coalition)�v�̍L��ӔC�҃X�e�t�@���E�N���t�H�[�h(Stephen Crawford)���͌����B �@2009�N�ɂ̓����^�i�B�̍ō��ٔ������A��t�����鎩�E�͏B�@�┻��Ɉᔽ���Ȃ��Ƃ������������������A���B�ɂ͌����ȑ������@�͂Ȃ��B �@���̖@���́A����d�v�ȓ_�ɂ����āA���y�����t�����鎩�E�Ƃ͈Ⴄ�A�ƃ}�T�`���[�Z�b�c�������A���͌����B���łɕa�C�Ŏ����̔��������҂��A���� �̐������I��点�������ȓ��^���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����_���B��t�͂��̂��߂ɕK�v�ƂȂ����������邱�Ƃ͋�����邪�A���҂̋��߂��������Ƃ��Ă� ��������K�v�͂Ȃ��B �@���������Δh�́A�������@�͈�t���E�ƕς��Ȃ��A�I�����̐l�X�͂�������s���邽�߂ɂ����菕����K�v�Ƃ��邾�낤���炾�A�ƌ����B�u�N�����f�@ �̗\������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�N������ǂɂ�������������ɂ����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B������������ŁA�Ď����Ȃ����^���ꂤ��̂ł��B���ꂪ�{ ���Ɏ����I�ȍs�ׂƌ�����ł��傤���v�ƁA�������@�ɔ�����u�I���͌��z(Choice is an Illusion)�v�̑�\�Ń��V���g���̎����ٌ�m�A�}�[�K���b�g�E�h�A(Margaret Dore)���͌����B���ɂ͎ア����̊��҂������댯�ɂ��炷�\���������܂܂�Ă���Ƃ����B �u����₷�����[�v�v �@�I���S���A���V���g���̖@�ɋK�肳��Ă���悤�ɁA�}�T�`���[�Z�b�c�̖@�Ăł��A���҂͏���Ⳃ���ɓ����O�Ɉ�A�̏��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�I �����̊��҂Ōږ��t���]��6�����ȉ��Ƃ̐f�f�����Ă��邱�ƁB�܂��A�ږ��t�͊��҂����N�Ɋւ��Č�����s���A�����`����\�͂����_�I�ɂ��邱�Ƃ��F �肵�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����ɁA��̐����́A15���̊Ԋu�������A2�x�ɂ킽���āA�����Ŏ厡��ɑ��čs���K�v������B�܂��A�Ƒ����ɊŌ��S������ ����l�łȂ��ؐl��2�l�K�v���B �@�����͌������悤�Ɍ����邪�A�h����Ƃ�����t�ɑ��锱��������������Ă��Ȃ����Ƃ���肾�Ɣ��Δh�̃h�A���͏q�ׂ�B�܂��A�Ƒ�����҂���A�� �Ô����ȏォ����Ȃ��悤����I�Ԃ悤���߂���ȂǂƂ������͂������邱�Ƃ��A����ɐS�z�Ȃ̂��Ƃ����B �@���������_���}�T�`���[�Z�b�c�������A���̃N���t�H�[�h���ɂԂ����Ƃ���A�u����₷�����[�v�A�܂��x�n�߂Ă��܂��Ύ��Ԃ��~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����c�_�́A���N�ɂ킽���Ĕ��Δh���咣���Ă��܂������A���t���͂Ȃ��̂ł��v�Ƃ����ԓ��������B �@���ہA�I���S���B���O�q�����̃f�[�^�ɂ��A�������𗘗p�������҂̑啔���͔��l�ŁA����̂���A�o�ϓI�ɂ����肵�ĕی��ɂ��\�����������l�X���� ���B�܂��A�������̂����Ȃ��B14�N�Ԃ�596��ŁA�]�ڐ��̂���ɋꂵ�݁A���������Ă���Ƃ������m�Ȑf�f���o���l�X���قƂ�ǂ��B �@�������A���Ȃ��Ƃ�1���́A����Ȃ鎡�Âł͂Ȃ������������ƂɂȂ����Ⴊ�������B2008�N�A�����̔x����������Ă����I���S���B�̃o�[�o���E���O �i�[���A�I���S���ی��v�����ɂ�鎩���̌��N�ی��ł͎厡��̏���������4,000�h���̖��Â��J�o�[������Ȃ����A�������ɕK�v�Ȗ�̗����̓J �o�[�ł��邱�Ƃ�m��A��҂�I�̂��B���̗�͑S�Ăɋc�_�������N�������B �u���ȓ��^�v�̂����܂��� �@�@�Ďx���҂����́A�������́A�����̖����I��点���������œ��^�ł��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂�����A���E�Ƃ͖@�I�ɋ�ʂł���Ƃ���B���҂͂�����������A�����I�Ɏ����̑̂ɓ���邱�Ƃ��o���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B �@���������Δh�̐l�X�́A���҂͕ʂƂ��āAALS�i�؈Ϗk�������d���ǁj�̐l���������̖@���Ɋ�Â��Ď���I�Ԃ��Ƃ��^��Ɏv���Ă���B���̕a�C���i�s����Ƌؗ͂⋦���^���@�\���ቺ���A�������蓮������A���ݍ��ނ��Ƃ����o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����炾�B �@�}�T�`���[�Z�b�c�@�̋K��͖@�I�ɂ����܂����ƁA���Δh�̃h�A���͎w�E����B���҂͐������I��点��̂ɕK�v�Ȗ���u���ȓ��^���Ă��悢�v�Ƃ����\���� �Ȃ��Ă���B�u���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ͏d�v�ȈႢ���B�܂��A���@�͂͂�����Ɓu���̂悤�Ȏ葱���͎����I�Łv�Əq�ׂĂ��邪�A�u���ȓ��^�v�Ƃ͖@�I�� �́A���P�Ɍo���ێ悷�邱�Ƃł����肤��A�ƃh�A���͌����B�u�o���ێ�ɂ́w�����I�ȍs�ׁx�͕K�v����܂���B����͎����̑I���̖�肾�ƌ����܂����A �@�ɂ���ʂ肾�ƁA�I���͕ۏ���Ă��Ȃ��̂ł��v�Ƃ����̂��ޏ��̎咣���B �@����A�}�T�`���[�Z�b�c�������A���̃N���t�H�[�h���̎咣�́A�ł͖�𓊗^�ł���̂͊��҂������Ɩ��m�ɏq�ׂ��Ă���A�Ƃ������̂��B�u��͎��ȓ��^����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���ꂪ�̋K��ł��B���ꂾ���ł��v�Ɣނ͌����B �I���S���A���V���g���ł͑命�����x�� �@�����������@������Ă���2�̏B�ł́A���Ȃ��Ƃ��Z����70%�����@�ɍD�ӓI�Ȉӌ��������Ă��邱�Ƃ��A�i�V���i���E�W���[�i���ƃ��[�W�F���X���c�̍s����2011�N�̐��_�����Ŗ��炩�ɂȂ����B �@�}�T�`���[�Z�b�c�̐l�����������ӌ��̂悤���B�ȑO�ɂ́A��t�̏����ɂ�鎩�E�͖@�����Ɏ���Ȃ��������A�ŋ߂̐��_�����̌��ʂł́A���B�����C�݂ō� ���ɑ����������@������B�ɂȂ肻���ł���B�p�u���b�N�E�|���V�[�E�|�[�����O�̍s�����ŋ߂̒����ł́A�Z����58%���������Ɏ^���[�𓊂���Ƃ����̂� ���A���Ɠ������̂�24%�ɂƂǂ܂����B IBTimes�@2012�N9��4�� |
| �������@�āA�Վ�����ւ̒�o�ڎw�� |
| �u�������@�āA�Վ�����ւ̒�o�ڎw���v�摜
�@���}�h�̍���c���ł���u�������@�������l����c���A���v�i������q�P�F�E����}�Q�@�c���j��7���ɖ�������J���A������ւ̖@�Ă̒�o��������A
�e�}���ň�������������i�߂���ŁA���N�H�ɂ��J�����Վ�����ւ̒�o��ڎw�����j���m�F�����B �@�c�A��7�����̑���ŁA15�Έȏ�̏I�����̊��҂ɑ��鉄���[�u�ɂ��āA�o�ljh�{��l�H�ċz��̑����ȂǁA�V���ɉ����[�u�����{���Ȃ��Ƃ���u�s�J �n�v��ΏۂƂ����u��1�āv�ƁA���ݍs���Ă���[�u�́u���~�v���܂߂��u��2�āv���܂Ƃ߁A������ւ̒�o�Ɍ����A���ꂼ��}���葱����i�߂邱�Ƃ��� �߂��B ��É��CB�j���[�X -�L�����A�u���C���@2012�N9��7�� |
| ��u���u�z�X�s�X�}�C���h����荇���v �n��Љ�̒��ŃP�A�̏z�� |
| ��t�@�R��@�͘Y�� �@�O�Ȉ�Ƃ��ĂP�U�N�A���̌�P�T�N�{�݃z�X�s�X�A���͂V�N�ԍݑ�z�X�s�X�����Ă���B�O�Ȉ�W�N�ڂ̂W�R�N�A�A�����J�̐��_�Ȉ�̃L���[�u���[�E���X���́w���ʏu�ԁx�Ƃ����{�ɏo�����Đl�����ς�����B �@�O�Ȉ�̍��A���҂��S���Ȃ肻���ȂƂ��ɉ����[�u���Ă������A�قƂ�ǒf��ꂽ�B������҂́A�����҂ɂƂ��ĕK�v�Ȃ��Ƃ��m�F���Ă��Ȃ��ƋC�t�����B �@�l�Ԃ͐g�̓I�A�Љ�I�A���_�I�A�����ăX�s���`���A���ȑ��݁B�X�s���`���A���e�B�͐l���̊�@�ɒ��ʂ����Ƃ��A������͂��]���i�P�j�@���Ȃǎ����̊O �̑傫�Ȃ��́A�܂��́i�Q�j���Ȃ̓��ʁ`�ɋ��߂�@�\�����B�X�s���`���A���e�B���@�\����A�a�C�ɖ|�M�i�ق�낤�j����Ȃ����Ȃ̑��݈Ӌ`���������� ���Ƃ��ł���B �@�X�s���`���A���e�B������̂ɕK�v�Ȃ̂��R�~���j�P�[�V�����B��������ʼnƂɖ߂��Ă������҂���ɁA�����Ȃ����\��w�����L���鎡�Â��Ă������A���̊��҂���́u���������Ă����̕a�C�͎���Ȃ��ł��傤�H�@���͂��̂܂܉Ƃɂ������v�ƌ������B �@�u���͗]�����������Ȃ��v�ƒQ�����҂���Łu�ǂ��������ł����H�v�ƕ����Ɓu�Ƒ��ɖ��f���|���邩������Ȃ����Ƃɂ������B�������ɉ�����v�ƌ����āA�j�R�j�R�Ƒ��̎����b���n�߂�l�������B �@�O�T�N����n��̒��ɏo�|���Ă����ݑ�z�X�s�X�P�A���n�߂��B��`���Ă�����Ă���{�����e�B�A�W�O�l�̂����A�Q�����S���Ȃ������̈⑰�B������������ �����P�A�𑼂̐l�ɂ����悤�ƁA�n��̒��ŃP�A���z���Ă���B����ꂪ�ڎw���̂́A�Ō�܂ŏZ�݂����Ǝv����n��Љ�B �@�ۑ�́A�ݑ�×{���J�n�����Ƃ��ɂ͗]���킸���ŁA�����̐l���P�J���ȓ��ɖS���Ȃ邱�ƁB�������ړI�ł���ƁA���҂��������ĕa�@�Ŏ��Â��Ă��邩�낤���B�l���̍Ōキ�炢�A��Â̊Ǘ�����������鐶�������l���Ă�����Ă������̂ł͂Ȃ����B �@�Ƒ��̉��͂̌��E�ȂǂŁA�ݑ����߂ē��@����l������B�����̐l�͉�삳���ł���Γ��@���Ȃ��čςށB�ɘa�P�A�a���́A�ݑ�P�A��⊮��������ɂȂ��Ă����̂��]�܂����B ��܂����E�ӂ݂��@�P�X�S�V�N���������܂�B�X�P�N�����n�l����a�@�����a�@�i�����s������s�j�z�X�s�X�ȕ����B�Q�O�O�T�N�u�P�A�^�E�������v���J�݂��A�ݑ��B�����Ɂw�a�@�Ŏ��ʂƂ������Ɓx�ق������B WEB TOKACHI�@2012�N9��11�� |
| �ɘa�P�A���i��������ԂƂ�܂Ƃ� ����f�ØA�g���_�a�@�Ɋɘa�P�A�Z���^�[�� |
| �@�����J���Ȃ͑�5��ɘa�P�A���i�������9��26���ɊJ���A�ɘa�P�A�`�[�������ϋɓI�Ɋ��f�ÂɊւ�邱�Ƃ��ł���悤�A����f�ØA�g���_�a�@�ȂǂɁu�ɘa�P�A�Z���^�[�v�����邱�ƂȂǂ����߂����ԂƂ�܂Ƃ߈Ă��ŗ��������B �@���ԂƂ�܂Ƃ߂́A���Ɛf�f���ꂽ�Ƃ����炠���銳�҂Ɋɘa�P�A��ł���悤�ɂ��邽�߂̕�����܂Ƃ߂����́B����̊ɘa�P�A�̐����������� ���߁A����f�ØA�g���_�a�@�Ȃǂɂ����āA�ɘa�P�A�Z���^�[�����邱�Ƃ����߂��B���Z���^�[�ɂ͊ɘa�P�A�`�[����ɘa�P�A�O���̉^�c�ɉ����A�n��̈� �Ë@�ւƂ̘A�g������ɘa�P�A�֘A���C��̉^�c�A�ɘa�P�A�f�Ï��̏W��Ȃǂ��s���@�\����������B �@�ɘa�P�A�Z���^�[�ɂ́A�ݑ�ŗ×{��������҂��u�ɏǏ��������ۂȂǂɁA�ً}�ɑΉ��ł���@�\�����߂�B�Ⴆ�A�ɘa�P�A�a���̂Ȃ����_�a�@�Ȃǂ� �����ẮA��ʕa���̈ꕔ���ً}�ɘa�P�A�a���Ƃ��A�u�ɂ̊ɘa��ړI�Ƃ����ً}���@���ł���̐�����邱�ƂȂǂ�z�肵�Ă���B �@�܂��A���f�Âɂ�����g�̓I��ɂ̕]�����O�ꂳ���悤�A����f�ØA�g���_�a�@�ɂ́A�O�����̖�f�\�Ɂu�u�ɓ��̐g�̏Ǐ�v�̍��ڂ�݂�����A�J���e�� �o�C�^���T�C���̗����u�ɂ̍��ڂ�݂��邱�ƂȂǂ𐄐i����B���_�S���I��ɂɑ���ɘa�P�A�̒��[�������邽�߁A���f�ÂɌg���Ō�t�Ɍ��C���s�� ���Ƃ�A�Ō�t�ɂ��p���������k�x�����s���̐������邱�Ƃ����߂�B �@���ԂƂ�܂Ƃ߂́A�ߓ����ɍŏI�ł��m�肵�A�����J���Ȃ̌��N�ǒ��ɒ�o�����B���J�Ȃ�2013�N�x�̊T�Z�v���ŁA�V�K���ƂƂ��āu����Ɛf�f���ꂽ ������̊ɘa�P�A�̐��i�v��8.2���~���v�サ�Ă���B���̎��ƂŁA����f�ØA�g���_�a�@�Ɋɘa�P�A�Z���^�[��������A���Z���^�[�ɋً}�ɘa�P�A�a�� ��݂���v�悾�B ���o���f�B�J�� �I�����C���@2012�N9��27�� |
| �u�������@�����v�͈�Êi���̊g����������˂Ȃ��\����L���q���C���^�r���[�� |
| �@�O��́A�u�������̖@������F�߂Ȃ��s���̉�v�Ăт����l�E����L���q���C���^�r���[�u�w�������@�����x�͎��͂̐l�Ԃ���h���E���~�߂錠���h��D���v���f�ڂ������܂����B����́A�ǎ҂��炢�������������ӌ��ɐ������������҂����͂����܂��B �u�������@�v�Ɋ�Â�������̐��X�́A��Ô�̒����i�k���j�@�\ �\�O��̋L���ɑ��āA�u�������@�����������Ƃ��Ă��A����Ȃɉe��������Ǝv���܂���ł����v�u�@���x�����ꂽ�瑸�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł͂Ȃ� �̂�����A�������ɔ�����l�́A�@���o���Ă������͓��ӂ��Ȃ�����������̘b�ł́v�Ƃ��������z�����Ă��܂��B����̖@�Ă̖��_�ɂ��āA�� �������ڂ��������Ă��������܂���ł��傤���H ������F�܂��A���}�h�́u�������@�������l����c���A���v���A�����`����E���������Ŗ@�Ă�����A�c���ʂ����Ƃ��Ă���Ƃ���ɖ�肪����܂��B �u�������@�������l����c���A���v�̑��q��́A�Q�̖@�Ă͊e�}�Ɏ����A���A��������Ă���ƌ����Ă����܂������A�u�������̖@�����ɔ������v ���s��������c���Ώۂ̃A���P�[�g�����ɂ��i�߁X���\�����悤�ł��j�A�e�}�Ō������ꂽ�l�q�͂Ȃ��A�c�A�̋c���̑����͐[���l�����A���t�������ŋc �A�ɖ��O��A�˂Ă��Ă��邾���̂悤�ł��B �@�e�}�̌����J���ψ���ł̐R�c���Ȃ��A�@�Ă����\���p�u���b�N�R�����g�����߂�Ȃǂ̎葱�����ʂ����ɁA���̗Վ�����ɏ�����c���悤�ƌ����̂́A���܂�ɗ��\�Ȃ����ł͂Ȃ��ł��傤���B ���������l�̑������ǂ��l����̂��B�����āu�I�����v��������ƍl����̂��B �@����͒�`�ł��Ȃ����̂ł��B�u�S���Ȃ��ĐU��Ԃ��āA�������̎����炪�w�I�����x�������̂��Ə��߂Ă킩��v�Ƒ����������̒������������Ă��܂��B�����@�����ňꗥ�ɒ�`���悤�Ƃ��Ă���킯�ł��B �u�@�����ł��Ă��e���͂Ȃ��B���Ȃ�g��Ȃ�������B�D���Ɏ��Â𑱂�������v�ƌ�����̂ł����A�@���ɏ]��Ȃ��l�́A�u���ł��g���Ė��ʂȎ��Â� ���Ă���l�v�u���Ȏ�`�ҁv�u���v�̃��b�e����\����悤�ɂȂ�ł��傤�B���ƂƂ��āA�ꗥ�Ɂu�������u�v�u�I�����v���`���A���������N�Ȃ����� ��`�ʂ�Ɏ��ʂ��Ƃ����琾�킹�邱�ƂɂȂ�܂��B �@�����S�̂ɕ��y�����A���ׂ������Ƃ��čL�߂邱�ƁB���ꂪ�@�����ł��B���̎��ɕ�����{�Ƃ��āA�q�ǂ����獂��҂ɂ܂œO�ꂵ�Ē蒅�����A��点�邽�߂̂�����{�u������悤�ɂȂ�܂��B �@�@�Ă������ƌ��Ă����܂��傤�B �@�@�ĂP�@�ĂQ�̑�O���u�I�����̈�Âɂ��č����̗�����[�߂邽�߂ɕK�v�ȑ[�u���u����悤�w�́v�A��\����u���y�ђn�������c�̂́A������������ �@���ʂ��ďI�����̈�Âɑ��闝����[�߂邱�Ƃ��ł���悤�A�����[�u�̕s�J�n�i���āj�ƒ��~�i���āj����]����|�̈ӎv�̗L�����^�]�Ƌ��؋y�� ��Õی��̔�ی��ҏؓ��ɋL�ڂ��邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ��铙�A�I�����̈�ÂɊւ���[���y�ђm���̕��y�ɕK�v�Ȏ{����u������̂Ƃ���B�v�Ƃ���܂��B �@����Œn�������c�̂́A�@����ϋɓI�ɍL�߂邽�߂̎��Ƃ��s�����ƂɂȂ�̂ŁA�w�Z��a�@�Ȃǂł́A�I�����̐l�H�ċz���݂낤�Ȃǂ̎��Â�f��|���� ���������Ƃ�ϋɓI�ɐ������Ă������ƂɂȂ�܂��B��������15�Έȏ�ɓK������Ƃ���A�Ƌ���ی��̗��ɋL�ڂ�����Ƃ����̂ł����A����ł͏����� ���͔��ɍ���ł��B �@��\����ł́u�����J���ȗ߂ւ̈ϔC�v�A�����R�ł́u���̖@���̎{�s��O�N��ړr�Ƃ��āA���̖@���̎{�s�̏A�I�����ɂ��銳�҂���芪���Љ�I�� �̕ω��������Ă��Č������������A�K�v������ƔF�߂���Ƃ��́A���̌��ʂɊ�Â��ĕK�v�ȑ[�u���u������ׂ����̂Ƃ���v�Ƃ���A�����J���Ȃɂ��� �āA����̏�ɑ����ĂR�N���ƂɌ������Ă����̂ł��B �@�܂�A���{�o�ςɘA��������Ô�팸�̐�D�Ƃ��āA���́u�������@�v�Ɋ�Â�������̐��X�́A����ҁA��Q�҂Ȃǂ̎Љ�I��҂ɑ����Ô�̒����i�k���j�@�\�̖��������ƂɂȂ�܂��B �\��t���Ɋ|���镉�S���w�E���鐺������܂����B�u���A��҂̔��f�ʼn����[�u���~�߂�ƁA��҂��E�l��Ƃ������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��v�Ƃ����ӌ��ł��B���̓_ �ɂ��ẮA�ǂ��ł��傤���H�@��������Ă��Ȃ�����ɂ����āA�ǂ̂悤�Ɂu�������v���i�߂��Ă���̂��Ƃ��킹�ċ����Ă��������B ������F���݂ł��A���Â̕s�J�n�ɂ��u�������v�͎��{����A�݂낤��ċz��̒��~���s���Ă��܂����A������Ƙb���������Ȃ���Ă���A���ɂȂ�P�[�X�͏��Ȃ��ł��B �@��t���E�l�߂ɖ����̂́A�Ƒ��ɐ��������������ɑ��k�������A������ƑP�I�ɍs�����ꍇ�B�a�@�̋Ζ���͌����̏�A������ʂɋ~�}��������Ă��� �a�l�Ƀx�b�h�������悭�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����Ȉ�t�̐Ӗ����y�����A�ƒf������邽�߂ɁA���́u�I������Â̌���v���Z�X�Ɋւ���K�C�h���C���v�� 2007�N�ɍ��肵�A���E��ɂ�鑊�k�̐���Ƒ��̓��ӂɊ�Â���Â𐄏����܂����B����ň�t����l�Ō���A�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ȃ�͂��ł��B �u�I������Â̌���v���Z�X�Ɋւ���K�C�h���C���v �@�������A���̂��т̖@�Ă̑�l���A��Z���͂���ɂ��t�s���Ă��܂��B �@��t�Q���ŏI������ł��邱�Ƃɂ��Ă��邩��ł��B���E���Ƒ��Ƃ́u�M���W�Ɋ�Â��v�Ƃ͂��邪�A���ӌ`���̋`���ɂ��Ă͏�����Ă��܂���B ����͎�Ԃ��Ȃ��A�����̈�t�Ŗ��������肵���Â̒�~���ł���悤��������_�������̂̂悤�ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B �@�������̖@�����ɂ��A���@���ɂ͕K����@���ɑ����āu�������Áv��f��|����M���������悤�ɂȂ�ł��傤�B�i�u�������Áv�Ɣ��肷��͖̂{�l�ł��Ƒ��ł��Ȃ��a�@�ł����j�B �@���̂悤�ɂ��Ă����A�Ƒ������ӂ��Ă��Ȃ��̂ɑ����������Ă���t�͖ƐӂɂȂ�܂��B �@�����Ė{�l���u����J�[�h�v���g�т��Ă���A�����̉\���������Ă��A�l�H�I�Ɂu������������v���ƂɂȂ肩�˂܂���B���Ƃ��A��ʎ��̓��ň� ���s���̂P�T�̎q�ǂ��̉Ƒ����A�ϋɓI�Ȏ��Â�v�����Ă���ꍇ�ł��A���N�̏]�O�̈ӎv�ɏ]���A��̎��Â������u�]���v�Ɏ������݁A���̑�������o ���Ă悢�̂��́A�c�_�̗]�n������Ƃ���ł��B �������@�����́u��Êi���v�̊g��������\���� �\����҂̉����̖��Ƃ��킹�āA�o�ς��܂߂����\�[�X�̊ϓ_����A�������̕K�v�����咣����ӌ�������܂����B�u���Â�҂l�̐��_�I�E���̓I���S���� �炷���߂ɂ́A��ÑS�̂̃{�����[�������炷���Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�u�����𑱂��邱�ƂŁA�Ƒ��̕��S�͑����A�����̂⍑�̕��S�������B�Ƒ��͍��Y ������Ԃ��A���̍����͈�������v�Ƃ������ӌ��ł��B���̓_�ɂ��ẮA�ǂ̂悤�ɂ��l���ł��傤���H ������F����A�Ό��L�W�����e���r�ŁA�u���{�o�ς̗��Ē����̂��߂ɂ͏I������ÑK�v�A���̂��߂Ɏ����͑���������ɓ���v�ƌ����Ă��܂������A����͑������̖@���������̌o�ϑ�̓�����ƌ��Ȃ���Ă���؋��ł��B �@���̖@���ɂ��A�����I������3�N���ƂɌ������A��`�������ē������ł���̂ŁA��p�Ό��ʂ̃G�r�f���X���Ȃ��������Q�̂��鍂��҂ɂ͕ی��̓K�����l�߂Ă������Ƃ��ł��܂��B �@���ꂪ�i�߂A���{�̌ւ鍑���F�ی����x���C�M���X�̂m�g�r�̂悤�ɁA���I�ی��Ŏ��鎡�Â͈̔͂͋��܂���e�����e���ɂȂ�܂��B�I�����łȂ��� ���݂낤�݂��Ă��炦�Ȃ��Ȃ�A���͂��̑��̍��z��Â͕ی��Ŏ��Ȃ��Ȃ�B���Ȃ獂���ȃv���C�x�[�g�f�Â�I������Ƃ������ƂɂȂ�A��Êi�� �͊g�傷��ł��傤�B�K�Ȉ�Â����Ȃ��l�����Ă����Ǝ����Ƃ����Љ�ɂȂ��Ă������˂܂���B �@�����ɐϋɓI�ɑ�������I�������邱�Ƃň�Ô���l�߂���A�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�������̈��S���S�̂��߂ɂ́A���̐l���Ƃɉߕs���̂Ȃ���Â�͂�����悤�ɂ��Ă����B���̂��߂̖@���x���l����̂��A�����̖����ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����B �\�{���͂��肪�Ƃ��������܂����B �v���t�B�[���@����L���q�i���킮���E��݂��j�F�u�������̖@������F�߂Ȃ��s���̉�v�Ăт����l�B2005�N���{ALS������A�C�B2009�NALS/MND���ۓ�����c�����A�C�B BLOGOS�@2012�N9��28�� |
| �i�s���� ���S���O��ICU���e��@�����S�̉���������I����QOL�Ƒ��� |
| �@�_�i�E�t�@�[�o�[�������iDFCI�j�S���Љ��ᇊw�ƃn�[�o�[�h��w�i�Ƃ��Ƀ{�X�g���j���_�����w��Holly G.
Prigerson�y������́C�i�s���҂̏I����QOL����Ɋ�^������q���������CArchives of Internal
Medicine�i2012; 172:
1133-1142�j�ɔ��\�����B����ɂ��ƁC���@��W�����Î��iICU�j���e�̉���C�s���̌y���C�F����ґz�C�{�݂̖q�t�ɂ��P�A�C���Âɑ����
�t�Ɗ��҂̋��͊W���C����QOL�Ƒ��ւ��Ă����B 9���ڂ��琬��\�����q�̃Z�b�g����� �@���҂̂����͂⎡���s�\�ɂȂ����ꍇ�C�P�A�̏œ_�͉�������I������QOL���P�Ɉڍs���邱�Ƃ������B�������C����̌����̔w�i���ɂ��ƁC�I����QOL�̗\�����q�Ɋւ��āC����܂ň�т����f�[�^�͑��݂��Ȃ������B �@�����ŁC�M�������҂ō���̌������{����DFCI�̌������ł�����Baohui Zhang���́C�l���Ŋ���1�T�Ԃɂ�����QOL�Ɋւ��C�ł��D�ꂽ�\�����q�̑g�ݍ��킹����肷�邽�߂ɍ���̌��������{�B���̌��ʂ�p���āC�������� ��QOL���P�Ɍ�������É���̗L�]�ȕW�I�����ɂ߂悤�Ǝ��݂��B �@����̌�����Coping with Cancer Study�̈�Ƃ��āC2002�N9��1������2008�N2��28���Ɏ��{���ꂽ�B�Ώۂ́CDFCI�Ȃǂ̎{�݂̐i�s����396��i���ϔN���59 �j�Ƃ��̉��҂ŁC�o�^���玀�S�܂Ńt�H���[�A�b�v�i�����l4.1�J���j�����B �@���܂��܂ȗ\�����q�̑g�ݍ��킹�������������ʁC �i1�j�Ŋ��̏T�ɂ�����ICU���e�iQOL�̒ቺ�Ɗ֘A�j �i2�j�@�����S�iQOL�̒ቺ�Ɗ֘A�j �i3�j�o�^���]���ɂ����銳�҂̕s���iQOL�̒ቺ�Ɗ֘A�j �i4�j�o�^���ɂ����銳�҂̏@���I�F����ґz�̒��x�iQOL�̏㏸�Ɗ֘A�j �i5�j���Î{�� �i6�j�Ō�̏T�ɂ�����o�ljh�{�g�p�iQOL�̒ቺ�Ɗ֘A�j �i7�j�a�@��N���j�b�N�̖q�t�ɂ��P�A�iQOL�̏㏸�Ɗ֘A�j �i8�j�Ō��1�T�Ԃɂ����鉻�w�Ö@�iQOL�̒ቺ�Ɗ֘A�j �i9�j���Âɑ��銳�҂ƈ�t�̋��͊W�iQOL�̏㏸�Ɗ֘A�j ��9���ڂ��琬��ϐ��Z�b�g�ɂ��C�Ŋ���1�T�Ԃɂ�����QOL�̂قƂ�ǂ�������邱�Ƃ��ł����B �@�����́u�I������QOL�s�ǂ��K�肷��ł��d�v�Ȉ��q�́C�@�����S�ƍŊ��̏T�ɂ�����ICU���e�ł������B���������āC��p�̂�������@��������C���@ ���҂�����������̓z�X�s�X�Ɉڂ����݂ɂ��C�I�����̊��҂�QOL�����P����\��������v�Əq�ׂĂ���B����Ɂu����̌����ł́C�x�[�X���C���ɂ��� �銳�҂̕s�����̋������C�I����QOL�s�ǂ̗L�͂ȗ\�����q�ł������v�Ǝw�E���Ă���B �ʼn߂���Ă����I����QOL �@Zhang���́u���҂̕s�����y�����C�ّz�����サ�C�p�X�g�����P�A�����������B�܂��C���Âɑ��銳�҂ƈ�t�̋��͊W����݁C�s�v�ȓ��@�≄�����Â�������邱�ƂŊ��҂͍Ŋ��̐������ł����炩�ɉ߂������Ƃ��ł���v�ƌ��_�t���Ă���B �@�č�����������iNIA�j���������v���O������Alan B. Zonderman�CMichele K. Evans�̗����m�́C�����̕t���_�]�i2012; 172: 1142-1144�j�Łu����܂ł̂����Âł͖������҂ɂ�����I����QOL�̖��͊ʼn߂���C���ʓI�����זE�Ő���L����V��������@�̊J���ɖ� ���������Ă����B�����̑S�o�߂ɂ킽���Ĉ�ѐ��̂��邪�Ð헪�𗧂Ă��ŁC�I����QOL�̌����͌������Ȃ��B����ɂ�������炸�C���̗̈�ɂ��� �錤���͂��܂�ɂ��s�����Ă���v�Ǝw�E���Ă���B �@����Ɂu���݁C���G�ő��l�Ȃ��Ð헪�̊J���⓱�������X�Ɛi��ł������ŁC�I����QOL�ɑ傫���e��������q�Ɋւ��ẮC���܂����m�ɒ�`�ł��� ���Ȃ��͈̂ӊO�ł���v�Əq�ׁC�u����̌����́C�č��Տ���ᇊw��iASCO�j�̐����Ɠ������C�i�s���҂ɑ���ɘa�P�A�̑����������x��������̂� ����v�ƕt�������Ă���B �����҂₻�̉Ƒ��́u�S�v����I�ɃP�A���邱�ƁB��̓I�ɂ͗�I�P�A�i�X�s���`���A���P�A�j����я@���I�P�A�����S�ƂȂ� ���f�B�J���g���r���[���@2012�N10��18�� |
| �`�I�����_�̈��y���@�` 2010�N�̈��y��������ш�t���E���͖@�{�s�O�Ɠ��� |
| �@���y�������@������Ă���I�����_�ɂ����āC���y���@�{�s�O��̈��y������ш�t�̛������E�i��t���E�j�̓��������������Ƃ���C2010
�N�̈��y��������ш�t���E���́C���@�{�s�O�̐����Ɠ����x���ł��邱�Ƃ����R��w��ÃZ���^�[�i�A���X�e���_���j��Bregje D.
Onwuteaka-Philipsen�����炪�s�������f�����Ŗ��炩�ƂȂ����B�ڍׂ�Lancet�i2012; 380:
980-915�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�B �{�s�O���20�N�Ԃ̓��������� �@�I�����_�ł�2002�N�ɁC���̏��������Έ��y������ш�t���E��F�߂���y���@���{�s���ꂽ�B����̌����ɂ��C2010�N�̈��y��������ш�t���E���́C2002�N�̓��@�{�s�O�Ɠ����x���ł��邱�Ƃ����������B �@2002�N�̈��y���@�{�s��C2005�N�ɂ͈��y��������ш�t���E������������ቺ�������C��t���E����]���銳�҂̑����Ȃǂ�w�i �ɁC2005�N����2010�N�ɂ����čĂя㏸�����B�������C2005�N�ɒቺ�������߂�2010�N�̈��y��������ш�t���E����2002�N�̓��@�{ �s�O�Ɠ����x���������B �@Onwuteaka-Philipsen������́C�I�����_���v�ǂ̎��S�o�^�f�[�^�ނ��C�I�����̈ӎv���肪���҂܂��͈�t�ɂ���ĂȂ��ꂽ�\�� �̂���Ǘ�肵���B���̌�C�����̏Ǘ��S��������t�ɒ����[�𑗕t���C���~�Ȃǂ̌������t���s�������ǂ����C���邢�͊��҂̎��𑁂߂邽�� �ɖ�܂𓊗^�������ǂ����Ȃǂɂ��Ē��������B����2010�N�ɂ�������y��������ш�t���E���𐄌v���C1990�N����2010�N�ɂ����Ă� ���y������ш�t���E�̕p�x�̐��ڂ����������B ���@���œ��������܂邩 �@���͂̌��ʁC2010�N�ɂ�������y�����邢�͈�t���E�̌����͐��v4,050���ŁC�I�����_�̑S���S����3�����߂��B���̂���77�����u���y���Ɋւ���n��R���ψ���v�ɕ���Ă����B���̊�����2005�N�Ƃقړ����ŁC���y���@�̎{�s�O�������������B �@Onwuteaka-Philipsen������́u���y���@�̎{�s�ɂ��ĕs�������鐺�����������C���y�������@�����ꂽ���X�ł́C���҂̖��m�Ȋ�]���Ȃ���Ԃň�t�����҂̎������P�[�X�͑������Ă��炸�C�I�����_�ɂ����ėL�ӂɌ������Ă���v�Ǝw�E���Ă���B �@���҂����m�Ɉ��y������]�����ꍇ�C��t���v����𓊗^������y���ƁC���y����]�ފ��҂̈ӎv�\�����Ĉ�t���v������������C���҂����瓊�^����� �����E�����@������Ă���̂́C���E�ł��I�����_�C�x���M�[�C���N�Z���u���N��3�J���݂̂ł���B���E�ɂ��ẮC�X�C�X����ѕč��̃I���S���C���� �^�i�C���V���g���̊e�B�ŔF�߂��Ă���B �@�I�����_�ł́C���y�����t���E��I�Ԏ�N���҂₪�҂������C�i�[�V���O�z�[����a�@������ʐf�Ï��ōs���Ă��邱�Ƃ��C����̌����Ŗ��炩�ɂȂ����B�܂��C���Ҕw�i�ɂ��Ă�20�N�Ԃقڕς��Ȃ������B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N11��1�� |
| ���{�~�}��w��A�I������Âɂ��Ă̒������ʂ����\ �l�H�ċz�̒��~�A�����E�h�{�⋋�̐����⒆�~�ɈˑR��R�� |
| �@���{�~�}��w��~�}��Âɂ�����I������Â̂�����Ɋւ���ψ����2012�N11��5���A�u�~�}��Âɂ�����I������ÂɊւ���i�ȉ��A�K�C�h��
�C���j�v�ɑ���~�}��Ï]���҂̈ӎ��̕ϗe�ɂ��āA�A���P�[�g�̌��ʂ\�����B�K�C�h���C�����o���Ă���5�N���o�߂��A�F�m�x�͍��܂��Ă������
�́A����ł̓K�p�ɂ��Ă͈ˑR�ۑ肪�c������炩�ɂȂ����B �@���̃K�C�h���C���͓��w�2007�N11���Ɍ��J�������̂ŁA1�N���2008�N�ɂ͋~�}�Ȑ����ΏۂƂ��ĔF�m�x��K�p�̒������s���Ă���B ���ʂ\���������́A�K�C�h���C���̌��J����5�N���o�߂��A�~�}��Â̏]���҂Ɉӎ��̕ϗe���������̂��ׂ�ړI�ōs��ꂽ�B�������Ԃ�2012 �N5��8������20���܂ł�13���ԁB�Ώۂ́A�~�}�Ȑ���658�l�Ƌ~�}��Âɏ]������Ō�t77�l�B �@�܂��A�u�K�C�h���C���̓��e��m���Ă��邩�v�̐ݖ�ɂ́A�~�}�Ȑ����82.4�����u���e���悭�m���Ă���v�܂��́u�����ނ˒m���Ă���v�ƉB2008�N�̒�������73.3����傫������A�K�C�h���C���̔F�m�x�����܂��Ă����B �@�u�I�����̏�Ԃɂ���ƍl�����銳�҂̐f�ÂɃK�C�h���C���𗘗p���Ă��邩�v�̐ݖ�ɂ́A�~�}�Ȑ����24.8�����u�傢�Ɏ�����Ă���v�܂��́u������Ă���v�ƉB2008�N�̒�������21.7��������錋�ʂƂȂ����B �@���w��̃K�C�h���C���ł́A�I�����Ɣ��f����銳�҂ɂ��ẮA�Ƒ��̑��ӂȂǂ��m�F������ʼn����[�u�𒆎~���邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă���B���̏�ŁA�� ���[�u�̒��~��ϋɎ��Â����Ȃ����@�Ƃ��āA�l�H�ċz�̒��~�A�l�H���͂��s��Ȃ��Ȃ�4�̕��@����Ă���B�u�������������@�ɂ��ċ��e�ł��邩�v �����ݖ�ł́A���@�ɂ���ċ��e�ł���x�������قȂ�X���������ꂽ�B �@��̓I�ɂ́A�u�l�H���́A���t�Ȃǂ��s��Ȃ��v�u�l�H�ċz��ݒ�⏸���^�ʂȂǁA�ċz�E�z�Ǘ��̕��@��ύX����v�ɂ��ẮA���e�ł���ƍm ��I�ɉ����~�}�Ȑ���͑����A���ꂼ��83.2���A76.9�����߂��B����ŁA�u�l�H�ċz�A�y�[�X���[�J�[�A�l�H�S�x�Ȃǂ𒆎~�A�܂��͎��O ���v�u������e���̕⋋�Ȃǂ𐧌����邩�A���~����v�Ƃ������@�ɂ��ẮA���e�ł���ƍm��I�ɉ����~�}�Ȑ��オ�A���ꂼ��42.5���A 67.0���B��R�������~�}�Ȑ��オ���Ȃ��Ȃ����Ƃ����������B���������X���́A08�N�̒������Ƒ傫���ω����Ă��Ȃ������B �@����܂ł�5�N�ԂɃK�C�h���C����K�p���悤�Ƃ����ǗႪ���邩�ǂ����������ݖ�ɂ͑S�̂�20.5�����u�K�p���悤�Ƃ����ǗႪ�������v�ƉB08�N�̒�������13.8���ɔ�ׂđ��������B �@�������A�u�K�p���悤�Ƃ������Ⴊ�Ȃ������v�Ɠ�����471�l�i71.6���j �̂����A253�l�i53.7���j�́u�K�p����Ӑ}���Ȃ������v�Ɖ����B �@�u�K�p���悤�Ƃ������Ⴊ�Ȃ������v471�l�̒��ŁA�u�K�p�������������A�ł��Ȃ������v�Ɖ����̂�114�l�i24.2���j�B�K�p�ł��Ȃ��������R �i�����j�́A�u�Ƒ��̈ӌ����܂Ƃ܂�Ȃ������v�i86�l�A13.1���j�A�u�@�I�Ȗ�肪�������ł���v�i73�l�A11.1���j�A�u��Ã`�[�����̈� �����܂Ƃ܂�Ȃ������v�i53�l�A8.1���j�Ȃǂ������B �@����̒����ł́A�K�C�h���C���̔F�m�x�͍��܂��Ă�����̂́A����ւ̐Z���ɂ͉ۑ肪�c�錋�ʂ������ꂽ�B ���o���f�B�J�� �I�����C���@2012�N11��26�� |