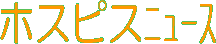
要 覧 − 病名告知
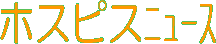
| ホ−ム>医学トピックス>ホスピスニュ−ス>バックナンバ−メニュ->要覧−病名告知 |
| 病名告知 |
| 2011年 |
|---|
| がん告知で大切なのは「患者の希望を断たず支えること」と医師 |
| 2012年 |
| がん告知後の道しるべ 医師と十分な意思疎通を |
| 第109回日本内科学会 内科医が取り組むべき課題を提言 |
| がん告知で大切なのは「患者の希望を断たず支えること」と医師 |
|---|
| 患者と直に対面してがんの告知を行なうことは医師にとっても苦行である。心ある医師たちは、冷静な表情の裏で、患者の心中を思い胸を痛める。 彼らが心がけているのは、患者の残りの人生を意義深いものにすべく、最善の治療を提供することだ。 「病気を診ずして病人を診よ」――これは東京慈恵会医科大学が掲げる医療理念だ。告知には人間とどう向き合うかが問われている。緩和ケア医療の最前線を走る同大学の相羽惠介教授(内科学講座 腫瘍・血液内科)が、告知の現実を語る。 * * * 医療は「机の上のお勉強」でなく「実学」である――そのことを最も感じるのが「がん告知」という局面ではないでしょうか。 告知に「こういうケースにはこうするとよい」というガイドラインはありません。患者さんはそれぞれ別の社会生活を営んでいるひとりの人間ですから、抱える悩みも様々です。だから個別に対応を考えていかなければならない。 やはり医師としてのキャリア、ベッドサイドでの実績がものをいいます。若い医師はどうしても、ストレートに物事を伝えすぎてしまう傾向があります。 当病院では告知の全権を主治医が、外科分野であればチーム医療の年長者が担うことになっている。患者をいたわりながらも事実を正確に告げる告知には、やはり失敗から学んだ経験が役に立つのです。 患者と医師が共同作業でがんに立ち向かうためには、真実の告知は原則必要です。やはり本当のことをいわないと、治療に協力してもらえない。医療は患者と医師の共同作業です。ただし「本当のことをすべて知りたいわけではない」という患者さんもおられます。 当科では患者さんとの意思疎通を確かなものにするため、初診時に問診票へ記入して頂きます。「すべて隠さず告知してほしい」「限定的で構わない」「まず家族にだけ告げてほしい」など、患者さんの希望をなるべく具体的に書いて頂き、それを参考に柔軟に対応します。しかし、それが本心とは限らないので、探りながらの対応が必要です。 適切な告知が必要なのはもちろんですが、その一方で告知が当たり前となったことによる問題点も感じます。それは末期がんの患者さんに「大丈夫です」といえる医師が少なくなったこと。 私は若い医師によくいうんです。たとえ余命が短い患者さんがいても、「大丈夫」と伝えることも必要だと。生きる希望を断ち切ってしまうわけにはいかない。いかなる場合においても、常に希望を持って頂く。 たとえ見通しが厳しかったとしても、「大丈夫」という言葉で患者さんの不安を引き受けてあげるタフさがなければ良医ではない。患者さんの希望を断ってしまうような余命告知は決して行なうべきではない。 もちろんご家族には予想される余命も含め現実的な告知をしますが、患者さんの希望を支えるためには、いつも真実をお伝えすることが最良とは限らないと思います。スキンシップも大切で、患者さんの肩や手に触れて、言葉では伝わらないシグナルやメッセージをお伝えすることもあります。 患者さんにとって告知はなかなか受け入れ難く、それは医師にとっても厳しい現実です。だからこそ、医師は患者さんの最期の瞬間まで、心身の痛みを分かち合う伴走者でありたいと思います。 NEWSポストセブン 2011年8月25日 |
| がん告知後の道しるべ 医師と十分な意思疎通を |
| がんと診断されて医師から告知を受けると、動揺しているにもかかわらず、病状やその後の治療の選択などを次々に考えなければならない。説明がよく分からないままだったり、聞きたいことが聞けなかったりすれば、いっそう不安は募る。 国立がん研究センター東病院 (千葉県)の小川朝生・臨床開発センター室長(精神腫瘍学)はこのほ 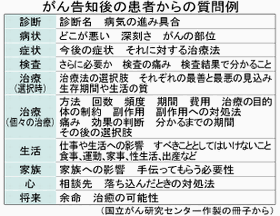 ど、患者と家族のため、よくある質問を項目ごとに整理した「重要な面談にのぞまれる患者さんとご家族へ」(図)をウェブサイト(http://pod.ncc.go.jp )で公開し、活用を呼び掛けている。 ど、患者と家族のため、よくある質問を項目ごとに整理した「重要な面談にのぞまれる患者さんとご家族へ」(図)をウェブサイト(http://pod.ncc.go.jp )で公開し、活用を呼び掛けている。告知を受けた患者の調査で「ほかの患者がどんな質問をするのか知りたい」「何を尋ねたらよいのか分からない」などの疑問が出されたのに応え、緩和ケアの進んでいる外国の先例などを参考に作成した。 質問項目は「どのぐらい深刻ですか」といった「病状について」、「どんな治療法がありますか」「合併症や副作用は」といった「治療について」、「仕事への影響」「してはいけないことはありますか」といった「生活について」などの10項目計53問。 主治医とのコミュニケーションを促すことを目的にしており、告知後の面談で医師が説明する順序にほぼ沿っているため、面談前にチェックしておいて聞き漏らしを防ぐことができる。 小川さんによると、患者自身が知るべきこと、決めることがたくさんあり、重い負担が不安や落ち込みを招く。家族にも悩みを打ち明けられないことは誰にもある。「心のつらさをなくすのは治療と同じぐらい大切。しんどいときは専門家に相談を」と勧めている。 47NEWS 医療新世紀 2012年5月22日 |
| 第109回日本内科学会 内科医が取り組むべき課題を提言 |
| 京都市で開かれた第109回日本内科学会から,今回の総会テーマと同一タイトルのパネルディスカッション「内科学の使命と挑戦」〔司会=中尾会頭,住友
病院(大阪府)・松澤佑次院長〕の模様を紹介する。国内外の医療や死生観に造詣の深い各演者からは,プライマリケアや予防研究の重要性が指摘され,同プロ
グラムの狙いである21世紀の医学における内科学の使命,内科医の取り組むべき課題と今後の挑戦を考える場となった。 助けての声に応える誠意ある内科臨床を 一般医療と終末医療を実践している,野の花診療所(鳥取県)の徳永進院長は,患者の「助けて」の声がある限り,臨床は枯渇しないとし,医師にとっては 「誠意」が普遍であるという考えを示した。また,生き生きとした内科臨床を実践すること,精神的ケアを学ぶことなど,内科診療に求められることを列挙し た。 がん患者に対する非告知が医師の礼儀だった時代から,告知が当然の時代に変わり,同院長は「どちらが正しいのか」と自問自答したことがあるという。そし て,「多くの患者と出会う中で,“どちらが正しいか”という問いこそが問題と思うようになった。告知/非告知だけでなく,病院死/在宅死,延命/鎮静など の双方向性のものは2つで1つであり,医療者が決め付けたり,押し付けたりするものではない。どちらであっても受ける誠意が医師には必要と考えるように なった」と述べた。 また,内科臨床の進歩によって在宅で診ることのできる範囲が広まった中で,今後は病院・施設満床の状況をカバーする在宅医療とケアの発展が期待されるとしたほか,内科臨床のさまざまな要素が関与している分野として,同院長が携わる終末医療を挙げた。 終末期と身体医療の関連は薄いと考えがちだが,胸腹水や高カルシウム血症への対応など,「体は死のときまで休まない。“生き生きとした内科臨床”を実践 することが大切」と述べたほか,患者がパニックに陥るのは精神科医が勤務している時間とは限らないため,ベッドサイドにいる内科医が患者・家族の心のケア を理解する必要性を指摘し,精神医学を学ぶことを推奨した。なお,終末医療に限らず,生命現象は反対語で成立していることを知り(吸気/呼気,摂取/排 泄,交感神経/副交感神経,失望/希望など),ホメオスターシスとは何かを意識して患者に向き合うことは内科臨床にとって最も肝要なことだと説いた。 同院長はさらに,内科診療としての終末医療のこれからの宿題として,生活臨床の見直しや胃瘻の適応の再考,多幸感の生まれる鎮静薬の開発などを望むとと もに,「患者の助けての声がある限り,臨床は枯渇しない。学んだものをもう一度学びほぐすunlearnを実践し,個々の患者に合った医療を提供していく ことが大切となる」と述べた。 生と死の間に老と病が加わった時代の人生モデル再考を 宗教学者の山折哲雄氏(元国際日本文化研究センター所長)は,人生50年の時代には「生」と「死」が同じ比重の「死生観」を誰しもが持っていたが,両者 の間に「老」と「病」が入り込んできた人生80年時代の人生モデルは手探り状態にあると指摘。現在の老人終末期医療は長く生きる,生かすことが優先される 傾向にあるのではと問題提起した。 少子高齢化時代をどのように生き,どう死を迎えるか−ということについて考えることは重要である。 つい30年ほど前まで,体感的な平均寿命はほぼ50年であり,当時は「死生観」という人生モデルが確固として存在した。しかし,この短期間に人生80年 の長寿社会となり,生と死の間に,「老」と「病」という問題が入り込んできたことで,政治や社会,そして医学も対応できない状況になっているとはいえない か。 同氏自身,20歳代に十二指腸潰瘍の手術を受け,40歳代で再度吐血・下血するも,その後,現在の80歳代まで現代医療に命を助けられた経験を持つ。 「医療の重要性は分かっている。ただ,現在の多くの高齢者がどのように最期を迎えているのかを考えると,長く生きること・生かすことが優先されているよう な気がする」ととつとつと語った。 折しも,『大往生したけりゃ医療とかかわるな〜「自然死」のすすめ』(中村仁一氏)がベストセラーとなっているように,大往生に対して潜在的要求を持っている層は少なくないのではないか−と自らの経験から話し始めた。 40歳代に十二指腸潰瘍が再発したとき,1週間の絶食を指示されたが,「5日目に地獄の飢餓感を覚えたが,6日目には飢餓感が引き,生命力が盛り上がっ てくる体験をした。平安・鎌倉時代の僧侶は死期が近づくと,自ら断食を行ったという記録があるが,“願わくは花のもとにて春死なん その如月の望月のこ ろ”と詠んで,その通りに死期を迎えた西行は計画的断食往生を行ったのではと考えるようになった。生と死の間に,老と病がはびこってきた中で,西行的な断 食往生という可能性に少し関心を持っていただければ」と会場に語りかけた。 メディカルトリビューン 2012年6月7日 |