 �@
�@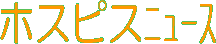 �@�@
�@�@
�o�b�N�i���o�[2012/1/1�`2012/12/2
| �@�z�|�� >��w�g�s�b�N�X>�z�X�s�X�j���|�X>�o�b�N�i���o�|�ƭ->2012/1/1�`2012/12/2 |
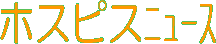 �@�@
�@�@| �@�z�|�� >��w�g�s�b�N�X>�z�X�s�X�j���|�X>�o�b�N�i���o�|�ƭ->2012/1/1�`2012/12/2 |
| �܂��͒ɂ݂����I�ɘa�P�A�ɑ傫�Ȍ��� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ����{�������P����c��������Q�f�Ï��u�r�n�[���N���j�b�N�v�i���s�{��z�s�j�n��S�N�@���i�S�X�j �@����̏I�����ŁA�ɂ݂Ɛ��_�I�ȋꂵ�݂���菜�����Ƃɓ���������Â��s���z�X�s�X�B�u��������Q�f�Ï��v�́A�u�r�n�[���������v�̈��̂����A���{�莛����̂̕����z�X�s�X���B�@���̔n��S�N��t�́A�O�ȏo�g�̊ɘa�P�A�ゾ�B �@�u��p�Ƃ����A�ڂŌ�����ΏۂƏ������钆�ŁA�g�ڂɌ����Ȃ����̂�ɂ����Áh�ɋ������N���Ă�����ł��B�S�O���߂��Ėڂ������Ȃ��Ă������i�j�A�V�������ƂɃ`�������W����Ȃ獡�����Ȃ����낤�Ɓc�v �@�ɘa�P�A�Ƃ����ƁA�P�ɒɂ݂���邾���́u�������Ȉ�Áv�ƌ�����ꂪ�������A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ɣn���t�͌����B �@�u�Ⴆ�Δx���҂��w���w�Ö@�̂݁x�Ɓw���w�Ö@�{�ɘa�P�A�x�̂Q�Q�ɕ����ė\�������ƁA��҂̂ق����������Ԃ����������|�Ƃ���������B����Œɂ݂��o�Ă���Ȃ�A�܂��͂��̒ɂ݂����ׂ��ŁA����ɂ���Ď��̃X�e�b�v�����܂���ł��B�������ɘa�P�A�̎p���L����ʂɒm���Ă��炤�ׂ������A���̂��߂ɂł��邱�Ƃ͐ϋɓI�Ɏ��g��ł��������v�i�n���t�j �@�n���t���@���߂�f�Ï��ɂ́A�ʏ�̈�ÃX�^�b�t�̑��ɑm�����풓���A���ʓI�Ȋɘa�P�A��i�߂��ő傫�Ȗ������ʂ����Ă���B �@�u��t��Ō�t�ɘb���Ȃ����Ƃł��A�m���ɂȂ猾����Ƃ������Ƃ����ۂɂ���B����͏I�����̊��҂ɂƂ��ā@�g��ȏ�̌��ʁh�����邱�Ƃɂ��Ȃ��ł��v �@���N�ɂ͐f�Ï�����a�@�ւ̋K�͊g�[��\�肵�Ă���B�n���t�̃`�������W�́A�m���ɐ��ʂ������n�߂Ă���B ZAKZAK�@2011�N12��9�� |
||||
|
���҂�5���ɂ��a�������C�j�[�Y���܂鐸�_��ᇊw�̖��� ���������Z���^�[���_��ᇉȁE���������ɕ��� |
||||
| �@����Ƃ����d��ȃ��C�t�C�x���g���^���鐸�_�I�Ռ��͐r��ł���C���a�Ȃǂ̐��_�Ǐ��悷�邪�҂͏��Ȃ��Ȃ��Ƃ����B���{�̂���f�[�^�ɂ��ƁC���҂̖�5�������a�Ɛf�f����C�K����Q���܂߂�Ɩ�20�������_�I��������Ă���Ƃ����B �@���̂悤�Ȕw�i����C���҂₻�̉Ƒ��ɑ��鐸�_��w�I�A�v���[�`����Ƃ��鐸�_��ᇉȂ̃j�[�Y�����܂��Ă���B���������Z���^�[�ł�1992�N�ɐ��_�ȁi2008�N�ɐ��_��ᇉȂɖ��̕ύX�j��ݒu�C���҂Ƃ��̉Ƒ��ւ̐��_��Â�ɘa�P�A�Ɏ��g��ł���B���Z���^�[���_��ᇉȕ��Ȓ��̐��������ɁC���_��ᇊw�̌���Ɖۑ�C���_�����ɜ늳�������҂ւ̖��ÂŒ��ӂ��ׂ��_����ʓI�Ȑ��_�Ö@�Ȃǂ����B ��ʂ̐��_�����Ƃ͈قȂ邪�ғ��L�̋ꂵ�݂��P�A �\�\���_��ᇊw�Ƃ́B �@�č���1970�N��ɔ��˂����C����Ɛ��_����Ƃ���w��ł���B�p��ł�psycho-oncology�Ƃ�������ŌĂ�Ă���B�č��ł͓����C���m����ʉ����Ă���C���m��̃����^���w���X�P�A�ɑ���Տ�����ł̎��v�����܂������Ƃ��w�i�ɂ������悤���B �@1986�N�ɍ��ۃT�C�R�I���R���W�[�w��iIPOS�j���n�݂���C���N�ɓ��{�x���Ƃ��ē��{�Տ����_��ᇊw��iJPOS�j���ݒu���ꂽ�B���{�T�C�R�I���R���W�[�w��̑O�g�ł���B����C�����Â���Ƃ��铖�@�ɂ����ẮC1992�N�ɐ��_�Ȃ̕W�Ԃ��f�����B�Ƃ��낪�C��ʂ̐��_�Ȃ���f���Ă�����̋ꂵ�݂𗝉����Ă��炦�Ȃ��Ƒi���銳�҂��u���_��ᇉȁv�̕W�Ԃ�T���ė��@����悤�ɂȂ�C���@�ł�2008�N�ɐ��_��ᇉȂɕW�Ԃ����߂��B �@���_��ᇊw�̎�Ȍ����̈�́C�����늳�����Ƃ��̃X�g���X���^���鐸�_�I���ƁC���_��Ԃ�����̕a�Ԃ�i�s�ɗ^������ł���B���̑��C���Җ{�l�ȊO��ΏۂƂ������҉Ƒ��ɑ���X�g���X�P�A��C�����Î҂̐��_�I���܂Ŏ�舵���Ă���B ���҂͐g�̓I�E�Љ�I�E�S���I�v���ɂ�肤�a�ǂ��� �\�\���_��ᇉȂ̖����Ƃ́B �@���݁C�킪���ł͖��N���悻50���l������ɜ늳���Ă���B���҂̖�5���ɂ��a���������C�y�ǂ̂���Ԃł���K����Q�܂Ŋ܂߂�Ɩ�20�������_�I��������Ă���Ƃ����f�[�^������C���_�Ǐ��L���邪�҂͖�10���l�ɒB����Ƃ����Ă���B���_��ᇉȂł́C���̂悤�Ȑ��_�I��������邪�҂ւ̎��É�����s���Ă���B �@���҂̂��a�Ɋւ��ẮC����ɜ늳����ȑO�ɂ��a���o������P�[�X�����邪�C����Ƃ����d��ȃ��C�t�C�x���g�ɂ��C����܂ł͐��_�I�ȓK���ɖ�肪�Ȃ������ɂ�������炸�C���߂Ă��a�ǂ���P�[�X�������F�߂���B �@����ɔ����X�g���X�Ƃ����Ă����܂��܂��B��̓I�ɂ́C�܂��C����ɂ��ɂ݂≻�w�Ö@�Ȃǂɂ��̂̂��邳�Ȃǂ̐g�̓I�v���B���ɁC�����늳�������ƂŎd�����ł��Ȃ��Ȃ�����C���Ô�����Ȃǂ̌o�ϓI�ȋꂵ�݂�������肷��Љ�I�v���B����ɁC�]���鍐������C�q�ǂ���z��҂ȂǑ�Ȑl�Ƃ̕ʂ���o�債���肷�邱�Ƃɂ��S���I�v����3������B �@���������l�����ɑ��Đ��_��w�I���ꂩ���Â���邱�Ƃ��傫�Ȗ����ł���B���@�̐��_��ᇉȂɂ͌��݁C��t5�l�i���2�l�C������Ƃ̕��C1�l�C����2�l�j�C�Տ��S���m3�l�i���1�l�C����2�l�j������C���@���̖�600�l�̂��҂̂���40�`50�l���x�̐f�Âɓ������Ă���B�����āC����15�`20�l�̊O�����҂ɂ��Ή����Ă���B ���ʂ�������p�ɔz���������҂̂��a�Ö@ �\�\���_��ᇉȂɂ����鎡�Â̎��ۂ́B �@���a�̔��ǂ͂���늳�����ڂɂ�������Ă���B���̂��߁C��q�����ʂ�C���E��A�g���d�v�ɂȂ��Ă���B�Ⴆ�C���҂̋ꂵ�݂��g�̓I�Ȓɂ݂ɗR��������̂Ɣ��f�����ꍇ�C�ɂ݂̎��Â���Ƃ���f�ÉȂƘA�g���čs���K�v�����邾�낤�B���邢�́C�Љ�I�Ȗ��ɂ����̂Ȃ�C�\�[�V�������[�J�[�Ƃ̘A�g���]�܂������낤�B���@�ł͊��҂̂��߂Ɉ�Î҂��A�g��}��Ƃ������O�����L���Ă���C���_��ᇉȑ���������Ȃ⑼�̐E��ւ��܂��ӎv�`�B������H�v�����Ă���B���ꂼ��̐�含��������ØA�g�����߂��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B �@�Ö@�Ɋւ��āC���ۂ̎��Âɂ������ʂ̂��a���҂Ƃ̑傫�ȈႢ�́C���ʂ�������p�ɑ��ĐT�d�������߂���_���B�Ⴆ�C���ɉ��w�Ö@�œf���C�ɋꂵ��ł��銳�҂ɑ��C����p�Ƃ��ēf���C���F�߂��Ă���I��I�Z���g�j���Ď�荞�ݑj�Q��iSSRI�j���������邱�Ƃ͔�����ׂ����B �@�܂��C�R�����ƍR����Ƃ̑��ݍ�p�ɂ��z�����K�v���B��ʂ̂��a���҂Ɠ��l�ɁC�R����͗L���ł͂��邪�C�}���Ō��ʂ��o�����Ɛ��}�Ɏg�p����̂ł͂Ȃ��C����p�ɑ��ĐT�d�Ȗ�ܑI���Ⓤ�^���@���K�v�ł���B �@����C���_�Ö@�Ƃ��ẮC��͂�ł���{�I�Ȏx���I���_�Ö@�iSPT�j��p���邱�Ƃ���ʓI�ł���BSPT�́C��Î҂����҂̔Y�݂�s���ɂ悭�����X���C�����◝���������Ċ��҂��x������Z�@���B���̑��C�\�������ꂽ�������Ö@�iPST�j������C���@�ł��������Ă���B�Ⴆ�C������̍Ĕ��ɑ���s���ɂƂ���Ă��邤�a���҂ɑ��āC�Ǝ��Ȃlj����ɖv�����鎞�Ԃ����悤�ɑ������肷��B ���҂̂��a���߂������t�s���̉����Ɍ������g�ݐi�� �\�\���_��ᇉȂɂ�����ۑ�Ǝ��g�݂ɂ��āB �@���@�ł̐��_��ᇉȐf�Âł́C�����Ԃɂ��銳�҂Ȃ琔���Őf�@�\�ł��邪�C�ꍇ�ɂ���Ă�30���`1���Ԃقǂ�v���邱�Ƃ�����B��ʂ̐��_�Ȑf�ÂƔ�׃J�E���Z�����O�ɂ��d�_��u�����Ƃ����_��ᇉȂ̓�����1���B�����C���_��ᇉȂ̈�t�����Őf�Âɓ�����ɂ͈�t�̐��Ɍ��E������B �@���|�I�Ȉ�t�s���̉����Ɍ����āC���{�T�C�R�I���R���W�[�w��ł͗Տ��o���̈����������t��F�肷��o�^���_��ᇈ㐧�x����N�i2010�N�j����݂��Ă���B�܂����x���n�܂��ē����C�܂�9�l�̓o�^�㐔�ɂƂǂ܂��Ă���B�F�������Ă��Ă����o�^�̈�t�������C����C�o�^�����t�̐��͑����邾�낤�B�܂��C���w��ł͌��݁C�����ψ����ݒu���Đ��㐧�x�̓������������Ă���B���_��ᇉȂ���Ƃ��Ċ������鐸�_�Ȉ�͂܂����\�l�Ə��Ȃ����߁C���_��ᇉȂ̈Ӌ`������C�j�[�Y�̍����𗝉����āC����͂�葽���̐��_�ȗ̈�̈�t�ɎQ�����Ăق����Ɗ���Ă���B �@����ł���ꂪ���g�߂�ŊJ���1�Ƃ��āC�Տ��S���m�̂ق��C�Ō�t�ȂǑ��E��Ƃ̘A�g����������B����ꂪ�s���������J���Ȋw�����̌��ʁC���҂ɂ�����u��I���_�Ǐ�X�N���[�j���O����v���O�����v���L�p�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����iPsychooncology 2010; 19: 718-725�j�B �@��q�������҂�5�������a�ł���Ƃ�������ɂ��Ă����C���͌��߂�����Ă���P�[�X�������B�����ŁC�Ō�t�ƘA�g���C���҂ɑ��鐸�_�Ǐ�̃X�N���[�j���O��������{���邱�Ƃ��d�v�ł���B���ɓ��@�ł͎��H���Ă��邪�C�S���̂���f�ØA�g���_�a�@�ł̕��y��ڎw���C���݂͂��̃v���O�����̐��x����荂�߂邽�߂̉���������s���Ă���B �@�܂��C���@�ł͕ʂ̌����O���[�v���s���Ă����t�����v���O�����Ɋւ��錤��������B�厡�オ�ǂ̂悤�ɂ��m���s���Ɗ��҂̐��_�I�V���b�N�������ł��a�炰�邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ����ϓ_�ɗ����C�厡������̋���v���O�����C�R�~���j�P�[�V�����E�X�L���E�v���O�����iCST�j�̍\�z��ڎw���Ă���B����2007�N����N5�`6��C�R�~���j�P�[�V�����Z�p���C��Ƒ肵�Č��C����{����Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N12��12�� |
||||
| �ݑ�Őf��E�ݑ�ŊŎ�� �g���ЂƂ�l�h�ł�����ōK���Ɏ��˂� |
||||
| ���}�����ȁi���j�������@���}�� ���Y �� �@�Z�݊��ꂽ�ꏊ���u���̂��݂��v�ɂ������ƍl����l�͏��Ȃ��Ȃ����C�Ƌ��̍���҂�����ŖS���Ȃ�ƁC�����Ă��͎₵���̒��Ŏ���ł�������ۂ�^����B�������C�ݑ��ÁE�Ŏ����s�����}�����ȁi���j�������̏��}�����Y���́u��]����ƂōŊ����߂�����̂ł���C���҂͍Ō�ɏΊ���ׂĎ��ʂ��Ƃ��ł���v�ƌ�����B���҂̊�]�ƃ}�l�W�����g�����������肵�Ă���C�g���ЂƂ�l�h�ł�����ōK���Ȏ����}������Ƃ����B���̎��Ԃ�T�����B �Ƌ����҂�4�p�^�[���� �u�ɂ݂⎡�Â̂��Ƃ͈�t���ӔC�������܂��B�F����͂ł��邱�Ƃ�����������Ă��炦��Ό��\�ł���v�B�s���œƂ��炵������85�̏�����ɏW�܂������}������K��Ō�t�C�P�A�}�l�W���[�C�w���p�[�C�{�����e�B�A��15�l�̑ł����킹���i�ł���B�����ψ���אl���Q�����Ă����B���i�̖�肪�Ȃ���C�ł����킹�ɓ������������̂́C���ꂪ�ŏ��ōŌ�ƂȂ�B �@�����͖��������1��3��̖K��P�A�𗘗p���C�x�b�h�̂��ɂً͋}�ʕ�p�̔��{�^���Ə��}�����Ȃւ̃z�b�g���C�����~����Ă���B2�J���O�܂ł͐Q�����肾�������C����Ŋɘa�P�A���Ă��邤���ɐQ�N�����ł���悤�ɂȂ�C�u�Ԃ����ɍs�������v�ƌ����o���قnj��C�ƏΊ�����߂����B �@�z��Ȃƍݑ��Â��f���铯�@�́C�K��Ō�X�e�[�V�����݂���B�����̎��_�́u�g���ЂƂ�l�h�ł�����Ŏ��˂�v�ł���B����܂ł�500�l�ȏ���Ŏ���Ă��������́C�Ƌ��̖������҂̊Ŏ�肪4�p�^�[���ɕ��ނł��邱�ƂɋC�t�����i�\�j�B 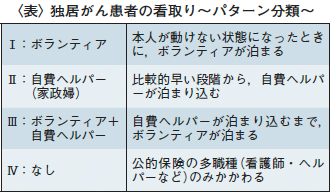 �@��������ŗ]��2�`3�J����70�Α㏗���̃P�[�X�ł́C�S���Ȃ�10���O����g�̉��̐��b�����鎩��w���p�[�C�����锑�܂荞�݂̉Ɛ��w�𗘗p���Ă����B���p������1���i24���ԁj��1��5,000�~���x�������B�Ƃ��炵�̓��@���҂ł����Ă��C���悢�掀�����߂Â����i�K��30���~�قǂ���C����ɖ߂�ݑ�ōŊ����}���邱�Ƃ��\�ɂȂ�v�Z���B �@����w���p�[��{�����e�B�A�̋��͂�����ꍇ�́C���I�ی������p���ĊŌ�t��w���p�[�Ȃǂ̑��E��A�g�őΉ�����B����������ň�ᑂ݂��Đ����ی���Ă���50�Α�j���̗�ł́C�]��2�J���̎��_�őމ@���C�ݑ��Â��n�߂Ĕ��N���߂�������C�钆�ɒ����ŋꂵ�މ\�����o�����߁C�����͐�����ɂ���ԃZ�f�[�V�������Ă����B �@��ɂ������邱�ƂȂ������ɖڂ��o�܂��邪�C�钆�͐[������̒��ɂ��邽�߉Ƒ������Ă�������Ȃ��B����̌o�߂ɂ���ĕ����ڂ��ĂъJ�����ƂȂ��C���̂܂���ł����\��������B�������C�a�@�ł̂炢���a�o�����玩��Ŏ��ɂ����Ɩ]�ޒj���́C��ԃZ�f�[�V������I���B���̌�C�v���Ԃ�ɗ������q�����܂�����ɗ��������B���e�̈��炩�ȕ\����������q�́u����͋ꂵ��Ŏ��ʂƕ����Ă������C�ƂĂ��ǂ��\��B����1�T�Ԃ͋ꂵ��ł��Ȃ�������ł��ˁv�ƁC����̌��t���q�ׂ��Ƃ����B�����ɊŎ��ꂽ�Ƌ����҂�10�l���邪�C�u�S�����N���Ɍ�����Ȃ��痷�����Ă���̂��s�v�c�ł���C�ݑ�z�X�s�X�P�A�̋ɂ݂�������Ȃ��v�Ɠ����͌��B �ݑ�ŏ��������҂̋����e �@���}�����͏z��Ȃ̈�t�Ƃ��ĕ��ݎn�߁C�����a�@���w�a�@�Ōo����ςB40���@�ɓƗ����C1989�N�ɏ��}�����Ȃ��J�@�������C�u���f�����͂���܂��v�ƍl���Ă����B�Ζ���̂���ɁC��i����u���f����J�ƈ�͋������������Ă���B���҂����肬��܂Ŏ��@�Ŏ��Â��C��̎{���悤���Ȃ��Ȃ��Ă���a�@�ɑ���v�ƕ����Ă�������ł���B �@�����C���߂���Ή��f�ɂ��������B�J�@����3�N�ځC�����̑咰���҂ɍݑ��Â��s���Ă����Ƃ��ɓ]�@���K�ꂽ�B�قُ݂Ȃ���S���Ȃ������҂����āu�a�@�ł͋����e�Ŏ��ʊ��҂������̂ɁC�ݑ�ł͂ǂ����Ĉ��炩�Ȏ����}����ꂽ�̂��v�ƍl����悤�ɂȂ����B �@�Ƌ��̊��҂����炩�Ȏ����}���邽�߂ɂ͎�����点�C����Ă��炤�P�[�X�������B�����s�������҂�����������Ȃ���C�u���ʂ܂Ŏ����Ƌꓬ��������v�Ǝw�E����B������C���҂ɂ́u�����������ʂ����ˁB�ǂ������ʂȂ�N�炩�ɐ����C���炩�ɗ����Ă�ō�����ˁv�ƁC���R�Ɏ��̘b����o���B ��ԃZ�f�[�V�����̗L�����L �@���}�����́u�����ɋC�t���Ă���l�ɁC�w���ȂȂ��x�ƌ����Ă��S�͒ʂ�Ȃ��B����F�߂邱�ƂŁC���߂Ė��ʂ̏Ί�ɂȂ��v�Ƙb���B�Z���]�������m���ꂸ�ɂ��銳�҂ɁC����S����������������Ƃ��C�u���߂Ė{���̂��Ƃ������Ă��ꂽ�l���v�Ɗ��ӂ��ꂽ�o�����S�ɍ��܂�Ă���B �@���Ă͒��Ԃ̋Ζ���Ɂu���ЂƂ�l�ł��ƂŎ��˂�v�Ɛ������Ă��C�u24���ԑΉ��ł���킯���Ȃ��v�ȂǂƕԂ��ꂽ�B����ǂ��C��̓Z�f�[�V�����őΉ����邱�Ƃ��ł��邵�C���܂��܂ȐE���{�����e�B�A�ƘA�g����C�����ł����B�Z�f�[�V�����ɂ͌ċz�}����S�z���鐺�����邪�C�ꂵ�݂���菜���C�����������߂̃Z�f�[�V�����͓��Ɉ��S�ɍs���Ă���B����ɂ���ăZ�f�[�V�������ɖS���Ȃ�\�����[���ł͂Ȃ����C�u���҂��K���ȏ�ԂŎ��˂�̂�����C�S�z�͂Ȃ��v�Ɛ����Ă����B �@���N4���ɂ͓��{�ݑ�z�X�s�X����ɏA�C�����B���N���s�����w�����̎��Îw�j�x�ł͍ݑ��u�ɃP�A�Ɋւ��鎷�M��S�����C���Õ��j�ɐ����邽�߂ɕK�v�Ȗ�ԃZ�f�[�V�����̗L�����ƕ��@�L�����B �@���@�͌��݁C���̈�Ë@�ւ⑼�E��ɍݑ�ɘa�P�A�̎��H���w�����Ă���B�u�g�ѓd�b��e���r�d�b�����邵�C����̈�Ís�ׂ������C���O�w�������Ă����ƍݑ�ɘa�P�A�̂قƂ�ǂ͈�t�����f���Ȃ��Ă����v�v�ƌ�����B �g�[�^���w���X�v�����i�[�̑��� �@�������C���܂��܂ȐE�킪1�̃`�[���Ƃ��Ă����������C�s���葱���Ȃǂ���������肷��Ƌ����҂ւ̃P�A�ɂ́C�i�ߓ��I�ȑ��݂��K�v�ɂȂ�B���}����������̂́C�ݑ�ɘa�P�A�̃`�[�����}�l�W�����g����u�g�[�^���w���X�v�����i�[�iTHP�j�v�ł���B�����͈�ÂƐ����̗��ʂ��犳�҂��T�|�[�g���C��t��P�A�}�l�W���[�C�w���p�[�C�{�����e�B�A�C�Ƒ��̊Ԃ��Ȃ��C����������ɂ͊Ō�t���K�C�ƍl���Ă���B���@�ł́C�K��Ō암���߂�ؑ��v���q����2�l���CTHP�Ƃ��Ċ��Ă���B �@���É���w��w�@�ł�2006�N����Ō�t�◝�w�Ö@�m�C��ƗÖ@�m�Ȃǂ�THP�̋�����s���Ă��邪�CTHP��C�Ƃ��Ă̗̍p���т͂܂��킸���B����ǂ��C���}�����́u��t�⑼�E��̕��S���m���Ɍ��邱�Ƃ��l����CTHP�̎��_���������l�ށC���ɊŌ�t�̑��݂��ݑ��ØA�g�̌�������v�Ƃ̌����������B �@����Ŏ��ƌ��������Ȃ���Ŋ����}����s�ׂ����R�̂��̂ƂȂ�ɂ́C�ӎ��̕ϊv���s���ł���B�����́u�a�@�̈�t�ɂ́C���҂��a�Ɩ������ē����C�����������邱�Ƃ������őP�ł͂Ȃ����Ƃ𗝉����Ă��炤�K�v������v�Ƒi����B�����āu�a�@�̈�t���ς��Α��̐E��ɂ��g�y���āC��Ì���ł����������y�낪�ł���͂��v�Ƒ�����B �@���炩�Ȏ����}�������邱�Ƃ��C�ݑ�ɘa�P�A�̗v���ł���B�Ⴆ�C���҂̓��퐶������iADL�j���ɒ[�ɒቺ�����Ƃ��C��ԃZ�f�[�V�������s���Βɂ݂�ꂵ�݂̕s���͏�����C�n���ł���̂�QOL�͌��シ��B �@�����́u���ЂƂ�l�̍ݑ�ɘa�P�A�́C�o���Ƃ������߂C��t�Ȃ�N�ł��ł���悤�ɂȂ�v�Ɛ�������B���N4���ɂ́C�����Ȃ�12�l�̈�t�炪�u�ݑ�z�X�s�X���S�l�b�g�v�𗧂��グ�C�ݑ��Â̘A�g���������Ă���B�u������x�̃��x���̈�t������ƈ���Ă����v�Ɩڂ��ׂ߂铯���́C�����ő傫�Ȗ��ƂȂ����ݑ�̏I������ÂɌ����C����Ȃ鋳��ƕ��y�ɗ]�O���Ȃ��B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N12��29�� |
||||
| �ݑ�Őf��E�ݑ�ŊŎ��@�n��ɍ����������������H | ||||
| ��t������i��t���j�������@�a�c ���u �� �@���҂��]�ގ���ł́i�Ŋ��܂ł́j�×{������������ɂ́C��w�I�Ȏ��_�ȊO�ɂ����܂��܂ȃA�v���[�`���K�v�ɂȂ�B�����s�Ɛ�t���C���m���ōݑ�×{�x���f�Ï����J�݂����t������i��t���j�������̘a�c���u���́C������s���ȂǂƂ̘A�g��[�߂Ēn��ɍ��������ݑ��Â̎��H�ɓw�߂Ă����B�a�C�ɂƂǂ܂炸�C���҂̐l������ɂ��ӔC�������ĕt���������Ƃ����݂Ă��������ɁC�ݑ��Â̎��H�ɂ��ĕ������B ���҂̍ݑ�����m���ŋ}�� �\�@���m�����ōݑ�̂��҂��傫���������ƕ��܂����B �@���ɂ��ƁC���m���ł��҂�����ŖS���Ȃ��������́C2005�N��3.7���i�S������5.7���j��47�s���{���̉�����3�ԖځB�Ƃ��낪�C2010�N�ɂ�7.4���i�S������7.8���j�Ƌ}�����܂����B�������C�S���I�ɑ����Ă���̂ł����C���m���͂�������鐨���ŐL�тĂ��܂����B �@��t�����ˎs�Ŋ������Ă����킽���́C�̋��ł̍ݑ��Â̕��y��ڎw���C2009�N�ɂ�������f�Ï����m���]���J�݂��܂����B�����́u�a�@��Â������y�n�ŁC�ݑ��Â��蒅���邾�낤���v�Ƃ�����������܂����B�������C���m�ɂ��ݑ��ÂɈӗ~�I�Ȉ�Ï]���҂͂���C����ŖS���Ȃ邪�҂̑����́C����瑽���̍ݑ��Ï]���҂̓w�͂��`�ɂȂ��ĕ\��Ă����̂��Ǝv���܂��B �@���̐����ɔ��f����Ă���̂́C�����Ƒ���������C�o�ϓI�]�͂��������肷��l�������܂܂��Ɛ��@���܂��B�Ƃ����̂́C�܂��ݑ�ɘa�P�A�̗��p���l���銳�҂���͏��ɕq���ŁC���琅������r�I����������������ł��B���������l�X�ɂ͖{�l��Ƒ��̑����I�ȗ͂����邱�Ƃ������C�ݑ�×{�̎菕�������邱�Ƃ́C����قǍ���ł͂���܂���B �@����ꂪ����Ƃ��Ă���͕̂n�����Q�Ȃǂ̂��߂Ɍo�ϓI�C�Љ�I�ɗ��ꂪ�キ�C���A�N�Z�X�ɂ��ア�l�X�́u���Ȃ����v�ɐڂ��邱�Ƃł��B�����������҂���͎������琺���������Ȃ�����C�킽�������̗͂��n��ɐZ�����Ă��Ȃ��Əo��Ȃ��̂ł��B�ݑ��Â̖{���I�ȕ��y�́C�u���Ȃ����v�ɂ�������Ή��ł���悤�ɂȂ邱�Ƃ��ƍl���Ă��܂��B �\�@�Ƒ��̖�����������҂͏��Ȃ�����܂���B �@�ƒ���s�Ҏ���Ȃǂł́C�Ƒ��̗��j��F�����đΉ����Ȃ���Ȃ�܂���B���Q�҂���Q�҂ɑ���W�ɁC���邢�͂����ɐU�镑���Ƃ��C���̂悤�ȍs���͑�O�҂ɂ͂ɂ킩�ɗ��������˂܂����C�����ɂ͉Ƒ��̉ߋ����B����Ă��邱�Ƃ��������Ȃ��B��Â╟���̃X�^�b�t���p���I�ɂ�����邱�ƂʼnƑ��̕��S������C�S�ɗ]�T���o��C�s�҂��ɘa���邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ��̂ł��B �@���҂��Ƌ��̏ꍇ�́C�ݑ��Â͍�������Ƃ����܂��B�����̖����N���A����C���̐��𐮂��邱�Ƃ��ł��܂��B�������C�Ƌ��V�l�͌o�ϓI�Ɏア����̐l�����Ȃ�����܂���B����ȂƂ��ł��C���҂���]�������͂��܂��܂Ȏx�����s���āC���肬��܂Ŏ���ɂ��Ă��炦��悤�ɓw�߂Ă��܂��B ��ԌĂяo���͓����f�ÂƖ��ڂɊW �\�@24���Ԃ��ł��Ăяo���ɉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł����B �@�悭�����̂́u24���ԑΉ��͌������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ�������ł����C24���ԑΉ��͕a����ÂƓ������C�����̐f�Ó��e�Ƀ����N���Ă��܂��B �@��t�̎d���̑傫�Ȃ��̂Ɂu�\�����邱�Ɓv������܂��B�ݑ��Âł������f�Â�K�ɍs���Ă���C��ԁE�x���ɕs���̌Ăяo�����邱�Ƃ͏��Ȃ����C���̌Ăяo���ɂ��Ă��u�啔���͗\�����ꂽ�Ăяo���v�ł��B��Ԃ�x���ɋN���肤�邱�Ƃ�\�����C�K�v�ɂȂ邩������Ȃ����u�⏈������肵�čs���܂��B����ɁC�Ƒ��̕��ɋN���肤�邱�Ƃ����炩���ߐ������Ă����܂��B���������Ή��ŁC��ԑ��k��Ăяo�������炷���Ƃ��ł��܂��B �\�@��Ԃ̑��k�̎��Ԃ́C�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����B �@��t���̂�������f�Ï��i��{���C�V���ˁj�̃f�[�^����ɐ������܂��傤�B2007�N4���`08�N3���̖�ԁi�ߌ�6���`�ߑO9���j�̗Վ����f�́C��{����������8.9��ŁC��Έ�1�l������ł�2.2��ł����B�V���˂͂��ꂼ��8.7��C2.2��ł����B��t1�l�Ō���2����x�ł��B �@���f�Ï��Ƃ��C�������Ԃ̍ݑ�Ґ���220�`240�l�Ő��ڂ��Ă��܂����B���Ґ����猎�ԌĂяo�����Z�o���Ă݂�ƁC50�l�̋K�͂ł�3�`4��C10�l�ł�0.5��ȉ��ł��B��������f�Ï��ł͈�Èˑ��x�̍�������f�Ă��܂��B�܂蓯���̏d�Ǔx�̊��҂�f�Ă��Ă��C���̈�t�̎����ݑ�҂�20�l���x�Ȃ�C��1����x�̌Ăяo�������Ȃ��Ɨ\�z����܂��B �@�������C��ԓd�b�̖�85���͈�t��Ō�t�̖K���K�v�Ƃ��Ȃ����e�ł����B�d�b���ʼn\�ł�������C�K��Ō�t�̘A�g�ŏ��ꂽ�肷��P�[�X�������̂ł��B�d�b�őΉ��ł�����Ԃ̑��k���e���C�唼�͓����̐f�Â���\�z��������̂ł����B �\�@��t���ł̊����͂ǂ��������̂ł����B �@1999�N�ɂ�������f�Ï���{���C2003�N�ɂ͂�������f�Ï��V���˂��J�݂��܂����B���ˎs�ɂ͍ݑ��Â����H�����t�͂���Ȃ�ɂ����̂ł����C����ł������͍ݑ��Éߑa�n�������Ǝv���܂��B �@�������r�I�X���[�Y�ɃX�^�[�g�ł��C�J�@����5�N���߂�������ɂ͎s���ōł��傫�ȍݑ��Ë@�ւƂ��āC�ݑ��Ê��҂�2�������悤�ɂȂ�܂����B�s���Ő���オ���Ă����ݑ��Â̋@�^���C����ɑ��i�ł����Ǝv���Ă��܂��B �s������g�ݑ��Ó�h�̑Ή��˗��� �\�@�s���ő�̍ݑ��Ë@�ւƂȂ������R�͂Ȃ�Ȃ̂ł��傤�B �@1�ɂ́C�ݑ��Â�v���C�}���P�A�ɐs�͂����Ë@�ւ̕��X�Ƃ�������A�g�ł������ƁB���ꂩ��C�K��Ō�X�e�[�V��������ی��̎��Ə��Ɗ��҂���̎x����ʂ��C�A�g��[�߂�ꂽ���Ƃ�����܂��B �@����1�C�s������̑��k�������邱�Ƃ������Ȃ������Ƃ�����܂��B�s��������C�Ƌ�����ی������X�̑Ή����˗������悤�ɂȂ����̂ł��B�����́u���Ȃ����v�ɐڐG���闝�O�ɍ��v���Ă����̂ŁC�艞���������܂����B �@�킽���́u���ˎs����ҋs�Җh�~�l�b�g���[�N�v�̉��5�N���߂܂����B�Љ�I�����𑽂��肪�������т���C�I�ꂽ�̂��ƍl���Ă��܂��B�u�ʕ��N��P�p�v��u�ʕ���̑����ً}�����v�Ȃǂ��V�X�e�������C��t�����̍���ҋs�ґΉ��}�j���A��������܂����B �@�ݑ�P�A�ł́C��t�Ɍ��炸�K��Ō�t����ی��ɂ�����鑽�E��ɉ����C�����̐E���Ȃǂ��܂��܂ȐE���@�ւ��A�g���C�n��̍���҂��Q�҂̃Z�[�t�e�B�[�l�b�g�Ƃ��Ċ��҂���Ă��܂��B �\�@���{�͐l���̍���ōݑ��Â̎��v���}���ɍ��܂��Ă��܂��B �@�S���̍ݑ�S���̐��ڂ́C����5�N�قǂʼn����~�܂�C�悤�₭�㏸�ɓ]���܂����B����҂�������C��Q�҂₪�҂��K�R�I�ɑ������܂��B���܂��܂Ȓ����ŁC�Ŋ��̗×{�ꏊ�Ɏ������]����l���������Ƃ͎��m�̎����ƂȂ��Ă��܂��B��ǂ⎕�Ȉ�Ƃ̘A�g���g�[����K�v�͂���܂����C���͖K��Ō�t�ł��B �@�ݑ�Ɍ��炸�a�@�ł������ł����C���҂ƈ�w�I�Ȗʂōł��ڂ���͈̂�t�ł͂Ȃ��Ō�t�ł��B�ݑ�ł̊ɘa�P�A��d�NJ��҂̃P�A�C��ጃP�A�Ȃǂ͖K��Ō�t�Ƃ̘A�g�Ȃ����Ă͕s�\�ł��B �@�킪���ł͂܂��܂���Ղ��Ǝ�ȖK��Ō�X�e�[�V�����̊g�[���d�v�Ȃ̂ł����C�킽���͍��ɂ��㉟�����ア�ƍl���Ă��܂��B�K��Ō�X�e�[�V�����͑S���I�ɐݒu�����L�єY�݁C���m���ł͌������Ă���قǂł��B����̊Ō�t����ނ��Ƃ͂��Ƃ��C���ɂ͂��Ж{�������Ă������������Ǝv���܂��B �ݑ��Ñ����a�@��s���ɐϋɓI�ȃA�v���[�`�� �\�@�����ւ̐l�ފm�ۂ��}���ł��B �@��������f�Ï����f�����2�̖ړI�͋��犈���ł��B�f�Ï��ł͓�����Ȏ��ȑ�w�⏇�V����w�C���m��w�̊w�����K���s���Ă��܂��B�܂��C�����̍ݑ�ゾ���łȂ��C�鋞������w�Ō�w���̊w�������K�{�݂Ƃ��Ď���Ă��܂��B����ɓ�����Ȏ��ȑ�w�a�@��Ղ̖�a�@�i�����s�j�C�݂��ƌ��a�a�@�i��ʌ��j�̗Տ����C������炵�Ă��܂��B �@��3�̒��Ɍf���Ă���̂́C����܂ł̊��ԂŔ|�����o�������C�n���Ë@�ւ݂̍����f�Ô\�͂̃��f������邱�Ƃł��B�ݑ��Â𒆐S�ɏ��Ђ̎��M��u����C���w����ɉ����C�n��̃l�b�g���[�N�������������s���Ă��܂��B �@�ݑ��Â̎��v�����܂��Ă��邽�߁C�f�Ï������łȂ��C���_�a�@�̈�t��Ō�t���n��̎��Ԃ�c�����Ȃ���C���҂̂��߂̈�Â��@�\���܂���B�ݑ��Â��s�������ϋɓI�ɕa�@��s���փA�v���[�`���C���҂₻�̉Ƒ��Ƃ̂�����n���ɐςݏd�˂Ă������Ƃ����z�ł��B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N12��29�� |
||||
| �ݑ�Őf��E�ݑ�ŊŎ�� ���k��@�Z�݊��ꂽ�ƂŎ��ɂ����I�n��l�b�g���[�N�̌���Ɖۑ� |
||||
| �i��@���� �� ���i��t�j�@�����炢�N���j�b�N�i���s�j �o�Ȏ� ��� �v���q ���i�K��Ō�F��Ō�t�j�@���_�˖K��Ō�X�e�[�V���� �������� �c�� �m�O ���i�P�A�}�l�W���[�j�@�P�A�v���������Ƃ��i�P�H�s�j �g�c ���N ���iNPO�j�@NPO�@�l�A�b�g�z�[���z�X�s�X �u�a�@�ł͎��ɂ����Ȃ��C�Ŋ��͎���Ō}�������v�Ɩ]�ސl�������Ă���B���ʁC�u�Ƒ��ɖ��f�͂��������Ȃ��v�Ƃ������R����a�@�ł̎���I�Ԑ����������B�Z�݊��ꂽ�ƂŎ��ʂ��Ƃ�]�݂Ȃ��炩�Ȃ����Ȃ��̂ł���C����͂Ȃ����B�ǂ���������ł���̂��B �@�������҂𒆐S�ɖ�300��̍ݑ�Ŏ����o��������t�̍��䎁�C�K��Ō�F��Ō�t�Ƃ��Ă��̋���Ǝ��H�Ɍg����㎁�C���T�[�r�X�����P�A�}�l�W���[�Ƃ��Ă�������Ă����c�����C����ʼnƑ����Ŏ�����o������s���ڐ��ł̌[�������𑱂���g�c���ɁC�ݑ�ł̊Ŏ��̌���Ɖۑ����荇���Ă�������B�����ȋc�_����́C�g�I�����ɂȂ�u�ƂɋA��v���ƂɕC�G���鉿�l��a�@�͒ł��Ȃ��h�Ƃ������C���ꂩ��̈�Â݂̍�����l�����Ŏ����ɕx�ތ��t������ꂽ�B �ݑ�Ŏ��Ƃ̏o� �l���Ƃ����d�����I��鎞�͉ƂɋA�낤�^�n���h�u�b�N�w���Ȃ��̉Ƃɂ����낤�x �����F�����͍ݑ�ł̊Ŏ��̌���Ɖۑ�ɂ��āC��t�C�Ō�t�C�P�A�}�l�W���[�i�P�A�}�l�j�C�s���̗��ꂩ��l���Ă����܂��B�܂����ȏЉ�����ˁC���̖��ɂ������悤�ɂȂ����o�܂�b���Ă��������B ����F���͑��ƌ�C�_�ˎs�̎s���a�@��4�N�ԋ߂܂������C�w������ɍu�`���Ĉȗ���肽�������ݑ�Ō�Ɉڂ�C8�N���o�߂��܂����B�ŏ��͊Ŏ��̎���͂���܂���ł������C���̖K��Ō�X�e�[�V�����ł͑����̃P�[�X���o�����Ă��܂��B���҂����Ƒ��̔Y�݂��]���������蕷���邱�Ƃ��C�K��Ō�̑f���炵�����ƍl���Ă��܂��B �c���F���̏ꍇ�C1986�N�ɋ��m�̑哪�i�����Ƃ��j�M�`���J�݂����N���j�b�N�̉^�c����`�����̂����������ł��B�哪�͍ŏ�����ݑ�ł̊Ŏ���ڎw���Ă���C�����K�v�ɔ����ĕ����C�P�A�}�l�̎��i�����܂����B���ɁC94�N�ɗ����グ���u�d���z�X�s�X�E�ݑ�P�A������v�Ŋw���Ƃ��傫�������ł��ˁB���́C�s�����t��ƂƂ��ɒn��Â���̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B �����F�s���ƈꏏ�ɍl����C�����Ƃ��Ă͉���I�Ȍ�����ł����ˁB �g�c�F�l�́C12�N�O�ɋ}�������������a�̍Ȃ��ƂŊŎ��܂����B�a�@�ŗ]�����m�����Ȃ��C�A���]����ł��B���������Ɂu�ɘa�P�A�͂ł��܂���v�ƒf��ꂽ���߁C�j�����̐e�q3�l�ŊŎ��܂����B���悤���܂˂̃P�A�ł������C���ł�����̂ł��B�炭�߂����o���ł������C����Q�Ȃ��ōȂ̂��Ƃ�S�z�������Ԃ͂ق��ɂ���܂���B�v�����猩��ΊԈႢ���炯��������������܂��C���ꂪ�����̎��Ԃ�����܂����B���f��f��ꂽ���Ƃ����C���ł͊��ӂ��Ă��܂��B�����āC����ȊŎ��̑����1�l�ł������̐l�ɓ`�������Ƃ����v�������܂�܂����B �@���̌�C���䂳��̖{�Əo�����C�c���C�哪�Ƃ��������X�ƒm�荇�����C�⑰�̐�����Î҂ɓ`����^����C�s���̖ڐ��Ɋ�Â��ݑ�z�X�s�X�P�A�̌[���������s���悤�ɂȂ�܂����B �����F�l�͕a�@��12�N�ԓ���, 1992�N�ɓ��ȂƐ��`�O�Ȃ̐f�Ï����J�Ƃ��܂����B�ݑ��ÁC�Ŏ������悤�ɂȂ����̂́C����҂Ƃ��Ă̊O���f�Ẩ����ł��B�ӂƂ������������Ńz�X�s�X�̌����҂������́E�����m�ꂳ��Əo��C�g�c�����ƈꏏ�ɍݑ�Ŏ��̃n���h�u�b�N�����邱�ƂɂȂ�܂����B2006�N�Ɋ��������w���Ȃ��̉Ƃɂ����낤�x�ł��B�{�l���]�ނȂ玩��Ŏ��ʂ͓̂�����Ƃł͂Ȃ��ƁC���̕��@���������������ł��B �g�c�F�u�l���Ƃ����d�����I��鎞�͉ƂɋA�낤�v������ł����ˁB �ݑ�Ŏ��̎��� �i1�j�މ@�O�J���t�@���i2�j�މ@�������f���i3�j�����d�b���i4�j�g�єԍ��o�^�^���� �����F�ŋ߁C�ݑ�Ŏ��͕��y���Ă��Ă���C�s�s���ŎM�������邱�Ƃ͈ȑO�Ɣ�חe�ՂɂȂ�܂����B���ꂩ��́C�a�@�`�{�݁`�ݑ�����܂����Ԃ��Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B��コ��́C�މ@�̌��܂������҂���̕a���ɂ͍s���܂����B ����F�͂��B�ƂɋA��������܂�����C�a����K��邱�Ƃɂ��Ă��܂��B �c���F���͂��ꂪ���ʂł��ˁB�����C�a�@�̏����ݑ�X�^�b�t�����L����̂͗e�Ղł����C�ݑ�ł̏���a�@�ɂ����ɖ߂��������ł��B �����F�l�ɂ͍ݑ�Ŏ��C���ɑމ@���́g���݁h4�_�Z�b�g������܂��B�܂��C�މ@�O�ɕa�@�ɍs���C�{�l��Ƒ��C�X�^�b�t�Ɖ�u�މ@�O�J���t�@�����X�v�B���ɁC�މ@�������ɉƂɍs���u�މ@�������f�v�B��ł��C���Ƃ�5���ł��C��ɉƂɏo�����܂��B��O���u�މ@�����̓d�b�v�ŁC����͖���܂������Ɠd�b���܂��B��l�́u�g�єԍ��o�^�v�B����́C�P�ɘA��������Ƃł͂Ȃ��C�Œ�d�b�C�g�ѓd�b�ԍ������ׂāC�����ƊŌ�t�̌g�тɓo�^���C���M��������R�[���o�b�N�ł���悤�ɂ��邱�Ƃł��B�u�o���Ȃ��Ƃ������邯�ǁC�����R�[���o�b�N���邩��v�Ɛ������Ă����܂��B �g�c�F����͑�ł��ˁB��Î҂����C�ɓ��邵���݂ɂ��s���B24���Ԃ����d�b�ɏo����킯���Ȃ��B �����F��ԕs���ȑމ@�O��ɂ��ꂾ������Ă����ƁC���҂����Ƒ��͈��S���Ă���܂��B�����āC���S�������͂��܂�肪������Ȃ��B ����F����͂悭������܂��B �����F�ݑ�ł�24����365���Ƃ������t�����ŁC�����ł͖����ƌ�����Î҂������ł��B�ł��C�ʏ�̃P�A����������s���Ă���C��Ԃ̌Ăяo���͂���قǂ���܂���B �@���͖l�́C���S�m�F�������Ė钆�ɍs���K�v�͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�[��3���ɑ����������C8���܂ň�҂͗��Ȃ��B�Ƒ�������5���Ԃ��߂����̂́u����v�ł͂Ȃ����B���̏�ʂɈ�t��Ō�t���K�����Ȃ���K�v�͂Ȃ����C����ꂪ�f�f�����r�[�C����͎Љ�I�Ȏ��ƂȂ�B�e�ʂ�V�Ђ�����Ƌ����Ă������Ȃ��B�l�́C�u�S���Ȃ��Ă��Q�Ă�K�v�͂Ȃ��B������肨�����肵�Ă�����v�ƌ����Ă��܂��B ����F���͖钆�ł��삯�t���Ă��ꏏ����Ⴊ�����ł��B���Ƃ��v�w�ł��Ƃ�ŊŎ��̂͐S�ׂ��ĕ|�����C�炢�B�N���ɂ��Ăق����Ƃ�������͎��R�����C����ɉ�����̂��厖���Ǝv���܂��B �ݑ�Ŏ��̓���Ɩ��� �ݑ�̑�햡��m�����X�^�b�t�͕a�@�Ζ��ɂ͖߂�Ȃ��^��� �����F��コ��͐�قǁC���҂���̘b���������蕷����̂��ݑ�̑f���炵�����ƌ����܂����ˁB ����F���͖K��Ō�t�̋���ɂ���������Ă��܂����C�Ō�t�����̘b���ƁC�ނ炪�������낤�Ƒz�����Ă��邱�ƂƁC���҂����Ƒ��̖{���̋C�������C�R�[�����Ǝv���Ă���悤�Ȉ�ۂ��܂��B �����F��Î҂̈���I�ȗ��i��������j��Ɗ��҂���̖{���Ƃ̊u����ł��ˁB ����F�{�����o�����ԓI�C�C�����I�ȗ]�T���Ȃ��̂�����ł����B �g�c�F���������C��t�ɖ{���̂��Ƃ������Ȃ����҂͏��Ȃ��Ȃ��悤�ł��B����C�w�_�Y�����ƍȂ��Ŏ����8�l�̒j�B�x�Ƃ����u������J���܂����B���钮�u�҂́C���������Z���^�[���_�����Ƃ�����搶�̑O�ŁC�F�����X�Ǝv�������_�ɋ����������ł��B�܂��C����l�́C��Î҂ɖ{��������ׂ邱�ƂȂǍl�����Ȃ��ƌ����܂����B �����F�m���ɁC���҂���͈�Â�P�A�̃T�[�r�X�҂ɂ͂Ȃ��Ȃ��{����ł������܂���B�s���v�������猙�₩��B��Ԓ�R������̂���t�ŁC�����ŊŌ�t�C�P�A�}�l�C�w���p�[�̏��ł��傤�B�l�̏ꍇ�C�N���j�b�N�̊O�ŋg�c�����Əo���������C���̐������Ƃ��ł����B����͋M�d�Ȍo���ł����B�����́C�ϋɓI�Ɋ��҂����Ƒ��̉�ɏo������ׂ��ł��B�ݑ�ł͖{�������Ƃ��ł��܂����B ����F�ݑ�ł͊��҂����Ƒ��Ƙb���@��������ł����C�����̂������ʼn������Ȃ����߁C���낢��Ȃ��Ƃ�b����܂��B�����ŋC�t�����̂��C�a�@�ł͉B���Ă����銳�҂����Ƒ��̖{���̎v�����C�ݑ�ł͒m�邱�Ƃ��ł���Ƃ����_�ł��B �����F���ꂪ�ݑ�̑�햡��ˁB ����F�ݑ�ŏ��߂ċ���邱�ƁC�������邱�Ƃ���������܂��B��x�ݑ�Ɍg������Ō�t���߂����ɕa�@�ɂ͖߂�Ȃ��̂́C���̂������Ǝv���܂��B �c���F����͉��̐��E�ł��ꏏ�ł��B�{�݂ɂ������E���ݑ�ɍs���ƁC�����߂�Ȃ��ł��ˁB �����F�����C�ݑ�Ō�E���ł́C���҂���̐l���̍Ō�̈�u�ɂ����������Ȃ��B����͏����₵���B�J�ƈ�́C���i���炩�������Ƃ��Ă������C�Ŋ����Ŏ�钷���t���������ł���������܂��B���ꂩ��́C�����������g��������Ō�t�h�����߂��邩������܂���ˁB �ݑ�Ŏ��ƕa�@��� �a�@�ƍݑ���Ȃ��͈̂ȑO������Ȃ��Ă���^�c�� �����F�a�@�`�{�݁`�ݑ���X���[�Y�ɍs�����ł���d�v���͖��炩�ł����C�a�@�̗����͂ǂ��ł��傤���B �c���F���͂�����a�@�̎��ጟ����ɒʂ��Ă��܂����C�a���̊Ō�t���ݑ��Â����Ă��Ȃ����Ƃɋ�������܂��B�Ⴆ�C�n��̐l���W�܂�J���t�@�����X�̃T�}���[�ɁC�����̐f�ÉȂł����ʗp���Ȃ���������C�Ŏg���B�N�ɓ`�������̂��C�s�v�c�ɂȂ�܂��B �g�c�F�a�@�ł͍��C�މ@�������傫�ȃe�[�}�̂͂��ł���ˁB �c���F����Œn��A�g���Ȃǂ͏[�����Ă��Ă��܂����C�ݑ��m���Ă���X�^�b�t�����肷���ʂ��悭���܂��B��啪���̐i�ޕa�@��Âƍݑ��Â��Ȃ��̂́C�ȑO������Ȃ��Ă���̂�������܂���B �����F�l���悭�v���̂́C�a�@�̃X�^�b�t�͊O���ʉ@����@�̑�ς��𗝉����Ă��邩�Ƃ����_�ł��B������a�@�ɍs���C�̌����ꌟ�����C������炤�̂�1��������̒ʉ@�ŁC�ւ��ė�������Q����ł��܂��Ⴊ�����B���@������{�l���Ƒ����y���낤�Ǝv������ł��邯�ǁC�u�����a�@�ɍs���Ȃ��Ă������C�Ƃ����������@���āC���ς����Ȃ��Ă�������y�v�ƌ����Ƒ��̋C�������`���Ȃ��B �c���F�ݑ�ł͈�Íޗ����\������Ȃ��C��Z�̐������삪����Ƃ������_�͗������Ă��܂��B�������C����ł��ݑ�����߂�{�l��Ƒ��̋C�����ɑ��鋤�����Ȃ��B �g�c�F�{�l��Ƒ��̐g�ɂȂ��čl����Ε�����͂��Ȃ�ł����B �����F����1�w�E�������̂́C���F��̎厡��ӌ����ł��B���_�a�@�̑��Z�ȃh�N�^�[�ɂ܂ŏ�������͍̂����Ǝv���܂��B�K��Ō�t�ɔC������ʖڂȂ낤���B ����F�f�f�̕����������Ă��炦��C��͊Ō�t�̕����K�C�ł��ˁB �c���F�������͕P�H�s�ŁC�v���F��̐v��������Ă��܂��B�������҂Œ��ׂ��̂ł����C�F�蒲���͕���2.4���ōςނ̂ɁC�厡��ӌ����̒�o���x�����߁C�F�茋�ʂ��o��܂ł�19.6���������Ă��܂����B���̒������ʂ́C�w�z�X�s�X�ƍݑ�P�A�x�Ɍf�ڗ\��ł��B �����F�ӌ����́C�J�ƈオ������1��5,000�~�̎����ɂȂ�܂����C�Ζ���ɂ͂��������C���Z���e�B�u���Ȃ��C��ɂȂ�̂ł��傤�B�މ@�����J���t�@�����X�����T�C���ی��F�肪�ė��T�ȂǂƂ����Ă���ԂɊ��҂���͖S���Ȃ��Ă��܂��B�A�肽���Ƃ������́C�����Ƃɖ߂��Ă����Ăق����̂ł��B �ݑ�Ŏ��̏��� �u���͂������ɂ����v�ƌ�����s����ڎw�������^�g�c �c���F�P�A�}�l�̗��ꂩ�猾���ƁC�u���邳���C�킵�͋A���v�ƌ������҂���Ԃ��₷���B�{�l�̈ӎu�������m�ł���C�ׁX���������͌ォ�琮���Ă����܂��B �g�c�F�l�͍ݑ�z�X�s�X�P�A�̈Ӌ`��`���邽�߁C�Ȃ̊Ŏ��̃P�[�X���ނɁw���т�̂��މƁx�Ƃ����G�{������܂����B�Ƒ����̕���ƍl����l�����������̂ł����C�l�͊��҂̎��Ȍ��f�̈Ӌ`������������ł��B��Â��鑤�́u���͂������ɂ����v�ƌ�����悤�ɂȂ�ׂ������C���̂��߂̕������߂��Ă���Ǝv���܂��B �����F���X�̐f�ÂŌ��C�ȃW�W�o�o�ɂ͕����Ă��܂��B�u���a�����C���߂łƂ��B���Ɖ��N���炢�����āC�ǂ�Ȃӂ��Ɏ��ɂ����H�v���āB�����C�{���Ɏ��ɂ����Ȑl�ɐq�˂�̂͂炢�B���ΖʂȂ�]�v��ˁB �g�c�F�w���т�̂��މƁx�̓ǎ҂ɃA���P�[�g���s�����̂ł����C�Ŏ��̑̌��҂Ɩ��̌��҂̊Ԃňӎ��̍����傫�����Ƃ�������܂����B�a�@��{�݂͐l�̎��̎��Ԃ��B���Ă��܂��C�Ŏ��̑̌��⎀�̊w�K�̋@���D���Ă��܂��B�̌��҂�������C�����Ƃ����ƍݑ�Ŏ��͑����Ă����Ǝv���܂��B �����F�Ƃɂ����a�@�́C�ǂ�ȏ�Ԃł��ƂɋA��Ƃ����I�����͂��邱�Ƃ����҂���Ɏ����Ăق����B �c���F���i�͑����މ@�����߂Ă��邭���ɁC����Łu����ȏ�Ԃł͋A��܂���v�ƌ����B����͂��������B ����F�ƂɋA�肽���Ƒ��k�����Ƃ��ɁC��Î҂Ɏ�����������邾���ŁC���҂����Ƒ��́u���������Ȃv�Ƃ�����߂Ă��܂���ł��B �����F�ɒ[�Șb�C�A�����ӂɎ���ł��������B �c���F�I�����ɂȂ�C�u�ƂɋA��v���ƂɕC�G���鉿�l��a�@�͒ł��܂���B�܂�C��Î҂���舵���Ă͂��邯�ǁC����͂�����Â̖��ł͂Ȃ��̂ł��B �g�c�F�l���ρC�����ς̖��ł��ˁB���{�l�͂����₨��ɂ͏ڂ������ǁC�����̍Ŋ��̂��Ƃ͍l���Ȃ��B �����F�I�����ɂȂ�����C��Î҂͎�������C�{�l��Ƒ��ɕԂ��Ă�����B�a�@���ǂ�������炢�����C��������Ȃ�A������B�u��͗������ǁC�������Ȃ��v�B���́C���̕ӂ�̉�������ԓ�����ǁB �i�I�j ���f�B�J���g���r���[���@2011�N12��29�� |
||||
|
��Â̖�������������100�̒� ���H�����ەa�@�@���쌴 �d�� ������ |
||||
| �@��N10���ɖ�100�̒a�������}���C�Ȃ�������t�Ƃ��ėՏ�����ɗ����C�u���C���M�ȂǕ��L���W�������ł̊���Œm���鐹�H�����ەa�@�i�����s�j�̓��쌴�d���������B���͐V����10�N��Ɍ������X�^�[�g���C���ɗ������S���Ƃ����B��������\�h��w�̏d�v��������C�u���l�a�v�ɑ���u�����K���a�v�Ƃ����V�������t���āB�܂��C�^�[�~�i���P�A�̕��y�ɂ��s�͂���ȂǁC���{�̈�w�̔��W�Ɋ�^���Ă����B�����ŁC��������߂Ă����g�l���̒B�l�h�ɁC����Љ�Ƃ̌����������C��Â̏������C�l���̓N�w���I������B �����E�`���̌p���ƈ�Ï��̗̒��ʂ���v�����ʂ��� ����������100���߂��������C�����̈�t�Ƃ��ăG�l���M�b�V���Ɋ����𑱂��Ă����܂��B����̏،��҂̗��ꂩ��C�L���ɘV���邱�Ƃ̈Ӗ��C�����E����Љ���}������{�̖������ɂ��Ă��b�����������܂����B �@���݁C���{�ɂ���100�Έȏ�̍���҂̐���3��9,000�l������܂��B�����I�O�́C��������100�l�ɂ������Ȃ������̂ɁC���ł͐��E�ōł������̐l�������B�S�̂�8������������߁C�j����2���ɂƂǂ܂��Ă���B�S�̂̔����͗v���҂ŁC�������ł��Ă��Ȃ��̂ł��ˁB����ł͍���܂�����C���������Ƃ�������҂��琬����K�v������B�����炸�؍����C���ɒ������l���̍���ɒ��ʂ��܂��B���������{�́C����Ɍ����ď��ɑΉ����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B ����̓I�ɂ͂ǂ̂悤�ȕ�����܂����B �@10�N�O�C(��)���C�t�E�v�����j���O�E�Z���^�[�ɐݗ������u�V�V�l�̉�v�́C75�Έȏ�̃V�j�A����C74�Έȉ��̃W���j�A����C20�`60�܂ł̃T�|�[�g��������킹�C1��1,000�l�̉������܂łɂȂ�܂����B������39�J���ɉ����C�n���C��L�V�R�ɂ��x���������āC����͓��{�̕�����K���C�푈�̌������̐���ɓ`�������ŁC�g�S���ʂ̌��N������C��w�E��Â̐i���ɍv������w���X�E���T�[�`�E�{�����e�B�A�̖����������Ă��܂��B������m�̕���C���X�|�[�c�̃T�[�N������������ŁC10��16���ɎO�d�ŊJ�Â����W�����{���[�ɂ�8,000�l���Q�����܂����B�����ł́C�킽����100�̒a�������j����150�l���̉�����t���_���X���I���Ă���܂����B �@��͂�C���낢��Ȋ�����ϋɓI�ɍs�����ƂŁC�K���������܂��āC���N��Ԃ��ǂ��Ȃ�Ǝv���܂��B�ł��邾�������̐l���K�����������ĕ�炵�Ăق������̂ł��B �u���̂��̎��Ɓv��ʂ��C���w�������ƃG�l���M�[�����Ƃ� ���f�ÁC�u���C���M�ȂǁC���Z�Ȑ����𑗂��Ă��܂����C���̌��C�̔錍�͂ǂ��ɂ���̂ł����B �@���������ʂ�C�킽����1���́C��c��ł����킹�C�ʒk�C�a����f�C�u���C���e���M�ȂǂŌߑO�������܂ŃX�P�W���[���͂����ς��ł��B�������C�킽���ɂ͔��Ƃ������C���ӊ����Ȃ��B���͑u�₩�ɖڊo�߂�B����ǂ��C100�ɂȂ����̂��@�ɁC�[��܂Ō��e�������̂���߁C12���ɂ͏��ɏA�����ƌ��߂܂����B�܂��C�킽���͂���5�N�ق�10����1��̃y�[�X�Ŋe�n�̏��w�Z�ɏo�����C�u���̂��̎��Ɓv�Ɏ��g��ł��܂��B�q�������Ɂu�N�����̖��͂ǂ��ɂ���́v�ƕ����ƁC�����Ă��͐S���Ɏ�Ă�B�S���͎_�f�Ɖh�{�����������t��]��葫������ɑ���|���v�ł����āC���ł͂Ȃ��B���͖ڂɌ����Ȃ��B�N�����������Ă��鎞�Ԃ��ڂɌ����Ȃ����C�G��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���ԂƖ��͎��Ă��āC�N�����ɂ͂��ꂪ�g����B�����������͎����̂��߂ɂ������Ԃ��g���Ă��悢����ǁC�傫���Ȃ����牽�Ɏg�����l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���������ӂ��Ɏ����̎��Ԃ��ǂ��g���Ă������Ƃ������Ƃ��C�����Ă���Ƃ������ƂȂ̂��Ɛ�������ƁC�ނ�͂����Ɨ������Ă����̂ł��ˁB5�N�O�̒����w�\�̂��݂ց|��\�܍̂킽������x���p��C������ɖ�o����Ĉȗ��C�C�O�̎q������������f���炵�������ɂ��ӂꂽ�莆���͂��悤�ɂȂ�܂����B���ꂩ���l�ɂȂ鐢�オ���̈Ӗ���m��C���E�ɕ��a�������炷���҂ɂȂ�C���ꂪ�킽���ɂƂ��ẴS�[���ł��B�킽���͋����Ŏq�������Ɛڂ��邱�Ƃɂ���āC�q���������炽������G�l���M�[��������Ă���킯�ł��B ��65�Έȏ�̔N��̂���̜늳���͍���2�l��1�l�Ƃ����Ă��܂��B�搶�͑�������^�[�~�i���P�A�̏d�v�����w�E���Ă����܂������B �@��w�̌��E��m��C�������炩�Ɍ}���邽�߂̈�Â��K�v���Ƃ����l���̉��C�^�[�~�i���P�A�ɗ͂����Ă��܂����B1993�N�ɕx�m�R��]�ސ_�ސ쌧���䒬�ɓ��{���̓Ɨ��^�z�X�s�X�Ƃ��ăs�[�X�n�E�X�a�@��ݗ����܂����B �@�^�[�~�i���P�A�́C�傫���ς��܂����ˁB�����O�܂ł͖����̂��҂̐g�̓I�Ȓɂ݂�ꂵ�݂���菜���C�C�����𗎂��������C�Â��ɐl���̏I�����}���Ă��炨���Ƃ����l�������嗬�ł����B�������C�ŋ߂ł́C�Ő�[�̕��ː����ÂȂǂ��o�ꂵ�C���Ă͎��Ö@���Ȃ��S���Ȃ��Ă������҂���𐔃J���`���N�C������������P�[�X��������悤�ɂȂ��Ă��܂����B�Ⴆ�C����S���Ȃ����č��A�b�v���Ђ̑n�Ǝ҂�1�l�C�X�e�B�[�u�E�W���u�Y���ɂ��Ă��C�X������̐؏���p����n�܂��Ċ̑����ڐA���C���ꂱ����s������8�N�Ԏ����������܂����B���ʓI�ȃ��\�b�h���g����̂ɁC���̗���ɔw�������闝�R�͂���܂���B�z�X�s�X�P�A�ł����Â�������߂��������ɁC�u���������@�͂���܂���C������g���܂��傤���v�ƒ�Ă���@������܂����B �i�[�X�v���N�e�B�V���i���[�������v���C�}���P�A�̐i�� �����{�̈�Â̏������ɂ��āC�ǂ̂悤�ȍl�����������ł����B �@��Ãe�N�m���W�[�����i���������̂́C��Ð��x�͂��̐��\�N�C�قƂ�ǐi�W���Ȃ��B�����ȁC�Y�ȁC�����Ȃ̈�t�s�������������C�z������܂���B��t�����ɋ����ꂽ�f�f�⎡�ÂƂ�������Ís�ׂ��i�[�X�ɂ��\�Ȃ�C���Ԃ͈�ς���͂��ł��B��t�̎d���ƃi�[�X�̎d����3����2���d�Ȃ荇���BX���Z�t�⌟���Z�t�Ȃǂ̎d�������l�ł��B���������I�[�o�[���b�v�����d�����݂��ɕ��S���C���͂��Ȃ���Ή�����`�[����Â������]�܂����B�č���J�i�_��40�N���O�Ƀi�[�X�����t�iNurse Anesthetists�j������̊ē̉��C�Ɨ����Ė������s���̐��𐮂��Ă��āC���݂ł͕č��Ŏ��{������p�̂�����8���ł��̐l���������Ă��܂��B�����ŁC���H���Ō��w��w�@�̏C�m�ے��ɂ���܂ł̏��Y�t�ɉ����C�����t�̗{���R�[�X��ݒu����v��𗧂Ă܂����B�܂��C50�N�O����w�E�������Ă����悤�ɁC���{�̃v���C�}���P�A�͊C�O�ɔ�ׁC���Ȃ�x��Ă���B���ɂւ��n�ł͌���ꂽ��Ë@�ւɊ��҂��W�����C�\���Ȉ�ÃT�[�r�X���ł��Ȃ��Ȃ��Ă�����肩�C�z�����ꂽ��t�����N���o�����Č�サ�Ă��܂��B���̑ŊJ�Ɍ����C�Ȃ�ׂ����������Ƀv���C�}���P�A�ɏ]���ł���i�[�X�v���N�e�B�V���i�[�����肽���B�l��3���l���炢�̎����̂�ΏۂɁC�X�[�p�[�o�C�U�[���̈�t�Ƌ��͂��Ď��т�ςݏグ�Ă�������ł��B��w�E���͂��ߔ��͑����ł��傤����ǁC�n��Z���ɂ͖����ɂȂ��Ă��炦����̂Ɗm�M���Ă��܂��B �u��������������C�S�͂Ő�����v�����b�g�[�� �����N�C�x���ƂȂ��Ă���ꂽ���l�̔F�m�ǁC����ɋ}�ȕa�ɒ��ʂ��C��������邲�l�q���d�g�ɏ��C�����̋������Ăт܂����B���l�ւ̐ڂ����ŐS�����Ă���������_�������������������B �@�{���Ɏ��Ƃ������̂�g�߂Ɋ����܂����B�Ɠ��Ƃ�68�N�O�Ɍ������Ĉȗ��C�ǂ������ł���C3�l�̑��q����ďグ���ǂ���C�����Ă킽���̎d�����T�|�[�g���Ă���錣�g�I�Ȕ鏑�ł����B����92�ɂȂ�܂����C20�N�O�ɉE�̔x�ɑ����̂��������Đ؏����Ă���B���̕��̔x���C���������������Ōċz�@�\���ቺ���Ă����B�]���_�f�s���Ɋׂ��ĔF�m�͂������C���t���o���Ȃ������̂ł��ˁB����ǂ��C�_�f��������R�~���j�P�[�V�������߂��Ă��܂����B100��92�Ƃ�������̕v�w�ł����C���݂��̎��������邩��C�����ʂ�������Ȃ��Ɗo�債�C�^����ꂽ������S�͓������Đ����悤�C���ꂪ�킽���̐l���_�ł��B���������������ĂƂɂ�������t����Ă݂�B�u��������ĕ������v�Ƃ������̉̂��킽���͍D���ł��ˁB ���f�B�J���g���r���[���@2012�N1��5�� |
||||
|
�]��1�N�������҂ւ̖�܂̒v���ʏ�����C�p���E�ψ��� �@�߉����ߘg�g�݂�� |
||||
| �@�p���̎��E�Ɋւ���ψ���Commision on Assisted Dying���C�]��1�N�����̖������҂�Ώۂɖ{�l����]�����ꍇ�ɂ͈�t����܂̒v���ʏ������\�ɂ�����s�����Ƃ��āCCMAJ��For
the record�������グ���iCMAJ 2012�N1��12���I�����C���Łj�B���ψ���͈��y���⎩�E�̍��@���̕K�v����i����ƂƂ��ɁC���m�Șg�g�݂���Ă���Ƃ����B �g�K�p���ҕ]���͈�t2�l�ȏ�Łh�g�ŏI��Ƃ͊��Җ{�l���h �@CMAJ�ɂ��ƁC����܂ł����т��ыc�_����Ă����������҂̈��y���⎩�E���߂�����ɑ��āC���ψ���̕��́u���Ȃ����E�́C��������߂�l��C���߂���\���ɑ��ăv���b�V���[�������Ă���l�ɂƂ��āC���S�u�����Ă��Ȃ��v�Ɩ�莋���C�u���s�̖@������ѐ���͖������҂ƈ�Î҂ɂƂ��ĕs���ł���v�Ɣᔻ�����B �@�����œ����ł́C�]��1�N�����̖������҂�ΏۂɁC���y������]����ꍇ�͈�t����܂̒v���ʏ�����������@�������肷�ׂ��Ǝ咣�B��Ɏ��̂悤�Ȏ��E�Ɋւ���@�߂̘g�g�݂�����B �@���m�ɒ�`���ꂽ���҂̓K�p���݂���i2�l�ȏ�̈ˑ��W�̂Ȃ���t���]���j �@�\�ł���Ί��҂��悭�m���Ă����t���������C���҂ƉƑ����T�|�[�g���� �@��܂̒v���ʏ�����, �s���g�p�ⓐ���\�Ȍ�����S�ɊǗ����� �@���E����]����͎̂��ÂɊւ���I�����̐����������҂Ƃ��� �@���E����]���銳�Җ{�l�����g�̖������߂̍ŏI��Ƃ��s�� �@2�l�ȏ�̈�t���]�����銳�҂̓K�p��ɂ��ẮC�i1�j�Ǐi�s���Ŏ����s�\�ł���C����12�J���ȓ��̎��S�������܂�閖����ԁC�i2�j���҂���̋��v�ł͂Ȃ��C���Җ{�l�̎����I�Ȉӎu�ɂ���]�ł��邱�Ƃ̏ؖ��C�i3�j���Җ{�l�����Ɋ�Â��I�����\�Ȑ��_��ԁ@���������B �@����ɁC��t�ɑ��āC���E����]���銳�҂����X�ɂ��Ȃ��������i�ŒZ2�T�ԁB�������C�]��1�J���ȓ��ł͍ŒZ6���j������悤�C�אS�̒��ӂ��Ȃ�����C�v���ɑΉ����ׂ��Ƃ��Ă���B �@�Ȃ��C�����ł́C�p�����Տ��]���������iNICE�j�����E�ɂ������܂̒v���ʏ����ɂ��Ď���������쐬���邱�Ƃ�v�����Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N1��16�� |
||||
|
��`�q�����ɂ����ɖ\���V�X�e�����J���C�����s�㑍���Ȃ� ���{�`���O�Ȏ�p�ŗL�p�������� |
||||
| �@�����s��w�����������Q���������̒r�c�a�����Ɠ������ȑ�w�y�����̕��c���ꎁ��̃O���[�v�́C���ɖ�̊��Ɋ֘A�����`�q���^����肵�C����̓K�ȓ��^�ʂ�\������Z�p�𐢊E�ŏ��߂ĊJ���B�������ȑ�w�������a�@�ʼn��{�`���O�Ȏ�p���銳�҂�ΏۂɃe�[���[���[�h�u�Ɏ��Â��J�n���C�L�p����������Ɣ��\�����B�u�����u�Ɏ��Âւ̏d�v�ȃX�e�b�v�ɂȂ�v�Ƃ��Ă���B ��������̓K���u�Ɏ��Â��\�� �@����J�����ꂽ�V�X�e���́C�����s����̉^�c��⏕���ɂ��u����E�F�m�Ǒ�v���ʌ����̌������ʁB �@���ɖɂ͑傫�Ȍl��������C�K�ȓ��^�ʂ̒T���ɂ͎��ԁC�R�X�g�C�J�͂�v���邪�C��`�q��͋Z�p�̐i���ɂ���`�q�v������肷�邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă����B �@�����Œr�c����́C�p�O�ɂ͒ɂ݂��Ȃ��C���I�Ȏ�p���s���鉺�{�`���O�Ȏ�p�ɒ��ځB�p����u�ɊǗ��ɕK�v�Ȓ��ɖ�̗ʂƊ��҂̈�`�q���^�ׁC���ɖɊ֘A���邢�����̈�`�q���^�������B����ɁC��`�q��͂Ɋ�Â����ɖ�̓��^�K�v�ʂ̗\�������J�������B������́u��������̓K���u�Ɏ��Â̎����ɍv������Z�p�v�Ƃ��Ă���B �@����C�������ȑ�w�������a�@�ʼn��{�`���O�Ȏ�p���\��ɑ����V�X�e����p�����e�[���[���[�h��Â����{���C�]���̕��@�ƗL�p�����r����B�����u�ɂ⑼�̎�p����u�ɂɂ����p�ł���悤�V�X�e���̊J�����p������Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N1��18�� |
||||
| ����s�����f���P�[�X�ɂ����Ãl�b�g���[�N�݂̍����͍� | ||||
| �@�킪���ł́C2006�N�̂�����{�@�����ɔ����C��������i��{�v��i����v��j�����肳��C���Ƃ��Ă̂���i�߂��Ă������ŁC�e�s���{���P�ʂł����l�̓�����������B�������C���҂ɕK���������b�������炳��Ă���Ƃ͂����Ȃ��B��49����{�����Êw��̓��ʊ��V���|�W�E���u�g�͂������� ���{�̋��X�܂Łh �n��ɂ����邪���v�ł́C���ÂɊւ���l�b�g���[�N�Â���Ɍ����C��i�I�Ȏ��g�݂����Ă���Ƃ���钷��s�̗�����f���ɁC�n��̂����݂̍���������ꂽ�B �@���N�x�\�Z�Ăɏ�����������lj� �@IT�����p�����n���ØA�g�Ŋɘa�P�A�𐄐i �@�펞���k�\�ȑ�����p�ӂ��ɘa�P�A�̋��n���� �@�n������Ɋ�Â��ɘa�P�A�d�v ���N�x�\�Z�Ăɏ�����������lj� �@��t�ł���C�����J���Ȍ��N�ǂ�������i�������Ð�劯�̗я��ᎁ�́C����v�挩�����̓����₪��f�ØA�g���_�a�@�ɂ��@������o�^�W�v�f�[�^�C���N�x�T�Z�v���̊T�v�ɂ��Đ��������B���N�x�\�Z�̊T�Z�v���ł́C�V�������������Ɋւ���\�Z���v�サ�C�d�_�I�ɐ��i����Ƃ����B �@��������i���c��́C5�l�̂��҂��ψ��Ɍ}�������Ƃ��ď��߂Ă̋��c��ŁC����v��̍���Ɉӌ����C����̗\�h�⑁�������C�����Â̋ςĂC�����Ȃǂ𐄐i����������ʂ����Ă���C����C����v�悪5�N�ڂ��}���C��������v��Ɍ��������������s���Ă���B �@����܂ł̂���v��ł́C�d�_�ۑ�Ƃ��āC�i1�j���ː��Ö@�C���w�Ö@�̐��i����т��̐���̈琬�i2�j���Ï����i�K����̊ɘa�P�A�̎��{�i3�j����o�^�̐��i�@���f�����Ă��邪�C�����́C�����Â̋ςĂ�S������f�ØA�g���_�a�@���C�e��Ì��̕a�@�ƗL�@�I�ɘA�g���C����܂ňȏ�ɒn��Ŏ��̍��������Â����{����K�v���Ɍ��y�����B �@�܂��C���܂ō��̎x�����قƂ�ǂȂ��������������Ƃ��āC�������_�a�@�\�z�Ə����ɘa�P�A���܂ޏ������C�̐��̐����Ȃǂ𐄐i���邽�߁C���N�x�\�Z�v���Ɍv�サ���B�T�Z�v���z�́C�����������Ƃ��Ė�7���~�Ƃ����B����ɁC�e����f�ØA�g���_�a�@�Őf�Â����Ǘ���W�v�����@������o�^�́C������a�����ޕʂȂǂɏW�v����Ă���C�n������܂��C�e�a�@�̓����ɍ��킹���f�Ìv��𗧈Ă����ŗL�p�ł���Ƃ����B �@�����́C����C����f�ØA�g���_�a�@�̎w��v���̌�������C�n��A�g��i�߁C���҂Ƃ��̉Ƒ������S�����S���Ă����Â�����n��A�g�N���e�B�J���p�X�̉^�p�C�n�抮���^�̂����Â��������K�v�Ƃ��C�u���ƒn�悪�������Ă����𐄐i���ׂ��ł���v�ƌ��B IT�����p�����n���ØA�g�Ŋɘa�P�A�𐄐i �@�ߔN�C��ËZ�p�̐i���ɂ��C�}�������҂̍݉@�����͒Z�k�X���ɂ��邽�߁C���Â�P�A����a�@�����Ŋ��������C�n��̐f�Ï��Ȃǂł��p�������P�[�X���������Ă����B����s��t��̖�c������́C����t�3�N�ԏ]�������C�ɘa�P�A���y�̂��߂̒n��v���W�F�N�g�iOPTIM�j�̊T�v��C�Ǝ��̎��g�݂Ȃǂɂ��Đ����BIT�𗘗p���đ�a�@���m���l�b�g���[�N�Ō��сC�ɘa�P�A�Ȃǂɖ𗧂Ă��ØA�g�V�X�e�����Љ���B �@OPTIM�́C����t����J�Ȃ���ϑ�������{���������ŁC�ړI�́C�킪���ɓK�����ɘa�P�A�n�惂�f���̍\�z�ł���B�������Ԃ͖�3�N�ԂŁC���肪�k�x���Z���^�[�����_�ɁC�ɘa�P�A�����Ō�t�Ȃǂ���\�������`�[���i�n��ɘa�P�A�`�[���j��K�v�ȕa�@�C�f�Ï��C���҂̎���֔h�������i�}�j�B�v��͒i�K�I�ɗ��Ă��COPTIM���s���Ɏ��m���C���k�x���Z���^�[�ƒn��ɘa�P�A�`�[�����ϋɓI�ɗ��p�����悤�ɂ����B 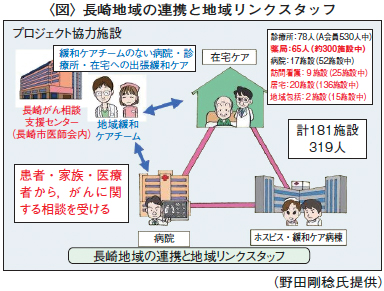 �@�܂��C���C��⑽�E�틤���J���t�@�����X�C���ጟ����ȂǂŊɘa�P�A�̕W������n��A�g�̋�����}��C�s�������̍u���E�u�K����J���C�[��������s�����B����t����Ǝ��ɍݑ�×{���Ҍ����̐H���̃��V�s��C�ݑ�×{��Z�o�p�̃\�t�g�C�K���w���p��DVD���쐬�����ق��C���r���O�E�E�B���Ɋւ���L��Ȃǂ��肪�����B �@����ɁCIT�𗘗p�����n���ØA�g��Ƃ��āC����t��哱�ŁC����s����ё呺�s�ɂ������a�@����Ãl�b�g���[�N�łȂ���u���������l�b�g�v�𗧂��グ���B���̃l�b�g���[�N�ɂ��C���茧����4,000�����ɓ�����a�@�̂����ꂩ�œ��@�C��f�������҂̌������ʂⓊ��C�Љ��̏��Ȃǂ����A���^�C���Ŕc���ł��C�ɘa�P�A�ɂ���������Ԑ����\�z�ł����Ƃ����B �@����́C����ɂ��āu�J�ƈ���͂��߂Ƃ�����Ï]���҂̍����C��Ã��\�[�X�̕s���C���q����ɔ����������̈����C�F�m�NJ��҂̑����Ȃǂɂ��Ή����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ܂Ƃ߂��B �펞���k�\�ȑ�����p�ӂ��ɘa�P�A�̋��n���� �@����s��t��̔��E�L�����k���E���Ȉ�@�i����s�j�@���l�́COPTIM�ɂ���Ċɘa�P�A�̌��ꂪ�C���_�a�@����ݑ�ւƃX���[�Y�Ɉڍs����悤�ɂȂ����Ƃ��C����͊ɘa�P�A�`�[���̂���a�@�ƂȂ��a�@�C�a�@�ƍݑ��Â̌���̋��n�����ƂȂ�C�펞���k�������K�v�Əq�ׂ��B �@OPTIM�́C�i1�j�ɘa�P�A�̕W�����i2�j�n��A�g�̋����i3�j���ɘa�P�A�T�[�r�X�̗��p�̌���i4�j�s���ւ̏��@��4�����ɂ��Ă���B �@�܂��i1�j��ڎw���āC��t�����̌��C��⑽�E�킪�Q�����郏�[�N�V���b�v�ȂǁC�d�w�I�ȋ��炪�s��ꂽ�B �@�i2�j��}�邽�߂ɂ́C�ɘa�P�A�C�����ÂȂǂɑ�����_�ɂ��āC�����̎{�݂��畡���̐E�킪�b�������n��J���t�@�����X��C�͋[���ጟ����C�{�ݐE���������C��Ȃǂ��J����C���҂̃X���[�Y�ȑމ@��݂Ƃ�Ȃǂ���������X�L���̌��オ�����ꂽ�B�܂��C�a�@�ł̈�Âƍݑ��Âɏ]������X�^�b�t�������Œ���I�ɘb���������݂��C�ݑ�P�A�̎���ɂ��ď������L�ł������Ƃ��Ӌ`�[�������Ƃ����B �@�����w�ɘa�P�A�`�[����������Ǘ�̂����C�ݑ��ÂɈڍs����������C�������̋��_�a�@����މ@�����Ǘ�ɍݑ�K��f�Â����������Ȃǂ��COPTIM�ɒ��肵��2008�N���납��傫���������Ă���C�i2�j��������x�B���ł����ƌ�����B �@�i3�j�Ɋւ��ẮC���Âɓ�a����Ǘ�ɂ��ẴR���T���e�[�V������C�o���ɘa�P�A���C�Ȃǂ̕�����u���C�i4�j�ɂ́C���J�u����ɘa�P�A�Ɋ֘A���鏑�ЂȂǂ����p���ꂽ�B �@�����̎{��ɂ��C�ݑ�×{���҂݂̂Ƃ萔�Ȃǂ́C���҂��܂߂ď㏸�X���ɂ���Ƃ����B�������́u����s�ł͈�t����S�ƂȂ�C�����̎{�݁C�E�킪�������Ċɘa�P�A�𐄐i���邱�Ƃ��ł����B����́C�e�a�@�ԁC���邢�͕a�@�ƍݑ��Â̌����L�@�I�Ɍ��ԑ��k���������߂���v�Ƌ��������B �n������Ɋ�Â��ɘa�P�A�d�v �@�����w�a�@����f�ÃZ���^�[�̈��V�a�l�Z���^�[���́C����f�ØA�g���_�a�@�Ƃ���OPTIM�ɎQ�悵�����ꂩ��C����ɘa�P�A�ւ̎��g�݂ɂ��ĕ��C�ۑ�Ƃ��āC�n���I�����̔c����}���p���[�s���ւ̑Ώ��Ȃǂ���������Ƃ����B �@���茧���ɂ́C����f�ØA�g���_�a�@����ѐ��i�a�@���v8�a�@����C���I�Ȃ����Â̒C�n��̂����ØA�g�̐��̍\�z�C���C���k�x���Ȃǂ̖������ʂ����B �@���Z���^�[�ł́C�����̐f�ÉȂȂǂ����f�I�ɉ^�p����7���傪����C�ɘa��Õ���́C�@���̒n��A�g�Z���^�[��n��̈�Î{�݂Ƌ��͂��C���҂��]�ސf�Ì`�Ԃւ̃X���[�Y�Ȉڍs�̎x����C�ɘa�P�A�̕��y�E�����S������B���̂��߁C���@�̐�]��t��Ō�t��ɍݑ����������C�ɘa�P�A�I�[�v���J���t�@�����X��C���Âɓ�a����Ǘ�ɑ���ݑ�n�C���X�N�J���t�@�����X�Ȃǂ��J�Â��C����Ɏ�X�̌��C��C�Ō�t�琬���ƂȂǂ��s���Ă���B �@���k�x������ł́C���ҁE�Ƒ�����̎x���Ɍg����Ă���C�d�b���k����7���C���ږʒk����3�����߁C���k���e�͎��ÂɊւ�����̂���3���C�s���E�S�̃P�A�͖�2���ɏ�����B���Ҍ����̃T�������J�݂��C�����C�e������މ@�x���C�ݑ��ÂȂǂ��e�[�}�ɂ����~�j���N�`���[��𗬉�Ȃǂ��Â��Ă���B �@�����āC����n��A�g�p�X���쐬���C���҂̐f�Ìv��C�������ʁC���Ìo�߂�����������Ƌ��L����c�[���Ƃ��ĉ^�p���J�n���Ă���B �@����ɁC���Z���^�[���́C�����������Ƃ��������̒n�������C��Î҂̐l���s���ɑΉ����邽�߁C����f�Â̒��j�ƂȂ闣���̕a�@���w�肵�C�e���r��c�V�X�e���𗘗p�������C�@��������C��B����v���t�F�b�V���i���{���v�����Ől�ވ琬��}�����肵�Ă���Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N1��19�� |
||||
| �I�����݂낤�u���Í����T�����v�c�V�N��w�� | ||||
| �@���{�V�N��w��i�������E����ы`(�₷�悵)���勳���j�͂Q�W���A����҂̏I�����ɂ�����݂낤�Ȃǂ̐l�H�I�����E�h�{�⋋�ɂ��āA�u���Â̍����T����P�ނ��I�����v�Ƃ̌������������B �@�I������Âɑ��铯�w��̊�{�I�ȍl�����������u����\���v�̉����łɐ��荞�܂�A�����̗�����ŏ��F���ꂽ�B �@�u����\���v��2001�N�ɍ��肳�ꂽ���A���̌�̎��Ԃɑ��������̂ɂ��邽�߁A10�N�Ԃ�ɉ������ꂽ�B�ߔN�A������H�ׂ��Ȃ�����҂Ɉ݂Ɋǂ��Ȃ��ʼnh�{�𑗂�݂낤�����y�B�a��̗͉̑ȂǂɌ��ʂ��グ�锽�ʁA���Ăł͈�ʓI�łȂ��A�F�m�ǖ����̐Q�����芳�҂Ȃǂɂ��L����������A���̐��c�_�ɂȂ��Ă���B �@�����łł́A�݂낤�Ȃǂ̌o�ljh�{��l�H�ċz��̑����ɑ��錩�������߂Đ��荞�܂ꂽ�B����҂ɍőP�̈�Â�ۏႷ��ϓ_������A�u���Җ{�l�̑����Ȃ�����A��ɂ傳�����肷��\��������Ƃ��ɂ́A���Â̍����T����P�ނ��I�����v�Ƃ��A�u���҂̈ӎv����薾�m�ɂ��邽�߂ɁA���O�w�����Ȃǂ̓������������ׂ��v�Ƃ����B YOMIURI ONLINE�@2012�N1��29�� |
||||
|
�����Љ�ی���Ë��c�� �ɘa�P�A�a���A�u�]���@�\�v�̔F��Ȃ��Ă��� �`�[���ɂ��u�O�����ː��Ǝːf�×��v���V�� |
||||
| �@�����Љ�ی���Ë��c���i��F�X�c�N�E������w��w�@�@�w�����w�����ȋ����j��1��30���ɊJ�Â���A1��27���ɑ����A�u�ʉ��荀�ڂɂ��āi����2�j�v���c�_�����i�����́A���J�Ȃ̃z�[���y�[�W�Ɍf�ځj�B �@30���̑���ŁA�ł������ȋc�_���W�J���ꂽ�̂��A�ɘa�P�A�a���̎{�݊�̌��������B���݂́u���ØA�g�̋��_�ƂȂ�a�@�������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�ƁA�܂��͍��c�@�l���{��Ë@�\�]���@�\�����s����Ë@�\�]�����Ă��邱�Ɓv�Ƃ����v�������邪�A������폜���A��t�̐l������͂��߁A���̎{�݊�����a���ł���A�u�ɘa�P�A�a�����@���v��u�ɘa�P�A�f�É��Z�v���Z��ł���Ă��������B�ɘa�P�A�̐��i���ړI���B �@�S���{�a�@�����̐��V���r���́A�u�ɘa�P�A�a���̑ΏۂƂȂ��Ë@�ւ𑝂₷���Ƃ͂������A��O�҂̕]���͑厖�Ȃ̂ŁA���炩�̌`�Ŏc���Ȃ����v�ƒ�āB�A����������ǒ��̉Ԉ�\�q���́A�u��O�ҋ@�\�̕]������v�����c���Ăق����B���{�̈�Â��q�ϓI�ɕ]�����Ă���̂́A���̋@�\�ł���A���҂���Ë@�ւ�T�����ɖ𗧂B�]�����邱�Ƃ��ނ��됄�i���闧��ɗ��ׂ��ł����āA�i�F��́j�n�[�h������������ƌ����č폜����̂́A���҂̎��_�Ɍ����Ă���v�Əq�ׁA�v�����c���悤�������߂��B �@����A���������Z���^�[�������̉ÎR�F�����́A�u���{��Ë@�\�]���@�\������̂��Ƃ�]���ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��v�Ǝw�E�A�ɘa�P�A�a���̂���ȊO�̎{�݊�Ŏ��͒S�ۂł���Ƃ����B �@���̂ق��A�l�X�Ȉӌ������������A���J�ȕی��Lj�Éے��̗�؍N�T���́A�u�ɘa�P�A�a���̎{�݊�Ɍ��炸�A��O�ҕ]���͏d�v�����A�F��a�@���Ɍ��肵�Ă��邱�Ƃ��A�ɘa�P�A�a���̐������肵�Ă���v���ɂȂ��Ă���v�Ɛ����A���ǁA�u�F��ɏ�����a�@�v�Ƃ̕\���������A�u���ØA�g�̋��_�ƂȂ�a�@�������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�ƁA�܂��͍��c�@�l���{��Ë@�\�]���@�\�����s����Ë@�\�]�����Ă��邱�Ƃ������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�Ɓv�Ƃ������߂ɕ�����������\���ɗ����������B �@�ɘa�P�A���͂��߁A����f�Ê֘A�́A�u�[�������߂��镪��v�A�܂�_���̈����グ���\�肳��Ă��镪��B�O���ɘa�P�A���A���̈�t��z�u����ꍇ�̓_�����A�b�v����ق��A��×p�����4�܂ɂ��āA���������̐�����14������30���Ɋɘa����Ȃǂ̉�����s���B �@����ɁA���ː����Ð��i�̂��߁A�u�O�����ː��Ǝːf�×��v��n�݁B���ː����È�s���̌���܂��A��t������f�@���Ȃ��Ă��A��t�̎w���ŊŌ�t��f�Õ��ː��Z�t�����`�[���Ŗ���ώ@���邱�Ƃŕ��ː��Ǝ˂����{����̐��ɂ��āA�_����V�݂���B �@����֘A�̎�ȉ��荀�ڂ͈ȉ��̒ʂ�B ���ɘa�P�A�̐��i �E�ɘa�P�A�a������ъɘa�P�A�f�É��Z�̎{�݊�̕ύX�i�Z��Ώۂ́A�u���ØA�g�̋��_�ƂȂ�a�@�������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�ƁA�܂��͍��c�@�l���{��Ë@�\�]���@�\�����s����Ë@�\�]�����Ă��邱�Ƃ������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�Ɓv�Ɂj�B �E�����ɘa�P�A���i�̂��߁A�u�����u�Ɋɘa�w�����v�A�u�ɘa�P�A�f�É��Z�v�A�u�O���ɘa�P�A�Ǘ����v��V�݁B �E�u�����u�Ɋɘa�w���Ǘ����v�ɂ��āA�ɘa�P�A�̌o����L�����t���w���Ǘ����s�����ꍇ��V���ɕ]���B �E�R�f�C���i���p�j�A�W�q�h���R�f�C���i���p�j�A�t�F���^�j���i���ˍ܁j�A�t�F���^�j���i�o��z���^���܁j��4���܂̈�×p����ɂ��āA����������14������30���Ɋɘa�B�@ ������̐f�ØA�g�̏[�� �E�u����f�ØA�g���_�a�@���Z�v�́A���҂����łȂ��A�u����̋^���v�̊��҂̏Љ�̏ꍇ���Z��\�ɁB �E����f�ØA�g���_�a�@�ɂ����āA�Љ�҂����@�Ɏ��炸�A�O�����w�Ö@�������ꍇ�́u���ØA�g�Ǘ����v��V�݁B �E�u���ØA�g�v����藿�v�́A�u���@���ɍ���v�����ꍇ�ɎZ�肪�\���������A�u���@���܂��͑މ@����30���ȓ��v�ɍ��肵���ꍇ�A�u�v��̕ύX�v���s�����ꍇ�ł��Z��\�ɁB �E�u�����p����w���Ǘ����v�́A��p�����{������Ë@�ւ����łȂ��A����ȊO�̈�Ë@�ւ�2�x�ڂ̎w�������ꍇ���Z��\�ɁB �E�u���҃J�E���Z�����O���v�́A�]�@��������Ë@�ւł��Z��\�ɁB�@ ���u�O�����ː��Ǝːf�×��v�̐V�� �E�O�����ː��Ǝˎ��{�v��Ɋ�Â��A1�T�Ԃɂ����ނ�5���Ԃ̕��ː��Ǝ˂��銳�҂ɑ��A��t�̎w���ɂ��Ō�t��f�Õ��ː��Z�t���̃`�[���ɂ�閈��̊ώ@��]���B �E���ː����È�i���ː����Â̌o��5�N�ȏ�j���Ζ����Ă���A��]�̊Ō�t�Ɛf�Õ��ː��Z�t�����ꂼ��1�l�ȏ�Ζ����Ă��邱�ƂȂǂ��v���B ���������@��ÊǗ����ɂ�������ː����Â̕]�� �E�������@��ÊǗ����̕�͈͂���A���ː����Â����O�B m3.com�@2012�N1��30�� |
||||
| �傫�ȓ]�������}�������{�̐��㐧�x�@��49����{�����Êw�� | ||||
| �@���{�̐��㐧�x���傫���ς�낤�Ƃ��Ă���B�w��P�ʂ̐���F�肩��C�����I��O�ҋ@�ւɂ��F��֓]������悤�Ƃ��Ă��邽�߂��B���É��s�ŊJ���ꂽ��49����{�����Êw��̓��ʊ��V���|�W�E���u���{�̐��㐧�x�F�傫���ς��R���Z�v�g�ƐV���ȕ������v�ł́C�킪���̐��㐧�x�̕��݂ƌv�悳��Ă���V���x�̊T�v�C���×̈�̐��㐧�x�̌����ꂽ�B �@���{���㐧�]���E�F��@�\�̐��㐧�x������ψ���Ƒ�O�ҋ@�����ψ���̈ψ����߂��i��̂�����L���a�@�i�����s�j�E��c��l�@���́C�킪���̐��㐧�x�̂���܂ł̌o�܂��Љ�C�u��啪���v����u�����v�ւ̓]���̕K�v�����w�E�����B �@�킪���̐��㐧�x��1962�N�̖����w���㐧�x����n�܂�C���̌�C�����̊w����㐧�x�������B81�N�ɁC�w��Ƃ̐��㐧�x�̐�������}��ړI�Ŋw��F��㐧���c��i�w�F���j�������B86�N�ɂ͊w�F���C���{��w��C���{��t��ɂ��1��ڂ̎O�ҍ��k��J����C�X�̊w��ł͂Ȃ��C���̎O�҂ɂ���Đ����F�肷������ւ̖͍����n�܂����B �@�O�҂̍l�����̈Ⴂ���玞�Ԃ͂����������C1993�N�Ɋ�{�I�̈�f�É�13�w��̐���̎O�ҔF�肪���ӂɒB�����B�܂��C99�N�ɂ͓��{�w�p��c����C���㐧�x�̐����Ƒ�O�ғI�Ȑ��㎑�i�F��@�\�̐ݒu�����ꂽ�B �ɘa��Ð��㐧�x�@�V���x�ւ̑Ή��͊w��Ō��� �@���{�ɘa��Êw������ő���w��w�@�ɘa��Êw�̍P���ŋ����́C�u�ɘa��Ð��㐧�x�v�̌���ɂ��ĊT�������B �@���{�ɘa��Êw��̐ݗ���1996�N�B����⑼�̎�������Ȏ����̑S�o�߂ɂ����Đl�X��QOL�̌����ڎw���C�ɘa��ÂW�����邽�߂̊w�ۓI���w�p�I�����𑣐i���C���̎��H�Ƌ����ʂ��ĎЉ�ɍv�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B �@�č��Տ���ᇊw��iASCO�j�ƕč����������iNCI�j���J�������ɘa�P�A�̌n���I����v���O�����iEPEC-O�j����{��ʼn����C2005�N���炱�̃v���O�����Ɋ�Â��g���[�i�[�Y���[�N�V���b�v���J�Â����B�܂��C2007�N����͂���f�ÂɌg����t��ΏۂƂ����ɘa�P�A���C���S���ŊJ�ÁB����܂łɖ�2��6,000�l����u�����Ƃ����B �@2009�N�Ɏb��w����ƌ��C�{�݂̔F����s���C2010�N����ɘa��Ð���̔F�莎�����J�n�����B���݁C�b��w�����619�l�C�F�茤�C�{�݂�445�{�݁C�ɘa��Ð����24�l�ƂȂ��Ă���B �@�ɘa��Ð���̗v���Ƃ��āC���I�m���ƋZ�p�Ɋ�Â��Տ����H�E�R���T���e�[�V���������E����w���ƁC���I�m���Ɋ�Â��Տ��������������Ă���B�܂��C���C�J���L�������ɂ́C�i1�j�Ǐ�}�l�W�����g�i2�j��ᇊw�i3�j�S���Љ�I���ʁi4�j���g����уX�^�b�t�̐S���I�P�A�i5�j�X�s���`���A���ȑ��ʁi6�j�ϗ��I���ʁi7�j�`�[�����[�N�ƃ}�l�W�����g�i8�j�����Ƌ���`�̑傫��8�̒�������B �@���݁C����p�̋��ȏ����쐬���ŁC����C����{���̂��߂̃Z�~�i�[�C����̐��U�w�K�Z�~�i�[���v�悵�Ă����\��Ƃ����B �@�V�������㐧�x�ɂ��āC�������́u�ǂ̂悤�ɑΉ����Ă������C�w��Ō������ł���v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N2��2�� |
||||
| �i�[�X���������u���ʑO�Ɍ�������v�g�b�v5 | ||||
| �@�����������l���Ō�̓���������A���Ȃ��͌�������ɂ��܂����B����͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����B �@�l���Ō�̎����߂������҂����̊ɘa�P�A�ɐ��N�g������A�I�[�X�g�����A�� Bronnie Ware ����B�ޏ��ɂ��ƁA���̊ԍۂɐl�Ԃ͂�������l����U��Ԃ�̂������ł��B�܂��A���҂�����������ɂ͓������̂��ƂĂ������Ƃ������Ƃł����A���Ɏ����ԋ߂ɍT�����l�X�����ɂ�������̒��ő����������̃g�b�v5�͈ȉ��̂悤�ɂȂ邻���ł��B �@ 1. �u�������g�ɒ����ɐ�����Ηǂ������v �@�u���l�ɖ]�܂��悤�Ɂv�ł͂Ȃ��A�u�����炵��������Ηǂ������v�Ƃ�������BWare ����ɂ��ƁA���ꂪ�����Ƃ����������ł��B�l���̏I���ɁA�B���ł��Ȃ����������������������ƂɊ��҂����͋C�Â��̂������B�������Ă����悩�����A�Ƃ����C������������܂ܐ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɁA�l�͋������O��������悤�ł��B �@ 2. �u����ȂɈꐶ���������Ȃ��Ă��ǂ������v �@�j���̑��������̌��������Ƃ̂��ƁB�d���Ɏ��Ԃ��₵�������A�����ƉƑ��ƈꏏ�ɉ߂����Ηǂ������A�Ɗ�����̂������ł��B 3. �u�����Ǝ����̋C������\���E�C�����ĂΗǂ������v �@���Ԃł��܂�����Ă������߂Ɋ�����E���Ă������ʁA���Ȃ��s���Ȃ����݂ŏI����Ă��܂����A�Ƃ������O���Ō�ɖK���悤�ł��B �@ 4. �u�F�l�W�𑱂��Ă���Ηǂ������v �@�l���Ō�̐��T�ԂɁA�l�͗F�l�̖{���̂��肪�����ɋC�����̂������ł��B�����āA�A�����r�₦�Ă��܂������Ă̗F�B�ɑz����y����̂��Ƃ��B�����ƗF�B�Ƃ̊W���ɂ��Ă����ׂ��������A�Ƃ���������o����悤�ł��B �@ 5. �u�����������ƍK���ɂ��Ă�����悩�����v �@�u�K���͎����őI�Ԃ��́v���ƋC�Â��Ă��Ȃ��l���ƂĂ������A�� Ware ����͎w�E���܂��B���K��p�^�[���ɗ��߂Ƃ�ꂽ�l�����u���K�v�Ǝv���Ă��܂������ƁB�ω��ӎ��ɋ���u�I���v������Ă����l���ɋC�Â��A������������܂ܐ��������Ă����l�������悤�ł��B �@ �@�ȏ�A�ǂ���d���������e�ł����B�����ǂ�ŁA���Ȃ��͖�������ǂ��߂����܂����B Pouch�m�|�[�`�n 2012�N2��5�� |
||||
| �؍��́u�ՏI�̎��v�͐��E�R�Q�� | ||||
| �@�c���k���i�L�����T���u�N�h�j�̃�������i�U�U�j�͍�N�P�����A�t������Ƃ����f�f�����B�\�E���̕a�@�ōR���Âƕ��ː����Â������A���ʂ͂Ȃ������B�Ƒ��ƘA�����r�₦�ċv�����A��l�ŋ�J���Ȃ���߂����Ă������A�����Ȃ�n�߂���N�P�O���A�m�l�̏������Ď�s���̗×{�@�Ɉڂ����B�×{�@���͒��ɍ܂�^���Ă��邪�A�������҂��Ǘ�������Ƃł͂Ȃ����߁A�ɂ݂߂���̂��e�ՂłȂ��B �@�Q�O�P�O�N�ɂ���Ŏ��S�����l�͂V���Q�O�S�U�l�B�������҂ɍł��K�v�ȃT�[�r�X�͒ɂ݂̒��߂��B�R���Â͂���قLjӖ����Ȃ��B�ɂ݂߂��Ȃ���l�������邱�Ƃ��d�v���B���Ƃ̑��k������A�ґz�E���K�ȂǂŐS���I�Ȉ�����ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������T�[�r�X���ɘa��Ái�z�X�s�X�j�Ƃ����B �@�������҂̂����ɘa��Â���l�͂X���ɂ����Ȃ��B��������̂悤�ɂ�����Ƃ�����ÃT�[�r�X�����Ȃ��l�͂R�Q�D�S���ɂ̂ڂ�B�S�O�D�V���͍���l�Q��L�m�R�ނȂǂ̐H���Ö@���ֈ�Âɗ����Ă���B��������Z���^�[�����S�҂̈⑰�P�U�U�S�l���A���P�[�g�����������ʂ��B �@��������ɘa��ÃT�[�r�X�͑S���S�S�@�ցi�V�Q�T�a���j�Œ��Ă���B��������Z���^�[�z�X�s�X�ɘa��Î��Ɖۂ̃`�F�E�W�������������́u�ɘa��Ð�i���̉p���͐l���P�O�O���l������T�O�a����ۗL����v�Ƃ��u���̊��K�p����Ί؍��ł͂Q�T�O�O�a�����K�v�ƂȂ邪�A���݂͂܂��Q�X�������Ȃ��v�Ǝw�E�����B �@�\�E����a�@�̋�����i�z�E�e�\�N�j�����i���t��ᇓ��ȁj�́u�a�����s�����Ă��邤���A���݂��������Â��D�ޕ��͋C������A�e���̎��f��������v�Əq�ׂ��B�������҂̒ɂ݂̊Ǘ��ɂ͖����ɍ܂��g����B���E�ی��@�ցi�v�g�n�j�ɂ��ƁA�؍������P�l������̃����q�l�g�p�ʂ͂P�D�Q�~���O�����Ő��E�U�Q�ʁB�P�ʂ̃I�[�X�g���A�͂P�T�R�D�S�~���O�������B�\�E����a�@�̋������́u�����ɍ܂͂قƂ�ǖ������҂��g�����A�g�p�ʂ����Ȃ��Ƃ����̂͊��҂����ꂾ����ɂ��ĖS���Ȃ��Ă���Ƃ������Ɓv�Ƙb�����B �@�V���K�|�[�����P�c�̂̃������c�ɂ��ƁA�؍��́u�ՏI�̎��v�͐��E�R�Q�ʂƂ����B�ی��������͍��N�A�S���S�S�J���̊ɘa��Ð��@�ւɂQ�R���E�H���i��P���V�O�O�O���~�j���x�����邱�Ƃɂ����B���F�i�A�W���j��a�@���lj����ꂽ�B���N�͈�ʕa�@���v�������Ζ������҂�ΏۂɊɘa��Â��ł���悤�f�Õ�V�_�����o���v�悾�B ��������@2012�N2��7�� |
||||
|
��14����{�A���}�Z���s�[�w�� �A���}�Z���s�[�⊿����������ÁC�ɘa��Âɍv�� |
||||
| �@����C������L�����p���C���a��\�h����ɂ͓�����Â��K�v�ƂȂ�B�����s�ŊJ���ꂽ��14����{�A���}�Z���s�[�w��i��������x�@�a�@���`�O�ȁE�ĐL�������j�̃V���|�W�E���u������Âւ̃A�v���[�`�v�i���������a��w����U�w�����E���c�����C����w��w�@���̋@�\�⊮��w�u���E�ɓ���L�����j�ł́C�A���}�Z���s�[�͌��N�E���e�₪�҂�QOL���P�ŁC�����͂��ÂŁC����͂����u�Ɏ��Âœ�����Â�ɘa��Âɍv������ƕ��ꂽ�B �`�G�R��Âɂ�����A���}�Z���s�[�`�Z���t�P�A�Ō��N�E���e��B�� �`�ɘa�P�A�ɂ�����A���}�Z���s�[�`���҂�QOL�����P �`���Á`���m��w�{�����̓�����Êm�����}�� �`�����u�ɂƊɘa��Á`�u�ɑ��݉��ł͖���ւ̐��_�ˑ����}�� �`�G�R��Âɂ�����A���}�Z���s�[�` �Z���t�P�A�Ō��N�E���e��B�� �@���{������Êw��̈����a�F�������́C�G�R��Âɂ�����A���}�Z���s�[�̖����ɂ��Č������C����̌��N�C�����C���e�͕a�C�̗\�h�ƃZ���t�P�A�ɂ��B������鎞��ɂȂ邪�C�A���}�Z���s�[�͌��N�E���e�ʂōv������Ƃ̌������������B ��t���S���犳�Ғ��S�̈�Â� �@���݁C���܂��܂Ȗʂœ����������ՓˁE�Z��������B�܂��C���E�I�Ȏ����͊��ɂ��L�����p�E�z�����������K�v�ł���C�Q�m���f�f��Đ���Â̔��B�ň�Â͎��Â̎��ォ��\�h�̎���ɓ������B�����ɑΉ������Â͕K�R�I�ɓ�����ÂɂȂ�C�ƈ����������͎w�E�����B �@���m��w�͏��w�I�C���v�w�I�ł���C���\���l�̃f�[�^���W�ߗ��_�I�Ɍ��_���o�����ƂŐf�f�E���Â��s�����C�ʓI��O�ɑ��ē������o���Ȃ��B���̂悤�Ȍl�̈�Â������ɂ͓`����w���܂ޑ���E��ֈ�ÁiCAM�j���L���ł���C���҂����邱�ƂŊ��Ғ��S�̈�Â�ڎw���̂�������Âł���B �@������Â̒�`�ɂ��ē��������́C�i1�j���Ғ��S�̈�Ái2�j�g�́E���_�i�S���j�C�Љ�i���j�C�쐫�i���j���܂߂��S�l�I��Ái3�j���Â����łȂ����a�\�h�C���N�ێ��C�����i�R����j�̂��߂̈�Á`��3�������C�u����܂ł̈�Â͈�t���S�̈�Â��������C����͊��Ғ��S�̈�Âɕς��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƌ��������B �@����ɓ��������́C�����{��k�Ђł̓��C�t���C�������f����ď]���̐��m��w���s���Ȃ��Ȃ������ʁC�C���t�������܂�K�v�Ƃ��Ȃ������C�I���C���K�C�}�b�T�[�W�C�A���}�Z���s�[�Ȃǂ̃G�R��Â��𗧂��C��Ў҂�������ƕ]���B�܂������{��k�Ќ�Ɂi1�j�G�l���M�[������Ȃ��G�R��Âցi2�j���Ò��S����\�h�E���N���S�ցi3�j�����̌��N�͎����Ŏ��Z���t�P�A�ց`�ω������Ǝw�E�����B �@�Ō�ɁC���������́u����̌��N�C�����C���e�͎��a�\�h�ƃZ���t�P�A�ɂ��B������邪�C�P�Ȃ钷���łȂ��C���N�Ŕ����������łȂ���Ȃ�Ȃ��B���Ɍ��N�E���e�ʂł̓A���}�Z���s�[���傫���v�����邾�낤�v�ƒ��߂��������B �`�ɘa�P�A�ɂ�����A���}�Z���s�[�` ���҂�QOL�����P �@�a�@�⊳�Ҏ���ւ̖K��A���}�Z���s�[���s�����f�B�J���A���}�����t��Tori�i�_�ސ쌧�j��\�Ńi�[�X�Z���s�X�g�̏��V���Âݎ��́C�A���}�Z���s�[�Ɗɘa�P�A�ɂ��Ď��g�̌o������Ɍ������C�A���}�Z���s�[�͂��҂�QOL�����P�ł���Ö@��1�Əq�ׂ��B ���҂��ł����y�Ȏp����S������ �@�z�X�s�X��ɘa�P�A�a���ł͌��݁C�{�����e�B�A�̃A���}�Z���s�X�g������I�Ɏ{�p���s���Ă��邪�C��̃A���}�Z���s�X�g������{�݂͏��Ȃ��B�a�@�Ō�t���A���}�Z���s�[�̍u�K��ŕ����C���҂Ɏ{�p���Ă���{�݂������Ă��邪�C�A���}�I�C���w���̖��Ȃǂł��܂蕁�y���Ă��Ȃ��B �@�����̌���܂��ď��V���́C�ɘa�P�A�ł̃A���}�g���[�g�����g�̗v�_�Ƃ��āi1�j����������ɂȂ����Ƃ��ɉ������Ăق��������l����i2�j���҂ƉƑ��̘b���悭�����i3�j���҂̒ɂ݂������ł��������悤�Ƃ����C���������i4�j�S�����߂ċC�����悳��^����{�p������i5�j�S�g�̃����b�N�X�ƏǏ�ɘa�ɓ����`�Ȃǂ��������B�܂��C�ɘa�P�A�ł̃A���}�g���[�g�����g�ł́C���҂��ł����y�ȑ̈ʂŎ{�p���邱�Ƃ��d�v�ł���C���̎p�����{���Ɋy���ǂ������m�F����K�v������Ƃ����B �@�A���}�g���[�g�����g�̌��ʂɂ́i1�j�����̎{�p�Ƒ��̃}�b�T�[�W�ɂ�镠���̉��P�i2�j�ア���܂ƕ����̎{�p�ɂ��֔�̉����i3�j�A���}�}�b�T�[�W�ɂ�鍂�x�����ѓ��퐶������iADL�j�̉��P�@�Ȃǂ�����B �@�ɘa�P�A�Ƃ��ẴA���}�g���[�g�����g���s���ۂ̊�{�p���Ƃ��ẮC�i1�j�{�p�҂̐��_�I����i2�j���҂̓����⌾����ǂݎ��C�S�����߂��{�p���s���i3�j���̐l�炵���������̂���`��������p���i4�j�Ƒ��̘b���X�����C���̋C�����𗝉�����p���i5�j�l���̏I���ɂ������Ӗ��������C�Â��Ȃ炸���邳�ƃ��[���A��Y��Ȃ��i6�j�`�[����ÂŃT�|�[�g����@�Ȃǂ��K�v�ł���B �@�Ō�ɓ����́C�A���}�Z���s�[�́C2002�N�ɐ��E�ی��@�ցiWHO�j���甭�\���ꂽ�ɘa�P�A�̒�`�ł���uQOL�����P���悤�Ƃ���A�v���[�`�v��1�ɂȂ���ƌ��B �`���Á` ���m��w�{�����̓�����Êm�����}�� �@���L���a�@�i�����s�j������Z���^�[���Ȃ̐��율�Õv�����́C���@�Ɋ����T�|�[�g�O�����J�݂��C�����̐i�s���҂ɒ��N�������Â��s���Ă����B�������́u����20�N�ȓ��ɁC����ɑ��鐼�m��w�Ɗ����ɂ�铝����Â��m�����邱�Ƃ��C�킪���̂����ÂɂƂ��ĕK�{�v�Ƌ��������B �u����v���P�ɗL���ȕ�� �@����͑S�g�����ł��邽�߁C�S�g�S�̂��ł��銿�����𗧂B���암����2006�N�t�ɊJ�݂��������T�|�[�g�O���̖ړI�́C������ɂ�邪�҂́i1�j���Ǐ�̊ɘa�i2�j���C��QOL����i3�j����p�y���ɂ��v��ʂ�̂��Â̐��s�i4�j�������ʂƍR��ᇌ��ʁ`�Ȃǂ̌����ł������B �@�������́C�i�s���҂��悷���{�a�Ԃ��u����v�ƌĂ�ł���B���҂́C���̂ɂ���ɂɉ����C���Âɂ�镛��p����ǁC����ɖƉu�זE������o�����T�C�g�J�C���̉e���ɂ���āC�C�́E�̗͂��ቺ�����C���Ȃ��B �@����ɗL���Ȋ�����́u��܁v�ł���C�⒆�v�C���C�\�S��ⓒ�C�l�Q�{�h���̎O���܂����҂̏�ԁi�j�ɉ����Ďg��������B�܂��C�قڑS��ɑ������s�����P����u�삨���܁v��C�����̐����G�l���M�[��~����u�t�v��₤�u��t�܁v�����p�����B�O�҂ɂ͌j�}䨗�ہC��҂ɂ͋��Ԑt�C�ۂȂǂ�����B �@�������͂���܂łɁC���ː��畆���ɑ��鎇�_�p�C�咰����̓]�ڗ�̏p��̕s�S�ɑ���u䟂����䓒�{�ܗ�U�v�C�����_�o��Q�ɑ����t�܁C������̃z�������Ö@�ɂ��z�b�g�t���b�V���ɑ���u�ČӍ܁{�삨���܁v�C���x�i�s����ւ̍R�����Ɗ�����̕��p�Ȃǂ����������Ǘ���o�������B �@�Ō�ɁC�u���҂����Â����t�́C���҂Ɋɘa�P�A�����߂邾���łȂ��C����̂��ÂɊ���������C����ɑ���V���ȓ�����w�����܂��v�ƌ��_�����B �`�����u�ɂƊɘa��Á` �u�ɑ��݉��ł͖���ւ̐��_�ˑ����}�� �@����ȑ�w��i�Ő��w�����̗�ؕ����́C�����u�ɂ̃��J�j�Y���Ɗɘa��Âɂ��čl�@�B�u�킪���ł͖����ɖ�i����j�ɑ������E�Ό����������C�u�ɑ��݉��ł͐��_�ˑ��͋N���炸�C�֔�C���S�E�q�f�C���C���\���Ώ��\�v�Ƃ����B ����g�p�ʂ͊؍������Ⴂ �@WHO�͊ɘa�P�A���u������ړI�Ƃ������Âɔ������Ȃ��Ȃ��������������҂ɑ��čs����ϋɓI�őS�l�I�ȃP�A�v�Ƃ��Ă���B �@�܂��C���R��̕��ނł͂����u�ɂ����̌�������i1�j���̂��������u�Ɂi2�j���ÂɊ֘A�����u�Ɂi3�j�S�g����Ɋ֘A�����u�Ɂi��ጁC�֔�Ȃǁj�i4�j���̂ɂ����Âɂ��W���Ȃ��u�Ɂi�ؓ��ɂȂǁj�`��4�ɕ����Ă���B �@WHO�̂����u�Ɏ��Â̍l�����ł́C��i�A�X�s�����Ȃǁj�C�㖃��i�R�f�C���Ȃǁj�C������i�����q�l�Ȃǁj��ɂ݂̋����ɉ�����3�i�K�Ɏg�������iWHO�O�i�K���Ƀ��_�[�j�C�u�ɂ̕]���ɂ���Ă͓�������̖���g�p���������Ă��邪�C�킪���ł͖���ɑ��������������C�Ɨ�؋����͏q�ׂ��B�܂��C�e���̖���g�p�ʂ�����ƁC���{�͊؍������Ⴍ�C�����͉p�����x�̎g�p�ʂ�ڈ��ɂ��ׂ��Ǝw�E�����B �@��������͉��ǐ�����ѐ_�o��Q���u�Ƀ��f����p���Ė���̐��_�ˑ����������������ʁC������̏ꍇ���u�ɑ��݉��ł͐��_�ˑ����}�����ꂽ�B����ɁC�����ł̌����Ń����q�l�̒��ɗp�ʂ�1�Ƃ����ꍇ�C������Ⴂ�p�ʂł����S�E�q�f�C�֔�͋N���邪�C���C��2.6�{�C�ċz�}����10.4�{�ȏ�̗p�ʂłȂ��ƋN����Ȃ������B�u�����3�啛��p�֔̕�C���S�E�q�f�C���C�̂����֔�ɂ͉��܂�p���C���S�E�q�f��1�C2�T�Ԃőϐ����ł���B�܂��C���C�͑��������ɑϐ����ł���̂ŗp�ʒ��߂ɂ��C�قƂ�ǂ͏����v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N2��16�� |
||||
|
��73����{�Տ��O�Ȋw�� �O�Ȃ̓w�͂ŏI�����̍ݑ��Â��\�� |
||||
| �@�ݑ�ōŊ����}�������Ƃ�����]�����l�͑������C���ۂɂ͂��܂��܂ȗv���̂��߂ɕa�@�ʼn߂�����������Ȃ��P�[�X�����₽�Ȃ��B�����s�ŊJ���ꂽ��73����{�Տ��O�Ȋw��i���������ȑ�w�O�Ȋw��O�u���E�ؒB�Ǝ�C�����j�̃��[�N�V���b�v�u�����܂ŏo����I�����̍ݑ��Áv�k�i��������q��ȑ�w������ÃZ���^�[�E��J�T�ە��@���i������O�ȋ����j�C������ȑ�w����ÃZ���^�[�ɘa��ÉȁE���R���l�����l�ł́C��������݂����d��ȂǁC�]���͍ݑ�ւ̈ڍs���s�\�ƍl�����Ă����ǗႪ�C�O�Ȉ�̎��g�݂ɂ���ĉ\�ƂȂ�P�[�X�����X�ƏЉ��C�I�����ɂ�����ݑ�×{�ɐV���ȉ\���������ꂽ�B �ɘa���Âւ̐ϋɓI����Œ��ǂł��ݑ�� �����h�ߔZ�k�V�X�e���ł����������� �����̒����ōݑ�ւ̈ڍs���X���[�Y�� �ɘa���Âւ̐ϋɓI����Œ��ǂł��ݑ�� �@�݂���̕����d��͏I�����ɒ��ǂɔ����o���ێ�s�\��q�f�Ȃǂ̏Ǐ�������N�����C�ݑ�×{�̍ő�̏�Q�ƂȂ�B�����w������E���B�E�ڐA�Đ��O�Ȃ̖؉��~���́C���Ȃ݂̈����d���̂������ǂǂ��C�ɘa���Âōݑ�x�����s����28��ɂ��ĕB�u�a�Ԃɉ������ɘa���ÂɐϋɓI�ɉ�����邱�Ƃň�ʓI�ɓ��@���K�v�Ƃ�����Ԃł��ݑ�ւ̈ڍs�͉\�v�Əq�ׂ��B �e�펡�Â�g�ݍ��킹 �@�����d��̏I�����ɂ͒��ǁC���t�ǁC���t�ȂǑ��l�ȍ����ǂ��������C�\��̒ቺ��I������QOL�ቺ�ɂȂ��邽�߁C���Ȃł͐ϋɓI�Ȋɘa���ÂɎ��g�݁C�ݑ�Â��x�����Ă����B�����Ŗ؉����́C���Ȃɂ�����ɘa���Ó��e�Ȃǂ����������B �@�Ώۂ�2008�`11�N6���ɓ��ȂŌo�������݂����d��58��̂����C���ǂǂ��C�ɘa���Âɂ��ݑ�x�����s����28��B �@���̌��ʁC�ݑ�S�Ö��h�{��25��i89���j�ɁC�ݑ�I�N�g���I�`�h�����牺����8��i29���j�Ɏ{�s�B�����́C�g�ь^�f�B�X�|�[�U�u�������|���v�i7���ԗp�j���ݑ�ł������\�ƂȂ������ƂŁC���������ɔ���������Ǐ�̉��P�ɖ𗧂����B�o�ljh�{�`���[�u�ɂ�钰�nj�����4��i14���j�Ɏ{�s�B����́C8Fr�o���h�{�p�`���[�u�̎g�p�ň�a�����y�����ꂽ���Ƃ���C�����h���i�[�W�p�b�N�ɂȂ����ƂŁC�p��̚q�f���������Ǘ�ł��ݑ�Ǘ����\�ƂȂ����B�����ǃX�e���g��5��i��������1��C����������4��j�Ɏ{�s�B���t�ǂɑ���A�ǃX�e���g�͎����ɂ��ő嗯�u���Ԃ�12�J���ƒ����C�����p�x�����Ȃ��S���^�����A�ǃX�e���g���g�p�����B�ɘa��p��8��i29���j�ŁC����͏����l�H���4��C�o�C�p�X��p3��C�o�C�p�X��p�{�����l�H���1��B�o��o�̒_���h���i�[�W�iPTBD�j��1��i4���j�B �@�ɘa���Â̑�����1���33���C2���30���C3���26���ŁC4��ނ�g�ݍ��킹�����11���������B���ǏǏ�̏o������̍ݑ���Ó����͒����l42���ԁi5�`645���ԁj�C�ݑ�×��͒����l42���i4�`76���j�������B �@�����̌��ʂɂ��āC�����́u�݂����d��Ǘ�̏I�����ł��C�a�Ԃɉ������ɘa���Âɂ��ϋɓI�ɉ�����邱�ƂŁC���ǂȂLj�ʓI�ɓ��@���Â��K�v�Ƃ�����Ԃł��C�ݑ��Âւ̈ڍs�͉\�ŁCQOL�̉��P�Ɋ�^����v�Əq�ׂ��B �����h�ߔZ�k�V�X�e���ł����������� �@�������͋��x�̕����c������ċz��������N�����C�ݑ�ւ̈ڍs��R����Â̌p��������ɂȂ邱�Ƃ������B��Ö@�l�Вc�����v���a�@�������ÃZ���^�[�i�����s�j�̏���\�S�Z���^�[���́C��ʂ̂������ɂ��Ή��\�ȉ��nj^�̕����h�ߔZ�k�V�X�e���iKM-CART�j���l�āC125��Ɏ{�s�������ʁC���҂̏Ǐ���P�ɗL���ŁC�ݑ�҂ɂ����S�Ɏ{�s�\�ł��邱�Ƃ�����B ��������S���t���\ �@�����h�ߔZ�k�ĐÒ��@�iCART�j�́C�������������ɁC�����h�ߊ�ŕ������̂���זE�Ȃǂ��������C����ɕ����Z�k��ŕ�����Z�k�C�A���u�~���Ȃǂ̒`��������������āC���҂ɐÒ�������́B�v���ɏǏɘa�����ق��C�K�v�Ȓ`�����ێ��ł��郁���b�g������B1981�N�ɕی��K�p����C30�N�ȏオ�o�߂��邪�C��H�C���삪���G�ŁC�זE�����̑����������͑����̖��ǂɂ���h�߂ł��Ȃ��Ȃǂ̌��_�ɂ��قƂ�Ǖ��y���Ă��Ȃ������B �@�����ŏ���Z���^�[����́C��ʓI�ȗA�t�|���v�Ƌz���킪���p�\�ŁC���삪�ȒP��KM-CART���l�āC2008�N6���ɓ����\�����s�����B �@2009�N2���`11�N3���ɂ�����125���KM-CART���{�s�������ʁC�̎敠����1���蕽��5.9L�C�Z�k�t�͕���0.8L�C���v���Ԃ͕���52���C����2.9��C�����܂ޏ������x��1L������8.8���B����p�͌y�x�̔��M�݂̂������B �k�Ǘ�1�l60�Α�j���C�X����̊̓]�ځF�����c�����ɂ��o���ێ悪�s�\�ƂȂ������߁C�ɘa�P�A�a���ւ̓]�@�����߂��C���Z���^�[����f�BKM-CART�ł�����14.9L���̎悵���Ƃ���C��������o���ێ�C�R�����̓������\�ƂȂ�ݑ�ֈڍs�C�ꎞ���E���ʂ������B �k�Ǘ�2�l60�Α㏗���C������F17��̃h���i�[�W�ł�������j����ɑS�g��Ԃ��������C���Z���^�[����f�B����8.6L���̎���KM-CART���{�s�����Ƃ���C�����ɑމ@���C3����ɂ͗F�l�ƃS���t�ɏo��������قǂɉ����B �@�Ȃ��C�ݑ�҂�KM-CART���{�s����ꍇ�́C�ߑO�Ɋ��ґ�ŕ������h�h���i�[�W���s���C���Ɉ�Ë@�ւō̎悵���������h�ߔZ�k�C�ߌ�Ɋ��ґ���h�ߔZ�k�t��_�H����B��̗�Ƃ��āC�ݑ�KM-CART���{�s���C�����c�����Ɖ����̕���y������C�S���Ȃ钼�O�܂ŎU�����ł����Ǘ�C���J���ɂ킽�镠���c��������������Ί炪�߂�C���炩�ɉi���ł����ǗႪ�����ꂽ�B �@���Z���^�[���́uKM-CART�͌y�x�̔��M�ȊO�ɕ���p���Ȃ��C�z���Ԃɒ��ӂ���Ζ������ҁC�ݑ�҂ł����S�Ɏ{�s���\�B�������ɑ��ẮCKM-CART�ŐϋɓI�ȏǏ�ɘa��}��ׂ��v�Əq�ׂ��B �����̒����ōݑ�ւ̈ڍs���X���[�Y�� �@�������q��ȑ�w������ÃZ���^�[������O�Ȃ̕���h�ꎁ�́C����I�����ɂ�����n��A�g�̎��g�݂ɂ��ĕB�����ɍݑ�×{���������ʁC�ݑ�S���͑S�����ς�12.4����啝�ɏ���42.2���ɏ�������Ƃ𖾂炩�ɂ����B �ݑ�S��42.2�� �@���Z���^�[��2006�N12����355���̋}�����a�@�Ƃ��ĊJ�@�B�ɘa�P�A�a������ː����Î{�݂��Ȃ��C�ڕW���ύ݉@�������Z�����ߒ������@������Ȃǂ̏���C�n��A�g�̊��p���s���ƂȂ��Ă���B �@���䎁�́C���Ȃɂ�����n��A�g�����p��������I������Â̌���Ɩ��_�ɂ��ĕ����B�Ώۂ́C2009�N8���`11�N10���̓��Ȏ��S�Ǘ�64��i�j��42��C����22��C���ϔN��69.0�}11.1�j�B�����̓���͑咰����31��C�݂���28��C�H������2��C�̂���C�_�X����C��������e1��B �@�Ȃ��C���Ȃł́i1�j�\���ȕa��������\�Ȍ���{�l�ɍs���i2�j������������a�i�s�����ۂ̗×{�̏�C�݂Ƃ�̏�ɂ��Ă̏������`��2�_����j�Ƃ��Ă���B���̂��ߍ��m�́C�{�l�ƉƑ����Ȃɂ��S���m41��i64���j���ł������C�{�l�ɂ͕a���݂̂ōׂ����_�͍��m���Ȃ����߉Ƒ��ƕʁX�ɐ��������������m��22��i34���j�ŁC�m��1��i2���j�݂̂������B �@64��݂̂Ƃ�̏�͍ݑ27��i42.2���j�ƍł������C2009�N�̍ݑ�S���̑S������12.4����傫���������B2�Ԗڈȍ~�͓��@18��i28���j�C�A�g�a�@16��i25���j�C���@�ɘa�P�A�a��3��i4.7���j�B �@�ݑ�S��̍ݑ���o�߂�����ƁC�O���ʉ@���ɍݑ�×{�������̂�22��i81.5���j�C���@����5��i18.5���j�ŁC�����ɍݑ�����J�n���������ݑ���������₷���X���ɂ������B���@���S��ɂ́C�a��̐i�s�������C�Ǐ�ɘa������C��N�ҁC�I�s�I�C�h�n���ɖ��ʓ��^�C���̎�e������Ȃǂ̓���������ꂽ�B �@����̉ۑ�Ƃ��āC�����́u���S���čݑ�×{���s���ɂ́C���@���K�v�ɂȂ����Ƃ��̂��߂�5�`10���ł��ɘa�P�A�ɓ��������a���̊m�ۂ��K�v�B�n��A�g�V�X�e���̍\�z���i�߂Ă��������B�ݑ�ɒ�R�������l�������̂ŁC�ݑ�ɘa�P�A��n��Z���ɐZ�������邱�Ƃ��K�v�v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N2��23�� |
||||
|
�I����Á\��t�ƈ�ʐl�͂Ȃ��I�����قȂ�̂� �P���E�}�[���C |
||||
| �@���N���O�A���h���W�߂鐮�`�O�Ȉ�ł���A���̃����^�[�ł�����`���[���[�́A�݂Ɂu��v���������B�S�Ăōł��ǂ��O�Ȉ��1�l�́A������������K���Ɛf�f�����B���̊O�Ȉ�́A���҂̐����̎��͒ቺ������̂́A5�N��������3�{�\�\5������15���Ɂ\�\�Ɉ����グ�����p����|���Ă����B �ڂ������̂́A��t���鎡�Â̑����ł͂Ȃ��A���Ȃ��� �@�������A68�̃`���[���[�́A��p�ɂ͌����������Ȃ������B�����A�ނ͋A��A�f�Â���߁A�a�@�ɂ͓�x�Ƒ��ݓ���Ȃ������B�Ƒ��Ǝ��Ԃ��߂������ƂɏW�������̂ł���B���J����A�ނ͉ƂŖS���Ȃ����B�ނ́A���w�Ö@�����ː����Â��O�Ȏ�p���Ȃ������B���f�B�P�A�i�č���Ҍ�����Õی����x�j�͔ނ̎��Ô�ɂقƂ�ǎg���Ȃ������B �@���������͂Ȃ����Ƃł͂��邪�A��҂����ʁB�����ł̔ނ�̓����́A�唼�̃A�����J�l���A�����ɑ����̎��Â��Ă��邩�ł͂Ȃ��A�����Ɂu���Ȃ����v�ł���B��҂́A�a�C�̐i�s�ɂ��Đ��m�ɗ������Ă���A�ǂ�ȑI����������̂���m��A�����Ǝv�����Â͂ǂ�Ȃ��̂ł������Ă�����B�������A�ǂ��炩�Ƃ����A��҂̍Ŋ��͐Â��ʼn��₩���B �@��҂��A��ʂ̐l�������Ɏ������Ȃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�������A�ނ�́A�ߑ��Â̌��E�ɂ��ĉƑ��Ə��������b���Ă���B���̎���������A��|����Ȏ��Â͂��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��m�F�������̂��B���Ƃ��Δނ�́A�����Ŋ��Ƃ������ɁA�S�x�h���~�}�i�b�o�q�j���{����A�N���ɘ]����܂�ꂽ���͂Ȃ��i�b�o�q�̐��������u�Ř]�����܂�邱�Ƃ͏\���ɂ���j�B �@��t���I�����̌��f�ʼn���]�ނ��ɂ��āA�W���[�t�E�i�E�K������́A2003�N�ɘ_���ɂ܂Ƃ߂��B�����ΏۂƂȂ�����t765�l�̂����A64�����A�������ċN�s�\�ƂȂ����ꍇ�A�~���̍ۂɎ��ׂ��[�u�Ǝ��Ȃ��[�u����̓I�Ɏw�����Ă����B��ʐl�̏ꍇ�A���������w�����s���l�̊����͂킸��20�����B�i���z���̒ʂ�A����̈�҂̕�����N�̈�҂������������u��茈�߁v������X���ɂ���B����́A�|�[���E���X�^�[����̒����Ɏ�����Ă���B�j �@��҂Ɗ��҂̌��f�ɂ́A�Ȃ����̂悤�ȑ傫�ȃM���b�v�����݂���̂��B������l���邤���ŁA�b�o�q�̃P�[�X�͎Q�l�ɂȂ�B�X�[�U���E�f�B�[������́A�e���r�ԑg�ŕ`����Ă���b�o�q�ɂ��Ē������s�����B����ɂ��ƁA�e���r�ł͂b�o�q�̌�����75�����������A67���̊��҂��A��ł����B�������A�����̐��E�ł́A2010�N�̒����ɂ��ƁA9��5000���ȏ�̂b�o�q�̂����A1�J���ȏ㐶���������҂�8���ɉ߂��Ȃ������B���̂����A�قڕ��ʂ̐����𑗂邱�Ƃ̂ł������҂͂킸��3���������B �@�̂̂悤�ɁA��҂��M����ɏ]���A���Â��s��������Ƃ͈قȂ�A���͊��҂̑I������{���B��t�́A���҂̈ӎu���ł��邩���葸�d���悤�Ƃ���B���A���҂Ɂu���Ȃ��Ȃ�ǂ����܂����v�ƕ������ƁA��t�͓�����̂�����Ă��܂����Ƃ��悭����B��X�́A��҂Ɉӌ������v�������Ȃ��B �@���̌��ʁA�ނȂ����u�~���v���Â���l�������A60�N�O��������ŖS���Ȃ�l���������B�Ō�w�̃J�����E�P�[�������́A�uMoving Toward Peace: An Analysis of the Concept of a Good Death�i���炬�ւ̓����F�ǂ����Ƃ����T�O�̕��́j�v�Ƃ����_���̂Ȃ��ŁA���������Ƃ������̂̏����������������A�Ȃ��ł��u�₷�炩�v�Łu�}�����ꂽ���́v�ł���A�u�I�����}�����Ɗ����v�A�u���̐l�X��Ƒ����P�A�Ɋւ���Ă���v���Ƃ��d�v���Ǝw�E�����B����̕a�@�́A���������_���قƂ�ǖ������Ă��Ȃ��B �@���҂́A�I����Âɂ��ď����L�����Ƃɂ��A�u�ǂ����ʂ��v�ɂ��āA�͂邩�ɑ������R���g���[�����邱�Ƃ��\���B�唼�̐l�X�́A�ŋ����瓦��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����Ƃ͂킩���Ă��邪�A���͐ŋ����������Ɛh���B�A�����J�l�̈��|�I���������̓K�ȁu��茈�߁v���ł��Ȃ��ł���B �@�����A�����Ƃ�������Ȃ��B���N�O�A60�̎��̔N��̏]�Z�ł���g�[�`�i�ނ́A�����d���̌��������ɉƂŐ��܂ꂽ�j������ɏP��ꂽ�B���ǁA����͔x����ɂ����̂ŁA�����]�ɓ]�ڂ��Ă��邱�Ƃ����������B�T3�`5��A���w�Ö@�̂��߂̒ʉ@�ȂǁA�ϋɓI�Ȏ��Â��s���āA�]����4�J���Ƃ������Ƃ������B �@�g�[�`�͈�҂ł͂Ȃ��B�������A�ނ́A�P�ɐ����钷���ł͂Ȃ��A�����̎������߂Ă����B�ŏI�I�ɁA�ނ͎��Â����ۂ��A�]�̎���}������p���邱�Ƃɂ����B�����Ĕނ͎��̂Ƃ���Ɉ����z���Ă����B �@���̌�8�J���ԁA����܂ł̐��\�N�ł͂Ȃ������Ǝv�����炢�A�y�������Ԃ��ꏏ�ɉ߂������B�ނɂƂ��Ă͏��߂Ẵf�B�Y�j�[�����h�ɍs�����B�Ƃł������Ɖ߂������B�g�[�`�̓X�|�[�c�D���������̂ŁA�X�|�[�c�ԑg���ςĎ��̎藿����H�ׂ�̂���D���������B�ނ́A�������ɂ݂��Ȃ��A�͂�Ƃ��Ă����B �@������A�ނ͖ڂ��o�܂��Ȃ������B3���ԁA����Ԃ������A�����ĖS���Ȃ����B����8�J���Ԃ̔ނ̈�Ô�́A���p���Ă���1��ނ̖��ŁA20�h�����x�������B �@�����g�ɂ��Č����A�厡�オ���̑I�������L�^���Ă���B�������邱�Ƃ͊ȒP�Ȃ��Ƃ������B�����̈�t�ɂƂ��Ă��������낤�B��|����Ȏ��Â͂Ȃ��B�₷�炩�ɉi������B���̃����^�[�A�`���[���[��]�Z�̃g�[�`�̂悤�ɁB�܂��A�������̎��̈�Ғ��Ԃ̂悤�ɁB �i�M�҂̃P���E�}�[���C��t�́A��J���t�H���j�A��w�̉ƒ��w�̌��Տ��y�����B���̋L���́A�E�F�u�T�C�g�̃\�J���E�p�u���b�N�E�X�N�G�A�ɔ��\���ꂽ���̂�ҏW�����j �E�H�[���X�g���[�g�W���[�i�����{�Ł@2012�N2��27�� |
||||
|
��30����{�F�m�NJw�� �p�[�L���\���a���Ö�EACE�j�Q��Ś����@�\������ |
||||
| �@�A���c�n�C�}�[�a�iAD�j���\�Ƃ���ϐ����F�m�ǂł́C�I�����ɚ�����Q�₱��ɋN������뚋���x�����d�v�Ȗ��ƂȂ�B�Q�n��w�ی��w�����ȃ��n�r���e�[�V�����w�u���̎R�����ۋ����́C�I�����ł��o���ێ�ł�����Ԃ��ł��邾���������߂ɁC�Ö@�Ś����@�\�����߂���@�������B�p�[�L���\���a�iPD�j���Ö�EACE�j�Q��Ś����@�\������ł���ƕ����B �I�����̌o�ljh�{����� �@�F�m�ǂ̏I�����ɁC�o��I�������I��ᑑ��ݏp�iPEG�j�Ȃǂ̌o�ljh�{�ւ̈ڍs���ł��邾��������邽�߂ɂ́C�뚋�̗\�h�ƐH�~�̑��i��}��K�v������B�R�������́C�I�����̔F�m�NJ��҂ɁC�����@�\�ɐ[���֗^����_�o�`�B�����T�u�X�^���XP�iSP�j�𑝂₷���ʂ̂����܂�p���āC���̗L�������������B �@��̓I�ɂ́C���ǂ���10�N�ȏ�o�߂����F�m�ǏI�����Ŕ���E�\��Ȃ��Ȃ�C�H�������̒��ɂ��ߍ��ށC�ނ���Ȃǂ̖�20��ɑ��C�i1�jSP�̕�������߂�A�}���^�W���i�`150mg�j��L-DOPA���܁i�`300mg�j�i2�jSP�̕�����h��ACE�j�Q��i3�j�O����������ňݔr�o���i�E�H�~���i��p�������Z�N�q���`��K�X�g�ݍ��킹�ē��^�����Ƃ���C�����ȏ�Ś����@�\�����サ�Ăނ����݂��������������łȂ��C�Ί��\��߂�C1�`2����x�̔���ȂǁC��⌾��ʂł̉��P���ʂ�����ꂽ�Ƃ����B �@�������́u�I�����̈��ՂȌo�ljh�{�ڍs�͗\�h���ׂ��ł���B�����@�\�����������܂����łȂ��C�������n�r���e�[�V������D�����\�t�g�H�C�~�L�T�[�H�ȂǐH�ׂ₷���`�Œ��邱�Ƃ�����v�Ƌ��������B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N3��1�� |
||||
|
��56����{���n���V�����w�� �V������Á@�����ɍőP�̗��v�ƂȂ�I���� |
||||
| �@�V������Âł́C�����őP�̗��v�ƂȂ�̂��������ɑ�����͂��ӎv���肷�邱�ƂɂȂ�C�ϗ��I�C�@�I�C�Љ�I�Ȗ��ɒ��ʂ��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�����s�ŊJ���ꂽ��56����{���n���V�����w��i����������q��ȑ�w��q������ÃZ���^�[�E��c�������j�̃��[�N�V���b�v�u�V�����̐��̑�َҁv�i����������c��w��[�Ȋw�E���N��×Z�������@�\�E�͌����l�����@�y�����E��C�������C���É��s����w��w�@�V�����E������w����E������q���j�ł́C�Ƒ��x�����s������̎厡��C�����̉Ƒ��C�㎖�@���̌����҂ȂǑ����ʂ���̔��\���s��ꂽ�B ��Ñ��Ɗ��ҁE�Ƒ��̋����ӎv����� �Ƒ��Q���^�̃`�[����Â��s�� �@�̉ߏ����͔�����ׂ� �q���ɂ͈�ÁC�e�ɂ͎q��Ďx���� ��Ñ��Ɗ��ҁE�Ƒ��̋����ӎv����� �@��q��������q�ی��Z���^�[����a�@�i�����s�j�V�����Ȃ̉�����F�����́C�V������Âɂ�����ӎv����݂̍���ɂ��ču���B�u��Ì���ł͈ˑR�Ƃ��Ĉ�t���犳�҂ւ̈���I�ȃR�~���j�P�[�V�������s���Ă��邪�C�{���ɕK�v�Ȃ̂͑��݃R�~���j�P�[�V�����B�K�C�h���C����}�j���A���ň��ՂɌ��肪�}����邱�Ƃ��Ȃ��悤�C�\���Șb�������Ɋ�Â������ӎv������s�����Ƃ��d�v�v�Ƒi�����B ���݃R�~���j�P�[�V�������d�v �@���������͂܂��C�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�ɂ��āi1�j��Ñ�����̓K�ȏ��̊J���i2�j���̊��҂ɂ�闝���i3�j���҂̎��Ȍ���\�͂̊m�F�i4�j���҂�������s���ۂ̎��R�ӎu�E�������̑��d�i5�j���҂̓��Ӂ`�̗��ꂪ�K�v�ł���Ɛ����B�u�C���t�H�[���h�E�R���Z���g���g���h�Ƃ���������������Ⴂ��t�⌤�C�オ�������C�{���̈Ӗ����\���ɗ������Ă��Ȃ����Ƃ�������B�R�~���j�P�[�V�����\�͂��s�\���Ȉ�ÃX�^�b�t�ƁC�͂�����ӎv�\�����ł��Ȃ����҂Ƃ̊ԂŁC�V���ȁg���C����Áh���o�����Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ɩ���N�B����Ɂu����������₷���`���邾���łȂ��C��t�Ɗ��҂��������L���C���ݗ�����}�邱�Ƃ��s���v�Əq�ׂ��B �@�܂��C2004�N3���Ɍ����J���Ȑ����Èϑ������ǂ����\�����u�d�ĂȎ��������V�����̈�Â��߂���b�������̃K�C�h���C���v�Ɋւ��āC�u���E��̎Q����O�ʂɑł��o�����_������I�B�ӎv����̌��_�����v���Z�X�����L���邱�ƂɈӋ`�����邱�Ƃ���������Ă���v�Əq�ׂ��B �@����Ɉ�ÃX�^�b�t�Ɗ��҂����L������̒��ɂ́C��������Ï���łȂ��C��Ã~�X�Ȃǐf�Ó��e�ɂ�����鎖����s���̈����j���[�X�C�l���ς�������܂܂�邱�Ƃ��w�E�B�u�o�����̃R�~���j�P�[�V�����ɂ����̋��L�����ݗ����݁C��Õs�M�������傭����C�l��l�Ƃ��Ĉ��������Ȉ�Â���������B�K�C�h���C����}�j���A���ɗ�����ՂȈӎv������}���̂ł͂Ȃ��C����ł̘b���������x������Â��肪�d�v�v�Ƃ̌������������B �Ƒ��Q���^�̃`�[����Â��s�� �@���É��s����w��w�@�V�����E������w����̈ɓ��F�ꎁ�́C�d�ĂȎ����̑�\�I�ȑ��݂ł���18�g���\�~�[�ɂ��āC�ŋ�10�N�Ԃ̓��@�V�����W�����Î��iNICU�j�ł̌o���ƁC�`�[����Âł̊ɘa��Â̎��H����u�\��s�ǂȎ����ł͉Ƒ��Q���^�̃`�[����Â��s���v�Əq�ׂ��B 18�g���\�~�[�Ŋɘa��Â�I�� �@�ɓ����́C18�g���\�~�[�̗\��ׂ邽�߁C2001�N1���`10�N12����10�N�Ԃɓ��@NICU�ɓ��@����18�g���\�~�[19��i�j��8��C����11��j��ΏۂɌ�����I�ɗՏ��o�߂����������B�Ώۂ̊T�v�́C���ύݑُT��36.2�T�C���Ϗo���̏d1,615.4g�C�鉤�؊J��68.4���C�@�O�o��36.8���C�o������̌��N�x������Apgar�X�R�A�̒����l��1��3�_�C5��6�_�B��p�{�s��6��B��������1�J��80���C6�J��20���C1�N10���B�����މ@����32���ł������B �@����ɓ����́C�ɘa��Â�I������18�g���\�~�[�ɑ��ē��@NICU�����g�`�[����Â̎��H�������B �@�Ǘ�͍ݑ�37�T�ŏo���̏����B29�T�ŗr���ߑ����w�E����C33�T�œ��@�Y�Ȃ��Љ�ꂽ�B�r���זE���F�̌�����18�g���\�~�[�Ɛf�f�C���e�C�c��C�V�����Ȉ�t�C�Y�Ȉ�t�Ƃ̘b�������̌��ʁC�u�O�ȓI�Ȏ��Â͖]�܂Ȃ������ȓI���Â̔͂��イ�Ŏ��Â���]����v�Ƃ̈ӌ��Ɋ�Â�37�T�Ōo�T���ʎ��R���ɂďo���B�o������ɕ�e�ɕ����ꂽ��C�C�Ǔ��}�ǂ���NICU�֓����C�ċz�Ǘ����J�n�����B�x�������C����79�Ŏ��S����܂ŁC��e�͂قږ����ʉ�ɖK��C�l�H�ċz�Ǘ����ŕ������⟔�����s�����B�ċz��Q���i�s���C�x�����������Č�������Ԃ̎����C�`�[���Řb�������C�a�@����뉀�ւ̎U�����āB�O���ɂ̓X�^�b�t�ƈꏏ�ɂĂ�Ă�V��������āC���V�̉��C��t�C�Ō�t���������ď��߂Ẳ��O�ւ̎U�������������B�Ƒ��͏I�n�Ί�Ŏʐ^��r�f�I�B�e���s�����B�����S���Ȃ����̂́C����3����B�Ƒ��͌�����������~�߁C���Ƃ̂��������̂Ȃ����Ԃ��߂������Ƃ��ł����B �@�����́u�\��s�ǂȎ����̊����ɂ͉Ƒ��Q���^�̃`�[����Â��s���B�����ƉƑ������[���������Ԃ��߂������߂ɉ����ł��邩���ꏏ�ɍl���Ă������Ƃ��厖�v�Əq�ׂ��B �@�̉ߏ����͔�����ׂ� �@�@���Ƃ̗���Ŕ�����������c��w��w�@�@�������Ȃ̍b�㍎�������́C�����̏I������Âɂ��āu�q���̍őP�̗��v��������邽�߂̔��f�́C�P�[�X�o�C�P�[�X�őΉ�����������Ȃ��B���̗̈�Ŗ@���O�ʂɏo�߂���ׂ��ł͂Ȃ��v�Ƃ̍l�����������B �Ƒ����܂ރ`�[���Ŕ��f �@�b�㋳���͂������N�̏����̏I������Âɂ��Ă̌�������C���O���̎��g�݂ɂ��ĕ����B�č���t��̃��[���ł́i1�j���Â���������\���i2�j���Â̎��{����ѕs���{�Ɋւ��郊�X�N�i3�j���Â����������ꍇ�ɐ����������������x�i4�j���Âɕt������ɂ݁C�s�����i5�j���Î��{�̏ꍇ�ƕs���{�̏ꍇ�ɗ\�z�����V������QOL�`��5���l�������ׂ����ڂƂ��ċ������Ă���B1989�N�ɍ��A����ō̑����ꂽ�����̌����Ɋւ�����i���{��1994�N�ɔ�y�j�ł́C�����̍őP�̗��v�̏d�v�����w�E����C�q���̍őP�̗��v�͉Ƒ��̍őP�̗��v����Ɨ��������̂Ƃ��Ĉʒu�t�����Ă���B���E��t��I�^���錾�ł��C�q���̍őP�̗��v�����`�ɍl�������ׂ����ƂƂ���C�s�K�v�Ȑf�f�s�ׁC���u����ь������炷�ׂĂ̎q����i�삷�邱�ƂƂ���Ă���B �@�����݂̂Ƃ���l�����ł́C�Ƒ��̖������d�v�ƂȂ�B����ɂ��āC�������́u���e�̔��f���q���ɒ������s���v��^����ꍇ�Ȃǖ@�I�K�����������������Ȃ��ꍇ�����邪�C���܂�@����������߂��Ȃ������悢�Ƃ���������Ƃ��Ă���v�Əq�ׂ��B �@�d�x��Q�V�����Ɖ������u�̍����T���C���~�Ɋւ��Ắu���ۂɂ̓P�[�X�o�C�P�[�X�Ŕ��f����������Ȃ��B�Ⴆ�Ύ��Â�i�߂Ă��������ɏ��ω����邱�Ƃ͂�����ł�����B�l�H�ċz������C���̌�O������E�l�ɂȂ�Ƃ������@�B�I�Ȕ��f�͂��ׂ��ł͂Ȃ��B���Â𒆎~������Î҂ɌY���Ȃ����Ƃ͖@�̉ߏ����ɂȂ�Ǝv���v�Ƃ̍l�����������B �@����̓��{�ł̃��[���Â���ɂ��Ắu���e�𒆐S�ɁC��t�C�Ō�t�C�@���ƁC�����ϗ��Ȃǂ̐��Ƃ������C�`�[���ŐT�d�ɔ��f���Ă������Ƃ��厖�B�`�[�������肵�����Ƃ�@�͑��d����Ƃ����X�^���X���d�v�v�Əq�ׂ��B �q���ɂ͈�ÁC�e�ɂ͎q��Ďx���� �@���҉Ƒ��̗���ōu�������T��q�́C���Y���̃g���u������A����ԂɂȂ���������12�N�O��4�ŖS�������o������C�u���쌧�����ǂ��a�@�ł�4�N�ԁC��t�C�Ō�t�C�����̐l���`�[���ł킪�q�̖����x���C�킽��������e�Ƃ��Ĉ�ĂĂ��ꂽ�BNICU�͕����̏�ł�����B�q���ɂ͈�Â��C�e�ɂ͎q��Ďx�����K�v�v�Əq�ׂ��B 1�l�̐l�ԂƂ��Ă��킢�����Ăق��� �@�T�䎁�̒����E�z�����́C���Y���̃g���u������ٕz���nj�Q�ɂ���_�f���������]�ǂƂȂ�C�o�����ォ��l�H�ċz����C�Ƒ��𒆐S�Ƃ������@�̃`�[���Ɏx�����4�N�Ԃ����B�T�䎁�͖����C������ĕ����͂��C�x�b�h�T�C�h�Ɋ��Y�����B�X�^�b�t�͗z�����������Ƃ��Ăł͂Ȃ��C1�l�̐l�ԂƂ��ĐS���炩�킢�������B �@�T�䎁�́u�M������X�^�b�t����������ꂵ�����ł��~�߂��C�e�Ƃ��ē����Ȃ���̐��̂��锻�f���ł����B�m����X�^�b�t�Ɏx�����čK���������Ǝv���v�Ɠ�����U��Ԃ����B�܂��C�d�ĂȐV�������P�A�����ÃX�^�b�t�ɑ��āu��e�́C���C�Ȏq���Y�߂��ɕ�e���i���Ƃ������ӂ̔O�ɂ����Ă��邱�Ƃ�m���Ăق����B��e�Ƃ��ĉ������������Ƃ����C�����ɉ����Ăق����v�ƁC�e���`�[���̈���Ƃ��Ď�̓I�ɃP�A�ɂ��������Â���̕K�v���������B�u�킪�q�������Ă��邱�Ƃ����Ɋ�сC�������킢�����Ăق����BNICU�͕����̏�ł�����B�q���ɂ͈�Â��C�e�ɂ͎q��Ďx�����K�v�v�Əq�ׂ��B�����͗z�����̓��@���Ɏ������o�Y�C���݂�3�l�̖��Ɍb�܂�Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N3��1�� |
||||
|
��30����{�h���w��@���ҍu�� �������Ò��~�̈�×ϗ��`�č��ł͊��҂̎��Ȍ��茠�͏I������Âɂ��K�p����� |
||||
| �@�č��ł̓��[�`���̈�Ís�ׂƂ��Ē蒅���Ă���l�H�ċz���~�Ȃǂ̉������Â̒��~�����C�킪���ł͑傫�ȋc�_�ƂȂ�C��t�̌Y���ӔC��₤�����ɂ����W����B�R�����j�X�g�̗��[�[���i���n�[�o�[�h��w�������j�́C���w��̏��ҍu���Łu���{��35�N�ȏ�O�̕č��ƍ��������v�Ƃ��C�č��Ɍ��݂̃��[�����m������܂ł̌o�܂��Љ���B �č��̗��j��ς���2�̍ٔ� �@1975�N10���C��ɕč���h�邪�����ƂɂȂ�ٔ����n�܂����B�J�����A����ԂƂȂ���21�̏����J�����E�N�B�������̗��e�����̐l�H�ċz����O���悤�C�i�ׂ��N�������̂��B�ٔ��́u�ċz��ɂȂ���Ă܂Ő������ꑱ�������Ȃ��v�Ƃ������C����������̖��̈ӎv�́C���@�ŕۏႳ�ꂽ�u���҂̎��Ȍ��茠�v���Ƃ��闼�e�ɑ��C�u�ċz��O���͎E�l�ň�×ϗ��ɂ�������B�ޏ��̌ċz����O�����Ƃ͈��y���̍��@���ɓ����J���v�Ƃ����厡�㑤�̋��ۂ̎p�������_�ƂȂ����B�����͏،��ɗ�������t�������l�H�ċz��O���ɂ͂������Ĕ�����������B �@��R�����i�����ٔ����j�͈�t���̎咣��F�߂����C�T�i�̌��ʁC�B�ō��ق͗��j�I�ȍٌ����������i1976�N3���j�B�i1�j�������`���Ɗ��҂̎��Ȍ��茠�̕ی�̗D��x�́C�N�P���x�Ɨ\��̃o�����X�ōl����ׂ��ł���C�̌����݂̂Ȃ����҂ɑ��āC�{�l�̈ӎv�ɔ�����N�P�̑傫�ȉ������u�𑱂���͕̂s�����i2�jincompetent�Ȋ��҂̎��Ȍ��茠���W������ׂ��łȂ��C�{�l���悭�m��Ƒ��ɂ��ӎv�̐���͍����I�`�Ƃ������R�̉��C7�l�̔����S����v�Łu���҂����Â����ۂ��錠���͌��@�ŕۏႳ��Ă���C�ċz����O���s�ׂ͎E�l�߂łȂ��v�Ƃ��������������C�����Ɉ�t��i�ǂ̋��|������������u�ϗ��ψ���v��a�@���ɐݒu���邱�Ƃ𐄏������B �@����1�̑傫�ȍٔ���1988�N3���Ɏn�܂����N���[�U�������B��ʎ��̂̌��ǂŐA����ԂƂȂ����i���V�[�E�N���[�U���̉Ƒ������̌�4�N�ڂɁu�o�ljh�{�̒��~�v��a�@�ɐ\�����ꂽ�Ƃ���C�u�ċz��O���̗v���͎邪�C�o���h�{�͊O���Ȃ��v�ƍٔ��ƂȂ����B��̃N�B������������C�ċz��O���͑S�ĂŃ��[�`���ƂȂ��Ă������C�a�@������~�Y�[���B�̏B�@�ł͌o�ljh�{�͈�Ís�ׂł͂Ȃ��C���~�͎��Ȍ��茠�̋y�Ȃ��u��@�v�ƒ�߂��Ă����ق��C�������~�̍����ƂȂ�{�l�̈ӎv�ɂ��Ă��m���ȏ؋������߂Ă����B �@�ŏI�I�ɘA�M�ō��قɎ������܂ꂽ���ٔ��́C�B�@�������Ƃ��C�Ƒ����̔s�i�ɏI��������C�����Ɂi1�j���҂����Â����ۂ��錠���͌��@���ۏႵ�������i2�j�o�ljh�{����Ís�ׁ`�Ƃ�������I�ْ肪�s���C��̂�蒼���ٔ��ɂȂ������B������Ɂu�i���V�[�͐A����ԂɂȂ�ǂɂȂ��ꐶ�����ꂽ���Ȃ��ƌ����Ă����v�Ƃ��������̏ؐl���o���������Ƃ��C�u���Ă��m�ł���؋��v�Ƃ��C1990�N12���C�B���F�ٔ����͌o�ljh�{���~�̖��߂������C�i���V�[�͂���2�T�Ԍ�C�▽�����B ���y���E�E�l�ƍ������閵�� �@�����͈ȏ���Љ����ŁC�u�č��ɂ�����c�_�́C�I������Âɂ����Ă����Ɋ��҂̌�������邩�ɐs����v�ƕ]���C���Ɍ�����1�̕���掦�����B�u�g���Áh���J�n���Ȃ�������C���~�����ꍇ�C�m���Ɏ��ʂƕ������Ă��Ă��C���҂ɂ́g���Áh�����ۂ��錠��������v �@1982�N8���C�ă��T���[���X�S�����ǂ��C�������Â𒆎~����2�l�̈�t���u�E�l�߁v�ō�������Ƃ����S�ď��̎��Ⴊ�������B2�퍐�͏p��C������ԂƂȂ������҂̉������Â��Ƒ��̗v���Ɠ��ӂ̉��ɒ��~����Ƃ����u�����n����t��Ɩ@���c�̂Ƃ̋��c�̏�ō쐬���ꂽ����̃K�C�h���C���ɏ]�������u�v���s�����킯�����C��R���i���p�C��R�i�ǑÓ���̏B�T�i�R�i�O�R�j�́C���i�s���ْ̍���������B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N3��15�� |
||||
| �����[�u�́u�s�J�n�v�ŁA��t��Ɛ�- ���}�h�c�A���@�Č��Ă�� | ||||
| �@���}�h�̍���c���ł���u�������@�������l����c���A���v�i������q�P�F�E����}�Q�@�c���j��3��22���ɑ�����J���A15�Έȏ�̏I�������҂��A�h�{�␅���̕⋋���܂މ����[�u�́u�s�J�n�v����]����ꍇ�A��t���[�u�����Ȃ��Ă��A���̖@�I�ӔC����Ȃ��Ƃ���u�I�����̈�Âɂ����銳�҂̈ӎv�̑��d�Ɋւ���@���āv�i���́j�̌��Ă��������B���c�A��2005�N�ɔ������A����A�����A�����ȂǗ^��}�̍���c��112�l���Q�����Ă��邪�A���Ă��o�����͍̂����߂āB �@���ẮA���ʂȂǂŊ��҂̈ӎv�\�������邱�Ƃ�O��ɁA2�l�ȏ�̈�t���A�u�s�����邷�ׂĂ̓K�Ȏ��Â����ꍇ�ł��A�̉\�����Ȃ��A�������ԋ߁v�Ɣ��肵���ꍇ�Ɍ���A�S���オ�����[�u���s��Ȃ��Ă��\��Ȃ��Ɩ��L�B�I�������҂̏��a�̎��Â��u�ɂ̊ɘa�ɂ��ẮA�u�����[�u�v�̑ΏۊO�Ƃ����ق��A���ݍs���Ă��鉄���[�u�̒��~�͊܂܂�Ȃ��B �@��t�̖����A�Y���A�s����̐ӔC�͖��Ȃ��Ƃ������A�����[�u���n�߂Ȃ��ꍇ�A��t�͊��҂܂��͉Ƒ��ɐ������A������悤�w�߂�Ƃ����B ������A���٘A�Ȃǂ���T�d�_������ �@���̓��̑���ł́A���{��t��⊳�Ғc�́A���٘A�Ȃǂ���q�A�����O���s�������A�e�c�̂���͓��Ăւ̔��Έӌ���T�d�_�����������B �@����̓��쌪���C�����́A�u�i�����[�u�́j�����T��������@�������邱�Ƃ��A�{���ɈӖ�������̂��B���~�̖����܂߂āA��͂���ɋ��E������v�Ǝw�E�B���̏�ŁA�u�I�����œx�d�Ȃ�i�ׂ��N����̂͂Ƃ�ł��Ȃ��v�Ƃ̊�@���������A�T�d�ȋc�_�����߂��B �@�܂��A��Q�Ғc�́uDPI���{��c�v�̎O�V���c���́A�u�Ȃ����̂悤�Ȗ@�����K�v�Ȃ̂��B�N�̂��߂ɕK�v�Ȃ̂��v�Ɣ��̍l���������B���٘A�̐l���i��ψ����Õ���̕�����������A���Ăɔ��̗����\��������ŁA�u�ӎv�\���̓P��̕��@��A���̗L���̊m�F���܂߁A�ߋ��̈ӎv�̕\������A�����Ɍ��݂̖{�l�̈ӎv�f���Ă����̂��v�Ɩ���N�����B �@����A���{����������̕��������œ��Ȉ�̗�ؗT�玁�́A�u��w�̐i���ɂ���āA��t�哱�^�̍s���߂�����Â��i�v�Ƃ��A���҂�QOL�̊ϓ_����A���x�̕K�v�����w�E�B�܂��A������̏�C�����ŁA��������t�̒����a�G���́A�u�������鐶���x���Ȃ�����A�����܂Ŋ��҂���̈ӎv�A��{�I�l���d�������v�Əq�ׂ��B �@���c�A�ł́A������ւ̖@�Ē�o��ڎw���Ă��邪�A���q��́u�ّ��ɖ@��������l���͑S���Ȃ��v�Ƃ��A�u���ꂼ��̐��}�ɂ������A�肢�������āA����ꂪ�o�����Ă�������������������ŁA�ŏI�I�Ȏ��܂Ƃ߂ɓ��肽���v�Əq�ׂ��B ��É��CB�j���[�X�@2012�N3��22�� |
||||
| ���悭�����邽�߂Ɂ@�������߂邱�Ƃ̑���@�L����m�̑̌n�u�����w�v | ||||
| �@���悭�����邽�߂Ɏ������߁A�����Ȃ�̎����ς��`�����čŊ��ɗՂށB���̎x���ƂȂ�V�����m�̑̌n�u�����w�v���L������݂��Ă���B �@�u�Ƒ��ɒm�点�Ă��Ȃ����͂���܂��H�v�B���O�̏��������x���͂������B�}�C�N������̂́A�A���t�H���X�E�f�[�P����q�喼�_�����B�s���ŊJ���ꂽ�u�����E���Ǝ����l�����v���J�Z�~�i�[�ł̍u�����B �@���ʂƃO���[�t�i�ߒQ�j�P�A���e�[�}�����A���[�����X�Ȍ��荞�݂A���ʑ̌��҂ɐڂ���ۂɔz�����ׂ��_�A�z��҂��������̔����ɂ��Ęb��i�߂��B �@�P�X�R�Q�N�h�C�c���܂�B�T�X�N�ɗ����A��q��Łu���̓N�w�v�N�u���A��ʂ̐l�X�ɂ��u���ւ̏�������v�̑��������Ă����B�����^�u�[�����镗�����������{�Łu�����w�v���J���Ă����������I���݂��B �@�����w�B�f�[�P�����_�����́u���Ɋւ��̂���e�[�}�ɑ��Ċw�ۓI�Ɏ��g�ފw��v�ƒ�`�t����B��w��N�w�A�S���w�Ȃǂ��܂��܂Ȋw���p���A���ƌ��������m�̑̌n�B�z�X�s�X�^���Ɛ[���ւ��������A���{�ł͂V�O�N�ォ�玀���w�Ƃ������t���p������悤�ɂȂ����B �������� �@�����w���i���̈�l�A�����i�i���܂��́E�����ށj���勳���ɂ��ƁA���̐V�����w�▼�ɒʂ���u�����ρv�Ƃ������t��"����"���ꂽ�͓̂��I�푈�O��B���̌��t�ɑ����Ď��Ɏv�����͂��A�Ŋ��Ɋւ���l�����܂Ƃ߂Ă������Ƃ���v�z�╶�w����̍�i�Q���`�����Ă���Ƃ����B���������`���̒��A���{�ɂ����鎀���w�́A�����ϗ���V�A�ԗ�Ȃǂ̌����Ƃ����ѕt���Ȃ��畝�L���̈���\�����Ă����Ɠ��������͘b���B �u�w���{�l�̎����ς��ĉ����낤�x�Ƃ̖₢�́w���{�l���ĉ��x�ɂȂ���A����̕�����₢�����ǂ�����ɂȂ�v �@�s���̊S�������B�V���|�W�E���Ȃǂ̔����̑����ɋ��������Ƃ����B�w�i�ɁA��Â������ɂ������͈͂̊g��A����Љ�̐i�s������B��Ì��ꂩ��̃j�[�Y�������A�N�w��@���w�Ȃǂ̊w��I�~�ςf�����u�l���I�Ȓm�̌��݁v�̕K�v����Ɋ����Ă���A�Ɠ��������͘b�����B �����̂��ւ̊S �@�����w�͎��ƌ��������w�₾���A�K�v�Ƃ��Ă���͕̂K�������V�j�A���ゾ���ł͂Ȃ��B���w�@��l�ԕ����w���̓�����a�i�ӂ����E�݂�j�����������w�̎��Ƃ��n�߂��̂́A�X�X�N�H�B�ŏ��̎��ƂŁA�w���������̊O�ɂ��ӂ�Ă���̂ɋ������B�u�w������͉��̂��߂ɐ�����̂����l���鎞���B���̂��⎀�ɊS������v �@����ɂ��������w�����S���Ȃ�ߒ�����L�`���ŒǑ̌����A��Ȃ��̂����������u���̋^���̌��v�ȂǁA����������������ƂŒ��ڂ��W�߂Ă����B����̎����w�E�X�s���`���A���e�B�����Z���^�[�������߂�B �@���g�A���ɒ��ʂ����o��������B�V���Ђŏ[�������������߂��������A�ˑR�S�g���܂Ђ���a�C�ɁB�ꖽ�͂Ƃ�Ƃ߂����̂́A�S�������Ȃ����X�B�����̊��҂����y�������肵�Ȃ���S���Ȃ�p�����Ďv�����B�u����ł����l�X�̂��߂ɉ����ł��Ȃ����̂��v �@���N�̓��@�A�Q�N���̃��n�r�����o�đ�w�Ɋw�m���w���A�Љ�����U�B���A�u���v�̉Ȗڂ��Ȃ��B�ŏI�I�ɕč��Ŋw��Ŕ��m�����擾�����B �@�����w�ւ̊S�����܂钆�A�̂��C�����Ȃ���������Ȋ�����W�J����B�M�S�ȃN���X�`�����ł���A���̂Ԃ�Ȃ��������̊j�ɂ͐M������B �@�u�����܂߁A�����邱�Ƃ��l����̂������w�v�Ɠ��䋳���B�u�����̖��͏����ł͖����B�l�ԂɊS�������A�Ⴂ��������w���̂��x�ɂ��čl���Ăق����v m3.com�@2012�N3��23�� |
||||
| �⑰�P�A�Ɂu�Տ��@���t�v�c�q�t��m���֗{���u�� | ||||
| �@���������������҂�⑰�ւ̐S�̃P�A���s���@���҂̗{���Ȃǂ�ڎw���u���H�@���w��t�u���v���A���k��ɐݒu���ꂽ�B �@�����A�_���A�L���X�g���Ȃǂ̒c�̂̊�t���A�R�N�ԊJ�u����B���ɊW�����@���I�ȐS�̃P�A����I�Ɉ����u���͍�����ł͏��߂āB �@�����{��k�Ќ�A�q�t��m���炪���S�ƂȂ��āu�S�̑��k���v�����A�Ƒ���S��������Ў҂���b�������𑱂��Ă����B�@���I�Ȓ�����}�邽�߁A�����ǂ𓌖k��ɒu�������ŁA�J�u����邱�ƂɂȂ����B�����́A��؊�|(������)�E���啶�w�������i�@���w�j�����C�B�y�����́A�w�O����V���ɂQ�l�̌����҂��������B �@�@���҂�Ώۂɍu�K����J�ÁB�⑰��̘b���p����A�@����M�ɑ���n��Z���̍l���܂����ڂ����Ȃǂ��w��ł��炢�A���҂ƈ⑰�̔Y�݂ɓ�����u�Տ��@���t�v����Ă�B �@���w���̑�w���A��w�@�������ɂ́u�Տ������w�v�u���Ə@���S���v�Ȃǂ��u�`�B�u�S�̑��k���v�����ň�t�̉��������̉��f�ɓ��s���A�I�����̊��҃P�A�ɐG�����K���s���v�悾�B �@�C�O�̕a�@�ł́A���҂���b�����E�ҁi�`���v�����j�����邪�A�����ł͈ꕔ�̕a�@�ɂƂǂ܂�B��؋����́u�@���̈Ⴂ�����`�ŏ@���҂��ւ��S�̃P�A�̂������͍��������v�Ƙb���Ă���B m3.com�@2012�N4��5�� |
||||
|
�I�s�I�C�h�n��̓K���g�p ���҂̔w�i�ɓK���������E�틦���̃e�[���[���[�h���Â����z |
||||
| ���V����w�����Ȋw�E�y�C���N���j�b�N�u���@��� ��q �� �@�ߔN�C�u�Ɋ��҂͑����̈�r�����ǂ�C���҂̔N��C�����K���C���������C�Љ�A�ւ̗v�]�Ȃǂ̃o�b�N�O���E���h���ʂɍl��������ŁC�ȕւœK���u�Ɋɘa���Â����߂��Ă���B�I�s�I�C�h�n��Ɋւ��ẮC�K���E�ˑ����⒆�Ő��Ȃǂɑ���뜜�Ƃ������v���ɂ��C�킪���͋ߔN�܂ŊC�O�Ɣ�ׂ��u�ɂɑ��铊�^�ɂ͏��ɓI�ł��������C�ŋ߂͐V������܂̓o��Ȃǂɂ��͕ω�������B���V����w�����Ȋw�E�y�C���N���j�b�N�u���̈�։�q��C�y�����ɁC����̔��u�ɂɑ���I�s�I�C�h�n��𒆐S�ɓK�Ȗ��Ð헪�ɂ��ĕ������B �I�s�I�C�h�͗L���Ȏ��ÑI���� �@�Ö@�́C�ł���ʓI�Ȓɂ݂̎��Ö@�ł���C�y�C���N���j�b�N��`�O�ȁC�ɘa�P�A�ȂȂǂŕ��L���s���Ă���B���N���j�b�N�ł́C�_�o�u���b�N�Ȃǂ̐��I�Ȏ��Â̌��ʂ����߂邽�߂ɖÖ@���s���邱�Ƃ��������C�ɂ݂̒��x��Ǐ�ɂ���Ă͖Ö@�����I���ƂȂ邱�Ƃ�����B���ɖ�ɂ̓I�s�I�C�h�n���ɖ�Ɣ�I�s�I�C�h�n���ɖ���B �@�I�s�I�C�h�͐��̓��̃I�s�I�C�h��e�̂Ƃ������Ɋ֘A�����ƌ��ѕt���C�]��Ґ��Ȃǂ̒����_�o�ɂ�����ɂ݂̊��o��݂点�邱�ƂŒɂ݂�}���鐬���ł���B�I�s�I�C�h�n��́C�����ڂ̋����ɂ���āC���I�s�I�C�h�Ǝ�I�s�I�C�h�ɕ��ނ���邪�C���u�ɂɗp������̂́C���I�s�I�C�h�̃����q�l�i�A���J���C�h�n�I�s�I�C�h�j��t�F���^�j���i�����I�s�I�C�h�j�C��I�s�I�C�h�̃R�f�C���Ȃǂł������B �@�ߔN�C��I�s�I�C�h�̃u�v���m���t�B���\�t���g���}�h�[��/�A�Z�g�A�~�m�t�F���z���܂��ی��K�p�ƂȂ�C�I���̕����L�����Ă���B �@�]���C���{�͔����u�ɂɑ���I�s�I�C�h�n��̎g�p�ɑ��ĉ��Ăɔ�ׂċɒ[�ɏ��ɓI�ł������B�������Ǐ��u�ɏnj�Q�iCRPS�j�ɑ�����{�C�č��C�h�C�c�̖�g�p�������i�g���}�h�[��/�A�Z�g�A�~�m�t�F���z����s�O�j�ł́C���I���̑�1�ʂ͂��������X�e���C�h�R���ǖ�iNSAIDs�j�����Ăł�50���ȏ�C�h�C�c�ł͖�40���ŁC���I�s�I�C�h�͕č�15���C�h�C�c23���C��I�s�I�C�h�͕č�19���C�h�C�c11���ɑ��C���{�ł͋��I�s�I�C�h��2���݂̂ł������B �@���I���ł��C���I�s�I�C�h�͕č�31���C�h�C�c18���C��I�s�I�C�h�͕č�26���C�h�C�c18���ɑ��C���{�ł͎�I�s�I�C�h2���C���I�s�I�C�h7���ł������B �@�I�s�I�C�h�n��͎g�p�̏K�����▃�ł��뜜����C�����ł͎g�p���}���I�ƂȂ��Ă���Ǝv���邪�C�g�p�ʁE���ԁE�S���Љ�I�w�i��L���銳�҂ɑ���K���Ȃǂ����C�������p������X�N�͉���ł���B �@���C�y�����́u���܂�g�p�ɗ}���I�ɂȂ�߂����C�Ǐ�ɂ�葼�̖Ö@��_�o�u���b�N�C�^���Ö@�ȂǂƂƂ��Ɏ��Ö@�̑I������1�ƍl����悢�v�Ǝw�E����B ���u�ɂ̎��Â�QOL�EADL�̉��P����ڕW�� �@����C�č��ȂǂŃI�s�I�C�h�n��̏����������̂́C�����u�ɂɑ��鐢�E�ی��@�ցiWHO�j�O�i�K���Ƀ��_�[�̉e��������ƍl������B�������C���C�y�����́u���u�ɂɑ��āC�y�x�̒ɂ݂͔�I�s�I�C�h�C�y�x�`�����x�̒ɂ݂͎�I�s�I�C�h�C�����x�`���x�̒ɂ݂͋��I�s�I�C�h�Ƃ������C�����u�ɂƓ��l�̏��������ׂẴP�[�X�ɓK�p����̂͌�����l�������Ǝv���v�ƌx����炷�B �@���҂ƈقȂ�C���u�Ɋ��҂͒ɂ݂̊ɘa�ɂ�葁���̎Љ�A���ʂ����C���̌�������Ԃɂ킽��ɂ݂̔����ȑO�Ɠ��l�̊�������ۂ������Ɗ�]����P�[�X�������B���̂��߁C�ɂ݂̎��Â�QOL����퐶������iADL�j�����P�����C�������������邱�Ƃ���ڕW�ɑg�ݗ��Ă�K�v������B �@���ẤC���҂̔N��C�����K���C���������C�Љ�A�ւ̗v�]�Ȃǂ̃o�b�N�O���E���h���ʂɍl�����C�K�Ȑf�f�ƕ]���̉��Ɏ��{���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ö@�ł���C�g�p�����܂̍�p�@���Ɗ��҂̃o�b�N�O���E���h���ł��邾�����m�Ƀ}�b�`���O������B�Ȃ��Ȃ��ɂ݂̎��Ȃ������u�ɂɑ��ẮC�Ǐ�ɂ���Ă͒ɂ݂Ə��ɕt�������菕��������`�ʼn�����邱�Ƃ��d�v�ł���B �@����C�y�����́u�ɂ݂͎�ꂽ���CQOL��ADL���ቺ������{���]�|�B���҂̐����╹���ǂɉe����^���Ȃ����x�Ŗ�܂��g�p���邱�Ƃ���v�Ƌ�������B ����������Љ�A��̐����K�����\���ɍl��������ܑI���� �@���u�ɂɑ���Ö@�ɂ̓I�s�I�C�h�n��̂ق��CNSAIDs�C�s�����n���ɖ�C��s�����n���ɖ�Ƃ�������I�s�I�C�h�n���ɖ�ȂǁC�Ǐ�ɂ�肳�܂��܂Ȏ�ނ̖�܂��g�p����Ă���B���ǂȂǂ��N�Q��e���u�ɂ̏ꍇ�́CNSAIDs���s�����n���ɖ�̃A�Z�g�A�~�m�t�F������ɗp������B�������CNSAIDs�ɂ͕���p�Ƃ��Đt��Q���\��������C�t�����̊��҂ɂ͎g�p�ł��Ȃ��B�܂��C�A�Z�g�A�~�m�t�F�����̏�Q���ɂ͎g�p�ł��Ȃ��B �@����C�����ɂ⒆���_�o�u�ɂȂǐ_�o��Q�����u�ɂɂ́C�]�������ɍ�p���Ēɂ݂�a�炰��R����C�����̒ɂ݂ȂǂɌ��ʂ̂���R�Ă��̂ق��CNMDA��e�̝h�R��P�^�~����R�s�����h�J�C���Ȃǂ��p������B���̂ق��C�����_�o�ɍ�p���郏�N�V�j�A�E�C���X�ڎ�Ɠe���ǔ畆���o�t�ܗL���܂�C�ߔN��s���ꂽ�v���K�o�����Ȃǂ��悭�p�����Ă���B�������C�����̖�܂ɂ̓��N�V�j�A�E�C���X�ڎ�Ɠe���ǔ畆���o�t�ܗL���܂������Ė��C�Ȃǂ̕���p��������̂������C�Љ�A��C�^���ƂȂǎԂ̉^�]�Ɩ��ɒ����ԏ]�������N�҂ɂ͐T�d�Ɏg�p����K�v������B �@�����̖�܂Ō��ʂ����Ȃ��ꍇ��C����p�╹�������Ȃǂ̎���Ŏg�p�ł��Ȃ��ꍇ�C���͂Ȓ��ɍ�p��L����I�s�I�C�h�n��͗L���ȑI�����ƂȂ�C���ɋ}���u�ɂɑ��Ă͑��������F�߂���B����ɏǏ�ɂ��_��ɗp�ʂ�ς��ď����ł��C�t�Ő��E�̓Ő����Ȃ��C���͊��҂�S������L���銳�҂ɂ��g�p�ł���B �@�������C�ˑ��ǁC���łȂǂ̃��X�N��C�֔�C���C�Ȃǂ̕���p�����݂��C���Ɍ��ʂɂ��l��������B�����ɎЉ�A����]�����N�҂ɂ͗L���Ȉ��i�ł��邪�C�K������h�~���邽�߁C�����̍��p�ʓ��^�������Ȃǂ̔z�����K�v�ƂȂ�B�܂��C�����u�ɂ̏ꍇ�C���҂�QOL��ADL�Ƃ̃o�����X���l�����C�I�s�I�C�h�n��Œɂ݂����ׂĊɘa����̂ł͂Ȃ����������ɘa���邱�ƂŖڕW��B������ꍇ������B �@�I�s�I�C�h�n�����������ꍇ�́C�܂��ˑ��ǁE���łȂǂ̃��X�N�̏��Ȃ���I�s�I�C�h����g�p���C����Ō��ʂ��\���ȏꍇ�͋��I�s�I�C�h�ֈڍs���Ȃ����Ƃ��I������1�ł���B���̓_�Ŏ�I�s�I�C�h�̃g���}�h�[��/�A�Z�g�A�~�m�t�F���z���܂�u�v���m���t�B���\�t��̏�s�́C���Â̕����L�����Ƃ�����B �Z���Ԃ̃��j�^�����O�Ŋ��ҌX�̎��ÓK�������� �@��܂̌��ʂ́C�ɂ݂̎�ށi�N�Q��e���u�ɁC�_�o��Q���u�ɁC�S�����u�ɂȂǁj�ɂ��قȂ�C�����̒ɂ݂����G�ɗ��ݍ����������u�ɂ����݂���B �@���C�y�����́u�ɂ݂̎��Âɂ����ẮC�����̎��Ö@���܂�g�ݍ��킹�������I�Ȏ��Â��s�����Ƃ��L�p�Ȃ��Ƃ������C2�T�Ԓ��x�̃��j�^�����O�ɂ��ɂ݂̌�����Ǐ�C���ҌX�̃o�b�N�O���E���h�Ǝ��Ö@�Ƃ̑����Ȃǂ���������ƌ����邱�Ƃ��K�v�ł���B���̂��߂ɂ́C���Ȃ̈�t�⑼�̈�Ï]���ҁC�X�^�b�t�Ƃ̑��E��A�g�E�����ɂ��C���@�O����̓��^����c�������Ö@�����邱�Ƃ���ŁC�y�C���Z���^�[�̐ݒu�Ȃǂ̍H�v���K�v�B�Љ�A��ڎw�������u�Ɋ��҂ɑ��āC��N�ҁC����҂ɂ�����炸�s����e�[���[���[�h�^��Â����z�ł���v�ƒ��߂��������B * ꎓ��m�i�ق�. �����u�ɂɑ�����Â𒆐S�Ƃ������Î��Ԓ����`���{�C�č��C�h�C�c�̔�r. Phama Medica 2010; 28�i2�j: 137-148. ���f�B�J���g���r���[���@2012�N4��26�� |
||||
|
�S���a�������A�u�K�v�v�����F�m�x�Ⴍ �I�����K�C�h���C���A����ւ̕��y�i�܂� |
||||
| �@�I�����K�C�h���C���͕K�v�����A�m���Ă�����̂����p���Ă�����̂��Ȃ��\�B�S���{�a�@����i�S���a�j���a�@�Ȃǂ�ΏۂɎ��{���������ŁA�I�����K�C�h���C�������y���Ă��Ȃ����Ԃ����炩�ɂȂ����B �@�S���a��2011�N�x�A�a�@����ی��{�݂Ȃǂ�ΏۂɃA���P�[�g�����{�B���̂����a�@�i427�J���j�A���V�l�����{�݁i325�J���j�A���V�l�ی��{�݁i200�J���j�A���×{�^�V�l�ی��{�݁i32�J���j�A�O���[�v�z�[���i638�J���j�A�K��Ō�X�e�[�V�����i319�J���j�̍��v1941�J��������i�����27���j�B�����ɁA�e�{�݂ɏ�������E���i��t�A�Ō�t�A���m�Ȃǁj�A���҂̉Ƒ��ɑ��Ă��A���P�[�g���s���A�E��7869�l�A�Ƒ�5215�l������i�������22���A15���j�B �@�I�����K�C�h���C���̕K�v���ɂ��Ď{�݂��Ƃɕ������Ƃ���A�u���������������v�Ɠ������̂́A�a�@�i409�J���j��62.8���A���ی��{�݁i546�J���j��73.4���A�O���[�v�z�[���i625�J���j��71.4���A�K��Ō�X�e�[�V�����i318�J���j��67.6���B��Â���̌���ōL���I�����̃K�C�h���C�������߂��Ă�����Ԃ����炩�ɂȂ����B �@�ː��s���a�@�i�x�R���j�̌ċz��O���Ȃǂ����������ƂȂ�A�W�w���ђc�̂͑������ŏI�����K�C�h���C���������B06�N�ɂ͓��{�W�����È�w��u�W�����Âɂ�����d�NJ��҂̖�����Â̂�����ɂ��Ă̊����v���A07�N�ɂ͌����J���Ȃ��u�I������Â̌���v���Z�X�Ɋւ���K�C�h���C���v�\�B���̌�����{��t�����{�~�}��w��A�S���a�Ȃǂ��I�����ɂ��ăK�C�h���C�������肵���B �@�������A�����̃K�C�h���C������Â���̌���ɂ͕��y���Ă��Ȃ��B�����̏I�����K�C�h���C����m���Ă��邩�A�E���ɕ������Ƃ���A�u�m���Ă���K�C�h���C���͓��ɂȂ��v�Ɠ������̂́A�a�@�E���i1870�l�j��64.1���A���V�l�����{�ݐE���i1347�l�j��74.3���A���V�l�ی��{�ݐE���i812�l�j��75.5���A���×{�^�V���E���i149�l�j��75.6���A�O���[�v�z�[���E���i2348�l�j��79.9���A�K��Ō�X�e�[�V�����E���i1326�l�j��68.2���ɏ�����B���J�Ȃ̃K�C�h���C���̔F�m�x�͔�r�I�����������̂́A�u�m���Ă���v�͕̂a�@�E���i1870�l�j��19.6�����ō��������B �@�I�����K�C�h���C���̗��p���Ԃ��ƁA�u���p���Ă�����̂͂Ȃ��v�Ɖ����̂́A�a�@�i408�J���j��66.7���A���ی��{�݁i536�J���j��47.2���A�O���[�v�z�[���i613�J���j��52.5���A�K��Ō�X�e�[�V�����i310�J���j��63.9���B�I�����K�C�h���C�������������Ă��A����ł̔F�m�͐i�܂��A���p������Ă��Ȃ����Ƃ������ꂽ�B �@�܂��A�I�����K�C�h���C���ɖ��L���ׂ�������E���i7852�l�j�ɕ������Ƃ���A�u�ӎv�m�F�ł��Ȃ��ꍇ�̑Ή��v��64.7���ƍł������A�����Łu�{�l�̈ӎv�m�F�̕��@�v�Ɠ��������̂�50.6���ɏ�����B�Ⴆ�Ό��J�Ȃ̃K�C�h���C���ł́A������̎����ɂ��Ă��G����Ă��邱�Ƃ���A���ݎ��̂̔F�m���i�߂Ό���̃K�C�h���C�������p�����\��������B �@����s�S��x���Ȃǂ̔�������������҂ɂ��ẮA�{�ݑ��ƉƑ����̏I�����Ɋւ���F���̃Y�����傫�����Ƃ����炩�ɂȂ����B�{�݂ɓ����Ă��銳�҂ɂ��āA�{�݂ƉƑ����ꂼ��ɏI�������Ǝv�����ǂ��������Ƃ���A���ł́A�{�݂��I�������Ǝv���Ă��銳�ҁi120�l�j�̂����A�Ƒ����I�������Ǝv���Ă����̂�90.8���B����ɑ��Ĕ���ł́A�{�݂��I�������Ǝv���Ă��銳�ҁi148�l�j�̂����A�Ƒ����I�������Ǝv���Ă����̂�79.7���B����ł́A���ɔ�ׂďI�����̗\��\����������ƂȂǂ���A�F���̃Y�����傫���Ȃ����̂ł͂Ȃ����ƍl������B �@���̒��������́A���J�Ȃ�2011�N�x�V�l�ی����Ɛ��i��⏕���őS���a���s�����u�I�����̑Ή��Ɨ��z�̊Ŏ��Ɋւ�����Ԕc���y�уK�C�h���C�����̂�����̒��������v�B�ڍׂ͑S���{�a�@����̃E�F�u�T�C�g�Ō��J����Ă���B ���o���f�B�J���I�����C���@2012�N4��26�� |
||||
| �f�f������̊ɘa�P�A��-����J�� | ||||
| �@��������i��{�v����āA�ɘa�P�A�Ɋւ����̓I�{����c�_���邽�߂́u�ɘa�P�A���i������v�̏����25���ɊJ���ꂽ�B��ł́A���f�f������ɘa�P�A����邱�Ƃ̏d�v�����A�����̈ψ�����w�E���ꂽ�B�c�_�̃X�P�W���[���ł́A�Z���I�Ȏ{��ɂ��Ă͗��N�x�\�Z�Ăɔ��f�����A�ɘa�P�A�`�[���̔z�u�⋳��Ȃǒ������I�ȉۑ�́A�f�Õ�V�⋒�_�a�@�̂�����Ȃǂ��������ċc�_�����邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�����ɂ͉ԉ���Y���i�i�q���������a�@���_�@���j���I�o���ꂽ�B �@�����҂Ƃ��̉Ƒ����ł�����莿�̍��������𑗂邽�߂ɂ́A�f�f������̊ɘa�P�A��A�f�f�A���ÁA�ݑ��Â̊e��ʂł̐�ڂȂ��ɘa�P�A���{�����߂���B����œ��{�ł͖����A�u�Ɋɘa�ɗp�������×p����̏���ʂ͏��Ȃ��A�����݂̂Ȃ炸��ÊW�҂̊Ԃł��A�ɘa�P�A�ɑ��鐳�����������i��ł��Ȃ��̂����B �@���������w�i���Č�����ł͍���̘_�_�Ƃ��āA���f�Ñ̐����f�Â̎�������̐�--�����ɋc�_��i�߂邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�f�Ñ̐��ł͊ɘa�P�A�ւ̃A�N�Z�X�̉��P����̂�����A�ɘa�P�A�`�[���ȂNJe�E��̓K���z�u��A�g�ɂ��ċc�_����B�f�Â̎��ł́A�����҂̐S��ւ̔z�����f�Âւ̊ɘa�P�A�̑g�ݓ�������g�̓I��Ɋɘa�̂��߂̖�g�p�����_�I��ɂ��܂߂���Ɋɘa--�Ȃǂ����荞�܂ꂽ�B �@�f�B�X�J�b�V�����ł́A�f�Ñ��A���ґ�\�o���̈ψ�����u���̐f�f������̊ɘa�P�A�̕K�v���v���������ꂽ�B����ɑ��Ă����E���N���i�ۂ̗я���ے��⍲���u�f�f������ѐf�f�v���Z�X�̒i�K����A�����Ɋ��ҕ��S���y�����邩�́A������{�@�̗��@���_�ɂ��܂܂��L�[���[�h���B���Ђ���������ŋc�_���Ăق����v�Ɖ������B �@����J���ψ��i���l�s�암�a�@��ܕ����j�́u�ݑ��Âɂ������×p����̓K���g�p���l����ƁA���ЂƂ��ی���ǂ��������A�g�̂�������c�_�ɉ����Ăق����v�Ɨv�������B �@�c�_�S�̂̃X�P�W���[���Ɋւ������ǂ́A�u���N�x���Ɏ��{�ł����Ă͂ǂ�ǂ��Ă��Ăق����v�Ɨv�]���A���N�x�\�Z�ɔ��f��������Z���I�ȋc�_�ƁA�Q�N��̐f�Õ�V�⍡��̋���Ȃǒ������I�Ɏ��g�ގ{��ƕ����ċc�_��i�߂邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B �@����ȍ~�̉�c�ł́A�P�c��R��ł̊��������h�Ƀq�A�����O�Ȃǂ����{���A��̓I�{��̒ɂȂ��Ă����B m3.com�@2012�N4��27�� |
||||
| �č��ł�18�̖�4�l��1�l���I�s�I�C�h�g�p�o������ | ||||
| �@�ď����E�W�F���_�[��������Sean Esteban McCabe����́C�č���18�̍��Z����ΏۂƂ����C��������ɂ��I�s�I�C�h�i�����I�s�I�C�h�j�̎g�p�o�����B�S�Ă̍��Z���̂��悻4�l��1�l�ɓ�����22.3���������I�s�I�C�h���g�p�����o��������Ƃ̐��茋�ʂ������ꂽ�iArch Pediatr Adolesc Med 2012�N5��7���I�����C���Łj�B�ŋ߁C�č��ł͎�N�҂̏����I�s�I�C�h�̖��ŗႪ�����C�Љ���ƂȂ��Ă���B�S�ċK�͂ō��Z���̏����I�s�I�C�h�g�p�o�������������̂͂��ꂪ���߂Ă��Ƃ����B ��ÖړI�̎g�p�o����17.6�� �@�����I�s�I�C�h�͓K���Ȏg�p�ɂ��C�}�����邢�͖����u�ɂɋ��͂Ȍ��ʂ������McCabe����B�č��ł́C2000�N���납�瓯�m��������̒��ɂȂǂɂ��p�����Ă���B����̎�N�҂ւ̏����@��͌��݁C1994�N�̖�2�{�ɂ܂ő����Ă���Ƃ̃f�[�^������悤���B����ɔ����C��ÊO�ړI�̏����I�s�I�C�h�g�p�inonmedical use of prescription opioids�FNMUPO�j�����㏸�CNMUPO�ɂ��21�Ζ����̎�҂̋~�}�O����f��4�N�Ԃ�2�{�ɑ������Ă���Ƃ����B �@������͑S�Ă̖g�p�ƌ��N�Ɋւ��钲���iNational Survey on Drug Use and Health�j�����{�B2008�`09�N�̖��N�t�C18�̊w����ΏۂƂ������ȋL�����̃A���P�[�g�œ���ꂽ7,374�l���̉���͂����B �@���̌��ʁC18�̍��Z���̂��悻17.6������ÖړI�̏����I�s�I�C�h���g�p�������Ƃ����邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B����CNMUPO�̊�����12.9���C��ÖړI���ۂ�����Ȃ��ꍇ�C22.3���̎g�p�o��������Ɛ��肳�ꂽ�B �@��ÖړI���ۂ����킸�C�g�p�o���̊����ɒj���̍��͂قƂ�ǂȂ��������C�l��ʂ̌������甒�l�ł̓A�t���J�n�č��l�܂��̓q�X�p�j�b�N�ɔ�ׁu�g�p�o���Ȃ��v���L�ӂɒႭ�C��ÖړI���邢��NMUPO�̎g�p�o�����������l�̊����͗L�ӂɍ����X�����m�F���ꂽ�B �@NMUPO��ł́C����������ȑO�Ɉ�ÖړI�̏����I�s�I�C�h���g�p�����o�����������B�܂��C��ÖړI�݂̂̎g�p�o������̐l�ɔ�ׁC�����g�p�̃��X�N�����債�Ă����Ƃ����B �@������͕č���18�̍��Z���̂��悻4�l��1�l����ÖړI���ۂ��ɂ�����炸�C�����I�s�I�C�h�̎g�p�o�����������ƌ��_�B��N�҂ɏ������ꂽ�I�s�I�C�h�̗ʂ␔���\���l���̏�C���NMUPO�ւ̈ڍs�����炷���ߒ��Ӑ[���ώ@���ׂ��ƍl�@���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N5��8�� |
||||
| ��26��D�y�~�G����Z�~�i�[�@�q���������҂Ɏx���� | ||||
| �@�ߔN�C�咰����������Ȃǂł�40�`60�Α�Ɣ�r�I��N�̜늳�҂��������Ă���B�`���C���h�E���C�t�E�X�y�V�����X�g�iCLS�j�ŁC�k�C����w�a�@��ᇃZ���^�[�̓��䂠���ݎ��́C�q���������҂̎x�������ɂ��ĕB�u�q��Đ���̂��҂̑������C�q���ɂǂ�������������悢�̂��Y��ł���C���������e�q�o���ւ̎x�������߂��Ă���v�Əq�ׂ��B �m�炳��Ȃ��ƕs����X�g���X�� �@CLS�Ƃ́C�a�C�̎q���C�a�C�̐e�����q���_�E�S���Љ�I�ɉ�������l�ŁC1950�N��ɕč��Œa�������B���ݍ�����25�l�C�S���E�Ŗ�4,000�l����������B���䎁�͓��@�̊ɘa�P�A�`�[���ɏ������C����̏������C���Ê��C�I������ʂ��āC�q���������҂���̑��k�ɉ����Ă���B �@�č��ł́C�e������ɂȂ����ꍇ�C�q���ɂƂ��ėL�v�ȏ��Ƃ��āC�i1�j�a�C�͂���Ƃ������O�iCancer�j�i2�j����͓`�����Ȃ��inot Catchy�j�i3�j����ɂȂ����̂͒N�̂����ł��Ȃ��inot Caused�j�`��3C���l�����Ă���BCLS�́C��@�I�ȏɂ����Ă��q�����u�͂̂��鑶�݁v�ƂƂ炦�C�q��������̗͂��ł���悤�x������Ƃ����B �@�����ɂ��ƁC�e�ٕ̈ςɂ��āC���Ƃ��c���ł������������Ă���C���̎������~�߂�͂�����B�q���́C�m�炳��Ȃ��Ƃ̂��҂ɂ��ꂽ�Ɗ����C�����Ύ��ۈȏ�Ɉ������Ԃ�z�����C�����̂����Őe���a�C�ɂȂ����Ǝv���B�s����X�g���X���C�s���C�H�~�s�U�C�s�o�Z�Ƃ��ĕ\�ʉ����邱�Ƃ�����B �s�A�T�|�[�g�̃T��������2��J�� �@�e���q���ɕa�C�ɂ��Ęb���Ƃ��́C�q���̔N���ɉ����ė������₷�����t���g���C�w�����ȏ�ł͐g�̐}�Ȃǂ��Q�Ƃ���Ƃ悢�B���O�ɓ`���������e���������C���������Ęb����^�C�~���O�ƐÂ��ȏꏊ��I�ԁB�W���͂��r�ꂽ��x�e���C�q���������p���ɂȂ�܂ő҂B �@�q�������S�ł��邽�߂ɂ́C�w�����܂ł͐e�Ƃ̃X�L���V�b�v���d�v�ɂȂ�B�e�̓��@�Ȃǂ̕ω��������Ă��C���ɓ��c���ł́C�e���Ȃǂ��玙��Ǝ����s���ē��퐶����������x�ۂ���邱�Ƃ��]�܂����B�v�t���ł́C�e�̕ω��Ɍ˘f���Ȃ�����e���C�������R�ƐU�镑���X��������C���������ɂ��钇�Ԃ̑��݂���������鏕���ɂȂ�B �@���䎁��͍�N5���ɁC�s�A�T�|�[�g�̈�Ƃ��āC�u�킩�J�t�F�v�Ƃ����q��Đ���̂��҂̂��߂̃T�������X�^�[�g�������B������2�E4���j���̌ߌ�2�`4���ɊJ�Â��C30�`50�Α�̏����𒆐S��7�`8�l�O��̎Q��������B�܂��C�e�̌������ɗ����q���̌ʃP�A�⓯�������̎q�����m���𗬂ł���������Ȃǂ̎x���������s���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N5��10�� |
||||
| �č��z�X�s�X�{�����e�B�A�Ŋ��̂Ƃ��܂� | ||||
| �����W�߂���⑰�̃P�A�܂� �@���������߂��ɂ���z�X�s�X�̌���B���{�ł͂܂������ꂽ�C���[�W�����邩������Ȃ��B�����A�z�X�s�X��i���A�����J�ł́A�����̎s�����{�����e�B�A�Ƃ��Ċւ���Ă���B �@�A�����J�A�G�b�O�n�[�o�[�^�E���ɂ���A�g�����e�B�z�X�s�X�ł́A�{�����e�B�A���d�v�Ȗ�����S���Ă���B �@�����̓��e�́A���҂̖K��A�N�ɐ���̃C�x���g�̏����A�����W�߂ȂǁB�܂����l���A�ߗׂ̈⑰�̂��Ƃ�K�ˁA�O���[�t�T�|�[�g������B�Q������{�����e�B�A�́A�O���[�v���Ƃɐ��I�Ȍ��C����B �@�挎�A�{�����e�B�A�̕\�������s���A����܂�3000���Ԉȏ㊈�����Ă���145�l�ɋL�O�i������ꂽ�B ��Ȃ̂͊��҂ւ̌h�ӂƖ��邳 �@�Ȃ��ł����҂̖K��ɂ͈�Ԃ�肪����������Ƃ����{�����e�B�A�������B10�N�ɓn�芈�����Ă����n���[�h����i81�j�͂����B �u�z�X�s�X�Ƃ����Ă��A�������ɂ��Ęb���Ă���킯�ł͂���܂���B���҂���Ɖ̂�����A�F������A�Ƒ��̂��Ƃ�b�����肵�Ă��܂��B����Ȏ��Ԃ����ꂵ���āA���̊Ԃɂ��A���̂ق������҂���ɉ�����Ă����ɒʂ��悤�ɂȂ��Ă��܂����B��Ȃ̂͊��҂���Ɍh�ӂ������āA�����Ă˂ɖ��邭�ڂ��邱�Ƃł��v�B �Ŋ��ɂЂƌ��������� �@�{�����e�B�A�����҂̎��ɗ��������P�[�X�������B�R�[�f�B�l�[�^�[�̃z�y����́A���̂Ƃ���������A�������犳�҂Ɍ��t�������Ăق����Ƙb���B �u���t����������A���҂���͍Ŋ��Ɏ����̂��Ƃ��C�ɂ����Đ��b�����Ă��ꂽ�l�������ɂ��邱�ƂɋC�Â��܂��B���ꂾ���̂��Ƃł���������A���炩�ɖ���ɂ����Ƃ��ł���̂ł��v�B �`�����e�B�j���[�X�@2012�N5��14�� |
||||
| ���m��̓�����ׁ@��t�Ə\���Ȉӎv�a�ʂ� | ||||
| �@����Ɛf�f����Ĉ�t���獐�m����ƁA���h���Ă���ɂ�������炸�A�a��₻�̌�̎��Â̑I���Ȃǂ����X�ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������悭������Ȃ��܂܂�������A�����������Ƃ������Ȃ������肷��A���������s���͕��B �@���������Z���^�[���a�@ �i��t���j�̏��쒩���E�Տ��J���Z���^�[�����i���_��ᇊw�j�͂��̂� 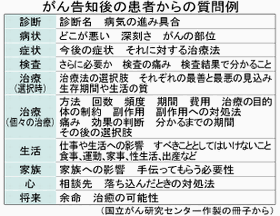 �ǁA���҂ƉƑ��̂��߁A�悭���鎿������ڂ��Ƃɐ��������u�d�v�Ȗʒk�ɂ̂��܂�銳�҂���Ƃ��Ƒ��ցv�i�}�j���E�F�u�T�C�g�ihttp://pod.ncc.go.jp �j�Ō��J���A���p���Ăъ|���Ă���B �ǁA���҂ƉƑ��̂��߁A�悭���鎿������ڂ��Ƃɐ��������u�d�v�Ȗʒk�ɂ̂��܂�銳�҂���Ƃ��Ƒ��ցv�i�}�j���E�F�u�T�C�g�ihttp://pod.ncc.go.jp �j�Ō��J���A���p���Ăъ|���Ă���B�@���m�������҂̒����Łu�ق��̊��҂��ǂ�Ȏ��������̂��m�肽���v�u����q�˂���悢�̂�������Ȃ��v�Ȃǂ̋^�₪�o���ꂽ�̂ɉ����A�ɘa�P�A�̐i��ł���O���̐��Ȃǂ��Q�l�ɍ쐬�����B �@���⍀�ڂ́u�ǂ̂��炢�[���ł����v�Ƃ������u�a��ɂ��āv�A�u�ǂ�Ȏ��Ö@������܂����v�u�����ǂ╛��p�́v�Ƃ������u���Âɂ��āv�A�u�d���ւ̉e���v�u���Ă͂����Ȃ����Ƃ͂���܂����v�Ƃ������u�����ɂ��āv�Ȃǂ̂P�O���ڌv�T�R��B �@�厡��Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����𑣂����Ƃ�ړI�ɂ��Ă���A���m��̖ʒk�ň�t���������鏇���ɂقډ����Ă��邽�߁A�ʒk�O�Ƀ`�F�b�N���Ă����ĕ����R�炵��h�����Ƃ��ł���B �@���삳��ɂ��ƁA���Ҏ��g���m��ׂ����ƁA���߂邱�Ƃ���������A�d�����S���s���◎�����݂������B�Ƒ��ɂ��Y�݂�ł��������Ȃ����Ƃ͒N�ɂ�����B�u�S�̂炳���Ȃ����͎̂��ÂƓ������炢��B����ǂ��Ƃ��͐��Ƃɑ��k���v�Ɗ��߂Ă���B 47NEWS ��ÐV���I�@2012�N5��22�� |
||||
|
�����[�u�́u���~�v�ł���t�Ɛ� ���}�h�c�A�A�������@�Ăœ�Ă�� |
||||
| �@���}�h�őg�D����u�������@�������l����c���A���v�i��E���q�P�F����}�Q�c�@�c���j��6��6���̑���ŁA�u�I�����̈�Âɂ����銳�҂̈ӎv�̑��d�Ɋւ���@���āi���́j�v�ɂ��āA��̈Ă����\�����B �@���ĂƂ��A�I�����ɂ��銳�҂̈ӎv�d���邽�߂ɁA�����[�u�Ɋւ���ӎv���肪�ł��邱�Ƃ�@���Œ�߂�ƂƂ��ɁA�@������߂�����ɍ��v�����Ή���������t��Ɛӂ��邱�Ƃ��ړI�B �@���Ă̑���͂��̑Ώۂɂ���B�����[�u�́A�i1�j�����[�u���J�n���Ȃ��ꍇ�i�s�J�n�j�A�i2�j�l�H�ċz��̎��O���ȂǁA���ɍs���Ă��鉄�����Â𒆎~�����ꍇ�\�\���l������B���N3���Ɍ��\�������Ăł́A�O�҂Ɍ����Ă������A�i2�j���Ώۂɉ�����Ă��V���ɏo���ꂽ�B�܂�����ȊO�̕������A3���̌��Ă���ꕔ�C�����ꂽ�B �@6���̑���ł́A���{��t��Ɠ��{�ٌ�m�A����ւ̃q�A�����O���s��ꂽ���A������̒c�̂���������_�ł́A�������̖@�����ɂ��Ďx���͓����Ȃ������B �@���㕛��̉H���c�r���́A�u�����[�u�̕s�J�n������Ώۂɂ��邾���ł͕s�\���ł���A�����[�u�̒��~����������_�͐i�������v�Ƃ������̂́A�u��������@���ŋK�肷�邱�Ƃɂ��A��t�Ɗ��҂̐M���W�Ɋ�Â�����܂ł���Ă�������ɍ������������˂Ȃ��B�@������O�ꂽ�Ή��������ꍇ�ɁA�@���ɑ����Ă��Ȃ��Ƃ���A��t���ӔC�Njy����邱�Ƃ��������Č��O�����v�Ƃ̍l�����������B����ɁA�����[�u�̒�`����Î҂̊Ԃł��K���������m�ł͂Ȃ���A�����J���Ȃ�e�w��̏I������ÂɊւ���K�C�h���C�������y���Ă���Ƃ͌�������ƁA����Ŋ��ґ��ɂ����Ă����r���O�E�E�B�����Z�����Ă���Ƃ͌����Ȃ����Ƃ���A����ɐT�d�ȋc�_���K�v���Ƃ����B �@���٘A�l���i��ψ���ψ����̑��q�l�����́A�u�������̖@�����ɔ��v�Ɩ����B���̗��R�Ƃ��āA�u���҂̎��Ȍ��茠�́A�������Â̏�ʂő��d�����ׂ��ł���A�����I�����Ɍ�����̂ł͂Ȃ��B�������A���͊��ґS�ʂ̎��Ȍ��茠��ۏႷ��@���͂Ȃ��B�����ۏႷ��@�������A�I�����ɂ����鎩�Ȍ��茠���������o���Ė@��������Ӗ��͂Ȃ��v�Əq�ׁA�u���҂̌����@�v�u��Ê�{�@�v�̂悤�Ȉ�ÑS�ʂɂ킽��@������邱�Ƃ��������߂���Ƃ����B �@�����c�ł́A��Q�Ҋ֘A�̒c�̂ɑ���q�A�����O���s�����A��Q�Ҋ֘A�c�̂��������̖@�����ɂ͔����Ă���A������c�_�̓�q���\�z�����B���q��͍Ō�ɁA�u�ّ��͔����A�����I�ȗ�������ŁA�c�����@��ڎw�������v�ƈ��A�B��c��A�u�������������Ȃ���A������ւ̖@�Ē�o�͓���B�������A��������������A���߂č��̋c�A�̋c���̔C�������O�ɂ͖@�Ă��o�������v�ƃR�����g�A�܂�6���̓�Ă̂�������̗p���邩�́A����̋c�_����ł���Ƃ��Ă���B �u�I�����v��2�l�ȏ�̈�t�����f �@�������̖@�����́A���{����������Ȃǂ��x�����Ă�����̂��B6���Ɍ��\���ꂽ��ẮA�O�q�̂悤�ɖ@���̑Ώۂ��u�����[�u�̕s�J�n�v�݂̂Ƃ��邩�A�u�����[�u�̒��~�v�������邩�ňقȂ�B �@�ȉ��A���ʕ���������ƁA�u�I�����v�́A�u���҂��A���a�ɂ��čs�����邷�ׂĂ̓K�Ȉ�Ï�̑[�u�i�h�{�⋋�̏��u���̑��̐������ێ����邽�߂̑[�u���܂ށj�����ꍇ�ł����Ă��A�̉\�����Ȃ��A���������ԋ߂ł���Ɣ��肳�ꂽ��Ԃɂ�����ԁv�ƒ�`�B �@�I������ÂɊւ��銳�҂̈ӎv����͂����܂Łu�C�Ӂv�B��Q�Ғc�̂Ȃǂ��猜�O�̐����オ���Ă������Ƃ���A�u�������ێ����邽�߂̑[�u��K�v�Ƃ����Q�ғ��̑������Q���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɗ��ӂ��Ȃ�������Ȃ��v�Ɩ��L���Ă���B�܂��A����n�������c�̂ɑ��āA�I������ÂɊւ���[���ȂǂɕK�v�Ȏ{����u����悤���߂Ă���B �@�����[�u�́u�s�J�n�v���邢�́u���~�v���ł�������́A�i1�j���҂�����̈ӎv�����ʓ��ŕ\���A�i2�j�u�I�����v�̔���́A�厡����܂�2�l�ȏ�̈�t���s���\�\�ȂǁB�܂��u�s�J�n�v���邢�́u���~�v�̈ӎv�́A���ł��P��ł���Ƃ��Ă���B �@���̏��������A��t�������[�u�́u�s�J�n�v���邢�́u���~�v�̂����ꍇ�A�u������A�Y���エ��эs����̐ӔC�i�ߗ��ɌW����̂��܂ށj�͖���Ȃ����̂Ƃ���v�ƋK�肵�Ă���B �@6���̑���ł͏o�ȋc������A�u��t���Ɛӂ��������ɊY�����邩�ǂ������A�ォ�猾�������ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��̂��v�Ƃ̎��₪�o���ꂽ�B����ɑ��A�c�@�@���ǂ́A�u�ǂ�Ȗ@���ł��A���̗v���ɊY�����邩�ǂ����������邱�Ƃ͂��蓾��v�Ƃ��A����̖@���Ăł����l���Ƃ����B���㕛��̉H���c�����A���ɖ@�������肳���A�u�����I�ɂ́A�\���ɐ������āA���ӏ������A�Ή����Ă������ƂɂȂ邾�낤�v�Ƃ̍l�����q�ׂ��B m3.com�@2012�N6��7�� |
||||
|
��109����{���Ȋw�� ���Ȉオ���g�ނׂ��ۑ��� |
||||
| �@���s�s�ŊJ���ꂽ��109����{���Ȋw���C����̑���e�[�}�Ɠ���^�C�g���̃p�l���f�B�X�J�b�V�����u���Ȋw�̎g���ƒ���v�k�i�������C�Z�F�a�@�i���{�j�E���V�C���@���l�̖͗l���Љ��B�����O�̈�Â⎀���ςɑ��w�̐[���e���҂���́C�v���C�}���P�A��\�h�����̏d�v�����w�E����C���v���O�����̑_���ł���21���I�̈�w�ɂ�������Ȋw�̎g���C���Ȉ�̎��g�ނׂ��ۑ�ƍ���̒�����l�����ƂȂ����B �����Ă̐��ɉ����鐽�ӂ�����ȗՏ��� �@��ʈ�ÂƏI����Â����H���Ă���C��̉Ԑf�Ï��i���挧�j�̓��i�i�@���́C���҂́u�����āv�̐����������C�Տ��͌͊����Ȃ��Ƃ��C��t�ɂƂ��Ắu���Ӂv�����Ղł���Ƃ����l�����������B�܂��C���������Ƃ������ȗՏ������H���邱�ƁC���_�I�P�A���w�Ԃ��ƂȂǁC���Ȑf�Âɋ��߂��邱�Ƃ�����B �@���҂ɑ���m����t�̗�V���������ォ��C���m�����R�̎���ɕς��C���@���́u�ǂ��炪�������̂��v�Ǝ��⎩���������Ƃ�����Ƃ����B�����āC�u�����̊��҂Əo����ŁC�g�ǂ��炪���������h�Ƃ����₢���������Ǝv���悤�ɂȂ����B���m�^�m�����łȂ��C�a�@���^�ݑ�C�����^���ÂȂǂ̑o�������̂��̂�2��1�ł���C��Î҂����ߕt������C�����t�����肷����̂ł͂Ȃ��B�ǂ���ł����Ă��鐽�ӂ���t�ɂ͕K�v�ƍl����悤�ɂȂ����v�Əq�ׂ��B �@�܂��C���ȗՏ��̐i���ɂ���čݑ�Őf�邱�Ƃ̂ł���͈͂��L�܂������ŁC����͕a�@�E�{�ݖ����̏��J�o�[����ݑ��ÂƃP�A�̔��W�����҂����Ƃ����ق��C���ȗՏ��̂��܂��܂ȗv�f���֗^���Ă��镪��Ƃ��āC���@�����g���I����Â��������B �@�I�����Ɛg�̈�Â̊֘A�͔����ƍl�����������C�������⍂�J���V�E�����ǂւ̑Ή��ȂǁC�u�͎̂��̂Ƃ��܂ŋx�܂Ȃ��B�g���������Ƃ������ȗՏ��h�����H���邱�Ƃ���v�Əq�ׂ��ق��C���҂��p�j�b�N�Ɋׂ�̂͐��_�Ȉオ�Ζ����Ă��鎞�ԂƂ͌���Ȃ����߁C�x�b�h�T�C�h�ɂ�����Ȉオ���ҁE�Ƒ��̐S�̃P�A�𗝉�����K�v�����w�E���C���_��w���w�Ԃ��Ƃ𐄏������B�Ȃ��C�I����ÂɌ��炸�C�������ۂ͔��Ό�Ő������Ă��邱�Ƃ�m��i�z�C�^�ċC�C�ێ�^�r���C�����_�o�^�������_�o�C���]�^��]�Ȃǁj�C�z���I�X�^�[�V�X�Ƃ͉������ӎ����Ċ��҂Ɍ����������Ƃ͓��ȗՏ��ɂƂ��čł��̗v�Ȃ��Ƃ��Ɛ������B �@���@���͂���ɁC���Ȑf�ÂƂ��Ă̏I����Â̂��ꂩ��̏h��Ƃ��āC�����Տ��̌��������ᑂ̓K���̍čl�C���K���̐��܂����Ö�̊J���Ȃǂ�]�ނƂƂ��ɁC�u���҂̏����Ă̐����������C�Տ��͌͊����Ȃ��B�w���̂�������x�w�тق���unlearn�����H���C�X�̊��҂ɍ�������Â���Ă������Ƃ���ƂȂ�v�Əq�ׂ��B ���Ǝ��̊ԂɘV�ƕa�������������̐l�����f���čl�� �@�@���w�҂̎R�ܓN�Y���i�����ۓ��{���������Z���^�[�����j�́C�l��50�N�̎���ɂ́u���v�Ɓu���v��������d�́u�����ρv��N�����������Ă������C���҂̊ԂɁu�V�v�Ɓu�a�v�����荞��ł����l��80�N����̐l�����f���͎�T���Ԃɂ���Ǝw�E�B���݂̘V�l�I������Â͒���������C���������Ƃ��D�悳���X���ɂ���̂ł͂Ɩ���N�����B �@���q���������ǂ̂悤�ɐ����C�ǂ������}���邩�|�Ƃ������Ƃɂ��čl���邱�Ƃ͏d�v�ł���B �@��30�N�قǑO�܂ŁC�̊��I�ȕ��ώ����͂ق�50�N�ł���C�����́u�����ρv�Ƃ����l�����f�����m�łƂ��đ��݂����B�������C���̒Z���Ԃɐl��80�N�̒����Љ�ƂȂ�C���Ǝ��̊ԂɁC�u�V�v�Ɓu�a�v�Ƃ�����肪���荞��ł������ƂŁC������Љ�C�����Ĉ�w���Ή��ł��Ȃ��ɂȂ��Ă���Ƃ͂����Ȃ����B �@�������g�C20�Α�ɏ\��w����ᇂ̎�p���C40�Α�ōēx�f���E����������C���̌�C���݂�80�Α�܂Ō����Âɖ���������ꂽ�o�������B�u��Â̏d�v���͕������Ă���B�����C���݂̑����̍���҂��ǂ̂悤�ɍŊ����}���Ă���̂����l����ƁC���������邱�ƁE���������Ƃ��D�悳��Ă���悤�ȋC������v�ƂƂƂƌ�����B �@�܂����C�w�剝������������ÂƂ������ȁ`�u���R���v�̂����߁x�i�����m�ꎁ�j���x�X�g�Z���[�ƂȂ��Ă���悤�ɁC�剝���ɑ��Đ��ݓI�v���������Ă���w�͏��Ȃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����|�Ǝ���̌o������b���n�߂��B �@40�Α�ɏ\��w����ᇂ��Ĕ������Ƃ��C1�T�Ԃ̐�H���w�����ꂽ���C�u5���ڂɒn���̋Q�슴���o�������C6���ڂɂ͋Q�슴�������C�����͂�����オ���Ă���̌��������B�����E���q����̑m���͎������߂Â��ƁC����f�H���s�����Ƃ����L�^�����邪�C�g��킭�͉Ԃ̂��Ƃɂďt���Ȃ�@���̔@���̖]���̂���h�Ɖr��ŁC���̒ʂ�Ɏ������}�������s�͌v��I�f�H�������s�����̂ł͂ƍl����悤�ɂȂ����B���Ǝ��̊ԂɁC�V�ƕa���͂т����Ă������ŁC���s�I�Ȓf�H�����Ƃ����\���ɏ����S�������Ă���������v�Ɖ��Ɍ�肩�����B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N6��7�� |
||||
| ���S�O�A�S�Ђ̐e�E����u���}���v�c�S�����̌� | ||||
| �@����ł݂Ƃ�ꂽ���҂̖�S�����A�S���Ȃ�O�A���łɂ��Ȃ��e�̎p�������ƌ��ȂǁA������u���}���v�̌��������A���ꂪ���₩�Ȃ݂Ƃ�ɂȂ����Ă���Ƃ̒����������A�{�錧�Ȃǂōݑ��Â��s���Ă����t��̃O���[�v���܂Ƃ߂��B �@�ݑ�f�Â��s����t���w�����҂炪�Q�O�P�P�N�A�{�錧�T�����ƕ������P�����̐f�Ï��ɂ��K��f�ÂȂǂʼnƑ����݂Ƃ����⑰�P�P�X�P�l�ɃA���P�[�g�����B �@�u���҂��A���l�ɂ͌����Ȃ��l�̑��݂╗�i�ɂ��Č�����B���邢�́A�����Ă���A�������Ă���A�����Ă���悤�������v����q�˂��B�҂T�S�P�l�̂����A�Q�Q�U�l�i�S�Q���j���u�o�������v�Ɠ������B �@���҂������������ƌ�������e�́A�e�Ȃǁu���łɎ������Ă����l���v�i�T�P���j���ł����������B���̏�ɂ��Ȃ��͂��̐l�╧�A���Ȃǂ̓������������B �@�u���}���v��̌�������A���҂͎��ɑ���s�����a�炮�悤�Ɍ�����ꍇ�������A�{�l�ɂƂ��āu�ǂ������v�Ƃ̍m��I�]�����S�V���ƁA�ے�I�]���P�X�����������B �@�����́A�����Ȋw�Ȃ̌����������Ď��{�B�u���}���v�̌��͌o���I�ɂ͂悭����邪�A�w�p�I�ȕ͂���߂Ē������B �@���������o�[�ł���ݑ��Â̐���A�������E���k���w���Տ������́u�w���}���x�̌�����荇����Ƒ��́A���₩�Ȃ݂Ƃ肪�ł���B���Ƃ����o��ϑz�ł����Ă��A�{�l�ƉƑ�������������̌��ۂƂ��ĕ]������ׂ����v�Ƙb���Ă���B m3.com�@2012�N6��21�� |
||||
| �ɘa�P�A�@�u�����v����u�����邱�Ƃ��x����v�� | ||||
| �R�����e�[�^�[ �\�a�c�s�������a�@ ���ƊǗ��� �b��g�a �� �@�����{�l�̎��S�����̑�1�ʂɂȂ����̂�1981�N�ł��邪�C����ȍ~������ɂ�鎀�S�Ґ��͑����̈�r�����ǂ��Ă���B���݁C���{�l��2�l��1�l�͂���ɜ늳���C3�l��1�l�͂���Ŏ��S����Ƃ����Ă���B����͔]������S�؍[�ǂ̂悤�ɋ}�����鎾���ł͂Ȃ��C�����͈����Ԃ��o�Ĉ������C���w�Ö@�Ȃǂ̗L���Ȏ��Î�i���s����I�������}���Ď��S����B���̂��߁C�u�ɂȂǂ̏Ǐ�̃R���g���[����ړI�Ƃ���I�����ɘa�P�A���ɂ߂ďd�v�ɂȂ�B���N�̃��C�t���[�N�Ƃ��Ă���̏I������ÂɎ��g��ł����\�a�c�s�������a�@�i�X���j���b��g�a���i�O�@���C�����ƊǗ��ҁj�ɁC�v���C�}���P�A�ɂ�����ɘa�P�A�ɂ��ĕ������B �ɘa�P�A�̌��_�̓z�X�s�^���e�B�[ �@���҂��������Ă��邱�Ƃւ̑�Ƃ��āC2007�N�Ɍ����J���Ȃ́u������{�@�v���{�s���C���̒��Ŋɘa�P�A�̕��y�������ł��o�����B����ɂ���āC�S���e�n�̒n�悪��f�ØA�g���_�a�@�Ŋɘa�P�A���C��Ȃǂ�����Ɏ��{�����悤�ɂȂ�C�Q���������Ƃ̂���v���C�}���P�A������Ȃ��Ȃ��Ǝv����B�������C����ɂ��ɘa�P�A�����y�����邩�Ƃ����ƁC�b�쎁�́u�܂��܂������͂����Ȃ��̂�����v�ƌ����B�u�u�ɃR���g���[���Ȃǂ̒m����Z�p�͑����g�ɕt�����Ƃ�����t�͑����̂��낤���C����͊ɘa�P�A�̕\�w�I�ȕ����B�ɘa�P�A��{���ɒ���̂ł���C�����Ɛ[�����O���w�Ԃ��Ƃ��厖�v�Ɠ����͎w�E����B �@�m���Ɋɘa�P�A�Ƃ����ƁC��ʓI�ɃC���[�W�����̂��u�ɃR���g���[���ŁC�Ⴆ�Δ�I�s�I�C�h���ɖ��I�s�I�C�h�̎g�����Ƃ��������Ƃł���B�������C���������m����Z�p���K�v�ł��낤���C�������C�����g�ɕt���������ł͊ɘa�P�A���w���ƂɂȂ�Ȃ��C�Ɠ����͌����B�ł́C�������w�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ɘa�P�A�̗��O�Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��B�����́u�ɘa�P�A�̌��_�̓z�X�s�^���e�B�[�i�����݁C�v�����C�D�����C�����ĂȂ��C���Y���j�ł���C��Â̌��_���̂��̂ł���v�Ƃ��C���̊�{���O�Ƃ��āi1�j1�l1�l�̐l�Ԃ̐��������x����i2�j�y�ɐ����邱�Ƃ��x����i3�j�Ƒ�����҂��x����i4�j�`�[���Ŏx����|��4������Ƃ���B �����̎��̌����ړI�Ƃ�����Âւ̓]�� �u1�l1�l�̐l�Ԃ̐��������x����v�Ƃ́C����Ȃ炪��Ƃ����a�������ɖڂ�������̂ł͂Ȃ��C���̕a���������Ă���l���g���ҁh�ł͂Ȃ������Ɠ����g�l�ԁh�Ƃ��đΉ����C���̕a�������邱�ƂŋN���鐶����̕s�ւ��Ȃǂ��ł��邾�����Ȃ����邱�Ƃ��C��ÓI�Ȏ��_�ŁC�{�l�Ƃ̑��k�̏�őΉ����邱�Ƃ��Ӗ�����B �u�y�ɐ����邱�Ƃ��x����v�Ƃ́C�ǂ̂悤�ȕa��ł���C�\�Ȍ��肳�܂��܂ȋ�ɂ���菜���C�y�ɐ���S���ł���悤�Ɏx�����邱�Ƃ��Ӗ�����B���̂��߂ɂ́C�a��Ɋւ�����C�����Č������Ȃ����Ƃ�ۏ���̐��Â���C�ݑ�P�A�ɂ����鐶���x���̐��̐����Ȃǂ��d�v�ɂȂ��Ă���B �u�Ƒ�����҂��x����v�Ƃ́C���҂Ɠ��l�ɑ傫�ȕs���C��Y�C��ɂ������Ă���Ƒ����P�A���邱�Ƃ��Ӗ�����B�������ĉƑ��ƈꏏ�ɃP�A�����Ă����̐�����邱�ƂŁC�Ƒ��ɂ��łƂ���\�ɂ�����B �u�`�[���Ŏx����v�Ƃ́C��t�C�Ō�t�C��t�Ȃǂ̈�ÐE�C����уP�A�}�l�W���[�C�w���p�[�Ȃǂ̉��E���C���ꂼ��̎��_�Ŋ��Җ{�l��Ƒ��̃j�[�Y��c��������ŁC�A�g���ĕK�v�Ȏx������邱�Ƃ������B �@�b�쎁�ɂ��Ɓu����܂ł̓��{�̈�ẤC�������������Ƃ�ړI�ɁC���N��ڕW�Ƃ��āC�a�@���S�ɔ��B���Ă����v�B�������C���̍l�����ł́C����̏I�����̂悤�Ɏ��Î�i���s�����Ƃ���ł́C���͂�\���ȑΉ������Ȃ��Ȃ�B�����ŁC�����́u���ꂩ��͐����̎��̌����ړI�ɁC������ڕW�Ƃ��āC�����̏�𒆐S�Ƃ�����Âɓ]�����Ă����K�v������v�ƌ����B �@�Ȃ��C�ȏ�̂悤�ȍl�����́C��������̏I�����ɂ������Ă͂܂�킯�ł͂Ȃ��B����Ƃ����͖̂���������1�ŁC�S�Ă̖��������́C�₪�Ă͎��Î�i�̐s����I�������}����B���Ƃ���C�ɘa�P�A�̗��O�̎���Ẫp���_�C���V�t�g�́C�S�Ă̖��������ɓ��Ă͂܂�ƌ����Ă悢���낤�B�u���ꂩ��܂��܂����{�̒�����Љ�͐i�W���Ă������C����͎���Ȃ����������l�������Ȃ��Ă�������Ƃ�����B���̂悤�Ȏ���Ɍ����ẮC�ǂ����Ă��������߂̈�Â��琶�����x�����Âւ̕����]�����K�v�ŁC���ꂪ�ɘa�P�A�̗��O�ł���Ƃ�����v�Ɠ����B �ɘa�P�A�̒S����Ƃ��Ẵv���C�}���P�A �@�ɘa�P�A�������̏�𒆐S�Ƃ�����ÂłȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����C�v���C�}���P�A�͂܂��ɂ��̏�ł���Ƃ�����B�u����܂ł��C�ɘa�P�A�����܂������Ă����́C�������̂���a�@�����C���ߍׂ����ݑ�P�A���s���Ă���v���C�}���P�A�ł��邱�Ƃ����������v���b�쎁�B�u���ꂩ��̊ɘa�P�A�̒S����Ƃ��ẮC�ނ���C�v���C�}���P�A����������ɂȂ�ׂ��v�Ƃ�����B �@����f�Â̒S����Ƃ��Ẵv���C�}���P�A��́C�a�@�Ζ���ɑ��āC����̃A�h�o���e�[�W�������Ă���B�܂��C�v���C�}���P�A��͓����납�犳�҂Ɛe�����ڂ��C���̐����K����E�ƁC�Ƒ����Ȃǂ�m���Ă��邽�߁C����̃��X�N�����ς���₷���B�����āC���X�N�������Ƃ��ɂ͌��f�E���������߂₷���C���҂ɂ�������₷���B�܂��C����ɜ늳�����ꍇ�ɍ��m����]���邩�ǂ����Ƃ������b���C�v���C�}���P�A��Ȃ�C�ǂ������������Ď��������邱�Ƃ��ł���B �@���҂ɂ��������ꂽ�ꍇ���C�����ǂ╹���ǂȂǂɂ��Ă悭�m���Ă���̂̓v���C�}���P�A��ł���B���������āC�u�v���C�}���P�A��͊��҂�����̐���ɏЉ��ɂ��Ă��C�S�Ă��ς˂�̂ł͂Ȃ��C�ł��邾�������������悤�ɂ��ׂ��v�Ɠ����B�u�������ɂƂ��Ă��C�v���C�}���P�A�ォ��̏��͋M�d�v�ƌ����B �@�������̉��Ŏ��Â��s���Ă���Ԃ́C�ł��邾���o�߂�c�����C���҂Ɛ���Ƃ̋��n�����߂�B���҂Ɛ��ゾ�����ƁC���҂͐���ɉ������ĕ����������Ƃ������Ȃ��Ƃ������Ƃ����邪�C�v���C�}���P�A�����ĂȂ�C���ꂪ�ł���B�܂��C���҂̉Ƒ����v���C�}���P�A��ɂȂ�C�����Ƒ��k���₷���B�u���҂ƉƑ��ɂƂ��āC�ł��s����������C�܂��C���ꂪ��������Ȃ��ƈ�Õs�M�ɂ��ׂ点���˂Ȃ��̂��C��Âւ̃A�N�Z�X���r�₦�邱�ƁB�����h���Ӗ��ł̃v���C�}���P�A��̖����͑傫���v�Ɠ����B �ݑ�P�A�ɕK�{�̃`�[����� �@����̉��ł̂��Â��I�������́C�������v���C�}���P�A�オ��Â̒��S�ɂȂ邪�C���̍ۂ��u�ɂ��͂��ߌċz����C�q�C�E�q�f�̃R���g���[���ȂǁC�ɘa�P�A�̋�̓I�Ȓm����Z�p���K�v�ɂȂ��Ă���B �@�v���C�}���P�A�ł��҂̊ɘa�P�A���s���悤�ɂȂ�ƁC�ǂ����Ă��������Ȃ��̂��ݑ�P�A�ł���B�������C1�l�̃v���C�}���P�A��̍s����ݑ�P�A�ɂ͌��肪����B�����ŁC�Ō�t�C�P�[�X���[�J�[�C�P�A�}�l�W���[�C�w���p�[�ȂǂƂ̘A�g���d�v�ɂȂ�B�b�쎁�̌o���ł́u���Ɋɘa�P�A�ɏK�n�����Ō�t�C�P�A�}�l�W���[�ƃ^�b�O��g�ނ��Ƃ��ł���C��t�̕��S�͑傫���y�������v�ƌ����B �u�ɘa�P�A�ł́C�ŏI�I�ɂ͊��҂̎����łƂ邱�ƂɂȂ�̂ŁC�����炢���Ƃ��肪�C���[�W���ꂪ���B�������C���̈���ŁC�u���҂̐��������x�����v�Ƃ����[����������C�܂��C���҂̐���������w�Ԃ��Ƃ������B���L���v���C�}���P�A�オ�C�{���̊ɘa�P�A��m��C���H���Ă���邱�Ƃ�]�݂����v�Ɠ����͌��B SUMMARY �@�ɘa�P�A�̌��_�̓z�X�s�^���e�B�[�ł���C��Â̌��_�ł��� �@�ɘa�P�A�̊�{���O�Ƃ��āC�i1�j1�l1�l�̐l�Ԃ̐��������x����i2�j�y�ɐ����邱�Ƃ��x����i3�j�Ƒ�����҂��x����i4�j�`�[���Ŏx����|��4���������� �u������Áv����u�����邱�Ƃ��x�����Áv�ւ̓]���Ƃ����ɘa�P�A�̗��O�́C����̈�ÑS�ʂɕK�v�ȃp���_�C���V�t�g�ł����� �@�ɘa�P�A�̒S����̎���ɂȂ�ׂ��C�v���C�}���P�A��͂��܂��܂ȃA�h�o���e�[�W��L���Ă��� ���f�B�J���g���r���[���@2012�N6��28�� |
||||
|
�f�f�����玡�ÏI����������P�A ��17����{�ɘa��Êw��J�� |
||||
| �@��17����{�ɘa��Êw�6��22�|23���C�_�ˍ��ۓW���ꑼ�ŊJ�Â��ꂽ�B�u��Î҂ɂł��邱�Ƃ́C���҂ɊS�������C���Y�������邱�Ɓv�ƍu���Ō���������������i���R���w�@�j�̂��ƁC�u�Ђ낭�@�ӂ����@�������v�Ƃ������e�[�}���f�����C�����̉��肪���\���ꂽ�B�{���ł́C�T�o�C�o�[�V�b�v�ƁC��������̊ɘa�P�A���c�_���ꂽ�v���O�����̂��悤�����B ��������������̎��ォ�玟�̎���� ���������� �@���҂ƈ�Î҂������d��ɕ��p�l���f�B�X�J�b�V�����u�T�o�C�o�[�V�b�v�Ƃ����l�����\�\���Â��I���Ă�����@�Ђ낭�@�ӂ����@�������v�i���������H�����ەa�@�E�R���p�q���j�ł́C�܂�MD�A���_�[�\������Z���^�[��Lewis Foxhall�����C����T�o�C�o�[��QOL�����߂邽�߂ɓ��@�Ŏ��{���Ă���u�T�o�C�o�[�V�b�v�N���j�b�N�v�ɂ��Ĕ��\�����B�����ł́C�Ĕ��h�~�𒆐S�Ƃ������҂ւ̃P�A�����łȂ��C�v���C�}���E�P�A���Ō�t�C�\�[�V�������[�J�[�ւ̋�����s���Ă���B�܂��C���ǂ⎡�ÂɊւ��錤�������Ƃ����B���́C����T�o�C�o�[�V�b�v�͂���̎��Ð��т⊳�҂�QOL�����߂�V�����삾�Ƃ��C��w�̔��W�Ɋ��҂����B �@����T�o�C�o�[�̗��ꂩ��́C����Ȃ��ݎ��iNPO�@�lHOPE�v���W�F�N�g�j�Ə����C�ꎁ�iTBS�e���r�j���o�d�B�܂����䎁�͎��g�̌o������C����Ɛf�f���ꂽ���҂́C�a�ɂȂ�ȑO�ɂ��������܂��܂Ȗ�����r�����邱�Ƃɂ���āC���g�̍����I�ȑ��݂������X�s���`���A���Ȓɂ݂������Ă���Ɛ����B�Q�Ȃ�����Î҂Ɍ����āC���҂̐����������Ɏx�����Ăق����Ƒi�����B����ŁC���������ɂ݂͎����̐�����Ӗ���₢�Ȃ������߂̋M�d�ȃL�����T�[�M�t�g�ł�����ƁC�O�����Ȍ������������B �@�����Ĕ��������������́C����T�o�C�o�[�͈�Î҂ɂƂ��āg���������ȏ��h�ł���Ƌ����B���́C����̍Ĕ����^���Ď�f�����a�@�ŁC������摗��ɂ���C�����s���ƕs�M���������o������C���҂̕s���������ł���菜���ɂ͑������f�̌����E��p���d�v�Ƃ̍l�����������B�܂��C���҂̌o���k�ɂ͎��É��P�̃q���g����������Ǝ咣���C���҂̐��Ɏ����X����悤��Î҂ɋ��߂��B �@��Î҂̗��ꂩ��͎O�����o�d�B������Ǖa�@�̊Ō�t�ł���]���b�q���́C���@�Ŏ��g��ł���T�o�C�o�[�V�b�v�P�A�v���O�����ɂ��Ĕ��\�����B���ғ��m���݂��̑̌�����荇������C�a�⎡�Âɂ��Ċw�Ԃ��ƂŁC���S���Ď��ÂɑO�����ɗՂނ悤�ɂȂ����Əq�ׂ��B �@��t�̉��R���j���i�����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�j�́C���ɂ͊��҂������̉Ƒ��̂ق��������s��������Ă���ꍇ������Ǝw�E�B���Z���^�[���݂����s�A�T�|�[�^�[�ɂ�鑊�k���C���҂�Ƒ�����炤�T�����Ȃǂ̎��g�݂ɂ��ĕ����B �@�Ō�ɓ�����̐���ł���R�����́C�u���҂炵���ł͂Ȃ��C���Ȃ��炵���v�Ƃ������b�Z�[�W��`���C�G�r�f���X�����łȂ����҈�l�ЂƂ�̃i���e�B�u�Ɋ�Â������Â��s�����Ƃ��Ă����B �@���̌�̃f�B�X�J�b�V�����ł́C����T�o�C�o�[�ł����Î҂ł�����Q���҂���C�u��Î҂͂��܂��ɂ���T�o�C�o�[����Ís�ׂ̑ΏۂƂ������Ă��Ȃ��X��������B��Î҂̍l����g�ǂ��g�g�݁h�Ɋ��҂���������ł͂��Ȃ����v�Ƃ�������N���Ȃ��ꂽ�B����ɑ��R�����́C����͈�Î҂Ɗ��҂Ƃ����Η��ł͂Ȃ��C�o�����ЂƂɂȂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��������C���̂��߂ɂ͈�Î҂����҂̏A�J���Ɋ֗^����ȂNj�̓I�ȃA�N�V�����v���������s���Ă����K�v������Əq�ׂ��B ��������̊ɘa�P�A������ �@WHO�̐V��`�i2002�N�j�Łu��������̊ɘa�P�A�v��搂��Ă���10�N�C���̋@�^�����X�ɍ��܂����B2012�N�x����̐V���ȁu��������i��{�v��v�ɂ����Ắu����Ɛf�f���ꂽ�Ƃ�����̊ɘa�P�A�̐��i�v���d�_�ۑ�̂ЂƂƂ���C�ɘa�P�A���C�̐��̌�������̐��̐�����}�邱�Ƃ��ʖڕW�Ƃ��Ė��L���ꂽ�B �@�܂��C�O�ɂ����ẮC���҂�QOL�Ɋւ���_�����N�X�������Ă���B���ł��S���W�߂��̂́C�]�ڐ��זE�x�����҂ɑ��鑁���ɘa�P�A�����̌��ʂ�������Jennifer S. Temel����̘_�����iN Engl J Med. 2010�mPMID: 20818875�n�j�B���w��ł́C�}�T�`���[�Z�b�c�����a�@����Z���^�[�ɂ�����Temel���ƂƂ��Ɏx���Ö@�����O���[�v�𗦂���William Pirl�������ق��C�u���ƃp�l���f�B�X�J�b�V��������悳�ꂽ�B �@�C���^�[�i�V���i�����N�`���[�u��������̊ɘa��Áv�ɂ�����Pirl���́C�u�ɘa��Â͐ϋɓI���Âƃz�X�s�X�̊Ԃ̃M���b�v���ǂ����߂�̂��H�v�Ɩ���N�B���f���P�[�X�Ƃ��āC�Ō�t�ɂ��d�b�J�E���Z�����O�ɂ��������̂�ENABLE�v���W�F�N�g�iJAMA.2009�mPMID: 19690306�n�j�̂ق��C�O�q�̘_���̌����f�U�C��������B���̌����ł́C�V���ɓ]�ڐ��זE�x���Ɛf�f���ꂽ����151�l���u���̕W�����Áv�Q�Ɓu���̕W�����Á{�����ɘa�P�A�v�Q�ɖ���ׂɐU�蕪���C�O�҂͊��ҁE�Ƒ����ᇓ��Ȉ�̗v�]���������ꍇ�̂݁C��҂͌��ɍŒ�1�x�͊ɘa�P�A�オ����B���̌��ʁC�ꎟ�G���h�|�C���g�ł���12�T�ڂ�QOL�ω��ɂ����ẮC�����ɘa�P�A�Q�̂ق����L�ӂ�QOL���ǍD�������B�܂��G���h�|�C���g�Ƃ��āC�����ɘa�P�A�Q�ɂ����ė}���Ǐ��P�����ق��C�������Ԃ̉����܂ł����F�߂�ꂽ�Ƃ����B �@���^�����ł́C�u�Ȃ������ɘa�P�A�ɂ���Đ������Ԃ����т��̂��v�Ƃ����_�Ɏ��₪�W�������BPirl���́u�i���̌����f�U�C���Łj���̗��R�܂ł͂킩��Ȃ��v�ƑO�u�����C�����ɘa�P�A�Q�ł͏I�����ɂ����ĉ��w�Ö@�𒆎~���鎞���������X���ɂ���C���̂��Ƃ��������Ԃ̉����Ɋ�^�����Ƃ���������B�܂�����ŁC�����̌��ʂɂ���œ_�Ă�ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ��q�ׁCQOL���P���������d�v�Ȍ��ʂł���Ƌ��������B�Ȃ����ݑ��̓]�ڐ��x�����������ɂ����ē��l�̌������i�s���Əq�ׁC����Ȃ�m���̏W�ςɊ��҂����B �@�����p�l���f�B�X�J�b�V�����u����Ɛf�f���ꂽ������̊ɘa�P�A�̎��H�̂��߂Ɂ\�\���ÂƊɘa�P�A�̗����v�i������JA���m�a�@�E�]���O�Y���C���R���w�@�E�����r�`���j�ł́CPirl���Ɠ��{�̉���6�l�����{�݂ɂ����鑁���ɘa�P�A�̎��g�݂�BPirl������ᇓ��Ȉ�Ƃ̖��ڂȘA�g�ɂ��O���ɘa�P�A�̎��݂��Љ���ق��C���{����͉@�O��ǂƂ̕����Ō�t�ɂ�鎿�⎆�X�N���[�j���O�Ȃǂ̎��g�݂����ꂽ�B �T����w�E�V�� ��2986�� 2012�N7��16�� |
||||
|
��54����{�V�N��w��J�� �u������Љ�ɂ�����V�N��w�v���e�[�}�� |
||||
| �@��54����{�V�N��w�6��28�|30���ɁC��댚�O��i�����j�̂��ƁC�u������Љ�ɂ�����V�N��w�v���e�[�}�ɁC�������ۃt�H�[�����ɂĊJ�Â��ꂽ�B �@�I������ԂɎ��������҂�O�ɁC�����őP�̈�Â���уP�A�ɂȂ�̂���Y�ޏ�ʂ͑����C��t�̊Ԃł��ӌ��̈�v�͓����Ă��Ȃ��B�V���|�W�E���u����҂̏I������Â��߂��鏔���\�\���ꂩ��̏I������Â͂ǂ�����ׂ����H�v�i�i�����������Ì����Z���^�[�E�����p�r���C���k��E��ލF���j�ł́C�I�����̍���҂ɑ���őP�̈�Â���уP�A�݂̍�����c�_���ꂽ�B �V���|�W�E���̂��悤 �@�܂��������q�㎁�i��ʌ��F�m�ǃO���[�v�z�[���E���K�͑��@�\���c���юЉ���@�l�T���j�Ə���z�ꎁ�i���k��j���C�I�����ɂ�����ߏ��E�ߏ�Ȉ�ÂƃP�A�Ɋւ��čl�@�����B �@�������́C���{�݁E�O���[�v�z�[���̌o�c�ҁC�Ǘ��ҁC�X�^�b�t��Ώۂɍs�����A���P�[�g���ʂ��Љ���B�u�ߏ��^�ߏ�Ȉ�Ís�ׂɂȂ�w�i�v�Ƃ��āC����𗝗R�Ɉ�Î҂⊳�҉Ƒ������Â��T���邱�ƂŁu�ߏ��v�ƂȂ�P�[�X��C���҂̈�w�I�m���s���ɂ���Î҂̑�����������Ă��܂��u�ߏ�v�ƂȂ�P�[�X��������ꂽ�Ƃ����B���́C�X�̊��҂ɍ������I������Â��������邽�߂ɁC��ÎҁC���҉Ƒ��C���X�^�b�t�Ԃ̏��̋��L���𑣐i����K�v����i�����B �@�܂��C�a�@�Ζ���̗��ꂩ�甭���������⎁�́C���g�̌o������u�Q�����肩�F�m�ǂ̍���҂ɑ���o�ljh�{�͉ߏ�Ȉ�Ís�ׁv�Ƃ̌������������B���̗��R�Ƃ��āC�{�l�̈ӎv�ł͂Ȃ��Ƒ��̗v���ɂ���Ď{�s�����P�[�X�������_��C���{�ɂ��1�N�������������Ȃ����Ƃɉ����C���̊Ԃ������ǂɑ���R�ۖÂ��J��Ԃ��s���C�ŏI�I�ɂ͔x���Ȃǂ̏d�ĂȊ����ǂɂ�鎀�S�������_���������B ��Îҁ|���ҊԂō��ӌ`����}�邱�Ƃ��d�v �@�剪�N�O���i�F�{���w�@�j�́C��Î҂ƈ�ʎs���́u���v�Ȏ��Áv�̑������̑���Ɋւ��钲�����ʂ��Љ���B���v�������ƂȂ鎡�Â̎��{�ɂ͈�t������ʎs���̂ق����m��I�ł���C�܂���t���a�Ԃ╛��p�Ƃ�������w�I������QOL���d���������ŁC��ʎs���͉Ƒ��̈ӌ���[���E�����Ƃ������S���I���v���d������X�����F�߂�ꂽ�Ǝw�E�B���ҁE�Ƒ��̏I�����̈ӎv����ɂ����ẮC����o��������Î҂̈ӌ����d�v�Ȕ��f�ޗ��ɂȂ邱�Ƃ���C�u��ʎs���ւ̌[�����s���C�Љ�œK�ȏI������Âɑ��闝����[�߁C��Î҂ƈ�ʎs���̍��ӌ`����}��w�͂����߂���v�ƌ�����B �@�u�I�������҂̈ӎv����ɕK�v�Ȃ��Ƃ́C���Җ{�l�ɂƂ��Ă̍őP��T�邱�Ɓv�Ƌ��������͉̂�c�O�q���i����j�B�G�r�f���X�Ɋ�Â��W���I�ȁu�őP�v�Ɗ��҂̉��l�ς⎀���ς��C��Îҁ|���ҊԂŋ��L������邱�ƂŁC���ꂼ��̊��҂ɂƂ��čőP�ƂȂ锻�f���\�ɂȂ�Ǝ咣�����B�܂��C���{�V�N��w��w����҃P�A�̈ӎv����v���Z�X�Ɋւ���K�C�h���C���x�쐬�Ɍg��������ꂩ��C�u�K�C�h���C���ɉ����Ĉ�Îҁ|���ҊԂō��ӌ`�����}��ꂽ���u�ł���C��ɖ@�I���ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��v�ƌ�����B �@����������Ì����Z���^�[�̐��c�������́C���Z���^�[�Ŏ��{����uEnd-of Life Care team�v�̊���������B���`�[���́C���҂ɉ����C�I�����̖����S�s�S�▝���ċz�펾���Ȃǂ̊��҂�ΏۂɁC��Ɋɘa�C�l�H�ċz��E�݂낤�E�A�t�̍����T����P�ނ̈ӎv����x�����s���B���҂́u�ߋ��v�̈ӎv�\���C�u���݁v�̈ӌ��C�������Î��{��ɗ\�z�����u�����v�̊��ҁE���҉Ƒ��̐����Ƃ����C3�̎��_����X�̊��҂ɑ���œK�ȏI������Â��l��������@�������C���`�[���̈ӎv����x���̎��H����Љ���B �T����w�E�V�� ��2988�� 2012�N7��30�� |
||||
| �y���k��z���҂���́g���������h�v�������Ȃ���A�J�x���Ƃ� | ||||
| ���� �s���i�Ջ���ȑ�w�y�����E���O�q���w�j���i�� �ߓ� �������i����Љ�ی��J���m�E�ߓ��Љ�ی��J���m��������\�^��ʎВc�@�lCSR�v���W�F�N�g�����j �� �e�뎁�i����l���a�@���w�Ö@�ȁE�ɘa�P�A�`�[���j �a�c �k�����i�k����w��w���y�����E���O�q���w�j �@5�N������������54���܂ŏオ��C�����t�������a�C�ւƎp��ς����邪��B16�|65�܂ł̓�������ł́C���N�V���ɖ�22���l�̊��҂����܂�Ă���B�{�N6���Ɍ��肳�ꂽ�C�����̂�������i��{�v��ɂ��A�J�x���̕K�v�������L�����ȂǁC���ÂƓ������ƂƂ̗������ۑ�ƂȂ�Ȃ��C��Î҂̗��ꂩ��͂ǂ̂悤�ȃT�|�[�g���ł���̂��낤���B�{���k��ł́C����̓����҂������炵�����������邽�߂́C�x���݂̍���ɂ��čl�@����B �u�������Ɓv�̈Ӌ`�Ƃ́H �����@�܂��u�������Ɓv���C���҂̕��ɂƂ��āC���邢�͂���̎��Â̏�łǂ̂悤�Ȉʒu�t���ɂ���̂��C����̌��҂ł���ߓ����炨�b�����������܂����B �ߓ��@���ɂƂ��ē������Ƃ́C�g�����̗Ɓh�ł�����܂����C�����g�����邱�Ƃ��̂��̗̂Ɓh�Ƃ����Ӗ������������ł��B���ꂾ���ɁC�ςݏd�˂Ă������Ȏ����̉ߒ�������ɂ���ă��Z�b�g����C������Ƃ������Ă��܂����Ƃɋ�����R��������܂��B�����l���̃C�x���g�̈�ƂƂ炦�C���̑O�����̌�������悤�ɓ������������ƍl����̂́C���҂ɂƂ��Ă������R�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B ���@�������ƂŎЉ�ɂ�������������������Ă��������C���������Ƃ����a�����������Ƃł��̖�����D����B����͂܂��ɁC�A�C�f���e�B�e�B�������͂������悤�ȋ�ɂł����C���̋�ɂ́C�S�g�ɑ傫�ȉe����^���܂��B �@����T�o�C�o�[�̂Ȃ��ŁC�A�Ƃ��Ă�����̂ق���QOL���悢�X���ɂ���Ƃ����������ʂ��k�Ă�A�W�A�ŕ���Ă��܂��B�������Ƃ����ÂɃv���X�̉e����^����_�ɂ��C���ڂ��ׂ����Ǝv���܂��B �a�c�@����l�̂��b�̒ʂ�C���҂���ɂƂ��āu�������Ɓv�́C�����⎡�Â̔�p���m�ۂ��邽�߂ɂ��C�g���C�t�h���[�������邽�߂ɂ��d�v�ȗv�f�ł��B�ł������Ï]���҂́C���Â��Ȃ��瓭���������҂����邱�Ƃ�F�����C���̒��Ŏd���̌p���ɍ���������Ă��������肷��K�v������܂��B�S�̂��猩��Ə��l����������܂��C�����Ă��鍢��̓����͐獷���ʂŁC���[����肪����ł���ꍇ������ƍl�����܂��B ���Â₻�̕���p�ɂ��A�J�p��������� �����@����ł͋�̓I�ɁC����̎��ÂƎd���Ƃ̗����̓���́C�ǂ��������_�ɂ���ƍl�����܂����B �ߓ��@�܂��C��p�����Â̑��I�����ɋ����邱�Ƃ������C���̂��߂̌�������@�ŁC�K���d�������f����܂��B�܂��C���w�Ö@�̂��߂̒ʉ@�������ԑ����C�X�P�W���[������������Ȃ邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B �����@2�N�O����n�܂����C���J�Ȍ��u����ƏA�J�v�i�}�j�̌����ǂɂ��l�b�g�����ł��C��p���̋}�Ȍ���C���w�Ö@�̗\��ύX�Ȃǎ��Ìv�悪�\�����ɂ����C�d���ɉe������Ƃ���������������܂����B 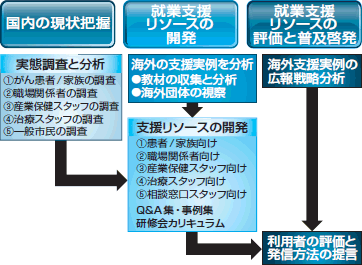 �@���Ƃ́C��͂艻�w�Ö@�̕���p�̖��ł��B����p�̒��x�ɂ͌l�������邽�߁C���̕s�m�肳�䂦�̔Y�݂�����悤�ł��B�S�g�Ɍ���錑�ӊ���W���͂̒ቺ�C������Ǐ�C�}���Ȃǂ��܂��܂ȕ���p�̏Ǐ�ɂ��C�v���悤�Ɏd�����ł����ɂ炳�������Ă�����́C���������܂��B ���@����p�ɂ��Ă͑�܂��ȑz��͉\�ł����C����ł��ڍׂȗ\���͂ł��Ȃ��Ƃ����̂�����ł��B�����C���w�Ö@�̍ŏ���1�R�[�X���o�����邱�Ƃɂ���āC2�R�[�X�ڈȍ~�̂��������̊��o�����߂Ă��܂��B�ł����犳�҂���ɂ́u1�R�[�X�ڂ̊Ԃ����͉��Ƃ����x�݂����炤���C�������ނł���悤�ȑԐ��𐮂��āC�ǂ�ȕ���p�����邩�C�l�q�����Ăق����v�Ƃ��b�����Ă��܂��B �����C���[�W��C�E������炭��g�����ɂ����h�� �ߓ��@����Ƃ��������ɑ��ĎЉ���C���[�W���C�A�J�ɉe�����Ă���Ǝv���܂��B�����g���ȑO�͂����ł������C����ƕ����ƂƂ����Ɂg���h��A�z���Ă��܂��B���R�u�d���̂��ƂȂ�ċC�ɂ��Ă���ꍇ����Ȃ���ˁv�ƍl�����������Ǝv���܂��B ���@�w�B�g�Ƃ��Ă̕a���x�i�X�[�U���E�\���^�O�C�݂������[�j�ł́g���Ă͌��j�����̕a���������C���j����������Ă���́C�����̃C���[�W�Ɏ���đ������h�ƋL����Ă��܂��B���ꂾ�����������オ�������ł��C�K�v�ȏ�ɔߊϓI�ȃC���[�W������Ƃ����a���ɔ킹���āC���܂��Ɉ�l�������Ă��銴�͂���܂��ˁB �����@���������C���[�W���ǂ��Ŕj���Ď��͂ɗ����Ă������C���̉ߒ��ŔY�܂����������ł��B �a�c�@�E��ŗ����Ɣz���邽�߂ɂ́C�a�C�̘b���u�ǂ��܂Łv�u�N�Ɂv���Ă悢���C���҂��g�����ɂ߂��Ƃ�v���܂��B���ɓ��������40�Ζ����ɑ��������̓������q�{����Ɋւ��ẮC�j����i�ɐ������ɂ����ȂǃW�F���_�[�̖������݁C���Ԃ����G������\��������܂��B �@�ŋ߂ł́C��Ƃ̌�������ړI�Ƃ����l���팸��K�ٗp�҂̑����Ȃǂɂ��C�E��Ō݂��ɏ��������Ƃ�����������������܂��B���ɒ����K�͂̊�Ƃ͐l�I�]�T�ɖR�����C�̒��s�ǂȂǂŐ�͂ɂȂ�Ȃ��l�ɂƂ��ẮC�K���������S�n�̂悢���ł͂Ȃ��B�����������C���҂���{�l�̊��������݁C���ʂƂ��Ď��߂���Ȃ��Ȃ�P�[�X�����Ȃ��Ȃ��悤�ł��B �܂��́C�A�J�ɂ��Ęb���₷�����͋C����� ���@�ȑO�C���҂���̋ߐ�̎Y�ƈ�^�Ō�t����A�����������������Ƃ����������ŁC�d���Ǝ��Â̒������X���[�Y�ɐi�݁u�����܂œ����Ă����I�v�Ɗ��������o��������܂��B��������ƁC�ق��̊��҂���̃P�[�X�ł����낢�남�肢���Ă݂����Ƃ����C�ɂȂ�u�E��ɎY�ƈ�̕��͂����܂����v�Ƃ������Ă��܂��̂ł����C��U�肪�����̂ł��i�j�B �a�c�@�Y�ƈ�̑I�C�`��������50�l�ȏ�̐E��́C���{�̑����Ə����̂킸��3���C�J���Ґ��ł݂Ă�4����ł��B����ɂ����̊�Ƃł��C�Y�ƈ�̖K�����1��ł�������C���邢�͒���K�₳���Ȃ��ꍇ������܂��B��̎Y�ƈ�ւ̃A�N�Z�X���m�ۂ���Ă����ƘJ���҂́C�S�̂̐������x�ł��傤�B �@���������������܂�����C�厡��̐搶�ɂ́C�����ł��Y�ƈ�I�Ȏ��_�������Ċ��҂���̏A�J�ɂ�������Ă�����������Ǝv���̂ł��B�u�E��̏�i�Ƃǂ�Șb�����Ă��邩�v�u�d�ʕ��̉^���E�o���E�����ԘJ���ւ̔z�����K�v���v�Ƃ������b����o�����Ƃ��C�����������ɂȂ�܂��B ���@���҂���́C�a�@�ŏA�J�̑��k���ł���Ƃ͍l���Ă����܂��C�܂��͈�Î҂��C��z���āC�A�J�ɂ��Ęb���₷�����͋C����邱�Ƃ���ł��ˁB �����@�x���ɓ������ẮC�u����ƏA�J�v�����̈�ō쐬�����u����Ɋw�ԁ@���҂̏A�J�x���ɖ𗧂�5�̃|�C���g�v�i�\1�j���Q�l�ɁC�ł��邱�Ƃ��珇�Ɏ��݂Ă�����������Ǝv���܂��B
�a�c�@���ÂƏA�J�̗����̎x���ɔM�S�ȊO�Ȉ���ᇓ��Ȉ�ɃC���^�r���[���s���Ă܂Ƃ߂����̂ł����C���Z�Ȓ��ł����g��ł���������悤�ȁg�D����h���W�߂�����ł��B ���@�����g�C�u5�̃|�C���g�v���Q�l�ɁC���҂���ɖ₢���������Ă��܂��B����Ɓu���������Ǐ������ꍇ�C�ǂ������炢���ł����v�ȂǂƁC��̓I�ȑ��k���ł��C���i�Ή��ɂȂ��邱�Ƃ������ł��B �u�������S�v�����ݏo���_��Ȏ��Ñ̐� �����@���{�Տ���ᇊw��Ɠ��{���ÔF���@�\�̐搶���̂����͂Ď��{���ꂽ�����ł́u���ÃX�P�W���[�������҂���̎d���̓s���ɔz�����Č��߂��邩�v�Ƃ����ݖ�ɑ��C���ː��ɂ��Ă�28���C���w�Ö@�ɂ��Ă�42�����u���߂���Ǝv���^�܂��v���v�Ɠ����Ă��܂��B���̐��l�ɂ͂悢�Ӗ��ŏ��X�����܂������C���搶�̎����Ƃ��Ă͂������ł����B ���@���w�Ö@�����ː����Â��C��{�I�Ɉ�t�̐f�@������K�v�ł�����C�Ζ��̐��ȂǕa�@�^�c��̌��E������܂��B�������f�ÉȂ��Ƃɖ����S���āC��含�����߂�قǁC�Z�ʂ͗����₷���Ȃ�Ǝv���܂��B�����g�C�Ö@�͈�C����Ă������C�a���͊O�Ȃ̈�t�������Őf�Ă���Ă���C�O�����ɋ}�ςŌĂ�邱�Ƃ͂���܂���B���[�`���̌����Ɩ������܂�����Ă��炸�C��r�I�܂Ƃ܂������Ԃ�����̂ŁC���҂���Ǝd���̘b���ł���킯�ł��B �����@�Ⴆ�ΏT��3�|4���O�����J���Ă���C���҂�����s���̂����j����I�����₷���Ȃ�܂��B������C�e�Ȃ̈�t�����̂��̖̂����ɐ�O�ł�����������Ă���C�������₷���Ƃ������Ƃł����B ���@�����ł��ˁB���̂��߂ɂ́C��������ᇓ��Ȉ���C�a�@�̒��Ŗ�����������o�����炢�̋C�T�������Ď��Ìv��ɉ�����Ă����K�v������܂��B����ő���ʐ��Ȃ̐搶���ɂ��u��ᇓ��ȂɔC���Ă������v�Ƃ����F�������Ў����Ă������������B�ŋ߂ł͑�������̊ɘa�P�A�̋C�^�����܂��Ă��܂�����C�`�[����Â̊ϓ_����C�A�J�̖��ւ̃R���T���g���u�Љ�I��ɂւ̃A�v���[�`�v�Ƃ����Ӑ}�Ŋɘa�P�A�`�[���ɂ��肢����Ƃ����̂��C��̕������ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���Ƃ���ł��B �a�c�@�u5�̃|�C���g�v�쐬�̉ߒ��ł��炽�߂ĔF�������̂́C��t�͕a�@�̒��Œ�Ă��₷������ɂ���Ƃ������Ƃł��B�u�d���Ǝ��Â̗������x������v���Ƃ���j�Ƃ��ĕ\�����Ă��������C���̏�ŊŌ�t��MSW�Ȃǃ��f�B�J���X�^�b�t���܂߁C�ǂ�Ȏx���������S���邩��������B���ꂾ���ŁC�͂����Ԃ�ς��̂ł͂Ȃ����Ƃ������G�Ă��܂��B ���@�܂��͌���̐ӔC�҂��ӎ���ς��āC�������S�ƃ`�[����Â����ɂ������Ă����B���ꂪ�ς�邱�ƂŁC�a�@�S�̂ɂ��_������܂�C���ʂƂ��āC���������銳�҂���ɂ�莑����V�X�e�����ł��邩������Ȃ��C�Ǝv���Ă��܂��B �����@���҂���̈�ԋ߂��ł�����葱����厡��̕��X�ɂ́C�ނ�̐������̊�]���ł�����蕷���Ă������������C�Ƃ����̂����̊肢�ł��B�u�Ĕ����āC���Ɣ��N������A�J�͍l���Ȃ��Ă�����ˁv�ł͂Ȃ��C���{�l�Ɂu���������v�Ƃ����v��������̂Ȃ�C�ŋ��̃T�|�[�^�[�Ƃ��āC��������Ȃ���x�������肢�������̂ł��B �@����������ǂƂ��āu�A�J�̖��ɔY�ފ��҂��C����ȍH�v�œ����₷���Ȃ����v�D����𑐂̍��I�Ɏ��W���C�Տ�����̕��X�Ƌ��L���Ă��������ƍl���Ă��܂��B ���k�ł����̏[���Ƃ����ɂȂ��郋�[�g�̐��� �����@�������N�ŁC����ƏA�J�ւ̊S�����������܂�C���҂����p�ł���c�[�������ɂ��������܂�Ă��܂��B����ߓ�����ɁC�\�ɂ܂Ƃ߂Ă��������܂����i�\2�j�B
�ߓ��@����ɓ����������̂͂܂��܂����Ȃ��̂ł����C���҂���ȊO�ɂ��C��Ƃ̕��C�����ďA�J�x���ɋ����������Ă����t�̕��ɂ��C�Q�l�ɂ��Ă���������Ǝv���܂��B �����@���������c�[���̊��p�𑣐i�������C���ꂾ���ł͉���������ꍇ�̂��߂ɁC�ʂɑ��k�ł��鑋���̏[�������߂���Ƃ���ł���ˁB �ߓ��@�u�ǂ��ɑ��k������悢���킩��Ȃ��v�Ƃ������͎��ۂɑ����ł��B �@����̎��ÂƎd���C��������x�ɑ��k�ł����͌���ł͖R���������C�n���[���[�N�C�N���������C�s�����C�����ۂȂǁC�����̋@�ւ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���_�͂��̗͂������Ă��銳�҂���ɂ́C�z���ȏ�ɑ�ςȂ��Ƃł��B �a�c�@�a�@�ɂ����āC�Љ�ی��J���m�i�ȉ��C�ИJ�m�j�̕��ƘA�g���C���҂���̑��k�ɑΉ��ł���悤�Ȏd�g�݂�����ł���Ƃ悢�ł��ˁB �ߓ��@����͎����C��Ò҂̕��X�ɂ��Ќ������Ă������������ƍl���Ă��邱�Ƃł��B �@���i��������Ă��Ȃ����҂���ɂ́C�a�@���ł̏���c�[���̏Љ�ŏ\���ł����C�s���Ɏ��߂�����ꂻ����������C�ی����t���Ȃ���邩�ۂ������ȃ��C���ɂ�����ȂǁC��͂���Ƃ�����������ق����悢�P�[�X������܂��B���͂ő��k�@�ւ�T���o���銳�҂������ł͂Ȃ��C�Ƃ����_���猾���Ă��C��Ë@�ւ���̃��[�g����������邱�ƂŁC�~������͑����Ǝv���܂��B ���@�g�ИJ�m�h�Ƃ������݂�m��Ȃ��Տ�����C�܂����R�̂悤�ɂ���Ǝv���܂��B�܂��C�����������ɖ��邢�ИJ�m�̕����ǂ��ɂ���̂����C�a�@���ł͂Ȃ��Ȃ��킩��Ȃ����̂ł��B�Ⴆ�C�Љ�ی��J���m��Ȃǂňꊇ���ď����Ă���������ƁC���ɏ�����܂��B �ߓ��@���ł����C��Q�N���Ɋւ��ẮC�ИJ�m�ɂ��S���K�͂�NPO�@�l�ȂǑg�D�I�Ȏx�����\�ƂȂ��Ă��܂��B����ƏA�J�̖��ł����l�ɁC�m�����������ИJ�m�𑝂₷�ƂƂ��ɁC�g�D�I�Ȏx���̐��𐮂��Ă����K�v�����肻���ł��ˁB �����@�@���ɁC������x�A�J�̑��k�ɏ���m�E�n�E�������������邱�ƁB����ɕ��G�ȃP�[�X�Ɋւ��ẮC�ИJ�m�Ȃlj@�O�̐��ƂɃR���T���g�ł���̐������������C�x�X�g���Ƃ������Ƃł��ˁB ���@������C�@�O�ł��@���ł��悢�̂ł����C����T�o�C�o�[�̕��ɏA�J�Ɋւ���A�h�o�C�X�����肢�ł���V�X�e���̐������K�v�Ǝv���܂��B���҂�����u�搶�v���瑣�������C�����҂̏W�܂��A�h���H�J�V�[�O���[�v�Łu���҂Ƃ��ā^�T�o�C�o�[�Ƃ��Ă����s�������v�Ƃ�������������Ă���������ƁC����D�ɗ����₷���ł��傤�B�W���̗v���́g����������h�ł��B��������Ďd���𑱂���R�c�ȂǁC�����I�ȃm�E�n�E��`�����Ă��炦�邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B �ߓ��@�m���ɓ����ғ��m���u�������Ɓv�ɓ������Ęb�����́C�܂��܂����Ȃ��ł��B���Âł�������E����������C�ēx���E����ۂɕa�C��ʉ@�̂��Ƃ��ǂ��`���邩�C�Ƃ������Y�݂����������������܂��B�ďA�E�ɐ��������������̓I�ȃA�h�o�C�X�����炤���ƂŁC�傫�ȗ�݂ɂȂ�܂��B���������̌����V�F�A�����̕K�v���́C���������܂��ˁB ���҂���̂ƂȂ��Ė������ꉻ���Ă��� �����@�u���[�g���v��u�������S�v�Ƃ����L�[���[�h��̌�������̂Ƃ��āC�u����ƏA�J�v�����ǂł́C���Җ{�l�C�Y�ƈ�C�厡����Ȃ��u�A���蒠�v�̂悤�ȃc�[�����������Ă��܂��B�����ʓI�Ȋ��p�̂��߂ɂ́C�ǂ�Ȏ��_��������悢�ł��傤���B �ߓ��@�����܂Ŋ��҂���̂ł��邱�Ƃ��C����Ǝv���܂��B �@�Ⴆ�Ύ��́C���Ò��ɗ��p�ł���Г����x�ɂ��Ċm�F���Ă����������߂ɁC�u�A�ƋK���Łg�x�Ɂh��g�x�E�h�Ɋւ�����́C�Z���ԋΖ��Ȃǂ̋Ζ����x�Ɋւ�����ׂ̂�v�Ƃ�������Ƃ��C���k�҂̕��ɂ��肢���邱�Ƃ�����܂��B����������Ƃ��C�̐����◝���ɖ𗧂��Ă���悤�Ɋ����Ă��܂��B ���@����́C��ᇓ��ȁE�O�ȁE���ː��ȁC�����ďꍇ�ɂ���Ă̓��n�r���e�[�V�����ȂȂǁC���Â��ו�������C�厡�コ����サ�Ă����ꍇ������܂��B�Ȃ̂Ŋ��҂���̐��������ďA�J�̖��������ł���c�[�����ł��邱�Ƃ́C�傢�Ɋ��}�ł��B �a�c�@���ÂƎd���Ƃ̗����̂��߂ɒ������K�v�ȑ����̎����ɉ����C���Â̕s�m�萫��C�a�C�̒m���s���Ȃǂ̖�������B���������ŁC�ǂ�Ȕz�����ǂ̂��炢���߂Ă���̂��C���҂����猾�ꉻ�ł���悤�C�c�[���Ȃǂ�ʂ��Ďx�����Ă�����Ǝv���܂��B �o��l�����ꂼ��̗���ŁC�ł��邱�Ƃ��l���� �����@���ꂩ��̎x���݂̍���ɂ��āC�������ꌾ�����������܂����B �ߓ��@�����ИJ�m�ɂȂ����̂́C�����₷���E�ꂪ�����邱�ƂŁC���������Ɠ�����l�������C���F���K���ɂȂ��̂ł͂Ȃ����C�Ƃ����v������ł����B���܂��܂���ɂȂ�Ƃ����o���������̂ŁC���̌o�����Љ�ɊҌ�����Ӗ������߂āC�ИJ�m�Ƃ��ē����₷���E�����i�߂����ƍl���Ă��܂��B �a�c�@�u���������v�Ƃ����v���́C�Љ�ɎQ���������Ƃ����q�g�̍��{�I�ȗ~���Ƃ������܂��B������i�݁C���݂�70�܂œ������Ƃ��ڕW�Ƃ��Ď������Ȃ��C��l�ł������̊��҂��u�����Ȃ��玡�Â��ł���悤�ɂȂ�v�Љ�����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ������ɂ���܂��B����Ƃ������������̑�\�ƂƂ炦�C���f���P�[�X���Ȃǂɂ���Ă���ɓW�J���ł���Ǝv���܂��B ���@��肻�̂��̂̔F�m�x�����@���x�̐����Ƃ������n�[�h�ʂ̉ۑ肪���낢�날��܂����C��Ղ͐l�Ɛl�Ƃ̊W���Ǝv���܂��B�l�Ɛl�̊W�ł́C�g����������h�̃o�����X�̗ǂ��W����ۂC���^�̊W���ɐӔC�����Ƃ����w�߂�����܂��B���҂���ɂ͂��Зǂ��W���̃X�L����g�ɂ��Ă������������ł����C���������f�ÉȁC����ɂ͐E����Ǝ�����f�����W���������C�T�|�[�g���Ă��������ł��ˁB �����@�u����ƏA�J�v�̖��́C�o��l�����ƂĂ������̂ł����C���ꂼ��̗��ꂩ��ł��邱�Ƃ�����Ə����������Ă�����������܂��B���N�x����n�܂������������i��{�v���5�N�Ԃ��I������Ƃ��Ɂu���҂���̏A�J���͂����܂ł悭�Ȃ����I�v�ƌ�����d�g�݂��C�F�ŘA�g���Ȃ������Ă��������Ǝv���Ă��܂��B�{���́C�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B �T����w�E�V�� ��2988�� 2012�N7��30�� |
||||
| �s���{�����_�a�@�Ɂu�ɘa�P�A�Z���^�[�v�ݒu��--���J�ȁE������ | ||||
| �@�ɘa�P�A���i�������7��11���A�����J���Ȃ��������u�ɘa�P�A�Z���^�[�\�z�v���ؗ��������B�e���_�a�@�Ɂu�ɘa�P�A�Z���^�[�v�����悤�Ƃ������̂ŁA�܂��͓s���{�����_�a�@�ł̐�����ڎw���B �@�ɘa�P�A�`�[���Ɗɘa�P�A�O���̘A�g�A�ɘa�P�A�f�Ï��̏W��E���͂ȂǁA�ɘa�P�A�ɂ��ĉ@�����f�I�Ȏ��g�݂�i�߂�̂��ړI�B m3.com 2012�N8��2�� |
||||
| ��Íu���E�����w����@�����̂m�o�n���J�ÁA�Q���҂��W | ||||
| �@�����{��k�Ђő����̐l�̖����D��ꂽ���Ƃ����������ɁA���ɂ��čl���悤�ƁA�����s�̂m�o�n�@�l�u���҂̌����I���u�Y�}���v�i�������E�r�i���ٌ�m�j�Ȃǂ́u��Íu���@�����w����v���J�Â���B�V�_�`�N���N�r���i������V�_�R�j�ȂǂőS�R��A�Q����͊e�T�O�O�~�B �@�u���͑�P��i�P�O���Q�V���j�������w�����҂ō�Ƃ̔g���]�L�q���u�t�́u���I���u���v����Q��i�P�Q���P���j�O�Ȉ�̓�m��ۊ삳��u�������߂Đ�����`�ݑ�z�X�s�X�̌��ꂩ��v����R��i���N�Q���Q�R���j���R�����w�������̒J�c���r����u���{�l�̎����ς̕ϑJ��U��Ԃ�v�B �@�₢���킹�͓��I���u�Y�}�������ǂO�X�Q�E�U�S�R�E�V�T�V�X�B m3.com 2012�N8��2�� |
||||
| ��Éߌ�@�u�����q�l���^�Ŏ��S�v�@�V�O��⑰��������i�@�R���n�َ���x�� | ||||
| �@����s�̑����a�@�Љ�ی����R�����a�@�i�ѓc�d���@���j�ň��N�P�P���A����s�̒j���i�����V�X�j���S���Ȃ����̂́A�����q�l���^���s�K���������߂Ƃ��āA�V�O��̈⑰�������A�a�@��ݒu�E�^�c����Вc�@�l�S���Љ�ی�����A����i�����s�j�Ȃǂ���A�Ԏӗ��Ȃǖ�P�U�T�O���~�̑��Q���������߂�i�����R���n�َ���x���ɋN�����Ă������Ƃ��P�R���A���������B �@��i�͂U���Q�X���t�B�i��ɂ��ƁA�j���͔����a�̎��Âœ��@���Ă����P�O�N�P�P���P�U���A�ċz����ɘa���邽�߉��_�����q�l�𓊗^���ꂽ���A��P�O����ɖ������ቺ���A����p�ɂ�莀�S�B����̒j���́A�ċz�s�S�ȂǕ���p���N�����v���������������̂ɁA���̉\�����l���������R�ƃ����q�l�𓊗^�����ȂǂƂ��Ă���B �@�a�@���́u�S���҂��s�݂ŁA���Ƃ������Ȃ��v�Ƙb���Ă���B m3.com 2012�N8��15�� |
||||
|
���E���Ԃ̕��i �݂낤�̐���ɂ��ā\����҂́u���R�Ȏ��v�����߂��ɂ́\ |
||||
| ���� ���@�_�ސ쌧���E�����ߊ}�f�Ï��i���{��s�j�����^���_�ސ쌧���z��ċz��a�Z���^�[���� �@���͒��N�C�_�ސ쌧���a�@�ŐS�����NJO�Ȉ�Ƃ��ċΖ����C��N�ސE��C���ʗ{��V�l�z�[����V�l�ی��{�݂Ȃǂ̘V�l�����{�݂ŁC�ӔC�҂Ƃ��č���҂̌��N�Ǘ��Ɍg����Ă��܂����B�V�l�{�݂Œ�����҂̎��Ɋԋ߂ɐڂ���悤�ɂȂ��ĕ��������̂́C�s���R�Ȏ��ɕ������Ă��鍂��҂����Ȃ��Ȃ��Ƃ������Ƃł����B �@�{�݂ł͍���҂��V���Ŏ��ɂ����ɂȂ����Ƃ��C�Ŏ�邱�Ƃ͂����C�������ɕa�@�֑���܂��B��������ƕa�@�ł́u�H�ׂ��Ȃ��a�l�v�Ƃ��Ĉ����C������肾�Ă��g���Ė����Ƃ�Ƃ߂悤�Ƃ��܂��B��t�͔N��ɊW�Ȃ������ł������������̂��`�����ƍl���Ă��邩��ł��B �@�������ߔN�C�u�݂낤�v�Ƃ����u�H�ׂ��Ȃ��a�l�����Â���v��y�ȕ��@���J������܂����B�������ň�Â̌���ł́u�H�ׂ��Ȃ��Ȃ��Ă��邩��C�݂낤�����܂��傤�v�ƁC���Ƃ��ȒP�Ɉ݂낤�̑��݂����߂��Ă���̂ł��B�����ɖ{�l�̈ӎv�̉�݂͂ق�̋͂��ł��B �@�����Ŗ���2����܂��B�ЂƂ́C����҂́u�V�����v�Ƃ͂ǂ��������̂��C�u���R���v�Ƃ͂ǂ��������̂��C��Ï]���҂ł����悭�������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���ЂƂ́C�ЂƂ��ш݂낤�݂���ƒ��~�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���͐[�����Ǝv���܂��B����҂��a�C�ł͂Ȃ��V���ŖS���Ȃ�Ƃ́C����H�ׂ��Ȃ��Ȃ��āC�͂��悤�Ɏ���ł������Ƃł��B���̎��R�Ȏ����}���悤�Ƃ��Ă���Ƃ��ɁC�݂낤�݂���Ƃǂ��Ȃ邩�B�Q������Ŕ��ꂪ�Ȃ��C�葫���d�k���A����ԂƂȂ��Ă��C�ݒ�����v�ł���ΐ������ꑱ���邱�ƂɂȂ�̂ł��B �@�t�����X�ɒ����؍݂��Ă������̒킪�C�t�����X�̈�t���炱��ȑ䎌���܂����B�u�V�l��Â̊�{�́C�{�l�����͂ŐH�����ł��Ȃ��Ȃ�����C��t�̎d���͂��̎��_�ŏI���B���Ƃ͖q�t�̎d���ł��v�B �@���������݂낤�����߂ėՏ��ɉ��p���ꂽ�̂�1979�N�B�A�����J�ł̐_�o�����ɂ�隋����Q�̎q�����Ώۂł����B���ݓ��{�ł́C�������H�ׂ��Ȃ��I�����̍���҂̉����̂��߂Ɏg���Ă��܂��B������������ɑ��āCPEG�i�݂낤�j���J�����������O�Ȉ�̃K�E�_���[��t�́C�K�����ڂ݂Ȃ�����҂ւ̉ߏ�{�s�Ƃ����CPEG�̊J�������͈Ӑ}���Ȃ��������Ԃ�J���Ă���Ƃ����܂��B���݁C�݂낤�̊��҂�40������50���l�ɂ��̂ڂ�Ƃ����Ă��܂��B �@�ʂ����č���Җ{�l�́C�݂낤�ɂ�鉄����]��ł���̂ł��傤���B�����s���N������ÃZ���^�[�̊O�������562����Ώۂɍs�Ȃ�������������܂��i1999�N�j�B �@�F�m�ǂ��i�s���C�H���̐ێ换��C�Q������C�����̈ӎv��\���ł��Ȃ���ԂɊׂ������Ƃ�z�肵���ꍇ�C�݂낤����]���邩�ǂ��������₵�܂����B���ʂ́C�݂낤�̊�]�҂�2.7���C�o�@�݊ǂ�6���C�_�H��3.9���C�������Ȃ����ł�����42���ł����B �@�����������I�ɂ́C�݂낤���������u�Ƃ��Ď{�s����Ă���Ƃ����ł��B�܂�����C���̒����̂��ߎQ�����Ă������PEG���݂����Ă����t30���ɁC���������҂̗���Ȃ�݂낤�ł̉�����]�ނ��Ƃ�������ɑ��C21���͔ے�I�ȉł����B�F�m�ǖ����́C���{�l���܂߂������̌����҂��C�o�ljh�{�@�̓K���łȂ��Əq�ׂĂ��܂��B �@PEG�̗ǂ��K���́C�]���Ǐ�Q��y�x�̔F�m�ǂŁC������Q�����������̂̈ӎ���Ԃ������Ȃ��Ǘ��C���̊O���ňꎞ��������H�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��ǗႾ�Ǝv���܂��B �@��Â̖ړI�́C�{���C���҂����悭�����邽�߂ɖ𗧂��̂łȂ���Ȃ�܂���B���݂̈낤�Ƃ��������ێ��̋Z�p���C���҂́u�����̎��v�iQOL�j�����߂��Ŗ𗧂��̂łȂ���C�g�����Ƃ�����������Ȃ��Ǝv���܂��B �@���́C�݂낤�̎�p��������t�����̑������C�݂낤�݂��ꂽ���N���݂̂��߂Ȗ��H���ڂ����͒m��Ȃ����Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B�l�Ԃ͒N�����C�Ō�܂Ől�Ƃ��ĈӖ��̂���l���𑗂肽���Ɗ肤���̂ł��B����������ł́C�{�l���Ƒ����]�܂Ȃ����̂����̉������C�N���~�߂邱�Ƃ��ł��܂���B �@���N��1���C���{�V�N��w��C�u����҂̏I�����ɂ́C�݂낤���݂��܂ތo�ljh�{�Ȃǂ͐T�d�Ɍ��������ׂ��ł���C���Â̍����T���⎡�Â���̓P�ށi���Ȃ킿���~�j���I�����Ƃ��čl������K�v������v�Ƃ��܂����B�}����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́C�݂낤������E���Ȃ������߂�V���������邱�Ƃ�C���҂̈ӎ��������߂�Ȃ��ƕ����������_�ŁC�݂낤�𒆎~����@�I�Ȋ�����߂邱�Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N8��23,30�� |
||||
| �������F��t�̏����ɂ�閖�����҂̎����A�ă}�T�`���[�Z�b�c�B�ō��@���� | ||||
| �@�����̈ӎv�ƐM���Ɋ�Â��Đ����A�����Ď��ʂ��Ƃ͂����炭�A�l�Ԃ����ő�̎��R���낤�B�������A���̎��Ȍ��茠�ƈ��S�����A���Î҂Ƃ��Ă̈�t�̖�����A���ɓI�ɂ͐����̉��l�ƏՓ˂���Ƃ�����ǂ����낤���H �}�T�`���[�Z�b�c�B�ő����������@���̌��ʂ� �@�}�T�`���[�Z�b�c�B�̏Z���́A������11���A�������������l���邱�ƂɂȂ肻�����B�a���̐l�X�ɁA�����̖����I��点�邽�߂ɏ������ꂽ������ȓ��^���邱�Ƃ��\�ɂ���@�Ă̏Z�����[���s���邩�炾�B��������ΑS�Ă�3�Ԗڂ̏B�ƂȂ�B �u�������@�v���x������l�X�́A�����������銳�Ҏ��g�ȊO�̐l�����̖�𓊗^���邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł��邩��A���̍s�ׂ͈�t�����鎩�E�Ƃ͌ĂׂȂ��Ƒi����B�������A���Δh�̐l�X�́A�����̔���������҂�Ⴊ���ҁA�n�����l�X���A���Ô��}���邽�߂ɉƑ��⑊���l���爳�͂���\�����o�Ă��錜�O������A���������l�X�̖����댯�ɂ��炷���ƂɂȂ�Ǝ咣���Ă���B �������͈��y���� �@�I���S���B��1994�N�A�I�����ɂ��銳�҂������𑁂߂����������Ă��炤���Ƃ�F�߂��B���V���g���B��2008�N�ɂ���ɑ������B�}�T�`���[�Z�b�c�B�̏Z�����[�̓��V���g���B�̖@�Ǝ����㓯��ł���A�I���S���̖@�����~���ɂ��č���Ă���ƁA�u�}�T�`���[�Z�b�c�������A��(The Massachusetts Death with Dignity Coalition)�v�̍L��ӔC�҃X�e�t�@���E�N���t�H�[�h(Stephen Crawford)���͌����B �@2009�N�ɂ̓����^�i�B�̍ō��ٔ������A��t�����鎩�E�͏B�@�┻��Ɉᔽ���Ȃ��Ƃ������������������A���B�ɂ͌����ȑ������@�͂Ȃ��B �@���̖@���́A����d�v�ȓ_�ɂ����āA���y�����t�����鎩�E�Ƃ͈Ⴄ�A�ƃ}�T�`���[�Z�b�c�������A���͌����B���łɕa�C�Ŏ����̔��������҂��A�����̐������I��点�������ȓ��^���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����_���B��t�͂��̂��߂ɕK�v�ƂȂ����������邱�Ƃ͋�����邪�A���҂̋��߂��������Ƃ��Ă���������K�v�͂Ȃ��B �@���������Δh�́A�������@�͈�t���E�ƕς��Ȃ��A�I�����̐l�X�͂�������s���邽�߂ɂ����菕����K�v�Ƃ��邾�낤���炾�A�ƌ����B�u�N�����f�@�̗\������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�N������ǂɂ�������������ɂ����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B������������ŁA�Ď����Ȃ����^���ꂤ��̂ł��B���ꂪ�{���Ɏ����I�ȍs�ׂƌ�����ł��傤���v�ƁA�������@�ɔ�����u�I���͌��z(Choice is an Illusion)�v�̑�\�Ń��V���g���̎����ٌ�m�A�}�[�K���b�g�E�h�A(Margaret Dore)���͌����B���ɂ͎ア����̊��҂������댯�ɂ��炷�\���������܂܂�Ă���Ƃ����B �u����₷�����[�v�v �@�I���S���A���V���g���̖@�ɋK�肳��Ă���悤�ɁA�}�T�`���[�Z�b�c�̖@�Ăł��A���҂͏���Ⳃ���ɓ����O�Ɉ�A�̏��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�I�����̊��҂Ōږ��t���]��6�����ȉ��Ƃ̐f�f�����Ă��邱�ƁB�܂��A�ږ��t�͊��҂����N�Ɋւ��Č�����s���A�����`����\�͂����_�I�ɂ��邱�Ƃ��F�肵�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����ɁA��̐����́A15���̊Ԋu�������A2�x�ɂ킽���āA�����Ŏ厡��ɑ��čs���K�v������B�܂��A�Ƒ����ɊŌ��S�����Ă���l�łȂ��ؐl��2�l�K�v���B �@�����͌������悤�Ɍ����邪�A�h����Ƃ�����t�ɑ��锱��������������Ă��Ȃ����Ƃ���肾�Ɣ��Δh�̃h�A���͏q�ׂ�B�܂��A�Ƒ�����҂���A���Ô����ȏォ����Ȃ��悤����I�Ԃ悤���߂���ȂǂƂ������͂������邱�Ƃ��A����ɐS�z�Ȃ̂��Ƃ����B �@���������_���}�T�`���[�Z�b�c�������A���̃N���t�H�[�h���ɂԂ����Ƃ���A�u����₷�����[�v�A�܂��x�n�߂Ă��܂��Ύ��Ԃ��~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����c�_�́A���N�ɂ킽���Ĕ��Δh���咣���Ă��܂������A���t���͂Ȃ��̂ł��v�Ƃ����ԓ��������B �@���ہA�I���S���B���O�q�����̃f�[�^�ɂ��A�������𗘗p�������҂̑啔���͔��l�ŁA����̂���A�o�ϓI�ɂ����肵�ĕی��ɂ��\�����������l�X�������B�܂��A�������̂����Ȃ��B14�N�Ԃ�596��ŁA�]�ڐ��̂���ɋꂵ�݁A���������Ă���Ƃ������m�Ȑf�f���o���l�X���قƂ�ǂ��B �@�������A���Ȃ��Ƃ�1���́A����Ȃ鎡�Âł͂Ȃ������������ƂɂȂ����Ⴊ�������B2008�N�A�����̔x����������Ă����I���S���B�̃o�[�o���E���O�i�[���A�I���S���ی��v�����ɂ�鎩���̌��N�ی��ł͎厡��̏���������4,000�h���̖��Â��J�o�[������Ȃ����A�������ɕK�v�Ȗ�̗����̓J�o�[�ł��邱�Ƃ�m��A��҂�I�̂��B���̗�͑S�Ăɋc�_�������N�������B �u���ȓ��^�v�̂����܂��� �@�@�Ďx���҂����́A�������́A�����̖����I��点���������œ��^�ł��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂�����A���E�Ƃ͖@�I�ɋ�ʂł���Ƃ���B���҂͂�����������A�����I�Ɏ����̑̂ɓ���邱�Ƃ��o���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B �@���������Δh�̐l�X�́A���҂͕ʂƂ��āAALS�i�؈Ϗk�������d���ǁj�̐l���������̖@���Ɋ�Â��Ď���I�Ԃ��Ƃ��^��Ɏv���Ă���B���̕a�C���i�s����Ƌؗ͂⋦���^���@�\���ቺ���A�������蓮������A���ݍ��ނ��Ƃ����o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����炾�B �@�}�T�`���[�Z�b�c�@�̋K��͖@�I�ɂ����܂����ƁA���Δh�̃h�A���͎w�E����B���҂͐������I��点��̂ɕK�v�Ȗ���u���ȓ��^���Ă��悢�v�Ƃ����\���ɂȂ��Ă���B�u���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ͏d�v�ȈႢ���B�܂��A���@�͂͂�����Ɓu���̂悤�Ȏ葱���͎����I�Łv�Əq�ׂĂ��邪�A�u���ȓ��^�v�Ƃ͖@�I�ɂ́A���P�Ɍo���ێ悷�邱�Ƃł����肤��A�ƃh�A���͌����B�u�o���ێ�ɂ́w�����I�ȍs�ׁx�͕K�v����܂���B����͎����̑I���̖�肾�ƌ����܂����A�@�ɂ���ʂ肾�ƁA�I���͕ۏ���Ă��Ȃ��̂ł��v�Ƃ����̂��ޏ��̎咣���B �@����A�}�T�`���[�Z�b�c�������A���̃N���t�H�[�h���̎咣�́A�ł͖�𓊗^�ł���̂͊��҂������Ɩ��m�ɏq�ׂ��Ă���A�Ƃ������̂��B�u��͎��ȓ��^����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���ꂪ�̋K��ł��B���ꂾ���ł��v�Ɣނ͌����B �I���S���A���V���g���ł͑命�����x�� �@�����������@������Ă���2�̏B�ł́A���Ȃ��Ƃ��Z����70%�����@�ɍD�ӓI�Ȉӌ��������Ă��邱�Ƃ��A�i�V���i���E�W���[�i���ƃ��[�W�F���X���c�̍s����2011�N�̐��_�����Ŗ��炩�ɂȂ����B �@�}�T�`���[�Z�b�c�̐l�����������ӌ��̂悤���B�ȑO�ɂ́A��t�̏����ɂ�鎩�E�͖@�����Ɏ���Ȃ��������A�ŋ߂̐��_�����̌��ʂł́A���B�����C�݂ōŏ��ɑ����������@������B�ɂȂ肻���ł���B�p�u���b�N�E�|���V�[�E�|�[�����O�̍s�����ŋ߂̒����ł́A�Z����58%���������Ɏ^���[�𓊂���Ƃ����̂ɑ��A���Ɠ������̂�24%�ɂƂǂ܂����B IBTimes�@2012�N9��4�� |
||||
|
����ł̊Ŏ�� �ƒ��ɑ���I������Â̋���E�x�����K�v |
||||
| �@�a�@�ł͂Ȃ��C�Z�݊��ꂽ�ƂŎ����}�������Ɩ]�ސl�͑������̂́C�x���M�[�ł͂���������ł����҂͑S���S�҂�25���قǂŁC���S�҂ł�29���ɂƂǂ܂��Ă���B���̐����͉ߋ�10�N�Ԃő������Ă��Ȃ��B�Ȃ��C����Ŏ����}���邱�Ƃ�����قǂ܂łɓ���̂��낤���B�Q���g��w�E�u�����b�Z�����R��w�����I������Ì����O���[�v��Kathleen
Leemans����́C���̖₢�Ɋւ��āu�ƒ�オ�I�������u�ɁC�ċz����C���ӊ��ɂ��܂��Ώ��ł��Ȃ����Ƃ�������1�ɂ���v��BMC
Family Practice�i2012; 13: 4, �I�����C���Łj�ɔ��\�B�ƒ���ΏۂƂ����I������Â̋����x���̕K�v����i���Ă���B ���̒��O�܂ŏ\���ȃP�A���K�v �@����̌����̑Ώۂ�SENTIMELC study�ɓo�^���ꂽ���S�҂̂����C�ˑR���ł͂Ȃ��C����ŗ\�����Ă��������}�������Җ�205��i60��������ɂ�莀�S�j�BLeemans����́C�����̊��҂̍Ŋ��̏�Ԃ���Ȃǂׂ邽�߂ɁC�e�S����ɃC���^�r���[���s�����B �@���̌��ʁC�a�@�Ŏ��S�������҂Ɣ�ׂđΏۊ��҂ł́i1�j�N��Ⴂ�i2�j�Ƒ��Ɠ������Ă���i3�j�j���ł���`���������������B �@�܂��C�S�g��ԁiPerformance Status�j�����������͎̂��S����1�T�ԑO����ŁC����ȑO��3�J���Ԃ͔�r�I�ǍD�Ȋ��҂����������B���S���钼�O�܂Ŋ��S�Ɉӎ������������҂�46���ɏ��C�c��54���̂����C�Ō�̏T��3���ȏ�ӎ��s���ł��������҂́C���̔������x�ł������B���҂�90�����C���S���铖���܂Ŏ��͂̐l�ƂȂ�炩�̃R�~���j�P�[�V��������邱�Ƃ��ł��C57���ɂ͈ӎv����\�͂��������B �@���҂̎�ȏD�i�́C���ӊ��i91���j�C�H�~�s�U�i86���j�C���C�i72���j�C�u�Ɂi56���j�C�ċz����i54���j�C�߂��݁i51���j�C�s���i46���j�ł��������C���̂����ċz����C���ӊ��C�u�ɂɂ��ẮC�����̉ƒ�オ�u�Ώ�����������v�Ɖ��Ă����i���ꂼ��27���C19���C12���j�B �@Leemans����́u���ɁC�ċz������u�ɂ͊��҂ɂƂ��ďd��Ȗ��ŁC�s��������������B�ƒ�オ�����̏Ǐ�ɂ��܂��Ώ��ł��Ȃ����Ƃ��C���҂�����Ŏ����}���邱�Ƃ�j�ޗv���ƂȂ��Ă���̂�������Ȃ��v�Ǝw�E������ŁC�ƒ��ɑ��čݑ�ł̏I������ÂɊւ��鋳��Ǝx�����s���K�v���������B�u�����������g�݂ɂ��C�g����Ō}���鎀�̎��h�����コ���邱�Ƃ��ł���v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N9��6�� |
||||
| �������@�āA�Վ�����ւ̒�o�ڎw�� | ||||
| �u�������@�āA�Վ�����ւ̒�o�ڎw���v�摜 �@���}�h�̍���c���ł���u�������@�������l����c���A���v�i������q�P�F�E����}�Q�@�c���j��7���ɖ�������J���A������ւ̖@�Ă̒�o��������A�e�}���ň�������������i�߂���ŁA���N�H�ɂ��J�����Վ�����ւ̒�o��ڎw�����j���m�F�����B �@�c�A��7�����̑���ŁA15�Έȏ�̏I�����̊��҂ɑ��鉄���[�u�ɂ��āA�o�ljh�{��l�H�ċz��̑����ȂǁA�V���ɉ����[�u�����{���Ȃ��Ƃ���u�s�J�n�v��ΏۂƂ����u��1�āv�ƁA���ݍs���Ă���[�u�́u���~�v���܂߂��u��2�āv���܂Ƃ߁A������ւ̒�o�Ɍ����A���ꂼ��}���葱����i�߂邱�Ƃ����߂��B ��É��CB�j���[�X -�L�����A�u���C���@2012�N9��7�� |
||||
|
��u���u�z�X�s�X�}�C���h����荇���v �n��Љ�̒��ŃP�A�̏z�� |
||||
| ��t�@�R��@�͘Y�� �@�O�Ȉ�Ƃ��ĂP�U�N�A���̌�P�T�N�{�݃z�X�s�X�A���͂V�N�ԍݑ�z�X�s�X�����Ă���B�O�Ȉ�W�N�ڂ̂W�R�N�A�A�����J�̐��_�Ȉ�̃L���[�u���[�E���X���́w���ʏu�ԁx�Ƃ����{�ɏo�����Đl�����ς�����B �@�O�Ȉ�̍��A���҂��S���Ȃ肻���ȂƂ��ɉ����[�u���Ă������A�قƂ�ǒf��ꂽ�B������҂́A�����҂ɂƂ��ĕK�v�Ȃ��Ƃ��m�F���Ă��Ȃ��ƋC�t�����B �@�l�Ԃ͐g�̓I�A�Љ�I�A���_�I�A�����ăX�s���`���A���ȑ��݁B�X�s���`���A���e�B�͐l���̊�@�ɒ��ʂ����Ƃ��A������͂��]���i�P�j�@���Ȃǎ����̊O�̑傫�Ȃ��́A�܂��́i�Q�j���Ȃ̓��ʁ`�ɋ��߂�@�\�����B�X�s���`���A���e�B���@�\����A�a�C�ɖ|�M�i�ق�낤�j����Ȃ����Ȃ̑��݈Ӌ`�������������Ƃ��ł���B �@�X�s���`���A���e�B������̂ɕK�v�Ȃ̂��R�~���j�P�[�V�����B��������ʼnƂɖ߂��Ă������҂���ɁA�����Ȃ����\��w�����L���鎡�Â��Ă������A���̊��҂���́u���������Ă����̕a�C�͎���Ȃ��ł��傤�H�@���͂��̂܂܉Ƃɂ������v�ƌ������B �@�u���͗]�����������Ȃ��v�ƒQ�����҂���Łu�ǂ��������ł����H�v�ƕ����Ɓu�Ƒ��ɖ��f���|���邩������Ȃ����Ƃɂ������B�������ɉ�����v�ƌ����āA�j�R�j�R�Ƒ��̎����b���n�߂�l�������B �@�O�T�N����n��̒��ɏo�|���Ă����ݑ�z�X�s�X�P�A���n�߂��B��`���Ă�����Ă���{�����e�B�A�W�O�l�̂����A�Q�����S���Ȃ������̈⑰�B�������������P�A�𑼂̐l�ɂ����悤�ƁA�n��̒��ŃP�A���z���Ă���B����ꂪ�ڎw���̂́A�Ō�܂ŏZ�݂����Ǝv����n��Љ�B �@�ۑ�́A�ݑ�×{���J�n�����Ƃ��ɂ͗]���킸���ŁA�����̐l���P�J���ȓ��ɖS���Ȃ邱�ƁB�������ړI�ł���ƁA���҂��������ĕa�@�Ŏ��Â��Ă��邩�낤���B�l���̍Ōキ�炢�A��Â̊Ǘ�����������鐶�������l���Ă�����Ă������̂ł͂Ȃ����B �@�Ƒ��̉��͂̌��E�ȂǂŁA�ݑ����߂ē��@����l������B�����̐l�͉�삳���ł���Γ��@���Ȃ��čςށB�ɘa�P�A�a���́A�ݑ�P�A��⊮��������ɂȂ��Ă����̂��]�܂����B ��܂����E�ӂ݂��@�P�X�S�V�N���������܂�B�X�P�N�����n�l����a�@�����a�@�i�����s������s�j�z�X�s�X�ȕ����B�Q�O�O�T�N�u�P�A�^�E�������v���J�݂��A�ݑ��B�����Ɂw�a�@�Ŏ��ʂƂ������Ɓx�ق������B WEB TOKACHI�@2012�N9��11�� |
||||
|
��17����{�ɘa��Êw�� �ݑ�ɘa�P�A���i�̂��߂̕�������� |
||||
| �@�킪���̔N�Ԏ��S�Ґ��͌��݂̖�110���l����2030�N�ɂ�180���l�ɑ�������Ɛ��肳��Ă���B����ɁC2�l��1�l�͂���Ŏ��S���鎞��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���C�ݑ�ɘa�P�A�̏[���������Ă���B�_�ˎs�ŊJ���ꂽ��17����{�ɘa��Êw��i������R��w��w�@�ɘa��Êw�u���E�������������j�̃C���^�[�i�V���i���V���|�W�E���u�ɘa��Ẫl�b�g���[�N�ƍݑ�v�ł́C�J�i�_����ɘa��Ãl�b�g���[�N�\�z�̎��ۂ��Љ��C���{����͍ݑ�ɘa�P�A���i�̂��߂̐f�Õ�V���肨��ђn��ł̎��g�݂����ꂽ�B �d�v�Ȃ͎̂��S�ꏊ�ł͂Ȃ��P�A�̏ꏊ �{�݊ԘA�g�E���E��A�g���K�v �܂��͈�Î҂���ӎ����v���K�v �d�v�Ȃ͎̂��S�ꏊ�ł͂Ȃ��P�A�̏ꏊ �@�A���o�[�^��w�i�J�i�_�E�G�h�����g���j��ᇊw�Ȋɘa��Ó��Ȃ�Robin L. Fainsinger�����́C�G�h�����g���Œn��ɘa��Ãv���O�����𗧂��グ�C�l�b�g���[�N�̍\�z�ɐ����B�ɘa��ẤC���S�̏ꏊ�ł͂Ȃ��P�A����ꏊ���d�v�ł��邱�Ƃ����������B ��Ô���グ�邱�ƂȂ��ݑ�P�A�� �@1990�N��C�G�h�����g���ł͊ɘa��Â����B���Ă��炸�C���҂�85�����}�����a�@�Ŏ��S���Ă����B���̂��߁C��Ô�̍����������C��Ô�팸�C�}�����a�@�̃x�b�h�������Ȃǂɔ���ꂽ�B �@������Fainsinger������́C1995�N����n��ɘa��Ãv���O�������J�n�����B����́C�}�����a�@�ł̊ɘa�P�A���ݑ�ɘa�P�A���邢�̓z�X�s�X�ɘa�P�A�a���Ɉڍs�����邱�Ƃ�ڎw�������́B�ɘa�P�A�Ǘ����������n��̊ɘa�P�A�Ɋւ�����⊳�ҏ��Ȃǂ�S�Ĕc�����C�n��ɂ��鍂���ɘa�P�A�a���C�}�����a�@�C����Z���^�[�C�z�X�s�X�ɘa�P�A�a���C�n��ɘa��Ð��R���T���e�B���O�`�[������эݑ�ɘa�P�A�����C���҂���ԂɓK�����ꏊ�Ŋɘa��Â�����悤�ɃR�[�f�B�l�[�V�������s���B���̃v���O�����͔҂ɂ��K�p�����B �@���v���O���������ɂ��C�����O�͋}�����a�@�ł̂���֘A����86���ł������̂��C�������49���Ɍ������C���@��������3����1�ȉ��ɒZ�k�����B �@�܂��C1993�`2000�N��7�N�Ԃɂ킽���Ė�1��6,000��̊��҂��t�H���[�����Ƃ���C���v���O���������ɂ��C��Ô�オ�邱�ƂȂ��C�ɘa��ÃT�[�r�X�̒������邱�Ƃ��ł����B����ɁC���S�ꏊ�͋}�����a�@�C�z�X�s�X�C�ݑ�Ȃǂɕ����ꂽ���C���S�O1�N�Ԃ̃P�A�̏ꏊ�͂قƂ�ǂ��ݑ�ł������B �@�������́u�Ŋ���1�N�Ԃ͎���ʼn߂����C�Ŋ��̐���������a�@�Ō}���邱�Ƃ́C����Œ������Ԃ��߂��������Ƃ������ҁE�Ƒ��̊�]�����Ȃ�����̂ł���B���S�ꏊ�ŃP�A�̎���]���ł�����̂ł͂Ȃ��C�d�v�Ȃ��Ƃ͎��S����ꏊ�����C�ǂ��ŃP�A���邩�ł���B�{�v���O�����̐����́C�ɘa��Âɑ����Ï]���҂⊳�ҁE�Ƒ��C��ʎs���̈ӎ����ς��C���ҁE�Ƒ����ɘa�P�A����ꏊ��I���ł���悤�ɂȂ������Ƃł���v�Əq�ׂ��B �{�݊ԘA�g�E���E��A�g���K�v �@���{��t��̎O��T�i��C�����́C�ݑ�ɘa��Â𐄐i���邽�߂ɂ́C�{�݊ԘA�g�Ƒ��E��A�g���K�v�ł��邱�Ƃ��������C����24�N�x�̐f�Õ�V����ɂ�����ݑ��ÁE�ɘa�P�A�ɂ�����f�Õ�V�̕]���Ȃǂ��T�������B �ۑ�͈�t�ȂǃX�^�b�t�̊m�� �@�ݑ�ɘa��Â��s�����߂ɂ͍ݑ��Â��g�債�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����C���{��t��������@�\��2011�N�̕ɂ��ƁC�L���f�Ï��ɂ��ݑ�×{�x���f�Ï��i�ݎx�f�j�̓͂��o��4�����炸�Ə��Ȃ��C�܂���s�s�قǓ͂��o�����Ȃ��Ƃ����n��Ԋi�����������B�L���f�Ï����ݑ��Â����{���Ȃ����R�Ƃ��āu��t�̗]�T���Ȃ��C�X�^�b�t�̊m�ۂ�����C�s�ݎ��̈�t�̊m�ۂ�����v�Ȃǂ�������ꂽ�B �@����24�N�x�f�Õ�V����ł́C�ݑ��Â̊g��ɂ�24���ԑΉ����[��������̐����K�v�Ƃ̊ϓ_����C�u��Έ�t3�l�ȏ�C�ߋ�1�N�Ԃɋً}���f5���ȏ�C�Ŏ��2���ȏ�Ƃ����lj��v�������@�\�����^�ݎx�f�E�ݑ�×{�x���a�@�i�ݎx�a�j�v���V�݂���C�����̕ی���Ë@�ւ̘A�g�ɂ���Ă����l�̓_�����Z��\�ƂȂ����B �@���ۂɂ́C�ݑ��Â̏[���Ƃ��āC�ً}���E��Ԃ̉��f���̈����グ�C�ً}���ݑ�ғ��@�f�É��Z�̈����グ�C�ݑ�^�[�~�i���P�A�ƊŎ�肪�ʂ̈�Ë@�ւ̏ꍇ�ł����Ă����ꂼ��̎{�݂ōݑ�^�[�~�i���P�A���Z�ƊŎ����Z�̎Z�肪�\�ƂȂ�Ȃǂ̕]�����Ȃ��ꂽ�B �@�܂��C�ݑ�ɘa�P�A�̏[���Ƃ��ẮC�ݑ����ᇊ��ҋ����w���Ǘ����̐V�݁C������K��Ō엿�̐V�݁C�ݑ���Ñ����f�×��i���̕ύX�j�̈����グ�Ȃǂ��s��ꂽ�B �@����ɁC�ݑ��Â�S���{�݂ƕa�@�Ƃ̘A�g���K�v�ł��邱�Ƃ���C�n��A�g�p�X�̕]�����f�Õ�V�Ɖ���V�̓�������Ŋg�[���ꂽ�B �@�O���C�����́u�ݑ�ɘa�P�A��i�߂�ɂ́C�e�n��ɂ�����{�݊ԘA�g�Ƒ��E��A�g���K�v�ł���C����Ȃ�����������̐Ӗ��ł���B�܂��C�ɘa�P�A���C�̊g����K�v�ł���B���ی����x�Ɋւ��ẮC�������҂̉��F���Z���Ԃɍs���C���邢�͏�Ԃ̈��������z���č���������s���ȂǁC���҂̏Ǐ�̕ω��ɑΉ��������T�[�r�X�ւ̃A�N�Z�X���m�ۂ�����K�v�ł���B�������C�ݑ��ÁE���̘A�g���l����ۂɂ́C�e�n��̓������l�������Ή������߂���v�Əq�ׂ��B �܂��͈�Î҂���ӎ����v���K�v �@���c�s���a�@�i���{�j�ɘa�P�A�`�[���̑��c�K���O�Ȏ�C�����́C2007�N�Ɉ�Ï]���҂Ǝs���𒆐S�Ƃ���u���c�ݑ�P�A���l�����v��ݗ��B���̊�����1�Ƃ��āC�ߗׂ̍ݑ�P�A���K��Ō�X�e�[�V������T���ꏕ�ƂȂ�悤�u�ݑ�P�A�}�b�v�v���쐬�����B����C�}�b�v���쐬���邽�߂Ɏ��{�����A���P�[�g�̌��ʂ���C�n��ɂ�����ݑ�ɘa�P�A�𐄐i���Ă����ɂ́C�܂���Ï]���҂ւ̌[���C�ӎ����v���K�v�ł��邱�Ƃ�����B �ݎx�f�ł͖K��f�Ñ̐�����ɉ� �u���c�ݑ�P�A���l�����v�́C�a�@�E�ݎx�f�E�ی���ǁE�K��Ō�X�e�[�V�����i�K��Ō�X�e�j�Ȃǂ��A�g���āC�ݑ�ɘa�P�A���p���I�ɒł���l�b�g���[�N�Â����ڎw���Ƃ������́B�u�ݑ�P�A�}�b�v�v���쐬���邽�߁C�ݎx�f51�{�݁C�K��Ō�X�e25�{�݁C�ی����90�{�݂�ΏۂɁC�ݑ�P�A�Ɋւ���A���P�[�g�����{�����B���͍ݎx�f26�{�݁i51���j�C�K��Ō�X�e8�{�݁i32.0���j�C�ی����36�{�݁i40.0���j�ł������B �@�܂��C�ݎx�f�ł́C�ݑ�P�A�}�b�v�ւ̎{�ݖ����J�����������̂́C11�{�݂Ə��Ȃ����ɓI�ł������B1�N�Ԃ̖K��f�Ó��e������ƁC�ɘa�P�A�ɓ������Ă���{�݂ƁC�ʏ�̐f�ËƖ����s���Ȃ���ݑ�P�A���s���Ă���{�݂ɓ�ɉ����ꂽ�B����C�K��Ō�X�e�ł́C�}�b�v�ւ̎{�ݖ����J��8�{�݂��������C�����̎{�݂��u�Ŏ�莞�̉Ƒ��ւ̏�������v��u�����ɖ�̕���Ǘ��v�Ȃǂ����ۂɍs���Ă���C�ɘa�P�A���C�ւ̎Q�����ϋɓI�ł������B�ی���ǂɊւ��ẮC�}�b�v�ւ̎{�ݖ����J��32�{�݂��������C�ϋɓI�ł��������C�K���w���͔����̎{�݂����{���Ă��炸�C�ɘa�P�A���C�ւ̎Q���\��Ȃ���19�{�݁C����舵�����s��8�{�݂������B �@�����������ʂ܂��C���c�O�Ȏ�C�����́u�ݑ�P�A�𐄐i�����ł́C�K��Ō�X�e���ϋɓI�ł�����҂ł��邪�C�f�Ï��ɂ��Ă͕����̎{�݂��A�g����K�v������B�܂��C�ی���ǂ�1�l�̖�t����ǂɏ]�����Ă���ꍇ�������C�ݑ�P�A����ɂ��鐔�l�̖�t�������ǂɍݑ�P�A���W���邱�Ƃʼn\�ƍl������v�Ƃ��C����Ɂu���܂��ɘa�P�A�͕a�@�łƂ����ӎ�����Ï]���҂ɂ���ʎs���ɂ����邽�߁C���C����w���ւ̋���𒆐S�ɁC�܂��͈�Î҂���ӎ����v���K�v�ł���v�Ƌ��������B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N9��27�� |
||||
|
�ɘa�P�A���i��������ԂƂ�܂Ƃ� ����f�ØA�g���_�a�@�Ɋɘa�P�A�Z���^�[�� |
||||
| �@�����J���Ȃ͑�5��ɘa�P�A���i�������9��26���ɊJ���A�ɘa�P�A�`�[�������ϋɓI�Ɋ��f�ÂɊւ�邱�Ƃ��ł���悤�A����f�ØA�g���_�a�@�ȂǂɁu�ɘa�P�A�Z���^�[�v�����邱�ƂȂǂ����߂����ԂƂ�܂Ƃ߈Ă��ŗ��������B �@���ԂƂ�܂Ƃ߂́A���Ɛf�f���ꂽ�Ƃ����炠���銳�҂Ɋɘa�P�A��ł���悤�ɂ��邽�߂̕�����܂Ƃ߂����́B����̊ɘa�P�A�̐����������邽�߁A����f�ØA�g���_�a�@�Ȃǂɂ����āA�ɘa�P�A�Z���^�[�����邱�Ƃ����߂��B���Z���^�[�ɂ͊ɘa�P�A�`�[����ɘa�P�A�O���̉^�c�ɉ����A�n��̈�Ë@�ւƂ̘A�g������ɘa�P�A�֘A���C��̉^�c�A�ɘa�P�A�f�Ï��̏W��Ȃǂ��s���@�\����������B �@�ɘa�P�A�Z���^�[�ɂ́A�ݑ�ŗ×{��������҂��u�ɏǏ��������ۂȂǂɁA�ً}�ɑΉ��ł���@�\�����߂�B�Ⴆ�A�ɘa�P�A�a���̂Ȃ����_�a�@�Ȃǂɂ����ẮA��ʕa���̈ꕔ���ً}�ɘa�P�A�a���Ƃ��A�u�ɂ̊ɘa��ړI�Ƃ����ً}���@���ł���̐�����邱�ƂȂǂ�z�肵�Ă���B �@�܂��A���f�Âɂ�����g�̓I��ɂ̕]�����O�ꂳ���悤�A����f�ØA�g���_�a�@�ɂ́A�O�����̖�f�\�Ɂu�u�ɓ��̐g�̏Ǐ�v�̍��ڂ�݂�����A�J���e�̃o�C�^���T�C���̗����u�ɂ̍��ڂ�݂��邱�ƂȂǂ𐄐i����B���_�S���I��ɂɑ���ɘa�P�A�̒��[�������邽�߁A���f�ÂɌg���Ō�t�Ɍ��C���s�����Ƃ�A�Ō�t�ɂ��p���������k�x�����s���̐������邱�Ƃ����߂�B �@���ԂƂ�܂Ƃ߂́A�ߓ����ɍŏI�ł��m�肵�A�����J���Ȃ̌��N�ǒ��ɒ�o�����B���J�Ȃ�2013�N�x�̊T�Z�v���ŁA�V�K���ƂƂ��āu����Ɛf�f���ꂽ������̊ɘa�P�A�̐��i�v��8.2���~���v�サ�Ă���B���̎��ƂŁA����f�ØA�g���_�a�@�Ɋɘa�P�A�Z���^�[��������A���Z���^�[�ɋً}�ɘa�P�A�a����݂���v�悾�B ���o���f�B�J�� �I�����C���@2012�N9��27�� |
||||
| �u�������@�����v�͈�Êi���̊g����������˂Ȃ��\����L���q���C���^�r���[�� | ||||
| �@�O��́A�u�������̖@������F�߂Ȃ��s���̉�v�Ăт����l�E����L���q���C���^�r���[�u�w�������@�����x�͎��͂̐l�Ԃ���h���E���~�߂錠���h��D���v���f�ڂ������܂����B����́A�ǎ҂��炢�������������ӌ��ɐ������������҂����͂����܂��B �u�������@�v�Ɋ�Â�������̐��X�́A��Ô�̒����i�k���j�@�\ �\�O��̋L���ɑ��āA�u�������@�����������Ƃ��Ă��A����Ȃɉe��������Ǝv���܂���ł����v�u�@���x�����ꂽ�瑸�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��̂�����A�������ɔ�����l�́A�@���o���Ă������͓��ӂ��Ȃ�����������̘b�ł́v�Ƃ��������z�����Ă��܂��B����̖@�Ă̖��_�ɂ��āA���������ڂ��������Ă��������܂���ł��傤���H ������F�܂��A���}�h�́u�������@�������l����c���A���v���A�����`����E���������Ŗ@�Ă�����A�c���ʂ����Ƃ��Ă���Ƃ���ɖ�肪����܂��B �u�������@�������l����c���A���v�̑��q��́A�Q�̖@�Ă͊e�}�Ɏ����A���A��������Ă���ƌ����Ă����܂������A�u�������̖@�����ɔ������v���s��������c���Ώۂ̃A���P�[�g�����ɂ��i�߁X���\�����悤�ł��j�A�e�}�Ō������ꂽ�l�q�͂Ȃ��A�c�A�̋c���̑����͐[���l�����A���t�������ŋc�A�ɖ��O��A�˂Ă��Ă��邾���̂悤�ł��B �@�e�}�̌����J���ψ���ł̐R�c���Ȃ��A�@�Ă����\���p�u���b�N�R�����g�����߂�Ȃǂ̎葱�����ʂ����ɁA���̗Վ�����ɏ�����c���悤�ƌ����̂́A���܂�ɗ��\�Ȃ����ł͂Ȃ��ł��傤���B ���������l�̑������ǂ��l����̂��B�����āu�I�����v��������ƍl����̂��B �@����͒�`�ł��Ȃ����̂ł��B�u�S���Ȃ��ĐU��Ԃ��āA�������̎����炪�w�I�����x�������̂��Ə��߂Ă킩��v�Ƒ����������̒������������Ă��܂��B�����@�����ňꗥ�ɒ�`���悤�Ƃ��Ă���킯�ł��B �u�@�����ł��Ă��e���͂Ȃ��B���Ȃ�g��Ȃ�������B�D���Ɏ��Â𑱂�������v�ƌ�����̂ł����A�@���ɏ]��Ȃ��l�́A�u���ł��g���Ė��ʂȎ��Â����Ă���l�v�u���Ȏ�`�ҁv�u���v�̃��b�e����\����悤�ɂȂ�ł��傤�B���ƂƂ��āA�ꗥ�Ɂu�������u�v�u�I�����v���`���A���������N�Ȃ����ɒ�`�ʂ�Ɏ��ʂ��Ƃ����琾�킹�邱�ƂɂȂ�܂��B �@�����S�̂ɕ��y�����A���ׂ������Ƃ��čL�߂邱�ƁB���ꂪ�@�����ł��B���̎��ɕ�����{�Ƃ��āA�q�ǂ����獂��҂ɂ܂œO�ꂵ�Ē蒅�����A��点�邽�߂̂�����{�u������悤�ɂȂ�܂��B �@�@�Ă������ƌ��Ă����܂��傤�B �@�@�ĂP�@�ĂQ�̑�O���u�I�����̈�Âɂ��č����̗�����[�߂邽�߂ɕK�v�ȑ[�u���u����悤�w�́v�A��\����u���y�ђn�������c�̂́A������������@���ʂ��ďI�����̈�Âɑ��闝����[�߂邱�Ƃ��ł���悤�A�����[�u�̕s�J�n�i���āj�ƒ��~�i���āj����]����|�̈ӎv�̗L�����^�]�Ƌ��؋y�ш�Õی��̔�ی��ҏؓ��ɋL�ڂ��邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ��铙�A�I�����̈�ÂɊւ���[���y�ђm���̕��y�ɕK�v�Ȏ{����u������̂Ƃ���B�v�Ƃ���܂��B �@����Œn�������c�̂́A�@����ϋɓI�ɍL�߂邽�߂̎��Ƃ��s�����ƂɂȂ�̂ŁA�w�Z��a�@�Ȃǂł́A�I�����̐l�H�ċz���݂낤�Ȃǂ̎��Â�f��|�������������Ƃ�ϋɓI�ɐ������Ă������ƂɂȂ�܂��B��������15�Έȏ�ɓK������Ƃ���A�Ƌ���ی��̗��ɋL�ڂ�����Ƃ����̂ł����A����ł͏��������͔��ɍ���ł��B �@��\����ł́u�����J���ȗ߂ւ̈ϔC�v�A�����R�ł́u���̖@���̎{�s��O�N��ړr�Ƃ��āA���̖@���̎{�s�̏A�I�����ɂ��銳�҂���芪���Љ�I���̕ω��������Ă��Č������������A�K�v������ƔF�߂���Ƃ��́A���̌��ʂɊ�Â��ĕK�v�ȑ[�u���u������ׂ����̂Ƃ���v�Ƃ���A�����J���Ȃɂ����āA����̏�ɑ����ĂR�N���ƂɌ������Ă����̂ł��B �@�܂�A���{�o�ςɘA��������Ô�팸�̐�D�Ƃ��āA���́u�������@�v�Ɋ�Â�������̐��X�́A����ҁA��Q�҂Ȃǂ̎Љ�I��҂ɑ����Ô�̒����i�k���j�@�\�̖��������ƂɂȂ�܂��B �\��t���Ɋ|���镉�S���w�E���鐺������܂����B�u���A��҂̔��f�ʼn����[�u���~�߂�ƁA��҂��E�l��Ƃ������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��v�Ƃ����ӌ��ł��B���̓_�ɂ��ẮA�ǂ��ł��傤���H�@��������Ă��Ȃ�����ɂ����āA�ǂ̂悤�Ɂu�������v���i�߂��Ă���̂��Ƃ��킹�ċ����Ă��������B ������F���݂ł��A���Â̕s�J�n�ɂ��u�������v�͎��{����A�݂낤��ċz��̒��~���s���Ă��܂����A������Ƙb���������Ȃ���Ă���A���ɂȂ�P�[�X�͏��Ȃ��ł��B �@��t���E�l�߂ɖ����̂́A�Ƒ��ɐ��������������ɑ��k�������A������ƑP�I�ɍs�����ꍇ�B�a�@�̋Ζ���͌����̏�A������ʂɋ~�}��������Ă���a�l�Ƀx�b�h�������悭�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����Ȉ�t�̐Ӗ����y�����A�ƒf������邽�߂ɁA���́u�I������Â̌���v���Z�X�Ɋւ���K�C�h���C���v��2007�N�ɍ��肵�A���E��ɂ�鑊�k�̐���Ƒ��̓��ӂɊ�Â���Â𐄏����܂����B����ň�t����l�Ō���A�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ȃ�͂��ł��B �u�I������Â̌���v���Z�X�Ɋւ���K�C�h���C���v �@�������A���̂��т̖@�Ă̑�l���A��Z���͂���ɂ��t�s���Ă��܂��B �@��t�Q���ŏI������ł��邱�Ƃɂ��Ă��邩��ł��B���E���Ƒ��Ƃ́u�M���W�Ɋ�Â��v�Ƃ͂��邪�A���ӌ`���̋`���ɂ��Ă͏�����Ă��܂���B����͎�Ԃ��Ȃ��A�����̈�t�Ŗ��������肵���Â̒�~���ł���悤��������_�������̂̂悤�ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B �@�������̖@�����ɂ��A���@���ɂ͕K����@���ɑ����āu�������Áv��f��|����M���������悤�ɂȂ�ł��傤�B�i�u�������Áv�Ɣ��肷��͖̂{�l�ł��Ƒ��ł��Ȃ��a�@�ł����j�B �@���̂悤�ɂ��Ă����A�Ƒ������ӂ��Ă��Ȃ��̂ɑ����������Ă���t�͖ƐӂɂȂ�܂��B �@�����Ė{�l���u����J�[�h�v���g�т��Ă���A�����̉\���������Ă��A�l�H�I�Ɂu������������v���ƂɂȂ肩�˂܂���B���Ƃ��A��ʎ��̓��ňӎ��s���̂P�T�̎q�ǂ��̉Ƒ����A�ϋɓI�Ȏ��Â�v�����Ă���ꍇ�ł��A���N�̏]�O�̈ӎv�ɏ]���A��̎��Â������u�]���v�Ɏ������݁A���̑�������o���Ă悢�̂��́A�c�_�̗]�n������Ƃ���ł��B �������@�����́u��Êi���v�̊g��������\���� �\����҂̉����̖��Ƃ��킹�āA�o�ς��܂߂����\�[�X�̊ϓ_����A�������̕K�v�����咣����ӌ�������܂����B�u���Â�҂l�̐��_�I�E���̓I���S�����炷���߂ɂ́A��ÑS�̂̃{�����[�������炷���Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�u�����𑱂��邱�ƂŁA�Ƒ��̕��S�͑����A�����̂⍑�̕��S�������B�Ƒ��͍��Y������Ԃ��A���̍����͈�������v�Ƃ������ӌ��ł��B���̓_�ɂ��ẮA�ǂ̂悤�ɂ��l���ł��傤���H ������F����A�Ό��L�W�����e���r�ŁA�u���{�o�ς̗��Ē����̂��߂ɂ͏I������ÑK�v�A���̂��߂Ɏ����͑���������ɓ���v�ƌ����Ă��܂������A����͑������̖@���������̌o�ϑ�̓�����ƌ��Ȃ���Ă���؋��ł��B �@���̖@���ɂ��A�����I������3�N���ƂɌ������A��`�������ē������ł���̂ŁA��p�Ό��ʂ̃G�r�f���X���Ȃ��������Q�̂��鍂��҂ɂ͕ی��̓K�����l�߂Ă������Ƃ��ł��܂��B �@���ꂪ�i�߂A���{�̌ւ鍑���F�ی����x���C�M���X�̂m�g�r�̂悤�ɁA���I�ی��Ŏ��鎡�Â͈̔͂͋��܂���e�����e���ɂȂ�܂��B�I�����łȂ��Ă��݂낤�݂��Ă��炦�Ȃ��Ȃ�A���͂��̑��̍��z��Â͕ی��Ŏ��Ȃ��Ȃ�B���Ȃ獂���ȃv���C�x�[�g�f�Â�I������Ƃ������ƂɂȂ�A��Êi���͊g�傷��ł��傤�B�K�Ȉ�Â����Ȃ��l�����Ă����Ǝ����Ƃ����Љ�ɂȂ��Ă������˂܂���B �@�����ɐϋɓI�ɑ�������I�������邱�Ƃň�Ô���l�߂���A�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�������̈��S���S�̂��߂ɂ́A���̐l���Ƃɉߕs���̂Ȃ���Â�͂�����悤�ɂ��Ă����B���̂��߂̖@���x���l����̂��A�����̖����ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����B �\�{���͂��肪�Ƃ��������܂����B �v���t�B�[���@����L���q�i���킮���E��݂��j�F�u�������̖@������F�߂Ȃ��s���̉�v�Ăт����l�B2005�N���{ALS������A�C�B2009�NALS/MND���ۓ�����c�����A�C�B BLOGOS�@2012�N9��28�� |
||||
|
�g�ђ[���ł��҂̃P�A�̎�������H ��V���Տ������̌��ʂ����\ E-MOSAIC�iSAKK 95/06�j���CESMO 2012 |
||||
| �@�ߔN�C�ڊo�܂��������ŕ��y���Ă���g�я��[���iPDA�j��X�}�[�g�t�H���́C��̂Ђ�T�C�Y�Ŏ����^�т��₷���C���܂��܂ȏ�
���f�������́E�����ł��邽�߁C�i�s���҂̃P�A�ւ̉��p����������Ă���B�X�C�X�̂���Տ������O���[�v�iSwiss
Group for Clinical Cancer
Research�j�́C�ɘa�P�A�̕K�v�Ȑi�s���Ҏ��g���Ǐ��PDA�Ŗ��T�L�^���邱�Ƃɂ��C���҂̏Ǐ���Î҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɕω�����
���邩�ɂ��āA���{�����N���X�^�[�����_������V���Տ����������{�B2012�N���B�Տ���ᇊw��N���w�p�W��iESMO
2012�G9��28���`10��2���C�E�B�[���j�ɂ����ē��O���[�v��Florian
Strasser�����C���̐��ʂ�����ꂽ���Ƃ����ꂽ�B �����̏Ǐ�C���p�����x���Ö@��ȂǂT�L�^ �@���O���[�v��Palm�Ђ�PDA�ŏǏ��h�{�ێ��ԁC���p�����x���Ö@��C�S�g��ԁiKarnofsly PS�j�C�̏d�Ȃǂ���͂ł���悤�ɂ��C���̃v���O������E-MOSAIC�Ɩ����B�]���̗p���L�^���Ɣ�r���āCE-MOSAIC������ QOL�iglobal quality of life�j�⊳�҂̏Ǐ�C���҂ƈ�t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɂǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ�����]�����邱�ƂƂ����B ��t�ɂ��o�^�K���u���Ìo���L���ŃR�~���j�P�[�V�����͂�L���c�v �@���҂̓o�^�K���́C�ɘa���Â��Ă���؏��s�\�i�s����ŁC�R������Â��O���ŎĂ���҂̑S�g��Ԃ̈����Ǘ�Ƃ����B��t�̓o�^�K���́C���Ìo ���L���ŃR�~���j�P�[�V�����͂�L���C�ɘa���Ö@�̌��茠��L����҂Ƃ��ꂽ�B��v�]�����ڂ́C�x�[�X���C����6�T�ڂɂ����鑍��QOL�̍��Ƃ��C�ړx�� ��EORTC-QLQ-C30�̍���29�C30���g�p�B2�Q�Ԃ�10�|�C���g�̍����F�߂�ꂽ�ۂɗՏ��I�Ӌ`��������̂Ɛݒ肵���B�����]�����ڂ��x�[�X ���C����6�T�ڂɂ�����Ǐ�̂炳�̕ω����G�h�����g���Ǐ�]���ړx�iESAS�j��p���ĕ]�������B�܂��C���҂ƈ�t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������邽 �߁C���҂̊������t�̗D���������o�I�A�i���O�X�P�[���iVAS�j�ŕ]�����邱�ƂƂ����B �p���L�^���Ɣ�ׂāC�Ǐy������t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������� �@�X�C�X������8�{�݂��Q�����C��t84�l�C����264�l���o�^���ꂽ�B���҂̐������Ԓ����l��5.8�J���iE-MOSAIC�Q6.3�J���C�p���L�^�Q 5.4�J���j�ł������B��͂́C�x�[�X���C���̑���QOL�₻�̑��̋��ϗʂŕ�����������ʃ��f���imixed effects model�j�ōs��ꂽ�B��v�]�����ڂł���x�[�X���C����6�T�ڂɂ����鑍��QOL��2�Q�Ԃ̍���6.84 �|�C���g�ƁC���v�w�I�L�Ӎ��͊m�F����Ȃ������iP��0.111�j�B����C�����]�����ڂł���Ǐ�̂炳�́CE-MOSAIC�Q�|4.9�i���P�j�C�p�� �L�^�Q2.0�i�����j�ł���CE-MOSAIC�Q�œ��v�w�I�L�ӂɉ��P���邱�Ƃ������ꂽ�iP��0.003�j�B�܂��C���҂̊������t�̗D������E- MOSAIC�Q�ŗL�ӂɌ��サ�����i��18.9�CP��0.014�j�C�p���L�^�Q�ł͑傫�ȕω��͌����Ȃ������i��4.7�CP��0.403�j�B �@�ȏォ��CStrasser���́u��v�]�����ڂ͒B������Ȃ��������CE-MOSAIC�̗��p���C�Ǐ�̂炳�⊳�҂ƈ�t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������� �P�����邱�Ƃ������ꂽ�v�Ƃ��A�u��������҃T�|�[�g�̂��߁C�c�[���̊J�����t�Ԃ̃l�b�g���[�N�\�z�ȂǁC����Ȃ���g�݂��K�v�v�Ƃ܂Ƃ߂��B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N2012�N10��5�� |
||||
|
�i�s���� ���S���O��ICU���e��@�����S�̉���������I����QOL�Ƒ��� |
||||
| �@�_�i�E�t�@�[�o�[�������iDFCI�j�S���Љ��ᇊw�ƃn�[�o�[�h��w�i�Ƃ��Ƀ{�X�g���j���_�����w��Holly G.
Prigerson�y������́C�i�s���҂̏I����QOL����Ɋ�^������q���������CArchives of Internal
Medicine�i2012; 172:
1133-1142�j�ɔ��\�����B����ɂ��ƁC���@��W�����Î��iICU�j���e�̉���C�s���̌y���C�F����ґz�C�{�݂̖q�t�ɂ��P�A�C���Âɑ����
�t�Ɗ��҂̋��͊W���C����QOL�Ƒ��ւ��Ă����B 9���ڂ��琬��\�����q�̃Z�b�g����� �@���҂̂����͂⎡���s�\�ɂȂ����ꍇ�C�P�A�̏œ_�͉�������I������QOL���P�Ɉڍs���邱�Ƃ������B�������C����̌����̔w�i���ɂ��ƁC�I����QOL�̗\�����q�Ɋւ��āC����܂ň�т����f�[�^�͑��݂��Ȃ������B �@�����ŁC�M�������҂ō���̌������{����DFCI�̌������ł�����Baohui Zhang���́C�l���Ŋ���1�T�Ԃɂ�����QOL�Ɋւ��C�ł��D�ꂽ�\�����q�̑g�ݍ��킹����肷�邽�߂ɍ���̌��������{�B���̌��ʂ�p���āC�������� ��QOL���P�Ɍ�������É���̗L�]�ȕW�I�����ɂ߂悤�Ǝ��݂��B �@����̌�����Coping with Cancer Study�̈�Ƃ��āC2002�N9��1������2008�N2��28���Ɏ��{���ꂽ�B�Ώۂ́CDFCI�Ȃǂ̎{�݂̐i�s����396��i���ϔN���59 �j�Ƃ��̉��҂ŁC�o�^���玀�S�܂Ńt�H���[�A�b�v�i�����l4.1�J���j�����B �@���܂��܂ȗ\�����q�̑g�ݍ��킹�������������ʁC �i1�j�Ŋ��̏T�ɂ�����ICU���e�iQOL�̒ቺ�Ɗ֘A�j �i2�j�@�����S�iQOL�̒ቺ�Ɗ֘A�j �i3�j�o�^���]���ɂ����銳�҂̕s���iQOL�̒ቺ�Ɗ֘A�j �i4�j�o�^���ɂ����銳�҂̏@���I�F����ґz�̒��x�iQOL�̏㏸�Ɗ֘A�j �i5�j���Î{�� �i6�j�Ō�̏T�ɂ�����o�ljh�{�g�p�iQOL�̒ቺ�Ɗ֘A�j �i7�j�a�@��N���j�b�N�̖q�t�ɂ��P�A�iQOL�̏㏸�Ɗ֘A�j �i8�j�Ō��1�T�Ԃɂ����鉻�w�Ö@�iQOL�̒ቺ�Ɗ֘A�j �i9�j���Âɑ��銳�҂ƈ�t�̋��͊W�iQOL�̏㏸�Ɗ֘A�j ��9���ڂ��琬��ϐ��Z�b�g�ɂ��C�Ŋ���1�T�Ԃɂ�����QOL�̂قƂ�ǂ�������邱�Ƃ��ł����B �@�����́u�I������QOL�s�ǂ��K�肷��ł��d�v�Ȉ��q�́C�@�����S�ƍŊ��̏T�ɂ�����ICU���e�ł������B���������āC��p�̂�������@��������C���@ ���҂�����������̓z�X�s�X�Ɉڂ����݂ɂ��C�I�����̊��҂�QOL�����P����\��������v�Əq�ׂĂ���B����Ɂu����̌����ł́C�x�[�X���C���ɂ��� �銳�҂̕s�����̋������C�I����QOL�s�ǂ̗L�͂ȗ\�����q�ł������v�Ǝw�E���Ă���B �ʼn߂���Ă����I����QOL �@Zhang���́u���҂̕s�����y�����C�ّz�����サ�C�p�X�g�����P�A�����������B�܂��C���Âɑ��銳�҂ƈ�t�̋��͊W����݁C�s�v�ȓ��@�≄�����Â�������邱�ƂŊ��҂͍Ŋ��̐������ł����炩�ɉ߂������Ƃ��ł���v�ƌ��_�t���Ă���B �@�č�����������iNIA�j���������v���O������Alan B. Zonderman�CMichele K. Evans�̗����m�́C�����̕t���_�]�i2012; 172: 1142-1144�j�Łu����܂ł̂����Âł͖������҂ɂ�����I����QOL�̖��͊ʼn߂���C���ʓI�����זE�Ő���L����V��������@�̊J���ɖ� ���������Ă����B�����̑S�o�߂ɂ킽���Ĉ�ѐ��̂��邪�Ð헪�𗧂Ă��ŁC�I����QOL�̌����͌������Ȃ��B����ɂ�������炸�C���̗̈�ɂ��� �錤���͂��܂�ɂ��s�����Ă���v�Ǝw�E���Ă���B �@����Ɂu���݁C���G�ő��l�Ȃ��Ð헪�̊J���⓱�������X�Ɛi��ł������ŁC�I����QOL�ɑ傫���e��������q�Ɋւ��ẮC���܂����m�ɒ�`�ł��� ���Ȃ��͈̂ӊO�ł���v�Əq�ׁC�u����̌����́C�č��Տ���ᇊw��iASCO�j�̐����Ɠ������C�i�s���҂ɑ���ɘa�P�A�̑����������x��������̂� ����v�ƕt�������Ă���B �����҂₻�̉Ƒ��́u�S�v����I�ɃP�A���邱�ƁB��̓I�ɂ͗�I�P�A�i�X�s���`���A���P�A�j����я@���I�P�A�����S�ƂȂ� ���f�B�J���g���r���[���@2012�N10��18�� |
||||
| �������ҁ@��ɂ�j�[�Y�������C�K�ɕ]���C�Ή� | ||||
| ��41����{�����S�g��w�� �@�������҂́C�l�Ƃ��Ă܂������Ƃ��Ă��܂��܂ȋ�Y������Ă���B�����s�ŊJ���ꂽ��41����{�����S�g��w��i���������Ȏ��ȑ�w��w�@���B �@�\���֊w����E�v�ۓc�r�Y�����j�̃V���|�W�E���u�����̂���ƐS�̃P�A�v�k������������Ȏ��ȑ�w��w�@�S�ÁE�ɘa��Êw����E�����p����C�����a�@ �@�\�����a�@�ɘa�P�A�ȁE�i��p�����i�ċz����ȊO���f�Õ����j�l�ł́C���_��ᇈ�C��ᇓ��Ȉ�C�ɘa�P�A��炪��Y��������������҂̐S�̃P�A�ɂ� ���ĕB��ɂ�j�[�Y�������C�K�ɕ]���C�Ή����邱�Ƃ̏d�v����i�����B���̈ꕔ�����B �S�l�I��ɂւ̓K�ȕ]���E�Ή��� ��ᇓ��Ȉ�́u���ē����v �X�s���`���A���j�[�Y�������x���� �S�l�I��ɂւ̓K�ȕ]���E�Ή��� �@��ʈ�ȑ�w���ۈ�ÃZ���^�[ ���_��ᇉȂ̑吼�G�������͂��҂Ƃ��̉Ƒ��̐S��f�鐸�_��ᇈ�̗��ꂩ��C�u�����ɂ͊e�N��C�����ɉ������S�l�I��ɂ�����C�����K�ɕ]���E�Ή����邱�ƂōK���Ȑ������ł���悤�ɂȂ�v�Əq�ׂ��B ���҂̐��_��w�I�L�a��50�� �@���҂ɂƂ��āu����v���Ӗ�������̂́u���v�ł���C���S������1�ʁC���ÁC�d���C�Ƒ��̖��Ȃǂ��܂��܂ȃX�g���X������Ă���B �@���Ò��̂��҂ɂ͂���ԁC�K����Q�C���a�Ȃǂ����������C���_��w�I�L�a���͖�5���ƍ����B�I�����̊ɘa�P�A�a���ł͂���ρC�K����Q�Ȃǂ������F�߂���B �@�吼�����́C����̂��߂ɋ�ɂ��������������3��ɂ��ďЉ���B �@29�̏������҂͕s�D���Ò��Ɏq�{�̂���������C�q�{�S�E�ƂȂ�B�u�q�����Y�߂Ȃ��ł͉��l���Ȃ��B�������Ȃ��Ă͂����Ȃ��v�C�u�q��������Ă���l�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�Ȃǂ̑i������C�S�I�O����X�g���X��Q�iPTSD�j�Ɛf�f�����B �@7�̎q��������36�̏������҂͍���r���̍�����Ŏ�p�C���w�Ö@���s�����C�Ĕ��B���҂͒S����̍��r�ؒf�̒�Ă�I�������C�Ď�p�ɓq����B�������C�����ɓ]�ځB�ċz����i�s���C�ɘa�P�A�a���ɓ��@�B�u�q�����c���Ď��˂܂���v�Ƒi���C�������܂��S�����B �@72��?�S�����҂͂��܂��܂Ȏ��Â������I�����ƂȂ�C�ɘa�P�A�a���ɓ��@�B?�̂��珬���Ȍ����J���C���ꂪ���X�Ɋg�債�C��cm�̌��ƂȂ����B���S���钼�O�܂ŁC�����̂悤��?�̌������Œ��߂Ă����B �@��L�̊��҂�ʂ��āC�����ɂ͊e�N��C�����ɉ������g�́C���_�S���C�Љ�C�����ʂƑ���ɂ킽���Y�C�S�l�I��ɂ����邱�Ƃ�������B�����K�ɕ]�����C�Ή�����K�v������B �@��Y�C��ɂ�K�ɕ]���E�Ή����邱�Ƃɂ���Č��C�ɂȂ�C�K���Ȑ������ł���悤�ɂȂ�����Ƃ���63�̓����҂��Љ�B���̊��҂͓������p�� �ɂ��a�ǂ��C���w�Ö@����C�͂��Ȃ��������C���a�̎��Â��Ĉӗ~�����P���C���w�Ö@���邱�Ƃ��ł����B���̌�C�����{��k�Ќ�ɋ�Y ������Ă��镟�����̐l�����ɊG�莆�ʼn������b�Z�[�W�𑗂�܂łɂȂ����B ��ᇓ��Ȉ�́u���ē����v �@�Ղ̖�a�@�i�����s�j�Տ���ᇉȂ̍��엘�������́u��ᇓ��Ȉ�͂��҂́w���ē����x�ŁC�Ö@���s�������łȂ��C�l���E�����������n�����Ƃ��d ���B���҂������Ă��邱�Ƃ��������グ�đ���u���C���܂��܂ȐE��ƃ`�[����g��ň�Â��s���Ă����K�v������v�Əq�ׂ��B �l���̖ڕW���l�������Õ��j������ �@��ᇓ��Ȉ�̎�Ȗ����́C�R�����C���q�W�I��Ȃǂɂ��ϋɓI���Âɂ��čŐV�̃G�r�f���X�Ɋ�Â������Õ��j�����҂Ƙb�������Ȃ��猈��C�{�s ���Ă������Ƃł���B�܂��C����Ǐ�̊ɘa�C����p�̃R���g���[���C�S�g��Ԃ̊Ǘ��C�����ǂ̎��ÁC���_�I�T�|�[�g�̑��C�Տ������E�Տ��������s���C�V�� ���G�r�f���X���m�����邱�Ƃ��d�v�Ȗ����ł���B�����āC����1���߂���������C�����ẪR�[�f�B�l�[�g�ł���B����́C���ɖ��������Ȋ��҂́u�� �ē����v�߂�ƂƂ��ɁC�`�[����Ấu���������v�Ƃ��āC�S�̂����n���Ȃ���C���҂ɂƂ��čœK�Ȏ��Õ��j������B �@���҂́C������߂���u�炢���Âɂ�����]������v�C�u���Â���߂����]�����Ȃ��v�Ƌꂵ�݁C����������C���[�W�̂��߂Ɂu���Â��邱�Ɓv�� �̂��ړI�����C�Ȃ�̂��߂���������Ȃ��u���Â̂��߂̎��Áv���s���Ă���B�܂��u���ÖڕW�v�������Ƃ��d�v�ł���C���ÖڕW�̂��߂ɂ́u�R������ �g��Ȃ��v���Ƃ��K�ȑI���ł���ꍇ�������B �@���҂͂悭���Â��l���̑S�Ăł��邩�̂悤�Ɏv������ł��܂��B���Â͎����ւ̌����������̈ꕔ�ł���C�����͐l���̈ꕔ�ł����Ȃ��B���ÖڕW�́u�l�� �̖ڕW�v�̒��ɂ���͂��ŁC���҂̐l���̖ڕW�C���������l�����C�l�Ԑ��C���l�ς��d�����Ď��Õ��j�����߂Ă����K�v������B �@���҂͂���Ɛf�f����Ă��玀�S����܂łɁC����̍������Â��Ă���l�iCancer Patient�j�ƁC����ȊO�̐l���܂ޑS�āiCancer Survivor�j�ɕ�������BCancer Patient����Cancer Survivor�Ɉڍs����ۂɓ��ɖ����Ă��܂����Ƃ������̂ŁC���Ì����������g�̓I�C�S���I�C�Љ�I�Ή�Survivorship Care���K�v�ł���B �@���{�l�����Ŝ늳������������́C������C�咰����C�݂���ȂǁC���S���������̂͑咰����C�x����C�݂���C�X����C�x����C������ł���B���{�̓� �����萢��ł́C�j����菗���ł������C���ɓ�����Ǝq�{�����B��ʎВc�@�lCSR�iCancer Survivors Recruiting�j�v���W�F�N�g�ɂ������҂̐����j�[�Y��������C�ł����������ƂƂ��āu���_�I�ɕs����ɂȂ�v�C�u���Â���Ɋ֘A�����p �������ށv�C�u����ɍs�������Ƃ��s���Ȃ��v�����o���ꂽ�B�܂��p�[�g�i�[�̂��Ȃ��҂͔Y�݂��[���C���҂̏A�J�͏d�v�ȉۑ�ł������B �X�s���`���A���j�[�Y�������x���� �@���H�����ەa�@�i�����s�j�ɘa�P�A�Ȃ̗я͕q�����́C�������҂̊ɘa�P�A�ɂ��āu�X�s���`���A���ȃj�[�Y�������C���҂��X�s���`���A���y�C����������O�Ɏx���邱�Ƃ��d�v�v�Əq�ׂ��B ���ꂵ���C���₩���C�Ί炪�厖 �@���ÂƊɘa�P�A�ŏd�v�Ȃ͎̂����ɂ���ė��҂̔䗦��ς���̂ł͂Ȃ��C���҂̕K�v�ɉ����Ăǂ�����ł���̐��𐮂��C���̂悤�Ȉӎ��������� ���҂��x���邱�ƁC�����ꊳ�҂����ƌ����������Ƃ��ɐS�̓��h�Ɋ��Y���Ă������Ƃł���B�ɘa�P�A�ł́C�g�̓I�C���_�I�C�Љ�I�C�X�s���`���A���Ȏ��_ �ŁC���a�C���y�C���ꂵ���E���₩���C�[�����ɂ��Ȃ��犳�҂��x���Ă����K�v������B �@�����̂���ł́C��������u�ɊǗ��ɂ����镛��p�C���ǐ�������Ȃǂł̟��o�t�∫�L�C�����p����Ȃǂւ̓��ʂȑΉ�����[�؏���_�o��Q���u�ɂȂǂ� �����u�ɂ��܂߂��T�o�C�o�[�ւ̒��ɕ⏕���_�ʂł̃T�|�[�g���K�v�ɂȂ�B�w�l�Ȏ�ᇂł́C���Փ���ᇂɂ�鉺���g�̕���C�N��������Q�Ȃǂւ̑Ή� ���K�v�ƂȂ�B �@�l�Ƃ��Đ����Ă������炱�����߂���̂Ɉ��E�����C����E�����C���Ȏ��������邪�C�����S�Ă���������Ȃ��Ă���]�����邱�ƂŃX�s���`���A���Ȗʂ� ���ǂ���Ԃʼn߂����Ă������Ƃ��ł���B�������C����ɂȂ�ƁC���Ԃ������C�W���⎩��������Q����C�l�Ƃ��Ă̗~������������Ȃ��Ȃ�C�X�s�� �`���A���y�C����������B���i����X�s���`���A���ȃj�[�Y����������悤�Ɋւ���Ă������Ɓi�X�s���`���A���R�~���j�P�[�V�����j�ŁC���҂��X�s���`�� �A���y�C����������O�Ɏx���邱�Ƃ��ł���B���̐l�炵���₻�̐l�̗����F�߂邱�ƁC�C���������Ĉꏏ�ɍl���邱�ƁC�����ȊO�̂��Ƃ��悭�������� �Ȃǂ��X�s���`���A���P�A�ƂȂ�B �@�܂��C���ꂵ���Ƃ������o����X�̐����Ŏ����Ƃ��d�v�ł���C�������L�̃P�A��1�Ƀ��C�N������B���C�N�����邱�ƂŏΊ�����߂����Ƃ��ł���B �@�@���͊��҂������܂��܂ȍ߂̈ӎ��ɑ��鋖����^�����邱�Ƃ�����B �@�ߔN�C���X�ɘV�l�z�[������{�݂Ŏ��S����l�������Ă���C�����d�v�Ȏ��_�ƂȂ��Ă���B �@��ɁC�炳�C�Y�݂��y�����邱�Ƃ������ӎ������������C�m���C�Z�p�C�o����ς݂Ȃ���C�ǂ���������ł��炦�邩�C�S��a�܂����邩�C�Ί�������Ă��炦�邩�Ƃ����v�����̋C�����Ŋ��҂Ɛڂ��邱�Ƃ��厖�ł���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N10��18�� |
||||
| �`�I�����_�̈��y���@�` 2010�N�̈��y��������ш�t���E���͖@�{�s�O�Ɠ��� |
||||
| �@���y�������@������Ă���I�����_�ɂ����āC���y���@�{�s�O��̈��y������ш�t�̛������E�i��t���E�j�̓��������������Ƃ���C2010�N�̈��y��������ш�t���E���́C���@�{�s�O�̐����Ɠ����x���ł��邱�Ƃ����R��w��ÃZ���^�[�i�A���X�e���_���j��Bregje D. Onwuteaka-Philipsen�����炪�s�������f�����Ŗ��炩�ƂȂ����B�ڍׂ�Lancet�i2012; 380: 980-915�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�B �{�s�O���20�N�Ԃ̓��������� �@�I�����_�ł�2002�N�ɁC���̏��������Έ��y������ш�t���E��F�߂���y���@���{�s���ꂽ�B����̌����ɂ��C2010�N�̈��y��������ш�t���E���́C2002�N�̓��@�{�s�O�Ɠ����x���ł��邱�Ƃ����������B �@2002�N�̈��y���@�{�s��C2005�N�ɂ͈��y��������ш�t���E������������ቺ�������C��t���E����]���銳�҂̑����Ȃǂ�w�i�ɁC2005�N����2010�N�ɂ����čĂя㏸�����B�������C2005�N�ɒቺ�������߂�2010�N�̈��y��������ш�t���E����2002�N�̓��@�{�s�O�Ɠ����x���������B �@Onwuteaka-Philipsen������́C�I�����_���v�ǂ̎��S�o�^�f�[�^�ނ��C�I�����̈ӎv���肪���҂܂��͈�t�ɂ���ĂȂ��ꂽ�\���̂���Ǘ�肵���B���̌�C�����̏Ǘ��S��������t�ɒ����[�𑗕t���C���~�Ȃǂ̌������t���s�������ǂ����C���邢�͊��҂̎��𑁂߂邽�߂ɖ�܂𓊗^�������ǂ����Ȃǂɂ��Ē��������B����2010�N�ɂ�������y��������ш�t���E���𐄌v���C1990�N����2010�N�ɂ����Ă̈��y������ш�t���E�̕p�x�̐��ڂ����������B ���@���œ��������܂邩 �@���͂̌��ʁC2010�N�ɂ�������y�����邢�͈�t���E�̌����͐��v4,050���ŁC�I�����_�̑S���S����3�����߂��B���̂���77�����u���y���Ɋւ���n��R���ψ���v�ɕ���Ă����B���̊�����2005�N�Ƃقړ����ŁC���y���@�̎{�s�O�������������B �@Onwuteaka-Philipsen������́u���y���@�̎{�s�ɂ��ĕs�������鐺�����������C���y�������@�����ꂽ���X�ł́C���҂̖��m�Ȋ�]���Ȃ���Ԃň�t�����҂̎������P�[�X�͑������Ă��炸�C�I�����_�ɂ����ėL�ӂɌ������Ă���v�Ǝw�E���Ă���B �@���҂����m�Ɉ��y������]�����ꍇ�C��t���v����𓊗^������y���ƁC���y����]�ފ��҂̈ӎv�\�����Ĉ�t���v������������C���҂����瓊�^������E�����@������Ă���̂́C���E�ł��I�����_�C�x���M�[�C���N�Z���u���N��3�J���݂̂ł���B���E�ɂ��ẮC�X�C�X����ѕč��̃I���S���C�����^�i�C���V���g���̊e�B�ŔF�߂��Ă���B �@�I�����_�ł́C���y�����t���E��I�Ԏ�N���҂₪�҂������C�i�[�V���O�z�[����a�@������ʐf�Ï��ōs���Ă��邱�Ƃ��C����̌����Ŗ��炩�ɂȂ����B�܂��C���Ҕw�i�ɂ��Ă�20�N�Ԃقڕς��Ȃ������B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N11��1�� |
||||
| ���{�~�}��w��A�I������Âɂ��Ă̒������ʂ����\ �l�H�ċz�̒��~�A�����E�h�{�⋋�̐����⒆�~�ɈˑR��R�� |
||||
| �@���{�~�}��w��~�}��Âɂ�����I������Â̂�����Ɋւ���ψ����2012�N11��5���A�u�~�}��Âɂ�����I������ÂɊւ���i�ȉ��A�K�C�h���C���j�v�ɑ���~�}��Ï]���҂̈ӎ��̕ϗe�ɂ��āA�A���P�[�g�̌��ʂ\�����B�K�C�h���C�����o���Ă���5�N���o�߂��A�F�m�x�͍��܂��Ă�����̂́A����ł̓K�p�ɂ��Ă͈ˑR�ۑ肪�c������炩�ɂȂ����B �@���̃K�C�h���C���͓��w�2007�N11���Ɍ��J�������̂ŁA1�N���2008�N�ɂ͋~�}�Ȑ����ΏۂƂ��ĔF�m�x��K�p�̒������s���Ă���B���ʂ\���������́A�K�C�h���C���̌��J����5�N���o�߂��A�~�}��Â̏]���҂Ɉӎ��̕ϗe���������̂��ׂ�ړI�ōs��ꂽ�B�������Ԃ�2012�N5��8������20���܂ł�13���ԁB�Ώۂ́A�~�}�Ȑ���658�l�Ƌ~�}��Âɏ]������Ō�t77�l�B �@�܂��A�u�K�C�h���C���̓��e��m���Ă��邩�v�̐ݖ�ɂ́A�~�}�Ȑ����82.4�����u���e���悭�m���Ă���v�܂��́u�����ނ˒m���Ă���v�ƉB2008�N�̒�������73.3����傫������A�K�C�h���C���̔F�m�x�����܂��Ă����B �@�u�I�����̏�Ԃɂ���ƍl�����銳�҂̐f�ÂɃK�C�h���C���𗘗p���Ă��邩�v�̐ݖ�ɂ́A�~�}�Ȑ����24.8�����u�傢�Ɏ�����Ă���v�܂��́u������Ă���v�ƉB2008�N�̒�������21.7��������錋�ʂƂȂ����B �@���w��̃K�C�h���C���ł́A�I�����Ɣ��f����銳�҂ɂ��ẮA�Ƒ��̑��ӂȂǂ��m�F������ʼn����[�u�𒆎~���邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă���B���̏�ŁA�����[�u�̒��~��ϋɎ��Â����Ȃ����@�Ƃ��āA�l�H�ċz�̒��~�A�l�H���͂��s��Ȃ��Ȃ�4�̕��@����Ă���B�u�������������@�ɂ��ċ��e�ł��邩�v�����ݖ�ł́A���@�ɂ���ċ��e�ł���x�������قȂ�X���������ꂽ�B �@��̓I�ɂ́A�u�l�H���́A���t�Ȃǂ��s��Ȃ��v�u�l�H�ċz��ݒ�⏸���^�ʂȂǁA�ċz�E�z�Ǘ��̕��@��ύX����v�ɂ��ẮA���e�ł���ƍm��I�ɉ����~�}�Ȑ���͑����A���ꂼ��83.2���A76.9�����߂��B����ŁA�u�l�H�ċz�A�y�[�X���[�J�[�A�l�H�S�x�Ȃǂ𒆎~�A�܂��͎��O���v�u������e���̕⋋�Ȃǂ𐧌����邩�A���~����v�Ƃ������@�ɂ��ẮA���e�ł���ƍm��I�ɉ����~�}�Ȑ��オ�A���ꂼ��42.5���A67.0���B��R�������~�}�Ȑ��オ���Ȃ��Ȃ����Ƃ����������B���������X���́A08�N�̒������Ƒ傫���ω����Ă��Ȃ������B �@����܂ł�5�N�ԂɃK�C�h���C����K�p���悤�Ƃ����ǗႪ���邩�ǂ����������ݖ�ɂ͑S�̂�20.5�����u�K�p���悤�Ƃ����ǗႪ�������v�ƉB08�N�̒�������13.8���ɔ�ׂđ��������B �@�������A�u�K�p���悤�Ƃ������Ⴊ�Ȃ������v�Ɠ�����471�l�i71.6���j �̂����A253�l�i53.7���j�́u�K�p����Ӑ}���Ȃ������v�Ɖ����B �@�u�K�p���悤�Ƃ������Ⴊ�Ȃ������v471�l�̒��ŁA�u�K�p�������������A�ł��Ȃ������v�Ɖ����̂�114�l�i24.2���j�B�K�p�ł��Ȃ��������R�i�����j�́A�u�Ƒ��̈ӌ����܂Ƃ܂�Ȃ������v�i86�l�A13.1���j�A�u�@�I�Ȗ�肪�������ł���v�i73�l�A11.1���j�A�u��Ã`�[�����̈ӌ����܂Ƃ܂�Ȃ������v�i53�l�A8.1���j�Ȃǂ������B �@����̒����ł́A�K�C�h���C���̔F�m�x�͍��܂��Ă�����̂́A����ւ̐Z���ɂ͉ۑ肪�c�錋�ʂ������ꂽ�B ���o���f�B�J�� �I�����C���@2012�N11��26�� |
||||
|
�����҂�QOL���P QOL�ቺ�ɂȂ��錑�ӊ������߂����Ȃ����Ƃ��d�v |
||||
| �@���݁C�h�C�c�̂����҂�320���l�ɏ��B�h�C�c�����Z���^�[�i�n�C�f���x���N�j��Volker Arndt���m�́u����̗\�オ���P�������Ƃ���C����C�����҂̐��͂���ɑ����邱�Ƃ��\�������B�������������҂�60����65�Έȏ�̍���҂���߂Ă��邪�C�����ɂ킽��QOL���Ⴂ���Ƃ����ƂȂ��Ă���v�ƃh�C�c����w��̑�30���c�ŕ����B �Љ�A�͈ˑR���� �@�����҂����ʂ���̂́C���̂��̂₪��̎��Âɒ��ڊ֘A�����肾���ł͂Ȃ��B��������[���Ȃ̂́C�����Ɋւ�閝���̎���������Ă��邱�Ƃ��痈��s���ŁC����͂������a��F�m�@�\�̒ቺ�ɂȂ���B �@�Љ�A���傫�Ȗ��ƂȂ��Ă���B1�N��ɍďA�J���Ă������҂͖��ɂ������C50�Έȏ�̊��҂ł�3����1�ɂƂǂ܂�B �@�������C�I�����_�ōs��ꂽ�����ł́C�ďA�J�̏͂���̎�ނɂ�肩�Ȃ�قȂ邱�Ƃ�������Ă���B�Ⴆ�C1�N��ɍďA�J���Ă������҂̊����́C�畆�܂��͐��B��̂���ł͍ő��80���ł���̂ɑ��C���t�̂����x����ł͋ɂ߂ĒႩ�����B �@�܂��C�h�C�c�n�悪��o�^����iGEKID�j���U�[�������g�B�ɋ��Z��������҂�Ώۂɐf�f��10�N�Ԃ�QOL������VERDI�����ł́C�����҂�QOL�͑S�̓I�ɂ͌��N�l�ɋ߂����̂́C���ɂ͎Љ���@�\����퓮��C����I�@�\�C�F�m�@�\���������ቺ���Ă���P�[�X������ꂽ�B �@QOL��ቺ������ɂ߂đ傫�ȗv���Ƃ��Č��ӊ����������邪�CArndt���m�́u���ӊ��ɂ��ẮC�q�ϓI�ɕ]������ړx���Ȃ����ߌ��߂�����邱�Ƃ������v�Ǝw�E�B���̑��C������Q�C�H�~�s�U�C�u�ɁC�ċz����C�ݒ���Q�Ȃǂ������ԑ����Ɗ��҂Ɉ��e�����y�ڂ��B ���ǂ��������g�����ߒ������������ɂȂ�ꍇ�� �@���̈���ŁCArndt���m�́u���a�����������ɁC�������g�����ߒ������҂����Ȃ��Ȃ��v�Əq�ׂ��B����͊O���㐬���iPosttraumatic growth�GPTG�j�Ƃ��Ēm���Ă���C�S�I�O���������炷�o���ɂ���Y����C���Ȍ`���⑼�҂Ƃ̊W�C�l���ɑ���l�����Ƀ|�W�e�B�u�ȕω����N���邱�Ƃ�����Ƃ������́B�����m�́u�����̂����҂�QOL�ɂ��ẮC�܂��s���ȓ_�����ɑ����B���҂̃A�t�^�[�P�A��{���I�ɉ��P���Ă����ɂ́C�����҂Ɏ��₷�邾���ł͕s�\���ŁC���̕���ł̌������������Ă����K�v������v�Ƌ��������B �@���x���g�E�R�b�z�������i�x�������j��Benjamin Barnes���m�ɂ��ƁC�U�[�������g�B�C�n���u���N�s�C�~�����X�^�[�s�Ŏ��W���ꂽ����o�^�f�[�^�̉�͂̌��ʁC�����҂�5�N�������͖�80���ł��邱�Ƃ��������Ă���B�������C�����������҂̎��S���X�N�͓��N��̌��N�l�Ɣ�ׂāC�����ɂ킽�荂�����Ƃ��������Ă���B����C������������������蒷�����Â��t������\�����������C�������҂̎��S���X�N�́C�f�f����8�`10�N��ł����N�l�Ƃقړ����ł���Ƃ����B �@�܂��C���������������a���҂̐��������f�f����͒������ቺ������̂́C���N�o�߂���ƌ��N�l�Ƃقڕς��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���������Ă���B�������C���������p�������a�̏ꍇ�́C���N�l�Ɣ�ׁC�����҂Ŏ��S���X�N�����炩�ɍ����܂܂ł���Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N11��22,29�� |