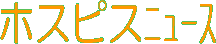 �@�@
�@�@�o�b�N�i���o�[2011/1/1�`2011/12/3
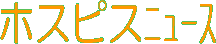 �@�@
�@�@| �@�z�|�� >��w�g�s�b�N�X>�z�X�s�X�j���|�X>�o�b�N�i���o�|�ƭ->2011/1/1�`2011/12/3 |
|
ICU�̏I������Âɑ卷 �@���╶���C��t�̎p���Ȃǂ��e�� |
|---|
| �@���V���g����w�ċz����ȁE�~�}��w�Ȃ�J. Randall Curtis������́C�W�����Î��iICU�j�ɂ�����I������Â̍��ƁC��t�ƉƑ��̍l������p�����I������Âɋy�ڂ��e���ɂ��Č������C���̌��ʂ�Lancet�i2010:
376; 1347-1353�j�ɔ��\�����B��������́u��t�́g�^�ʂ�̎菇�h�ɂȂ肩�˂Ȃ������ێ����u�̎��O���̌���Ɋւ��ď\���ɒ��ӂ��ׂ����ƁC�܂��Տ���͐����ێ����u�̎��O���𔗂�{�݂���̈��͂��x�����C�����Ɋ��҂��]�܂Ȃ���Â��s�����Ƃ��Ȃ��悤���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��Ă���B �W�w�I�A�g�ɒx�� �@�~����Âɂ����Ċ��҂��ŐV�̐����ێ����Â���ꏊ��ICU�ł���B�~����Â͍��z�ő����̈�Î�����K�v�Ƃ��邪�C�d�Ăȑ�����s�S�������Ă��������ێ����邱�Ƃ��ł��闘�_������B�������C������ICU�̎��S�������͍����C�I������Â��p�ɂɍs����ꏊ�ł�����BICU�ł͐����ێ��ɏd�_��u�����߁C���̍����I������Â̒�����C�Տ���ɂƂ��ċ~���ƏI������Â̒��ɍs�����Ƃ͑傫�ȕ��S�ƂȂ��Ă���B �@ICU�̏I������Âɍ��������闝�R�Ƃ��Ă͏@���C�����CICU�̈�Ñ̐��C�I������Âɑ����t�̎p���C�����̏d�Ǔx�C�P�[�X�~�b�N�X���ށC�\��Ə�����QOL�Ɋւ����t�̗\���Ȃǂ̈Ⴂ����������B �@Lancet������Series of Critical Care�Ɍf�ڂ��ꂽ�_���ł́C�l���̍���ɂ��ICU�̏I������Â̎��v�͑��傷��Ƃ��Ă���B�č��ł͑S���S��5����1��ICU�Ŕ������Ă���C85�܂ł͔N��������Ă����̔䗦�͌������Ȃ��B���_���ł́u�Љ�ƍ��Ƃ͑��債���鍂��Ґl���C���ɐ���������������������L���鍂��҂ɓK�ȋ~�����Â����K�v������v�Əq�ׂĂ���B �@�I������Âƈ�Ã`�[���Ƃ̘A�g�ɂ͒n�捷������B�Ⴆ�C21�J���̏W�����Ð���1,961�l��Ώۂɍs��ꂽ�A���P�[�g�ł́C�u�Ƒ��̂��Ȃ����҂ɂ��ďI������Â̌����ɊŌ�t���܂߂�v�Ɠ�������t�͖k���ƒ�����62���ł������̂ɑ��C�쉢�ł�32���C���{�ł�39���C�u���W���ł�38���C�č��ł�29���ɂ����Ȃ������B�I������ÂɊւ��ďW�w�I�A�g���i��ł��Ȃ����Ƃ́CICU�œ����Տ���ɂ�����R���s���nj�Q�C���a�C�S�I�O����X�g���X�̑����Ɋ֘A���Ă���B �Ƒ��̊֗^�̒��x�ɂ��n�捷 �@���B17�J���C37��ICU�ōs��ꂽETHICUS�����ɂ��ƁC�I�����̈ӎv����Ɋւ���Ƒ��Ƃ̘b�������͓쉢�i47���j���k���i84���j�ƒ����i66���j�ň�ʉ����Ă����B�Ƒ��̊֗^�ɂ��Ă̓C���h��100���C���`��98���C���o�m����79���C�X�y�C����72������t�����X��44���܂ő傫�ȍ���������B �@Curtis������́u�I������ÂɊւ��āC��t�͌���Љ�ɂ����鑽�l���ƕ��G����F�����C�ɍ��킹�ăA�v���[�`����K�v������v�Əq�ׂĂ���B�������炪��Ă���ICU�ɂ�����ӎv����A�v���[�`�ł́C�܂���t���\���]������B���ɁC�Ƒ��̖�����]�����C����2�i�K�Ɋ�Â��čŏI�I�Ȏ��g�ݕ������߂�B��t�͊��҂�Ƒ��Ƌ����ňӎv������s�����C���̍ہC���҂̏�Ƒ��̍D�݂ɍ��킹�ďC�����ׂ��ł���B �@��������́CICU��Ã`�[���Ɗ��҉Ƒ��Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����𐬌�������v�f�Ƃ��āi1�j���I�Șb�������̏���m�ۂ���i2�j��t���Ƒ����玿�����i3�j���҂����̂ĂȂ����Ƃ��Ƒ��Ɋm��i4�j���Ҏ��g���D�ގ��ÂƉ��l�ς��d������?�Ƃ������_�������Ă���B �@�����\�������l�����łȂ��CICU�̊��ґS���ɂƂ��ăR�~���j�P�[�V�����͏d�v�ł���B��������ɂ��ƁC�t���I�ł͂��邪�C�������т����҂̉Ƒ��̕����C���S�������҉Ƒ����ICU�Տ���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɖ������Ă��Ȃ��Ƃ����B �@���ɂ��e�����傫�� �@�����ێ��̊J�n�ۗ��܂��͒�~�Ɋւ��āC��t�̊Ԃōl�������قȂ�B���錤�����ʂɂ��ƁC�k���ł͎��S��47���������ێ��ۗ̕��܂��͒�~��ł��������C�쉢�ł�18���݂̂ł������B �@�@���͗ՏI�Ǝ��S�C�I������Âɑ���l���������E����d�v�Ȍ�����q�ŁC���ҁC�Ƒ��C�Տ���̏@�����W����B�Ⴆ��ETHICUS�����̌��ʂł́C��t�����_�����i81���j�C�M���V�������i78���j�C�C�X�������i63���j�̏ꍇ�C���Â͒�~�������p������邱�Ƃ��������C��t���J�g���b�N�i53���j�C�v���e�X�^���g�i49���j���邢�͖��@���i47���j�̏ꍇ�͒�~����邱�Ƃ������B�@���͂܂��C�L��������Ă���Ƃ͂����C���ՓI�ł͂Ȃ��]���̎�e�����肷��d�v�ȗv���ł�����B �@Curtis������́uICU�Ŕ������鎀�S���͑���������C�����ێ��̊J�n�ۗ��܂��͒�~�Ɋւ���d�v�Ȍ�����s����ŁC�L�v�ȐM���ł���G�r�f���X��w�j�����@���Ă���v�Ƃ��C�u�����������Â̒�~�́C���̎菇�Ɠ��l�̗Տ��菇�ł���B���̂悤�Ȍ����ICU�œ����Տ���ɂƂ��ă��[�`���̎菇�ƂȂ肤�邽�߁C�Տ���͐����ێ��̒�~�����߂�{�݂���̈��͂��x�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ێ����u���~���錈��̗��_�I��������ËL�^�Ɏc���ׂ��ł���v�Əq�ׂĂ���B �@��������́u�I������ÂɊւ��ĉ\�Ȍ��萢�E�I�Ɉӌ�����v������ɂ́C�����̖������ۓI�ȃt�H�[�����ŃI�[�v���Ɍ������Ă����K�v������B������n��ɂ����āC�i�̍����~����Â���邽�߂ɂ͗ϗ��I�Ȉӎv����C�W�w�I�`�[���ɂ�����R�~���j�P�[�V�����ƘA�g�C���҂Ƃ��̉Ƒ��Ƃ̌��ʓI�ȃR�~���j�P�[�V�����C�`�[�����Ɗ��ҁE�Ƒ��Ƃ̑Η��_�̊m�F�Ɖ����ɏd�_��u�����P�����s���ł���v�ƌ��_�t���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N12��2�� |
| ��t�̏@���ς��I������Âɉe�� |
| �@�����h����w��Clive Seale�����́C�Տ���̏@���ς��I������Âɗ^����e�����������Ƃ���C���_�_�҂��邢�͕s�m�_�҂̈�t�ł́C�I�����̒��Î��ÂȂǖ������҂̎����𑁂߂鎡�Â��s���\�����C�[���M�S������t�ɔ�ׂĖ�2�{�������Ƃ����������B�ڍׂ�Journal
of Medical Ethics�i2010; �I�����C���Łj�ɔ��\���ꂽ�B�܂��C�M�S�̂�����t�́C���Ö���g�p�������Âɂ��Ċ��҂Ƙb���������Ƃ����Ȃ����Ƃ������ꂽ�B ���߂̎��S�Ǘ������ �@Seale������́C�p���̈�t8,857�l��ΏۂɗX���ɂ��A���P�[�g�����{�����B�ΏۂƂȂ�����t�̐��ɂ́C���ɏI������Â̈ӎv����Ɍg��邱�Ƃ̑����_�o�Ȉ�C����҃P�A�C�ɘa�P�A�C�W�����ÁC�a�@����C��ʓ��Ȉ�ȂǕ��L���̈悪�܂܂ꂽ�B �@�A���P�[�g�ł́C���߂̎��S�Ǘ�ɂ��āC�Ŋ��܂Œ��Ö�������I�Ɏg�p�������ǂ����C�܂��C���̎��Â�I�����邱�ƂŎ��������܂�\�������邱�Ƃ����҂Ƙb�����������ǂ�����q�˂��B�����ɁC���g�̐M�▯�����C��t�ɂ�鎀�̂ق����C���邢�͈��y���ɑ���l�����������B���悻4,000�l�����i��42���j�C����3,000�l�����S�Ǘ�̎��Âɂ��ĕ����B �@�҂̂��������𔒐l��t����߂Ă���C�����̈�t�ł͐M�S�[���Ɖ����������ł��Ⴉ�����B��t�̐��ƐM�̊W������ƁC����҈�Â̐���͑��̐���Ɣ�ׂăq���Y�[���k��C�X�������k�������C�ɘa�P�A�̐���ɂ͑��̐���ɔ�ׂăL���X�g���k�C���l�������ق��C�u�M�S�[���v�Ǝ��F���Ă����t�������X���ɂ������B ���y����ق������̎^�ۂɂ��e�� �@���𑁂߂邱�Ƃ�\���C�܂��͂�����x�Ӑ}�����ӎv��������邩�ۂ��́C��t�̐��ɑ傫���W���Ă����B���������ӎv������s���Ɖ�����t�́C�ɘa�P�A����ɔ�ׂĕa�@����łق�10�{�������B �@�܂��C���ɂ�����炸�u�M�S���قƂ�ǂȂ��v�܂��́u�M�S���ɂ߂Ĕ����v�Ǝ��F���Ă����t�ł́C�������������𑁂߂邱�Ƃ�\���C�܂��͂�����x�Ӑ}�����ӎv������s���Ɖ��������u�M�S���ɂ߂Ă����v�܂��́u�M�S�����Ȃ肠���v�Ǝ��F�����t�̂ق�2�{�ł������B �@�ł��M�S�[����t�ł́C�I������Â̈ӎv����ɂ��Ċ��҂Ƙb�����������Ƃ�����Ɖ����l���C���̈�t�ɔ�ׂĒ����ɏ��Ȃ������B �@���������p���͎��̂ق�������y���̖@�����ɑ���x���ɂ����f����Ă���C�ɘa�P�A����ƐM�S�[����t�́C���łȔ��̎p�����������B �@�A�W�A�n�Ɣ��l�̈�t�ł́C���̂ق�������y���̖@�����ɑ��锽�̎p�����C���̖����O���[�v�ɔ�ׂĊɂ₩�ł������B �@Seale������́u��t�̉��l�ςƗՏ��ɂ�����ӎv����Ƃ̊W�ɂ��āC�F����[�߂�K�v������v�ƌ��_�t���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N12��9�� |
| �q�݂̂Ƃ�A���������@�������Ҏx���c�́A�I�����P�A�̎�����쐬 |
| �@��������̂��ߗ]��������ꂽ�q�ǂ��̐e�ɕK�v�ȐS�\���Ȃǂ�������������u���̎q�̂��߂ɂł��邱�Ɓ@�ɘa�P�A�̃K�C�h���C���v�����Ҏx���c�̂��쐬�A12��19���ɑ��s�ŊJ�����V���|�W�E���Ŕ��\����B�����āu���v�ɓ��ݍ������ł͗�̂Ȃ����q�́A�q�ǂ����݂Ƃ����Ƒ����ÊW�҂�̌o���̌����Ƃ���������e�ƂȂ��Ă���B �@�u����̎q��������v�i�����s�j�𒆐S�ɁA�������Â�ɘa�P�A�Ɍg����t�E�Ō�t�A�\�[�V�������[�J�[�A�{�싳�@�A�q�ǂ���S�������Ƒ��炪���͂��č�����B�u�q�ǂ��ɂƂ��Ă̎��v�u�e��Ƒ����ł��邱�Ɓv�u�ɂ݂̌y���v�u�^�[�~�i���i�I���j���̉߂������v�ȂǂP�O���ڂ��A�a�T���P�U�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��B �@��������̎q�ǂ��������鋰�|���ɁA���Y�����ɂ͂��낢��Ȍ`������Ɛ������Ă���B�q�ǂ��̎v���d����̂��őP�Ƃ��A���̂��߂ɉƑ��E��Ã`�[���E�w�Z�̋��t�炪�悭�b�������ׂ����Ǝw�E����B�a�C�̎q�ǂ��̂��傤�����ւ̔z���⎀�ʌ�̔ߒQ�i�O���[�t�j�ւ̌������������l������e���B �@�q�ǂ��̊ɘa�P�A�ɂ��āA��w����̌��L�Ȃǂ͏o�ł���Ă��邪�A�Ƒ��ɂ���Î҂ɂ��ʂ���S�\������₷�����������͂���܂łȂ������B�N��������A�S���̐����ی����A���ʎx���w�Z�Ȃǂɔz�z����B�Ƒ��ɂ͎��ÊJ�n���ɑ��̏��ނƈꏏ�Ɉ�t�����n���ȂǁA�V���b�N�ɂȂ�Ȃ��`�Ŏ�ɓ������悤�H�v����Ƃ����B �@�쐬�Ɍg���������̃\�[�V�������[�J�[�A������q����́u�q�ǂ����S���Ȃ�\�����l���邾���ō߈������o����e������B�q�ǂ��̎v���Ɋ��Y�����߁A�e���ÊW�҂��悭�b�������Ăق����v�Ƙb���B �@�V���|�͂P�X���ߌ�R���A���s�k�撆�V���T�̑�㍑�ۉ�c��ŁB�₢���킹�͓���i�O�R�E�T�W�Q�T�E�U�R�P�P�j�B m3.com�@2010�N12��19�� |
| ���w������u����v�@����y�����i���A�A�j���c�u�c�𐧍� |
| �@���҂����炷�ɂ́A���w���̂�������u����v���s���B���N�A���ː���ɘa��ÂɌg����Ă���������w��w���t���a�@�y�����i�ɘa�P�A�f�Õ����j�̒���b�ꎁ�̑i���ŁA�����Ɋw�Z������������悤�ƁA�n��E�w�Z�W�҂�̑��̍��I�Ȋ����̗ւ��L�������B �݂��s�� �@�u����̗Տ���Ƃ��āA�i�s����̊��҂�f�Ă������A����̒m�����Ȃ������䂦�ɑ������Ă��銳�҂����܂�ɑ����B���������m���̂Ȃ��͍����S�ʂɌ�����B�w�Z�ő������狳���ĊS����������̂���ԁv�ƒ��쎁�͘b���B �@���쎁�ɂ��ƁA�č���M���ɐ�i���ł́A����ɂ�鎀�҂������B�������A���{���������������A�Q�l�ɂP�l���늳�i�肩��j���A�R�l�ɂP�l�����S���Ă���B���f���͉��Ċe�����W�O����ɑ��A���{�͂Q�O���ȉ��B�q�{��i�����j����\�h�̃��N�`���ڎ�����l�̏��B�u���E��̂���卑�Ȃ̂ɂ���ł��Ă��Ȃ��B�s���̓������݂��A�ی��̈�̎��Ƃ������I�ɃJ�o�[���Ă��Ȃ��v �@�����m��A���ƌ����������߂ɂ��w�Z����̏[�����K�v���Ƃ����B�����A�q�{��ȂǂŖ��𗎂Ƃ��l���Q�O�A�R�O��ŋ}�����A���Ƃł����w�R�N���납��n�߂Ȃ��ƊԂɍ���Ȃ��B �@�����Œ��쎁�́A���k�����ɕ�����₷���������������鋳�ނƂ��āA�A�j���̂c�u�c�𐧍쒆���B�����w�K��ی��̈�̎��ƂŎg���A�ƒ�Ɏ����ċA���Đe�q�ł�����w��ł��炨���Ƃ����킯���B �e�q�ŕ� �@�P�P�����{�A��ʌ����˒��Łu�m�낤�@����̂Ђ݂v�Ƒ肷��n�����[�^���[�N���u��Â̍u����s��ꂽ�B �@�u�t�́A���쎁�Ǝq�{��̑̌������鏗�D�̌��䈟�I����B���쎁��m�铯���̂o�s�`��̓��������Ŏ������A������X�����w�Z�̍Z����w�Z�W�҂��Q�������B �@���o�s�`��̌��c���X�q����́u���Z���ɂȂ閺�����邪�A�����x�����炢�B�q�{�f�̃N�[�|����z��O�ɁA���ƂŐ������m����A���t���邱�Ƃ��ƂĂ��厖�B�������̓����Ŋw�Z�W�҂̈ӎ��������ԕς���Ă����v�Ƙb���A�Q���������q���w�����u�l���Ƃ̂悤�Ɏv���Ă����B���Ў��ƂŘb�������v�B�I����̃A���P�[�g�ł��ی�҂̂V�������Ƃ�~���Ă����B�ÒJ���Y�������c�u�c�z�z�ɂ͐ϋɓI�ȍ\�����B �@���쎁�́u���Ƃɑg�ݓ���邱�Ƃ͕����Ȋw�ȂƂ����c���B���w���Ώۂ̍u����͈��̎��Ƃł���A�L����Ίw�Z����ւ̓˔j���ƂȂ邩������Ȃ��v�Ǝw�E�B���̂����ŁA�u����̂��Ƃ��Œ���m���Ă����A����Ɛf�f���ꂽ�Ƃ�����ɐU�镑���邱�Ƃ�����B���k�����A�j���̂c�u�c��S���ɔz�z���A�e�q�ŕ��ł���悤�ɂ������v�Ƙb���B �Y�o�j���[�X�@2010�N12��26�� |
| ���{�Ɂu�Ŏ�蕔���v�@���E��Â̌���Ł@��t�E�V���̖����} |
| ���u�Ŋ��v�������E���@�{�݂ŖS���Ȃ�����ґ� �@�����҂̍Ŋ���E����Ƒ����Ŏ�邽�߂̕�����p�ӂ�����ʗ{��V�l�z�[�����A�����ł��݂���悤�ɂȂ����B�a�@�ł͂Ȃ������{�݂Ő��U���I���邨�N��肪�����A������Ⴂ�E�������������A�x���Ă���B�l�̍Ŋ��Ɍ��������A�ɂ݂��o���Ȃ���A����҂Ɋ��Y���d���Ɏ艞���������Ă����҂����̔N���N�n��ǂ����B �@�u�ق�A���q�����掂�q���I�v �@�����s�̓��{�u�O���[���q��������v�ō����R���A�����^�~����i�Q�P�j���A�W�U�̏��������҂Ɍ�肩�����B���̓��͂��@���߂ŁA�Ԉ֎q�ɍ��点�����\��͌������A�E���̕K���̎��q���ɂ����\��B���O���Ă�Ō����������u���Ȃ����l���˂��v�Ƃ����₭�B����ƁA���@�̂悤�ɏΊ炪���ڂꂽ�B �@�����̐��w�Z�����t�A���ƁB�{�݂ɏA�E���ĊԂ��Ȃ��A���߂ĂP�l�Ŗ�ɓ������B�[��A�F�m�ǂ̒j�������҂�������N���o���Ă����B�u��Ђɍs���Ȃ���v�B�O�ɏo�悤�Ƃ���̂�K���Ŏ~�߂��B�u�Â��Ċ�Ȃ��B���ɂ��悤��v�B�J��Ԃ���肩���A�ǂ��ɂ������ɖ߂����B �@�@�@���@�@�� �@�{�݂͂R�K���ĂŌv�R�X�̋���������A�Q�K�t���A�̉��܂����ꎺ���u�Ŏ�蕔���v�Ɏw�肵�Ă���B��̂�삫�イ�Ԃ܂ʼn^�ԍہA�l�ڂɂ��Ȃ��悤�z���B�����ɂ̓x�b�h�̂ق��z�c���~�����̃X�y�[�X������A�Ƒ����Q���܂�ł���B�u���Ɛ����v�ƂȂ�ƐE���͉Ƒ��ɏh�������߂�B �@�{�݂ł̊Ŏ��́A���f���Ď��S�ɗ������t�����Ȃ���ΐ��藧���Ȃ��B�������t�����Ȃ���Όx�@����h�ɒʕ邵���Ȃ��A�u�ώ��v���ĂƂ��Čx�@�̌������K�v�ƂȂ�B �@���z�[���ł́A�Ŋ����Ŏ��Ƒ��₩�Ɏ厡��ɘA�����A�삯������t�����S�f�f�������B���̌�A�E����͈�̂����Ē��ւ�������u�G���[���P�A�v���s���B �@���{�����҂̕��ϗv���x���N�X���܂�A�����҂��{�݂ŖS���Ȃ�P�[�X�܂��A�����J���Ȃ͂O�U�N�̉���V����Łu�Ŏ����Z�v��V�݁B����ɂ��A�Ŏ����s�����{���������Ƃ����B �@��������͂܂��V�l�ŁA�Ŏ�������Ƃ͂Ȃ��B�u�����ڂ���g�߂ȓ����҂��ˑR�S���Ȃ�����A��������̂ł́v�B�������ȕs���������Ȃ��B �@��N�������A���j�����܂ꂽ�B�u�d���������̂ł́v�u�����ł���Ă�����̂��v�B�����S�z����F�l�����ɂ́A�u�������NJy�����v�Ƌ����ē�����B�u���p�҂Ɋ��Y�������v�Ƃ����v���͗h�炢�ł��Ȃ��B �@�@�@���@�@�� �@��Ɓ`���̏��߂̂��߂��`�Ƃā` �@��N�̑�݂����A�s�̔F�m�ǎ҂̃O���[�v�z�[���u�H���i�R�X���X�j�v�ɁA����҂̉̐��������B�z�[���Ō��U���}���邨�N���X�l�̗ւ̒��S�ŁA�R�������i�������j����i�Q�O�j���L�[�{�[�h��e���B�䏊����N�z�����̍��肪�Y���B �@�O�W�N�t�ɍ��Z���o�ăz�[���ɏA�E�B��N�̏t��A�X�W�̏����Ƃ́u�ʂ�v���o�������B�ʓ��Ńf�C�T�[�r�X�ɏ]�����Ă����ߑO���Ɉٕς��A���x�݂ɋ����삯�����B���͂Ȃ��������A���S���������\��Ŗڂ���Ă����B�u���܂ł��肪�Ƃ��B�悭�撣�����ˁv�Ɛ����������B �@�u�Ƒ��̂悤�Ȃ��̂ł�����c�c�v�B��ނɗ܂����ӂ�A���t���Ȃ��Ȃ������Ȃ��B �@�����҂̍Ŋ��ɏ��߂Č����������̂́A��N�̂P�����B���P�O�O�̏����������B���������Ȃ��A�ӎv�̑a�ʂɓ�a�������A���N�قǂ��ƕ\���C�������ǂݎ���悤�ɂȂ����B��̎��A�����̍D���ȁu�����S�̉S�v���悭�ꏏ�ɉ̂����B��������Ă���邱�Ƃ��������B �@�����͏��X�ɐ����A�x�ɐ������܂�悤�ɂȂ����B��p�ɂ͑ς����Ȃ��B�H���ׂ�A�ċz���u�Ђイ�A�Ђイ�v�Ƌꂵ���ɂȂ��Ă����B�u�撣���āv�B�����ɐ��b�������B�x���̖�A�O�o���Ɍg�ѓd�b�ŖS���Ȃ����ƒm�炳��A��債���B �@�c�����납��ꏏ�ɕ�炷�c����ɂ��킢����ꂽ�B�u���N���̖��ɗ��������v�B����Ȏv���ʼn��̐��E�ɔ�э����A�炢�ʂꂪ�����d�����Ƃ͎v��Ȃ������B�u�Ō�Ɍ�����Ȃ��悤�ȃP�A���������v�B���͂����l���Ă���B m3.com�@2011�N1��7�� |
| �d�a�̎q�����z�X�s�X���@�Ó�̐X�̌Ö��ƂŊJ�݂� |
| �@��������Ȃǂ̏d���a�C���Q�Ɠ����q�ǂ��������h���ł���"�q�ǂ��̃z�X�s�X"��_�ސ쌧��钬�ɂQ�O�P�Q�N�H�ɊJ�݂��悤�ƁA�����Ȉ��m�o�n�@�l�̃����o�[�炪������i�߂Ă���B �@�Ó�̊C����]�ł��鍂��̌Ö��Ƃ��ė��p�����{�݂̖��̂́u�C�݂̂���X�v�B���������{�݂͓��{���Ƃ����A�^�c������c�@�l�̗����b��T������i�S�P�j�́u�q�ǂ����������R�ɐG��A������͂�{����ꏊ�ɂ������v�Ƙb���Ă���B �@�b�コ��ɂ��ƁA�q�ǂ��̃z�X�s�X�͏d���a�C�̎q��ƉƑ������S���ċx�{���邽�߂̈�ÃP�A�t���h���{�݂ŁA�p������e���ɍL�܂����B�������̓��{�ł́A�ݑ�Ő��b������Ƒ��ً͋}���Ȃǂ̎q�ǂ��̗a���悪�Ȃ���A�S�g�Ƃ��ɋx�܂�Ƃ����Ȃ��Ƃ����B �@���������Ƒ��̕��S���y������u��Q�̉Ɓv�����낤�ƁA�����ɘa�P�A�Ɏ��g�ލגJ�������H�����ەa�@�i�����j���@���炪���āB���̑�����l������ƂȂǂ̊��������Ă��铌���̂m�o�n�@�l�������̍b�コ�A�S���`���̎c�����Ö��ƂR������A�O�X�N�Ɏ{�݂��^�c������c�@�l�����������B �@����ƃG�C�Y�̊��҂������@�ł��Ȃ����{�̊ɘa�P�A�a���i�z�X�s�X�j�Ƃ͈Ⴂ�A�C�݂̂���X�ł͏d�Ǔx�ɂ�����炸���܂��܂ȏ�Ԃ̎q�������B�J��͊Ō�t���풓���A���ʂ͐e�q�ŔN�V���Ԓ��x�A�h���ł���{�݂�ڎw���B �@�u���͔_�Ƃ⋙�t�Ȃǒn���̐l�����͓I�Ȃ̂ŁA�~�J������n�����Ԃ�̌�����@������肽���v�ƍb�コ��B�X�ł̖ؓo���A�߂��̊C�݂ň�V�т��ł���B �@���݂́A�e�q�Ŕ��܂��h�����Ȃǂ̃o���A�t���[�H�����������A�̌��h�������ꒆ�B �@��N�P�Q����{�A�S�g�������Ȃ��Ȃ��a�������������q�����i�W�j��A��đ̌��h��������t�����ˎs�̐��������i�S�S�j�́u�a�C�̎q�����Ƒ��͉Ƃɂ����肪���B���������{�݂𑝂₵�Ăق����v�Ɗ��҂����B m3.com�@2011�N1��7�� |
| �H�̊�тÂ炷�H�v |
| �@���ʗ{��V�l�z�[���A�u���[�o���C�̊Ǘ��h�{�m�̒����L���q���u��̃`�L���g�}�g�N���[���ςł��v�ƃX�v�[���Ōy�����������B��̃W�����ƃt�H�A�O���̃��[�X�A�X���[�N�T�[�����A���ʒ��̃��[�X���胍���C�����c�c�B �@��N�P�Q���P�P���A�N���X�}�X�c���[������ꂽ�_�˃|�[�g�s�A�z�e���i�_�ˎs������j�̍L�ԁB�P�O��̊ۃe�[�u�����Ƒ��A�ꂪ���ꂼ��͂݁A�t�����`�̃t���R�[�X���y����ł����B �@�ꌩ�A���ʂ̃p�[�e�B�[�B�Ⴂ�́A�V����a�C�A��ᇂȂǂł̂ݍ��ޔ\�͂��ቺ�����u������Q�v�̐l�����̚����H�Ƃ������Ƃ��B �@�P�Ȃ闬���H�Ƃ͏����Ⴄ�B�Ƃ�݂������胀�[�X��ɂ����肵�āA��炩�������̒��ł�����x�ł܂�ɂȂ��Ă̂ݍ��߂�悤�H�v����Ă���B �@���Ɉ�Ñ�̖�艀�q�������z�e���Ƌ��͂��ĂQ�O�O�X�N�����悵�A����łQ�x�ځB���҂���u���܂ɂ͊O�H���v�Ƃ̐��������Ƃ����������Ƃ����B���{�݂̓����҂��K�ꂽ�B �@�p�[�L���\���a�ɔ����뚋���x���ɋꂵ��ł����{��Òj����i�W�P�j�́A�Ȃ̍K�q����i�V�U�j�ƂQ�l�ŖK�ꂽ�B���i�͂��܂��̂ݍ��߂��A�H�����c�����Ƃ��������A���̓��͊��H�B �@�u�y���݂ŁA�O������l�N�^�C�I�тɔY��ł�����ł���v�Ɩڂ��ׂ߂�K�q����B���̉��ʼnÒj����́u�l�N�^�C�Ȃ�Ē��߂�́A�v���Ԃ肾����ˁv�ƏƂꂽ�B �� �@�����H�́A�ߔN�i���𐋂��Ă���B����̈�̓~�L�T�[���������H�ނ��v�����̂悤�Ɍł߂�Q�����܂��B �@�_�ˎs���J���Q���ڂɂ�����ʗ{��V�l�z�[���u�u���[�o���C�v�ŃR���\���X�[�v�������������B�ȑO�Ȃ�~�L�T�[�ɂ�����ꂽ��X�[�v�ƍ������Ă������A�j���W���ƃL���x�c���Q�����܂Ōł߂�ꂽ��Ԃœ����Ă����B�m���ɂ��ꂼ��̖��������B �@�Ǘ��h�{�m�߂钆���L���q����i�R�T�j�́u�����������̂͌뚋��h���v�����_�B���͋C�����������̗v�f�ƍl���A�s����G�߂��Ƃɓ��ʂȃ��j���[�̐H�������B �@���H�ɂ����o�C�L���O�������Ƃ��̂��ƁB���i�͚����H�����H�ׂȂ����p�҂��A�z�^�e�̈��肸���ɁA�����Ǝ��L�����B��������͋����킹�����m�ƋV�B���Ӑ[����������B��������̂ݍ��ނ̂����͂����B�u�D���Ȃ��̂Ȃ�H�ׂ������A�H�ׂ���v�B�����M���Ȃ����B �� �@��ނ̍Ō�ɁA�{���s�������̔����a�@�̊ɘa�P�A�ȁi�z�X�s�X�j��K�˂��B�v�Q�O���B�����̂��҂��A�c���ꂽ�l���̎��Ԃ��߂����B �@�����A�e�������Ǘ��h�{�m���܂��A�̒������A���̓��̒��H�Ɨ[�H�̊�]���Ƃ�B���j���[�ɂ͒��邻�ꂼ��Q�P�i�̎ʐ^�����ԁB�r�t�e�L�₤�ȏd�A�������H��C�N�̓��Ă��Ȃǃ��X�g�����畉���̓��e���ւ�B�ǂ��I��ł���H�̒l�i�i�Q�U�O�~�j�͕ς��Ȃ��B��Ԑl�C�͓�Ă����ǂ������B �@���a�@�̉h�{�Ǘ��ȋZ�t���̓n�ӑP������i�T�S�j�́u���j���[�ɍڂ��Ă��Ȃ��������ޗ��̓s�����t���悤��������Ή�����v�Ƙb���B �@�Ƃ�킯�l�C�ŁA���ʂȗ����́A���������тƂ����B�T�����l���ۂ�J���s���o�N�^�[�ɂ��H���ł̐S�z������A�a�@�ł̒͂���߂č���Ȑ����B�����a�@�ł��ɘa�P�A�ȈȊO�̕a���ł͏o���Ȃ��B�k�̏ォ��A���R�[�����ł�����ŁA�R�O���ȓ��ɐH�ׂĂ��炤�B �@���N�̏t��A�S���H�~���o���A�ӂ�������ł����V�O��̑咰���҂̒j���������B�u���������сA�H�ׂ܂��v�B�n�ӂ���̒�Ăɒj���̊�F���ς��Ɩ��邭�Ȃ����B�u���������v�ƐH�ׂ�p�ɁA�ȂƑ��q���܂��B�P�J����ɑ��E����ԍۂ܂ŁA�H�������y����ł����Ƃ����B �@�u�����������o�����H�����A���҂���̐l���̍Ō�̐H���ɂȂ�B�o�������̂��Ƃ��������B������Ȃ��悤�Ɂv �A�T�q�E�R���@2011�N1��7�� |
| ����ł݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ�!?�@��p�A��Ìn���w�Z�Ɂu���S�̌��J���L�������v���J�� |
| �@����ŏ��߂Ė��̑�����m��I�@��p�m������Ȋw�Z�i�ȉ��m�����j�͐��E�ŏ��߂Ď��S�̌��J���L���������J�݂��A12��8���Ɍ��J���\����s�����B�w���͎��ۂɈ⌾��������A�����A�o���A�������̎��S�̃v���Z�X��̌����邱�Ƃ��ł���B �@�ɂ��ƁA�m������2009�N�ɐE�Ɛ��N���X�Ƀ��C�t�P�A���Ɗw�Ȃ�ݒu���A2010�N�A��p���畔�i���ȏȂɑ����j����⏕��500����p�h���i��1400���~�j���A�u���V�������w�Z���^�[�v��ݗ������B�Z���^�[�ł̓O���[�t�P�A�A�I�����P�A�A�e��֏ꓙ�̐�勳���ȊO�ɁA10�̓����������ݒu����Ă��鎀�S�̌���������A�w���͊��S�Ȏ��S�̃v���Z�X��̌����邱�Ƃ��ł���B �@�m����ꃉ�C�t�P�A���Ɗw�ȏ�����緒B�\���ɂ��ƁA���S�̌��J���L�������͂܂��������瓱���Ƃ��āu���H�O����v���s���A���̌�A�w���͈⌾��������A���ɑ����ɒ��ւ��A��e���B�e���Ă��犻���ɓ���B�w�������̎w���ɂ��A���̂Ǝ����̐��U�ɕʂ�������A�{���̈�̂̂悤�ɑ��V�t�����g�̂��߂ɍs�������A�o���A�������̈�A�̃v���Z�X��̌�����B �@緒B�\���ɂ��ƁA�w�Z�����C�t�P�A���Ɗw�Ȃ�ݗ������ړI�́A�e���ʂŊ���ł��鑒�V�t�̈琬�ł���B�w���̊����̒��ł̑̌����Ԃ�10���قǂł����Ȃ����A�u�ԋ߂Ɏ��������A����̗���ɗ����čl���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�v�������B���҂�⑰���X�ɑ��d���v�����A���̉��l������̌����邱�ƂŁA���V�T�[�r�X�̌���ɂȂ����Ă����ƌ����B �@�w�������̗��ߎ��́A���S�̌��J���L�������͈�w�A�S���w�A�@���Ȃǂ̊p�x���玀�����߂邾���łȂ��A�u���̉��̈ӎ��v�Ƃ����ӎ��T�O�ɒB���邱�Ƃ��ł���ƌ����B���V�Ƃɏ]������҂͋V���������Ɏ���s�������łȂ��A�u���҂̊��o�v�d���邱�Ƃ��X�ɏd�v�Ȃ̂ł���B �@���S�̌��J���L�����������Ō�w�Ȃ̗т���́A�u�����ɓ��������̏u�ԁA��������̂��Ƃ��܂���萋���Ă��Ȃ����Ƃ��v���o���āA�������c�O�Ɏv�����v�ƌ��B�̌����I����āu�����v������A������1��1�b���ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv�����������B �@�܂��A�w�Z���́A�ډ��A���O�҂����S�̌��v���O�����ɎQ���ł���ƕ\�������A�����I�ɂ͒n��A�e��c�́A�X�ɂ͖��Ԋ�Ƃɂ܂ł��̑Ώۂ��L���A��葽���̐l�ɑ��Ƃ͈�����u���̂��̋���v���Ăق����Ƃ��Ă���B ���P�b�g�j���[�X24�i���j�@2011�N1��8�� |
| ���̂Ƃ����� |
| �@�u���R�Ȏ����v�ς��ӎ� �@�������߂��A�����߂��Ƃ킩������A�ǂ�Ȏ��Â�P�A���������B �@�����J���Ȃ��Q�O�O�W�N�A��ʂ̐l������ΏۂɎ��{���������ɂ��ƁA�������U�J���ȓ��ɔ����Ă���ꍇ�A�V�P���̐l��������Â��u�]�܂Ȃ��v�u�ǂ��炩�Ƃ����Ɩ]�܂Ȃ��v�Ɖ����B �@����Ŋ�]����̂́A�u��ɂ�a�炰��v���T�Q���ōő��B�u������Â𒆎~���āA���R�Ɏ������}��������v���Q�W���ŁA�����͂P�O�N�O�̓��l�̒�������{�������B �u���҂���@���̂܂܂Łv�ŏЉ����ӋI�q����́A�ǂɂ��h�{�⋋�Ƃ������[�u�����݁A���̉ƂŖS���Ȃ����B �@�X�O�N��ɂW�O���l�䂾���������̔N�Ԏ��S���́A�O�R�N�ɂP�O�O���l�����B�Q�O�Q�O�N��ɂ͂P�T�O���l��Ɛ��v����Ă���B �@��t�̑[�u�Ő������I��点��u���y���v��u�l�H�ċz����O���v�̎��Ⴊ�\�ʉ����A������I������Âɒ��ڂ��W�܂����B�ŋ߂́u���҂ɂƂ��āA�ǂ�ȍŊ����]�܂������v�ɏœ_���ڂ��Ă��Ă���B �u�I�����v�Ƃ͋�̓I�ɂǂ�ȏ�Ԃ������̂��A���͖��m�Ȓ�`�͂Ȃ��B�u�����v�ɂ��Ă��A���������ɂ�����̂��͂͂�����ƌ��܂��Ă��炸�A�l���̏I�����߂���c�_���{�i������̂͂��ꂩ��ɂȂ�B �@���J�Ȃ̐l�����ԓ��v�ɂ��ƁA���{�l���S���Ȃ�ꏊ�́A���Ă͈�Ë@�ւ�莩����������B���ꂪ�V�U�N�ȍ~�͋t�]�B�O�X�N�ɂ͈�Ë@�ւŖS���Ȃ����l���W�P���A����͂P�Q���������B���͂O�U�N�A�Q�S���ԑ̐��ʼn��f�����t�ւ̐f�Õ�V�����������u�ݑ�×{�x���f�Ï��v�̐��x�����A�ݑ�ւ̎x����i�߂Ă���B�����A�n��ɂ���Đf�Ï��̐��⎿�ɂ͂��������B �@�Ŋ����ƂŌ}���邽�߂̎x���̂����݂Ƃ��āA��t�̉��f��K��Ō�A�ꍇ�ɂ���Ă͉��ی��𗘗p�����K�������w���p�[�̃T�[�r�X�Ȃǂ�����B�I������ÂɊւ�����J���̍��k���N���ɂ܂Ƃ߂����́A��Âɉ����āA���҂̐������x���邵���݂��܂߂����̕��y���ۑ�ɂ������B �@���k������̒�����q�勳���́u�܂���Â╟���ɂ������l���A�I������Âɂ��Ă̐��m�Ȓm���������A�킩��₷���������邱�Ƃ��K�v�B��ʂ̐l���A�����ɂȂ��Ă���������ʼnƂʼn߂����邱�ƂȂǁA������[�߂Ăق����v�Ƙb���B �@�����I�����c�H�@�˘f���Ƒ� �@�E���̏Ǐ�łQ�O�P�O�N�P�O���ɎO�d�����̕a�@�ɓ��@�����W�V�̊}�Ԉ�j����́A������h�{�̕⋋�ł�����������悤�Ɍ����A�ꎞ�͑މ@�ւ̊��҂��������B�����A���@�S���ڂ̂P�V���ɂR�W�x���M���o���A���ꂩ��͘b���قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ����B �@����������̗ʂ́A�����łƂ��Ă�����肸���Ƒ��������B���̂��߈�j����͂�����݁A�z�����K�v�ɂȂ����B �u���͏I�����Ȃ̂��v �@���j�̖r����i�T�Q�j�́A�����Ă����B�ʏ�̒E���Ȃ�A�P�A�Q���̓_�H�ʼn���͂��B����͂����̒E���Ƃ͈Ⴄ���Ƃ��A��t�̖r����ɂ͂悭�킩���Ă����B �u�����������Ă���ꍇ�A�����[�u�͒f��v�B��j�����������O�w�����̎ʂ����A�S����ɓn���Ă����B�ł��A���܂����́u������f��v�����Ȃ̂��A�ǂ����B �@��j���w��������낤�Ǝv�������ڂ̂��������́A�O�X�N�V���A�Ȃƈꏏ�ɐX���̗F�l�v�Ȃ�K�˂��Ƃ��������B���N��̂��̒j���́A�]�[�ǂ̌��ǂłQ�N�ȏ�Q�����肾�����B�Ăт����Ă������͂Ȃ��A�@����ǂ�ʂ��ĉh�{�𑗂荞�܂�Ă����B �@��j����͂��̗����I���Ă����A�C���^�[�l�b�g�Œ��ׁA�w�������������B�����ɂƂ��Ă̍Ŋ��������ӎ������悤�������B �@�r����́A��j��������H�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��A�މ@���ĉƂŗ×{�ł���悤�A�݂Ɍ����J���ĉh�{�𑗂�u�݂낤�v���������Ă����B��j����̏�Ԃɍ��킹�A���ی��̕ύX�\���������B�u�Ŋ��͎���Łv���A��j����̊肢�������B �@�����A�e�͈̂��������B���@�U���ڂ̂P�O�N�P�O���P�X���A�����ُ�ɑ��܂�p�����o���B������������A�ӎ����͂����肵�Ȃ��Ȃ����B �@�r����̖����́A�����Ă����B �u�{���Ɂw�I���x�Ɣ[���ł����Ȃ�A���킸�w�����ɏ]���B�ł��A�w���������邱�ƂƁA�Ƒ����w�I�����x�ƔF�߂邱�Ƃ͕ʖ�肾�v�B�r����͂����l���Ă����B �u�v�������v �@�Q�P���ߑO�V������B�r�����̎U������Ƃɖ߂�ƁA���Ԃ̓d�b�������B�\�����ꂽ�����̎s�O�ǔԂ́A��j�����@����a�@�̂��̂������B �u�����A��������v �@�d�b���Ƃ�ƁA��͂��Ζ����̊Ō�t���炾�����B �@�ċz��~�̘A���@�Ŋ������� �@�Q�O�P�O�N�P�O���Q�P�����B�Îs�̊}�Ԗr����i�T�Q�j������̓d�b���Ƃ�ƁA�W�V�̕��A��j�����@����a�@�̊Ō�t���炾�����B �u��������̖������R�O���炢�ŁA�ċz���~�܂��Ă��܂��B���ꂳ��ɂ͘A�������Ȃ��̂ł����A�����ɗ��Ă��炦�܂����v �@�r����́u����͖������B����������Ȃ��v�B���̎����ԋ߂��ƁA���߂Ď��������B �@�������������߂����̑[�u�͈���Ȃ��B�r����́A��j����̊�]���L�������O�w�����̎ʂ���a�@�ɓn���Ă����B����ŁA�u�̉\��������Ȃ�A�l�H�ċz��𒅂��Ăق����v�Ɨ���ł������B �@���݂��̂ĂɎ��Ƃ̊O�ɏo�Ă��āA�a�@����̓d�b�ɏo���Ȃ�������i�W�T�j�̂Ƃ���ɁA�r���Ԃŗ������A�ꏏ�ɕa�@�ɍs�����ƂɂȂ����B���Ƃւ̓r���A�r����͂�������Ԃ��~�߂ĕ�ɓd�b���A���B �u�ċz��𒅂��邩�����Ȃ����A�a�@�Ŗ����Ă��邩���m��Ȃ��B���ԂȂ����Ԃɍ���ւ�A���ꂳ��̂ق�����w�{�l�̊�]������A�����Ȃ��Ă����x�Ɠ`���Ă����āv �@��ƍ������A�Q�l�ŕa�@�ցB���@����W���ڂ̒��������B�u���������ȁv�Ɩr�������ƁA��́u���������ˁv�Ɠ������B �@���Ƃ���T���قǂŁA�a�@�ɒ������B�����Ƃ������̃x�b�h�ŁA�ċz�ƐS�����~�܂�����j���Q�Ă����B�_�H�⓱�A�A�_�f�}�X�N�͂����܂܂������B�r�����̓������A��t�����S���m�F�����B �@�ߑO�W���P�O���B�����͔x���������B �@��́A��j����ƌ������ĂT�V�N�ڂ������B�v�ɂ͂����Ɛ����Ă��Ăق��������B�ł��A���@�̌㔼�͂�������A���o�āA�ꂵ�����������B���킢�����������B �@��t�̖r����́A�����Ɩ����������B�����A�w�������Ȃ�������\�\�B�����ƁA�ċz��𒅂��Ă������낤�B �@�����č���A�킩�������Ƃ�����B �@�Ƒ��Ƃ����̂́A�Ō�܂Ŋ�]���̂ĂȂ����̂ȂB�u�I�����v���Ǝ����ɂ́A���̎��Ԃ�������A�ƁB �@���g�̊��҂̉Ƒ��Ɉӌ����Ƃ��A�u������f�ł���ˁv�Ǝ��R�Ɍ��ɂł���悤�ɂȂ����B �@�����n���Ă��ꂽ���O�w�����́A���܂��r����̎茳�ɂ���B�����̂Ɏg�����p�\�R�����A���炭�͎��Ƃ̋��Ԃɂ��̂܂܁A�u���Ă������肾�B �@���i����b�������� �@�a�C�ʼn������߂��A�����������Ƃ��ɔ����āA���Âɂ��Ă̊�]�������Ă������ʂ����O�w�������B�u���r���O�E�C���v�i�k�v�j�Ƃ��Ă��B�l�����ς��A�o�^����߂��菑����������ł���B �@�悭�m���Ă���̂́A�P�X�V�U�N�ݗ��̓��{����������i�����ǁE�����j���n�߂��u�������̐錾���v�B������x�点�邽�߂̉����[�u��A������A����Ԃ����J���ȏ㑱�����ꍇ�̐����ێ���f����e�ŁA�{�l�������A�������{������ۊǂ��A�R�s�[���Ƒ���Ɏ����Ă��Ă��炤�B��P�Q���T��l���o�^���Ă���B���͔N�ԂQ��~�B �@���ۂ̈�Ì���ł́A�{�l���]�܂Ȃ��ߏ�Ȉ�Â�����A���Ăق������Â����Ȃ������肷�邱�Ƃ�����B���ʂ�����A����Ȏ��Ԃ��������\��������B �@��ʂ�Ώۂɂ��������J���Ȃ̂O�W�N�̈ӎ������ł́A�k�v������Ă������p����Ƃ����l���Ɏ^�������̂͂U�Q���B�P�O�N�O�̓��l�̒�������P�S�|�C���g���������O���t�B �@�Ǝ��̏�����p�ӂ���a�@���o�Ă����B �@�S���{�a�@����̏����̏ꍇ�A�A�t��o�ljh�{�ȂǘZ�̈�Ís�ׂɂ��āA��]����A���Ȃ���I�ԁB���������Q�Q�O�O�a�@�̎Q�l�ɂ��Ă��炤���߂ɍ�����B �@����������Ì����Z���^�[�i���m����{�s�j�̏����́A�{�l�����f�ł��Ȃ����Ɏ厡�オ���k���ׂ��u�㗝�l�v�L���A�I�������}�������ꏊ��I��ł��炤�̂��������B �@���H�����ەa�@�i�����s������j�̏����ł́A�u�l�H�ċz��A�i�S��~�������́j�S���}�b�T�[�W�ȂǍő���̎��Â���]����v�u�����⋋���s�킸�Ŋ����}�������v�Ȃǂ̌܂̒�����A�����̍l���ɍł��߂����ڂɃ}�������Ă��炤�B�ҍ����ɒu���Ă���B �@�����A�����͂��ꂼ��̕a�@�ɂ����銳�҂�Ώۂɂ��Ă��āA���ʂ��Ȃ��a�@�𗘗p���銳�҂͐ڂ���@��Ȃ��B���̂��߁A���݂���m��Ȃ��l�������B �@���ʂ͊��҂̎��Õ��j�ɂ��āA�Ƒ�����t�Ƙb�����������ɂ��Ȃ�B�Ƃ͂����A�{�l�̈ӎv���u���̎��v�ɓˑR������Ă��A�Ƒ��͌˘f�������m��Ȃ��B �@���H�����ەa�@�̂k�v��������я͕q�E�ɘa�P�A�Ȉ㒷�́u���ʂ͂����܂ŁA�{�l�̊�]��m�邽�߂̈��i�B�����ďI���A�ł͂Ȃ��A���i����Ƒ���Ɗ�]��b�������A�l����[�߂Ăق����v�Ƙb���B �A�T�q�E�R���@2011�N1��16,21,22,23�� |
| ����鍐�́w�]���킸���̉ԉŁx�@�a�@���ŋ����Q����Ɏ��S�@�� |
| �@�����鍐����A�]���킸���Ɛf�f���ꂽ�W�F�V�J�E���[�X����i�Q�T�j���P�R���ɕăC���f�B�A�i�B�G�o���X�r���̃Z���g�E�}���[�a�@���Ō������������A���̂Q����̂P�T���Ɏ��S�����B �@�v�̃_�j�G���E���[�����X����i�Q�U�j�͓��B�̃��C�c���Z���ォ��̒m�荇���B�W�F�V�J����͍�N�X���ɂ����鍐����A�]����������Ȃ����Ƃ�m�炳�ꂽ�B�������A���[�����X����́u�ޏ��̍Ō�̖]�݂����Ȃ������v�ƌ��������ӁB�a�@���̃`���y���ōs��ꂽ�������ɂ͗F�l��P�T�O�l����Ȃ����B �@���ł̓W�F�V�J����̂����̃W�F���[�E���[�X���q�t�߁A�u�Q�l�͌���Ă�苭���Ȃ�ł��傤�v�Əj���B�������A���̂Q����̂P�T���ߌ�V���R�T���A�W�F�V�J����̓��[�����X����ɊŎ���Ȃ���Â��ɑ�������������B �@�W�F���[����́u�������Ƒ��͐[���߂��݂ɕ�܂�܂������A�������̊�т́A������͂邩�ɏ�����̂ł����v�Ƙb���B�W�F�V�J����ƃ��[�����X����̊Ԃɂ͂P�U�J���ɂȂ鑧�q������A�W�F���[����́u�W�F�V�J�́A�������Ƒ��̒��͌����Đ藣���Ȃ����̂��Ƃ������Ƃ������Ă��ꂽ�v�Ƙb���Ă���B MSN Japan�Y�o�j���[�X�@2011�N1��19�� |
| �R�N�O�ɍ��m���c�������ۂ����a�c�ׂ���A����́H |
| �@�����P�S���A�H����炪��̂��߁A�W�O�Ŏ����������m�g�j�̖����f�B���N�^�[�A�a�c�ׂ���B��R�N�O�ɁA���m�������A��p����ʂȉ������Â���]�����A�a�@����s���̃P�A�n�E�X�Ŋɘa���Â��Ă����悤���B���������A����Ƃ̌����������ɂ��āA����͂ǂ����Ă���̂��B �@�Ղ̖�a�@�O�ȕ����E�����m���t�́u�a�c�����ׂĂ̎��Â����ۂ����̂��A���邢�͍R������Â��������ۂ��ĕ��ː����ÂȂǂ͎Ă����̂����킩��Ȃ��̂ŁA�͂����肵�����Ƃ͌����Ȃ��v�Ƃ�����ŁA�������B �u�����O�҂ł���Ύc�O���B�H������ɂ͕��ː��ƍR������Â̑g�ݍ��킹�Ŏ�p�Ɠ����̎��Ì��ʂ�������P�[�X���������Ȃ��B���́g���ʁh�����N�̉����Ȃ̂��A���邢�͐��N�ɋy�Ԑ������Ԃ̉����Ȃ̂��͌l���������Ĉ�T�ɂ͌����Ȃ��B�܂��R����܂��g�����Ƃŕ���p��������̂����������A��������������v�f���l�����킹�������ŁA�ŏI�I�ɂǂ����ׂ��������߂�̂͊��҂��g�B��Ȃ̂́A���҂����̑I�����ɂ��Ă悭�������邱�Ƃ��Ǝv���v �@�ŋ߁A�T�����ȂǂŁu�R����܂͌����Ȃ��v�Ƃ������_�����A�����邪�c�B �u�ꕔ�͔[���ł��镔�������邵�A�c�_�ނ��Ƃ͂������Ƃ����A�����Ă����g�ɘ_�h�B��t������I�Ɋ��҂ɉ����t����̂́A���҂̕s���v�ɂȂ��肩�˂Ȃ��v�ƍ�����t�B �u�m���ɕW�����Âł̍R����܂̎g�����ɂ͖��_�͂���v�ƌ��̂́A���ۈ�Õ�����w���w�Ö@�����������a�@�����E�����L��t�B �u���ʂ╛��p�̏o���ɂ͌l�����傫���A����p�̃��X�N���l�����ɁA�N�ɑ��Ă��ꗥ�Ƀh�J���Ǝg���Ă���A���ƂŒ������Ă����|�Ƃ����l�����͊��Җ{�ʂ̈�Âł͂Ȃ����A���ׂ��ł͂Ȃ��B����p�ŋꂵ�܂Ȃ��M���M���̐��ŁA�ʂ̓��^�ʂ�����߂Ă����ׂ₩�Ȕz�������ׂ����v �@�����A������t���A�ŋ߂́u�R����܂͌����Ȃ��v�Ƃ����ꕔ�̘_���ɂ͔ے�I���B �u���܂ǂ��w�R����܂������Ȃ��x�ȂǂƂ�����t�����邱�Ƃɋ������ւ����Ȃ��B�܂��Ƀi���Z���X���v �@�ǂ��܂ł̎��Â���]���邩�́A���҂̐l���ς������B�����āA�a�c����̈��炩�Ȏ���ے肷����̂ł͂Ȃ����A�R����܂Ɋ�]��������������������̂��B ZAKZAK�@2011�N1��25�� |
| �q�ǂ��I������ÁF�{�l�̈ӎv���d�@�w��w�j�āA�u���Ò��~�����v���L |
| �@���{�����Ȋw��i�\������j�̗ϗ��ψ����ƕ���́A�d���a�C�₯���������q�ǂ��̏I������ÂɊւ���w�j�Ă��쐬�����B�N��ɂ�����炸�A�{�l�̋C������ӌ����ő�����d���邱�Ƃ������Ƃ��A���Ò��~�⍷���T�����������鎖�Ԃ�F�߂����A���j�����߂�ۂ̗��ӓ_��菇�������Ă���B �@�I������Â��߂����Ă͂O�V�N�Ɍ����J���Ȃ����Җ{�l�̈ӎv�������{�Ƃ���w�j�\�������A�q�ǂ��̃��[���͂Ȃ������B���w��͉�����ʂ̈ӌ�������ŔN���̐��������ڎw���B �@�w�j�ẮA��t��Ō�t��̈�Î҂��q�ǂ��ɕ�����₷���������A�q�ǂ��������̋C������ӌ������R�ɔ�������@����m�ۂ���ƂƂ��ɁA���e�i�ی�ҁj�͂��̈ӎv�d���Ď��Õ��j�����߂邱�Ƃ����߂Ă���B �@���Â̍����T����l�H�ċz��̎��O���Ȃǂ̎��Ò��~�ɂ��ẮA�q�ǂ��̍őP�̗��v�ɂ��Ȃ��ƍl������ꍇ�Ɂu��Ăł���v�Ɩ��L�����B�������A���e�ƈ�Î҂̔[�������܂ł̘b������������ߒ��ւ̑����̈�Î҂̎Q�������f�����̏��ʂւ̋L�^�|�|�Ȃǂ̓_�����ڂ�����B����ɋs�҂̗L���ɂ��āA�W�@�ւƋ��͂��Ċm�F����A�Ƃ��Ă���B �@�������A���Ò��~�E�����T���Ɣ��f�����́A�q�ǂ��̕a�C���Ԃ����҂ňႢ���傫�����Ƃ�w�i�ɁA���L����Ƌ@�B�I�Ȏ��Ò��~�̔��f���N�����˂Ȃ��Ƃ̗��R�Œ�߂Ȃ������B �@���w��͈�ʂ̈ӌ������߁A�Q���Q�U���ߌ�P�����A����c���[��L�O�z�[���i�����s�V�h��j�Ō��J���_����J���B�₢���킹�͊w����ǁi�O�R�E�R�W�P�W�E�O�O�X�P�j�B ���������������������������� �@����� �@���u�N��v�������������@����ɂ͍ٗʍL�� �@�x�R���ː��s�̕a�@�ŋN�����������҂̐l�H�ċz��O�����i�O�X�N�Ɉ�t�͕s�N�i�j���A�����J���Ȃ��O�V�N�ɂ܂Ƃ߂��I������Â̎w�j�́A��ɑ�l��ΏۂɌ������Ă����B����A�������߂Ȃ��܂܁A�W�����Î��ɂ���q�ǂ�������̂��������B�܂��A�O�W�N�ɍ��������ÃZ���^�[�i�����j�́A�Ƒ��̓��ӂĐS�x��~���\�z����鏬���R�O�l�̎��Ò��~�����{�����ƌ��\�B���������m�ۂ��郋�[�����K�v�ɂȂ��Ă����B �@���{�����Ȋw��͎q�ǂ��ɂƂ��āA�q�ϓI�ɂ��őP�Ƃ����鎡�Â̕ۏ��ڎw�����B�w�j�ẮA�q�ǂ��́u�C�����v�d���ĕ��j����̓����҂ɉ����A���e�A��Î҂��܂ފW�ґS�����b�������A�[���ł���ӌ��̈�v��ڎw���葱����_�����ڂ���Ă���B �@�q�ǂ��̈ӎv�̊m�F�@�́A�q�ǂ��̏I������Ẩۑ肾���A�w�j�Ă͔N��ɂ��Ă̐������͂��Ȃ������B�q�ǂ��̔��B��a��͈�l�ł͂Ȃ��A�ɉ����āu�P�[�X�E�o�C�E�P�[�X�v�ɑΉ����邱�Ƃ��q�ǂ��̍őP�̗��v�ɂȂ�Ƃ̔��f���炾�B�������R�ŁA�͂������Ƃ����q�ǂ��̎��Â̒��~�E�����T���̊����߂Ă��Ȃ��B���̌��ʁA�����̎d���Ȃnj���̍ٗʂɈς˂�ꂽ�_�������B �@�w�j�č쐬�̈Ӌ`�ɂ��āA�S���҂́u�q�ǂ��{�l�A���e�A��Î҂�������Ȃ��葱�����������v�Ƙb���B���w��w�j���ɏ��o�������Ƃ́A���肬��̔��f�𔗂��Ă�����Ì���ɂƂ��ĘN��ɂȂ�Ƃ݂��邪�A�����ɏ����Ȉ�̊Ԃɂ́u���ՂȎ��Ò��~�������炳�Ȃ��悤�ɂ��ׂ����v�Ƃ̐��͎c��B�w�j�Ă����������ɋc�_��[�߂邱�Ƃ����߂���B ����jp�@2011�N1��27�� |
|
�d�x�̔F�m�ǂɂ͊ɘa�P�A�� �u���I�A�V�X�v�ɉ������� |
| �@�d�x�̔F�m�NJ��҂͎����̏Ǐ���\���ɓ`���邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁C��t�����҂����҂̏�Ԃ�c�����ɂ����B�����ŁC�P������w�a�@�ɘa�P�A�Z���^�[�̘V�N���_�Ȉ�ł���Klaus Maria Perrar���m�́C�����������҂ɑ���P�A�ɂ��āu�����_�ł́C�F�m�ǂ͎����s�\�Ȏ����ł��邽�߁C�I�����ɂ͊ɘa�P�A���s���ׂ��ŁC���҂���ɂɊ����Ă���Ǐ�����ɂ߂āC���̏Ǐ��\�h�E�ɘa����ƂƂ��ɁC�s�v�Ȉ�w�I��������炷���Ƃ��ɂ߂ďd�v�ł���v�Ƒ�8��h�C�c�ɘa��Êw��c�Ŏw�E�����B �o�߂ƂƂ��Ɋ��҂̍l�����͕ς�� �@Perrar���m�ɂ��ƁC�F�m�NJ��҂́C�����̌o�߂ƂƂ��Ɏ��g�̕a�C�ɑ��銴�������ς���Ă���Ƃ����B�����i�K�ł͔]�@�\������ȂƂ�������C���̍ۂɎ��g�̒m�I�\�͂�����Ă��邱�ƂɋC�t���C�ꂵ�ފ��҂������B�������C�F�m�ǂ��i�s����ƁC�����̊��҂��K����������悤�ɂȂ�C���ɂ͔��ǑO�����������銳�҂�����B�܂�C�i�s����ɂ�C�����̊��҂��y�ϓI�ƂȂ�C���������N�Ŗ��͓I�ł���Ǝv���悤�ɂȂ�B�������C���̂悤�Ȍo�߂͏\���ȉ��Ԑ��������Ă���ꍇ�ɂ̂ݔF�߂���B �@�܂��C�����m�́u�i�s�ƂƂ��ɐV��������~�ςł��Ȃ��Ȃ�C���Ԃ̊T�O������Ă����B����ɔ����C���g�̐����̗L�����⎀�ɂ��Ă̒m��������Ɏ����Ă����v�Ɛ����B���ہC�����m�͂���܂łɁC�V�l�z�[���ɓ������Ă���d�x�̔F�m�NJ��҂��e�������e�̎��ɒ��ʂ�����ɁC�ꎞ�I�Ɏ�藐�����Ƃ͂����Ă��C�����Ɍ��̐����ɖ߂�l�q��ڂɂ��Ă���B �@�����m��́C����ɔ����d�v�����Ƃ��āu���҂����ǑO�Ƀ��r���O�E�B���Ȃǂ̌`�Ŏ������ӎv�\�����C����Ƃ����nj�ł��C������x���含���ۂ���Ă����Ԃł̈ӎv�\���̂ǂ���d���ׂ����v�Ƃ��������������Ă���B �@����C�u�F�m�ǂ����ׂē���Ɉ����̂͊ԈႢ�ł���v�Ƃ��w�E�B�F�m�ǂƂ����ƁC���Ǘ����ł������A���c�n�C�}�[�^�F�m�ǂ��v�������ׂ邪�C�炢�ϑz�⌶�o�Ȃǂ̐��_�Ǐ������Ƃ��郌���B���̌^�F�m�ǂȂǂ�����C���ꂼ��o�߂��قȂ�B�Ⴆ�C�A���c�n�C�}�[�^�ł͔F�m�\�͂����N�ɂ��킽�菙�X�ɒቺ���邪�C�܂�Ɍ�����N���C�c�t�F���g�E���R�u�a�ł͔F�m�ǂ͒��������C2�`3�N�Ŏ��Ɏ���B�܂��C�]���ǐ��̏ꍇ�́C�F�m�ǂ��i�K�I�Ɉ������C����������������Ƃ���������������C���̌^�ł͎��E���������Ƃ����B �@���݁C�F�m�ǂ̏I�����Ɋւ���f�[�^�͂قƂ�ǂȂ��B���Ҏ��g�̕a���Ɨ����������Ă������߁C��ɂ�������Ǐ�ɂ��Ēm�邱�Ƃ�����ŁC�܂������_�ł́C��ɂ̓x�����i�u�ɂ͕����邩������Ȃ����j�𑪒肷��L���ȋ@����Ȃ��C�������邵���Ȃ��B���̂��߁C�����m�́u����C�I�����O�ƏI�����ɂ�����F�m�ǂ̐f�f�@�����P����C����ɂ��\�オ���シ�邱�Ƃ��ɖ]�܂��v�Ƌ��������B �u���I�A�V�X�v�Ƃ��������� �@�h�C�c�ł͋ߔN�C�d�x�̔F�m�NJ��҂ɑ���V���ȃP�A�̌`�ԂƂ��āu���I�A�V�X�v�����݂��Ă���B�d�x�F�m�NJ��҂́C����ɂ��ӎv�a�ʂ��S���C���邢�͂قڕs�\�ŁC�Q������C�܂��͂قƂ�ǐg�̂������Ƃ��ł��Ȃ����߁C���x���ł������Ȃ�B�u���I�A�V�X�v�ł́C���������d�x�F�m�NJ��� 6�`8�l���J�[�e����ǂ̈ꕔ�Ŏd��ꂽ�啔���ŋ����������C�P�A�X�^�b�t��14���ԏ풓����B �@���݁C���̕]�����s���Ă��邪�C���ɔ��\���ꂽ�ɂ��ƁC���҂̒��ӗ͍͂��܂�C�h�{��Ԃ����P����C�؋ْ��Ɛ��_�I�ْ����ቺ����B���X�^�b�t�̖ڂ����҂ɓ͂��₷���C�ʏ�̎{�݂�薞�����������Ă����B�܂��C�Ƒ��͊��҂�a���邱�Ƃŕ��S���y���Ȃ����Ɗ����Ă���Ƃ����B����ɁC�����̒ǐՒ����ł́C���̂悤�Ȍ`�Ԃʼn��������҂̕������������邱�Ƃ��m�F����Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N1��27�� |
| �q��Ă������@�a�@�̎q�ɏ����@�����t�̑哏�k��� |
| �@������̓T�[�J�X��V���n�̃V���[�Ńp�t�H�[�}���X���铹���t�i�N���E���j���A�a�@�ɓ��@���̎q�ǂ�������K�₷��u�z�X�s�^���E�N���E���v�B���{�ł͂܂�����݂̔������������A���Ă̕a�@�ł͎��Â̈�тƂ��Ē蒅���A�Ɖu�͂����߂���̌��p�ɂ��Ă̌������i��ł���Ƃ����B����ȃz�X�s�^���E�N���E���̓��{�ł̕��y��ڎw�������t�̑哏�k���i�S�P�j�����É��s���́u�a�Ɠ����q�ǂ��������A�q�ǂ��炵�������߂���`�����������v�Ƙb���Ă���B �@�������̃T���^ �u�����[�N���X�}�X�I�v�\�B�Q�O�P�P�N�P���P���A���É��s���S���ɂ��閼�É����ԏ\���a�@�B�l���̂Ȃ������a���ɁA���邢�����������B�P�W�O�Z���`�̒��g��N�₩�ȃI�����W�F�̂Ȃ��ɕ�݁A�傫��������F�̌C�ɐԂ��@�B�����āA�T���^�N���[�X�̈ߑ��B�啔���̃J�[�e���z���Ɂu�����[�N���X�}�X���āc������������I�v�Ƃ������q�ǂ������̕\��ɂ́A���Ɋ��҂Ɗ�т����ӂ�Ă����B �u�����̕a�@�́A��t�A�Ō�t�����Ȃ����A�O���ł��銳�҂͉ƂɋA��̂ŁA�������₵���Ȃ��ł��B������A���N�����͕K���a�@�̎q�ǂ������ɉ�ɗ��܂��B�N�ɂƂ��Ă������͑厖�B�����ɃT���^���āA�e�L�g�[�Ȋ��������āA�Ȃ����ł���H�v �u���\�͂Ŗ��O���Ă悤���H�v�u������ɏ����Ă���̓ǂ�ł���I�v�u�͂��A���̎��v�A�v���[���g�v�u���A����A�ڂ��́I���̊ԂɎ�����́H�v�\�B�▭�ȃ{�P�ŏ���U������́A��i�̂悤�ȕ��D�A�[�g���I�B���Â̕���p�ő����̔��������������q���A�N�₩�Ȏ���ɖڂ��P�����A�x�b�h�̏�Ŕ�ђ��˂�悤�ɂ��Ď��L���Ă����B �u���ߐ��������̑��̌��Ԃ���V�N�ȕ�������悤�ɁA�q�ǂ��������a�@�̒���l�߂���C�̒��łӂ��Ƒ������鎞�Ԃ������Ă��������B�����̊Ԃł��A�炢���Â�Y��āA�q�ǂ��炵�������߂��u�Ԃ�����̂��������ł��v �@���a�C�Ɍ������E�C�� �@�z�X�s�^���E�N���E���ɂ��Ēm�����̂́A���Ƀv���̓����t�Ƃ��Ė{�i�I�Ɋ������Ă����O�R�N�B�č��ŊJ���ꂽ�����t�̋Z�p���������ŋ�_�����l�����������A���Œm�荇�������Ԃ̕a�@�K��ɓ��s�����̂����������������B �u�K���͏I����100+ ���̊��҂����@����z�X�s�X�B����ڑO�ɂ����l������O�ɁA���|����Ȃ�����A���{�ł���������Ȃ����Ⴂ���Ȃ��Ǝv���܂����v �@�č��ł̊����͑�l���Ώۂ��������A�^����ɓ��ɕ����̂́A�w�Z�ɒʂ����Ƃ��ł����A���Âɑς���q�ǂ������̎p�������B�����Ɏ��痦���铹���t�`�[���̃����o�[�ɂ��Ăъ|���ď�����i�߁A���O�S�N�ɂ͖��É����ԏ\���a�@�ł̊������X�^�[�g�B�K��͌������Q��B�T�[�J�X��V���[�ɏo�����鍇�Ԃ�D���Ẵ{�����e�B�A�������B �u���߂͕s��������܂������A�q�ǂ����������ł�����������y�����B���N�ȏ㌾�t�������Ă����q���w���肪�Ƃ��x�ƌ����Ă��ꂽ���Ƃ�����܂����B�l�����ɂ͕a�C���������Ƃ͂ł��Ȃ�����ǁA�a�C�ɗ����������E�C�͂������邩������Ȃ��Ɗ����Ă��܂��v �@���̕a�@������v�]������悤�ɂȂ�A�O�U�N�ɂ͂m�o�n�@�l�z�X�s�^���E�N���E�������ݗ��B���݂̊����́A����K�₾���őS����T�O�a�@�ɍL�����Ă���B�ŋ߂́A�T�[�r�X�Ƃ𒆐S�ɁA�����t���L�̃R�~���j�P�[�V�����p�ɂ��Ă̍u���𗊂܂�邱�Ƃ������Ƃ����B �u�����t�̖����́A����̈������Ė��B����̉��ɐ��荞�ނ悤�ɂ��Ď����Ă�����̂������o���e�N�j�b�N�́A�a�@��T�[�J�X�����łȂ��A�q�ǂ��̋���Ɍg��邷�ׂĂ̐l�ɎQ�l�ɂȂ�Ǝv���܂��v �@�����̕a�@�K��̒��߂�����́A�P��̂��N�ʁB�������A�܂̒��g�́A�C�O�̌����悩�玝���A�����O�݂��B�u�Ȃɂ���A�g���Ȃ������v�Ƃڂ₫�A�������ւ̑z����c��܂���q�ǂ������̏Ί��w�ɁA�Ԃ��@�̃T���^�́A���̕a�@�K��Ɍ������Ă������B 47NEWS�@2011�N1��30�� |
| �i�s�����҂ɂ͑����i�K�ŏI������Âɂ��Ęb���K�v������ |
| �u�i�s�����҂́A���������ɏI������Â̑I�����ɂ��Ĉ�t�Ƙb�������ׂ��ł���v�Ƃ���č��Տ���ᇊw��̐V�������j���������\���ꂽ�B�����̒��҂ł���ăf���[�N��w�i�m�[�X�J�����C�i�B�j���f�B�J���Z���^�[�y����Jeffrey M. Peppercorn���m�́A�u�����Âɂ����Ė��\�ȕ��@�͂Ȃ����A���҂Ɍ�����^���A�����ɒ��ړI�ɑΏ����鎡�ÁA�Ǐ�Ǘ���ړI�Ƃ����ɘa�Ö@�A�Տ������ւ̎Q���Ȃǂ̑I���������邱�Ƃ�m���Ă��炤�K�v������v�Ǝw�E���Ă���B �@���݁A�����鎡�ÑI�����ɂ��Č����Șb�����������Ă�������҂�10�l���S�l�ɖ����Ȃ��Ɛ��肳��Ă���A���҂̎��̒��O�i�����O���琔�T�ԑO�j�ɂȂ��ď��߂Ęb���������s����P�[�X������Ƃ����B�������A���̂悤�Șb�͂����Ƒ��������ɍs���ׂ��ł���Ƃ����B�܂��A���ړI�Ȏ������Âɉ����Ďx���E�ɘa�P�A���s�����Ƃɂ���āA�����̎��iQOL�j�����シ�邾���łȂ��A�]�����������邱�Ƃ������G�r�f���X�i�Ȋw�I�����j������Ɠ����͕t�������Ă���B �@����̐����ł͎�Ɉȉ��̂��Ƃ���������Ă���F * �i�s�����Âɂ����邷�ׂĂ̒i�K�ɂ����āA�����̎���D�悷��K�v������B * �ŏ��ɐi�s���Ɛf�f�������_�ŁA��t�͂����Ɋ��҂̗\�エ��ю��ÑI�����ɂ��Ċ��҂Ƙb�������K�v������B * ���҂́A�Տ������ɎQ������@���^������ׂ��ł���B �@Peppercorn���́u���҂����Â��牽�����Ɩ]��ł��邩�A��������Ă��邩����t���������邱�Ƃ��d�v�ł���v�Əq�ׂĂ���B�܂��A��t�͕s�m���ȓ_���܂߂Ċ��҂̗\��ɂ��Ė��炩�ɂ���K�v������B���̎�̓��ݍ��b������������ɂ͎��Ԃ���ǂƂȂ邱�Ƃ����邪�A�u��x�ɒ�����ʂ���яڍׂɂ��ẮA�ʓI�ɑΏ�����K�v������v�Ɠ����͎w�E���Ă���B�܂��A����̐����ł́A�ɘa�P�A���܂߂Đi�s���̎��Ìv��̘b�������ɗv�����p��ی��K�p�̑ΏۂƂ��邱�Ƃ𐄏����Ă���B �@�ă����e�t�B�I�[��-�A�C���V���^�C��Montefiore-Einstein�����ÃZ���^�[�i�j���[���[�N�j��Steven Libutti���m�́u���҂�Ƒ������̂悤�Șb�����鏀�����ł��Ă��邩�ǂ��������ɂ߂邱�Ƃ��d�v�ł���v�Əq�ׂ�ƂƂ��ɁA�u�����̈�t�͎��Â���߂邱�Ƃ�����A�ŏ��Ɍ����������̂͊��Ҏ��g�ł���ꍇ�������v�Ǝw�E���Ă���B �@Peppercorn���́u�i�s�����҂ɑ��A��t���炱�̂悤�ȗ����Șb���Ȃ��ꍇ�́A���҂̕�����q�˂�ׂ��ł���v�Əq�ׂĂ���B NIKKEI NET �����������N�@2011�N2��2�� |
| ��Ɋɘa�≄�����Â̌���ɗϗ��I�Ȗ��͂Ȃ� |
| �@���C���[�E�N���j�b�N��ʓ��Ȉ��Paul S. Mueller���m��́C�������Â̌p���E��~�ɂ��Ă̖���C��Ɋɘa�̂��߂̒��Áipalliative
sedation�j�����e���邱�Ƃɂ��āu��t�ɂ�鎩�E����y���Ƃ͕ʕ����v�Ɣ��\�����B �@�����m��́C��Ɋɘa�̂��߂̒��Â��K�Ȋɘa�P�A�ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă���_���������Ă���B ����p���͓`����ׂ� �@Mueller���m��́u�l���̏I�������}�������҂́C���y�����߂�X���ɂ���C���S���ɂ̏������ŏd�v�ƂȂ�B�������C�����̈�t�́C�ɘa�P�A�̎��ϗ����̐���ɂ��ċ^��������Ă���C�������Â̒�~���Ɋɘa��ړI�Ƃ������Â����߂炢�������v�Ǝw�E������Łu���E����y���Ƃ͈قȂ�C�������Â̑I�����Ɋɘa�̂��߂̒��Â��s�����Ƃ͗ϗ��I�ɂȂ������Ȃ��v�Ƌ������Ă���B �@��Ɋɘa�̂��߂̒��ẤC������邢�͑ς��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��d�x�̋�ɂɑ���d�v�Ȏ��Âł�����B���̈���ŁC�����m�́u���̎��ÂƓ��l�C���҂�㗝�l�͕���p���ɂ��Ēm��K�v������B�Ⴆ���̂悤�Ȓ��Âɂ��C�Љ�𗬂�����Ȃ�����C�v���I�Ƃ��Ȃ�뚋��ċz��Q���N�������肷�郊�X�N������v�Əq�ׁC�u��Ɋɘa�≄�����Â̗ϗ��������m����C�K�Ɏ{�s�����悤�ɂȂ邱�Ƃ�����Ă���v�ƕt�������Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N2��3�� |
| ����͈��Ɏア�c�����������ȁA�v�Ɩ��}���\�� |
| �@���������2�N�O�Ɉ�t����u�]��3�����v�Ɛ鍐���ꂽ���ꌧ���l�s�̌��Ō�t�E��݂ǂ肳��i26�j���A�a���ɕ������Ɏ��Âƃg���[�j���O���d�ˁA��N���Ƀz�m�����}���\���i42�E195�L���j�Ŋ������ʂ������B �@�S�g�Ƃ��Ɏx�����̂́A�鍐��Ɍ��������v�̍_������i26�j���B2�l��5���A���s�����̘Z�������قŖ�120�l��O�Ɂq��l�O�r�r��2�N�Ԃ�U��Ԃ�A�u�����悤�Ǝv�����Ƃ��厖�B��Ȑl�̈��������v�킹�A���C�����ꂽ�v�ƌ�����B �@���s���̕a�@�̊Ō�t��������́A�̒��Ɉٕς�������2009�N1���Ɏ�f���A�݂���ƍ�����ꂽ�B�Ƒ��̑O�ł͋B�R�Ƃ��Ă������A�����A���ۂ��Ă����_������u�݂ǂ�͖̑̂l�̑̂ł�����B�ꏏ�ɏ��z���悤�v�ƌ����A���߂ė܂𗬂����B �@���N2���A�Ƒ���_������́u�]��3�����A�����Ă��N���z���Ȃ��v�ƈ�t���獐����ꂽ���A��ɂ͓`�����Ȃ������B�s�����������������A�]���ȊO�����₷��ƍ_���������Ă���A�u�����̗]���͎����Ō��߂�B���������Ǝv������A�͉̂����Ă����v�ƍl������悤�ɂȂ����B �@�R����܂ɂ�鎡�Â𑱂������A�u�a�C�����炱�����������A�ł��邱�Ƃ��Ƃ��Ƃ��낤�v�ƁA1000�̖����������ށu���m�[�g�v��������B�������ȓX�ŐH������A���s�ɍs���c�c�ƂÂ����B �@�_������̉����ŁA2�l�Ŏ��X�Ɩ��������ɕς��Ă������B���N4���ɂ́u�������悤�v�Ƃ����_������̐\���o���A��̈ӎu�ō����͂͏o�����ɁA��̒a�����Ɏs���̃z�e���Ō��������������B �@���N7�����ɂ͏Ǐ��P�������A2�x�ڂ̎�p�ň݂�3����2��E�o�B��́A�u�����v�������������_������̎v�����������悤�ɂȂ�A10�N4���ɍ����͂��o�����B �@�z�m�����}���\���o������m�[�g�ɂ͋L���Ă������A���̍������̓I�ɍl����悤�ɁB2�l�ŃW���ɒʂ��ȂǗ��K��ς݁A���N12��12���A�_������ƈꏏ�ɁA�t���}���\�����8���Ԃő��肫�����B �@��͍����A�ʉ@���Â𑱂���B�u�w����͈��Ɏア�x�͖{���������I�@��������̕����v�Ƒ肵���u����ŁA�_������́u���Ƃ����u�Ԃ�ڂ����ς������������A�Ȃ��狳���܂����v�Ƙb���A��́u�傫�ȈÈłɕ��蓊����ꂽ�����ł������A�����͏\���K�����Ǝ������A�l�������Z�b�g�ł��܂����B�v��x���ĉ�����l�Ɋ��ӂ��Ă��܂��v�Ƙb�����B m3.com�@2011�N2��8�� |
| �u�Տ��m�̉�E�T�[���v��ݗ� |
| �@���@���҂̐S�̃P�A��ݑ���ɏ]������m�����u�Տ��m�v�Ɩ��t���Ĉ琬���Ă������ƁA�m���ň�t�̑Ζ{�@�P����i56�j�炪2��16���A�u�Տ��m�̉�E�T�[���v�����s�E�������s�����_�ɐݗ�����B �@�S���I�ɂ����������g�݂ŁA�Ζ{����́u���V�a���̋ꂵ�݂⋰�|�ƌ��������l�Ɋ��Y�����Ƃɂ����@���҂̖���������͂��v�ƁA�^���҂̍L����Ɋ��҂��Ă���B �@���Q���̎��ɐ��܂ꂽ�Ζ{����͋���œN�w���w��A�V�����i�E����j�ŏC�s���A38�ŗՍϏ@�Œʎ��h�ǒ��ɏA�C�B���e��M�҂��Ŏ�����o������A����ɏI�����P�A����ϗ��ւ̊S�����܂����B �@��O���N���Ď����n�߁A2000�N�A�鋞���w���ɓ��w�B�ǒ������C���ĕw�ɑł����B06�N�Ɉ�t���i�����A���C�����a�@�ł̋Ζ����d�˂钆�Ō����Â̌��E���ڂ̓�����ɂ����B �@��t�s���ɂ��ߍ��ȋΖ��B�u�a�C��f�Ċ��҂�f�Ȃ��v�ƌ�����悤�ɁA������a�̊��҂����ʂ��Ă��鎀�ւ̋��|��a�炰�邷�ׂ��\���ɂ͎������킹�Ă��Ȃ��B���Ƃ����āA�@���Ƃ��a�@�ɏo���肷��u���N�ł��Ȃ��v�Ɣ����ڂŌ�����B �@���Ă̕a�@�ɂ́A�Տ���������u�`���v�����v�ƌĂ�鐹�E�҂�����B������Q�l�ɁA�u�m���̖����v��ǂ����߂ē�������邱�Ƃɂ����B �@����ł́A��Ã\�[�V�������[�J�[��z�[���w���p�[�Ȃǂ̎��i���擾�����m���Ɍ��C���s���������Łu�Տ��m�v�ɔF��B��P�T�Ԃ̕a�@���K���s������A�a�@��ݑ�ł̖@�b�⑊�k�A������ړ��̉�Ȃǂɏ]�����Ă��炤�B�^������m���͂��łɖ�20�l����A����A��ƂȂ�a�@����Ǝ҂���Ƃ����B �@12���ɊJ������t��Ō�t�A�m�o�n�W�҂�Ƃ̈ӌ�������ł́A�u���y���⑸�����͈�t�����̖��ł͂Ȃ��v�u�m��������ɂȂ��ނɂ͏\���ȃJ���L���������K�v�v�Ȃǂ̐����オ�����B����Ӗ�E���s��O�Ȍ𗬃Z���^�[�������́u�����Â͐S�̖�肪��ɂȂ��Ă���A�Ƃ��ɍl���鎞�����v�Ƙb�����B �@16���ɂ͎Q������m���炪�獇�킹���A��X�^�[�g���B���݂͉p���ŗՏ��w���w�сA���{�Ƃ��s�������Ă���Ζ{����́u���҂Ɂw�l�͎���ǂ��ɍs���̂��x�Ɩ��ꂽ��A�@���҂Ƃ��ĂȂ��荇����B�@�h���Ċ������L���Ă��������v�Ƙb���B �@�₢���킹�͓���i�O�V�T�E�X�T�S�E�P�O�O�T�j�ցB m3.com�@2011�N2��15�� |
| �����咰����������ɕ��S�Ȃ����Â��邩�H ���̕��@�Ƃ� |
| �@�����̐؏�����ȑ咰����̒�����ɂ́A�]���l�H���̑��݂��s�Ȃ���B�������A�S�g�����ɂ��J����p���K�v�Ȃ��߁A���ɖ�������̊��҂ɂ͐S�g�̕��S���傫���B�����ŋ�����ʂ����߂ɁA�咰�ɃX�e���g�𗯒u���鎡�Â��������ꂽ�B�J����p�����Ȃ��̂Ŋ��҂̕��S�����Ȃ��A�����ŐH�����ł���ȂǁAQOL�i�����̎��j�����P�ł���ɘa�P�A�̈�Ƃ��Ċ��҂���Ă���B �@ �@�咰����₻�̑��̂���̂��߁A�咰���������ꋷ�N����ƕ��ɂ∳�����ȂǂŁA�g�̓I�A���_�I��ɂ�������B����̐؏����s�\�ȏꍇ�A�]���͐l�H���݂��邱�Ƃ������B�������A�l�H���͑S�g�����ɂ��J����p�������ɁA�g�p�Ɋ����K�v������ȂǁA���ɖ������҂ɂƂ��Ă͐S�g�Ƃ��ɕ��S���傫���B�����ŋߔN�A�咰�̒��ɃX�e���g�𗯒u���邱�Ƃŋ�������P���鎡�Â����{�����悤�ɂȂ��Ă���B �@2005�N����2010�N�܂łɑ咰�X�e���g�𗯒u�������Ì��ʂ\�����A�s���L���a�@�i���{�L���s�j���������NJO�Ȃ̔��i��t�ɘb�����B �u����͍����p���s�\�ȁA�咰�ɕǂ������������ҁi�݂����q�{�������̏ꍇ���܂ށj19���ɑ��āA�咰�X�e���g�𗯒u���܂����B�X�e���g�͈ٕ��Ȃ̂Œ����Ԓu���ƕ��Q�����邽�߁A�]�����N�ŋ�������̎�p������A�������͐l�H�����X�e���g��������]���銳�҂�ΏۂƂ��Ă��܂��B���u����Ƌ����P����A�y�ɂȂ邾���łȂ��A�H�����ł���悤�ɂȂ�A�މ@���ĉƂʼn߂�����悤�ɂȂ����l�����܂��v NEWS�|�X�g�Z�u���@2011�N2��19�� |
| �������Ò��~�V���̕a�@���o���@����Ȏq�ǂ��̊��� |
| �@�~���������������߂Ȃ��q�ǂ��̋~�}���҂ɁA����ʂ����炵����l�H�ċz���~�߂��肷��u�������Â̒��~�v���������Ƃ�����a�@�͂V���A����ʂ������葝�₳�Ȃ��Ȃǂ́u�����T���v�͂R�S�����o�������Ƃ̒������ʂ��A���T�ꍑ�������Ì����Z���^�[�����f�Õ�����̌����ǂ��Q�U���܂łɂ܂Ƃ߂��B �@���セ���������҂̉Ƒ��ɁA�I�����Ƃ��Ď��Ò��~�⍷���T���������\��������Ƃ�����t�́A�U�O���ȏゾ�����B �@�I�����̎q�ǂ��ɉ������Â𑱂���ƁA�q�ǂ��̑�����`���ꍇ������ƍl�����t������A�����ǂ́A���̈�[�����������錋�ʂƂ݂Ă���B �@�����ł́A���~�⍷���T���Ɋւ���@����w�j�Ȃǂ̌��I�V�X�e�����������߂鐺�������A���Â̑I���f�����Ì���̌˘f���������яオ�����B �@�����ǂ͂Q�O�O�X�N�A���{�����Ȋw��Ɠ��{�~�}��w��̖�X�T�O�̐��㌤�C�{�݂ɃA���P�[�g�B�S�X�W�{�݂�����������B �@�ߋ��R�N�ԂɁA�Տ��I�ɔ]���Ɣ��f�����P�T�Ζ����̎q�ǂ��������̂͂R�V���B�������Â̒��~�o���͂V���łT��ȏオ�T�{�݁A�����T���͂R�S���łP�O��ȏオ�Q�O�{�݂������B �����ƒm�肽���@�j���[�X�́u���t�v ���������i2007�N2��16���j�I�����̊��҂ɑ��A�l�H�ċz���l�H�S�x���u��������A�h�{�⋋������Ȃǐ����ێ��̂��߂̏��u���s�����ƁB���Â𒆎~����ۂ̔��f����Ë@�ւ̎葱�����߂��K�C�h���C���ɂ��āA�����J���Ȃ͍�N�X���^�i�P�j�^���҂̈ӎv���d����{�Ƃ���^�i�Q�j�^���Âɂ��Ċ��҂ƍ��ӂ������e��������^�i�R�j�^�厡�ゾ���łȂ����̈�t��Ō�t���܂ވ�Ã`�[�������Õ��j�����߂�\�Ȃǂ𒌂Ƃ������Ă����\�B���Ȃ̌�������Ă���ɋc�_�𑱂��Ă���B �������Ò��~�i2006�N6��15���j�l�H�ċz���h�{�⋋�Ȃǐ����ێ����u���܂߂����ׂĂ̎��Â��~�߂邱�ƂŁA�ŕ��̓��^�Ȃǂɂ��u�ϋɓI���y���v�Ƌ�ʂ��āu���ɓI���y���v�Ƃ�������B���R�Ȏ���]�ފ��҂������̈ӎv�Ŏ��Â����ۂ����ꍇ���u�������v�ƌĂԁB���C����y�������̉��l�n�ٔ����́u���錩���݂̂Ȃ��a�C�Ŏ���������A�Ƒ���ɂ�鐄����܂ߖ{�l�̈ӎv�����邱�Ɓv�Ȃǂ����e�����Ƃ��ċ��������A��Ì���ɂ͂���̓I�Ȏw�j�����߂鐺���o�Ă���B 47NEWS 2011�N2��25�� |
|
�����댳�C�m �ɘa��È�E��ÏG�ꂳ��C���^�r���[�@�c���ꂽ���ԂŁA�ǂ����������� |
| �@�\�\��Â���̒����u���ʂƂ��Ɍ�����邱�ƂQ�T�v�ɁA���_���͊w�҃t�����N���́u�ǂꂾ���������������͂ǂ��ł��������ƂŁA�l���̎���Ӗ��ɂ͊W�Ȃ��v�Ƃ�����|�̌��t��������Ă��܂��B��������������̌��͂���܂����B �@����@�����A����܂��B�P�O��A�Q�O��ł��A���������炩�Ȋ�ŁA�u�搶�A�����l���ł����v�ƌ����Đ������������܂��B�u�l�͍K���ł��B����͂���܂���v�ƌ����c���Ă������Q�T�̐N�����܂����B�l�Ԃ̒�m��Ȃ������������܂��B����ŁA����ɂȂ��Ă��u�l���A�s�K���肾�����v�ƌ����ĖS���Ȃ�������܂��B �@�\�\�u���̒��̂��Ȃ��v�Ƃ����m�悪����܂��B�����a�̖����~�����ƁA�ޏ��ɍ������邽�߂ɂ�����l�A�����Y��e�̘b�ł��B�P�O��ɂȂ�����̖��́A������̍��������ۂ��āA疗y�Ƃ��Ď�������܂��B�P�O��ł����̂悤�ȐS���ɂȂ��̂��A�ƈ�ۂɎc��܂����B �@����@���܂�Ȃ���ɓ�a�̑��_�NJg���ǂ�����A�Q�O�㔼�Ŗ����̒_�ǂ���ɂȂ����N�����܂����B�l����������ɂ́A�z�X�s�X�ŒW�X�Ɛ������Ă����B�u�O�̕a�@�ł͎��Â̘A���ŋꂵ����������ǁA�����ł݂͂�ȗD�������Ă���čK���ł��v�ƌ����̂ł��B�Ŋ��̓��܂ň��炩�ł����B�N�����[���l���⎀�ɂ��čl�����̂łȂ��ł��傤���B �@������̂��߂P�S�ŖS���Ȃ������n������́A���O�٘̕_���Łu�a�C�ɂȂ��āA�����邱�Ƃ���Ȃ��̂��Ƃ킩��܂����v�ƃX�s�[�`���Ă��܂����B�ޏ��́u���X�[�p�[�f���b�N�X�v�Ƃ������a�L���o���Ă��܂��B�ނ�ޏ������̂悤�ɁA���Ǝ��ɖ{�C�Ō��������A�����Ă��邱�Ƃ��ǂꂾ���K���Ȃ̂��ɋC�����܂��B �@���������S���ɂ��ǂ蒅���邩�ǂ����́A�N��ɊW�Ȃ��B�ł��邾�����������āA��������̐l�Ɉ͂܂�Ď��ɂ����ƍl�������ł����A����̐l�ɕ���������Ă���ŁA�Ƒ��͂�������̂ɒN�����ɍۂɗ��Ă���Ȃ������A�Ƃ����������܂��B �@�u���肪�Ƃ��v�ƌ����c���ĖS���Ȃ��Ă������Ⴂ�q�����̂P�O���̂P�ł��͂�����A�l���ւ̊��ӂ̓x�����͑����邵�A�p�n�k�����܂�Ǝv���܂��B�����āA���������͖͂{���N���������Ă�����̂Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���܂��B �@�\�\�����l����ƁA�������ʂ�����������x�̍R������Â�A���܂��܂ȉ������ẤA�ނȂ������������܂��ˁB �@����@�R����܂ō�������\�������锒���a�Ȃǂ�ʂɂ��āA�����������Â��邱�Ǝ��̂ł́A�l���̖����x�͕ς��Ȃ��Ǝv���܂��B����͖{���ł͂Ȃ��ł��傤�B�c���ꂽ���Ԃłǂ���������������ŁA�قƂ�ǂ̕��ɂƂ��Ė{���A������ړI�͂��������������Ƃł͂Ȃ��͂��ł��B�R����܂��g���āA���̊Ԃɂ������s�ɍs�����A�Ƒ��ƈꏏ�̎��Ԃ��Ȃ�ׂ��߂������A�����������ɂƂ��čR����܂͗L�v�Ȃ��̂ł��B����ǂ��A�u���邱�Ɓv�������ړI���ƁA����͂قڗ����܂��̂ŁA���ǖ�������邱�Ƃ͓���B�R����܂̕���p�ŁA�������Đh���ڂɂ������̂ł͂Ȃ����A�ƌ���������������܂��B �@���������Â���Ӗ��͉����A�����������Ƃ�b�������A�u���͂��ꂪ����������܂����������v�Ƃ��A�u���̎����ɂƂ��āA���Â͂�������قǏd�v�ł͂Ȃ��v�Ƃ������ɘb����悤�ɂȂ�A�~����l�������Ȃ�ł��傤�B �@�������Ď���ł������Ǝ��̂ɑP���͂���܂���B��Î҂₲�Ƒ��̈ꕔ������K�v�ȏ�Ƀ^�u�[�����Ă��邱�Ƃ��A���҂���̌ǓƂ������Ă���Ǝv���܂��B�F���}���鎀�̓^�u�[�ł����ł�����܂���B�ނ��뎄�����͂悫�l���̂��߂ɁA�^�u�[�����Ȃ��Řb�������ׂ�������}���Ă���̂��Ǝv���܂��B���ꂪ���E�ō���Љ�����[�h���A�Q�O�S�O�N�ɂ͔N�ԂP�V�O���l���S���Ȃ�i���݂͂P�P�S���l�j�v���̑卑�v������{�����悵�čs���A�͂������Ă����ׂ����̂ł��傤�B �@�P�T�N�O�ɁA����̍��m�̓^�u�[�ł������A���͍��m���邱�Ƃ�������O�ɂȂ��Ă��܂��B����Ɠ����悤�ɁA���͎����^�u�[�ł��A���̒��͕ς���Ă����Ǝv���܂��B YOMIURI ONLINE�@2011�N3��1�� |
| �݂낤�@�I�������ǂ��}���邩 |
| �@�N���Ƃ��đ̂����ƁA������H�ׂ��Ȃ��Ȃ�A�₪�ĐÂ��ɑ����������|�B���Ă͂��������V�������������Ȃ������B �@���܂͐H�ׂ��Ȃ��Ȃ��Ă������Ȃ���i������B���̑�\�i���u��ᑁi�낤�j�v�ł���B���Ȃ��̕ǂɖ��ߍ��ǂ��璼�ځA�݂ɗ����H������B �@�I�������}��������҂Ɉ�ᑂ�����ׂ����ۂ����߂���A��Ì���̊����͐[���B���{�V�N��w��̒����ł́A�F�m�ǂ̖����ŐH�������Ȃ��Ȃ����l�ɑ��A��ᑂ�_�H�ʼnh�{�Ɛ�����⋋���邩�ǂ����̌��f������|�ƈ�t�̂��悻�X�����l���Ă���B �@�K�v���͌X�̊��҂̏�Ԃɂ���ĈقȂ�A��T�ɘ_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����A���ՂɈ�ᑂ����邱�Ƃ́A�I�����ɂ���l���ꂵ�߂邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B �@�I�����̈�ᑂɂ��āA�ɂ₩�ȃ��[�������߂���B���܂��܂Ȋp�x����_�c��[�߂����B �@��ᑂ͗L�����̍����h�{�⋋�̕��@���B���ہA�̗͂����Č�������̂�H�ׂ���悤�ɂȂ�A���銳�҂�����B �@���́A�������߂��A�{�l�̈ӎv�m�F���ł��Ȃ��P�[�X���B��t�����Ă���āA�Y�މƑ������Ȃ��Ȃ��B �@�V���̏ꍇ�A�l�H�I�ȉh�{�̓��^�͖����ȉ����ɂȂ���A���炩�ȍŊ���D�����ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B����A��ᑂ�����Ȃ���A���s�����Ȃ������ƌ�ʼn���ނ�������Ȃ��B�ǂ����I��ł������͏����Ȃ��B �@�{�l�̈ӎv���u������ɂ����P�[�X������B�މ@��Ɏ{�݂�ݑ�ł̐H������y�ɂȂ�悤�A��ᑂ�������Ԃ�����B �@�O�����f������B���܂̌Y�@�ł́A���Â̍����T���⒆�~�͈�t���߂ɖ����\��������B�@�I�A�ϗ��I�ۑ�����A���̎Љ�I���ӂ�}�肽���B �@���ʗ{��V�l�z�[���ł݂Ƃ���d�˂Ă�����t�A�Δ�K�O����̈ӌ����Q�l�ɂȂ�B�����u�w�������x�̂����߁v�ŁA��ᑂ�����ۂ̒��ӓ_�������Ă���B �@�{�l�̗��v�����ł���A������H�ׂ��Ȃ��Ƃ������肪�Ȋw�I�ɂȂ���邱�ƁB��t����ᑂ̃����b�g�ƃf�����b�g�̗��ʂ�{�l�ƉƑ��ɐ���������ŁA�����I�ȓ��ӂ邱�Ƃ��K�v���B �@�������s����Ȃ�A�Ȃ�ׂ��ꂵ�܂��Ɏ��R�ȍŊ����}�������|�B�����]�ސl�͑������낤�B �@��������̂�H�ׂ��Ȃ��Ȃ�����A�ǂ����邩�B�{�l�̈ӎv���o���_�ɂȂ�B���C�Ȃ�������l���A�Ƒ��Ƙb�������Ă��������B �M��web�@2011�N3��4�� |
| ����Q�O�P�T�N���@���Ґ������A�ǂ����� |
| �@����̐i�W�ł��Ґ����������A��t��a�@�x�b�h�����s������Ƃ�����u����̂Q�O�P�T�N���v�̓������������B�ߔN�A���Â̑S�Ă�a�@�ōs���̂ł͂Ȃ��A��������̐f�Ï���K��Ō��ϋɓI�ɗ��p���Ȃ���A�n��ł��Â�ɘa�P�A�Ɏ��g�ޓ��������������Ă���B�a�@�ւ̈�ɏW�����y������{��Ƃ��āA��ÊW�҂̒n��A�g�ɑ�����҂͑傫�����A�c�[���̉^�p�⊳�҂̕s�������ȂǁA�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ�������B �@�����J���Ȃ̎��Z�ɂ��ƁA�c�オ�U�T�Έȏ�ƂȂ�Q�O�P�T�N�ɂ��Ґ����s�[�N�ɒB����B�O�R�N�ɂQ�X�W���l���������҂́A�P�T�N�ɂT�R�R���l�ɂ܂ő����A�T�O�N�܂łقډ����̏�Ԃ������Ƃ����B���挧���N�c��̂���o�^�W�v�ɂ��ƁA�����ŐV���ɂ���Ɛf�f���ꂽ�o�^���͂O�S�N�ɂR�V�T�U���A�O�T�N�ɂR�W�V�U���A�O�U�N�͂S�P�X�W���ƒ����ɑ������Ă���B ������ŗ×{�� �@���J�Ȃ͂O�V�N�ȍ~�A�s���{�����Ƃɒn�悪��f�ØA�g���_�a�@���w�肷��ȂǁA�n��ԁA�a�@�Ԃ̈�Ð����̊i�����Ȃ����u��迉��v��i�߂Ă����B����ɁA�u�Q�O�P�T�N���v�ɔ����A����ł̒����×{��ɘa�P�A�A�ʉ@���Ȃ���̐ϋɓI���Â��ł���������ɂ��͂����Ă���B �@������f�ØA�g���_�a�@�Œ����w��w���t���a�@����Z���^�[�̋I�쏃�O�Z���^�[���́u���҂ւ̃A���P�[�g�ł́A�U�`�V�����w����ōŊ����}�������x�Ɠ����Ă���B����ł̗×{���x����ɂ́A�n��Ƃ̘A�g���K�v�v�Ɛ�������B ���n��A�g�̃c�[�� �@�n��A�g�����H�����ŗL���ȃc�[���ɂȂ�ƒ��ڂ���Ă���̂��u�n��A�g�N���e�B�J���p�X�v���B�a�@�ł̌������p�Ȃǂ��o�āA����ɋA�莡�Â𑱂��邪�҂ɑΉ������f�Ìv��\�ŁA�f�Õ��j�⊳�ҏ����ꌳ�Ǘ��B�a�@�Ƌ߂��̐f�Ï��A�K��Ō�X�e�[�V�����Ȃǂ̈�Ë@�ւŏ������L���A���҂ւ̐����ɂ��𗧂Ă�B�����ł͓���`���̃p�X�̐�����i�߂Ă���A�S���P������̉^�p��ڎw���Ă���B �@�I��Z���^�[���́u�n��̐f�Ï��ŁA����̊ȒP�Ȑf�Â��s����悤�ɂȂ�A�҂����Ԃ����Ȃ��čςށA�������߂��ȂNJ��҂ɂƂ��Ă������b�g������B�p�X�̖�����d�g�݂ɂ��Ď��m��i�߁A���S���Ēn��Ŏ��Âł���悤�ɂ������v�Ƙb���B �����݂�m���� �@����A�މ@���Ď���ɖ߂銳�҂���͕s���̐�������B�����S�J���̒n�悪��f�ØA�g���_�a�@�̈�A���������a�@�i����s�]�Áj�́u���k�x�����v�ɂ́A�u���܂ł̐搶�𗣂��͕̂|���v�Ȃǂ̂ق��A����ł̃P�A���@��Ŋ����݂Ƃ邱�ƂɔY�މƑ�����̑��k������Ƃ����B �@��Ô�̎x�����Ɋւ��Ă̖₢���킹�������A�މ@��ɂ͈�x�ɂ܂Ƃ܂����z�̈�Ô�K�v�ɂȂ邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B �@���k�ɉ�����Տ��S���m�̓����`�l����́u���@���ɂ͈�t��Ō�t���g�߂ɂ��邪�A�n��ɋA��ƔY�݂�ł�������ꂪ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł́v�Ǝw�E����B�u���k�͓��@�A�O����킸�A�N�ł����p�ł���B�����Ƃ��k�x�����̑��݂�m���Ă��炦��悤�w�߂����v�Ƙb���A�n��A�g�̒��ł̖����̑傫�����������Ă���B NetNihonkai�@2011�N3��9�� |
| ���{�݊��w��ŏI�����̊ɘa�P�A�ɂ��Č��� |
| ��ʈ��E�ޗǗю� �@�����Â̐i�W�͖ڊo�܂����C�V���Ȏ��Ö@�̓o�ꂾ���łȂ��ɘa�P�A�̗��O�����������y���C��Î҂̈ӎ������߂邱�ƂƂȂ����B����ŁC���Տ��ɂ����Ă̓X�^�b�t���̏[����V�X�e���̉��҂ȂnjX�̈�Ë@�ւɂ���Ă��������C���z�ƌ����Ƃ̊Ԃɑ傫�ȃM���b�v�����݂���B��83����{�݊��w���i3��3�`5���C�X���O��s�j�̓��ʊ��V���|�W�E���u���w�Ö@��̐�ڂȂ���Â̎��H�v�ł͂��������܂��C�ɘa��ÉȁC������O�ȁC���w�Ö@�ȁC���ꂼ��̐��I���ꂩ�痦���Ȉӌ������\���ꂽ�B���̒��ŁC��ʈ�ȑ�w���ۈ�ÃZ���^�[�ɘa��Éȋ����̓ޗǗю����́C����Ö@�Ɍg����ᇓ��Ȃ��o�Ċɘa�P�A�ɐ�]���Ă���o������C�u���w�Ö@��̈�ÂɃX���[�Y�Ɉڍs���邽�߂Ɂv�Ƒ肵�C�I�����̊ɘa�P�A�ɂ��Č������q�ׂ��B �I�����ւ̕s���\�u����ŊŎ��ꂽ���v��11�� �@�g�ɘa�P�A�́C����̐f�f������n�܂�h�Ƃ̗��O�͍L����Î҂ɕ��y���Ă������C�����ɂ͑����̂��҂����̉��b�ɂ�������Ă��Ȃ��B���ɁC�i�s����ł͂�����ϋɓI�Ȏ��Â��I������������Ȃ����������邪�C�����Őg�̒u������Ȃ����Ă��܂����҂����Ȃ��Ȃ��B�Ⴆ�u�]��6�J���ȓ��̖�����ԁv�Ƃ������ŁC�u�×{�ꏊ�v�Ƃ��Ď������]����҂�63.3���ɒB������C�u�Ŏ��̏�v�Ƃ��Ď������]����҂�10.9���Ɍ������邱�Ƃ�������Ă���i�����J����2007�N�x�����j�B �@���̎�ȗ��R�́u��삵�Ă����Ƒ��ɕ��S��������v�i79.5���j�C�u�a�}�ς����Ƃ��̑Ή����s���v�i54.1���j�ł���C�ɘa�P�A�ɂ������Î҂̎x�����s�\���ł��邱�Ƃ��������Ă���B �@�ޗǗю��́C���ÏI����̈�Â�ڂȂ��ڍs���邽�߂ɂ́C�܂��u���҂̕s�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƒi�����B �a�@�オ�������� �@��L�����ł����グ��ꂽ�悤�ɁC���ÏI����̈�ÁC���Ȃ킿�I�����̊ɘa�P�A������Ƃ��ẮC����C�n��̊ɘa�P�A�a���C�n��̕a�@�E�f�Ï��Ȃǂ�����B�ޗǗю��́C�����̎{�݂́u���҂���̏ɉ����ēK�ɑI�������ׂ��v�ł���ɂ�������炸�C����ł́g�I������h�ɂ͎����Ă��Ȃ��Ǝw�E���C���̗��R���������������B �@���҂̊�]�͈�l�ł͂Ȃ��B�u�Ō�܂Ŏ��Ìp���������v�Ƃ����l������C�u���S�Ȃ��Ƃʼn߂��������v�Ɗ�]����l������B���҂̊�]�ɉ������ɘa�P�A�̂��߂̃L�[�p�[�\���͕a�@��ł���Ƃ��C�����́u�i�����̈�ÐE�́j�������Ƃ��āC�a�@��̐s�͂��s���v�Ƌ��������B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N3��22�� |
| �⑰�ւ̊ɘa�P�A�C�Ƒ��́g�@�\�h�ɂ��قȂ���@�����ʓI |
| �@�������҂̐��_�I��ɂ�s����a�炰�邽�߂̊ɘa�P�A�����C�ߐe�҂�S�������⑰�̑r������������Ƃ��{���̖ړI�Ƃ���Ă���B�⑰�ɑ���ɘa�P�A�ɂ��āC�ăj���[���[�N�EMemorial
Sloan-Kettering Cancer Center��David Kissane���炪�s���������_������r�����iRCT�j�Ȃǂ𒆐S�ɂ܂Ƃ߂��L�����CCMAJ3��22���I�����C���łɌf�ڂ��ꂽ�B�Ƒ��́g�@�\�h�ɂ���Ċɘa�P�A�̕��@��ς��邱�Ƃ����ʓI�ł���\���Ȃǂ��������Ă���B �g���S�h�Ɓg���ԓI�h�Ƒ��͉��P���ʂ��� �@�L���́CEnd-on-Life Care�Ƒ肳�ꂽ�C�I�����P�A���e�[�}�Ƃ���V���[�Y�̍ŏI��i�S9��j�BKissane���́u�ɘa�P�A�́C�L�`�̌����Ƃ��Ă͉Ƒ����ΏۂƂ���C����͑f���炵���ڕW�ł͂���B���������ۖ��C�Ώۂ͊��҂ɕ�P�[�X���唼���v�ƔF�߂�B �@�ŏ��ɏЉ��̂́C�����炪���N�O�C���҂̉Ƒ��ɑ���ɘa�P�A�ɂ��čs����RCT�iAm J Psychiatry2006; 163: 1208-1218�j�B�������҂�257�Ƒ��ɑ��ăX�N���[�j���O���s���C81�Ƒ��E363�l��팱�҂Ƃ����B81�Ƒ��������_���Ɂi�䗦2�F1�j�C�Ƒ��w���ɘa�P�A�W�c�i53�Ƒ��E233�l�j�ƑΏƏW�c�i28�Ƒ��E130�l�j�Ƃɕ������B���҂̎����x�[�X���C���Ƃ��āC6�J�����13�J�����2�x�ɂ킽�蒲�����s�����B�����́C�ȈՏǏ�]���ړx�iBrief Symptom Inventory�GBSI�j��x�b�N���]���ړx�iBDI�j�Ȃǂ�p�����B �@���̌��ʁC�Ƒ��w���ɘa�P�A�ɂ����ẮC���҂̎���13�J���ň⑰�̔ߒQ�x�ւ̉e���͑S�̓I�Ɍy�x�ł��������C�x�[�X���C������BSI��BDI���_�����������⑰�̔ߒQ�x�₤��ԂɊւ��Ă͌����ȉ��P���F�߂�ꂽ�B�܂��C�ΏۉƑ��̋@�\���^�C�v�ʂɁC�i1�j�G�ΓI�C�i2�j���S�C�i3�j���ԓI ��3�O���[�v�ɕ����Č����������ʁC�i1�j�ł͂���Ԃ͕ς��Ȃ��������C�i2�j�Ɓi3�j�ł͉��P�X��������ꂽ�B�܂��C�i1�j�͊ɘa�P�A���̂��̂����₷��X��������C������́u�G�ΓI�ȉƑ��ɑ��Ă͌ʂɊɘa�P�A���s���������ʓI��������Ȃ��v�ƁC�Ƒ��̋@�\�ɂ��ɘa�P�A�̕��@��ς���K�v�������������B �����z�X�s�X�Ɛ��l�z�X�s�X�ňقȂ���Ԃ���@ �@���ɋL���́C�ŋߍs��ꂽ�ɘa�P�A�Ɋւ���61�̌�����ΏۂƂ����C�ă����t�B�X��w��Robert A. Neimeyer����ɂ�镪�͂��Љ�iCurr Dir Psychol Sci2009; 18: 352-356�j�B����ɂ��ƁC������l���������l�����̂���10�`15���͂��̌���������邱�Ƃ�����ł���Ƃ����B �@�ɘa�P�A���ł��K�v�Ƃ���̂́C�q����S�������e��C�S���Ȃ����q���̌Z���o�����Ƃ����B���̂��߁C�����z�X�s�X�ł͒����I�Ȋɘa�P�A���⑰�ɑ��čs���Ă���B�J�i�_�E�u���e�B�b�V���R�����r�A�B�̏����z�X�s�XCanuck Place�ł́C���҂̎���3�N�ɂ킽��S���Ȃ����q���̒a�����▽���ɁC�⑰�ɃO���[�e�B���O�J�[�h�𑗂��Ă���B���z�X�s�X�ł͒ʏ�C���҂̎���1�N�قǂ͈⑰���ɘa�P�A�ɎQ�����Ă���Ƃ����B�܂��C���������⑰��ł��������݂���B �@���z�X�s�X�̊ɘa�P�A�R�[�f�B�l�[�^�[�CKerry Keats���́u�������҂��P�A����Ƃ������Ƃ́C���̉Ƒ��܂ŃP�A����Ƃ������ƁB���z�X�s�X�̖����͊ɘa�P�A�T�[�r�X�ɍ��ʂ܂��C��������邱�ƁB���z�X�s�X�ł͉Ƒ��S�̂̊ɘa�P�A���s���Ă���v�Ƙb���B �@���Đ��l�z�X�s�X�̏ꍇ�C�����ł͂��邪�⑰�ւ̊ɘa�P�A���s���Ă���{�݂����݂���B�������C���Ԃ͏����z�X�s�X�Ɣ�ׂĒZ���B�J�i�_�E�I���^���I�B�̐��l�z�X�s�XThe Hospice at May Court�ł́C�\�[�V�������[�J�[�ɂ�閳���̊ɘa�P�A���Љ�邨����ݏ���⑰�ɑ����Ă���B���T�Ԍ�ɂ͓��z�X�s�X�E�����⑰�ɘA�������C���̌�̗l�q��q�˂Ă���B�\�[�V�������[�J�[�œ��z�X�s�X�̊ɘa�P�A�R�[�f�B�l�[�^�[�ł�����Francine Beaupre���́u�ߒQ�͐l���ꂼ��ɈႤ�v�Ƙb���B���ۂɊɘa�P�A����⑰�͂܂��܂����Ƃ����B �@�Ǝ��Ɋɘa�P�A���s��Ȃ����l�z�X�s�X�ł́C�����̑��ݎx���O���[�v��{�����e�B�A�O���[�v�C���邢�͌l�̕ی����K�p�����͈͂ł̐��_���͈�ɂ��f�ÂȂǁC�n��ɑ��݂���T�[�r�X���⑰�ɏЉ��{�݂�����B�⑰�̔ߒQ�x���[���C�S�g�ɉe�����y�ڂ��قǐ[���ȏꍇ�́C���f�B�P�A�i��Õی����x�j�̓K���͈͓��Őf�Â�����C����������_���͈�ւ̏Љ���s���Ă���B �@�L���͍Ō�ɁC�u�őP�̊ɘa�P�A�ɂ́C�ߐe�҂���������Ƒ��Ǝ������⑰�ւ̃P�A���܂܂��v�ƌ��C�J�i�_�E�I���^���I�B��Hospice Toronto�ŃN���j�J���T�[�r�X�ے�Belinda Marchese���̌��t�Œ��߂������Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N3��25�� |
|
�����m����̏����Ɏ��ȑr���̋��� 3�i�K�̏����ߒ����o�Ď���ɍ��� |
| �@�j���[���[�N�B����w�Ō�w����Robin Lally�������́C�����҂��C��������m����Ă���C����ł��邱�Ƃ������悤�ɂȂ�܂ł̐S�̓����Ɋւ��錤�����ʂ\�����B �@�������ł́C���m�������҂́C���߂Ă̏C�m��Ȃ��ꏊ�C�����Ȃ�Ȃ����t�₳�܂��܂ȐE��̐l�Ƃ̏o��ȂǁC����܂ł͖��W�������V���Ȑ��E�Ɏ��g�����������Ȃ���f�f���ʂ�����Ă����ߒ������炩�ɂȂ����B ���m����̐S���ω��͍l������Ȃ����Ƃ����� �u���Ȃ��͓�����ł��v�ƍ��m���ꂽ�Ƃ��C���Y�����̐S�ɂ͉����悬��̂��B���݁C�č��ł͏�����8�l��1�l���l���̂����ꂩ�̎��_�œ�����ɂȂ�Ƃ���Ă���ɂ�������炸�C����������������m����Ă��玡�Â��p���J�n�����܂ł̊ԂɋN�����A�̐S���ߒ��ɂ��Ă͂��܂茤������Ă��Ȃ������B�������C���Â��J�n�����܂ł̊��ԁC���҂͑����ȃX�g���X��������Ɨ\�z����C�����̃X�g���X���K�ɉ�������Ȃ��ƁC�����^���w���X�ɉe�����y�ڂ����˂Ȃ��B �@Lally�������́C���̂悤�ȏɂ��āu�f�f����C��Ï]���҂̈ӎ��͊��҂̐g�̂ւ̉e���⎡�ÂɌ����Ă���C���m�����҂̎��ȊT�O�ɗ^����e���͍l������Ȃ����Ƃ������v�Ǝw�E���Ă���B �@�����œ��������͍���C�č��������̓�����Z���^�[�ŃX�e�[�W0�`�U�Ɛf�f���ꂽ������18��i37�`87�j�ɑ��C�f�f����6�`21����ɖʐڂ����{�B���҂ɓ�����̍��m�������̂��Ƃ���z�����C���̂Ƃ��̌o����b���Ă�������B �@���̌��ʁC�唼�̏������g�����ҁh���邢�́g�������ҁh�Ƃ��������������ߒ��ɂ����āu���Ȃ̑r�����v�C�܂�C�M���Ă������ȑ������������s���������Ă��邱�Ƃ����������B�܂��C���l�̖ڂ��C�ɂ���C����ǂ������������g�̍s���̂����ɂ���Ȃǂɂ���Ă����ȊT�O���h�炢���B �@�܂����������́C���҂�������������܂łɂ́C�i1�j�̊m�F�i2�j�s�����N�����i3�j�����@���琬��3�i�K�̏����ߒ������ǂ�Ƃ��闝�_��W�J���Ă���B �唼�̏����͕ω������� �@Lally�������ɂ��ƁC���m���������͊�{�I�ɁC�������g�Ǝ��͂̐l�X�ɂǂ̂悤�ɉe������̂��Ƃ������Ȃ銋�����������C�ے�I�Ȏv�l��}���ċC���]����}�邱�ƂŌ��ݒu����Ă�����R���g���[������悤�ɂȂ�C�ŏI�I�ɂ͂����l���̈ꕔ�Ƃ��Ď���ď��������߂�悤�ɂȂ�B �@�����C����̌����ł͑����̏��������g�̕ω�������C�g������̍��m�h�ɂ���āC�l���Ǝ��͂̐l�X�ւ̊��ӂ̐S���Ċm�F�ł����Əq�ׂĂ���B�܂��C�唼�̏����͑O�����Ɏ~�߁C����������ł���ƍl���Ă���B �@���������́u������̍��m���������́C�������������̂悤�Ɋ�����̂ł͂Ȃ����ƁC���m�����̎v�l�͌����Ĉُ�ł͂Ȃ��C�ق��̐l�������悤�ɍl���Ă��邱�Ƃ�m��ׂ����v�Ƌ����B����ɁC�u�����҂ł��邱�Ƃ𗝗R�ɎЉ�ƐE��Œ��ʂ���s�����ȏ�ʂ��玩�g����邽�߁C����ł��邱�Ƃ�����C���g�̒u���ꂽ���R���g���[������ۂɔ������銳�҂̐��_�I�G�l���M�[�̑傫���ɋ������v�ƕt�������Ă���B �@�܂�����̒m���ɂ��āC���m��1�`2�T�Ԃ̑����i�K�œ����҂��S�ɂǂ̂悤�Ȋ�����L���Ă��邩�𗝉����C�����҂ɑ��鑁���S���T�|�[�g�̈Ӌ`���l����ۂɖ𗧂ƌ��_�t���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N3��31�� |
| �l���Ō�̊肢�́u�ȂɎw�ւ��v�@���͂̋��͂�97�Βj���̑z������ |
| �@����̖�w�Ɍ���_�C�������h�̎w�ցB����߂Ă����x�e�B�[�E�|�b�^�[����i86�j�́A�����₭�悤�Ɂu�f�G����A�{���ɂ��ꂢ�ˁv�Ɗ�т̌��t�����ɂ������Ă��������ł��B �@�ĕ�����WHDH��Ď��{�X�g���E�O���[�u�Ȃǂɂ��ƁA�}�T�`���[�Z�b�c�B�ɏZ�ރy�e�B�[����ƕv�̃G���F���b�g����i97�j�����������̂́A������65�N���O�̂��ƁB�G���F���b�g����͔ޏ��Ƀv���|�[�Y���������A�o�ϓI�ȗ��R�ɂ��_�C�������h�̎w�ւ邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�u���ꂪ�����ƋC������ŁA������Ă����̂ł��v�B �@����������A�ނ͔O�肾�����Ȃւ̃v���[���g��n�����Ƃ��ł��܂����B���̉A�ɂ́A�ނ�̏Z�ޗ{��Z���^�[���Î{�݁A��ΓX�Ȃǂ���̂ƂȂ������͂��������̂ł��B �@�܂��A�{��{�݂��v�Ȃ̂��߂Ɂu2�x�ڂ̌������v���v�悵�A�����m�ہB�����āA�Ԃł̈ړ����̂ɕ��S�ƂȂ��Ă��܂����߁A�~�}�Ԃ̉^�c��Ёi���č��̋~�}�Ԃ͂قڎ��c�j�����}����`���A����ɂ����ΓX�̓_�C�������h�̎w�ւ݂̂Ȃ炸�A�V���������w�ցA�u�[�P��V�����p���Ȃǂ��i���Œ��܂����B �@�����̎����̓z�X�s�X�{�݂����S�B�����A�v�̃G���F���b�g����͌��N�̐�������A�ŋ߃^�[�~�i���P�A�i�I�����P�A�j���Ă���̂ł��B�����Łu�l���Ō�̊肢�́H�v�ƕ����ꂽ�ۂɁA���킸�x�e�B�[����ւ̎w�ւ̃v���[���g�ƉB����Ɏ��͂����͂��āA�g�Ō�̊肢�h�������������͂��𐮂��܂����B �@�O��̃_�C�������h�̃v���[���g�݂̂Ȃ炸�A������x�������܂ōs�����Ƃ��ł���ƒm�����G���F���b�g����́A��I���̐H���̃��j���[�ȂǍׂ��������ɂ��Q���B�����Č}���������A�x�e�B�[����̍K�������Ȏp�����邱�Ƃ��ł����ނ́A�u�Ȃ�čK���Ȃv�ƁA�S������ł��������ł��B �@�l���킹��̂��D���ŁA���}���`�b�N�ł�����Ƃ����G���F���b�g����B�������ł̐����̌��t�͂�������ł��܂��B �u�����Ǝ��������Ă���A�����Ƃ����ƌ�������ǂˁc�c�B�ł��A�ꐶ�����Ă����v �i���i���h�b�g�R���@2011�N4��7�� |
| �����҂̑����������u�ɂ��o�� |
| �@�~�V�K����w�����w����юY�ȁE�w�l�Ȋw�� Carmen R. Green������́u�����҂�20���́C�f�f��2�N�ȏ�o�ߌ���C����֘A�̖����u�ɂɔY�܂���Ă���v�Ƃ̒������ʂ\�����B����̌�������C��������т邱�Ƃ́C�u�ɂƂ����V���Ȏ����ɒ��ʂ��邱�Ƃł���Ƃ�����������������ɂȂ����B ����Ƃ������̌��オ�u�ɖ����g�� �@Green������ɂ�鍡��̌����́C�����҂̎x���g�D�ł��郉���X�E�A�[���X�g�����O���c�i�e�L�T�X�B�I�[�X�`���j�̏����ɂ��s��ꂽ���̂ŁC200�l�߂������҂��ΏۂƂȂ����B�����̌��ʁC�팱�҂�40�������f�f�Ȍ���u�ɂ��o�����C�u�ɂ̌o���͏����ő������Ƃ����炩�ɂȂ����B�܂��C�u�Ɋ֘A�̋@�\��Q���������Ƃ����������B �@�u�ɂ̌����Ƃ��đ傫�����̂́C���l�ł͂���̎�p�i53.8���j�C�A�t���J�n�č��l�ł͍R���Ái46.2���j�ł������B�����͋����u�ɂ��u�ɍĔR�C�ɂ݂ɂ��@�\��Q�������C�u�ɂɂ��}�����j�����p�ɂɌo�����Ă����B�܂��C�u�ɂ�L����A�t���J�n�č��l�ł́C�u�ɂ̌�������i���邱�Ƃ���葽���C�u�Ɏ��Â̕���p�ɂ��Ă̌��O�����������B �@�č����������ɂ��ƁC���݂ł́C����Ɛf�f���ꂽ�l��60�������Œ�5�N�͐�������Ƃ����B��������́C�Љ�̍�����i�ނƁC�u�ɂ̑i���͏d��Ȍ��N��̌��O��ی�����̉ۑ�Ƃ��đ傫���Ȃ��Ă���Ǝw�E�B�u������u�ɂɋꂵ�ސl�������C�����ҁC���ɃA�t���J�n�č��l�⏗���̖����u�ɂ̖�肪�傫���Ȃ���钆�C���Â̎�������Ɍ��コ���邽�߂ɂ���ꂪ�s���ׂ����Ƃ͑����v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N4��7�� |
|
�`�I�s�I�C�h���ɖ�` �����u�ɂɂ͐T�d�Ɋ߃��E�}�`�iRA�j��ό`���ߏǂɂ͗L���ȉ\���� |
| �@�I�s�I�C�h���ɖ�́C�����u�ɁC�d�x�̋}���u�ɁC���p�����u�ɂ̊ɘa�ɂ͌������Ȃ����C�̖����u�ɂɑ��Ă�������g�p���邱�Ƃ��\�ł���B�ŋ߁C�����u�ɂւ̎g�p�𐄏�����ӌ��������Ă��Ă��邪�C���̈���ŁC����p�C�E�e���C�ˑ����C���E�Ǐ�̔������X�N�Ȃǂ̖ʂ���C�g�p�ɔᔻ�I�Ȍ���������B �@�����������C���C�v�`�q��w�a�@�k�Ɓl���E�}�`�Ȃ�Matthias Pierer���m��́C�����u�ɂɑ��ăI�s�I�C�h���ɖ���g�p����ۂ̒��ӓ_�ɂ��āCAktuelle Rheumatologie�i2010; 35: 184-188�j�ʼn���B�u�����u�ɂɂ͐T�d�Ɏg�p����K�v�����邪�C�߃��E�}�`�iRA�j��ό`���ߏǂɂ͗L���ȉ\��������v�Ƃ����B �����u�Ɋɘa�Ö@�ƕ��p���ׂ� �@�����u�ɂւ̃I�s�I�C�h���^�Ɋւ���f�[�^�͌����Ă���C3�T�ԁ`3�J���ԂƂ����Z���Ԃ̃����_������r�����������{����Ă��Ȃ��B �@Pierer���m�炪�ߋ��̕����������Ƃ���C�����u�ɂɑ���L�����v�w�I�Ɏ����������͑��݂�����̂́C�T���Ă��̌��ʂ͎ォ�����Ƃ����B�����������Ƃ���C�����m��́u�����u�ɂł́C�I�s�I�C�h���ɖ�̓I�s�I�C�h���܂܂Ȃ����ɖ�Ɣ�ׂ��u�Ɋɘa���ʂɗD��Ă���킯�ł͂Ȃ��v�Ǝw�E�B���̂��߁C�����u�ɂɑ��ăI�s�I�C�h���ɖ�̎g�p�����݂�ꍇ�́C�K�������u�Ɋɘa�Ö@�ƕ��p���邱�Ƃ����߂Ă���B �@�I�s�I�C�h���ɖ�̓��^���J�n����ۂɂ́C3�T�Ԉȓ��ɂ��̊��҂̎��K�p�ʂ����肵�C�ɂ݂̋��x�Ɋւ��鎩�o�I����ё��o�I�ȃp�����[�^�C�o�C�^���T�C���C�g�̋@�\�C�ˑ����C�Տ������l����O�ɋL�^����K�v������Ƃ����B�܂��C�ł���Βlj��ŗ��w�Ö@�C�S���Ö@�C�^���Ö@�C�܂��͂��̂����ꂩ�̎��Ö@�p����̂��悢�Ƃ��Ă���B �@����ɓ����m��́C3�J����ɂ�������x�Č��ʂ��m�F���邱�Ƃ𐄏����Ă���B�������C�I�s�I�C�h���ɖ�ł́C���E�Ǐ�����\�������邽�߁C�ˑR���~���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�x��ꍇ�́C����10�������X�Ɍ��ʂ��Ă����悤�������Ă���B �ŐV�̃K�C�h���C���ł��ό`���ߏǂւ̎g�p���x�� �@Piere���m��ɂ��ƁC�I�s�I�C�h���ɖ�̎g�p�����ɗL���Ȃ̂�RA�ł���BRA���҂ւ̃A���P�[�g�ł́C���҂�18�����ɂ߂ďd�x���u�ɁC37�����d�x���u�ɁC33���������x���u�ɂ�L���Ă��邱�Ƃ��������Ă���B���̊����́C�늳���Ԃ��������҂����łȂ��C2�N�ȓ��ɔ��ǂ������҂ł����l�ł������B �@�����m��́u���������u�ɂɑ���I�s�I�C�h���ɖ�̒����I�g�p�������������͋ɂ߂ď��Ȃ��B�������C�������̌����ł́C����ɂ��RA���҂̐g�̋@�\�Ɛ��������P���邱�Ƃ��F�߂��Ă���CRA�ւ̎g�p����������闝�R�ƂȂ��Ă���v�Ɛ������Ă���B �@����ɁC�ŐV�̃K�C�h���C���́C�ό`���Ҋߏǂ�ό`���G�ߏǂȂǕό`���ߏǂɑ��Ă��C�I�s�I�C�h���ɖ���g�p���邱�Ƃ��x�����Ă���B���ɁC�Z���I�Ȏg�p�͗L������r�I���S�Ƃ���Ă��邪�C���̗L�����ƈ��S���Ɋւ��āC�p���Z�^���[�����X�e���C�h�R���ǖ�iNSAID�j�ƒ��ڔ�r���������͑��݂��Ȃ��B�������C�������̌����ŁC���I�s�I�C�h���ɖ�i�t���A�S�j�X�g�j�ł���C�p���Z�^���[����NSAID�����������ʂ������邱�Ƃ���������Ă���Ƃ����B �@�ȏォ��C�����m��́u���E�}�`�������ɂ�閝���u�ɂɑ��ăI�s�I�C�h���ɖ�𓊗^����ꍇ�́C�K���X�̊��҂̏�Ԃ����ɂ߂Ȃ���C�ʂɎ��Ìv������肵�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƒ������Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N4��7�� |
| �z�X�s�X�F�����a�@�A�J�݂U�N�@�]���A���̐l�炵���@�������̊ɘa�P�A �@�X�^�b�t��ہA�S���₷ |
| �@���������a�@�i�{���s�������j�ɖ������҂�̐l���̍Ŋ����݂Ƃ�ɘa�P�A�a���i�z�X�s�X�j���J�݂���ĂU�N�B��t��Ō�t�A���w�Ö@�m�A��Ã\�[�V�������[�J�[�A��t�A�{�����e�B�A���`�[���ƂȂ��Ē�����킸�P�A�ɂ������Ă���B �@�u���҂ƉƑ��̐S����₷�̂��������̎d���v�Ɗ⍲���ގq�Ō�t���B�R������ÂȂǂ͂��Ȃ����A�ɂ݂�_�I�ȋ�ɂ���菜���A�]�����ł�����肻�̐l�炵���߂�����悤�x�����A�N�ԂP�Q�O�`�P�R�O�l�𑗂��Ă���B �@�u�Ō�t�̗͂������ł���悤�A��t�Ƙb���������d�˂܂��B�X�^�b�t���S����ɂ��Ċ��҂�������B�݂Ƃ����Ƒ��ƃX�^�b�t�̊W�͑����A�⑰���W�܂�N�P��̂�����ɂ͑����̐l���W�܂��Ďv���o����荇���܂��B��肪���͑傫���ł��v �@�����a�@�̃z�X�s�X�͑S���I�ɂ��������x���ɂ���B�{��z��@���́A��t���D���s�ŊJ���ꂽ�S���ɘa�P�A�w���ҍu�K�ɎQ�����A���̐����Ɂu�m�M�����Ă��v�Ƃ����B �@�U�N�ԁi�O�T�N�S���`�P�P�N�R�����j�Ŏ��ꂽ���҂͉��ׂQ�R�Q�R�T�l�B�u�J�ݓ����́g���ʏꏊ�h�Ǝv���Ă��܂������A�z�X�s�X���ǂ̂悤�ȏꏊ���������[�܂�A���҂��Ƒ����v�����ς���Ă��܂����v�Ƌ{��@���͘b���B �@�ŏ�K�̂P�P�K�ɍ����z�e���̂悤�ȃ��r�[����K�Ȍ��A�O�����h�s�A�m�̐����t����z�[���Ȃǂ�����A�H�����ʉ�����R�B�Â����͋C�݂͂�����Ȃ��B �@�O�X�N�X��������މ@���J��Ԃ��Ă��鏗���́u�̂�т�Ǝ��R�C�܂܂ɉ߂����Ă��܂��B������t��Ō�t�����Ă����̂ň��S���ĉ߂����܂��v�Ƙb���A����뉀�Ɏ������~�J����E�ݎ�����B ����jp�@2011�N4��18�� |
|
��28����{�X�g�[�}�E�r�����n�r���e�[�V�����w�� �L���銳�ҁE��Î҂ƒn��̋��͘A�g |
| �@������i�ޒ��C�X�g�[�}�E�r���P�A��K�v�Ƃ��銳�҂̐����N�X�������Ă���B���ɍ���҂̃X�g�[�}�Ǘ��ł́C���҂̏������K�v�ȏ�ʂ������ɂ�������炸�C�x���̐��̕s���⊳�҂̂��߂炢�ȂǁC�������ׂ��ۑ�͏��Ȃ��Ȃ��B�����s�ŊJ���ꂽ��28����{�X�g�[�}�E�r�����n�r���e�[�V�����w��i���������w�a�@�Ō암�E�����~�`�R�Ō�t���j�̃V���|�W�E���u�r���P�A���x����悩�˃b�g���[�N���n��l�b�g���[�N�v�k���������m��ÍĐ��@�\�E�q�{�H�������C�R�z�w����w�i���R���j�E�����q�y�����l�ł́C���E��ɂ��n��l�b�g���[�N�ɂ��āC�s���C��t�C�Ō�t�̗��ꂩ�甭�\���s���C�����ȋc�_���J��L����ꂽ�B���̈ꕔ���Љ��B �R���`�l���X���[�_�[�̉���ʼn��{�݂̔r�֏�Q�����P �`�I�X�g���C�g�T�����`�I�X�g���C�g�ƉƑ����x�� �`�ݑ�z�X�s�X�P�A�`���҂̎��Ȍ���ƉƑ��̎x�����ŗD�� �R���`�l���X���[�_�[�̉���ʼn��{�݂̔r�֏�Q�����P �@NPO�@�l���{�R���`�l���X����̃R���`�l���X���[�_�[�ł��邭��ߕa�@�i�������j�n���ÃZ���^�[�̎�q�c����q�Ō�t���́C��ÐE�̔z�u���`���t�����Ă��Ȃ��O���[�v�z�[���̎{�ݒ�����r���P�A�̎w�����˗�����C�E���ɑ��čs�����r���P�A�w���̌o�����Љ�B�u���E�̉���ɂ����{�ݐE���̒m����Z�p�̌��オ�\�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B����C�n��̃l�b�g���[�N�Â���ɂ́C���E�ɂ��{�݁i����j�ɓ��荞����⌻��̈ӎ����v�ւ̎��g�݂��K�v�v�Əq�ׂ��B �r�փP�A�͏d�v�������S �@��q�c�Ō�t���́C�܂��ȉ��̉���v���ݒ肵���B�i1�j�r���P�A�E�A���P�[�g���i2�j�r�փP�A�̊w�K��i3�j���H�̂��߂̎{�ݓ��~�[�e�B���O���i4�j�Ǘ�J���t�@�����X���i5�j�P�A�v�����̓W�J���i6�j���g�݂̕]���B �@�A���P�[�g����́C�r���P�A�i���ɔr�փP�A�j�̏d�v���𗝉��������C�r�փP�A�S�Ɋ�����E���̐S����炩�ɂȂ����B���̗��R�Ƃ��ẮC�i1�j��ÓI�Ȕz���̕K�v���i2�j�r���g���u���Ɩ��s���̓��������i3�j�r�֊m�F�̍���i4�j�g�C���U���ɑ��鋑�ہi5�j��n���̑�ς��@�Ȃǂ�������ꂽ�B��������������̂ɉ����K�v���Ƃ����₢�ɑ��Ă͐E���̖�80�����u�m���̏K���v�Ɖ����B �@���Ō�t���͉���v��́i2�j�ȍ~�ŁC�A�Z�X�����g�c�[���i���ʂ��`�F�b�N�\�j�Ŕr�ւɊւ���������W���C�������ɃJ���t�@�����X�����{�B����1��Ƃ��ăJ���t�@�����X��ʂ��Ď��ۂ̃A�Z�X�����g�@�ƃP�A�v�����̗��Ăɑ��Ďw�����s����78�̔]���ǐ��F�m�ǂ̒j�����҂��Љ���B�Ǘ�͔r�ւ�2���ԂȂ������Ƃ��ɍ��܂�}�肷����@�ŕ��ʕց`��ւ��F�߂��C���ł����������ƕ֔邪�������C�s���s�ׂ��Ȃ��C��앉�S���Ȃ��Ȃ����B �@����̃R���`�l���X���[�_�[����ɂ��Z���t�E�G�t�B�J�V�[�i���Ȍ��͊��j�̕ω���General Self-Efficacy Scale�iGSES�j�ŕ]�������Ƃ���C�E���ł͖ڗ������ω��͂Ȃ��������C�����N�X�^�b�t3�l�͉����ɓ��_���㏸���Ă����B �@�Ō�ɁC���Ō�t���́u���{�݂ł͔r���P�A�ɋ�a���Ă���C���̉����ɂ͒m���̏K���Ə��̋��L�����K�v�B���E��ɂ��J���t�@�����X�͗L���ŁC����ɂ̓A�Z�X�����g�c�[���̗��p�͕K�{�B��ÐE�̂��Ȃ���쌻��ł͐E���̋���ȊO�ɁC�厡��Ƃ̘A�g�E�������d�v�v�ƌ��_�����B �`�I�X�g���C�g�T�����`�I�X�g���C�g�ƉƑ����x�� �@�X�g�[�}���ݎҁi�I�X�g���C�g�j�ɑ���Љ�̔F�m�◝���͋ߔN�[�܂��Ă��邪�C����ł������҂₻�̉Ƒ��ł��������荇���Ȃ��Y�݂⍢��͑��݂���B���R��w�a�@�������Ҏx���Z���^�[���`�[���̉���M�}���́C2004�N�ɊJ�݂��ꂽ���Z���^�[�̊����̈ꕔ�Ƃ��ĊJ�n���ꂽ�I�X�g���C�g�T�����̂���܂ł̊������e��C�Q���҂̊��z�Ȃǂ��Љ�B�u�I�X�g���C�g�T������S�̂��ǂ���Ƃ��Ċy���݂ɂ��Ă���Q���҂������v�Əq�ׂ��B ���҂���̗v�]�ŊJ�� �@���Z���^�[�́C�a�@�̊e���傾���łȂ��C�s�����t��C���̈�Ë@�ցC�{�����e�B�A�g�D��c�̂ƘA�g��}��Ȃ���C���҂��I�Ɏx�����Ă����g�D�ł���C���̊����̈�тƂ��đ����̃v���W�F�N�g�`�[�����������s���Ă���B �@�I�X�g���C�g�x���`�[���iOST�j������1�Ƃ��ė����グ��ꂽ���C�I�X�g���C�g�̌o���҂₻�̉Ƒ����W�܂��āC�o����Y�݂����L���C�݂��̑��k�ɏ���ꂪ�ق����Ƃ������҂̗v�]�ŁC2004�N1������I�X�g���C�g�T�������J�Â����悤�ɂȂ����B �@���Z���^�[���ŁC�ʏ�C������1�ؗj����10�`15���ɊJ����C�I�X�g���C�g�₻�̉Ƒ��C���邢�́C���ꂩ��I�X�g���C�g�ɂȂ�l���C���O�̗\��Ȃ��ŎQ���ł���V�X�e���ƂȂ��Ă���B �@�����̖ړI�́C�i1�j�����̈ӎv�Ŏ��R�ɎQ������W���̒i2�j��y�E��y�I�X�g���C�g���C�𗬂̒��ŏ������i3�j���̓���b���C���Ԃ̑��݂��݂��Ɋ�����i4�j�X�g�[�}������O�����ɓ���𑗂��悤�Ɏx���@��4�ł���C�����̓I�X�g���C�g�r�W�^�[�i�Љ�A�����I�X�g���C�g�ŁC��y�̃I�X�g���C�g�ɂ��̌o����ʂ��m������x������l�j�̎��i�����I�X�g���C�g�����S�ɊJ�Â��ꂽ�B �@�@���f����L�C�n�����ւ̌f�ڂȂǂ̍L���̐��ʂ�����C�ߋ�5�N�Ԃ̎Q���҂͖�������15�l���x�B�Q���҂̒��ɂ́u�����Œ���ւ����ł���悤�ɂȂ�C�X�g�[�}�̘b�����ʂɂł���悤�ɂȂ����v�C�u�����v���̐l�����邱�Ƃ�m��C�O�����ɐ����Ă����C�������킢���v�Ȃǂ̊�т̐���������C�Q���҂ɂƂ��Ă͐����̒��̑�Ȃ��̂Ƃ��Ĉʒu�t������悤�ɂȂ��Ă���B �@�ŋ߂̎Q���҂̊����́C�j������40���C�N���50�Α�20���C60�Α�30���C70�Α�30���C80�Α�10���C���̑�10���ƍ�����ڗ��B����́C�Љ�l�ɂ͎Q�����Â炢�����̌ߑO����ߌ�ɂ����ĊJ�Â���Ă��邱�Ƃ��W���Ă���\��������C����̌����ۑ��1���Ƃ����B����ɁC���쎁�́u���ƖړI�ŎQ������l�⌤���ړI�ŎQ������]�����ÎҁE�w���Ȃǂ�����C����Ώ������߂�����_���v�Ǝw�E�B����ł��u���̎����O���[�v�����̎x���ƌ����𑱂��C�T�����̏��S�i�u�j���Ȃ��ł��������v�Əq�ׂ��B �`�ݑ�z�X�s�X�P�A�`���҂̎��Ȍ���ƉƑ��̎x�����ŗD�� �@�V���Ή@�i�������j���V���@�R�@���́C�ݑ�z�X�s�X�P�A�̊T�O��ǂ��z�X�s�X�P�A�̂��߂̃|�C���g���T���B�������҂ɑ���P�A�ɏœ_�āC���ۂ̏Ǘ����Ȃ���ݑ�z�X�s�X�P�A�ɂ�������Ï]���҂̍s���w�j�Ȃǂ��Ă����B ���҂̖����x���d�� �@�V���@���͂܂��C���E�ی��@�ցiWHO�j�̊ɘa�P�A�̒�`�i2002�N�j���Љ�CQOL���P���d������A�v���[�`���̂��̂��ɘa�P�A�ł���Əq�ׂ��B �@���@���̓z�X�s�X�E�ɘa�P�A�̍l�����̏d�v�ȓ_�Ƃ��āC�i1�j�����邱�Ƃ̑��d�ƒN�ɂł��K���u���ւ̉ߒ��v�ɑ���h�Ӂi2�j���𑁂߂邱�Ƃ��x�点�邱�Ƃ����Ȃ��i3�j�ɂ݂Ȃǂ̏Ǐ�ɘa�i4�j���҂Ɏ����K���܂Ő����Ă���Ӗ�������������悤�ȃP�A�i5�j�Ƒ����x����P�A�@��5�������C���̂悤�ȗ��O�Ɋ�Â����P�A���ݑ�ōs�����Ƃ��ݑ�z�X�s�X�P�A�ł���Ɛ����B�����āu���҂̎��Ȍ�����x���邱�ƂƁC�Ƒ����x���邱�Ƃ��ŗD�掖���Ƃ��ׂ����v�Ƒi�����B �@����ɓ��@���́C�ǂ��i�ݑ�j�z�X�s�X�P�A����邽�߂ɕK�v�ȏ����ɂ��Đ����B�i1�j���̋��L���i���E��ɂ��`�[���P�A�̎���S�ۂ��邽�߁j�i2�j24���ԑΉ��̑̐������i3�j�z�X�s�X�P�A�ɓK�����l�ނ̋���Ɣz�u�i4�j�ɘa��Âɒʋł�����t�̈琬�i5�j��Ë@�ցi��t�j���m�̘A�g�i6�j���ҁE�Ƒ��̎��ɑ���F������v�����邱�Ƃ��d�v�ł���Ƃ����B���Ɂi6�j�ɂ��ẮC���̕����ɑ�������Â̓W�J�Ƃ��āC�Ƒ��ɑ��āu�Ƃł݂Ƃ��Ă��悢�v���Ƃ𗝉������邱�Ƃ�����Ƃ����B �@�z�X�s�X�P�A�́C�����߂Â����퐶������iADL�j���ቺ���Ă�������̊��҂�QOL�����コ����Ƃ����ꌩ�C�����������݂ł��邪�C�d�����ׂ��͊��҂̖����x�ł���B���ꂪ��������Ă��邩�ǂ����́C���ǁC���҂̎�ςɈˑ����邪�C���@���́u��Îґ������҂�Ƒ��ɉ���������������֎~�����肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��C���҂�Ƒ��������Ă���Ƃ��ɂ͂��ł���������L�ׂ���Ԑ����ێ����Ă������Ƃ�����Əq�ׂ��B �@���Ƃ��ē��@���́C�V��1�N�ڂŖ����̗�������ƂȂ���30�Α�̏������҂��Љ�B���̏Ǘ�̓X�g�[�}�݂��C�c����60cm�ɂȂ������C�H�ׂ邱�Ƃ��y���݁C���J�����[�A�t�����iTPN�j�̎��ȍ쐻���}�X�^�[���C�H���̌o���ێ���p�����ĉh�{�ێ��ɂ��w�߂��B�Ō�̓X�g�[�}���\���@�\���Ȃ��Ȃ�C�݃`���[�u�i�}�[�Q���]���f�j���ȑ}���ɂ��ݓ��e�r�t���s���C����̐�����S�������B����ɂ��āC���@���́u�X�g�[�}�E�r���P�A�Ƃ����Ă��C�h�{�T�|�[�g�`�[���iNST�j�Ƃ��ĐH�̃P�A���l�����g�[�^���ȃP�A���l���邱�Ƃ��d�v���v�Əq�ׁC���҂̖����x�����߂��ł̃g�[�^���T�|�[�g�̏d�v�������������B �@���̂ق����@���́C�_�X�����ɂ��������𗈂���65�̏������҂�CS��������71�Ώ������҂̗���Љ�B������ɂ����Ă��C�Ō�͎���ʼn߂��������Ƃ������҂̊�]������C�Ƒ��i�v��q���C���Ȃǁj�̊Ō���P�A�`�[������������Ƃ����`�ŁC�����̂����݂Ƃ肪�ł����Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N4��21�� |
| �a���Ŋ�������̍Ō�̊肢�@�������̗͂���đ��q�́g���Ǝ��h���{ |
| �@�������������s���悤�Ƃ�����e��O�ɂ��āA�Ō�̊肢�������Ă��������Ǝv���͉̂Ƒ��ɂƂ��ē��R�̐S�����낤�B�ăt�����_�B�ł��܁A�x����Ɠ����A������ԂɊׂ��Ă��鏗��������B�Ƒ��͗\�ߕ����Ă����ޏ��̊肢�������邽�߂ɖz�����A���N���Z�𑲋Ɨ\��̖����q�̑��Ǝ����A���̗͂͂���ĕa���Ō��s�����B �@�ĕ�����WJXT-TV�Ȃǂɂ��ƁA���̏����̓t�����_�B�W���N�\���r���̃z�X�s�X�ɓ��@���Ă��郁�A���[�E���B���b�g����B�c�O�Ȃ���A���܁u�x����Ƃ̓����ɕ����Ă���v�iWJXT-TV���j��ԂɊׂ����ޏ��́A�ŋ߂͉Ƒ��ɑ��锽���������Ȃ��Ȃ��Ă����B6�l�̎q�ǂ����Y�݁A7�l�̑������Ɏ������̑�ȕ�ƁA���悢��i���̕ʂꂪ�߂Â��ė������Ƃ�������Ƒ��́A�\�ߕ����Ă�����]�̂�����2��������ׂ��A�������ɂ킽�菀����i�߂Ă��������B������4��21���A�g�������ł��Ȃ����A���[����̂��ƂɁA�e���▖���q�̃u���C�N����̓������炪�W�܂�A��̊�]��������C�x���g���s��ꂽ�B �@���A���[����̑̒����l�����āA��t�����������Ԃ́u45�������v�i�ĕ�����CBS�n��WTEV-TV���j�B�܂��ŏ��ɍs��ꂽ�̂́A�v���[���[����Ƃ�20�N�ڂ̌����̐����������B�������������u���C�N����́u�����A������������Ɍ������v�iWJXT-TV���j�ƌ��A���S�[�������悤�B���߂ĕv�w�̈����m���ߍ��������e�̎p������ƁA���x��2�ڂ̊�]��������ׂ��u���C�N������ƂȂ�A��̕a���ɃK�E���Ɗp�X���������������������������ƁA�ގ��g�̓��ʂȑ��Ǝ����n�߂��B �@�u���C�N����̑��Ƃ����͂������Ƃ����A2�ڂ̊�]��������ꂽ���A���[����B�{���A�č��̍��Z�ł͉ċx�ݑO��5�����ɑ��Ǝ����s����̂���ʓI�����A�u�x�߂��đ҂ĂȂ��v�iWTEV-TV���j�Ƃ̔��f�ɂ��A�a���ł́g���Ǝ��h���s�����Ƃɂ����������B���͂��ďW�܂������������������̐����𒅂ĉ��o���A�u���C�N����ɂ͗p�ӂ������̑��Ə؏�����n���ꂽ�B �@���̂Ƃ��̏́A�o�}���f�B�[�E�Z�N���X�g����ɂ���ē���ŎB�e����Ă���A�u���C�N����̑��Ƃ����������������グ�Ė��邭���C�ɏj���Ă����l�q�B����Ȏq�ǂ������̃p���[�ɐG�����ꂽ�̂��A���A���[����́u���Ə؏��������v�Ɛ�����������ƁA���L���������������Ƃ����B����ɂ́u����3���Ԃŕꂪ�������B��̔����v�ƁA�}���f�B�[������������悤���B �@���͂̑傫�ȋ��͂������āA���A���[����̊肢��������ꂽ�ƁA���ʼn��낷�Ƒ������B�u���C�N����́A�����̓��������W�܂��Ă��ꂽ���Ƃ��u�S���������o���v�Ɗ��ӂ̋C�����ł����ς����Ƃ����B �i���i���h�b�g�R���@2011�N4��28�� |
|
�`�ݑ�݂Ƃ�` ��a�@�M�ƉƑ��ւ̕��S�����o���A�[�� |
| ��25��D�y�~�G����Z�~�i�[ �@���݂킪���ł́C���҂̖�9������Î{�݂Ŏ��S���Ă���B�������C�u�ݑ�ł݂̂Ƃ�v����]���銳�҂͑����B�ݑ�ɘa�P�A����Ƃ����Ö@�l�Вc�u�H��ӂ����܍ݑ�ɘa�P�A�N���j�b�N�i�������j�̗�؉�v�@���́C���@�̎��g�݂ɂ��ĕ����B �x�����̖��_�͑��E��A�g �@���N���j�b�N�̂ق��C�{�錧��2�J���i������@�C�ɘa�P�A�N���j�b�N���j�̐f�Ï������u�H��ł́C�ł��邾���ݑ�ʼn߂��������Ɗ���Ă���I�������ҁC�_�o��a���ҁC�ʉ@�̍���ȍ���҂Ȃǂ�ΏۂɁC�v��I�ȖK��f�Â��s���Ă���B�X�^�b�t�́C��t9�l�i���8�l�C����1�l�j���͂��߂Ƃ��āC�Ō�t�C��ƗÖ@�m�C�\�[�V�������[�J�[�C�P�A�}�l�W���[�C�I���t�C�w���p�[�C�`���v�����i�a�@�t�q�t�j�Ȃnjv87�l�̃X�^�b�t���]�����Ă���B����ł݂Ƃ������҂́C��N1�N�Ԃ�308�l�C2009�N��315�l�C2008�N��251�l�ł���B �@�ӂ����܍ݑ�ɘa�P�A�N���j�b�N�́C2007�N10���ɊJ�@�B���݂́C��t2�l�i��j�C�Ō�t4�l�C�\�[�V�������[�J�[1�l�C������2�l�̂ق��C������@����1�`2�T��1��`���v�����ɂ��C���ɂ������Ƃ����ݑ�ɘa�P�A���s���Ă���B �@��؉@���ɂ��ƁC�O���͍s���Ă��Ȃ����߁C���������������Ă���C�����͂��ׂăX�^�b�t�̋����ɉ��B��Î{�݂Ȃǂ̌Œ莑�Y�ɉ��p�͂Ȃ����߁C�ƒ�7���~�̂�����ʓI�Ȗ��Ƃ���āC�f�Ï����J���Ă���Ƃ����B �@���@���́C�ݑ�ɘa�P�A����鑤�̖��_��1�Ƃ��āC�u���E��A�g�v���������B�ݑ�ɘa�P�A�̌���ł́C�����̐E��Ń`�[�����`������K�v�����邪�C�E�킲�ƂɎ��Ə����Ⴄ�B1��1���Ɨ��̎Z�̎��Ə��ł��邽�߁C���ꂼ�ꂪ�������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̒��Ŋ��҂��ƂɃ`�[�����`�������Ƃ��C���O�̓���C�������C�l�ԊW�̍\�z���s�����Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��B���@���́C�K�R�I�ɓ���g�D���ɑ��E������낦��������Ȃ����������B �@�܂����ґ��̖��_�Ƃ��āC�u�g��a�@�M�h�Ɓg�Ƒ��ւ̕��S���h�ɏW��ł���v�Ǝw�E�B�a�@�ōŊ����������邱�Ƃ�]�ސl�����́C���ɂ��Ă͌��Ȃ��̂Ƃ��Ęb���C�_�H���Ȃ���S�d�}��l�H�ċz���t���C�S���}�b�T�[�W������Ȃ��玀�ʂ̂����������ɕ��ł���ƍl����l�������B �@����C����ł݂Ƃ��邱�Ƃ���]����l�����́C���ɂ��Ďd�����Ȃ����̂Ƃ��Ęb���i�g����Ă���h�Ƃ����̂Ƃ͈Ⴄ��ہj�C���͐l���̃S�[���ł���C�����ʂ�̐������ɂ��Ă���B�u�����̊������C�n��ɂ����鎀�̕����̌p���ɂȂ��邱�Ƃ����҂��ē��X�̎d�����s���Ă���v�ƕ����B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N5��19�� |
| �Ŋ���I�ԁ@�I������Â����O�w�� |
| �@�啪�s�ň�l��炵�̏����]����i�V�T�j�́A���N�����A��ⳂɃy���𑖂点��B�l���̍Ŋ����}�������ɂǂ�Ȉ�Â��������A���Â�̂��B �@�q�P�r���ʂȉ������Â͂��Ȃ��q�Q�r��ɂ̊ɘa�͍ő������Ăق����q�R�r�A����ԂɂȂ������̐����ێ����u���O���A�u�݂낤�v�i�����Ɍ����J���āA�݂Ƀ`���[�u�ʼnh�{�𑗂���@�j�͋��ۂ���\�\�B �@�S���������e���R�������A�P���͎����p�ɕۊǁA�Q���͋ߏ��ɏZ�ނQ�l�̑��q�ɓn���A�u���̎����������t�Ɍ����āv�Ɨ��ށB�������������́u���O�w�����v�ȂǂƌĂ��B �@�V�N�O�B��������̕v�́A�P�N���炸�̓��a�����̖��ɖS���Ȃ����B��������������˔�����A�Ђ��̒ɂ݂Ȃǂ�����A�Ŋ��̎����l����悤�ɂȂ����B �@�S�z�Ȃ̂��݂낤���B�ȑO�A�ߏ��̏������F�m�ǂŐH�ׂ��Ȃ��Ȃ�A�݂낤�ɂ��邩�ǂ����ʼnƑ��Ԃ̈ӌ��������ꂽ�A�ƕ������B �@�u�݂낤�ŕa�C���ǂ��Ȃ�Ȃ炢�����A�Q������ł����������Ă��邾���Ȃ�炢�B���R�Ȏ����}�������v�B����Ȏv���Ŏw�����������悤�ɂȂ����B �@�����s�`��̉�ЎВ����R�q(���Ƃ�)����i�T�S�j�̕�e�A�a�q����i���N�W�R�j�́A���A�a���������A��N�Q���ɉE����ؒf�����B�F�m�ǂ�����b�ňӎv�a�ʂł������߁A���R���a�C�̌��ʂ����������ƁA�u�����[�u�͖]�܂Ȃ��v�ƌ����B �@�U���ɕa�@�ň݂낤�����߂�ꂽ�ہA��̊�]��`���Ēf�������A��t�́u�������Ȃ��Ȃ�āA�]�ˎ��ザ�Ⴀ��܂����v�ƌ����A�������Ă��炦�Ȃ������B �@���ǁA��͈݂낤�̑���ɕ@����̃`���[�u�ʼnh�{�⋋�������A�ꂵ�����Ō��������B�₪�Ĕx���ɂȂ�A���V���ɖS���Ȃ����B �@���傤�ǂ��̂���A��Ã��l�T���X�u���������l����v�ŁA�u���̐������A���m�[�g�v��m�����B�I������ÂɊS������Î҂�ō��u�����炵���������ɂ��l�����v���A���R�L�q���̎��O�w�����Ƃ��čl�āA���͎s�̂���Ă���B �@���R����͂����ɂP�O�����w���A�F�l�ɂ��z�����B�����́u�����[�u�͖]�܂Ȃ��v�ȂǂƊ�]���������݁A�Ƒ��Ƃ�������b���������B �@�u�����Ƒ������������m�[�g������A��̎��ɖ𗧂Ă�ꂽ�̂Ɂv �@�I������Â̑傫�Ȗ��̈�́A�{�l�̊�]���s���ȏꍇ���唼���߂邱�Ƃ��B����Ȓ��A�Ŋ��̈�Â�����I�сA���͂ɓ`���Ă����u���O�w���v���A�������L�������B YOMIURI ONLINE�@2011�N5��23�� |
|
���Җ{�l�ɑ���ӎv����͋�� �Ƒ��ȂNJ��҂̑㗝�l�ɋ����X�g���X |
| �@�č����q����������David Wendler���m�ƃ`���[���q��w������w�ϗ��������i�X�C�X�j��Annette
Rid���m�́C���Җ{�l�ɑ����đ㗝�l�����Ö@�̌���Ɋ֗^����ۂɔ�鐸�_�I�e����������������40���̃V�X�e�}�`�b�N���r���[���s���C�㗝�l��3����1�������_�I�ɕ��̉e�����Ă��邱�Ƃ����������Ɣ��\�����B�����m�́C�����������S���y�����邽�߂̕������Ă��Ă���B �����̑㗝�l�����_�I���S���o�� �@�㗝�l���s������̑唼�́C�I������ÂɊւ�����̂ł���B�����͂��ꂽ40���̌����i�č�32���C�J�i�_6���C�t�����X�ƃm���E�F�[�e1���j�́C29�������I�������C11������ʓI�������s�������̂ŁC�v2,854�l�̑㗝�l����f�[�^�����W�����B�����̑㗝�l�̂قƂ�ǂ͊��҂̉Ƒ��ł������B �@��ʓI��������C���Â̌���Ɋ֗^�������ʁC�㗝�l��3����1�������_�I���S�������Ă��邱�Ƃ����������B����C���I��������́C�㗝�l�̑��������_�I���S�������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�d�x�̕��S�ƂȂ��Ă���P�[�X����������C��ʓI�ɂ͐��J���ԁC�ꍇ�ɂ���Ă͐��N�Ԏ��������B�قƂ�ǂ̏ꍇ�C�㗝�l�͎��������������f�������Ă��邩�ۂ��ŔY�݁C�X�g���X��߈����Ȃǂ������Ă����B �@�����[�����ƂɁC�����Ȃ���ǂ��e�������ƕ��Ă���㗝�l������C���̏ꍇ�ɂ͊��҂��x���邱�ƂɈӋ`�������Ă���P�[�X�����������B �@����ΏۂƂȂ��������̂����C�����^�i�B����w��Yoshiko Y. Colclough���m�炪2007�N�ɔ��\�������n�č��l�̑㗝�l��Ɋւ��錤���ł́C�㗝�l���傫�Ȑ��_�I���S�������Ă��Ȃ����Ƃ�����Ă���C�l��I�ȗv�������������B ���҂̊�]��m�邱�Ƃ��|�C���g �@����̌����ł́C�㗝�l�̃X�g���X���ɘa���邽�߂̕������������Ă��Ă���B��Ȃ��͈̂ȉ��̒ʂ�B �@�i1�j���҂̊�]���͂����肵�Ȃ��ꍇ�ɂ́C���X���b�������̋@��𑁂߂ɐ݂��C���҂Ɏ��O�w�������쐬���邱�Ƃ����߂� �@�i2�j�㗝�l���a�@�̊���s���Ɗ�����ꍇ�ɂ́C���P����u���đ㗝�l�����̊��Ɋ����悤�Ɏ菕������ �@�i3�j�ӎv����̃v���Z�X�ɂ����āC�㗝�l���Y��ł���ꍇ�́C���̌����肵���P���� �@�i4�j�ӎv����Ɋւ��Ĉ�t�Ƒ㗝�l�Ƃ̊Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����ɖ�肪����ꍇ�ɂ́C�㗝�l�̒��ő�\�҂����߁C���̐l���ƈ�t������I�Șb���������s���B�܂����̍ۂɂ́C��t�͖��m�Ȑ���������悤�S������ �@�i5�j�㗝�l�����Ԃ������Ĕ[���ł��锻�f���������Ƃ��ł���悤�ɁC�\���Ȏ��ԓI�]�T�������đ㗝�l�����߂Ă��� �@�i6�j���Җ{�l�ɑ���ӎv����Ɋւ��āC�Ƒ��ƈ�t�C�܂��͉Ƒ��ԂɑΗ������݂���ꍇ�C�Η��̌����肵�đ���u���� �@�i7�j�㗝�l���ӎv����̐ӔC��1�l�ŒS�����Ƃɕ��S�������Ă���ꍇ�ɂ́C��t�͂��̕��S�����L���ׂ��ł���B�����������̊ώ@��������C���Âɑ��銳�҂̊�]���悭�������Ă���̂́C��t�����Ƒ���e�����l�ł��邱�Ƃ��������Ă���C���̓_�ɂ͏\�����ӂ��Ĉӎv������s�� �@�i8�j�㗝�l�����g�̌���ɂ��ĕs���Ȃǂ��������ꍇ�C��t�͑㗝�l�̌�����x������ƂƂ��ɃJ�E���Z�����O���s���ׂ��ł��� �@����̌������āCWendler���m��́u�S�̂Ƃ��āC���Âɑ��銳�҂̊�]��m�邱�Ƃ͑㗝�l���ӎv���������ۂɏd�v�ȃ|�C���g�ł��邱�Ƃ����������B���҂���]���鎡�Â肷����@���܂߂āC�㗝�l�̐��_�I���S�����炷���@����������K�v������v�ƌ��_�t���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N5��26�� |
| �����P�Q�a�@���u�ɘa�P�A���C�v�@����t�ɋ`���� |
| �@���҂�̒ɂ݂Ɋ��Y�����t����Ă邽�߁A���Ɍ�������Z���^�[�i���Ύs�j�Ȃnj����S�P�Q�a�@�͖{�N�x����A���C���̎���t�Ɂu�ɘa�P�A���C�v��u���`���t�����B�`�����͑S�����Ƃ����B���ÂɌg����t�S���̎�u���������߂钆�A�ɘa�P�A�Z���Ɍ��������g�݂Ƃ��Ē��ڂ��ꂻ�����B �@�ɘa�P�A8 �����C�́A�����P�Q�a�@�Ŋw�ԗՏ����C��i����v�S�W�l�j�̏������C�Q�N�ڂ̕K�C�ȖڂƂ��A�{�N�x�͂R�V�l���A��������Z���^�[�ȂǂT�a�@�łU�����珇���J�����v���O�����ɎQ������B �@���C�ł́A��×p����̓��^��A�I�����Ɍ����Ǐ�ȂNJ�b�m�����w�Ԉ���A���҂̐��Ɏ����X�������������ł���悤�O���[�v���[�N���������B�܂��A������������m�����t���Ɗ��Җ���������u���[���v���[�v��ʂ��A���҂̗����̌�����B �@���͂Q�O�O�W�N�A��������i��{�v��Ɋ�Â��A�e�n�́u����f�ØA�g���_�a�@�v�Ɋɘa�P�A�̌��C��J�Â��`���t�����B�S���łP�O���l�Ƃ������邪��f�È�t�S���Ɏ�u���Ăъ|���邪�A����܂łɏC�������͖̂�Q���l�Ƃ����B �@��������Z���^�[�̐�������Y�@���́u���̓I�A���_�I�Ȓɂ݂������ł����t�́A����Ɍ��炸���҂��]�ވ�Â�ł���B��t�Ƃ��Ă̊�b���w�Ԏ����Ɍ��C����Ӌ`�͑傫���v�Ƃ��Ă���B �y�ɘa�P�A8 ���z�@���������������ƌ����������҂ƉƑ��́u�����̎��i�p�n�k�j�v���P��ڎw�����u�B���Ï���������s���Đi�߂�̂����z�Ƃ����B��ɂ��ɂ݂⌑�Ӂi�����j���̃R���g���[�������m��̔ߒQ�ւ̑Ώ����������}���鐸�_�I��ɂ̊ɘa�Ȃǂ��w���B �_�ːV��NEWS�@2011�N5��29�� |
|
�I�������҂̐ϋɓI���y���C��e�ł����ᇓ��Ȉ��10���ȉ� �؍��C��������Z���^�[�̌��� |
| �@����ȂǂŏI�������}���Ă���l���C�����ێ���ړI�Ƃ�����Ñ[�u�𒆎~���邩�C���邢�͂���ɓ��ݍ���ŐϋɓI���y����I�Ԃ��|����̈Ⴂ�ł��Ȃ蓚�����Ⴄ���Ƃ��\�z���������c�_����ɂ́C�܂����̈Ⴂ��F�����邱�Ƃ��d�v���B���̂��сC�؍�����3,000�l����ΏۂƂ����������ʂ��؍��E��������Z���^�[��Young Ho Yun����ɂ����ꂽ�B �@����ɂ��ƁC�u�����ێ���ړI�Ƃ������Áv�Ȃǂɑ��C��e�ł���Ɖ�����ᇓ��Ȉ�̊����͈�ʂ̐l�Ƃقړ������������C�u�ϋɓI���y���v�u��t�ɂ�鎩�E�v�́C10���ȉ��Ƃ��Ȃ�Ⴂ�����ɂƂǂ܂��Ă����B ���ҁC��ʎs���̖����ϋɓI���y�����u��e�ł���v �@Yun����ɂ��ƁC�؍��ł́C2009�N�ɍō��ق����������x�����锻���������܂ŁC�I������Â̂�����Ɋւ���Љ�S�̂ł̋c�_�͂��܂�s���Ă��Ȃ������Ƃ����B����C�a�@�Ŏ����}���邱�Ƃ������Ȃ��Ă���Ȃ��ŁC�I������ÂɊւ��錤���̂قƂ�ǂ͈��y���ieuthanasia�j���t�ɂ�鎩�E�iphysician-assisted suicide�j�������Ǝw�E�B �@�����ł��҂₻�̉Ƒ��ifamily caregiver�j�C��ᇓ��Ȉ�C��ʎs���炪�I�����̎��ɍۂ��C�ǂ̂悤�Ȉ�Â�{���ɕK�v�Ƃ��Ă��邩�C�ӎ��������s�����B �@����Z���^�[����ѓ�����16�̑����a�@�Őf�Â��Ă��邪�ҁi1,242�l�j�C���̉Ƒ��i1,289�l�j����ю�ᇓ��Ȉ�i303�l�j�C�������̓��v�K�C�h���C���Ɋ�Â����o���ꂽ��ʎs��1,006�l�������ΏۂƂȂ����B �@�����̌��ʁC�u���v�Ȑ����ێ����Â̒��~�v�u�ϋɓI���u�ɃR���g���[���v�ɂ��ẮC������̃O���[�v��90���O�オ��e�ł���Ɠ����Ă����B �@����C�u�ϋɓI���y���v����сu��t�ɂ�鎩�E�v�ɑ��Ă͂��Җ{�l�ƈ�ʎs���̖�����e�ł���Ɠ����Ă����̂ɑ��C���҉Ƒ��͂��ꂼ���40���ƒႭ�Ȃ�C��ᇓ��Ȉ�ł͂��ꂼ��10���ɓ͂��Ȃ����ʂƂȂ����B �@����̌��ʂɑ��C���y���ɑ����e���͉��Ăɔ��Ⴍ�C���̔w�i�ɂ͉��ĂƃA�W�A�̌l�C�Ƒ��Ԃ̈ӎv����V�X�e���̈Ⴂ������̂ł͂Ȃ����ƍl�@�B����C��ᇓ��Ȉオ���y���⎩�E�ɏ��ɓI�Ȃ̂́C���Ă̍��X�Ɠ��l�Ƃ��Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N5��31�� |
| �_�H�s�v�A�����q�l�g�p���ݑ�z�X�s�X�̋Ɉ� |
| �@6��5���ɍs��ꂽ�S���ݑ��Ð��i���c���Â̎s���u���ōu�����s��������a�Y���i����ݑ�P�A�N���j�b�N�@���j�́A���@�ōs���Ă���ݑ��Âɂ��Đ��������B �@����ݑ�P�A�N���j�b�N�̊J�@�́A2000�N2���B���݂́A��t4�l�i���2�l�A����2�l�j�A�Ō�t2�l�A����5�l�A�{�����e�B�A�i�A���}�j1�l�Ƃ����̐��ŁA���ꂼ��30�ӏ��ȏ�̖K��Ō�X�e�[�V�����A�K���쎖�Ə��ƘA�g���Ȃ���A����s�𒆐S�Ɏ���14�s����K�₵�Ă���B �u���@�̍ݑ��Á��ݑ�z�X�s�X�v�Ƙb��������B���N���j�b�N�ł́A��������̊��҂̂ق��A�Q������̍���ҁA��a���ҁi�ŔN����4�j��Ώۂɍݑ�z�X�s�X����A2010�N�ɊŎ�������Ґ���187�l�i�ݑ�160�l�A���{27�l�j�B�J�݈ȗ��A1,630�l�̊Ŏ����s���Ă����B �u�l�͊Ŏ��܂���B�Ŏ��̂͂��Ƒ��v�u�Ƒ�������ŊŎ�邽�߂̉�����Áv�ƍl���������́A�u���r���[�ȋC�����̊��҂���͎܂���B�Ŏ��Ƃ����o����Ƒ�������邱�Ƃ��厖�v�Ƙb���B �@������1,600�l�ȏ���̊Ŏ��Ɍg����Ă����o������A�ݑ�z�X�s�X�̐����̃|�C���g�����̂悤�ɏЉ��B �E�u�_�H�͌����s��Ȃ��v �@���S�Ö��h�{�͌��炵�A���R�ȋꂵ�܂Ȃ��ċz��Ԃ̂��߂ɂ́u�]���Ȑ��͂���Ȃ��A�Ŋ��܂Ō�����v���Ŏ��̋ɈӂƂ����B �u�_�H�͉������Ă�����Ă���Ƃ����Ƒ��̈��S�������ŁA���҂���ɂƂ��Ă͍���v�i������j �E�u�ɂ݂͉䖝���Ȃ��v �@�ɂ݂��䖝���邱�Ƃ͐S�g�Ƃ��ɏ��Ղ��邾���ŁA���̈Ӗ����Ȃ��B�ɂ݂�������ʂ��K�ȓ��^�ʂł����āA���r���[�ȃ����q�l�̎g�����͂��Ȃ��Ƃ̂��ƁB �E�u�ċz����̑Ή��v �@�x����A�x�]�ځA�ċz�펾���̌ċz����́A����ł�24���Ԏ_�f���g�p�ł��A�����q�l�����̎g�p�Ōċz����y�����邱�Ƃ��ł���B �@�܂��A������́A�ݑ�ŊŎ�������҂̂����A�f�Ó�����1�T�Ԗ�����13���A1�T�ԁ`1����������35��������Ƃ����ɂ��āA�a�@�ɑ��āu�Љ�܂��܂��x���v�Ǝw�E����B �u��҂͖S���Ȃ��Ă����ߒ��ɂ��ċ���������Ƃ�����܂���B�S���Ȃ��Ă������ɂ��������Â����Ă��܂��B�ł��A�]�����Z���Ɣ��f�������҂͂���̂܂܂�`���Č��������ق����悢�v�ƁA���҂��c���ꂽ���Ԃ�L�Ӌ`�Ɏg�����߂ɑ��߂ɏЉ�Ăق����Ǝ咣�����B �@���̂ق��A�u����̎��^�����ł́A�Ŏ��ɕK�v�Ȃ��Ƃɂ��Ė���A�u�\����K�v�͂Ȃ��B���ɂ��Ă����邱�ƁB���ʂɖ߂����߂ɂ͉����K�v���l���邱�ƁB�ނ���A�c���ꂽ�l�̃����^���P�A���厖�ł��B�X�s���`���A���Ƃ��������Ƃ����ڂ���Ă��邪�A���{�͂܂��܂����n�ȍ��B���R�̂ł��邱�ƁA�l�͎��ʂƂ������Ƃ��������l���Ă������Ƃ��K�v�v�Ɠ������B �P�A�}�l�W�����g�I�����C�� 2011�N6��6�� |
| �ɘa�P�A�̏[����ڎw���C����܂����c�_���|��83����{�݊��w�� |
| �@�����Â̐i�W�͖ڊo�܂����C�V���Ȏ��Ö@�̓o�ꂾ���łȂ��ɘa�P�A�̗��O�����������y���C��Î҂̈ӎ������߂邱�ƂƂȂ����B����ŁC���Տ��ɂ����Ă̓X�^�b�t���̏[����V�X�e���̉��҂ȂnjX�̈�Ë@�ւɂ���Ă��������C���z�ƌ����Ƃ̊Ԃɑ傫�ȃM���b�v�����݂���B�O��s�ŊJ���ꂽ��83����{�݊��w��k����O��s���a�@�i�X���j�E��c�D�@���l�̓��ʊ��V���|�W�E���u���w�Ö@��̐�ڂȂ���Â̎��H�v�k��������ʈ�ȑ�w���ۈ�ÃZ���^�[�ɘa��ÉȁE�ޗǗю������C����E�����ǃZ���^�[�s����a�@�E���X�؏�Y�@���l�ł͂��������܂��C�ɘa��ÉȁC������O�ȁC���w�Ö@�ȁC���ꂼ��̐��I���ꂩ�痦���Ȉӌ������\���ꂽ�B �`�ɘa��Éȁ` �I�����ɕs���\�u����ł݂Ƃ�ꂽ���v��11�� �g�ɘa�P�A�́C����̐f�f������n�܂�h�Ƃ̗��O�͍L����Î҂ɕ��y���Ă������C�����ɂ͑����̂��҂����̉��b�ɂ�������Ă��Ȃ��B�����̓ޗǗы����́C����Ö@�Ɍg����ᇓ��Ȃ��o�Ċɘa�P�A�ɐ�]���Ă���o������C�I�����̊ɘa�P�A�ɂ��āC���҂̕s�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ̌������q�ׂ��B �a�@�オ�������� �@�ߔN�ł́C����ɔ����g�̏Ǐ��_�Ǐ��a�炰�邽�߂̊ɘa�P�A�́C����̐f�f�����玡�Âƕ��s���čs���ׂ��Ƃ���Ă���B����ŁC���ɐi�s����ł͂�����ϋɓI�Ȏ��Â��I�����C�S�ʓI�Ȋɘa�P�A�ֈڍs����������Ȃ����������邪�C�ޗǗы����́C�����Őg�̒u������Ȃ����Ă��܂����҂����Ȃ��Ȃ��̂�����ł��邱�Ƃ��Љ���B �@�Ⴆ�u�]��6�J���ȓ��̖�����ԁv�Ƃ������ŁC�u�×{�ꏊ�v�Ƃ��Ď������]����҂�63.3���ɒB����ɂ�������炸�C�ŏI�I�ȁu�݂Ƃ�̏�v�Ƃ��Ď������]����҂�10.9���Ɍ������邱�Ƃ�������Ă���i�����J���ȕ���19�N�x�����j�B����ɁC���̎�ȗ��R�́u��삵�Ă����Ƒ��ɕ��S��������v�i79.5���j�C�u�a�}�ς����Ƃ��̑Ή����s���v�i54.1���j�ł���C�ϋɓI�Ȏ��Â��I��������C���Ȃ킿�I�����̊ɘa�P�A�ֈڍs���邽�߂̈�Î҂̎x�����s�\���ł��邱�Ƃ��������ꂽ�B �@�������́C�ɘa�P�A��ڂȂ��ڍs���邽�߂ɂ͂܂��C�u���҂̕s�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƒi�����B�I�����̊ɘa�P�A������Ƃ��ẮC�����n��̊ɘa�P�A�a���C�n��̕a�@�E�f�Ï��Ȃǂ�����Ƃ����_�ɐG��C�����̎{�݂͌X�̊��҂̏ɉ����ēK�ɑI�������ׂ��ł���ɂ�������炸�C����ł́g�I������h�ɂ͎����Ă��Ȃ����Ƃ��w�E�����B�������͂��̗��R�Ƃ��āC�u��t�i�a�@��j���C���ҁE�Ƒ��̈ӌ���c�����Ă��Ȃ��v�C�u��t�i���j���C�ݑ�łǂ̂悤�Ȉ�Â�ł���̂��𗝉����Ă��Ȃ��v�C�u��t�i���������j���C�R����ÏI����̊��҂̎���ɕK�������ϋɓI�ł͂Ȃ��v�Ȃǂ̖��_���������B �@���҂̒��ɂ͍Ō�܂Ŏ��Ìp���������Ƃ����l������C���S�Ȃ��Ƃʼn߂��������Ɗ�]����l������B�I�����ɂ����Ĉ�Âɋ��߂���̂͌X�̊��҂ɂ���ĈقȂ�B��Î҂ɂƂ��ďd�v�Ȃ��Ƃ́C���҂Ɏ��Ȍ���̋@���^���邱�ƂƁC���ꂼ��̊�]��c�����Ă������Ƃł���Ƃ����B �@�������́C���҂̊�]�ɉ������ɘa�P�A�̂��߂̃L�[�p�[�\���͕a�@��ł���Ƃ��C�u�Ĕ������Ƃ��C�R����Â��I������Ƃ��́C���҂̊�]���m�F����ǂ��@��v�Əq�ׁC�u�����̈�ÐE�̒������Ƃ��āC�a�@��̐s�͂��s���ł���v�Ƌ��������B �`������O�ȁ` �g���z�̊ɘa��Áh�ɐ^�̒S����� �@�킪���ł͂���f�Âɂ����ĊO�Ȉオ�O�Ȏ��ÈȊO�̋Ɩ����L���S���Ă����Ƃ����w�i������B��ʕa�@�∤�m������Z���^�[�ŏ�����O�Ȉ�Ƃ��đ����̂��Â��s���Ă������É���w������O�Ȃ̏����O�y�����́C���g�̌o���Ɨ����Ȍ����������āC������O�Ȉオ���݂����Â̏�łǂ̂悤�Ȗ������ʂ����Ă��邩���Љ���B �^�t�ȊO�Ȉ�ɂ����E�͂��� �@�����y�����͔��\�̖`���Łu���́C����Ȃ��Ƃ�b���ׂ��ł͂Ȃ��̂�������Ȃ��v�ƑO�u��������ŁC���܂��ɑS���̑����̕a�@�Łu�O�Ȉ�͎�p�ɉ����Đf�f�≻�w�Ö@��S���C�e�Ȃ̖�������~�}��M���̑Ή��܂ōL���S�����Ă���v�Ǝw�E�����B �@�Ⴆ�C���y�������Ζ����Ă����n�����j�s�s�̈�ʕa�@�ł́C���Ȃ̖��������Ȃ������K��1�l���������C�����ĒS�����҂݂̂Ƃ���s���Ă����Ƃ����B���R�C�x���̓����Ȃ��܂ܒʏ�Ζ��ɖ߂�@������Ȃ��Ȃ����߁C�p���Ɂu���삪�����ȁv�Ǝv������グ����O�Ȉオ2�l�C�������܂ܐQ�Ă������Ƃ��������Ƃ̂��Ƃł���B���҂��炷��u��p�����Ă��������t�ɁC�ɘa�P�A���܂߂čŌ�܂Őf�Ă��炢�����v�Ƃ����C���������邩������Ȃ����Ƃ�F�߂Ȃ�����C�u�O�Ȉ�ɂ���͂���E�͂���v�Əq�ׂ��B �@�܂��C���҂��݂Ƃ�����ɁC�O�Ȉ�͎厡��Ƃ��Ď��S�m�F�⎀�S�f�f���̍쐬�ȊO�ɁC����̏��u���̂̔����C�č��܂ōs�����C���Ґ��̑����ɔ����C�݂Ƃ�̌����������邽�ߕs���s�x�ŏA�J����������Ȃ������o�Ă���B�Ɩ��̎�̂ł���͂��̊O�Ȏ�p�ɉe�������˂Ȃ��ł���C���y�����́C���҂d�Ɍ����邱�Ƃ͐l�ԂƂ��ē��R�̍s�ׂ��Ǝv�����C�u�O�Ȉ�Ƃ��ėD�悷�ׂ����Ƃ͉����ƍl����悤�ɂȂ����v�Əq�ׂ��B �@��J�̓x�����ƊO�Ȏ�p�ɂ�����~�X�����ɂ́C�֘A����������Ă���B���y�����ɂ��ƁC�ߔN�ł͊��҂ւ̕��ׂ��Ⴂ���ߓ���������p�̌������}�����Ă��邪�C�J����p�Ɣ�ׂāu����ɏW���͂��K�v���v�ƌ����B�V�~�����[�^�[��p���������ł́C�����s���ɂ��G���[������ۑ�B���ɗv���鎞�Ԃ̉���������Ă���iLancet 1998; 352: 1191�j�C�O�Ȉオ�s���s�x�̂܂�p���s���f�����b�g�͊ʼn߂ł��Ȃ��Ƒi�����B �@���y�����͊ɘa�P�A�̗��O�ɂ��đ傢�Ɏ^������Ƃ�����ŁC�u���`�̊O�Ȉ�́C��͂��p�Ö@���ɂ߂�̂��ł��d�v�ȐӖ��v�Ǝw�E�B���̋Ɩ��ƕ��s���Ċ����ł���قǁC��p���I������Â��ȒP�ȓ��e�ł͂Ȃ��C�u���z�̊ɘa��Â̂��߂ɂ́C�^�̒S���肪�K�v�v�Ƃ��C�u�F���܂̕a�@�̊O�Ȉ���Ɂv�Ƃ܂Ƃ߂��B �`���w�Ö@�ȁ` �u�Ō�܂œ��a�������v�Ƃ������҂ɂ������� �@���݂̂���Ö@�́C�Տ������ɂ���ăG�r�f���X�̊m�����ꂽ���Ö@�������ƂȂ�C���҂����]���ɂ�����炸���ÏI���ƂȂ邱�Ƃ������B�����̍��X�؉@���́C����Ö@�̑����Ŋ��Ă����o������C���ݓ��{�ŏ��F����Ă��邪�Ö�����ɗp���邱�ƂŁu�Ō�܂Ŏ��Â𑱂���Ƃ����I���������肤��v�ƕ����B ���q�W�I���Ö�̈ێ����Âɉ\�� �@����E�����ǃZ���^�[�s����a�@�́C�����a�@�Ȃ���1975�N�ɉ��w�Ö@�Ȃ�ݒu�����a�@�ł���B���@�̉��w�Ö@�Ȃɂ́C�Z�J���h�I�s�j�I�������߂ė��@���銳�҂������Ƃ����B���X�؉@���́C2009�N�ɍs��ꂽ������w�a�@�ɂ�鎀���ϒ����ł��C�u�Ō�܂ŕa�C�Ɠ����v��I�����銄�����C���҂�81���ɑ��Ĉ�Î҂ł�19���ł��������ƂɐG��C��Î҂Ɗ��҂̎��_���قȂ邱�Ƃ͂��т��ю�������Ă���Ǝw�E�����B �@����ɁC���@���͂��̐��l�ɐG�ꂽ��ŁC���@�Z�J���h�I�s�j�I���O���ɂ�����ő�̎�f���R���C�u���Ò�R���ƌ���ꂽ�B�ɘa�������Ö@�͂Ȃ��̂��v�ƁC���Ö@�����߂Ă̗��@�ł��������Ƃ��Љ�k34���i219�ᒆ75��j�l�B����ɁC���̂���40���i75�ᒆ30��j�����ۂɂ͋~�����ÂƂ��ĕی��K�������w�Ö@���\�ł��������Ƃ���C�u��Î҂́C�W�����Â��Ȃ��Ȃ�ɘa�P�A�̂݁C�ƌ��_���Ă��܂��Ă悢�̂��v�Ƌ^��𓊂��������B �@���@���́C���q�W�I���Ö�̓o��ɂ��u�����߂��Ƃ��C��]���銳�҂ɂ͌p�����Ď��Â���L�p�����G�r�f���X�Ƃ��Đ�������\��������v�Ƃ��C�؏��s�\�咰���҂�Ώۂɍs��ꂽ2���̗Տ������iBRiTE�����CARIES�����j���Љ�B�������ł́C���Ƃ��������Ă����q�W�I���Ö���p�����^���邱�ƂŐ������Ԃ̉�����������\����������Ă���B�܂��C���@�ċz����Ȃōs�����x�����̌����ɂ����Ă����l�̌��ʂ�����ꂽ���Ƃ�����B �@���@���́u���w�Ö@���~�Ŕ[������銳�҂���͂���ł悢�B�������C�����ÂŎ���҂̂͂炢�Ƃ������҂��������̂��v�Ƃ��C�����������҂Ɏ�������L�ׂ�I�����Ƃ��ĕ��q�W�I���Ö�ւ̊��҂��q�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N6��16�� |
| ���҂𑽐E��Ŏx�������n��Â��肪�ۑ�|��13����{�ݑ��w�� |
| �@�ݑ��Â͍ݑ�ł݂Ƃ邱�ƂƂƂ炦��ꂪ���ł��邪�C�ݑ��Âɂ�������Î҂ɂƂ��čݑ��Ấu�ݑ�Ő�����v���x���邱�Ƃł���B�L���s�ŊJ���ꂽ��13����{�ݑ��w��k������Ö@�l��C��i���{�j�E���c��i�������l�́u�w������x���x����ݑ��Áv���e�[�}�ɊJ���ꂽ�B���̒��ŁC�V���|�W�E���u������ᇊ��҂����y�ɕ�炷���߂Ɂv�i��������Ö@�l��C����k�z�[���P�A�N���j�b�N�E���R�G�l���j�ł́C����̐f�f������Ŋ��܂Łu������v���Ƃ�n��Ŏx���邽�߂ɂ́C�Z�݊��ꂽ����ł́u���y�Ȑ����v���C��Î҂��܂߂��ׂĂ̐l�X���x��������n��Â�����\�z����K�v�����w�E���ꂽ�B ���҂̐��������x������̐��� �@����L���X�g���a�@�i���{�j�n���ØA�g�Z���^�[�̎O���q���́C�}�����a�@�ɂ�����މ@�����Ō�t�̖����ɂ��Ď����C���҂��u�ǂ������������v���x������̐��𐮂��Ă������Ƃ��d�v�ł���Ƌ��������B �@���E�n��ł̊Ō�A�g�������E���i �@���ҁE�Ƒ��́u�ƂɋA��v���Ƃɂ��āC����Ŏ����炵���������߂�����Ƃ������҂��������C��Î҂���ɂ��ɂ��Ȃ����Ƃւ̕s����C�Ƒ��̈�Ï��u�����S�����Ƃւ̌˘f���C�މ@����ނ����Ȃ��Ƃ���������߂ƕ���C�܂������̊��҂ł͎������ԋ߂Ɋ�����Ռ��Ɨ��_�������Ă���B���������āC�މ@�x���E�މ@�����͒P�Ȃ�ꏊ�̈ړ��ł͂Ȃ��C�u���̐l���ǂ������������v���x�����邱�Ƃł���B �@���̂��߁C�މ@�����Ō�t�͓��@���҂̑މ@�x���v���Z�X�Ƃ��āC�܂��C�W�҂̋C��������������u���킹��v�ƂƂ��ɁC�މ@�Ɍ������`�[���Ƃ��ė͂��u���킹��v�B����1�Ƃ��āC��Ã\�[�V�������[�J�[�ƂƂ��ɁC�މ@�x���̕K�v�Ȋ��҂��s�b�N�A�b�v���邽�ߕa���Ō�t�Ƃ̕������J���t�@�����X��C�ݑ�E�a���o���̈ӌ���������уP�A���Ȃ����ߖK��Ō�t�C�a���Ō�t�C��t�C�h�{�m�Ƃ̃J���t�@�����X���s���Ă���B���ɁC�ݑ�×{�ւ̈ڍs�Ɍ����Ċ��ҁE�Ƒ��̐S�g�̏�Ԃ��u������v�ƂƂ��ɁC�K�v�Ȉ�ÁE���̐����u������v�B�����āC�@������n��ւƃP�A���u�Ȃ��v�B����ɁC�ݑ�x���̐��������܂ł̗×{��c�����C�ً}���Ɂu������v���Ƃ������ƂȂ�B �@����C�O�����҂̗×{�����x���Ƃ��āC�O���ւ̎�f���C�O�����w�Ö@���Ȃǂɗ×{��c���C�]�����C���Ö@�̕ύX��ɘa��Âւ̈ڍs�ɍۂ��Ă̓^�C�����[�ɂ������C�a��̕ω���\�����K�v�ȃT�|�[�g�����ɂ߂�B�܂��C�×{�ꏊ�E�×{���@�̈ӎu������x�����C�×{���𐮂��������S���Ă���B���������O���ł̓K�Ȏx���ɂ��s�K�v�ȓ��@����������Ƃ����B �@�O�֎��́u���҂��ǂ��������������x����̐������Ă������Ƃ��d�v�ł���B�܂��͉@���E�n��ł̊Ō�̘A�g�̋����E���i��}��C�n��S�̂̍ݑ��Â̎������シ��悤�x���a�@�Ƃ��Ď��g��ł��������v�Əq�ׂ��B �f�f����Ŋ��܂ł��������ƊŌ�t���P�A�� �@��Ö@�l�v�t��ݑ�ɘa�P�A�Z���^�[�ق��҂��i���Ɍ��j�̎s�����q�����́C�ɘa�P�A�F��Ō�t�E�K��Ō�F��Ō�t�̗��ꂩ��ݑ��Âւ̎��g�݂�B���҂͂���Ɛf�f���ꂽ���_����C���������ƊŌ�t���p�[�g�i�[�ƂȂ��čŊ��܂Őf�Ă������Ƃ��d�v�ł���Əq�ׂ��B �K��Ō�Ɨ×{�ʏ����ŊŌ�̘A������}�� �@�s���������^�c����K��Ō�X�e�[�V�����́C2006�N�ɗ×{�ʏ����C������f�C�z�X�s�X��L����K��Ō�z�X�s�X�Ƃ��ĊJ�݂��ꂽ�B�×{�ʏ���쎖�Ƃ́C�K��Ō삾���ł͎��Ԃ�}���p���[�ɐ��������邽�߂ɐ݂���ꂽ���̂ŁC�K��Ō�ƘA�������Ċɘa�P�A����邱�ƂŊŌ�̘A������������Ƃ����B �@�������ɂ��ƁC���҂���]����ꏊ�ň��y�Ɏ����炵���߂������߂ɂ́C����Ɛf�f���ꂽ���_����C����������Ō�t�����҂̃p�[�g�i�[�Ƃ��ĕa�@��t�̐�������₷���`������C���Â̑I����×{�̏���Ƃ��ɍl����ȂǁC�Ŋ��܂Őf�Ă������Ƃ��d�v�ł���B����́C���҂̐�����m���Ă��邩��������Ō�t�����炱���C���̊��҂ɂӂ��킵���ɘa�P�A���l���邱�Ƃ��ł��邩��ł���Ƃ����B �@�������́u�ݑ��Â͈�t�ƊŌ�t���������ăP�A���l���C���E��ƘA�g�C�܂��͒n��ƕa�@���A�g���邱�ƂŁC���ҁE�Ƒ��́w���̂��x��厖�ɍl�����P�A��W�J���邱�Ƃ��ł���B�ݑ��Â͈�w�̎��_�ƊŌ�̎��_�����ւƂȂ��Ďx���Ă���v�Ƌ��������B �K�╞��w���ŃA�h�q�A�����X������(�A�h�q�A�����X�����҂������̕a�C�̏�Ԃ⎡�Â̖ړI�A�g�p�����܂̕���p�Ȃǂ𗝉�������ŁA�ϋɓI�Ɏ��Õ��j�̌���ɎQ�����A���̎��Ö@������Ă�������) �@�Z�R����ǐV���̓�{���q�q���́C���ܖ�ǂ̊ϓ_����ݑ��Âɂ�����K�╞��w���̎��ۂ�B�K�╞��w���ɂ��A�h�q�A�����X�����サ�C�ݑ��Â̎��̈ێ��E���オ���҂ł���Əq�ׂ��B ���ׂĂ̖�ǂ��s���ɂ͉������ׂ����� �@��t�̍ݑ��Âւ̂������́C���҂͂��Ƃ���Î҂ɂ����܂�m���Ă��Ȃ��̂�����ł���B����ǂł́C2000�N����ݑ�҂ւ̖K�╞��w�������{���Ă���B���̗���Ƃ��ẮC�ʉ@����Ȋ��҂�ΏۂɁC�厡�オ�K�╞��w���̕K�v����������C��������ɖK��w�����L�ڂ���B������C��t�͖K��v�揑���쐬�C���ґ�֖K�₵�ĕ���C���ȊǗ��C����p�Ȃǂ̏����W���s���ƂƂ��ɁC���ҁE�Ƒ��ɕ���w�����s���C���P���ׂ��_������Ύ厡��փt�B�[�h�o�b�N����B �@���ۂ̋Ɩ��́C��������邱�ƂŊ��҂̕��S���y�����C����ł��c����ꍇ�́C���̌��������ɂ߁C��̈ꗗ�\�Ɛ��������쐬���C�ɃZ�b�g����ȂǃA�h�q�A�����X���オ��悤��̊Ǘ����s���Ă���B�܂��C�c����m�F���C����̏����ɔ��f����悤�Ɉ�t�Ɉ˗�����B �@����C���ׂĂ̒��ܖ�ǂ��K�╞��w�����s���ɂ͉ۑ�������B�o�������t�̕s���C�ݑ��ÂɊւ���m���s���ɉ����C�����͖���̊Ǘ��̖���K�v���ɂ����ɗp�ӂł��Ȃ����ƁC����Ɋւ���m���s���̖��C����ɗA�t�����͖��ے��܂��ł��Ȃ����Ƃ⑽��ނ̍��J�����[�A�t�Ƃ��̊�ޗނ̍ɂ̖��C�A�t���ނɊւ���m�����Ȃ����ߏ����̖����_���w�E�ł����C�\�������ł��Ȃ����ƂȂǂ����ƂȂ�B �@�������C�K�╞��w���ɂ��C���҂̎���ł̐����ɓK�����Ö@��I���E�p���ł��邱�Ƃ���A�h�q�A�����X�����サ�C���҂̗×{�����̎��̈ێ��E���オ���҂���C���҂ɂƂ��Ẵ����b�g�͑傫���B��{���́u���҂����łȂ���Î҂ɂ��K���t�̖�����m��C���p���Ă��炢�����v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N6��16�� |
|
�u����҂̏I�����̈�Â���уP�A�v�Ɋւ���u����\���v�C�����Ă\ ���{�V�N��w��CQ��A��lj����ʃP�[�X�ɂ������^��ɓ����� |
| �@���{�V�N��w��́u����҂̏I�����̈�Â���уP�A�v�Ɋւ���g����\���h����10�N���o�����N�i2011�N�j�C���w���53��w�p�W��i6��15�`17���C�����s�j�̃V���|�W�E���u����҂̏I�����̈�Â���уP�A�F�w����\���x10���N�ɂ������āv�ʼn����Ă\�����B�V���Ȏ��݂Ƃ���Q��A��lj����C��Ì���Ő�����ʂ̃P�[�X�ɂ������^��ɓ����悤�Ƃ��Ă���B����C���w��̌����T�C�g��ʂ��Ċw�������R�����g���W���C�ŏI�Ă��܂Ƃ߂�Ƃ����B �u�őP�̈�Â���уP�A�v���錠����i��E���i���邽�߂�11�̗����\�� �@���w��ϗ��ψ���ψ����̔ѓ��ߎ��i�}�g��w��w�@�l�ԑ����Ȋw�����ȋ����j�ɂ��ƁC����̉����̈Ӑ}�́C����10�N�Ԃ̎Љ��̕ω���֘A�̈�̃K�C�h���C���̔��\���C������ɑ���������\���Ƃ��邱�Ƃł������B �@�����Ăł́C����\�����o���ړI���C���ׂĂ̐l���L����u�őP�̈�Â���уP�A�v���錠����i��E���i���邱�Ƃƒ�`�B���w���11�̗�������̂悤�ɋL���Ă���B ����1�D�N��ɂ�鍷�ʁi�G�C�W�Y���j�ɔ����� ����2�D�ƕ����d�����Â���уP�A ����3�D�{�l�̖��������� ����4�D�Ƒ��̃P�A���Ώۂ� ����5�D�`�[���ɂ���ÂƃP�A���K�{ ����6�D���̋����K�C�� ����7�D��Ë@�ւ�{�݂ł̌p���I�ȋc�_���K�v ����8�D�s�f�̐i���f������ ����9�D�ɘa��Â���уP�A�̕��y ����10�D��ÁE�������x�̃p���_�C���ϊ��� ����11. ���{�V�N��w��̖��� �@���ꂼ��̗���ɂ́u�_���v��������C�I������Â̎��Ԃɑ����đO��̗���\�����������ݍ����e�����荞�܂ꂽ�B����1�ł́C�u�őP�̈�Â���уP�A�v�������������ŁC��ᑑ��݂��܂ތo�ljh�{��C�ǐ؊J�C�l�H�ċz�푕���̓K���͐T�d�Ɍ��������ׂ��Ƃ��C���Â̍����T���⎡�Â���̓P�ނɂ����y���Ă���B �@�܂��C����6�u���̋����K�C�Ɂv�͍���̉����Ŗ��m�����ꂽ���ځB��ÁE�����E�҂ւ̋��炾���łȂ������ɑ���[�����K�v�ł���C�u�I�����ɂ�����őP�̈�Â���уP�A�v�ɂ��Ĕ��M���Ă������Ƃ́C���w��Љ�ɕ����u�ӔC�v�Ƃ��Ă���B Q��A�͊w��������W�C�����X�V���Ă��� �@�ѓ����ɂ��ƁC2001�N�ɔ��\���ꂽ����\���́u�I�����̒�`�v���}�X�R�~�ł��т��ш��p�����Ȃǘb����Ă��̂́C��̐����Ȃ��Ƃ����������̈ӌ������������Ƃ����B�����ō���̉����ł́C��Ì���Ő������Ï]���ҁC���ҁC�Ƒ��̋^��ɓ��{�V�N��w�����Q��A���lj�����邱�ƂɂȂ����B �@�����́C���̂悤�ȗ���������B �@�Ⴆ�C�������ֈ�Â��ے肷�邱�Ƃ́C���ҌX�̉��l�ς̑��d�Ɩ������Ȃ����Ƃ�������ɂ́C�u�i����2�̎�|�́j�I�����̈�Â�P�A�ł����Ă��C�P�Ɍo���Ȃǂɂ��ƂÂ��Ĝ��ӓI�ɑΉ����邱�Ƃ͋�����Ȃ��C�Ƃ�����Î҂̂���ׂ��p���������̂ł��B�ꍇ�ɂ���ẮC���҂�Ƒ��̐Ȃ�肢�����Ȃ��邽�߂ɑ�ֈ�Â������ꍇ������܂��v�ƉB �@�܂��C�{�l�����m��]��ł���̂ɁC�Ƒ������m��]�܂Ȃ��ꍇ�̑Ή��ɂ��Ắu�Ȃ��a����m�肽���̂��C�Ȃ��m�点�����Ȃ��̂������ꂼ�ꂩ�畷���o���K�v������܂��B�i�����j�a�����m�ɂ�����邲�Ƒ��̕s������菜���C�ŏI�I�ɂ͖{�l�̈ӂɓY����悤�w�͂���ׂ��ł��v�Ɠ����Ă���B �@����́C�����Ăw��̌����T�C�g�Ɍf�ڂ��C�w�������R�����g���W�B���̌��ʂ𗝎���Ɏ���C�ŏI�ł��܂Ƃ߂Č��\����BQ��A�ɂ��ẮC�w�������̎���𐏎���W���ėϗ��ψ���ŋc�_���C���ł����Ƃ��납�甭�\���Ă����\�肾�Ƃ����B �@�V���|�W�E���̍Ō�ɂ͎��^�������s��ꂽ�B��ꂩ��́u�őP�̈�ÂƊ��҂̈ӎv�͈قȂ�B����1�Ɨ���2���������ׂ邾���ł͕�����ɂ����v�C�u�ɘa��ÂɊւ��āC�ɂ݂̗\�h����ꂽ��ǂ����v�C�u��Ï��u�̌���ɂ������@���̖�肪����_�ɐG���ׂ��v�C�u���R�����܂߁C�l�̈ӎv�f�����Â������Ăق����B���_�̌��ǂ������邾���̗���\���ɂȂ�Ȃ��悤�Ɂv�Ȃǂ̈ӌ������X�ɏo���ꂽ�B �@�i��̐A���a�����i���É���w��w��������w����Z���^�[�����j�͂����������ӌ��ɑ��C�u�Ⴆ�C���R���ɂ͗ϗ��̖��łȂ��@�I��肪���݂��C���������X�e�[�g�����g�ł͂����Ȃ��B�w����̊F���܂ɂ͗~���s�����c�闧��\���ɂȂ邩������Ȃ��B���̂��߂ɂ��C�ʐ��̂��錻��̈�Â���^��_�������o���CQ��A��~�ς��C�����X�V���Ă������Ƃ��C�ۑ�̋��L�ɂȂ���̂ł͂Ȃ����v�ƒ�Ă����B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N6��23�� |
| �`�I�����ݑ�P�A�` �K��Ō�t�ƈ�t�Ƃ̘A�g�ɉۑ�|��15����{�ݑ�P�A�w�� |
| �@����̏I����������ʼn߂��������Ɗ肤���҂͑������C�����ɂ͐��X�̉ۑ肪�w�E����Ă���B������w��w�@���N�Ȋw�E�Ō�w��U�ɘa�P�A�Ō�w����̑剀�N�����́C��Ð��E�̒��ł����҂�Ƒ��ɍł��g�߂ȖK��Ō�t���猩���ݑ�×{�̖��_�ɂ��Ē����C���̌��ʂ�����B�����́u���f���ɓ��s���C�n��a�@�̕���ɎQ������ȂLj�t�Ƃ̘A�g���X���[�Y�ɂ��邽�߂̓w�͂��K�v�v�Ǝw�E�����B ��L�ő��ݗ����� �@�剀���́C���҂�Ƒ����]�ލݑ�×{���������邽�߂ɂ́C�Ō�t���c�����Ă���ݑ�×{�̖��_�𖾂炩�ɂ��C���̑Ή�������L���邱�Ƃ��L�v�ł���Ƃ̊ϓ_����C�K��Ō�t���猩���I�������҂̍ݑ�×{�Ɋւ�����_�ƁC��ɂ��Ē������s�����B �@�������Ԃ�2009�N12���`10�N3���B�Ώۂ́C�֓��n����24���ԑΉ��̖K��Ō�X�e�[�V�����ɏ����Ō�t�ŁC�ߋ�1�N�ԂɏI�������҂�3��ȏ�S������25�l�i�j��1�l�C����24�l�j�B�Ō�t�o��10�N�ȏオ24�l�C�K��Ō�o��10�N�ȏオ12�l�C�ߋ�1�N�Ԃ�10���ȏ�ɂ���������l��19�l�ŁC�o���L�x�ȖK��Ō�t�������̂������B �@��s�����̃��r���[����I�������҂̍ݑ�×{�Ɋւ�����_�𒊏o���C�C���^�r���[�K�C�h���쐬�C���\�����ʐڂœ���ꂽ���ʂ͂��C�J�e�S���[�������s�����B �@���̌��ʁC���E��Ƃ̘A�g�Ɋւ�����Ƃ��āC�i1�j�K��Ō�̈˗����x���C���ҁE�Ƒ��Ƃ�����鎞�Ԃ��Z���i2�j��t�Ɗ��ҁE�Ƒ��Ƃ̘b�������ɓ���Ȃ��\�Ȃǂ��w�E���ꂽ�B �@�K��Ō�t�̑�Ƃ��āC�i1�j�n��a�@����Â������ɐϋɓI�ɎQ���i2�j�Q�����Ă����t��a���Ō�t�ɃA�s�[������\�Ȃǂ�������ꂽ�B �@��t�̖��Ƃ��āC�i1�j�ݑ�P�A���T�|�[�g����J�ƈ�ƘA�������Ȃ����Ƃ�����i2�j�I�������҂̊ɘa�P�A�ɊS���Ȃ��Ɗ�����a�@�オ����\�Ȃǂ�����C���̑�Ƃ��āC��t�̎w���m�ɂ��邽�߂ɁC�K��J�n�O�Ɏ��O�w���̎�茈�߂�K�����邱�Ƃ�������ꂽ�B �@�a�@�Ō�t�Ɋւ��Ă��C�i1�j�މ@�w��������ł̐����ɍ����Ă��Ȃ��i2�j�I�����ݑ�P�A�ɊS���Ȃ��Ɗ�����a���Ō�t������\�Ȃǂ̎w�E������C�ݑ�×{��a�@�Ō�t�ɗ������Ă��炤���߂Ɏ���ł̗l�q�����ʂŃt�B�[�h�o�b�N����Ȃǂ�������ꂽ�B �@���҂Ɋւ��ẮC��×p����ɕΌ��������҂��u�ɃR���g���[�����s�\���ɂȂ�_�ɑ��āC��×p����Ɋւ�����͓��ɒ��J�ɍs���Ȃǂ̑�����ꂽ�B �@�ȏ�ɂ��āC�����́u��t�̏I�����ݑ�P�A�ւ̖��S���w�E���鐺�����������C��t��̒����ɂ��ƁC��t�͌����ĊS���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�K��Ō�t�����O�w������茈�߂Ă����悤���ӂ�����C��t�ɑ�����͌����ł͂Ȃ����ʂōs���L�^���c���ȂǁC��L�̍H�v�����邱�Ƃň�t�̋��͂�������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̍l�����������B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N6��23�� |
| ���҂̂��a�͉ߑ�]���@�L�a���͈�ʐl���Ɠ��� |
| �@���҂̂��a�L�a���ɂ��Ă͖�莋����Ă�����̂́C���Ȃ��s���ȕ����������B���X�^�[��w�i�p�j��Alex
J. Mitchell���m��̍��ی����`�[���́C���҂̋C����Q���������������̃��^��͂����{�B�u���҂̂��a�L�a���͂���܂ʼnߑ�]������Ă����\��������v��Lancet
Oncology�i2011; 12: 160-174�j�ɔ��\�����B �������Ԃɂ��e�����邤�a �@����̉�͌��ʂɂ��ƁC���҂̂����C���a���������Ă��銄���͖�6����1�ŁC�C����Q�S�̂��܂߂Ă���3����1�ł���B�������C�����҂��������钆�C���a�������Â̂܂܌�������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��CMitchell���m��́u���a�����łȂ��C�s����Q��K����Q�Ƃ������֘A�C����Q�irelated mood disorders�j�ɂ��œ_�����킹���̌n�I�ȃX�N���[�j���O�v���O�������K�v�ł���v�Ƃ��Ă���B �@���a�͂��҂ɂƂ��ďd��ȍ����ǂ�1�ŁC���ɐ[���ȉe�����y�ڂ��B���a�ɂ��C���Âɑ���R���v���C�A���X���ቺ���C���@���Ԃ���������B�܂��������Ԃɂ��e�����y�ڂ��B����ɂ��Ă̌����͂���܂ő������s���Ă�����̂́C���҂ɂ����邤�a�⑼�̐��_�����̐��m�ȗL�a���͕s���ł������B �@�����œ����m��͍���C���܂��܂ȕa�@���ŁC���҂̂��a�C�K����Q�C�s����Q�Ȃǂ̗L�a�����������邽�߂Ƀ��^��͂����{�����B����┒���a�Ȃǂ̐�厡�Î{�݁i�������҈ȊO�ɂ��C���܂��܂ȕa���̊��҂��܂܂��j�Ŏ��{���ꂽ24�����i�v4,007��j�Ɗɘa�P�A�{�݁i�ӊ���i�s���҂��܂܂��j�Ŏ��{���ꂽ70�����i�v1��71��j�𒊏o�B�����̎����͂�������C�P�����������҂��Ï]���҂��ʒk�ɂ�肤�a�f�f���s�������̍��������ł���B�������C�قƂ�ǂ͊��҂�����Ɛf�f����Ă����5�N�ȓ��̃f�[�^�ł������B ���a�ȊO�̋C����Q�ɂ����� �@��͂̌��ʁC����┒���a�Ȃǂ̐�厡�Î{�݂ōs��ꂽ24�����ł́C���a�C�y�x���a�C�K����Q�C�s����Q�̗L�a���́C���ꂼ��14.3���C9.6���C9.8���C15.5���ł������B�ɘa�P�A�̎{�݂ōs��ꂽ70�����ł́C���ꂼ��14.9���C19.2���C19.4���C10.3���ł������B �@�܂������̏�Q�����邱�Ƃ������C�O�҂̎����ł͌y�x���a���܂߂����a�S�́C������ѓK����Q�C�s����Q���܂߂��C����Q�S�̗̂L�a���͂��ꂼ��24.6���C24.7���C29���B��҂̎����ł͂��ꂼ��20.7���C31.6���C38.2���ł������B �@Mitchell���m�́u�����̐��l�͂��܂荂���Ȃ����C�����Čy���͂ł��Ȃ��B����S�̗̂L�a�����㏸���C�����������܂��Ă��邱�Ƃ���C�傤�a�Ƃ���̍�����͉p����34���l�C�č��ł�200���l�Ɛ��v�����i����L�a���~���a�̗L�a���Ōv�Z�j�v�Ƌ����B�܂��C�u����̌����ł́C�ɘa�P�A�{�݂Ƃ���ȊO�̕a�@�ŁC���a�L�a�����邢�͕s����Q�L�a���ɗL�Ӎ��͔F�߂��Ȃ������B���̂��Ƃ���C���Î{�݂�a���̈Ⴂ�͂���قlje�����Ȃ����Ƃ��������ꂽ�v�ƕt�������Ă���B����ɁC�N���Ȃǂ��a�̊댯���q�����Ă��C�傫�ȕω��͌����Ȃ������B �@�����m��́u��t�����ږʒk�������̍�����������͂������ʁC����a�@�Ȃǂɂ����邤�a�݂̗̂L�a���́C����܂ōl�����Ă����قǍ����Ȃ��C6�l��1�l���x�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B���̐��l�́C�v���C�}���P�A�ɂ����銄���Ɠ����ł���v�Ƃ�����ŁC�u���a�ȊO�̋C����Q���������Ă������܂߂�ƗL�a����30�`40���ł������B���̂��Ƃ����t�́C���a�����Ɍ��炸�s����Q�C�K����Q�Ȃǂ̋C����Q�ɂ��Ă����ӂ��K�v������v�ƌ��_�t���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N7��7�� |
| �u�ݑ�v�Ӌ`�T��@�z�X�s�X�E�ݑ�P�A�� |
| �@�I�����P�A�Ȃǂɂ��čl������{�z�X�s�X�E�ݑ�P�A������̑S�����P�U�A�P�V�̗����A����R���x���V�����Z���^�[�Ō����ŏ��߂ĊJ�Â��ꂽ�B����҂�d�x�Ⴊ�������鏬���̍ݑ����n��łǂ��x���Ă������A�ɘa�P�A�݂̍���A�݂Ƃ�̌���Ȃǂ��܂��܂ȃe�[�}�œ��_�����B �u���ʂ̕|���Ȃ��ˁv�P�W�̖��@�ՏI�������� �@���挧�ł݂Ƃ�x�����s���Ă����ʎВc�@�l�Ȃ��݂̗��̎ēc�v���q��\�������A������������F�l�����g�̘r�ɕ��������Ă݂Ƃ���������Љ���B �@�F�l�R�l�̎q�ǂ������ƈꏏ�ɁA�ċz���~�܂�u�Ԃ܂ʼn߂������̌������A�u�P�W�̖��́w���ʂ̂��|���Ǝv���Ă������ǁA�ՏI�̎��ɂ��ɋ��邱�Ƃ��ł��āA���ʂ͕̂|���Ȃ��ˁx�Ɗ��ł��ꂽ�v�ƐU��Ԃ����B �@���̌o������݂Ƃ�̈Ӌ`�ɂ��Ďēc��\�́u�F�Ƃ������ւ�邱�Ƃ��ł����B�����ė��h�Ɏ��ʂ��Ƃ��l�Ԃ̈Ӗ��A�Ƃ������Ƃ������Ă��ꂽ�B������֖��̃o�g�����Ȃ��ł���v�Ƙb�����B �@�l���K�͂����Ȃ������̗����ł̍ݑ��Âɂ��āA�����Ō��w�̑�p���������́A��t��Ō�t�A�w���p�[�Ȃǂ̃}���p���[�����肸��]����ݑ�����Ȃ�Ȃ��������������B�u���K�͗����ł͕ی������̎Љ��Ր������i�܂��A�ݑ�×{������B�ݑ���x����I�����P�A�̎d�g�݂Â���̂��߂ɂ͌����A�����A�ݏ��E�������K�v�v�Ǝw�E�����B �@�{�Ó��s�Ɗ��q�s�ōݑ��Â���|����h�N�^�[�S���f�Ï��̑א�b��@���́A�ݑ�Ŕ畆�ڐA�̎�p���s���ȂǁA�{�݂Ɠ����̎��Â��s���Ԑ������邱�Ƃ���������B �@�{�Ó��s�ł́A�n��Ƃ̕t���������Ȃ��A�Ǘ����Ă���Q������̍���҂ւ̖K��f�Â�݂Ƃ����������������A�u�������҂ɏ\���ȃP�A���ł���悤�ȍݑ�x�������Ă��������v�ƌ�����B �@�����w���ی��w�Ȃ̌Îӈ��q�u�t�́A�����̍���҂͏Z�݊��ꂽ���ōŊ����}�������Ɩ]�ވ���ŁA���O�̉Ƒ��Ɖ߂��������Ƃ��肤������Љ���B�����ł̊Ō��݂Ƃ�̑̐��̍\�z��Α���̐ݒu�Ȃǂ̉ۑ�������Ȃ���A�u�Ƒ���e���A�ߏ����݂��Ɏx���������������߂���v�Ƙb�����B �䕗���̒�d�u�s���v�@�n��A�g�̃T�|�[�g�� �ЊQ���̍ݑ�P�A �@�m�o�n�@�l��_����ҁE��Q�Ҏx���l�b�g���[�N�̍��c�T�q�������́A�k�Ђ�ً}���ɔ����邽�߂Ɂu�w��E�߁E�E�E�H�E�Z�E��x�Ƃ����������ƕ�炵�Ɏ��_�����Ă��l�b�g���[�N�Â��肪�K�v�v�Ǝw�E�B����Ɏ����A�����A�����̎d�g�݂��s�����Ƃ����B �@�����F��̓c���ב�\�́A�����{��k�Ђ̔�Вn�ň�������Ő������������Ԃ��x�������B�d�����l�H������̃}�C�N�ŃR�~���j�P�[�V��������钇�Ԃ��k�Ђŋ@����Ȃ����A���Ŏ��c����Ă�����������ƂȂǂ�B�u�@��𑗂�Ȃǎx���������A�܂��\���łȂ��v�Ǝx���p���̕K�v����i�����B �@�K��Ō�t�̋���痢����͐l�H�ċz���z����Ȃǂ��g����Óx�̍����ݑ�҂��䕗���̓d���m�ۂɕs��������Ă�����w�E�����B�u�ЊQ�Ɍ�����ꂽ�Ƃ��ł�����ň��S���ĉ߂�����悤�ȃT�|�[�g���s����n����ꏏ�ɍl���Ă����K�v������v�Ƒi�����B �@�t���[�W���[�i���X�g�̎R��I�q����́A�P�A��K�v�Ƃ���l�ւ̊S�����̒��ł����Ɏ������A�k�Ў��̍ݑ�P�A�ɂȂ���Ǝw�E�B�S���̖ӘV�l�z�[�����Љ�Ȃ���u�Ⴊ��������l���A���I�ȃP�A��g�ɕt�����Љ���i�l�ށj�����邱�ƂŁA�����Ƃ����Ƃ��̈��S�ƈ��S�ɂȂ���v�Əq�ׂ��B �@���V�l�ی��{�݁E���̉����k���̈��c������́A�ݑ�×{�҂̓�����̐�����ߗׂƂ̕t�������Ȃǂ̐�������c�����邱�Ƃ��ً}���̑Ή��ɂȂ���Ƙb�����B ����^�C���X 2011�N7��19�� |
| �y�����s�E�ɘa�P�A���Ԓ����z�i�܂ʑމ@���J���t�@�����X�]�Q����ǂ͖�P�� |
| �u�މ@���J���t�@�����X�v�́A���@����ݑ��ڂ̂Ȃ��ɘa�P�A����邽�߂ɏd�v�����A�J���t�@�����X�ɎQ�������ǂ͖�P���Ə��Ȃ��A�ˑR�Ƃ��Ď��g�݂��i��ł��Ȃ����Ԃ����炩�ɂȂ����B �@�ݑ�×{�x���f�Ï��ȂǂƘA�g�����ǂ��Q���ɂƂǂ܂�A�ݑ�Ɏ��g�ޑ����̖�t���A�u�J���t�@�����X�֎Q���ł��Ȃ��v�u���҂Ɋւ���������Ȃ��v�Ȃǂ̔Y�݂�����Ă����B�����s�ɂ�邪��̊ɘa�P�A�̐��̎��Ԓ������ŕ��������B �@�����́A�u�����s��Nj@�\���V�X�e���v�ŁA�u����ɌW�钲�܂̎��{�v�����Ă����ǂR�S�R�Q����ΏۂɎ��{�B�Q�V�O�R������L�����������B �@�����҂ɑ���މ@���J���t�@�����X�ւ̎Q�����т́A�u����v��36���ƁA�S�̂̂킸���P�E�R���ŁA���x�͂�����̂́A���ۂɊJ�ǖ�t���a�@�ɏo�����ĘA�g����邱�Ƃ̓������������ƂȂ����B �@��ǂ��A�g���Ă��鑼�̈�Ë@�ւł́A�u�A�g���Ă���ݑ�×{�x���f�Ï�������v����Q���A�u�K��Ō�X�e�[�V����������v����P���ƁA�A�g��Ë@�ւ������ǂ͏����������B �@���̈�Ë@�ւƂ̘A�g�ŁA��ǃT�C�h������Ɗ����邱�Ƃ́A�u�J���t�@�����X�ɎQ���ł��Ȃ��v���ő��B���̂ق��A���ݑ��Âւ̎Q�悪��������҂Ɋւ���������Ȃ����l��s���ŘA�g�̎��Ԃ����Ȃ�������̍ɊǗ��E���ʁ|�|�Ȃǂ����������B����ŁA��ǎ��g���ݑ�ɘa�P�A�̐��i�ɕK�v�ƍl����̂́A�u�w�K��ɂ��X�L���A�b�v�v�ŁA�m���̌����K�v�Ƃ��Ă����B �@�I�s�I�C�h���܂́A�V���̖�ǂ���舵���Ă������B��舵���̂Ȃ���ǂ́A�u�Y�����҂��Ȃ��Ȃ��i���v���Ȃ��A����Ⳃ����Ȃ��j�v���������߁A���ɂ��Ȃ����l��s�����ʓX�܂֏Љ��a�@���g�p���Ă��Ȃ��|�|�Ȃǂ𗝗R�Ƃ��ċ����Ă���B �@�I�s�I�C�h���܂̎�舵���̂����ǂł̕��ϒ��܌����́A�P�J���Łu�O���v�u�P���ȏ�Q�������v�����ꂼ��Q������A��舵���̐��͂����Ă��A�����т͂قƂ�ǂȂ��Ƃ������ʂ������B���܂Ƃ��ẮA���f�����e�b�v�l�s�p�b�`�i56�E�P���j���l�r�R���`�����i62�E�S���j���I�L�V�R���`�����i72�E�Q���j���I�v�\�����t�i57�E�X���j���I�L�m�[���U�i57�E�V���j�|�|�ȂǂŁA����ȊO�̐��܂̎�舵���͏��Ȃ��A���ɒ��˖�͋ɂ߂ď��Ȃ������B �@���ے��܂̎��{�͑S�̂̂P�������ɂƂǂ܂����B�����{�̗��R�Ƃ��ẮA�u�ݔ����Ȃ��v���������߁A���̂ق��u�Y�����҂����Ȃ��v�Ȃǂ̗��R�������B �@�K�╞��w���́A��R���ōs���Ă������A09�N�x�̔N�ԕ���w�������ł́u�O��v���T���A�u�P��ȏ�T���v���P���������B���̂��Ƃ�����A�K�╞��w���̑̐��͂����Ă��A���ۂɂ̓I�s�I�C�h���܂̕���w�����т͂قƂ�ǂȂ���ǂ��������Ƃ����������B �@���܂����{���Ă����ǂ̕��ϐE�����͂S�E32�l�������B ���� 2011�N7��26�� |
| �u����҂ƉƑ��̉�v������J�� |
| �@���}�h�̍���c���őg�D����c�A�A�u����҂ƉƑ��̉�v��8��4���A������J�Â��A2012�N�x�̗\�Z�T�Z�v���Ȃǂɂ��ċc�_�����B �@��\���b�l�߂鎩���}�̔��ҏG�v���́A����̖`���A�u�����̓M�A�����ւ��鎞�ɗ��Ă���B����܂ł̓��[�M�A�ł���Ă����B����͂���܂ʼn������Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B������{�@���ł��A���҂��������A��������i���c��������A�������Z���^�[�Ȃǂ��a�������B�����������������������A���悢���i�ƍ����̃M�A�ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����͂��̍���c�v�ƈ��A�B �@����ɂ́A�l�X�Ȋ��҉�o�ȁB�����J���Ȃ̂�������i���c��ψ��ŁANPO �@�l�O���[�v�E�l�N�T�X�������̓V��T��́A���҂̐g�̓I�ɂ݂�_�I�Ȓɂ݂̌y���ɂ͈��̎��g�݂��s���Ă������̂́A���҂̌o�ώx���ƏA�J�x���͎��c���ꂽ�̈�ł���Ǝw�E�B�u���̐�ڂ����̐�ځv�ɂȂ�Ȃ��悤�A���z�×{��x�̕��S����z�������ɉ����Čy������ق��A�u���҂̓��������i�쐧�x�v�̊m���Ȃǂ����߂��B �@�����Ȋw�R�c����i�����x������������ψ��ŁA��������̌��҂̉�X�}�C���[��\�̕Жؔ��䎁�́A�����F��K���O�Ȃǂő����̊��҂�����g�����A�����Ă��錻����Љ�A�h���b�O�E���O������v�]�B����ɁA�R����܂̕���p��Q�~�ϐ��x�ɂ��Č��J�Ȃ̌�����Ō��c�_����Ă��邱�Ƃ܂��A�u�~�ό���A���҂��A���i���J�����������Ƃ⎡�Âɓ���������t���i���錠���͎c��B����ɂ��A��Â��ޏk���邱�Ƃ��Ȃ��悤�A�T�d�ɐ��x�v����K�v������v�Ƌ��߂��B �@���̂ق��A�u�V�[�Y����x�b�h�T�C�h�܂ŁA�V�[�����X�Ȃ����̐��̊m���v�A�u���k�x���Z���^�[�̏[���Ȃǂɂ��A���E���k�̐��̏[���v�A�u�������_�a�@��A����������Z���^�[�̐����v�Ȃǂ̗v�]���オ�����B �@����ł́A���J�ȁA�����Ȋw�ȁA�o�ώY�ƏȂ̎O�Ȃ��A2010�N�x�̗\�Z�Ǝ��s��2011�N�x�\�Z������B���J�Ȃ̏ꍇ�A2010�N�x�̂�����\�Z�z316���~�ɑ��A���s�z��314���~�ł���_����Ҏ��͎w�E�B�s���{���̎��Ƃɑ���A���̕⏕�I�Ȑ��i�̗\�Z�ł��邱�Ƃ���A�u�����ł������Ȃ��\�Z���Ȃ����ׂĎ��s���Ȃ��̂��B�����ꐶ�����ɂȂ�A�s���{���������v�Ƃ��A���Ȃ̑Ή��𑣂���ʂ��������B �@���}�h�c�A�A�u����҂ƉƑ��̉�v��8��4���̑���ɂ́A20�l��̍���c���A��30�l�̋c���鏑���o�Ȃ����B���c�A�͖�55�l�̍���c�����琬��B �u���̊��҂̗v�]�́A�X�R�̈�p�v�A��c�� �@����ł́A��������i���c��ł̌������Љ�ꂽ�B �@�����c���ŁA���{��w���̖�c��l���́A�������߂��錻��F�����A�u���҂̗v�]�́A�����A����̐���s���̂ق��A��Õs�M�A��Êi���Ȃǂ̖��Ƃ��Č��݉����Ă��邪�A�\�ʂɏo�Ă���͕̂X�R�̈�p�B������{���I�ɉ������邽�߂ɂ́A���̒�ɒ���ł���l�X�Ȗ����������Ă����K�v������v�Ɛ����B �@���������ɂ́A�܂������I����ɗ�������{�v��𗧂āA���E�Z���I�v������肵�Ă����K�v�����w�E�B���ɏd�v�ۑ�Ƃ��āA�i1)������v�i�����ւ̕a�C�ƌ��N�A����A�\�h�A�����f�f�⎀���ςȂǂ̋���j�A�i2�j��Ò̐��̉��v�i�{�݊����^����n�抮���^�ւ̈ڍs�Ȃǁj�A�i3�j��Ãf�[�^�o�^���x�i����o�^�j�̊m���i���ғo�^����S�����̓o�^���x�ɂ��A���f���炪��̎��Ð��т܂ŁA�S���K�͂œo�^�j��3�_���������B �@�����c��̎O�̐��ψ����́A�\�Z�T�Z�v���̗v�]�ɓ������āA�d�����ׂ����삪�Љ�ꂽ�B ���������ψ��� �@�i1�j����Տ����������x���@�\�̐ݗ��A�i2�j�A�J�f�~�A�n��̎x�������Ƒn��x���@�\�̐ݗ��A�i3�j����o�C�I�o���N�̐ݗ��ƃQ�m���E�G�s�Q�m����͋��_�̐��� ���ɘa�P�A���ψ��� �@�i1�j�f�Ñ̐��ƘA�g�̐��A�i2�j�×{�Ɋւ��鑊�k�x���A�i3�j���猤�C�A�i4�j�n��ɘa�P�A�Ɋւ��鎿�I�ȕ]�� ������������ψ��� �@�i1�j����������Z���^�[�̐ݒu�A�i2�j�������_�a�@�̐ݒu�A�i3�j��������p��܂̊�ƒm���̐��i�@ m3.com�@2011�N8��4�� |
|
�I�������҂Ɂgdignity therapy�h�͗L�� ���̃����_������r�����Ŗ��炩�� |
| �@�}�j�g�o��w�i�J�i�_�j��Harvey Max Chochinov������́u���҂̑������d�������V�������_�Ö@�ł���gdignity
therapy�h�i���Ȃ��̑�Ȃ��̂��Ȑl�ɓ`����v���O�����j�́C�W���I�Ȋɘa�Ö@�⊳�Ғ��S�̗Ö@�iclient-centered
care�j�Ɣ�ׁC�I�������҂�QOL���P�Ƒ����ێ��C����ɉƑ��̕��S�y���̓_�ŗL�ӂɗD��Ă����v�Ƃ̃����_������r�����iRCT�j�̌��ʂ�Lancet
Oncology�i2011; 12: 753-762�j�ɔ��\�����B����̌��ʂ́C���̗Ö@�����ׂĂ̏I�������҂ɕ��L�������ׂ����Ƃ��������Ă���B QOL�Ȃǂ��܂��܂Ȏ�ϓI���ڂŌ��� �@�I�������҂̃P�A�́C�g�̓I���S�y���̖ʂŋߔN�傫���i�������B�������C���҂̏�I�C�Љ�I�C���_�I�j�[�Y�ɉ����邽�߂̉����i�͂قƂ�NJJ������Ă��炸�C�������̂܂܂ł���B �@Chochinov�������Ǝ��ɊJ�������ʉ����_�Ö@�ł���dignity therapy�́C���҂��ł��m���Ă��炢�����C�܂��͖Y��Ȃ��łق����Ǝv�����Ƃɂ��āC�����ɏ������߂���C�l�ɓ`���邱�Ƃɂ�芳�҂̋�ɂ��y�����C�I�����̐l����L���ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B�ȑO�ɍs��ꂽ��T�������ł́C�قڂ��ׂĂ̊��҂ɗL���ł��邱�Ƃ���������Ă����B �@��������͍���C���ۂ�dignity therapy�����҂̐��_�I��ɂ��y�����C�I�����̐l����L���ɂ��邩�ۂ����������邽�߁C���̗Ö@�Ɋւ��鏉�߂Ă�RCT�����{�B�J�i�_�C�č��C�I�[�X�g�����A�̕a�@�܂��͒n��{�݁i�z�X�s�X�܂��͎���j�Ŋɘa�P�A���Ă���18�Έȏ�̏I��������326����Cdignity therapy�i108��j�C���Ғ��S�Ö@�i107��j�C�W���ɘa�P�A�i111��j�̂����ꂩ�Ƀ����_���Ɋ���t�����B�����J�n���ƏI�����ɁC���_�I�L�����C�����C����ԁCQOL�𑪒肷��e�ړx�̃X�R�A���B�܂������I����C���҂̏I�����o���ɂ��Ď��L�������[��p���Ē��������B �@�����̌��ʁCdignity therapy�Q�ł́i1�j���Â͗L���������i2�j�i���Âɂ���ājQOL�����P�����i3�j�������ۂ���Ă��銴�o�����債���i4�j�Ƒ��̎����ւ̌����⑸�d�̎d�����ω������i5�j�Ƒ��ɂ����b��������?�ƕ������҂̊������C����2�Q�����L�ӂɍ��������B �@Dignity therapy�͂܂��C���_�I�L��������̖ʂŊ��Ғ��S�̗Ö@���L�ӂɗD��C�߂��݂Ƃ���Ԃ̌y���Ŋɘa�Ö@���L�ӂɗD��Ă��邱�Ƃ����������B�������C��ɂ̃��x���Ɋւ��Ă͗L�ӂȌQ�ԍ��͔F�߂��Ȃ������B �@��������́udignity therapy�����⎩�E��]�Ƃ����������ȋ�ɂ��y���ł��邩�ۂ��ɂ��Ă͈ˑR�����̗]�n�����邪�C���ȕɂ��I�����o���Ō��ʂ��F�߂�ꂽ���Ƃ���C���̗Ö@���I�������҂�ΏۂɗՏ��Ŏ��{���邱�Ƃ͗L�v�ƍl������v�ƌ��_�t���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N8��11�� |
| ��Ì���ł����[���A�u�����߂��Ă��v�u��҂Ɗ��҂̕Ǖ����v |
| �@�q����זE�@�������炢�́@�Q�ĕ�点�r �@���s�������̗���L���X�g���a�@�B��������̂T�O��j�����S���Ȃ�P�O���O�ɉr������B�������Âł͂Ȃ��A�g�̓I�ȋ�ɂ����A�c��̓��X�������ł��[�����ĉ߂����z�X�s�X�B���݂����ȋC���������[���A�Ő�Ԃ����Ƃ���v�����`����Ă���B �@���a�@���_�z�X�s�X���̔��ؓN�v����i�V�Q�j�́A���a�T�X�N�ɓ��{�łQ�Ԗڂ̃z�X�s�X�a���𗧂��グ�A����܂łQ�T�O�O�l�ȏ�̖����Ŏ���Ă����B�u�����߂��A�Ƃ������Ƃ����o���Đ�����̂́A�m���ɏ��Ƃ͂������ꂽ�ł��B�ł��A�K�������Ƃ��ł���B���͐l�Ԃ̖{�����Ǝv���܂��v�Ɗm�M����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�@�@�~�@�@�~ �@���@�����̒��ŁA���҂������y���݂ɂ��Ă��������̉�b�B �@���u�g�C�O���s�h�͂ǂ��ł������H�v �@���ҁu����ς�j���[���[�N�i�����j�͂����ł��˂��v �@���u�����ڂ��i�̒��j�́H�v �@���ҁu���������t���t�����܂����A�Q�A�R���o�ĂΑ��v�v �@�Ǐ������������҂��ꎞ�މ@����ۂ́A�u���v�B���۔������܂���v�ƌ����āA�u���۔��v�̕��������傫�ȓ������q���h�J���Ɗ��҂̐g�̂ɉ����B���ː����Â��撣�������҂���ɂ́A�u�\����v�悷��B �@����Ƃ��A�H������̒��N�������A�H���̋���i���傤�����j�ŕ����H�ׂ��Ȃ��Ȃ����B�[���ȏ��Ŕ�����́u�Ō`���H�ׂ�����ˁB�g�����炢��������g���g�����Ɠ��邩������Ȃ��ˁv�B������ď����́u�����g���g���Q�ĂȂ��ŁA�g���ɂł����킵�悤������H�v�B�ŕa�ő��ɂ����v�����������u�g��������ł����A�g�����炢�Ȃ甃���ɍs���܂���v�B����ƁA�{���ɂQ��̃g���̎h�g���g���g���ƐH�ׂ�ꂽ�Ƃ����B �@�����ȘA�g�v���[�Ɂu�I�`�v�܂ł��B��҂����҂��v���S���A���l�B���̃z�X�s�X�Ȃ�ł͂̌��i��������Ȃ��B �@�������A����͒P�Ȃ�_�W�����̂��Ƃ�ł͂Ȃ��B�݂���[���v�����S�����邩�炱���A�܂����낪�ʂ������A���[���A�����[���A�ށB�����āu������́v�����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�@�@�~�@�@�~ �@��Ì���ŏ����Ƃ͕s�ސT���A�Ƃ����������邩������Ȃ��B�������v�z�ƁA���c������́A�a�@�Ƃ����ǂ����ْ����̂����Ԃł́A���̏�����߂���Ȃ��܂����肷����ʂ�����A�Ǝw�E����B�u�܂��n�߂ɏ�������ƁA�s�v�c�Ƃ��݂��̌ċz�������Ă���B����̓R�~���j�P�[�V�����̑O�i�K�v�Ƃ����B �@�����Ƃŏk�܂鑊��Ƃ̋����B�������킹�邱�Ƃ́A���܂�e�����Ȃ��ғ��m�����g�������킹��`���[�j���O�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��낤�B�u���̌��p�ő���ɑ��銴�x���オ��ƁA���t�ɕ\���ȏ�̐^�ӂ��`���̂ł͂Ȃ����v�Ɠ��c����͂����B �@������́u��҂Ɗ��҂Ƃ�������̕ǂ�������߂ɂ����͕K�v�v�Ƌ�������B���Â����t�ƁA���Â���銳�҂̊Ԃɂ́A�㉺�W�������₷���B�����u�����Ƃŋ����������Ək�܂�A�M���W�����܂��B�Ŋ��̏ꂾ���炱���A�Γ��̗���̃R�~���j�P�[�V�����͑�v�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�@�@�~�@�@�~ �@�����������⍢��ȋǖʂɗ�������Ă��A�l�͂Ȃ������Ƃ��ł���̂��B �@�u����ڑO�ɂ������ɓI�ȏŏ���Ƃ������Ƃ́A����Ԃ��A����������A�����ō����w������Ƃ����S�\�����ł��Ă���Ƃ������Ƃł��傤�B����͐l�ԂƂ��Ă̐��n�x�ɂ��Ȃ����Ă���̂ł́v�Ɠ��c����B �@�Ŏ�鑤�A�Ŏ���鑤�A���݂��̂炳��������Ƃ������ɒu���A�v������܂���������Ƃ肷��B������́u�w�`�ɂ�������炸���x�Ƃ��A���̎��{���̗͂��A�ő���ɔ��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�B MSNJapan�Y�o�j���[�X�@2011�N8��15�� |
|
������Â��琶�����x�����Â� ��16����{�ɘa��Êw��J�� |
| �@��16���{�ɘa��Êw�7��29�|30���C�b��g�a���i�\�a�c�s�������a�@�j�̂��ƁC�����ۂ�|�p�����̊فi�D�y�s�j���ɂĊJ�Â��ꂽ�B�J�Ãe�[�}�́u���̂���������
���̂����Ȃ� �ɘa�P�A�\�\�a�@����n��ցv�B�܂��܂��������鍂��E�����Љ�̐i�W�̂Ȃ��ŁC��ÑS�̂��Ƃ炦�Ȃ����C�ɘa��Ẩʂ����ׂ��������l����ׂ����܂��܂ȃv���O�������p�ӂ��ꂽ�B QOL��ቺ������_�o��Q���u�ɂ̍������߂����� �@�����⒆���_�o�̒��ړI�ȑ����C������@�\�s�S�ɂ���Đ�����_�o��Q���u�ɂ́C�G�o�h���ŎܔM�ɂ�h���悤�Ȓɂ݁C�d���l�ɂȂnj���Ȓɂ݂�U������B�я��v�]��_�o�ɂⓜ�A�a���_�o�ǁC������ᇂ̐Ґ���_�o�p�ւ̐Z���Ȃǂ���\�I�����C�����q�l�ɂ��������ɂ�������̖����u�ɂł���C���҂�QOL�����ቺ�����邱�Ƃ���L���Ȏ��Ö@���͍�����Ă���B�V���|�W�E���u�_�o��Q���u�ɂ̃��J�j�Y������}�l�W�����g�܂Łv�i����������s���s���a�@�E�y���u�Y���C����ȑ�E��ؕ��j�ł́C�ߔN���炩�ɂȂ��Ă����_�o��Q���u�ɂ̃��J�j�Y����f�f�E���Âɂ��čŐV�̒m�������ꂽ�B �@�Óc�����i����w�@�j�́C�_�o��Q���u�ɂ̃��J�j�Y���ɂ��ĕ����B�_�o����Q�����ƃO���A�זE�̈�C�~�N���O���A������������C�זE�ԏ��`�B�����ł���P2X4��e�̂��ߏ�ɔ����B����ɂ��C�]�R���_�o�h�{���q�ł���BDNF�����o����C�Ɋo�j���[������Cl�|���ݏo���|���v�̔����ቺ�������N�����C�ʏ�}�����̐_�o�`�B�����ł���GABA���������Ƃ��č�p�B���̂悤�ȗ���ŐG�h�����u�ɂ������N�����Ƃ����B �@����Ɏ���́C�_�o��Q���u�ɂ̈ێ��ɏd�v�Ȗ������ʂ����A�X�g���T�C�g�̑��B�Ƀ~�N���O���A�̊��������֘A���Ă��邱�Ƃ��𖾁B����̑n��ɂ�����^�[�Q�b�g�ƂȂ�\�������������B�V���ȑn���i�߂����ŁC����͊����F��V�K��p���������������̗Տ��K�����߂����u�G�R�t�@�[�}�v��B���̈��Ƃ��āCSSRI�Ȃǂ̍R���_�o�����u�ɂ�}������Ƃ̌������ʂ��������B �@�Z�J���F���i����a�@�j�́C�_�o��Q���u�ɂ̐f�f�E�]���C�Ö@�ɂ��ĊT���B���́u�_�o��Q���u�Ɋ��҂͐l����7�����x�v�Ƃ����t�����X�̉u�w�������ʂ���C���{�ɂ����Ă����݊��҂�����\�������������B�Ö@�Ɋւ��ẮC���{�y�C���N���j�b�N�w��{�N7���ɔ��\���C�����쐬�ɂ���������u�_�o��Q���u�ɖÖ@�K�C�h���C���v���Љ�B�{�K�C�h���C���ł́C�_�o��Q���u�ɂ̑��I���ɂ͎O�n�̍R����ƃv���K�o�����i���i�� �����J�J�v�Z���j����������Ă���B���Ɍ��ʂ̍����I�s�I�C�h�͒����I���^�̈��S�����m�ۂ���Ă��Ȃ����߁C�����\�オ�����̊��҂ł͑�O�I���ƂȂ��Ă���B �@����Ɏ��́C�_�o��Q���u�ɂ��]�������q�l��R���Ƃ���Ă������Ƃɂ��Ă��G��C�I�s�I�C�h���L���ȏǗ������Ǝw�E�B���̏�ŁC�ڗp�������C�I�s�I�C�h�ƃv���K�o�����Ƃp����C�p��ȃX�N���[�j���O���s���ȂǁC�ˑ��̗\�h�ւ̏\���Ȕz�������߂��B �@����ߎq���iKKR�D�y��ÃZ���^�[�j�͊ɘa�P�A��̗��ꂩ��C�_�o��Q���u�ɂ̃}�l�W�����g�ɂ��Ĕ����B���́C�_�o��Q���u�ɂ̌����ɂ́C��p�≻�w�Ö@�C����̐Z���C����ɕ��������ȂǑ��ʓI�ȗv�f�����邽�߁C�������C�ɂ݂̕��ʁC�����C���x�Ȃǂ��x�b�h�T�C�h�ŏڍׂɒ��悵�C�o�ߊώ@��ӂ炸�C���E��ł������d�v�������������B����ɖÖ@�ɂ��ẮC���ՂȃI�s�I�C�h�̓��^�E���ʂɌx����炵�C���ɕ⏕��ƕ��p���Ȃ���T�d�ɊǗ����ׂ��Ɛ������B���ɕ⏕��ɂ��Ă�����p�͔������Ȃ����Ƃ���C�e��܂̃����b�g�E�f�����b�g���n�m���C���҂̔w�i�C�a�Ԃɉ��������^��S�����邱�Ƃ��Ăт������B �@��t�̍��쌳�F���i��ʈ�呍����ÃZ���^�[�j�́C�R�����ɂ�閖���_�o��Q�ɂ��āC�\�h�C���ÂƂ��ɗL���ȕ��@���m�����Ă��Ȃ����������B�������܂�1�ł���I�L�T���v���`���Ɋւ��ẮCCa/Mg���^�ɂ���Ė����_�o��Q�̔����p�x�̌��������҂���Ă�����̂́C�������������CONcePT trial�ł́u�咰�����FOLFOX�Ö@�̑t������ቺ������v�Ƃ̒��ԉ�͌��ʂɂ���Ď������~�ƂȂ�C���m�Ȍ��_�͏o�Ă��Ȃ��Əq�ׂ��B�܂����́C�]����Ƃ��ėp�����Ă���NCI-CTCAE��DEB-NTC�̈�v�����Ⴂ���ƁC�����_�o��Q�̔���������P���̕]���ɍ������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��C�]���ɓ������Ă͊��҂̎��o�Ǐ�̏d�v���������B��t�C�Ō�t�C��t�ɂ��J���t�@�����X�T�s���C�V�[�����X�Ȋɘa�P�A�ɓw�߂Ă���ƌ��B �����Љ�������ɏ��邩 �@�p�l���f�B�X�J�b�V�����u������E�����̎���ւ̏����v�i�������k�喼�_�����E�O�����j�ł́C���ꂩ��̎Љ�̕ω��Ɉ�Â��ǂ��Ή����C�]�����Ă������c�_���ꂽ�B �@�ݑ��Â̑������I���݂ł��鍕���v���i��Ö@�l�Вc�G�C��j�́C��������n���P�A�V�X�e�����C��ÁE���E�\�h�E�Z�܂��E�����x���T�[�r�X����ڂȂ������V�X�e���ƕ]���B�������x����24���ԃP�A�̐��ƁC�����a�@�E�L���f�Ï��E�����f�Ï��Ƃ̘A�g�������v�ƂȂ�Əq�ׂ��B����͈�Î҂̌��C�̏�C���E��̒��ԂÂ���̏�C�Z�������N�ɂ��Ċw�ԏ�Ƃ��āu�n���Ë����w�Z�v��ݗ��B�Z���ƈ�Ë@�ւ��o�����I�ɂ�����荇���V���ȃR�~���j�e�B�֊��Ҋ����������B �@���茪�����i������w�@��j�́C�l���\���̕ϗe����݂���Ð���̉ۑ���T���B���͂��ꂩ��̈�Â݂̍���Ƃ��āC�S�l�I�Ȉ�ÁC�������̂��̂��x�����ÁC��������Ŏ��̈�Âւ̓]�������߂��Ă���Ƌ����B����ɁC���҂̎��Ȍ���̏d�v�������܂��Ă��邱�ƂɐG��C���Ƃ̏�����x�����K�v���Ƃ��C��Â̐�ڂ��Ȃ�������S���ƒ��𐄐i���ׂ��ł͂Ȃ����ƒ�Ă����B �@�ғN�v���i����j�́C�s�s���ł̋}���ȍ���Ǝ��S�ґ������������C�ݑ��Â̕��y��B�����̈�t������ʐ���Ƃ��Ĉ���Ă��邱�ƁC��t1�l�ł͍ݑ��Â�S���Ȃ��Ƃ����F�������邱�ƁC�a�@�ƒn����Ȃ��K�ȃR�[�f�B�l�[�^�[�����Ȃ����ƁC���҂��a�@�ˑ��I�ł��邱�ƂȂǁC����̖��_���������B����܂��C���ݐ�t�����s�Ƌ����Ői�߂Ă��钴����Љ��̂܂��Â���v���W�F�N�g�i���v���W�F�N�g�j���Љ�B�ݑ��ÁE�Ō�E���T�[�r�X���_�̊J�݂�J�ƈ�ɑ���on the job�̌��C�v���O�����̊J���Ȃǂ��Љ���B �@�哇�L�ꎁ�i����������Ì����Z���^�[�j��"�a��ɑ��鋤��"�Ƃ����l�ԓI�ȉc�݂Ƃ��Ďn�܂�����ẤC�Z�p�̍��x���C�l���̊m���C�Љ�̋��剻�E���G���ɔ����Z�p�I�ȉc�݁C�Љ�I�c�݂ɕς���Ă������Ǝw�E�B������Љ���}�������C�ݑ��Â��j�ƂȂ�C��ÁE���E�������A�g����"�����C�x����"��Â����߂��Ă���ƁC��ÊE�̕ϊv�𑣂����B �T����w�E�V�� ��2941���@2011�N8��22�� |
| ���m�ő�Ȃ̂́u���҂̊�]��f�����x���邱�Ɓv�ƈ�t |
| �@���҂ƒ��ɑΖʂ��Ă���̍��m���s�Ȃ����Ƃ͈�t�ɂƂ��Ă���s�ł���B�S�����t�����́A��Âȕ\��̗��ŁA���҂̐S�����v������ɂ߂�B �@�ނ炪�S�����Ă���̂́A���҂̎c��̐l�����Ӌ`�[�����̂ɂ��ׂ��A�őP�̎��Â���邱�Ƃ��B �u�a�C��f�����ĕa�l��f��v�\�\����͓������b���ȑ�w���f�����×��O���B���m�ɂ͐l�ԂƂǂ�����������������Ă���B�ɘa�P�A��Â̍őO���𑖂铯��w�̑��H������i���Ȋw�u���@��ᇁE���t���ȁj���A���m�̌��������B �@���@���@�� �@��Ấu���̏�̂����v�łȂ��u���w�v�ł���\�\���̂��Ƃ��ł�������̂��u���m�v�Ƃ����ǖʂł͂Ȃ��ł��傤���B �@���m�Ɂu���������P�[�X�ɂ͂�������Ƃ悢�v�Ƃ����K�C�h���C���͂���܂���B���҂���͂��ꂼ��ʂ̎Љ�����c��ł���ЂƂ�̐l�Ԃł�����A������Y�݂��l�X�ł��B������ʂɑΉ����l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@��͂��t�Ƃ��ẴL�����A�A�x�b�h�T�C�h�ł̎��т����̂������܂��B�Ⴂ��t�͂ǂ����Ă��A�X�g���[�g�ɕ�����`�������Ă��܂��X��������܂��B �@���a�@�ł͍��m�̑S�����厡�オ�A�O�ȕ���ł���`�[����Â̔N���҂��S�����ƂɂȂ��Ă���B���҂��������Ȃ���������𐳊m�ɍ����鍐�m�ɂ́A��͂莸�s����w�o�������ɗ��̂ł��B �@���҂ƈ�t��������Ƃł���ɗ������������߂ɂ́A�^���̍��m�͌����K�v�ł��B��͂�{���̂��Ƃ�����Ȃ��ƁA���Âɋ��͂��Ă��炦�Ȃ��B��Â͊��҂ƈ�t�̋�����Ƃł��B�������u�{���̂��Ƃ����ׂĒm�肽���킯�ł͂Ȃ��v�Ƃ������҂���������܂��B �@���Ȃł͊��҂���Ƃ̈ӎv�a�ʂ��m���Ȃ��̂ɂ��邽�߁A���f���ɖ�f�[�L�����Ē����܂��B�u���ׂĉB�������m���Ăق����v�u����I�ō\��Ȃ��v�u�܂��Ƒ��ɂ��������Ăق����v�ȂǁA���҂���̊�]���Ȃ�ׂ���̓I�ɏ����Ē����A������Q�l�ɏ_��ɑΉ����܂��B�������A���ꂪ�{�S�Ƃ͌���Ȃ��̂ŁA�T��Ȃ���̑Ή����K�v�ł��B �@�K�ȍ��m���K�v�Ȃ̂͂������ł����A���̈���ō��m��������O�ƂȂ������Ƃɂ����_�������܂��B����͖�������̊��҂���Ɂu���v�ł��v�Ƃ������t�����Ȃ��Ȃ������ƁB �@���͎Ⴂ��t�ɂ悭������ł��B���Ƃ��]�����Z�����҂����Ă��A�u���v�v�Ɠ`���邱�Ƃ��K�v���ƁB�������]��f�����Ă��܂��킯�ɂ͂����Ȃ��B�����Ȃ�ꍇ�ɂ����Ă��A��Ɋ�]�������Ē����B �@���Ƃ����ʂ��������������Ƃ��Ă��A�u���v�v�Ƃ������t�Ŋ��҂���̕s���������Ă�����^�t�����Ȃ���ΗLj�ł͂Ȃ��B���҂���̊�]��f���Ă��܂��悤�ȗ]�����m�͌����čs�Ȃ��ׂ��ł͂Ȃ��B �@������Ƒ��ɂ͗\�z�����]�����܂ߌ����I�ȍ��m�����܂����A���҂���̊�]���x���邽�߂ɂ́A�����^�������`�����邱�Ƃ��ŗǂƂ͌���Ȃ��Ǝv���܂��B�X�L���V�b�v����ŁA���҂���̌����ɐG��āA���t�ł͓`���Ȃ��V�O�i����b�Z�[�W�����`�����邱�Ƃ�����܂��B �@���҂���ɂƂ��č��m�͂Ȃ��Ȃ������A����͈�t�ɂƂ��Ă������������ł��B�����炱���A��t�͊��҂���̍Ŋ��̏u�Ԃ܂ŁA�S�g�̒ɂ݂������������҂ł��肽���Ǝv���܂��B NEWS�|�X�g�Z�u���@2011�N8��25�� |
|
�`�i�s�x����҂̏I������Á` �ĂƃJ�i�_�Ńp�^�[���قȂ� |
| �@�č����������iNCI�j�ی��Ȋw�E�o�ϊw�����Joan L. Warren���m��́u�č��̐i�s���x����̍���҂ł́C�J�i�_�E�I���^���I�B�̍���҂Ɣ�ׂĕa�@��~�}�f�Î��̎�f�͏��Ȃ����̂́C���w�Ö@���Ă��銄���͍����v�Ƃ��錤�����ʂ�Journal
of the National Cancer Institute�i2011; 103: 853-862�j�ɔ��\�����B �قȂ��Õی��V�X�e�� �@�č����J�i�_������҂�ΏۂƂ�����I��Õی����x����������Ă��邪�C�I������Â̕⏞�͈͈͂قȂ�B�č��ł͈��̊���������҂ɑ��Ă̓��f�B�P�A���z�X�s�X�P�A���J�o�[����B����C�J�i�_�ōł��l���̑����I���^���I�B�ł́C�č��̃z�X�s�X�ɑ�������v���O�����͂Ȃ����C�}�����̓��@�{�݂�O���C�ݑ��Âɂ��ɘa�P�A����Ă���B �@Warren���m��́C�č��̒n�悪��o�^�ł���SEER�iSurveillance�CEpidemiology and End Results�j�v���O�����ƃ��f�B�P�A�̃f�[�^�C�I���^���I�B�̂���o�^�f�[�^��p���ė����̏I������Â��r�����B �@1999�`2003�N�ɔזE�x����iNSCLC�j�Ŏ��S����65�Έȏ�̊��҂𒊏o���C���S�O5�J���Ԃ̕ی������f�[�^�́B���w�Ö@��~�}��Î��̎�f���C���@�C�f�f���玀�S�܂�6�J�������̒Z�����҂ƁC��6�J���ȏ�̒������҂̎x���Ö@���Ɋւ���f�[�^�����W�����B �@�����Ƃ��I������ÃT�[�r�X�̗��p���͍����C���S�O1�J���Ԃ̗��p���͓ˏo���Ă����B�I���^���I�B�̍���҂̓��@���Ƌ~�}�f�Î��̗��p���́C�č��̍���҂ɔ�ׂėL�ӂɍ��������B �J�i�_�ł͔������@�����S �@�I���^���I�B�ł́C�命���̒Z�����҂�����ōŊ����}�������Ɗ�]���Ă������C�ݑ����]����Z�����҂̂����C�@�����S����48.5���ƕč���20.4����2�{�ȏ㍂���Ƃ������ʂ������B �@���S�O��5�J���Ԃɉ��w�Ö@���Ă����č��̍���҂̊����́C�I���^���I�B�̍���҂ɔ�ׂėL�ӂɍ��������B �@�����O���[�v�́C���̒m���͕č��ł͈�t�͂��ϋɓI�Ȏ��Â��s���C���҂͂��W���I�Ȏ��Â��邱�Ƃ������Ƃ�������̌����𗠕t������̂��Ǝw�E���Ă���B �@�č��̍���҂ɂ̓z�X�s�X�T�[�r�X�𗘗p����Ƃ����I���������邪�C�I���^���I�B�̍���҂ɂ͂��ꂪ�Ȃ��BWarren���m��́u�I���^���I�B�ł̓z�X�s�X�T�[�r�X���Ȃ����Ƃ��C���@����~�}�f�Î��̎�f���Ɖ@�����S���̍����ɂȂ����Ă���\��������v�Ǝw�E���Ă���B �@����Ɂu�����̒m���́C��Ð������Ď҂�א��҂ɑ��ďI������Â̌�������ƂƂ��ɁC��ÃT�[�r�X��v���O�����݂̍���ɕϊv�𑣂����������ƂȂ邩������Ȃ��v�ƌ��_�t���Ă���B �ӎv����̎����オ���ʉۑ� �@�_�[�g�}�X��Ð���E�Տ��f�Ì������i�ăj���[�n���v�V���[�B���o�m���j��David Goodman���m�́C�����̕t���_�]�i2011; 103: 840-841�j�Łu�I������Â͕č��ƃJ�i�_�E�I���^���I�B�Ƃ̊Ԃ̈Ⴂ�����łȂ��C�č������邢�̓J�i�_�����ł��n��ɂ���ĈقȂ�v�Ɛ����B���̏�ŁC�u�d�v�Ȃ̂͊��҂����ꂼ��Ɍ����������l�Ȉ�Â���]���Ă������ŁC�����������͖����ꂪ�����Ƃ������Ƃ��B�Љ�S�ʂɂ����镽�ϓI�Ȋ��҂̊�]���C�X�̊��҂̊�]�ƃj�[�Y�����������̂��ƌ��ߕt���Ă��܂��ƁC�I������Â̎������コ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�v�ƃR�����g���Ă���B �@�����m�́u�ł��]�܂����`�̏I������ÂƂ́C���҂��ӎv����v���Z�X�ɎQ���ł���P�A���v�Ǝw�E�B�u��݂����Ƀz�X�s�X�P�A��ɘa�P�A�̗��p�������߂�悤�ȃV�X�e�����v��i�߂邱�Ƃ�������ł͂Ȃ��B�ϋɓI�Ȏ����I�P�A��x���Ö@�C�ɘa�P�A�Ȃnj��s�̃P�A�����҂��ǂ̂悤�Ɋ����Ă��邩�ɂ��ė�����[�߂�ƂƂ��ɁC���҂��\���Ȑ���������őI���ł���悤�ɁC�ӎv����̎������コ���邱�Ƃ��̗v�ł���v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N8��25�� |
|
�����g�����h��T�� �����w�@���E��A�g�ƍ��ӌ`���̎d�g�݂� |
| �@������Љ�̓������ڑO�ɔ����Ă���킪���ł́C����҂��߂����Ă��܂��܂Ȗ��ɒ��ʂ��Ă���C���}�ɑ��߂��Ă���B���n�r���e�[�V�����i�ȉ����n�r���j�̑Ή���މ@�܂ł̓���t���邱�ƁC�����Ċ�]����I�������}�������邽�߂̍��ӌ`���ȂǁC��Ï]���҂���Ƃ͂��ǂ���@���m�����ׂ��C����C���҂ւ̑Ή��ƌ����ɒǂ��Ă���B����́C����҂̖��ɏœ_�Ă��B�Ώ��@�̊m���╁�y���}����隋����Q�̃��n�r���Ɋւ���A�g�ƏI�����̑މ@�O�A�g�C���҂̈ӎv�\��������Ȃ����ۂ̍��ӌ`���ɂ��āC3�l�̐��Ƃɕ������B Transdisciplinaly Team Approach/������Q���n�r���ɂ������t�̖��� �� ���v �� �@����҂̔x���̑����͌뚋�̊֗^����������C������Q�ւ̑}����Ă���B����ȑ�w���n�r���e�[�V������w�̒����v�����́C������Q�̃��n�r���ɂ͈�t��Ō�t�C���w�Ö@�m�iPT�j�C��ƗÖ@�m�iOT�j�C���꒮�o�m�iST�j�Ȃǂ��܂��܂ȐE�킪�_�����z���ĘA�g����Transdisciplinaly Team Approach�iTTA�j���s���Ƒi����B��t�⎕�Ȉ�t��TTA�ł̂܂Ƃߖ��ɂȂ邩�C���[�_�[�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ă����̃X�^�b�t�̋Ɩ���K�ɕ]�����邱�Ƃ����߂���Ƃ��Ă���B �H�ׂ�s�ׂœ����閞���� �@������Q�̃��n�r���ɂ��ẮC����������w���ւ̋���@����Ȃ����߂ɁC�������̕������������Ȃ��B�Ⴆ�Ώd�x�̚�����Q���҂Ɉ�ᑂ��{�s������́C���n�r���ɐϋɓI�ł͂Ȃ���t�����Ȃ��Ȃ��Ƃ����B�������́u�h�{�����N���A�ł��Ă��C���n�r���ɂ���ĉ�����H�ׂ���悤�ɂȂ邩������Ȃ����C�����ł��H�ׂ�s�ׂ����������邱�Ƃ����҂̖������ɉe������͂��v�Ɛ����B �@������Q�̃��n�r���ł́C��t��Ō�t�ȊO�ɂ������̐��E�킪����I�ɂ�������Ă���B�������C�P�Ȃ錩����������𖧂ɍs���݂̂ł͕s�\���ŁC�������́u���E��Ԃő���Ȃ����Â�⊮������TTA���d�v�ɂȂ�v�Ƙb���B����ɁCTTA�̐��������Ƃ��āi1�j���ÖڕW�m�ɐݒ肷��i2�j�@�\�̋A���\�����\�ł���i3�j�e�\�����̖��������肳��đ��݂ɑ��d�������i4�j�K�i�ȃ��[�_�[������i5�j�m���ƋZ�\����̃V�X�e��������?���Ƃ�������B �@���@���҂̍ݑ����z�肵�ď�̏�ŕ����P���́C�ǂ̐E�킪�s���ׂ����Ƃ����^��Ɠ��l�ɁC������Q���Âɂ����E�����s���Ăȕ����͕K������B�ǂ̐E�킪�������邩�́C�ɉ����ă`�[�����Ō������邱�Ƃ��]�܂����B�������́CTTA�Ń��n�r��������ł���u���҂̏���ɉ������ŗǂ̎��Â��ł��C�`�[���\�����̔\�͂����サ������v�Ɛ�������B �@TTA�̗L�p���́C���{�ېH�E�������n�r���e�[�V�����w����{���������Ŏ����Ă���B������Q���F�߂���]���Ǐ�Q���҂�TTA�ɂ��ېH�@�\�Ö@�ʼn������124��i����Q�j�Ɣ����Q27���ΏۂɁC�ېH�����@�\�̕ω��������B �@����Q�Ōp�����Ē����ɎQ���ł���69���Տ��I�d�Ǔx���ނŌ���ƁC�����2.86�}1.13����ŏI��ɂ�4.62�}1.63�ւƗL�ӂɉ��P���Ă����B����C�����Q�͏���2.52�}1.29�C3�J����̕]���ł�2.81�}1.44�ƗL�ӂȕω��͂Ȃ������B�ېH���x���͉���Q������2.54�}1.41�C�ŏI��6.07�}2.42�ŗL�ӂɉ��P�����̂ɑ��C�����Q�͂��ꂼ��1.38�}0.86�C2.52�}2.27�ƗL�Ӎ��͔F�߂�ꂸ�CTTA�ɂ�����̗L���������炩�ƂȂ����B �@����w�ōs���Ă��郊�n�r�����҂ւ̋�̓I�ȉ����Ƃ��ẮC�������e�̕]���ɂ͒S�������ː��Z�t�����łȂ��CST��Ō�t�Ȃǂ�������Ă���B�������́C�w������̍s���͂��Ă���ST�̖����ɂ��āu��{�I�ɂ͚����@�\�̕]�����s������C�������ɂ����Ȃ��čׂ����w�����o�����肷�ׂ��v�ƍl���Ă���B�����P�����Ō�t��PT�COT�炪�⊮�������Ȃ�����H����BTTA�̍œK�Ȏ��{�̂��߂ɏd�v�ȃJ���t�@�����X��~�[�e�B���O��K�X�J�Â��Ă���B �v�Ɉʒu�����t�ɕK�v�Ȕ\�� �@���n�r���̂��߂ɂ��܂��܂ȐE�킪�Z������`�[���̒��ŁC��t�͂ǂ̂悤�Ȗ������ʂ����ׂ����B�������́u���ׂĂ���t�����炱�Ȃ��͓̂�����C�������s������C�X�^�b�t�Ɏw�����o�����肷��Ȃǃ��[�_�[�Ƃ��Ă̖������ʂ������ƂɂȂ�v�Ɛ�������B����ɁC�uTTA�ɂ�������t�⎕�Ȉ�t�͒P�ɑ��݂��邾���ł͈Ӗ����Ȃ��B�@�\�̋A���𐳊m�ɗ\���ł��C���Âɑ��閾�m�ȐӔC��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��t��������B �@������Q�̃��n�r������肴������n�߂Ă���C��������TTA�̏d�v���������Ă������C�X�^�b�t�̗�����̂͊ȒP�ł͂Ȃ������Ƃ����B�]���ɂȂ����@�_��p���邱�Ƃɑ���X�^�b�t�̔����͂�ނ����Ȃ����C�uTTA�����܂������Ȃ��v����1�ɂ́C��t�̎p��������v�Ǝw�E����B�������́u�w��t�Ƃ��̑��吨�x�Ƃ����ƑP�I�ȑԓx��ς��Ȃ���C�A�g�͂��܂������Ȃ��B��肪����Α����ɉ��P�_���w�E���邱�Ƃ͏d�v�����C�X�^�b�t�̍s�ׂ�ے肷�邾���łȂ��C������̏̎^���d�v�ł��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƍ����}�l�W�����g�ƃR�~���j�P�[�V�����\�͂����߂���Ƃ����B �@����C�������n�r���̐��オ���Ȃ��{�݂Ŕ��Ȃǂ̗���Ƃ���TTA�ɉ���炴������Ȃ���t�⎕�Ȉ�ɂ��ẮC�u�K���������[�_�[�Ƃ��Ă̗����S���K�v�͂Ȃ��v�Ƙb���B���̏ꍇ�́C�u�X�^�b�t�̈ӌ��Ɏ����X���Ă���w����^����Ƃ����X�^���X�ł������낤�v�Ƃ̌����������B�������C�u��t�̓X�^�b�t�Ɏ��Â�C����ɂ��Ă��C�悭������Ȃ�����ƚ����@�\�̕]�����K�ɂł��Ȃ��悤�ł́C�`�[���̓S�[�������������˂Ȃ��v�ƒ��ӂ𑣂��Ă���B �@�������ɂ��ƁC���n�r�����\���ɋ��炷���w���E��ȑ�w�́C����30�Z�قǂ����Ȃ��B������Љ�ڑO�ɔ��鍡�C������Q���͂��ߍ���҂ɓK�ȃ��n�r�����s�����t�̎��v���}���ɍ��܂��Ă���B���{�ېH�E�������n�r���e�[�V�����w�����{���n�r���e�[�V�����w��C�S�������n�r���e�[�V�����a���A�����c��ł̌��C�C�u���ȂǁC�w�Z�ȊO�ł��w�K�ł����݂͐����Ă���C���@��A�Ȉ����Ȉ�Ȃǂ̎Q���҂������Ă���B�������́u���n�r���Ȃ̈�t�̎�����́C���ȂƔ�ׂĂ������B�w�ׂ�@��͂�������̂ŁC��]�҂͂ł��邾���Q�����Ăق����v�ƌĂт����Ă���B ���z�̊Ŏ��́g�I�[�_�[���[�h�h�̔��z�� �ɘa�P�A�̎��Ⴉ��l���� �R�� ���q �� �@�ݑ��a�@�ȂNJŎ��̏ꏊ�͂��܂��܂��邪�C�킪���ł͈�ʓI�ȊŎ�肪���i����Ă��������ۂ߂Ȃ��B���V����w�Y���a�@����ɘa�P�A�Z���^�[�̎R�����q�Ō�t���́u���z�̊Ŏ��̓I�[�_�[���[�h�I�Ȕ��z�ōs���C����������ɂ͌o�ϓI�ȕ]���ƒn����̎��܂Ƃ߂��s���v�Ǝw�E����B�ɘa�P�A�̎��Ⴉ��C������Љ�ɔ������މ@�O�A�g�̃q���g��T�����B �ݑ�Ŏ��u�K�������ŗǂłȂ��v �@�R���t������N�܂ŋΖ����Ă�������w���V����@�ł́C�މ@�x���`�[���ƈ�ÃT�[�r�X�x���Z���^�[�C���ÃZ���^�[���X�N������g�݁C����҂₪�҂Ȃǂ̑މ@�x�����s���Ă���B�މ@�x���`�[���͌�1��a������f���C�S���X�^�b�t����މ@�����̑��k������C���ɂ͒��ڎx�����s�����肵�Ă���B����̓w�͂����ł͑Ή��ł��Ȃ��ɂ���C�@���̈�ØA�g�ψ���ʼn��P���@�Ȃǂ����B �@�a����f���̑��k������2009�N4���`10�N7����474������C����87�����Ǐ�̈�������s����Ȃǂ̗��R��1��̑��k��x���ł͉������Ȃ������B���@�ł͊��҂����@����ۂɁC�މ@�������������X�N���[�j���O���s���C�މ@�x���̌v���g�ݗ��ĂĂ���B2010�N2�`10���ɃX�N���[�j���O����1��966��ł͖�95���̊��҂��x����K�v�Ƃ����C��3���͕a����f�ÉȂł̑Ή��őމ@���C�`�[���̒��ڎx�����K�v�������̂�2�����x�������B �@���t�����`�[���ł̑މ@�x�����s���P�[�X�̑唼�͏I�����̊��҂ŁC�������̑��d���d������B���҂��a��𐳂����������C���g�ʼn߂��������l�����߂邱�Ƃ��ł���悤�C�ł��邾����������̏����s���Ă���B�܂��C�Ƒ��ɂ����l�ɓ��������C���҂ƉƑ�������̉߂�������b�������@�������悤���߂Ă���B���҂̑މ@�ɍۂ���Ɩ��A�g���n�߂�O�ɂ͊��҂�Ƒ����`���މ@��̉߂������Ƃ��̗��R���m�F���C�ݑ�P�A�ڍs����S�������Ë@�ւƏ��V�����Ƃ̘A�g�͌p������邱�Ƃ��`���C���҂�������s������菜���悤�ɂ��Ă���B �@�Ŏ��ɂ��āC���҂ƉƑ��̈ӌ����قȂ邱�Ƃ���������B���t���́u�ǂ����I�Ԃ��ƈӌ����킹��̂ł͂Ȃ��C�Ƒ������҂̎������d����C�����ɂȂ��悤����������v�Ƙb���B�����ē���ꂽ���҂ƉƑ��̊�]���@���̒S����ɓ`���Ęb�����킹�C���j����ւƓ����B�ݑ�ł̊Ŏ��͍���Ƃ��Đ������ꂽ���C���t���́u�K�������ݑ�ł̊Ŏ�肪�ŗǂ̑I�����ɂȂ�Ȃ����Ƃ�����v�ƍl���C�ݑ�肫�̐����͍s���Ă��Ȃ��B �@�ݑ�P�A�Ȃǂ��s����Ë@�ւƘA�g����a�@�̗���Ƃ��ẮC�u�A�g��̐��������Ɓg�S�[���h�̋��L���~�����v�Ƒi����B���ɍݑ�×{�x���f�Ï��̊Ŕ��f���Ă��Ă��C�������҂�����Ȃ��炷���ɕa�@�֓����Ԃ��{�݂����Ȃ��Ȃ��B �@�킪���̍ݑ�P�A�̌���ł́C�l�ނ̎����ɂ�炴������Ȃ����ʂ�����C�l�̈ٓ��Ŏ{�݂̗͗ʂ��傫�����E���ꂽ��C���҂̋��Z�悪2����Ì��O�ŏ��߂ĘA�g����{�݂��������肷��P�[�X������B���t���́u�A�g��̐��m�ȏ�W��Ă��Ȃ����ߎ{�݂܂��͒S���Ҍl�����ׂ邵���Ȃ��C����ł͂��܂�ɂ�������I�v�ƒQ���B �@���҂̑މ@�ɂ���Đf�ÁE�Ǘ��̃o�g���𑼎{�݂ɓn�����ƂɂȂ邪�C���҂̖]�݂͉��X�ɂ��ĕω�������̂ł���C�r���Ŋ�]���ς�邱�Ƃ�����B�u�o�g����n������Î҂ɂ͊��҂̊�]�͕ς����̂Ƃ����O��ŃS�[�����l���Ă����Ȃ��ƁC�S�[���̋��L�ɂ͌��ѕt���Ȃ��v�ƘA�g������i����B �@�ʂ̖��Ƃ��ẮC�Ƃ��炵�̏ꍇ�ɕa��Ǘ�����x���̐����m�F���邪�C�Ƒ������������C���_�����ǂ��Ă����肵���ꍇ�Ɉ�t��Ō�t�C�P�A�}�l�W���[�Ȃǂ��O���[�v�őΉ�����ݑ��Î{�݂̕�������ăT�[�r�X�̒��ł��邱�Ƃ���C�Ƒ��̎����I���S�����Ȃ��Ƃ����B���ҁE�Ƒ��ƒS����̈ӌ�����������P�[�X�����Ȃ��Ȃ��C�x���`�[���ɂ�鏕����x�����K�v�ƂȂ��Ă���B �I�[�_�[���[�h�I�ȃA�v���[�`�� �@���ꂼ��̊��ҁE�Ƒ��̃j�[�Y�ɉ������x���͌������Ȃ��B�a�@�Ɛf�Ï��ŗp����ݑ�p�̈�Ë@��i���j���قȂ�ꍇ�́C��������f�Ï��Ɉڂ��C�����Ŋ��̎�舵�����w��������ōݑ�Ɉڍs�����邱�Ƃ������B���҂�2����Ì��O�Ő�������Ȃ�C�o�b�N�x�b�h�̂��߂ɖK��f�Â��\�ȗL���f�Ï��Ɉ˗�����B��]�̊Ŏ�葜�͓����ł��C�Ŋ��ɂ��ǂ蒅���܂ł̓��̂�͐l�ɂ���đ傫���قȂ邱�Ƃ���C�R���t���́u�^�[�~�i���������I�[�_�[���[�h�I�ȃA�v���[�`�����߂���v�ƕ��͂���B �@�ݑ�ڍs�ɔ����A�g�͊ɘa�P�A�����łȂ��C����҈�Âł������̖����͂�ށB���t���́C�A�g�𐬌������邽�߂ɒS���ғ��m�̈ӎv�a�ʂ����ނ̂��Ƃ�ŏI��点���C�ł��邾���Ζʂ��d�b�ȂǂŒ��ژb���悤�ɂ��Ă���B�܂��u���҂�Ƒ��̎v���͏�ɕω�����Ƃ����O��Ŏ����X���C�A�g����ɐq�˂������Ƃ�����Η����ɕ����v���ƂŁC�s���̎��Ԃ𖢑R�ɖh���ł���Ƃ����B �@�^�[�~�i�����ɂ��銳�҂̍ݑ�ڍs�ɂ͏[�������x���̐����������Ȃ����C���������Ɩ��ɑ���]���͍����Ȃ��B���t���́u�A�g�Ɩ��ɔ�₷���Ԃ͒����C�Ō�T�}���[�ɐf�Õ�V�͕t���Ȃ��B�l�C���ł͂��܂ł��P�v�I�Ȏd�g�݂͂ł����C�o�ϓI�ȗ��t����K�v�Ƃ��Ă���v�Ƒi����B����ɁC�n��̘A�g���ׂ�����̏��ɂ͂��������C�u�����I�ɕK�v�ȏ������L����ɂ̓V�X�e�������K�v�v�Ƙb���B �����F�m�NJ��҂ւ�AHN�C��t9�����u����v ���c�^�̓��{�炵���I������Â� ��c �O�q �� �@�F�m�ǖ����Ōo���ێ悪����ƂȂ������҂ւ̐l�H�I�Ȑ����E�h�{�⋋�iArtificial Hydration and Nutrition�GAHN�j�����錈�f�ɂ��āC��t�����9��������Ɗ����Ă��邱�Ƃ��C���{�V�N��w��̒����ŕ��������B������S������������w��w�@�l���Љ�n�����ȃO���[�o��COE�u�����w�̓W�J�Ƒg�D���v���C�������̉�c�O�q���́C�p�Ď��̎������d�^�ł͂Ȃ��C���Ԃ������č��ӌ`���𐬂����{�炵���I������Â��K�v�Ǝw�E���Ă���B �u�K���Ȑl���̏I�����v�Ƃ����l�� �@��������2010�N�x�����J���ȘV�l�ی����N���i�����Ƃ̈�Ƃ��Ď��{�B��c���́u�w�����͉����ׂ����́x�ƍl����݂̂ł́C���҂͖{���ɖ]�ލŊ����}�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�ƍs���߂��������[�u�ɋ^��𓊂�������B�܂��C�������̕��������u�w������x�C�w�����Ȃ��x�̓_�ł͂Ȃ��C���Ƃ��������K���Ȑl���̏I�����ƂƂ炦�ċc�_���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƒi����B �@�����Ώۂ͓��{�V�N��w��̈�t���4,506�l�ŁC��N10�`11���ɗX���ɂ�閳�L���̎��L�����⎆�Ŏ��{���C�L����1,554�l�i����34.5���j�ł������B�҂̂����j����84���ŕ��ϔN���53.8�C���ϗՏ��o���N����27.2�N�B���Ȃ͑������Ɉ�ʓ��ȁC�V�N�ȁC�z����ȁC�_�o���ȁC�����f�ÉȂł������B�傽�錻�݂̋Ζ���͈�ʕa�@32���C��w�a�@18���C�f�Ï�17���C�×{�a��10���C�V�l�ی��{��6���������B �@�����̔F�m�NJ��҂Ƃ̂��������́C45��������I�ɂ���C36�����������Ƃ�������Ɠ������BAHN�����̈ӎv����ɂ���������o����68��������Ƃ����B���̌o���҂ɁC�ӎv����ɂǂ̒��x���������������q�˂��Ƃ���C�u���ɑ傫���v16���C�u������x�v46���C�u�����������v27���ŁC89�����Ȃ�炩�̓���������Ă��邱�Ƃ����������B �@����Ɗ����闝�R�i�����j�ɂ��ẮC�u�{�l�ӎv���s���Ȃ��Ɓv��73���ƍł����������B�����āC�o���ێ�̌p��������������̂́u�x���⒂���̊댯�����邽�߁v�Ƃ����̂�61���C�u�Ƒ��̈ӎv���s����ł���v��56���������B�܂��CAHN�������T���邱�Ƃɂ���51�����C�s�����Ƃ�33�����u�ϗ��I�ɖ�肪����v�Ɗ����C45�����u���f���������Ȃ��v���Ƃ��������B�����́uAHN�����ɍۂ��ẮC��͂荢��ȏ�ʂɒ��ʂ��Ă���Ƃ̗����Ȏv�����\��Ă���̂ł͂Ȃ����B������f�𔗂��Ă���Ƃ����̂��������낤�v�Ƃ̌����������C���f�ӔC�S�ʂ���t�ɋA���錻��Ɍx����炷�B �@�I�����̎����������Â̍����傫�����E���邪�C�ېH����Ȋ��҂̉Ƒ��Ɉ�ᑂ��u�قƂ�Ǐ�Ɏ����v�Ƃ�����t��53���ŁC�����_�H�����l�C�o�@�o�ǂ�44���������B����C�\�Ȍ���o���ێ�őΉ����CAHN�͍s��Ȃ��Ƃ����I�������قږ�����t��34���ŁC�ɉ����Ď����I������I�ԌX���ɂ������B �@��������AHN���������̂́C���~�Ɏ���P�[�X�����Ȃ��Ȃ��BAHN������̒��~�o����q�˂��Ƃ���C44�����u����v�Ɖ����B���̗��R�i�����j�ɂ́C������x���Ȃǂ̈�w�I���R��68���ƍő��ŁC43���͉Ƒ��̊�]�ɂ���Ē��~�����f�����o����L���Ă����B�ق��ɂ͈�t�Ƃ���AHN�p���͊��҂̋�ɂ������Ă��܂����Ƃ��璆�~�f�����̂�23���C��Ã`�[���Ƃ��Ă̔��f��21���������B�܂��CAHN�p�������҂̑�����N�Q����Ƃ��Ĉ�t�l�Œ��~�����߂��̂�14���C��Ã`�[���Ƃ��Ă�13���ɏ��CAHN����������҂̂��߂Ɋ������Ă������������ɂȂ����B �@�������AHN���~�ɑ��C�S�z�ޗ������Ȃ��Ȃ��B�o���҂�AHN���~�őz�肳������q�˂�ƁC33�����u�}�X�R�~�������v�Ɠ����C�����ɔ��W�����˂Ȃ������Ɍ��O�������Ă����B������29�����u�@�I�ɖ�肪����v�C21�����u�ϗ��I�ɖ�肪����v�ƍl���Ă����B ������AHN�����T���́u�ɘa�P�A�v �@AHN�͐H���̑�ւł��邽�߁C�����T���͉쎀�����邱�Ƃɑ�������ƍl�����Î҂�����B��������c���ɂ��ƁC�����̔F�m�NJ��҂�AHN�����Ȃ����Ƃ́C�����w�I�Ɋɘa�P�A�̍�p�������炷�Ǝw�E����_��������iPrintz 1988�CSullivan 1993�CAhronheim 1996�C�A�� 2000�j�B�����ɂ��ƁC���҂ɂƂ��ċ�ɂ̏��Ȃ��Ŋ��̂��߂ɂ́uAHN�͕s�v�v�ł���C�uAHN�̍����T���C���~�͗ϗ��I�ɑÓ��v�ł���B�����́uAHN��K�v�Ƃ��銳�҂̑唼�́C���Ԃ����قLjӎv�\����o���ێ悪�ł��Ȃ��Ȃ�B�����Ȃ�O�ɁC�l���̍Ŋ��̒i�K���ǂ̂悤�ɐ����������C���҂𒆐S�ɘb�������Ă������Ƃ���v�Ƙb���B �@�����́u���Җ{�l�ƉƑ����C�{�l�ɂƂ��čőP�̐l���̏I�������ɂ₩�ɓ����o����ӎv����̃K�C�h���C�����K�v�v�ƒ���B���ہC���{�V�N��w��̃��[�L���O�O���[�v�͊��Җ{�l�ƉƑ��̂��ǂ��I�����̑I�����菕������u�ӎv����v���Z�X�m�[�g�v�̎���ł��쐬���Ă���B�����́u��t�������ɍŊ��̑I����C���Ă��Ă͂����Ȃ��v�Əq�ׁC�I�����݂̍�����l�����Î҂̊w���ψ���ɁC���ґ���������ׂ��Ƃ̍l�����������B �@�I�����ɂ����鎩�����d�̎p���������č��ł́C��t�Ȃǐ��Ƃɂ͏������߂���x�ŁC���߂�͖̂{�l�����̑㗝�l�Ƃ����X��������Ƃ����B�������C�����́u���̕��@�͓��{�ɂ͂Ȃ��܂Ȃ��B���{�l�͈�Î҂ɂ��ꏏ�ɍl���Ă��炢�����Ƃ̎v�����������߁C���Ƃ��T�|�[�g����`�ō��c��i�߁C��������ƍ��ӂ��`������d�g�݂����߂���v�Ǝw�E���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N9��8�� |
| ��������Living Will�iLW�j�̕��y�^���͊��҂̐l�����d�̉^�� |
| ��c ���v�@�����a�@�@�\��B����Z���^�[�i�����s�j���_�@���^���{��������������� �@20���I�㔼�̈�w��Â̐i���͂߂��܂����C�l�H�ċz��C�l�H���́C���w�Ö@�C�h�{�⋋�Ȃǂ̉������Â��傢�ɔ��B���܂����B���̂��ߎ��錩���݂̎���ꂽ�I�����̊��҂��C���炩�Ɏ��R�����������Ƃ��������₩�Ȋ�]������������C�h�������[�u�ŋꂵ�ޏ������Ă��܂����B�u�ɑ�̐i���ɂ��C�������҂ł����̓I�ɂ݂̂��߂Ɉ��y�����l����K�v�͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�������{�̂��҂̈ꕔ���C���܂��ɒɂ݂ŋꂵ��ł��錻���͈�t�̑Ӗ��▢�n�ɂ����̂Ŕ߂������Ƃł��B �@�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�iIC�j���Ȃ��ƁC���������Â��ł��Ȃ���Ê��ƂȂ�C���y�������̔��������҂̎��Ȍ�����ŗD�悷������ɐi��ł���CLW��o�^������{����������̉����12��5��l�ɂȂ��Ă��܂��B����ł����{�����̐番��1�ɉ߂��܂���B �������Ƃ͉��ł����H �@�������Ƃ́C�s���Ŗ����̊��҂��{�l�̈ӎv�ɏ]���C�����ێ��[�u�ɂ�鉄�����Â�f��܂����C�ɂ݂̏����Ȃǂ̏\���Ȋɘa�P�A���C�l�Ƃ��Ă̑�����ۂ��C���炩�Ɏ��R���𐋂��邱�Ƃł��B���{����������́C���𑁂߂�ϋɓI���y���⎩�E�����Ƃ͍l���Ă��܂���B�l�H�ċz���l�H���͂Ȃǂ̉����[�u�̒��~�́C�ꌩ�����𑁂߂�s�ׂƂȂ蓾�邽�߁C��@�ƍl�����t�������C�������Ɍ����^���ł����Ă��C���~����̂����߂炤��t�͏��Ȃ�����܂���B������́C�����[�u�Ȃ��ɂ͐������Ȃ���Ԃ͏I�����ƍl���Ă���C�����[�u�̒��~�⍷���T���́C���҂ɑ�������]�̈ӎv��������C�E�l��ϋɓI���y���Ƃ͍��{�I�ɈقȂ�ƍl���܂��B �@���ɐA����Ԋ��҂ւ̑Ή������ł��B�����I�A����ԂƂ́C��w�I�ɂ͑J�����̈ӎ���Q�������C3�����ȏ�̎��Âɂ��S�炸�C�ӎv�̑a�ʁC���͉^���C���͐ېH���s�\�ŁC�A�ւ͎��֏�ԁC�ዅ�͓����Ă��ӎ��ł��Ȃ���Ԃɂ��邱�Ƃł����C���͔����Ă͂��Ȃ��������̂ł��B���{�ł́C�]������O���C��ʎ��́C���邢�͔]�̎�p��ȂǂɐA����ԂɊׂ�l�������C��a�@��3��l�C��ʈ�Î{�݂܂őS���I�ɂ݂��3���l�ʂ���Ɛ��肳��܂��B �@���{�w�p��c�����悤�Ȓ��������̐A����Ԋ��҂ɑ���Ή��́C��×ϗ���C�Љ�o�ϓI�ɂ������Ēʂ�ʏd�v�Ȗ��Ƃ��āC�u���ƈ�Ó��ʈψ���v��ݒu���Č������C1994�N�ɐA����Ԋ��҂̈�Ò��~��3�������o���܂����B�i1�j���҂��s�\�̏�Ԃɂ���C�i2�j�ӎ��̂��������ɁC���҂���������]�̈ӎv��\���C�i3�j�������Â̒��~�͒S���オ�s���C�ł����B�I������Â̑ΏۂɐA����Ԋ��҂�Ƃ肠���ė~�����̂ł��B���E��LW���݂Ă��C�w�ǂ��ׂĂ̍��łƂ肠���Ă��܂��B �������̖@�����^�� �@���{����������̍l�������߂��@���v�j�ẮC2003�N�̕�ɍ���͌����J����b�ɒ�o����܂����B���������@�ɂ́C���t��o�@�ĂƋc����o�@�Ă�2������C������͋c�����@���߂����܂����B���}�h�́u�������@�������l����c���A���v�i���R���Y�����j�������オ��܂����B�����ϗ������ޗ��@�́C�ϗ��ςɊ�Â��l����������ɂ킽��̂ŁC�����I���ӂ̌`������ł��B�c���A����2005�N���2007�N�܂�9��̋c������ŊW�c�̂���q�A�����O���s���܂����B���{��t��C���{�ٌ�m�A����C�S���{�a�@����C�e�@���c�́i�����C�L���X�g���C�_���Ȃǁj�C���{�~�}��w��Ȃǂ̏\���c�̂̑�\���o�Ȃ��đ��������@�Ɏ^�ۂ̈ӌ���q����܂����B �@�c���A�����S����c���Ɂu�������̑I���ɂ��āv�̃A���P�[�g���s���܂����B��111���ŁC�������u�����[�u�����Ȃ��I���v�C�u��t�̖ƐӁv��F�߂Ă��܂������C�Ƒ��̔��̏ꍇ�ɂ͓������O�����܂����B�����܂��ċc���A���́C2007�N�̋c�A����Łu�Վ���Ԃɂ����鉄���[�u���~�Ɋւ���@���v�j�v�Ă\���܂����B�A����Ԃɂ͐F�X��肪����̂ŊO����܂����B���̋c�A�̗Վ���Ԃł̖@���v�j�Ă̎�ȍ��q�́C�i1�j���҂̈ӎv�Ɋ�Â������[�u���~�̎葱�������K�肵�C���~���̓K�Ȏ��{�Ɏ�����C�i2�j���҂������[�u���~�̈ӎv���Ŏ����C2�l�ȏ�̈�t���u�Վ���ԁv�Ɣ��肷��C�h�{�E�����⋋���܂މ����[�u�𒆎~�ł���C�ł����B �@�������C���̋c�A�̗v�j�ẮC���{��t��Ɠ��٘A�̈ӌ����ŃX�g�b�v���܂����B���{��t��̈ӌ��́u�������@�����ɍ����I���ӂ������Ă��邩�͐r���^��B���̂悤�ȏł̖@�����͈�Ì���̍����������v�ł����B���{����������́C�������̏�����������Ă���C��t�͖Ɛӂ����悤�ɓw�͂��Ă���̂ł��B�ŋ߂̑傫�Ȉ��y�������͖w�Ǔ��������ɂ����̂ł��B�܂������̎咣�́C�I�����ɑ��������������ƍl����l�̌����E�咣������ė~���������ŁC�������Â��������҂͂ǂ����ő������悢�̂ł��B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N9��22�� |
|
��16����{�ɘa��Êw�� �n��R�~���j�e�B�[�̒��Ńz�X�s�X�P�A��W�J |
| �@�a�@�Ŏ����}����l�����|�I�ɑ������C�ݑ�z�X�s�X�P�A�ւ̒n���Ȏ��g�݂��L�������B�D�y�s�ŊJ���ꂽ��16����{�ɘa��Êw��k����\�a�c�s�������a�@�i�X���j�E�b��g�a�@���l�̓C�k�u�R�~���j�e�B�P�A�Ƃ��Ẵz�X�s�X�P�A�v�i�������X���b��a�@�E���}�~��ɘa�P�A�ȑ��������j�ł́C�킪���ōݑ�z�X�s�X�P�A�̐��I�Ȏ��g�݂𑱂��Ă����C�P�A�^�E�������N���j�b�N�i�����s�j�̎R��͘Y�@���C�ӂ����ȃN���j�b�N�i�R�����j�̓������Â݉@���C�R���ԏ\���a�@�̖��i�a�V���@�����C�e�n�ł̍ݑ�P�A�̌o������ɁC�n��R�~���j�e�B�[�ɂ�����z�X�s�X�P�A�̌���Ɖۑ�ɂ��Ęb���������B 20�N�ő傫���ς�����ɘa�P�A �����@�킽�����z�X�s�X�P�A���w�юn�߂���20�N�O�́C���{�ł��������w����Ȃ��C�C�O�Ŋw�Ԃ�������܂���ł����B���{�̊ɘa�P�A�͂���20�N�ő傫���L�������Ǝv���܂��B ���i�@�킽����22�N�O�C�K��Ō�������Ȃ���������ɉƂɋA�肽���Ƃ�������������҂�����C�a���̊Ō�t�ƉƂɘA��čs�����̂��ݑ�z�X�s�X�P�A�Ɏ��g�ނ��������ł��B �R���@�킽���͊O�Ȉ��16�N�C�z�X�s�X���14�N���āC���݁C�ݑ���̐f�Ï����J����6�N�ɂȂ�܂��B�O�Ȉ�̂���C���҂���Ɂu�ƂɋA�肽���v�ƌ���ꂽ�̂��C�ݑ�z�X�s�X�P�A���n�߂邫�������ɂȂ�܂����B���@���̓x�b�h����S�������Ȃ������l���C�ƂɋA��Ǝ����ŕ����Č��ւ܂Ō}���ɗ��Ă��ꂽ���Ƃ�����C�ݑ�z�X�s�X�P�A�̗͂���X�����Ă��܂��B �����@�����ɂ���3�l�́C���낢��ȏo��̒��Ől���̍ŏI�͂𑗂銳�҂�����x����ꏊ���C�a�@�ł͂Ȃ��ʂ̏ꏊ�ɂ���̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂɋC�t�����̂��Ǝv���܂��B�V�X�e������Õی����Ȃ���������ǁC���҂���̂��߂ɉ����K�v���Ƃ��������̐S�̐��ɓ������ꂽ���ʁC�����ɂ��ǂ蒅���܂����B �Œ�5�N�̗Տ��o���ƕ��L���l�ԗ͂��K�v �����@�ɘa�P�A����ɂ������ƍl�����҂������Ă��܂����B���ɂ��ꂵ�����Ƃł����C�킽���͎��K�ɗ���w���ɂ́C�u�ŏ�����ɘa��Âɔ�э��ނȁv�ƌ����Ă��܂��B�o���オ�����V�X�e���̒��Ŋw��ł����̂ł͂Ȃ��C�����ň�Â̌��ƈł���������Ɗw�сC��������őI�����邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B �R���@�킽���̓z�X�s�X�Ɍ��C�ɗ���l�Ɂu����̗Տ��o�����Œ�5�N���炢�͐ς�ł��āC���̈�Â̌���ʼn������Ȃ̂���������ƌ��Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ɠ`���Ă��܂��B�܂��C�S�g�̏�Ԃ�f�Ă������߂ɂ́C���ꂭ�炢�̗Տ��o�����Ȃ��Ƃł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ���i�@��{�͖ڂ̑O�̊��҂���ɑ��ĉ����ŗǂ̕��@����������Ɣ��f�ł��邱�Ƃł�����C��͂�4�`5�N�͂�����ł��傤�ˁB����̊��҂����|�I�ɑ����̂ŁC����̐f�f�C���Â��܂߁C���ȓI�Ȑf�f�w�͐g�ɕt���Ă����Ăق����ł����C�O�ȓI�ȋZ�p������ƈ��S�ł��B �R���@���҂���̐l�����݂Ƃ�Ƃ����Ӗ��ł͐l�ԗ͂��K�v�ł��B����͂ǂ�������g�ɕt�����܂����B ���i�@��Â̐��E�����ɂǂ��Ղ�Ђ����Ă����炢���Ȃ��Ǝv���܂��ˁB�킽���͎Ⴂ���납��C�_�ƉƁC�����C�ٌ�m�C��w�Ȃǂ��낢��ȐE��̐l�Ƃ̕����1�`2�J����1���Ă��܂��B�l�Ɛl�Ƃ̊W���̒�����C�l�Ƃ��Ă킽�������ɋ��߂��Ă�����͉̂������l����@������邱�Ƃ͑�ł��B �����@�킽������͂肢�낢��ȐE��̐l�ƕt���������Ƃ��ɂ��Ă��܂��B�킽���̓v���l�^���E���Ő���I�[�����߂��ɁC���҉�̕����Ă�s���u�����J�����肵�Ă��܂����C�����ł킽�������̖���137���N�̐��̂����炾�Ƃ������Ƃ��w�т܂����B���̂悤�Ȃ��ƂɎv�����͂�����C���҂���ƌ������������Ƃ��Ɋ̂������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����肵�܂��B �R���@�킽���͊ɘa�P�A��ɂȂ邽�߂ɂǂ̂悤�ȕ��������炢�����Ɗw���ɕ����ꂽ�Ƃ��C�u��҂ɂȂ�����C�����Ǝd���������킯������1�N���炢���悵�āC���̊Ԃɂ��낢��Ȑl�����Əo��̂�������Ȃ��v�ƌ����Ă��܂��B�킽����2�N�Q�l����1�N���悵�܂������C���ꂪ�ǂ������Ǝv���Ă��܂��āi�j�B��͂莋����L���邽�߂ɂ́C�����ꏊ�ɂ������邱�Ƃ������Ƃ͂����Ȃ��C�����܂��B�D�œ�ɂɍs�����Ƃ��C�L���u���[���X�̖{�ɏo������̂��C���̐��E�ɓ��邫�������ɂ��Ȃ�܂����B �N����Ȃ��ōݑ���x�� �R���@�R�����ł́C��̓I�ɂǂ̂悤�Ȏ��g�݂����Ă��܂����B ���i�@�R�����ł͉��ی����x���X�^�[�g������������s���ƈꏏ�ɂȂ��āC�ݑ�ɘa�P�A�x�����Ƃ�n��P�A�̒��ɑS���g�ݍ���ŁC��啔��𗧂��グ�Ă��܂����B���̒��ł̈�Ԃ̖ڋʂ́C�N�����݂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���҂��Ƃɖ߂肽���Ɗ�]����C�N��ɂ�����炸�C�����ɑ��k�ɏ���đ����s���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B���������N��30�l���炢�����p���Ă��āC2�J����1�x�͈�ÁC�����C�Ō�̊e���삩��70�`80�l���W�܂��Ď��ᔭ�\���s���Ă��܂��B �@�H������̎�p��C�Ĕ�����3�J����w�a�@�ɓ��@���Ă������̂̒ɂ݂��R���g���[���ł����C�Q������Œ��S�Ö��h�{�iIVH�j�J�e�[�e����}�����Ă������҂����܂����B�u�ƂɋA�肽���v�ƌ����̂ŁC�����Ɏ����牺���˂����čݑ�ɐ�ւ����Ƃ���C3����ɂ͋N���オ���Ă��łH�ׂ�ꂽ�B�����đ��q����̌������ɕ����ďo�Ȃ��C�̋��ɂ���Q��ɍs�����Ƃ��ł����̂ł��B �@�킽���́C���҂���̑S�l�����݂Ƃ��ꏊ�ɋA���Ă�����Ƃ����X�^���X�ŁC���ꂪ�ł���͈̂�Ï]���҂ł͂Ȃ��C�Ƒ���F�l�C�R�~���j�e�B�[�̐l�������Ǝv���Ă��܂��B �n��̒��Ń`�[���P�A��W�J �R���@�킽���̓z�X�s�X��Ƃ��ăz�X�s�X�P�A�̑����Ɋ����C�z�X�s�X�P�A�̃`�[�����n��̒��œW�J���Ă����d�g�݂��l���܂����B3�K���Ă̌�����1�K�ɁC�ݑ���x����24���Ԃ̖K��Ō�X�e�[�V�����ƁC��Ãj�[�Y�������Ĉ�ʂ̃f�C�T�[�r�X�����Ȃ��������ɑ���f�C�T�[�r�X�C�킽���ǂ����^�c����ݑ��Îx���f�Ï��C����ɖK����X�e�[�V�����C������x�����Ə�������܂��B1�J���ɏW�����邱�Ƃɂ���ă`�[���P�A�����ɃX���[�Y�ɂł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B������2�`3�K�͍�����Q�̂��ߒʏ�̃A�p�[�g�ł͏Z�݂ɂ�������������������A�p�[�g�ł��B�������n��̒��Ńz�X�s�X�P�A�̃`�[���P�A��W�J���Ă������߂̋��_�ƂȂ��Ă��܂��B�{�����e�B�A�̖�2���͍ݑ�ł݂Ƃ������̂��⑰�ł��B�n��̒��Ńz�X�s�X�P�A��W�J���Ă����ƁC���낢��Ȑl�����ƐV���ȉ������Ԃ��Ƃ��\�ɂȂ�܂��B �ݑ���炱���ł����݂Ƃ� �R���@���ŋ߁C40�Α�̖����Ƃł݂Ƃ������ꂳ�C���x�͎���������ɂȂ��Ă��܂��āC�������Â�I�Ȃ��ƉƂɖ߂��Ă��܂����B�u�킽���͎����̖����݂Ƃ����Ƃ��ɁC�����炢�낢��Ȃ��̂������Ă����������C���ꂩ��̎��Ԃ͉Ƒ��Ɏ������S���Ȃ��Ă����v���Z�X�����������v�ƌ����̂ł��B1�l�̐l���l�����I���Ă����Ƃ��C�{���ɑ����̂��̂����͂̐l�����Ɏc���Ă����B����͍ݑ��24���ԁC������Ԃ̒��ɂ��Ă����̌��ł��邱�Ƃ��Ǝv���܂��B �����@�킽���̂Ƃ���ł��ݑ�Ȃ�ł݂͂̂Ƃ�̃G�s�\�[�h�͂�������܂��B����Ƃ��C�X������Œ��ǂ��N���������ĐH�ׂ��Ȃ��Ȃ������҂��C�u���܂��V�Ղ炪�H�ׂ����v�Ƃ�����ł��B���̖]�݂����Ȃ��Ȃ���Ǝv���C���Ή����c�ޗF�l�Ɂu���̍Ō�ɁC����Ŏ���ł��������Ă����V�Ղ��g���āv�Ɨ��݂܂����B�킽�����������̐l�������悤�ɂ��ĘA��čs���ƁC���҂���́u���܂��v�Ƃ����ēV�Ղ�������炰�C�H�����I���ƁC�u�����͂��ꂪ�������v�ƌ����̂ł��B�{���Ɏ����̋߂���F�̈������҂�����C���̕����Ȋԕ����Ǝv���܂����B �u�Ƒ��ɖ��f�����������Ȃ��v�̖{���Ƃ́H �R���@���҂���ɍݑ�P�A�̗ǂ���`���Ă��C��͂���f��������Ƃ����b��1��͏o�Ă��܂��B�ł��C�u�{���́H�v�ƕ����ƁC�u�Ƃɂ������v�ƌ�����ł���ˁB �����@�Ō�w����100�l�ɁC��������������ɂȂ����Ƃ��C�ǂ��ʼn߂�����������������C�قƂ�ǂ��Ƒ��ɖ��f�������邩��Ƃł͖S���Ȃ�Ȃ��Ɠ����܂����B�Â����Ȃ��Ƒ��W�Ȃ̂��Ǝv���܂����B �R���@���f��������Ƃ����Ă��C���҂���ɂ́C����Ȃɂ������Ԃ�����킯�ł͂Ȃ���ł���B ���i�@�킽���͖�����⑧�q����Ɂu�e��������̎����̑��݂���v�ƌ����܂��B���̐e���ő�̋�Y�ɑ����Ƃ��ɁC�����ǂ��I���Ă��������~�߂邱�ƂŁC���Ȃ����������ꂩ��ǂ������Ă��������l���邱�Ƃ��ł���̂��ƁB �s������菜���C�w�������� �����@�݂�Ȃ݂Ƃ�̎d����������Ȃ�����C�����N���邩�s���Ȃ�ł��B����Ă��������C���������������Ă��C�ł��Ȃ��Ƃ����C�������ƂĂ������Ǝv���܂��B������C�K��Ō�t�����킽���������C�u���v�C�ł����B�킽�������������Ƌ����Ă����邩��v�Ƃ݂Ƃ�̌㉟�������Ă����邱�Ƃ��K�v���Ǝv����ł��B �R���@�u����ԐS�z�ŕs���Ȃ��Ƃ͉����v�J�ɕ����Ă����ƁC�����Ă��͉����ł��邱�ƂȂ�ł��ˁB������C�O�����ĉƑ��̂��낢��ȕs�����āC�u���ꂾ�����炱���ł��܂���v�Ɠ`���Ă����ƁC�ŏ��́u�ƂĂ������v�Ƃ����Ă����l���C���̂܂ɂ��u����Ȃ�ł���v�C�����āu����Ă悩�����v�Ƃ����B�����������Ƃ��ł���Ǝv���܂��B �@���ЁC�F��������҂����S���čŊ����}������悤�ɁC�ł�����葽�����w�сC�o����ς�ŁC�n��ɏo�čs���Ăق����Ǝv���܂��B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N10��13�� |
| ���ґ����猩�����z�I�Ȃ��������̍�@ |
| �@���������̍ہA�ǂ�ȕi�������҂Ɋ��邩-�B����Ȃǂœ��މ@���J��Ԃ����s�̉������b�q�i���Ƃ��E�肦���j����i�S�Q�j���A�����i�̏Љ�E�̔���a���K��}�i�[�̏��M����C���^�[�l�b�g�T�C�g���J�݂����B���ґ����猩�����z�I�Ȃ��������̍�@���f�ځB�u���҂ƋC�������Ȃ��鏕�����ł�����ꂵ���v�Ƙb���Ă���B �@��������͎q�ǂ��̂���A�オ��ƈ��������p��ǁB�����Əo�Y�̌�ɂ͗�����ᇁi����悤�j���E�o���A���Ẩe���Ŕ��������̎�p�����B���͗Γ��������A���@�͌v�P�Q��ɋy�ԁB �@�a���������A��Ћ߂����Ă����R�O�㔼�Ɂu�����闝�R��ړI������̂��v�Ƌ^����o���u���@�o�������Ď����ɂ����ł��Ȃ����Ƃ��������v�ƍ�N�A�܂��̓u���O���J�݁B������ق��̓��@���҂����������ň���J����p���v�������Ƃ����B �@���N�W���ɂ̓T�C�g���Ƀl�b�g�V���b�v���J�X�B�x�b�h�ɐQ�]��Ŗ{��ǂނ��߂̖���Ԃ�����p�̍��z�c...�B���҂̗��ꂩ�猵�I�A�����������i����ׂĂ���B �u�`���I�Ȃ��������́A���҂ɂ͂���������v�Ƙb���B���z�́u���҂���u�ł��Ί�ɂȂ邨�������v�ŁA���̂��߂ɂ͑���̕a��C�������l���邱�Ƃ��厖���Ƃ����B �@�u���O�R�[�i�[�ł́u�咰����͓��@��Q�T�Ԃ��炢�����������̃^�C�~���O�B�i�����i�́j�H�ו��ȊO���v�ƁA�a�C�⊳�҂̓������Ƃɂ��������̍�@���������B �@���ǂ̕s�����c��A������f���������Ȃ���������B������u���������R���V�F���W���v�Ɩ��t���A���҂̏Ί�ɂȂ����Ă𑱂��Ă���B �@�T�C�g�̃A�h���X��http://cocoro-sakura.jp/�@ m3.com�@2011�N10��21�� |
|
�����Љ�ی���Ë��c�� �����A���ː����Â̏[���Ƒ����ɘa�P�A���� |
| �@�����J���Ȃ̒����Љ�ی���Ë��c���i��F�X�c�N�E������w��w�@�@�w�����w�����ȋ����j��10��27���J����A�����A�����K���a��A�����Ǒ���e�[�}�ɋc�_�i�����́A���J�Ȃ̃z�[���y�[�W�Ɍf�ځj�B �@�����ł́A���ː����ÂƊɘa�P�A���œ_�B���J�Ȃ́A���ː����Âɂ��ẮA���Ґ����L�тɔ䂵�ĕ��ː����Èオ���Ȃ����Ƃ���A���ː��Ǝ˂̂��тɕ��ː����Èオ�f�@����u����f�@�v�̂ق��ɁA�u��I�Ȑf�@�v�̃p�^�[�����z�肵�A���ː����Èオ��I�w���̉��A�`�[���Őf�Âɓ�����Ă�B����ɂ��A�Ⴆ�A���ː����È�̐f�@�͏T1��ȏ�ȂǂɌ��炷�ȂǁA���S���y������B �@�ɘa�P�A�́A�����ł͂Ȃ��f�f����������{����ƂƂ��ɁA�g�̂����łȂ����_�ʂł̃P�A�������ɍs�������ۑ�B�܂��A�ɘa�P�A�a�����A�Ŏ�肾���łȂ��A�O����ݑ�ւ̉~���Ȉڍs���x��������g�݂̕]����ڎw���B���̂ق��A��×p����ɂ�14���̏������������邪�A30���ɉ������邱�Ƃ������ۑ�B �@�����K���a��̒��ł̏d�_�ۑ肪�A���A�a�B���͓����̌������ɂ����ē��A�a���t�ǂ�4���ȏ���߂錻��܂��A�O���ŁA��t��Ō�t�A�ی��t�ȂǑ��E�킪�A�g���ďd�_�I�Ɉ�w�Ǘ����s�����f�Õ�V��ŕ]��������j�B �@������́A�����S�ʋ։������{���Ă���a�@�͖�64���ɂƂǂ܂��Ă��邽�߁A�����K���a���ҁA�����E�ċz�펾�����҂Ȃǂ̎w���Ǘ����s���a�@�ɂ��ẮA�����Ƃ��ĉ����S�ʋ։���i�߂邽�߂̕�������B �@�����Ǒ�̃��[���́A���j�B���O���Ɣ�r����ƁA���{�͌��j�́u���܂��v�B���̈���A���ܑϐ����Ĕ���ő����_�ł��邽�߁ADOTS�i���ڊĎ����Z�����w�Ö@�j���O���Ő��i����B�܂����j�ł͑މ@�����������Ă��邱�Ƃ���A�މ@��Ɋւ���K����߂�悤�i�߂�ق��A���j�ȊO�̍����ǂ������҂ւ̑Ή��̐�������B ���A�a�̃`�[���ł̈�w�Ǘ���]�� �@���������Z���^�[�������̉ÎR�F�����́A���{�̕��ː����Â̒x���F�߁A�u���ː����Èゾ�������҂�f�Ă���킯�͂Ȃ��A���Ȃ̈�t���f�Ă���B���ː����Èオ�������Ȃ�������Ȃ��Ƃ�������O���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ǝw�E�B��×p����̏������Ԃ̉������x���B���̂ق��A����o�^���i�ւ̃C���Z���e�B�u��ݒ肷��ق��A��w�����m�̕]���Ȃǂ����߂��B �@���{�o�ϒc�̘A����Љ�ۏ�ψ����É��v�����㗝�̖k�����ꎁ�́A�u�ݑ�×{�̒��ł����Ɋɘa�P�A��i�߂邩�A���̃V�X�e�����ǂ��l���A���グ�Ă����ׂ������悭�����Ȃ��B���̓_�ɂ��Ă��������Ă��炢�����v�ƃR�����g�B���̑����̈ψ����A�ɘa�P�A�̐��i��]�������B �@���{����햱�����̊����v���́A�ɘa�P�A�a�����@�܂ł̑ҋ@���Ԃ́A����f�ØA�g���_�a�@�̖�35����2�T�Ԉȏ�Ƃ����f�[�^�ɂ��āA�u�����Ɛ[���B�ɘa�P�A�Ƃ����I�����ɒH����܂łɎ��Ԃ��������Ă���A�ɘa�P�A�a�����@�Ɏ���܂ł̎��Ԃ͂����艽�{�������v�Ǝw�E�A����ɁA�u��������̊ɘa�P�A�����{����Ȃ�A��葽���̊ɘa�P�A�a�����K�v�v�ƃR�����g�B����ɑ��A�ÎR���́A��ጃP�A�ȂǂƓ��l�ɁA�u�ɘa�P�A�a���v���Ȃ��Ă��A�ɘa�P�A�`�[�������A�e�a�������̐����\���Ƃ����B �@���̂ق��A���A�a�ւ̈�w�I�Ǘ��₽����A���j��ɂ��Ă��A�l�X�ȋc�_���o�����A��{�I�ɂ͈ψ��̎x��������ꂽ�B���ɓ��A�a��ɂ��ẮA�`�[����Â̏d�v�����������ꂽ�B m3.com�@2011�N10��26�� |
| �ՏI�ԋ߂̊��҂̊肢�c�ЂƂ߉��������Ƃ́H |
| �@����ڑO�ɂ������҂̑������Ŋ��Ɋ肤���Ƃ́A�u������y�b�g�ɂЂƂ߉���Ɓv�Ƃ����B�u�f�C���[�E�e���O���t�v�������B �@���҂̏I�����P�A���s���z�X�s�X���x�����鎜�P�c�́u�w���v�E�U�E�z�X�s�X�v���A�z�X�s�X�E����Ώۂɍs����������蒲���ɂ��ƁA�����ԋ߂ɔ��������҂���u�y�b�g�ɉ�킹�ė~�����v�Ɨ��܂ꂽ���Ƃ�����E���́A�S�̂�60���ɏ�����Ƃ����B �@���ɑ��������w�肢���Ɓx�́A�u��������f�[�g�Ȃǃ��}���`�b�N�ȋ@������V���Ă��ė~�����v�i57���j�A�u���j����p�[�e�B�[������Ăق����v�i50���j�ȂǁB �u�w���v�E�U�E�z�X�s�X�v�̂փU�[�E���`���[�h�\������́A�u�l���̍Ŋ���ڑO�ɍT�����Ƃ��A�����Ȃ��ƂŁA�傫�ȈႢ�����܂����́B�Ⴆ�A�F�l�ƈ���A�Ƒ��̒a������ɏo�Ȃ�����A������y�b�g�ɉ�����肷��l������B���̈���ŁA��������̒n�ɗ�������A������l�ƌ���������ƁA�Ȃɂ��B�����̂���傫�Ȃ��Ƃ����߂�l������v�Ƙb���Ă���B �W���[�j�[Online 2011�N10��31�� |
| �����{��k�ЂŊ������g�䂪�݁h�����̈ꏕ�̂��߂� �I������ÂɊւ���{�l�̈ӎv�m�F�J�[�h�����܂��� |
| ���[�O��i�c���`�m��wSFC��������ȏ����i�K��j�A���_�ی������m�A�Љ���m�j �@�]�[�ǂȂǂł�����A����ԂƂȂ�A������ʂ܂܉�����銳�҂����O�ɂ��āA�u���̕��͉ʂ����č��̏�Ԃ�{���ɖ]��ł���̂��낤���v�ƁA�Տ���Ȃ�N������x�͎��₵�����Ƃ�����Ǝv���܂��B����̈ӎv�������Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɔ����āA���炩���߈�Âɑ��郊�N�G�X�g�𖾂炩�ɂ��Ă����Ăق����B���̕v�͋{�錧�̓������̂���a�@�ɋΖ����Ă���̂ł����A�����{��k�Ђ�̌����ĉ��߂Ă��̏d�v����Ɋ����܂����B �@�ЊQ���ɂ́A�����\�ɏo�Ȃ��g�䂪�݁h�����݉����܂��B���ɐg���Ă��������A�����⊵��Ȃ����̂��߂ɂ݂�݂�̒�������A�v�̋Ζ���ɂ����X�Ɣ�������Ă��܂������A���̑����́A�]�����̌��ǂ�F�m�ǂŐQ������ƂȂ�A�ӎv�̑a�ʂ��ł��Ȃ�����҂ł����B���̋~��ǂ���̏Љ��ɂ́u�Ôg�ň��9�l��������s���s���v�u�{�l�͂��̉ƂŗB��̐����ҁv�ȂǂƏ�����Ă���܂����B�����ɂ݂܂������A����荢�����̂́A�Ƒ������Ȃ��Ȃ������߂ɁA���҂��g�̊�]��ӎv�̏����ł��Ȃ��Ȃ��Ă������Ƃł��B �މ@���҂������Ȃ��a�@�A�Ƒ� �@���X�ɑ����Ă��銳�҂��������邽�߂ɂ́A��Ԃ��������������҂��珇�X�ɑމ@������K�v������܂��B�Ƃ����Ă��A�߂��̕a�@����{�݂͂ǂ�����Ў҂Ŗ����ł������A���܂��܌��������{�݂�����u�肪�����邩��݂낤�ɂ��āv�Ƃ��A�u�M�d�ȗ×{�a�������̂�����A���v���オ��悤�ɋC�ǐ؊J�⒆�S�Ö��h�{�Ȃǂň�Ë敪���������Ă��ꂽ���v�ȂǁA������������������邱�Ƃ��������̂ł��B�܂��A�v�̋Ζ���̎���ł͂���܂��A����̐k�Ќ�ɂ͉��L�̂悤�Șb���悭���ɂ��܂����B �i1�j�Ƒ��ƘA�����r�₦�� �@���{�݂��S�Ĕ������̂̐H����ۂ�Ȃ��Ȃ�A�̒�������ē��@�����A�F�m�ǂ̂�����̃P�[�X�ł��B�ӎv�̑a�ʂ��ł��Ȃ��̂ŁA�Ώ����j�𑊒k���邽�߂ɉƑ�������Ƃ̂��ƂŔ����B�������A�u���ő̒���������v�u�Ԃ�������Č�ʎ�i���Ȃ��v�ȂǂƁA�ʒk�̓������邸��Ɖ�������Ă��܂��܂����B�d�b�ŗ��@���Ñ������Ƃ���A�u���������������ÂȂ��̐l�͖]��ł��Ȃ��v�Ɠf���̂Ă�悤�Ɍ����ĉ��M�s�ʂɁB�ʂ����Ė{�l�̈ӎv�����̂Ƃ���Ȃ̂��m�F�ł��Ȃ��̂Ŏ��Â̒��~���ł����A�Ƒ��ƃR���^�N�g�ł��Ȃ����߂ɕa�@����̍s��������܂炸�A�������@��]�V�Ȃ�����Ă��܂��܂����B �i2�j��Ô�����Ȃ̂ŕa�@����������Ȃ� �@�a���肵�����������̊��҂���̘b�ł��B�u���@���Ĉ�Â���K�v�����Ȃ��Ȃ����̂őމ@�ł��v�Ɠ`�����Ƃ���A�{�l���Ƒ��ƕ�点�邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă��܂����B�������A�Ƒ����u�Ƃ��������Ԃ����̂ōs���ꂪ�Ȃ��B���{�݂��ƕa�@���݂̃P�A�����邩�S�z�B���̂܂ܓ��@�����Ăق����v�Ə���܂���B�Ƃ��낪�Ō�t�ɘb�����Ƃ���A�Ƒ��̖{���́w���z20���~�̏�Q�N���������Ă��邵�A�g�̏�Q��1���ň�Ô�͖����Ȃ̂ŁA�a�@�ɂ��̂܂ܓ���Ă����������ʓ|���Ȃ��x�Ƃ̂��ƁB����������Z���ɂƂǂ܂��Ă���A�Ƒ��͕��ʂɐ������Ă��邻���ł����B�{�l�̊�]�Ȃǂ��\���Ȃ��ł��B�މ@�������s���ɏI��������߁A���ǐ悪�����Ȃ��܂ܕa�@�ɂƂǂ܂邱�ƂɂȂ�A�{�l�͍ǂ�����ł��܂��܂����B �i3�j���ԑ̂���ƂɈ������Ȃ��Ƒ� �@�]�����킸���Ȋ��҂���ɂ��āA�u�Ŋ��͉Ƃʼn߂��������ƌ����Ă�������v�Ɖ�������ɘA��ċA�낤�Ƃ��܂����B�Ƃ��낪�삯�����e������u�ƂŎ��Ȃ����炲�ߏ��l�ɏ���v�u�a�@�Ő������Ă��̂��K�����v�u�ƂŖS���Ȃ��Č����ɂł��Ȃ�����x�@������B�p�g�J�[����܂��Ă�Ȃ�Ċi�D�����Ȃ��v�ȂǂƉ������Ēf�O������܂���ł����B�����u�ł̘b�Ȃ������������Ă���Ȃ��B�{�l�����ނŊ�]���c���Ă���Ă����������̂��ȁv�Ƃۂ�Ƃ��ڂ��������ł��B �I�����̈ӎv�\���̈ʒu�t���̂����܂��� �@����̐k�Ђ�ʂ��Ď������́A�u���肵��������˔@�Ƃ��ďI���v���Ƃ�g�������Ēm��܂����B�܂��A�ˑR�P���Ă��鎩�R�ЊQ�ɂ���Ĉ�Ë@�ւ�Ƒ����猩������Ă��܂��\�������邱�Ƃ����܂����B�����炱���A�u���Âɂ���ĉ������߂Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�����͂ǂ̂悤�Ɉ�Â��s���Ăق����̂��v�Ƃ����ӎv���A�`�Ƃ��Ďc���Ă����K�v����Ɋ������̂ł��B �h�i�[�J�[�h��͂����u�I������Èӎv�\���J�[�h�v�i�\�ʁj�B 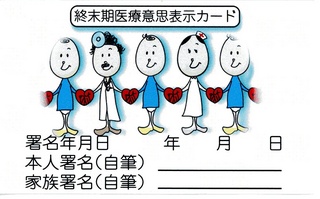 �@���z��`���Ə��邩������܂��A��Â͊��҂���̊�]�������邽�߂̂��̂��Ǝ������v�w�͍l���Ă��܂��B�����ňӎv�\�����ł��Ȃ��Ȃ������ɁA��Ë@�ւ���{�݁A�Ƒ��⑼�l�̓s���Ő�������邱�Ƃ�]�܂��A�u�����̍Ŋ����炢�͎����̈ӎv�Ō��߂����v�Ƃ������҂���̑z��������A���d�����ׂ��ł��傤�B �@���ʁB�×{�ꏊ�̂ق��A�����Ɋ֘A����9�_�ɂ��āA��]���L�ڂł���悤�ɂ����B�T�C�Y�͈�ʓI�Ȗ��h�Ɠ����B �@�������v�w�̂���Ȏv�����`�ɂ����̂��A����̈ӎv��\���h�i�[�J�[�h��͂����u�I������Èӎv�\���J�[�h�v�ł��B�������A�I������Âɂ��Ċ�]��`���邽�߂̏��ނ́A�l�b�g��T��������ł�������܂��B�����A�����ŊȒP�ɏ����A�g�тł���^�C�v�͔����ł��܂���ł����B���������J�[�h�Ȃ�A�T�C�������Ċۂ�t���邾���ōŒ���̈ӎv���\���ł��܂����A�C���ς�����炢�ł����������܂��B�����A����҂ɂƂ��Ă͎�����������������܂��A�����̊W�ŌX�̈�Ís�ׂɂ��Ă̐���������܂���B���e�ɂ��Ă��\�������Ă��Ȃ��ʂ�����܂����A�������̎��̂��Ƃ��Ƒ��ł悭�b�������Ă����������߂̑f�ނɂ͂Ȃ�Ǝv���܂��B ���o���f�B�J�� �I�����C���@2011�N11��8�� |
|
������Ȃ���̎����ρi�O�ҁj �u���v��m��Ȃ���t |
| �@���̎������҂��A�s�{�ӂɂ����X�ɖS���Ȃ��Ă����B�؈ޏk�������d���ǁiALS�j�Ől�H�ċz��̑�������]���Ȃ��������ҁA�p�[�L���\���a�ŏI�������}�������ҁA��N���A���c�n�C�}�[�a����Ɏ��E�������ҁA����Ă�ɒ_�X�����������d�퐫���Ǔ��Ìŏnj�Q�iDIC�j���������ҁc�B �@�i���ɐs���邱�Ƃ̂Ȃ��u���v�ɂ��āA��t�Ƃ��Đl�ԂƂ��ĉ��X�ƌJ��Ԃ��Ă��鎩�⎩���̈�[���Љ�����B �@������g�����ρh�ɁA�����͂������Ȃ��B100�l����100�ʂ�̉����邱�Ƃ��\�����m���Ă��邪�A���̂悤�Ȏd�������Ă���ƁA�X�́g�l�̎��h�Ƃ������̂ɐv���ɔ����������ŁA�ǂ̂悤�Ȏ������I�Ɉ��������Ȃ肪�����B�V�r�A�Ɏ������߂悤�Ƃ������ŁA���̒������Ōy���ɉ��߂��Ă��܂��B �@�����Ȃ��Ƃ������A���͂��̂悤�Ȏd���������Ƃ��Ă�����ɂ́A�����ǂ��������̂������܂��ɗ������Ă��Ȃ��B�p�����������Ƃ����A���̑Ώ��̎d����m��Ȃ��B �@��t�Ƃ��āA�����f���A���S�鍐�͂ł���B�������A�����u��҂ɑ��ĉ��������Ă������炢����������Ȃ����A�V�ɏ�����悤�Ƃ��Ă���l�ɉ������Ă������炢�����A�܂������v�l�͒ǂ����Ȃ��B �@�܂�A���́g�E�ƓI��p�t�h�Ƃ��������ł����āA���o�I�ɂ͎����������Ă���B�l�Ԃ̎��𗝉�������t�Ƃ����g�l�ԓI���p��h�i����Ɏ����n�������t�����j�Ƃ́A�قlj����B �@������O�����A�l�̐������u���v������B����A���͊m���ɁA�����đ啝�ɂ��̐��𑝂₵�A���݊����剻�����Ă����B�߂������A���{�l��2�l��1�l�͊��Ŏ��S����悤�ɂȂ�Ƃ����Ă���i�S�؍[�ǂ͂��̔����ŁA�]�����͔�����j�B �@���ꂪ�����Ӗ����邩�Ƃ����A�u�ɂ₩�Ɋm���ɐi�s����a���}�����A����ɔ����͂�����\���ł��鎀��������v�Ƃ������Ƃł���B����ɁA�]�������Ȃ�̐��x�ŎZ�o�\�ɂȂ�B�l�X�̐ؖ]���Ă���g���m�ȏ��h���A��Â̕���ɂ��Z�����Ă����㏞�ł���B �@��������t�́A�u�l�̑����̑��d�v�Ƃ������ڂ̉��A�����Ɂu�����Ă��Ȃ������v�Ƃ����g���u������̂��߁A���m��]���Ȃǂ̏��J���ɖ�N�ɂȂ��Ă���B�u����җl�ɂ��C���������܂��v�́u���җl�������߂��������v�ւƎ�q���ϊ����A�u���Ƃ����a�������������Ȃ������v���̂��A�u����5�N��������10%�ł��v�Ȃǂƍ�������悤�ɂȂ����B�����Č��ǁA�藧�Ă��Ȃ��Ȃ�A�u�����̂Ȃ��l�����߂����Ă����������߂ɁA�a�C�ƌ��������Ă��������v�ƌ������B �Ȋw�͎�����₳�Ȃ� �@������O�̂��ƂƂ��Ċ��Ⴂ���Ă����Ȃ��̂́A�u�ǂ�قljȊw���i���E���W���悤�Ƃ��A�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł���B �@��w�͉Ȋw���琬�藧���Ă��邪�A��ÂƂ����Z�p�͌o�������菊�Ƃ��������ł���B�u�ړI���Ⴄ�v�ƌ�����A���̒ʂ肩������Ȃ����A����ڐA��Đ���ÁA�Q�m�����̗��p�Ƃ�������[��Â��A�l�̎���ώ������邱�Ƃ͂Ȃ��B����Ɍ����Ȃ�A�����̔錍����������������������قǁA���ɒ��ʂ����Ƃ��̈����͓����ɂ����B �@�]�Ƃ�������́A���_������^���A�m�o���i��A���̂��Ƃ��L�����čĐ�����B�l�Ԃ̒m���Ɗ����͔]�ɂ���Ďx�z����Ă���B������A�������]�E�_�o���Ȉ�́u�]�͗B��ڐA�ł��Ȃ�����ł���v�ƌւ炵���Ɍ��B�������A����Ԃ��A����ł��܂��ΒN����������̂Ȃ��A�܂��Ă⑼�҂̒��Ő����邱�Ƃ��Ȃ�����Ƃ������Ƃł���B ���o���f�B�J�� �I�����C���@2011�N11��9�� |
|
�����Љ�ی���Ë��c��@�ݑ�×{�x���f�Ï��A3�p�^�[���̑̐������� �ЕېR�Ƃ̍�����c�A�u��t�͈̂��v�����ւ̋ꌾ�� |
| �@�����J���Ȃ́A�����Љ�ی���Ë��c���i��F�X�c�N�E������w��w�@�@�w�����w�����ȋ����j��11��9���A�ݑ��Â��e�[�}�ɋc�_�A�ݑ�×{�x���f�Ï��i�ݎx�f�j�̎{�݊�ɂ��āA�n��Ńl�b�g���[�N��g�ޏꍇ�Ȃǂł��Z��ł���悤���������j��ł��o�����i�����́A���J�Ȃ̃z�[���y�[�W�Ɍf�ځj�B �@�ݎx�f�̓͂��o�{�ݐ��́A2010�N7�����݂�1��2487�{�݁B2006�N7����9434�����瑝�����Ă�����̂́A���L�єY��ł���B24���ԘA�������t��Ō�t�����炩���ߎw�肷��Ƃ����v���Ȃǂ��l�b�N�ɂȂ��Ă���B���̂��߁A�i1�j�����̈�t�����ݐЂ��A���@�݂̂Ŋ�������L���f�Ï��A�i2�j�����̈�t���ݐЂ��A�قڎ��@�݂̂Ŋ������邪�A�ً}���̓��@�̂ݍݑ�×{�x���a�@�i�ݎx�a�j�ƘA�g�A�i3�j�ݎx�a���܂ޑ��̈�Ë@�֓��ƘA�g�E�⊮�������\�\�Ƃ���3�p�^�[����z��A���̑̐����x����_���ݒ肪��������錩���݁B �@���J�Ȃ́A�ݑ��Ð��i�̉ۑ���A�i1�j����Ҍ����Z��̕��y���i�⎩��ȊO�̏ꏊ�ɂ�����T�[�r�X�̏[���A�i2�j�}�ώ��̑Ή��ȂǁA�ݑ�×{�ւ̕s�����y��������g�݁A�i3�j�K��f�Â�K��Ō쓙�̈�ÃT�[�r�X�̏[���A�������Ă���B�i2�j�̎{��̈���A�ݎx�f�̎{�݊�̌������B �@�i1�j�̊֘A�ł́A�O���2010�N�x����Ō��z���ꂽ�A�}���V���������̖K��f�×����������B����҂������W�߂��}���V�����Ɍ����I�ɖK��f�Â��s���P�[�X���ꕔ�Ɍ���ꂽ���߁A��ʂ̃}���V�����⍂��Ҍ����̋��Z�n�{�݂Ȃǂ̗ތ^�ɂ�����炸�A�u���ꌚ�����Z�ҁv�ɑ���K��f�×���830�_���������A2�l�ȏ�K�₷��ꍇ��200�_�Ɍ��z���ꂽ�B�������A����Ƀ}���V�����ƌ����Ă�����҂���ł���Ƃ͌���Ȃ����߁A�ꗥ�Ɍ��z�ɂ���̂ł͂Ȃ��A���Ԃɔz�������Ή�����������B �@���̂ق��A�ݑ�ɘa�P�A�̐��i�A�n��̍ݑ�_�@�\�̕]���Ȃǂ���������B�ݑ�_�@�\�́A10��21���̒��㋦�ƎЉ�ۏ�R�c���싋�t��ȉ�́u�ł����킹��v�ŁA�f�Ñ����ł��o�����\�z�i�w�u��ÁE���̘A�g�̃n�u�v�A���㋦�f�Ñ��x���Q�Ɓj�B��ÂƉ��Ɋւ���q�g�E���m�E�g�D�E�����I�ɃR�[�f�B�l�[�g����u�n��A�g���_�i�n�u�j�v���A���̌��悲�Ƃɐݒu����悤�����B �@11��9���̒��㋦����ł́A�㔭���i�̎g�p���i��ɂ��Ă��c�_�i�w�u�㔭�i���i�A���Z�����i���ۏ��d�v�v�A���B�ψ� �x���Q�Ɓj�B �u�ݎx�a�́A200���������ێ��v�A��؉ے� �@���J�Ȃ̒�Ăɑ��A�u�ݑ��Â̖��_�𖾂炩�ɂ����ŁA���܂��܂Ƃ߂��Ă���v�i���N�ی��g���A����ꖱ�����̔���C�j�ȂǁA�l�������͕̂]�����ꂽ���A���_�����X���ꂽ�B �@����A���̎����\�����B���쎁�́A�O�q�̍ݎx�f��3�p�^�[���́A�u�G�Ƃ��Ă͗����ł���v�Ƃ��A���ۂɂ͐f�Ï��ɕ�����t������P�[�X�͏��Ȃ����߁A�ݎx�a�ƘA�g�����p�^�[������ɂȂ�ƌ����邪�A�u�ݎx�a�̓͂��o�́A�S����331�{�݁i2010�N7�����݁j�����Ȃ��B����Ō����I�ɉ\�Ȃ̂��B�s�s���͂܂��\��������Ȃ����A�n���ł͋����I�������l����K�v������B�s�s���Ƃ���ȊO�̒n��ŁA���낢��ȃp�^�[����z�肵�čl���Ă������Ƃ��K�v�v�Ǝw�E�B �@���������Z���^�[�������̉ÎR�F�����́A�ݑ��Â̏d�v����F�߂A�Ⴆ�A�ݑ�ł̊Ŏ��ȂLjꕔ���������]�������ƁA����ȊO�̕������ǂ��ς�邩�A��ÑS�̂̂���悤���l�����_���ݒ肪�K�v���Ƃ����B�܂��ݑ�ɘa�P�A�ɂ��ẮA����S�ۂ����i����K�v���������B �@�ݎx�a�̎{�݊�ɂ��āA200���ȏ���ΏۂƂ��ׂ����Ƌ��߂��̂��A���{�a�@���C�����̖��㋱�k���B�ݎx�a�́A�]���́u���a4�����ȓ��ɐf�Ï������݂��Ȃ��v�ꍇ�݂̂��Ώۂ��������A2010�N�x����ŁA�u200�������̕a�@�v���lj����ꂽ�B���̓_�ɂ��āA���J�ȕی��Lj�Éے��̗�؍N�T���́A�u��a�@�́A���@�⍂�x�ȊO���ɓ�������̂���{�B�����a�@�͊O����ݑ�Ȃǒn���Â�S���v�Ɠ����A200�������Ƃ����v���͈ێ�����̂��Ó����Ƃ����B�u�Ȃ������I�ɑ�a�@�ɁA�ݎx�f��F�߂�A��������ݑ�Ɏ��g��ł��钆���a�@��f�Ï�����������邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��v�i��؉ے��j�B �@����ɁA�c�_�́A�u�ݑ��Â̏d�v���͋��ʔF���ɂȂ��Ă��邪�A���ꂪ�i�܂Ȃ��B�{���̌����͂ǂ��ɂ���̂��A1��c�_����K�v������̂ł͂Ȃ����B�f�Õ�V��̕]�������ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���J�ȂƂ��āA�S�̂Ƃ��Ăǂ�ȕ����ɂ���̂����c�_���A���̒��Őf�Õ�V�̂�������������ׂ��v�i���쎁�j�ȂǁA���҉Ƒ��܂Ŋ܂߂��ݑ��Â��x����̐��܂Ŕ��W�����B �u��t�͈̂��A�Ƃ̔����Ɉ��W����v���v�A���B�ψ� �@9���̑���ł́A10��21���̎ЕېR��싋�t��ȉ�Ƃ́u�ł����킹��v�ւ̋ꌾ���悹��ꂽ�B��������̂́A�����T���������{��t���C�����̗�ؖM�F���ŁA�u��싋�t��ȉ�̏o�Ȏ҂͊w��4�l�ŁA���㋦�ψ����w�҂̈ӌ��𒆈㋦�ψ��������Ƃ����`�ň�a�����o�����v�ƃR�����g�B �@����ɏo�Ȃ������s�{��t���̈��B�G����������ɑ����A�ЕېR��싋�t��ȉ��̑�X�\�E������w���_�����̔����܂��A���̂悤�Ɍ�����B �u��싋�t��ȉ����́A�w����ȉ�c�͗v��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�����Ǔ��m�̑ł����킹�ł����̂��x�Ƃ̔������������B�ł͈ψ��͉��̂��߂̑��݂��Ă���̂��B��싋�t��ȉ��́A��Î҂��{�݂̊W�҂��o�Ȃ����A���̎p���ɑ����㋦�Ƃ��Ĉًc������B�܂��A�w���̌���ł́A��t���ł��̂��Ǝv���Ă���P�[�X�������B��������Ȃ���ΑO�ɐi�܂Ȃ��x�Ƃ����ӌ����o���ꂽ�B �@���ɍݑ��Â̌o���̂����t�́A�ݑ��Â͈�t�����Ő������Ȃ����Ƃ�g�������Čo�����Ă���B�ɂ�������炸�A�����������������Ă��邱�Ƃ͔��Ɉ⊶�B�m���ɁA���ɂ������Â̕����ɂ��ẮA��X��t�͖@�I�ɐӔC�������߁A��X��t���O�ʂɏo��B�������A�S�̂Ƃ��ẮA�w��t�͈̂��x�ȂǂƎv���Ă����t������Ƃ͓���v���Ȃ��B���ی����x���n�܂�O�̗��j����m���Ă��闧��̐l���A����������ۂ������ċc�_�����Ă�̂��ƍl���A���W����v����������v�B �y�����z2011�N11��23���Ɉȉ��̓_��������܂����B �E�ォ��4�i���ځA�u���ꌚ�����Z�҂ɑ���K��f�×���1�l�ڂ�830�_���������A2�l�ڈȏ��200�_�Ɍ��z���ꂽ�v�Ƃ���܂������A�������́u���ꌚ�����Z�҂ɑ���K��f�×���830�_���������A2�l�ȏ�K�₷��ꍇ��200�_�Ɍ��z���ꂽ�v�ł��B m3.com�@2011�N11��10�� |