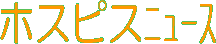 �@�@
�@�@�o�b�N�i���o�[2010/2/1�`2010/12/5
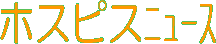 �@�@
�@�@| �@�z�|�� >��w�g�s�b�N�X>�z�X�s�X�j���|�X>�o�b�N�i���o�|�ƭ->2010/2/1�`2010/12/5 |
| �z�X�s�X�͕s�v�̎���� |
|---|
| �@���s�k��̑����a�@�u�k��a�@�v�i���S�����j�̕��@���ŏ�����O�Ȉ�̔���M�O����i�T�S�j�́u�z�X�s�X�i�ɘa�P�A�a���j�������Ƃ��K�v���낤���v�ƈӕ\��˂����Ƃ��������B �@�킪���̃z�X�s�X�́A�f�Õ�V��̗D����������1990�N�㏉������S���ɍL�������B�z�X�s�X�̉ʂ����������͑傫���B�ȑO�͂����ȂǂŒɂ݂̂���͓̂��R�Ƃ���Ă������A�z�X�s�X�ł̈�×p����Ȃǂ̓K�Ȏg�p�ő����̏ꍇ�A�Ŋ��܂ŋꂵ�܂Ȃ��Ă��ނ悤�ɂȂ������炾�B �@�u���Î�i�������Ă���Ƃ��ɂ́A�����Ɋɘa�P�A�����邵���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�������Ö@�͂ǂ�ǂ��A���ÂƊɘa�P�A���ɍs������ɂ��Ă���v�Ɣ����t�B�u�ǂ�ȕa���ł����Ă��ɘa�P�A���K�ɍs��������킯�ł��v�Ƌ�������B �@�ŋ߂̂��Â͊e�f�ÉȂ̋�����ƂɂȂ��Ă����B���Â̑I�������L�������̂͂������A�S���オ�R���R�����邱�Ƃ�"���̂Ă�ꂽ"�ƕs����������҂������Ă����Ƃ����B �@�k��a�@�ł͊O�Ȉ�̔����t�炪��p��̊��҂ɂ��āA�K�v�ɉ����ĉ@���̊ɘa�P�A�`�[�����u�Ɋɘa�����Ă��炤���A�厡��Ƃ��Ă̐ӔC���Ō�܂ʼnʂ������j���т��A���҂̕s�������ɂ��w�߂Ă���B �@�ɘa�P�A���L�͂ɍs���A��ÃX�^�b�t�ɂ��x���̐����[�����A�z�X�s�X���s�v�ɂȂ�����҂��������B �����V���@2010�N1��6�� |
| ��13����{������Êw�� �W�����ÂɂƂ���Ȃ�������ÂƂ��Ă̂��Â̒Nj� |
| �@3�l��1�l������ŖS���Ȃ鍡���C����̕W�����Â��m�����邽�߂̌��������E���Ŋ����ɍs���Ă���C��p�Ö@�C���ː��Ö@�C���w�Ö@����g�������Â͊m���ɐ��ʂ��グ�Ă���B���������̈���ŁC����ɑ��錻�݂̈�Âɕs��������Ă��銳�҂�����̂������ł���C��ֈ�Âɖ�����Ă����l�X�����Ȃ��Ȃ��B�����s�ŊJ���ꂽ��13����{������Êw��̃V���|�W�E���u����ɑ��铝����ÓI�A�v���[�`�v�ł́C�����_�ł͕W����ÂƂ͂Ȃ��Ă��Ȃ�3�̂��Ái�Ö@�j�ɂ��Ă̍u���Ɠ�����Â̎��_�������ꂽ�����u�ɂɑ���ɘa�Ö@�݂̍���Ɋւ���u�������\���ꂽ�B �`�ɂ݂̊ɘa�P�A�` ���m��w�Ɠ��m��w�̓����ɂ���I�ȋ�Ɋɘa���d�v �@��������Z���^�[�����a�@�i�����s�j��p�E�ɘa��Õ��̉��R���l�����́C������Âɂ�����ɂ݂̊ɘa�P�A�ɂ��ĉ���B�u���݁C�����u�ɂ̂قƂ�ǂ͗}���邱�Ƃ��ł��邪�C����ł������ł��Ȃ��ɂ݂͂܂����݂���B�u�Ɋɘa�̂��̂̕���p��_�I��ɁC�Љ�I�ȋ�ɁC�X�s���`���A���ȋ�ɂւ̑Ή��Ȃǂ��K�v�ł���C���m��w�Ɠ��m��w�̗�������g���铝����ÓI�A�v���[�`�����߂���v�Əq�ׂ��B �]�܂��S�l�I�A�v���[�` �@1986�N�ɔ��\���ꂽ���E�ی��@�ցiWHO�j��3�i�K���_�[�́C����łȂ��Ƃ��{�s�\�ŁC�u�ɊǗ��Ɍ��I�ȕω��������炵���B���݂̂����u�Ɏ��ẤC����WHO���_�[����{�Ƃ��Ă���C���̒��S�ƂȂ�̂������q�l�ɑ�\����鋭�I�s�I�C�h�ł���B �@���ɕ⏕��Ƃ��ẮC�i1�j�R�z����i2�j�R����i3�j�R�s������i4�jN-���`��-D-�A�X�p���M���_�iNMDA�j��e�̝h�R��i5�j�X�e���C�h�i6�j���̑��i�����Ȃǁj�\������C��Ö@�Ƃ��ẮC�i1�j�_�o�u���b�N�i2�j�x���Ö@�i3�j�F�m�s���Ö@�i4�j���w�Ö@�i5�j�o��I�����_�o�d�C�h���iTENS�j�i6�j�I���\�Ȃǂ��p������B�������CWHO���_�[�ȊO�̎��Ö@�́C�Ȋw�I�����Ƃ����_�ł͗Տ��I�������s�\���Ȃ��̂�����C���̂��Ƃ͊ɘa��ÂƂ������ꐫ�����ނ����Ȃ����������邪�C����͉Ȋw�I�Ȍ����̐��i���d�v�ł���B �@���҂�QOL���l����ꍇ�C���m��w�݂̂őΏ�����ƕ���p�̘A���������C�����̎��������߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ�����B���������ꍇ�C�K�������銳�҂ɂ͓��m��w�ɂ��x���Ö@���L�p�ƂȂ�B����ɁC�ɘa�P�A����Ƃ����t�C���_�Ȉ�C��C�Ō�t�C��t�C���̑����܂��܂Ȉ�Ï]���҂�@���ƁE�J�E���Z���[�Ȃǂ���̂ƂȂ����S�l�I�ȃ`�[����Â����z�I�Ȋɘa��Âƌ�����B �l����Ⴢ�ɑ����I���̌��ʂ����� �@���݂̖��Â͔��Ɍ��ʓI�����C�����q�l���g���Ă������ɂ����؋ْ��̒ɂ݂�_�o��Q���u�ɂȂǂ�����B���R�����́u���̂悤�Ȓɂ݂ɂ��I�����悢�K���ƂȂ�v�Əq�ׁC���̗��_�Ƃ��ĐN�P�̏��Ȃ��Ƌْ��ɘa���ʂ��������B �@�������́C�����_�o��Q�ɂ��l���i�葫�j��Ⴢ�ɑ����I�����Â̌��ʂ���������i�s���̑O�����I�[�v���������Љ�B���̎�̕���p�̓^�L�T���n�R����Â�������҂ɂ悭������B���ɕ⏕���2�T�ԓ������Ă����ʂ��F�߂��Ȃ����҂�ΏۂɁC�ɂ݂�Ⴢ�ɑ����I���̗L������ visual analogue scale�iVAS�j�ŕ]�����铯�����̍ŏI���т͂܂��W�v����Ă��Ȃ����C�{�p�̉������邲�Ƃ�VAS�l�����P����X�����F�߂��Ă���Ƃ����B �`���Z�x�r�^�~��C�_�H�Ö@�` �� I /II�������������O�Ői�s���i�s�}����QOL�̉��P�Ɋ��ҍ��܂� �@���Z�x�r�^�~��C�iVC�G�A�X�R���r���_�j�_�H�Ö@�iIVC�j�͑�ʂ�VC��Ò����^���邱�Ƃɂ�肪��זE�����ł����鎡�Ö@�ł���C�������N�S�����܂��Ă���B���ۓ�����Ë���Z���^�[�i�����s�j�̖��V���������́CIVC�̗��j�I�o�܂�U��Ԃ�Ȃ���C���̎��Ö@�̍�p�@����ʒu�t�����T���B�u���݁C�����̗Տ��������i�s���ł���C�K���C���^�ʁE���^���ԁC���w�Ö@�Ƃ̕��p���@�̊m�����]�܂��v�Əq�ׂ��B IVC�̎n�܂��"����ꂽ30�N" �@1976�N�CEwan Cameron��Linus Pauling�́C����̕⏕�Ö@�Ƃ��đ�ʂ�VC�𓊗^���邱�ƂŁC�������҂̐������Ԃ���������Ɣ��\����1�j�B����� VC��10g�C10���ԓ_�H���^���C���̌�͌o���Œ����ԕ��p������������100��ƑΏƌQ1,000����r���������ŁCVC���^�Q�̕��ϐ������ԁi210���j���ΏƌQ�i50���j���4.2�{���������Ƃ�������I�ȕł������B���̌�CPauling��͓��l�̕��@��6�{�����Ƃ������ʂ����\�������C79�N�Ƀ��C���[��ȑ�w�̃O���[�v����C�i�s����ɑ���VC��ʓ��^�̌��ʂ�ے肷��_�������\����Ĉȗ�2�j�CIVC�̌����͂قƂ�Ǎs���Ȃ��Ȃ����B �@���������V�����́CPauling���VC 10g��10���ԓ_�H���^������C����ɑ�ʂ�VC���\�Ȍ��蕞�p�������̂ɑ��C���C���[�̃O���[�v��2�����Ԍo�����p���������ł���Ǝw�E�B�u2���̎����̃v���g�R���͑S���قȂ�C���C���[�̘_���������Ă���ɑ���IVC�̌��ʂ��ے肳�ꂽ�̂�IVC�̌����҂ɂƂ��ĕs�K�ȏo�����ł������v�Əq�ׂ��B �@2005�N�ɂȂ�C�w�I���Z�x�̃A�X�R���r���_������זE���E���Ƃ����_�����č����q���������iNIH�j�Ȃǂ��甭�\����3�j�CIVC �͌��������悤�ɂȂ��Ă����B �ߎ_�����f������זE���U�� �@����ɑ���VC�̍�p�@���́C2007�N�ɂȂ��Ă悤�₭�𖾂��ꂽ4�j�BVC�͐��̓��ʼnߎ_�����f�iH2O2�j�����邪�C���Ǔ��ł̓J�^���[�[�ɂ�萅�Ǝ_�f�ɕ��������B����C����זE�ɐN������H2O2�́CDNA ����у~�g�R���h���A�����Q���C����זE�����Ɏ��炵�߂�B2008�N�ɔ��\���ꂽ�i�s����ɑ���IVC�̑� I �������ł́C�ō���1.5g/kg�i�̏d60kg�̐l��90g�j�܂ł̈��S��������Ă���5�j�B �@���݁CIVC�P�Ƃł͑� I ������ �i�����Ō`����/Cancer Treatment in America Group�G�i�s����/�}�M����w�j�Ƒ�II�������i���������p��/�g�[�}�X�E�W�F�t�@�[�\����w�j���s���Ă���CIVC+���w�Ö@�ɂ��Ă��C���C��w���t��ᇓ��Ȃ��͂��ߍ����O�̎{�݂ő� I �������Ƒ�II���������i�s���ł���B �@�܂��C�����ł͂��邪�C�t���Ⴊ�č��C�J�i�_�C�؍��Ȃǂ������Ă���C���V�����̎�����ł����������p��������̔x�]�ڗ�Ŏ�ᇏ����Ⴊ����Ƃ����B �@���݂�IVC�v���g�R�����m�������̂�Hugh D. Riordan���m�ł���C"Riordan IVC Protocol"�ƌĂ�Ă���BVC 15�`100g��30�`200�����x�����ē_�H���^������̂����C���V�����́u����͉h�{�Ö@�̗p�ʂł͂Ȃ��v�ƒ��ӂ𑣂����B�֊��́CG6PD�����ǁC���x�t�s�S�C�������S�s�S�ł���B �@�Ō�ɁC�������́u�悤�₭���ڂ���n�߂����Ö@�ł͂��邪�C���ɍ�����300�{�݂ŕ⏕�Ö@�Ƃ��čs���Ă���B���ː��≻�w�Ö@�Ƃ̕��p���܂߂�����̔��W�Ɋ��҂������v�Əq�ׂ��B * 1�jProceedings of the National Academy of Sciences�iPNAS�j 1976; 73: 3685-3689. * 2�jNew England Journal of Medicine 1979; 301: 687-690. * 3�jPNAS 2005; 102: 13604-13609. * 4�jPNAS 2007; 104: 8749-8754. * 5�jAnn Onc, Advance Access �iJuly 25, 2008�j ���f�B�J���g���r���[���@2010�N1��14�� |
| ��t�́C���ɑ���"�S"�{���n��̎���ɍ�������ÁE���V�X�e���̍\�z�� |
| �V�t�Βk ���V�l�@�@�@�@���{��t�� �H�c���q���@1926�N���܂�D�t���[�̋L�^�f���� �@�V�t�ɓ�����C����́C�L�^�f��ēƂ��āC�w�s�𐫘V�l�̐��E�x�Ȃǂ̍�i��ʂ��āC����҈�Â�I������ÂȂǂɊւ��Ă��C���܂��܂Ȗ���N�����Ă���ꂽ�H�c���q�����}���C���E�ɗނ����Ȃ����q����Љ���}�������{�̈�ÁE���E��������������_�Ɛi�ނׂ����������ɂ��Č���Ă����������D �@���V�@�ߔN�C������i�݁C��Â���̕K�v�ȕ������������ŁC�Ŏ��ɂ��Ă���ÊE�̖�肩�Ǝv���Ă��܂��D���ǂ���ÒS���҂́C��w�E��p�̐i���ɂ���z������ËZ�p�Ƃ���"�Z"�������ĕ�d���邱�Ƃ��厖�ł����C�ŋ߁C�S�l�I�Ȉ�Â̕K�v���������Ă��܂��D �@�������C��Â��邢�͈�t������̏]���̍l�����ł͑Ή�������Ȃ������ǂ�����܂��D�����ŁC�H�c�搶���f���ʂ��Ď�����Ă���C��Â���ɂ��Ă̂��l�����f�������Ǝv���܂��D �@�H�c�@�ŏ��ɂ��f�肵�Ă��������̂ł����C���͈�w�E��Â̐��Ƃł͂Ȃ��C���ʂɕ�炵�Ă���l�ԂƂ��Ď���������������������C���̐��ł���f���ʂ��Ė���N���Ă��܂����D�ł�����C�S���f�l�̎��_�ł̘b�C����Ӗ��ŕ��ʂ̐l�Ԃ̗����Ȉӌ��Ƃ������Ƃł���������������Ǝv���܂��D �@ �@���V�@�͂��D�����������_���猾���Ă��������̂��厖���Ǝv���Ă��܂��D�Ƃ���ŁC������������Ƃ��낢��Ȃ��Ƃ��v���o���܂����C���͏��a17�N���܂�ł��̂ŁC�I����3�`4�������̂ł����C�搶�́C�����������̎v���o������܂����D �@�H�c�@���͑吳15�N�C�����B�̑�A���܂�ŁC����啪�N��Ȃ��̂ł�����C������ۂɎc���Ă���̂́C��O�̏��w�Z���珗�w�Z����C�Ƃ������ɂ��������̖L���Ȃ������̂��Ƃł��D�ꂪ���d�ɋl�߂���{�̂��ߗ����Ƃ͕ʂɁC�Ƃ̋߂��̒��������X�ɒ����������Ă��Ă��炤�C�傫�Ȃ��M�ɂ��낢��ȗ������Z�b�g���ꂽ�����������̂������������Ɉ�ۂɎc���Ă��܂��D����ɁC���Ƃ͈Ⴂ�C�m�荇����ߏ��ɂ��N�n�̂���������������Ƃ������K������܂����D �@�����́C���̎q�͒����𒅂����Ă����̂ł����C�ꂪ���\�n�C�J���Ȑl�ŁC�����Ē����������Ă��ꂸ�C�������͈�Ԃ����m���𒅂āC���q�l��������̂�҂��āC���������������������������̂��ƂĂ��y���݂ł����ˁD �@���V�@�m���ɁC�������ɂȂ�Ɛe�މ��҂�����t�������̂���l���W�܂��āC�ɂ��₩�ɉ߂��������オ����܂������C�ŋ߂́C�Ƒ������ŎO�������߂����ƒ낪�����Ȃ����悤�ł��ˁD�̂́C���N�ʂ����������c�c�D�J���^���╟���D�j�̎q�́C�����g���₷���낭�D �@�H�c�@�����C���N�ʂ����炢�C�J���^���₷���낭�C�H���������܂����ˁD �@���V�@���́C�������Ȃ�ł̗͂V�т╗�K���C���܂茩�����Ȃ��Ȃ�܂����D�������C�嗤�͏������ɓ���Ƒ�ςȊ��g�ɏP���邻���ł�����C���������ł��傤�ˁD �@�H�c�@��̕��ł�������C�g�����āC�������Ă��뉺10�x���炢�ł����D �@���V�@���C�Ŋ����Ȃ��삳��ł��炵���̂ł����D �@�H�c�@�����C���͂��܂��v�ł͂Ȃ��C�̑��Ƃ��X�|�[�c�͎����ċ��ŁC����قNJ����ł͂���܂���ł����D �@���V�@�w������́C���{�ʼn߂����ꂽ�̂ł��ˁD �@�H�c�@�����ł��D���R�w���ɓ���C�Ƃ���A�������̂ŁC3�N�ԗ��ɓ����Ă��܂����D �@���V�@�w��������g�f��ɓ���ꂽ���̎v���o�͉�������܂����D �@�H�c�@�w������͑����m�푈�^���������ŁC�s��̔N�̑��Ƃł��D���ł͐H�ו����قƂ�ǂȂ��C�Ђǂ����������Ă��܂����D�Ō�̈�N�Ԃ͊w�k�����Ƃ��Ē�����s�@���쏊�ŗ��̃G���W��������C���͐��ՍH�ł����D�s��̔N�̎O���C���Ǝ��ŋ�P������C�L�O�ʐ^���Ȃ�����ł����D���ƌ�C��A�̉Ƃ܂ŁC���ʂȂ�O���l���̂Ƃ�����\���ȏォ���āC����ƋA��܂����D �@�O�N�����Ĉ����g���āC�{�Вn�̐É��ŏo�ŎЂɋ߂��̂ł����C�����ɏo�����āC����c�����̂����e�ɂ�����GHQ�̃`���y���Z���^�[�ɋ߂܂����D���̎��C���R�w���̉��t�̉H�m���q�搶���C������g���X�Ɉ��������Ă��ꂽ�̂ł��D �@�����C���������ł͊�g���X���g�b�v�ł������C��g�ΗY���́u���ꂩ��͉f�������̎���ɓ���v�Ƃ�����u���Ă���ꂽ�C��̌����ŗL���Ȗk�C����w�̒��J�F�g�Y���m�̌������i��g�f�搻�쏊�̕�́j�ɁC�X�^�b�t�ɓ���Ȃ����Ɛ����|�������̂ł��D���́C�f��͂悭������Ȃ������̂ł��f�肵���̂ł����C�u�{�̕ҏW�͂ǂ��ł��傤�v�ƌ����C�w��g�ʐ^���Ɂx�̕ҏW�X�^�b�t�Ƃ��āC���J�F�g�Y�������ɓ������̂ł��D �@�������J�F�g�Y�������ɂ́C�ʐ^�̐��E�ł͔��ɗL������������m�V������g�ʐ^���ɕҏW���ŁC����ƁC����U���Ă����������H�m���q�搶�̑��q����ʼnf��ē̉H�m�i���C�f�����肽���Ƃ������Ƃœ����Ă����܂����D �@�ŏ��͕ҏW�����Ă����̂ł����C�f��̕������Z�����Ȃ�C������̃X�^�b�t�Ɉ��������C���o�����炨�����낢���̂ł�����C�f��̎d��������悤�ɂȂ����̂��C���̐��E�ɓ��������������ł��D �@���V�@�����f��̂��Ƃ͑S��������܂��C�f�������̂͑�ς��Ǝv���܂��D���́C���{�씪�ēC�݂ˎq��v�Ȃ́C���̐e�̊��҂������W�ŁC���ɐe�������Ă���āC���c�i�������j�̎���֍s���܂��ƁC����Ƃ��\�z�̓r���Ȃ̂���ςȂ���J������Ă���̂�������܂�������D �@�H�c�@���́C�h�L�������^���[�f��ŁC���{�씪����͌��f��ł�����C���낢��ȓ_�ňႢ������܂�����ǁC�f��Â���͊m���ɑ�ςł���ˁD ��t�{���̎g���ƏI������� �@���V�@�搶������ꂽ�f��C�w�s�𐫘V�l�̐��E�x�w���S���ĘV���邽�߂Ɂx�w�I���悯����ׂĂ悵�x�Ȃǂ́C������ÊE������l���Ă����ׂ��C���܂��܂Ȗ����N����Ă��܂��D�������C�����̖������z���Ă������Ƃ͔��ɓ���Ƃ������܂��D �@�I������Âł́C������Ƃ����ʂƂ������Ƃ́C���̐l�̖��Ȃ̂ł��傤���C��ÒS���҂Ƃ��ẮC���N�ɂȂ��āC������x���A���Ă������������Ƃ����̂��{���̎g���ł���C���̂��߂Ɏ����̎��Ă�m����Z�p�����킯�ł��D�������C���{�l�̍l�������C�g���������������Ă���Ă����̂́C���������ȂƂ������Ă���C���̓_�͌������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��D �@�����C�I������Âł��z�X�s�X��Âł��C���������铹�͂Ȃ��̂��ƓO��I�ɓw�͂���̂���t�̎g���ł���C�ŏ�����z�X�s�X��ÂƂ��I������ÂɐϋɓI�Ɏ��g�ނ��Ƃ́C�u��Õ����v�ȂǂƔᔻ�𗁂т��˂��C��t���Ƃ��ẮC�Ȃ��Ȃ����ݐ�Ȃ�����Ƃ��낪����܂��D �@�h�L�������^���[�f��́C���炭���͎����̂ł��傤���C�ڂ̑O�ɋN�����Ă��錻�����f�������Ă�����킯�ŁC���낢��Ȃ��̂����߂��Ă���͂��ł����C�����͉�������������炢���̂ł��傤�ˁD �@�H�c�@��������������炢�����Ƃ�������͍���܂��ˁD���̍�i���i���Ă��邱�Ƃ����ł����āC������Ƒi������C������Ɗ����Ă�������킯�ł�����C����͍�i�̖��ł����Č�����̖��ł͂Ȃ��ł���ˁD �@���V�@�m���Ɉ�ۂɎc��f���́C�S�����Ɏc���Ă��܂��ˁD�w�ԂЂ��x�Ƃ�����i���C�{���ƖY��Ă��܂��܂����C�f��̉f�������͏����܂���C�������ł���ˁD �@�H�c�@���������悤�ɉf���̗͔͂��ɋ����āC"�S���͈ꌩ�ɂ�����"�ƌ����܂����C�{�������ς��ǂނ����C�p�b�ƌ����f����ŕ������Ă��܂��D������C����Ӗ��ŁC�f�������Ƃ����̂͐ӔC������Ǝv���܂��D �@���܂ʼnf�搧��̂Ȃ��ŁC�ǂ̂��炢��Â̎d���ɂ�������Ă������v���Ԃ��Ă݂܂�����C��g�f�搻�쏊��1964�N�ɁC���{��t��̊��ŁC�wTV��w�����u���x�Ƃ����e���r�ԑg���������̂ł����C���̎��̉�͕������Y�搶�ł����D���́C�����C�䒃�m���̈�t��قɎf���āC�����搶�����̒��Ō����Ă���قǕ|���搶���Ƃ͒m�炸�ɂ��b�����Ă����̂ł��D �@�����������̂́C�u�]�o���v�u�_�o�ǁv�u����ǁv�Ȃǐ��{�ŁC���ꂪ��w�ɂ���������ŏ��ł��D1960�N��̌㔼�ŁC���{�̈�w�������������Ői�����C�܂��Ɉ�w�ɑ���M���������܂�Ƃ���ł����D �@���V�@���a30�N�ォ��́C���{�̌o�ς��������C��w���}���ɐi����������ł��ˁD �@�H�c�@��������w�̔ԑg������Ȃ���C�u�Ȃ�Ĉ�w�͂������̂��낤�v�ƁC�傫�ȐM�������������̂ł��D���ꂼ��̐�啪�삪���̂������i�����Ă����r���������Ǝv���܂��D �@���̌�C�S�R�Ⴄ�d���ɓ������̂ł����C���̈�w�ɑ��Ď�����{�I�ȋ^����������̂́C�\�N�������Ȃ�1972�N�C���̖�������ŖS���Ȃ������ł��D�������ʂ������ɂ���C���o���S�̂ɓ]�ڂ��Ă������Ƃ���U�ŕ�����܂������C���߂͂��������Ă��܂��C������������Ȃ������D���Ƃ������Ƃœ��@���C���J���ŖS���Ȃ����̂ł��D���̎��C�ŏI�I�ɒɂ݂����ɂЂǂ��Ȃ��āc�c�D �@���V�@�ɂ݂��Ђǂ������̂ł��ˁD �@�H�c�@�����D�����q�l��ł��Ă�������̂ł����C�����Ԃł܂��ɂ���̂ŁC�u���Ƃ����Ă��������v�Ƃ��肢����ƁC�u�̂Ɉ�����������łĂȂ��v�ƌ�����̂ł��D���͋����C�ɂ݂ɑΉ������Â��Ȃ����Ƃ�s�v�c�Ɏv���܂����D �@���ꂩ��C�Ō�ɁC�������߂��ȂƎv�������ɁC�������Ƒ��͕�������o����C����҂��x�b�h�ɔ�я���āC���̑̂��������Ă���D�����C�S���}�b�T�[�W���Ǝv���̂ł����C���炭���āC�u���Ƒ��̕��C�ǂ����v�ƌ����ē�������C���͎���ł��܂����D���́C���̎��C��Â͐l�������ƂɏW�����C�ǂ�����Ă������Ȃ��������ƂŏI���ɂȂ�v�z�����Ȃ��̂��Ǝv���܂����D �@�l�Ԃ͂ǂ�Ȃ��Ƃ����Ă����ʁD�����Ĉ�Â͍ł����ɑΉ����Ă���w��ł���C�Z�p�ł���킯�ł��D�������C���������Ă����߂������Ƃ������Ƃł��������l���Ă��Ȃ����ƂɁC���ɋ^��������܂����D �@�l�Ԃ����ʎ��ɁC�ł��g�߂ɑ��݂����҂����ɂ��ĉ����l���Ă��Ȃ��̂͂��������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����̂ł��D�ł��C����҂���́C���h���ׂ��C�����|�����݂ł�����C����Ȃ��Ƃ�������e��������҂�����g�߂ɂ��Ȃ������̂ŁC���͂�������ݍ��܂܁C���\�N���߂��Ă��܂����킯�ł��D �@���V�@����̖�����Âɂ��ẮC�������d�˂��C���{��t��ł��C�w������ÂɊւ���P�A�̃}�j���A���x�i�������N9��15�����s�j��w����ɘa�P�A�K�C�h�u�b�N�x�i����20�N3�����s�j���̍��q���쐬���C����ɔz�z����Ȃǂ��āC�����Â̐����̌����}���ēw�͂����Ă���Ƃ���ł��D ���E�����ɑΉ�����V�X�e���̏d�v�� �@�H�c�@���̌�C���܂��܂ȌX���̍�i�������Ă����Ȃ��ŁC�����Ăш�ÂɌ��������������ƂȂ����̂��C�w�s�𐫘V�l�̐��E�x�Ƃ�����i�ł����D �@���́u�F�m�ǁv�ƌ����܂����C1982�N�����́u�s���ǁv�ɂ͑Ή��������Ȃ���̓I�Ȏ��Õ��@���Ȃ��ŁC���鐻���Ђ���F�m�ǂɑ�����̂�������l����w�p�f������肽���Ƃ����b����g�f��ɗ����̂ł��D����������S�����邱�ƂɂȂ�C�ďC�҂ŁC�������}���A���i��ȑ�w�������������J��a�v�搶���C�u�F�m�ǂɑ��Ĕ��ɂ��炵���Ή������Ă��邩��v�ƏЉ�Ă����������̂��C�F�m�ǂ̕���50�l���炢���@���Ă���F�{��K�a�@�ł����D������10���C�B�e�Ŗ�1�J�������̂ł����C���́C�F�m�ǂ��ǂ�Ȃ��̂��S���m��Ȃ������̂ŁC�l�Ԃ�����Ȃӂ��ɂȂ��Ă��܂��ƒm��C�{���ɃV���b�N�ł����D�@���̎����N�m�搶�́C�u�m���ɔF�m�ǂ͎���Ȃ����C���̎d���ŏ�Ԃ͉��P�o����v�ƌ����C��������l�́C�����Ă����m�\�ł͂Ȃ��C�c���Ă��������đΉ����Ȃ����Ƃ����̂��匴���ł����D �@���Y�ꂪ�Ђǂ��Ȃ�C�����������������Y��Ă��܂����l�́C�u����������������Ȃ��́v�Ƃ��u�܂��������Ƃ������āv�ƁC�Ƃ̐l�Ɉ������Ƃ̎w�E�������ꂸ�C���x���{���āC���_�s���ɂȂ�C�ُ�s���������Ă���D����ŁC��ɕ����Ȃ��Ȃ��ĕa�@�ɂ���킯�ł����CK�a�@�ł́C����҂�����Ō�t������C���N��肪��������Ă���ɔے�I�Ȍ��t���g��Ȃ��̂ł��D �@�����ɂ���l�͉�������Ă������ē{���Ȃ��D�{���Ȃ��Ƃ������Ƃ́C�����̑��݂͔ے肳��Ă��Ȃ��Ƃ������ƂŁC���_�����������ĉ��₩�ɕ�点��悤�ɂȂ�D�ł�����C�m�\�͐����Ă��邯��ǁC���������ĐÂ��ȏI�����}���邱�Ƃ��o����킯�ł��D�����搶�́C�u�����ł͖�͂قƂ�ǎg���܂���D�������1�T�ԁC�x���Ă�1�J���C�撣���Ă��������Ή������Ă���C�݂�ȗ��������Ă��āC�Ǐ��P�����ꍇ������܂��v�ƌ����܂����D���ꂪ������悤�ȉf����B�肽���Ƃ������̂��C�w�s�𐫘V�l�̐��E�x�ł��D �@���́C���̉f������邨��҂���Ɍ��Ă������������ɁC�u��̂ǂ��̎{�݂ł����D�a�@�Ȃ̂ł����v�ƕ����ꂽ�̂ŁC�u�����C�a�@�ł��v�Ɠ�������C�u�a�@�Ȃ̂ɁC���̎��Â����Ă��Ȃ�����Ȃ����v�ƌ���ꂽ�̂ł��D���́C�n�b�Ƃ��܂����D�܂�C����҂���̈ӎ��̂Ȃ��ł́C��삪���ÂɌ��ѕt���Ă��Ȃ��D�Ȃ������d�v�����Ȃ��̂��낤�ƕs�R�Ɏv���C�܂��C�h��ŕ������܂܂ɂȂ�܂����D �@�����C���N����F�m�ǂ̕�������č����Ă���Ƒ��͂��������̂ł����C�ǂ����Ă����������炸�C���ԑ̂������āC�݂�Ȗق��Ă��܂����D��f��ɂ́C�Ƒ��ȂǁC�吨�̐l�����ɗ����܂����D�܂�C��������ĎЉ���ɂȂ��Ă��Ȃ������F�m�ǂ̖�肪�C���̉f��ɂ���ăI�[�v���ɂȂ��Ă������̂ł��D �@���́C�S���z�������Ă��Ȃ������̂ł����C��f����������ƂȂ��āC�u�����ꂪ�Ȃ邩������Ȃ��D���̎�����������삪�K�v�Ȃ�C�����̖��Ƃ��čl���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����b�������̏ꂪ�C���������ŋN���Ă����̂ł��D�t�Ɏ�����������������̂́C�F�m�ǂւ̑Ή��������邾���ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��C�܂�C�Ή��o���Ȃ��Ƒ����吨����Ƃ������Ƃł����D�ǂ��̒n��ł��C���ɑΉ��o����V�X�e�����v��ƒɊ����C�w���S���ĘV���邽�߂Ɂx�Ƃ����f������邱�ƂɂȂ����̂ł��D �@���́C�w�s�𐫘V�l�̐��E�x����������C���ʗ{��V�l�z�[���i���{�j�������ƕK�v���Ǝv�����̂ł����C�����ł͕K�����������`�����悤�ȑΉ������Ă��Ȃ��D�Љ�Ή��o����悤�ɂƍl���āC�ǂ��{�݂�T�������Č������̂��C���r�c���̃T���r���b�W�V�����ŁC�w���S���ĘV���邽�߂Ɂx�́C���ׂĒr�c���Ŏ�ނ��邱�ƂɂȂ�܂����D �@���̍��́C�ǂ��̓��{�������I�ŁC���ւ�F�m�ǂ̂��N��肪���鏊�͕K���܂��Ă���̂ł��D�߂�Ɖ��z�Ƃ������ƂŁC�V�����v�̓��{�̂Ȃ��ɂ́C�L�������邮�����悤�ɂȂ��Ă��āC�F�m�ǂ̂��N��肪��������1���������Ă���Ƃ����{�݂�����܂����D �@���V�@���݁C�����̒s��Ή��̕a���͊O�֏o��ꂸ�C���邮�����L�ɂȂ��Ă��܂��ˁD �@�H�c�@�����ł��D��������ĔߎS�ȋC�����ɂȂ�܂����D�Ƃ��낪�C�T���r���b�W�V�����ł́C���ւ��f�C���[���̃x�����_�̌˂��J���Ă��āC�F�m�ǂŜp��l�͏o�čs���Ă��܂��D����ƁC�p��l���Ƃ�"�p����p�[�g"�Ƃ����A���o�C�g�̒S���҂����āC�����ƈꏏ�ɕ����āC�����тꂽ���A���Ă���DK�a�@������i�Ή������Ă����̂ł��D �@����ɁC�����C�������i��ł���ƌ����Ă����C�A�����J��X�E�F�[�f���Ȃǂ̕�����i���ɍs�����ƍl���܂����D�A�����J�́C�V�l���Z�ނ��炵���n�悪�o���Ă����̂ł����C���̒n�悾���ł����̂ŁC���S�̂Ƃ��đΉ����Ă����X�E�F�[�f���ɍs���Ď�ނ����킯�ł��D �@���V�@������i���Ƃ��ẮC�k���̃X�E�F�[�f����f���}�[�N���L���ł��ˁD �@�H�c�@�����C�f���}�[�N�͔F�m�ǂ̐l�͕a�@�ɓ��@�����Ă���ł������C�X�E�F�[�f���ł̓��^���Ƃ������ŃO���[�v�z�[�������������Ƙb��ɂȂ��Ă��܂����D�f���œ��{�ɃO���[�v�z�[�����Љ�ꂽ�̂́C�w���S���ĘV���邽�߂Ɂx���ŏ����Ǝv���܂��D�܂����{�ł́C�u�O���[�v�z�[���v�Ƃ������t���Ȃ��C���͉f��̂Ȃ��Łu�O���[�v�n�E�X�v�ƌ����Ă��܂����D �@���́C�O���[�v�z�[������ނ��āC�ƂĂ����ꂵ�������̂ł��D�Ƃ����̂́CK�a�@�ł́C���ꂾ�����������Ă���̂ɁC�[���ɂȂ�ƁC�݂�ȁu���낻��ƂɋA��܂��v�ƌ����ăi�[�X�̏��ɗ���D�������Ƃɂ���Ƃ͂�����v���Ă��Ȃ��D�ǂ������炢���̂��낤�ƍl���Ă��܂����D �@���ꂪ�C���^���̃O���[�v�z�[���ł́C�݂�Ȏ����̉Ƃɂ���Ǝv���ė��������Ă���̂ł��D���{�Ƃ͂����Ⴂ�ɑ����X�^�b�t���Ƒ��Ƃ��đΉ����C�䏊�ŗ�������������C�݂�Ȃňꏏ�ɐH����������ƁC�ƒ�I�ȕ��͋C������グ�Ă��āC�F�m�ǂ̐l�ɂ͂��������Ή����K�v�Ȃ̂��Ƌ��������܂����D �@1990�N�Ɂw���S���ĘV���邽�߂Ɂx���������鐔�J���O�ɁC�����ȁi�����j���u����ҕی��������i�\�J�N�헪�i�S�[���h�v�����j�v�\���C����ƑO�シ��`�ł����̂ŁC�����̕������Ă��������܂����D �I������ÂŖ�����t��"�S" �@���V�@�F�m�ǂ̕��̉�삩��C�����V�X�e���̂�����ւƁC�u�V�����x����v�Ƃ����e�[�}�̍�i�������Ă���ꂽ�킯�ł��ˁD�����āC�w�I���悯��� ���ׂĂ悵�x������ꂽ�c�c�D �@�H�c�@�͂��D���̂����C�قƂ�ǂ̐l���I�����ɂ͕a�@�ɉ^��Ă������{�̃T���r���b�W�V�����ɁC�ɘa�P�A�ɑΉ��o�����t���풓����悤�ɂȂ��āC80���̐l���{�݂ōŊ����}����悤�ɂȂ�D�]���Ƃ����̂ł��D���̍��ɂ͊ɘa�P�A�a�����o���āC����̏I�����ɂ��Ă����ɂȂ��Ă��܂����D �@�����āC�x�R���̎ː��s���a�@�Ől�H�ċz����O�������߂Ɋ��҂��S���Ȃ����Ƃ������Ƃŕa�@�����Ӎ߉�������Ƃ̕����āC���������ƕ����Ă�����Âɑ���s�M���̂悤�Ȃ��̂��\�����Ė�莋����C�b�������Ă������͋C���o���Ă����ȂƊ����܂����D���ꂪ���������ł������̂��C�w�I���悯��� ���ׂĂ悵�x�ł��D����܂ł́C�l�Ԃ̎��ɂ��Ă��ꂱ�ꌾ���͙̂H�z�ł͂Ȃ����C�m�����Ȃ����C���̂������Ȃ��Ƃ��������ł������C����80���z��������C���������Ă������Ƃ����C�ɂȂ��Ă������̂ł��D �@��قǁC��̂��b���f���āC����҂���́C�ӔC�킳��C������������i�ׂ��N�������̂ł�����C����Ƃ���܂ł�낤�ƍl����͓̂��R�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����C��͂�C��w�C��Â������ǂ��Ƃ炦�邩�Ƃ������Ƃ��C���炵�Ȃ�������Ȃ��Ǝv���̂ł��D �@����͋��炾���ōςޖ��ł͂Ȃ��C����҂����l�ЂƂ�̌��ӂƂ������C�v�z�̖��ł��D�͂����肵���v�z��������Ǝ����Ă��邨��҂���ł���C���҂���͔[�����邵�C���Ƃ��i�ׂ��N�����Ƃ��Ă��C�Ή��o����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��D�����������Ƃ��l���ė~�����Ǝv���Ă������̂��C���̉f��Ȃ̂ł��D �@���V�@���̐搶�̂��b�ɁC����C���{�̈�ÁE���ɋ��߂��邱�Ƃ��S������Ă���悤�Ɏv���܂��D���̒��������Ȃ�������Ȃ��Ǝv���܂����C��t�ɂ́C��͂苳�炪�厖�Ȃ̂ł����C�ǂ��������Ă��܂��ˁD �@�z�X�s�X��ɘa�P�A�ȂǏI�����Ɉ�Ò�����ꍇ�́C�m���C�����C�N�w�C�ϗ������łȂ��C�@���Ȃlj����S���x������̂��Ȃ��Ɩ������낤�Ǝv���܂��D �@���ꂩ��́C������t�̐��c�̂Ƃ��Ă��C�������o���_�Ƃ��Đ������Ă��������Ǝv���܂��D�C���t���G���U�̃��N�`���ڎ�Ȃǂɂ�����"�u�[�X�^�[����"�ł͂���܂��C���ӂƂ��u�Ƃ��������̂��C�Ō�͐����̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��čL�܂�C�傫�ȗ͂ɂȂ��Ă����܂��D �@��Âɂ����ẮC�w����ËZ�p���厖������ǂ��C���ɑ���"�S"��|�����Ƃ̏d�v����搶�ɂ��w�E�����������悤�ȋC�����܂��D �@�H�c�@���Ȃǂ������͙̂H�z�ł�����ǂ��C�{���Ɉ�l�̊��҂Ƃ��āC����҂���Ɋ��҂��邱�Ƃł��D �@���V�@���̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��D�����C���N�ɔ]�O�ȁC8�N���炢�O�ɏ������2��̎�p���Ă��܂��D�ڂ݂Ď�������Â��銳�҂Ƃ�������ɂȂ�ƁC���G�Ȃ��̂�����܂��ˁD �@�������C�݂�Ȃ̋C������傫���������Ƃ����̂͑�ςȂ��Ƃł����C�f��́C�f�����C�������L���Ă����܂�����C���������_�͂����ł��ˁD �@�H�c�@�����ł��D�w�s�𐫘V�l�̐��E�x�����������̔��������āC�u�����C�f���̎d�������Ă��Ė{���ɂ悩�����v�Ǝv���܂����D �@���V�@���ꂩ��800���l�Ƃ�����c��̐��������҂Ƃ�����N��ɒB���C�Ŏ����삪�K�v�ƂȂ��Ă��܂��D����ɁC�F�m�ǂ̕����������Ă��܂�����C���̒����ǂ��Ή����Ă������͑傫�Ȗ��ł��D���������Ƃ����ǂ����̎���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��C�����̊F����ɂ����Ƃ��C�t���ė~�����̂ł��D �@���͂����C�u�n��̊F���C�t���Ď��g��ł���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ƙb���Ă���̂ł����C�܂��F�m�ǂƂ����_��Q�Ƃ��������X�ɑ��Ēn��Љ�̎v���͌����Ă��Ȃ��̂�����ł��ˁD �@�H�c�@�����ł��ˁD�ł��C�w�s�𐫘V�l�̐��E�x�������������猩����C�F�m�ǖ��ւ̔F���͔��ɍL�����Ă����悤�Ɏv���܂��D �@���ł́C�������ƌ����Ă��C�����s�v�c����Ȃ�����ɂȂ�܂�������ˁD �@���V�@�]���ǐ��̔F�m�ǂ͖h���邩���m��܂��C����͈�w�I�ȑ傫�Ȗ���ł��D �@�������C���ǂ��ꂽ�����ǂ����邩�Ƃ������Ƃ��厖�ŁC�F�m�ǂɌ��炸�C������Î҂��C�n��̈�t��𒆐S�ɂ��āC�����̃j�[�Y�ɉ�������悤�ȁC�n��̎���ɍ�������ÁE���V�X�e���̍\�z�𐄐i���Ă����ׂ����ƍl���Ă���̂ł��D �@��ÁE���E�����̕���ŁC�ǂ̂悤�Ȗ������ʂ����Ă������C���C����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��D �@�{���͖{���ɁC���肪�Ƃ��������܂����D ����j���[�X�@2010�N1��20�� |
| ��22����{�����a�@���_��w�� ���g�ݐi�ނ��҂̐S�̃P�A�Ɋ��� |
| �@����f�ØA�g���_�a�@�ɂ�����ɘa�P�A�`�[���̐ݒu���K�{�ƂȂ�C�ɘa�P�A�ƕ����"�S�̃P�A�i���_��ᇊw�j"�����ڂ����悤�ɂȂ��Ă����B���s�ŊJ���ꂽ��22����{�����a�@���_��w��̃V���|�W�E���u�ɘa�P�A�Ɛ��_��ᇊw�̖ڎw�����́v�ł́C���҂��悷�邳�܂��܂Ȑ��_�Ǐ��S����Ԃɂ��āC�����Â̌���̍őO���ŐS�̃P�A�Ɍg��鐸�_�Ȉォ��̕��s��ꂽ�B �S���Љ�I����@�̊J�����i�� �@����Տ��ɂ����邳�܂��܂ȐS�����ʂ̖��ɂ��Č��y�������É��s����w��w�@���_�E�F�m�E�s����w�̖��q���j�y�����́C���҂ł͂����鎞���ɑ��ʂȐ��_�Ǐ��S����Ԃ��F�߂���ƊT���B�����������҂̌X�̐��_�Ǐ��S����Ԃɑ��āC�Ȃ�炩�̉�����K�v�ƂȂ��Ă��Ă���C���݂͐S���Љ�I����@�̊J�����i��ł��邱�Ƃ�����B �@���q�y�����ɂ��ƁC���_��w�I�f�f�̊ϓ_����́C���҂͑S�a���ɂ����Ė��ɂȂ�炩�̐��_�Ǐ����C���ɕs���C�}���̕p�x���������Ƃ�������Ă���B����Ƌ������Ȃ��琶����u����T�o�C�o�[�v�ɂ����Ă��C�Ĕ��E�]�ڂ̕s���C���Ȃ킿"�Ĕ��s��"�̕p�x�͍����B �@�܂������̉u�w�����ɂ����āC���҂͈�ʐl���ɔ�ׂĎ��E������2�{���x�C�L�ӂɍ����C���ɐi�s����̊��҂Őf�f�㐔�����ȓ��̎��E���ł��������Ƃ����ʂ��Ď�����Ă���B�ŋ߂̊ɘa��Â̌���ł́C�I�������҂ɂ����đ����F�߂���u�����I��ɁiPsycho-existential suffering�j�v�i���Ȃ̑��݂ƈӖ��̏��łɋN�����Đ������Ɂj�ɊS�������C���̌������i��ł���B �@�܂����y�����́C�R����^�Ɋ֘A���Ĕ����������Țq�C�E�q�f�Ƃ��āC�Óf��p�̋����R�������J��Ԃ����^����Ă��銳�҂ł́u�\�����S�E�q�f�v����30���ɔF�߂���ƕB�_�H���ɓ�������C�_�H�{�g����������C���˂̑O�ɃA���R�[�����ł����ꂽ�����ň��S�C�q�f�𗈂����Ƃ�����Ƃ����B �@�����������҂̍Ĕ��s��������I��ɂȂǂɑ��ẮC���ۓI�ɂ��W�����Ö@���m������Ă���킯�ł͂Ȃ��B���݂킪���ł́C���Ɍ����J���Ȃ̌����ǂ����S�ƂȂ�C�Ĕ��s���ɑ��Ắu�������Ö@�v�C�����I��ɂɑ��Ắu�f�B�O�j�e�B�Z���s�[�v�̊J�����i�߂��Ă���Ƃ����B �@�������Ö@�́C��肪��������ΐ��_�Ǐ��P����Ƃ����V���v���ȃ��f���ŁC�u�������Z�@�i5�X�e�b�v�j�v�őΉ��\�Ƃ����l���̂��ƂɎ��Ã}�j���A�����쐬����Ă���C���ۂɏp��̓����҂ɑ��ēK�p�������ʁC���_�Ǐ��P�������Ƃ�������Ă���B �@�f�B�O�j�e�B�Z���s�[�́C�i�s�E�I�������҂̎����I��ɂ��ɘa���C���҂̌Ƃ��Ă̑������ێ����邽�߂̎��ÂŁC9�̎���v���g�R���Ɋ�Â��ʐځi30�`60����3�C4��j��^����C���������������Ŋ��҂Ƌ�����ƂŕҏW���s���B �@���y�����́C�����������҂ɑ��邳�܂��܂Ȑ��_�Ǐ�C�S����Ԃɑ��ĐV���ȐS���Љ�I����@�̊J�����]�܂�Ă��邱�Ƃ��w�E�����B �����Âɐ��ʂ������_�Ȉオ�K�v �@���҂͂��܂��܂Ȑ��_�Ǐ��悷�邱�Ƃ������B��ʈ�ȑ�w���ۈ�ÃZ���^�[���_��ᇉȂ̑吼�G�������́C���҂̐��_�Ǐ�͎��Â���ѓ��퐶���̂��܂��܂Ȗʂɕ��̉e�����y�ڂ����Ƃ��w�E���C�����Â₪�҂���т��̉Ƒ��̐S���Ȃǂɐ��ʂ������_�Ȉ�̐f�Â̕K�v�������������B �o�^���_��ᇈ㐧�x���X�^�[�g �@�吼�����́C���҂ɂƂ��Đ��_�Ǐ��"���"�ł���Ǝw�E���C�u���҂́C���w�Ö@�����C���a�̂ق����ꂵ���ƌ����v�Əq�ׂ��B�܂��C���҂̖�9���͏p�㉻�w�Ö@���Ă��邪�C�}���Ǐ��悷�邪�҂ł́C��5�������p�㉻�w�Ö@���Ă��Ȃ��Ȃǂ̕�����C�ӎv�����Q��QOL�̒ቺ�C����ɉƑ��̐��_�I��ɂ⎩�E�ȂǁC���܂��܂Ȃ����Âɋy�ڂ����_�Ǐ�̕��̉e��������ƊT�������B �@���̂����œ������́C�����Â₪�҂̐S���C���_��w�I�Ȗ��ɐ��ʂ������_�Ȉ�ɂ��f�Â̕K�v�������������B �@�܂��C���҂̉Ƒ��͎����̋�Y��i���Ă͂����Ȃ��ƍl���C�Ƒ��̋�Y�͉ߏ��]�������X�������邪�C���҂̉Ƒ���"��2�̊���"�ƌ����Ă���C���ÂƃP�A�̑Ώۂł���Ǝw�E�B�����Âɏ]�����鐸�_�Ȉ�́C���҂̉Ƒ��̐S���ɂ����ʂ���K�v������Ƃ����B �@���������g�͊��ɁC�����̂��ҁC�Ƒ��̐f�Â��s���Ă��邪�C��������̐f�Â��s���Ȃ��Ō����Ă�����̂�����C������Ҍ����邱�ƂŁC���_��ÑS�̂̔��W�Ɋ�^�ł���ƍl���Ă���Ƃ����B �@�ŋ߂ɂȂ�C"�T�C�R�I���R���W�[�i���_��ᇊw�j"�Ƃ����w�₪���ڂ����悤�ɂȂ����B���{�T�C�R�I���R���W�[�w��ł́C�{�N�x����u�o�^���_��ᇈ�v���x���J�n���C�z�[���y�[�W�ihttp://jpos-society.org/�j��œo�^���_��ᇈオ���J�����\��ł���B�������́C�����Âɂ����鐸�_��ᇈ�̕K�v�������������B �i�s���҂̑傤�a�ɑ���Ö@�A���S���Y�����T�� �@���҂ɍ������邤�a�ƓK����Q�́C��ʐl���ɔ�ׂėL�a���������C���Âɓ������Ă͂���̕a��C���Â��l�������Ή����K�v�ɂȂ�B��������Z���^�[�����a�@�i�����s�j���_��ᇉȂ̐��������́C���҂ɍ������邤�a�C�K����Q�̐f�f�C�����C����@�̎��ۂȂǂɂ��ĊT�������B ��Ã`�[���̘A�g�����Ή����d�v �@�������ɂ��ƁC���@�ł͂��҂̂��a�̐f�f�ɂ��ẮC���ʂȐf�f����p�����Ă���킯�ł͂Ȃ��C�č����_��w��ɂ�鐸�_�����̕��ނƐf�f�̎������4�ŁiDSM-IV�j���p�����Ă���B�������C���f�f��ɂ���u������Q�v�C�u�H�~�ቺ�v�C�u�v�l�E�W���͒ቺ�v�C�u���ӊ��v�Ƃ������Ǐ�͂���ɂ��Ǐ�Ƃ̋�ʂ�����B�Ⴆ�C�݂��i�s����ƁC����̏Ǐ�Ƃ��ĐH�~�ቺ�������邱�Ƃ�����B�����́u���a�̐f�f��Ɋ܂܂�邱���̏Ǐ���ǂ̂悤�ɕ]�����Ă������́C����ꂪ��ɔY�ނƂ��낾�v�Əq�ׂ��B �@���̂��߁C���҂̂��a�f�f�@�Ƃ��āCDSM-IV�̐f�f��݂̂ɕ߂���Ȃ���I�f�f�i����̏Ǐ�ɂ��\���������Ă������j�C���O�I�f�f�i����̏Ǐ�ɂ��\��������Ǐ�͊����O���j�C��֓I�f�f�i����̏Ǐ�Ɋ֘A����\��������ꍇ�͑�֊���̗p����j�Ȃǂ������̃A�v���[�`�@����������Ă���B�ǂ̃A�v���[�`�@����ΓI�ɐ������Ƃ������̂ł͂Ȃ����C���݂́u�ߑ�]��������ߏ��]�����Ă��a���������Ă��܂����Ƃ̃f�����b�g�̂ق����傫���v�Ƃ����̂��Տ��łقړ����Ă���R���Z���T�X�ł���C��I�f�f���p�����邱�Ƃ������Ƃ����B �@�܂��C���a�ɑ���Ö@���s���ꍇ�ɂ́C���҂Ɋ��ɏo�����Ă���Ǐ�Ȃǂ��l���Ȃ���C�R����̑I�����s���K�v������B�����́C���Z���^�[�ł͐i�s���҂̑傤�a�ɑ���Ö@�̃A���S���Y�����쐬���Ă���ƕ����B�傤�a�̏d�Ǔx�]���Œ����x����d�ǁC���邢�͌y�ǂł��x���]�W�A�[�s���n�R�s����̃A���v���]�������^�Ŗ����ȏꍇ�ɂ́C��ʓI�ȍR���p�����邪�C���҂̌X�̕���p�v���t�B�[���ɂ���Ďg���������Ă���B�Ⴆ�C�R�����𓊗^���Ă��ēf���C�ŋꂵ��ł��邪�҂ɁC����ɓf���C�̃��X�N�̂���I��I�Z���g�j���Ď�荞�ݑj�Q��iSSRI�j��Z���g�j���E�m���A�h���i�����Ď�荞�ݑj�Q��iSNRI�j�𓊗^���邱�Ƃ̓��X�N�������ƍl�����Ă���B �@�܂�������́C���@���_��ᇉȂɏЉ��CDSM-IV�ɂ��傤�a�Ɛf�f���ꂽ�Ǘ�̂����C���_�ȏЉ��3�����ȓ��Ɏ��S���m�F���ꂽ20���ΏۂɁC�I�������҂̂��a�ɑ��鐸�_�ȉ���̗L������\���I�Ɍ��������B���̌��ʁC�\��1�����ȓ��ł�����9�ᒆ8��́C�R���^�ɂ��Ǐ���P�͔F�߂��Ȃ������B�����́u�\��1�����ȓ��̂��҂ɍR����𓊗^���郁���b�g������̂��B�ނ��땛��p��������ɏo�Ă��܂��̂ł͂Ȃ����v�Ǝw�E�B�I�������҂̂��a�ɂ��ẮC�����čR����͓��^�����C���ӊ��ɂ��Ă̓X�e���C�h�𓊗^����ȂǁC�����ɏǏ���ɘa���邱�ƂőΉ����Ă����̂��悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ����B �@����ɓ����́C���҂̂��a�̓����Ƃ��āC�u�ɂȂǂ̐g�̏Ǐ�̊ɘa��Љ�I���i�Ƒ��̃T�|�[�g�̒ቺ�Ȃǁj�C�����I��ɂ��֘A���Ă���Ƃ���Ă���Ǝw�E�B�����̊֘A�v�����܂߂��g�[�^���ȃP�A���K�v�ł���C��Ã`�[���̘A�g�����Ή����d�v�ł���Ƌ��������B ����ώ��Â͂���늳�̓����𗝉������x���I�P�A�� �@����ς́C���҂��ɘa�P�A�a���ɓ��@���鎞�_�Ŗ��C���̒��O�ɂ͖�8���Ɍ�����B���É��s����w��w�@���_�E�F�m�E�s����w�̉��R�O�u�t�́C���҂ɂ����邹��ώ��Âɂ��āC����ψȊO�ɂ����܂��܂ȋ�ɂ�L���Ă��邱�Ƃ�z�����C�x���I�ȑΉ����K�v�ł��邱�Ƃ��w�E�����B �I�s�I�C�h�֘A�̂���ςւ̑Ή��ɂ��K�n�� �@���R�u�t�́C���҂ɂ����邹��ώ��Âł͂܂��C����늳�̓������悭�������ăP�A�ɓ����邱�Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ����������B���Ȃ킿�C����̌o�߁C�Ƒ��\���C�������C�a��������e�Ȃǂ̏\���Ȕc�����K�v�ł���C����ς̎��Â����łȂ��C���ҁC�Ƒ��ւ̎x���I�ȃP�A���K�v�ł��邱�Ƃ��w�E�����B �@�܂�����ς́C�u�Ɏ��Âɑ��ĕp�p�����I�s�I�C�h�Ɋ֘A���Đ����邱�Ƃ��������C�ɂ݂Ƃ���ς̊ɘa�̗����͓�����Ƃ������B����ςƂȂ邱�Ƃ��u�ɕ]��������ɂȂ邱�Ƃ�����C������f�������邱�Ƃ��������߁C���_�Ȉ���ɂ݂̎��ÁC�I�s�I�C�h�̎g�����Ɋւ����{�I�m�����K������K�v������Ƃ����B �@�I�������҂ɂ����邹��ς͕p�x�����������ɁC��t�I�Ŏ��Ô������ɖR�������Ƃ������B��ÂƂ��ẴS�[�����s���ĂȂ��Ƃ������C�ǂ̎��_�ł���ς̎��Â���[�������I���ÂɈڍs����̂��Ƃ�����������B���u�t�́u�g�̓I���ʂ⊳�҂���т��̉Ƒ��̈ӌ���O���ɁC��ÂƂ��Ă̍őP�̃S�[�����l���C��I�Ȏ��_����P�A�ɓ�����K�v������v�Əq�ׁC��Ã`�[���Ə��C��ẪS�[���C���̗D�揇�ʂȂǂ����L���C�A�g���邱�Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ����������B ��I�P�A�������ɘa�P�A�`�[���̈琬�� �@����f�ØA�g���_�a�@�i�ȉ��C���_�a�@�j�ɂ�����ɘa�P�A�`�[���̐ݒu���C2007�N4���ɋ`�������ꂽ�B��������Z���^�[���a�@�i��t���j�Տ��J���Z���^�[���_��ᇊw�J�����̏��쒩�������́C�ɘa�P�A�`�[���ɂ����Đ��_�Ȉ�́C���_�Ǐ�ƐS���Љ�I�������킹���]���Ǝ��Â��s�����Ƃ����߂��Ă��邱�Ƃ���C��I�ȃP�A�������I�ɘa�P�A�`�[���̈琬�̕K�v�������������B �����Âɂ����鐸�_�ی����Ƃ��x������̐��� �@���쎺���́C�R���T���e�[�V�����E���G�]�����_��Ái�Տ��e�ȂŌ����鐸�_�Ǐ�̐f�Áj�ɂ����鐸�_�Ȉ�̖����ƁC���I�ɘa�P�A�`�[���ɂ����鐸�_��ᇈ�Ƃ��Ă̖����ɂ��Ĕ�r���C�O�҂ł͐��_�Ǐ�̊ɘa�����߂���̂ɑ��C��҂ł͕�I�ȏǏ�̊ɘa�C���Ȃ킿���_�Ǐ��łȂ���ÃX�^�b�t�C�Ƒ����܂߂��Ή������߂���Ǝw�E�B�܂��R���T���e�[�V�����E���G�]�����_��Âł́C���ÂɊւ��Ď��Ԃ̑����͏��Ȃ��C������x�g�̎��ÂƓƗ������Ή�����{�I�ɂȂ���邪�C���I�ɘa�P�A�`�[���ł́C���Â̒i�K�܂����Ή����K�v�Ŏ��Ԃ̐���������C���ʂ��𗧂Ă��Ή������߂���Əq�ׂ��B �@���{�ɘa��Êw�2008�N�ɍs�����u����f�ØA�g���_�a�@�̊ɘa�P�A�y�ё��k�x���Z���^�[�Ɋւ��钲���v�̌��ʂɂ��ƁC���_�a�@�ł̊ɘa�P�A�`�[���̕��ψ˗�������1�����Ԃŕ���4.5���C35���̎{�݂�3�����Ԃň˗�������10�������ł������B�܂����{�ɘa��Êw��ɏ������Ă����t�� 76���ŁC���{�T�C�R�I���R���W�[�w��ɏ������Ă����t��28���C�Ō�t���F��܂��͐��Ō�t�ł������̂�57���ł������B �@�������́C�킪���ɂ�����ɘa�P�A�`�[������������_�Ƃ��āC�����o�[�̂قƂ�ǂ����C�ŁC�Ζ����ԓ��̊������m�ۂ���Ă��Ȃ��i�l�̃{�����e�B�A�j���ߌ��C�@��s�����Ă���C�ߓx�Ɍl�̔\�́E�ӗ~�Ɉˑ����Ă���ʂ����邱�Ƃ��w�E�B�܂��g�D���̈ʒu�t�����s���m�ŁC�������̌n������Ă��Ȃ����ƂȂǂ��������B �@���_��ᇊw�͔�r�I�V�����w��ł���C�킪���̐��_��ᇈ�͂܂����ɏ��Ȃ��B���Z�Ȍ���ŗՏ��̍őO���ɗ����_�Ȉ�ɂƂ��āC�]���̋Ɩ��ɉ����Ċɘa�P�A�`�[���̉^�c�ɉ���镉�S�͑傫���B�������́C��ʐf�Âɂ����Ă͐��_�Ǐ�̑Ή����قƂ�ǂȂ���Ă��炸�C�Ō�t�C��Ã\�[�V�������[�J�[�C�S���E�ւ̐��_��w�I������قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ��ȂǁC����ł̉ۑ�͑����Ƃ��āC�����Âɂ����鐸�_�ی����Ƃ��x������̐���琬�̕K�v���C�܂����_�ی����Ƃƃv���C�}���P�A�E�`�[���̘A�g�V�X�e���̍\�z�̕K�v���Ȃǂ�����B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N1��28�� |
| ���̂ɂ�����������50�l�̓��@���҂��݂Ƃ����u����\�m����L�v |
| �@���[�h�A�C�����h�B�̃z�X�s�X�Ŏ����Ă���L�̃I�X�J�[�́A���i�͐l�ɉ������a�@�����C�܂܂ɂ��܂���Ă���̂ł����A���@���҂����ɂЂ��Ō�̐����Ԃ����́A�܂�Ō������Ă��邩�̂悤�ɂ��̊��҂̂��𗣂�Ȃ������ł��B �@����܂ł�50�l�̊��҂��݂Ƃ�A�������҂̎��̃^�C�~���O���u�\�m�v����\�͕͂a�@�̃X�^�b�t��萳�m��������Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA�I�X�J�[�����҂̃x�b�h�ɔ�я��ƁA�a�@���犳�҂̉Ƒ��֘A������悤�ɂ܂łȂ��Ă��܂��B �@�ڍׂ͈ȉ�����B �@Cat predicts 50 deaths in RI nursing home - Telegraph �@����5�̃I�X�J�[�́A�q�L�̂Ƃ��ɏd�x�̔F�m�ǂ̊��҂��P�A���郍�[�h�A�C�����h�B�v���r�f���X��Steere House Nursing and Rehabilitation Centre�Ɉ�������܂����B �@�I�X�J�[�͕��i�͕a������a���ւƕ����܂��A1�l�̊��҂̂��ɂ����Ƌ���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A���̐����ԑO�����͂��̊��҂̂��𗣂�܂���B���ɂ����Ă��銳�҂̕a������ߏo���ꂽ�Ƃ��ɂ̓h�A���Ђ������Ē��ɓ��낤�Ƃ��܂��B �@�I�X�J�[�́u�\�m�\�́v�͎��ɕa�@�̃X�^�b�t��萳�m�ł��B����Ƃ��A�Ō�m�炪�u�]���킸���v�Ɗ����Ă������҂̃x�b�h�ɃI�X�J�[���ڂ����Ƃ���A�I�X�J�[�͂����������Ŕ�яo���Ăق��̕a���֍s���A���̕a���̊��҂̂��ɍ���܂����B�I�X�J�[���삯���a���̊��҂͂��̖�̂����ɑ����������A�Ō�m���]�������Ԃƍl���Ă������̊��҂͂��̌�2���Ԃ������Ƃ̂��Ƃł��B �@�a�@�ɂ̓I�X�J�[�̂ق���5�C�̔L�����܂����A���̂悤�ȁu�\�m�\�́v��������̂̓I�X�J�[�݂̂Ƃ̂��ƁB �@�u���E����w�y�����ŘV�l�a�����David Dosa���m�́A2007�N��New England Journal of Medicine���ɃI�X�J�[�́u�\�m�\�́v�ɂ��Ď��M���܂����B����Ȍ���߂����ɊO��邱�ƂȂ����҂̎���\�m�������ADosa���m�͂���͋��R�ł͂Ȃ��Ɗm�M���Ă��܂��B �@���ł�Dosa���m��a�@�̂ق��̃X�^�b�t��́A�I�X�J�[���x�b�h�ɔ�я�芳�҂ɓY���Q������ƁA���̊��҂̉Ƒ��ɒm�点�邱�Ƃɂ��Ă���悤�ł��B �u�����̂悤�Ƀu���u�������A2���قǕa�����犊��o���Ăǂ����ʼn�����H�ׂ�ƁA�܂����҂̂��ɖ߂��Ă��܂��B�Q���̔Ԃ����Ă��邩�̂悤�ł��v�� Dosa���m�B �@�I�X�J�[�ɂ��ď����ꂽDosa���m�̒����uMaking rounds with Oscar: the extraordinary gift of an ordinary cat�v�ł̓I�X�J�[�̍s���ɂ��Ċm�ł���Ȋw�I�Ȑ����͒���܂��A�u�K���̂ɂ������������Ƃ��ł���Ƃ���錢�̂悤�ɁA�I�X�J�[�͍זE�����ʂƂ��̓Ɠ��Ȃɂ�������P�g���������킯�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����v�Ǝ�������Ă��܂��B �u������������L�v�Ƃ����ƕs�g�Ȋ��������邩������܂��A���҂̉Ƒ���F�l�̓I�X�J�[��s�C�����邱�Ƃ͂Ȃ��A���҂̍Ŋ��ɃI�X�J�[�������ɋ��Ă���邱�ƂɊ��ӂ��A���ɐV���̎��S�L���Ȃǂł��I�X�J�[���̎^���邻���ł��B �u�l�X�͑�Ȑl������������鎞�ɃI�X�J�[�������ɋ��邱�ƁA���������̏�ɋ����Ȃ������Ƃ��Ă��I�X�J�[�������ɋ��Ă��ꂽ�Ƃ������Ƃɑ傫�ȈԂ߂����������Ă��܂��v��Dosa���m�͌���Ă��܂��B �@�Ȃ��A���̕s�v�c�ȔL�̃I�X�J�[�ɂ��Ă�Dosa���m�̒����́u�I�X�J�[�\�\�V���ւ̗�������m�点��L�v�Ƃ���2010�N2��19���ɑ��쏑�[������{����s����邻���ł��B Web gigazine.net�@2010�N2��3�� |
| ��10����{�N���j�J���p�X�w��@�~���Ȓn��A�g�p�X�̉^�p�@���l�@ |
| �@�������i�ޒn��A�g�N���j�J���p�X�����C�]�����Ƒ�ڍ����܂́u������^�v�₪��C���A�a�Ȃǂ́u�o�����i���z�j�^�v�C�u�ݑ�x���^�v�ƌ`�͑���ɂ킽��B�s�ŊJ���ꂽ��10����{�N���j�J���p�X�w��k������g�����a�@�i���j�E���g�a�����@���l�̃p�l���f�B�X�J�b�V�����u�n��A�g�p�X�̌��Ɖe�v�k�I�[�K�i�C�U�[���ᑐ���a�@�i���{�j�E�R���p���@���C�����s���a�@�i�x�R���j�߃X�|�[�c�O�ȁE���c���ꕔ���l�ł́C�~���Ȓn��A�g�p�X�̉^�p�@�����������B ����f�Âɂ�����p�X�݂̍�� �@������{�@�̐���Œn��A�g�p�X�ւ̊��҂͑傫���c��B�p�X�̉^�p�ɂ͂��������Ƃ��_�a�@�̘A�g���s�������C���Ƃ���f�Âł͂��������������Ȃ����҂��قƂ�ǂł���B���m������Z���^�[�����a�@�����O�Ȃ̈ɓ��u��㒷�́C�x����̈�ɂ�����n��A�g�p�X�݂̍�������������B �������ׂ��ɘa��Â̎�舵�� �@2006�i����18�j�N�����̂�����{�@�ł́C�s���{���ɂ�������i��{�v��̍�������߁C�x�C���C�咰�C�݁C�̑���5�傪���12�N�x�܂łɒn��A�g�p�X�̐������`���t�����B���m���ł�2007�N�ɂ�������i�v������܂Ƃ߁C5�傪��A�g���c���ݒu���C�e����̈�̃��[�L���O�O���[�v�𗧂��グ���B �@�����Ńp�X�ɎQ�悷�邪�_�a�@��14�{�݁B�n�悲�Ƃɂ��������Ƌ��_�a�@�̃l�b�g���[�N�͈قȂ邪�C���ʃp�X�̎g�p��ڕW�Ƃ��Ă���B�������C���m���𓌐��ɕ�����Ɠ��̋��_�a�@��3�{�݂ƕ肪����C����p�X�̃����b�g�ɂ���������B�����Ĕx����f�Â̓����Ƃ��ĊO�Ȏ�p����ː����Â��s���{�݂����肳��C���_�a�@�Ŋ�������P�[�X��100���߂����߂�Ƃ����B �@�ɓ��㒷�͔x���\��s�ǂōĔ��̉\���������C�����ɂ͌h�����ꂪ���Ȃ��ߘA�g������Ǝw�E�B���̂��ߏp��� I A�E I B���Ɣ�r�I�y���Ǘ��ΏۂɘA�g�p�X�̉^�p���l���Ă���B�p�X�ł͂����ɏp��o�ߊώ@�Əp��e�K�t�[���E�E���V���z����iUFT�j���^���������C���㒷�́u�Ĕ��ɘa�P�A�ɂ��Ή��ł���p�X�����߂��Ă���v�Əq�ׂ��B�p�X�ɂ͊��җp�ƈ�Îҗp�̋����f�Ìv�揑�C�f�[�^�L���V�[�g�⊳�҃J���e�u�������L�v���쐬����C5�傪��̃z�[���y�[�W�𗧂��グ�ď������L�C�X�V���Ă���B �@���㒷�́C�{���͘A�g�̂Ȃ��ŘA�g�p�X�̓������l����ׂ������C�ŏ�����u�������肫�v�Ői�߂��Ă��邱�ƁC�p�X�Ǘ���f�[�^�W�v�C�Ǘ��҂���܂��Ă��Ȃ����Ƃ���_�ɋ������B�܂��C����A�g�p�X�́u�A�E�g�J�����ǍD�Ȕ]�������ڍ����܂ƈႢ�C�A�E�g�J�������ɂ����ɘa��Â��ǂ��g�ݍ��ނ̂����ۑ�ł���v�Ƃ܂Ƃ߂��B �A�g�����҂̃l�b�g���[�N�[������ �@������{�@�̐����ɔ����C����f�ØA�g���_�a�@��2012�N4���܂ł�5�傪��̒n��A�g�p�X�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������q��ȑ�w�a�@�n��A�g���̉����T���q���́C�A�g�����҂̃l�b�g���[�N�͑S���I�ɍL������邪�C�A�g���i�̖������ɂ́C�A�g��������̂���Ȃ�[�����K�v�Ǝw�E�����B ���ƃm�E�n�E�̋��L�� �@�킪���̂��S����2005�N��32���l���C���S�ґS�̂�3���ɂ̂ڂ�C���ґ�����142���l�Ƃ����B�������͂����ØA�g���l����ꍇ�C3 �̃t�F�[�Y������Ɛ��������B�i1�j��������}�������Â܂ł́u�Љ�F�f�a�A�g�v�i2�j�}�������Ì�̃t�H���[�A�b�v�����Ƃ����O���f�Ãx�[�X�́u�t�Љ�F�a�f�A�g�v�i3�j�Ō�ɏI�����C��삪�K�v�ɂȂ����Ƃ��̓��@�a���ɂ����u�ݑ��Áv�|�ł���C�e�n��ō쐬����邪��n��A�g�N���e�B�J���p�X�̖ړI�̑唼�́i1�j�Ɓi2�j�ɂ���B �@�����́C������w�̐i���ɂ�肪���Â͈�����ɂ������E�G�[�g���傫���Ȃ��Ă���Ƃ����B����܂ōs���Ă��������Â�U��Ԃ�C1�a�@�ł̎��Ê����^�ŕa�@��t�Ɏ����Őf�����Ƃ����X��������C2����Ì��ɂ��҂̎���\�Ȑf�Ï������Ȃ��C���҉Ƒ��̕a�f�A�g�ւ̗������Ⴂ���Ƃ����Ƃ̒������ʂ��������Ƃ����B �@2009�N���݁C�S���ʼn^�p����Ă���n��A�g�p�X��63����C1,320�l�̊��҂��p�X�ɂ���Â��Ă���B�����炪����f�ÂŘA�g�������i�����j��q�˂��Ƃ���C�u�n��l�b�g���[�N�̖����n�v�������Ƃ��鐺��110�l�ƍł����������B���̂ق��C�u�ݑ��Â̖����n�v�i70�l�j��u�A�g��f�[�^�x�[�X�̖����n�v�i53�l�j�C�u�z�X�s�X�{�݂̕s���v�i50�l�j�ȂǁC�l�b�g���[�N�ƈ�����̎M���s�\���Ȃ��Ƃ����炽�߂ĕ�������ƂȂ����B �@�����s�A�g�����ҋ��c��ł́C�N2��قǎ����҂�������������݂��Ă���B�����́u�A�g�p�X�����ǂ̃m�E�n�E���������邱�Ƃ��s���B���Â���ێ����ւƌp���f�Âɂ������A�g������l�Ƌ@�\���[�������C���ړI�C�ԐړI�Ɉ�ÎҁE���҉Ƒ����x���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ��B���̂����Łu�A�g�����҂��܂��n��A�g�p�X�𗝉����邱�Ƃ��K�v�v�Ƒi�����B �p�X�̖{���͒n���Â̌���ɂ��� �@�n��A�g�N���j�J���p�X������ɂ͈�Î҂̘A�g����̎n���C�R�X�g�팸�Ȃǂ��܂��܂Ȗ��ɒ��ʂ���B�������C�����a�@�@�\�����ÃZ���^�[�]�_�o�O�Ȃ̍����p�����́C�p�X�����̖{���̓o���A���X�i�s�������j�̌����J��Ԃ����ƂŒn���Â̎������コ���邱�Ƃɂ���C����ȊO�̎����ɂƂ���ĖړI���������ׂ��łȂ��Ƒi�����B �ړI�Ǝ�i�̏s�ʂm�� �@�������́C�l����37���l�̒��茧�����n��i�|���s�C�呺�s�C�Δn��ܓ��Ȃǂ̗����j�̃��n�r���e�[�V�����A�����c��ŁC��ƕ���Ƃ��Ĕ]�����p�X�̍쐬��i�߂Ă����B�d�������̂͋@�\��Q�����P�C�y���C�����邱�ƁB�����́u��Îғ��m�̃R�~���j�P�[�V��������̂����C�݉@���Ԃ̒Z�k�Ȃǂ͎�i�ɂ������C����ɂƂ���Ă̓p�X�̖{�����������v�Ǝw�E�����B �@�p�X�쐬�Ŗ�肾�����̂́C�]�����̕a�Ԃ�Ǐ�C���Ö@�͕K�������ψ�łȂ��C���̒B���ڕW��݂��邱�Ƃ�����������Ƃ��Ƃ����B�p�X�̖{���ł���n���Â̎�����Ɖ��P�ɂ́C�ڕW�ƂȂ��̓I�ȃA�E�g�J���̐ݒ肪�K�v�ł���C���̂��߂ɓK�p�E���O���݂����B �@����ƕ���ł́C�����C�]�[�ǂƔ]�o���ʼn����@���o�Ď���މ@�������߂钆���ǂɍi��p�X�^�p���J�n�����B�I�������p�X�͒��茧���ی������ɂ��鎖���ǂňꊇ�Ǘ�����C�o���A���X�̉�͂��s��ꂽ�B �@���̌��ʁC�����@1�����ڂɂ�25�ᒆ13��C���މ@����25�ᒆ19��Ƀo���A���X���������B��͌��ʂɊ�Â��C���ׂĂ̔]�������Ώۂ̒n��A�g�p�X���쐬���ꂽ�B �@�����́C�n��A�g�p�X�̈Ӌ`�ɂ��āu���؍�Ƃ��J��Ԃ��C�n��S�̂ŃA�E�g�J���E�}�l�W�����g���s�����ƂŁC�ǂ̕a�@�ɓ��@���Ă����̍�����Â����S���Ď���̐����\�z�ł���v�Əq�ׂ��B �J�ƈ�̕��S���炷�p�X������ �@�n��A�g�p�X�̕��y�́C�����ɖ����Ȃ������ł��C���S���𑝂₳���ɉ^�p�ł��邩���ۑ�ƂȂ��Ă���B�k�����N���j�b�N�i�k�C���j�̉��c�W�ᗝ�����́C���ۂɉ^�p���Ă��镡���̒n��A�g�p�X�������Ȃ���C�J�ƈ�̕��S�y�������������̌��ɂȂ�Ƙ_�����B �Q�l�ɂ��ׂ�TS-1�p�X��MedIka �@���c�������́C�p�X�ɑ���Ζ���ƊJ�ƈ�̗���s�����s���ɂȂ���C�����ɏ��ɓI�Ȏp���ɂȂ��Ă���Ǝw�E�B�u�s�����������܂܂ł͌����������ۏł��Ȃ��B�p�X�����܂����p���邱�ƂŌ����Ǝ��������ł���ƍl����悢�v�Əq�ׂ��B �@�Ώێ����́C����̂ق��o��������I��ᑑ��ݏp�iPEG�j��C�ǎx�b���C���A�a�C�̉��Ȃǂ�����Ƃ��C�u�J�ƈオ�A�g�p�X�����̃|�C���g�ɂȂ�v�Ƌ��������B�J�ƈ����芪�����͌������𑝂��Ă��邪�C�u�n��A�g�p�X�ւ̎Q���́C�����������S���y�����C���҂�Ƒ��̊�т�n��̐M�������܂邱�ƂɂȂ���ƍl����ׂ��v�Ƙb�����B �@�L���Ȓn��A�g�p�X�Ƃ��ē��N���j�b�N�œ�������e�K�t�[���E�M�����V���E�I�e���V���J���E���z���J�v�Z���܁iTS-1�j�p�X���������B�a�@�̐����Ō�t�C��t�̎w�������C�z��O�̎��Ԃ��N�����24���ԑΉ��őΏ��ł���Ƃ����B���������͌o�ߒ��̌����Ƃ��⌟���̒E���Ȃǂ��h����J�ƈ�̃����b�g�ƁC�}�����̈�Âɓ����Ȃǂ��ł���a�@�̃����b�g�C��ɕa���c�����Ă��炦�Ă���Ƃ������҂̃����b�g������C�~���ȉ^�p��������ʂݏo���Ɛ��������B �@�n���ØA�g�l�b�g���[�N�́uMedIka�v�ł́C�����⏈���E��p�摜�f�[�^�ȂǘA�g�{�݂ɐf�Ï����ł͓`������Ȃ������J���ł��C�d�q�J���e�V�X�e���Ƃ̑g�ݍ��킹�Ō���ɕ��S�������Ȃ������J�������ł���ƏЉ���B���������́u�J�ƈ�̐��ݔ\�͂������o���C���`�x�[�V���������߂�n��A�g�l�b�g���[�N�����グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ܂Ƃ߂��B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N2��4�� |
| �V�E����T�O�l�̗E�C |
| * ���X�ŐV���F�V�E����T�O�l�̗E�C�@[��]���c�M�j �@�o�ŎЁF���Y�t�H�@�@���i�F�� 1,680 * [�]��]�d�����i��Ɓj ���܂����������������p�@�h�Ӎ��� �@����ŖS���Ȃ����l�X�́A���ɗՂދL�^�ł���B�^�C�g���Ɂu�V�v�Ƃ���Ƃ���A�P�X�W�P�N���s�́w�K���T�O�l�̗E�C�x�̑��҂Ƃ����ʒu�t���Ȃ̂����A�O�삩���R�O�N�Ƃ����Ό��̗���́A���{�l�̎����ς�₤���c�M�j����̎�������ɐ[�������Ă��ꂽ�悤���B �@�O��E����Ƃ��ɁA���c����͂��܂��܂Ȑl�́q�L���Ȏ��r��`���o���B�����O�A�R�{�����A�Č������A���H�M�q�A�J�����X�W�A�{�c���ގq�c�c���삾���ł��U�O�l���鎀�̐�B�̃h���}�́A���ꂼ��[���]�C��ǂݎ�̋��Ɏc���B �@�������A�S�Ȃ炸���l����r��Œf�����Ă��܂��̂�����A���O�͂���B�߂����������������B�Ƒ���d�����Ă���v��������A���������B�������c����́A�ނ炪���̎v�����O�b�Ɠہi�́j�ݍ���ŁA�܂������Ɏ��ƌ����������p���A�h�ӂƋ��������߂ĕ`���B�O��̂��Ƃ����ɂ���Ƃ���A�q�u�ʂ�̎��v�������Ă����ꍇ�ɂ����Ă��A��]�łȂ���]�ƗE�C���A��������Ǝ�ɂ����铹������̂��Ƃ������Ƃ������Ă��ꂽ�l�X�̂��Ƃ��A�L�^���Ă������������r�̂ł���B �@����ɁA�O��ƍ���Ƃ̊Ԃɗ��ꂽ�Ό��́A���ɗՂލۂ̈ӎ���ς����B�a����]���̍��m��畏��i������j����Ă�������ɒ����ꂽ�O��ł́A����ƒm�炸�ɖS���Ȃ����l�̕�������������B����͗��Ԃ��A�^�����B���ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƒ��̊����i�����Ƃ��j�̕���ł��������B�����A����ł͑唼�̐l�����m���A�Ƒ��Ǝ���g���Ȃ���l������߂������Ă���B�܂��A�R�O�N�O�ɂ͗�O�I�ȑ��݂������ɘa�P�A��z�X�s�X���L�܂������ƂŁA��ɂƓ����̂ł͂Ȃ��A�Ƒ��ƂƂ��ɉ��₩�ɐl�������I���������܂ꂽ�B �@�q�ʂ�̎��r���ǂ��}���邩�́A�Ƒ��ɂƂ��čŌ�̋�����Ɓ\�\�����炱���A�q��]�ƗE�C�r���A�Ƒ��S���ŕ������������̂ɂȂ����B���c���Љ�����X�́q�L���Ȏ��r�́A�ǎ҂�������i�N�����A�K���I�j�����}����ۂ̂���{�ł���Ɠ����ɁA���Ȃ��������ȉƑ��̕���W�ł��������̂��B ����Ȃ����E���ɂ��@�R�U�N���܂�B��ƁB�w�K����L�̒��x�w�����Ȃ����́x�ȂǁB �����V���@2010�N2��6�� |
| �r�f�I�Ŕ]��ᇂ̎��Ö@�I���ɕω��@������͉������Ìh���ECPR���ۂ� |
| �@�}�T�`���[�Z�b�c�����a�@�i�{�X�g���j���Ȃ�Angelo Volandes���m��́C�]��ᇊ��҂ɖ������҂̊e�펡�Â̗l�q���B�e�����r�f�I�f�������������C���̌�̎��Ö@�̑I�����ǂ̂悤�ɕω����邩�ׂ��B���̌��ʁC�r�f�I������͊ɘa�P�A�݂̂�I�����C�S�x�h���iCPR�j�����ۂ���X�����F�߂�ꂽ�B �@ �l���̍Ō��Â��ɉ߂����I�� �@�r�f�I�ɂ�3�ʂ�̏I������Â̗l�q�����^����Ă���B���̉f���������������҂́C���Ö@�̑I�����ɂ��Č����Ő������������̊��҂ɔ�ׁC�������l���̍Ō��Â��ɉ߂��������Ɩ]�ތX�����������Ƃ��킩�����B���ہC�r�f�I�������������ґS�����u�]��ᇂ��i�s���Ă��������Â��邱�Ƃ�]�܂Ȃ��v�Ɠ������̂ɑ��C�r�f�I���������Ȃ��������҂ł͔����ɂƂǂ܂����B �@Volandes���m��́CMGH����Z���^�[�ň����_�o�P��̎��Â��Ă��銳��50���Ώۂɒ������s�����B�܂�CPR���s��ꂽ���҂�l�H�ċz��ɂȂ��ꂽ���҂��ǂ̂悤�Ȍo�߂����ǂ邩�Ȃǂ��܂߁C�I������ÂɊւ���m���ɂ��Ċ��҂Ɏ��₵���B�܂��C�]��ᇂ������Ɏ������ꍇ�� CPR���邩�ۂ����������B �ɘa�P�A���{�I���Â̌��i���f�� �@���҂͌����݂̂ł̐�������Q�i�ΏƌQ�j�ƁC�����ł̐����ƃr�f�I�����̗�������Q�i�r�f�I�����Q�j�Ƀ����_���Ɋ���t����ꂽ�B�ΏƌQ�ɂ́C�i1�j�����iCPR��@�B�I�l�H�ċz���܂ށj�i2�j��{�I���@���Ái�R�ۖ��A�t���^���܂ށj�i3�j�ɘa�P�A�̂݁\��3�i�K�Ɋւ��Č����Ő������s�����B�r�f�I�����Q�ɂ͏�L�̐����̌�C���̐������e��⊮����6���Ԃ̃r�f�I�f�����������B �@�r�f�I�ɂ�CPR�̖͗l��W�����Î��ł̐l�H�ċz��ɂ�鉄�����Ẩf���C���@���_�H�ōR�ۖ�𓊗^����Ă����{�I���Â̗l�q�̂ق��C�����z�X�s�X�ŕ��ʂɐH�����Ȃ���_�f�Ö@�Ȃǂ̊ɘa�P�A���Ă�����i���f���o���ꂽ�B���̌�C�]��ᇂ��i�s�����ꍇ��3�i�K�̎��Â̂����ǂ̃��x����I�Ԃ��C������CPR���邱�Ƃ�]�ނ��ۂ����₵���B�܂������ɁC���Ҏ��g���]�I�����ɂǂ�قNJm�M�������Ă��邩���]�����C�r�f�I�����Q�ł̓r�f�I�̓��e�ɑ��銴�z���������B ���������ɘa�P�A�� �@���̌��ʁC�r�f�I�����Q�ł�23�ᒆ21�Ⴊ�ɘa�P�A�݂̂��C1��͊�{�I���Â�I�������B�c���1��͌��f��ۗ����C�������Â�I�������҂͂��Ȃ������B�ΏƌQ�ł͖��i27�ᒆ14��j����{�I���Â�I�����C6�Ⴊ�ɘa�P�A���C7�Ⴊ�������Â�I�BCPR���邩�ۂ��Ɋւ��Ă͗��Q�Ƃ���������O�ł͍����Ȃ��C�������u�Ȃ��v�C3����1���u��v�C�c�肪�u�킩��Ȃ��v�������B�������C�r�f�I�����Q�͐����E�r�f�I�����̌�ł́C2�������21�ႪCPR��]�܂Ȃ������B����C�ΏƌQ�ł͐����O�ƂقƂ�Ǖω����Ȃ������B �@Volandes���m�́u�r�f�I�����Q�ł́C�ɘa�P�A��I�����闦���啝�ɑ������������łȂ��C�������邱�Ƃň��S�ł����Ƙb���Ă����B�r�f�I�ɂ���Ĉ�t�Ɗ��҂̘b���������i�݁C���҂��m�M�������Ď��Ö@��I���ł���悤�ɂȂ�B���コ�܂��܂Ȃ��҂�ΏۂɁC�r�f�I���ǂ�قǖ��ɗ��̂��ׂ���肾�v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N2��11�� |
| ���`�[����Á��^�̊��҂��x���� |
| ����ߎq�E�s����a�@�����@ �@����̊O�����w�Ö@��ɘa�P�A�A�����ǂ̎��ÂȂǂő��E�킪�Q������`�[����Â��s���Ă���s����a�@ �i���{�j�̈���ߎq��܁E�Z�p�����ɁA�`�[����Â̈Ӌ`��W�]�����B �`�[����Â����߂���w�i�� �@�u���G�������Â���t�����ŒS���͖̂����ŁA��t�́w���ɂ��ׂĔC���āx�A���҂́w���̖��͗a���܂��x�Ƃ������]���̑ԓx�ł͑Ή��ł��Ȃ��B�a�C�ɗ����������p������������̂ɂ́A���܂��܂ȐE�킪���������������v ��a�@�ł̓����̓X���[�Y�������̂� �@ �@�u�P�X�W�O�N�㖖����A���@���҂̕���w���̈ꕔ���t���S�����A��t������w�����̎��Â������������Ⴄ�ڂŌ��Ă��炦��x�Ɨ������������L�������B���̌���R����܂̎��Â╛��p�ɂ��Ă̐�������t�ɑ����Ĉ�����Ȃǂ��āA���X�Ɍ��݂̃`�[���̌`�Ԃ��������v �@�u�E�킪�Ⴆ�Ί��҂ւ̃A�v���[�`����̎����ς��A���܂��܂Ȋp�x���犳�҂��x�����邱�Ƃ��A���ł͋��ʔF���ɂȂ����B�����E���Q������`�[���̑ł����킹������v �ǂ�Ȃ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ������B��t�������S���Ă������Ƃ͂ǂ��Ⴄ�� �@�u�Ⴆ�Ύ����p�O���w�Ö@���������ꍇ�A�}��`���Ȃ���A����זE���Ȃ��ł��āA�ǂ̂悤�ɑ����Ă����̂��A�Ƃ������b����n�߂�B���m���ė��_������A�傫�ȕs����������肷�銳�҂ɁA��p�O�ɂ�����������Ă������Ƃ̕K�v����A����p�̒E�т͂����������Ă��邱�Ƃ̗��Ԃ��ł��邱�ƂȂǂ��A���Ԃ������ė������Ă��炤�v �@�u���҂ɖ���������悤�Ȏ��A��Ԑg�߂ɂ���Ō�t���w���������Ă�����悤�ȂЂƐ��������A��Ŋ��ӂ��ꂽ�P�[�X�������B�̂Ȃ�w�搶�ɕ����܂��傤�x��������������Ȃ����A�������L���A�`�[���ŕ��j������ł��Ă��邩�炱���A�����������Ƃ��ł���v �]�܂����`�[����Â̎p�� �@�u�Ȋw�I�����Ɋ�Â�����Â��X�^�b�t���n�m���Ă��邱�Ƃ���O��B���ʂ̔F���������A�����ڕW�Ɍ������Č݂��ɐ����������邱�Ƃ��d�v�B���ꂼ��̕���̐��ƂƂ��Ď��R�ɂ��̂������A�ЂƂ�ЂƂ肪���[�_�[�ɂȂ�邱�Ƃ����z���B��t���^�ł͂Ȃ��A��t���ق��̐E����w���f�B�J���X�^�b�t�x�Ƃ��āA�^�ɂ��銳�҂��x����ׂ��ł͂Ȃ����v 47NEWS 2010�N2��16�� |
| �ɘa�P�A |
| �ΐ쌧�������a�@�ɘa�P�A���ȁ@���쏟��t ���ҁA�Ƒ��̐����̎����P �@�u�ɘa�P�A�Ƃ́A�l���������������ɂ����ɒ��ʂ��Ă��銳�҂Ƃ��̉Ƒ��ɑ��āA�����̑�������ɂ݁A�g�̓I�A�Љ�I�A�X�s���`���A���Ȗ��Ɋւ��Ă�����Ƃ����]���������Ȃ��A���ꂪ��Q�ƂȂ�Ȃ��悤�ɗ\�h������Ώ������肷�邱�ƂŁA�N�I���e�B�[�E�I�u�E���C�t�i�����̎��j�����P���邽�߂̃A�v���[�`�ł���v �@ �v�g�n�i���E�ی��@�ցj�́A�Q�O�O�Q�N�Ɋɘa�P�A�����̂悤�ɒ�`���Ă��܂��B�ɘa�P�A�Ƃ́A�����������������ɔ����ɂ݂��͂��߂Ƃ���g�̂̂炳�A�C�����̂炳�A�����Ă���Ӗ��≿�l�ɂ��Ă̋^��A�×{�ꏊ���Ô�̂��ƂȂǁA���҂�Ƒ������ʂ��邳�܂��܂Ȗ��ɑ����������Â̂��Ƃł��B �@ �܂��ɘa�P�A�́A�a�C�̎����⎡�Â̏ꏊ���킸�A���ł��ǂ��ł������K�v������܂��B�]���A�ɘa�P�A�́u�Ŏ��̈�Áv�ƁA�Ƃ�ꂪ���ł������A����ɂ�肪�i�s�������҂����łȂ��A��葁������s���邱�Ƃ��d�v�ł���ƍl������悤�ɂȂ�܂����B �@ ���E�̊ɘa�P�A�̗��j�͌��X�A�������[���b�p�ŗ��̏���҂��h�������������{�݂��n�܂�ŁA������z�X�s�X�Ƃ����܂����B�₪�āA�a�ƂȂ藷�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ������ɂ䂭�a�l�̈Ԃ߂ƈ��炬�̏�Ƃ��Ă��A�g�p�����悤�ɂȂ�܂����B �@ ���̌�A�P�X�U�V�N�p���̃V�V���[�E�\���_�[�X��t�́A�Z���g�N���X�g�t�@�[�E�z�X�s�X�����݂��A�ɘa�P�A����{�Ƃ�������z�X�s�X�̊�b�����A���E�̐�삯�ƂȂ�܂����B �@ ���{�͂V�R�N�A���{�̗���L���X�g���a�@�Ƀz�X�s�X�a�����݂����܂����B�W�V�N�ɂ͐�t���̍����×{�����˕a�@�i���݂̍�������Z���^�[���a�@�j�Ɍ��I�ȋ@�ւƂ��ď��߂ĊJ�݂���A�S���e�n�̍������a�@�ɍL����܂����B �ǔ��V�� 2010�N2��17�� ���Ï���������{�̗��� �@���{�ł͌��݁A���U�̂����łQ�l�ɂP�l�́A����ɜ늳���Ă��܂��B�N�Ԃ̑S���S�Ґ���P�P�O���l�̂����A��R���̂P������ɂ�薽�𗎂Ƃ��Ă���A���S�����̑�P�ʂł��B �@ �{���ǂ�ȕa�C�̊��҂ł��ɘa�P�A���K�v�ł����A���҂͐��������A��ɂ𒆐S�Ƃ����炢�Ǐ�̔����p�x���������߁A�ɘa�P�A�ł͒��S�I�ȕa�C�ƍl�����Ă��܂��B�����āA�Q�O�O�U�N�A������{�@���������܂����B�d�_�I�Ɏ��g�ނׂ��ۑ�̈�Ƃ��āA���Ï����i�K����̊ɘa�P�A���{���������܂����B �@ ���݁A�ɘa�P�A���Ă���͎̂�ɓ��@���̊��҂ł��B�z�X�s�X�E�ɘa�P�A�a���ւ̓��@�ƁA�ɘa�P�A�`�[���ɂ��f�ÂƂ�����̕��@������܂��B�O�҂͒�߂�ꂽ�a�@�ɂ���܂��B�ΐ쌧�ł́A�ϐ������a�@�Ə����s���a�@�ł��B �@ ��҂͂���f�Ë��_�a�@�̎w����Ă���a�@�܂��́A�ɘa�P�A��ϋɓI�Ɏ�����Ă���a�@�ɂ���܂��B����f�Ë��_�a�@�́A�����w�����a�@�A�����ÃZ���^�[�A�ΐ쌧�������a�@�A�����ȑ�w�a�@�A�����s���a�@�̂T�a�@�ƂȂ��Ă��܂��B �@ ����͊O���f�Âł��Ή����i��ł����ƍl�����܂��B�z�X�s�X�E�ɘa�P�A�a���ɓ��@�ł���̂͂����ނˁA����̐i�s�ɔ����g�̂̂炢�Ǐ��_�I�ȋ�ɂ�����A�������鎡�Ö@���Ȃ����A���Â���]���Ȃ����҂��Ώۂł��B �@ ����A�ɘa�P�A�`�[���́A���@�×{���ɐ�����A�厡��݂̂ł͑Ή�����Ȗ����T�|�[�g���܂��B�����o�[�͌����J���ȂŒ�߂��Ă���A�g�̂�S�������t�Ɛ��_�Ǐ��S�������t�A�ɘa�P�A���Ō�t�̌v�R�l�ł��B���̑��A��t�A�\�[�V�������[�J�[�A���w�Ö@�m�i���n�r���j�A�h�{�m�炪�Q�����Ă���{�݂�����܂��B �ǔ��V�� 2010�N2��24�� |
|
2010����^�É�����Z���^�[�E�R���������R�����g �@����֘A�@��t�ȊO���E�̕]���͉���I |
| �@�É������É�����Z���^�[�̎R����������2��17���A����̈�ł̎����f�Õ�V����̓��e�ɂ��āu�G�|�b�N���C�L���O�v�Ƃ���R�����g�\�����B��t�ȊO�̐E�킪�]������Ă���A�`�[����Â̎��H��ڎw�����@���܂߂�����f�Ë��_�a�@�Ȃǂ̒ǂ����ɂȂ�Ƃ��Ă���B �@���ɁA����Ō�֘A�̍��ڐV�݂ɐG��āA�u��含��]���������ڂ�������ꂽ���Ƃ͂Ȃ������v�Ƃ��Ă���B �@�����f�Õ�V����́A�u�[�������߂���̈�v�ɂ����Â��ʒu�t���A����f�Ë��_�a�@�ƌ���{�݂Ƃ̘A�g�̐��A���_�a�@�ł̃��n�r�������Ȃǂ���f�Â�����ɏ[��������������������B �@����Ō�̐�含�̕]���ł́u���҃J�E���Z�����O���v�i500�_�j���V�݂����B�ɘa�P�A�̒m���������t�Ɓu�U�J���ȏ�̐��̌��C���C�������Ō�t�̓��ȁv���Z��v���Ƃ����B �@�Z��v�������͓̂��{�Ō싦��̔F��Ō�t�ŁA���w�Ö@�A�����u�ɁA�ɘa�P�A�A������Ȃǂ̕���ŏ\���ȃX�L���E�m��������ƔF�߂�ꂽ�Ō�t���a�����Ă���B �@����ȊO�̂��̂��܂߂āu���̌��C�v���ǂ���`�����̂��͌����_�ł͕s���B����Z��ł���̂����W�҂̊S���ɂȂ�B�É�����Z���^�[��ÍL�́A�u�J�E���Z�����O�͒ʉ@�A���@��ʂ��čs���Ă���v�Ƃ��A���ԂɌ����������ݒ肳��邱�Ƃ����҂��Ă���B m3.com�@2010�N2��22�� |
| �u�L���A����P�A�ցv�A���҂̑��k�x���̂�����ŃV���|=���� |
| �@�g�߂ɂ��҂�����Ƃ�����ɂǂ̂悤�ɐڂ�������̂ł��傤���B�Ȃ�ƂȂ�����������Ă�������̂Ȃ��b�����Ă��܂������ł��B���҂͐^���ɔY��ł���ɂ�������炸�������ɂȂ����ׂ͂Ȃ��̂ł��傤���B���̓���e�[�}��^���ʂ��猩�����悤�ƃV���|�W�E�����s���܂����B �@���f�B�J���^�E���Đ��̓V���|�W�E��(30�N��̈�Â��l�����E���\���ݑ�{�����e�B�A����)��2��21��(��)�A���H���Ō��w(�����s������)�A���X�ES�E�W�����������A���z�[���ōÂ���A�u���҂̑��k�x���̂�����v���e�[�}�ɍu���ƃV���|�W�E�����s���܂����B�ݑ�Ō�Ɍg���W�҂͂������A�S�̂����300������������܂����B �@�u���ł́u�}�M�[�Y�E�L�����T�[�E�P�A�����O�E�Z���^�[�̎��ہv�Ƒ肵�āACEO�̃��[���E���[���̘b������܂����B �@�`���A�n�n�҂̃}�M�[�E�P�Y�E�C�b�N�E�W�F���N�X�́uabove all what matters is not to lose the joy of living in the fear of dying(��ԑ厖�Ȃ��Ƃ͎��̋��|�̒��ł��������т�����Ȃ����Ƃł���)�v�̈�u���p���ŁA���݂̖������k�x��������W�J���Ă���Ƃ̘b����n�܂�܂����B���҂����ȓ����͂̑r�����]���Ɩ��͂ɏP��ꂽ�ۂɂ́A1)���ʂł̃T�|�[�g�A2)�S���E�Љ�E����ʂł̃T�|�[�g�A3)���C�t�X�^�C�������̍œK���A4)����̐f�f�ɑΉ������ŐϋɓI�Ȗ������ʂ����@��̒�4�v���O������p�ӂ��A���҂��u�ϋɓI�ɐ�����v���Ƃ�����`������̂��}�M�[�Z���^�[�ł���Əq�ׂĂ����܂����B �@�}�M�[�Z���^�[�̓~���[�W�A���ł���A����ł�����A�a�@�����ĉƒ�̗l�ȏꏊ�ƂƂ炦�A���p�҂����K�Ȏ��Ԃ��߂������߁A���܂��܂ȍH�v���Ȃ���Ă��܂��B���Ɍ���K�����Ȃǂ��s���Ă��܂��B���҂̒N�����C���˂Ȃ����p�ł���{�݂��Ƃ̎v������A�������l���Z���^�[�͂��ׂĈ�Î{�݂ɗאڂ��č���Ă��܂��B �@���t����悤�ɗ��K�҂�65%�͂��҂ŁA35%�����̉�҂�F�l�E�Ƒ��A�܂�65%�������A35%���j���������ł��B �@���������{�݂��a�������w�i�ɂ́A3�l�̂���1�l�����U�̂�������ɂ�����A200���l�̉p���l������������Đ����Ă���A���N29��3000�l������Ɛf�f����Ă���A�p���̑S���S��27%�͂���ł��铙�A���{�ł����l���邢�͂���ȏ�̏ɂ���܂��B�����đ��l���Ƃ͎v���Ȃ��؎��Ȗ��ł��B �@�����͑傫�ȉۑ�ŁA���̑����͑P�ǂȎx���҂̊�t�ƃC�x���g�Ȃǂ̎��Ǝ����Řd���Ă��邻���ł��B���{�ł��ꕔ�̓Ďu�Ƃ����ɗ��炸�A�P�ӂ̊�t����������W�܂�ΐݒu�͉\�ł��B����A�l�b�g���[�N�����`�A�o���Z���i�A�I�[�X�g�����A�A���{�ɂ��g�傷��v��ł��B���̂��˂肪���E�Ɋg�傷�邱�Ƃ����҂������̂ł��B �@�p�l���f�B�X�J�b�V�����ł́A�p�l���[�̎��̌��܂����l������ɓ��c���s���܂����B������������{�ւ̓��������҂��邱�Ƃňӌ��̈�v�����܂����B �@���c�M�j���̃��b�Z�[�W(���)�u���{�Ń}�M�[�Z���^�[�̒a���Ɋ��҂���v�̃R�����g�ɓ��������Ȃ����p������܂����B �y�}�M�[�Y�E�L�����T�[�E�P�A�����O�E�Z���^�[�Ƃ�?�z �@�����ƂŒ����뉀�̌����Ƃł��������̃}�M�[�E�P�Y�E�B�b�N�E�W�F���N�X(1988�N������̐鍐���A1995�N�����킪��Ŏ���)�̈�u���A���ҁE�Ƒ��A�܂��F�l�Ɏ���܂ŗl�X�Ȃ���̔Y�݂ɉ����閳�����k�x���{�݂Ƃ��āA1996�N�ɃC�M���X�̃G�W���o����1�ӏ��ڂ��J�݂���܂����B(�C�M���X��NHS=�����a�@�́u����Z���^�[�v�́u�~�n���v�ɁA�u�ʓ��v(�@�O)�Ƃ��Đݒu�A�S�z�`�����e�B&���̉^�c��̂ɂ��^�c) �@���̌�A�p�����Ŏ��v�����܂�A2002�N�ɃO���X�S�[�ő�2���A2009�N�܂łɑS�p��7�ӏ����J�݂���A���p�҂͊��ҁE�Ƒ��E�F�l���܂߂� 77,000�l�ɏ��܂��B2012�N�܂łɍX��5�ӏ����J�ݗ\��ȂǁA���̋@�\�͐��E�I�ɂ����ڂ���Ă��܂��B PJ�j���[�X�@2010�N2��23�� |
| �ɘa��ÁF�����F��� �m�o�n�@�l�A�P�O�N�łP�O�O�O�l�ڎw���|�|�S������ |
| �����{�ł͔F������ �@����Ȃǂ̊��҂̒ɂ݂�a�炰����A���_�I�ȃP�A�ɂ��g���ɘa��Â̐����F�肷�鐧�x���S���A�X�^�[�g����B�ɘa��Â̏d�v���͈�ÊW�҂̊Ԃł��\���F������Ă��炸�A���オ�s�����Ă���Ƃ��āA�m�o�n�@�l���{�ɘa��Êw��i�������E�]������鋞�勳���A�����X�O�O�O�l�A�����ǁE���s����j���I�肵�A�P�O�N�ԂłP�O�O�O�l���x�̔F���ڎw���B�Ⴂ��t����Đ��オ������Ί��҂�Ƒ��̊�]�ɉ��������̍����ɘa��Â̕��y�ɂȂ���Ɗ��҂����B �@���w��ɂ��ƁA�ɘa��Â����H����z�X�s�X���˂̒n�A�p���ɂ͐��㐧�x������A��w�ł��ɘa��Â��L���������Ă���B����A�����Ő��a��������Ë@�ւ͖�Q�O�O�{�݂����Ȃ��A����̒ɂ݂���菜�������q�l�Ȃǂ̈�×p����̏���ʂ����Ăɔ���Ȃ��Ƃ����B �@�����O�V�N�U���ɍ��肵����������i��{�v��ł́A���Â̏����i�K����̊ɘa��Â̎��{�ƂƂ��ɁA���m��������t���琬����K�v�������L���ꂽ�B�����ŁA���w��͓��N�X���A����F�萧�x�����ψ����ݗ������B �@����̐\�������́A�T�N�ȏ�̊ɘa��Â̗Տ��o�����w��F��{�݂ł̂Q�N�ȏ�̗Տ����C������ɘa��Â�S�������Q�O��̏Ǘ�|�|�ȂǁB��P��̎����͐\���҂T�U�l�̂����A���ސR���łP�X�l�ɍi��A��N�P�P���ɕM�L�����A������������{�B�ŏI�I�ɂP�Q�l�����i���A���̔F���ƂȂ�B �@���w�����F�萧�x�ψ���ψ����̍P���Łi�˂Ƃ����Ƃ�j�E�����w�@�����́u���̍����ɘa��Â���邽�߂ɁA���i�ɐR�������B���N�A�ė��N�͂����ƍ��i�҂������邾�낤�v�Ɛ�������B �@���w��͂܂��A��t�s�������Ɍ����ėՏ����C��̃J���L�������ł̊ɘa��Â̕K�C���Ȃǂ����B�P�������́u����C�R�[������҂ƍl���Ă���B�Ⴂ�l�����C�̎��ɐ��ォ��ɘa��Âɂ��ċ�����āA�n��Ŋ��Ă����悤�ɂȂ�v�Ƙb���B �����Ƃ� �@���m�o�n�@�l���{�ɘa��Êw�� �@��ÁA�����̊e��啪��������ɘa��Â��m�����邽�߁A�X�U�N�ɐݗ����ꂽ�B����̖��͈�t�ŁA���͎��Ȉ�t�A�Ō�t�A��t�ȂǁB����Z�~�i�[�̊J�Â�f�ÃK�C�h���C���̍쐬�ȂǂɎ��g��ł���B �����V���@2010�N2��27�� |
|
��14����{�ݑ�P�A�w�� �e�E��̖ڐ��ʼnƑ��x���̌���𑨂��C�����T�� |
| �@�ݑ�P�A�ɂ�����Ƒ��x���́C�E��܂��͑Ώۂ���������ɂ���ĈقȂ�B�����s�ŊJ���ꂽ��14����{�ݑ�P�A�w��̃V���|�W�E���u�Ƒ��x���̎��ۂƉƑ��E���E�̃p�[�g�i�[�V�b�v�v�ł́C�e�E�킩��Ƒ��x���̌��������C���悢����̂��߂̋c�_���s��ꂽ�B���̂Ȃ�����3����Љ��B �`�K��h�{�w���`�Ǘ��h�{�m�����ʂȎ���ɌʂɑΉ� �@�n��h�{�P�APEACH�iPerfect Eating And Comfortable Health�j���i�_�ސ쌧�j�ł́C�K��Ō�X�e�[�V����������ݑ�Ō�Ɠ��l�C�Ǘ��h�{�m���ݑ�ł̗Տ��h�{�̎x�����s���Ă���B�����Ə��̍]�����]��\�́C�K��h�{�w���̏d�v�ȃ|�C���g�������Ȃ���L�͈͂ő��ʂȎ���ɑΉ�����Ɩ���������C�u�ݑ�P�A�͋��ɂ̌ʑΉ����ł����ł���v�Əq�ׂ��B �ێ�ʂ̐�ΗʁC���Ҏx���̒��S�҂̔c�����d�v �@�����Ə��́C���a�̗\�h����ю��Âɂ������h�{�Ǘ�����邱�Ƃ𗝔O�Ƃ���B���Ɠ��e�͍ݑ�̖K��h�{�Ǘ������łȂ��C�f�Ï��̊O���x���C�����H�����C���ی��{�݂ł̉h�{�Ǘ��C�H�犈���ƕ��L���C���{�݁C���E��Ƃ̘A�g��}��Ȃ�����{���Ă���B �@�K��h�{�w�����s����222��̓���́C�]���Ǐ�Q��44.8���ƍő��ŁC�_�o�؎����C���A�a�C�F�m�ǁC�ċz�펾���̏��������B�˗����e��7���͐ېH�E������Q�C�����Œ�h�{�̉��P���������C��h�{�͙⚋���̏�Q�ɋN�����Ă��邱�Ƃ������B �@�]���͉h�{��ԁC�ېH�E�����@�\�C�H�����ɂ��čs�����C�]�����ɍł��d�v�ȐH���ێ�ʂɂ��ẮC�S�̂̉����Ƃ������Ηʂł͂Ȃ��C�����ǂ̒��x�H���Ă��邩��c�����邱�Ƃ��K�v�ł���B�܂��C���҂̎x�������ꂪ�ǂ̂悤�ɍs���Ă��邩�����ۂ̐H���P�A�ɂȂ���B �@�H���P�A�ł́C�i1�j�h�{�]���i2�j�o�ljh�{�i3�j�h�{�⏕�H�i�̗��p�Ȃǂ̉h�{�Ǘ��i4�j�H������ʂȂǂ̐H�ו��̎w���i5�j�p���̒����i6�j�r���Ǘ��i7�j���A�a�C�t��Q�H���܂ޒ����w���i8�j�^�[�~�i���P�A�i9�j�w���p�[�ւ̎w���|�Ȃǂ������I�Ɏx�������B���ɂ͐H�ނ̔������ɕt���Y���C�d�q�����W��p�b�N�N�b�L���O�𗘗p���������@�C�蔲���̍H�v���w������B �@���̉ߒ��ł́C�i1�j�ݑ���̔c���i2�j����̗D�揇�ʂ̌���i3�j��������̑��E��Ƃ̋��L�i4�j���̎��o���i5�j���P�����ێ���ڕW�Ƃ���i6�j�Œ�C���m�ɂ���i7�j�撣�肷������҂ւ̏��̎d���|�ɏd����u���B����́C�H���ێ�ʂ̌����C�w���p�[�ɂ��H�������C�~�L�T�[�H����̃X�e�b�v�A�b�v�Ȃǂ��܂��܂ł���C�����ɌX�ɑΉ����C�q�ϓI���l�ɓK�����������h�{�Ǘ��m�̖����͑傫���B �@�]����\�́u���������H�ׂ邽�߂ɂ́C�������������C������H�ׂ�@�\�C�S�g�̌��N��3�̗v�f���K�v�ł���C���̎����̂��߂ɖK��h�{�w����𗧂Ă����v�Əq�ׂ��B �`�ݑ�×{�̑��E��A�g�`���E��Ԃ̘A�g����n�߁C�ݑ�`�[�����\�z �@�����J���Ȋw�����ǂ̒����ł́C�ݑ��Â�����@���S�̓]�A�����ǂ�����3���͉��j�]����@���R�Ƃ��Ă���C�a�Ԃ̏d�ēx�C��Փx���ݑ�P�A���~�̌�����q�ɂ͂Ȃ炸�C�Ƒ��ւ̎x�����d�v�ł��邱�Ƃ��������ꂽ�B��������f�Ï���{���i��t���j�̐�z�����@���́C�ݑ�×{���x�������t�̗��ꂩ��C�Ƒ��x���̎��ۂ⓯�E��Ԃ̘A�g�ƍݑ�`�[���\�z�̕K�v�����������B �Ƒ��ւ̎w���m�� �@��z�@���ɂ��ƁC�Ƒ��̎x���͍ݑ�P�A�̑O��ł���C�f�@���ɉ��҂̌��N���ɂ����k�ɉ����C�ݑ�×{������I�Ɍp�����邽�ߎ��Â���уP�A�̒P�����Ɉӎ���u���Ă���B�×{�w���́C3�H�A�����Č��H�����ꍇ�A������C1���̐ێ搅���ʖڈ���1,000mL�C���ނ̏d�݂�r�A�ɗ��ӂ���ȂNj�̓I�ɍs���B��t�C�Ō�t�͂ǂ̂悤�ȕω����������Ƃ��ɕ��ׂ������Ƒ��ɖ��m�ɓ`�B����K�v������Ƃ����B �@���@���͑��E��A�g�ɂ��āC�a�@�厡��E�ɘa�P�A�S����ƍݑ��Â����f�Ï���t�C�a���E�O���Ō�t�ƖK��Ō�t�C�a�@��t�ƒ��ܖ�ǖ�t�Ȃǂ��L����M�d�ȏ������L���邱�Ƃ��d�v�����C���E�퓯�m�̘A�g����n�߂邱�Ƃ�����B�����āC�u�o�����Ζ�����{�݂͈قȂ邽�߁C�ݑ�ł̃`�[�����\�z���C�a�@�ƒn��̘A�g��i�߂邱�Ƃ����ۓI�ł���v�Ƃ����B �@����ɁC���@���́u��t�ɔ�זK��p�x�������C�؍ݎ��Ԃ�������ÂƃP�A�̑o�����n�m���Ă���K��Ō�t�������ݑ�P�A�̍������x���Ă���v�Ƃ̌������������B �@���f�Ï��ł́C�K��Ō�X�e�[�V�����Ƃ̍����J���t�@�����X����1��J�Â��C�@���ɂ̓X�e�[�V�����S���Ō�t��z���āC�T1��̒���A�����s���B�}�������⍇���Ǖ������͖����A��������ď������L���Ă���B �@����C���E��`�[���̈���Ƃ��Ă̈�t�̖����ɂ��ẮC�f�f�C���Õ��j�̌���C�a������C�Έ�t�Ή����������B �@����C�n��̗L���f�Ï��C�V�l�ی��{�݁C���{�E�i�[�V���O�z�[���C�L���V�l�z�[���C�O���[�v�z�[�����C�ݑ�̉�������ɂ���×{�҂̋��ꏊ�ƂȂ��ăP�A����邱�Ƃ͈Ӌ`�[���C�����̎{�݂��X�p�z�X�s�X�Ƃ��ċ@�\���邱�Ƃ����҂����B �@���@���́u��ÁC���ی��ɏZ�܂��̋@�\�ƉƑ��̎x�������킹��4����̂ƂȂ��ď��߂čݑ�ł̗×{���p�����C�������邱�Ƃ��ł���v�Əq�ׂ��B �`�Ŏ��̃P�A�`�q���̔N��C�w���p�[�C�w�Z�W�҂֔z�� �@���E�ی��@�ցiWHO�j����`����ɘa�P�A�ł́C���҂̉Ƒ����ΏۂƂȂ��Ă���B�������R�K��Ō�X�e�[�V�����i�����s�j�̕����D�������́C�ݑ�ŊŎ����s�����ꎖ�����C�Ŏ����s���q���ɑ��Ă͔N��Ɍ��������Ή��ƁC�w���p�[�C�w�Z�W�҂ȂǖK��Ō�t���s���ɘa�P�A�̑Ώۂ͕��L���E��ɋy�Ԃ��Ƃ��������B �Ŏ��̕]���܂ł��Ō�t�̐ӔC �@�����40�Α㏗���C������ᇁC�Ƒ��͕v��7�̑��q�B���������͂܂��C����ł̊ɘa�P�A���Ԃ͊��҂̊Ō�C���_�I�x���ɉ����C���ҕv�w�ƍ��z�×{��葱���C���҂̊�]�����������邽�߂̘b���������������B�q���ɑ��ẮC���҂��a����������Ȃɗ�����C���e�Ƌ�����}��w�Z�����ł̔Y�݂ɂ��Ή������B�܂��C�×{���Ƒ��ɂƂ��Ă悢�v���o�ƂȂ�悤�C�v�w���b�������鎞�Ԃ�����悤�z�������B���҂���]�����^����ւ̏o�Ȏ����Ɍ����āC���O�Ɋw�Z�W�҂֕a���q���̐S���ߒ��̐����Ɗw�Z���̊m�F���s���C�A�g��}�����B �@�^����ւ̎Q����C�a���������ہC�������́u���肵���Ŏ��̂��߂ɂ̓`�[���̍ĕҐ����s���ł���v�Ƃ��āC�w���p�[�̕s�����y�����邽�ߓ��s�K������{�����B�ՏI�����O�͎q���ɍ��m���C���V�Ȃǂ̍���̐���s����������邱�ƁC����т��̘b�@��v�Ɗm�F���C���J�Ȑ������s��ꂽ�B �@�ՏI�����̓����͉��f��ɗՎ����f���˗����ĊŌ�t���Ŏ�邱�Ƃɔ������B�v�ɂ́C��Ԋm�F�Ǝq���ւ̔z���C�w�Z�Ƃ̘A�g�ɂ��ď����C�ՏI���̑Ή�����������B�Ŏ���͋��t�̓��h���q���։e�����邱�Ƃ�h�����߁C�w�Z�W�҂֊Ŏ��̗l�q����C�q���ɑ���S���I�z���C���F�ւ̓`�������ƂƂ��ɒ�Ă����B�O���[�t�P�A�͑��V����іK���d�b���k��ʂ�2�N���������B �@�č�����u�e�̏I�����ɗ�����������x������A�v���[�`�v�ł́C�Ԍ��I�C�Z���Ԃ̊������悷��q���̓����������C���̔N��ɍ������Ή����K�v���Ƃ��Ă���B�I�����̐e������6�`8�Ύ��̉Ƒ��ɑ��ẮC�e�̎����ɂ��ēK�X������C�i1�j���������鎖���ɂ��Ă̐����i2�j���͐e�̋���ȓ{���߂��݂Ɉ��|����邱�Ƃ�����Ƃ����F���i3�j���t�Ȃǂ�����肪�[���l���ւ̎����̐����i4�j���̔��B�ߒ��œK�Ȋ������ێ��ł���悤�Ȕz���i5�j�������s���C���|�C�w�Z���|�C���ӂ̔O�C�����I�ȗ}���⎩���S�̒ቺ��������ꍇ�̏�������ւ̎�f�|�Ȃǂɂ��ăA�h�o�C�X����K�v������B �@�������ɂ��ƁC�K��Ō�t���s���ɘa�P�A�̑Ώۂ́C���҂ƉƑ������łȂ���t�C�w���p�[�C�P�A�}�l�W���[�C�w�Z���t�C�Տ��S���m�C�q���̗F�l�ȂNJŎ��ɂ�����邷�ׂĂƂ���B�܂��C�O���[�t�P�A�͕K�v�ȊŌ�ł���C�ݑ�Ŏ��̕]���܂ł�������ӔC������Ƃ����B �@�������́u�q�����Ƒ����ݑ�ŊŎ�邱�Ƃ͍ݑ��Â̖��������邱�Ƃł���C�q����w�Z���ݑ�̂悳��m�邱�Ƃ͏d�v�ł���v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N3��4�� |
|
��14����{�ݑ�P�A�w�� �n��ł̊Ŏ����x������V�����I���� |
| �@���Ɍ������_�ی������Z���^�[�̋���{�����́C�n��Ń^�[�~�i���P�A���x������V���Ȏ��g�݂Ƃ��āg�܂����ǃz�X�s�X�h���Љ�C�u�ݑ�ƕa�@�̒��ԂɈʒu�����O�̑I�����Ƃ��Ă̊T�O�Ƌ@�\��L����v�Əq�ׂ��B �������o�c���� �@�܂����ǃz�X�s�X�ɂ�3�̃^�C�v������C���Ɍ����ɂ͗L���f�Ï��^�C�v1�{�݁C�z�[���z�X�s�X�^�C�v2�{�݁C�×{�ʏ���쎖�Ə��^�C�v6�{�݂��W�J����Ă���B �@�L���f�Ï��^�C�v�́C���@�ݔ������L���f�Ï��Ɋɘa�P�A�̋@�\���������C���f��K��Ō��ێ����ً}���̈ꎞ���@�������B��Έ�1�l�Ɣ��Έ�4�l�i��Ί��Z1�l���j��z���C2008�N�͂���Ɠ�������̏I�������܂ޓ��@130��C�ݑ�55����Ŏ�����B �@�z�[���z�X�s�X�^�C�v�͏�Έ��v�����C�ƒ�ɋ߂����ŊŌ���E�ɂ��24���Ԃ̃P�A�������B�T1��̊ɘa�P�A����̉��f�ƁC�����̍ݑ�P�A�z�X�s�X������Ƃ���K��Ō�X�e�[�V�����̗��p���\�ł���B��N�͊J��1�N��8����Ŏ�����B �@�×{�ʏ���쎖�Ə��^�C�v�́C�K��Ō�X�e�[�V�����ɕ��݂��邢�͗אڂ��C�ʏ��ɂ��ݑ�P�A�C�z�X�s�X�P�A�����B���}�T�[�r�X�C���퐶���̐��b�C�@�\�P�������{����邪�C���p�҂͂܂����Ȃ��B �@�L���f�Ï��̓��@�_���͈�ʕa�@�̔����ɖ������C������Ղ͌������B���ʂ������������ō��֓��@�_���̉����v�]���邱�Ƃ��K�v�ł���B�z�[���z�X�s�X�Ɨ×{�ʏ���쎖�Ə��ɂ��ẮC�J�ݎx���ɑ��錧�⏕���̑n�݁C���c�Z��̋��̊��p�̕�����C�l�ވ琬�C�[���ƂƂ��ɍs���K�v������B �@���莁�́u�X�̎��g�݂ɍs���x���������邱�Ƃɂ���ăV�X�e�������邱�Ƃ��Ă������v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N3��4�� |
| �q�ǂ��z�X�s�X�A���{�ɂ��@�R�J���A�d�a�̎q��Ƒ��؍� |
| �@�d���a�C���Q�Ƌ��ɐ�����q�ǂ���A���̉Ƒ����x������{���́u�q�ǂ��z�X�s�X�v���A�_�ސ쌧��钬�Ɠޗǎs�A�k�C�����s�̂R�J���ŁA���N����Q�O�P�Q�N�ɂ����ĊJ�݂����B�R�U�T���ԁA�a���Q�ƂƂ��ɕ�炷�q�ǂ���Ƒ����u���̉Ɓv�Ƃ��đ؍݂��A���̊Ԃ̋x�������̐�����i�߂Ă���B �@�q�ǂ��z�X�s�X�͉p���Œa�����A�d���a�C���Q�̎q���Z���ԗa����{�݂Ƃ��ē����ȂǂōL�����Ă���B �@�����Ȉ��ł���u�����ݑ��ÁE�ɘa�P�A������v��\�̍גJ�����E���H�����ەa�@���@���ɂ��ƁA���������{�݂͓��{�ɂ͂܂��Ȃ��B���R�Ɉ͂܂ꂽ����̂悤�Ȋ��ʼnƑ����h���ł��A���ӂ̈�Î{�݂Ƃ̘A�g��ڎw���Ă���A������͐_�ސ쌧��钬�̌Â����Ƃ𗘗p���ĊJ�݂��邱�Ƃɂ����B �@�Ö��Ƃ́A�q�ǂ������ɖ��̎��Ƃ�����m�o�n�@�l�u�����邿����u�h�u�`�b�d�i�r�o�[�`�F�j�v������B��\�̍b��T������̋`���͏����܂Ђő����s���R�Ȓ��A��Ƃ̉�߁A���̌Ö��Ƃ����L�B�S�N�O�ɔx����ŖS���Ȃ�O�Ɂu�Ő�[�̈�Âł�������Ȃ��l�̂��߂Ɏg���āv�ƌ����c���Ă����B �@�P�S�N�O�A�]��ᇁi����悤�j�������V�̑��q������ł݂Ƃ����l���s�̉����^�|����i�S�V�j�������ɋ��͂���B�u�����͂قƂ�ǖ���Ȃ���Ԃ����������A�O�ɏ��������߂Ă͂����Ȃ��Ǝv���Ă����B���������ꂪ���邾���ň��S�ł���v �@������͐V���ɂm�o�n�@�l������A���ӂ̈�Î{�݂ƘA�g�B�Q�N��̊J�݂�ڎw���B�גJ����́u�q�ǂ��͂������A�ŕa�ɂ����肫��̐e�A�e�ɊÂ���̂��䖝���Ă��邫�傤�������A�x���ł�����������v�Ƙb���B �@�ޗǎs�ł͓��厛�̏h�V�u�،��i������j���v���A�z�X�s�X�Ƃ��ė��p����v�悪�i�ށB���s��t���a�@��`�q�f�Õ��̕x�a�����������S���ɓ��厛�����È�a�@�Ɉڂ�A���Ƌ��͂��ĉ^�c���@����������B �@�x�a����͓��厛�߂��̍��Z�o�g�ŁA���s��ł̔C�������̂��@�ɁA�n���ɖ߂�Љ�v���������ƍl���Ă����B��Ƃ���Ƃ�Ƒg�݁A�ǂ�Ȋ��Ȃ�߂����₷���̂��A�����v���W�F�N�g�̗����グ���v�悵�Ă���B �@�x�a����́u���͐̂���A�n��̐l�̈��炬�̏ꂾ�����B���s���܂܂Ȃ�Ȃ��l�������A���낰��ꏊ��ڎw�������v�Ƙb���A�N���̈ꕔ�J�݂�ڎw���Ă���B �@�k�C�����s�ł́A��a���̂��߂̖�O�{�݁u����Ղ��L�b�Y�L�����v�v�ō��t����z�X�s�X���݂��n�܂�B asahi.com �@2010�N3��10�� |
| ���ҁF�{���A�m���ā@�߂��݁A�炳�c�̌���銈���L���� |
| ����Ì���̎Q�l�Ɂ^���Z�Ŏ��ƁA���k�狤�� �@�����̌������l�������A���܂��܂ȏ�Ŗ{�������n�߂��B�������҂�Ƒ��A�Ⴂ����ɂ��A�����Ɨ������Â��ɍL�����Ă���B �@����������邾���ł����܂��������B�q�ǂ��Ɏ����ł��Ȃ��̂��߂����A�v�w�����ł��v�ɐ\����Ȃ��C�����ɂȂ遄 �@���T�̑��q�ɂ����`�����B���X�u�}�}��Y��Ȃ��łˁv�ƌ����ẮA�v�ɓ{��ꔽ�Ȃ��遄 �@�m�o�n�@�l�u���N�ƕa���̌��@�f�B�y�b�N�X�E�W���p���v�i�����s������A�d�b�O�T�O�E�R�S�T�X�E�Q�O�T�X�j�͍�N�P�Q������A�z�[���y�[�W�ihttp://www.dipex-j.org�j�łQ�O-�V�O��̓�����̌��҂S�R�l�́u���v���A���������Á��Ĕ��E�]�ځ��������f�f���̔N��--�̂T���ڂɕ����Č��J���Ă���B �@�o�ꂷ��l�����͑S�������ŁA�ꕔ�͉����╶�݂͂̂����A�唼�͊���o���Č���Ă���B�p�I�b�N�X�t�H�[�h��̎��g�݂����f���Ƃ������̂ŁA�����J���Ȋw������̏��������B�O���B����̑̌��҂ɂ��b���Ă���A�߂��ꕔ���J����\�肾�B �@�u����T�|�[�g�������܁v��\�̎O�D������i�R�S�j�����������F������s���͂V�N�O�ɓ���������A���[��؏��B�m�l�ɂ��̊������������u�����̑̌����𗧂Ȃ�v�ƂO�W�N�āA�C���^�r���[�����B�u���Řb�������Ƃ͂��������A���炢������̂͏��߂āB�b���Ȃ��玩�R�Ɨ܂����ӂꂽ�B�u�߂��݂�炳��f���o�����Ƃ��ł����B���҂̘b���������蕷�����Ԃ̂Ȃ���t���w�����ɂ����Ăق����v�Ƃ����B �@�C���^�r���A�[�̓I�b�N�X�t�H�[�h��Ō��C�����Տ��S���m���w�u�t�珗���S�l���S�������B���̈�l�A�ˏ�T�q����i�S�U�j�́A���g������̌��҂��B�����s���̊Ō��ł���̊ɘa�P�A�Ȃǂ������Ă����O�U�N�Q���A���������������B���Ì�A�����ɖ{�i�I�ɉ����A���҂����̘b�����B�u�����{���ɂ炢���Ƃ͈�t��Ƒ��ɂ��������A���a�̗F�l�����肾�����B�T�C�g�����āA�P�l����Ȃ��Ɗ����Ăق����v�Ƙb���B �@�f�B�y�b�N�X�E�W���p���̍��v�Ԃ肩�����ǒ��i�T�O�j�́u���낢��ȗ���̐l�̌�肩��A�����������ł���P�[�X�����T����͂��v�Ɗ��҂���B�F�m�NJ��҂Ƃ��̉Ƒ��A���f�A���Ȃǂ̃f�[�^�x�[�X�������������B �@���҂̍���Ȃ��݂���i�S�R�j�������s�L���恁�͍�N�P�P�����{�A�Q�n���ɐ���s�̌����ɐ��苻�z����K��A������e�[�}�Ɏ��Ƃ������B�{���A�ځu�������v�ŏЉ�ꂽ���䂳��ɁA���k���������z���𑗂����̂����������B���Z����P�W�O�l���^���Ɏ����X�����B �@���䂳��͂R�V�̎��A�������������B��p�⎡�Â̌��ǂœ����̋Ζ����ސE���A�ďA�E�B��N���ɂ��҂̏A�J���x�������Ђ�ݗ������B �@���Ƃł͕����E��ÐE���u���R�N�����O�ɁA���҂̑������ȑO�̐E��ւ̕��A��]�݂Ȃ���]�E��]�V�Ȃ�����Ă��錻���A�Ȃ���Ђ�ݗ������̂��ɂ��Đ����B�u����ɂȂ������Ƃɉ����Ӗ�������͂��B�}�C�i�X�̌o���ɉ��l�����������A�������ɐ����Ă������Ǝv���Ă��܂��v�ƌ�����B �@���Ƃ������V�a�炳��i�P�V�j�́u�h���}�ȂǂŌ��邪�҂̃C���[�W�ƈႢ�A�͋����O�����Ȑ��������S�Ɏc�����v�B�S���̒��R���m�q���@�i�S�R�j�́u���k����������̖������g�߂ɍl���邫�������ɂȂ�v�Ɗ��҂���B �@���䂳��́u���z����ǂނƁA�b����������~�߂Ă��ꂽ�悤�ň��S�����B���ȏ��̒m�������łȂ��A���̑̌��k�����Ƃ͑厖�B�������Đl���ƂłȂ��Ɗ����Ă��炦���炤�ꂵ���v�Ƙb���Ă���B m3.com�@2010�N3��15�� |
| ����Ɋւ���}�X�R�~�͊y�ϓI���ɕΌ� |
| �@�ăy���V���o�j�A��w�Տ��u�w�E�������v�w��Jessica Fishman����́C�}�X���f�B�A�̂���ɑ���p�������C����i3��16���j��Arch Intern Med 2010; 170 �I�����C���łɕ����B�̑����͂�����ϋɓI���ÂɊւ�����̂��قƂ�ǂŁC����I������Â͂��܂���グ���Ă��Ȃ��悤���B �����Ǝ��S�C���ÂƏI������Â̏��ʂɑ傫�ȍ� �@Fishman����͑����̔��s������L����V��8���ƎG��5���Ɏ��グ��ꂽ���ÂȂ�тɗ\��Ɋւ���������B�Ώۂɂ�New York Times�CNewsweek��Time�Ȃǂ��I�ꂽ�B2005�`07�N�̊֘A�f�[�^�x�[�X�ɃA�N�Z�X�C��������グ���L���S�̂ɐ�߂�L�[���[�h�ʂ̋L���̊����������B �@436���̂���Ɋւ���L���̂����C140���i32.1���j�������Ɋւ�����̂ŁC���S�ȂǂɊւ��Ă̋L����33���i7.6���j�ƗL�ӂɏ��Ȃ������B�܂��C�ϋɓI���Â̔�t�������グ���Ă����̂�57���i13.1���j���������C�����Â̗L�Q���ۂɊւ���L����131���i30.0���j�ł������B �@�ߔ����̋L���i436����249���j�͐ϋɓI���Â�S�ʓI�Ɏ��グ�Ă������C�I������Â��邢�̓z�X�s�X�Ɋւ����0.5���ɂ����Ȃ������i436����2���j�B �@������͍���̒������ʂ���C�}�X���f�B�A�̂��������p���ɂ�芳�҂�����f�Â�\��ɑ��C�s�K���Ɋy�ϓI�ȃC���[�W������Ă���\��������Ǝw�E�����B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N3��17�� |
| ���ǂ��a�@�̎ʐ^�Z���s�[�@�v�����`�ɂ��Đ�����͂����N |
| �@���[�N�V���b�v���n�܂�Ƃ����ɒ��w�P�N�̏��q���k���a�@���̔��X�ɑ������B�u�V�������̂͂��邩�ȁv�ƂԂ₫�Ȃ���A�َq�̃R�[�i�[�Ŏʐ^���B��n�߂�B �@�Q���R���ɋ{�錧�����ǂ��a�@�̐�����x���w�Z���ǂ��a�@�������ōs��ꂽ�u�ʐ^�Z���s�[�v�ł̈�R�}�B�قُ܂����p�Ƀ����Y�������Ă���ƁA���@���u���̎q�͐H������������A���َq���H�ׂ��Ȃ��́v�Ƌ����Ă��ꂽ�B���̎q�̏Ί�ɋ����l�܂����B �@���݁A���{�ʐ^�Ö@�Ƌ���͒��쌧�����ǂ��a�@�Ƌ{�錧�����ǂ��a�@�̉@���w���Łu�ʐ^�Z���s�[�v�����{���Ă���S����������P�J�����₷�B��\�̎���M�q����i�T�P�j�́A���ǂ��a�@�������̌��_���Ɗ����Ă���B �@�O�S�N�ɒ��쌧�����ǂ��a�@�ōs�����A�ŏ��́u�ʐ^�Z���s�[�v�B��̕���p�̂��߃x�b�h�ʼn߂������Ԃ̑������q���k���Q�������B�Ԃ����ɏ��A�k�����ŎB�����ʐ^�͂킸���R�A�S���B�Ԃꂽ�ʐ^���������F���_��I�ƖJ�߂��B�ޏ��͊�сA�J���������B�ϋɓI�ɎQ�����A�̂��S���������肵�Ă������Ƃ����B���䂳��́u�Ō�͎����̑��ŕ����đމ@�����B�ʐ^�̗͂�M���邫�������������v�ƐU��Ԃ�B �@�u�މ@�������Ł[���B�C�s���Ă��[�v�B��N�W���ɒ��쌧�����ǂ��a�@�̃��[�N�V���b�v�Œj�q���k�����������b�Z�[�W���B�f���ɕ\�����ꂽ�S�̐��B�u�ʐ^�Z���s�[�v�Ŏq�ǂ������͎v�����`�ɂ��A������͂����N���Ă���悤�Ɍ������B ���m�o�n���{�ʐ^�Ö@�Ƌ���� �@�u�ʐ^�Z���s�[�i�ʐ^�Ö@�j�v�͂m�o�n���{�ʐ^�Ö@�Ƌ�����O�V�N�ɐݗ���������M�q��\������Ö@�B �@�ʐ^���B��A�D���ȃJ�b�g��I��Ńv�����g�B������R�O�Z���`�l���̉�p���ɒ���t���A���R�ɏ���t���āA���t��Y����u�X�N���b�v�u�b�L���O�v���s���B�ʐ^��ʂ��Ď��R�Ȏ��ȕ\�����y���ނ��ƂŁA�Ώێ҂�������₳��A���M��ӗ~�ȂǁA������͂����N������@�B�ʐ^�̋Z�p�͕K�v�Ƃ��ꂸ���L���l���Q���ł���B�m�I��Q�Ҏ{�݁A����Ҏ{�݁A�ɘa�P�A�a���ȂǂP�O�J���Ŏ��{����Ă���B �@������i�O�R�E�R�V�T�T�E�Q�O�W�T�j�́A���[�N�V���b�v�̐��b������t�@�V���e�[�^�[�̈琬�ɗ͂����Ă���B���N�͓����Ƒ��Ŏ��{�\��B�R���Ԃ̍u���ŁA�ʐ^�Ö@�̗��_�A���H��A�e�{�݂ł̒��ӎ����Ȃǂ��w�сA���{���@���K�����A������̌����ďC���ƂȂ�B�u�����C��������ƂȂ�A��������ŋ@�ނ�ݗ^���ă��[�N�V���b�v�����{�ł���x���v���O���������p�ł���B �����V���@2010�N3��18�� |
| ���ԗ�����A���a�̌����|�|���� |
| �@����s�o�g�̃W���[�i���X�g�E���ԗ����Q�V���A����s�Η����̒���u���b�N�z�[���ŁA�u����Ƌ��ɐ�����v�Ƒ肵�ču�����A����̂��a�̌���������B �@�u����͒���s��t���ÁB���Ԃ���͐����A�Ȋw����ł̊����̂ق��A��w���e�[�}�ɂ��������ł��m����B�O�V�N�P�Q�����N���i�ڂ������j����̎�p���A���݂́u�Ĕ��҂��v�łR�J���Ɉ�x�A�����������ɒʂ��Ă���Ƃ����B �@�����O�̍D��S�ŁA����ɂ��Ă���ނ��d�ˁA�m��Βm��قǁu�����ǂ������̂��������Ă��Ȃ��v�ƋC�t�����Ƃ����B�����āu���J���̉������ʂ̂��߂ɂ���Ɠ������Ƃ��A�����̎��̈ێ���I�v�ƌ�����B �@���Ԃ���́u�q�g�͎��ʂׂ������Ƃ������o�����ׂ��ł��B�߂��݂�Q�����甲���o���A��������邽�߂ɁA��҂́A�g�̓I��ɂ��琸�_�I��ɂ܂őS�l�I�Ȃ���̋�ɂ�a�炰��ɘa�P�A�����A�{���͂ł��Ȃ��v�Ƙb�����B �����V���@2010�N3��28�� |
|
��12����{�ݑ��w�� �牺�A�t�͊Ǘ��E���S�ʂ���S�g��Ԃ̉��P�ɗL�� |
| �@�ʏ�C�A�t�͌o�Ö��I�ɍs���邪�C�ݑ�×{���҂ł͐Ö�����̓��^������ȏꍇ������B����C�牺�A�t�͔�r�I��Z���ȕւŁC�Ƒ��ł��Ǘ����\�Ƃ��������_������B��Ö@�l���`�����q��ՃN���j�b�N�i�_�ސ쌧�j�̍����o����́C�ݑ�×{���҂ɑ��Ĕ牺�A�t���{�s�����Ǘ�������B�u�牺�A�t�ɂ��E���ȂǑS�g��Ԃ̉��P�������C�Ǘ�����ш��S�ʂ��l������ƍݑ��Âɂ����ėL���Ȏ��Î�i�ł���v�Əq�ׂ��B �������҂ł͊Ŏ��̏������\�� �@�Ώۂ͍ݑ�Ŕ牺�A�t���{�s����25��i�j��12��C����13��C���ϔN��85.9�j�B��b�����͂������ҁi�x�C�݁C�咰�C�X�C�]��ᇁC�畆�C�A���j��13��C�ҁi�������C�]�[�ǁC�p�[�L���\���a�C�����ǐ��x�����C�̍d�ρC�����S�s�S�j��12��ł������B �@�A�t���{�s���������ȗ��R�́C�i1�j�o���ێ�ʒቺ�ɂ��E���̕�i2�j�ӎ���Q�ɂ��o���ێ换��i3�j�x���܂��̓C���E�X�̎��Ái4�j���ÖړI�i5�j�Ƒ��̊�]�\�Ȃǂł������B�܂��C�牺�A�t��I���������R�́C�i1�j�z���Ԃ��s����i2�j�Ö��m�ۂ�����i3�j���Ȃ܂��͎��̔��j�̊댯���������i4�j�Ƒ��哱�̓_�H�Ǘ��\�Ȃǂł������B �@�牺�A�t�{�s���͔N�X�㏸���C��N��11��Ɏ{�s����Ă����B�牺�A�t�̓��^�����͕���11.6���C���^�ʂ͕���607.9mL/���ł������B �@���S��16��C���P��9��ł���C������������҂Ɣ҂ƂŔ�r����ƁC�������҂ł͎��S10��C���P3��ł������̂ɑ��C�҂ł͂��ꂼ��6��C6���50���ɉ��P���F�߂�ꂽ�B���^�����Ⓤ�^�ʂɂ������҂Ɣ҂Ŗ��炩�ȍ��͔F�߂��Ȃ������B �@�牺�A�t�𒆎~�������R�́C�i1�j�S�g��Ԃ̉��P�i2�j���S�i3�j�Ǐ��̋z����Q�ɂ�镂��i4�j�h�����̔畆���ԁi5�j�Ƒ��̊�]�\�ł������B �@�牺�A�t�̗��_�Ƃ��ẮC�i1�j�҂ł͗L���i50�������P�j�i2�j��������ɏ��Ȃ��ߏz���Ԃւ̉e�������Ȃ��i3�j�������҂ł͖{�l��Ƒ��������}����܂ł̋C���̐����C�S�̏��������鎞�Ԃ��ł���\�Ȃǂ��l����ꂽ�B����C���_�Ƃ��Ă͕���̑�����h�����ɔ畆���Ԃ��F�߂��邱�Ƃ�����C���̏ꍇ�͒��~����K�v������B�Ȃ��C�d�x�̊����ǂ͔F�߂��Ȃ������B �@���䎁�́u�牺�A�t���{�s���邱�ƂŁC�ݑ�I�����̊��҂�Ƒ��Ɏ����}����܂ł̎��Ԃ����邱�Ƃ��ł����v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N4��1�� |
|
��12����{�ݑ��w�� �n���Ì��C�ň�ØA�g��@�\�����𗝉� |
| �@��Ö@�l�Вc���t��쒆��@�i�����s�j�ł́C�n��ł̈�Îx�������̈�Ƃ��Ēn��a�@�̏����Տ����C��ւ̒n���Ì��C�����{���Ă���B���@�̈��B���q���i�c��`�m��w�����w�����ɘa�P�A�`�[���j��́C�����C�����C��ɗ^����e���ɂ��Č������邽�߁C���C�O��ɃA���P�[�g�����{�B�u�މ@�O�J���t�@�����X�ւ̎Q���ȂǁC�މ@���������炩�����C�ݑ�ڍs�̗����̌����邱�Ƃň�ØA�g����ы@�\�����ɂ��Ă̗�����[�߂邱�Ƃ��ł��邽�߁C�n���Î��K�͏����Տ����C��ɗL�p�ł���ƍl����ꂽ�v�Ƒ�12����{�ݑ��w��ŕ����B ���ی����x�̗����͑啝�ɑ��� �@�Ώۂ́C1�����Ԃ̒n�挤�C���s���������Տ����C��35�l�i�����100���j�B�ݑ��ÁC���ی��C���K���e�Ɋւ��āC���C���{�O��ɋL�ڎ��A���P�[�g�����{�����B���C���e�́C�O���f�ÁC�ێ����͊��҂̐f�Â���ђ���K��f�ÂȂǂŁC�K��f�Âł́C�މ@�O�J���t�@�����X����n�܂�ݑ�ڍs�̗����̌����C�n�摽�E��ɂ��T�[�r�X�S���҉�c�ɂ��Q��������̂ł���B �@���C���68.6�������C�O�ɒn���t�Ƃ̘A�g�o���������C���̏Ǘ�͑������ɁC�����C���������C�p�p�nj�Q�ł������B�����u�]������Ȃ́C�������ɓ��ȁC�O�ȁC��A��ȁC�w�l�ȁC�����Ȃł������B �@�ݑ�×{�x���f�Ï��̎d�g�݂�m��҂́C���C�O�͂킸��2.9���ł��������C���C���100���ƂȂ����B68.6�����މ@�O�J���t�@�����X�ɎQ�����C���̂���75�������̗L�p����K�v���������C����a�@��t�Ƃ��ĐϋɓI�ɎQ������Ɖ����B �@�K��f�Ó��s�̊��z�Ƃ��ẮC�̑������ɁC�u���҂̎����������������v�C�u��ØA�g�܂��͋@�\�����ւ̗������[�܂����v�C�u���҂�Ƒ��̈��S�v�C�u�M������̊������v�C�u��I�����x���̏d�v�������������v�C�u���L���Տ��\�͂̕K�v�����������v�C�u�R�~���j�P�[�V�����̓�����������v�Ȃǂ�������ꂽ�B �@���ی����x�𗝉����Ă���҂͌��C�O�͂킸��8.6���ł��������C���C���71.4���ɑ��������B���C�O�C88.6�����厡��ӌ����쐬�̌o��������C���̓���͑������ɁC����ω��E���������ɔ����v���̔����C��Ï��u���Ǘ�C�����C�F�m�ǂł������B�S���҉�c�ɂ�68.6�����Q�����C91.4�������C��ɉ��ی��ɂ������t�̖����𗝉������B �@�g�߂Ȏ҂����ی��𗘗p���Ă��銄���́C���C�O��14.3�����������C���C���100�������g�̉��K�v���ɍݑ��Îx������ی��ɂ�鐶���x������]�����B�̌����������K���e�́C�������ɁC��ØA�g����эݑ�K��f�ÁC���͂̎��ہC�n���ÑS�ʁC�ݑ�^�[�~�i���P�A�ł������B���C�O�C��ԗՎ��K��ւ̎Q����]�҂�17.1���݂̂ł��������C���C�ߒ��ł͑���������I�ɎQ�������B�܂��C�ݑ�ł̊Ŏ��̌o�����M�d�Ǝ~�߂Ă����B �@���B���́u�K��f�Âł́C�n��ŗ×{���銳�҂̐��������̌����邱�Ƃ��M�d�Ǝ~�߁C����̈�ØA�g��ݑ�ڍs�Ǘ�ւ̐ϋɓI�֗^�����҂����B���C��̑����͌��C���ɒn���t�Ƃ��Ċ������C��t�Ɗ��ҁC�Ƒ��Ԃ̈��S��M���W�\�z�Ɍg��邱�ƂŁC���҂Ɋ��Y���C�Ƃ��Ɏ��a�Ɠ������_���Ċm�F�����v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N4��1�� |
| �z�[���z�X�s�X�F�u���������v�J���@�u������̍Ŋ��̋��ꏊ�v�n��̒��Ɂ@�^�F�{ |
| �@����̔F�m�NJ��҂炪��������z�[���z�X�s�X�u���������v�̊J�������P�R���A�F�{�s��R��t�Q�̓����ł������B�Ö��Ƃ����C������������������ŁA�Ō�t��w���p�[���Q�S���ԑ̐��œ����҂������B�u�V�V���v�Ȃǂ��܂��܂ȗ��R���玩��ōŊ����}����̂�������A�ƒ�I�ȕ��͋C�ʼn��₩�ɉ߂����鋏�ꏊ�Ƃ��Ē��ڂ��ꂻ�����B �@���������́A�m�o�n�u�V���ƕa���̕������������������v���^�c�B��\�̒|�F�珻�E�F�{�ی��Ȋw����C�����i�S�W�j�́A�V���s�̗����ŕی��t�����Ă������A�a�@���������ꂽ�q�ǂ��̉ƂŖS���Ȃ鍂��҂������̂ɏՌ������B�u�n��̒��ł��̐l�炵���Ŋ����}���Ăق����v�ƂQ�����������n�߁A�����ɊJ�������B �@�F�{�s�����̖؉��a�v����i�V�X�j�͂P�N�O�ɃC���t���G���U�]���ɂ�����A�C�ǂ�؊J�����B�ȑO��炵�Ă����{�݂ł́A���R�ɕ������Ƃ͋����ꂸ�A�C�ǂɓ��ꂽ�ǂ��Ȃ��悤�ɂƎ�܂�t�����Ă����B�Q���ɂ��������ŕ�炵�n�߂Ă���͏Ί��������ȂǕ\����邭�Ȃ����B�ȏ��q����i�V�U�j�́u�{���͎����������ǎ���������A�q�ǂ��������ɗ���鋗���ł͂Ȃ��B���S�����\��ɂȂ����̂����ċC�������y�ɂȂ����v�Ƙb���B�|�F����́u����ł��{�݂ł��Ȃ�������̋��ꏊ�ɂ������v�Ƙb���Ă���B���w�Ȃǖ₢���킹�͂O�X�U�E�R�Q�X�E�V�W�R�R�B �����V���@2010�N4��14�� |
| ��Ö��A�T�W�l���M���@��吶�A����ŃV�i���I�@�^�a�̎R |
| �@��Â����邳�܂��܂Ȗ����e�[�}�ɁA��吶���V�i���I���������ĉ�����u��Ö�胍�[���v���C�v���A�a�̎R�s�I�O�䎛�̌������ł������B����́A�ɘa�P�A����Ã~�X����Ô��聤�����\�h----�̂S�e�[�}�ɂ��āA�Տ����K���T�����T�N���T�W�l���S�ǂɕ�����ĉ������B�V���A�X���ƃ��[���A����������������\�ɁA�w���⊳�҂�͌������Ă����B �@�ɘa�P�A�̃O���[�v�́A��������Ɛf�f���ꂽ���҂ƉƑ��̋�Y��\���B����̍��m��ɘa�P�A�����߂��ʂȂǂ����荞�݁A��Ï]���҂̊����i�����Ƃ��j���\�������B�܂��A��Ã~�X���e�[�}�ɂ����O���[�v�́A��Ã~�X�Ŗ���D��ꂽ���҂R�l����l���B�ߌ���H���~�߂邽�߂ɁA��Ï]���҂ɉ������߂��邩���u�_�v�ƈꏏ�ɍl���郆�j�[�N�ȉ��o�Ŕ��\�����B �@��Ö�胍�[���v���C�́A��Â̂���ׂ��p�����҂ƉƑ��̗���ɂȂ��čl���Ă��炨���ƁA�u�����ȁE�ɘa�P�A�v�̎��Ƃ̈�łX�X�N������{���Ă���B����́u�Տ����K�ɓ���O�̍��̒i�K�ŁA�������Ȃ̂��l����@��ɂ��Ăق����v�Ƃ��Ă���B m3.com�@2010�N4��17�� |
|
���ÁC�h�{����ьċz�Ǘ� �G�r�f���X�Ɋ�Â��؈ޏk�������d���ǁiALS�j�̃P�A �\���Ă�ALS�f�Â̈Ⴂ�܂��ā\ |
| �V�� �L�a ���@�k����w���_���� �O�{ �� ���@�R�����r�A��w�_�o���ȋ��� �@�_�o�ϐ�������1�ł���؈ޏk�������d���ǁiALS�j�͉^���j���[�������N������a�ł���C�����͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ����C�����]�[�����͂��߂Ƃ��āC��N�P�I�ċz�⏕�inoninvasive ventilation�FNIV�j�C�o��������I��ᑑ��ݏp�ipercutaneous endoscopic gastrostomy�FPEG�j�Ȃǂ��܂ނ������̎��Ö@������B�č��_�o�w��iAmerican Academy of Neurology�FAAN�j�ł�1999�N�ɔ��\����ALS���ҊǗ��̂��߂̃G�r�f���X�Ɋ�Â��f�Îw�W�ipractice parameter�j�ɐV���ȃG�r�f���X�������C10�N�Ԃ�̉������s�����B�ψ�����o�[�ł���O�{�������V���L�a�����f�Îw�W�����̊T�v�ɂ��Ă��b�������������B �������ꂽ�����]�[���̗L�p�� �V���@�{����AAN����������ALS�̐f�Îw�W�ɂ��āC������Ƃɓ��������O�{�搶�����}�����Ă��b�����������܂��B����C�����Ɏ������w�i�ɂ��Ă��������������B �O�{�@�������10�N�O��1999�N�ɑO��̐f�Îw�W�����\����܂����BALS�̐��オ�G�r�f���X�Ɋ�Â��C�܂��́C�G�r�f���X���Ȃ��Ƃ��́C����ꎩ�g�̌o��������悢ALS�̐f�Â𐄏��������̂��f�Îw�W�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��܂����B���ꂩ��10�N�̊ԂɁC��N�P�I�ċz�⏕�inoninvasive ventilation�FNIV�j�Ɋւ��閳����������܂ނ������̏d�v�Ȍ������уG�r�f���X�����\����܂����B���݂ł��č��H�i���i�ǁiFDA�j���珳�F���ꂽALS���Ö�̓����]�[�������ł����C�ΏǗÖ@�ɂ������̐i�����݂�ꂽ���ƂȂǂ���C�G�r�f���X�Ɋ�Â����f�Îw�W�����Ɏ���܂����B���X�ɂ��č��܂ł̎��Ö@�𑱂��悤�Ƃ���ێ�I�Ȉ�t�̍s����ς���ɂ͂�������Ƃ����G�r�f���X�̗��Â����K�v�ł��B �V���@����̐f�Îw�W�̂Ȃ��ŁC�B��̃��x��A�̎��ÂƂ��Đ�������Ă���̂̓����]�[�������ł��ˁB �O�{�@�����]�[���͕č��Ŕ�������Ă���13�N�o���܂��B���݂ł��B��̖�܂ł��郊���]�[���̏d�v��������C��������Ă��܂��B�����]�[���ɂ�4�̃N���X I �̔��\������C����ɂ��C���x��A�Ƃ��Đ�������܂����B�܂�C���̐f�Îw�W�̂Ȃ��ł́CALS���Âɂ����ă����]�[���́u�K�����^���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Áv�ƈʒu�Â����Ă��܂��B �V���@�č��̃����]�[�����p���͂������ł����B �O�{�@60�`65�����炢���Ǝv���܂��B��ܔ�����i��900�h��/���j�ł��̂ŁC�قƂ�lj������Ă��錒�N�ی����F�߂Ă����l���������p���Ă���̂�����ł��B�܂��C�����]�[���ɑ���F�����\���ł͂Ȃ���t���C���҂���ɂ�����Ɛ������Ȃ��P�[�X������܂��B�O��̐f�Îw�W�ł������]�[���ɂ��Ă͋L�ڂ��Ă���̂ł����C����̓��x��A�Ƃ��Ė��m�ɐ�������܂����B �V���@�����]�[�����������ꂽ�����́C�������Ԃ͐���������������x�ł��邪�C�i�s�͒x�点��Ƃ������Ƃł������C����10�N�ԂŐV�����G�r�f���X�͂������̂ł����B �O�{�@��K�͂ȃf�[�^�x�[�X���g��5�`10�N�Ԃɂ킽����{�����R�z�[�g�����ɂ��C�������Ԃ�6��������21�������������Ƃ���Ă��܂��B�܂��Cxaliproden�̗Տ������ŕ��p���������]�[���ɂ���post hoc analysis���s���C�����]�[���̒����I�ȉ������ʂ��m�F����܂����B���͓����l�����Ă����������ʂ�����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B �V���@�\���N�g���Ă��܂������C�����ȕ���p�͌��ӊ��ƚq�C�ł���C�����ł����L�p�Ȗ�܂ł��B �O�{�@����͂͂����肵�Ă��܂��B����p�̂��߂Ƀ����]�[�����g�p���Ȃ����Ƃ͏��Ȃ��Ǝv���܂��B �o��������I��ᑑ��ݏp�͑̏d����C�����ɗL�� �V���@���ɉh�{�Ǘ��ɂ��Ă������������܂��B���{�ł͂��Ȃ荂���p�x��PEG�����݂���Ă��܂����C����̉����ł͂ǂ̂悤�Ɉ����Ă��܂����B �O�{�@PEG�ɂ��ẮC�V�����d�v�ȃG�r�f���X���o�����߁C�u�h�{��Ԃ̈�����̏d�����������ȏꍇ�ɂ͍s���ׂ��ł��鎡�Ái���x��B�j�v�ƈʒu�Â��Ă��܂��B����10�N�ŁC�č��ł�PEG�̓�������2�{�ɂȂ�܂������C�܂��\���Ƃ͌����܂���B �V���@PEG�͉������ʂɂ��L���ł���ƋL�ڂ���Ă��܂��ˁB �O�{�@�m����PEG�̓����ɂ�鉄�����ʂ����������������܂��̂ŁC���x��B�ƂȂ��Ă��܂��B���̌l�I�Ȉӌ��ł����C���̌��ʂ͂���������������Ƃ����������Ȃ��ƌ��_���o�Ȃ��Ǝv���܂��BQOL�Ɋւ��Ă̓v���X�y�N�e�B�u�Ȏ������Ȃ����߂ɁC���_�Â����Ȃ��Ƃ����]���ł��B �V���@�h�{�⏕�܂Ɋւ��ẮC�������ł��傤���B �O�{�@�u�N���A�`�j���͎��ÂƂ��ėp����ׂ��ł͂Ȃ��i���x��A�j�v�C�u���p�ʃr�^�~��E�͍l�����ׂ��ł͂Ȃ��i���x��B�j�v�Ƃ��Ă��܂��B���҂���Ƀr�^�~��E��N���A�`�j���̐ێ�����߂�ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B ��N�P�I�ċz�⏕�̓������������� �V���@���Ɍċz�Ǘ��̖��ɂ��āC�傫���ύX���ꂽ�_�����������������B �O�{�@�����Ƃ��傫���ς�����̂́CNIV����������ѓw�͐��x���ʁiforced vital capacity�FFVC�j�ቺ��x�点��̂ɗL���ł���Ƃ����G�r�f���X���o�����߁C�uALS�̌ċz�s�S���Âɂ�NIV���l�����ׂ��ł���i���x�� B�j�v�Ɛ������ꂽ���Ƃł��B1999�N�̎��_�ł́CFVC��50���ɂȂ����犩�߂��ق����悢���낤�Ƃ������x�������̂ł����C���m�ȃG�r�f���X���o�����Ƃɂ���Đ����x���オ��܂����B �V���@�ċz�@�\�ቺ�̐f�f�ɂ��āC��ԃI�L�V���g���[����эő�z�C���iMIP�j�͗��� FVC�����ċz�s�S�̑������o�ɂ����ėL���ȉ\��������C�܂��C���FVC�́C���u���ؗ͒ቺ�̌��o�ɂ����ė���FVC�����L���ȉ\��������Ə�����Ă��܂����B �O�{�@�m���ɗ���FVC��60�����x�ł����Ă��C�s�����ʂł͂悭����Ȃ��Ƒi���銳�҂���ł́C���FVC�𑪒肷���20���ȏ�ቺ����P�[�X������܂��B�܂��C�ċz�����s����i���邪�C���ʂł���ʂł�FVC���ۂ���Ă��銳�҂���Ŗ�Ԏ_�f�Z�x����i�I�L�V���g���[�j����ƁCdesaturation�̎��Ԃ������C�p�x�������������܂��BFVC�͂�����傫���̂ŁC���낢��Ȃ��̂�g�ݍ��킹�Čċz��Ԃ̈��������o���Ȃ���Ȃ�܂���B�����ŁCFVC�ȊO�̌ċz�@�\�]���@�ɂ��Ă��낢��Ȍ������Ȃ��ꂽ���ʁC���x��C �̐����ƂȂ����킯�ł��B �V���@���{�ł�NIV�����ɑ����g���n�߂Ă��܂����C�č��ł͂������ł��傤���B �O�{�@�ċz�@�\���������Ă���C�قƂ�ǂ̕���NIV�����߂܂��B��T�ɂ͌����܂��C�����̊��҂���́C������Q�C����Ⴢ��Ȃ���CNIV�����ŏ��Ȃ��Ƃ�1�`2�N�����邱�Ƃ��ł��܂��B�������CNIV���g���Ă��������ɁC���ɋ���Ⴢ̂��銳�҂���ł͎���Ɏg���Â炭�Ȃ�܂����C�ŏ�����g���Ȃ����҂�������܂��B���������ꍇ�C�C�ǐ؊J��I�Ԃ̂��C�ɘa�P�A���s���̂��Ƃ�����肪�N����܂��B �V���@����f�Â̂Ȃ��ŁC�u�C�ǐ؊J�����܂����H�v�Ƃ����b�͕K������̂ł����B �O�{�@��Î҂����҂��Ȃ�ׂ��G�ꂽ���Ȃ��b��ł��̂ŁC������肪�N�������Ƃ��ɘb���Ƃ������Ƃɂ��Ă��܂��B��������t�ɂ���Ă��̃A�v���[�`�̎d�������Ȃ�Ⴄ�Ǝv���܂��BNIV�Ɋւ��Ă͉������ʂ����邵�C������QOL�����P���邱�Ƃ�b���C��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��C�Ƃ����ӂ��ɘb���܂��B �V���@���{�ł͌ċz���ꂵ���Ȃ�ƁC�C�ǐ؊J�ւƈڍs���Ă���X��������̂ł����CNIV�ɂ���Ċ��҂���ɑ傫�ȑI���̗]�n���c���悤�ɂȂ��Ă������Ƃ͔��ɍD�܂������Ƃ��Ǝv���܂��B �O�{�@�����ł��ˁBNIV���o�����邱�Ƃɂ���āC�C�ǐ؊J���ǂ̂悤�Ȃ��̂������҂�������x�\���ł��闘�_������܂��B �V���@���{�ł�NIV�̓������\���Ɍ�������Ȃ��܂܁C�l�H�ċz��ɒ��ڈړ����Ă��܂������߁C�ɘa�P�A���\���Ɍ�������]�n���Ȃ������̂�������܂���ˁB ���f�B�J���g���r���[���@2010�N4��22�� |
| �I�����͕a�@��]�@���{��t��{���ӎ����� |
| �@���{��t��Ƃ�܂Ƃ߂���Ð��x���v�ɑ�����{���̈ӎ������ɂ��ƁA�u�{���̑������I�����ɂ͕a�@�ɓ��@�������ƍl���Ă���B���݂̈�Ñ̐��ł͕s�\���v�Ǝw�E�A�u�{���͈�Ô�̗}����Õ���̌����ł���A���̓]��������ׂ��ł���Ǝv���Ă���v�ƕ��͂��Ă���B �@�ݑ��ÂƉ��E�×{�ɂ��āA�u����ōŌ�܂Łv�Ɗ肤�{���͂Q����ŁA�u�\�Ȍ��莩��i�I�����͕a�@�A�z�X�s�X�A�ɘa�P�A�a���ɓ��@�j�v���T�����߂��B�a�@�ł̏I������]�ޗ��R�Ƃ��Ắu�Ƒ��ɑ傫�ȕ��S�����������Ȃ��v���������Ă���B��t��́A��t�A�ی��t�A�P�A�}�l�W���[�Ȃǂ̑��E��A�g�A��Ë@�ցA���{�݂Ȃǂ̋@�֘A�g�A�ߗZ���̋��͑̐��̍\�z�Ȃǂ́u�n��l�b�g���[�N�Â��肪�ݑ��Â̐��i�ɖ𗧂v�Ƃ��Ă���B �@�܂��A�������ł́u��Â̎��v�u�A�N�Z�X�v�u�R�X�g�v����Â̂R�v�f�ƒ�`���A�{�����ł��d�����Ă���_�́u��Â̎��v�ł��邱�Ƃ������A��t��ɑ��āu��Â̎��̈ێ����]�܂�Ă��邱�ƁA�ێ����邽�߂ɂ͍����̊m�ۂ��K�v�ł��邱�Ƃ𐭕{�ɋ����咣���Ă����ׂ��v�ƒ��Ă���B �@������20�Έȏ�̕{���ݏZ�҂��ΏۂŁA��N�P������Q���ɂ����Ď��{�A�Q�U�R�P�l����L�����B �������V���@2010 �N4��24�� |
| �]���킸���̐��k�ɑ��Ə؏��A�w�Z�Ɠ�������1�����������Ǝ����J�� |
| �@�č��ł�5�����{����6����{�����ƃV�[�Y���ł����A����A������1�����߂��������A�J���U�X�B�̍��Z�ň�l�̐��k�̂��߂ɑ��Ǝ����s���܂����B �@�Ď��J���U�X�V�e�B�E�X�^�[�ɂ��ƁA���̑��Ǝ��ɗՂ̂́A���B�^���K�m�L�V�[�E�n�C�X�N�[���ɒʂ�18�̃R�[�i�[�E�I���\������B�ނ̂��߂ɊJ���ꂽ���Ǝ��ɂ́A���e�Ƒc����A�����Ĕނ̐��b������z�X�s�X�̊Ō�m�炪�Q�܂����B���̓R�[�i�[����͍����ނ��ރK���̂��ߗ]���킸���Ɛf�f����A���Z���{���\�肵�Ă��鑲�Ǝ��܂Ŗ��������Ȃ��ƌ����Ă����̂ł��B �@�������R�[�i�[����́A4���ɓ����Ă���a�����B�a�Ŏ�����g�̂ɔ]�������N���Ă��܂������g���}�q�A��������ׂ邱�Ƃ�����Ȃ��Ă��܂����B�����m�����w�Z���Ɠ�������́A�Ȃ�Ƃ��R�[�i�[����ɑ��Ə؏�������Ă��炢�����ƁA�}篁A�ނ̂��߂̑��Ǝ����v��B���e�ɐ\���o�܂����B �@�����A���̌v������R�[�i�[����̗��e�́u����̕���Ƃ͂����A�K���̒ɂ݂ŋꂵ��ł��鑧�q�ɊO�o�͖����ł͂Ȃ����v�i�J���U�X�V�e�B�E�X�^�[�����j�Ɗ����������B�������R�[�i�[����́u�i���Ǝ��́j�X�e�[�W�ɏオ�肽���v�ƍ���B���e�����̋����ӎu�ɐS��ł���A���Ǝ��Ɏ^�������̂ł��B�����Ă��ׂĂ̏�����������4��15���A���̓������}���܂����B �@���̓��w�Z���͓��ʂɎ��Ƃ��Ő�グ�A500�l�߂����k���u���ɏW���B�����ɐԂƔ��̑��ƃK�E���𒅂��R�[�i�[���ʘH�ɓo�ꂵ�ABGM�Ɂu�Е����X�v������钆�A�m�l��ɎԂ�����������X�e�[�W�ɏオ��܂����B �@���̍Œ����ɂݎ~�߂̓_�H���Ă����R�[�i�[����B��`�����F�l�����Ƃ̊ԂŁA�ɂ݂��Ђǂ������ꍇ�̃W�F�X�`���[���ŏ��Ɏ�茈�߂Ă����܂����B�u�ɂ݂���������w1�{�A�䖝�ł��Ȃ��ɂ݂������w2�{�������邱�Ɓv�i�J���U�X�V�e�B�E�X�^�[�����j�B�������R�[�i�[����͍Ō�܂Ŏw��2�{�����邱�Ƃ͂����A�Ō�܂ő��Ǝ��������������ł��B �@�����������̐��������Ă��܂��ނ̎p�����āA���ł͎v�킸���������F�l���B�����A�R�[�i�[����͔O��̑��Ə؏�����ɂ��āA�ƂĂ��K�������������Ɠ`�����Ă��܂��B �@������4��21���̖�A�R�[�i�[�����18�N�Ԃ̒Z�����U����܂����B�ނ̕��́u�Ƒ��ƗF�l�Ɉ͂܂�āA�܂��ɔނ��]�ʂ�ł����v�i�J���U�X�V�e�B�E�X�^�[�����j�ƌ���Ă��܂��B �i���i���h�b�g�R���@2010 �N4��26�� |
| �u�ޗnj��z�X�s�X����v�����P�O�N�@���f��f���A�b�v�ڎw�� |
| ���u�����Ï[���v���N�A���̕ύX �@�����Ƀz�X�s�X�i�ɘa�P�A�a���j���J�݂��悤�ƁA�Z�����������������u�ޗnj��z�X�s�X����v�i�n�l�^��Y��A��S�O�O�l�j���P�O�N���}���A��Â������͂T���ɂT�O��̐ߖڂ��}����B���̊ԁA�����ɂ̓z�X�s�X���J�݂���A�I������Âւ̗������i���A�ˑR�Ƃ��ĉۑ�͑����B���N�S���Ɂu�ޗnj��̃z�X�s�X�Ƃ����Â������߂��v�ɖ��̂�ύX���A�����Â̏[���Ɍ����āA�����̕����L���n�߂��������ނ����B �@�u���̂܂܂ł͓ޗnj��́A�z�X�s�X���Ȃ��Ō�̌��ɂȂ�܂���v�B�O�O�N�H�A�͍����ŊJ���ꂽ�u����ŁA�n�l����͒d��̈�t�̌��t�ɂ����R�Ƃ����B�����A�����̃z�X�s�X�̓[���B��@�����o���A������̘V�l�z�[���̓c�����ꉀ���i�����j�ɑ��k�����B�u�����ł͎s���^���̌��ʁA�z�X�s�X���ł����B�������Q�l�ł��܂����v �@���P�Q���Ƀz�[���y�[�W�𗧂��グ�ĉ�����W�����B�������A��Âɂ��Ă̒m���͂قƂ�ǂȂ��A�O�P�N�S������Q�J���ɂP����x�A��t��Ō�t��������������n�߂��B�����͖�P�T�l����������͔��N��ɖ�P�T�O�l�ɑ����B�O�Q�N�ɂ́A�z�X�s�X�J�݂����߂��R���W�O�O�O�l���̏������W�߁A�m���ɒ�o�����B �@���������w�͂��������сA�O�T�N�T���A���ے����a�@�i�c���{���j�Ɍ������̃z�X�s�X�i�Q�O���j���ł����B�ޗǎs���ޗǕa�@���ɘa�P�A�a���i�P�O���j�̐ݒu�����߂��B �@�������A�߂��Ŋɘa�P�A����Ԑ��ɂ͂قlj����B�ɘa�P�A�̕��y�x�������w�W�̈�A�l���P�O�O�O�l������̈�×p����̏���ʂ́A�ޗnj��͑S���łQ�X�Ԗځi�O�W�N�j�B�z�X�s�X�ȊO�̈�Ë@�ւł́A���y���i��ł��Ȃ��̂����Ԃ��B �@�����o�[�ŏ�q���̏����i�U�S�j�́A��P�T�N�O�Ɏq�{����̕�e���݂Ƃ����o������A�u�e�������Ɉ�͊ɘa�P�A���ł���a�@���K�v�v�Ǝw�E����B��e�͂��w���ɓ]�ڂ������A�����̕a�@�ł͒ɂ݂���邱�Ƃ��ł����A���s�̕a�@�܂Œʂ킴��Ȃ������B�u�����Q���Ԃ������đ�ς������B�ɂ݂������t�������ł����ƈ琬���Ăق����v�Ƒi����B �@����A�n�l�����O����̂��A���f��f���̒Ⴓ���B������N�P�P���ɍ��肵���u��������i�v��v�̌�����Ƃɉ�������ہA��f���̐��l�ڕW���œ_�̈�ɂȂ����B�O�V�N�̒����ł́A�x����͂P�W�E�V���A�q�{����͂P�W�E�O���ŁA��������S���łS�S�ʁB���l�ڕW�͌��ǁA���Ɠ������́u�T�O���ȏ�v�ɗ������������A�u�ޗǂłT�O���͖����v�Ƃ����ӌ����o���B��f���A�b�v�̓���������������Ƃ��A��̊������L���邫�������ɂȂ����B �� �T���Q�R���ɂT�O��ڕ��� �@�T�O��ڂ̕���́A�T���Q�R���Ɍ�������فi�ޗǎs�o��H���j�ŁA�s���t�H�[�����̌`�ŊJ���B�Q������B�₢���킹�͓���i�O�V�S�T�E�R�R�E�Q�P�O�O�j�B m3.com�@2010�N4��28�� |
| �����[�����ߒ�ď� |
| �@���҂�ł�������J���Ȃ�������i���c��i��A�_�Y�����E���������Z���^�[���_�����j���A�Q�O�P�P�N�x�̂����Ɍ����A�ɘa�P�A��S���{�݂̊g�[�ȂǂP�S�O�̐����{����܂Ƃ߂���ď��ȏ����J���ɒ�o�����B �@�ɘa�P�A�Ɋ֘A����x�b�h�����݂̖�R�T�O�O������R�N�ԂłP�����ɑ��₷���Ƃ�A���҂̂��߂̑��k�Z���^�[�̐ݒu�A���Ê��Ԃ������Ȃ銳�҂ւ̈�Ô���ȂǂX�{����A���ɏd�v�ƈʒu�t�����B �@��ď��쐬�͋��c��̍�Ɣǂ��S���B��N�x�A�S���U�J���ōs�����^�E���~�[�e�B���O�A���҂��ÊW�҂ւ̃A���P�[�g�ŏW�܂����P�����߂��ӌ����܂Ƃ߂��B 47NEWS�@2010�N05��6�� |
|
�ݑ���a�@�������� �e���̉��l�������Ǝ��̋��|�� |
| �@�����h����w�iUCL�j�v���C�}���P�A�E���O�q���w��Ann P. Bowling������͍���҂̎��ɑ��鋰�|�ɂ��Č������s�������ʁC���������W�c�̍���҂ł́C�e���̉��l�������Ǝ��̋��|���������Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B���̌��ʂ͐e���̉��l�ȂljƑ��̃l�b�g���[�N�����̋��|���ɘa����Ƃ̂���܂ł̔F���Ɩ�������B ���ł���e���̐��ɍ� �@Bowling������́C65�Έȏ�̍���҂��琬�閯���I�ɈقȂ�W�c�i1,000�l�j�Ƃ��ׂĂ����l�n�p���l�ŎЉ�C����C�o�ϓI�w�i���ގ����Ă���W�c��ΏۂɁC���ɑ��鋰�|�Ȃǂ������B �@�팱�҂͂��ׂāC�p���Ɠ��v�ǁiONS�jOmnibus�����i�����ɔ��l�n�p���l�j��Ethnibus�����i�����I�ɈقȂ�j���璊�o���ꂽ�B�팱�҂ɁC�i1�j���ʂ��Ƃɑ��鋰�|�i2�j���ʑO�̋�Ɂi3�j�����~�߂��Ȃ����|�i4�j���ɕ��ւ̋��|�\��4���ڂɂ��Ď��₵�C��5�|�C���g�ړx�ō̓_�����B �@�L�������m�F���ꂽ����[��p���āC����҂�QOL�Ɋւ���35�̎�����s�����B �@Ethnibus�Q�̖�3����1���ƒ����4�l�ȏ�̐��l�Ɠ������Ă����̂ɑ��āCONS�Q�ł�1���ɂƂǂ܂����B����ɁCEthnibus�Q�œƋ��҂�20�l��1�l�ɂƂǂ܂������CONS�Q�ł͖����߂��B �@Ethnibus�Q�ł�3����2�����ł���e����4�l�ȏア���Ƒ��l�b�g���[�N��L���Ă����̂ɑ��āCONS�Q�ł�3����1�ł������B QOL�������قNj��|�S�͒Ⴂ �@��͂̌��ʁCEthnibus�Q�̔����ȏ�ł́CQOL�ɑ���X�R�A���ł��Ⴉ�����B������̌Q�ɂ����Ă��CQOL�������قNj��|���x���͒Ⴉ�������C���|���x����ONS�Q�ɔ�ׂ�Ethnibus�Q�ŗL�ӂɍ��������B �@�C���h�l�C�p�L�X�^���l�C�J���u�C�n���l�C�����l���܂�Ethnibus�Q��4����3���i77���j�����Ɋւ���4���ڂ̎���ɑ��āu�ɓx���邢�͂��Ȃ�̋���v���������B �@�K�v�ȂƂ��ɉ�삵�Ă����e���������҂ł́C�����4�̂���3�̍��ڂ̋��|�����債�Ă����B���̌Q�ł́C�a��C���N�̎����C400���[�h�i��360m�j�̕��s��������̋��|�̑���Ɗ֘A���Ă����B����͎��̋��|���y���������CONS�Q�Ɍ���ꂽ�B �@Bowling������́C�p�����܂ޑ����̐�i���ł͍ݑ��5����1�ȉ��ŁC�ŋ߂̌X���Ɋ�Â���2030�N�܂łɍݑ��10�l��1�l�����ƂȂ�Ǝw�E�B�u�ݑ�ł̃P�A�̎��ƏI�����̏Ǐ���u�ɂɊւ��鋰�|���ݑ���a�@���̑����𑣐i����v����1�ł��邽�߁C���̂��Ƃ͍���̈�ÃT�[�r�X�ɂƂ��ďd�v�ȈӖ������v�Ǝw�E���Ă���B �@��������́u�ݑ�ōŊ����}����l��������ɂ́C�R�~���j�e�B�[�ł̎��̍����ɘa�P�A�T�[�r�X����l�Ɏ���悤�ɂ���Ȃǂ��āC�l�X�̋��|�ɑΏ�����K�v������v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N5��13�� |
|
��8��p���ɘa�P�A�֘A�w��� �ɘa�P�A�����ׂĂ̎����Ɋg�傷�� ��Âɂ������3�̃p���_�C���V�t�g |
| �����P�v�i���Ƃ����ȕ��ؒʂ�f�Ï��j �@��8��p���ɘa�P�A�֘A�w��i8th Palliative Care Congress�j���C2010�N3��10�|12����3���ԁC�p���암�̃{�[���}�E�X���ۉ�c��ŊJ�Â��ꂽ�B���w���Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland�i�ȉ�APM�j�CThe Palliative Care Research Society �iPCRS�j�CRoyal College of Nursing Palliative Nursing�̋��Âōs��ꂽ�B���w��͊u�N��European Association for Palliative Care�i�ȉ�EAPC�j�ƌ��݂ɊJ�Â���Ă���B �@����̎Q���҂͖�500�l�ŁC���{����̏o�Ȃ͕M��1�l�ł������i2008�N�C�O���X�S�[�ŊJ�Â��ꂽ��7����ɂ́C���{�����10�l�߂����Q�����Ă����j�B�܂��C�Q���҂̓E�K���_����̃Q�X�g�X�s�[�J�[�ɂ�鏵�ٍu���uInternational Initiative:Learning from Developing Country�v���͂��߂Ƃ��āC���W�r�㍑���܂߂����E�I�ȍL����������Ă����B �@���{�̊ɘa��ÂɊ֘A���邢�����̊w��i������j�ł́C�Q���҂�3000�l���z���邱�Ƃ��������C�p���ł͎Q���҂����Ȃ��B���̗��R���CAPM�n�ݎ҂̈�lRichard Hillier���ɕ������Ƃ���C���̓����͈ȉ��̒ʂ�ł������B�u�p���ł͊ɘa��Â����̈�Ƃ��ĔF�߂�ꋳ��̑̌n���������̂ŁC�����Ɋw��̂��̂ɎQ�����Ȃ��Ă��\���ȏ��ƃL�����A�A�b�v���\�ƂȂ��Ă��邩��ł��傤�v�B �������ɂ��ɘa�P�A���\�\�d�v�����͔F�m�� �u�F�m�ǂ̊ɘa�P�A�v�œo�ꂵ�������t���� �@����̊w��̓����́C����܂łɂ������āu������������������ցv�̗����������������̂ł������i�����Ō����u�������v�Ƃ́C���Â�]�߂Ȃ��Ȃ��������̂����C����ȊO�̂��̂��w���j�B���̗���͊J��錾����̑S�̍u���iPlenary�j�̉���uHaving the last laugh-using the performing arts in improving quality of life and well-being in dementia care�v�ɏے��I�ɕ\��Ă����B���ɋ�������Ă����̂́C������鐬�n�Љ�̉ۑ���u�F�m�ǁv�Ƃ��C�w��C����̎�ȑΏێ������u�F�m�ǂ̊ɘa�P�A�v�ɓ��Ă����Ƃł������B����́C�{�w��{���̈Ӑ}�ł��邱�Ƃ͑O�q��Hillier�����F�߂Ă����Ƃ���ł���B �@���̓����́C1997�N�ȗ��C�p���ɘa�P�A���c��National Council for Palliative Care�����i���Ă����u�ɘa�P�A��������Ɋg�傷��v���j�̂��ƁC2005�N�p������ʼn����ꂽ�u���Ȍ���\�͂��������l�̈ӎv�d����@�v�Ƃ������ׂ�Mental Capacity Act��C�p����Department of Health�����s�����wEnd of Life Care Strategy�x�i2008�N�j�̉e���������̂ł���B �@�w����e�Œ��ڂ��ׂ��́C��S�̂�ʂ��āC�����ňӎv����ł��Ȃ��Ȃ�O�ɍ쐬���鎩���̃P�A�v��ł���Advance Care Planning�i�č��Ō����Ƃ����Advanced directive �j�Ɋւ���u���┭�\�������������Ƃł���B���̉ۑ�́C�u�F�m�ǂ̐l�����ւ̍��m�v�Ƃ������Ɛ[��������肪����䂦�ɁC����̈�t�����C�Ƃ�킯�F�m�ǂ̊��҂��ɂ킽��f�Â����ʈ�iGeneral Practitioner�j�ƁC���ǂ̐������Ď҂̊ԂɈӐ}�̘��������邱�Ƃ��b��ɏ��C�����I�^�p�̍������������ɂȂ��Ă����B���̏́C1960�N��㔼�ɋߑ�z�X�s�X�^�����J�n����C�u����̍��m�v�����܂��܂ȋc�_���Ă����ƍ������Ă���悤�Ɋ�����ꂽ�B �@�܂��C�F�m�NJ��҂̊ɘa�P�A�̎��H�@�Ƃ��ẮC�_�o���Ȃ�V�N�ȂƂ̘A�g�̂��ƁC����܂ł́u����̊ɘa�P�A�v�̒m���E�ԓx�E�Z�\���\�����p�\�ł��邱�Ƃ����ꂽ�B����́C�F�m�NJ��҂̃j�[�Y�́i���̕]��������̂����j�C��s���ɑ���s���C�ǓƂȂǂ���菜���R�~���j�P�[�V������C�ɂ݁C�畆��O�A���̕s�����Ȃǂ�a�炰���u�ɊǗ��Ȃǂł���C�u����̊ɘa�P�A�v�Ƌ��ʓ_���������߂ł���Ƃ����B �@����C����̊ɘa�P�A�̗̈�ł́CBreak Through Pain�Ƀt�F���^�j���̌o�@���^���C�����ăI�s�I�C�h�֔̕��Ƃ��ăi���L�\���̓����Љ�ꂽ���ƈȊO�C�V�K�Ȃ��̂͂Ȃ������B�������C�������@�_�̃Z�b�V�����̑������ڗ������i����́u�T�[�r�X���p�҂̌����ւ̎Q���v�����j�B Good Death���������O�q���I�A�v���[�` �@���̂ق��C�p�[�L���\���a�C�t���a�C�]�����̊ɘa�P�A�̓��ʍu������悳��C�����̎����̊��҂����ɘa�P�A�j�[�Y�̉�͂Ƒ����Ă��u���O�q���I�A�v���[�`�v�Ƃ��ċc�_���ꂽ�B�Ƃ�킯��ۓI�������͎̂���2�_���Q���������E�̋��ʂ̈ӌ����������Ƃł���B1�ڂ́C�����̖����������C���ɂ͈�ÓI����ɂ��ꎞ�I�ɉ��P����\�������邽�߂ɁC�ϋɓI��ÂȂǂ̓K�����܂߂��P�A�̂�����̔��f�����iEvidence�j�m�ɂ��邱�Ƃ��}���ł��邱�ƁB����1�́C�Ƒ��E��Îґo���́u�z���v�̒������C����̊ɘa�P�A�ɔ䂵�Ċi�i�ɓ�����Ƃ��ł���B �@�Ƃ���ŁC����̊w��̕����Ƃ��āC���̂Ƃ炦�����߂���C�Љ�炨��ш�Â̊ϓ_����̋c�_�����N����K�v���̔F�������܂��Ă������Ƃ�����B�ނ炪�߂����Ă���̂́C��Â̒��ł���܂Ń^�u�[������Ă����u���v���u�N�ɂ��K���K��v�ƂƂ炦�������ƁC�����āC����܂ł�Cure���߂�����Â�Good Death�������ÂւƓ]�����Ă������Ƃł���B �@I. Higginson�́C��Â̑�1�̃p���_�C���V�t�g�͋ߑ��w�̔��W�ɂ�銴���ǂ̍����ł���C��2�͋ߑ�z�X�s�X�^���̊J�n�ł���i�Ђ�����Cure ��Nj����C�l�Ԃ��w�I���f���݂̂Ƃ��Ĉ����C��Ì��ꂩ��l�Ԑ��D���Ă����ߑ��w�ɑ���A���`�e�[�[�j�ƌ��B����Ȃ�C�u�I�����P�A�̔������ւ̊g��v�́C�����gGood Death�h�Ƃ��Ĉ�ÑΏۉ�������3�̃p���_�C���V�t�g�ɂق��Ȃ�Ȃ��B �V������Õ����Ƃ��Ă̊ɘa�P�A�Ɛ��E�I�D�ʐ��̊m�ې헪 �@�p���Ŋɘa�P�A����含�̈�Ƃ��ĔF�m���ꂽ�����1991�N�C�M�҂͉p���̎��فiThe British Council�j��Â̊ɘa�P�A�u�K��i1�T�Ԃɂ킽��St Christopher�fs Hospice�ŊJ�Áj�ɎQ���������C���̏�ɂ͓����������͂��߁C��āC�A�t���J�C�A�W�A�e������50�l�߂��̎Q���҂��݂��C�p�������E�̊ɘa�P�A�̒��_�ɗ��������̂悤�ȏ������B�Ȃ��C���̔N�ɂ́wTextbook of Palliative Medicine�x���ŁiOxford University Press�j�����s����C�܂��C�p���ɘa��Êw��̑S����������J���L����������������\����C�u�K���ő�X�I�Ɍ��\����Ă���B �@���ꂩ��19�N�C����̊w��̒��O�ɁC�ł��Â��ɘa��Î��ł���C����EAPC�̋@�֎��ł���gPalliative Medicine�h����,��24��1�����APM�̌����@�֎��Ƃ��Ă����F����C���̍ŐV���i��24��2���j�͖{�w��̏��^�W�����˂Ă���B���̓����́C�p���������ʂ胈�[���b�p�Ɛ��E�̊ɘa�P�A�̌������ƂȂ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B �@���̓_�܂��čl����ƁC���W�r�㍑����̃Q�X�g�̏��قȂǂ̍���̂��܂��܂Ȋ��́C�p����w�E���C�ɘa�P�A�̐V����������O�ʂɉ����o���C���̍�������z����p���������C�ɘa�P�A�Ƃ����V������Õ����ɂ����Đ��E�I�D�ʐ����m�ۂ��悤�Ƃ��镶���I�헪�Ƃ��Ď~�߂邱�Ƃ��ł��邾�낤�B ���{�̊ɘa�P�A�֘A���c�̂͋������č���̕������̋c�_�� �@���{�́C�߁X�C�c��̐��オ��ʂɍ�����C���E�ɑO��̂Ȃ��Љ�I�E��ÓI��������悤�Ƃ��Ă���B���̒��ŁC���܁C�����ɘa�P�A�����҂ɖ���Ă��邱�Ƃ́C�ɘa�P�A�̑Ώۂ�������������C���ׂĂ̎����ɕ��Չ����邱�Ƃ��ł���悤�C��Î҂ƎЉ�̋���헪����蒼�����Ƃł��낤�B�Ƃ�킯�C�F�m�ǂ͂��ׂĂ̐l�ɂƂ��Ĕ��ǂ����鎾���ł��邱�Ƃ��Ăт����C�F�m�Ǒ����̒i�K����u���ƌƒn��Љ�ɂ���v��D��I�ɍu����K�v�����낤�B �@���{�ɂ͂������̊ɘa�P�A�֘A�c�̂����邪�C�c�O�Ȃ���ނ�͖������L���C�������ĉ��������������Ȃ��B���������āC�����̔N���W��ł́C���l�̎������C���������ŁC���Ɍ���邱�Ƃ������i�M�҂̌l�I������������Ȃ����j�B����́C�u�Љ�I�E�����I�\�ی`�ԂƂ��Ă̈�Áv�̕ϊv�҂Ƃ��đ��݂�����u�ɘa�P�A�̗��j�I�����v�ɑ���֘A���c�̂̔F���ƍ���̐헪���̌�����B �@����C���{�̊ɘa�P�A���c�̂���̃e�[�u���ɂ��C��������C���ꂩ��̕�������ɖ͍�����悤���҂������B�p���̊ɘa�P�A�j�͂��̍D�����Ă���B �T����w�E�V�� ��2879���@2010�N05��17�� |
| ��107����{���Ȋw��@�I�������҂ւ̌��t�|�{���{�͐T�d�ɍs���ׂ� |
| �@�ɘa��Â���I�������҂ւ̍R�ۖ^�͎��o�Ǐ���ɘa������Ƃ̕����邪�C�x�d�Ȃ錟����_�H�Ŋ��҂̋�ɂ������\�������O�����B�T�c�����a�@�i��t���j�ɘa�P�A�Ȃ̜A���Ҏ��́C��ʕa�@�ɂ����铯���҂ւ̊����ǎ��Â̌����c�����C���t�|�{�̕K�v���𒆐S�Ɍ����B�������߂��Ɨ\�������ꍇ�́C���t�|�{�̓K���͐T�d�ɔ��f���ׂ��Ƃ̌������������B ���S���O�ł͏Ǐ�ɘa�Ɋ�^���Ȃ� �@�Ώۂ́C2009�N1�`9���ɓ��@�ɘa�P�A�ȂɈ˗��̂������@�����S��̂����C���w�Ö@�Ȃǂ̐ϋɓI���ÏI����Ɍo�Ö��I�R�ۖ^���s����78 ��i�j��39��C����39��j�B�������C�R�ۖ�̎�ށC���t�|�{�̗L������ь��ʁC�Ǐ���P�̗L���ɂ��Č�����I�ɉ�͂����B �@���̌��ʁC37��i47.7���j�C43��i�d������j�ōR�ۖ^�J�n���ώ@���ꂽ�B�������̓���́C�ċz��n37.2���C������n32.6���C�A�H14���C�畆��g�D�Ȃ�16.2���B�����͗Δ^�ۂ��J�o�[����L��ȍR�ۖp�����Ă����B �@�R�ۖ^�J�n�G�s�\�[�h�̂���33��i76.7���j�Ō��t�|�{�����{����Ă����BPalliative Prognostic Index�ł͗\��3�T�Ԉȓ���\���ł��邱�Ƃ���C�A�����͎��S����3�T�ԈȑO�i19��j��3�T�Ԉȓ��i14��j�ɕ����Č����B���̌��ʁC��҂̂���4 ��͎��S3���ȓ��Ɍ��t�|�{���s���Ă���C�������̌��ʂ��������邱��Ɏ��S���Ă����B�܂��C���t�|�{�Ȃ��ł͏Ǐ�ɘa�������Ȃ��P�[�X�͌����Ȃ������B �@����ɁC3�T�ԈȑO�Q�ł�7���ȏ�Ŏ��o�Ǐ�̊ɘa������ꂽ�̂ɑ��C3�T�Ԉȓ��Q�ł�14�ᒆ5��ɂƂǂ܂����B����5��̌��t�|�{�͎��S2 �T�ԈȑO�ɍs���Ă���C���S���O�̌��t�|�{�͏Ǐ���P�Ɋ�^���Ȃ��\���������ꂽ�B�܂��C�c��9��̌o�߂͈����̈�r�����ǂ��Ă����Ƃ����B �@�����́u�K�ȍR�ۖ^�ɂ��C�I�������҂ł����o�Ǐ�̊ɘa�����҂ł���B�Տ�����ł́C�o���I�ȍR�ۖ�̑I���͂�ނ����Ȃ����C�������߂��Ɨ\�������ꍇ�ɂ͌��t�|�{�̎{�s�͐T�d�ɔ��f����ׂ����v�ƌ��_�B���ȂƊɘa�P�A�Ԃŋc�_�����ۑ�͑����C�����̌����𑱂��Ă����Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N5��20�� |
|
��Â���Ȃ��I ����������Z���^�[�@�����x���I�u���J�Ȃ͈�Ì���̏��킩���Ă��Ȃ��v |
| �u�ݑ�Ö@��{�C�Ő��i����C�͂���̂��v�@��l�ɂ�����̘_���ɋ^�╄ �y������i���� ��傤�����j �@�O����グ���悤�ɁA���N30�����l������ŖS���Ȃ��Ă����B�u3 �l��1�l������ɂ�����v�ƌ����Ă��鎞��ł���A����������ɂȂ����ꍇ��A�����Ɛf�f���ꂽ�ۂɁA�ǂ̂悤�Ȉ�Â������̂��A�ǂ̂悤�ɋ�ɂ��Ƃ��Ăق����̂��A�����͂ǂ̂悤�Ɏc���ꂽ���Ԃ��߂����̂��K���Ȃ̂��A�\�ߍl���Ă������Ƃ��K�v���B �@�܂��A�ݑ�ōŌ���}���銳�҂́A���݂��S�Ґ���10�������B�c���90���ȏ�͕a�@�ŖS���Ȃ��Ă���B���_�a�@�Ɋɘa�P�A�a���������Ă��Ή��ł���a�����͂Ȃ��B�����̊��҂₻�̉Ƒ��̈ӌ��܂����Z�݊��ꂽ�ƒ��n��ŗ×{�ł�����������d�v���B �@���̓_�A�y�����́u�a�@�Ɍ��炸�ݑ����{�ݓ��ɂ����Ă��ɘa�P�A��ł���̐��𐄐i���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ́A���_�a�@�A�A���{�݁A�ݑ�×{�x���f�Ï���z�X�s�X�E�ɘa�P�A�a�����܂ޒn��ɂ����邪���Â̘A�g���͑̐��̍\�z���������Ȃ��B�����������͈�Ì���ł͍��܂��Ă�����̂́A�����J���Ȃ��܂������킩���ĂȂ��v�Ƒi����B �@���J�Ȃ͂��҂̍ݑ�Ö@��i�߂Ă���B�w�i�ɂ́u��Ô�̍팸�v������Ƃ݂���B�����A���݂ǂꂭ�炢�̂��҂��ݑ�ŊŎ���Ă���̂��A�����č���ǂꂭ�炢�������Ă����̂��ȂǁA���Ԃ͂܂��܂������Ă��Ȃ��B�������������Ă��Ȃ������������Ŗ��炩�ɂ��A�ݑ�ɂ�����ɘa�P�A��ł���̐����l����̂��ړI���B �@�Ƃ��낪�A�y�����͈ȉ��̂悤�Ɍ��J�Ȃ̍ݑ�Ö@���i�̖��_���w�E����B�u�����J���Ȃ̑�3�������헪�������Ƃł́A���҂̍ݑ�ɘa�P�A�Ɋւ��錤�����s���Ă���B���̒��ŁA�鋞��w�̍]���搶�⍑������Z���^�[�̓I��搶���A�ݑ�ł̊Ŏ�肪�ǂꂭ�炢�����邩�Ƃ������Ƃ��������Ă���B �@�������������ɂ��ẮA���҂������S���Ȃ�킯�łȂ��̂ŁA�p�����ăt�H���[�A�b�v���Ȃ��ƌ����̈Ӗ����Ȃ��B�������A���J�Ȃ͂��̌����ɗ��N�x�ȍ~�̗\�Z�͂��Ȃ��Ƒ����ł���B���ǁA�ꕔ�̂����f�@�������Ƃ��Ȃ���t�Ƌ�����������l���A���h���̗ǂ����ʂ����߂Ċ���Ŕ��f���Ă��邱�Ƃ��傫�Ȗ�肾�v �@�ݑ��Â��x����ɂ́A��ÊW�҂̒n���ȓw�͂��K�v���B���ہA�M�Ƃ��ĐϋɓI�ɍݑ��ڎw���J�ƈ�t�̐��͏��Ȃ��A������Ƃ����̐�������Ȃ��܂܁A���ł���T���Ԃł���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�ݑ��Â̐��i�͏d�v�Ȏ{��ł��邪�A���߂����ł͌���͍�������B �_�C�������h�E�I�����C���@2010�N5��27�� |
|
���҂̎��͂̑��҂��C�u�������̂��߂ɐ����Ă��Ăق����v�Ɗ肢�C ���̐����Ō�܂ōm�肵�Ă����̂́C������O�̂��� |
| ����L���q���ɕ��� �@��41����s��m���t�B�N�V�����܁i���{���w�U�����Áj�ɁC��w���@���w�����Ȃ��g�́\�\ALS �I�������x���I�o���ꂽ�B��т��߂��ʒ��҂̐���L���q���ɁC��܍�ɑ��������b�Z�[�W���a���̌���Ɏv�����ƁC���ꂩ����g�݂������Ƃ��f�����B �\�\��܁C���߂łƂ��������܂��B ����@���肪�Ƃ��������܂��B���̂悤�ȑ傫�ȏ܂����������Ƃ͂܂������l���Ă����Ȃ������̂ŁC�Ƃɂ��������܂����B���܂��ɋ����������Ă��āC���͂ǂ��ɂ����Ă��܂��̂��낤�C�Ƃ����C�����ł��i�j�B �@�{�����������Ƃ͉Ƒ��ɂ͓����ɂ��Ă����̂ŁC��܂ɂ���Ēm���Ă��܂������C�ǂ�����������������̂��B�Ƒ����C���������̂��Ƃ�������Ă���{���������Đ��ɏo�Ă���킯�ł�����C���X���G�Ȗʎ����ł����B �\�\�R�����̖��c�M�j����̍u�]���������ɂȂ��āC�������ł������B ����@�����̌��t�����ꂵ�������ł��B���c�����g���]����Ԃ̑��q������Ŏ�������e�Ƃ��āC���Ǝ��̋��Ԃł̊������w�]���i�T�N���t�@�C�X�j�\�\�킪���q�E�]����11���x�i���Y�t�H�j�ɏ�����Ă������Ƃ�����C�����g�̉ߋ���U��Ԃ�w�����Ȃ��g�́x��ǂ�ł����������̂�������Ȃ��C�Ə���ɐ������Ă��܂��܂����B �@�܂��C�����䂭�g�̂̃P�A�ɂ����Č��ꉻ����Ă��Ȃ����Ƃ����X����C�����w�ɂ������Ƃ�]�����Ă����������̂��C���肪���������ł��B �a�l�̓A�X���[�g�C���҂̓g���[�i�[ �\�\ALS���̋L�^�Ƃ����ƁC�����I�ȁu���a�L�v�Ǝ���邩������܂��C����Ƃ͂܂������ʂ̂��̂ł���ˁB�u�A���I�Ȑ��v���m�肵�C�A������Ă邪���Ƃ��P�A������B�������������܂��B ����@ALS�̊��҂���͕����Ղ�ʂ��āC�u��w�ɂ������Ă��鏬�w��������Ƃ��������āv�Ƃ������~���P�ʂ̗v�������Ă��܂��B�u���H �w�̈ʒu�����������́H�v�ƌ����ƁC�p�`�b�Ƃ܂������Ԃ��Ă���B��������ʒu�̒������n�߂āC�܂��܂�����OK���o��܂ŁC���x���J��Ԃ��̂ł����ւ�Ȏ��Ԃ�������܂��B �@1��24���ԁC�Ƒ��ƃw���p�[����ւł��������g�̂̔������������ƌJ��Ԃ��Ă���̂��CALS�̉��B�Ԃߍ����Ă���ɂ�����܂���B �\�\�����ɐZ���Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��ƁB ����@�����B���҂���͐_�o���������܂��Đg�̂ɋɗ͏W�����C�x�X�g�ȑ̒��ɃR���g���[�����Ă��炨���Ƃ��܂��B�u�����͐������4����3�ɍ���ĉ����Ɉ��܂��āv�u�����͋C�������܂�悭�Ȃ�����C�ċz��������Ɨ��Ƃ��āC�ċC�̗ʂ�450����475�ɂ��āv�ȂǂƎ��ɍׂ����w�肵�Ă���������܂��B�����������������X�Ƒ����Ă���ƁC�ǂ��̒��͊F�ō��Ƃ����C�T�����܂�Ă��āC�a�l�Ƃ����ǂ��I�����s�b�N�̃A�X���[�g�̂悤�ɂȂ��Ă����ł���B���҂́C���̉��Ŏx����g���[�i�[�̋C���ł��B �\�\����́C���҂��������M�ł��Ȃ���ԁiTLS : Total1y Locked-in State�j�ɂȂ��Ă������Ȃ̂ł����B ����@�ˑR���̏�ԂɂȂ�킯�ł͂Ȃ��̂ŁC���̃X�^���X�͕ς��Ȃ��ł���B����܂ł��o���̐ςݏd�˂��������ăP�A�����Ă��Ă���C���҂���̊�����āC�������������̂����������ǂݎ���Ă��Ă��܂����ˁB������̌ċz�ł��B�������ĖS���Ȃ�u�Ԃ܂ŁC���҂̈ӎv�����ݎ�낤�Ƃ��Đg�̂��ƂĂ��厖�ɂ������܂��B �@�ł�����C����Ȑg�̉������Ă����l�ɂƂ��ẮC���b����g�̂�r�������Ƃ������Ȃ̂ł��B����������߂��������̂́C��̂����ɓB��ł��̂Ƃ��ł����B�ċz�킪�O���ꂽ����g�̂����݂��Ă���Ԃ͗�Âł����܂������C�Α���̃{�C���[���_�������u�Ԃ��ł��炩�����ł��ˁB �@����Ȃӂ��ɁC�g�̂�S��ӎ��Ɠ����ɑ�Ȃ��̂Ƃ��Ĉ������Ƃ�S�g�ꌳ�_�ƌĂт܂����C��⑼��ALS�̉��̗l�q����C�����������_�͎��R�ɐg�ɕt�����Ǝv���܂��B �\�\���{�ɂ͐̂���C���������l����������܂���ˁB ����@�ނ���ǂ��̍��ɂ��C�����I�ȐS�g�ꌳ�_�͂���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ł͎嗬�łȂ������ł��B �@�����ł́u��C�v���䂦�ɉ䂠��̃f�J���g�I�ȐS�g�_�Ɋ�Â��������ϗ��ς��嗬�ŁC�܂������ȍ����v�l����]���d�v������Ă��邽�߁C���Ȍ��肪�ł��Ȃ��Ȃ����琶���Ă��Ă��Ӗ����Ȃ��ƍl����ꂪ���ł��B �@���������v�l��ALS�̈�Âɂ����f����Ă��܂���B�Ⴆ�C�p���ł͗D�ꂽ�ɘa�P�A�̃v���Z�X������܂����C�����l�H�ċz��̑����� QOL�̒ቺ�ł���Ƃ��āC�I�Ȃ��悤������܂��B���Ȍ���ł��Ȃ��Ȃ�̂����玩���ł��Ȃ��Ȃ�B������ċz���I�Ȃ��Ƃ����l�������嗬�ł��B�I�[�X�g�����A�̊��҉�ł�ALS���҉Ƒ���ΏۂɁC���₩�Ȏ����}���邽�߂̍u�K��s���Ă��܂��B �u����ł����������v�ւ̋��� �\�\�ċz��̑I���ɂ��ẮC�{�l�̈ӎv���d�v���Ƃ��āC���O�w������r���O�E�B���������Ă����ׂ��Ƃ��镗�����C���{�ł����܂��Ă��܂��ˁB ����@������C�����I�ȐS�g�_�Ɋ�Â����̂ł��傤�B���{�͐����ɔ�ׂĒx��Ă���ƌ����܂����C�u���Ȃ��͐����������C���������Ȃ����v�Ƃ����₢���̂��̂��C���������Ƃ����c�_������܂��B �@�S�̒��ł͐��������Ɗ���Ă��銳�҂���ł��C��X�ɕs������������C�����������Ă��邱�ƂʼnƑ����ꂵ�ނƎv���ƁC���̐��������C������\�o���邱�Ƃ͓���B�����̖��u�ċz��𒅂��Ȃ��v�I�������Ă��܂����Ƃ�����܂��B���{�͌��݂̂Ƃ���ċz���I�Ԃ��Ƃ��ł��鍑�ł����CALS����8000�l���̂����C�ċz��𒅂��Ă��Ȃ�7���̒��ɂ��C������������璅�����Ȃ����͂��Ȃ肢�܂��B�������ɋ߂��������Ő����̑I���𔗂��� ALS���҂̔߂��݂��C���͓����납��Ђ��Ђ��Ɗ����Ă��܂��B �@�l�Ԃ͌ǓƂł����C�Ƃ�ڂ����Ő����Ă���킯�ł͂Ȃ��C���҂Ƃ̊W���Ő��������l�������ω����Ă����܂��B�N���ɍD����]�܂����ꂵ�����C������Ɣ߂����B�ł�����u���ɂ����v�Ƃ����҂ɑ��ĉƑ��C�F�l�C���l�Ȃǂ̑��҂��u�������̂��߂ɂ��������Ă��Ăق����v�Ɗ肢�C���̐����y�邱�ƂȂ��m�肵�Ă����̂́C������O���Ǝv���̂ł��B�������C���������������R�Ȋ��o���CALS���߂����Â���̓X�|�b�Ɣ��������Ă���悤�Ɋ����܂��B �\�\�u�@�B�Ɉ͂܂�Đ�������Ă��āC���킢�����v�Ƃ�������������܂��B ����@��ʓI�ɂ́C��Ë@��ɗ���Ȃ��ŁC�u�Ŋ��܂Ŏ����炵���v�u���R�Ɂv�S���Ȃ邱�Ƃ��ǂ����Ƃ��ƍl�����Ă��邩������܂���B�ł��������́C���Ƃ��܂������̂������Ȃ��Ȃ��Ă��C�ċz��𒅂��C�o�ljh�{�ɂȂ��Ă��C�����炵�������킸�ɖ��邭�����Ă���l��m���Ă��܂���ˁB���̓_�͂�������Ɠ`���Ă��������ł��ˁB �\�\�w�����Ȃ��g�́x�ɂ́C�f�Ï��̒����m��搶���C�ċz��𒅂��Đ����邱�ƂɈӖ�������Ɨ�܂������Ă��ꂽ���Ƃ�������Ă��܂����B ����@������Ӗ����������ĔY�ꂵ��ł����ɑ��āC�u����ł������Ă�������ˁv�Ƌ������Ă����l�͖{���ɏ��Ȃ������̂ł����C�����搶�͈�т��āu�n���Ẫp�C�I�j�A�ɂȂ���Č�������ˁv�ƕ�����C�Â��Ă��������Ă��܂����B �@�搶�́C�ꂪ�u���ɂ����v�Ȃǂƌ����Ă��C�u���x�͂�����֍s���܂��傤���v�Ȃ�Ď���������ł��i�j�B����ƕ���C�u���[��c ���Ⴀ�C�����~���Ɂv�Ɓi�j�B�x������l�͊��҂̔߂��݂͎~�߂Ă���荞�܂ꂸ�ɋ������肽�����̂ł��B�������C��ɂ������Ă���ƍm�肵�āC�u��������ɐ����Ă��������v�ƌ����Ă����Ă��������B ���ׂĂ����H���琶�܂ꂽ �\�\�u���̕a���́C�����邱�Ƃ�̌�����w�тȂ����@���^���Ă����v�ip. 160�j�Ƃ���܂����C�l�H�ċz���o�ljh�{���ϔO�I�ȋc�_�ɌŎ������C���H���J��Ԃ������Ƃœ���ꂽ���̂��ƂĂ��傫���悤�Ɋ����܂����B ����@���͂���܂ň�Â���������Ƃ��܂������Ȃ��C�ˑR��̉�쌻��ɑ��ݓ��ꂽ��ł��B �@������C����܂ʼnƑ��͑S���������т�H�ׂĂ����̂ɁC��ᑂɂ����Ƃ���ꂾ�����}�ɐH�ׂ镨���ς��Ȃ�Ă��Ƃ͔O���ɂȂ������B����o�ljh�{�܂ɂ͓f���C���Â��Ă����̂ŁC�ɗ̓~�L�T�[�H�������Čo�ǂň݂ɗ����Ė����Ȃ��܂����B�ǂ��l�܂点���ɒ���������@���H�v���C�J�����[�v�Z�����I���W�i���̌o�ljh�{��������肵�܂����B���̑��̃P�A�ɂ��������Ė쐫�I�ȉ������Ă����̂ł����C����ł����12�N�Ԍ��C�ɐ�����ꂽ�̂ŁC����ł悩�����C�Ƃ����m�M�������܂����B �\�\��Î҂̂ق����ӊO�ɂ��C�l�H�ċz���o�ljh�{�ɔے�I�ȏꍇ��������������܂���B ����@����͈�Â��W��������Ă��܂��āC��Έ�̐l�ԊW��������Ă����Ȃ�����ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���҂ƈ�Έ�̊W�ł̊��҂���͗B�ꖳ��̑��݂ł�����C�ł��邱�Ƃ͕Ђ��[���玎���Ă݂����Ȃ�͓̂��R�ł��B�����̉��҂��˘f���������n�߂�̂́C�������̂���ɂł���Ƃ��C���҂̂����ŋ�ɂ������Ă���ȂǂƑ��l�Ɍ���ꂽ�Ƃ�����ł��B�܂��C�����Ă��Ă��d�����Ȃ��Ƃ������ƌ�������Ă��܂����҂����Ȃ��炸�����ł����ǂˁB �N�ł���삪�ł���Љ�� �\�\12�N��ALS�̉����o������āC��a���̌���⍡��ɂ��āC�ǂ��l���Ă����܂����B ����@���C�a�C�ɂȂ��Ď��Â��Ă�����Ȃ����Ƃ��킩��ƁC�ꑫ��тɎ��ʘb�ɂȂ��Ă��܂��C���́g�ԁh�̂��ƁC�u�P�A�v���X�|���Ɣ����Ă���悤�Ɋ����܂��B�ł�����Ō�ɂ���Ă��́g�ԁh�͖��߂��邵�C���C�Ȃ�������L���Ȑl�����߂����Ă���l�����܂��B �@���������g�ԁh�̃P�A�̑���͎��H�̌o�����炵���w�ׂ܂���̂ŁC�N�ł���{�I�ȉ��\�\�g�̂��s���R�Ȑl�̎Ԉ֎q�ւ̈ڏ��O�o�̉�C�g�C���������\�\���ł���Ƃ����ȂƎv���܂��BNPO�@�l�������ł��C���̖��o���Ҍ�����20���Ԃ̍u�K����s���Ă��܂��B�g�̂̉�Ȃǂ͌���Ŏ��Ԃ������ė��K����ΐg�ɕt���̂ŁC���̍u�K��ł͎�Ɉӎv�`�B������ȏd�x��Q�҂ɑ���x���̗��O�ɂ��ċ����Ă���C����܂łɖ�900�l�̃w���p�[��{�����Ă��܂��B �@�F����Q�ɑ��Đ������l������g�ɕt����C��Q�̂���l�ւ̕Ό����Ȃ��Ȃ�ł��傤�B����ɕ��s���ĉ���L�������āC�Ƒ��ȊO�ɂ������˗����₷��������C�A���o�C�g�ʼn�����`������ł���ƁC���̏�Q�Ҏ{��ɂ����Ă��܂��B �\�\�Ƒ������ŕ�������ł��܂�Ȃ����Ƃ���Ȃ̂ł��ˁB ����@�Ƒ������őΏ����悤�Ƃ���ƁC����ɉ��₨���̍H�ʂɔ��ʂĂāC�`���b�Ɓu���Ȃ��Ȃ�Ίy�ɂȂ�v�Ƃ����l���������ԁB�₪�đ��݂̔ے肪�n�܂�܂��B�ł�����Ō�܂ł��̐����m�肵�Ŏ�邽�߂ɁC���ꂱ���u�P�A���Ђ炢�āv�C���l�Ƒ����Ƃ���͑���C�Ƒ��͈����v���o�̋��L�Ƃ������Ƒ��ł����ł��Ȃ��x����������ׂ����ƁC�o������w�т܂����B �u�v�ł͂Ȃ��u�W�v���l�ԑ��݂̍Œ���� �\�\�w�����Ȃ��g�́x�ł͏�������Ȃ��������Ƃ�����̂ł��傤���B ����@���ɂ����Ƃ����l�Ɂu������v�Ɨ�܂��̂͘������Ɣᔻ����邱�Ƃ�����܂��B�u�炢�v�u���ɂ����v�Ƃ����v���ɋ������Ċy�Ɏ��˂�悤�Ɏx�����邱�Ƃ��d�v���ƁB�Ȃ������������҂���ɁC���邢�͊��ғ��m���u���Ȃ��ɂ́g������`���h������v�ƌ����Ă���̂��C���̖{�ɂ͏\���ɂ͏�������Ȃ������ł��B �@���̓����́C���́C���܂��܂Ȉ�É�쐧�x������Ă���ALS�����҂̐������܂ɒ[�I�Ɍ����Ă��܂�����C�ނ�̂��Ƃ͂����ǂ����ɏ��������ł��B���̕�̕���͕��w�I�Ń��}���`�b�N�ł�������܂����C����Ƃ͈Ⴂ�C�d�x��Q�҂����̔j�V�r�Ȑ�������G��ȃA�N�e�B�r�X�g�Ƃ��Ă̊���L�������e�ɂȂ�ł��傤�B �@�Ⴆ���{���iALS�����ҁ^���{ALS�����j����́C���Z�����l�����āC���܂ꂽ�Ƃ����玊���s������ŗv���x5�������Ƃ����l�Łi�j�C�l�́u������ӎv�v�����ł͐������Ȃ����Ƃ��C�悭�킩���Ă���l�ł��B�l�͌��q�̂悤�Ɂu�v�Ƃ��đ��݂���̂ł͂Ȃ��C�u�W�v�𑶍݂̏����ƒm���Ă���B�{�l�͎��o���Ă��Ȃ���������܂��i�j�B �\�\�V���̂��̂Ȃ̂ł��傤�ˁB ����@���Ƌ��{����́C�悭�R���r��g��ō��̉�c�ȂǂŔ������܂����C�ޏ��͖{���ɒZ�����t���������܂���B����������c��܂��Đ������Ă��邩��C�ǂ����Ă����̍l�������u�����h����Ă��܂��āC���{����̎v���Ƃ́C��������Ă��邱�Ƃ�����܂��B�ł����{����́C����ł������ƒB�ς��Ă���B�ޏ��̑��҂�M����́C�l�����˔\���C�ޏ��̗×{���x���Ă���Ǝv���܂��B �\�\���ꂩ�炱�̖{����Ɏ������ɁC�Ђƌ����肢���܂��B ����@�ǂޕ��ɂ���Ă͂Ƃ�����Ǝ��̒ɂ��L�q�����邩������Ȃ��̂ł����C���̌o�����Ă������Ƃ�f���ɏ���������ł��BALS�����҂̉Ƒ�����́C�{��ǂ�Łu����������Ă������Ƃ��Ԉ���Ă��Ȃ������v�u�ق��Ƃ����v�Ƃ������܂��̂ŁC���������Ă�������������邩������܂���B �@�Ƒ��̉������Ă�����C�ݑ���̍őO���ŔY��ł���Ō�t����E�w���p�[�����ɁC�Ђ炩�ꂽ�P�A�Ő��̊�]���Ȃ������̑̌���͂���ꂽ�炤�ꂵ���ł��B �\�\���肪�Ƃ��������܂����B �T����w�E�V�� ��2881���@2010�N05��31�� |
|
�I������Á@����S�҂�4����1��������\�͌��@ ���O�w�����̏d�v�������� |
| �@�~�V�K����w���Ȃ� Maria J. Silveira��������́C����S��3,746���ΏۂƂ����I������ÂɊւ���S�ďc�f�����̌��ʁC4����1�������g�̏I������Âɂ����āC����\�͂������Ă������Ƃ��킩�����Ɣ��\�����B ���O�w�����Ɋւ����𑽂� �@�M�������҂�Silveira�������́u�⌾��iliving will�j�ɋL����Ă��鉄�����ÂɊւ����]��ٌ�m�ւ̑�s�����ϔC�idurable powers of attorney�j�Ȃǂ����O�w�����iadvance directives�j�ɖ��L���Ă������҂̂قƂ�ǂ́C���炪�]��Â��Ă����v�Əq�ׂĂ���B �@���������ɂ��ƁC����܂ŏI������ÂɊւ��镡�G�Ȍ���𑼐l�ɑ�s���Ă���킴������Ȃ�����҂̐��́C�c������Ă��Ȃ������B����̌������ʂ́C�I�����ɐN�P�I���Â�����I���ÁC�ɘa�P�A�̂�������{�s���ׂ����𑼐l�Ɍ��߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����҂����������邱�Ƃ������Ă���B �@�܂��C����̌����ł́C�⌾��̍쐬�ƈӎv����㗝�l�̑I���͂Ƃ��ɏd�v�Ȃ��Ƃ����炩�ɂȂ����B �@���������́u�I������ÂɊւ��錈��́C�����Ί���I�v�f�����Ƃ��獢��Ȃ��̂ł��邪�C����̌������ʂ́C���g�ƉƑ��̂��߂ɁC���O�Ɉӎv�������Ă����K�v�����邱�Ƃ��������Ă���C��ÂɊւ���⏑�̍쐬���s�����̈ϔC�ɔ�₷���Ԃ͖��ʂł͂Ȃ����Ƃ������Ă���v�Əq�ׂĂ���B �@���O�w�����ɂ́C�ʏ�C�⌾��ɋL����Ă��鉄�����Âɑ����]�L���邩�C��ÂɊւ����s������t�^����㗝�l��I�����Ă������ƂL���Ă����B���O�w�����́C�č���50�B���ׂĂŔF�߂��Ă���C�ٌ�m�𗊂܂Ȃ���Δ�p���������ɍ쐬�ł��邱�Ƃ���C���������͂����������@�𐄏����Ă���B �@�������C���O�w�����Ɋւ��鑭�������͑����C�Ⴆ�Α����̐l�́u�������ꂽ�ӎv�̑�s�́C���҂���ÂɊւ���ӎv����������łł��Ȃ��ɂȂ����ꍇ�ɂ̂ݍs�g����邱�Ɓv�C�u�쐬�����ӎv�̓��e���������ɂ�肢�ł��P��ł��邱�Ɓv�Ȃǂ𗝉����Ă��Ȃ��B���̂悤�Ɏ��O�w�����́C�����Έ�ÂɊւ��錈��ɊW���Ȃ��⌾����s�����̈ϔC�ƍ�������Ă���B ���O�̈ӎv�\���҂ł͂قƂ�ǂ���]�ʂ� �@����̉�͑Ώۂ́C����w�Љ�����̑S�ďc�f�����ł���Health and Retirement Study�ɎQ�������č��ݏZ�̍���҂̂����C2000�`06�N��60�Έȏ�Ŏ��S�����č��l3,746��ł���B���O�w�����ɂ��ӎv�����Ă����̂�68���ŁC���̂���90�������I�����Ɍ���I���Â܂��͊ɘa�P�A��v�����Ă����B�ӎv����̕K�v�����������C�������g�ł͕s�\�ȏ�Ԃɂ������҂̂����C����I���Â�v���������҂�83���C�ɘa�P�A��v���������҂�97�����C���g�̊�]�ɉ��������Â��Ă����B �@Silveira�������́u��ÂɊւ���⌾����쐬�������s�����̈ϔC���s���Ă����҂ł́C�@�����S����N�P�I���Â̎{�s�����Ⴉ�������C����͊��҂̂قƂ�ǂ������]���Ă������Ƃł������v�Əq�ׂĂ���B �@�N�P�I���Â�]�����h�̂����̔����́C���ۂɂ͐N�P�I���Â��Ă��Ȃ������B����Ɋւ��āC���������́u���O�̈ӎv�Ŏ����ꂽ��Â��F�߂��Ȃ������ƌ��_�t����҂����邩������Ȃ����C����̌����ł́C�N�P�I���Âɑ����]���������ꍇ�ɂ́C����������]�Ɍ��y���Ȃ������ꍇ�Ɣ�ׁC���ۂ̐N�P�I���Â̎{�s�Ƃ̊Ԃɔ��ɋ����֘A���F�߂�ꂽ�B�I������Âɂ����āC����I���ÂƊɘa�P�A�͏�ɑI�����ƂȂ邪�C�N�P�I���Â͎{�s�s�\�ȏꍇ������C�P�ɂ��ꂪ�����������̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂĂ���B �@���������ɂ��ƁC�����̊��҂��I������ÂƎ��O�w�����Ɋւ���b����t�̑������o���ė~�����Ɩ]��ł���B���������́u��t�͂��̂��߂̕�V����ׂ��ł���B�ŋ߁C�I�����̈ӎv��������[�`���ōs�����Ƃɑ��āC���f�B�P�A���x�������n�߂����Ƃ͕]���ł���v�Ƌ������Ă���B �@����Ɂu�I�����̓K�Ȍv��𗧂Ă邽�߂ɂ́C���Ԃ̂�����b���������K�v�ł���B���̂��߂̎��ԂƏꏊ�C��V����Ò҂��m���ɓ�����悤�Ȉ�ÃV�X�e�������邱�Ƃ��d�v���B����҂̑����������]��ł���v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N6��10�� |
| ����̎��S�҂R�N�łU�����@���J�Ȃ����ԕ� |
| �@75�Ζ����ł���ɂ�鎀�S�҂��R�N�ԂłU���߂������������Ƃ��U��15���A�����J���Ȃ����\������������i��{�v��̒��ԕ��ŕ��������B��{�v��́u10�N��20�����v��ڕW�Ƃ��Ă���A���Ȃ́u�B���ł���y�[�X�v�Ƃ���B���ː����Â�R������ÁA�ɘa�P�A�Ȃǂ��g�[�������A�����N�҂̋i���́u�R�N�ȓ��Ƀ[���v�̖ڕW��B���ł��Ȃ������B �@����2007�N�S���{�s�̂�����{�@�Ɋ�Â��A11�N�x�܂ł̂T�N�ԂŒB�����ׂ��ڕW����{�v��Őݒ�B���ԕ��͗��N�x�̍ŏI�Ɍ����A��̕]���〈�����̂��߁A���҂Ȃǂ��Q�����邪������i���c��̈ӌ��荞��ł܂Ƃ߂��B �@���ԕ��ɂ��ƁA����̉e����r�����邽��75�Ζ����ŔN�����������̎��S���́A��{�v��̍��莞�_�Ŕ������Ă���05�N�̎��S����100�Ƃ���ƁA08�N��94.4�ŁA5.6�����������B���Ȃ́u���_�a�@�̐����Ȃǂ��e�������̂ł́v�Ɛ�������B �@�������c��ł́u���ËZ�p�̐i���ȂǂŎ��S���͊�{�v�����O����N�Q�����x�������Ă���A�w10�N��20�����x�̖ڕW���Ⴗ����v�Ȃǂ̌����������B�u�����I�ɂ͂���̎�ޕʂɁA����ɂȂ闦�Ǝ��S���̌����A�������̌���ɂ��ēK�Ȑ��l�ڕW��ݒ肷�ׂ����v�Ƃ̎w�E���o���B �@����A�u�T�N�ȓ��ɂ��ׂĂ̂��_�a�@�ŕ��ː����Â�ʉ@�ɂ��R������Ái�O�����w�Ö@�j�����{����v�Ƃ����ڕW�͍��N�S�����_�ŒB���B�������Â���̊ɘa�P�A�����{�ł���悤�ɂR�N�ԂłP���l�ȏ�̈�t�����C���C������ȂǁA���Â̂�����͍L�����Ă����B �@���������N�҂̋i������08�N�x�����ō��Z�R�N�j�q��12.8���Ȃǁu�R�N�ȓ��Ń[���v�͒B���ł��Ȃ������B���f�̎�f�����u50���ȏ�v�̖ڕW�B���͌������B���c��́u�ʓI�ȏ[�������łȂ��A��Â̎��̕]���Ȃǂ��K�v�v�Ǝw�E���Ă���A���Ȃ�12�N�x�ȍ~�̊�{�v�����Ɍ����đΉ�����������B ���{�o�ϐV�� �d�q�Ł@2010�N6��15�� |
| ��ʌ�������Z���^�[�V�a�@�@�����Q�T�N�x�^�c�J�n |
| �@��c���i�m���͂P�T���̒���ŁA�ɓޒ������Ɍ��݂��錧������Z���^�[�V�a�@�̊T�v�\�����B�{�̍H�����E���Z�����ȂǗ\�Z�͌v��R�P�U���~�ŁA�����Q�R�N�U���ɒ��H�A�Q�T�N�x�ɉ^�c�J�n��\�肵�Ă���B �@�V�a�@�͓S�R���N���[�g�n��P�P�K�n���P�K���āB�����ʐς͌��݂̕a�@�����P���������[�g�����̖�T���V�V�O�O�������[�g���B�a�����͂T�O�O���ŁA�P�O�O����������B �@��p���͌��݂̂V������P�Q���ւƑ��݁B����̒ɂ݂�a�炰��ɘa�P�A�p�a�����P�W������R�U���֔{��������B��t���͌��݂̂X�U�l����̑������������ŁA�Ō�t�͖�R�V�O�l�����P�O�O�l������������j�B �@�܂��A�����Ȃ���̔������\�ɂ���ŐV�̐f�f���u�u�o�d�s�|�b�s�v�Ȃǂ̍��x��Ë@����B�����͎�p���łb�s�X�L��������ː����ÂȂǂ��\�ȁu�n�C�u���b�h��p���v�̎������ڎw���Ƃ����B �@���݂̕a�@�͏��a�T�O�N�J�@�ŁA�V�����Ȃǂ̉ۑ肪�������B��c�m���́u�����̊��҂ɉ�������悤�A�Ő�[�̈�ÂƓ����Ɋ��҂�Ƒ��ɗD�����a�@�������Ă��������v�Əq�ׂ��B �Y�o�j���[�X�@2010�N6��15�� |
|
�u�ƒ��Ð���v�͎��ƃA�N�Z�X�A�ǂ����D�悷�ׂ��� ���{�v���C�}���E�P�A�A���w��A��1��w�p���̃V���|�W�E���ŋc�_ |
| �@��1����{�v���C�}���E�P�A�A���w��w�p��6��26����27����2���ԁA�����s���ŊJ�Â��ꂽ�B�{�w��́A���{�v���C�}���E�P�A�w��A���{�ƒ��Êw��A���{�����f�È�w��̎O�̊w����N4���ɍ������Ēa���A���̍ŏ��̊w�p���ɓ�����i�w���ق��̂Ăđ哯�ɂ�3�w������� - �O���E���{�v���C�}���E�P�A�A���w������ɕ����x���Q�Ɓj�B���ʂ̉ۑ肪����E�F�萧�x�̊m���ŁA27���̃V���|�W�E���Ƃ��ĊJ�Â��ꂽ�̂��u�{�w��ɂ��������E�F��㐧�x���l����v���B �@�{�w��͐V���Ȑ���Ƃ��āu�ƒ��Ð���v��n�݁A��Ö@�Ɋ�Â��u�L���\�Ȑ���v�Ƃ��ĔF�߂�悤���߂Ă���B�F�萧�x�����ψ���ψ����߂�A�ɓ����M�E�����a�@�@�\�{�����������Z���^�[�Տ��������������́A�u�����J���Ȉ㐭�Ǒ����ۂƍL���K���ɘa�Ɋւ��鋦�c���s�����Ƃ���A������Ƃ������C�{�݂Ō��C���Ă��Ȃ��l�����Ƃ��ĔF�߂�킯�ɂ͂����Ȃ��A�ƌ���ꂽ�v�Ɛ����B����ɁA�i1�j���ɍL�����\�ƂȂ��Ă���A���{���Ȋw��́u�������Ȑ���v�A���{�����Ȋw��́u�����Ȑ���v�Ƃ̈Ⴂ�̖��m���A�i2�j�e���ʁi���{��t��A���{��w��A���{���㐧�]���E�F��@�\�Ȃǁj�ւ̐����A�Ȃǂ����߂�ꂽ�Ƃ����B �u�L���\�Ȑ���v��ڎw�� �@4���ɍ�������ȑO�A�O���{�v���C�}���E�P�A�w��ł́A�F���Ɛ���̓�K���Ă̐��x�A�O���{�ƒ��Êw��͐��㐧�x���^�c�A�O���{�����f�È�w��ɂ͐��㐧�x���Ȃ��A�u�a�@������v�{���Ɍ�����������C�v���O�����̍\�z�Ɏ��g��ł����B�����̊e���㐧�x���p������`�őn�݂����̂��A�u�ƒ��Ð���v���B �@�u�ƒ��Ð���v�́A�u�v���O�����F��v�B�܂�A2�N�Ԃ̑���Տ����C���I����A�w��F�肵��������C�v���O������3�N�Ԍ��C������t�ɑ��A�u�ƒ��Ð���v�̎��i��t�^����`����{�Ƃ���i2014�N3���܂ł́A�O���{�v���C�}���E�P�A�w��̐���A�R�[�X�i�����5�N�Ԃ̌��C�C���ҁj�Ƃ���ȂǁA�ڍs�[�u����j�B �@�����Ƃ��A�u�ƒ��Ð���v���߂����ẮA (�P)�u�L���\�Ȑ���v�Ƃ��ĔF�߂��邩�A�i2�j�ڍs�[�u���݂̍���A�i3�j�u�a�@������v�i�a�@�����f�Ð���j�Ƃ̊W�\�\�ȂǁA����̌����ۑ肪���X����B �@�O�q�̈ɓ����̔����́A(1)�Ɋւ�����́B���J�Ȃ̌����́A�u������C�v���O�����Ō��C�����l�͂������A����ȊO�̈ڍs�[�u�Ő��㎑�i����t���A�L���\�Ȑ���Ƃ��ĔF�߂Ă����̂��v�Ƃ�����|�B����́A�i2�j�̈ڍs�[�u���݂̍���Ƃ��W�����肾�B�O���{�v���C�}���E�P�A�w��ł́A�u�F���{2�N�Ԃ̌��C�v�Ő���̎��i�邱�Ƃ��\�������B����ɁA�e�̈�̐��㎑�i������t���J�Ƃ���ɓ������āA���邢�͊��ɊJ�Ƃ��Ă����t�ɂ��āA�u�ƒ��Ð���v�̎擾���\�Ƃ��邩�Ȃǂ��_�_���B �u�J�ƈ���擾�ł��鐧�x�ɂ��ׂ��v�Ƃ̈ӌ��� �@�V���|�W�E���ł́A�t���A���牺�L�̂悤�Ȉӌ����o���B�u�ƒ��Ð���v�̎��Ɨʂ��ǂ����D�悷�ׂ����A�܂�u������C�v���O�����C���ҁv�ȊO�ɁA�ǂ��܂ňڍs�[�u��F�߂邩�ɂ��ẮA�w����̒��ł��傫���ӌ���������Ă���B �@�u�ȑO�ɂ����ނ����ہA�ƒ��Ð���̗{�����ɂ��āA�w���͔N�Ԗ�20�l�����A������ 100�l�A200�l�ɂ������x�Ɛ��������Ƃ���A�w���{�̐l����1��2000���l�B���̐g�̉��ɂ��������l�������悤�ɂȂ�ɂ́A�����������N������̂��x�ƌ���ꂽ�̂���ۂɎc���Ă���B����̗{���Ƃ����Ă��A�v���C�}���E�P�A�̐���̗{���͓���B�N�I���e�B�[��������������A�܂��̓A�N�Z�X���m�ۂ��Ȃ��ƎЉ�I�ȐӔC���ʂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���̐���������Ă����t���A�W�F�l�����ȕ���ɎQ���������Ƃ����ꍇ�ɁA���̃n�[�h���͓��ʂ͂��܂�グ�����Ȃ����������̂ł͂Ȃ����B�N�I���e�B�[�ƃA�N�Z�X�r���e�B�[�̌��ˍ�����F�����ċc�_����K�v������v�i��ꏃ�i�E�������a�@�����f�Éȋ����j �@�u�ƒ��Ð���̎��͏d�v�����A�܂��̓A�N�Z�X�A�ʂ̊m�ۂ��d�v�ł͂Ȃ����B�ł��邾�����̍����ƒ��Ð����{����������͖ڎw���A3�N�Ԃ̌��C������Ă��ꂩ��F�肷��̂��x�X�g�ł͂���B���������́A���ɐf�ÂɖZ�����J�ƈオ���i������悤�ɁA�ڍs�[�u�Ƃ��āA���������̔F��ł������̂ł͂Ȃ����B�ƒ��Ð���́A����قǃn�C���X�N�Ȏ�Z������킯�ł��Ȃ��B�ƒ��Ð������ɋM�d�Ȃ��̂Ƃ��āA�o���ɂ��݂���̂ł͂Ȃ��A�����ƕ������l�͉ƒ��Ð���Ƃ���悤�ȑ������ȋC�����ōŏ��͐����m�ۂ���B�����āA���K�̌��C�����ƒ��Ð��オ�炿�A���̐l�����������ɒS���̂�҂̂͂ǂ����v�i����b�E��t���w�������a�@�����f�Õ������j �@����ɊJ�ƈ�̗��ꂩ��A���̂悤�Ȉӌ����o���B�u���x�Ƃ��ẮA�����w������\�z�x���o���Ă����B����A���{��t��w���������\�z�x���o���A���́w���㐶�U���琧�x�x�����邪�A���ɕ�����ɂ������x�ɂȂ��Ă���B���ǂ��J�ƈ�Ƃ��ẮA�ǂ������炢��������A�Y��ł���Ƃ��낾�B�����ō���3�w��A�����āA���{�v���C�}���E�P�A�A���w��ݗ����ꂽ�B����͂��̘A���w������A���J�ȁA���邢�͓���ɂ�����ƒ��Ă����K�v������̂ł͂Ȃ����B���̏�ɓ���ƌ��J�Ȃ��Ă�ŋc�_���Ȃ��ƁA���ꂼ�ꂪ�܂�����ɂ���Ă������ƂɂȂ�B���ǂ��J�ƈ�A�v���C�}���E�P�A��S���Ă��闧��Ƃ��ẮA�ȒP�Ȏ��������ēo�^���āA���̌�A�����ł���悤�Ȍ`��A���w��Ƃ��Ē��Ă������������v�B �u�a�@������v�̈ʒu�Â����ۑ� �@����ɁA����̌����ۑ�ł���A(3) �́u�a�@������v�i�a�@�����f�Ð���j�́A�u�ƒ��Ð���̌��C3�N�{�a�@������2�N�v�Ƃ����`���z�肳��Ă��邪�A���������u��K���āv�ł͂Ȃ��A�u�ƒ��Ð���ƕa�@������̌��C�͕���ł���ׂ��v�Ƃ����ӌ�������B �@�x�R��w�����a�@�����f�Õ������̎R�鐴�́A�u�a�@������̏K�����ׂ����j�I�\�́v�Ƃ��āA�i1�j���Ȃ𒆐S�Ƃ������L�������f�Ô\�́i1���A2���~�}���܂ށj�A(�Q)�a�����Ǘ��^�c����\�́A�i3�j���Ȃ�R���f�B�J���Ƃ̊W������\�́A�i4�j�a�@��Â̎������P����\�́A�i5�j�f�Â̌���ɂ����ď����E������C������炷��\�́A�i6�j�f�Âɍ������������Ɍg���\�́A��6��������B �@�u�a�@������v�̖����₻�̌��C�̂�����͂܂������ۑ肪�������Ƃ�����A�ɓ����́u�܂��͉ƒ��Ð���ɂ��Đ�ɋc�_��i�߂����B���ǂ́A���J�Ȃ��ǂ�Ȑ��x�ł���A����Ƃ��ĔF�߂邩�ɂ���āA�ƒ��Ð���̐��x�v�����߂邱�ƂɂȂ邾�낤�v�Ƃ̍l���������Ă���B �@���̂ق��A�u�ƒ��Ð���v�ɂ��ẮA�O�q�̂悤�ɓ��{��t��́u���U���琧�x�v�Ƃ̌��ˍ����Ȃǂ̖�������B �@���{�v���C�}���E�P�A�A���w��̐���ɂ��ẮA����̒��ł��R���Z���T�X�������Ă��Ȃ����������Ȃ��Ȃ��B�e�҂̍l�����قȂ邱�Ƃ���A�ˑR�Ƃ��Đ��x�E����̖��̂����G�ŁA���ꂪ�W�҈ȊO�ɂƂ��Ă͕�����ɂ����c�_�ɂȂ��Ă���̂��������B �@�V���|�W�E���ɂ́A���f�B�A�̗��ꂩ��NHK����ψ��̊�{�T�����o�ȁA�u���㐧�x�������ɔF�m����邽�߂ɁA�ǂ�����ׂ����v�����₳��A���̂悤�ɉ����B�u�w�����ɔF�m�����x�Ƃ͓�����Ƃ����A���G�Ȑ��x�ɂȂ������ɖ����B�w���̃}�[�N�̂���Ƃ���ɍs���A���S�ł���A���ꂪ�F�̃R���Z���T�X�Ƃ��Ă���x�Ƃ�����Ԃɂ����Ă����Ăق����Ƃ����̂��P���Ȋ肢�B���̂��߂ɂ́A���x�������S�ɕۏႵ�Ȃ���Ȃ炸�A���̐��x�v��������Ƃ��Ă����K�v������B���Ƃ��ẮA��i�̐��x�j�ł���Έ�Ԃ��ꂵ���Ǝv���Ă���v�B m3.com�@2010�N6��28�� |
| ��������₵�̉́@�̎�̈��c�o�����a�@���Ԗ�@��� |
| �@�̎�̈��c�ˎq����A�R�I�����肳��̎o�����U���Q�V���A���s�t��̓��k��a�@�ɘa�P�A�Z���^�[���Ԗ₵�A�������̐��Ŋ��҂̐S����₵���B �@�~�j�R���T�[�g�Ƃ��āA��Îx���̂m�o�n�@�l�L���[�I�[�G���i���s�j����悵���B���҂ƉƑ��A�{�����e�B�A���T�O�l���Q���B���c����ƗR�I����͊��҂̎������Ȃ���A�u�ԂƂ�ځv�u�~�i�F�v�u�Ă̎v���o�v�ȂǁA�l�G�܁X�̉̂��I�����B �@���҂����͗܂𗬂��Ȃ���A�o���̃n�[���j�[�ɕ����������B�a���œ��w���������ނ��Ƃ�����t��̗�悵������i�V�U�j�́u�ƂĂ����ꂢ�Ȑ��Ŗڂ̑O�ʼn̂��Ă��������đf���炵�������v�Ɗ������Ă����B �@���c�������ɘa�P�A�Z���^�[��K���̂͂S�x�ځB�R�I����́u���������a�@�ɂ�����͈̂�u�����A��l�����������t�ō�����̂ŏ����ł����҂ƉƑ����܂������v�Ƙb���Ă���B �͖k�V��@2010�N6��29�� |
| �a�@�����U�����Ɣ����Q�O���@�������ÁA�������� |
| �@�É������Îs���a�@�ŖS���Ȃ�����������̒j���̈⑰���A�s�K�Ȏ��Â�������������Ƃ��Ďs�ƒS����Ɍv�P�Q�O�O���~�̑��Q���������߂��i�ׂ̍T�i�R�����ŁA�������ق͂V���A���������p������R�������������A�a�@���̋��U������F�߁A�s�ɂQ�O���~�̎x�����𖽂����B �@���Â��̂��̂ɂ��Ă͈�R�ɑ����s�K�ȓ_�͂Ȃ��Ƃ����B �@���v�K���i�����Ђ��E�������j�ٔ����́A�ɘa�P�A�Ƃ��Ēj���ɓ��^���ꂽ���_�����q�l���P�O�O�~���O��������T�O�~���O�����ɔ�������悤���Ƒ��ɑ��A�Ō�t�����ۂ͌��炵�Ă��Ȃ��̂ɂV�T�~���O�����Ɛ��������_�ɂ��āu�Ƒ��͐��_�I��ɂ����v�Ǝw�E�B �@�u�Ƒ����ɘa�P�A�ɔ�����̂ŁA��ނȂ������������v�Ƃ̎s���̎咣���u���Ó��e�ɑ���Ƒ��̕s���́A�Ӑ}�I�ȋ��U�����𐳓������闝�R�ɂȂ�Ȃ��v�Ƒނ����B �@��N�R���̈�R�É��n�ُ��Îx�������ɂ��ƁA�j���͌ċz��Ȃǂ�i���Q�O�O�R�N�S���A�s���a�@�ŏd���x����Ɛf�f���ꂽ�B���Ò��̂U���ɋً}���@���A����܂ł̍R����܂ɑ����ė��V���X�����牖�_�����q�l�𓊗^���ꂽ���A�R����Ɏ��S�����B m3.com�@2010�N7��8�� |
|
��51����{�_�o�w�� ALS�@���C�E����̕K�v�����w�E |
| �@�����̉���u�t�́C2009�N3���ɁC���{�_�o�w��F��̐���4,500�l�S����ΏۂɁuALS�I������ÂɊւ���ӎ������v���s�������ʁCALS�ɑ��郂���q�l�E���Ö�g�p�C�l�H�ċz��̑����E���O���Ɋւ��錤�C�C����̕K�v�����w�E�����B 47�����Ɗw�Ń����q�l���J�n �@�������̉������34���B���݁C�킪���ł�ALS�̌ċz��ɑ���I�s�I�C�h�i�ȉ������q�l�j��p�����ɘa���Â͕ی��K�p����Ă��Ȃ����C21���������q�l�̏�����������Ɖ��Ă���C2�N�O�̒����i�����ʐM�Ў��{�j��14���������Ă����B�������C����47���������ɘa�P�A�`�[���Ƃ̘A�g�Ȃ��C�Ɗw�Ŏg�p���J�n���Ă���C�Տ�����̕K�v�����������ꂽ�B �@�܂��C����C�K�v�ȏꍇ�͕ی��K�p�̗L���ɂ�����炸�����q�l���g�p����Ƃ̉�47���Ɣ�r�I�����������Ƃ���C����C�g�p���l����_�o���Ȉオ������\��������C���}�ɋ���̐��𐮂���ׂ��ł���B���Ö�̎g�p��e�F����Ƃ̈ӌ��������������C ����ŁC�����q�l�E���Ö�̎g�p�ƈ��y���Ƃ̍�������27���Ɣ�r�I��������ꂽ�B �@���݁C�킪���ł́C�������������玖������O���̂ł��Ȃ��̂Ȃ��ŁCALS���҂�30�����l�H�ċz������Đ������Ă���B����̒����ł́C�l�H�ċz�푕���̔��f�ɂ��āC�u�{�l�ƉƑ��̈ӎv���ɏd������v�Ɓu�{�l�̈ӎv���d������v���Ƃ��ɔ������߂Ă���C�Ƒ��̈ӎv���d��������{�I�����̉e���������������B �@���҂܂��͉Ƒ�����l�H�ċz��̎��O����v�]���ꂽ���Ƃ̂����t��21���C���O���ɂ��Ắu�F�߂�ׂ��łȂ��v24���C�u�i�����t���Łj�F�߂Ă��悢�̂ł͂Ȃ����v59���ƁC�ӌ�������Ă����B�l�H�ċz��̎��O����^���Ɋ肤���҂ɓ���������������C�܂�20�������R�L�ڗ��ɁC���҂�Ƒ�����̉���ȗv�]�C���݂̉����ł͂����ɂ͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ�����̂Ȃ��ōőP��s���������i���Ă����B �@���̂悤�Ȍ��ʂ���C����u�t�́u�����̐_�o���Ȑ��オ�I������Âɂ����č���ɒ��ʂ��Ă����BALS�ɑ���z�X�s�X����q�l�̕ی��K�p�̎����ƂƂ��ɁC���҂ɑ��铯���\����������Ȃ��܂��̂ɂȂ���Ȃ��悤�ɁC�×{���̉��P�Ɏ��g�ނƓ����ɏI�����̌���v���Z�X���܂ތ��C�⋳��v���O�������K�v���v�Ǝw�E�����B �@�l�H�ċz����O�����Ƃ̐���ɂ��ẮC���܂��܂ȗ��ꂩ�瑽���̎^�ۗ��_���q�ׂ��Ă���B���u�t�́C�×{�����\���ƌ����Ȃ�����̂Ȃ��Ő����ϗ��̐��Ƃ͂����̖����ǂ̂悤�ɕ��͂��Ă���̂��C�܂��@�I���ꂩ��̌����͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂���������K�v������Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N7��8�� |
| �葫�̃}�b�T�[�W���⑰�̈Ԃ߂ɂ����� |
| �@�J�������X�J�������i�X�g�b�N�z�����j����a���Ȃ�Berit Seiger Cronfalk���m��́u������l���S���Ȃ�����͈⑰�̔߂��݂��[���X�g���X���������C�����b�N�X���ʂ̂���}�b�T�[�W��8�T�Ԏ�ƁC�⑰�̈Ԃ߂ƂȂ�v�Ƃ̌������ʂ�Journal
of Clinical Nursing�i2010; 19: 1040-1048�j�ɔ��\�����B �߂��ނ��ƂƑO�����ɐ����邱�Ƃ̃o�����X�ɗL�p �@��g�D�̃}�b�T�[�W�͗D��������������s�����ƂŁC�畆�̐G�o��e�̂����������C�I�L�V�g�V�������o�����B�I�L�V�g�V���͌��N�ƃ����b�N�X���ʂ����߂�ƌ�����z�������ŁC�Ⴆ�C��e���q���ɕ�������܂���ۂɕ��傳���B �@����̌����́C���e������ŖS�����C�ɘa�P�A�`�[���i�X�g�b�N�z�����E�V���[�N�w���j�ƘA��������Ă���ȁC�v�C���C�o���Ȃǂ�18��i34�`78�j���Q�������B �@�}�b�T�[�W�͎肩���ɍs���C����I�̂�9��C�肪8��ŁC�葫������1��ł������B �@�⑰��1��25���̃}�b�T�[�W���T��1��C8�T�ԎC�ꏊ�͎���C�Ζ���C�a�@�̂����ꂩ��I���ł����B �@�}�b�T�[�W�͊��k�n���邢�̓T���U�V�̔������̃I�C����p���C�������ƒ����ɂȂł�C�y������������C�~��`���Ƃ����������ōs��ꂽ�B�}�b�T�[�W�̌�C�⑰�ɂ�30���ԃ����b�N�X���邱�Ƃ𐄏������B �@�v���O�����̊J�n�O�ƏI��1�T�Ԍ�ɁC���ꂼ��60���Ԃ̖ʒk���s���ăf�[�^�����W�����B����ɁC�v���O�����I����6�`8�T�Ԃ̒ǐՒ������s�����B �@���̌��ʁC17��͑O�����ɐ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������C1��͂��̌�C�V���ɓ��e�̕s�K�ɐڂ��C�S�̖�������Ă������Ƃ����炩�ɂȂ����B �@�������C����ʒk�������⑰�͑S���C���Â��u�Ԃ߁iconsolation�j�v�ƂȂ����Əq�ׂĂ���B�܂��C���Âɂ��āC�i1�j���X���~���̎�ƂȂ����i2�j�������̂������i3�j���炬�̎��Ԃ������i4�j������͂����炦�鎞�Ԃ������\��4��ނ̃R�����g���c���Ă���B �@Cronfalk���m�́u�⑰�ɂƂ��ă}�b�T�[�W�́C�g�̂ɐG����邽�߈��炬�ɂȂ���C�������C�ǓƊ��̌y���ɖ𗧂����悤���B�܂��C�}�b�T�[�W�͓��e�̎���̔߂��݂Ɠ��e�����Ȃ��Ȃ��������ɓK������Ƃ���2�̕K�v���̃o�����X����邤���ŁC�L�p�ł������v�ƌ��_�t���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N7��15�� |
| ���ɏꏊ�Ȃ�p������ԁA�p���� |
| �@�����}����̂ɍœK�ȍ��͉p���\�\�p���u�G�R�m�~�X�g�iEconomist�j�v�̒�������u�G�R�m�~�X�g�E�C���e���W�F���X�E���j�b�g�iEconomist Intelligence Unit�AEIU�j�v��14���A���̂悤�Ȓ������ʂ\�����B �@EIU�́A�o�ϋ��͊J���@�\�iOECD�j����30�����Ƃ��̑�10�����̈�t�E���ƂȂǂ�ΏۂɁA�I������Âɑ��鍑���ӎ��A�g���[�j���O�̗L���A���ɍ܂̎g�p�A��ҁE���ҊԂ̃R�~���j�P�[�V�����̓������Ȃǂ���Ƃ��A�u�N�I���e�B�[�E�I�u��f�X�iQOD�A���̎��j�v��]�������B �@�p���́A���{�ɂ��I������ÃT�|�[�g��A�z�X�s�X�Ԃ̃l�b�g���[�N���[�����Ă���_���]������A40�������g�b�v�ɗ������B2�ʂɂ̓I�[�X�g�����A�A3�ʂɂ̓j���[�W�[�����h�������N�C���B�A�C�������h�A�h�C�c�A�č��A�J�i�_���g�b�v10���肵���B �@�f���}�[�N22�ʁA�t�B�������h28�ʂȂǁA�x�T���Ƃ���鍑�̕����������L���O����20�ʂƒ�]�������ق��A���[�X�g10�ɂ̓|���g�K���A�؍��A���V�A���������B�ʼn��ʂ̓C���h�������B�i���{�͍��z�Ȉ�Ô�ƈ�Âɏ]������l���̕s����������A�Q�R�ʂƒႢ�]���������j ���x�T���ł̏I������Ð������}�� �@EIU�́A�u�Ő�[�̈�ÃV�X�e����L����x�T���v�ł���Ð��x�ɏI������Â�g�ݍ���ł��Ȃ����������Ǝw�E�B�l�̎��������сA����҂�����������Ȃ��A�����������X�ŏI������Â̎��v���}���ɍ��܂�Ƃ̌��ʂ����������B �@�܂��A�ɘa��Â͕a�@�����ōs����ׂ����̂ł͂Ȃ����ƁA����ł̎���I�Ԑl���������Ƃ������A������m�̈琬����������悤�E�߂Ă���B AFPBB News�@ 2010�N07��15�� |
|
�u���k�Θb�O���v�ł�낸���k�A���������Z���^�[ �g�����h��̈�A������100���ȏ�̑��k�A�������ĂɂȂ������ |
| �@���������Z���^�[��7��16���A�L�҉���J���A����12������J�݂����u���k�Θb�O���v���͂��߁A�ŋ߂̎��g�݂��Љ���B �@���O���̗\���7��1�������t�J�n�A������100���ȏ�̑��k�����A7�����͂قڗ\��Ŗ��܂��Ă���Ƃ����B��t�����łȂ��A�Ō�t�Ȃǂ��Ή�����̂������ŁA1����1���Ԃ�2��6250�~�A�a���f�f���s���ꍇ�ɂ�3��1500�~���i�ڍׂ͓��Z���^�[�̃z�[���y�[�W���Q�Ɓj�B1��������8���̑��k�ɑΉ����Ă��邪�A�j�[�Y�̑���ɉ����č���A�Ή�����������\��B �@�������̉ÎR�F�����́A�u�g�����h�́A�w�K�Ɏ��Â��Ă��Ȃ��x�w�厡�ォ�猩�̂Ă�ꂽ�̂ł͂Ȃ����x�Ɗ�������A�Ő�[�̎��Â��Ă����͂���ʂ����҂ł����A�ɘa�P�A��_�I�P�A��K�v�Ƃ��Ă���ꍇ�ȂǂɎg���錾�t�B���k�Θb�O���̐ݒu�́A���������g�����h���Ȃ������Ƃ̈���B���̃Z�J���h�E�I�s�j�I���O���́A���Ö@�̃I�v�V��������A������������`�����A��w�I�Ȃ��ƂɌ��炸�A�l�X�ȑ��k�ɉ����Ċ��҂̔[���邱�Ƃ�ڎw���Ă���v�Ɛ�������B �@�u���k�Θb�O���v�̐ݒu�ɐ旧���A��350�J���̑S���̂���f�ØA�g���_�a�@�ɁA���������œ��O���̎�|�Ȃǂ��������莆�𑗕t�����B�u�����a�@�ɂ́A600�x�b�h�����Ȃ��A���҂�S������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�n����������҂͗��Ă���B���k�Θb�O���Ŏ��Ö@�𑊒k�A���������f�ØA�g���_�a�@�ŎĂ��炤���Ƃ�����v�i�ÎR���j�B �@�Ή�����̂����A���̊��҂���ш�Î҂ɎQ�l�ɂȂ鎖��ɂ��ẮA�l�����肳��Ȃ��`�Ńz�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă����\�肾�Ƃ����B����ɁA�u��X���v�������Ȃ������Ƃ���ō����Ă���g�����h�����邩������Ȃ��B�g��낸���k�h���s���A�����������Ƃ������Ă��邾�낤�B�������ɉ�X���������Ă��āA�s���ɒ��Ă����v�i�ÎR���j�B�����Z���^�[�̗��O�ɁA�u���������Ȃ��v�̂ق��A�u���Җڐ��Ő������Ă��s���v������i�w�u�����͂��͂��炸�v�A�ÎR�E���������Z���^�[���������錾�x���Q�Ɓj�B�u���k�Θb�O���v�́A�X�̊��҂ւ̑Ή��ɂƂǂ܂炸�A����f�ØA�g���_�a�@�Ƃ̘A�g�A�������ĂƂ��A���������g�݂ƌ�����B ��t�ɂ�1��5000�~�̎蓖��V�� �@�u���k�Θb�O���v�̓����́A1���Ԃ̑��k�S�̂�ʂ��ĊŌ�t���ւ�邱�ƁB�i1�j���ҁE�Ƒ�����f�[���L���A�i2�j��t�E�Ō�t�E���ҁE�Ƒ��Ƃ̖ʒk�i�ɂ���ẮA�����告�k���A�S���m�������j�F30�`40���A�i3�j�Ō�t�E���ҁE�Ƒ������̖ʐڂ��s���A��t�̐����ŕ�����ɂ����_���Ȃ����������m�F�F10�`15���A�i4�j�Ăш�t�����Ȃ��āA�����F10�`20���A�Ƃ�������ɂȂ��Ă���B �@���������Z���^�[���헪�������̐��c�P�F���́A�u��t�͐��I�ȗp����g���Đ����������B��t��r���ŊO���A�Ō�t��������ɂ����Ƃ��낪�Ȃ������������ƂȂǂ�ʂ��āA���҂̗�����[�߂邱�Ƃ��\�v�Ɛ�������B �@7��12������15���܂ł�4���Ԃ�23���ɑΉ��B7�����I������Ái�^�[�~�i���P�A�j�A16�����u���݂̎��Ö@�ł������v�ɂ��Ă̑��k�B�����Z���^�[�Ŏ��Â��s�����ƂɂȂ����̂�1��݂̂ŁA���͑Ή�������t�̐������A���݂̎厡��̂��ƂŎ��Â��p�����邱�ƂɂȂ����B �@��ł͋L�҂���A�u�Ɖu�Ö@�ȂǁA�Ȋw�I�ȃG�r�f���X���Ȃ����Ö@�A���R�f�Âł���Ă��鎡�Ö@������B���̕ӂ�͌X�̈�t�͂ǂ����f���Đ�������̂��v�Ƃ̎��₪�o���B����ɑ��A�ÎR���́A�u�K�C�h���C����G�r�f���X���������������B���������Ă��̕ӂ�̔��f�́A�X�̈�t�ɂ���ĈقȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B�����A���R�f�Âɂ��Ă͉�X�̓R�����g�ł��Ȃ��v�ȂǂƉB���N�H�i��T�v�������g�Ȃǂɂ��ẮA�������N�E�h�{�������Ƌ����������n�߂Ă���Ƃ����B �@�Ȃ��A�u���k�Θb�O���v��S�������t�ɂ́A1����5000�~���蓖�Ƃ��Ďx�����Ă���B�u���N4���̐f�Õ�V����ł́A�w�Ζ���̕��S�y���E�������P�x���d�_�ۑ肾�����B���k�Θb�O���́A�ʏ�Ɩ��ɉ����čs�����̂ł���A��t�ɕ��S��������v�i�ÎR���j�B �g��낸�O���h�ɉ��ł���������S�� �@�@16���̋L�҉�ł�6���̉�ɑ����A���҉�̑�\���o�ȁB��������̌��҂̉�u�X�}�C���[�v��\�̕Жؔ��䎁�́A�u6���ɁA�g��낸�O���h��݂���Ƃ������\������A���҉�ɐ���������A�g��낸�O���h�Ƃ����l�[�~���O�������ƌ���ꂽ�B�g�Z�J���h�E�I�s�j�I���O���h�ƌ����Ă��A�g�I�s�j�I���h���ĉ��A�ƂȂ�A�n�[�h���������Ɗ����Ă���B�g��낸�O���h�ł���A������������Ȃ����Ƃ�����S���ɂȂ�B�����A�w�����Z���^�[�̐搶�̌��t��������Ȃ��x�Ƃ����₢���킹���邱�Ƃ�����A�R�~���j�P�[�V�����X�L�����Ăق����v�ƃR�����g�B����ɉÎR���͉A���Ɂu���k�Θb�O���v�̑Ή��ɓ������t�ɂ��ẮA�R�~���j�P�[�V�����X�L���̃Z�~�i�[�����{�����Ƃ����B �@���������p��̊��҉�ł���NPO�@�l�O���[�v�E�l�N�T�X�������E�V��T��́A�u�������ɁA�w���������x�Ƃ��ăT�C�������闓�����邪�A���ۂɂ̓T�C�������Ă������ł��Ă��Ȃ����Ƃ����錻��ŁA�Ō�t�����������O�������邱�Ƃ͉���I�B�Ō�t���S�����邱�Ƃɉ@���ŋ^�₪�������ƕ����A�����Ă���B�n���Ȃǂł́A���҂��Z�J���h�E�I�s�j�I�����o�����Ƃ���A�w�����f�܂���x�ƌ�����P�[�X������B���k�Θb�O���̂悤�ȍD�܂������Ⴊ���y���Ă������Ƃ����҂��Ă���v�Ƃ̊��z���q�ׂ��B �@�V�쎁�́A�u���k�x���Z���^�[�v�����y���Ȃ������A�h���b�O�E���O�̖��Ȃǂɂ��Ă�����B�ÎR���́A�u���k�x���Z���^�[�ɂ́A�f�Õ�V��ł̕]�����Ȃ��B�h���b�O�E���O�́A�i�K���O�����̍����ƂȂ�j�w55�N�ʒm�x�ɂ��Ē��㋦�ŋc�_���Ă������ƂɂȂ��Ă���B�����A�w55�N�ʒm�x�����ł͉����ł��Ȃ���������A�i����}�������f����A�V�����헪�́j���C�t�E�C�m�x�[�V�����헪�̒��ŁA����ȂǂŁi�K���O�������j�F�߂Ă����Ƃ������������o�Ă���̂ł͂Ȃ����B�����������肷����ƁA�����F�ی����痣��錜�O������v�Ƃ̍l�����������B 6�Z���^�[�ʼnۑ������헪���ĂɎ��g�ށB �@���̂ق��A16���̉�ł́A����������4������Ɨ��s���@�l�����ꂽ�Z�̃i�V���i���E�Z���^�[�Ԃ̎��g�݂Ȃǂ��Љ�ꂽ�B �@���������C�⍲�ŕٌ�m�̋��c�������́A�u�����Z���^�[���A���{�̎i�ߓ��Ƃ��Ă̖������ʂ������߂ɂ́A�K�o�i���X�̖ʂł����P���ׂ��_�����邪�A���̓Ɨ��s���@�l�ʑ��@�ł́A�P�N�x��v�A���B���x�A�]�����x�A�l�����x�ȂǁA�����Z���^�[�ɂ͂Ȃ��܂Ȃ��_�����X����v�Ǝw�E�B �@�u�i�V���i���E�Z���^�[�́A���Ɛ헪�̗v�Ƃ��ċ@�\���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ⴆ�A���{�ɂ́A�����V�[�Y�������Ă��A�m�I���Y�Ɍ��т��Ȃ��B�Տ������ł��A�w�`�[���W���p���x�Ŏ��g�ޕK�v������A���Z���^�[�͓��{�́w���T�[�`�A�h�~�j�X�g���[�^�[�x�Ƃ��ċ@�\���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�i���c���j�B �@�Ɨ��s���@�l�����ꂽ�i�V���i���E�Z���^�[�ԂŁA���ʉۑ�̉�����헪���ĂȂǂɌ����āA���H���當���Ȋw�Ȃ�Web�T�C�g�u�n�c�J�P�A�C�v�̃V�X�e�����g���āA�c�_�����Ă����\�肾�Ƃ����B �@�Ȃ��A�����A�u���Ɛ헪�Ƃ��Ă̂����V���|�W�E���v�̑�1�e�A�u��K�̓Q�m�����w�����̕������v���J�Â��ꂽ�i�w�Q�m����w�����̃J�M�́uAll Japan�v�Ɓu����f�Áv�x���Q�Ɓj�B���̎�|���ÎR���́A�u����Z���^�[���ł�������́A���E�̃I�s�j�I�����[�_�[���������A���͓��{�͐��E������c����Ă���B�����_�ł킪�������҂̂��߂ɂǂ�Ȍ��������ׂ������I�[���W���p���ŋc�_���邱�Ƃ��ړI�B�w���ȂNJW�Ȃ����g�܂Ȃ��Ɖ��Ăɏ��ĂȂ��B�R�z�[�g�������I�[���W���p���ł��Ȃ��ƈӖ����Ȃ��v�Ɛ��������B m3.com�@2010�N7��17�� |
|
�������Ò��~�̑Ó����́u�i�@�����Ō��_�o���ʁv ��苦���a�@����������V���| |
| �@�ō��ق̏㍐���p�ŏI��������苦���a�@�����ł́C�������Ò��~�̑Ó�����@��ōق����Ƃ̓�������炽�߂ĕ�������ɂ��ꂽ�B�s���ƈ�Â��l����V���|�W�E�����s�ψ���̃V���|�W�E���u��苦���a�@���������Ɩ@���l����v��7��18���C�����s���ŊJ����C�����̓����҂ƂȂ�����t�̉Ƒ���Ō�t�C�@���̐��ƂȂǂ���ÂƃV�X�e�����قȂ�i�@����Ís�ׂ̐�������_�t���邱�Ƃɖ���������ȂǂƂ���ӌ������B�l�Ƃ��Ď��ʂ��Ƃd����s�ׂ��u�ƍ߁v�ƌ��Ȃ���錻��ł́C��Ï]���҂̏d���Ƌ�Y�͌��E�ɗ��Ă���B �����ʼn������Ò��~�̓K�@��͎����ꂸ �@��苦���a�@�����́C1998�N11���ɓ��a�@�ɐS�x��~�ʼn^�ꂽ�b�����҂ւ̏��u�ɒ[����B���҂͑h�����l�H�ċz��͊O�ꂽ���̂̋C�Ǔ��`���[�u�͎c���ꂽ�܂܂ō�����Ԃ͑����C�d�NjC�ǎx���Ȃǂŗ\�f�������Ȃ��ƂȂ����B�厡��̐{�c�Z�c�q���͊��҉Ƒ��Ƃ̂��Ƃ���o�āC�������Ò��~�̂��ߋؒo�ɖ�𓊗^�����B���ꂩ��3�N��C������������E�l�e�^�œ������ߕ߁C�N�i����鎖���ɔ��W�����B �@��R�̉��l�n�ٔ����ł͎E�l�߂̐�����F�߁C����3�N�C���s�P�\5�N�������n�����B��R�̓������ٔ����ł͉������Â̒��~���Ƒ��̗v���Ō��f���ꂽ���̂ƔF�肵�Č��Y�������̂́C�L�߂͕ς��Ȃ������B�ō��ق܂ő���ꂽ����N�i2009�N�j12���ɏ㍐���p�B�������Â̒��~�������t���E�l�߂ɖ��ꂽ�����ōō��ق����f�������̃P�[�X�ƂȂ������C�������Â̒��~����������͎�����Ȃ������B �u���Ƃ��Y���ňЊd���Ă܂Ŏ�肽�����́v�Ƃ� �@�{�c�Z�c�q���̌Z��ŃV���|�W�X�g�߂��c��`�m��w��w�@�����E���������w�����̐{�c�N�����́u�ٔ����͗��O�I�C���z�I�ȍl���ōٔ��ɗՂ�ł���B���̓_�����������̎i�@���f���������v�ƐU��Ԃ����B �@�ٌ�m�ō��������Z���^�[�������Z���^�[���C��劯�̑��`��Y���́C�Y���i�ׂł́u���ۂɂ����������Ƒi��̎������قȂ��Ă��܂����߁C�i�@����Âɉ������ɂ͌��E������v�Ƃ̌������������B�����āu���Ƃ��Y���ňЊd���Ă܂Ŏ�肽�����v�͂Ȃ�Ȃ̂��B�I������ÂŎ����ׂ��́C���p�Ŏ����鐶���ł���v�Ƒi�����B �@�T�c�����a�@�i��t���j��A��Ȍږ�̏����G�����́C������Љ�ł͓������ɗގ������肪��������Ǝw�E���C�u���肬��̓w�͂������ɂ�����߂邱�Ƃɂ��������͂���̂ł͂Ȃ����v�ƒ�N�B��Ís�ׂ̑Ó����́u�@���̂悤�ɉ�㈓I�C�����I�ɍl����̂ł͂Ȃ��C�X�̏ɍ��킹�čl����ׂ��v�Ǝ咣�����B ���l�Ȋ��o�C��������錻���@�ŋK��ł��邩 �@�s���̕a�@�ɋΖ������t���_�؎�b���́C�����d��ŗ]���킸�����������҂̎�p��f�O����������Љ���B��p���������Ȃ��������Ƃ��S�Ɉ����������Ă������C�⑰����́u�Ŋ��̂��ʂꂪ�ł����v�Ɗ��ӂ��ꂽ�Ƃ����B�����͎ӎ��������Ƃ��ӊO�Ɋ��������̂́C��t�Ƃ��ċM�d�Ȍo��������ꂽ�Ƃ��C�u��Ì���ł����������Ȃ����o�⊴�����̂ɁC�@���ňꂭ����ɋK�肷�ׂ��łȂ��v�Ƌ��������B �@�R���f�B�J���̗��ꂩ����ӌ����������B�Ō�t�̍P������q���́C���銳�҂��Ō�t�ƃR�~���j�P�[�V���������Ă����Ƃ��ɉ������Â̋��ۂ����Ă������C�Ō�t����t�ɓ`���Ă���������Ă��炦�Ȃ������������������B�u�Ō�t�����҂̈ӎv���L�^���C��������ƂɈ�ÎҊԂ̈ӎv�����}��ׂ��łȂ����B�E����ŊŌ�t�������ł�����𐮂���K�v������v�Ƌ��߂��B �@�{�c�Z�c�q���̐f�Â��Ă������҂̉Ƒ��ł���֓����q���́C���҂ƈ�t�̊W�Ɍ��y�����B�����͐f�@�ɓ�����{�c���̎p���ɑ��銳�҂̐M���͌��������Ƃ��C�u��t�����҂̖ڐ��ɗ����C���҂̂��߂��v���Ă���̂��Ƃ������Ƃ����҂͕q���Ɋ�������Ă���B���ꂪ��������ΐM���W�͐��܂��v�Ƙb�����B �@�i���̎肪�ǂ��܂ň�Âɉ�����ׂ��Ȃ̂��Ƃ����c�_�́C���l�ȍl����s����Ȑ��ǂȂǂ̉e���ŋ�̍���u����ɂ͎����Ă��Ȃ��B��Ï]���҂����҂̂��߂��v���Đl�Ԃ炵�����˂�菕��������ΗL�߂ɂȂ鋰�ꂪ�����ȏ�C�����ɕK�v�Ȉ�Ís�ׂƎi�@���f�̕������𑁋}�Ɍ��o���Ȃ���C��Èޏk�̗���͎~�܂�Ȃ��B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N7��20�� |
|
��106����{���_�_�o�w�� ����Z���^�[���_��ᇉȂ��V�����Ɩ����f���� |
| �@�����Âɐ��_�Ȉオ�Q�悷��V�X�e�����[�����Ă����B��t������Z���^�[���_��ᇉȂ̏H���L�ƕ����́C���_��ᇉȂ������a�@���_�Ȃ̐V�����Ɩ����f����W�J����`�����X�ɂȂ�\��������Əq�ׂ��B �\�h�I����Ȃǂ̖����� �@�ߔN�C���_�Ȃ��܂߂����܂��܂Ȃ����Ñ̐��������������B���_�Ȉオ��������ɘa�P�A�`�[���ւ̐f�É��Z�C���_�Ȉ�Ȃǂ̏���`���t��������f�ØA�g���_�a�@���x�C���ҁE�Ƒ��ւ̐S�̃P�A�C���_��ᇈ�̈琬�Ȃǂ𐄐i���邪����{�@�C��������i��{�v��̐����Ȃǂł���B4���ɂ͂��҂ւ̃J�E���Z�����O�����ݒ肳�ꂽ�B �@�������C�S���̋��_�a�@�ŁC���_�Ȉオ�풓���Ă���{�݂͂܂�3����2�B���_�Ȉオ�֗^����ɘa�P�A�Őf�É��Z�Ă���{�݂�2���ɂ����Ȃ��B���x���\�����p������Ă��Ȃ������C����f�Â̌��ꂩ��͂��܂��܂Ȗ��������҂���Ă���B �@�H�������ɂ��ƁC���Z���^�[�ɐ��_��ᇉȁi�����j���ݒu���ꂽ�̂�2009�N4���B���_�Ȉ�2�l�i���1�l�j�C�Տ��S���m2�l�ŁC���҂₻�̉Ƒ��C�⑰��ΏۂƂ����O���f�ÂƓ��@�R���T���e�[�V�������s���Ă���B���f���҂̂������@���҂�6���B�I�����ȊO�̊��҂�8�����߂�B�Ƒ����邢�͓��Z���^�[�ȊO�̊��҂͂܂������ɂƂǂ܂�B �@�f�f���͔������̓K����Q�C�傤�a�₹��ςȂǂ������B����琸�_�����̐f�Âɉ����C�N�P���傫�����Â��銳�҂ɑ���\�h�I����C�����ÂɊւ���ӎv����x���E���Ӕ\�͕]���C�F�m�ǁC���������ǂȂǂ�L���銳�҂̂��Îx���C���@��v����ꍇ�̐��_�ȕa�@�Ƃ̘A�g�Ȃǂ��s���Ă���B �@�������́u�R���T���e�[�V�����E���G�]�����_��Â������i�C�����a�@���_�Ȃ̐V�����Ɩ����f����W�J����`�����X�Ƃ��邱�Ƃ��\��������Ȃ��v�Əq�ׁC��ᇐ��_�Ȃ̊g�[�Ɍ��������_�Ȉ�̐ϋɓI�Ȏ��g�݂𑣂����B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N7��22�� |
| ��15����{�ɘa��Êw�� |
| �@��15����{�ɘa��Êw�6��18�|19���C�������ۃt�H�[�����i�����s���c��j�ɂĎu�^�וv��i�}�g���f�B�J���Z���^�[�a�@�j�̂��ƊJ�Â��ꂽ�B�n��15�N�ڂ��}����{�w��́C�ɘa�P�A�̏d�v�������܂�ƂƂ��ɉ���������������C���N3���ɂ�9000�l��˔j����ȂǁC�E��̊_�����Ċɘa�P�A�̂�����ɂ��ċc�_�����ƂȂ��Ă���B �@����́C�u���ł��ǂ��ł����̍����ɘa�P�A���v���e�[�}�ɁC�ŐV�̒m���������ƂƂ��ɁC��莿�̍����ɘa�P�A���߂����������ȋc�_�����킳�ꂽ�B�{���ł́C��ʓI�ɂ͂܂��܂����y���Ă��Ȃ������ɘa�P�A�ɃX�|�b�g�Ă��V���|�W�E���u�����̊ɘa�P�A�v�i���������H�����ەa�@�E���V���a���C�����w�@�E�����^�����j�̂��悤���Љ��B ���l�Ƃ͈قȂ鏬���̊ɘa��Â������ɐ��i���邩 �@�V���|�W�E���ł͂܂��C���c���������i���s��������ÃZ���^�[�j�������ɘa�P�A�̓����Ƃ킪���̌���ɂ��ĉ���B���͂܂��C���ݏ����̊ɘa�P�A�͂����S�ƂȂ��Ă��邪�C�_�o�؎����C��Ӑ������C���F�ُ̈�C�d�x�]���܂ЂȂǁC���܂��܂Ȏ����ɂ����Ă��K�v�ł��邱�Ƃ����������B�������C���a�����l�ő̂̃T�C�Y���l�����傫�����ƁC���҂̐�ΐ������Ȃ����ƂȂǂ���C�V�X�e���̊m����Z�p�̌��オ����Ǝw�E�B���̏�ŁC����͒n���ÁE����E�����E��ƂƂ̘A�g��C�����ɘa�P�A���{�݂̊J�݂Ȃǂɂ��C�ɘa�P�A��i�߂Ă����ׂ��Əq�ׂ��B �@���X�ؐ��s���i�������_�E�_�o�Z���^�[�a�@�j�́C�_�o�E�؎����͎������Ȃ��������������ƁC���X�ɐi�s���邽�߈�ʂɁg�^�[�~�i���h�ƂƂ炦������Ԃ������Ԃɂ킽�邱�Ƃ���C�u�ɘa�P�A�v�Ƃ����l�����͐_�o�E�؎����̈�ɂ͐Z�����Ă��Ȃ��ƌ��������B�������C����́g�ł��邱�Ƃ͉��ł��s����Áh����C�g�L�Ӌ`�Ȑ���S�����邽�߂̈�Áh�ɃV�t�g���邽�߂ɁC�_�o�E�؎����ɂ����Ă��ɘa��ÓI�ȍl���������ׂ��ł͂Ȃ����Əq�ׂ��B �@������Âɂ����ẮC�����q�ǂ��ɂƂ��čőP�̑I���ƂȂ�̂��C�Y�ޏ�ʂ������B�������C���������q�ǂ���Ƒ�����̓I�Ɉ�ÂɎQ��������͐����Ă���̂��낤���C�����������悢�Ǝv���Ă��邱�Ƃ������t���Ă͂��Ȃ����낤���B�L�c���q���i���m���q���w�@�j�͊Ō�t�̗��ꂩ�炱�̂悤�Ȗ����N���C��������̏I�����P�A�ɂ��čl�@�B�Ō�t�̖����Ƃ��āC�����E�Ƒ��Ƙb��������W��z���C���Y���Ȃ���K�ȏ���K�Ȏ����ɍs�����Ƃ�C��ɂ̊ɘa�Ɍ��ʓI�ȃP�A�Z�p����ÎҊԁC�Ƒ��Ƃ̊Ԃŋ��L���邱�ƂȂǂ̏d�v����������B �@�O�c�_�����i��������f�Ï��V���ˁj�́C1999�N�̐f�Ï��J�݈ȗ��s���Ă����C�킪���ł͂܂��F�m�x�̒Ⴂ�����̍ݑ��Âɂ��ďЉ�B�d�ǎ���n��Ŏx���邽�߂ɂ́C�K��f�Â�K��Ō삾���łȂ��C�z�[���w���p�[���̐����x���E���x���̏[���C�Z�����@�{�݂�f�C�T�[�r�X�{�ݓ��̃��X�p�C�g�P�A�̐����C�P�A�R�[�f�B�l�[�^�[�̐ݒu�ȂǁC���{�݁C���E��ŘA�g���Ă������Ƃ��s���ł���Ƃ����B �@�����̏I������Âɂ����ẮC�ݑ�ʼn߂��������Ƃ����Ƒ��̗v�]�����Ȃ��Ȃ��B�������C���ۂɂ͏������҂������f�Ï��̕s�����w�E�����ȂǁC�ۑ�������R�ς��Ă���B���̂悤�ȂȂ��C�e���҂̔��\��ɍs��ꂽ���_�ł́C��ꂩ��u�����̍ݑ��Âɂ�����肽���Ǝv���Ă��C�������̈�Î{�݂ł͂Ȃ��f�Ï����ɂ͏����ꂸ�C�ϋɓI�ɂ�����邱�Ƃ�����v�Ȃǂ̐������������B�n��ɂǂ̂悤�ȃj�[�Y������̂���c�����C�K�ȏ����s���Ȃǒn��A�g���������邱�ƂŁC�����ɘa�P�A�C�����ݑ��Â̐V���ȃX�e�[�W���J����\������������V���|�W�E���ƂȂ����B �T����w�E�V�� �@2010�N07��26�� |
| ���a�Ɉ��炬�u�q���̃z�X�s�X�v�@��t��c�̔��� |
| �@�d���a�C�̎q���₻�̉Ƒ����x����u�q���̃z�X�s�X�v�̐ݗ���ڎw���A���̏����Ȉ�炪�Q�X���A�C�Ӓc�́u���ǂ��̃z�X�s�X�v���W�F�N�g�v�𗧂��グ��B�����I�Ȏ{���݂�����ɓ���A���ʂ͎q���̊Ō�Ŕ�J����Ƒ����x��������悤�ɊŌ�t��ɂ��K��P�A�����Ɋ�������B�u�ł��邱�Ƃ���n�߁A���X�Ɋ����̕����L���Ă��������v�Ə����Ȉ��͘b���Ă���B �@�q���̃z�X�s�X�́A��a�̖��̊Ō�ɔ��������e�ɋx����^���悤�ƊŌ�t�����𐔓��ԗa�������̌�����ɂP�X�W�Q�N�ɉp���Őݗ����ꂽ�̂��n�܂�B �@���I�ȃg���[�j���O������t��Ō�t�A���w�Ö@�m�炪�q����l��l�̏�Ԃɍ��킹����Â����ق��A�q���������y���܂���p�[�e�B�[�Ȃǂ̃C�x���g������ɊJ�����B �@�u�z�X�s�X�v�Ƃ������t����A�������҂�̂��߂̊Ŏ��̏��z�����ꂪ�������A�a�C�̎q����Z���ԗa���邱�ƂŁA���e��̐S�g�̔���������u���X�p�C�g�P�A�v�ړI�̗��p���唼���B���݁A�p�����ɂS�O�ȏ゠��A�J�i�_��I�[�X�g�����A�A�h�C�c�ȂǑ����̍��ɂ��a�����Ă���B �@���{�ł��ޗǎs�ȂǂŐݗ��Ɍ������������i��ł���A���ł����H�A�p������q���̃z�X�s�X�n�ݎ҂�������Č𗬉�J���ꂽ�̂����������ɁA���s��������ÃZ���^�[�̑��c�������E�ɘa��ÉȌ��������Ȉ㒷�炪���S�ɂȂ��ď�����i�߂Ă����B �@�p���̎{�݂͎�ɒn��Z����̊�t�i�N�ԂR�`�T���~�j�ʼn^�c����Ă��邪�A��t�����̐Z�����Ă��Ȃ����{�ł͎����ʂȂljۑ肪�����B�����ŁA�u�ł��邱�Ƃ���n�߂悤�v�i���c����t�j�Ƃ܂��̓{�����e�B�A�ł̖K��P�A�����Ɏ��g�ނ��Ƃɂ����B �@�Ō�t��w���炪�d���a�C�̎q���̉ƒ��K�₵�A�����Ԃ��q���ƈꏏ�ɗV��ʼn߂����B���̊ԁA�ی�҂͋x��������Ƃ����d�g�݂��B�w����ɂ͏����A�p���Łu�v���C���[�J�[�v�ƌĂ��g�V�т̐��Ɓh�ɂȂ��Ă��炤�_��������Ƃ����A���ƒ�̑I����o�ĂP�O��������X�^�[�g������\��B �@���̂ق��A�q����S�������⑰���A�����o���������⑰�̃J�E���Z�����O�Ɍg��鎎�݂��v��B�܂��A�C�Ӓc�̂��ł��邾�������ɎВc�@�l��������B �@���c����t�́u�����ݏo�����Ƃ��厖�B�v���W�F�N�g�ւ̎^���̗ւ��L���Ȃ���A�����I�Ȏq���̃z�X�s�X�ݗ��ɂȂ��Ă��������v�Ƙb���Ă���B �@�u���ǂ��̃z�X�s�X�v���W�F�N�g�v�������́A�Q�X���ߌ�V��������s�s����̎s��������ÃZ���^�[������z�[���ŁB���ꖳ���B�ڂ����̓z�[���y�[�W�i���������F�^�^�������D���������������������������������D�����^�j�ŁB �Y�o�j���[�X�@2010�N7��27�� |
|
�R������Ò����H�ׂ��� ���o���͂����������V�s ������Z���^�[�ƃL�b�R�[�}���J���� |
| �@������Z���^�[�i��t�s������j�ƁA�L�b�R�[�}���i��c�s��c�j�͂Q�W���A�R������Â̕���p�ŐH�~�s�U�ɋꂵ�ނ��Ҍ����̃��V�s�̋��������Ɏ��g�ނƖ��炩�ɂ����B�����̑�\�I�Ȃ�����a�@�ƐH�i��肪�A�g���A���҂̐����̎��̌���Ɏ��g�ޏ��̃v���W�F�N�g�ƂȂ�B �@�Z���^�[�ɂ��ƁA�R������Â𑱂��鑽���̂��҂ɂƂ��āA���������H�����y���߂邱�Ƃ͐�����x���ɂȂ�A���Âւ̎Q���ӗ~�𑣂����Ƃɂ��Ȃ���B�����A�R������Â��Ă���Ԃ́A�H�������Ă��u��������ł���݂����v�ȂǁA���o�Ȃǂُ̈��i����Ⴊ�����B �@���������ł́A�Z���^�[�ōR����܂̒ʉ@���Â��銳�҂T�O�l�ɁA�_���A�h���A�Ö��A�ꖡ�ȂǂV��ނ̖��o�̊���������������ق��A���o��k�o(���イ����)�̃A���P�[�g���s���B �@���̃f�[�^���L�b�R�[�}�������͂��A���҂̖��o�̕ω���c�����A�Q�O�P�Q�N�R���܂łɁA���҂ɂ��������t���⒲�����@�Ȃǂ̃��V�s���Z���^�[�̉h�{�m��ƈꏏ�ɊJ������B �@���쌴�̓Z���^�[���́u�R����܂̎�ނɂ���Ė��o��Q�̕\������Ⴄ�̂ŁA���J�j�Y�����𖾂��A�h�{�̉��P�ƐH�ׂ��т̉�ڎw�������v�Ƒ_����b���B �@����A����͖����ŋ��͂���L�b�R�[�}���̃R�[�|���[�g�R�~���j�P�[�V�������ł́u�Г��ő����Ă������o��n�D(������)�Ɋւ��錤�����A�ΊO�I�ɂ����ɗ��Ă邱�Ƃ͉�X�̗�݂ɂȂ�v�Ƙb���Ă���B m3.com�@2010�N7��29�� |
|
��21����{�ݑ��Êw�� �މ@��ɘa�P�A�̈ӎv������Ō�t������ |
| �@�������q��ȑ�w������ÃZ���^�[��Îx�����̒���l�]�t���́C�ݑ��Ñ̐��̐����Ɍg������o������n��A�g�ɂ��ĉ�����C�u�މ@��ɘa�P�A�a���ւ̓��@�ɂ�����ӎv����̒����ɉʂ����Ō�t�̖����͑傫���v�Əq�ׂ��B �ɘa�P�A�`�[�����C�ߗɘa�P�A�a���ƘA�g �@���Z���^�[�͔����s�𒆐S�ɓ����n��ŋ}������Â�S���C�n���Ë@�ւƋ@�\���S�Ƌ@�\�A�g���s���C���Ȋ����^��Â���n�抮���^��Â�ڎw���B�s���̋ߗוa�@�Ƃ�2������1��̉�c�������C���@���҂̏�e�{�݂̑މ@�x���̖��_����C�P�A���[�J�[�������Č������s���Ă���B���N4 �N�ڂ��}���邪�C�J�@�����͍ݑ��Â�ɘa�P�A���s���s���̐f�Ï�����ыߗׂ̊ɘa�P�A�a����L�����Ë@�ւ��s���B�@���ł��ɘa�P�A�Ɋւ���F���̑����ݑ��ÂɊւ���m���C�ӎ����s�����Ă����B �@�����������C���@������ёމ@��Ɋɘa�P�A��K�v�Ƃ��銳�҂̑����C�n���Ë@�ւ���̗v�]�ɉ����C�ɘa�P�A�`�[���������グ��ꂽ�B�I������Վ����Ɍ��肹���C�����ɂ���Ǐ����菜���C���Â�ݑ�×{�Ɉڍs����Z���W���^�ɘa��Â�ړI�Ƃ����B�������e�́C�u�`�����̊J�ÁC�@���O�ւ̒m���̕��y�C�n���Ë@�ֈ�t��K��Ō�X�e�[�V�������j�Ƃ����ݑ��Âł̊ɘa�P�A�̐��i�C�u�ɃR���g���[���𒆐S�Ƃ����R���T���e�[�V�����ȂǁB �@�܂��C�K��Ō�t��ݑ�×{�x���f�Ï��̈�t�ƘA�g���C�ݑ�×{���x�����Ă���B���҂̊�]�ɂ��C�ɘa�P�A�`�[���܂��͎s�O�̊ɘa�P�A�a���ŏǏ�R���g���[�����s���B�n��ł́C�ݑ�֖߂邽�߂̊ɘa�P�A�ł���C�Ǐ�R���g���[���ł���Ƃ����F�����Z��������B �@���݁C�K��Ō�͈˗��̗����ɉ�����\�ł���B�ً}���͎x���Z���^�[�����x���ɑ����ɑΉ����C�K��f�ÁC���f�������ȓ��C�ɘa�P�A�a�@�ւ̖ʒk��1�T�Ԉȓ��ɗ\�\�ł���B�����̌��ʁC�ݑ�Ŏ��͑������Ă���B �@�@���ɂ����Ă���Ã`�[���Ԃ��A�g���邱�Ƃő���������\�ɂȂ����B������Ō�t�ւ̑��k�C��t�̉���C�O�ȓI�ɘa�P�A�̈˗��C���@�O����̑މ@�x���Ȃǂɂ��C�u�ɃR���g���[�������͌������C�ɘa�P�A�a���ւ̓��@���҂͑����C�K��Ō삨��іK��f�Â��˗������t�C�Ō�t���������C�Ō�t����͒n���x���Z���^�[����T�[�r�X�̗��p�ɂ��Ċ��҂ƉƑ��ւ̏����Ȃ���Ă���B �@����Ή����ׂ��ۑ�Ƃ��ẮC�����ƌ�����Ǘ�C�o�ϓI���œ��@��ݑ�×{�����Ȃ��Ǘ�C���͂��Ȃ�����҂���ѐg��肪�Ȃ��Ƌ��Ǘ�C���{�݂Ȃǂ�����@��������҂�F�m�ǏǗ�Ȃǂւ̑Ή�����������B �@����t���́u�ݑ���̐����ɂ͓��X�̒������d�v�ł���v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N8��5�� |
| �F��Ō�t�̋���ے����J�݁^���쌧�Ō싦�� |
| �@���쌧�Ō싦��i�n�ӏƑ��j�͂��̂قǁA�~�}�Ō�F��Ō�t�̋���ے����J�݂��A�P�O�l�̎�u�������ꂽ�B�F��Ō�t�͊ɘa�P�A�A������Ō�ȂǂQ�P�̕���ʂɔF��B�~�}�Ō�̕���ŔF��Ō�t��ڎw������ے���ݒu����̂́A���l���ŏ��߂āB �@�F��Ō�t�́A���蕪��ō����Ō�Z�p�����l�ނ̈琬��ړI�ɓ��{�Ō싦��A�P�X�X�V�N����F����J�n�B�T�N�ȏ�A�������蕪��łR�N�ȏ�̎����o���҂ŁA�������߂鋳��ے��i�U�J���A�U�O�O���Ԉȏ�j�̏C���҂�ΏۂɔF��R���i�M�L�����j���s���Ă���B �@�~�}�Ō�̕���ł́A����܂œ����A���A�X�A���m�ɂ�������ے���ݒu������@�ւ��Ȃ��A�u�]�҂ɂ͓]���Ȃnjo�ϓI���S���傫���������Ƃ���A���Ō싦��J�݂����B �@��w�ȂNj���@�ւ��ݒu��̂ƂȂ�P�[�X�������A�s���{���Ō싦��J�݂���̂́A�~�}�Ō�Ɍ���Α��Ɏ����łQ��ځA�S����ł͂W��ځB�����ł́A�����w��w�����X���Ɋɘa�P�A�F��Ō�t����ے����J�݂���B �@�����s���������̌��Ō싦��Ō쌤�C�Z���^�[�ő�P�����̓��w��������A�������͂��߁A���l���A��B����W�܂����P�O�l�̎�u�����\���ďH�R���q����i�R�O�j�������w��w���t���a�@�����u�F��Ō�t�ɕK�v�Ȑ��m���E�Z�p���K�����A���H�͂�g�ɂ������v�Ɛ鐾�B����A��u���͊�b�E���ے��𗚏C����ق��A�P�P�����{����~���~�}�Z���^�[�̂����w�a�@�ȂǂłT�T�Ԃɂ킽���Ď��K�Ɏ��g�݁A���N�T���̔F��R���ɗՂށB �@�n�Ӊ�́u�����҂��ƌ��O�Ő������Ȃ���̎�u�͓���B�������̎��g�݂��ӗ~�̂���Ō�E�̃X�L���A�b�v�ɂȂ���v�Ƙb���Ă���B �@�V�����݁A�S���łV�R�U�R�l���F��Ō�t�Ƃ��ēo�^�B�����ł͂P�T�̕���łV�O�l�A�����~�}�Ō�ł͂V�l���o�^����A��Ë@�ւŊ��Ă���B �l���V���@2010�N8��11�� |
| ��15����{�ɘa��Êw��@�K�C�h���C���iGL�j���� |
| �K�C�h���C���iGL�j�^�p�̌��� �@�����̗ш㒷�́C����܂ł̕�������Palliative Sedation�i�ɘa�I���Ɂj�̌���ɂ��ĕ��͂��C���㌟���ׂ��ۑ�������������ŁC�uGL��t���[�����[�N���K�ɉ^�p����Ă��邩���C��K�͂Ȏ��Ԓ����Ō�����K�v������v�Ǝw�E�����B ��t�̖������Â̈�w�I�K���̔��f�ɍ��� �@���Â̐����\��ւ̉e���́C���̘_�������Ă���i24���Ԉȓ��̎��S38���C1�T�Ԉȓ�96���C3�T�Ԉȓ�94���B���Â���̕��ϐ������Ԃ�1�`6���j�C���Â̗L���Ő������ԂɗL�Ӎ��͂Ȃ��Ƃ��鑽�{������������iAnn Oncol 2009; 20: 1163-1169�j�B�ш㒷�ɂ��ƁC���Â��������k�߂�\���͒Ⴂ���C�����ǂȂNJ��ҌX�̏�Ԃ��قȂ邽�߁C�ʏ�̈�Ís�ׂƓ��l�ɒ��ӂ��K�v������Ƃ����B �@�܂��C���Ì���܂ł̉ߒ��Ɍ��y����15�_���ł́C���Җ{�l�̈ӎv�m�F��Ƒ��̊֗^�̏́C����{�݂ő傫���قȂ��Ă���C�܂��C��Î҂���̏�s�\���Ɗ����Ă���Ƒ���22�����邱�Ƃ��킩�����B �@�Ƒ��̈ӎv����̖W���ɂȂ�v���Ƃ��ẮC����ς�A���r�o�����g�Ȋ��҂ւ̎v���C��ɂȂ̂��m�ɕ]���ł��Ȃ����Ƃ��������C�Ƒ��̕s���x�������Ȃ�v���ɂ́C���Ì�����҂̋�ɂ����Ȃ����ƁC���s���C�������k�߂鋰�|�C��Î҂̎v�����̂Ȃ��C���҂Ƃ̋c�_���Ȃ����ƂȂǂ��������Ă����B �@���ÂɎ^�������t��8�`9�����ł������̂ɑ��C���Â̐��m�Ȉ�w�I�K���̔��f�ɍ���������Ă����t�������߁C4����1���s�K���Ȓ��Â��s�����Ƃւ̕s��������Ă����B��9���̉Ƒ����Ǐ�ɘa�ɂȂ������ƍm��I�ɕ]�����Ă������ŁC�Ƒ����߈����△�͊��C�g�̓I�E���_�I��J�������Ă���Ƃ��������ꂽ�B�܂��C���Â̗L�����Ɋւ��ẮC���̐������͖�9���ƍ����C���ʔ������Ԃ�60���`48���ԂƂ��������ꂽ�Ƃ����B �@�Ō�ɓ��㒷�́C���㌟�����ׂ��ۑ�ɂ��Č��y�B�uGL��t���[�����[�N���K�ɉ^�p����Ă��邩�C��K�͂Ȏ��Ԓ������s���K�v������v�Ƃ��C�u�ɘa�P�A�X�^�b�t�̐��_�I�ȃP�A��J�����̐������Ȃ��ƁC���Â̎{�s�����オ��Ƃ���������C�����̊֘A������������K�v������B�܂��C����C����GL�̓K���ƂȂ�ݒ�̊g����������Ă����ׂ��v�ƌ��B �����ɗՏ�����̐���傫�����f �@�����̒r�i�z�X�s�X���́C2007�N�̒���GL�Ɋւ��鎿�⎆��������C���܂��܂ȉ����E�lj��̗v�]�_���������C����炪����̉����ɔ��f����Ă��邱�Ƃ����������B 85�����Ώۊg���v�] �@2007�N�C���w����̊ɘa�P�A�`�[���S���҂�ΏۂɁC2005�N�Œ���GL�Ɋւ��鎿�⎆���������{���ꂽ�i�����51.8���C127�{�݂��j�B���̍ہC85.5����GL�g�p�҂���Ώۊg������߂鐺�����C���̂����u�ɘa�P�A�`�[���̃T�|�[�g�̂��Ɓv�Ƃ����43.5�����߂Ă����B���̌��ʂ��C����GL��ƕ���ł̌����Ɋ�Â��C��GL�g�p�҂̓K���Ɂu�ɘa�P�A�`�[���������͊ɘa�P�A�ɏK�n������t�̐f�ÁE�����̂��ƂŐf�Â��s���Ă����Ã`�[���v�Ƃ������ڂ�������ꂽ�Ƃ����B �@�r�i�z�X�s�X���ɂ��ƁC���̒�������C���̂ق��̉����E�lj��̗v�]�_����������ɂ���C����������̉����ɔ��f����Ă���Ƃ����B�܂��C�u�����ϗ��w�I��Ձv�̍����������C�u�ϗ��w�I�Ó����v�Ƃ��ĉ��߁C���̓��e�ɂ��ĉ\�Ȍ��薾�m�ɏq�ׂ�\�����̗p�B���̂����C�����\��Ƃ̊֘A�ɂ��ẮC����܂ł̕����݁C�K�ȕ��@����邱�Ƃɂ�萶���\��Ɋւ���e���͏��Ȃ��Ɣ��f���Ă���B �@���ÂɎg�p�����܂ɂ́C���I���Ƃ��ă~�_�]�����݂̂𐄏��B���L���łȂ��ꍇ�C�N�����v���}�W���ƃ��{���v���}�W�����폜���C�v���|�t�H�[���Ȃǂ�lj��B�܂��C�ݑ�ł̑Ή��Ƃ��Ă͍��܂Ŏg�p�ł����܁i�W�A�[�p���C�u���}�[�p���C�t�F�m�o���r�^�[���j��lj������B �@����ɁC���Â̎�ށi�����I�E�Ԍ��I�E�[���E�j���Ƃɋ�̓I�Ȓ��Â̕��@��V���ɋL�ڂ����B�Ȃ��C���܂ɂ��Ă͍���C��̓I�Ȏg�p�@�̌������K�v�ł���Ƃ����B�܂��R���_�a��́C�����܂ł���ςɑ��鎡�Ö�Ƃ��ėp���邪�C��Ɋɘa�̂��߂̒��Ö�Ƃ��Ă͐������Ă��Ȃ��Ƃ����B �@����ɁC������ɂ͒��Î{�s�Ɋւ���t���[�`���[�g���ڍׂɎ����C�܂��C���Ò�R���̋�ɂf����c�[���Ƃ��āu���Ò�R���Ɣ��f���邽�߂̑Ή��`�F�b�N���X�g�v�Ɓu���Â̐��������i��j�v���t���ꂽ���Ƃ�������1���B �@����Ȃ�ۑ�́C�ɘa�P�A�ɏK�n������t�̗v���̖�����~�_�]�����ȊO�̒��Ö�C�ӎv����\�͂̕]�����@�Ɗ�C�������ӁE�Ƒ����ӂ̕K�v���Ȃǂ��������C����Ȃ錟�����s���Ă����\���ł���Ƃ����B ��ʐf�ÉȂł̓K�Ȓ��Â��\�� �@�D�y��F�a�@�̒����M�v���@���i�ɘa���Éȁj�́C����̒���GL�������@�ɁC��ʐf�ÉȂɂ�������Â̌�������C����݂̍���������B�u����̉����ł����p���邱�ƂŁC��ʐf�ÉȂł��K�Ȓ��Ẩ^�p���\�ɂȂ�v�Əq�ׂ��B ���ҁ\�Ƒ��\��ÎҊԂ̗ǍD�ȃR�~���j�P�[�V�����\�z�� �@�����̑Ώۂ́C�}�����a�@�O�ȕa����2003�`06�N�Ɏ��S�����I��������175��̂����C��Ɋɘa��ړI�ɒ��Â��s����32��B�܂��C���ÊJ�n�ɍۂ��Ă̖��_�𒊏o�����Ƃ���C�u���҂ɖ����m�v�C�u���ҁE�Ƒ����a��𗝉����Ă��Ȃ��v�C�u�����Ă��܂����Ƃւ̕s���C���|�v�C�u���҂ƉƑ��^�Ƒ����ňӌ����قȂ�v�Ȃǂ������яオ�����B�����ŁC2005�N��GL�����ƂɁC���Â��~���ɉ^�p�ł��Ȃ��������R�ɂ��ĕ��́E���������B �@�܂��C��w�I�K���̌����̂����C�u���Ò�R���v�́C�\���Ȏ��Â�s�����������ł̔��f�Ȃ̂�������C�g���悢�捷���������̂Ȃ��Œ��Â��n�܂����h�Ƃ���������ꂽ�B�u�S�g��ԁE�����\��̕]���v�Ɋւ��ẮCGL�ł͎����I�^�[�����Â̑Ώۂ͗\�㐔���ȉ��Ƃ���Ă���C���ۂ̓��^���Ԃ͕���5���̌��ʂ��猩��ƒ��Â̊J�n�����͑Ó��ƍl����ꂽ�Ƃ����B �@�����m�̏ꍇ�C���Җ{�l�̈ӎv����͓���C��ɂ��������Ă����Ȃ��C�Ƒ��݂̗̂����Œ��Â��J�n����ꍇ�������B���҂Ɉӎv����\�͂��Ȃ��ꍇ�ł��C�Ƒ��̂���̈ӌ������Ƃɂ���̂��C�Ƒ����̈ӌ��͈�v���Ă���̂��ɏ\���Ȕz�����Ȃ���Ă��Ȃ��P�[�X������ꂽ�B �@�܂��C���肬��̏Œ��Â̌�������߂邱�Ǝ��̂���Îґ����犳�ҁE�Ƒ��ւ̈��͂ɂȂ�\���ւ̔z�����K�v�Ƃ��������ȓ_��������ꂽ�B����ɁC���҂ƉƑ��^�Ƒ����̈ӌ����قȂ�ꍇ�ɂ́C�Ԍ��I�^���ÂŊ��҂̋�ɂ��ŏ����ɂ��邱�Ƃɓw�߁C�Ƒ����̈ӌ��s��v�̉����ɂ́C�Ƒ��W�ɔz�����C��葁������̏���R�~���j�P�[�V�����̍\�z���s���ł��邱�Ƃ������ꂽ�B �@�������@���́u�����̖������̂��߁C�a��ω��ɑ��������ƁC���ҁ\�Ƒ��\��ÎҊԂ̗ǍD�ȃR�~���j�P�[�V�����̍\�z��i�߂Ȃ���C�K�ȃ^�C�~���O�Œ��Â̓�����}��K�v������v�Ƌ��������B �@�ȏ�܂��C�����@���́C��ʐf�ÉȂɂ�����K���Ȓ��Õ��y�̂��߂̌����ۑ�ɂ��ĒB�u����GL�����p���邱�ƂŁC��ʐf�ÉȂɂ�������Â̓K�ȉ^�p���\�ɂȂ�ƍl������B����C���Âɂ���ɂ��ɘa����邱�Ƃ̍�����ς����ɂ̑Ó����C���Â����肷�邽�߂̕K�v�Ȉӎv����\�̖͂����Ƃ������ۑ�̉�����ڎw�����ƂŁC���悢�I�����P�A������Ă������Ƃ����҂����v�ƌ��B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N8��19�� |
|
�u�R���Â��I�����Ă���ɘa�P�A�v�̎���͏I����� ��RCT�ő�������̊ɘa�P�A���������ԉ����ɂ���^ |
| ���D�y�a�@���@���E���w�Ö@�Z���^�[���@���R �א� �����̔w�i�F�Ō`����ł͊ɘa�P�A�̏d�v�����F������Ă��Ă��� �@�����̎�p�s�\���邢�͍Ĕ��Ō`���҂́C�Ö@�ɂ�萔�����̉����͓�����ɂ���ŏI�I�ɂ͎��S����B���S����O�ɂ͒ʏ킪��͑傫���Ȃ��Ă���C����ɂ��e����̓I��ɂɔ������ƂƂ��ɁC���_�I��ɂ͐f�f�������т��đ����B�ꎞ�I�Ɂu����͏k�����܂�����v�ƌ�����Ƃ��͂���ɂ���C�S�̂�ʂ��Ă͑��傷�邱�Ƃ̂ق��������C�㔼�͂��܂��܂ȃo�b�h�j���[�X�������}���邱�ƂƂȂ�B����Ö@���Ă�����Ԃ́u�l���̍Ō�̐����v���̂��̂Ȃ̂ł���B �@�������������_�ɗ��ƁC�Ō`������Âɂ�����ɘa��Â̐�߂�ʒu�͏d�v�ł���C���j�𐬂��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B �@����C�x���҂Őf�f��������ɘa�P�A����������Q�̂ق���QOL�͗ǍD�ŁC�������Ԃ����������Ƃ̕č��̃����_������r�����iRCT�j�̌��ʂ����ꂽ�̂ŏЉ��iN Engl J Med2010; 363:733-742�j�B �����̃|�C���g�F��������̊ɘa�P�A�Q�ŗǍD��QOL����ѐ������Ԓ����l���� �@�V���ɓ]�ڐ��זE�x����Ɛf�f���ꂽ�O�����҂ɂ����āC�f�f��̑����̊ɘa�P�A�������C���Ó]�A�ƏI������Âɋy�ڂ��e�������������B �@�����̊��҂��C����̕W�����Âɑ����ɘa�P�A��g�ݍ��킹�čs���Q�ƁC�W�����Â݂̂��s���Q�̂����ꂩ�Ƀ����_���Ɋ���t�����B�x�[�X���C���� 12�T�ڂ�QOL�ƋC�����C���Â̋@�\�]���E�x�iFunctional Assessment of Cancer Therapy-Lung�GFACT-L�j�ړx�ƁC�a�@���ɂ�����s���Ɨ}���ړx�iHospital Anxiety and Depression Scale�j��p���ĕ]�������B��v�A�E�g�J���́C12�T�ڂɂ�����QOL�̕ω��Ƃ����B �@�����_�����̑ΏۂƂȂ���151��̂����C27�Ⴊ12�T�ڂ܂łɎ��S���C107��i�c��̊��҂�86���j���]�������������B�����ɘa�P�A�Q�̂ق����C�W�����ÌQ��� QOL ���ǍD�ł������kFACT-L�ړx�i0�`136�_�ŁC�X�R�A�������ق�QOL���ǍD�ł��邱�Ƃ������j�̕��σX�R�A98.0�_ vs. 91.5�_�CP��0.03�l�B�܂��C�����ɘa�P�A�Q�̂ق����C�}���Ǐ��悷�銳�҂����Ȃ������i16�� vs. 38���CP��0.01�j�B �@�I�����ɐϋɓI���Â������҂́C�����ɘa�P�A�Q�̂ق����W�����ÌQ��菭�Ȃ������ɂ�������炸�i33�� vs. 54���CP��0.05�j�C�������Ԃ̒����l�͑����ɘa�P�A�Q�̂ق������������i11.6���� �� 8.9�����CP��0.02�j�B ���̍l�@�F�ɘa�P�A�̕���ł��ϋɓI�ɗՏ������� �@�R���Â��I�����Ă���ɘa�P�A���s���Ƃ�������͏I������B���E�ی��@�ցiWHO�j��2002�N�ɔ��\�����ɘa�P�A�̒�`�́u�����������������ɂ����ɒ��ʂ��Ă��銳�҂₻�̉Ƒ��ɑ��Ď����̑������CQOL�����P���邱�Ƃł���i�ꕔ���j�v�Ƃ��đ�������̊ɘa�P�A�̕K�v����������Ă��邪�C���߂Ă��ꂪ�����ꂽ�B �@�{�����ɂ�����ɘa�P�A�̎��ۂ́uNCP Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care, Second Edition, 2009�v�Ɏ�����Ă��邪�C���{��t��́u����ɘa�P�A�K�C�h�u�b�N2008�N�x�Łv�Ɏ�����Ă���悤�Ȓʏ�̊ɘa�P�A�ɃJ�E���Z���[�ɂ�閧�ڂȐ��_�I�P�A����������悤�Ȃ��̂ł���B �@���_�I�T�|�[�g�ɂ�鐶�����Ԃ̉����͈ȑO�������Ă���iCancer2008; 113: 3450-3458�j�C�@���͖��炩�Ƃ͌����Ȃ����C�����Âɂ�����ɘa�P�A�̏d�v���́C�f�[�^�Ƃ��ďؖ��������B�G�r�f���X�̊m���ɕK�v�Ȃ̂͗Տ������ł���B �@������Â̕���ł́CRCT�̏d�v������t�ɏ\���F������C���{�ł̑�U���C��V���Տ������̎��{�����������Ă���̂͊�����B�������C�ɘa��Â̕���ł̓��{�̗Տ����������ɏ��Ȃ��̂��c�O�ł���B�ϗ��I�ȍ�������z���C�������v�w�҂ɑ��k���Ċe�푽�{��RCT����悵�Ă��炢�����B �@�e�[�}�͂�������B�Ⴆ�C���ӊ��̖Ö@�ɂ��Ă͓��ɁC���{�Ŕėp�����X�e���C�h�{���Ɍ��ӊ����P�ɗL���Ȃ̂��C�Ȃǂł���B�����i�G�r�f���X�j�ƌ�����ߋ��̘_�������Ă��G���h�|�C���g�͌��ӊ��ifatigue�j�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��̂ł���i�u����̌��ӊ��ɐ��_�h���L���v�Q�Ɓj�B �@����C��������̊ɘa�P�A���d�����邠�܂�C�����I���Â̏�Q�ƂȂ�悤�Ȃ��Ƃ͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����`���Łu�Ō`����v�ƌ��肵���͖̂łȂ��邱�Ƃ��܂��Ȃ�����ł���B �@��Ō`����C�Ⴆ�C���t��ᇂ⏬������ł͏��قȂ�B���������p��̍R����Âɂ������u�ɃR���g���[���̂��߂̃I�s�I�C�h�ʂ������߂ɕ֔�ƂȂ�r���N���X�`�������ʂ���������Ȃ��̂ł���C��t�́u�P�l�̊���������_�v�ł����Ȃ��B�����I���ÂɊւ��ẮC�u���ɂ͊��҂ɉ䖝��������K�v������v�̂���ނ����Ȃ��B��������̊ɘa�P�A�ɂ����ẮC���������������I���������l���ɓ��ꂽ�����I���f���K�v�Ƃ���邾�낤�B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N8��27�� |
|
�I�������҂ւ̎_�f�z���͎����C�z���Ɣ�ׂđ�����P�ɍ����Ȃ� �I�[�X�g�����A�C�č��C�p��������RCT |
| �@�I�����̊��҂ɑ��C����̉��P�ړI�ł����Ύg�p�����_�f�z���B�ăf���[�N��w��Amy P. Abernethy����́C�I�������҂ɕ@�J�j���[���ɂ��_�f�z�����s���Ă������C�z���Ɣ�r���đ�����P�ɍ����Ȃ����Ƃ�Lancet9��4���I�����C���łɕ����B NR�X�P�[���Ōċz��]�� �@Abernethy����ɂ��Ɗɘa�P�A��70���̈�t����������҂Ɏ_�f�z�����s���Ă���Ƃ����B�������C�_�f�z�������ɂ��Ă̖��炩�ȃG�r�f���X�͂Ȃ����Ƃ���C�������3���������œ�d�ӌ������_������r�����iRCT�j���s���C�I�������҂ւ̎_�f�z���̌��ʂ����������B �@�Ώۂ́C�I�[�X�g�����A�C�č��C�p���̌v9�{�݂̔x�����C�ɘa�P�A�C����C�v���C�}���P�A�Ȃǂ̊O���f�ÉȂɒʉ@���̐�������1�����Ɣ��肳�ꂽ�I��������239��k18�Έȏ�C�������_�f�����iPaO2�j��7.3kPa�CMedical Research Council�iMRC�jdyspnea�X�P�[��3�ȏ�l�B�n���i�w���O���r����100g/L�j�C���Y�_���ǁiPaO2��6.7kPa�j�C�F�m�@�\��Q�kMini-Mental State Examination�iMMSE�j�X�R�A��24�l�C�i��������C���߂�7���ԂŌċz��܂��͐S�C�x���g���ǂ͏��O�����B �@�����̊��҂����Âɂ���Ԃ����肳������C�@�J�j���[���ɂ��2L/���̎_�f�����Ȃ��Ƃ�15����/���z������_�f�z���Q�i120��C�j�� 76��C���ϔN��73�j�ƁC�@�J�j���[���Ŏ����C���z�������鎺���C�z���Q�i119��C�j��71��C���ϔN��74�j�ɕ����C7���ԁCNumeric Rating�iNR�j�X�P�[����p���Ē��[�̑���̒��x��10�i�K�ŕ]�������B �@�Ȃ��C�����ǐ��x�����iCOPD�j�C�����x����͎_�f�z���Q�ł��ꂼ��59���C15���C�����C�z���Q�ł͂��ꂼ��68���C13���Ɍ���ꂽ�B QOL���P�C����p�����͓��� �@�x�[�X���C������6����̌v7���ԕ]���ł����̂́C�_�f�z���Q120�ᒆ112��i93���j�C�����C�z���Q119�ᒆ99��i83���j�ł������B�����̊��҂ɂ����钩�̕���NR�X�P�[���́C�x�[�X���C���ɔ�ׂĎ_�f�z���Q�ł�4.5����0.9�ቺ�i���Εω����|20���C95��CI�|1.3�`�|0.5�j�C�����C�z���Q�ł�4.6����0.7�ቺ�i���|15���C�|1.2�`�|0.2�j�������C���Q�ԂɗL�Ӎ��͌����Ȃ������iP��0.504�j�B����C�[���̕���NR�X�P�[���́C�_�f�z���Q��4.7����0.3�ቺ���i���|7���C�|0.7�`0.1�j�C�����C�z���Q�ł� 4.7����0.5�ቺ�i���|11���C�|0.9�`�|0.21�j�������C���l�ɗ��Q�ԂɗL�Ӎ��͔F�߂��Ȃ������iP��0.554�j�B �@���Q�ɂ�����QOL���P����ѕ���p�����ɍ��͂Ȃ��������C�ɓx�̖��C�͎_�f�z���Q10���C�����C�z���Q13���C�@�̉��ǂ͂��ꂼ��2���C6������ꂽ�B�_�f�z���Q�ł͕@����̖��ȏo����1�ᔭ�����Ă����B �@�����I����C�S��Ɏ_�f�z���ɂ��Ď��₵���Ƃ���C43��i18���j���_�f�z����]�܂Ȃ��ƉB���̂ق��ɁC������Ă����b�������Ȃ��Ɖ����̂�63��i26���j�C�����I����Ɏ_�f�z������]�����ۂɓ��������̂�41��i17���j�C�_�f�z������]���������ۂɂ͓������Ȃ������̂�74��i31���j�C�c���18��i8���j�͖��ł������B �@�J�j���[���ɂ��@�ւ̎_�f�z���́C�����C�z���Ɣ�ׂđ���̉��P���ʂɍ����Ȃ��������Ƃ���CAbernethy����͊��҂̗\����l�������S�����Ȃ����Â��s���ׂ��ł���Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N9��9�� |
|
�L�m�R�ܗL���o�����Ői�s���҂̂��C�s�������P�̉\�� �Ă̌����O���[�v���v���Z�{�ΏƓ�d�ӌ��ɂ��p�C���b�g���� |
| �@��Harbor-UCLA Medical Center��Charles S. Grob����̓}�W�b�N�}�b�V�����[���Ȃǂ̃L�m�R�Ɋ܂܂�錶�o�����V���V�r�����i�s���҂̕s���₤�Ǐ�����P����\����Arch Gen Psychiatry9��6���I�����C���łɕ����B12���ΏۂƂ����v���Z�{�ΏƓ�d�ӌ������ŁC���ƂȂ镛��p�͌���ꂸ�C�V���V�r��0.2mg/kg�̓��^�ɂ�肤�C�s���]���X�R�A�̉��P�X�����F�߂�ꂽ�Ƃ����B 30�N�ȏ�O�Ɍ��������N���u����Ă����̈�C�ƒ��҂� �@Grob����ɂ��ƁC�i�s���҂̕s�����]���Ȃǂɑ��錶�o��̌�����1950�`70�N��ɂ����Đi�߂��Ă���ꕔ�ł͋��͂ȉ��P���ʂ����ꂽ���C�����I�E�����I�Ȉ��͂ɂ�蓹���Œ��f���ꂽ�Ƃ����B �@�����炪���ڂ�����p�����҂���錶�o������1�C�V���V�r���͂��܂��܂Ȏ�ނ̃L�m�R�Ɋ܂܂�Ă���C�̓��ő�ӂ��C�Z���g�j����e�̂̃A�S�j�X�g�Ƃ��č�p���C���o��p�������N�������Ƃ��m���Ă���B������́C�ŋ߂̗Տ��I��������V���V�r���̓q�g�̐��_�I���N�ւ̊댯�����Ȃ����ƂȂǂ����炩�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���C�ȑO�̌�������35�N�ȏ���o������C�������s�����Ƃɂ����Ƃ����B �@�ΏۂƂȂ����̂�36�`58�C12��̐i�s���ҁi11�Ⴊ�����j�B4��͌��o�܂̎g�p�o�����Ȃ��������C8��͉ߋ���LSD��}�W�b�N�}�b�V�����[���C�y���[�e�Ȃǂ̎g�p�����������B�e�Ǘ�̓V���V�r��0.2mg/kg����уv���Z�{�Ƃ��ăi�C�A�V���i�j�R�`���_���܁j250mg��2�����ꂼ��ʂ̋@��ɓn����C���p�����B�ǂ���̔팟�n���ꂽ���͎����S����t�݂̂��c�����Ă����B���팟��̕���Z�b�V�����͐��T�ԋĐ݂���ꂽ�B �@�e�Z�b�V������1���O����6�����܂ł̕]�����s��ꂽ�B�]�����ڂ͌����C�S�����C�̉��Ȃ�тɁC����s���Ɋւ��钲���[�ɂ��X�R�A�B �@�Z�b�V�������{�O��ɂ����鐶���w�I�Ȗ��C������o�b�h�g���b�v�Ȃǂ̐��_�I�Ȉ��S���Ɋւ�����͌����Ȃ������ق��C�Տ��I�ɗL�ӂȗL�Q���ۂ��Ȃ������B�s���Ɋւ���]���X�R�A�iState-Trait Anxiety Inventory�GSTAI�j���Z�b�V�����J�n�O���ɔ�ׁC�J�n1�����C3�����ŗL�ӂɉ��P���Ă����B�܂��C���Ǐ�iBeck Depression Inventory�GBDI�j�ɂ��Ă�6�������_�ŗL�ӂȉ��P���F�߂�ꂽ�B �@������͍���̃p�C���b�g�����ɂ��C�i�s���҂̕s���₤�Ǐ�̉��P��ړI�Ƃ��������p�ʂ̃V���V�r�����^�̎��{�\���ƈ��S�����m�F���ꂽ�ƌ��_�B���N���u����Ă����Ƃ������邱�̗̈�ŁC����̒lj������s���K�v�����x��������̂Ƃ��Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N9��9�� |
| �S���܂���{�ɘa��Ö�w�� |
| �@���T���́A���{�ɘa��Ö�w��N��A�S��ڂɂ��ď��߂Ēn���s�s�̎������s�ŊJ�Â����B�n���J�Âɂ�������炸�A���O�o�^���Q�O�O�O�l���A�Q���҂͍�N�i���l�s�j�̖�Q�P�O�O�l������Ƃ��̂Ɨ\�z����Ă���B �@�����Ԃ��Ȃ��w��A�n���s�s�ŊJ�Â��A����s�s���ł̊J�Â����Q���Ґ��𑝂��Ƃ����̂́A�W�҂ɑ���w��̔F�m�A�w��̈�̕K�v���̍��܂�Ƌ��ɁA�w��̐�����������������B �@���ہA������͍�N�Q�T�O�O�l�A���N�X�����_�łR�O�O�O�l��D�ɒ����A�N�X���W�𐋂��Ă���B��t�̊ɘa��Âɑ���S�̍��������������錋�ʂ��B�Ȃ��A���N��̎��O�o�^�҂̂����A�W�O�O�l�ȏオ�����Ƃ������ƂŁA����Ȃ������̑����������܂��B �@�ɘa��Ö�w��́u������{�@�v���{�s���ꂽ�Q�O�O�V�N�ɁA����ȑ�w�̗�ؕ����𗝎����Ƃ��ė����グ��ꂽ�B���N�R���Q�S���ɕa�@��t�A��ȑ�w�����A�ی���ǖ�t�̗L�u�A�^���҂炪�W���A�ݗ�����ƋL�O�u����J�Â��ꂽ�B �@���O�W�N�S���̐f�Õ�V����ŁA�u�ɘa�P�A�f�É��Z�v�ɂ����āA�ɘa�P�A�̌o����L�����C��t�̔z�u���Z��v���Ƃ��ĉ������A��t�̖{�i�I�Ȋɘa�P�A�ւ̎Q����㉟�����A����ɁA�w��ւ̊S�������グ��`�ƂȂ����B �@�O�X�N�ɂ́A�ɘa�Ö@�F���t���x�𗧂��グ�A�g��C�̖�t�h���o�b�N�A�b�v���鎖�Ƃ��J�n�����B �@����A�ɘa��Âւ̊ւ��́A���@���҂ɑΉ�����a�@��t�����Ɍ����Ȃ��B�ݑ�ŏI����Â��܂߂��ɘa�Ö@�̕K�v���A�d�v���ւ̔F���̍��܂��w�i�ɁA�ݑ�̈擙�Ŋ���n��̖�ǖ�t���F���t��ڎw���ȂǁA���̈�̖�t�A��b��S����w�����ғ��ւ��S���L���Ă������B �@�ɘa�Ö@�̓`�[����Â��O��ł���A���N��̎��O�o�^������Ɩ�t���قƂ�ǂ����A��t���T�O�l���A�Ō�t���V�O�l���A���ɗՏ������Z�t�◝�w�Ö@�m�ȂǁA���l�Ȉ�Ï]���҂��o�^���Ă���Ƃ����B�������������E��Ƃ̌𗬂̏��ł��邱�Ƃ��A�w��̑傫�Ȗ��͂̈�ɂȂ��Ă���B �@�P�O���ɂ́A��t�ő�́g�w��h�ł����S�R����{��t��w�p������s�ŁA�P�P�����{�ɂ͊s�ő�S����{��NJw��A��t�s�ő�Q�O����{��Ö�w��N��ƁA�S���K�͂́g�w��h�������B �@�����̖�t�ɂ́A�����������ʂȋ@��𗘗p���āA��b��Տ��̒m����[�߁A�����̋Z�\�ɐ������Ăق����B�܂��A�u���U�w�K�v�ɐ^���Ɏ��g�ގp�����A���K�����͂��߂Ƃ�����w���Ɏ����Ăق����B ����@2010�N9��24�� |
| ����҂̖����t�s�S���Âɑ傫�Ȓn�捷 |
| �@���V���g����w��Ann M. O'Hare��������́u�z�X�s�X�ւ̎���⎀�S�O�̓��͒��~�Ȃǂ̏I�����P�A�ɂ��āC�����t�s�S�iESRD�j�̍���҂̎��Ó��e�ɂ͑傫�Ȓn�捷������v�Ƃ̌������ʂ�JAMA�i2010; 304: 180-186�j�ɔ��\�����B ���Ë��x�����n��ō��늳�� �@ESRD���҂̂Ȃ��ŁC����75�Έȏ�̊��҂��}���ɑ���������B����̒������͊��҂ւ̕��σ��f�B�P�A�x�����z�́C���ÊJ�n����1�N�Ԃ�10���h������B�����ESRD���҂ɑ�����ۂ̎��Ó��e����т��ꂪ�n��Ԃłǂ̒��x�قȂ邩�ɂ��Ă͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��B �@������O�fHare��������͎��Ë��x���قȂ鏔�n��ɂ킽��CESRD�늳���ƍ����ESRD���҂̏I�����P�A�ɂ��Ē��ׂ��B�����ł͑S��ESRD �o�^�̃f�[�^��p���C2005�N6��1���`06�N5��31���ɒ������͂��J�n�܂��͐t�ڐA����65�Έȏ��4��1,420��i���l�܂��̓A�t���J�n�č��l�j��ΏۂƂ����B�n��I�ȏI�����P�A�̋��x�́CDartmouth Atlas of Healthcare�̎w�W��p�����B �@���̌��ʁC���l�ł͎��Ë��x�������n��ق�ESRD�̜늳�����������Ƃ��������C���̌X���͍���҂ōł������ł������B �@����������́u�A�t���J�n�č��l�ł́C����ҁi�j����80�Έȏ�C������85�Έȏ�j�ɂ̂ݓ��l�̊֘A�������݂����B�I�����P�A�̋��x���ł������ܕ��ʂ̒n��ݏZ�҂ł͍ł��Ⴂ�ܕ��ʂ̒n��ݏZ�҂Ɣ�ׂāCESRD���ǑO�ɐt������ɂ�鎡�Â���m�����Ⴍ�i62.3����71.1���j�C�܂����t���͊J�n���Ɂi�O���t�g�܂��̓J�e�[�e���ɑ��āj�t�B�X�e���i���̓A�N�Z�X�̂��߂ɁC�ʏ�͑O�r�ŁC������Ö��ɐڑ�������V�����g��p�ɂ��쐻�j������m�����Ⴂ�i11.2����16.9���j�v�Əq�ׂĂ���B ���ғ����̍���ɂ�炸 �@�S�̓I�ɁCESRD���ǂ���2�N�ȓ��Ɋ��҂�51���i2��1,190��j�����S���C�I������Ô�ł��Ⴂ�ܕ��ʂ̒n���47.1������ł������ܕ��ʂ̒n���52.6���ɂ킽�����BO�fHare��������́u���S�O�ɓ��͂����~���ꂽ�����́C�I������Ô�ł��Ⴂ�ܕ��ʂ̒n��ݏZ�҂ł�44.3���C�ł������ܕ��ʂ̒n��ݏZ�҂ł�22.2���ł������B���S�O�Ƀz�X�s�X�P�A�������҂̊����́C�I������Ô�ł��Ⴂ�ܕ��ʂ�33.5���ɑ��ł������ܕ��ʂł�20.7���ŁC�@�����S�̊����͂��ꂼ��50.3���C67.8���ł������v�Əq�ׂĂ���B �@���̂悤�Ȍ����Ȏ��Â̒n�捷�́CESRD���ǎ��ɑ��肵�����ғ����̍���ł͐����ł��Ȃ������Ƃ��Ă���B �@����������́u�����ESRD���҂̃P�A�ɂ́CESRD���ǑO�Ǝ��S�O�̗����Ŗ��𖾂̑傫�Ȓn�捷������B����̌��ʂ���CESRD���ÂɊւ��Ă̓G�r�f���X�Ɛf�ÃK�C�h���C���Ɋ�Â�����I�Ōp���I�ȃC���t�H�[���h�E�R���Z���g�邱�Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃ��킩�����B���̂悤�ȓw�͂́C���͂̊J�n�ƒ��~���܂߂����Â̌��肪�n��I�Ȑf�ÃX�^�C���ł͂Ȃ��C���҂̈ӎv�Ɖ��l�ςɑ����čs��������Ɍ������̂ɖ𗧂��낤�v�ƌ��_���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N9��30�� |
| �������҂̒j���p�[�g�i�[�͂��a���X�N������ |
| �@�Ȃ�K�[���t�����h�������ɂȂ����j���́A���̒j���ɔ�ׂďd�ǂ̂��a����ѕs���œ��@����䗦����40���������Ƃ��A�f���}�[�N�̑�K�͌����Ŏ����ꂽ�B�����̊������ړI�ɒj���ɐS���w�I���������炷���Ƃ𗠕t������̂ł͂Ȃ����A�j�����Ȃ̏d�ĂȎ����⎀�ɒ��ʂ����ۂ̐��_�I��ɂɎア���Ƃ�[�I�Ɏ������_�ʼn��l�̂��錤���ł���ƁA���̕���ɏڂ����ă_�i�E�t�@�[�o�[Dana-Farber���������i�{�X�g���j���_-�����ɘa�P�A�Z���^�[����Holly G. Prigerson���͏q�ׂĂ���B �@����̌����́A1994�`2006�N�Ƀf���}�[�N�ɍݏZ���A�����ǂ��������p�[�g�i�[�i�Ȃ܂��͓�������K�[���t�����h�j�����j���Q��538�l��ǐՂ������́B �@���烌�x���Ȃǂ̈��q�ɂ��덷�̂Ȃ��悤���v�l��������A���̂悤�Ȓj���͑��̒j���ɔ�ׁA���a��s���Ȃǂ̋C����Q�œ��@����䗦��39���������Ƃ����������B���@���X�N�̓p�[�g�i�[�̓������ł��i�s���Ă���ꍇ�ɍ����������A���ۂ̓��@���͂Q��538�l��180�l�Ə��Ȃ����̂ł������B���̂ق��A�p�[�g�i�[�����S�����j���́A�p�[�g�i�[�������������čĔ����Ȃ������j���ɔ�ד��@�̔䗦��3.6�{�ł��邱�Ƃ��킩�����B �@�ă������A���E�X���[���E�P�^�����OMemorial Sloan-Kettering���Z���^�[�i�j���[���[�N�j��Wendy G. Lichtenthal���́u����̒m������A�j�����W���I�ȉ���p�[�g�i�[���������X�N�Ȃǂ̈��q�ɂ��X�g���X���Ă��邱�Ƃ��������v�Əq�ׂ�ƂƂ��ɁA�u�p�[�g�i�[��S�������ꍇ�́A��Ȑl���������ɂ݂ɉ����A�p�[�g�i�[�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�ɑ���^���A���X�̐����p�^�[���̕ω��ɂ��ꂵ�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ɛ������Ă���B �@Prigerson���́A�ق��ɂ��u��̓`���iemotional contagion�j�v�ƌĂ����q���֗^���Ă���Ǝw�E�B�����̍Ȃ̏���v�ɓ`�d�i�ł�ρj���Ă���\��������Əq�ׂĂ���B �@Lichtenthal���́A���̂悤�ȑ�K�͌����́A�Ƒ��ɏd�_��u�����P�A�̏d�v��������ɂ����_�ňӖ��̂�����́B�d�ǂ̂��a�ɂȂ郊�X�N�̓��ɍ����p�[�g�i�[�́A���Â��������A�ӔC���ߓx�ɕ������肷��\�������邽�߁A��Ã`�[���͊��҂̃p�[�g�i�[�ɂ��ڂ�z��K�v������v�Əq�ׂĂ���B NIKKEI NET �����������N�@2010�N10��7�� |
|
�Ƒ����҂̑��������҂ƌo�������L �x���҂ƉƑ��Ώۂ̎��I�����Ŗ��炩�� |
| �@�G�f�B���o����w�i�p�j��Scott A. Murray������́C�x���҂Ɗ��҂̉Ƒ����҂ւ̖ʒk�ɂ�鎿�I�����̌��ʁC�u���Ҏ��g�����łȂ��Ƒ����҂��܂��C������Ƒ��ł��銳�҂̌o����ڂ̓�����ɂ��C���̌o�������L���Ă��邱�Ƃ����������v�Ɣ��\�����B���̌��ʂ܂��C��������́u�I���������łȂ��C��삪�K�v�ƂȂ�S���Ԃɂ킽���ĉƑ����҂ɑ���x�����K�v�ł���v�Ǝ咣���Ă���B ���\�͂����Ȃ���P�[�X�� �@���҂��ł��[����Y���o������̂́C�i1�j����f�f���i2�j���Â��I���A����Ƃ��i3�j�Ĕ������������Ƃ��i4�j�I�����@�̎l�̎��_�ł��邱�Ƃ��������Ă���B �@����̌����ł́C���҂̉Ƒ����҂����l�ɁC���҂��o������K�������Y�̓T�^�I�ȃp�^�[�������Ɍo�����Ă���\�����������ꂽ�B �@Murray������́C�x����19��Ƃ��̉Ƒ�����19���ΏۂɁC�Œ���1�N�Ԃ܂��͊��҂����S����܂ł̊��Ԃɕ�����̖ʒk���s�����B�ʒk��3�J����1��̃y�[�X�ōs���C�ʎZ�Ŋ��ґΏۂ̂��̂�42��C���ґΏۂ̂��̂�46��s��ꂽ�B �@�����̖ʒk���e�͂������ʁC�����ĉ��҂͊��҂����ǍD�Ȍ��N��Ԃɂ��������C���҂ɂȂ�炩�̌��N��̖�肪����Ɖ��\�͂����Ȃ���ꍇ�����邱�Ƃ���������ɂȂ����B ���҂ɂ͐S���I�x�����K�v �@�܂��C���҂͉��̒��Ŕ��ʂāC���҂̎��������L���Ă���悤�Ɋ����邱�Ƃ����т��т��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B���ɁC���̂悤�Ȋ���͎��Ԃ��o�߂��C�������߂Â��ɂ�ċ��܂邱�Ƃ����������B �@��������́u���҂͊��҂Ɠ������C����̃W�F�b�g�R�[�X�^�[�ɏ���Ă���悤�Ɋ����Ă���C����̌o�߂ɂ��X�g���X��s�����s�[�N�ƂȂ�e���_�ő傫�Ȋ���̕������݂��o������v�Ɛ������Ă���B �@�����܂��C��������́u���҂��[����Y���o�������L�̎l�̎��_�ŁC���҂ɂ��S���I�E�o���I�x������ׂ��ł���v�ƌ��_�t���Ă���B�܂��C�u���鎞�_�ŃX�g���X����������C�������K�v�Ǝv�����肷�邱�Ƃ͕��ʂł���Ɖ��҂��������邱�Ƃ��C���g�̗͂ɂȂ邩������Ȃ��v�ƕt�������Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N10��21�� |
|
���r���O�E�E�B���̕��y�E��Ì���ւ̐Z���Ȃǂ�� ���J�ȁE�I������Â̂�������k��A���Ď��܂Ƃ� |
| �@10��28���A�����J���ȁE�I������Â̂�����Ɋւ��鍧�k��i�����F�����E��q��w�@�w�����ȋ����j�́A���Ă����܂Ƃ߁A���e�ɑ�ō��ӂ����B����A����̕ύX�E�⑫�A���ڗ��Ă̒����Ȃǂ��s���A�����J����b�ɒ�o����\��B�I������Â̂�����ɂ��ẮA1987�N�ȗ��A5�N���Ɓi����̂�7�N�j�A4���ɓn���Ĉ�ʍ����E��Õ����]���҂ւ̈ӎ������ƁA����Ɋ�Â��������d�˂��Ă����B����̕��́A2008�N3���Ɏ��{���������i�q�̐��F1��4402�l�j�܂��Ă܂Ƃ߂����́B �@�������ʂ��A���k��́A(1)�I������ÂɊւ��銳�ҁE�Ƒ��A��Õ����]���҂̏��i���̉����A(2)�ɘa�P�A��ł����̊g��A�ɘa�P�A�Ɋւ���Õ����]���҂ɂ����鐳�����m���̕��y�A�u�ɘa�P�A�������}���邱�Ɓv�Ƃ̃C���[�W�̕��@�Ǝ��ÁE�ɘa�P�A�����s�ōs���u�p�������P�A�v�̐Z���A(3)���r���O�E�E�B���ƏI�����̂���������肷��ۂ̃v���Z�X�̏[���A(4)�Ƒ��P�A�E�O���[�t�P�A�̋c�_���i�A(5)���҂��ӎv��\���ł��Ȃ��A�܂��͔��f�ł��Ȃ��Ȃ����ɂ����锻�f��s�ғ��̂�����̌�����A�����̏I������Âɑ���S�̌���A�Ȃǂ̕K�v����B�����܂Ƃߌ���A�I������Â̂�����ɂ��Ĉ��������������s���A���ǂ��I������Â��������邽�߂̋�̓I�ȕ������̒���������悤�v�]�����B �@�������ʂ���́A�ȉ��̂悤�ȌX�������炩�ɂȂ����B �@ �I������Âɑ���S�͍����i80-96���j���A�������Âɂ��ĉƑ��Řb�����������Ƃ�����l�͔������x�i48-68���j�ł���A�\���ɘb�����������Ƃ�����l�͏��Ȃ��i3-7���j �A �������Âɂ��ĉƑ��Ƙb�����������Ă���l�̕����A�������Âɑ��ď��ɓI�ȌX���������� �B ���r���O�E�E�B���i���ʂɂ�鐶�O�̈ӎv�\���j�̖@�����ɂ��āA��ʍ����͖@�����ɔے�I�Ȉӌ���6���������A��t�E�Ō�E���͈ӌ������Ă��� �C �������ÂɊւ��āA51-67���̐l����t�Ɗ��҂̊Ԃŏ\���Șb���������s���Ă��Ȃ��ƍl���Ă��� �D ��Õ����]���҂̊ԂŁA�I������Ԃ̒�`�≄����Â̕s�J�n�A���~���Ɋւ���ꗥ�Ȕ��f��ɂ��ẮA�u�ڍׂȊ�����ׂ��v�Ƃ̈ӌ��Ɓu�ꗥ�Ȋ�ł͂Ȃ���ÁE�P�A�`�[�����\���Ɍ������ĕ��j�����肷��悢�v�Ƃ̈ӌ��œ��Ă��� �E �uWHO�������u�Ɏ��Ö@�v�ɂ��Ă悭�m���Ă����Õ����]���҂͏��Ȃ��i20-31���j�A�O���ɔ�ׂĂ�⌸�����Ă��� �@��c�̖`���A��J�וv�E�㐭�ǒ��́A�u�I������Âɂ��ẮA�����̊S�������A�l�̉��l�ς����l�����Ă���B�e�ՂɌ��_�邱�Ƃ̂ł��Ȃ������������A���J�ȂƂ��ẮA�d�v�Ȗ��Ƒ����A������I�����̂�����ɂ��āA�����̈ӎ��������s���Ȃ��猟�����d�˂Ă��������v�ƈ��A�B�r�㒼�ȁE�c��`�m��w��w����Ð���E�Ǘ��w���������́A�����u������ÂɊւ����ʎs���̈ӎ��ƈ⑰�̕]���v���o���A������ÂɊւ��A�a�@�Ŏ��S�������҂̈⑰�����̌��ʂƁA���n��ɂ������ʏZ���̈ӎ������̔�r���Љ�B�u��ʏZ�������҂̈⑰���A�Ƒ��̉�����Â̈ӌ���m���Ă����̂͑S�̂̔����ȉ��B������Âɂ��Ă͈⑰�̕����m��I�ł���A��t���ӌ����ƕ]�����銄�������������v�Ƃ��āA�u������Âɂ��Č�������ۂɂ́A��ʍ��������Ȃ��A�⑰�̑̌������Ƃ��d�v�v�Ǝw�E�����B �@����͗Y�E������w��w�@�@�w�����w�����ȋ����́A�u�I�����ɂ́A��G�c�ɕ����āA�~�}��Â̂悤�ɒZ���Ԃ̂��́A���Ȃǔ�r�I�����ɓn����́A����ɂ�鎾�a�Ȃǒ����ɓn����́A�Ƃ���3�敪������B���ꂼ��ɂ��Čʂ̋c�_���s���ƂƂ��ɁA���{��t�����{�~�}��w��E���{���w��E���{�V�N�a�w��ȂǁA�֘A����w��̃K�C�h���C�����r�������Ă͂ǂ����B�܂��A�ɘa�P�A�̏[���x�̎��Ԃ�A���i���̉����ɂ����ĕK�v�Ƃ���Ă�����̎�ށE�ʁA�O���[�t�P�A�̎���A�܂����r���O�E�E�B���ɂ��āA���ݎ��ۂɊ��҂ɋL�q���Ă�����Ă���a�@���ǂꂭ�炢����A�ǂ̂悤�Ȗ�肪���邩�A�ǂ̂悤�Ȍ`�Ŋ��p����Ă��邩�E���Ȃ����ȂǁA����ɂ������̓I����Ȃǂ����W���A�����ǂȂǂŋc�_��[�߂邱�Ƃ��]�܂����v�Ɨv�]�����B �@���̂ق��A�u�I������ÂɊւ�����i���̉����͏d�v�����A����ŁA��ÁE�Z�p�̍��x���E��剻�ɂ����i���̊g��͕K�R�B���ׂĂ̔��f�����Җ{�l�E�Ƒ��̑I���E����Ɉς˂��A���������悤�ɂȂ�ƁA���Ɋ�@�I�ɂ��銳�ҁE�Ƒ��ɁA�ߑ�ȕ��S�ɂȂ�͂��Ȃ����Ɗ뜜�����B���ނ̐\���E�葱���Ȃǂ����ł��c��Ȏ�ԂɂȂ邾�낤�v�i�ɓ����Ă��E���{��a�E���a�c�̋��c���\�j�A�u��������"�I����"�Ƃ������t�͓K�Ȃ̂��B�I�������Ȃ���������l�A��Q����������A����Ԃł����Ă����ɐ����Ă���l�͂��āA"�I����"�Ƃ������m�Ȏ��Ԃ�����킯�ł͂Ȃ��v�i�쓇�F��Y�E��䉝�f�N���j�b�N�@���j�A�Ȃǂ̈ӌ���������B m3.com�@2010�N10��28�� |
| �ɘa�P�A�l�ς��@�I�ׂ�H���A�A�Q�E�N�����Ԃ����R |
| �ɘa�P�A�l�ς��@�I�ׂ�H���A�A�Q�E�N�����Ԃ����R (1) �@�Ŏ�����ẪC���[�W�������ɘa�P�A���l�ς�肵�Ă���B�����P�W���ɃI�[�v���������{�̘a��s���a�@�E�ɘa�P�A�a���́u����Ɠ������҂���Ƀ����b�N�X���Ă��炤�������邱�Ƃ������v�ƁA�̒��ɂ���đI�ׂ鑽�l�ȐH����p�ӁB�N���E�A�Q���ԁA�Ƒ��̏o��������R�����A�y�b�g�̖ʉ���������Ă���Ƃ����B ����������l�b�g�� �@�ɘa�P�A�a���͋�a���̂Q�t���A�����z���A�P�U���ɂQ�Q�x�b�h��z�u�B�a�@�̃��j�z�[����W���s���N�F�ɐV�����A�e�������ԍ��ł͂Ȃ��Ԍ��t�ŋ�ʂ����B���������p�ӂ��A���C�͉Ƒ��Ɠ����悤�ɉƒ땗�C�ɋ߂��A�����������f�U�C�����B�C���^�[�l�b�g�����p�ł�����{������k�b���Ȃǂ��݂����B �@���Ɂu�H�ׂ邱�Ƃ�������͂ɂȂ�v�ƕa�@�H�ɗ͂����Ă���B�u�ɘa�P�A���ʐH�v�Ƃ��đ��a���̐H���ɔ�ׁA�e�i�����ʂɂ������ɁA�D���Ȃ��̂������ł��H�ׂ���悤�i����{�ɑ��₵���B���҂��H�ނ���������Œ������ł���B�u���Âɔ�ꂽ�Ƃ��ɐS�g�̏�Ԃ𐮂��Ă��炤���߁A���i�̐����ɋ߂Â���悤�S�����Ă���v�ƊŌ�t���̐�������݂���B���������A�C�f�A�ɂ͊��҂ւ̃A���P�[�g�����f����Ă���Ƃ����B �@�������͊Ŏ��Ƃ͂قږ������������Y�t�B�Y�Ȃő����̉Ƒ��Ɛڂ����l������̗ǂ��������A�u���҂����Ƒ��̋C�������ق����Ăق����v�ƕa�@���痊�܂ꂽ�Ƃ����B �@���a���ł͍R����܂̕���p�Ŗ��o���ς������A�オ���тꂽ�肷��ȂǐH�������ɂ����Ȃ������Ҍ����ɁA�������N���ڂ𗁂тĂ���u�P���H�i���w�Ö@�H�j�v��p�ӂ����B���҂ւ̃A���P�[�g����I�����Ă���c�q�A�T�C�_�[�A�݂��ȂǏ\����ނ�B���҂̑̒��ω��ɍ��킹���A���߂ׂ̍����T�[�r�X���s���Ă���B �ɘa�P�A�l�ς��@�I�ׂ�H���A�A�Q�E�N�����Ԃ����R (2) ���s����菜�� �@���������������҂��L���ɐ��������߂ɂ́u�Ǐ�R���g���[����_�I�ȕs������菜�����Ƃ��K�v�v�i���������E���a�@����Z���^�[���j�Ƃ��āA�R����܂Ȃǂ̕���p��ɘa�P�A�ɒʂ�����t��Ō�t�A�\�[�V�������[�J�[�炪�펞���k�ɂ������Ă���B �@���V����w��w���t�����V����@�̎R�����q�E���ÃZ���^�[�Ō�t���́u�ɘa�P�A�́A����̎��Â̐������ɐ��Ƃ���������ĕs������菜���Ƃ��납��n�܂�B�������A�Ƃ�����Ί��҂���͓��ɕ��������Ă��܂������ŁA�P�A������ɂ��Ă��܂��P�[�X������B�P�A�������Ǝv�킹�镵�͋C�Â���͏d�v���v�Ǝw�E����B �@���Ҏx���c�́u����Ƌ��ɐ������v�i���s�k��j�̕l�{���I����́u���҂̍s���𐧌����Ȃ��̂́A�Ǐ�R���g���[���Ɗ��҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����\�͂Ɏ��M������Ƃ������ƁB��Ɋ��҂̕��������Ă���Ă���Ƃ������S����������v�ƕ]�����Ă���B MSN�Y�o�j���[�X�@2010�N10��31�� |
| ���������p�𑗂肽���@�Ō�̑����A�Ƒ����₷�@���ρA�h���X���̐l�炵�� |
| �@�S���Ȃ����l�̊�Ɏ{���u���ɉ��ρv��A�̂ɒ����鑕���ȂǁA�a�@��V�Ǝ҂��S���Ă����̐l�́u�������v�̐g�x�x�ɁA�Ƒ����������悤�ɂȂ��Ă����B�O�������̐l�炵��������v���Z�X�ɉƑ����Q������A�̐l�̑�������邾���łȂ��A�Ƒ���������e���鏕���ɂ��Ȃ�悤���B �@��̗p�̉��ϕi�Ȃǂ��J���A�̔�����u�f�h�i�������j�v�i�R�������֎s�j�̏��@���i�����́E�ނ˂̂�j�В��i�S�R�j�́A�P�X�X�V�N�ɕ�����������ő��E�����̂����������ɍ��̓��ɓ������B �@����������Ƃɔ��ŋA���đΖʂ������̈�̂́A�����Ђ����ڗ����A�������Ȑ��O�̖ʉe�͂Ȃ������B�����ɂ��A�Ȃ��l�܂����@����͂ݏo���@�т��̂�����ƁB���̎��������̂ɉ��N�����������B �@��̂̃P�A�̑����Ɋ�������삳��́A���i�J���ɉ����A�Ō�t�����u�K����Q�O�O�V�N���瓌���A���s�𒆐S�ɊJ�ÁB�ǂ�������͂����ɖ��܂�u�������߂��Î҂͑����v�Ɗ�����B �@�]���A�����̕a�@�ł͊��҂��S���Ȃ�ƉƑ��͕a������o����A�Ō�t�����㏈�u�������B�g�����ϕi�͊Ō�t���������s�p�i���قƂ�ǁB �@�����s�̑���ؗѓ��a�@�ɘa�P�A�a���ɂO�U�N����Ζ�����]���֔��i�������E���݁j�Ō�t���i�S�X�j�́A�ȑO�̋Ζ���Ōo����������Ȍ�����ɋ^��������Ă����B�������f�h�̍u�K��Ŋw�m�������ƂɁA�Ƒ������㏈�u�ɎQ�����ʂ�̎��Ԃ����Ă�悤�A�a�@�̎d�g�݂𐮂����B �@�R�N�O�A���a�@�ł���ŖS���Ȃ��������T�O�̏����̐e���́A�a�@�̕��C�Ŗ�P���Ԃ����ď����̑̂����ꂢ�ɂ��A�Ō�t��ƈꏏ�ɉ��ς��{�����B�Q�̑������u�������Ɠ����߂ɂ���v�Ƃ����݁A�����낢�̃}�j�L���A�������B�����Ȃ���قُސe���̊���]������͊o���Ă���B���́A�Ƒ��̂W�������㏈�u�ɎQ������B�u�ߒQ�̃P�A�ɂȂ�Ƃ�������������v�ƍ]������B �@�ω��́u���ɑ����v�ɂ��y��ł���B�I�[�K���W�[�Ȃǂӂ���_�炩���f�ނō�����h���X���̑������u�����炳����v�̃u�����h�łO�V�N����̔����镟���s�̒����q�i�Ȃ��́E�܂����j����i�S�U�j�B�ޏ������̎����]�@�ɂȂ����B �@�������p�̌̐l�����������P�O�̖����u�����݂����v�ƕ|����A�u�Ŋ��̎p�͐g���̐S�ɍ��܂��v�Ǝ����B���ӂȃf�U�C�������A��������������낤�ƌ��ӂ����B�����͌��ɖ�V�O���B�����N��������e�⎩�����g�̂��߂Ɂu���̂Ƃ������Ă��Q�ĂȂ��悤�Ɂv�Ɨ��ޗႪ�����Ƃ����B �@�u�P�A�Ƃ��Ă̎����ρv���O�S�N�ɒ����A��Î҂�����̉��ςɒ��ڂ��邫�����������������Ō�t�̏��ь��b�i���₵�E�݂��j����i�S�X�j�́u���x�������͒N��������Ŏ�i�݂Ɓj�肩��ڂ�w�������A�ߔN�͐g�߂Ȏ������玩���̖��Ƃ��čl����悤�ɂȂ����B���㏈�u�̌���𑽂��̐l�ɒm���Ăق������A�������ǂ����������Ƒ��ɓ`���Ă����̂��厖�ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă���B m3.com�@2010�N11��2�� |
|
�I�������u�ɕۗL���C���S2�N�O����o����3�J���O�ł���ɑ��� �āE�R�z�[�g���� |
| �@�J���t�H���j�A��w��Alexander K. Smith����́C�č����̍ݐE���E�ސE���E������̌��N�ƖL����������Health
and Retirement Study�iHRS�j�̎��S��̃f�[�^����C���S����2�N�O�ɂ��u�ɂ������C���S3�J���O�����u�ɕۗL���͑������邱�Ƃ�����B �N��w���u�ɏo�����ς�� �@�������߂��l�ł́CQOL�̊ϓ_�����u�ɊǗ��ɓI���i�������Âɏd�_���u�����悤�ɂȂ�B�������CSmith����ɂ��ƁC���ۂ��u�ɊǗ��͎��S����Ō�̔N�܂Ō��߂����ꂪ���ł���Ƃ����B �@������́C�������߂��l���u�ɕۗL�������邽�߁C1994�`2006�N��HRS�ɓo�^���ꂽ��ʏZ���̂����C�����Ώo�����钆���x�ȏ���u�ɕۗL���̑Ζʎ������L�^������4,703��̍���Ҏ��S�f�[�^�T���v���i���ϔN��75.7�C���F�l��83.1���C�j��52.3���j��p�����B�Ȃ��C�I�����f�f�́C����i27.6���j�C�S�����i29.7���j�C����i11.8���j�C�ˑR���i16.7���j�C���̑��i14.2���j�ł������B �@�N��C���C�l��Ȃǂ̈��q�ŕ��������u�ɕۗL���́C���S��24�J���O�̎��_��26���ł���C�ȍ~�C4�J���O�܂ŕω��͌����Ȃ������i28���j�B�������C3�`1�J���O�ɂȂ�ƁC4�J���O�ɔ�ׂ��u�ɕۗL�����L�ӂɑ������Ă��邱�Ƃ��킩�����i46���j�B �@����������C66�Έȏ�̏ꍇ�C10�Α������Ƃ��u�ɕۗL�����ቺ���邱�Ƃ������Ă���B����24�J���O�C65�Έȉ��ł�39���Ɍ���ꂽ�u�ɂ��C86�Έȏ�ł�23���ł���C���̌X���������Ɍ���Ă����͎̂���1�J���O�ł������i60�� vs. 42���j�B �@����1�J���O�ɂ������u�ɕۗL���́C�߉����60���C��߉����26���ɂ��ꂼ��F�߂��C���҂��ׂ�Ɗ߉�����u�ɕۗL�����L�ӂɍ����������Ƃ���C�߉����u�ɕۗL���Ƃ̋������ւ����炩�ɂȂ����B����C�I�����f�f�ɂ����邻�ꂼ����u�ɕۗL���k����i45���j�C�S�����i48���j�C����i50���j�C�ˑR���i42���j���̑��i47%�j�l�ɂ͍��͌����Ȃ������B �@�I�����ɂ������u�ɂ�QOL�̒ቺ�ɑ傫���e�����邱�Ƃ��w�E����Ă���BSmith����́C�u�ɂ͎��S����2�N�O����F�߂��邽�߁C�����������҂ɂ����Ă��I�������҂Ɠ����悤���u�ɊǗ��ɖڂ�������ׂ����Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N11��5�� |
| �y�b�g�Ŗ��₵�A�z�X�s�X�ɘa�P�A�L���� |
| �@��������Ȃǂ̊��҂��P�A����u�z�X�s�X�E�ɘa�P�A�a���v�ŁA�y�b�g�̎������݂�������a�@���S���I�ɑ����Ă���B����܂ŕa�@�ł́A�����ǂ̋��ꂪ����Ƃ���A�y�b�g�͂��@�x���������A���_�I�Ȗ��₵��X�g���X��a�炰���w�I�Ȍ��ʂ̑傫���ɒ��ځB�ɘa�P�A�ł͊��҂₻�̉Ƒ����T�i���j��ԂɊׂ邱�Ƃ�����A���҂�͂Â���g�Ƒ��h�Ƃ��Ă̖������y�b�g���S���Ă���B �@�x�m�R����]�ł���R���������s�̋ʕ�ӂꂠ���f�Ï��B�Y��Ȏ��R�̂��Ƃŗ×{�����𑗂肽���Ƒ���ޗǂȂǂ�������҂����Ă���B �@�U�O��̕v�Ȃ͖�S�J���ԁA�����̃`�����ƈꏏ�ɕa���ŗ×{�����𑗂����B �@�ӂ����炵�̕v�Ȃ��`�������Ƒ��Ɍ}��������ɍȂ̕a�C�����������B�v�i�U�R�j�́u�a�@�Ƀy�b�g�Ȃ�ă_�����Ǝv������A�����Ƃ����̂ŋ������B�Ȃ�����ŖS���Ȃ�Ŋ��܂ŋC���������肵���Ǝv���܂��v�ƌ��B �@���a�S�W�N�A���I�Ƀz�X�s�X���J�Ƃ�������L���X�g���a�@�i���s�j�ł͓���������̗����������Ă����B�z�X�s�X�͓Ɨ����łȂ����߁A�������y�b�g�̓P�[�W�ɓ���Ď������݁A�傫�ȃy�b�g�͌��ւł̖ʉ�Ƃ��Ă���B�z�X�s�X���a�@�u�s�[�X�n�E�X�a�@�v�i�_�ސ쌧�j�ł́A�����̋��Ȋ��҂ɔz�����Č��������͗��p�ł��Ȃ����A��^���Ȃǂ��e�������ʂ����둤�̃h�A����o����ł���悤�H�v����B �@�܂��挎�P�W���ɃI�[�v���������{�a��s���a�@�̊ɘa�P�A�a���ł��y�b�g�̖ʉ���������Ă���Ƃ����B���a�@����Z���^�[���̕���������t�́u���������a���������銳�҂�Ƒ��̋C�������ǂ��ɘa����̂�����Î҂̏d�v�Ȏd���v�Ƃ��Ă���B �@�����������ۂ̓y�b�g�̎���l�����������Ă���̂����R�����A�y�b�g�̈�w�I���p�ɂ����ڂ���Ă���B �@���҂͕a�C�̐i�s�ɔ����A�ӎ������⌶�o�Ȃǐ��_�Ǐ���u����ρv���N����B�\�h�ɂ͕a��������̊��ɋ߂���Ԃ����邱�Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ��ŋ߂̌����Ŗ��炩�ɂȂ�A�ɘa�P�A�ł̃y�b�g�̈ʒu�Â�������ɏd�v�ɂȂ��Ă���B �@����������x�ȚM���i�قɂイ�j�ނƂ̐G�ꍇ���͐l�Ԃɓ��݂���X�g���X���y����������ʂ��l�����A��Â̕⏕���ÂƂ��ċߔN���E�ŗp�����Ă���B �@���̂��߂X���Ɋɘa�P�A�a���z�I�[�v�������a�̎R���c�ӎs�̓�a�̎R��ÃZ���^�[�ł́A����܂ł̃y�b�g�̖ʉ�ɉ����A�߂��A�j�}���Z���s�[�����{����\�肾�B �@���҂�Ƒ��̐��_�I�P�A����ɂ����ʈ�ȑ�̑吼�G�������i���_��ᇉȁj�́u�l�Ԃ͌܊����h������Ɛ��_�I�Ɉ��肷��B����̓��a�́A�Ƒ��̐��_�I���S���傫���T�a�Ȃǂ̐f�f�������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���҂����₩�ɉ߂�����A���̉Ƒ��̐��_�I�P�A�ɂƂ��Ă����ʂ͑傫���A�y�b�g�̎������݂ɂ͑傫�ȈӖ�������B������y�b�g�ɗ����̂���a�@�͑����邾�낤�v�Ƙb���Ă���B MSN�Y�o�j���[�X�@2010�N11��6�� |
| �ӎv�\���s�\���҂̑㗝�l�̑����͎��g�ŏI�����̌������] |
| �@�ӎv�\���s�\�܂��͊�ď�Ԃ̊��҂̑㗝�ӎv����҂̔����ȏ�́A�����ێ��̑I���������ōs�������ƍl���Ă���A��t�Ƌ��L������A�C���邱�Ƃ���]���Ȃ����Ƃ��A�V���������Ŗ��炩�ɂ��ꂽ�B �@�ăs�b�c�o�[�O��w�i�y���V���x�j�A�B�j�y�����ŁA�d�ǎ����ɂ�����ϗ��E�ӎv����v���O�����ӔC�҂�Douglas B. White���m��ɂ�鍡��̌����́A���@���̎��S�m������50���ŁA�l�H�ċz��Ɉˑ�����ӎv�\���s�\�̐��l���҂̑㗝�ӎv�����230�l��ΏۂƂ������́B�ӎv����҂́A�ň��̐l�̎��ÂɊւ��āA���Ò��̍R�������̑I���ƁA�g�̖]�݂��Ȃ��h�ꍇ�ɐ����ێ����Â𒆎~���邩�ǂ����Ƃ���2�̉���̏ɂ��ċL�������B �@�����̌��ʁA�ӎv����҂�55�����A���Ò��̐����ێ����Â̒��~�⒆�~�����Ȃǁg���l��t�^���ꂽ�ivalue-laden�j�h����������ōs�������ƍl���Ă����B����40���͂��̂悤�Ȍ������t�Ƌ��L�������ƍl���A5���݈̂�t�ɑS�ӔC���Ăق����ƍl���Ă����B �@�܂��A�ň��̐l�̎��Â��ē����t�ւ̐M���́A�ӎv����҂������ێ��Ɋւ��錈��������ōs�������x�����ɉe�����y�ڂ��L�ӂȈ��q�ł���A�܂��j����J�g���b�N���k�͈ӎv����̌��������낤�Ƃ��Ȃ����Ƃ����������B�������ʂ́A��w���uAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine�i�ċz��E�N���e�B�J���P�A��w�j�v�I�����C���ł�10��29���f�ڂ��ꂽ�B �@White���́u����́̕A����܂ōl�����Ă������������̑㗝�l��ICU�i�W�����Î��j�ɂ����錈�茠���R���g���[���������ƍl���Ă��邱�Ƃ��������Ă���B���̌��ʂ́A�㗝�l�ƈӌ������L�����t�Ƃ����̌���ɍŏI�I����������t�Ƃ���ʂ���K�v���������Ă���v�Əq�ׂĂ���B ���N���eEXPO�@2010�N11��7�� |
| �m���̂���n�@�ƂŊŎ��A�������ʎx�� �����V�@�����q����i�m���t�B�N�V������Ɓj |
| �@���ҁE�Ƒ��̗��ꂩ���Â���T�[�r�X�͂ǂ������Ăق������B�P�S�N�Ԃ̉��̖��A�v���Ŏ�(�݂�)�����̌������m���t�B�N�V������Ƃ̍����V�����q����ɕ������B�i������E���F���q�j �@�\�\��N�o�ł��ꂽ�u���߂�ˁA�ڂ����a�C�ɂȂ��āv�ł́A�p�[�L���\���a�������A�R�N�O�ɂV�V�ŖS���Ȃ����v�̊Ŏ��̌���ԗ��X�ɂÂ����B���a�����͂ǂ����������B �@�u�V���L�҂������v����N���}���A�������ꂩ��Ƃ������ɔ��ǂ��A�P�O�N��ɂ͎Ԃ����ɂȂ����B�P�R�N�ڂɒ��˂�]�ŋً}���@�������́A�Ђǂ������������A�@�������Ŏ��ɂ������B���̌�A�ƂɘA��A�肽���ƌ����ƈ݂Ɍ����J���ǂ���h�{�𒍂��w�݂낤�x�ɂ���A���Ă悢�ƌ����A��P�N�ԁA�v���T�̕v����삵���B�ƂōŊ��܂ŊŎ�낤�Ɖ��z�܂ł����̂ɁA�I�������}����Ɠ��@�����߂��A���ǂ��̂܂ܕa�@�Ő������B�x���Ă������E�����Ȃ���ΉƂł̊Ŏ��͎����ł��Ȃ��v �@�\�\��Â��Ċ��������Ƃ́B �@�u�ʂ̈�t�̈ӌ������߂��猙�Ȋ�������ȂLj�t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɔY�B�l�Ԃ�f��Ƃ��������O�ꂵ�Ăق����B��t���m�̘A�g���s�\���B���@����ƍݑ��Ƃ̉�����A���҂��A�g���Ċ��҂�f��Ƃ������z���Ȃ��B�ȑO�A��ނŖK�ꂽ�I�����_�ł́A�ݑ�オ�a�@�̈�t�ƑΓ��ȗ���Őf�Â��Ă����̂���ۓI�������v �@�\�\���҂̂p�n�k�i�����̎��j�ɂ��Ă͂ǂ����B �@�u���@���A�����ł��@�\���ێ��������ƁA�{�l���ق��������R�[�q�[���ЂƂ������܂�����A���Ȃ̈�t�Ɍ�����A����ċC�ǂɓ�������ǂ�����̂��ƂЂǂ�������ꂽ�B�ł��A�މ@���Ă�����o(��������)���n�r���ŁA���z������ő��t(������)���o���A���t���̂ݍ��ތP���������v�͑�D���Ȃ�����ׂ���H�ׂ邱�Ƃ��ł����B�����̎��Ƃ͂����������Ƃ��Ǝv���B�i�׃��X�N����������Ɉ�ÊW�҂̑�ς��͂킩�邪�A���ҁE�Ƒ��Ƌ��͂��āA������͂������o����Â����Ăق����v �@�\�\���ɑ��ẮB �@�u�����g�A����̋^��������ƌ���ꂽ���A�₦������̋z�����K�v�ŁA�݂낤��l�H���(��������)�������a�l������Č����ɍs���ɂ��Ȃ������B���Ƒ��ւ̎x���̓[���ɓ������B�ݑ�ł̖�Ԃ̉��̐����[�������A���E�ɂ͈��̈�Ís�ׂ�F�߂�ׂ����v �@�\�\�ق��̉ۑ�ɂ��āB �@�u�V��̏Z�܂��ւ̕s���������̂ɁA���{�̏Z���͎����w�͂���{�B�w�Ŋ��܂ōݑ�Łx�ƌ����̂Ȃ�A����ň��S�ɉ߂����邽�߂̉��C�x����A�ǎ��Ŏ荠�ȍ���Ҍ������ݏZ��𑝂₷���Ƃ��]�܂��v YOMIURI ONLINE�����������K�����@2010�N11��10�� |
| �ݑ�͉��҂�QOL����^���w���X�ɍD�e�� |
| �@�n�[�o�[�h��w��Alexi A. Wright���m��́C�������߂Â��Ă��邪�҂Ƃ��̉��҂�ΏۂƂ������������{�������ʁC�u�z�X�s�X�P�A���Ȃ��玩��Ŏ����}�������҂Ɣ�ׂĕa�@��W�����Î��iICU�j�Ŏ����}�������҂ł́C�I������QOL���Ⴍ�C����ɉ��҂̔ߒQ���ɐ��_�����ǂ��郊�X�N�����������v��Journal of Clinical Oncology�i2010; �I�����C���Łj�ɔ��\�����B �I�����̈�Ó��e���傫���e�� �@Wright���m�́u�ǂ��Ŏ����}���邩�́C���Җ{�l�����łȂ��Ō삷��Ƒ��ɂƂ��Ă��傫�Ȗ��ł���B����̒m���́C�a�@���̒ጸ���邢�̓z�X�s�X���p�̑�����ړI�Ƃ���������C�������߂����҂�QOL���P�ɖ𗧂���C���ʌ�ɉ��҂����_�����ǂ��郊�X�N��ቺ������\�������邱�Ƃ��������Ă���v�Əq�ׂĂ���B �@�����m��́C�i�s����342��Ƃ��̉��҂�ΏۂɁC��K�͌����gCoping with Cancer�h�̈ꕔ�Ƃ��đO�������������{�B�o�^�����玀�S���܂Ŋ��҂�ǐՒ��������i�ǐՊ��Ԃ̒����l��4.5�J���j�B�����m��͎��S�O2�T�Ԉȓ��̏I�����ɂ����銳�҂�QOL��]������Ɠ����ɁC���̎����ւ̓o�^���Ɗ��҂̎��S��6�J�����_�ł̉��҂̃����^���w���X��]�������B �@���̌��ʁC�I�����߂��Ɋ��҂�����Â̓��e�����҂ɂƂ��Ă����҂ɂƂ��Ă��ɂ߂ďd�v�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����BICU��a�@�Ŏ����}�������҂ł͎���Ńz�X�s�X�P�A���Ď����}�������҂Ɣ�ׂĐg�̓I��ɂƐ��_�I��ɂ��傫���CQOL���Ⴉ�����B�܂��C����Ńz�X�s�X�P�A���Ď����}�������҂̉��҂Ɣ�ׂ�ICU�Ŏ����}�������҂̉��҂ł́C�S�I�O����X�g���X��Q�iPTSD�j���ǃ��X�N��5�{���������B �@�����m�́u���҂̍Ŋ����ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������́C���҂̎���C���҂��ǂ̂悤�ɐ�����̂��Ƃ������Ƃɑ傫�ȉe�����y�ڂ��B����̌�������C���҂������}����ꏊ�ƏI�����̈�ẤC���҂̎��ʑ̌��ɉe�����邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B���҂������}����ꏊ�ɂ���Ċ��҂�QOL�ɍ���������Ƃ͗\�z���Ă������C�ߒQ�̉ߒ��ɂ����ĉ��҂̃����^���w���X�ɂ���قǂ̍����F�߂�ꂽ���Ƃɋ����Ă���v�Əq�ׂĂ���B �@�܂��C�u���ʌ�̉��҂̐��_��w�I�Տ��Ǐ�ɂ��Ē��ׂ������͂ق��ɂ��������邪�C����̌����ł͊��҂̎��S�O��̗����ʼn��҂�ǐՒ��������B���̌����́C���҂������}����ꏊ�ɂ���ĉ��҂����_�����ǂ��郊�X�N���قȂ邱�Ƃm�Ɏ��������߂Ă̌������v�Ɛ������Ă���B ���҂ō������_��Q���ǃ��X�N �@Wright���m��́CICU��a�@�Ŏ����}�������҂̉��҂̂���21.1���i19�l��4�l�j��PTSD�ǂ�������C����Ńz�X�s�X�P�A���Ď����}�������҂̉��҂ł�4.4���i137�l��6�l�j�ł��������Ƃ𖾂炩�ɂ����B���l�ɁC�a�@��ICU�Ŏ����}�������҂̉��҂�21.6���i37�l��8�l�j�ł͉�������ɕt���Ȃ��Ȃ�悤�ȋ����ߒQ�������ԑ����i�J�����ߒQ��Q�j����C����Ńz�X�s�X�P�A���Ď����}�������҂̉��҂ł�5.2���i77�l��4�l�j�������B �@�����m��́C���ҁE���ҁE��t�Ԃł̏I�����ɂ��Ă̘b�������̑����⊳�ҋ���̉��P�Ȃǂ�ʂ��āC�a�@�Ŏ����}���邱�Ƃ�I�����邪�҂����������镡���̕��@�𐄏����Ă���B �@�����m��́u�������߂Â����Ŏ������鎡�Â̋��x��������QOL�⎩���̎���Ɉ�����l�̐��_��Ԃɉe�����y�ڂ����Ƃ��������Ă����Ȃ�C���҂͎��O�ɔz��҂��t�ȂǂɊ�]��`����Ȃǂ̎�i���\�ɂȂ�C���v�Ȏ��Â��s�킸�ɍςނ��낤�v�Əq�ׂĂ���B �@�����m��́C���҂������̗\������S�ɗ������Ă��邩�ۂ��Ȃǂ̊��҂ƈ�t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V������ӎv����Ɋւ����肨��ю�ᇈ�Ƃ��҂����w�Ö@�Ȃǂ̎��Â̒��~���l����ۂɉ����e������̂��ɂ��Č������v�悵�Ă���B �@�u�i�s���҂̖�70���������̗\��ɂ��Ēm�肽���ƍl���Ă��邪�C�����̎�����m���Ă���ƕ��閖�����҂�3����1�ɂ����Ȃ��B���҂������̗\��⍡��̎��Â��t�����錩���݂ɂ��Ēm�炳��Ă����Ȃ�C���҂��قȂ����I�������邩�ۂ��C�܂���w�I�]�A���قȂ������̂ɂȂ邩�ۂ��ɂ��ĉ𖾂������ƍl���Ă���v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2010�N11��11�� |
|
�}��v������{�̍���ҏI�����P�A�̐��̉��v �p���ɘa�P�A���c��E�I�����P�A�Z�~�i�[�ɎQ������ �����P�v�i���Ƃ����ȕ��ؒʂ�f�Ï��j |
| �@�M�҂�2010�N10��26���C�p���ɘa�P�A���c��iNational Council for Palliative Care�GNCPC�j�̎�ÁC�p���R�~���j�e�B�P�A����C�p���P�A�t�H�[�����̋��Â̂��ƁC�����h���ŊJ�Â��ꂽ����҉��{�݂ɂ�����I�����P�A�Z�~�i�["My Home, My Care, End of life care in care homes"�ɎQ�������B�ߔN�C����̐f�Ì���ő������鍂��҃P�A�̉ۑ�����̒[����T�邱�ƂƁC����܂��܂��������钴����҂̏I�����P�A�̑̐����w�Ԃ��Ƃ��ړI�ł���B �@�p���ł͋ߔN�l���������X���ɓ]����ƂƂ��ɁC�a�@�ł̎��S���������n�߂Ă���B�����č���C���{�ݓ����҂͑���������̂́C�����ɂ�����Ŏ��͌����������邱�Ƃ���������Ă���iPalliat Med. 2008�mPMID : 18216075�n�j�B �@�p�����{��NCPC�̉ߋ��̂��܂��܂Ȓ����́C���̌��������{�݂ɂ�����ɘa�P�A�̐��I�m���E�Z�p�̕s���ƁC����҂̈ӎv���肪�\���ɑ��d�����̐��ɂȂ����Ƃ��Ǝw�E���C����̏I�����P�A�݂̍�������{�I�ɉ��v������j�������iNational Health Service : End of Life Care Strategy, 2008�j�B�{�Z�~�i�[�͂��̉ۑ�������߂������{�݂Ƃ��̊W�@�ւ�ΏۂƂ����C�S���K�͂̍ŏ��̃L�����y�[�����ł���B �ӎv�������������g�g�� �@�Z�~�i�[�ɂ͉p���S�y����C�ɘa�P�A����C�Ō�t�C�\�[�V�������[�J�[�ȂǁC���{�݂�ی����ǁC�W�@�ւɋΖ�����130�l���Q���B���{����͕M�҂ƊŌ싳��W�҂��܂߂�3�l���Q�������B�Z�~�i�[�ł́CEnd of Life Care Strategy�ɉ������C�s���C���{�݁C���ҁC�Ƒ��C��ÊW�ҁC�ɘa�P�A���Ƃ����Ēn��P�A�g�D�������S���K�͂̊�悪�g�܂ꂽ�B�����āC�ɘa�P�A���C�Љ�I�j�[�Y�̕ω��ɏ]���Ċ��݂̂łȂ�����҃P�A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����R���C�ɘa�P�A�́u��`��̂���ׂ��p�v�Ɓu���j�I�w�i�v�Ƃ̗��ʂ�����ꂽ�i�\�j�B �\�@�Z�~�i�[�̃v���O���� ���u�` �E�u�l���̏I�����}�����l�X����������v �@Martin Green�i�p���R�~���j�e�B�P�A���� �������j �E�u�I�̐��Ƃł̗]���\�\�I�����P�A�ւ̑����I�A�v���[�`�v �@Julienne Meyer�i�u�I�̐��ƃv���O�����v��\�j �E�u�ƂĂ��d�v�ȁw���l�x�\�\���҂̑̌����v �@Brian Baylis�i�F�l�̊Ŏ��o���ҁj �E�u�ē����Ƃ̋����v �@Dame Jo Williams�i�P�A�̎��Ǘ��ψ���ψ����j �E�u�P�A�`�[���̃P�A�v �@Jan Holdcroft�i�X�^���t�H�[�hMHA �P�A�O���[�v���{�ݒ��j �E�u�n��ŏI�����}����\�\���{�݂̖����v �@Jim Marr�i�o�[�`�F�X�^�[�z�[�����P�A�Ǘ��ҁj �����[�N�V���b�v�i���ȉ�j�F�����̓t�@�V���e�[�^�[ �E�u�I�����P�A�����X�^�b�t�̃P�A�v �@Victoria Metcalfe�iAnchor Homes���F�m�ǐ��Ɓj �E�u���{�݂Ɗɘa�P�A��剻�̘A�g�ɂ��P�A�v �@Jo Hockley�i�i�[�X�R���T���^���g�E�ɘa�P�A���Ō�t�j �E�u�F�m�ǂ̐l�X����������v �@Karen Harrison Daning�i�p���ɘa�P�A���c�� �F�m�ǐ��Ō�t�j �E�u�F�m�\�͒ቺ�Ҏx���@�Ɨ��p�҂̈ӎv����v �@Simon Chapman�i�p���ɘa�P�A���c�� ����ыc��������j ������҃P�A���ԉ�ЂŁC����������P�c�̓o�^���Ȃ���Ă���B �@�܂��C�ɘa�P�A�ƍ���҃P�A�̋��ʓ_�Ƒ���_�������ꂽ�B�Ƃ�킯�������ꂽ�̂́C����҃P�A�ł͊��̊ɘa�P�A�ɔ䂵�āu���ɂ��Č�邱�Ɓv������̓`���Ƃ��ď��Ȃ����ƁC�����Ă��ꂪ�C�F�m��Q���Ȃ����������͌y�������ɁC����̊�]����I�����P�A�ւ݂̍�����q�ׂ邱�Ƃ�W���錴����1�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ������B����ɁC�uDying Matters Coalition�i���ɂ�����鏔�c�̘̂A���́j�v�̊������Љ��C���{�݂Łu������镶���v�y���邱�Ƃ̏d�v���������ꂽ�B �@�Q���҂͍u�`�����łȂ�2��̃��[�N�V���b�v�ւ̎Q�����`���t����ꂽ�B�M�҂��I�������e�[�}�́C�u�ɘa�P�A���ƂƉ��{�݂̘A�g�v�Ɓu�F�m�\�͒ቺ�Ҏx���@�iMental Capacity Act�GMCA�j�Ɨ��p�҂̈ӎv����v�ł������B�O�҂ɂ����ẮC����҂̏I�����̓����i�����̍���҂̏I�����ɂ͒ɂ݂�ċz����o�����Ă��邪�i�������Ȃ��j��C���̖������ɂ͉��{�݂ƈ�ÂƂ̘A�g�݂̂łȂ��ɘa�P�A���ƂƂ̘A�g���J�M�ł��邱�Ƃ����܂��܂Ȏ���ɂ�苭�����ꂽ�B�܂��C��҂ł�2007�N�ɔ�������MCA�̌���ɂ�����^�p�̎��ጟ�����Ȃ���C�]���ɂ������ė��p�҂̎�̐��̑��d���\�Ƃ��邽�߂�MCA�𗘗p���邱�Ƃ������ꂽ�B �@�M�҂́CMCA��������������̓n�p���ɁC�uMCA�̏���͖@���Ƃ̊֗^��K�v�����̐����ȂǕ��G�Ȏ葱��������Ɏ������݁C�I�����P�A�ɂ����镉�S��������v�Ƃ̈ӌ��𑽐������Ă����B����������C�Q���҂̊��l���ɂ��̖���₢�����Ă݂��Ƃ���C�قڋ��ʂ̌��t���Ԃ��Ă����B����́C�u�m���Ɏ�Ԃ͂����邪�C�{�l�̈ӎv��œK�ȃP�A�̍������W�c�Ō�������C���̉ߒ��ƌ��_�������������悤�ɂȂ�C��ÁE�P�A�W�҂���鋭�͂ȕ���ƂȂ��Ă���v�������B ���{�ւ̋��P�\�\�ɒ[�ɏ��Ȃ����{�݂ł̊Ŏ�� �@���{�ʼn��ی��@���������Ċ���13�N�ɂȂ�B�������C2008�N���J�Ȃ̐l�����Ԓ����ɂ��ƁC�S�����ɂ����鎀�S�̏ꏊ�Ƃ��đ������߂�̂͑��ς�炸�a�@�ł���i80.5���j�B����҉��{�݁i�ȉ��C���{�݁j�ɂ����鎀�S�́C���X�ɑ����X���ɂ�����̂̂킸��2.1���ł����Ȃ��C����ł̎��S��12.7���ł���C�����̊����͂���10�N���傫�ȕω����Ȃ��i2000�N��OECD�����ɂ�������{�݂ł̎��S�͑S���S�̖�30���j1�j�B����C���S�̐����������i���J�Ȃ̐��v�ł�2006�N��100���l����2030�N�ɂ�170���l�ɑ����j�C�����̑��������{�݂ł̎��S����]���錻��2�j��C���{�̕a�@�݉@�����Z�k���̎{��Ȃǂ��炷��ƁC����҂́u���v�͍�����{�̑傫�ȎЉ�I�E�o�ϓI���ƂȂ邾�낤�B �@����C�ŋ߂̉��{�݂̊Ŏ����{�̒����ł́C30�|60���̎{�݂ŊŎ�肪�s����̐��ɂ���Ƃ̉������Ă���B�������C�����͐�q�������S�̏ꏊ�̓��v�ƏƂ炵���킹��Ɛ��������Ȃ��i�M�҂������̉��{�݂ɖK��f�Â���Ă��邪�C�Ŏ����s���Ă���{�݂�1���������Ȃ��j�B���̂��Ƃ́C���{�݂̌��O�Ɩ{���̑������Ă���B�����āC���̌����́C�i1�j��ÂƂ�24���Ԃ̘A�g�s���C�i2�j�E���̋���ƌo���̕s���C�i3�j�ɘa�P�A�̐��ƂƂ̘A�g�s���C�i4�j���p�҂̏I�����ɂ�����ϋɓI��Âɑ���ӎv���s���C�Ȃǂł���3�C4�j�B �@���̈���ŁC���M�ɉ����邱�Ƃ́C�I�����Ɣ��f���ꂽ����҂����{�݂Œ��J�ɉ�삵���ꍇ�Ƌً}���@�����ꍇ�ɕ����Ĕ�r����ƁC���@�����Q�̂ق����\�オ�������S�މ@���������Ƃ����������Ƃ��ĕ���Ă��邱�Ƃł���5�j�B �ی����x�������ŗD��ۑ� �@2010�N�CLien Foundation, Economist Intelligence Unit�́COECD�����������́u���̎��F�I�����P�A�̐��E�����L���O�v�\����6�j�B���̕ɂ��ƁC�����I�Ȕ���ʼnp������1�ʁC���{�͑�23�ʂł���C���̍��́C����̐헪���̗L���ɋA����ƃR�����g����Ă���B���݂̓��{�̏I�����P�A�̐����Ώۂ́C2007�N�̂�����{�@�̔����ƂƂ��Ɋ��̊ɘa�P�A���嗬�ƂȂ�C����҂̑����Ƃ����l�����ԓI���v�⍑���̈ӎ����������x�v�ɔ��f���ꂸ�C�����v��◘�p�Ғ��S�̎p�����R�����B�ߔN�̊��̑����͍���҂̔��ǂɂ��e�����傫���C���͊��ɍ���҂̎����ɂ��Ȃ��Ă���B �@�����̎����́C����C���{�݂ɂ�����S���҂̑�����\�����Ă���C���̊ɘa�P�A�͕K�R�I�ɍ���Ҋɘa�P�A�Ƃ̏d�����Ӗ����Ă���i���R�̂��ƂȂ���C���ȊO�̎����̊ɘa�P�A���d�v�ۑ�ł��邱�Ƃ͘_���܂��Ȃ��j1�j�B�������C�����̎��H���疾�炩�ɂȂ������Ƃ́C���ʗ{��V�l�z�[���C�V�l�ی��{�݂�×{�^�a�����C���ی����œ������̗��p�҂ɂ͑��̈�Ë@�ւƂ̘A�g���ی��㌵������������Ă��鎖���ł���B����ł́C���{�݂ɂ�����I�����P�A�̎��H�͂قڕs�\�ł���ƌ����Ă悢�B���}�Ȑ��x�v�̌��������K�v�ł���B ���炨��ї��p�ҎQ�����J�M �@1999�N�C�p���̎Љ�w��David Clark�͂��̒����wReflections on Palliative Care�x�̂Ȃ��ŁC�p���̍���Ҋɘa�P�A�̒x��̌��������W�҂̋���s���Ə����̗��ɂ���Ǝw�E���Ă���B���̏́C���ꂩ��10�N�]���o�����̓��{�̌���ɕ�������B����ɁC��s�����ł́C�����Ώۂ����{�݂̊Ō�E��C�����ȂׂĂ��ׂĂ̐E���Ƃ��Ă�����͎̂U������邪�C���S�I���݂ł�����E�ɏœ_�Ă������E�����͔��ɏ��Ȃ��B����ł́C����̉��{�݂̃P�A�̎�����̂��߂̏d�_�I����Ώۂ���肵�C���̋�����e���m�����邱�Ƃ͓���B �@�M�҂������h���ɑ؍ݒ��C��8����BBC�̃e���r�ԑg�ŁC�Z�~�i�[�����ɂ͂��̓��e�̏Љ�Ȃ���C�����ɂ͉p���ɘa�P�A�̑�\�I���݂ł���Finley���j���uLiving and Dying Well�F�ǂ������ǂ����ʁv���Ƃɂ��Č��̂����܂��ܖڂɂ����B�����́C��q����Dying Matters Coalition�̎s�����犈���̈�ƍl������i������u������点�钼�B���v�ɕM�҂͊��S�����C�����������j�B �@�܂��C�p���ł́u���p�҂̈ӎv�̑��d�v�̗��s��MCA�Ƃ��Ĉ�Î҂Ǝ{�݊W�҂ɖ@�I�ɋ`���t�������C�u�I�����̌l�̈ӎv�̑��d�v�͓��{�̎Љ�I�E�v���I�������炷��Ƃ܂��������̂�Ǝv����B�������C����ɑ����Ƃ��āC��ÁE���{�ݗ��p�ҁi�����̏ꍇ���̉Ƒ��j�ɂ��ꂼ��̗��p�{�݂̉^�c�ɎQ�����Ă��炢�C�ނ�̈ӌ����^�c�ɔ��f�����邱�Ƃ���n�߂�̂������I�ł͂Ȃ����낤���B �P�g����҂̋}���ȑ��� �@�M�҂́C�ߔN�C�s����̂Ȃ��a��ȒP�g����ҁi�����҂��܂߂āj���C��a�@��������肨���b����@������Ȃ����B�������C�ނ�̎����͐g�̓I�C�S���E�Љ�I�Ƒ���ɓn�邱�Ƃ��قƂ�ǂŁC���̉����͈�t�E�Ō�t���͂��߁C���n�E�C�P�A�}�l���E��S�̂ƁC�����ψ��⒬����Ȃǒn��W�҂Ƃ̖��ڂȘA�g���K�v�ŁC�W�҂ɑ����̕��S�������鍢��ȍ�Ƃł���B�������C�M�҂�͂��̌X��������̓��{�̏������Ƃ��Ď~�߁C����I�Ɍo����~�ς����_�ƑΏ����@�̗ތ^��������悤�S�����Ă���B �@���p�̏I�����P�A�̗��j�̋��ʓ_�́C���v�͂������Ԃ̑�����[�������邱�Ƃł��낤�B �Q�l���� 1�jWHO Europe. Palliative Care for Older People; 2004. 2�j�����J���ȁD�I������ÂɊւ��钲�����������; 2004. 3�j���{�_�́C���D���ʗ{��V�l�z�[���ɂ�����I�����P�A�̌���Ɖۑ�D�Љ���w�D2006 ; 46�i3�j: 63-74. 4�jHirakawa Y, et al. End-of-life care at group homes for patients with dementia in Japan. Findings from an analysis of policy-related differences. Arch Gerontol Geriatr. 2006 ; 42�i3�j: 233-45. 5�j�I�c���C���D���ʗ{��V�l�z�[���ɂ����钴����҂̊Ŏ��P�A�\�\���ɋ}�����a�@���@��Ƃ̔�r�ɉ����āD���{�V�N��w��G���D2010 ; 47�i1�j: 63-9. 6�jEconomist Intelligence Unit, Lien foundation. The quality of death; Ranking: end-of-life care across the world; 2010. �T����w�E�V����2906���@2010�N11��29�� |