�@
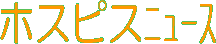 �@
�@�@�@�o�b�N�i���o�[2008/1/3�`2010/1/1
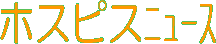 �@
�@| �@�z�|�� >��w�g�s�b�N�X>�z�X�s�X�j���|�X>�o�b�N�i���o�|�ƭ->2008/1/3�`2010/1/1 |
| �I�����P�A�ł͐e�����̉������̗v | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �@�P�[�X�E�F�X�^�����U�[�u��w�i�I�n�C�I�B�N���[�u�����h�j�Ō�w��Maryjo Prince-Paul�������́C�u�ɊǗ����K�ł���Əq�ׂ閖�������҂������Ƃ���C�Љ�I���N��Ԃ̖��ƉƑ��W�̃g���u�����C���҂�QOL�ɔے�I�ȉe����^���Ă��邱�Ƃ����������ƁC�č��z�X�s�X�ɘa��Êw��̔N���W��ŕ����B �u�ɊǗ������d�v �@ Prince-Paul�������ɂ��ƁC�I�����Ɋ���I�C�S���I��ɂ��o�����銳�҂����Â����t�́C�e���W�̖��𐳖ʂ���]�����C�Ƒ��Ɋ֘A����c�_�𑣂����Ƃɂ�芳�҂�QOL���P���菕�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����B �@���̂悤�ȓw�͂ɂ��C���҂�����Nj����Ă����l���̒B������������悤�ɂȂ邪�C������u�ɂ���I�ȏǏ�̊Ǘ������d�v�ȏꍇ������Əq�ׂ��B ���_�I���N��Ԃ�QOL�ɍŏd�v �@Prince-Paul��������́C�F�m��Ԃɖ�肪�Ȃ��C���狖�e�ł����u�ɂ̔��Ǘ���ł���z�X�s�X����50��i���ϔN��60�j��ΏۂƂ����p�C���b�g�����ɂ��CQOL�T�u�ړx�̑��ւ�]�������B���ɐl���̒B�����C���ւ̏����C�`�B�s�ׁC���_�I���N��ԁE�Љ�I���N��Ԃ������IQOL�ɂǂ̂悤�ɉe�����邩��]�������B ���̌��ʁC���_�I���N��Ԃ͑����IQOL�Ɋւ��čő�̗\�����q�ł������B����C�z�X�s�X�̃X�^�b�t�����҂��ꂵ�߂Ă���\���̂���e���W�̖��ɐ��ʂ�����g�ނ��ƂŁC�S���I���N��Ԃ̉��P�ɏd�v�Ȗ������ʂ����邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B �@���������́C����̌����Ŋw�ۓI�ȃA�v���[�`��p���āC�����̃C���^�[�x���V�����̌��ʂׁC�e���W�̃R�~���j�P�[�V�����𑣐i���邱�Ƃ�QOL������ɉ��P���邩�ǂ����ׂ�ׂ��ł���ƕ����B ���f�B�J���g���r���[���@2007�N4��12�� |
|||||||||||||||||||||
| ��27����{��w���i2007�N4��5���`4��8���j�A���ŊJ�Á@�I�����ɋ��߂����ÁE�P�A�Ƃ� | |||||||||||||||||||||
| �@�I�����i�^�[�~�i���j���}�������҂ɑ������鐶��S�����Ă��炤���߂ɂ͂ǂ̂悤�ȃP�A�����߂���̂��B �@��27����{��w���̃V���|�W�E���u�I������Á`�����̂��鎀�̈�w�`�v�i����������w�@��w�E���ؓN�v�w���j�ł́C�I������Â���ѐ����ϗ��Ɋւ���ӎ������̌��ʂ����ꂽ�B�܂��C���ҁE�Ƒ��Ɛڂ��邱�Ƃ̑����Ō�t���Ō�̗��ꂩ�猩���^�[�~�i���P�A�ɂ����鐶���ϗ��ɂ��Ĕ��\���C�Ŏ��̍őO���ɂ�����n��Ƃƃz�X�s�X�オ�C�I������ÁE�P�A�ɂ��Čo����������B �A������\�����t����b�ɓ���� �@�킪���̃z�X�s�X�E�ɘa�P�A�̃p�C�I�j�A�ł�������̔��؊w���́C����܂łɖ�2,500����z�X�s�X�ŊŎ���Ă���B���w���͊�u���ŁC�P�A�̖{���ɂ��ĊT�������B �@��w�̂Ȃ��ɃP�A�Ƃ����T�O���o�Ă����̂͂���قǐ̂̂��Ƃł͂Ȃ��B�L���A�icure�F���ÁC�����j�͂�����x�̂Ƃ���Ō��E�����邪�C�P�A�icare�F�z���C�����C���Ȃǁj�͒������邱�Ƃ��ł���B�~���g���E���C�����t�́C�P�A�̖{���Ƃ��āu�o�������v�Ɓu�Ƃ��ɐ�������W�v�������Ă���B���ꂩ���P�A����Ƃ������Ƃ́C����ɒ��邾���łȂ��C���肩��������̂��̂������Ă��炤�Ƃ����Ӗ����B�����āC�P�A�����l�Ƃ����l���C���݂��ɃP�A��ʂ��Đl�ԓI�ɐ������邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă���B �@���w���́C�z�X�s�X�ɓ������������̊��҂��u�����֗��Ė����ꂽ�v�Ƙb�������Ƃ��Љ�B���̌��t�̗��ɂ́C�������������K���Ƃ����炳��s�����C�z�X�s�X�ɗ��ď��߂Ă킩���Ă��炦���Ƃ����C��������Ƃ����B�������҂̋��ʂ̊肢�́u�Ǐ�̃R���g���[���v�Ɓu�C���̗����v�����C���Ɍ�҂ɂ��ẮC�u����͂炢�ł��ˁv�Ƃ������A�������\�����錾�t���C��b�̂Ȃ��ɓ���Ă����K�v������Ƃ����B �@�܂��C�������҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɂ����ĔƂ��₷���ԈႢ�� 1 ���u���Ղȗ�܂��v���Ƃ����B����ɓ��w���́C����I�ԓx�ɂ���Ċ��҂Ɂu���ʂ��Ƃ��|���v�Ȃǂ̎㉹��f�����Ă����邱�Ƃ��C�P�A�̖{���ɂȂ���Ƃ̍l�����������B �@�Ō�ɁC���w����coping humor�ɐG��C���������҂̌��t�u�o�������������ł��B�o��͏t�ďH�~�C�l�G�ɂ��邳���ł��傤�B���̂悤�Ȗ������҂͎l�G�i�����j���l���Ȃ��Ă���������������ł��v�������C�u�P�A�̏�ɂ������������ȃ��[���A���������ނ��Ƃ��C�傫�ȗ͂ɂȂ邱�Ƃ�����v�ƒ��߂��������B �قƂ�ǂ�������Ò��~���m�� �@���s���t��̌ږ�߂�哇���Ȉ�@�̑哇�v���@���́C�I������Â���ѐ����ϗ��Ɋւ���A���P�[�g�̌��ʂ�����B �@�A���P�[�g��2000�`06�N�Ɍv 4 ��s���Ă���C�����Ώۂ͈㎖���b��̉���ƁC������̈�Ë@�ւɒʉ@���銳�҂ł���B �@��t�C���҂Ƃ� 8 ���ȏオ�����܂��͕����I���@���ƉB���̐��̑��݂ɂ��Ă͈�t�������^�I�������B���{�l���ʂ̎����ς�����Ǝv���͈̂�t�� 6 ���C���҂� 4 ���B�������C��蓥�ݍ�����u�������s��Ȏ��R�̂Ȃ��ɂ������ނƁC�����_��I�Ȃ��̂Ƃ��C���R�̂Ȃ��� 1 �́g���̂��h�Ƃ��������o���o�������Ƃ����邩�v�ɑ��ẮC���҂� 7 �����u����v�Ɠ����Ă����B �@�A����Ԃł̉�����Ò��~�́C��t�C���҂Ƃ��قƂ�ǂ��m�肵�Ă����B�I������Â�Ō�E���������ꏊ�Ƃ��āC��t�͈��|�I�Ɏ�������C���҂ł͎���ƕa�@���������Ă����B���҂̔N��ʂł��Ⴂ�������C�����30�Ζ�����80�Έȏ�ɁC�a�@��60�`70�Α�ɁC�z�X�s�X��30�`50�Α�ɑ��������B �@�킪���ł͌��݁C���S�ꏊ�� 8 �����a�@�ł���B�Ŏ��ɑ���Ƒ��̖����x���ł������͎̂�����C�a�@�ł��ɘa��̈�Â̂ق���������̈�Â��������x�����������B �@�I������Â������{�݂Ƃ��āC��t�ł�2000�N�ɔ�ׂ�2006�N�ł͎������C�z�X�s�X�������Ă����B6 �N�ԂŊ��̍��m�ɑ���ϋɓI�p�����i���Ƃ����炩�ƂȂ����B���̈���ŁC���E�ی��@�ցiWHO�j�����u�Ɏ��Â̔F�m��C�����q�l�g�p���̊��҂ւ̐����C�I�����ݑ��Âւ̎Q���ɂ��Ă� 6 �N�O�ƕς�炸�C���@���́u�[���ƌ��C���]�܂��v�ƌ�����B �@2006�N�̃A���P�[�g�ł͊Ŏ��̌����ׂ��Ă���B�Ŏ��ꂽ���҂�85����70�Έȏ�ŁC90�Έȏ��23�����߂��B����҂��������߂��C4 ��������ł̊Ŏ��ł������B�����ꂩ�̏��u�E���Â�I���������҂�����̏��u�E���Â����ۂ������҂̂ق��������x�͍��������B����҂̏I�����ɂ������Ñ[�u�̑I������ɂ��Ă͎厡��̍l��������Ȃǂ̏d�݂��傫�����C��̏��u�E���Â����ۂ����P�[�X�ł͖{�l�̃��r���O�E�B�����傫�ȗv�f�ł��邱�Ƃ��킩�����Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2007�N5��24�� |
|||||||||||||||||||||
| �S����̌���ƌ��O���I�s�I�C�h�����̏�ǂ� | |||||||||||||||||||||
| �@�_�i�E�t�@�[�o�[���������i�{�X�g���j��Janet Abrahm���m�́u�I�s�I�C�h�����Ɋւ��Ĉ�t�͌�����Ă��邾���łȂ��C�ߏ蓊�^���邢�͖�ܗ��p�̌��O�ȂǐS���Љ�I�ȏ�Q�����邽�߁C���ʓI���u�ɊǗ����W�����Ă���v�ƕč��z�X�s�X�ɘa��Êw��N���W��̃V���|�W�E���ŕ����B ��t���g�������ݒ� �@����������Brigham and Women's�a�@�i�{�X�g���j���u�Ɋɘa��Ãv���O�����̊Ǘ��҂ł���Abrahm���m�́u���҂̎��Ȑ\���ɂ��ɂ݁C���邢�͕\��Ŗ��炩�ɉ䖝�ł��Ȃ��ɂ݂ł���Ƃ킩���Ă��C��t�̓I�s�I�C�h�̑��ʂ����߂炤���Ƃ������B���ꂪ�u�ɊǗ��ɂ�����ő�̏�ǂł���B�����ɘa��Ð���̖�����1�́C�I�s�I�C�h�̍��p�ʎg�p�Ŋ��҂̉��K�x�͏オ��Ƃ������Ƃ𑼂̈�t�ɂ��������邱�Ƃ��v�Əq�ׂ��B �@����ɁC�����m�́u�S����̑����́C�����u�ɂ��邢�͏d�x�̋}���u�ɂ�i���銳�҂ɒZ���ԍ�p�^�I�s�I�C�h���g�p����ۂɁg���Ƀ|�C���g�h臒l����t���g�̂Ȃ��Ō��߂Ă���X��������B�����P�Ƃ̖�܂��u�ɊǗ����s�\���ȏꍇ�͑��̖�܂p���邪�C�����͂�������L�����^�ʂ�������Ă���B��t����������ő哊�^�ʂɒB���Ă���Ƃ��ɂ́C�K���ʂ̃I�s�I�C�h�����^����n�߂Ă���B���̂��߁C�Ⴆ��2�`3��ނ̃I�s�I�C�h�ƃt�F���^�j���p�b�`�Ȃǂ�p�����Ԃɍ��킹�̎��ÂɏI����Ă��܂����ƂɂȂ�B�\�����u�ɃR���g���[��������Ă��Ȃ��Ƃ��������C�ނ����t�̎��Ȗ����͈̔͂���O�֓��ݏo���Ă��Ȃ����Ƃ𗠂Â��Ă��邾���ł���v�Ɛ������Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2007�N5��31�� |
|||||||||||||||||||||
| ��12����{�ɘa��Êw���J���� | |||||||||||||||||||||
| �@����2007�N6��22�A23���A��12����{�ɘa��Êw�����R�s�ŊJ�Â��ꂽ�B �@�u�n����ފɘa��Áv�Ƒ肵������̑���ɂ͖�4000���̎Q���҂��������B �@�`�[����ÁA�ݑ��ÁA�ɘa��Ë���A�X�s���`���A���P�A�A�ϗ��Ɩ@�A�x�C�V�b�N�T�C�G���X�A�����ɘa��ÁA����ȊO�̎����ɑ���ɘa��ÁA��Ã{�����e�B�A���̃e�[�}�ŁA���ʉ���ƈ�ʉ�������킹��700�����܂�锭�\���������B �@�܂��A������{�@�̎{�s�Ȃǂ̒ǂ����ɂ��b�܂�A����c���A���J�ȁE���ȏȂ̐l�X���u���E�V���|�W�E���E���e��ɎQ�����A�s���ƌ���݂̌��̗����ƐM����[�߂邱�Ƃ��ł����B �E��12����{�ɘa��Êw������2007�N6��23�� �E���{�ɘa��Êw��z�[���y�[�W |
|||||||||||||||||||||
| �ߑ�ɕ]������邱�Ƃ������I�������҂̐������� | |||||||||||||||||||||
| �@�I�������҂̐������Ԃɂ��āC��t���ߑ�ɕ]���������ł��邱�Ƃ��C���̖��Ɋւ���ŏ��̑�K�̓v���X�y�N�e�B�u�������s�����V�J�S��w��ÃZ���^�[�̌����`�[���ɂ���Ė��炩�ɂ��ꂽ�B ���ۂ��5.3�{�������\�� �@�I�������҂��z�X�s�X�ɑ�������t�����҂̗\��ɂ��ĕ]�������Ƃ���C��t�����͎��ɒ��ʂ��Ă��銳�҂̐������Ԃɂ��āC���ς��Ď��ۂ���5.3�{�����\�����Ă����B��t�̗\���������������̂́C���҂�20���ɂ����Ȃ������B �@���̌����̃��[�_�[�ł���V�J�S��w���Ȃ���юЉ�w�Ȃ�Nicholas Christakis�y�����́C�u���҂̊�]�ƈ�v���鎀���}���邽�߂ɂ́C������x�̎��O�x�����K�v�����C�����͂����Ȃ��Ă͂��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B �@���y������̓V�J�S�n��� 5 �a�@�̊O������ŁC��t343�l�C����468�l�Ɋւ���f�[�^���W�߁C�V���҂̓����ʒm���玀�S�܂ŘA��130���Ԃɂ킽�芳�҂̌o�߂�ǐՂ����B����ɁC��t�ɑ��� 4 ���Ԃ̓d�b�������s���C���҂̐������Ԃ��ǂ̂��炢�Ǝv�����ɂ��Ă̈�t�̐����l�����B �@���ۂ̐������ԁ` 3 ���� 1 �ŗ\���ł������̂��u���m�ȗ\���v�ƒ�`����ƁC�\����63���͐������Ԃ��ߑ�]�����C20�������m�C17���͉ߏ��]�����Ă����B �@����ɕ����L���āC���ۂ̐������Ԃ̔����` 2 �{�܂łƗ\���������̂��u���m�ȗ\���v�Ɋ܂߂��Ƃ��Ă��C��͂��t�̗\���͉ߓx�Ɋy�ϓI�ł������B��t��468�l�̊��҂̔����ȏ�i55���j�ɂ��āC���ۂ̐������Ԃ��� 2 �{�ȏ㒷������������̂Ɨ\�������B ���f�B�J���g���r���[���@2007�N7��6�� |
|||||||||||||||||||||
| �č��̍ݑ��Á@��t�̊S�Ⴂ���Ǝ��̃z�X�s�X���x�� | |||||||||||||||||||||
| �@���{�Ƃ͈�Õی��V�X�e�����قȂ�č��̍ݑ��Â̌����T�����B�����ł́C�ݑ��ÂŕK�v�ƂȂ�l�H�ċz���_�H�@�ނƂ�������Ê��ی��ŃJ�o�[����Ȃ����߁C���̂悤�Ȑݔ���v�����Ԃł̍ݑ��Â͍̒���ƂȂ��Ă���B �@�V�J�S��w�V�N��w����Deon Cox-Hayley�y�����́C�����̍ݑ��Âɂ��āu���@���Â�����قǂł͂Ȃ����C��Ë@�ւɒʉ@�ł��Ȃ��l�����p������́v�Ƃ���l��������ʓI�ŁC���p�͒ᗦ�ɂƂǂ܂��Ă���Ǝw�E����B �@�܂��C�Đ��{�̒����ł́C������80���ȏオ�ݑ����]���Ă��邱�Ƃ������ꂽ���C���ۂɍݑ���}���銄����20�����x�ł���B����ŁC�L���X�g����w�i�ɂ����z�X�s�X���x��C��含�̍����Ō�t������Ȃǂ̓���������B �@�O��Ðݔ��͎��ȕ��S �@���{�̂悤�ȍ����F��Õی����x���Ȃ��č��ł́C�����I�Ɏ����Ŗ��ԕی��ɉ�������K�v������B�������C65�Έȏ�̍���ҁC�g�̏�Q�ҁC�l�H���͊��ҁC����єN��Ɍ��炸�o�ϓI�x�����K�v�Ȑl�́C�������ꂼ��Medicare�CMedicaid�ƌĂ��F�ی����������Ă���B�������C�l�H�ċz���_�H�Ȃǂ̈�Ðݔ��́C�@�O�ł͂�����̕ی��ł����ȕ��S�ƂȂ邽�߁C��Ï��u���K�v�ƂȂ�ݑ��Âւ̌o�ϓI�n�[�h���̍�������C�ݑ��ÂŒ�����Â͕K�R�I�Ɍ��肳���B �@Cox-Hayley�y�����́C�ݑ��Â̕��y���ᗦ�ɂƂǂ܂邻�̑��̗v���Ƃ��āC��Îґ��̊S���Ⴂ�_���w�E���Ă���B��ËZ�p�̐i���ƂƂ��Ɉ�Îґ��̍��x��Â������ӎ������܂������Ƃ���C�ݑ��Â⍂��҈�Âɑ���S�����ɐ���̊ԂŒႭ�C�v���C�}���P�A��Ƃ̘A�g�����ɂ����ɂ���Ƃ����B�Ⴆ�C�ʉ@���ł��Ȃ��Ȃ������҂̓v���C�}���P�A��ɍݑ�ł̐f�@���˗����邱�Ƃ��ł��邪�C�v���C�}���P�A�オ�Ή��ł��Ȃ����x�Ȑ��Z�p��v���鎨�@�Ȃ��ȂȂǂ̐��Ȃ̐f�@���K�v�ɂȂ����Ƃ��́C�~�}�Ԃ𗘗p����Ȃǂ��Ď�f���邩�C������߂邵���Ȃ����B �@���ۂɁC���y�����͍ݑ��ÂɎ��g�ނȂ��ŁC��ÎҊԂ́u�A�g�v�ɑ���S���R�����_���������邱�Ƃ������Ƃ����B���y�������K��f�Â��s���Ă��銳�҂��ً}�ň�Ë@�ւ���f�����ꍇ�ɁC��Ë@�ւ����҂ɓn����������̋L�ڂ��s�\���ł��邽�߁C�v���C�}���P�A��͊��҂̏������Ƃɂ�����C��f������Ë@�ւɎ��Ó��e���m�F�����肷��K�v����������B���y�����́u��Â��A���I�Ȃ��̂ł����āC���҂��v���C�}���P�A��Ɉ����p�����Ƃ����ӎ����Ⴂ�̂ł͂Ȃ����v�ƕ��͂���B���i�K�ł́C�ݑ��Â͈�w����ł��قƂ�ǎ��グ���邱�Ƃ��Ȃ��C�w��Ȃǂ̑S�đg�D���ݗ�����Ă��Ȃ��B �@���I�w�i�����Ƃɍ��t���z�X�s�X���x �@�ݑ�ł̍��x��Â̎���������č��ł��邪�C���{�����ݑ�̊����������w�i�ɂ́C�L���X�g���̍l���Ɋ�Â��z�X�s�X���x�̐Z��������B���{�ł͈�ʓI�ɁC�u�z�X�s�X�v�Ƃ̓^�[�~�i���P�A���s���{�݂��w�����C�č��ł͐��`�[���ɂ��ݑ�ł̊Ŏ��x�����Ӗ�����B��t�Ɂu�ϋɓI���Âɂ��a��̉��P�������߂��]�� 6 �����v�Ɛf�f���ꂽ�i�K�Ŋ��҂��]�߂C�z�X�s�X���`�[���ɂ��x�����J�n�����B�z�X�s�X����Ƃ���Љ���m�����[�_�[�I�Ȗ������ʂ����C�K��Ō�C�w���p�[�ɂ���삪����ق��C�{�����e�B�A��@���W�҂���������S�g���ʂł̎x�����s����B�T 1 ��̕p�x�Ńz�X�s�X�`�[���̉�c���J����C�x�����e���b��������Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2007�N10��4�� |
|||||||||||||||||||||
| �z�X�s�X��L���ɗ��p���Ȃ��č���t | |||||||||||||||||||||
| �@�n�[�o�[�h��wBrigham and Women's�a�@�i�{�X�g���j��Gail Gazelle���m�́C�z�X�s�X�E�P�A�͑����̓_�ň�t�Ɗ��҂̑o�����������ꂽ�܂܂ł���Ƃ��錩����New
England Journal of Medicine�iNEJM 2007; 357: 321-324�j�ɔ��\�����B����͈�t�Ƀz�X�s�X�̗L���ȗ��p�@��������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B �z�X�s�X�E�P�A�̔����͊����� �@���̖��� 1 �́C�č���t�̑����́C�z�X�s�X�E�P�A�����ȊO�̊��҂ɍl�����Ȃ����Ƃł���B�č��ł́C�z�X�s�X�E�P�A�͊�����łȂ��A���c�n�C�}�[�a�C����^�C�v�̔x������S�����̊��҂ɂ��K�p�����B����ɁC���܂��܂Ȏ����ň����N������鐊��ł��z�X�s�X�E�P�A������B�Ⴆ�C�x���C�㕔�A�H�����ǁC�s���ǁC�i�s���̑̏d�����C������Q�C�i�s���Ő[�݂���ጐ���ᇂȂǂł���B �@�{�X�g���n��̃z�X�s�X�������̈�Ãf�B���N�^�[�����C���Ă���Gazelle���m�́u����ł��C�z�X�s�X���҂̔����߂��͖��������҂ł���B���̂ق��́C��40�����S�����̖������ҁC�F�m�ǖ������ҁC����ҁC�x�����C�]�������҂ł���v�Əq�ׂĂ���B �Z�����p���� �@���� 1 �̖��́C�č���t�̓z�X�s�X�E�P�A��]���������̊��҂ɍl�������C�]�������̊��҂����Ă͂܂�ƍl���Ă��邱�Ƃł���B�܂�C�����̊��҂͌��݂̊��K�I�Ȏ����������Ƒ����z�X�s�X�ɓ]�@�����ׂ��ł���B �@�z�X�s�X�ł� 6 �����Ԉȏ�̃P�A�����邪�C���҂̗��p���Ԃ̒����l��26���ԂŁC�č����̃z�X�s�X�ł͊��҂� 3 ���� 1 ���c��̐l���̍Ō�̏T�Ƀz�X�s�X�ɏЉ��C�]�@���Ă���B���̂��߁C2005�N�ɂ�120���l�ȏ�̊��҂��z�X�s�X�E�P�A�𗘗p�������̂́C���̑����͑Ó��Ȋ��Ԃ��Z�������B �@�z�X�s�X�ւ̓��@���x���Ȃ錴���ɂ́C�a�@�����s���̕a�̏I�������҂Ɏ����̂��߂̎��Â��s�����Ƃ���������B����ɁC�z�X�s�X�ɓ��銳�҂́C�h�����ۂ������҂łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�������������������� 1 �ł���BGazelle���m�́u�������C���@���x���ł��d��Ȍ����͈�t���g�̍l�����ł��낤�v�Ǝw�E���Ă���B �z�X�s�X�E�P�A�̔F���Ɍ�� �@�ł́C��t���g�̂ǂ̂悤�ȍl���������ƂȂ�̂��B�� 1 �ɁC�č���t�̑����́C���҂̎��͎��������̐f�Â̎��s�Ƃ݂Ȃ��Ă��邱�Ƃł���B�� 2 �ɁC�z�X�s�X�̂��Ƃ��o������C���҂̖]�݂��Ă��܂��Ƌ���邱�ƂŁC�����QOL�����コ�����萶�����Ԃ���������悤�ɓw�͂���̂��������ƈ�t���l���Ă��邽�߂ł���B�� 3 �ɂ́C�č���t�͖]�݂̂Ȃ���Ԃł��邱�Ƃ����҂ɓ`����ۂɎv�����̂���Ή������邽�߂̓K�ȌP�����Ă��Ȃ����Ƃł���B �@Gazelle���m�́C�� 4 �̓_���ł��d��Ƃ��C�u�z�X�s�X�E�P�A�͕s���̕a�̐i�s���ɒ��ʂ����Ƃ��ɁC�ł�����芳�҂����K�ɐ�������悤��������ړI�Ńf�U�C�����ꂽ�P�A�ł���̂ɁC�č��̈�t�̓z�X�s�X�E�P�A�͎����������Ƃ��̂��߂̍Ō�̎�i�ƍl���Ă��邱�Ƃ��v�Ǝw�E���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2007�N11��15�� |
|||||||||||||||||||||
| �I�����ɘa��ẪK�C�h���C������ | |||||||||||||||||||||
| �@�č����Ȋw��͏I�������u�ɁA�ċz����A���a�̊ɘa�P�A�K�C�h���C�������ł\�����B �@���K�C�h���C���Ŏ��グ��ꂽ�e�����A�Ȃ�тɊe�����̋��x�ƕt�L���ꂽ�G�r�f���X�̃��x���͎��̒ʂ�ł���B * �d�ĂȎ�����L����I�������҂ɑ��ẮA�u�ɁA�ċz����A���a�ɂ��Ē���I�ɕ]�����ׂ��ł���B * �d�ĂȎ�����L����I�������҂ɑ��ẮA�u�ɊǗ��ւ̗L�������ؖ����ꂽ���Ö���������ׂ��ł���B�����҂̏ꍇ�A�����������Ö�ɂ͔�X�e���C�h���R���ǖ�A�I�s�I�C�h�A�r�X�z�X�z�l�[�g������B�������҂���э�����҂ł́A�r�X�z�X�z�l�[�g�͍��ɂ̊ɘa�ɗL���ł���B * �d�ĂȎ�����L����I�������҂ɑ��ẮA�ċz����̊Ǘ��ւ̗L�������ؖ����ꂽ���Ö���������ׂ��ł���B����ɂ́A�y������Ȃ��ċz����҂ɑ���I�s�I�C�h���_�f���ǂ̒Z���I�y���̂��߂̎_�f�Ȃǂ�����B * �Տ���́A�d�ĂȎ�����L����I�������҂ɂ����邤�a�̎��Âɂ́A�L�������ؖ����ꂽ���Ö���������ׂ��ł���B�����҂ɓK�������Ö@�ɂ́A�O�n�R���܁A�I��I�Z���g�j���ċz���j�Q�܁A�S���Љ�I����Ȃǂ��l������B * �Տ���́A�d�ĂȎ�����L���銳�ґS���ɑ��āA���O�w�����Ȃǂō���̃P�A�̕��j�ɂ��ď��ʂ��쐬���ׂ��ł���B��̓I�ɂ́A�F�m�ǂ̊Ǘ��A�o�ljh�{�A�����҂ɂ����鉻�w�Ö@�̌p���܂��͒��~�A�������������S�s�S���҂ɂ�����A���^���ד���̒�~�̐���Ȃǂ�����B m3.com 2008�N1��18�� |
|||||||||||||||||||||
| �y�T�C�R�I���R���W�[�ƃ����^���P�A�z�@�O���[�v�Ö@ | |||||||||||||||||||||
| �ۍ◲�@���C��w��w�������E���_��w �@�T�C�R�I���R���W�[�̗̈�̒��ŁC���҂���ւ̐S���Љ�I��������ڂ���Ă��܂��B �X�s�[�Q���E���f���̏W�c���_�Ö@ �@�X�^���t�H�[�h��w�̃X�s�[�Q���iSpiegel D�j��́C���u�]�ڂ��N�����������҂���𐔖����̃O���[�v�ɕ����C�u�W�c���_�Ö@�v���s���܂����B�����90���Ԃ̃v���O�����T1��C1�N�Ԃɂ킽��s�������̂ŁC�t�@�V���e�[�^�[�i�i�s���j�͐��_�Ȉ�C�\�[�V�������[�J�[�Ȃǂ����߂Ă��܂��B10�N�̒ǐՂ̌��ʁC����Q�ł͕��ϐ������Ԃ�36.6�����ƁC�ΏƌQ��18.9�����ɔ�ׁC��2�{�̉������݂��܂����B �t�@�E�W�[�E���f���̍\�������ꂽ��� �@UCLA�̃t�@�E�W�[�iFawzy FI�j��́C�����̈������F��̊��҂���𐔖����̃O���[�v�ɕ����C�S6��̏W�c������s���܂����B����́C���ł����R�ɘb���Ƃ����̂ł͂Ȃ��C���߂�ꂽ�e�[�}�̘b������C�����N�Z�[�V�����̕��@���w�ԂƂ������̂ŁC���ɁC�O�����ŐϋɓI�ȃR�[�s���O�i�Ώ��l���j���l�����邱�Ƃ�ڕW��1�ɂ��Ă��܂����B���̌��ʁC 6�T�Ԃ̉���v���O�����I������ł́C����O�Ɣ�r���C���Ԃ̉��P�C�Ɖu�@�\�̑������݂��C6�N��ł͍Ĕ����Ȃ�тɎ��S���ɗL�Ӎ��������܂����B ���C�厮�u�����҂���ւ̍\�������ꂽ����v �@40���̌����̌��ʁC�����ł͉���O�ɔ�r���āC���ԂɗL�ӂȉ��P���݂��܂����B�����6������̃t�H���[�A�b�v�����ł́C�Q���҂�2/3�́C������I�����Ă��������I�ɉ������C�����������肷��ȂǁC���̊��҂���ƘA������荇���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B����͑�5��ŐG�ꂽ�C����̌o�߂ɂ悢�e����^����u�\�[�V�����T�|�[�g�v�C�܂��́u�\�[�V�����l�b�g���[�N�v�����邱�ƂɂȂ�܂��B�܂�C���̂悤�ȉ���́u�\�[�V�����l�b�g���[�N������v�Ƃ��Ă̈Ӌ`�������ƂɂȂ�̂ł��B �@�W�c�ʼn�����s���ƁC�����a�C�����������҂��m�Ŏx�����������Ƃ��\�ɂȂ�܂��B���̂��߁C���҂���̌Ǘ����̌y����C��̓I�Ȗ�����������̂ɂ����ɖ𗧂��������\�ɂȂ�����C����ɂ͈�Î҂̐l�I�E���ԓI���������߂邱�Ƃɂ��Ȃ�����@�ł���Ǝv���܂��B �@���̂悤�ȉ�����C�������x���łȂ��C����̂���f�Â̏�ł�������O�̂悤�Ɏ��Õ��j�̒��ɑg�ݍ��܂�Ă������Ƃ����҂��Ă��܂��B cancercareonline 2008�N1��24�� |
|||||||||||||||||||||
| �����ċz�펾���̏I������Á|��ɁE��Y�̊ɘa�ɊŎ���g�ݍ��� | |||||||||||||||||||||
| �@��17����{�ċz�P�A�E���n�r���e�[�V�����w��̓��ʍu���u�I������Âɂ����Ă̌ċz�P�A�͂ǂ�����̂��悢�̂��v�ŁA�K���V�A�a�@�i���{�j�z�X�s�X�̓���W�����́A�u�����ċz�펾���ł͒����ɂ킽��I�����̋�ɁE��Y�ɑ���ɘa�P�A�ɊŎ���Â�g�ݍ���ł����K�v������v�Əq�ׂ��B �@���쎁�́u�ɘa�P�A�Ƃ́C������ړI�Ƃ������Âɔ������Ȃ��Ȃ������҂ɑ���S���E���_�ʂ��܂ޑS�l�I�P�A�������B�I�����ɂ��銳�҂́C�߂������̎����̎����ӎ���������Ƃ��C�g�̓I��ɂ����łȂ��C���܂��܂ȋ�ɂ��Y��������B�ɘa�P�A�̖ڕW�́C���҂Ƃ��̉Ƒ��ɂł������ō���QOL���������邱�Ƃɂ���v�ƒ�`�����B �@�I������ẤC���{�ł͖��������҂̂��߂̈�ÂƂ����C���[�W�������B�č��ł͋ߔN�C�����҈ȊO�ɂ��ɘa�P�A�K�����g�傳��C�S�Ă̖�3,000�̔F�z�X�s�X�𗘗p�����70���l�̂���32����������҂ł���B �@�����ċz�펾���̏I�����͊��Ɣ�r���Ē����ɂ킽��B�����ǐ��x�����iCOPD�j��Ԏ����x���Ȃǖ����ċz�펾���̖������҂ɕK�v�Ȋɘa�P�A�ɂ́C�ċz�����P�CႂȂǂ̏Ǐ�ƕs���⋰�|�C�ǓƂւ̑Ή��C�������҂ւ̎x�����K�v�ƂȂ�B�s�\�Ȋ��҂ւ̉ߏ��Â̖�������B����ɁC�d�ĂȌċz�s�S��Ԃł́C�����l�H�ċz�Ǘ���]�̗L����h�����u���ہiDNR�j�w���̎��Ȍ��肪�s�\�Ȃ��߁C���O�Ɋ��҂�Ƒ��Ƃ悭�b�������K�v������B �@�����́C�ċz�펾�����@���҂̎��S�Ǘ�Ɋւ���ɘa�P�A�̎��Ԃ▝���ċz�펾�����҂̈ӎ������̃f�[�^�������C��������̏I������Ẩ��P��K��Ō�X�e�[�V�����C�ݑ�z�X�s�X�Ȃǂ̏[��������̉ۑ�ł��邱�Ƃ����������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N1��24�� |
|||||||||||||||||||||
| �I������ÁF�������Â̈ӎ������ց@��ʂƈ�ÊW�҂�--���J�Ȍ����� | |||||||||||||||||||||
| �@�����J���Ȃ́u�I������ÂɊւ��钲����������v�i�����A�����E��q�勳���j�̏����2008�N1��24���J����A�������Â���]���邩�Ȃǂɂ��āA��ʂƈ�ÊW�ґo����ΏۂɈӎ�������N�x���Ɏ��{���邱�Ƃ����߂��B���ʂ���ɁA�I������Â̎��̌�������������܂Ƃ߂�B �@�����͖�P���T�O�O�O�l��ΏۂɎ��{�B���ӎv�\���ł��Ȃ��Ȃ������ɒN�ɔ��f���Ă��炢�����������錩���݂��Ȃ��Ƃ��A�ǂ��ʼn߂���������--�Ȃǂ��B �@��ÊW�҂ɂ͏I�����̒�`�≄�����Ò��~���Ɋւ���ꗥ�Ȋ���K�v���ǂ����ɂ��Ă��q�˂�Ƃ����B m3.com 2008�N1��25�� |
|||||||||||||||||||||
| �r�^�~�������ɔ����u�ɂɗL���ł���\�� | |||||||||||||||||||||
| �@���͉��̃r�^�~���A�����g�j���T�v�������g�A���̑��̕⏕�I���Ö@���A�i�s�X�������҂̑����ɂ݂������������u�ɂ���ь��ӊ��̊ɘa�ɗL���ł���\�����V���������Ŏ�������Ă���B �u�����̊��҂��Ђǂ��ɂ݂̂��߂ɒ��Â���Ă��܂��p�ʂ̖����K�v�Ƃ���ꍇ�������B���ӊ����������߂ɋN���オ������A����������肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ����҂������B���̂悤�Ȋ��҂͈���̑唼����������Ԃ�A�x�b�h�ɉ����������Ԃʼn߂����Ă���v�ƁACancer Treatment Centers of America�i�C���m�C�B�j�̓�����w���啛�ӔC�҂ł���Timothy C. Birdsall���m�͌��B �@Birdsall���m��́A�i�s�X�����ŁA���w�Ö@�������ҁi�ꕔ�̊��҂͕��ː��Ö@�����p�j50���ΏۂƂ������������{�����B �@�팱�҂͂��ł��u�ɂ̂��ߖ���эR���ǖ�̓��^���Ă����B�u���ӊ��̂��߂ɂł��邱�Ƃ͂܂������Ȃ��v��Birdsall���m�͏q�ׂ�B �@�팱��50�ᒆ36��́A��Ƃ��ėΒ����o���A�����g�j���A���͉��}���`�r�^�~���i�r�^�~��C 1,000mg����уr�^�~��E 400���ےP�ʈȏ���܂ށj����Ȃ�⏕�Ö@�����B �@�����J�n���ɂ́A�⏕�I���Â��s�����Q�ł́A�u�ɂ��ς�����͈͂Ɣ��肳�ꂽ�팱�҂�40%�ł���A6������ɂ�67%���u�ɂ��ς�����͈͂ƂȂ����B �@�ΏƓI�ɁA�⏕�I���Â��s��Ȃ������Q�ł́A�J�n�����u�ɂ��ς����͈͂ł������̂�35%�ŁA6�������ɂ͂��̐�����22%�ɒቺ�������Ƃ��{�������疾�炩�ɂȂ����B m3.com 2008�N2��14�� |
|||||||||||||||||||||
| �Ƒ��̗v���ʼn������~�A���{�w�p��c���I������Âɒ� | |||||||||||||||||||||
| �@�a�C�̈����Ŏ���Ƃ�Ȃ��Ȃ������҂ɑ����Â̂�������������Ă����A���{�w�p��c�́u�Տ���w�ψ���I������Õ��ȉ�v�i�ψ������_�Y�����E��������Z���^�[���_�����j��2��15���A�������\�����B �@�w�p��c��1994�N�́u���ƈ�Ó��ʈψ���v�Łu���҂̈ӎv���s���Ȏ��́A�������Â̒��~�͔F�߂�ׂ��ł͂Ȃ��v�Ƃ��Ă������A����A��N5���ɍ����������u�I������ÂɊւ���w�j�v��ǔF���邩�����ŁA�Ƒ��ɂ�銳�҂̈ӎv�̐����F�߂��B �@���ł́A���҂̈ӎv���m�F�ł��Ȃ��܂܁A�Ƒ����牄�����Â̒��~�����߂�ꂽ�ۂ̑Ή��ɂ��āA�ڂ����L�q�B���Ƒ��S���̈ӎv����v���Ă��邩�����~�����߂闝�R�͉����\�\�Ȃǂ��A�l�X�ȐE��ō\�������Ã`�[�����J��Ԃ��m�F�A�L�^���ׂ����Ƃ����B �@�Ƒ��̋��߂�����锻�f�͈�Ñ��ɔC�������A�u�q�ϓI�Ȕ��f���]�܂��v�Ƃ��āA��Ë@�ւɁA�I������ÂɑΉ����鐧�x��ϗ��ψ���Ȃǂ̋@�ւ̏�݂����߂��B �ǔ��V�� 2008�N2��15�� |
|||||||||||||||||||||
| �I�����̓�����S�E�q�f�̊Ǘ��@�a���Ɛf�@�ɂ�錴�����肪�d�v | |||||||||||||||||||||
| �@�s�b�c�o�[�O��w��Gordon J. Wood���m��́C�I�����ɂ����������S�E�q�f�Ǘ��̗Տ������Ɋւ��郌�r���[�\�����B �@�����m��́C���̊�{�ƂȂ�̂͏ڍׂȕa��Ɛf�@�ŁC���҂ɂ��Ǐ�̏d�Ǔx�����肵�C����ɂ��錴���ɂ��Ă̎肪����������o�����Ƃ��ł���Ɖ�����Ă���B �@Wood���m��́u�ł��\���̍������������肳���ƁC�Տ���͈��S�E�q�f�̌����ƂȂ��Ă���@���C����̓`�B�����C��e�̂����ʂ���B���̌�̖���ẤC�֘A�����e�̂ɑ��ēK�ȝh�R����������邱�Ƃ����S�ƂȂ�v�Əq�ׂĂ���B �@�������C���^�ʂ��\���ŁC24���ԗ\�h�I���^���s���Ă���ꍇ�ł��C�Ǐ�̊ɘa�������Ȃ����Ƃ�����B���������ꍇ�ɂ́C�����̚q�f�o�H��}�����邽�߂ɁC�������̎��Ö@��g�ݍ��킹���o���I�Ŏ����I�Ȏ��Â��s���ׂ��ł���B �@�܂��C�o�����^�������łȂ��ꍇ�ɂ́C���܁C�牺���ˁC���o���n�����Ȃǂ̑�֓��^�o�H���l�����ׂ��ł���B �@�����̌����ŁC�O����ȕa���f�@�ɂ��C�K�v�s���ȏ�����邱�Ƃ�������Ă���B�z�X�s�X����61���ΏۂƂ��� �����ł́C�����̊��҂�75���ŁC���S�E�q�f�̌������m���ɓ˂��~�߂邱�Ƃ��\�ł������B�ł����������́C���w�I�ُ�i��ӁC��܁C�����C�v33���j�C�ݓ��e�r�o��Q�i44���j�C����������̖��i���ǁC�ݏo���C�����C�֔�C�v31���j�ł������B �@�ɘa�P�A�ɂ�����40�̊��҃G�s�\�[�h�̈��S�E�q�f�������������̌����ł́C�t���̌�����59�����肳��C��܁i51���j�ƕ֔�i19���j���ł����������B �@�����m��́u���҂��H�~�s�U��i���Ă���ꍇ�́C�P��I�ɒ�x�̈��S��悵�Ă���\�������邽�߁C���ɒ��ӂ��ׂ��ł���B�܂��C�I�����̑S���҂ł͕֔����菜���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N2��21�� |
|||||||||||||||||||||
| �I������ÃK�C�h���C���\�@���̉��P��ڎw�� | |||||||||||||||||||||
| �@�č����Ȉ�w��́C�I�����ɂ�����ɘa��ÂɊւ���V���ȃK�C�h���C�����쐬�����B �@���̐V�����K�C�h���C���ł́C�d�x�̎�����L����I�������҂ɑ����u�ɁC�ċz����C�}���̗L�������I�ɕ]�����C���ʂ��ؖ�����Ă��鎡�Â��s���C���ׂĂ̏d�x�������҂ɂ��Ď��O�ɏI�����P�A�̌v��𗧂Ă邱�Ƃ����߂Ă���B �@�č����Ȉ�w��̈�w����E�o�ŕ���Տ��v���O�����E�N�I���e�B�[�E�I�u�E�P�A����Amir Qaseem���m�́u�č��l�̑����͏I�����ɏd�x�Ȏ��������ǂ��C�Ƒ����P�A�ɓ�����B�I�����̏Ǐ���y���E�ɘa���鎡�Ö@�ɂ��čŗǂ̃G�r�f���X�����W���Č����������ʁC�u�ɁC�ċz����C�}�����ł������Ǐ�ł��邱�Ƃ��킩�����B���̂��߁C����̃K�C�h���C���ł͂����̏Ǐ�����グ���v�Əq�ׂĂ���B �@�K�C�h���C���́C�u�ɁC�ċz����C�}���ɑ��ėL�������ؖ�����Ă��鎡�Ö@��p����悤�������C��t�ɂ͏I�����̏d�x�������҂ɑ��Ē���I�ȕ]�����s���悤���߂Ă���B �@���҂��u�ɂ͍R���ǖ�C�I�s�I�C�h�ƃr�X�z�X�z�l�[�g�ŊǗ��\�Ȃ��Ƃ��ؖ�����Ă���B�ċz�����L����I�������҂ɑ��ẮC�ʏ�̎��Ö@�Ŋɘa����Ȃ��ꍇ�̓I�s�I�C�h�ʼn��P�\�ł���C��_�f���ǂ̒Z�����P�ɂ͎_�f�Ö@���s���B�}���̊��҂ɂ͍R����ƐS���Љ�I����ɂ�鎡�Â��\�ł���B �@�I�������u�ɁC�ċz����Ɨ}���ɑ���ɘa��Ẩ��P�Ɍ������č����Ȉ�w��̐f�ÃK�C�h���C���̂����Ȑ��������͈ȉ��̒ʂ�B �@��������1�F�d�x������L����I�������҂ɑ��ẮC��t���u�ɁC�ċz����Ɨ}���ɂ��Ē���I�ȕ]�����s�����ƁB �@��������2�F�d�x������L����I�������҂ɂ́C�L�������ؖ����ꂽ���Ö@��p�����u�ɊǗ����s���B���҂��u�ɊǗ��ɂ́C��X�e���C�h�R���ǖ�C�I�s�I�C�h�ƃr�X�z�X�z�l�[�g�Ȃǂ�p����B �@��������3�F�d�x������L����I�������҂ɂ́C�L�������ؖ����ꂽ���Ö@��p���Čċz����̊Ǘ����s���B�ʏ�̎��Ö@�Ōċz����ɘa����Ȃ��ꍇ�ɂ̓I�s�I�C�h�C��_�f���ǂ̒Z�����P�ɂ͎_�f�Ö@���s���B �@��������4�F�d�x������L����I�������҂ɂ́C�L�������ؖ����ꂽ���Ö@��p���ė}���̊Ǘ����s���B���҂̗}���ɂ͎O�n�R����C�I��I�Z���g�j���Ď�荞�ݑj�Q��C�S���Љ�I����Ȃǂ��s���B �@��������5�F��t�́C���ׂĂ̏d�x�������҂ɂ��Ď��O�ɏI�����P�A�v��i���O�w�����̍쐬���܂ށj�𗧂ĂĂ����B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N3��13�� |
|||||||||||||||||||||
| �v���C�}���P�A�オ�z�X�s�X�P�A��\���I�ɓ������� | |||||||||||||||||||||
| �@�wAmerican Family Physician�x3��15���̑����ŁA�z�X�s�X���҂̏Љ�Ǝ��Âɂ�����v���C�}���P�A��̖������q�ׂ�ꂽ�B�z�X�s�X�P�A�́A�ɘa���Â�]�ޖ����������҂̒N�ɂł����p�ł�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B �@�u�ƒ��́A�l���̏I���ɋ߂Â��Ă��銳�҂̃P�A�ɂ����Ă��������̂Ȃ��������ʂ������Ƃ��ł���v�ƃA�C�I����w�a�@�i�A�C�I���V�e�B�j��Michelle T. Weckmann���m���L�q���Ă���B �@�u�p�����ăP�A���s���A�e�E�q�E���ɂ킽���Đl�ԊW�������Ă��āA���҂̉��l�ρA�Ƒ��̖��A�R�~���j�P�[�V�����̃X�^�C���ȂǑ��҂ɂ͕�����Ȃ��m�����������ƒ�ゾ���炱���A���҂ƉƑ����z�X�s�X�Љ�̃v���Z�X�ɓ�����B�v���C�}���P�A��͐f�Ă��銳�҂Ɛe�����W�ɂ��邱�Ƃ������̂ŁA�z�X�s�X�P�A�����߂�̂��K�v�Ȏ��������Ȃ̂��f�ł���ȂǁA�I������Âɑ��ēƎ��̖�����S�����Ƃ��ł���B�v �@�u�z�X�s�X�P�A�Ɋւ��Đ����������҂̉��҂ƉƑ��̑唼�̎҂��A���҂��I�����Ɛf�f���ꂽ���Ƀv���C�}���P�A�ォ��z�X�s�X�ɂ��Ă̏��������ƕ������������Ɠ����Ă���v�ƁAWeckmann���m�͋L���Ă���B �@�u�z�X�s�X�͏I�����ɂ��銳�҂����悭�x�����A�D�ꂽ�P�A������i�ɂȂ肤�邱�ƁA�����āA�v���C�}���P�A�オ���҂̎��܂ŃP�A�S�̂̎w�����Ƃ葱���Ă���Ɗ��҂ւ̃P�A����������邱�Ƃ��A�����Ŏ�����Ă���c�c�܂��z�X�s�X�́A��ܓ��^�A�Ǐ�̊Ǘ��A���҂Ƃ��̉Ƒ��Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̍ۂɂ͈�t�ɂƂ��Ă��������̂Ȃ����\�[�X�ɂȂ�B�v �@�Տ��ɂ������X�̐����͈ȉ��̒ʂ�ł���B �@* ���Ɗ��ȊO�̐f�f���Ă��銳�҂́A�z�X�s�X�T�[�r�X�Ńx�l�t�B�b�g�邱�Ƃ��ł��A�\�オ2�J���ȏ�ł���z�X�s�X�ɏЉ�ׂ��ł���B�����Ƃ��L���ȃz�X�s�X�������Ԃɂ��Ă͋c�_���c����Ă��邪�A�قƂ�ǂ̎��Z���ŒZ��2�`3�J���Ԃł���B�ɒ[�ɒZ�������́A�ނ�����҂̑̒�������A���ɂȂ���B �@* �ł��邾�����������Ƀz�X�s�X�P�A�ɂ��Ċ��҂���щƑ��Ƙb�������ׂ��ł���A������P�A�ڕW�̑I�������L����ϓ_����Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�x������Љ�́A�T�[�r�X�Ɋւ���Ƒ��̖����x���Ⴍ�Ȃ�A���҂̑̒�������B�����ɂ��ƁA�z�X�s�X�ւ̏Љ�x�������Ɗ����Ă���Ƒ���11%����18%����B �@* NYHA���ރN���XIV�̐S�s�S�i���Î��Ɏ��o�Ǐ�j�ŁA���K���Âł��Ǐɉ����Ȃ����҂ɂ́A�z�X�s�X�ւ̏Љ�K���Ă���B �@* ���퐶���̂��ׂĂ̊����ɉ�삪�K�v�ŁA�ӎv�a�ʂ����͂�ł��Ȃ��悤�ȔF�m�NJ��҂ɂ́A�z�X�s�X�ւ̏Љ�K���Ă���B m3.com 2008�N3��27�� |
|||||||||||||||||||||
| �����q�l�ɂ�邪���u�ɊǗ��@�ɘa�P�A�ɂ�����Ӌ`�m�� | |||||||||||||||||||||
| �@�����q�l�Ȃǂ̃I�s�I�C�h��QOL�����P������ɖ�Ƃ��Ăł͂Ȃ��C"�������҂̂��߂̖���"��"�Ō�̎�i"�Ƃ��Ă̂ݎg�p�����ƌ������Ă��邱�Ƃ���C���҂͕K�v�ȏ�ɋꂵ��ł���B �@�u���X�g����w�ɘa�P�A��Colette Reid�㋉�u�t��́A�u���҂̊ԂŃI�s�I�C�h�͎��𑁂߂�Ƃ����l�����L�܂��Ă���v�Əq�ׁC�u���҂̓I�s�I�C�h�����������Ǝ������������Ɗ����邽�߁C�u�ɊǗ��ɑ傫�ȉe��������v�Ƃ��Ă���B�ȑO�̌����ł́C���҂�40�`70���͂��܂��܂ȗ��R�ɂ�萳����������u�ɂ�K�ɊǗ�����Ă��Ȃ��Ɛ��肳��Ă���B �@���u�t�́C�����q�l�Ȃǂ̃I�s�I�C�h�������ŏ��Ɋ��߂�ꂽ�Ƃ��C���҂��ǂ��������邩���������ƍl���C55�`82�̓]�ڂ���18���Ώۂɂ�����u�ɊǗ��Ɋւ���Ȗ��ȕ�����蒲�����s�����B �@���҂͑S�ᔒ�l�ŁC�����������ł������B�����q�l�ɑ��錩���ƌo���́C���݂Ɋ֘A���� 4 �̃J�e�S���[�ɕ��ނ��ꂽ�B�܂�u���̗\�z�v�C�u�Ō�̎�i�Ƃ��Ẵ����q�l�v�C�u���Ƃ̖����v�C�u�d���Ȃ��n�߂�v�ł������B �@�����̊��҂�"�Ō�̎�i"�Ƃ��ă����q�l�𑨂��Ă��邱�Ƃ����������BReid�u�t��́u���҂̓I�s�I�C�h��"�Ō�̎�i"�Ƃ��Ă̂ݗ��p������Ís�ׂƑ����Ă��邽�߁C�u�Ɋɘa�̂��߂Ƀ����q�l�����߂�ꂽ�ꍇ�C�����̎������߂��ƍl���Ă��܂��v�Ɖ��߂����B �@�܂��C���u�t��́u���҂͎��ʊo�傪�ł��Ă��Ȃ����߁C���ʂƂ��Ēɂ݂��o������Ƃ��Ă��C���ɖ�Ƃ��ă����q�l�Ȃǂ̃I�s�I�C�h�����ۂ����B���Ƃ̖����ɑ��銳�҂̈ӌ�����C���҂��I�s�I�C�h�ɑ�����Ƃ̐M����]�����Ă��邱�Ƃ��킩��B���������āC���҂̈ꕔ�͑I���𔗂���Ƃ��傫�ȋ��|�������邩������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�C����͒��ɖ�Ƃ��ẴI�s�I�C�h�����҂��M�����Ă��Ȃ����Ƃ������Ă��邩��ł���v�Əq�ׂĂ���B ���҂ƗՏ���̋��炪�K�v �@Reid�u�t�́u�����̕�����蒲������C���҂̓����q�l�ɑ�����Ƃ̂��߂炢���������C���ꂪ���҂̕s�������߂邱�Ƃ����������B���҂͂܂��C���Ƃ��i����ł��邪�j�����q�l���g�����ƂŎ����𑁂߂邱�Ƃ�S�z���Ă���Ƃ��C���̕s����e���ɘb���Ă����B�I�s�I�C�h���u�ɊǗ��ɂ��Ĉ�w���̋���͉��P������邪�C���݂���ꂪ���{���Ă���ʂ̌����ɂ��ƁC���Ƃւ̋���̕K�v���͖��m�ł��邱�Ƃ�������Ă���B�ɘa�P�A�`�[���͐��ƂƊ��҂̑o�������炷�邱�Ƃ��ł���̂ŁC���̖����͏d�v�ł���v�Ƃ��Ă���B �@��ᇎ��Ì������}�[�j���Ȋw�������i�Ɂj�̊ɘa�P�A���j�b�g�ӔC�҂ł���Marco Maltoni���m�́C�u���҂��I�s�I�C�h���Â��J�n���邩�ۂ������f����Ƃ��Ɍ�������3��v�f�́C���Ƃ̔\�́C�������R�~���j�P�[�V�����C�M���W�ł���v�Əq�ׂĂ���B �@�����m�́u�ɘa�P�A�̒a�������ꏊ�Ŏ��{���ꂽ����̌����́C�I�s�I�C�h�ɑ���傫�ȕs���Ɗɘa�P�A�̕��j���܂��\���ɒ�܂��Ă��Ȃ��Ƃ����C������ȓ_�������Ă���B����́C���N�̌��N���炪���҂���Ă����悤�Ȍ��ʂ������炵�Ă��Ȃ����Ƃ��������Ă���B���݂������̎�ᇊw�҂�����̖����ɂȂ�܂ŃI�s�I�C�h�̎g�p���T����X��������Ƃ�����肪�c����Ă���B�u�ɊǗ��Ɗɘa�P�A�͏I���������łȂ��C���̑O�̒i�K�̂���ɂ��ϋɓI�ȑI�����Ƃ��邱�Ƃ��K�v�ł���v�ƌ���ł���B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N4��3�� |
|||||||||||||||||||||
| �I�������҂̉������Â̍����T���E���~�ɂǂ��Ή����邩 | |||||||||||||||||||||
| �O�c ���� �i������w��w�@��È��S�Ǘ��w�y�����j �@�I������ÂɊւ�����I�w�j���Ȃ��Ȃ��ŁC��Ì��ꂪ�������Â̍����T���E���~�̖��ɓK�ɑΉ�����ɂ́C�ǂ̂悤�Ȓm�����K�v�Ȃ̂��B���Â̍����T���E���~�����e�����v���C���P���ׂ��葱���ɂ��āC��Ì��ꂪ���O�ɔc�����Ă������Ƃ��d�v���B �@�ł́C���Â̒��~�͈�ł��Ȃ��̂��ƌ����ƌ����Ă����ł͂Ȃ��B�����_�ł��C���Â̒��~�E�����T���͂Ȃ���Ă���B���Â̒��~�Ȃǂ����e����邽�߂ɂ́C(1)���Ò��~�����e�����(2)���P���ׂ��葱���\��2�_�ɂ��āC���̓��e�𐳊m�ɔc�����C�T�d�ɔ��f����ƂƂ��ɁC���̌��ʂ��L�^�Ɏc���Ă������Ƃ��d�v�ɂȂ�B �@���C��w�����C��苦���a�@�����A������̎����ɂ����Ă��C(1)���҂�������Ԃɂ��邩(2)���Ís�ׂ̒��~����]���銳�҂̈ӎv�����邩�����ƂȂ����B �@�I������Â̌���ł́C�Ƒ����瑁�����_�Ŏ��Â̒��~�����߂��邱�Ƃ�����B���҂̈ӎv���c���ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́C�ʏ�͉Ƒ��̂Ȃ��������҂�I�o���C����҂����ӂ�����Â����{����B�������C�������Â̒��~���ł��Ȃ��ꍇ�ł��C����҂����Â̒��~����]���邱�Ƃ�����B���̏ꍇ�C��Ë@�ւ͊��҂̍őP�̗��v�f���Ĉ�Â�i�߂邱�ƂɂȂ�B �@�`�[���ŏI������Â̐i�ߕ�����������ꍇ�C�e��Ï]���҂͐ϋɓI�ɔ������ׂ��ł���C�����łȂ���`�[����Â��������Ȃ��B�܂��C���Җ{�l�̈ӎv���s���ŁC�Ƒ������f�ł��Ȃ��ꍇ�C��Ã`�[����ϗ��ψ���Ŕ��f���ĉ������Â𒆎~�ł���Ƃ����B �@���{�~�}��w��́C��N10���ɋ~�}��Âɂ����ĉ������Â𒆎~����v����葱�����K�C�h���C���Ƃ��Ċw��x���ŏ��߂Ď������B�I�����ɂ��āC(1)�s�t�I�ȑS�]�@�\�s�S(2)�����ێ��ɕK�{�ȑ���̋@�\�s�S���s�t�I�ŁC�ڐA�Ȃǂ̑�֎�i���Ȃ�(3)�L���Ȏ��Ö@���Ȃ��C�����ȓ��Ɏ��S���\�������(4)�s�\�Ȏ��a�̖����ł��邱�Ƃ��C�ϋɓI�Ȏ��ÊJ�n��ɔ����\��4�ɕ����Ē�`�����B�����C�����V���Ђ��s�����A���P�[�g�̌��ʂł́C�~�}�~���Z���^�[�̑������w�j�̗̍p���������Ă���Ƃ����B �@�w�j�̓��e�����m�Ɉ�Ì���ɓ`����Ă��Ȃ��Ǝv���邽�߁C�w�j�̓��e�ɂ��Ċw��ɂ�����W�Ȃǂ�����C���m�ȗ����Ɋ�Â��������i�ނ̂ł͂Ȃ����Ǝv����B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N5��1�� |
|||||||||||||||||||||
| �s���L���a�@�@�����ɂ��u����蒠�v�̉^�p�J�n�@���ÂɊւ���u�[���v�Ɓu�Ǘ��v��_���� | |||||||||||||||||||||
| �@���{�̎s���L���a�@�𒆐S�Ƃ���u�n��ɘa��Ãl�b�g���[�N���c��v�́A�����ɂ����҂̎��ȊǗ��c�[���Ƃ��āu����蒠�v�̉^�p���J�n����B�L���s��t��A�L���s�Ƌ��͂��ăX�^�[�g��������̂ŁA����\�h�A���f�A���Â��[��������ɉ����A���g�̎��Ó��e�⌟�����ʂ̐����A���L�@�\�Ȃǂ������Ă���̂������B�\�h�⌟�f�A�Z�J���h�I�s�j�I���A�ݑ�Ö@�Ȃ�11���ڂ����݂܂łɎ���3-4�a�@�ƁA�f�Ï���40�{�݁A�K��Ō�X�e�[�V������10�{�݂��Q������B �@���c���������^�p����u����蒠�v�́A�s���L���a�@�̊ɘa�P�A�`�[�����쐬�����I���W�i���̂��́B �@���c���24���ɂ��u����蒠�v�̉^�p�Ɍ����A�n���t��⎩���̂�����������J���B���݁A�蒠�i�āj�ɂ��Ċ��҂⊳�Ғc�̂ւ̃A���P�[�g���������{���ŁA�A���P�[�g���ʂ��t��Ȃǂ̈ӌ���������Ȃ���A�ŏI�I�Ȃ���蒠�̌`�������߂�B �@���a�@�ɘa�P�A�`�[���̗я��ᎁ�́A����蒠�ɂ��āu2�l��1�l������ɂȂ鎞��ɂȂ����B����ɂȂ�O�ɒm���Ă��炢�������Ƃ������̂��傫�ȓ����ŁA���҂łȂ��l�ɂ��g���ė~�����v�Ƙb���B m3.com 2008�N5��19�� |
|||||||||||||||||||||
| ��6����{�Տ���ᇊw��w�p�W����`�����Z�~�i�[�@Medical Oncologist���m���Ă��������ɘa�E�x���Ö@ | |||||||||||||||||||||
| ���R �Y�l�i�����L���a�@ �ɘa�P�A�ȁj �@�]���C����̉��w�Ö@���s���ꍇ�͓��@���K�{�ł��������C�ߔN�C����p�̏��Ȃ��R����܂̊J���ɂ��C�O���ł̉��w�Ö@���\�ƂȂ����B���҂͎���ł̐����𑱂��Ȃ��玡�Â��s�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�CQOL�̌�������҂���Ă���B���̈���ŁC�O���Ŏ��Â�S�������t���u�ɊǗ��̌o�������Ȃ����߂ɁC���҂̒ɂ݂ɑ��ď\���Ȕz�����s���Ƃǂ��Ȃ����Ƃ�����B ����ɘa��Â͍R��ᇎ��Âƕ��s���čs���ׂ����́\��������̊ɘa�P�A�̓������\ �@����ɘa��ÁE�ɘa�P�A�Ɋւ��C�u�ɘa��Â͏I�����݂̂̈�Âł���v�Ƃ�������������҂݂̂Ȃ炸��Î҂̑��ɂ����܂��ɑ��݂���B���E�ی��@�ցiWHO�j�ɂ��C�ɘa�P�A�͏I���������ł͂Ȃ�������������R��ᇎ��Âƕ��s���ĊJ�n������̂Ƃ���Ă���B���ۂ̗Տ��ɂ����Ă��C��������̓K�Ȋɘa�P�A�ɂ���đމ@�≻�w�Ö@�̍ĊJ�Ɍ��т��ꍇ��C�t�ɍR��ᇎ��Â̌��ʂɂ���āC�Ⴆ�Β��ɖ�̌��ʂȂǁC�������ɂɑ��鎡�Â��y���ł���ꍇ������C���҂̓{�[�_���X�ȊW�ɂ���B �@�ɘa�P�A�ɂ����ĖÖ@�͏d�v�Ȉʒu���߂邱�Ƃ���C�w����Ö@����x�ɂƂ��Ă��C�ɂ݁C�ċz����C�����ǕǂȂǂɓK�ɑΏ����邱�Ƃ����߂���B �@�i�s�E�Ĕ����̂��҂ɍ�����������Ǖǂ́C�q�C�E�q�f�C�����c�����C���ɂȂǂ̏�����Ǐ���������C���҂�QOL�����ቺ������B���̂悤�ȏ����Ǖǂɑ��C�Ö@�Ƃ��Ă͏����Ǖ���}����p��L����R�R������i�L���u�`���X�R�|���~���Ȃǁj��X�e���C�h�C���f��p�̂���h�p�~����e�̝h�R��i�n���y���h�[���Ȃǁj���p�����Ă������C�ߔN�C�\�}�g�X�^�`���A�i���O���܂ł���I�N�g���I�`�h�̗L����������������C�{�M�ł�2004�N�Ɂu�i�s�E�Ĕ������҂̊ɘa��Âɂ���������Ǖǂɔ���������Ǐ�̉��P�v�ɂ��ĕی��K�������F���ꂽ�B �@�����Ǖǂ̎��Âɂ��āC�����ǕǂƐf�f���ꂽ�ꍇ�ɂ͑��������ɃI�N�g���I�`�h�ɂ��Ǐ�y����ϋɓI�Ɍ������C�����Ɏ�p�K���f����̂��]�܂����B �\���]�ڂ�L����ꍇ�ɂ́C�r�X�z�X�z�l�[�g����ː����Â��܂ޏW�w�I���Â��d�v�\ �@�����C�O���B���C�x���Ȃǂɂ����č��p�x�ɔF�߂��鍜�]�ڂ́C���������ɂ�a�I���܁C�Ґ������ɂ��_�o�Ǐ���Ƃ����B �@�ŋ߁C1�N�ȏ�̗\�オ���҂����Ǘ�ɑ��āC����QOL���ێ����\�Ȍ��肪��Ƌ������邽�߂̐헪���w���u�\�h�I����ɘa�P�A�iprotective cancer palliative care�j�v���d�v������Ă��Ă���B���̂悤�Ȋϓ_��������]�ڂɑ���W�w�I���Â̕K�v�������܂��Ă���B���]�ڂ�L���銳�҂ɑ��ẮCWHO���������u�Ɏ��Ö@�ɉ����C���ː����Â�r�X�z�X�z�l�[�g�̕��p�ȂǁC�ϋɓI�Ȏ��Â����߂��Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N5��22�� |
|||||||||||||||||||||
| ����̌��ӊ��ɐ��_�h���L�� | |||||||||||||||||||||
| ���D�y�a�@���w�Ö@�Z���^�[���@���R�א� �@���҂̑����͂��̌o�ߒ��Ɍ��ӊ������o����B���̈ꕔ�͓��ٓI�v���i���C�s���C�����ǁC�d�����ُ�C�R���_�a��Ȃǁj�ł��邪�C�����͂�����g�������t���h�ɂ�����ٓI���ӊ��ƍl�����Ă���C�Տ�����ł͑Ώ��ɓ�a���邽�߂ɗL���ȖÖ@���҂��]�܂�Ă����B �@��N�i2007�N�j�M�҂́C����̌��ӊ��ɗL�������ؖ�����Ă���̂͐��_�I�T�|�[�g�v���O�����C�^���Ö@�C�G���X���|�G�`�����܂݂̂ł���C���̎��_�ł͐��_�h���`���t�F�j�f�[�g�i���i�����^�����j�̗L�����͏ؖ�����Ă��Ȃ��C���Ƃ�����B �@���`���t�F�j�f�[�g��HIV���҂̌��ӊ������P���邱�Ƃ���C���҂̂�������P����̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂���Ă�����܂ł��邪�C�v���Z�{��ΏƂƂ����P�Ƃ̗Տ������ł͗L�p����������Ă��Ȃ������B �@����CMinton��̓��^��͂̎�@��p���āC�P�Ƃ̗Տ������ł͗L������������Ȃ�����2�����킹�ĉ�͂����B������2�ł́C�L�Ӎ����������Ȃ��������C����������`���t�F�j�f�[�g���^�Q�Ō��ӊ��̉��P�X��������C�Ǘᐔ�����Ȃ����Ƃɂ�錟�o�s������������Ă����B �@���҂̌��ӊ��ɂ����āC���`���t�F�j�f�[�g���^�Q�ł̓v���Z�{�Q�ɑ��C�L�ӂɗǍD�ȉ��P���������B �@���`���t�F�j�f�[�g�́C�킪���ł͂���̌��ӊ��ɕی��K�p���Ȃ��C���݁C��ʕa����O���ł̓��^�͍���ł��邪�C�\���Ȓm����o����L����ɘa�P�A��Ɍ��蓊�^�ł���悤�ȃV�X�e�����K�v��������Ȃ��B �@�܂��C�킪���Ŕėp����Ă��镛�t�玿�X�e���C�h��QOL�S�ʂ��y�x���P���邪�C����̘_���ł͂��̕���p�̂��߂Ɏg�p�͐��������ׂ��ł���C�ƋL�ڂ���C���ӊ����^�[�Q�b�g�ɂ������t�玿�X�e���C�h���^�̘_�������Ȃ����߁C���^��͂̑ΏۂƂȂ��Ă��Ȃ��B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N6��4�� |
|||||||||||||||||||||
| WHO�����������Ȃ��������u�Ɂ@�����q�l�̃{�[���X���^���I���� | |||||||||||||||||||||
| �@�V�����e�a�@�i�x�������j�w�ۓI�u�ɃZ���^�[��Barbara Schlisio�CAndreas Kopf�̗����m�́CWHO�������u�Ɏ��Ö@���t�������C�I�s�I�C�h��g�ݍ��킹�Ă��\���Ȑ��ʂ��Ȃ����҂ւ̑Ώ��@�ɂ��ĕ����B �@Schlisio���m��́C���ɂ̂��߂ɋ~�}�O���ɔ������ꂽ45�̏������҂ɑ��C�t�F���^�j��150��g/���C�����q�l������90mg/���Cnovaminsulfone 1g��1��4�^�����{�������C�u�ɂ��u�ɃX�P�[���ň��Î���8�C�����ɂ�10�imax�j�ɒB���Ă����B �@������10�����ƂɃ����q�l10mg���{�[���X���^�����Ƃ���C45����̈��Î��u�ɂ��u�ɃX�P�[����4�܂Ŋɘa���ꂽ���C�����u�ɂ͕ω�����10�̂܂܂ł������B���̂��߁C���҂͑S���������C�K�v����ጎ��Â���ł��Ȃ���Ԃł������B�����q�l�̉e���ŏ��X�ɒ��Âł������߁C�u�Ɋɘa�Ö@���t�����Ȃ������̓����q�l�ϐ��̔����ł͂Ȃ����Ƃ����������B �@�܂��C�������鐸�_�����i���a�j�Ȃǂ̑��̗v�����F�߂��Ȃ������B���Ǘ�ɂ����ẮC�u�ɂ����S�ɂ̓I�s�I�C�h���ł͂Ȃ����Ƃ������ƍl����ꂽ�B �@����ɁCMRI�����Ő卜�E�P���܂��������C�����̌��ɂ̐������t�����B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́C�S�g���I�s�I�C�h�̌��ʂɂ͌��E�����邱�Ƃ��o����m���Ă���B �@�����ŁC�����q�l�ƃu�s�o�J�C����Ґ��d���O�J�e�[�e���o�R�œ��^�����Ƃ���C�ň��̏���E���邱�Ƃ��ł����B���҂̖��C�͂���قǂЂǂ��Ȃ��Ȃ�C�Ԃ����ɍ��邱�Ƃ���ጎ��Â����邱�Ƃ��\�ɂȂ����B �����q�l�̃{�[���X���^ �@�����q�l�̃{�[���X���^�͎������^�����ʂ������B�u�ɂ�50���ɘa���ʂ�������͎̂������^�ł͖�7���Ԍ�ł���̂ɑ��C�{�[���X���^�ł͖�60����ł���B10���Ԋu�œ��^����ۂ̕K�v�ʂ́C���҂�����܂łɓ��^����Ă�����܂̔�o�������q�l�����ʂ̍��v����Z�o�����B �@����̏Ǘ�ł́C�t�F���^�j��150��g/���̓����q�l150mg�Ò��C�����q�l������90mg�o���̓����q�l30mg�Ò��ɑ������邽�߁C���v��180mg�ł���B�{�[���X�p�ʂ͊��܂̖�10���Ƃ���邱�Ƃ���C1��̓��^�ʂ͓��Ǘ�ł�10�`20mg�Ƃ������ƂɂȂ�C�����10���Ԋu�œ��^����B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N6��12�� |
|||||||||||||||||||||
| �u��ᑂ�l�H�ċz��͊�]���Ȃ��v��9�����@����������ÃZ���^�[�́u���O�w�����v�����Ŗ��炩�� | |||||||||||||||||||||
| �u�������I�������}���Ă��A��ᑂ�l�H�ċz��͒����Ȃ��łق����v�����l���銳�҂�9�����Ă��邱�Ƃ��A����������ÃZ���^�[�̒��ׂŖ��炩�ɂȂ����B �@���̒����́A����������ÃZ���^�[�a�@�ɊO���ʉ@���̊��҂���o�����u���̈�Âɑ����]�i�I�����ɂȂ����Ƃ��j�v�Ƃ������ނ̓��e���W�v�������́B��ᑂ�l�H�ċz��͊�]�����Ȃ�����ŁA�_�H�ɂ��Ă�3���̊��҂���]���Ă���A���u�̎�ނɂ���Ċ�]���銳�҂̊������قȂ邱�Ƃ����������B �@���@�ł͍�N5������A�I�����Ɋ��Җ{�l�̈ӎv���ł��邾�����d�������Ƃ̍l������A���C�Ȃ����Ɋ�]�҂ɏ�L�̏��ށi������u�I�����̎��O�w�����v�j���L�������A������@���ŕۊǂ���Ƃ������݂��n�߂Ă���B���́u���O�w�����v�́A�{�l���I�����Ɉӎv�a�ʍ���ɂȂ����Ƃ��Ɏ��o���A���̓��e���Q�l�ɂ��Ȃ���A��Î҂ƉƑ����̑㗝�l�ƂŎ��Õ��j����������l����Ƃ����d�g�݂��B
�@�I�������u�Ɋɘa��Z�f�[�V�����ɂ��ẮA��]���銳�҂���r�I�������A��]���Ȃ����҂������B��̓I�ɂ́A�u�ł��邾���ɂ݂�}���Ăق����v�Ɖ������҂�70.3���ŁA���̂����u�K�v�Ȃ���Ö���g���Ă��悢�v�Ƃ����̂�62.5�����������A�����18.8���̊��҂́u�i���ɖ�Ȃǂ��g�킸�Ɂj���R�Ȃ܂܂ł������v�Ɖ��Ă����B �@����������ÃZ���^�[�̎O�Y�v�K���́A�u�u�Ɋɘa�≄�����u�Ɋւ����]�́A�K�������wall or nothing�x�ł͂Ȃ��A�ǂ̂悤�ȏ��u����]���邩�͐l�ɂ���đ傫������Ă���B���ҌX�ɍׂ��Ȋ�]�����Ƃ��ł���̐�����邱�Ƃ����Ƃ��d�v���v�Ƙb���Ă���B ���o���f�B�J�� �I�����C���@2008�N7��10�� |
|||||||||||||||||||||
| ���҂̂��a�́C���C����������Ō�t�ɂ�镡���I�ȉ���ɂ���ĉ��P���� | |||||||||||||||||||||
| �@���҂��C�}����s���������Ƃ͈�ʓI�ł��邪�C���̈ꕔ�͂��a�Ɛf�f����郌�x���ɒB����ꍇ�������B�������C���҂̂��a�́C�C�t����Ȃ��܂܌��߂����ꂽ��C���Â���Ȃ��܂܌o�߂��邱�Ƃ������ł���B �@����C���҂̂��a���Âɂ��ẴG�r�f���X�͖R�����C�L���Ȏ��Ö@�ɂ��Ă̌����͂قƂ�ǂȂ���Ă��Ȃ������B�p����Strong��́C����Z���^�[�ɒʂ����҂�ΏۂɁC�Ō�t�����{���邤�a�ւ̕����I�Ȏ��É���̌��ʂ��������B �@�Ō�t�ɂ����ʂȉ���ɂ���āC���҂����a�ł��邱�Ƃ����o���C�Ώ��Z�\��g�ɕt���C��t�Ƃ��a�ɂ��ẴR�~���j�P�[�V������}�邱�ƂŁC���a�ɑ��ēK�Ȏ��Â��{����C���҂̗}���C�s���C���ӊ��̏Ǐy�����ꂽ�B �@����̌����ł́C�ʏ펡�Âɂ����Ă��S����ɂ��a�ł��邱�Ƃ�����Ă���C���̌��ʂƂ��āC���߂�����Ă������a�ɑ��鎡�Â��J�n���ꂽ�\��������B���������āC����ɂ����ʂ́C���ۂ̌���ł͂���ɍ�����������Ȃ��B �@�{�����ł́C���҂ɑ�����ʂȉ�����C�����^���w���X�̐��Ƃł͂Ȃ��C������Ō�t�����{���Ă���_�͒��ڂ��ׂ��ł���B����f�ÂɃ����^���w���X�̐��Ƃ��펞�������������邱�Ƃ͖]�܂����̂�������Ȃ����C�l�I�������Ìo�ϓI�Ȋϓ_���炷��ƁC���ۂɂ͂��̂��߂̃n�[�h���͂��Ȃ荂���B �@�ނ���C����̌����ōs��ꂽ�悤�ɁC����f�Âɕ��i�g����Ă���X�^�b�t���P�����C�����̈�Î��������p���Ȃ��炤�a���Â̌��ʂ��I�ɍ��߂Ă������Ƃ̂ق��������I�ł��낤�B�����������f���́C���҂ɂ����邤�a���Â݂̂Ȃ炸�C���̑��̂�����g�̎����ɍ������邤�a���Âɂ��K�p�ł���\��������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N7��10�� |
|||||||||||||||||||||
| �I�����̉������ÁA�a�@�R�������~�E�s�J�n | |||||||||||||||||||||
| �@�I������Â̎��Ԃ�ۑ�ɂ��āA�ǔ��V���Ђ��S���̕a�@��ΏۂɎ��{���������ŁA�ŋ߂P�N�Ԃɖ������҂ւ̐l�H�ċz��̑����Ȃǂ̉������Â̒��~�E�����T���������͉̂{�݂̂R�P���ɓ�����P�P�V�a�@�ŁA����͏��Ȃ��Ƃ��P�X�O�Q���ɏ�����B �@�����̕a�@�̂S�O������t�����̔��f�������Ƃ��A��N�T�����\�̍��̏I������ÂɊւ���w�j�����߂�A�����E��ɂ�錟�����m�����Ă��Ȃ����Ƃ��킩�����B�����i�߂��Ô�팸�Ȃǂ̂�����ŏ\���Ȉ�Â��ł����A�I������Âɖ�肪����Ƃ����a�@�͂X�P���ɒB�����B �@�l�H�ċz���l�H���́A�h�{�⋋�Ȃǂ̉������Â𒆎~�����̂͂W�U�a�@�A�������s��Ȃ��u�s�J�n�v�͂X�O�a�@���o�������B�����ꂩ���������̂͂P�P�V�a�@�B���������{�݂����Œ��~�͌v�R�X�T���A�s�J�n�͌v�P�T�O�V���������B�����̂����A�P�Ƃ̈�t�ɂ�锻�f�����������̂͂P�X�a�@�i�P�U���j�A�����̈�t�͂Q�W�a�@�i�Q�S���j�������B �ǔ��V�� 2008�N7��26�� |
|||||||||||||||||||||
| ��Y����Ƒ��@�u���v��荇����� | |||||||||||||||||||||
| �@�U���Q�T���t�̃j���[�X�t�o���ŁA�]�[�ǂłT���ɂW�W�ŖS���Ȃ����c����݂Ƃ����̌����u�K���Ȏ��ɕ��Ƃ́v�Ƃ����e�[�}�Ōf�ڂ����Ƃ���A�S�O�`�U�O��̏�������莆��d�b�A���[���ȂǂŔ�������ꂽ�B �@�����s�̎�w�i�U�T�j�̎莆�ɂ́A�P�O�P�̕���}���x���Ő挎�S�������̌����Â��Ă����B���N�P���ɓ��@���A�_�H�A�A���A�_�f�}�X�N�Ȃǂ̑[�u���A�}�X�N������Ă��܂�����ƁA����̓x�b�h�ɔ���t����ꂽ�B�����̒��Z�i�W�O�j�͉����[�u�ɓ��ӂ������A�����́u�V�����̂ɂ����܂ł��Ȃ���H�v�Ƌ^���������Ƃ����B �@��t�ł��鎄�̕��i�V�P�j�́A�厡��Ƃ��đc��̉����[�u����߂��B���̏����̃P�[�X�ɂ��ĕ����ƁA�u�P�O�P�̕��ɗA����_�f�}�X�N�Ȃǂ̎��Â͗����ł��Ȃ��B�a�@�͂���������������̂��낤���H�v�Ƌ^����������B �@���̂ق��A�]�[�ǂ̕v�i�U�X�j�̉����𒆒f���������i�V�O�j�A�ӎ��̖߂�Ȃ���Ԃ̕�i�U�X�j���P�N�ԁA�����������������i�U�O�j�\�\�ȂǁA���������Ɍ��f����������������B �@�g���⎩�g�̎��́A�N���������������Ȃ��B�܂��ĉƑ��Ō�荇�����Ƃ͏��Ȃ��B�Q�V�̎����g�A�c�ꂪ�Α���ō��ɂȂ�̂�ڂ̓�����ɂ��āA�͂��߂Ď������������B �@���ɂ��ăI�[�v���ɘb������������A�a�@�Ƃ̈ӎv�a�ʁA�Ђ��Ă͏I�����P�A�̏[���ɂȂ���B�F����̎莆�Ȃǂ�ǂ݁A�����Ɋ������B m3.com 2008�N7��31�� |
|||||||||||||||||||||
| �����҂̔����߂����\�����u�ɊǗ����Ă��Ȃ��\�� | |||||||||||||||||||||
| �@�����҂̔����߂����\�����u�ɊǗ����Ă��Ȃ����Ƃ�������K�͕������r���[�̌��ʂ����ꂽ�B���̌����ł́A�u�ɂ����E����d�v�Ȍ���v���Ƃ��āA�n���I�n��A���ƌo�ς̒ᐅ���A�����Á^�Ǘ��̔���{�݂��������Ă���B �u�����҂ɂƂ����u�ɂ͏d��Ȉ�Ï�̖��ł���B�����҂��u�ɊǗ��Ɋւ���K�C�h���C��������ɂ�������炸�A�\���Ȏ��Â��s���Ă��Ȃ��Ƃ�����肪�������Ă���v��Mario Negri�w�������i�C�^���A�j��Dr. S. Deandrea��͋L���Ă���B�u�u�ɊǗ��w�W�́A���҂������u�ɒ��x�ƒ��ɗÖ@�̋��x�Ƃ̍��v�x��]������ړx�ł���B���̃X�R�A�́A���ɖ�̏������s�\���ł��邱�Ƃ��Ӗ�����v�B �@���r���[�S���̌����҂�́u�u�ɊǗ��ipain management�j�v�A�u�w�W�iindex�j�v�A�u����imeasure�j�v�Ƃ����p���p����MEDLINE�i��w���T�C�g�j���������A�����҂̕s�\�����u�ɊǗ��ɂ��ĕ]��������������肵���B �u�u�ɂ�������2��̂���1��߂����A�\�����u�ɊǗ����Ă��Ȃ��v�ƃ��r���[�S���̌����҂�͋L���Ă���B�u���̊����͍������A��������ш�Î{�݊Ԃŕs�\���Ȏ��Âɂ��đ傫�Ȃ�����݂���v�B �u��K�͊��҃T���v����Ώۂɒ��ɗÖ@�̎���]�������ŁA�u�ɊǗ��w�W�͗L�p�ł���ƍl������v�Ɩ{�����̒��҂�͌��_�t���Ă���B�u�u�ɂ̍����L�a�������A�u�ɊǗ�����������Ă�����̏�ǂ���菜�����߁A�w�j�����s�Ɉڂ��ɂ������ẮA����̌������ʂ͏d�v�ȈӖ������v�B m3.com 2008�N7��31�� |
|||||||||||||||||||||
| ��49����{�_�o�w��@�؈ޏk�������d���ǁiALS�j���҂̎��Ì���v���Z�X�ɂ�����ϗ���T�� | |||||||||||||||||||||
�`�I������ẪK�C�h���C���`�l�H�ċz��O���͊댯 �@��䉝�f�N���j�b�N�̐쓇�F��Y�@���́C�����J���Ȃ̏I������Â̌���v���Z�X�̂�����Ɋւ��錟����̈ψ��߂��o������C��N5���ɂ܂Ƃ߂��K�C�h���C���ɂ��āC�u���݂̖@���ł͎��ʌ����͔F�߂��Ȃ��v�Ȃǂ̏d�v���ڂ�����C��������̏I�������l���邤���ł̍���̉ۑ���������B �G�r�f���X�����c�_�� �@�쓇�@���́u�I������Â̌���v���Z�X�̂�����Ɋւ���K�C�h���C���v�ɂ��āu�����͂܂��n�܂�������Ō��_�ɂ͒B���Ă��Ȃ��v�Ƃ̔F���������������ŁC(1)���̂̌����ɂ͑��l��������̂ŁC�I���������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ�(2)�ɘa��Âł��ׂĂ̒ɂ݂͒��Â��܂߂Ċɘa�ł���̂ŁC�ϋɓI���y���͑ΏۂƂ��Ȃ�(3)�l�H�ċz����O�����Ƃ͕���s�ׂɓ�����댯�ł���(4)���ʌ����͌����Ƃ��ĔF�߂��Ȃ��\�Ȃǂ��d�v���ڂƂ��Ē����B �@���@���́C�e�d�v���ڂɂ��ċ�̓I�ȗ�������Ď��̂悤�ɉ�������B (1)�l�Ԃ̈ӎv�������ɏu�ԓI�ɕς�邩��Ꭶ�B�������܂Ԃ������z�����Ă��Ă��C�ڂ̑O���J���X������C��u�ɂ��ĕs�g�ȋC���ɕω�����B�܂��C�A����Ԃɂ���l�Ԃ����킢�������Ǝv���Ă��C�{�l�ɂƂ��Ă͐����Ă���Ƃ����u�d���v��100���s���Ă��鑶�݂ł���C�]����Ԃ̐l�ł��Ƒ��ɂ��Ă݂�C���݂��Ă��邾���ňӖ�������̂�������Ȃ��B�l�Ԃ͒��a�����S�̂̂Ȃ��Ő����Ă��鑶�݂Ȃ̂ŁC�I���������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B (2)���݂̓��{�ł͈�t�ɒm��������Β��Â��܂߁C���ׂĂ̒ɂ݂͊��S�Ɋɘa�ł��邱�Ƃ����҂ɓ`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���҂��₦����̓I��ɂ������Ƃ͂��肦�Ȃ��B (3)�l�H�ċz��͑��������Ƃ���C�S�g�Ɏ_�f�������������ȑ��݂ƂȂ�̂ŁC������O�����Ƃ͂��̑S�̂������s�ׂɓ�����B���������̂��O���Ƃ��������Z�����Z�I�l���������ׂ��ł͂Ȃ��B (4)���{�̖@���ɂ͐����錠���͂��邪���ʌ����͂Ȃ��B�������ʌ�����F�߂���C������]���Ă��Ȃ��l�ɑ��Ă����ʂ��Ƃ��������ꂽ��C��̓I�Ȏ��̕��@�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�Ȃǂ̊댯�������邽�߁C�T�d�ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���ׂĂ̎��Â��ɘa�P�A�Ɂ@QOL����̂��߂̃P�A���l���� �@(��)�����a�@�@�\�V���a�@�̒����F���@���́u�������Â������Ƃ����I���ł͂Ȃ��C���ׂĂ̎��Â͑S�l�I��ɂ̊ɘa�ł���Ƃ����ɘa�P�A�t���[���ɕς��Ă����K�v������v�Əq�ׁC����_�o�w��Ƃ��ėϗ��̖��ւ̋c�_��[�߂Ă����K�v����i�����B �����E�킪�`�[���� �@�������@���͂܂��C���Ö@���m�����Ă��Ȃ���a�́C�����ẨȊw���f���ł���EBM��N���e�B�J���p�X�݂̂Ă͂߂邱�Ƃ��s�\�ŁC��w�����f�Õ�V�̌n�̂Ȃ��ŏ\���Ɉ����Ă��Ȃ����Ƃ��w�E���C���҂��u�Ȃ���Ȃ��a�C�Ȃ琶���Ă����̂͂炢���C�Ӗ����Ȃ��v�ƍl�����Ƃ��C�{�l��Ƒ��C��Î҂��ǂ��Ή�������悢�̂��C���j�Ղ��Ȃ���Ԃł͈�Â𑱂����Ȃ��Ȃ�\��������Ɩ���N�����B �@���̂����ŁC�����@���́u���ʂȉ������Â��������鎀���v�Ƃ�����������߂���@�Ƃ��āC�ɘa�P�A���f���̗L�p�������������B�ɘa�P�A�T�O�̂Ȃ��ł́C�u���v����e����̂ł͂Ȃ��C���Ɏ���a�C�ƂƂ��ɐ����邱�Ƃ��m�肷��B���Â͐g�̓I��ɂ��Q�C�S���I��ɁC�Љ�I��ɂ���C��I��ɂ��܂߂��S�l�I�ȋ�ɂɑ���ɘa�Ö@�Ƃ��Ĉʒu�t����B�܂�C���Â̂�����߃C�R�[�����C���邢�͎��Â���^�[�~�i���P�A��180�x��ւ��ĉ������Â��s��Ȃ��Ƃ����l�����ł͂Ȃ��C�f�f���_����ɘa�P�A���n�܂�Ƃ����l�����ł���B���̃��f���ɏ]���C�K�v�Ȏ��Â�P�A�͖��ʂȉ������Âł͂Ȃ��Ȃ�C�s���������C��ɂ���������C���Ɏ���a�C���a�ƂƂ��ɐ����邱�Ƃ��m��ł���悤�ɂȂ�B �@���莾�����҂̐����̎��̌���Ɋւ��錤���ǂ�2007�N�x�ɂ܂Ƃ߂��uALS�̕�I�ċz�P�A�w�j�v�ł́C�ɘa�P�A�t���[���ւ̕ύX�m�Ɏ����Ă���B����ɂ��ƁCALS�̌ċz��P�A�͌ċz�푕�����������Âƍl����̂ł͂Ȃ��C�ɘa�Ö@�ƈʒu�t���C�ċz���w�Ö@�C�ېH�����T�|�[�g�C���w�Ö@�C��ƗÖ@�ɂ����퐶������iADL�j�̒����C�ɂ݂̃R���g���[���C�X�s�[�`�Z���s�[�ɂ��R�~���j�P�[�V�����T�|�[�g�C�S���Ö@�C�P�[�X���[�N�ȂǑ����E��P�A�Ƃ��ă`�[���ōs���Ă������j��������Ă���B �@���̂����ŁC�����@���́u�����ɍ������ɘa�P�A�Ɋւ��鎩�Ȍ���̓P�A�`�[���Ƃ̌𗬂̂Ȃ��ōs���C�a�Ԃ̕ω��C�P�A���e�C���Ԃ̕ω��ɂ���ē��e�͏�ɕω����Ă������́v�Ƃ����CQOL����̂��߂̐V�����C���t�H�[���h�E�R���Z���g�̍l������B�u��Â̂Ȃ��̖���ϗ����ɑւ���̂ł͂Ȃ��C�P�A��[�߂�c�_�����ׂ��v�Əq�ׁC�{���̊ɘa�P�A�T�O�𐳂������y���邱�ƂɐϋɓI�Ɏ��g��ł����p�����������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N8��7�� |
|||||||||||||||||||||
| �����\��s�ǂȐV�����́u�Ŏ��̈�Áv�@�u�����������ވ�Áv�ւ̔��z�]���� | |||||||||||||||||||||
�D�� ���v �@����L���X�g���a�@�����ȕ��� �@�ŋ߁C�����\��s�ǂȐV�����̎��Õ��j�������āC�V������ÂɌg���a�@��8���ȏオ���Â̍����T���⒆�~���o�����Ă���Ƃ̒������ʂ�����Ă���C�킪���ł��u�ߏ�ȉ������Áv���������������L�������B����L���X�g���a�@�ł͐����\��s�ǂȏ�ԂɊׂ������̎��Îw�j�Ƃ��āC1998�N10���Ɂu�V�����̗ϗ��I�C��w�I�ӎv����̃K�C�h���C���v���쐬�����B���K�C�h���C���́C���ꂼ��̏Ǘ�ɑ����Ã`�[���̎��Õ��j�ƁC�Ƒ��Ƃ̘b�������̒��N�̒~�ς��琶�܂�C���@�ϗ��ψ���̏��F�č쐬���ꂽ�B �u��肷���̈�Áv�͔�ϗ��I �@1986�N�̒����V���Łu�����̂܂ܐV����2�N���v�Ƃ����L�����f�ڂ��ꂽ�B���̎��́C���@�ŏd�lj�����Ԃŏo����C�V�����W�����Î��iNICU�j�ł̎��Â̂��߂ɓ������������a�@�ɔ������ꂽ�B�������C���Â̂����Ȃ��ӎ����ċz���s�\�ȏ�Ԃ��������܂ܐl�H�ċz���2�N����������Ă���C����̎��̎��Â�����C���e�u���炩�ɐ������āv�E�a�@�u�O���ʐl�H�ċz��v�̊ԂŐ[���ȑΗ����������B���̎����́C����L���X�g���a�@�ɂ����Đ����\��s�ǂȐV�����̗ϗ��I�����l���钼�ڂ̌_�@�ƂȂ����B �@�D�˕����́u�ߔN�̈�ËZ�p�̋}���Ȕ��W�́C�]���~���s�\�ł������d�NJ��҂ɑ��Ă���w�I�ɉ�����C���Ɋ����ł���悤�ɂȂ����B����C�����\��s�ǂʼns�\�Ȗ������҂ɑ��Ă��@�B�I�ȉ������\�Ȏ���ɂȂ��Ă����B����1950�N�ォ��60�N��ɂ����ċ}���ɔ��W�����l�H�ċz����\�Ƃ��鐶���ێ����u�̊J���́C���������`�Ɋ�Â��������Âɑ傫�ȍv���������B�������C���̎����́C�����Ɋ��҂́w���Ǝ��x�����܂ł̂悤�Ɏ��R�Ȍ`�Ōo�߂�����̂ł͂Ȃ��C���B����������ËZ�p�ɂ���đ���ł���l�H�I�ȉߒ��ɕς���Ă��܂������Ƃ��Ӗ�����v�Ǝw�E����B����́C�V������Â̕������O�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B �ϗ��I���e�͈͂����� �@�D�˕�����́u���l�Ԃ炵����ÂƂ́H�v�Ƃ����ϓ_����C���@�̏�����ÂɌg���E��63�l�ɃA���P�[�g���s�����B���̌��ʂ����ƂɁC���̕a�@�ł͂ǂ̂悤�ȍl������m�邽�߁C���̐V�����f�Ñ��݉����V�X�e���iNMCS�j�ɑ�����30�{�݂̐E��427�l�ɃA���P�[�g���s�����B���̌��ʁC�u���������̎q���ł������Ȃ�ǂ����܂����v�Ƃ�����ɑ��ẮC���Â̒��~��167�l�ƍł������C�����ł킩��Ȃ���119�l�C�ɘa�I���Â�108�l�C�ϋɓI���Â�59�l�̏��ł������B �@�������q��ȑ�w��q������ÃZ���^�[�̐m�u�c���i������́C��w�I�ӎv����ɂ������̓I�Ȏ��Ís�ׂ̕��ނ��s�����BClass A�͂����鎡�Â�ϋɓI�ɍs���CClass B�͎�p�C���t���͂ȂǑ傫�ȕ��S�̂���������x�ȏ�̎��Â𐧌�����CClass C�͌��ݍs���Ă���ȏ�̎��Â͍s�킸�C��ʓI�{��ɓO����C�h���p�͎��s���Ȃ��CClass D�͐l�H�ċz����܂߂�����܂ł̂��ׂĂ̎��Â𒆎~����Ƃ������ނł���B�D�˕������Class A��ϋɓI��ÁCClass B�𐧌��I��ÁCClass C���ɘa�I��ÁCClass D���Ŏ��̈�ƒ�`���CNICU�ɂ������̓I�ȗϗ��I�C��w�I�ӎv����ɉ��p���Ă���B �ӎv�����̑Ή��ɔz���C�Ƒ����S�̊ɘa�P�A����� �@���K�C�h���C��������̕ω��ɂ��āC�D�˕����́u�Ŏ��̈�Â���������Ƃ����āC�K���������S���͑����Ă��炸�C�ނ��댸�����Ă���B�����ɍŊ��̂Ƃ��C���̍őP�̗��v����Ã`�[���ƉƑ��������ɘb�������悤�ɂȂ���Class A�i�ϋɓI��Áj�̓K���͏��X�Ɍ������CClass C�i�ɘa�I��Áj�܂���Class D�i�Ŏ��̈�Áj�������Ă����B�����ėϗ��I���e�͈͂̃K�C�h���C���쐬�i1998�N�j�Ȍ�́C�قƂ�ǂ�Class C�܂���D�ŖS���Ȃ��Ă���v�Ƃ��C�����Ɂu�Ō�͉Ƒ��C���ɕ�e�̋��Ŏ�������������闦���N�X�����Ă���B�ߏ�Ǝv����h����Â͍����T�����C�ق�100����e�̋��ŊŎ���Ă���v�ƕt��������B �@�ł́C����Class C��D��K�������ꍇ�C���̌�̑Ή����ǂ����邩�B�����ւ̔z���Ƃ��ẮC�ō��̊ɘa�P�A�C�ɂ݁C�s���CQOL�ȂǁC�Ƒ��ւ̔z���Ƃ��ẮC���̎�e�ɑ��鏀������C�ʉ�Ԃ���C�����X�L���V�b�v��P�A�ւ̎Q���Ȃǂ�������B�܂��C�Ŏ��ւ̔z���Ƃ��ẮC�ł���ΉƑ��S���̗�����C�Ō�͉Ƒ��C���ɕ�e�̋��̂Ȃ��ł̊Ŏ��C�Ƒ��̊�]�ɂ��M���ł���@���ƂȂǂ̗�����������C�u�����I�ɂ͉ƒ�ł̊Ŏ��Ƃ������Ƃ��ۑ�ƂȂ�v�Ɠ������B����ւ̔z���Ƃ��ẮC�\���Ȕ߂��݂̕\�o�C���㏈�u�ւ̎Q���C�L�O�B�e��`���̕i�C���ʂ��Ȃǂ�������B �َ��ɘa�P�A�̌������K�v�� �@����C�ŋ߁C�َ��f�f���傫���N���[�Y�A�b�v����Ă���B2004�N�ɕč���Leuthner SR�́C�َ��f�f��̐V�����I�����Ƃ��āC�u�َ��ɘa�P�A�v�̊T�O���Љ�Ă���B �@�D�˕����́u����َ��f�f������I�ɐi�����邱�Ƃ��\�z�����B�����Ȃ�ƁC�َ����Ẩ\����T������Ɠ����ɁCFetus as a patient�CFetus as a human�Ƃ��āC���̐l���Ƒ������ɂ���َ��ɘa�P�A�̑I�����̌������V���ȃe�[�}�ƂȂ��Ă��邾�낤�v�ƓW�]����B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N8��28�� |
|||||||||||||||||||||
| �����u�ɂ̐_�o�u���b�N�Ö@�\�K�C�h���C���쐬�ɖ]�܂��������� | |||||||||||||||||||||
| �@��42����{�y�C���N���j�b�N�w��Ȃǂɂ��u�����y�C��2008�v�������s�ŊJ���ꂽ�B���ڂ��ꂽ�Z�b�V������1���V���|�W�E���u�����u�Ɏ��ẪK�C�h���C���쐬�Ɍ����āv�B�_�o�u���b�N�Ö@���܂ނ����u�Ɏ��ÂŖL�x�Ȍo��������3�l�̃V���|�W�X�g���C�K�C�h���C���쐬�Ɍ����C�����u�ɊǗ��̌����ۑ������B �ɘa�P�A�̒��S�͂����u�ɊǗ��@�y�C���N���j�V�����Ɋ��� �@���Ɉ�ȑ�w�a�@�ł̓y�C���N���j�b�N���̂Ȃ��Ɋɘa�P�A�`�[����݂��C�R���T���e�[�V���������łȂ��C����I���Â�ϋɓI�ɍs���Ă����B����������w�u�ɐ���Ȋw�̑���a�d�����i�y�C���N���j�b�N�����j����Љ�ꂽ�B���@�ł͑�������C�y�C���N���j�b�N���������u�ɊǗ��Ɏ��g��ł����B �@�������́C�I�����̊ɘa�P�A�ł͍ŋ߁C�����I�ȃP�A�����߂���X���ɂ���C���̒��S�ƂȂ邪���u�ɊǗ��ɂ����āC�������x���̒m����Z�p�����y�C���N���j�V�������ɘa��Â̒S����Ƃ��Ċ��҂���Ă��邱�Ƃ��w�E�B���̂��߂ɁC�����u�ɂ����łȂ��C�u�ɑS�ʂ̌n���I���Âւ̎��g�݂��d�v�ɂȂ�Ƃ̍l�����������B �y�C���N���j�V�����̊֗^�@�ɘa�P�A�ɑ����̃����b�g�� �@�����u�ɊǗ��̑�������1�l�Ƃ��Ēm���鏺�a��w�a�@�ɘa�P�A�Z���^�[�̔����o���Z���^�[�����A�y�C���N���j�V�������ɘa�P�A�Ɍg��邱�Ƃ͑����̃����b�g������Ƌ��������B �@���Z���^�[���́C�y�C���N���j�V�������ɘa�P�A�Ɍg��邱�ƂŁC�ɂ݂̊m���ȕ]���C�Ö@�Ɛ_�o�u���b�N�Ö@�ɂ��I�m���u�ɊǗ����\�ɂȂ�C���҂�QOL����ƂƂ��ɁC�o�ϓI���S�̌y�����}���Ƃ����B �@���ہC�y�C���N���j�V�����ł��铯�Z���^�[������]�̌`�ŏA�C����2001�N�ȍ~�C�u�ɊǗ��Ȃǂ̏Ǐ�}�l�W�����g�̈˗��������B2004�N�ȍ~��2000�N�̖�4�{�ɒ��ˏオ�����i�\�j�B�S�̂̈˗�������2002�N�̊ɘa�P�A�f�É��Z�J�n�ɔ����Ă���ɑ����������C�����q�l���g�p�ʂ͋t�ɒ��������������B �_�o�u���b�N�Ö@�̋@����@�K�C�h���C���ʂ���Î҂̗����� �@�����w�����E�h���w�̕���ޏ����y�����́C�����u�ɂ̎��Ö@�Ƃ��đ����̗��_�����_�o�u���b�N�Ö@�̋@���������X���ɂ���Ƃ��C�K�C�h���C����ʂ��C�֘A�����Î҂̗�����[�߂Ă����K�v����i�����B �@����w�a�@�ł�2005�N8���C�����ȃy�C���N���j�b�N�Ƃ͓Ɨ������`�̊ɘa�P�A�Ȃ��V�݂��ꂽ�B �@���̂悤�Ȑf�ÃV�X�e���̕ω��ɔ����C�y�C���N���j�V�����͂����u�Ɋ��҂Ƃ������@��������B�Љ�҂̑����͏I������ŁC���ɐ_�o�u���b�N�Ö@�̎������킵�Ă���B���̂��߁C�_�o�u���b�N�Ö@�̎{�s��������������X���ɂ���Ƃ����B���l�̕ω������{�݂ł��N���Ă���B �@���y�����́u�_�o�u���b�N�Ö@�ɂ́C�ɂ݂Ɋ֗^����_�o�݂̂̑I��I�u���b�N�C�����Ԃ̒��ɁC���ɖ�g�p�ʂ̌����C�̈ӎ���_�����ւ̉e���r���ȂǁC�����̈Ӌ`������v�Ƃ��u�K�C�h���C����ʂ��C�����u�ɂɂ�������Î҂̐_�o�u���b�N�Ö@�ɑ��闝����[�߁C���悢���Â�ڎw�������v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N9��4�� |
|||||||||||||||||||||
| �I������Âɂ����銳�ҁE�Ƒ��ɂƂ��Ă̍őP���T�� | |||||||||||||||||||||
| �@��13����{�ɘa��Êw��̃V���|�W�E���u�I������Âɂ�����Տ��ϗ��F����Ȏ��ǂ��l����H�v �@�����͍�������掦���ꂽ���z�Ǘ������C�I�����ɂ����ėA�t�E���Â��ǂ����ׂ����ɂ��Ċe����̐��Ƃ����c���J��L�����B �y�Ǘ�1�z�Ƒ��̈ӌ����قȂ�ꍇ�C�A�t���ǂ����邩 �@2�N�O�ɗ�������ɂč��Փ����S�E�o�p���s����50�Α㏗���B���w�Ö@�{�s�������������i�s���C3�����O����T�u�C���E�X���J��Ԃ��C�ۑ��I���Ái�ꎞ�I��H�E�A�t�j�ʼn��P���Ă������C2�T�ԑO����͌o���ێ�𐧌��C�A�t1,000mL/���ł������C1�T�ԑO���畠���������C�ӎ������̂��ߖ��m�Ȉӎv�\�����ł��Ȃ��Ȃ����i�ċz����͂Ȃ��j�B��Î҂́C�A�t�p���ɂ�镠���E�ċz����̈��������O���C�Ƒ��ɗA�t���ʂ̑��k�������Ƃ���C���E���q�i�p����]�j�ƕv�i���~��]�j�̈ӌ��̈�v�������Ȃ��B �K�v�\���Ȉ�w�I���̒� �@�r�i���V����L���X�g���a�@�z�X�s�X���́C�v���q���������̊�]�Ƌ�Ɋɘa�̂Ȃ��Ŋ������Ă���͓̂����B1,000mL�ȏ�̗A�t�ŕ��������������O�����ώ@�����̌��ʂ���C���Ǘ�ōł������ł��Ȃ��Ή��́u�A�t�̑��ʁv���Ǝw�E�B�t�ɐ������ׂ��Ή��́C�ӎ��������ɂ��銳�҂̈ӎv�𐄒肵�C�Ƒ��Ԃ̊�]�����C�Ƒ��ɂł��邱�Ƃ��ꏏ�ɍl���Ă����Ȃ���C���ҏ�Ԃ��J��Ԃ��]�����āC�A�t�ʂ⎡�Ó��e���������Ă������Ƃ��Ƃ̍l�����������B �@�T�q(��)���C�t�E�v�����j���O�E�Z���^�[�s�[�X�n�E�X�a�@�E�Ō암�����C��Î҂Ƃ��Č����c�����C�a��̔��f�ƌ��ʂ���������邱�Ƃ�����Ƃ��C�P�A�̍ۂɂ́C(1)�Ƒ������o�[�e�l�̊��҂ɑ���v����(2)���҂Ȃ�ǂ����ė~�����Ǝv������(3)�\�ł���ΉƑ����ꏏ�ɃP�A������\���Ƃ��d�v�ŁC�Ƒ������炱���m�肦�銳�҂̍D�݂ɍ��������ɐ������邱�Ƃ�P�A��ʂ��ĉƑ����̗̂l�q��m�邱�Ƃ��l�����ׂ����Ƃ����B ���ҁE�Ƒ��̗�����ӌ������p������� �@���q���j���É��s����w��w�@�y���� �́C���Ǘ�ɂ��āu�A�t�̌��ʂ������\��Ɉ��e�����y�ڂ��̂ł͂Ȃ����ȂǁC���q����̕a��F���Ɍ��������\��������B��Ñ����犳�ґ��ɓ`������ɂ��Ă��C�A�t���]���̗ʂŌp�������琶�����ۂĂ�̂��C�����E�ċz����������鋰��͂ǂ��Ȃ̂��C���ʁE���~������ǂ��Ȃ̂����C���ׂĊ��ҁE�Ƒ��ɂ킩��悤�ɓ��탌�x���̌��t�Ő������ē`���C���ҁE�Ƒ��̗�����ӌ�����邱�Ƃ��d�v�ɂȂ�v�Əq�ׂ��B �y�Ǘ�2�z���_�I��ɂɑ�����Â��ǂ����邩 �@2�N�O�ɐt����Őt�E�o�p���s����50�Α�j���B3�����O�ɋ��œ]�ڂƐf�f���ꂽ�B1�����O���玩��ł̉�삪����ƂȂ�C�ɘa�P�A�a���ɓ��@�B���҂́u�����鉿�l�Ǝv���Ă����d�����ł����C�Ƒ��ɕ��S�������Ă���B���c�������Ƃ͂Ȃ��C���y�������ė~�����B�����Ȃ炸���Ɩ��点�ė~�����v�Ɨv������B �͕t���C�x���C�E�C�t����P�A �@�r�i�z�X�s�X���́C��Ɋɘa�͈ӎ�������g�̋@�\�ɗ^����e�����ł����Ȃ����@��D�悷�ׂ��ł���C��ʓI�ɂ͊Ԍ��I���ɂ���ɂ�D�悵�C�\���Ȍ��ʂ������Ȃ��ꍇ�Ɏ����I�E�[�����ɂ��l������Ƃ����p�����������B �@���ہC���Ǘ�̂悤��"�S���Љ�I�ȋ��"�ɑ���킪���̒��Â̌�����C�ɘa�P�A�a����ɒ����������ʂɂ��ƁC�����I�Ȑ[�����ɂ��s�������҂ŁC�S���Љ�I��ɂ����Â̗��R�ƂȂ����҂�1���ɂ����Ȃ��B�����I���ɂ͑啔���������\��1�T�Ԗ����̊��҂ɑ��čs���Ă���B �@�Ō암���́C�掦���ꂽ�͈͂ł͉Ƒ��̈ӌ����s�������C�u���ҁE�Ƒ��̕a�ɔ����r���̃v���Z�X�ƔߒQ��m��C���҂ƉƑ��̊W���₻�ꂼ�ꂪ���҂��ɂ������Ǝv���Ă��邱�Ƃ��l�����ׂ��B�������C��Ⴢɔ����s�����⍇���ǂɑ��郊�X�N���ŏ����ɂ���P�A���d�v�v�Ƃ̌������������B ���a���z�肷�ׂ� �@���q�y�����́C�u�����Ɩ��点�ė~�����v�Ƃ����i�����Ӗ����邱�Ƃ����Ҏ��g�ƂƂ��Ɍ������ׂ����Ǝw�E�B�u�{���͏��������߂Ă���̂�������Ȃ����C���҂��F�����Ă����w�I�͐��m�łȂ���������Ȃ��B�Ƒ����d�ׂɊ����Ă���͎̂v���߂����̉\�����������C�⌾��V�̏����̂��Ƃ��w�E�����炷�܂��Ă����ׂ����ƂɋC�t����������Ȃ��v�ƌ����B �@���Ǘ�̏ꍇ�C�����I�Ȓ��Â��s�����Ƃ��i��ɂ���͉������邪�C����܂��\���\�Ǝv����l�ԂƂ��Ă̐������ł��Ȃ��Ȃ�j�C�Ԍ��I���Â��������Ƃ��i�����̊ԋ�ɂ���������C�o�����ɍĂё����C���ɂȂ�\��������B���ʁC�����̊Ԃł��ӎ��̂��鎞����������邱�ƂɂȂ�j�C���_�I��ɂɑ���ʏ�P�A�����������Ƃ��i�l�ԓI�����𑱂��Ȃ���Ŋ��̂Ƃ����߂����邪�C���ʂ��o�Ȃ������ꍇ�C�炢�����𑗂邱�ƂɂȂ�j�̂��܂��܂ȃ����b�g�E�f�����b�g����������Ƃ��납��n�߁C���Җ{�l����і��炩�ɂ���Ă��Ȃ��Ƒ��̗����ƈӌ����m�F����K�v������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N9��18�� |
|||||||||||||||||||||
| ���������҂̊Ǘ��͕s�\���@�K�Ȏx���Ö@���f���̊J���� | |||||||||||||||||||||
| �@���݁C����ƂƂ��ɐ�����l�͐��E���Ŗ�2,500���l�Ɛ��肳��C�V���ɂ���Ɛf�f����鐬�l��60���ȏ��5�N�ȏ�̐��������҂ł���Ƃ����B�������C���������҂̑����́C����̂��܂��܂ȏǏ�⎡�ÂƂƂ��ɐ����邤���ŕK�v�ȊǗ����K�ɍs���Ă��Ȃ��̂�����ł���B �@�G�f�B���o����w�i�p�j�ɘa��Õ����Marie Fallon������́C�u���������҂̂��߂̓��ʂȎx���Ö@���f���̊J�����K�v���v�Ƒi���Ă���B �@Fallon�����́C�u���������҂̑����́C�ً}�ɑΏ������ׂ��v�����������ꂸ�C�����Ɣ��̋��ԂŒu������ɂ��ꂽ�܂ܐ����Ă���v�Əq�ׂĂ���B �@�������́u����܂Ŋɘa�P�A�Ŗڎw���Ă������Ƃ́C�Ǐ�X�y�N�g���̍Ŋ��ɂ���C���Ȃ킿�����������Ă��銳�҂��������邱�Ƃł������B�������C���������҂̐��͑������Ă���C���̑����͂��܂��܂ȏǏ������Ȃ��琶���Ă���̂����B�����̎����͎�������̂��C�������̌����Ă���Ǐ�͎��ÂɗR��������̂Ȃ̂��C���邢�͂��܂��f�f����Ȃ�����̍Ĕ��ɊW������̂��C�킩��Ȃ����҂����邾�낤�v�Ǝw�E���Ă���B �@����ɁC�������́u�����҂͂������ɂ�鎡�Â��I�������C�I�������҂���悤�ȃP�A��x�����Ă��Ȃ��B�������C����Ƃ��̎��Â������҂̒����̌��N�ɋy�ڂ��e���͏d��ł���B�قƂ�ǂ̃P�[�X�ő����̏Ǐc��CQOL�͒Ⴂ�B�܂��C�s�K�ɂ�����̍Ĕ���f�f����銳�҂�����v�Əq�ׂĂ���B �@�������́u���҂̂��߂̓��ʂȎx���Ö@���f�����J�����邱�Ƃ��K�v���B�����āC�]���̊ɘa�P�A�̐��m�������̃��f���ɃC���v�b�g����邱�Ƃ��]�܂����B�����Ǝ�����1�̘A���̂ŁC���҂��K�������g�g�݂̖��m�ȃ��f���ɂ����܂�Ƃ͌���Ȃ��B����Ƃ��Ă̂����̉ۑ�́C���̘A���̂��敪�����邱�Ƃł͂Ȃ��C���̑S�̂�����Ή����邱�Ƃ��v�Ǝw�E���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N9��18�� |
|||||||||||||||||||||
| ���m�A�u���錩���݂������Ă��Ȃ��Ă��A�m�肽���v��72.1�� | |||||||||||||||||||||
| �@���c�@�l���{�z�X�s�X�E�ɘa�P�A�����U�����c�͂��̂قǁA�S���̒j��1000����Ώۂɍs�����u�]��������ꂽ�ꍇ�A�ǂ̂悤�Ȉ�Â��A�ǂ̂悤�ȍŊ����߂����������v�ȂǁA�z�X�s�X�E�ɘa�P�A�ɑ���l�X�̈ӎ����A���P�[�g�����������ʂ����J����\�肾�B �@���̎����́A���{�z�X�s�X�E�ɘa�P�A�����U�����c���i���j��ꐶ���o�ό������Ɉϑ����Ē����������ʂ̃��|�[�g�̗v��B �@�������ʂ���A���m�̊�]�ɂ��ẮA�u���錩���݂������Ă��Ȃ��Ă��A�m�肽���v�l��72.1���ł���A30��A40��ō����X���ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B �@�܂��A�]����1-2�����Ɍ���ꂽ��A�u����ʼn߂��������v�l��8�������A���ꂪ�u�����\���Ǝv���v�l�́A�j����17�|�C���g�̑傫�ȍ�������A�ƕ��Ă���B ����������Z���^�[�@2008�N9��26�� |
|||||||||||||||||||||
| ���ꂩ��̊ɘa�P�A�@�X�s���`���A���P�A�C�Ƒ��P�A�̏d�v�������� | |||||||||||||||||||||
| �@"�r���Ɖ\QOL�̎��_����"���e�[�}�Ɍf���C�_�ˎs�ŊJ���ꂽ��10��QOL������Ċ��Z�~�i�[�̓��ʍu���u���ꂩ��̊ɘa��Áv�ł́C����w�@�̔��ؓN�v�w�@�����C�ɘa�P�A������ŋ߂̘b��ɂ��ču�����C���ꂩ��̊ɘa�P�A�͑Ώێ������g�債�C�ΏǓI�ȑ��ʂ���\�h�I���ʂ��܂߂�悤�ɂȂ�ق��C�X�s���`���A���P�A��Ƒ��P�A���܂��܂��d�v�ɂȂ邱�Ƃ����������B ����X�s���`���A���P�A �@���؊w�@���́u�X�s���`���A���P�A���Ƒ��P�A���ȒP�ɍs������̂ł͂Ȃ��v�Ƒi�����B�X�s���`���A���y�C���Ƃ́C�������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ȕa��ɂȂ�����C���̐l�ɐ��b�ɂȂ�Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��Ȃ����肵���Ƃ��ɁC�����̑��݈Ӗ��≿�l�ւ�"��"�������ƂŐ������Y���Ӗ�����B�Ⴆ�C����ȂɂȂ��Đ����Ă��Ă����傤���Ȃ��C���������Ȃ�����Ȃɋꂵ�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��C�ǂ������ʂ̂�����撣���Ă��d���Ȃ��C����Ȏ������������Ă���Ȃ��ȂǂƂ���"��"�ł���B��������"��"�ւ̑Ή����X�s���`���A���P�A�ł��邪�C���������Ղȗ�܂��C�Ԉ���������ɂ�芳�҂̃X�s���`���A���y�C�����������Ă���B �@�܂��C�Ƒ��P�A��3��v�f�͗\���ߒQ�̃P�A�C���̎�e�ւ̉����C���ʌ�̔ߒQ�̃P�A�ł��邪�C�����ł��X�s���`���A���P�A�Ō����铯�l�̉߂����J��Ԃ���Ă���B�����C��4���̈⑰�����ʌ�̂炩�������ƂƂ��āu���͂Ɏ����̋C���𗝉����Ă��炦�Ȃ������v�C�u���͂���v�����̂Ȃ����t��������ꂽ�v���Ƃ������Ă���B���w�@���́u�v����肪�Ȃ��ƌ����Ă��C���ӂ���ł͂Ȃ��C�P�ӂ���̂��́B�����ɔߒQ�P�A�̓���̗v��������v�Ǝw�E����B�P�ӂɂ��s�ׂ͐����悤���Ȃ�����ł���B ����I�ԓx�Ǝg�̓��ݍ��݂��� �@�ł́C�ǂ�����悢�̂��B���؊w�@���́u����I�ԓx�Ǝg�̓��ݍ��݂ɂ��̃|�C���g������悤�Ɏv���v�Əq�ׂ�B �@����I�ԓx�Ƃ́u���Ȃ��������������Ƃ����͂��̂悤�ɗ������܂������C����ł�낵���ł����v�ƁC���҂̌��t�������̌��t�Ɍ��������Ċ��҂ɕԂ��Ă������ƁB���̂悤�ȑԓx�Ɏg�̓��ݍ��݂������C���҂̃��[�h�ʼn�b���p�������C���҂ɑO�q����"��"�i�㉹�j�����ׂēf���o���Ă��炦�悢�B �@�Ƒ��ɑ���\���ߒQ�̃P�A�⎀�̎�e�ւ̉��������l�ł���B���̏ꍇ�́C���҂̖ڂ̑O�ōs���Ȃ����߁C�ꏊ�⎞�Ԃ����āC�߂��݂��Ƃ��Ƃ�\�����Ă��炤�B�������邱�Ƃɂ��C���ʌ�̔ߒQ����̉v���Z�X���X���[�Y�ɂ����C�܂����ʌ�̔ߒQ�P�A�ɂ́C�⑰���m�̎x�������i�����O���[�v�j���L���Ȃ��Ƃ������B �@���w�@���́u���ꂩ��̊ɘa�P�A�ł́C�X�s���`���A���Ȓɂ݁C�Ƒ��̒ɂ݂ɂ��ϋɓI�ɂ�������Ă����K�v������v�ƌ��B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N10��2�� |
|||||||||||||||||||||
| �ċz��O���̈ӎv���d���@�ϗ��ς��ٗ�̒@�`�k�r�j���̗v�]�@��t�A�a�@���͓�F | |||||||||||||||||||||
| �@��t������s�̋T�c�����a�@�̗ϗ��ψ�����Ƃ�4���A�S�g�̋ؓ��������Ȃ��Ȃ��a�A�؈ޏk�������d���ǁi�`�k�r�j�̒j�����҂���o�����u�a�i�s���Ĉӎv�a�ʂ��ł��Ȃ��Ȃ������͐l�H�ċz����O���Ăق����v�Ƃ����v�]���ɂ��āA�ӎv�d����悤�a�@���ɒ��Ă������Ƃ�10��6���A���������B �@�`�k�r���҂̂��������v�]�ɂ��ĕa�@�̗ϗ��ς����f�����͈̂ٗ�Ƃ����B �@���a�@�̋T�c�M��@���́u���s�@�ł͌ċz����O���i�E�l�e�^�ȂǂŁj�ߕ߂���鋰�ꂪ����A����B�Љ�I�ȋc�_���K�v�v�Ƃ��āA�ċz��O���ɂ͓�F�������Ă���B��a���҂��x������W�҂���u�����̈ӎv�ŊO�����Ƃ�F�߂�A���҂����͂ɋC���˂��Ď���I��ł��܂����ꂪ����v�ƌ��O���Ă���B �@���҂͓������ɏZ��68�̒j���ŁA49�ł`�k�r�ǁB1992�N�Ɍċz����Ɋׂ�A���a�@�Ōċz���t�����B���݂͂������ɓ����ق��ɃX�C�b�`��t���ăp�\�R���𑀂�A���M�����Ȃǂ����Ă���B �@�@���̎�������ϗ��ς͍��N3���܂�3��ɂ킽���ċc�_�B�ψ����̓c������T�]�_�o�O�ȕ����ɂ��ƁA�T�d�ӌ������������A�ŏI�I�ɂ�14�l�̈ψ��S�����u�O�����ɐ�����{�l�ƉƑ����\���l������Ŗ]��ł���A�ӎv�ɉ����`�œ����Ă͂ǂ����v�Ƃ̈ӌ��ł܂Ƃ܂�A4���ɉ@���Ɍ����œ`���A���ӓ_�����ʂɂ܂Ƃ߂��B �@���ʂ́u�ӌ��͐^���Ɏ~�߂��v�Ƃ�����ŁA�i�P�j�{�l�̈ӌ�����͕͂̏ω�����\��������A�p���I�ɔc������i�Q�j�ӎv�a�ʂ��ł��Ȃ��Ȃ������ɂ��{�l�̈ӌ����m�F����K�v������A�\����͍�����-���ƂȂǂ��āB�u�ϗ��ς����ꂩ������ɍl��������v�Ƃ��Ă���B m3.com 2008�N10��7�� |
|||||||||||||||||||||
| �u�Ŋ��̓z�X�s�X�v�ߔ�������]�@�j��1,000�l�A���P�[�g | |||||||||||||||||||||
| �@�킪���ł͏I������QOL����ցC�z�X�s�X��ɘa�P�A�̑ۑ�ƂȂ��Ă���B�i���j���{�z�X�s�X�E�ɘa�P�A�����U�����c���S���̒j����1,000�l�Ɏ��{�����A���P�[�g�ł́C�Ŋ��̗×{�����ŕK�v�ɉ����z�X�s�X�E�ɘa�P�A�a���ɓ��肽���Ɠ������l���ߔ����ɂ̂ڂ�C�I������Î{�݂ւ̊S���������Ƃ��킩�����B����C����ł̍Ŋ���]�ނ��̂́u�����͓���v�Ƃ���l��6������C���x���p�C�Ƒ��̖���S�z���čݑ��Â�������߂Ă�����Ԃ����炩�ɂȂ����B 8�����u����ł̍Ŋ��v���肤 �@�A���P�[�g�́C�����c�����N2��12������2�T�Ԃ����āA��ꐶ���o�ό����������������j�^�[���璊�o����20�`89�̒j��1,010�l�ɑ��ėX���Ŏ��{�B�L������97.2���i982�l�j�ł������B �@���m��72.1�����Ȃ��錩���݂̗L���ɂ�����炸��]����Ɠ������B�N��w�ʂł�30�Αオ80.2���C40�Αオ73.9���ƁC6���䂾�������̔N��w���������B�]��1�`2�����̏ꍇ�Ɂu�������邩�ǂ����͕ʂɂ��Ď���ʼn߂��������v��80.1���ɂ̂ڂ����B���������������ƁC�����\�ƍl����l��18.6���ɂ������C���ɏ�����10.3���ƒj����3����1���x�ł������B �Ƒ��ƍݑ�オ�s�� �@����ōŊ����߂������߂̏����Ƃ���66.5�����u��삵�Ă����Ƒ������邱�Ɓv���������B����Ɓu�}�ώ��̈�Ñ̐������邱�Ɓv�i46.7���j�C�u�Ƒ��ɕ��S�����܂肩����Ȃ����Ɓv�i43.5���j����ʂ��߂��B�u���f���Ă�����t�����邱�Ɓv��42.8����4�����C�����c�́u��삷��Ƒ��̕��S�y���ƍݑ��Ñ̐��̐���������̏d�v�ۑ�v�ƕ��͂����B�܂��C�O���i2005�N�j�ɔ�ׁu���f���Ă�����t�����邱�Ɓv��5.5�|�C���g�C�u�Ƒ��̗��������邱�Ɓv��32.3������5.3�|�C���g�ƁC���ꂼ��5�|�C���g�ȏ㑝�������Ƃ���C�����c�́u����ōŊ����߂������߂ɂ͉Ƒ��ƍݑ��̑��݂��s���v�Ƃ̌������������B �@���ɒ��ʂ����Ƃ��̐S�̎x����1�ʂ��z��ҁi77.4���j�C2�ʂ��q���i71.4���j�ŁC���ꂼ��3���ȉ��������F�l���t�C�����a�C�������ԂȂǂƂ̍����ۗ������B�c���ꂽ���Ԃ̉߂��������u�Ƒ��Ɖ߂������Ԃ𑝂₵�����v��61.5���ōő��ł������B���Ȃ݂Ɂu�ۂ�����v�Ɓu�������v�̂ǂ��炪���z�̎��ɕ����Ƃ�����ɂ́C73.9�����u�ۂ�����v��I�B���̗��R�ōł����������̂́u�Ƒ��ɖ��f�����������Ȃ�����v�i79.3���j�ŁC�Ƒ��Ɖ߂��������Ǝv�����̂́C���f�͂��������Ȃ��ƍl���Ă��邱�Ƃ��w�i�ɂ���ƌ�����B�u�������v�h�̍ő����R�́u���̐S�Â��������������v�i80.9���j�ŁC�u�����ł��������������v�i30.3���j��傫�����������C�������߂鎞�Ԃ�]�ސ������|�����B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N10��16�� |
|||||||||||||||||||||
| �I�[�X�g�����A�A�q�ǂ��z�X�s�X��K�˂� | |||||||||||||||||||||
| �@�u�����w�v����Ƃ���A���t�H���X�E�f�[�P����q�喼�_�������X����{�A��ÊW�҂�̌��C�Ƃ��ăI�[�X�g�����A�̃z�X�s�X��K��A���{�ɂ͂Ȃ��q�ǂ����̃z�X�s�X�Q�{�݂����@�����B���s��ނ���A�q�ǂ��̏I������Âɂ��ăI�[�X�g�����A�̌�������B �@�q�ǂ��z�X�s�X�͉p�����N���ŁA�W�Q�N�ɃI�b�N�X�t�H�[�h�Ɂu�w�����E�_�O���X�E�n�E�X�v���ł����̂��n�܂�B�p���ɂ͂T�O�{�݈ȏ゠��Ƃ���A�I�[�X�g�����A�ɂ͂R�{�݂���B���@�����̂́A�ő�̓s�s�V�h�j�[�ɂ���u�x�A�E�R�e�[�W�v�ƁA�����{�����ɂ��鍑���ŌẤu�x���[�E�X�y�V�����E�L�b�Y�v�B �@�q�ǂ��z�X�s�X�̑Ώۂ́A����Ɍ��炸�A�������߂Ȃ����܂��܂ȕa�C�̎q�ǂ������B�t������ʼn�삷��Ƒ����x����B�Ŋ����}�����Ƃ��ė��p����P�[�X�͂ނ��돭�Ȃ��A���@��𗣂�Ēn��ɋA��A�ƒ�ōŊ����}���邽�߂̎菕��������̂���Ȗ������B�{�݂̖��̂�ŔɁu�z�X�s�X�v�̕����͂Ȃ��A�Â���ꂵ����A�z�����錾�t�͎g��Ȃ��B �@����1�A�V�h�j�[�k���̊C������ɋ߂��u�̏�ɂ���u�x�A�E�R�e�[�W�v�́A�V�h�j�[�̖��Ԏq�ǂ��a�@���O�P�N�ɊJ�݂����B�{�ݖ��ɂ́u�L�����v��̃R�e�[�W�̂悤�Ȋ��o�Ŋy����łق����v�Ƃ̊肢�����߂��A������ł͈����邵���召�̃N�}�̂ʂ�����݂��o�}����B�{�݂ŕ�炷���u�X�N�[�^�[�v���X�^�b�t�̈���Ƃ����B �@���シ������P�W�܂ł̎q�ǂ����؍݂��A���N�W���܂łɂR�S�V�l�����ꂽ�B�_�o�̓�a��_�o�؎������S�̂̂S�����ŁA���������]���܂ЂȂǂ̐�V����Q�������B�����ōŊ����}�����q�ǂ��͈ꕔ�ŁA�Ƒ��ŒZ���h������u���X�p�C�g�v��A�q�ǂ��Ǝ��ʂ����Ƒ����Ώۂ́u�ߒQ�P�A�v������B �@�I�����̑؍݊��Ԃɐ����͂Ȃ����A���X�p�C�g�ȂǂɎg���ꍇ�͍Œ��W���ԁB��삷��e�̐��_�I�E���̓I���S�̌y���ƁA�Ƒ��ʼn߂�������ꂽ���Ԃ��ɂ��邽�߁A�Ǝ��͂��ׂĐE����{�����e�B�A����s���A�Q�S���Ԏ蓖�Ă�_�P�A������B�q�ǂ��ɑ��ẮA�V�т�ʂ��ĕa�C���Q����C��������������悤���g�ށB�����a�C�����q�ǂ����W�߁A�{�����e�B�A���L�����v�ɘA��Ă������Ƃ�����B �@��Q�̉ƒ�Ƃ��ė��p���Ă��炤�̂����O�ŁA�h������H����Ȃǔ�p�͂��ׂĖ����B���ݔ��P�O���~�ƔN�Ԗ�P���V�O�O�O���~�̉^�c�����̂قƂ�ǂ͒n��Z����̊�t�Řd���A�s�����͎q�ǂ��a�@����Ă�B �@�{�݂ɂ́A�q�ǂ��̌��P�O�����ƁA�Ƒ����Q���܂�ł���Q����������B�����ł͈�Ís�ׂ͂����A���u�����g���B���p�X�y�[�X�ɂ̓e���r��c�u�c���y���ގ����o���A��������̑q�ɂ̂ق��A�������z���鏬�^�v�[���̂���u�X�p���[���v������B �@�X�p���[���ɂ͐��̂����炬�������A�u�n�C�h���Z���s�[�v�ƌĂ����₵�ɗ��p�����B�O�o������Ԃ����̎q�ǂ��ɂ́A�C���]���̌��ʂ�����Ƃ����B �@�ʓ��́u�N���C�G�b�g�E���[���v�ɂ̓v���C�o�V�[��ۂ��ߖh���ݔ�������A�e���v����{���߂��݂��Ԃ��A�吺�ŋ������Ƃ��ł���B�q�ǂ����e�Ɨ���ĂP�l�ŗV�Ԏ��ԂɎg�����Ƃ��ł���B�u�ߒQ�P�A�v�ɂ��K�v�Ƃ����B �@�V�h�j�[�x�O�ɏZ�ރw�����E�J�j���O�n������͂T�N�O����A�Q������̖��i�^���[����i�W�j�ƔN�S��قǗ��p���Ă���B�u�H�����������邱�Ƃ��炨�ނ����܂ŁA�f���炵�������Ă���B�o���R�j�[�Ŗ��߂鎞�Ԃ����Ă邱�ƂŐS�����炮�B�����q�ǂ����݂Ƃ�Ȃ�a�@�ł͂Ȃ��A�����������B���炩�ȋC�����ɂȂ��ł��傤�v�Ƙb�����B m3.com 2008�N10��20�� |
|||||||||||||||||||||
| �ݑ�ɘa�P�A�̏[���l�ވ琬���ۑ� | |||||||||||||||||||||
| �@��N�{�s���ꂽ������{�@�ōݑ�ɘa�P�A�̐���������j��������C���@�E�O���f�Â���ݑ�×{�Ɉڍs���閖�����҂��������Ă��邪�C�M���\���łȂ��n��ł͈�Ì���̍����������Ă���B��t���ŊJ���ꂽ��19����{�ݑ��Êw��̃p�l���f�B�X�J�b�V�����u�ݑ�I������Áv�ł́C�ݑ�ɘa�P�A�Ŋ��҂̎��Ȍ�����ǂ̂悤�Ɏx�����Ă����̂����b������ꂽ�B �ݑ�ɘa�P�A�̂���ׂ��p�@�����x������Ɋɘa�ɂȂ��� �@�R�[�f�B�l�[�^�[�߂����@���́C����̍ݑ�I�����P�A�i�ȉ��C�ݑ�ɘa�P�A�j�ɂ����鎩���x���̏d�v���ɂ��ďq�ׂ��B���̂Ȃ��ŁC�Z�݊��ꂽ�Ƃ�1���̑唼�����҂ƉƑ������ʼn��₩�ɉ߂������߂ɂ́C���Ҏ��炪�P�A�`�[������K�ȏ����C���Ȍ���ł��邱�Ƃ���Ƌ����B���̂��Ƃ��u�ɂȂǂ̋�Ɋɘa�ɂ����ʂ�����C���ʂƂ��ă����q�l�g�p�ʂ̈��艻�ɂȂ���Ƃ����B �K��Ō�t�s���@�ݑ�ɘa�P�A�̎��̊m�ۂ��ۑ� �@���l�s�`�k��ÃZ���^�[�K��Ō�X�e�[�V�����̉�����㎁�́C�s�s���𒆐S�ɋ}���ȍ�����i�ނȂ��ŁC�ݑ�ɘa�P�A���x����K��Ō�̃}���p���[�s�����[�������錜�O���q�ׂ��B2006�N�x��7��1�̊Ō�t�z�u�������Ë@�ւ̐f�Õ�V���Z����������a�@�̊Ō�t�̗p���������e���ŁC�K��Ō�t�̕s�������܂�����������Ƃ����B �@����C�֓��̓s�s���ł͋}���ȍ�����i�s���C2004�N�Ɣ�r����2015�N�̍���Ґl���͓����s�Ŗ�4���C��ʁC�_�ސ�C��t��3���ł͂��ꂼ��6?8����������Ɨ\������Ă���B����C�S���̖K��Ō�X�e�[�V�����̑����͖�5,470������2000�N���납��قډ����ŁC����}���������܂����{�݂�ݑ�ł̊ɘa�P�A�̃j�[�Y�ɑΉ��ł��邩�s���ȏɂ���B ���O�w�����쐬��ʂ��Ċ��҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������i �@������w��w�@��×ϗ��w����̖����^�q���́C���҂̎��Ȍ���̌����d���C��ÊW�҂Ɗ��ҁE�Ƒ��Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����𑣐i������c�[���Ƃ��Ď��O�w�������쐬����Ӌ`�ɂ��ďq�ׂ��B�����́C�č���100���l�ȏオ���p���Ă���"Five Wishes"���Q�l�ɂ������O�w����"����4�̂��肢"����Ă���C��Ë@�ւȂǂł̏����̉��ρE�g�p�������Ă���i�z�[���y�[�W�̃A�h���X�́Chttp://www1.ocn.ne.jp/~mbt/�j�B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N10��23�A30�� |
|||||||||||||||||||||
| 2008�N�x���C�t�E�v�����j���O�E�Z���^�[���ۃt�H�[�����u�I������ÁE���̗ϗ����ɂǂ����g�ނ��v�@�I������ÁE�ɘa�P�A�ł͗ϗ��I�z�����d�v | |||||||||||||||||||||
| �@����l�����܂��܂�������Ȃ��C�I������Â�ɘa�P�A�̗ϗ������d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă��Ă���B�����s�ŊJ���ꂽ2008�N�x���C�t�E�v�����j���O�E�Z���^�[���ۃt�H�[�����u�I������ÁE���̗ϗ����ɂǂ����g�ނ��@�Ō�E���E����҈�Âɂ�����QOL�̊m���v�ł́C�č��Ɠ��{�ŏI������Â�ɘa�P�A�ɒ��N�g����Ă����t����ъŌ�t��́C���҂����łȂ����҂̉Ƒ��Ƃ̂������C���ÂƂƂ��ɃR�~���j�P�[�V������ϗ��I�Ȕz�����K�v�ł��邱�Ƃ��������ꂽ�B �I������Â͊��Ғ��S�� �@�x�X�C�X���G���f�B�[�R�l�X��ÃZ���^�[�i�{�X�g���j�ɘa�P�A�Ō�t��Julie Knopp���́C���Z���^�[�ōs���Ă���I������ÁC�ɘa�P�A�ɂ��ĉ�����C�I������Â͏�Ɋ��Ғ��S�ŁC���͓G�łȂ��ƌ��_�����B ���҂ƉƑ����P�A�̈�� �@�ɘa�P�A�Ƃ́C(1)�ɂ݁C�Ǐ�̃R���g���[���C�őP�̋@�\���P�ɏd�_��u���������I�C�S�l�I�Ȏ��Âł���(2)��Ã`�[���Ɗ��ҁC���̊��ҊԂ̐������R�~���j�P�[�V�������܂P�A�̖ڕW�ɂ��Ęb���������̂�(3)���҂Ƃ��̉Ƒ����P�A�̈���Ƃ��Ĉ���(4)�P�A���ǂ��ōs���邩���l��(5)���҂̎���̎���̃P�A���܂ނƂ����B �@�܂����҂̃P�A�̖ڕW�́C(1)����ڎw����(2)�œ_�������Ă��邩(3)�S�l�I�����d�v�ł���B�P�A�Ɋւ���f�B�X�J�b�V�����́C(1)�@�\�I�ȕύX(2)���_�ʂ̕ω�(3)�V�����f�f(4)�}�����a�@�ւ̓��@?�Ȃǂ̉\�������邽�ߕK�v�ł���B����́C(1)�v���C�}���P�A�I�t�B�X(2)�}�����a�@(3)���n�r���e�[�V�����Ⓑ���P�A�Ȃǂ̉��{�݂Ȃǂōs���C���ނɎc���Ă����B �@��Ï]���҂́C(1)�\��(2)�����̌o��(3)�]���̎w�W(4)�ӎv����̑㗝�C���r���O�E�B���C�P�A�̃S�[���Ɋւ���b�������Ȃǂ�ʂ��Ċ��ҁE�Ƒ��̈ӎv����ߒ��Ŏ菕�����ł���B �u�S�ɂ�����v���I������Â̌� �@����w��w�@�ɘa��Êw�̍P���ŋ����́C����܂�20�N�ԃz�X�s�X�ɘa�P�A�Ɍg����Ă����o������C�킪���̏I������Â̖��_�ɂ��ču���B�u�S�ɂ�����icare�j�v���Ƃ��I������Â̌��ł���Əq�ׂ��B �@�P�A�ɓK���ƌ��E�͂Ȃ� �@�܂��C�P�������́u�S�ɂ�����icare�j���Ƃ́C�K���ƌ��E�̂Ȃ����̂Ŋɘa�P�A�̖{���Ȃ̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ��B �@����Љ�̉��l�ςƂ��āC�x�C�Ⴓ�C���N��3���d������Ă���B���̈���ŁC�n���ҁC����ҁC�a�l�����ʂ���Ă���B����́C�����̉��l�ςɂ��čl���Ă����K�v������Ƌ^��𓊂��������B�܂������^�u�[������Ă��邪�C���ɂ͌��肪����C���悭�����邽�߂ɂ́C�����ӎ����Đ����Ă������Ƃ��d�v���C�Ɠ������͎w�E�����B �@���݂̏I������Â͎��Â����S�ł���C���Âł��Ȃ��ꍇ�͏Ǐ�ɘa��P�A���s�\���ɂȂ�C���_�I�x�����s�����邽�߁C���҂͌ǓƂƕs���̂Ȃ��ōŊ����߂������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�����ŁC���ÂƃP�A�̓K���Ȕz�������߂��Ă���B �@�܂��C�����Âł͐f�f�⎡�Âɂ�鎡�����D�悳��C�Ǐ�ɘa�͐ϋɓI�ɍs��ꂸ�C����⌤�C���\���ɍs���Ă��Ȃ��B���@�����ɏǏ�ɘa���\�ɂȂ�C�O���ʉ@�⎩��×{���\�ɂȂ�B�������C�I������1?2�����ɕ����̏Ǐo������ƁC���@��]�V�Ȃ�����邱�ƂɂȂ�B�����ŁC��Ã`�[���͊��ҁE�Ƒ��Ƙb�������C�[���̂����œK�ȏǏ�̊ɘa���s���Ă����K�v������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N11��6�� |
|||||||||||||||||||||
| ��13����{�ɘa��Êw��@�Ǐ�ɘa�̂��߂̍ŐV�̋Z�Ƃ��̊��p�@��T�� | |||||||||||||||||||||
| �@����ɔ����S�g�̋�ɂɑ���ɘa��Â̗����x�ꂪ�w�E����Ă���B�É��s�ŊJ���ꂽ��13����{�ɘa��Êw��̃��[�N�V���b�v1�u�W�w�I�I���R���W�[�F�Ǐ�ɘa�ɂ�����ŐV�̋Z�v�ł́C�ɘa��ÃX�^�b�t�Ƃ��Ēm���Ă�������"�ŐV�̋Z"�̊T�����Љ�ꂽ�B �����Ǒ�@�܂������N�����Ă��邩�𖾂炩�ɂ���w�͂� �@�ɘa��Â��銳�҂ɋN���銴���ǂ͈��������Ȃǂɍ���������̂������C�s�������Ƃ͗l�����قȂ�B�É������É�����Z���^�[�����ljȂ̑�ȋM�v�����́C�ɘa��Âɂ����銴���ǂ̂������ɑΏ��ɒ��ӂ�v������̂Ƃ��ăJ�e�[�e���֘A���������ǁC�P���w���y�X�ɂ��S���E�畆�����ǁCC. difficile�֘A�����Ȃǂ������C���̋�̓I�ȑΏ��@����������B�܂��������́C�ɘa��Âɂ����銴���ǂɂ��܂��Ώ����邽�߂̕��@�Ƃ��ẮC�u�܂��C�����N�����Ă��邩�𖾂炩�ɂ���w�͂����߂���v�Əq�ׂ��B �K�Ȑf�f�Ǝ��ÂŏǏ��P����Ǘ�͑��� �@�ɘa��Â̌���ł́C���҂��ˑR�C�����s���̔��M���N�������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B��ȕ����́u���̌����Ƃ��Č����Ƃ��ꂪ���Ȃ��̂ɃJ�e�[�e���֘A���������ǂ�����v�ƌ����B����̓J�e�[�e���̗��u���ʂ����S�Ö����������ɂ�����炸���ǂ���B���M�C������ɂ����ŋǏ������ɖR�������Ƃ��������C�t�Ɍ����C�Ǐ������ɖR�������M�ł̓J�e�[�e�������ǂ��^���ׂ����ƌ�����B�����Ȍ����������Ƃ��Ă̓��`�V�����ϐ����F�u�h�E���ہiMRSA�j�Ȃǂ̃O�����z���ہC�Δ^�ۂȂǂ̃O�����A���ۂ���������B�f�f�͌��t�|�{�ɂ��m�肷��B���Â̓J�e�[�e���̔��������ŁC�R�ۖ�Ƃ��Ă̓o���R�}�C�V���ɃZ�t�F���n��Ȃǂp����B �@�ɘa��Â̌���Ŕ�������P���w���y�X�����ǂɂ́C�Ɖu�}����X�g���X�̉e���Ȃǂ���C����߂ďd�ĂȂ��̂������B���������Ċɘa��Âɏ]�������t�́C�����납�炱�̂��Ƃɗ��ӂ��C���������d�ĂȃP�[�X�ɑ������Ă������ɑΏ����邱�Ƃ����߂���B �@�ɘa��Âɂ�����@�����ǂ̉����̍ő�̌�����C. difficile�����ł���B�f�f��C. difficile�g�L�V�������ɂ�邪�C���ꂪ�A���ł�C. difficile������ے�ł��Ȃ��m���͍����B���������āCC. difficile������z�肵���f�f�I���Â��e�F����Ă���B���Âɂ̓��g���j�_�]�[����o���R�}�C�V���̓��������������B �@��������́C����܂łɊɘa��Â̌��ꂩ�犴���ljȂɊ�ꂽ�R���T���e�[�V�����̗��R�͂��C�ɘa��Âɂ����銴���ǐf�Âʼn������ƂȂ��Ă��邩���������C���̐��тɂ��ďЉ���B �@����ɂ��ƁC���v105���̃R���T���e�[�V�����̂����R�ۖg�p���53���C�R�ۖ�g�p���52���ł������B�R�ۖg�p��̂���36���́u�����ǂ��ǂ����킩��Ȃ��v�Ƃ������̂ŁC17���́u�K�Ȏ��Â��킩��Ȃ��v�Ƃ������́B�R�ۖ�g�p��̂���43���́u���Â��������P���Ȃ��v�Ƃ������̂ŁC9���́u���Ò��ɐV���Ȗ�肪���������v�Ƃ������̂ł������B�܂�C�R���T���e�[�V�����̂����̂��Ȃ�̕������C�u�����N�����Ă���̂��킩��Ȃ��v�Ƃ������R�Ő�߂��Ă��邱�ƂɂȂ�B �@���Ȃ݂ɁC�����ljȂւ̃R���T���^���g���105���̏Ǐ�̕ω�������ƁC64���ɉ��P���F�߂�ꂽ�B���Ȃ킿�C�����ǂƐf�f���t���C�K�Ȏ��Â��s���C�����̏Ǘ�ŏǏ��P���邱�Ƃ������ꂽ�B �@�ȏ�̐��т����āC�������́u�ɘa��Âɂ����銴���ǂɂ��܂��Ώ����邽�߂ɂ́C���̑���E�������肷��C���炩���ߌX����m���Ă����ȂNJ����ǐf�Â̊�{�Ƃ������ׂ��w�͂�����ɋ��߂���v�Əq�ׂ��B�܂��C�������́C�����Ǘ\�h�ɂ͉@����������d�v�ł���ƕt���������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N11��6�� |
|||||||||||||||||||||
| �}�b�T�[�W���i�s�����҂��u�ɂ��ɘa���A�C�������P����\�� | |||||||||||||||||||||
| �@�}�b�T�[�W���i�s�����҂��u�ɂƋC�����I�ɉ��P����\���������A���{���������_���������̌��ʂ����ꂽ�B �u�l�X�Ȏ��̏��K�͎����ɂ����āA�}�b�T�[�W�Ö@���u�ɂ⑼�̏Ǐ���ɘa����\������������Ă���v�ƃR�����h��w�f���o�[�Z��w����Jean S. Kutner���m��͋L���Ă���B �u�i�s���ɔ����u�ɂ́A�g�̓I�E���_�I��ɂ̌����ƂȂ�A���҂̋@�\�I�\�͂�QOL��ቺ������B�}�b�T�[�W�́A�Z���s�X�g�ɂ�����i���݊��A�R�~���j�P�[�V�����A���Ì��ʂ����Ƃ����~���j�A�����N�[�[�V���������̗U���A���t�E�����p�z�̘��i�A���ɍ�p�̑����A���ǂƕ���̒ጸ�A�l�̎�ɂ��������̉���A�������G���h���t�B���̕��o�����A�u�ɃV�O�i�����ɂ��鋣���I�Ȋ��o�h����ʂ��A��ɂ̃T�C�N�����Ւf����\��������v�B �@�{�����̖ړI�́A�}�b�T�[�W���i�s�����҂��u�ɂƋ�ɏǏ��ጸ���AQOL�����P������ʂɂ��ĕ]�����邱�Ƃł������B �u�}�b�T�[�W�́A�i�s�����҂��u�ɂƋC�����I�ɉ��P����\��������v�Ɩ{�����̒��҂�͋L���Ă���B�u�����I�Ȍ��ʂ��Ȃ����ƂƁA���Q�ʼn��P���݂�ꂽ���Ƃ���A���҂ւ̋C�z��ƊȒP�Ȑg�̂ւ̐ڐG�Ƃ�����@���A�{���ҏW�c�ɗL�p�ł���\�����������ׂ��ł���v�B m3.com 2008�N11��6�� |
|||||||||||||||||||||
| �I�����ɂ��Ă̘b�������ɂ���Ė������҂̐ϋɓI���Â���������\������ | |||||||||||||||||||||
| �@�O�����������{�����R�z�[�g�����̌��ʂɂ��ƁA�I�����ɂ��ėՏ���Ƙb�������ƁA�������҂̃X�g���X���y�����ϋɓI���Â���������Ƃ����B �u�I�����ɂ��Ă̘b�������́A���҂������߂Â������Ɏ�����ÂɊւ���ڕW�Ɗ��҂m�ɂ���@��ƂȂ�v�ƁADana-Farber���������i�{�X�g���j��Alexi A. Wright���m��͘_���ŏq�ׂĂ���B�u�����������̘b�������́A��w�I���Â̌��E�ƁA�����������Ă���Ƃ��������ɒ��ʂ��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���A�����͗����Ƃ��S���I�X�g���X�������N�����\��������B �@�I�����ɂ��Ă̘b�������ɂ���Ċ��҂̓]�A�����P����Ƃ����G�r�f���X���Ȃ���Ԃł́A��t��͊��҂̎������d�������Ƃ�����]���A�S���I�ȊQ���y�ڂ��Ƃ������O�Ɣ�r�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B �@�{�����̖ړI�́A�I�����ɂ��Ă̗Տ���Ƃ̘b���������A�ϋɓI���Â���菭�Ȃ����ƂƊ֘A�������ǂ�����]�����邱�Ƃł������B2002�N9������2008�N2���܂ŁA332�g�̐i�s�����҂Ɣ�����ȉ��҂�o�^�����玀�S���܂Łi�����l�A4.4�J���ԁj�ǐՒ��������B����ɁA��Ɏc���ꂽ���҂̐��_�����Ɛ����̎��𒆉��l��6.5�J����ɕ]�������B �@��͂ɂ��ƁA�u�I�����ɂ��Ă̘b�������́A�������߂Â����Ƃ��ɐϋɓI�Ȏ��Â����炷���ƁA����уz�X�s�X�ւ̏Љ�̎������������ƂƊ֘A����v�ƁA�������҂�͏q�ׂĂ���B�u�ϋɓI���Â͊��҂̐����̎��̒ቺ����ю��ʂւ̓K���s�ǂƊ֘A����v�B m3.com 2008�N11��6�� |
|||||||||||||||||||||
| ����̎q�̏I�����x���悤 | |||||||||||||||||||||
| �@���Â̂��ׂ��Ȃ��Ȃ�������̎q���̂��߁A�e���Ï]���҂�"�Ŋ��̓��X"�ɂł��邱�Ƃɂ��Ęb�������W���15���A���҉Ƒ��ł���u����̎q��������v�i�����j����t�s�̖������b�Z�ŊJ���B �@����́A��������̏I�����P�A�ɏڂ������H�����ەa�@�̏�����a��t��Ƌ��͂��āA�������̎��g�݂ƂȂ�w�j�u�^�[�~�i�����̊ɘa�P�A�̃K�C�h���C��-���̎q�̂��߂ɂ��邱�Ɓv�i���́j�̍쐬�Ɏ��g��ł���B �@�W��ł͌����������ɒ��ʂ���q�������́u���v�ւ̗����⌠���A�ݑ��a�@�Ȃǂł̎c���ꂽ���X�̉߂������A��ɂ̌y���A���ʌ�̐e�̃P�A�Ȃǎw�j�ɐ��荞�ޓ��e�ɂ��Ęb�������B �@�w�j�͗��N�x���Ɋ����\��ŁA����̔�����q����́u����1�ł͂Ȃ��A�ǂ�������B�e���t�A�w�Z�̐搶�Ȃǂ����̎q�̂��߂ɋc�_���邫�������Ɏg���Ăق����v�Ƙb���Ă���B m3.com 2008�N11��10�� |
|||||||||||||||||||||
| ����O�Ƀ��r���O�E�E�C�������A�u�^���v�U��������@�]�����N�u�����v�P�� | |||||||||||||||||||||
| �@�������������Ƃ��̎��Õ��j�����O�ɏ��ʂɎ����u���r���O�E�E�C���v�Ɏ^������l���U�����邱�Ƃ������J���Ȃ̃A���P�[�g�����ŕ��������B�������]�����N�ȓ��̖�����ԂɂȂ����Ƃ��A�������Â�]�ނ̂͂P�O�l�ɂP�l�������B �@�����͍��N�R���A��ʍ����T�O�O�O�l�ƈ�t���Ï]���҂X�O�O�O�l��ΏۂɎ��{�B�I������Â̂�������l���邽�߂ɂT�N���Ƃɍs���A����͂R��ڂŁA�S�̂̂S�U���������B �@����ɂ��ƁA���r���O�E�E�C���Ɂu�^������v�Ɖ�����ʂ͂U�P�E�X���ŁA�ߋ��̐��l�������������ŏ��̂X�W�N�ɔ�ׂP�S�E�R�|�C���g�������B��t�͂V�X�E�X�����^�������B���̂����A�u�@�������ׂ����v�Ɠ�������ʂ͂R�R�E�U���ɂƂǂ܂�A�u��t���Ƒ��Ƒ��k���A���̊�]�d����v�Ƃ̍l���͂U�Q�E�S���ɒB�����B�������A��t�ł͖@���������߂��̂��T�S�E�P���Ɖߔ����ɒB���Ă���B �@����A���������錩���݂��Ȃ��ƍ�����ꂽ�ꍇ�A�������Â�]�ނ͈̂�ʂ��P�P���A��t�͂V���B�Ƒ��̏ꍇ�ł́A��ʂłQ�S�E�U���A��t�łP�P�E�U���ƂȂ�A�����̂Q�{���x�ɑ������B m3.com 2008�N11��13�� |
|||||||||||||||||||||
| ��22����{�Տ����Ȉ�w��@IT�����ŕς��n���ØA�g | |||||||||||||||||||||
| �@�d�q�J���e������l�b�g���p���L����Ȃ��C�n���ØA�g��㎖��v�̃V�X�e�����l�ς�肵����B����s�ŊJ���ꂽ��22����{�Տ����Ȉ�w��̃V���|�W�E���uIT�ƈ�Áv�ł́C���[�����O���X�g�����p���C�ݑ�ł̊Ŏ����O���[�v�f�ÂŎx���钷��ݑ�Dr.�l�b�g�̊��������ڂ��W�߂��B �ꗼ�����Ɏ厡������� �@����s�ߍx�ň�t�̑����͂ɂ��ݑ��Â̎M�ƂȂ�g�D�Ƃ���2003�N�CNPO����ݑ�Dr.�l�b�g���ݗ�����Ă���5�N�B�O���[�v�f�Âƃ��[�����O���X�g�̊��p�𒌂Ƃ��銈���̎��ۂɂ��āC����ݑ�Dr.�l�b�g�����ǒ��߂锒�E���Ȉ�@�̔��E�L�@�������\�B���N2���܂ł�175��̎厡��Љ�̈˗����C����0.81���Ŏ厡�オ���肵�Ă���C�ݑ�ɘa�P�A�̕��y�Ȃǂւ̌��ʂ�����Ă���Ƃ����B �撣��Ȃ��ݑ�P�A��ڎw�� �@NPO����ݑ�Dr.�l�b�g�́C�J�ƈオ�O���f�Â��Ȃ���C�傫�ȕ��S���Ȃ��K��f�Â��ł���V�X�e���Â����ڎw���C(1)24���ԁE365���Ή��\(2)�d�q���[���ɂ��A�g�\��2���Q�������Ƃ��C�厡����̈�t���o�b�N�A�b�v����O���[�v�f�Ñ̐����\�z�B2008�N4�����݁C�K��f�ÂɑΉ�����A�g��i�厡��C���厡��j65�l�C��ȁC�畆�ȂȂǂ̋��͈�37�l�C�a�f�A�g�Ɍg���a�@��t36�l�C���v138�l�������o�[�Ƃ��Ċ������Ă���B �@���Ɠ��e�́C�މ@��ɍݑ�×{�Ɉڍs���銳�҂̎厡�オ������Ȃ��ꍇ�ɁC�o�^�����o�[�̂Ȃ�����厡��C���厡����Љ��B�����ǂ��˗��������ҏ����s��5�n��ɔz�u�����R�[�f�B�l�[�^�[��t�ɓ`�B�B�R�[�f�B�l�[�^�[��t�͊��Ҍl�����肳��Ȃ��悤�z�����Ď����C���Z�n�Ȃǂ̏������[�����O���X�g�ɒ��C��グ�����Ŏ厡��C���厡����茈�肷��B���N2���܂ł�175��̈˗�������C����8���ȏ�͈ꗼ�����Ɏ厡�オ���肵���B�܂��C�ǐՂł���154�ᒆ116�Ⴊ���S���Ă���C�����ݑ��48��Ɩ�4�����߂Ă����B �@2007�N�t����́C����f�ØA�g���_�a�@�̊ɘa�P�A�J���t�@�����X�Ƀ����o�[���Q�����C�ݑ�ڍs���������̊��ҏ���d�q���[���ŕ���悤�ɂȂ����B2008�N����͒n��A�g�ɔM�S�ȋ��_�a�@�̈�t�炪�����o�[�ɉ����C�d�q���[����Œ��ڍݑ�厡�����悤�ɂȂ����B���̂悤�Ɋ��҂̏���L����C2008�N�t�ȍ~�͍ݑ�ڍs�̓o�^�ǗႪ���ԕ���3�Ⴉ��9��ւ�3�{�ɑ������Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N11��20�� |
|||||||||||||||||||||
| ��34����{�f�Ø^�Ǘ��w��@��Ñi�ׂƐf�Ø^�Ǘ����I������Â̎��Ⴉ��l���� | |||||||||||||||||||||
| �@�����s�ŊJ���ꂽ��34����{�f�Ø^�Ǘ��w��̓��ʊ��u��Ñi�ׂƐf�Ø^�Ǘ��@�I�����ɂ�����ꎖ�Ⴉ��l����v�ł́C���ۂ̏I�������҂̐f�Ø^�ɑ��āC�I������ÂɊւ���K�C�h���C���ɂ�錟���Ȃ��ꂽ�B �Ƒ��̈ӎv�����ɓI���Â� �@���a��w�a�@�f�Ø^�Ǘ����̊��q�R�����́C�^�N4���ɐS�x��~�Ɋׂ�ً}���@���Ă���92�̒j�����҂̎�����Љ���B����ɂ��ƁC�f�Ø^�͊O���f�Ø^�C���@�f�Ø^�C�Ō�L�^������C�厡��̏�����Ō�t�̋L�ځC���҂̗l�q�C�����L�^�Ȃǂ������ɋL�q����Ă����B �@����̌o�߂�����ƁC���@�����̌ߌ�9���ɒj�����������Ă����×{�{�݂œ|��Ă���Ƃ�����{�݂̃X�^�b�t�ɔ�������C�~���~�}�Z���^�[�֔������ꂽ�B���������͐S�x��~�Ɛf�f����C���̌�A�h���i�������^�Ȃǂɂ��S�����ĊJ���C������Ԃɂ����܂����B����CT�����̌��ʁC�]�ޏk�C���O�����ɍ��������C�܂�������CT�ł͗����w���ɍd�����F�߂�ꂽ�Ƃ����B �@��6�a���ɂ́C���҂̉Ƒ��ɃC���t�H�[���h�E�R���Z���g�����{�����Ƃ̋L�q������B���̂Ȃ��ŁC�厡��͍̌���X���̌��ʂ������Čo�߂�������C����Ȏ����ċz���l�H�ċz�Ǘ����ɔF�߂�����̂́C���E���U�債�Ό����˂��Ȃ����Ƃ��������Ƃ����B �@���̐��������Ƒ�����CT�������˗�����C�������ʂ����������C�Ƒ�����_�H�̎g�p��������юg�p���~���v�]���ꂽ�B �@�܂��C�S�x�h�����s��Ȃ����ƁC�m�F�͉Ƒ�������̂��Ƃɍs�����ƁC�����ĕa����U�̊�]���������B �@��7�a���ߑO11��50���ɂ́C�]�����˂��F�߂��Ȃ����Ƃ������B����ɁC��13�a���ߑO10��10���ɂ��Ăь������s�������C�]�����˂͓������m�F���ꂸ�C�����ɐ_�o���Ȉ�ɂ��]�g�������s��ꂽ���C�L���Ȋ����d�ʂ͎�����Ȃ������B�����œ����ߌ�6���C�厡�ォ�犳�҂̉Ƒ��Ɂu�Տ��I�ɂ͔]���ƌ����Ȃ��Ă��������߂�Ƃ͍l���Â炢��ԁv�ƍēx�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�Ɋւ���������Ȃ���C�Ƒ�����l�H�ċz����O���ė~�����Ƃ̗v�]���������B �@���̂Ƃ��厡��́C�����_�ł͐l�H�ċz����O���������I�ɑΉ��ł��Ȃ����Ƃ���������B��������Ƒ�����́C�O�q�̓_�H�g�p�����Ɠ��l�Ɏ_�f�Z�x��������v�]������C�厡��͉\�ł���Ɠ������B �@��������_�f�Z�x��������Ȃǂ̑[�u�����ۂɍs���C��15�a���C�Ƒ�����̎莆�ɂ�肳��Ɏ_�f�Z�x���C�����܂ʼn����邱�Ƃ���]����C�Ƒ�������̂��ƂɎ��{���ꂽ�B��17�a���ߑO1��8���C���҂̎��S���m�F���ꂽ�B�����܂ł̈�Ñ[�u�Ɋւ���O���C���@�f�Ø^�ƊŌ�L�^�͂قړ����e�ł������B �厡��܂ވ�Ã`�[���ɂ��I�����̔��f���K�v �@���q���ɂ����ꂽ�f�Ø^�ɂ��āC���{��ȑ�w���x�~���~�}�Z���^�[�̉��c�T�s������͏I�������Â��K�ɍs��ꂽ���ǂ������ϓ_�ɃK�C�h���C���ɏƂ炵���킹�Č������B���̏����Ƃ��ẮC�����̈�t�i�厡��Ǝ厡��ȊO�̈�t�j�ɂ��I�����̔��f�C�{�l�̎��O�w������ѐ��O�ӎv�̊m�F�C�Ƒ��̈ӎv�m�F�C��Ã`�[���i�����̈�t�C�Ō�t����܂ށj�ɂ�鉄���[�u���~�̑I���̏��Ԃōs�����B �@�������́C�܂��ً}���@�������҂̗e�Ԃ��L�ڂ�����7�a������ё�15�a���̃J���e�ɒ��ڂ����B��7�a���̃J���e�ɂ͐[�����C���E�U��C�]�����ˏ����Ȃǂ̋L�ڂ�����C�����đ�15�a���ɂ͔]�g�����R�ł��邱�ƁC�����]���������Ȃ����ƂȂǂ��L�q����Ă����B �@�����̋L�ڂɂ��C�����ċz�̏����Ɋւ��Ă͊m�F���ł��Ă��Ȃ��������Ƃ���]���Ƃ͐f�f�ł��Ȃ��܂ł��C�]���ɋ߂���Ԃł���Ǝ厡��ɂ�蔻�f���ꂽ���Ƃ������������B���҉Ƒ��̈ӎv�Ƃ��ẮC��13�a���̋L�^�Ɋ��҂̐l�H�ċz����~�߂ė~�����Əq�ׂĂ��镔�����m�F�ł����B��14�C16�a���̐f�Ø^�ɂ́C�Ƒ��̈ӌ������厡�オ�_�f�Z�x��ቺ���C1�C�ʂ����Ȃ�����[�u��������ƋL����Ă���B �@��L���҂̐f�Ø^���������Ƃ���C�������́u�厡�オ��������u�⊳�҂̉Ƒ����������l���Ȃǂ����m�ɋL�ڂ���Ă���v�ƕ]�������B�������C���{�~�}��w��̓��K�C�h���C���ɂ����āC�I�����̔��f�͎厡��Ǝ厡��ȊO�̕����̈�t�ɂ���Ĕ��f�����ׂ��Ƃ��Ă��邱�ƂɐG��i�\�j�C�u�����̈�t���������ďo�������_�ł���Ƃ͏\���Ȋm�F���ł��Ȃ������v�Ǝw�E�����B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N11��20�� |
|||||||||||||||||||||
| ��63��QOL������@��Õ���j�~��QOL�̊ϓ_�ōl�@ | |||||||||||||||||||||
| �@�����s�ŊJ���ꂽ��63��QOL������ł́C���ʍu���̏o���҂�Q���҂炪QOL�̊ϓ_�����Õ���̗\�h���l�@�����B �u���������v�Ȃ�4�̌������ �@���H�����ەa�@�̓��쌴�d���������́C����QOL�ƈ�Ê����\�z���C����������菇�ɂ��ču�������B���������́CQOL�ɂ�(1)�Љ���̔\��(2)�����E�m�����ۂ����(3)�ꂵ�݂̊ɘa(4)���������\��4�̌���������ƑO�u�������B�����āu�l�͎���������^�����Ă���C�����̖����L�p�Ɏg���Ă���Ǝ����ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ڕW�i�S�[���j�ւ̒B�����ȂǁC�炭�Ă����������������ď��z���邱�ƂŐ�����������v�ƁC�I�����̊��҂ɂƂ��Ă͐����������������d�v�ł��邱�Ƃ����������B ��t�͌��t�������E�l�ł��� �@���쌴�������͕č��Ɠ��{�̊ɘa�P�A�a���̈Ⴂ����C�I�����ɑ��鑨������_�����B���{�ł͊��҂Ɍ���p�ӂ��邪�C�č���4�`5�l�̑��������嗬�ł���Ƃ����B���̂��߁u�č��ł͕����ɂ���ł�����C�Ϗ܂��y���߂�������Ԃ��ȒP�ɒu����B���҂��ǓƂȂ܂��Ȃ��Ȃ��悤�ɂ��Ă���v�Əq�ׂ��B�܂��C�č��̊ɘa�P�A�ɂ�����ی��f�Â͂����鎾���ɑΉ����Ă��邪�C���{�͖@���ł���ȂLjꕔ�����Ɍ����Ă���_���������ׂ��ۑ�Ƃ����B �@��w�҃E�C���A���E�I�X���[�́u��w�̓T�C�G���X�ł͂Ȃ��C�A�[�g�ł���v�Ƃ������t���Ɂu�a���Ȃǂ����m���邱�Ƃ��C����Ӗ��ł̓A�[�g�ł���v�Ǝ咣�����B���������́u�w�]����1�T�ԁx���Ƃ��ȒP�Ɍ����Ⴂ��t�����邪�C��t�͌��t�������E�l�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�ǂ��܂Ō����ׂ����C�����ׂ��ł͂Ȃ����ȂǁC�����̂Ȃ��ŏ������ςݏグ�Ȃ��犳�҂̐S�������ق������Ƃ��̗v�v�Ƒi�����B �@�Ō��QOL�̌���ɂ͑��҂̖������Ƃ����p�����s���ł���C�u��t���������a�̈ێ������ɂ��ׂ�����ɂ���B�Љ�I��QOL����ɂ͖����������i���Ȃ���Ȃ炸�C������ǂ��q�������ɓ`���邩���l���ė~�����v�ƌĂт������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N12��4�� |
|||||||||||||||||||||
| �u���y���v�̏u�Ԃ�����ց@�p�e���r�A���E�����Ɣᔻ | |||||||||||||||||||||
| �@�p�e���r�ǂ��A���͂Ōċz���ł��Ȃ��Ȃ錴���s���̕a�������A2006�N�Ɂu���y���v�����p���l�j���̎��S�̏u�Ԃ����߂ĕ�������\�肾�Ɣ��\�A���E���������Ƃ̔ᔻ���Ă���B �@�X�J�C�j���[�Y�E�e���r��12��10���ߌ�9���i���{����11���ߑO6���j�����������B���y���͉p���ł͈�@�Ƃ���Ă���A�X�J�C���͔����y���̊����Ƃ�̔ᔻ�ɑ��u�j����������]�v�Ɣ��_���Ă���B �@�ԑg�͋c��ł����グ���A�u���E���p�́u�����Ȗ��ŕ����̋K�����ǂ����f����v�Ɠ��ق����B �@���̒j���������i�T�X�j����5�J���̓��a�̖��A���̏������ň��y����F�߂Ă���X�C�X�̕a�@�ŁA�Ȃ�����钆�A�^�C�}�[���g���Đl�H�ċz����~�߁u���E�v�����B m3.com 2008�N12��11�� |
|||||||||||||||||||||
| �e���r�Ɏ^�ۂ̈ӌ��������@�p���́u���y���v���� | |||||||||||||||||||||
| �@�p�X�J�C�j���[�Y�E�e���r��12��10���A2006�N�Ɂu���y���v�����p���l�j���̎��S�̏u�Ԃ�\��ʂ���������B�����҂̊S�͍����A�^�ۂ��܂��܂Ȉӌ�����ꂽ�B �@�m��h����́u���N���ꂵ��ŖS���Ȃ����v���v���o�����B�ɂ���Ă͎��疽�����������ׂ����v�Ƃ̈ӌ�����ꂽ���A�u���y�����B�e���邱�Ƃɂ͓��ӂł��Ȃ��B�p��m��v�Ȃǂ̔ᔻ�I�Ȑ����オ�����B �@�p���ł͍ŋ߁A�������������O�r�[�I�肪���y�����邱�Ƃ�I�сA�������`�������e���@�I�ӔC�����Ȃ����ʂ��ƂȂ������Ƃŋc�_���ĂB���̒���Ƃ����āA���y���ɔ�����c�̂��u���������҂������Ȏ��݂��v�Ɣ��������߂Ă���B�e���r�Ǒ��́u�l�X���S�����߂Ă���e�[�}�ɂ��ċc�_���h������̂͏d�v���v�Ȃǂƕٖ������B m3.com 2008�N12��11�� |
|||||||||||||||||||||
| �������̖@������i����@���J�ȁE�I������Í��k��ŊW�c�̂��q�A�����O | |||||||||||||||||||||
| �@12��15���C�����J���ȁi���J�ȁj�̑�2��I������Â̂�����Ɋւ��鍧�k��J����,���{����������Ȃ�5�c�̂���q�A�����O���s��ꂽ�B����������̈�`���O���́C�������̖@���������炽�߂đi�����B �@�����k��̖ړI�́C���҂̈ӎv�d�����]�܂����I������Â̂�������������邱�ƂŁC2��ڂ̍���͏I������ÂɊW�̐[��5�̈�ÁE���Ғc�̂̑�\�҂��Q�l�l�Ƃ��ď��v����C�ӌ����q�ׂ��B �@���{�����������1976�N�̔����ȗ��C���r���O�E�E�C���i�������̐鐾���j����Ď����̎��l�Ɋ֗^�ł��錠���C���R�Ɏ����}�����錠�����咣���Ă����B��`���͂��̂悤�Ȋ�����ʂ��āC�������͍����̊Ԃɏ�������������邱�Ƃ��w�E�B���J�Ȃ�2007�N�Ɍ��\�����u�I������Â̌���v���Z�X�Ɋւ���K�C�h���C���v�ł��C�{�l�̈ӎv���ő�����d���邱�Ƃ����荞�܂�Ă���B �@�������C�����ɂ��ƁC�K�C�h���C���ǂ���ɏI������Â����{����C�����[�u�̕s�J�n�⒆�~���I�����ꂽ��C����ł͈�t�̖@�I�ӔC�������\��������C�������̕��y��j��ł���B���̂悤�ȏɑ��āC�����́u�{�l�̈ӎv�ɔ����ĉ����[�u����������̂́C��O�҂̉��l�ς̋����Ől�����Ƃ��Ă��������ׂ��ł͂Ȃ��v�Ǝ咣�B��������@�������C���炩�Ȏ��̌����������Љ�̏d�v�������������B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N12��16�� |
|||||||||||||||||||||
| �I�������ҁ@��t�Ƃ̑Θb�Ŏ��S���O��QOL���� | |||||||||||||||||||||
| �@�_�i�E�t�@�[�o�[�������i�{�X�g���j��Alexi A. Wright���m��́C��t�ƑΘb�������I�������҂ł́C�Θb�����Ȃ��������҂Ɣ�ׂĐ��_�I��ɂ𖡂키���Ƃ����Ȃ��C���O�̍Ō�̏T�ɐϋɓI���Â͍s���Ȃ��X��������CQOL�������X���ɂ���Ɣ��\�����B �@�I�����ɂ�����Θb����C���҂͎������]�ގ��Â݂̍����C���̃S�[���m�ɂ���@�������B�������C���̂悤�ȑΘb�Ŋ��҂͈�Â̌��E�Ɛl���ɂ͌��肪����Ƃ��������ɒ��ʂ��邱�ƂɂȂ邽�߁C�S���I��Y�̌����Ƃ��Ȃ肤��B �@����܂ł̌����ł́C��t�Ɗ��҂͎��ɂ��Č�邱�Ƃ����߂炤���Ƃ������X�������炩�ɂ���Ă���B�������C���ۂɂ��̂悤�ȑΘb���C���҂̐S���I��Y����і����̎��Ó��e�Ɗ֘A���Ă��邩�ۂ��ɂ��Č������������͂Ȃ������B �@�����ŁCWright���m��́C�������҂�ΏۂɁC�I�����ɂ������t�Ƃ̑Θb�����S�O�Ɏ鎡�Ó��e�Ɗ֘A���邩�ۂ������������B����C�i�s���̂��҂Ƃ��̐e���̉���332�g���ΏۂƂ��C���҂�o�^�����玀�S�܂ŒǐՂ����B�ǐՊ��Ԃ̒����l��4.4�����ŁC���S����6.5������i�����l�j�ɂ͉��҂̐��_������QOL��]�������B�Ώۊ���332�ᒆ123��i37.0���j�����ۂɈ�t�ƏI�����Θb���s�����B �@�����̑Θb�́C��t�ƑΘb�����Ȃ��������҂ɔ�ׂāC�l�H�ċz�i1.6����11.0���j�C�h���p�{�s�i0.8����6.7���j�CICU���@�i4.1����12.4���j�̉��L�ӂɏ��Ȃ��C���S�O�̐ϋɓI�Ȉ�É�����L�ӂɌ������Ă����B �@�܂��C�I�����Θb���s�������҂ł́C��葁���Ƀz�X�s�X�{�݂ɓ��@���Ă����i65.6����44.5���j�B�z�X�s�X���@�����̑����͊��҂�QOL���P�Ɗ֘A���C�ϋɓI�Ȉ�É���̑����͊��҂�QOL�ቺ�Ɗ֘A���Ă����B ���f�B�J���g���r���[���@2008�N12��18�� |
|||||||||||||||||||||
| ��33����{���̗Տ�������@������{�@����2�N�`�ݑ�z�X�s�X�P�A���i�Ɍ������c�_ | |||||||||||||||||||||
| �@���N�{�s���ꂽ������{�@�ȍ~�C�z�X�s�X�P�A�͋}�����a�@��ݑ�ւƍL������邪�C�ݑ�z�X�s�X�P�A�i�ݑ�P�A�j�̕��y�͊e�n��ő傫�ȉۑ�ł���C����ɂ͒n��A�g���������Ȃ��B �@�V�g��w��w�@�z�X�s�X�E�ɘa�P�A�Ō�w�̋G�H�`���q�����ɂ��ƁC�z�X�s�X��Ð�i���ł���p���̃x�b�h��L���͑S�����ς�76���C���ύ݉@�����͓�12.9���B����{�݂ł�60�����މ@���čݑ�P�A�ֈڍs����B���@�̎���͍ݑ��]�҂��D�悳���B �@�ݑ�P�A�ł́C����ɒu�����ً}���g�p��܂̗��p���\�ŁC�������\�ȊŌ�t���Ǐ�̊Ǘ��ɓ�����B�K��̐��������͂Ȃ��C�Ƒ��̐��_�I�x�����܂߂ĊŌ�t�����f���C���܂荞�݂ŊŌ삪�s����ꍇ������B �@����C�킪���ł͌����J���ȁi���J�ȁj�u�I������ÂɊւ��钲������������v�ɂ��ƁC�ɂ݂���Ԃ̗×{�ōݑ�P�A������ł��闝�R�́C��삷��Ƒ��ւ̕��S���ł����������B�܂��C���N���\���ꂽ�K��Ō쎖�Ƌ���u����҂̃^�[�~�i���P�A�E�Ŏ��̏[���Ɋւ��钲���������Ɓv�ł́C�I��������삷��Ƒ��̕s����Ƃ܂ǂ��̐�������C�K��Ō�t�̓^�[�~�i���P�A���J�n����ɓ������ĉƑ����̈ӌ���c������悤�w�߂邱�Ƃ����L���ꂽ�B �@����ɁC��Ìo�ό����@�\�u�K��Ō엘�p�҂ɂ�����I�����P�A�Ɋւ��钲���v�ł́C�ݑ�Ŏ��S�������͖{�l�ƉƑ��Ƃ��ɍݑ����]���Ă������Ƃ����ꂽ�B �@�������́u�ӎv����̓����҂͖{�l�Ƃ��̉Ƒ��ł���C���̃v���Z�X�����J�ɍs���邱�Ƃ��C�ݑ�ł̊Ŏ�肪�i�ނ��߂̏d�v�Ȋ�{�I�����ł���B���̌}������b�������y����Љ�ɍL�߂Ă������Ƃ��C�n��A�g����эݑ�P�A�𐄐i�����ՂɂȂ�v�ƌ��_�����B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N1��1,8�� |
|||||||||||||||||||||
| �ݑ�I�������ҁF��Ɋɘa�̂��߁A��t�̎Ԃ��ً}�ԗ���--�����Ȃƌx�@�� | |||||||||||||||||||||
| �@�ݑ��Â���I�������҂̋�ɂ�a�炰�邽�߁A���y��ʏȂƌx�@���͂O�X�N�x����A�ً}���Âɋ삯�����t�̐�p�ԗ����A�ً}�����ԂɔF�肷�邱�Ƃ����߂��B�~�}�ԂƓ��l�Ɍ�ʋK���̈ꕔ���Ə�����A�D�摖�s�Ȃǂ��������B�]���͏a�Ɋ������܂��t�̓������x��邱�Ƃ���艻���Ă����B�����Ȃ́u��Â̏ꂪ���l�����钆�A�K�v�ȑ�B�s���������ȋ~�}�Ԃ̕⊮�ɂ��L�����v�Ƙb���Ă���B �@���H�^���ԗ��@�̕ۈ���Ɠ��H��ʖ@�̎{�s�߂̈ꕔ����������B���z�͂R���ŁA�{�s�͂S���P���̗\��B �@�����Ȏ����Ԍ�ʋǂɂ��ƁA�i�P�j��Ë@�ւ̏��ݒn���I�������҂̎���Ɨ���Ă���i�Q�j��t�ɏI������Â̎��т�����--���Ƃ��v���B�Ԏ�͖��Ȃ����A���̎ԗ��ɒ��ӊ��N�ł���ԐF�̌x�����ƃT�C����������t����K�v������B�h�F�ɂ͐������Ȃ��B�u���ӏZ���ɒm��ꂽ���Ȃ��Ƃ̊��҂̗v�]������A��ʎԂƂ̋�ʂ����ɂ������邽�߁v�i�Z�p���ہj�Ƃ����B �@�����J���Ȃ͂O�W�N�R���ɏI������ÂɊւ��钲�����T�O�O�O�l�ɑ��Ď��{�B�Q�T�Q�V�l�i������T�O�E�T���j�������B�������]���U�J���ȓ��̖�����ԂɂȂ����ꍇ�A�U�R��������×{����]�����B����łU�U���͎�������ƉB���R�́��Ƒ��ɕ��S��������i��W���j���Ǐ}�ς����Ƃ��̑Ή����s���i��U���j--�������B m3.com 2009�N1��13�� |
|||||||||||||||||||||
| ���ҁu����̐��E�v�u���܂�ς��v�M���銄���Ⴍ�@���傪�����ϒ��� | |||||||||||||||||||||
| �@���҂͈�ʂ̐l�ɔ�ׂāA����̐��E��܂�ς��Ȃǂ�M���Ȃ��X�����������Ƃ��A������̑�K�͒����Ŗ��炩�ɂȂ����B�܂��u�]�܂������v���}���邽�߂ɕK�v�Ȃ��ƂƂ��āA���҂����N���ƕς��Ȃ�������]�̂ɑ��A��t��Ō�t����������҂��銄���͒Ⴍ�A�F���̍�����������ɂȂ����B �@�����́A���҂̎����ς�m�邽�ߓ�����̌����`�[������N�P������P�N�Ԃ����Ď��{�B����a�@���ː��ȂɎ�f�������銳�҂R�P�O�l�Ɠ��a�@�̈�t�P�O�X�l�A�Ō�t�R�U�U�l�A����ג��o������ʂ̓����s���R�T�R�l�̌v�P�P�R�W�l�����͂����B���҂͂V�T�������Íς݂ŁA���Ò��̐l�͂Q�O���������B �@�u����̐��E������v�ƍl����l�̊����͈�ʐl�̂R�S�E�U���ɑ����҂͂Q�V�E�X���A�u���܂�ς�肪����v�͈�ʐl�Q�X�E�V���A���҂Q�O�E�X���ŁA���҂̊������ڗ����ĒႩ�����B������ړI��g�������������͊��҂̕�����ʐl��荂���A�u�����̎����悭�l����v�Ƃ����l�����҂ɑ��������B �@�u�]�܂������v�Ɋւ��ẮA���҂̑��������N�Ȏ��Ɠ��l�̐����𗝑z�Ƃ��A�u�i���ʂ܂Łj�g�̉��̂��Ƃ������łł���v�i�X�R���j�u�ӎ����͂����肵�Ă���v�i�X�W���j--�Ȃǂ�]�B����A��ÊW�҂͂����ɂ��Ă̊��҂����ꂼ��R�O-�S�O�|�C���g�Ⴉ�����B�܂��A�u�������܂ŕa�C�Ƃ����������Ɓv��]�ފ��҂��W���ɒB�������A��t�͂Q���ɂƂǂ܂����B m3.com 2009�N1��14�� |
|||||||||||||||||||||
| �]����Ԃ̏������珗���@�p�A�Q����ɒ鉤�؊J | |||||||||||||||||||||
| �@�p���ŁA�]����ԂƐ鍐���ꂽ�D�P���̏����i�S�P�j�ɒ鉤�؊J��p���{�����̐Ԃ�����܂ꂽ�B �@�p���^�C���Y�ɂ��ƁA�D�P25�T�����������͎���œ��ɂ�i������ɓ|��A�a�@�ɉ^�ꂽ����t����]����鍐���ꂽ�B�]�ɂł�����ᇂɂ��o���������Ƃ����B �@��t�َ͑��̔x�̐����𑣂�����ŁA2����ɒ鉤�؊J��p���s���A�̏d��1000�O�����̏��̎q�����܂ꂽ�B���̎q�͌��݁A�W�����Î��ɓ����Ă���B�����͂��̌�A���S�����B �@�F�l��1�l�́u�i�����̕v���Ȃ́j�����ێ����u���~�߂���ɁA���܂ꂽ�Ă̖��ɉ�ɍs���Ȃ�āv�ƌ��A�v�̕��G�ȐS�����v��������B m3.com 2009�N1��14�� |
|||||||||||||||||||||
| �č������w��ɘa�P�A�Ɋւ���Տ����j�ɂ��Đ����\ | |||||||||||||||||||||
| �@�y���V���x�j�A��w��ÃZ���^�[��Paul N. Lanken������́C�č������w��̊ɘa�P�A�Ɋւ���Տ����j�����\�����B �@�Տ����j�����ɂ��ƁC�ɘa�P�A�̒�`�͂��̐��N�ŕω����Ă���B�����C�ɘa�P�A�͏I�����P�A�Ƃ��ĊJ�n���ꂽ���C���݂ł͏I�����ł��邩�ۂ��ɂ�����炸�C�K�ȏꍇ�ɂ͂��ׂĂ̕a���ɑ��ēK�p�����B�܂��C�ɘa�P�A�͊��҂����łȂ����҂̉Ƒ��ƗF�l�̃P�A��C���Âɓ������t�ƈ�Ð��Ƃ̃P�A���܂ނ��̂Ɨ�������Ă���B �@�����ł́C�ɘa�P�A�͋�ɂ̗\�h�ƌy����ړI�Ƃ���ƒ�`����Ă���B���@�Ƃ��Ă͏Ǐ�̃R���g���[����x���̒�����C�ڕW��QOL�̈ێ��Ɖ��P�ł���B �@Lanken������́u�����ł́C�ɘa�P�A�͂��ׂĂ̕a���̊��҂����p�ł��C���҂Ƃ��̉Ƒ��̗v�]�ƈӌ��ɉ����Čʉ������ׂ��ł���Ƃ����T�O�������������Ă���v�Ɛ������Ă���B �@�č������w��́C�ɘa�P�A���s���ۂɂ͈ȉ���11���ڂ̐��I���l�ς�g�ݍ��ނׂ��ł���Ƃ��Ă���B �@(1)���҂Ƃ��̉Ƒ��ɏd�_��u�����Ƃ��ł��d�v�ł���B���l���҂͎��Â̖ڕW�����肷�錠����L���� �@(2)���҂ƉƑ��̈ӌ����m�F�E���d���� �@(3)�P�A�̌v��Ǝ��{�Ɋւ��āC���Ҏ��g���v�]����͈͂܂ʼnƑ��̊֗^�����サ�C�x������ �@(4)�ɘa�P�A�́C���҂��njƂȂ����ꍇ�ɊJ�n���ׂ��ŁC�ʏ�C���ÂƉ������Âp���� �@(5)���ɖ����܂��͐i�s���̌ċz�펾���C�܂��͏d�ǎ����̊��҂ȂǁC�nj����܂��͒v���I�����̂��ׂĂ̊��҂ɂ́C�N���Љ�I���ɂ�����炸�C�ɘa�P�A�ւ̃A�N�Z�X����ׂ��ł��� �@(6)�Ƒ��ɑ��鎀�ʃP�A�͊ɘa�P�A�ɂ�����s���ȗv�f�ł��� �@(7)��Ò҂͈��̊ɘa�P�A�\�͂����ׂ��ł���B����ɂ͋���C�P�����K�v�ł���B�܂��C�ɘa�P�A���Ƃ���K�X�������邱�Ƃ���ł��� �@(8)�ɘa�P�A�������ƂƉƑ��̐S���I�C����I�ȃj�[�Y��F�߁C�x�����ׂ��ł��� �@(9)���҂ƉƑ��̃j�[�Y�ɓK�ɑΉ����C���҂ƉƑ��̕�����_�I�ȉ��l�ςd���Ċɘa�P�A�Ɏ��g�ޓw�͂����� �@(10)�ɘa�P�A�Ɋւ�����I������s�� �@(11)�ɘa�P�A�Ɋւ��Ă���Ȃ錤�����s�� ���f�B�J���g���r���[���@2009�N1��29�� |
|||||||||||||||||||||
| ���҂̂U�����u�ɂ݊�����v | |||||||||||||||||||||
| �@�c����w�Ȃǂ��A���҂Q�W�X�T�l��Ώۂɒɂ݂Ɋւ���A���P�[�g�������Ƃ���A�����P�U�R�S�l�̂U�����ɂ݂������A�����W���������Â����Ă��ɂ݂��c���Ă������Ƃ����������B����̒ɂ݂Ɋւ����K�͂Ȏ��Ԓ����͏��߂ĂƂ����B���{�͂�������i��{�v��̒��Ŋɘa�P�A�̐��i���d�_�ۑ�ɋ����Ă��邪�A��w�̏[�������߂�ꂻ�����B�O�W�N�U-�V���A�U�X�̊��Ғc�̂̉���ɃA���P�[�g�p����z�z�����B �@�ɂ݂̌o���ɂ��ẮA�u�������Ă���v�i�Q�S���j�A�u���Ă������v�i�R�X���j�ƂU�����̊��҂��o���B���̂����A�����ȏ�̊��҂����퐶���Ɏx��𗈂��Ă����B �@�܂��A�ɂ݂̎��Â����U�U�X�l�ɐq�˂��Ƃ���A�u���S�ɂƂꂽ�v�Ɠ������̂͂P�V���̂݁B�u������x�Ƃꂽ�v�i�T�Q���j�A�u���܂�Ƃ�Ȃ������v�i�P�O���j�A�u�܂������Ƃ�Ȃ������v�i�S���j--�ȂǁA�W���ȏ�̊��҂ɉ��炩�̒ɂ݂��c���Ă����B�ɂ݂̎��Â̖����x�ł��A��������ꂽ�̂͂T�V���ɂƂǂ܂����B m3.com 2009�N2��5�� |
|||||||||||||||||||||
| �A����Ԃ̃C�^���A�l�������S�@������~��A�����ɏՌ� | |||||||||||||||||||||
| �@17�N�O�̌�ʎ��̂ŐA����ԂƂȂ�A�Ƒ��̗v����2���A�����[�u���~���ꂽ�C�^���A�l�����A�G���A�i�E�G���O��������i�R�W�j��9���A�k�����E�f�B�l�ɂ�����@��̕a�@�Ŏ��S�����B������~���߂����ẮA���[�}�@�����i�o�`�J���j������铯���̐��_��2�����Ă��������ɍ����͏Ռ����Ă���B �@���@��̕a�@�͊��ɉh�{�⋋�ǂ���̉h�{�Ɛ����̕⋋���~�߂Ă����B���ڂ̎����͕s�������A������~���u���e�������Ƃ݂���B �@������~�����߂�Ƒ��̑i���͍�N�A�ō��قŔF�߂�ꂽ�B�����E�h�x�����X�R�[�j�����́A������̈��y���Ƃ��Ĕ�������o�`�J���Ȃǂ̈ӌ��ɔz�����A������~��j�~���邽�߂ً̋}���߂��t�c���肵���B �@�������A���h�o�g�̃i�|���^�[�m�哝�̂͐��߂ɏ������������ɂȂ������߁A�������͂��炽�߂ĉ�����~�j�~�̖@�Ă�����ɒ�o�A�R�c���n�܂��Ă����B �@�G���O��������̎���9���A�R�c���̏�@�Ŕ��\����A�c���炪�قƂ������B m3.com 2009�N2��10�� |
|||||||||||||||||||||
| �������F�Z�݂Ȃꂽ�ƂŁ@�ݑ�×{�A�ǂ������H | |||||||||||||||||||||
| ���a�@�A�n��̈�t��ƘA�g���� �@������ �@�u�]���́A���҂����@���Ă����u�������n�܂炸�A���̂܂ܕa�@�ŖS���Ȃ�P�[�X�����������v�B���҂̍ݑ�×{�ɏڂ������{�L���s�̎s���L���a�@�̗я����t�͖��_���w�E����B �@���P�Ɍ����āA���J�Ȍ����ǂ͍�N���A��ÎҌ����Ɂu�ݑ�ɘa�P�A�̂��߂̒n��A�g�K�C�h�v���쐬�����B����ɂ��ƁA�ݑ�×{�̏����͓��@�̏u�Ԃ���n�܂�B���҂͈�t��Ō�t�ɑމ@��̊�]��`���A�K�v�ȏ���������W���˗�����B�a�@�́A���҂̑މ@��̐������������Ȃ���A�Ǐ�𑁊��ɔc�����A���Â�i�߂�B �@�ݑ�×{�ł́A�a�@�̎厡��ɉ����A�n��̐f�Ï���t��K��Ō�t�A�w���p�[�Ȃlj�쎖�ƎҁA��t�瑽�l�ȗ���̐l�̘A�g���K�v���B�މ@�O�ɁA�����̊W�҂Ɗ��ҁA�Ƒ����W�܂�ł����킹���J���A�������S�⊳�҂̕s���ւ̑Ή�����m�F���邱�Ƃ��]�܂����B �@�ǎ҂���̓����ɂ́u�Ƌ��ł��ݑ�×{�͉\���v�Ƃ̎��₪�������B�L���s�̓��c��@�i���c�וF�@���j�͎s���L���a�@�ƘA�g���A�ݑ�×{�̃l�b�g���[�N����i�߂�B���c����́u�Ƌ��̊��҂́w�Ƒ��ɖ��f��������x�Ɖ������������B�������A�ŏ��ɉƑ�����������`���A���̌�̓w���p�[��{�����e�B�A��̋��͂邱�Ƃōݑ�×{�͉\�ɂȂ�v�Ƒi����B �@����p �@��p�͏Ǐ��n��ɂ���ĈقȂ邪�A����قǍ��z�ł͂Ȃ��B���J�ȂȂǂ̎����ɂ��ƁA�ݑ�S���������s���{���قǂP�l������̘V�l��Ô���������B �@�ݑ�×{�̎�Ȕ�p�́A��t�̉��f���A�K��Ō�E���̗��p�����ゾ�B�����s�V�h��ŖK��Ō�X�e�[�V�������^�c����H�R���q�Ō�t�ɂ��ƁA���銳�ҁi��Õی��P�����S�j�́A�K��Ō���P�J���̂����P�V���v�Q�O�p���āA���ȕ��S�͌���P���U�O�O�O�~�������B�S�O�Έȏ�̖������҂͉��ی������p�ł���B �@���ۑ� �@�ۑ�́A�a�@���̗������B�n��ɐM���ł���f�Ï���K��Ō�X�e�[�V���������邱�Ƃ����߂���B���J�Ȃ��S���̑����a�@�₪��Z���^�[��t��ΏۂɎ��{���������ł́A�ݑ�×{�̓K�p�ƂȂ銳�҂̂��������]�@�������Ă����B����Z���^�[�̈�t�ł��u�ݑ�×{�̏\���Ȓm���◝��������v�Ɠ������̂͂T�V���������B �@���J�Ȃ͍ݑ�×{�𐄐i���邽�߁A�Q�S���ԑΉ��Ȃǂ������ɂO�U�N����ݑ�×{�x���f�Ï����x���n�߁A���݂P���J������B�����A���ۂ͍ݑ�ɑΉ����Ȃ��f�Ï��������B�K��Ō�X�e�[�V�������S���ɖ�T�S�O�O�J���i�O�V�N���݁j���邪�A�O�V�N�͏��߂đO�N������������B �@�܂��A�ݑ�×{�ɑ��銳�ґ��̗��������߂悤�ƁA�e�n�Ŋ��Ҍ����̑��k�����u�ݑ�ɘa�P�A�x���Z���^�[�v�̐ݒu���n�܂����B�����s�ݑ�ɘa�P�A�x���Z���^�[���^�c���铌�������N���a�@�i�����s�V�h��j�̐씨�����E�ɘa�P�A�����́u�a�C�ɂȂ��Ă��Ƃʼn߂����Ƃ����I�����ɋC�Â��Ăق����B�K���Ƃɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��A�Ǐ���������a�@�֖߂�����B���҂���]�ɉ����ĉƂƕa�@���s�����ł���d�g�݂�����Ă��������v�Ƙb���B m3.com 2009�N2��24�� |
|||||||||||||||||||||
| ������w�����F����Ɓu�������܂ł��������v�ӎ��@���҂ƈ�t�ɊJ�� | |||||||||||||||||||||
| �@������w�̌����O���[�v�ɂ��u�����ρv�Ɓu�]�܂������v�Ɋւ���A���P�[�g�ŁC���炪��������ɂȂ����ꍇ�Ɂu�������܂ŕa�C�Ƃ��������v�Ɠ��������҂̊�����81���ŁC��t��19���Ƒ傫�ȊJ�������邱�Ƃ��킩�����B�Ŋ��܂łӂ���ʂ�Ɏ����炵�����������Ɗ肤���҂̎v���ƁC���l���̎����Ŏ���Ă�����t�̍l�����e�����Ă���悤���B ���҂́u�����炵���v���d�� �@���A���P�[�g�͍�N1�`10���ɁC����w�a�@�ɘa�P�A�f�Õ����ŕ��ː��Ȃ̒���b��y�����Ɠ���w��w�@���N�Ȋw�E�Ō�w��U�ɘa�P�A�Ō�w����̋{�����ߍu�t�炪�C��Ï]���҂₪�҂̎��ɑ���ӎ��̔c����ړI�ɍs�����B�����ː��ȊO����f���̂���310�l�i�j��59���j�Ƒw����i�K����ג��o������ʎs��353�l�i��38���j�C���@�ł���f�ÂɌg����t109�l�i��88���j�ƊŌ�t366�l�i��4���j����̉��W�v�B���҂�75�������Â��݂ŁC20�������Ò��ł������B �@�]�܂������Ɋւ���u�������܂ŕa�C�Ƃ��������v�Ƃ̖�ɂ́C����81���Ǝs��66�����u��ɕK�v�v�C�u�K�v�v�C�u���K�v�v�Ƃ����B��t��19���C�Ō�t��30���ɂƂǂ܂����B���҂�s������t�ƊŌ�t���d���������ڂ́u��邾���̎��Â͂����Ǝv����v�i����92���j�C�u���邳�����킸�ɉ߂����v�i��95���j�C�u�����ӎ������ɁC�ӂ���Ɠ����悤�ɖ����𑗂��v�i��88���j�Ȃǂł���B ��Ï]���҂́u���ɔ�����v�X�� �@�t�ɁC��Ï]���҂����҂�s�����d�������̂́u�c���ꂽ���Ԃ�m���Ă����v�i��t89���j�C�u������l�ɉ���Ă����v�i�Ō�t92���j�Ȃǂł������B���҂�s���������ӎ������ɉ߂����čŊ����}�������ƍl�������C��t��Ō�t�͗]����c�����邱�ƂŎ����}���鏀���𐮂������Ƃ���X���ɂ������B �@�ǂ̉҂������x�d�����Ă����̂́u�̂ɋ�ɂ������Ȃ��v�C�u�����a�@�ȂǁC�������]�ޏꏊ�ʼn߂����v�C�u�M���ł����t�ɐf�Ă��炦��v�Ȃǂł������B �@�{���u�t�͖]�܂������ɑ���F���̊J���ɂ��āC�u���a���C���҂͂���������Ȃ�����O�����ɖ������߂������Ƃƍl���C��Ï]���҂͉��w�Ö@�Ȃǂ̐ϋɓI�Ȏ��Â��I�����ɂȂ��Ă������邱�ƂƑ����Ă���̂�������Ȃ��v�ƕ��́B�u�����܂ł���Ï]���Ҍl�̍l���ł���C�����Ċ��҂̋C���ɑ��閳�����⎡�Îp���̕\��ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ��B���̂����Łu��Ï]���҂͊��҂Ƃ̃M���b�v�܂��C�X�̊��҂��d�����邱�Ƃ��ꏏ�ɍl���ďI�����×{���x����K�v������v�Ƃ܂Ƃ߂��B �u���ւ̋��|�v�͈�t������ �@�����ςɂ��āu����̐��E�͂���v�C�u��₽����͂���v�̖���m�肵�����҂�2�����ŁC��ʎs������10�|�C���g���Ȃ������B�Ō�t�͂������4���ȏ�ł������B�S�̓I�ɁC�j�������������`���I�Ȏ���̐��E�ς�L����X���ɂ������B�^���_�I�Ȍ����ɂ��Ắu�����͌��܂��Ă���v�C�u�����͉^���ȂǂŌ��܂�v�Ƃ������҂�35�����ŁC4�Q�ōł����������B �@����y�����́u���҂͎���̐��E��썰�ȂǓ`���I�����ς��������C�^���_�I�ȌX����������v�Ǝw�E�����B �@�u�����|���v�Ɠ�������t��64���ŁC���҂�51���ƈ�ʎs����56�����������B�ގ�����u���͋��낵���v�Ƃ̖�ł��C�Ƃ���37���ł��������҂�s�������C��t�̂ق���48���Ƒ��������B���y�����́u��Î҂́w�����w�I�Ɏ��͖��ƂȂ�x�ȂǁC�����Ȋw�I�ɑ�����ӎ������邩��ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N2��26�� |
|||||||||||||||||||||
| �������ɘa�P�A�l�b�g���[�N�@�L��^�u�ɘa�P�A�n��A�g�p�X�v�J���ց@�Ǐ�ʖ�܃p�X���p�ō쐬 | |||||||||||||||||||||
| �@�������ɘa�P�A�l�b�g���[�N�́A�ɘa�P�A�n��A�g�N���e�B�J���p�X�̊J���Ɍ������c���X�^�[�g�������B�p�X�쐬������̂قǔ����A3���̉�ł́A�Ǐ�ʖ�܃p�X���p�^�̊ɘa�P�A�p�X�̑f�č���i�߂�\�肾�B����ɂ���ē������n�悩��ɘa��Â̊�Ս�肪�i�߂��錩�ʂ����B�L��̒n��A�g��O��ɂ����ɘa�P�A�p�X�̉^�p�͂܂����Ⴊ�Ȃ��A���̐��ʂ����ڂ����B �@����܂ł����Â͎��Â��D�悳��A�u���₷�v�P�A���\������Ă��Ȃ������B���ꂪ���ʓI�ɁA�ɘa�P�A�p�X�̍쐬��x�点���B���҂̑����ɔ����A���ҁE�Ƒ��̂��Âւ̈ӎ��̍��܂�Ɍ㉟������A�ɘa�P�A�̎��v�����܂��Ă����B �@�����������A2007�N10���ɔ��������������ɘa�P�A�l�b�g���[�N�́A������A���c��A�`��A������A�䓌��A�]����A�n�c��A������A�r���A������Ȃǂ����t�A��t�A�Ō�t�A�l�r�v�Ȃǂ��Q�����A�ɘa��Ẫl�b�g���[�N�̍\�z��i�߂Ă���B1�����̊�����ł́A�n��A�g�ɘa�P�A�p�X���J�����邱�Ƃ����肵���B �@ ���̌�����A19���ɂ͒n��A�g�p�X�̍쐬����̏�����s���A3���̎����܂łɁA�㓡�������i���{�Տ����t�w����A���ۈ�Õ������w�@���m�ے��j�炪�A�Ǐ�ʖ�܃p�X���p�̒n��A�g�ɘa�P�A�p�X�̑f�Ă���邱�Ƃ����܂����B �@ �Ǐ��1�Ƃ��Ă�����u�ɊǗ��p�X�́A���łɓ���̎{�݂ƃN���j�b�N�Ԃʼn^�p���Ă��鎖��͂��邪�A�L��A�g�̊ɘa�P�A�p�X�̍쐬�͏��߂Ă̎��݁B���ꂪ��������A5�傪��Ŋ��p���邱�Ƃ��ł���B ��܃p�X�͏Ǐ�R���g���[�����J�M �@��̓I�Ɋɘa�P�A�n��A�g�p�X�̓K����ɂ��Č㓡���́A���ҁA�Ƒ����ɘa�P�A�̗����Ǝ��ꂪ�ł��Ă��邱�Ƃ�A���҂̃p�t�H�[�}���X�̒ቺ�A�Ⴆ�Έӎ���ԁA���o�Ǐ�̗L���i�ċz��A�u�ɁA����A�q�C�E�q�f�A�r����Q�A�s���j�Ȃǂ������Ă���B �@ ����܂�����̊ɘa�P�A�n��A�g�p�X�Ƃ��ẮA�傫��3�i�K�ɕ����čl������B��1���ϋɓI���Ái���w�Ö@�Ȃǁj�J�n�����̑�������̊ɘa�P�A�p�X��2����������ȍ~�̒��Ԋ��̊ɘa�P�A�p�X��3���T�|�[�e�B�u�P�A���S�̊Ŏ��̊ɘa�P�A�p�X�|��3�i�K�B�ɘa�P�A�p�X�́A�]���̎����̒n��A�g�p�X�ƈႢ�A�Ǐ���R���g���[������Ǐ�ʖ�܃p�X�𒆐S�ɒu���A�ɘa�P�A�p�X�S�̂��쐬���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B �@ �Ⴆ�A�u�ɂɊւ���Ǐ�ʖ�܃p�X�ł́A���o�Ǐu����v�ꍇ�A�u�Ȃ��v�ꍇ�����ŁA��I�s�I�C�h�E�I�s�I�C�h�A��X�e���C�h�E�X�e���C�h���������ɍ܂Ȃǂ̑���E�����̖�g�p�X�P�W���[�����A����E�����E�V���v���ɃA���S���Y��������Ă���B�܂��A�r�֏�Q�ɑ����܃p�X�ł́A���Nj��u�Ȃ��v�ꍇ�A�u�^������v�̏ꍇ�A�����āu���S����v�̊e�Ǐ�ɉ�������ܑI���̖ڈ���������܃p�X���쐬����v�悾�B �@ ����ɁA�����̏Ǐ�ʖ�܃p�X�̗��p�ŁA�l�b�g���[�N�I�ɂ����҂̏ω��ɑ��E��̘A�g��Ƃɏ]������X�^�b�t���A�_��ɑΉ��\�ƍl������B m3.com 2009�N3��4�� |
|||||||||||||||||||||
| �I�����̍��z��ܔF�߂��@�p�����Տ��]�������̉����K�C�h���C�� | |||||||||||||||||||||
| �@�p�����Տ��]���������͂��̂قǁC�I�������҂̎��ÃK�C�h���C���������������C�T�E�T���v�g����w��ËZ�p�]���w�Ȃ�James Raftery�����́u�K�C�h���C������������Ă����z�Ȗ�܂��g�p���ɂ�������͂قƂ�lj��P���ꂸ�C�ނ��뎡�Â����Ȃ��Ȃ銳�ҌQ���ق��ɏo�Ă���ȂǕʂ̖�肪�N����\��������v�Ǝw�E���Ă���B �@�p�����Տ��]���������́C1999�`2008�N��QOL�Œ������������N���iQuality adjusted life year�GQALY�j�ɑ����p���ʂ��p�����Տ��]���������̒�߂��z"3���|���h"���͂邩�ɏ����Ă������Ƃ𗝗R��11��ނ̖�܂����O���Ă����B�������C���̔��f���ϗ���C�@����C������̃W�����}�ݏo���Ă���C�p�����Տ��]���������͏I�������҂̎��Ö�ɑ���p���ʂ�臒l���������悤���߂��Ă����B �@����̉����K�C�h���C���́C�]��2�N�ȓ��Ɛf�f����C���݂̉p���ی��T�[�r�X�iNHS�j�̎��Âɔ�ׁC���Ȃ��Ƃ��]����3�����͉����ł���ȂǁC�������ɖ��炩�Ȍ��ʂ�����Əؖ��ł��邲���ꕔ�̎��Â�ΏۂƂ��Ă���B �@Raftery�����́C����܂ʼnp�����Տ��]������������p���ʂ𗝗R�ɏ��O���Ă������ׂĂ̂��Ö�ɂ��āC�V�����������ǂ̒��x�e�����邩���������B���̌��ʁC�������͂���܂ŏ��O���ꂽ��܂ŐV�������܂͂قƂ�ǂȂ��C�����̗��v�������炷��ւ̖�܂����݂��Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ����B �@�܂��C�������́u����W�c��"����"��݂���C���ꂪ���̏W�c�őO��ƂȂ�B���\�Z��ς��Ȃ��܂܁C����̏W�c�ɑ��g�p�ł�����z��臒l�������ݒ肷��ƁC���Â����Ȃ��Ȃ�ʂ̏W�c���o�Ă���v�Ǝw�E���Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N3��19�� |
|||||||||||||||||||||
| �ɘa�P�A���C�A7���������{�@���_�a�@�̎w��v�� | |||||||||||||||||||||
| �@����f�ØA�g���_�a�@�̖�7�����A�w��v���Ƃ��Ē�߂�ꂽ2����Ì��ł̊ɘa�P�A���C�����I�Ɏ��{���Ă��Ȃ����Ƃ�3��19���A�����J���Ȃ̂܂Ƃ߂ŕ��������B �@ ���J�Ȃ͓s���{���ɑ��A���N10�������݂̋��_�a�@�̌��������߂Ă���A2008�N10�����̎w��v���̏[���Ɋւ�����܂Ƃ߂��B08�N4��1�����݂̋��_�a�@����351�a�@�B �@ ���J�Ȍ��N�ǂ�������i���ɂ��ƁA�[�������Ⴉ�����w��v���́u2����Ì��ł̊ɘa�P�A���C�����I�Ɏ��{���Ă���v�i108�a�@�A30.8���j�̂ق��A�u�@������o�^�̏W�v���ʂN�������Z���^�[�ɏ����Ă���v�i162�a�@�A46.2���j�A�u�ɘa�P�A�`�[���ɐ��I�Ȓm���ƋZ�\������̐�]�Ō�t������v�i204�a�@�A58.1���j�A�u���k�x���Ɋւ��Ċ��Ғc�̂Ƃ̘A�g���͑̐��̍\�z�ɐϋɓI�Ɏ��g��ł���v�i212�a�@�A60.4���j�A�u�O���Ő��I�Ȋɘa�P�A��ł���̐������Ă���v�i240�a�@�A68.4���j�Ȃǂ������B �@ ����A���ׂĂ̕a�@���������Ă����̂́A�u���k�x�����s�������ݒu���Ă���v�u�w�W���o�^�l���x�Ɋ�Â��@������o�^�����{���Ă���v�Ȃ�3���ڂ����Ȃ������B m3.com 2009�N3��25�� |
|||||||||||||||||||||
| �������C�ӎv����ɉe��������t������@�����͉\���@���r���O�E�E�B��������c�_ | |||||||||||||||||||||
| �@4��14���C�����J���Ȃő�4��u�I������Â̂�����Ɋւ��鍧�k��v���J�Â��ꂽ�B �@�������ɂ́C����̈�Ï]���҂ɂƂ��ČY�����̃��X�N������ȏ�C�K�C�h���C���ƂƂ��ɖ@�����͕K�v�Ƃ��������������ŁC�@�����̕���p�Ƃ��āC���҂̈ӎv�����g�@�h�Ɋ�Â������_�ňӎv���肪���E�����뜜������B �@�܂��C�������̈ӎv����ōł��d�v�Ȃ̂́C���Җ{�l�̈ӎv�����C�c�_�̂Ȃ��ł͂��̈ӎv�m�F�̓���������ꂽ�B �@�I������Âɂ����鑸�����ɂ��Ă̋c�_�ł́C���݁C��t�C�@�w�҂����̃R���Z���T�X�Ɏ����Ă��Ȃ����B �@����C��Ì���ł́C���ҁE�Ƒ����瑸������]�ވӎv�����ۂɎ�����Ă���B �@���J�Ȃ�2007�N�Ɍ��\�����u�I������Â̌���v���Z�X�Ɋւ���K�C�h���C���v�ł́C�����������Җ{�l�̈ӎv���ő���ɑ��d���邱�Ƃ����Ƃ��Ă���C�{�l�C�Ƒ��C��ÃP�A�`�[���ȂǁC�O�ꂵ�����ӎ�`�̏d�v���������Ă���B �@�������C���ۂ̈�Ì���ł́C���r���O�E�E�B���⊳�҉Ƒ��Ƃ̘b�������ɂ�葸�����̈ӎv��������Ă��C���ۂɂǂ̂悤�ȍs�ׂ��Y�@�ɒ�G����̂����s���Ȃ��ƂŁC�j�[�Y�ɉ����邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ��w�E����Ă���B �@�����������Ƃ���C��Ï]���҂���́C�K�C�h���C���ɕ����C�������ɂ�������Ï]���҂���邽�߂̖@���������߂鐺���オ���Ă���B �č��̈ӊO�Ȏ����@�@�����͂Ȃ���Ă������ŁC�@����×ϗ��d �@���������Ȃ��C�u�����̑����̓��r���O�E�E�B���ɂ͎^���Ȃ̂ɁC�Ȃ����̖@�����ɂ͏��ɓI���H�v�Ƃ����^����悳��Ă���C������w��w�@�@�w�����w�����ȋ����̔���͗Y���́u�s���m�Ȗ@�̓`���閾�m�ȃ��b�Z�[�W�v�Ƒ肵�����\���s�����B �@�����́C�č��̖@����Ƃ��Ă���C���r���O�E�E�B���̖@�������s���Ă���č��ɂ�����C�������ɂ������@���߂̎���ɂ��ďЉ���B �@�܂��C�č��̃��[�X�N�[���̋��ނł���casebook�̂Ȃ�����C37�̔x�������҂���u���w�Ö@�ƃy�[�X���[�J���~�߂Ă���v�Ƃ����ӎv�������ꂽ��t����̑��k�ɂ��ďЉ�Bcasebook�ł́C�u�i�@���́j�ϗ��ψ���ő��k���Ȃ����v�Ə��������Ă���C���ꂪ�@���ƂƂ��Ă̍őP�̓����Ƃ��Ď�����Ă���C�u�����E�l�Ƃ����ނ̋L�q�ɂȂ����Ă��Ȃ��v�Ƃ����B �@�܂��C���l�ɕč��̈�t���Ǝ������̂Ȃ����玟�̂悤�Ȗ�����������B �@���̂ɑ������j�����C�l�H�ċz�������ďW�����Î��iICU�j�ɉ^�э��܂�C�]����ԂƔ��f���ꂽ�B�j���̓h�i�[�J�[�h���������Ă���C����̈ӎv�\������������Ă����B�������C����ڐA�`�[�����Ƒ��ɘA����������Ƃ���C����ɔ����ꂽ�B�ǂ����ׂ����H �@����ɑ��鐳���́u�Ƒ��̈ӎv�d���������߂�ׂ��ł���v�Ƃ������̂ŁC������́u�č��ł͖@����C�]�������Ƃ��Ă���C����͖{�l�i�����j�̈ӎv�ɂ��Ɩ��L����Ă��邪�C�i�č��ł́j�@�������ň�Â͓����Ă��Ȃ����Ƃ�������Ă���v�Ƃ����B �@�܂��C�č��ł́C�@�ƈ�Ái�ϗ��j�̖����͈قȂ�C��҂����d�v���ƍl�����Ă���Ƃ��C���r���O�E�E�B���@�̓K�p���Ȃ��Ă��C�i1�j���Җ{�l�̈ӎv�d�C�i2�j���a�⎩�E��]�̏ꍇ�͕ʁC�i3�j��肪����Ηϗ��ψ���ł����k?�Ƃ������_�ɏ]���Ĉ�Â̕��j�����܂�C�@�ɗ���ԓx�͎���Ă��Ȃ��Əq�ׂ��B �@����ɁC�č��ł́C���r���O�E�E�B��������l�͏����ŁC�����Ă���l�ł��K�p���O��������̂����Ԃ��Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N4��16�� |
|||||||||||||||||||||
| �������҉��f�ԁF�ً}�ԗ��Ɏw��--�Ȗu�ݑ�z�X�s�X�Ƃ��̖v | |||||||||||||||||||||
| �@����ł̗×{��]�ޖ������҂����f����u�ݑ�z�X�s�X�Ƃ��̖v�i�Ȗ؎s���X���j�̏����ŁA��t�̓n�ӖM�F����i�S�X�j�����ґ���ً}�ɉ��f����ۂɎg�p�����p�Ԃ��A���H��ʖ@��ً̋}�ԗ��Ɏw�肳�ꂽ�B���������́u��b�ł��������҂̒ɂ݂�����Ă��������v�Ƃ����n�ӏ����̋����肢�������B �@�ً}�ԗ��̎w��͓��H�^���ԗ��@�̕ۈ���Ɠ��H��ʖ@�{�s�߂̈ꕔ�����ɂ����̂ŁA�O�W�N�P�O���ɐ��{�̍\�����v����ŔF�߂�ꂽ�B�n�ӏ����̎Ԃɂ͐ԐF���ƃT�C���������t�����A�ً}���ɂ͋~�}�ԂƓ��l�ɗD�摖�s���������B �@�����ɂ̓����q�l�Ȃǂ̖Œɂ݂�a�炰��ɘa�P�A���オ���Ȃ��B�n�ӏ������O�W�N���ɊŎ�i�݂Ɓj�������҂͌v�W�Q�l�B�ً}���̉��f�ł��~�̋A�ȃ��b�V���Ɋ������܂�A�Ԃ������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��������B�����ŁA�\�����v����ŋً}�ԗ��̎w���F�߂�悤��Ă��A����̉����ɂȂ������B �@�n�ӏ����́u���҂��w�ꂵ���x�w�ɂ��x�Ƒi���Ă���̂ɁA��ʏa�œ������x���Ȃ��Ă��܂��̂́A���҂̉Ƒ��ɂƂ��Ă��X�g���X�v�Ǝw�E����B���̂����Łu���҂ɑ��āA�ɘa�P�A���オ���Ȃ�����̂����{�I�Ȍ����B��t�������Ƒ��₹�T�C�������g��Ȃ��Ă��ςނ悤�ɂȂ�v�Ƙb���Ă���B m3.com 2009�N4��24�� |
|||||||||||||||||||||
| �]��ᇂɔ������ɂ͑��߂̑Ή����@���ɁE�Ă�l����E����� | |||||||||||||||||||||
| �@�]��ᇊ��҂̑����ł͍����I���Â����݂����C���҂̗]���͒Z�����Ƃ������B�P������w�ɘa��ÉȂ�Heidrun Golla���m��́u�]��ᇂł͓��W���Ƃ�������ꂽ�X�y�[�X�Ŕ]����������邽�߁C�Ǐ�͂���߂ďd���C�����i�K����ɘa�P�A�̎��{���������ׂ��ł���v�Ɣ��\�����B �X�e���C�h�̓K�������I�Ɋm�F �@�������]��ᇂ܂��͓]�ڐ��]��ᇂ̊��҂ł́C���ɁC���S�C�q�f�C�Ă�l����C��ჁC���o��Q�Ȃǂ̐g�̏Ǐ�ɉ����C�l�i�̕ω��C�F�m��Q�C�ӎ���Q�C����ςȂǂ̏d�����_�Ǐ����������B �@�g�̏Ǐ�ɂ��ẮC�]��ᇊ��҂̖�50���ŋْ��^���ɗl�̓��ɂ���������B��ᇂ̑��B�C����C�܂��͐��t�̏z��Q�ɂ���Ĕ]�����㏸����ɂ�Ēɂ݂���������B��ᇂɂ��]����͌��ǐ�����ł���C��ʂɃX�e���C�h��i��@�f�L�T���^�]��4mg/���j���t������B�������C����p���X�N�����ߐT�d�ɓ��^���C�K���ɂ��Ă͒���I�Ɋm�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�X�e���C�h���^������ɂ��\���Ɍy�����Ȃ���ΐ��E�ی��@�ցiWHO�j������i�K�I���@�ɏ]�����u�Ɋɘa�����݂�B �@�����̔]��ᇊ��҂ł́C�����̌o�ߒ��ɂĂ�l������邪�C��ᇂ̑��B���x���ɂ₩�Ȃق����}���ɑ��B����ꍇ�����C������̔����p�x�͍����Ȃ�B �@���삪�A�����Ĕ�������ꍇ��Ă�d�Ϗǂ�����ꍇ�͓��Ö@�̓K���ƂȂ�B�W�A�[�p���C�����[�p���C�N���i�[�p���̌��ʂ͂قړ��������C�����[�p���̂ق������ʂ̎������Ԃ��������߁C�d�Ϗǂ̎��Âɂ͓K���Ă���B �@�x���]�W�A�[�s���n����J��Ԃ����^���Ă��\���Ȍ��ʂ������Ȃ��ꍇ�́C�t�F�j�g�C���܂��̓o���v���_�̋}���O�a����������B�܂��C���߂ĂĂ�l���삪�������]��ᇊ��҂ɂ́C�R�z�����\�h�I�ɓ��^����B �@�]��ᇊ��҂ō��p�x�ɍ������鐸�_�����ɂ́C���a�C�s���C����ς���������B����ςɑ���Ö@�ł̓x���]�W�A�[�s���n��ƍR���_�a��p����B��҂ɂ�������I���̓n���y���h�[���ł���B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N4��23,30�� |
|||||||||||||||||||||
| ���҂ւ̃G���X���|�G�`�����^�̐�����l����@�X�C�X�ōs��ꂽ���^��͂��� ���D�y�a�@���@���E���w�Ö@�Z���^�[���@���R�@�א� |
|||||||||||||||||||||
| ���̍l�@�F�G���X���|�G�`�����^�͗��v�Ƃ̃o�����X�ɂ����čl�����ׂ� �@���҂̕n������ь��ӊ��ɑ��C�킪���ł͊T��Hb 8g/dL�ȏ��ۂ��x�ɗA�����s���邱�Ƃ��������C���Ăł͂��̊ȕ��C���S���C�Տ������ŗ��t�����ꂽ���ӊ��ւ̌��ʂɂ��Hb 12g/dL��ڕW�ɃG���X���|�G�`�����܂����^����邱�Ƃ������B �@Bohlius��͏�L�^��ɑ��C53 �̃����_������r���������^��͂��C�m���ɃG���X���|�G�`�����^�Ŏ��S���������グ�Ă��邱�Ƃ��������B �@�ΏƌQ�ɑ��G���X���|�G�`�����^�Q�ŁC�Ȃ����S�����������ʂɂȂ������͕s���ł��邵�C���w�Ö@���{�s�������҂ʼne�������Ȃ����R���s���ł���B �@�e�Ǘ�̎�������͂���悢�Ǝv���邩������Ȃ��B�������C�I�������҂̏ꍇ�C�}�ς����ɂ���������ƑS�g��Ԃ����������ɂ���C���S�����ꍇ�͌�������肷��w�͂͂����u����ɂ�鎀�S�v�Ɛf�f����̂���ʓI�ł���B���̌X���́C�킪���ł��ɘa�P�A�a���Ō����ł��邪�C���ۂ̎����͊����ǁC�S�����i����������ѕs�����j�C�d����Ǔ��Ìŏnj�Q�ɂ��o���C�e�파���ǂȂǂ������Ǝv����B �@�����̕a�Ԃ���肵�Ă��������Ԃ����QOL���P�ɂȂ��邱�Ƃ͋H�ł���̂ŁC���Ƃ��Ă��I�������҂ɐϋɓI�Ɋe�팟�����s�����Ƃ͔�����ׂ����ƍl����B �@���̂悤�Ȕw�i����C�G���X���|�G�`�����^�ɂ�鎀�S�������̌����͓��肳��Ă��Ȃ����C�G���X���|�G�`���ɂ���ᇑ��B�⌌���ǂ̑����Ȃǂ���������Ă���B �@�{�����̌��ʂ���C�����Hb 12g/dL��ڕW�ɃG���X���|�G�`�����^�𐄏����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ������C�S�������̈����͂킸���ł��邱�Ƃ���C�_���̌��_�ɂ�����悤�ɁC�G���X���|�G�`�����^�͌��ӊ��̉��P�Ɨ��v�Ƃ̃o�����X�ɂ����čl�����邱�ƂɂȂ낤�B �@�킪���ɂ����Ă͌��ӊ��������n���̂��҂ɂ͎�Ƃ��ĐԌ����A��������Ƃ�������̑Ή��̂܂܂ł悢�Ǝv����B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N5��19�� |
|||||||||||||||||||||
| �L�����E���n��@�u�����u�ɊǗ��}�j���A���v�쐬�@�������鎡�Â��f�ځ^���s�ł̊ɘa�P�A�̕W������ڎw�� | |||||||||||||||||||||
| �@���̂قǍL�����̌��n��ی��c��́A�ɘa�P�A�̕W������ڎw���A�u�����u�ɊǗ��}�j���A���v���쐬�����B�}�j���A���ɂ́A�u�ɂ̕]�����@���͂��߁A�I�s�I�C�h���ɖ�̎g�p���@�ȂǁA���������u�Ɋɘa���Â��L�ڂ����B5��12���ɂ́A�ɘa�P�A�}�j���A���̓�����������s��t��قŊJ���ꂽ�B����͊ȈՔŃ}�j���A�����쐬����\��ŁA�����I�ɂ͒n��A�g�p�X�ւȂ��邱�Ƃ�����ɓ���Ă���B �@���n��ɂ́A����ÃZ���^�[�̂ق��A�����ϕa�@�A�����J�Еa�@�Ȃ�400���ȏ�̌��I�a�@��3�A200���ȏ�̌��I�a�@��2���݂���B �@���n��ی��c��́A����܂łɁA�]�����̂ق��A�b�^�̉��A�}���S�؍[�ǂȂ�6�̎����̒n��A�g�p�X���쐬���Ă���B���݁A�����c��ł́A�ɘa�P�A���܂߂�5�傪��i�݁E�x�E�咰�E�̑��E������j�̃}�j���A���쐬�Ɏ��g��ł���A����͌���ÃZ���^�[�ɘa�P�A�Ȓ��̍��c�ˎi�������S�ƂȂ��Ċɘa�P�A�}�j���A�����쐬�����B���n��̊ɘa�P�A�̕W������ڎw���B �@�}�j���A���ł́A�v�g�n�����}�j���A���ɂ��ċL�ڂ��Ă��邪�A���c���́A�u�v�g�n�����ɂ������߂���Ɗ��҂̂p�n�k���ቺ����B���҂��Ƃɍׂ��Ȕz�������邱�Ƃ��d�v�v�ƒ��ӂ𑣂����B �@��I�s�I�C�h���ɖ��NSAIDs�ɂ��ẮA�u���Ɏg���₷�����A�ݒ�ᇂ̗\�h����ԏd�v�v�Ƃ����B �@�}�j���A���ɂ́A���҂̃I�s�I�C�h�ɑ��������������߂̃|�C���g���L�ڂ��Ă���B �@�I�s�I�C�h�́A�g�p�ʂƗ\��ɂ͑��ւ��Ȃ��A�����k�߂镛��p�͂Ȃ����Ƃ�A��t�̎w���̉��œK�Ɏg�p����Β��łɂȂ�\���͔��ɒႢ���ƂȂǂ�������Ă���B���̂ق��A�I�s�I�C�h�̎g�p�ړI�╛��p�����҂ɐ�������悤�L���Ă���B �@���c���́A�u�I�s�I�C�h���g�p����ɓ�����A�Œ�20-30���̐������K�v�B�P�[�X�ɂ���ẮA��t�E�Ō�t�̋��͂��K�v�v�Ƃ��A�W�҂�ɋ��͂����߂��B m3.com 2009�N5��20�� |
|||||||||||||||||||||
| ��109����{�O�Ȋw��@���҂����O�Ȉ�ɂ��ɘa��� | |||||||||||||||||||||
| �@�O�Ȉ�͂��҂̂��ׂĂ̌o�߂������闧��ɂ���B���ɂ킪���ł͂��̌X���������B���̂��߁C�ɘa��Âɂ�����O�Ȉ�̖����ɂ́C��啪�����i�݂��鍡���ł��傫�Ȋ��҂����Ă���B�����s�ŊJ���ꂽ��109����{�O�Ȋw��̃V���|�W�E���u�O�Ȉ�ɂƂ��Ă̊ɘa��Â̈ʒu�Â��v�ł́C�O�Ȉ�ɂ��ɘa��Â̌����ꂽ�B �����I�Ȋɘa��Ó����Ő������ԁC�o���ێ���Ԃ���2�{�� �@2003�N�C�킪���ŏ��߂Ċɘa��Êw�u�����J�݂������c�ی��q����w�O�ȁE�ɘa��Êw�̓������u������́C��ӁC�h�{�C�Ɖu�C�u�ɁC���_�S���ȂǁC������ϓ_���炪�҂̊ɘa��Â��s���CQOL����\�オ���������P���鐬�т�����ꂽ���Ƃ𖾂炩�ɂ����B �p�O��ɍR�_���h�{�f���^ �@���������炪�ڎw���Ă���̂́u�g�̂ɂ����_�ɂ��D�������Áv���B�����B�����邽�߁C���҂��ꂼ��ɑ��āC�G�l���M�[�o�����X�̈ێ��C��Ә��i�̐���i�`���ى��̗}���j�C���̐N�P�̌y���i�R�_����p�̑��i�j�C�n�������̑��i�C����Đ��\�E�`�������\�̑��i�C�Ɖu�\�̈ێ��E���i����ъ����}���ȂǁC�����I�Ȏ��g�݂��s���Ă���B �@�Ⴆ�C�G�l���M�[�o�����X���C�ێ����邽�߂ɁC���A�~�m�_�iBCAA�j�̌o���h�{�����{���Ă���B�̐؏���Ȃǂ̊��҂ł́C�Ɖu�\�Ɛ����ւ���G�l���M�[�o�����X���}�C�i�X���ɌX���Ă���C��ʓI�ȃA�~�m�_�_�H�͂��Ƃ��CBCAA�̓_�H���s���Ă����P���邱�Ƃ͓�����CBCAA�o���h�{�@�Ȃ�v���X���������邱�Ƃ��ł���B �@���̐N�P�̌y����}��ړI�ł́C�R�_����p������h�{�f�𓊗^���Ă���B�A���M�j���C�O���^�~���C�O���^�`�I���C�܂��̓r�^�~���ށC���ʌ��f�C�|���t�F�m�[���������ȂǁC�R�_����p��L���邳�܂��܂ȉh�{�f����p4���ԑO�܂œ��^���C����ɏp��15���Ԉȓ��ɍĊJ����B �@�n�������𑣐i���邽�߂ɂ́C�����s�O�a���b�_�̓��^���s���B�h�R�T�w�L�T�G���_�iDHA�j��G�C�R�T�y���^�G���_�iEPA�j�Ƃ�����n-3�n���b�_�ƁC��������̑����s�O�a���b�_�ł���n-6�n���b�_���ɓ��^����ƁC���ꂼ��P�Ɠ��^�̏ꍇ�Ɣ�ׂāC�n�������܂ł̊��Ԃ�L�ӂɒZ�k�ł��邱�Ƃ��킩���Ă���B �@�Ɖu�\�̈ێ��E���i�Ɗ����}���ւ̑�Ƃ��ẮC�O�o�̊e��h�{�f��j�_�C�C���X�����l�������q�iIGF�j-1�C�H���@�ہC�I���S���Ȃǂ��o���E�o�����^����Ɖu�w�I�h�{�Ö@�������B�����������Â�����ƁC�p�㊴���ǂ̔��������O�Ȏ�p�S�̂Ŗ�4����1�ɒቺ���邱�Ƃ��m�F����Ă���B �V�K��ጂ�41������2�`6���Ɍ��� �@����������͂���ɁC�ɘa�P�A�h�{�T�|�[�g�`�[���𗧂��グ�C���H���Ă����B�����Ȋ������e�͎��̒ʂ�B�h�{��Q�i�㌴���j�̉�́E�����C�H�~�E�o���ێ�̉C���ʉh�{�f�ɂ��Ǐ�ɘa�E�m�o�ُ퐥���E��\�h�C�R�G���U�C��Q10�E�����b�ܗL�H�ɂ��ċz�Ǐ�ɘa�C�A�t���{��̐ݒ�i���t���̗L���]���܂ށj�C�ԐڔM�ʌv�ɂ����Î��G�l���M�[����ʂ̑���B �@�����ɁC�������̍\�z�C�u�Ɋɘa���܂ޑS�l�I��Â̎��H�C���ҊԁE�Ƒ��ԃR�~���j�e�B�[�̍\�z�Ȃǂ��ɘa��Â̒��Ƃ����B �@����C���������V�V�X�e��������5�N�Ԃɂ�������ʂ��C�ɘa�P�A�a���ɓ��@�����I��������699��Ō��������B���̌��ʁC���@2�`4�T��ɂ͊��҂�54���ʼnh�{��Ԃ�ǍD�Ɉێ��ł��C�����O�ɔ�ׂĐ������Ԃ�o���ێ�\���Ԃ�2�{�߂��ɉ��������B �@�܂��C�u�ɊǗ���ϋɓI�ɍs�������C����g�p�ʂ͖��炩�Ɍ��������B�V�K��ጂ͓����O��41���ŔF�߂�ꂽ���C������2�N�ȍ~��2�`6���ł������B�J�e�[�e���֘A���������ǂ������O��8������C������ɂ�4�`5���Ɍ������C�牺���ߍ��^�J�e�[�e���g�p���1����ɗ}����ꂽ�Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N5��21�� |
|||||||||||||||||||||
| ����������N���҂̏I�����@�{�l�Q����"���O�P�A�v��"���d�v | |||||||||||||||||||||
| �@�d�ĂȃC�x���g��������O�ɏI�����̌v��𗧂ĂĂ������ƂŁC�����₻�̉Ƒ��C��Ò҂Ƃ̊Ԃ̐M������R�~���j�P�[�V�����������ł���B�č���������ÃZ���^�[��N���l��w�����Maureen E. Lyon���m��́C���������̎�N���҂ƉƑ����d�ĂȃC�x���g����������O�ɏI�����̊�]�ɂ��Ă悭�b���������Ƃ́C��N���҂̉�]�ދC��������������C��I���邢�͐��_�I�ȒɎ�킹�邱�ƂɂȂ�Ȃ��Ɣ��\�����B �q���͈�w�I����ւ̎Q������] �@���̌����́C��N���҂ƉƑ������Ƃ̏����Č��ݓI�Ȍv��𗧂Ă邱�Ƃ��ł���C���������Ɋւ����w�I����Ǝ��ÂɊւ���e�q�Ԃ̈ӌ�����v���₷���Ȃ�C�ǍD�ȃR�~���j�P�[�V����������Ƃ̍l���Ɋ�Â��s��ꂽ�B��������"���O�P�A�v��"���������郉���_�����R���g���[�������Ƃ��Ă͏��߂Ă̂��̂ƂȂ�B���O�P�A�ɂ́C�I�����ɐ�����L�Q���ۂ�ɘa�P�A�C�����ׂ����f�ɂ��Ă̐������܂܂��B �@Lyon���m��́C�Ƒ��Ɛ������Ă����NHIV�����҂Ƃ��̐e�i38�e�q�y�A�j��ΏۂɁC���I�ɍ\�z���ꂽ�v���O������p���āC�Ƒ��Ԃ̌��������܂邩�C��b�̎����オ�邩�C���f���X���[�Y�ɍs���邩�ۂ������������B���̌��ʁC�I�����̌���ɂ��Ęb���������Ƃ��C�Ƒ��Ԃ̌����C��N�҂̖������Ȃǂ����߂邱�Ƃ��킩�����B �@�����m�́u�����͈ȑO����C��҂����g�̖��������ɑ������ň�w�I��������������Ɩ]��ł��邱�Ƃ�m���Ă����B�����̐e�ƈ�Ò҂́C�����N���邩������Ȃ��������������C�x���g�ɂ��čl���邱�Ƃ�������ł���̂ɁC�܂��Ă�C���̂��Ƃ̖{�l�ł���q���Ƙb���������ƂȂǍl�����Ȃ���������Ȃ��B�������C���Ƃ̃A�h�o�C�X���邱�Ƃɂ��C��]�����킸�Ɏv�����������Ęb���������Ƃ��ł��邾�낤�v�Əq�ׂĂ���B �@�����ӔC�҂œ��Z���^�[��Added Lawrence D'Angelo���m�́u����̌�������C��N�҂͈�A�̏I�����P�A�𗝉����C���f�ɎQ���ł��邱�Ƃ��킩�����v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N5��21�� |
|||||||||||||||||||||
| ��38����{�����u�Ɋw��@�����u�ɂɂ͑����̎��Î�i��I������ | |||||||||||||||||||||
| �@�����u�Ɏ��ẤC1986�N�ɔ��\���ꂽ���E�ی��@�ցiWHO�j���������u�Ɏ��Ö@�ɂ��C�Ö@�����S�ƂȂ��Ă��邪�C���ː��Ö@��_�o�u���b�N�C��p�Ö@�Ȃǂ��܂߂������̎�i����g�����Ή����d�v�ƂȂ��Ă���B�_�ˎs�ŊJ���ꂽ��38����{�����u�Ɋw��̃V���|�W�E���u����̒ɂ݂ɑ��鑽�ʓI���Áv�ł́C�e�̈悩�炪���u�ɂɑ��鎡�Â����\���ꂽ�B �Ö@����{�ɓ���u�ɂɂ͑��̎��Ö@���l�� �@�����u�Ɏ��Âɂ�����Ö@�Ƃ��āC��X�̃I�s�I�C�h���܂��Տ���������C���݂��V���Ȑ��܂̊J�����i�߂��Ă���B���a��w�a�@�ɘa�P�A�Z���^�[�E�����o���Z���^�[���́C�����u�Ɏ��Âɂ�����Ö@�̌���������C�Ö@�݂̂ő������u�ɊǗ����\�ł��邪�C���ꂾ���ł͉����ł��Ȃ�����u�ɂɂ́C���̎��Î�i���l�����ׂ��ł���Əq�ׂ��B �Ö@�݂̂ł͖�2�����u�Ɏc�� �@�����u�ɂɑ�����Â�����w�i�Ƃ��āC1986�N��WHO���������u�Ɏ��Ö@�����\����C�I�s�I�C�h�̎g�p���������ꂽ�B�킪���ł��C����10�N�Ԃɂ����閃�����ʂ̐��ڂ�����ƁC�����q�l�͌����X���ɂ�����̂́C�I�L�V�R�h���ƃt�F���^�j���������X���������C���O���Ɣ�ׂĂ܂����Ȃ����C�S�̂Ƃ��Ă̖���̎g�p�ʂ͑����̈�r�����ǂ��Ă���B�����̓����Ƃ��ẮC2006�N�x�̕a�@�E�f�Ï��ɂ����閃��Ǘ��}�j���A���̉����ɂ��C����̎�舵�����ɘa����C2008�N�x�ɂ͐f�Õ�V�����ɂ��C�����u�Ɋɘa�w���Ǘ������V�݂���CWHO���������u�Ɏ��Ö@�Ɋ�Â��āu����v����������ꍇ�ɎZ�肪�\�ƂȂ�C�����͖���̎g�p�������㉟��������̂Ǝv����B �@���������܂��C����Z���^�[���́u�I�s�I�C�h����ʂ̑����́C����̎g�p�ɑ����R�����Ȃ��Ȃ��Ă������߂Ǝv���邪�C�t�ɒɂ݂̃A�Z�X�����g���\���ɂȂ���Ȃ��܂܁C���Ղɏ�������邱�Ƃ������Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����B�Ö@�̊�{�͒ɂ݂̃A�Z�X�����g�ł���C����ɂ���ēK�ɖ�܂�I�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƌ��������B �@�����u�ɂɑ���Ö@�Ɋւ��ẮCWHO���������u�Ɏ��Ö@�Ɋ�Â��ă����q�l�𒆐S�Ƃ�����ɖ��K�Ɏg�p���邱�Ƃɂ��C�����u�ɂ̖�8���̓R���g���[���\�ł���Ƃ���Ă���B�������C��2���͖Ö@�����ł͉��P�ł��Ȃ�����u�ɂł���C���������ꍇ�͍ēx�C�ɂ݂̃A�Z�X�����g���s���C�y�C���N���j�V�����⑼�Ȃ̈�t�Ƒ��k���邱�Ƃ��d�v�ł���C�K�v�ɉ����Đ_�o�u���b�N����ː��Ö@�Ȃǂ��{�s�����B �@���Z���^�[���́u���ÑI�����������C�e�ȂƘA�g�����Ă���C�܂��C�×{�̐��̒�����������Ƃł��Ă���قǁC�ǍD���u�ɃR���g���[�����\�ł���C���҂�QOL�͌��シ��Ǝv����B�����u�ɊǗ��ɂ����ĖÖ@����{�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����C�����̎��ÑI����������Ă������Ƃ��d�v�ł���v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N5��28�� |
|||||||||||||||||||||
| �c���D����̂��玀�����݂߂�F�ɂ݂̓[���ɂł��� | |||||||||||||||||||||
| ����b��E������t���a�@�y�����A�ɘa�P�A�f�Õ��� �@������A��������c�u���ŊJ�Â��ꂽ���J�u���Ŋ�ꂽ����ɓ��������Ǝv���܂��B �@�u�č��ł��f�̎�f���������̂͂Ȃ����B�������Ԉ���Ă���̂ł́v�Ƃ�����������������܂����B �@�Ԉ���Ă͂��܂���B���f�́A���{�̏ꍇ�A�q�{��A�咰����A������A�x����A�݂���ɗL���Ƃ����Ă��܂��B�ǂ�Ȃɐ����K���ɋC�����Ă��A���ł���ꍇ������܂��B���̂悤�Ȃ�����A���f�ő��������ł���A�������Ƃ��\�ł��B�Ƃ��낪�A�ł��L���ƍl������q�{��ł��A���{�̎�f���͂Q�����x�ł��B����A�č��̏����̂W�S�����Ă��܂��B������Ȃǂ��A���l�̌X���ł��B �@�č��̏ꍇ�A��Ô��}����Ӗ�������a�C�̗\�h���d������Ă��܂��B���f�͊�{�I�ɖ����A����������{�����e�B�A����f���㉟�����܂��B���{�ł��A����͊J�ƈ�̖������d�v�ɂȂ�ł��傤�B �@������́A�u���Ȍ��f�v���ł���B��̂���ł��B���C�Ń^�I����X�|���W���g��Ȃ��ŁA��ł��������Ă݂Ă��������B�e�̉��ɂ����肪�Ȃ������`�F�b�N���Ă��������B�����g�œ�������������R�c�M�q����̌��t�ł͂���܂��A�����̏ꍇ�A�u���܂�ɔ~�����̃^�l�v�̂悤�Ȋ��G�������ł��B �@����̏Ǐ���Ƃ�ɘa�P�A�ւ̎�����ڗ����܂����B�܂��A����̒ɂ݂̓[���ɂł��邱�Ƃ��o���܂��傤�B��D�́A�����q�l�Ȃǂ́u��×p����v�ł��B���ݖ�ȂǕ��ʂ̖�Ɠ����悤�Ɏg���܂��B����̒ɂ݂͂Ƃ�����������������X��������܂��B�������A���{�̂P�l������̈�×p����̏���ʂ́A�č��̂Q�O���̂P�ɂ����܂���B �@�u�Z�J���h�I�s�j�I�����������A�S���オ�����Ă���Ȃ��v�Ƃ������k������܂����B�ԂȂǍ����ȏ��i���Ƃ��A�����̐l���J�^���O���W�߂�ł��傤�B����������������̎��Â�[�����Ď�ɂ́A�Ȃ�����u�Q�Ԗڂ̈ӌ��v���K�v�ł��B�E�C���o���Ă��肢���Ă݂Ă��������B�����āA����ɂ��Ă̓��{�̎����ς��Ă������߁A���K�v�Ȃ̂́A�w�Z�ł̂���ƍl���Ă��܂��B �����V���@2009�N6��9�� |
|||||||||||||||||||||
| �I������Â��l����c�u�ǂ�������v��t�Ƙb�����@��Ã��l�T���X�@���t�H�[���� | |||||||||||||||||||||
| �@�ǂ�����āA�����炵���Ŋ����}���邩�B�[���ł��闝�z�I�ȍŊ��Ƃ́\�\�B�u�I������Â��l����v���e�[�}�Ƃ����u��Ã��l�T���X���t�H�[�����v���T���Q�P���A���s�t��̓d�̓z�[���ŊJ���ꂽ�B�I������Â�ݑ�P�A�ɏڂ����R�l�̐��Ƃ��A����̎��g�݂�ӌ����Љ�Ȃ��甒�M�����c�_�����킵�A�W�܂����U�O�O�l�]��̎s���́A�^���Ȗʎ����ŕ����������B ���@�p�l���f�B�X�J�b�V�����@�� �p�l���X�g �@���É��w�|��w���A��`���O���� �@��䉝�f�N���j�b�N�@���@�쓇�F��Y���� �@��g�̋��N���j�b�N�E�[�l�����}�l�W���[�i�{�錧���s�j�@��Ώt������ �R�[�f�B�l�[�^�[ �@�O���Y�E�ǔ��V�������{�ЕҏW�ψ� ����Â̖��� �@�\�\���҂����̊ԍۂɖ���������Η��z�I�ł����A��Â͂ǂ�Ȗ������ʂ�����̂ł��傤���B �@��`�@�ɂ݂��������Ă��A����ǂ��Ȃ�̂��Ȃǂ̐��_�I�ȔY�݂͐s���܂���B���N������S�����āA���̐l�Ȃ�̈��炩�ȍŊ����}������悤�Ɏx����̂���Â̐Ӗ��ł��傤�B���ꂩ��̈�×ϗ��ɂ́A���������̐l�̍K���ɂȂ���̂��Ƃ������_���K�v�ł��B �@�\�\��Â��t�ɍŊ��̏u�Ԃ̖�����W���Ă���Ƃ���͂���܂��B �@��@�����́A�����̉^��������A�����̂Ȃ���������������ɂ���܂��B�ł��A��t��Ō�t�ɉ������āA�ӎv�\�����ł��Ȃ������Ƃ����b���悭�����܂��B���҂����̓���f���ɓ`���A�V���������⊴�����ł���悤�Ȋ���肪��ł��B �@�\�\���҂̊�]���������邽�߂ɁA�ǂ�ȓw�͂�S�����Ă��܂����B �@�쓇�@���̏u�Ԃ́A�����ł͒m�邱�Ƃ��ł��܂���B�܂薞���Ȑ��͌o���ł��Ă��A�����Ȏ����ǂ����͔��f�ł��Ȃ��B������A���҂ƕ��������Ĉꐶ�����b�������u�����悩�����v�Ƌ����ł��鐶������T���Ă����B���̐ςݏd�˂̒��ŁA������A�����K���ƍl���Ă��܂��B �@�\�\�u����ȍŊ����}�������v�Ǝ����Ă��銳�҂͂��܂����B �@��@���傤���ɂ݂����؈ޏk�i�����キ�j�������d���ǂ̍��X���ݎq����́A�l�H�ċz������Ȃ�����I�т܂����B�n���̒��w�Z�ōu�����A���̈Ӗ���₢������Ȃǒ���̓��X�𑱂��Ă��܂��B�ǂ����ʂ��ł͂Ȃ��A�ǂ������邩�B���̗E�C�Ɋ����������ł��B ���u�ݑ�v�x�� �@�\�\����ł̍Ŋ���]��ł��A�����ɂ́u��ނ��a�@�Łv�Ƃ������������̂ł́B �@��`�@����҂́A�Ŋ��͂�͂�Z�݊��ꂽ�Ƃ����]�݂܂��B���͂��������v�]�ɉ����邽�߁A�V�����^�C�v�̍���ҏZ��̏[���𐄐i���Ă��܂��B����ҏZ��͈�Âƕ������������A�Ŋ��܂Ŏ����炵���������T�|�[�g����B�݂��߂Ȏ����}����悤�Ȏ��Ԃ́A������Ȃ��Ȃ�͂��ł��B �@�\�\�ݑ��Ây�������ʼnۑ�́B �@�쓇�@���͂Q�O�O�U�N�Ɂu�ݑ�×{�x���f�Ï��v�Ƃ������x�����܂����B�������A���ۂɂ́A�ݑ��Âɂ��ǂ�����ɂ���l���啔���ł��B���̌����́A�����邱�Ƃ��\���ɐ������Ȃ���҂ɂ���܂��B�������s�\���Ȃ܂܁A���r���O�E�C�����쐬����͖̂{���]�|�ŁA���Ղɓ��ӂ��Ă͂����܂���B �@�\�\���{�̉ƒ�ł́A���͘b�肩�牓������ꂪ���ł��B�{���ɂ���ł����̂ł��傤���B �@��`�@���������ۂ���̂ł͂Ȃ��A�O�ꂵ�đ����Ăق����Ƃ����̂��A�܂����r���O�E�C���ł��B�d�v�Ȃ͖̂{�l�̈ӎv�d���邱�Ƃł��B�l�����ς��ΓP���ύX���ł��܂��B�݂Ȃ����N�Ȃ����ɁA�Ƒ��Ƃ��悭�b�������Ȃ���A���Ў����̎��ɂ��čl���Ă݂ĉ������B �ǔ��V���@2009�N6��18�� |
|||||||||||||||||||||
| �x�����̒����C������@�e�[�p�[�^�X�p�C����Z�X�e���g���L�p | |||||||||||||||||||||
| �@�i�s�x����ȂǂŒ����C������𗈂��C�d�ǂ̌ċz�����悵���Ǘ�ւ̑Ώ��Ƃ��āC�C�ǎx����p�����C���X�e���g���u�p���s���Ă���B���{��w���n�����u�a�@���Ȃ̍א�F�������́C�e�[�p�[�^�X�p�C����Z�X�e���g�iTSZS�j��}������25��̗Տ����т������C���̕��@���x�����̒����C�������ɂ�����ً}���I�Ȓ�����������łȂ��CQOL�̉��P�ɂ��L�p�ł���ƕ����B �Z���Ԃŗ��u�\�ŁC�����Ɍ��� �@TSZS�̓X�p�C�����`��ɂ���ċ��ȕ��ւ̗��u���\�ł���C���a����ׂ肵���e�[�p�[�`��ɂ���ċC�ǂ����C�ǎx�ɂ����Ă̗��u���\�ȋ����X�e���g�ł���B�א싳���́C����1��TSZS���C�lj������獶�E�����ꂩ�̎�C�ǎx�ɂ����đ}������25��i�j��17��C����8��C���ϔN��66.2�C51�`88�j�ɂ��Đ��т��܂Ƃ߂��B �@�Ώۂ͂�������_�f�z�����C���x�̌ċz�����悵�ė��@�������҂ŁC�������͔x����23��C�H������i�p��j1��C�咰����̔x�]��1��ł������B �@�X�e���g���u��ɂ��Â��ł����Ǘ��25�ᒆ10��݂̂ŁC���w�Ö@�݂̂�9��C���w�Ö@�ƕ��ː��Ö@��1��B�ȏォ��C�����̔x���҂������ȑΏۂƌ�����B15��ł͋C�ǂ��獶�E�����ꂩ�̎�C�ǎx�ɂ�����1��TSZS��}�����C10��ł͂��̂ق��ɑΑ���C�ǎx�ɂ��Z���X�p�C����Z�X�e���g��}�����āC�Ɍ^���u�܂��͐l���^���u�Ƃ����B �@���ʂƂ��āC13��Ŏ_�f�z���𒆎~�ł��C6�Ⴊ���ʁC4�Ⴊ�p���܂��͑����ł������B�ċz����x��\��Hugh-Jones���ނ́C�X�e���g�}���O�ɑS�Ⴊ�ł��d��V�x�ȏ�ł��������C�}����� I �x9��CII�x5��CIV�x11��Ɖ��P���F�߂�ꂽ�B16�Ⴊ�މ@���C9��͑މ@�Ɏ���Ȃ��������C�މ@�\�ł����Ă����Җ{�l�̊�]�ɂ����@�𑱂�������������Ƃ����B23�Ⴊ���Ɏ��S���Ă���C�����͈��t��9��C����3��C���̗���10��C�x��1��ł������B���������͕���105.5���i7�`528���j�B �@��������TSZS�̒����Ƃ��āC(1)�d���C�ǎx����S�g�����̕K�v���Ȃ�(2)�Z���Ԃŗ��u���ł��C�����Ɍ��ʂ�������(3)�p�Ȃ��\�ŁC�C�ǎx���}��ǂ��Ȃ�(4)���u��ɕ��啨��p��ɋz������K�v���Ȃ��\���Ƃ��������B�������C�S��Ƀ}�N�����C�h�̏��ʒ������^���s���Ă���Ƃ����B �@����C�Z���Ƃ��ẮC(1)���u��Ɉʒu�̏C�����ł��Ȃ��i���Ă͂����Ȃ��j(2)�X�e���g���ɍċ���𗈂����Ƃ�����(3)����������i�����̕K�v�̂Ȃ���ɓK�p����j�\���Ƃ��w�E�����B �@�����25��ł�TSZS�̑}���E���u�ɔ����d��ȍ����ǂ͑S�������Ȃ��������Ƃ���C�������́u���������̏I�����ŋC������𗈂�����ɑ��钂������C�����QOL�̖ʂ��猩���ꍇ�CTSZS�͗L�p��airway stent�ƌ�����v�ƌ��_�t�����B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N7��16�� |
|||||||||||||||||||||
| �ɘa�P�A�`�[���̉ۑ�ɏœ_�@�I�������҂ւ̑Ή����b��� | |||||||||||||||||||||
| �@��14����{�ɘa��Êw��w�p��19�A20���̂Q���Ԃɂ킽��A���s�ŊJ���ꂽ�B�����̃e�[�}�́u�ɘa��Á|���_������H�ց|�v�B�ɘa�P�A�`�[���̉ۑ�����グ�����������ق��A�m�a�l�iNarrative
Based Medicine�j�̊ϓ_����ɘa��Â݂̍�����l����V���|�W�E�����g�܂ꂽ�B�I�������҂ւ̑Ή����b��ƂȂ����B
�@�w��Q���ڂɂ́u���҂̐S�Ɋ��Y���`�ɘa��Âɂ�����m�a�l�̊ϓ_�`�v���e�[�}�ɃV���|�W�E�����J���ꂽ�B���s���w���t���a�@����T�|�[�g�`�[���̊ݖ{���j���́A�a�����҂̐l���̒��œW�J����P�́u����v�ƂƂ炦��m�a�l�ɂ��āA���҂���̕���̕����o�����d������l�����Љ�B�x�R��ی��Ǘ��Z���^�[���V�����́A��Â̌���łm�a�l���d�a�l�iEvidence Based Medicine�j��������Ƃ̎��_��W�J�����B �@ �ݖ{���ɂ��ƁA�m�a�l�Ƃ͕a�����҂̐l���̒��œW�J����P�́u����v�ƂƂ炦�A���҂�̌���Ƃ��đ��d�����@�B�����ɁA��w�I�Ȏ����T�O�⎡�Ö@���u��Îґ��̕���v�ƂƂ炦�A���҂̕�������荇�킹�āu�V��������v�����o���v���Z�X�����Âƈʒu�t����B �@�ݖ{���́u�ɂ݂��߂��镨��v�Ƒ肵�āA�A�ǂ��҂̃G�s�\�[�h���Љ���B���҂̓I�s�I�C�h�Śq�C���������o������A�ɂ݂��䖝���Ăł��I�L�V�R�h���̎g�p�����ۂ������Ă����B�������m�a�l�Ɋ�Â����A�v���[�`�ɂ���āA�ŏI�I�ɃI�L�V�R�h���̓��^�����ꂽ�Ƃ����B �@�V���� �́A�ݖ{���͊��҂ƈ�t�Ƃ̋�̓I�Ȃ����̒�����A���҂̕���i���a�j���܂������o�����Ƃ��|�C���g�Ƃ��Ďw�E�B���̃P�[�X�ł́g�ɂ݂����������h�Ƃ����͈̂�Îґ��̕���ł���A���̂��Ƃɉe������߂���ƁA�u�i���҂̕�������āj�ɂ݂�����C�Ɋ|���長�����ɂȂ��Ă��܂��v�ƒ��ӂ𑣂����B �@�܂��A���ɗ��҂̕��ꂪ����Ă��Ă��A�C�荇�킹�ĐV������������o�����Ƃ͉\�ł���Ƃ̌�����B��������ɂ́A���҂̈Ⴂ��A�C�荇�킹�̕K�v�������o���Ă������Ƃ��s���ł���Ƃ����B �@�V�����͂m�a�l�Ƃd�a�l�̊W�ɂ��āA�Η��I�ȗ������嗬�ł���Ɛ����B���̏�ŁA���҂̐��E�ς͈قȂ���̂́A���҂ƈ�t�Ƃ̑Θb�̌���ɂ����āA�m�a�l�͂d�a�l���E����������Ƃ̍l�������������B �u�m�a�l�ɃG�r�f���X��荞�߂�v �@�m�a�l�̎�@�����܂��@�\����A��Î҂Ɗ��҂Ƃ̊ԂőΘb���i�݁A���̌��ʁA���ÂɊւ��鋤�L�̕��ꂪ���o�����B���̕�����\�z����O������̗v�f�Ƃ��āA�G�r�f���X���m�a�l�̒��Ɏ�荞�܂��Ƃ����B �@�V�����̓G�r�f���X�̋�̗�Ƃ��āA�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�Ȃǂ�B�u�m�a�l�̍\���̒��ɃG�r�f���X�͏\���Ɏ�荞�ނ��Ƃ��ł���v�Ɨ͐������B m3.com�@2009�N7��17�� |
|||||||||||||||||||||
| ��������߁A�Ăё̓��ց@���nj^�Ŗڋl�܂���� | |||||||||||||||||||||
| �@���������Ȃǂ̂��߁A����זE�����o�ɍL���萅�����܂��������̎��ÂɁA�������Ă�߂��A�h�{����Ɖu�����͑̂ɖ߂��u������ߔZ�k�ĐÒ��@�v�i�b�`�q�s�j�����ڂ���Ă���B���u�̖ڋl�܂肪���������]���̕��������ǁB���҂͕����̒���⑧�ꂵ�������P�����B�u�����͔����Ƒ̂����v�Ƃ̍l�������������A�J���҂�́u�������猳�C�ɂȂ�v�ƌĂт����Ă���B ���h�{���̊O�� �@����̕����́A�݂���◑������Ȃǂɂ�邪�������̂ق��̍d�ςł������A���Ȃ����ς�ς�ɖc��đ��ꂵ���Ȃ�����H�������Ȃ��Ȃ����肷��B �@�����≖���̐����A���A�ܓ��^�̂ق��A���o�ɐj���h�����������Â��s���Ă������A���ʂ͂P�T�Ԓ��x�ƒZ���B�h�{������a�Z���^�[ �i�R�����h�{�s�j���������̏���\�S��t�́u�h�{��ԂɊW����A���u�~���A�Ɖu�ɊW����O���u�������ꏏ�Ɏ̂ĂĂ��܂����߁A����ɕ��������܂�₷���Ȃ�A�J��Ԃ����тɑS�g��Ԃ��}���Ɉ�������v�Ɛ�������B �@���̌��_��₤�̂��b�`�q�s�B���������������Ȗ��ɒʂ��A������A�g�̂ɗL�Q�Ȃ���זE�A�ۂȂǂ���߂��ď����������A�A���u�~����O���u�����͉�����A��P�O���̂P�̗ʂɔZ�k���ĐÖ����犳�҂ɖ߂��B�P�X�W�P�N�ɕی����K�p���ꂽ�B ���O������ �@�������̕��@�́u�̍d�ςȂ���Ȃ����A���������̕����ł́A����זE�┒�����Ȃǂ̍זE�������������ߖ����ڋl�܂肵�A���~����P�[�X�����Ȃ��Ȃ������v�ƁA���肳��B �@���肳��͂Q�O�O�P�N�����Ë@�탁�[�J�[�Ƌ����ʼn��ǂɒ���B���������q�������̃|���X���z���Ȃǂłł��������̃t�B���^�[���g���A�������������O���ɉ����o���Ă�߂���]���̕��@���A�O����������ɂ�߂��ċl�܂�ɂ�����������ɕς����B �@��N�Ď��_�łS�O�l�̊��҂Ɍv�P�R�O����{�B�P��ɔ��������͂R��`�V��~�����b�g���ŁA�ł����������̍d�ρE�̂���̒j�����҂ɂ́A�R�N�R�J���̊ԂɂQ�W�Â��s�����B�A���u�~����₤���t���܂͈�x���g�킸�ɉh�{��Ԃ͏��X�ɉ��P�A���{�Ԋu�������Ȃ����B �@���肳��́u����̕����̏ꍇ�A�����q�l�Ȃnj��ʂ̍������ɖ�ł������̒������������y������Ȃ��ꍇ���������A�b�`�q�s�Ȃ�ċz����Ȃǂ��܂߂����o�Ǐ�͂��݂₩�ɉ��P���A��ɂ���菜����v�Ɛ����B �@���҂͐H�~�������čs���͈͂��L����B����p�Ƃ��Čy�����M�Ȃǂ�������ꍇ�����邪�A�V���b�N�Ȃǂ̏d���Ǐ�͂���܂łɂȂ��Ƃ����B ���ϋɎ��� �@���肳��͍�N�A�����̈�Ë@�ւɂ���A�t�|���v�Ȃǂ��g������y�Ȃb�`�q�s�V�X�e�����J�������B���ÑO�̏������P�O���قǂōς݁A���������̌����������A���̖ڋl�܂����������@�\�ŔS�t�̑�����������Ȃǂɂ��g����悤�ɂȂ����B �@���݁A������̃O���[�v�ɋ��͂��Đi�߂Ă���̂��A�݂���ɂ�邪���������҂̕��o���ɍR����܂𓊗^���鎡�ÂƁA�b�`�q�s�Ƃ̕��p�B����܂ŁA�R����ܓ��^�O�ɔ����������͂��ׂĎ̂ĂĂ������u�V�J���̂b�`�q�s��g�ݍ��킹�A�����悭�h�{�A�Ɖu������������Č��Ǔ��ɖ߂��A��莡�Ì��ʂ����܂�̂ł́v�Ə��肳��B �@���N�S���ɂ͂b�`�q�s�̕��y�Ȃǂ�ړI�ɂ�����������ݗ����ꂽ�B���肳��́u�]���͊ɘa�P�A�̈�Ƃ��Ăق��ڂ��s���邱�Ƃ����������b�`�q�s���A���������ɑ���ϋɓI�Ȏ��Âƈʒu�Â��A�W�����Â̘e���Ɉ�Ă����v�Ƙb���Ă���B ������Ì��N�j���[�X�@2009�N7��21�� |
|||||||||||||||||||||
| ���͂���]���Ȃ���������ւ̊ɘa�P�A�̍H�v | |||||||||||||||||||||
| ��� ��@����l���a�@�t�Z���^�[�� �@�����t��Q���҂ɑ��鎡�Â̑I�����͌��t���͂����ł͂Ȃ��B���ɒ�����҂ւ̓��͂̓v���X�ʂ��}�C�i�X�ʂ̂ق����傫�����Ƃ����� �B���A�܂Ȃǂɂ��ΏǗÖ@�ʼn��P���邱�Ƃ�����B �A�t���n���ɂ̓G���X���|�G�`�����L�p�����g�p�p�x�͒Ⴍ�A���y���]�܂�� �B �B������̍ۂ́A������Q��F�m�ǂƂ���������҂Ȃ�ł͂̏�Q���܂߂�ADL�]�����K�{ �B �C�P�A�v�����̌���ɂ́A�Ƒ��̎����ӌ����l������B �D�x������Љ�͎��Â̑I������D���B�Œ�ł��t�@�\��15���������t����ɏЉ��B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N7��23,30�� |
|||||||||||||||||||||
| �ɘa�P�A�ƃv���C�}���P�A�̗Z����ڎw���@��14����{�ɘa��Êw�� | |||||||||||||||||||||
| �@���{�ɘa��Êw��ł͊ɘa��Â̐���F�萧�x���n�܂�C�ɘa��Â̐�含���邢�͈�ʐ�������Ă���B�܂��C�s���哱�^�̑�K�͌����u�ɘa�P�A���y�̂��߂̒n��v���W�F�N�g�v���S��4�n��ŊJ�n����C�ɘa�P�A�͒n���Â̂Ȃ��ɍL�����Ă��Ă���B���s�ŊJ���ꂽ��14����{�ɘa��Êw��̃p�l���f�B�X�J�b�V�����u�ɘa�P�A�ƃv���C�}���P�A�̐ړ_�v�ł́C�n���ÂƐړ_����������ɘa�P�A�̌�����C����̕������͊ɘa�P�A�ƃv���C�}���P�A�̗Z���ł��邱�Ƃ������ꂽ�B �`�����Տ����C�̃v���C�}���P�A���C�` �ɘa�P�A�̊�{�I�ԓx�̏K���ɗL�p �@2004�N4������V���Ȍ`�ŊJ�n���ꂽ�����Տ����C���x�ł́C�v���C�}���P�A�̊�{�I�f�Ô\�͂̏K�����ړI�ɋ������Ă���B���v�����a�@�i���쌧�j�����f�ÉȁE�n��P�A�Ȃ̎R�{���㒷�́C���@�ł̃v���C�}���P�A���C�C�ɘa�P�A���C�ւ̎��g�݂��Љ�C�����Տ����C�Ńv���C�}���P�A���K�����邱�Ƃ́C�ɘa�P�A�ɕK�v�Ȋ�{�I�ԓx�̏K���ɂȂ���Əq�ׂ��B �v���C�}���P�A�Ɗɘa�P�A�̓I�[�o�[���b�v �@�v���C�}���P�A�̊�{�I�f�Ô\�͂́u�ڂ̑O�̊��҂̋C������v�ɃA�v���[�`�ł��邱�Ƃł���C�ɘa�P�A�͕a���⎾���ɂ�����炸��ɂ̗\�h�ƌy����}��CQOL�����コ���邱�Ƃł���ƒ�`����Ă���B�R�{�㒷�ɂ��ƁC���̃v���C�}���P�A�̗��O�Ɗɘa�P�A�̊�{�����̓I�[�o�[���b�v����Ƃ����B���Ȃ킿�C QOL�E�R�~���j�P�[�V�����̏d���C�S�l�I�A�v���[�`�C�Ƒ����܂߂��P�A�̓_�ł���B�����āC�����������Տ����C���Ԃɂ����Ċw�Ԃ��Ƃ��d�v�ł���C�����ǂ̐��̈�ɐi�ނɂ��Ă��K�v�Ȕ\�͂ł��邱�Ƃ���C��Î҂Ƃ��Ă̊�b�ƂȂ镔���ł���Ƃ����B �@�����������Ƃ܂��C���@�ł͑����f�ÉȂ𒆐S�Ƀv���C�}���P�A���C�Ɗɘa�P�A���C���s���Ă���B �@���C�ł́C�S����Ƃ��Ċ��҂������Ƃ�ʂ��Ċ�{�I�f�Ô\�͂̌���C��f��ʒk�̏��ʂ��ăR�~���j�P�[�V�����\�͂̌����}���Ă���B�܂��C���ɔ҂̗ՏI�̏�̌o�����d�����Ă���B �@�҂�End of Life Care������ȓ_�Ƃ��āC(1)�ǂ��܂ł��\�ȏ�Ԃłǂ����炪�s�\�Ȃ̂��̔��f���C���҂ɔ�ׂē��(2)�҂ł͗\��\��������C�I���̌����Ȃ���삪�����\��������(3)�R�~���j�P�[�V���������Ȃ��ꍇ�������C���ÖڕW���ǂ��ɒ�߂�̂��C���҂�����]��ł���̂����킩��Ȃ����߂Ɋ��҂�QOL�����コ���邱�Ƃ�����`���Ƃ���������B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́C���E��ŗՏ��ϗ��J���t�@�����X���s���C��������B���̂Ȃ��Ō��C��́C��w�I�Ȑ����������������Ƃ͌���Ȃ����Ƃ��w�сC��t�̎��_�Ƒ��̐E��̎��_�̈Ⴂ�ɂ��Ēm�邱�Ƃ��ł���B �@�n��P�A�Ȃ̒n���Ì��C�ɂ����ẮC���C�オ���ۂɍݑ�P�A�̌�����o���ł��邱�Ƃ���C���̌�C�a�@�œ����ɂ��Ă��C�ݑ�×{�̃C���[�W�������₷���Ȃ�ƍl������B �@���㒷�́u�����Տ����C�ɂ����ďd�v�Ȃ��Ƃ́C�v���C�}���P�A�̊�{�I�Ȑf�Ô\�͂̊l���ł���B����͊ɘa�P�A���s�������ŕK�v�Ȋ�{�I�ԓx��g�ɕt���邱�ƂɂȂ���C�����ǂ̐�啪��ɐi��ł��d�v�ł���v�ƌ��_�t�����B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N8��13�� |
|||||||||||||||||||||
| �I������Â�����V���Ȓm���@���҂ƉƑ��̕s���ɂǂ��Ώ����邩 | |||||||||||||||||||||
| �@�I������ÂɊւ��镡���̌��������\���ꂽ�B�������Â݂̍���������t�Ƃ̎��O�̘b��������C�I�����ɕK�v�Ȉ�Ô�̑��k�C�l��E�����ɂ��I������Ô�̍��C�I�����ɂ����銳�ҁE�Ƒ��̈�t�ɑ���S���I�ω��Ȃǂ𖾂炩�ɂ������̂ł���B ��t�Ƃ̎��O���c�ň�Ô�팸 �@65�Έȏ�̍���҂�ΏۂƂ����č��̌��I��Õی��ł��郁�f�B�P�A�ɂ��x������3����1�́C���N���S����5���̎҂ɔ�₳��Ă���B�܂��C���S�O1�N�Ԃɗv������Ô��3����1�����S�������ɔ�₳��Ă���ȂǁC�I������ÂɎx�o������Ô�̕s�ύt���w�E����Ă���B��s�����ɂ��C�����̈�Ô�̑����́C�h���p��l�H�ċz��̑����Ȃlj������u�ɂ����̂ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ��Ă���B �@�_�i�E�t�@�[�o�[�������i�{�X�g���j���_��ᇊw�E�ɘa�P�A��������Baohui Zhang����́C�I������Â݂̍���ɂ��Ď��O�Ɉ�t�Ƙb�������Ă������҂ł́C���S���O��1�T�Ԃɗv�����Ô�Ⴍ�Ȃ�Ɣ��\�����B����́C�č������_�ی��������ƕč����������ɂ��C�i�s���҂�ΏۂƂ������{�ݏc�f�����ł���Coping With Cancer�����̎Q����627�l��603�l��Ώۂɂ���������蒲���̌��ʁC���炩�ƂȂ����B �@������́C�x�[�X���C���Ƃ��ē��������J�n���ꂽ2002�`07�N�ɁC�I������Â݂̍���ɂ��Ĉ�t�Ƙb�����������ǂ��������C���S����܂ŒǐՂ����B �@���̌��ʁC�x�[�X���C�������ł�188�l�i31.2���j���I�����P�A�ɂ��Ă̊�]����t�Ƙb���������ƕ����B�I������Â݂̍���ɂ��Ĉ�t�Ƃ��炩���ߋ��c���Ă����팱�҂ł́C���S���O��1�T�Ԃɗv�������ϑ���Ô��1,876�h���ł������̂ɑ��C���c���Ă��Ȃ������팱�҂ł�2,917�h���ł������B �@�팱�҂̎��S��ɁC���҂ɍs����������蒲���̌��ʁC�I�����ɂ���������Ô�����팱�҂قǁC���S���O��1�T�Ԃ́u���̎��iquality of death�j�v���Ⴂ���Ƃ������ꂽ�B �u���̂Ă�ꂽ�v�Ɗ�����Ƃ� �@���V���g����w���Ȃ�Anthony L. Back�����́C����ڑO�ɍT�������҂�Ƒ�����t����u���̂Ă�ꂽ�v�Ɗ�����̂́C(1)���̖ڑO�Ŏ��Â̌p�������r��(2)���̒��O�܂��͎���ɐS�̐������t���Ă��Ȃ��`�Ƃ���2�̗v�f���琶����ƕ����B �@��������́C(1)���Õs�\�̂���܂��͐i�s���x�����ŁC�]��1�N�ȉ��Ɛf�f���ꂽ����55�l(2)�����̊��҂̎��ÁE���ɓ���������t31�l(3)�Ƒ�����36�l(4)�Ō�t25�l�\��ΏۂɁC�����o�^����4�`6�����エ���12������̎��_�ŕ�����蒲�����s�����B �@��������́u���҂�Ƒ����҂́C�����i�K����S���ォ�猩�̂Ă��邱�Ƃ�����C���ҁE�Ƒ������݂̍j�ɂ��Ă�����t�ɂ����I�Ȏ��Â����Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜���Ă����B��t�͊��҂�Ƒ��������鋰�|�ɋC�t���Ă���C���S��������C�p���I�Ɏ��Âɓ����邱�ƂŁC�s�����������悤�Ǝ��݂Ă����B�������C����ł��Ȃ��C����������ɂ�C�S����ɂ�����I�Ȑf�Â̋@�����C�W��������邱�Ƃ���C���̂Ă�ꂽ�Ƃ��������������҂�Ƒ��������v�Əq�ׂĂ���B �@����ɁC�������́u�������������Ƃ��⎀��ɂ́C�ǂ̂悤�ɐS�̐�����t���邩�Y�ނ��Ƃ�����B����ő����̈�t�́C���҂�Ƒ��̐S�̐���������ł��Ȃ��Ɗ����Ă��Ȃ�����C���҂�Ƒ������̂Ă��Ƃ͎��o���Ă��Ȃ��v�Əq�ׁC�u���̒m������C�Տ���́C�Ō�t�Ȃǃ`�[����Ẫ����o�[�ƂƂ��ɁC�z�X�s�X�{�݊O�ł̊ɘa�P�A�⊳�҂�Ƒ��̊Ŏ��ɍۂ���S�̐����̕t�������x�����邱�Ƃɂ��C���҂ɑ��w��t�Ƃ��Č����Č��̂ĂĂ��Ȃ��x�Ƃ����p�����������Ƃ̕K�v����F���ł��邾�낤�v�Əq�ׂĂ���B ���E��]�̉A�ɂ���s�� �@�I���S���B�ł́C�S�ĂŗB��C��t�̛ɂ�鎩�E���@�I�ɔF�߂��Ă���B�I���S���ی��Ȋw��w���_�Ȃ�Linda Ganzini���m��́C��t�ɂ�鎩�E����]���Ă��銳�҂̓��@�͌��݂̏Ǐ�ł͂Ȃ��C�ނ��낱�ꂩ���ɗ\�z������ɂ⎩�������������Ƃւ̕s���ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B �@�����m��́C��t�ɂ�鎩�E����]���Ă��邩�C���邢�͊֘A�̊��҂̌����i��c�̂ɐڐG����56�l�̊��҂ɑ��ĕ�����蒲�����s���C���@�ƂȂ肤��29�̐ݖ�ɑ�1�i�d�v�ł͂Ȃ��j�`5�i�ł��d�v�j��5�i�K�ŕ]�������B �@���̌��ʁC�ł��d�v�ȗ��R�Ƃ��ċ�����ꂽ�̂́C(1)���ɍۂ��Đg�Ӑ��������C����Ŏ��ɂ�������(2)�������������邩��(3)���ꂩ���̋�ɂ�QOL�������邱�ƁC�����Ŏ����̐��b���ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃւ̕s���\�Ȃǂł������B���݂̐g�̓I�ȏǏ�Ɋւ��ẮC���R�Ƃ��ďd�v�ł͂Ȃ��ƕ]�����ꂽ�B �@�����m�́u���̒m���́C���߂Ċ��҂��Տ���Ɏ��E����]�����ۂɂ́C�g�̓I�ȏǏ�C���邢�͂��̂Ƃ���QOL�����R�ł͂Ȃ��C���̐�ɔ��ł��낤�ς���������ɂɑ���\������C���E����]���Ă��邱�Ƃ��������Ă���B���҂̎��ɑ����]�͂���قNj������̂ł͂Ȃ��C�����̐l���͎����Ⴍ�ĈӖ����Ȃ��C�����l�ł���ƐM���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ނ���C�ς���ꂻ���ɂȂ����ꂩ���̃��X�N����g������Ă���悤���v�ƕ��́B�u��t�ɂ�鎩�E�̛��˗�����鎖�Ԃɒ��ʂ����ۂɂ́C��Î҂͊��҂�����������R���g���[���ł��銴�o���x���C���ꂩ��\�������Ǐ���ǂ̂悤�ɊǗ����邩�ɂ��ċ��炵�C���S������K�v������v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N8��20�� |
|||||||||||||||||||||
| ���҂̒ɂ݁i�y�C���j | |||||||||||||||||||||
| ���҂̒ɂ݁i�y�C���j �@�i�P�j�g�̓I�ɂ݁i�Q�j���_�I�ɂ݁i�R�j�Љ�I�ɂ݁i�S�j�X�s���`���A���Ȓɂ݂���Ȃ�u�S�l�I�v�Ȃ��̂Ƃ����B��`�����̂́A���E���̃z�X�s�X�a�@���p���ɊJ�݂����V�V���[�E�\���_�[�X�i�P�X�P�W�\�Q�O�O�T�j�B�̂̒ɂ݂���菜���̂��z�X�s�X��Ái�ɘa�P�A�j�̑�O���A���݂̓X�s���`���A���Ȓɂ݂̃P�A���d�v������Ă���B��`�͒�܂��Ă��Ȃ����A���ɒ��ʂ��Đ����鎩�ȏ����̋��|��A�l���ւ̔ߒɂȂǂ��w���Ƃ����B �@��������ȂǏd���a�ɂ���l���u������Ӗ����Ȃ��v�u���ɂ����v�ƌ��ɂ����Ƃ��A�ǂ��~�߂�����̂��낤?�B�z�X�s�X��Â̎��H�҂Ƃ��Ēm����R��͘Y��t�ƁA��×ϗ������̃J�[���E�x�b�J�[���s���w�@�������A���ɒ��ʂ������ҁE�Ƒ��́u�ɂ݁v�ɂ��đΒk�����B�J�E���Z�����O��X���̌��C�ȂǂɎ��g��ł���u�s���z�X�s�X�E�����v�̎�Ái�����{�V���ЂȂnj㉇�j�B�u�����炵��������Ƃ������Ɓ@�l�Ԃǂ����炫�ā@�ǂ��ւ����̂��v�Ƒ肵�A8���P���ɕ����s�ł������Βk���Љ��B �@���{���̘b�� �@ �@�R��@�͘Y���@�z�X�s�X��i�ȉ��A�R�j�@��������̊��҂̐l���ɓ��s���Ă����B����̒ɂ݂͎��ɐl�Ԑ���D���قNj������A�i���ɖ�Łj��菜�����Ƃ��ł���B����������ɑ̗͂������A�x�b�h��Ŕr�����˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�����A�V�����[�𗁂т���ł��Ȃ��Ȃ�ƁA�����߂��ƕ�����B�u�����I���ɂ������v�Ǝ��͂ɑi�����ʂ��o�Ă���B�X�s���`���A���y�C�����B �@ �@�J�[���E�x�b�J�[���@��×ϗ������ҁi���A�x�j�@���͖����̂��҂Ɂu�I��点��ׂ����Ƃ��I��点�܂������v�Ɛq�˂Ă����B���̊F������A�⌾�������Ă��܂����H�@�������錾�́H�i���l�̂���j�@���̂悤�ɁA���ׂ����Ƃ͎c���Ă���B���ɑ�������]�ނ̂��������Â�I�Ԃ̂��ɂ��ẮA���߂Ă����Ȃ��ƌ�X�܂ʼnƑ���Y�܂��邱�Ƃɂ��Ȃ�B �@ �@�R�@�S���Ȃ�܂ł̐��T�Ԃ̗͑͂̒ቺ���������A�b�����Ƃ��������Ƃ�����Ȃ�B�����u��Șb�͍��̂����Ɂv�Ə������Ă���B �@�x�@���ӂ�����A�����肵�����l�͂��܂��A�Ƃ������B�u���Ȃ��͓`���������Ƃ�`���邱�Ƃ��ł��܂��v�ƁB �@ �@�R�@���ׂ����Ƃ͂�������B�����̑��V��A���ڂ����߂Ă��������Ƃ������҂������B����F�߂�̂͂炢���A�F�߂Ă��܂��Ƒ厖�Șb���ł���B �@ �@�u���͂��Ƃǂꂭ�炢�ł����v�Ɗ��҂ɂ悭�������B���̏ꍇ�A���͋t�Ɂu���Ȃ��͂ǂ��v���܂����v�Ɛq�˂�B�u���Ɓ������炢�ł��傤���v�ƕԂ��Ă���Ɓu���������v���܂��v�ƔF�߂Ă��܂��B�{�l�͑̂�����Ă������Ƃ��\�������Ă���B����Ȃ��Ƃ���܂����A�Ɣے肵�Ă��܂�����R�~���j�P�[�V�����͐������Ȃ��B �@ �@�x�@�m���Ɏ���F�߂�̂͂炢�B�ł����Җ{�l����Ԙb���������Ƃ́A�����͂��ꂩ��ǂ��Ȃ�̂��A���̐��Ƃ͉����A�����Ď����̐l���͉����������B�{���ɘb���������Ƃ����ɏo���Ȃ��̂͂����Ƃ炢�B �@ �@�R�@�Ƒ����{�l�̎�����F�߂��A�{���̘b���ł��Ȃ��������߂Ɍ�����Ă���Ƒ��͂�������B�d�v�Ȃ��Ƃ́A���������Ȃ����Ƃ��B �@�����ɂ��� �@ �@�R�@�u���ɂ����v�ƌ���ꂽ��u�ꐶ�����ŕa���Ă����̂Ɂv�Ǝ��Ȕے肳�ꂽ�Ɗ�����Ƒ������邩������Ȃ��B�ł��A���Ȃ��̑i�������͗������Ă��܂���A�Ǝ~�߂邱�ƂłȂ��肪�ł���B �@ �@�x�@���ɂ����A�Ƃ������t�́u�ꏏ�ɂ��Ăق����v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B�a���������Ƃ͂ł��Ȃ��Ă��A���ɂ��邱�Ƃ͂ł���B �@ �@�u�������]���Ȃ��v�Ƒi���銳�҂����邾�낤�B��]�͂��Ď��Â��������A���͂⎡�Â͂��Ȃ�Ȃ��B���́u���̐��ʼn�����l�͂��邩�v�ƕ����B�u���̐��Ȃ�Ă��邩�������v�Ɠ����銳�҂͂��Ȃ��B�N�����u�����ɉ�����v�Ƙb���Ă����B������ЂƂ̊�]�ł͂Ȃ����B �@ �@�R�@�l�͐�����Ӗ������������Ƃ��A�����̗͂����傫�Ȃ��̂ƂȂ�������A�܂��͎����̓��ʂɊ�]�����������͂������Ă���B�u���ɂ����v�ƌ����o�����Ƃ��́A�{�������Ă���͂����n�߂��ƂƂ炦�邱�Ƃ��ł���̂ł́B �@ �@�x�@�l�ނ̓l�A���f���^�[���̎��ォ��A���̐�������ƍl���Ă����B�@���@�h�̖��ł͂Ȃ��A���͏I���ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ă����B��_��k�Ђ̌�ɂ́A�S���Ȃ����l�̐���C�z���������l����������B����͔ے肷�ׂ��̌��ł͂Ȃ��A�厖�ȑ̌����B �@ �@�R�@���~�Ɍ}���A���������悤�ɁA�������͕����I��̒��Ő����Ă���B���͕ʂ�ł͂Ȃ��A�܂���܂��傤�A�Ƃ������ƁB�a�͎������Ƃ��Ă����͕K���K���B�L���̎��Ԃ̒��Łu���Ȃ��]�v�����������Ȃ��玄�����͐����Ă���B �����{�V���@2009�N8��24�� |
|||||||||||||||||||||
| ��ᇊO�Ȉ�E�����̉@���̒n��ƂƂ��ɕ��ވ�� �k ��11�� �l�n��ɘa�P�A�x���l�b�g���[�N |
|||||||||||||||||||||
| �b��g�a�i�\�a�c�s�������a�@���j �@�n��ɘa�P�A�x���l�b�g���[�N�̈�Îx���V�X�e���́C�g���q�h�Ƃ��ăl�b�g���[�N���x���܂��B���̃V�X�e�����x����`�[���ɂ́C��t�C�Ō�t�C��t���܂߁C��ÂɊW���鑽�E�킪�Q�����܂����C�ł��d�v�Ȗ������ʂ����Ă���̂��K��Ō�t�ł��B �@�K��Ō�t�̖����́C�a��̊ώ@�C��ɏǏ�̕]���C�Ǐ�ɘa���Â̌��ʂ̕]���C�w���Ɋ�Â����Â̎��{�C��Ë@��̊Ǘ��ƉƑ��ւ̎w���C�Ƒ��ɑ���Ō삨��щ��̎w���C���@�C�Ŏ��̎w���Ȃǂ̂ق��C��t�Ɗ��҉Ƒ��Ƃ̋��n���ȂǑ���ɂ킽��܂��B�L�\�ȖK��Ō�t���Ή����邱�ƂŁC���҂�Ƒ������Ĉ�t���s���Ȃ������𑗂邱�Ƃ��ł���킯�ł����C���̂悤�ȖK��Ō�t�̖�����d�v���Ɏ������߂ċC�t�����̂�1996�N7������ł��B �@���N4���ɑO�C�n�̕����J�Еa�@�ɖK��Ō쎺���J�݂���C��]�̖K��Ō�t3�����ݑ�̌���ɕ����n�߂�3������̂��Ƃł��B����܂Ŗ�9�N�ԁC����l�ōݑ�z�X�s�X�P�A���s���C����ł̏Ǐ�ɘa���Â̒m����Z�\�����߂Ă��܂������C���̒m����Z�\��K��Ō�t���Z���ԂŊo�������ƂŁC��t�Ƃ��Ă̎��̋Ɩ������Ȃ�y������܂����B�܂��C�K��Ō�t�������銳�҂�Ƒ��̂��܂��܂ȏ��i�a��ɑ���s���C�ƒ�̖��C�o�ϓI�Ȗ��Ȃǁj�́C�����g�ɑ����̊w�т������炵�܂����B �@���̂悤�ȖK��Ō�t�̓����Ԃ���݂āC���́u�ݑ�z�X�s�X�P�A���܂ލݑ��Â̒S����͖K��Ō�t�ł���v�ƁC���_�t���܂����B�����āC���̉�����ŁC�u�a���ɂ�����I�����ɘa�P�A�̒S����͊Ō�t�ł���v�Ƃ����_�t���Ă��܂��B���݁C�����̕a�@�ł���I�������҂���Y��������܂ܓ��@���Ă��܂��B���̋�Y�ɓK�ɑΉ��ł��Ă��Ȃ��傫�ȗ��R����t�̖��S�ł���ƌ����C��t�̊ɘa�P�A���炪�i�߂��Ă��܂����C���͂ނ���Ō�t�̋��炪�d�v���ƍl���Ă��܂��B �@2007�N10������A�g���n�߂�5�̖K��Ō�X�e�[�V�����͂������24���ԑΉ��ŁC��1�N���ȏ�o�߂������͈��S���ĔC���邱�Ƃ��ł��܂��B�������ƂȂ����̂́C���҂̕a�}�ɕω������Ƃ��̑Ή����x�����Ƃł����B����܂ŁC��r�I���肵���l�̉�쒆�S�̖K��Ō���s���Ă������߂��Ǝv���܂��B��Ƃ��āC�Ƒ��ɂ͕a��ɏ����ł��ω�������Ƃ��͖K��Ō�t�ɓ`����悤�O���������Ƃɂ��܂����B���̖K��͑�̏T1��ł����C�a�����Ȃ����Ƃ��ɂ͉Ƒ��̗����ĖK��Ō�t�ɕp��ɖK�₵�Ă�����Ă��܂��B�S�����Ă���K��Ō�t�Ɗ�����킹��̂́C�P�A�J���t�@�����X�C��1��̏\�a�c�ɘa�P�A�Z�~�i�[�C�����āC���S�m�F�̂Ƃ��ł����C�ŋ߂ł͔�r�I������킹��@������Ȃ��Ă��܂��B �@�K��Ō�X�e�[�V�����̑��k���͓��@�̕a�f�A�g���z���̊ɘa�P�A�F��Ō�t�ŁC������̒���C�a��ւ̑Ή����@�̎w���C���ƖK��Ō�X�e�[�V�����Ƃ̋��n���Ȃǂ̋Ɩ��ő��Z�ƂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ɁC�ɘa�P�A���n��ɍL�����Ă䂭�ƁC�a�@�ɘa�P�A�`�[���̐�]�Ō�t�̒n��ɘa�P�A�`�[���Ƃ̘A�g�Ɩ����d�v�ƂȂ�܂��B �@����ɁC��Îx���`�[���Ƃ��đ��݊�������ɍ��܂����̂��ی���ǂ̖�t�ł��B���݁C���˖���܂߂���܂͕ی���ǂ̖�t���z�����C����ŕ���w�����s���Ă��܂��B�����q�l�C�T���h�X�^�`���Ȃǂ̒��˖�̎��v�������C�����̖�ǂŖ��ے��܁i�C���t���[�U�[�|���v�ւ̕�[�Ȃǁj���s����̐�����������Ă��܂��B�ی���ǂ̉ۑ��24���ԑ̐��̊m���ł����C�����t��Ƒ��k���Ȃ��為�Ў����������ƍl���Ă��܂��B [�A��] ��ᇊO�Ȉ�E�����̉@���̒n��ƂƂ��ɕ��ވ�� �T����w�E�V���@2009�N08��24�� |
|||||||||||||||||||||
| �c���D����̂��玀�����݂߂�F�]������ | |||||||||||||||||||||
| ����b��E������t���a�@�y�����A�ɘa�P�A�f�Õ��� �@�����픚�����A�L���ɂ͖�R�T���l�̎s���ƌR�l���Z��ł��܂����B�I��̔N�̂P�X�S�T�N���܂łɁA���̂�����P�S���l�����S�����Ɛ��v����Ă��܂��B �@���S�n����P�E�Q�L���̒n��ł́A���̓��̂����ɂقڔ������S���Ȃ�A��蔚�S�n�ɋ߂��n��ł͂W���ȏオ���S�����Ɛ��肳��Ă��܂��B�픚����̔�����M���ő��������l�͌v�V���l�ɂ��̂ڂ�ƌ����܂��B �@���������̓��́A��P�x����o�܂���ł����B��u�Ŗ���D��ꂽ�V�����̕��X�́A����ȑM���i�����j���^��̖ڂŌ��グ�����̏u�ԁA�قƂ�Ǔ����Ɏ��S�������ƂɂȂ�܂��B���̂悤�ɁA��������u�ɉ������̐l�Ԃ������Ɏ���͉ߋ��ɂ͂���܂���B �@�����Ƃ͎������Ⴂ�܂����A�ˑR�̐S������ȂǁA�v�������Ȃ��ˑR�̎����������A����ɂ�鎀�ɂ́A���܂ł̎��Ԃ����Ȃ肠��܂��B�悭�u�]���R�J���v�ȂǂƂ����b�����ɂ��܂����A������Ȃ��ƕ������Ă���A�����̏ꍇ�͔N�̒P�ʂ̎��Ԃ��c����Ă��܂��B���ہA�]�����N�Ɛ鍐���ꂽ���҂��A���̌㉽�N�������Ă���Ƃ�������́A�߂��炵���͂���܂���B�������A�ǂ����ŋ߂́A��t�̌�����o��u�]���v���A�̂��Z���Ȃ��Ă���悤�Ɏv���܂��B �@�l�́A�y�X�����]�������m���邱�Ƃɔ��ł��B���������A�]����\������̂͂ƂĂ�������Ƃł��B��Âɑ���Љ�̖ڂ��������Ȃ�A�i�ׂ������钆�ŁA��t���u���Ȗh�q�I�v�ɗ]����Z���b���X��������悤�Ɋ����܂��B���m��葁���S���Ȃ�Δ���܂����A�]����Z�������Č��ʂƂ��Ē�����������A�u����v�ɂȂ��킯�ł��B�a�@�ł̓��ӏ��Ɉ������Ƃ��肪�����Ă���̂Ɠ����Ƃ�����ł��傤�B �@����́A���Ɏ���Ȃ��Ă��A�l���̎d�グ�����邾���̎��Ԃ�^���Ă���܂��B�č��ł́A�u�S���a�ň�u�̂����Ɏ��ʂ̂̓S�������B����Ŏ��ɂ����v�Ƃ����l�������ƕ����܂��B �@����́A�v������蒷�����Ԃ��c�����a�C�ł��B���̎��Ԃ��u�ꂵ�����ԁv����u�l���̏W�听�̎��ԁv�ɕς��邱�Ƃ��A�ɘa�P�A�̑傫�Ȗ�ڂł��B �����V���@2009�N9��8�� |
|||||||||||||||||||||
| ����T�o�C�o�[��n��Ŏx����\����f�ØA�g�������@��17����{�z�X�s�X�E�ݑ�P�A������ | |||||||||||||||||||||
| �@���݂̈�ÃV�X�e���ł́C����̐f�f���玡�ÁC���ɂ͎��̊Ŏ��܂ł�1�����̈�Ë@�ւň�т��čs�����Ƃ�����ɂȂ��Ă��Ă���B���̂��߁C�f�ØA�g��}��C����Ƌ������Ȃ��琶����u����T�o�C�o�[�v��n��Ŏx������g�݂��s���Ă���B���m�s�ŊJ���ꂽ��17 ����{�z�X�s�X�E�ݑ�P�A������̃p�l���f�B�X�J�b�V�����u����T�o�C�o�[�T�|�[�g�̎�g�Ɛf�ØA�g�v�ł́C�a�@��ݑ��Â��ꂼ��̗��ꂩ�猩������f�ØA�g�̌���ƍ���̉ۑ�ɂ��ĕ��ꂽ�B ���_�a�@�Ɛf�Ï����p�X�ł���f�ØA�g�� �@���m���̂���f�ØA�g���_�a�@�͌��̒����ɕ݂��C���S�悩�犳�҂���f����B���m��w��Êw�u����ÊǗ��w����̏��ѓ��狳���́u�s���{������f�ØA�g���_�a�@����f�Ï��܂ŁC���S�̂ŋ��ʂ̖ړI�������Ă���T�o�C�o�[�̃T�|�[�g�Ɏ��g�ޕK�v������v�Əq�ׂ��B 8��̂���f�ØA�g�p�X���쐬 �@2001�N�ɒn�悪��f�Ë��_�a�@���x���n�݂���C���̌�̑�3������10���N�����헪�ɂ��2006�N2���Ɂu����f�ØA�g���_�a�@�̐����Ɋւ���w�j�v���o���ꂽ�B���w�j�ł́C�s���{������f�ØA�g���_�a�@�͓s���{����1�������x�C�n�悪��f�ØA�g���_�a�@��2����Ì���1�������x���]�܂����Ƃ��Ă���B���N8���C���m��w�a�@�͍�����w�@�l�Ƃ��ď��̓s���{������f�ØA�g���_�a�@�Ɏw�肳�ꂽ�B�Ӗ��͐f�ÁE���C�E���̐��̐����C��ÃX�^�b�t�̌��C�̎��{��f�Îx���C����f�ØA�g���c��̐ݒu�ƒn��̂���f�Â̎x���Ȃǂ��B �@���ы����́C�����̂���f�Ë��_�a�@�ƒn��̃`�[���̐��̗��z�}��B4�ɕ�����铯���̕ی���Ì���1���������_�a�@�����݂��C�n�撆�j�a�@��f�Ï��ȂǂƗL�@�I�ɘA�g���邱�Ƃ��]�܂����B���������ۂɂ́C������3�����̂���f�ØA�g���_�a�@�́C���l���̖�70�����W�����鍂�m�s�Ɠ썑�s�𒆐S�Ƃ��钆���ی���Ì��ɕ݂��Ă���B���̂��߁C���҂̊O����f�́C�����ی���Ì��ݏZ�̊��҂͎������Ŋ������邪�C�������̈��|�ی���Ì��ł͖�3����1�C�������̍����ی���Ì��ł͖�4����1�������ی���Ì��Ŏ�f�B����ɁC���҂̓��@�́C���|�ی���Ì��̖��C�����ی���Ì��̖�3����2�������ی���Ì��ł���Ƃ����B �@�������́u�����Â̋ςĂ̎����ɂ́C���m���S�̂Őf�ØA�g���l����K�v������v�ƍl���C����f�Â̒n��A�g�N���j�J���p�X�����C�A�g�����̎��g�݂�i�߂Ă���B2009�N2���ɂ͂����ʂɃ��[�L���O�O���[�v���\���B�s���{������ђn��̂���f�ØA�g���_�a�@�C��a�@�C�f�Ï��̈�t�Ȃǂ��Q�����C5�傪��i�݁C�咰�C�x�C���C�́j�ɉ����ĕw�l�Ȃ̂���C�O���B����C�ݑ�ɘa�P�A�̌v8�̃p�X���e�O���[�v�Ŕ��N�Ԃ����č쐬�����B�e�[�}�͏p��̃t�H���[�A�b�v�Ƃ��C9���ɔ��\�Ɠ��_���o�Ċm��B���H�C8�̃p�X�a����C�V�����e�[�}��I��Ŕ��N�Ԃō쐬���C���N3���ɂ͂܂�8�̃p�X���a������\�肾�B������J��Ԃ��C�₦���V�����p�X�̒a����ڎw���Ƃ����B �@�������́u���m���S�̂Ōp���I�Ɍ������邱�Ƃ��d�v���B��w���ǂ������̂Ȃ���������C�݂��̊炪������l�b�g���[�N���\�z�������B����f�ÂɌg���l�X�����ʂ̖ړI�������C�n��ł���T�o�C�o�[���T�|�[�g���Ă����v�ƌ��B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N9��17�� |
|||||||||||||||||||||
| �ɘa�P�A�ȕa���̏������ | |||||||||||||||||||||
| KKR�D�y��ÃZ���^�[��ᇃZ���^�[���@�镔�@�G �@���@�͎l�N�O�̑S�ʉ��z�E�{�ݖ��̕ύX���@��ɁC����f�ẪV�[�����X�ȑΉ���ڕW�Ƃ��āC�S������\����Ȃ�ɘa�P�A�ȕa�����J�݂����D�����x����f�ÂɌg����Ă������ɂƂ��ẮC�ɘa�P�A�ȕa���͏Ǐ�ɘa��I�����̊Ǘ��ɑ�ϗL�v�ȕa���ł���D �@���̊ԁC�����a�@�̒��̊ɘa�P�A�ȕa���݂̍����͍����Ă����D���̌�C�u�n�悪��f�ØA�g���_�a�@�v�Ɏw�肳��C�ɘa�P�A���C����J�Â����D����ďC�́u����ɘa�P�A�K�C�h�u�b�N�v�����s���ꂽ�̂��C�ɘa�P�A�Ƃ������t�����ҁE�Ƒ���s���ɍL���Z�����Ă����̂����̎����ł���D �@�������C�ŋߋC�ɂȂ邱�Ƃ�����D�ɘa�P�A�ƃz�X�s�X�P�A�����`��Ƃ͎��͎v���Ă��炸�C�ɘa�P�A�ȕa���ł͏Ǐ�ɘa��ϋɓI�ɍs���C�ݑ�x�����O���ɒu���Ă������C�Ŏ��̏�Ƃ��Ă̏Љ�⑊�k�����܂��ɑ����̂������ł���D�܂��C�ɘa�P�A�ȕa���ɓ��@�����Ȃ�C�o���F�̏I�������߂�����ƌ�����Ă��銳�҂�Ƒ������邱�Ƃ������ł���D �@�ϋɓI���Â��s���a������ݑ�×{�ւ̈ڍs���x������C��Ɋɘa����Ƃ���a�����ɘa�P�A�ȕa���ƍl���Ă���D���̋�ɂ͂����u�ɂ����ł͂Ȃ��C�S���I�E�Љ�I�u�ɓ��̑S�l�I��ɂ��Ӗ����Ă��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��D���̖ڕW�B���̂��߁C�f�Ï��̈�t�Ɗ�̌�����A�g��|������C�K��Ō�t�Ƃ̘A���𖧂ɂ����肵�Ă���D����I�����ً̋}�Ή��ɂ�����S���Ă���D �@���̑S�l�I��ɂ̊ɘa�͉����ɘa�P�A�ȕa���ł����o���Ȃ����Ƃł͂Ȃ��D��ʕa���ł��S�l�I��ɂ̑Ή���������O�ƂȂ�C�ɘa�P�A�ȕa���̑��݈Ӌ`���Ȃ��Ȃ������ɏ��߂āC�킪���ɖ{���̊ɘa�P�A�����t���C�ǎ��̂���f�Â��o����ƍl���Ă���D ����j���[�X�@��1153���i����21�N9��20���j |
|||||||||||||||||||||
| �A���}�Ŋɘa�P�A�@��ˎs���a�@ | |||||||||||||||||||||
| �@��ˎs���a�@�i��ˎs���l�S���ځj���A���҂̊ɘa�P�A�Ƃ��ăA���}�̍�����g�����F������}�b�T�[�W�Ɏ��g��ł���B�@���̊O����t��e�a���ɂ̓A���}�����v���o��B�I�����W��x���_�[�Ȃǂ̍���ɂ��ӂ�A���҂���́u�a�@�Ɠ��̂ɂ����ƈ���Ă��ꂵ���v�ƍD�]���B �@�A���}�Ɏ��g�ނ̂́A��t���t�A�Ō�t���Q�O�l�ł���u�A���}�Z���s�[�ψ���v�B�S���̌����a�@�ł͏��߂Đݒu���ꂽ�Ƃ��������Ȉψ���B �@��ˎs���a�@���A���}�Z���s�[�ɒ��ڂ��n�߂��̂͂O�U�N�B���҂̃X�g���X���ɂ�a�炰�邽�߁A�ɘa�P�A�`�[���́u��֕⊮�Ö@�ψ��v�Ƃ��Ċ������n�߂��̂��͂��܂肾�����B �@���̌�A�E����ΏۂɎ葫�̃}�b�T�[�W�̕�����d�ˁA�O�W�N�P���ɂ��҂₻�̉Ƒ���ΏۂɃA���}�}�b�T�[�W���B���̔N�̂V���ɂ́A�e�a����O���v�P�T�J���ŃA���}�����v���g�����F�������n�߂��B �@�a���Ń}�b�T�[�W���邪�҂̂Ȃ��ɂ͖����Ă��܂��l�������A���̃����b�N�X���ʂ��\��Ă���Ƃ����B���N�R���ɂ́A��ˎs��t��̈�t���Q�����āu��˃A���}�Z���s�[���c��v��ݗ�����\�肾�B���c�ǐM�ψ����́u����͑S�a���Ŋɘa�P�A�̈�Ƃ��ă}�b�T�[�W�����Ă��������v�Ƙb���Ă���B �A�T�q�E�R���@2009�N09��21�� |
|||||||||||||||||||||
| �s�����J�u���F����Ƃ̌����������@�z�X�s�X��E�R�肳�u�� | |||||||||||||||||||||
| �@�������a�u�������v�̗]�T�� �@����Ƃ̌����������ɂ��čl����s�����J�u�������̂قǁA�b��s�������̂����������s���z�[���ŊJ���ꂽ�B�����s�́u�P�A�^�E�������N���j�b�N�v�@���ŁA�ɘa�P�A�̐��ƂƂ��Ēm����R��͘Y�@�����u�t�Ƃ��ď�����A�u����ƌ��������`�n��Ŏx����v���e�[�}�ɍu�������B �@�R�莁�͂X�P�N����A�z�X�s�X��Ƃ��Ă��҂Ƃ�������Ă���B��������������A��\��́u�ڂ��̃z�X�s�X�P�Q�O�O���v�u�z�X�s�X�錾�v�ȂǁB �@�u���ŎR�莁�́A�������a�ƌ����錻���w�i�ɁA�u�i����ɂȂ��Ă��j�w���Ŏ����c�c�x�ł͂Ȃ��w����ς莄�����x�ƃ����N�b�V�����u���ĂƂ炦�������ǂ��v�ƁA�]�T�̂���S�\���̏d�v��������B���̏�Łu��l�̈�t�����łȂ��A�Z�J���h�I�s�j�I���A�T�[�h�I�s�j�I�����A�[���������Ö@��I�����ׂ����v�Ƙb�����B �@�܂��A�z�X�s�X��̌o������w���ƂƂ��āA��ɏǏ�ɘa�̑�����C���t�H�[���h�E�R���Z���g�i�����Ɠ��Ӂj�̑����������Ӗ������������l�ւ̃P�A--�Ȃǂ������A���ɃC���t�H�[���h�E�R���Z���g�ɂ��āu���҂̐l���͊��Ԍ���B���̒��Łw�l�Ԃ炵���x�w�����炵���x������ɂ́A�����ōl���A���f���邱�Ƃ��d�v�B��t�����m�ŃE�\�����A���̐l�̐l���Ȃ����ƂɂȂ�v�Ƙb�����B m3.com�@2009�N9��30�� |
|||||||||||||||||||||
| ���y���͊ɘa�P�A�̏�Q�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��@�x���M�[�C���y���@�{�s��̒������� | |||||||||||||||||||||
| �@�u�����b�Z�����R��w�I����������O���[�v�i�u�����b�Z���j��Lieve Van
den Block���m��́C2002�N�ɂ�����u���y���@�v�����肳�ꂽ�x���M�[�ł́C���@�̎{�s����ɘa�P�A���銳�҂͌������Ă��Ȃ����Ƃ������ꂽ��BMJ�i2009;
339: b2772�j�ɔ��\�����B ���y�������@�� �@����܂ł̌�������C�I�����ɂ͐����̒Z�k����w�I���f��������邱�Ƃ��������Ƃ����炩�ɂ���Ă���B�܂�C�v���I�Ȗ�܂̎g�p��C�p���I�Ȓ��Ö�̓��^�C�܂��͏Ǐ�ɘa�̂��߂̖�ܓ��^�̋����ȂǁC���ʓI�Ɏ����𑁂߂鏈�u���Ȃ���Ă���Ƃ������Ƃł���B �@�x���M�[�ł́C2002�N�Ɉ��y�������@�����ꂽ���C�ɘa�P�A�����{�����Ñ̐��̐������i��ł���BVan den Block���m��́C2005�`06�N�̃x���M�[�ɂ�����ˑR�����������S��2,000���͂����B����̌����́C�I�����̈ӎv����Ǝ��ۂɎ��I������Â̊W�����߂Ė��炩�ɂ�����K�͌����ł���B �@���҂̂���32����85�Έȏ�ŁC�j����͂قڔ������C������43���͂���ł������B���҂ł͑��̎����̊��҂ɔ�ׂāC���̛Ƃ��ĐH���␅���𓊗^�����ɒ��Ö�̏����ʂ𑝂₵�Ē��Ï�Ԃ��ێ�����邱�Ƃ������X���ɂ������B �@���̒��O��3�����ԂɃX�s���`���A���P�A�������҂́C�قƂ�ǂ܂��͑S���Ă��Ȃ����҂ɔ���y���܂��͈�t�ɂ�鎀�̛�I������X���ɂ��邱�Ƃ������ꂽ�B�����̒m���́C���y���Ɗɘa�P�A�͌����Ė���������̂ł͂Ȃ��C�݂��ɑ���̊W�ɂ��邱�Ƃ������Ă���B �@����ɏW�w�I�Ȋɘa�P�A�����l�قǁC�Ǐ�ɘa��ړI�Ƃ���������C�H���␅����ێ悹���ɒ��Ö�̏����ʂ𑝂₵�Ē��Ï�Ԃ�ۂ��ƂŎ����𑁂߂Ă����B�܂��C�����������҂ł͑����Ď����𑁂߂�I������Â����f����X����������ȂǁC�W�w�I�Ȋɘa�P�A�Ɛ������Ԃ�Z�k�����w�I�Ȉӎv����ɂ͊֘A���F�߂�ꂽ�B�����ɁC�I������Âɂ�����ӎv����Ɗɘa�P�A�͑������邱�ƂȂ��������邱�Ƃ������ꂽ�B �@�����������̒m���́C�x���M�[�ł͊ɘa�P�A���邱�Ƃ̂ł��Ȃ����҂��C���Ҏ��g�܂��͑�O�҂̈ӎv�ɂ���āC�ߓx�Ɉ��y���܂��͈�t�ɂ�鎀�̛�I�����Ă���Ƃ������O�����S�ɕ��@������̂ł͂Ȃ��B �@�����m�́u�����ł����l�̂��Ƃ������邩�ۂ��ɂ��Ă͂���Ɍ������K�v�����C���ʂ́C���ꂼ��̖@�I��ɘa�P�A�V�X�e���C�Տ�����ɂ�������y���݂̍����l�����Ȃǂɍ��E�����ƍl������v�Ǝw�E�������ŁC�u��t�ɂ�鎀�̛��e�F����Ă���ăI���S���B�ł́C��t�ɂ�鎀�̛�I�������l�̑������z�X�s�X�P�A���Ă����B�܂��C�@�����ɂ��z�X�s�X�ւ̏Љ�]�@���������C��t�ɑ���ɘa�P�A�g���[�j���O�����y�����ƕ���Ă���v�Əq�ׂĂ���B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N10��1�� |
|||||||||||||||||||||
| ��t�E�Ō�t�͊ɘa�P�A�`�[����L�p�ƕ]�� | |||||||||||||||||||||
| �@�É��ϐ�����a�@�ɘa��ÉȂ̐{�ꏺ�F�Ȓ��́C�ɘa�P�A�`�[���iPCT�j�̈˗��҂ł����t�E�Ō�t���Ƃ���PCT��L�p�ƕ]�����Ă����A���P�[�g���ʂƁCPCT�̉�����u�ɂ�q�C�C�s���C�s���̌y���Ɋ�^�������Ƃ��������銳�Ғ����̌��ʂ��C���É��y�C��2009�ŕ����B ����ɂ���u�ɁC�q�C�C�s���C�s�����y�� �@�{��Ȓ��ɂ��ƁC���@��PCT�̓R���T���e�[�V�����݂̂ɓO���鉢�Č^�ł͂Ȃ��C�قږ������҂ɉ�C���_�I��Y���܂߂����҂̋�ɂ�]�����āC�厡���a���Ō�t�Ɩ��_�����L���C�厡��Ή�������ȍۂɂ́C�厡��ɘA����C���ڏ����⌟�����s���Ƃ����X�^�C�������H���Ă���Ƃ����B �@���Ȓ��͍���C���@�̂��È�79�l�C���Õa���Ō�t154�l�ɑ��āCPCT�̗L�p���Ɖ�����@�C�J���t�@�����X�݂̍���Ɋւ���A���P�[�g�����{�����B������͈�t62���C�Ō�t94���������B �@���̌��ʁCPCT���u�ƂĂ��L�p�v�C�u�L�p�v�Ƃ͈̉�t��96���C�Ō�t��97���ƈ�Î҂̑命�����߂Ă����ق��C������@���u�����݂̂ɂ��ׂ��v�Ƃ����͈�t�E�Ō�t�Ƃ��Ɍ���ꂸ�C�u���݂̂܂܂ł悢�v�i��t78���C�Ō�t77���j�C�u���݂������ڐf�Â𑝂₷�ׂ��v�i�� 15���C16���j�ƂȂ��Ă����B �@����C�J���t�@�����X�ɂ��Ă͎厡��C�a���Ō�t�CPCT���ꓰ�ɉ�čs�����Ƃ͓���������t�̔����́u����̂܂܂ł悢�v�Ƃ������C�Ō�t�̉ߔ���������J�Â�������߂Ă����B �@���Ȓ��͂���ɁCPCT�Ɉ˗��̂���������78�l�̃J���e�ɋL�ڂ��ꂽ�e��ɏǏ�Ɋւ��āCPCT����O��̕ω���Support Team Assessment Schedule���{��ŁiSTAS-J�j���w�W�ɔ�PCT��t���������ɒ��������B �@���̌��ʁC�e�Ǐ�ɂ��ċ�ɂ̂��������҂̂����CSTAS3�ȏ�i���т��ы����Ǐ����܂��͎����I�ɑς����Ȃ��������Ǐ�j�̊����́CPCT����O����u�ɂ�53.1������0���C�q�C��76.9������7.7���C�s����66.7������11.1���C�s����33.3������6.3���Ɖ��P������ꂽ���C�y�Ǘ�ł͉��P���F�߂�ꂽ�ċz����C����ςɂ��Ă͒����x�ȏ�̏Ǘ�ł͉��P�����C���ӊ���PCT��������Ă����������B �@�ȏ���܂Ƃ߂āC���Ȓ��́u�厡���a���Ō�t�Ɩ������L����悤��PCT��������Î҂̑唼���L�p�ƕ]�������B���҂ɂƂ��Ă͉���ɂ��C�u�ɁC�q�C�C�s���C�s���̌y�������҂ł��邪�C�����x�ȏ�̌ċz����C����ς���ь��ӊ��̉��P�͍�������v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N10��1�� |
|||||||||||||||||||||
| �]�ށu�Ŋ��v�����߂ā@������ �S���� | |||||||||||||||||||||
| �@�������ɂ��čl���錧���Ƃ̍��k��i����t���Áj���S���A�앗�����̌���t��قŊJ���ꂽ�B�u�������鐶�v�u�������鎀�v���l�����ɖ�R�T�O�l���W�܂�A�ꕔ�̒��O�����ɓ��肫��Ȃ��قNJS�̍������������킹���B �@���{������������Ȃ�̌��͌\��Y��\�A�����a�@�@�\����a�@�̐ΐ쐴�i�@���A�ߔe��ꎖ�����̉i�g�����ٌ�m�A�����܂�[�N���j�b�N�̎R�����i�@�����������A�ɘa�P�A�A�@���A�ݑ��Â̂��ꂼ��̗��ꂩ��I�����̖��ɂ��ču�������B���̐l�炵���Ŋ����}���邽�߂ɍs���A��ÁA�������g�����g�ނׂ����ƂȂǂ�b�����B �@��Î҂̗\�z��傫������Q���҂ɋ}����A�ʎ��Ƀ��j�^�[��݂��ĊJ�Â����B���^�����ł͏I������ÁA�ݑ���Ɋւ��鎿�₪������ꂽ�B�u�ɘa�P�A���������A�K������������ɓ���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��v�Ƃ�������ɑ��A���͑�\�́u�K���������̕K�v�͂Ȃ��B�厡��ɂ����Ƃ����Ƃ��͉�����f��Ƃ������Ƃ�\���o�Ă��������v�Ɠ������B �@�u�ݑ�ł݂̂Ƃ��i�߂�ɂ͉����K�v�Ȃ̂��v�Ƃ�������ɎR���@���́u���͍ݑ�𐄐i���邪�A��������L���V�l�z�[���ł݂͂Ƃ�̌o�����Ȃ��ȂǁA����͎���鏀���͂ł��Ă��Ȃ��B�v�挩�������K�v�v�Ƙb�����B�܂��u�Ƒ��̑��͍ݑ��]�܂Ȃ����Ƃ������v�Ƃ����w�E�ɑ��Ắu���Ȃ����͂ł��x���ł���d�g�݂�����悭�Ȃ�B�Ⴆ�Γ��������a����w�f�C�z�X�s�X�x�����邪�A�o�c�I�Ɍ������L����Ȃ��v�ȂǏI����������ʼn߂������߂̌����I�Ȏx�����K�v�Ƃ����B �@��ꂩ��́u����̏�Ől�Ԃ̖��ɂ��ċ�����K�v������v�u��Â̑��Ƙb�������@��K�v�v�Ȃǂ̗v�]���������B �����V��@2009�N10��5�� |
|||||||||||||||||||||
| �ݑ�z�X�s�X�A�I�ׂ��c�� | |||||||||||||||||||||
| ������ʈ�t�A��� �@���͂��̏t�A�W�P�̑c����S�������B����̔������x�ꉄ����������҂ł��Ȃ���Ԃ������B�c���͎c��C�͂�U��i���Ď���ōŊ����}����ݑ�z�X�s�X����t�Ɋ肢�A�]�݂����Ȃ����B�����A�����ł͑c���̂悤�Ɏ���ł̎���]��ł��A���Ȃ����Ȃ��l�����|�I�ɑ����B�l���̍Ŋ����ǂ��}���邩�̑I�����ł��Ȃ�����͕ς����Ȃ��̂��낤���B �@���Ƒ������� �@�c���̗L�x�́i����Ƃ݂�����j���X���i���������j����Ɛf�f���ꂽ�̂͂R���Q�V���B���Ɋ̑�����p�ɂ��]�ڂ��Ă����B�ݑ�z�X�s�X�͉Ƒ����]�B���Â̓����q�l�𓊗^���A�������Ȃǂ̊ɘa�P�A�̂݁B���ւ��a���ɑ��ς�肵�A��������Ƒ��ɂ���삪�n�܂����B �@���{�ݑ�z�X�s�X����ɂ��ƁA����ŖS���Ȃ邪�҂͑S�̂̂킸���U���B�O�S�N�̌����J���ȏI������ÂɊւ��钲������������ɂ��ƁA���҂��I�����̗×{�ꏊ�Ƃ��Ď������]���Ă��銄���́A�u�Ŋ��܂Łv�Ɓu�K�v������Έ�Ë@�ւ�z�X�s�X�֓��@�v�Ƃ̉����킹��ƂU�O���ɂȂ�B���̂ǂ��ł��Ȃ��A�킪�ƂōŊ����}�������Ƃ����̂́A���������Ȗ]�݂Ȃ̂��B �@���́A�E��̒��Ԃ����ɖ����������A�v�V���ԁA�啪�����c�s�̕���̎��ƂɋA�Ȃ����B�c���͐����ɉ�������Ƃ͕ʐl�̂悤�ɂ₹�Ă������A�������ꂢ�ɐ����A�͂ɂ��悤�ȏΊ�Ŏ����}���Ă��ꂽ�B�c���͎���B��̒j�̑��Ƃ������Ƃŏ����Ȏ�������������Ă��ꂽ���A���e��������������獂�Z���w�ȍ~���炭�͊��������ꂸ�ɂ����B���̎��Ԃ����߂������v���������A�؍ݒ��͎l�Z�������ɂ����B �@���f�����Ă���Ă�����t���A�]�������m�����ʂɂ���������Ƃ��ł����B�_���Ȋ���ŕ����Ă����c���͘b���I���Ƃɂ�����Ƃقُ݁A�u�Ŋ��܂ł�낵�����肢���܂��v�ƈ�t�̎��������B���ꂩ��X����ɑc���͋A��ʐl�ƂȂ����B�݂Ƃ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A���Ɍ���͂Ȃ��B���܂�̍ۂɂ����Ă����͂ւ̋C�����������A�ł������A�����̈���������ƂȂ����X�Ɛ������c���̎p��ڂɏĂ��t���邱�Ƃ��ł����B����ȑc���ɑ��h����C�������`���A�S�\�����ł��Ă����B �@�l�̎������ꂾ�������������ꂽ�̂́A���ɂƂ��ċM�d�ȑ̌��������B�c���̎����������Ȃ������ȏ�A�Ƒ��ɂƂ��Ă��ݑ�z�X�s�X�͖�������I���������Ǝv���B �@������̐f�Õ�V �@����ł̎���j��ł���w�i�ɂ́A���f�Ŋɘa�P�A�����Ă�����t�̏��Ȃ�������B�s��ɔ�Z�݊��ꂽ�ƂɈ��������l�������ł��낤�n���œ��ɏ��Ȃ��A���{�ݑ�z�X�s�X����̃f�[�^�x�[�X�Ō�������ƁA�����Ζ����镟�䌧�암�ł��o�^���ꂽ�a�@�͖��������B����������t�������Ȃ��w�i�ɂ��āA�O�S�N�U���̊J�@����U�O�O�l�̂��҂����f���Ă��̂W��������ł݂Ƃ����痢�y�C���N���j�b�N�i���{�L���s�j�̏��i�����q�������i�S�T�j�́u�����m�炸�ɐf�Õ�V�����߂��Ă��邱�Ƃ�����v�Ǝw�E����B �@�펞��Q�O�l�̖������҂������N���j�b�N�ł́A�}�ςȂǂ̘A���������킸�ɓ���A������ł���t�Q�l�ƊŌ�t�T�l������X�^�b�t���Q�S���ԑΉ����Ă���B���R�o��͖c��݁A�O���f�Âʼn��f�̐Ԏ������Ă���B �@�f�Õ�V�������������ł́A�l�����x�̒Ⴂ�n���ł̕��y�ɂ͂Ȃ���Ȃ��B�K���c���̏Z��ł����啪�������ɂ͂��������a�@������A�Ŋ����݂Ƃ��Ă��ꂽ�{��G�l��t�́u�j�[�Y�����ݎ�邽�߁A�ݑ�Ƃ����I�������m���ɒm�点��d�g�݂��K�v���v�Ǝw�E����B�痢�y�C���N���j�b�N�̍ݑ�z�X�s�X�𗘗p���ĕv���݂Ƃ������{���c�s�̏����i�T�U�j���ݑ�Ƃ����I�����ɏo�����܂Ŏ��Ԃ�v�����o������A�u���k��������Ώ��̓����鑋�����~�����v�Ƒi����B �@�O�P�N����w�肪�n�܂�������f�ØA�g���_�a�@�ł́A���̒��ړI�̈�Ɍf���Ă���B�������A���N���j�b�N�ōݑ�z�X�s�X�𗘗p�������҂́A�l�I�ɂȂ���̂����҂���̏Љ�⎩�͂ŏ���T���o�����l���قƂ�ǂ��Ƃ����A����ł͊ɘa�P�A�̏���Ƃ��Ă͏\���ɋ@�\���Ă���Ƃ͌����Ȃ��B �@���u�ɘa�v�Ɉӎ��� �@��t�̈ӎ����v���K�v���B���w�Ö@��O�Ȏ�p�Ȃǂ́u�����v��Â�S����t�ɂ́A�ɘa�P�A�����ÂƐϋɓI�ɂƂ炦������͂܂����Ȃ��B���i�������́u���킾���ŁA���҂̐l���S�̂����Ă��Ȃ���t�������B�Ŋ����������ċt�Z�^�̈�Ìv��𗧂Ă邱�Ƃ��K�v���v�Ƒi����B �@�����肪�s�����Ƃ���Ɋɘa�P�A�ւ̈ڍs�����߂Ă��A���҂��s�M�����������˂Ȃ��B���i�������́u�ɘa�P�A�Ǝ������Â�g�ݍ��킹�A��d�����X�Ɉڍs������`�����z�v�Ƙb���B �@����ŁA�ݑ�z�X�s�X�̖��͌l�̎����ςƐ藣�����Ƃ��ł��Ȃ��B�鑤���Ƒ����܂ߍl����K�v������B�c���͌h�i�i��������j�ȕ����k���������߂��A���Ɏ��ɑ���N�w�������Ă����B�c���̎���ʂ��āA�u�����ɒ[�Ɋ������邱�Ƃ͐ϋɓI�Ȑ��ɂȂ���Ȃ��v�Ƃ̎v�������������B �����V���@2009�N10��14�� |
|||||||||||||||||||||
| �u�q�ǂ��z�X�s�X���{�ɂ��v�c�n�ݎ҂��d�v���i�����s�ŃZ�~�i�[ | |||||||||||||||||||||
| �@�d���a�C��������q�ǂ��ƁA�Ō�𑱂���Ƒ����x����u�q�ǂ��̃z�X�s�X�v�ւ̗�����[�߂�Z�~�i�[���A���s�k��̎s��������ŊJ���ꂽ�B���{�ɂ͂܂��Ȃ��A���E�ŏ��߂ĉp���ɐݗ����������炪�A�{�݂̏d�v���O��V�O�O�l�ɑi�����B �u�[�������邱�Ǝ�`���v �@�����ł̃z�X�s�X�ݗ���ڎw����t���w�����A�ی��W�҂�ł�����s�ψ���̎�ÁB �@���s�ςɂ��ƁA�q�ǂ��̃z�X�s�X�́A�p���E�I�b�N�X�t�H�[�h�ɂP�X�W�Q�N�A�u�w�����n�E�X�v�����E�ŏ��߂Đݗ�����A���̌�A�h�C�c��J�i�_�A�I�[�X�g�����A�ȂǂɍL�������B �@�Z�~�i�[�ōu�������A�n�ݎ҂̃V�X�^�[�E�t�����V�X�E�h�~�j�J����ɂ��ƁA���n�E�X�ɂ͉��y���≷���v�[���A�Ԃ����ŋ����ł���قǍL���Ē����L���A�V��Ȃǂ�����A�N�Ԗ�R�O�O�g�̉Ƒ����P��ɐ����ԏh���B��t��Ō�t�炪�`�[����g�݁A��ɂ�a�炰��ɘa�P�A��Ƒ��E�⑰�̃T�|�[�g�ɓ�����Ƃ����B �@�t�����V�X����́A�Ƒ��͎q�ǂ��ƈꏏ�ɑ؍݂��邩�A�Ō�̔�����₷���߂ɋA��邩��I�Ԃ��Ƃ��ł���Ɛ����A�u�{�݂́A�q�ǂ��������y�������Ƃ���������o�����āA�[�������邱�Ƃ���`���ꏊ���v�Ƌ��������B �@���j�i�X�j���d�x�̔]��Q�ŁA���n�E�X�𗘗p���Ă�����{�l�������A�u�ǓƂɂȂ肪���ȐS�ɗ]�T�����܂��v�Ƙb�����B �@���̌�A�t�����V�X����⏬���Ȉ�A�z�X�s�X�Ō�t�炪���_�B���{�ł̐ݗ��Ɍ����ẮA���q�ǂ��ɗ]�������m���鐥��ɂ��ċc�_���K�v���z�X�s�X�Ƃ������t������A�z�����A��R�������遤�^�c�������W�߂�̂�����\�\�Ȃǂ̉ۑ肪���������B �@���s�ψ����̌�����E���s��������ÃZ���^�[���@���́u�z�X�s�X�ւ̗������[�܂�A�ݗ��Ɍ����đ傫�ȗ͂����܂��v�Ɗ��҂��Ă����B �ǔ��V���@2009�N10��20�� |
|||||||||||||||||||||
| �F�m�ǂ͒v���I�Ȏ����ł���Ƃ̗������K�v | |||||||||||||||||||||
| �@�����̔F�m�ǂ͐��_�ʂ�����N�����̂ƍl����l���������A���ۂɂ͍L���͈͂ɉe�����y�ڂ��v���I�Ȏ����ł��邱�Ƃ��V���������Ŏ����ꂽ�B���҂̉Ƒ���������F���������Ă���ƁA���S�̂�����s�K�v�Ȏ��Â�������ȂǁA���҂ɂ̓l�K�e�B�u�Ȍ��ʂƂȂ邱�Ƃ�����Ƃ����B �@�������҂ŕăn�[�o�[�h��w��w���i�{�X�g���j�y������Susan Mitchell���m�ɂ��ƁA�č��ł͔F�m�ǂ���v�Ȏ��S������1�ƂȂ��Ă��邪�A���҂��ǂ̂悤�ȍŊ����}���邩�͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��Ƃ����B�u�Ƒ������炩���ߒm���������Ă���A���҂ɋ�ɂ̏��Ȃ���Ñ[�u�������邱�Ƃ��ł���v�Ɠ����͎w�E���Ă���B�č��ł͌���500���l���F�m�ǂɜ늳���Ă��邪�A40�N��ɂ͂��̐���3�{�ɂȂ�Ɨ\�z����Ă���B �@��w���uNew England Journal of Medicine�v10��15�����Ɍf�ڂ��ꂽ����̌����ł́A�F�m�NJ��҂̏I�����ɂ��Ă̗�����[�߁A�P�A�����コ����ׂ��A22���̃i�[�V���O�z�[���i�����×{�{�݁j��18�J���ɂ킽�錤�������{�B�ΏۂƂ���323�l�̊��҂́A�Ƒ���F���ł��Ȃ��ق��A6��ȏ�b�����Ƃ��ł����A���ւ�����A�S�ʓI�ɉ��Ɉˑ����Ă��閖���̔F�m�NJ��҂ł������B���Ԓ��ɑΏێ҂�55�������S�B�����ƂȂ��������ǂ͔x�����ł������A�����Łi�x���ȊO�̌����ɂ��j���M�A�ېH�Ɋւ���Q���������B�{�ݓ����҂̑���������i46���j�A�u�Ɂi39���j�Ȃǂ̏Ǐ�ɋꂵ��ł����B �@40�����銳�҂����S�O��3�J���Ԃɏ��Ȃ��Ƃ�1��̑傫�Ȉ�Ñ[�u�i���@�A�~�}�̗��p�A�Ö��h�{�A�o�ljh�{�Ȃǁj���Ă����B�������A�����̔F�m�ǂ����Ɏ��鎾���ł���A�����ǂ��N���肤�邱�Ƃ��Ƒ����������Ă����ꍇ�́A���S�O3�J���ԂɊ��҂����S�̑傫����Ñ[�u����䗦��27���ł������̂ɑ��A�Ƒ��̗������s�����Ă����ꍇ��73���ł������B �@Mitchell���́A�Ƒ��Ɖ��҂̊Ԃ̃R�~���j�P�[�V���������コ����ƂƂ��ɁA�F�m�NJ��҂ɂ����i����j���҂Ɠ����悤�Ɏ��̍����ɘa�P�A����уz�X�s�X�𗘗p�ł���悤�ɂ���K�v������Ƃ��Ă���B�ăC���f�B�A�i��w��w���i�C���f�B�A�i�|���X�j������Greg Sachs���m�͓����̘_���ŁA�u�����×{�{�݂ł��u�Ɏ��Â��\���łȂ��A�s�K�v�Ȏ��Â��郊�X�N�������v�Ǝw�E�B�i�s�����F�m�NJ��҂͑��̎������Ȃ��Ă��z�X�s�X�P�A���鎑�i������Ƃ��Ă���B�܂��A�u�Ƒ��͐f�f��̑����i�K�ŏI�����P�A�ɂ��Ęb�������A���߂ɂǂ����邩�����߂Ă����̂����z�I�v�Ɠ����͏q�ׂĂ���B �����������N�iNIKKEI NET�j�@2009�N10��22�� |
|||||||||||||||||||||
| �Ñ�M���V���⒆���ɋN���@�Q�O���I�㔼�A�ĂōČ��m�� | |||||||||||||||||||||
| �@���y��ʂ��������҂̐��_�I�A���̓I��ɂ��ɘa���鎎�݂͒����̏C���@�ŁA����ɌÂ��͌Ñ�M���V���̐_�a�ł����H����Ă����Ƃ����B �@�P�X�V�O�N��O���A������Č����u���y�T�i�g���W�[�i�����w�j�v�Ƃ��Ċm�������̂��A�ăR�����h�B�̎{�݂ŘV�l���ɓ������Ă����e���[�X�E�V�����[�_�[�V�[�J�[�������B �@�ޏ����R�����h�B�Ŕ������������y�T�i�g���W�X�g�̈琬�v���W�F�N�g�͋��_�������^�i�B�A�I���S���B�ƈڂ��Ȃ��甭�W�B"�����q"�����͑S�Ċe�n��C�O�ł���������悤�ɂȂ����B �@���y�T�i�g���W�[�ɂ́u���y�A��w�A���_���̒��a�v���K�{�Ƃ���A��Â̗��ꂩ��́A�������҂ɑ���ɘa�P�A�̈�ł�����B �@�I���S�����N�Ȋw��w�̈�t���o�[�g�E���`���[�h�\���́A�|�[�g�����h�ߍx�̕a�@�Ŋɘa�P�A�̌����Ǝ��H�Ɏ��g��ł���Ԃɉ��y�T�i�g���W�[�ɏ��荇�����B �@�u�n�[�v�̉������҂Ɉ��炬��^����̂́A�]�g���ώ@���Ă���Ε�����B�Ƒ��̋�Y��a�炰����ʂ�����v�B�������҂̈�Ғ��Ԃ�����×{�ɉ��y�T�i�g���W�[��������A�ȂƂƂ��Ɉ��炬���Ƃ����B �@�K���o�������郊�`���[�h�\���́u�����I�ȈႢ�ɍl������K�v�͂��邪�A���{�ł����y�T�i�g���W�[�͎������Ǝv���v�ƌ�����B m3.com�@2009�N10��28�� |
|||||||||||||||||||||
| �z�X�s�X�̐������Ă��Ȃ��������ґ����@��Ò҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����s������� | |||||||||||||||||||||
| �@�n�[�o�[�h��w��Haiden A. Huskamp���m��́C�i�s���҂̑������f�f��4�`7�����̊ԂɃz�X�s�X�ɂ��Ĉ�t�ȂǂƘb�����������Ă��Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ�����Archives of Internal Medicine�i2009; 169: 954-962�j�ɔ��\�����B �b���������̂͂킸�������� �@�z�X�s�X���牶�b�銳�҂͏��Ȃ��Ȃ����C���̈���Ńz�X�s�X�Ɋւ���b��͊��҂̖����܂ŏo�Ȃ�������C�S���b�������Ȃ����Ƃ���������B�������C�i�s���҂ł͑����Ƀz�X�s�X����������̂͗L�v�ł��邱�Ƃ������ƍl������B �@�Ⴆ�C�z�X�s�X�ł͐N�P���̒Ⴂ���Â��s���邽�߁C���҂͂��悢QOL�邱�Ƃ��ł���B �@��t�����҂ɑ��ăz�X�s�X���Љ�邱�Ƃ͏d�v�ł���B������Huskamp���m�炪�č����̕����̒n��ŃX�e�[�WIV�̔x����1,517���ΏۂƂ��������ł́C�]�ڂ���Ɛf�f���ꂽ���҂̑����́C�f�f���4�`7�����ԂɈ�Ò҂ƃz�X�s�X�ɂ��Ęb�������Ă��Ȃ����Ƃ��킩�����B �@�����m��́u��t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����𑝂₷���ƂŁC�z�X�s�X�ւ̊��҂̔F���s����\��Ɋւ������ɑΉ��ł���v�ƍl���Ă���B�܂��C�X�e�[�WIV�̔x���҂̐������Ԓ����l�͐f�f�����4�`8�����ł��邽�߁C�z�X�s�X�ɂ��Ă̘b��������f�f��4�`7�����ȓ��ɍs�����Ƃ��K�Ƃ��Ă���B �@�f�f�̖�4�`7������Ɋ��҂܂��͊��҂̑㗝�l�ɃC���^�r���[���s�����Ƃ���C�C���^�r���[��2�����ȓ��Ɏ��S�������҂Ńz�X�s�X�ɂ��Ď厡��Ƙb���������s��ꂽ�̂͂킸��53���ŁC�������Ԃ���蒷�����҂ł͂��̊����͂���ɒႩ�����B �@�����ҁC�p�[�g�i�[�Ɠ����̊��ҁC���w�Ö@���Ă��銳�ҁC�n���ҁC�}�C�m���e�B�l��C�p�ꂪ�b���Ȃ����҂Ȃǂł́C��t�ƃz�X�s�X�Ɋւ���b�������������Ȃ��X��������ꂽ�B �\��̍l�������e�� �@�����̗]����2�N�����ƍl���Ă��銳�҂ł́C�]������蒷���ƍl���Ă��銳�҂Ɣ�ׁC�z�X�s�X�ɂ��Ęb���������Ƃ����Ȃ葽�����Ƃ��킩�����B���̌��ʂ���C��t�͊��҂Ɨ\��ɂ��ẴR�~���j�P�[�V������L���ɍs���Ă��Ȃ����Ƃ�C�\��̐������\���ɗ��������Ă��Ȃ����߁C���҂����g�̗\����y�ώ����Ă���\�����������ꂽ�B �@�u�ɂ܂��͌ċz�s�S���ł��d�x�̊��҂ƁC�d�Ǔx���Ⴂ���҂ł́C�z�X�s�X�ɂ��Ă̘b�������ɍ��ق͌����Ȃ������B �@�]���̉�������u�Ɋɘa����]�������҂�4����3���́C�z�X�s�X�ɂ��Ď厡��Ƙb�����������Ƃ���x���Ȃ������B�b�������̌��@�͊��҂Ɍ���������킯�ł͂Ȃ��悤�ŁC���҂�4����1���͑h���s�v�iDNR�j����]���Ă����ɂ�������炸�C��t�Ƙb�������@������Ȃ������B �@������ÂɊւ���b�������́C����I�ɂȂ�₷�����Ԃ�������B���̂����w�͂�����Ȃ��ȂǁC��t�ɂƂ��ėe�Ղł͂Ȃ��B�܂��C�b��������x�点����C�S���b�������ɉ����Ȃ����҂�����B �@�b������ꂽ�Ƃ��Ă��C�z�X�s�X�̂��ׂĂ̑��ʂ��\���ɐ����ł���킯�ł͂Ȃ��B��t��DNR�ɂ��Ă̘b���������������҂̂����C�z�X�s�X�ɂ��Ă��b�����������҂́C�킸��3����1�ł������B���̂��Ƃ���C���҂ƈ�t���b�������̃`�����X���킵�Ă��邱�Ƃ�����������B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N10��29�� |
|||||||||||||||||||||
| �d�q�V�X�e���ł�����u�Ɏ��Â����P�@�K�C�h���C���ɉ������ӎv������x�� | |||||||||||||||||||||
| �@�O���C���@���킸�C���҂ɑ����u�Ɏ��Â͕s�K�ł��邱�Ƃ������B���[�v���q�g�E�J�[����w�a�@�i�n�C�f���x���N�j��VI���ȗՏ��w�E��܉u�w��Walter E. Haefeli������́C�o���L���ȗՏ���t�̎w���Ƒg�ݍ��킹���v�V�I�ȓd�q�V�X�e�����u�Ɋɘa�ɗL�p�ł��邱�Ƃ������Ŏ����ꂽ��Pain�i2009; �I�����C���Łj�ɔ��\�����B���̓d�q�c�[��AiDPainCare�́C�u�Ɏ��ÂɊւ��鍑�ۓI�K�C�h���C�������E���Ă��炸�C���҂ɂ�鎩�ȕ]���ł��u�ɂ��y�������Ƃ��Ă���B ������AiDKlinik�̕⏕�I�K�C�h �@�����̈�t�����̓d�q�����K�C�hAiDKlinik�̓h�C�c�A�M���猤���Ȃ��珕�����C���Ȃ���ܕ��̋��͂�2003�N�ɊJ�������V�X�e���ŁC�h�C�c�����Ŕ̔�����Ă���6��4,000��ޒ��̐��܂��Љ�Ă���C��p�ʁC����p�C�댯�Ȗԑ��ݍ�p�C�����̏d���̉�����x������c�[���ł���BAiDKlinik���g�p����ƁC�������ꂽ���Ó��e����������܂��͈�ËL�^�ɒ��ړ]�����邱�Ƃ��ł���B���̃V�X�e���͌��݃h�C�c��10�����̕a�@�ɓ�������Ă���C�l�J�ƈ�����p�ł���B �@����Haefeli������́CAiDKlinik��⏕����R���T���e�B���O���W���[���Ƃ��āC�d�q�u�Ɋɘa�K�C�hAiDPainCare���J�������B �@�������́u����̌����́C��܂̏������瓊�^�Ɏ���܂ł̖��Â̈��S���Ɏ���u���Ă���v�Əq�ׂĂ���B�����ł́C����w��Hubert J. Bardenheuer�����̊ē��ŗՏ���w�������j�b�g�iThilo Bertsche�ψ����j�����ۓI�Ɋm�����ꂽ���ÃK�C�h���C����d�q�`���ɉ��H���������B���s���J��Ԃ�����C���̃V�X�e���͓��@�̕��ː���ᇁE���ː����ÉȂŎ��Â��Ă��邪�҂��u�Ɏ��ÂɎg�p����C���ʂ��グ�Ă���B �⏕���ɖ�̏������s�\�� �@�\���I��������C�@�O�ŊJ�n���ꂽ������u�Ɏ��Âł́C���̓I�Ƀ����q�l�x�[�X�̒��ɖߏ��ɓ��^����Ă���C�R�����R���`�]���n���܂Ȃǂ̕⏕���ɖ���\���ɏ�������Ă��Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ����BBertsche�ψ����́u�Ȃ��ł��⏕���ɖ�́C���҂��u�Ɏ��Â����P�ł��邱�Ƃ������ɂ�������炸�C���܂菈������Ă��Ȃ��v�Ǝw�E���Ă���B �@�V���ɊJ�����ꂽAiDPainCare�c�[�����g�p����ƁC�⏕���ɖ�ƃI�s�I�C�h���ɖ�ɂ���u�Ƀs�[�N��ˏo�ɂ̊ɘa���Âɂ����鏈���̗L���������P����邱�Ƃ��킩�����BAiDPainCare�͌ʂ̊��҂ɑ����u�Ɏ��Â��x������ړI�Ŏg�p����邾���łȂ��C�I�s�I�C�h���Â̈�ʌ����Ɩ@�I���ɑf�����A�N�Z�X���邱�Ƃ��ł���B���̌��ʁC�����ɖ�̏����Ɋւ��鍪���̂Ȃ��s��������������Ƃ��Ă���B���҂ɓn�������v�����g�A�E�g�\�ł���B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N10��29�� |
|||||||||||||||||||||
| ���_��ᇈオ���X�L���̋��L���@�T�C�R�I���R���W�X�g�̉�����Â�����|��22����{�T�C�R�I���R���W�[�w�� | |||||||||||||||||||||
| �@��22����{�T�C�R�I���R���W�[�w���P�A�Q�̗����A�L�����̃����p���N�g�h�q�n�r�g�h�l�`�ŊJ���ꂽ�B����e�[�}�́u�����Âɂ�����S�̃P�A�̊g����v�B���҂̑����X�����������ŁA���_�I�ȃP�A��S���T�C�R�I���R���W�X�g�̖����ɂ��Ă̋c�_���s��ꂽ�B �@ �w��Q���ڂ̃V���|�W�E���u�ɘa�P�A�`�[���ɂ�����T�C�R�I���R���W�X�g�̖����v�ł́A��ᇓ��Ȉ�A�ɘa�P�A�a����Ȃǂ��A���ꂼ��̗��ꂩ��u���_��ᇈ�v�ɋ��߂�@�\�A�A�g�݂̍���Ȃǂɂ��Ă̌������q�ׂ��B ���߂��鐸�_��ᇈ�ɂ��A�h�o�C�X �@��������Z���^�[�����a�@�̒_�X���Ȃ̐X����펁�͎�ᇓ��Ȉ�̗��ꂩ��A���_��ᇈ�ɋ��߂�������ɂ��ĉ�������B����҂ƌ��������ۂɂ́A���_�I���ʂ̃T�|�[�g�̏d�v����Ɋ������ʂ������Ǝw�E�B���_��ᇈオ���R�ɉ���ł�����Â����A���_��ᇈオ���R�~���j�P�[�V�����X�L�����w�ԏd�v�������������B �@�X���������_��ᇈ�ɋ��߂�_�Ƃ��ċ������̂́A�@���_�Ȏ�f�ɑ���S���I���⊴�̌y���A�R�~���j�P�[�V�����X�L������̂��߂̐��_��ᇈ�̎��_���猩���A�h�o�C�X�B���_��ᇈ㓯�m�̘A�g��_��ᇈ�̒n��݂̐����C���҂̉Ƒ��ւ̐��_�I�T�|�[�g�\�̂S�_�B �@���_�ȓI����ɂ��ẮA�Ό����R���������҂��������ƂɐG��A��R�����������Ɏ�f�ł��鑶�݂Ƃ��ĔF�m���Ă��炤�K�v������Ƃ����B���̂P�̎��g�݂Ƃ��āA���_�Ȃ���f���邱�Ƃ̕��̃C���[�W���y�����邱�Ƃ��ӎ������u�X�����v���Љ���B�Q���҂���́u���_�Ȃ̐搶�ɂ����k�ł��邱�Ƃ��S�����Ɗ������v�u������������钆�ŁA�������m�����������邽�߂ɂ��������𗧂��Ă���v�Ȃǂ̐������A���_�Ȉ����f���₷�����Â���̈�Ƃ��ċ@�\���͂��߂Ă���Ƃ����B �@�܂��A��ᇓ��Ȉ�́A���҂ɂƂ��Ĉ����������m������Ȃ��P�[�X���������Ƃ��w�E�����B�����A�u���������ł����ɖ{�l�̉��l�ρA���f�͂�ۂ����邩�B�������ꂽ�����������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��d�v�v�Əq�ׁA���_��ᇈ�̎��_����̃A�h�o�C�X�Ȃǂ��Ȃ���A�R�~���j�P�[�V�����X�L�����K�v������Ƃ����B �@�܂��A��w�a�@�₪����a�@�ł͐��_��ᇉȓ��m�̘A�g���\�ł���Ƃ������A�ݑ�P�A�A�z�X�s�X�ւ̓]�@�Ȃǂ̒i�K�ł́u���_��ᇈ�̉���������I�Ɍp���ł��Ȃ��ꍇ������v�Ƌ��������B�]�@���ɂ͐��_��ᇈ�̈�ØA�g�����߂���ق��A���_��ᇈ�̒n��݂��������邽�߂̐��_��ᇈ�̈琬���ۑ�ɋ������B���҉Ƒ��̃P�A�̏d�v�������܂��Ă���Ƃ��A�u���҂̎��Ò������łȂ��A��������_�I�T�|�[�g���K�v�v�Əq�ׂ��B ���_��ᇈ�u���X�̃R���T���ɉ����邱�Ƃ������̑b�v �@���É��s����a�@�ɘa�P�A���̉��R�O���͐��_��ᇈ�̗��ꂩ��u�����A����̎{�݂̏��Љ�Ȃ��琸�_��ᇈ�݂̍���ɂ��ĉ�������B������{�@����ȍ~�A�u�����̕a�@�Ő��_��ᇈオ���҂̐S�̃P�A�����悤�ɂȂ��Ă��Ă���v�Ƃ̔F����\���B���߂�������Ƃ��ẮA���҂�Ƒ��̐��_�����A�S���v���Z�X�ւ̎x���Ȃǁu���܂��܂ȋ@�\�����邪�A���X�̃R���T���e�[�V�����ɒ��J�ɑΉ����邱�Ƃ����ׂĂ̊����̃x�[�X�v�Əq�ׁA��Ã`�[����A���ҁE�Ƒ��̃j�[�Y��S�[����c�����邱�Ƃ��ۑ�ɋ������B �@�܂��A���m���ł́u���_��ᇊw���C�v��W�J���A�����T�C�R�I���R���W�X�g�̋ςĂ�i�߂Ă��邱�Ƃ�����B�ɘa�P�A�`�[����A�ɘa�P�A�a�������a�@�́u���_�Ȉ�v�u�S�Ó��Ȉ�v��ΏۂƂ��Ĕ����̃��[�N�V���b�v�ŋc�_������́B���C��ł̓��[�����O���X�g���쐬����Ȃnj𗬂�[�߂��ɂȂ��Ă���A����͂��������l�b�g���[�N�������ɐ������Ă��������ۑ�ɂȂ�Ƃ����B �@�ɘa�P�A�a���̓����Ƃ��āA�@���a�A����ςȂǂ̐��_�����̕p�x�������A��Ɋɘa�̍���ǗႪ�����X�^�b�t�����͊�������P�[�X�������B���S�މ@�������⑰�P�A���ۑ�\�Ȃǂɂ����y�B���̏�Łu���҂̈��J���ŗD�悷��ȂǁA�a���ŗL�̉��l�ςɔz�����ׂ��v�Ƃ����B �ɘa�P�A�a���@���_��ᇈ�̃t�H���[������Q�{ �@��������Z���^�[���a�@�ɘa��ÉȂ̏��{���v���́A�ɘa�P�A�a����̗��ꂩ��A���_��ᇈ�Ƃ̘A�g�̌���ɂ��ĕ����B�ɘa�P�A�a���ł́A��ʕa���ɔ�ׂĐ��_��ᇈ�̃t�H���[������Q�{��18.4���ŁA����ς�傤�a�̐f�f�������A�u�Ǐ�ɘa�ɓ�a����P�[�X�v�����_��ᇈ�ɏЉ���X��������Ƃ����B �@�ɘa��È�ƁA���_��ᇈ�Ƃ̘A�g�����߂�d�g�݂Ƃ��ẮA�T�Q��̒��J���t�@�����X���^�p���Ă��邱�Ƃ������B�Ǘጟ����A����Ƃ�����������ʂ��āA�u���݂��ɘb���₷���W�����ł��Ă���v�Əq�ׂ��B�܂��A�ɘa�P�A�a�����ł̋���ɂ����_��ᇈ�Ɋ֗^���Ă��炤�K�v�������������B �u������v�̋�Ɍy���ɔz���������n�r�����@�㏞�I���n�r���̗L������ �@�É������É�����Z���^�[�̓c�K���q���͂Q���̃V���|�W�E���ŁA�u���n�r���X�^�b�t����̂��҂̐��_�S���I���ʂւ̃A�v���[�`�v���e�[�}�ɍu�������B���n�r���̖ړI�Ƃ��āA���a�⎡�ÂŐ����������̒��Łu�g�̓I�A�Љ�I�A�S���I�A�E�ƓI�ɍő���̋@�\��������ׂ��������邱�Ɓv�Ǝw�E�B�r������S�̋�ɂ̌y���ȂǁA�u�w������x�ɔz���������n�r���A�w������x�ɉe�����y�ڂ������ɃA�v���[�`���邱�Ƃ��]�܂��v�Ƃ̌������������B �@�g�̓I�r�����Ȃǂɑ���A�v���[�`�̎���Ȃǂ��Љ���B�Ⴆ�A�]��ᇂɂ��㉺���^���A���o��ჂȂǂ̋@�\��Q�ȂǁA�a���ŏI������Âł̊ɘa��ÂɃV�t�g�����߂���P�[�X�ɐG��u���̎����ɋ@�\���P�ړI�̃��n�r�����s�����Ƃ́A���ʂƂ��ē��삪�ł��Ȃ��Ȃ錻���ɒ��ʂ����Ă��܂��\��������v�Ƃ̌�����\���B�Ώ��@�Ƃ��ẮA����ꂽ�@�\���̂̉�ڎw���̂ł͂Ȃ��A�ق��̂��̂����p���Č����Ă���@�\��₤�Ƃ����g�㏞�I���n�r���e�[�V�����h�̕K�v�����������B �@�S���I���ʂɔz���������n�r�����s���ۂɂ́A���ꂼ��̊��҂́u�Љ�I�w�i�A�Љ�I�����A�d�����ȂNJ������ɔz�����A��Ɗ�����I������v���Ƃ̏d�v�����w�E�����B���҂̗v�]��ӎu�d����ق��A���a�₹��ςȂǂ̏Ǐ���P�[�X�ł́u���_�A�S���I���ʂ̐��m�Ȕ��f�v�����߂���Ƃ����B m3.com�@2009�N11��17�� |
|||||||||||||||||||||
| ��47����{�����Êw��|������{�@��C�a�@�̘A�g��\�Z�̊m�ۂ� | |||||||||||||||||||||
| �@�킪���ł�2007�N4���ɂ�����{�@���{�s����C����i�߂��Ă���B���l�s�ŊJ���ꂽ��47����{�����Êw��i�������ȑ�w�Y�w�l�Ȋw�����E���R�O�����j�̓��ʊ��V���|�W�E���u������{�@�C����v���{���v�����͂���f�Â̎��Ƌϓ_�����ǂ��܂ŒB�����Ă��邩�H���̌��ƒI�v�i�����i����R��C������w���q������Ȋw�E�]���O�Y�����jPart1�u������{�@�Ɋ�Â������Â͕ς�������H2�N�Ԃ�U��Ԃ�v�i�i���������Z���^�[�E�_�Y�������_�����j�ł́C������{�@�ɂ�苒�_�a�@��F��a�@���w�肳�ꂽ���C�����̕a�@��f�Ï��Ȃǂ̘A�g�̕K�v����\�Z�̊m�ۂȂǂ̉ۑ肪���邱�Ƃ����ꂽ�B���̈ꕔ���Љ��B �����s���_�a�@�E�F��a�@������ �@����E�����ǃZ���^�[�s����a�@�̍��X�؏�Y�@���͓����s�̂�������i�v��Ɋ�Â��������ɂ��ďq�ׁC�u���_�a�@�C�F��a�@�����͂��Ă���̍����Ɍ����������s���Ă���v�ƕ����B �ۑ葽�����C�����ڎw���A�g �@�����s����f�ØA�g���_�a�@�́C�s�ɂ����邪���Ãl�b�g���[�N�̒��S�Ƃ��āC�n�悪��f�ØA�g���_�a�@�ƘA�g���ē����s����f�ØA�g���c��̐ݒu�C�@������o�^�f�[�^���W�C�n��A�g�̐��i�C��������̋���C��Ï]���҂̎��̌���Ȃǂ��s�����Ƃɂ��C�s�ɂ����邪���Â̐��i��ڎw��������S���Ă���B������s����f�ØA�g���_�a�@�Ƃ��Ċ�������L���a�@�Ɠs����a�@�C�n�悪��f�ØA�g���_�a�@�Ƃ���12�{�݂��C����ɓs����10�{�݂��s�F�肪��f�Õa�@�Ƃ��Ďw�肳��C�����24�{�݂ɂ��2008�N6���ɂ͑�1���s����f�ØA�g���c��J�Â���C����o�^����C�n��A�g�p�X����C���k�E���C���C����C�ɘa���[�L���O�O���[�v��ݒu�C�������J�n���ꂽ�B �@����o�^����ł́C2�s����f�ØA�g���_�a�@��12�n�悪��f�ØA�g���_�a�@���C2009�N3�����獑������Z���^�[�֓o�^���J�n���C10�����s�F�肪��f�Õa�@��2010�N�����a�@�֓o�^����\��ł��邪�C�\�㒲���̕��@���ۑ�ƂȂ��Ă���B�n��A�g�p�X����ł́C5�傪��̊e�a�@�̐��ƂƓ����s��t��ƂŁC�s�S�̂œ���t�H�[���̃N���j�J���p�X�쐬��ڎw����2010�N2������{�s�J�n�\��ł��邪�C�f�Õ�V���ۑ�ƂȂ��Ă���B���k�E���ł͍�������Z���^�[�Ō��C�������k����z�u���Ă��邪�C���k�����Ɏ{�݊ԍ������邱�ƁC�����s��Ë@�ֈē��T�[�r�X�Ђ܂��̊��p�@�Ȃǂ��ۑ�ƂȂ��Ă���B���C����ł�5�N��1���l�̈�t�Ɋɘa�P�A���C����u�����邱�Ƃ�ڎw���Ă��邪�C�u�t�s�������ƂȂ��Ă���B �@���X�؉@���́u����܂ŁC�����Âɂ����đ�w�a�@���a�@���A�g���Ċ������邱�Ƃ͂Ȃ������B�ۑ�͑������C���݁C���_�a�@�C�F��a�@�͑��݂ɋ��͂��C��t��C�f�Ï��Ƃ��A�g���Ă���̍�����ڎw���w�͂��Ă���v�Ƃ܂Ƃ߂��B �������^���ҁE�Ƒ��C��ÊW�ҁC�s���́u�O�ʈ�́v�Ōv�������C���i �@��������������i�v����莞�ɑO�E�̓�����Ñ�ۂ����X�^�b�t�Ƃ��č���ɂ���������������B��ی����̑����������́C�����ł͊��ҁE�Ƒ��C��ÊW�ҁC�s���́u�O�ʈ�́v�Ōv�������C���i���Ă��邱�Ƃ��Љ���B �ӌ����ő�����f�����v�� �@��������������i�v��́C���ґ�\4�l���܂ވψ�15�l���琬�邪������i���c��ɂ��C���ҁE�Ƒ����ÊW�҂̈ӌ���������č��肳�ꂽ�B�v��̓����Ƃ��āC(1)����Ö@���㐔�Ȃǂ̐��l�ڕW���(2)����ʂ̎{���1�Ƃ��āu���ҁE�Ƒ���ւ̎x���v�̍��ڂ�ݒ�(3)�v��̐��i�ɂ������e�@�ւȂǂ̖�����(4)��������i���c��Ōv���]���\�Ƃ����B����ɁC���҂�W�҂̈ӌ����ő���������ꂽ�w�i�Ƃ��āC (1)�����ɔM�S�Ȍ��c��c���̑���(2)�ӌ��������ꂽ�v�����͌��N�������̕��j(3)�v�����̕��ӂ͌v��S���X�^�b�t�ɔC����ꂽ(4)���ҁE�Ƒ��C�W�҂̎��g�݂����т��у}�X�R�~�Ɏ��グ���C�����̒��ڂ��W�߂��\��4�_���������B �@�������ł�2009�N�x��������Ɨ\�Z1��700���~�̂����C4,400���~�����_�a�@�@�\�����ɁC340���~�����ҁE�Ƒ��ւ̎x���ɏ[�ĂĂ���B�܂��C���ԃ��x���̊����Ƃ��āu���������v���n�݂���Ă���B����́C�����̂���f�ØA�g���_�a�@�ɂ���f�Âɂ����鍂�x��Ë@������邱�Ƃ�ړI�ɁC2007�N����3�N�Ԃ�7���~��ڕW�Ɋ�ƁC�c�́C�l�����t������̂ŁC�قږڕW�z��B�����錩���݂ł���B �@���������́u�����ɂ����邪���́C���݂ł͊��ҁE�Ƒ��𒆐S�ɁC��ÊW�ҁC�s���̎O�҂����łȂ��C����ɋc��C����@�ցC��ƁC�}�X�R�~���������w���ʈ�́x�̊����ւƍL�����Ă���v�ƌ��B ��茧�ł͂����̈ӎ������� �@����ȑ�w�O�Ȋw�u���̎�э������͊�茧��������i���c��ψ��Ƃ��Ă̗��ꂩ��C������{�@�{�s��̊�茧�̂����ɂ��āu�����̈ӎ��Ɗɘa�P�A�ɑ���S�����サ�����C����̈琬���ۑ�v�Əq�ׂ��B ��������QOL�̌���ڎw�� �@��茧�̂����Â̖��_�Ƃ��Ēn��i����a�@�i���C������オ���Ȃ��C�i�s���������Ƃ���������B�����̖����������邽�߂ɁC2008�N�ɍ��肳�ꂽ��茧��������i�v��ł́C����ɂ�鎀�S�Ґ��̌����i�������̌���j�Ƃ��҂�QOL�̌����2�̑傫�Ȓ��Ƃ��Đ��荞�݁C��̓I�ɂ́C2012�N�܂łɎ��S��10���ȏ㌸�C75�Ζ����N������S��20�����C�i���������N�[��/���l20���C���f��f��50���C���ː����È�20�l/��ᇓ��Ȉ�܂��͂��ÔF���50�l�C���k�x���E���C����o�^�̐��i��ڕW�Ƃ����B �@���ۂɂ�����{�@�{�s��C����w����茧����f�ØA�g���_�a�@�Ƃ��āC8�����a�@���n�悪��f�ØA�g���_�a�@�Ƃ��Ďw�肳��C����w�Ɗe�n�拒�_�a�@�͏��ʐM�l�b�g���[�N�u����ď��n�C�E�F�C�v���\�z���āC�ɘa�P�A�e���J���t�@�����X���J�Â��C2009�N9���܂ł�2,546�l���Q���C�ɘa�P�A�̈ӎ������コ���Ă���B �@�܂��C�������̌���̂��߁C�s�����J�u���Ȃnj��f�[���̂��߂̊��������N7���܂ł�5��J�ÁB����w�ƌ��������a�@�ɂ͊��҂̈ӌ������̏�Ƃ��āu����T�����v��ݒ肵�C����w�̂���T�����ɂ�6�����Ԃ�1,000�l�ȏオ�K��Ă���B �@����o�^��2005�N��5,391������2008�N�ɂ�7,650���ɑ������C����w�O�Ȃł̂����p��������600�������800���ɑ��������B �@�����ɂ͐�������QOL�����コ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����C�����������コ����ɂ͑��������E�����f�f�ɂ��؏����Ɛ؏��𒆐S�Ƃ����W�w�I���Â̎��̌��オ�CQOL�̌���ɂ͈�Î҂Ɗ��҂̈ӎ�����Ɗɘa�P�A�̏[�����K�v�ł���B �@��ы����́u��茧�ł͂����̈ӎ������サ�C�ɘa�P�A�ɑ���S�����܂������C�\�Z�̊m�ہC��ᇓ��Ȉ�ƕ��ː����È�̈琬���ۑ�ƂȂ��Ă���B�܂��C�����ȑO�Ɉ�Õ����H���~�߂�K�v������v�Əq�ׂ��B �l�ނ̊m�ہC�a�@�Ԃ̘A�g�\�z���K�v �@2007�N�ɒn�悪��f�ØA�g���_�a�@�Ɏw�肳�ꂽ������w�a�@��2006�N6�����炪��f�ØA�g�Z���^�[���J�݂��C����f�Ñ̐��̐�����i�߂Ă����B���@��A��Ȃ̋��R���b�����́C�n��ɂ�����A�g���_�a�@�Ƃ��Ă̎��g�݂ɂ��ďq�ׁC�u�l�ނ̊m�ہE�琬�E�h���E���C�̎��{�C�A�g�a�@�E��@�E�f�Ï��Ƃ̘A�g�̍\�z�E�������K�v���v�Ǝw�E�����B �l�ޕs�����[�� �@������w�a�@����f�ØA�g�Z���^�[�ɂ����邪��f�Ñ̐��̐����ւ̎��g�݂Ƃ��ẮC����f�Ê�敔��ł́C��1���J���t�@�����X���J���C�W�w�I���Â��K�v�ȏǗ�ɂ��ē��_���s���C���w�Ö@����ł́C���w�Ö@���W�����̐R���E�o�^�E�Ǘ��ƁC���w�Ö@�Ō�F��Ō�t�ɂ��O�����w�Ö@�̏[����}���Ă���B����f�ØA�g����ł́C����f�ØA�g�N���e�B�J���p�X�̏[����ڎw���C5�傪��юq�{�C�����C�O���B�C�H���̂���̘A�g�p�X�����_�a�@���ʂŊ����C�g�p���J�n���C����f�ØA�g�Z�~�i�[���e�n���t��Ƌ��Â��C�A�g���������Ă���B �@�����E���C����ł́C����v���t�F�b�V���i���{���v���O�����Ƃ̘A�g�ɂ��C�������Ï]���҂̈琬�ɓw�߂Ă���B����o�^����ł́C�@������o�^��C�̂���o�^�����҂�u���C������i�߂Ă���B����\�h�E�f�ÍL��E���k����ł͂���S�����k�E�x���ȂǁC����ɘa�P�A����ł͊ɘa�P�A�Ɋւ��鑊�k�Ȃǂ��s���Ă���B���̂悤�ɁC���@�̂����Ñ̐��͐���������邪�C��t���͂��߂Ƃ���l�ޕs���͐[���ł���C�����Ñ̐��̂���Ȃ�[���̂��߂ɂ́C�����Ï]���҂̊m�ۂƈ琬����т���f�ØA�g�V�X�e���̍\�z�Ƌ����C�����x���̌p���Ƒ��z���K�v�ł���B �@�n��̘A�g���_�a�@�̗��ꂩ�獡��̑�Ƃ��āC�l�ނ̊m�ہE�琬�E�h���E���C�̎��{�C�A�g�a�@�E��@�E�f�Ï��Ƃ̘A�g�̍\�z�E�������K�v�ł��邪�C���̂��߂ɂ́C�A�g�a�@�E��@�E�f�Ï��̂����Ñ̐��̐����C�A�g�a�@�ւ̋������Ɣ�̎x���C�f�Õ�V�̏[�����K�v�ł���B�����Â̋ςĂɂ͒n���Â̍Đ����s���ł���C����ɂ͑�w��ǐ��x�̕������ł����ʓI�ł͂Ȃ����C�Ƌ��R�����͏q�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N11��26�� |
|||||||||||||||||||||
| �I�����ł̎��Ò��~���l����|��68����{�]�_�o�O�Ȋw�� | |||||||||||||||||||||
| �@�]�_�o�O�Ȏ����̏I������Âł͏d�ǂ̔]�����⓪���O���ȂNJ��Җ{�l�̔��f�\�͂������Ă���P�[�X�������C���Â̍����T���⒆�~�̔��f������B�_�ˑ�w�a�@�ň�Â̎��E���S�Ǘ����������߂�]�_�o�O�Ȃ̍]�����y�����́C���Ò��~�Ɋւ���ߋ��̔����K�C�h���C����U��Ԃ�C�����_�ł̂��悢���f���������C���w��ŕ����B �K�C�h���C���╡���ӌ��Ŕ��f�� �@����������������҂̎��Â𒆎~���ĉ����J���E����Ò��������C��w���y��������C�h�����_�f�]�ǂƂȂ������҂̐l�H�ċz����O���ċؒo�ɖ�𓊗^������苦���a�@�����i�㍐�R���j�ł́C��������Ƒ��̗v���ŏ��u������t���L�ߔ��������B�]���y�����́C2�̍ٔ��ɂ���āu�ϋɓI���y���͗e�F���ꂸ�C�����őς����Ɍy���̂��߂̎��Ò��~�̗p�����������ꂽ�v�ƕ��͂������C�u�Ƒ��̑���ɂ��Ă͋��e���f��������Ă���v�Əq�ׂ��B �@����1996�`2009�N�ɐV�����ꂽ13���̈��y���Ɋւ��鎖����������B���̌��ʁC1��͋ؒo�ɖ�̓��^�ʂ����Ȃ��������ߎ��S�Ƃ̈��ʊW�͂Ȃ��Ƃ��ꂽ�B�c��͐ϋɓI���y���ł͂Ȃ����Â̒��~�̎���ŁC�u���ׂĂɋ��ʂ���̂́C���ޑ�������Ă��N�i�܂łɎ���������͍��̂Ƃ���Ȃ��_�ł���B�ː��s���a�@�����݂͎̂��Ò��~�̌���v���Z�X�ɖ�肪����C�L�^���s���������v�ƐU��Ԃ����B �@���N7���Ɏ{�s������������ڐA�@�ł́C����̂��߂̒��~���Â��v���ƂȂ�C���Җ{�l�����ʂňڐA���ۂ������Ă��Ȃ��ꍇ�C�Ƒ��̏����ő����E�o�ł���悤�ɂȂ�B�����J���Ȃɂ�钆�~����v���Z�X�̃K�C�h���C���ł́C�`�[���ɂ��ӎv����Ȃǂ��K�v�Ƃ��C���҂��ӎv�s���ȏꍇ�͉Ƒ��Ƒ��k���Đ��肵�������ōőP�̈�Â��s�����ƂƋL���Ă���B�������C���Ò��~���\���ǂ����ɂ��Ă̏I�����̗v���⒆�~���@�ɂ͐G����Ă��Ȃ��B �@���{��t�����{�w�p��c�C���{�W�����È�w��Ȃǂ̃K�C�h���C���ł́C������f�̕\���������܂��Ȃ��̂����Ȃ��Ȃ��Ƃ����B�������C���{�~�}��w��ɂ��Ắu�w�Ƒ������{�l�̈ӎv���]��u�x���C�������Â𒆎~����x�ƌ���I������������e���Ă���v�Ǝw�E�B�u���Ò��~�͉Ƒ��̑���Ȃǂōٔ����̔��f��������邪�C���J�Ȃ�e�w��̃K�C�h���C���Ŕ��f�����m�ɂȂ����C���ɋ}���������ł͓��{�~�}��w��̃K�C�h���C�����Q�l�ɉ@���ł̔��f��m�ɒ�߂������Ń`�[����ϗ��ψ���ȂǂŔ��f���ׂ��v�Ƃ܂Ƃ߂��B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N11��26�� |
| ������F���������L�����y�[���@��Q�T����{��������w��E�����V���| �@���P�O��̎��A�Y�ݐ[���@�ǂ����������A�x���邩 |
|---|
| �@��Q�T����{��������w��Q�O�O�X�N�P�P���Q�V�`�Q�X���A��t���Y���s�̓����x�C�z�e�����}�ŊJ���ꂽ�B��������⌌�t�����̊��҂��K���ɁA���C��
�Ȃ��Ăق����Ƃ����肢�����߂��u�N�̏Ί�@�݂�Ȃ̖��v���e�[�}�ɁA���{�������t�w�����{��������Ō�w��Ɠ����J�Â��ꂽ�B���ł͂V�������鏬����
���A���ǂ⎡����̎����ȂǑ����̖�肪�c����Ă���B����ŁA�������]�߂Ȃ��q�ǂ�������̂��������B���Җ{�ʂ̈�Â̂������A�x���Ɍ�������
�t��Ō�t�A�\�[�V�������[�J�[�̔����Ȃǂ��Љ��B �@�w����Ԓ��A���Ҏx���c�́u����̎q��������v�Ɠ��{��������Ō�w��J�����A�����V���|�W�E���u�P�O�㊳�҂̎����߂�����v�B������ӎv���肪 �\�ȂP�O�㊳�҂̃P�A�ɂ��āA��t��Ō�t�A�`���C���h�E���C�t�E�X�y�V�����X�g�i�b�k�r�j�Ȃǂ��܂��܂ȗ��ꂩ��A�ӌ����o���ꂽ�B �@���ꐫ�ƕ������K�v�|�|��t�E������a���� �@�P�O��̊��҂́A��l��f�Ă���l�ɂ͗������ɂ���������������������Ă��鐢��B�������m�����Ă������W�r��̎����ŁA�ƂĂ��s����ȏɒu����� ����B���̕s����Ȏ����ɁA���Ǝ��𗝉����悤�Ƃ������Ƃ́A����ɕs���肳��������ނƂ������Ƃ܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�h�ꓮ���ނ����������~�߂āA�u���v���v�Ǝx����ꐫ�ƁA�����Ɍ��������悤�����������K�v���Ǝv���B���̊T�O�̔��B�́A�P�O����Ƃق� ���l�Ɠ������炢�ɂȂ�Ƃ����邪�A�q�ǂ��ɂ���ĕ�������B�q�ǂ����ǂꂮ�炢�����l���Ă��邩���X�Ɍ��ɂ߂ĉ�b���A�ނ炪���߂Ă������`�� �Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�M���W���y��ƂȂ�A���Ǝ��Ƃ����s����ő傫�Ȗ���ނ�͎����̒��ɉ��Ƃ�������āA�����}���Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�� �Ă���B �@�������̓x�b�h�T�C�h�Ɂ|�|�Ō�t�E�c���b������ �@�q�ǂ��́A�������g�Œɂ݂��ɂ�i���ɂ����Ƃ��낪����B���Ɏv�t���͐S�g���ɐ��l�ֈڍs���l�ԊW���`�����Ă��������ł���A�����g����������� ���Ă���B �@�G���h�I�u���C�t�̂Ȃ��ŁA�Ō�t�Ƃ��Ăǂ��x���Ă������ƍl�����Ƃ��A���̎q�ƌ����������Ɓ����ɂ��邱�Ɓ��Ō�t�Ƃ��Ď����̎����Ă���͂��ő�� �o�����Ɓ�������͂��x���邱�Ɓ���]�����������邱�Ɓ����d���邱�Ɓ|�|�Ȃǂ��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B��������Î҂́A���҂Ȃǂɉ��������邩���� �炸�s���ɂȂ������A�x�b�h�T�C�h�ɍs���Â炢�Ƃ������Ƃ��o������B�Ō�̐��E�Ƃ��Ď��������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɩ��������́u�K�������̓x�b�h �T�C�h�ɂ���v�ƐM���A���ƌ��������鎩���ł��肽���Ǝv���Ă���B �@�������̎q�ǂ��̎��ւ̑Ή��|�|�b�k�r�E���c�T�q���� �@�a���Ŏq�ǂ����S���Ȃ������A�N��ɂ�����炸�c���ꂽ�q�ǂ����e�����܂��܂Ȕ����������B���[���Ȃǂ̕��y�ɂ��A���h�͕a�������ł͂Ȃ��O����K�� �w���ɂ��L����B���������Ƒ��̔������A��Î҂��ǂ��T�|�[�g����̂��l����K�v������B����ŁA�q�ǂ���S�������e�̍l�����ɔz�����邱�Ƃ�����B �@�����̎q�ǂ��̎��ɁA�c���ꂽ�q�ǂ������͂��܂��܂ȑr�������������B�A���o�����������肷�邱�ƂŁA�C���������A�S�̒��ɖS���Ȃ����q�ǂ����� �z�u���邱�Ƃ̎肪����ɂ��Ȃ�B����m�����ɂ���v�t���̎q�ǂ��ւ̃O���[�t�P�A�i�ߒQ�ւ̎x���j�́A�F�l�̎���`����^�C�~���O�̔z����A�`������� �S���A�Љ�I�w�i���l���������E��ɂ�鐸�_�I�ȃT�|�[�g���K�v���B �@���Z�J���h�I�s�j�I���̑��k�����|�|�\�[�V�������[�J�[�E������q���� �@��N�x�̑��k�����́A���ז�P���W�O�O�O���ŁA�����͕�e����̑��k�����A�ŋ߂ł͖{�l����̑��k�������Ă���B���Ò�����{�l�̑��k����P�[�X�� ���邪�A����͂P�O��̊��҂����S�ɂȂ��Ă���B �@�������Ƃ�����Ȃ��Ă����i�K�ɂȂ�ƁA�Z�J���h�I�s�j�I���̑��k�������B�u�����������Ƃ�����Ȃ����v�Ƃ����̂��ǂ��`���邩�Ƃ����������A��� �]���҂ɗ������Ă��炢�����Ǝv���Ƒ��������B �@�݂�Ȃ����݂��̂��Ƃ��v������Ċ撣�肷���邩�炱���A���Ԃ����ݍ���Ȃ��Ƃ������Ƃ��P�O��̊��҂̏ꍇ�ɂ͑����Ǝv���B�\�[�V�������[�J�[�́A�Z ���e�̎x�������A�Ƒ����ǂ����҂��x���Ă��������ꏏ�ɍl���闧��ɂ���B��������҉Ƒ��ƈꏏ�ɁA�G���h�I�u���C�t�̋ǖʂ��l���Ă��������Ǝv���B �@���q�ǂ��̎������ꂸ�|�|���҉Ƒ��E�����m�q���� �@���͏��w�T�N�Ŕ����a�a���A�U�N���̓��a�̊ԂɂT��̍Ĕ����J��Ԃ����B�T��ڂ̍Ĕ��̎��́A�����ƈႤ�Ɗ����Ă����B �@��t�Ɂu����ȏ㑱����Ɩ{�l�ɂƂ��ċ�ɂł����Ȃ��v�ƌ���ꂽ���A���Â��~�߂邱�Ƃ͎��������Ă��邱�Ƃ��Ƌ��|���������B�o��͂��������肾 ���A�ڂ̑O�Ɏ����̎q�ǂ��̎�������Ƃ������Ƃ��A�ǂ����Ă�������Ȃ������B�]����鍐�������ƂŁA���̋C�͂��Ȃ��Ȃ�����Ǝv���ƕ|�������B �@��t��Ō�t�͍őP��s�����Ă��ꂽ�Ǝv�����A���̎��͂��ꂪ������Ȃ��قǐ��_�I�ɕs���肾�����B�q�ǂ��ƈꏏ�Ɏ��ƌ����������Ęb�������A�������� �����Ă�Ƒ��͂���Ǝv���B����ŁA���_�I�ɕs���ɂȂ��Ęb���E�C���Ȃ��������̂悤�Ȑe������B�Ƒ��̂��Ƃ��l���ăT�|�[�g���Ă��炢�����Ǝv���B �@���^�[�~�i�����̃P�A�u�K�C�h���C���v�������|�|���[�N�V���b�v �@�u����̎q��������v�̃��[�N�V���b�v�ł́A�u�^�[�~�i���P�A�̃K�C�h���C������낤�v���e�[�}�Ɉӌ����������ꂽ�B �@��������̎����������サ�A�q�ǂ�����������ŖS���Ȃ邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ��Ă������A�^�[�~�i�����̃P�A�ւ̈ӎ����Ê��̐����͏\���Ƃ͂����Ȃ��B�� ���œ���ł́A���N�̔��s��ڎw���Č�����i�߂Ă����B �@����́A�K�C�h���C���̂����u�q�ǂ��̐S�Ɋ��Y���āv�Ɓu�^�[�~�i�����̉߂������v�̍��ڂɂ��ĕ��͂�B�u���m���O��ɂȂ��Ă���̂ł́v�u�� �a�P�A�́A�v��������Βʂ���̂ł͂Ȃ����v�u�w�`���Ă�����x�Ƃ������t�͂ǂ����v�|�|�ȂǂƎq�ǂ���S�������Ƒ����t�A�Ō�t�炪���܂��܂Ȉӌ��� �q�ׂ��B �@�K�C�h���C���쐬�ψ���̍גJ�������H�����ەa�@���@���́u�K�C�h���C�����ł��邱�ƂŁA�����Ă����q�ǂ������̐e�ł��A����Ȃ������q�ǂ������̂��� ���l���Ă��炦��v�Ƙb�����B �@���v���͂����H�@����̎q�ǂ��G��W �@��D���ȉƑ����̉��̃T�b�J�[�{�[���A�������Ȃ��Ă����N�W���|�|�B���P�K�ł͏�������̎q�ǂ������̊G��W���J���ꂽ�B�S������W�߂�ꂽ�S�V �_���W������A�͋����G�Ɍ�����l�������₦�Ȃ������B �@�|�X�^�[�ɂ��Ȃ����u���ł��������傾��v�́A�����s��c��̈�c�T���N���A�Q�U�J���̎��ɕ`������i���B�T���N�̏����Ȏ�`�ŁA�����̂��Ƃɂ��� ���́u���ꂳ��v��\���A�u�q�ǂ������v���w�ŕ\�������B�T���N�͂R�V�J���ŖS���Ȃ����B���e�́A��i�Ɂu���̂ɂ�Ƃ肳��ƂЂ悱�����̂悤 �ɁA���ł��ꏏ����v�ƃ��b�Z�[�W���Ă���B �@�{�����e�B�A�ŊG��W�ɎQ�������A��̐�������i�R�V�j�́A�u�T�����c���Ă����Ă��ꂽ���̂��A���������`�œ`���Ă�������v�Ƙb���Ă����B �����V���@2009�N12��12�� |
| ���̂̎n�܂�E�Ȃ�ł��Ȃɂ�F�z�X�s�X�P�A�^��� �@���V�R�N�A�������҂Ɏ��g�݁@�S�l�I�`�[���A�v���[�`�|�|����L���X�g���a�@ |
| �@�����̓I�E���_�I�ɂ݊ɘa �@�������҂Ȃǎ����̋߂��a�l�̋�ɂ�a�炰�Ȃ���A���_�I������ʂ��Đ���S���ł���悤�Ō삷��z�X�s�X�P�A�B�z�X�s�X�a���ݗ��͂P�X�W�P�N�̐���O�����a�@�i�l���s�j�����{��P�������A�z�X�s�X�P�A�̎��g�݂͂V�R�N�A����L���X�g���a�@�i���s�������j�Ŏn�܂����B���S�ƂȂ����̂��A���a�@�̔��ؓN�v�E���_�z�X�s�X���i����w�@��w���j���B �@�����z�X�s�X�P�A�Əo�������̂́A�V�Q�N�B�ăZ���g���C�X�̃��V���g����w�a�@���_�Ȃɗ��w���Ă��鎞�������B�R�N�Ԃ̗��w�̍ŏI�N�A��t��Ō�t�̂ق��ɁA�@���Ƃ�\�[�V�������[�J�[�A�{�����e�B�A�܂ŎQ�����Ė������҂̊Ō�ɂ�����`�[���A�v���[�`�����߂Ēm�����B������́u�ڂ��炤�낱��������v���B�������܂����v�ƐU��Ԃ�B �@�A����A����L���X�g���a�@�̐��_�_�o�Ȉ㒷�ɏA�C�B���V�R�N�̉āA�O�Ȉォ��A���銳�҂ɂ��đ��k�����B�U�Q�̖����̒�������̒j���ŁA����̒ɂ݂Ǝ��ւ̋��|������A����ԂɂȂ��Ă����B���G�ȉƒ뎖��������A�厡����Ή��ɋꗶ���Ă����B �@�����Œ�Ă����̂��`�[���A�v���[�`�������B�厡��Ɣ�����A����Ƀ\�[�V�������[�J�[�ƊŌ�t�A�q�t���T�Ɉ�x�b�������Ȃ���A�ɂ݂̊ɘa�⎀�ɑ��鋰�|����菜���J�E���Z�����O���n�߂��B�₪�Ēj���̒ɂ݂����_��Ԃ��A�Ƒ��W�����P���Ă������B�艞���������A���N�u�n�b�c�o�v�Ɩ��t�����@������������B�uOrganized�@Care�@Of�@Dying�@Patient�i���ɂ䂭�l�X�̂ւ̌n���I�Ȕz���j�̗��ł��B�a���͎����Ȃ�����ǁA�䂪�����̃z�X�s�X�v���O�����ł����v �@�����A�ۑ�͎c�����B�����A���҂̎��͈�w�̔s�k�Ƃ����l�������x�z�I�������B�u�ł��A�����̊��҂ɂ͗A�����畉�S�ɂȂ�ꍇ������B���Â����Ȃ��P�A�̊T�O�����Ă����̂́A���͂ɒ�R�����������ł��ˁv �@�a���̊�����肾�����B�l���̍Ō���߂����ɂ́A�u�L���Ă����������āA������肵���ꏊ�v�����z�B�����A�啔���̕a���ł͎�����������B �@�����ŁA�p���̃z�X�s�X�a����ڕW�ɁA�a�@���Ƀz�X�s�X�a�������݂��銈�����n�߂��B�W�Q�N����R�N�����ĂQ���~�̊�t�����W�߂�v�悾�������A�e�n�Ɏ^���҂����܂�A�P�N�X�J���ŖڕW�z��B���B�W�S�N�ɐV�a�@�̂V�K�Ɍ��P�P���S�l�����R���̂Q�R���ƁA�L�b�`����r�[��������z�X�s�X�a�������������B �@���݁A���{�z�X�s�X�ɘa�P�A����o�^�̎{�݂͂P�X�T�J���ɑ������B�������A������́u�S���S�҂̂����A�z�X�s�X���֗^���ĖS���Ȃ�l�͔N�T�A�U�����x�B�P�����炢���z�X�s�X�Ŏ����}���邭�炢�ɂȂ�ɂ́A�܂��܂��{�݂͕K�v�v�Ƙb���B �@����ɂ́A����Ŏ����}����l�̂��߁A�ƒ�ւ̖K��Ō�������Ƒ��₷�K�v������B�u����܂ł́w�݂Ƃ�̂��߂̕a���x���������A����́w�ݑ�×{���x�����鋒�_�x�Ƃ������ʂɂ��ڂ������Ă����K�v������v�Ɣ�����͎w�E����B �����V���@2009�N12��16�� |
| �ċz��O���ň�t�s�N�i�@�x�R�n���u�E�l�F�荢��v�@�V���Ҏ��S�̎ː��s���a�@ |
| �@�x�R���̎ː��s���a�@�Ől�H�ċz����O���ꂽ�������҂V�l�����S�������ɗ��݁A�E�l�e�^�ŏ��ޑ������ꂽ���O�ȕ����̈ɓ���V�@��t�i�T�S�j�ɂ��āA�x�R�n���͂Q�P���A�ċz����O�����E�l�̎��s�s�ׂƔF�肷��͍̂���ȂǂƂ��āA���^�s�\���ŕs�N�i�����ɂ����B �@�n���́u�ċz��̑������珜���܂ł���A�̍s�ׂƂƂ炦��ƁA���O���͂����܂ʼn����[�u�̒��~�ɂ����Ȃ��v�Ɣ��f������Łu���O�������҂̎��S�Ɍ��ѕt�����Ƃ͕K�������������A�E�ӂ��F�߂��Ȃ������v�Ɛ��������B �@��蔭�o���_�@�ɁA�����J���Ȃ͉������Âɂ������w�j����������A�ŏI�I�Ȕ��f�͈�Ì���ɔC����Ă���B����̌���ŁA�@�������܂ߏI������Â̋c�_������[�܂肻�����B �@�S���Ȃ����̂͂T�O�`�X�O��̒j���V�l�B���̂����P�l�̌ċz����O�����Ƃ��āA���e�^�ŕʂ̈�t�i�S�X�j�����ޑ������ꂽ���A�n���͂��̈�t�����^�s�\���Ƃ����B �@�ɓ���t�͂Q�P���[�A�L�҉���u���O���͎u����s�ׁB���҂̂��߂Ɉ�ԗǂ��Ȃ�A�܂������I��������v�Ƙb�����B �@�x�R���x�͍�N�A�ɓ���t������ޑ����������A���҂̉Ƒ��ɏ�������͂Ȃ��A�������Â�]�܂Ȃ��ƈ�t�����O�m�F�����P�[�X������u�d�������͋��߂Ȃ��v�Ƃ���ӌ�����t���Ă����B �@���l�Ɋ��҂̌ċz�킪�O���ꂽ�k�C�����H�y�a�@�A�a�̎R�������a�@�I�k���@�ł��A���ꂼ���t���E�l�e�^�ŏ��ޑ������ꂽ���A����������^�s�\���ŕs�N�i�����ƂȂ����B �@�����̏I������Îw�j �@�����J���Ȃ��ː��s���a�@�̖����A���Ƃ�ŋc�_���Q�O�O�V�N�T���ɍ��肵���B�i�P�j��t��Ō�t�Ȃǂ̃`�[�������҂ɏ\���ȏ������Ď��Âɂ��Ęb�������A�{�l�ӎv����{�ɍ��ӓ��e�����i�Q�j�{�l�ӎv���m�F�ł��Ȃ��ꍇ�͉Ƒ��ȂNjߐe�҂̈ӎv�d-�Ȃǂ����B���̓I��ɂ̊ɘa�P�A�[�����ŏd�v�Ƃ�������Łu�ϋɓI���y���v�͑ΏۊO�Ƃ����B���{�~�}��w��́u�������Â̒��~�v��I�����Ƃ��ĔF�߂�w�j������B�e��Ë@�ւ��Ǝ��̎w�j�Â�������Ă���B �@���ː��a�@�̌ċz��O�� �@�x�R���̎ː��s���a�@�łQ�O�O�O�`�O�T�N�A�l�H�ċz����O���ꂽ�T�O�`�X�O��̒j���V�l�̊��҂����S�B�������������Ԃ������B������i�߂��a�@�����O�U�N�R���Ɍ��\�����B�x�R���x�͂O�W�N�V���A�E�l�e�^�œ����̊O�ȕ����ɓ���V�@��t�����ޑ������u�d�������͋��߂Ȃ��v�Ƃ���ӌ�����t�����B�ʂ̈�t���P�l�̌ċz��O�����ɓ���t�Ƌ��d�����Ƃ��ď��ޑ������ꂽ�B m3.com�@2009�N12��22�� |
| �����J���ȂŁC��5��I������Â̂�����Ɋւ��鍧�k�� |
| �@2009�N12��24���C�����J���ȂŁC��5��I������Â̂�����Ɋւ��鍧�k��i����=��q��w��w�@�@�w�����ȋ����E����j���J�Â���C�S���{�a�@�����C�����̖ؑ������Ɛ�䉝�f�N���j�b�N�@���̐쓇�F��Y�������ꂼ�ꔭ�\���s�����B�܂��C�����ǂ́C��N�i2008�N�j10��27���ȗ��C4��ɂ킽�鍧�k��̓��e���܂Ƃ߂��u�I������ÂɊւ��钲�������k������q�i�āj�v��B�I������Â̖@�����ɂ��ẮC�u�K�v�v���邢�́u�@�ɗ���ׂ��ł͂Ȃ��v�ƁC�قȂ�ӌ������L���ꂽ�B �ؑ������Ɛ쓇�F��Y���̔��\���e���ΏƓI �@���\�ɐ旧���đ����M������J�������������������u���C���������Â��K�v�ł���B�������肵����苦���a�@�����̍ō��ق̏㍐���p�́C���������ɋ��L�ł����������ƂȂ��Ă���v�Ǝw�E�B�u�C���t�H�[���h�R���Z���g����C�C���t�H�[���h�`���C�X�C����ɃC���t�H�[���h�f�B�V�W�����̎���ƂȂ��Ă���C���Ȍ��茠�͑��d����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��C�I������Â��߂���c�_���L���s���邱�Ƃ����߂��B �@�ؑ����́C���N�i2009�N�j5���ɑS���{�a�@������S�ƂȂ��Ă܂Ƃ߂��u�I������ÂɊւ���K�C�h���C���`���悢�I�������}���邽�߂Ɂ`�v�̍���ړI����e���Љ���B�K�C�h���C���ɂ́C���r���O�E�E�B���i�I�����Ɋւ��鐶�O�̈ӎv�\���j���s���m���C�Ȃ��ꍇ�́C���̈�t�C�Ō�t�ȂǂƉƑ��������Ęb�������C���Â��J�n���Ȃ��C���邢�͎��Â𒆎~���邱�Ƃ����߂邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��ׂ��ł���C���ӂɎ���Ȃ��ꍇ�C��O�҂��܂ޗϗ��ψ���ȂǂŌ��������̌��_�Ɋ�Â��đΉ�����K�v������Ɩ��L����Ă���B �@�����́u��������g����Ƃ������̂ł͂Ȃ����C�����Ɍ[�ւ��C���m����w�͂��s���Ă���B�����ΏۂɁC�K�C�h���C�����g�p���Ă��邩�Ȃǂ�q�˂�A���P�[�g���J�n�����Ƃ���ł���v�Əq�ׂ��B �@����ŁC�쓇���́u�I�����v�Ƃ������t�͍\���T�O�ł�����̂ł͂Ȃ����߁C��^�̏����⌠�����߂邱�Ƃ͊댯�Ǝw�E�B�܂��C�ɘa��Â��i�����C�I�����܂Œɂ��Ȃ��C�ꂵ���Ȃ������邱�Ƃ��\�ɂȂ����C�ɘa��Â�m���Ă����t��20�����x�Ƃ������_�ɖ�肪����Ǝw�E�����B �@�����̖��ɂ��āu�l�����̋ؓ��͌����Ă����v�ƍ��� �@�����q�i�āj�́C�i1�j�I������ÂɊւ��钲�����ʁC�i2�j�I������Â̂�����Ɋւ��鍧�k��̎�Ȉӌ��C�i3�j�܂Ƃ߁\��3���ځB�u���r���O�E�E�B���C�@�����v�Ɋւ���ӌ��Ƃ��ẮC�i1�j�{�l�̈ӎv�d���ׂ��ł���C����Ɉ�Ï]���ґ��͑Ή��ł���悤�@�������K�v�ł���C�i2�j�������߂�ׂ����ł͂Ȃ��C�܂��́C���ҁE�Ƒ����\���������邱�Ƃ��ł��C���҂��{����������������d�v�ł���C�i3�j�l�I�ȗϗ��̖��ł���̂ŁC�@�ɗ���ׂ��ł͂Ȃ��\�Ƃ��������e�����L����Ă���B �@�u�܂Ƃ߁v�̍��ŁC�u�I�����ɂ����Ăǂ̂悤�Ȉ�Â������ׂ������l�Ȉӌ�������v�ƋL���ꂽ�_�ɂ��āC�Q�l�l����u����܂ł̋c�_�Ői�����Ȃ������Ƃ������Ƃł́v�Ƃ����ӌ����o���B�������C��������́u�Ⴆ�C�C���t�H�[���h�R���Z���g�̊T�O�͓_�̖��łȂ��C�v���Z�X�̖��ł��邱�ƁC�I�����͊����Ő�Ȃ����Ƃ��킩�������ƂȂǁC�傫�Ȑi�����������Ǝv���B�@�����̋c�_�ł��C���ɂǂ��܂Ƃ߂��邩�͍���̉ۑ�ł��邪�C�l�����̋ؓ��͌����Ă����v�ƌl�I�������q�ׂ��B �@�܂��C���{��a�E���a�c�̋��c���\�̈ɓ����Ă����́u�i�I������ÂɊւ��钲�����ʂ̍��ڂŁj63�����ƒ�ɋA�肽�����C66���͉ƒ�ł͍���Ɗ����Ă���ƂȂ��Ă��邪�C���̒��g�Ɉ�����ݍ��܂Ȃ�������Ȃ��B��Â͍ݑ�̕����i��ł��邪�C���q����ɂ��C�P�g��2�l�ƒ�������C�ݑ�ŏI������Â͐��藧�̂��B����C�Ƒ����܂߂��o�ϓI�C���̓I��ɂ��l���C�I������Â��c�_���Ă����K�v������v�Ǝw�E�����B �@����̊J�Â͖��肾���C����I�ɋc�_���s���\��B ���f�B�J���g���r���[���@2009�N12��25�� |