�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
| �@�z�|�� > ��w�g�s�b�N�X > �o�b�N�i���o�|���j���| > 2016�N1���`2016�N12�� |
|
�N1��̌��t�����ŗ�������ɂ�鎀�S��20�����点��\�� �X�N���[�j���O�v���O�������{�ւ̓W�] |
|---|
| �@�o�㏗���ɔN1��̗�������X�N���[�j���O���������{���邱�Ƃɂ��A��������ɂ�鎀�S��20���ጸ�ł���\�������邱�Ƃ��A�p���̑�K�͌����Ŏ������ꂽ�B �@��������͂قƂ�ǂ��i�s�����i�K�Őf�f����A���҂�60����5�N�ȓ��Ɏ��S���Ă���B�������A�V���ɊJ�����ꂽ�\�t�g�E�F�A��p���Č��t�������ʂ͂��邱�Ƃɂ��A����I�Ȍ����ł���𑁊��ɔ����ł��A���S���̑啝�Ȓጸ�����҂ł���Ƃ����B �@�����𗦂����p�����h����w�iUCL�j������Ian Jacobs���́A�u������������q�{��̂悤�ɁA���ɂ�闑������X�N���[�j���O�v���O���������p�ł���悤�ɂȂ�W�]���J���ꂽ�v�Əq�ׂĂ���B���̌����́uThe Lancet�v�I�����C���ł�12��17���f�ڂ��ꂽ�B �@����̎����ł́A2001�`2005�N��50�`74�̏���20���l�ȏ��o�^���A�X�N���[�j���O���Ȃ��Q�i�S�̂�50���j�A���t�}�[�J�[�iCA125�j�ƒ����g�ɂ�錟����N1���Q�i25���j�A�����g�����̂ݎ�Q�i25���j��3�Q�ɖ���ׂɊ���t�����B���̐V���������@��1�����̌��t�����ł͂Ȃ��ACA125���o���I�ɕ��͂��Ē����ȑ�������m������́B��11�N�̒ǐՊ��Ԓ��ɁA�X�N���[�j���O���Ȃ������Q�ł�630 �l�A���t�����Q�ł�338�l�A�����g�����݂̂̌Q�ł�314�l����������Ɛf�f���ꂽ�B �@����̕��͂ł́A�X�N���[�j���O�ɂ��L�ӂȋ~�����ʂ͂Ȃ��悤�ɂ݂������A�o�^���_�Ŗ��f�f�̗��������������������O����ƁA����20���̎��S���ጸ���F�߂�ꂽ�BJacobs���ɂ��ƁA��������ɂ�鎀�S��1���h���̂�641�l�̃X�N���[�j���O�����{����K�v������Ƃ������A�č�����iACS�j��Robert Smith���́A�u�ǐՊ��Ԃ������Ȃ�قǂ��̐����͏������Ȃ�Ǝv����v�Əq�ׂĂ���B �@����̌����ł́A���t�������������ɂ����āA1���l������14�l���s�K�v�ȊO�Ȏ�p���A���̂���3�����p��Ɏ�ȍ����ǂ��������Ă����BJacobs���́A����ɒǐՂ𑱂���A�X�N���[�j���O�̃��X�N�E�x�l�t�B�b�g����p�Ό��ʂɊւ���^������������͂����Əq�ׂĂ���B �@�t���_�������M����UMC���g���q�g����Z���^�[�i�I�����_�j��Rene Verheijen���́A�u��������̃X�N���[�j���O�Ƒ����������A���z�ɂ�������炸����������ɂ��قnj��ʂ��グ�Ă��Ȃ����Âɑ���A�L���ȑ�ƂȂ�\��������B����ŁA���ׂĂ̏����œ������ʂ������邩�ǂ����A����Ɍ������d�˂�K�v������v�Ǝw�E���Ă���B m3.com 2016�N1��5�� |
| �o�q�̂��X�N�A�Е����a�ŏ㏸ ��K�͒��� |
| �@������`�q�����o�q�̈��������ɂȂ����ꍇ�A��������̔��a���X�N�������Ȃ�Ƃ��钲�����ʂ�5���A���\���ꂽ�B�����́A20���l��Ώۂɍs��ꂽ�B �@�����A�č���t��G���iJournal of the American Medical Association�AJAMA�j�ɔ��\���ꂽ�����_���ɂ��ƁA�o�q�̈���̔��a�́A�K�������A�����������������≽�炩�̂���ɂȂ邱�Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��Ƃ����B �@���ہA�ꗑ���o�����̈��������Ɛf�f���ꂽ�ꍇ�A��������̂��X�N��14���قǏ㏸����݂̂������B�ꗑ���o�����͓���̗��זE���琬������o�q�ŁA2�l�Ƃ��S��������`�����������Ă���B �@2�̗��זE���琬�����A�ʏ�̐����w�I���傤�����Ɠ����x�̈�`�I�ގ����������o�����ł́A�Е������a�����ۂ̂�������̂��X�N�̏㏸��5�����������B �@�����Ώۂ̑o�q�́A�f���}�[�N�A�t�B�������h�A�X�E�F�[�f���A�m���E�F�[�̏o�g�ŁA1943�N�`2010�N�܂ł̊��Ԃɂ킽��ǐՒ��������{���ꂽ�B�����̍��X�͂��ׂďڍׂȕی��L�^�f�[�^�x�[�X��ێ����Ă���B �@�O���[�v�S�̂̂��Ǘ��́A��3�l��1�l�̊����i32���j�������B�������Ɍv�Z����ƁA�Е�������Ɛf�f���ꂽ�ꗑ���o�����̂����Е��̂��X�N��46���ƎZ�o���ꂽ�B �@���o�����̏ꍇ�A�Е�������Ɛf�f���ꂽ�o�q�̂����Е��̂��ǃ��X�N��37���������B �@�܂��A2�l�Ƃ�����̂���Ɛf�f���ꂽ�����́A�ꗑ���o������38���A���o������26���������B �@�o�q�œ�������ɂȂ�m�������������̂́A�畆�����m�[�}�i�������F��A58���j�A�O���B����i57���j�A���m�[�}�畆����i43���j�A��������i39���j�A�t������i38���j�A������i31���j�A�q�{����i27���j�Ȃǂ������B �@�_���̋������M�҂ŁA��f���}�[�N��w�iUniversity of Southern Denmark�j�̃��R�u�E�C�F�����{���O�iJacob Hjelmborg�j���́u����̌����͋K�͂��傫���A�ǐՊ��Ԃ��������߁A�����̂���ɑ���d�v�Ȉ�`�I�e�����݂邱�Ƃ��ł���v�Əq�ׂ��B �@���E�ł͖��N��800���l������Ŏ��S���Ă���B����̐��ʂ́A���̎����̈�`�I���X�N�ɂ��āA���҂��t��������[�߂�̂Ɉꏕ�ƂȂ�\��������ƌ����`�[���͘b���Ă���B AFPBB News 2016�N1��6�� |
| ���A�a�\���R�ł��X�N���㏸ ���ړI�R�z�[�g������� |
| �@���A�a���҂����łȂ��AHbA1c�l��6.0�`6.5���ȏ�ȂǓ��A�a�̉\�����ے�ł��Ȃ��A���邢�͋����^����u���A�a�\���Q�v�ł����X�N���㏸���邱�Ƃ��A���������Z���^�[�⍑�����ۈ�Ì����Z���^�[�Ȃǂ̌����ł킩�����B�ڍׂ́uInternational
Journal of Cancer�v�I�����C���ł�12��1���f�ڂ��ꂽ�B �@����܂œ��A�a���҂ł́A���A�a�����̂Ȃ��l�ɔ�ׂĂ��ׂĂ̂���늳���X�N��1.2�{�����A�Ȃ��ł��咰������X����A�̂���A�q�{��������Ȃǂ̃��X�N��1.5�`4�{���܂邱�Ƃ�����Ă���B����A�����`�[���͑��ړI�R�z�[�g�����iJPHC Study�j�̓��A�a�����̃f�[�^��p����HbA1c�l�Ƃ��X�N�̊֘A�����������B �@1998�`2000�N�x�����2003�`2005�N�x�Ɏ��{���ꂽ���A�a�����̎Q���Ғ��AHbA1c����f�[�^������A����̒������܂łɂ���ɜ늳���Ă��Ȃ�����2��9,629�l�i�j��1��1,336�l�A����1��8,293�l�j��Ώۂ�HbA1c�l�Ƃ���늳���X�N�̊֘A�����������BHbA1c�l���i1�j5.0�������A�i2�j5.0�`5.4���A�i3�j5.5�`5.9���A�i4�j6.0�`6.4���A�i5�j6.5���ȏ�A�i6�j���m�̓��A�a��6�Q�ɕ����Ă���늳���X�N�͂����B �@�ǐՊ��Ԓ���1,955���̂��������Ă����B�N���ʁABMI�A�g�̊����x�Ȃǂ��܂��܂Ȉ��q��������͂ɂ��AHbA1c 5.0�`5.4���Q�ɔ�ׂ�5.0�������Q�i�n�U�[�h��1.27�j�A6.0�`6.4���Q�i��1.28�j�A6.5���ȏ�Q�i��1.43�j�A���m�̓��A�a�Q�i��1.23�j�ł��X�N���㏸���Ă���i5.5�`5.9���Q�̃n�U�[�h���1.01�j�A���A�a�Ƃ͐f�f����Ȃ������A�a���^����HbA1c���l�i6.5���ȏ�j�ł����X�N���㏸���邱�Ƃ��킩�����B �@�܂��AHbA1c��5.0�������ƒ�l�������Q�ł����X�N�̂킸���ȏ㏸���݂�ꂽ���A�̂���������ĉ�͂����HbA1c�l�͒����I�ɂ��X�N�㏸�Ɗ֘A���Ă����B �@�����`�[���́A���̌��ʂ��u�����I�ȍ����������ׂĂ̂��X�N�㏸�Ɗ֘A���邱�Ƃ𗠂Â�����̂��v�Ƃ��Ă���A���̋@���Ƃ��āA�������̓~�g�R���h���A��ӂȂǂ���Ď_���X�g���X�i�����邱�Ƃ�DNA�����A������ɂȂ���\�������邱�Ƃ�A����זE�̑��B�ɂ͑�ʂ̓���K�v�Ƃ��邽�߁A�����I�ȍ�������Ԃ͂���זE�̑��B�𑣐i���Ă���\�������邱�Ƃ��w�E���Ă���B m3.com 2016�N1��8�� |
|
�����ǃo���E�����e�͏����� �ǂ��Ȃ�H10�N��A20�N�� |
| �@�߂������A�Տ�����ɋN����ł��낤�ω���̈�ʂɗ\�����Ă��炤m3.com�̐V�N�A���P�[�g�u��v��w��g�b�v�ɕ����I�w�ǂ��Ȃ�H10�N��A20�N��̈�Áx�v�B�e�̈悩��̉����ɏЉ�Ă����i�͊e�w��̌��������ł͂Ȃ��A�Ҍl�̌����ƂȂ�܂��B�������A������]�����邱�Ƃ���A�������������搶�̎����͋L�ڂ��܂���j�B ���q���{�݂̏��^���������\�\���{���ː���ᇊw�� �i1�j10�N��ɑ傫�Ȕ��W�������܂��f�f�⎡�Â̋Z�p�A���@�́H PET��CT�ɂ�镪�q�W�I��A��_�f�Ȃǂ̉摜�����^�[�Q�b�g�ɂ������ː����ÁB �����Ǝ˒��̎�ᇂ̏k����X�N����̈ʒu�ω��ɍ��킹�Ď��Ìv����ɑΉ��ł���K�����ː�����(adaptive radiotherapy�FART)�̎��p���B ���q�����Î{�݂̏��^���A�ቿ�i���ɂ�邳��Ȃ���ː����Âւ̐i�o�B�{�݂̏��^�����i�߂A�z�q�����Â͌��݂�X�����Âɒu���ւ�邩������Ȃ��B �i2�j20�N����f�Â̗v�ł��邾�낤�f�f�⎡�Â̋Z�p�A���@�́H ���ː����ÁA���ɋ��x�ϒ����ː����ÁiIMRT�j����ђ�ʕ��ː�����(SRT)�͊ԈႢ�Ȃ��c�邾�낤�B Oncologic imaging�̐f�f�́A�`�Ԃ����łȂ��@�\�摜���i�����邾�낤�B �C���W�E��192�o���Ǝ˂�[�h125�g�D���Ǝ˂Ȃǂ̏��������Â������炭�c��B���ɂ͋Z�p���w��łق����B �i3�j10�N��ɂ͎{�s����@�����Ǝv����f�f�⎡�Â̋Z�p�A���@�A���邢�͊��Ґ�������ƌ����܂�鎾���́H �摜�f�f�Ɋւ��ẮA�o���E����p��������Ǒ��e�͏����Ă����B �Z�V�E���j��p�������������ÁB �x��ᇐj�����͌����Ă����\�\���{�ċz��O�Ȋw�� �i1�j10�N��ɑ傫�Ȕ��W�������܂��f�f�⎡�Â̋Z�p�A���@�́H �n�C�u���b�h��p����p�����p���i�r�Q�[�V�����̈�ʉ��A����т���N�P�̋��o����p�̐i�� ���ɑ��镪�q�W�I�Ö@ �x�ڐA�ȂǑ���ڐA�ɂ����鋑�┽���̗}���Ȃǂ̖Ö@ �i2�j20�N����f�Â̗v�ł��邾�낤�f�f�⎡�Â̋Z�p�A���@�́H �C�ǎx���ɂ�郊���p�ߐ����iEBUS�j ���o����p �x�ڐA �i3�j10�N��ɂ͎{�s����@�����Ǝv����f�f�⎡�Â̋Z�p�A���@�A���邢�͊��Ґ�������ƌ����܂�鎾���́H �c�u�����̏c�u�����p�ߐ��� �o��I�Ȕx��ᇂ̐j���� �@�{�A���P�[�g�́A���{����@�\�Ŋ�{�̈�Ɉʒu�Â����Ă���19�̈�A�Ȃ�тɌ����_�ŃT�u�X�y�V�����e�B�̈�Ɉʒu�Â����Ă���29�̈�̐����F�肷��v50�w��̑�\�Ҍl��Ώۂɍs���܂����i��������2015�N11��20���`12��25���j�B m3.com 2016�N1��12�� |
|
�A�X�s������p�A�O���B�����}���y�č��Տ���ᇊw��z �O���B����f�f��̐i�s���}�� |
| �@�č��Տ���ᇊw��iASCO�j��1��4���A����I�ȃA�X�s�����̕��p�őO���B���ɂ�鎀�S���X�N�������ł���\��������Ƃ����K�͂Ȓ����ώ@�����̌��ʂ��Љ���B�T���t�����V�X�R�ŊJ�Â��ꂽ��A���B����V���|�W�E���iASCO-GU�j2016�Ŕ��\���ꂽ�B �@�����ł́APhysicians�f Health Study�ɓo�^���ꂽ2��2071�l�̃f�[�^����́B27�N�Ԃ̒ǐՒ����őO���B���Ɛf�f���ꂽ�̂�3193�l�ŁA����403�l���v���I�ȑO���B���i�]�ڂ��邢�͑O���B�����j�������B �@�N��A�l��ABMI�A�i���Œ����������ʁA�O���B���Ɛf�f���Ă��Ȃ��j���ŏT3��ȏ����I�ɃA�X�s�����p���Ă���Q�ł́A�v���I�ȑO���B���̃��X�N��24���ቺ�����B�܂��A�O���B���Ɛf�f��ɓ���I�ɃA�X�s�����̕��p���J�n�����Q�ł��A�O���B���ɂ�鎀�S��39���ቺ�����B�������A�A�X�s�����̓���I���p�ƑO���B���S�̂̔��Ǘ��ɂ͊֘A���͔F�߂��Ȃ������B �@�����҂�Christopher Brian Allard���́A�u�v���I�O���B���̗\�h�ɃA�X�s�����𐄏�����͎̂������������A�S���njn�ւ̌��ʂ�\���̂���O���B�����҂ɂ͓���I�ȃA�X�s�������p��������������ЂƂ̗��R�ɂȂ飂Ɛ����B����Ɂu�A�X�s�����͑O���B���̐i�s��}�����Ă��邩������Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B m3.com 2016�N1��20�� |
| 2016�N�̐V�K�����ǁA�����\����č�������� |
| �@�č�������iACS�j��1��7���A2016�N�̕č��ɂ�����V�K�����ǐ��Ɗ�����\�����铝�v���Љ���BA Cancer Journal for Clinicians���Ɍf�ځB �@ACS�̕uCancer Statistics, 2016�i�����v2016�N�j�v����ъ֘A�L���uCancer Facts & Figures 2016�i���̊T�v�ƃf�[�^2016�N�j�v�ɂ��ƁA�č��ł̊����S���͒����ɒቺ�B�����S���́A2012�N�ɂ̓s�[�N������1991�N����23���ቺ���A���̊Ԃ�170���l��������Ƃꂽ���ƎZ���ꂽ�B�܂��A2016�N�̐V�K�����ǂ�168��5410���A������59��5690�l�Ɨ\������Ă���B �@�č��ł́A�x���A�咰���A�O���B���A������4��Œj�������킹�������̖����߁A���ɔx���ɂ�������4�l��1�l�ɂ̂ڂ�B2016�N�̗\���ɂ��ƁA�j���ł͑O���B���A�x���A�咰�����V���ɐf�f��������44�����߁A���̂���5�l��1�l���O���B���Ɨ\���B�����ł͓����A�x���A�咰����3��őS�Ǘ�̖����߁A�V���ɐf�f��������29�����������߂�Ɨ\������Ă���B �@2009-2012�N�̃f�[�^������ƁA�j���ł͐V�K�����ǂ����N3.1�������������A�����ł͂قډ����������B�j���ŐV�K�����ǂ������������Ƃ��āA�O���B���̌��f�ɉߏ�f�f����23-42���ƍ����ƌ�����PSA��������������Ȃ��Ȃ������Ƃ��������Ă���B����A�x���̔��ǂ́A�i���҂̌����ɔ����j���Ƃ��ɒቺ�B�咰���̐V�K���ǂ��}���Ɍ��������A���̈���Ƃ��Č��f���ɑ咰�|���[�v��\�h�I�ɐ؏��ł���咰�X�R�[�v�̕��y����^�����ƕ��͂��Ă���B �@����A2003-2012�N�ɔ��Ǘ����オ�����̂́A�����a�A����A�G�����A�������A�̊��A�X���A�t���A�b��B���������B�j���ʂŌ���ƁA�j���ł̓����m�[�}�A������������A�j�������A�Ίۊ��A����������щ��������������A�����ł������A�O�A���A�q�{�����������������B �@ACS���Gary Reedy���́A�u�������ቺ�������邱�Ƃ͊�������Ƃ����A�ˑR�A�����͎����̑��ł���A���̎���������킢�͂܂��I����Ă��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B m3.com 2016�N1��22�� |
|
40��̃}�������f�Ɍ��_�y�č�������z �}�������f�A�����N��̑�����w��]�� |
| �@�č�������iACS�j��1��11���A�������f�Ɋւ���č��\�h��w��ƕ���iUSPSTF�j�̐V�����̔��\���āA�uUSPSTF�̊�����ACS�̓������f�̐��������ɈႢ�͂��邪�A����I�ȃ}�����O���t�B���f�̉��l�Əd�v���́AACS�����c�̂��F�߂Ă���v�ƁA�������Ɏ^������p�����������B�V�����́A2015�N4�����\�̑��ĂɊ�Â��ŏI�����ŁAAnnals
of Internal Medicine���Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@ACS��2015�N10���ɍ쐬�����������f�K�C�h���C���ł́A45-54�̑S�����ɖ��N�̃}�����O���t�B���f�𐄏��B40-44�Ώ����ł����Ă���]�҂͖��N�̃}�����O���t�B���f�̑I�����\�ɂȂ�A55����͊u�N���f�ւ̐�ւ����I���\�Ƃ��Ă���B �@����AUSPSTF�̐V������2009�N�̊����Ɠ��l�ɁA�������X�N�̂Ȃ�50-74�̏����ɑ��Ă͊u�N���f�𐄏��B���f�ɂ͑��������̃����b�g���������ŁA�U�z���̃��X�N�A�ߏ�f�f�A�ߏ莡�ÂȂǂ̃f�����b�g������Ƃ��āA�u50�ΈȑO�̌��f�ɂ��ẮA���f�̃����b�g�ƃf�����b�g�����Ă�����Ōʂɔ��f���ׂ��v�ƁA40��ɂ͊u�N���f�̑I������F�߂Ă���B�܂��A��1�x�ߐe�ҁi�e�A�q�A���E�j�ɓ������҂�����40-49�̏����ɂ��ẮA50�ΈȑO�Ƀ}�����O���t�B���f���邱�ƂɃ����b�g�����邱�Ƃ����L�����B �@ACS�́u40��㔼�ł͑O�������������ǃ��X�N���������Ƃm�Ɏ��������������A��]�҂����̎������ł����f���J�n�ł��邱�Ƃ������Ă���v�ƁA�V�����Ă�]������l���������Ă���B m3.com 2016�N1��27�� |
|
�����̍���҂��s�v�ȑO���B����E�����f���Ă��� �]��10�N�����ɂ�������炸��f����l��15���� |
| �@�����̍���҂��A�s�v�Ȏ��ÂɂȂ���\���̂���O���B����E������X�N���[�j���O���Ă��邱�Ƃ��A�č��̌����Ŕ��������B�č��̈�Ð��x�ł͂��̖��ɂ��N��12���h���i��1,400���~�j���������Ă���Ƃ����B �@����̌����͕ăw�����[�t�H�[�h�E�w���X�V�X�e���i�f�g���C�g�j��Firas Abdollah����ɂ����̂ŁA�_���́uJAMA Oncology�v�I�����C���ł�1��21���f�ڂ��ꂽ�B �@�����ł́A2012�N�̍s���댯���q�T�[�x�C�����X�V�X�e���iBRFSS�j�����ɉ���65�Έȏ�̍����15���l�̃f�[�^�����W�������ʁA�Ώێ҂�51���͑O�N�ɑO���B���ٍR���iPSA�j�����܂��̓}�����O���t�B���Ă����B�����̌��f�����l�̂�����31���͗]��10�N�����ł������B �@�u�]����10�N���邱�Ɓv�̓X�N���[�j���O���s�����ǂ����̊�ł���A�����̃K�C�h���C�����]��10�N�����̐l�ɂ͑O���B����E������̃X�N���[�j���O���s��Ȃ����Ƃ𐄏����Ă���B����҂�15.7���͔��̃X�N���[�j���O���Ă������ƂɂȂ�B �@���̃X�N���[�j���O���{���́A�R�����h�B��11.6������W���[�W�A�B��20�����܂ŁA�S�Ăł�����������B�O���B����̔��X�N���[�j���O���{���������B�ł́A������ł����X�N���[�j���O���{�������������B �@Abdollah���́A�u��t�����҂��A�]�����������������őO���B����������̃X�N���[�j���O�̕K�v�������肷�ׂ����B�X�N���[�j���O�́A�������������Ȃ���X�N��ᇂ����������A�s�K�v�Ȏ��Âɂ�蕛��p��QOL�ቺ�Ȃǂ�������\��������v�Ƙb���Ă���B m3.com 2016�N2��1�� |
|
����A�R����܂��p���������k�߂�H �u�������Â��Ȃ��v���������ꍇ���H |
| �V�������@�鋞��w��w���O�Ȉ�t �@���āA�����͂��Â̘b��Ő���オ���Ă��܂��B�g�ɘ_�N�h�́u���������Ŏ����v�ƌ����Ă��܂��B�g��펯�N�h�́u�������Â����Ȃ��Ŏ��R���������҂���v�Ƃ����ӌ��ł��B�����āg�펯�N�h�́u���m��w�I���Â�D�悵�āA�����Ă��낢��Ƃ������Ƃ������Ă������v�Ƃ������ł��B �@�܂��A�ɘ_�N�������悤�Ɋ��������ł�����̂ł��傤���B�ی��K�p������ɂ��ی��a���Ƃ��Ċ܂܂�Ă�����̂͂���܂���B���Ȃ��Ƃ������J���Ȃ́A�����ɂ����ގ����钼�ڂ̌��ʂ�F�߂Ă͂��܂���B �@�܂��A�L�g���a�q����̏����w�؉��F�̍ȁx�ł��L���ȍ]�ˎ���̊����̖���ł������؉��F�́A�Ȃ������Ȃ�������ɂ��đS�g�����������������̂ł��傤�B�������������ł͎���Ȃ�����A�E�o��p�������������̂ł��B���������œ�������A�S�g�����Ȃǂ͕s�v�Ȃ͂��ł��B�܂�A�ɘ_�N�������悤�ɂ�������������Ŏ������Ƃ͖����ł��傤�B �@����ŁA�����p���邱�Ƃ͈Ӗ�������Ǝv���܂��B�R����܂̕���p���y��������A�Ɖu�́A�܂茒�N�͂��ێ����i�����肷��ɂ͑������҂ł���Ǝv���Ă��܂��B �@�������A�Ɖu�͂Ƃ������t�͒ʏ�͌��N�͂̈Ӗ��Ŏg���Ă��܂��B�������Ɖu�͂��オ��Ƃ����R�����g������������A�����オ��̂��A�����ω�����̂����m���߂Ă��������B�����̏ꍇ�A���̂������B���ɂ��ĖƉu�͂Ƃ��������͓K���Ɏg���Ă��܂��B �u�������Ȃ��v�����������Ƃ����蓾�� �@�ł́A��펯�N�̔����͂ǂ��ł��傤�B�u�������Ȃ��Ōo�߂��݂�v�Ƃ������Ƃł��ˁB����͑����̂���ł���A���͂��ꂪ���������Ƃ����蓾�܂��B�����Ŗ��ƂȂ�̂��A�����������Ƃ������Ƃł��B����́u������ᇁv�Ƃ������܂����A�����Ƃ����Ӗ��́A�]�ڂ�Z��������Ƃ������Ƃł��B�ǐ��̎�ᇂ͓]�ڂ�Z���͂��܂���B�L���ȗǐ���ᇂ͎q�{�؎�ŁA�����傫���Ȃ��Ă����͖�肪�Ȃ����Ƃ������̂ł��B�������D�P����3�L���O�����̐Ԃ����������ɓ���Ă����C�Ȃ��Ƃ�z������A�q�{�؎�̑傫�������ł͓��ʂȉe���͏��Ȃ��Ɨ����ł��܂��B �@���������鏊�Ȃ͓]�ڂƐZ���ł����A���ꂪ�������Ă��Ȃ��i�K�ł́A�����̂������ɂȂ�̂��A�܂�]�ڂ�Z�������鐳�m�ȓ����͕s���Ȃ̂ł��B�ł�����A��t�����҂��A����Ɛf�f�����ĕ��u����Ƃ����E�C�����Ă��A�������Ǝ�p�����Ċy�ɂȂ낤�Ƃ���̂ł��B ���҂̂Ȃ��ɂ͖����ÂŒ���������l�� �@�����ŁA��펯�N�̂悤�ɂ������u�����ꍇ�́A���̌�ǂ��Ȃ������Ƃ������ʂ��Љ�ŋ��L����K�v������̂ł��B����̊��҂���̂Ȃ��ɂ́A�����Âŗ\�z�O�ɒ���������������܂��B����Ȋ�ȏǗႪ�A���͊�ՓI�ɏ��Ȃ������Ȃ̂��A����Ƃ����\�ȕp�x�ŋN�����Ă��邱�ƂȂ̂������͂킩���Ă��Ȃ�����ł��B�����I�ɂ���̓]�ڂ̎������\�z�ł���قǃT�C�G���X���i������A��펯�N���咣����悤�ȗ����ʒu���L���ȑI�����̂ЂƂɂȂ�܂��B �@����ŁA�������i�s���Ď�p�����Ă��A�܂��R������Â����Ă���x�ꂾ�Ɗ������邱�Ƃ�����܂��B����ȂƂ��Ɂu���Ɏ��Â��Ȃ�����v�Ƃ������R�Ŏ�p��R������Â������čs�����Ƃ͊Ԉ���Ă��܂��B���������c���������k�߂Ă��܂�����ł��B�������Â��Ȃ����Ƃ��A���͂�����������Â��Ă���{�݂ł͏펯���Ƃ������Ƃ����蓾�܂��B�ł���A��펯�N�̈ӌ��͐������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@���ǂ́A������펯�N�̈ӌ��ɏW��܂��B��{�͐��m��w�I���ÂŌ��ɔF�߂��Ă�����̂ɗ���܂��傤�B�����āA�⊮��ÂƂ��Ċ������Â�I�����邱�Ƃɂ͑�^���ł��B�܂��A���炩�ɗL���Ȏ��Â��Ȃ��Ƃ���A�܂�����Ɗm��f�f�����Ȃ��i�K�Ȃǂł́A�����ÂƂ����I���������蓾��̂ł��B ���V�������i�ɂ��݁E�܂��̂�j 1959�N���܂� 1985�N �c��`�m��w��w������ 1985�N�` �c��`�m��w��w���O�� 1993�N�`1998�N �p���I�b�N�X�t�H�[�h��w��w�����m�ے� 1998�N�` �鋞��w��w���O�ȂɋΖ� ���L���m�������Տ���ŁA�ڐA�Ɖu�w�̃T�C�G���e�B�X�g�A�����ăZ�J���h�I�s�j�I���̃p�C�I�j�A�ŁA���_���E�J���|�E��f�B�J�����K�̌[�֎ҁA��̓g���C�A�X�����B���������B�Ȃ��A�f�@��]�҂͒鋞��w��w���t���a�@�܂��͌��v���c�@�l��������a�@�Ŏ�f���Ă��������B��w�a�@�͏Љ�K�v�ł��B Business Journal 2016�N2��2�� |
| ����͎��̐鍐�ł͂Ȃ� |
| �@�Q���S���́A�u���E����f�[�v���B���E�ł͖��N���悻�P�R�O�O���l���A����Ɛf�f����Ă���A�V�T�O���l�ȏオ�A����ɂ���Ď��S���Ă���B�K���ɍ��Ђ͊W�Ȃ��A�q��������A����҂�����Ƃ����đ�ڂɌ��Ă��炤���Ƃ��ł��Ȃ��B �@�u���E����f�[�v�́A���ۑ���A���iUICC�j�ɂ���Ď��{����Ă���B���̓�UICC�́A���̖��ɐl�X�̒��ڂ��Ђ����邽�߂ɃL�����y�[����W�J���Ă���B�܂����̓��́A����̐f�f�A���ÁA�\�h�̂��߂̐V���ȕ��@�ɂ��ĕ��L���c�_���s���A�ӌ��������邫�������ɂ��Ȃ��Ă���B �@�Q�O�P�U�N�́u���E����f�[�v�̃X���[�K���́A�u����͉�X�̎�ɕ�����v�B���X���[�K���́A��t�ƉȊw�E���͂����킹�邱�ƂŁA����̔��Ǘ��Ƃ���ɂ��e����ቺ�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���B���X�N���s��ᇕa�@�U�Q�Ԃ̃A�i�g�[���[�E�}�t�\���@���́A���̂悤�Ɍ���Ă���| �u���E�ōł����������́A�S���ǎ����ŁA�Q�ʂ����������ł��B���V�A�ł͖��N���悻�T�O���l��������ᇂ̐f�f���Ă���A���̂����Q�T���l�ȏオ�S���Ȃ��Ă��܂��B���V�A�����łȂ��A���E���ň�����ᇂ����������Ă��܂��B�ŋ߂V�N�Ԃ����ł�������ᇂ̔��Ǘ��͂P�P�p�[�Z���g�������܂����B���R�͂���������܂��B���ώ��������т����Ƃ����̈�ł��B���Ȃ킿���ώ������������قǁA����̔��Ǘ��������Ƃ������Ƃł��B���̂��ߐ��E�ł͈�����ᇂƂ̓������d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���A�w����f�[�x����߂�ꂽ�̂ł��v�B �@�������Ȋw����Â��i���𑱂��Ă���B����w�͍ŋ߁A�������Ă���肷�鍂���x�Z���T�[�̊J���v���W�F�N�g�\�����B���Z���T�[�́A����̋^�������邩���l�ł��`�F�b�N���邱�Ƃ��\�Ƃ���B�w�҂����͂܂��A�ǂ̓���������ɖ`����Ă���̂�������ł���悤�ɂ�����j���Ƃ����B �@�����ɂ���זE�����邱�Ƃ肷��u�d�q�@�v�̐����́A�C�X���G���A�h�C�c�A���V�A�ł��s���Ă���B���V�A�E�V�x���A�A�M�Nj�m���H�V�r���X�N�̊w�҂����́A���t�A���t�A�g�D�A�ċC�ȂǂŎ�ᇃ}�[�J�[�̌��o���\�Ƃ��鏬�^�ň����ȋ@����A�����㐶�Y�֓�������i�K�ɒB�����Ɣ��\�����B �@���v���ɂ��ƁA���{�ł͖��N���悻�S�O���l���A����ɂ���Ď��S���Ă���B�܂����{�ƃ��V�A�̈�t�����́A�����������̌��N�ɂ��܂蒍�ӂ��Ă��Ȃ��Ƃ��Č��O���Ă���B����Łu����v�Ƃ������t�́A����Ɛf�f���ꂽ�l�X���V���b�N�Ɋׂ��B�}�t�\���@���́A���̂悤�Ɍ���Ă���| �u�ŋ߂܂ň݂���̔��Ǘ��Ő��E�ꂾ�������{�́A���̂悤�Ȃ��Ƃ��s�����B���{�́A�E���̒���������s��Ȃ��ٗp��ɂƂ��ĕs���ƂȂ�@���̑������̂��B���̂��ߍ����{�݂̈���̂T�X�|�U�P�p�[�Z���g�������i�K�Ŕ�������Ă���A��p�͓������ōs���Ă���B���Ȃ킿�A���Â̗L�����́A�i�s�x�ɂ������Ă���Ƃ������Ƃ��B����Ől�X�ɂ͖����ɁA����ɂȂ����Ƃ������Ƃ́A����鍐���ꂽ�Ƃ������Ƃ��A�Ƃ������o������B����͑傫�Ȍ�����B�ŐV�f�[�^�ɂ��ƁA�������͂��҂̔����ȏ�����������Ă���B����ŁA�w����x�Ƃ������t�̉��ɂ́A�P�O�O�ȏ�̕a�C���B��Ă��邱�Ƃ𗝉�����K�v������B�����̕a�C�́A�l�X�Ȍ`�ŐZ�����A�l�X�ȕ��@�Ŏ��Â����B���̒��ɂ́A�X�O�p�[�Z���g�̊����Ŋ�������a�C������B������S�O�N�O�̎����܂��w�����������A�q�{����̏����̂X�O�p�[�Z���g���S���Ȃ��Ă����B�����������͍��A�q�{����̏����̂X�W�p�[�Z���g�����������Ă���B�������A�������������邾���łȂ��A���������͂��̌�A���N�Ȏq�����o�Y���Ă���B�畆������������������B�����̒i�K�̊������́A�X�O�p�[�Z���g�ȏゾ�B����́A���̐鍐�ł͂Ȃ��B�l�X�͂����m��K�v������B�����`���A��������K�v������c ���̂��߂ɂ��w����f�[�x���K�v�Ȃ̂��v�B Sputnik 2016�N2��3�� |
|
���������͑咰����̌��o�ɗL�� �����������ƑI�ׂ�悤�ɂ���Ύ�f��������ł���H |
| �@�N1��̕��������ɂ��咰����̌��o���ɂ͈�ѐ����F�߂��A2�`4�N�ڂ̃X�N���[�j���O���L���ł��邱�Ƃ��A�V���Ȍ����ŕ��ꂽ�B �@���������҂�1�l�ł���ăJ�C�U�[�E�p�[�}�l���e�i�J���t�H���j�A�B�j��Douglas Corley���ɂ��ƁA��t��̊Ԃł́A���������̗L�������N�X�ቺ����\�������O����Ă����Ƃ����B�咰�̎�ᇂ�|���[�v�́A�傫���Ȃ�Ȃ���ΕւɌ��t�������邱�Ƃ͂Ȃ����߁A����̌����ő傫�Ȏ�ᇂ����ׂĔ�������A�؏����ꂽ�ꍇ�A���N�ȍ~�̂���̌��o�����啝�ɒቺ����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă����B �@����̌����ł́A�J�C�U�[�E�p�[�}�l���e���N�ی��̉����Җ�32��5,000�l�ɑ��Ď��{���ꂽ�N1��̕���������4�N�ԒǐՁB1�N�ڂɂ́A���������ɂ��A��ɑ咰����Ɛf�f���ꂽ���҂�84.5���ɂ����o���ꂽ�B���N�̌��o���x�������̂͗\�z�ǂ���ł��������A2�`4�N�ڂɂ�73�`78���̗L�������F�߂��A�V���ɑ傫���Ȃ�������������I�Ɍ��o�ł��邱�Ƃ������ꂽ�ƁA�����O���[�v�͏q�ׂĂ���B���̒m���́uAnnals of Internal Medicine�v��1��25���f�ڂ��ꂽ�B �@�č�����iACS�j��Richard Wender���́A�u����������10�N�Ԏ�A���S��h�����ʂ�10�N��1��̑咰�����������Ɠ����x�ƍl������v�Əq�ׂĂ���B�咰�����������́A10�N��1��̎�f�łق�100���̂����|���[�v���ł���Ƃ������_�����邪�A�I������1�����Ȃ��ꍇ�A�����������ɒ�R�̂��銳�҂̓X�N���[�j���O���Ȃ��\��������B �@�����������͐N�P�I�ȏ��u�ł���A���Í܂̎g�p�⋭�͂ȉ��܂̕��p�ɂ�鏀�����K�v�����A���������͕s�������Ȃ��A����Ō��̂��̎�ł���B�咰����X�N���[�j���O�ł͕��������Ɠ����������̗������Ă��A�e���������ɓK����������I�ׂ�悤�ɂ���A��f�҂�������͂�����Corley����͎w�E���Ă���B�������A���������ŗz���ƂȂ������҂ɂ͕K�����������������{���Ȃ���ΈӖ����Ȃ���Wender���͏q�ׂĂ���B �@����̌����́A�W���I�ȕ��������ɏœ_�Ă����̂ł���A�č��H�i���i�ǁiFDA�j���V���ɏ��F�����uCologuard�v�ƌĂ�錟���ɂ��Ă͌������Ă��Ȃ��BCologuard�͐���������DNA�o�C�I�}�[�J�[�̌�����g�ݍ��킹�����̂ŁA�W���̌��������������o�����F�߂��Ă��邪�A���ʓI�Ȏ�f�p�x�ɂ��Ă͖������炩�ɂ���Ă��Ȃ��B m3.com 2016�N2��4�� |
| ����̗L����DNA�A���t1�H�ŕ����鎞�� |
| �@���i�����Ői�����邪��̑��������@�B���ł��A���ł���O�ɂ�������鋆�ɂ̑��������@���A�yDNA�����z�ł���B �@����̐�V�I���X�N�肷�邽�߂ɁA���t���̍זE��DNA������������@���B���t���̎悵�Č����@�ւɑ�������ŁA1�������x�Ō��ʂ��o��B �@��p�͌������e��N���j�b�N���ƂɈႢ�A5000�~���x����20���~�܂ŕ��L���B�č��ł͐���ɍs�Ȃ��A���D�̃A���W�F���[�i�E�W�����[���������āu����\�h�̂��߂̓��[�؏��v�������B �@���t�����ł������ł���\�\���{���̌����Z�p�ŁA���ܔ��ɑ傫�Ȓ��ڂ𗁂тĂ���̂́y�}�C�N���A���C���t�����z�ł���B �@����������Ƃ�����U�����錌�t�̍זE�Ɉ�`�I�ȕω����N����Ƃ����������ʂ����p���������@�ŁA�}�C�N��RNA�ƌĂ���`�����ׂĂ���̔��������ɂ߂�B�����w���̃x���`���[�ł���L���[�r�N�X���J�������B �@�݂���A�咰����A�X������A�_������ȂǏ�����n����ȑΏۂŁA�����O���[�v�́A��������������X��������܂߂��������������m����98���߂��ɂȂ�ƕ��Ă���B �@���łɎ��p������Ă��āA���t�̎悾���ł��ނ̂Ŕ��Ɏ�y�����A������10���~�قǂƏ��X���z�B���������ǂ����A���i�͉������Ă������낤�B �@���t�����̂Ȃ��ł��킸����H�ł����ł���Ƃ����̂��A���Ɍ��̃x���`���[��Ɓu�}�C�e�b�N�v�Ə��a��w�̃O���[�v�����g��ł���y�o�C�I�`�b�v���t�����z���B �@���t1�H���o�C�I�`�b�v�iDNA��^���p�N���A�����Ȃǂō\�����ꂽ��j�ɏ悹��ƁA3���ȓ��ɂ���̗L�������f�ł���Ƃ����B�����ł́A���a0.1mm�ȉ��̃X�e�[�W0�̂���肵���Ƃ����B�N���Ɏ��p�����\�肳��Ă���A������p�͐����~�Ƒz�肳��Ă���B �T���|�X�g2016�N2��5���� |
|
���Â��Ē���������l�͂ǂ�Ȑl�H ����73�l��ΏۂɌ��� |
| �@���Â����l�͂ǂ̂悤�Ȑl�����������₷���̂ł��傤���H���Ì�ɁA�ǂ̂悤�ȗv�f���������ɊW���Ă��邩��������܂����B �����Ẫ��n�r���Œ����� �@����Љ�錤���́A����ɂ�錒�N��Ԃ̈����Ȃǂɑ��ă��n�r�����Ă���73�l�̂��҂�ΏۂƂ��܂����B���҂̊�{�I�ȃv���t�B�[���A�މ@��̌o�߁A�������Ԃ�^���@�\��ԂȂǂ̃f�[�^���W�߂�ꓝ�v�I��͂��s���܂����B ���^���@�\�������ƒ��������� �@���̌��ʂ������܂����B �@�@�\�I�����x�]���\�ɂ����č��v�_����80�_�ȏ�̊��҂́A80�_�����̓_�����o�������҂��L�ӂɒ����������ip = 0.002�j�B �@�މ@���ł̋@�\�I�����x�]���̉^���X�R�A�ip��0.004�j�A�@�\�����x�]�������@�ip��0.001�j�A�J���m�t�X�L�[�̃p�t�H�[�}���X�X�e�[�^�X�ip��0.022�j�A���s�\�́ip��0.026�j�A�A��ip��0.009�j�A�����āA�ݑ��Â��邱�Ɓip��0.045�j�͗L�ӂɐ����Ɗ֘A���Ă����B �@���҂̂����ŁA���n�r��������ɍ������s�\�́A�^���@�\������ꂽ�l�A�܂��A�ݑ��Â���l�Ȃǂ����������Ă���Ƃ������Ƃ�����܂����B �@���̌������ʂ���A�����҂����́u���@���҂̃��n�r���ɂ��^���@�\����͂��҂̒������Ɗ֘A���Ă���B���҂ɂ����ă��n�r���ɂ�莩�������i����Ă��邱�Ƃ́A�\��ǍD�ł��錩���݂��傫�����҂̖ڈ�ƂȂ肤��v�ƌ������q�ׂ܂����B �@���n�r���ɂ�荂���^���@�\�����҂͒���������\����������������܂���B���҂����n�r�������邱�Ƃ́A�]����L�����߂ɂ��Ӗ������邱�ƂȂ̂�������܂���B medley 2016�N2��7�� |
|
�R���܂��r�t�B�Y�X�ۂɓ��� �V���o�C�I�|�鋞������A���������̊J�����J�n |
| �@�V���o�C�I����́A�鋞������w�Ƌ����ŐV�K�R����܂̋��������J�����J�n����B�r�t�B�Y�X�ۂ�A����i�Ƃ����A�S�j�X�g���q���������ɂ���Ƃ����A����܂łɂȂ���p�@�������B�J����������w����A�J���̐i���ɉ����S���E�ɂ�����J���E�����E���Ɖ��Ɋւ���Ɛ�I���C�Z���X���擾���錠���������B �@���������J������̂́A��ᇉ��q�̈��ł���s�s�q�P�̎�e�̂̈�s�q�`�h�k�|�P�Ɍ������镪�q���������Ƃ����܁B����e�̂͂���זE�₪�זE�ɔ������Ă���A�����W�I�ɓ����q����������ƁA����̃A�|�g�[�V�X��U������B �@�ʏ�A�s�q�`�h�k�͎�e�̂Ɍ���������A��e�̂��R�ʉ����Ă���A�|�g�[�V�X��U������B�Ƃ��낪�ʏ�̍R�s�q�`�h�k�|�P�R�̂͂R�ʉ�������A�|�g�[�V�X�U�������ォ�����B����ɑ��A�鋞������w��w���̐Γc��������́A�A���p�J�Ȃǃ��N�_�Ȃ̍R�̂��P��h���C������Ȃ���ϗe�Ղł���_�ɒ��ځB�R���F�����ʂ����o���A�ʏ�̍R�̂�蕪�q�ʂ����������萫��g�D�ւ̎����\�ɗD�ꂽ�u�i�m�A�S�j�X�g���q�v�Ƃ��邱�Ƃɐ��������B �@����ɁA���̃i�m�A�S�j�X�g�����@�\���r�t�B�Y�X�ۂɑg�ݍ��B������������͂��ߑ����̂���͎_�f�̂Ȃ����ɍD��Ő����B����A�r�t�B�Y�X�ۂ����C���ۂ̂��߁A�Ö����^����Ƃ���g�D������ł���̂Ɠ��l�̏ꏊ�ɑI��I�ɐ������n�߁A�s�s�q�P�i�m�A�S�j�X�g������B �@�������f���ł́A���̂s�s�q�P�i�m�A�S�j�X�g�����r�t�B�Y�X�ۂ͒�_�f��Ԃɂ��邪��g�D�ɂ����đI��I�ɑ��B�A�R�����p�A���S�����m�F����Ă���B���҂͗Տ������J�n�Ɍ������O�Տ������Ɋ֘A�������g�݂������Ő��i�B����I�V��̊J���ɂȂ���B m3.com 2016�N2��10�� |
|
�זE�x�����҂Ƀ��N�`�����^ ����ȂǁA��t�哱�ŋ������� |
| �@������w��Ȋw�����������a�@�A�_�ސ쌧������Z���^�[�A���������Z���^�[���a�@�̂R�@�ւ͂W���A�זE�x����ɑ��邪�N�`���Ö@�̑��{������t�哱�������J�n�����Ɣ��\�����B�x����זE�ō��p�x�ɔ������镡���̍R����W�I�Ƃ���A���×p���N�`���̑�Q���i�o�Q�j�ƂȂ�B�Q�N�Ԃ�ʂ��A���Ĕ��������Ԃ��w�W�ɁA�v���Z�{�Q�Ƃ̔�r�ɂ�肪�N�`���̗L������]������B �@�������ł́A��p�ł���̊��S�؏����Ȃ���A���̌�A�p��⏕���w�Ö@�����{�����זE�x���҂��ΏہB�U�O���\�肵�Ă���B �@���Ö@�Ɏg�����×p���N�`���͂���y�v�`�h���N�`���ŁA�זE���Q���s�זE�i�b�s�k�j��U�����邱�Ƃɂ��R��ᇌ��ʂ��B �@���^������ᇍR�����q�̃y�v�`�h������זE�Ɏ�荞�܂�A���̍זE�\�ʂɌ`�������G�s�g�[�v�y�v�`�h�Ǝ�v�g�D�K����`�q�����́i�l�g�b�j�N���X�P�C���q�̕����̂��b�s�k�ɔF������邱�Ƃɂ��A���̎�ᇍR���ɓ��ٓI�b�s�k��U������B���̂b�s�k�́A���l�ɃG�s�g�[�v�y�v�`�h�Ƃl�g�b�N���X�P�C�����̂��זE�\�ʂɒ���Ă���W�I��ᇍזE�ɑ��čזE���Q�����������B m3.com 2016�N2��10�� |
|
����זE�����_���������鎡�Ö@ ����p���Ȃ��A������������ |
| �y�H���T�ꃂ�[�j���O�V���[�z�i�e���r�����n�j2016�N2��3������ �u����זE�������ނ�����ː����Â͂ł��Ȃ��̂��낤���H�v �@�����A����̎��ÂƂ��čs���Ă�����ː����ẤA�̂̊O������ː��Ăđ̓��̂���זE�ɓ͂�����B�������A����זE�̎�O�ɐ���ȍזE������ƁA����������Ă��܂��̂���_���B �@�e���r�����̃R�����e�[�^�[�A�ʐ�O�͋��s�匴�q�F��������K�˂��B����̕��ː����Â̎�_����������u�z�E�f�����q�ߑ��Ö@�v���A��؎������ɕ������B ����זE����荞�݂₷���z�E�f�̖�܂𓊗^ ����u����זE����荞�݂₷���z�E�f�̖�܂��A�S�g�ɓ_�H�œ��^���āA����זE�ɂł��邾���z�E�f�̖�܂��W�܂�����Ԃ��������܂��v �@���ɁA������Ƃ����@�B���g���Ē����q��̂ɏƎ˂���B�����q�̓z�E�f�Ɣ�������Əd���q�����������邪�A����͂���זE��j��͂������B�������A�זE���Ŕ��������d���q�����͂������́A���̍זE1���ɂƂǂ܂邽�߁A�ׂɐ���ȍזE�������Ă������܂œ͂��Ȃ��B����A����זE������_�������ł��鎡�Ö@�Ȃ̂��B �ʐ��u���Ð��т͂ǂ��Ȃ�ł��傤�v ����u�]��ᇂ⓪��ᇂ�......�]�����͗ǂ����т��o�Ă��܂��v �@�܂��Ǘᐔ�����Ȃ����A�������͊��҂ł���B���݁A�Տ������̍ŏI�i�K�ɂ���B�C�ɂȂ镛��p�ɂ��Ă��A����זE������j�Đ���ȍזE�ւ̕��ː��ʂ�Ⴍ�}������̂ŁA�������ł���悤���B �@�����A���i�K�ł͂ЂƂ�_������Ƃ����B�����q�́A�̂̕\�ʂ���6�`7�Z���`�̏ꏊ�܂ł͓͂����A������[���Ƃ���ɂ͂Ȃ��Ȃ����B���Ȃ��B����זE�̈ʒu�ɂ���ẮA���̎��Ö@���L���ɋ@�\���Ȃ����ꂪ����B �z�E�f�́u�I�v���₵�Ē����q������m�����₷ �@���́u7�Z���`�̕ǁv���邽�߂̌������A������̕Љ��ꑥ�����̉��Ői�߂��Ă���B�Љ������́A�R����܂��ɏ��̃J�v�Z���ŕ��܁u�i�m�}�V���v���J���������A��������p���悤�Ƃ����̂��B�܂�A�z�E�f���܂��J�v�Z���ɂ���݁A����זE�ɏW���I�ɓ͂���B �Љ��u�i�����q�Ǝ˂̑O�ɁA�z�E�f�́j�I�𑝂₷�킯�ł��B����ƁA�������悭�����q�������ɔ������āA���ː����o��v �@���̕��@�Ȃ�A���݂̕��@�Ɣ�ׂăz�E�f�̏W�ϓx��20�{�ɏオ��\�������邻�����B����ƁA���Ƃ�7�Z���`���[���ꏊ�ɓ͂������q�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�u�I�ɓ�����v�m���͂����ƍ��܂�B �@�z�E�f�����q�ߑ��Ö@�͗Տ������̍ŏI�i�K�ŁA�i�m�}�V�����u�z�E�f�̐��܂��J�v�Z���ɓ���Ďg�������v��ԁB�܂�A���p�ւ̌��ʂ��������Ă��Ă��邻�����B���S���̊m�F���\���ɍs���K�v�����邪�A�Љ�������5�N�قǂŏ\���ɗՏ��܂ł�����\��������Ƃ����B �@�X�^�W�I�ł͋ʐ샊�|�[�^�[�ɁA�R�����e�[�^�[�ŏ��D�̍��ؔ��ہA�H���T��A�i�A�F��Ȃ݃A�i��������Ԃ����B �����u���̋@�B�i������j�A�����炮�炢�ł����v �ʐ��u10�����炢...�����炨���͂�����܂��B���̑�菬�����̂ŁA�ł������{�݂͂���܂���v �H���u���Â͂���ς肨����������H�v �ʐ��u�ŏ��͐�i��Âɂ͂Ȃ��Ȃ��ł��傤���ˁv �F���u���̎Ⴂ�l������40�A50��ɂȂ邱��ɂ́A�펯���K�����ƕς���Ă���킯�ł���ˁv �ʐ��u�ς���Ă���Ǝv���܂��v J-CAST�j���[�X 2016�N2��11�� |
|
������\�h�͍��Z�����̐H������ 1��10�O�����̐H���@�ۂ� |
| �@������͓��{�l���������ǂ��邪���1�ʂŁA12�l��1�l�����U�ɂ�����Ƃ�����B�������A�����z���������e������Ƃ����A�Ⴂ����̔��Ǘ��������̂��������B �@���̓������h���ɂ́A���Z���̎�����H���@�ۂ̖L�x�ȐH�����Ƃ�ƌ��ʂ����邱�Ƃ����߂Ă킩�����B�ăn�[�o�[�h��̃`�[�����������܂Ƃ߁A�ď����Ȋw���uAAP�v�i�d�q�Łj��2016�N2��8�����ɔ��\�����B �Ⴂ�����������\�h���ӎ����ăT���_��H�ׂ悤 �o�O�̎Ⴂ�����ł̔��ǃ��X�N24���� �@�����`�[���́A�������肵�����N�L�^������č��Ō�t���N�����̒�����1991�N����27�`44����������9��534�l��ΏۂɁA�H�����Ɠ�����̔��Ǘ��̊W��20�N�ԒǐՂ����B�����āA4�N���Ƃɓ�����̔��ǂƐH���Ɋ܂܂��H���@�ۂ̗ʁA�얞�x�������̊i�w���iBMI�j�A�̏d�ω��ʁA���o�̕p�x�A�A���R�[���ێ�ʁA������̉Ƒ����ȂǂƂ̊֘A�ׂ��B�܂��A�Ώێ҂Ɂu�v�t���̐H���������v���s�Ȃ��A���Z����̐H�����e�����B �@���̌��ʁA�H���@�ۂ��������̂�H�ׂĂ��������ł́A���Ȃ������ɔ�ה��ǃ��X�N��12�`19���Ⴍ�Ȃ����B���ɍ��Z����ɐH���@�ۂ𑽂��ہi�Ɓj���Ă��������́A���Ȃ������ɔ�ׁA�S�̂̃��X�N��16���Ⴍ�Ȃ���肩�A�o�O�̎Ⴂ�����ł̔��ǃ��X�N��24�������������B�܂��A���Z����̐H����1��10�O�����̐H���@�ۂ�lj�����ƁA���X�N��13�����邱�Ƃ��킩�����B �����̓����ǂƁu�v�t���̓��[�v�̊W�� �@������́A�����z�������̃G�X�g���Q�������ǂɋ����W���Ă���A�H���@�ۂ��G�X�g���Q���l��}���邱�Ƃ��m���Ă���B �@����̌����ɂ��āA����̃E�H���^�[�E�E�B���b�g�����͂�������Ă���B �u������̗\�h�ɂ́A�Ⴂ������ʕ�����H�ׂ邱�Ƃ��L�v�ł��邱�Ƃ��ؖ����܂����B�H���@�ۂ��G�X�g���Q���l�������A�������������炷���߂ƍl�����܂��B����܂ł̌�������A���[�̍זE�̔��B�́A���Ɏv�t���ɔ��������ƍR���������o���̉e�����邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B������A���Z����̐H���������̓����ǃ��X�N��}���邽�߂ɂƂĂ���Ȃ̂ł��v �@�H���@�ۂ̑����H�ו��́A�C���A�C���A�L�m�R�A��A�ʕ��A�����Ȃǂ��B���Ȃ��̎v�t���̂��삳��̐H��ɂ���1�i�T���_�ނ������Ă����悤�B J-CAST�j���[�X 2016�N2��13�� |
|
���̂��Âɂ����ʊ��� �X����́u�i�m�i�C�t���Áv |
| �@�ߔN�ɂȂ�A��������������X����ɑ��A���ٓI�ȃ^���p�N������������A��ᇃ}�[�J�[�Ƃ��đ��������̗L�͂Ȏ�i�ƂȂ��Ă���B�������A���̂Ƃ����p�\�ȃX�e�[�W3�܂ł��X����̔����͖�15���ŁA�c��̖�85���͎�p�s�\�ł���B�����A�R����܂������ÑI�����̂Ȃ������X�e�[�W4A���X����ɑ��A�i�m�i�C�t���Â̗Տ��������n�܂��Ă���B �@����́A����זE�ɑ̊O����j���h���A�j�̐�[�̓d�ɂ�3000�{���g�̓d����Z���Ԓʓd�����邱�Ƃɂ��זE�ɍE�i���ȁj���J���A��������ł����鎡�Â��B������ȑ�w�a�@��������Ȃ̐X���j�T��C�����ɘb�����B �u�i�m�i�C�t���Âɂ��ẮA18��̊̂���ɑ��ėՏ����������{���A�L�����ƈ��S�����m�F�ł��܂����B�����ŁA��N4������Ǐ��i�s���ʼn��u�]�ڂ̂Ȃ��X�e�[�W4A���X����ɑ��A8���ڕW�Ƃ��ėՏ��������s�Ȃ��Ă��܂��B����6��Ɏ��{���܂������A���̑����̏Ǘ�Ŏ�ᇂ��������Ȃ��Ă��܂��B���̎��Â͓]�ڂ̂���X�e�[�W4B�ɂ͓K�����܂���v �@�X����̃i�m�i�C�t���ẤA�S�g�������s�Ȃ��A�g�̂̕\�ʂ��璴���g�̉摜�����Ȃ���j���h���B�X���̎���ɂ͈݂�\��w�������邪�A�������ђʂ��Ē��ːj���x�̑����̐j���A��������͂ނ悤�Ɏh���B �@�Ⴆ��3�Z���`���X����̏ꍇ�A��������͂ނ悤��2�Z���`�̊Ԋu��4�{�̐j���h���B�j�̐�[��1.5�Z���`�����d�C�������\���ŁA�v���X�̐j����}�C�i�X�̐j�Ɍ������ēd�C�������B3000�{���g�̍��d���ŁA1�̐j�̊Ԃ�1������1�b�Ƃ����Z���Ԃ�80������160���ʓd����ƁA����זE�Ƀi�m���[�g���i1�i�m���[�g����10������1���[�g���j�̍E���J���A�זE�����n���o���B �@����ő�������ƂȂ��A����זE���������ׂĎ��ł�������B�i�m�i�C�t���ẤA2008�N�ɃA�����J�Ŏn�܂�A�����͊̂��Â��傾�����B �u�P���^�b�L�[�B���C�r����w�̃}�[�`�����m�̃O���[�v�́A�X�e�[�W4A���X����200��ɂ��̎��Â����{���܂����B50��Ŏ�ᇂ��k�����A��p�\�ƂȂ�A�c��150��͍R����ܕ��p�ʼn����������Ă��܂��B �@���ϐ������Ԃ́A�R����ܒP�Ƃɔ�ׂĖ�2�{��24�����ɉ��тĂ��܂��B�Ǐ��̍Ĕ���3���ŁA�i�m�i�C�t���Â��X���ɂƂǂ܂��Ă��邪��������}������ʁi�Ǐ�����\�j�����邱�Ƃ�������܂����B���̂��߃A�����J�ł́A�X���ÂɎg����Ⴊ�����Ȃ��Ă��܂��v�i�X����C�����j �@�X����̃i�m�i�C�t���ẤA10������2�T�Ԓ��x�̓��@��v����B�ʓd�͈͂ł́A����זE�Ǝ��ӂ̐���זE�����ł��邽�߁A�݂⒰�̔S���ɒ�ᇂ���������A�X�����N�����肷�邩�炾�B�����̉̂��߈��ÂƐ�H���K�v�ŁA�̂��Â�������@���Ԃ������B���Ăł͔x����A�O���B����A�t����Ȃǂ̎��Âɗp�����Ă���A����͓��{�ł���������邱�Ƃ����҂���Ă���B NEWS�|�X�g�Z�u�� 2016�N2��14�� |
| �u���ҎQ���^��Áv�𑣐i ���m�̂����Ë@�ցA�^�u���b�g�Ŋ��҂��Ǐ�����ȊǗ� |
�@�x�m�ʂƕx�m�ʃt�����e�b�N�́A���m������Z���^�[�����a�@�̓��@���Ҍ����x�b�h�T�C�h�V�X�e�����\�z�B�u���҂Ɠd�q�J���e�̏������L���A���ҎQ���^��Â𑣐i����v�i�x�m�ʁj�ړI�ŁA2������^�p���J�n����B �@���@���҂��A�����̕a���ŁA����Z���^�[�����a�@����ݗ^�����^�u���b�g�𗘗p�B�a�@�̐f�Õ��j�A��Ô�T�Z�Ȃǂ̓`�B�����A�f�ÃX�P�W���[���A�f�ÁE���ÁE�������ւ̈ē��\���A�ߋ��̐f�ÁE�����L�^�Ȃǂ��m�F�ł���B�̂̏Ǐ�A�H���ʁA�����ʂȂǂ����Ҏ��g���^�u���b�g����d�q�J���e�ɓ��͂ł��邽�߁A�Ǐ�̕ω��̔F���⎩�ȊǗ��ӎ������܂�A���Âւ̎�̐�����߂�Ƃ��Ă���B �@�܂��A���@���̗��������߂邽�߁A�@���̔��X�ւ̃f���o���[�����◝�e���̃V�����v�[�\��Ȃǂ̋@�\��������Ƃ����B���@���ɓ��p�i���s�������ꍇ�A���Ҏ��g�����X�܂ōs�����Ƃ����������A���ւ������������Ȃ��Ƃ�����B�܂��A�����������e���܂ňړ����Ă݂������Ȃ������Ƃ������Ƃ�����B�����������Ԃ��������Ƃ����B �@����A�Ō�t�ɂƂ��ẮA�����I��ƕ��ׂ̌y�����\�ƂȂ�B�Ō�t�͏]���A���҂̑̂̏Ǐ�A�H���ʁA�����ʂȂǂ��x�b�h�T�C�h�Ńq�A�����O���A�i�[�X�X�e�[�V�����ɖ߂��ēd�q�J���e�ɓ��͂��Ă����B�f�ÃX�P�W���[���̐����Ȃǂ�����1�l�ЂƂ�Ɍ����ōs�Ȃ��Ă���B �@�{�V�X�e���𗘗p����ƁA���҂��^�u���b�g����d�q�J���e�V�X�e���֓��͂���̂��T�|�[�g���邾���ł悭�A����������ƕ��ׂ��y������A���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����Ƃ�������P�A�ɒ��͂ł���Ƃ����B 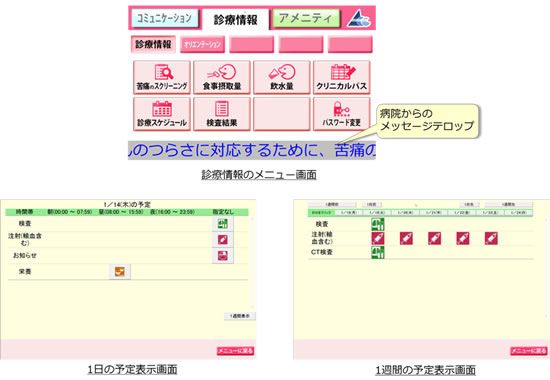 �@�^�u���b�g�ɂ́A�x�m�ʂ�10.1�^���C�h�uARROWS Tab Q555/K32�v���̗p�B��630g�̌y�ʂŁA�o�b�e���쓮���Ԃ͖�11���Ԃ̂��߁A���҂̋N������A�Q�܂ň��S���ė��p�ł���Ƃ��Ă���B �@�����̂��Ґ��͑����X���ɂ���A1981�N�ɓ��{�l�̎��S������1�ʂƂȂ����B2015�N�ɂ́A��������98����A����ɂ�鎀�S��37���l�ɂȂ�Ɨ\������A�����������Ă��邪�҂ɁA�œK�Ȏ��Â������I�ɓK������H�v�����߂��Ă���B����Z���^�[�����a�@�ł́A���S�Ȉ�Â���邾���łȂ��A�u���҂̐ϋɓI�Ȏ��Âւ̎Q���v�𑣂��A���Âɂ��D�e����^�������������l���B ASCII.jp 2016�N2��16�� |
| �����j���O�ł���זE�̑��B��}���ł��邩������Ȃ� |
| �@����זE�̑��B��}���邱�ƂŒm����Ɖu�זE���u�i�`�������L���[�זE�v�ł����A�����j���O�Ȃǂ̉^���ɂ��A�i�`�������L���[�זE�����������A����זE�Ȃǂ̎�ᇂ̑��B��}���ł���\�����A�}�E�X�ɂ������Ŏ�����܂����B �@�R�y���n�[�Q����w�̓}�E�X���Ԃő��点�A����זE���U������Ɖu�n���ɉ^�����^����e�������܂����B���̌��ʁA����4km�`7km�������}�E�X�̖Ɖu�n�������������A�V������ᇂ̑��B��\�h�����ق��A�����̎�ᇂ̐������ő��60���}���ł��邱�Ƃ��킩�����Ƃ̂��ƁB�R�y���n�[�Q����w��Pernille Hojman���́u�^������ᇂ̐������ړI�ɃR���g���[���ł��邱�Ƃ����߂Ď������Ƃ��ł��܂����v�Ƙb���Ă��܂��B �@�����`�[���͔畆�E�x�E�̑��Ȃ�5��ނ̂�����������}�E�X���g���ĉ^���Ƃ̊֘A�����������܂����B�^���ɂ��A�h���i���������o����邱�ƂŁA�����ł���זE�Ɛ키�i�`�������L���[�זE�𑗂�o���Ɖu�n���h������邽�߁A��ᇂ̑��B��}���邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��ƁB�܂��A�^�����̋ؓ�����C���^�[���C�L��-6(IL-6)�Ƃ������������o����Ă���A�i�`�������L���[�זE�Ɏ�ᇂ��U��������w�����o���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B �@����܂ʼn^���Ńi�`�������L���[�זE�����������邱�Ƃ͎w�E����Ă��܂������A�^���ɂ����o�����X�g���X�z���������A����זE���U������w�����o���Ă��邱�Ƃ����߂Ď����ꂽ���ƂɂȂ�܂��B�l�Ԃɑ��ē������ʂ����邩�͂܂���������Ă��܂��A�^�����o��̌������������������\�h�ł���Ƃ����������ʂ����邱�Ƃ���AHojman���̌����`�[���́A���҂̉^���p�^�[���ׁA����̃}�E�X�Ɠ��l�̉e�������邩�ǂ��������Ă����Ƃ̂��Ƃł��B GIGAZINE(�M�K�W��) 2016�N2��18�� |
|
���Ì�̐������Ԃ��������҂̓����́H ���n�r���ɂ���Ď������Đ������Ă���l |
| �@�������_�E�_�o��Ì����Z���^�[�a�@�̑������M�q��t�ƁA���V�h�j�[��w�̃����_�E�N���C�����m��̌����`�[���́A�^���@�\�Ȃǂ������郊�n�r���e�[�V�������A�ݑ��ÂȂǂŎ����������������Ă��邪�҂́A���̌�̐������Ԃ������Ȃ��Ă����Ɣ��\�����B �@�����ł́A���Â��A�̒��s�ǂ�g�̋@�\���ቺ���Ă������ƂŁA���n�r�����Ă�����{�A���B�̂���72�l��ΏۂɁA�^���@�\�̉���X�̊����\�́A�މ@��̌��N��ԁA�������ԂȂǂ��A�ő��25�����Ԓ��������B �@�����̌��ʂ̓X�R�A�����邽�߁A�u�@�\�I�����x�]���@�iFIM�j�v�Ƃ����A�^����H���ȂǓ��퐶����18���ڂɕ��ނ��A���ꂼ��̉��ʂɉ����āu���S�����v����u�S��v�܂ł�7�i�K�Ŏ����]���@�𗘗p���Ă���B �@���̌��ʁA���n�r���ɂ����FIM�̃X�R�A��80�_�ȏ�i������x�����ł��Ă���j���������҂́A80�_�����i��삪�Ȃ���ΐ���������j�̊��҂����������Ԃ����������B �܂��A�X�R�A�������������҂̓����͂����Ƃ���A���n�r���ɂ���āu�a�@�Ǝ�����s�����ł�����s�\�́v�A�u�y���^�����ł���g�̔\�́v�܂ʼn��Ă���A�ݑ��Â��Ă���A�Ƃ������X��������ꂽ�Ƃ����B �@�����҂�́A�u���҂����n�r����ϋɓI�ɎA�������������𑗂�\�͂����邱�Ƃ́A�\���ǍD�ɂ���\������������v�ƃR�����g���Ă���B �@���\�́A���ۂ���T�|�[�e�B�u�P�A�w��uSupportive Care in Cancer�v2015�N10�����iVolume 23, Issue 10�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�B Aging Style 2016�N2��21�� |
| ���ǂƐl�H�łɎg����S���`�b�v�̊֘A�� |
| �@���N���O���炻�̈��S���ɂ��Č��O�̐����オ���Ă����l�H�ł̖��ɂ��āA�Đ��{���悤�₭�d�������グ���悤���B�ď���Ґ��i���S�ψ���(CPSC)��2��12���A���ی��(EPA)�A���a��Z���^�[(CDC)�Ƌ����ŁA�l�H�ł̏[�U�܂̌����Ƃ��Ďg�p����Ă���Ã^�C���ɊܗL����鉻�w�����̊댯���ɂ��āA�������J�n����Ɣ��\�����B �@�č��ł�2014�N�ANBC�e���r�����q�T�b�J�[�I��̂��ǂƐl�H�łɎg����S���`�b�v�̊֘A���ɂ��ĕ��B�ԑg�ɓo�ꂵ�����V���g����w�̏��q�T�b�J�[�`�[���̏y�w�b�h�R�[�`�A�G�C�~�[�E�O���t�B���ɂ��ƁA�l�H�ł̏�Ńv���[�����Ă����w���������u���X�Ɓv����ǁB���������w����38�l�̂����A34�l���S�[���L�[�p�[�������B �@�܂��A���̒��ɂ̓��V���g���B�Ńv���[���Ă����I����\���l�������A�S�Ċe�n�ł����l�ɁA����ǂ����w���������m�F����Ă���B�唼�̓����p��┒���a�ȂǁA���t�̂����늳�����Ƃ����B �@�܂��A�Ď�USA�g�D�f�[��2015�N3���A�u�S�Ċe�n�̊w�Z��q�ǂ������̗V�я�A�ۈ牀�Ŏg���Ă���l�H�ł���A���N�ɊQ���y�ڂ��댯�������鍂�Z�x�̉������o���ꂽ�B����ł��ĘA�M���{��2�@�ւ́A�l�H�ł͈��S���Ƃ��Ďg�p�𐄏����Ă���v�u�[�U�܂Ƃ��ăS���`�b�v���g�p���Ă���l�H�ł̗��p���g�債�Ă��邱�ƂɊ֘A���āA��ɑI��̂�����畆�����ǁA������͂��߂Ƃ��錒�N��̌��O�����サ�Ă���B�l�H�ł𗘗p���Ă��鋣�Z��͑S�Ă�1��1,000�����ȏ゠��A�����̐l�H�ł����ׂēP�����ē���ւ���ɂ́A100���h��(��1��1,260���~)����R�X�g��������v�ȂǂƓ`�����B �@����ɂ���1�N���NBC�́A�uNBC�j���[�X�͐l�H�ł̊댯���ɂ��ĕs�������܂��Ă��邱�Ƃ��J��Ԃ��Ă������A�A�M�K�����ǂ͂���ɂ��āA�قڒ��ق��т��Ă���BEPA�������J�����̑O�ł̃C���^�r���[�����ۂ����v�ƕ����B������A�ĉ��@�G�l���M�[�E���ƈψ����EPA�̒S������ɏ��Ȃ𑗕t�B2015�N11��6���܂łɃS���`�b�v���g�p�����l�H�ł��̗p���Ă��鋣�Z��̈��S���Ɋւ��邳��Ȃ���̒�o�����߂��B�������AEPA�͂��̗v���ɂ������Ă��Ȃ������B Forbes JAPAN 2016�N2��21�� |
| ���Âŕs���Ɏv�����ƁA�u��p�v�u����p�v��}����1�ʂ�? |
| �@��Ï��������͂��̂قǁA��Ï��T�C�g�uimedi(�A�C���f�B)�v��Ŏ��{�����u����̎��Â�\�h�v�Ɋւ��钲�����ʂ\�����B�������Ԃ�2015�N12��16���`2016�N1��31���ŁA�L����1,097�[�B �@�u����̑��������̂��߂ɂ����Ȃ��Ă��邱�Ɓv��q�˂��Ƃ���A�u����I�Ȍ��f�v��598�[�Łu�Ƃ��ɂȂ��v(499�[)���������B �@�����āu���ÂɊւ��ĕs���Ɏv�����Ɓv���ŕ����ƁA�u�]�ځv(475�[)���ł������A�ȉ��Ɂu��p�v(466�[)�A�u����p�v(362�[)�������Ă���B �@����\�h�̂��߂ɂ��Ă��邱�Ƃ��ŕ������Ƃ���A�u�H���ɋC�����Ă���v��452�[�ōő��B�����Łu�։��v(343�[)�A�u�����̐����v(285�[)�A�u�^���v(198�[)�ƂȂ��Ă���B�u�Ƃ��ɂȂ��v�Ƃ�����125�[�������B �@���Âɂ́A�W������(��p�E�R����܁E���ː�)�̂ق��ɁA�����̖Ɖu�זE���g���Ă�����U������Ɖu�זE���ÂȂǂ�����B�����ŁA�u����̕W�����ÈȊO�̎��Ö@�v��m���Ă��邩�q�˂�ƁA�u�m���Ă���v(545�[)���ł��[���W�߂��B�u�悭�m���Ă���v(216�[)�ƍ��킹��ƁA�u�m��Ȃ��v(336�[)���A�m���Ă���l�̕���2�{�ȏ㑽�����ʂƂȂ��Ă���B �@���݁A��������Ò��̐l���g�߂ɂ��邩�������Ƃ���A�u����v�̍��v��657�[(�{�l230�[�A�F�l�m�l199�[�A�Ƒ��E�e��228�[�̍��v)�������B�u���Ȃ��v(440�[)�ɔ�ׂđ����Ȃ��Ă���B �@�uimedi�v�ł́A�������K���a�Ȃǂɂ��ďڂ������M���Ă���B �}�C�i�r�j���[�X 2016�N2��24�� |
|
�R�J�E�R�[���ł��Ö�̌��ʂ����シ��H PPI���p���̃G�����`�j�u�̋z���������P |
| �@�R�J�E�R�[�����x���Âɂ悭�݂�����̉����ɗL�p�ł���\�����A�V���Ȍ����Ŏ������ꂽ�B �@�זE�x����̋��͂Ȏ��Ö�ł���^���Z�o�i��ʖ��F�G�����`�j�u�j�̌��ʂ́A�݂�pH�l�ɂ���č��E�����B�������A�^���Z�o���g�p���銳�҂̑����̓v���g���|���v�j�Q��iPPI�j�ƌĂ�鋹�Ă��h�~��p����K�v������APPI�ɂ���Ĉ݂�pH�������Ȃ�i�A���J�����ɌX���j�ƁA�^���Z�o�̋z�����͒ቺ���A���ʂ��ጸ���Ă��܂��B���錤���ł́APPI�̎g�p�ɂ��^���Z�o�̌����Z�x��61���ቺ���邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă���B �@�G���X���XMC�������i�I�����_�A���b�e���_���j��Roelof van Leeuwen�������錤���O���[�v�́A�_�������ł���R�[�����^���Z�o�ƈꏏ�ɕ��p���邱�Ƃɂ��A�݂�pH���t�]�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƍl�����B �@�����ł́A�^���Z�o�p����זE�x����28�l��ΏۂƂ��A�팱�҂̔����ɂ�PPI�p���Ă�������B�ŏ���7���Ԃ͖�܂ƂƂ��ɖ�230ml�̐������݁A����7���Ԃ͓��ʂ̃R�J�E�R�[���E�N���V�b�N�����ތQ�ƁA�t�̏����ň��ތQ�ɁA���҂�ׂɊ���t�����B �@���̌��ʁA�R�[���̐ێ�ɂ��^���Z�o�̋z�����ɁA�Տ��I�ɂ����v�I�ɂ��L�ӂȏ㏸���݂�ꂽ�Ƃ����B���̌��ʂ́uJournal of Clinical Oncology�v�I�����C���ł�2��8�����ꂽ�B �@�������҂�́APPI�p���銳�҂Ń^���Z�o�̌��ʂ��ő�ɍ��߂���@�Ƃ��āA1�ʖ����̃R�[��������ł��炤���Ƃ͗e�ՂɎ��s�ł���Əq�ׂĂ���B�ăm�[�X�E�F���E�w���X�E�v���C���r���[�a�@�i�j���[���[�N�B�j��Alan Mensch ���́A�u�^���Z�o��K�v�Ƃ��銳�҂̑����́A�݉�����ɖ�ɂ��ݎ_�����炷���߂�PPI�p����K�v������B���̑�Ƃ��ăR�[���𗘗p���邱�Ƃ͋����[���v�Ɛ������Ă���B �@�R�[�����I�ꂽ�̂́A�I�����W�W���[�X�A�Z�u���A�b�v�A�h�N�^�[�y�b�p�[�Ȃǂ̑��̈����ɔ�ׂĈ݂̎_���x���ꎞ�I�ɑ��傳������ʂ������������߂��Ƃ����B �@���҂̊��z�Ƃ��ẮA250ml�̃R�[���̔E�e���͗ǍD�ł������B�����O���[�v�́A�݂�pH�Ɉˑ����鑼�̂��Ö�ɑ��Ă����̐헪���L���ł���\��������Ƃ��A�Y�������܂Ƃ��ă_�T�`�j�u�A�Q�t�B�j�`�u�A�j���`�j�u�Ȃǂ������Ă��邪�A����̌����ŕ]�����Ă����K�v������Ƌ������Ă���B m3.com 2016�N2��25�� |
| ���S�����P�x1�ʁ@�Ȃ��L�����̐l�͎��ȂȂ��Ȃ����̂� |
| �@��N�A���������Z���^�[���A�s���{���̂���Ɋւ���������f�[�^�\�����B�����ł͍L�����g����ɂ������Ă����ȂȂ��h���ł��邱�Ƃ��킩�����B �@���S����1995�N��39�ʂ���2014�N��8�ʂւƑ傫�����ʂ��グ���L���B����͑S����̉��P���ŁA���̐����������Β����ǂ��z���̂����Ԃ̖�肾�B���ώ����͒j��12�ʁA����6�ʁA�i�����i�j���j��41�ʁA��ؐێ�ʂ�23�ʁi�j���j�A36�ʁi�����j�A�H���ێ�ʂ�25�ʁi�j���j�A35�ʁi�����j�ƁA���ϓI�Ȍ��̂ǂ��ɁA����Ŏ��ȂȂ��q���g���B��Ă���̂��낤���B �@�L���w�ɍ~�藧�����L�ҁB�^�N�V�[�ɏ��ƁA���������^�]��i60��E�j���j�ɘb���B�j���͑���Ƃ�ސE��ɉ^�]��ɁB�Ȃɂ͐旧����A���͌����B�j���ЂƂ肳�܂��B���͈��܂Ȃ����A������1��2�A3���B���f�́u�����Ƃ��Ȃ��v�Ƙb���B �u���N�Ȃ̂ŕK�v�Ȃ��B����ɂȂ�����A�a�@�Őf�Ă��炦���������̂��Ɓv �@�Ə��B��H�@���S�����P�x1�ʂ��炭���ۂƂ͂قlj����B�^�������Ȃ��猧����K�ˁA���N�����ǂ����ۉے��̍��X�ؐ^�Ƃ���ɕ������B �u�m���ɁA�L�����̂��f�̎�f���́A���ς������艺�������Ă��܂����v �@10�N�ȍ~�͎�f������̎��g�݂��������A12�N����̓f�[�����t�������̂��f�[�����g�Ɂg�A�C�h�B�C���p�N�g�̂����M�����݂�B �u���ꂪ����t���Ă���A�S�����l�������Ă��܂����v�i���X����j �@�L�����̂����Â̋��_�A�L����w�a�@�̐��R��F����i���ÃZ���^�[�Z���^�[���j�́A�u��Ë@�ււ̃A�N�Z�X�ƘA�g�̗ǂ��v���w�E����B�����ɂ�16�̂���f�ØA�g���_�a�@������A�A�g����f�Ï��̐��͑S��8�ʁB�u�����������炷���ɐf�Ă��炤�v�B���̌����̈ӎ����A�g���鋒�_�a�@�ւ̏Љ�ɂȂ���A����̑��������A�������Â������炷�B �@��f�̃n�[�h�����Ⴂ�w�i�ɂ́A�픚�n�ł���L���̓���������Ƃ����B �u�픚�̌������c���ꐢ��ƈ�Â̊ւ��͐[���A���������Ƃ̐M���W���ł��Ă��܂��B�������������Ë@�ւ���f����X��������܂��v�i���R����j �@�[�H�̂��߂ɗ���������L���̖�����������鋏�����u�l�G��v�̓X���i39�j�́A�u�m���ɕa�@�̐��͑����v�Ƙb���B�u������������A�d���I���̖�Ԃł��A�f�Ă��炢�܂��ˁv �@���͂���f�Â���Ƃ��Ȃ���t���A���҂̂��k�ɏ��u�����낸���k��v��12�N����J�n�����B����̌��C���F�肳�ꂽ���k��́A����658�l���������Ă���B �@���J�E���}���N���j�b�N�i�����s�s�j�@���̏��}���p�h��������k��̈�l�B����Ȍo����b���B �u�������ƍ��R���X�e���[�����ǂ̎��ÂŒ��N�f�Ă���j�����҂���i60��j�Ƃ̎G�k�̒��ŁA���f�̘b���o����ł��ˁB��x�������Ƃ��Ȃ��Ƃ����̂ŁA�����g�������Ă݂���Ɗ��߂܂����v �@���������̌㉟���������āA�j�������f����ƁA�Ȃ�Ƃ������ɂ����������B���������Ŏ�p���ł������߁A1�N�قnjo�����������C���B�ق��ɂ��A�݂����咰�����������������B �@�L���s�̓����́A�S���ɐ�삯�āu����o�^�v���s���Ă���_���B�����̕��˔\�ɂ�邪��̉e���ׂ邱�Ƃ�ړI�ɁA�L���s��t�1957�N������{�B�u��Î҂̂���ɑ���ӎ��������v�Ƙb���̂́A�L���s���L���s���a�@���@���̓�{������B �u�s���ɂ͂��_�a�@�������B���݂��ɐ����������A���ꂪ��Â̎��̍����ɂȂ����Ă���B��a�@��������Ȃ��Ƃ����悤�ȁA���R�̑叫�łȂ��̂��A�����̂�������Ȃ��v �@����p�F�m���͑I������Łu��������{��v��搁i�����j���B������z������͂���̂��낤���B dot.�h�b�g 2016�N2��26�� |
|
�č��œ��[�؏��p��I�����鏗�������� 2005�`2013�N��36������ |
| �@�č��ł́A�S�̓I�ȓ����Ǘ��͉����ł���ɂ�������炸�A���[�؏��p���鏗���̔䗦��2005�N����2013�N�܂ł�36���������Ă��邱�Ƃ��A�č���Ì����E�i�������@�\�iAHRQ�j�̃f�[�^�ɂ�薾�炩�ɂ��ꂽ�B����10���l������ł�����66�l����90�l�ɑ����������ƂɂȂ�A�Ȃ��ł��������[�؏���10���l������9�l����30�l�ւ�3�{�ȏ�ɋ}���B2013�N�ɂ͗����؏����S�̂�3����1���߂�܂łɂȂ��Ă���B �@�������[�؏�����N��ቺ���Ă��邱�Ƃ��킩�����B2013�N�ɗ����؏����������̕��ϔN���51�ŁA�Б��؏�����������61����10�ΎႩ�����B �@���Ȃ��Ă��\�h�I�ɗ����؏����鏗�����A10���l������2�l����4�l�ȏ�ւƔ{�������B������̈�`�I���X�N�̂��鏗���͗\�h�[�u�Ƃ��ė����؏����邱�Ƃ�����A2013�N�ɂ͏��D�ʼnf��ē̃A���W�F���[�i�E�W�����[�����̎�p���b��ƂȂ����B�܂��A�����E�Б��̂�����̓��[�؏��p���O���ł̎��{�������Ă���A2013�N�ɂ͑S�̂�45�����O�����u�ł��������Ƃ����ꂽ�B �@���̃f�[�^�́A�����Ẫp�^�[�����ω����Ă��邱�Ƃ��������̂ł���A���N�A�����A���S�̂��߂̏����̑I���̗L�����ɂ��āA����ɖ��m�ȍ������K�v�ł��邱�Ƃ���������ɂ��ꂽ�ƁAAHRQ�̗����ł���Rick Kronick���͏q�ׂĂ���B �@�ă��m�b�N�X�E�q���a�@�i�j���[���[�N�s�j��Stephanie Bernik���ɂ��ƁA���[�؏��p��I�Ԋ��҂Ɠ��[�����p��I�Ԋ��҂ŁA�S�̓I�Ȑ������͂قړ����x�ł���Ƃ����B����ł����̂悤�ȌX�����݂��闝�R�Ƃ��ẮA��`�q�X�N���[�j���O�̑����A�Č����Â̌���A����̂Ȃ����̓��[�̂��ǃ��X�N��ጸ�������Ƃ��������̗v���Ȃǂ�����ƁA�����͐������Ă���B �@�ăE�B���X���b�v��w�a�@�u���X�g�E�w���X�Z���^�[��Frank Monteleone���́A�K���������[�؏��p���K�v�łȂ��Ă��A��ɉ��x���}�����O���t�B������A���̂��тɕs���ɂȂ���́A�؏����Ă��܂��ق����悢�ƍl���鏗��������Əq�ׂĂ���B����́̕A�č��l����25���ȏ���߂�13�B�̃f�[�^�Ɋ�Â����́BAHRQ�͕č��ی��Љ���Ȃɑ�����@�ւł���B m3.com 2016�N3��3�� |
|
���Ñ��u�u�����q�v�̊��p�����i�� ���{�����E�����[�h�ł��镪�� |
| ���E���̕a�@�ݒu�^�a�m�b�s�V�X�e���i���������Z���^�[�j �z�q���ő������V�Z�p �@�z�q�����ÃV�X�e�����肪����������쏊�B���ɊC�O�W�J�Ő�s���Ă���A�����O�łP�O�{�݈ȏォ��̎��т�����B�����ł͋ߔN�A���É��z�q�����ÃZ���^�[�i���É��s�k��j��k�C����w�ɔ[�������ݔ����ғ����Ă���B���É��z�q�����ÃZ���^�[�ɂ͂���זE��h��Ԃ��悤�ɗz�q�����Ǝ˂���X�|�b�g�X�L���j���O�Ǝ˃V�X�e����B�k��Ƃ͌ċz�œ�������ւ̏W���Ǝ˂��\�ɂ������̒ǐz�q�����ÃV�X�e���������J������ȂǐV�Z�p�����a�������Ă���B �@���ɓ��̒ǐz�q�����ÃV�X�e���̊����͊C�O�̌Ăѐ��ɂȂ�A�č��̈�Î{�݂ւ̐V���ȓ��������܂����B���V�X�e���͂�����ӂ̐��핔�ʂɒ��a�P�E�T�~�����[�g���̋��}�[�J�[��u���A���̈ʒu���b�s�Ŋm�F���ċz�œ��������ǐՂ���B����̈ʒu���������o���A����̓����Ɨz�q���̏Ǝ˃^�C�~���O��������B���}�[�J�[�����Ìv��͈̔͂ɂ��鎞�����z�q�����Ǝ˂��A����זE�ւ̏Ǝˉe����ጸ������B �@�k��ł͓����ÃV�X�e�����P�S�N����^�p�B�����ł͋��s�{���ł��X�|�b�g�X�L���j���O�ƎˋZ�p�Ɠ��̒ǐՏƎˋZ�p�𓋍ڂ����V�V�X�e�����P�W�N�x���ɉғ�����\��B�C�O�͂���܂ŕč������S���������A�V�V�X�e���ō���̓A�W�A�s�ꂩ��̎��_���B ����זE�����I�����ƎˁA�uBNCT�v16�N�x�ɂ��Տ� �@���ː����Õ���ł͏d���q����z�q������ᇂɏƎ˂�����@�̂ق��A�z�E�f�����q�ߑ��Ö@�i�a�m�b�s�j�V�X�e���������Ŏ��p���ւ̏��������X�Ɛi��ł���B �@���������Z���^�[�i�����s������j�ł͒�����������g�����a�@�ݒu�^�a�m�b�s�V�X�e���̗Տ�������������P�U�N�x���Ɏ��{�����B �@���V�X�e���́A�̓����^������܁i�z�E�f��܁j����ᇍזE�ɏW�ς����A�����q���Ǝ˂���B���q�����ÃV�X�e���͎�ᇂ̂���ꏊ���Ǝ˂��邽�߁A����זE���ӂ̐���זE�ւ̏Ǝˉe����ጸ������Z�p�̊J�����s���ɂȂ�B �@����A�a�m�b�s�V�X�e���͑I��I�ɂ���זE�������Ǝ˂ł���B���҂ɂ͂���ɑI��I�ɏW�ς���z�E�f�����������O���^���A�z�E�f���������W�ς����i�K�Œ����q���Ǝ˂���B����זE�ւ̉e��������Ɍ��点�A����p�����Ȃ��B �a�@���Ɂg���q�F�h �@���������Z���^�[�̎��Ñ��u�͂b�h�b�r�i���]����j���J���������`�E���^�[�Q�b�g�V�X�e���ƁA�����̕č��q��Ђ̒����������g�ݍ��킹�Đ���B���^�̒���������ʼn��������z�q�������`�E���^�[�Q�b�g�ɏՓ˂����Ē����q������B�]���͈��肵���M�O�����q�邽�߂Ɍ��q�F���K�v�������B �@�������q�F�͈�Î{�݂ɂ͂Ȃ��A���ËZ�p�̌����J����i�߂�ɂ͊��҂����q�F�{�݂Ɉڑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���q�F�͊j�R���̈��S���̖�������A����܂ň�Õ���ł̎��p��������ƌ����Ă����B �@�V�V�X�e���͒�����������g�����ߏ��^�����\�ŁA�j�R���̐S�z���Ȃ��B�Z�_���Ⴂ���`�E���̎g�p�Ɍ�����p�̗�p�V�X�e������ː����ʌ��f�̎������ݔ����J�����A�a�@���ւ̐ݒu���\�ɂ����B �@�a�m�b�s�V�X�e���͉��Ăł������J��������قǐi��ł��炸�A���{�����E�����[�h�ł��镪��Ƃ��Ċ��҂ł���B����͗Տ������ɉ����A�V���ȃz�E�f��܂̊J���Ȃǎ��p���܂ł̓��̂�͕�����ł͂Ȃ����A�u���{���̐V�K���ËZ�p�𐢊E�ɔ��M�ł���v�i�ɒO�����������Z���^�[�����a�@���ː����ÉȒ��j�Ƌ�������B �j���[�X�C�b�` 2016�N3��6�� |
|
���זE���łƊ��Ɖu����ɓ������� ��t�傪DGK���j�Q�������� |
| �@��t��w��w�@���w�����Ȃ́A����זE�ڎ��ł�����Ɠ����ɁA����Ɖu�����߂邱�Ƃɐ��������B����̑��B�ƖƉu�@�\�̒ቺ�ɂ������y�f��j�Q���鉻�����������B������ʂɂ��A����זE�����ʓI�Ɏ��ł�������\��������B����܂ł̍R����܂͐���ȍזE�̑��B�@�\�ɂ���p���Ă��܂��B�Ƃ��ɐҐ��זE�ł́A�������B�\���ቺ���ĖƉu�n�̕s�S�̈������ƂȂ��Ă����B���q�W�I���Ö�́A����זE�ɕW�I����ς������������Ă���Ȃǂ̉ۑ肪�������B �@�⍪��v������̌����O���[�v���y�f�W�A�V���O���Z���[���L�i�[�[�i�c�f�j�j�̈�ł��郿�A�C�\�U�C���i�c�f�j���j��j�Q���鉻�������B����זE�̍זE���ڗU������ƂƂ��ɁA����Ɖu�̘��i��p�����邱�Ƃ�˂��~�߂��B �@�c�f�j���́A�������F���̍זE����̑��B�����͂ɑ��i�����邾���łȂ��A�Ɖu�@�\��S���s�����p���̑��B��~��s��������U�����邱�Ƃ��m���Ă���B�c�f�j���̊�����j�Q�ł���A����זE���̒��ڗU���ɉ����A����Ɖu�����߂邱�ƂŁA����זE���𑣐i���邱�Ƃ������܂��B�c�f�j���j�Q�܂͖��̂��Ö�ƂȂ邱�Ƃ����҂����B �@�ŐV�̃n�C�X���[�v�b�g�X�N���[�j���O�n��p���ē�����w�n��@�\�̉��������C�u�����[��T���A�c�f�j������ٓI�ɑj�Q���鉻�������݂����B����ꂽ�������͎��ۂɂ���זE�̎��ł𑣂��A�s�����p�������������邱�Ƃ��m���߂��B�������̍œK���ȂǂɎ��g�݁A������R����܂̑����J����ڎw���B m3.com 2016�N3��7�� |
|
����ɂȂ�₷�������S���ɂ����H�I �ϋɓI�Ȑl�͕s�v�c�ȃp���[������ |
| �@���퐶���̉����ɂ��ϋɓI�ŁA�v��𗧂ĂĎ��s����l�́A�����łȂ��l�Ɣ�ׁA�ꕔ�̂���̔��ǃ��X�N�͍������A�S�̂ł݂�Ƃ���Ŏ��S���郊�X�N��15�����Ⴂ�Ƃ����s�v�c�Ȍ��ʂ��o���B �@���������Z���^�[�Ȃǂ̃`�[�����������܂Ƃ߁A2016�N3��5�����\�����B���̃^�C�v�̐l�͌��f��ϋɓI�Ɏ邽�߁A�������闦�͍����Ȃ邪�A���̕����i�s���Ă��Ȃ���ԂŔ�������邱�Ƃ��������炾�B �l���ɐϋɓI���ƒ��������闝�R���킩���� �]������S�؍[�ǂ̎��S���X�N��26���Ⴂ �@�����`�[���́A�k�͊�肩���͉���܂ŁA�S��8�̓s�{���̒j��5��5130�l��8�N�Ԃɂ킽���ĒǐՂ����B�ǐՊ��Ԓ���5341�l������ǁA����1632�l�����S�����B�Ώێ҂ɂ͎��L���A���P�[�g�p���𑗂�A���퐶���Ōo������o��������ɑ���Ώ��̕��@���A���i�ׂ��B �@��̓I�ɂ́A��肪�N���������ǂ��Ώ����邩�A����6�̍s���p�^�[���������A���ꂼ�ꎩ���ɂ��Ă͂܂�p�x�����B�i1�j��������v��𗧂āA���s����i2�j�N���ɑ��k����i3�j�̃v���X�ʂ������o���w�͂�����i4�j������ӂ߁A����i5�j�ς��邱�Ƃ��ł�����Ƌ�z�����������肷��i6�j���̂��Ƃ�����đ��̂��Ƃ�����A��6���B �@�����āA�u�ϋɓI�E�v��I�v�ɑΉ�����^�C�v���u�Ώ��^�v�A�u���ɓI�E�ꓖ����I�v�ɑΉ�����^�C�v���u�����^�v�Ɩ��t���A���̐��i�p�^�[���Ƃ��ǁA���S�̃��X�N���r�����B �@����ƁA�u�Ώ��^�v�̐l�́u�����^�v�̐l�ɔ�ׁA����S�̂̔��ǃ��X�N�͂قړ������������A�܂����̑���ɓ]�ڂ��Ă��Ȃ��i�K�̑�������i���ǐ�����j���r����ƁA���Ǘ��i�����闦�j����13�����������B�������A�t�ɂ���S�̂̎��S���X�N�͖�15���Ⴉ�����B�܂��A�u�Ώ��^�v�̐l�͌��f�ł������闦��35�������������B �@�����`�[���ł́u���i�ɂ���Ă���ɂ����郊�X�N�ɍ��͂Ȃ����A�Ώ��^�̐l�͌��f�ɂ��ϋɓI������A����̑��������ɂȂ���A����������l�������Ȃ�v�ƃR�����g���Ă���B �@���Ȃ݂ɍ���̌����ł́A�]������S�؍[�ǂ̃��X�N����r���Ă���B�u�Ώ��^�v�̐l�́u�����^�v�̐l�ɔ�ׁA�]������S�؍[�ǂŎ��S���郊�X�N��26���Ⴍ�������B�����Ȃ�ƁA���i�̍��������ɉe�����Ă���Ƃ����������B J-CAST�j���[�X 2016�N3��9�� |
| �����̎��S�Ґ����ł������u�咰����v���X�N�����߂�NG�K�� |
| �������茾���� �����̎��S�Ґ��������u�咰����v�̃��X�N�����߂�NG�K�����Љ�Ă��� ��������������ł���A����\�[�Z�[�W�Ȃǂ��̂悤�ɐH�ׂĂ��� �^�o�R���z���Ă���A�^���s���������Ĕ얞�ɂȂ��Ă����4�� �@�ˑR�ł����A���{�l�����ɂƂ��āA�ł����S�Ґ��̑�������̕��ʂ͂ǂ����Ǝv���܂����H �@�u������A���ȁc�c�H�v�u�݂���Ȃ��́H�v�ȂǂƂ��낢��Ȉӌ������邩�Ǝv���܂����A2013�N�̎��_�ŏ����̎��S�Ґ����ł��������ʂ͑咰�ł��B �@�����ō���͍����������i�č��j�Ȃǂ̏����Q�l�ɁA�咰���X�N�����߂Ă��܂������K�����܂Ƃ߂܂����B ��1�F��������������ł��� �@���������݂�����ƁA�咰���X�N�����܂�Ƃ����Ă��܂��B�u���݂������Ăǂ̂��炢�H�v�Ƃ������A�����������i�č��j�ɂ��A1����3�t�ȏ�̃A���R�[�����v���ӂ��Ƃ��I �@�����A�����͐��܂�Ȃ���ɂ��ăA���R�[������������\�͂��j����荂���Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B���̈Ӗ��ł́A�����Ă��������x�ɂƂǂ߂Ă݂ẮH ��2�F�^�o�R���z���Ă��� �@�����������ɂ��A�^�o�R�͑咰����̎��S���X�N�����߂�Ƃ���Ă��܂��B �@���E�ی��@�ցiWHO�j�̊O���g�D�ł��鍑�ۂ����@�ւ���́A�咰�݂̂Ȃ炸���܂��܂ȕ��ʂ̂��X�N�����߂�Ǝw�E����Ă��܂��B �@�i���҂͍������։����J�n���A�����łȂ��l������̐l�̉��ɒ��ӂ������ł��ˁB ��3�F�^���s���������Ĕ얞�ɂȂ��Ă��� �@�^���s����얞�͑咰���X�N�����߂�ƁA�e��̌����@�ւ���x�����o����Ă��܂��B �@���E�ی��@�ցiWHO�j�ɂ��A�H������A������A�t������Ȃǂ̃��X�N�܂ō��߂�Ƃ��B�^���s�����Â����Ă͂����Ȃ��̂ł��ˁB ��4�F����\�[�Z�[�W�A�n���Ȃǂ��̂悤�ɐH�ׂĂ��� �@�ԓ���\�[�Z�[�W�A�n���Ȃǂ̉��H����H�ׂ�����ƁA�咰���X�N�����܂錤�����ʂ��o�Ă��܂��B �@�����������i�č��j�͂����܂ł��g�\���h�Ƃ����͈͂ŐG��Ă��܂����A���E��������ƃA�����J��������ɂ��A�g�m���ȁh���X�N�v�����Ƃ���Ă��܂��B �@���Ȃ݂ɍ��������Z���^�[�i���{�j�̌����ł́A���ޑS�̂̐ێ�ʂ������Ƃ����ʂ�1��100g�ȏ�Ƃ��Ă��܂��B100g�Ƃ́A�ӊO�Ƃ����ɐێ�����Ă��܂������ȗʂł���ˁB �@�����̗l�ɁA�ԓ�����H����H�ב�����悤�Ȑ����́A������ƋC�������������������c�c�B �@�ȏオ�咰���X�N�����߂鐶���K���ł������A�������ł������H�@�ߋ��ɑ咰������������Ƒ�������ꍇ�́A���������C���������ł��ˁB ���C�u�h�A�j���[�X 2016�N3��14�� |
|
�����j���O�@�V�����I����Ƃ���זE���k������ �A�h���i��������ł݂Ȃ���u�퓬�́v |
| �@�E�H�[�L���O�ƕ���ŁA�����ɐl�C��2��X�|�[�c�̃����j���O�B�F�m�ǂɂȂ�ɂ����A�V����x�点��A���邭�O�����ɂȂ�......�ȂǑ����̌��N���ʂ����邪�A�ŋ߁A����זE���k��������Ƃ������������������\���ꂽ�B �@�܂��}�E�X�̎����i�K�����A���ׂ̋����^��������ƕ��傳���A�h���i�������A�Ɖu�V�X�e���̍U�����u�i�`�������L���[�זE�iNK�זE�j�v�������������A����זE�����ł����邽�߂��B�����i�[�ɂƂ��đ���y���݂��܂��������B �����j���O�̌��N���ʂ��܂�1������ �}�E�X�̎����ł́A����זE��50���k�܂��� �@�������܂Ƃ߂��̂́A�f���}�[�N�E�R�y���n�[�Q����w�̃y���j�[���E�z�C�}�����m��̃`�[���B�ԂŃ����j���O�𑱂����}�E�X�́A�����^�������Ȃ������}�E�X�ɔ�ׁA����זE��50�����k�������Ƃ����������ʂ��A���ۈ�w���u�Z���E���^�{���Y���v�i�d�q�Łj��2016�N2��16�����ɔ��\�����B �@�`�[���́A�A�h���i����������זE�ɋy�ڂ��e���ׂ邽�߁A�x����A�̑�����A�畆����Ȃ�5�̂���ɂ��������}�E�X���A���ꂼ��ԂŃ����j���O����O���[�v�Ɖ^�������Ȃ��O���[�v��2�ɕ������B�l�Ԃ������j���O������ƃA�h���i���������傳��邪�A���̏�Ԃ��Č����邽�߁A�����j���O�g�̃}�E�X�ɐl�ԕ��݂̗ʂ̃A�h���i�����𒍎˂����B �@���̌��ʁA�����j���O�g�̃}�E�X�́A�^�������Ȃ������}�E�X�ɔ�ׁA5��ނ̂���זE�̑傫�������ς�50���k�������B����זE���U������NK�זE���A�h���i�����ɂ���đ����������炾�B�}�E�X�̑̓��ׂ�ƁANK�זE�����t�̒����ړ����A����זE��T�����ĂďW���A�U������l�q���ώ@���ꂽ�B �@����NK�זE�����R�����}�E�X���g���A�����j���O��������������������A����זE�͏k�����Ȃ������B�܂��A�A�h���i�����̓������~�߂��}�E�X�ɂ������������������A��͂肪��זE�͏k�����Ȃ������B�����j���O�ł����}������ɂ́A�\���ȃA�h���i�����̕����NK�זE���K�v���Ƃ킩�����B �@�Ƃ���ŁA�Ȃ��A�h���i����������זE���k��������̂��B�悭���s�܂̃R�}�[�V�����ȂǂɁu�A�h���i�����o���`�I�v�Ƃ����L���b�`�R�s�[������B�A�h���i�����́A�R���ŃN�}�ɑ��������̂悤�ɁA�����A���|�A�{��A������ԂɂȂ�ƕ��t���番�傳���B�u���̊�@�v�̎��ɔ��˓I�ɏo�邽�߁u�����z�������v�ƌĂ��B���ɂ����u�Ύ���̔n���́v�̌����B���ꂪ�A����זE��E�C���X���U������NK�זE�𑝂₵�Ċ������A�u�����́v�ɉ�����킯���B �u���v�Ɓu�E�ҁv�̋��͌R���u����זE�v����U�� �@�����`�[���͍���A�C���^�[���C�L��6�iIL-6�j�Ƃ����Ɖu�`�B���q���A�A�h���i������NK�זE�́u����זE���ŋ������v�Ɉ���Ă��邱�Ƃ������BIL-6�́A�����j���O�Ȃǂ̋����^��������Ƌؓ��g�D������o�����B���b��R�Ă�����A���ǂ̉��ǂ�h������A�̂ɂ�������������̂����A����Ƃ̊֘A�͂킩���Ă��Ȃ������B�Ƃ��낪�A�Ȃ��NK�זE������זE�̏ꏊ�Ɉē�����K�C�h���߂Ă������Ƃ����������B �@�uIL-6������̔��ǒn�_�܂�NK�זE���؋�������܂��B��X�ɂƂ��āA���̃��J�j�Y���͋����ł����B�Ȃ�IL-6������Ȗ�����������̂��A����̌����ۑ�ł��v�ƁA�z�C�}�����m�͌���Ă���B �@�܂�A���������}�����B�����j���O������ƃA�h���i���������傳��A����זE���a�鎘�uNK�זE�v��������B����A�ؓ����炪��זE�̉B��ꏊ��˂��Ƃ߂�E�ҁuIL-6�v�����o�����B���邱�ƂŁA���ƔE�҂����X�Ƃ���זE�ގ��ɏ��o���Ă����킯���B �@�z�C�}�����m�́u�}�E�X�̎����i�K�ł����A�A�h���i�������\���ɕ��o����^�����A����זE�̏k���ɗL���ł��邱�Ƃ�������܂����B����܂ŁA���҂ɂǂ�ȉ^�����������A�h�o�C�X����̂���������ł����A�����j���O�̂悤�Ȃ�����x���ׂ̂���^�������߂��܂��v�ƌ���Ă���B J-CAST�j���[�X 2016�N3��14�� |
|
1�^���A�a�ł��X�N�͍��܂�̂��H �����ɂ��قȂ�Ɣ��� |
| �@1�^���A�a���҂ł́A��ʏW�c�ɔ�ׂĔ��Ǖp�x�����܂邪�������ŁA�ꕔ�̂���ł̓��X�N���ቺ���邱�Ƃ��A�V���������Ŏ����ꂽ�B1�^���A�a���҂ł́A�݂����̑�����A�X������A�q�{�̂���A�t������̔��ǃ��X�N�͍��܂邪�A�O���B����������̃��X�N�͒ቺ���Ă����Ƃ����B���̒m���́A�uDiabetologia�v�I�����C���ł�2��29���f�ڂ��ꂽ�B �@�������҂�1�l�A�p�G�W���o����w�i�X�R�b�g�����h�j������Sarah Wild���ɂ��A�����ꂽ���X�N�̌X����2�^���A�a��얞�̊��҂ł݂�����̂Ɨގ����Ă���A�C���X�������Âł��X�N���㏸����\���͏��Ȃ��Ƃ��Ă���B �@�Ȃ��A�����́A����̒m����1�^���A�a�Ƃ��X�N�̊֘A���������������ŁA�����̈��ʊW���ؖ��������̂ł͂Ȃ��ƒf���Ă���B �@�ă����e�t�B�I�[����ÃZ���^�[�i�j���[���[�N�s�j�Տ����A�a�Z���^�[���߂�Joel Zonszein���́A�u����̌����ł́A1�^���A�a���҂ł��X�N���㏸���闝�R����������Ă��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���A�S�Ώۊ��҂��C���X�������Â��Ă���A�Ώێ҂̒���2�^���A�a���҂����݂��Ă����\��������Ƃ��w�E���Ă���B �@���̌����ł́A�I�[�X�g�����A�A�f���}�[�N�A�t�B�������h�A�X�R�b�g�����h�A�X�E�F�[�f����5�J������1�^���A�a���҂̃f�[�^�����W�����B����1�^���A�a�̊��ҏW�c�ƈ�ʏZ���̏W�c�Ƃ̊Ԃł��Ǘ����r�����B3900���l�E�N�̒ǐՊ��Ԓ��A1�^���A�a���҂̂�����9,000�l������ǂ����B �@���̌��ʁA�j����1�^���A�a���҂ł͂���S�̂̃��X�N�㏸�͔F�߂��Ȃ��������A�����ł�7���̃��X�N�㏸���F�߂�ꂽ�BWild���ɂ��ƁA�j���ł͑O���B���X�N��44���ቺ���Ă���A����ɂ��S�̂̂��X�N�ɏ㏸���݂��Ȃ������Ƃ��Ă���B�O���B����������Ƃ������j���œ��ٓI�Ȃ������͂��珜�O����ƁA����S�̂̃��X�N�͒j����15���A�����ł�17���㏸���Ă����B �@�����ޕʂɂ݂�ƁA�݂��X�N�͒j����23���A�����ł�78���㏸���A�̑����X�N�͒j����2�{�ɁA�����ł�55���㏸���Ă����B����ŁA�����̓����X�N��10���ቺ���Ă����B�������A�����̂���͔��Ǖp�x���Ⴍ�A���ۂ̃��X�N�͂킸���Ȃ��̂��Ƃ����B �@�܂��A���X�N��1�^���A�a�̔��ǒ���ōł������Ȃ�A1�^���A�a�Ɛf�f��1�N�ȓ��̂��X�N�͒j���Ƃ�2�{�ȏ�ɏ�����B���A�a��a���Ԃ������قǂ��X�N�͒ቺ���A�j���̏ꍇ�͐f�f����20�N��A�����ł͐f�f����5�N��Ɉ�ʏW�c���x���ɂ܂Œቺ���Ă����B�������A�f�f��Ƀ��X�N�����������̂́A�����̂����o���ꂽ���Ƃɂ��\��������Ƃ����B �@2�^���A�a�Ƃ͈قȂ�A1�^���A�a�͐����K���ɂ͊֘A���Ă��Ȃ����A�u�։��⌸�ʁA�^���Ȃǂ̐����K���̉��P�͂��X�N�̒ቺ�ɂȂ�����̂ŁA1�^���A�a���҂ɂƂ��Ă��d�v���v�ƁAWild���͏q�ׂĂ���B m3.com 2016�N3��14�� |
|
�^�o�R��������Ȃ��I ���S�Ґ�1�ʁu�x����v���X�N�����߂�NG�K��3�� |
| �@���{�l�̎�Ȏ����������������ł����H�@���E��s���̎��̂������ƁA20�ォ��80��̑S�N��Łg����ɂ�鎀�S�h�������Ɣ��\����Ă��܂��B �@����̎�ޕʂɌ���ƁA�ł����S�Ґ��������������ʂ�2013�N�ł͒j�����v�Ŕx���ő��ɂȂ��Ă��܂��B �@�����ō���́A�����������i�č��j�␢�E�ی��@�ցi���A�j�Ȃǂ̏�����ɁA�x���X�N�����߂Ă��܂�NG�K�����܂Ƃ߂܂��B ��1�F�i�������Ă���^�Ƃ�E��ŒN���̃^�o�R�̉����z���Ă��� �@�x����̃��X�N�����߂�m���ȗv���́A��͂�i���B �@�������z���Ă���ꍇ�͂������A�Ƒ���E��ŒN�����z���Ă���^�o�R�̉����ԐړI�ɋz���Ă���ꍇ���A�x���X�N�����߂�ƕ������Ă��܂��B �@���肪�z���Ă���ꍇ�́A�i���ꏊ��ς��Ă��炤�ȂǓ������������ł��ˁB ��2�F�t���[�c�����\���ɐێ悵�Ă��Ȃ� �@�t���[�c�����\���ɐێ悷��ƁA�ꕔ�̌����Ŕx����̃��X�N����������Ƃ������ʂ������Ă��܂��B �@���E��������Ȃǂ��A�ʕ��̐ێ悪�x�����\�h���Ă����\��������Ə��\���Ă��܂��B �@���E�ی��@�ցi���A�j�́A�\���Ȗ��ʕ������ɂ���ƁA���o�i���������j����A�H������A�݂���A�咰����i�����A�����j�Ȃǂ�\�h�ł���\���������Ƃ��Ă��܂��B �@��������H�ׂĂ����͂��܂���̂ŁA�ӎ��I�Ȑێ��S�|�������ł��ˁB ��3�F�^���s���������Ă��� �@�ꕔ�̌����ł́A�\���Ȑg�̊������x�����\�h���Ă����\����������Ă���Ƃ��B �@�m���ɗ\�h������ʂ��Ȃ��Ă��A�\���ȉ^���͌��N�ɑ傫�ȃ����b�g������܂��B���E�ی��@�ցi���A�j�␢�E��������ɂ��A�g�̊����͑咰�����\�h����Ƃ���Ă��܂��B�܂��A��������\�h���Ă����\���������Ƃ��B �@�H������ȂNJe��̂��X�N�����߂���얞�̗\�h�ɂ��Ȃ����肵�܂��̂ŁA���ЂƂ��^�����n�߂����ł��ˁB �@�ȏ�A�x����̃��X�N�����߂鐶���K�����܂Ƃ߂܂������A�������ł������H�@�x����ȊO�̕a�C�̗\�h�ɂ��𗧂��܂��̂ŁA���ӂ��Ă݂Ă��������ˁB �����A���[�o�j���[�X 2016�N3��16�� |
|
��p�ʃA�X�s�����̕��p�ňꕔ�̂��X�N���ጸ ���ɑ咰�E�����ǂ���ŋ������� |
| �@��p�ʃA�X�s���������p���邱�Ƃɂ��A�咰����A�����ǂ�����͂��߂Ƃ��āA����S�̂̃��X�N��3���ጸ����\�������邱�Ƃ����ꂽ�B�������A�։v���F�߂���̂�6�N�ȏ㕞�p�����ꍇ�Ɍ�����Ƃ����B �@�A�X�s�����͂���������N��������̐����w�I�o�H�ɍ�p����ق��A���ǂ┭���`�����̗ʂ��y������ƁA�ă}�T�`���[�Z�b�c�����a�@�i�{�X�g���j��Andrew Chan���͐������Ă���B �@�uJAMA Oncology�v�I�����C���ł�3��3���f�ڂ��ꂽ����̌����́A�A�X�s�����̕��p�Ƃ��X�N�ጸ�̊֘A�������ɂƂǂ܂�A���ʊW�𗠂Â�����̂ł͂Ȃ����A���̌����ł����l�̌��ʂ������Ă���Ƃ����B �@�t���_���̒��҂�1�l�ł���ăe�L�T�X��wMD�A���_�[�\������Z���^�[��Ernest Hawk���́A�u�{�����́A�S�؍[�ǃ��X�N�̒ጸ��߉����ÁA�u�Ɋɘa�ȂǁA���̗��R�ŃA�X�s�����p����l�ɂ����āA�����ǂ���A�咰���ጸ���邱�Ƃ���������V���Ȓm���ł���v�Əq�ׂĂ���B �@����̌����ł́A�Ō�t���N�����iNHS�j����ш�Ï]���ҒǐՒ����iHPFS�j�ɎQ������13���l���̒j����ΏۂƂ��āA�A�X�s�����Ƃ���̊֘A�����������B30�N�ȏ�̒ǐՊ��ԂŁA����8��8,000�l���̂���2���l���A�j��4��8,000�l��̂���7,500�l��������ǂ����B �@��p�ʃA�X�s�������T2��ȏ㕞�p�����ꍇ�A�A�X�s���������I�ɕ��p���Ă��Ȃ������ꍇ�ɔ�ׂĂ���S�̂̃��X�N��3���Ⴍ�A�����ǂ����15���A�咰�����19���̃��X�N�ጸ���݂�ꂽ�B�������A������A�O���B����A�x����Ȃǂ̎�v�Ȃ���̃��X�N�ጸ�͔F�߂��Ȃ������B �@�܂��A�A�X�s���������I�ɕ��p���邱�Ƃɂ��A�咰�������ɂ��X�N���[�j���O���Ă��Ȃ��ꍇ��17���A�Ă���ꍇ��8.5���̑咰�����\�h�ł���\��������Ƃ����B �@�č�����iACS�j��Eric Jacobs ���ɂ��ƁA������͌��݂̂Ƃ���A�X�s�����̎g�p�ɂ��āA�^���������\�����Ă��Ȃ��Ƃ����B�S�؍[�ǂ�]�����̊����̂���l�́A��ʓI�ɃA�X�s��������������邪�A�����łȂ��l�́A�ݏo���Ȃǂ̃��X�N�Ǝ����\�h�̕։v�Ƃ̃o�����X����������K�v������Ɠ����͏q�ׂĂ���B �@�A�X�s�����p���ׂ��������Ă���l�́A�܂���t�ɑ��k����悤Jacobs���͊��߂Ă���B�܂��A�A�X�s�����p���Ă��Ă��咰����X�N���[�j���O���Ȃ��Ă悢�킯�ł͂Ȃ��Ɠ����͏q�ׁA�u50�Έȏ�̐l�͂���Ȃ��咰�����ɂ��Ĉ�t�ɑ��k���ׂ����B�|���[�v�����������ɂȂ�O�ɐ؏��ł���v�Ɛ������Ă���B m3.com 2016�N3��17�� |
|
�咰����́u���w�\�h�v�ɓ��A�a���ÖL�p�ȉ\�� ���l�s����̌����O���[�v�����\ |
| �@���A�a���Ö�̃��g�z���~���p����ƁA�咰�B��؏���ɁA�����郊�X�N�������B��̐V�K���ǂ���эĔ������}�������Ƃ̌������ʂ��A���l�s����w�̒_�X������a�w�̒����~���炪�����B�����Ȋ�����ɂ��咰����́u���w�\�h�v�̎����ɂȂ�����̂Ɗ��҂����B�ڍׂ́A�uLancet Oncology�v�I�����C���ł�3��2���f�ڂ��ꂽ�B �@����o�ł͐��E���ŋi�ق̉ۑ�Ƃ���Ă���B�Ȃ��ł��咰����́A�����K���̉��ĉ���w�i�ɂ킪���ł����Ґ����}�����Ă���A�V���ȑ��߂��Ă���B �@��������́A����̋��ɂȑ�͗\�h�ɂ���Ƃ��A��܂�p�����u���w�\�h�v�ɒ��ځB����܂ŁA���A�a���Ö�̃��g�z���~���ɂ��咰����}�����ʂ��������鐔�����̌���������Ă�����̂́A��b�������x���̌��ʂɂƂǂ܂��Ă������Ƃ���A����A�咰�|���[�v�؏��p���{�s�������҂�ΏۂɁA�p��̃��g�z���~�����^�̗L�����ƈ��S�����������郉���_�����v���Z�{�ΏƓ�d�ӌ��f�U�C���̔�r���������{�����B �@�Ώۂ́A�咰�B��܂��̓|���[�v��������Ő؏������A�a����151�l�B�Ώۊ��҂����g�z���~��250mg/���p����Q�i79�l�j�ƃv���Z�{�p����Q�i72�l�j��2�Q�Ƀ����_���Ɋ���t�����B����J�n����1�N��ɓ��������������{���A�咰�O����a�ςł���B��܂��̓|���[�v�̐V�K���Ǘ��A�Ĕ������r���������B �@���̌��ʁA����J�n����1�N��̑B��̐V�K���ǂ���эĔ����́A�v���Z�{�Q�ɔ�ׂă��g�z���~���Q�Ŗ�40���L�ӂɒቺ���Ă����i30.6����51.6���A���X�N��0.60�A95���M�����0.39�`0.92�AP��0.016�j�B�咰�|���[�v�̐V�K���ǂ���эĔ��������l�ɁA�v���Z�{�Q�ɔ�ׂă��g�z���~���Q�Ŗ�33���Ⴂ���Ƃ��킩�����i38.0����56.5���A��0.67�A0.47�`0.97�j�B�Ȃ��A���g�z���~���̕��p�ɂ��d�ĂȗL�Q���ۂ͔F�߂��Ȃ������B �@������́u�咰�B��₪���؏�������X�N�͍����Ƃ���Ă���A���g�z���~���̕��p���咰���X�N�̒ጸ�ɂȂ���ƍl������v�Əq�ׂĂ���B�܂��A������HealthDay�̎�ނɉ����A���g�z���~���͉��w�\�h���4�̕K�{�����i����p�����Ȃ��A��p�@�������炩�A���p���₷���A�����j�����Ă��邱�Ƃ���A�u�S�؍[�ǂ�]�[�ǂ̗\�h�ɃA�X�s�������g���Ă���悤�ɁA����̗\�h�ɂ��A�n�C���X�N���҂ɂ͖�܂ɂ��\�h��������p�������̂����������Ȃ��ƍl���Ă���v�Ɗ��҂������Ă���B m3.com 2016�N3��18�� |
|
�咰���X�N��ጸ����6�̕��@ ���Ɍ��ʂƐg�̊������d�v�Ȗ��� |
| �@����Ɖh�{�w�̐��Ƃɂ��ƁA�咰���X�N���y�����邽�߂�6�̃X�e�b�v�����炩�ɂȂ��Ă���A����ɏ]���A�咰����Ǘ�̔����͗\�h�ł���Ƃ����B �@�č��̓��v�ł́A�咰����͂��S�����̑�2�ʂł���A���Ґ���3�Ԗڂɑ����B�č����������iNCI�j�̐���ł́A2016�N�̑咰���Ґ���13��4,000�����B�č���������iAICR�j��Alice Bender���́A�u����܂ł̌����ŁA�H���E�̏d�E�g�̊����ɂ���āA�č��̑咰�����50���͗\�h�ł��邱�Ƃ���������Ă���B����͖��N��6��7,200��ɑ�������v�Ƙb���Ă���B �@�G�r�f���X�ɗ��Â���ꂽ6�̕��@�͈ȉ��̒ʂ�B �@ ���N�̏d���ێ����A�����̎��b�ʂ��R���g���[������B�����̎��b�́A�̏d�ɂ�����炸�咰���X�N�㏸�Ɋ֘A����B �A �K�x�ȉ^�������I�ɍs���B�Ƃ̑|�����烉���j���O�܂ŁA���܂��܂Ȋ������l������B �B �@�ێ��̖L�x�ȐH�ו�����������ۂ�B1��������H���@��10g�i���ł����1�J�b�v��j��ۂ�ƁA�咰���X�N��10���ቺ����Ƃ����B �C �ԓ��̐ێ�ʂ����炵�A�z�b�g�h�b�O��x�[�R���A�\�[�Z�[�W�Ȃǂ̉��H���������B�����d�ʂŔ�r����ƁA���H���ɂ��咰���X�N�͐ԓ���2�{�ɂ��Ȃ�B �D�A���R�[���͎~�߂邩�A�T���߂ɂ���i�j����1��2�t�A������1�t�j�B �E�j���j�N�������Ղ�ۂ�B�G�r�f���X�́A�j���j�N�̖L�x�ȐH�����咰���X�N��ጸ���邱�Ƃ��������Ă���Ƃ����B �@3���͑S�đ咰����[�����ԁB����ɔ����č�����iACS�j�́A50�Έȏ�̐l�͑咰����X�N���[�j���O�ɂ��Ĉ�t�ɑ��k����悤���߂Ă���B�X�N���[�j���O�ɂ��Ǐo��O�ɂ�������A���Â��₷���Ȃ�A�����������܂�B m3.com 2016�N3��22�� |
|
�������҂̔D�P�o�Y����������J ��Ï��T�[�r�X�iMinds�j�A�K�ȏ��̂��������� |
| �@��Ï��T�[�r�X�iMinds�j�͂��̂قǁA�u�����҂̔D�P�o�Y�Ɛ��B��ÂɊւ���f�Â̎����
2014�N�Łv���I�����C���Ŗ������J�����B���B�̓K����ɂ�������T�o�C�o�[�̑����ɔ����A���{����E���B��Ì�����i�����{����E���B��Êw��j�Ȃǂ��ҏW�������̂ŁA�������҂̔D�P�o�Y���l����ۂɈ�Ï]���҂�������𐳂����������A�K�ɔ��f���đI����i�߂Ă����v���Z�X���Љ�Ă���B �@���̎�����́A����24-25�N�x���J�Ȋw������⏕���u�������҂ɂ�����D�s���ێ��̂��߂̎��ÑI������ъ��Ҏx���v���O�����E�W�K�C�h���C���̊J���v�ǂƓ��w����߂ĕҏW�����B���{�����w����B����ւ̒����œ������҂�8���߂����D�s���Ɋւ���b���f�@���Ŏ����o���Ȃ�������A�������҂ɔD�s���̖�肪�����Ă����B��È�ɃR���T���e�[�V�������s���Ɖ������B���オ24���ɂƂǂ܂����肵�����Ƃ�������쐬�̂��������ɂȂ����Ƃ����B �@������̑z�藘�p�҂́A������]�̂���������҂̐f�ÂɌg���������È�A���B��È�ƃ��f�B�J���X�^�b�t�Ƃ��Ă���B���҂ւ̏����Î҂̃R�~���j�P�[�V�����A�����Ɛf�f���ꂽ���҂̏����̔D�P�A������]��L����������҂ɑ�������ÂȂǁA5�̑區�ڂŌv31�̃N���j�J���N�G�X�`�����iCQ�j��ݒ肵�A�f�f������D�P���E�o�Y��̊Ǘ��܂ʼn�����Ă���B m3.com 2016�N3��23�� |
|
�����m�[�}7�����ňُ�Ȃق���F�߂��y�č�������z �����m�[�}�́u�ق���̐������Ȃ��v���Ƃ����� |
| �@�č�������iACS�j��3��8���A�ق��낪�����ƃ����m�[�}�i�������F��j���ǃ��X�N�������ƍl�����Ă������A�t�Ƀ����m�[�}�ɂ͂ق���̐������Ȃ��A7�����ňُ�Ȃق��낪�S���Ȃ��ꍇ������Ƃ��錤�����Љ���BADD�́A�ق���̐��Ɍ��炸�A����I�Ȏ��ȃ`�F�b�N�����߂Ă���B �@���̌����ł́A�����m�[�}����566�l��Ώۂɔ畆�Ȑ��オ�ق���̐��𐔂��A�i1�j����Ȃق���A�i2�j����Ɍ����邪�����m�[�}�̓����������ق���\�\�ɕ��ނ����B���̌��ʁA�����m�[�}���҂�66���͂ق��낪�S���Ȃ���20�����ŁA77���ɂ̓����m�[�}�̓����������ق���͑S���F�߂��Ȃ������B���̈���ŁA�����m�[�}�̓����������ق��됔��5�ȏ゠�銳�҂́A�\��̈����X�����m�F���ꂽ�B��������3��2����JAMA Dermatology���Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@�����҂�Alan C. Geller���́u�ق��낪������Ό��f����K�v���Ȃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�ق���̐��͕K����������I�Ȉ��q�ł͂Ȃ��v�ƌ��ʂ͂�����ŁA�u�畆�̐F�������l�́A�ق���̐��ɂ�����炸�S�����畆���f���A���ȃ`�F�b�N�̕��@���m���Ă����K�v������v�Əq�ׂ�B �@ADD�́A�畆�̎��ȃ`�F�b�N������1�x�A�S�g���f�鋾���g���Ė��邢�����ōs�����Ƃ𐄏��B�����ɂ������ʂ́A�苾�Ŋώ@�����߂Ă���B���ȃ`�F�b�N�̏ڍׂ͉��L�̒ʂ�B �yADD�����ȃ`�F�b�N�Ɋ��߂�u�����m�[�}�̓���ABCDE�v�z �@A�FAsymmetry�i��Ώ̐��j�@�ق���̕Б����قȂ� �@B�FBorder�i�Ӊ��j�@�Ӊ����s�N���A�������̓M�U�M�U���ĕs���ɂȂ� �@C�FColor�i�F���j�@�F���s�ψ�ŁA���F�⍕������������A�s���N��ԁA���A�Ȃǂŕ����邱�Ƃ����� �@D�FDiameter�i���a�j�@���a��6 mm���A���M�ɂ��Ă�������S������傫�������� �@E�FEvolving�i�i���j�@�g��X����`��F���̕ω����F�߂��� �@ADD�́A���ȃ`�F�b�N�ňُ킪����A�����ɔ畆�Ȑ���ւ̎�f�𐄏�����ƂƂ��ɁA��L�̓����Ɍ��炸�A�ȉ��̂悤�ȏǏ���ΐ���ɑ��k���邱�Ƃ����߂Ă���B �V�����o�����ق��� �ق��̕��ʂɂ�����̂ƊO�ς��قȂ�ق��� ����Ȃ������ꕨ �ق���̕Ӊ����锭�Ԃ�V���Ȏ�� ����݁A�ɂ݁A���� ���ݏo���◎���A�o���̏o�� m3.com 2016�N3��23�� |
|
�V�������u��Â̋ɘ_�A�펯�A��펯�v �����Ŋ�Ԃ��Ȃ�l�A�������ނƁu�������v�}���c�Ԃ��Ȃ�Ȃ��l���댯�A�ǂ����ׂ��H |
| �V�������^��w���m�A��t �@����́A�A���R�[���Ƃ���̘b�Ő���オ���Ă��܂��B2���ɏ����b���Y�E���m������Z���^�[��������`�q��Ì����������炪���\�����A��������Ŋ炪�Ԃ��Ȃ�l����ʈ����𑱂����80�܂ł�20���̐l���H����A�̂���ɂȂ�Ƃ������ɂ��Ăł��B���������������ɔ��\�����Ȃ̂ŁA�M�ߐ�������܂��ˁB �@���̕ɂ����āu��ʈ����v�Ƃ́A�A���R�[���̗ʂ�1���ʂ�46�O�����ȏ�ƂȂ��Ă��܂��B1����180�~�����b�g���ł�����A��13���̃A���R�[���x�̓��{���Ŋ��Z����ƁA���傤��2���ɂȂ�܂��B�r�[���̓A���R�[���x����5���Ȃ̂ŁA��1���b�g���ɂȂ�܂��B�炪�Ԃ��Ȃ�l���A�������{��2���܂��̓r�[��1���b�g�����T5���ȏ���ݑ������20���̐l��80�܂łɂ���ɂȂ邻���ł��B �@�������A�A���R�[����23�`46�O�����ŏT5���ȏ�ł́A20������5���Ɍ������܂��B�܂��A�炪�Ԃ��Ȃ�Ȃ��l����ʈ����i46�O�����ȏ���T5���ȏ�j���Ă�80�܂łɐH����A�ɂ��ł���m����3���������ł��B �@���̔��\���A�g��펯�N�h�́u�l�͊炪�Ԃ��Ȃ�Ȃ�����A���������ł�������3�������H����A�̂���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂��B�炪�Ԃ��Ȃ�l��7����1�̊m��������A����A���R�[�������ށv�Ǝ咣���Ă��܂��B�g�ɘ_�N�h�́u�l�͊炪�Ԃ��Ȃ邩��A��������A���R�[���ʂ�45.9�O�����ȉ��ƂȂ�悤�ɂ�������ƌv�Z���Ĉ��ށB46�O�����ȏ��20���A���ꖢ���ł�5�������璴�Ӗ�������s�ׂ��v�Ǝ������Ă��܂��B�g�펯�N�h�́A�u�e�l���قǂقǂ̗ʂ̂����������Ȃ߂�����Ȃ��́v�Ƃ����̂悤�ɑ�l�̃R�����g�ł��B �@�������낢�ł��ˁB�A���R�[���x���̍������������ޏK��������n��ɂ͐H���������A�Ƃ��������Ƃ�M�҂͈�w���̍��ɏK���܂����B�������A����̌����͒��ڂɔS�����A���R�[�����h�����Ă���������Ƃ����X�g�[���[�ł͂Ȃ��A�̂ɋz�����ꂽ�A���R�[�����H����A�̂���������N�����Ă���Ƃ������Ƃ������ł��B�����炱���A�A���R�[�����ӂł���l�A�܂�炪�Ԃ��Ȃ�Ȃ��l�̓A���R�[���̊Q�����Ȃ��A�A���R�[�����ӂł��Ȃ��l�A�܂�炪�Ԃ��Ȃ�l��1����46�O��������Ƃ���̔��������}���ɏ㏸���܂��B�Ƃ������A�炪�Ԃ��Ȃ�l�͗v���ӂƂ������b�Z�[�W�ł��ˁB ����ɂȂ�Ȃ��A���R�[���̐��������ݕ� �@�ł́A��펯�N�̂悤�Ɋ炪�Ԃ��Ȃ�Ȃ��l�́A�A���R�[���̗ʂɐ����͂Ȃ��̂ł��傤���B���̌����͐H���ƍA�̂���Ɋւ��āA�炪�Ԃ��Ȃ�Ȃ��l�͏��X����ł��A�炪�Ԃ��Ȃ�l���������T�����ꍇ�ƍ��͂��܂肠��܂����A�Ƃ������_�ł��B �@�A���R�[���͊�{�I�ɒ~�ϓłł��B�l���ꐶ�Ɉ��߂�A���R�[���̗ʂ͌��܂��Ă���Ƃ����Ă��܂����A���̗ʂ����炩���ߐ��m�ɒm�邱�Ƃ͂ł��܂���B�A���R�[�������݂�����ƁA�̉�����̍d�ρA�����Ċ̂���ȂǂŎ��S���܂��B�܂�H����A�Ɍ����Ă͑債�����ł͂Ȃ��炪�Ԃ��Ȃ�Ȃ��l�̈������A�̑����̂��̂ɑ���댯�͂���̂ł��B �@�̑���8�`9���̋@�\���Ȃ��Ȃ��Ă悤�₭�s����F�߂���Ƃ������܂��B���̊̈ڐA�ł͎����̊̑��̖�������āA�����ĈڐA�p�ɒ��܂��B����Ȃ��Ƃ����Ă��A�҂̊̋@�\�͂���قǖ�肠��܂���B�܂�A���\�ȗ\���\�͂��̑��ɂ͂���̂ŁA�u���ق̑���v�ȂǂƂ������܂��B �@�ɘ_�N��45.9�O�����̃A���R�[�������ނƂ����咣�ł����A���̐��������ЂƂ̊�ŁA���͐l���ꂼ��Ȃ̂ł��B�����āA45.9�O�����𐳊m�ɗʂ邱�Ƃ����\�ʓ|�ł��B�����A����Ȉ��ݕ��ł͂�����������������܂���B �@���_�́A�[�����Ȃ��悤�ɁA�A���R�[�����y���݂Ȃ��班�X�����������Ƃ��A�u���͕S��̒��v�Ƃ������鏊�Ȃ��Ǝv���܂��B�A���R�[���͒~�ϓłƂ������Ƃ�O���ɂ����āA�����g�̑̂Ƒ��k���Ȃ���A���ꂼ��̓K�ʂ͈̔͂Ŋy���݂܂��傤�B���ǁA�펯�N�̌����ʂ�ł��B ���V�������i�ɂ��݁E�܂��̂�j 1985�N �c��`�m��w��w������ 1993�`1998�N �p���I�b�N�X�t�H�[�h��w��w�����m�ے� 1998�N�` �鋞��w��w���O�ȂɋΖ� Business Journal 2016�N3��26�� |
|
���N�I�Ȑ����K���Łu����v�͖{���ɖh����̂��H 30�N�������������� |
| �@���{�l�̎��S�����P�ʂ̂���B���N�̌����Ŏ��Ö@�͂��Ȃ�̐i���𐋂��Ă��܂����A�܂��́u����ɜ��Ȃ����Ɓv����Ԃł���ˁB�wDr.�n�Z�̃N�X���ƃT�v�������g�̂��𗧂��ŐV���x�ł́A�����K��������̜늳���Ƃǂ̂悤�ɊW����̂�30�N�ɂ킽���Ē��������C�X���G���̃O���[�v�̕��Љ��Ă��܂��B ����ς�A�����h���ɂ͌��N�I�Ȑ����K������� �@��������ԋC�ɂȂ�a�C�͂���ƒs���ǂŁA���Ƃ����������Ɗ���Ă��܂��B�����ō����́A����ɂ��Ă̂��b���B �@����͑�\�I�Ȑ����K���a�̂P�ł��̂ŁA���N�I�Ȑ����K�����A����̗\�h�ɂ͈�ԂƂ������e�ł��B �@����͂���Ɖh�{�̊W����舵���Ă����厏Nutr Cancer���ɁA�C�X���G���̃O���[�v�iTel Aviv University�j���������̂ł��B �@�����ł́A30�N�Ԃɂ킽���Đ����K���Ƃ���늳���Ƃ̊֘A�ׂ܂����B1982�N�̌����J�n���ɁA���N�Ȓj��632���i40-70�j��ΏۂɁA�H��������g�̊����Ȃǂ̒����A�����A�̏d�A�g���A���t�������s���܂����B �@���̍ہA�P�N�ȓ��ɂ���Ɛf�f���ꂽ13���A����ыɒ[�Ȑێ�J�����[�̂S���͏��O����Ă��܂��B �@���̌�A����24.2�N�Ԃ̒ǐՒ��������Ƃ���146���i23.7%�j���A����ɜ�������Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B �@���ɁA�H�����e�Ȃǂ̐����K���Ɋւ����͂��s�����Ƃ���A��r�I�悭���ۂ��Ă���O���[�v�ł́A�قƂ�ǐۂ�Ȃ��Q�ɔ�ׂāA�S���X�N��38�����Ⴂ���Ƃ��������������ł��B �@�Ȃ��A�����[�����ƂɁA�ʕ������܂葽���ۂ�O���[�v�ł́A�t�Ƀ��X�N�̑������F�߂��Ă��܂��B �@�ȏ�̌��ʂ���A�����h�������K���E���C�t�X�^�C���Ƃ��ẮA �@BMI������͈� �@�^�o�R�͋z��Ȃ� �@�H���@�ۂƖ�̐ێ悪���� �@�^���K�� ���d�v�ł��邱�Ƃ�������܂����B �@�܂��A���̂悤�Ȍ��N�I�Ȑ����K���E���C�t�X�^�C�����s���A�S���X�N��37���ɒቺ����ƌ��_����Ă��܂��B �@����ς�A�����h���ɂ͌��N�I�Ȑ����K������ԂƂ�����ł��ˁB �܂��܂��j���[�X�I 2016�N4��12�� |
| ���F�̌��ł��҂̔�J���P���ėՏ����� |
| �@�j���[���[�N�s�̖@�������E�������_�E�N�E�B�`�F�b�N����i64�j�͌��t�̂���̈��ł��鑽����������̊��҂��B2014�N�ɉ��w�Ö@�ɂ�鎡�Â��A���זE�ڐA�����B���Â��n�߂�ƁA����Ȃ��Ȃ�A���_�I�ɂ����Ղ����B�d������A��Ɣ����Ă��āA�����ɉ��ɂȂ��ċx�ނ悤�ɂȂ����B �@�N�E�B�`�F�b�N����͍�N�A�}�E���g�E�T�C�i�C�E�A�C�J�[����ȑ�w�̗Տ������ɎQ�������B�����̖ړI�́A����I�ɖ��邢���F�̌����Ǝ˂��邱�Ƃő����̂��҂�Y�܂��Ă���ɒ[�Ȕ�J��C���̗������݂��ɘa�ł��邩�m���߂邱�Ƃ��B �@4�T�Ԃɂ킽���Ė���30���A�������F�̌�������ʂȏƖ����u�̋߂��ɍ������B���𗁂тĂ���Ԃ̓R�[�q�[������e���r�̃j���[�X�������肷�邱�Ƃ����������B�N�E�B�`�F�b�N����͂����ɏǏ�̉��P�����������B�ȑO���悭�����悤�ɂȂ�A�����̔�J�����P�����B�u�K�������������B���𗁂т�ƈȑO�������C�ɂȂ����v�B �@���߂̗Տ������ɂ�54�l�̂��҂��Q���B�������͖��邢�̔��F�̌����A�c��̔팱�҂͔��Â��Ԃ����𗁂т��B�����`�[���̃��[�_�[��1�l�ŁA�}�E���g�E�T�C�i�C�̎�ᇉȊw�������AHeiddis Valdimarsdottir�����挎�̕ĐS�g��w��c�iAPS�j�N����ŕ������Ԍ��ʂɂ��ƁA���F�̌��𗁂т����҂ł͗������݂̏Ǐ傫���ɘa���ꂽ���A�Ԃ����𗁂т��O���[�v�ɂ͎����I�ȕω��͌����Ȃ������B �@�}�E���g�E�T�C�i�C�̐S���w�҂œ��ȋ����̃E�B���A���E���b�h���́u�K�����҂͌����s�����邱�Ƃ��������Ă���v�Ƙb���B���Ö@�́u��J�ƋC���̗������݂����邪�҂ɑ傫�Ȍ��ʂ��������v�Ƃ����B���b�h�������̌����`�[���̃��[�_�[��1�l���B �@�G�ߐ����Q�iSAD�j�\�\���Ǝ��Ԃ��Z���Ȃ�~�ɋN���邤�\�\�⎞���ڂ��̉e���Ȃǂ��܂��܂ȏǏ�̎��Âɖ��邢�������ʂ����\�������邱�Ƃ͈ȑO���猤���҂��w�E���Ă����B�p�������_��w��̃I�����C�����u�u���e�B�b�V���E�W���[�i���E�I�u�E�T�C�J�C�A�g���[�E�I�[�v���v�͐挎�A����900�l�O�オ�Q������20�̌����ɂ��Ă̕��͂����グ���B����ɂ��ƁA���Ö@�͋G�߂���Ȃ��T�^�I�Ȃ��ɑ��Ă��u�lj��I�Ȏ��É���v�Ƃ��Ė𗧂\��������Ƃ����B �@�J���t�H���j�A��w�T���f�B�G�S�Z�̖��_�����\�j�A�E�A���R�����C�X���G�����ɂ��ƁA���Ö@�͑S�Ă̊��҂Ɍ��ʂ�����Ƃ͌�����Ȃ��B�d�x�̂��ɂ͌����Ȃ��\��������A�K���������]���̎��Ö@�̑���ɂ͂Ȃ�Ȃ����������A���Ö@�ɂ́u�K�����҂̐����̎������P������ݓI�ȗ́v������Ƃ����B�A���R�����C�X���G�����̓}�E���g�E�T�C�i�C�̌����`�[���ƘA�g���Ă���B �@���𗁂т�Ɗ��҂̋C����������郁�J�j�Y���͂܂����S�ɂ͉𖾂��ꂽ�킯�ł͂Ȃ����A���Ö@�͐����ɉe������u�T�[�J�f�B�A�����Y���v�ƌĂ��24���Ԏ����̐����̃��Y���Ȃǂɍ�p���Č��ʂ������炷�\��������ƍl�����Ă���BValdimarsdottir���ɂ��ƁA���҂͂��̃��Y��������Ă��邱�Ƃ������B �@�ŐV�̌����͂��҂̂��̒���ɒ��ڂ��A�팱�҂ɔ�J�̓x�����A���̏Ǐ�A�����Ɋւ�����ɂ��ẴA���P�[�g�������s�����B���̌��ʁA�S�Ă̊��҂����Â��K�v�Ȃقǂ̔�J�ɔY�܂���Ă��邱�Ƃ����������B �@�팱�҂͖���30���A��w���p�ӂ������ʂȏƖ��@��̋߂��ɍ���悤�w�����ꂽ�B�炩���18�C���`�i46�Z���`�j�̋�����45�x�̊p�x�ŋ@���u���A�����ƍ����Ă��邩����A�R�[�q�[������{��ǂ肵�Ă����܂�Ȃ��B�@�킪��������̖��邳��1�����N�X�B�Ⴆ�A�����̖��邳��200���N�X���������ʂŁA���ꂽ���ɉ��O���U�������1���`5�����N�X������ȏ�̖��邳�̌��𗁂т邱�ƂɂȂ�B�����`�[���͔팱�҂����A�ǂ̂��炢�̎��ԁA���𗁂т�����ǐՂ����B �@�����`�[���͕č�������������l������340���h���i��3��7000���~�j�̕⏕���Ō����Âɂ���5�N������̌������n�߂�B���̌��������҂̔�J�A�������݁A������Q�A�T�[�J�f�B�A�����Y���ɂ��čs���A�}�E���g�E�T�C�i�C�ƃ������A���E�X���[���E�P�^�����O����Z���^�[�ŕ����200�l�̊��҂��Q������\�肾�B �@�����Ɋւ��X���[���E�P�^�����O�̐S���w�҃L���T�����E�f���A�������́u����F�m�s���Ö@�����邪�A�i���Ö@�́j���Ɏ�y�v�Ƙb���Ă���B �@�}�E���g�E�T�C�i�C�̗Տ������ɔ팱�҂Ƃ��ĎQ�������j���[���[�N�̉f���ҏW�҃V���[���E�����A������́i48�j�͑�����������̎��ÂŔ����Ă����Ƃ����B��N�A���זE�ڐA�������Ƃ͔��͂���ɂЂǂ��Ȃ����B �@�͂��߂͌����Â̌��ʂ��^���Ă������������A���ʂ͂������B�����ω����������N�������߁A�������I���܂ŏǏǂ̒��x���P�������C�Â��Ȃ������B�u�i�����Â��j��߂�ƈႢ���������B�w�܂����Ă���x�Ǝv�����v�B �E�H�[���E�X�g���[�g�E�W���[�i�� 2016�N4��12�� |
| �얞���q�{�����Ɋ֘A�����p���� |
| �@���P�c�́u�p���������v�́A�얞���q�{����̑����Ɗ֘A���Ă���\��������ƌx�����Ă���B �@���������ɂ��ƁA1990�N��ɂ�10���l��19�l�̊����Ŏq�{����Ɛf�f����Ă������A2013�N�ɂ�10���l��29�l�̊����܂ő��������B �@�����҂�́A�얞�Ǝq�{����Ƃ̊֘A���͖��m�ɂȂ��Ă��Ȃ����̂́A���b����o��z���������e�����y�ڂ��Ă���\��������Ƙb���B�������A����Ɍ������K�v���ƔF�߂Ă���B �@�p���ł́A���N��9000�l���q�{����Ɛf�f����A��2000�l�����S���Ă���B �@�����҂�́A�ߋ�20�N�Ԃ̎��Ö@����Ő��������㏸���Ă�����̂́A�q�{����ɂ����鏗���̐����Ȃ������Ă���̂��A����Ȃ錤�����K�v���Ǝw�E�����B �@�p���������̃W���i�T���E���[�_�[�}�������́A�u�q�{����̏ǗႪ����قǂ܂ŋ}�����Ă���̂͌��O�����v�ƌ����A�u���ׂĂ̗��R�͕������Ă͂��Ȃ����A��3����1�̏Ǘ�͔얞�Ƃ̊֘A��������B���̂��߁A�q�{����̏Ǘᑝ���얞�x�̏㏸�ƘA�����Ă���͈̂ӊO�ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ��B �@���Ƃ�́A�]���Ȏ��b���o���z������������q���זE�̕����𑣂��A��ᇂ��`�������m���������グ�Ă���\��������Ǝw�E���Ă���B���̂ق��A�^���s����N��A��`�q�Ȃǂ��v�����Ƃ���Ă���B �@�p���O�q���ǁiPHE�j�̃A���\���E�e�b�h�X�g�[�����m�i�h�{�w�j�́A�u����߂���얞���ꕔ�̂���̃��X�N�����߂邱�Ƃ͕������Ă���B���̂��߁A�H�ׂ�ʂ�ێ�J�����[�A�����A���b�ɋC��t���邱�Ƃ͏d�v���v�Əq�ׂ��B ���Fhttp://www.bbc.com/japanese/36033990 WEDGE Infinity 2016�N4��13�� |
|
��̊ԐH�œ�����Ĕ����X�N�㏸ ��̐�H���Ԃ�13���Ԗ������ƃ��X�N��36������ |
| �@�钆�̊ԐH���D���ȓ����҂ł͍Ĕ����X�N�������\�����A�ăJ���t�H���j�A��w�T���f�B�G�S�Z�iUCSD�j���[�A�Y����Z���^�[��Ruth Patterson����̌����ł킩��A�����_�����uJAMA Oncology�v�I�����C���ł�3��31���f�ڂ��ꂽ�B �@���b�g��p�����ߋ��̌����ŁA��Ԃ̐�H���Ԃ������ƁA����̓]�A�s�ǂɂȂ��錌���l�㏸�A���ǁA�̏d������\�h�ł��邱�Ƃ�������Ă���B���̂���Patterson����́A1995�`2007�N��Women's Healthy Eating and Living�iWHEL�j�����i�����̌��N�I�ȐH���Ɛ����Ɋւ���Տ������j�ɓo�^���A�����̓�����Ɛf�f���ꂽ27�`70�̏���2,400�l���̃f�[�^�����������B �@���Ȑ\���ɂ��H���f�[�^��p�������ʁA�S�̂ł́A��Ԃ̐�H���Ԃ͕���12.5���Ԃ������B��Ԃ̐�H���Ԃ�13���Ԗ����̏����ł́A13���Ԉȏ�̏����Ɣ�ׂāA��7�N�Ԃ̒ǐՊ��Ԃɂ����������Ĕ����X�N��36�����������B �@�Ȃ��A�����ʂ̂���܂��͐V���Ȍ���������Ĕ��Ƃ݂Ȃ��A�ԐH�͌ߌ�8���ȍ~�ɂ����鍇�v25kcal�ȏ�̐ێ�Ƃ����B��H���Ԃ����������ł́A�ߋ�3�J���̌����l������HbA1c�Z�x���Ⴍ�A�������Ԃ����������B �@�������A��Ԃ̐�H���Ԃ̒����́A�ǐՊ��Ԓ��̓�����ɂ�鎀�S�A��������Ȃ����S�̃��X�N�ɂ͉e�����Ȃ������BPatterson���́A�u����̌����͐�H���Ԃ̒Z���ƍĔ��̊֘A�������o�����ɉ߂��Ȃ����߁A��H�𐄏�����ɂ͎����������B�������A�����͎�ᇂB������R���ƂȂ�\��������A�܂������̎���ʂ̕s�������X�N���㏸������Ƃ̊����͑����v�Əq�ׂĂ���B HealthDay News 2016�N3��31�� m3.com 2016�N4��15�� |
|
�ȂɈ�����Ă���j���͑咰�����������̎�f���������H ����A�����ł͌�����Ԃɂ�鍷�݂�ꂸ |
| �@����j���̏ꍇ�A�K���Ȍ��������𑗂�A�Ȃ����w���ł���ƁA�������ɂ��咰���f����\�����������Ƃ��A�ăV�J�S��w�V�N��w�E�ɘa��ÉȒ���William
Dale����̌����ł킩�����B �@55�`90�̑S�Ă̒j���J�b�v��800�g���������������ʁA�ߋ�5�N�Ԃ̑咰�����������̎�f���́A�����j���ł͓Ɛg�j���ɔ�ׂ�20���߂��㏸�����B����ɁA�����j���̎�f���́A�Ȃ��v�w�W���K�����Ǝv���Ă���ꍇ�͖�30���A�Ȃ����w���ł���ꍇ�͖�40���A���ꂼ��㏸���Ă����B �@����A���������̎�f���́A�v�̍K���x�ɂ�����炸�Ɛg�����Ɠ����x�ł���A�v�̊w���ō��������邱�Ƃ��Ȃ������B �@Dale���́A�u�����̉ƒ�ł͏�������Ô���Ǘ����Ă���B���̂��ߏ����́A�v�̌��N�Ɋւ���I�������z���A���肷��]�n�����Ǘ��҂ƂȂ�B�����ł͌����ɂ�錒�N�ւ̗��v�͂��܂�F�߂��Ȃ��������A����͏����̂ق����F�l�⑼�̐e���ȂǁA�v�ȊO�̐l�̏����𗊂��Ă��邽�߂ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă���B �@�z��҂̉e���ɂ��ė�����[�߂邱�ƂŁA�咰����X�N���[�j���O������ł��邩������Ȃ��B�č��ł́A�咰����͂��S�����̑�2�ʂ����A�����̃X�N���[�j���O�������Ă��Ȃ��l��40���߂��ɋy�ԁB�č����a�Ǘ��\�h�Z���^�[�iCDC�j�́A��{�I��50�Έȍ~��10�N���ƂɌ�������悤���߂Ă���B �@�u�����������ɂ���C���������ȂقǁA�v�Ɍ��N�I�ȍs�������Ă��炢�����Ƒ����A�Ȃ����͓I���ƍl���Ă���v�قǁA���̏����������\���͍����v��Dale���͘b���A���̒m������A�K�ȑ����Ɣz��҂̏���������A�j���̌��f��f���͌��シ�邱�Ƃ��������ꂽ�Əq�ׂĂ���B m3.com 2016�N4��18�� |
|
�m���Ă��������A����ɂȂ�₷��4�̌��� ���{�l�Ƃ���ɂ��� |
| �@���������J���@�l���������Z���^�[��2015�N�̔��\�ɂ��ƁA���{�ł͂���̜늳���͖�98����ɂ̂ڂ�Ƃ���A���̂���37���l�߂��̐l���S���Ȃ�Ɨ\�z���܂����B���{�l��3�l��1�l���A�������ŖS���Ȃ��Ă���Ƃ������Ă��܂��B �@����Ƃ����a�C�́A��̂ǂ�Ȍ����ŋN����a�C�Ȃ̂ł��傤���B����́A����̌����ɂ��ďڂ������Љ�܂��B 1.�i�� �@�ߔN�A���܂��܂Ȍ������ʂɂ���āA����͐����K���̉��P����\�h�ł���a�C�ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B �@����̈ꕔ�͈�`���̂��̂�����܂����A��`�q�I�ȗv�����������K���ɂ�����v���̂ق����傫���Ƃ���Ă��܂��B �@�����K���ɂ�����v���̒��ł��A�ł��e��������Ƃ���Ă���̂��i���ł��B �@�����͔����̂��镨���Ƃ��Ă��m���Ă���A�����̉��ɂ�400��ވȏ�̉��w�������܂܂�Ă��āA���̂�����60��ނɂ͔������m�F����Ă���Ƃ����Ă��܂��B �@�����̉��͋z���Ă���l�݂̂Ɍ��炸�A����ɂ���l���i���ɂ���đ̓��Ɏ�荞�ފ댯��������܂��B 2.�H���� �@�H�����ɂ����āA�����̎��߂��͈݂���A�M���߂���H�ו���A�X�p�C�X�Ȃǂ̎h��������h���H�ו��̐H�߂��͐H������̃��X�N�����܂�܂��B���ɂ���ؕs���⓮�����H�i�̉ߏ�ێ�A��ʂ̈���������������N���������ɂȂ���܂��B �@�܂��A���H�H�i�Ɋ܂܂�Ă���H�i�Y�����ɂ́A�����̂��镨�����܂܂�Ă���Ǝ咣����l�����܂��B �@��Ȕ������^����H�i�Y�����Ƃ��āA�}�[�K�����Ɋ܂܂�Ă���g�����X���b�_��A�n����x�[�R���Ȃǂ̉��H�Ɏg�p����锭�F�܂̈��Ɏ_�i�g���E���A�����̑���Ɏg�p����l�H�Ö����ł���A�X�p���e�[���Ȃǂ��������܂��B 3.�E�C���X��ۂȂǂւ̊��� �@����̎�Ȍ����́A�����K���ɂ����̂Ƃ���Ă��܂����A���̈ꕔ�̓E�C���X��ۂȂǂւ̊������e�����Ă���ꍇ������܂��B �@�E�C���X��ۂȂǂ�������N��������Ȃ���̎�ނƂ��āA�̉��E�C���X���炭��̑�����A�s�����ۂ��炭��݂���A�q�g�p�s���[�}�E�C���X�iHPV�j���炭��q�{��Ȃǂ��������܂��B 4.�X�g���X �@�X�g���X�́A����ɑ傫�ȉe����^���錴���Ƃ���Ă��܂��B �@�ʏ�͔������������_�f�i�_���X�g���X�j�͑��₩�ɏ�������܂����A�X�g���X�����܂�ƁA�̂����R�_���͈ȏ�Ɋ����_�f�����܂�₷���ƂȂ�̓��ɒ~�ς���邱�Ƃɂ���āA��`�q�������A����𑣐i������̂ł��B �@���ɁA40�Έȏ�ɂȂ�Ƒ̓��Ŋ����_�f�������₷���Ȃ�܂��B �����K���ɋC�����Ă����\�h���悤 �@���̂悤�ɁA����͎��B�̓��X�̐����K���̐ςݏd�˂��啔���̌����ɂȂ��Ă���̂�����ł��B �@�i��������͂Ȃ�ׂ��T���A�o�����X�̂悢�H������邱�Ƃ�A��������X�g���X�����߂Ȃ��悤�Ȏ��Ԃ̎g���������邱�Ƃ���ł��B�������ł��邱�Ƃ��琶���T�Ԃ����������ƂŁA����̗\�h��S�����Ă����܂��傤�B health�N���b�N 2016�N4��13�� |
| 1��2�t�ȏ�̃R�[�q�[�Œ������50�����h���邱�Ƃ����炩�� |
| �@�݂Ȃ����1���ɉ��t�̃R�[�q�[�����݂܂����H �@���͖ڂ��o�܂����߂ɁA�d�����͏W���͂����߂邽�߂Ɉ��ނ����������Ǝv���܂����A�R�[�q�[��1��2�`3�t���ނ����ŁA���̂��h����Ƃ����������\����܂����B ��1�����t�̃R�[�q�[�Œ��̂��X�N�������� �@�A�����J�̓�J���t�H���j�A��w�ŁA����ق�̐��t�̃R�[�q�[�ő咰����Ⓖ�����h����Ƃ����V�����������ʂ��o���̂ł��B �@���̂���́A�A�����J�ł͒j���Ƃ��ɂ�����₷������̑�3�ʁB���{�ł�1980�N����ɂ���ׁA���ɑ咰����̎��S�Ґ��͒j���Ƃ��ɖ�3�{�ɑ����Ă��܂��B �@�������R�[�q�[�����ނ����ŁA���X�N�������邱�Ƃ��ł���Ȃ�A����Ȃ����b�͂���܂���B �����҂ƌ��N�Ȑl�̃R�[�q�[����ʂ��I �@�A�����J���w��ɂ��A����1�N������95,000�l�ȏオ��������ɁA39,000�l�ȏオ��������̐f�f���Ă��āA���̂���͈ˑR������X���ɂ���܂��B �@�����҂����́A�ߋ�6�����ȓ��ɒ��̂���Ɛf�f����5,100�l�̒j���ƁA���̂���̊������̂Ȃ�4,000�l�̒j���Ƃ�Ώۂɔ�r�����B �@�Q���ҒB��1���Ɉ��G�X�v���b�\��C���X�^���g�R�[�q�[�A�܂��A�m���J�t�F�C���̃R�[�q�[����уt�B���^�[�R�[�q�[�ȂǁA�ǂ�Ȏ�ނ̃R�[�q�[�ł����ׂĕ��邱�ƂɂȂ��Ă��������ł��B �@����ɁA���҂̉Ƒ����A�H�����A�^���Ƌi���̗L���������ׂ܂����B �@���̒������ʂɂ��ƁA�R�[�q�[�����ނ��ƂŁA���̂���̃��X�N�����炷���Ƃ��킩�����Ƃ����̂ł��B1����1�`2�t���ނ����ł��A���̂���̃��X�N��26��������A1����2�t�ȏ���ނ�50���܂ʼn����邻���ł��B ���J�t�F�C��������m���J�t�F�C�������ʂ͓��� �@����ɁA�J�t�F�C�����肩�m���J�t�F�C�����ɊW�Ȃ��A�ǂ���̃R�[�q�[�ɂ����X�N�����炷���ʂ����邱�Ƃ��킩��܂����B �@�R�[�q�[�Ɋ܂܂�鑼�̕������l�̒��̌��N�����߂Ă���悤�ł��B�J�t�F�C����|���t�F�m�[���͍R�_����p������A���ݓI�Ȍ�������זE�̐�����j��ł���̂ł͂Ȃ����ƌ����҂����͍l���Ă��܂��B �@���Ƃ��A�R�[�q�[�������̉ߒ��Ő����郁���m�C�W�������̉����𑣐i���A�܂��W�e���E�y���i�R�[�q�[�̃G�L�X�Ɋ܂܂��J�t�F�X�g�[���ƃJ�t�F�I�[���Ƃ��������j�ɂ͐l�̂̎_���I������h�����ʂ����邽�߁A����̔��a���Ƃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂ł��B ���ǂ�ȃR�[�q�[�ł����̂��X�N�����点�� �@���̌����_���̑�꒘�҂ł���X�e�t�@�j�[�E�V���~�b�g���m�́A�u�R�[�q�[�ɂǂꂭ�炢�K���Ɍ����������܂܂�Ă��邩�́A�R�[�q�[�̓��A�����A�������@�ɂ���ĕω����܂��B �@�܂��A�s���̂悢���ƂɁA�R�[�q�[���ǂ�ȃt���[�o�[�ł��낤�ƁA�ǂ�Ȍ`�Ԃł��낤�Ɓi���Ƃ��A�J�v�`�[�m��G�X�v���b�\�Ȃǁj�A�W�Ȃ����̂���ɂ����郊�X�N�����点��Ƃ������Ƃł��v�Əq�ׂ܂����B �@��J���t�H���j�A��w�Ƌ����ŁA���̌���������ɑ�K�͂ɐi�߂Ă���̂��C�X���G���̍������R���g���[���Z���^�[�̃��i�[�g���m�ł��B �@�u�C�X���G���ł́A�R�[�q�[�̏���ʂ��A�����J��菭�Ȃ��̂ł����A�o���G�[�V�����̓A�����J���������A���낢��ȃR�[�q�[������܂��B����ł����ʂ́A�A�����J�Ɠ����ł����v�Əq�ׂĂ��܂��B �@�O���o�[���m�́A�u�R�[�q�[������\�h�ɂȂ邱�Ƃ��ؖ����邽�߂ɂ́A����Ȃ钲���������K�v�ɂȂ�܂��v�Ƃ��A�Ō�Ɂu�R�[�q�[�����N�Ɉ��e���������炷���Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B �@�����̃R�[�q�[�����̂���ɂ����郊�X�N�����炷�\���������̂ŁA�R�[�q�[�D���̐l�ɂ͂ǂ�ǂ�R�[�q�[���y����łق����ł��v�Ƃ����Ă��܂��B �@���Č^�̐H�����蒅���Ĉȗ��A���{�ł��咰���҂͂��Ȃ��̂ڂ�ɑ����Ă��܂��B�������̌������ʂ��{���Ȃ�A�����̐l�̖����R�[�q�[�ɂ���ď����邱�ƂɂȂ邩������܂���B�݂Ȃ��������\�h�̂��߂ɁA�R�[�q�[�K����������Ă݂܂��H �E�[�}���G�L�T�C�g 2016�N4��18�� |
| �����h�����߂ɐۂ肽���ʕ� �������ʂȂǂ̌��ʂ� |
| �������茾���� �����h�����߂ɐێ悵�����ʕ����Љ�Ă��� �o�i�i�͂���̗\�h�͂������A�������ʂȂǂ̌��ʂ����҂ł���ƕM�� �H���@�ۂ��L�x�ŕ֔��\�h���咰�����h����p�̂���A�{�K�h��2�� �咰���ɂȂ肽���Ȃ��l�A�����ۂ𑝂₵�����l���ۂ�ׂ��ʕ��́H �@�G�߂̕ς��ڂɉ����A�V�N�x�ʼn����ƖZ�����̒�����������Ȃ��̎����B��y�ɐۂ��H�ו��ő̒������������ɂ����Ă������炱��قǂ��肪�������Ƃ͂Ȃ��ł���ˁB���������}�K�w���e�ƌ��N�ЂƂ��������x�ł́A���N�ێ�����K���a�ɖ𗧂A�ǂ��ɂł������Ă���ʕ����Љ�Ă��܂��B �n�����o�i�i�Ɛ��o�i�i �@�G�߂̕ς��ڂŋC���̕ω����������A�̒��Ǘ�������G�߁B������ԂƂ����厖�ȂƂ��ɑ̒�������Ȃ����߂ɁA�ǂ�ȋG�߂ł��̒����ێ����A���܂����邽�߂̎�y�ȐH�ו��Ƃ��Ē��ڂ���Ă���̂��o�i�i�Ȃ̂������B �@�o�i�i�́A�H���@�ۂ��L�x�ŁA�s�n���H���@�ۂƐ��n���H���@�ۂ�2��ނ����邻���ł����A�o�i�i�͂���2��ނ̐H���@�ۂ��܂�ł���炵���ł��B�ǂ���������̓��_�ۂ�r�t�B�Y�X�ۂ𑝂₵�Ă���A���ɐ��n���H���@�ۂ́A���ɗn����ƃQ����ɂȂ�A�����ŗ]���Ȏ����i�R���X�e���[���j���z�����ĕ�ݍ��ݕւƂ��đ̊O�֔r�����铭�����B �@���ɐ��o�i�i�ɂ́A�H���@�ۂƓ��������������������f���v���������܂܂�Ă��Đ������ʂ����҂ł���̂ŁA�֔�ɔY��ł���l�ɂ��X�X���������B���ɂ��A�|���t�F�m�[�����܂܂�A���b�̋z���}���A�����ቺ��p�A�V���}���A����̗\�h�A�������ʂȂǂ̌��ʂ����҂ł��A�|���t�F�m�[����ۂ肽����A�n�����o�i�i���I�X�X���Ƃ̂��ƁB �@�o�����X�������H����������A�̒��Ǘ��ɕs���������Ă�����A�o�i�i�������ł����B �@�u�X�̃o�^�[�v�Ƃ��Ă��A�{�J�h�́A���E��h�{���̍����ʕ��ŁA�R���X�e���[����������s�O�a���b�_�̃I���C���_��m�[���_�A���m�����_���͂��߁A�V���h�~�ɖ𗧂r�^�~��E��r�^�~��A�EC�A�J���E���A�}�O�l�V�E���A�����Ȃǂ̃~�l�����𑽂��܂�ł��邤���ɁA�A�{�K�h�̎��b�̓m���R���X�e���[���ł���A�����d���ǂ�\�h����s�O�a���b�_�Ȃ̂������B �@�Ȃ̂ŁA�����Ȃǂƈ���āA�R���X�e���[���̐ۂ肷����S�z����K�v���Ȃ��A�J���_�ɂƂ��Ă��̂������w���V�[�ȐH�ނ炵���ł��B �@�H���@�ۂ��L�x�ŕ֔��\�h���咰�����h����p������A�s�K���ȐH������_�C�G�b�g�Ȃǂʼnh�{���s���������ȕ��ɁA�܂������K���a�i���l�a�j��ɃA�{�K�h�͔��Ɍ��ʓI�ɓ����H�i�Ȃ̂������ł��B ���C�u�h�A�j���[�X 2016�N4��19�� |
|
���Ɖu�̎�����Ö@2017�N������ �O�d��A���N�`���ȂǑg�ݍ��킹 |
| �@�O�d��w�����I����Ɖu�Ö@�����Z���^�[�́A���N�`���A�A�W���o���g�A��ᇓ��ٓI�s�זE��e�́i�s�b�q�j���ςs�זE�A���̂R�̂���Ɖu�Ö@��g�ݍ��킹���s�����b���������Ö@���J�����A�Q�O�P�V�N�x���ɌŌ`����K����ڎw�������ɓ���\�肾�B�����ƂƂ̘A�g���������n�߂Ă���B���Z���^�[�̎��m�����́A�t�����Ȃǂɉۑ肪�w�E����Ă���Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q����鎟����̂���Ɖu�Ö@�ƈʒu�t���Ă���B �@�R�o�c�|�P�R�̂ȂǖƉu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��̓o��ł��Â��傫���ς��Ƃ݂�����̂́A�t�������҂ł��銳�ґw��������Ȃǂ̌��E���w�E����Ă���B�O�d��w�����I����Ɖu�Ö@�����Z���^�[�̌��c�������C�u�t�A������㏕���i���E�É�������w��w�����@�j��́A�����̎�_���������ׂ�������̕����I�Ɖu�Ö@�̊J����i�߂Ă����B �@���c����́A��ᇑg�D�̔��������Ɖu�I�ɕs�����ɂȂ��Ă��邽�߂ɖƉu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q�����Ȃ����Ƃ������������B�����Ń��N�`���ƃA�W���o���g��p���Ĕ������̖Ɖu�����������A�����ɂs�b�q���ςs�זE�A���Ö@��g�ݍ��킹�邱�Ƃ��l�Ă����B �@���N�`���́A�Ǝ��̃f�U�C���Z�p�ō����\�������y�v�`�h�R���ƁA��ᇑg�D�ɐZ�����Ă���}�N���t�@�[�W���R���זE�Ƃ��ė��p�ł���f���o���[�V�X�e���i���s��w��w�@�H�w�����ȁE�H�g�ꐬ�����Ƌ����J���j��p���ĐV�K�v�����B�A�W���o���g�͕a���̂����m����s�������l��e�́i�s�k�q�j�̃A�S�j�X�g�ƂȂ�b���f�I���S�c�m�`�i����Ռ������E�Έ䌒���[�_�[�J���j���g���Ă���B�}�N���t�@�[�W�̓��N�`���ƃA�W���o���g�ɂ���Ċ���������Ď�ᇑg�D���ōR�����s���A����ɂ���Ăs�b�q���ςs�זE�̎�ᇑg�D�ւ̐Z�����������ƍl���Ă���B �@�����R����l�I�A���`�Q���Ȃǂ̎�ᇑg�D�ɓ��ٓI�ɔ�������R���ɑ���s�b�q��`�q��g�ݍ��s�זE�͎�ᇂւ̍U���͂����߂��Ă���A�����̃R���r�l�[�V�����Ŏ��Ì��ʂ����܂�Ɨ\�z����Ă����B���ۂɃ`�F�b�N�|�C���g�j�Q��ɒ������ϐ���������ᇂ��ڐA�����}�E�X�ɓ��^����ƁA��ᇑg�D���قڊ��S�ɏ������Ă���A�������̖Ɖu�I�ȕs������Ԃ�ς��ċ��͂ȍR��ᇌ��ʂ��������Ƃ��m�F�����B �@��Տ����S�������Ȃǂ̎����Ɍ�����������i�߂Ă���A���Z���^�[�͒�g��ƂƋ��͂��ĂP�V�N�x�̎����J�n���v�悵�Ă���B�s�זE����p����זE�Ö@�͌��t���Âւ̉\���������Ƃ���Ă��邪�A���Z���^�[�̓��N�`���ƃA�W���o���g��K�ɑg�ݍ��킹�邱�ƂŌŌ`����ɂ��������鎡�Ö@��_���Ă���B �@�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��́A����̎����������҂ł��鎝���I���ʂȂǂ����ڂ���Ă�����̂́A�t�������Q�O�`�R�O���ɂƂǂ܂邱�Ƃ�A�X����A�咰����A�O���B����Ȃǂ����ɂ���Ă͌��ʂ��Ⴂ���Ƃ��ۑ�ɂȂ��Ă���B�s�����b���������Ö@�͂����������_�������ł���\��������B m3.com 2016�N4��25�� |
|
�����Ǘ��Ɗ��̃G�r�f���X�u�s�\���v ���{���A�a�w��E���{���w���������2������\ |
| �@���{���A�a�w��Ɠ��{���w��̍����ψ����4��21���A���A�a���҂̌����Ǘ��Ɗ��늳���X�N�ɂ��āu�����_�Ŏ��̍����G�r�f���X�͑��݂��Ȃ��v�ƌ��_�t����u���A�a�Ɗ��Ɋւ���ψ����2��v�����\�����B2013�N7���ɔ��\���ꂽ���̈ψ���ł́A���{�����ɂ�����u�w�̕]���Ɋ�Â��u���A�a���S�Ă̊��A�咰���A�̑����A�X�����̃��X�N�����Ɗ֘A���Ă����v�Ƃ̌����������Ă����B �@��2��ł́A���i�Ȍ����Ǘ��Ə]���^�̌����Ǘ��ɂ�錌�ǃC�x���g�̕]����ړI�ɍs��ꂽ7���̃����_������r�����iRCT�j�̊����S�܂��͊��늳���X�N�ɂ��Ẵ��^��͂Ɍ��y�����B �@4����RCT�iUKPDS33�AUKPDS34�AACCORD�AVADT�j��3.5-10.7�N�Ԃ̒ǐՊ��Ԃɂ���������S�̊����́A���i�����Ǘ��Q5��3892�l�N��222��A�]���Ǘ��Q��3��8743�l�N��155��B�ϗʌ��ʃ��f���ɂ�铝�����X�N���1.00�i95��CI 0.81-1.24�GI2��0���j�������B�ʂ�3����RCT�iADVANCE�APROActive�ARECORD�j��2.9-5.5�N�̒ǐՊ��Ԃɂ�������늳�̊����͌��i�Ǘ��Q4��7924�l�N��357��A�]���Ǘ��Q4��5009�l�N��380��œ������X�N���0.91�i95��CI 0.79-1.05�GI2��0���j�������B �@�������A������RCT�͊�����v�]�����ڂł͂Ȃ����ƁA�ǐՊ��Ԃ��\���łȂ����A��ӌ����������܂܂�Ă��邱�ƂȂǂ�����́u�����_�Ō����Ǘ��ɂ����늳���X�N��]�����鎿�̍���RCT�͑��݂��Ȃ��v�ƋL���Ă���B �@�ψ���ł͂���ɁA���`�A�X�E�F�[�f���A�č��ɂ�����3���̊ώ@���������r���[�������A�����R���g���[���Ɗ��늳���X�N�̊֘A�Ɉ�v�������ʂ͌���ꂸ�A�u�����_�ł͎��̍����u�w�������ʂ��W�ς��Ă��Ȃ��v�ƌ��_�B�u����A�Ȗ��Ɍv�悳�ꂽRCT��ώ@�����̎��{�����҂����v�Ƃ��Ă���B m3.com 2016�N4��28�� |
| �Ăɋ}�㏸����u���X�N�v��\�h����{�̐H�i�S�� |
| �@�u�{�H�ނɂ͂��̎��ɕK�v�Ȍ��N���ʂ�����v�Ƃ͂悭�����܂��B������ƑO�́A����̉��̉ԂȂǂ��{�H�ނŁA�g�V�p����r�����铭����������́h����������܂����B �@�����āA���ꂩ��Ăɂނ����Ĕ��������Ȃ�{�H�ނ́A��������̂�����Ă������̂���������o���܂��B�����A�Ă͏��������łȂ��g���X�N�g�����߂鎇�O���Ȃǂ̗v���������ł��I �@�܊p�ł���A�H������g���X�N�g�ɑ��Ă̌��N���ʂ����҂ł���Ɗ������ł���ˁH �@�����ō���́A�Ǘ��h�{�m�ł���M�҂��A�Ă̂��X�N�����߂�v���Ɓg����\�h�h�ɂȂ�{�̐H�i�ɂ��Ă��Љ�v���܂��B �����X�N�����߂�Ă̐����K�� �@�J���I�ȉĂ͊y�������Ƃ���������B�����A�C�����Ȃ��Ɓg���X�N�h�����߂邱�Ƃ�����̂ŗv���ӂł��I �@�ł͂ǂ�ȉĂ̏K�����A���X�N�����߂Ă��܂��̂ł��傤���H �i1�j�ăo�e �@�ҏ��������ߔN�A�ăo�e�ɂȂ�����������܂��B���ɓ�������^����d���ȂǂŊ������܂肩���Ȃ��l�́A�ăo�e���X�N�����܂�܂��B��ꂽ�͖̂Ɖu�͂��ቺ���₷���A���r��╗�ׂ��͂��߁A����ɂ͂���Ȃǂ̕a�C���X�N�����߂Ă��܂��܂��B �@�ăo�e�ŐH�~�s�U�ɂȂ�ƁA����זE�ɑł��������̂��牓�̂��Ă��܂��܂��B�����ĕ|���̂́A�ăo�e������Ă������ƁB �@�ăo�e�͐H�~�s�U����\�I�ȏǏ�ł����A�݂���̏Ǐ�ɂ����̐H�~�s�U������܂��B�u�H�~���Ȃ����ăo�e�v�Ǝv���Ă�����A�݂���ɜ늳���Ă����Ȃ�Ă��Ƃ�����܂��B �@�̒��Ɉٕς���������A���߂Ɉ�Ë@�ւɂ����悤�ɂ������ł��ˁB �i2�j���� �@�L���~�\�[����^���N�g�b�v�ȂǁA�����ɂȂ�G�߁B�������A�Ă͎��O����1�N�̒��ň�ԑ����G�߂ł�����܂��B �@1��15���قǂ̎��O���ł���Ζ��͂���܂��A�����Ԏ��O���ɂ�����A�V�~�ɂȂ�ǂ��납�畆�K���̃��X�N��啝�ɍ��߂Ă��܂��̂ł��B �i3�j���C���� �@���C�����Ŋy��������������Ƃ������G�߁B�����ŗ₦���r�[���������ȏ�ɔ������������܂���ˁB���ɉĂ�19�����ł����邢�̂ŁA���ݎn�߂��x���Ȃ�����A�����Ԃ̉���ɂȂ�����Ɛ[���ɂȂ�₷���̑��_���[�W����I �@�����ĉ���ƂȂ�ƃ^�o�R���z���l�������A�z��Ȃ��l�ł����l�̃^�o�R�̉��Ŕx���X�N�����߂Ă��܂��܂��B����ɁA�Y�Ƀ��[������H�ׂ�A���܂݂ƃ��[�����̉����ň݂��X�N�����߂܂��B �i4�j�₽���H�ו� �@�₽�����̂�H�ׂ�@����Ă͑����܂���ˁB���ɑ̂��₷�A�C�X�N���[����V���b�v�����Ղ�̂����X�͓����������Ղ�I �@����זE�͗₽�����̂ⓜ������D���Ȃ̂ŁA������p�ɂɐH�ׂ�ƁA����זE�����C�ɂ����Ă��܂����X�N�����߂Ă��܂��܂��B �����X�N��}����Ă��{�̐H�i4�� �@�����̂��X�N�̑����āA�{�H�ނ�ϋɓI�ɐH�ׂĂ���זE�ɑR�������ł���ˁH�@���ɃI�X�X���̐H�i��4���Љ�v���܂��B �i1�j�g�}�g �@��-�J���e�������Ղ�̃g�}�g�́A���X�����ĉĂɊۂ����肷��̂����������ł���ˁB���Ƀt�@�C�g�P�~�J����1�ł�����A�|���t�F�m�[����1��ł�����g���R�s���h�͍R�_���͂������A���C�ȍזE�����菕�������Ă���܂��B �@�I���[�u�I�C�����u�߂���A�~�L�T�[�ɂ����čӂ��X�[�v�Ƃ��Ĉ��肷��ƁA�h�{���������I�ɐۂ邱�Ƃ��ł��܂��B �i2�j�~���� �@�~�����͔�������Ă����g�N�G���_�h�𑽂��܂݂܂��B�Ă̔�ꂪ���܂��Ă��܂��ƁA��ӃT�C�N�����~���ɉ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����A�N�G���_�͂��̔������P���Ă���A��ӂ��グ�Ă���܂��B �i3�j�ɂ�ɂ� �@�H�~�s�U�̉ẮA����ɂ�ɂ������Ŋ��͂����������́B�l�X�Ȍ����ŁA�ɂ�ɂ���ێ悷�邱�Ƃɂ���āA�����X�N�ጸ�A�݂��X�N�ጸ�Ȃǂ��킩���Ă��Ă��܂��B�������A�ɂ�ɂ��͕č�������������������g����\�h�ɐ�������H�i�Q�h�̒��Ńg�b�v�N���X�̐H�i�ł��B �@�ɂ�ɂ��͐��̏�Ԃł����1��1�ЁA�K�[���b�N�I�C���ł�1��2?5g�i������1�j��ڈ��ɐH�ׂ�Ƃ����ł��ˁB �i4�j���傤�� �@���傤���́A�ɂ�ɂ����l�g����\�h�ɐ�������H�i�Q�h�ɑ��݂����B �@����ɁA���傤���ɂ͋����E�ۍ�p������̂ŁA�ăo�e�ő̗͂���܂�Ɖu�͂������肪���ȑ̂����C�ɂ��܂��B���̋����E�ۗ͂��A����זE�̑��B�⊈������h���ƌ����Ă��܂��B �@�Ă͂����߂���₵����ǂ�A��z�ȂǃV���v���ȗ����������ł����A���̂悤�Ȗ��g���Ȃ���H�ׂ�Ƃ����ł��ˁB ���K�����X�N��}����Ă̐����K�� �@�܂��A�Ă͑̂��₵�����Ȃ��悤�ɋC���������Ƃ���B�̂��₵�����Ȃ����Ƃ͉ăo�e�\�h�ɂ��Ȃ�܂��B �@���ɉ����g�����s�s�ǂɂȂ��Ă��܂��l�������̂ŁA�����g�͌����A�㔼�g�͊�{�����ł��\���܂��A�����肾���͉��߂�悤�ɕ��I�т�����̂��R�c�ɂȂ�܂��B �@��[���L�c���ꏊ�������̂ŁA�H�D���̂���Ɏ��������悤�ɂ���Ƃ����ł��ˁB�₽�����̂�H�ׂ����Ƃ́A�l�����x�̂��������ނ̂��I�X�X���ł��B �@�Ă͓��Ǝ��Ԃ������̂ł���X�������Ă��܂������ł����A�����̔�����������Ǝ�邽�߂ɂ��A���邳�ł͂Ȃ����v�����Ȃ��琶�����Y���𐮂��Ă����悤�ɂ���ƁA�[�������邱�Ƃ��Ȃ��A�ăo�e�\�h�ɂȂ�܂��B �@�������ł������H�@����͏{�̂���\�h�ɂ��Ă��Љ�v���܂����B��������̎�ނ̏{�f�ނ�H�ׂ邱�Ƃ��������̌��C�ȑ̂�����Ă���܂��I �@���ɁA�H�~�s�U�̂Ƃ��͌����H�ނ̑I�ѕ������Ă��������ˁB ���C�^�[�@�]�����b�q �����A���[�o�j���[�X 2016�N5��6�� |
| ����ɂȂ��Ă������c�邽�߂̕��@�@�܂���P�� |
| �@������҈�Â̂��̎���B�Q�V�N�O�ɂ͏Ǘ���x���������i�ƂĂ��������Ƃ������Ɓj���d��������O�̎���ɂȂ��Ă��܂��B�i�����ɂQ�ȏ�̈����V���������Ƃ������Ɓj�܂����͈�`�q�ُ�ł��邪��𑝂₵�܂��B �@����Ҍ��t�������҂̑��̂���̍������ŋ߂悭�o���킵�܂��B�i�x����A�݂���A�咰����Ɣ����a�A�����p��A������Ȃǁj����҂̂��ÁA�P�ł���ςł��B���ꂪ�Q�ȏ�ɂȂ�Ɩ{���Ȗ��Ȍv�悪�K�v�ɂȂ�܂��B �@�ł͊��҂���͂ǂ���������̂ł��傤�B�������ɂ��|�ꂻ���ȃ��{���{�̊��҂������Ƃ��܂��傤�B��Î҂͂����a�C�������Ă���Âł͎����Ȃ��V�����i�s���Ă��邱�Ƃ��l���A����ȏ�̎��Â͂������đS�g�̏�Ԃ�����������Ɣ��f���Ă��܂��܂��B�܂��p���邱�ƂŃ_���ɂȂ肻���Ȑl�͎�p�����Ȃ��Ƃ����I�������܂��B����䂦���t�̕a�C���ϋɓI�Ȏ��Ái���������߂鎡�Áj���s��Ȃ����Ƃ��I��A�����̂��߂̎��ÂƂ����y�U�ɏオ�邱�Ƃ��ł��܂���B�y�U�ɏオ�邱�Ƃ��ł��Ȃ���ŏI�I�ɂ���Ŗ��𗎂Ƃ��܂��B�i�N���͂���̎�ނŕς��܂��j�܂�܂��y�U�ɏオ���Ԃ���邱�Ƃ����҂���ɂƂ��Đ����c����@�Ȃ̂ł��B �@�ǂ̂���ł����Ă��N��APS�i���i�ǂꂮ�炢���C���j�����Âɂ����郊�X�N�t�@�N�^�[�Ƃ��Ă������܂��B�N��͂ǂ����悤���Ȃ��ł����A���Ƃ͐Q������ɂȂ�Ȃ��A�{�P�Ȃ��Ȃ�PS���ێ����邱�ƁA�N��̊��ɎႢ�ł��˂ƌ����鐶���𑱂��邱�Ƃ��y�U�ɏオ��|�C���g�ɂȂ�܂��B �@���̂��߂ɂ͕��i����^�����āA�K���������������邱�Ƃł��B�����ăe���r�A�V���A�l�b�g�Ȃ�ł������ł����瓪���g�������A�l�Ƃ����ς��b�������ē���b���邱�ƂŔF�m���܂߂�PS���ێ����P�ł��܂��B���̌��ʌ����ڂ��Ⴍ�Ȃ�A��Î҂����Âł���̂ł͂Ɣ��f���܂��B �@���N�H�i�ʼn��������ł����Ƃ悭������܂����A����Ȃ��̂�莩�R�Ɏ�ꂽ��A���A���ՂȂ��H�ׂ܂��傤�B�����ƃR�X�g�p�t�H�[�}���X�͂��ꂪ��Ԃł��Ɠ`���Ă��܂��B�܂��X�O�ȏ�̕������ꂩ�炳��ɒ��������邽�߂ɂ͉�������ƕ����ꂽ��A���܂Ő����Ă����������J��Ԃ��Ă��������B���ꂾ�����C�ȂX�O�͂������Ȃ��B�����炱�̕a�C�ł��s���s�����Ă���Ə�����Ă��܂��B �@�ȑO�������悤�Ɂi���R�Ɏ��鈫����ᇁ@�����邪����ǂ��͂��邪�S����Â��s��Ȃ��͊ԈႢ�j�����ɒ������Ȃ�����ƍ�������Ă��錌�t���҂̏ꍇ�i�O���B�����b��B����Ȃǁj�͂܂����t�̎��Â��s���̂ł����A���t�����̐i�s���������ȏꍇ�i�h�E�������p��▝�������p�������a�Ȃǁj�Ȃǂ͂���̎�p��D�悷�邱�Ƃ������ł��B���̂悤�Ɋ��҂��Ƃɍ��킹�邱�ƂłQ�ȏ�̂�������������l�Ԃ��O���ɂQ�����܂����B ���ȏ��͂Ȃ��킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�ǂ����Ă����ȏ��ɍ���Ȃ����҂���͂������܂��B���Տ��ł͂����Ɉ�Ô�Ȃǂ̎Љ�I�v���������Ă��܂��B�{�����f������̂ł����A���҂���Ƙb�������Ȃ����Â��s���Ă��܂��B�����͂��̊��҂��ƁA�a�C���ƂňႢ�܂��B �@�O��̋L���i��Ã~�X�Ŏ��S��R�ʁ@�č��ɂ������È��S�[�ւŃf�[�^�͍��ЂƂ��H�j��error�Ƃ����̂͂ǂ����Ə������Ă����������̂���T��ł̈�Â�����Ă��錻��ɑ��Č�o���ŕ]������Ȃ�Ƃ����R�c�݂����Ȃ��̂ł��B livedoor�j���[�X 2016�N5��8�� |
|
�L���l�̗����[�؏��p�A���҂̎��ÑI���ɂ��e���� �̕���݂��� |
| �@�L���l�̂��ÂɊւ�����A�����[�؏��p�̑����̈���ƂȂ��Ă���\�������邱�Ƃ��A�V���Ȍ����Ŏ������ꂽ�B�������҂ł���ă~�V�K����w��������Z���^�[��Michael Sabel���́A�����[�؏��p���őP�̎��Âł��邩�̂悤�ȕ������݂���Ǝw�E���Ă���B�������A����̌����ł͈��ʊW�͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B �@����̌����ł́A2000�`2012�N�ɓ�����̐f�f�����č��̗L���l17�l�̏������W�����B����4�l�������[�؏��p���Ă���A�ޏ���̎��ÂɊւ����45���͂��̎�p�ɂ����y���Ă����B����ŁA10�l�͕Б��݂̂̓��[�؏��p�܂��͓��[�����Ö@���Ă������A�ł͎�p�ւ̌��y��26���ɂƂǂ܂邱�Ƃ����������B���̊��ԂɁA���Z���^�[�ł̗����[�؏��p�̎��{����4������19���ւ�5�{�ɑ��������Ƃ����B �@�����Ƒ����̂��銳�҂�ABRCA��`�q�ψق������҂ȂǁA�����[�؏��p���Ó��Ƃ����Ǘ���ꕔ�ɂ͂��邪�A�u���X�N�̍����Ȃ����҂ł��������������F�߂���v��Sabel���͎w�E����B�����̏����͎�f���_�ňӎv���ł߂Ă���A���̑I�����ɂ��Đq�˂邱�ƂȂ���]���q�ׂ�Ƃ����BSabel����̓��f�B�A�����̈���ƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���A����A��v�Ȉ���o�ŕ��iChicago Tribune�ALos Angeles Times�AUSA Today�Ȃǁj�Ɍf�ڂ��ꂽ700���ȏ�̋L���͂����B �@���Ƃ��A���D�N���X�e�B�i�E�A�b�v���Q�C�g��36�œ�����Ɛf�f����A2008�N�ɗ����[�؏��p�����B�������A���̏��D��BRCA�ψق�Ƒ���������A�Ĕ����X�N�������������Ƃ�����f�B�A�͂����ꕔ�ł������Ƃ����B �@�u���̂悤�Șc�́A���������҂͂���Ȃ������[�؏��p����K�v������Ƃ̈�ۂ�^���Ă��܂��v��Sabel ���͌����B�N�P���̍������Â�I�ԏ��������������̑��̗v���Ƃ��ẮA��`�I���X�N�Ɋւ�����̑�����A���[�Č��̌���Ȃǂ��������Ă���B �@Sabel���́A�����[�؏��p����ɍőP���Ƃ���������Ȃ����悤�ɁA��t�����f�B�A�ɓ`���Ă����K�v������Ǝw�E����B����ɁA�����͐���ς��������ɁA������I�����ɂ��Ĉ�t�Ƙb�������ׂ����ƕt�������Ă���B���̌����́uAnnals of Surgical Oncology�v�I�����C���ł�4���Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@����̌������A�V�e�B�E�I�u�E�z�[�v������ÃZ���^�[��Courtney Vito���́A�u�ꕔ�̊��҂͗����[�؏��p����ɍl���Ă��邪�A���̎�p�͈�w�I�ɓK���ƂȂ�Ȃ����Ƃ�����B�����Â͂��܂��܂Ȉ��q���l�����ČʂɌ��肳�����̂ł���A���҂Ƌ��͊W��z�����Ƃ̂ł����t��I�Ԃ��Ƃ��d�v�ł���v�ƃR�����g���Ă���B m3.com 2016�N5��10�� |
|
����+��DNA�̕����Ő�����f9�����y�č����w��z ��Õی�DB�̌�������͂ɂ��g���A���h�̐��� |
| �@�č���2014�N�ɏ��F���ꂽ�����Ƒ咰���Ɋ֘A����DNA�ψق��ɒT������}���`�^�[�Q�b�g��DNA�����imulti-target
stool DNA test�Gmt-sDNA�A���i��Cologuard�j�B1���l��ΏۂƂ����Տ������ł͌����������̌��o���x92���A�O���a�ς̌��o���x42���A�����ٓx��87���Ƃ̐��т�����Ă���B �@���̂قǁA���f�B�P�A�f�[�^�x�[�X��p���������������ɂ����Տ��ł̐��т��č����w��iAACR�j�N������Ŕ��\���ꂽ�B���w�4��19���t�����[�X�ŏЉ���B�������̊������͖�88���A�z����̐���������f����90.2���ŁA�����O���[�v�͌��f���̌���Ɋ�^����̂ł͂Ȃ����Ƃ̌����������Ă���B �@�Ώۂ͎��o�ǏȂ��A�咰����|���[�v�̜늳���A�Ƒ����̂Ȃ����ϓI���X�N�̃��f�B�P�A��v���i��L�����f���̂��銳�ҁB2014�N10������15�N8����mt-sDNA�������I�[�_�[���ꂽ393���̓�������������88.3���B����51��i14.7���j���������z���ŁA�咰�������ɂ�鐸���������K�v�Ɣ��肳�ꂽ�B �@�܂��A51��̂���46��i90.2���j���������������A3�Ⴊ�������̎��{�ɓ��ӂ����A2��͎�f�Ɍ���Ȃ������B �@��������������46��̂���4�Ⴊ�咰���Ɛf�f�A21��ɐi�s�B��܂��̓|���[�v���A9��ɔ�i�s���B����������B12��͉A���Ɣ��肳�ꂽ�B �@�umt-sDNA�̎��Տ��ł̐��т��Տ������Ɠ��l�Ȃ̂��A�S���������v�ƌ����O���[�v�B�l�X�ȑ咰���������o�ꂵ�Ă���ɂ�������炸�A�č��ɂ������f����60�����x�ɂƂǂ܂��Ă���B����̌������т܂��A��N�P�I�Ŋ��҂ɗD�����������ɂ�茟�f���̌��オ���҂ł���̂ł͂Ȃ����Əq�ׂĂ���B m3.com 2016�N5��11�� |
|
�u���ÂƎd�������v���Ԓ��� �Ζ����ς����l��4�����K�� |
| �@���Ј��Ƃ��ē����Ă������ɂ���ɂ�����A���̌���d���𑱂��Ă���l�́A�Ĕ��ւ̕s�������łȂ��u���ÁE�o�ߊώ@�E�ʉ@�ړI�̋x�ɁE�x�Ƃ����Â炢�v�u��������ς�����A�x�E�����肷�邱�ƂŎ�������������v�Ƃ������A�Ə�̔Y�݂����Ȃ��Ȃ��\�\�B �@�O�HUFJ���T�[�`���R���T���e�B���O��2016�N3��4���ɔ��\�����u���ÂƎd���̗����Ɋւ��钲���v�ŁA���̂悤�Ȏ��Ԃ����炩�ɂȂ����B ����i�s�x�u2���ȍ~�v�̗͖͑ʂ��瓭��������̂����� �@�����ɋ��͂����j��978�l�̂����A����ɂ��������N��͒j����40�A50������킹���85.7���ɒB�����B������40��ȉ���77.6�����߂�B����̎�ނł́A�j���͑咰����A�����͓����ł����������B �@����ɜ늳���Ă���1�N�Ԃ́A�J�����Ԃ��u�T40���Ԗ����v�ƈꎞ�I�ɗ}�����l�̊�����41���ɏ�����B�������ɂ��ẮA�u�y���ȋƖ��ւ̓]�����Ƃ̐����ȂǁA�d�����e�̕ύX�v�Ɓu�Ζ����Ԃ̒Z�k�v���������Ɠ������l�����ꂼ��2���ɂȂ����B �@�Ζ���́A�늳��������E��œ����Ă���l��86���A�ސE�̌�ɓ]�E�E�ďA�E���Č��݂������Ă���l��14���������B�]�E���������E��Ɏc���Ă���l�́A9�������Ј��̂܂܂Ȃ̂ɑ��āA�]�E�҂͖�4�������Ј�����p�[�g��A���o�C�g�A�_��Ј��A�h���Ј��Ƃ������K�Ј��ɕς���Ă����B �@�늳���̐E���ސE�������R�ōł����������̂́A����̐i�s�x���u1���v�ȑO�ł́A�u���ÂƎd���𗼗����邽�߂Ɋ��p�ł��鐧�x���Ζ���ɐ����Ă��Ȃ��������߁v���ł������A17.2���������B�u2���ȍ~�v�ɂȂ�Ɓu�̗͖ʓ�����p�����ďA�J���邱�Ƃ�����ł��������߁v�������Ȃ�A32.8���ɏ�����B J-CAST�j���[�X 2016�N5��14�� |
| ����݂̐ێ�Ō������X�N�v�����}���ł���? |
| �@�؍��̊w�p���w�t�[�h�T�C�G���X�E�A���h�E�o�C�I�e�N�m���W�[�x�̍ŐV���ɂ��̂قǁA�؍��̌����҂ɂ�邭��݂̌������ʂ��f�ڂ��ꂽ�B����݂́A�������זE��W�I�ɂ����}������\��������Ƃ����B �} ����݂��g���������u���Ɩ�̂���݂݂��ρv  �@�f�ڂ��ꂽ�_���́u����݂̎������o���̑g�����͂���ю��ȕ����\�̗}���ɂ�邪�זE�̑��B�ɑ���}�����q�Ƃ��Ă̓����v�B �@���ԏ��q��w�̉h�{�Ȋw�E�H�i�}�l�W�����g�w���̃L���E���������̌����`�[���́A����݂̎������o��(WLE)�̐����Ɍ�������זE�̑��B�}�����ʂ����邩�ׂ��Ƃ����B����݂̎������o���ɂ́A���b�_��g�R�t�F���[���Ȃǂ��܂��܂Ȑ������܂܂�Ă���B �@�������זE�͎�ᇂ̒��ɑ��݂��鏬���ȍזE�̈��W�c�ŁA���ȕ����\�����B���̂��߁A��ᇂ̓]�ڗ������߁A���ː���R����܂ɑ����R�͂����߂�\��������Ƃ̂��ƁB�_���ł́A����݂̎������o�����A�u��������v�̊��זE(CSC)�̎��ȕ����\��}��������ʂ�����\���𖾂炩�ɂ��Ă���B �@�L�������́A�u��������͗L���Ȏ��Ö@�������Ă���A����ɂ���v�Ȏ����̂ЂƂɂȂ��Ă��܂��B����̌����ɂ���āA��������̎��Âɂ���݂����ʓI�ł���\����������܂����v�ƌ�����B �@����Ɂu���̌������ʂ́A��������A������A�O���B����̕���ɂ�����ߋ��̌����̏�ɒz���ꂽ���̂ł���A����݂̂���\�h���ʂ𗝉������ŁA����O�i�������ƂɂȂ�܂��v�Ƃ��t����������B �}�C�i�r�j���[�X 2016�N5��15�� |
|
10��ʼnʕ�����������H�ׂ�Ɠ����X�N���ቺ 1��3�M���̐ێ��25���� |
| �@10�㏗�����ʕ����ʂɐH�ׂ�ƁA�����̓����X�N���ቺ����\�������邱�Ƃ��킩�����B�v�t���ł̃����S�A�o�i�i�A�u�h�E�̐ێ悪�����X�N�ቺ�ɋ����֘A���A1����3�M����ێ悷��ƁA0.5�M���̂ݐێ悷��l�ɔ�ׂāA���N���̃��X�N��25���ቺ�����Ƃ����B �@��N���ł̃I�����W��P�[���̐ێ���A�킸���ɓ������\�h������ʂ����邪�A�t���[�c�W���[�X�ɂ͌��ʂ�F�߂Ȃ������Ƃ����B �@�����ł́A�Ō�t���N�����iNHS�jII�ɓo�^���� 27�`44�̏���9���l���ɂ��āA����2�N���1991�N�ɋL�����Ă��������N���l���̐H�����Ɋւ��鎿��[�͂����B�����1998�N�A4��4,000�l���̏�����2��ڂ̒������s���A�v�t���̐H�������v���o���Ă�������B�܂��A1991�`2013�N�܂�4�N���ƂɈ��H���̐ێ�ׁA�O�N�̐H�������v���o���Ă�������B������̔��Ǐ�2�N���ƂɊm�F�����B �@20�N�Ԃ̌����ŁA3,200�l�����Z����������ǂ��A����1,350�l�ł͎v�t���̐H�����̏������ł����B�����̉�͂̌��ʁA�v�t���̉ʕ��̐ێ�ʂ������قǓ����X�N�͒Ⴂ�ƌ��_�Â���ꂽ�Ƃ����B �@�������҂̕ăn�[�o�[�h��wT.H.�`�������O�q����w�@�i�{�X�g���j��Maryam Farvid���́A�u���̌����͊ώ@�����ł���A���ʊW�̃G�r�f���X�͒ł��Ȃ����A�ʕ��̐ێ�Ɠ����X�N�ቺ�̊֘A���������ꂽ�v�Əq�ׂĂ���B���̌����́uBMJ�v5��11�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B m3.com 2016�N5��24�� |
|
�A�X�s�����̃Q�m����ÂŊ��\�h�� J-CAPP Study II�A7000�l�ڎw���o�^�J�n |
| �ΐ�G�����@���s�{����啪�q�W�I���\�h��w �@2016�N4���A�č��\�h��w���ψ���iUSPSTF�j���A�S���ǎ����Ƒ咰���̈ꎟ�\�h�ړI�ł̒�p�ʃA�X�s�����̎g�p�Ɋւ��A�V���Ȋ����\�����B�S���ǎ�������ё咰���̈ꎟ�\�h���̂��߂̓���g�p���������ꂽ�B �@���{�ł͐S���ǎ����̗\�h�ɍL���g�p����Ă��邪�A�咰���Ɋւ��Ă͓����̌����݂͂���̂��B�����ŗՏ�������i�߂鋞�s�{����ȑ�w���q�W�I���\�h��w�̐ΐ�G�����ɘb�����B�i���S���ǎ����̏ꍇ�̈ꎟ�\�h�ƈقȂ�A�咰���̈ꎟ�\�h�́u���v�̔�����\�h����_�Œ�`���قȂ�j ���{�ł��߂����������X�N��ɐ����̉\�� �\�\����A�č��ł�50�Α�A60�Α�̐l�ɐV���ɑ咰���̈ꎟ�\�h���ɑ���A�X�s�����̗\�h��������������܂����B���{�œ��l�̗\�h���������������\���͂ǂ̒��x����̂ł��傤���B �@�����̗Տ������ɂ��A��p�ʃA�X�s�������咰����咰�B��̔�����}�����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl���Ă��܂��B���������āA���{�ɂ����Ă��߂������A�咰���̃��X�N�̍����l�ɑ��ẮA���X�N�y���̂��߂ɃA�X�s�����̕��p�𐄏������悤�ɂȂ�Ǝv���܂��B�������A�ǂ̂悤�Ȑl���A��������A�ǂ̒��x�̊��ԕ��p����̂��ǂ����́A�܂��A�m�肵�Ă��܂���B�����𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA���݁A7000�l�̊��҂���ɑ���Տ������iJ-CAPP StudyII)�����{���ł��B ��M�܂Ƃ��Ĕ̔�����Ă���A�X�s�����̎g�p��NG �\�\�����ɓ������ĉ������ׂ��ۑ��č��Ƃ͎���قȂ�_�͂���܂����B �@�咰����咰�B��\�h�ɑ��铯��̃G�r�f���X�͊m���������܂��B�������A���{�̕ی��f�Âł͑咰���\�h�̂��߂ɃA�X�s�������������邱�Ƃ͔F�߂��Ă��܂���B�����_�ł́A�����܂ł��Տ������Ƃ��Ċ��҂���ɓ��^����i�K�ł��B �@�O�q�̒ʂ�A������u�ǂ̂悤�Ȑl�Ɂv�u��������v�u�ǂ̒��x�̊��ԁv�g�p���邱�Ƃ��A�ł������I�ň��S�����������Ă��܂���B����炪���{�ʼn������ׂ��ۑ�ł��B�č��l�ɔ�ׁA���{�l�͔�X�e���C�h���R���ǖ�iNSAIDs�j�ɑ��镛��p���������₷���\�����l�����邽�߁A���{�l�ł̃f�[�^���o�����Ƃ͏d�v�Ǝv���܂��B �@�܂��A�č��ł͖�ǂȂǂŒ�p�ʃA�X�s�������r�I�e�Ղɓ��肷�邱�Ƃ��\�ł����A���{�ł͖�ǂŒ�p�ʃA�X�s�������w�����邱�Ƃ͂ł��܂���B��ʗp���i�̉�M���ɍ܂Ƃ��Ĕ̔�����Ă���A�X�s�������͊ܗL�ʂ������A���n���ɂȂ��Ă��Ȃ����̂�����܂��B��M���ɍ܂Ƃ��Ĕ̔�����Ă���A�X�s��������咰���\�h�̂��߂ɕ��p����̂͊댯�ł���A���̓_�͒��ӂ��K�v�ł��B �S�Ⴊ��p�ʃA�X�s�����Q�ɓo�^�A24���Ԃ̑��k�̐��� �\�\J-CAPP StudyII��7000��Ƃ��Ȃ�̋K�͂̓o�^�҂�\�肵�Ă���Ƃ̂��Ƃł����A���݂̕�W�A�\��o�^�Ǘ��B�����邽�߂̍H�v�Ȃǂ�������Ă��������B �@��N�i2015�N�j������o�^���J�n���A���݁A800�l���x�̕����Q�����Ă��܂��B��r�I�����ɐi��ł���Ǝv���܂��B�������A�\��o�^����7000�l�ł��̂ŁA�܂��܂��撣���ĕ�W����K�v������܂��B�o�^�Ґ��𑝂₷���߂ɁA�|�X�^�[��`���V�̍쐬�A�{�������Љ�铮��̍쐬�A���̓�����^�u���b�g��a�@�̑ҍ��ŕ��f����Ȃǂ̍H�v�����Ă��܂��B�܂��A�}�X���f�B�A�ɂ��{�����̘b������x�����グ�Ă����������̂ŁA�F�m�x�����܂������Ƃɂ���Ă��G���g���[���₷���Ȃ��Ă��܂��B �@�{�����̓v���Z�{�Q��ݒ肹���A�S��������Q�Œ�p�ʃA�X�s�����p�ł���悤�Ƀf�U�C�����Ă��܂��B�܂��A1�V�[�g31���̃J�����_�[�V�[�g�̗��ʃA���~PTP������A�����Ԃ̕ۊǂ���r�I����Ȃ��߁A1�N���̃A�X�s�������^�����n���ł��邱�ƁA24���ԑ̐��łǂ̂悤�Ȏ���ł��Ή��ł��鎖���Ǒ̐��𐮂������ƁA�����A�j���[�X���^�[�Ƃ��Ċ��\�h��咰���Ɋւ�������s���Ă��邱�ƁA�Q���ґS���ɃA���R�[���̑�Ӎy�f�̈�`�q���^�𑪒肵�A�����ɂ�邢�낢��Ȕ��������������邱�ƁA�Ȃǂ̍H�v�����ӗ��̌���ɗL���ƍl���Ă��܂��B �\�\����̋�̓I�ȖڕW�ɂ��ċ����Ă��������B �@��p�ʃA�X�s�����ɂ��咰���\�h�̓K�ȃ��X�N�w�ʉ��̂��߂ɂ́A��`�q���^�̌������瓾����m�������ɏd�v�ł��BJ-CAPP StudyII�ł͒�p�ʃA�X�s�����ɂ��咰���\�h���ʂ̍Ċm�F�ł͂Ȃ��A�����Q���҂̊e���`�q���������A�A�X�s�������L���ȏW�c���i�荞�ނ��߂̈�`���𖾂炩�ɂ��悤�ƍl���Ă��܂��B�ŏI�I�ɂ͑咰�������X�N��̒��ŁA��p�ʃA�X�s�������L���ŕ���p�̏��Ȃ��l����`�q���^����K���A�咰�B��̊����Ȃǂ���i�荞�݁A����̌��ʓI�ȓ��^�ɂ��A�咰���̔��������I�Ɍ��炷�Q�m����Â̎�����ڎw���Ă��܂��B m3.com 2016�N5��24�� |
|
�^����13��ނ̂���̃��X�N���ጸ �������A�e�j�X�A�W���M���O�A���j�ȂǂŌ��� |
| �@�^���ɂ���đ����̂���̃��X�N���L�ӂɒጸ����\�����A��K�͂ȃ��r���[�Ŏ������ꂽ�B�T��2�`3���Ԃ̉^�������邾���ł��A������A�咰����A�x����̃��X�N���ጸ����Ƃ����B �@����ɁA���X�N�͉^�����Ԃ�������قǍی��Ȃ��ቺ��������悤���ƁA�����̕M�����҂ł���č�����������Steven Moore���͏q�ׂĂ���B�������A�^���Ƃ��X�N�ጸ�̈��ʊW�͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B �@����̌����ł́A����I�ȉ^����13��ނ̂���̃��X�N�ጸ�Ɋ֘A���Ă���Ƃ̌��ʂ�����ꂽ�B�Y�����邻�̑��̂���́A�����a�A������A�H������A�̂���A�t����A�݂���A�q�{��������A��������A�N������A������B �@���s�̘A�M���{�ɂ��^���K�C�h���C���́A�T150���̒����x���狭�x�̉^���i��������e�j�X�Ȃǁj�܂���75���̌������^���i�W���M���O�␅�j�Ȃǁj�Ƃ���Ă���B����͐S���̌��N��ړI�Ƃ�����̂����A����\�h�ɂ��L�p����Moore���͎w�E���Ă���B �@����œ_�Ă��̂́A�d����Ǝ��������]�Ɏ��ԂɁA���N����̂��߂Ɏ���I�ɍs���^�����B���҂�ɂ��ƁA�č����l�̖��͐��{����������Œ���̉^�����Ԃ����Ă��Ȃ��Ƃ����B �@�����O���[�v�́A�č�����у��[���b�p��12���̌����f�[�^�����A19�`98�̐��l140���l�̃f�[�^�x�[�X���쐬�B���Ȑ\�����ꂽ�^���̓��e�ɂ���āA26��ނ̂���̃��X�N�ɍ����݂��邩�ǂ��������������B �@������������̂����A�����̃��X�N�ጸ�ɉ^���Ƃ̊֘A���݂��A�����͔얞��i�����Ȃǂ̈��q���l�����Ă��L�ӂȒጸ���F�߂�ꂽ�B���X�N�͑S�̂�7���ጸ���A���X�N�ጸ�͈̔͂�42���i�H������j����10���i������j�ɋy�B�咰����Ɣx����́A���ꂼ��16���A26���ጸ�����B���̒m���́uJAMA Internal Medicine�v�I�����C���ł�5��16���f�ڂ��ꂽ�B �@�u����A�^��������\�h�ɖ𗧂��R�͖��炩�ɂ��Ă��Ȃ����A�^��������Ƃ��܂��܂Ȃ���Ƃ̊֘A���F�߂��Ă���z�������̒l���ቺ����ق��A�C���X��������уC���X�����l���B���q�̒l�����䂳���v��Moore���͘b���B �@�t���_���̒��҂�1�l�ł���ăm�[�X�J�����C�i��w�i�`���y���q���j������Marilie Gammon���́A�u�^������l�̍זE�͎_���X�g���X���ɂ����ADNA�������C������\�͂������B�H��������͂��߂Ƃ���v�����̍�������ɑ啝�ȃ��X�N�ጸ���F�߂�ꂽ���Ƃ͔��Ɋ�����v�Ɛ������Ă���B m3.com 2016�N5��26�� |
|
�咰�����������̑O���̐�H�͕s�v�H ���ʂ̒�c�ԐH�̂ق����K���Ă���\���� |
| �@�咰�����������ŁA�݂���ɂ���炢�����͕K�v�łȂ��\�����A�V���Ȍ����Ŏ������ꂽ�B�ʏ�A�����������̑O���ɂ͌Ō`�H���T���Đ��������H��ێ悵�A���܂����ޕK�v������B����������̌����ł́A���ʂ̒�@�ېH��ێ悵�Ă������ւ̈��e���݂͂�ꂸ�A�ނ���]���̐��������H��ێ悷������A���͌����ɓK������ԂɂȂ邱�Ƃ��킩�����B �@�������҂ł���ăJ���t�H���j�A��w�A�[�o�C���Z�Տ���������Jason Samarasena���́A�u�咰�����������̑O���ɉ����H�ׂĂ͂����Ȃ��Ƃ����v�����݂͌��ł���\��������v�Əq�ׂĂ���B �@�č�����iACS�j�ɂ��ƁA�č��ł͍��N13��4,000��ȏ�̑咰���f�f�����Ɛ��肳��Ă���B50�Έȏ�̐l�ɂ͓������ɂ��X�N���[�j���O����������Ă��邪�A��������ς��Ƃ������R�Ō������Ȃ��l�������Ƃ����B �@����̌����ł͊���83�l��ΏۂƂ��āA�咰�����������̑O���ɐ��������H��ێ悷��Q�ƁA��@�ېH�i�}�J���j�A�`�[�Y�A���[�O���g�A�����p���A�����`�~�[�g�A�A�C�X�N���[���Ȃǁj�����ʐێ悵�Ă��悢�Q�̂����ꂩ�Ɋ���t�����B��@�ېH�Q�̊��҂͎��b�A�`���A�Y�����������킹��1,000�`1,500kcal�ێ悵���B �@���̌��ʁA��@�ېH�Q�̂ق����A���������H�Q�������̏�����Ԃ��ǍD�Ȋ��҂����������B�܂��A��@�ېH�Q�͌����������̔�J�����Ȃ������B�H���̖����x�͒�@�ېH�Q��97���A���������H�Q��46���ł������B �@��@�ېH�́u��c�ԐH�v�Ƃ��Ă�A������n���ŗe�Ղɉt�����邽�߁A�咰����r�o����₷����Samarasena���͐�������B����Ŗ�A�ʕ��A�i�b�c�ށA��q�ށA�����Ȃǂ̐H���@�ۂ��L�x�ȐH�i�́A����ʉ߂���Ƃ��ɖ������ł��邱�Ƃ������A�����̖W���ƂȂ邱�Ƃ�����B�Ȃ��A�Ō`����H�ׂ��ق��������Y��ɂȂ�̂́A�u�����炭�A�H�ׂ邱�Ƃɂ���Ē����h������A�r����������邽�߂ł���v�Ɠ����͏q�ׂĂ���B �@����̌����͏��K�͂Ȃ��̂����A���̌����ł����l�̌��ʂ��o�Ă����Samarasena���͎w�E����B�ăJ�C�U�[�E�p�[�}�l���e��ÃZ���^�[�i�J���t�H���j�A�B�j��Theodore Levin���́A�u���̒m���͗L�v�����A�����������̏������@��ύX����ꍇ�͎��O�Ɉ�t�ɑ��k����K�v������B���ɓ��A�a���҂Ȃǂł́A��@�ېH���������鉿�l������v�Ƃ��Ă���B �@���̒m���͕ăT���f�B�G�S�ŊJ�Â��ꂽ�č�������a�T�ԁiDDW�j��c�Ŕ��\���ꂽ�B m3.com 2016�N6��2�� |
| �S���E�̂��Ö��p�A20�N�ɂ�1500���h������ |
| �@��Ï���Ђ̂h�l�r�w���X�E�z�[���f�B���O�X(IMS.N)�͂Q���A�S���E�̂��Â̂��߂̈��i��p�́A���z�ȖƉu���Â̏o���ŁA�Q�O�Q�O�N�܂łɂP�T�O�O���h��������Ɨ\�z����������\�����B �@�Q�O�Q�O�N�܂Ŗ��N�V�D�T���P�O�D�T�����ƂȂ邱�Ƃ��������̂ŁA�P�W�N�܂łU���W�����Ƃ����h�l�r�̍�N�̗\�z������B �@�����̐��l�́A�l�����╥���߂������������Ö�̎s�̉��i�Ɋ�Â��Ă���A���w�Ö@�ȂǗl�X�Ȏ��Ö@�ɕt������f���C��n���Ƃ���������p�ɑΏ����邽�߂̎��Ö�̔�p���܂܂�Ă���B �@�h�l�r�ɂ��ƁA�ߋ��T�N�ԂłQ�O�ȏ�̎�ᇃ^�C�v�ɑΉ������V�O����V���Ȃ��Ös��ɎQ���������Ƃ�w�i�ɁA�Q�O�P�P�N�ɂX�O�O���h�����������E�̂��Ö��p�́A�P�T�N�ɂ͑O�N��P�P�D�T�����̂P�O�V�O���h���ɒB�����B �@�����A�����ɂ��ƁA���������V��̔����ȏ�͌��݁A�킸���U�J���ł̂ݓ��肪�\�ŁA���I�ی��戵�ň�Ô�̕����߂��������i�̐��͂���ɏ��Ȃ��Ƃ����B �@��A�̐V��̓o��ɂ���āA���Ҏ��g�̖Ɖu�V�X�e��������זE���U�����鎡�Â��\�ɂȂ�A�i�s�����F���i�s���x����ȂǁA�ł��v�����̍����a�C�̐������͂���܂łɂȂ����܂����B �@�Ĉ��i��胁���N(MRK.N)�ƃu���X�g���E�}�C���[�Y�E�X�N�C�u(BMY.N)�����̕���ł͍ő�肾���A���V���E�z�[���f�B���O�X(ROG.S)�͐�T�A����N�������Âł͂R�O�N�Ԃ�̐V�Ö@�ƂȂ�Ɖu�Ö@�̔F��Đ��{����Ă���B �@�h�l�r�ɂ��ƁA���݂T�P�P�Ђɂ��T�W�U�̂��Ö@���A�J���̒�������ь���X�e�[�W�ɂ���B �@�����́A���Êw��ł͍ł��d�v�Ƃ����A�����J�Տ���ᇊw��i�`�r�b�n�j�̕ăV�J�S�ł̔N������̒��O�Ɍ��\���ꂽ�B ���C�^�[ 2016�N6��2�� |
| �]��12�J���鍐�B�咰����́h�X�e�[�W�S�h����328���Ō��I�Ɋ��������@����T�o�C�o�[�����H�����V���v���ȁu�V�̏K���v�Ƃ́H |
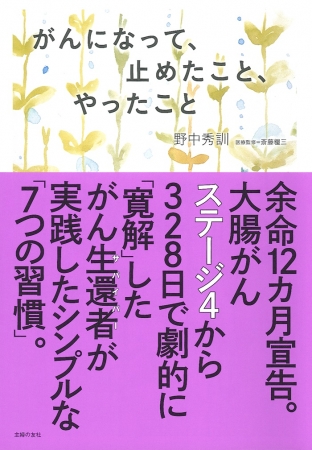 �m������Ў�w�̗F�� �n �w����ɂȂ��āA�~�߂����ƁA��������Ɓx2016�N5��12������ �@���҂̖쒆�G�P���́A�N�Ƃ�������̉�Ђ��O���ɏ��n�߂�2014�N�ɑ咰�����o�B�u�X�e�[�W�S�v�u�]���P�N�v�̐鍐������A�u�ǂ������炪���邩�v�ɂ��Ď�T��ŏ����W���A�l�X�Ȏ��Ö@��͍��B���̒�����u�����������Ǝv�����́v�͑����Ɏ��H���A1�N��Ɏ�����̊����ɂ��ǂ蒅���܂ł̋O�Ղ��A�{���͖{�l�̐S���������ċL���Ă��܂��B �@�쒆���́A���̉ߒ��Łu����͐����K���a�v�Ƒ����A�����K���̒�����u����ɂȂ鈫���w�V�̏K���x�v��o���A�u������������߂́w�V�̏K���x�v�ɓO����P���Ă����܂��B �@�����I�t���͂��߂Ƃ������X�̐H�����̌������ƁA�X�g���X�}�l�W�����g�𒆐S�ɂ��邱�̐������P�́A���ʂȕ��@�ł͂���܂���B����Ȃǂ̍��m���A������߂����Ă����l�͂������A�����K���a�̗\�h��A���`�G�C�W���O�A���e���l���Ă���l�ȂǁA���X�Z���������錻��l�Ȃ炷�ׂĂ̕��ɎQ�l�ɂȂ���̂�����͂��B �@�u���N�Ŏ����炵�����������������v�ƍl���邷�ׂĂ̐l�ɁA�ǂ�ł���������������ł��B �@�u�V�̈����K���v�Ɓu���P�����V�̏K���v�͑ɂȂ��Ă��� �������o����܂ł́u�V�̈����K���v �X�g���X �\���\�H �H�ɖ��ڒ� �ߓx�ȉ^�� �x�݂̂Ȃ����� �����_�o�̗��� �\���̌����� ��������������߂ɉ��P�����u�V�̏K���v �H�������P���� ���Q���N�����K�������� �̂̒��̈������̂��o�����߉�ł��� �n�[�u���𗘗p���� ���K���s������A�I�A�}�b�T�[�W���Ȃǂ𗘗p���� �v�l��H��ς��ăX�g���X���Ȃ��� ��������O��I�Ɍ����� �@����͐����K���a�ł��B �@�S���a�A�]�����Ƃ��������������̔��ǂɈ�`�q���֗^���銄���͒Ⴍ�A����ł����T�`�P�O���ɉ߂��Ȃ��B �@�����K���ɋN�����Ĕ��a���邱�Ƃ������̂ɁA���̐����K������u�����܂܁A����Ȃǂ����Ŏ������Ƃ���̂͋\�Ԃł��B �@���҂̐����K�������߂邱�ƂŁA��`�q�̃X�C�b�`����ւ��A���ÂɌ��т����邱�Ƃ͎�����Ă��܂��B �@����Ȃǂ̐����K���a���������Ƃ���Ȃ�A�܂��͐����K�������߂邱�ƁB �@�����ł���ɂȂ����ӔC�́A�����łƂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B ���҃v���t�B�[���@�쒆�G�P�i�̂Ȃ��Ђł̂�j 1968�N���܂�B1988�N�A��������𑲋Ƃ������@�탁�[�J�[���ЁB2012�N�A�A���`�G�C�W���O�̃X�y�V�����e�B�����������u�A���`�G�C�W���O������Ёv�ݗ��B2014�N6�����o�B46�A�T�����[�}�������߂�9�N�A���]�Ȑ܂��o�āA��Ђ��O���ɏ��n�߁A�������ړ]�������ɓˑR�̕��ɂ����[�Łu�咰����X�e�[�W�S�v�����m�����B�����Ɋ̑��A�E�B���q���[�����p�߁A�哮�������p�ߓ]�ځB�]��12�J���鍐�������1�N�Ŋ����B�u���O�u���ɂȂ��āA�~�߂����ƁA��������Ɓv���b��ɁB http://ameblo.jp/hidenory88 ��������STORYS.JP�ł��u���傤��1�N�O�ɗ]��12�J���鍐�����b�B�v��A�� http://storys.jp/hidenori.nonaka/ ������� �w����ɂȂ��āA�~�߂����ƁA��������Ɓx ���ҁF�쒆�G�P ��w�ďC�F�֓��ƎO �艿�F�{��1400�~�{�� �����F2016�N5��12�� �l�Z���A288�y�[�W ISBN�F978-4-07-415356-5 http://books.rakuten.co.jp/rb/14112724/ �����h�b�g�R���j���[�X 2016�N6��5�� |
|
�u�g�ѓd�b�Ŕ]��ᇁH�v�������ʂɕĐ��Ƃ�^�� �d�g�ɔ��I�����Q�̂ق����������������ƂȂǂ��w�E |
| �@���b�g�̌����Ōg�ѓd�b�Ǝ�ᇂ̊֘A�������ꂽ���Ƃ�����Ă��邪�A�č����q���������iNIH�j�̐��Ƃ�́A���̌����̑Ó����ɋ^���悵�Ă���B �@5��27���ɕč����ƓŐ��v���O�����iNTP�j�����\�����������ʂɂ��ƁA�g�ѓd�b�Ŏg���Ă�����̂Ɠ���̓d�g�ɔ��I�����Y�̃��b�g�ɁA2��ނ̎�ᇁi�]�̐_�o�P���ѐS���̗ǐ��_�o���j���g�Ⴂ�m���h�Ŕ��������Ƃ����B�E�H�[���E�X�g���[�g�E�W���[�i�������B �@���̌�����2500���h���K�͂ŁA�g�ѓd�b�̌��N�ւ̉e����]�����������Ƃ��Ă͍ł���K�͂���I���Ƃ����B�u���E�̃��o�C���ʐM�̗��p���l����A���Ǘ����킸���ɏ㏸���邾���ł��L�͈͂ɉe�����y�т���v�ƁANTP�͏q�ׂĂ���B �@�������AAP�ʐM�ɂ��ƁANIH�̐��Ƃ�͂��̌����Ɍ��ׂ�����Ǝw�E���Ă���B���Ƃ��A����̌����ł͔D�P�����琶��2�N�܂ŁA�ɂ߂č����ʂ̓d�g�Ƀ��b�g�𔘘I���Ă��邪�A����ł���ᇂ����������̂͗Y���b�g��2�`3���݂̂������B�����b�g�ɑS����ᇂ��������Ă��Ȃ����Ƃ�A�d�g�ɔ��I�������b�g�������I���Ȃ��������b�g�̂ق������S���������������Ƃ�����Ƃ����B����ɁA�d�g�ɔ��I���Ȃ��������b�g�ł́A�u����v�W�c�ŗ\�������̂Ɠ����䗦�ł̎�ᇔ��ǂ͔F�߂��Ă��Ȃ��B �@�����̓_����A�O�����r���[�����{����NIH��Michael Lauer���́A�u�������҂�̌��_������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̎����͌���͂��啝�ɕs�����Ă���A�����̗z����ɂ͋U�z���̋^��������B�d�g�ɔ��I�������b�g�̂ق��������������Ƃ����������A�^�f������ɐ[�߂�v�Əq�ׂĂ���B �@NTP�ɂ��ƁA���̌����̍ŏI�I�Ȍ��ʂ�2017�N�H�܂łɔ��\�����\��Ƃ����B �@NIH�́A�u����܂ł̑�K�͌����Ŏ��W���ꂽ�q�g�̊ώ@�f�[�^���݂�ƁA�g�ѓd�b�̎g�p�ɂ�肪��̔��ǃ��X�N���㏸���邱�Ƃ������G�r�f���X�͂킸���ł���B�����̌����ł́A�g�ѓd�b�ƗL�Q�Ȍ��N��Q�̊֘A�͎�����Ă��Ȃ��v�Ǝw�E����B���Ƃ��A�ŋߔ��\���ꂽ�I�[�X�g�����A�̌����ł́A��30�N�O�̌g�ѓd�b�̏o���ȗ��A�]��ᇂ̜늳���͑S�������Ă��Ȃ����Ƃ�������Ă���B �@����ŁANTP�̃v���W�F�N�g�Ɋւ���Ă���������Ƃ́A�u�S�����X�N���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��Ǝ咣�����_�ŁA���̒m���ɂ͉��l������v�Ƙb���B���̌������č��̘A�M�ʐM�ψ���iFCC�j�̈��S�K���ɋy�ڂ��e���͕s���ł���B m3.com 2016�N6��9�� |
| �������[�h�ł���̒��킩�邱�Ƃ�Microsoft������ |
| �@Microsoft�̉Ȋw�҂͌����G���W���̌������[�h�͂��邱�ƂŁA����������Ă���C���^�[�l�b�g���[�U�[�𑁊������ł���Ƃ����������ʂ\���܂����B �@Microsoft�̉Ȋw�҂ł��錤���҂ł���G���b�N�E�z���r�b�c���m����у������E�z���C�g���m�炪���\���������́AMicrosoft�̌����G���W���ł���Bing�̃f�[�^�����X�����҂̃��[�U�[�����ʂ���Ƃ������́B�X������͑���������������ʂł����A�������[�h�͂����@�ł́A�܂��f�f���Ă��Ȃ��X�����҂܂Ŏ��ʉ\�ŁA�X������̑����������\�ɂȂ�ƌ����Ă��܂��B �@�X�������5�N�������͂킸��3���Ɣ��ɒႢ�̂ł����A�����i�K���X��������ł���A5�N��������5�`7���܂ő��������邱�Ƃ��ł��܂��BMicrosoft�̉Ȋw�҂̎�@�ɂ���X������̔�������5�`15���ŁA�U�z����(�f�f���x)�͂킸��10������1�Ƃ̂��ƁB�a�@�̐f�f�ł����X������ƌ�f����Ă��܂��ƁA����Ȃ錟���ɂ���Ô�̑�����A�������s���̌����ɂȂ�܂��B �@����Ō������[�h���g������@�ł́A���͂Ɏg�p�����f�[�^�͓���������u���[�U�[���v�̂悤�Ȏ��ʗv�f�͊܂܂Ȃ��Ƃ̂��ƁB���[�U�[�����͌��ʂ�m�邱�Ƃ͂Ȃ��A�s�p�ӂɕs����^���Ă��܂��S�z�͂Ȃ��B�����������҂��l�����ł��Ȃ����߁A�X�������o�������[�U�[�ɘA�����邱�Ƃ��ł��܂���B�]���āA���̘_���I�X�e�b�v�͌������[�h���环�ʂł����f�[�^���ǂ̂悤�Ɋ��p���邩�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@�z���r�b�c���m�́u�����������炢���̓����wCortana for health�x�����܂��\�������邩������܂���v�Ƙb���Ă���A1�̕��@�Ƃ��ẮA���[�U�[�Ƀf�[�^���W�̋������߂���ŁA�a�C�̒������������Ɍx������w���X�T�[�r�X�̈ꕔ�Ƃ��Ċ��p���邱�Ƃ��l�����Ă��܂��BMicrosoft�ɂ���Đݗ����ꂽ�uHealth �� Wellness�v�Ƃ������N���������g�D��CTO(�ō��Z�p�ӔC��)�ł�����z���C�g���m�́A����̌����Ɋւ���ڍׂ̒�f���Ă��܂����AMicrosoft�̃T�[�r�X�Ƃ��ăf�[�^�����p����Ă������Ă���̂�������܂���B �@���m��́u�E�F�u�����������璊�o���ꂽ�w���X�P�A�f�[�^�v�Ƃ�������́A��Â̐��ƂɂƂ��ĐV�����e���g���[�ł���ƍl���Ă���A�z���r�b�c���m�́u��v�Ȉ�w�����ɂ��̎�̃f�[�^�����p�ł���Ǝv���Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂��B �@�������[�h�͂���Ƃ����A�C�f�A�͐V�������̂ł͂Ȃ��A2009�N�ɂ�Google���E�F�u�������O�͂��邱�ƂŃC���t���G���U�̗��s�𑁊������ł���Ƃ����������ʂ\���Ă��܂��B �@�܂��A2013�N�ɂ�Microsoft�̌����`�[�����E�F�u�������O����A�����J�H�i���i��(FDA)���C�t����葁��������̕���p������Ƃ����������ʂ�����Ă��܂��B����Google��Microsoft�������[�U�[�̃E�F�u���������f�[�^�́AFDA�ɑ��Ē��ړI�ȉ��l�����f�[�^�ɂȂ邱�Ƃ�A�a�C�̑��������V�X�e���Ƃ��Ċ��p�����\���������Ă��Ă��܂��B GIGAZINE 2016�N6��9�� |
|
�]��ᇂɑ���E�C���X�Ö@�A���������ŗL�]�����m�F �Ĕ����P���҂Ő������� |
| �@�����i�K�̃E�C���X�Ö@�ɂ��A����̔]��ᇊ��҂Ő������Ԃ̉������F�߂�ꂽ�Ƃ����B����̑�I�������ł́A�悭�݂��鍂�����x�̔]��ᇂł���Ĕ����P���̊��҂Ɉ�`�q���ς����E�C���X�𒍓������Ƃ���A�E�C���X�Ö@�Q43�l�̕��ϐ������Ԃ�13.6�J���ł������̂ɑ��A�E�C���X�Ö@���Ă��Ȃ��Q��7.1�J���ł������Ƃ����B �@�����𗦂����ăJ���t�H���j�A��w���T���[���X�Z�iUCLA�j��Timothy Cloughesy���́A�u����̗Տ��f�[�^����A���̎��Â��R�^�ۖ�ƕ��p���邱�Ƃɂ��A����זE�������邱�ƂȂ�����זE�����ł����A����ɑ���Ɖu���������ł��邱�Ƃ����߂Ď����ꂽ�v�Əq�ׂĂ���B�����Ö@���J��������Tocagen�Ђ̌ږ�ł����铯���́A�u���̎��Ö@��]�ڐ��咰����������ȂǁA���̂���ɂ����p�ł���\��������v�ƕt�������Ă���B �@���Â������҂̈ꕔ��2�N�ȏ㐶�����A����p���قƂ�ǂ݂��Ȃ������Ƃ����B�u�]��ᇂ͒v���I�Ȏ����ł���A�Ĕ�����Ǝ��Â̑I�����͋ɂ߂ď��Ȃ��A�������Ԃ͒ʏ�͌��P�ʂł���v�ƁA�������҂�1�l�ł���ăN���[�u�����h�E�N���j�b�N��Michael Vogelbaum���͌����B �@���̎��Â����ʂ�����@���͈ȉ��̒ʂ肾�B�܂��A���ˍ�Toca 511�����邪��זE�ɔ\���I�Ɋ������A�V�g�V���f�A�~�i�[�[�ƌĂ��y�f�̈�`�q������זE�ɗ^����BToca 511�͂���זE���V�g�V���f�A�~�i�[�[�����悤�Ƀv���O�������A���Â̑��i�K�ɔ�����B���ɁA���҂ɍR�^�ۖ�Toca FC�𓊗^����ƁAToca 511�ɂ���Ĉ����N�����ꂽ��`�q�̕ω��Ɋ�Â��A����זE��Toca FC���R�����5-�t���I���E���V���i5-FU�j�ɓ]������B����ɂ��A����זE���������ɁA����זE��_���Ď��ł����邱�Ƃ��ł���B �@���̐V�K�̉��σE�C���X�͑��B�^���g���E�C���X�x�N�^�[�iRRV�j�Ƃ��Ēm���邪�A�Տ������̌��ʂ����\���ꂽ�͍̂����߂ĂƂ����B��I�������̖ړI�͈��S���ƔE�e���̕]���ł���A���i���č��H�i���i�ǁiFDA�j�̏��F��ɂ͒ʏ�A��III���܂ł̎������K�v�ƂȂ�B�u����̌��ʂ͐i�s���̑�II/III�������ł���Toca 5�������x��������̂ł���A�]��ᇊ��҂̐V���Ȏ��ÑI�����ւ̊�]�������炷���̂��v�ƁAVogelbaum���͏q�ׂĂ���B���̌����́uScience Translational Medicine�v6��1�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B m3.com 2016�N6��13�� |
| 8���ȏオ��p�s�\���X����@�V��ʼn\�� |
| �@�C�Â��Ȃ������ɐi�s���Ă����X�i�����j����B�������ꂽ�l�̂����A��p���\�Ȃ̂͂킸��2���قǂ��B�������ߔN�A�V�����R����܂̓o��ŁA��p�\�Ȋ��҂������Ă���B �@����Ȃ�藧�Ă��������Ă���̂��A���É���w�a�@������O�ȏy�����̓���w��t���B�����t�͎�ᇓ��Ȃ͈̔͂ł���R����܂ɂ����ʂ��Ă���A�����̎��Â���g���Ċ��҂̗]�����Ԃ������Ă���B �@���ڂ��ׂ����Â͓�B�ЂƂ́A�u��p�s�\���X������A��p�\�ɂ���v���Ö@���B �u�X����́A��p�������ɉ\�ɂ��邩���A������]�߂邩�ۂ��̕�����ڂł��v�i�����t�j �@�傫���W���Ă���̂��A4��ނ̍R����܂����킹���t�H���t�B���m�b�N�X�ƁA�i�u�p�N���^�L�Z���Ƃ����V�����R����܂��B���ꂼ��13�N��14�N�ɍ����ŏ��F���ꂽ�B��������]���̍R����܂�苭�����ʂ����邱�Ƃ��A�Տ������Ŏ�����Ă���B �u�]���@�ɐV�����R����܂������A���Â̑I�����������܂����B������g�ݍ��킹�A��p�s�\�Ɛf�f���ꂽ�X������k��������̂ł��v�i���j �@���Ƃ��Ƃ́A�u��p�\���X����v���Ώۂ������B��p�O�ɍR����܂𓊗^���A�ꍇ�ɂ���Ă͕��ː����Â����邱�Ƃł���זE���k���A��p���\�ɂȂ�B������������@�́u�p�O�Ö@�v�ƌĂ�A�܂��X���ẪK�C�h���C���ɂ͒�߂��Ă��Ȃ����A����𒆐S�ɗp�����Ă���B �@����ɋߔN�A�u��p�s�\���X����v�ɑ��Ă��A��p�\�ɂȂ邱�Ƃ�ڎw���āA�R����ܓ��^����ː����Â������Ȃ���悤�ɂȂ��Ă����B��p�\���X����Ɏ{���̂Ƃ͈Ⴂ�A�u�ǂ��܂ł�邩�v�̌��ɂ߂�������A����ɂ���Ď��Ì�̏�Ԃ��傫���ς��B�������A���u�]�ڂ�����ꍇ�ɂ͂����Ȃ��Ȃ��B �@�É����ݏZ�̉�Ј��A�R�{�O�q����i�����E50�j��15�N5����CT�i�R���s���[�^�[�f�w�B�e�j�������ʁA�X�����������B���łɃX�e�[�W4�܂Ői�s����p���ł��Ȃ��B�u�R����܂𓊗^���Ă��A����p�ŋꂵ�ނ����v�ƈꎞ�͎��Â𓊂��o�����ƍl�������A���~�i������j�̖]�݂������ē����t�̊O������f�����B �@�R����܂���ː��Ŏ�p�\�ȂƂ���܂Ŏ����Ă����ꍇ�A�ǂ������u�헪�v���Ƃ邩�͈�t�̔��f�ɂ��B�����t�́A�t�H���t�B���m�b�N�X��������p���y���i�u�p�N���^�L�Z������g�p���邱�Ƃ������B �@�R�{����ɂ̓i�u�p�N���^�L�Z�����悭�����A���������Ȃ��Ă������B��8�J����ɂ́A�X���̂�������p�߂Ȃǂ���p�Ő؏��B��p�ォ��Ĕ��\�h�̂��߂̍R������Â��Ă��邪�A�����Ĕ��͂Ȃ��A�u5�N������0���v����̉\���������B�T��1��̍R������ÂɁA�O�����Ɏ��g��ł���B �@���ڂ���Ă��鎡�Â̂����ЂƂ́A�����d��ɑ���V�������Â��B�����d��Ƃ́A����זE��������������Ƃ͕ʂ̑���Ȃǂ��Ă��閌�ɁA����щ��Ă����Ԃ��B �@�����������t�́A����ȑ�w�Ƃ̋����Տ������Ƃ��āA�݂���◑������Ő��ʂ��o���Ă��鎡�Ö@�����p���Ă���B �u���Ȃ��Ƀ��U�[�o�[�Ƃ��������������݂��A�������畠�o���ɒ��ځA�R����܂̃p�N���^�L�Z���𓊗^���܂��v�i�����t�j �@�����̖��ǂ�S����ʂ��Ė�܂�Z��������̂ɑ��A����Ɍ������ă_�C���N�g�ɖ��t����Ƃ������ƂɂȂ�B �@�����t�Ƌ��������`�[���́A�X����ŕ����d��ɂȂ��Ă���33�l�Ɏ��{�B8�l���s�\��������p������悤�ɂȂ����B���̓��e�́A���E�I�Ɍ��Ђ̂����w�G���uAnnals of Surgery�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�B �u�������A�����d��͏������̂�CT�ł�������Ȃ����Ƃ������B�Ȃ̂Ŏ��́A�i�s�X����ł���ΐR�����o���������Ȃ��܂��v�i���j �@�R�����o���́ACT�Ȃǂ̉摜�f�f�ł͌��o�ł��Ȃ������]�ڂ�f�f�ł���B�����d�킪������Ȃ���A�R����܂���ː��Ŏ�p�\�Ɏ����Ă����B���Õ��j���傫���ς��̂ŕK�{�̌������Ƃ����B �u�X����Ŏ�p�s�\���ƌ����Ă��A�����Ă�����߂Ȃ��łق����B�w���Â�����x�ƌ����Ă��A���ЃZ�J���h�I�s�j�I�����Ă��������v�i���j dot. 2016�N6��14�� |
|
�A�Ŋ����������A�����L�b�g���p���}�� �������쏊�|�Z���t�@�[�}�A����҂Ɗ����҂̔A���̎��ʋZ�p���J�� |
| �@�������쏊�ƏZ�F�����q��Ђ̏Z���t�@�[�}�C���^�[�i�V���i���͂P�S���A�A�̂Ȃ��Ɋ܂܂�铜�⎉���Ȃǂ̑�ӕ���ԗ��I�ɉ�͂��邱�ƂŁA����ҁA�����ҁA�咰���҂̔A���̂����ʂ����b�Z�p���J�������Ɣ��\�����B����A���Z�p�����ƂɁA�A��p�����ȕւȂ������@���m�����A�����̎��p����ڎw���B �@�����ƏZ���́A�����̉t�̃N���}�g�O���t�A���ʕ��͌v�ƁA���Ђŋ����J��������̓\�t�g��p���āA����ҁA�����ҁA�咰���҂̊e�P�T�A���̂Ɋ܂܂���ӕ����ڍׂɉ�͂����B��ӕ��̐��n���⎉�n���̈Ⴂ�ɒ��ڂ��đ���������œK�����邱�ƂŁA���ꂼ��̔A���̂���]���̂Q�{�ȏ�ƂȂ�P�R�O�O�����ӕ������o�ł����B �@�������猒��ҌQ�A�����ҌQ�A�咰���ҌQ�̔A����ӕ����r�����Ƃ���A�ܗL�ʂ��傫���قȂ��ӕ����P�O���x���邱�Ƃ����������B�����̑�ӕ�������ҁA�咰���҂̔A���̂��i�荞�ރo�C�I�}�[�J�[�Ƃ��A�听����͂��s�������ʁA����ҁA�����ҁA�咰���҂��ꂼ��̔A���̂����ʂł����Ƃ����B�A���̑�ӕ�����͂��邱�Ƃœ�����Ȃǂ��ȕւɎ��ʂ����b�Z�p�̊J���͍������ƂȂ�B �@����A����ƃo�C�I�}�[�J�[���ƂȂ镨���Ƃ̊֘A���ڍׂɒ��ׂ�v��B��̓I�ɂ͓����ҁA����҂̊e�Q�O�O�A���̂�p���ėՏ��]�����������{�B�o�C�I�}�[�J�[�肵�A�����L�b�g����ڎw���Ă����B���R�f�Ẩ��ł̂��X�N�����Ƃ��Ď��p�����邩�A�̊O�f�f�p���i�i�h�u�c�j�Ƃ��ď��F�\�����邩�͖���Ƃ����B �@�����͈�Ë@�ւŌ��t���̎悵�Ď��{����̂��嗬�ƂȂ��Ă���B�ȕւŔ�N�P�ȔA��p���邪�������p���ł���A�ݑ�ł̌��̍̎悪�\�ɂȂ��f�������サ�A���������ɂȂ���Ɗ��҂���Ă���B m3.com 2016�N6��15�� |
|
�R�[�q�[�͂���̌����ɂȂ�Ȃ����Ƃ𐢊E�ی��@�ւ����\�@ �������M��������ݕ��͂���̌����ɂȂ� |
| �@�u�R�[�q�[���N������̌����ƂȂ锭���������܂ށv�ƁA�ߋ��ɐ��E�ی��@��(WHO)�͔��\���Ă��܂������A25�N�ɂ킽���ăR�[�q�[�Ƃ���̊W���������ꂽ���ʁA�u�R�[�q�[�͂���������N�����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��킩��܂����B����ŁA��ނɊW�Ȃ��u�M��������ݕ��v������������N�����\��������ƕ���Ă��܂��B �@WHO�̔��\�ɂ��ƁA�R�[�q�[���N�������łȂ��X������E�O���B����Ȃǂ̌����ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA�ނ���̑������q�{����ȂǁA20��ވȏ�̂��X�N�����炷���Ƃ��ł��邱�Ƃ����������Ă��܂��B �@WHO�̎w�j�̓]���́AWHO�̊O���g�D�ł��鍑�ۂ����@��(IARC)���R�[�q�[�Ƃ���Ƃ̊W����������1000�ȏ�̘_�����Ē����������ʂ������́B�����𗦂���IARC�̃f�C�i�E���[�~�X���m�́uIARC�����߂ăR�[�q�[���w������̉\����������́x�ɕ��ނ���1991�N����A�R�[�q�[�Ɋւ���Ȋw�I�Ȓ������ʂ͂ǂ�ǂ��Ă����A�M���������܂��Ă��܂����v�ƌ���Ă���A�ߋ��̌����̔팱�҂̒��ɂ͋i���҂��������ƂȂǂ�����A�R�[�q�[�Ƃ���̊Ԃɂ́u�R�[�q�[���A����̃��X�N�����点��Ƃ����W������v�ƁA����܂ł̔��\�Ƃ͐^�t�̌��_�Ɏ������Ƃ̂��ƁB���݁AIARC�̓R�[�q�[��A���R���̉��w�����ɂ��R�����p��������ݕ��Ƃ��ċL�^���Ă��܂��B �@IARC���u������̉\��������v�Ǝw�肵����������Ɏ�艺���邱�Ƃ͏��߂Ăł͂Ȃ����̂́A�߂����ɋN����Ȃ��o�����������ł��B �@����ŁAIARC�́u�M��������ݕ���ێ悷�邱�Ɓv������������N�����Ɣ��\�B�܂��؋��͌���I�ł�����̂́A�u�������Ăł̓A�����J�E���[���b�p���6�x�قǍ����ێ�70�x�߂��̈��ݕ���ێ悷��v�Ƃ��������ɒ��ڂ��������ŁA�H������Ɓu�M��������ݕ���ێ悷�邱�Ɓv�̊Ԃɂ͊W�����邱�Ƃ���������܂����B �@�A�����J��National Coffee Association�ɂ��ƁA�A�����J�l�͕��ς���1��3�t�̃R�[�q�[��ێ悵�A2015�N�ɂ����ăR�[�q�[�Ɏx����ꂽ���z�͑S�̂�742���h��(��7��8���~)�������Ƃ̂��ƁB�A�����J�ȊO�ł����E���ŃR�[�q�[�̏���ʂ͑����Ă��܂��B �@National Coffee Association�̓R�[�q�[��90�x�`96�x�Œ��o���邱�Ƃ������߂Ă��܂����A���ޑO�ɂ͓K�ȉ��x�ɂȂ�܂ŗ�܂��ׂ��ł���Ƃ��Ă��܂��B GIGAZINE 2016�N6��16�� |
|
�����a���X������ɊW�H 2�̌����ەێ��҂̂����������� |
| �@�j�[���[�N��w�̌����ɂ��ƁA�X������̔��Ǘ��Ǝ����a�������N����������2��ƊԂɂ͑��֊W���������B �@�����2��ނ̍ۂ����o���ɏZ�݂��Ă���l���X������ɂȂ������������������Ƃ������A�ʂ����Ă��̐^���́H �u�X���v�̂���̏����Ǐ��?�@�u�r�̈߂��܂Ƃ����T�v�Ƃ� �@�X������͍ł����낵���u���i����j�v�̈���낤�B �@�X������́A�����ɂ͂قƂ�ǎ��o�ǏȂ��A�������i�s�������B�܂��A���͂̑g�D�֓]�ڂ��₷�����߁A�������ꂽ���ɂ͂��łɂ��Ȃ�i�s������Ԃ̂��Ƃ������A�E�o��p���s���Ȃ����Ƃ������B �@�c�O�Ȃ���A�X�������5�N��������10���`20���Ƃ����Ă���B �@�X������̏����ɂ́A�w���̒ɂ݁A���t�i��������j�A�̏d�̌����Ȃǂ̏Ǐ����邱�Ƃ����邪�A�ǂ���X������Ɍ������Ǐ�ł͂Ȃ��A������X������������Ă��܂��v���ł���B �@�X������̂��̂悤�ȓ����́u�r�̔�𒅂��T�v�ɗႦ���邱�Ƃ�����B �����a�ۂ��X������̃��X�N�����߂�H �@�j���[���[�N��w�̌����O���[�v�͔팱��732�l�ɂ��Ă̒ǐՒ�����10�N�ȏ�ɂ킽���čs�����B �@���̌��ʁA����2��ނ̌����ۂ��X�������Ƃ̊Ԃɑ��֊W������ꂽ�̂ł���B �@P.gingivalis�i�|���t�B�����i�X�E�W���W�o���X�j�Ƃ����ۂ������Ă����팱�҂́A���̋ۂ������Ă��Ȃ��l�ɔ�ׂĖ�1.6�{�A�܂��AA.actinomycetemcomitans�i�A�N�`�m�o�`���X�E�A�N�`�m�~�Z�^���R�~�^���X�j�Ƃ����ۂ������Ă���팱�҂ł́A��2.2�{���X�������������������Ƃ��������̌��ʂ������ꂽ�B �@����2�̍ۂ͂Ƃ��Ɏ����a�̌����ۂł�����B �����̎����a���X������̊W�@���߂���T�d�ȉ��� �@����A�X������ƌ����ۂƂ̊ԂɊ֘A��������ꂽ�킯�����A����͂����܂ł���͏�́u���֊W�v�ł����āu���ʊW�v�ł͂Ȃ����Ƃɒ��ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�����̌����ۂ��X������������N�����̂��A�܂��A�����N�����Ƃ�����ǂ̂悤�ȍ�p�ň����N�����̂��B�����͍��̂Ƃ���S���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B �����a�ۂ��X��������Ȃ��~�b�V���O�����N �@�����K���̗���́A�������A�S���a�A�]�����A�얞�A���A�a�A����Ȃǂ̗v���ƂȂ邪�A���l�Ɍ��o���̉q��������������B�]���āA�X������̔����Ǝ����a�ۂ̔ɐB�ɋ��ʂ��錴���́A�����K���̗���Ȃ̂�������Ȃ��B �@���������̈���ŁA�����a�ۂ��X������������N�����Ƃ�������������B�����a�ۂɂ�鉊�ǂ��g�D�ɔg�y���A����̈������ƂȂ�Ƃ����l�����ŁA���̉\�����[���ł͂Ȃ��B �����a�\�h��O�ꂷ�邱�Ƃł����\�h�ł��関��������? �@�����A�������Ƃ��X�����h����Ƃ�����A�ǂ�Ȃɑ����̐l���~���邾�낤���B�܂��A����⎕�Ȉ�@�ő��t�Ȃǂ��������邱�ƂŊȒP���X�����X�N��]���ł���悤�ɂȂ邩������Ȃ��B �@���̂Ƃ��뎕���a�ۂ��X������̈��ʊW�͖��炩�łȂ��B����̌����̐i�W���҂����Ƃ��낾�B������ɂ��Ă��A�����������Ŏ����������薁�����Ƃ��܂߁A�����K���𐮂��邱�Ƃ����N�ɂ͑�ł���B CIRCLE 2016�N6��17�� |
| ���DNA�̕ψق�\���A��ܑϐ��ւ̌ʉ���ÂɗL�p�ł���\�� |
| �@����̐��m�Ȑf�f�⎡�Ö@�̑I���ɍۂ��āA�]���̐����ɑ�����̂Ƃ��āA���t��p����u���L�b�h�E�o�C�I�v�V�[�i�t�̐����j�v�̗L�]���������ꂽ�B�����𗦂����ăJ���t�H���j�A��w�f�[�r�X�Z�iUCD�j��������Z���^�[��Philip Mack���ɂ��ƁA���L�b�h�E�o�C�I�v�V�[�ł́A��ᇂ��猌�t���ɗ��ꍞ��DNA�͂���B �@�������1��5,000�l�ȏ��ΏۂƂ��āAGuardant360�ƌĂ��V�^�̈�`�q�X�L������p���Ċ��҂̌��t����DNA�͂��A70��ނ̂���֘A��`�q�ɂ�����ˑR�ψق̗L���ׂ��B�{�����͂��̌������J������Guardant Health�Ђɂ�鎑�����Ď��{����A�ăV�J�S�ŊJ�Â��ꂽ�č��Տ���ᇊw��iASCO�j�N���W��Ŕ��\���ꂽ�B �@��ᇂł͐V���ȕψق��l�����邱�ƂŎ��Âւ̒�R����������B���̂��߁A���̌����ɂ�����̎��Âɑ����R�������m�ł��A�W�I���Â�p�����t�ɂƂ��Ă��d�v�ȏ������Ƃ����B����̌����œ��ɂ悭�݂�ꂽ����̎�ނ́A�i�s���x����i37���j�A������i14���j�A�咰����i10���j�ł������B �@��ᇂ��猌�t����DNA�����o����邱�Ƃ͐��\�N�O����m���Ă������A�����̑�p�ƂȂ邩�ǂ�������ɖ��ł������ƁAMack���͐�������B����̌����ŁA���t���̎��DNA����A��ᇌ��̂ɂ��݂��锭���̕ψق��ɂ߂Đ��m�Ɍ��m�ł��邱�Ƃ����������B �@����398�l��ΏۂɁA���L�b�h�E�o�C�I�v�V�[�ł̈�`�q�����̌��ʂ��Ɣ�r�����Ƃ���A94�`100���̊m���őg�D���̂Ɠ����ψق����t���̂ɂ��܂܂�Ă����B�܂��A��ᇂ���܂ւ̑ϐ����l�������Ƃ��ɂ݂���ω������o�ł��邱�Ƃ��킩�����B�����������ґS�̂�63�����ł́A���L�b�h�E�o�C�I�v�V�[�ɂ��A�č��H�i���i�ǁiFDA�j�ŏ��F�������͗Տ������Ō��ʂ��m�F����Ă����܂��痘�p�����鎡�ÑI���������������B �@���L�b�h�E�o�C�I�v�V�[�̔�p�͏]���̐����Ɠ����x�ɂȂ�Ɨ\�z����Ă��邪�A�����_�ł́A����̏����f�f�ɂ͈ˑR�Ƃ��đg�D�����ƕa���f�f���K�v���Ƃ����BMack���́A�u�n�������a����͑g�D���̍זE�̊O���⋓������قƂ�ǂ̎�ᇂ̎�ނ��킩��B���Ƃ��A�̑�����̎悵���a�ς����͔x�������ƌ������邱�Ƃ�����v�Ɛ����������A���L�b�h�E�o�C�I�v�V�[�̐^���́A����̐i�s���o���I�ɊĎ�����ۂɔ��������Ƃ̌����������Ă���B �@�ʂ̐��Ƃ�́A����̊��҂ł͐f�f�ɂ����Ă����L�b�h�E�o�C�I�v�V�[���L���ȑ�֎�i�ɂȂ肤��Ǝw�E���A��Ƃ��ĊO�ȓI���u�ɓK���Ȃ�����҂⌒�N��Ԃ̈������ҁA���]�⍜�ɓ]�ڂ������ҁA�o�����X�N�̍������҂Ȃǂ������Ă���B�܂��A����̌����ł͈�`�q�Ɋ�Â����Âɏœ_�ĂĂ��邪�A����Ɖu�Ö@�̌��ʂ�\�����錟�����J���ł���\��������Ƃ����B m3.com 2016�N6��20�� |
| ���o��95��!�l�H�m�\��p���Ă���זE����肷����@��ĉȊw�҂����� |
| �@��r�I���x�������Ƃ���邪��f�f�@�̑����́A�f�f���Ɏg�p���鐶�̕W���ɂ��זE�ւ̃_���[�W�����O����Ă���B �@���̌���Ŕj�ւ̓˔j���ƂȂ蓾�邪�A�J���t�H���j�A��w���T���[���X�Z�A�J���t�H���j�A�E�i�m�V�X�e���������̃o�[�n���E�W���������������錤���O���[�v���J�������A�l�H�m�\�ɂ�邪��f�f�@���B �E�Ǝ��ɊJ���������������g�p �@�܂����ڂ��ׂ��́A����f�f�Ɏg�p���錰�����ł���B����̓W�������������g���Ǝ��ɊJ���������̂��B�A�i���O�]�f�W�^���ϊ��킨��эL�ш�̓������ԃT���v�����O�E�I�V���X�R�[�v�̗��_�����ꂼ��ő���Ɋ��������Ǝ��̌��q���ԉ��L�Z�p�œ������̌������́A���łɓ������擾�ς݂ł���B �@�������̃��J�j�Y���ɂ��ẮA�t���b�V�������ĎB�e����J�����Ǝ��Ă���B���[�U�[�̔j��ƂƂ��Ɍ��Ǔ��𗬂�錌�t�זE���B�e����d�g�݂ƂȂ��Ă���B �@1��̃v���Z�X�̓i�m�b�A�܂�1�b��10������1�Ƃ��������ŏu���ɍs����B���������āA1�b�Ԃɂ�3600�����ɂ��y�ԉ摜���B�e�E��������邱�ƂɂȂ�B �E�[�w�w�K�ł���זE�Ɣ�זE����� �@�����āA�l�H�m�\�̏o�Ԃł���B �@�ꌾ�ɐl�H�m�\�ƌ����Ă��w�K��@�͂��܂��܂ł��邪�A�����Ŏg�p����̂͐[�w�w�K�i�f�B�[�v���[�j���O�j���B �@���̕��G�ȃA���S���Y���Ɋ�Â��A�f�[�^����͂��A�傫���E���x�E�����ʂ��܂ތv16�_�̓����𒊏o����B���̌��ʁA95�p�[�Z���g�̊m���ł���זE����肷�邱�Ƃ��\�ł���B �E�זE��j�Ȃ� �@�ʏ�A�ق�̂킸���Ȏ��Ԃł̎B�e�ɂ́A���Ɠx���ł̎��{�����߂���B����ɔ����A�זE���j��A��͂��s���Ȃ��Ȃ鋰�ꂪ����B �@����A����̂���f�f�@�͒�Ɠx���ōs���邽�߁A�זE�ւ̃_���[�W�̋���͂Ȃ��B �@������@�ɁA����ɑ���m��ꂴ��V���ȑ��ʂ̉𖾂Ɍ����A����O�i���邱�Ƃ����҂������B �}�C�i�r�j���[�X 2016�N6��21�� |
| �u�N���\���v���ĉ������n���Ȗ�@���͂���\�h�Ɍ��ʂ��肻�� |
| �@���{�l�̎��S������1�ʂ́u����v�B�N�Ԃ��悻37���l�̐l���S���Ȃ�A���̐��͔N�X�����Ă���Ƃ����A���낵���a���B �@����Ȃ���ւ̗\�h���ʂ����҂ł���������B������A�݂����咰����A������܂ŁA�l�X�Ȃ����\�h����\�������Ƃ����B ���[���f�B�b�V���̕t�������̃C���[�W������������A�����H�ׂ�R�_���͂��A�b�v �@�C�ɂȂ��̖��O�́u�N���\���v�B�u�C�\�`�I�V�A�l�[�g�v�Ƃ����h�{�f���܂ށA�A�u���i�Ȃ̖�̈�킾�B �@�C�\�`�I�V�A�l�[�g�Ƃ́A��Ɋ܂܂��h�������̈�ŁA�̓��ɓ���ƍR�_���������ʂɍ��B�������R�_���������S�g�̍זE���ɂ���L�Q�Ȋ����_�f�ʼn����A����̔�����}����ƍl�����Ă���B �@�����̐��E�I���Ђł���u���ۂ����@�ցv�iIARC�j�̔��\�ł��A�u�u���b�R���[�A�L���x�c�A�N���\���ȂǁA�A�u���i�Ȗ������̃��X�N������������v�Ǝw�E�����قǁA���ʂ����҂ł����Ȃ̂��B �@���ł��N���\���́A100�O����������̃C�\�`�I�V�A�l�[�g�̊ܗL�ʂ��A�u���i�Ȗ�̒��Ń_���g�c�ɑ����B1���ɂǂꂭ�炢�H�ׂ���悢�̂��A�����_�ł͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ����A����I�ɐێ悷��Ό��ʂ����҂ł���ƍl�����Ă���B�����A�ߏ�ێ悪�t�@�\��Q�������N�����Ƃ���������A�H�ׂ����ɂ͗v���ӂ��B �M���[�U�ɍ������сA�V�Ղ�ɂ��Ă��������� �@�t�����킹�Ɏg���C���[�W�������A�����@���킩��Ȃ��l�������������A�N���\���_�Ƃł́u�N���\������M���[�U�v�u�N���\���̃T���_�v�u�N���\������ꂽ�X�[�v�E�݂��`�v�u�N���\���̍������сv�u�N���\���̂��Ђ����v�u�N���\���̓V�Ղ�v�u�N���\������O���^���v�ȂǂȂǁA���V�s�͗l�X���B �@�ԑg�ł́A�����H�ׂĂ���N���\���_�Ƃ�28�`81��6�l�́A���t���̍R�_�������̗ʂ𑪒肵���B����ƁA4�l�����N��̕��ς�葽�����l�ɁB����49�̏�����20�̕��ς����y���ɍ������l���o���B�N���\������X�H�ׂ邱�ƂŁA����\�h�ɂȂ���R�_���͂��グ���\��������B J-CAST�j���[�X 2016�N6��23�� |
|
������������\�h�ɂȂ邩���H���z������Ƃ̊֘A�� 2���l�̃f�[�^�̉�͂��� |
| �@���̒��ȂǁA�������ɂ����Ă̏ꏊ�ɂł��邪��i���z������j�́A�i��������ɂ���Ăł��₷���Ȃ�܂��B����Ɏ��̉q�����W���Ă��邩�ǂ����ɂ��āA�f�[�^�̉�͂ɂ�錟�����s���܂����B �����z�����o�Ȃ������l�͎����������Ă������H �@�����ŏЉ�錤���́A�ߋ��̌����œ���ꂽ�f�[�^���g���āA���̉q����ԂƓ��z������̓��v�I�֘A�ׂ����̂ł��B �@�ǐՒ����Ŏ��̏�Ԃƕa�C�̔����Ȃǂ����ꂽ�Ώێ҂̂����A���z������Ɛf�f���ꂽ8,925�l�ƁA���z������ł͂Ȃ�����12,527�l���r���邱�ƂŁA���Ƃ��Ǝ��̏�Ԃ��悩�������ǂ����ɈႢ�����邩�ׂ܂����B �@���̏�Ԃ�]�����邽�߂ɁA�����ȂǂŎ��������i�r�����j�̐��A���������������邩�A���N���Ȉ�ɂ������Ă��邩�A�����̕a�C���Ȃ����A�����ꎕ�i���`���j���g���Ă��邩���w�W�Ƃ��܂����B ������������l�œ��z�������Ȃ� �@���̌��ʂ������܂����B �@�����ǂ���̕����ɁA���炩�̓��z������Ƃ̕��̊֘A���A�r����5�{�����i�I�b�Y��0.78�A95%�M�����0.74-0.82�j�A���N���Ȏ�f���邱�Ɓi�I�b�Y��0.82�A95%�M�����0.78-0.87�j�A���������������邱�Ɓi�I�b�Y��0.83�A95%�M�����0.79-0.88�j�A�����������Ȃ����Ɓi�I�b�Y��0.94�A95%�M�����0.89-0.99�j�ɑ��Ċώ@����A���`�������Ƃ̊֘A�͊ώ@����Ȃ������B �@�r���������Ȃ��A����������������A���N���Ȃɍs���A�����̕a�C���Ȃ��l�ŁA���ꂼ�ꓪ�z������̔��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���`���Ƃ͊֘A�������܂���ł����B �@�����ǂ́u�r���������Ȃ��A���N���Ȃɍs���A���������������邱�Ƃ�����Ƃ���A���̒��̉q����Ԃ��ǂ����Ƃ́A���z������̃��X�N���킸���Ɍ��炷��������Ȃ��v�ƌ��_���Ă��܂��B �@�������Ō��̒��𐴌��ɕۂ��ƂŁA�ق��ɂ����N�ɗǂ����ʂ��������Ă��܂��B������Ă����������H�����y���ނ��߂ɂ��A�������̏K�������܂��傤�B ���Q�ƕ��� The role of oral hygiene in head and neck cancer: Results from International Head and Neck Cancer Epidemiology (INHANCE) Consortium. Ann Oncol. 2016 May 27. [Epub ahead of print] medley 2016�N6��24�� |
| ����̍ŐV���Õ��@�I���f�Ö@�͌��ʃA���H�i�V�H |
| �@�ߔN���܂��܂Ȃ��Ö@���m������A���Â̑I�����������Ă���̂͂������Ƃł����A�u������Ė{���Ɍ��ʂ�����́H�v�Ǝv���Ă��܂����̂�����܂��B �@�����ŁA����͍ŋߘb��̐��f�Ö@�ɂ��āA��t�ɉ�����Ă��������܂����B ���f���ĂȂ�ł����H �@���f���q�Ƃ́A�퉷�Ŗ��F���L�̋C�̂ł���A���q�ʂ����������Ɍy���C�̂ł��B �@���w�I�Ȑ����Ƃ��ẮA�_���܂�A�Ҍ��܂Ƃ��ē������Ƃ��m���A�_�f�Ɛ��f����������Ƃ��͐��f�͊Ҍ��܂Ƃ��ē����āA�����I�ȔR�Ă��N�����������邱�Ƃ��m���Ă��܂��B �@�܂��A�F���ɂ����Đ��f�́A�ł��������݂��錳�f�ł��邱�Ƃ��m���Ă��܂��B ���f��ێ悷�邱�ƂŐg�̂ɂǂ̂悤�ȉe��������܂����H �@���f��ێ悷�邱�Ƃɂ���āA�������̐g�̂ɗL�Q�Ƃ����Ă���ߏ�Ȋ����_�f����菜���A�����_�f�ɂ��g�D�̏�Q��}������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����������܂��B �@�ߏ�Ȋ����_�f�́A�Ⴆ�Ύ��O������ː��𗁂т���A�i���A�ߓx�Ȉ����Ȃǂɂ���Ĕ������邱�Ƃ��m���Ă���A�X�g���X�������_�f�̔����𑣐i����d�v�Ȉ��q�ł��B �@�����ɂ���Ĕ������������_�f�̂����A���Ɏ��͂̑g�D���_��������͂������A�_���[�W��^���₷���^�C�v�̊����_�f����������\��������̂ł͂Ȃ����A�ƍl�����Ă��܂��B ���f�͂ǂ̂悤�ɃK���זE�ɉe�����܂����H �@����זE���̂́A�����K���̗���ɂ��ߏ�Ȋ����_�f�̉e���Ȃǂ��āA���������ꂼ��̑̂ɖ����������������Ă��܂����A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�̂ɔ�����Ă���Ɖu�@�\�ɂ���Đ��̂��珜������Ă��܂��B �@�������A�̖̂Ɖu�͂��ቺ���Ă�����A�����_�f���ߏ�ł��邱�ƂȂǂɂ���āA����זE�����ł�����ꂸ�A�̂̒��ő��B���Ă��܂��ꍇ������܂��B���ꂪ����̔����ł���ƍl�����Ă��܂��B �@���̔����𐅑f�̂������_�f����������͂𗘗p���đ̂̍R�_���͂����߁A����זE�̔�����B��}���悤�Ƃ����̂����f�Ö@�ł��B �@�܂��A���f�ɂ̖͑̂Ɖu�̏d�v�ȗv�ł��锒�����̊��������߂Ă������ʂ�����Ƃ������Ă��܂��B �K�����Âɂ����Đ��f�͂ǂ̂悤�Ɏg�p����܂����H �@��ʓI�Ɉ�Â̈ꕔ�Ƃ��čs���Ă����Ë@�ւ͂܂��������Ȃ��悤�ł����A���f�K�X�̋z����A���f�𐅂ɗn�����������̈��p�Ȃǂ��s���Ă���悤�ł��B �@���f�Ö@�̗l�X�Ȏ����ɑ���L�p�����������_�������������\����Ă���悤�ł����A���i�K�ɂ����ẮA���炩�Ȍ��ʂɊւ���m�͓����Ă��炸�A�܂������i�K�ɂ��鎡�Â̈�ƍl�����܂��B ��t����̃A�h�o�C�X �@����ɂ͐V�������Ö@�����X�ɊJ������Ă��āA�ȑO�͎���ɂ�����������Ȃ���₠����x�i�s��������Ȃǂ������Ԃ�₷������ɂȂ��Ă��Ă��܂��B �@�������A����͐[���ȕa�C�ł��̂ŁA�܂��͂�������m���������Â������Ȃ����Ƃ�������ł����A����̉\���̈�Ƃ��Đ��f�Ö@�ɂ�邪�Âɂ����҂��������ł��B �K�W�F�b�g�ʐM 2016�N7��1�� |
| �u�T�J���l�Y�~������l�ނ��~�� |
�@����ɂȂ�̂̓q�g�����ł͂Ȃ��B�����g�����l�Y�~���C�k���l�R������ɂȂ�B�Ƃ��낪�A�t���J���Y�̏������n�_�J�f�o�l�Y�~�͒����̏�ɂ���ɔ��ɂȂ�Â炢�B���̔閧������������{�̌����҂��������B ���n�`��A���Ɠ����Љ� �@�n�_�J�f�o�l�Y�~�i�ȉ��f�o�j�́A���̂ő̒�10�Z���`�قǁ��ʐ^�B�u�ςȓ��̖т̂Ȃ���v�Ƃ����w���t���ŕ��ꂽ�̂�19���I�I��肾�������A1981�N�u�T�C�G���X�v���Ɍf�ڂ��ꂽ��҂̘_�������ڂ��ꂽ�B �@����ɂ��ƃf�o�́A�ɐB��S����C�̏����A1�`���C�̉��̑��́A���@��A�q��āA�a�̒��B�A�O�G�̌��ނȂǂ����[�J�[�ƕ��������Ƃ���u�J�[�X�g�Љ�v������Ă���Ƃ����B����̓n�`��A���Ȃǂ̍����ł��Ȃ��݂ŁA�i���w�҂́u�^�Љ�����v�Ɩ��Â��Ă������A�M���ނł͖��������B����ȎЉ�����M���ނ́A���܂��Ƀf�o�Ƃ��̋߉��̈��݂̂����m�F���Ȃ��B �@90�N�ォ��A�s�����Ԋw�҂�i���w�҂��f�o���������Ŏ��炵�n�߂��B���{�ł������̃R�~���j�P�[�V���������ʼn��m�J��v����i���E������w�����j�������w�������ȂǂŃf�o�����炵�Ă����B �@���̂����s�v�c�Ȃ��Ƃ��킩���Ă����B�����悤�ȑ傫���̃}�E�X�̎����͂�������2�`3�N�Ȃ̂ɁA�f�o�̎����͂��̏\���{�̕���28�N�B40���钷���҂����ꂽ�B������8���ȏ�̊��ԂŘV���̒���͂قƂ�nj������A���R�̏�Ԃł�������邱�Ƃ��Ȃ��A��2010�N�O��ɕ��ꂽ�B �@���݁A���{�Ńf�o���������Ŏ����Ă���̂́A�k�C����w��`�q�a���䌤�����̎O�Y���q�u�t�̌����������ł���B �@���x�E���x�Ǘ����Ȃ��ꂽ���玺�ɂ́A�������̃A�N���������̔����p�C�v�łȂ����u�[���g���l���v�����ׂ��A��200�C�̃f�o�����傱�܂��Ɠ�������Ă���B�傫�Ȃ��������������Ă���͔̂D�P�����������B�쐶�ł͍��������������Ă���f�o���A�����ł̓C���A�j���W���Ȃǂ�H�ׂĂ���B ����d�̂���h��@�\ �@�O�Y����̐��͕��q�����w�ł���B���ꂪ�Ȃ��f�o�H �u�ςȐ��������D���v�B���m�_���̌������قڏI���A���̃l�^�T�������邤���Ƀf�o�ɏo������B�ʔ��������Ɏ䂩�ꂽ�B�����w�������̉��m�J�������ɒʂ��Ď���@��`�����Ă�������B���̃f�o������������炢�A11�N�A����h�V�c��`�m��w�����̎x���ł��̌������Ɏ��玺��������B14�N�ɂ͂܂邲�Ɩk��Ɉڂ����B �@�����̖ڕW�́A�������f�o�̒����Ƃ���ϐ��̉𖾂ł���B�u�ŏ���iPS�זE����낤�v�ƁA�f�o�̔畆�זE�ɎR�����q�Ƃ����l�̈�`�q�����đ��\���̂���iPS�זE��������BiPS�זE�͓��ʂȃl�Y�~�̔畆�ɈڐA�����ƁA���B���āu��`��v�Ƃ������̂�������B����͑��\���̏ؖ��̂ЂƂ��B �@�Ƃ��낪�f�o��iPS�זE�͈ڐA���Ĕ��N�����Ă����������Ȃ��B�u�f�o�̂���ϐ��ɊW�H�v�ƎO�Y����͍l���A���̃��J�j�Y���ׂ��B �@���N5���̔��\�ɂ��ƁA���͓�̎d�g�݂������B��`������̂ɓ����͂���ERAS�Ƃ��������`�q���@�\�������Ă������ƁB������́A�ʏ��iPS�זE�ł͓����Ȃ�����}����`�qARF���A�f�oiPS�זE�ł͓����Ă��āA���������ꂪ�����Ȃ��ꍇ�́A�זE��V�������đ��B���~�߂�f�o���L�̂��}�����J�j�Y�����������Ƃ�˂��~�߂��BARF�̓q�g�������Ă��邪�A�f�o�̂悤�ȓ�d�̖h��@�\�͒m���Ă��Ȃ��B �@���̃��J�j�Y���𖾂ƁA�f�o�̒������x�����`�q�𖾂����̖ڕW���B�f�o�͏ȃG�l�������B�}�E�X�Ɣ�ׂ�Ƒ̉���5�x�Ⴂ32�x�A�S������3����1��1��180�B�������l�X�ȑϐ��ɊW���邩�B �u�q�g�ɂ����g���邩�ǂ����킩��Ȃ����A�f�o�̓����͖{���ɖʔ����B�����҂ɂƂ��ĕ�̎R���Ǝv���܂��v�ƎO�Y����͌����B dot.�h�b�g 2016�N7��3�� |
|
���[MRI�̎B�e���̎p�������x�ɉe�� ����ʂɂ���ᇈʒu���ω�����\�� |
| �@������̎�p�O��MRI�摜���B�e����Ƃ��A���҂�����ʁi���Ԃ��j�̎p��������Ă���Ɛ��m�ȃf�[�^�������Ȃ��\�������邱�Ƃ��A�ău���K���E�A���h�E�E�C�����Y�a�@�i�{�X�g���j�̕��ː��Ȉ��ɂ�鏬�K�͌����Ŏ����ꂽ�B����ɑ��A��ʁi�����j��MRI�ł͏ڍׂ����m�ȏ��邱�Ƃ��ł��A���ʓI�Ȏ�ᇓE�o�ɂȂ���ƁA�����𗦂���Eva Gombos���͏q�ׂĂ���B �@�����҂����[������ᇓE�o�p����Ƃ��A��ʓI�ɂ́A��ᇂ̑傫���E�`��E�ʒu���m�F���邽�߂ɓ��[MRI���p�O�Ɏ��{�����B�ă��m�b�N�X�E�q���a�@�i�j���[���[�N�s�j��Kristin Byrne���́A�u���[MRI�̖{���̗��_�́A�����܂��͑Α��̓��[�ɕʂ̂��Ȃ������p�O�ɖ��炩�ɂ��邱�Ƃɂ���v�Ɛ�������B �@���̂Ƃ��AMRI�͕���ʂŎ��{����邱�Ƃ������B���̗��R�́A��ʂɂȂ�Ɠ��[�����܂��܂Ȋp�x�Ře�ɐ��ꉺ���邽�߁A�B�e�̂��тɌ�����������Ă��܂����߂��Ƃ����B�������A���҂���p����Ƃ��ɂ́A�B�e���Ƃ͋t�̎p���ł����ʂ��Ƃ邱�ƂɂȂ�ƁA�����O���[�v�͎w�E���Ă���B �@����̌����ł́A���B��ᇓE�o�p���������12�l�ɒ��ځB�ŏI�I�ɂ��̂���6�l���A��p�̑O��Ƃ��ɋ�ʂœ��[MRI���B�������B�S�̂Ƃ��āA����ʂ�MRI�����ꍇ�A���[����ѓ��[���̎�ᇂ̈ʒu�ɁiMRI�X�L������Łj�����ȕό`���F�߂�ꂽ�B���̒m���́uRadiology�v�I�����C���ł�6��22���f�ڂ��ꂽ�B �@�W���I�ȕ���ʂ̉摜�ƁA��p���̋�ʂ̎p���Ƃ̊Ԃł́A��ᇂ͕ψʂƕό`�ɂ��傫����`�ω����Ă����ƁAGombos���͕��Ă���B���̂��Ƃ���A�����̏�Ȓ��҂ł���Mehra Golshan���́A��ʂƕ���ʂ̗�����MRI�����{����A�c�������ᇂ����o���鏕���ƂȂ�A�Ď�p��h�����߂̐؏��}�[�W�����m�ۂł���Ƃ̍l���������Ă���B���[������p���鏗����15�`40���͎c����ᇂ�E�o���邽�߂̍Ď�p���K�v�ɂȂ�ƁA�����͎w�E����B �@Gombos���́A����̌����͏��K�͂ł��邽�߁A����ɑ�K�͂Ȍ����ɂ�錟���K�v�ł���Ƌ������Ă���BByrne���́A����̌��_����m�ł��錋�_�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��A�u���[MRI��ʂŎ��{����̂́A�p���Ɉ�ѐ����������邽�߂��B����͌�̎B���Ōo�߂��݂邽�߂ɏd�v�ł���v�Əq�ׂ�ƂƂ��ɁA��p���O��MRI���{�ɂ͗]���Ȏ��Ԃ�K�v�Ƃ��邽�߁A�����ǂ▃���֘A�̃��X�N�����܂�Ƃ������_������Ǝw�E���Ă���B m3.com 2016�N7��4�� |
| �����~����!? ������95���̂������@�Ƃ́H |
| �@������������Ƃ�����u����v�ł����A���̌������@�͂��܂��܂ł��B�ŋ߂ł́A�Ȃ�Ɗ��ł���u�����v��p��������̍ŐV�������@����������Ă��邻���ł��B �@����́A���́u�����v��p��������̌����ɂ��Ĉ�t�ɏڂ����b���Ă��܂����B �����Ƃ͂Ȃ�ł����H �@�����Ƃ́A���`������ɕ��ނ����ג��������̑��̂ł��B �@�C���[�W�I�ɂ�1�~�����炢�̒����̂��̂��z�����₷���ł����A�l�Ԃ₻�̑��̓����̒��ǂȂǂɊ�����̂̒��ɂ́A�Ȃ�ƒ�����1���[�g���ȏ゠����̂����܂��B �@���ɑ����̎�ނ����݂��A�����݂͂�����킩���Ă�����̂�����2������̐������n����ɑ��݂��Ă��܂��B�R�̏ォ��C��܂ŁA�ƂĂ��L���͈͂ɐ������Ă��邱�Ƃ��m���Ă��āA���ɊC�ɂ��ސ����Ɋւ��Ă͂܂��m���Ă��Ȃ����̂��A���������݂���̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B �������ǂ����p���Č������s���̂ł����H �@����́uC.�G���K���X�v�ƌĂ������̚k�o�𗘗p�������̂ł��B����������܂߁A���҂̔A�ɂ́A�l�Ԃɂ͂����������Ȃ����̂́A���k�o�̔��B���������ɂ͈Ⴂ��F�m�ł���Ǝv����u�Ɠ��̂ɂ����v������܂��B �@���ɉs�q�Țk�o��������C.�G���K���X�́A�D���Ȃɂ����ɂ͐ϋɓI�ɋ߂Â��Ă����A�����Ȃɂ�������͉�������A�Ƃ��������������Ă��܂��B�����ŁA���҂̔A�ɂ�C.�G���K���X���߂Â��Ă����A���Ȃ��l�̔A����͉��������Ă����A�Ƃ������ɋ����[�����ۂ�����ꂽ�����ł��B �����𗘗p���������̐��x�̍����́H �@�������ʂɂ��ƁA95.8�����̊m���ł��҂ƁA�����łȂ��l�̔A�������������Ƃ������Ƃł��B �@�����C.�G���K���X���A���ɉs�q�Țk�o�������Ă���Ƃ����A�����ׂ����ʂƂȂ�܂����B �����𗘗p���������ɂ����郁���b�g�́H �@�܂��A���҂ɂƂ��ĕ��S�̏��Ȃ������ł���Ƃ������Ƃł��B �@�܂��A�ȑO�ɂ́A�k�o���s�q�ł��錢�ɂ���ĔA������������������@���l�����Ă��܂������A�������̔A�����������Ă��邤���Ɍ����g�A�k�o���敾���Ă��܂��A�p�����̂��錟���@�Ƃ���͍̂���ł����B �@���̓_�AC.�G���K���X�ɂ��ẮA�P�̂��敾���邱�Ƃɂ�錟���̒��f���Ȃ��A������ȈՂŌ����ɂ������p�����ɏ��Ȃ��Ƃ����A�����̃����b�g������Ƃ�����ł��傤�B �����𗘗p���������́A���{�ŕ��y����ł��傤���H �@���݂͂܂������i�K�ł���A���p���ɂ͂��̐M�����⍪���ɂ��āA�������̌����K�v���ƍl�����܂��B �@���̌������Č��\�ŁA���ۂ�90������m���ł�����ł���Ƃ�����A���{�ł͂������A���E���ɍL�����y���錟���ƂȂ邱�Ƃ��\�z�ł��܂��B �Ō�Ɉ�t����A�h�o�C�X �@����ɑ��錤���́A���i�����ő������Ă��܂��B���̂悤�ȉ���I�ȕ��@�ł���𑁊������ł���A�����̊��҂��~�����ƂɂȂ�ł��傤�B �@�����𗘗p���������́A�����b�g�������A���ɗ��z�I�Ȍ����@�Ƃ�����̂ŁA�������҂ƊS�����Ă��܂��B �j�t�e�B�j���[�X 2016�N7��4�� |
| �S���̕ی�A����\�h�ɂ��H�R�[�q�[�̂��ӊO�Ȍ��� |
| �@�������茾���� �@�R�[�q�[�̂��A���N�ւ̈ӊO�Ȍ��ʂ�6�Љ�Ă��� �@�R�[�q�[�𑽂����ސl�́A�l�X�Ȃ���̜늳�����Ⴍ�Ȃ�Ƃ������������� �@�S���̕ی�A���ɂ̉����A���A�a�̗\�h�Ȃǂɂ����ʂ����҂ł���Ƃ��� �@�F����̓R�[�q�[�����D���ł����H�@�u���N���Đ^����ɃR�[�q�[���[�J�[�̃X�C�b�`���I���ɂ���v�u�R�[�q�[�����܂Ȃ���1�����n�܂�Ȃ��v�Ƃ����l�����邱�Ƃł��傤�B �@�R�[�q�[�ɂ͔��e���ʂ�A�a�C�\�h���ʂ����邱�Ƃ��L���m���Ă��܂��B�����ō���́A�wWooRis�x�̉ߋ��L����A�C�O�̌��N�E���n���T�C�g�wRodale Wellness�x�̋L�����Q�l�ɁA����Ȍ��\�̐��X���܂Ƃ߂Ă��Љ�܂��傤�I ��1�F����̗\�h �@���{�l�̎�����ʂɓ���g����h�B�ŋ߂ł͌|�\�l�ł��늳����l���ڗ����A���N���Ȃ邩������܂���B �@���i���炪��\�h��S�����������̂ł����A �����ɂ��ƁA1����4�t�ȏ�R�[�q�[�������l�j���́A�Ȃ�ƑO���B����̊m�������܂Ȃ��l���59�����Ⴍ�Ȃ邻���ł��I �Ƃ����̂��A�R�[�q�[�ɂ̓A���`�I�L�V�_���g�́g�|���t�F�m�[���h���L�x�Ɋ܂܂�Ă��邩�炾�����ł��B�Ȃ��A�����̌����ł̓R�[�q�[�𑽂����ސl�̊̑�����늳����50���Ⴉ�����Ƃ������ʂ��o�Ă���A�܂��J�i�_�̌����ł͓�����̜늳�����Ⴂ�Ƃ������ʂ��o�������ł��B ��2�F�������S�̊댯�������� �@�R�[�q�[�ɗl�X�ȕa�C�\�h���ʂ�����Ƃ������Ƃ́A���̕����������т�\��������Ƃ������Ƃł���ˁB �@�č��̈�w���ɔ��\���ꂽ�����ɂ��ƁA�ǂ�Ȍ����ł����Ă��A1��4�t�R�[�q�[�����l�̎��S���́A���܂Ȃ������l���16���Ⴉ���������ł��B �@�܂��A1��3�t�̃R�[�q�[�ŁA�S�����ɂ�鎀�S����21����������Ƃ������ʂ��o���Ƃ��B����Ȃ璩���瓰�X�Ɗy���߂����ł��ˁB ��3�F���ɂ̉��� �@���ɂŔY�ސl�Ƃ����͈̂ĊO�������̂ł��B �@�ߋ��L���u�����c�R�[�q�[��������!? ����łł���g�ˑR�̕Γ��Ɂh������������@5�v�ł��`�������悤�ɁA�J�t�F�C���͓��ɖ��ɂݎ~�߂ɂ��z������Ă��邱�Ƃ����邻���Ȃ̂ł��B �@�m���E�F�[�Ŏ��{���ꂽ�����ɂ��ƁA1������3�t���x�̃R�[�q�[������ł���l�́A���ɂɂȂ�m������ԏ��Ȃ����������ł��B�������A���݂����͎��ɂ���Ȃ铪�ɂ������N���������ɂȂ邻���ł��̂Œ��ӂ��܂��傤�B ��4�F���A�a�̗\�h �@30�`40��ɂ��Ȃ�ƋC�ɂȂ��Ă���̂����l�a�B���ł����A�a�͖��̊댯�������ςȕa�C�ł��B �@�������A�č��n�[�o�[�h��w�̌����ɂ��ƁA������ł���R�[�q�[�̗ʂ�����1�t�������ނ��ƂŁA�Ȃ�Ɠ��A�a�̊m����11���������Ƃ������ʂ��o�������Ȃ̂ł��B �@�t�ɁA�R�[�q�[�̗ʂ����炷���Ƃɂ��늳����17�����������Ƃ��I�@��1�`2�t��������ł��Ȃ��Ƃ����l�͂���1�t���₵�Ă݂ẮB�������A����4�`5�t����ł���Ƃ������͂���ŏ\�����Ǝv���܂��I ��5�F�̑��̃f�g�b�N�X �@�R�[�q�[�𑽂����ނ��ƂŊ̑�����̊m����50����������Ɛ�ɏq�ׂ܂������A��������̂͂��A�R�[�q�[�͊̑���|������ق��A�̑�������\�h���铭��������Ƃ����̂ł��I �@�Ȃ�ƁA�R�[�q�[��1��2�`3�t���ނƁA�̍d�ς̊m����66����������Ƃ����������ʂ����邻���ł��B�̑��̌��N���S�z�ȕ��͊o���Ă����Ă��������ˁI ��6�F�S����ی삷�� �@�R�[�q�[�͌��N��̌��\�𐔑��������Ƃ�������܂������A�܂��I���ł͂���܂����I�@�Ȃ�ƁA�č��S������̌��\�ɂ��ƁA1��3�`5�t�̃R�[�q�[������ł���l�́A�S�����Ŏ��S����m�����Ⴂ�����ł��I �@�S�����́A����ɑ����ē��{�l�̎��S�����Ƃ��đ����a�C�ł��B�R�[�q�[�����߂A�ǂ���̗\�h�ɂ����ʂ����肻���ł��ˁB �@�������ł������H�@�R�[�q�[�ɂ͑f���炵���a�C�\�h���ʂ�����܂��B�������A���E�ی��@�ցiWHO�j�̌��\�ɂ��ƁA�������������̌��\�����R�[�q�[�ł��A�M������Ƃ������Ă���a������댯�������邻���ł��I �@���ݕ��̉��x��65�x�ȏゾ�Ɗ댯�����A�b�v���邻���Ȃ̂ŁA��������ꂽ��A������܂����肵�āA�M������R�[�q�[�����܂Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�܂��ߌ�x�����ԂɈ��ނƁA�����ɉe�����o��\��������܂��̂ŗv���ӁI �@���ɂ��厖�Ȃ͎̂��̂����R�[�q�[�Ɛ����g���A����������邱�ƁB�R�[�q�[�̔�������������Ɋւ��ẮA�ߋ��L���u�Ȃ�قǁI�R�[�q�[���Ƃ��`������g���Ȃ��̃R�[�q�[���}�Y���h���R5�v�����Q�l�ɂ��Ă��������ˁB ���C�u�h�A�j���[�X 2016�N7��5�� |
|
�A�ׂ���킩��H �A�ł���̑����������߂����V���� |
| �@�������쏊�ƏZ�F�����O���[�v�́A�A���g���ē������咰����̊��҂����ʂ���Z�p���J�����A���N6���ɔ��\�����B���N�Ȑl�A�����ҁA�咰���ҁA�e15�l�̔A�����瓜�⎉���Ȃ�1300�ȏ�̑�ӕ������o���Ĕ�r�B���҂��ǂ����ŊܗL�ʂ��傫���قȂ镨����200�ȏ㌩���o�����B����ɂ��̒����炪��Ɗ֘A���[���Ǝv�����10��ނ��w�W�i�o�C�I�}�[�J�[�j�Ƃ��či�荞�ނ��Ƃł���̗L���ɉ����A������E�咰����̎�ނ̎��ʂɂ����������Ƃ����B �@�����ŊJ���ɓ���������b�����Z���^�̍�����`�[�t�T�C�G���e�B�X�g�͂����b���B �u�A�Ȃ�ȒP�ɋ�ɂȂ��̎�ł���B�����ɂ��픘������܂���v ���ȈՂȎ��p���ڎw�� �@���i�K�ł́A�ǂ̒��x�̐i�s��̂��猩������̂��Ȃǂ͂킩���Ă��Ȃ��B����͗Տ��f�[�^�̌����𑝂₵�A���x�̌����}��B�܂��A�Ⴂ�����ɑ���������Ƒ咰���猤�����X�^�[�g���������A����ł��邪��̎�ނ����₵�Ă��������Ƃ����B �u�����́A�����L�b�g�ȂNJȈՂȕ��@�Ŏ��p����i�߂Ă������j�ł��B��f�҂�����ō̂����A�������@�ւɑ��t���邾���Ő��m�ɐf�f�ł���d�g�݂��m�����A����̑����f�f�⑁�����ÂɂȂ������B��������Â������Ƃ̍Ĕ��̑��������ɂ��g����̂ł́A�ƍl���Ă��܂��v�i�������j dot.�h�b�g 2016�N7��6�� |
|
�{���͎�p���Ȃ��ق��������u����v? �u�Ƃɂ�����Ȃ���I�v�͓��{�̂������ȕ��K�� |
| �g�̂̈ꕔ�������Ƃ������� �@�A�Ɉ�����ᇂ��ł����������ƍA������B��N�A���y�v���f���[�T�[�̂����A�A������̎�p�����т�E�o�������Ƃ͋L���ɐV�����B �@�w����Ŏ��ʂ̂͂��������Ȃ��x��w���̂��߂ɐ����邩�x�ȂǁA���ÂɊւ��钘��������������O�Ȉオ���B �u���Ƃ��A�����̈�������̏ꍇ�A��p�ł͂Ȃ����ː����Âł���A���т�E�o����K�v���Ȃ��̂ŁA�����������Ƃ�����܂���B�l���ꂼ����Ⴄ�̂ŁA�w�ǂ�ȋ]�����Ă���p�������ق��������x�Ƃ����̂͑��v�ł��B���̐l�̔N�����X�^�C���A���l�ςɂ���āA�����ȑI�����������Ă�����ׂ��ł��v �@���ƈ��������ɐ�������??�B�����邽�߂Ƃ͂����A��p�́u�㏞�v�͂��܂�ɑ傫���B �@�������A������ɂ́A����ȃf�[�^������B��N�A�A�����J�̃P�[�X�E�G�X�^�����U�[�u��w�𒆐S�Ƃ��������O���[�v���u�i�s���������̍A������͎�p�����Ă����Ȃ��Ă��A�������͂قڕς��Ȃ��v�Ƃ����������ʂ\�����B �@'90�N����'13�N�܂ł̍A�����҂̃J���e�͂������ʁA��p�������l��5�N����������50%�������̂ɑ��A��p�����Ȃ������l(���ː���R������Â�I�l)����50%�Ɠ������������Ƃ����炩�ɂȂ����̂ł���B �@���R�Ȃ��甭���@�\�ɂ��ẮA��p�����Ȃ��������҂̂ق������ێ�����Ă����B �@�u����ɂȂ���������邵���Ȃ��v�A�u��p���������铹�͂Ȃ��v�Ɗ��҂ɂ����߂Ă����҂�����B�����A��x�����~�܂��čl���Ăق����B����̎�p�́A�g�̂̈ꕔ�����i���Ɏ����A�Ƃ������̑��ʂɉ����āA��p�����Ă�����������ǂ��납�A�t�Ɍ��N�������k�܂�댯��������̂��B �č��ł͈��ՂɃ��X�����Ȃ� �@�����������Ȃ̉����N�Y�@���́A�u�Ⴍ�đ̗͂̂��邤���ł���A��p�����č�����ڎw���̂�������������Ȃ����A����҂̏ꍇ�͂����Ƃ͌�����Ȃ��v�ƌ��B �u���{�ł͂܂��܂��w����C�R�[����p�x�Ƃ����l�����������ł����A�A�����J�ł͈��ՂɃ��X����ꂸ�ɁA���ː��ł̎��Â����C���ɂȂ��Ă���B��p�͑S�g������o���Ȃǐg�̂ɂ��Ȃ�̕��S��������܂��B�K���\�͂��ቺ��������҂Ȃ�Ȃ�����B���̂��߁A��p���邱�Ƃł���ɒ��q�������Ȃ邱�Ƃ��N���肤��̂ł��B �@�����鍐�����A�F�s���ɂȂ�A��҂Ɍ�����܂�p���Ă��܂��B�w��p��ǂ�Ȑ������҂��Ă��邩�x�܂Ŏv�������点����l�͂Ȃ��Ȃ����܂���B�ł����ɍ���҂̏ꍇ�́A���̌�̐l���̂��Ƃ��l���A�ł��邾����p������A���̎��Ö@��T���Ăق����v �@��p���������ƂŎ����͏������т邩������Ȃ����A�l�Ԗ{���̑�ȋ@�\�������\��������B�x�b�h����N���オ�邱�Ƃ��ł����A���̂܂ܐl�����I���邩�A����Ƃ��l�Ԃ炵�������𑱂��āA�l����S�����邩??�B �@���Ȃ��Ƃ�����͈�t�̌����Ȃ�Ō��߂邱�Ƃł͂Ȃ��A�����őI�����ׂ����Ƃ��낤�B �ǂ������K���������̂� �@�H������̎�p�́A�u�l�Ԗ{���̐H�ׂ�Ƃ����@�\�v�������\��������B �@�p��A�Č������H���������Ȃ��Ă��܂��u�H������v��A�H�ו������ݍ��݂ɂ����Ȃ�u������Q�v�ȂǁAQOL(�l�Ԃ炵�������E�l���̎�)�ɑ傫���e��������ǂ��c�邱�Ƃ�����B �@�ň��̏ꍇ�A�݂Ɍ����Ē��ځA�h�{�𑗂荞�ށu��ᑁv��t������Ȃ��Ȃ�A���R�ɓ����ǂ��납�A�x�b�h���痣��邱�Ƃ��ł����u����Ȃ��ƂȂ��p�Ȃ��Ȃ���悩�����v�ƌ������l�������B �@���҂ɂƂ��Ă͔��ɓ�����f�ƁA�炢�\�����������H������̎�p�����A�ɂ�������炸��p�����������҂������̂͂Ȃ����B ���Ɏ�p�͐������Ă��c �u�H������͔��ɓ����p�̈�ł��B�������A���ꂾ���Ɉ�҂́w���ł�������p������Ď��т�ς݂����x�ƍl����̂ł��B�����H������̏ꍇ�A�����p�߂ɓ]�ڂ����Ă��邱�Ƃ������A��p�����Ă����S�ɂ������肫�邱�Ƃ͓���A�Ĕ��̉\���������B �@�܂��H������͐i�s���₷�����߁A��p�̂����ōזE������������A�S�g�ɉ��u�]�ڂ��A��p����1�N���炸�ŖS���Ȃ���Ƃ����P�[�X�����Ȃ�����܂���B���������p�͂����A���ː��ƍR����܂ɂ�鎡�Ö@�̂ق����A�ނ��냊�X�N�͏��Ȃ��ƌ����܂��v(������Ȑ��̊O�Ȉ�) �@�݂���̂��ߎ�p�ň݂�S�E�o������c�炳��(75�E����)�́A����ȋ��̓���f�I����B �u�݂��Ȃ��̂ŁA�قƂ�ǐH�����ł��Ȃ��Ȃ�A�̏d�����Ȃ茸��܂����B�ؓ��������A���ł͕������Ƃ��܂܂Ȃ�܂���B �@���͎h�g����D���������̂ł����A����������H�ׂ��Ȃ��B�����ƈ��������Ɂw�H�ׂ�y���݁x���������̂ł��B�x�b�h�̏�ň�����a�@�̓V������グ�Ă���Ɓw��p�������l���Ƃ��Ȃ������l���A��̂ǂ������K���������̂��낤���x�ƕ�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��ˁv �@���Ɏ�p�͐������Ă������ǂ̕s���͏�ɂ��܂Ƃ��B�݂���̑�\�I�ȍ����ǂƂ��ċ�������̂����ǂ��B�݂�؏������ꍇ�A�H�ו������ڏ�����咰��ʉ߂���̂ŏ��������ꂸ�l�܂��Ă��܂��A�җ�ȕ��ɂɏP����B�̗͂��ቺ���Ă��鍂��҂ɂƂ��ẮA���̊댯��������B �咰����́u���Ƃ����v �@����̒��ł͔�r�I�؏����e�ՂƂ���邽�߁A��p�������߂���咰����B�����A�����ɂ��u���Ƃ����v������B �@�����������ɋ߂��Ƃ���ɂł����ꍇ�A���(��劇���)���܂߂Ă����؏�����K�v������A�l�H��傪�K�{�ƂȂ�B �@�咰����̎�p�������R����t����(65�E����)�������B �u�l�H�������Ă���w�ւ��R�ꂽ��ǂ����悤�x�Ƃ����s���ƁA�L�����C�ɂȂ�A�Ȃ��Ȃ��O�o�ł��Ȃ��Ȃ�܂����B��x�o�X���s�ɍs�����̂ł����A�s���Ƌْ��̂��ߎԓ��Ńp�j�b�N�Ǐ���N�����Ă��܂�����ł��B����ȗ��A���o�͂��Ă��܂���B �@�����邽�߂ɂ͎d�����Ȃ����Ƃ��Ƃ͕������Ă���̂ł����A�c��̐l�����l������A�����Ǝ�p�ɑ��ĐT�d�ɍl����悩�����ƌ�����Ă��܂��v 70�߂������p�ȊO�̓��� �@���݂ł́A�����c����p���@������A�ꕔ�̈�Ë@�ւł͎��ۂɍs���Ă���B�����̔N��ƍ���̐l�����l���A���������ɂƂ��čŗǂ̑I���Ȃ̂����A����x�l����K�v������B ���Ăł͐�Ȃ��̂��펯 �@����̎�p�́A���̊��҂̔N��Ƒ傫�ȊW������B �@�u�O���B����́A70����Ύ�p������K�v�͂Ȃ��v�ƒf������̂́A��t�ł���A��ÃW���[�i���X�g�̕x�ƍF�����B �u�O���B����͍���҂ɑ�������ł����A���̂���ɂ�鎀�S�Ґ��́A����̒��ł�10�ʂƌ����đ�������܂���B�O���B����͑��̂���ɔ�אi�s���x���̂ŁA���u���Ă����Ă����Ȃ����U���I������̂ł��B �@�����玄�́A�N�z�̊��҂��瑊�k����ƁA�K���w��p�͎~�߂��ق��������x�ƃA�h�o�C�X���Ă��܂��B�����ł����O���B�͌������L�x�ŁA��p�̍ۂɑ�ʏo�����₷����A��p�̌��ǂŔA���ւ�C���|�e���c(ED)�ɂȂ邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B �@��҂́w��������p�Ȃ̂Œɂ݂��Ȃ����A�����I���܂���x�Ƃ����߂Ă��܂����A��p�~�X��p��̍����ǂ̃��X�N���l����ƒf�����ق��������ł��v �@�������ۂɂ́A��҂Ɉ�x����Ɛf�f�����ƊO�Ȏ�p�őO���B��؏����邱�Ƃ�I�Ԑl���A���₽�Ȃ��Ƃ����B �u�w���|�ǁx�ƌ����܂����A�����ق��������ƐM������ł���l�����{�l�ɂ͑����B�O���B����̎��Â̊�{�͊O�Ȏ�p�ł͂Ȃ��z�������Ö@�ł��B���̂���͒j���z�������̕���ő傫���Ȃ�̂ŁA�����z�������𓊗^����A����̐�����x�点�邱�Ƃ��ł���B �@���łɉ��Ăł�70�Έȏ�̊��҂̑O���B����́w�O�Ȏ�p�����Ȃ��x�̂��펯�ƂȂ��Ă��܂��B���{�ł�70�Έȏ�̊��҂͎�p���Ȃ��ق��������v(�x�Ǝ�) �x����E����������̏ꍇ �@���{�l�j���̎����ŁA�����Ƃ������x����B�i�s���������߈�҂͂����ɐ肽���邪�A������܂���p�����Ȃ��ق��������ꍇ������B �u70��ȏ�̊��҂ɂƂ��āA�x��؏����邱�Ƃ͂��Ȃ�̕��S�ɂȂ�܂��B����⓮�����N�����₷���Ȃ�A���퐶���𑗂邱�Ƃ����ɍ���ɂȂ�B����Ɏ�p���������ƂŁA�x���Ȃǂ̍����ǂ��N�����\���������Ȃ�A��p������������Ɏ����𑁂߂�\��������܂��v(�ċz����̊O�Ȉ�) �@����̒��ł������Ƃ����Â�����A���������Ⴂ�̂����������B����������͑����̔���������A�����������ɂ͂��łɂ��Ȃ�i�s���Ă���ꍇ�������B �u��ᇂ�1�p���Ă���Ǝ�p�͂��Ȃ��ق��������B�X�e�[�W�W�ɂȂ�Ƒ��̑������p�߂ɓ]�ڂ��Ă���\���������B��肫��Ȃ��������A��p�ɂ�芈�������A��葝�B���邱�Ƃ�����B �@�ł�����A�������������������_�Ŏ�p�͂����A�ۑ��I�Ȏ��Â��l����ׂ��ł��傤�B��p�������炻�̂܂ܕa�@����o��ꂸ�A���N��ɖS���Ȃ�Ƃ������҂������B�������A��p������ĕ��ː����ÂȂǂɂ���A2�`3�N�����邱�Ƃ͒���������܂���v(������̊O�Ȉ�) ��w�a�@����Ԋ�Ȃ� �@��p�����Ȃ��ꍇ�A���ː��A�R����܁A�d���q���Ȃǂ̎��Ö@����ɋ������邪�A�O�o�̉������́A�����u���鎡�Áv�����ڂ���Ă���ƌ����B �u�w�g���Z���s�[�x�ƌĂ��A���̓I�ɂ�����Ƃ炦�A�����镔���ɂ̂ݕ��ː��Ă邱�Ƃ��ł��鎡�Ñ��u�ł��B������_�����Ƃ��ł��邽�߁A����p��啝�ɗ}���邱�Ƃ��ł��܂��B���{�ɂ͂܂�20��قǂƏ��Ȃ��ł����A�A�����J�ł͂ǂ�ǂy���Ă��܂��v �@����Ɏ�p�ȊO�ŁA������L���Ȏ��Ö@���u�}�C�N���g�v���Ɖ������͌����B �u�}�C�N���g�Ƃ́A�j�̐悩��d�q�����W�Ɠ����d���g���ˏo���A������Ă��Ă��܂����̂ł��B�x����������ȂǑ����̂���ɑΉ����Ă��܂��BCT�Ō��Ȃ���s���̂ł���̕��ʂ��s���|�C���g�ŏĂ����Ƃ��ł��A��2�`3�p�̂���܂ʼn\�ł��B �@����̏ꍇ�A�]�ڂ��Ȃ����Ƃ��厖�Ȃ��Ƃł�����A�g���Z���s�[��}�C�N���g�����Ȃ���A�Ɖu�Ö@��������̂��x�X�g�ł��B��������ƁA5�N���������ʏ�̎�p���20%�オ��܂��B���Ƃ��A�X�e�[�W�UA�̔x�������p�����ꍇ�A5�N��������5�����܂����A�O�q�������@�Ȃ�7���ɂȂ�B�Ɖu�Ö@�œ]�ڂ��u���b�N����̂ł��v �p��Ɍ�����Ă��x�� �@��p�ȊO�̎��Ö@�͓��X�i�����Ă�����̂́A��͂��҂̌�������f�ɂ���āA�u����ʎ�p�v���������銳�҂͌��₽�Ȃ��B �@�����Y���(32�E����)�́A��(62��)�̎�p��S��������҂ɂ�������B �u���͌��f�Ŋ̑��ɉe�����������̂ŁA�傫�ȑ����a�@�Œ��ׂĂ��炢�܂����B����ƌ����̌��ʂ�������҂���A�͂�����Ɓw�̑�����ł��ˁx�ƌ���ꂽ�̂ł��B���h�������́A��҂ɂ����߂���܂܂Ɏ�p���܂����B �@�ł����ۂɐ��Ă݂�Ǝ�ᇂ͗ǐ��ŁA�܂�������K�v�͂Ȃ�������ł��B�Ƃ��낪���̈�t�́w�����Ȃ��ėǂ������ł��ˁB���������͐��Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ�����x�ƕ��R�ƌ����̂����̂ł��B��p�ȗ��A���͑����Ă��܂��āA�������@�̂��ߎd�������߂���Ȃ��Ȃ����B �@�Ȃ����̎��A�Z�J���h�I�s�j�I�������Ȃǂ��āA���̈�҂̈ӌ����Ȃ������̂��A�{���Ɍ�����Ă��܂��v �@�C��t���Ȃ�������Ȃ��̂́A��w�a�@����a�@�Ȃǂւ́u�ߐM�v���B�����ÃW���[�i���X�g�́A�s���a�@���ނ����w�a�@�̂ق����댯���Ƃ����B �u��t�̐���������w�a�@�ł́A��l�̈�t���Z�p�͂����Ԃ͑�������܂���B�^�������n�Ȉ�҂ɓ�����\�����\������B��p�����邩���Ȃ����̔��f�́A��҂̗͗ʂ̍��������Ƃ��傫�������ł��B���O�����ő傫�ȑ�w�a�@��I��Łw��p�����Ȃ��ق����悩�����x�ƌ������l���Ȃ��Ȃ�Ȃ��̂͂��̂��߂ł��v �@�����������f�B�J���N���j�b�N�������̔��쑾�Y�����u������p����Ȃ�A��w�a�@���s���a�@�������v�ƌ����B �u��w�a�@�ɂ����҂̑����̍ŏI�ڕW�́A�����ɂȂ邱�ƁB���̂��߂ɂ͐��Ԃ������ƌ��킷�_���������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B������ނ�́A���낢��ƐV������p������������̂ł��v �@��҂̌������Ƃ�ӐM����̂ł͂Ȃ��A�Ƃɂ����������g�ŏ����W�߂�B�����Ď����̉��l�ςɏƂ炵���킹�Ď��Ö@�����߂�K�v������B ����r�W�l�X�{ 2016�N7��12�� |
|
�V���̂���͍ٔ��ƌ|�\�l���� ����c�勳���u�����Ɨ\�h�̋L�����v |
| �@����Ɋւ�����{�̐V���́A��Ã~�X��ٔ��A�����l�̂���ȂǎЉ���Ƃ��Ď��グ��L���͑������A�\�h�⑁��������i����[���I�ȋL���͋ɂ߂ď��Ȃ��Ƃ����������A����c��w�X�|�[�c�Ȋw�w�p�@�E���_��N�����̌��������܂Ƃ߂��B �@�_���́A���ی��N��uHealth Communication�v�i�d�q�Łj��2016�N6��17�����ɔ��\���ꂽ�B ��Î��́A�i�ׂȂǎЉ��肪�ő� �@�����ł́A2011�N��1�N�ԂɑS����5�Ђ̒��[���Ɍf�ڂ��ꂽ�A����Ɋւ���5314���̋L���𒊏o�A���e�ɉ����ċL���͂����B����ɂ��ƁA���グ������̕��ʕʂł́A�x���g�b�v��575���A���Ŕ����a331���A������302���A�̂���261��......�Ƒ����B�������A���̏��Ԃ͎��ۂ̔N�Ԏ��Ґ��̑����Ƃ͈�v���Ă��炸�A���҂������咰�����݂���̋L�������Ȃ������B �@�L�����e�[�}�ʂɂ݂�ƁA��Î��̂�~�X�A�i�ׂȂǂ̎Љ��肪�����Ƃ�����797���i15.0���j�A���ɂ���֘A�̖{��f��A�C�x���g�J�Â�762���i14.3���j�A����ɂȂ����|�\�l�Ȃǒ����l�̘b�肪650���i12.2���j�Ƒ����B�܂��A�����{��k�Ђ��������N�ł�����A�k�ЂƂ���̋L����653���i12.3���j�������B ���������̏d�v���i�����L���͂킸��1.8�� �@����A����̎��Â�A�I�����Ɋւ���L����399���i7.5���j���������A�����K���ɂ��\�h�@��������L����86���i1.6���j�A�܂����f�⑁�������̏d�v����i�����L����98���i1.8���j�����Ȃ������B �@���̌��ʂ���A�������́u�䂪���̐V���̂���́A�Љ���ɕ��Ă���A�����ƕč���p���A�����̐V���̂悤�ɗ\�h�ƌ[���ɏœ_�Ă���M���ׂ��ł��v�ƕ��Ă���B J-CAST�j���[�X 2016�N7��15�� |
|
���Âɂ��o�r���� ���匤�̋��q�y�����i���R�o�g�j�u�� |
| �@���Q�b�`�s�u�J�ǂQ�T���N�ƈ��Q�V���n���P�S�O���N�L�O�̓��ʍu����P�U���A���R�s��蒬�P���ڂ̈��Q�V���Ђł���A���s�傉�o�r�זE�������̋��q�V�y�����i�S�T�j�����R�s�o�g�����A�l�H���\�����זE�i���o�r�זE�j�����p�������Âɂ��ĉ�������B �@���q���́A�������Ȋw�������ȂǂŔ����a�∫�������p��̎��ÂȂǂ̌����ɓ�����A�Q�O�P�Q�N���猻�E�B���o�r�זE�Z�p��p��������⊴���ǂ̎��Ö@�̌����J���Ɏ��g��ł���B �@���q���͍u���ŁA�̓��ɓ������E�C���X�ȂǕa���ۂƐ키�Ɖu�זE�̒��Łu�s�����p���v�͗D�ꂽ�U���͂ƃZ���T�[�������A����זE�Ƃ��킦��ƏЉ�B�����̍זE�ɗR�����邪��זE���u�G�v�ƔF������s�����p���͏��Ȃ����Ƃɉ����A����Ɏ�邽�߁A����זE�ւ̖Ɖu�����͎キ�A���Âւ́u�Ⴂ�s�����p���������ɑ��₷�����ۑ肾�����v�Ɛ��������B �@�����ɑ��₷���Ƃ��ł��A�ǂ�ȍזE�ɂ������ł��邉�o�r�זE���������ꂽ�ƕ��������q���́u���͂ȃc�[���ɂȂ�v�ƒ����B�����ł��o�r�זE����s�����p������邱�Ƃɐ������A����܂ł̎����ł́A���܂��܂Ȃ���זE�ɑ��Č��ʂ��������Əq�ׂ��B �@�u���͎s�����P�O�O�l�����u�B��ꂩ����p���̎����ɂ��Ď��₪����A���q���́u���̌����݂����R�`�S�N�B���ۂɐl�̂ɓ���Ă������̂Ɏd�グ��K�v������v�Ƙb�����B ���Q�V��ONLINE 2016�N7��17�� |
| �u����ɂȂ�Ȃ�����P�ʁv���������̌��N�̃q�~�c�ɔ��� |
| �@6�����A���������Z���^�[���S��47�s���{���́A����늳�����\���Ęb����Ă�ł���B�f12�N�ɐV���ɁA����Ɛf�f���ꂽ���Ґ��͑S���Ŗ�86��5,000�l�������Ƃ����B���Z���^�[�͏W�v�����f�[�^����͂��A����̕��ʂ��Ƃɓs���{���ʁE�j���̜늳�����Z�o�����̂��B �@���̌��ʁA�g����ɂȂ�Ȃ����h�Ƃ��āA�������ڗ����Ă���̂����������B������1�ʁA�咰����1�ʁA����Ɉ݂����q�{����ł�2�ʂŁA�g�[�^���i�S���ʁj��1�ʂƂ��������̌��ʂɁI���̐����́A���̎��������������ɂƂ��Ă��\�z�O�������悤���B �@���������ł�8�N�O����u��������i�v��v���s���Ă���B�{���͍���̌��ʂ��ӂ܂��āA��ނ�\�����̂����A�����������ی����������N���i�ۂ̒S���҂͍��f�����肾�����B �u���������g����ɂȂ�Ȃ����h��1�ʂ��������Ƃ́A���������V���̕Œm��܂����B�W�v�͍��������Z���^�[���s�������̂ł��̂ŁA�����炩��͂Ȃ�Ɛ\���グ�Ă������̂��B�H�����Ƃ̊W�ł����H���܂����͑S���Ő��Y��1�ʁA�{�����Y�ʂ�1�ʂł����A����Ƃ̈��ʊW�ɂ��Ă͔c�����Ă��܂���c�c�v �@ �@�������́A���Ȃ�O���玭�����̐H�����́A�����\�h������ʂ������̂ł͂Ȃ����Ƃ����������������Ă���B �u�f02�N�Ɏ�������w�̋������A�g���|�ɍR�����p������h�Ƃ����������ʂ𖾂炩�ɂ��Ă��܂��B����Ɂf13�N�ɂ���������w��w���̌����`�[�����g���|�ɂ͔畆����זE�̑��B��}��������ʂ��������h�Ƃ������e�̌������ʂ\���܂����v�i��ÃW���[�i���X�g�j �@���|���̔������悤�ɂȂ����̂�40�N�قǑO���Ƃ������A���܂⎭�����̓��Y�i�Ƃ��Ă��L�����B �u�f02�N�ɂ́A��������w�����܂����̕\��̃A���g�V�A�j���ɁA����זE�̑��B�}����p�����邱�Ƃ��m�F�����ƁA���Ă��܂��B���̃A���g�V�A�j���͍R�_�������̃|���t�F�m�[���̈��ŁA�����������Ȃǂɂ��L�x�Ɋ܂܂�Ă��܂��v�i�O�o�E��ÃW���[�i���X�g�j �@�܂��A����N���j�b�N�@���ŁA����̐H���Ö@�Ɋւ��钘���𑽂����ϗz����搶�͎��̂悤�ɕ��͂���B �u�������������ł����A����늳���̒Ⴂ���́A��̐ێ�ʂ���r�I�����ł��ˁB�H�����ȊO�ɂ��A����\�h�ŏd�v�Ȃ̂͐����K���ł��B�������������肵��37�x�O��̑̉���ۂ��Ƃ́A������t���Ȃ��錍�ł��B���������Ӗ��ł́g�����h�ł��鎭�������́A����ɂȂ�ɂ��������Ƃ�����ł��傤�v �@���Ȃ̓��v�ɂ��A�N�o�ʂőS��3�ʁA����Ɂg����𗘗p���Ă�����O���ꐔ�h�ł͑S��2�ʂƁA�������C�y�ɉ���𗘗p���₷���̂������B�����S��������ȑ�w�����ŃO���[�o�������w�����������̏��c��������͌����B �u�����ł�����w��������͐�i�x�Ƃ��A�{�݂̘b���b���l�������̂ł����A�������ł́w��������́~�~�Ɍ����x�Ƃ��A���\�ɂ��Č�荇���̂ł��B�������s���ɂ���������̑K��������܂����A�قƂ�ǂ�����ŁA�Ȃ��ɂ͂��������ނ��Ƃ��ł���Ƃ��������܂��B�����ɔ�ׂ�A����g�p���͑����Ĉ����A�����̌������������D���Ă��܂��v �@���c����̌����ɂ��A����͂���\�h�Ɍ��ʂ�����Ƃ����B �u����܂ő啪��k�C���ȂǁA7�̉���n��350�l��Ώۂɂ��āA�̌��������s���܂����B�V����a�C�̎�Ȍ����́A�̓��Ŏ_�f���ω����Đ����銈���_�f�ł��B�������O����X�g���X�Ȃǂő������āA����Ȃǂ̕a�C�������܂����A����ɂ͂��̊����_�f�������������p������̂ł��B�������̂��̗̂͂�����܂����A�����b�N�X���邱�Ƃ�����\�h�ɖ𗧂��Ă���Ǝv���܂���v �������g 2016�N7��18�� |
| �I���K3���b�_�A�咰���҂̎��S���X�N�ጸ�Ɋ�^�� |
| �@�咰����̊��҂��A�}�O����T�P�Ȃǂ̎��b���������Ɋ܂܂��I���K3���b�_���ʂɐێ悷��ƁA�����������܂�\��������Ƃ̌����_����20���A���\���ꂽ�B �@�����́A�č���17���l�ȏ�̃f�[�^����ɍs��ꂽ�B���̂�����1659�l���咰����ǂ������A�����ł̓I���K3�̑�ʐێ�Ǝ��S���X�N�ጸ�Ƃ̊Ԃɑ��֊W�����������ꂽ�B �@�p��w���u���e�B�b�V���E���f�B�J���E�W���[�i���iBMJ�j�̏�����a�w��厏�u�K�b�g�iGut�j�v�ɔ��\���ꂽ�������ʂɂ��ƁA�f�f��̃I���K3���b�_�̐ێ�ʂ�1��������0.1�O���������̊��҂ɔ�ׂāA��0.3�O�����ێ悵���l�ł́A���S���X�N��41���Ⴉ�����B �@�����ɔ��\���ꂽ�����́A�u����̔��������̌����ł��m�F�ł���A�咰���҂́A�����̋��̐ێ�𑝂₷���ƂŁA�������Ԃ��������b������\��������v �Ƃ��Ă���B �@�I���K3���b�_�͐���ꕔ�A������ѓ���̃i�b�c���ȂǂɊ܂܂��B AFPBB News 2016�N7��20�� |
| ������A���늳���\���ŏ���100����˔j |
| �@���������Z���^�[�������Z���^�[��7��15���A2016�N�ɐV���ɂ���Ɛf�f����鐔�������늳���Ǝ��S���̂��v�\�����Z�o�A������̑����T�C�g�u������T�[�r�X�v�ɂĂ��̓��e�����J�����B �@���{�̂��v�́A�늳�f�[�^��4�`5�N�A���S�f�[�^��1�`2�N�x��Č��\����Ă���B���O���ł́A�����̒x��𐔊w�I�Ȏ�@�ŕ���āA�����_�ł̂��v��\�����鎎�݁i�Z���\���j�����{����Ă���B��N9���A�����J���Ȑl�����ԓ��v���2014�N�̂��S�������\����A���N7���ɂ́A������2012�N�̂���늳���S�����v�l�����\���Ă���B�����̍ŐV�f�[�^��p����2016�N�̂���늳������ю��S�����\�����ꂽ�B �@2016�N�̂��v�\���ł́A�늳���\����101��200��ŁA100�������\�����ʂ��Z�o���ꂽ�B���{�̜늳���͓��v���쐬����n�߂�1970�N�ォ���т��đ����A���S����37��4,000�l�ŁA����т��đ����̈�r�����ǂ��Ă���B�늳���A���S���Ƃ������̎�Ȍ����́A���{�̍���Ґl���̑����ƌ��Ă���B �@�늳�Ґ��\���̓���́A�j����57��6,100��A������43��4,100��ŁA2015�N�̗\���i98��2,100��j�Ɣ�r����ƁA�j�����v�Ŗ�2��8,000��̑����A���ʕʂł́A�咰�A�݁A�x�A�O���B�A���[�i�����j�̏��ɂ���늳���������A���ʂ���N�̓��v�\���Ɣ�r����ƁA�݂�3�ʂ���2�ʂɁA�x��2�ʂ���3�ʂɂȂ����B�܂��j���ʂ̜늳���ł́A�j�����O���B�A�݁A�x�A�咰�A�̑��̏��ŁA�����͓��[�A�咰�A�x�A�݁A�q�{�̏��ő��������B �@����A���S�Ґ��̓���́A�j����22��300�l�A������15��3,700�l�A��N�̗\���Ɣ�r����Ɩ�3,000�l�̑����ƂȂ����B���ʕʂł́A�x�A�咰�A�݁A�X���A�̑��̏��Ɏ��S���������A��N�̗\�����珇�ʂ̕ω��͂Ȃ������B�j���ʂ̎��S���ł́A�j�����x�A�݁A�咰�A�̑��A�X���̏��ɁA�����͑咰�A�x�A�݁A�X���A���[�̏��������B �@������ł́A����n��̊m���Ȃ����̂��߁A�ߋ��̎��тƏ����\���̗����̃f�[�^������K�v������Ƃ��A2014�N�̗\�����Z�o�����J���Ă���B�\���l�́A����܂ł̌X�����������ꍇ��O��ɎZ�o���邽�߁A��Ɍ��J����铖�Y�N�̎����l�Ɠ˂����킹�邱�Ƃɂ��A�����łǂꂾ���̜늳�A���S�����点�����̕]���A���͂��s�����Ƃ��\�ɂȂ�Ƃ��Ă���B m3.com 2016�N7��21�� |
| �A���R�[���A����̒��ڂ̌����ƔF�� |
| �@�j���[�W�[�����h�̃I�^����w�̈�t�ɂ�錤���́A�A���R�[���ێ�͂��i�̒��ڂ̌����ƂȂ�Ǝ������B�_���́uAddiction�v���Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@�A���R�[���ێ�ɂ���Ĝ늳�A�������邪��ɂ́A�������A�A���A�H���A�̑��A�����A��������ѓ��[�̂�����B �@�����f�[�^�ɂ��ƁA�A���R�[����2012�N�S���E�ł̃K���ɂ�鎀�S������5.8���܂��50�����̌����ƂȂ����Ƃ����B�ł��������X�N�̓A���R�[���̖\���ɊW���Ă��邪�A���ʂȂ����ߓx��ۂ����������܂��A���S�Ƃ͍l�����Ȃ��ƌ����҂͏q�ׂĂ���B �@�O�ɁA���l�̌����`�[���͂��Ƃ����ʂł��A���R�[���ێ�ɂ���ĘV��A�K���ɂ���Ď��ʊm���������Ȃ�Ɗ֘A�t�����B �@��ɓ`����ꂽ�Ƃ���ɂ��ƁA���V�A�̃A���R�[������ʂ�5�N�Ԃłق�3����1�������A�A���R�[�����ł̌����������x���������B Sputnik 2016�N7��22�� |
|
�u�i���v�͓����҂ɂ�����A���}�^�[�[�j�Q��̌��ʂ���߂� ��i���҂ɔ�ׂčĔ������㏸ |
| �@�i���́A�ꕔ�̓����Ö�̌��ʂ����コ����\�����A�V���������Ŏ����ꂽ�B �@�uBritish Journal of Cancer�v�I�����C���ł�6��9���f�ڂ��ꂽ�ɂ��ƁA�A���}�^�[�[�j�Q��p���Ă�������҂̂����A�i���҂͔�i���҂ɔ�ׂē�����Ĕ�����3�{�ł��邱�Ƃ��킩�����B�������A�����̈��ʊW���ؖ����ꂽ�킯�ł͂Ȃ��Ƃ����B �@����ŁA�i���́A���w�Ö@��^���L�V�t�F���Ȃǂ̑��̎��Ö�A���ː��Ö@�ɂ͂قƂ�lje�����y�ڂ��Ȃ����Ƃ����������B �@�u����Ȃ錤���ō���̒m�����m�F�����A������̎��Ö@��I������ۂɂ͊��҂̋i�����l������K�v���������邾�낤�v�ƁA�����𗦂��������h��w����Z���^�[�i�X�E�F�[�f���j�y������Helena Jernstrom���͏q�ׂĂ���B �@�A���}�^�[�[�j�Q��ɂ́A�A�i�X�g���]�[���i���i���F�A���~�f�b�N�X�j�A�G�L�Z���X�^���i�A���}�V���j�A���g���]�[���i�t�F�}�[���j��3�܂�����B����́A�o�㏗���ŃA���h���Q������G�X�g���Q���ւ̕ϊ���}���邱�ƂŁA�z��������e�̗z���̓�����זE�̑��B���h������G�X�g���Q���ʂ̒ጸ�ɓ����B �@�����҂�3�l��2�l�́u�z��������e�̗z���v�^�C�v�̓�����ł���Ƃ���邪�A�č�����iACS�j�ɂ��ƁA�����ɔ������ꎡ�Â���A�ق�100���̊��҂�5�N�ȏ㐶���ł���Ƃ����B �@�i�����A���}�^�[�[�j�Q��̌��ʂ����コ���錴���͕s�������A�u�����炭�����Ɋ܂܂�鐬���̈ꕔ���A������זE�������̖�܂ɒ�R���������悤�ɓ����Ă���\��������v�ƁA�����͎w�E���Ă���B �@����̌����́A2002�`2012�N�ɓ�����Ɛf�f���ꂽ����1,065�l��5�N�ԒǐՂ������̂ŁA�Ώۏ�����5�l1�l�́A�������p���s���O����i���K�����������B�ǐՊ��Ԓ��A�i���҂ł͓�����Ĕ����̂ق��A����⑼�̌����ɂ�鎀�S������i���҂����������Ƃ��킩�����B�Ȃ��A���Ò��ɋ։����������͂����ꕔ���������߁A�։��ɂ��A���}�^�[�[�j�Q��̌��ʂ��������ǂ����͕s���ł���Ƃ����B �@�ă��m�b�N�X�E�q���a�@�i�j���[���[�N�s�j�̓�������Ƃł���Stephanie Bernik���́A�i���͑����̂��X�N�����߂�Ǝw�E���A����A�A���}�^�[�[�j�Q��p���̓����҂ł́A�i���ɂ��]�����Z���Ȃ�Ƃ̖��m�ȃG�r�f���X������ꂽ���Ƃ���A�u�������Ԃ��������߂ɂ͋։����s���ł��邱�Ƃ��������Ă����ׂ����v�Əq�ׂĂ���B m3.com 2016�N7��27�� |
|
��5�N���ΐ�������60������ ��������\�A�j��59.1���A����66.0���Ƃ�������㏸ |
| �@���������Z���^�[�������Z���^�[�𒆐S�Ƃ�������J���Ȋw������⏕���u�s���{������o�^�f�[�^�̑S���W�v�Ɗ������v�̎����̊��p�ɂ�邪��y�т���f�Ó����c���̌����v�����ǂ�7��22���A�u�n�悪��o�^�v�f�[�^�����p���Ă����5�N���ΐ��������Z�o���A�������\�����B �@�n�悪��o�^�́A�s���{���̂�����ړI��1950�N����ꕔ�̌��ŊJ�n���ꂽ�B����̏W�v�Ώېf�f�N�ł���2006�`2008�N�ɂ����ẮA�O��W�v��7������21���ɑ啝�ɑ������A�n������k�����B�܂ő������B �@�S����5�N���ΐ�������62.1���őO���3.5�|�C���g���������B�j����59.1���i3.7�|�C���g���j�A������66.0���i3.1�|�C���g���j�Ƃ�������㏸���Ă���B�������A2006�`2008�N�̜늳�܂���ƁA�O���B����������ȂǗ\��̂悢�����������ƂȂǂ̉e�����l�����A���ʕʁA�i�s�x�ʂ̏ڍׂȕ��͂Ȃ��Ɏ��Ö@�̉��P�Ȃǂ��e�����Ă���Ƃ͂����Ȃ��ƁA�����ǂ͏q�ׂĂ���B �@���ʕ�5�N���ΐ������ɂ��āA�j���ł́A70�`100���Ɣ�r�I�����Q�ɁA�O���B�A�畆�A�b��B�A�N���A�A���A�����A�t�E�A�H�i�N�������j���܂܂�Ă���B����ŁA0�`39���ƒႢ�Q�́A�����a�A������������A�H���A�̂���ъ̓��_�ǁA�]�E�����_�o�n�A�x�A�_�̂��E�_�ǁA�X���������B �@�����ł́A�����Q���b��B�A�畆�A���[�A�q�{�̕��A�A���A�q�{�A�����ŁA�Ⴂ�Q�́A�]�E�����_�o�n�A������������A�̂���ъ̓��_�ǁA�_�̂��E�_�ǁA�X���ƂȂ��Ă���B �@�Տ��i�s�x�ʐ������ł́A�ǂ̕��ʂł��A��l�ɗՏ��i�s�x�������Ȃ�ɂ�A���������ቺ���Ă���A�����̕��ʂł͑����Őf�f���ꂽ�ꍇ�ɂ͐��������ǍD�ł��邱�Ƃ��킩�����B�N��K���ʐ������ł́A�����ނˁA����ƂƂ��ɐ��������Ⴍ�Ȃ�X��������ꂽ���A��N�҂�荂��҂̐��������������ʂ�A�N��Ɛ������Ƃ̑��ւ��͂�����ƌ����Ȃ����ʂ��������Ƃ��Ă���B m3.com 2016�N7��27�� |
|
�咰�����f�Ȃ����R�g�b�v5�y�č�������z �قڑS�����u��ׂ��v�ƔF�����Ă�����̂́c |
| �@�č�������iACS�j�͑咰�����f�������Ƃ��Ȃ�2000�l��ΏۂƂ������������{�B6��30���̃����[�X�ő咰���������f���Ȃ����R�g�b�v5�\�����B �@�咰�����f���҂̂قڑS�����咰�����f��m���Ă��邾���łȂ��u�����͌��f����ׂ��v�ƍl���Ă���Ɠ�����B���̃M���b�v�̔w�i�ɂ͑咰�������Ȃnj��f�̓��e�ɑ���m���s��������悤���B �@����̒����ɂ��A���f�������Ȃ����R�g�b�v5�Ɠ�����ɂ�鐳�����m���i�J�b�R�����j�͈ȉ��̒ʂ� �@�����͊ȕւł͂Ȃ��A��ɂ��ƕ����Ă���A�܂��A�咰���������f�ɂ��Ĉ�t�Ƙb���̂��p���������i���ۂɂ́A�ɂ݂�s�������Ȃ�����ōs���錟��������j �@���̉Ƒ������Ȃ�����X�N�͒Ⴍ�A���f����K�v���Ȃ��Ǝv���Ă���iACS�ȂǑ����̒c�̂́A���ϓI���X�N�����l�S���Ɍ��f�𐄏����Ă���j �@���f���K�v�Ȃ̂́A�Ǐ���l�������Ǝv���Ă���i���Ǐ�ł����f����ׂ��j �@������p���S�z�i����ł̌����͔��Ɉ����B���f��p�̂قƂ�ǂɈ�Õی����K�p�����j �@�����炭����͍ł��d�v�Ǝv���錜�O�����A���f�̂��߂Ɏd�����x�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��A����痣�ꂽ�{�݂ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���ȕ��S�ƂȂ��p�������ȂǁA��ԂƔ�p���S�z�i���̂悤�Ȗ�肪�N����Ȃ�����������j �@ACS�ƊW�c�̂͑咰�������f�ŗ\�h�ł��鐔���Ȃ�����1�Ƌ����B�u���f�̃n�[�h����������菜�����Ƃ͍ŗD��ۑ�v�Əq�ׂĂ���B m3.com 2016�N7��28�� |
|
�n���C�H�͂��Ƃ������b�ł����N�ɂ悢 ���A�a�A�S�����A������̗\�h�Ɍ��� |
| �@�n���C�H�́A���Ƃ����b���������Ă��A������A���A�a�A�S�����̗\�h�ɗL���ł��邱�Ƃ��A�V���ȃ��r���[�Ŗ��炩�ɂ��ꂽ�B�����𗦂����ă~�l�\�^��w������Hanna
Bloomfield���́A�u�n���C�H��ۂ��Ă���l�͐S�؍[�ǂ�]�����ɂȂ郊�X�N���Ⴍ�A������ⓜ�A�a�̔��Ǘ����Ⴂ�v�Əq�ׂĂ���B �@�ă��V���g����w�i�Z���g���C�X�j��Connie Diekman���́A���̒m���͒P�Ƃ̐H�i��h�{�f�ł͂Ȃ��A�S�̓I�ȐH���p�^�[�������N�̌��ł��邱�Ƃ��ĔF�������Ă������̂��Ǝw�E����B�u�n���C�H�̌��N���ʂ́A�A�����H�i�𒆐S�Ƃ���p�^�[���ɂ����̂ł��邱�Ƃ���Ɏ�����Ă���A����̌����͂��̗L�]�������߂ė��t������̂ł���v�ƁA�����͘b���Ă���B �@����̌����ł́A1990�N����2016�N4���܂łɔ��\���ꂽ�v56���̌����ɂ��Č��������B�n���C�H�̒�`�́A�O�a���b�ɑ��Ĉꉿ�s�O�a���b�̔䗦�������i���Ƃ��I���[�u�����������������b�����Ȃ��j�A�ʕ��Ɩ�𑽗ʂɐێ�A�}���ȐA���i��q�ށA���ށj�𑽗ʂɐێ�A������V���A���𑽗ʂɐێ�A�ԃ��C����K�ʐێ�A�����i��K�ʐێ�A������ѓ����i�̐ێ悪���Ȃ����̐ێ悪��r�I�����A�Ƃ���7�̗v�f�̂���2�ȏ���������Ƃ��A���N�I�Ȏ��b���̐ێ�ɂ��Ă͐������Ȃ������B �@�ꕔ�̌����ł́A�����̎��͒Ⴉ�������̂̑咰���X�N�̒ጸ�̉\������������Ă������A�u�S�����ɂ�鎀�S���ɑ���e���͔F�߂��Ȃ������v�ƁABloomfield���͘b���B1���̑�K�͌����ł́A�n���C�H�ɂ��S�؍[�ǁA�]�����A���A�a�̃��X�N��30���ጸ���A�����X�N��50���ȏ�ጸ���邱�Ƃ������ꂽ�B����̌����ł͈��ʊW�͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ����A�n���C�H�̓R���X�e���[���A�̏d�A�����l��ቺ������ق��A�R�_���������L�x�ł��邱�Ƃ����N���i�������炷�ƍl�����Ă���B �@�u�n���C�H�����H����ꍇ�́A�܂��A�����ɂ̓I���[�u�����L���m�[�����݂̂��g�p���邱�Ƃ���n�߂�Ƃ悢�v��Bloomfield���͏q�ׁA�{���Ƌ��𑽂��H�ׁA�ԓ������炵�A�|�e�g�`�b�v�X�̑���Ƀi�b�c�ނ�H�ׂ�悤�ɂ���Ƃ悢�ƕt�������Ă���BDiekman���́A��𑝂₵�A�V���A���A�T���_�A����ɂ͓��ɂ��ʕ����g�b�s���O���邱�Ƃ����߂Ă���B���ɁA�������ɓ��ނ�lj�������A���ނɒu���������肷��Ƃ悢�Ƃ����B �@����̌����́uAnnals of Internal Medicine�v�I�����C���ł�7��19���f�ڂ��ꂽ�B�č��ޖ��R�l�Ȃ��{��������ɏ��������B m3.com 2016�N8��1�� |
| �u����ɂȂ������炱���A�ł��邱�Ɓv�C�m�x�[�V�������q�̎v���Ƃ� |
| NPO�@�l�}�M�[�Y���� ������\�@��ؔ��� �uCongratulations!�v �@3�N�قǑO�A���҂̎x���҂������W�܂鍑�ۉ�c�ɎQ���������̂��ƁB��ؔ���(32)�́A���g�������҂ł��邱�Ƃ����͂ɍ�����ƁA����Ȍ��t��������ꂽ�B������A���l���̐l����B ��́A24�̎��ɓ������鍐���ꂽ�B�{�E�ł���L�҂̎d�����x�E���A���Â��A8������ɐE�ꕜ�A�����B �@�u���߂łƂ�!�v�Ɛ���������ꂽ�̂́A�u����ɂȂ������Ƃ��}�C�i�X�ł͂Ȃ��A���Ƃ��v���X�ɂ������v�ƕK���ɂ������Ă������B���Ăł́A����ɂȂ�����̖��ɑ��āA�u���߂łƂ�!�v�ƌ������������邱�Ƃ�m�����B �u�����̐l�����ۂ��ƔF�߂Ă��炦���悤�ȋC�������B���z�̓]�����Đ����ȁA�Ǝv���܂����v �@�u�����Ă��邾���őf���炵���v�ƁA�S�̒ꂩ�犴���邱�Ƃ��ł����B���̏o�������@�ɁA��̋C�������������ς���Ă������B �@��͂��܁A�����E�L�F�Ɍ��ݒ��́u�}�M�[�Y�����v�̃I�[�v�������N10���ɍT���A�z�����Ă���B�}�M�[�Y�Z���^�[�Ƃ́A���҂Ǝx����Ƒ������R�ɉ߂�������A��Â̒m���̂�����Ƃɖ����ő��k�ł���ꏊ�B�p���˂Ƃ���B �@��̓}�M�[�Y�Z���^�[����{�ɂ����ׂ�NPO�𗧂��グ�A������\�߂�B���҂₻�̉Ƒ��Ɂu��v��u�o��v��������ƍl����B �u�w�Ƃ肠�����s���Ή��Ƃ��Ȃ�x�Ǝv����ꏊ�B���ƂȂ��������Ɍ�����g����h�̂悤�ȑ��݂ɂȂ��v �@�����҂Ƃ��āA���Ď������K�v�Ƃ����T�[�r�X�����肽���A�Ƃ����v���͂������B�ł��A�ǂ��ɂ����͎̂��������ł͂Ȃ������B��̌��t�����u�Ƒ������̊��ҁv�B����ł��邱�Ƃ��킩��ƁA��͎d�������߁A�C�O�ɒP�g���C�����Ă������������ɋA�������B�Ƒ�����������ł̈�厖�������B �@�����ڐ��Řb����l�����Ȃ������B �݂Ȑ��_�I�ɂǂ��������������� ��������Ȃ������A�Ɨ�͌����B �u�������܂ő�ςȎv�������Ȃ��� ���ޕ��@���A��������Ȃ����ȁv �@�p���̃}�M�[�Y�Z���^�[�̑��݂�m��A�������{�ɏЉ�悤�Ɨ͂𒍂��ł����A��������\�̏H�R���q�Ɏ����ɍs�����B�����̐l���������݂Ȃ���A�Ȃ�Ƃ��}�M�[�Y�����̒��H�ɂ����������B �@��́A�{�E�̕L�҂Ƃ��Ă̎d���̃y�[�X���ɂ߂邱�Ƃ͂Ȃ��B����ɂȂ������������炱���A�u�Љ�v�Ƃ����傫�Șg�g�݂ɑ��ē`�����邱�Ƃ�����B�����M���Ă���B �������E�݂� ���{�e���r�ɓ��Ђ���3�N�ڂɁA�������鍐�����B8�����̓��a�������o�āA�E�ꕜ�A�B2014�N5���ɁA�{�E�ƕ��s��NPO�@�l�}�M�[�Y�����𗧂��グ��B�����E�L�F�Ɍ��ݒ��́u�}�M�[�Y�����v�͍��N10��10���I�[�v���\��B Forbes Japan 2016�N8��13�� |
| �č��ň���N��������グ���祥��@����A�̎����ɂ�鎀�S�����ቺ�H |
| �@�č��ň����\�ȔN�21�Έȏ�Ɉ����グ���Ĉȍ~�A�A���R�[���������̎����ɂ�鎀�S���X�N���������Ă���\�\�ă��V���g����w�̌����҂炪�A�@�I�ȋK�������N�ɗ^����e���������������ʂ\�����B �@�č��ł́A1984�N����A�M�@�ɂ���Ď�ނ��w���ł���Œ�N�21�ɒ�߂��Ă���A�S��50�B�ň����\�ȔN���21�Έȏ�ƂȂ��Ă���B����͈����^�]��ƍߗ}���̖ړI�Ŏ{�s���ꂽ���̂����A�����҂�͈������J�n����N��̕ω����A���̌�̌��N��Ԃɂ��傫���e�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ����B �@21�ɂȂ�܂ň��������Ă��Ȃ������l�ƁA���Ă����l���r���邽�߁A1990�`2010�N�܂ł̍��������̃f�[�^����A����N�21�Έȏ�ɂȂ�O��ɂ�����1967�`1990�N�̊Ԃ�18�ɂȂ����l�̃f�[�^�𒊏o���A�̎����ƌ��o�A��������̎��S���͂����B �@���̌��ʁA��w�ɒʂ��Ă����l�ł́A�����J�n�N��̈Ⴂ�Ǝ����̎��S���ɗL�ӂȈႢ�͂Ȃ������B�������A��w�ɒʂ��Ă��Ȃ������l�́A21����������J�n�����ꍇ�A21�Έȉ�����J�n�����ꍇ�ɔ�ׁA�A���R�[�����̎����ɂ�鎀�S����8���A���̑��̊̎������S����7���A���o�A��A����ɂ�鎀�S����6���ቺ���Ă����B �@��w�ݐЌo���ō������������Ƃɂ��Č����҂�́A�u��w�ł͓`���I�ɖ����N�҂̈�����\������������镶��������A���ꂪ�����J�n�N��̕ω����Ȃ����Ă���̂ł́v�ƃR�����g���A��w���̑��������ɑ��Čx����炵�Ă���B �@���\�́A2016�N6��24���A�ăA���R�[�����ŏnj�����uAlcoholism: Clinical and Experimental Research�v�I�����C���łɌf�ڂ��ꂽ�B �Q�l���� The Impact of the Minimum Legal Drinking Age on Alcohol-Related Chronic Disease Mortality. Aging Style 2016�N8��17�� |
| ���ł���ގ��A�]�ڂɂ����ʁ@�}�E�X�����Ŋm�F�@�č����q�������� |
| �@���̈��̋ߐԊO���Ă���@�ŁA����זE���U������Ɖu�זE�̃����p���������������A����זE��ގ����鎡�Ö@���J�������ƁA�č����q���������i�m�h�g�j�̏��ыv����C�������炪�A�P�V���t�̕Ĉ�w���̓T�C�G���X�E�g�����X���[�V���i���E���f�B�V���ɔ��\�����B�}�E�X�̎����œ]�ڂ���ɂ������Ɗm�F�����Ƃ����B �@�����p���̒��ɂ́A����Ď������g���U������̂�h���u���[�L���̍זE������B����̖Ɖu�Ö@�́A�����p���̓�����S�g�Ŋ����������邽�߁A���N�ȍזE���U�����Ă��܂��u���ȖƉu�����v���N���鋰�ꂪ���邪�A�������̓x��������߂�ƌ��ʂ���܂�̂��ۑ肾�����B�J�������̂́A����זE�����Ńu���[�L�������@�B���т���́u���̃W�����}�������������͂Ȗ�܂ƂȂ蓾��v�Ƙb���Ă���B �@���т����́A����̔g���̋ߐԊO���Ă�Ƌ߂��ɂ���זE��j�鉻�w�����𗘗p�����B���̕����ƁA�u���[�L���́u���䐫�s�זE�v�Ɍ��т��₷�����q��g�ݍ��킹�������̂��쐻�B������ڐA�����}�E�X�ɒ��˂��āA����̕����ɂ������Ă��B����Ɛ��䐫�s�זE���j��ă����p�������������A����זE���������Đ������Ԃ��L�т��B ZAKZAK�[���t�W 2016�N8��18�� |
|
�I�����C���T�|�[�g��������҂͎��Ö����x������ �����̏������f�f��ɃT�|�[�g���p |
| �@������Ɛf�f���ꂽ�̂��ɁA�\�[�V�������f�B�A��ʂ��Ęb����������A�I�����C����Ŏ��Ö@�Ɋւ������x�����������ł́A�ŏI�I�Ȏ��Ì���ɑ��閞���x���������Ƃ��A�V���������Ŏ����ꂽ�B �@�u����̒m���́A���҂�������̎��Ö@��I������ۂɕK�v�Ƃ���x���̃j�[�Y����������Ă��Ȃ����Ƃ�����������̂��B�������A�����_�ł́A�Տ�����ł��ׂĂ̊��҂��\�[�V�������f�B�A��I�����C���E�R�~���j�P�[�V�������ő���ɗ��p���邱�Ƃ͓���v�ƁA�������哱�����ă~�V�K����w��w����Lauren Wallner���͏q�ׂĂ���B �@���̌����́A������Ɛf�f���ꂽ�̂��Ƀ��[����g�сi�V���[�g�j���[���A�\�[�V�������f�B�A�A�I�����C���T�|�[�g�O���[�v�ւ̎Q���Ȃǂ̎g�p�o���Ɋւ��鎿��ɉ���2,460�l�̏�����ΏۂƂ������́B �@��͂̌��ʁA�S�̂�40���ȏ�̏������u�Ƃ��ǂ��v�A���邢�́u�p�ɂɁv�I�����C���ŃR�~���j�P�[�V�������Ƃ����Ɖ��Ă����B�܂��A��30���̏����̓��[���܂��͌g�у��[���A���邢�͂��̗������A��12����Twitter��Facebook�Ȃǂ̃\�[�V�������f�B�A���g�p���Ă���A�I�����C���T�|�[�g�O���[�v�̗��p����12���̏����ɂ݂�ꂽ�B �@���ꂼ��̃��f�B�A��p���闝�R�͈قȂ�A���[����g�у��[���͓�����Ɛf�f���ꂽ������N���ɓ`�����i�Ƃ��ėp�����Ă������A���Ö@�����ɂ�鐄�����e�Ɋւ���������ɂ́A�\�[�V�������f�B�A��I�����C���T�|�[�g�O���[�v��p����X�����݂�ꂽ�B����ɁA�����̃��f�B�A�́A������̐f�f�����̂��̔ے�I�Ȋ����X�g���X�ɑΏ����邽�߂ɂ��L���p�����Ă��邱�Ƃ��킩�����B �@�����������f�B�A��p���鏗���̓����́A�Ⴂ�����������A���l��A�W�A�l�̏����قǃI�����C���E�R�~���j�P�[�V������p����p�x�������A���l��q�X�p�j�b�N�n�ł͂����̗��p���͒Ⴉ�����B�܂��A�I�����C���ŃR�~���j�P�[�V�������Ƃ鏗���ł́A�����̎��Ì���ɑ��čł��m��I�ŁA���̌���͐T�d�ɂȂ��ꂽ���̂Ŗ����x�������Ɖ��銄�������������B �@�������A���̒m���́ATwitter��Facebook�Ƃ������\�[�V�������f�B�A�̗��p�����ׂĂ̓����҂ɂƂ��ėL�v�ł��邱�Ƃ��ؖ�������̂ł͂Ȃ��A���߂ɂ͒��ӂ��K�v�ł���ƁA�����O���[�v�͋������Ă���B �@�����́A�ꕔ�̓����҂ł̓\�[�V�������f�B�A�͎��Â̈ꏕ�ƂȂ肤�邪�A���҃P�A�̈�ɑg�ݍ��ނ��Ƃɂ͐T�d�ȍl���������A�u������Î҂́A���҂��I�����C����Ŗڂɂ���������ׂĔc�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A�����������̎���ʂȂǂ̎��Ԃ͂悭�킩���Ă��Ȃ��B���悢���Ҏx�����s���ɂ́A�܂��A���������_���\���ɗ�������K�v������v�Əq�ׂĂ���B �@���̒m���́A�uJAMA Oncology�v�I�����C���ł�7��28���f�ڂ��ꂽ�B m3.com 2016�N8��22�� |
| �늳�ҋ}���̂��܁c�]���[�V����ɕ����u����Ƃ̌��������� |
| �u����܂ł���Ɗւ���Ă��āA�����������邱�Ƃ́A�a�����������Ă͂����Ȃ��Ƃ������ƁB�a�C����w�Ԃׂ����Ƃ͎R�قǂ���܂��B�a���ɂȂ������ƂŁA����܂Œz���Ă������Ƃ��������Ƃ����l������ł��傤�B����ǂ����ŏ��߂Ď����̐l���ɂ����đ�Ȃ��Ƃ͉����������Ă���Ƃ������Ƃ͂���̂ł��v �@�������̂́A�]���[�V����B7��15���A��������Z���^�[�́A�f16�N�ɐV���ɂ���Ɛf�f�����l�����߂�100���l��˔j����Ƃ����\�����ʂ\�����B�܂��A����̂��߂ɖS���Ȃ�l���f16�N��37��4,000�l�ƁA�ߋ��ō��ɂȂ錩���݂��Ƃ����B �@�X�s���`���A���X�g�Ƃ��āu�����ɐ����������v�Ƃ����l���N�w��`�������Ă����]������́A����܂ő����̂��҂����̑��k���A�܂����̍Ŋ���������Ă����B����ɂȂ����Ƃ��A�����̂��߂ɁA�����ĉƑ��̂��߂ɂǂ���������̂��H����ȁA���҂����̔Y�݂ɂ��č]������ɕ����܂����B �y����Ɛf�f����܂����B���ʂ̂��|���ł��z �@�l�͐��܂ꂽ�u�Ԃ��玀�Ɍ������Ă���Ƃ����܂��B�킩���Ă͂��Ă��N�ɂł������K��鎀���|���̂͂Ȃ��ł��傤�H����͂��Ȃ������疳�ɂȂ�Ǝv���Ă��邩��ł��傤���B �@���܂����͉i���ł��B���ʂƂ��͓��̂Ƃ��������ȕ���E���̂Ă�Ƃ��ł�����̂ł��B���Ƃ͂��̐��łȂ��ׂ����Ƃ��I���Ă��܂������A���Ă������ƁB���̂Ƃ��ɂ��܂������������Ă��邩�Ƃ����ƁA���}���̐l�ł��B��ɐ�������Ȑl��Ƒ������}���ɗ��Ă����̂ł��B�����Ă��̐��ɋA����ׂĂ̂��Ƃ������ɂȂ�A�������ɂ���������Ă����܂��B���������}�����Ȃ�����A���̐��ōs�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B �y�������������ɂ́A�ǂ�ȐS�\�����K�v�ł����H�z �@���܂̏�����A�����������ӂ��ď[���������邩�ǂ����Ƃ������Ƃɐs���܂��B�u����Ȃ炢���Â����܂ŁH�v�����v�����Ƃ�����ł��傤���A���Â��A���������莕�����肷�邱�ƂƓ����悤�ȓ���̏K���Ƃ��Ď���܂��傤�B������߂��������Ƃ����ӂ��Ȃ���ςݏd�˂Ă��������ɁA����Ƃ����a�����牓������A�������������Ă���Ƃ������Ƃ���������܂��B�������Ĉ�����ɐ����Ă����Ȃ�A���Ƃ��Ĕ����ėՏI���}�����Ƃ��Ă����ӂ��Đ������Ƃ��ł��܂��B �y�q���ɂ��a�̂��Ƃ�b���ׂ��ł��傤���H�z �@���q����̔N���C���ɂ����Ǝv���܂����A�����̏ꍇ�A�c���Ƃ�����Ȃ�ɂ����Ə𗝉����Ă��܂��B���̋���͂ƂĂ���Ȃ��Ƃł��B�u�q���̃g���E�}�ɂȂ����炩�킢����������v�ȂǂƉߏ�ɔz�����A�a���ɂ����q��������Ȃ����Ƃ�����Ƃ����܂��B����ǂ��A����͂�����ƈႤ�Ǝv���܂��B������l�͎��ʂ̂��Ɨ������邱�ƂŁA���������Ă��邱�Ƃ͑������ƂȂ̂��ƒm�邱�Ƃ��ł���̂ł��B �������g 2016�N8��22�� |
|
�咰���u���E�ŗ\��ɍ��v�̃C���p�N�g �� �p���E��B��w������E�����O�Ȑf�Ïy�����ɕ��� |
| �@���{�ł��늳���������Ă���咰���B����20�N�Ŏ�p��������Z�p�̐i���A���w�Ö@�̃G�r�f���X�W�ςɊ�Â����Ð��т̌���ɂ��A�i�s���咰���̐������Ԓ����l�͗Տ������A�ώ@�������킸�ő�30�J�����x���������Ƃ��w�E����Ă���B����Ȓ��A�����̗Տ������ł���Ȃ鎡�Ð��т̌���Ɋ�^����\����������A���ڂ��W�߂Ă���̂��u�咰���������̍��E�ɂ��\��̈Ⴂ�v���B2�l�̐��Ƃɂ���܂ł̌o�܂�W�]�����B��1��͋�B��w������E�����O�Ȑf�Ïy�����̉��p�����B���N5���̕č��Տ���ᇊw��iASCO�j�ł̃n�C���C�g������܂߁A�咰�́u���E�v�ɂ܂��b�����������������B �@ ��ܕʂł́u�������Ԃɍ��Ȃ��v�����E�ʉ�͂ō� �@���N5���A�č��Տ���ᇊw��iASCO�j�N���W��Ŕ��\���ꂽ�ACALGB/SWOG 80405�����̒T���I��͂̌��ʂ��傫�Ȓ��ڂ��W�߂��B�i�s���咰������1140�Ⴊ�Q�������������ł́A���w�Ö@�ւ̍RVEGF�R�̃x�o�V�Y�}�u�A�܂��͍REGFR�R�̃Z�c�L�V�}�u�̒lj��Ö@�ɂ��\����r�B2014�N�̓��w��N���W��Ŕ��\���ꂽ���͂ɂ����āA���Q�ł̑S�������ԁiOS�j�����l�Ȃ�тɖ������������ԁiPFS�j�ɗL�Ӎ��͌����Ȃ��Ƃ̌��ʂ������B �@�������A������ꂽ�T���I��͂ł͂Ȃ�ƌ����������i���s�����AS���A�����j���E�i�Ӓ��A��s�����j���Ŋ��҂�w�ʉ����AOS�����l����͂����Ƃ���A����������33.3�J���A�E��������19.4�J���ƗL�ӂȍ�������ꂽ�B��ܕʂ̉�͂ł��A����������OS�����l�̉������F�߂�ꂽ���A��܂��Ƃɐ������Ԃ̍��͌����Ȃ��������͂ƈقȂ�A����̉�͂ł͉E�������Q�Ńx�o�V�Y�}�u�A���������Q�ł̓Z�c�L�V�}�u�̐������ԉ������m�F���ꂽ�B �E�ƍ��̑咰�͂���ȂɈႤ �@�咰�����E�ɕ����ĉ�͂���Ƃ����l�����̔w�i�ɂ͉�������̂��B�u���Ƃ��ƉE�ƍ��̑咰�͐����w�I�ɈႤ�B�O�Ȉ�ɂƂ��ẮA�咰�����E�ɕ����čl����͎̂��R�Ȃ��Ɓv�Ɖ����B�����w�I�ɂ��E�i�߈ʁj�咰�͒����n�A���i���ʁj�咰�͌㒰�n�ƈقȂ�R���������A�x�z���ǂ��E���咰�̏ꍇ�ɂ͏㒰�ǖ������n�A�����咰�̏ꍇ�ɂ͉����Ԗ������n�ƈقȂ邱�Ƃ���A��p�̍ۂɂ���p���ʂ��E�������ŏ������錌�ǂ��S���Ⴄ�Ǝw�E����B �@�����ɂ��ƁA����܂łɂ����E�̑咰�ɂ����Ē����ۑp���قȂ�Ƃ̕�����ق��A�E�ƍ��ł͑咰���̜늳�̔䗦���Ⴂ�A���s�������璼���܂ł����킹�������̑咰����7�����߂�B���n�Տ��ł̑咰���̔������₷�����قȂ�A���̏ꍇ�A�����⌋���̒��ǂ����������ɔ�������邱�Ƃ��������A�E���͕ւ��t��Ȃ̂Ŕ������x��邱�Ƃ��\��̈����Ɋ֘A���Ă���̂ł͂Ƃ��l�����Ă����������B �咰���́u���E�v�ŗ\�オ�قȂ�Ƃ̕��ߔN�W�� �@1985�N������́A���E�̌������Ŋe�����`�q�̔����l�����قȂ邱�Ƃ�����n�߂Ă���A�������2010�N���ɉE����������DNA�̉���z��̌J��Ԃ��i�}�C�N���T�e���C�g�j�̕s���萫�imicrosatellite instability: MSI�j�z�����A���咰���ɂ�p53��`�q�ψق������݂���Ƃ̕\���Ă���iCancer Genet Cytogenet 2010; 196: 133-139�j�B���ɂ������X�e�[�WIV�咰���ł��E�������ł��i�s�����������ٓI���S���������Ƃ̑��{�����̌X���X�R�A�}�b�`���O�����iInt J Surg. 2014;12(9):925-30�j�A�������̕��ʂ͊��҂̗\��Ɋ֘A���A�E�������ł��s�ǂł������Ƃ̍����O��15�������܂ރV�X�e�}�`�b�N���r���[�ƃ��^�A�i���V�X�iJ Gastrointest Surg 2016; 20: 648-655�j�Ȃǂ̕��W�ς�����B �������̈ʒu���gprecision medicine�h�����̗L�]�ȃ}�[�J�[�� �@����ACALGB/SWOG 80405�����̒T���I��͂��傫�����ڂ��ꂽ�|�C���g�ɂ��āA�u�咰���̗\�オ�������̍��E�ō������邱�Ƃ��ő�K�͂̕�W�c�ŏؖ����ꂽ���Ɓv�u�������̍��E�ŕ��q�W�I��̊����傫���Ⴄ�\���������ꂽ�v�_�������������B�u�č��𒆐S�ɋ@�^������オ���Ă��銳�Ҍl�̔w�i���q���l�������œK����Áiprecision medicine�j�̎����ɁA�咰���������̈ʒu���L�]�ȑ�փ}�[�J�[�ł���\���������ꂽ���Ƃ����ڂ��ꂽ�̂ł́v�ƕ��͂���B����́A���E�ɂ��\��̍��̕]������ړI�Ƃ��������ł͂Ȃ��A���炩���ߍ��E�̈ʒu����w�ʈ��q�Ƃ��Č����v��𗧈Ă��Ă������Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��邾�낤�Ƃ��b�����B �@ �u���E�v���͊O�Ȏ��Â̕��j�ɂ��e��? �@�咰���̌����a�ϕ��ʂɂ��\��̍��̉𖾂́A�O�Ȏ��Âɂ����炩�̉e���������炷�̂��낤���B�u������p�ɂ��ẮA�E�ƍ��̊��Ń����p�ߊs���x�ɍ��������肷�邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�����A���\��̌��オ�����߂邱�Ƃ���A���̑咰����������̓]�ڑ��ɂ����Ă��ϋɓI�Ȑ؏����s������A�����X�e�[�W�ł��E�������̏ꍇ�͗Տ��I�����x�������ƍl���A�p��⏕���w�Ö@��ϋɓI�ɍs������Ƃ������ω����o�Ă���\���͂���v�Ɖ����B�؏��s�\�E�Ĕ����ɂ��ẮACALGB/SWOG 80405�����ĉ�͂̌��ʂ���A�E�������̏ꍇ�x�o�V�Y�}�u���A�������������̏ꍇ�ɂ̓Z�c�L�V�}�u���g�������Â��I������邱�ƂɂȂ�̂��A�傫�ȊS�������Ă��邻�����B�������A�u���Տ��ŁA���E�̈ʒu����łǂ��炩����̖�܂�I������Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ̍l�����������B m3.com 2016�N8��23�� |
|
�K�x�ȉ^���������҂́u�P���u���C���v�����P���� �L����Q��ጸ |
| �@�������҂ɂ��������炳��閝���I�ȋL����Q�⒍�ӗ͂̒ቺ�̈ꕔ�́A�ߓx�ȃX�g���X���ׂɂ���Ĉ����N������Ă���A�K�x�ȉ^�����s�����Ƃł���������Q���y���ł���\�����A�V���������Ŏ����ꂽ�A �@�u����̒m������A�����x���猃�����^�����s���Ɛ��_�ʂɃx�l�t�B�b�g�������炵�A�L����Q�̒ጸ�ɂ��Ȃ��邱�Ƃ��킩�����v�ƁA�������哱�����ăm�[�X�E�F�X�^����w�t�F�C���o�[�O��w����������Siobhan Phillips���͏q�ׂĂ���B �@���҂ɐ�����L����Q��v�l�͂̒ቺ�́u�P���u���C���v�ƌĂ�A�����ɉ��w�Ö@����ː��Ö@��ɂ����炳�����̂ƍl�����Ă��邪�A�u����̒m������A�����̏�Q�̈ꕔ�͐��_�I�Ȃ��̂ɋN������\�����������ꂽ�v�ƁA������͎w�E���Ă���B �@������́A�u�������҂͋����X�g���X�A���ӊ����˂ɕ����Ă���A��ʂ��s����ŁA���M��r�����Ă���ꍇ�������B����������Ԃ����������Ɛ��_�I�ȏd�ׂƂȂ�A���̌��ʁA�L����Q�Ǝv�����ԂɂȂ�₷���Ȃ�v�Ɛ������Ă���B �@����̌����ł́A�����Ì�̐�����1,400�l����ΏۂɁA�����J�n���_��6�J����ɂ�����^���ʂ⎩�Ȍ��͊��A�}����Ĕ��ւ̌��O�Ƃ��������_�I��ɂ̒��x�A��J���Ɋւ��鎩�Ȑ\���ɂ�钲�����s�����B����ɁA�����_���ɒ��o����362�l�̏����ɂ͉����x�v�����Ă��炢�A�^���ʂ�ǐՂ����B �@���̌��ʁA�ΏێґS�̂Ɖ����x�v�ʼn^���ʂ��v�������T�u�O���[�v�ł͂�������A�������⎩�]�ԑ��s�A�W���M���O�A�^�������ւ̎Q���Ƃ����������x���猃�����^���ɂ��g�̊����ʂ̑����ɔ����A���Ȍ��͊������܂�A�X�g���X�⌑�ӊ����y�����邱�Ƃ��킩�����B������ɂ��ƁA�����������_�I�ȃx�l�t�B�b�g�͋L���͂̌���ɂ��Ȃ����Ă���Ƃ����B �@���̌����́A���ړI�Ȉ��ʊW���ؖ�������̂ł͂Ȃ����A�^���ʂ̑����ɔ����ď����͎��M�����A���_�I��ɂ̒��x���y�����Ă���A�����̉��P���L����Q�̌y���ɂ��֘A���Ă���\���������ꂽ�B �@�Ȃ��A���̒m���́uPsycho-Oncology�v7��8���I�����C���łɌf�ڂ��ꂽ�B m3.com 2016�N8��25�� |
| �ߑ̏d�Ń��X�N���܂邪��A�V����8�� ���� |
| �@�ߑ̏d�ɂ��A�݂��������ǂ̂���̑��A����̔]��ᇂ�B���ᇂƐf�f����郊�X�N�����܂鋰�ꂪ����Ƃ��錤���_����24���A���\���ꂽ�B �@�Ĉ�w���u�j���[�C���O�����h��w�W���[�i���iNew England Journal of Medicine�j�v�Ɍf�ڂ��ꂽ���ی����@�ւɂ����ł́A�ߑ̏d�̐l���늳���₷���Ƃ���邪��̈ꗗ�ɁA�V����8��ނ��lj����ꂽ�B �@�t�����X�ɖ{����u�����E�ی��@�ցiWHO�j�t���́u���ۂ����@�ցiIARC�j�v��2002�N�A���������H������A�t������A������A�q�{����Ȃǂ́A�ߑ̏d�ɂ�肻�̃��X�N�����܂�\��������Ɣ��\���Ă���B �@�����č���A�݂����̑�����A�_�̂�����A�X���i���������j����A��������A�b��B����̑��A������Ƃ��Ēm����]��ᇂ̈��⌌�t�̂���ł��鑽����������Ȃǂ��V���ɒlj����ꂽ�B �@�����`�[���́A�ߑ̏d�Ƃ���̃��X�N�Ɋւ���_��1000���ȏ�ׂ��B �@���́A�k�Ă≢�B�A�����̏��������ɂ݂��邪��̖�9���́A�얞�Ɋ֘A���Ă���ƍl������Ƃ��Ă���B�܂��A�ߏ�Ȏ��b�͉��ǂ𑣂��A����̐����𑣐i���鋰�ꂪ����G�X�g���Q����e�X�g�X�e�����A�C���X�����̉ߏ蕪��ɂ��Ȃ���Ǝw�E���Ă���B �@�����`�[���́A�����ɂ킽��̏d�����̐������A�����̂��X�N��ጸ������ꏕ�ƂȂ�Ƃ��Ă���B AFPBB News 2016�N8��25�� |
|
������i���ŐH���ٌ^��烊�X�N�� ����A�֎��ŐH�����̍Ĕ��}���\�Ǝw�E |
| �@���s��w��8��25���A�H���G����炪��̔�������\���i�O����a�ρj�Ƃ����ٌ^���̔������x�ɂ́A�����A�i���A�Ή��F��̐ێ�Ƃ���3�_���֘A���Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����Ɣ��\�����B�܂��A���������Â��s���������H�����҂ł́A�H�����ٌ̈^���̐��������قǁA�H������̂ǂَ̈�����������̊댯�����������ƁA�����āA�֎��ɂ���ĐH������̍Ĕ���}���ł��邱�Ƃ𐢊E�ŏ��߂Ĕ��������Ƃ��Ă���B���̌����́A����w��w�����Ȃ̕����w������̌����O���[�v�ɂ����̂ŁA�������ʂ́A�uGastroenterology�v��8��1���t���Ōf�ڂ���Ă���B �@�H������ɂ́A�ߓx�Ȉ�������Ȍ����Ƃ����G����炪��ƁA�ݎ_�t�����֘A����o���b�g�B�����2�̃^�C�v�����邪�A�G����炪��͓��{�l�̐H������̖�90�����߂Ă���B�܂��A�H���G����炪��͐H�����ł̂����⓪�̝G����炪��̍������Ђ��N����Filed cancerization���ہi�L�攭���ہj�������炵�A���Ì�ɕʂ̕��ʂł��Ĕ����邽�ߗ\�������Ɉ���������B �@�H���G����炪��́A�O����a�ςƂ����ٌ^��炩�甭������ƍl�����Ă��邪�A����܂ňٌ^���̒��x�ƐH�������A������Filed cancerization���ۂƂ̊֘A���͂킩���Ă��Ȃ������B����̌����Ƃ�����������߂��ꍇ�̌��ʂ��A�\���Ȍ�������Ă��Ȃ������B �@�����ŁA�����O���[�v�́A���������Â����������H������330�l�ɋ��͂��˗����A���Ì�̌o�ߒ��ɂǂ̂��炢�̊��ԂŁA�ǂ̂��炢�̊����ŁA�H������⓪�̂��������邩������ǐՒ��������{�����B�܂��A�S���ɋ֎�����ы։��w�����s���A�֎��E�։��ɂ�锭����}�����ʂ������B����ɁA�H�����ٌ̈^���̒��x��gradeA�`C�ɕ��ނ��A�َ�������̔������ώ@�����B �@���̌��ʁA �E�O����a�ςƂ����ٌ^���̔����ɂ́A�����A�i���A�Ή��F���H�ׂȂ��A�₹���֘A���� �E�H�����ɑ������ٌ̈^��炪����ƁA�H������������A������̔����������Ȃ� �E�֎�������ƁA�َ����̐H����������Ɍ��������邱�Ƃ��ł���B���ɁA�H�����ɑ������ٌ̈^��炪���銳�҂ł�4����1�Ɍ��������邱�Ƃ��ł���B����A�։��̒Z���I�Ȍ��ʂ͊��҂ł��Ȃ����� ���Ƃ����炩�ɂȂ����Ƃ��Ă���B �@�����́A���������҂ł���H�����҂̎��Ì�̐����w���̏d�v���������Ă���B����͌o�ߊώ@������ɉ������ƂŁA���̑���̂���̔����⍡��m�F�ł��Ȃ������։��̌��ʂȂǂ����Ă����\��ƁA�����O���[�v�͏q�ׂĂ���B m3.com 2016�N8��30�� |
| ���Â�Google�̐l�H�m�\������I |
| �@UCLH�i�����h����w�a�@�j�́A��Ɍ��o�A�����A�A���A�@�o�A���@�o�A���t�B�A�b��B�A�H���A�C�ǂɌ����u������v�̎��ÂɁAGoogle�̐l�H�m�\�uDeepMind�v�𗘗p����Ɣ��\���܂����B �@��̓I�ɂ́A���ː����Â̌������ɖ𗧂Ă���\��ł��B ���ː����Â̌v�掞�Ԃ��A4����1�ɒZ�k�I �@������́A�j���ł�75�l��1�l�A�����ł�150�l��1�l�����ǂ���ƌ����Ă���A�����đ��l���Ƃ͌����Ȃ��a�C�B���̎��Âɂ͕��ː����Â��p�����Ă��܂��B �@�������A�������ӂɂ͌��N�ȍזE��_�o�����邽�߁A�Ǝ˂���ʒu��p�x��Ȗ��Ɍv�悷��K�v�A���B �@�����[�X�ɂ��A���̏Ǝ˃}�b�v�̍쐬�i�Z�O�����e�[�V�����j�ɂ͂��悻4���Ԃقǂ�����܂��B�����ŁA�ߋ�700���̑O���l�H�m�\�Ɋw�K�����v�Z�����������A1���Ԃ܂ŒZ�k����z��B�����b�g��2�B �E���҂̃P�A�Ɏ��Ԃ�������B �E�Z�O�����e�[�V�����A���S���Y���̊J���B �@���̃A���S���Y���J�����i�߂A���̕��ʂւ̕��ː����Âɉ��p�ł���Ƃ������Ă��܂��B �@�������f�f��������10���œ��肵����A�p�^�[�����̓�����_�����ւ̑Ή����ߋ��̎������ɉ��P����IBM�̃��g�\���ɑ����A�l�H�m�\�̃����b�g����ÂւƐ��������V��������ƂȂ邩������܂���B �K�W�F�b�g�ʐM 2016�N9��4�� |
|
���l���ɑ��肷���̊��Ԃ������ƁA�o��Ɉꕔ���X�N���㏸���� WHI����7���l���̉�� |
| �@���������l���ɉߑ̏d�ł�����Ԃ������قǁA�o��Ɉꕔ�̂��X�N�����܂�Ƃ̌������ʂ��A�uPLOS
Medicine�v8��16���d�q�łɌf�ڂ��ꂽ�B �@���ۂ����@�ցiIARC�A���������j��Arnold����́AWomen�fs Health Initiative�����ɎQ�������o�㏗��7��3,000�l����ΏۂɁA�ߑ̏d�iBMI 25�ȏ�j��얞�i��30�ȏ�j�̊��ԂƂ��X�N�Ƃ̊֘A�������B �@���̌��ʁA���l���̉ߑ̏d���Ԃ�10�N�����邲�ƂɁA������◑������Ȃǂ̔얞�Ɋ֘A�������X�N��7���㏸�B�Ƃ��ɕo�������Ǝq�{�̂��X�N�͊e5���A17���㏸���A�ߑ̏d�̒��x�ŕ��̉�͂ł͊e8���A37���܂ŏ㏸�����B m3.com 2016�N9��5�� |
|
�i���ɂ��x�����X�N�u�m���v�� ������A���^�A�i���V�X�����Ń��X�N��1.3�{ |
| �@���������Z���^�[��8��31���A���{�l�̔�i���҂�ΏۂƂ����i���Ɣx����Ƃ̊֘A�ɂ��ĕ����̘_�����A��͂��郁�^�A�i���V�X�����̌��ʂ����\�����B���̌����ł́A�i���̂���l�͂Ȃ��l�ɔ�ׂĔx����ɂȂ郊�X�N����1.3�{�ŁA���ۓI�ȃ��^�A�i���V�X�̌��ʂƓ��l�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B�������ʂ͊w�p���uJapanese
Journal of Clinical Oncology�v�Ɍf�ڂ���Ă���B �@�\���i���Ɣx����̊֘A�ɂ��ẮA�����̒����A�����ɂ�胊�X�N�v���Ƃ��Ċm���ł��邱�Ƃ����炩�ŁA���{�ł͔x����̎��S�̂����A�j����70���A������20���͋i���������ƍl�����Ă���B�܂��A�x����ȊO�̂���Ƃ̊֘A�����炩�ŁA����̎��S�̂����A�j����40���A������5���͋i���������ƍl�����Ă���B �@�i���Ɣx����̊֘A�ɂ��ẮA1981�N�ɕ��R�Y��������Z���^�[�������u�w�����i�����j�����E�ŏ��߂ĕB2004�N�ɂ́A���ۂ����@�ցiIARC�j�����̂������̔�����F�߂�Ɏ����Ă���B���{�l��ΏۂƂ�������������܂łɑ������\����Ă���A���Z���^�[�ɂ�鑽�ړI�R�z�[�g�������������Ă��邪�A�x����S�̂Ɋւ��ČX�̌����ł͓��v�w�I�ɗL�ӂȌ��ʂ�����ꂸ�A���{�l��ΏۂƂ����Ȋw�I�����Ɋ�Â����X�N�]�����u�قڊm���v�ɂƂǂ܂��Ă����B �@����̌����ł́A���{�l�̔�i���҂�ΏۂɎi���Ɣx����̊֘A�����426�{�̌����̂����A�K�p�������9�{�̘_�����ʂɊ�Â����^�A�i���V�X���s�����B���̌��ʁA���{�l��ΏۂƂ����u�w�����̃��^�A�i���V�X�ɂ����āA�i���Ɣx����Ƃ̊Ԃɓ��v�w�I�ɗL�ӂȊ֘A���F�߂�ꂽ�B�i���ɂ�鑊���X�N�͖�1.3�{�ŁA���ۓI�ȃ��^�A�i���V�X�̌��ʂƓ��l�B�����f�U�C���A�o�ŔN�A�𗍈��q�̒����L���ɂ���đw�ʂ��Ă��قړ������ʂł������B�o�Ńo�C�A�X�͓��v�w�I�ɗL�ӂł͂Ȃ��A�o�Ńo�C�A�X��⊮���Ă����ʂ͕ς��Ȃ������Ƃ����B �@����̌������ʂ܂��A���Z���^�[�Љ�ƌ��N�����Z���^�[�𒆐S�Ƃ��錤���ǂ́A�i���ɂ�������{�l��ΏۂƂ����Ȋw�I�����Ɋ�Â��x����̃��X�N�]�����u�قڊm���v����u�m���v�ɃA�b�v�O���[�h�����B����ɔ����A���{�l�̎���ɍ��킹�i���A�����A�H���A�g�̊����A�̌`�A������6���ڂł���\�h�@����Ă���K�C�h���C���u���{�l�̂��߂̂���\�h�@�v�ɂ����Ă��A���l�̂����̉����u�ł��邾��������v����g�ł��邾���h���폜���u������v�֕����̏C�����s���A�i���̖h�~��w�͖ڕW���疾�m�ȖڕW�Ƃ��Ē����B m3.com 2016�N9��5�� |
| ���{�́u�O�Ȏ����`�v |
| �@���{�̈�ÂƃA�����J�̈�Â͑傫���Ⴂ�܂��B��펞�̌R���ɑ��闼���̍l�����̂悤�ɈقȂ�̂ł��B �@�������̂́A�����������Z���^�[����\�h�E���f�����Z���^�[�̃Z���^�[���ŃO�����h�n�C���f�B�b�N��y�������̐X�R�I�V���B���̓A�����J�A�~�l�\�^�B�ɂ��鐢�E���w�̖��a�@�ƌ����郁�C���[�E�N���j�b�N�ɍݐЂ������Ƃ�����A���Ă̂��Â̈Ⴂ��m����l�҂��B �@�܂��A�A�����J�͈�t�̐������ɑ����B�~�}���҂��^��Ă����Ƃ��Ă��A�Ζ����Ԃ��I�������҂͂������ƋA���Ă����܂��B���ꂾ���l���ɗ]�T������킯�ł��B �@����A���{�ł͈�Ï]���҂����Ȃ��Ȃ��ŁA���ߍׂ�����Â��{�����Ƃ�ړI�Ƃ���̐��ɂȂ��Ă���A��҈�l�ЂƂ�̕��S���傫���B���ꂼ��̈�t�̋Z�ʂ͍����Ă��A���Z�̂��߂�������~�X���N���Ă��܂��\��������܂��B�f�@�Ɏ��Ԃ��������Ȃ��B �@���Ăň�l�ЂƂ�̈�t�̋Z�p�̍��͂Ȃ��B�ނ��날��̈�ɂ����Ă͓��{�l�̂ق����ォ������܂���B��������ÃV�X�e���S�̂Ƃ��Č����ꍇ�A�A�����J�̂ق����悭�ł��Ă���_������܂��B �@���{�ƃA�����J�ł͌��N�ی����͂��߁A��Ð��x���傫���قȂ�܂��B�F�ی��ŒN������背�x���̗ǎ��Ȉ�Â�����Ƃ����Ӗ��ł́A���{�̈�Â͔��ɗD��Ă��邪�A�����Ɉ�Âɑ���R�X�g�������邽�߂ɖ����������Ă���ʂ�����̂ł��B �@�A�����J�ł͊��҂���Õی��ɉ������Ă���ꍇ�ł��A�����b�g�����Ȃ����ʂȃR�X�g���肩�����Ís�ׂ��{���ꂽ�ꍇ�A�ی���Ђ���ی������x�����Ȃ��ꍇ������B �@�]���Ċ��҂͖{���ɕK�v�Ȍ����͂Ȃɂ��A��p�Ό��ʂ̍������Ö@�͂Ȃɂ��Ƃ����_�Ɋւ��ăV�r�A�Ƀ`�F�b�N����悤�ɂȂ�B��ÃV�X�e�����̂����S���������A�R�X�g�Ɍ���������Â�I������悤�ɏo���オ���Ă���̂��B �@�A�����J�ł́A�a�C�ɂȂ����Ƃ��ŏ��ɂ�����̂́A�����́w���������x�ł��B�ނ�͈�ẪR���T���^���g�̂悤�Ȗ����ł��B�����������ꍇ�A�܂�Ń��X�g�����̃��j���[���L����悤�Ȋ����Łw��p�Ȃ炢����A����ɕK�v�Ȍ����͂�����A���ː����Â�����Ȃ炢���炩����x�ƃR�X�g��X�N�A�����b�g�ɂ��Đ������Ă���܂��B �@���������͎��ۂɎ��ÂɊւ��킯�ł͂���܂���̂ŁA�q�ϓI�Ō����ȗ��ꂩ��x�X�g�Ȏ��Ö@��I���ł���悤�A�h�o�C�X���Ă����B ���{�̏ꍇ���ƁA�ŏ��ɂ��������̂��O�Ȃ̈�t���ƁA�ǂ�������p�����邩�Ƃ������Ƃ��肪�D�悳�ꂪ���ŁA�ʂ����ĕ��ː����Â������̂��A�R������Â������̂��Ƃ����������I�ȗ���ł̎��Õ��@���I��Ȃ����Ƃ�����܂��B ���{�ƃA�����J�ł́A����̎��Ö@���傫���قȂ��Ă��܂��B �@��悪��p�ŐE�l�C���ԓ��{�l�́A�O�Ȏ�p����ɑI�ԌX���ɂ���܂��B���ہA�̑����͂��߁A��p�̓�����ʂ̂���̎�p�@�ɂ͓��{�l�̈�҂��l�Ă������̂���������܂��B�g�b�v�N���X�̓��{�l�O�Ȉ�̋Z�p�͐��E��Ƃ����Ă����ł��傤�B�O�Ȏ�p�͓��{�̂��ƌ|�ŁA���ÂƂ����܂���p�Ƃ����̂́A���̂悤�ȓ`���ɍ����������̂Ȃ̂ł��B �A�����J��6�������ː����� �@�e���r�h���}�ł��A�����J�͖������f�f�オ��l���ɂȂ���̂�����܂����A���{�Ől�C���o��͉̂Ԍ`�̊O�Ȉオ������́B�w�킽���A���s���Ȃ��̂Łx�Ƃ������E���D�܂��̂ł��B �@���҂̂ق��ł��w�������ł��m���ɖ��������Ăق����x�ƁA�Q�ԐߓI�Ȋ����ň�҂Ɏ�p�����肢���邱�Ƃ������B�����Ȃ�ƁA���Ƃ��n�[�h���������Ă��ł��邾�����ׂĈ����Ƃ��������Ă��܂����Ƃ����b�ɂȂ肪���ł��B �@����A�A�����J�ł͕��ː����Â�������ɍs���Ă���B�A�����J�̂��҂�6�������ː����Â�I������ƌ�����قǂ��B �@�A�����J�ɂ͓��{�̂悤�ȊO�Ȏ����`�͂���܂���A�ǂ̎��Ö@�����œK���A�R�X�g�ƃ��X�N�Ɍ���������Ís�ׂȂ̂��Ƃ����_���Âɔ��f���܂��B�����������y�̂Ȃ��ŁA���ʂ��������ː����Â����B���Ă����B �@�������C���[�E�N���j�b�N�œ����Ă����Ƃ��ɂ́A���ː��Ȃ����ň�t��90�l�����܂����B�����ă��W�f���g(���C��)���������炢�̐����܂����B���{���������̕a�@�ŁA���ꂾ���̐��̕��ː��Ȉ������Ă���Ƃ���͂���܂���B �@���{�ł͓����悤�Ȏ��Ì��ʂ��\�z����Ă���ꍇ�ł��A���ː����Â��O�Ȏ�p�������銳�҂������B�������Ⴆ�A�O���B����Ȃǂ̏ꍇ�A��p�������2�l��1�l�͔A�R��Ȃǂ̖�肪�����āA�ꍇ�ɂ���Ă͂��ނ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B����A���ː����Âł��Ƃ����������ǂ͎c��ɂ����B �@���{�̕��ː���Â��x��Ă��邩�Ƃ����A��T�ɂ����Ƃ������܂���B�ނ���A���{�̂ق����i��ł��镪�������܂��B�Ⴆ�Ηz�q����d���q���Ƃ������A�Ő�[�̕��ː����ẤA���{�̋Z�p�A�{�݂����E�ň�ԏ[�����Ă��܂��B �@�ł͂��������������Ȃ̂��Ƃ����ƁA�܂����ː��Ȉ�̐������ɏ��Ȃ��B������x�̑傫���̎s���a�@�ŕ��ː����Â�����Ă���Ƃ���ł��A���ː��Ȉオ�풓���Ă��Ȃ��Ƃ��낪��������܂��B�����Ȃ�Ƒ�����̈�t���A���ː����Âɑ��闝����m�����[�܂�܂���B �@������A���ː��Ȉ�̎d���̓��e���悭�m��Ȃ��l�́w������͉��M�Ŏ��Â̐v�}���Ȃɂ��������Ă��邾���ŁA�܂Ƃ��ɓ����Ă��Ȃ���Ȃ����x�Ȃ�Č����킯�ł��B���������Ό����܂��ꕔ�̓��{�̕a�@�ɂ͍������c���Ă���̂ł��ˁB���̂悤�Ȏ����A�����Z�p��{�݂������Ă����{�͕��ː����Â��Ȃ��Ȃ��A�����J�قǂɂ͍L����Ȃ��̂ł��B �@�A�����J�ł͊O�Ȏ�p��A���Ĕ��������҂������Ƃ�����A�w���ː�������Ă���h�N�^�[�ƁA�R����܂�����Ă���h�N�^�[�����邩��A���ꂼ��̈ӌ����Ă݂܂��傤�x�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������A���{�ł͊O�Ȉオ���҂�����������ł��܂��X���ɂ���A���ː��ȂɂȂ��Ȃ����Ƃ��Ȃ�����������B �@�J��Ԃ��܂����A���ĂɋZ�p�̍��͂���܂���B��������Ñ̐��A�V�X�e�����Ⴄ�̂ł��B��قǁA�펞���ɂ�������Ă̗���o���܂������A����͂��Âɂ����Ă͂܂�܂��B���{�͐펞�ł��X�̖������x���グ�邱�Ƃɗ͂��X���܂����B����͍��x�ȊO�Ȏ�p��ڎw���ČX�̈�t���������������Â̌���Ǝ��Ă���B �@����ŃA�����J�́A�w���[�_�[���g���A�ʓ|������e�����Ă��܂��x�Ƃ����ӂ��Ɏl������������������Ƃ����V�X�e���d���̍l�����B���ʁA��t�̐����Ⴄ�̂ł��B �@���x�̍��A�����̈Ⴂ�Ȃǂ�����̂ŁA���Ă̈�Â�P���ɔ�r���āA�D������邱�Ƃ͂ƂĂ�����B�������A�A�����J�̈�Â����邱�ƂŁA���{�̈�Â̖��_�������Ă���̂ł��B �T������ 2016�N9��10�� |
|
���ː��Ȉ�́u0.5�b�v�œ����������������Ɣ��� ���炩�ُ̈�����o���Ă��� |
| �@�P����ς��ː��Ȉ�́A�}�����O�����i���[X���摜�j�ُ̈��0.5�b�Ō���������Ƃ����V���Ȍ��������ꂽ�B�č��Ɖp���̌����O���[�v�ɂ��������ʂŁA�o���L�x�ȕ��ː��Ȉ��X���摜�ŋ^�킵��������f��������ł���Ƃ̐��𗠂Â��錋�ʂƂȂ����B �@���ۂɂ́A���ː��Ȉオ�}�����O�����̕]���ɂ킸��0.5�b������₳�Ȃ��Ƃ������Ƃ͌����ĂȂ����A����̌��ʂ���A������ɂ͕��ː��Ȉオ�����ɂ킩�錟�o�\�Ȓ����݂��邱�Ƃ����������Ƃ����B �@������Ȓ��҂�Jeremy Wolfe���́A�u���ː��Ȉ�́A�}�����O�������ŏ��Ɍ������_�Łw�����x�����B�����́A���̒������摜���Ɏ��݂��鉽���Ɋ�Â��Ă��邱�Ƃ�˂��~�߂��B���オ�ُ�������}�����O���������Ĉ�u�ʼn����ɋC�Â��Ƃ��������́A�ɂ߂Ĉ�ۓI�ł���v�Əq�ׂĂ���B���ꂾ���łȂ��A���ː��Ȉ�͕a�ς̑��݂��Ȃ��Α��̓��[�����Ă��A���炩�ُ̈�����o���邱�Ƃ��\�ł���ƁAWolfe���͕t�������Ă���B �@�����͕ăn�[�o�[�h��w��w��w�@�i�{�X�g���j��Ȋw�E���ː��Ȋw�����ŁA�ău���K���E�A���h�E�E�C�����Y�a�@�̎��o�I���ӌ������𗦂��Ă���B���̌����́A�uProceedings of the National Academy of Sciences�iPNAS�j�v��8��29���I�����C���f�ڂ��ꂽ�B �@Wolfe���́A�u����̌��ʂ���A����Ƃ������[�ɂ��ُ�Ɍ����鉽��������A��������o�ł���\��������Ǝ������ꂽ�B�����̌��ʂ��l�����킹��ƁA���ː��Ȉ�́A���̎��_�ł͂킩��Ȃ������̑S�̓I�Ȉُ�̒���ɋC�Â��Ă���ƍl������v�Ɛ������Ă���B �@���̒�����`���邱�Ƃ��ł���A����ɗD�ꂽ�摜�c�[���̊J�����w�I�P���̌���ɂȂ���\��������ƁA�����͘b���Ă���B m3.com 2016�N9��12�� |
|
�����҂͔얞�ɂȂ�₷�� �Ƃ��ɑ咰����A������ō������X�N |
| �@�č��ł́A�����҂́A��ʏW�c�ɔ�ׂĔ얞�ɂȂ�₷�����Ƃ��A�V���������Ŏ����ꂽ�B�Ƃ��ɑ咰����i������������j��������҂Ŕ얞�������������Ƃ����B �@���̌����́A1997�`2014�N�̕č����N������蒲���iNational Health Interview Surveys�j�ɎQ�������č����l�i18�`85�j53��8,000�l���̃f�[�^����͂������́B�Ώێ҂̂���3��2,000�l���������҂ł������B �@��͂̌��ʁA�얞�҂̊����̐��ڂ́A��������̂Ȃ��l�ł�1997�N��21������2014�N�ɂ�29���������̂ɑ��A�����҂ł�22������32���ɑ������Ă����B �@�얞�̔N�ԗL�a���́A��������̂Ȃ��l�ɔ�ׂĂ����҂ō����A�Ƃ��ɑ咰�����҂Ɠ������҂ő傫���������Ă����B�Ȃ��ł����l�̑咰����A������A�O���B�����҂ő����������������B �@�얞�̗L�a�����傫�����������咰����A������A�O���B�����҂��ꂼ��̓�����j���ʂɂ݂�ƁA�����̑咰�����҂ł́A��N�A���l�A�ߋ�2�`9�N�ȓ��ɂ���Ɛf�f���ꂽ�l�A�j���ł͍���A���l�A����Ɛf�f����Ă���10�N�ȏ�o�߂����l�����������B�������҂ł́A��N�A���l�A�ߋ�1�N�ȓ��ɂ���Ɛf�f���ꂽ�l�A�O���B�����҂ł́A��N�A���l�A�ߋ�2�`9�N�ɂ���Ɛf�f���ꂽ�l�Ƃ������������݂�ꂽ�B �@�����ӔC�҂߂�ăR�����r�A��w�i�j���[���[�N�s�j���C���}�����O�q���w����Heather Greenlee���́A���̒m���̈ꕔ�́A�ߔN�A�얞�Ɋ֘A����ƍl�����Ă���������咰����̊��Ґ����������Ă��邱�ƂŐ����ł��邪�A���̑��̂���ɂ��Ă͂���Ȃ錤�����K�v�Ƃ̍l�����q�ׂĂ���B �@�܂������́A�u�얞�ɂ���āA�����҂̌��N�ʂł̕��S�������邱�Ƃ͖��炩�ł���A�̏d�Ǘ��Ȃǂ̖ڕW���߂������̎��{�����߂���v�ƕt�������Ă���B �@���̒m���́A�uJournal of Clinical Oncology�v�I�����C���ł�7��25���f�ڂ��ꂽ�B m3.com 2016�N9��21�� |
|
�i�s�����҂̉��Ƒ��A2-3���ɋ����}���y�č��Տ���ᇊw��z ��쎞�ԉ����ŃZ���t�P�A���Ԃ��Z�k |
| �@���S���̍��������҂̉Ƒ����҂̂���4����1����3����1�������}����s���̏Ǐ���o�����Ă��鑼�A1��8���Ԉȏ�����ɔ�₷�Ƒ��͉�쎞�Ԃ̑����ƂƂ��ɐ�����^���Ȃǂ̎����̌��N�ێ��̎��Ԃ��������A���_�I���N�̈����ɂȂ����Ă���\�����������ꂽ�B�č��Տ���ᇊw��iASCO�j��9��6���̃����[�X�ŁA2016�N��ᇊɘa�P�A��c�iPalliative Care in Oncology Symposium�A�T���t�����V�X�R�j�̔��\�\�艉����Љ���B �@�����O���[�v�́A�X���A�x���A�]��ᇁA�������A�����A���t��ᇂ��邢�͑�4���̊��Ɛf�f���ꂽ���f�B�P�A�҂���삷��Ƒ�294�l�Ɏ���[�ɂ�鉡�f���������{�B �@�����̌��ʁA���҂̌��N��Ԃ���������̂ɔ������҂̎��g�̌��N�ێ��̔\�͂��ቺ���Ă����B�܂��A�҂�4����1�߂��������}���Ǐ�A3����1�ȏオ���E����A�܂��͋����s���Ǐ����Ă���A���g�̌��N�ێ��̂��߂̍s���X�R�A�̒ቺ�ƗL�ӂɊ֘A���Ă����B�܂��A���X�R�A�̒ቺ�͉��̊��Ԃ⎞�Ԃ̒����A�T������̓����̑����A���҂̌��N��Ԃɂ��֘A���Ă����B �@�����O���[�v�́A����̌������@�ɉ��҂��x�����邽�߂̕]���c�[����T�[�r�X�̊J�����i�ނ��Ƃ����҂������Əq�ׂĂ���B m3.com 2016�N9��21�� |
| ��t�����������炢���ɕ��@�����������哮���𗣂͌��� |
| �@�u����v�u�]�����v�u�S�����v�Ȃǂɂ�鎀�̒��ɂ́A�ꂵ�݂�ɂ݂����̂�����A��r�I�u�|�b�N���v�Ǝ��˂���̂����݂���B����ŁA�l�X�ȁu���ɕ��v�̒��ŁA�ǂꂪ��Ԑh���������ɂ߂�͓̂���B �@����A�{���͓��Ȃ�O�ȁA�Ŏ�����ȂNJe�Ȃ̈�t����ށB���ソ���������������������ɕ��͎�Ɂu�ɂ݂����������́v�A�u�����ꂵ�ނ��́v�A�u���_�I���S���傫�����́v��3�̃O���[�v�ɕ�����ꂽ�B �u�ɂ݂����������́v�Ƃ��ċ}���㒰�Ԗ������ǏǂȂǂ̕a�����o�����A����܂�3000�l�ȏ�̎��ɐڂ��Ă������̏o���u�a�@�̃z�X�s�X��E���쎛���v��t�͂����������������B �u����������A���������q�{����̖����Ő_�o�Z���������ꍇ�A���ɂ������q�l�Ȃǂ��g���Ă��ɂ݂��\���ɘa�ł��Ȃ��ꍇ������B���ł�����������̒ɂ݂��ł��������A���҂�������ԂɂȂ�قǑ�ʂ̒��ɍ܂𓊗^���˂Ȃ炸�A���҂���ɂƂ��ĕs�^�ŋC�̓łƂ����ق��Ȃ��v �u�哮���𗣂��������ɂ݂��܂��v�Ƙb���̂͒r�J��@�@���̒r�J�q�Y��t�i�z��j���B �u�O�w�\���̌��ǂ̕ǂ��`�[�Y�̂悤�ɗĂ����B�哮�����S���̕��܂ŗ�Ɣw���ɂ��Ȃ�̈������⌃�ɂ�����B���܂�̒ɂ��ɋC�������̂Łw���ʏu�ԁx�܂ŋꂵ�ނ��Ƃ͂���܂��A���͐�ɔ��������ł��ˁv NEWS�|�X�g�Z�u�� 2016�N9��21�� |
| Microsoft���l�H�m�\���g�������Âւ̎��g�݂��J�n |
| �@Microsoft�Ɍ��킹��ƁA����̓R���s���^�[�E�C���X�݂����Ȃ��̂ŁA�u�R�[�h�v��ǂ݉������Ƃʼn����ł���̂��������B���̃R���s���[�^�[�E�\�t�g�E�F�A��Ƃ́A�l�H�m�\���g�����V���ȃw���X�P�A�̎��g�݂��J�n����B���̖ړI�́A����זE���^�[�Q�b�g�ɂ��������������@���������邱�Ƃ��B �@�V���ȃw���X�P�A�̎��g�݂ɂ�����v���W�F�N�g��1�ł́A�@�B�w�K�Ǝ��R���ꏈ�������p���A���ݗ��p�\�Ȍ����f�[�^���������āA���ꂼ��̂��҂ɍ��킹�����Ãv�����̍�����s���B �@IBM��Watson Oncology�Ƃ������ŁA�������e�̃v���O���������{���Ă���B������A���҂̌��N�Ɋւ�����ƌ����f�[�^���Ƃ炵���킹�ĕ��͂�����̂��B �@Microsoft�̃w���X�P�A�̎��g�݂ɂ�����ʂ̃v���W�F�N�g�ł́A���ː����ɃR���s���[�^�[�r�W���������p���A���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɕω������ᇂ̗l�q�𑨂���B����1�̃v���W�F�N�g��Microsoft���u���[���V���b�g�v�ȖڕW���f����v���W�F�N�g�ƌĂԂ��̂ŁA����͎��������R�[�h�������ăR���s���[�^�[���v���O���~���O����悤�ɁA�������R�[�h�Ńv���O���~���O���悤�Ƃ�����̂��B�l�̖Ɖu�V�X�e�����Ή��ł��Ă��Ȃ������Ɋւ��āA�l�̍זE�����̖����C���ł���悤�ɍăv���O�������{�����@�����̌����Ō�����̂��ړI���B �@Microsoft�́A�N���E�h�E�R���s���[�e�B���O�����p���Ă��̎�̃v���W�F�N�g�ɒ��킷�邱�Ƃ́u���R�Ȑ���s���v�Ɛ������A�J�X�^�}�[�ɂ������������c�[���������@��͍����Ă����Ɛ�������B �@�u���������̃R���s���[�^�[���V���R���łł��Ă���̂ł͂Ȃ��A�����Ă��镨���ɂȂ�Ƃ����Ȃ�A�����������R���s���[�^�[���v���O����������@���������͗������Ă��Ȃ���Ȃ�܂���v��Microsoft�̖����ł���Jeanette M. Wing�͌����B �@�m���ɁA���ꂾ���̌����f�[�^������AMicrosoft�⑼�ł����Â��n�߁A���N�Ǘ��ɋ@�B�w�K�����p�����Ƃ��A���f�����l�𐊎コ����a�̎��Ö@�����o�����ƂɊ��҂ł��邩������Ȃ��B TechCrunch 2016�N9��21�� |
|
�։�30�N�����`�q�Ɂu���Ձv�y�č��S���w��z �t���~���K���S�������܂ރQ�m���R�z�[�g�̃��^��� |
| �@�i������`�q�̊������𐧌䂷��ߒ���1�ł���DNA���`�����ƌĂ��u���Ձv���c�����Ƃ��Q�m���R�z�[�g�̃��^��͂Ŗ��炩�ɂȂ����B �@���m�̃q�g��`�q��3����1�ɓ�����7000����̈�`�q�ŋi���ɂ�郁�`�������ʂ̉e�����m�F����A�ꕔ�͋։�30�N����c�����Ă����Ƃ̌��ʂ�������Ă���B�č��S���w��iAHA�j��9��20���ACirculation: Cardiovascular Genetics���̌f�ژ_�����Љ���B �@�����O���[�v�͐S���Ɖ���Ɋւ���Q�m���R�z�[�g�iCHARGE�R���\�[�V�A���j��16�O���[�v�ɎQ��������1��6000��̌��t���̂�p����DNA���`�������ʂ̃��^��͂����{�B���R�z�[�g�ɂ�1971�N����J�n���ꂽ�t���~���K���S���������܂܂��B���݂̋i���ҁA�O�i���ҁA�ߋ��̋i�����Ȃ��̐l���r�������ʁA�i1�j�i���Ɋ֘A����DNA���`�������ʂ�7000��ȏ�̈�`�q�Ŋm�F���ꂽ�B���̐��͊��m�̃q�g��`�q��3����1�ɑ�������i2�j�։������Q�ł́A�։�����5�N�قǂ�DNA���`�����̑啔���͋i�����Ȃ��Ɠ������x���ɉ��Ă����i3�j�������ADNA���`�������ʂ̈ꕔ�͋։�30�N����������Ă����A�i4�j�ł����v�w�I�ɗL�ӂȃ��`����������ꂽ���ʂ́A�S���ǎ�����ꕔ�̊��̂悤�ɋi���������ƂȂ鑽���̎����ő������������`�q�Ɗ֘A���Ă����\�Ȃǂ̒m��������ꂽ�B �@�����O���[�v�́A����̎�v�ȉ�͂͒����̉e�������邽�߂Ƀf�U�C�����ꂽ���̂ł͂Ȃ����A�i����DNA���`�����ɗ^����e�������������Ƃ��Ă͂���܂łɂȂ��K�͂Ɛ����B����̌������ʂ͋i�����q�g�̑̂ɕ��q���x���Œ����I�ȉe����^���邱�Ƃ������������A�։��ɂ��DNA���`�����̑啔�����i�����Ȃ��̐l�Ɠ������x���ɉł���Ƃ������Ƃ���݂ɂȂ�j���[�X�Ƃ��q�ׂĂ���B m3.com 2016�N10��5�� |
|
�V�������ː��Ö@�ō���x���҂̐����������P ASTRO���\��2�� |
| �@�Ő�[�̕��ː��Ö@�ɂ��A��p�����Ȃ�����̑����x���҂̐��������L�ӂɉ��P����悤�ł��邱�Ƃ��A�V����2���̌����Ŏ����ꂽ�B���̎��Ö@�͑̊�����ʕ��ː����ÁiSBRT�j�ƌĂ�A10�N�قǑO���痘�p����Ă���B �@���̌����ł́A�ăq���[�X�g���E���\�W�X�g�a�@��Andrew Farach���炪�S�Ă���f�[�^��p���āA2004�`2012�N�ɃX�e�[�WI�x����Ɛf�f���ꂽ60�Έȏ�̊��҂̋L�^�����r���[�����B���Ԓ��ɕ��ː��Ö@�������҂�2�N�������́A2004�N��39������2012�N�ɂ�58���ɏ㏸�������A�O�Ȏ�p�݂̂̊��҂ɂ͌��I�ȉ��P�݂͂��Ȃ������B�e���҂������ː��Ö@�̎�ނ͕s�������A�����������SBRT�̗��p�����ɂ͑��ւ��݂����Farach���͌����B �@�č��ޖ��R�l�ǁiVA�j�̃f�[�^�Ɋ�Â����̌����ł́A�X�e�[�WI�x���Җ�1,700�l�i���ϔN��72�j�ɒ��ځB�ꕔ�̊��҂͕W���̕��ː��Ö@���A��500�l��SBRT�����B���ː��Ö@�������҂�4�N�������́A2001�N��13������2011�N�ɂ�28.5���ƁA2�{�ȏ�ɑ��������B�����Ԃ�SBRT�̗��p��5������60���ɑ��債�Ă����B����ɁASBRT�������҂̎��S���X�N���]���̕��ː��Ö@�ɔ�ׂĖ�30���Ⴂ���Ƃ��킩�����B �@���̌��ʂ���A�N��⌒�N��Ԃ̂��ߎ�p���K���Ȃ��������҂ɂ́A���ː��Ö@���������ׂ��ł��邱�Ƃ����������ꂽ�ƁAFarach���͏q�ׂĂ���B����A�č�����iACS�j��Len Lichtenfeld���́ASBRT�ȊO�ɂ��������̉��P������ł���v��������Ǝw�E����B���Ƃ��A�������҂Ɠ]�ڂ̂��銳�҂��ȑO�������m�ɕ��ނł���悤�ɂȂ������Ƃɂ��A�K�Ȋ��҂ɕ��ː��Ö@��p���邱�Ƃ��\�ɂȂ����Ƃ��l������ƁA�����͐������Ă���B �@SBRT�ł́A��蒼�ړI�Ɏ�ᇂ�_���A���܂��܂Ȋp�x���獂���ʂ̕��ː����W���I�ɏƎ˂���B1�`2�T�Ԃ̊Ԃɂ킸��3�`5��̎��Â��邾���ōς݁A�]���̕��ː��Ö@��������p�����Ȃ��A��ᇎ��ӂ̑g�D���鑹�������Ȃ��Ƃ����B�������A����̐i�s�������҂�O�Ȏ�p���\�Ȋ��҂̏ꍇ�́A���ː��Ö@����p�≻�w�Ö@�̑���ɂȂ�ƍl����ׂ��ł͂Ȃ���Lichtenfeld���͘b���Ă���B�܂��A�������҂ɑ��ĕ��ː��Ö@���O�Ȏ�p�Ɠ������炢�L���ł��邩�𖾂炩�ɂ���ɂ́A�Տ��������K�v�ł���Ƃ̂��ƁB �@���̌����̌��ʂ́A�ă{�X�g���ŊJ�Â��ꂽ�č����ː���ᇊw��iASTRO�j�N���W��ŕ��ꂽ�B���̒m���͍��ǂ��Ĉ�w���Ɍf�ڂ����܂ł͗\���I�Ȃ��̂Ƃ݂Ȃ��K�v������B m3.com 2016�N10��7�� |
|
����������Z���^�[�a�@���̖{���u�m���Ƀ_���ȊO�Ȉオ�������܂��v ���{�̈�Â͂ǂ����c��ł���̂��H |
| �@�N��10����p���Ȃ���҂��u����̐���v�ɔF�肳���B����Ȉ�҂̋Z�p���M�p�ł���͂����Ȃ��B �@��Ђ��̈�Âɂ�������p�̎��́B���{�̕a�@�͂ǂ��Ɂu�c�݁v������̂��H�@�����p�̑�ƁE�y������ƈ�Ìo�ς̐��ƁE���R�K�O�����z���l�Ō�荇�����B ��҂��`�F�b�N����d�g�݂��Ȃ� ���R�@��Ô�̖c�����~�܂�Ƃ����m��܂���B9��13���Ɍ����J���Ȃ����\����'15�N�x�̓��{�̈�Ô��41�E5���~�B�O�N�x��3�E8%���ŁA13�N�A���ߋ��ō����L�^���Ă��܂��B �y���@������ËZ�p�̍��x���ň�Ô�����Ȃ��Ă����̂́A������x�A�d�����Ȃ����Ƃł��B�������A�Ȃ��ɂ́u�T������v������Ԃ��w�E���Ă���悤�ɁA���ʂȈ�Â����邱�Ƃ��m���ł��傤�B �@�������A��ÂƂ������͖̂{���L�v�Ȃ��̂ł��B�������A����̓��{�ł͂��ꂪ�K���������܂��@�\���Ă��Ȃ����ʂ�����A���ʂ������B ���R�@�����L�v�ʼn������ʂȈ�Âł��邩�f����̂́A���ɓ�����ł��B �y���@�Ƃ�킯���{�ł͂����ł��B�u���̎�p���͉Ȋw�I�Ɍ��ʂ�����ƔF�߂���ׂ����ǂ����v�Ƃ�����Â̐��������B��������ł��B �@�{�����̂悤�Ȑ������́A���m��������҂������Ȋw�I���n����s���ׂ��ł����A���{�ł͒��㋦(�����Љ�ی���Ë��c��A���N�ی����x��f�Õ�V����Ȃǂ̐R�c���s�����J�Ȃ̎���@��)���i��É�c�ȂǂŁA�������ʖ��Ԑl�A�o�ϊw�҂��������čs���̂ł��B�Ȋw�I�Ȑ��������u�f�l�ڐ��v�ōs���Ă���̂ł��B ���R�@��Â̌���ł����{�ł́u�]���v���s���Ă��܂���B���҂������Â��ǂ����̂��������ǂ����f����̂́A���{�̏ꍇ�͎厡���l�ɔC����Ă��܂������ł��B�q�ϓI�Ȏ��_�������Ă���B �y���@���������߂Ă��邪����L���a�@�ł́A�u�`�[����Áv��ϋɓI�ɐi�߂Ă��܂����A�A�����J�ɔ�ׂ�Ƃ܂��\���ł͂���܂���B�����������{�S�̂ł́A���̂悤�ȃ`�[����Â��s���Ă���Ƃ���͂قƂ�ǂȂ��B �@�����̈�҂ƂƂ��ɊŌ�t���t�A�Z�t���ꏏ�ɔ��f���A���Â��s���̂��`�[����Â̖{���ł��B�������A���{�͈�҂ɔ�ׂđ��̐E��̌������キ�A�`�F�b�N�@�\�������Ȃ��̂ł��B �@�Ƃ�킯��w�a�@�͂����ł��B���o����p�̎��s�ŁA�����̎��҂��o���Q�n��w��w�������̓T�^�ł��傤�B ���R�@��w�a�@�̃V�X�e���͖{���ɂЂǂ��ł���B�����E���ꂩ�������Ƃ�����܂��B �@30�N�قǑO�A�����߂Ă�����Ђ̐f�Ï��̏����Ɍ����āA���Ԃ��ԑ�w�a�@�ň݃J�����̌������܂����B�u�ُ�Ȃ��v�ƌ����āA�ƂɋA�������̖�A�S�g�z�����N��������ł��B�X�t���t�����A�}���X���ɂȂ��Ă��܂��āB �@���t�ɕ\���Ȃ��قǂ̌��ɂł����B�Ⴂ��҂ł������A���̓������݃J�����̗��K��ɂ��Ă�����ł���B �y���@�����炭�X�ǂ̂Ƃ�����������Ă��܂�����ł��ˁB ���R�@���ǁA�~�}�Ԃʼn^���3���Ԃ�������Ԃł����B���Ƃʼn�Ђ̐f�Ï����ɕ������������A�u��w�a�@�͊�Ȃ��Ƃ��낾����A�S����ɂ����ƈ݃J�����̌o�����L�x�Ȃ̂��m���߂Ȃ��������O�������v�Ƌt�ɓ{���܂����B �Z�p�̂Ȃ����� �y���@��w�a�@�Ƃ����g�D�������Ă�����͎R�̂悤�ɂ���܂����A������傫�Ȗ��̓K�o�i���X(�g�D�̓���)�̖��ł��B �@���Ƃ��ΐ�قǂ��o���Q�n��̃P�[�X�B���o����p����肽�����҂������ꍇ�A�������点�Ă����S���ǂ������f����̂��K�o�i���X�ł��B �@���͌Q�n��̃P�[�X�ł��A��p�����s������҂����ɐӔC����点��̂͊Ԉ���Ă����Ǝv���܂��B�{���A��p���s�킹�Ă����w���́u����͈����Ȃ��v�ƁA��҂����ׂ�����ɂ���͂��ł��B���ɂȂ�����҂͎g�����ɔR���Ď�p�������̂�������Ȃ��B���o���Ƃ����Z�p�̃����b�g��M���Ă������̂ł��傤�B�����A�r�����������B �@���̂悤�Ȉ�҂ɖ�����ŕ��o����p���������͕̂a�@�̃K�o�i���X��������������������ł��B ���R�@�A�����J�̏ꍇ�́A�a�@�̃��X�N�Ǘ����O�ꂵ�Ă���BNASA�̐��Ƃ��Ă�ł��āA�F���H�w�̃��x���Ń��X�N�Ǘ����s���Ă���Ƃ�������邭�炢�ł��B �@���̂��N������ӔC�͈�`�I�ɂ͈�Ë@�ւ�����āA��҂����B���̑���A��Ã`�[���S���Őf�Ó��e���`�F�b�N���Ė��ʂŊ댯�Ȏ��Â͐�s�킹�Ȃ��悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă���̂ł��B �y���@�������A�Z�p�͂̍�����҂���Ă邱�Ƃ���ł��B�������A���܂̓��{�̐��x�ł͂Ȃ��Ȃ����ꂪ����B�Ȃ��Ȃ�A������Ƃ������㐧�x���m�����Ă��Ȃ�����ł��B �@���̐��ł���x������ɂƂ�܂��傤�B �@�x����̎�p�͔N�ɖ�3�����s���Ă��܂��B�O�Ȉオ�Z�p������E�ێ����邽�߂ɂ́A�ł��邾�����������p���o�����邱�Ƃ��̗v�ł��B���z�I�ɂ͖���1�x�͎�p�������ق��������B�����l����ƔN��300�Ⴍ�炢�́A1�l�̈�҂��������邱�ƂɂȂ�B �@����ƁA3�����̎�p���s���̂ɕK�v�Ȉ�҂̐���100�l���x�ł��B�t�ɂ����A�x����̐���͂���ȏ�K�v�Ȃ��B�O�Ȉオ�����Ŏ�p���s���N����20�N�Ƃ��āA���N5�l��������琬���Ă�������ōςނ킯�ł��B ���R�@���ۂɂ́A�x����̐���͉��l���炢����̂ł��傤? �y���@���ꂪ1000�l������̂ł��B15�N�O�ɂ�1500�l�����܂����B�����5�N�ȓ���50�̏Ǘ�����Ȃ��A����ɔF�肳���Ƃ������x�ɂȂ��Ă��邩��ł��B5�N��50��Ƃ����A�N��10��A����1����Ȃ��̂ł���B �@���̂悤�Ȑ��x�ł͋Z�p�̎���ۏł���킯������܂��A����Ȉ�҂��u����v�Ƃ͌Ăׂ܂���B �@��H�����Ė����B��ł��Ă��邩��A���m�ɑłĂ�悤�ɂȂ��ł��B���Ɉ�x�������Ƃ������Ȃ���H��M�p�ł��܂����H�@�܂��Ă�O�Ȉ�͐l�l�̐g�̂��d���ł���B ���R�@���㐧�x���܂߂āA���낢��ȉ��v���K�v�ł��ˁB �@�Ƃ�킯��w�a�@�̑g�D���v�͏d�v�ł��B�܂��a�@���w���番������ׂ��ł��傤�B�o�c���o�̂Ȃ���w���̋����������o�����ʁA��Ãj�[�Y�ƃ~�X�}�b�`�̉ߏ蓊���𑱂��Ă���B�a�@�����邱�Ƃł܂Ƃ��Ȍo�c�̂ɕϊv���A��w���͊�b������Ⴂ��҂̂��߂̋���ɐ�O����d�g�݂ɂ��ׂ��ł��B �y���@���������ӌ��ł��B��b����������Ă��āA�������ɂ������Ă��鋳���������a�@����I�ԂƂ����̂͂��������B �@��b�����͊w���ł��������A�Տ������͕a�@�łȂ���ł��܂���̂ŁA��w�a�@�ł���B�������A�Տ���������������s���悤�ȕa�@�͑S����10����������Ώ\���ł��B ���R�@��ËZ�p���W�ς��邱�Ƃ��A���ꂩ��̓��{�̈�Âɂ͕K�v�ɂȂ��Ă��܂��ˁB���x�Ȏ�p�͈ꕔ�̕a�@�ōs���ׂ��ł��B �@���̂��߂ɂ́A���{�̈�Î��Ƒ̂̋K�͂͂܂��܂����������܂��B���E�I�Ɍ���ΔN��1000���~���x���̔���グ�������āA���߂Đ��E�W���̈�Î��Ƒ̂Ƃ����܂��B �y���@���{�Ńg�b�v���x���̂���a�@�ł��邪�ł��甄��グ��350���~���炢�ł�����ˁB �@���҂���͕a�@�̔���グ�ƈ�Â̎��͊W�Ȃ����낤�ƍl���邩������܂��A����Ȃ��Ƃ͂���܂���B �@���Ƃ��ACT��MRI�Ƃ������@������̂ɂ��A���{����1��8���Ԃ��炢�����ғ����Ă��Ȃ��B�A�����J�ł͂�����ƌ�㐧���ł��Ă��ċ@�B��16���ԓ����Ă��邩��A���ʂ����Ȃ��B ��̗ʂ�����Ȃ����R ���R�@�A�����J�ł͍��x��Â̏W�������i��ł��܂��B�s�b�c�o�[�O�Œn���P�A���s����Î��Ƒ̂�1��4000���~�K�͂̔���グ������A���E��������Ƃ��W�܂��āA�c�_�����Ȃ���ŐV�̈�Â��s���Ă���B �@�܂��A��Â̎���R�X�g���r���Č��\���邱�Ƃ͉��ď����œ�����O�ɂȂ��Ă��܂��B���Ƃ��A�I�[�X�g�����A�̌����a�@�́A�B���{���C���^�[�l�b�g�Ő��ѕ\�����J���Ă��܂��B�\��O�̍ē��@�̔������A�x�b�h���痎���č��܂����P�[�X�̔������ȂǁA�l�X�Ȍ��J�������ĕa�@��I�Ԃ��Ƃ��ł���̂ł��B �y���@����͂������V�X�e���ł��ˁB �@���{�ł́A�f�Õ�V�̐��x�����߂���ׂ��ł��傤�B�u�T������v�����W���Ă���悤�ɖ�̈��݂������Љ���ɂȂ��Ă��܂����A����͈�҂����҂Ɂu�{���ɖK�v���ǂ����v���������@���Ă�����Ȃ�����ł��B30�������āu������ނ����H����^��������v�Ɛ����ĕ��������Ƃ��Ă��A�f�Õ�V��������킯�ł͂Ȃ��B ���R�@��̈��݂������N����̂́A���҂��ǂ̂悤�Ȉ�Â��Ă���̂��A�ꌳ�Ǘ��ł��Ă��Ȃ�����Ƃ����ʂ�����܂��B �@5�N�O�Ɏ�ނ����A�����J�̗�ł́A��t�ƕی���Ђ��`�[����g�݁A��Ô�̍팸�Ɏ��g��ł��܂����B�ی���Ђ����҂����̎�f���A������Ȃǂ̏�����t�ɒ��A���҂��a�@�ɗ���̂�҂̂ł͂Ȃ��A�t�Ɉ�t����f���ׂ����҂��w�����܂��B���̎��a�Ǘ��Ɨ\�h�̌��ʁA��Ô�ߖ�ł�����A��t�ɕ�V���x�����̂ł��B �@��Ô��}���������Â̎���������Ƃ͌���܂���B���쌧��������ł��B���쌧�͈�Ô�Ⴂ����Ō����̕��ώ����A����҂̌��N���������{��ɂȂ��Ă��܂��B �y���@���ʂȖ���Â��Ȃ����ɂ͊��Ҏ��g�̈ӎ����ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̖{���ɕK�v���ǂ����A�����̐g�̂ɖ₢�����Ă݂�B �@���͂��܍������̖�ƁA�ȑO�\��w����ᇂ�������̂Œ��̖������ł��܂��B�R���X�e���[������������Ƃ����Ė���o���ꂽ���Ƃ�����܂������A���̌��f�Ő��l���������Ă����̂ŁA���̖�͂�߂܂����B �@���M�p�������Ȃ��ŁA�{���ɕK�v�Ȗ�͂Ȃɂ������ōl���邱�Ƃ���Ȃ̂ł��B �y������@����E��傤����/'46�N���܂�B�_�ސ쌧���a�@�@�\�������A��������B���͋����O�Ȋw(�Ƃ��ɐi�s�x����̎�p)�B��Ë���A��Ð��x�ɑ��w���[�� ���R�K�O�@�܂�܁E�䂫�Ђ�/'53�N���܂�B�L���m���O���[�o���헪�����������劲�E�o�ϊw���m�B�Љ�ۏ�R�c�������ψ��B���͎Љ�ۏᐧ�x���v�̍��۔�r�A��ÎY�Ɛ��� �T������ 2016�N10��8�� |
|
���]�ڗ}���ɕ��ז����L�� �k��A�N�������f���}�E�X�ōR���܂̌��ʂ��� |
| �@�k�C����w��10��5���A���ז�̐����ł����X�e���C�h�n�R���ǖ�̃t���t�F�i���_�i���i���I�p�C�����j���A����̓]�ڂƍR����܂ɑ��邪��̒�R�͂�}���邱�Ƃ������Ɣ��\�����B���̌����́A����w��w�@��w�����Ȏ�ᇕa���w����̓c���L�Ƌ�����ƁA�t��A��O�Ȃ̎��M�Y������̋��������ɂ����́B�������ʂ́uScientific
Reports�v���Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@���{�ł͖��N��2���l���N������ɜ늳���Ă���A���̂���8,000�l�����S���Ă���Ƃ����Ă���B�N������͉��x���Ĕ����J��Ԃ��̂������ŁA�[����������N���̕ǂ̋ؑw�ɓ��B����[���Z������ɕ�������B����͗\�オ�ǍD�����A�Z������͔x�Ȃǂɓ]�ڂ��₷���\��s�ǂł���B�Z������̎��Âɂ͒ʏ�A�V�X�v���`���Ȃǂ̍R����܂��p�����邪�A��ܑϐ��̊l���Ɖ��u����ւ̓]�ڂ��\��s�ǂ̌����ƂȂ�Ƃ����B���̂��߁A��ܑϐ����������A�]�ڂ�}���邱�Ƃ��K�v�Ƃ���Ă����B �@�������ł́A�q�g�N������זEUM-UC-3���u���Ń��x�������ă}�E�X���N���ɈڐA���A�N�����f���}�E�X���쐬�����B�ڐA����45����ɁA�x�]�ځA�̑��]�ځA���]�ڂ��m�F���ꂽ���߁A�������Ƃ��Ă��N���A�]�ڐ�Ƃ��Ă̔x�A�́A�����炻�ꂼ�ꂪ��זE�����o���Č������Ɣ�ׁA�]�ڂ�������זE�ł̂ݍ����������������q�ɂ��āAmRNA�}�C�N���A���C�@��p���Ėԗ��I�Ɍ��������B���̌��ʁA�]�ڂ�������זE�ł̓A���h�P�g�Ҍ��y�f��3�{����25�{�ɑ������Ă��邱�Ƃ��B�]�ڑ��ł̃A���h�P�g�Ҍ��y�f�̑����́A���ۂ��N�����҂̎�p�Ǘ�25��̕a���g�D�ł��F�߂�ꂽ�Ƃ����B �@�R������Âł́A���ł�������זE�̎��͂ʼn��ǂ��N����A���ǐ������C���^�[���C�L��1����o�B����ɂ�肪��זE���ŃA���h�P�g�Ҍ��y�f�̗ʂ��������A��ō�p����������Ė�ܑϐ����l������B����ɓ������ŁA�A���h�P�g�Ҍ��y�f������זE�̓������i�邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�t���t�F�i���_�͂��̃A���h�P�g�Ҍ��y�f��j�Q���邽�߁A�t���t�F�i���_���N������זE�ɓ��^����Ƃ���זE�̓������~�܂�A�R����܂̌��ʂ����邱�Ƃ��킩�����Ƃ����B �@����������A���ז�Ȃǂ̈����Ȗ�̐����ł��v��ʍR�����p�����邱�Ƃ����炩�ƂȂ�A�����̂��Ì���ւ̒蒅�����҂����ƁA�����O���[�v�͏q�ׂĂ���B m3.com 2016�N10��11�� |
| �i���̃��X�N�́u�m���v ����A�]�E�S�����A���c���ˑR���nj�Q |
| ���䂫�� ��w���C�^�[ �@���̉āA�u���������i�����J���ȁj�v���������ꂽ�B�i���A�i���Ǝ����Ƃ̈��ʊW���u�m���v�`�u���W�̉\���v��4�i�K�ŕ]�������_�������B �@�{�l�̋i���Ǝ����Ƃ̈��ʊW���ؖ�����Ă���u����i�x�E�����E�H���Ȃǁj�v�́u�m���v�B����܂Łu�\������v�������u�]�����v�u�S�؍[�ǁv�u���A�a�v���A�u�m���v�Ɋ댯�x���オ�����B �@�i���̉e���Ɋւ��Ă��茵�����B�u�i���֘A�̔N�Ԏ��S�Ґ���1��5000�l�Ɛ��肳���v�Ƃ������������Z���^�[�̃f�[�^�������āA���{�̎i����́u���E�ł��Œ�v�ƒf���A������100���։����𐄐i���ׂ����ƒ��Ă���B �@���Ȃ݂ɁA�i���ɂ�鐄�v���S�Ґ��́A���N1���l�ȏオ�S���Ȃ���1960�N��̔N�Ԍ�ʎ��̎��S�Ґ��ɕC�G����B �@�����́A�O��̓����I�����s�b�N��3�N��ɍT����61�N����ǔ��V�����u�����푈��葽�����ҁv�Ƃ����h���I�ȃ^�C�g���ŁA��ʎ��̂̌�������ނ����A�ځu��ʐ푈�v���X�^�[�g�B���Ă̎��Ⴉ���̕K�v��_�����B �@���_�̐���オ���w�i�ɁA���H��ʖ@�̉��������܂苭�����s���A���S�ʂ̋Z�p�v�V�������Č�ʎ��̎��͌������Ă����B2015�N�̌�ʎ��̎��́A4117�l�B70�N�ɋL�^�����ő�1��6765�l��4����1�ȉ����B �@�i���֘A���ɂ��ẮA���v�l�ɋ^��̐����������A���ڎ��ł͂Ȃ��_���d�含�������ɂ������Ă���B�����A���S�Ґ��̑����͕���Ȃ��B20�N�Ɍ����A���炩�̖@�����͂��肻�����B �@�i���Ƃ̈��ʊW���m���Ƃ���鎾���́A�u�x����v�u�]�����v�u�S�؍[�ǁv�u���c���ˑR���nj�Q�iSIDS�j�v������B���e�Ƃ��i���҂ł�SIDS���ǃ��X�N�́A��i���v�w�̖�5�{�B��e�̎i��������2�`3�{�ɏ㏸����B �@�D�P�̕Ɠ����ɋ։��𔗂���l�͏��Ȃ��Ȃ����낤�B�����Ŋ��ق��ė~������������Ȃ����A�i���҂̐g�̂ɕt�������c�����������ōĂѕ��U�����u�T�[�h�n���h�X���[�L���O�v�̃��X�N������Ȃ��B�����Ǝq���̏����̂��߂ɁA�։������ق��������B DIAMOND online 2016�N10��12�� |
|
�I�v�W�[�{���Ĕ�NSCLC���҂ɑt���� BMS�A2����P3�ŐV���ʂ����\ |
| �@�č��̃u���X�g���E�}�C���[�Y �X�N�C�u�Ђ�10��9���ACheckMate-057���������CheckMate-017������2���̏d�v�ȑ�3���Տ������̍ŐV�̌��ʂ\�����B�������ɂ����āA���×���L����Ĕ����זE�x����iNSCLC�j���҂ŁA�u�I�v�W�[�{�v�i��ʖ��F�j�{���}�u�j�̓��^�������҂�3����1�ȏオ�t���p�����ł������̂ɑ��A�h�Z�^�L�Z���̓��^�������҂ł͑t���p�����̊��҂͂��Ȃ������Ƃ��Ă���B �@���݁A�C�O�ɂ����ẮA�u���X�g���E�}�C���[�Y �X�N�C�u�Ђ��A�P���A���זE�x����A�A�H��炪��A�̍זE����A�H������A�咰����A�݂���A���t����Ȃǂ̂�����ΏۂƂ��A�I�v�W�[�{�P�ܗÖ@�܂��͑��̎��Ö�Ƃ̕��p�Ö@�ɂ��Տ����������{���B �@���{�ł́A�����i�H�Ɗ�����Ђ�2014�N9���ɍ����؏��s�\�Ȉ������F��̎��Ö�Ƃ��Ĕ������Ă���B���̌�A2015�N12���ɐ؏��s�\�Ȑi�s�E�Ĕ��̔זE�x����A2016�N8���ɍ����؏��s�\�܂��͓]�ڐ��̐t�זE����ɑ��鏳�F���擾�B�܂��A�z�W�L�������p���ѓ�����ɂ��Ă����F�\�����Ă���A�݂���A�H������A���זE�x����A�̍זE����A�P���A��������A�A�H��炪��A�������������A�_������Ȃǂ�ΏۂƂ����Տ����������{���ł���B �@CheckMate-057�����ɂ����āA�t�����ԁiDOR�j�̒����l�̓I�v�W�[�{�Q��17.2�����i95���M����ԁF8.4-�]���s�\�j�A�h�Z�^�L�Z���Q��5.6�����i95���M����ԁF4.4-6.9�j�ł���ACheckMate-017�����ł́A�I�v�W�[�{�Q��25.2�����i95���M����ԁF9.8-30.4�j�A�h�Z�^�L�Z���Q�ł�8.4�����i95���M����ԁF8.4-�]���s�\�j�������BCheckMate-057�����ł́APD-L1�������x��1���ȏ�̊��҂ɂ�����DOR�����l��17.2�����i95���M����ԁF8.4-�]���s�\�j�APD-L1�������x��1�������̊��҂ɂ����Ă�18.3�����i95���M����ԁF5.5?�]���s�\�j�������B�������ɂ����āAPD-L1 ��������є����҂̗����ɂ����Ď����I�t�����F�߂��ACheckMate-057�����ł́A���S�t�����҂�4�l��1�l��PD-L1�������x��1�������̊��҂������B �@�������ɂ����铝�����S����͂ł́A�I�v�W�[�{�̐V���Ȉ��S���V�O�i���͔F�߂��Ȃ������B1�N��2�N�̒ǐՊ��Ԃ̊ԂɁA��蒷���Ԃ̓��^�ɂ�������炸�V���Ȏ��ÂɊ֘A���鎀�S��͔��������A1�N�̒lj��ǐՊ��Ԓ��ɂ�418�ᒆ11��ŐV���Ȏ��ۂ��F�߂�ꂽ�B m3.com 2016�N10��14�� |
|
����̓�喼�オ�������u��҂̑I�ѕ��E��̈��ݕ��E���z�̐������v �{���̃X�N�[�v�Βk |
| �Ԓr�M ���������E�܂��Ɓ@�N�S�����a�@�E�a�@�Ǘ��ҁB���E�_�ސ쌧������Z���^�[�����B���͑咰���� ���R���F �Ȃ���܁E�͂�Ђ��@��������Z���^�[�Ȃǂ��o�āA���ݐ_�ސ쌧������Z���^�[���@���B���͔x���� �@��ËZ�p�����X�i�����Ă���͎̂����B�����A���ꂪ�{���Ɋ��҂̂��߂ɂȂ��Ă���̂��낤���B����̖����l���u��p�A��A���z�̐������v�ɂ��Č��B ��ґI�т͖{���ɓ�� �Ԓr�@���͑咰�����ł����A���ÁE��p�̋Z�p�͒����ɐi�����Ă��܂����B �@���o���̎�p���L���s����悤�ɂȂ����B�������o���̎�p�����ɗD��Ă���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�J����p������Ă���Ƃ������Ƃł�����܂���B����͗Տ������̌��ʂ���������邱�Ƃł��B �@�����A���o���̎�p���L���F�m����A������̏Ǘᐔ�������Ă��Ă��邱�Ƃ͎����ŁA���̌X���͑����ł��傤�B ���R�@���̐��͔x����ł��B���̍l����悢��p�Ƃ́A��U��������Ƃ��ꂢ�Ɏ��F�ł��Ă�����S�m���Ȏ�p�ł��B���̂��߂ɁA�����g��������C��t���Ă��邱�Ƃ͂悢������m�ۂ��邽�߂ɋɗ͏o����}����w�͂����Ă��܂��B�t�ɂ����A���ꂪ�ł��Ă��Ȃ��Ɖ���Ȏ�p�ɂȂ�킯�ł��B �@�x����̎�p�ł́A��������ۂ��Ȃ���A�x�@�\�̉�����ڎw���Ƃ������ꂪ�ŋ߂̃g�����h�ł��B �Ԓr�@��������̎�p�ł��A�l�H�������Ȃ��ōςގ�p�������Ă��܂�����B �@��p�o���ɂ��邩�A�J����p�ɂ��邩�́A�厡��̔��f���傫���B�����ɂ͋Z�ʂ̍����W���Ă��܂��B���̐搶���ƕ��o���ł͂ł��Ȃ����A�ʂ̐搶���Ɖ\���Ƃ����A����̕��ʂ�����܂��B ���R�@���҂���̗��ꂩ��A��p�̏�肢�O�Ȉ��I�ԕ��@�͂ƂĂ�����ł��ˁB �Ԓr�@��������҂ɂ��Ă��Ƒ���g�����a�C�ɂȂ�����A�N�Ɏ�p�𗊂������Ɩ����킯�ł�����A���҂��猩��Ȃ�����ł��傤�B �@�����A�a�@���̂Ƃ͂������ď����J���i��ł���ʂ�����܂��B������a�@�̑I���Ƃ����Ӗ��ł́A���߉��N���̏Ǘᐔ���Q�l�ɂ���Ƃ����̂��A������Ó��ȕ��@�Ƃ�����ł��傤�B �@�������A�Ǘᐔ�������{�݂͋Z�p�̕��ϒl���������Ƃ͊ԈႢ����܂��A10�l�O�Ȉオ������10�l�Ƃ���p����肢�Ƃ͌���܂���B ���R�@�����܂��͏Ǘᐔ�̑����a�@��T���̂��������Ǝv���܂��B���́A���҂�������m�肽���̂͏Ǘᐔ�̑����a�@�̂ǂ̈�t���D�G���Ƃ������Ƃł���ˁB �Ԓr�@�������A���ꂪ�킩������B�����A�Ǘᐔ�������ق����A���ϓI�Ɍ��Ď�p�̐������������Ƃ����f�[�^������܂��B�A�����J�̐S���O�Ȏ�p�̒����̗��t��������̂ł��B ���R�@���̌��J�Ƃ����Ӗ��ł́A�ŋ߂͎�p�̗l�q���r�f�I�Ř^�悳���悤�ɂȂ�܂����ˁB �Ԓr�@���������Ǝ�p�̏�肢�A���肪��ڂł킩��܂��B �@���ہA�Ƃ��鎾���̃g�b�v�Ƃ����Ă����t�̎�p�̃r�f�I���w��ȂǂŌ��āA���R�Ƃ������Ƃ�����܂��B���̕���Ő擪�𑖂��Ă���l�̎�Z�Ȃ̂ł����A�ƂĂ���肢�Ƃ͌����Ȃ��B�����A�������I���݂ŏǗᐔ�����͏d�˂Ă��Ă���̂ŁA�w��ő傫�Ȋ�͂ł���킯�ł��B �@����A���Ŋw��ł̗���͂܂��܂������[�ł��A��肢�l�͌���킩��܂��B �u�_���v�҂��ɑ����t ���R�@��ʂ̕��̓r�f�I������@����Ȃ��ł����A���Ƀr�f�I�������Ƃ��Ă������������悭�킩��Ȃ��ł��傤�B�������A���̂悤�ȏ���J����邱�Ƃŏ��Ȃ��Ƃ���t�����̊ԂŁA�]�����������Ƃ͂ł���B �@���҂�����A��p�̘r���������ǂ����͂킩��Ȃ��Ă��A���f�ŃR�~���j�P�[�V���������Ă��邩�ǂ����́A�N�ɂł��킩��܂��B�R�~���j�P�[�V���������Ȃ��Ă���p����肢��҂��Ȃ��ɂ͂��邩������܂��A��͂�A�s�����������Ď�p�Ɍ��������A�M�����������Č��������͑傫������Ă��܂��B �Ԓr�@�^����������܂�p�ɗՂނƕK������̎�ɂȂ�܂�����ˁB �C������Ȑ��㐧�x ���R�@�ŋ߁A���X������͔̂F������㐧�x�̖��ł��B�F���E����̎擾�ɂ͈�萔�̎�p�Ǘ���o�����Ȃ��Ƃ����܂��A���Ă��Đ����҂����Ƃ���ɋC�������Ă��܂��āA���̏Ǘ��������ƐU��Ԃ�A���̏Ǘ�Ɋ������w�͂�����Ȃ��Ɗ����邱�Ƃ�����܂��B �Ԓr�@�V�����Z�p�����̈�҂ɂǂ����C�����邩�͔��ɑ�Ȗ��ł��B�F���͈��̌o����ςƂ����Ӗ��ŁA��̎w�W�ɂ͂Ȃ�Ǝv���܂��B ���R�@���܂̎Ⴂ��҂������F���̎��i������Ă��Ȃ��ƁA�u���̐l�ǂ�ȋ�����Ă�����?�v�Ƃ����ڂŌ����܂�����ˁB �@�����A�n���̕a�@�ɂ��閼���Ă̊O�Ȉ�̂Ȃ��ɂ́A�F���̉��l�Ȃ�ĔF�߂Ȃ��Ƃ����l������ł��傤�B �Ԓr�@�Ƃ͂����A�����Ƃ��Ĉ�҂����i�������Ă��Ȃ��ƗD�G�ȃX�^�b�t���W�܂��ė��Ȃ��B���̂悤�Ȑ��x�̉��ŁA�Z�p���p�����Ă������Ƃ͂ƂĂ��d�v�ȉۑ�Ȃ�ł��B �@�������O�Ȋw�����Ă���Z�p�F�萧�x�͂�����Ƃ������̂ł��B���ۂɎ�p������Ă���r�f�I���o���A����肵�Ă��炤�B�N�ł��\������ΊȒP�ɒʂ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA����Ȃ�Ɍ��������̂ł��B���ۂɁA���債�Ă����Ƃ���Ă����͑����ł���B ���R�@����a�@�����r�ŗL���Ȉ�҂����������ƁA�Ǘᐔ������Əオ�邱�Ƃ�����܂��B�������A���̐搶�������ł����p�����āA���̐���̖ʓ|�����Ȃ��Ƃ����P�[�X������B �@�Ⴂ�l�����ɂ����Ă���Ȃ��̂ŋZ�p�̌p�����Ȃ��A�搶����N���}����ƁA�܂��}�ɕa�@�̃��x�����������Ă��܂��Ƃ������Ƃ�����B �Ԓr�@�T������͖�̈��݂����̖���Njy���Ă��܂����A�m���ɂ����������҂���͂��܂��ˁB�������܂���a�@�ɂ́A10��ވȏ���������ł��銳�҂��������܂��B ���R�@����҂��{����10��ވȏ�̖��������ƕ��p�ł���̂��ǂ����A�S�z�ł��ˁB �Ԓr�@�{���ɂ�����ƔF�m�ǂ��n�܂��Ă���悤�ȍ���̕����A�Ƌ����Ȃ��炱�ꂾ�������̖������ł���Ƃ����̂͋����ׂ����Ƃł��B80�����l���A�{���ɂ��ꂾ���̖K�v�Ȃ̂��B���炵���ق����悢�Ǝv����P�[�X������B ���R�@�c��̃`�F�b�N�͂Ȃ��Ȃ�����B�t�Ɉ��݂����邱�Ƃ�����ł��傤�B���A�a�̖��2�����ŁA�ጌ���ɂȂ��Ă��܂��A�Ȃ�Ă��Ƃ����肤��B �Ԓr�@�ߔN�A���Â̌���ł��A�����Ȗo�Ă��܂����B�I�v�W�[�{�̂悤�ȐV�^�̖Ɖu���Ö�͔N��3500���~�����鍂�z��ŁA�b��ɂȂ��Ă��܂��B ���R�@���ꂩ����{�̈�Ô�͑�ςȂ��ƂɂȂ�܂���B�����������݂���̖ǂ�ǂ�o�Ă��܂�����B �Ԓr�@�����z�ȍR����܂⎡�Ö@�́A���ꂩ����{�l���c�_���ׂ��傫�Ȗ��ł��ˁB ���R�@�����̉Ƒ�������ɂȂ����Ƃ�����A�]���������ł����т�Ȃ獂������g�������Ǝv���͎̂��R�Ȃ��Ƃł��B���ɓ��{�̏ꍇ�͍����F�ی��ł����A���z�×{��x�̂������ň��̊z�ȏ�͎x����Ȃ��Ă������ł�����B �@�������A�t�ɂ��ꂪ���ł������āA�ŋ���������g���Ă������̉������ڒɂނ킯�ł͂Ȃ��̂ŁA��ẪR�X�g�ɖ��S�ɂȂ��Ă��܂������ł��B �@1�N�������Ԃ��������߂ɁA������܂ł�������ŋ��ŕ��S�ł���̂��B���Ƃ��������Ԃ����тĂ��A���܂�ɍ�����ł���R�X�g�p�t�H�[�}���X�̈�����ÂɂȂ�܂��B ���ɒl�i�͂����邩? �Ԓr�@���Ăł͈�ẪR�X�g�p�t�H�[�}���X�ɂ��ċc�_����Ă��܂����A���{�ł͂��̂悤�ȋc�_�����邽�߂̃f�[�^�����܂�o�Ă��܂���B���������b������u���ɒl�i������̂��v�Ƌt�ɔ����B ���R�@�C�M���X�ł͔�p�Ό��ʂ̈����V���Â͂Ȃ��Ȃ����F����܂���B�A�����J�ł��A����L���Ȃ�����a�@�ł́A�咰����ɗL���Ƃ��ꂽ�V�K�R����܂��g��Ȃ����Ƃ����߂܂����B���ʂ������̍R����܂Ƃقړ����Ȃ̂ɖ��{������Ƃ����̂����̗��R�ł��B���Ă͈�ẪR�X�g�ɕq���Ȃ̂ł��B �@���{�͍����̒N���������Ɉ�Â�����Ƃ����Ӗ��ł́A���Ɍb�܂�Ă��܂��B�������A���̗��ő�ςȂ��Ƃ��N�������ƔF�������ق��������B ���{�̈�Â͔j�]���O �Ԓr�@�{���ɓ��{�̈�Ð��x�͔j�]���O�ł��B �@��Ô��c�������Ȃ����߂ɁA��t��a�@���w�͂ł��邱�Ƃ́A�܂�����܂��B���Ƃ��Ύ��ʒ��O�܂ōR������Â����K�v������̂��ǂ����B ���R�@�I�v�W�[�{�̂悤�ȍ��z��͂��ꂩ��ǂ�ǂ�o�Ă��܂����A�����Ȃ��Ă����܂��B �@�ɘ_��������܂��A����N��ȏ�̍���҂ɂ͍��z�̖���g���̂���߂�Ƃ����c�_�ɂȂ邱�Ƃ����肦�܂��B����܂Ń^�u�[������Ă������̒l�i����Ìo�ρE��p�Ό��ʂ̖ʂ���^���ɍl���Ȃ�������Ȃ������ɗ��Ă��邱�Ƃ͊m���ł��傤�B �Ԓr�@�I�v�W�[�{�̂悤�Ȗ�ł����ʂ��肬��܂Ŏg���K�v������̂��B��҂Ƃ��Ă������Ȃ��Ƃ킩������A������Ɗ��҂ɐ������Ă�߂邱�Ƃ���ł��B ���R�@���݂́A�����z�b��ɂȂ��Ă��܂����A����łقƂ�nj��ʂ̂Ȃ����ז��R�������̂悤�Ȃ��̂���ʂɎg���Ă���Ƃ�������������܂��B���ꎩ�͈̂����ł��A�o���ς���ΎR�ƂȂ�܂��B �Ԓr�@���R�搶�͂����g�ł͉���������܂�Ă��܂����B ���R�@�l�͌����������̂ŁA�~���܂�2��ވ���ł��܂��B�����厡��̊��߂�����_�C�G�b�g�����������A��������߂ɂȂ��Ă��܂����B�~�ɂȂ��Ă����̂܂オ��Ȃ���A��߂悤�Ǝv���Ă��܂����c�c�B �Ԓr�@������炵�Ă���������ł���B �@���́A�R���X�e���[���̖������ł��܂��B����p�̃��X�N���������������ŁA���҂�V���ɂ����Ȃ���A�����̐g�̂ɖ{���ɕK�v�Ȃ��͉̂������l����悤�ɂ��Ă��܂��B ���R�@�ǂ̂悤�ȃ��X�N�����e���A����ǂ��I�Ԃ��́A���ǂ͂ǂ��V���Ă������A�����Ă����ɂ��Ď��ʂ��Ƃ������ɂȂ���܂��B �@�ł��邱�ƂȂ�ꂵ�܂��A�Ƒ��ɖ��f���������ɐ��������Ƃ����l�������ł��ˁB�����Ȃ�ƐS������������������܂���B�����A���ꂾ�Ƌ}�߂��邩������Ȃ��B�Ƒ��Ɍ����c�������Ƃ����邾�낤����A2~3���͈ӎ��������āA�����Ɛ�����a�C�����z�ł��傤�B �Ԓr�@���͐t�s�S����r�I���₩�Ȏ��ɕ����Ǝv���܂���B���ʂ܂ʼn��ł��H�ׂ��āA����ƈӎ����|�[�b�Ɣ����Ȃ��ĖS���Ȃ��ł��B ���R�@�]�����ǂ��߂��������̂��A�����ǂ��}����̂��Ƃ������́A�l���ρE�����ςɒ������܂��B�����܂Ŋ��҂���ƃR�~���j�P�[�V���������邩�ǂ����B �@��p���邩�ǂ������������҂̉Ƒ��ɁA�u�搶�̉Ƒ��������a�C��������ǂ����܂���?�v�ƕ�����邱�Ƃ��悭����܂��B�����Ŏ����u�����̉Ƒ����������p���܂���v�ƌ����Ɣ[�����Ă��炦�܂��B �Ԓr�@���̂悤�ɐq�˂��邱�Ƃ͑����ł��ˁB���R�Ȃ���A��҂̂ق������m��������܂��B �@�����牽�ł����҂���ɔ��f������Ƃ����̂͊Ԉ���Ă���Ǝ��͎v���Ă��܂��B���ׂĂ̏������҂���ɓ`���Ĉꏏ�ɍl���A���̏�Ŏ��Â̐ӔC�͂��ׂĔw�����B����������t�Ɗ��҂���̊W�����z�ł͂Ȃ��ł��傤���B �T������ 2016�N10��15���E27�������� |
|
�얞��2�^���A�a�̊��҂͊̑�����ɂȂ�₷�� �얞�ɓ��A�a����������ƃI�b�Y2.6�{�� |
| �@�E�G�X�g���͒��̑�����BMI�̏㏸�A2�^���A�a�̑��݂́A�̑�����̔��ǃ��X�N�����߂���q�ł��邱�Ƃ��A�V���������Ŏ����ꂽ�B �@�u������3�̈��q�͊̑����X�N�̑����Ɩ��炩�Ɋ֘A���Ă���v�ƁA�������҂�1�l�ł���č�����iACS�j��Peter Campbell���͏q�ׂĂ���B�č��ł́A�̑�����̔��Ǘ���1970�N�㔼����ق�3�{�ɑ����Ă���A�\�������߂Ĉ����^�C�v�̂���ł���Ƃ����B �@������́A�얞�����2�^���A�a�Ɗ̑�����Ƃ̊֘A�ׂ邽�߁A�č��ōs��ꂽ14���̌����ɎQ���������l157���l�̃f�[�^���Ē��������B�Ȃ��A�����J�n���_�ɂ͎Q���҂̂����̑�����ǂ������҂͂��Ȃ������B �@�ǐՊ��Ԓ��ɁA�Ώێ҂̂���6.5����2�^���A�a�Ɛf�f����A2,100�l�����̑�����ǂ����B�얞����������2�^���A�a�̊��҂Ɣ얞����2�^���A�a���������Ă��Ȃ����҂ɂ�����̑�����̔��Ǘ����r�����Ƃ���A2�^���A�a������Ɗ̑�����ǂ��闦��2.6�{�ɏ�邱�Ƃ��킩�����B���̊֘A�͈�����i���A�l��Ƃ��������X�N���q������F�߂�ꂽ�Ƃ����B �@�܂��ABMI��5kg/m2�㏸����ƁA�̑����X�N�͒j���ł�38���A�����ł�25���������A�E�G�X�g���͒���5cm������Ɗ̑����X�N��8�����������B �@�����ɂ��ƁA�uCancer Research�v10�����Ɍf�ڂ��ꂽ���̒m���́A�̑����얞�Ɋ֘A��������̂ЂƂł��邱�Ƃ������x��������̂ŁA�K���ȑ̏d���ێ����ׂ����R�ɂ��Ȃ�Ƃ��Ă���B �@����̌����́A�얞�Ɗ̑�����Ƃ̈��ʊW���������̂ł͂Ȃ����A���҂�́A�얞�ⓜ�A�a���ߔN�̊̑�����̋}���ȑ����Ɋ�^���Ă���\�������������ߋ��̌������ʂ𗠂Â�����̂��Ƃ��ACampbell�����u�ߏ�ȃA���R�[���ێ�Ɗ̉��E�C���X�ւ̊����������̑�����̌����ł͂Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B �@�얞�ⓜ�A�a�����E���Ŗ������Ă��錻����ӂ݂�ƁA����̒m���͌��O�q���̊ϓ_������d�v�ɂȂ�B�u�̑�����̃��X�N���q�Ƃ���B�^�̉��E�C���X��C�^�̉��E�C���X�Ȃǂɂ��Ă͍L���[������Ă��邪�A�����̈��q�͎��ۂɂ́A�얞�ⓜ�A�a�ɔ�ׂ�Ƃ͂邩�ɏ��Ȃ����̂��v�ƁA���҂�1�l�ł���č������������iNCI�j��Katherine McGlynn���͎w�E���Ă���B m3.com 2016�N10��25�� |
|
���[�Č��͂����Ɏ�ׂ��H�@�Č��̒x�ꂪ���҂̕s�����ɂȂ��� ������ɑ�����[�؏��p��̎��� |
| �@�������p�ɂ����[�؏���ɂ́A���[�Č��܂Ő��J�����琔�N�̊��Ԃ��������ɏp�シ���ɍČ��p�����ق����A���҂̐��_�I�ȃX�g���X�͌y�������\�����A�J�i�_�̌����Ŏ������ꂽ�B �@�u�p�シ���ɓ��[�Č��������҂ł́A�Č��܂łɎ��Ԃ�v�������҂ɔ�ׂāA���_�I�ȋ�ɂ�Č��O�̃{�f�B�[�C���[�W�̈����A�������̌����Ȃǂɋꂵ�ފ��Ԃ��Z���Ă��މ\�����������ꂽ�v�ƁA�������҂ł���g�����g��w��Toni Zhong����͏q�ׂĂ���B �@����̌����́A���[�؏��p��ɓ��[�Č�����106�l�̓����҂�ΏۂƂ������̂ŁA30�l�͓��[�؏��Ɠ����ɍČ����A76�l�͓��[�؏����畽�ς�3�N��ɍČ������B �@���[�؏��p���s���O�ɂ́A�Ώۊ��҂�26���ɕs�����x���̏㏸���݂��A9���ɂ͂��Ǐ�̈������F�߂�ꂽ�B���Q�Ƃ��ɁA���[�Č���ɂ͂��������s�����͌y�����Ă����B �@�������A���[�Č��܂łɎ��Ԃ�v�������҂ł́A�{�f�B�[�C���[�W������ւ̖����x�A���N�Ɋ֘A����QOL�ɑ���]�����Ⴉ�����B���̂��Ƃ���A�����������҂ł́A�Č���҂Ԃɐ��_�I�ȃX�g���X���Ă������Ƃ��������ꂽ�Ƃ����B �@����ŁA���[�Č�����6�J����ɂ́A�{�f�B�[�C���[�W�Ɋւ���X�R�A�ɗ��Q�Ԃō��͏������A12�J���エ���18�J����ɂ͐������ւ̖����x�Ɋւ���X�R�A�ł����݂͂��Ȃ��Ȃ����B �@���̒m���́A�uPlastic and Reconstructive Surgery�v10�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@������ɂ��ƁA�J�i�_�ł́A�č��ɔ�ׂē��[�؏��p������[�Č��܂łɊ��Ԃ�v����P�[�X����ʓI�ł���Ƃ����B�p�シ���̓��[�Č����K���A�����������]���銳�҂ɂ��ẮA�u���[�؏��p�シ���̓��[�Č����R�[�f�B�l�[�g����悤�ɂ�����w�͂��Ȃ����ׂ����v�ƁA������͌��_�Â��Ă���B m3.com 2016�N10��28�� |
|
�H�����\��s�ǂɒ����E�����ۊ֗^ �F�{��A���A���^�C��PCR�@�őg�D���̃t�\�o�N�e���E�������o |
| �@�F�{��w��w�@�����Ȋw�������̔n��G�v�����̌����O���[�v�́A��������o���ɐ�������ہu�t�\�o�N�e���E���v���A�H������̗\��̕s�ǂɊ֗^���邱�Ƃ�˂��~�߂��B���҂̂���g�D�����A�c�m�`�̉�͂ȂǍs���A���ۂ��������݂���ƁA���ǐ�����ς����Ɋ֘A�����`�q�Q���ϓ����邱�Ƃ����������B �@���[�O���g����_�ۈ����Ȃǂ̃v���o�C�I�e�B�N�X�X�i�����ɗǂ��e����^����������j�⒰�����𐮂���@�\���f�ނ�ێ悵�A�����ۑp�i�t���[���j�o�����X�����P���邱�Ƃ��\���ǍD�ɕۂ�̑�Ƃ��ĉ\�����l������B �@�����O���[�v�́A�F�{��w��w�������a�@�Ŏ�p�����H�����҂R�Q�T�l�̏����āA�؏����ꂽ����g�D�Ɣ�g�D�i����g�D�j����c�m�`�𒊏o�B��`�q�̒�ʂׂ��郊�A���^�C���o�b�q�@��p���đg�D���̃t�\�o�N�e���E�������o�����Ƃ���A����g�D����͐���g�D�����L�ӂɑ����̓��ۂ̂c�m�`�����o���ꂽ�B����g�D���瓯�ۂ����o���ꂽ���҂́A�R�Q�T�l���V�S�l�ŁA��Q�R�����߂Ă����B �@����g�D���瓯�ۂ����o���ꂽ���҂ƌ��o����Ȃ��������҂̂Q�O���[�v�ɕ����A��p��̐������Ԃ��r�B���̌��ʁA���ۂ����o���ꂽ���҃O���[�v�́A���o����Ȃ��������҃O���[�v�ɑ��A�L�ӂɐ������Ԃ��Z���������Ƃ����������B �@���ɁA���ۗz���ƉA���̐H�����璊�o�����q�m�`��p���āA��`�q��͂ɂ���`�q�̕ϓ����B���ۗz�����҂ł́A���ǂ𑣂�����ς����i���ǐ��T�C�g�J�C���j�Ɋ֘A�����A�̈�`�q�Q���ϓ����Ă��邱�Ƃ��m�F�ł����Ƃ��Ă���B�����f�[�^���ڍ�͂���ƁA�u�b�b�k�Q�O�v��u�b�w�b�k�V�v�Ƃ������������̗A���Ɋւ��邽��ς����i�P���J�C���j�̈�`�q�̗ʂ��������Ă��邱�Ƃ����������B �@����̌���������o��ۂł��铯�ۂ��P���J�C������āA�H������̐i�W�Ɋ֗^���Ă���\�����������ꂽ�B���ۂ͒����t���[���ɂ����ėD�ʂȑ��݂ł͂Ȃ����A�咰����g�D���獂�p�x�Ō��o����A�咰����̐i�W�ɉe����^���Ă���\���̂��邱�Ƃ�����Ă���B �@���o�ɋ߂��H���̂���ł����e���ɂ������Ƃ݂��A���ۂ̏ڍׂȉ�͂Ɩ������𖾂��邱�ƂŐV���ȑΉ��@���T���ł���B���̈�Ƃ��čl������̂������t���[���̉��P�B���_�ۂ�r�t�B�Y�X�ۂȂǂ̑P�ʍۂ𑝂₷���Ƃ��\��̏��P�ɓ����\��������B m3.com 2016�N10��31�� |
|
�I�v�W�[�{�̐V�K��p�� ����ATh9�זE�ɍ�p���Ĉ������F��Ɍ��� |
| �@���s��w��10��26���A����Ɖu�Ö@�̐V��u�I�v�W�[�{(R)�v�i��ʖ��F�j�{���}�u�j�̐V�K��p�Ƃ��āA���������ɐ��p�[�Z���g�������݂��Ȃ��u9�^�w���p�[T�זE�iTh9�זE�j�v�ɍ�p���āA�������F��i�����m�[�}�j�̊��҂Ɍ��ʂ����邱�Ƃ������Ɣ��\�����B���̌����́A����w��w�@��w�����Ȃ̑�˓Ďi�����A��X���D�����m�ے��w���A��������������̌����O���[�v�ɂ����́B�������ʂ͍��ۉȊw���uOncoimmunology�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@�q�g�̑̂̒��ɂ́A�����ɂƂ��āu�ٕ��v�ł���ۂ�E�C���X�����͂Ŕr������V�X�e�����Ɖu�@�\�����݂��A���N�ȏ�Ԃł͂���זE���u�ٕ��v�Ƃ��Ď�菜����Ă���B������u����Ɖu�v�ƌĂсA�i�s�������҂ł͂��̖Ɖu�זE�������Ȃ��Ȃ�X�C�b�`�������Ă��܂��A����Ɖu������Ă��邱�Ƃ��킩���Ă���B���̃X�C�b�`�iPD�|1�Ƃ������q�j���������Ċ��҂̂���Ɖu�������邱�Ƃł���זE��j��V�RPD�|1�R�̃I�v�W�[�{�����A���̐V�����̂͊��ґS�̂�3�����x�ŁA�c���7���ɂȂ����ʂ��Ȃ��̂��͂܂��킩���Ă��Ȃ��B �@�����O���[�v�́A���҂��ꂼ�ꂪ���Ɖu�̏�Ԃ̈Ⴂ���V��̌��ʂ̈Ⴂ�Ɗ֘A������̂ł͂Ȃ����Ɖ��������āA���ꂼ��̎�ނ̍זE�A���q1�ЂƂɂ��āA���Ì��ʂ����������ҌQ�ƂȂ��������ҌQ�ō����Ȃ��������B���̌��ʁA�����p���̈��ł���Th9�זE���A���Ì��ʂ����������҂ŃI�v�W�[�{���^��A�������Ă��邱�Ƃ������B �@����ɁATh9�זE�������Ǔ��ō��o���������s���A�RPD-1�R�̂�������ƁA�Ȃ��ꍇ�Ɣ�ׂāA�������悭Th9�זE�����o���邱�Ƃ��B�܂��A�������F��̃}�E�X���f����p�����������s���ATh9�זE�����o���C���^�[���C�L��9�Ƃ������q���ǂ̂悤�ȍ�p�������������������ʁA�C���^�[���C�L��9�̍�p���ɂ��鎎��𓊗^�����}�E�X�ł́A�����łȂ��}�E�X�ɔ�ׁA�������F������i�s�������Ƃ���A�C���^�[���C�L��9�ɂ͈������F��̐i�W��}�����p�����邱�Ƃ��킩�����Ƃ��Ă���B �@����́A��������Th9�זE�����j�^�����O���A�I�v�W�[�{���^�㑁���Ɏ��Ì��ʂ肷��o�C�I�}�[�J�[�Ƃ��Ă̊��p��Th9�זE�̋@�\�����߂邱�ƂŁA�R��ᇌ��ʂ����߂�\���̔g�y���ʂ����҂ł���ƌ����O���[�v�͌��Ă���B�I�v�W�[�{���^��ɂ��Th9�זE���������銳�ҁA���Ȃ����҂̂���Ȃ�ڍׂȈႢ����͂��Ă����Ƃ��Ă���B m3.com 2016�N10��31�� |
| ����זE ��p�����ɂ��̏�ʼn�������Z�p ���H�傪�J�� |
| �@�����H�Ƒ�w�̌����`�[���́A���t���˂���ƁA��������������זE�ɂ������ȕ����ɂ̂ݔ������ċߐԊO�������A���҂̑̂������邱�ƂȂ��A����g�D����肷��Z�p���J�����A�}�E�X���g���������Ŏ������B �@���H��̋ߓ��ȍ]�����ƌ��ۍ��O�����̃`�[���́A��������̎�ᇑg�D�Ŋ���������u��_�f�U�����q�v�ɒ��ځB����܂ł̌����ŁA�R����܂������ɂ����Ȃ�����A����זE�̓]�ڂɊւ�邱�Ƃ��������Ă���A����̑��������ɂȂ���f�f�}�[�J�[�Ƃ��Ă̊��p�����҂���Ă��邪�A���炩���߂���זE�Ɉ�`�q�����Ȃ���Ȃ炸�A���̏�ł̐f�f�͓�������B 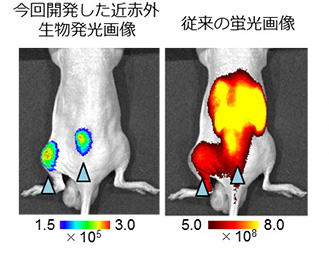 �@�����ŁA����זE�����nj`����W���A�����I�Ȏ_�f�s���̊����Ɓu��_�f�U�����q�v����������Ȃ������𗘗p���āA�ߐԊO�����������Ȃ���ς������q��g�ݍ��킹���������J���B �@�畆����̃}�E�X�̐K���̐Ö��ɒ��˂��A�S�g�ɍs���n�点�������ł́A���^��1���Ԃň�������ɐN���ꂽ���ʂ���肵���B �@�܂��A����܂ő咰����̐f�f�ł́A���^�����������N����̑��A�t���Ȃǂ̔r���튯��ʂ�S�ߒ��Ŕ������Ă��܂����Ƃ���A��ᇂ̈ʒu����肷��̂�����������A�����x�Ȑf�f���\�ɂȂ�Ƃ����B �@�����`�[���́A�u��_�f�U�����q�v���A����̔�����]�ڂ̉ߒ��łǂ̂悤�ɋ@�\���Ă���̂�����̓I�ɖ��炩�ɂ���Ƙb���Ă���B �@�Ȃ����̌������ʂ́A�p�Ȋw���l�C�`���[�̎o�����u�T�C�G���e�B�t�B�b�N�E���|�[�c�v�d�q�łɌf�ڂ��ꂽ�B �n�U�[�h���{ 2016�N11��3�� |
| �����ɂ�邪�ҁA2012�N��36���l ���A�@�֒��� |
| �@���p���iParis�j�ŊJ�Ấu���E�����c�iWorld Cancer Congress�j�v��2���A2012�N�Ɉ����������Ŕ��������V�K���҂�70���l�ȏ�ŁA����֘A�̎��҂���36��6000�l�ɏ��Ƃ��钲���f�[�^�����\���ꂽ�B�����̔��������͎�ɕx�T���ł̂��̂��Ƃ����B �@�����`�[���́A����������l�Ƃ��Ȃ��l�̂��ǃ��X�N���r���A����̔N�ԐV�K�Ǘᐔ�̖�5%�A�N�Ԏ��Ґ���4.5%�ɁA�A���R�[�����֗^���Ă���Ƃ̌��ʂ��Z�o�����B �@�������\���T��������̗\�����̋������M�҂ŁA���A�iUN�j�̍��ۂ����@�ցiIARC�j�̃P�r���E�V�[���h�iKevin Shield�j���́AAFP�̎�ނɁu�A���R�[���ɂ���Ă������N������鋰�ꂪ���邱�ƂɁA�����̐l���C�t���Ă��Ȃ��v�ƌ�����B �@�A���R�[���ƍł������֘A�����F�߂�ꂽ�͓̂�����̐V�K�f�f��ŁA�A���R�[���ɋN������S����Ǘ��4����1�ȏ���߂Ă����B�����Ŋ֘A�����������̂͑咰����ŁA�S�̂�23%�������B���̂��Ƃɂ��ăV�[���h���́A���ɓ�����ł́u���ǃ��X�N���i�A���R�[���́j�ێ�ʂƂƂ��ɑ�������v���Ƃ͖��炩���Əq�ׂ��B �@�A���R�[���Ƃ���ɂ�鎀�S�Ƃ̊֘A�ɂ��ĕ]���������ʂł́A�H������ōł��֘A���������A�����ő咰���������B �@���E�ی��@�ցiWHO�j�̐��g�D�ł���IARC�́A�A���R�[���������u�O���[�v1�̔��������v�ɕ��ނ��Ă���B����́A�A���R�[��������������N�����ƍl�����Ă��邱�Ƃ��Ӗ����邪�A�V�[���h���ɂ��ƁA���̔��Nj@�\�ɂ��Ắu���m�ɂ͕�����Ȃ��v�Ƃ����B �@���E�S�̂ł݂�ƁA���a���S���ł��傫���n��͖k�āA���B�A���B�i���ɓ����j�Ȃǂ����A���W�r�㍑�ł̈���ʑ����ƂƂ��ɁA���̌X���ɂ͊ɂ₩�ȕω����݂���ƁA�����`�[���͎w�E���Ă���B AFPBB News 2016�N11��3�� |
| �g�����A�Ăł͑O���B����̃��X�N�傳����Ƃ̌����� |
| �@���N�����������ł��邩�ǂ����͐H�ޑI�т��d�v���B�ŐV�̌����ł͐V���Ȓm�������炩�ɂȂ��Ă���B���̐H�ނ̈���W���K�C�����B���N�I�ȃC���[�W�͂�����̂́A�H�ו�����ŁA�̂Ɉ������̂ɂȂ肩�˂Ȃ��Ƃ����̂ł���B �@�n�[�o�[�h��w�ŐH�ƌ��N�Ɋւ��錤�������Ă����č��{�X�g���ݏZ�̓��Ȉ�t�E�吼�r�q���͂��������B �u�W���K�C���ɂ̓r�^�~��C�Ȃǂ̃r�^�~���ނ�J���E���A�}�O�l�V�E���A�S�Ȃǂ̃~�l�����ɉ����A��ɂ͐H���@�ۂ��܂܂�܂��B �@�������A����ǂ����邽�߂ɖ��Ɖ��������Ē�������邱�Ƃ������A���ꂪ�얞����K���a�Ȃǂ̌����ɂȂ�B�܂��A�W���K�C���̓A�~�m�_�̈��ł���A�X�p���M���ƁA�u�h�E����ʓ��Ȃǂ̊Ҍ������܂݁A�����ŗ��҂����M����Ɓw���C���[�h�����x���N���A��ʂ̃A�N�����A�~�h�����܂��B�A�N�����A�~�h�͍��ۂ����@�ցiIARC�j���A�w�l�ɑ������炭����������x�����ɕ��ނ��Ă��镨���ł��v �@�����ŃW���K�C��������t���C�h�|�e�g��|�e�g�`�b�v�X�ɂ́A���̃A�N�����A�~�h���܂܂�Ă���Ƃ������Ƃ��B�g�����Ƃ����A�S���ҁi100�Έȏ�̐l�j��ΏۂƂ��������ŋ�����D���ɂ��u�V�Ղ�v��u�J�c�v�����������A����ł����͑O���B����̃��X�N�傳����Ƃ̌������o�Ă���Ƃ����B �@�ăV�A�g���ɂ���t���b�h�E�n�b�`���\���������ł́A�V�A�g���n��ݏZ�̑O���B����Ɛf�f���ꂽ�j��1549�l�ƌ��N�Ȓj��1492�l�i35�`74�j��ΏۂɁA�t���C�h�|�e�g��t���C�h�`�L���A���̃t���C�A�h�[�i�c�Ȃǂ̗g�����H�i�̒���I�ȏ���ƁA�O���B����̃��X�N�����∫���x�̍����Ƃ̊֘A�ɂ��đ�K�͒��������{���A2013�N6���Ɍ��ʂ\�����B�O�o�E�吼���͂��������B �u�����̗g�������T��1�x�ȏ�H�ׂ��j���́A����1���̒j���Ɣ�r���āA�O���B����̃��X�N�����ꂼ��30������37���ɏ㏸���܂����B�����̉ߒ��ŁA�I�������Y���A�A�N�����A�~�h�A�w�e���T�C�N���b�N�A�~���A���F�����Y�����f�Ȃǂ̔���������������邩��ƍl�����Ă��܂��v �@DHA��EPA�Ȃǂ��܂ށu���v�́A����������H�ו��������͂������A�t���C�ɂ��Ă��܂��ƑO���B����̃��X�N���o�Ă���Ƃ����B �@�����Ƃ��A�u�咰����Ƃ͈Ⴂ�O���B����͑��������ł���Ύ��S���X�N�͒Ⴂ�v�i�吼���j�Ƃ����B�ʂ̖��ł����āA���ɍ���҂����܂ɐH�ׂ邾���Ȃ���Ȃ����Ƃ͓��̕S���҂������ؖ����Ă���B �K�W�F�b�g�ʐM 2016�N11��5�� |
|
����זE�ƍU�߁I����ɓ���������̈З� ���̗Տ������Ŗ�7���̖��������P���� |
�Ð� ���i :��w���m �����암�n��a�@�O�� 6�J���̃P�g���H�Ö@���s����70�E�����̎���B(��)�F2014�N8���A�x�̉E���22�~28mm�̂����F�߂�B(�E)�F4�J����̓��N12���ɂ͓����ʂ̎�ᇂ����S�ɏ���(�ʐ^�F���Ғ�) �@����זE�́A�u�h�E�����G�l���M�[���Ƃ���\�\�B����́A1931�N�Ƀm�[�x�������w�E��w�܂���܂����I�b�g�[�E���[���u���O���m���A�}�E�X�́u���������זE�v��p���������ʼn𖾂��A1923�N����̈�A�̘_���Ŕ��\�������̂ł��B �@2�l��1�l������ɜ늳���A3�l��1�l������ŖS���Ȃ�Ƃ���钆�A�����̂��Â̑傫�Ȗ��_�Ƃ����A����90�N�ȏ���O�ɔ������ꂽ�������A�܂�������������Ă��Ȃ��������Ƃɐs����ł��傤�B���ł́A����זE�͐���זE��3�`8�{���̃u�h�E������荞�܂Ȃ���A�����������ێ��ł��Ȃ����Ƃ��������Ă��܂��B �u�h�E�����R��Ԃ̑̂����ݏo���u�P�g���́v �@���̗��R�́A2�l�����܂��B1�́A���Â̌���ɂ����āA���҂̉h�{�Ǘ���H���w�����e���y�����ꑱ���Ă������ƁB�����āA����1�́A�����̑㖼���ł���Y���������A�������������Ă������߂ɕK�v�ȁA3��h�{�f�̒��j��S���Ă������Ƃł��B �@�m���ɁA�������l�Ԃ̐��������́A�������̓��ŕ�������Ăł���A�u�h�E������ȃG�l���M�[���ɂ��Ă���ƒ����l�����Ă��܂����B�������A���_�����Ɍ����A�u�h�E�����͊�����ƁA�l�Ԃ̑̓��ł̓u�h�E���ɑ���A�ً}�p�̃G�l���M�[�����ݏo����܂��B���ꂪ�A�������Â̌��Ƃ��Ă���u�P�g���́v�Ƃ����_���̑�ӕ����ł��B �@���̃P�g���̂́A�牺���b��������b����������邱�ƂŎY������܂��B�����āA����זE���P�g���̂��G�l���M�[���ɂ��邱�Ƃ��ł���̂ɑ��āA����זE�͊�{�I�ɂ��ꂪ�ł��܂���B����זE�ɂ́A�P�g���̂��G�l���M�[�ɕς���y�f�������Ă��邩��ł��B �@�����ɁA���Â̑傫�ȃq���g���B����Ă��܂��B����זE�Ƃ����ǂ��A���ʍזE�Ɠ��l�ɁA�h�{����₽���Ύ��łւ̓���H�炴��Ȃ�����ł��B �@�P�g���̂̂������Ƃ���́A�P�ɂ���זE�̉h�{�������Ƃ����ł͂���܂���B�����U������y�f�i��-�O���N���j�^�[�[�j�̊�����ቺ������ȂǁA���ꎩ�̂ɍR�����p�����邱�Ƃ��A���������Ȃǂʼn𖾂���Ă��܂��B����ɁA����̔����N���ƍl��������_���������A�~�g�R���h���A�̊������𑣂��u������`�q�v�̃X�C�b�`�����铭�������邱�Ƃ��A�ŋ߂ɂȂ��Ă킩���Ă��܂����B �@�����A���E���ƂȂ�Տ������i�u�X�e�[�W�W�̐i�s�Ĕ��咰���A�����ɑ��`������EPA�������������������ɂ��QOL���P�Ɋւ���Տ������v�j�����Ƃɑ̌n�t�����A�u����Ɖu�h�{�P�g���H�Ö@�v�Ƃ́A���̃P�g���̂����Ẫx�[�X�ɐ������A����זE����点�Đ���זE�����C�ɂ��邽�߂́A�H�ɂ�邪��̕��ƍU�ߐ�@�ɑ��Ȃ�܂���B �����̐ێ���u����Ȃ��[���v�ɂ���P�g���H�Ö@ �@���̐H�Ö@�̊�{�ƂȂ�̂́A��H�ł���Y�������̋ɒ[�ȃJ�b�g�ł��B���̑���ɁA�Ɖu�@�\�̎w�W�ƂȂ邽��ς����i����ށA�哤�ށA���Ȃǂ���ێ�j�ƁA����̐i�s�Ɖ��ǂ�}����I���K3���b�_��EPA�i�G�C�R�T�y���^�G���_�B���̎h�g��A�}�j���ȂǂɊ܂܂��j�̐ێ���������A����ɁA���̔R�Đ��̍�������P�g���̂̎Y�������͂ɑ����Ă���钆�����b�_�iMCT�I�C������Ɋ��p�j���A1������ɕ����Đێ悷��悤�ɂ��Ă��܂��B �@�H�����j���[�̏ڍׁA�h�{�̑g�ݍ��킹�Ȃǂ́w�P�g���H������������x�ɏ���܂����A�������������b�A������ς��A�ᓜ���̃P�g���H�ɁA�R����܂���ː��Ȃǂ̉��w���Âp����ƁA���҂̂���זE���k���A���ł���m���ł���u�t�����v���A�b�v���邱�Ƃ��A���̗Տ������Ŗ��炩�ɂȂ�܂����B �@���̐H���Ö@�́A3�J���̌p�����x�[�X�ɁA���{�̈��S�����m�F����Ă���1�N�܂ł�ڏ��ɍs���܂��B�Q���҂̗Տ��J�n����3�J���㎞�_�ł̕a���̒��ԕɂ��APR�i�����t���j��6��ASD�i�i�s�}���j��1��APD�i�����j��2��ƂȂ��Ă��܂��B�����̍ō��P�g���̐���1000��M����ƁA����͏k������X���ɂ��邱�Ƃ����Ď��܂��B �@���āA����9���1�N��̕]���͂ǂ��Ȃ����̂ł��傤���B3�ႪCR�i���S�����j�A3�ႪPR(�����t��)�A1�ႪSD(�i�s�}��)�A2�ႪPD(����)�ɂ�鎀�S�ƁA�t������67���A�a���R���g���[������78���Ƃ������ʂɂȂ�܂����B�Տ��Ώێ҈ȊO�̖Ɖu�h�{�P�g���H���{�҂��܂߂�Ɓi����18�l��3�J���ȏ���{�j�A���̕a���R���g���[������83���ɂ��̂ڂ�A�Ɖu�h�{�P�g���H�Ɖ��w�Ö@�̕��p�̗L�Ӑ����A����ɖ��m�Ɏ�����Ă��܂��B �u�P�g���H�v�̎��{���댯�Ȑl������ �@�������A���̋ɒ[�ȓ����J�b�g�ɂ��Ɖu�h�{�P�g���H�����ׂĂ̊��҂���Ɏ��{�ł���킯�ł͂���܂���B�̑��ɂ���̌�����(�ŏ��ɔ�����������)������銳�҂����A��V�I�ȗv�f���W����T�^���A�a�̐l�ɂ́A�K�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B �@�܂��A�̑��ɂ���̌�����������ꍇ�́A�P�g���̂��������A�S�g�ɑ���o��������S���̑����A�P�g���̂��G�l���M�[�ɂł��Ȃ����Ƃ����R�ɂȂ�܂��B �@�܂��A�T�^���A�a�̏ꍇ�́A���t��̉t�̔Z�x���_���ɌX���u�P�g�A�V�h�[�V�X�v�����������邱�Ƃ����R�ł��B���̃P�g�A�V�h�[�V�X�Ɍ�������ƁA�q�f�⓪�ɁA�p���A�Ђǂ��Ƃ��ɂ͍����̈������ɂ��Ȃ�܂��̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B �@���̗Տ������ł��APD�i�����j�ɂ���ĖS���Ȃ�ꂽ��L��2��́A�C���X�����������̓����͂Ȃ��������̂́A������������K���ɂ��U�^���A�a�̌X���������܂����B��������l����A�U�^���A�a�ł��ɂ₩�ȓ����������s���A�����₪��̕a�����R���g���[���ł���͂��ł������A�����������Ƃ��瓜�A�a�̊��҂���ɑ��ẮA�����_�ŃP�g���H�𐄏��ł��Ȃ��Ƃ����c�O�Ȍ��ʂ�������Ă��܂��B  �@�������A�C���X�����̓���������ł������A�P�g���̂������瑝���Ă��P�g�A�V�h�[�V�X�������N�����Ȃ����Ƃ��A���̗Տ����܂߂������̗Տ��������疾�炩�ɂ���Ă��܂��B�Ɖu�h�{�P�g���H��3�J���ȏ�ɂ킽���Čp�������A���A�a�̂Ȃ����҂���̑��P�g���̐��ƁA���t�y�єA���_�����A���J������������pH�ׂĂ݂�ƁA�P�g���̐����ٗl�ɍ����ɂ��S�炸�i��l��28�`120��M�j�A����pH�ƔA��pH�̂�������A��l���Ɏ��܂��Ă��邱�Ƃ�������܂��B �@�Ƃ͂����A������ɂ��Ă����Âɂ�����P�g���H�Ö@�́A�f�l���f�ōs���ׂ��ł͂���܂���B���҂̉h�{�Ǘ���H���w�����e��R����܂Ȃǂ̕���p��ɐ��ʂ����A��t�̎w���̂��Ƃōs����K�v������܂��B���̂��߂ɂ��A���{�a�ԉh�{�w��F�肷��u����a�ԉh�{���Ǘ��h�{�m�v�̏[���ƁA���Âɓ��������H���Ö@�̕ی��K�p���̎������A�������}���ɂȂ�ł��傤�B �Ð� ���i�i�ӂ邩�� ���j Kenji Furukawa ��w���m 1967�N�R�������܂�B1992�N�Ɍc��`�m��w���H�w���d�C�H�w�ȑ��B���̌�A�R����ȑ�w��w����w�Ȃɓ��w�B1999�N�A������O�Ȉ���u�]���A�������q��ȑ�w������O�Ȃɓ��ǁB��w�ł́A�X���ǂɏ������A�����A�X�������p�������{����ւ��Ă����B2006�N�A�i�����j�����s�ی���Ì��Љ`���a�@�O�Ȃ��o�āA�����암�n��a�@�O�ȂɋΖ��B�m�r�s�i�h�{�T�|�[�g�`�[���j�ɏ]�����A�{�i�I�ɂ���̉h�{�Ö@���J�n�B����Ɖu�h�{�Ö@�̗Տ����т��グ�āA14�N�A����܂ł̉h�{�Ö@�̃P�g�W�F�j�b�N���ɐ����B15�N1�����A�X�e�[�W�W�̂��҂�ΏۂɁA���E���̗Տ��������J�n�B���݁A����Ɖu�h�{�P�g���H�Ö@�̕��y�ɓw�߂Ă���B ���m�o�σI�����C�� 2016�N11��10�� |
| �u���N���i�݂��x���v ����̐i�s�X�s�[�h�͔N��ňႤ�H |
| �@���{�l�̎����E���ʂł���u����v�B �@2015�N�ɂ���ŖS���Ȃ����l��37��346�l�������ł��B ����͈�ʂɁu���N���̂���͎Ⴂ�l�ɔ�ׂĐi�s�X�s�[�h���x���v�Ƃ����邱�Ƃ������̂ł����A���ۂɔN��Ƃ���̐i�s�X�s�[�h�͊W����̂ł��傤���H �ڂ������Ă����܂��傤�B �u���������v����������10�N�ȏ�o�� �@��ʓI�Ȍ����uX�������v�ł�������̂͒��a��1�Z���`�̑傫���ɂȂ����Ƃ��ł��B �@���̂Ƃ��̏d���͖�1�O�����A����̍זE���͖�10���Ƃ����Ă��܂��B �@���̃T�C�Y�Ō������Ă���u���������v�ƌĂ�܂����A���͂���זE���������Ă��炷�ł�10�N�ȏ�o�߂��Ă����Ԃł��B �@����̏Ǐ��2�`3�Z���`�قǂ̑傫���ɐ��������Ƃ��ɏo�Ă��܂����A����̎�ނ��Ԃɂ���Ă�5�Z���`�ȏ�ɂȂ��Ă��ڗ������Ǐo�Ȃ����Ƃ�����܂��B �@���̂��߁A�Ǐo�Ă���ł͂��łɂ����̑���֓]�ڂ��Ă�����A��������������肵�Ă���\��������̂ł��B �u����v�͂ǂ�����Đi�s����H �@����́A�傫���Ȃ�Ȃ�قǐi�s�X�s�[�h�������Ȃ�܂��B �@�u���傫���Ȃ�v�Ƃ����̂́u����זE�̐�����������v�Ƃ������Ƃ��w���A�������זE�����Ȃ���u����v���傫���Ȃ��Ă������Ƃ������܂��B �@�����B����Ǝ��͑g�D�ւ̐Z���ɉ����A�S�g�ɓ]�ڂ��͂��߁A����̑��B��}����̂�����ɂȂ�܂��B�R����܂ł�������������Ă��A����זE�ɑϐ��������ꍇ�͍R����܂������Ȃ��Ȃ�A���B�X�s�[�h�������Ȃ�܂��B ���N���͐i�s�X�s�[�h���x���H �@�悭�u�Ⴂ�l�͂���̐i�s�������v�u���N���̂���̐i�s�X�s�[�h�͒x���v�ȂǂƂ����邱�Ƃ�����܂����A����͌��ł��B �@����̐i�s�X�s�[�h�́A���ł����ꏊ���ނɂ���ĈႢ�܂��B�݂����x����͔�r�I�i�s�������ł����A������͂��₩���Ƃ���Ă��܂��B �@�N��ɂ���Ă���̐i�s�X�s�[�h���ς�邱�Ƃ͂���܂���B����ŁA����ɂ́u�ᕪ���^����v�Ƃ����āA����זE���זE�Ƃ��Ă̋@�\�������Ȃ���Ԃłł��Ă�����̂Ɓu�������^����v�Ƃ�������זE��������x�זE�Ƃ��Ă̋@�\���c������Ԃłł��Ă�����̂�����܂��B �@����̐i�s���x�������̂́u�ᕪ���^����v�ł���A����͂��N�������Ⴂ�l�̂ق����ł��₷���X��������܂��B �@�܂��זE�������Z���̂ʼn��w�Ö@�ɂ悭��������ƌ����Ă��܂��B �@�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�N��ɂ���Ă���̐i�s�X�s�[�h�͕ς��킯�ł͂���܂���B �@���ł����Ă����������A�������Â��]�܂����̂ł��B OVO [�I�[���H] 2016�N11��13�� |
|
�咰���̓]�ڑ��i������ ���A���זE�̑�ӕ����I���R���^�{���C�gD-2HG |
| �@����w��11��8���A����זE�ŎY�������I���R���^�{���C�gD-2HG���咰����̓]�ڂ𑣐i���邱�Ƃ������Ɣ��\�����B���̌����́A����w��w�@��w�n�����ȏ�����O�Ȃ̃q���[�E�R���r����w�@����̌����O���[�v�ɂ����́B�������ʂ́A�p�Ȋw���uScientific
Reports�v�Ɍ��J���ꂽ�B �@�ߔN�̂���̌����ł́A�����`�q�₪��}����`�q�ُ̈�Ɗ֘A���āA����זE�̑�ӂ��A����̌`����i�s�ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����B �@�]��ᇂ┒���a�̍זE�ł́A�G�l���M�[��ӂɊ֗^����C�\�N�G���_�E���y�f�iIDH�j�̈�`�q���ψق��2-�q�h���L�V�E�O���^�[���_�i2HG�j����ʂɒ~�ς����B2HG�́A�זE������ւƓ����u����ᇐ���ӕ��i�I���R���^�{���C�g�j�v�Ƃ��Ēm���Ă���B���Ăł́AIDH�̍y�f������W�I�Ƃ��āA�I���R���^�{���C�g�̒~�ς�h�����Ƃɂ��A����̐i�s��}���鎡�Ö@���������֔�����A�ꕔ�͗Տ��������s���Ă���B����ŁA�t������i�t�זE����j�ł́AIDH�̈�`�q�ψق̕p�x���Ⴂ�悤�Ȃ���זE�ɂ��A���̃I���R���^�{���C�g�����ʂȂ��瑶�݂��Ă��邱�Ƃ�����Ă���B �@�咰����ɂ��Ă��A�זE���̂��܂��܂ȑ�ӎY���̔Z�x�Ɉُ킪�݂��邱�Ƃ��킩���Ă������A��ӎY���̔Z�x�ω����P�ɕa�C�̌��ʂƂ��ĕ\��Ă���̂��A���ꂪ����ɕa�C�̐i�s�𑣐i������������̂��ɂ��Ă͖��炩�ł͂Ȃ������B �@�����O���[�v�͍���A���N���E��70���l���S���Ȃ�ƌ����Ă���咰����ɂ��āA2HG�̖����ׂ��B���̌��ʁA�咰����̍זE�ɃI���R���^�{���C�g�ł���2HG���~�ς��Ă��邱�Ƃ��킩�����B�܂��A���̒~�ς���2HG�iD/L�ِ��́j�̂����AD�^��2HG�iD-2HG�j�́A�G�s�Q�m���i��`�q�̔�������j�̕ω���U�����āA���]�ԗt�]���iEMT�j�ɂ���Ď���̍זE�ɐZ�����A�����ɓ���A���ꂽ�g�D�ւ̂���]�ڂ������N�������Ƃ����o�����Ƃ��Ă���B �@����ɁA�Տ����̂��瓾��ꂽ����זE��p���āAIDH�̕ψق̂Ȃ��ꍇ�ł�D-2HG�̔Z�x���ʏ�̍זE�Ɣ�ׂč������ƁAD-2HG�̃��x���������قǂ���̃X�e�[�W���������u�]�ڂ��Ă���m�����������Ƃ��������B �@�����̌������ʂ���A����͈�`�q�̕ψقɉ����A����̑�Ӄ��J�j�Y���ɂ��œ_�Ă邱�Ƃɂ��A����]�ڂ̐V�����f�f�@�⎡�Ö@�̊J�������҂����ƁA�����O���[�v�͏q�ׂĂ���B m3.com 2016�N11��14�� |
|
���Ղ����R�ɂ���u��Õ⏕�^�g�D�v�Ŋ��Җ����x������ ����ᇂ̎�p�������҂� |
| �@�����p�łЂǂ����Ղ��c���Ă��܂������҂ł��A��Õ⏕�i�p�����f�B�J���j�^�g�D�ŏ��Ղ��B�����R�ȊO�ςɋ߂Â��邱�ƂŁA���҂̖����x�����シ��\�����A�I�����_�̌����҂ɂ����ꂽ�B �@���̊O�Ȏ�p��ɁA���ՂɈ�Õ⏕�^�g�D���{��������56�l��Ώۂɒ��������Ƃ���A���҂̑������{�p��ɊO�ςւ̖����x�����サ���Ƃ����B �@���������҂�1�l�A�}�[�X�g���q�g��w�i�I�����_�j���@��A�E���O�Ȃ�Rick van de Langenberg���́A�u����܂ň�Õ⏕�^�g�D�ɑ��銳�҂̕]���͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ��������A����̌����ŁA���҂͎{�p��ɏ��Ղ̊O�ςɂ��S���I�ȃX�g���X������A�Y�݂����邱�Ƃ��킩�����v�Əq�ׂĂ���B �@�č���ʌ`���O�Ȋw��iAAFPRS�j�̎�����ł���Fred Fedok���ɂ��ƁA��Õ⏕�^�g�D�́A�č��ł͊��ɐ��\�N�ɂ킽���čs���Ă���A�u���̋Z�p�́A�畆�ɐF�f�����ď��Ղ����R�ɂ݂��邱�Ƃ̂ł��镔�ʂł���A�ǂ��ɂł��p�����Ă���B�C�ɂȂ镔�ʂ̐F����������ΔZ������ȂǁA�����̏ꍇ�́A�畆�̐���ȐF�f�ɐ^����悤�ɐF������v�ƁA�����͏q�ׂĂ���B �@�܂��A�畆�Ȑ����Jessie Cheung���i�ăC���m�C�B�E�B���[�u���b�N�j�́A��Õ⏕�^�g�D�͓������p��̏������҂ōł��悭�s���Ă���A���[�S�E�����[�Č��p�̍ۂɁA���֎��ӂ̔畆�̐F�ɑ����a�������P�ł���Ƃ��Ă���B �@����̌����ł́A����ᇂւ̊O�Ȏ�p�������҂ɒ��ڂ��A2007�`2015�N�ɃA���X�e���_���̕a�@�ň�Õ⏕�^�g�D�̎{�p����56�l�̊��҂�Ώۂɒ������s�����B���҂̕��ϔN���56.6�ŁA75���������������B �@�{�p��̂Ȃ��ɂ́A��p�ɂ��F������ꂽ���O�ɐԐF�������P�[�X��A�Ɏc�����������Ղ̐Ԃ݂��B�����߂Ƀ^�g�D���{�����P�[�X�Ȃǂ��݂�ꂽ�B �@�Ώۊ��҂ɁA�{�p�O��̊O�ςɑ��閞���x��0�`10�_�ŕ]�����Ă�������Ƃ���A���σX�R�A�͎{�p�O��3.8����{�p��ɂ�7.8�܂Ō��サ���BLangenberg���ɂ��ƁA�{�p��ɂ͊��҂̑S�ʓI�Ȗ����x��QOL�����サ���Ƃ����B �@��Õ⏕�^�g�D�̓K���ƂȂ銳�҂ɂ��āACheung���́A�畆�ɉ��ǂ��Ȃ�����͂ǂ̂悤�ȕϐF���{�p�̑ΏۂɂȂ�Ɛ������Ă���B��p�ɂ��ẮA�Č��p�̈ꕔ�ł���ꍇ�ɂ͕ی��K�p�ɂȂ�Ƃ����B�ꎞ�I�ȐԂ݂��o��i���Ёj�̌`���A�����ǂȂǂ̕���p���l�����邪�A�u�������������ǂ�������邽�߂̏��Ղ̃P�A�ɂ��āA���҂͐�������͂����v�Ɠ����͏q�ׂĂ���B �@����ŁAAAFPRS��Fedok���ɂ��ƁA�قƂ�ǂ̊��҂͈�Õ⏕�^�g�D�̑��݂�m�炸�A�畆�Ȉ��`���O�Ȉ�����̑����̓^�g�D�{�p�̒m�����������킹�Ă��Ȃ��Ƃ����B�^�g�D�{�p�ɂ́A���ʂȌP���ƌo�����K�v�Ƃ���邪�A�����̏ꍇ�́A���Ղ�����Č��̌o���L�x�ȃ^�g�D�{�p�t�Ƌ��͂��Ă���Əq�ׂĂ���B �@�畆�Ȉ��Terry Cronin���i�t�����_�B�����{�����j���A�u�畆�Ȉ��`���O�Ȉ�̑����́A�p�[�}�l���g���C�N�A�b�v��p�����f�B�J���^�g�D����Ƃ�����e�A�[�e�B�X�g�ƘA�g���Ă���v�Əq�ׂĂ���B �@���̌����́A�uJAMA Facial Plastic Surgery�v�I�����C���ł�9��22���f�ڂ��ꂽ�B m3.com 2016�N11��16�� |
|
1��1���̋i���Ŕx�ɔN��150�̈�`�q�ψ� 5,000��ȏ�� |
| �@�i���͔x�₻�̑��̑���̒�������`�q�����Ɋ֘A���邱�Ƃ��A�ă��X�A�����X�����������i�j���[���L�V�R�j��Ludmil Alexandrov����̌����ł킩��A�_�����uScience�v11��4�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@������̌����O���[�v�́A�i���҂Ɣ�i���҂̂���5,000��ȏ�͂����B����͍זE��DNA�̓ˑR�ψقɂ�萶���A�^�o�R�̉��ɂ͂���������N�������Ƃ��킩���Ă���70��ވȏ�̉��w�������܂܂��B�i���Ƃ���̊֘A�������u�w�I�G�r�f���X�͑������݂��邪�A����̌����ł́A�i���ɂ��DNA�̕��q�̕ω����ώ@���A��ʉ������Ƃ����B �@���̌��ʁA1��1���̃^�o�R���z���l�ł́A�x�ɖ��N����150�̗]��ȓˑR�ψق��N���邱�Ƃ����������B����ɂ��i���҂̔x���ǃ��X�N���������R�̐��������B�g�̂̑��̕����̎�ᇂɂ��A�i���Ɋ֘A����ˑR�ψق��݂�ꂽ�B���Ƃ��A1��1���̋i���̏ꍇ�A�A�����̍זE�ł͔N�ԕ���97�A�����ł�39�A���o�ł�23�A�N���ł�18�A�̑��ł�6�̓ˑR�ψق��N����B �@Alexandrov���́A�u����̌����́A�i��������������N�������@�ɂ��ĐV�������@�������炷���̂��B�����̕��͂́A�i���������̕ʌ̃��J�j�Y���ɂ��A����ɂȂ���ˑR�ψق������N�������Ƃ��������B�^�o�R�̉��́A���ڔ��I����鑟���DNA�����邾���łȂ��A���ړI�E�ԐړI�ɔ��I����鑟��ōזE�̓ˑR�ψق̑��x�𑁂߂�v�Əq�ׂĂ���B �@�č����a�Ǘ��\�h�Z���^�[�iCDC�j�ɂ��A���E�ł̓^�o�R�������ŔN��600���l�ȏオ���S���Ă���B�ȑO�̌����ł́A�i���Ə��Ȃ��Ƃ�17��ނ̂��֘A���邱�Ƃ�������Ă���B m3.com 2016�N11��17�� |
| �̑�����ɂ��u���ː����Áv �Ǐ����䗦9���ȏ� |
| �@�̑�����ɂ͎�p��W�I�g�Ďp�A�̓����ǐ�Ö@�Ƃ����������I���Â�����B�̑��̗̈�ł͏o�x��Ă������ː����Â��Z�p���i�����A�傫�Ȃ�������ŁE�k��������ȂǁA���Â̑I�����ƂȂ��Ă����B �@�ʏ킪���3�厡�ÂƂ����Ύ�p�A�R������ÁA���ː����Â��B�������̑�����̏ꍇ�A��p�A���W�I�g�Ďp�A�̓����ǐ�Ö@�ƂȂ��Ă��āA���ː����Â��܂܂�Ă��Ȃ��B �@�}�g��w�a�@�z�q�����ÃZ���^�[�����̟N��p�K��t���������B �u�̑��͕��ː����������B�܂�_���[�W���₷������ł��B���ÂɕK�v�Ȑ��ʂ��Ǝ˂���Ɛ���ȑg�D�������Ă��܂����߁A�̑�����ł͕��ː��͍����I�Ȏ��ÂłȂ��A�Ǐ�ɘa�̏�ʂȂǂŎg���Ă��܂����v �@�̑����̂���͌ċz�ƂƂ��ɓ������߁A�s���|�C���g�ŏƎ˂��邱�Ƃ͓�������B�������ߔN�A�啝�ɉ��P���ꂽ�B �u�G�b�N�X�����Ë@��̐i���͖ڊo�܂������̂�����܂��B����f���I�����^�C�~���O��҂��������ďƎ˂���Z�p��A�^�[�Q�b�g��ǔ����ďƎ˂��邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂����B�܂��G�b�N�X�����W�߂ăs���|�C���g�ŏƎ˂����ʏƎ˂̋Z�p�ɂ���āA�K�v�Ȑ��ʂʂȂ���ᇂɂ��Ă邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����v�i�N���t�j �@���݂́A5�Z���`�܂ł̔�r�I���^�ŁA�����̊̍זE����Ȃ�Εی��K�p�ƂȂ�B�ʏ�A���Â�4�`5��ʉ@���A�Ǝ˂��s���B���ː����Ì�ɂ��Ĕ����Ȃ������i�Ǐ����䗦�j��9������B���W�I�g�Ďp���s���Ȃ��A���ǂ�x�ɋ߂��a�ς��A�悢�K���Ƃ���Ă���B �u��ʏƎ˂̃����b�g�͖��ɂȂ��Ƃł��B����҂ⓜ�A�a�Ȃǂ̎��a������l�́A�̂̕��S�����Ȃ����ː����Â��I�����ɑg�ݓ���čl���Ăق����v�i���j �@��ʏƎ˂���^�⑽���̂���ɓK���Ȃ����R�̓G�b�N�X���̓����ɂ���B�G�b�N�X���͕a�ςɏƎ˂��ꂽ��A�ʉ߂��Ă����B�����A���^�Ȃ�Ήe�������Ȃ����A�Ǝ˔͈͂��傫���Ȃ�ΐ���g�D�ɔ����Ă������ː��������Ȃ�B���̎�_����������̂��z�q����d���q�����B �u�z�q���E�d���q���̓^�[�Q�b�g�̕a���ɍł��������ʂ�������A�����Ŏ~�܂�܂��B�a�����̐��ʂ̓[���B������͂̐���g�D�̔픘����������̂ł��B��ʏƎ˂ł̓G�b�N�X���̒ʉ߂��l�����A�Ǝː��ʂ�}���܂����A�z�q���E�d���q���ł͐��ʂ��\���ɂ����邱�Ƃ��ł��܂��v�i���j �@�z�q���E�d���q���ł�����̌��͎O�܂łƐ���������B�������A�傫���͊�{�I�ɖ������B�̑��̕Б������ς��ɍL�����Ă���悤�ȏꍇ�ɂ��Ή��\���B �@�����s�ݏZ�̈��r�V����i�����E60�j��2�N�O�̌��N�f�f�Ŋ̋@�\�̐��l�̈������w�E����A���������Ƃ���A�摜�ɂ͊̑��̉E����苒��������Ȏ�ᇂ��f���o���ꂽ�B�f�f�͊̍זE����B���̈ꕔ�͖喬�ɐZ�ݍ��݁A�̑��O�ɂ��L�����Ă����B �@�K���̋@�\�͗ǍD���������߁A��p�Ŋ̑���4����3��؏����A�p��d���ɕ��A�ł����B�������A5�J����A�c���ꂽ�̑��ɂ��Ĕ������B�Đ؏��͓���A�̓����ǐ�Ö@���s�������A4�J����ɂ܂��Ĕ��B���Ǔ��ɂ�����͐Z�����Ă���A�ǐ�Ö@�̎��{������������B��コ��͒}�g��w�a�@�z�q�����ÃZ���^�[�̔������������B �u��p�Ő؏������f�[�߂��Ɏ�ᇂ�����A�̑������Ɍ������Č��Ǔ���8�Z���`�ɂ킽���ĐZ�H���Ă��܂����B�����K���ɂ��c�̂��Đ����A�̋@�\���c���Ă��܂����v�i���j �@��コ���20�Z���^�[�ɒʉ@���A���v66�O���C�̗z�q�����Â��s�����B���̌��ʂ���͏��ŁB���Ò��A���Ì�͕���p���Ȃ��A�̋@�\�����肵�Ă���B �u�܂��Ĕ��̐S�z������܂����A�W�����Â�����ƌ����Ă���1�N���A�[�������������߂�����Ă��܂��B���҂���ɂ́A�Ƃɂ����I�����𑽂������Ăق����B�Z�J���h�I�s�j�I���ŗ��Ă����������Ƃ���̕��@���Ǝv���܂��v�i���j dot.�h�b�g 2016�N11��21�� |
|
�זE����������V��`�q���� ��B���A�uGRWD1�v��p53�^���p�N���ʂ����������������i |
| �@��B��w��11��18���A�זE����������V���������`�q�uGRWD1�v�𐢊E�ŏ��߂Ĕ��������Ɣ��\�����B���̌����́A����w��w�����@���זE�����w����̓��c��r�����A����w���̖h���w�������̒��R�h�ꋳ���A���������Z���^�[�������̐��쓧���쒷��̌����O���[�v�ɂ����́B�������ʂ́A���q�����w��uEMBO Reports�v��11��17���t���ŃI�����C���f�ڂ���Ă���B �@����זE�ɂ����ẮAp53�ƌĂ��זE���B�́g�u���[�L�h���ł���^���p�N���ُ̈킪�p�ɂɋN�����Ă��邱�Ƃ��m���Ă���B����������ŁAp53�Ɉُ�̂Ȃ����҂��������݂��Ă���B �@����ɑ����Ă���זE���ł́Ap53�^���p�N����MDM2�Ƃ����^���p�N���̓����ŕ�������Ă���B�זE���ُ�ȑ��B�h����DNA�_���[�W�Ȃǂ̃X�g���X�ɎN���ꂽ�ꍇ�ARPL11�Ƃ����^���p�N����MDM2�Ɍ��������̋@�\��}����B���̌��ʁAp53�ʂ��������A�זE�̑��B���~�߂Ĉُ���C��������A�C��������Ȃ��ꍇ�͍זE�����E�����A����h���ł���B �@�����O���[�v�͍���AGRWD1��RPL11�Ƃ����^���p�N���Ƃ̌��������p53�^���p�N���ʂ����������A�זE�̂��𑣐i�����邱�Ƃ����߂Ė��炩�ɂ����B����ɁA���҂̃f�[�^�x�[�X�̉�͂���A�������̂���̎�ނɂ����ẮAGRWD1�^���p�N���ʂ̑����͂���̈����x���㏸�����A�\��s�ǂ̗\�����q�ƂȂ蓾�邱�Ƃ������Ƃ��Ă���B �@����̌����̔��W�ɂ���āAGRWD1���������ɂ�邪�Õ��j�̂��K�Ȍ����AGRWD1��W�I�Ƃ���V���ȍR����܊J���ɂȂ��邱�Ƃ����҂����ƁA�����O���[�v�͏q�ׂĂ���B m3.com 2016�N11��24�� |
|
����Â�AI���p�� ������A5�N��Ɏ��p����ڕW |
| �@���������Z���^�[�i������j�A�l�H�m�\�i�`�h�j�Z�p�J���̃x���`���[�ł���v���t�@�[�h�E�l�b�g���[�N�X�i�o�e�m�A�����s���c��j�A�Y�ƋZ�p�����������͂Q�X���A�`�h�Z�p�����p���������ÃV�X�e���̊J���v���W�F�N�g���n�߂�Ɣ��\�����B�����ۗL����c��ȗՏ��f�[�^��}���`�I�~�b�N�X�f�[�^�Ȃǂ����p���ă��f�B�J���`�h�Z�p���J�����A����̎������J�j�Y���̉𖾂�f�f�A���ÁA�n��Ȃǂɉ��p���Ă����B�T�N���ڕW�Ɏ��p����ڎw���B �@���{�ōŐ�[�̂������s���Ă��鍑����ƁA�����̂`�h��������[�h����o�e�m�A�Y�������A�g���āA�v�V�I�Ȃ����ÃV�X�e���̊J���Ɏ��g�ށB�܂������~�ς��Ă����Տ��A�u�w�f�[�^�A�Q�m���E�G�s�Q�m�����A�摜���A���t���̂�זE�Ȃǂ������f�[�^�x�[�X���\�z����B�o�e�m�ƎY�����E�l�H�m�\�����Z���^�[�̐[�w�w�K�i�f�B�[�v���[�j���O�j�E�@�B�w�K�Z�p��p���ăf�[�^����͂��A����̐V���Ȑf�f�V�X�e���A�n��v�V�X�e���A�ʉ���Î����x���V�X�e���Ȃǂ��J������B �@�v���W�F�N�g�́A�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̐헪�I�n���������i���Ɓi�b�q�d�r�s�j�́u�C�m�x�[�V�����n���Ɏ�����l�H�m�\��ՋZ�p�̑n�o�Ɠ������v�����Ƃ��Ď��{�����B�ő�łR���W�O�O�O���~�̏������錩���݁B�b�q�d�r�s���Ƃŋ��߂��Ă���Q�N�S�J����܂łɂo�n�b�i�T�O���j���擾���A�T�N����߂ǂɎ��p����ڎw���B �@������̊Ԗ씎�s���������͋L�҉�ŁA�`�h�Z�p����Õ���ɉ��p���錤�������{�͊C�O���x��Ă��邱�Ƃ��w�E���������ŁA�u�x�X�g�E�I�u�E�x�X�g�̕��X���W�܂����B���{�̎��b�q�����W���Đ��E�ɔ��M���Ă��������v�ƈӗ~��������B�܂��A���{�̗D��Ă���_�Ƃ��ĕi���̍����Տ��f�[�^�A�摜�f�[�^�Ȃǂ��L�x�Ȃ��Ƃ������A���̃f�[�^���f�B�[�v���[�j���O�����邱�ƂŐ��x�̍�����ÃV�X�e�����\�z�ł���Ƃ̊��҂��������B m3.com 2016�N11��30�� |
|
���{�b�g�x���t�����؏��p�ŗD�ꂽ���p���]�A ���o���E�J����p�ւ̈ڍs�A�����ǁA�f�[�z���̃��X�N���Ⴂ |
| �@���o�����t�����؏��p�ɔ�r���āA���{�b�g�x���t�����؏��p�͗D�ꂽ���p���]�A��������Ƃ̃��^��͌��ʂ��A�uThe
Journal of Urology�v11�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@�V���K�|�[���A�^���g�N�Z���a�@��Jeffrey J. Leow����́A�t�����؏��ɂ����郍�{�b�g�x����p�ƕ��o������p�̓]�A���r���镶�����r���[�����{�B25���̌������犳��4,919�l�̃f�[�^��ΏۂƂ����i2,681�l�����{�b�g�x����p�A2,238�l�����o������p���Ă����j�B �@���̌��ʁA���{�b�g�x����p�������҂́A��ᇂ��傫���AR.E.N.A.L. nephrometry�X�R�A�iRNS�j�̕��ϒl�������X�����݂�ꂽ�B�܂����{�b�g�x����p�������҂́A���o������p�������҂ɔ�ׂāA���o������p�܂��͊J����p�ւ̈ڍs�i���X�N��mRR�n0.36�j�A�����ǂ���ю�v�����ǁi���ꂼ��RR 0.84�A0.71�j�A�f�[�z���iRR 0.53�j�̃��X�N���Ⴍ�A���������Ԃ�4.3���Z�������B��p���ԁA����o���ʁA�p��̐��莅�����h�ߗʂ̕ω��́A���Q�œ����x�������B m3.com 2016�N12��7�� |
|
���[�Č��͍�����ɂ����b�������炷 ��N���҂ɔ�ׂč����ǃ��X�N�͏㏸�����A�։v�������x |
| �@���[�؏��p��������̓����҂́A�Ⴂ�����Ɠ��l�ȓ��[�Č��ɂ��x�l�t�B�b�g���邱�Ƃ��A�V���������Ŏ����ꂽ�B�����̔N��͏p�㍇���ǂ̃��X�N�ɉe�����y�ڂ��Ȃ��������Ƃ���A�����O���[�v�͎�p�̓K����N����Ŕ��f���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ��Ă���B �@����̌����́A�č�����уJ�i�_�œ��[�؏��p��ɓ��[�Č�������������1,500�l�ȏ��ΏۂƂ������́B�Ώۊ��҂̂���45�Ζ�����494�l�A45�`60��803�l�A60�Β��̍������234�l�ł������B �@���̌��ʁA�Č��������[�ւ̖����x�́A��p�O�̓��[�ɑ��閞���x�Ɣ�ׂ�45�Ζ����Q�A45�`60�ΌQ�ł͓������������A60�Β��Q�ł͂��Ⴂ���x�ł������B �@�܂��A���Ҏ��g�̑g�D��p�����ꍇ�ɔ�ׂāA�C���v�����g�ɂ����[�Č������ق����p�㍇���ǂ̔��Ǘ��͒Ⴉ�����B�����ǂ̔��Ǘ��́A�C���v�����g���g�p�����ꍇ��45�Ζ����Q�ł�22���A45�`60�ΌQ�ł�27���A60�Β��Q�ł�29���ł���A���Ƒg�D�ɂ��Č��̏ꍇ�͂��ꂼ��33���A29���A31���ł������B �@���̒m���́A�uJournal of the American College of Surgeons�v�I�����C���ł�10��26���f�ڂ��ꂽ�B �@���҂�1�l�ł���ă~�V�K����w�w���X�V�X�e���`���O�ȋ�����Edwin Wilkins���́A�u�O�Ȉ�����҂��A������ɓ��[�Č����s���̂͂悢�I�����ł͂Ȃ��Ƃ�������ς�����Ă��邩������Ȃ����A����̒m������A����̏����ł����[�Č��ɂ����QOL��g�̃C���[�W�����シ��\��������A�܂��A����͗L�ӂȍ����ǂ̃��X�N���q�ł͂Ȃ����Ƃ������ꂽ�v�Əq�ׂĂ���B �@������ɂ��ƁA�č��ł�2016�N�ɓ�����Ɛf�f���ꂽ���҂�25���l�߂��ɏ��A���̂�����4����62�Έȏオ��߂�Ɨ\������Ă���B�����Â̂��߂ɓ��[�؏��p���鏗���͂���10�N�Ԃő������Ă��邪�A���[�Č�����͎̂�N�̏�����������҂ŏ��Ȃ��Ƃ����B m3.com 2016�N12��8�� |
|
���������͎q�{����̗\��ɉe�����Ȃ� �]�ڂ̊댯���q�̓X�e�[�WIIB�A�Ԏ��Z���A�����p�ߓ]�� |
| �@�����̎q�{�B�����҂ŁA���������͐������ɉe�����y�ڂ��Ȃ��Ƃ̌������A�uAmerican
Journal of Obstetrics & Gynecology�v10�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@�����A�ؒ��ȋZ��w��Jing Chen����́A�q�{�B���̏���194�l��ΏۂɌ��������������{���A���������̗\��ւ̉e�������������B159�l�ŒǐՂ��������A������������33�l�Ɨ������Ǘ����E�o�p����126�l���r�����B �@���̌��ʁA�������Ǘ����E�o�p�Q�Ɨ��������Q�ŁA�������ԂɗL�Ӎ��͔F�߂��Ȃ������i���a��������P��0.423�A�S��������P��0.330�j�B���a�������Ԃ̈����ƗL�ӂɊ֘A����Ɨ������\����q�́A��ᇃT�C�Y�i4 cm�ȏ�j�A�[���Ԏ��Z���A�����p�ߓ]�ڂł���A�����p�ߓ]�ڂ͑S�������Ԃɂ����ւ����B �@�������Ǘ����E�o�p����153�l�ɂ����āA�����]�ڂƐ[���Ԏ������A�����p�ߓ]�ځA�q�{�T�g�D�Z���Ƃ̊W�ɗL�Ӎ����F�߂�ꂽ�B�����̃��^��͂ł́A�Տ��a����I�`IIA�ɑ���IIB�ł��邱�ƁA�[���Ԏ��Z���A�����p�ߓ]�ځA�q�{�̕��Z���A�q�{�T�g�D�Z�����A�����]�ڂɑ��ւ��Ă����B m3.com 2016�N12��8�� |
| ����]�ڂƎ��b�ێ�̊֘A���A�}�E�X�����Ŋm�F ���� |
| �@����̓]�ڂ�j�~������@���A�}�E�X�����Ŕ��������\��������Ƃ̌����_����7���A���\���ꂽ�B�_���\�����X�y�C���̌����`�[���ɂ��ƁA����̓]�ڂ͎��b�̐ێ�Ɋ֘A���Ă���\��������Ƃ����B �@�p�Ȋw���l�C�`���[�iNature�j�ɔ��\���ꂽ�_���ɂ��ƁA�X�y�C���E�o���Z���i������w�������iIRB�j�Ȃǂ̌����`�[���́A����킩�瑟��ւƊg�U������^�C�v�̎�ᇁi����悤�j�זE�������Ƃ����B�]�ڂƂ��Ēm���邱�̃v���Z�X�́A����̒v������傫�����߂錴���ƂȂ�B �@�܂������`�[���́A���̎�ᇍזE���uCD36�v�ƌĂ���e�̂������Ƃ𖾂炩�ɂ����BCD36��e�̂ɂ��ẮA���b�̐ێ�߂��邱�Ƃ��m���Ă���B �@�l�̎�ᇂ��ڐA�����}�E�X��p���������ł́ACD36��e�̂�j�Q����R�̂𓊗^���邱�ƂŁA�]�ڂ��u�L�ӂɌ��������v�ƌ����`�[���͏q�ׂĂ���B���̕��@�ł́A�l�̌��o�i���������j����A�畆����A������ȂǂɌ��ʂ��݂�ꂽ�B �@�����`�[���́A�ꕔ�̃}�E�X�œ]�ڍזE�����S�ɏ��ł������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ȃ���A�u���̂悤�Ȃ��Ƃ́A����I�ɋN������̂ł͂Ȃ��v�Ɨ͐������B �@����ɁACD36��e�̂��L�x�ȍזE�����}�E�X�ɍ����b�̉a��^����lj������ł́A��`�q�I�ɋ߂��}�E�X�ɕ��ʂ̉a��^�����ꍇ�ɔ�ׂāA�]�ڂ̔��ǐ��������A�]�ڂ̋K�͂��傫���Ȃ����ƁA�����`�[���͐������Ă���B �@�]�ڂ́A����זE����ᇂ��痣��A���t����p�n��ʂ��Ĉړ����A�̂̕ʂ̕��ʂɐV���ȃR���j�[���`�����邱�ƂŔ�������B�����`�[���ɂ��ƁA���̖�90���́A�]�ڂ������ŋN����Ƃ����B �@����זE�̂��ׂĂ��]�ڂ�����킯�ł͂Ȃ��B�]�ڂ��N��������זE����肵�ĎE���ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��A�����̍ŗD�掖���̈�ɂȂ��Ă���B �@����̍ŐV�̌������ʂɂ��ACD36�͍R����܂̗L�͂ȕW�I���ƂȂ�ƌ����`�[���͎w�E�����B ���x������ �@�����𗦂���IRB�̃T���o�h�[���E�A�X�i�[���E�x�j�^�[�iSalvador Aznar Benitah�j���́AAFP�̎�ނɁu�����̌����������I�ɁA��ᇂ��]�ڂ��N�������R�Ǝd�g�݂Ɋւ��闝���̌���Ɋ�^���邾���łȂ��A�]�ڍזE���U��������@���l�Ă��邽�߂̐V���Ȉ���ƂȂ邱�Ƃ����҂��Ă���v�Ƙb���B �@�x�j�^�[���́A��ނɉ������d�q���[���Łu���݂́A�l�ɓ��^���邽�߂̐V���ȎՒf�R�̂̊J����i�߂Ă���B���̎Ւf�R�̂ɂ��ẮA���҂ւ̗Տ��������r�I�Z���ԁi4�`10�N�j�Ŏ����������ƍl���Ă���v�Ɛ��������B �@���̏�ŁA����̓]�ڂɂ����鎉�b�ƐH���̖����������邽�߂ɂ́A����Ɍ������d�˂�K�v������Əq�ׁA�u�����A����̌��ʂ��x������ł��邱�Ƃ͊m�����B�H���Őێ悷�鎉�b�_�ɑ��āA�]�ڍזE���ɂ߂č������������Ƃ��A����̌��ʂ����������Ă���v�Ƒ������B �@���҂͒ʏ�A���Âɂ��̂ւ̕��S�ɑΏ����邽�߁A�����̃J�����[��K�v�Ƃ���B���̂悤�ȗ��R������A����̌������ʂɂ͐T�d�ȑԓx�ŗՂޕK�v������Ƃ̐�������ł͏オ���Ă���B AFPBB News 2016�N12��8�� |
|
�����]��ᇂ̐V���Ö@���J�� ���É��s��A�^�[�Q�b�g�́u������|��RNA�v |
| �@���É��s����w��12��1���A�^���p�N���ɖ|��Ȃ�RNA�̂����g������|��RNA�h�ƌĂ��RNA���^�[�Q�b�g�Ƃ������Ö@���A�����]��ᇂɗL���ł���\����|�{�זE��}�E�X��p�����������疾�炩�ɂ����Ɣ��\�����B���̌����́A�����w�@��w�����Ȉ�`�q����w����̋ߓ��L�����Ə����[�C������̌����O���[�v���A���É���w�A������w�A�i�m��ÃC�m�x�[�V�����Z���^�[�A���������Z���^�[��������Ƃ̋����ōs�������́B���������ʂ́A�p�Ȋw�G���uNature
Communications�v�i�d�q�Łj��12��6���t�Ōf�ڂ���Ă���B �@����� �g���זE�h�Ƃ���ɗR�����鑽�l�Ȃ���זE���琬�邪�A���זE�̍��o�����̑g�D���l���́A���Â�����ɂ��Ă������ƂȂ��Ă���A���זE�����ł�������@���K�v�Ƃ���Ă����B���זE���������g���ێ�����ߒ��ɂ́A�g�G�s�Q�m���h �ƌĂ��V�X�e���ɂ���`�q��ON�^OFF�̒��߂��d�v�Ȗ������ʂ����Ă���B�G�s�Q�m���ɂ��ON�^OFF���߂ɂ̓^���p�N���ɖ|��Ȃ�RNA�ł���g������|��RNA�h���[���֗^���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��Ă����B �@�]��ᇂ̂ЂƂł���O���I�u���X�g�[�}�i�P���j�́A�]��ᇂ̒��ōł����p�x�ɔ������邫��߂Ĉ����x�̍�����ᇁB���݁A���̎�ᇂɑ���L���Ȏ��Ö@�͂Ȃ��A�V�������Ö@�̊J�������߂��Ă���B����̌����ł́A�q�g�]��ᇂ��炪�זE���쐻���A���זE�̈ێ��ɂ�����钷����|��RNA�̖����ɂ��ďڍׂɉ�́B���̌��ʁA������|��RNA�̂ЂƂł���uTUG1�v�ɂ��A���זE���ێ�����Ă��邱�Ƃ𐢊E�ŏ��߂Ė��炩�ɂ����Ƃ����B �@���ɁA�g�RTUG1�Ƃ��ē�����܁iTUG1�̋@�\�������I�ɗ}���邱�Ƃ��ł����܁j�h���쐻���A���זE���ڐA�����}�E�X��p���āA���Ö�Ƃ��Ă̗L�����ɂ��ĉ�͂����B�L���Ȃ��Ö���J�����邽�߂ɂ́A��܂����݂̂ɑ���͂���K�v������B�����œ������ł́A�i�m��ÃC�m�x�[�V�����Z���^�[�Љ��ꑥ�Z���^�[���A������w�{�c����Y�y�����̋��͂̂��ƁA��܂����݂̂ɓ͂��邱�Ƃ��ł���g�^�щ��h�ƍRTUG1�Ƃ��ē�����܂�g�ݍ��킹�����Ö�iTUG1-DDS�j���쐻�B����TUG1-DDS��p���邱�Ƃɂ��A�RTUG1�Ƃ��ē�����܂����݂̂ɑ��B���邱�Ƃɐ����B�����TUG1-DDS�ɂ�鎡�Â��L���ȍR��ᇌ��ʂ��������Ƃ��m�F�����Ƃ����B �@���̌����ɂ����ĊJ������TUG1-DDS�́A�P���ɑ���L�]�Ȏ��Ö�ɂȂ邱�Ƃ����҂����B�����O���[�v�́A����A����ɓ����Ö@�ɂ��ĕ���p�����܂߂���͂�i�߁A���S���Ɋւ��鎎�����s���ATUG1-DDS�̎��p����ڎw���Ƃ��Ă���B m3.com 2016�N12��9�� |
|
�u�}�W�b�N�}�b�V�����[���v�ł��҂̐�]�����ɘa �}����s�������J���ɂ킽��ጸ |
| �@���҂͂����A�����Ă��Ă��Ӗ����Ȃ��Ƃ�����]���iexistential distress�j�ɏP���邱�Ƃ�����B�V����2���̏��K�͌����ŁA���o��p�̂���u�}�W�b�N�}�b�V�����[���v�Ɋ܂܂�鐬���V���V�r���ɂ��A���̂悤�Ȋ�����I�ɉ��P����邱�Ƃ������ꂽ�B�����ɎQ���������҂�1�l�́A�V���V�r���p����Ɓu�_�̈��ɕ�܂ꂽ�v�Ɗ����A���̌�����|��s���͏������܂܂������ƁA�L�҉�Řb���Ă���B �@�������A�V���V�r���͕č��������ǁiDEA�j�ɂ��ł��댯�ȁg�X�P�W���[��1�h�Ɏw�肳����@�ł��邽�߁A��t���g�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�uJournal of Psychopharmacology�v12�����Ɍf�ڂ��ꂽ�������̕t���_�������M�����ăR�����r�A��w��ÃZ���^�[�i�j���[���[�N�s�j��Craig Blinderman���́A�u��K�͌����ō���̌��ʂ����Â�����A�V���V�r���̕��ނ���t���g�p�ł���g�X�P�W���[��2�h�ɕύX���邱�Ƃ��������ׂ��ł���v�Əq�ׂĂ���B �@�ăj���[���[�N��w�iNYU�j�����S����ÃZ���^�[��Stephen Ross �������������̌����ł́A����29�l��ׂ�2�Q�Ɋ�����A�V���V�r���܂��̓r�^�~���܂�1�^�����B�V���V�r���𓊗^�������҂�80���ɋ}���ȋ�ɂ̊ɘa���F�߂��A�s������ї}���̌����X�R�A�ɂ��A���̌��ʂ�6�J�����������B �@���̌����ł́A�ăW�����Y�E�z�v�L���X��ȑ�w�i�{���`���A�j�̌����O���[�v���A�����Ɋւ�邪��ɜ늳���鐬�l51�l�ɒ�p�ʂ̃V���V�r���𓊗^���A5�T�Ԍ�ɂ���ɍ��p�ʂ𓊗^�����B���̌��ʁA�قƂ�ǂ̊��҂̕s����}�����y�����A6�J�����ʂ��������ƁA�����𗦂�������w������Roland Griffiths���͏q�ׂĂ���B������̌������P�������Ď����ɂ��Ǘ��̉��Ŏ��{���ꂽ�B �@�t���_���̋����҂ŕăj���[���[�N�v���X�r�e���A���a�@�̐��_�Ȉ�ł���Daniel Shalev���́A��@�̌����͓�����A���̗L�p�������������Ǝw�E���Ă���BNYU�̌����O���[�v�͌��݁A��K�͂ȑ�3�������̎��{�ɂ���FDA�̏��F��҂��Ă���i�K���Ƃ����B�W�����Y�E�z�v�L���X��w�̌����ɎQ�������ʂ̔팱�҂́A�L�҉�Łu�V���V�r���p����ƁA�Â��_�����ꂽ�悤�������B�Ƒ���q�ǂ������ƍēx�Ȃ��邱�Ƃ��ł��A�������т����߂����v�ƌ���Ă���B m3.com 2016�N12��13�� |
|
������ʂł��g�������h�Ȃ�A�������ቺ �ʌ��@�\���� ���R�ɔ�����������Ɣ���ɋN�����邪��̎��ʂ̌��� |
| �@�ʎq�Ȋw�Z�p�����J���@�\���ː���w�����������̊`���u�Îq������́A���ː��̔���̑��ʂ������ꍇ�A�Z���Ԃň�x�ɔ��������A�����������Ԃ̔���̕�������������Ƃ��邪��̔����m�����Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B����������Ƃ��邪��Ǝ��R�������邪�����`�q��͂ŋ�ʂł������ȃ}�E�X���g���A�K���}���Ǝˌ�̂���̔������𖾂ɂȂ����B �@����A������t���ȂǕ����̑���̂���ɂ��ă}�E�X��b�g�Ŏ������邱�Ƃɂ��Ă���B�f�[�^��~�ς��A���ː�����ɂ�锭����ւ̉e���̉𖾂����҂����B �@�`��������́A�זE���B�Ɋւ���`�q�u�o�������i�s�b�`�j�P�v�ɒ��ڂ����B�����s�b�`�P�̂����Е����ُ�ɂȂ����u�s�b�`�P��`�q�w�e�������}�E�X�v�͏��]����ǂ��₷���B �@���R�������邪��ł̓s�b�`�P����Ƃ��ُ�A���ː�����ɂ�邪��ł͐���ȃs�b�`�P�̌������m�F����Ă���B�}�E�X�̕��ː��Ǝˌ�ɂ���g�D���̎�B�s�b�`�P�̏�Ԃ���`�q��͂��A����̌����ׂ��B �@���̃}�E�X�̐��㒼��ɃK���}�����Ǝ˂��A����T�O�O���܂łɔ�����������̔������ׂ��B���ʂT�O�O�~���V�[�x���g�����̃K���}�����P�����x�Ǝ˂����ꍇ�A�}�E�X�̂U�U��������ǁB���̂����A���R�����̂��R�Q���A����ɂ�邪�R�S���ƂȂ����B �@����A�ŏI�I�Ȕ���ʂ������ɂȂ�悤�ɒ���ʂ̃K���}�����S���Ԃ����ďƎ˂����ꍇ�A����̔��������T�T���Ŕ���ɂ�锭���͂P�U���ɂȂ邱�Ƃ����������B �@���ʂ͕ĉȊw�����f�B�G�[�V�����E���T�[�`�d�q�łɌf�ڂ��ꂽ�B �����H�ƐV�� 2016�N12��15�� |
|
��p���Ɋ��זE��pH�Z���T�[�Ŏ��ʁy�č����w��z ����88���A���ِ�90�� |
| �@����p�ɂ����鐳��g�D�̉ߏ�Ȑ؏�����g�D�̎��c���ɔ����Ď�p�͊��҂ɂƂ��ċɂ߂đ傫�ȕ��S�ƂȂ�B���̂��ѐV���ɊJ�����ꂽ����p�̍ۂɁA����g�D�Ǝ�ᇑg�D�������x�Ɏ��ʂ��邽�߂̌��t�@�C�o�[pH�Z���T�[�̎��ʔ\�������������ʂ����炩�ɂȂ����B�č����w��iAACR�j��11��30����Cancer
Research���f�ژ_�����Љ���B �@����Љ�ꂽ�V�������w�t�@�C�o�[�v���[�u�́A���זE�������ΐ���זE���_����悷�邱�Ƃ𗘗p���ăf�U�C�����ꂽ���̂ŁA�p���ɑg�D��pH�𑪒肵�Ċ��זE�Ɛ���זE�����ʂ����ʂ���d�g�݁B�v���[�u��g�D�ɓ��Ă�ƁA���̕��ʂ�pH�ɉ����ăv���[�u��[��pH�C���f�B�P�[�^�[����������̐F���ς��A���̐F�����N�����u�����v���[�u�̑��[�ɂ��鏬�^�X�y�N�g�����[�^�[�Ō��o����B�g�D�������鎩�Ȍu���ɂ�銱��h�����߁ApH�̑���̓v���[�u��g�D���痣������ɍs���B����V�O�i���́A�v���[�u��g�D���痣������A��10���Ԃ͈����ۂB �@���[�؏��p4���i�Ĕ������������|�s��1���A�]�ڐ����F��3���j�ɐV�v���[�u�����p���A���ʂ�a���w�I�����ƑΔ䂳�����Ƃ���A�v���[�u�ɂ���ᇂƐ���g�D���ʂ̊���88���A���ِ���90���ł������B �@�����O���[�v�́A�v���[�u���p�ɋ������T���v���������Ȃ����ƁA�v���[�u�ɂ�錟���̓��ٓx�����߂�K�v�����邱�Ƃ��A����̌����̉ۑ�Ǝw�E�B����A�u���̑�������́A�ق��̈�ËZ�p�ɔ�ׂĔ�p���ʂ������̂ŁA���낢��Ȏ�p�ōL���g���邱�Ƃ������܂��B���݂̓f�[�^�x�[�X�𑝂₷���߂ɐ؏��g�D�T���v���𑽐��W�߂Ă���A�߂������ɂ͗Տ�����������ɓ���Ă���v�ƃR�����g�B��Ƃ̋��͂āA���̃v���[�u�̎��p�����������i���Ă������ʂ��������Ă���B m3.com 2016�N12��19�� |
|
��܂̊��זE�I��I�^���Z�p���J�� ���R��A�V�K���䐫T�זE�uHOZOT�v�ɂ�� |
| �@���R��w��12��16���A2006�N�Ɋ�����Зь����J�������V�K�̐��䐫T�זE�uHOZOT�i�z�]�e�B�j�v��p���āA��ᇗZ���E�C���X���܂�����זE�֑I��I�ɉ^������Z�p�̊J���ɐ��������Ɣ��\�����B���̌����́A�����w�@�㎕��w���������ȁi��j������O�Ȋw����̓����r�`�����A����w�a�@�V��Ì����J���Z���^�[�̓c�V��y�����A�ь��̒����C����������̌����O���[�v�ɂ����́B�������ʂ́uScientific
Reports�v�I�����C���ł�11��30���t���Ōf�ڂ���Ă���B �@�S�g�ɍL����������זE�������I�Ɏ��Â��邽�߂ɂ́A����זE�֎��Ö��I��I�Ƀf���o���[����Z�p�̊J�����K�v�s���B���̂��߁A����זE�ւ̑I��I�ȃf���o���[�Z�p�̊J���́A�i�s�������҂̐����������ڎw�������ŏd�v�ȉۑ�ł���B �@���݁A��ᇗZ���E�C���X��p�����E�C���X�Ö@�̗Տ��J�����i�߂��Ă��邪�A�E�C���X�̂���זE�ւ̑I��I�ȃf���o���[�Z�p���Ȃ����߂ɁA�S�g�ɍL�������]�ڑ��ɃE�C���X���^�����邱�Ƃ͍�������BHOZOT�זE�́A�q�g�`�ь�����������ꂽ�V�K�̐��䐫T�זE�ŁA����זE�֑I��I�ɐN������@�\��L����B �@����A�����O���[�v�́AHOZOT�זE�̂���זE�ւ̑I��I�ȍזE���N�����ʁiCell-in-Cell activity�j�𗘗p���āA��ᇗZ���E�C���X�𓋍ڂ���HOZOT�זE���쐻�B����זE�֑I��I�Ɏ�ᇗZ���E�C���X���f���o���[����Z�p���J���B��ᇗZ���E�C���X�𓋍ڂ���HOZOT�זE�́A����זE�ւ̑I��I�ȃf���o���[�@�\�ɂ���Ă���זE���ɐN�����ăE�C���X���g�U�����邽�߁A���o���ɍL��������������̂���זE�����ł����邱�Ƃ����f���ŏؖ������Ƃ����B �@����̌������ʂɂ��A����זE�֑I��I�ȍזE���N�����ʂ�L����HOZOT�זE���E�C���X�̃L�����A�זE�Ƃ��ėp���邱�ƂŁA��ᇗZ���E�C���X��p�����E�C���X�Ö@���A�����I�ɕ����d��]�ڂ�L���邪�҂ɂ��K���ł���\�����o�Ă����B�q�g�ւ̓��^���\�ƂȂ�A�i�s�������҂̐����������P����\�������҂ł���B �@����A��ᇗZ���E�C���X�𓋍ڂ���HOZOT�זE�̗Տ��J�����i�߂A�����d��]�ڂɑ���V���Ȏ��Ö@�̊J�������҂����A�ƌ����O���[�v�͏q�ׂĂ���B m3.com 2016�N12��21�� |
|
�݊��̔���ɐ_�o�X�g���X���֘A ����A���זE���u�_�o�������q�v���Y�� |
| �@������w��12��16���A�݂���̔���Ɛ_�o�X�g���X�̖��ڂȊ֘A�ƁA���̃��J�j�Y���𖾂炩�ɂ����Ɣ��\�����B���̌����́A����w��w�������a�@��������Ȃ̑��͗������A���r�a�F�����炪�A�č��R�����r�A��w�ȂǂƋ����ōs�������́B���������ʂ́A�Ċw�p���uCancer
Cell�v�I�����C���łɓ����t���Ŕ��\����Ă���B �@�w���R�o�N�^�[�s�����ۊ����҂̌����ɂ��A�݂��Ґ��͌����X���ɂ�����̂́A���ď����ɔ�ׂē��{�͈ˑR�Ƃ��Ĉ��|�I�����݂̈���Ǘ��L���Ă���B�i�s�݂���͍R����܂���ː��̎��Â������Ȃ����Ƃ������A5�N��������20���ɖ����Ȃ��̂�����B���������ǂ���ł������̐V������܂��J��������ʂ����Ă���咰����ƑΏƓI�ɁA�݂���ɂ͂���������܂̑t�����͂���قǍ����Ȃ��B���̂��߁A�݂���ɂ͕ʂ̎��ÕW�I���������A�v���[�`���K�v�ƍl�����Ă���B �@�݂���זE�̂܂��ɑ��݂����ᇔ��������A����זE�̑��B����������Ă��邱�Ƃ��A��܂��݂���Ɍ����ɂ�������ƍl�����Ă���B��ᇔ������ɂ͖Ɖu�זE�݂̂Ȃ炸�A���ۉ�זE�⌌�Ǔ���זE�ȂǑ����̍זE�����݂��邪�A�����O���[�v�͐_�o�זE�ɒ��ځB�������d�ˁA����܂łɐ_�o�V�O�i�����݂���̔��ǂɏd�v�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă������A���̏ڍׂȃ��J�j�Y���͂킩���Ă��炸�A�܂������̎�@�͐g�̂ւ̕��S��댯�����傫�����Ƃ���A���É��p�̎����ɂ͎����Ă��Ȃ������B �@����A�������O���[�v�́A�}�E�X�݂̈���g�D���ڂ����ώ@���A�݂��i�s����ߒ��ŁA����זE���u�_�o�������q�v�ƌĂ��z���������Y�����A����ɔ��������_�o�זE������g�D�ɏW�܂�A�����X�g���X�h�����邱�Ƃň݂���̐������������Ă������Ƃ𐢊E�ŏ��߂Ė��炩�ɂ����B�܂��A���́u�_�o�������q�v��}������A�_�o�X�g���X����o����זE���������邱�ƂŁA�݂���̐i�s��}���邱�Ƃ��ł����Ƃ����B �@�_�o�X�g���X���݂���ɗ^����e���͂���܂ŏڂ����킩���Ă��Ȃ��������A����_�o�זE�Ƃ���זE�����ݍ�p�������Ȃ��炪����`�����Ă����ߒ����ڍׂɖ��炩�ɂȂ����B���̑��ݍ�p��}���邱�Ƃ��A�V�����݂��ÂƂ��ėL���ȉ\��������B �@����זE�̑��B�ڗ}����]���̍R����܂ɉ����āA�_�o�זE�Ƃ̑��ݍ�p��}�����܂ɂ��A�݂��Â̌��ʂ����߂邱�Ƃ��ł���ƍl������B�_�o�������q��W�I�ɂ�����܂͂��łɗՏ���������ۂ̗Տ��ł��܂��܂Ȏ����Ɏg�p����Ă��邱�Ƃ���A�݂���ɑ��Ă������̗Տ����p�����҂����A�Ɠ������O���[�v�͏q�ׂĂ���B m3.com 2016�N12��21�� |
| ����ɑ��郏�N�`���Ö@�̗L�������}�E�X�Ŋm�F |
| �@�ă~�V�K����w��27��(���n����)�A�u�i�m�f�B�X�N�v�ƌĂ�鏬���ȍ\���ł���זE�ɓ��L�̍R����Ɖu�V�X�e���ɓ������A����זE�ɑ���Ɖu���l�����鎡�Ö@���A�}�E�X�ɂ������ŗL���ł������Ɣ��\�����B��ᇍזE������Ɖu�V�X�e���ɂ���Ĕr�������邱�ƂŁA���l�̏�Ԃɑ��������Â�ł��A����p�̌����Ȃǂ����҂����B �@����זE(��ᇍזE)�͂��Ƃ��ƒʏ�̍זE�ł��������̂��O�I�Ȏh���Ȃǂŕψق��A���B�������̂ŁA�ʏ�ł͓��X�Ɖu�n�ɂ���đ��B��}����ꂽ��A�r������Ă���B������u����(�������)�v�Ƃ��������́A��ɂ��̐��䂪���炩�̌����Œǂ����Ȃ��Ȃ����ꍇ�������Ă���B �@����זE�̑��B��}����Ɖu�Ö@�ɂ́A�C���^�[�t�F�������܂�Ɖu�����܂Ȃǂ����邪�A��p����͈͂��L�����߁A����זE�ɂ܂ʼne�����y�ڂ��A���܂��܂ȕ���p�����݂���B���̂��߁A���q�W�I��̂悤�Ȃ���זE�݂̂���ٓI�ɍU�����鎡�Ö@���������߂��Ă���B �@���̂��Ã��N�`���ł́A��ᇍזE�ɓ��L�̕ψقł����ᇐV���R��(�a����)���d���i�m�f�B�X�N���g���B�i�m�f�B�X�N�́A�傫����10nm���x�̍����x�������|�^���p�N���ō\������Ă���B�ɂ߂ď��������߁A���N�`�������𐳂����튯�̐������זE�Ɍ����I�ɑ���͂�����B�����āA��������̐V���R����F������T�זE�����邱�ƂŁA���̋Z�p�͂���ψق��^�[�Q�b�g�����A����זE�������A��ᇂ̐�����}������B �@��ʓI�ȗ\�h���N�`���ƈႢ�A���Ã��N�`���́A���N�`���i�m�f�B�X�N���Ɖu�V�X�e���̈������������A�����̂���זE�Ɛ�킹�邱�ƂŁA���җp�Ƀp�[�\�i���C�Y���ꂽ�`�ŁA���łɔ�����������זE���E�����Ƃ��ł���B �@���̌��ʁA�����m�[�}(�������F��)��A�咰������Č������}�E�X�ɑ��A�}�E�X�̂�������T�זE��27%����ᇂɑ��Ċ��삳����A�܂��ᇂɑ��Ĕ��������邱�Ƃ��ł����B����ɁA10���ȓ��ɂ���זE�����������邱�Ƃɐ��������B �@�����ׂ����ƂɁA��ᇍזE����������70����ɓ��l�̎�ᇍזE�𒍓����Ă��蒅���Ȃ����Ƃ�����Ă���A����͂��傤�ǖ����N�`���Ȃǂ̂悤�ɁA��ᇍזE�ɑ��ĖƉu�L�����������邽�߂ɁA�Ĕ��܂ŗ}���邱�Ƃ��ł���Ƃ����B �@�����҂́A���̋Z�p������K�͂ȓ��������Ŏ����邱�Ƃ����҂��Ă���B PC Watch 2016�N12��28�� |