�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@
| �@�z�|�� > ��w�g�s�b�N�X > �o�b�N�i���o�|���j���| > 2014�N11���`2015�N12�� |
| 2014�N11�� �̑�����@���{�l���L�ψ� ��`�q��͂Ŕ����@��������Z���^�[�Ȃ� |
|---|
| �@���{�l�̊̑�����̊��҂����ɓ����I�Ȉ�`�q�̕ψق����邱�Ƃ��A���������Z���^�[�A������Ȃǂ̌����`�[�����A���҂�̈�`�q��͂��猩�����B�`�[���́u���{�l���������V���Ȕ�����v���̉𖾂ɖ𗧂Ă����v�Ɛ������Ă���B�Q���t�̕ĉȊw���i�d�q�Łj�Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@�����͓��ċ����Ŏ��{����A�̑�����̂X�����߂�u�̍זE����v�̊��҂̂���g�D�ׂ��B�Ώۂ͓��{�l�S�P�S�l�����Đl�P�O�R�l���č��ݏZ�A�W�A�l�R�W�l�\�\�Ȃnjv�U�O�W�l�B��͂̌��ʁA����ɂ���`�q�̕ψق͋��ʂ��Č���ꂽ���A���{�l�ɂ́A���̑��ɓ����I�ȕψق̃p�^�[�����������B �@��ʂɊ̑�����̌����́A�a�^�E�b�^�̉��E�C���X�ւ̊����������Ƃ���邪�A�E�C���X���W���Ȃ���E�C���X���̂���������Ă���B�����������{�l���L�̈�`�q�̕ψق̓E�C���X�����Ƃ͊W�Ȃ��A������̊��҂ɂ������A�V���Ȏ��Ö@�̊J���ɖ𗧂\��������Ƃ����B �@���������Z���^�[�̎ēc���O�E���쒷�i����Q�m�~�N�X��������j�́u���҂̐H���Ȃǐ������̃f�[�^�ƍ��킹��A���{�l�̊̑�����̐V���Ȍ����������邩������Ȃ��v�Ƙb���B m3.com 2014�N11��4�� |
| ���זE�ł����ގ� |
| �@����זE��ގ����銲�זE���J�������Ƃ����������ʂ�ăn�[�o�[�h���זE�������Ȃǂ̃`�[�����ĉȊw���ɔ��\�����B �@�`�[���́A����ȍזE�ɂ͓������A����זE�ɂ��������őf�ɒ��ځB��`�q�H�w�̋Z�p���g���A�l�̐_�o���זE�ɓőf�ւ̑ϐ��Ɠőf����o����@�\�����������B �@�}�E�X���g���������ŁA�]��ᇂ̑啔��������������A�̓��ŕ�������Q���ɕ��ŁA���̊��זE����ꂽ�Ƃ���A�őf�ł���זE�����ł��A�}�E�X�̐����������P�����Ƃ����B �@�`�[���͂���Ɍ��ʂ��グ����@���������Đl�ւ̉��p��ڎw���v��ŁA�T�N�ȓ��ɂ͗Տ��������n�߂����Ƃ��Ă���B m3.com 2014�N11��11�� |
| �u�y�v�`�h�v�ł��Á@�F�{�傪�Տ����� |
| �@���Ɏ��Õ��@�̂Ȃ����̂���ɑ��āA�A�~�m�_���A�Ȃ��������u�y�v�`�h�v�R��ނ𓊗^���āA������U������Ɖu�͂����߁A�����₪������̌��ʂ��Ƃ���Տ������̐��ʂ��A�F�{���w�@�����Ȋw�������̐�����������̃O���[�v���P�Q���A�Ĉ�w���i�d�q�Łj�ɔ��\�����B�y�v�`�h���g���^�C�v�̂��Ö�͖��J���ŁA���^�C�v�Ƃ��Đ��E���̎��p����ڎw���B �@���������Ɠ��喼�_�����ňɓ����Ȍ��o�a�@�i�F�{�s������j�̎�������t�ɂ��ƁA��p����ː��ł̎��Â��ł��Ȃ����҂R�V�l�ɑ��āA�R��ނ̃y�v�`�h���������Ē��˂œ��^�B����ƁA���^�������҂̐������Ԃ͖�S�E�X�J���ŁA���^���Ă��Ȃ����ҁi�P�W�l�j�̖�R�E�T�J����蒷�������B���^�������҂̂����P�l�́A�����S�ɏ������Đ������Ƃ����B �@���ʂ�����ꂽ���҂ł́A�y�v�`�h���R���זE����ĖƉu�זE�̈��u�L���[�s�זE�v�������������Ă��邱�Ƃ��m�F�B�����������L���[�s�זE�́A����זE�̕\�ʂɊ���o���y�v�`�h��ڈ�ɁA����זE���U������Ƃ����B�܂��A�L���[�s�זE������������y�v�`�h�̎�ނ������قǁA���Ì��ʂ��������Ƃ����������B �@�R��ނ̃y�v�`�h�́A�O������q�g�Q�m����̓Z���^�[���ŕăV�J�S��̒����S�㋳�����A����זE�̈�`�q����͂��ē��肵���B �@���݁A�����̐����Ђ����i�Ƃ��Ă̎��p����ڎw���Ď������B�����_�����́u�قƂ�Ǖ���p���Ȃ��A���҂̐����̎���ۂĂ鎡�Ö@�v�Ƙb���Ă���B�V�J�S��̒��������́u�����̃y�v�`�h�̍������L���Ȃ��Ƃ�������A����̂��Â̕��������������ʁv�Ƃ��Ă���B m3.com 2014�N11��13�� |
|
�������玩�͂Ő��҂����l���������H���Ă���9�̂��� �S�ăx�X�g�Z���[�w�����R�Ɏ��鐶�����x |
| ������ڎw���Ď��s���Ă���9���� �@���I�Ȋ����ɂ��ċL������w�_����1000�{�ȏ㕪�͂��܂����B���m�_���̌������I���Ă��������ɃC���^�r���[�𑱂��A���̑Ώێ҂�100�l���܂����B �@�킽���́A���I���͂̎�@�ŁA�����̏Ǘ�����x���ڍׂɕ��͂��܂����B���̌��ʁA���I�Ȋ����ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ������Ɛ��������v�f�i�g�́A����A���ʓI�Ȏ����j��75���ځA�����яオ��܂����B �@�������A�S���ڂ�\�ɂ��ďo���p�x�ׂ�ƁA75�̂����̏��9���ڂ́A�قڂ��ׂẴC���^�r���[�ɓo�ꂵ�Ă��邱�ƂɋC�Â��܂����B �@���Ƃ��Γo���73�Ԗڂɑ��������u�T����̃T�v����ێ悷��v�B����͒����Ώے��́A�����킸���Ȑl���b���Ă��ꂽ�����ł����B����������p�x�̂����Ƃ���������9�̗v�f�ɂ��ẮA�قڑS�����A�u������ڎw���Ď��s�����v�ƌ��y���Ă����̂ł��B �@����9���ڂƂ͎��̂Ƃ���ł��B �E���{�I�ɐH����ς��� �E���Ö@�͎����Ō��߂� �E�����ɏ]�� �E�n�[�u�ƃT�v�������g�̗͂���� �E�}�����ꂽ������������� �E���O�����ɐ����� �E���͂̐l�̎x��������� �E�����̍��Ɛ[���Ȃ��� �E�u�ǂ����Ă������������R�v������ �@����9���ڂɏ��ʂ͂���܂���B�l�ɂ���ďd�_�̒u�������قȂ���̂́A�C���^�r���[�Ō��y�����p�x�́A�ǂ���������x�ł����B�킽�����b�������I�����̌o���҂͂قڑS�����A���x�̍��͂���9���ڂقڂ��ׂĂ����H���Ă����̂ł��B �@�����Ŗ{����9�͂ɏ͗��Ă��A1�͂�1���ڂ��������Ă����܂��B �@�e�͂ł́A�܂����̏͂̃e�[�}�ɂ��Ẳ���ƁA����𗠕t����ŐV�̌������Љ�܂��B���ɁA���I�Ȋ����𐋂����l�̎��b���L���܂��B�͖��ɂ́u���H�̃X�e�b�v�v�Ƒ肵�āA���̏͂̃e�[�}�����H���₷���������ɂ��āA�������̕��@�����Љ�܂��B President ONLINE 2014�N11��16�� |
| �얞�����̂���A�N�T�O���l�@�v�g�n�A���������X�N |
| �@���E�ی��@�ցi�v�g�n�j�̐��g�D�A���ۂ����@�ցi�{���t�����X�E�������A�h�`�q�b�j�͂Q�V���܂łɁA�ߑ̏d��얞�������ł���ǂ���l�����E�ŔN�Ԗ�T�O���l�ɏ��Ƃ̌������ʂ��p��w�������Z�b�g�E�I���R���W�[�ɔ��\�����B�j����菗���̔��ǃ��X�N�������Ƃ����B �@�h�`�q�b�́u�얞�����ǂ̎�v�ȃ��X�N�v���ɂȂ��Ă���v�ƌx���B���W�r�㍑�̌o�ϐ����ɔ����A�얞�����E�I�ɐ[���Ȗ��ƂȂ钆�A����}���悤�e���ɑ������B �@�h�`�q�b�ɂ��ƁA�Q�O�P�Q�N�̐V���Ȃ��ǎ҂̐���R�E�U���i��S�W���P��l�j���ߑ̏d��얞�������������B�S�̂ɑ���얞�R���̂���̊����́A�������j�����R�{�߂����������B �@�얞�͐H����咰�A�t���Ȃǂ̂���̃��X�N�v���Ƃ���Ă���B �@�h�`�q�b�́u�Ⴆ�Εo��̓�����Ȃǂ̂P�O���͌��N�I�ȑ̏d��ۂ��ƂŔ��ǂ�h�����Ƃ��ł���v�Ǝw�E�A�얞��̏d�v�������������B m3.com 2014�N11��28�� |
| 2014�N12�� �������ʁA���Ȃ�����p�@�b�^�����̉��̐V��@�_�˂Ŏ����� |
| �@�b�^�̉��E�C���X�i�g�b�u�j�ɂ���ċN����b�^�����̉��̐V�����o�����Ö�ɂ��āA�����J���Ȃɐ����̔��̏��F���\������Ă���B�_�ˎs������ŊJ���ꂽ�u���{������֘A�w��T�ԁv�ŁA����ɂ��V��̗Տ������i�����j�̕��������B�W���I�ȃC���^�[�t�F�������Â����ʂ������A����p�����Ȃ��Ƃ����A���Â̑I�������L����Ɗ��҂����B �@�g�b�u�Ɋ������Ă���l�͑S���łP�T�O���`�Q�O�O���l�B�����͌��t����̊����ŁA�P�X�W�W�N�ȑO�̏W�c�\�h�ڎ��X�Q�N�ȑO�̗A���̂ق��A����n�A�s�A�X�̌��J���ȂǂŊ����҂Ɗ������p���邱�Ƃ���Ȋ����o�H�Ƃ��Ēm����B�̍זE�̔j��ƍĐ������N�J��Ԃ���A���u����Ɗ̍d�ρA�Ђ��Ă͊̂���ɂȂ���B �@�b�^�����̉��̕W���I�Ȏ��Â̓E�C���X�̑��B��}���钍�˖�u�y�O�C���^�[�t�F�����v�ƍR�E�C���X��u���o�r�����v�̕��p�����A�y�O�C���^�[�t�F�����͔��M�₾�邳�A�S�g�̒ɂ݂Ȃǂ̋�������p���N�����B�܂��A���{�l�̂b�^�����̉��̖�V�����߂�u�P���^�v�Ƃ����E�C���X�̌^�ɂ͌����ɂ����Ƃ�����������B �@�V��͂��̂P���^���ΏۂŁA�E�C���X�̈�`�q�̕�����W���đ��B���~�߂�u�\�z�X�u�r���v�i��ʖ��j�ƁA�E�C���X�̃^���p�N��������j�Q����u���W�p�X�r���v�i���j��z���B�Ĉ��i��ƃM���A�h�E�T�C�G���V�Y�Ђ̓��{�@�l���X���ɏ��F�\�������B �@�����̌��ʂ��܂Ƃ߂��A�������ۈ�Ì����Z���^�[�̉��E�Ɖu�����Z���^�[�i��t���s��s�j�̍a���j�Z���^�[���ɂ��ƁA�̍d�ϊ��҂V�U�l���܂ނR�S�P�l�ɂP���P�����P�Q�T�Ԍo�����^���A�R�R�W�l�������B���̒��ɂ̓C���^�[�t�F�������Â̌��ʂ��Ȃ��������҂W�W�l���܂܂�Ă����B����p�͕@��A�̉��ǁA���ɁA���邳�ȂǁA��������y�����̂������B �@�E�C���X�ɒ��ڍ�p�����͊J��������ɂȂ��Ă��邪�A�g���Ă���ԂɃE�C���X���ω����A�ϐ���������댯��������B�����A�V��ɂ��Ă̓E�C���X�ւ̍�p�̕��@�����̖�ƈႢ�A���Ɏ��ÂɎg���Ă���č��ł́A���̂Ƃ���ϐ����������Ƃ����͂Ȃ��Ƃ����B �@�a��Z���^�[���́u�o����Ȃ̂Ŏ��Â����₷���B����p���قƂ�ǂȂ��A�C���^�[�t�F�����������Ȃ������l�ɂ��L���Ȃ̂͘N�v�Ɗ��҂���B m3.com 2014�N12��2�� |
| ���H�߂��A���͂Q�� |
| �@�u���{�l�͂��܂���ł����v �@�C�O�̑厖���A���̂�`����j���[�X�̍Ō�ɕt���ꕶ�ɁA�u���{�l���������Ȃ炢���̂��v�Ƃ������f�B�A�ᔻ�����邻�����B�c�O�Ȍ�������A�ᔻ�������Ȃ闝�R��������B�u���{�l�́c�c�v�̊Ȍ��Ȉꕶ���u���̑��̍��̐l�v�Ƃ�����r�Ώۂ̂��镶���ɒu�����ƁA�Δ�̈Ӗ�������тт�B�u����`���͂��܂����v�ƌ����A�u�h��͂��܂���ł����v�Ƃ�Ă��܂��悤�ɁB �@�Ȋw�I�^����Nj����ē���ꂽ�������ʂ��A�u�Љ�v�Ƃ��������ɒu�����ƁA�����̈Ӑ}���������ރP�[�X������悤�Ɋ�����B �@�u���𑽂��H�ׂ�j���͓��A�a�ɂȂ�₷���v�B���������Z���^�[�Ȃǂ̌����`�[�������{�l�U���l�ȏ���ǐՂ��A���H�ƕa�C�̊֘A����Ă���B�����ł́A����Ȃǂ̓��𑽂��H�ׂ�l�قlje�����傫�������B���������A���H���T�������Ȃ�B�������A�ǂꂭ�炢�H�ׂ�ƕa�C�ɂȂ�₷���̂��B �@�^���Ë�����Y�E���Z���^�[����\�h�E���f�����Z���^�[���ɂԂ���Ɓu�����X�N�Q�ɓ����閈���P�O�O�O�����ȏ�̓���H�ׂĂ���l�́A���{�l�̂T���̂P���x�ł��傤�v�Ƃ̓������Ԃ��Ă����B���{�l�̂W���̓��X�N�Q�ɒB���Ă��Ȃ��B���P�O�O�O�����̌����ɓ�����̂́u�Ă����ٓ��̔�����T���v�u���傤���Ă��̌����[�X�R���v�Ȃǂ��Ƃ����B �@����Ȃǂ̓��͓S�����L�x�Ȃ��ߐԂ��B���������ԓ����C���X��������ɉe�����A���A�a���X�N�����߂�Ƃ̃f�[�^�����Ă̌����ɂ������B�u�ł͓��{�l�́H�v�ƒ��ׂ��̂��A���̌������B��A�̌����ł͓��H���咰���X�N�����߂����ŁA���ɖL�x�ȖO�a���b�_�𑽂��ێ悷��قǔ]�������X�N���ቺ���邱�Ƃ����������B����ɑ��A�����̓��{�l�̕��ϓI�ԓ��ێ�ʂ͂P����U�O�O�����B�̂�葝�����Ƃ����Ă����Ă̂R���̂P���x���B�Ë�������u�P���W�O�O�����܂łȂ猒�N�I�v�Ǝw�E����B �@�����̌������ƁA����̐H�ނ̒�����Z������Ɉӎ��������₷�����A���ꂼ��̌����͐H�ޓ��m�̗D��܂ł͔��肵�Ă��Ȃ��B�u�w�����͈����i�����j�x�ƌ��ߕt�������l���ǂ����ɂ����ł��傤�v�B�Ë�����́u����v�����Ɏc��B m3.com 2014�N12��4�� |
| ��̎q�{�ڐA���o�Y�@�X�E�F�[�f���łQ�� |
| �@�X�E�F�[�f���ŁA��e�̎q�{���ڐA���ꂽ�����Q�l���j���P�l�����o�Y�����B�q�����c��̎q�{����a��������͏��߂ĂƂ����B�P�Q���R���t�̉p���f�[���[�E���[�����`�����B �@�����ɂ��ƁA�o�Y�����̂́A���܂���q�{���Ȃ������i�Q�X�j�ƁA���Â̂��ߎ���̎q�{��E�o���������i�R�S�j�B�Q�l�́A�C�G�[�e�{����̈�t��ɂ��A�o�Y�ړI�Ő��̎q�{�ڐA���Ă����B����͂��̏����Q�l���܂ތv�X�l�Ɏq�{���ڐA���A����܂łS�l���D�P�����Ƃ����B �@�j���Q�l�͖�P�J���O�ɒ鉤�؊J�Ő��܂�A����ŏ����Ɉ���Ă���B �@�X�E�F�[�f���ł͂X���A�U�O��O���̒m�l����������ꂽ�q�{�̈ڐA�������������E���̏o�Y�ɐ����B������܂߂�ƁA�q�{�ڐA�ɂ��o�Y�̐����͌v�R��ɂȂ�B �@�����́u���̂��߂ɂł���ō��̓��ʂȑ��蕨���v�Ǝq�{��E�o���Ē�����e���̎^����p��w�����̃R�����g���Љ�B�q�{���Ȃ��A�o�Y��]�ޑ����̏����Ɋ�]��^����Ƌ��������B �@�p���ł��A�]���Ɏ���������������ꂽ�q�{���o�Y�ړI�ňڐA����v�悪�i�߂��Ă���Ƃ����B m3.com 2014�N12��4�� |
| �咰����]�ځA�^���p�N���̕ω��ŗ\���@���s��O���[�v |
| �@�咰����ɂ���^���p�N���̕ω��Ŏ�p��̌o�߂�\���ł��邱�Ƃ��A�������E���s�喼�_�����≀������E�����w�����ȏy������̃O���[�v�������A�R�����\�����B�ω�������ƁA���S�������܂�]�ڂ��N����₷���Ȃ�Ƃ����A�f�f�@�Ƃ��Đ��N��̎��p����ڎw���Ă���B �@�咰����͏����ł���̎��S�����̃g�b�v���߂�B�咰����ł͓��ɓ]�ڂ���Ǝ��S�ɂȂ��邽�߁A�]�ڂ̎d�g�݂̉𖾂Ƃ����}������@�̊m�����ۑ�ƂȂ��Ă���B �@�O���[�v�́A�咰����̍זE�ɂ���^���p�N���s�������̓��蕔���ɕω��i�����_���j������ƁA�זE�̉^�����������ē]�ڂ��₷���Ȃ邱�Ƃ�˂��~�߂��B�]�ڂ̂���d�x�̊��҂T�V�l�̂���זE�ׂ����ʁA��W���̂S�U�l�ɕω����������B�܂��A��p��̐��������ω�������ꍇ�́A�Ȃ��ꍇ�ɔ�ׂĒႭ�Ȃ����B �@�ω��̂���咰����̍זE���R�̂Ō��������@�����ɊJ�����Ă���B�������喼�_�����́u����זE�ɕω��̂��銳�҂͓]�ڂ̋��ꂪ�����A�����ɍR����܂𓊗^����Ȃǂ̎��Â��l������v�Ƙb���Ă���B m3.com 2014�N12��4�� |
| �y�v�`�h�R�퍬���A���ÂɌ��ʁ@�F�{��O���[�v |
| �@�F�{���w�@�����Ȋw�������̐����������i�Ɖu���ʊw����j��̃O���[�v���A�A�~�m�_���A�Ȃ��������u�y�v�`�h�v���g�������Ö�̎��p����ڎw���Ă���B �@�y�v�`�h�͂Q�O�N�ȏ�O�A���Ö�̗L�͌��Ƃ��Č������ꂽ���A���ʂ��Ⴍ�A���p������Ȃ������B����������͂P�P���A�R��ނ̃y�v�`�h���������ē��^���������Ì��ʂ��Տ������̌��ʂ��A�Ĉ�w���u�N���j�J���E�L�����T�[�E���T�[�`�v�i�d�q�Łj�Ŕ��\�����B �@���������ɂ��ƁA����זE���͂��߂Ƃ���זE�̒��ł́A��`�q��v�}�ɑ��푽�l�ȃ^���p�N���������B���̃^���p�N���̒f�Ђ��u�y�v�`�h�v�B�y�v�`�h�́A�g�k�`�i�q�g�������R���j�ƌĂ�镪�q�Ɍ������āA����זE�̕\�ʂɊ���o���B �@���������́A�ăV�J�S��̒����S�㋳���i�O������q�g�Q�m����̓Z���^�[���j�̋��͂āA���o�ƐH���㕔�̝G����炪��̈�`�q����́B�̓��̂Q�O��ވȏ�̐���ȍזE�Ɣ�r���A����זE�����Ŋ����ɓ����ă^���p�N��������`�q�����B���̂����O�̃^���p�N���ɗR������y�v�`�h���A�Տ������Ɏg�����Ƃɂ����B �@�y�v�`�h�́A���҂̘e�̉��Ȃǃ����p�߂̋߂��ɒ��˂œ��^����ƁA�Ɖu��S���u�R���זE�v�̕\�ʂɂ���g�k�`�Ɍ�������B�R���זE�͖Ɖu�זE�̈��u�L���[�s�זE�v�ɁA�U���̖ڈ�ƂȂ�y�v�`�h�̎�ނ�`�B���Ċ������B�����������L���[�s�זE�́A����זE�̕\�ʂɊ���o���y�v�`�h��ڈ�ɍU������d�g�݂��B �@�Տ������ł́A��p��R����܁A���ː��ł̎��Â��ł��Ȃ����҂R�V�l�ɁA�T�P��̃y�[�X�łX�^�B���̌�́A�S�T�ɂP�^�����B����ƁA���^�������҂̐������Ԃ͖�S�E�X�J���ŁA���^���Ă��Ȃ��P�W�l�̖�R�E�T�J����蒷�������B���^�������҂̂����P�l�́A�����S�ɏ��������B�����O���[�v�ŗՏ���S���������������_�����́u�傫�Ȍ��ʁv�ƕ]������B �@�܂��A�L���[�s�זE������������y�v�`�h�̎�ނ������قǁA���Ì��ʂ��������Ƃ������B���������́u�ȑO�͂P��ނ̃y�v�`�h�ł͌��ʂ��Ⴍ�A��Ƃ��Ď��p���ł��Ȃ��������A��������������ƌ��ʂ����܂邱�Ƃ����������v�Ƙb���B �@�����A�g�k�`�ɂ͑����̌^������B����͓��{�l�̂U�������u�`�Q�S�^�v��ΏۂƂ������A�^������Ȃ���y�v�`�h�̎�ނ��قȂ邽�߁A���Âł��Ȃ��B����̗Տ������ł��A�^�����킸�ɓ��^�ł��Ȃ����҂������B �@���������́u�L���[�s�זE������������ɂ́A���Ԃ�������v�Ƙb���A�]���̏��Ȃ������̊��҂����A��p��̍Ĕ��\�h�̕������ʂ͍����Ɗ��҂���B �@�y�v�`�h��̌����͈ꎞ�A���ɂȂ��Ă������A�Q�O�P�Q�N����ĂщߔM���Ă���Ƃ����B�y�v�`�h��ɂP�R�N�Ԏ��g��ł��鐼�������́u����̐��ʂ́A��b���牞�p�܂ŏ����Y�̋Z�p�ɂ���ē���ꂽ�B�ʂ̎�ނ̃y�v�`�h��p������A����זE�ɂ��Ɖu�}���̓��������������肵�āA����Ɍ��ʂ����߂����v�Ƙb���Ă���B m3.com 2014�N12��4�� |
| ���{�l�̂��߂̂���\�h�@�@�����͑����߂��ɒ��� |
| �@�Ȋw�I�ȍ���������A����œ��{�l�ɐ����ł���ƍl�����邪��\�h�@���A���������Z���^�[�̌����ǂ��u���{�l�̂��߂̂���\�h�@�v�Ƃ��āA�C���^�[�l�b�g�Ō��J���Ă���B �@�����̐i�W�ɔ������e���X�V���邱�Ƃɂ��Ă���A���N�X���̉����ŁA�����N�������ڕW�Ƃ��ׂ��̊i�w���i�a�l�h�j���u�P�X�`�Q�T�v����u�Q�P�`�Q�T�v�ɉ��߂��B�����N�j���͏]���ʂ�Q�P�`�Q�V�B �@�a�l�h�͑̏d�i�L���j��g���i���[�g���j�̂Q��Ŋ��������l�ŁA�Q�Q���W���A�Q�T�ȏ�͔얞�Ƃ����B���{�l��ΏۂƂ�����K�͌����ŁA�얞�����łȂ������߂�������̃��X�N���グ�邱�Ƃ������ꂽ�̂܂����B �@�U���ڂɂ܂Ƃ߂�ꂽ�\�h�@�͋����悤�ȐV�����͂Ȃ����A�����Ƃ������Ȃ��Ƃ����肻���B �@�Ⴆ�A�M�����H���͗�܂��ĐH�ׂ�B�H���̉��ǂ₪��ɂȂ���\��������B �@�܂��A�a�^�A�b�^�̉��E�C���X�����������Ƃ��Ȃ��l�́A��x�͌�������悤���߂Ă���B�����҂͔��҂ɔ�ה����X�N�����ɍ�����A����������������A�����h�����ʂ����҂ł��鎡�Ö@�̊J�����i��ł��邽�߂��B�������Ă�����̑��̐���ɑ��k���悤�B �@�����͋z�킸�ɑ��l�̉���������B�����̓A���R�[���ʊ��Z�łP���Q�R�O�����i�r�[����r�P�{�j���x�܂ł��K�ʂƂ����B�^���́A���s�₻��ȏ�̊������P���U�O�����x�B �@�e���ڂ̏ڂ��������A����\�h�ɂ��ē��O�̌����łǂ��܂Ŗ��炩�ɂȂ������́u������T�[�r�X�v�ihttp://ganjoho.jp/public/pre_scr/prevention/�j�œǂ߂�B m3.com 2014�N12��9�� |
| �咰����}����H�i�����@�p�p�C�A�̎�A���R�� |
| �@�p�p�C�A�̎�ȂǂɊ܂܂�鐬���ɁA�咰����̑��B��}����^���p�N���̓��������߂�@�\�����邱�Ƃ����R��Ǝ�������̃`�[�����˂��~�߁A�P�W�����\�����B���Â�\�h�ɗL���Ȗ�܂̊J���ɖ𗧂Ƃ��Ă���B �@���R��̒����X�����ɂ��ƁA�咰����͑咰�̍זE�Ƀ^���p�N�����ߏ�ɒ~�ς��邱�ƂŁA�זE�B�������`�q�̓��������������A����̑��B���i�ށB �@�`�[���́A�咰����̑��B��}�����钆�S�I�Ȗ�����S���^���p�N���ɒ��ځB �@�p�p�C�A�̎��L���x�c�A�N���\���̈ꕔ�Ɋ܂܂��H�i�����u�x���W���C�\�`�I�V�A�l�[�g�i�a�h�s�b�j�v��l�̑咰����זE�ɉ�����ƁA����}���^���p�N�����A����𑝂₷�A�ߏ�~�ς����^���p�N���Ɍ������A���B��`�q�̓������ז������B���̌��ʁA����̑��B���}����ꂽ�B �@�a�h�s�b�͂���Ԃ����ƂŌ��ʂ��o�邪�A��ʂɐێ悷��Ƒ̂Ɉ��e�����o��Ƃ����B �@���������́u���R�E�̐���������S���̍����R����܂��J���ł���\��������B��p�͎ア��������Ȃ����A���S���Ďg�p�ł����ɂȂ邱�Ƃ����҂ł���v�Ƙb���B �@���ʂ͉p�I�����C���Ȋw���Ɍf�ڂ��ꂽ�B m3.com 2014�N12��19�� |
| ����J�t�F�@�L���鋤���@���҂���t���A�Γ��ɑΘb |
| �@���҂�Ƒ��A��ÊW�҂�̑Θb�̏�u����N�w�O���@���f�B�J���E�J�t�F�v�����e�n�ŊJ�����悤�ɂȂ�A���ڂ��W�߂Ă���B���Z�ȕa�@�Ȃǎ��Â̌���ɑ����Ċ��҂ɑΘb�̋@�����銈�����A�u��Â̌��ԁi�����܁j�v�߂�Ƌ������Ă�ł��邪�A���ł͒ᒲ�������B���N�ɓ���A��ʎВc�@�l�u����N�w�O���v�i�����s�j�����̒n��x������ɔ����������y�ɏ��o�����Ƃ���A���s�ƓޗǁA���ɂł��J�Â����������B �@����N�w�́u�a�C�⎀�ƌ��������A�ǂ������邩�v���l����p�����w���B��싻�v�i�������j�E���V���勳���i�a���E��ᇊw�j���B�f�@�ł��J�E���Z�����O�ł��Ȃ��A��t�Ɗ��҂��Θb���閳���́u����N�w�O���v���Q�O�O�W�N�ɓ���ɊJ�݂����Ƃ���A�\�E�������B��Â��i�����锼�ʁA�a�C���Y�ƂƂ��ɐ����鎞�Ԃ������Ȃ������҂�ɁA��l�̓N�w��`����u���t�̏���ⳁv�����ڂ��ꂽ�B �@��t���l�ʒk������O���ɑ��A�J�t�F�͂W�l�قǂ̃O���[�v�Θb�̏ꂾ�B����N�w�̗��O�Ɏ^�������t�₪��̌��҂炪�S����T�O�J���ʼn^�c���Ă���B �@���͍�N�܂ŁA���̂Q�J�������Ȃ��A�u���҂̑������ɂ��J�t�F�𑝂₵�����v�Ɠ��@�l���R���Ɏx�����������B��Ë@�ւ⊳�Ғc�̂��������Ŏ^�����A�P�O�����܂łɑ��{�łR�J���A���s�{�łP�J���A�ޗnj��łP�J���̌v�T�J���Ōp���I�ȊJ�Âɂ����������B���Ɍ��ł���싳���̍u���Ȃǂɍ��킹�ĊJ����A�Q�{�Q���łS�O�O�l���Q�������B �@���x�����̓��p�q��t�i�S�U�j�́u���҂͎厡��ɉ���������A�Ƒ��ɐS�z�����܂��ƍl�����肵�����B���S���Ďv���������͈ӊO�ɏ��Ȃ��v�Ǝw�E�B�J�t�F�����������̂́A�Q���ґS���̋C�����ɏ㉺�W���Ȃ��Γ��ɑΘb���邱�ƂŁA���₵��C�t�������邩��Ƃ����B���x���̏��c���q�E�_�˖�ȑ勳���i�T�R�j�́u���߂��܂Ƃ��Ă��Ă͕����Ȃ��{����������B��t��Ō�t�玡�Â��鑤�̊w�тɂ��Ȃ���v�Ƙb���Ă���B �����_�Ȃ��Ƃ��\��a�� �@�P�O�����{�A���{����s�ŊJ���ꂽ�u��オ��N�w�O���@���f�B�J���E�J�t�F�@�����܂�v�B�u�Ĕ��̏ꍇ�A�R������Â�����Ӗ����Ă���Ǝv���܂����B���̑̂ɂ͂��߂���C�����邵�A�Ƒ��͎Ăق����ƌ������A���f�ł��Ȃ���ł��v�B���Ĕ������Ƃ����������ꂵ�����̓��𖾂������B �@�u�R����܂̓x�b�h�ɒ��ݍ��ނ悤�Ȃ���ǂ��B���ł���ˁv�u����Ő��_�I�ɗ������ނƁA���������f����̂��{���ɓ���v�u�����y���߂Ȃ���������������Ȃ��v�u���Â����Ă����Ȃ��Ă�����͎c��B��Ԍ������̂́A�����Ō��߂Ȃ����Ƃł́v �@���̓��̎Q���҂̑����́A���҂₪��̌��ҁB���ꂼ��̌o���܂��A�����Ɍ��t���������B���_�͂Ȃ����A�Θb���i�ނɂꏗ���̕\��a�炢���B �@�����܂�́u����N�w�O���v���x�����̓��p�q��t���ݑ��ÃN���j�b�N���c�ޖT��A�Q�N�O�ɊJ�݂����B���ɂP��A�J�t�F��p�Ɏ肽�������[���}���V�����ɎQ���҂��W���A�R�[�q�[�Ȃǂ����݂Ȃ���Q���Ԉȏ��荇���B�����a�Ŗ�p����Ћ߂𑱂��A�����܂�ɂP�N���ʂ��S�O��j���́u�ƒ��E��ł́w�{���ɂ炳�����Ă��炦�Ă���̂��x�Ɗ����Ă��܂��B�����͑��������Ȃ��Ă��A�ǂ����@���Ă��炦��C�y��������v�Ƙb���B �@�\��s�v�Ŗ����B���߂�ꂽ�b����Ȃ��A�Q���҂����͂���ƂƂ��ɐ������Y��ߐe�҂Ƃ̎��ʂ̔߂��݂����B����t�͌����B�u�S�̒ɂ݂͐l���ꂼ��B�J�t�F�ł͂��݂��������������A�w���̂܂܂ł������x�ƂȂ�����v m3.com 2014�N11��28�� |
| �y�f���^�����B�}���@�݂��Âɑ��s�� |
| �@����̍y�f�𓊗^���邱�ƂŁA����זE���ɂ��镨�������B��}���镨���ɕω������Ď��Â����@����s����̃`�[�����������A�Q�T�����\�����B �@�l�݂̈�����ڐA�����}�E�X�ւ̓��^�����ł͂��傫���Ȃ炸�A�V���Ȉ݂���̎��Ö@�Ƃ��Ď��p����ڎw���B����זE�����B������}������A����܂łɂȂ����Ö@�ɂȂ�Ƃ��Ă���B �@�`�[���̔��㐳�a�i�₵��E�܂������j�y�����ɂ��ƁA���̍y�f�́A����}�����ʂ�����v���X�^�O�����W���c�Q�i�o�f�c�Q�j������זE���ɍ��o�����������B�����Ń}�E�X�ɓ��^����ƁA����זE���ɂ��郊�����������邱�Ƃło�f�c�Q������זE���ō����Ȃǂ�����A����̍זE�j�ɑ��B�}���̐M���𑗂��e�̂ƌ��ѕt���A���ʂ������B �@�y�f�𓊗^���Ȃ������}�E�X�̂���זE�͂Q�T�ԂłR�{�ɑ��B�������A���^�����}�E�X�ł͑傫���ɕω��͂Ȃ������B �@�`�[���́A��p������i�s����̊��҂�ΏۂƂ��đz��B����זE�Ɏ�e�̂������ꍇ�Ɍ��ʂ�����A�S�Ă݂̈���ɗL���Ȃ킯�ł͂Ȃ��Ƃ����B�����ł͐H��������X������̍זE�ł����ʂ��m�F���ꂽ�B m3.com 2014�N12��26�� |
| ��ؑ����H�ׂ�j���A�݂��X�N�ቺ |
| �u�R�_���v�e���� �@��𑽂��H�ׂ�j���́A���Ȃ��j�������A���{�l�ɑ��������݂���ǂ��銄�����Ⴂ�Ƃ����������ʂ��A���������Z���^�[�����\�����B �@�����K���Ƃ��ǂ̊֘A�Ȃǂɂ��ĂP�X�W�W�N����ǐՂ��Ă���l�̑�K�͒����̎Q���Җ�P�X���l�́B���ʕ���H�ׂ�ʂłT�O���[�v�ɕ����A���ꂼ��݂��ǂ̊댯�����ׂ��B �@���ςP�P�N�Ԃ̒ǐՊ��Ԓ��ɂQ�X�X�T�l���݂���ɂȂ�A����ʕ����ł�����������O���[�v�Ŕ��ǂ̊댯�����ቺ����X�����������B �@����A����̕��ʕʂɕ��͂ł����P�T���l�ɂ��Ē��ׂ�ƁA�݂̏㕔�R���̂P�ɔ��ǂ����̂͂Q�T�W�l�A���̉��̕����ɔ��ǂ����̂͂P�S�P�Q�l�ŁA�����݂���ɂ��ẮA����ł�����������j���́A�ł����Ȃ������j���ɔ�ׁA���ǂ̊댯�����V�W���ɉ��������B�j������𑽂���鏗���ɂ��Ă͍��������Ȃ������B m3.com 2014�N12��27�� |
| �������Ă��}�V���֎~�@�畆������ |
| �@�I�[�X�g�����A�̂قƂ�ǂ̏B�łP������A�l�H�I�Ɏ��O���Ăď����F�̔���������Ă��}�V���̏��Ɨ��p���֎~���ꂽ�B�����͔畆����̔��Ǘ������E�ōł��������̈�ŁA�K�����i�h�͋֎~�����}���Ă���B�u���W���̂ق��A�č��̈ꕔ�Ȃǂł����p���֎~����Ă���B �@�n�����f�B�A�ɂ��ƁA�R�T�ɂȂ�O�ɓ��Ă��}�V�����g���ƁA�����̍��F��ɂȂ�m�����啝�ɍ��܂�Ƃ̒���������B�I�[�X�g�����A�ł͖�Q�O�N�O�����҂𒆐S�ɓ��Ă��p�@�B���l�C�ƂȂ������A�����̂���]�c��P�O��̒j���ɒ��������Ƃ���A���Ă��������Ɠ������̂́A�P�O�N�O�͂U���������̂��A�ŋ߂ł͂S����܂Ō����Ă���Ƃ����A�ӎ��̕ω�������������B �@�֎~�����͍̂ő�s�s�V�h�j�[������j���[�T�E�X�E�F�[���Y��A�r�N�g���A�A�N�C�[���Y�����h�Ȃǂ̊e�B�Ǝ�s���ʒn��B���]�c��́A���Ă���������]�ނȂ�A�@�B�̑���ɁA���Ă������悤�Ɍ�����X�v���[�Ȃǂ̗��p�����߂Ă���B m3.com 2015�N1��6�� |
| �s�����ہA�������������@�k�C���X�s���Ŏ��{�@�݂���\�h�Ɍ��� |
| �@�݂���̌����ƂȂ�s�����ۂ̑��������Ə����Ɍ����A���w���⍂�Z����ΏۂƂ��������������Ői��ł���B�k��̈�t�炪���S�ƂȂ�A�{�N�x�͒t���s�ȂǏ��Ȃ��Ƃ��X�s���ōs��ꂽ�B�������͊������Ă���̊��Ԃ������ɏ��ۂ��邱�ƂŁu�m���Ȉ݂���\�h�ɂȂ���v�Ƃ��āA�����͎��{���L�������l�����B �@��������ΏۂɌ�����i�߂Ă���̂́A�k���w�@��w�����Ȃ���\�h���Ȋw�u����n����t��ȂǁB �@�����̎菇�́A�܂������̂Ȃǂ��ی�҂�ɐ�����������ŁA��]�҂̔A���������āA�݂̔S���ɂ��݂��s�����ۂ̗L���ׂ�B�z���ƂȂ������k�ɂ́A�ċC�������ēx�s���A�Ăїz���������ꍇ�A��]�҂ɂ͏��ێ��Â��s���B �@���ێ��Â͐��l�̏ꍇ�Ɠ��l�ŁA�Q��ނ̍R�������ƈݎ_��}�����̌v�R��ނ��P���Q��A�P�T�ԕ��p����B����łW�������ۂł���Ƃ����B �@����\�h���Ȋw�u���̊ԕ��i�܂ׁj���T���C�u�t�i�S�S�j�ɂ��ƁA��p�͔A�������P�l�V�O�O�~�B�z���̏ꍇ�́A�ċC�����Ə��ێ��Âł���ɂP���Q��~�قǂ�����B�ی��͓K�p����Ȃ��B �@�{���̎�ނł́A�{�N�x�̌����́A�t���s���͂��ߓn���Ǔ������A���O�A�،Ó��A�m���A���т̊e���A�I�z�[�c�N�Ǔ����y���A��m�Ǔ��R�m���A�\���Ǔ��莺���̌v�X�s���Ŏ��{���ꂽ���Ƃ��m�F���ꂽ�B m3.com 2015�N1��6�� |
|
�c�u��ᇂ����{�b�g�u�_���B���`�v���g����p �É������É�����Z���^�[ |
| �@�����É�����Z���^�[�i���j�ŁA���E�̔x�̊Ԃ̏c�u�ɔ��������ᇂ���p�x�����{�b�g�u�_���B���`�v���g���Đ؏������p���n�܂��Ă���B�c�u��ᇂ̃_���B���`��p���s���̂͌����{�݂ŏ��߂āB�����I�ɂ́A�c�u��ᇂ���p�̃��X�N�������x����ւ̓K�p���ڎw���B �@�_���B���`��p�͑咰����A�݂���A�O���B����Ȃǂ̕��삪��s���A�c�u��ᇂ�x����Ȃnjċz�핪��ł͓������i��ł��Ȃ��B�ċz�핪��Ŏ�����Ă���̂́A�S���ł���w�a�@�𒆐S�ɏ\���J���Ƃ����B �@���Z���^�[�ł̎�p�́A�L��������S����������Տ������Ƃ��āA�Q�O�P�S�N�R�����炱��܂łɂR������{�����B�c�u��ᇕ���̃_���B���`��p�̎��i�����Q�l�̈�t���������Ă���B���㐔�N�Ōv�Q�R������{�����ʂ͂���v��B �@�c�u��ᇂ̎�p�͌��݁A�J�������o���i�������j�ōs���̂���ʓI�B�_���B���`��p�͋��o���Ɠ��l�Ɏ�p�̏����������čςޏ�A�p����f���摜���N���ŁA��q�i���j�̓����̎��R�x���������ƂȂǂ���A���x�̍�����p���\�Ƃ����B �@���Z���^�[�͏c�u��ᇂ̗Տ�������i�߂Ȃ���A�S�����ӂ̌��ǂɋ߂��A��p������x����ł��Տ������̎��{����������B��o�v�ċz��O�ȕ����́u�����S�Ŋm���Ȏ�p���ł���B�R�X�g�ʂȂǕ��y�ɉۑ�͂��邪�A���ʂƈ��S��������Ɋm�F���A���ۂ̎��Âɖ𗧂ĂĂ��������v�Ƙb���B m3.com 2015�N1��7�� |
| �̌��R�����[��������Q�Ł@�u����Ǝd���v�p�`�W |
| �@���҂����Â��Ȃ���d���𑱂��邱�Ƃ��x������@�^�����������܂��Ă���B�����������A���������Z���^�[���A���҂�Ƒ������̍��q�u����Ǝd���̂p���`�v��Q�ł��C���^�[�l�b�g�́u������T�[�r�X�v�i���������F�^�^���������������D�����j�Ō��J�����B�S�W�Q�y�[�W���Ń_�E�����[�h�ł���B �@���̍��q�́A�����J���Ȃ́u����ƏA�J�v�Ɋւ��錤���ǂ��Q�O�P�P�N�x�Ɏ��{�������҂�ւ̃A���P�[�g����ɁA�P�R�N�Q���ɏ��ł����\�B����ɑ����̔��������������߁A�lj���ނ����Ċ��҂̑̌��R������啝�ɑ��₵�ē��e���[���������B �@�����̊��҂��Ԃ������Y�݂��v�W�P�̖₢�Ɠ����ɂ܂Ƃ߁u�f�f���畜�E�܂Łv�u���E��̓������v�u�V�����E��ւ̉���v�u�����ƌ��N�ی��v�u�Ǝ���q��āv�̂T�͂ɐ������Čf�ځB���҂̑̌��𒆐S�Ƃ����R�������v�S�V����B �@�Ⴆ�u���f��������O�Ɏ���I�ɍ~�i��ސE��\���o��ׂ����v�Ƃ����₢�ɂ́u�E��Ǝ����̑o���Ƀ����b�g������ŊJ����l����̂��|�C���g�v�Ɠ����A�u�ӔC�҂̎������Ȃ��Ă��Ɩ��͉�����v�Ƃ����̌��R������z����ȂǁA�����I�ȉ�������C���[�W���₷���悤�A�\�����H�v�����B �@���ׂĂ̂p���`�Ɂi�P�j���Ј��i�Q�j�K�ٗp�ҁi�R�j���c�Ǝҁi�S�j���E�ҁ\�̂ǂ�ɊW������e�Ȃ̂�����������Ă��邽�߁A�����̏A�ƏɊW���鍀�ڂ������E���ēǂނ��Ƃ��ł���B �@�u�f�f���ꂽ��͂��߂Ɍ���v������B�x���c�̂���I�Ȑ��x�̏������T�C�g���Љ�Ă���B m3.com 2015�N1��13�� |
| ����]�ڑ�����`�q����@����A���Ö�J���Ɋ��� |
| �@����זE�̓]�ڂ𑣂��V���Ȉ�`�q���A���s��̌��c�_����y�����i���ː���ᇐ����w�j�̃`�[�������肵�A�Q�R���t�̉p�Ȋw���l�C�`���[�R�~���j�P�[�V�����Y�d�q�łɔ��\�����B���c����y�����́u����]�ڂ�}�����鎡�Ö�̊J���ɂȂ���\��������v�Ƙb���Ă���B �@����זE�̓]�ڂɂ͂���܂ŁA��`�q�u�g�h�e�P�v���d�v�Ȗ������ʂ������Ƃ��m���Ă����B�g�h�e�P������������ƁA�����̃^���p�N������������A����זE�̐����ɕK�v�Ȏ_�f��h�{���^�Ԍ��ǂ��V��������邪�A���̎d�g�݂������ڂ������R�͕s���������B �@�`�[���́A�l�̑S��`�q����͂��A�g�h�e�P���������������`�q���u�t�b�g�k�P�v�ł��邱�Ƃ�˂��~�߂��B���ʂ̂t�b�g�k�P�����Ċ���������������זE���}�E�X�ɈڐA�����Ƃ���A�x�ɑ����̂���זE���]�ڂ������Ƃ��m�F�B�t�b�g�k�P�������Ȃ��悤�ɂ����}�E�X�ɔ�ׁA�]�ڂ�������̐��͖�Q�E�T�{�������B �@�܂��A�l�̓����҂ŁA�a������菜���Ă���T�N��̐��������r�B�a�����̂t�b�g�k�P�����������Ă������Җ�Q�O�l�̐������͖�T�O�����������A�������ォ�������Җ�P�R�O�l�̐������͖�V�O���������Ƃ����B m3.com 2015�N1��26�� |
| ����U�����郊���p�����^�@�O�d�厡���A���p���ڎw�� |
| �@�O�d��Ȃǂ̌����O���[�v���A����זE�������U������悤��`�q���삵���Ɖu�זE�̃����p�������҂ɓ��^����Տ������i�����j���n�߂��B�����S���̉e�R�T�ꋳ���i��ᇓ��ȁj�́u����Ƃ����H������̎��ÂɌ��ʂ����҂ł���v�Ƌ������Ă���B �@�����͍��N�P�����{������{�B���������Z���^�[�i�����j�Ȃǂ��Q�����A����Q�N�ԂŌv�P�Q�l�ɓ��^�B�����ڂ��m�F�ł���A�H������̎��Ö�Ƃ��ĂT�`�P�O�N��̎��p����ڎw���B �@�����p���͒ʏ�A�E�C���X�Ȃǂ̊O�G���U�����邪�A�����ɂP�̊����ŁA����זE�Ɍ�������̃^���p�N�����U��������̂����݂���B���̃^���p�N���͐H������̍זE�ɑ����Ƃ����B �@�O�d��͂Q�O�O�T�N�ɁA����זE���U�����郊���p�������B�O�W�N�ɂ͖��Ԋ�ƂƋ����ŁA���̃����p���̒��ɂ�����L�̈�`�q���A���҂̌��t������o���������p���ɑg�ݍ��݁A��ʔ|�{���邱�Ƃɐ��������B �@�P�O�N����P�R�N�ɂ����āA�]�������N���x�Ƒz�肳�ꂽ�����̐H�����҂P�O�l�ɓ��^���A�Տ��������s�����B�傫�ȕ���p���Ȃ����Ƃ������A�����玡�Ö�J���Ɍ������������J�n���鏳�F�Ă����B �@����܂ł����҂̃����p����|�{���đ̂ɖ߂������͎��݂��Ă����B�����A����זE���U�����郊���p���̐����̂����Ȃ��A���^���Ă����ʂ͌���I�������Ƃ����B �@�e�R�����́u�����̑̂�����o���������p�����g�����߁A�R����܂ƈႢ�A���҂ւ̕��S�����Ȃ��Ȃ�͂����v�Ɛ������Ă���B m3.com 2015�N1��27�� |
| �ꌩ�E�C�b�O�A���͖X�q�@����Z���^�[�Ȃǂ��J�� |
| �@�R������Â̑�\�I�ȕ���p�ł���E�т��A�E�C�b�O�i����j�����y�ɃJ�o�[�ł���E�C�b�O��������ȖX�q�B���t���āu�E�C�b�O�Ȃڂ����v�����������Z���^�[�����a�@�i�����j�Ȃǂ��J�������B��N�W���̔�������N���܂łɖ�P�U�O�O������A�\�z�ȏ�ɍD�]���Ƃ����B �@�ȂƃA�N�������a�̃j�b�g�X�ɐl�H�т�t���Ă���A�ꌩ�V���[�g�w�A�̃E�C�b�O�B�����E�C�b�O���їʂ����Ȃ��A�U�T�O�����ƃX�J�[�t�̂悤�Ɍy���B�t���[�T�C�Y�ŁA�X�q�̉��ɒʂ����S���ő傫���߂ł���B �@�E�C�b�O�͐��\���~�ƍ��z�ȏ��i�������A�����Ԃ��Ԃ�Ɠ������߂����ĕs�����Ƒi����l������B�o���_�i��X�q���悭�g���邪�A���Ԃ����p���a�C�ł��邱�Ƃ��v���o�����Ă炢�Ƃ������҂�Ƒ������Ȃ��Ȃ��B�����œ��a�@�̖��j�q�i�̂���E�������j�A�s�A�����X�x���Z���^�[�����A��×p���烁�[�J�[�̓����`�����`�Ɩ�P�N�����ĊJ���Ɏ��g�B �@�u�����܂ʼnB�����Ƃ�ړI�Ƃ����E�C�b�O�ƈႢ�A����Ȃǂʼn��K�ɂ��Ԃ�邱�Ƃ��d�������v�i���j���߁A�������ɓ�����Ɣ����߂���ĖX�q�̉��������邱�Ƃ����邪�A�w���҂���́u�O�o���ɂ��Ԃ��ďd���v�Ȃǂ̐������Ă���B���́u���l�͈ӊO�ɋC�ɂ��Ă��Ȃ��B�����ƋC�y�ɐ������Ă����Ǝv���Ă��炦����ꂵ���v�Ƙb���B �@�����`�����`�������A����ō��݂P���U�W�S�W�~�Ŕ̔����A����グ�̂����{�̉��i�P���T��~�̂P�O�������������Z���^�[�Ɋ�t�����B�₢���킹�́A �t���[�_�C�����i�O�P�Q�O�j�Q�P�O�X�O�R�B m3.com 2015�N1��27�� |
| �̌������ł��X�N�]���@�A�~�m�_��� |
| �@���t���Ɋ܂܂��Q�O��ނ̃A�~�m�_�̔Z�x�𑪒�E��͂��A���̃o�����X�̕ω�����A����̉\����T�錟��������{�݂������Ă���B�P���T�~�����b�g���̍̌������ŕ����̂�����ɒ��ׂ���ȕւ��������ŁA��f�҂̓��X�N�������Ɣ��肳�ꂽ����ɍi���Ď��̃X�e�b�v�ł��鐸������������B�S���ɐ�삯�Q�O�P�P�N�H�ɓ��������O��L�O�a�@�i�����j�ŁA�M�ҁi�T�S�j���������Ă݂��B �@���X���l����f �@���a�@�̑������f�Z���^�[����f�����͍̂�N�X�����{�̂��Ƃ������B�t�����ς܂��A�ҍ����Ŗ�P�O���B���O���Ă�č̌����Ă��炤�B���������ꂾ���B�a�@��������킸���R�O���قǂŁA���ׂĂ��I������B �@���̌����́u�A�~�m�C���f�b�N�X���X�N�X�N���[�j���O�i�`�h�b�r�j�v�ƌĂ��B���̑f���J�������Z�p��Տ����p�������̂ŁA���݁A�j���͈݁A�x�A�咰�A�O���B�̂S��ށA�����͈݁A�x�A�咰�A���[�̂S��ނ̂���ɉ����A�ʂɂ͔���ł��Ȃ����̂̎q�{��i�����j����A�q�{�̂���A��������̂����ꂩ�ł��郊�X�N��]���ł���B �@���̑f�ɂ��ƁA���{�����Ë@�ւ͌��ݑS���ɖ�X�O�O�B�N��ǂ����Ƃɑ����Ă���B��f�Ґ��͉��ז�X���l�ɒB�����B���t�ɂ͐V�����X���i���������j���������錩���݂ŁA���^�{�Ȃǂ���ȊO�ł̎��{����������Ă���B �@�ق�̌y���C�����Ŏ������B�����A�����قǂ����Ď���ɓ͂������ʕ��́A������ƋC�ɂȂ���̂������B �@�������N�b�̈Ӗ� �@���N�Ȑl�ł͌����A�~�m�_�̔Z�x�䗦�͂قڈ��ɕۂ���Ă��邪�A����Ɉُ킪�N����Ɣ䗦�������ɕς��B�ω��̃p�^�[���͑����a�C�ɂ���Ă��ꂼ����������邽�߁A����̃��X�N����ɗ��p�ł���B �@���X�N�͂O�E�O�`�P�O�E�O�܂ł̐��l�Ŏ�����A����Ƀ��X�N�̒Ⴂ�����烉���N�`�i�O�E�O�`�S�E�X�j�A�����N�a�i�T�E�O�`�V�E�X�j�A�����N�b�i�W�E�O�`�P�O�E�O�j�̂R�i�K�ɕ��ނ����B �@�M�҂͈݂Ɣx�������N�`�A�O���B�������N�a�B���͑咰���B���l���W�E�S�Ń����N�b�������B �@����̎�ނō������邪�A�����N�b�̃��X�N�͈�ʂ̂S�E�O�`�P�P�E�U�{�܂ō����Ȃ�B�咰�͂W�E�Q�{�B��ʂ̗L�a������l�ɂP�l���Ƃ���A�P�Q�Q�l���P�l������Ƃ����v�Z�ɂȂ�B �@�`�h�b�r�́A����̗L���ڒ��ׂ錟���ł͂Ȃ��B���X�N�̍����l�������o���A���������Ɍ��т���̂������B�����N�`�ł�����łȂ��Ƃ͌�����Ȃ����A�t�Ƀ����N�b�ł��A�K����������Ƃ͌���Ȃ��B �@������I�Ɍ����� �@�Ƃ͂����u���X�N�������v�ƌ�����Εs���ɂȂ�B�����A�������f�Z���^�[���C�ږ�̎R����i��܂��ǁE�݂̂�j��t�̊��߂ɏ]���A�P�Q�����{�A�咰���������������B���ʂ́u�ُ폊���Ȃ��v�B������A���̑O�i�K�̃|���[�v��������Ȃ������B �@�����R�傳��͌����B�u���Ƃ���������Ȃ��Ă��A�����N�b�̐l�͒���I�ɐ����������Ăق����B�摜�Ŕ����ł��Ȃ������ȕa�ς���������\���͂��邵�A���݂̑̎����A����ɂȂ�₷����Ԃł���Ƃ�������B�H������^���Ȃǂ̐����K�����������A����ɑ���Ɖu�͂����߂邱�Ƃ���ł��v �@���{�l�̂Q�l�ɂP�l������ɂȂ鎞��B����̍����ɂ́A�����̐l����f�ł���ȕւő̂̕��S�����Ȃ��������������Ȃ��B���݁A�`�h�b�r�ȊO�ɂ��A���܂��܂ȕa�@�⌤���@�ւ��V���Ȍ����@�J���Ɏ��g��ł���B �@���Ȃ݂ɂ`�h�b�r�Ɍ��N�ی��͓K�p���ꂸ�A�������̗̂����͂Q���~��Ƃ����{�݂������B�i�������ԍ�B��j m3.com 2015�N1��27�� |
| �i�s�咰����̕��o����p�A�������X�O���� |
| �@���Â𑽂��肪���鍑���R�O�a�@���Q�����������ŁA�i�s�����咰����̎�p�������҂̂T�N���������J����p�ƕ��o����p�łǂ�����X�O�������Ƃ̒������ʂ��A���{�Տ���ᇌ����O���[�v�����\�����B �@�č��Ő挎�J���ꂽ�����킪��V���|�W�E���Ŗ��炩�ɂ��ꂽ�B�����́A���������Z���^�[�𒆐S�Ƃ��铯�O���[�v���A�����ɊJ���������Ȍ�����A�J������؏��������čs�����o����p�̒������т��A�]���̊J����p�Ɣ�r���邽�߂ɍs�����B �@�咰�̑������߂錋���ƁA�����̈ꕔ�ɂł��������ΏۂƂ����B�i�s�x�́A���咰�̕ǂ̋ؓ��w���Ă��邪�����p�ߓ]�ڂ͂Ȃ��X�e�[�W�Q�ƁA�����p�ߓ]�ڂ�����X�e�[�W�R�B�Q�O�O�S�`�O�X�N�ɂR�O�a�@�Ŏ�f�����咰���҂P�O�T�V�l�����́B���҂�ׂɊJ����p�i�T�Q�W�l�j�ƕ��o����p�i�T�Q�X�l�j�ɕ����A�X�e�[�W�R�̊��҂ɂ͍R������Â��s���ĂT�N�ԒǐՂ����B �@���̌��ʁA��p��̂T�N�������́A�J����p���X�O�E�S���A���o����p���X�P�E�W���ŁA�����̎��Ð��тƂȂ����B�ߋ��̍��������ł́A�J����p�ƕ��o����p�����킹���T�N�������̓X�e�[�W�Q�Ŗ�W�O���A�X�e�[�W�R�Ŗ�V�O���Ƃ���A����̐��т͂����傫���������B �@��p��A�T�N�ԍĔ������ɐ��������������A�J����p�V�X�E�V���A���o����p�V�X�E�R���ŗ��҂͓����������B �@���\�����啪��w������E�����O�Ȃ̒��҉�j�����́u�咰����́A�n��������t����p���s���A�J���ł����o���ł��A�����̍������������邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�B���ۓI�ɂ��ւ�鐬�т��v�Ƃ��Ă���B m3.com 2015�N2��6�� |
|
�r�b�O�f�[�^���p�Ɋ��҂Ɖۑ�A����V���| DPC�f�[�^�����p�����������ʂȂǂ��Љ� |
| DPC�i�f�f�Q����ށj�Ƃ́A�uDiagnosis Procedure Combination�v�̗��ŁADiagnosis�i�f�f�j��Procedure�i���ÁE���u�j��Combination�i�g�ݍ��킹�j�������BDPC�i�f�f�Q����ށj�Ɋ�Â��f�Ï��f�[�^�́A�r�b�O�f�[�^�ƂȂ�B �@���{��t��������@�\����Â���V���|�W�E���u���{�ɂ������Ãr�b�O�f�[�^�̌���Ɩ����v��2��12���ɊJ�Â���A��ÊE�ł��}���ɐi�ރr �b�O�f�[�^�̊��p�݂̍���ɂ��ċc�_���ꂽ�BDPC�f�[�^���g�����ƂŁA�a�@��n��ł̐f�ÌX���͂ł���悤�ɂȂ�Ȃǎ��Â�����Ăւ̍v�������҂�������A��ꂩ��͈�Ì���̈ޏk�ɂȂ��肩�˂Ȃ��Ƃ̕s���̐�����ꂽ�B ���p�̂��ߐV���Ȏd�g�ݕs�� �@�ŏ��ɓo�d����������w��w�@��w�n�����Ȉ�Ìo�c����w�u�����C�y�����̎R�{���ꎁ�́A�u��Ï���K�̓f�[�^�x�[�X�ƃv���C�o�V�[�̕ی�v�Ƒ肵�āA���{�ɂ����Ï��̌���ƍ�����ɒ�o�\��̌l���ی�@�ĂȂǂɂ��ĉ�������B���Z�v�g���E���茒�f�����f�[�^�x�[�X�iNDB�j�⍑�ۃf�[�^�x�[�X�iKDB�j�A���F��f�[�^�x�[�X�ȂǁA���{�͐��E�ɐ�삯�Ĉ�Ê֘A�̓d�q�����i���A����Łu�f�[�^��~���ė��p���悤�Ƃ����l���ɖR���������v�Ǝw�E�B�������ׂ��ۑ�Ƃ��āu�ړI�̈قȂ�f�[�^�x�[�X�����̂��߂̋���ID�̐����v�u�f�[�^�w������̃v���C�o�V�[�ی�̎d�g�݁v�Ȃǂ������A�����̓G�r�f���X�Ɋ�Â����������Ă��ł���悤�ɂȂ�Ɗ��҂����B �@2015�N4���ɁA�����ł͌����J���ȂƓ�����w�A���ł͋��s��w�ɂ��ꂼ��ݒu�����NDB�̃I���T�C�g���T�[�`�Z���^�[�ɂ��Ă��Љ���B�Z���^�[���ł͌����҂��K�v�ȃf�[�^�͂ł���悤�ɂȂ�A�Z�L�����e�B�m�ۂ̎�Ԃ��Ȃ���悤�ɂȂ�B �l���ی�Ō����Ɏx��� �@����ŁA�l���ی�̃��[�������������ɏ]���āA���Ăł͉u�w���������ɂ����Ȃ��Ă���Ƃ����B���{�ł��u���̕ی삪�D�悳��A�ǂ����p����邩���l�����ĂȂ��B���{�ɂ͖�2000�̌l���ی샋�[��������Ƃ���A�A�g���������̍ۂɂ͔��ɑ傫�ȏ�ǂɂȂ��Ă���v�Ǝw�E�B���ĂƂ��āA��w�E��Ï��l�b�g���[�N�����A���̒��ł�����È�w����̃f�[�^�x�[�X�����ѕt������悤�Ȏd�g�݂���邱�Ƃ��Ă����B �@���������Z���^�[�������Z���^�[���v�����������Ô�������̐ΐ�x���W���~�����ꎁ�́A�u��Ãr�b�O�f�[�^�̌������p�F���̌���Ɖۑ�v�Ƃ��āADPC�f�[�^���g�������͂̎�����Љ���BDPC�f�[�^��1800����a�@�ō쐬����A�N��1000�����̑މ@���҂̓��@�f�[�^�ƊO���f�[�^�����J�Ȃɒ�o����Ă���B �@�����Ȋw�����ǂł͌��J�Ȃɒ�o�����f�[�^�̃R�s�[���W�߂Č������s���Ă���B2012�N�x�Ɏ��{���������w���Â̕��͂ł́A�x���i4.51���l�A���בމ@��9.98����j �̎��Ö@�͂����B�J���{�v���`���ƃp�N���^�L�Z���̑g�ݍ��킹��4834�l�̊��҂ɍs��ꂽ���A���@�����̕��z��3���A10���A17�`24����3�p�^�[�����邱�Ƃ����������B�ΐ쎁�́u���ғ����̉e���Ƃ��������A�{�݊Ԋi��������̂ł́v�Ǝw�E�����B �@�܂��A�}�N���I�ȕ��͂̎��_�Ƃ���DPC�f�[�^�Ɋ܂܂�Ă���X�֔ԍ����g���āA�}���S�؍[�ǂł̋~�}�����͂�������Ȃǂ��Љ���B���Ð��т̕]����ڍׂȕ��ʕʂ̉�͂ȂǂɓK���Ȃ��Ƃ��A�ΐ쎁�́uDPC�f�[�^���j�Ƃ��āA�K�v�ȃf�[�^��lj��E�⑫���邱�Ƃŕ��͂̌������E�v������}���v�Ƙb�����B �@��t�ŁA���f�f�[�^�̕��͂Ȃǂ��s���~�i�P�A�В��̎R�{�Y�m���́u�r�b�O�f�[�^����̈�ÂƗՏ��Ƃ̂�����v�Ƃ��āA�Տ�����łǂ̂悤�Ɉ�Ï��ƌ��������ׂ����ɂ��ċc�_��W�J�B��Â̕��G������ߑ����i��ł��錻��Ƃ��āA�S�������g�����̘_����1��5�{�ǂ�ł�20�N�����邾���̒~�ς����ɂ���A����ɑ�ʂ̒m�������X�ςݏd�Ȃ��Ă���ƗᎦ�����B �@����ŁA2010�N�x�̒����ł́ALDL�R���X�e���[���l��160mmHg�ȏゾ����1��5665�ᒆ�A 9�������Â��Ă��炸�A�u��Âւ̃x�X�g�A�N�Z�X�ݏo���ɂ͂ǂ̂悤�ȏ����ǂ̂悤�ɓ`�B���ׂ������l����K�v������v�Ǝw�E�B�ǂ�ȂɃf�[�^���ςݏd�Ȃ��Ă��u���E�Ƃ��āA�f�[�^�����ꂽ���������A���g�̐l�̖����ւƊҌ�����ӔC�͕ς��Ȃ��v�Ƃ܂Ƃ߂��B DPC�f�[�^�̎g�r�Ɍ��O�� �@�p�l���f�B�X�J�b�V�����ł͍ŏ��ɁA���{��t���C�����̐Έ䐳�O�����A���E���ŋc�_���i��ł���u�f�[�^�x�[�X�ƃo�C�I�o���N�ɂ�����ϗ��I�l�@�Ɋւ��鐢�E��t��錾�āv�ɂ��Đ��������B�����̓w���V���L�錾�ɕ⑫����`���������A���E���Ŕ������傫���������߁A�p�u���b�N�R���T���e�[�V���������߂邱�ƂɂȂ����Ƃ��āA���{�ł��ϋɓI�Ȉӌ����e�����߂��B �@��ꂩ��́uDPC�f�[�^�̕��͂����҂̑����މ@�𑣂����߂Ɏg���Ȃ��悤�ɂ��Ăق����B����ł͂����������Ď^���ł��Ȃ��v�Ƃ����ӌ�����ꂽ�B�R�{���ꎁ�́u�N�����Ɛ肵�ĉ��������邱�Ƃ͔����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ǝw�E�B�ΐ쎁���u��O�҂̌����@�ւ��璆���I�ȃI�s�j�I�����ł�悤�ɁA�f�[�^�̉�͂̏����āA���낢��Ȑl�Ɏg���Ă��炤�v�A�R�{�Y�m�����u���̊��p���L�����Ă����͔̂������Ȃ��B�o�Ă������ʂ��ǂ�����č��̎{��ɂ��Ă������Ƃ����A���Q�̂��荇�킹�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��v�Ɠ������B m3.com 2015�N2��15�� |
| ���g�z���~���A��i���҂̔x��3���� ��i���҂Ń��X�N�����A�i���҂Ń��X�N���� |
| �@�č����w��iAACR�j��2��2���A��i���̓��A�a���҂Ń��g�z���~���ɂ��x�����X�N����3���ቺ���邱�Ƃ��������������Љ���BCancer Prevention Research���Ɍf�ځB �@�������́A40�Έȏ�̓��A�a����4��7351�l�i�j��54���j��ΏۂɁA���g�z���~���̏����Ɣx�����X�N�̊֘A�����������R�z�[�g�Ō����B1994-1996�N�̓��A�a���Ö�Ɋւ���������W���A6�J���ȓ���2��ȏチ�g�z���~�����������ꂽ��46�����u�g�p�ҁv�ƒ�`�����B �@15�N�̒ǐՊ��Ԓ��A�x���Ɛf�f���ꂽ747�l�̂����A80�l����i���҂ŁA203�l�������_���i���҂������B�S�̂Ƃ��Ă̓��g�z���~���̎g�p�Ɣx�����X�N�ቺ�Ɋ֘A���͌����Ȃ��������A ��i���̓��A�a���ҌQ�ł�43���A5�N�ȏチ�g�z���~�����g�p���Ă�����i�����҂ł�52���̔x�����X�N�ቺ������ꂽ�B �@���v�w�I�ɂ͗L�Ӎ��͂Ȃ����A5�N�ȏ�̃��g�z���~�������g�p�ŁA��i���҂ɍł������B�����X�N��31���ቺ���A�i���҂ɑ������זE�x�����X�N��82�����������B �@�����҂́u���g�z���~������i���҂ł̓��X�N�������A�i���҂ł̓��X�N�����߂�Ƃ����A�i�����ɂ�胊�X�N���قȂ�\�����������ꂽ�̂͗\�z�O�������v�ƌ������ʂ́B����A��K�͌����ɂ�����̕����W�c�i���ɔ�i���ҁj�ɂ����āA�x���₻�̑��̊��\�h�Ƀ��g�z���~�����L������������K�v�����������Ă���B m3.com 2015�N2��17�� |
|
�u��Ôے�{�v�Ƃ̌��������� �w�����R�Ɏ��鐶�����x�ɂ��� |
�� �q�O�i���s����c�a�@ ���킳�������P�A�Z���^�[ ��ᇓ��ȁ^�ɘa�P�A���ȁj �@�ߓ������͂��߂Ƃ����A������u��Ôے�{�v�̗ނ́A�������N�ŏ��X�ɋ}���ɑ����Ă���B �@����́A���{�����̌��ۂȂ̂��Ǝv���Ă�����A�C�O�ł��́w�����R�Ɏ��鐶�����\�\�]���鍐����u���I�Ȋ����v�Ɏ������l���������H���Ă���9�̂��Ɓ@�P���[�E�^�[�i�[ (��)�x����Ԃ悤�ɔ���A���{�ł��|��{���A�}�]���Ńx�X�g�Z���[1�ʂɂȂ����A�Ƃ������Ƃ��A�u�������Ôے�{�̗ނ��Ȃ��`�v�Ǝv���w�����Ă݂��B �@�ǂ��z�Ƃ��āA�ꌾ�Ō����u�댯�v�B �����A���낢��Ǝv���Ƃ�����������̂ŁA�܂������u�댯�v�Ǝv���������珑���Ă������Ǝv���B ���u�R����܂���ː���ے肵�Ȃ��v�Ə����Ȃ��猋�ǔے�I�Ȉ�ۂ�������邱�� �@���̖{�̑�܂��ȗv�_�����A���E�ɂ́u����v�Ɛf�f�����t���猵�����]�����������Ȃ�����A�������猀�I�ȉ��݂��A����������A���������������B������B���̕��B�́A����܂łقƂ�ǒ��ڂ���Ă��Ȃ������̂��A���̒��҂����E��������ăC���^�r���[�⒲�����s���A���ʂ���s���p�^�[���𖾂炩�ɂ����Ƃ������́B �@���ʓI�ɁA9�̋��ʓ_�Ǝ��H�𖾂炩�ɂ��A��������҂���̃G�s�\�[�h�������Ȃ��珑���A�˂Ă���̂��{���ł���B �@���҂́A�`���Łu���̖{�͎�p�A�R����܂���ː����Ái������3��Ö@�j��ے肵�Ȃ��v�Ə�����Ă���̂����A���ʓI�ɏ�����Ă�����e�́u3��Ö@���������ǃ_���������B����9�̎��H���s�����玡�����v�Ƃ������̂ŁA�i�Ӑ}�͂��Ă��Ȃ��ɂ���j���ʓI�ɓǎ҂�3��Ö@�ɂ��Ĕے�I�Ȉ�ۂ�����悤�Ȃ���ɂȂ��Ă���B �@����܂ł́u��Ôے�{�v�́A�ߌ��Ș_���ň�Â�ے肷����̂�����A�u������Ƌɒ[���Ȃ��v�Ƃ�����ۂ�����āA���ʓI�Ɂi������ƐT�d�ɂȂ���j�K���Ȉ�Â���A�Ƃ����p�^�[���͑��������B �@�������A�{���͂����������ߌ������ꌩ���Ȃ��Ƃ���Łi�I�J���g�ȕ����͂��邪�j�A���ʓI�ɐ��m��w��ے肷��悤�ȗ����{�̒��Ő��ݏo���Ă���Ƃ��낪�u�댯�ł���v�Ǝ����l�������̗��R�ł���B �@�܂��A���̈�Ôے�{�₪��r�W�l�X�̕��X�ƈꏏ�ŁA3��Ö@���Ď���������Ȃ̂ɂ����͏������A���p�������̕��@�������Ď������̂��A�Ə����Ă��鎖����U�������B ���u����͉����ł���v�ƌ����Ȃ�����u����������H���܂��傤�v�̘_�� �@�����ЂƂ́u�댯�v�́A����܂��`���Ɏ����ꂽ�u����͉����ł���v�̈ꕶ�B ���ہA���̒��҂��s���������́A����ɂȂ��Ď������l�B�̎�����W�߂āu���ʓ_���܂Ƃ߂��v�����ł���A�m���Ɂu�����v�̑����o�Ȃ��B �@�������A������܂��{����ǂނƂ���Ȃ��Ƃ͓����甲���Ă��܂��悤�Ȃ��肾�B �����A�Ƃ����ꕶ�����邩��Ƃ����āA���̖{��ǂ�ň�Â��邱�Ƃ���߁A���̖{�̒ʂ�Ɏ��H���Ă��������鎞�Ԃ�Z�������Ⴊ�������Ƃ�����A����͖Ɛӂ������̂ł͂Ȃ��B ���u������Ăǂ��Ȃ́v�ȑ�֗Ö@�𑽐��Љ�Ă���_ �@�{���ł́A3��Ö@�ł͂Ȃ����̑�֗Ö@�Ŏ������A�Ƃ������Ă��鎖�Ⴊ�������o�Ă��邪�A���̑S�Ă��Ȋw�I�ɂ͌�����Ă��Ȃ��A�������͔ے肳�ꂽ�悤�ȓ��e�ł���B���ɂ͏@�����������A������Ɣw�������Ȃ镔��������i�ґz�Ȃǂ��̂��̂�ے�͂��Ȃ����j�B �@��֗Ö@���Ȃ��猒�N�I�ɉ߂����Ă���Ⴊ����A�Ƃ������Ƃ����͔ے肵�Ȃ��B�������A���̉e�ł���玡�Ö@���Ȃ�����S���Ȃ��Ă������X���{���ɂ�������̂��Ƃ��������͌��R�Ƃ��Ă���B���̂��ƂɐG�ꂸ�A�ꕔ�́u�܂�Ȏ���v��������グ�A���ꂪ���l�ɂƂ��Č��ʂ����肻���ȏ�����������̂́A��͂�u�댯�v�ƌ��Ȃ�����Ȃ��i��قǂ��q�ׂ��悤�Ɂu�����v�Ǝv���Ȃ��悤�ȏ�����������j�B �@���X�̈�Ôے�E��֗Ö@��^�n�̖{��ǂ�ł��Ďv�����Ƃ����A�e�[�}�͑S�āu���邩�A����Ȃ����v�ŁA����Ώ����E�K���A����Ȃ���Ε����E�s�K�A�Ƃ������l�ς�����悤�Ɏv����B����͖{���ɂ����Ă������鉿�l�ςł���B�l�݂͂ȁA���ׂ��炭���Ɍ������Ă���Ƃ����̂ɁH���Ƃ�����A�l�Ԃ͂ǂ�����Ă��K���ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B �@3��Ö@�ł͍K���ɂȂ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ������������{�Ȃǂł͌J��Ԃ��咣����邱�Ƃ����A�J�ł͂��ꂪ�^�����Ǝv�킳��Ă���ʂ����邩������Ȃ��B �@���������ۂɂ́A3��Ö@���Ď��������X�́A���Ȃ��Ƃ�������������֗Ö@�ȂǂŎ��������X�����ԈႢ�Ȃ��吨���邵�A�����ƈ��҂ɂ��ꂪ���ȍR����܂ł͂��邪�A���Ȃ茵�����]���ƌ��킴��Ȃ��S�g�ɂ��]�ڂ������҂���ł��A����Ŏ���Ƃ������������ă[���ł͂Ȃ��̂ł���B �@�����āA�����3��Ö@�{�ɘa�P�A�ŁA����Ȃ��܂ł��A�����Ă��鎞�Ԃ��������莿�̍���������Nj����邱�ƂŁA���ʓI�ɍK���Ǝv����l����S��������X������B �@�{���́A�C�O�̐��������ȐS���m�̕��������Ă��ĐM���ł������Ƃ�����ۂ��������_�A����܂ł̈�Ôے�{�ƈقȂ�D�����ȑ����A�����Đ�ɏq�ׂ��u3��Ö@�ے肵�Ȃ��v�u�����v�ƌ����Ȃ�����nj�ɂ͂����Y�ꂳ����悤�ȍ\���A�Ƃ������_����A�l�I�ɂ͂�蒍�ӂ��ēǂނׂ��{�ł���ƍl����B ���K���Ƃ͉����A�Ƃ������� �@�����܂ŁA�{���ɔے�I�Ȉӌ��������A�˂Ă������A���Ⴀ���̖{�͓ǂނׂ��ł͂Ȃ����A�Ƃ����ƁA�ǂ�ł����Ĉ����Ȃ��{�ł͂���Ǝv���B �@��������Î҂́A�����̂悤�Ɋ��҂���₲�Ƒ��Ɍ��������t��`���Ă���B�a���̍��m�A�Z���\��A�\�z����鎡�Â̕���p�A����Ƒ̗͂������Ă����o�߂Ȃǥ���B �@�����t�͂����̌��t�������āu�v�ƕ\�����Ă����B��X��Î҂͓��X�A���҂���Ɂu�v�̌��t��f���Ă���̂��ƁB�m���ɁA�̂悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B�����̌��t�������Ă��āA���҂���̋C������������������A�O�����ɂ���v�f�͂ЂƂƂ��ĂȂ��̂�����B �@���҂���֗Ö@�Ȃǂ������A�Ƃ�����]���o�����Ƃ���������Ȃ��ɔے肵�Ă��Ȃ����B���������Ӗ��u�v�ŁA���҂����̎��Ö@�ƑO�����ɐ����Ă������Ƃ����C�����܂ňނ������Ă��₵�Ȃ����B �@�u������͒����Ȃ��̂ŁA���Ƃ͎����̎��Ԃ��ɉ߂����ĉ������v�Ƃ����ނ̌��t���������āA���������ǂ�قǂ̐l���u�����̎��Ԃ��Ɂv�߂�����̂��낤���B���Ɍ������āA�O�����ɐ�����A�Ƃ����͕̂����̂��Ƃł͂Ȃ��B��X��Î҂́A���̖��z���Ȃ��ׂ��ł���B �@����T�����Ȃǂŏo����҂���́A�O�����ȕ����{���ɑ������A���Ɍ������đO�����Ƃ�����肠���܂ł����Ɍ������đO�����A�����̐l���������A�Ƃ������ӂ�������B�����������X�Ɛڂ��Ă���ƁA�ɘa�P�A�ŋ�������u�������߁A����邱�Ƃ���v�Ƃ������\�����{���ɉR�������v����B �@�����A���̕��X�����������ɓˑR�����������S���ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��B�F����A�����̊�����ꂵ�݂����z������ŁA������������������I�A�Ƃ����Ƃ���ł���B�N�������ȒP�ɏ��z������悤�ȓ����ł͂Ȃ��B���̕��݂̎菕���Ƃ��āA�{���͏����ɂȂ镔��������̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł���B �@���Ɂu���Ö@�͎����Ō��߂�v�u���O�����ɐ�����v�u�w�ǂ����Ă������������R�x�����v�Ƃ����������́A�������ӂł��镔�������X����B ����Â̖ړI�͖����������Ƃ� �@�����́uNo�v�ł���A�Ǝ��͍l����B��Â̖{���̖ړI�́u�l�����K���ɐ��������Ă��炤�菕�������邱�Ɓv�ł���B �@���ہA�u�K���v�͂��ꂼ��̐l�ɂ���ĈႤ���̂ł��邵�A�ʓI�Ɂi�����ɂ́j�v���ł���Ȃ��B����ŁA���̒����͖��m�Ɍv�����ł���B�Ȃ̂ŁA���������邱�Ƃ́u�K���v�𑪂��֎w�W�̂ЂƂɉ߂��Ȃ��̂��Ǝv���B �@�{���ł́A�������Ē���������A�Ƃ������Ƃ��ΓI�ȉ��l�Ƃ��Ă���B�������A����9�̎��H�Ŗ��l������킯�ł͂Ȃ��u�����v�ł���ȏ�A���̖{�������������u���Â̎�����v�Ƃ��ĂƂ炦��Ȃ炻��͂�͂�댯�ł���B�������A���̓_�ɒ��ӂ��āA�O�����ɐ����邽�߂̃q���g�A����������Ȃ��琶�����邽�߂̃q���g�邽�߂̖{�Ƃ��ẮA�ǂމ��l������B �@��X��Î҂́A�Ȋw�҂Ƃ��ē`����ׂ����Ƃ͂�����Ɠ`����ׂ������A�댯�Ȏ��Ö@�⍼�\�Ɋ��҂����������Ƃ��Ă���̂Ȃ�A����͎~�߂�ׂ��ł���B����������ŁA���҂���B�������ɑO�����ɐl�������邱�Ƃ��ł��邩����ɍl�������Ȃ��ƂȂ�Ȃ��B����́u�����炵�������ĉ������v�ƒʂ��Ղ̌��t�������邱�Ƃł͌����ĂȂ��B�����g�ɂ��܂������͂Ȃ����A�Ȋw�҂ł���l�ԂƂ��āA���҂���ƌ��������o�傪�܂��͑�ł���Ǝv���B m3.com 2015�N2��21�� |
|
�]�����Ŕ��������A���S���X�N��3�{�� �]�������҂ɑ������X�N���[�j���O�� |
| �@�č��S������iAHA�j��2��12���A�]�������҂̔���������]�����҂�荂�����Ƃ��������������Љ���B2015�N�x���۔]�����w��Ŕ��\�B �@���̌�����1997-2001�N��VISP���{�ݎ�������A���ɜ늳���Ă��Ȃ��y�x�������]�������ҁi35�Έȏ�j3247�l�̃f�[�^����͂������́B��ʕ�W�c�̔������ɂ͕č����������̃f�[�^��p���A�]�������҂Ɣ�]�������҂̔�������1�J���A6�J���A1�N�A2�N�̎��_�Ŕ�r�����B �@��������N��Œ��������Ƃ���A�]�������҂͈�ʕ�W�c����������1�N��1.2�{�A2�N��1.4�{�����A���ǂ����]�������҂͔��ǂ��Ȃ������҂�莀�S���X�N���ő�3�{�������Ƃ����������B �@�܂��A50����]�������҂�2�N�ȓ��Ɋ��ǂ���\���́A50�Έȉ��̊��҂��1.4�{���������B�팱�҂����ǂ������́A�畆���A�O���B���A�����A�x���A�N�����ȂǑ���ɂ킽�����B �@�����҂͌������`�����₷�����߁A�]�������ǃ��X�N���������Ƃ��m���Ă���B����A���Ǖǂɂ���čזE�����������ƁA����Ȑ����@�\�ɕω��������炷��A�̎��ۂ��N����A�����ɂȂ��邱�Ƃ��l������Ƃ����B�����҂́u�i���A�����A���̉Ƒ����Ȃǔ������X�N�����߂���q�����]�������҂ɂ́A���X�N���[�j���O�𑁊��ɍs���ׂ��v�Əq�ׂĂ���B m3.com 2015�N2��26�� |
|
�S���z�������Ɋ��]�ڗ\�h���� ���������Z���^�[�AANP�̌��Ǎ�p����m�F |
| �@�����z��a�����Z���^�[�y�v�`�h�n�������̖�K������̌����O���[�v�͂��̂قǁA�S�����番�傳���z�����������ǂ�ی삷�邱�Ƃł��܂��܂Ȏ�ނ̊��]�ڂɑ���\�h�A�}�����ʂ��F�߂�ꂽ�Ɣ��\�����B�S�[���i�g���E���A�y�v�`�h�iANP�j���^�}�E�X�̔x�]�ڂ��ΏƌQ���L�ӂɏ��Ȃ������ق��A���Ǔ���זE�ɐڒ�������זE����}�����郁�J�j�Y�����m�F���ꂽ�Ƃ����B���Z���^�[�ł͔x����p���Ώۂ̑��{����������\�肵�Ă���A�V���Ȋ����Â̊m���Ɋ��҂��Ă���B �@ANP��1984�N�ɔ������ꂽ�S���z�������ŁA��ɐS�s�S���Âŗp�����Ă���B���Z���^�[�ł́A����܂łɔx����p������ANP���p�ʂ�3���Ԏ������^����Əp��s������L�ӂɗ}���ł��邱�Ƃ�A�ǐ��x��������������x�����҂ł��܂��܂ȐS�x�����ǂ��\�h�\�Ȃ��Ƃ���Ă����B �@���̒ǐՒ����̌��ʁA�����Ǘ\�h�ړI��ANP���^�Q�i��p�{ANP�j�́A��p�P�ƌQ���p��2�N���Ĕ����������ǍD�Ȑ��тł������B���Q�ŔN���ʁA���i�s�x�Ȃǂv��͂��Ă����l�̌��ʂł��������Ƃ���AANP�����]�ځA�Ĕ��}���ɉ��炩�̌��ʂ������炵�Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�@�B�}�E�X�������F����ڐA�����x�]�ڃ��f���}�E�X���쐬���A�ΏƌQ��ANP���^�Q�Ŕ�r�����B �@���̌��ʁAANP���^�Q�͗L�ӂɔx�]�ڂ����Ȃ������BANP�̍�p�ɂ��Ă������������A���ɂ�ANP��e�̂��������Ă��Ȃ��������Ƃ���AANP�����ȊO�ɍ�p���Ă���\�����������ꂽ�B������ANP��e�̈�`�q�����Ǔ���זE�œ��ٓI�Ɍ��������}�E�X���쐻���A���l�̎������J��Ԃ����B��`�q�����}�E�X�ł͔x�]�ڂ��L�ӂɑ������Ƃ������������߁AANP�̊��]�ڗ\�h���ʂ͌��ǂւ̍�p���ʂł��邱�Ƃ����������B�܂��AANP�ɂ���čł��}��������`�q���A���ǂɓ��ٓI�ɔ�������ڒ����q��E�Z���N�`���ł��邱�Ƃ����肵���B �@�ȏォ��A���Z���^�[�́u��p�Ō������o�����V�����זE�́A��p���̉��ǂŎ�N���ꂽE�Z���N�`���̔������i�ɂ���Č��ǂ֕t���A�Z�����邱�Ƃ�����A���ꂪ�p�㑁���̍Ĕ��A�]��̈���ƂȂ��Ă���BANP�́A����E�Z���N�`���̔�����}���邱�ƂŊ��̏p��Ĕ��A�]�ڂ�}�����Ă���ƍl������v�Ƃ̌����������Ă���B m3.com 2015�N3��3�� |
|
���g�z���~�������U��T�זE���� ���R��A�זE���̑����Ƌ@�\������ |
| �@���R��w��w�@�㎕��w���������Ȃ̌����O���[�v�́A�Q�^���A�a���Ö�u���g�z���~���v�ɂ���זE���E������G�t�F�N�^�[�b�c�W�s�זE�̔敾���ۂ������A����זE���U�������p�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B �@�b�c�W�s�זE�́A�敾���q����̕��̃V�O�i���ɂ���Ă���זE�̎E���\�́A���B�\�͂̏����ɂ��A���̑������זE������B�敾���q�̋@�\��j�Q����R�̂����҂ɌJ��Ԃ����^����ƁA�b�c�W�s�זE���敾����A���I�Ȏ��Ì��ʂ��݂���P�[�X������B���g�z���~���ɂ͔敾���q�j�Q�R�̂Ɨގ������p������A�]���̂��ÂƑg�ݍ��킹�邱�ƂŎ��Ì��ʂ����シ�邱�Ƃ����҂����Ƃ����B �@���A�a�łȂ�����ȃ}�E�X�ɂ���זE���ڐA�A���g�z���~�������R�����������B���̌��ʁA����k�������B�����ɐZ�������b�c�W�s�זE����́A�זE���̑����Ƌ@�\�������������B�s�זE�����}�E�X��G�t�F�N�^�[�b�c�W�s�זE�����������}�E�X�ł́A�����̏k���݂͂��Ȃ������B m3.com 2015�N3��12�� |
| NHK�̊���ÂɊւ���ԑg������ |
| �����K�k�i��@�Ǘ���匌�t���Ȉ�j �@NHK�@�����s�����@�u�����Á@���ӂ����ɂǂ����������v�����܂����B �@�ԑg�͂P�l�̂T�T�̓������҂̗Ꭶ����A����ɑ��邠�ӂ����ɍ��f���銳�҂̌���������\���ł͂��܂�܂��B �@���������͈�t�Ƃ̃R�~���j���P�[�V�����̃Y���ł����B���j�^�[���݂Ȃ���A���Âɂ��Ęb����t�B���҂̈ӌ����Ă���Ȃ��A�����̂��Ƃ��킩���Ă���Ȃ��Ɗ��҂��s�M������������A�����錾�����̕W�����Â̔ے�i�ߓ������ɑ��锽�_�̗��j�@����̃e���r�o���ɑ��锽���@�ɒ[�Ȓf���j�ɂ݂����ޏ��͂Ƃ�ł���ÁA������u�Ö@��簐i���܂����B �@�Ƃ�ł��{�������ς��ǂށA�R����܂͑�����܂Ǝv�����݁A����Ɍ������N���i����������Q�N���߂��܂��B �@�Q�N��Đf�@�����ۂɂ́A������͗����ɐi�s���A������̒ɂ݂��o�����A���������܂�a��͈������Ă��܂����B�����ē�����͊����������Ԃɐi�s���Ă����̂ł��B �@������܂ƐM�������Ă����R����܂̕W�����Â��A�ޏ��̒ɂ݂͉��P���ACT�ɂċ������ᎂ��قڏ�������Ƃ������Â̌��ʂ�����܂����B�R����܂̉��b�ł��B�ޏ��͉ߋ��̌�������ɂ��܂��B �@�W�����Â�ے肷���t�ɂ���ނ������悤�ł��B�����ł͎�L�݂̂ŋߓ��搶�Ǝv����Z�J���h�I�s�j�I���������҂������Ă��܂����B���̊��҂���͖����Ȏ��Â��邱�Ƃ��ł����ɂ݂Ŏ��S�����悤���Ƃ����ł��B�ɂ₩�Ȃ���ے�I�ȗ���ł����B �@���{���̏�����t���R�����g���Ă��܂��B���҂���t�ւ̕s�M��������͈̂�Î҂������t���̈�Â��s�����ƂŁA���҂���̖{���̊�]����荞�߂Ă��Ȃ����炾�ƁB �@�l���ρA��Âɑ��鉿�l�ς��l���A�a�C�Ƃ��Ă̂���ł͂Ȃ��l���Ƃ��Ă̂������Î҂͎~�߂Ȃ�������Ȃ��ƁB�����Ă��̉�����Ƃ��Ĉ�Î҂̃R�~���j���P�[�V��������̏�ʂ���܂����B �@�܂��鋞���搶���G�r�f���X�Ɋ�Â������̐M������������܂��B�����ē����ẪT�C�g���ʐ����̂P�Q�W�O�O�O�O������{���ɖ𗧂Q�U�X���֍i�荞�ރT�C�g���������Ɗ�������܂��B������ƂƂ��Ă̎�̑I���������Ȃ����Ƃ������ʂł��B�ł��قƂ�ǂ̈�ʂ̕��͂��̃T�C�g��m��܂���B�ߓ��搶�̖{�ɔ�ׂ�A���炩�ɍL��s���ł��B �@�ꕔ���҂̐����ׂ����Ƃɂ����y����Ă��܂����B���ł����₵�A���̏�Ō��S���������A��B�����Ĉ�Î҂ɉߓx�Ɋ��҂������Ȃ��A�ˑ��������Ȃ��Ƃ����ł��B�����܂߂Ď����͎̑̂����Ŏ��K�v������܂��B �@�T���Ċ��҂Ɋ��Y�����߂̎��ԁA�\�͂���Î҂����ׂ��Ƃ̃I�[�\�h�b�N�X�Ȃ܂Ƃ߂ł��B �@�������͍ŋ߃Z�J���h�I�s�j�I�����s���Ă��܂����A��t�ɕs�M����������͂������t�����J�ɐ������Ă��[���ł��Ȃ�������������Ⴂ�܂��B���_�I�ɕs����ȕ����͂��ꂱ�������^���P�A�[���s��Ȃ��Ƃ��Âǂ���ł͂���܂���B �@��������ʓI�Ɋ�łƂ���������������Ⴂ�܂��B����͌䎩�g�̍l���ł��̂ł��傤���Ȃ��ł����A��̊��҂���̂悤�ɕa�@���痣���Ƃ��ɘa�Ö@���s���̂Ȃ�Έ�Î҂͑Ή��\�ł����A���҂������̎v������ł���W�����ÈȊO�̈�Â���Î҂ɗv������邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B �@�����������҂���ɑΉ����邱�Ƃ́A��ʓI���������鎞�Ԃ���قƂ�ǂƂ�Ȃ���t�ɗv������̂͌�������������܂��B �@�Z�J���h�I�s�j�I���͎��Ԃ����܂��B�ł���ʐf�Âł����������҂���Ɋ��Y�����߂̒����Ԃ̊O���f�Â͑��̊��҂���̐f�Â����Ă����t�ɂ͌���s�\���Ǝv���܂��B �@�������A�R�����e�[�^�̂悤�ȊŌ�t�̕���\�[�V�������[�J�[�A�Տ��S���m�A��t���̈�Î҃`�[�������p����Ή\�Ǝv���܂����A��t�����ɐ����̉��P������߂邱�Ƃ͌������ɖR�������Ǝv���܂����B �@�R����܂����ʂ��������Ǘ����Ă������������Ƃ͍K���ł����B����ʼnA�d�_�����������Ă������肪�����ł��B m3.com 2015�N3��16�� |
|
���זE���B��l�H��`�q�ŗ}�� �C�m�����J���@�\���V�Z�p�J�� |
| �@�C�m�����J���@�\�i�i�`�l�r�s�d�b�j�́A�l�H���������ΐF�u�������i�f�e�o�j�Y����`�q������A���������זE��E�C���X�����ɔ��������đ��B�}��������Z�p���J�������B �@�l�H��`�q�����ɂ�萳��Ȉ�`�q�����V�X�e���������u�Ǝ㐫�v���U�����āA�{������邽��������j�Q�����Ă��܂����@�B����A��Ì����@�ւƘA�g������i�߁A����⊴���ǂɑ����`�q���Ö@�ւ̉��p��ڎw���B �@�i�`�l�r�s�d�b�̌����O���[�v���V�Z�p�J���Œ��ڂ����̂́A�זE������������ߒ��ŁA�d�v�Ȉ�`�q�Í��u�R�h���v�B�R�h���͂R�̉���z�琬�邍�q�m�`�̈�`�Í��̂��ƁB�c�m�`����|���A�����̍\���ޗ��ł���A�~�m�_�𐳊m�ɑI�Ԃ��ƂɊ֘A����@�\��S���Ă���B �@��������R�h���̂Ȃ�����g�p�p�x�̏��Ȃ��u��p�x�R�h���v��I�сA�����l�H�f�e�o��`�q�̔����Ɗ֘A�t���Ăf�e�o�����������悤�ɋZ�p������s�����B���l�H��`�q��咰�ۂɓ�������ƁA��p�x�R�h�����D�ʐ������āA�R�h����F�����Ă��������ɓ������q�m�`�i�A�~�m�_���^�Ԗ���������j��Ɛ肵�Ă��܂��A���ʂƂ��đ咰�ۖ{���̂��������Ȃ����A���B��j�Q����B��`�q�����V�X�e���̐Ǝ㐫���U�����đ���Z�p�ɗ��p�����B �@�����ŁA�����p�A�f�m�E�C���X��q�g����זE�ɂ��������Ƃ��둝�B�}�����ʂ��݂�ꂽ�B m3.com 2015�N3��19�� |
| �k�o�P�������A���̂̓����ōb��B�������o |
| �@�č�������w��iENDO�j��3��7���A�k�o�P���������҂̔A���̂̓�����k���ōb��B���܂��͗ǐ��i������j�̂������L���邩��88.2���̊m���œ���ł��邱�Ƃ��������V���Ȍ������Љ�B�T���f�B�G�S�ŊJ�Â̑�97��N����Ŕ��\���ꂽ�B �@�{�����ł́A��ᇂ��^����b��B���߂̐����Ǝ�p�����{�̊���34�l����A��w�a�@�b��B�ȏ��@���ɔA���̎�B�O���[�u�������P���m���k�o�P�����ɔA���̂�������ē�����k�������B�P���m�Ǝ����R�[�f�B�l�[�^�̂������34�̔A���̂ɑ����ᇂ̏�Ԃ�m�炳��Ă��Ȃ������B �@���̌��ʂ́A34���̒�30���̂ɂ����āA�O�ȕa���ɂ��m��f�f�i15�l���b��B���A19�l���ǐ��b��B�����j�ƍ��v�B���x�i�^�̗z�����j��86.7���ŁA�b��B���ł��邱�Ƃ��a���w�I�Ɏ����ꂽ���̖̂�87���𐳊m�ɓ��肵�����ƂɂȂ�B�܂��A���ٓx�i�^�̉A�����j��89.5���ŁA10��̂�����9��ŗǐ����̂𐳂����F���������Ƃ��Ӗ�����B �@���݂̍b��B���f�f�@�͐��x�s�\���̂��ߎ��Â��J��Ԃ�����s�K�v�ɍb��B��p�����{�����P�[�X�����ɑ����Ȃ��ŁA�㋉�ӔC��t��Donald Bodenner���́A�u�k�o�P�����𗘗p����A��t�͍b��B���𑁊����o�ł���݂̂Ȃ炸�A�K�v�̂Ȃ���p������ł���v�Ǝw�E�B����ɁA�u�k�o�P������p������@�͐��h�z���זE�f��p�����ꍇ�̐f�f���x���킸���ɉ���郌�x���ɓ��B���Ă���B�P�����̚k�o��p���邱�ƂŁA��N�P���Ŕ�p��}�����邱�Ƃ����_�ɂȂ�v�Ɛ������Ă���B �@����A�����`�[����Auburn University College of Veterinary Medicine�ƒ�g���Ă��̃v���O������W�J���Ă������Ƃ��v�撆�B��w���́AUAMS���҂̌��̂�p���āA�b��B�������o�ł���悤��2�C�̌��̚k�o�P�������{����\��Ƃ����B m3.com 2015�N3��19�� |
|
�R���܂̌����ځA���牷�x�ō� �j���[���[�N�B����A�}�E�X�Ŋm�F |
| �@�ăj���[���[�N�B����w���Y�E�F���p�[�N���������̌����O���[�v�́A�R����܂ɂ�鉻�w�Ö@�̌��ʂ��A���f���}�E�X�̎��牷�x�ɂ���č��E�����m�����܂Ƃ߂��B�ቷ��Ԃ��ƍR����܂̌����ڂ������錋�ʂ�����ꂽ�B �@�R����܂̑O�Տ������ŁA�}�E�X�̎����f�[�^�ɂ�����݂�ꂽ���R�̈ꕔ���A����̌����ɂ���Đ����ł���\��������B���̂��߁A�Տ������Ȃǃ}�E�X��p�����R����܂̌��ʂ��m�F��������Ɏ��牷�x���l������ׂ��Ƃ��Ă���B �@�����O���[�v�́A�X�����f���̃}�E�X��p�������������{�B���ϋC�����R�O�x�b��������Ŏ��炵���}�E�X�̏ꍇ�A�ʏ�̉��x�Q�Q�x�b�Ŏ��炳�ꂽ�}�E�X�ɔ�ׂčR����܂̌����ڂ��悩�����ƌ������Ă���B�R����܂ɗ��p�����̂́u�V�X�v���`���v�B �@�ቷ��ԂŎ��炵���}�E�X�̏ꍇ�A���̊����}�E�X�ɂƂ��ăX�g���X�ɂȂ�A�X�g���X�z���������㏸�������߂Ƃ��Ă���B �@�X�g���X�z�������ł���m���G�s�l�t�����Z�x���㏸����ƁA���̓��̑�ӂ����������̉����ێ������ăX�g���X�ɓK������B�����O���[�v�ł́A���̓K�������ɂ���ăV�X�v���`���ɑ��邪��זE�̒�R�������܂����Ƃ݂Ă���B �@��Ƃ��āA���X�g���X�z�������̍�p�����Ւf��v���p�m�[�����g���đj�Q����A�ቷ�Ŏ��炵���}�E�X��������ԂŎ��炵���}�E�X���݂ɃV�X�v���`���ɑ��鍂�������������҂ł���Ƃ��Ă���B �@�}�E�X�̂���זE�̑��B�Ǝ��Ì��ʂɃX�g���X��^����e�������x���̎��_���瑨�����������ʂ͒������A�R����܂̔��������]���l�����Ă��������_��ł���\���������Ă���B �@���̐��ʂ́A�p�I�����C���Ȋw�G���u�l�C�`���[�R�~���j�P�[�V�����Y�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�B m3.com 2015�N3��30�� |
|
�얞�ŏ����̂��X�N��40���㏸ 4�l��1�l���̏d�֘A�̂���� |
| �@�얞�����̂��X�N�͑�������������40���������Ƃ��A�p�L�����T�[�E���T�[�`UK��Julie Sharp����̌����ł킩�����B �@����̌����ł́A�얞�����̖�4�l��1�l�́A���U�̂����ɑ̏d�Ɋ֘A���邪��ǂ��郊�X�N�����邱�Ƃ����������B�̏d�֘A�̂���Ƃ́A�咰����A�_�X����A�q�{����A�t������A�X������A�H������A�o��̓�����Ȃǂ��B�p���ɂ����āA�얞����1,000�l��274�l�����U�̂����ɑ̏d�֘A����ǂ������A���N�̏d�̏����ł�1,000�l��194�l�������B �@�����T�[�`�ɂ��ƁA�얞�������̂��X�N�����߂���@�͑����l������Ƃ����B�Ⴆ�A���b�זE�̃z�������A���ɂ����𑣐i����Ƃ����G�X�g���Q���Y���Ȃǂ��֘A������@���B�������A�E�G�X�g���ׂ�����ΒN�ł����X�N���y���ł���ƁA������Ƃ͏q�ׂĂ���B �@Sharp���́A�u�։��A���N�̏d�̈ێ��A���N�I�ȐH���A�ߎ��Ƃ��������C�t�X�^�C���̕ύX�́A���Ȃ��̂��X�N��ጸ����傫�ȃ`�����X���B���̕ύX�ł���\�h���ۏł���킯�ł͂Ȃ����A�L�v���Ƃ͌�����v�Əq�ׂĂ���B �@�u���ʂ͊ȒP�łȂ����A�X�|�[�c�W���ɓ������A�������}�C������������A��D�����i�v�ɂ�����߂��肷��K�v�͂Ȃ��B��w��O�Ńo�X���~��A���b�ⓜ���̑����H�i�����炷�ȂǁA�����ɂ킽�莝���ł��鏬���ȕω����傫���e������v�Ɠ����̓A�h�o�C�X����B m3.com 2015�N3��30�� |
| �[���łT��ނ̂���̃��X�N�����܂� ���̂ق�12��ނ̕��ʂł͊W�Ȃ� |
| �@�[��������ƂT��ނ̂���̃��X�N�����܂�ƕ��������B �@�č��J���t�H���j�A�B�̃I�[�N�����h�E���f�B�J���Z���^�[�𒆐S�Ƃ��錤���O���[�v�́A���̌��ʂ��p�[�}�l���e�E�W���[�i�����I�����C���ł�2015�N�R���P���ɕ����B �����x�܂ł̈����Ɖߓx�̈����Ŕ�r �@�ߓx�̈����́A�g�̂̓��蕔�ʂɂ����邢�����̃^�C�v�̂��ǂ̃��X�N�̑����Ɗ֘A���Ă���ƕ���Ă���B����ŁA���ʂɂ���Ă͌��ʂ��������ďo�Ă���ꍇ������B���C���A�������܂��̓r�[���̂ǂ�����ނ��ɂ���Ă����ʂɍ����o�Ă���B �@�����O���[�v�́A12��4193�l��ΏۂƂ��āA�y�x���璆���x�̈����ƁA�ߓx�̈����̔�r�A�����̎�ނƂ���̃��X�N�Ƃ̊֘A�������������B �[���łT��ނ̂���̃��X�N������ �@���̌��ʂƂ��āA���������܂Ȃ��l�Ɣ�r���āA�ߓx�̈����i�P���ɂR�t�ȏ�j������l�́A�u��C���^������v�u�x�v�u���[�v�u���������v�u�����m�[�}�v�̂T��ނ̂���̃��X�N�����������B �@�y�x���璆���x�̈����ł��A�x����������S��ނ̂���Ɗ֘A���������B �@���̂T��ވȊO��12��ނ̕��ʂ̂���ɂ��ẮA�����Ƃ���̃��X�N�͊W���Ă��Ȃ������B�Ȃ��A12��ނƂ́A�u�݁v�u�X���v�u�̑��v�u�]�v�u�b��B�v�u�t���v�u�N���v�u�O���B�v�u�����v�u�q�{�́v�u�q�{��v�u�����n�v�B �@���_�Ƃ��āA�ߓx�̈����͈ꕔ�̂���̃��X�N�傳���邪�A�ʂ̂���ł̓��X�N�͑������Ȃ��Ɩ��炩�ɂȂ����B�y�x���璆���x�̈����̉e���͖��m�̊֘A�����v�f�����X�N�Ɋւ��\��������A����Ƃ̊W�ɂ��Ă͖��m�ł͂Ȃ��Ɛ������Ă���B �@���i��������̏K��������Ƃ���A�C�ɂ���Ɨǂ��������B Med�G�b�W 2015�N3��31�� |
| �P�����������I �|���I�E�C���X�ł���������V�Ö@���o�� |
| �@������ᇂ��|���I�E�C���X�Ɋ��������ĎE���\�\����ȓł������ēł𐧂��ȃf���[�N��w�̐V�Ö@���CBS�ԑg�u60�~�j�b�c�v�����W���܂����B�Տ������̃t�F�[�Y1���炢���Ȃ肪����l����������A�u��ՂƂ��������悤���Ȃ��v�ƏՌ����Ă�ł��܂��B �@�ԑg�̗���ɉ����āA�Ă����܂��ˁB �@�ŏ��ɓo�ꂷ��̂�2012�N�Ɉ����̔]��ᇂ́u�P���iglioblastoma�j�v�Ɛf�f���ꂽ�i���V�[�E�W���X�e�B�X����i58�j�ł��B2�N���ɓn���ĕ��ː��Ö@�≻�w�Ö@�ŗ}���Ă����̂ł����A��ᇂ��Ĕ����܂����B �@���̎�ᇂ�2�T�ԂŔ{�ɐ������܂��B�Ĕ���́u�]��������7�����v�Ɛf�f����܂������A���̔����ɂȂ鋰�������܂��B���Ö@�͂��������c����Ă��Ȃ��������߁A�f���[�N��w�̗Տ������̔팱�҂ɒ��ނ��Ƃɂ��܂����B �@��N10���A�����������̃|���I�E�C���X��]��ᇂɒ����B�������Ȃ��炱������Ă��܂��B�u1��1������A���ꂾ���B����łق��̐l�����Ɋ�]���^������Ȃ�|���ȂȂ��v�A�u��w���̑��q2�l�̑��Ǝ����A�������A���̊����������ł��v �E�C���X�͔]���Ɋg�U���Ȃ��́H �@3D��MRI�Ń^�[�Q�b�g�̎�ᇂɑ_�����߂�o�H�̊���o���́A�_�o�O�Ȓ��W�����E�T���v�\����t���S�����܂����B�`�[���̒��ł̓X�i�C�p�[�̖����B �T���v�\����t�u�A�^�b�N����̂��厖�����A�U���ΏۂłȂ����̂ɓ�����Ȃ��悤�ɂ���̂��厖�B�ق����������������ς�����ˁv �X�R�b�g�E�y���[�L���u�]���Ɋg�U���Ȃ���ł����H�v ��t�u����Ȃɉ����܂ł͂����܂���B�|���I�͔�r�I�傫�ȕ��q�ł�����ˁB�]�̓^�C�g�ȃX�y�[�X�Ȃ̂ňړ������ɂ����肪�����ł���v �@�팱�҂̓i���V�[����17�l�ڂł��B�����������̃|���I�E�C���X�̐Z���ɂ�6���Ԕ���������܂����B���A���Â͂���ł����܂��ł��B��p�����ː����Ȃ��B������������1������A���ꂾ���ŏI���Ȃ�ł��B���Ƃ͐�������ɂ���1��MRI����������āA�P���ƃ|���I�A�ǂ����������̂����`�F�b�N���܂��B �@��w�̃��S�̃t�[�f�B�[�ƃW�[���Y�̂�������A���̐l�̓i���V�[����Ɏ��Â����߂��w�����[�E�t���[�h�}���iHenry Friedman�j��t�A���啍���]��ᇌ����Z���^�[�̂��̕��ł��B �t���[�h�}���������u����͎��̑S�L�����A�ōł����҂ł��鎡�Ö@���A�ȏ�s���I�h�v �L���u���Â�ς���^�[�j���O�|�C���g�ɂȂ�ƁH�v �������u���Ƃ����ˁB������艞���͂���v �閧�̓|���I �@���͂��̃|���I�B���ʂ̃|���I�Ƃ͈Ⴄ��ł��B���q�����w���̃}�T�C���X�E�O���[�}�C���[�iMatthias Gromeier�j��t��25�N�Ԃ����Ă�������J�̌����ŁA��`�q�g�݊������{����Ă��܂��B �L���u�w�킩�����I �|���I�ł���זE���E�������� �x���ē����Ɍ����ƁA�݂Ȃ���Ȃ�Ă������Ⴂ�܂����H�v �O���[�}�C���[��t�u�N���C�W�[���Ƃ��A�R����Ƃ��A�܂����낢�댾���܂��ˁi�j�B�݂�ȋ��ʂ��Č����̂́A���X�L�[������Ƃ������Ƃł��v �������u�������čŏ��̓i�b�c�i�����������j�Ƃ����v���܂���ł�����B��Ȃ���A��Ⴡi�܂Ёj�ɂȂ邾�������Ăˁv �@�O���[�}�C���[��t�͂ق��ɂ�HIV�A�V�R���A���]�̃E�C���X�������܂����B���A�I�̂̓|���I�ł����B�|���I���Ǝ�ᇂ̎�e�̂ɂ������������邩��ł��B�����A������E�����߂ɂ����Ȃ������Ă��炢�s�b�^�V��������ł��B �@��`�q�g�݊����ł́A�|���I�̊�{�I�Ȉ�`�q�z��̈ꕔ���C���t���G���U�E�C���X�̂��̂Ƒg�݊����܂����B�������Ă����Ε��ʂ̍זE�ł̓T�o�C�u�ł��Ȃ��̂ŁA��Ⴡi�܂Ёj�⎀�S�������N�����S�z�͂���܂���B�t�ɂ���זE�ł̓T�o�C�u�ł���B�����ĕ�����J��Ԃ��ߒ��œőf�����A�זE��ŎE����Ƃ����킯�ł��B �@��t�͕ĐH�i���i�ǁiFDA�j�ɁA���̃t�����P���V���^�C���݂����Ȍp���ڂ��E�C���X�̔F�����߂܂����B���AFDA�͈�ʎs���Ɋ������L�܂�̂��x�����ĐT�d�ł����B������7�N�Ԃɓn���Ĉ��S���̌������s���A��39�C�ɒ������Ă��|���I�����ǂ��Ȃ����Ƃ�������ď��߂āA2011�N�ɂ悤�₭�l�̂ւ̗Տ�������FDA����F�����肽�̂ł��B �팱��1�� �@�ŏ��ɔ팱�҂ɂȂ����̂́A20�ŗ]����������鍐���ꂽ�X�e�t�@�j�[�E���v�X�R�[���iStephanie Lipscomb�j����ł��B��͂�i���V�[����Ɠ����P���ŁA���ɂŕa�@�ɍs�������ɂ͂����e�j�X�{�[���قǂ܂Ő������Ă��܂����B �@��ʂ̉��w�Ö@�Ŏ�ᇂ�98%�͓E�o�ł����̂ł����A2012�N�ɍĔ��B�Ĕ������P���ɂ͂������Ö@�͂���܂���B�����Łu�l�ԂɎ����̂͂��Ȃ����ŏ����v�Ɛ���������Ŕ[�������ŗՏ��ɂ̂��݂܂����B �X�e�t�@�j�[�����u�����A�����������͉̂����Ȃ�������ł��v �L���u���ꂳ��͂Ȃ�Č����Ă܂������H�v �X�u��t�Ɍ����Ă��w�c�͂��H �ȂɁH ���Ȃ�āH�x���Ă��������������̂ŁA�w��������A��낤��A�ˁI�x���Č�������ł��i�j�B�|����Ƒ��̋C�����͂悭�킩���Ă�������A�����|����Ƃ���͌��������Ȃ������v �L���u�{���͂������A�|��������ˁc�v �X�u�c�͂��i�܂��ށj�v �������u����Ⴛ���ł���B�T�C�R���]�����悤�Ȃ��̂�����B�ǂ����ɓ]���邩�������ɓ]���邩�͓]�����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��v �@5���ɒ�������2������B�c�O�Ȃ����ᇂ͂ނ���傫���Ȃ��Ă܂����B�T�C�R���͈������ɓ]�����Ă��܂����c�B�u����̓_�����v�Ɣ��f������t�͕��ʂ̗Ö@�ɖ߂��Ď�p����낤�Ɛi�����܂��B���A�X�e�t�@�j�[����́u���������l�q���������v�Ǝ~�߂܂����B �@��������5������B���鋰�錩�Ă݂����ᇂ͂Ȃ�Ɛ������~�܂��Ă���ł͂Ȃ��ł����I �����シ���傫���Ȃ��Č������̂͒P�Ɏ�ᇂ����ǂ��N�����Ă������炾�Ƃ킩��܂����B�g�̖̂Ɖu�n���o�����A����Ɛ���Ă����̂ł��B ����͂Ȃ��Ɖu�n�������Ȃ��H �|���I�Ö@�̌����Ƃ́H �L���u���������ŏ�����Ɖu�n������Ɛ���Ă�ςޘb�Ȃ̂ɁA�Ȃ��l�̂͂��ꂪ�ł��Ȃ���ł��傤�H�v �O���[�}�C���[��t�u����זE�Ƃ�����͎����̎���ɃV�[���h�菄�炵�āA�Ɖu�n����͌����Ȃ��Ȃ��Ă��܂���ł��B���������o�[�X����A���ꂪ���̗Ö@�ł��B��ᇂ����������邱�Ƃł��̃V�[���h���Ƃ��āA�Ɖu�n�ɂ���������A�Ƌ����ē����Ă���ł���v �L���u�Ȃ�قǁB�|���I�ɂ킴�Ɗ��������ĖƉu�n�ɃA���[��������킯�ł��ȁv ��t�u���̒ʂ�v �@����E�����X�^�[�g����̂̓|���I�E�C���X�̂悤�Ɍ����܂����A���ۂɎE�������͑̓��ɔ�������Ɖu�n�����C���ł��A�Ƃ����킯�ł��B �����Ď�ᇂ͏����� �@�������ăX�e�t�@�j�[����̎�ᇂ�21�����A���ŏk���𑱂��A���܂��ɂ́c�c�����Ă��܂��܂����B����͒���3�N���MRI�B��ᇂ͂�����������ĂȂ��Ȃ��Ă܂��B�c���Ă���̂͏����ɍs������p�������ł��B �L���u�������č������ɃX�e�t�@�j�[�������Ă邱�Ǝ��́A�]���̗Ö@�ł͍l�����Ȃ����ƂȂ�ł���H�v ��t�u�����ł��v �L���u�X�e�t�@�j�[�A������ŏ�������ꂽ���͂ǂ�ȋC�����������H�v �X�e�t�@�j�[�����u�����Ă��܂��܂����A���ꂵ���āv ���s �@�t�F�[�Y1�̗Տ��ł͒����ʂ��������グ�Ă䂫�A�K�ʂ�����o���Ȃ���Ȃ�܂���B3�l�ڂŔߌ��͐��܂�܂����B���߂Ă̎��s�B �@3�{�ɏグ����14���̃h���i�E�N���b�O�iDonna Clegg�j����i60�j�̏ꍇ�́A���ǂ��������Ȃ�߂��Ĕ]����������̂��ꕔ��Ⴢ��A�r���Œ����𒆒f������Ȃ����ʂɁB�ꂵ�݂Ȃ���3�T�Ԍ�ɖS���Ȃ�܂����B �@�ł�����̓t�F�[�Y1�̐�����A�����悤���Ȃ����Ƃł͂���܂��B����A�X�e�t�@�j�[�����3�N�o�����������C�ōĔ����Ȃ��܂܂ł��B��1�����������������������ŗǂ��c�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��̂���w�̌������Ƃ���ł��ˁc�B �������炪���j�� �@���̒m����ƂɁA�`���̃i���V�[����ł͒����ʂ�85%�J�b�g���܂����B �@������4�`6�����͉��NJ��B�Ɖu�n���ڊo�߂āA��ᇂ��E���n�߂鎞���ł��B�m���Ƀi���V�[������h���i����̂悤�ɂ������Ȃ��Ȃ�A�E���g����܂�Ǐo�܂����B����3������ɋ}����MRI�����ɖ߂����Ƃ���A�����O��2�{�ɖc��オ���Ă��܂����B����}���邽��Avastin�Ƃ����K����p�����Ƃ���A���������ďǏ�͗��������܂����B �@�|���I��������4�������B�ʏ�Ȃ�2�A3�T�ԂŔ{�ɐ�������͂����P���́A�����������������Ȃ��܂܂ł��BMRI�Œ��ׂĂ݂�ƁA��ᇂ̐^�ɂ́A�ۂ�����ƌ����c �@�|���I�ŖƉu�n���o�����A�������炪���˂������Ă����̂ł��B ����܂ł̌��� �@����܂ł̎����Ń|���I�E�C���X�Ö@�����������҂͍��v22�l�B�������S���ꂽ����11�l�ŁA�قƂ�ǂ͒����ʂ����������ł̂��Ƃł����B����ł��]���鍐���͒����������Ƃ����̂����߂Ă��̋~���c�B �@�c��11�l�͉𑱂��Ă���A����4�l�́u�����v�̏�ԂŔ��N�ȏ�N���A���Ă��܂��B���ϔ��N�������L�т��v�Z�B�X�e�t�@�j�[�����A���_�[�Z�����m�̂悤��33�A34�������s���s�����Ă�Ȃ�ď]���̗Ö@�ł͍l�����Ȃ����Ƃ��ƃZ���^�[�̏����͌����Ă܂���B �M�Y���[�h�W���p�� 2015�N4��1�� |
| ������a���_�������@���q�����ÐV��@�J�����@�_�ˑ� |
| �@����זE�ɐ��f�̌��q�j��Y�f�C�I���̃r�[���Ď��ł�����̂��u���q�����Áv���B�������a���̂��ɒ���݂Ȃǃr�[���ŏ����₷�����킪����Ǝ��Â͓���B�a�������Ƀr�[���Ă��@�̊J����_�ˑ��w���t���a�@�i�_�ˎs������j�̊̒_�X�O�ȁi��p���i�O�����\���j�����j�A���ː���ᇉȁi���X�ؗǕ������j�Ȃǂ̃`�[�����i�߂Ă���B �y���̊J���댯���z �@���q�����Âł́A���f�̌��q�j�ł���z�q��Y�f���q����ꕔ�̓d�q���͂�������Y�f�C�I�����u���q������v�ʼn������A�r�[���ɂ��Ďg���B �@�r�[���̓G�l���M�[�ɂ���đ̓��̂ǂ��܂œ͂��������܂�B�����͂��蔲���A�ŏI���B�_�߂��ŃG�l���M�[����o���Ď~�܂�A����זE�Ƀ_���[�W��^����B �@�����őO�����ăR���s���[�^�[�f�w�B�e�i�b�s�j�ŕa���̈ʒu��`���c�����Ă���A�r�[���̃G�l���M�[�߂��a�����W���I�ɂ������B �@�����݂⒰�ȂǏ����ǂ̓r�[���Ō����J���₷���A����炪�a���ɐڂ��Ă���Ɖe�����������Ȃ��B���̂��߁A���Ȃ��̂���͈ꕔ�������A���q�����Â���������B �y�L�]�Ȍ��ʁz �@�������Ɍ����A�_�ˑ�a�@�̒_�X�O�Ȃ͕��Ɍ������q����ÃZ���^�[�i���̎s�j�Ƌ����łQ�O�O�U�N�A�a���Ə����ǂ̊ԂɁu�X�y�[�T�[�v�ƌĂ�镨�����ݍ��ގ�p�����A���̌�ɗ��q���Ă�Ƃ�����@�̗Տ��������n�߂��B �@�̑���_�̂��A�X���ȂǕ����⍜�Օ��̂���ŁA�؏��ȂǑ��̕��@�ō����������߂Ȃ��i�s�����ǗႪ�ΏہB�X�y�[�T�[�ɂ͑̂ɂ��܂舫�e�����y�ڂ��Ȃ��Ƃ����S�A�e�b�N�X�₨�Ȃ��̎��b�g�D�u��ԁv���g�����B �@��N�P�Q���܂łɂP�R�U������{�B���q���Ǝ˕����ɂ���̍Ĕ����Ȃ������������Ǐ����䗦�͑S�̂łW�O�������B�Q�N�������͊̂���i�P�R��j�łT�O���A�X�̔�������i�W��j�łS�S���B�_������i�P�Q��j�ł͂S�U���Ɖ��w�Ö@�̂P�X�����������B �@�`�[���𗦂���̒_�X�O�Ȃ̕��{�I�y�����́u���̕��@�Ƃ̔�r�����������ƕK�v�����A�L�]�Ȏ��Ö@�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����v�ƌ����B �y�f�ނ����ǁz �@���{�y�����ɂ��ƁA�Տ�������ʂ��A�����ǂƂ̊Ԃ��Œ�P�Z���`�قNj�������Ƃ�������A�X�y�[�T�[�̓K�ȓ�������m���ł����B �@���̓S�A�e�b�N�X���̓��Ɏc�邱�ƁB�J���V�E�����������čd���Ȃ�A����������邱�Ƃ�����B�����őf�ނ����ǂ��邱�Ƃɂ����B �@������Ƃ̋��͂āA�����̖D���Ɏg����p�p�̎��̑f�ނŃX�y�[�T�[������B�̓��ł͖�R�J���ŋz������A�ܐ������悭�A���q�����~�߂���ʂ������̂��������B �@���������ŗL�������m�F�B�o�ώY�ƏȂ̎x�����ĊJ�����{�i�������B��S�O�̈�Ë@�ւƌ����������A���N����Տ������Ɏ��g�ށB �@������ɉ���鍪�{����R�`�勳���i���ː���ᇊw�j�́u�X�y�[�T�[�̓G�b�N�X���ɂ���ʓI�ȕ��ː����Âɂ��g����B���p�������Ύ��Â̌��ʂ����S��������I�ɍ��܂�Ǝv���v�ƌ��B �@���{�y�����́u����菭���ł������̊��҂�����A�����S�Ɏ��Âł���悤������i�߂����v�Ƙb���Ă���B �_�ːV�� 2015�N4��2�� |
| �����A���͂���ⓜ�A�a�̌����ɁH |
| �쐴�M�i�݂Ȃ݁E���悽���j�t�[�h�v���f���[�T�[�A��ʎВc�@�l���{�I�[�K�j�b�N���X�g���������\���� �@�I�t�B�X�ŏW�����Ďd�����������A�c�Ƃ̊O��肩��߂��Ă������A�ދ��Œ�����c���I��������ɁA�z�b�ƈꑧ�������āA�ʃR�[�q�[��y�b�g�{�g���̃W���[�X����C�Ɉ��݊������\�\����Ȍo���������Ă���l�������Ǝv���܂��B �@�������A���̊ʃR�[�q�[��W���[�X�ɂ͂ǂꂭ�炢�̍����������Ă��āA���̍������ǂ�ȉe���������炷���A�Ƃ����Ƃ���܂ł͂��܂�l�������Ƃ��Ȃ��ł��傤�B�Ⴆ�A��ʓI�ȊʃR�[�q�[�ɂ͊p������3���A�u�R�[���v�̂悤�Ȑ����������ɂ͓�������10���̓����������Ă��܂��B �@�ł́A�X�|�[�c�h�����N�̂ق��������̂��Ƃ����ƁA�����ł�����܂���B��ʓI�ȃX�|�[�c�h�����N�ɂ��A�p����6�`7���̓����������Ă��܂��B����ɂ����A�t�@�[�X�g�t�[�h�X�ȂǂŔ̔����Ă���V�F�C�N��̃h�����N�ɂ́A�p����20���ȏ�͓����Ă���Ƃ����Ă��܂��B �@�u�����̎�肷���͑̂ɂ悭�Ȃ��v�Ƃ��������͒m���Ă��܂����A���E�ی��@�ցiWHO�j�̃K�C�h���C���ɂ��ƁA���l����юq����1��������̓��ށi�Y�������Ƃ͕ʁj�̐ێ�ʂ́A�S�J�����[����5�������ɂ��ׂ��Ƃ���Ă��܂��B��ʓI�Ȑ��l��1���̐ێ�J�����[�́A1800�`2200�L���J�����[�Ƃ����Ă��܂��B����2000�L���J�����[�Ƃ����ꍇ�A����5���ƂȂ��100�L���J�����[�ŁA�ʃR�[�q�[1�`2�{���ɓ�����܂��B �@�v�Z��A�ʃR�[�q�[��2�{�����߂A���̓��͂������ނ�ێ�ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�������A���ۂɂ͂���ōςނ킯�͂Ȃ��̂ŁA�ێ�J�����[�ɐ�߂铜���̊����͂ǂ�ǂ��Ă��܂��܂��B�����āA���ꂪ���ʓI�ɑ̂ɑ傫�ȃ_���[�W��^���Ă��܂��̂ł��B �@�����ɂ̓J�����[�͂���܂����A�������̑̂ɕK�v�ȉh�{�f�͂قƂ�NJ܂܂�Ă��܂���B�����������H�i�̂��Ƃ��u��̃J�����[�v�Ƃ����܂��B�A���R�[���A���Ă┒���������ꂽ�������Ȃǂ���̃J�����[�̈��ł��B�ꕔ�Łu��̃J�����[�͑̓��Ɏc��Ȃ��̂ő���Ȃ��v�Ȃǂƍl���Ă���l�����܂����A����͑傫�ȊԈႢ�ł��B �@�K�v�ȉh�{�f���܂܂Ȃ���̃J�����[�́A�̓��ɐۂ荞�ނƑ傫�ȕ��S�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�J�����[������Ƃ������Ƃ́A�̂̃G�l���M�[���ɂȂ�Ƃ������Ƃł���A�Ȃ�炩�̌o�H�Ńu�h�E���ɕω�����Ƃ������Ƃł��B�u�h�E�����G�l���M�[���ɂȂ�ɂ́A�̓��̂��܂��܂ȋ@�\�╨�����g���K�v������܂��B �@���̈���A�N�����Ƃ����K�{�~�l�����̈��ł��B���̃N�������A�זE���ɂ���u�h�E���������h�A���J���錮�̖��������邱�ƂŁA�u�h�E�����זE�̓����Ɏ�荞�ނ��Ƃ��ł��܂��B�����i�A���R�[���������j�ɂ́A�N�����͂܂������܂܂�Ă��Ȃ��̂ŁA�����Ɋ܂܂��u�h�E�����G�l���M�[�����邽�߂ɂ́A���̐H�i����ێ悵���N�������g�����ƂɂȂ�܂��B �@�܂�A�����̓N������̓��ɂ����炳�Ȃ��ǂ��납�A������ێ悵���N������Q��Ă��܂��̂ł��B���̏�A�G�l���M�[���̂��߂ɕK�v�Ȃ����ЂƂ̉h�{�f�ł���r�^�~��B1���܂܂�Ă��Ȃ��̂ŁA�̂ɂ͑����̕��S��������܂��B �����̉ߏ�ێ�Ŕ]�@�\�ɂ��ω� �@�A�����J�̕ی��w�W�]����������2010�N�ɔ��\�����u���E���a���ג������v�ɂ��A�������܂ވ��ݕ��̉ߏ�ێ悪�����Ƃ���鎀�S��̂����A���A�a��13��3000�l�A�S���ǎ�����4��4000�l�A�����6000�l�ƂȂ��Ă��܂��B���ڂ��ׂ��́A����78������`���������Ŕ������Ă���Ƃ������Ƃł��B���A���{�ł͕n�����̈��������ɂȂ��Ă��܂����A���̒��ԓ��肾���͔��������Ƃ���ł��B �@�܂��A�A�����J�̃v�����X�g����w�ōs��ꂽ�A���b�g��p���������ł́A�������ߏ�ێ悷�邱�Ƃɂ���Ė��炩�Ɉˑ������F�߂�ꂽ��A��x�����̓��^����߂čĂї^�����ۂɂ́A�ȑO�����ێ�ʂ��������������ł��B����ɁA�����̋�����₽�ꂽ���b�g�̓A���R�[���̐ێ�ʂ������A�]�@�\�ɕω����N���Ă��邱�Ƃ��킩�����Ƃ����܂��B���ɑ��ʂ̍�����ێ悷�郉�b�g�̔]���ł́A�R�J�C���A�����q�l�A�j�R�`���Ȃǂ̈ˑ����ɂ��ω��Ɠ��l�̐_�o���w�I�ȕω����N�����Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B �@���b�g�̎��������̂܂ܐl�Ԃɓ��Ă͂܂�킯�ł͂���܂��A�܂�������������Ƃ����킯�ɂ������Ȃ��ł��傤�B���������A�������邮�炢�Ȃ�ŏ��������������Ӗ�������܂���B�������������Ƃ��ӂ݂�ƁA�d���̍��Ԃ⑧�����ɍ��������Ղ�̊ʃR�[�q�[�Ȃǂ����݊����K���́A��߂��ق��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ������荂���X�N�ȍ����Ö������ �@4��3���t���T�C�g�L���w����I�ލ����A����ⓜ�A�a�̌����Ɂc�h�{�f�Ȃ����J�����[�A�R�J�C���Ɠ��l�̈ˑ����x�ł́A�ʃR�[�q�[��y�b�g�{�g���̃W���[�X�ɓ����Ă��鍻���̖��ɂ��Ă��`�����܂������A�u�����������Ă��Ȃ��[���J�����[�̈��ݕ�������ł��邩����v�v�Ȃǂƌ����Ă���l�͗v���ӂł��B �@�[���J�����[�̈��ݕ��́A���͍�����ێ悷��������X�N��������������Ȃ�����ł��B�A�X�p���e�[���A�X�N�����[�X�A�A�Z�X���t�@���J���E���Ȃǂ̍����Ö������A�[���J�����[�̈��ݕ��ɂ͎g���Ă��܂��B �@�A�X�p���e�[���̍\�������̈�Ƀ��^�m�[��������܂��B���̃��^�m�[���͌����Ɏw�肳��Ă���A�̓��ŃA�X�p���e�[�����番������ċz������܂����A�ێ�ʂɂ���Ă͎��Ɏ��邱�Ƃ�����܂��B���ۂɐ��̐H�Ɠ�������ɂ́A��ނɃ��^�m�[���������Ĕ����Ă��������ł����A���l�����𗎂Ƃ�����A��������Ƃ������Ƃ��p�ɂɋN�����悤�ł��B �@�A�X�p���e�[������̊ʃR�[�q�[��W���[�X��������Ƃ����āA�����ɏd��Ȏ����ɂȂ���킯�ł͂���܂��A����������������m���Ă������ق��������ł��傤�B�܂��A�A�X�p���e�[���͂���A�]��ᇂ┒���a�Ƃ̊֘A�������^���Ă��܂��B �@�X�N�����[�X�ƃA�Z�X���t�@���J���E���́A���R�E�ɂ͑��݂��Ȃ����S�ȉ��w���������ŁA�������̑̓��ł͕������邱�Ƃ��ł��܂���B���������āA���̂܂܋z������Ĉٕ��Ƃ��đ̓����߂���A�̑���t���ɑ���ȃ_���[�W��^���A�Ɖu�͂�ቺ�����Ă��܂��܂��B �@�X�N�����[�X���A�Z�X���t�@���J���E�����A�����Â݂�����܂����A��������ē������z�������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�J�����[�Ƃ��Ă͌v�Z�ł��܂���B���ꂪ�u�[���J�����[�v�̈Ӗ��Ȃ̂ł��B�u�J�����[���Ȃ��̂ŁA�̂ɂ悳�����v�Ǝv���l�����邩������܂��A�����Ă����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��̂ɖ����Ă����܂��傤�B ���낵�����ʓ��R�[���V���b�v �@����ɁA������������I�Ɍ��ɂ���Ö����Œ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A���ʓ��R�[���V���b�v�ł��B����ِ͈������A�ʓ��u�h�E���t���A���邢�̓u�h�E���ʓ��t���ȂǂƂ��Ă�܂��B�Ăі��ɂ���āA�u�h�E����ʓ��̊ܗL�ʂȂǂɑ����̈Ⴂ�͂���܂����A�قړ����ƍl���Ă����ł��傤�B �@���ʓ��R�[���V���b�v�́A���ݕ������łȂ��A�X�C�[�c�A�y��Ⓚ�H�i�Ȃǂ̉��H�H�i�ɂ����L���g���Ă��܂��B�A�C�X�R�[�q�[��A�C�X�e�B�[�Ȃǂɓ����K���V���b�v���A���̍��ʓ��R�[���V���b�v�ł��B���ޗ��̓R�[���A�܂�Ƃ����낱���ł����A���̂Ƃ����낱���͈�`�q�g�݊����ɂ���č��ꂽ���̂ł��B �@���ʓ��R�[���V���b�v�́A���͍������������������l���㏸������Ƃ����Ă��܂��B�������A�R�X�g���������߁A������H�i�ɊÂ݂����邽�߂Ɏg���Ă���̂ł��B�����l�̖�肾���ł͂Ȃ��A���̉�������ɂ���얞�ⓜ�A�a�Ȃǂ̌����ɂȂ邱�Ƃ�����A�A�����J�ł͎g�p�֎~�̉^�����W�J����Ă��܂��B �@�������A�ʕ��ȂǂɊ܂܂�Ă���ʓ��ƁA���ʓ��R�[���V���b�v�̊Â݂̎�̂ł���ʓ��͈Ⴄ���̂Ȃ̂ŁA�ʕ��͈��S���ĐH�ׂĂ��������B�ʕ��ȂǂɊ܂܂��ʓ��́A�H���@�ۂȂǂ̓���������A�̓��ɂ������z������Ă����܂��B�ʕ��ɂ́A�������̑̂ɕK�v�ȃr�^�~����~�l�����A�A���h�{�f�Ȃǂ��L�x�Ɋ܂܂�Ă���A���N�I�ȐH�ו��Ƃ����܂��B �@����A���ʓ��R�[���V���b�v�͎������̑̂ɑ���ȕ��S��������̂ŁA���ݕ�����H�H�i�Ȃǂ�ʂ�����肷���ɒ��ӂ������Ƃ���ł��B���ʓ��R�[���V���b�v�͒ቷ�ŊÂ݂������Ƃ������������邽�߁A�A�C�X�N���[������������A�₽���َq�ނȂǂɂ��悭�g���Ă���A�m��Ȃ��Ԃɂ�������ێ悵�Ă��܂��댯��������܂��B �@���ʓ��R�[���V���b�v�̓��{�ł̎s��K�͂́A�N�Ԗ�800�`1000���~�Ƃ����Ă��܂����A���{�X�^�[�`�E�����H�Ɖ�ɉ������Ă���\���ЂŖ�9���̃V�F�A�Ƃ����ǐ��Ԃɂ���܂��B�����Ɠ��l�ɗ����������ł��邽�߁A���̖�肪�}�X���f�B�A�Ŏ��グ���邱�Ƃ͂قڂ���܂���B�����炱���A�������͎���I�ɍ��ʓ��R�[���V���b�v���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���ɁA�q�������ɂ͐ێ悳���Ȃ��悤�Ȕz�����K�v�ł��B �@���ۓ��A�a�A��(IDF)�̕ɂ��ƁA���E�̓��A�a�l���͔����I�ɑ��������Ă���A2014�N���݂œ��A�a�L�a�Ґ���3��8670���l�A���E�l����8.3�����늳���Ă��܂��B�܂��A���̂܂ܗL���ȑ���{���Ȃ��ƁA���̐���35�N�܂ł�5��9190���l�ɑ�������Ɨ\�����Ă��܂��B �@���A�a�̑������͐�i����20���A���W�r�㍑�ł�69���ɂ����Ƃ����Ă��܂��B�����J���Ȃ̔��\�ɂ��ƁA���{�l��5�l��1�l�͓��A�a����т��̗\���R�ł��B���A�a�͌����đΊ݂̉Ύ��ł͂���܂���B���A�a�Ƃ̉���f���邽�߂ɁA�܂��͍��ʓ��R�[���V���b�v����̈��ݕ�����Ɏ��Ȃ����Ƃ���n�߂܂��傤�B Business Journal 2015�N4��3,10�� |
|
�R���X�e���[�����������A�咰�����p��̐��������グ�� ���ݖ�u�X�^�`���v�A��p�ł̌��،��� |
| �@�咰����̎�p�������l���A�R���X�e���[������������ݖ�u�X�^�`���v������ł����ꍇ�A����ł��Ȃ������l�ɔ�ׂĐ������Ԃ����тĂ����ƕ��������B��p�l�ł̌������ʂ��B �X�^�`���͑咰����ɁH �@��p�̍�����p��w��w�@�����a�@�̌����O���[�v���A�咰����̐�厏�N���j�J���E�R�����N�^���E�L�����T�[����2015�N�Q��21���ɕ����B �@�R���X�e���[������������ݖ�u�X�^�`���v�́A�����ُ�ǂ̎��ÂɍL���g���Ă���B�ŋ߁A�X�^�`���ɍR�����p������Ǝ������A�������o�Ă��Ă���B �@�����O���[�v�́A�咰����̎�p�����l���X�^�`��������ł����ꍇ�A���̌�̐������Ԃɉe�������邩�ǂ������A��p�l��ΏۂƂ��Č������B ���̈�Ãf�[�^�x�[�X���猟�� �@�܂��A��p�̂���o�^�V�X�e������A������������iCRC�j�̐i�s�X�e�[�W�P�A�Q�A�R�ŁA������ړI�Ƃ�������̐؏���p�����l�̃f�[�^���W�߂��B�Y��������P��7000�l������̌��̑ΏۂƂ����B �@���ɁA�������N�ی����x�̃f�[�^�ׁA���̐l�������A�咰����Ɛf�f���ꂽ�Ƃ����炳���̂ڂ��ĂP�N�ȓ��ɃX�^�`������������Ĉ���ł������ǂ����ׂ��B���̌��ʁA13���ɓ������2000�l���X�^�`��������ł���A�c��̖�P��5000�l�͈���ł��Ȃ������B �@�W�߂��f�[�^�v�I�ɉ�͂��A�X�^�`��������ł����l�ƈ���ł��Ȃ������l�ŁA����Ŏ��S���Ă��Ȃ��l�̊����i������ٓI�������j�ƁA�S�̓I�Ȑ��������r�����B�f�[�^�́A�N��A���ʁA�f�f�����N�A�ʉ@���A���@���A�������Ă���a�C�̉e�����O���悤�ɁA�v�Z�ŕ�����B ����ł��������������� �@���ʁA�X�^�`��������ł����l�̕����A����ł��Ȃ������l�ɔ�ׂĂ���Ŏ��S�����l�̊�����23�����Ȃ������B��������Ȃ����S�ɂ��Ă����S�����l�̊�����18�����Ȃ������B �@����ɁA���ʁA����̐i�s�X�e�[�W�ʁA�N��ʂɉ�͂��Ă��A��͂�X�^�`��������ł����l�̕�����p��̐����������������B�܂��A���A�a�⍂����������l�ł��������ʂ������B �@�X�^�`���̕��p�́A��p�l�ł͑咰����̗\��ɗǂ��e����^���Ă����B�����A�W�A�l�̓��{�l�ł����l�̌��ʂ������邾�낤���B Med�G�b�W 2015�N4��3�� |
|
���w�Ö@�������Ȃ��咰����ɁA�����̈����u���זE�v���E���L�]�ȐV���� �ăy���V���x�j�A�B����w�A�l�Y�~�̎����ŏؖ� |
| �@�ŋߒ��ڂ̐V�������q�W�I�A���w�Ö@�������Ȃ�������������̗L�]�Ȏ��Ö�ƂȂ肻�����B���̐V��́A����זE���E�������ł͂Ȃ��A�R����܂������Ȃ������̂P�ł���u���זE�v�����_�������ɂł���ƕ��������̂��B ����I�ȐV�� �@�č��y���V���x�j�A�B����w�n�[�V�[�������𒆐S�Ƃ��������O���[�v���A����̐�厏�L�����T�[�E���T�[�`����2015�N�S���P���ɕ����B �@�u���זE�iCSC�j�v�́A���X�ɂ���זE�ݏo���A���낢��Ȏ�ނ̂���ɕω�����\�͂����B�����̈�������ȍזE���BCSC�͑咰����ɂ����݂��Ă���B �@���̂��߁A���זE���E�����Â��ł���A������k�������萶�����Ԃ���������ł���B�����O���[�v�͍���A�uONC201/TIC10�v�Ƃ����V�����R����܂ɒ��ڂ����B �@ONC201/TIC10�́A����p���N�����Ȃ��ŁA����זE�������E������I�ȐV�B�uTRAIL�v�ƌĂ��^���p�N�����A����זE�����E������d�g�݂����p���Ă���B �l�Y�~�Ō��� �@�����O���[�v�͈ȑO�AONC201/TIC10����p����������זE�ł́A�uAkt�v�uERK�v�Ƃ����^���p�N�����ז����邱�Ƃ��ł��āA���̕ω��ɂ��uFoxo3a�v�Ƃ����^���p�N�������o���āA���ʓI�ɂ���זE�̎��E�𑣂��uTRAIL�v�����o����ƕ����B �@�uAkt�v�uERK�v�uFoxo3a�v�́A�ǂ�����זE�ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�ȃ^���p�N���B�����Ō����O���[�v�́A���̐V������������́u���זE�v��_�������ɂł��������Ɨ\�z���āA�l�Y�~�Ō����s�����B �@���؎����ł́A���זE�̖ڈ�ɂȂ�^���p�N���ł���uCD133�v�uCD44�v�uALDH�v���\�ʂɏo�Ă���זE���u���זE�v�Ƃ����B ���זE���E���� �@�����̌��ʁA�l�Y�~�̌�����������ł��A�V���[���Ŕ|�{��������זE�ł��AONC201/TIC10�͂ǂ���ɂ����Ă����זE�����ł������B �@���̐V��̐����uTIC10�v�́A�R����܁u�t���I���E���V���i5-FU�j�v�̌����Ȃ����זE���V���[���̒��ő����ĉ�ƂȂ�̂�j�~�����p�����ƕ��������B �@���זE�́A�Ⴄ��ނ̃l�Y�~�ɈڐA���Ă��A���┽�����N�������ɂ���Ƃ��Đ����ł�������������Ă���B������ONC20/TIC10�𓊗^����ƁA���זE�́A�Ⴄ��ނ̃l�Y�~�ɂ͐����ł��Ȃ��Ȃ����B���̐�����j�~������ʂ��A5-FU���ONC20/TIC10�̕����D��Ă����B �@����ɏڂ������ׂ��Ƃ���AONC201/TIC10�͗\�z�ʂ�ɁA���זE�ł��uAkt�v�uERK�v�̓������ז����Ă����B����ɁuFoxo3a�v�����o���A���ʓI�ɁuTRAIL�v�����TRAIL����p���邽�߂ɂ���������́uDR5�v���A���זE�����E�ɒǂ�����Ă����B �@ONC201/TIC10�͌�����������̍����ɗL�]�Ȗ�ƂȂ邾�낤�ƌ����O���[�v�͌��Ă���B Med�G�b�W 2015�N4��6�� |
| �����h����w�u�R�[�q�[���̑�����Ɍ��ʓI�����v |
| �@���݁A���{�l�̑����S����3���قǂ��߁A80�N�ォ�玀�S������1�ʂƂȂ��Ă���g����h�B���̂����A�x�A�݁A�咰�Ɏ����A�ߔN�ł͕��ϔN��̏㏸�ɔ����A���������邷��������Ǝ��S�Ґ�4�ʂ𑈂��Ă���̂��g�̑�����h���B���Â͓��X�i���𑱂��Ă��邪�A�ˑR�Ƃ��č���������̂����B �@���̂��߁A�Ȋw�I�����Ɋ�Â��\�h�����߂ďd�v������A�e��̃K�C�h���C����������Ă��邪�A������ɂ̓R�[�q�[�̐ێ�Ɋ̑�����̃��X�N��ጸ������\�������邱�Ƃ����\����ڂ��W�߂Ă���B �R�[�q�[�Ɗ̑�����̊֘A���V���ɔ��� �@���E��������͂��̂قǁA���X�N������ւ́A�H����h�{�A�g�̊����A�̏d�̉e���͂���v���O�����̍ŐV�̌��ʂ��܂Ƃ߂ĕB�v���O�����ł́A���E������W�߂�ꂽ34�̌����f�[�^�u�j��800���l����W�߂��A�̑�����24,600�P�[�X���܂ށv�ׂ��Ƃ����B �@2007�N�ȗ��ƂȂ����̑�����Z�N�V�����̃A�b�v�f�[�g�ŁA�����ȏ؋�������ꂽ�͈̂ȉ���4�_�B�̏d���߂�얞���̑�����̃��X�N�������邱�ƁA���ɂ����悻3�t�ȏ�̃A���R�[�������̐ێ悪�̑�����̗v���ɂȂ邱�ƁA�A�t���g�L�V���ɉ������ꂽ�H���̏���̑�����̃��X�N�������邱�ƁA�����ăR�[�q�[�����ނ��Ƃ��̑�����̃��X�N�����ƌ��т����邱�Ƃ��B �@���̂����A�̏d����є얞�A�R�[�q�[�ɂ��Ă̔����͐V���Ȃ��̂��Ƃ����B ���̖h��̊������ɉ\����T�� �@�̏d��얞�Ɗ̑�����̊֘A���������ꂽ���ƂŁA�̏d������̗v���Ƃ��Ċ֘A�t������P�[�X�����߂�10���邱�ƂɂȂ����B�얞�̓C���X�����A�C���X�����l�������q�A�G�X�g���Q���Ƃ���������̐����𑣂�������肾���z�������̃��x���ɉe����^���A�܂��̑�����̔����Ɣ��B����������̂̉��ǔ����������������邱�Ƃ��������Ă���B �@����̔��\�łƂ��ɒ��ڂ��W�߂Ă���R�[�q�[�ɂ��ẮA�܂܂�鉻���������̖h��������������邱�Ƃ�������A�ق��ɂ����ǂ����炵DNA�ւ̃_���[�W��h�����ƁA�܂�DNA���C������\�͂������A�C���X�����ɑ���q���x�����P�����邱�Ƃ̉\��������Ƃ������Ƃ��B �R�[�q�[�Ŋ� �@�������A����ł̓R�[�q�[�̐ێ���̑�����\�h�̌���I�ȃA�h�o�C�X�Ƃ��邽�߂ɂ́A�܂������̏o�Ă��Ȃ��^�������悤���B�Ⴆ�A�R�[�q�[�����ޗʂ�~���N�^�����̗L���A���邢�͒����Ŏg��ꂽ�R�[�q�[�ɃJ�t�F�C���������Ă������A���M�����[���C���X�^���g���Ƃ������_�����m�ł͂Ȃ��Ƃ����B����͂����������𖾂炩�ɂ���K�v������ق��A�̂̑��̕��ʂւ̉e�����T�d�ɒ��ׂȂ���Ȃ�Ȃ��悤���B �@������������I�ɐێ悷�邱�Ƃ��e�ՂȃR�[�q�[�Ȃ����ɁA���ۂ̗\�h�@�Ƃ��Ċm�������ɂ߂ėL�v�Ƃ����A����̂���Ȃ錤����҂������Ƃ��낾�B�Ȃ����E��������ł͊̑�����̃��X�N�����������邽�߂�2�̂��Ƃ𐄏����Ă���B����́A���N�I�ȑ̏d���ێ����邱�ƁA�����ăA���R�[����ۂ�ꍇ������ɒj���ōő�2�t�A������1�t�ɐ������邱�Ƃ��B�����̌��N���l���Ă��������ŎQ�l�ɂ��Ă͂��������낤���B FUTURUS�i�t�g�D�[���X�j 2015�N4��7�� |
|
�R����܂ɈӊO�ɂ��A���c�n�C�}�[�a�̎��Ì��ʁA�V��̊J���ɁH ���������ŋL���r���̉��m�F |
| �@�R����܂Ƃ��ĊJ�����ꂽ�A�A���c�n�C�}�[�a�Ɍ��ʂ�����\�����o�Ă����B�č��̃A���c�n�C�}�[�a���������iADCS�j�E�G�[����w���܂ތ����O���[�v���A2015�N�R��31���ɕ��Ă���B �A�~���C�h���̃v���[�N�`�����Ւf �@�uAZD0530�v�ƌĂ�Ă����́A��ɂȂ邪��ł���Ō`����̎��Â̂��߂ɊJ�����ꂽ�B����̎��Âł͐������Ȃ��������̂́A�A���c�n�C�}�[�a�ǂ������}�E�X�ɗ^�����Ƃ���]�זE�ɓ��������āA�L������������ʂ�����Ɗm�F�ł����B �@�����O���[�v�́AAZD0530���A���c�n�C�}�[�a�̎w�W�Ƃ����A�~���C�h�����ł܂�Ƃ��Ɉ����N�������_���[�W���u���b�N����Ƒz�肵�Ă���B�A���c�n�C�}�[�a�̏����i�K�́uFYN�y�f�v�̊������̎ז��ɂ��A�]�זE�Ԃ̃V�i�v�X�A�������킹��ω���j�~������ʂ����蓾��悤���B �l�ł̗Տ��������n�܂� �@�����O���[�v�ɂ��ƁA����͐l�ł̗Տ��������n�܂�\��ƂȂ��Ă���B�Տ������ɂ���āA���S����L�����Ȃǂ��m�F�����A�A���c�n�C�}�[�a�ɋꂵ�ސl�ɂ͘N��������炷���ƂɂȂ肻�����B Med�G�b�W 2015�N4��9�� |
|
�č��ł͎q�ǂ��̂����҂͑����Ă���A���̑唼���ʂ̕a�C�ɂ������Ă��� �����ł͂Ȃ��A�u���Ì�v�̋������K�v�� |
| �@�č��Ŏq�ǂ��̎���ɂ���ɂȂ����l�̒������s���A������������Đ��������l�������Ă���Ƃ������Ԃ����������B����Ŏ��Â��I��������ɁA�ʂ̖����I�ȕa�C�ɂȂ��Ă���ꍇ�������A���Ì�̑Ή����d�v���ƕ��������B 2005�N����U���l���� �@�č��m�[�X�E�F�X�^����w���܂ތ����O���[�v���A�č�������c�iAACR�j�����s����L�����T�[�E�G�s�f�~�I���W�[�E�o�C�I�}�[�J�[�Y���v���x���V��������2015�N�S�����ŕ����B �@0�`19�Ƃ����q�ǂ�����ɂ���Ɛf�f���ꂽ�l���ǂꂭ�炢���邩�ׂ������͏��Ȃ��悤���B �@�����O���[�v�́A�Q�̑�K�͂ȃf�[�^�x�[�X��ΏۂƂ��āA�č��̏������������Ґ���ǂꂭ�炢����ɂȂ����l������̂��ׂ��B �@�Q�̑�K�͂ȃf�[�^�x�[�X�Ƃ́A�č����������iNCI�j�̓��v�f�[�^�ł���uSEER�v�ƌĂ��f�[�^�x�[�X�A�č��ƃJ�i�_�̏������������҂P��4000�l�ȏ�̌����ł���uCCSS�v�̃f�[�^�x�[�X���BSEER�ł́A1975?2011�N�̂������Ɛ������ɂ��Ă̏�������Ă���B �����҂�39���l�Ɛ��� �@���̌��ʁA�č��̏��������Ґ��͂��悻39���l�Ɛ��肳��i�č��������̃`�[����2005�N�ɍs�����������U���l�̑����j�A���悻84�����f�f����T�N�ȏ㐶�����Ă����B �@�����҂̂��悻70�����y�`�����x�̖����I�ȕa�C�ɂ������Ă����B32���͏d�x�̏�Q�A���Ɋւ�閝���I�ȕa�C�ɂ������Ă���Ɛ��肳�ꂽ�B �@20�`49�̔N��ł́A�����҂̂��悻35�����u�_�o�F�m��Q�v�Ƃ����]�̖�������Ă����B���̔N��O���[�v��13�`17�����@�\�^���_��Q�A�����̐����A�ɂ݁A�s���^�������Ă����B �@��������Â��邱�Ƃ����ɏW�����Ă��܂����������A�����I�ȕa�C�̔�������d�ēx�͏d��Ȗ��Ƃ����B �@�q�ǂ�����ɂ�������������l���a�C�ɂȂ�₷���v���ׂāA�L���Ȏ��Ì�̑Ή��A���n�r���̃��f�������K�v������ƌ����O���[�v�͎w�E����B Med�G�b�W 2015�N4��11�� |
| �������]�̘V����!? �u�����s���v�������N�����\�z�ȏ�̃��X�N�Ƃ� |
| �@������Q�Ă������c�c�B�C�������������t�͑̒�����������ȋG�߂ł��B�ԕ��ǂɔY�܂���A�Ȃ��Ȃ��Q�t���Ȃ��l���������ƂƎv���܂��B �@����Ȓ��A�ǎ��Ȑ������Ƃ�͓̂�����̂ł���ˁB�m�炸�m�炸�̂����ɐQ�s���ɂȂ��Ă��܂��H �@�����ō���́A���эO�K����̒����w������������u��v���ɂ߂Ȃ����x���Q�l�ɁA�g�����s���ɂ�郊�X�N�ƓK�Ȑ������ԁh�ɂ��Ă��`�����܂��B �Q�s�����Ƒ���₷���Ȃ�H �@�l�͐Q�Ă���ԂɁA�l�X�ȃz�������債�A�זE�̃_���[�W���C�����Ă���Ƃ����܂��B���̂��߁A�Q�s���ɂȂ�Ƒ̂����邭�Ȃ�܂��ˁB�z�������o�����X�̕��ꂩ��H����������đ���₷���Ȃ�̂������ł��B �@�H�~���グ��g�O�������h�Ƃ����z�������̕��傪�����A�t�ɁA�H�~��}����g���v�`���h�Ƃ����z�������̕��傪���邽�߁A���J�����[�̃W�����N�t�[�h�����H�ׂĂ��܂��Ƃ����܂��B���������ΐQ�s�����ƁA�����|�e�g�`�b�v�X��P�[�L�A�s�U�Ȃǂ̂����Ă肵�������Ɏ肪�L�тĂ��܂��܂��ˁB �Q�s�����O���B����������̃��X�N���グ��!? �@�Z�������ĐQ�s���Ƃ����l�͗v���ӂł��B�������Q�s���ƕ����Ă͂����܂���B�Q�s�����a�C�������N�������Ƃ�����̂ł��B �@�������Ԃ��Z���قǁA�O���B����������̃��X�N�������Ȃ邱�Ƃ�����Ă��܂��B �@�t�ɐ������Ԃ���������ƁA�������ɕ��傳��郁���g�j���̕��厞�Ԃ������Ȃ�A���̃����g�j�������z��������}�����A���z�������֘A����A�Ƃ��ɓ�����̃��X�N���ቺ���邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B�� �K�Ȑ������ԂƂ� �@�����s���ɂ��̂ւ̉e�����[�����Ƃ������Ƃ��킩��܂������A�t�ɐQ�����Ă��܂��̂��A�����s���Ɠ��l�ɐS�g�Ɉ��e�����y�ڂ��܂��B7���Ԑ����������Ƃ����S���X�N�����Ȃ��Ƃ����܂����A�l�����傫���A�N��ɂ���Ă��ς���Ă���Ə��т���͒����̒��ŏq�ׂĂ��܂��B �@�Ⴆ�A�q�ǂ��̂����10���ԐQ�Ă����v�Ȃ̂ł����A����60����߂����6���ԐQ��Ώ\���������ł��B�Q�����͔]�̘V���������N�����Ƃ���Ă��܂��B�Q�s��������Ƃ����ċx���ɂ܂Ƃ߂ĐQ�Ă������Ƃ����̂��t���ʂȂ̂ł��ˁB �@��Ȃ̂́g�S�n�悭�ڊo�߂�h���ƁB�u�悭���ꂽ�ȁv�Ǝv������A�_���_���Ɠ�x�Q����̂͂�߂��ق����悳�����ł��B �@�ȏ�A�g�����s���̃��X�N�ƓK�Ȑ������ԁg�ɂ��Ă��`�����܂������A�������ł������H�@�̒�����������ȏt�����炱���A�ǎ��Ȑ����ɂ��čl���Ă݂�Ƃ�����������܂���ˁB �@�̂̂��邳����������A�����n���̂��鐶����S�����Ă݂܂��傤�B Peachy 2015�N4��12�� |
| �`���R���[�g�������Ƃ����������A�R�����p�����߂���@����������� |
| �@��������n�D�i�Ƃ��đ����̐l�Ɋ��Ă���`���R���[�g�B���̌����ł���J�J�I�̎��́A���N�ɗǂ��Ƃ����|���t�F�m�[����L�x�Ɋ܂�ł��܂��B �@���̓x�A�J�J�I�̉h�{�f����葽���ێ������܂܁A�����Ȃ킸�ɉ��H����V���Ȏ�@����������܂����B3��24���Ƀf���o�[�ŊJ�Â��ꂽ�A�����J���w��̉�ɂāA�e���̌����҂ɂ��\�������`�[�����ŐV�̌������ʂ\���܂����B �R�_��������ێ����邽�߂� �@�J�J�I�̓`���R���[�g�ɂȂ�܂ł̃v���Z�X�ŁA�傫�ȕω������ǂ�܂��B�J�J�I�̖������E�݁A���̒�����ꂢ��q�����o���Ĕ��y�����A�����Ŋ��������܂��B����������q�̓��[�X�g����A������~���N�A���̑��̍ޗ��ƍ������킳�ꂽ��ŁA�ŏI�I�Ƀ`���R���[�g�ƂȂ�̂ł��B �@���̂悤�Ȑ����ߒ��̒��ŁA�|���t�F�m�[���Ȃǂ̉h�{�f�̈ꕔ�͎����Ă��܂��̂ł��B�|���t�F�m�[���́A�����S���a�ւ̑ϐ������߂�ƌ����Ă���R�_���������܂�ł��܂��B���̍R�_��������ێ����邽�߂Ɍ����`�[���́A�`���R���[�g�̐��Y�H���ɐV������Ƃ��ЂƂ����邱�Ƃɂ��܂����B �@����́A�J�J�I�̎������q�����o���Ĕ��y�Ɗ������s���O�ɁA�����ԐQ������Ƃ������̂ł��B���̍�Ƃ��ǂ̂悤�Ȍ��ʂ�^����̂��������邽�߁A�����`�[����300�̎����g���A�������̈قȂ�ۑ����Ԃ������܂����B�ۑ����Ԍ�͒ʏ�Ɠ������H�H����p���܂��B �@���ʂƂ��Ă킩�����ŗǂ̕ۑ����Ԃ�7���Ԃł����B�ۑ������Ȃ��������̂�A�X�ɒ����ԕۑ��������̂Ɣ�r����ƁA��葽���̍R�_���������ێ�����Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�����`�[���ɂ��A7���̓J�J�I���O���̊k�����葽���̉h�{�f���z�����Ȃ�����A�h�{�f������قǂ͒����Ȃ��A���傤�Ǘǂ����Ԃ��Ƃ������Ƃł��B �œK�ȃ��[�X�g���Ԃ�Njy �@����܂Ń��[�X�g�̍H���Ń`���R���[�g�̉h�{����������ƐM�����Ă��܂������A�����`�[���͂��̉e���ɂ��Ă��G��Ă��܂��B�����������Ƃ́A�����ቷ�Œ����ԃ��[�X�g������q�̕��������̍R�_���������܂݁A7���ԐQ��������������o������q�̏o�����x�X�g�������Ƃ������Ƃł��B �@�o���オ�����`���R���[�g�͉h�{�����L�x�Ȃ����łȂ��A�������Â��Ȃ�܂����B�ꂢ��q�����̒��̊Â��ʓ��ƒ����Ԑڂ��Ă������߂Ǝv���܂��B�����`�[���͍���������𑱂��A���[�X�g�̍H�������������v��𗧂ĂĂ��܂��B ���C�t�n�b�J�[ 2015�N4��17�� |
| �Ȃ��A���W�F���[�i�E�W�����[�͌��N�ȓ��[�A�����E���ǂ�؏������̂� |
| �@�č��l���D�̃A���W�F���[�i�E�W�����[����i39�j���A���������\�h���邽�߂ɁA���N3���A�����̗����E���ǂ�؏������p�����B2013�N5���ɂ́A�������\�h���邽�߂ɁA���N�ȗ����[��؏����čČ������p���Ă���b��ƂȂ����B �@�u����ŁA���̎q�������́w�}�}�͗�������Ŏ��x�ƌ���Ȃ��čςނ悤�ɂȂ����v�B�A���W�F���[�i�E�W�����[����́A3��24���t�̃j���[���[�N�^�C���Y�Ɍf�ڂ��ꂽ��L�̒��ł�������Ă���B ��`��������E��������nj�Q�Ƃ� �@�W�����[����́A�זE�̂���h������}����`�q�uBRCA1�v�ɐ��܂���ُ킪����A�������Ȃ����87���̊m���œ�����ɁA50���̊m���ŗ�������ɂȂ�Ɛf�f����Ă����B�W�����[����̕�e��49�ŗ�������Ɛf�f����A����������ǂ��A56�ŖS���Ȃ��Ă���B �@����̑c�ꂪ��������A�f���������ŖS���Ȃ��Ă���A�����ɏ����̂���̒��݂�ꂽ���Ƃ������āA����A�����E���ǂ̗\�h��p�ɓ��ݐ����Ƃ����B3�l�̎��q��3�l�̗{�q�̑��݂����f�ɑ傫���e����^�����悤���B �@����̑����͐����K���A���Ƃ������v���������������Ԃ����Ĕ��ǂ���B�������A5�`10���͈�`���̂���ł��邱�Ƃ��������Ă��Ă���B����1���W�����[����̂悤�Ȉ�`��������E��������nj�Q�iHBOC�j�ŁA�W�����[����̂悤��BRCA1�ɕψق̂���^�C�v�̑��ABRCA2�ƌĂ�邪��}����`�q�ɕψق�����ꍇ������B���{�ł��AHBOC�̐l�̂����N�Ԗ�7000�l��������◑������Ɛf�f����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��v�����B �@�C�O�̃f�[�^�����AHBOC�̐l��������ɂȂ�m����41�`90���A���������8�`62���B���{�̏������ꐶ�U�œ�����ɂȂ�m����8���A���������1�������烊�X�N��5�`60�{�������킯���B��x������ɂȂ����l�����Α��̓��[�◑���ɂ���ǂ���m����HBOC�̐l�ɔ�ׂč������Ƃ��������Ă���B�e����q�ɂ��̈�`�q�ψق��p�����m���́A���ʂɊւ�炸50���B�j�������̕ψق��p���ƁA��10���̊m���őO���B���j��������ɂȂ�B �@�W�����[�����N�ȓ��[��؏�����2�N�O�ɂ�HBOC�Ɋւ����ނ��������A���{�̕����̐��Ƃٌ͈������ɁA�u�����E���ǂ̗\�h�؏����������ׂ��ł͂Ȃ����v�ƌ��ɂ����B������́A�}�����O���t�B�i���[X�������j�Ǝ��G�f��g�ݍ��킹�����f�A�Ⴂ�l�̏ꍇ��MRI������g�ݍ��킹��Α����������\�ł���̂ɑ��A�����́A���Ղ̉��ɂ��鏬���ȑ���ŕ����ɍL����₷�����Ƃ����葁��������������S�����������炾�B �@3�J�����甼�N��1���̌������Ă����Ƃ��Ă��A���������Ƃ��ɂ͂��łɐi�s�������Ƃ����P�[�X�����ۂɂ���B�W�����[���������A��ᇃ}�[�J�[�uCA�|125�v�͐��킾�������A��t�Ɏ�ᇃ}�[�J�[�͑��������50�`75�����������Ƃ̐������Ă���B �\�h��p�͂ǂ��܂Ō��ʂ����邩 �@�����E���ǂ�؏�����A���������80�`90���\�h�ł��A������ɂȂ郊�X�N��50�����点��B�č��̃K�C�h���C���ł́A�u�����E���ǐ؏��ɂ�闑�����X�N�ጸ��p�́A���z�I�ɂ�35�`40�̊Ԃŏo�Y�������������_�A���邢�́A�Ƒ��ōł�������������ǂ����l�̔N��ł̎��{���l������v�Ƃ����B �@���{�ł��A���L���a�@�A���H�����ەa�@�A�c��`�m��w�a�@�Ȃǂŗ����E���ǂ̗\�h�؏����s���Ă���B�����A���{�̏ꍇ�A�\�h���Âɂ͕ی����g��������ŁA100���~���炢������̂���_���B���o�����鏗���������E���ǂ�؏�����ƍX�N����Q�̂悤�ȏǏo�邱�Ƃ�����A�܂��A�킸��������������ɂȂ郊�X�N�͎c��Ƃ������f�����b�g����E���m���������ŁA�\�h��p���邩�ǂ����������ׂ����낤�B �@�W�����[�������L�̒��ŁA�uBRCA1�z���̏������ׂĂɗ\�h��p�����߂�킯�ł͂Ȃ��v�Ə����Ă���悤�ɁA��������̗\�h���Âɂ́A��p�̑��ɁA�����z�������̃^���L�V�t�F���p������@������B��p���Ȃ��I���������l�ɂ́A�č��̃K�C�h���C���ł́A���N��1��o�T�����g�����Ǝ�ᇃ}�[�J�[�̌������邱�Ƃ���������Ă���B���Ȃ݂ɁA���[�̗\�h�؏��ɂ��Ă��A�{�l����]����A���{�ł��������̕a�@�Ŏ���悤�ɂȂ��Ă��Ă���B �@HBOC���ǂ����́A��`�J�E�Z�����O���������ŁA���t��������Ε�����BHBOC�̉\��������̂́A�`�F�b�N�V�[�g��1�ł����Ă͂܂�l���B ���`������������̊ȒP�`�F�b�N�V�[�g�� �@����A�������ꂼ��̉ƌn�ɂ��āA���Ȃ����g���܂߉Ƒ��̒��ɊY�������������ꍇ�A�`�F�b�N�����Ă��������B �� 40�Ζ����œ�����ǂ����������܂����H �� �N����킸��������i���ǂ���E��������܂ށj�̕�����������Ⴂ�܂����H �� ���Ƒ��̒��ł���l�̕����������킸����������� 2�ȏ㔭�ǂ������Ƃ�����܂����H �� �j���̕��œ�����ǂ��ꂽ������������Ⴂ�܂����H �� ���Ƒ��̒��ł��{�l���܂ߓ�����ǂ��ꂽ����3���ȏア������Ⴂ�܂����H �� �g���v���l�K�e�B�u�̓�����Ƃ���ꂽ������������Ⴂ�܂����H �� ���Ƒ��̒���BRCA�̈�`�q�ψق��m�F���ꂽ������������Ⴂ�܂����H ��1�ł��Y������A��`������������ł���\������ʂ�荂���B ��HBOC�R���\�[�V�A���쐬 �@��`�J�E���Z�����O�ƌ���������a�@�́A���Ƃ������{HBOC�R���\�[�V�A���̃E�F�u�T�C�g�ihttp://hboc.jp/facilities/index.html�j�ʼn{���ł���B�����I�ɂ́A������������ɂȂ����l����`�q�ψق̗L���ׁABRCA1��BRCA2�ɕψق����邱�Ƃ�������A��e�A�o���A������������̂���������B�����ɂ͕ی���������1��20���`30���~������B���łɉƑ��Ɉ�`�q�ψق����邱�Ƃ��������Ă���l����������ꍇ�̌������͖�5���~���B��`�J�E�Z�����O���ی����g���Ȃ��Ƃ��낪�قƂ�ǂŁA�Ⴆ�A���L���a�@�Ȃ珉���7200�~�Ƃ����B �@�W�����[����̂悤�ɉe���͂̋������D���A�����E���ǂƓ��[�̗\�h�؏���I�сA��������\�������Ƃ͗E�C���錈�f���BHBOC�̏ꍇ�A��`�q�ψق����邱�Ƃ�������W�����[����̂悤�ɑO�����ɗ\�h���Âɂ���Ă���ɂȂ郊�X�N�����点��B�����A�Ⴂ�l�Ȃ�A��`�q�����̌��ʂ��A�����A�o�Y�A�A�E�ɉe�����鋰�������B�č��ł́A2008�N�Ɉ�`�q��ʋ֎~�@�����肳��A�̗p�A���i�A��Õی��̉����Ȃǂł̕s���Ȉ������ւ��Ă���BHBOC�̐l�����z�̕��S�����Ȃ��Ă��A��`�q������\�h���Â�����悤�ɁA�ی��f�É���ڎw���������o�Ă��Ă���A����́A���{�ł��A��`�q�����̌��ʂ����ʂɂȂ���Ȃ��悤�ɁA��Ñ̐������ł͂Ȃ��@���̐�����i�߂邱�Ƃ��d�v�ɂȂ��Ă��������B PRESIDENT Online 2015�N4��26�� |
|
�����p�ߓ]�ڑ���DDS�𓌑�J�� �L�����A�a50�i�m�ȉ��A��܂����ǂ�L�ӂɓ��� |
| �@������w��w�@�H�w�n�����Ȃ̕Љ��ꑥ������̌����`�[���́A�����p�ߓ]�ڂ�W�I�Ƃ����S�g���^�ɂ��h���b�O�f���o���[�V�X�e���i�c�c�r�j���J�������B��܂̓����p�ߓ]�ڑ����̌��ǂ�L�ӂɓ��߂��A����ɓ]�ڑ��̐[���ւ��Z������B �@�c�c�r�ł���i�m�L�����A�̗��a���T�O�i�m���[�g���ȉ��ɐ��䂷�邱�Ƃɂ���Ď��������B���ǂ���Ė�܂͑̓��̂��ׂẴ����p�ߓ]�ڑ��ɑ��ċϓ��ɖ�͂��邱�Ƃ��ł���Ƃ݂��A���҂ւ̕��S�����Ȃ��V���Ȏ��Ö@�Ƃ��āA����̍Ĕ��}���Ɛ������Ԃ̉����̂ق��A�p�n�k�i�N�I���e�B�E�I�u�E���C�t�j�̌��オ���҂����B �@�c�c�r�́A����������܂��i�[�����a�����̒��j�Ɛe�����̊k�������������q�~�Z���^�̃i�m�L�����A�B�����O���[�v�͗��a�R�O�i�m���[�g���A�V�O�i�m���[�g���̃i�m�L�����A�̂ق��A���a�W�O�i�m���[�g���̊����̃h�L�\���r�V������|�\�[����p���Č��ʂ��r�����B �@�R�O�i�m���[�g���̃i�m�L�����A�������Ö����^��ɑI��I�Ƀ����p�ߓ]�ڂɏW�ρA�]�ڂ���̐�����}�����邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�����p�ߓ]�ڎ��Âɂ�����i�m�c�c�r�v�ł͗��a�T�C�Y�̐��䂪�d�v�Ƃ��Ă���B���łɕč��Ńi�m�L�����A�ƂƂ��ɑ�P���Տ������i�o�P�j�A�o�Q�̎��������{���B m3.com 2015�N5��1�� |
|
�u�v�u�I�����W�{���F�v�u�ԁ{���v�u���v�A�咰���炷��Ɖʕ��̐F�Ƃ́H �S�̃p�^�[���̂����R�̓��X�N�ቺ�Ɋ֘A |
| �@��Ɖʕ��̐H�ׂ��镔���̐F�ɂ͂��܂��܂���B �@���̂����咰����̃��X�N���ł��傫�����炵�Ă����F�����������B �@�����A���R��w��WP�E���I����̌����O���[�v���A�h�{�w�̍��ێ��ł���u���e�B�b�V���E�W���[�i���E�I�u�E�j���[�g���V������2015�N�S�����ŕ��Ă���B �S�̃O���[�v�ɕ����Č��� �@��Ɖʕ��̐F�ƁA�咰����̃��X�N�̊֘A���ɂ��Ē��ׂ������͂���܂łȂ��B �@�����Ō����O���[�v�́A���̊֘A���ɂ��Ē����l1057�l��ΏۂƂ��āA2010�N�V������2014�N�V���ɂ����Č����s�����B �@��Ɖʕ��́A��ɂ��̐H�ׂ��镔�ʂ̐F�ɂ���āA�u�v�u�I�����W�Ɖ��F�v�u�ԂƎ��v�u���v�̂S�O���[�v�ɕ�����ꂽ�B �@���̐F���Ƃɍł��H�ׂ�l����ł��H�ׂȂ��l�܂ł��S�̃O���[�v�ɕ����āA�咰����̃��X�N�Ƃ̊W���������B �͊֘A���Ȃ� �@�u�I�����W�Ɖ��F�v�u�ԂƎ��v�u���v�̖��ʕ��𑽂��H�ׂĂ���l�͑咰����̃��X�N���Ⴍ�Ȃ��Ă����B �@�ł��H�ׂ�O���[�v���ł��H�ׂĂ��Ȃ��O���[�v�Ɣ�ׂ��Ƃ��ɁA���X�N����Ԍ��炵���̂́A�I�����W�Ɖ��F��84�����炷���ʂ��m�F�ł����B���͐ԂƎ���77�����炵�Ă����B����47�����炵���B�͊W���Ă��Ȃ������B �@��Ɖʕ���H�ׂ�ʂ̑S�̂������قǑ咰����̃��X�N�͏��Ȃ������B �@�ŋ߂ł̓N���~���咰��������炷�Ƃ����������������i�N���~�����������}����A�č��n�[�o�[�h��w�̕��Q�Ɓj�B�C�`�S���咰��������炷���ʂ����Ă���i�C�`�S�̐����ő咰�����\�h���Q�Ɓj�B �@���ʕ���H�ׂ�Ƃ��ɁA�����F���ӎ����Ă��܂��������B Med�G�b�W 2015�N5��4�� |
|
�Q�T�Ԃő咰����ɂȂ�₷���̂ɁH�I�H���̕ύX�ł܂������Ԃɒ����t���[���Ȃǂ���� �H���́u���m�^�v�����u���H���@�ۂƒᎉ�b�̃A�t���J�^�v |
| �@�咰����̏��Ȃ��A�t���J�̐l�ɁA�Q�T�Ԃ����H�ׂ��̂�ς��Ă�������Ƃ���A�܂������Ԃɑ咰����ɂȂ�₷�����̏�Ԃɕς���Ă��܂����B �@�H���̉e���͕|���B �@�č��s�b�c�o�[�O��w��w�����܂ށA�p���A�t�B�������h�A��A�t���J�A�I�����_�̍��ۋ��������O���[�v���A�I�����C���Ȋw���l�C�`���[�E�R�~���j�P�[�V�����Y2015�N�S��28���ɕ����B �咰����ɍ��ɂ�鍷 �@��A�t���J�̔_���n��ł͂P���l������T�l�����ŁA������ꍇ������咰�|���[�v����߂����ɂȂ��B����ŁA�A�t���J�n�č��l�ł́A�咰����̔������͂P���l������65�l��10�{�ȏ���̊J��������B�����A�t���J���N���Ƃ���ɂ�������炸�啝�ɈقȂ�B���m�ł͂���ɂ�鎀�S�łQ�Ԗڂɑ����̂��咰���B �@�����������̍��͉��Ȃ̂��B �@�����O���[�v�͐H���Ɍ��������߂��B �@�A�t���J�n�č��l�̐H���̓A�t���J�̐H����蓮�����̃^���p�N���Ǝ����������A���n���̐H���@�ۂ����Ȃ����Ƃ��A���X�N�����̌����ƍl������B �@�č��l�̂ق��ł́A�咰�ɂ���_�`�_�̐��������܂��Ă���ق��A�咰�̒Z�����b�_�ʂ��Ⴍ�A�S���̑��B���̂��X�N�ɂȂ���悤�Ȍ����l�����܂��Ă���ƕ������Ă���B �@�����悤�Șb�Ƃ��ẮA�咰����̏��Ȃ����{�l���n���C�ɈڏZ����ƁA�n�����̂悤�ɑ咰�������Ȃ�܂łɂP���サ��������Ȃ��Ǝ�������������B �H����ς���Ƃǂ�ȉe���H �@�����O���[�v�́A50�`65�̃A�t���J�n�č��l�Ɠ�A�t���J�̔_���n��̏Z��20�l���ɁA�s�b�c�o�[�O��w�ƃA�t���J�̎{�݂ɏh�����Ă��炢�A�H���̃p�^�[�������ւ��Ă݂��B �@���X�N�ɉe�����y�ڂ��i���Ȃǂ̗v�f���Ȃ����ŁA���ꂼ��̐H�ނƒ����@���g���ď��������H�����������ĂQ�T�ԐH�ׂĂ��炤�Ƃ������̂��B�@��A�t���J�̓c�ɂ̐l�ɂ��ẮA�����ۂŒ�^���p�N���̐H������A�u���m���v�̐H���ɁA�܂��@�ۂō��^���p�N���A�����������b�̐H���ɕύX���A�A�t���J�n�A�����J�l�ɂ͂��̔����s�����B �@�O��ɕւƒ��̒���咰�����������Œ��ׂ��B�Q�T�ԑ����āA�����̉��w�I�ȕω��A�����w�I�����̕ω��𑪒肷�邱�ƂɂȂ�B �H���ɂ�蒰���ۂ��ς�� �@���̌��ʁA���I�ȕω�������ꂽ�B �@�č��l�̕��͒����̉��ǃ��x����������A����̃��X�N�ƊW���鉻�w�������ቺ�B�A�t���J�̐l�́A����ɊW����v���l�����I�ɑ��������B �@�ω������v�f����̓I�Ɍ��Ă����ƁA�����ǂ̍זE��ւ̑��x�A�H�����ۂ̔��y�̒��x�A���X�N�Ɋ֘A����ۂ̑�ӊ����A���ǂɊW���錟���l�Ƃ��������̂��B���ꂼ�ꂨ�݂��̂��̂ɕς���Ă��܂��Ă����B �@���ɁA�A�t���J�n�č��l�ł́A�����ۂ̎�ނ��ω��B����ɑR����d�g�݂ŏd�v�Ȗ������ʂ����ƍl�����Ă���Z�����b�_�̈�A�u���_�G�X�e���v�̐��Y�����������Ƃ��낪���ڂ����ƌ����O���[�v�͐�������B���_�G�X�e���́A�Ɖu�̒������ł��鐧�䐫T�זE�iT���O�ATreg�j�𑝂₷�Ƃ��ĊS���W�߂Ă���i��`�q�A�H���@�ہA�����ۂ̂R�ɈӊO�ȊW�A�����t���[���̐V�����������Q�Ɓj�B �@�����t���[���̓����ɂ��Ă͌������Ȃ����낤�B �@�A�t���J�n�č��l�ł́A�H���@�ۂ����悻10g����50g�ȏ�ɑ��������Ƃ��A���X�N�̒ቺ�f���������l�̕ω��ɂȂ����Ă���ƌ����Ă���B �@�������̎��b�ƃ^���p�N���̌������𗧂����\��������B �t�ɐH���̉��P�� �@���m�^�̐H�����獂�H���@�ہA�ᎉ�b�̓`���I�ȃA�t���J�̐H���ɂ킸���Q�T�ԕς��������ŁA���X�N�ɂȂ��錟���l�Ɍ���������ꂽ�B�t�Ɍ����A�咰����̃��X�N�����炻���Ǝv���A�H���ɂ��Ă͓��e��ς���Ǝv���̂ق������ɐ��ʂ͏o�Ă���Ƃ����킯���B�����Ēx������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��������B �@�����O���[�v�́A����̌�����20�l���̏��l���������_�܂��A����ɑ�l����ΏۂƂ��������Ԃ̌������s���K�v�����肻�����Ǝw�E���Ă���B Med�G�b�W 2015�N5��8�� |
| ����זE�ւ̋ߐԊO�����Ɖu�Ö@�ɂ�鎡����FDA�ɏ��F����� |
| �@�̂̊O��������ĂĂ���זE�����ł�����V�������Ö@�u���Ɖu�Ö@�v���A�č����q���������iNIH�j�̓��{�l�����҂炪�J�������ƕ��Ă���i�ǔ��V���A���{�A�C�\�g�[�v����́u�W�]�vPDF�j�B�߂��č���3��w�ň��S�����m�F���邽�߂̗Տ��������n�߂�Ƃ����B �@����זE�Ɍ������邽��ς����i�R�́j�ɁA�ߐԊO���ʼn��w�������N�������w�����iIR700�j��lj��B���̍R�̂𒍎˂ő̓��ɓ���A����זE�ɍR�̂�����������ő̊O����ߐԊO���Ă�ƁA�����z������IR700���A���͂̉��x���}���ɏ㏸�����邱�Ƃɂ���Đ��̖c�����N����A���̈��͔g�ɂ���čזE������Q�����ƍl�����Ă���悤���B �@�ߐԊO�����Ɖu�Ö@�́A�Z���Ԃ̋ߐԊO���Ǝ˂ōL�͂ɎU���������זE�����ł��邱�Ƃ��ł���̂ŁA�Ⴆ�Ύ�p�Ŏ�肫�邱�Ƃ���������X�����∫�������A�������̕����]�ڂȂǂ̂���ɑ��ďk����p���s���āA��p�I���O�ɁA�ߐԊO�����Ɖu�Ö@�Ŏ��c�������̂���זE�����S�ɏ��ł����Ď��Â��I��邱�Ƃ��\�ł��낤�B �@�܂��A���t���𗬂�Ă��邪��זE�┒���a�זE�Ȃǂ́A�R�̂̒��˂ƃ��X�g�o���h�^��ѕz�^�̏Ǝˑ��u�Ȃǂł̏A�Q���̒����ԏƎ˂Ȃǂ��s���āA��p�O��̌�������זE�̏����ɂ��]�ڗ}���⌌�t����̎��Âɉ��p���邱�Ƃ��\�ł���B �X���b�V���h�b�g�E�W���p�� 2015�N5��9�� |
|
����̎���זE�Ö@���X�e�b�v�A�b�v �u�L���[T�זE�v�̍U���͂����߂���@ |
| �@����Ɖu�Ö@�ɂ��Ă̍ŋ߂̘_����ǂނƁA����܂ł���Ă݂Ȃ��ƌ��ʂ̕�����Ȃ���������̖Ɖu�Ö@���A�_���I�Ɍ��ʂ�\�z�ł��鎡�ÂւƊm���Ȉ���ݏo�����Ǝ�������B �u�L���[�זE�v�̍U���͂����߂� �@����Љ��č��X�^���t�H�[�h��w����̘_���������悤�ɂ���̊m���ɍU���ł���u�L���[T�זE�v�����o�����Ƃ�����̂ŁA�Տ����p���߂��Ǝv�킹��Ǝ��̕��@���Ă��Ă���B �@�L�͉Ȋw���l�C�`���[���I�����C���łɌf�ڂ��ꂽ�B �@�^�C�g���́u��`�I�n���̈قȂ�̂����IgG�Ǝ���זE�̎h����g�ݍ��킹���T�זE�Ɖu��U���ł���iAllogeneic IgG combined with dendritic cell stimuli induce antitumour T-cell immunity.�j�v���B �@�����炪��זE�Ƃ͂����A�Ⴆ�A����l�̂���זE��ʂ̐l�ɈڐA����Ƃ��̂���זE�������c��͓̂���B��`�I�n���̈قȂ�̂̃L���[T�זE�̍U���͂͋����B���̂悤�ȃL���[T�זE��l�H�I�ɂ��܂����o����������S�ɍ����ł���Ǝ������B �]���̕��@�͎�Ԃ��|���� �@�]���A�L���[T�זE�����o�����߁A�i�P�j����̍זE�Ƃ���̍זE����ʂ��邽�߂ɕK�v�Ȃ���̍זE�����������Ă���u������ٓI�y�v�`�h�v����肷��i�Q�j����זE�ɂ���čU������^�[�Q�b�g�����܂����ɂ߂���悤�ɂ���i�R�j�������U������L���[T�זE��U������B���������菇���K�v�Ƃ���Ă����B �@���ɍŋ߁A���̃R���Z�v�g���������A�L���[T�זE���g���Ă�������S�Ɏ����邱�Ƃ��ł���Ǝ����_�������X�Ɣ��\����A�����m�[�}�i�������F��j�ɂ��Ă͗Տ������܂Ŏn�܂����B �@�m���ɂ��̕����͋��ɂ́u�v���V�W�������f�B�V���v���i�R���X�e���[�����������͖����̐l�ɈӖ��Ȃ��A�u�s�v�v��F�߂铮���ɒ��ڂ��Q�Ɓj�B �@���ʂ�\���ł���_���I�Ȏ��Ö@�����A�v���g�R�������G���B���y�ɂ͎��Ԃ�������B �Ȃ�����זE�͍U�������̂� �@���������ȒP�ȃL���[T�זE�����o�����@���Ȃ������������̂����̌������B �@�܂����₳���Ƃ͂����肵�Ă���A��`�I�Ȍn���̈قȂ邪��זE���U�������ߒ����ڍׂɕ��͂��Ă���B �@���̌��ʁA���n���̂���זE���o������ƁA�Ɖu��S���R�́uIgG�v������זE�Ɍ�������B����זE�̕\�ʂł��݂��Ɍ��������u�R���R�̕������v�������̂����ɂȂ�Ɠ˂��~�߂��B �@���̍R���R�̕����̂��A������@�m�������זE������������B����זE����荞��ŁA����זE�͂���Ȃ�ł͂̓�����T�זE�ɓ`���A�������U������悤�ɂ���B �@���Ɏ���זE�����������邽�߂̏������������Ă���B���B���邪��ɑ��ĂR�̃^���p�N���𒍎˂���Ƃ�������S�ɏ����ł���Ǝ������Ƃɐ��������B�u����Ɍ�������IgG�v�Ǝ���זE���h������uTNF���v�ƁuCD40L�v�ł���B �@���������ꂽ����זE�͂�������ł�����B ����זE������������Ƃ悢 �@����ɁA����g����IgG������זE�Ɍ��������Ă��A����זE���������ł���Ǝ����Ă���BIgG�ɂ���Ď���זE�����������邽�߂ɂ́A�K����������\�ʂɍR�̂������ł���R�������݂���K�v�͂Ȃ��B �@���ۂɗՏ����p����Ƃ��ɖ��ɗ���B �@���̌����͂܂��������f���̑O�Տ��i�K�B�l�ւ̉��p������ɓ���āA�Ō�ɐl�ł��������ۂ��N����Ǝ����Ă���B �@���_�͓K�Ɋ�������������זE�ɂ���זE������������ƁA���Ȃ̂���ɂ������Ɖu�������N������Ƃ������̂��B �l�ւ̉��p�͋߂� �@�d�v�Ȃ̂́A���̃v���g�R���͖����ɂł��l�ɉ��p�ł���_���B���N�ی��͎g���Ȃ����A����זE�ɂ�邪��̖Ɖu�Ö@�͉䂪���ł������Ԃy���Ă���B���̎��Â���ɒ��Ă���{�݂̐��������B����܂ł̕��@�́A�����͐��������A���܂�����������Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ������B �@���̈Ӗ��ŁA���ݕ��y���Ă������זE���Â������ς��邾���ŁA���m���ȕ��@�ւƋZ�p���X�e�b�v�A�b�v��������\��������B Med�G�b�W 2015�N5��10�� |
|
����Ɠ����V�����A�r�^�~��A�֘A�́uATRA�v�����ʁA�č��n�[�o�[�h��w���� |
| �@����̑匳��f�V�������Â��������邩������Ȃ��B �@�r�^�~��A�̊֘A�����ł���u�I�[���g�����X�^���`�m�C���_�iATRA�j�v������̑匳�ƂȂ�זE���E���\��������ƕ��������B �@�č��n�[�o�[�h��w�������������ʂŁA���L������Ɍ��ʂ���������V�������ÂɂȂ肻�����B�u�}���O�������������a�iAPL�j�v�ƌĂ�锒���a�̈��ł͏��߂Ă̕W�I��̌��ɂȂ邩������Ȃ��B ����̊��זE������ �@���ۓI��w��厏�l�C�`���[�E���f�B�V���̃I�����C���ł�2015�N�S��13���ɕ��Ă�����̂��B �@�����O���[�v�����ڂ����̂́A����̑匳�ƂȂ銲�זE���B �@���זE�́A������]�ڂ�ϐ��ɂ��e������B����̊��זE�����₷��傫�ȈӖ��������A�����������U���ł����͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ������B �@�����O���[�v�ł́A�uPin1�v�ƌĂ��^���p�N�����ז����镨������肵���BPin1�͑����̃^�C�v�̂�����R���g���[�������`�q�̈�Ƃ��Ē��ڂ������́B50��ވȏ�̂����`�q�₪��}����`�q������B�u�����`�q�̑匳���߁v�Ƃ������ʒu�t���ɂ���B���זE�ɂ��������Ȃ��B �@�]���APin1�͒��ڂ���Ă������A�������ז����錤���ɐ������Ă��Ȃ������B �@�����O���[�v�́A���̒��ɂ���8200���̉��w�i��ԗ��I�ɒ��ׂāAPin1���ז��ł��镨����˂��~�߂��B �@���ʂ���Ɣ��肳�ꂽ�̂��A�u�I�[���g�����X�^���`�m�C���_�iATRA�j�v�ƌĂ����̂��B�r�^�~��A�̈ꕔ���ω��������w�������B����זE�Ŋ�������Pin1������I��ʼn��������݁A�������Ă����ƕ��������B �����`�q�̗Z����j�~���� �@�]���AATRA�������a�̈��ł���u�}���O�������������a�iAPL�j�v�Ɍ��ʂ������ƕ��������B���̔����a�͂Q�̂����`�q���݂��ɂ������Ɣ����a���N�����BATRA�͂��̗Z�����ז�����̂��B����APin1��ATRA���W����Ƃ����킯�ŁA�����`�q���������Ĉ���������悤�ȏꍇ�ɂق��̂���ł����ʂ������\��������ƌ����O���[�v�͍l���Ă���B �@�u�Z����`�q�v�ƌĂ�錻�ۂŁA����̌����Ƃ��Ă��̂Ƃ��뒍�ڂ���Ă��Ă���B�V�������ÂƂ��Ĕ��W���Ă��邩������Ȃ��B �@����ɁA������̒��ł����Â̍���ȁu�g���v���l�K�e�B�u�̓�����v�̂���זE�ɑ��āAATRA���g���Č��ʂ����B�g���v���l�K�e�B�u�Ƃ́A���Â̕W�I�ɂȂ�R�̃^���p�N���̂�����������Ă��Ȃ�������w���B�����z�������ɔ�������G�X�g���Q����e�̂�v���Q�X�e������e�̂̂ق��AHER2�Ƃ����^���p�N�����Ȃ��B�����ɂ����̂���肾�B���ʂƂ��āAATRA�ɂ���āA�g���v���l�K�e�B�u������̍זE�̐�����}���ł���Ǝ����Ă���B �@�����}�����ސV�������ÂƂ��ďd�v�ɂȂ邩������Ȃ��B Med�G�b�W 2015�N5��11�� |
|
�q�{��̃��X�N�𗝉����Ă܂���? 1��̃Z�b�N�X�Ŕ��ǂ���\���� |
| �@MSD�͂��̂قǁA���f�B�A�Z�~�i�[�u�w�q�{��(����)���� "���̖��"�x�`�{���̕|���́w�m���Ă��Ȃ����Ɓx��������Ȃ��`�v��s���ɂĊJ�Â����B���Z�~�i�[�ł́A�u�q�{��
�`�Y�w�l�Ȉ�ɂȂ��Ċ��������Ɓ`�v�Ƒ肵�ANTT �����{�֓��a�@ �Y�w�l�Ȉ㒷�E�ߓ��ꐬ��t���u�������B ���{�ł�1���ɖ�10�l�̏������q�{��Ŏ��S �@�q�{�ɔ���������R���̂���́A�q�{�̉�(�q�{�̕�)�ɔ�������u�q�{�̂���v�ƁA�q�{�̓����(�q�{��)�ɂł���u�q�{��v�ɕ�������B�q�{�̂���͕o���50��ȍ~�̏����ɑ����݂���̂ɑ��A�q�{���20�`30��̎Ⴂ�����ɋ}�����Ă���Ƃ����B �@�q�{��́A���N���E�Ŗ�50���l���V���ɔ��ǂ��A��28���l���S���Ȃ��Ă���Ɛ��肳��Ă���B���{�����Ō��Ă��A���N��1���l�ȏ�̏������V���Ɏq�{��ɂ�����A��3,000�l���S���Ȃ��Ă���Ƃ���(�u���������Z���^�[ ������T�[�r�X�v���)�B �@"�������L�̂���"�ƌĂ����̂̒��ł��A�q�{��(����������܂�)�͓�����Ɏ����Ŝ�(��)�����������A����20�`30��̂���ł͑�1�ʂɁB�Ⴂ�����̔��ǂ������Ă��闝�R�Ƃ��ẮA�����̒�N��Ȃǂ��l������Ƃ̂��ƁB�u�q�{��͐����̂��鏗���Ȃ�A�N�ɂł��N���肤��a�C�ł��B���������{�̂ǂ�����10�l���̐l���q�{��ŖS���Ȃ��Ă���̂ł��v�Ƌߓ���t�B �q�{��̌�����? �@�q�{��̌����́A�u�q�g�p�s���[�}�E�C���X(HPV=human papillomavirus)�v�̊����ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ��Ă���Ƃ����B����HPV�́A�����̂��鏗����80%�ȏオ50�܂łɊ�������ƌ�����E�C���X�ŁA�����̏ꍇ�́A�������Ă��Ɖu�͂ɂ���Ď��R�ɑ̓�����r�������Ƃ����B�������A����������N�����\���̂���u�����X�N�^�v��HPV���r���ł����Ɋ��������������ꍇ�A5�`10�N�ȏォ���Ďq�{��ǂ���\��������Ƃ̂��ƁB �@�����X�N�^��HPV�ɒ����ɂ킽�莝����������ƁA����ȍזE�Ƃ͈قȂ����`�Ԃ̍זE�ɕω����Ă����Ƃ����B���̂悤�Ȉُ�ȍזE�ō\�����ꂽ�����u�ٌ`���v�Ƃ����A���ꎩ�̂͂���ł͂Ȃ��B�ٌ`���ɂ͒��x������A�ُ�זE�����Ȃ��y�x�̏ꍇ�ɂ͎��R�Ɏ��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ƃ̂��ƁB�������A����g�D���������₷���Ƃ����u�O����a�ρv(�u���x�ٌ`���v�u��������v)�ł́A�Z������ɐi�s����\�������܂�Ƃ����B ���Â������̐l���ɗ^����e�� �@�q�{��̐i�s����0���`4��(�������傫���قǐi�s���Ă���)�ɕ������A����ɉ����Ď��Ö@���قȂ�B�ߓ���t�́A�u�����̎q�{��͑S���ƌ����Ă����قǎ��o�ǏȂ����Ƃ���A�������x��A"�C�Â����Ƃ��ɂ͊��ɐi�s���Ă���"�Ƃ����P�[�X�����Ȃ�����܂���v�ƌ��B �@�q�{��ǂ����ꍇ�A��������̒i�K(�O����a��)�Ō�����A�u�~��(����)�؏��v�Ƃ����q�{�̈ꕔ��؏������p�Ŏ��Â��邱�Ƃ������Ƃ̂��ƁB�q�{�������ł��邱�Ƃ���A��w�I�ɂ́A���̌�̔D�P�E�o�Y���\�Ƃ���Ă���B �@����A����זE����ᖌ(���E�E�_�o�g�D�������g�D�Ɛڂ��鏊�ɂ��閌��̂���)�������čL���̂̑g�D���ő��B���Ă��܂��Ă���ꍇ�́A�i�s���ɉ����āA�q�{�S�E��p�A�L��(�͂�)�q�{�S�E�o��p(�q�{�E���ǁE�����E�q�{���͂̂���сE�����p�߂ȂǁA�L�͈͂ɐ؏������p)�A���ː����ÁA���w�Ö@�Ƃ��������Ö@���Ƃ���B �@�ǂ̎��Ö@��I�������Ƃ��Ă��A���܂��܂Ȍ��ǂ����X�N������A�w�ƁA�d���A�����A�����A�o�Y�A�玙�ȂǏ����̐l���ɑ傫�ȉe����^����Ƃ����B��ȉe���Ƃ��Ď��̂悤�Ȃ��̂���������B �~���؏��p�ɂ���ċN���肤���ȉe�� �E�D�P����܂ł̊��Ԃ̒����� �E���Y���o���̏d�̃��X�N���� �E�Ĕ��̐S�z �L�Ďq�{�S�E�o��p����ː����Âɂ���ċN���肤���ȉe�� �E�D�悤���̑r��(�D�P�ł��Ȃ��Ȃ�) �E����������E�o�����ꍇ�A���������nj�Q(�X�N����Q�̂悤�ȏǏ�) �E�����p�ނ���(�����p�t�̒��~�ɂ�鉺���E���������E�O�A���E�����̂ނ���) �E�r�A��r�֏�Q�A����(�ւ�����) �E�����S�R(���낤)���N��(�ڂ�����)�S�R(�������N���̓��e�����S�ɘR��o��) �E���e���傤�ǃ��X�N�̑��� �E�]�ڂ�Ĕ��̉\�� �E�v�w��p�[�g�i�[�Ƃ̊W�̔Y�� �@����Ɋ��҂̒��ɂ́A���Ԃ�"�q�{��͐������ǂł���"�Ƃ������Ԉ�����F���ŋꂵ�ސl��A�a�C�̂��Ƃ��p�[�g�i�[�֑ł��������Ȃ��ȂǁA�����⌋���ւ̂��߂炢��������l�������Ƃ����B �q�{�f�̎�f���A�A�����J85%�A���{38% �@���̂悤�ɁA���ǂ���Ǝ��Â͂������A���Ì�̕��S���傫���ƍl������q�{��B�ł́A�ǂ�������h�����Ƃ��ł���̂��B�ߓ���t�́u�\�h�Ƒ��������̂��߂ɂ́A�q�{�f���邱�Ƃł��v�ƌ��B �@���E�e���̎q�{�f��f�����r����ƁA�A�����J���g�b�v��85.0%�B�����ŁA�I�[�X�g���A�A�h�C�c�A�X�E�F�[�f���A�m���E�F�[�A�j���[�W�[�����h���A���ꂼ��75.0%�ȏ�ƍ�����f�����ւ�B�����̍��X�ɑ��A���{�̎�f����37.7%�ɂƂǂ܂��Ă���̂�����(�uOECD Health Statidstics 2013.�v���)�B �@����ŁA�q�{��ɂ́u�B����v�Ƃ����i�s��������ނ̂��̂�����A"���N�O�̌��f�łُ͈킪������Ȃ������̂ɔ��ǂ���"�Ƃ����P�[�X���B�����炱���A��������q�{��������ɂ��N���肤��a�C�Ƃ��đ����A����I�Ȍ��f��S�����邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂��Ƃ����B �@�a�C�������Ă��A���ʂƂ��Ďq�{��E�o���邱�ƂƂȂ�A���𗎂Ƃ��ĕa�@�����Ƃɂ��銳�҂𐔑������Ă����Ƃ����ߓ���t�B�u���͎q�{�f���`�������Ă��������炢���Ǝv���Ă��܂��v�ƌ�C�����߂�B�����ē��{�̏����Ɍ����āA�u�q�{�͐����ێ��ɕK�v�Ȃ̂ł͂���܂��A������̂��̂���a������ł��B�������Y�w�l�Ȉ�͎q�{����邽�߂ɁA�\�h�@�⎡�Ö@�̊J������ɍl���Ă��܂��B�\�h�ɏ��鎡�Â͂���܂���B���ЁA���f�ɍs���Ăق����Ǝv���܂��v�ƌĂт������B �}�C�i�r�j���[�X 2015�N5��11�� |
| �K���f���}�A�畆��ᇕ��ʂ̎E�ۂŏL�����y�� |
| �@�K���f���}���{�@�l�͂P�P���A�����L���Ö�u���[�b�N�X�Q���O�E�V�T���v�i��ʖ��E���g���j�_�]�[���j�������Ɣ��\�����B������Ȃǂ̔畆��ᇕ��ʂ��E�ۂ��āA����ɋN�����鈫�L���y�����邽�߂̖�܁B �@�u���畆��ᇕ��ʂ̎E�ہE�L�C�̌y���v�̌��\�E���ʂŔ��������B���g���j�_�]�[�����̂͌o���܁A���ˍ܂ł��łɔ̔�����Ă��邪�A�O�p�܂Ƃ��Ă͏��߂Đ��i�����ꂽ�B�����J���Ȃ́u��Ï�̕K�v���̍��������F��E�K���O����c�v���o�ĊJ���v�����A�K���f���}�������Տ��������s�����B���Ђ����{�ŊJ������\���A�̔������ВP�Ƃōs�������߂Ă̈��i�B m3.com 2015�N5��12�� |
| �f���J�����������Ȍ��̓�����������ϑ� |
| �@�f���J�����͂P�Q���A���ÃE�C���X���܁u�f�S�V���v�̎��p���Ɍ�������ʐ��Y�@�̊J���ɒ��肷��Ɣ��\�����B�����܂��J�����̓�����w��Ȋw�������̓�����I��������ϑ������B �@�f�S�V���͈�`�q���σw���y�X�E�C���X�i�g�r�u�|�P�j��p�������Ö�B����̃E�C���X�Ö@�Ƃ����V����������J�����I�Ȏ��Ö�Ƃ��Ċ��҂���Ă���B�P�����爫���]��ᇂ̈��ł����P����ΏۂƂ�����Q���Տ������i�o�Q�j����t�哱�����Ƃ��ĊJ�n���ꂽ�B �@���p���Ɍ����đ�K�͂Ȑ������@�⎎�����@�̊m���A�E�C���X���̂��̂܉����邽�߂̋Z�p�E�o���Ȃǂ��K�v�B�f���J�����̓��N�`���ƃE�C���X��������̐����Ńm�E�n�E�������Ă���A��ʐ��Y�@�̊m����������邱�ƂƂȂ����B m3.com 2015�N5��13�� |
|
��������������̍Ĕ���ጸ���� ER�z��������̓]�A�ɗL�Ӎ� |
| �@�����ɂ��玙��������ɓ�����ǂ��������́A�������Ȃ����������ɔ�ׂāA����̍Ĕ�����т���ɂ�鎀�S�̉\�����Ⴂ���Ƃ��킩�����B�ăJ�C�U�[�p�[�}�l���e��������i�I�[�N�����h�j��Marilyn
Kwan����̌����ŁA�����_�����uJournal of the National Cancer Institute�v�I�����C���ł�4��28���f�ڂ��ꂽ�B �@�ȑO�̌����ŁA�����͏����̓����ǂ̃��X�N�ቺ�Ɗ֘A���邱�Ƃ�����Ă���BKwan����͍���A������1,636�l��ΏۂɁA1997�`2000�N�ɐf�f���ꂽ�Q��2006�`2013�N�ɐf�f���ꂽ�Q�����������B�قƂ�ǂ̓J�C�U�[�p�[�}�l���e�̊��҂������B �@����̌����́A�����Ɠ����҂̂��ǂ��]�A�̊֘A�������������A���ʊW�͏ؖ����Ă��Ȃ��B �@���̊֘A���́A�ł���ʓI�ȃG�X�g���Q����e�́iER�j�z����������܂ރ��~�i��A�T�u�^�C�v�̓�����œ��v�I�ɗL�ӂł��������A���̃T�u�^�C�v�ł͓��v�I�ɋ����֘A���͂Ȃ������B �@���������̓�����Ĕ����X�N�͑S�̂�30���Ⴍ�A�������Ԃɂ�����炸���X�N�͒ቺ���Ă������A�������Ԃ�6�J�������̏����ł͊֘A�������قNj����Ȃ������B�܂��A���������ł͓�����ɂ�鎀�S���X�N��28���Ⴉ�����B �@Kwan���́A�u�q�ǂ��̐��Ȃǂ̑��̈��q���ւ�邪�A����������ƁA�����ǃ��X�N����5�`10���ጸ����B���������������łȂ���e�̌��N�ɂ��ǂ��\�������邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�����ɂ͐��U�̌��o������������ȂǑ����̗��R�ŕی��p������v�Ƃ����B m3.com 2015�N5��14�� |
|
�i�s��������ɂ����ʃA��! �L���[�o���u�x���N�`���v�ɐ��E������ |
| �@���𐳏퉻���s����A�H���⎑�������łȂ����i�Ȃǂ̗A�����\�ɂȂ�B�����č��A���E�̌����҂��L���[�o��������炳����Ɋ��҂��Ă���Ƃ����B �@���̖�Ƃ́uCimavax�v�B�x����̃��N�`���Ƃ��āA���Ɍ��ʂ�����Ƃ���Ă���B �i�s��������̃X�e�[�W�������߂��� �@�C�M���X�̂������ɂ��A�uCimavax�v�͎�ᇂ̐�����W���A�]�ڂ�h���͂�����Ƃ����B�������������Ƃɐi�s�����X�e�[�W�ɂ��銳�҂��A�����炩���Âł���i�K�ւƈ����߂����Ƃ��\���Ƃ��B �@���ۂɔ�r�����ꍇ�A���̃��N�`�����g�������҂́A�g���Ă��Ȃ��l�ɔ�ו��ς�4�`6�J������������A�Ƃ����f�[�^�����邻���B�Ƃ͂����A�����Ċ�Ղ��N��������̂ł͂Ȃ��A�������҂̖��܂ł͋~�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����B �ł����낵���u�Ĕ��v��h���\���� �@����Ɏ������N�`���͌��݁A�A�����J�ɂ����݂���B�������Ȃ���uCimavax�v�̗��_�́A�Ő��̒Ⴓ�ƁA���Ȃ�育��Ȓl�i�œ���ł��邱�ƁA�����ĉ���������̍Ĕ���h���\���������Ƃ��낾�Ƃ��B �@���ł����낵���̂́u�Ĕ��v�B���Ƃ������ɔ������đ����i�K�Ŏ�p���A�؏������Ƃ��Ă��A�Ĕ��̃��X�N�͍����܂c�葱���邻�����B �@���Y�E�F���p�[�N��������CEO�A�L�����f�C�X�E�W�����\������WIRED�̒��Łu�����͎����ɂ���Ă��̃��N�`�������x���A�b�v�����A�ł���Ί��S�ɍĔ���h�����̂Ƃ��Ẳ\����T���Ă��������v�ƌ���Ă���B �w�r�[�X���[�J�[�̐l�ɂ����ʂ����� �@4���ɂ̓j���[���[�N�B�̃��Y�E�F���p�[�N�������ƁA�L���[�o�̕��q�Ɖu�w�Z���^�[���A�uCimavax�v�̌������͂ɍ��ӂ����Ɣ��\������A�i�W�̊��҂����܂��Ă���B �@���̃��N�`���́A�x����̃��X�N�������w�r�[�X���[�J�[��A�����I�Ȕx�����̐l�ɂ��A���ʂ�����悤���B�������i�݁A�ꂵ��ł��鑽���̊��҂��A���̖�ŋ~���邱�Ƃ��肤�B IRORIO�i�C�����I�j2015�N5��15�� |
|
�e�����A�̒Z�k���x���炪�X�N��\�� ����ɂȂ�l�ő����Ȃ邱�Ƃ����� |
| �@�W���I�Ȑf�f�����͂邩�ɑ����i�K�ł���̔��ǂ���������DNA�̕ω��p�^�[�����A���߂ē��肳�ꂽ�B���ƂȂ�̂́A���t���̃e�����A�̏�Ԃ̕ω����Ƃ����B �@�e�����A�Ƃ�DNA���̖��[��ی삷��u�L���b�v�v�ŁA����ƂƂ��ɒZ���Ȃ邱�Ƃ���A�����w�I�N��̏d�v�Ȏw�W�ƍl�����Ă����B����̌����ł́A����ɂȂ�l�̓e�����A���ʏ���������y�[�X�ŘV�����n�߂邱�Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B�����I�ɂ���ɂȂ�l�̃e�����A�̒����́A15�Ώ�̐l�Ɠ������x�܂ŒZ�k���邱�Ƃ�����Ƃ����B �@�u���̃e�����A�̕ω��p�^�[�����𖾂���A�����\������o�C�I�}�[�J�[�ƂȂ�\��������v�ƁA�����̕M�����҂ł���ăm�[�X�E�F�X�^����w�t�F�C���o�[�O��w���i�V�J�S�j�\�h��w������Lifang Hou���͏q�ׁA�u���̃p�^�[���͂��܂��܂Ȃ����ŋ����֘A���邱�Ƃ��F�߂�ꂽ�̂ŁA��������������A�ŏI�I�ɂ͕��L�������̐f�f�ɂ��̏��u�𗘗p�ł���\��������v�ƕt�������Ă���B �@�uEBioMedicine�v�Ɍf�ڂ��ꂽ����̌����ł́A13�N�������Ė�800�l�̃e�����A�̕]����ǐՂ����B�ŏI�I��135�l�����܂��܂Ȃ���̐f�f�����B���̌��ʁA����̐f�f�����͂邩�ɑO�̒i�K�Ńe�����A�ɒ����ȒZ�k���݂������A�f�f�̂��悻3�`4�N�O�ɂ͒Z�k���~�܂邱�Ƃ�˂��~�߂��B���̐��m�ȗ��R�͕s�������A�Z�k���~�܂鎞���́A���҂̖��f�f�̂���זE�����𗘂����n�߂鎞���Ɉ�v����\��������Ɠ�����͎������Ă���B �@Hou���́A�u�e�����A�̋}���ȒZ�k�����艻������ȓ_���F�߂�ꂽ�B�܂��A���g�̓��Ő��͂�L�����߂Ƀe�����A�̒Z�k�������邱�Ƃ��킩�����v�Ɛ�������B����́A���҂̐���ȍזE���������ɂ����j�~���鎡�Â̊J����ڎw���A���̏�����v���Z�X���ǂ̂悤�ɓW�J����̂���˂��~�߂����Ƃ����B m3.com 2015�N5��18�� |
|
�u�����R�Ɏ��鐶�����v�����H���Ă��܂� �w�����R�Ɏ��鐶�����x�|��҂̃��|�[�g |
| �t���[���C�^�[ ���c���� �@�����|���w�����R�Ɏ��鐶�����`�]���鍐���猀�I�Ȋ����Ɏ������l���������H���Ă���9�̂��Ɓx�i�P���[�E�^�[�i�[���`�v���W�f���g�Ёj�́A���������܂ő����̕��X����A�D�]�����������Ă��܂��B�a�ɂ�����݂̂Ȃ炸�A���N�ȕ�������u�m���Ă����Ă悩�����b����R�ڂ��Ă����v�ƌ����Ă���������̂́A���ꂵ��������ł��B  �@�����Ă悭�A���Ȃ��͂��̖{���ǂ����p���Ă���̂ł����A�u9�̂��Ɓv�����H���Ă���̂ł����A�ƕ�����܂��B���傤�͂���ɂ��ď����܂��B �@�{���ɂ́A�u9�̎��H���ځv�ɂ��킹�āA9�͂��ꂼ��ɁA�M�҂̃P���[�E�^�[�i�[���m�����߂�u���H�̃X�e�b�v�v�Ƃ������ڂ�����܂��B�����������ɂ��Ȃ���ɂ���9�̎��H���ڂɎ��g�ނ��߂̋�̓I�ȕ��@���L���Ă��܂��B �@�����A1�́A2�͂Ɩ|�Ȃ���A�Љ��Ă���u���H�̃X�e�b�v�v�͂����������ɂ���Ă��܂����B�Ȃ��ł��Ƃ�킯�y���݂ɂ��Ă����̂��A5�́u�}�����ꂽ������������v�́u���H�̃X�e�b�v�v�ł��B �@�}�����ꂽ����B��Ȃ菬�Ȃ�A��������g���E�}�I�ȋL���͕����Ă�����̂ł��B������Ƃ����B�ӂ���́A������Â��ɕۂ��߂ɁA�����āA�����������L���ɂ͂ӂ������Ă���̂ł��B�����Ɏ�𒅂��悤�ƁH�@����Ȃ��Ƃ��A�����������ɂ��Ȃ���ɂ��āA���g�߂��肷��́H �@����5�͂̎��H�̃X�e�b�v�ŏЉ��Ă����������̕��@�̂����A�u����͂����v�Ǝv�����̂́A���̂��̂ł����B ������I�ɂȂ����u�Ԃ̃��X�g������ �@���A��Ƃ�̂���Ƃ��ɁA����܂ł̐l���Ŋ�����Ԃ����Ƃ��̂��Ƃɂ��āA�����o���Ă݂Ă��������B�ǂ����Ƃ��A�������Ƃ��܂߂āB�ł��邾���c������܂ł����̂ڂ��āA�v���o���Ă��������B�����I�����炻�̃��X�g��ǂݒ����āA���ꂼ��ɂ��Ăł��邾���ڂ����v���o���Ă��������B�i�e�B�b�V�������Y��Ȃ��j�B �@�ǂݏI������炻�̃��X�g�����p����V�����A�����łƂ肨���Ȃ��Ă��������B����̓��X�g�ɏ����o�����o�����ɂ��Ă̖����ꂽ������������Ƃł��B�� �@����B5�T�C�Y�̑傫�ȃm�[�g���g���A���J���ɁA5�N�Ԃ��ƂɃy�[�W�������܂����B0�`4�A5�`9�A10�`14�A�Ɛi��ł����āA45���猻�݂Ɏ���܂��B �@�����č����̃y�[�W�Ɂu�������Ɓv�A�E���Ɂu�������Ɓv���������Ƃɂ��܂����B �@�����Ȃ�3�A4�̋L���ɂ����̂ڂ�̂���ςȂ̂ŁA�܂��́u45�Έȍ~�v����X�^�[�g�B40��A����͉��������A30��O�����Ă���Ȃ��Ƃ��������ȂǂȂǂƊ��S�ɂЂ���Ȃ���A������Ԃ����A�܂苭���L���Ɏc���Ă���v���o���A���A�����L���Ă����܂����B �@�h�����Ƃ��v���o���̂́A����Ȃ��̂ł��B���w�Z�̂Ƃ��ɁA�j�̎q�ɂ���ꂽ�S�Ȃ����t�Ƃ��B�����߁A�����߂��A�Ƃ������ߍ��Ȋw�������Ƃ��B����ǂ����̂悤�ɁA���[�N���Ǝv���Ď��g�ނƁA�v���̊O�A�W�X�Ə����o���܂����B���������A����͉���ˁA�Ђǂ����Ƃ����������A�ƁB �@�������ĐԂ����܂ł����̂ڂ�ƁA�����̐l���̈��N�\���ł�������킯�ł��B���͂���߂āA���ɂ��āA�ڍׂɎv���o���Ă�����Ƃł��B �@���҂́u�e�B�b�V�������Y��Ȃ��v�Ȃ�ċL���Ă��܂����B���ꂪ�h���̂��낤�ƁA���͐g�\���Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�Ƃ��낪�B���炽�߂Ď����N�\��O�ɂ���ƁA�����Ȃ��Ƃ��A�Ȃ���������Ă�������Ă����̂ł��B �@30��ɑ��������������̃��C�t�E�C�x���g�A�����Ďd���̎R�A�R�B���ꂪ40��̂��܂̎����Ƃ�܂��ɂȂ����Ă����̂ł��B�����A���낢�날�肷���B���܃^�C�w���Ȃ͓̂��R����A�ƁB �@���߂Ă����ƁA�u�������Ɓv�̂��ƂɁA�傫�ȁu�������Ɓv���N���Ă���̂��A��̔����ɂȂ�܂����B �@10��㔼�́u�������Ɓv�Ɏ������������Ƃ̈�ɁA�u���y�R���N�[���Ŏ��s�v�Ƃ�������������܂��B�s�A�m�̑S���R���N�[���̒n��\�I�ɏo�ꂵ�A�����ɁA�{�Ԃő厸�s�����Ă��܂����̂ł��B����ł̓J�l���Ȃ�i���������A�A��A�Ƃ������}�j���͑勃���A���炭�Ȃɂ���ɒ����Ȃ����X�������܂����B �@����ǂ��A���̑厸�s���@�ɁA���̓s�A�m����ɂ��悤�Ƃ������͎̂Ă܂����B���J���͂ځ[���ƕ��S���ĉ߂��������̂́A���Z3�N���ɂȂ��Ăɂ킩�Ɏ����n�߁A�Ȃ�Ƃ������Ŏu�]���铌���̑�w�ɍ��i���܂����B �@���ꂪ����������A���ꂪ�������B���ׂĂɂ����āA�u�������Ɓv�́u�������Ɓv�ɂȂ����Ă����B���̃��[�N�����Ȃ���A���͎����̐l���̗���ɂ��āA����قǏڍׂɍl���邱�Ƃ͂Ȃ������ł��傤�B �@�e�B�b�V���͂܂�ŕK�v�Ȃ��A�ƂĂ��������肵���C���ŁA���̍�Ƃ��I���邱�Ƃ��ł��܂����B �@���čŌ�́A�茳�Ɏc�����u�킪�l���̑�N�\�v�m�[�g�̏ċp�̋V���ł��B �@�ł���قǍL����ł��Ȃ�������A�����ł��̂�R�₷���ƂȂǁA�ł���ꏊ������܂����ˁB���͋ߏ��̂����ɗ��݁A�얀���{�̍ۂɁA�R�₵�Ă��������܂����B���u�ƂƂ��ɂ����Ă����āA������͂Ȃ��Ă��肢����ƁA�Z�E����͉��������Ă��������܂����B �@���̍�Ƃ̂������ŁA���͋C�����܂����B�l���́A���������V���v���ɗ������̂Ȃ̂��ƁB�����̋L���̂Ȃ��ōl���Ă���Ƃ��ɂ́A���̐l���ɂ͎��ɂ��܂��܂Ȑh���v���A����ȋL���������Ă���A�Ɣ��R�ƁA�v������ł��܂����B �@����ǂ������o���Ă݂�ƁA�����Ȃ��āA�����Ȃ��āA�����Ȃ����B�Ȃ��A���ꂾ�����B�Ƃ����킯�ł��B�Ȃɂ��Ƃ����ʉ���B�悱���܂Ȏv���ōs�������Ƃ̌��ʂ́A����Ȃ�ɏI����Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B���Ⴀ�A���ꂩ��͂悢���Ƃ��A�悢�v���������čs���A�����������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ���Ȃ��́A�g�̂��S�������A�悭�Ȃ��Ă�������Ȃ�Ȃ��́A�Ǝv�����肷��킯�ł��B �@���̂悤�ɁA�u����̗]���鍐�v�Ƃ������n���痧���������l�X�̌�肩�瓾���A��̓I�ȁu���H�̃X�e�b�v�v���A�{���ɂ͖��ڂ���Ă��܂��B�a�ޕ��݂̂Ȃ炸���N�ɕs�����������ɂƂ��Ă��A�S���y�����邽�߂ɁA���Ђ���ǂ��������߂������܂��B �t���[���C�^�[�@���c ���� 1967�N�ޗnj����܂�B�����O�����w������w�Ȃ𑲋ƌ�A�V���L�҂��o��99�N���t���[�ɁB2010�N8���Ɂw�K�T�R�`���w�S�b�̎���x�̎d�|�l�v�i�V���Ёj�����s�A10�����V�A�g���ݏZ�B2013�N����͓��{�ƃV�A�g�����s�������Ȃ����ގ��M�𑱂��Ă���B �v���W�f���g 2015�N5��23�� |
|
�o�����̕��e�̔N����t���X�N�Ɋ֘A ���������U���X�N�͒�l�A�S�z�̕K�v�͂Ȃ� |
| �@�o�����ɕ��e������������l�͔����a����p��Ȃnj��t�E�Ɖu�n�̂��X�N�������\��������A����1�l���q�ł��̊֘A���������Ƃ��A�č�����iACS�j��Lauren Teras����̌����Ŏ������ꂽ�B �@�_���́uAmerican Journal of Epidemiology�v�I�����C���ł�5��11���f�ځB�������A���ʊW�͏ؖ�����Ă��Ȃ��B �@����ACS�����ɓo�^���ꂽ13��8,003�l�̃f�[�^�͂����Ƃ���A1992�`2009�N��2,532�l�����t�E�Ɖu�n�̂���ǂ��Ă����B �@�S�̂ɁA���e����������l�ł����̂��X�N�������������A1�l���q�ł͓��ɍ��������B1�l���q�̏ꍇ�A�o�����ɕ��e��35�Έȏゾ�����l�����t����ǂ���\���́A25�Ζ����������l�ɔ�ׂ�63�����������B����̕�e�Ƃ����̂���̃��X�N�̊֘A�͂Ȃ������B �@Teras���́A�u�����̂���̐��U���X�N�͂��Ȃ�Ⴍ�A���U�̂ǂ����̎��_�Ń����p��A�����a�A������Ɛf�f�����\���͂��悻20�l��1�l���B���̂��ߕ��e������ł����Ă��S�z����K�v�͂Ȃ��B�����A���E�I�ɍ���̕��e�����q�ǂ����������Ă��邱�Ƃ���A���̊֘A�����m�F���Đ����w�I�������������߂ɁA����Ȃ錤�����K�v���Ƌ������ꂽ�v�Ƙb���B �@1�l���q�œ��ɂ��̊֘A���������������Ƃ́A�������Ɍy�x�̊����ɔ��I����邱�Ƃ��Ɖu�n�̔��B�������A�Ɖu�֘A�̎������X�N��ጸ����Ƃ����u�q�������v���֘A����\�������������ƁA������͏q�ׂĂ���B m3.com 2015�N5��25�� |
| ���Â͂�����������?�@����ی��̓z���g�ɕK�v? |
| �@���U�ł���ɂ�����m���͒j��62%�A����46%(���������J���@�l���������Z���^�[�������Z���^�[
�ŐV���v 2015�N4��22��)�BCM�Ȃǂł�������ʂ�A2�l��1�l�͂���ɂȂ鎞��ł��B���Âɂ�����"����"�ɂ����S�ł͂����܂���B ���͓��@�E��p�ȊO�̎x�o�����S�ɂȂ� �@�a�C�ɂ������ē��@�����ꍇ�A���������������炢���@����̂ł��傤�B�����J���Ȃ̕���23�N���Ғ����ɂ��ƁA���ύ݉@������32.8���ƂȂ��Ă��܂��B�������A����͂��ׂĂ̔N��A���ׂĂ̕a�C�̕��ςŁA���_��Q��A���c�n�C�}�[�Ƃ������a�C�A����̕��܂Ŋ܂߂����́B���e���悭�����35�`64�E�����V����(����)�̏ꍇ�A�݂�16.2���A����12.3���A���[��9.4���ƁA2�T�ԑO�サ�����@���Ă��܂���B���̂悤�ɁA�ŋ߂͓��@���Ԃ��Z���A���z�×{��x�����邽�߁A�a�C�ɑ�������͒��~�ōs����Õی��͕s�v�Ƃ�������������܂��B 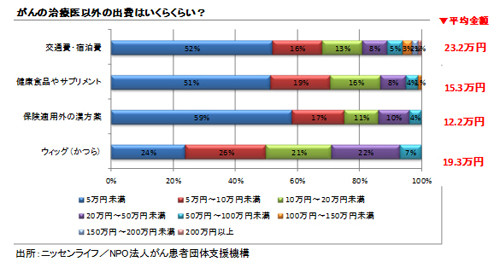 �@�m���ɁA�����̒i�K�ł�������邱�Ƃ��ł��A���@�E��p�݂̂Ŏ��Â��I���邱�Ƃ��ł���A����قǑ��z�̔�p�������邱�Ƃ͂���܂���B�����s�K�ɂ��i�s�����i�K�ł̔�����������A�����p�߂ւ̓]�ڂȂǂ��������ꍇ�́A���@�̑O��ɍR����܁A���ː��Ƃ��������Â��s�����ƂɂȂ�܂��B�����̏ꍇ�����͒ʉ@�ł̎��ÂƂȂ�A��p�ƈႢ���Âɂ�������������܂��B�ƂȂ�ƁA���z�×{��x������Ƃ͂����A���x�z�����ς�(�������͋߂�)�̈�Ô�𐔃J���ɂ킽���Ďx�������ƂɂȂ�̂ł��B �@�����ĕa�@�ւ����Βʂ����ƂɂȂ�ƁA��Ô�ȊO�̂��������낢��K�v�ɂȂ�܂��B�a�C�Ɠ������߂ɂ́A���퐶��������܂Œʂ�Ƃ͂����Ȃ����Ƃ����������Ƃ�����������̂������B���̃f�[�^�ɂ���悤�ɁA���Â̏ꍇ�͉����̕a�@�֒ʂ��l�������A��ʔ��h����͑傫�ȕ��S�̂ЂƂB�R����܂ɂ͒E�т�����̂��������߁A�E�B�b�O���K���i�ł��B���Ȃ݂ɁA�E�B�b�O�͏����ł̈�Ô�T���̑Ώۂɂ͂Ȃ�܂���B ���Â͓����Ȃ��瑱������? 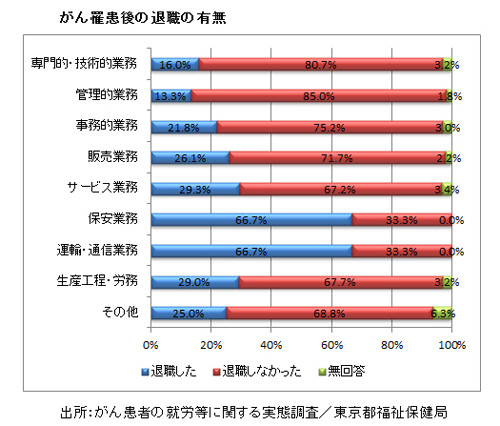 �@�����������邱�Ƃ͂������ł����A���Ò��A����܂łƕς��Ȃ������������邩�Ƃ������Ƃ��傫�Ȗ��ł��B���ː���R������ẤA�ǂ����Ă�����p������܂��B�̒����������ŁA����܂Œʂ�d���𑱂��邱�Ƃ��ł���ł��傤��? �@�����s�ی������ǂ�����25�N10���ɍs���������ɂ��ƁA�E��ɂ�����đ傫�ȍ�������܂����A������̐E��ł�2�����x�̐l�͑ސE�����Ă��܂��B �@�ސE�����l�͂������ł����A�ސE���Ȃ��܂ł���Ђ��x�ނ��Ƃ������Ȃ�܂����A�x�E���ď��a�蓖���̎x���z�͕W����V���z��3����2�ł�����A�K�R�I�Ɏ����͂���܂ł������Ȃ��Ȃ�܂��B���̃f�[�^�ł킩��ʂ�A�l�Ō����6����A���тƂ��Ă�������̐l�͎������������Ɠ����Ă��܂��B �@�O�L�́u�ŐV���v�v�ŔN��ʂ̂��S��������ƁA�j���Ƃ�40�㔼���炢�ő����n�߁A�j���̏ꍇ��50�㔼���炢�ŋ}���ɑ������܂��B�Ƃ������Ƃ́A����Ȃ�ɒ��~���ł��Ă���͂��̐���ł�����A���ÂɌW��x�o���ɂ��Ή��ł��邩������܂���B 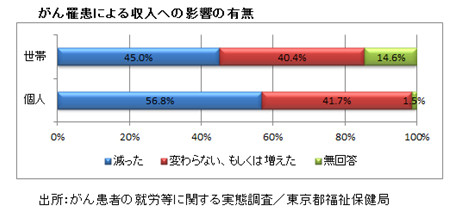 �@�����ŋ߂́A���ɏ����̏ꍇ20�`30��œ�����A�q�{����ɂȂ�l�������Ă��āA��N������X���ɂ���Ƃ����܂��B���Y���`������Ă��Ȃ�����ɂƂ��āA���Â̂����Ƃ��ė���ɂ�����̂̂ЂƂ��A����ی��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������B�Ƃ͂����A����ɂ�����͓̂��{�l�̔����A����Ɏ���������̂͂��̔������x�ł�����A�K�v�ȏ�ɐS�z���č����ی������x�����ƌv�̃o�����X������Ă͖{���]�|�ł��B �����ɕK�v�ȕۏ���e��I�сA����I�Ɍ������� �@����ی��ƂЂƌ��ɂ����Ă��A�f�f�A���@�A�O�厡��(��p�A���ː��A�R�����)�A�ʉ@�Ƃ��������ÑS�ʂ��J�o�[������́A�f�f�����d���������́A�N���̂悤�ɕ������Ď����́A���Ô�����z�ŕۏႷ����̂ȂǁA���̓��e�͂��낢�날��܂��B 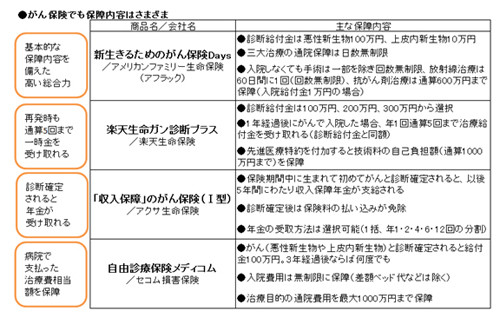 �@���c�Ƃ�������I�ۏႪ���Ȃ��A����ɂȂ�\����������(����͈�`���Ȃ��Ƃ����Ă��܂���)�A��x�Ɏ��ƃ��_�������Ă��܂������c�c�ȂǁA�����̏��Âɍl���ĕK�v�Ȃ��Ƃ�ۏႵ�Ă���鏤�i�ŁA�Ȃ��������̂Ȃ��ی����̂��̂�I�Ԃ��Ƃ��d�v�ł��B �@�܂��A���Â͂ǂ�ǂ�i�����Ă��܂��������I�Ȍ��������K�v�ł��B���Ƃ��A20�N���炢�O�̂���ی��́A�f�f�A���@�A��p�̓J�o�[���Ă��܂����A���ː���R������Â͍l������Ă��Ȃ����̂��قƂ�ǂł����B�ŋߐl�C�̍��x��i��Â������͕W�����ÂƂȂ�A����ɐi���������Õ��@���o�ꂷ�邩������܂���B����ی������̐����ی����l�A����I�Ɍ��������Ƃ��K�v�Ƃ��������ł��B �����҃v���t�B�[���� ��ؖ퐶 �ҏW�v���_�N�V�������o�āA�t���[�����X�̕ҏW&���C�^�[�Ƃ��ēƗ��B�������̏��y�[�W��S�ݓX��̊��E�\���E��ނ𒆐S�Ɋ����B�}�l�[���̕ҏW�Ɋւ�������Ƃ����������ɁA���݂͂����Ɋւ���G���A���ЁAMOOK�̕ҏW�E���C�^�[�Ɩ��Ɍg���B�t�@�C�i���V�����v�����i�[(AFP)�B �}�C�i�r�j���[�X 2015�N5��27�� |
|
�O���B����̃z�������Ö@���v�l��Q�������炷 ����̈�`�q�ψقŃ��X�N14�{�� |
| �@�O���B���ÂƂ��ăz�������Ö@����j���ł́A6�J���ȓ��ɐ��_�@�\�̒ቺ���݂��A���Ȃ��Ƃ�1�N�ȏ㎝������ꍇ�����邱�Ƃ��A�V���Ȍ����Ŏ������ꂽ�B���̃��X�N�́A����̈�`�q�ψق����j���œ��ɍ��������Ƃ����B�z�������Ö@�́A�e�X�g�X�e�����l��ቺ�����邱�ƂőO���B����זE�̑��B��}���鎡�Ö@�ł���B �@�ă��t�B�b�g����Z���^�[�i�^���p�j�̔��m������Brian Gonzalez ��������������̌����ł́A�O���B����58�l��ΏۂɁA�z�������Ö@�̊J�n�O�A6�J����A12�J����ɕ]�������{���A�O���B�E�o�p����84�l����ёO���B����ł͂Ȃ�88�l�Ɣ�r�����B �@���̌��ʁA�z�������Ö@�Q�ɂ͐��_�@�\�̒ቺ���F�߂�ꂽ�B���Ɉ�`�q�ψ�rs1047776��L����j���ł́A�z�������Ö@�ɂ�鐸�_��Q�𗈂��m�����A���̕ψق������Ȃ��j����14�{�ł������B �@Gonzalez���́A�u�z�������Ö@����������j���́A���_�@�\�ʂ̕���p�ɂ��Ēm���Ă����K�v������v�Ǝw�E����B�����̓e�X�g�X�e�����l�̕ω����v�l��Q�̌����ƂȂ����\��������Ƃ̌����������Ă��邪�A�z�������Ö@�ɂ�錑�ӊ���}�����e�����Ă���\��������Əq�ׂĂ���B �@���́̕uJournal of Clinical Oncology�v�I�����C���ł�5��11���f�ڂ��ꂽ�B �@�ău���K���E�A���h�E�E�C�����Y�a�@�i�{�X�g���j��Anthony D'Amico ���́A����̌����͏��K�͂ł��邽�߁A����Ɍ����d�˂�K�v������Ǝw�E�������A�ȑO�̌����Œ����̃z�������Ö@�ɂ�鐔�w�I�\�͂ւ̉e�����F�߂�ꂽ��������A����̒m���ɂ͂���Ȃ�̍���������Ƃ̍l�����q�ׂĂ���B�������A���ݎ��{�����Z���Ԃ̃z�������Ö@�ł͑傫�ȉe��������Ƃ͍l���ɂ����A�����̋^��_������Ɠ����͕t�������Ă���B �@�ă��m�b�N�X�E�q���a�@�i�j���[���[�N�s�j��David Samadi���́A�O���B���҂Ƀz�������Ö@�����{���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ̌����������B�z�������Ö@�ɂ͌��ӊ��A�j���X�N���A�}���Ȃǂ̕���p�̂ق��A�S����Q�̌��O������Ǝw�E���A�ŐV���̊O�Ȏ�p�őO���B�����؏�����A���ւ�@�\�̕���p����������Əq�ׂĂ���B m3.com 2015�N5��28�� |
|
�r�^�~���T�v�������g�Ŕ畆���X�N���ጸ�� �j�R�`���A�~�h�Ō��� |
| �@�����œ��肵�₷���j�R�`���A�~�h�Ƃ����r�^�~��B3�T�v�������g���A�畆���X�N��ጸ����\���������ꂽ�B�I�[�X�g�����A�A�V�h�j�[��w�畆�ȋ�����Diona Damian����ɂ�錤���B �@�����̌����ł́A�j�R�`���A�~�h���畆�זE�̃G�l���M�[�����߁ADNA�C���𑣐i���A�畆�̖Ɖu�n���������邱�Ƃ�������Ă���B �@Damian����́A�ߋ�5�N�Ԃ�2��ވȏ�̔F��畆�����F�߂�����66�̍����X�N����400�l�߂���ΏۂɗՏ����������{�����B�Ώێ҂�3����2���j���ŁA�������߉��A�������Ȃǂ̖���������L���Ă����B�Ώێ҂̔����̓j�R�`���A�~�h��1��2��A1�N�ԕ��p���A�c�蔼���̓v���Z�{�p�����B �@�畆�Ȉオ3�J�����Ƃɂ��f�������Ƃ���A�j�R�`���A�~�h�Q�ł�1�N�Ԃ̌������ԏI�����̐V�K�F��畆����̔��Ǘ����v���Z�{�Q����23���Ⴉ�����B�܂��A����ɂȂ肤��畆�̌����؏�̔���3�J����11���A9�J����20�����������B�������A12�J����ɕ��p����߂�ƁA�։v�݂͂��Ȃ��Ȃ����B �@Damian���́A�u����ʓI��B3�ł���i�C�A�V���́A���p�ʕ��p����Ɠ��ɂȂǂ��������邪�A�j�R�`���A�~�h�ł͂����̕���p���Ȃ������B�������A���i�K�ł��̐����̐ێ����ʏW�c�ɐ���������̂ł͂Ȃ��v�Ƙb���Ă���B �@����̌����́A�č��Տ���ᇊw��iASCO�j�N���W���5��30���ɔ��\�����\��B�Ȃ��A�w��\���ꂽ�m���͈�ʂɁA���ǂ��Ĉ�w���Ɍf�ڂ����܂ł͗\���I�Ȃ��̂Ƃ݂Ȃ����B m3.com 2015�N5��28�� |
| �č��A��`�q�ψقɍ������R����܂�T���������J�n |
| �@�č����������iNCI�j�́A�i�s��������1000�l��ΏۂɁA�K�������F����Ă��Ȃ��R����܂̒�����A�e���҂̈�`�q�ψق���|����Ɍ����ڂ̂�����T����K�͂ȗՏ������i�����j�ɒ��肷��B�����̍R����܂́A�P�Ɏ�ᇂ������������ʂ�_���̂łȂ��A���҂̈�`�q�ψقɉ����Ď�ᇂ�_����u�W�I��v���B �@�uNCI-Match�v�Ɩ��t����ꂽ���̗Տ������́A�u�v���V�W�����E���f�B�V���i������Áj�v�Ƃ����V����̔��W��ڎw���A��ᇂ̑��B�Ɋւ��ˑR�ψق𐳊m�ɑ_����R����܂̊J���ɂȂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B���Ȃ��Ƃ�������10�Ђ��v20��ȏ�̎���������̒P��̎����ɒ���B �@NCI�̃W�F�[���Y�E�h���V���[��������1���̎����J�n�̔��\�ŁA�u����͍��܂łɎ��{���ꂽ���ōł���K�͂��ł������Ȃ���̎������v�Əq�ׂ��B�����S����t��͗����A�č��e�n�̖�2400�J���̎������{�{�݂Ŋ��҂̑I����n�߂錩�ʂ����B �@���a�̈�`�q�I�����Ɋւ��闝�����i��ł���A����ɔ���������ÂƂ����T�O�ւ̊S�����܂��Ă���B�I�o�}�哝�͍̂��N1���A���a�������N�����ˑR�ψق����A�����W�I�Ƃ��鎡�Ö�̊J�����i��ړI�Ƃ���2��1500���h���i��270���~�j�̍\�z���Ă����B��ᇊw�́A�����҂�������Âōł��i��ł���ƍl���Ă��镪��ŁA�����҂͂��̓��̂ǂ��ɂ��邩�ɊW�Ȃ��A�ˑR�ψق�W�I�Ƃ��鎡�Ö�̊J����i�߂Ă���B �@���̔��\�́A�č��Տ���ᇊw��iASCO�j�̔N����c�ōs��ꂽ�BASCO�́uTAPUR�v�Ƃ���NCI-Match�Ɠ��l�̎����ɂ����肷��B���̎����Ɋւ��ẮA����܂łɐ���5�Ђ����ɔ̔�����Ă���13�̈�`�q�W�I���������Ƃ��Ē��邱�Ƃō��ӂ��Ă���BASCO�̃��`���[�h�EL�E�V���X�L�[�ō���ÐӔC�ҁiCMO�j�́A���̖ړI�́u��ᇂ̈�`�q�z�����͂�����Łi���̊��҂̂���ɂ��ď��F����Ă��Ȃ��j�W�I��𓊗^����ƁA���҂ɉ����N���邩�v�����ɂ߂邱�Ƃ��Ƙb���B �@����2�̎����́A����Ɋւ����`�w�̗������i�݁ADNA�z���ǂ̔�p�����ĂȂ��قǂɒቺ���Ă��邱�Ƃ��A���҂̎��Â�R����܊J���̎�@�ɂ����ɕω��������炵�Ă��邩�������Ă���B����̊w�p�@�ւ�ꕔ�n��̂������́A���҂ɍ��������Ö����邱�Ƃ����҂��A�i�s�������҂̑����̎��DNA�̈�`�q��̓T�[�r�X����Ă���B�������A���ꂪ�a����P�Ɍ��т������ɂ��Ă̏��͂قƂ�ǂȂ��B �@������Â̐��i�͂ɂȂ��Ă���̂́A������������`�q�ψق����܂��܂Ȏ�ނ̎�ᇂɂ����Ă������ʂ��Ă���Ƃ����������B���̂��߁A�Ⴆ�Γ�����̕ψق�W�I�ɂ���̂ɗL���ȍR����܂��A�ʂ̑���Ŕ���������ᇂɂ��L�������������҂����܂��Ă���B�X�C�X�̐����胍�V���E�z�[���f�B���O�̓����Ö�u�n�[�Z�v�`���v�i��ʖ��F�g���X�c�Y�}�u�j��HER2�Ƃ�����e�̂�W�I�Ƃ��邪�AHER2�����l�݂̈���ɂ��L���ł��邱�Ƃ��������A��Ɉ݂���ւ̓K�������F���ꂽ�B �@�������A���V���̍R����܁u�[���{���t�v�i��ʖ��F�x�����t�F�j�u�j�́ABRAF�ƌĂ���`�q�ɓ���̕ψق��݂��鈫�����F��ɗL����BRAF�j�Q�܂����A�����ψق�����������ɂ͂قƂ�nj��ʂ��Ȃ����Ƃ��������Ă���B �@�ĐH�i���i�ǁiFDA�j�̎�ᇒS���ӔC�҂ŁA�������������̊��U����߂郊�`���[�h�E�p�Y�h�D�[�����́A�u����͑����̐l�X�����҂�����A�����ƕ��G�Ȗ�肾�v�Əq�ׂ�B�����́A���̃A�v���[�`�̕��L��������z�肷�邱�Ƃɂ́u�����g�A�����T�d�Ȗʂ�����v�Ƙb�����B �@����1�̖��́A��`�I�����ɂ���Ď�ᇂނ���ƁA�x����������Ƃ�������ʓI�Ȃ���10����Ȏ����ɕ�����Ă��܂����ƂŁA����͐����Ђɓ���˂�����B���̏ꍇ�A�����Ђ͊ȓˑR�ψق�W�I�Ƃ���P��̎�����̗Տ������̂��߂�1���l���̊��҂��ӂ邢�ɂ����Ȃ��ƁA�\���Ȋ��҂��W�߂��Ȃ��\��������ƌ����҂����͎w�E����B����̂悤�ɁA���\��ނ̎�����ׂ�1�̎����̂��߂Ɋ��҂�I�肷������͂邩�Ɍ����I�ŁA�L�]�Ȏ��Ö�����v���Ɋ��҂ɒł���悤�ɂȂ�Ƃ݂���B �E�H�[���E�X�g���[�g�E�W���[�i�� 2015�N6��2�� |
|
10��ő����Ă���ƁA���̌�̑咰���X�N�͂Q�{�ɁA�č��n�[�o�[�h��w���� �X�E�F�[�f���̒j���̃f�[�^���� |
| �@10��ő����Ă���ƁA���̌��40�N�߂��̊Ԃɑ咰����ɂȂ郊�X�N���Q�{�ɂȂ�ƕ��������B �@�č��n�[�o�[�h���O�q����w�@���܂ތ����O���[�v���A������n�̕a�C�̐�厏�K�b�g���I�����C���ł�2015�N�T��18���ɕ����B ��24���l�̃f�[�^ �@�����O���[�v�́A���E�I�ɂR�Ԗڂɑ�������ł���咰����̃��X�N�����ɂ͐��l�ł͔얞�Ɖ��ǂ��e�����Ă���Ɛ�������B �@10��̔얞�≊�ǂ̉e���ɂ��Ă͕s��������B�얞�̎w�W�ƂȂ�BMI�A���ǂ̎w�W�ł��錌�t�����̒l���ǂ̂悤�ɂ��̌�̂���ɉe�����邩�B �@�����O���[�v�̓X�E�F�[�f����2010�N�܂ōs���Ă����������̂��߂�16�`20�̒j���ōs���Ă����g�̌����̌��ʂ���A��24���l���̃f�[�^�����W�B����ɑS������o�^�f�[�^���g���ABMI�ƌ��t�����̒l�Ƒ咰����Ƃ̊֘A�ׂ��B ���ǂ����X�N���߂�v�� �@�g�̌����̎��_�ł�81���߂�������̏d�������B����Œ����x�̉ߑ̏d���T���A���x�̉ߑ̏d��1.5���A�얞���P���B �@2010�N�܂łɖ�900�l���咰����ɂȂ����B �@BMI�Ƒ咰����Ƃ̊W�ׂ��Ƃ���A10������BMI��27.5�`30�̉ߑ̏d�̐l��BMI��18.5�`25�̐���̏d�̐l�Ɣ�ׂđ咰����ɂȂ郊�X�N����Q�{�ƂȂ��Ă����BBMI��30�ȏ�̔얞�̏ꍇ�͖�2.4�{�B �@���t�����ł̉��ǂɂ��ẮA���t�����ʼn��ǂ̒������Ă����ꍇ�A����͈͂̐l�Ɣ�ׂđ咰����ɂȂ郊�X�N�͖�1.6�{�������B �@BMI�Ɖ��ǂ͎Ⴂ�i�K���璍�ӂ����������ǂ��̂��낤�B Med�G�b�W 2015�N6��4�� |
| �E�C���X��p�����Ɖu�Ö@���i�s�����m�[�}�ɗL�� |
| �@��`�q���삵�����Q�̃w���y�X�E�C���X�������m�[�}�i���F��j�̐i�s��x�点��\���������ꂽ�B�����O���[�v�ɂ��ƁA���E�e�n�̊���436�l��ΏۂƂ�������̌����́A�u�E�C���X�Ɖu�Ö@�v���L�v�ł��邱�Ƃ����������߂Ă̑�3���������Ƃ����B �@��3�������́A���K�͂̏W�c�ň��S���ƗL�����������ꂽ��Ɏ��{�����A�ŏI�I�ȑ�K�͎������B�{�����͎��Ö@���J�����Ă��鐻����Amgen���玑������Ă���A�uJournal of Clinical Oncology�v��5��26���f�ڂ��ꂽ�B �@���̌����ł͐Z�����̎�p�s�\�ȃ����m�[�}���҂�ΏۂɁATalimogene Laherparepvec�iT-VEC�j�ƌĂ��E�C���X�Ö@�܂��́u�ΏƁv�̖Ɖu�Ö@�̂����ꂩ�𒍎˂����BT-VEC�́A�P���w���y�X�E�C���X1�^��2�̈�`�q���������邱�Ƃɂ��A����זE���ł͕������ꂸ�A����זE���ő��B���ē������炪��זE��j����悤�ɂ������́BT-VEC�͂���ɁA�Ɖu�n���h�����Ď�ᇂ��U�������镨�����Y������B �@T-VEC�Q��6�J�����鎡�Ô������F�߂�ꂽ�͖̂�16���ɂƂǂ܂������A�ΏƌQ��2���ɔ�r����Ƃ͂邩�ɗD�ꂽ���ʂ������BT-VEC�Q�̊��҂ɂ�3�N�ȏ㔽�������������҂������B�����ɎQ�������p�����h����w��������Kevin Harrington���ɂ��ƁAT-VEC�̂悤�ȃE�C���X�Ö@�͎�ᇂɑ��ē�ʍU�����d�|���邱�Ƃ��ł��A����p�����Ȃ����Ƃ�����҂����܂��Ă���Ƃ����B �@T-VEC�ɑ��锽���́A��r�I�i�s�x�̒Ⴂ���҂�A����܂Ŏ��Â������Ƃ̂Ȃ����҂œ��ɋ��������B������́A���̎��Ö@����p�s�\�̐i�s�����m�[�}���҂̑��I�����ÂƂ��ėL�]���Əq�ׂĂ���B �@�X�e�[�W3����уX�e�[�W4�����̊��҂ł́A���ϐ������Ԃ�T-VEC�Q�Ŗ�41�J���A�ΏƌQ�Ŗ�22�J���������B����Ɉ����x�̍��������A�i�s��������ɂ�����T-VEC�����I�����ÂƂȂ肤�邩��]�����錤�����i�s�����Ƃ����B �@�č��̐��Ƃ����`�q���σE�C���X��p�����Ɖu�Ö@�̗L�]����F�߁A�]���̔畆���ÂɊv���������炷���̂��Əq�ׂĂ���B�ł��v�����̍����畆����ł��郁���m�[�}�̔��Ǘ��́A�č��ł���30�N�����������Ă���A�č�����iACS�j�̐���ɂ��A���N��1���l�������m�[�}�Ŏ��S����Ƃ���Ă���B m3.com 2015�N6��8�� |
|
�H���������Α咰����̃��X�N������ �q���g�͘a�H�ƃA�t���J�����ɂ��� |
| �@�Z�ޏꏊ���ς��ΐH�������ς��B�H�̉��ĉ��́A�������������Đl�ɋ߂Â��Ă����̂�������Ȃ��B ������2�T�ԂŒ��������ω� �@2014�N�̕č�����iACS�j�̒����ɂ��ƁA�č��ɂ�����咰����̜늳�i�肩��j������ю��S���͒j���Ƃ��A���ׂĂ̂���̒��łR�Ԗڂɍ����B�Ƃ��ɃA�t���J�n�č��l�͔��l�ɔ�ל늳����25���A���S���ł�50���������B�ł́A�A�t���J�n�̐l��͑咰����ɂȂ�₷���̂��Ƃ����ƁA���������킯�ł��Ȃ��BWHO�i���E�ی��@�ցj�ɂ��2008�N�̃f�[�^�ł́A�A�t���J�n�č��l�̑咰����늳����10���l�ɑ���65�l�A����ɑ���A�t���J�l��10���l�ɑ���5�l�ƁA�傫�ȊJ��������B �@���̗��R�����҂̐H�����̈Ⴂ�ɂ���ƍl�����ăs�b�c�o�[�O��w�̃X�e�B�[�u���E�I�L�[�t�����猤���`�[���́A50�`65�̃A�t���J�n�č��l�Ɠ�A�t���J�l�e20�l�̒����ۑp�i���������j�͂��A���������������{�B�A�t���J�n�č��l�ɂ̂�9�l�Ƀ|���[�v�����������B���̌�A���ꂼ��̃O���[�v�ɑ��荑�̐H�ނƒ����@��p�����H����2�T�Ԑێ悵�Ă��炢�A�����������s�����B �@����ƁA�����ׂ��ω�������ꂽ�B������2�T�ԂŌ݂��̒������ɋ߂Â��Ă����̂��B�A�t���J�n�č��l�̃O���[�v�ł́A���ǂȂǂ���̃��X�N�ƂȂ���q���������A����̗}���ɏd�v�Ȗ������ʂ����u�u�`���[�g�v���������Ă����B����A��A�t���J�l�̃O���[�v�ɂ͂��̋t�̂��Ƃ��N���Ă����B �@�I�L�[�t�����́u�A�t���J�n�č��l�́A���i�̐H���ŐH���@�ۂ̐ێ�ʂ𑝂₵�A�������̎��b�Ƃ���ς��������点�A����̃��X�N�����炷���Ƃ��ł��邾�낤�v�ƌ����B J-CAST�j���[�X 2015�N6��14�� |
|
��N�҂̑咰����͍���҂Ƃ͈�`�I�ɈقȂ� ���Ö�̑�ӂɂ��Ⴂ |
| �@�咰����ɂ͍���҂Ǝ�N���҂ł͈�`�I���ق�����A��N�҂ɂ͈قȂ鎡�Â��K�v�ł��邱�Ƃ��A�V���Ȍ����Ŏ����ꂽ�B�č��ł͑咰����̑S�̂̔��Ǘ��͌������Ă�����̂́A��N���҂̔䗦�͏㏸���Ă���B����܂ł̌����ŁA50�Ζ����̊��҂ł́A����҂ɔ�ׂđ咰����̈����x���������Ƃ����炩�ɂ���Ă���B �@����̌����ł́A�Ⴂ���ҁi������31�Ζ����j����̎悵���咰����̎��5���̂ƁA����ҁi������73�Β��j����̎悵��6���̂̈�`�q���r�����B���̌��ʁA�u�זE�̔����E��ӁE���B�Ɋ֗^����2�̏d�v�Ȉ�`�q�V�O�i���`�B�o�H�ł���PPAR�����IGF1R�ɍ��ق��F�߂�ꂽ�v�ƁA�ăR�����h��w����Z���^�[��Christopher Lieu���̓j���[�X�����[�X�̂Ȃ��ŏq�ׂĂ���B����2�̃V�O�i���`�B�o�H�̕ω��́A����̂���Ɋ֘A���邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă���Ƃ����B �@�����ł͂���ɁA��N���҂���̎悵����ᇂ́A��܂̑�ӂ�S���o�H����������Ă��邱�Ƃ��킩�����B�����̕M�����҂ł��铯����Z���^�[��Todd Pitts���́A�u���w�Ö@��͂���זE���U��������̂����A�Ⴂ�l�͂��̉��w�Ö@��̑�ӂ�����҂Ƃ͈قȂ�B���̂��Ƃ���A��N���҂ł͓]�ڐ��咰����ɑ���]���̉��w�Ö@�̌��ʂ��Ⴂ���R������ł���\��������v�Əq�ׂĂ���B �@����̌����́A�ăV�J�S�ŊJ�Â��ꂽ�č��Տ���ᇊw��iASCO�j�N���W��Ŕ��\���ꂽ�B�w��\���ꂽ�m���͒ʏ�A���ǂ��Ĉ�w���Ɍf�ڂ����܂ŗ\���I�Ȃ��̂Ƃ݂Ȃ����B �@�����O���[�v�́A���̒m���𗠕t���邽�߂̑�K�͌������v�悵�Ă���B�u���z�������Ȃ�A�����̍ŏI�ڕW�́A�咰����ɂ�郊�X�N�������Ǝv�����N���҂ɂ����ƗD�ꂽ���Â���邱�Ƃł���v��Lieu���͏q�ׂĂ���B m3.com 2015�N6��15�� |
|
�O���B�������X�N�A�H�����e�Ŕ{�� �f�f��̐H���p�^�[���͎��S���X�N�����E |
| �@�č����w��iAACR�j��6��1���A�O���B���Ɛf�f���ꂽ��A���H���A�ԓ��A����э����b�����i�𒆐S�Ɏ��j���ł͑O���B���֘A���̃��X�N�ƑS�������S�̃��X�N����r�I�����A���ʕ��𒆐S�Ɏ��j���̑S�������S�̃��X�N����r�I�Ⴂ���Ƃ��������������Љ���B�{�����́AAACR��ł���Cancer Prevention Research���Ɍf�ځB �@�����`�[���́A��t��ΏۂƂ������N�����̈�Ƃ��čs��ꂽ�A�Տ���Ԃ�H���Ɋւ���A���P�[�g�̃f�[�^�́B�O���B���̐f�f���畽��14�N�ǐՂ��A�H���p�^�[�������S���ɋy�ڂ��e���ɂ��ĕ]�������B �@���̌��ʁA���m�H�ˑ��x���ł������j���l���ʌQ�ŁA�ˑ��x���ł��Ⴂ�j���l���ʌQ�����O���B�������X�N��2.53�{�����i153�����j�A�S�������S���X�N��67���������Ƃ����������B�܂��A��A�ʕ��A���A����ёS�����𒆐S�ɍ̂�j���ł͑S�������S���X�N��36���Ⴍ�A�O���B�������X�N���Ⴉ�������A�L�Ӎ��͔F�߂��Ȃ������B �@�_�����҂�Jorge E. Chavarro���́A�u�O���B�����҂̍ł��d�v�Ȏ����̈���S���njn�����ł��邽�߁A�S�������S���Ɋւ��鏊���͗\���ʂ肾�����v�Ɛ����B���̏�Łu�S���njn�����̗\�h���Ӑ}�����H�������́A��]�ڐ��̑O���B���̎��S���X�N�}���ɂ��K�p�\�ł��邱�Ƃ��������ꂽ�v�Ƃ̌����������Ă���B m3.com 2015�N6��19�� |
|
1�H�̌��t�Łu�����v�f�f������3���I ����������A�݂���A�咰����N���ɂ����p�� |
| �@1�H�̌��t��������3���������邾���Őg�̂ɂ����邩�ǂ������킩�����I�ȕ��@�����a��w�̌����҂��J�������B�u����v�Ƃ킩������A�u�ǂ����v��˂��~�߂�̂͗e�ՂŁA���������E���ÂɂȂ���Ɗ��҂����B�N���ɂ����p����ڎw���Ƃ����B ����ɏڂ��������ŕ��ʓ��� �@���a��w�]���L�F�a�@�̈ɓ����W��t�i48�j��Ɛ_�ˎs�̈�Ë@���Ђ����̐f�f�@���J�����A�ɓ���t�����̂�17���i2015�N6���j�Ɏ��ۂ̐f�f�菇���I�����B���S�����@�ŕ������������t���������ȋ����`�b�v�ɏ悹�A���O���Ȃǂĕ������Â�����ƁA���j�^�[�Ɍ���_�������Ă���B����זE���Ɖu�זE�ɍU�����ꂽ���Ɍ��t���ɗn���o���u�k�N���I�\�[���v�Ƃ����������B���t���ɂ��ꂪ���������Ƃ������ƂɂȂ�B �@3���ł���̗L�����f�f�ł��A����ɏڂ��������ł���̂��鑟����킩��B�ɓ���t�́u���̐f�f�@�͌��N�f�f�̍̌��̗]������p���邾���łł��܂��v�Ƙb���B J-CAST�j���[�X 2015�N6��18�� |
|
�R�[�q�[�ɑ̂̉��ǂ�}������ʁA�u����ł���l�ł���̃��X�N���Ⴂ�v���R�ɂ� �������ސl�͂T�̉��Ǖ��������Ȃ� |
| �@�R�[�q�[����ł���l�́A����̃��X�N���Ⴂ�ƌ����Ă���B���̗��R�̂P�́A�R�[�q�[�����ނƑ̂̒��ʼn��ǂ��N���ɂ����Ȃ邽�߂�������Ȃ��B �@�č����������𒆐S�Ƃ��������O���[�v���A����̈�̐�厏�L�����T�[�E�G�s�f�~�I���W�[�E�o�C�I�}�[�J�[�E�A���h�E�v���x���V��������2015�N�T��21���ɕ����B �R�[�q�[���ǂ����R��T�� �@�R�[�q�[������ł���l�͒��������Ƃ���������B�܂��A�q�{����A�咰����A�畆����A�O���B����A�̑�����ȂǁA���܂��܂Ȃ���̃��X�N���Ⴂ�Ƃ���������B �@�S�g�ɖ����I�ȉ��Ǐ�Ԃ������ƁA����ⓜ�A�a�A���^�{�Ȃǂ̂��܂��܂ȕa�C�ɂȂ���B����Ɋ֘A���āA�R�[�q�[�����ނƑ̓��̉��ǂ��}�����A����ɂ�肪��̃��X�N��������̂ł͂Ȃ����Ƃ�������������B �@�����O���[�v�́A�R�[�q�[������ł���l�́A����ł��Ȃ��l�ɔ�ׂĎ��ۂɑS�g�̉��ǂ̗l�q���Ⴄ�̂��ǂ����A��͂��s�����B �@�Ώۂ͔N�y�̔�q�X�p�j�b�N�n�̔��l1728�l�B���i�R�[�q�[�����ޗʂ́A�A���P�[�g�Œ��ׂ��B�܂��A�̌����s���A�u���~�l�b�N�X�r�[�Y�v�Ƃ����u���r�[�Y���g�������@�ŁA���ǂ̍ۂɌ����ɕ��o�����77��ނ̉��Ǖ����𑪒肵���B �@�R�[�q�[�����ޗʂƉ��Ǖ����ɂ��āA����ꂽ�f�[�^�v�w�I�ɉ�͂��A�֘A���ׂ��B �T�̉��Ǖ��������Ȃ����� �@���ʁA���ׂ�77��ނ̂���10��ނ̉��Ǖ����̓R�[�q�[�����ޗʂƊW���Ă����B��������Ƃ���A�ŏI�I�ɂT��ނ̉��Ǖ������W���Ă�����̂Ƃ��Ďc�����B �@��������R�[�q�[�����ސl�͑S�����܂Ȃ��l�ɔ�ׁA�u�C���^�[�t�F�������iIFN���j�v���R���̂P���x�A�uCX3CL1�v���S���̂P���x�A�uCCL4�v���Q���̂P���x�A�uFGF-2�v���R���̂P���x�A�uTNFR2�v���R���̂P���x�ɏ��Ȃ������B �@�uIFN���v�uCX3CL1�v�uCCL4�v�̂R�́A���ǂ̍ۂɒP���܂��̓}�N���t�@�[�W�ƌĂ��Ɖu�זE���������������艊�Ǖ��ʂɏW�߂��肷�邽�߂ɕ��o�������̂��B�uFGF-2�v�́A���ǂɊւ��זE�𑝂₷�B�uTNFR2�v�́A���ǔ������L���镨���B �@����̌��ʂ���A�R�[�q�[������ł���l�́A�̖̂����I�ȉ��ǂ��}�����Ă���X��������ƕ��������B���̂��Ƃ́A�u�R�[�q�[����ł���l�́A����▝���I�ȉ��ǂ̃��X�N���Ⴂ�v���R�̈�[�ɂȂ��Ă��邾�낤�ƌ����O���[�v�͏q�ׂĂ���B �@�R�[�q�[�D���ɂ͂��ꂵ���j���[�X���B Med�G�b�W 2015�N6��19�� |
|
�咰�ۂ𒍎˂����炪���ŁI�H����I�Ȃ���̎��Ö@�ƂȂ邩�H �咰�ۂ𗘗p��������Ɖu�Ö@�̊J����ڎw���� |
| �@�咰�ۂ�����זE�����ł����錻�ۂ͈ȑO����m���Ă������A���̃��J�j�Y���͕s���������B���̂��т̉�͂ŁA�咰�ۂ��̓��ɓ���Ƒ̖̂Ɖu�̎d�g�݂�����������A����ɂ�肪���ł��Ă���ƕ��������B�܂��l�Y�~�ł̎����̒i�K�����A����I�Ȃ���̖Ɖu�Ö@�ƂȂ�\��������B 150�N�O����m���Ă͂��� �@�h�C�c�̃w�����z���c�����������iHZI�j�̌����O���[�v���A����̐�厏�C���^�[�i�V���i���E�W���[�i���E�I�u�E�L�����T�[����2015�N�S��13���ɕ����B �@���̒��ɏZ�ޑ咰�ۂ́A�_�f�������Ă��Ȃ��Ă���������u�ʐ����C���ہv�ɑ�����B �@����̑g�D�ł́A����זE�����������B���Ă��邽�߁A�_�f�s���̏�ԂɂȂ��Ă���B����Ȃ���̑g�D�ɑ咰�ۂ�A���t���Ă��ƁA�咰�ۂ̓R���j�[�Ƃ�����ƂȂ��đ�����B���ʓI�ɁA����̐�����x�点����A��������ł������������B �@���̌��ۂ��ŏ��ɔ������ꂽ�̂�150�N�ȏ���O�����A���܂��ɏڂ������J�j�Y���ɂ��Ă͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��B�������A�V�������Ö@�ɂȂ�\���͏\���ɔ�߂Ă���B �@�����O���[�v�́A�l�Y�~�̎����ŁA�咰�ۂ�����זE�����ł����郁�J�j�Y������͂����B �Ɖu�̎d�g�݂������� �@�l�Y�~�Ɏ����p�̑咰����זE�iCT26�זE�j�𒍎˂��āA�w���ɂ���̉����点���B����̒��a���Tmm�ɂȂ����Ƃ���ŁA�����p�̑咰�ہiTOP10�j��Ö����˂����B �@����ƁA�l�Y�~�̔w���̂���͏��ł����B �@�����ł����l�Y�~�ɂ�����x��������זE�𒍎˂����Ƃ���A���ł��Ă��Ȃ������B����ɂ��A����̏��łɂ́A�̖̂Ɖu�������W���Ă���Ɨ\�z���ꂽ�B���N�`���Ɠ��������ŁA�̓��̖Ɖu�̎d�g�݂ɂ���āA�ЂƂ��сu�ٕ��v�Ɣ��f����A�L�����ꂽ����זE�́A�Q��ڂɑ̓��ɂ���Ă����Ƃ���A���₩�ɔr�����ꂽ�Ƃ����̂��B �@�Ă̒�A�Ɖu�זE���ŎE�����l�Y�~�ɂ���זE�𒍎˂��A���ł����Ƃ���ő咰�ۂ𒍎˂����Ƃ���A����͏��ł��Ȃ������B �Q���T�זE���� �@����ɉ�͂�i�߂��Ƃ���A����̏��łɂ�T�זE�ƌĂ�郊���p�����d�v�ł���ƕ��������BT�זE�ɂ͂��낢���ނ����邪�A��Ȃ��̂̓L���[T�זE�iCD8�{T�זE�j�ƃw���p�[T�זE�iCD4�{T�זE�j��2��ށB�Ɖu�זE�̕\�ʂɏo�Ă���^���p�N���ɂ͔ԍ����U���Ă���A�uCD�v�Ɣԍ��ŕ\�������B���̂����Q�̎�ނ̍זE�����Ă���Ƃ����킯���B �@�ŏ��̂����咰�ۂŏ��ł�����Ƃ��Ɏ�ɓ����̂̓L���[T�זE�������B�����ăL���[T�זE�A�w���p�[T�זE�Ƃ��ɂ���זE���L�����A�Q��ڈȍ~�ɂ��̗��҂����͂��āA���₩�ɂ���זE���E���Ă����B �����Ɖu�זE���ڐA �@���̃��J�j�Y���̊m�F�̂��߂ɁA�u�{�q�ړ��v�Ƃ����������s�����B����זE�����ł������o���̂���l�Y�~����A�L���[T�זE�ƃw���p�[T�זE��������A�����m��Ȃ��l�Y�~�̌��t�ɈڐA����B���̃l�Y�~�ɂ���זE�𒍎˂���ƁA����͂ł��Ă��Ȃ������B �@����ɁA������o�����L���[T�זE�́A���ɂ��傫���Ȃ����l�Y�~�ł��A�ڐA���Ă���������ł������B �@������o�����w���p�[T�זE���ڂ�����͂����Ƃ���A�R�����p�Ɋ֘A�[���u�O�����U�C��B�v�u�t�@�X���K���h�iFasL�j�v�u��ᇉ��q�A���t�@�iTNF-���j�v�u�C���^�[�t�F�����K���}�iIFN-���j�v������Ă���ƕ��������B �Ȃ邩�u�咰�ۂ��Áv �@����̌��ʂ���A�咰�ۂ����ڂ���זE���U������̂ł͂Ȃ��A�̖̂Ɖu�͂��������`�������Ă�������ł����Ă���ƕ��������B �@���J�j�Y�����ꕔ�𖾂ł������Ƃɂ��A���̉���I�Ȃ���̖Ɖu�Ö@�̎��p���Ɍ����āA�܂�������ݏo�����ƌ����O���[�v�͏q�ׂĂ���B Med�G�b�W 2015�N6��23�� |
|
����זE������_�����A�����q���ɂ��V�������q�����ÁA������܂ތ����O���[�v���� MRI�ł������肵�čU�� |
| �@�u�����_�J���V�E���E�K�h���j�E���E�����q���v�ƌĂԁA����זE�������U������V�������Â��J���������悤���B �@���{�̓�����w�E�i�m��ÃC�m�x�[�V�����Z���^�[���܂ތ����O���[�v���AACS�i�m��2015�N�U��11�����I�����C���łŕ����B MRI�����Ŏg���K�h���E�������p �@�����O���[�v��MRI�̑��e�܂Ȃǂɗ��p����Ă���u�K�h���j�E���v�ɒ��ڂ����B �@�K�h���j�E���́A�����q�����Ǝ˂���Ƃ����߂܂���B���̐����𗘗p����ƁA����זE�����ɒ����q�����Ǝ˂��A�I��I�Ɏ��Â��邱�Ƃ��\�ɂȂ�A���Âɍ������ʂ��グ��\��������B �i�m�J�v�Z���Ɏ��߂� �@���ɂ��̃O���[�v�́A�u�����_�J���V�E���v�Ɓu�K�h���j�E��-�W�G�`�����g���A�~���ܐ|�_�iGd-DTPA�j�v�ƌĂ��Q�̕��q��g�ݍ��킹(Gd-DTPA/CaP)�A���̕���������זE�����ɏW�܂�悤�ɍH�v�B�i�m�J�v�Z���̒��Ɏ��߂�ꂽ�`�ɂ����B �@���̏��MRI�����Ȃ���A���̕������^�[�Q�b�g�Ƃ��Ē����q�����Ǝ˂����B MRI�Ŋm�F�ł��� �@���ʂƂ��āAGd-DTPA/CaP�́A���̔Z�x�Œ����q�����Ǝ˂����Ƃ���A50���̂���זE�����ł���ƕ��������B�����q�ĂȂ���Ԃł͂���זE�ɂ����Q�������B �@���Â̓����͂���זE������_���Ď��Âł��邱�Ƃɂ���BGd-DTPA/CaP��Gd-DTPA����ᇂ̂���ꏊ�ɒ~�ς����邱�Ƃ��\�ŁAMRI�Ŏ�ᇂ̂���ʒu�𐳊m�ɓ���ł���B�����ɒ����q�����Ǝ˂��邱�ƂŁA���̍זE���������A����זE������_���Ē����q�����Ǝ˂��邱�Ƃ��\�ƂȂ�B ���p���̌��ʂɒ��� �@�����O���[�v�̓l�Y�~�Ŏ����B�}�E�X�̑̏d�����͌���ꂸ�A���S���̍������ÂƂ��āAGd-DTPA/CaP���L�]�Əؖ����Ă���B �@����A����ɂ��Âւ̖{�i�I�ȓK�p���L���ƂȂ邩���ڂ��ꂻ�����B Med�G�b�W 2015�N6��25�� |
| �����ُ�ǂ̎��Ö�u�X�^�`���v�����������}�� �c�傪�}�E�X�Ŋm�F |
| �@�c��`�m��w��6��25���A�����ُ�ǂ̎��Ö�Ƃ��Ďg�p�����X�^�`�����܂ɗ�������̔�����i�s��}��������ʂ����邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\�����B �@�����ʂ͓���w��w���Y�w�l�Ȋw�����̏��їC�� ���C�����ƕ�Johns Hopkins��w��w���a���w������Tian-Li Wang �y�����AIe-Ming Shih ������̌����O���[�v�ɂ����̂ŁA6��24���t(���n����)�̕ĉȊw���uClinical Cancer Research�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@�X�^�`�����܂̓R���X�e���[���̍�����j�Q���邱�Ƃ��玉���ُ�ǂ̎��Ö�Ƃ��ėp�����Ă���B�ߔN�A���܂�����̔�����}����\�������ڂ���Ă��邪�A��������ł͂��̌��ʂ��ؖ�����Ă��Ȃ������B �@�������ł́A���������R�ɔ�������}�E�X�ɃX�^�`�����܂𓊗^�����B���̃}�E�X�͒ʏ�A����5�T���炪�o�����邪�A�X�^�`�����܂𓊗^�����}�E�X�ł͂��̔�����i�W���}�����Ă����B�q�g�̗�������זE���ڐA�����}�E�X�ł����l�ɁA�X�^�`�����܂̓��^�ɂ���Ď�ᇂ̔�����i�s���}�����邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�܂��A�t�@�\��̋@�\�ւ̉e���͔F�߂��Ȃ������B �@����ɁA�q�g�̗�������זE�ɃX�^�`�����܂�Y�����Ĕ|�{����ƁA���B���}�������ƂƂ��ɁA�זE���c��������זE���ɋ�E���ł��邱�Ƃ���A�A�|�g�[�V�X��I�[�g�t�@�W�[�Ƃ������v���O�����זE�����֗^���Ă��邱�Ƃ��������ꂽ�B���ہA���܂̓��^�ɂ��A�A�|�g�[�V�X��I�[�g�t�@�W�[�Ɋ֗^����^���p�N���̔������זE���x���ł���ᇃ��x���ł������Ȃ��Ă����Ƃ����B �@�������O���[�v�́u����͖{�����̌��ʂ����ƂɁA���K�p�ʂ₻�̓K�����\���ɍl��������ŁA�q�g�̗������̔�����i�s�����ۂɗ}�������邩�������s���邱�Ƃ����҂��܂��B�v�ƃR�����g���Ă���B BIGLOBE�j���[�X 2015�N6��25�� |
|
�r�^�~��D�Ƃ���Ƃ̊ւ��ɒ��� ���������̐����������H |
| �@��������̏����ł́A���t���Ƀr�^�~��D�������Ɛ������������Ȃ�ƕ��������B����ƃr�^�~��D�Ƃ̊W���S�����߂Ă���悤���B ����ƃr�^�~��D�̊W���˂Ē��� �@�I�[�X�g�����A�A�N�C�[���Y�����h��w���O�q���w���𒆐S�Ƃ��������O���[�v���A�h�{�w�̍��ێ��ł���A�����J���E�W���[�i���E�I�u�E�N���j�J���E�j���[�g���V��������2015�N�T��13���ɕ����B �@���˂ăr�^�~��D�Ƃ���Ƃ̊W���w�E���錤���͑����B �@�����O���[�v�́A�r�^�~��D�̑̓��ł̌`�Ԃł���u25�q�h���L�V�r�^�~��D�i25�iOH�jD�j�v�Ɨ�������̐l�̐������Ƃ̊֘A�����������B �@�I�[�X�g�����A���������ɎQ�����A2002�N����2005�N�ɂ���זE�̍L�������N�P���i���イ�����j�̗�������Ɛf�f���ꂽ������ΏۂɁA�����r�^�~��D�Ɛ������Ƃ̊֘A���ɂ��Ċ댯�x�𐄒肵���B �댯�x�͂V���Ⴍ �@�o�ߊώ@���Ԓ��ɑS�̂ł�59���̏��������S���A���̂�����95���̎��S�͗�������ɂ����̂ł������B �@�r�^�~��D�������Ɣ���ł����l�ł́A�����ɂ킽���Đ�������l�������ƕ��������B�����̊댯�x�͂V���Ⴍ�Ȃ��Ă����B�a�C�̐i�s���Ă��Ȃ���Ԃł̐������Ԃł���u�������������ԁv�͍����Ȃ������B�a�C����������܂ł̊��Ԃ͍����Ȃ��A�a�C���������n�߂Ă���̊��Ԃ������Ȃ�Ƃ����킯���B �@���ʊW�͕�����Ȃ����A�h�{��Ԃ̉��P������̐��������P������\��������̂�������Ȃ��B Med�G�b�W 2015�N7��1�� |
|
���p���߂�!? ���t�A�ɂ����A���t�ł����������I����ʂɈꔭ���� |
| �@�a�C��������y�ɑ����ɔ�������Z�p�����X�ƒa�����Ă���B���������Z���^�[�Ȃǂ͌��t1�H�Œ������ɂ��������f�f�@���J�����Ă���B4�N��܂łɁA�x�����݂���Ȃ�13��ނ̂����f�f�ł��錟���@�̎��p����ڎw���Ă���B �@�ǂ��������J�j�Y���Ȃ̂��B����זE�͔��������u�Ԃ�����L�̃}�C�N��RNA���o������������A����RNA�����t���Ō��o���邱�Ƃł�������\�ɂȂ�Ƃ����B�}�C�N��RNA�͂���̂ł��鑟��ɂ���ă^�C�v���قȂ邽�߁A���ʕʂɂ����ʂł���B ��̂Ђ炩����L�̐��̃K�X �@������Ȏ��ȑ�w�͂�����L�́u�ɂ����v�ɒ��ڂ����B��̂Ђ�̏����Ȍ�����o�Ă���A�l�̚k�o�ł͂킩��Ȃ��悤�Ȑ��̃K�X���@�B�Ō��o����B��������������ł�����ł���Z�p���B�c����w�̌������́u���t�v�̐��������ʕ��͌v�ŕ��͂����Ƃ���A����ǂ��邱�Ƃő��t�̈ꕔ�̐������ω����邱�Ƃ����炩�ɂȂ����Ƃ��Ă���B �u���t�Łi����̑����������j�ł���Ƃ́A���E�����v���Ă��Ȃ��������A�������肵���m�ł���G�r�f���X���o�Ă��Ă��܂��v�i�c����w�̐��{���O���C�y�����j �@�Q�X�g�ŁA����̑����f�f�ɂ��킵�����ۈ�Õ�����w�̖k�������w���͂����b�����B�u�}�C�N��RNA�͏]���̕��@�����ɐ����Ȑf�f���ł��A��ᇃ}�[�J�[�Ƃ���ׂĂ������ɔ����ł��܂��v �@���t��̉t�A�L���Ȃǂɂ�錟���́A����́u�f�f�v�Ƃ������́A�u�X�N���[�j���O�v�i���X�N�������l������j�̒i�K���������B *NHK�N���[�Y�A�b�v����i2015�N6��30�������u���Ȃ��̂����܂��`���������Âւ̒���`�v�j J-CAST 2015�N7��2�� |
|
���E���A�u���̂���f�f�v�Z�p ���t1�H�A������3���Ō��ʂ��킩��I ��w�m���[���̃x���`���[��Ƃ��N��������� |
| �@����͈�Â̊v���ɂȂ邩������܂���B����f�f�ɉ���I�Ȏ�@���a���ł��B �@�_�˂ɂ���e�q2�l�����̃x���`���[��Ƃ��A�����`�b�v���g���āA���t1�H�A���莞��3���Ƃ�������܂ł̂���f�f�̓�����Z�p�E��@���J�������̂ł��B ���f�̂ނ������� �@�ߔN�A���{�ł�2�l�ɂP�l������ɜ��A���̂�����3�l�ɂP�l�����𗎂Ƃ��A�����̎��S�����̃g�b�v�ł��葱���Ă��܂��B����͔N�Ԗ�37���l���̐l�̖���D���Ă���̂ł��B �@���̃R�����ł������g�̑咰����𑁊������E���Â��Ă����o�܂����b���Ă��܂������A����Ƃ����̂͏����Ǐo�ɂ����A�ɂ݂Ȃǂٕ̈ςɋC�Â����Ƃ��ɂ͎�x��Ƃ����P�[�X�����Ȃ�����܂���B�u����͌��f�Ŕ�������a�C�v�ł���A�u�ǂꂾ�����������ł��邩�v����������̂ł��B�������A���f�̎�f����2�����x�B �@�o���E���≺�܂�����A�}�����O���t�B�ł͓��[���@�B�ɉ����ׂ����悤�Ȓɂ݂��Ȃǂ̋�ɁA�\������d�����x��Ŏ�f����ʓ|�������A�����Ĉꕔ���z�ȗ����B����ʂ��Ƃɍs���Ƃ������Ƃ����S�O����l�������̂ł��B�������A����ɂ�7~10���҂������̂��ʏ�ł��B �@�u�Ȃɂ����o�Ǐo����a�@�ɍs���v�Ɛ扄���ɂ��Ă��܂������l�̋C������������Ȃ��ł�����܂��A�g�������Ă���̋��낵����m��A���f�̑����i���銈�������Ă��鎄�́A���f��f���̒Ⴓ�ɑł�͂Ȃ����̂��A�����䂭�v���Ă��܂����B �@����Ȑ܁A��ɂ��ʓ|��������ꂸ�A���̏�ł��f�f�ł��Ă��܂�����I�Ȏ�@���J�����ꂽ�A�Ƃ����j���[�X�����E���삯����܂����B �@�����͂������A�A�����J��V�A�������ވ˗����E�����Ă��钆�A�Ȃ�Ǝ��A�e���r�����u���[�j���O�o�[�h�v�ŁA���E�ŏ��߂Č������ɓ��邱�Ƃ��ł��܂����B �@�_�˂ɂ����Ë@���Ёi�L�j�}�C�e�b�N�̌������ŏo�}���Ă��ꂽ�̂́A������̂���l�B �@�����l�̒��J�썎�V����ƒ��j�̗T�N�i�䂤���j����B���߂Ă̎�ނɂ܂��\������X�����l�q����ۓI�ł����B �@��ÊW�̃x���`���[���W�����錤�����̈�ԏ����ȕ������ނ�̏�B�킸��30�u�قǂ̏����ȃX�y�[�X�ŁA�����ɑ傫�Ȋ���u���A�I�Ɨ①�ɂ�u������A����ꏊ�ɍ����Ă��܂����炢�B �@����Ȃ���A����Ȋ��Ő��E�����ڂ���f�f�@���a�������̂��Ɛ�債�Ă��܂��܂����B �������ăV���v���Ȏd�g�� �@�f�f���@�͂������ăV���v���I?�����`�b�v�̕\�ʂɌ��t�i�s��������菜���������j�𐂂炵�A�������Ŕ`���Č��邾���B �@�������ĕ��͂ɂ��Ă݂�Ƃ킸��1�s�ŏ����Ă��܂��Ƃ����ȒP���ɂ͂Ȃ�Ƃ������ł��B �@���������ڂ����d�g�݂��Љ��ƁA����J�����ꂽ�̂́A���̋����`�b�v�ƕ\�ʂɓh�鎎��ł��B�`�b�v�͓������łł��Ă��āA�\�ʂɎ����h�邱�Ƃʼnߎ_����\�����Ƃ����V�K�����̖�������A���̂悤�Ƀg�Q�g�Q���������̏�ԂɂȂ�܂��B �����`�b�v�̕\�� �@�����Ɍ����𐂂炷�ƁA���҂��������킹��u�k�N���I�\�[���v�Ƃ�������֘A�����������g�Q�ɋz������Ƃ����̂ł��B���̃k�N���I�\�[���͂���Ɖu�ɍU�����ꂽ�Ƃ��Ɍ��t���ɗn���o�镨���ŁA���҂łȂ���Α��݂��܂���B�܂�A�g�Q�Ƀk�N���I�\�[�����������Ă���A���ꌌ�t�̎�����͂��Ɣ��ʂł���̂ł��B �@�����āA���X�`�b�v�ɂ͋����i�m���q�i�v���Y�������ʁj�ŁA�d�ꑝ�����ʂɂ���Č������������������A�u���������Ŕ`���ƃk�N���I�\�[�����ΐF�Ɍ����Č����邽�߁A����̗L������ڂŊȒP�ɔ��ʂł���Ƃ����d�g�݁B �@�摜�ɂ͎��̂悤�ɕ\��܂��B��i���ǐ���ᇂ̊��҂̐f�f���ʁA���i��������ᇁi������j�̊��҂̐f�f���ʂł��B  �@����֘A�������܂�ňÈłɌ��鐯�̂悤�Ɂu������ᇁv�̑��݂������Ă���܂��B �@���a��w�]���L�F�a�@������Z���^�[�ɓ����W�u�t�Ƃ̋��������ɂ��ƁA���҂Ɨǐ���ᇂ̊��ҁA�v20�l�̌��t�Ŏ������Ƃ���100���ԈႢ�Ȃ�����̗L����f�f�ł��������ł��B �]���̂���f�f�@�Ƃ̈Ⴂ �@���Ȃ݂ɁA���t�����ł����f�f������@�Ȃ猻�݂ł��L���s���Ă��܂��B���t���̎�ᇃ}�[�J�[�ƌĂ�邪��̎w�W�ƂȂ����ȕ����̐��l�𑪂�Ƃ������̂ł��B �@�������A�������Ă����o�����Ȃ����Ƃ�����A���̐f�f�Ƒg�ݍ��킹�Ď��{����Ă��܂��B�����g�A�A���Ƃ������ʂ��o������ɉ������A�������ōČ�����������咰���������ꂽ���Ƃ�����܂����B�܂��A�������ʂ��o��܂ł�1�T�Ԃ��s���ȋC�����ő҂��܂����B �@���ɂ��A�����g�Q���ACT�APET�Ȃǂ̉摜�f�f������܂����A������͈�t���摜�����Ă���̐i�s�x����Ȃǂf������@�ŁA�����̂���͏��������ߔ���������̂ł��B�����Ƃ��̊댯�����邵�A��ᇂ��������ēE�o��p�����Ă݂���ǐ���ᇂ������Ȃ�Ă��Ƃ��悭�����b�ł��B �@����̋����`�b�v�̐f�f�@�ł́A���t���Ɋ܂܂�邪��֘A�������摜�Ō��邽�߁A������ᇁi������j���ǂ����̌��ʂ͈�ڗđR�ƌ����܂��ˁB �u�����v����u�������v���� �@��Ԓm�肽���̂́A�ǂ̕��ʂ̂��킩��̂��H �@����̑傫�����킩��̂��H �@���ɓ]�ځE�Ĕ��̋��|������銳�҂ɂƂ��Ă͐؎��Ȗ��ł��B���J�썎�V����ɂ��ƁA�u���ꂼ��̕��ʂ��ƂɌ��̌`��傫���ɓ���������܂�����A���ʂ��\�ɂȂ�܂��v�Ɨ͋��������B �@���i�K�Ŏ����ς݂Ȃ̂́A�݂���E�咰����E�H������A�����āA��������ԓ���Ƃ���邷��������̏�����n�B����͋����������s�����a��w�ɓ����W�u�t��������Z���^�[�Ζ��̂��߂������ł��B �@���_��͓�����E�q�{����Ȃǂ̕w�l�Ȍn�A�܂��畆����A�A������Ȃǂ��\�������ŁA����́u���t�̂���v�ƌĂ�锒���a�����������Ƃ̂��Ƃł��B �@�܂��ACT��PET�Ȃǂ̉摜�����ł͂������ł���̂́A��ᇂ�10�~���ȏ�̑傫���ɐ������Ă���Ƃ���Ă��܂����A���̎�@�ł͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���H �u�ǂ�Ȃɏ����Ȃ���ł����t���̃k�N���I�\�[���̌��𑨂���̂ŁA0.1�~���Ƃ���������́w��x�������邱�Ƃ��ł��܂��B�v �@��ᇂ��̂��̂����Ō�����̂ł͂Ȃ��A�����܂ł����t���Ɋ܂܂�邪��֘A�����̕��q�����o����̂ŁA�u���������v�ǂ��납�u�w���x���������v���\�ɂȂ�Ƃ����̂ł��B �@�����āA����قǂ̐f�f���킸��3���Ƃ����Z���Ԃłł���̂́A4�`5��������O�������K�v�Ȃ����߂��Ƃ��B �@�K�v�Ȍ��t�ʂ�5�}�C�N�����b�g����1�H�ɂ������Ȃ����߁A���̌����̂��łɎc�������t�Ńp�b�Ɛf�f���邱�Ƃ��\�ł��B���p������A�܂��Ɏ�Ԃ��ɂ݂�����Ȃ����̂悤�Ȑf�f�ł��ˁB ���Ƃ��Ƌ������i�̉�Ђ����� �@�i�L�j�}�C�e�b�N�́A1999�N�n�Ɠ����͑�胁�[�J�[�̋@�B���H�𐿂������Ă��܂������A��ւ�肵��2005�N�Ƀo�C�I���Ƃɓ]���B2010�N�ɓƎ��̗ʎq�����Z�p�����p���āA�]���̕����I���H�@�ł͂Ȃ����w�I��@�̐V�Z�p�ł����镪�q�̌��o���\�ɂ��������ł��B �@���o����镪�q�́A�����ł͂���܂���B���p�͈͖͂������Ƃ����܂��B���Ƃ��A����A�_�ƁA�H�i�֘A���̊J���E���o�E�����B�_�C�I�L�V�����̊����������̌��o�E�����E�y�땪�́B�ŃK�X������w����̌��m�Ȃǃo�C�I�e����܂ŁB �@�Ȃɂ��ƂĂ��Ȃ��X�P�[�����ł����A����2�l�Ƃ���w�m���̓[���������Ƃ�����������ł��B �@�u�����m��Ȃ��̂��悩�����B���肪�Ȃ�����A�w����͂�����x�Ǝv������A�����ɈႤ�����ɐ�ւ���B�ǂ��ɂ��������ĂȂ�����w���Ȃ����O�ł���H�x�Ȃ�ĒN�ɂ����匾���Ȃ��B���Ȃ�ĂȂ����玩�R�Ȃ�ł��v�Ə����V����B �@���̌����Ɋւ��Ă͌��I�ȕ⏕�������A�\�Ȍ��莩�Ȏ����B�����Ɏ����ɍs���̂���s�@�オ���������Ȃ�����Ɣ��������ĎԂŒʂ��A�T�N����͑�w�𒆑ނ��w�K�m�ōu�t�̃A���o�C�g�����Ȃ��猤���𑱂��Ă��܂����B2�l����̏����Ȍ������Őe�q���܂����Ȃ���A���̌�����������������p������邱�Ƃ�����Ă��܂��B �@�������̊肢�����Ȃ����͖ڑO�܂ŗ��Ă��邩������܂���B �@���łɓ��{�⒆���Ȃǂœ����擾�ς݁B���E����30�`40�����̌�������ڎw���Ă��邻���ł��B�ی��K�p�͎���ɓ���Ă��܂��A�P�N��ɂ����p����ڎw���A��p�͐���`�����~��z�肵�Ă���Ƃ��B �@2�l�͖������̂悤�Ɍ���Ă��܂��B �u���p�������A�����̐l�ł������`�b�v�������������ł���B��Êi���̉����ɂȂ������B�������͐��E�ň�ԏ����ȃO���[�o����Ƃ�ڎw���Ă��܂��v ����r�W�l�X 2015�N7��4�� |
|
�u��������v���҂͌����ă[���ł͂Ȃ� �w�����R�Ɏ��鐶�����x����t�Ƃ��ēǂ�� |
| �� �q�O�@���s����c�a�@�E���킳�������P�A�Z���^�[��t �@�u�A�����J�Ńx�X�g�Z���[�ƂȂ�A���{�ł��ł��d�˂Ă���v�ƕ������̂��A�w�����R�Ɏ��鐶�����x�i�P���[�E�^�[�i�[���^�v���W�f���g�Ёj����ɂƂ邫�������ł����B��t�Ƃ��āA���̐l�C�̗��R��m�肽���Ǝv���܂����B���ǂ������ƁA�����̕��Ɩ{���̔����郁�b�Z�[�W�ƁA�{����ǂލۂ̒��ӓ_�����L�������āA���҂�����ÊW�҂�ΏۂƂ����Ǐ���Ŏ��グ��Ɏ���܂����B �@�{���ł́A���҂������E��ނ����u���I�Ȋ����v��100�]��̎��Ⴉ�瓱���o���ꂽ9�̋��ʓ_�������Ƃ��Ď�����Ă��܂��B���E���ɁA�������]���鍐���Ȃ�����A�������猀�I�ȉ����������A���������蒷�����������肷�������������̂ł��B �@�܂��A���҂��o�������ᇓ��Ȉソ���͊F�u��������I�Ɋ������������ҁv��f�����Ƃ�����A�Ɖ��������ł��B �@�������������A����10�N�قǂł����R�Ɋ���������i�s���Ȃ���ɂ��Ă͉������ڂ̓�����ɂ��Ă��܂����B �@���Ƃ��Έ��������p��Ɛ鍐����A�R������Â������߂��Ă���A����Ƃ����j���̊��҂����܂��BA����͍R������Â���Ȃɋ��݁A�r������ς�����ƕa�@�Ɍ���Ȃ��Ȃ�܂����B�����āu��������Ȃ��Ă͎�f���A�R������Â������߂���ƁA�p�������c�c�v�Ƃ������Ƃ��J��Ԃ��Ă��܂����B �@�܂�Łg�������������h�̂悤�ȓ��X�̖��A�悤�₭�R������Âɓ��ݐ낤�Ƃ���A����̊�����CT���B�����Ƃ���A�i�s���Ă���ɈႢ�Ȃ��c�c�Ǝv���Ă����a������������Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��B�����̎��͎厡��ł͂Ȃ��S����Ƃ��Ċւ���Ă����̂ł����A�u���������ŏ��̐f�f����f�������̂ł͂Ȃ����H�v�Ɩ₤A����̓{��̕\��́A�����قɏĂ��t���Ă��܂��B �� ���F������Ƒg�D�����͂��Ă��܂�����A����͐��N��A�����Ƃ���ɂ��ĔR�������߁A��f�ł͂���܂���ł����B �ɘa�P�A�a������މ@����l�� �@�܂��A���̂悤�ȗ������܂��B�z�X�s�X�ɓ������Ă���B����Ƃ��������́u��������v�Ƒ��@�Ő鍐���ꂽ���҂���̃P�[�X�ł��B �@�ޏ��́A�]����3�J���Ɛ鍐����Ă��āA�ɘa�P�A�a���ɓ��邽�߂Ɏ���蕥���A�g�Ӑ������ς܂��Ă��܂����B�������A���@��ɉ��x���������Ă��A����̉e�͏������܂܁B3�J���ŖS���Ȃ�ǂ��납1�N�ȏソ���Ă�����͑傫���Ȃ炸�A���퐶���ɂ��x��͂Ȃ��̂ŁA�����g�̐l���̂��߂ɂ��މ@���邱�Ƃ��������߂����Ƃ���u���Y���߂�Ƃ��������Ă��܂��ċA��ꏊ�������̂Ɂv�ƁA���f���Ă�������Ⴂ�܂����B �@�ŏI�I��B����͊ɘa�P�A�a������މ@�ƂȂ���{�݂Ɉڂ�܂������A���̌�����炭�A����͑S���i�s�������N�Ԓ��������邱�Ƃ��ł��܂����B �@�������A�����͈�ʓI�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��ɂ߂ă��A�ȃP�[�X�ł��B���������̂悤�Ȏ��R�Ȋ�����������u�i�s���Ȃ�����v�̉\�����[���ł͂Ȃ��A�Ƃ��������́A�����ƒm���Ă��悢�Ɗ����܂��B����ɁA�R������Â����邱�ƂŊ����ɂ��������A�Ō`����ł������Ƃ��Ă������ă[���ł͂���܂���B �@�������AA�����B������A�{���ɋ������Ă���u9�̎��H���ځv�A���Ƃ��u���{�I�ɐH����ς���v�Ȃǂ̎��g�݂��A�ӎ��I�Ɏ��H���Ă͂��Ȃ������͂��ł��B �@���̂悤�ɁA����Ƃ͂���Ӗ��s�v�c�ȕa�C�ŁA���v�I�ȗ\�������ʂ����Ȃ��炸�͂��ł��܂��B����ɂ�������炸�A�{���ł͍ŏ��Ɂu����͉����ł��v�ƑO�u�����Ă��Ȃ���A�ǂ�ł���Ɓu����������H���܂��傤�v�Ə�����Ă���Ƃ���A�����āu���ꂪ�w�����R�Ɏ��鐶�����x�ł��v�ƃ^�C�g���Ɏ����Ă���Ƃ��낪�A���ӂ��ēǂނׂ��{�Ǝv�������R�ł��B �u���Â̎�����v�Ƃ��ēǂނׂ��ł͂Ȃ� �@�{���ɋ������Ă����u���I�Ȋ����v�̂��鎖��ɂ��Ă��w�E���ׂ��_������܂��B �@�h���i����Ƃ���58�̏����̃P�[�X�ł��B �@�ޏ��̓X�e�[�W3�̐i�s����������Ɛf�f����A���̐؏���p���o�āA�l�H�����`������Ɏ���܂��B�����ďp�㐔�T�Ԍォ��A�Ĕ���}���邽�߂̍R������Âɒ��݂܂��B�����������������Ȃǂ̕���p�ŏW�����Î��ɓ��@���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����ޏ��͈�t����A����̍R������Â̒��f�ƋA��������߂��邱�ƂɂȂ�܂��B �@�����Ńh���i���I�������̂́A�J�i�_�́u�N�[�K�[�}�E���e���Z���s�[�E�Z���^�[�v�ōs����A�I�ƃn�[�u�ɂ��W�����Ẫv���O�����ł��B����́u�R����܂�g�̂���o���������ق����悢�v�Ƃ����ґz�T�[�N���̗F�l�̏����ɂ����̂ł����B �@�v���O�����̊��Ԓ��A�h���i����͌��N�I�Ȗ�Ƌ��̗������y���݁A����p���T�[�������u�ɂ�鎡�Â��A����ɂ͎Q���҂Ƃ̌𗬂ʼnߋ��̊���U�����Ă��������ł��B �@�����́A�u�����̂��܂܂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ�����Ԃœ��������ޏ��ł������A10���Ԃ̃v���O�������I�������Ƃ��ɂ͉��L����������悤�ɂȂ��Ă����Ƃ����܂��B �@���ꂩ��ޏ��͒ʏ�̐����ɖ߂�A�����鑷�̐����������A���⏬���A�����A�����i���T�����H���Ö@�A�r�^�~���܂̐ێ���ґz�𑱂��܂��B�����đމ@����2�N�ځA�l�H�����O����܂łɉ����𐋂��܂��B����ɂ��ꂩ��6�N�ȏ�o���Ă��A�h���i����͏��N��Ԃ�ۂ��A���̎q����{�����e�B�A�����ɗ��ł���̂������ł��B �@���̕`�ʂ���A�u�N�[�K�[�}�E���e���Z���s�[�E�Z���^�[�̃v���O�����ɎQ���������ʁA���C�ɂȂ����v�Ƃ������b�Z�[�W����ʓI�ɂ͓ǂݎ�邩������܂���B�������A�����������P�[�X���u���I�Ȋ����v�Ǝ��グ�Ă��邱�Ƃ��A�{���𒍈ӂ��ēǂ����������R�̂ЂƂł��B �@�������A���̃v���O�������h���i����̃����^���ʂ��������Ă��ꂽ�Ƃ������Ƃ͂��邩������܂���B�����������Ɍ����A�ޏ������̃v���O�����ɎQ�������Ă��Ȃ��Ă��A�����ւƌ������Ă����\���͍����̂ł��B �@�Ȃ��Ȃ��ʓI�ɁA�R������Â̕���p�ő̒������������̂ł���A����𒆎~���邾���ł��A�̒��̉����������邱�Ƃ͒������͂Ȃ�����ł��B�����āA�X�e�[�W3�Ŏ�p�������̂ł���A���̌�R����܂����Ȃ��Ă��Ĕ����Ȃ��A�Ƃ����\�������Ȃ��͂Ȃ��A�܂�͂��̃v���O�����Ŏ������A�Ƃ������͂���̎�p�ł��������A�Ƃ����\���̕��������̂ł��B �@����9�̎��H�Ŗ��l������킯�ł͂Ȃ��u�����v�ł���ȏ�A���̖{�������������u���Â̎�����v�Ƃ��ĂƂ炦��Ȃ炻��͂�͂蒍�ӂ��������悢�ƌ��킴��܂���B�ł��A���̓_�ɒ��ӂ��������ŁA�O�����ɐ����邽�߂̃q���g�A����������Ȃ��琶���邽�߂̃q���g�邽�߂̖{�Ƃ��ẮA�ǂމ��l�����邩������܂���B �@��X��Î҂́A�Ȋw�҂Ƃ��ē`����ׂ����Ƃ͂�����Ɠ`����ׂ������A�댯�Ȏ��Ö@�⍼�\�Ɋ��҂����������Ƃ��Ă���̂Ȃ�A����͎~�߂�ׂ��Ǝv���Ă��܂��B����������ŁA���҂���B�������ɑO�����ɐl�������邱�Ƃ��ł��邩����ɍl�������Ȃ��ƂȂ�Ȃ��Ƃ��v���Ă��܂��B���̖{��ǂ��Ƃ����������ɁA���҂��O�����Ȋ�]�����Ă��A�Ƃ����̂ł���A���̖{�͂ЂƂ̖������ʂ������ƌ�����Ǝv���܂����A���́u��]�v���̂������ے肷����̂ł͂���܂���B����Ȃ�Ύ��́A�l�ԂƂ��Ă��̊�]���x���A��w�̉Ȋw�҂Ƃ��ăA�h�o�C�X�����A���҂���̐����铹�Ɋ��Y���čs�������Ǝv���܂��B �� �q�O�i�ɂ��E�Ƃ��Ђ�j ���s����c�a�@�E���킳�������P�A�Z���^�[��t�B2005�N�A�k�C����w��w�����B�ƒ��Â��u������A�ɘa�P�A�ɖ�������A�ɘa�P�A�E��ᇓ��Ȉ�Ƃ��Č��C����B2012�N���猻�E�B�ɘa�P�A�`�[���̋Ɩ��𒆐S�Ƃ��āA��ᇓ��ȁA�ݑ��Âɂ��ւ��B���{���Ȋw��F����Ȉ�A���ÔF���A����Ö@����Bhttp://tonishi0610.blogspot.jp/ President ONLINE 2015�N7��4�� |
|
���t�A���t�̌����œ�����̑����������\�� ��N�P�I�Ȃ��o�Ɋ��� |
| �@�����҂̌��t�E���t���Ɋ܂܂���ᇗR����DNA���������ꂽ�ƁA�ăW�����Y�E�z�v�L���Y��w�̌����O���[�v�������B�����𗦂������@��A�E���O�ȏy������Nishant
Agrawal���́A�u���DNA�̓X�N���[�j���O�A���������A���Î��̃��j�^�����O����ю��Ì�̌o�ߊώ@�ɗ��p�ł���\��������v�Əq�ׁA�߂������ɂ͔�N�P�I�Ȃ�������������Ƃ̌��ʂ��������Ă���B �@Agrawal���ɂ��ƁA����̌�����100�l�����̊��҂�ΏۂƂ����\���I�Ȃ��̂ł���A�����̐��\�����コ���ēI�m�ȓK���ǂ��߂�ɂ́A����ɑ�K�͂Ȍ��������{����K�v������Ƃ����B�ڕW�́A������̎c����Ĕ��̊Ď��̂ق��A��ʏW�c�܂��̓n�C���X�N�W�c�̓�����X�N���[�j���O�ɂ����̌����𗘗p�ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��ƁA�����͕t�������Ă���B���́̕uScience Translational Medicine�v��6��24���f�ڂ��ꂽ�B �@������̎�Ȋ댯���q�̓A���R�[���A�^�o�R�i���݃^�o�R���܂ށj�AHPV�i�q�g�p�s���[�}�E�C���X�j�����ł���A����͌��O�A�O�㕔�A�j����ю������܂߂����o�A�A�̌�ǂ���эA���ɔ�������B �@����̌����ł́A������ƐV���ɐf�f���ꂽ���A�Ĕ���������93�l�̑��t���̎悵�A47�l����͌��t���̎悵���B71�l�i76���j�̑��t���̂����41�l�i87���j�̌��t���̂Ɏ��DNA�����������B���t�Ƒ��t�̗������̎悵��47�l�̂���45�l�ŁA���Ȃ��Ƃ������ꂩ�̑̉t���Ɏ��DNA�����ł����B �@��̓I�ɂ́A������̑����̌����ƂȂ��Ă���HPV�̍��Ղׂ��ق��AHPV�ɖ��W�̂���ɂ��ẮA����̂���֘A��`�q�̕ψقׂ��B���ʂ͂���ƁA���t�����͌��o����A���t�����͍A�̂���̔����ɗD��Ă����B2�p����A���ǂ��ɂ����Ă��������邱�Ƃ��ł����Agrawal���͏q�ׂĂ���B���̌����̔�p�͐��S�h���ɂȂ�Ɨ\�z����邪�A������50�h�����������z���Ƃ��Ă���B �@�č�����iACS�j��Leonard Lichtenfeld���́A���̂悤�Ȍ�������������A����̑��������E���Âɑ傫���v������͂����Əq�ׂĂ���B���̂���ɂ��Ă��A���ٓI��DNA�ψق����������A��������o���錌�t�������\�ɂȂ�Ɠ����͏q�ׁA�u����̌����͏����i�K�̂��̂����A���̎������\�ł��邱�Ƃ�����������v�ƕt�������Ă���B m3.com 2015�N7��6�� |
| ���ł���V���Ȏd�g�݂��I �זE����̌��ƂȂ�^���p�N���u�T�C�N����E�v�A��������Ɠ�����┒���a�� |
| �זE��������DNA���j��������� �@�߂�����͂Ȃ��y���邪���Ƃ��B���̂��Ƃ킴�́A�זE����ɂ����Ă͂܂�悤���B �@�זE����̌��ƂȂ�u�T�C�N����E�v�Ƃ����^���p�N������������ƁADNA���j������ԂƂȂ�A�����Ă��܂��悤�Ȉ�`�q�̓ˑR�ψق����ݏo�����ƕ��������̂��B �זE����̌��u�T�C�N����E�v �@�č��X�N���v�X�������𒆐S�Ƃ��������O���[�v���A�����w�̐�厏�J�����g�E�o�C�I���W�[����2015�N�T���V���ɕA�����Ɍ������̃E�F�u�T�C�g�ŏЉ���B �@�זE�͂Q�ɕ���Ƃ��ɁA��`�q��ۂ��Ă���uDNA�v�����A�����R�s�[�����ꂼ��̐V�����זE�ɕ��z����K�v������B �@����ȍזE����ł́A�uCdk2�v�Ƃ����y�f�ɃT�C�N����E���������Ďn�܂�BCdk2�����������āADNA�̕����Ɍ������B�܂�A�K�ʂ̃T�C�N����E�͍זE����Ɍ������Ȃ��B �@�Ƃ��낪�T�C�N����E�́A�u��������Ƃ��ɂȂ���v�ƁA�������[�_�[�̃X�e�B�[�u���E���[�h���͐�������B �ǂ����Ă���ɂȂ���̂��H �@�����O���[�v�͂���܂ł̌����ŁA�T�C�N����E���ߏ�ɑ��݂��邪��זE������A���̂悤�ȓ�����̐l�͐��������Ⴂ�Ɣ��������B �@�܂��A�T�C�N����E����������ƁA�זE��������DNA���s����ɂȂ�A��`�q�ɕ����I�ȏd���⌇���Ƃ������ˑR�ψق��N����₷���Ȃ�Ɠ˂��~�߂��B �@�����O���[�v�́A���̃��J�j�Y���̉𖾂ɒ��B DNA���j��������Ă��� �@�����O���[�v�͂܂��A����̐l�̓��B�זE�ƁA���̍זE����`�q���삵�ăT�C�N����E�������זE�Ɠ����x�ɉߏ�ɍ�点�����̂�p�ӂ����B���҂��r���āA�T�C�N����E�̓����ׂ��B �@���ʁA�T�C�N����E���ߏ�ȍזE�́ADNA�̕����ɂ����鎞�Ԃ������ɒ����Ȃ��Ă����B �@����ɁADNA���������I����̂�҂����ɁA�זE�����̃X�e�b�v�Ɉڂ낤�Ƃ��Ă���̂����������B �@DNA�́A�������悤�Ƃ���͂Ǝ��̃X�e�b�v�Ɉڂ낤�Ƃ���̗͂��҂ɂ���āu�j�����v���ꂽ�悤�ȏ�ԂƂȂ�A������邩�A��������ꂽ�ǂ��炩�ɍs�������Ȃ��Ȃ��Ă����B���̌��ʁADNA�͌����⑹�����N�����Ă����B �@���̗l�q�́A�u���Ŏ��o�����Ď��ۂɖڂŊm���߂�ꂽ�B ����ɂȂ���DNA������ �@�T�C�N����E���ߏ�ȍזE�œˑR�ψق��N����₷���̂́A�j������Ԃ����������ʂ������ƕ��������Ƃ���ŁA�����O���[�v�͎��ɂ��̌��ۂƂ���Ƃ̊֘A���ɂ��Ē��ׂ��B �@�T�C�N����E���ߏ�ȍזE�Ō����������Ă���DNA�̕����ׂĂ݂�ƁA�ア�����ɊY�����Ă���A����������Ɗ��ɒm���Ă��镔�������������B �@����זE��DNA�z��f�[�^�x�[�X���g���Ă���Ɍ���i�߂��Ƃ���A������œˑR�ψق��N���Ă���ƒm���Ă���16�J���̂����U�J���́A�T�C�N����E���ߏ�ɑ��݂��Ă��邱�Ƃƒ��ڊW���������B����ɂ��̂����̂P�J���́A���ɔ����a�ŃT�C�N����E�Ƃ̊֘A�����ؖ�����Ă��镔���������B �Ȃ������ɐ�ɐi�����Ƃ���̂� �@����́A�T�C�N����E������DNA�������x���ƁA�Ȃ��҂����Ɏ��̍זE����̃X�e�b�v�i�����Ƃ���̂��A���̗��R�̉𖾂܂łɂ͎���Ȃ������B�����O���[�v�́A���炩�̃`�F�b�N�|�C���g�����������d�g�݂������̂ł͂Ȃ����Ɨ\�����Ă���B �@�����O���[�v�́A����DNA�������炪��ɂȂ�܂ł̉ߒ����ڍׂɉ𖾂������ƍl���Ă���B���̂P�X�e�b�v�Ƃ��āA�T�C�N����E�̉ߏ�ɂ��DNA���������זE�́A�Q�m��DNA�S�̂̔z����v�悵�Ă���B �@����������������J�j�Y�����͂����肷��قǁA���Ԃ��A������~�߂���@�̓���ɂ��Ȃ��邱�ƂɂȂ�B Med�G�b�W 2015�N7��8�� |
|
�����������p���ɐv������ ����ȂǁA�u������p�������o�Z�p���J�� |
| �@������w��w�@��w�n�E��w�n�����Ȃ̉Y�싱�Ƌ����A��B��w�a�@�ʕ{�a�@�̎O�X���m�����A�č��̍����q���������̏��ыv����C��������̌����O���[�v�́A��p���ɔ����������v���Ɍ��o����Z�p���J�������B �@�V���ɊJ�������u���C���[�W���O�����p���A�P�~�����[�g���ȉ��̔����ȓ��B��ᇂł����Ă������őI��I�ɉ�������B�������؏���p�ł͔�������̎��c�������ƂȂ��Ă���B�؏��f�[�Ŕ�������������邱�Ƃ��ł���Ǐ��Ĕ��̕p�x�����I�ɒጸ�����B���݁A�X�v���[�u������̗Տ����i�Ƃ��Ď��p�������Ɏ��g��ł���B �@�����O���[�v�́A�Q�O�P�P�N�ɊJ����������זE�Ŋ��������邽��ς��������y�f�i�K���}�|�O���^�~���g�����X�y�v�`�^�[�[�j�̊�����q���Ɍ��o�ł���u���v���[�u���J���B����A�������p�œE�o�������̂ɎU�z���ėL�������������B �@���̌��ʁA��Z�������ǂ���ȂǁA���܂��܂ȓ��B��ᇂ����点�A����܂œ���ł͕�����Ȃ�������ᇂ����������B�Ƃ��ɓ��Ǔ����̂P�~�����[�g���ȉ��̂���g�D�ɂ��L���ŁA�u���v���[�u�U�z����T�����x�őI��I�ɋ����u�����x������ꂽ�B �@���e�́A�a���f�f�ɂ�����E�o�������̂̔�������̌��o�B�܂��A�̓��g�p���z�肵�Ă���A������w�G�b�W�L���s�^�����瓊�������u���F�f��ƃ��[�J�[�̌ܗˉ���i�D�y�s�k��A�V������ܗˉ��w����Ж��ύX�j�Ƌ����ŗՏ������Ɍ��������S���������J�n����B m3.com 2015�N7��15�� |
|
iPS���Ɖu�זE�Ö@�A��t�匤���J�n �����Ƌ����A3�N���̈�t�Տ������ڎw�� |
| �@��t��w��w���t���a�@�͗����w�������ƁA���o�r�זE�i�l�H���\�����זE�j��p��������Ɖu�זE���Â̋����������J�n�����B���݁A�����w���������������Ώۂɔ�Տ����������Ă���B���i��Ë@�푍���@�\�i�o�l�c�`�j�Ƃ̋��c���n�߂Ă���A�R�N�ȓ����߂ǂɐ�t��ň�t�哱�Տ��������J�n���邱�Ƃ�������ł���B �@����w�́A�����F�̈��i���Ë@����Ƃ��Ȃ����x��Âł���u��i��Âa�v�Ƃ��āA�u�i�s���G����炪��ŕW�����Ì�̍Ĕ��\�h�v�ɑ���i�`�������L���[�s�i�m�j�s�j�Ɖu�זE�Ö@���Q�N�Ԏ��{���Ă����B �@���Ҏ��g�̌��t���̌����A�����R��ᇌ��ʂ�����Ƃ����m�j�s�זE�����o���Ċ����������A����זE�Ƃ��Ċ��҂ɓ��^����B�@�����^���L���ł��邱�Ƃ����������B�܂��A�Ĕ���������̊��҂�ΏۂɁA�m�j�s�זE����ᇂ̉h�{���ǂɒ��ړ��^�����Ƃ���A���̊��҂Ɏ�ᇂ̏k�����ʂ��݂�ꂽ�B�����A�m�j�s�זE�͌��t���ł̓����p���S�̂̂O�E�P���ȉ��ŁA���₷�ʂɂ͌��E������A���҂̏�Ԃɂ���Ă͂��܂葝���Ȃ��Ȃǂ̌��_���������B�܂��A�����S�ɏ��ł����l�͂��Ȃ������B �@�����w�������͂m�j�s�זE����A�R�����q�𗘗p�����u���o�r�|�m�j�s�זE�v�̍쐻�ɐ����B��Տ������œ������^�Ö@�̊J����i�߂Ă���B���o�r�|�m�j�s�זE�́A����ڍU�����邱�Ƃ����҂����B�u�J��Ԃ������̂��o�r�|�m�j�s�זE�𓊗^�ł���A����ɑ傫�Ȍ��ʂ�����ƍl������v�i��t��w���@�����ȁE����ᇊw�@���{���F�����j�B �@�Ɖu�w�I�Ɏ����l�����������o�r�|�m�j�s�זE�𑝂₵�ėp���邽�߁A���҂̕��S�����Ȃ��R�X�g�������B������Ō��ʂ��m�F�����A���̎�ᇂɂ��K�����g�傳���B �@����A�L�����E���S�����m�F�����̂��A�����J���Ȃ̋��āA�q�g�̓���ᇂȂǂ�ΏۂƂ����Տ����������{����B�����w����������b�������Տ����������{���A��t��w�͂��o�r�|�m�j�s�Տ������A�������̎��{���s���A�����x���`���[�ł��闝���Ɖu�Đ���w����Ǝ�����ڎw���������ȂǂɎ��g�ޗ\��B����ɑ��邉�o�r�זE�𗘗p�����Տ������͐��E���ƂȂ�B m3.com 2015�N7��17�� |
| �X�g���X�����قlj����╠�ɁA����ɂ��Ȃ���u���ǐ��������v |
| �@�X�g���X������������قǁA���ǐ��������̏Ǐ�����������₷���Ȃ�B����ɂ��Ȃ��蓾�鉊�ǂ�����������H ���ǂ����̕a�C �@�J�i�_�̃}�j�g�o��w�̌����O���[�v���ݒ��ȕ���̐�厏�A�����J���E�W���[�i���E�I�u�E�K�X�g���G���e�����W�[��2015�N�V�����ŕ����B �@�u�N���[���a�iCD�j�v�u��ᇐ��咰���iUC�j�v�Ȃǂ́u���ǐ��������iIBD�j�v�́A�������������������s���̓�a�B�����Ă����Ƒ咰����ֈڍs����ꍇ������B �@����܂ł̌�������A���ǐ��������̐l�ɂƂ��āA�X�g���X�́A�����̎��o�Ǐ�����������錴���ɂȂ�Ƃ����f�[�^�������Ă���B �@�����O���[�v�́A�X�g���X��������Ǝ��ۂ̉��ǂ̏�Ԃ���������̂��ǂ����A�����s�����B���ǂ͂���̔����Ƃ��W����ƒm����B�W�̗L���͌��߂����Ȃ��B ���ǂ������H �@�Ώێ҂͉��ǐ���������478�l�B�Ǐ��X�g���X�̒����ƌ��ւɂ�鉊�ǂ̌������Ă�������B �@�Ǐ�̓x�����ɂ��ẮA�a�C�̓��e���ƂɂR�̎w�W�Ɋ�Â��čs��ꂽ�B��ᇐ��咰���̏Ǐ�́u�}�j�g�oIBD�w�W�iMIBDI�j�v�A�N���[���a�̏Ǐ�́u�n�[�x�C�E�u���b�h�V���E�w�W�iHBI�j�v�A��ᇐ��咰���̏Ǐ�́u�p�E�G���E�^�b�N�w�W�iPTI�j�v�ŕ]�������B �@�X�g���X�̓x�����ɂ��ẮA�u�R�[�G���̎��o�X�g���X�ړx�iCPSS�j�v�ɂ���đ��肵���B �@�����̓x�����́A�ւ̒��ɑ�����Ɖ��ǂ������Ɣ���ł���^���p�N���̈��ł���u�֒��J���v���e�N�`���iFCAL�j�v�̑���l�Ŕ��f�����B�ւPg������FCAL��250��g�i�}�C�N���O�����A�}�C�N����100�����̂P�j�ȏ�ƂȂ�ƁA���ǂ������ł���Ɣ��f�����B �@����ꂽ�f�[�^����ɂ��ē��v�w�I�ɉ�͂��s���A�����A�X�g���X�̓x�����A�Ǐ�̋����̊ԂŊ֘A����]�������B ���ڂ͂Ȃ��炸 �@�������X�g���X�̓x������������ƁA�N���[���a�A��ᇐ��咰���Ƃ��ɏǏ�͋����Ȃ��Ă����B�X�g���X�̎ړx�ł���CPSS���P�|�C���g��������ƁA���ǐ��������̏Ǐ�̋����͂V���قLj������Ă����B �@����ŁA�X�g���X�̓N���[���a�A��ᇐ��咰���Ƃ��ɁA���ǂ̓x�����ɂ͉e�����Ă��Ȃ������B �@�܂��A���ǐ��������̏Ǐ����ꍇ�iMIBDI���R�ȉ��j�͋����Ȃ��ꍇ�ɔ�ׂāA��ᇐ��咰���̉��ǂɂ��Ă̓��X�N��3.94�{�قǍ��������B�N���[���a�̉��ǂ́A�Ǐ�̋����ɂ͊W���Ă��Ȃ������B ������ɂ��撍�ӂ� �@����̌��ɂ��A�X�g���X������������قǁA���ǐ��������̏Ǐ�����������₷���Ȃ邪�A���ۂ̉��ǂ����܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��悤���ƕ��������B �@���ǂɂ���āA�ǏN�����Ă������ŁA�X�g���X���܂��قȂ�d�g�݂œ����B����ɒ����ɂ킽�钲�����K�v�ƌ����O���[�v�͕t��������B �@������ɂ���X�g���X�͏Ǐ�̂��ƁB���ӂ͕K�v�ƌ����������B Med�G�b�W 2015�N7��18�� |
|
�u����̐��Ҏҁv����w�ԁu����l�v�̋��ʓ_ �w�����R�Ɏ��鐶�����x����t�Ƃ��ēǂ�� |
| ���{�T�F��t�A��w���m�@��Ñ��k�E�F�u�T�C�g�ue�|�N���j�b�N�v�ihttp://www.e-clinic21.or.jp/�j���^�c���� �@����Ƃ����̂́A����ȕa�C�ł��B �@�ق��̕a�C�ƌ���I�ɈႤ�_�́A�u�������v�����҂����l�ЂƂ�ɂ���ĈقȂ邱�Ƃł��B�������A�K�C�h���C���ɉ������W�����Â͑��݂��܂��B����������ȏ�Ɂu���҂��S�ɕ����Ă�����v�ɂ܂œ��ݍ��ޕK�v�����邱�Ƃ������̂ł��B�����������ƁA�S�̎����悤�ŁA����y�[�X���x�����������Ȃ�܂��B �@�w�����R�Ɏ��鐶�����x�i�P���[�E�^�[�i�[���^�v���W�f���g�Ёj�ɂ́A��w�I�E�Ȋw�I�ɂ͐����̂��ɂ������I�Ȋ����̎��Ⴊ�u��E��������v�Ƒ��̂��āA�������o�ꂵ�Ă��܂��B �@�����g���A�{���ɋ������Ă����悤�ȁu��E��������v��ڂɂ������Ƃ͑��X����܂��B���܂ŁA�̂ז�4000���̂��҂���̈�Ñ��k�ɉ����Ă��܂������A�̊��ł͔N��4�`5��A��E��������ɐڂ����ƋL�����Ă��܂��B �u�m��Ȃ��Ԃɂ��������v�Ƃ����l�� �@�������ۂɊ��҂���ɐڂ�����́A�傫��2�̃O���[�v�ɕ������܂��B �@�܂��́A����V�l�����{�݂ɓ������̂��҂���̏ꍇ�ł��B �@�N����d�˂Ă��銳�҂���̏ꍇ�A���Ȃ��Ƀ��X�����邾���ŁA�����ȕ��S�ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B �@���̂��߁A��p���\�Ȕ͈͂ł����Ă��A�{�l�₲�Ƒ��Ƙb�������A�ϋɓI�Ȏ�p�ɂ͒��킹���A�����Č���邱�Ƃ�����܂��B �@�u��p�ɒ��܂��A�o�߂������v�Ƃ����I���ɁA���{�l���z�b�Ƃ���镔��������̂ł��傤���B�����������̒��ɂ́u�Ȃ�������������Ȃ��Ȃ��Ă����v�A�������́u�i�s���Ȃ�����Ɛ��N�ԋ������āA�V���ŖS���Ȃ����v�Ƃ������Ƃ��悭����܂��B �@�����Ƃ��A���̘V�l�����{�݂́u�H�{���v��^�������H���Ă��܂��B�����̓w�͂��A����זE�̏��ł�A���}�~�ɁA����t���Ă���̂�������܂���B �@����ŁA���̖{�́u9�̎��H���ځv�ɑ�������悤�Ȏ����ɗ��ӂ������A�؏���p�����Ă��Ȃ��̂Ɂu���m��Ȃ��Ԃɏ������v�Ƃ����l�����ɂ����ڂɂ�����܂��B�������u��E��������v�ł��B �@���͂����́u��E��������v�ɂ́A���ʂ������R���A�K���ƌ����Ă悢�قǑ��݂��Ă���Ɗ����Ă��܂��B 3�厡�Ấu���ԉ҂��v�ɂ����Ȃ� �@�������́A�ue�|�N���j�b�N�v�Ƃ����E�F�u�T�C�g��ŁA���X�ʂ̑��k���t���Ă��܂��B���̂��߁A��x���k�ɏ�������Ƃ̂�������u�T�o�C�o�[�v�i����̐��Ҏҁj�ƂȂ�A�A�����������邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B���́A�T�o�C�o�[�̕������A����Ƃ��܂��t�������R�c��m���Ă��܂��B �@���͔ނ�Ɛڂ��Ȃ���A���̂悤�Ȗ₢�������悭�J��Ԃ��Ă��܂��B �@�u������l�Ǝ���Ȃ��l�Ƃ̌���I�ȈႢ�́H�v�ƁB �@��͂�u�l������ς����v�u�H����ς����v�Ƃ����Ⴂ���A�悭�������܂��B�܂�A�u���܂ł̂܂܂ł͑ʖځv�Ƃ������ƂȂ̂ł��B���܂ł̎������X�g���X�������A�a�C�ɂȂ����킯�Ȃ̂ł�����A�ϋɓI�Ɋ��҂��u�������g�v��ς���K�v������̂ł��B �@�܂��͐H������ς��邱�Ƃ���n�߁A��◷�s�A�������A�l�Ƃ̂��t�������̎d���܂ŁB��̓I�Ȃ��Ƃ�ς���ƁA�u�l�����v�͑傫���ω����A����܂łɕ��ׂƂ��Ă������Ă����X�g���X�����炷���Ƃɂ��Ȃ���̂ł��B�����āA�ǂ����Ă��u���ԉ҂��v���K�v�ȏꍇ�ɂ́A�����3�厡�Ái���m��w�j�����ɗ��p����悢�̂ł��B �@���������A3�厡�ÂƂ͖��\�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�u���ԉ҂��v�ɂ����Ȃ����Ƃ𗝉����Ă����K�v������܂��B3�厡�ẤA�قƂ�ǂ��Ώǎ��Âł��B����ɂ͑Ώǎ��Â����łȂ����{���Â��s���ł��B �@����̍��{���ÂƂ́A���Ȃ킿���g�̎��Ȏ����͂����߂āA����̕a���ɑł������ƁB���̂��߂ɂ�3�厡�ÂƂ͕ʂɂǂ����Ă����Ȏ����͂����߂��i���s���ƂȂ�܂��B���܂ł̐�������ߓx�ȃX�g���X���A���Ȏ����͂�ቺ�����A������������̂ł�����A���܂ł̐�������l������ς��邱�Ƃ���ł��B �@�������͎��Ȏ����͂�L�ӂɍ��߂邽�߁A���҂���ɒ���w�i�C���A�����j�Ȃǂ̕⊮��֗Ö@�����߂Ă��܂��B�������A3�厡�Â��Ȃ��ɔے肷��킯�ł͂���܂���B���Ɋ��p����Δ��ɗL�p�ł��B �@�������Ȃ���A�厡��̌����Ȃ��3�厡�Â���̂ł͂Ȃ��A�K�����ɏq�ׂ�2�_����������Ɖ������ė~�����̂ł��B �@1�_�ڂ́A�u��낤�Ƃ��鎡�Ö@�̖ړI�v�u�����b�g�ƃ��X�N�v�u���Â̍����v�u��ֈĂ̗L���v��S����ɐu���Ă������Ƃł��B �@�܂��ڎw���Ƃ��낪�u�����v���u���X���鉄�����Áv���A�͂��܂��u�@�\�v�u�ɘa���Áv���A�u�`����̃A���o�C���Áv�����A�m���߂Ă����܂��傤�B �@2�_�ڂ́A�u���������\���ǂ����v���m�F���Ă������Ƃł��B���≢�Ăł͕W�����Â���ɂ��Ȃ�����A�R����܂̓��^�ʂ����������ȂǁA�l�ɍ��������Â��s���Ă��܂��B���̂悤�ȏ��܂߂Ȕz�������Ă���邩�ǂ������ŏ��ɐu���Ă��������Ƃ���ł��B ��t�Ɗ��҂ňقȂ�u����v�̈Ӗ����� �@�����Ċ��҂���́u����v�Ƃ������ƂɊւ��āA�������F�����Ăق����Ǝv���܂��B �@���́u����v�Ƃ������t�́A��t�T�C�h�Ɗ��҃T�C�h�ŁA�傫�ȍ�������̂ł��B �@�����̊��҂���ɂƂ��āu����v�́u���C�Œ���������v���Ƃł���͂��ł��B �@�������A���Ƃ��R����܂��肪�����t���猩���ꍇ�A�R����܂ɂ���Ă���50���ȏ�k���������Ԃ��Œ�4�T�Ԃ���A�u���ʂ���v�ƔF�߂��܂��B �@�ɒ[�Ȃ��Ƃ������A���҂���̂���50���ȏ㏬�����Ȃ��āA�R������Â�4�T�Ԍ�ɖS���Ȃ����Ƃ��Ă��B��t���炷��ƁA���̃P�[�X�́u�R����܂͌������v�A�����āu�R����܂ɂ���Ă��������v�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��B����́A���҂���ɂƂ��Ắu�����v�Ƃ́A���Ȃ肩�����ꂽ�C���[�W�ł͂Ȃ��ł��傤���B �@��Â̌���ɂ����ẮA���҂���ƈ�t�̔F���̊ԂɁA���̂悤�Ș�������������܂��B �@�����ē˂��l�߂čl����ƁA�D�G�Ȉ�t���Ő�[�̈�Â����p���Ă��A�u�����v���Ƃ��ł��Ȃ��a�����Ȃ��炸����܂��B �@�����g�A�Ⴂ���͔]�O�Ȃ̓���I��Ŕ]�O�Ȃ̃X�y�V�����X�g��ڎw���܂����B�Ƃ��낪�ǂꂾ���Z��s�����Ă��A���������l���v���悤�ɂ͎����Ȃ��̂ł��B�]�O�Ȉゾ���������A�u��ÂƂ͉��̂��߂ɂ��邩�H�v�Ƃ������{�I�Ȗ₢�Ɏ������g���������Ȃ��Ȃ�A��Â̍őO������u�~���v���Ƃɂ��܂����B�����āA���҂���̊����Ɍ��炸�A�l�i�����܂߂��S�̂𑨂�������ւƍl�������V�t�g���܂����B����ƁA��������i�������Ă����̂ł��B�T�o�C�o�[��ڂ̓�����ɂ����Ƃ��A���͔ނ炩�瑽���Ɋw�Ԃׂ����ƋC�t�����̂ł��B �@��ʓI�Ȉ�Â̌���ł́A�W�����ÈȊO�Ŏ��������҂���i�u��E��������v�j�́u��O�v�Ƃ���A�u�Ȃ��������̂��v�Ƃ����_�Ɋւ��Ă͂܂������S��������Ȃ��Ȃ�܂��B����͔��ɂ��������Ȃ����Ƃł��B �@�{���I�Ȃ��Ƃ������A���Ƃ��u��O�v�ł���������͂��ł��B�u��O�v�Ƃ������b�e����\��̂Ȃ�A���́u��O�v�̎���𑝂₹�悢�̂ł��B�ǂ�������u��O�v�������邩�A�ǂ̂悤�Ȃ��ƂŁu��O�v�������邩�A�{���̂悤�ɋ��ʍ���T���āA�L����ʂɍL�߂�悢�̂ł��B �@�u��O�v�ƂȂ�m�����オ�邱�Ƃɂ́A�{���ɂ������悤�ȃ��K��ċz�@�A�H�����̉��P�ȂǁA���܂��܂ȗv�f������܂��B �@�������́A�Ƃ��ɃT�o�C�o�[���܂ނ���̊��҉�̊F����Ƌ��Ɋ������Ă��܂��B���ǂ̂Ƃ���A�{���ɂ���悤�ȁu�����Ă���l������v�Ƃ������������A���҂���̒��ړI�ȗ�݂ƂȂ邩��ł��B �@�T�o�C�o�[���C�y�ɏ��M������A�N�����A�N�Z�X�ł���E�F�u��̃V�X�e����A���A���ȃR�~���j�e�B�[���e�n�ɂł���A����ɑ���C���[�W���ς���Ă���Ǝv���܂��B �� �{�e�ŏЉ�Ă���w�����R�Ɏ��鐶�����x����i�P���[�E�^�[�i�[���j�̃E�F�u�T�C�g�ihttp://www.radicalremission.com/�j�ł́A���I�Ȋ����i�����R�Ɋ���������i�s���Ȃ���j�ɂ��āA�N�ł����e�E���J�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B �� ���{�T�i�������ƁE�䂽���j ��t�A��w���m�B1957�N���܂�A����w��w���A����w�@��w�����ƁB�����ȁAICU�̌��C���o�Ĕ]�O�Ȑ���ɂȂ�A�����]��ᇂ̎��ÂɎ��g�ށB�זE�H�w�Z���^�[�ł���̖Ɖu�Ö@�A��`�q���Â̌������s���B���̌�A���݂̈�ÁE��w�ɋ^��������A���Ԃ̈�t�����Ɓu21���I�̈�ÁE��w���l�����v��ݗ��B 2001�N����A�{���ʼn������Ñ��k�E�F�u�T�C�g�ue�|�N���j�b�N�v�ihttp://www.e-clinic21.or.jp/�j���^�c����B President ONLINE 2015�N7��18�� |
|
����I�ȃ}�����O������������́u�ߏ�f�f�v�ɂȂ���\�� �X�N���[�j���O�Ŏ��S���ɗL�Ӎ��Ȃ� |
| �@�}�����O�����ɂ�����I�ȓ�����X�N���[�j���O���u�ߏ�f�f�v�̌����ƂȂ�A�ꕔ�̏������s�K�v�Ȏ��Â��Ă���\���̂��邱�Ƃ��A�ăn�[�o�[�h��w����у_�[�g�}�X��w�ɂ�錤���Ŏ�����A�uJAMA Internal Medicine�v7��6�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@���̒m���ɑ��A�č�����iACS�j��Richard Wender���́A�}�����O�����̕K�v���ɋ^�����������������邱�ƂɌ��O�������Ă���B�����ɂ��ƁA����܂ł̌����ł̓}�����O�����ɂ����40�Έȏ�̏����̓�����ɂ�鎀�S�������Ȃ��Ƃ�20���ጸ���邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă���A���̌��ʂɂ��Ă͋c�_�̗]�n�͂Ȃ��Ƃ����B �@����A�ă_�i�E�t�@�[�o�[�������i�{�X�g���j��Harold Burstein���́A�����鏗�������N�}�����O��������K�v������Ɣ��˓I�Ɍ��߂���O�ɁA�}�����O�����ɂ���Ăł��邱�ƂƂł��Ȃ����Ƃɂ��āA�c�_�𑱂���]�n������Ǝw�E����B�ă��V���g����w�i�V�A�g���j��Joann Elmore���́A����̒m������A�댯�ȓ�����Ƒ����Ɏ��Â���K�v�̂Ȃ����B��ᇂ�����ɐ��m�ɋ�ʂ��邽�߂̌����̕K�v������������ɂ��ꂽ�Əq�ׂĂ���B �@����̌����ł́A�č����������iNCI�j���Ǘ�����SEER�iSurveillance, Epidemiology and End Results�j����o�^���p���āA547�S�ɋ��Z����40�Έȏ�̏���1,600���l�̈�Ãf�[�^�ׂ��B���̂���2000�N�ɓ�����Ɛf�f���ꂽ5��3,207�l��10�N�ԒǐՂ��A�e�S�̃}�����O�������{���ƁA2000�N���_�ł̓����Ǘ�����ђǐՊ��Ԓ��̓�����ɂ�鎀�S�����r�����B �@���̌��ʁA�X�N���[�j���O�̎��{����10����������ƁA������̐f�f�����S�̂�16���������A2 cm�ȉ��̏����Ȏ�ᇂ̐f�f����25�����������B�������A������Ŏ��S���鏗���̐��ɂ͗L�ӂȒጸ�͔F�߂��Ȃ������B �@���̌����ł́A�ŋ�2�N�ȓ��Ƀ}�����O�����������������ɒ��ڂ��A3�`4�N�����ɎĂ���l��S���Ă��Ȃ��l��Ώۂɂ��Ă��Ȃ����߁A���ꂪ���ʂɉe���������炵���\���������Burstein���͎w�E����B�܂��A�ǐՊ��Ԃ̒������\���Ƃ͂������A�����Ȏ�ᇂɂ��Ă�15�`20�N�o�߂��Ȃ��Ǝ��S���ւ̉e�����\��Ȃ����Ƃ������Wender���͂����B�܂��A���̌����͑�K�͂ȃf�[�^�Z�b�g�Ɋ�Â����̂ł���A�X�̊��҂Ɋւ�����͂��܂蓾���Ȃ��ƁABurstein���͏q�ׂĂ���B m3.com 2015�N7��21�� |
| ��҂̂��m���u��ÂɎ����v�Ƒ����ɂ��� |
| �@��������m���ꂽ�ꍇ�A���҂���S���I�V���b�N�͑傫���B�N�ł��C�������œ����Ă��܂����Ƃ��낤�B �@���m���A��p������̊��҂̐S���I�Ή��ɁA���̌�̎����̏�Ԃ��傫���ւ���Ă���Ƃ�������������B���Ƃ�����̏p���Ԃ������ꍇ�A�ǂ���̑ԓx���u�������v����̂��낤���B a.��ÂɎ���� b.�i����ł��邱�Ƃ��j�۔F���A�{�� �@���{�l���҂�a�̑ԓx�����A��t�ɏ]���ɂȂ�B�������A�����䖝�łȂ���Β���������̂�b�炵���B �@���������w�@�̎R���������́Aa�̂悤�ȑԓx�����A��t�̌����Ƃ���̒����̗]���ɂȂ�P�[�X�������̂ł͂Ȃ����Ƌ^���悷�B �u�������͈�t���̂��l�Ǝv���Ă���̂ŁA�]���ɂȂ肪���B�ł��]���͒N�ɂ��킩��Ȃ��B��t�Ɉˑ������A��{���y��\�o����^�C�v�̐l�����������B���������l�𑽂����Ă��܂������A�������̍D�Ⴉ������܂���v �@�R�������͎�̓I�ɂ���ƌ��������A��t�̗]���鍐��傫�������Đ��͓I�ɍu���⎷�M���s���Ă���B �@�u2009�N4���ɑ咰��������A���łɊ̑��ɓ]�ڂ��Ă��܂����B��t�̍��m�͒W�X�Ƃ��Ă��āA���̊��������MRI�̉�ʂ����Ȃ���b���B���҂̐S��Ɋ��Y��Ȃ��ԓx�ɁA���]���܂����B �@�܂��咰������܂����B����3�J���`���N��Ɋ̑��̂����؏�����\��ł������A�咰����̎�p�̂Ƃ��ɖ�̕���p�������āA�A�����M�[�������ܐ��̉��ȂǂŎ��ɂ����܂����B����Ȃ̂ɁA�厡��́w��p�͑听���x�ƌ����B�{�肪���ݏグ�Ă��܂����B���ɂ����Ă���̂ɁA�����听�����ƁB �@�ł��A�������킸�ɉ䖝�����B����ƏǏ�͂܂��܂������Ȃ����B���������Ƃ��ɓ{���\�o����l�����������ł��ˁB����ɋC�Â��A��̕���p�������Ċ̑�����̎�p�ɓ��ݐ�܂���ł����B�R����܂��g��Ȃ��A���ː����Â��Ȃ��A������W�����Â����Ȃ�����I�����܂����B�w1�N��ɂ͎��ɂ܂���x�ƈ�t�͌������B�W�X�Ƃ������̂ł��B���̌�A��ֈ�Â�F��A�H����^���ɒ��ӂ���Ȃǂ��āA���ł������Ă���B����͏������傫���Ȃ��Ă��܂����A��t�̃o�C�I���W�J���Ȍ����Ăǂ���ɂ͂����Ȃ��B�ЂƂ̖��͕s�v�c�ł��v �@�����������̌�������A�R�������͂��҂̋C�����̂�����ɋ������������Ƃ����B 1�Ԓ����������͓̂����S�����l �u�C�M���X�̑�w�a�@�̃L���O�X�E�J���b�W�Ƃ����Ƃ���ŁA�����҂̋C�����̎������������ɂǂ��e�����邩�ׂ��f�[�^������܂��B�����Ǐ�̊��҂ɁA�p��3�J���̐S����Ԃ��m�F����ƁA�傫��4�ʂ�ɕ�����܂����B �E��]���Ă���l �E��ÂɎ�e����l �E�i����ł��邱�Ƃ��j�۔F����l �E�����S�����l �@�����������ނ����āA13�N��܂ŒǐՒ����������B �@1�Ԓ����������͓̂����S�����l�ł����B����Ȃɕ����Ȃ��Ǝv�����l�B2�Ԗڂ��۔F����l�B��t���Ԉ���Ă���A���͂���Ȃ��Ǝv���悤�Ȑl�ł��B���{�l�ɂ͗�ÂɎ�e���悤�Ƃ���l�������̂ł����A��������Ƃ��Ƒ������ɂ܂��B��]���Ă���l���A����������ł��܂���B �@����͎����̐�������������́B����܂ł̎����̐��������X�g���X�ɂȂ��Ă��������B��p�͂܂������A�R����܂���ː����ÂȂǎ����̑̂̑��ݎ��̂��������ď����邱�Ƃ��A���͂�߂��B�������������l�������Ă��āA�Ƃ����ԓx�ł��B���̑���A�̂̎����̐������Ɛ키�B����̌����ɂȂ����X�g���b�T�[��r�����āA�₳�������J�ɐ�������B���̐����������ɂ͍����Ă����悤�Ɏv���܂��v �@���v�ɂ��A���{�l��2�l��1�l�͂Ȃ�炩�̂���ɂȂ�Ƃ����B���m�ɂǂ��S���\���邩�A�����đ��l���ł͂Ȃ��B�C�����̑O�������ɁA����̐i�s����������̂ł���B �@����͐l���ɂ�����ő勉�̃s���`���B�������A����܂ł̈�����f����A�V���ȃ��C�t�X�^�C�����m�������`�����X�ł�����̂��B President ONLINE 2015�N7��22�� |
|
���f�͐l�H�m�\�ŁI Deep Learning��������ᇂ��������Ȃ� |
| �@���f����Ȃ�A�l�H�m�\�������a�@�ɍs���ׂ����B�l�H�m�\�����f�ɉ��p���邱�ƂŁA������ᇂ������x�Ō����o���Z�p�̊J�����i��ł���B���f�B�J���C���[�W��Deep Learning�̎�@�ʼn�͂���ƁA�n��������t��萳�m�ɂ���g�D�Ȃǂ̕a�ς������o���B�l�H�m�\�̐i�����A�����̐l�����~���Ɗ��҂���Ă���B �C���[�W�f�[�^����a�C�� �@Deep Learning�ŁA�C���[�W��͐��x������I�ɐi�����Ă���B�T���t�����V�X�R�ɋ��_��u���x���`���[���Enlitic�́ADeep Learning����Ãf�[�^�ɉ��p�����V�X�e�����J�����Ă���B�C���[�W�f�[�^��Deep Learning�̎�@�ʼn�͂��A�a�C�肷��B�C���[�W�f�[�^�ɂ̓����g�Q���ʐ^�AMRI�ACT�X�L�����A�������ʐ^�Ȃǂ��g����B�������ʂɈ�����ᇂȂǂ����邩�ǂ����������ɂ����m�ɔ��肷��B �@Enlitic�̓C���[�W��͂̋Z�@�ɂ��āA���Ƃ̍����ɂ������Ƃ��Č��J���Ă��Ȃ��BTED�ł̍u�������Ȃǂ���ɑz������ƁA���̗֊s�������яオ��B�܂���͂��s���O�ɁA��ʂ̃C���[�W�f�[�^���g���ăV�X�e�������炷��B��̎ʐ^�����̃v���Z�X�ŁA�V�X�e����5�N�o�ߌ�ɑ��݂��Ă��銳�҂̃f�[�^�ƁA5�N�ȓ��Ɏ��S�������҂̃f�[�^����͂���B5�N�������i5�N�o�ߌ�ɐ������Ă��銳�҂̔䗦�j��\������V�X�e�������炵�Ă���̂��B �@�����Ŏg���Ă���f�[�^�͕a���W�{�i�l�̂���̎悵�����́j�ŁA�g�D�̌������ʐ^�������Ă���B�V�X�e���͓��̓C���[�W����l�X�ȓ������w�K����BEnlitic����`��������Ƃ́A�g�D�\���̓����������B��̓I�ɂ́A�g�D�\�ʂƍזE�̊W��A�זE�Ƃ������芪�������̊W�ȂǁA���̂̑g�D�\�����w���B�V�X�e���́ADeep Learning�̎�@�ł����\���������w�ԁB�w�K�����������V�X�e���ɁA�팱�҂̑g�D�C���[�W����͂���ƁA5�N���������Z�肷��B �@�܂��A�������̔팱�҂̑g�D�C���[�W�̒�����A������ᇂȂǖ��̌�����肷��B�܂�A�V�X�e���͑g�D�\���̓�������A������ᇂȂǂ�T���o�����Ƃ��ł���B���܂ł͐��オ�ڎ��ŒT���Ă������A�\�t�g�E�G�A�������x�ł����̌�����肷��B �l�H�m�\�̋Z�@����Âɉ��p���� �@Enlitic�n�ݎ҂�CEO��Jeremy Howard�́ATED�ł̍u����C���^�r���[�ŁA�l�H�m�\�ɂ��Č������q�ׂĂ���BHoward��Enlitic��n�݂���O�ɂ́AKaggle�ŎВ����C�����BKaggle�Ƃ̓f�[�^�T�C�G���X�̃x���`���[��ƂŁA��ƌ����ɋ������͂Ȃǂ̃T�[�r�X�����BHoward��2014�N��Enlitic��n�݂��A�f�[�^�T�C�G���X�̋Z�@����Âɉ��p���錤����i�߂Ă���B �@Deep Learning�̃C���[�W�p�^�[����c�����鍂���\�͂���Âɉ��p���邱�ƂŁA�O�̗̈�Ō������i��ł���BRadiology�i���ː���w�j�ł́A�����g�Q���ʐ^��MRI��CT�X�L�����ő̓��̑g�D��c������B�C���[�W�f�[�^�����ᇓ�������͂��A��`�q���Ƒg�ݍ��킹�f�f����BPathology�i�a���w�j�ł́A�l�̑g�D���ώ@����B�g�D�̌������ʐ^�̃C���[�W����͂���BDermatology�i�畆�Ȋw�j�ł́A�畆�̎ʐ^����Ǐ�肷��B�����O�̕����Deep Learning�����p�����V�X�e���̊J�����i��ł���B�l�Ԃ����������肪�ł���܂łɂ͎��Ԃ������邪�A�R���s���[�^�[�͒Z���Ԃł�����w�K����B �@���̎�@�́A2011�N��Stanford Medicine�i�X�^���t�H�[�h��w��w���j�ŊJ�����ꂽ�BComputational Pathologist�iC-Path�j�ƌĂ�A�}�V�����@�B�w�K�̎�@�ł���g�D�����ʂ���B������̎��ʂɓK�p����AC-Path�͍זE������6642��ނɕ��͂���BC-Path�����炵�āA�팱�҂̑g�D�C���[�W����͂���ƁA����זE�����o����B BPnet 2015�N8��5�� |
|
����f�ÁA ���s�s�Ȏ{�݊i�� �G�r�f���X���m�ł��ی��K�p���ꂸ�A���҂��s���v |
| �n�Ӌ��i�l���I���R���W�[�Z���^�[�@���j �@����f�Â̋�迉��i����Ăj������ċv�����B��迉��Ƃ́u�����ɉ��b�◘�v���s���n��悤�ɂ��邱�Ɓv�B�܂�A����̐f�f�A���Âɂ��āA�n��ɂ��Ⴂ�A�a�@�ɂ��Ⴂ���Ȃ��悤�Ɏ��͂��炢�܂��傤�A�Ƃ����w�͖ڕW�ł���B �@�K�C�h���C���̕��y��W���I���Â̍l���������y���������A�ւ����Ȉ�ǃ��W�����͉A����߂��B�܂��A���Ă͔��i�Ύ��ӂō������g���Ă���������̂ւ�����DMpC�Ƃ��������W�������M��҂�����Ɍ������Ă����B�������A�n��A�a�@�A�{�݂ɂ���āA�u�ی��������Ȃ�����v�Ƃ������R�łւ����Ȃ��Ƃ�����Ă���Ƃ��������B �@��w�a�@�Őf�Ă�����Ă���Ĕ�������̕o�O�����������E���p���厡�ォ�炷���߂�ꂽ�A�Ƃ������ƂŁA�Z�J���h�I�s�j�I�����ɗ����B �@�����E���p�̓z���������̂���o�O������ł́A�Ӗ��̂��鎡�Î�i�ł���Ƃ͎v���̂����A���̏����̏ꍇ�A���R�������������肨�������B�t���x�X�g�����g��A���}�^�[�[�j�Q�܁A�G�L�Z���X�^���{�A�t�B�j�g�[���́A�o��łȂ��Ǝg�p�ł��Ȃ��̂ŗ����E�o��p������A�Ƃ����̂��B���ہA���̌��ł́A�o�O�����ŁALHRH�A�S�j�X�g�ɃA���}�^�[�[�j�Q�܂p���邱�Ƃ͕ی��ŔF�߂��Ȃ��Ƃ����B �@�É����́A���̈Ӌ`�𐳂����F�߂Ă���A�ی��ł��K�ɑΉ�����Ă���B���NEJM�ɘ_�����ł��t���x�X�g�����g�Ƀp���{�T�C�N���u���������PFS����������A�Ƃ����������ʂ��A�o�O�̏ꍇ�́ALHRH�A�S�j�X�g�ƃt���x�X�g�����g�p����ƂȂ��Ă���A����ꂽ���ʂ��A�u�o�O�Ǘ�ł́A�͂��߂Ă�PFS�������ʁv�ƂȂ��Ă���B�܂��ASOFT�g���C�A���ATEXT�g���C�A���ł��A�o�O�ɃA���}�^�[�[�j�Q�܂��g�p���邱�Ƃ̗L�p����������Ă���B �@���̂悤�ɁA��������l����Γ�����O�̂��ƁA�����ăG�r�f���X�����m�ɂ��߂���Ă��Ƃ��A�ی��ł͔F�߂��Ȃ�����Ɗ��҂��s���v�����Ă���̂��B �@����͂����������낤�B m3.com 2015�N8��5�� |
|
�u�}�C�N��DNA�v�Ƃ����f�ЁA����̖ڈ�ɂȂ邩������Ȃ� ���܂��܂ȍזE�ɌŗL�̃}�C�N��DNA���ł��� |
| �@��`��������DNA�B���̒f�Ђł���u�}�C�N��DNA�v�ƌĂ���Ԃ����������O���[�v���A���x�̓}�C�N��DNA�����Ƃ��Ƃ̍זE���ƂɈقȂ�ŗL�̓��������Ɗm�F�����B �@����זE�̖ڈ�ɂȂ邩������Ȃ��B �G���[�ŏo�Ă��� �@�č��o�[�W�j�A��w��w�����܂ތ����O���[�v���A�����w�̗L�͎��Z���E���|�[�c��2015�N�U�����ŕ����B �@DNA�͂S��ނ��琬�鉖��ƌĂ�镪�q���Ȃ����Ăł��Ă���B�}�C�N��DNA�͐��N�O�ɔ������ꂽ�Z��400�������DNA���B�זE�̒���DNA���܂Ƃ߂Ă���u���F�́v�̊O�ɑ��݂��Ă���B�u�i�����O�j�v�̌`�ɂȂ��Ă���̂��������B �@�}�C�N��DNA�́ADNA�����`��R�s�[�����Ƃ��ɃG���[���������Đ��������B ���͌ł����������ꏊ �@�����O���[�v�́A�l�Ԃ̂��܂��܂Ȃ���זE����}�C�N��DNA�́B����זE���Ƃɓ���̃p�^�[�������Ɣ��������B �@����ɁA���܂��܂�DNA�C���@�\�Ɉُ�̂���j���g���̍זE�̃}�C�N��DNA�����BDNA�C���@�\�̒��ł����Ɂu�~�X�}�b�`�C���v�ƌĂ�鉖��̊ԈႢ���C������@�\�Ɋ֘A����Ɠ˂��~�߂��B �@�}�C�N��DNA�́ADNA�̒��ł��]�ʊ����������ȕ����Ŕ������Ă���B�s�����ȕ����ł͔������Ȃ����A����̒��ł��u�O�A�j���v�Ɓu�V�g�V���v�Ƃ����Q��ނ̉���ł������Ă���uGC����v�ƌĂ�镔���͌������ł����ɂȂ�₷���BDNA����^���p�N��������Ă���A���̊Ԃɂ�������RNA�ɓ]�ʂ���Ă���A���̂Ƃ��ɃG���[���������₷���B �@�}�C�N��DNA�͓��ɂ��̂悤�ȕ����Ő��������B �}�C�N��DNA�������Ɨv���ӂ� �@DNA�C���@�\�̑���������ƁA�咰����Ȃǂ̂���ɂȂ�₷�����A����זE�͈�`�q�̕ψق⑹���������߂Ƀ}�C�N��DNA�̐��������Ȃ�B�܂��ł��Ă���ꏊ�ł�����������̂ŁA�ǂ��̂��������Ă���\��������B �@�����ڈ�ł���u�o�C�I�}�[�J�[�v�Ƃ��ė��p�ł���\�������҂����B Med�G�b�W 2015�N8��10�� |
|
���E�����{��p�AICV�i����Ö��j����ᇌ���t���Ły�č���A��Ȋw��z ���x��3�����őS�ᐶ���A�J����p�̈ڍs�Ȃ� |
| �@�č���A��Ȋw��iAUA�j��7��29���A���x��3�̉���Ö�����ᇌ��������{�b�g�ŏ��������Ǘ�ɂ��ďЉ���B���E�ŏ��߂Đ��������Ǘ�ŁAThe Journal of Urology���Ɍf�ځB �@�]���̉���Ö�����ᇌ����͊J����p����{�����A����̃��{�b�g�O�Ȏ�p�ł́A7�ӏ��̏��؊J��4��ނ̃��{�b�g���݂̂��g�p���Ď��{�B���x��3�̉���Ö�����ᇌ�����L����t��������9�l�����{�b�g�O�Ȏ��Â����B�p���7�J���̒ǐՒ����ł́A9�l�S���������B8�l�ɂ͍Ĕ��̒���͂Ȃ��������A1�l���Ґ���ᇂł��̌�Ď�p�����{���Ă����B �@��J���t�H���j�A��w��A��ȁi���T���[���X�j��Inderbir S. Gill���́A�u�J����p�ւ̈ڍs�⎀�S����Ȃ��K�v�ȑS��Z�����s��������̃��{�b�g��p�̌����I�Ȏ��т́A���ꂩ��̐t���A��Ö��A�̑��ɂ����郍�{�b�g��p�ւ̖�˂��J�����v�Əq�ׂ�ƂƂ��ɁA�u�܂������i�K�ł͂��邪�A���{�b�g�ɂ�鉺��Ö�����ᇌ���؏��͏����ւ̑傫�ȉ\��������v�Ɗ��Ҋ��������Ă���B m3.com 2015�N8��12�� |
| ���Â̂��߂̃f�[�^�����A���^�C���Ŏ擾�ł��鏬�^�̐����w�Z���T�[ |
| �@���E����1�N�Ԃ�800���l���S���Ȃ�u����v�̑R��i�Ƃ��Ă͉��w�Ö@�E���ː��Ö@�Ȃǂ�����܂����A�����������Â��ǂꂮ�炢���ʓI�ɂł��Ă��邩�����A���^�C���ɑ���\�ȃZ���T�[��MIT�̃R�b�z���������J�����܂����B �@�����̓s���Z�b�g�̐�ł܂߂邮�炢�̃T�C�Y�B �@���Âɂ����āAMRI(���C���摜)�₻�̑��̃X�L�����Z�p��p���邱�ƂŁu��ᇂ̃T�C�Y�����݂ǂꂮ�炢�Ȃ̂��v���m�F���邱�Ƃ͍��ł��ł��܂����A���Â��ǂ̒��x���܂������Ă���̂���m��ɂ͐����ɑ傫�������Ă���̂�����B���w�Ö@�E���ː��Ö@�Ƃ��u���ꂮ�炢�Ō����v�Ƃ����ŏ��ʂ��킩��Ȃ����߁A�m���Ɍ������x���̎��Â�����ƁA�傫�ȕ���p���o�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�����Ŗ��ɗ��̂��A���̏��^�̐����w�Z���T�[�ł��B����̐��̑g�D����(����)���ɑ̓��ɖ��ߍ��ނ��ƂŁA���҂̃f�[�^�����A���^�C���Ń��j�^�����O�ł���悤�ɂȂ�A���w�Ö@����ː��Ö@�ł��ꂼ��̏ɉ������K�Ȏ��Â����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�̂ŁA����p���ŏ����ɗ}���邱�Ƃ��ł��܂��B �@�Ȃ��A��Ƃ��Ă��Âɗp�����邱�Ƃ��z�肳��Ă��܂����A�Ⴆ�Βr��ňقȂ�ꏊ��pH�l��n���_�f�ʂׂ�Ȃǂ̊����j�^�����O�ɂ��g����A�ƊJ���Ɍg������}�C�P���E�V�[�}�����͌���Ă��܂��B �@���Ȃ݂ɃV�[�}������MIT���̃x���`���[�ł���}�C�N���`�b�v�X�E�o�C�I�e�b�N�̋����ݗ��҂ł�����܂��B�}�C�N���`�b�v�X�E�o�C�I�e�b�N�ł́A���S��ނ̖�������̖��̒��Ɏ��߂��}�C�N���`�b�v���J���B���̃`�b�v�͓d�C����Ŗ����J�����邱�Ƃ��ł��A�̓��ɖ��ߍ���ł����ō���16�N�͒��˂Ⓤ������Ȃ��Ă������荞�ނ��Ƃ��ł��܂��B GIGAZINE(�M�K�W��) 2015�N8��13�� |
|
����זE�����ł����l���m�F�A�č��ŊJ�����̐V�^�Ɖu�Ö@�uTCR�Ö@�v�Ƃ́H ���Í���ȁu������������v�Ō��ʂ� |
| �@�u������������v�Ƃ������Â̓�����t�̂�����B �@���̂��сuTCR�Ö@�v�ƌĂ��V�����^�C�v�̖Ɖu�Ö@�����ʂ��グ���B �V�����Ɖu�Ö@�uTCR�Ö@�v �@�č��y���V���x�j�A��w��w��w�@�𒆐S�Ƃ��������O���[�v���A�L�͉Ȋw���l�C�`���[�̈�w���Ŏo�����ł���l�C�`���[�E���f�B�V����2015�N8�����ŕ����B �@�Ɖu�Ƃ́A�̂����Ƃ��Ǝ��A����⊴���ǂȂǂٕ̈��ɒ�R����@�\�B���̖Ɖu�̗͂𗘗p���āA������U�����悤�Ƃ����̂��Ɖu�Ö@���B �@TCR�Ö@�́A��`�q����̋Z�p�𗘗p���āA�Ɖu�ɂ���Ă�������܂��U�����悤�Ƃ����V�������ÂƂȂ�B �@����זE�\�ʂɂ́A����̖ڈ�ƂȂ�悤�ȁu����R���v�Ƃ����^���p�N�����o�Ă���B��`�q����̋Z�p���g���ƁA����ւ̍U����S�������p���̈�uT�זE�v�����̂���R���ɂ҂����肭�����`�ɂ��邱�Ƃ��ł���B���̂���R���ɂ��������߂�T�זE�̕\�ʂɔ�яo���^���p�N�����uTCR�v�ƌĂԁB�uT�זE��e�́v�𗪂������t���B �@�������T�זE�́ATCR�ł���R��������������݁A����זE�������Ĕj�E���B���ꂪTCR�Ö@�̐^�������B ���Â�����u������������v�Ō��� �@�����O���[�v�́A������������Ƃ������t�̂���ɑ���TCR�Ö@�����{���A�L�����ƈ��S�����������B �@���̌��́A���Ö@�̎��p���Ɍ����ĂR�i�K�ōs���錟�̂P�ԖڂƂQ�Ԗڂł���A�t�F�[�Y�P�Տ���������уt�F�[�Y�Q�Տ������ƂȂ����B �@�Ώێ҂́A�������������20�l�B���̂���͋ɂ߂Ď��Â�����A�T�N��������50���قǁB �@T�זE�̕W�I�Ƃ��Ē��ڂ�������R���́uNY-ESO-1�v�ƁuLAGE-1�v�̂Q�B���ꂼ�ꑽ����������̂U���Ō�����BT�זE�̕\�ʂ��Q�̍R���ɑΉ��ł���悤�ɂ���B ���Â̂��߂�T�זE�͓_�H�Ŗ߂� �@�����O���[�v�͂܂�������������̑Ώێ҂���̌����A���t�̒�����T�זE�����o�����B�y���V���x�j�A��w���Ǝ��ɊJ���������@�ň�`�q������{���B���̑���ɂ��T�זE�́A����R���uNY-ESO-1�v�ƁuLAGE-1�v�Ƀs�b�^��������TCR�����B �@�Ώێ҂͐�ɒʏ�̎��Âōs���邢����u�����ڐA�v�ł��鎩�Ɗ��זE�ڐA��p����B����ɂQ����ɁA����̂���R���ɑΉ��\��TCR������T�זE���P�l�����蕽��24���A�_�H�ɂ���đ̓��ɖ߂��ꂽ�B�_�H�ő̂ɖ߂��ꂽT�זE�́A�����ɑ��݂��邪��זE���U������������B �@�_�H�ɂ��A�C���^�[���C�L���U�Ƃ������ǐ��̖Ɖu�����̑̓����x���������Ȃ������A���ꂪ�����̕���p�͋N���Ȃ������B���̓_�H�������Ŏ��S�����l�����Ȃ������B �����ł����l�� �@T�זE�̓_�H��A����21.1�J���ǐՒ����ŁA20�l��15�l���������A10�l�͂���̐i�s���~�܂����Ɗm�F����Ă���B �@�����O���[�v�́A���Â̌��ʂ��R�p�^�[���Ŋm�F���Ă���B20�l�̂�����14�l�ł́A����זE���قڌ��o����Ȃ��Ȃ�܂ł̌�����B�������B�Q�l�ł͂���זE���[���܂ł͂����Ȃ��Ȃ����������B�����A�a��̉��P�ɂȂ���ꂽ�B�P�l�͕a��̐i�s��}�����݈��肳���邱�Ƃɐ��������B �@TCR�Ö@�ō��o����T�זE�������Ă�����A����זE���ˑR�ψق��N������TCR�Ƃ������ɂ����Ȃ����肵���ꍇ�́A����̐i�s���m�F���ꂽ�B ���ϐ������Ԃ�32.1�J���� �@�����2015�N�S���̎��_�̎��Ð��тɂ��Ă������O���[�v�͕��Ă���B �@����܂ł̕��ϒǐՊ��Ԃ�30.1�J���ɂȂ��Ă���B���i�s���Ȃ��ł��镽�ϊ��Ԃ�19.1�J���A���ϐ������Ԃ�32.1�J���B �@���Â̌����ɂ�������u������������v�̖Ɖu�Ö@�Ƃ��āA�����TCR�Ö@�͈��S�Ō��ʓI�ƌ����O���[�v�͂܂Ƃ߂Ă���B�u���t�̂���̖Ɖu�Ö@�ɂ�����d�v�ȃX�e�b�v���v�ƌ����O���[�v�B �@������������ɑ��Ă�蕝�L���K�p�ł��邩�B�Ɖu�Ö@�ւ̊S�����������ɁA���ۓI�ɂ����ڂ��ꂻ�����B Med�G�b�W 2015�N8��14�� |
| ���ǂ��炪��A�Y���܂Ɠ��������Ɋ֗^�A�č�MIT���� �ˑR�ψق������u�T�N�����V�g�V���i5CIC�j�v |
| �@���f�n�Y���܂̐����Ƃ��Ēm���Ă���u�������f�_�i����������j�v�B�̂̒��ł͈ٕ��ɔ������āA���̎������f�_�����ʂɍ����B�������炪��ɂȂ���d�g�݂�����ƕ��������B �@�č��}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�iMIT�j�̌����O���[�v���������̂��B �Ȃ��ړ_������̂��s������ �@�L�͉Ȋw���ł���č��Ȋw�A�J�f�~�[�I�v�I�����C���ł�2015�N�W���S���ɕ����B �@�a�C�ɂȂ�����A�댯�ȉ��w�����ɂ��炳�ꂽ�肷��ƁA���ǂ��N�����Ă���B �@�����I�ɉ��ǂ������ƁA����������ƕ���Ă����B �@���̉��ǂƂ���Ƃ̐ړ_�ɂ��Ă͏��X�Ɍ������邪�A�s��������B �@�����O���[�v�͖����̉��ǂ�������N�����d�g�ׂ݂Ă���B ���ǂƂ́u�Ɖu�v�̎d�g�݂̈�� �@�����������ǂ͕a���̂ɑR���ċN������́B�ٕ��ɒ�R����u�Ɖu�v�̎d�g�݂̈�ƂȂ�B �@���ǂ��N����ƁA�N���҂͕����̕����ōU�������B���̕����Ƃ��ẮA�I�L�V�h�[���Ƃ��Ēm����u�ߎ_�����f�v�̂ق��A���ǂ��L������ʂ�����ƒ��ڂ���Ă���u��_�����f�v�A����Ɏ������f�_������B �@���ꂼ��̕����́A�N���҂��U���������ŁA�������g�̌��N�ȑg�D�ɂ��_���[�W��^����̂Ŗ��ɂȂ�B �@�����O���[�v�́A�������f�_���A���N�ȑg�D�ɂ���DNA�ɂ���V�g�V���Ƀ_���[�W��^����Ɣ������Ă���B�V�g�V�����u�T�N�����V�g�V���i5CIC�j�v�Ƃ����ʂ̉��w�i�ɕς��Ă��܂��B �ˑR�ψق������N���� �@DNA�̓R�s�[���J��Ԃ��đ����Ă����d�g�݂�����B���̑����Ă����Ƃ��Ƀ~�X���N����ƁA��`��ω����Ă��ɂ��Ȃ���ƒm���Ă���iDNA�̏h�}�A����ݏo���A�i���������u����t���O�����g�v�Ƃ����d�g�݂��Q�Ɓj�B �@�����O���[�v�́ADNA�̕����������I�ɋN�����āA�T�N�����V�g�V�������������Ƃ��ɂǂ̂悤�ȉe�������邩�ׂ��B �@���ʂƂ��āA�ˑR�ψق��N�����Ɠ˂��~�߂��B�l�ł����ǐ��̒��̕a�C�������l�̑g�D�W�{�̌����ŁA�������x���łT�N�����V�g�V��������ƌ������B �@�a�ς��W�܂�ƓˑR�ψٗ���30�{�ɂ܂ō��߂�ƌ��_�t���Ă���B �@���ǂ̈�����������₷���`�Ō�������悤���B�ł��邾���a�炰�������̂��B Med�G�b�W 2015�N8��15�� |
|
����������ɂ͍����ʁE�Z���Ԃ̕��ː��Ö@���x�^�[ ����p�����Ȃ�QOL���� |
| �@�����X�e�[�W�̓�����̎��Âɂ́A��r�I�Z���Ԃ̕��ː��Ö@�R�[�X���D��邱�Ƃ��A�V���Ȍ����ŕ��ꂽ�B���Ȃ����ʂ̕��ː����ԏƎ˂�������A���[�S�̂ɍ����ʂ̕��ː���Z���ԏƎ˂���ق����A����p�����Ȃ��A�����̎��iQOL�j���ǍD���Ɩ��炩�ɂ��ꂽ�B �@�����̑�꒘�҂ł���ăe�L�T�X��wMD�A���_�[�\������Z���^�[������Simona Shaitelman���́A�u�Z���Ԃ̃R�[�X�������҂́A�Ƒ��̖ʓ|���݂邤���ō�����Ȃ��ƕ��Ă���B����͓�����̕��ː��Ö@���鏗���ɂƂ��ďd�v�ȗD�掖�����v�Ɛ������A�u���҂̑����͉Ƃ̒��ł��O�ł��������Z�ȃ��[�L���O�}�U�[�ł���A�����̏d�v�Ȏd���������Ă���B���������̗v���ɑΏ����邱�Ƃ��d�v���v�ƕt�������Ă���B���̌����́uJAMA Oncology�v��8��6���f�ڂ��ꂽ�B �@�����҂Ǝ��Â̑I�����ɂ��Ęb�������Ƃ��A��t�͂��̍����ʂ�p������@�i�Ǖ����S���[�Ǝ˂ƌĂ��j�̎g�p����Ɍ������ׂ����ƌ����O���[�v�͏q�ׂĂ���B�č��ɂ����������̕��ː��Ö@�́A��ʂɒ���ʂ��ԏƎ˂�����̂ƂȂ��Ă���i�ʏ핪���S���[�Ǝˁj�B�����O���[�v�ɂ��ƁA�č����ː���ᇊw��iASTRO�j�̃K�C�h���C���ł��̐V�����Ǖ����Ǝ˂̎��Â���ׂ����҂̂����A���ۂɎĂ���̂�3����1�ɂƂǂ܂�Ƃ����B �@����̌�����40�Έȏ�̑���������i�X�e�[�W0�`2�j�̏�����300�l��ΏۂƂ��āA���[������p�i���B��ᇓE�o�p�j�̌�A�Ǖ����Ǝ˂���Q�ƒʏ�̏Ǝ˂���Q�Ɋ��҂�ׂɊ���t�����B �@���̌��ʁA�Ǖ����ƎˌQ�ł͒ʏ�Q�ɔ�ׁA���Ò��̓��[�ɁA���]�A�畆�̐F�f�����A���ӊ��Ȃǂ̕���p�����Ȃ������B���Â���6�J����ł��A�Ǖ����ƎˌQ�͒ʏ�Q�ɔ�ׂČ��ӊ������Ȃ��A�Ƒ��̐��b������ۂ̍�����Ȃ������B �@�ă��m�b�N�X�E�q���a�@�i�j���[���[�N�s�j��Stephanie Bernik���́A���̍����ʂ̉Ǖ����Ǝˎ��Âł͎��Î��Ԃ̒Z�k�ɂ�闘�v�������邾���łȂ��A����p���y���ςނ��Ƃ����������Ǝw�E���Ă���B�������҂�1�l��MD�A���_�[�\������Z���^�[�y������Benjamin Smith���́A�u����̌����͕����̌����Ă����s�[�X�߂���́B�Z���Ԃ̎��ÃR�[�X�͂��͂�P�Ȃ�I������1�ł͂Ȃ��A�S���[�Ǝ˂�K�v�Ƃ��銳�҂Ƃ̘b�������ɂ����ėD��I�Ɍ������ׂ����̂ł���v�Əq�ׂĂ���B m3.com 2015�N8��20�� |
| ����זE�ɏW���U���@�ɏ��J�v�Z���u�i�m�}�V���v�̈З� |
| �@���N6���A���Â̌���ɘN�������B�炸�Ɏ��Âł���u�i�m�}�V���v�̊J�������\���ꂽ�̂��B���̃i�m�}�V���A�����̈�Âɑ�ϊv���N�����\�����߂Ă���B �@���a�킸��50 nm�i1nm��100������1mm�j�́u�i�m�}�V���v����ÂɊv�����N�����Ă���B �@�i�m�}�V���Ƃ́A�R����܂ȂǗl�X�ȋ@�\���l�ߍ������q�̋ɏ��J�v�Z���̂��ƁB������w��w�@�H�w�n�����ȁ^��w�n�����Ȃ̕Љ��ꑥ�����𒆐S�Ƃ��錤���`�[�����i�m�e�N�m���W�[����g���ĊJ�����Ă���B �@���̍ő�̓����́A�̓��Ɏ�荞�܂��Ǝ����I�ɂ���זE�����o���A�R����܂�p���āu�_�������v���邱�Ƃ��B �@�Տ��ł͂܂��A�Ö����˂�_�H�Ńi�m�}�V����l�̂ɒ�������B�ʏ�A�̓��ɓ��肱�ٕ��͏�������邪�A�i�m�}�V���͐��̓K�����������A��������Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă���A���Ǔ����X�C�X�C�Ɖj���B �@����זE�̎��ӂɂ́A�����q�������W�܂鐫���iEPR���ʁj������B�����q�̏W���̂ł���i�m�}�V���͂���EPR���ʂ𗘗p���āA���ǂ̌��Ԃ��炪��זE���ɐN������B �u����זE�̎��͂͌��ǂ̖ڂ��e�����ߐ��������B�i�m�}�V���͌��ǂ̖ڂ��ׂ�������ȍזE�ɂ͓͂��Ȃ����A�ڂ��e������זE�ɂ͓͂��▭�ȑ傫���ɂȂ��Ă��܂��B�����Ă���זE�̊j�ɋ߂Â��A�W���I�ɍU�����܂��v�i�Љ������j �@����זE�͐���̍זE�Ƃ͈Ⴂ�A���_�����B�i�m�}�V����pH�l�̐▭�ȈႢ�����m���A�R����܂���o����B �u���@�̒e�ہv�ƌĂ��i�m�}�V���́A�^�[�Q�b�g�ƂȂ�g�D��זE�ɖ�����ʓI�ɓ��B������u�h���b�O�f���o���[�V�X�e���iDDS�j�v�����x�ɔ��W���������́B����זE�݂̂�W�I�Ƃ��邽�߁A���N�ȍזE�ւ̕���p�����Ȃ����Ƃ��ő�̃����b�g���B�ʏ�̍R������Â���ː����Â̓�_�������ł���B �@����Ƀi�m�}�V���ƕ��ː���g�ݍ��킹�����Ö@���J�������B�̊O���璆���q���Ă�Ɣ������Ă���זE�����ː����o���������i�m�}�V���ɍڂ��A����g�D�ɏW�߂�̂��B���̂����Ŋ����ɒ����q���Ă�A����זE�������j���d�g�݂ł���B�Љ�������́A�}�E�X�ł�����������B���̐��ʂ͍��N6���Ɍ��\���ꂽ����B �u���̎��Ö@��MRI�Ńi�m�}�V��������זE�ɏW�܂��Ă��邱�Ƃ��m�F���Ȃ��璆���q�����Ǝ˂��āA�s���|�C���g�̕��ː����Â��ł���̂ł�萸�x�������B�ʏ�A����̊J����p��1�����߂��̓��@���ԂŔ�p�������݂܂����A�i�m�}�V���𗘗p�����g��Ȃ���p�h�����y����A���҂̕��S��S�g�Ƃ��啝�Ɍy���ł���B�����I�ɂ͂���̓��A���p�����҂ł��܂��v�i�Љ������j �@���łɌ��݁A�i�m�}�V���𗘗p����5�̍R����ܗՏ��������i��ł���A������p�̃i�m�}�V���͍��N���ɂ����J�Ȃɏ��F�\�������\�肾�B�������ɂƂ��đ傫�ȕǂƂȂ邪�������������͈������ߕt���Ă���B����̓A���c�n�C�}�[�a��Đ���Âւ̓W�J���l�Ē��Ƃ����B NEWS�|�X�g�Z�u�� 2015�N8��22�� |
| ���ÂɌ����H |
| �@�p�\�R���̉�ʏ�ł����߂������̍זE�B���ꂪ���Ԍo�߂ƂƂ��ɁA�݂�݂鏬�������ڂݎn�߁A�����ď����Ă������\�\�B �u�����̔]��ᇍזE���������t���X�R�ɂ��×p�̃E�C���X�gG47���i�f���^�j�h�����āA���Ԃ�ǂ��Ă��̗l�q���B�e���Ă��������̂ł��B�܂��]��ᇍזE�̖�30�̂�����1��G47���Ɋ������A2���ԂőS�ł��܂����v �@�����b���̂́AG47���̐��݂̐e�A������w��Ȋw�����������̓�����I�i�Ƃ����j��t���B�E�C���X�Ö@�����̍Ő�[���_�ł���ăW���[�W�^�E����w�ƃn�[�o�[�h��w�ł��×p�E�C���X�̊J���Ɋւ��AG47�����J���B���̌�A���{�ŗՏ����܂̐����@���m�������A���Ö�Ƃ��Ċ����������B �@���݁A���ÂƂ����A�u��p�i�O�ȗÖ@�j�v�u���Ái���w�Ö@�j�v�u���ː����Áv�Ƃ���3��Ö@���P�ƂŁA���邢�͑g�ݍ��킹�čs����B�Z�p�̖ڊo�܂����i���Ŏ��邪��������A����T�o�C�o�[�Ƃ������t������悤�ɁA����Ƌ����ł���悤�ɂ��Ȃ����B����ł������̎����̑�1�ʂł��邱�Ƃ͂����Ȃ��B �@����ȂȂ��ؖ]����Ă���̂�3��Ö@�Ɏ������Ö@�̊J���B�E�C���X�Ö@�͗L�͂Ȍ��̈���B�]���Ƃ͂܂������قȂ�A�v���[�`�ł�����������Ƃ������̎��Ö@�B�ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��B�������͉������B �u�E�C���X�͏h��̍זE���ɓ��荞�݁A�זE����̎d�g�݂��������āA���B���Ă����܂��B�זE���ł�����x�܂ő�����ƁA���x�͂��̍זE�̍זE����j�ĊO�ɏo�Ă����A�܂����̍זE�ɓ��荞�ށB�����̐��������Âɗ��p�����̂��A�E�C���X�Ö@�ł��v �@G47���̂��ƂɂȂ����̂̓w���y�X�E�C���X�i�P���w���y�XI�^�j�B�����т�Ȃǂɐ��v������^�C�v�ŁA���l��7�`8������x�͂����������Ƃ̂��邠��ӂꂽ�E�C���X���BG47���́A�g���i�K���}�j34.5�h�gICP6�h�g���i�A���t�@�j47�h�Ƃ����O�̈�`�q����`�q�H�w�Z�p�ɂ���ĉ��ς������̂ŁA�������́A����זE�ő��B����@�\�����킹�Ă���זE�����ő����A�ɒ[�ɓŐ�����߂邱�Ƃɐ��������B �u�R����܂���ː����Âŕ���p���N����̂́A����זE�����łȂ��A����זE�ɂ���p���y�Ԃ��߂ł��BG47���͂���זE�����ő�����̂ŁA���_��͕���p��}���邱�Ƃ��ł��܂��v �@����ɓ������́A�u�E�C���X�Ö@�̒��ڂ��ׂ��_�́A�g�Ɖu�̗͂������ɂ���h�Ƃ���v�Ƌ�������B �@����ƖƉu�̊W�͕��G���B �@�{���A����זE�ɂ͖Ɖu�������ɂ����B�{�l�̍זE���甭�����Ă��邽�߁A���Ԃ̍זE�Ƃ݂Ȃ���邩�炾�B�����A�ŋ߂ɂȂ��āA����זE�͐���זE�Ƃ͈�����^���p�N�������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�g����R���h�ƌĂ�邻���̃^���p�N�����܂��Ɖu�V�X�e���ɔF�������A����זE�͖Ɖu�ɔr�������B �@�������A����זE�͖Ɖu���^�[�Q�b�g�Ƃ���ڈ�����畢���B���Ă��܂��ȂǁA���܂��܂ȁg�B�ꖪ�h�����邽�߁A����R�����Ɖu�V�X�e���ɂȂ��Ȃ�������Ȃ��̂��B �u�Ɖu�V�X�e�������蔲���Đ����c��������זE�́A�ǂ�ǂB���n�߂܂��B�Ƃ��낪�AG47���Ɋ�����������זE�́A�E�C���X�̃^���p�N����������ԂŔj��܂��B�Ɖu���E�C���X��r������ߒ��ŁA�^���p�N�ɂ���Ă���R�����F������邽�߁A�Ɖu�זE�̓E�C���X�����łȂ�����זE�ɂ��U�����d�|����悤�ɂȂ�̂ł��v�i�������j �g�E�C���X�����ɂ��R������ʁ{�Ɖu�ɂ��R������ʁh�B���̓�����҂ł���Ƃ��낪�A�E�C���X�Ö@�̑傫�ȓ����Ƃ������Ƃ��B�ŋ߁A�������F��i�����m�[�}�j�Ƃ����畆����ɕی��K�p�ɂȂ����V��Ɂu�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��v������B����́A�Ɖu�זE�̍U������}���Ă��܂��悤�ȐM�����Ɖu�זE�ɓ���̂�h���B�u�E�C���X�Ö@�ɖƉu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��p����A�L�����͂���ɍ��܂�̂ł͂Ȃ����v�Ɠ������͊��҂���B dot.�h�b�g 2015�N8��25�� |
| �K���זE�����̗ǐ��זE�ɖ߂����Ƃ��\�ł��錤�����ʂ����炩�� |
| �@�K���͈�ʓI�Ɋ������邱�Ƃ���������Ƃ��Ēm���Ă��āA��p���Â�R������ÂȂNJ��҂ɑ傫�ȕ��S�������鎡�Ö@���K�p�����̂ł����A�A�����J�ɂ���Mayo
Clinic�a�@�̌����O���[�v���K���זE�����̗ǐ��זE�ɖ߂������ɐ������Ă���A�V���ȃK�����Â̕��@�Ƃ��đ傫�Ȓ��ڂ��W�߂Ă��܂��B �@�ʏ�̍זE�͐ڒ��^���p�N���Ƃ��������̂������ōזE���m���Ђ������Ƃ��ł��Ă���A���̐ڒ��^���p�N���͏��g�D���`������̂ɕK�v�s���ȃK���}�����q�ł�����ƒ����ԍl�����Ă��܂����B�������Ȃ���AMayo Clinic�̌����҂����͂��̗��_�Ɉ٘_�������A�ڒ��^���p�N�����K���זE�ɂ����݂��A�K���זE�̐����ɕK�v�ȗv�f�ł���Ƃ������_���咣���Ă��܂����B�ڒ��^���p�N���ɂ́u�K���}�����q�v�Ɓu�K���זE�̐����ɕK�v�v�Ƃ�����������2�̑��ʂ������Ă���\��������Ƃ����킯�ł��B �@�����Ō����O���[�v�������������Ƃ���A�K���זE���ɐڒ��^���p�N�������݂��邱�Ƃ��킩��A�܂��A�ڒ��^���p�N���Ɉُ킪���������Ƃ��ɃK���זE����O���킵���X�s�[�h�Ő������邱�Ƃ��������܂����B�����O���[�v���咣�������_�������������Əؖ����ꂽ�Ƃ����킯�ł��B �@���̎����ł͂���1�d�v�Ȃ��Ƃ��������Ă��܂��B����́u�ڒ��^���p�N���v�ƁumicroRNA�v�Ƃ������q�ɑ��ݍ�p�����邱�Ƃł��B�ʏ�̍זE���m���ڐG����ꍇ�AmicroRNA�͍זE�̐����𑣂���`�q�̓������X�g�b�v�������p������̂ł����A�K���זE���̐ڒ��^���p�N���Ɉُ킪��������ƁAmicroRNA�ɂ��ُ킪�łĂ��邱�Ƃ��킩��܂����B �@����Ɍ����҃O���[�v�͎����𑱂��A�ʏ�̍זE���ɂ���microRNA��j��ƁA�זE�̌�����ؒf����PLEKHA7�Ƃ����^���p�N���̐������h����A�זE�����B���J��Ԃ��K���זE�ɐ�ւ�邱�Ƃ��������܂����B�܂��A���̃v���Z�X�]������A�܂�K���זE����microRNA��ʏ탌�x���ɂ܂ŏC������ƁA�K���זE�̐������~�܂�ǂ��납�A�������މ������̍זE�ɖ߂������Ƃ��m�F����܂����B�ȒP�Ɍ����A�זE�̉ߓx�ȑ��B�Ɗ�@�I�Ȑ�����h���@�\(microRNA)���C�����邱�ƂŁA�K���זE�̐������X�g�b�v�������̍זE�ɖ߂����Ƃ��ł����A�Ƃ����킯�ł��B �@�����𗦂���Antonis Kourtidis���m�́u��A�̎����ɂ��ڒ��^���p�N����microRNA�Ƃ����������ꂽ���ݓ��m�ɑ��ݍ�p�����邱�Ƃ��킩�������Ƃ́A����̃K�����ÂɌ���������������܂���v�Ƙb���Ă��܂��B�������A�K���זE�����̗ǐ��ȍזE�ɖ߂����̂́A�}���̓��K���A�x�K���A�N���K���ł̏ꍇ�݂̂ł��B�����O���[�v�́u���������w�Ö@���p��K�v�Ƃ����ɃK�����Â��ł��関�������邩������Ȃ��v�Ɗ�]������Ă��܂��B �@�Ȃ��A���{�ł͒����w��w���̌����O���[�v���A2014�N��microRNA�������x�̍����������K���ɒ�������ƁA����ȍזE�ɖ߂����Ƃ��\�Ȃ��Ƃ𐢊E�ŏ��߂Ĕ������܂����B�������A���{�̒����w��w�����s���������̓}�E�X���g�������̂Ȃ̂ŁA����̎����ɂ��l�Ԃւ̌��͂��ؖ�����邱�Ƃ����҂����Ƃ���ł��B GIGAZINE 2015�N8��27�� |
|
������̋g�������㉻�}���Ɍ��ʁy�č�������z �g�̋@�\�̑r���h���A�������S���\�h�� |
| �@�č�������iACS�j��8��14���A���������҂̐g�̋@�\�ێ��ɂ̓E�F�C�g���t�e�B���O���L���ł���Ƃ̌������Љ���B�uJournal of Clinical Oncology�v���Ɍf�ڂ��ꂽ�����_���B �@���������҂͈�ʏW�c�Ɣ�r���āA�ؗ͒ቺ��A���̐Ǝ㉻�A�Ք�J���Ȃǂ̋��㐫�𗈂������X�N�������ƌ�����B �@�ăy���V�����F�j�A��w��Justin C. Brown����ɂ�鍡���ł́APhysical Activity and Lymphedema�iPAL�j�����̃f�[�^��p���āA�E�F�C�g��p�����ؗ̓g���[�j���O�����������҂̋��㉻��h�~���邩�ǂ��������������B�팱�҂͐Z����]�ڂ̂Ȃ�����������295��Ƃ��A�����͏��X�ɋ��x���グ��E�F�C�g���t�e�B���O���T2����{�B1�N��ɒ������s���A10�|�C���g�̃X�R�A�ቺ���������팱�҂�g�̋@�\�r���ƕ]�������B �@���̌��ʁA�g�̋@�\�r���ƕ]�����ꂽ�팱�҂͑ΏƌQ147�l��24�l�i16.3���j�������̂ɑ��A�E�F�C�g���t�e�B���O�Q�ł�148�l��12�l�i8.1���j�ɂƂǂ܂��Ă��邱�Ƃ����������B �@�����҂�́A�g�̋@�\�X�R�A��10�|�C���g�ቺ���邲�Ƃɑ������S���X�N������6�����ˏオ�邱�Ƃ��ӂ݂�Ɩ{�������ʂ͑������S�\�h�̓_����L�Ӌ`���Ƃ��Ă���B �@����̗p�����g���[�j���O�ł́A1-2�|���h�̌y���E�F�C�g����J�n���A�g���[�i�[�̎w���̉��ŏ��X�ɕ��ׂ𑝂₵���B�u�y���ׂ���n�߁A�������i�s���A�̂̐������ƁB�ɂ݂������鎞�͉^���ʂ����炷�B�W���ɍs���Ȃ��ꍇ�́A�ƒ���ɂ���y�����́i�X�[�v�ʂȂǁj�������グ�Ă��悢�v��Brown���B�����p����̂��銳�҂̏ꍇ�A�^�����͘r�Ɉ����т����邱�Ƃ����������Ƃ��Ă���B m3.com 2015�N8��28�� |
|
�咰����̑��������Ɍq�������ƁA�������Q�[���̊J���Ɏ��g�ވ�t�����܂��B �������ƈꏏ�ɕւ��ώ@ |
| �@�u����R���v�Ɩ��t����ꂽ�A������̃X�}�z�Q�[���B �@�����̕ւ̏�Ԃ����ƁA�������L�����N�^�[������זE���̓G�Ɛ���Ă����Ƃ������́B �@�ւ̏�Ԃɂ���Ă͑咰������^���鎖������A�v���C���ɃA���[�g���o�Č��f��i�߂���Ƃ����A�咰����̑��������Ɉ���Q�[���ł��B �咰�ۂ��[�l�� �@�Q�[���ł͗l�X�ȑ咰�ۂ��o�ꂵ�A������g�ɂ܂Ƃ����Ő퓬�\�͂�g�ɂ��鎖���ł��܂��B �@HP�ł́u�咰�ۋ[�l���}�Ӂv��݂��A�[�l�������L�����N�^�[�Ƌ��Ɋe�ۂ̓�������������Ă��܂��B �ߋ��ɓ�a����������t���J�� �@����R���͖������J��ڎw���āA�������E�J�����ł��B �@���S�ɂȂ��Ď�|���Ă���̂́A�Έ�m���B�Έ䂳��͌����̎��O�Ȉ�ŁA�ߋ��ɒ�ᇐ��咰���Ƃ�����a���o�����Ă��܂��B �@15�̎��ɔ��ǂ��Đ��N�ꂵ��A�l�H�������t�������ňꖽ���Ƃ�Ƃ߂܂����B �@�����Z�p�ŐΈ䂳����~������t�ɓ���A�������t�ɂȂ錈�ӂ����������ł��B ���������Ŗ����~������ �@�O�Ȉ�Ƃ��Đi�s�������҂�ڂ̓�����ɂ��A���������E���f�̑������X�����Ă����Έ䂳��B �@�������g���f�͑厖���h�ƌĂт����邾���ł́A���ʂ����܂肠��܂���B �@�����ɋC���킸�����̌��N���ӎ����Ă��炦�Ȃ����ƔY���ʁA�u����R���v�̐���Ɏ���܂����B �@�܂��Έ䂳��́A�g�ւŋ~���閽������h�Ɓu���{���w��v��ݗ��B�咰���f�����グ�A����̑��������𑣂����Ƃ�ڕW�Ɋ������Ă��܂��B ���̏Ǐ���ꂽ���f�� �@���Ȃ݂ɁA�ւɎ��̂悤�ȏǏ���ꂽ�瑁�}�Ɍ������������ǂ��ƁA�Έ䂳��͊��߂Ă��܂��B �����o�� �ׂ��Ȃ� �����ƕ֔���J��Ԃ� �ւ��c���Ă��銴�������� �@�u����R���vhttp://unkogakkai.jp/�@�́A�Έ䂳��̂ق���|�Ɏ^���ł���l�B���{�����e�B�A�Ő���B���݂��A�����w��ɋ����̂�����ւ̎Q�����Ăъ|���Ă��܂��B IRORIO�i�C�����I�j 2015�N8��31�� |
|
�݊�10�N�늳�m���̗\�����f�����쐬 ���������Z���^�[�A�����K�����X�N���q��ABC���ނ����p |
| �@���������Z���^�[��9��2���A�l��10�N�Ԃň݊��ɜ늳����m����\�����郂�f�����쐬�����Ɣ��\�����B���ړI�R�z�[�g�����iJPHC�����j�Ō��t���̎�ł�����1��9000�l��16�N�����ĒǐՂ����f�[�^����ɁAABC���ނ���K�����X�N���q�����p���ĎZ�o���Ă���B���Z���^�[�ł́u���f���̐��x�͊m�F�ς݂����A�Ɨ������ʂ̌����ł̌����͍s���Ă��炸�A����͑Ó����̊m�F�Ǝ��p�����]�܂��v�Ɗ��҂��Ă���B �@�݊��̃��X�N���q�Ƃ��Ă̓w���R�o�N�^�[�E�s�����ہiHp�j�̊������������A�ߔN�͈݊����X�N���ނƂ���Hp�����ƈϏk���݉��iAG�j�̗L�����A���ꂼ�ꌌ�t����l���画�肵�g�ݍ��킹��ABC���ނ��p������悤�ɂȂ��Ă��Ă���B����ŁAHp�����̑��ɂ��݊��Ɋւ��v���Ƃ��ċi���⍂�����H�i�Ȃǂ��m���Ă��邪�A���Z���^�[�ɂ��Ƃ����̗v����g�ݍ��킹���l�̈݊����X�N���Z�o���鎎�݂͂Ȃ���Ă��Ȃ������B �@�����œ��Z���^�[�́A�����K���Ɗ��Ȃǂ̊W�𖾂炩�ɂ���ړI�ŁA1993�N�Ɉ�錧���ˁA�V���������A���m���������A���茧��ܓ��A���ꌧ�{�ÁA���{���c��6�ی����Ǔ��ŕ�炷40�]69�ɃA���P�[�g�����{���A�̌����ł�����1��9000�l��2009�N�܂ŒǐՁB�i����݊��̉Ƒ����A�������H�i�̐ێ�ɉ����AABC���ނőΏۂ�4�Q�ɕ����Ĉ݊��\�����f���̍\�z�����݂��B �@ABC���ނƐ��ʁA�N��Ƒ��̃��X�N���q�i�i���A�Ƒ����A�������H�i�ێ�j����10�N�Ԃň݊��ɜ늳���郊�X�N���Z�o�����Ƃ���A�j�����늳����m����0.04���i40�AHp�A���AAG���A���̃��X�N���q���j����14.87���i70�AHp�z���A���̑S���X�N���q�L�j�ƂȂ����B���̃��X�N���q�����O�����ꍇ�̊m���́A0.06�]8.71���͈̔͂Ɏ��܂����B �@�����̏ꍇ�́A0.03���i40�AHp�A���AAG���A���̃��X�N���q���j����4.91���i70�AHp�z���A���̑S���X�N���q�L�j�ŁA���̃��X�N���q���l�����Ȃ��ꍇ��0.04�]2.43���ƂȂ����B �@����ɁA�l��10�N�Ԃ̈݊��늳�m�����Z�o�ł���悤�A�N���݊��̉Ƒ����AABC���ނ��ȈՃX�R�A���������@���l�Ă����B �@���Z���^�[�ł́u�Z�o���ʂ͍ŋ߂̃��^��͌��ʂƂ���v���Ă���A�j����10�N�Ԉ݊��늳�m���͏�����荂���A�N��̉e�����j���ł�苭���o��X���ɂ������v�ƃR�����g���Ă���B �@�܂��AHp�A����AG�̖����Q�͈�т��Ĉ݊����X�N���Ⴂ���߁A���f�̂���������㌟������K�v������Ƃ������A�u�݊����X�N�̍����Q�͐����K���̌�������K�v�Ȍ��f����Ȃǂ̗\�h�s����ی��s����S�����A���X�N�̒Ⴂ�Q�ł������K���ւ̒��ӂ�݂̏Ǐ���Έ�t�̐f�@�⌟������p�����K�v�v�Ƃ��Ă���B m3.com 2015�N9��4�� |
|
�������X�N��n3�n�s�O�a���b�_�Œጸ ���������Z���^�[�An6�n�ێ摽���ƃ��X�N�㏸�� |
| �@���������Z���^�[�̑��ړI�R�z�[�g�����`�[���ɂ��A�s�O�a���b�_�̐ێ�ʂƓ�����Ƃ̊֘A�ɂ��Ē������ʂ��܂Ƃ܂����B����ɂ��ƁA�G�C�R�T�y���^�G���_�i�d�o�`�j��h�R�T�w�L�T�G���_�i�c�g�`�j�Ƃ��������|�R�n�s�O�a���b�_�̐ێ�ʂ������ƁA�z��������e�̗z���̓�����ɜ�郊�X�N���Ⴂ�X�����݂�ꂽ�B�܂����|�U�n�s�O�a���b�_�̐ێ�ʂ������ƁA������̃��X�N�����܂邱�Ƃ����������B �@�����`�[���͂P�X�X�O�N����n�܂����u�w�����Ƃ��Ċ��A�H�c�A����A����ȂǂX�̕ی����Ǔ��ɍݏZ�̂S�T�`�V�S�̏�����R���W�O�O�O�l��ΏۂɁA�Q�O�P�P�N���܂łP�S�N�Ԃɂ킽��ǐՒ������s���A���̒����Ɋ�Â��A�s�O�a���b�_�ێ�Ɠ����҂Ƃ̊֘A�͂����B�R�z�[�g�����͉u�w������@�̂P�B �@�P�S�N�Ԃ̊Ԃɓ�����Ɛf�f���ꂽ�̂́A�T�T�U�l�B�P�X�X�T�N�ƂX�W�N�Ɏ��{�����A���P�[�g�����ƂɁA�s�O�a���b�_�̑������A�d�o�`�A�c�g�`�A�h�R�T�y���^�G���_�i�c�o�`�j�Ȃǂ��܂ނ��|�R�n�s�O�a���b�_�A����ɂ��|�U�n�s�O�a���b�_�Ȃǂ�ێ�ʕʂɃO���[�v�������A�O���[�v�Ԃ̓�����늳���X�N���r�����B �@���͂ɂ�����A����܂ł����{���Ă��������Ɋ֘A���鑼�̗v���A�Ⴆ�Ώo�Y�A�i���A�����ȂǂƂ������O���[�v�Ƃ̌��ʂɉe�����o�Ȃ��悤�ɔz�����A�s�O�a���b�_�Ƃ̊֘A�ɂ����i�荞�B �@������ɂ́A�z�������ˑ����Ɣ�ˑ������m����B����̕��͂͂��̗L�������ׁA�z��������e�̗z���i�G�X�g���Q����e�̂ƃv���Q�X�e������e�̂��Ƃ��ɗz���j������ɂ����āA�d�o�`�A�c�g�`�A�c�o�`���ꂼ��̐ێ�ʂ������O���[�v�ɂ́A���X�N���Ⴍ�Ȃ�X���������ꂽ�Ƃ����B����A���|�U�n�s�O�a���b�_�̐ێ�ʂ������O���[�v�́A�ł����Ȃ��O���[�v�ɔ�ׁA�Q�E�X�S�{���X�N�����܂�X���ɂ��邱�Ƃ����������Ƃ��Ă���B �@���|�U�n�s�O�a���b�_�ɂ̓��m�[���_�A�A���L�h���_�Ȃǂ�����B�����d���̗\�h��Ɖu�����@�\�Ȃǂ���������Ă��邪�A�z��������e�̗z���̓�����ɂ͍D�܂����Ȃ���p���݂�ꂽ�Ƃ�����B�����ɂ����������̜늳���͑����X���ɂ���A�H���Ƃ̊֘A���͂悭�������Ă��Ȃ��B��b�����ɂ��A���|�R�s�O�a���b�_�ɂ͓���̂���זE�̑��B��}��������ʂ��A���|�U�n�s�O�a���b�_�ɂ͂���זE�̑��B���i������\���̂��邱�Ƃ���������Ă���B��������s�̉��Ăł̉u�w�����ł́A���Ȃ炸������v�������ʂ�����ꂸ�A�܂��ē��{�l��ΏۂƂ��錤��������܂łقƂ�ǂȂ������B m3.com 2015�N9��7�� |
| �����V�l�ɂȂ�\�����@���Ấg����Q��A�h |
| �@�����Â̐i���͖ڊo�܂����A���҂̐������͊m���ɏ㏸���Ă���B�������Â̐��ʂ̈���ŁA�u�������E���z�������Ô�̕��S�ɔ敾����l�������Ă���v�Ƃ��������B�܂��A�d�����������Ȃ����Ƃɂ��������ŁA�u�����V�l�v�ɓ]������\��������B�����ł��Â̂����ɂ��Ċ�{�I��3�̃|�C���g��Q��A�œ�����B Q1�F����Ŏd�����������Ȃ��B�����͂ǂ��Ȃ�H A�F��Ј���������͏��a�蓖���̎x�������� �@����Ȃǂ̕a�C�₯���œ����Ȃ��Ȃ����ꍇ�A1���ɂ��W����V���z��3����2���u���a�蓖���v�Ƃ��Ďx�������B�W����V���z�Ƃ́A�Љ�ی��̕ی��������߂�Ƃ��Ɏg���W����V���z��30�Ŋ��������́B���z��1��5��~�ł���A���a�蓖����1��1���~�ɂȂ�B�����A���̊��Ԓ������^���x������ꍇ�ɂ͎x������Ȃ��B���^���蓖����菭�Ȃ��Ƃ��ɂ́A���̍��z���x�������B �@�x���J�n�́A�����A������3���ԑ��������ƁA4���ڂ���B�x�����Ԃ́A�ЂƂ̎����ɂ��ō���1�N6�J���Ԃ��B�ԂɐE�ꕜ�A�̎����������Ď蓖�����Ȃ��Ă��A1�N6�J���ȏ㉄�����Ƃ͂ł��Ȃ��B �@���@���łȂ��Ă��g����̂ŁA��p����@�ɂ͗L���x�ɂ𗘗p���A���̌�O���ʼn��w�Ö@���X�^�[�g���Ă��珝�a�蓖�����g���Ƃ������@������B �@��ނ������ސE�����ꍇ�ɂ́A�ٗp�ی��̊�{�蓖�i������u���Ǝ蓖�v�j�����邱�Ƃ��������悤�B���Ԃ͌����A���E�������̗�������1�N�ԁB�u�J���̈ӎv�Ɣ\�͂�����l�v���x���ΏۂȂ̂ŁA�u�a�C�ł܂����������Ȃ��v�Ƃ����ꍇ�ɂ͎ł��Ȃ����A1�T�Ԃɐ�����1�������Ԃł������ӎv������Ύ\���B Q2�F����ł���Q�N�������炦��H A�F����œ����Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃł��N���̐\���͉\ �@��Q�N���́A�a�C�₯���������Ő�����d���Ɏx������������Ƃ��A������ۏႷ�邽�߂Ɏx���������I���x���B�������ł����l�ŁA65�Ζ����ł���Ύ����̗L���ɂ�����炸��Q�N�����ł���\��������B �@�ڂɌ�����@�\��Q������ꍇ�͂������A�u���Âɂ�錑�ӊ��₵�т�ȂǂňȑO�̂悤�Ɏd����Ǝ����ł��Ȃ��Ȃ����v�Ƃ����P�[�X�ł��A���߂Ĉ�t�̐f�@����������1�N6�J���o�߂��Ă��ω����Ȃ���ΑΏۂɂȂ�B Q3�F�����̂��Ƃ��s���c����ɑ��k����H A�F�܂��͋߂��̂��k�x���Z���^�[�Ő��x�̊m�F�� �@�߂��́u���k�x���Z���^�[�v�ő��k�ł���B�S���̂���f�ØA�g���_�a�@�Ȃǂɔz�u����Ă��鑊�k�����ŁA�����Â̒m�����L�x�ȊŌ�t��\�[�V�������[�J�[�i�Љ���m�j���ʂ̕s����Y�݂ɉ����Ă����B���k�͒��ڂł��d�b�ł��\�ŁA���Җ{�l�A�Ƒ��A�n��ɏZ�ސl�����p�ł���B�����Ŏ��������p�ł��鐧�x�A�Љ�A�̌��ʂ��Ȃǂɂ��đ��k���������ŁA�����ȂǂŌʂɑ��k����Ƃ������낤�B dot.�h�b�g 2015�N9��7�� |
|
�}�����U�z���A�S���I�e��1�N�p�� �s���◎�_�A�s���␇���ɂ����e����� |
| �@�č����w��iAACR�j��8��26���A�}�����O���t�B�[�ɂ��������f�ɂ����ċU�z���ƂȂ��������̑啔�����A�s���◎�_�A�܂��s���␇���ւ̈��e�����o�����Ă���A�ꕔ�̏����ł͂��������e����12�J���Ԃɂ킽�莝������Ƃ����������ʂ��Љ���BCancer Epidemiology, Biomarkers & prevention�Ɍf�ځB �@�����ɂ��ƁA�}�����O���t�B�[�ɂ��������f�ŋU�z�����ʂɂȂ��������ł́A���ʂ���������܂ł̊ԂɁA88�����߂��݁A�܂��́A�����ւ̑Ώ��s�\�Ȃǂ̗��_���o�����Ă����B�܂��A83�����s�������o���A67���ł͗]�ɂ�d���ւ̑Ώ��s�\�A53����������Q����A�}�����O���t�B�[�ɂ��U�z���̐S���Љ�I�ȉe���������ɔ������Ă��錻��������ɂȂ����B�܂��A�U�z���̌��ʂ��o��������3����1�ŁA�S���Љ�I�e�������f��̍Œ�1�N�Ԃɂ킽�莝�����Ă������Ƃ����������B �@�����҂́u�}�����O���t�B�[�ɂ�錟�f�̃����b�g�A�f�����b�g�̑��ɂ��A�U�z�����ʂ̐S���Љ�I�e���������ɂ킽���Ď�������\��������Ƃ����_�ɂ��āA���炩���ߏ�����邱�Ƃ��d�v�v�ƁA�q�ׂĂ���B m3.com 2015�N9��9�� |
| ��������זE���C���v�����g�ŕߑ��A�]�ڗ}���Ɉꏕ�@�Č��� |
| �@�č��̌����`�[���͂W���A�̓��Ŋg�U���邪��זE��ߑ�����ɏ��̑̓����ߍ��^��Ë@��i�C���v�����g�j���J�������Ɣ��\�����B���i�K�ł́A�}�E�X�����Ō��ʂ�������Ă���Ƃ����B �@��ʓI�Ɂu�]�ځv�ƌĂ��v���Z�X�ł́A�ŏ��ɔ�����������̕��ʂ���זE���ړ����đ��̑���ł���������B���̔����̒x��ɂ���āA���҂����𗎂Ƃ��P�[�X�͏��Ȃ��Ȃ��B �@�����Ɋ܂܂��u�����z��ᇍזE�i�b�s�b�j�v�̑��������́A�f�f�Ƌ~�����Â�v��������\��������B�����A�b�s�b�͂��������P�ʂŁA�����̏ꍇ�����Ԃɂ킽���Č������z���Ă���V���ȕ��ʂɒ蒅���邽�߁A�������邱�Ƃ����ɍ���ƂȂ��Ă���B �@�p�Ȋw���l�C�`���[�E�R�~���j�P�[�V�����Y�ɔ��\���ꂽ����̌����́A�b�s�b�̕ߑ����A����זE�̊g�U�Ƃ���̓]�ڂ�h�������ɂȂ�\���������������̂��B �@�_���������M�҂ŕăm�[�X�E�G�X�^����w�̃��j�[�E�V�F�[���́A�`�e�o�̎�ނɁu�C���v�����g���ڐA�����}�E�X�́A�C���v�����g���ڐA���Ȃ������}�E�X�ɔ�ׂāA�x�ɂ����鎾�a�̕��S���������y�����ꂽ�v�ƌ�����B �@����̎����ŁA�V�F�[���ƌ����`�[���́A���a��T�~���̐����𐫂̉~�Ղ��쐻���A�}�E�X�P�C�ɂ��Q����̓��ɖ��ߍ��B �@�Ɖu�זE�����Ƃ�Ƃ��ėp���邱�̃C���v�����g�ɂ́A�ߑ����ꂽ�זE�̑��݂����o���邽�߂̃X�L���i�[�����ڂ���Ă���B �@�V�F�[���́u������g�ݍ��킹�ėp����V�X�e���ɂ��A�]�ڐ������̑����������\�ɂȂ��Ă���v�Ƃ��Ȃ���A�u��P�̉��b�́A�]�ڂ̔����B�̑S�̂ɍL���g�U����O�ɓ]�ڂ�������v�Ɛ��������B�܂��g�U�����זE�ɂ�鎾�a�̕��S���y���ł��邱�Ƃɂ��A���ʓI�Ȏ��Â��s����ł��낤���Ԃ̉������\�ɂȂ邱�Ƃ��l������Ƃ��Ă���B �@����Ȃ鉶�b�Ƃ��ẮA�C���v�����g�œ]�ڐ�����זE�����W���ĕ��͂��邱�Ƃɂ��A�œK�Ȏ��Ö@�̓��肪�e�ՂɂȂ邱�Ƃ���������B �@�����p�}�E�X�œ���ꂽ����̐��ʂ́A�l�ԂōČ��s�\�ƍl���闝�R�͉����Ȃ��ƃV�F�[���͎w�E����B�u�זE���V���ȑ���ɈڐA����Ƃ����l�����̖{�́A�}�E�X�Ɛl�ԂƂ̊ԂɈႢ�͂Ȃ��B�ڍׂ̈ꕔ�͕ς�邩������Ȃ����A��������ɂ��Đl�ԗp�C���v�����g�̐v���\�z�ł���ƍl���Ă���v�Əq�ׁA�l�Ԃ̂��҂�ΏۂƂ����Տ������𑁊��ɊJ�n�ł��邱�Ƃ�]��ł���Ƙb�����B �����ʐM�� 2015�N9��10�� |
| �Ƃɂ�����I�X�������̐V����͂��́u���ݕ��v |
| �@�����̓T�^�Ƃ������X���i���������j����B�N�Ԃ̎��S�Ґ��͜늳�Ґ��ɂقڕC�G���A���҂̐������͋ɂ߂ĒႢ�B�����������d�v�ɂȂ邪�A���̂��߂ɂ�����ݕ����L���ł��邱�Ƃ��킩���Ă����B �@���{�����l�a�Z���^�[���@���̕ЎR�a�G��t�͂����b���B �u�����X�������5�N��������1�Z���`�Ō�����Ζ�80���A2�Z���`�ł�50�����炢����A�����Ɏ�p�Ő؏��ł���Ύ��Ð��т͈�������܂���B���͑�������������A�قƂ�nj�����Ȃ����Ƃɂ���܂��v �@�X������́A1�Z���`���炢�܂ł��X���̒��ɂƂǂ܂�A�ɂ݂������Ȃ��B�傫���Ȃ�A�X���̊O�Ɋ���o���Ď��͂̐_�o�ɐZ������ƁA�s������ݒɂ��o�Ă���B�ɂ݂������Ȃ�̂́A�����Ƒ傫���L�����Ă��炾�B�Ȃ������Ɍ��f�Ō������Ȃ��̂��B�ЎR��t�͌����B �u���Ȃ��̒��̏���������́ACT�i�R���s���[�^�[�f�w�B�e�j��MRI�i���C���f�w�B�e�j���������g�����̂ق��������₷����ł��B�Ƃ��낪�A��C�͒����g��ʂ��ɂ�������������̂ŁA��C����������܂ވ݂̌�둤�ɂ����X���͔������x���������܂���B�����ɂ�����Ό������Ă��܂���ł��ˁB�X���ɑΉ���������ȓ��������g���Δ����ł��܂����A���̏Ǐ���Ȃ��l�Ɍ��f�Ŏ��{����ɂ̓n�[�h�����������܂��v �@���ː��픘����ɂ��Ȃ������g�ŁA�Ȃ�Ƃ��X���S�̂������Ȃ����̂��\�\�B �@���Z���^�[���f���̃X�^�b�t�����ǂ蒅�����������A�u�����g�����̎��Ƀ~���N�e�B�[��350�~�����b�g�����ށv�Ƃ������@�������B�~���N�e�B�[�ň݂������ƂŁA�݂̒��̋�C���ړ����Ē����g���ʂ�₷���Ȃ�A�X����90���O��܂Ō�����悤�ɂȂ����̂��B �u���낢��Ȉ����������܂����B�Y�_�����⒂�f���[�U���Ă���A���~�ʂ̈����́A�݂̒��ɓ���ƍׂ��ȖA���ז��ɂȂ�B���k�n�̃������e�B�[�́A�݉t�Ɣ������Ă������Č����Ȃ��Ȃ�B�~���N�e�B�[�̓K�x�ȑ������A���傤�ǂ������x�ɒ����g��ʂ��A�������茩�₷���Ȃ�Ƃ킩��܂����v�i�ЎR��t�j �@�ʏ�̒����g������10�����x�ŏI��邪�A�u�X�����G�R�[�v�Ɩ��t�������̌����ł́A40�����x�����Ē��J�Ɍ��Ă����B���҂̎p����ς��Ȃ���\���ώ@������Ƀ~���N�e�B�[�����p���Ă��炢�A����ɂ��܂Ȃ��X��������B dot.�h�b�g 2015�N9��10�� |
|
MRI�̗͂͐f�f��������Ȃ��I���͂ł���ɖƉu�זE���V��̎��Â��o�� �u�^�j��Ȕ��z�v�����ÂɐV�� |
| �@�ʏ�摜�f�f�ɗp������u�j���C���摜�f�f���u�iMRI�X�L���i�[�j�v��p�����A�V�������z�̉���I�Ȃ��Ö@���J�����ꂽ�B �@���͂����ĂȂ��ړI�ŗ��p������̂��B �f�f�݂̂Ȃ炸 �@�p���V�F�t�B�[���h��w�𒆐S�Ƃ������ی����O���[�v���A�L�͉Ȋw���l�C�`���[�̎o�����ŃI�����C�����Ȋw���̃l�C�`���[�E�R�~���j�P�[�V�����Y����2015�N�W��18���ɕ����B �@�u�j���C���摜�f�f���u�iMRI�X�L���i�[�j�v�́A1980�N�ォ��̓��̂��܂��܂ȑ���̕a�C�ׂ邽�߂̉摜�f�f�ɗp�����Ă��Ă���B �@�����O���[�v�́A�uMRI�͐f�f�����̂��́v�Ƃ������z���A�V�������Âւ̉��p�ɐ��������B ���͂Łu���c�v �@���̎��Ö@�ł́A�܂��u�}�N���t�@�[�W�v�Ƃ����Ɖu�זE��̂�����o���B�}�N���t�@�[�W�́A����ɒ�R����Ɖu�̎d�g�݂�����������\�͂������Ă���B �@���o�����}�N���t�@�[�W���V���[���̒��ő��B������B���ɁA����זE���E���E�C���X���u�����v�Ƃ����`�Łu�����v������B�����āuSPIO�v�Ƃ������́A�S���܂ރi�m���q����荞�܂���B����ɂ��}�N���t�@�[�W��MRI�̎��C�ő��c�ł���悤�ɂȂ�B �@�������čH�����}�N���t�@�[�W��̓��ɖ߂��BMRI�ő̊O���瑀�c���A����̂���ꏊ�܂Ń}�N���t�@�[�W���āA����̑g�D�ɋ����I�ɏW�߂�B����̂��̏�ŖƉu�͂����߂āA�E�C���X������זE���E���A�]�ڂ�Z�����j�~�ł���B���������d�g�݂��B �]�ڂ���������E���� �@�����O���[�v�́A���̕��@�Ńl�Y�~�̑O���B����Ƀ}�N���t�@�[�W��U���B�x�ɓ]�ڂ�������ɂ��}�N���t�@�[�W���W�߂���Ɗm�F�����B �@�}�N���t�@�[�W�ɑ����������E�C���X�̓����ŁA����̑g�D�͎��ۂɏk�������B�]�ڂ�Z����h�����ʂ��m�F�ł����B ���A���^�C���Ŋm�F �@���˂��邾���ł͂���ɓ��B����̂��s�\�������Ɖu�זE���A���C�ő��c���Ă���g�D�Ɍ����悭�W�߂���B �@����̓E�C���X�Ŏ��������A�������@�ōR����܂��זE�ɉ^���āA����p�̌y���ɂ��Ȃ�����B �@�̂ɖ߂������×p�̍זE���A����g�D�Ɍ������Ă����l�q�����A���^�C���摜�Ŋm�F�ł���Ƃ�����傫�ȓ������B �@�^�j��Ȕ��z�������I�Ȏ��Â͐��܂��B Med�G�b�W 2015�N9��10�� |
|
�咰�����������̎��Ԃ�����Ƃ��X�N���ቺ �������Ԃ�6���ȉ��Ń��X�N2�{�� |
| �@�咰�����������𑁂��I��点�Ăق����A�Ƃ͎v��Ȃ��ق����悢�B�����ɂ����鎞�Ԃ������قǁA��ɑ咰����ɂȂ�m�����Ⴂ���Ƃ��V���Ȍ����Ŏ������ꂽ�B���̒m���́A�����������̎������ԂɊւ��錻�s�̃K�C�h���C���𗠕t������̂��ƌ����҂�͘b���Ă���B �@�咰�����������ł́A��t�������ȃJ�����̕t�����ׂ��ǂ����҂̑咰�ɑ}������B�Ō�܂ő}��������A�ǂ������������������Ƃɂ��A��t�����O�ɑ咰�̓��ǂׁA�����O����a�ς̒��Ȃ������m�F���邱�Ƃ��ł���B�K�C�h���C���ł́A�u�ُ�Ȃ��v�̏ꍇ�̑咰�����������̏��v���Ԃ͏��Ȃ��Ƃ�6���ȏ�ł���Ƃ��Ă���B�ُ�Ȃ��Ƃ́A�����ُ킪�����炸�A�����̂��߂̑g�D�̎�����Ȃ��ꍇ�ł���B �@����̌����́A�ă~�l�\�^�B�̑�K�͐f�Ï���51�l�̈ݒ��Ȉオ6�N�ԂɎ��{������7��7,000���̑咰�������ɂ��X�N���[�j���O���������r���[�����B�������̔����܂ł̏��v���Ԃ͕��ϖ�9�����������A��10���̈�t�ł͌X�̕��ώ��Ԃ�6�������ł��邱�Ƃ��킩�����B �@���ώ��Ԃ�6�������̈�t�ɂ��X�N���[�j���O�������҂́A����6���ȏ�̈�t�̌��������Q�ɔ�ׂāA5�N�ȓ��ɑ咰����ǂ���m����2�{�ɂȂ��Ă����B����A�������̔����ɂ����鎞�Ԃ�8�����Ă��A�咰���X�N������ȏ�ጸ���邱�Ƃ͂Ȃ��悤�������Ƃ����B �@�u���̌��ʂ���A���s�̃K�C�h���C���Ő��������Ƃ���A�������Ԃ������̎��̎w�W�Ƃ��ė��p���邱�Ƃ��x�������v�ƁA�����̕M�����҂ł���ă~�l�A�|���X�ޖ��R�l�iVA�j�w���X�P�A�V�X�e����Aasma Shaukat���͏q�ׂĂ���B �@�咰�����������̎��Ԃ��Z���Ȃ闝�R�͂��܂��܂����A�u��ʂɁA�����ɂ����鎞�Ԃɂ�����炸�A�ǂ̈�t���咰���ǂ����S�Ɍ������邱�Ƃ�ڎw���Ă���v�ƁAShaukat���͘b���Ă���B���̌����́uGastroenterology�v�I�����C���ł�7��8���f�ڂ��ꂽ�B m3.com 2015�N9��11�� |
| ������A�����5�N���ΐ������\ - �S����64.3%�A�̑�35.9% |
�@���������Z���^�[(������)��9��14���A�S���̂���f�Ë��_�a�@��177�{�ݖ�17���Ǘ��ΏۂƂ����A��v5���ʂ̂����5�N���ΐ����������\�����B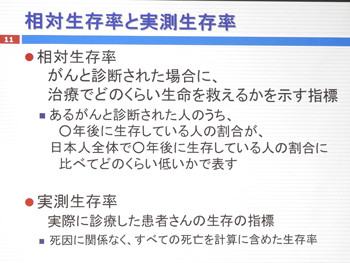 �@���ΐ������Ƃ́A����Ɛf�f���ꂽ�ꍇ�ɁA���Âłǂ̂��炢�������~���邩�������w�W�B5�N���ΐ������ł���A���邪��̂���5�N��ɐ������Ă���l�̊������A���{�l�S�̂�5�N��ɐ������Ă���l�̊����ɔ�ׂĂǂ̒��x�Ⴂ���ŕ\�����B���\���ꂽ�̂�2007�N�ɂ���f�Ë��_�a�@�Ŏ��Â��J�n�������҂�5�N���ΐ������B 5�N���ΐ������Ǝ����������̈Ⴂ �@���\�ɂ��ƁA�S�����5�N���ΐ�������64.3%�A�e���ʂŌ���ƈ݂�71.2%�A�咰��72.1%�A�̑���35.9%�A�x��39.4%�A�������[��92.2%�������B���킹�ēs���{���ʂ̃f�[�^�����\���ꂽ���A�f�[�^�̈��萫�����߂邽�߂ɁA�\��c����90%�ȏォ�W�v�Ώۂ�50��ȏ�̎{�݂�2�{�݈ȏ゠��s���{���̃f�[�^�̂��\���Ă���A�P���ɔ�r���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B 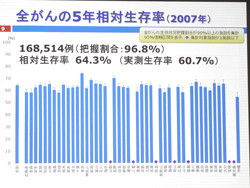 �@�܂��A�N��z��a���Ȃǂ��W�v���Ă���A������́u�N��̕��z�A�a���A��p�̊����ȂǂŐ������͕ς���Ă���B���������v�f�����Ȃ��番�͂��Ă����������Ƃɍ���̃f�[�^�̈Ӌ`������B�e�s���{�������͂�ʂ��āA�Ⴆ�Ό��f�̎�f�����グ�邽�߂̎��g�݂���������ȂǁA��𗧂Ă邽�߂̃x�[�X�Ƃ��Ăق����v�Ƃ��Ă���B �@�܂��A�N��z��a���Ȃǂ��W�v���Ă���A������́u�N��̕��z�A�a���A��p�̊����ȂǂŐ������͕ς���Ă���B���������v�f�����Ȃ��番�͂��Ă����������Ƃɍ���̃f�[�^�̈Ӌ`������B�e�s���{�������͂�ʂ��āA�Ⴆ�Ό��f�̎�f�����グ�邽�߂̎��g�݂���������ȂǁA��𗧂Ă邽�߂̃x�[�X�Ƃ��Ăق����v�Ƃ��Ă���B�@�W�v����ɂ������Ẳۑ������A�������c�����邽�߂ɒn�������̂ɊO���Ɖ�K�v�ƂȂ����ۂɁA�l���ی�Ȃǂ𗝗R�ɋ��͂����ގ����̂��������Ƃ����B���̓_�ɂ��Ă�2016�N�f�f�Ⴉ��͑S������o�^�����{����A�e�{�݂ł̐����m�F���������~���ɂȂ�Ɗ��҂���Ă���B�Ȃ��A2016�N�f�f��̏W�v���ʂ����\�����̂�2023�N�̗\��ŁA2022�N�̔��\�܂ł͌���̉ۑ������邱�ƂɂȂ�B �@2008�N�Ǘᕪ�ȍ~�́A�s���{���ʂł͎�v5���ʈȊO���W�v�E���\����������Ō�����i�߂Ă���ق��A�{�ݕʐ����������\������j�����A������́u�{�ݕʑ��ΐ������ł͐����̂������茰���ɂȂ�B�����̈��萫�E���ΐ������̈Ӌ`�Ɋւ��闝����[�߂�K�v������v�Ƃ��Ă���B 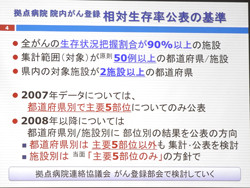 �}�C�i�r�j���[�X 2015�N9��15�� |
| �����{�ő����g�̂���h �����͊̉��E�C���X�����̑��� |
| �@���������Z���^�[�ɂ��u�S������늳���j�^�����O�W�v�i2011�j�v�̌��ʂ��݂Ă݂悤�B����͐��x�̔�r�I�����f�[�^������ꂽ39���{���ɂ��āA����늳�⎀�S�Ɋւ��30���ڂׂ����̂��B �@�����{�ł����Ƃ��늳�����Ⴂ�A�܂肪��ɂ�����ɂ������́A�j���͉��ꌧ�A�����͊��B���S�����Ⴂ�̂́A�j���͍��쌧�A�����͉��R���������i���̕\�j�B������S���������Z���^�[�������Z���^�[���v�������̏��c�q�厁�����ڂ����̂́A�L�������B �u�L�����̜늳���͕��ς�荂�߂ł����A���S�����Ⴂ�B���҂��Ƃ炵���킹��ƁA���f��[�������Ȃǂ̗L���Ȃ��������{���Ă��āA���������E�������Â���������ł��Ă���\��������ƍl���Ă��܂��v�i���c���j �@�L�����ɂ́A�u�n�悪��f�ØA�g���_�a�@�v��11�J������A���̈�L����w�a�@���u�s���{������f�ØA�g���_�a�@�v�����˂Ă���B���c���ɂ��ƁA�n��̂����Â��ǂꂾ���d���Ă��邩���݂�u���_�J�o�[���v�ł��A�L�����͍����Ƃ����B �@�����ʂ̜늳���ł݂�ƁA�����{�ɑS�̓I�ɑ��������̂��̂��B�S�����ς�100�Ƃ���ƁA�����{�̑啔����100���������A�����{�́A�Ƃ��ɋߋE�n���Ȑ���120����{�������������B�݂���͒j���Ƃ��ɒ����n���̌��Ƙa�̎R���ɁA�x����͎O�d����a�̎R���A���Ɍ��ȂNjߋE�n���ɑ��������B����A�咰����͎l��4���ł̜늳���̒Ⴓ���ڗ������B �u�̂���̌����̑唼���̉��E�C���X�̊����ł��B�E�C���X���̉��̔��Ǐ�g�僋�[�g�Ȃǂׂ�ƁA�Ȃ������{�ɑ����̂��킩��Ǝv���܂��B���̂���ł́A�i�����≖���ێ�ʁA����ʂȂǂ��W���Ă���ƍl�����܂��v�i���j �@�����ނ������{�����l�a�Z���^�[�́A���{�́u�s���{������f�ØA�g���_�a�@�v�ŁA����Əz��̕a�C����Ƃ���B �u�S���a������銳�҂���̑�����A���҂���͌������W����z��̕a�C�ɂ�����₷���ȂǁA���҂͐藣���Ȃ��W�ɂȂ��Ă��܂��v�i���Z���^�[�a�@���E���߁m���l�i�܂��Ɓj�n��t�j �@���Z���^�[�́A�x�����H������̊��Ґ��������A�X�����i�s�����H������A������ȂǁA��p�̓������ӂƂ���B�܂��A�݂����H������̓��������Âɂ������B17�N3���ɑ��s�����悩�璆����̑��{���߂��Ɉړ]����B�~�n���ɂ͖��Ԃ̏d���q�����Î{�݂����z�����\��ŁA��p�A�Ö@�A���ː����ÂȂǂ̏W�w�I���Â�S���ŐV�̈�Ë@�ւƂ��ăX�^�[�g���B �@��n�߂ɊO����f�̕��@�����P���A���f�A�����A���Õ��j�̌���܂ł�1�����x�ŏI��点��V�X�e���ɕς����B���̌��ʁA���@�̕��ϑ҂���������20������2�T�ԂɒZ�k�ł����B �u����܂ł́A5�N�������������ɏグ�邩�ɂ�������Ă��܂����B�������͑厖�Ȃ��Ƃł����A���ꂾ���ł͍��̂����Â͐��藧���Ȃ��B�҂������𑁂߂�ȂǂŌ������ʂ⎡�Â�҂��҂���̕s����a�炰�A�����x���グ��w�͂𑱂��Ă����܂��v�i���j �������{�̂��S���E�늳�� ���S���i�j���j�@1�ʁF�a�̎R���@�ʼn��ʁF���쌧 �@�@�@�i�����j�@1�ʁF���ꌧ�@�ʼn��ʁF���R�� �늳���i�j���j�@1�ʁF���挧�@�ʼn��ʁF���ꌧ �@�@�@�i�����j�@1�ʁF�L�����@�ʼn��ʁF�� �i�É����A���{�A�������A�{�茧�A���������͏����j dot.�h�b�g 2015�N9��15�� |
| 50�`60�Α�ɐS���ǎ����Ƒ咰����\�h�̂��߂̃A�X�s�����g�p�𐄏� |
| �@�č��\�h��ÃT�[�r�X��ψ���iUSPSTF�j��2015�N9��15���u�S���ǎ����iCVD�j����т���\�h�̂��߂̃A�X�s�����g�p�v�Ɋւ��銩���h���t�g�Ă\�B10��12���܂ł̈ӌ���W���J�n�����B�����Ăł́C�A�X�s�����ɂ�鏉���\�h�̑Ώێ����ɑ咰���lj����ꂽ�B �咰����\�h�ւ̎g�p�C�O���ł́u�������Ȃ��v �@CVD�Ɋւ���O��i2009�N�j�̊����ł͐��ʁC�N��Ɨ\�h�����҂���鎾���ȂǂŊ������敪����Ă����B�܂��咰����Ɋւ���O��i2007�N�j�̊����́u���ϓI���X�N��ւ̃��[�`���ȗ\�h�����𐄏����Ȃ��i�O���[�hD�j�v�ł������B �@�����ꂽ�����h���t�g�Ăł́C�����2�̎����̃A�X�s�����\�h�����Ɋւ��銩�����BCVD�ɂ��Ă͐��ʂ�CVD�̋敪��p�~�C�N��敪���ύX���ꂽ���C�咰����\�h�̊����O���[�h���㏸�����B �@�����h���t�g�Ă̊T�v�͎��̒ʂ�B�\�h�����̔��f�ɂ͔N��̑��C10�N�ȓ���CVD���X�N��A�X�s�����ɂ��o�����X�N���l�����邱�Ƃ����L����Ă���B 50�`59�F10�N�ȓ��̐S���ǎ����iCVD�j���X�N��10���ȏ�ŏo�����X�N���������C�]����10�N�ȏ��50�`59�ɂ�����CVD�Ȃ�тɑ咰����̏����\�h��ړI�Ƃ�����p�ʃA�X�s�����g�p����������k�O���[�hB�i�����j�l 60�`69�F10�N�ȓ���CVD���X�N��10���ȏ��60�`69�ɂ�����CVD�Ȃ�тɑ咰����̗\�h��ړI�Ƃ�����p�ʃA�X�s�����̎g�p�̔��f�͌ʂɍs���k�O���[�hC�i�Ώێ҂̏ɉ����������j�l 50�Ζ����C70�Έȏ�̓G�r�f���X�s�\���i�O���[�hI�j MedicalTribune 2015�N9��16�� |
|
�ق���Ǝv�����炪���� �畆����̈��E�����m�[�}�̌��������Ƃ� |
| ���̂ق���A������������畆����? �@�قڂ��ׂĂ̐l�ɕK������ƌ����Ă����ق���B���̐��͌l�������邪�A�̂̂����鏊�ɂ���l���唼���B �u�����ڂ���v�Ƃ������t�ɑ�\�����悤�ɁA�ق���͂��̐l�̃`���[�~���O�|�C���g�ƌ����邱�Ƃ��������ŁA�C�ɓ���Ȃ��ꏊ�ɂ���ꍇ�͔��e���`�ŏ������邱�Ƃ��\���B �@���̂悤�ɁA�����Ӗ��ł������Ӗ��ł��������̌����ڂ��ۂɉe����^����ق��낾���A���͂��̂ق���Ɏp�`�������畆�����邱�Ƃ͂��������낤���B �@�{�e�ł́A��R�畆�� �X�L���i�r�N���j�b�N�̉@���ł��镞���p�q��t�̉�������ƂɁA�畆����̎�ނ⌟���E���Õ��@�Ȃǂɂ��ďЉ�Ă������B �畆����̎�ނ��w�� �@�畆����́A�畆���\������זE�������ɕω��������̂̑��̂��B�傾������ނ͈ȉ��̒ʂ�B �����זE����c�c�\��̊��זE(�\��̉��w�ɑ��݂���זE)�Ȃǂ��\������זE���甭�a���� ���L��(�䂤���傭)�זE����c�c�L���w�ƌĂ��A���זE�����\�瑤�ɋ߂����������������� ���{�[�G���a�c�c�L���זE���l�A�\��̗L���w�̍זE�����������́B���B���\��̒������ɂƂǂ܂��Ă���A�]�ڂ���P�[�X�͏��Ȃ� ���p�W�F�b�g�a�c�c�����Y�����銾�튯�R���̍זE���甭�a���� �@�畆����͂��̂悤�ɕ����̎�ނ����邪�A�����̔畆����͂��܂�ɂ݂��Ȃ��A�����o�̏ǗႪ�����Ƃ����B �u�����p�߂�����ɓ]�ڂ��邱�Ƃ͂���܂����A���������œ]�ڂ܂ł����Ȃ����̂������ł��B�݂���Ȃǂ̂悤�ɏd�lj����₷���P�[�X�́A���܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�畆����S�ʂ́A60�Έȏ�̍���҂Ŕ��ǂ���P�[�X���唼�ł��ˁB���O���ւ̖\�I�ł��Ƃ��A�������ǂ̌J��Ԃ��Ȃǂ��A�畆���ǂ̃x�[�X�Ƃ��Ă���܂��̂Łv�B �ق���ƌ��ԈႦ�₷�������m�[�} �@�畆����̂��悻50%�͊��זE����ƗL���זE����ɂ���Đ�߂���ȂǁA����2����\�I���݂ƌ�����B����Ȓ��A10���l��1.5�`2�l�قǂ̔��Ǘ��ŁA�N��1,500�`2,000�l�قǂ̊��҂ݏo���Ă���畆���A�ق���Ɏ��Ă���u�������F��v(�����m�[�})���B �@�����m�[�}�́A�����j�������F�f�זE�u�����m�T�C�g�v���������������Ƃ������Ŕ��ǂ���B���F���̐F�f������(�����イ)���ł��A�ق��̔畆��������A��r�I�]�ڂ��₷���ƌ����Ă���B���ǂ���͂�����Ƃ��������͂킩���Ă͂��Ȃ��B �u�����m�T�C�g�͑̒��ɂ��邽�߁A�����m�[�}�͂ǂ��ɂł��Ă����������͂Ȃ��̂ł����A���{�l�͖��[�ɂł��₷���w���[���q�^�x�ƌ����Ă��܂��B���Ȃ킿�A���̗����A�܂Ȃǂɂł��₷���A���{�l�͂����̕��ʂ�30%���炢�̊����ŏo�����܂��B���Ă̐l�́w�\�݊g��^�x�ƌĂ�A�̂Ȃǂɂł��邱�Ƃ������ƌ����Ă��܂��v�B �����m�[�}�Ƃق���̊ȒP�Ȍ������� �@����ł̓����m�[�}�̌������A���Ȃ킿�ق���Ƃ̌��������ɂ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����̂��낤���B������t�͈ȉ���3�̓�����������ꍇ�A�����m�[�}�Ƌ^���������悢�Ƙb���B ����1 �F�ɔZ�W������A�`�����тȂ��� �u�����m�[�}�ł悭������̂́A�`���s���ł��邱�Ƃł��B�܂�A�`�����т�������A���E�Ŕ�Ώ̂�������A���F�ɔZ�W���������肵�܂��B����ɁA�畆�̈ꕔ������オ���Ă���ꍇ��A���ʂ�����ꍇ�������m�[�}�̉\��������܂��v�B ����2 ���a��6mm�ȏ�̂��� �u�����m�[�}�͒��a��6mm�ȏ�ƌ����Ă͂��܂����A�S�����S�������ł͂���܂���B����ɁA���ʂ̂ق���ł�6mm�T�C�Y�̂��̂�����܂��B6mm�ȏオ�����m�[�}�́w��Ώ����x�ł͂Ȃ����߁A���ꂮ�炢�̃T�C�Y�̂ق���炵�����̂��������ꍇ�ɂ́A���v���ǂ�����a�@��N���j�b�N�Ō��Ă��炤�̂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�B ����3 �C�Â��Ȃ������ɏo���������� �@���ƂȂ��ł͂��邪�A���g�̂ق���̏ꏊ��c�����Ă���l�����Ȃ��Ȃ����낤�B�����A������ӂƁA���m��ʏꏊ�ɂق���炵�����̂���������A�}���ɐ������������m�[�}�̉\�������邽�ߗv���ӂƊo���Ă������B �@�����͈�ʓI�ȃ����m�[�}�̌������������A���ɂ͓��L�̍����F�f�̂Ȃ��u�A�E�����m�e�B�b�N�E�����m�[�}�v�ƌĂ��^�C�v������Ƃ����B���Ɠ������A���Ԃ݂��������F�ŁA������Ƃ������₽���̂悤�Ɍ�����Ƃ����B�����A10���l��1.5�`2�l�قǂ̔��NJm���̃����m�[�}�̒��ł��A����ɂ܂�ȏǗ�B����炵�����̂������Ă��A�����܂Ő_�o���ɂȂ�K�v�͂Ȃ��ƌ����������B �����E���Õ��@��m�� �@����A�����m�[�}�Ƃ��ڂ������̂������Ă��܂����ꍇ�́A�畆�Ȃ�a�@�ȂǂŒʏ�́u���f�v�������́A�ق�����g�債�Ċώ@����u�_�[���X�R�s�[�v�ƌĂ�錟������̂���ʓI���B �u�_�[���X�R�s�[�̌��ʂ��^�킵���ꍇ�A�w�����x�Ƃ����畆�̈ꕔ���̎悷�錟�������܂��B�������ă����m�[�}�������ꍇ�́A�����Ɋ����̊g��؏���p�������ق��������ł��ˁB�_�[���X�R�s�[�͕��ʂ̔畆�Ȃł��ł��܂����A���f��������߁A�Z�J���h�I�s�j�I���𐄏�����ꍇ������܂��B���Â͊����̊g��؏���p�Ə��������p�B�ւ̓]�ڂ��Ȃ����m�F����w�Z���`�l�������p�ߐ����p�x���A���邢�͏��������p�ߓ]�ڂ��������ꍇ�́w���������p�ߊs���p�x�����܂��v�B �@�؏���́A�R����܂�C���^�[�t�F�������g�p���邪�A�����i�K�Ő؏�������̑S�g�����Ŗ��Ȃ���A�R����g�p�Ȃǂ��T����P�[�X������B������t�́A�u���������E�f�f�������Ύ�p������݂̂ł��݂܂����A���Ì���Ĕ��E�]�ڂ��Ȃ�������I�Ȍ����E�f�@�͕K�v�ɂȂ��Ă��܂��v�Ƙb���B �@�u�����v�Ƃ������������ʂ�A�����m�[�}�͕��u���Ă��������p�߂Ȃǂɓ]�ڂ��Ď��S����\��������B���ꂾ���ɁA�����납�玩���̑̂�̒��ɋC��z��悤�ɂ��Ă����A�����ł��s���Ɏv�������Ë@�ւ���f����悤�ȏK�������悤�ɂ��Ă������B �L���ďC: �����p�q(�͂��Ƃ� �Ђł�) �������q��ȑ�w���ƁB�畆�Ȑ���B���{�畆�Ȋw��A���{���[�U�[�w��A���{�Տ��畆�Ȋw��A���{�A�����M�[�w��ɏ����B��w���ƌ�ɓ������q��ȑ�w�a�@��JR���������a�@�̔畆�ȂɋΖ�������A2005�N����R�畆�� �X�L���i�r�N���j�b�N�̉@���߂�B �}�C�i�r�j���[�X 2015�N9��17�� |
|
�z�������̉e���ő�����O���B����̎��Ë����A�R���X�e���[���̖�X�^�`�������ʂ��� �u�A���h���Q���Ւf�Ö@�v�̌��ʂ����߂� |
| �@�z�������̉e���ő�����^�C�v�̑O���B����ɃR���X�e���[���̖Ӗ������悤���B �@�O���B����̎��Âł���u�A���h���Q���Ւf�Ö@�iADT�j�v���n�߂��Ƃ��ɁA�R���X�e���[�����������ł���X�^�`�����g���ƁA�a�C�̐i�s�������Ƃǂ߂�����Ԃ����т�Ƃ������́B �ז��ł���H �@�č��n�[�o�[�h��w��w���̃_�i�E�t�@�[�o�[�������𒆐S�Ƃ��������O���[�v���A����̐�厏�ł���W���}�iJAMA�j�I���R���W�[����2015�N�V���ɕ��Ă�����́B �@�O���B����̒��ɂ͒j���z�������̉e���ő�������̂�����B���̏ꍇ�ɁA�j���z���������ז�����u�A���h���Q���Ւf�Ö@�v�����ʂ������B �@�����O���[�v�����ڂ����̂́A�e�X�g�X�e�����̑O�i�K�̕����uDHEAS�i�f�q�h���G�s�A���h���X�e�����T���t�F�C�g�j�v��O���B����̂���זE����荞�ގd�g�݁B �@�X�^�`���ɂ���Ă��̎�荞�݂��ז��ł���Ɖ����𗧂Ă��B �ꏏ�Ɉ��ނƂ�����������Ȃ� �@�����O���[�v�͑O���B����̂���זE���g���Č��������{�B���ۂɁA�X�^�`���ɂ����DHEAS�̎�荞�݂��ז������ƕ��������B �@����ɁA1996�N�P������2013�N11���̊Ԃ̃f�[�^�Ɋ�Â��āA�O���B����̃A���h���Q���Ւf�Ö@���Ă���926�l�ɂ��āA�ꏏ�Ɉ���ł����X�^�`���̌��ʂɂ��Ē��ׂ��B �@283�l�i31���j�̓A���h���Q���Ւf�Ö@���n�߂鎞�ɃX�^�`��������ł����B �@�X�^�`���p���Ă����j���́A���p���Ă��Ȃ������j���Ɣ�ׂāA�A���h���Q���Ւf�Ö@�̂Ƃ��ɑO���B����̐i�s���~�܂��Ă�����Ԃ̒����l�����тĂ����B�X�^�`��������ł���l��27.5�J���ɑ��āA����ł��Ȃ��l��17.4�J���B �@�֘A����������D�荞��ł��A���v�w�I�ɈӖ��̂��鍷�ł���Ɣ��肳��āA�댯�x��83���ɂȂ��Ă����B �@�]�ڂ̂������l�ƂȂ��l�̗����ŃX�^�`���̗L����������Ɗm�F�ł����B �@�X�^�`�����ꏏ�Ɉ��ނƗǂ���������Ȃ��B Med�G�b�W 2015�N9��18 |
|
������1�l������ɂȂ�Ȃ��������n�̑� ���̗��R�����炩�Ɂ\��p���f�B�A |
| �@2015�N9��13���A�����암�̍L���`������������͒����̑����������ƂŒm���Ă���B��������j�юs䫉Y���̂��鑺�́A�l��3653�l�̂����A������1�l������ɜ늳����Z�������Ȃ����Ƃ��킩�����B���̌�����č��̂����Ì����`�[�����˂��~�߂��B��p�̃o�C�������f�B�A�EAnyElse���`�����B �@��Ð�[�Z�p����������č��̂��钲���`�[���́A���̑��ɐ������Č��n�̋C�y��Z���̐H�����A�����K���ɂ��ē��O�ɒ��ׂ��Ƃ���A�������炪����������Ă�����̂��u�T�g�C���̏�H�v���ƒf�肵���B�o�ϓI�ɕn�����ƒ낪�����A�H�����͎��R�ɒn�Y�n�������H����`�ɂȂ��Ă��邪�A�y�n���₹�Ă��邽�߁A�T�g�C�����炢�����ʎY�ł���_�앨���Ȃ��A1��3�H�T�g�C���Ƃ͐藣���Ȃ��H�����𑗂��Ă���B �@䫉Y���Y�̃T�g�C���ƌ����Έ�тł͗L���ŁA�ߗׂ̌i���n�E�j�тł͕K���݂₰�i�Ƃ��Ĕ����Ă���̂�ڂɂ��邱�ƂɂȂ�B�܂��A䫉Y���Y�̃T�g�C���͐���ɂ͍c��Ɍ��コ��A�����邪��ύD�Ɠ`������B �@�T�g�C���������}������̂ɂ�3�̌���������Ƃ����B 1�j�T�g�C���̓A���J�����H�i�ŁA�l�̂ɒ~�ς����_�������𒆘a�����p������B���ꂪ����זE���B��}������Ƃ����B 2�j�J���E�����͂��߁A�^���p�N���A�J���V�E���A�}�O�l�V�E���A�S�A�����A�J���e���Ȃljh�{�f���L�x�ŁA�Ɖu�͂����߂���ʂ�����B 3�j�T�g�C���̂ʂ߂萬���E�K���N�^�����A�Ɖu�͌���Ƃ���זE���B�̗}���Ƃ��Ɍ��ʂ�����B ���C�u�h�A�j���[�X 2015�N9��19�� |
|
���g�z���~�����p�������X�N�ቺ�Ɗ֘A�� �p�Q�ɔ�ה��Ǘ���34���̒ቺ |
| �@�r�O�A�i�C�h�iBG�j��ł��郁�g�z���~���̕��p���A���A�a���҂ɂ����铪����̔��ǃ��X�N�ቺ�Ɗ֘A����\�����A�uHead & Neck�v9�����Ɍf�ڂ̘_���Ŏ����ꂽ�B �@��p�E�����ÃZ���^�[��Yung-Chang Yen����́A2002�N�ɐV���ɓ�����Ɛf�f���ꂽ���A�a����6��6,600�l��ΏۂɁA2011�N�ɂ����铪����̃��X�N�����g�z���~�����p�Q�Ɣp�Q�i�e�Q3��3,300�l�j�Ŕ�r���������B���Q�Ԃ͕��������A���ʁA�N�����v�������B �@������̔��Ǘ��́A���g�z���~�����p�Q�Ŕp�̑ΏƌQ�ɔ�ׂ�34���ቺ���邱�Ƃ��킩�����k������n�U�[�h��iHR�j0.66�l�B���l�ɁA���g�z���~�����p�Q�ł́A�ΏƌQ�ɔ�ׂĒ��������X�N�i������HR 0.66�j����я��������i������HR 0.5�j���ꂼ��̃��X�N���L�ӂɒቺ���Ă����B �@������́A�u�����̒m������A���g�z���~���̕��p�ɂ́A���A�a���҂ɂ����铪����̔��ǂ�\�h����Ƃ������Տ��I�ȃx�l�t�B�b�g������\�����������ꂽ�v�Əq�ׂĂ���B m3.com 2015�N9��24�� |
|
�זE���Q��T�זE��iPS�זE�Ŏ�Ԃ� ���f�B�l�b�g�|����A�V���ȖƉu�זE���Âŋ����J����{���� |
| �@���f�B�l�b�g�́A�l�H���\�����זE�i���o�r�זE�j��p�����V�����Ɖu�זE���Âɂ��āA������w�Ƌ����J����{���ӏ�����������B����̒����[�������ƁA�Ɖu�זE�̈��ł���זE���Q���s�זE�i�b�s�k�j�����o�r�זE�����Ď�Ԃ点�čĐ����Ď��ÂɎg�����Ƃ�ڎw���B �@�b�s�k�͂����E�C���X�Ƃ̒�����ŘV���E�敾���Ă��܂��B���Ì��ʂ����コ���邽�߂ɁA�b�s�k�����҂���O�Ɏ��o���A�̊O�ő��������đ̓��ɖ߂����Ö@���s���Ă���B �@����ɑ�����������́A�b�s�k�זE���炉�o�r�זE��U�����A�ēx�b�s�k�ɖ߂����ƂŁA��Ԃ�ƂƂƂ��ɂb�s�k���ʂɓ��邱�Ƃ��o����V�����Z�p�J���ɐ������Ă���B���������Z�p�ƃ��f�B�l�b�g�̋Z�p�A�זE�|�{���H�{�݁i�b�o�e�j�𗘗p���ĊJ������������B m3.com 2015�N9��29�� |
|
�̍זE���Ĕ��\���Ɂu�V�}�[�J�[�v �����z���DNA�Ŋ��̏d�Ǔx��\�� |
| �@�č�������w��iAGA�j��9��10���A�̍זE����p�O�̌����z���DNA�icirculating tumor DNA�j���o�ɂ��A�̍זE���̑����Ĕ����\���ł��A���Õ��j�����Ă���Ƃ����������ʂ��Љ���B���w��̃W���[�i���ACellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology���Ɍf�ځB �@�����҂�́A�̑��E�o��̈ڐA�ȂǂŊ̍זE���؏����A�p�O�Əp��Ɍ������̂��̎�ł�������46�l�ɑ��đS�Q�m������́B��ᇂ��番������DNA�Ƃ��̊��҂̐����DNA�Ƃ��r�����Ƃ���A46�l�S���̌��̂���ψق����o���ꂽ�B�������A�����z���DNA�����݂����̂�7�l�݂̂ŁA�����z���DNA�́A��ᇂ��傫���A�̑��؏���2�N�ȓ��̍Ĕ����X�N�̍����Ɋ֘A�t����ꂽ�B�܂��A�����z���DNA���x���́A���̐i�s���x�Ǝ��Ì��ʂɔ��f����邱�Ƃ����������B �@��C�������҂ł���L����w�̑��֎i���́A�u�����z���DNA���x�������̐i�s��̍זE���ɑ��鎡�Ì��ʂ𐳊m�ɔ��f���Ă��邱�Ƃ�˂��~�߂��B����̌����ɂ��A�z���DNA��͂�ʂ����Q�m���v���t�@�C���̓��肪�̍זE���̌ʎ��Â̎w�j�ƂȂ蓾��v�Əq�ׂĂ���B �@�̍זE���͔������x��邱�Ƃ������A5�N��������11���ɗ��܂�B���̐i�s���Ď����A���Ì��ʂ������銳�҂���肷��V���ȕ��@�������邱�Ƃ��A�̍זE���̐������̉��P�ɂ͋��߂��Ă���B�����ҏW���́A�u�i�s�����̍זE���̎��Â̗L���������߂邽�߂ɁA����̗L�]�ȃf�[�^�Ɋ�Â�����̌������]�܂��v�Əq�ׂĂ���B m3.com 2015�N9��30�� |
|
�ƒ�p�E���܂̎g�p���������X�N�Ɋ֘A �����̔��I�Ō��t���X�N��4���㏸ |
| �@�����ŎE���܂ɔ��I���������͔����a����p��ǂ��郊�X�N����⍂�����Ƃ��A�V���ȃ��r���[�Ŗ��炩�ɂ��ꂽ�B�܂��A�����ܔ��I�Ɣ����a���X�N�̊Ԃɂ��ア�֘A���F�߂�ꂽ�Ƃ����B �@�uPediatrics�v9��14���I�����C���ł���ш����10�����Ɍf�ڂ��ꂽ���̒m���́A�E���܂����ڂ���̌����ƂȂ邱�Ƃ𖾂炩�ɂ�����̂ł͂Ȃ��B���ɂ������Ƃ��Ă��A���ǂɎ��锘�I�ʂ��ǂ̒��x�Ȃ̂��A�܂����ǂ̗ՊE�������݂���̂��͂킩���Ă��Ȃ��ƁA�ăn�[�o�[�h��w���O�q���w���i�{�X�g���j�y������Chensheng (Alex) Lu���͏q�ׂĂ���B�������A����ł������ɑ���u����̂������ł���Ɠ����͎w�E����B �@��������͂܂�Ȏ����ł���A�č�����iACS�j�̐���ɂ��ƁA�č��ō��N���炩�̂���Ɛf�f���ꂽ15�Ζ����̏�����1��400�l�����B���t����ł��锒���a����у����p��͏�������̂Ȃ��ł����ɂ悭�݂���B �@�ăj�N���E�X�����a�@�i�}�C�A�~�j�̏�����ᇈ�Ziad Khatib ���ɂ��ƁA�����K��������I�ɂ�萶�����l�̂���Ƃ͈قȂ�A��������̑����͋����I�ɐ�������̂����A����̃��r���[�������悤�ɁA�������̌����ł͎E���܂ƈꕔ�̏�������Ƃ̊֘A���F�߂��Ă���Ƃ����B �@�����Lu����̌����ł́A1993�`2013�N�Ɏ��{���ꂽ16���̍��ۓI�Ȍ����̌��ʂ������B������̌������A����̏����ƌ��N�ȏ������r���A�e�ւ̖�f�ɂ��ߋ��̎E���ܔ��I�ɂ��ĕ]���������̂��B �@���̌��ʁA�����p�E���܂ɔ��I���������͔����a�܂��̓����p��ɂȂ郊�X�N��43�`47���������Ƃ������B����A���O�p�̎E���܂Ƃ���̊֘A�͔F�߂��Ȃ������B�����܂ɔ��I���������͔����a���X�N��26�����������B �@����͖{��1���l��1�l�̔����a���ǃ��X�N���A1���l������1.5�l�ɑ�������Ƃ������Ƃ���Khatib���͐������A�����킸���ȃ��X�N������������댯���q���ƕt�������Ă���BLu���́A�u���̏���e�����ɒm���Ă��炢�A�e���ōőP�̔��f�����Ă��炤���Ƃ��d�v�v�Ƃ̍l���������Ă���B �@�E���܂��g������ɁA���̉a�ƂȂ�H�ו���u���Ȃ��A�U���܂�ߊl���p����Ȃǂ́u�w�I�ȑI�����v���Ƃ邱�Ƃ��ł���B�܂��A�����͊w�Z�A�����A�V�я�Ȃǂ̎���ȊO�̏ꏊ�ŎE���܂ɔ��I���邱�Ƃ����邽�߁A���̂悤�ȏꏊ�ŎE���܂̎g�p�𐧌����邱�Ƃɂ��Ӗ�������Ɠ����͎w�E���Ă���B m3.com 2015�N10��1�� |
|
�咰����CVD�\�h�ɃA�X�s�������� �č�ƕ���A50-59�ɐ�������B |
| �@�č��ƒ��w��iAAFP�j��9��16���A�S���ǎ����iCVD�j����ё咰���̈ꎟ�\�h�ɒ�p�ʃA�X�s�����̕��p�𐄏�����č��\�h��w��ƕ���iUSPSTF�j�̊����Ă��Љ���B �@�������Ăł́ACVD����ё咰���̈ꎟ�\�h�Ƃ��āi1�j�S���ǎ����̃��X�N�������A�i2�j�o�����X�N���Ⴂ�A�i3�j�Œ�ł�10�N�̕��ϗ]��������\�\50-59�̒j���ɑ��A��p�ʃA�X�s�����Ö@�𐄏��i�O���[�hB�����j�B�S���ǎ���������X�N������60-69�ɂ��ẮA�A�X�s�����\�h���^�̉��b�͂�����̂́A�����I�ȃ����b�g�����Ȃ����Ƃ���A���҂�CVD��o�����X�N�A���̓I�Ȍ��N�A�l�I���l�ς�n�D�Ɋ�Â��l�̔��f�ɔC����Ƃ��āAC�����Ƃ����B �@�܂��A50�Ζ����܂���70�Έȏ�ɂ��ẮA�A�X�s�����\�h���^�̗L�v���ƗL�Q����]������ɂ͌��s�G�r�f���X�ł͕s�\���ƌ��_�B���N��w�ɂ�I�����Ƃ��Ă���B �@AAFP��Jennifer Frost���́A�u60-69���50-59�ɑ��鐄���x�������̂́A��N��w�̕����A�X�s�����ɂ�鏃���v�������A����҂�CVD���X�N���������A�o�����X�N���������߁v�Ɛ������Ă���B �@�����Ăɂ��Ă�10��12���܂ňӌ����W�BAAFP��USPSTF�̍ŏI���_���\��Ɏ��g�̊����̍X�V���s���\��B m3.com 2015�N10��2�� |
| �����������܁A����ɂȂ�����...�H �Q�ĂȂ����߂�5�̐S�\�� |
| �@�����l�̂���Ɋւ���A���̃j���[�X�ŁA���f�̐\�������������Ă���B���܂̓��{�́A2�l��1�l������ɂȂ鎞��B�u�܂�������������ɂȂ�Ȃ�āc�c�v�ł͂Ȃ��A�����������������ɂȂ�����c�c��ƍl����ق��������I���ƁA�����̐l���C�Â��͂��߂Ă���̂�������Ȃ��B �@���������ہA����ɂȂ����Ƃ��̂��߂ɁA�ǂ�ȐS�\�������Ă����ׂ��Ȃ̂��A�킩��Ȃ����Ƃ������̂��������B�Q�ĂȂ����߂ɁA�������ɂł��邱�Ƃ͉�������̂��낤���H �@����Ō���Ō�t�ŁA���҂ƉƑ���F�l���x������Z���^�[�̐ݗ���ڎw���ANPO�@�l�}�M�[�Y�����̗����ł������_���b�q����ɘb�����B ��1.����͑��������ł���Ε|���Ȃ����Ƃ�m�� �@����ƂЂƌ��ɂ����Ă��A�Ǐ���i�ݕ����l�ɂ���Ă��܂��܂ł����A�����������قǁA�����̉\���͍��܂�܂��B���Ƃ��������Ȃ��Ă��A���܂͂���ƂƂ��ɐ����鎞��A����͖��������Ɉʒu�Â����鎞��ɂȂ�܂����B �@����̑��������̂��߂ɂ́A���f�����I�Ɏ邱�Ƃł��B �@���{�l�̂���̜늳���͔N�X�������Ă���̂ł����A���f�̎�f���͉��Ă̖���30?40%���x�B�s���ł��f�̖����N�[�|������z���Ă���̂ɂ�������炸�A�g���������Ȃ��̂ł��B����I�ɂ��f����A�������Ȃ���Έ��S�ł��܂��B���ꂪ�A����ɑ���S�\���ɂ��Ȃ����Ă����̂ł��B ��2.�����ɂƂ��đ�Ȃ��͉̂����A���C�ȂƂ�����ӎ����� �@����ɂȂ�ƁA���Â̂��߂ɐg�̂̏�Ԃ��ς��A�������ς��܂��B����܂Ŏ��R�ɂł������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�\�����o�Ă��܂��B�����A����̎��Ö@�͈�Î҂Ƒ��k���Ȃ����{�I�Ɏ����őI�ׂ܂��̂ŁA�����ɂƂ��đ�Ȃ��͉̂������i����ӎ����Đ������Ă���ƁA�����Ƃ����Ƃ����킸�ɂ��ނ��Ƃ�����܂��B �@�Ⴆ�A�s�A�j�X�g����e�t�ɂƂ��Ắg��h����Ȃ̂ŁA�肪���т�镛��p�̏��Ȃ��R������Ö@��I�ԁB�Ƒ��ƈꏏ�ɂ��鎞�Ԃ��ɂ������l�́A�ʉ@�ʼn\�Ȏ��Ö@��I�ԁB�H�ׂ邱�Ƃ��D���Ȑl�́A�H���ɂł��邾���e�������Ȃ����Ö@�𑊒k���Ă݂�B���̂悤�ɁA����ɂȂ��Ă��D�悵�����K���Ȏ��Ԃ�A��Ȏd����������ꍇ�́A���Ö@��I������ۂ̂ЂƂ̎w�j�ɂȂ�Ǝv���܂��B �@��t���炪�ǂ��Ȃ邩�̐����͂����Ă��A�������ǂ��ω����邩�ɂ��Ă̐��������Ȃ��ꍇ������̂ŁA�����̊�]����t�ɓ`������悤�ɂ��Ă������ق��������ł��傤�B ��3.�g����������̏��h�����W���� �@����Ƃ����a�C�͐獷���ʂŁA����̎�ށA�Ǐ�A���Ö@�A�����Ď��Â��I��������Ƃ̌o�߂��l���ꂼ��ł��B�C���^�[�l�b�g�ɂ́A����̏���̌��k����ꂩ�����Ă��܂����A�����ɓ��Ă͂܂�Ƃ͌���܂���̂ŁA�U���Ȃ����Ƃ���ł��B �@���ɁA����������ɂȂ��Ă��܂��Ɨ�ÂȔ��f���ł��Ȃ����Ƃ�����܂��̂ŁA���C�ȂƂ�����g����̐��������h�ɖڂ�ʂ��Ă����ƁA�����Ƃ����Ƃ��ɖ𗧂��܂��B �@��Ԃ̂������߂́A���������Z���^�[�����J���Ă���T�C�g�u������T�[�r�X�v�ł��B������ł́A����Ɋւ����{���͂������A����̗\�h�⌟�f�Ɋւ�����A���҂̎x�����x��A����ƂƂ��ɓ��������邽�߂̃|�C���g�A���Ƒ������̕��Ɍ��������҂ւ̑Ή��̎d���̃A�h�o�C�X�ȂǁA�M�p�ł�����邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�e�s���{���ɂ͂���f�ØA�g���_�a�@������A�����̂��k�x���Z���^�[�́A���̕a�@�̊��ҥ�Ƒ��łȂ��Ă��d�b�ő��k���ł��܂��B ��4.���m�̓`�����A�~�ߕ����Ƒ��Ƙb�������Ă��� �@�ǂ�Ȑl�ł��A����ƍ�������Ɠ��h����܂��B�����^�����ɂȂ��Ă��܂��āA�厡��̐������Ă��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��P�[�X���߂��炵������܂���B�Q�ĂȂ����߂ɐS�̏��������Ă��Ă��A��͂�Q�ĂĂ��܂����̂Ȃ̂ł��B�ł�����A�����⎡�Âɂ��Ă̑厖�Ȑ����́A���ЂƂ�ł͂Ȃ��A�Ƒ���F�l�ȂǐM���ł���l�ƈꏏ�ɕ������Ƃ��������߂��܂��B�����A�[���ȏǏ\�z�����ꍇ�A��t���璼�ځA���m���E�C���Ȃ��Ƃ����������邩������܂���B�]���������Ȃ��������邩������܂���B���̂��߂�������������ɂȂ�����A�ǂ��܂Ŏ�����m�点�Ăق������A�ǂ��������Ɏ�����m�肽�����A�Ƒ��ɓ`���Ă������Ƃ���ł��B �@�܂��A���e��q���ɐS�z�����������Ȃ�����Ƃ����āA�a�C���B�����Ƃ͂������߂��܂���B�ǂ�Ȃɍ���̐e�ł��A�e�͎q���̕a���m���āA�ꏏ�Ɏ�`���邱�Ƃ͎�`�������̂ł��B������m�炳��Ȃ������e�䂳�A���Ȃ�i�s���Ă���`�����āA�����Ƒ����m���Ă�����ƁA�{��ɂ��������������Ă���p���A���͖ڂɂ��Ă��܂����B �@�܂��A�q�������킢����������Ƃ������R�ł����`���Ȃ������ꍇ�A�u�����������q������v�Ǝ�����ӂߑ����邨�q��������܂��B���������ꂪ��Őe��S�����Ă��܂��ƁA�ꐶ���ꂪ�g���E�}�ɂȂ�̂ł��B�ł�����u�a�C�͂���̂����ł��Ȃ��v�Ƃ�����Ɠ`���Ă����Ă��������B��������������ɂȂ����Ƃ��A�����e�₨�q����ɐ^����`����o������Ă������Ƃ���Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B ��5.�R���Â����邩���Ȃ����A�Ƒ��Ƙb�������Ă��� �@���҂���̂Ȃ��ɂ́A�R���Â������Ȃ��Ƃ���������������Ⴂ�܂��B�ł��������邱�Ƃɂ���Ď������߂Â��\��������Ƃ������������`������ƁA�u���ɂ����͂Ȃ��v�Ƃ���������������̂ł��B�ł����玩�����A�ł��邾�����������邱�ƂƁA�����y����ʼn������Ȃ��悤�ɕ�炷���ƂƁA���̗������ɂł���悤�Ƀo�����X���l���Ȃ���I�����邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B �@�������ۂɂ���ɂȂ�ƁA�������g�����Ƒ����A���܂��܂Ȕ��f�ɔY�݁A�����A�ꂵ�ރP�[�X���悭����܂��B�b�������̂Ȃ��ŁA�ӌ����Η����邱�Ƃ��߂��炵������܂���B�����Ȃ�����Ȃ����ŁA�Ƃ��Ƃ�Y��ŁA�����āA�[���������܂Řb�������Ă��������B����̓��a�ɐ����͂���܂���B�ł��������[���̂����������ł���ƌ����������Ƃ͂ł���̂ł��B����ɂȂ��Ă���l�����P���������Ƃ�������銳�҂�������܂��B�ł��ł��邱�ƂȂ�A���C�Ȃ���������X���y���ݐl���̋P���𖡂���ĉ߂��������A���͂����v���̂ł��B �@�Ō���_������́A�u����ɂȂ������҂��m�̃l�b�g���[�N�͂������ł���B����ƍ������ăV���b�N�ŗ�������ł����l���A�g����F�h�����̌��C�Ȏp�Ɨ�܂��ɂ���ėE�C�Â����A���������ƑO�������Đ����Ă������������̂ł��B�����āA����ɂȂ���������Ƒ����x���悤�Ƃ���l���A�a�@�ɂ��n��ɂ��������܂���v�Ƌ����Ă��ꂽ�B �@�g�������h�̂Ƃ��̂��Ƃ́A�ł���l�������Ȃ��B�l���������Ȃ��B�����v���l�����邩������Ȃ��B�������A����̓��a�����z���Ė��邭�����Ă���l����������B����ɂ��čl���邱�Ƃ́A�����̐�������Ƒ��ɂ��čl���邱�ƁB�����Ƃ����Ƃ��̂��߂ɐS�̏��������Ă������Ƃ��A���X���ɐ����Ă������������ɂ��Ȃ邾�낤�B �n�t�B���g���|�X�g 2015�N10��6�� |
|
�R����܂̕���p�y���ɐV�������@�A�哤���Ȃǂ���������h�{�⋋�܂����� �u�C���g�����s�b�h�v���v���`�i���܂̓Ő����y�� |
| �@�č��J�[�l�M�[�E��������w���܂ތ����O���[�v���A�L�͉Ȋw���l�C�`���[���̎o�����ŁA�I�����C���Ȋw���ł���T�C�G���e�B�t�B�b�N�E���|�[�c����2015�N�U���ɕ������́B �@�����O���[�v�����ڂ��Ă���̂́u�v���`�i���܁v�ƌĂ��^�C�v�̍R����܁B �@�����ʂ�A�v���`�i�i�����j���g������B�v���`�i�ɂ͍זE������ז����鐫��������A���̐����𗘗p���Ă���B35�N�ȏ�ɂ킽���čL���g���A�V�X�v���`���A�J���{�v���`���A�I�L�V�v���`���Ȃǂ��܂��܂Ȏ�ނ�����B �@����p�Ƃ��ẮA�t���ւ̃_���[�W�Ƃ��������̂�����B �i�m���q��荞�ݔ��� �@�����O���[�v�ɂ��ƁA�v���`�i���܂̕���p�́A���N�ȑg�D�ɒ~�ς��ċN����B �@�������זE�ɑ��邽�߂Ƀi�m���q���g����̂��A����ł�����זE�ɓ͂��̂͂킸���P�`10���B�̂ɔ����Ɖu�@�\�̂��߂ɁA�唼�͊̑����B���ɑ����Ă��܂��B �@�̑����B���ɏW�܂�ƁA����̎��Âɂ͗��p�ł��Ȃ��Ȃ�A�ނ���Ő������ɂȂ�B �@�����O���[�v�́A���{�ł���ʓI�Ɏg���Ă���h�{�܂ł���u�C���g�����s�b�h�v���A�̑����B���ɂ��i�m���q�̎�荞�݂�ጸ����Ɣ����B�C���g�����s�b�h�͑哤���Ȃǂ�����ꂽ�����܂ƂȂ��Ă���B �@���������ɂ���āA�v���`�i���ܓ��^����24���Ԍ�A�v���`�i���܂̒~�ς��̑��ł͖�20���A�B���ł͖�43���A�t���ł͖�31����������Ɗm�F�B�Ő��̕���p���啝�ɒቺ����ƌ������B ����זE�ւ̌��ʂ����߂�\���� �@����ɁA�C���g�����s�b�h�̒����ɂ��A�v���`�i���܂�������ۂ��đ̓��ɂƂǂ܂鎞�Ԃ������Ȃ��Ă����B��葽���̖A����זE�ɓ͂��A�p�ʂ����炷�\��������Ƃ����B �@�����O���[�v�͗Տ������Ŋm�F���悤�Ɛi�߂Ă���Ƃ����B �@���Ɉ�Ì���Ŏg���Ă���h�{�܂ł��邾���ɁA�������߂��̂�������Ȃ��B Med�G�b�W 2015�N10��9�� |
| �]�E�ɂ����Ȃ����R���𖾁A�Č��� |
| �@�]�E�́A���̑傫���̂ɂ�������炸�A����ɂȂ邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B���́u��v���߂��錤�����ʂ�8���A���\����A�]�E�����A����ɑ���h��@�\�̔閧�����炩�ɂ��ꂽ�B�q���g�͈�`�q�̒��ɉB����Ă����Ƃ����B �@�č���t��G���Ɍf�ڂ��ꂽ�����_���ɂ��ƁA�]�E�ɂ́A��ᇂ̌`����}������^���p�N���u���T�R�v���R�[�h�����`�q�̈ꕔ���ω������R�s�[���R�W���邪�A�l�Ԃ́A���̎�̃R�s�[���Q���������Ă��Ȃ��Ƃ����B �@����́A�]�E�̑̂��i���̉ߒ��ŁA��ᇂ̌`����j�~�����`�q�̒lj��̃R�s�[�𑽐��쐬���Ă������Ƃ��Ӗ�����B �@�]�E�͐l�Ԃ��͂邩�ɑ����̍זE�������Ă��邽�߁A�T�O�`�V�O�N�Ԃ̈ꐶ�̂����ɂ���ɂȂ郊�X�N�́A�l�Ԃ�荂���ƒʏ�͍l������B�������ۂ͂����ł͂Ȃ��̂͒����ԁA��Ƃ���Ă����B �@�]�E�̎����̖c��ȃf�[�^�x�[�X�͂������ʁA����Ŏ��ʃ]�E�͑S�̂̂T���ɖ����Ȃ����Ƃ����������B����ɑ��l�Ԃł́A����͎����̂P�P�`�Q�T���ƂȂ��Ă���B �@�_���̋����厷�M�҂ŁA�ă��^��w��w���n���c�}���������̏�����ᇈ�A�W���V���A�E�V�t�}�����́u�_���I�ɐ��_����ƁA�]�E�͓r�����Ȃ����̂���ǂ���͂��ŁA���ۂɂ́A�������X�N�ɂ�荡���͂�����ł��Ă���͂����v�Ƃ�����ŁA�u��葽���̂��T�R����邱�Ƃ��A���̓�������������������Ă��鎩�R�̕��@���ƍl���Ă���v�Ƒ������B �@����ɁA������댯�������鑹�������זE���E�����邽�߂́A���U���I�ȑ̓����J�j�Y�����A�]�E�ɂ͐��܂��������Ă���ƌ����`�[���͎w�E�B���̂��Ƃɂ��Ę_���ł́u�u�������]�E�̍זE�ł́A���̊������A���N�Ȑl�Ԃ̍זE�̔{�ɂȂ��Ă���v�ƋL����Ă���B �@�_���̋������M�҂ɂ́A�ăA���]�i�B����w��Đl�C�T�[�J�X�c���^�c���郊���O�����O�E�u���U�[�Y�E�]�E�ی�Z���^�[�̐��Ƃ������A�˂Ă���B �@�����`�[���́A����̐��ʂ��l�Ԃ̍R���Ö@�̐V���ȊJ���ɂȂ��邱�Ƃ����҂��Ă���B �����ʐM�� 2015�N10��9�� |
|
���S���ɂ����炷�B�ꂽ�댯 �V�K�f�f�̂��҂ŐS���g�D�̑�������������� |
| �@���҂́A������ᇂɂ���ĖڂɌ����Ȃ��S���ւ̑������Ă���\�������邱�Ƃ��A�I�[�X�g���A�̌����Ŗ��炩�ɂ��ꂽ�B�V���ɂ���Ɛf�f���ꂽ���҂ł͐S�����̑��݂������z�������≻�w�����̌����Z�x���������Ƃ���A�Տ��I���Ȃ��Ă����S���g�D�����Ă���\�������������ƁA�����O���[�v�͌��_�Â��Ă���B �@�č��S���a�w��iACC�j��Ana Barac���ɂ��ƁA�ߔN�A����̉��w�Ö@���S���ɓŐ���p�������炷���Ƃ��킩���Ă������߁A�S����Ƃ������̊Ԃ̕ǂ�����蕥���Ă���A�������͉��w�Ö@�����{����O�ɐS�����̉Ȋw�I�w�W���`�F�b�N���邱�Ƃ������Ƃ����B����������̌����ŁA���҂͉��w�Ö@����O���炱�������w�W�̒l�������A����̐i�s�ƂƂ��ɂ���ɏ㏸���邱�Ƃ��킩�����B �@�����ɂ��ƁA���̌��ʂ͂���ƐS���a�ɑ����t�̍l������ς���\��������Ƃ����B�{�����͊���555�l��ΏۂɎ��{����A��w���uHeart�v��9��28���f�ڂ��ꂽ�B �@����̌����ł́A���҂����w�Ö@���J�n����O�ɁA�S�����̒���ׂ��A�̌��t���������{�����B�Ⴆ�ΐS�؎��k�𐧌䂷��g���|�j���ƌĂ�鉻�w�����́A�S��������N���������Ƃ����邩����������̂ɗp������ƕăJ���t�H���j�A��w�T���t�����V�X�R�Z�iUCSF�j������Ann Bolger���͐������Ă���B �@���҂�2�N�Ԃɂ킽��ǐՂ��A���̊Ԃɖ�3����1�����S�����B���͂̌��ʁA�g���|�j�����͂��߂Ƃ���e�z�������̒l�́A����̏d�Ǔx�ƂƂ��ɏ㏸���Ă���A�Ȃ��ɂ͒ʏ��100�{�ɂȂ���̂��������B������̎w�W�ɂ����҂̑S�����ɂ�鎀�S���X�N�Ƃ̗L�ӂȊ֘A���F�߂��A21�`54���̏㏸���݂�ꂽ�B �@���ԐړI�ɐS���ɑ�����^����@���Ƃ��ẮA�Ⴆ�ΐg�̂�������U�����邽�߂ɉ��ǔ����傳���A���ꂪ�S���ɊQ���y�ڂ����Ƃ��l������Ƃ����B�܂��A�p�C���y���A���E�J���b�W�E�����h����Alexander Lyon���ɂ��ƁA���ؓ���j��Ő��������Y�����邱�Ƃɂ�蒼�ړI�ɐS����������\��������Ƃ����B �@�������A��ᇂ̑��B�ɕK�v�ȐV���ȏ����ǂ��`�������Ƃ��ɂ��̂悤�ȃz�������≻�w�������Y�������ȂǁA�ʂ̗��R���l�������Barac���͎w�E����B����ł�����̌��ʂ́A���҂̐S���̏�Ԃ�]�����A���������邽�߂̖���Â��s�����Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ��������̂��Ɛ��Ƃ�͘b���B �@�u����̓��a���ɐS�����܂Ŕ��ǂ��邱�Ƃ͊��҂ɂƂ��ċɂ߂Č��������̂��B���̂悤�ȏ�����邽�߂Ɏ��s���������v�ƁABolger���͏q�ׂĂ���B m3.com 2015�N10��13�� |
|
�g���������l�͂��X�N�������\�� 10cm�����Ȃ�Ə�����18���A�j����11�����X�N�㏸ |
| �@500���l����X�E�F�[�f���l�j����ΏۂƂ��������ŁA�w�������قǂ��X�N���������Ƃ��������ꂽ�B���̌����ł́A���l���̐g����10cm�����邲�ƂɁA���X�N�������ł�18���A�j���ł�11�����܂邱�Ƃ������B���g�̏����͓�����̔��ǃ��X�N��20�����܂�ق��A�j���Ƃ��ɐg����10cm�����邲�ƂɃ����m�[�}�i�������F��j�̃��X�N����30���㏸���邱�Ƃ��킩�����B �@�u���̌����́A����܂ő��̌����Ŏ�����Ă����m���𗠂Â�����̂��B�ߋ��̌����ł́A�g���Ƒ咰����̊֘A�����炩�ɂ���Ă���v�ƕč�����iACS�j��Susan Gapstur���i����̌����ɂ͊֗^���Ă��Ȃ��j�͘b���B����ŁA���̂悤�Ȓm���������̂́A�����܂ł��g���Ƃ��X�N���֘A����Ƃ������Ƃ����ł���A�u���g�����炪��ɂȂ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��v�Ɠ����͋������Ă���B �@�g���Ƃ��X�N�Ɋ֘A���݂��闝�R�ɂ��āAGapstur���́A�g���͂��X�N�̕\��ł���\��������Ƙb���B�u���l���̐g���́A��`���q�Ɛ����ߒ��ŐG��Ă������q�f���Ă���B���̂��ߍ���̌�������A��N���ɔ��I����郊�X�N���q�̈ꕔ�ɂ��āA��������肪���肪������\��������v�Əq�ׂĂ���B �@����̌����ł́A1938�`1991�N�ɃX�E�F�[�f���ŏo������550���l�̏������r���[�B1958�N�ȍ~�܂��͑Ώێ҂�20�ɂȂ������_����A2011�N���܂őΏێ҂̌��N��Ԃ�ǐՂ����B���l���̐g���ɂ�100cm����225cm�܂ł̕����������B �@�����𗦂����X�E�F�[�f���A�J�������X�J�������i�\�[���i�j��Emelie Benyi���́A�u����͒j����Ώۂɐg���Ƃ���̊֘A�ɂ��Č��������ő�K�͂̌������v�Əq�ׂĂ���B�u����̌����͑����q���ł���A����̌������ʂ��l���x���̂��X�N�ɂǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ�����\������͓̂���v��Benyi���͏q�ׁA���g�̐l���F����ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��Ƌ������Ă���B�����O���[�v�͂���ɁA�g��������ɂ�鎀�S���X�N�ɋy�ڂ��e���Ɋւ��錤���̎��{��\�肵�Ă���B �@���̌������ʂ́A�悲��X�y�C���A�o���Z���i�ŊJ�Â��ꂽ���B����������w��iESPE�j�N���W��Ŕ��\���ꂽ�B�Ȃ��A�w��\���ꂽ�����͈�ʂɁA���ǂ��Ĉ�w���Ɍf�ڂ����܂ł͗\���I�Ȃ��̂Ƃ݂Ȃ����B m3.com 2015�N10��15�� |
|
�������m���ł����h�� �q�ǂ������ɕK�v�ȁu����v�Ƃ� |
| �@���{�ł͍��A2�l��1�l������ɂ�����A3�l��1�l������ŖS���Ȃ�Ƃ����Ă���B��������q�ǂ������ɂ���̐������m���������邱�Ƃ́A�q�ǂ������̖�����邽�߂ɂ��K�v�s�����B�x�l�b�Z������T�C�g�ł́A�u����v�̑��l�҂ł�����A������w��w���y�����̒���b�ꎁ�ɘb���f�����B ������ �@�l�Ԃ̑̂́A��60���̍זE����ł��Ă��܂��B�����זE�̈ꕔ�́A��������Ƒ��B���J��Ԃ��Ă��܂��B�e�זE�́A�זE�̐v�}�ł����`�q���R�s�[���đ����܂����A ���ɂ̓R�s�[�~�X�ɂ���āA��`�q�̓ˑR�ψق��N����ꍇ������܂��B���ꂪ�u����זE�v�ł��B����͍���ɂȂ�قǂ�����₷���ƍl�����Ă���A���E��̒������ł�����{�́A����ɂ�����\���������l�����E�ꑽ���Ƃ����܂��B �@���݂̓��{�ł́A2�l��1�l������ɂȂ�A3�l��1�l������ŖS���Ȃ�̂�����ŁA���Ґ��͔N�X�������Ă��܂��B��i���̒��ł����������Ă���͓̂��{�����ł��B���Ăł́A����������̒m�����q�ǂ������ɋ����āA�\�h�⑁�������ɂȂ��邽�߂́u����v���n�܂��Ă��܂����A���{�ł͂܂��܂��B���̂��Ƃ��A���Ǘ��������錴���̈�ɂȂ��Ă���ƍl�����܂��B �@����́A������Ƃ����m���Ŏ��S�����������܂��B���Ƃ��A�����K���̉��P�Ŗh����\�������܂�܂��B�܂������w�ł́A��������Ȃ�9���ȏオ�����ł���̂ł��B�����Ɍ����邱�Ƃ��d�v�ŁA���̂��߂ɂ͌��N�Ȏ��Ɍ��f���邱�Ƃ��]�܂�܂��B���Ăł�7�`8�������f���Ă��܂����A���{��2�`3�����x�ɂƂǂ܂��Ă���A����⌟�f�ɂ��Ċw�Z�ŏK���Ă��Ȃ����Ƃ�����ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B �@����́A�������m�������ĂA������m�������S���������邱�Ƃ��ł��܂��B�q�ǂ��̖�������邽�߂ɂ��A�������u����v�Ɏ��g�ނ��Ƃ�]��ł��܂��B livedoor�j���[�X 2015�N10��19�� |
|
���\�����O��זE��̊O�Ŗ������� �����ȂǁA���Ö@���p�Ɋ��� |
| �@�����w�������Ȃǂ̋��������`�[���́A�u���\�����O��זE�v�ƌĂ��זE�̊O�Ŗ����ɑ���������|�{���@���J�������B���זE�͌��t�̂��ƂƂȂ鑢�����זE�̂悤�Ɏ��ȕ����\�͎����Ȃ������\�����������̂ŁA���זE�l�̍זE�Ƃ�����B�������~���邾���Ŋ��זE�����l���ł���Ƃ�������܂ł̊��זE���̊T�O���V���Ȏ�@�������B�Ɖu�זE�ɕ���������Ȃǂ��čזE�Ö@�ւ̉��p���l������B �@�������זE�͊e��̌��t�זE����肾�����̂Ő��̊O�ő�����������@������Ɍ�������Ă�����̂́A���p�I�ȕ��@�͊m������Ă��Ȃ��B�����`�[���́A�d�Q�`�Ƃ����]�ʈ��q������������ƖƉu�זE�ł���a�זE�̕����������i�K�Œ�~���A�a�O��זE�����\�����O��זE�Ƃ��Ă̓����������Ƃ����m��������ɐi�߂Č��������B �@�d�Q�`�̓������ꎞ�I�ɑj�Q���邽�߂ɁA�d�Q�`�̑j�Q����ς��ł���h������ς����}�E�X�̑������זE�Q�֓����B�a�זE�ւ̕�����U������������ł����̍זE��|�{����ƑO��זE�i�K�ŕ�������~���A���\�����O��זE�������i���ȕ����j�����B���̍זE�͖�P�J���łP���{�ɂ܂ő��B���|�{�𑱂�����葝���������B���̑O��זE���}�E�X�ɈڐA����ƁA�����p�����������Ȃǂ��܂��܂Ȕ�������������B��ɔ����������o�����זE�Ƃ����Ӗ��ł��̍זE���u���k�r�i�l�H���������j�זE�v�Ɩ��Â����B �@���k�r�זE�͐Ԍ����⌌���͂��܂��炸���̓��ł͎��ȕ������Ȃ����̊O�ł͖����ɑ��₹��B����܂ł́A�������\�Ǝ��ȕ����\�̈ێ��͊��זE�������ێ��������Ȕ\�͂ƍl�����Ă����B�܂��A���̊O�ł��̏�Ԃ����肾���ɂ́A�������Ȃǂ̎�@�ɂ�薢�����ȏ�ԂɊ����߂��K�v������Ǝv���Ă����B����̌����ɂ���āA�P�ɕ������~�����邾���Ŋ��זE�����l�����鎖�����߂Ď����ꂽ���ƂɂȂ�A�u���זE���v�̊T�O��ς���\�������锭�����Ƃ��Ă���B �@���p��Ƃ��ẮA���҂̑����O��זE���炉�k�r�זE���쐻���A����זE�₪��R�����ٓI�ȃL���[�s�זE���ʂɍ쐻���邱�Ƃɂ�邪��זE�Ö@�Ȃǂ����蓾��B�������זE��Ɖu�זE��p������`�q���Â̌����̐i�s�ɂ��𗧂Ƃ݂���B����ɂ́A�P�ɕ������~������Ƃ������l�̕��@��p���āA���̑g�D�ɂ����Ă����זE���ł���\��������B m3.com 2015�N10��26�� |
| �u���H���̔����vWHO�g�D�������ɔF�� |
| �@���E�ی��@�ցiWHO�j�̊O���g�D�ł��鍑�ۂ����@�ցiIARC�j�́A�x�[�R����\�[�Z�[�W�Ȃǂ̉��H�����u�l�ɑ��Ĕ���������v�A����Ȃǂ̐ԓ����u�����炭����������v�Ƃ��Đ����Ɏw�肵���B �@���E�ی��@�ցiWHO�j�̊O���g�D�ł��鍑�ۂ����@�ցiIARC�j�͂��̂قǁA�n����x�[�R���A�\�[�Z�[�W�Ȃǂ̉��H�����A�u�l�ɑ��Ĕ���������v�Ƃ���u�O���[�v1�v�Ƃ��Đ����Ɏw�肵���B �@IARC�́A����A�r�Ȃǂ̐ԓ����A�u�l�ɑ��Ă����炭����������v�Ƃ���u�O���[�v2A�v�ɕ��ނ����B �@���̌��_�́A800������u�w�����̕��͂��A22�l�̐��Ƃł���ψ���R�����ē���ꂽ���̂ŁA���ʂ́wLancet Oncology�x���Ŕ��\���ꂽ�i�w�ǂɂ͖����o�^���K�v�j�B���͂ɂ́A���܂��܂ȍ��▯���A�H�����ɂ킽��f�[�^���܂܂�Ă��邽�߁A�u���R���A�����ȂǂŐ��������Ƃ͍l���ɂ����v�Əq�ׂ��Ă���B �@�֘A�����ł������ɕ\��Ă���̂́A�u���H���̏���ʁv�Ɓu��������v�Ƃ̊֘A�����A���H���͈݂���Ƃ��֘A�t�����Ă���B �@����𗠕t����؋��̂ЂƂƂ��āA�ψ���ł�2011�N�̃��^���͌��ʂ����p���Ă���B����́A����I�ɐێ悷����H����50g���₷���ƂɁA�l����������ɂȂ鑊���X�N��18�������Ȃ�ƌ��_�t�������̂��B �@����ɂ��̒����ł́A����I�ɐێ悷��ԓ���100g���₷���ƂɁA�l����������ɂȂ鑊���X�N��17�������Ȃ邱�Ƃ��킩���Ă���B �@�؋��������Ă��邽�߁A�ԓ��Ƃ���Ƃ̑����Ɋւ���ψ���̌��_�́A�u�����炭�v����������Ƃ����\���ɂƂǂ܂��Ă���B�������A��������̂ق��ɁA�����������O���B����Ƃ����������邱�Ƃ��킩���Ă���B �@���Ƃ���Ƃ̊W�ɂ��ẮA���̃��J�j�Y���Ɋւ��鋭�͂ȃf�[�^������B���Ђ��������Ȃǂ̓��̉��H���@�ɂ���āA�j�g���\�������⑽�F�����Y�����f�Ȃǂ̔������w�������`�������̂��B �@�Ă��A�g����ȂǍ����Őԓ��������ꍇ���A�w�e���T�C�N���b�N�F�����A�~���Ȃǂ̊��m�̔���������A���̋^�������镨�����`�������B AFPBB News 2015�N10��27�� |
|
���ʌ��t�Ŋ��Ɖu�Ö@���ʂ��ʕ]�� ���f�B�l�b�g�ȂǁA�f�f��Ŏ��p�� |
| �@���f�B�l�b�g�͉��R��w��w�@���R�Ȋw�����Ȑ�����p�H�w��U�̓~��Y�y�����ȂǂƋ����ŁA����זE�ɑ���Ɖu�����̃��x�����������ʂ̌��t�����ʕ]������V�Z�p���J�������B����Ɖu�Ö@�̃R���p�j�I���f�f��Ƃ��Ă̎��p�������҂ł��A���Ö@�̎��p�����㉟��������̂Ƃ��Ď��p�����}���B �@�����O���[�v�́A���̂ق�������w��w�������a�@�A����Õ�����w�̃����o�[�ȂǁB����Ɖu���Â��悭�����Ă���Ǘ�ł͌��t���ɂ��܂��܂ȍR����R���R�̂��������錻�ۂɒ��ڂ��A���R�ׂ̂�R�̌����@���J�������B�����̂���R������ς����͕s�n�����₷���Ƃ����ۑ肪���������A�Ǝ��J���̉n���Z�p�̊��p�ʼn����A�����x�ȍR�̌��o���\�Ƃ����B �@���p�����̂́A����ς������q���ɑ��݂���a�����̍����c��ł���V�X�e�C���c��ɑ��ĉȊw�Z�p�C�����{�����n���Z�p�B����ɑS���E���n������R�����u���������r�[�Y�ɌŒ艻���邱�Ƃō����x�R�̌�������Ƃ����B �@����Ɖu�Ö@�́A����זE�ɂ��Ɖu�@�\�̗}������������������Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q�܂̊J���i�W�ȂǂŁA�V���Ȓi�K���}������B�����A���Ì��ʂ������܂łɐ��J����v����ꍇ�����邽�߁A��ᇂ̑傫�������f�Ă����̂ł͕]����������Ƃ�����B��ᇖƉu�����̊������ׂ�f�f���߂��Ă���A����̐��ʂ̓��A���^�C���ł̖Ɖu�����̒�ʑ�����\�Ƃ�����̂Ƃ��Ċ��҂����B�����オ��Ɖu�Ö@�̊m���ɖ𗧂Ƃ݂���B �@���̂悤�Ȏd�g�݂̐f�f��̊J���ɂ́A����R�����Q�O�O��ނ��鑽�푽�l���������Ƃ��ۑ�B����ɑ������O���[�v�ł́A�P�O�O��ޒ��̑S���̂���R������ς�����g�݊�������ς����Ƃ��č����Y���郊�\�[�X�̐������i�߂Ă���B m3.com 2015�N10��28�� |
|
�x�����ċC�Ŏ��ʂ��錟�m��J�� �t�B�K���Z���|�Y�����A�ċC��VOC���畡���x���}�[�J�[�����̑g�ݍ��킹���o�� |
| �@�Y�ƋZ�p�����������́A�g�N���}�O���[�v�̃t�B�K���Z���Ƌ����ŁA�ċC�Ŕx����̃X�N���[�j���O���ł���K�X���m����J�������B�ċC���̊������L�@�������i�u�n�b�j���畡���̔x����}�[�J�[�����̑g�ݍ��킹�����o���A���҂������x�Ŏ��ʂł���A���S���Y�����J���B�ȈՃK�X�N���}�g�O���t�B�[�^�u�n�b���m��Ƃ����B�Տ������Ɖ��ǂ�i�߂Q�O�P�V�N�̎��p����ڎw���B �@�u�n�b��ߏW���₷���z���܂ŋz���E�Z�k���A�Z�k�����K�X���J�����ŕ����B�����x�̔����̎��Z���T�[�ŕ���������Z�x�̂u�n�b�����m����B�����������x���̎����}�[�J�[���������m�ł���B�x���҂ƌ���҂̌ċC�K�X�����ƔZ�x�͑��u�Ōv�������v�I�ɉ�͂����Ƃ���A�u�^���A���`���V�N���w�L�T���A�A�Z�g���A�|�_�A�t�����A�v���s�I���_�A�A�Z�g�C���A�P�|���`���X�`�����A�m�i�i�[���Ȃǂ̂u�n�b���x����}�[�J�[�����̌��ƂȂ����B �@����ꂽ�ċC�K�X�����ƔZ�x�̌v�����ʂ�p���A�������̃f�[�^���l�ɕ��ނ���@�B�w�K�A���S���Y���ł���T�|�[�g�x�N�^�[�}�V���i�r�u�l�j�Ŋw�K�����A��f�f�҂Ɋւ����B����̔x����}�[�J�[�����̃Z�b�g�ɂ�荂���^�z�����Ɛ^�U�����ł̃X�N���[�j���O���ł��邱�Ƃ����������B���̌��ʂɊ�Â��A�x����ƌ���������x�Ŕ���ł���A���S���Y�����J�����A�ċC�u�n�b���m��v���g�^�C�v�ɑg�ݍ��B �@�܂����҂́A�M�d�����f�Z���T�[�f�q��p���Ē��ڌċC���̐��f�K�X�Z�x�𑪒�ł���ċC���f���m��v���g�^�C�v�����삵�Ă���B���s���Đ��f�K�X�Z�x�ƌ��N��ԁE�����K���Ƃ̑��ւ𖾂炩�ɂ��Ă���A���N�Ǘ��ւ̉��p��ڎw���Ă���B m3.com 2015�N10��29�� |
|
�咰���X�N���[�j���O�����Č��\ 50-75�̑S���l�X�N���[�j���O���������� |
| �@�č��ƒ��w��iAAFP�j��10��14���A�č��\�h��w��ƕ���iUSPSTF�j��10��6���ɔ��\�����咰���̃X�N���[�j���O�����Ɋւ��銩���Ă��Љ���B���Ăł́A�咰���̓X�N���[�j���O�����ɂ�莀�S�����ጸ���邱�Ƃ����߂ċ���������ŁA50-75�ɂ͋��������iA�����j�A76-85�́A���̓I�Ȍ��N��ߋ��̃X�N���[�j���O���Ɋ�Â��ʂɑΉ�����悤�������Ă���iC�����j�B �@�����ẮA���ϓI�ȑ咰�����X�N�̂��閳�nj�50�Έȏ��ΏۂƂ��A2008�N�łƓ��l�ɁA50-75�̑S���l�ɃX�N���[�j���O���������������B76-85�ɂ͌ʑΉ��Ƃ��Ă���A�X�N���[�j���O�����̗L�v���������Q�Ƃ��āi1�j����܂Ō��������Ȃ��A�i2�j�����������ꂽ�ꍇ�A���Â��邾���̌��N��Ԃ��ۂ���Ă���A�i3�j�����ɉe������悤�ȍ����ǂ��Ȃ��\�\�������Ă���B����A85����咰���X�N���[�j���O�͊��߂Ȃ��Ƃ̊�����lj����Ă���B �@�X�N���[�j���O�@�ɂ��ẮA2008�N�����ł́A5�N��1��̓S���������ƁA3�N��1��̖Ɖu���w�I���������iFIT�j�A�������͍����x�O�A���N���������igFOBT�j�̕��p���������Ă������A���s�Ăł͓��ɁA10�N��1��̓S���������ƔN1���FIT�̕��p�ɂ��ĉ�����Ă���B �@USPSTF��11��2���܂Ńp�u���b�N�R�����g���W���Ă���B m3.com 2015�N10��30�� |
|
�j�������T�v�������g�͑O���B���҂ɖ��v ���������⎀�S�̃��X�N�ጸ���� |
| �@�O���B���҂ɂ����āA�j�������T�v�������g�̗L�p���͔F�߂��Ȃ����Ƃ��V���Ȍ����Ŏ����ꂽ�B���ː����Â̕���p�̃��X�N�A���ǂ���̊g�U���X�N�A����ɂ�鎀�S���X�N�̂�������A�T�v�������g�Œጸ���Ȃ������B�����̕M�����҂ŕăt�H�b�N�X�`�F�C�X����Z���^�[�i�t�B���f���t�B�A�j�̌��C��ł���Nicholas
Zaorsky���ɂ��ƁA�V���ɂ���Ɛf�f���ꂽ���҂�2�l��1�l�͉��炩�̃T�v�������g�������Ă���Ƃ����B �@����̌����Œ��ڂ����̂́A�u�j�������v�u�O���B�̌��N�ɂ悢�v��搂��鐻�i�ŁA���̑����̓{�g���Ɂu�Տ��I�ɗ��؍ς݁v�u��A��Ȉオ���E�v�Ȃǂƕ\������Ă��邪�A���ۂɗՏ������͎��{����Ă��Ȃ��B2001�`2012�N�ɕ��ː��Ö@����36�Έȏ�̊���2,200�l�ȏ��Ώۂɒ����������ʁA��10�������Ò��܂��͂��̌��4�N�Ԃɖ�50��ނ̒j�������T�v�������g�̂���1��ވȏ���g�p���Ă����B �@90���ȏ�̃T�v�������g�͑O���B���ɗL���Ƃ����m�R�M�����V���o�����ܗL���Ă���A�ꕔ�ɂ͐��������炩�ɂ���Ă��Ȃ����̂��������i�u���̑��v�u��Ɣ閧�̍y�f�v�Ȃǂƕ\���j�B�T�v�������g�ɂ��L�Q�ȕ���p�݂͂��Ȃ��������A�^����H���Ȃǂ̐����K���̈��q���l������ƁA�T�v�������g�g�p�҂ɑS�������̌���͔F�߂�ꂸ�A�O���B����̓]�A�ɑ���։v�͂Ȃ��ƁA�����`�[���͌��_�Â����B �@�T�v�������g�ƊE�̎��ƎҒc�́A�L�p�h�{���R����iCRN�j��Duffy MacKay���́A���̕ɑ��A�j���p�T�v�������g�̎�v�����ɂ��Ă͗Տ������ŗL�ӂȌ��N�ւ̌��ʂ�������Ă���Ɣ��_�B����ɁA�u����̌����̎咣�͌��_���肫�Ńf�[�^��T���ē���ꂽ���̂ł���A�Ȋw�I������������Ă��Ȃ��v�Əq�ׁA�u������̐��i�����������Âł���Ƃ�搂��Ă��Ȃ��v�Ɠ����͕t�������Ă���B �@1994�N�ɐ��肳�ꂽ�č��̉h�{�⏕�H�i���N����@�ł́A�T�v�������g�̈��S���Ɋւ���ӔC�͐����҂��P�Ƃŕ������̂Ƃ��Ă���B�̔��ɂ͕č��H�i���i�ǁiFDA�j�ւ̓o�^���K�v�����A�\�����e�͐����҂Ɣ̔��҂̎���Ǘ��Ɉς˂��Ă���B �@���̒m���́A10��18�`21���ɕăT���A���g�j�I�ŊJ�Â��ꂽ��57��č����ː���ᇊw��iASTRO�j�N���W��Ŕ��\���ꂽ�B�Ȃ��A�w��\���ꂽ�����́A���ǂ��Ĉ�w���Ɍf�ڂ����܂ł͗\���I�Ȃ��̂Ƃ݂Ȃ��K�v������B m3.com 2015�N11��2�� |
|
�X���f�f�̃o�C�I�}�[�J�[�� ������A�����L�b�g���J�� |
| �@���������Z���^�[�͂X���A���t���̃A�|���|�v���e�C���`�Q�i�������`�Q�j�Ƃ�������ς����̃A�C�\�t�H�[���i�ِ��́j���A�����X������X���X�N�����Œቺ���邱�Ƃ������Ɣ��\�����B���łɂ������`�Q�A�C�\�t�H�[�������̃L�b�g���ɂ������B�͋[���f�ȂǂŗՏ��ł̗L�p����]�����A�X���f�p�̌��t�o�C�I�}�[�J�[�Ƃ��Ď��p����ڎw���B �@���Z���^�[�������E�n��Տ���������̖{�c�ꕶ���j�b�g���̌����O���[�v�̐��ʁB�����J���ȁA���{��Ì����J���@�\�i�`�l�d�c�j�́u�v�V�I�����Î��p���������Ɓv�̎x�����Ă���B �@�������`�Q�A�C�\�t�H�[���͑P�ʃR���X�e���[���i�g�c�k�j���`�����邽��ς����ŁA����l�̌��t���Ɉ��ʑ��݂���B�������O���[�v�͎��ʕ��͂̌��ʂ���A�������`�Q�A�C�\�t�H�[�����X������X���X�N�����̊��҂Œቺ���邱�Ƃ������������B �@�č������������i�m�b�h�j�Ƃ̋��������ł́A�č��̑����X���ҁi�P�C���A�Q�C���X����X�W��j���܂ނQ�T�Q��̌��t��p���Ă������`�Q�A�C�\�t�H�[���𑪒肵���Ƃ���A����҂ɔ�ב����X���҂ł������`�Q�A�C�\�t�H�[�����ቺ���Ă��邱�Ƃ����������B�܂��A�������X����o�C�I�}�[�J�[�ł���b�`�P�X�|�X�Ɣ�ׂč������x�łP�C���A�Q�C���X��������o�ł��邱�Ƃ��m�F�����B���̌��ʂ���A�m�b�h�͂������`�Q�A�C�\�t�H�[�����A�X����ł̐M�����̍������t�o�C�I�}�[�J�[�ɂȂ肤��\��������ƕ]�����Ă���B �@�]���A���t���̂������`�Q�A�C�\�t�H�[���Z�x�v���ɂ͎��ʕ��͂�p��������@�����Ȃ������B���ʕ��͂�p�������@�͍����ȋ@���K�v�Ƃ��A��ʂ̗Տ������Ƃ��Ďg�p����ɂ͉ۑ肪����B�����ŁA�������O���[�v�͊ȕւȌ����L�b�g�u�g���������@�`�o�n�`�Q�@�b�|�����������������@�d�k�h�r�`�@�������A�����p����v���J�������B �@�������{���������ŏW�߂�ꂽ�X������܂ޏ����펾�����҂ƌ���҂̌��t���̂����L�b�g�ő��肵���Ƃ���A�b�`�P�X�|�X�Ɣ�r����荂���x�ɑ����X��������o�ł����B�b�`�P�X�|�X���������Ȃ��X�Ǔ������S�t����ᇂ▝���X���Ȃǂ��X���X�N�������������x�Ō��o�����B�������`�Q�A�C�\�t�H�[���Ƃb�`�P�X�|�X�Ƃ̑g�ݍ��킹�ŁA�����X���o���͂���Ɍ��サ���B �@�`�l�d�c�̎x�������������Ɛ_�ˑ�w�Ȃǂ����͂��u�������`�Q�A�C�\�t�H�[����p�����X����͋[���f�v���J�n����\��B���̖͋[���f���܂߂�����̌����ɂ���āA�������`�Q�A�C�\�t�H�[���̌������{���ɑ����X������X���X�N������K�ɃX�N���[�j���O�ł��A���f�Ɏ��p���ł��邩�ǂ������m�F���Ă����B�J�����������L�b�g�͌����p����ŁA�̊O�f�f��Ƃ��Ă̏��F�擾���ڎw���Ă���B �@�������ʂ͉p�Ȋw���l�C�`���[�n�I�����C���Ȋw���u�T�C�G���e�B�t�B�b�N�E���|�[�c�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�B m3.com 2015�N11��10�� |
|
TV�̌��߂�����v�����ɂ�鎀�S���X�N�Ɋ֘A 1��3�`4���Ԃ̎����Ń��X�N15���㏸ |
| �@TV�̌��߂����A��v�Ȏ��S�����̂������Ɗ֘A���邱�Ƃ��A�V���ȕč��̌����Ŗ��炩�ƂȂ����B�č��l��92���͎����TV�������A���l��80�����]�ɂ̔����ȏ�ɂ�����1������3���Ԕ��ATV�����Ă���Ƃ����B �@����̌����ł́A�č����������iNCI�j��Sarah Keadle���炪�A�����J�n���ɖ����������Ȃ�����50�`71��22��1,000�l���̑Ώێ҂��A���S�܂���2011�N12���܂Ŗ�15�N�ɂ킽��ǐՂ����B �@���̌��ʁA�Ώێ҂�TV�����鎞�Ԃ������قǁA�S�����A����A���A�a�A�C���t���G���U/�x���A�p�[�L���\���a�A�̎����Ƃ����������Ŏ��S����\�������������B �@TV�̎������Ԃ�1��1���Ԗ����̑Ώێ҂ɔ�ׂāA1��3�`4���Ԃ̑Ώێ҂ł͌������Ԓ��̎��S���X�N��15�������A1��7���Ԉȏ�̑Ώێ҂ł�47�����������B�i��������A�J�����[�ێ�ʂȂǂ̊댯���q���l�����Ă��ATV�����Ǝ��S���X�N�㏸�ɂ͊֘A�����݂�ꂽ�B���������̊֘A���Ƃ́ATV�̌��߂��������̎����ɂ�鎀�S��������Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B �@�����̎��S���X�N�㏸�́A�����I�ȑΏێ҂Ɣ��I�ȑΏێ҂̂�����ł��݂�ꂽ�Ƃ����B����̌����́A�uAmerican Journal of Preventive Medicine�v�I�����C���ł�10��27���f�ڂ��ꂽ�B �@Keadle���́A�u�ߔN�A�����ԍ����Ă���ƌ��N�ɑ����̈��e�����y�ԉ\��������Ƃ��錤�����������Ă��邪�A����̌���������ɑ������̂ł���B�����]�ɂɂ�����TV�������Ԃ̒����A�L�͈͂ɋy�Ԏ��S���X�N�̏㏸���l����ƁA�����Ԃ�TV�����͂���܂ŔF������Ă��������d�v�Ȍ��O�q���̉���̕W�I�ƂȂ肤��v�Ƙb���Ă���B m3.com 2015�N11��13�� |
| ���̒E�т��A���߂Ȃ��R������� |
| �@���܁A����ɑ��Ă͗l�X�Ȏ��Ö@���o�Ă��Ă��܂����A2015�N���݂ōł��|�s�����[�Ȏ��Ö@�́h�R����܁h�ł��B �@�ʉ@���Â��\�ŁA��p����ː����Âƈꏏ�Ɏ邱�Ƃ��ł���B�Ƃ������ƂŢ�ł���y�ȑI������Ƃ����R����܂ł����A����p���������Â̑�\�i�ł�����܂���ˁB �ڗ����炱���A�C�ɂȂ�E�� �@�R����܂��g�p����ƁA�����ꏭ�Ȃ���A���]�₩��݁A��������Ԍ����̌����A�f���C��q�f�A��J���₾�邳�Ȃǂ̏��Ǐ�ɋꂵ�ނ��ƂɂȂ�܂��B �@�����A�����͊m���ɋꂵ���ł����A�T�ڂɂ����킩���Ă��܂����̂ł͂���܂���B �����āA�R����܂ɂ́h�E�сh�Ƃ����A�����ڂɑ傫�ȃn���f�B�L���b�v������郊�X�N�����邱�Ƃ��L���ł��B �ʏ�́A�R����܂̓��^���Ă���2?3 �T�ԂŖڂɌ����ĒE�т��n�܂邱�Ƃ������悤�ł��B �E�іh�~�Ɂh��p�L���b�v�h �@�I�[�X�g�����A�̃r�N�g���A�B�A�����{�����̃J���u���[�j�a�@(Cabrini Hospital )�ł͂��̂قǁA�R������Ò��̊��҂���̔��̖т���邽�߂̗�p�L���b�v�i�X�q�j�����ʂ����������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B �@���݁A�r�N�g���A�B�S�y�����p�L���b�v�����߂āA���a�@�Ɋ��҂��l�߂����Ă�Ƃ̂��Ƃł��B ��t�̃~�V�F���E�z���C�g���ɂ��ƁA�ŏ��͂��̃L���b�v���h�|���h�Ǝv�����҂��������������Ƃ̂��Ƃł��B �@�ł����A���̃L���b�v�œ����₽���ۂ��Ƃɂ��A����̌��ǂ����k�����A�т̎Y���Ɋ֗^���Ă��颖ѕ�זE��ɂ������āA�R����܂��Z������̂�h�����ʂ�����̂������B �@���͂��̏��i�A���w�Ö@�ɂ��E�т�h�����߂́w�y���M���R�[���h�L���b�v�iPenguin Cold Cap)�x�Ƃ��ď��i������Ă���A���ۂɃA�����J��C�M���X�A�J�i�_�Ȃǂł̓����^���Ȃǂʼn^�p����Ă���悤�ł��B �@��J�����𗬂��Ă���颃A�C�V���O����ǂ��Ǝv���܂� �@�A�C�W���O�Ƃ́A����A�X�|�[�c�I�肪�������������ɍs���悤�Ȃ��̂�������܂���B �@�A�C�V���O�̌��ʂ̈�Ƃ��āA�ꎞ�I�E�Ǐ��I�ɁA�זE�̐V��Ӄ��x����ቺ�����A���Ȃ��_�f��h�{�f�ōזE�������ł���������o�����Ƃ�����܂��B �@�������A���̌�͒ʏ�ʂ�̌����ɂȂ�̂ł����A���̍ۂɂ͌��������債�A��J�����𗬂��Ă������ʂ�����̂ł��B ���̍���������܂��A�M�҂Ȃǂ͗₦�s�^�ł���p�ł���̂ł́H�ȂǂƎv���Ă��܂��܂����B ���낢�뉞�p�ł������ł��B �@����p�̒E�яꏊ�Ƃ��Ă͓��炾���łȂ��A���т₻�̂ق��̖̑т��܂܂�Ă��܂��B �@���������E�тɂ���p�L���b�v���������ǂ����͕�����Ȃ��ł����A��p���ꎞ�I�Ɍ��ǂ����k������Ƃ������Ƃ����킩��A�l�X�ȕ����ɉ��p�ł������ł����A�J�c���Ȃǂɗ���Ȃ��Ă��A���S�ɍR������Â𑱂���ꂻ���ł��ˁB �K�W�F�b�g�ʐM 2015�N11��14�� |
|
��ᇗn�𐫃E�C���X�̍���P2���{ �^�J���o�C�I�A�č������f�[�^���p |
| �@�^�J���o�C�I�͎�ᇗn�𐫃E�C���X�u�g�e�P�O�v�̑������Ɖ��Ɍ����A�����ő�Q���Տ������i�o�Q�j�����{����B�����ł͍Đ���Ó����i�̏����E�����t�����F���x�����p������j�����A�����o�P�̃f�[�^�����Ő\����������č��o�Q�f�[�^�����������o�Q��V���Ɏ��{�����ق������F�R�����N���A���₷���Ɣ��f�����B�Q�O�P�W�N�x�̍�����s��ڎw���A�����ɍ����o�Q���J�n�ł���悤������i�߂Ă���B �@�g�e�P�O�͒P���w���y�X�E�C���X�P�^�i�g�r�u�P�j�̎�ʼn����ŁA����Ǐ��ɒ������邱�Ƃɂ���Ď�ᇑg�D���őI��I�ɑ��B���A��ᇑg�D��j�邱�Ƃ����҂���Ă���B�����̎�ᇗn�𐫃E�C���X�͈�`�q��g�݊�������O����`�q��}������ȂLj�`�q�H�w�I���ς��s���Ă��邪�A�g�e�P�O�͎��R�ψٌ^�̃E�C���X�ł��邽�߁A���S���ɗD���ƂƂ��ɋ����R��ᇌ��ʂ������Ɛ�������Ă���B �@�����ł͌Ō`�����ΏۂƂ����o�P�����������Z���^�[�����a�@�Ŏ��{���B�ڕW�Ǘᐔ�U��̂����P�Ǘ�ւ̓��^���I���Ă���A�������ɂ������o�P���I���ł��錩�ʂ��B �@�č��ł͂��łɃ����m�[�}��ΏۂƂ����o�Q�ɒ���B�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q�܁E�R�b�s�k�`�|�S�R�̂Ƃ̕��p�Ö@�ŁA�ڕW�Ǘᐔ�S�R��̂����R�V��̊��ғo�^�������B�P�U�N�x���̂o�Q�I�����v�悵�Ă���B�����A�č��o�R�ɂ͑����̏Ǘᐔ�̑g�ݓ��ꂪ�K�v�ł��邽�߁A�^�J���o�C�I�Ƃ��Ă͏����E�����t�����F���x�����p�ł��鍑���J�����s������l���B �@���̂��߁A�č��o�Q�I����ɂ��̃f�[�^�������\���Ɋ��p�ł���悤�ȍ����o�Q�̎��{���v�悵�Ă���B�č��o�Q�̒��ԉ�͌��ʂł͏d�Ăȕ���p�͂Ȃ��A���S�t���i�b�q�j���R��A�����t���i�o�q�j���U��ƈ��̗L�����������Ă���B�����o�P�f�[�^�݂̂ł̐\�������A���̗L������������Ă���č��o�Q�f�[�^�����p���Đ\�������������F�������N���A���₷���ƍl���Ă���B �@�����o�Q�̎����f�U�C�����������B�P�܂ɂ��邩�A�č��o�Q�̂悤�ɍR�b�s�k�`�|�S�R�̂Ƃ̕��p�Ö@�ɂ��邩�͖���B �@�P�O�����Ɏ�ᇗn�𐫃E�C���X�Ƃ��Ă͏��߂ĕăA���W�F���́u�s�|�u�����v���Ăe�c�`���珳�F���ꂽ�B�s�|�u�����͂g�e�|�P�O�Ɠ����g�r�u�P�̎�ʼn��������A�������E�}�N���t�@�[�W�R���j�[�h�����q�i�f�l�|�b�r�e�j��`�q��}�����邱�ƂŖƉu������p���������Ă���B �@�^�J���o�C�I�̒�������В��́A�s�|�u���b�Ƃg�e�|�P�O�̈Ⴂ�ɂ��āu���R�ψٌ^�E�C���X�̂g�e�|�P�O�̕����A�E�C���X���̂̎�ᇍזE��j����ʂ������B���̂��ߎ�ᇗR���R��������������o����A��ᇖƉu���ʂ����܂�B����p�����Ȃ��A�D�ꂽ���S���������Ɗ��҂��Ă���v�ƁA���̗D�ʐ������������B m3.com 2015�N11��16�� |
|
�q�ǂ��̑��������͗������X�N���Ⴂ ���nj��F�ł��\�h���� |
| �@�q�ǂ��̑��������قǗ������X�N���Ⴂ�\�������邱�Ƃ��A�V���Ȍ����Ŏ������ꂽ�B����ɁA���nj��F�����Ă��鏗���̗������X�N���Ⴂ���Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B �@����̌����ł́A4�^�C�v�̂悭�݂��闑������i���t���A�S�t���A�ޓ����A���זE�j�̊댯���q�𖾂炩�ɂ��邽�߁A8,000�l���̏����̃f�[�^�͂����B �@�����𗦂����p�I�b�N�X�t�H�[�h��w��Kezia Gaitskell���ɂ��ƁA�ߔN�A��������̏Ǘ�̑��������͗������甭���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����炩�ɂ���Ă���Ƃ����B�Ⴆ�A�������x���t����ᇂ̑����͗��ǂ��甭�����A�ꕔ�̗ޓ�����ᇂ���і��זE��ᇂ͎q�{�����ǂ��甭������ƍl�����Ă���B �@�q�ǂ��̂��Ȃ������ɔ�ׁA�q�ǂ���1�l���鏗���͗�������S�̂̃��X�N��20���Ⴍ�A�ޓ�����ᇂƖ��זE��ᇂ̃��X�N��40���Ⴉ�����B�q�ǂ���1�l�����邲�Ƃɗ������X�N��8���ጸ�����B �@����ɁA���nj��F���Ă��鏗���͗�������S�̂̃��X�N��20���Ⴍ�A�������x���t����ᇂ̃��X�N��20���A�ޓ�����ᇂƖ��זE��ᇂ̃��X�N��50���Ⴉ�����B �@���̌����́A�悲��p���o�v�[���ŊJ�Â��ꂽ�p������������c�Ŕ��\���ꂽ�B�Ȃ��A�w��\���ꂽ�����͈�w���f�ڎ��̂悤�Ȍ����ȐR�����Ă��Ȃ����߁A�\���I�Ȃ��̂Ƃ݂Ȃ����B�܂��A����̌����ł͈��ʊW�͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B �@�q�ǂ��̂��Ȃ������̗������X�N���������R�Ƃ��āA�u�q�{�����ǂ̂悤�ȕs�D�Ǐ�Ɨ������X�N�㏸���ɂ����炷�������֘A���Ă���̂�������Ȃ��v��Gaitskell���͎w�E����B���nj��F�ɂ��ẮA��ᇂ̌����ƂȂ�ُ�ȍזE�̗��ǂւ̓��B�����F�ɂ��W�����Ă���\�����l������B�u����̌��ʂ́A��������̊��m�̊댯���q�Ƃ̊֘A���A��ᇂ̃^�C�v�ɂ��قȂ邱�Ƃ������ꂽ�_�ŋ����[���v�Ɠ����͌��_�Â��Ă���B �@��c�c���ʼnp�����h����w�iUCL�j������������Charlie Swanton���́A���������1�̎����ł͂Ȃ��A�قȂ鎾�������ʂɂ��1�ɂ܂Ƃ߂����̂��Ǝw�E���A�u���܂��܂ȃ^�C�v�̗�������ɉ����e�����y�ڂ��̂��A�ǂ̈��q������Ɋ֗^����̂���m�邱�Ƃ��d�v���B���̒m���̔w�i�ɂ���@�����𖾂��A���ׂĂ̏����Ń��X�N��ጸ������@��������K�v������v�Əq�ׂĂ���B m3.com 2015�N11��16�� |
|
�j���s�D�Ő������X�N�������\�� ���q�����ُ�ɏ��Ȃ��j���ł̓��X�N10�{ |
| �@�D�s�\�̒Ⴂ�j���͐������X�N�������\�������邱�Ƃ��A�ă��^��w��Heidi A. Hanson����̌����Ŏ�����A�_�����uFertility and Sterility�v11��19�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@1996�`2011�N�ɕs�D���Â̈�Ő��t���͂����j����2���l���A�D�s�\������Ƃ킩���Ă��铯���̒j���ΏƌQ�Ɣ�r�����B�S�̂�421�l������Ɛf�f����A�ł����������͍̂��F��A��������A�O���B�������B �@��͂̌��ʁA��D�s�\�̒j������������ǂ���\���͑ΏƌQ��3�{�������B���ɐ��q�����ُ�ɏ��Ȃ��j���ł́A���X�N��10�{�ƂȂ����B���q�̌`��^�����Ȃǂ̖�肪����j���ł��A���X�N�͏㏸���Ă����B �@����A����܂ł̌������ʂƂ͑ΏƓI�ɁA���t���ɐ��q�̂Ȃ��j���ł́A���X�N�̏㏸�݂͂��Ȃ������B�܂��A�D�s�\�ƑO���B���X�N�Ƃ̊֘A���F�߂��Ȃ������B�������A����̌����͒��ړI�Ȉ��ʊW�𖾂炩�ɂ������̂ł͂Ȃ����߁A�s�D�������j�����p�j�b�N�Ɋׂ�K�v�͂Ȃ��Ƃ����B �@�j�����B�E��A��w��iSMRU�j�����Robert Oates���́A�u����̌����́A���҂ւ̂��悢���Òɖ𗧂V�������@�������炷�B�܂��A�s�D�₪��ɂȂ��鐶���w�I�@���𖾂炩�ɂ��A���ÂɌ��т��邽�߂ɕK�v�Ȍ����̋��͂Ȋ�ՂƂȂ邾�낤�v�ƃR�����g���Ă���B m3.com 2015�N11��30�� |
| �J�[�^�[���đ哝�́A�]��ᇂ̎��Ð����\ |
| �@���V���g���i�b�m�m�j �č��̃J�[�^�[���哝�́i�X�P�j�͂U���A�ŋߎ��]��ᇁi����悤�j�̎��Â��������A�a�������������Ƃ����������Ɣ��\�����B �@�W���[�W�A�B�̋���Ŏ��g���S��������j�w�Z�̐��k��Ɍ��A�n�������ŏ��ɕĂ����B �@���k�̂P�l�i�P�Q�j�ɂ��ƁA�J�[�^�[���́u��T�����C���摜���u�i�l�q�h�j�����̌��ʁA����͌�����Ȃ������v�Ƙb���A�o�Ȏ҂��甏�肪�N�����B �@�����͂���ɐ����ʼn��߂āA�u�l�q�h�����ł͌��̕a�����V���ȕa�ς�������Ȃ������B������R�T�Ԃ��ƂɖƉu�Ö@��y���u�����Y�}�u�̓��^���鎡�Â𑱂��Ă����v�Əq�ׂ��B �@�J�[�^�[���͍��N�A�̑�����̎�p�������A�W���ɂ͔]���̂S�J���ɂ���g�D�������������Ƃ𖾂炩�ɂ����B���������̂R����ɂ́A�����ʂ���j�w�Z�̋��d�ɗ����Ă����Ƃ����B �@���Â�S�������ăG�����[��w�̈�t�c�͐挎�A�����̂��Â͏������Ɣ��\���Ă����B CNN.co.jp 2015�N12��7�� |
| �Ȋw�E�̃^�u�[�A����g�\�h�h�Ɂu�זE�����v�Ƃ����V�����������삩�璧�� |
| �k�C����w ��`�q�a���䌤���� ���c���V ���� ����́u�\�h�v�͓�� �@�u�����H�ׂ�����\�h�ł���!�v�Ƃ������悤�Șb����悭���ɂ��邱�Ƃ����邩������Ȃ����A���͂������Ȋw�I�Ɏ����邱�Ƃ͓���A�Ȋw�̐��E�ɂ����Ă���g�\�h�h�̌����͂���܂Ń^�u�[������Ă�������ł���Ƃ����B�������k�C����w ��`�q�a���䌤���� ���c���V�����́A���̉Ȋw�E�̃^�u�[�ɐ荞�݁u����̗\�h��v�̊J����ڎw���Ă���B �@���c���������ڂ����̂́A���ݗՏ��̑ΏۊO�ƂȂ��Ă���A�����ɂ����ău���b�N�{�b�N�X�ƂȂ��Ă��邪��́u�������a�ρv���B����͐��N�����ď��X�ɒ~�ς���Ă����a�C�ŁA�����`�q����т���}����`�q�ɂ������̕ψق����邱�Ƃɂ���Ĕ��ǂ���B�܂�A����ȍזE���������ψق��Ă������Ƃł���ɂȂ�Ƃ����킯���B �@�������Ȃ���A����̒������i�K�ł̕a�ς͌������㐳��ɂ݂��邽�߁A���݂̕a���f�f�Z�p�ł͔������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���Ăł͍��N����A���ݓI�ȕa�ς̑��������Ƒ�Ƃ�����������ɗ\�Z���t�����Ă���Ƃ������A���{�ł͎c�O�Ȃ��炻������������͂܂��Ȃ��B �@���c������2009�N�A����ȍזE�Ƀe�g���T�C�N�����Ƃ����R�������������邱�ƂŁA����^���p�N����������Ƃ����זE���쐬�B����𗘗p���āA����זE�Ɉ͂܂ꂽ�Ƃ���ɂ���זE�����݂���Ƃ����A����܂Ńu���b�N�{�b�N�X�ƂȂ��Ă�������̒������i�K�̊����Č������B���̍ہA����זE�̎Љ�炪��זE���͂����o����A�̊O�ɔr�o���������֔����Ă����Ƃ����A����g�������h�I�Ȍ��ۂ��N�������Ƃ����B���ꂪ�A���c���������C���e�[�}�Ƃ��Č����Ɏ��g�ށu�זE�����v���B 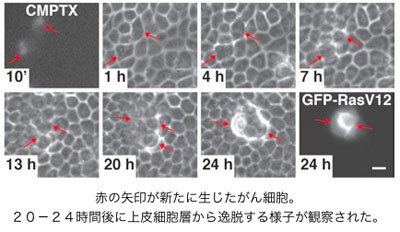 �@���͂��̍זE�����̌����A�C�f�B�A�́A���c��������w�@���̂���A�����҂Ɠx�X�a瀂��N���������o�[�ɑ��u�����͖{���ɂ���̂悤�Ȃ��Ȃ��A�ǂ�������ގ��ł���̂��낤���v�ƍl�����Ƃ��ɑM�������̂������B���c�����́u��X�̎�ɕ����Ȃ��悤�ȋɈ��l���o�������ۂɂ͌x�@�������ɂ����邪�A���������ނ̂悤�Ȑl�Ԃɑ��Ă͎���̐l�Ԃ��Ȃ�Ƃ��r���A���邢�͋������悤�Ǝ��݂�B���l�ɁA�����x�̍�����ᇍזE�͖Ɖu�זE�Ƃ�������ȍזE�������ɂ����邪�A�g�`���C���h�̎�ᇍזE�͎���̐���זE���Ȃ�Ƃ��Ή�����̂ł͂Ȃ����낤���v�ƍl�����̂��B �@����܂ł̂����́A����זE�ƕψٍזE�����ꂼ��|�{���āA���̈Ⴂ���݂�Ƃ������̂��قƂ�ǂ������B���c������̃`�[�����s�����u����זE�ƕψٍזE�������āA���̎Љ������v�Ƃ��������́A���ɉ���I�ȃA�C�f�B�A�ł������ƌ����悤�B �u�זE�����v�͂ǂ����ċN���� �@�ł́A�זE�����͂ǂ����ċN����̂��낤�B���́A����זE�����ψٍזE�����A�݂���F�����Ă���Ƃ������Ƃ͂��łɖ��炩�ɂȂ��Ă���B�������A���ꂪ���q�̈Ⴂ�ɂ����̂Ȃ̂��A�����I�Ȍ`�ɂ����̂Ȃ̂��Ƃ��������Ƃ͂킩���Ă��炸�A�זE�����̐��E�̑傫�ȓ�ƂȂ��Ă���B �@�u��X�̌������ł́A���݂��̔F���@�\���ǂ̂悤�ȕ��q���J�j�Y���ŋN�����Ă���̂��Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ������B����������܂łɂȂ��V���������Ȃ̂ŁA�ǂ�����Ă������������q����������悢���킩�炸�A��T��̏�ԁv(���c����) �@���������ł́A����זE�ƕψٍזE���������Ƃ��ɂ����ʂ⓭�����ω����Ă��镪�q��T���Ă���Ƃ��낾�Ƃ������A���̂Ȃ��ł��זE���i�ƂȂ�u�r�����`���v�Ƃ����^���p�N���̍�p�����łɖ��炩�ɂȂ��Ă���B �@�r�����`���͍זE�����̍ہA�ψٍזE�̋��E�ɔZ�k���Ă���B����͐���זE������̉e���ŋN������̂ŁA�_�C�i�~�b�N�ɍ\����ς��邱�Ƃ��ł���t�B�������g�\���̃r�����`�����A�זE�����̍ۂɓˋN��ɐL�тĂ��āA�ψٍזE��˂��悤�Ɂg�U���h���n�߂�B���炩�ɁA����זE���ψٍזE��F�����Ă���ƌ����錻�ۂ��B ����זE�ƕψٍזE�̋��E�Łu�r�����`���v���Z�k�B�ψٍזE���U������ �@���c�����ɂ��ƁA�זE�����ɂ̓r�����`���ȊO�ɂ������̕��q���ւ���Ă��邱�Ƃ��l������Ƃ����B����זE�ƕψٍזE�̔F���@�\�̑S�e�́A���܂����炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B �@�זE�����͕���26�N�`����30�N�̕����Ȋw�� �V�w�p�̈挤���ɍ̑�����Ă���A����܂��܂����W���Ă������̂Ǝv����B�������A����́g�\�h�h��ړI�Ƃ����������̂ɂ͂��̉Ȋw������͗��p�ł��Ȃ��Ƃ����B�����ŁA���c�����͌��݁A���E���̂���\�h��ѐf�f����u�זE�����v�Ƃ������ۂ𗘗p���ĊJ�����邱�Ƃ�ڕW�ɁA�N���E�h�t�@���f�B���O��錤����l���Ƀ`�������W���Ă���B �@�זE�����𗘗p��������̗\�h��Ƃ��ẮA2�̕��@���l������B�ЂƂ́A�זE�����̍ۂɓ��ٓI�ɋ@�\���Ă��镪�q�𖾂炩�ɂ��A�����W�I�ɂ�������J������Ƃ������́B����זE�̍U������\�͂����߂�A�܂��͕ψٍזE���̃f�B�t�F���X����߂�Ƃ������A�זE�̎Љ�������B�����ЂƂ́A�זE�����͂����߂���悤�Ȓᕪ�q�������肵�A������Ƃ��ėp����Ƃ������̂��B �@�܂�����܂ł́A����̗\���R�זE�����݂��邩�ǂ�����f�f����p���Ȃ��������A�זE�����̍ۂɐ���זE�ƕψٍזE�̋��E�ŔZ�k���Ă���^���p�N�����o�C�I�}�[�J�[�Ƃ���A�f�f��J���ւ̉��p�������Ă���B �@�u���͂��Ƃ��ƈ�w�̏o�g�Ȃ̂ŁA�g�����o�ł������h�Ƃ����C�����Ō��������Ă���B�זE�����Ƃ����V������������𗘗p���āA����܂Ń^�u�[������Ă�������̗\�h�ɁA�N���E�h�t�@���f�B���O��ʂ��Ă݂Ȃ���ƈꏏ�Ɏ��g��ł��������v(���c����) �@�C�M���X�ł́uCancer Research UK�v�Ƃ��������ւ̊�t�������s���g�D������BCancer Research UK�ł͂��Ƃ��A�X���ɂ��铯�g�D�̓X�܂ňߕ��Ȃǂ��w������ƁA���ꂪ�����ւ̎����ƂȂ�B���c�����ɂ��Ɓu���Ăł́A������̌�����̂ق��Ɉ�ʂ̕��̃h�l�[�V����(��t)���傫�Ȕ�d���߂Ă���v�Ƃ����B �@�����ɂ����āA����̃N���E�h�t�@���f�B���O�̖ڕW�ł���500���~�Ƃ����̂͌����đ傫�ȋ��z�ł͂Ȃ��B�������A����̃`�������W�̐��ۂ��A���{�ɂ����邪���A�Ђ��Ă̓T�C�G���X�ւ̊�t���������t�����邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����̎����ƂȂ肻�����B �}�C�i�r�j���[�X 2015�N12��7�� |
|
ALL�i�}�������p�������a�j��CAR-T�Ö@��9�����S���� 6�J�����76���ōĔ����� |
| �@�X�C�X�E�m�o���e�B�X�́A�ăy���V���o�j�A��w�y�����}����w��w�@�Ƌ����J�����Ă���L�����R����e�́i�b�`�q�j�Z�p��p��������̖Ɖu�זE�Ö@�i�b�`�q�|�s�Ö@�j�u�b�s�k�O�P�X�v�ɂ��āA�ŐV�̗Տ������f�[�^�\�����B�}�������p�������a�i�`�k�k�j��Ώۂɂ�����Q���Տ������i�o�Q�j�ł͂X���ȏ�̊��҂Ŋ��S������B�������B���ƈڐA�ɂ���`�q���Âł́A��萻���Ђōł��J������s���Ă���A���N�ɂ��č��ŏ��F�\���\��B �@�����E��N���l�̍Ĕ��^����`�k�k���҂�Ώۂɂ����o�Q�ł́A���҂̂X�R���i�T�X�ᒆ�T�T��j�Ŋ��S�����i�b�q�j���F�߂�ꂽ�B�U�J������Ĕ����Ȃ������Ǘ�͂V�U���A�P�Q�J����͓��T�T���B���݂�������Ԃ��ێ����Ă���Ǘ�͂P�W��Ƃ����B��ȕ���p�̓T�C�g�J�C�����o�nj�Q�ŁA�W�W���̏Ǘ�ŕ��ꂽ�B �@�т܂�זE�^�a�זE�������p��i�c�k�a�b�k�j�A�h�E�������p��i�e�k�j��Ώۂɂ����O���o�Q�ł́A�R�J�����_�̑S�t�����i�n�q�q�j���c�k�a�b�k�Q�łS�V���i�P�T�ᒆ�V��j�A�e�k�Q�łV�R���i�P�P�ᒆ�W��j�B�U�J�����_�łb�q��B�������Ǘ�͂��ꂼ��R�Ⴀ�����B�������������ԁi�o�e�r�j�̒����l�͂c�k�a�b�k�Q���R�E�O�J���A�e�k�Q���P�P�E�X�J���������B �@�m�o���e�B�X�͂����̎������g�債�A���B�A�J�i�_�A���B�ł��o�Q���J�n�����B���ƈڐA�̈�`�q���Ö�����邽�߂̔|�{�{�݂�č��Ō��݂��A�č��H�i���i�ǁi�e�c�`�j�̂f�l�o�F�����B�č��ł͗��N�ɂ����F�\�����A�Q�O�P�V�N�̔�����ڎw���B �@�b�s�k�O�P�X�́A�`�k�k�Ȃǂɍ���������b�c�P�X�R����F�������`�q�����҂̂s�זE�ɑg�ݍ��݁A�����������זE�����ґ̓��ɖ߂����Ö@�B�ăW���m�E�Z���s���[�e�B�N�X��ăJ�C�g�E�t�@�[�}�����l�̂b�`�q�|�s�Ö@���o�Q���ŁA���N�ɂ����F�\���\��B m3.com 2015�N12��10�� |
|
���H���ł���ɂȂ�H�@�{���͂ǂ�ȕ������̂� ������炯�̉��H���E�ԓ���� |
| �@�H�ɂ��Ă̑傫�ȊS�����܂�1�������B�n����\�[�Z�[�W�Ȃǂ̉��H����A������ؓ��Ȃǂ̐ԓ��Ȃǂ̐ێ�ƁA������̊W������荹������Ă���B �@���N10���A���A�E���E�ی��@�ցiWHO�j�̕����@�ւł��鍑�ۂ����@�ցiIARC�j���u�ԓ��Ɖ��H���̐ێ�̔����v�Ƃ��������o���A���H���ɂ��Ắu�l�ɑ�����������v�A�ԓ��ɂ��Ắu�����炭����������v�Ƃ����̂��B�}�X���f�B�A�������傫���A�S�z�ɂȂ����l�тƂ����̔����T�������鎖�ԂɂȂ��Ă���B �@�~���ėN�����悤�ɋN�����ԓ��E���H���ɑ���S�z���B�����A����̔��\�͂ǂ̂悤�Ȉʒu�Â��̂��̂Ȃ̂��B�܂��A���{�l�͂��̔��\���ǂ̂悤�Ɏ~�߂�悢�̂��B�����������̐ێ悾���ɊS�������Ă���悢�̂��B���X�ɋ^�₪������ł���B �@�����ŁA����琔�X�̋^����A������̃��X�N��A����̗\�h��w�Ȃǂɏڂ������Ƃɓ��������Ă݂��B�����Ă��ꂽ�̂́A���������Z���^�[����\�h�E���f�����Z���^�[�\�h���������̍����Î��B���������́A�����IARC�̔��\���A���{�l�̐ԓ�����H���̐ێ�Ƃ���̃��X�N�̊W������������u�ԓ��E���H���̂��X�N�ɂ��āv�\�B�������͂��̉���̍쐬�ɏ]�������B �@�O�тł́A���ۂ����@�ւ̍���̔��\���Ȃɂ��Ӗ����A����������҂��ǂ��~�߂�悢�̂������Ƃɂ���B��тł́A���{�l��Ώۂɂ�������܂ł̌������ʂ���A���{�l�͐ԓ��E���H���̐ێ��S�z���ׂ��Ȃ̂��A������̃��X�N�̂Ȃɂ��C�ɂ�����悢�̂����B �����̎w�E�ł͂Ȃ� �\�\���ۂ����@�ցiIARC�j���A10���Ɂu�ԓ��Ɖ��H���̐ێ�̔����v�ɂ��ĕ����܂����B���H���ɂ��āu�l�ɑ�����������v�A�ԓ��ɂ��Ắu�����炭�l�ɑ�����������v�Ƃ�����e���ƕ����܂��B���������A���́̕A�ǂ̂悤�Ȍo�܂łȂ��ꂽ�̂ł��傤���H ���� �� �����i�ȉ��A�h�̗��j�@���\���������ۂ����@�ցiIARC�j�͐��E�ی��@�ցiWHO�j�̕����@�ւŁA�N3��uIARC���m�O���t�v�Ƃ������������o���Ă��܂��B�e���ł́A���Ƃ��u���ː��v��u�E�Ə�̔���v�Ƃ���������̃e�[�}��݂��Ă��܂��B �@�e�[�}���Ƃɐ��Ƃ�����A����\�Ȑ��E���̘_�������ƂɁA�ǂ̂��炢�_���̌��ʂ���v���Ă��邩�Ȃǂ���A������̊m�����肵�Ă��܂��B �@�ŐV�́u���m�O���t�v��114���̃e�[�}���u�ԓ��Ɖ��H���v���������߁A����A���̐ێ�̃q�g�ɑ���e�������グ���܂����B�����āA10���̔��\�Ɏ������킯�ł��B �\�\�ԓ�����H���Ɣ�����̊W���ɂ��āA�����҂����͏��߂Ďw�E�������ƂȂ̂ł����H �����@�����B���߂Ďw�E�����悤�Ȃ��Ƃł͂���܂���B �@���Ƃ���2003�N�ɂ́A���E�ی��@�ւƍ��A�H�Ɣ_�Ƌ@�ցiFAO�j�������Łu�H���A�h�{�y�і��������\�h�v�ɂ��ĕ��Ă��܂��B���̒��ł��A�u�m���v�u�قڊm���v�u�\������v�u�s�\���v�Ƃ���4�i�K�Ŋ֘A����ݒ肷�钆�ŁA���H���Ƒ咰����̊֘A���ɂ��Ă�2�Ԗڂ́u�قڊm���v�Ƃ��A�u�Ȃ�ׂ����H���͐ۂ�Ȃ��悤�Ɂv�Ə����Ă��܂��B �@�܂�2007�N�ɂ́A���E��������iWCRF�j�ƕč������@�\�iAICR�j�������Łu�H���A�h�{�A�g�̊����Ƃ���\�h�v�ɂ��ĕ��Ă��܂��B10���ڂ́u�����v��1�Ƃ��āu�������H�i�v�����グ�A�u���i�����A�ؓ��j�̐ێ���T����B���H�������͂ł��邾��������v�Ƃ��A�l�ɑ��Ắu���̐ێ���T500g�i18�I���X�j�ȉ��Ƃ��A���H�������͂ł��邾���H�ׂȂ��悤�ɂ���v���Ƃ��������Ă��܂��B �@�����ߋ��̕��A���̎��_�Ŕ��\����Ă������E���̌��������ƂɁA������̊m�����肵�����̂ł��B�ł��̂ŁA��@�Ƃ��Ă͉ߋ��̂��̂�����̂��̂������Ȃ̂ł��B ����͍̕s���w�j���������̂ł͂Ȃ� �\�\����܂łƍ���̔��\�ŁA�����Ⴂ�͂���̂ł����H �����@2003�N��2007�N�̂Ƃ��̕ł́A���ܐ��������悤�ɁA�ڕW�⊩���Ƃ������`�ŁA����\�h�̂��߂̃K�C�h���C����������Ă��܂��B����ɑ��č���̍��ۂ����@�\�́̕A������̊֘A���̗L���̔��肷�邾���ɗ��܂��Ă��܂��B���̍��́A���ꂼ��̌����@�ցA���̎������̈Ⴂ����ł��B �@������̃��X�N��]������ɂ͒i�K������܂��B�܂���1�i�K�Ƃ��āA�댯�i�n�U�[�h�j������̂��A���邢�͗\�h���ʂ�����̂��A�Ȃǂ��]������܂��B���ɑ�2�i�K�ŁA����ɂȂ�₷���E�ƓI�Ȕw�i������̂��Ƃ��������Ƃ܂��A���X�N��\�h���ʂ̕]��������܂��B�����āA��3�i�K�ł悤�₭�A�ǂ������s�����Ƃ�ׂ����Ƃ������s���w�j�̕]�����Ȃ���܂��B �@2003�N��2007�N�́̕A��3�i�K�̍s���w�j�܂Ŏ������̂ł����B�ł��A����̍��ۂ����@�ւ͑̕�1�i�K�ǂ܂�̂��̂ł��B���ۂǂ����ׂ����Ƃ������s���́A����̕��āA�e�������ꂩ�猈�߂�ׂ��b�Ȃ̂ł��B �\�\����̍��ۂ����@�ւ̕ŁA���H���́u�O���[�v1�v�A�ԓ��́u�O���[�v2A�v�ɕ��ނ��ꂽ�ƕ����܂��B�����̕��ނ��ǂ��l������悢�̂ł��傤���H �����@����Ō����ƁA�����ΏۂƂȂ������E�̌����̂����A���H���ɂ��Ă͖�3����2�̌��������X�N���グ������̂��̂������Ƃ������ʂ���A�u�l�ɑ��Ĕ���������v�Ƃ���u�O���[�v1�v�ɔ��肳��܂����B�ԓ��ɂ��Ắu�����炭�l�ɑ��Ĕ���������v�Ƃ���u�O���[�v2A�v�ɔ��肳��܂����B �\�\�O���[�v��5���邻���ł����A������̃��X�N���u�O���[�v1�v�͂����Ƃ������A�u�O���[�v2A�v�͎��ɍ����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B �����@�����A�����ł͂���܂���B���̔���́u���ʂ̈�v�x�v�����������̂ł���A�����āu���X�N�̍����v���������̂ł͂���܂���B �@�����A���X�N�̍����ɂ��Č����Ȃ�A�u���H������������H�ׂ�l���咰����ɂȂ�m���́A�H�ׂȂ��l�ɔ�ׂĉ��{�v�Ƃ������b�ɂȂ�܂����A���̃O���[�v�����͂��������b�ł͂���܂���B�����܂ō���Ō����ƁA���E���̌����̖�3����2���A�u���H���̐ێ悪�咰����̃��X�N���グ��v�Ƃ��������ň�v���Ă���Ƃ����b�ł��B���ꂾ����v���Ă���Ƃ������Ƃ́A���H���̐ێ�Ɣ����ɂȂ�炩�̈��ʊW������Ƃ������_�Ɏ������킯�ł��B �@���Ƃ��A�u�O���[�v1�v�ɕ��ނ���Ă�����̂̂Ȃ��ł��A�i���ɋN������S���E�̂��S�͔N��100���ł������̂ɑ��A�A���R�[����60���A���H����3��4000�l�ł��������Ƃ�?������Ă��܂��B �@�܂��A�ԓ��ɂ��ẮA����܂ł̐��E�̌����̂����A�����قǂ����X�N���グ������ň�v�����Ƃ������Ƃł��B����ƁA�����Ȃǂ̐ԓ��ɂ͓S�����܂܂�Ă��āA���ꂪ�_���E�R�_���̓_�ł͎_����������ɓ����Ƃ������悤�ȁA������Ɋ�^����\������������A�u�����炭����������v���Ӗ�����u�O���[�v2A�v�ɕ��ނ��ꂽ�̂ł��B 50�O�����ȏ�͊댯�Ƃ������ �\�\����1�A����̍��ۂ����@�ւ̔��\�ł́A�u���H���ł�1��50�O�����̐ێ�ɂ�18�p�[�Z���g�A�ԓ��ł�1��100�O�����̐ێ�ɂ�17�p�[�Z���g�A�咰����̃��X�N�����߂�v�Ƃ����Ă��܂��ˁB �����@�������A����ɂ��Ă������̕��̌�����Ă�ł���悤�ł��B�u���H����1���̐ێ��50�O�����܂ł͑��v����50�O��������Ɗ댯�v�Ƃ��A�u�ԓ��͐ێ��100�O�����܂ł͑��v�ŁA100�O��������Ɗ댯�v�Ƒ����Ă���l������悤�ł����A����͂܂������̌���ł��B �\�\�ǂ��������Ƃł��傤�H �����@���H���̏ꍇ�A�u�ێ�ʂ�50�O����������ƁA���X�N��18�p�[�Z���g���܂�v�A�܂��ԓ��̏ꍇ�A�u�ێ�ʂ�100�O����������ƁA���X�N��17�p�[�Z���g���܂�v�ƌ����Ă���̂ł��B50�O������100�O�����Ƃ����ێ�ʂŃ��X�N����������Ă���킯�ł͂���܂���B �e�[�}���i���Ă����䂦�ɒ��ڂ���₷������ �\�\�ߋ��ɂ����ۓI�ȋ@�ւ��A���H����ԓ��Ɣ�����̊W���ɂ��Ďw�E���Ă����Ƃ����b�ł������A�ߋ��ɂ͂���قǑ����ɂȂ�Ȃ������C�����܂��B����ǂ����Ă����܂ő����ɂȂ����̂ł��傤�H �����@2003�N��2007�N�́̕A������H����g�̊����Ȃǂ����������̂ł��B���̐ێ�ɂ��ẮA���̒��̂����ꕔ�̍��ڂɂ����܂���ł����B����ǂ��A�����1�e�[�}�ɍi�������\�Łu�ԓ�����щ��H���v�����グ��ꂽ�̂ł��B�����ɎЉ��l�тƂ̊S���W�����Ă��܂����̂��Ǝv���܂��B �\�\�l�X��������������Ɣ��f���邽�߂ɂ́A�₯�ɋ�̓I�ȃe�[�}�ɍi�邱�Ǝ��́A��肪����C�����܂��B���\����@�ւ́A���������e�����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��C������̂ł����E�E�E�B �����@�������ɁA����̂悤�ȕ]��������ƁA�H���c�̂ȂǗ��Q�W�Ɋւ���Ă���c�͖̂Ҕ���������Ƃ������Ƃ͗\�z�ł��܂��B �@�������A���̈���ŁA�Ȋw�I�ȕ]���������������Q�W���炭�锽���Ȃǂɍ��E����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������l����������܂��B�֘A�c�̂���R���^�N�g���āA�u����ς肠�̌��ʂ͂�蒼���܂��v�ƂȂ�����A����͂���ō���܂��B �\�\�����ł����B����̔��\�͐��E�Ɍ����Ă̂��̂ł������A���������{�l�͓����ǂ��ێ悷��悢�̂����C�ɂȂ�܂��B �@��������͂��߁A���{�̌����҂́A���{�l��ΏۂƂ���H���Ɣ�����̊W���̌������W�߂ĂƂ�܂Ƃ߂��ƕ����܂��B��тł́A���{�l��Ώۂɂ����b���Ă��������Ǝv���܂��B ���� �Ái�����Â� �������j���B���������Z���^�[����\�h�E���f�����Z���^�[�\�h�����������B���m�i��w�j�B1996�N�A�F�{��w��w�����ƁB2000�N�A��B��w��w�@�\�h��w�u�����m�ے��C���B���N4����荑�������Z���^�[�ցB���T�[�`���W�f���g�A�������A�������o�āA2013�N��茻�E�B�����Ȍ�������͌��O�q���w�A���N�Ȋw�A�u�w�E�\�h��w�B JBpress 2015�N12��11�� |
| 2016�N����n�܂频S������o�^� �����̂��Âɂǂ̂悤�ɖ𗧂̂ł��傤�� |
| ��S������o�^��Ƃ͂ǂ�Ȑ��x �@�S������o�^�Ƃ́A���{�ł���Ɛf�f���ꂽ���ׂĂ̐l�̃f�[�^���A����1�ɂ܂Ƃ߂ďW�v�A���́A�Ǘ�����V�����d�g�݂ł��B ���Z�n��ɂ�����炸�S���ǂ��̈�Ë@�ւŐf�f���Ă��A����Ɛf�f���ꂽ�l�̃f�[�^�����̃f�[�^�x�[�X�ňꌳ�Ǘ������悤�ɂȂ�܂��B �@����ɂ��A����܂ł̂����ł͐��m�ɔc���ł��Ȃ������f�[�^�����W���Ă�����悤�ɂȂ飂Ɗ��҂���Ă��܂��B ���܂ł̊Ǘ��ł́A�_���Ȃ̂ł��傤��? �@���݁A����Ɛf�f���ꂽ�l�̃f�[�^�����W����d�g�݂ɂ́A��n�悪��o�^�v���x������܂��B �n�悪��o�^�ł́A�s���{�������ꂼ��̎����̓��Őf�f���ꂽ����f�[�^���W�߂����̂ł��B�������A�s���{�����ƂɃf�[�^�����W���Ă���ƁA����ɂ������Ă��瑼���Ɉړ������l�Ȃǂ̃f�[�^���d������\��������A��������c���ł��Ȃ����Ƃ����Ƃ���Ă��܂����B �@�܂��A���ׂĂ̈�Ë@�ւ��n�悪��o�^�ɋ��͂��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���ׂĂ̂��҂̃f�[�^�����W���邱�Ƃ��ł����A���m�Ȃ���f�[�^���W�߂邱�Ƃ��ł��܂���ł����B �o�^�葱���ɂ��� �@���̐��x�ł͢����o�^���̐��i�Ɋւ���@����Ɋ�Â��A�S���̈�Ë@�ւ́A���Ɛf�f���ꂽ�l�̃f�[�^��s���{���m���ɓ͂��o�邱�Ƃ��`��������܂��B �@���̂��߁A���҂�Ƒ����ɂ����邪��o�^�̎葱���͕s�v�ł��B �@����Ɛf�f���ꂽ���_�ŁA�{�l�̂���Ɋւ��������I�Ɉ�Ë@�ցA�s���{����ʂ��āA���������Z���^�[�̒��ɐݒu����Ă��频S������o�^�f�[�^�x�[�X��ɓo�^����Ă����܂��B ���W���ꂽ�f�[�^�͉��Ɏg����̂ł��傤�� �@�S��������W�����f�[�^�́A���̃f�[�^�x�[�X�ɂ܂Ƃ߂��A���v�̐��Ƃɂ���ĕ��͂��s���܂��B �@���͂ɂ���ē���ꂽ�ŐV�̓��v���́A���������Z���^�[�������Z���^�[�̃E�F�u�T�C�g�����o�^����v��Ő������J����A�N�ł��{�����邱�Ƃ��ł��܂��B �@�����̓��v���͈�ʂɌ��J�����Ɠ����ɁA����s���{���̂������͂��߁A���f�⎡�Â̑̐��Â���A�����Ȃǂɖ𗧂Ă��܂��B �ǂ�ȏ���W�����̂ł��傤�� �@���m�ȓ��v�����Ƃ邱�Ƃ���̖ړI�Ƃ���邽�߁A�����o�^���̐��i�Ɋւ���@����ŁA����o�^�ɂ������Ċ��Җ{�l�̓��ӂȂ��Ă��悢�Ƃ���Ă���A����l�Ɍl����m��ꂽ���Ȃ���Ƃ������R�ŁA����o�^�����ۂ��邱�Ƃ͂ł��܂���B �@�W�߂�����̒��ɂ́A�����Ɛf�f���ꂽ�l�̎����A���ʁA���N�����A�Z���v�����̐f�f���s������Ë@�֖�������̎�ޣ�����̎��Ó��e��Ȃǂ�����܂��B�������A�f�f���ʂ⎡�Ó��e�́A��Ë@�ւɒ��ڊm�F���邱�Ƃł���A�S����̏����Ȃ����ł̊J���́A���Җ{�l��Ƒ��̊J���������F�߂��Ă��܂���B �@�f�[�^���W�߂邱�ƂŁA����̒n��I�ȕ��A�ǂ̎��Â����ʓI�Ȃ̂���������A���Âɖ𗧂̂ł���Ύd���̂Ȃ����ƂȂ̂�������܂��A�����I�Ɍl����W�����̂́A�R�k�̖����l����ƕs���ɂȂ�l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ł����A���ꂩ��̂��ÂɈ�𓊂��邱�ƂɂȂ����Ȃ��ƂȂ̂ł��B �K�W�F�b�g�ʐM 2015�N12��12�� |
|
�V���Ȋ����ÕW�I�����A������ �����v���̃��J�j�Y���𗘗p |
| �@���������Z���^�[�i������j�͂X���A���O���Ƃ̋��������ŁA����̂Q�̈�`�q���Ƃ��ɋ@�\���Ȃ��Ȃ�Ƃ���זE�����ł���u�����v���v�̃��J�j�Y���𗘗p�����V���Ȃ���̎��ÕW�I�������Ɣ��\�����B�x����Ȃǂŕψق���b�a�o��`�q�̋@�\�����R�O�O��`�q������������悤�ɕ⏕���铭���������Ƃ�˂��~�߂��B�����`�[���́A�b�a�o��`�q���ψق��Ă��邪��̐V���Ȏ��Ö�Ƃ��āA���R�O�O����ς�����j�Q�����܂̊J����ڎw���B �@�b�a�o��`�q�͔x���זE����∫�������p��Ȃǂŕψٌ^������Ƃ���邪�A��`�q���̂̋@�\�͎����邽�߁A���̈�`�q�ڃ^�[�Q�b�g�ɂ������Ö�͊J���ł��Ȃ��B�����A�s������������`�q�̋@�\��⏕����ʂ̃p�[�g�i�[��`�q�����݂���ꍇ������B���̌��ۂ́u�����v���v�ƌĂ�A�p�[�g�i�[��`�q��j�Q���Ă���זE�����ł����鎡�Ö@�̊J�������ڂ���Ă���B �@������Ƒ��O���̌����`�[���́A�b�a�o��`�q�Ƃ��R�O�O��`�q�̑g�ݍ��킹���A���̍����v���̊W�����邱�Ƃ������B��`�q�ψقłb�a�o����ς������ُ�ɂȂ�������זE�͐������邽�߂ɂ��R�O�O����ς����̋@�\���K�v�ŁA���R�O�O��`�q���@�\���Ȃ������זE�����ł���\�����m�F�����B���̃��J�j�Y���Ɋ�Â��A���R�O�O����ς����̋@�\��j�Q�����܁i���R�O�O���ٓI�j�Q�܁j��V���ȍR����܂Ƃ��ĉ��p�ł���Ɗ��҂��Ă���B �@������͂Q�O�P�Q�N�ɑ��O���ƕ�I������g�_������сA�V���ȍR����ܑn�o��ڎw�������������s���Ă���B m3.com 2015�N12��14�� |
| ���f�����S�����߂�H�댯�Ȍ��� |
| ���c���F�@�V����w���_���� �@���݁A5�̂���ɑ���W�c���f�����ɂ���Đ��i����Ă��܂��B�݁A�咰�A�x�A���[�A����Ɏq�{�̊e����ł��B�������A�ǂ̂��f�����S������������ʂ��Ȃ����A�ނ��뎀�S�������߂Ă��܂����̂ł��邱�Ƃ́A�{�A�ڂŏq�ׂĂ����Ƃ���ł��B �@���f�ł�������ΕK�����Â��s���Ă��܂�����A����͌��������̖��łȂ��A���Â̕��@�ɂ��^�`�����邱�Ƃ��Ӗ����܂��B �@�ł͑��������E�������Â��ł���͂��̂��f�ŁA�Ȃ����S����������Ȃ��̂ł��傤���B �@�u�����v�Ƃ����C���[�W���l�X�̔]���ɏĂ����Ă��܂��B���{�ł́A���a27�N�Ɍ��J���ꂽ���V���ē�i�w������x���ЂƂ̂��������������悤�Ɏv���܂��B�f��̒��ŁA�������������l���𖼗D�E�u�����������Ă��܂������A�u����͕K�����ʕa�C�v�ł��邱�Ƃ���������Ă��܂����B�������A�{���ɂ����Ȃ̂ł��傤���B �@���̐́A����זE�̂����܂���ɈڐA����ƁA�����܂��傫�Ȏ�ᇂɐ������ē���������ł��܂��Ƃ������������E���łȂ���܂����B�����ł��邱�Ƃ����Ƃ̋��ʔF���ƂȂ�A�₪�Đ��E���̐l�X�̒m��Ƃ���ƂȂ����̂ł��B �@�����������ɂ�����ڐA���悤�Ƃ��Ă��A���ʂ͋��۔������N���邽�߁A���܂������܂���B�����ڐA�����������̑̓��łǂ�ǂ�傫���Ȃ����Ƃ���A��قǂ����̈������̂�I��Ŏ������s�����ƍl�����܂��B���������̌��ʂ�������A����̐�����_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B �@�������Â����ɁA�a�C����u�����ꍇ�ɂ��ǂ�o�߂��u���R�j�v�Ƃ����܂��B�w����a���w�̌n�|���̎��R�j�i���c�N�璘�j�x�ɂ��A�q�g�݂̈����咰����́A1�̂���זE�������g�Q������������������Ŕ����ł���قǂ̑傫���i���a1�Z���`���[�g���ȏ�j�ɐ�������܂łɁA���_��25�N���炢������̂������ł��B�����������ɂ͌l�����傫���A�܂��A�����������Ƃقڗ�O�Ȃ���p�Ȃǂ̎��Â��s���邽�߁A�{���̎��R�j�͒N�ɂ��킩���Ă��܂���ł����B ���u�ƍŐV���ÁA5�N�������͓����H �@�Ƃ��낪�ŋ߁A�ӊO�Ȏ��������X�Ɩ���݂ɏo�����悤�ɂȂ�܂����B �@���Ƃ��ACT�ɂ��x���f���s���A�����ȕω��܂Ō�����悤�ɂȂ�܂������A���錤���ɂ��A���a��3�Z���`���[�g���ȉ��̎�ᇂł́A�T�C�Y�Ƃ��̌�̉^���A�܂莀�Ɏ��邩�ǂ����Ƃ͖��W�ł��邱�Ƃ��킩��܂����B �@������Ɛf�f�����l��22�����炢�́A���u���Ă����R�ɏ��ł��Ă��܂��\�����������Ƃ́A�{�A�ڂł��łɏЉ���Ƃ���ł��B �@�܂��A�C�O�ōs��ꂽ�����ɂ��ƁA���S�����l�̉�U���s�����Ƃ���A���܂��ܔx����������153�l�̂����A43�l�͐��O�ɔx����̐f�f�͎Ă��炸�A�Ǐ�����������Ȃ����������ł��B �@����ɍ����ōs��ꂽ�����ɂ��A���������ň݂���Ɛf�f����Ȃ���A�Ȃ�炩�̗��R�Ŏ��Â����������Ȃ�����38�l�̓��{�l��ǐՂ����Ƃ���A5�N��ɐ������Ă����l��63�`68���������Ƃ����̂ł��B�݂���Ɛf�f���ꂽ���_�ł́u�i�s�x�v�͕s���ł����A���ς���2���i�����\�L�̓��[�}�����^���ݕǂɗ��܂�j���炢�������Ƃ���A�ŐV���Â����ꍇ��5�N�������Ƃقړ������������ƂɂȂ�܂��B �@����͕��u����ƕK���傫���Ȃ�A�����܂����Ɏ���Ƃ̐_�b�́A���łɕ��ꋎ���Ă��܂��B����̈����x�ɂ͑傫�Ȍ̍�������A�l�{���Q�Ȃ��̂���Ɉ��Ȃ��̂܂ł��܂��܂Ȃ̂ł��B���Q�Ȃ�������f�ł��������Ď��Â���A5�N�������͍���������Ɍ��܂��Ă��܂��B �@���f�̐��Ƃ́A�����g�Q��������CT��������ɑւ��āu���f�̐��x�����܂����v�Ǝ������Ă��܂��B�������A���̓w�͉͂ߏ�Ȑf�f�iover-diagnosis�j���������A�ߏ��Â̋]���҂𑝂₵�Ă��邾���ł��B �@���f�̊��U������u���{����v�̂悤�ł����A���������N���A���������ɁA�ǂ�Ȃ��Ƃ����Ă���̂��A�����ɂ킩�錾�t�Ő������Ăق������̂ł��B�u�s���N���{���v�Ƃ������̉^�����x�����Ă�������J���ȁA�����s�A���{��t��A�����V���ЂȂǂ́A���v�����̗L�����܂߂Ď���̐ӔC�m�ɂ���K�v������ł��傤�B �@���f�𐄐i����g�D�̃z�[���y�[�W�́A�ǂ���u��̂����R�v�Ƃ̑O��ł����Ă��āA�M�҂ɂ֑͌�L�������\���@�ɂ��������܂���B �Q�l�����FGut 2000;47:618-21. Business Journal 2015�N12��15�� |
|
�}�����U�z���A��̊����X�N4���� �f�f�㐶���Q�ł̓��X�N��76������ |
| �@�č����w��iAACR�j��12��2���A�}�����O���t�B�����ʼnߋ��ɋU�z���Ɛf�f���ꂽ���Ƃ̂��鏗����10�N�ȓ��ɓ����ǂ��郊�X�N�����܂�\�����������������ʂ��Љ���BCancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention���Ɍf�ځB �@�����ł́A1994-2009�N�ɕč���40-74�̏���130���l��Ώۂɍs��ꂽ�}�����O���t�B����220��������́B��������10�N�ɂ킽���ĒǐՒ������A�������X�N�ɂ��ĕ]�������B���̊Ԃ�4��8735�l�̏����������Ɛf�f���ꂽ�B �@��ʓI�ɁA�}�����O���t�B�����ŋU�z���ƂȂ����ꍇ�́A�lj��̉摜�������A����ɂ��̈ꕔ�͐������s����B�����̌��ʁA������10�N�Ԃ̓������X�N�́A�}�����O���t�B�����ŋU�z���Ɛf�f���ꂽ�Q�ł́A�A���������Q�Ɣ�ׂ�39�������A�U�z���Ɛf�f���ꐶ�������Q�ł�76�����������B �@���̌������哱����Louise M. Henderson���́A�u���̃��X�N�v���Ɠ������X�N�S�̂��Č������钆�ō���̌��ʂ�L�p�ȃc�[���ɂ������v�Əq�ׂĂ���B m3.com 2015�N12��16�� |
|
�X�}�z�ōR���ܕ���p���j�^�����O �pAZ�A�Տ������ŗL�p������ |
| �@�p�A�X�g���[�l�J�i�`�y�j�͂��̂قǁA���Ђ��J�������R������ÂŁA�X�}�[�g�t�H����p���ĕ���p�Ȃǂ����j�^�����O����T�[�r�X�̌����n�߂�Ɣ��\�����B�X�}�[�g�t�H���̃A�v��������Ǘ����x������u�R���p�j�I���E�f�o�C�X�v�Ƃ��ėL�p����������B �@��Õ�������̃\�t�g�E�G�A�J���Ȃǂ���|���镧�{�����e�B�X���J�������X�}�[�g�t�H���A�v����p���āA�R������Â��Ă��銳�҂̕���p�Ȃǂ��Ǘ�����f�W�^���T�|�[�g�T�[�r�X�̗L�p����������B�`�y���J�������R����܁u�I���p���u�v�u�b�����������������v�p���Ă���Ĕ��v���`�i���������x�������҂�Ώۂɂ����Տ������ŃX�}�[�g�t�H���E�A�v���������������Č�������B�����͕č����������̎哱�ŗ��N�P�`�R�����ɊJ�n����\��B �@���҂��X�}�[�g�t�H��������͂�������p���Ȃǂ����Â����Ë@�ւ̃E�F�u�|�[�^���ɒ��ڑ��M����邽�߁A����p�̔c���Ⓤ�^�ʂ̒����Ȃǂ��������ł���Ɗ��҂��Ă���B m3.com 2015�N12��16�� |
|
�O���B����̃z�������Ö@���A���c�n�C�}�[�a���X�N�Ɋ֘A 3�N�Ԃ̒ǐՊ��Ԓ��ɐf�f�����\����88���㏸ |
| �@�O���B����̃z�������Ö@�ɂ��A�j���̃A���c�n�C�}�[�a���ǃ��X�N�����I�ɏ㏸����\�����A��K�͂Ȉ�Ãf�[�^�̉�͂ɂ�莦�����ꂽ�B�O���B����̒j���́A�A���h���Q���Ւf�Ö@�iADT�j����ƃA���c�n�C�}�[�a���X�N���ق�2�{�ƂȂ�A1�N�ȏ�ADT�����ꍇ�͂���Ƀ��X�N���㏸����ƁA�����̕M�����҂ł���ăy���V���x�j�A��w�i�t�B���f���t�B�A�j�y�����}����w��w�@��Kevin Nead���͏q�ׂĂ���B �@�č����������iNCI�j�ɂ��ƁA�j���z�������ł���A���h���Q���͑O���B����̑��B�𑣐i����Ƃ���Ă���A���̃z��������}���鎡�Ö@��1940�N�ォ��嗬�ƂȂ��Ă���B���݁A�č��ł͖�50���l�̒j�����O���B���ÂƂ���ADT���Ă���Ƃ����B�������A��t��̊Ԃł�ADT�����҂̔]�@�\�ɂ��e�����y�ڂ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����^����������Ă����ƁA�č�����iACS�j��Otis Brawley���͐�������B �@����̌����ł́A�ăX�^���t�H�[�h��w�a�@�i�J���t�H���j�A�B�j����у}�E���g�E�T�C�i�C�a�@�i�j���[���[�N�s�j�̊���550���l�̈�ËL�^�ׁA�]�ڂ̂Ȃ��O���B���Җ�1��7,000�l����肵���B���̂�����2,400�l��ADT���Ă����B �@��ɃA���c�n�C�}�[�a�̐f�f�������҂��m�F�������ʁAADT�������҂́A�Ă��Ȃ����҂ɔ�ׁA��3�N�Ԃ̒ǐՊ��Ԓ��ɃA���c�n�C�}�[�a�Ɛf�f����郊�X�N��88�����������B�܂��AADT��12�J���Ԉȏ�Ă������҂ł̓��X�N��2�{�ȏ�ƂȂ邱�Ƃ��킩�����B �@�Ȃ��A�j���z���������A���c�n�C�}�[�a���X�N�ɉe�����y�ڂ��̂��낤���B���̗��R�͂������l�����邪�A�ăA���c�n�C�}�[�a����iAA�j��Keith Fargo���ɂ��ƁA�A���h���Q���ɂ̓��A�~���C�h�ƌĂ��`���̌����Z�x��Ⴍ�}�����p������悤���Ƃ����B�A���c�n�C�}�[�a���҂̔]���ɂ́A���A�~���C�h���ÏW�����A�~���C�h���i�v���[�N�j���݂���B�܂��AADT�����҂̌��ǂ₻�̑��̏d�v�Ȍ��N��Ԃɉe�����y�ڂ��A���ꂪ�]�@�\�ɉe������\���������Nead���͏q�ׂĂ���B �@�������A���Ƃ�͂��̒m���Ɋ�Â��ĉ��炩�̈�w�I�������o���̂͑����Ƃ��Ă���B���̂悤�Ȋώ@�����ł͈��ʊW�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł����A���̖��m�̈��q���e�����y�ڂ��Ă���\���������Nead���͘b���BFargo��������ɓ��ӂ��A���̒m���Ɋ�Â��Ė�܂̓��^�𒆎~���ׂ��ł͂Ȃ��Əq�ׂĂ���B �@���̌����́uJournal of Clinical Oncology�v�I�����C���ł�12��7���f�ڂ��ꂽ�B m3.com 2015�N12��24�� |
| �������A���Ò��̐l�Ɍ������[�L���b�v���@���܂Ƃ߂������q���z�z |
| �@�������͂��̂قǁA���Ò��̐l���L�̔��Y�݂ɑΉ��������[�L���b�v���@���܂Ƃ߂������q�w���҂���̂��߂̊O���P�ABOOK�x�s�����B �@���Ђł́A1990�N�㏉�߂����Ë@�ւƘA�g���A�����┒���A�����ƂȂǔ��ɐ[���Y�݂������l�Ɍ����āA���[�L���b�v�A�h�o�C�X��A�Y�݂̃J�o�[�ɓK������p���i�̊J���Ɏ��g��ł����B  �@2006�N6���ɂ͊����̋��_�ƂȂ�{�݁u������ ���C�t�N�I���e�B�[ �r���[�e�B�[�Z���^�[�v�𓌋��s�E����ɊJ�݁B�܂��A����̎��Ò��͕���p�Ƃ��āA���F�̕ω��A�܂�E�܂т̒E�тȂǂƂ������O����̕ω����N���邱�Ƃ���A2013�N10������͂����̕���p�ɔY�ސl�Ɍ����A���ł̃A�h�o�C�X���s���Ă���B �@���̂قǔ��s���������q�ł́A���Â̕���p�ɂ��O����̕ω��ɑ��A���[�L���b�v�ɂ���ăJ�o�[����e�N�j�b�N��O���P�A�̕K�v�����Љ�Ă���B �@���e�́A�u���҂���ւ̃��b�Z�[�W�v�u���F�̃J�o�[���@�A�e�N�j�b�N�v�u���R�Ȕ��̕`�����v�u��ۓI�Ȗڂ��ƂɎd�グ��A�C���[�L���b�v�v�u���[�L���b�v�ƃE�B�b�O�ɂ��C���[�W�`�F���W�̕��@�v�u���Ñ̌��҂̃R�����v�ȂǁB �@�����q�́A�S����380�J���̐�p���i��舵���̉��ϕi���X�A�f�p�[�g�⏬���q��]�̕a�@�ȂǂŖ����z�z���Ă���B�܂��A������ ���C�t�N�I���e�B�[ �r���[�e�B�[�Z���^�[�̃E�F�u�T�C�g����{���E�_�E�����[�h���\�B �}�C�i�r�j���[�X 2015�N12��27�� |