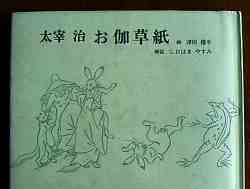|
太宰治の杉並時代(3) 昭和8年から10年。 それが、病んだ。転地療養のため、杉並から離れて千葉に移った。失意がおそった。 涙ぐましい闘いの末、巣を求めるように、杉並に戻ってきた。 病気と人間関係のはざまに、ボロボロになって。 杉並は太宰を再生させた。 不作の時代から、「燈籠」「姥捨」「満願」と、中期を告げる作品群が生まれ 次の三鷹時代の開花を促した。 昭和11年から昭和13年。 この頁では、この時期をたどる。
パピナール中毒に病み、芥川賞に怒り、初代の姦通に失意のどん底に落ちたとき この道はどれだけ安息感をもたらせたか。 太宰は杉並に戻ってきた。パピナール中毒に苛まれ、芥川賞事件に自らも傷つき、「脳病院監禁」と反発しながら中毒を克服する。そんな、ヨレヨレ、ボロボロの中で、古巣に帰ってきた。 不作の時代と言われながらも、燭光を見いだしている。静かに作品を書きためていた。「満願」のように、日傘をくるくる回す明るさが見えてきた。その明るさを確認したい。 昭和10年(1935)27歳 「玩具」「雀こ」の発表 杉並に戻る前、千葉船橋の家でパピナール中毒は更に進行した。太宰の精神状況はひどくなる。その中で、短編が生まれた。7月、『作品』七月号に「玩具」「雀こ」を発表した。私は、津軽弁で書かれた「雀こ」が大好き!!津軽の雪の広い広い原に、新芽が萌える前、子供達が集まって古芝を燃やす。二組に分かれて歌の掛け合いをする。東国のカガイのように!! ――雀、雀、雀こ、欲うし。 ほかの方図(ほうず)のわらは、それさ応(こた)へ ――どの雀、欲うし? て歌ったとせえ。 そこでもってし、雀こ欲うして歌った方図のわらは、打ち寄り、もめたずおん。 ――誰をし貰ればええべがな? こうして、相談して「タキ」を貰うことになり、そう言ってやると、タキのグループでは、心根っこわるくして、羽がないから呉れられぬ。と歌い返して来る。こっちでは、羽こ呉れるから飛んで来いと歌い返す。こうしたやりとりがあって、マロサマとタキの話が展開する。(筑摩現代文学大系 太宰p60) 井伏鱒二に献じられた。横道お許しの程。 パピナール中毒の状況こんな美しい話を書いているとき、パピナール中毒の最中とは信じられないが、その状況はひどい。中畑氏はこう述べる。 『・・・その頃、この船橋の縁の下をヒョイとのぞいてみたら、国許から送ってやったリンゴ箱に、たっぷり三倍半のパビナールの空アンプルが入っておって驚いたことも鮮かに憶えています。』(新文芸読本 太宰治 p26 河出書房新社) このパピナールも、地元の医者を半ば脅かして処方させたもので、友人達から借りた借金の額は500円近くに及んでいたという。足りなくて、あの縁を切っている兄文治にも申し込みをする。 これらを見ると、極限に来ていたことがわかる。創作意欲とどのようにつながっていたのか、天才とはわからぬものとつくづく思う。 第1回芥川賞騒動 こういう状況で、芥川騒動が起こる。太宰の杉並時代・後期を特色づける一つであろう。あの太宰にして、と、今では、信じられないが、芥川賞にこだわった。故郷に対する名誉なのか、お金なのか?? 尋常ではない。 この第1回と第3回の受賞について、自作が対象外になったことを巡って、太宰と選考者「川端康成」「佐藤春夫」との間で、論争というか、騒動めいたやりとりがあった。太宰が受賞に固執した理由を巡って、パピナール中毒、借金などが分析される一方、これを契機に、太宰の心理、書き方に変化が生じたことが指摘される。 騒動は2回起こった。最初は 第1回芥川賞を巡ってであった。8月、第1回芥川賞候補に、太宰の書いた「逆行」「道化の華」が推されていることを知らされたのに、(佐藤春夫の義兄からという)、選考の結果、受賞作は石川達三「蒼氓」で、太宰と高見順、衣巻省三、外村繁は次席になった。『文芸春秋』9月号に、芥川賞選考の経緯が公表された。その中で、川端康成が太宰の生活について 『・・・なるほど道化の華の方が作者の生活や文学観を一杯にもっているが、私見によれば、作者目下の生活に厭な雲ありて、才能の素直に発せざる憾みあった』 と指摘するところがあり、太宰は、憤激した。ここから騒動が始まった。 太宰は、『文芸通信』10月号に、「川端康成へ」として、「芥川賞後日異聞二篇」を書いて反論した。 『・・・おたがいに下手な嘘はつかないことにしよう。・・・日本にまだない小説だと友人間に威張ってまわった。・・・ 小鳥を飼い、舞踏を見るのがそんなに立派な生活なのか。刺す。そうも思った。大悪党だと思った。・・・』 文中名前の出た 檀一雄は「小説 太宰治」の中で 『・・・第一回芥川賞の受賞を切望した、太宰の気持ちの中には、例の激しい虚栄心があったろうが、モヒ剤入手への中毒者心理もあったろう。また、その入手の際の友人、知己から借り入れた、金に対する心の苛責もあったろう。・・・』と書く。これが第1回芥川賞騒動であった。なお、これを機に、太宰は、太宰を支持し芥川賞の選考委員でもあった「佐藤春夫」に師事する。 9月、「猿ケ島」を『文学界」九月号に発表した。 同月、授業料未納で、東京大学を除籍された。 10月、太宰は「ダス・ゲマイネ」を『文芸春秋』十月号に発表した。芥川賞最終候補者に、文芸春秋社から、原稿依頼があったものである。 12月、「地球図」を『新潮』に発表した。また随筆「もの思ふ葦」(その一)を『日木浪曼派』に連載した。 この秋、京城にいた田中英光との文通がはじまった。 こうして、昭和10年は暮れ、昭和11年、初めての創作集『晩年』が出版されるが、パピナール中毒に悩まされ、再度の芥川賞候補にも入選せず、衰弱と失意の中、杉並に戻ってくる。 昭和11年(1936)28歳 1月、「めくら草紙」を『新潮』一月号に発表。 2月10日、パビナール中毒が進み、佐藤春夫の忠告で、佐藤の実弟「秋雄」の勤務する済生会芝病院に入院した。太宰は、入院中も飲酒やパビナール注射を止めず、全治せぬまま同月23日、退院させられた。 例えば、檀と緑川貢が見舞いに来たときの話だが、檀は「小説太宰治」に、こんな風に書いている。 『「いまさき、佐藤春夫先生ご夫妻が、見舞いに来られたところだ」 ・・・・・ 夕暮れだった。その明暗の静かな推移を量りながら、私達は酔っていた。暮れていた。 「出かけようか?」 と、太宰、 「ああ」 と、私は即答した。 ・・・・』 こうして、太宰は和服に着替えて、みんなが見舞客のふうで、ぞろぞろと自動車に乗って、大川を渡って玉の井へ繰り出して、大酒を飲む。これでは、病院もたまったものではなく、退院にしたのであろう。 4月、「陰火」を『文芸雑誌』四月号に、「雌について」を『若草』五月号に発表。 『晩年』の刊行 この頃、パビナール中毒の進行による衰えに、周囲の友は太宰の余命があまりないことを予感した。また、太宰の希望もあって、創作集の刊行を計画した。6月25日、檀一雄の尽力により、創作集『晩年』を砂子屋書房から刊行した。7月11日、上野精養軒で出版記念会が行われた。友人30数名が集まる盛大な会であった。 太宰の生家に出入りし、東京の太宰の面倒見を頼まれていた「中畑慶吉」はこの時の様子を次のように書く。 『太宰の出版記念会が上野の精養軒で行なわれたのは、船橋時代でした。例によって仕入れの上京を利用して立ち寄った私は、彼があまりにもよれよれの着物を着ていたのでびっくりしてしまいました。元来、修治さんという人は大変おしゃれで、専門家の私が見ましてもおどろくほどゼイタクなものを着るのが常でしたのに……。・ さて、その(出版記念会・安島記)翌日の朝、私は船橋の借家を訪ねました。ところが、またぞろ、ヨレヨレの寝巻を着ています。「どうした」というと、だまって金六十円也の質札を見せました。昨晩のうちに六百円の着物は一枚の紙きれに化けてしまったわけです。・・・私は「ハハァ、取り巻きに貸したか、それとも一緒に豪遊してしまったナ」と想像いたしました。・・・私は、この入質にはダンカズ(檀一雄)さんが一枚かんでいると今でも想像しとります。』(新文芸読本 太宰治 p25〜26 河出書房新社) 第2回芥川賞騒動6月29日、パビナール中毒による妄想もあってか、太宰は川端康成に、自作「晩年」が芥川賞受賞作品となるように願って、切々たる手紙を書いている。 『・・・生まれてはじめての賞金、わが半年分の旅費 あわてず あせらず 十分の精進 静養もはじめて可能 労作 生涯いちど 報いられてよしと 客観数学的なる正確さ 一点 うたがい申しませぬ 何卒 私に 与えて下さい 一点の駆引ございません・・・』(新潮日本文学アルバム 太宰治 p42−43) また、三日にあけず、佐藤春夫宅を訪問し、涙ながらに訴えたとの話もある。 7月、「虚構の春」を『文学界』七月号に発表。 太宰のショックは大きかった 。それは怒りとなって、「創世記」に「山上通信」を書き加えて鬱憤をぶちまけた。太宰は佐藤春夫にさえ裏切られたと受け取り『・・・先日、佐藤先生よりハナシガアルからスグコイという電報がございましたので、お伺い申しますと、・・・私は照れくさく小田君など長い辛抱の精進に報いるのも悪くないと思ったので、一応おことわりして置いたが、お前はほしか、というお話であった。・・・』(新潮文庫 二十世紀の騎手 創世記 p135) と、 一種の内輪話の暴露めいたことを書いた。ここから、佐藤春夫との行き違いが生ずる。佐藤春夫は太宰の才能を認めながら、「芥川賞」と題して作品を書き 『・・・以後、あの男とは第三者を交えずには対話も出来ないと不安である。・・・』 と言うまでになった。しかし、後に「希有の文才」として『・・・それ以来自分のところへ近づかなくなった彼に対しては多少遺憾に思いながら遠くからその動静を見守っていたものである。・・・』(小学館 群像日本の作家17 太宰治 p149)としている。 この経緯については、多くの研究書があり、野原一夫 太宰治 生涯と文学は詳しい。こうして、太宰の芥川事件は2度の山場を過ごしたことになる。 パピナールの克服 10月、 「狂言の神」を『東陽』、「創生記」を『新潮』、「喝采」を『若草』各十月号に発表した。10月13日、井伏鱒二らのすすめにより板橋江古田の武歳野病院に入院した。 その時の状況を中畑さんは次のように云う。 『・・・だんだんと中毒がひどくなって、井伏先生と北さんと私の三人で相談して入院させることになったのです。いやがる太宰を自動車に押しこめ、病院へ向う途中、ちょうど言問橋の真中あたりで薬品が切れ、暴れ出したので兵児帯でしばっておとなしくさせました。この頃になると、いくら注射しても数十分ともたなかったんじゃないかと思います。』(新文芸読本 太宰治 p26 河出書房新社) 井伏鱒二は次のように書く。 『・・・「僕の一生のお願ひだから、どうか入院してくれ。命がなくなると、小説が書けなくなるぞ。怖ろしいことだぞ。」と強く言った。すると太宰君は、不意に座を立って隣の部屋にかくれた。襖の向こふ側から、しぼり出すような声で啼泣するのがきこえて来た。二人の番頭と私は、息を殺してその声をきいていた。やがて泣き声が止むと、太宰は折りたたんだ毛布を持って現れ、うなだれたまま黙って玄関の方に出て行った。・・・』(井伏鱒二 文士の風貌 p276) この入院は、太宰が「脳病院監禁」と称するもので、主治医(中野嘉一)の手記によれば、 『・・・入院した晩、逃走の虞ありというので、開放病棟から鍵のかかった病棟に収容された。一週間位はおちつきなく、恐らく夢中であったろう。 しかし、よほどの薬効と辛抱があったのであろう、こんなひどい禁断症状を克服して、11月8日には、面会謝絶が解かれて、パビナール中毒症は根治した。11月12日、 退院した。鰭崎潤宛の書簡(十一年十一月二十六日付)によれば、禁断症状がなくなってからは、毎日、聖書を読み続けたという。退院するときのやりとりがすごい。退院の前日、太宰の兄津島文治さんは太宰に津軽で羊の牧場守をさせると言い、津島家の番頭(北、中畑の二人)は湘南地方の病院で静養させるべきと主張し、井伏鱒二は東京で小説を書かせるべきだと説いた。この時の会談は『有耶無耶に終わった』(井伏)。 翌日(退院の日)、病室で太宰と 兄・津島文治の対面があり、井伏鱒二が立ち会った。井伏は、その時の様子を次のように書いている。 『・・・文治さんはふと気を変へたやうに坐りなほし、太宰君に東京で小説を書いても差支へないと手短かに云ひ、「それでは、毎月七十円づつ送る」と云つた。太宰君は言下に「九十円」と云つた。文治さんは「では、九十円。しかし一度に送ると、一度に遣つてしまふから、月三回に分けて送る。それも直接には送らぬ。中畑から井伏さんに送らせて、井伏さんからお前に渡してもらふ形式にする」と云つた。 この方式による送金は、太宰が流行作家になった後も続き、戦後になってやめになった。 再度、杉並に!!(後期) パピナール中毒を克服して退院した太宰は、杉並に戻ってきた。杉並時代後期の開始となる。 昭和11年11月12日、井伏夫人と初代があらかじめ見つけておいた杉並区荻窪の白山神社近く、光明院裏の照山荘アパートに入った。その夜から「HUMAN LOST」を書きはじめた。 こんな都会の中に?と、びっくりするような、周囲とは全く違った鬱蒼とした森の中に白山神社はある。 光明院は少し場所を離れて、高台にある。(右) これでは、照山荘アパートは見つけようもない。太宰はここに、3日しか居なかったと言うが 「HUMAN LOST」を書きはじめた場所だけに、とても残念。 太宰は、このアパートが気に入らず、3日後の15日に、天沼一丁目238番地「碧雲荘」に移った。現住居表示では天沼3丁目19にあたる。前期に一度、居住した「天沼稲荷」の近くである。荻窪駅から来る場合には、教会通りを荻窪税務署方向に進めばよい。
突き当たりが天沼通りで、荻窪税務署の前を通り越して、杉並第五小学校方面に向かう。(右) この画像では表現されないが「栄寿司」の風情がいい。その角を曲がると 『新潮日本文学アルバム 太宰治』には 『武蔵野病院退院後、太宰が井伏夫人とともにさがした下宿碧雲荘(東京都・杉並区天沼3丁目) この宿で初代との7年間の生活にピリオドを打った』と付記している。 太宰夫婦は2階の和室8畳間を間借りした。檀によれば、階上に炊事場が一部屋あって、間借りでも随時、炊事出来るという状況であるとしている(小説太宰治)。この夜から、武蔵野病院の体験を一気に「HUMAN LOST」に投入したらしい。野原一夫は 『・・・鰭崎潤宛の書簡(十一年十一月二十六日付)によれば、「一面の焼野原に十日間さまよう」思いで書き進めたのである。自分のなかに渦巻いている憤怒のはげしさが、傷心の深さが、そしてまた必死の抗議の念が、芸術家としてのゆとりを太宰から失わせてしまったと考えてよいのではあるまいか。・・・』(太宰治 生涯と文学) 初代が 武蔵野病院に太宰を見舞い、面会謝絶だった頃、その帰りに、篠原病院に小舘を見舞うのが常だった。その時「哀しい間違い」(東京八景)を起こしたという。昭和12年(1937) 29歳 1月、「二十世紀騎手」を『改造』一月号に発表。3月、小舘善四郎から初代との若気の過ちを知らされた。太宰は苦慮した。吉沢 祐(初代の母の弟=叔父)は次のように書く。 『存在はした一事(前後の事情を知る私は、敢てこれを些細な一事とみる。太宰も、その悲しさ故に水上行となったではないか)が歪曲と誇張をもって紙面に温存され、これを鵜呑にして虚構と実相を混同、徒に伝えて怪しまぬ者も過重の蔑視に遭い弁明の場を与えられぬことが己の身に及んだ時、始めてその思いを知るだろう。 太宰は水上温泉で初代とカルチモンによる心中を企てたが失敗した。作品 「姥捨」があり、多くの年譜はこのように記す。また、野原一雄は『「姥捨」は太宰の私小説のなかで比較的虚構性の強い作品で、明らかに事実とちがった作り話と思われる箇所もいくつかある。』としたうえで『・・・汚れた服装のまま二人はその日のうちに別々に東京に帰ってきている。太宰は碧雲荘に戻ったのだろうが、初代は井伏家の玄関をたたいている。憔悴しきった初代の姿に、井伏夫人は思わず玄関先で手を取り合って泣いたという。』 と書いている(太宰治 生涯と文学)。ところが、先の長篠康一郎氏は、この出来事は、作品からの写しで、事実とは違うのではないかとの指摘をする。 『「水上温泉でカルチモン心中を図った」という年譜は、この「東京八景」と「姥捨」の物語から、それぞれ想像して作成されているにすぎない。・・・ 「姥捨」が事件の真相を正直に書いた作品だとすると現地の実状とあらゆる面で合致しないのである。・・・昭和十二年三月下旬の現地は連日降雪の日が続いて、・・・この大雪の中で、実際に睡眠薬(カルチモン等)心中を図ったら、まず助かる見込みは皆無であったろう。・・・』とする。まだまだ、問題が山積している。 6月10日、現実に、初代の叔父吉沢祐の仲介で太宰は初代と離婚した。そして、 「鎌瀧」へは、青梅街道からも、天沼通りからも行ける。
天沼診療所の隣に鎌瀧はある。 昭和13年9月、ここを引き払って、山梨県御坂峠の天下茶屋に移った。 太宰は単身、自分の夜具と机、電気スタンド、洗面道具だけを持って、引っ越してきたらしい。西日のさすひどい部屋だったという。井伏は何回も太宰に 『どうだ君、初代さんとよりを戻す気はないかと言う。すると、太宰は、居直ったかのように、きっとして、その話だけは絶対にお断りしたいと、きっぱりした口をきく。・・・』 一方、初代は浅虫の生家に戻るまで、井伏の家に泊まっていた。 『・・・茶の間の濡縁に私の家内と並んで腰をかけ、涙をぽたぽたこぼしているのを見たことがある。・・・』(いずれも、井伏鱒二「琴の記」) 何とも切ない話である。東京八景では、さらに寂しい話を書く。 『私たちは、とうとう別れた。Hを此の上ひきとめる勇気が私に無かった。捨てたと言われてもよい。人道主義とやらの虚勢で、我慢を装ってみても、その後のH々の醜悪な地獄が明確に見えているような気がした。 この頃から、太宰には支持者が現れる。若い文学憧れの食客だ。井伏鱒二は次のように書く。 『・・・東京の下宿生活を切りあげるために逃げて行つたのである。全く逃げ出すよりほかはなかつた。彼は山に籠る前には荻窪の鎌滝といふ下宿屋にゐたが、いつも二人か三人の食客を泊めてゐた。昼間はその食客の友人がやつて来て、いつ行つてみても四人五人の客のゐなかつたことがない。 酒は平野屋といふ酒屋から帳面で取寄せてゐた。食事は下宿でつくる客膳といふのを持つて来させ、酒の肴にはタラコだとかウニだとか花ラッキョウだとか、そんなものを近所の漬物屋から取寄せてゐた。それが毎日のことなので接客費もかさばつて行く。 太宰が「晩年」を出した翌年のことで、彼の実兄の代理人(中畑さんといふ人)から送る金で都合つけてゐたが、とてもそれでは凌げない。下宿へも平野屋へも次第に借金が殖えて行つた。中略 かんかんに腹を立てた北さんが、こんな風に私に云つたことがある。 まあ、それはそれでもいいとして、厚紙の将棋盤をチャブ台にして、二人の賓客が酒をのんでる。何たることだね。これはどうしても、貴方にお頼みしたいのですがね。ときどき貴方が鎌滝に行つて、居候がゐたら追ひかへして下さい。金を送れば、無駄づかひする。送らなければ、悄気こんで死ぬと云つたりする。やつぱし、これはどうしても居候を追ひ返して頂くことですな。」 山岸外史が人間太宰治で、鎌滝時代として、この頃の太宰を書いている。 『・・・その婆まから「そう、いちいち、客膳などださなくっていいものだヨ。あんたはお人好しすぎるのですよ。経費がかさんでしかたがないじゃないか」などと小言などいわれたり・・・』 と伝える。新しい家に、鎌瀧と横に書かれた表札を眼にすると、太宰を思いやる女主人が浮かんでくる。山岸は晩年太宰と距離を置いくが、最も親しい仲間だけに、この時代の太宰の変化を見逃さなかった。 『太宰の当時のこんな変化をミゴトにみていた批評家に保田与重郎君がある。慧眼だったと思う。「今日、居所の変化とともに、その作風まで変化するような作家は稀有のことである。太宰がいかに平生、その人間生活のなかで、その限界までの純粋思考をもって生きているのかがこれでわかる」ように書いていたが、この絶讃どおりに、太宰はたえずぎりぎりの線までの人間生活をしていたのである。 として、「ここに、太宰としての時代的蘇生がでてくるのである」と変化を見ている。もう、 「満願」で、病気の夫との接触を三年も辛抱した若い奥さんが、今朝、それを医者から許されて、白いパラソルをくるくるっと回して、さっさと飛ぶように小径を走る情景を描くのは間もない。 6月25日、単身熱海温泉に行き1ヶ月程滞在、「二十世紀旗手」を書きあげた。同月、新鋭文学叢書の一巻として『虚構の彷徨』を新潮社より刊行した。 9月、「姥捨」を『新潮』、「満願」を『文筆』各九月号に発表した。 9月13日、杉並の鎌瀧方を引き払い、井伏鱒二が滞在している山梨県南都留郡河口村御坂峠の天下茶屋に移った。 本来ならば、このページはここまでで終わるのが普通であろうが、武蔵野を追う者としては、どうしても、次の三鷹時代へつなげておきたい。それで、ごく、かいつまんで、その後を付記する。 いつまでも立ち話が続く。 杉並を離れて 9月19日、井伏鱒二を通じて結婚の話のあった石原美知子(明治45年生、東京女高師文科卒、当時都留高女在職)と見合いをし、11月6日婚約した。この間、長篇「火の烏」の執筆に専念。 昭和13年9月13日、杉並の天沼・鎌瀧方を引き払い、御坂峠の天下茶屋に移った時の様子を津島美知子が次のように書く 『・・・それでこの茶店は「天下茶屋」とよばれていた。 この年は随筆の発表が多く、「『晩年』に就いて」「一日の労苦」「多頭蛇哲学」「答案落第」「緒方氏を殺した者」「一歩前進二歩退却」「富士に就いて」「校長三代」「九月十月十一月」などがある。 昭和14年(1939)31歳 1月8日、東京杉並区清水町の井伏家で、井伏の媒酌によって石原美知子と結婚式をあげ、甲府市御崎町56番地に新居を構えた。 2月、「I CAN SPEAK」を『若草』二月号、「富獄百景」を『文体』二、三月号に発表した。 4月、「女生徒」を『文学会』「懶惰の歌留多」を『文芸』、「葉桜と魔笛」を『若草』各4月号に発表。同月、「黄金風景」が国民新聞の短編コンクールに当選し、賞金50円を得た。上林暁の「寒鮒」も当選した。 5月、書下し創作集『愛と美について』を竹村書房より刊行。美知子を伴って上諏訪、蓼科に遊んだ。 6月、家探しに上京、またコンクールの賞金で美知子の家族と三保、修善寺、三島に遊んだ。 7月、『女生徒』を砂子屋書房より刊行した。 8月、「八十八夜」を『新潮』、「美少女」を『月刊文章』、「畜犬談」を『文学者』「ア、秋」を『若草』に発表した。 9月1日、三鷹市下連雀113番地に転居した。この後は、押しも押されもせぬ作家として三鷹時代に入る。 昭和11年から昭和13年までの2年間、太宰が実際に杉並に居住したのは、数えるほどの日数だろう。そして、この期間は総じて不振の時と言われる。ところが、実際は書いていた。 『昭和十二年、十三年は沈滞の年であるといわれる。事実、発表された作品は少ない。 杉並時代の後期は、前期とは違った波瀾万丈の中に、安定した三鷹時代を用意したようだ。 作品 《逆行》(1935年)、《晩年》(1936年)《HUMAN LOST》(1937)、《富嶽百景》《女生徒》(1939)、《走れメロス》(1940)《右大臣実朝》(1943)、《お伽草紙》(1945)、《津軽》(1944)、《冬の花火》(1946)、《ヴィヨンの妻》(1947)、《斜陽》(1947)、《人間失格》(1948)など。
(2000.07.01.記)
|