|
太宰治の杉並時代(1) 太宰治は上京して間もなく、杉並に住んだ。
三鷹市、太宰旧宅近くの玉川上水縁に設置されている。 (撮影 田村 茂 と記されている) 杉並在住 太宰の杉並在住は、その痛切さの割に、あまり紹介されない。作家としての地位が確立する前のためか、作品の数によるのか、さびしい限りで、もっともっと取り上げられるべきではないか。 それは、昭和の初めである。まだ、学生服と羽織・袴を使い分けて師匠に接し、仲間と無頼を続けた太宰。酔ってオマワリサンにいたずらをし向け、薬剤中毒に苦しみ、最初の奥さんとの別れに失意の日を過ごすなど、作品の背景となる生々しい生活があった。 パピナール中毒が原因して、千葉県に転地する事があったので、杉並の在住は途切れ、2度にわたった。それを前期と後期に分ける考え方がある。前期が、昭和8年から10年の3年間、後期が昭和11年から13年までの2年間である。場所は5度変わっている。しかも、その間に、旅をし、入院し、知り合いのところに泊まり込んでいるのだから、めまぐるしい。しかし、杉並時代は、生活の上でも、人との交わりの上でも、作品の上でも、作家としての出発の上でも、とてつもない大きな出来事があった時代ではなかったのか? 左、教会通り、右中央、若杉小学校・東京衛生病院入り口 なぜ杉並に来たのか 大正末期から昭和初期にかけて、中央線沿線には、文士・作家が集まった。その理由に、家賃の安いこと、気楽なこと、仲間が集まってムードが漂っていたことなどがあげられている。一見、太宰には遠いことのように見えるが、十分な仕送りを得ながらも、常に金欠状況だったことを知ると、意外に、家賃の原因があったのかも知れない。しかし、本質的には、人が引き寄せたことは確かだろう。 井伏鱒二も、山岸外史も言っている。青梅街道はまだ未舗装で、道幅も狭く、駅の周辺を除けば、荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺といずれも畑や林が多かった。店舗も少なく、のんびりした中に、細い路地に人情が行き交う風情があった。同時に、地代が1年間に倍になるというほど、郊外都市として急速な開発が進んでいた時代でもあった。 その商店街は、歩く身がぶつかるほどの空間であるが、今も懐かしい店舗が集まっている。 手焼き煎餅屋さんがあり、交差するみち角には、手作り豆腐のお店がある。 井伏鱒二への憧れ 『・・・私と太宰君との交際は、割合に古い。はじめ彼は、弘前在住のころ私に手紙をくれた。その手紙の内容は忘れたが、二度目の手紙には五圓の爲替を封入して、これを受取つてくれと云つてあつた。私の貧乏小説を見て、私の貧乏を察し、お小遣のつもりで送つたものと思はれた。 東京に出て來ると、また手紙をくれた。面曾してくれといふ意味のものであつた。私が返事を出しそびれてゐると、三度目か四度目の手紙で強硬なことを云つてよこした。曾つてくれなければ自殺してやるといふ文面で、私は威かしだけのことだらうと考へたが、萬一を警戒して直ぐに返事を出し、萬世橋の萬惣の筋向ふにある作品社で曾つた。 井伏との最初の面会は、昭和5年5月とされている。太宰は、昭和5年4月、東大仏文科に入学しているから、入学・上京してすぐ井伏に面会の申し入れをしたのだろう。 井伏への原稿ねだり 太宰が上京する以前から、井伏とは交流があった。「弘前在住のころの手紙」と「5円の為替」について書かれているが、ここに、太宰が井伏に心酔し、生涯にわたる深い関わりを持った鍵がありそうに思える。 原稿依頼のため、昭和3年に、太宰は「細胞文芸」の3号を持って、わざわざ、井伏に面会を求めたことがある。その時、井伏は会わなかったと言う。その後のやりとりが、恐らく、手紙でなされたのであろう。5円はその時の原稿料とされている。この頃から太宰が、いかに井伏を敬慕していたかがわかる。 太宰と井伏を結びつけたもの 山椒魚? 太宰も井伏も好きでたまらない私は、どうしてこんなに太宰が井伏を慕うのか、ある種のとまどいと疑問を持ち続けてきた。ところが、1994年、村上護の次の分析に接し、一挙にその疑問は解けた。 『太宰治が杉並区天沼に住むようになったのは、井伏の家が近かったからである。それは昭和八年からだが、その以前に太宰は井伏の周辺を長くうろついた。そのあたりのことから書いていかないと、井伏と太宰の奇妙な交遊は、なかなか理解しがたいように思う。
同人雑誌を発刊 明治42年(1909)青森県北津軽郡金木村大字金木に誕生 上京、井伏との面会、初代の上京、分家・除籍 郷里では大騒ぎになった。芸者との結婚もさりながら、人も知る政友会の有力県議(長兄・文二)の家族に、共産党支持者がいるとあっては、一大事に違いない。11月9日、上京した長兄・文二によって、太宰の分家(義絶)・除籍、学費、生活費の負担を前提に、初代との将来の結婚を承認することで決着した。これらを仮証文にまとめ、初代は帰郷した。 11月19日、太宰の分家・除籍の手続きがとられた。11月24日、長兄・文二は、太宰の名で小山家と結納を取り交わした。ところが、突如、太宰の自殺未遂が起きた。 自殺未遂 小動神社は鎌倉でも、西のはずれ、腰越にあり、素盞烏尊を祭神とする。本来は漁師の守り神であろう。
左手には、稲村ヶ崎へと、遙かに海岸が続く。 太宰杉並在住の頃の心象風景が偲ばれる。 唐突ともとれるこの出来事は、太宰自身に深い傷を残したが、同時に、太宰愛好者にも、研究者にも、様々に受け取られ、分析されている。非合法活動、初代との問題に対する長兄・文二の手回しに、太宰が反抗したものとの解説が多い。翌年正月、太宰と長兄・文二の間に取り交わされた「覚」の内容からも、それは伺える。 昭和6年(1931)23歳 1月27日、太宰と長兄は、原籍の移転、小山初代との結婚、今後の生活費や学費などについて詳細な「覚」を取り交わす。太宰は単身上京して、津島家の東京の番頭とも言える「北芳四郎」宅に身を寄せていた。「覚」は、長兄が一方的に示したものという。 その内容は、昭和8年の大学卒業までの間、月額120円づつ長兄が負担すること。ただし、帝国大学からの処罰、検事の起訴、浪費等の場合はこの額を減ずる。というものであった。その減額規定の中に、「社会主義運動に参加し或いは社会主義者又は社会主義運動へ金銭或いはその他の物質的援助を為したるとき」という1項目があり、津島家の考えが浮かび出ている。 非合法活動 初代は断髪し洋装になって、来る人たちの食事の世話をした。時には、仕事も手伝って、生き生きとしていたという。やがて、非合法運動に関わる津軽出身者が出入りした。郷土の言葉で話すことができ、懐かしい故郷の食事があることで「砂漠の中のオアシス」とされた。しかし、太宰は作品の中で、この時代を次のように書く。 「長兄は、H(初代)を芸妓の職から解放し、私の手許に送って寄こした。Hはのんきな顔をしてやって来た。五反田は、阿呆の時代である。私は完全に、無意思であった。・・・・ずるずるまた、れいの仕事の手伝いなどを、はじめていた。けれども、こんどは、なんの情熱も無かった。遊民の虚無(ニヒル)。それが、東京の一隅に、はじめて家を持った時の、私の姿だ」(太宰治 東京八景) 昭和7年(1932)24歳 3月、新宿区淀橋柏木町に移転。 9月、芝白金三光町の旧大鳥圭介邸の離れの1室を借りる。同郷の先輩・三兄圭治の学友である、東京日々新聞記者「飛島定城」一家が同居した。同居の経過については、飛島定城の奥さんの「多摩」さんが、次のように書いている。 『・・・春の頃太宰さんが、芝白金三光町によい家があるから一緒に住みませんかといって来ました。主人は五所川原の出で、太宰の兄さんの圭治さん(昭和五年に死去)とは親友であり、長兄の文治さんからも前に、修治をよろしく御願いします、といわれて居りましたので、一緒に住むことになり芝白金に引越しました。 この家で「思い出」の二章まで書いたという。その状況について野原一夫は「太宰治 生涯と文学」で次のように紹介する。 『・・・第二章まで書きあげた原稿を太宰は手紙を添えて井伏に送り、井伏は次のような読後感を太宰に書き送ってくれた。 いよいよ、杉並と井伏鱒二が表面に出てきた。杉並時代の始まりである。まず、住んだ家の辺りを訪ねてみよう。
太宰は、昭和8年(1933)2月、飛島定城家と共に、杉並区天沼3丁目741番地に転居した。 (2000.07.01.記)
|
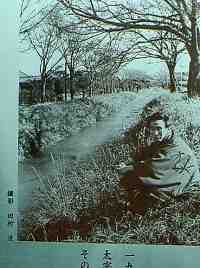

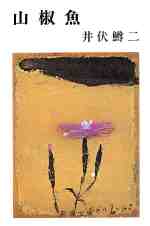 二人の機縁は、井伏が小説「山椒魚」を発表したときにはじまっているのである。「山椒魚は悲しんだ」ではじまるこの小説に太宰は感心した。あらすじを書くまでもないが、山淑魚が自分の棲家としている岩屋から出られなくなり、狼狽し、かつ悲しむ話である。これを井伏はユーモラスに描いている。しかし、作中で発せられる山椒魚の自嘲の声は、また井伏鱒二自身の声と重なり、みずから人間失格を宣言しているようにも受け取れる。
二人の機縁は、井伏が小説「山椒魚」を発表したときにはじまっているのである。「山椒魚は悲しんだ」ではじまるこの小説に太宰は感心した。あらすじを書くまでもないが、山淑魚が自分の棲家としている岩屋から出られなくなり、狼狽し、かつ悲しむ話である。これを井伏はユーモラスに描いている。しかし、作中で発せられる山椒魚の自嘲の声は、また井伏鱒二自身の声と重なり、みずから人間失格を宣言しているようにも受け取れる。