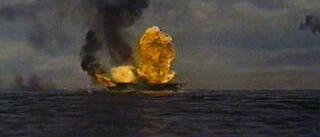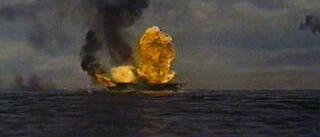ミッドウェイ ★☆☆
(Midway)
1976 US
監督:ジャック・スマイト
出演:チャールトン・ヘストン、ヘンリー・フォンダ、三船敏郎、グレン・フォード
<一口プロット解説>
史上最大の空母機動部隊同士の決戦であったミッドウェイ海戦を描く。
<入間洋のコメント>
かつて第二次世界大戦中、今後は海上戦闘においても航空兵力が勝敗の鍵を握るであろうと言われ、「ミッドウェイ」では三船敏郎が演じている山本五十六などもそのことは重々承知していたにもかかわらず、日本では昔ながらの大艦巨砲的な考え方から抜けられなかったと言われている。しかし歴史とは皮肉なもので、海における航空兵力を象徴する空母機動部隊同士の対決とは、世界史を見渡しても第二次世界大戦中の太平洋地域以外では発生していない。そもそも歴史的に空母機動部隊を編成するだけの空母を保有したことがある国は、アメリカと日本のみであり(イギリスも第二次世界大戦中何隻かの空母を保有していたが、大西洋はUボートを中心としたドイツの通商破壊戦との戦いが主であった為、空母機動部隊を編成する意味はほとんどなかった)、更に第二次世界大戦後になると空母はほとんどアメリカの専売特許になり、もう1つのスーパーパワーであったソビエトですら、建造するだけでなく維持するのにも莫大な費用のかかる空母は数隻保有するのがせいぜいであった。しかも、1990年以後の湾岸戦争やアフガニスタン攻略、対イラク戦を見ていると、そのアメリカですら空母は艦載機で地上施設を攻撃する為に使用するか、或いは海上から補給をサポートする為の洋上基地として使用しており、相手が存在しないという事情も勿論あろうが空母機動部隊の考え方からは遥かに遠ざかってしまったと言わざるを得ない。要するに、現時点から振り返って見ると空母機動部隊、場合によっては空母そのものの存在が20世紀中盤のしかも太平洋地域に限定された極めてローカルな存在であったことになる。そのように考えてみるとミッドウェイ沖海戦とは史上最大の洋上航空作戦であったのみならず、空母機動部隊同士の戦闘がどのような様相を呈しどのような特徴があるかということに関する貴重な実戦記録の提供源でもあることになる。「ミッドウェイ」という映画は、評価が高い映画だとはお世辞にも言えないが、そのような見方でこの作品を見ているとなかなか興味深いものがある。
それでは、何が興味深いかというと、空母機動部隊同士の戦闘とは細かなインテリジェンスとマネージメントが不可欠である上に、1つの偶然が良い方にも悪い方にも最大の効果を持ってはね返ってくる可能性があり、従って一種のギャンブルが大きな結果の違いをもたらす場合があるということが図らずも示されている点である。まずインテリジェンスについてだが、勿論他のどのような形態の戦闘であろうが当て嵌まることではあろうが、殊に空母機動部隊同士の戦闘においては相手の動きを的確に捉えることが極めて重要になる。何故ならば、後述するようにインテリジェンスで先手を取ることは、複雑な空母機動部隊の運用というマネージメント上の問題に関しても優位に立つことを意味するからである。そもそも、アメリカが日本の暗号を的確に解読していなければアメリカの3隻の空母はハワイの真珠湾に閉じ篭もったままだったはずであり、ミッドウェイ島周辺には位置していなかったはずである。真珠湾奇襲の時には、日本の動きを把握出来ずにアメリカ側が大損害を被ったが(ルーズベルト陰謀説はここでは問わないことにしよう)、それとは全く逆の結果になったのは、インテリジェンスの有無が勝敗を分けたことを如実に物語っている。いずれにしても、日本軍もアメリカ軍も索敵機を放射状に飛ばして極めてシステマティックに相手の艦隊を捜索するのは、インテリジェンスで優位に立ち、相手に第一撃を加えることはもとより、マネージメントの上でも優位に立つことが空母戦においては極めて重要であると考えられていたからである。
それでは次にそのマネージメントの重要性についてだが、「ミッドウェイ」ではそれが手に取るように分かる。ニミッツ提督(ヘンリー・フォンダ)が、病気で入院しているハルゼー提督(ロバート・ミッチャム)に、誰か替わりのものを推薦してくれと言った時、ハルゼーはスプルーアンス提督(グレン・フォード)を推薦するが、スプルーアンスは巡洋艦隊の指揮官であると言ってニミッツ提督は最初の内は渋る。何故ならば、ニミッツ提督は空母機動部隊の運用がいかに高度な戦術とマネージメントを必要とするかを知っていたからであり、スプルーアンスの空母戦の経験不足を心配したからである。それでは、空母機動部隊の運用がいかに高度で複雑であったかをこの映画に即して述べてみよう。まず、空母に搭載されている航空機の任務として索敵に加え対艦攻撃、対地攻撃、上空護衛があることが、この映画を見ていてもはっきりと分かる。更に対艦攻撃の場合には、雷撃隊、爆撃隊、護衛戦闘機隊から構成され、対地攻撃の場合には爆撃隊と護衛戦闘機隊から構成されることが分かる。また、対艦攻撃の場合には、魚雷や対艦用の爆弾を搭載しなければならないのに対し、対地攻撃には対地攻撃用の爆弾を搭載しなければならない。それに加えて、敵方の動きを見る為に主に非熟練のパイロットで構成される第1次攻撃隊をまず送った後、状況が明確になってから真打ちである熟練パイロットで構成される第2次攻撃隊を送ってとどめを刺すという戦術が取られる場合もある。事態をもっと複雑にするのは、空母の甲板は飛行場とは違い1隻に1つしかない為、1隻の空母に対して発艦と着艦を同時に行えないにも関わらず、何波かに分かれる索敵、対艦攻撃、対地攻撃、上空護衛部隊の発着艦をスケジューリングしなければならないことである。更に更に問題を複雑にするのが、索敵機から入る報告によって状況が逐一変化することであり、これら全ての事象をコントロールすることがいかに至難の技であったかは疑う余地もない。要するに空母機動部隊同士の戦闘とは、従来のパワーと数にあかせて撃って撃って撃ちまくる戦艦同士の戦いにはない高度なマネージメント能力が要求されたということである。複雑極まりないスケジューリングが何らかの状況で狂った時に危機管理がうまく機能していないと、「ミッドウェイ」での日本軍のように、上空には戦闘機の援護が何もない、4隻の空母全ての甲板上には爆弾を積んだ爆撃機が鈴なりになっているというような最悪の状況下で敵の攻撃を受ける結果となりダメージが必要以上に大きくなる。何やら空母機動部隊の運用とは会社組織の運営にも似ているのではないかということが、一介のエンジニアである自分にも理解出来る。
しかしながらポイントはまだ先にある。すなわち、このような高度で繊細なマネージメントを必要とするが故に、場合によっては1つの偶然、1つの不運が戦況を大きく左右する結果にも繋がるのである。たとえば、単純に10隻の戦艦部隊と20隻の戦艦部隊が戦闘を行った場合、1隻1隻の戦艦の能力は同一であると仮定すると、20隻の戦艦部隊を指揮する提督が余程無能でない限り恐らく勝敗の行方は戦闘が始まる前からほぼ見えているだろう。何故ならば戦闘の帰趨を制する要因がほとんど純粋な火力でしかないからであり、小さな運不運が局面で発生したとしてもそれが連鎖的に他の要因に影響を与えるトリガーとはなり難いからであり、大勢に影響を与える可能性が少ないからである。たとえば、本書でも紹介した「ビスマルク号を撃沈せよ!」(1960)でビスマルク号が発射した砲弾がイギリスの戦艦フッドの弾薬庫に運悪く命中してフッドが瞬きもしない内に海上から姿を消しても、いかにドイツが誇る不沈戦艦ビスマルクといえどもプリンツ・オイゲン号とただ2隻だけでは、一端発見されてしまえばイギリスの戦艦隊の圧倒的な数的優位の前では極めて不利なことに変りはない。これに対して、高度で繊細なマネージメントが必要な空母機動部隊同士の戦闘の場合、局面での運不運が別のマネージメント上の問題を生み出すことになり、局面であったはずの運不運が連鎖的に別の問題を発生させた結果、戦局を大きく変える要因になる可能性が十分にある。たとえば、「ミッドウェイ」では、重巡利根からの索敵機の発進が30分遅れたという不運に踊らされて、敵艦隊がなかなか発見されない為敵の空母部隊は近くに存在しないと判断し一度は既に装着してあった対艦用爆弾を対地用に切り替えるが、その遅れた索敵機から米空母艦隊発見の知らせが入ってきた時点で再び、対地用爆弾を対艦用に装着し直すという予期せぬ事態を招く。ところがそれが完了するのが、丁度ミッドウェイ島を攻撃した第1次攻撃隊が戻ってくる時分と重なり、先に第1次攻撃隊を着艦させてから、第2次攻撃隊を発艦させざるを得なくなる。従って、ここでもアメリカ軍に遅れを取ってしまう。更に源田参謀がそれはまずいなと呟くように、その時何のマネージメントの誤りからか上空には援護する戦闘機が1機もいないという状況になっている。そこへ、すなわち上空援護もなく爆弾を装着した爆撃機が4隻の空母全ての甲板に並んでいるところにアメリカの爆撃隊が来襲する。アメリカ側から見れば極めてラッキーだが、逆に言えばこれは日本側がたった1つの不運によってデリケートなマネージメント上の均衡を崩し、それによって発生した危機的状況に的確に対処出来なかったことをも意味する。
これに対して、アメリカ側はスプルーアンスの状況判断、というよりもギャンブルが極めて適切であったことが分かる。スプルーアンスのギャンブルとは、日本軍による爆撃を受けたという報告がミッドウェイ島からもたらされた時に、ミッドウェイ島を爆撃した爆撃隊が帰還する時の混乱したタイミングを見計ってすかさず反撃に移れば最大の戦果が挙げられることを計算し全兵力を挙げて攻撃に転じたことだが、実はこの時点でアメリカ側は日本側の空母は2隻しか把握出来ていなかった為、もし全兵力を投入して判明している2隻を攻撃している間に、他の2隻から攻撃を受けたならば、今度は自分達が丸裸の状態で攻撃を受けなければならない恐れがあったことになる。しかしこの判断が吉と出る。スプルーアンスのギャンブルとは穴馬狙いの無謀なギャンブルではなく、言ってみれば計算されたリスクであり、ミッドウェイ海戦時のアメリカのように数的に劣勢に立たされている側は、リスクはどこかで犯さなければならないのである。何故ならば双方同じ条件で全く同じことをしていれば、いかにマネージメントが重要であるといえども数的に優位に立っている方が、立場的にも優位に立てることは動かないからである。しかし、そのリスクは、無謀な賭けであっても良いというわけではなく、リスクがある程度計算されたすなわちマネージメントされたものでなければならない。ハルゼーがスプルーアンスを見込んだ理由とは、スプルーアンスが計算されたリスクを考慮出来る人物であるということを知っていたからではなかろうか。かくして、空母機動部隊同士の対戦においては、いかに高度なマネージメントが必要とされ、いかに素早く正確な情報を掴めるかというインテリジェンス面が重要となり、それにも関わらず、いやそれだからこそいかに1つの小さな幸運を大胆且つ有効に利用出来るかが極めて重要になる。すなわち、空母機動部隊同士の対決においては、情報化時代の現代の企業が抱えている問題と同種の問題が解決されなければならなかったということである。ラストシーンでニミッツ提督が、戦力は日本の方が圧倒的に優位でありしかも経験でも勝っていたはずなのに我々は何故勝てたのであろうかと問い、我々の方が幸運であったと自ら答えるが、インテリジェンスとマネージメントそして運がうまく噛み合ったのがアメリカ側であったのに対し、それら全てに関して齟齬をきたしたのが日本側であったということであり、その結果が余りにもストレートに出てしまったのがミッドウェイ沖海戦であったということである。ミッドウェイ沖に結集したパワーと数では圧倒的な優位を誇っていた日本は、それにもかかわらず空母機動部隊同士の対決の本質のところで敗れてしまったことになる。これを読んでいる読者の中には、ミッドウェイ海戦のことではなく我が社の近未来のことが言及されているのではないかと錯覚を起こした人もいるのではなかろうか。その我が社がミッドウェイ海戦時のアメリカ側になるのか日本側になるのかは、もはや歴史の中の単なる1イベントでもなければ映画という虚構の世界に属するフィクションなどでも全くなく、現実世界における死活問題であることは言わずもがなである。ひょっとすると似たような状況にある今日のIT戦争において生き残る為には、この映画が参考になるかもしれないと言えばさすがに言い過ぎであろうか。
※当レビューは、「ITエンジニアの目で見た映画文化史」として一旦書籍化された内容により再更新した為、他の多くのレビューとは異なり「だ、である」調で書かれています。