 ウィンダミア湖
ウィンダミア湖
物語の舞台を訪ねる旅
ノーベル賞受賞式に出席するためにスウェーデンに行った作家の大江健三郎さんが、『ニルスの不思議な旅』の作者セルマ・ラーゲルレーブの住んでいた家を訪ねたという記事を新聞で読んだ。子どもの頃「ニルスの不思議な旅」を愛読していた大江さんにとって、スウェーデンは憧れの地で、「四国の森の中で少年の僕が抱いた夢がかないました。家も風景も彼女が描いたままで、感無量です」と感想を述べている。
この記事を読んで我が意を得たりという思いだった。私も同じような経験をしているのだ。私の場合はスウェーデンではなくて、イギリス。アーサー・ランサムという作家が一九三〇年代に書いた「ツバメ号とアマゾン号」シリーズ(岩波書店刊)一二冊を小学生の頃に読んですっかり虜になった。
物語の舞台になるのはイギリスの湖水地方。夏休みにロンドンから四人の兄弟姉妹が湖水地方にやってきて、地元の女の子二人と知り合い、湖でヨットを走らせたり、無人島でキャンプをしたりする。盗まれた原稿を取り戻したり、鉱脈を発見したりと、必ず冒険話があって、わくわくしながら読んだ。そして、自分もヨットを操縦してみたい、島でキャンプをしてみたいと思ったものだった。
数年前の冬、ロンドンに赴任していた友人を訪ねてイギリスに旅行することになった。どこへ行こうかなと考えていたときに、「ツバメ号とアマゾン号」のことを久しぶりに思い出した。イギリスのどこかに舞台になった湖があるんじゃないだろうか。もう一度読み返してみると、訳者のあとがきに、湖水地方にあるウィンダミア湖がモデルと書かれている。
しかし、わかっているのはそれだけ、湖水地方はイングランドの最北部の避暑地で、イギリスでは有名な観光地でだが、日本人はほとんど行かないようだ。ガイドブックでは、ロンドンから鉄道で四時間くらいかかるというくらいの情報しかわからない。ただし、ウィンダミア湖を地図で見てみると、なるほど「ツバメ号とアマゾン号」の本に載っている(架空の)地図によく似ている。
 ウィンダミア湖
ウィンダミア湖
とりあえず行くだけ行ってみよう、現地に行けばいろいろわかるだろうということで、イギリスに出発した。イングランド北部への鉄道はロンドンのユーストン駅から出ているので、そこでウィンダミアまでの切符を買う。ウィンダミアへはオクセンホルムという駅から支線に乗り換えるが、そこへいく特急列車が発車する寸前だった。
「ツバメ号とアマゾン号」シリーズの一冊、『ツバメ号の伝書バト』には、名前は違うがオクセンホルム駅での乗換のときに伝書鳩を飛ばすところ、乗り換えてウィンダミア駅に近づくに連れて湖が視界に入ってくるところが描写されている。電車の窓からはおそらくそのままの光景が見えた。電車は半世紀前とは違うが、周りの風景はその頃とほとんど変わっていない感じがした。この辺りはナショナル・トラスト運動で当時のままの景観が保護されているのだ。石畳の道も、自動車がすれ違えない狭さ。しかし、地元の人は不便はある程度我慢しても、昔のままの景観を残す道を選んでいる。
ウィンダミアのベッド・アンド・ブレックファストに宿をとって、湖の近くまで行ってみた。物語に出てくる湖は、ウィンダミア湖と隣のコニストン湖のイメージを合わせて作られたと聞いたので、翌日は隣のコニストン湖にバスで向かう。こちらのほうが、家も少なくて、物語の印象そのままだった。郵便局と雑貨店を兼ねている店では、「ツバメ号とアマゾン号」シリーズの未完になった一三巻目や、ウィンダミア湖やコニストン湖のどこがモデルになって物語が書かれたかを検証した本を見つけて、早速購入した。短い旅行だったが、静かな湖畔の情景は心に焼きついている。
 コニストン湖
コニストン湖
子どもの頃読んで印象に残っている童話や物語は誰にもあるものだ。それが外国の話のとき、舞台になっている風景をどれだけ実感しながら読んでいるのだろう。私もアーサー・ランサムの書いた物語を、自分の知っている猪苗代湖や富士五湖の光景に重ね合わせながら読んでいた。
しかし、実際にイギリスの湖水地方に行ってみると、自分の思い描いていた光景とはかなり違うことに気がつく。石積みの壁と石葺きの屋根の家、牧草地を仕切る塀もすべて石積み。湖の色も湖岸の木々も日本とはかなり違う。現地へ行くことで物語をまた違った目で読むことができる。
これは面白いなと思った。その場所へ行くと、作家にちなんだ博物館があることも多いし、いろんな資料も手に入る。日本と違ってヨーロッパやアメリカでは昔のものがそのまま残っていることが多い。わざわざ訪ねてみて、ビルが建って開発が進んでいてがっかりということは少ないのだ。それ以来、少ない機会だが海外に旅行するときには、折を見て昔読んだ小説や物語の舞台になった場所を訪ねるようにしている。
A.A.ミルンが『クマのプーさん』のモデルにしたロンドン郊外のハートフィールド。ここには、物語に出てくる「プー棒投げ橋」がそっくりそのままあった。マーク・トゥエインの『トム・ソーヤーの冒険』の舞台になったミズーリ州のハンニバルには、彼らが隠れたミッシシッピ川の中州や探検した洞窟がそのまま残っていた。
これから、行ってみたいところは、エーリッヒ・ケストナーの『エーミールと探偵たち』の舞台になったベルリン。東西ドイツが統一されたので、エーミールが乗った市内を回る鉄道にもそのまま乗ることができるはずだ。マルタン・デュ・ガールの『チボー家の人々』のパリ郊外の別荘地メゾン・ラフィットへも足を運びたい。
こうした旅行は資料を探し始めるところからが楽しみが始まる。調べていくうちにいろんなことがわかってくる。博物館があったり、銅像があったり、地図を眺めているだけで想像がふくらむ。そして、現地を訪ねると、いろんな資料や本が手に入るし、思いがけず出会った人に作者や物語にまつわる話を聞くこともできる。
いろんな旅行の形があるだろうけど、私は、何かひとつテーマを持っていくことを奨めたい。前から気になっていた絵画を見る、豪快な自然を鑑賞する、珍しい動物を見てくる、そこでしか味わえない珍しい料理を食べる、いろんなテーマがその人なりにあるだろうけど、子どもの頃に読んだ物語の現地を訪ねるのもそのひとつだ。探してみるといろんなところがあるはずだ。(1995.9.18)(ダイヤモンド・エクゼクティブ掲載)
湖水地方については、「データベース不思議発見」の中に、「イギリス湖水地方に「カワイイ」の好きな日本人があふれている」、クマのプーさんについては、「クマのプーさんはカナダ出身という不思議な新聞記事」という記事があります。
ムーミンとトーベ・ヤンソンさんについて書いた「世界に37もあるムーミンのサーバーを見ながら、データベースの未来に思いを馳せる」、イギリスの作家のジェームズ・ヘリオット氏の逝去に寄せた「世界一有名な獣医にして作家、ジェームズ・ヘリオット氏が78歳で亡くなった」という記事もあわせてご覧ください。
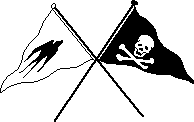
Illustration by Akila Yoneya
Original Illustration by Arthur Ransome
from Swallows and Amazons
インターネットをどんなふうに楽しんでいるか書いてくださいと原稿を依頼されて、はたと考え込んでしまった。ライターという仕事柄、楽しむのではなくて、原稿のためにいろいろ調べることのほうがずっと多いのだ。海外の個人の面白そうなホームページを探したり、企業のサイトの批評を書いたり、「宝くじ」とか「いるか」とかテーマを決めて関連するページを集めたり。さて、僕はどんなふうにインターネットを楽しんでいるんだろう。そうして思いをめぐらしてみたら、インターネットを始めた頃のことを思い出した。
へえー、こんなサイトがあったのかと驚きの連続だった日々。小さい頃から本を読むのが好きで、それこそ図書館の本を手当たり次第に読んでいた。今でも立派な活字中毒者だ。そんな僕にとってやはり一番面白いのは、作家や小説のサイト。ただ、データが詰まっているだけじゃなくて、インターネットは画像の情報がたくさんあるのがうれしい。
二年ほど前、インターネットを始めたばかりの頃は、どうもインターネットは面倒臭いものだと思っていた。人から面白そうだと聞いたURLを入れて、そこのサイトまで言ってみる。しかし、誰かがすごいぞと言っていたからといって人の好みは千差万別だから、僕にとって面白いとは限らない。
リンクをたどって関連のサイトも見てみるが、どうもそれほど興味をひかれるものはなかった。画像や音声が出てきて何か今までに見たことも聞いたこともないものというのはその通りなんだけど、だから何? という感じが強かったのだ。
しかし、Yahooという検索できるサーバーがあると聞いて、半信半疑で使ってみて、インターネットに関する印象は一八〇度変わった。Yahooには、世界中のいろんなサイトが登録されていて、キーワードで検索できるという。これは面白そうだと思い早速アクセスしてみた。
そして、最初に探してみたのが、アーサー・ランサムという作家のサイトだ。日本では超マイナーだから知っている人は少ないと思うが、イギリスではそこそこ有名な作家だ。『ツバメ号とアマゾン号』で始まる一二冊の子供向けの物語を書いているが、これがイングランド北部の湖水地方を舞台に、六人子供たちが小帆船に乗って冒険するという話で、小学生の頃胸躍らせて読みふけったものだった。
『ツバメ号とアマゾン号』に関する思いはずっと持続していて、六年ほど前、イギリスまで出かけて、物語の舞台になった湖に行ってきた。単行本のあとがきに書いてあった、ウィンダミア湖という名前だけを頼りに、ロンドンから列車で数時間のところまで足を伸ばしたのだ。
今でこそ、海外旅行の情報も豊富になって、普通の観光地以外の場所のこともよくわかるようになったが、その頃は日本で得られる情報は皆無に近かった。湖の名前は分かっているが、そこに何があるかは不明。でも、取りあえず行ってみたら、現地でアーサー・ランサムに関するガイドブックなんかも見つけることができたし、オーストラリアの大学の講師で、やはりアーサー・ランサムが好きでイギリスまで来たという女性にも知り合った。
つまり、マイナーなものに関する情報というのは、今の世の中では極めて少ないのだ。現地まで行けば何とか集めることもできるが、それも全体からすればほんの一部だ。湖水地方でも、アーサー・ランサムの書斎がそのまま保存されているという博物館は休館で見ることができなかったし、それ以外にも見逃した場所はたくさんある。日本に帰ってきて、集めてきた資料を読み返していたら、ここも行けばよかった、そこも行けばよかったという場所がたくさん出てきて悔しい思いをした。
さて、旅行の話が長くなってしまったが、Yahooでアーサー・ランサムを検索してみると、驚くことに、 ホームページがあった のだ。イギリスにはアーサー・ランサム学会というのがあって、そのことは僕も知っていたが、そのメンバーの一人でニュージーランドの大学にいる人がホームページを開いていた。僕が訪ねた湖水地方の写真もふんだんに使われわれているし、バイオグラフィー、著作リストなど、資料的にもそろっている。
へえー、インターネットにはこんな情報もあるのかと、それ以来味を占めて、いろんな作家や小説のサイトを探し始めた。二年前にはそれほどなかったが、月ごとにという感じでいろんなサイトが増えていく。もちろん消えていくサイトもある。最初に紹介した
アーサー・ランサムのページ
も今はもうない。ニュージーランドの大学にいたのは学生で卒業したから閉じてしまったのだろうか。真相はわからないが、インターネットはそういうものなのだと、いつかまた誰かが新しいページを始めるのを期待している。もちろん僕が始めてもいいのだが、英語の壁もあるし、まだまだ先のことになりそうだ。
( アーサー・ランサムのページ
は今は復活している。というか、URLが変わったので僕が見失っただけのようだ)
旅行が好きで、小説も好きなので、物語の舞台を訪ねる旅というのが好きだ。アーサー・ランサムでイギリスに行った以前にも、マーク・トゥエインの『トム・ソーヤーの冒険』の舞台になったアメリカのハンニバルというミシシッピ川のほとりの田舎町に行ったことがある。A.A.ミルンの『クマのプーさん』の舞台になった、ロンドン郊外のハートフィールドにも行って、絵本のイラストと同じ橋を見てきた。
インターネットで作家や小説のサイトを調べていて気がついたのだが、ホームページにはそうした旅行の参考になる情報が多いのだ。『ナルニア国物語』を書いたC.S.ルイスはオックスフォードの大学の先生だったが、C.S.ルイスのホームページにはオックスフォード市内の地図が載っていて、関連のある場所が細かく紹介されている。
僕が一度訪ねたことのあるA.A.ミルンのハートフィールドの地図もクマのプーさんのサイトにちゃんと載っていた。僕が行ったときには、手書きの変な地図一枚しかなくて、迷いながら、夕方暗くなる少し前にやっとたどりついたのに。地図を詳細に検討してみると、そのときには行かなかった面白そうな場所がたくさんあるようだ。
もちろん地図だけではない。どのページにも現地の写真がたっぷり載っている。行ってみたい小説の舞台はいくらでもある。海外だからとても全部は行けないだろうなと思っていたが、インターネットなら仮想体験ではあるけれど、世界中どこへでも行けてしまうのだ。
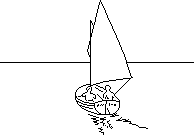 |
| Illustration by Akila Yoneya Original Illustration by Arthur Ransome from Swallows and Amazons |
小説の舞台へ行きたいと思うのは、日本で読みながら思い描いている光景と実際のがかけ離れているからだ。『ツバメ号とアマゾン号』で小帆船が湖を走る光景を読むとき、僕が思い浮かべているのは、自分の記憶にある例えば、福島県の猪苗代湖とか、静岡県の富士五湖なんかの風景だ。
実際にイギリスまで出かけてわかったのだが、向こうの湖と日本の湖は全く違う。文章で表現するのは難しいが、植物も人も建物も、色も形も全然違うのだ。その体験をして以来、印象に残っている物語の舞台には出来るだけ行ってみたいと心に決めている。
インターネットはその準備のための情報収集を助けてくれるし、現地に行ったような疑似体験もさせてくれる。でも、ホームページで見たからといっても満足できるわけではなくて、なおさら現地に行きたくなる。
この夏、アメリカ東海岸に仕事で行くので、ついでにボストン近郊やカナダに物語の舞台を訪ねてみようと思っている。今情報収集を心がけているところだが、インターネットのおかげで、今までにない充実した旅行ができそうだ。(1996.7.10 )(別冊スコラ81掲載)
岩波文庫1021「ドリトル先生アフリカゆき」(ヒュー・ロフティング作・井伏鱒二訳)は、全288ページのうち後半65ページがあとがきと解説に当てられている。小学生の頃、学校の図書館でドリトル先生シリーズを見つけて、12巻全巻をわくわくしながら、読んだ覚えがあるが、そのときには、こんなに長い解説は付いていなかった。
解説には、興味深いことが書かれていた。石井桃子さんの文章を引用しよう。
こうして、「ドリトル先生物語全集」十二巻が、日本で出版されてから、今日までに十六年がたちました。そして、アメリカで、最初の「ドリトル先生物語」が出てからでは、じつに六十年です。六十年というのは、長い年月です。そのあいだには、さまざまなことがおこり得、また、人間の考え方も大きく変わります。ことに、最近の六十年は、人間の歴史の上でも、大きな転換のときでした。
第二次世界大戦、ベトナム戦争も、そのあいだにおこりました。そして、それまで、ながく、いくつかの大国の、植民地とされていたところが、多くの独立国として歩きはじめました。これは、当然、それまで差別されていたひとたちの人権の問題にもつながってきます。つまり、人びとは、世界を、人間を、それ以前とはちがった見方で見はじめ、考えはじめたということです。
このようなことは、子どもの本の評価にも関係してこないわけにはゆきません。「ドリトル先生物語」の場合にも、このなかにあらわれた、黒人にたいするロフティングの取り扱い方が大きな論議のまとになりました。ことに、黒人問題を大きな苦しみとしてアメリカでは、「ドリトル先生物語」は、公共図書館の公開の書棚にだしておくところは、ほとんどなくなったようです。これらの本の版元であるリッピンコット社が、いまも出版しつづけている本は、『ドリトル先生アフリカゆき』と『ドリトル先生航海記』の二冊だということです。
確かに、今日の目から見ると、誠実で、民族をこえて人間というものに愛情を抱いていたと思われるロフティングの作品のなかに、人種差別の気持ちがなかったとはいえない箇所にぶつかると、私たちはびっくりさせられます。しかし、一方、私たちはまたロフティングが生まれ、育った時代を考えてみる必要があるようです。彼が生まれた十九世紀の終わりごろといえば、イギリスは、世界のすみずみにまで植民地をもち、大英帝国の威容を誇っていたのでした。ロフティングも、いま生まれれば、心から人種差別に反対しただろうと、私には思えてなりませんが、一八八六年にイギリスに生まれた彼は、やはり、その時代の子であることをまぬがれなかったのです。
この文章を読んだのは、確か昨年、96年のことだったが、ちょっと驚いた。ドリトル先生にはそんな経緯があったのだ。ニューヨークへ行く機会があったが、書店でロフティングの本を探してみたが、見つからなかった。カナダのトロント公立図書館で調べたところ、そこには、「ドリトル先生物語全集」12巻が全部そろっていた。
石井桃子さんの文章によれば、
「アメリカのリッピンコット社では、一時、ロフティングの最後の婦人の妹さんが編集した「ドリトル先生物語選集」といえるものを出しました。しかし、この本はもとの本のもつ力をもたなかったのでしょうか、まもなく絶版になりました」
本を調べてみたが、そうした修正のあとは見えない、日本で読むドリトル全集と同じものという感じだった。
それ以来、アメリカではドリトル先生はどうなっているんだろうと思っていた。Yahoo!など、インターネットの検索サーバーで調べても、ヒュー・ロフティングやドリトル先生に関するサイトは、レックス・ハリスンが主演した映画『ドリトル先生不思議な旅』以外のものは見あたらない。
日本では、岩波書店が単行本と文庫でドリトル先生シリーズを出し続けて、今でも、本好きの子供たちには人気があると思うが、アメリカでは、本も出ていないし、ドリトル先生はほとんどの子供が知らない存在なのだろうか。
ドリトル先生に関する疑問は、この10月カナダに行ったときに少し解決した。バンクーバーの書店で、ドリトル先生シリーズの最初の2巻のペーパーバック版を見つけて、早速購入したのだ。
2冊のドリトル先生シリーズ、Bantam Doubleday Dell Booksの「The Story of
Doctor Dolittle」と「The Voyages of Doctor Dolittle」(日本訳ではそれぞれ「ドリトル先生アフリカゆき」と「ドリトル先生航海記」)を読むと、息子のクリストファー・ロフティングのあとがきが添えられていて、不適当とされる部分は書き換えて出版したと断わっている。
「The Story of Doctor Dolittle」で主に問題になると思われるのは、11章の「黒い王子」と12章の「薬と魔術」の部分だ。この物語で、ドリトル先生はアフリカに行くのだが、帰る途中にジョリギンギという国で捕まって牢屋に入れられてしまう。そして、脱出するために、黒人の王子のバンポに「顔を白くしてやる」かわりに、逃がしてくれともちかけるのだ。
バンポ王子は、『眠り姫』というおとぎ話を読んで、お姫様に憧れて自分も白い顔になりたいと願っている。結局、ドリトル先生は、薬品を調合してバンポ王子の顔を白くして、王子に用意してもらった船で脱出する。
今回カナダで買ってきた「The Story of Doctor Dolittle」では、その部分がすっかり抜け落ちて、バンポ王子に催眠術をかけて脱出したというふうに書き換えられていた。
こうした問題は、「ちびくろサンボ」「トム・ソーヤーの冒険」などいろいろとあるが、ここでは深くは取り上げない。ただし、そのことが影響して、12巻のドリトル先生物語の大半が、アメリカでは絶版で手に入らない状態にあるのは残念なことだ。
ドリトル先生物語の英語のペーパーバックを手に入れて、日本語訳と比べながら読んでいるのだが、いろいろな発見があって面白い。
たとえば、ドリトル先生の友人で、ネコ肉屋のマシュー・マグというのが出てくる。ネコ肉屋は英語では、cat's
meat man。小学生の頃読んでいたときには、ネコ肉屋っていったい何だろうと不思議に思っていたのだが、研究社のCD-ROM英和辞典「リーダーズ+プラス」で調べると、ちゃんと載っていた。
cat's meat n. 猫の餌肉(串に刺した馬肉・くず肉; cf. →dog's meat),下等肉.
a cat's-meat man 猫の餌肉売り(cat's meat をはしょって "Smeat" と大声で売り歩く)
ネコ肉屋なんて、ロフティングが作った職業かと思ったが、実際にある職業なのだ。
こうして、原文と比較しながら読んでいるうちに、いろんなことがわかってきた。「ドリトル先生アフリカゆき」の冒頭はこうなっている。
むかし、むかし、そのむかし−−私たちのおじいさんが、まだ子どもだったころのこと−−ひとりのお医者さんが住んでおりました。
「ドリトル先生アフリカゆき」が出版されたのは1920年。子どもの視点で書いているとして、おじいさんが、まだ子どもだったころというのは、60年くらい前、1860年くらいの話ということだろうか。
小学生の頃、最初に読んだときは、どの時代かはあまり考えなかったのだが、本当はいつ頃の話なのだろう。ドリトル先生は、いつも燕尾服にシルクハット(正しい言い方かどうかわかりませんが)という今なら、古めかしい正装をしているが、当時の人はみんなそうだったんだろうか。
改めて読み直してみると、いろんな疑問が湧いてくるが、逆にわかってくることもいろいろある。物語の年代については、「ドリトル先生航海記」の中に、こんな記述があった。
パドルビーのちっぽけな家に行ってごらんになると、古めかしいとびらの上の壁に、石がはめこんであって、こんな字がかいてあります。
「著名ナル博物学者ジョン・ドリトル博士、紀元一八三九年、当家ニテ笛ヲ奏セラル。」
これは、ドリトル先生シリーズの大半の語り手である助手のトミー・スタビンズの家にドリトル先生がやってきて、笛を吹いて楽しんだという話のあとに出てくる。ここで、ドリトル先生物語の年代がわかる。もう少し詳しく12巻を読んでいくと、それぞれの出来事の年代がわかるかもしれない。
ドリトル先生について、もうひとつの興味は、ドリトル先生の住んでいる「沼のほとりのパドルビー」はどこだろうということだ。
もちろんそういう地名はイギリスにはないが、ドリトル先生シリーズを調べていけば、ここがモデルになっているかもしれないという町はわかるかもしれない。
(ここで、ようやく話が「物語の舞台を訪ねて」に近づきます)
そのころ、パドルビーは、ものしずかな小さい町でした。町のまんなかを、ひとすじの川が流れておりました。その川には、王者橋という、たいへん古めかしい石橋がかかっていて、橋のたもとに市場がありました。橋をわたった川むこうは、墓地になっておりました。
たくさんの帆かけ船が、海からその川をさかのぼってきて、この橋のそばに、錨をおろしました。
ロフティングは、イギリスのメイドンヘッドという町で生まれている。ここは、ロンドンの西、あまり遠くないところにあって、テムズ川に面しているから、「たくさんの帆かけ船が、海からその川をさかのぼってきて、」というのに、あっているかもしれない。
機会があれば、メイドンヘッドに行って、どんな町か確かめてみたいと思っている。
ロフティングに関してわかる情報は少ない。自伝や伝記も出版されていないようだ。「ドリトル先生アフリカゆき」の解説を読むと、ロフティングという人は、かなり変化に富んだ人生を送っている。
小さい頃から、将来は土木工学を専攻して海外の建設事業に従事しようと決めていた。16歳でアメリカに渡って、マサチューセッツ工科大学に入学。しかし、MITは卒業せず、ロンドンの工科大学を卒業。その後、カナダやアフリカやキューバーで鉄道建設に従事する。
おそらくアフリカでの鉄道建設が、ドリトル先生の中にも生かされているのだろうけど、ロフティングはアフリカのどこの鉄道を敷いたのだろう。
1912年に、アメリカで結婚するが、落ち着く暇もなく第一次世界大戦が始まり、アイルランド軍の将校として出征する(ロフティングはメイドンヘッドの生まれだが、イングランドの血とアイルランドの血が半分くらい混じっていた。こういう場合は、アイルランド軍で出征することもあるのだろうか。いきなり将校というのは、その前に軍隊生活の経験があったのだろうか。このへんはよくわからない)。
このとき、戦地からエリザベスとコリンという2人の子どもに書き送った絵物語が、ドリトル先生の原型になっているそうだ。
ロフティングは戦後、アメリカで作家生活を送るが、家庭的には不幸せで、夫人を2度も病気で失い、3度目の結婚の後、アメリカ東部からカリフォルニアに移るが、そこで健康を害して執筆もとだえがちになってしまう。そして、『ドリトル先生と秘密の湖』(12巻の中でいちばん好きだった作品だが、詳しくはまた書くことにする)を書き上げてまもなく、1947年9月20日に、サンタ・モニカで亡くなっている。
1947年に亡くなったということは、今年で没後50年、著作権が切れることになる。先日、Yahoo!で検索したら、グーテンベルク・プロジェクトが早速ロフティングの作品の電子化を始めていた。まず、「The
Story of Doctor Dolittle」がアップロードされていた。もちろん、修正されていないロフティング書いた元の原稿のままだ。これが手に入ってたのはうれしい。さらに、今後、12冊全部が電子化されれば、こんなにうれしいことはない。
ドリトル先生の原書2冊を手に入れて、知りたいこと、調べたいこと、行ってみたいところがたくさん出てきた。ドリトル先生やロフティングに関するサイトは世界的にもあまりないようだから、これから、少しこだわっていろいろ調べてみたいと思っている。
(1997.11.16)
*ドリトル先生シリーズが好きな方、ヒュー・ロフティングに興味のある方、suzuki.yasuyuki@nifty.ne.jp まで、メールをお寄せください。
*MSNニュース&ジャーナルに、「期待はずれの映画『ドクター・ドリトル』が示すもの」という記事を書きました。