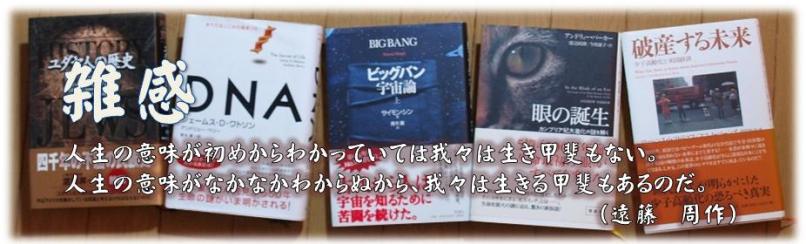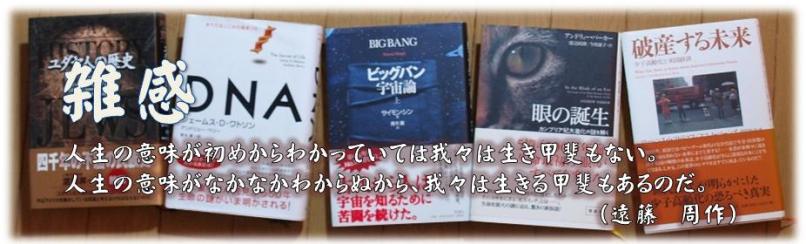|
ベンツと言えば高級乗用車の代名詞みたいな存在である。だからクルマ好きにとっては一度はハンドルを握ってみたくなるものだ。その高級車のベンツ、しかもその中でも高価なSクラスの販売台数で中国が世界第二位となったそうだ。
近年の中国の経済発展には目を見張るばかりである。人口13億人は世界の全人口の20%以上であるが、この人達がいま物凄い勢いで「アメリカンドリーム」を追求しているのだ。
現在の経済成長率は8%を優に上回っているから5年で1.5倍、10年で2倍以上の経済規模になるということだ。果たしてこのようなことが続けてゆけるのだろうか.。
レスター・ブラウン 米地球政策研究所理事長が新聞に寄稿していたが、「2004年、アメリカの一人当たり食肉の消費量は125キログラムだった。中国がこの水準に達すれば、年間消費量は現在の6400万トンから1億8100万トンに増加する。これは、目下の世界食肉生産量2億3900万トンの、ほぼ5分の4に相当する。もし、中国が、今のアメリカ並みの割合で石油を使えば、日量9900万バレルの石油が必要になる。目下、世界の石油生産量は日量7900万バレルであり、ハッキリ言ってこれは不可能な数字である。石炭も同様である。・・・・中国による化石燃料の使用から生じる炭素排出量だけでも、現在の世界の排出量と並ぶだろう。手に負えないほど急速な気候変動が発生し、食料の安全保障を脅かし、沿岸部の都市を水浸しにするかもしれない。・・・・・・」
人口が増加し、経済規模が拡大しているのは何も中国だけではない。インドやブラジル等もしかりである。果たして人類はどうなるのだろうか。「現状維持」という選択肢も命脈がつきて来ているのである。我々は周りをみて暮らすのではなく、もっと規模の大きな鳥瞰図的な視点でものを見、考えてゆかなければならないのではと思うのである。現代科学の知見からして今後は予測可能なのである。今まさにそれに適応した道を歩み始めなければならないと思うのです。石油、穀物、原材料、そして水資源の枯渇、次の世代までに解決しておかなければならない問題は累積しています。今は「靖国」問題での日中対立なんか論じているときではないのです。
安田喜憲さんは「地球文明の寿命」という書物のあとがきで、「松井さんと私の見解の相違は、ストック依存型の物欲文明に目覚めた人間は、もはや後戻りできず、破滅への道を歩むしかないという松井さんに対して、私は現在の地球を支配しているストック依存型の文明も、人類文明史における一断面にすぎず、フロー依存型文明に美しい世界があったように、人間は新たな文明世界を構築できるのではないかと主張したところにある。もちろんその前には大きな激動を人類は体験しなければならないが、その先には美しい新たな世界を人類は構築することができるのではないかというのが、私の考えである。その考えに確信を抱いたのもインドであった。ベナレスの袋小路の小さな一室に、死を待つ老人とそれを見守る家族が、静かに過ごしている。何千、何万もの人々が このベナレスにやってくる。死は恐れの対象ではなく、シヴァ神の祝福からの人生でもっとも大切な贈り物なのである。遺体はガートで火葬されたあと、ガンジス河に流される。しかし、薪の値段が高くて遺体を十分に焼くだけの薪が買えないため、遺体のいくつかは半焼けのままガンジス河に流される。その半焼けの遺体がプカプカ浮くその中で、人々は沐浴し、その水を口にする。それは、われわれにはおぞましい恐怖の光景にさえ見える。しかし、その中に入るとなぜか魂が癒され、死への恐怖が消えるのを感じるのは私だけではあるまい。そこに満あふれているのは優しさであり、祈りであり、魂の救済と開放であった。」と書いているが、物質文明的な生活様式を離れ、精神的な世界に生きるという人間の生き方以外に破滅から逃れる道はないのだろう。
遠藤周作が書いた「深い河」にも同じような光景の叙述がありましたが、現代の物質文明とは異質の価値観でしか、我々が救われる道はないのかも知れません。メソポタミアに始まった文明は地球システムの中に人間圏といわれるものを作り、発展してきました。それが行き詰まってきているのです。今、我々は立ち止まり、来し方を振り返り、現状を認識し、未来を展望しなければと思うのです。その余裕は余りにも少なく、早急に決心しなければならないのではないでしょうか。
|