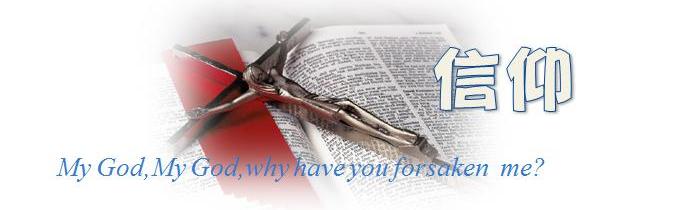 |
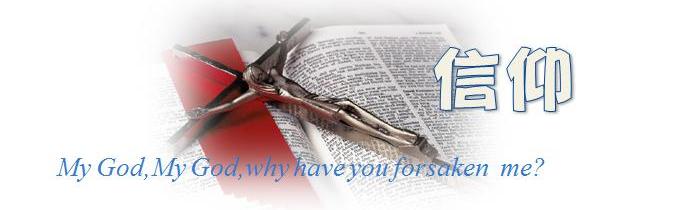 |
| |
|
「それから彼らはカペナウムにきた。そして家におられるとき、イエスは弟子たちに尋ねられた。『あなたがたは途中で何を論じていたのか』。彼らは黙っていた。それは途中で、だれが一ばん偉いかと、互いに論じ合っていたからである。そこで、イエスはすわって十二弟子を呼び、そして言われた、『だれでも一ばん先になろうと思うならば、一ばんあとになり、みんなに仕える者とならねばならない』。そして、ひとりの幼な子をとりあげて、彼らのまん中に立たせ、それを抱いて言われた。 『だれでも、このような幼な子のひとりを、わたしの名のゆえに受けいれる者は、わたしを受けいれるのである。 わたしを受けいれる者は、わたしを受けいれるのではなく、わたしをおつかわしになったかたを受けいれるのである』。」 (「マルコによる福音書」9;33〜37) |
今朝の礼拝で牧師先生がこの箇所をテキストにして、神の前において一番すぐれているとされる者について語られました。「偉い」というと「社長」とか「首相」とかを連想する人が多いのでしょうが、「偉い」という意味は「尊敬に値する」ということです。「社長」とか「首相」がイコール尊敬に値するかと言うと必ずしもそうではないかも知れません。日本で「偉人」というと「お札の顔」を連想してしまいます。なにをもって尊敬するのか、高い地位についた人なのか、人類に貢献するような業績を上げた人なのか、私たちはすぐそう考えてしまいます。イエスが語った「偉い者」はそうではありませんでした。幼な子は母親など自分以外の者の気持ちを察することは出来ません。要求ばかりするばかりのが幼な子ではないでしょうか。そんな幼な子を受けいれるということは、見返りを全く求めない、一方的に与えるだけの姿勢、そんな態度ではないでしょうか。幼子に注ぐような愛情を皆のために捧げる、そうすれば自ずと受けることになるのが尊敬です。賞賛を受けようと思えば、先ず己を貧しくすることではないでしょうか。 |
一番になろうとか、二番になろうとかそんなことは意味がない。常に懸命に皆に仕え、自分の境遇を神から与えられた恵みと感じて正しく受け止める。そこにこそ自分という存在の意味が見出せるのではと思えてなりません。 |