中学における黙読指導
・「音読」と「黙読」
「音読」は「黙読」する上で欠かせない要素である。中学等の初期英語学習に
はとても大切なことでその指導も様々な方法でなされている。中学校では当然「音読指導」が中心になされなければならない。下記の理由参照
| subvacalization | 「文字」→「単語」→「語群」→「文」として読む場合、まず視覚像が聴覚像 を呼び起こし、次に聴覚像が調音像を呼び起こして筋肉に命令を与え、舌・唇な どの発声器官を動かして音声に変える。この作用と同時に脳の中で調音像が「概 念」を呼び起こしている。読む作業は音読・ 黙読を問わず聴覚像や調音像を離れては為し得ない。つまり、黙読であっても 「意識化に音を出している」のであると考えられる。 |
|
黙読と音読の速度
〜初期学習者〜 *上段が音読 *下段が黙読 |
1学年
45 45 |
2学年
80 78 |
3学年
110 125 |
4学年
135 156 |
5学年
150 180 |
6学年
170 210 |
(Boston University Education Clinic)〜米国小学生の難易度普通教材の.wpm
〜
上記の結果で2学年位まではなんと「音読」の方がNativeであっても速いので
ある。
次に一般のNative SpeakerのReading Speed(silent reading)を見てみよう。
| Scale of Speeds in Words per Minute |
|
170-199 [Very slow]
200-229 [Slow] 230-249 [Average] 250-299 [Above average] 300-349 [Medium fast] 350-449 [Fast] 450-549 [Very fast] 550-650 [Exceptionally fast] |
(Read better,Read faster;1965)資料が古いためその信頼性にかけるかもしれ
ない。
実際は更に速くなっていると考えられる。
因みに中学3年生の検定教科書の場合一概には言えないが(県内7教科書使用
)、だいたい
1ページあたり70〜100語で(未習語各ページ7〜10含む)ある。教科
書1ページを少なくともnew words提示含めて15分以上は授業では一般に使用
する。中学教科書の約3倍近くをNativeは1分で読み、かつその内容を理解してい
る。
次に日本の生徒・学生を見てみよう。
| 中学生 | 高校生 | 大学生 | |
| 音読 | 80 | 100 | 120 |
| 黙読 | 100 | 150 | 200 |
(目標とされる.wpm)表は小川先生(1963)の研究
音読速度の実際:
普通大学生で、85wpm(words per minute)である。高校1年生でも57wpmと
いう結果である。
では中学生はどうかと言えば個人差があるが、50wpmを下回る可能性は大で
ある。
実際中学でも授業で「Repetition(Recitation), Chorus reading, Group(Pair)
reading, Individual reading, Presentation(Demonstaration)」の順でこれ
以上は時間の関係で出来ないことが多いだろう。黙読指導の時間的ゆとりがない
と思われる。
しかし、「速読即解」の能力開発には多少なりとも黙読指導をしていく必要は
ある。
Outputの前に情報発信者の情報を素速くキャッチする力が今後必要とされるだ
ろう。
よって中学英語科における速読即解能力は今後ますます必要となってくると思
われる。
参考にTOEFULの結果における日本人を見てみよう。
(TOEFL結果参照)
この表では更に下に続けてヨーロッパ諸国を記述するまでもなく、「下から数
えて7番目」の成績である。しかし、ごらんの通りこの試験自体を受験する受験
者の総数において日本は圧倒的にNo.1なのである。であるから、「受験の門戸が
大きく開かれている日本」はその平均において下がってしまうのはやむを得ない
ことなのかもしれない。
「読解テスト」も各国に遅れをとっているのは一目瞭然である。
テスティングにおいてはどうしても「読解」の問題が出題されるわけであるか
ら、その能力の開発には力を注がざるを得ないだろう。「主題」を的確につかみsummarizing
できるような方法を児童・生徒に与えることが必要である。
「速読」を通して英文の要旨を捉えるコツ
を児童・生徒に身につけさせるために:
上記小川(1963)/高梨・高橋(1987) の研究に基づき、速読(黙読)の目標を中学で100wpm以上において学習させていきたいと思う。
このソフトは上記の理論に基づき中学生からの速読を学習するもので、主に初
めてのSilent-readingにおける教材である。
20〜30秒(教材難易度で担当教師側で熟考)で50words前後(2年次検定
教科書の約1ページ内)の読みを実現させるための教材である。
30秒すると画面が切り替わり、次のページを表示、「予測」、「主題把握」
、「内容に関する質問」とつながる。
START!
時間で下記のように絵が変化する。
 →
→
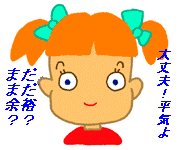
→

「要点のとらえ方」
「Reading for enjoyment」,「Reading for information」とそのどちらの場
合においても一字一句正確に読んでいるのではなく、自分に必要な箇所を拾い読
みしたり全体を流し読みしながら書かれている内容のあらましを捉えていること
が多い。
そのためには「Pre-reading」「While-reading」「Post-reading」が必要であ
る。
ここでは「Pre-reading」として「予備知識」(挿し絵や概略を通して主題を
予想させる)、「While-reading」として「スキミング・スキャニング」「パラ
グラフリーディング」、「Post-reading」として「テスティング・Summarizing
」を活用する。
"The main ways of reading are as follows:
-skimming:quickly rnning one's eyes over a text to get the gist of it.
-scanning:quickly going through a text to find a particular piece of information.
-Extensive reading:reading longer texts, usually for one's own pleasure.
This is a fluency activity, mainly involving global understanding.
-Intensive reading:reading shorter texts, to extract specific information.
This is more an accuracy activity involving reading for detail.”
尚教材はきわめて簡単な未習の英文とし、内容的には生徒が興味関心を示す現実世界に直結するようなものとする。
"One of the most important points to keep in mind when teachin reading comprehension
is that there is not one type of reading but several accoding to one's reasons for reading.
Students will never read efficiently unless they can adapt ther reading speed and technique to their aim when reading.
By reading all texts in the same way, students would waste time and fail
to remember points of importance to them because they would absorb too
much non-essential information. The exercises....should therefore make
the students more confident and efficient readers."
by Gret"Developing Reading Skills"
Skimming指導法:
「斜め読み」「飛ばし読み」である。その意義は「概要を掴む」ことにある。
・題名と挿し絵等からまず全体の主題を想定
・配置された絵や図表など視覚的要素によって主題の展開方法を予測
・内容について問題意識をもち、読む目的を認識しながら目を走らせる
・イタッリク、ゴシック体の文字は要点に関連するものとして注意
・5W1Hの表す焦点をもとめる
・読みに入ったら各パラグラフの最初の文と最後の文を先に読み、意味を正し
くつかむ
・手がかりになるような抽象的語句や表現、反復語句を記憶しておく
・重要語は概してContent wordが多いので、名詞、形容詞、動詞、副詞に重点
を置き、中 心思想や主題が集約されている語を探す
・速く目を走らせるために"Meaning Chunk, Thought Unit"を単位として捉え、ほぼ中 央の語に視点を置く
・"Heading"があればそれらを集約して主題に収束
・重要語だけを拾い、後戻りしないようにする
「速読」以前に平常授業でやっておくべき基礎的事項:
・主要部、補部に分ける
・名詞句を探す
・"Predicate"の基本的語用をおさえておく
・副詞節を探す
・"Key word"だけのパラグラフを提示し削除された機能語などを推測し、完全な文への変 換や全体の意味の推測を行う
・音読練習の際にまとまった意味をもつ語群だけを反復し、リズム感をあてな
がら音声と意 味が小さなまとまりから大きな単位に拡大していくようにする
・制限時間内で競争意識をもたせる
Scanning指導法:
スキミングが全体の概念を捉えるのに対し、スキャニングは特定の情報・概念 を求める手法である。マルチメディアな時代のニーズに合った読み方で、「学習 者が自分にとって必要な情報とそうでない情報を判別し価値判断を加えて取捨選 択」するのである。
・読む前に求めている事項を確認し記憶しておく
・求める事項のおおよその位置を予想しておく
・手がかりになる設問を用意しておきそれらに答えられるようにする
・求める情報を見つけたら、その箇所は十分に時間をかける
・作業中は常に目的意識をもたせる
・求める事項に関連する上位語や抽象的表現に特に注意する
・求める事項以外の語句はできるけ速く通り過ぎる
・横へ斜めへ視点を動かすのも良い
Summarizing指導法:
読みとった内容を整理し、まとめる。物語文では、場面・人物・出来事の3要素
を基軸にそれぞれ時間経過に合わせて簡潔にまとめる。5W1Hに焦点を当てれ
ば良い。
論説文では、主題及びそれに関わる思想・概念の展開論理の骨組みを再構成出
来ることが基本である。そのためパラグラフごとの中心思想を全体の構成と合わ
せて主題を発見することが重要である。単なる感想文ではなく、構成、書き手の
意図を十分考慮した分析と統合の作業で、論理的思考能力を伴ったものでなけれ
ばならない。
・原文の3分の1程度の文でまとめる
・反復している語句、表現を整理する(Redundancyのcut)
・各パラグラフのトピックを見つける
・主題や中心思想を集約した重要語を整理活用
・真理・本質を凝縮した比喩を活用
・要約文の音読、リズムをつくる
・他
Paragraph reading指導法:
読むこと本来の活動は、小さな文単位の解読ではなく大きなパラグラフや文章
というまとまりのある文集団を読解することで、そこには思想や内容がある。
・パラグラフは一般に"Topic sentence"が含まれる
・パラグラフの展開に注意する:演繹型、帰納型で文の最初か最後、中間にTopic
sen-
tenceがくる場合が多い。欠く文も存在するが中学生の読解英文としては良い
文とは言えまい。
・パラグラフ内の文は一定の論理に従って統一性と密接な"Cohesion" をもって
配列される。
・主題の展開順序:
①時間的順序
②空間的順序
③重要度の順序
・パラグラフの構成論理:
①事実反復
②定義
③分析・分類
④比較・対照
⑤因果関係・理由
・パラグラフリーディングの作業手順:
①各パラグラフが何について書かれているか「主題の発見」
②主題が述べようとしている思想、内容を見つける
③中心概念が含まれる文を見つける
④中心概念の支持文を整理する
⑤各パラグラフの内容を文章全体にまとめ、主題に集約する
具体例:
(1)上位語・下位語、または一般的事項・特定事項の区別
trains, cars, airplanes, wagons, they are vehicles
(2)主題の発見
The human body is wonder. The head contains the brain, eyes, ears, nose, and mouth. The
torso holds the lungs and let us digest food. The arms allow us to work
with tools. The hands hold these tools .....
(3)パラグラフの統一性を乱す文の発見
That afternoon the world seemed at peace. I had a headache. The sky was blue, the air clear. Hawks turned in lazy circles overhead......
(4)中心概念と中心概念を含むトピックセンテンスを見つける
(5)トピックセンテンスを生徒自身で構成させる
Thousands of soldiers are killed. Whole cities are destroyed. Many innocent
people suffer. Then wounded come home. They begin a new and uncertain life.
"Key word"を並べる:
the killing of soldiers, destroyed cities, suffering people, the wouded.
uncertain life.→→"War is very harmful"
(6)文脈を乱したパラグラフを正しく並べ替える
[1] In Canada , for example, a lot of trees are dying because of acid rain.
[2] Canada and some countries in northern Europe have the same problems.
[3] Acid rain is becoming a big problem all over the world today.
Answer:[3][2][1]
(7)パラグラフに小見出しをつける
(8)段落の無い文章を中心概念を見つけることによって、いくつかのパラグ
ラフに分割
その他
「速読即解」関連事項:
Eye span
P.A.Kolers(1973)の読み違いの分析結果:
1)読者は文字という視覚刺激をそのままの形で短期記憶装置に格納するので
はなく、文法や意味的まとまりにおいて記憶する。
2)文字の列を何らかの単位に区切って読むという作業を伴う時その単位は通
例文字や語ではなくそれより大きな意味単位の句や節であろうと考えられる。
平成3〜5年度のオーラルコミュニケーション能力の育成に関する調査:
「談話能力の習得状況」が低い
「異なる文化で育った人々に対して公の場で自分の意見を述べる時には、誰も が理解しやすいレトリックを用いるべきである。」「そのレトリック構成する主要素がスピーチやディベ ート指導にある。」〜国立教育研究所広報:渡邊先生(1995,於東松山総合会館講 演)〜
"Rhetorical communication"
"Remember that the paragraph should contain one central idea only, that
it should have unity, coherence, continuity, and adequate development...."
「パラグラフ展開の大原則」