|
|
工藤孝浩先生の”城ケ島ノート”にも、嬉しい記事が掲載されました。
以下、全文転載をいたします。
| "城ケ島ノート”NO.19 [ 十六万坪のエドハゼに 思う ] 工藤孝浩 :'62年横浜生まれ、東京水産大学卒業。 現在は東京湾湾口から相模湾を一望できる神奈川県城ヶ島の 「神奈川県水産総合研究所』で魚類生態学.人為的環境改変と生物の対応を研究 既報のとおり、6月10日に『東京湾・ハゼサミット』が開催され、私が基調講演を行 なった。今だから話すが、当初私は講演依頼をお断り申し上げていた。 表向きにはある理由を述べていたが、本心では十六万坪の埋立問題を避けて通れ ないであろうことにプレッシャTを感じ、直前まで近年経験がないほど気が乗らな かった。 |
 |
| 地方公務員である私の立場は微妙である。よその自治体が抱えるややこしい問題など、ほっかぶりすればそれ ですむ。そんな火中の栗をあえて拾う行為は、公務員の世界では出世や給与に響きかねない。 しかも、東京都職員をはじめ当該事業関係者には少なからず知人がおり、私個人が負うリスクよりも、そうし た方々に迷惑が及ばぬかが心配だったのである。 思い悩む私に対し、ハゼサミットに集結する多くの市民団体からのラブコールは熱烈だった。 「基調講演を務められるのはあなただけだ」との多くの声に背中を押され、腹をくくった。そして私の気持ち を決定的に吹っ切ってくれたのが、当日会場に持ち込まれた十六万坪産のエドハゼだった。 「工藤さん、これエドハゼじゃありませんか?」いまひとつ確信が持てないといった口ぶりの東大海洋研究所 向井博士が指さす水槽の中に、まさにエドハゼが泳いでいた。私がエドハゼで.あると断言すると、採集者の 安田船長が大きくガッツポーズを作った。この優美なハゼの泳ぎを見るのは初めてで・私は木棺にしばし釘付け になった。 東京湾西岸のエドハゼの分布は、多摩川以北にかぎられている。これまで20年間近く、神奈川の海で魚採りに 精を出してきたが、この魚を手にしたのは多摩川河口の川崎側で2回だけ。本当に江戸前にしかいないのだ。 初めてのエドハゼは、ここで調査を重ねればまたお目に掛かれるだろうと、すぐに標本にしてしまった。 ところが、多摩川にもそう多くは生息していないらしく、再会の機会はなかなか訪れなかった。 2回目は研究室内で標本を同定・測定しているとき、多くのハゼ類の中から体がよじれ、槌色した哀れな姿に 体面した。情けないかな、採集時には存在に気づかなかった。最初のエドハゼを生きているうちにじっくりと 観察しておくべきだった。 ご承知のように、魚は生きている時と死後とでは体色が変化する。特にエドハゼを含むウキゴリ属では、標本 になって体の透明感が失われると全く別の魚のような印象すら受ける。今は質が高い魚類図鑑が出版され、誰も が生きたエドハゼの写真を見ることができるが、それらはすべて水槽内で撮影されたものだ。 フィールドでの映像記録はもちろん、観察例すらも皆無であろうと思われる。そんな謎多き魚が東京のど真ん 中、十六万坪にいるのだ。登壇直前に対面したエドハゼに、自分は公務員である以前に研究者であることを再 確認させられた。 とはいえ、同じ役人の心情として、都には現在の市民との対立の図式を乗り越え、この事業を軟着陸させてく れることを切に望んでいる。8月2日に仕立船による都主催のハゼ釣り大会が開催されるが、十六万坪は釣り場で はないと聞く。これではいろいろと勘繰られても仕方あるまい。釣り場に十六万坪を加える英断をすれば、 批判が多い当該事業の環境アセスメント調査よりも信用され、誰もが納得する科学的データを収集することだっ てできる。そうなれば、市民との歩み寄りの第一歩になるし、私も都のお手伝いに喜んで参上したい。 |
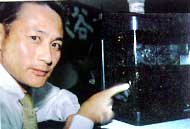 |
 執念でエドハゼを採取した安田さん 執念でエドハゼを採取した安田さんは、生きた証拠を水槽に入れて会場 に持ち込んだ |
 |
|
|
 |