 |
情報、其之参拾壱 2001.1/27 [ 欧米が選んだ「自然再生」という治水対策 ] 雑誌”つり人” 2001年3月号より |
|
「21世紀の公共事業のあり方を求めて」より つり人3月号より全文転載 浦 壮一郎 写真・文 |
 |
 |
欧米での治水対策は「自然再生」が主流になりつつある。コンクリートで河川を固める従来の近代工法では、結局のところ洪水を防止することはできず、実は自然再生こそが最も効率的な治水対策になると欧米は気づいたのである。「公共事業のあり方を求めて」から、ダムや護岸工事に代わる新たな治水対策について考えてみたい。 |
|
|
|
元WWFドイツ、オーストリア所属、中央・東ヨーロッパ環境管理コンサルタントの力一ル・アレクサンダー・ジンクさん「湿地など氾濫原を再生することによって、洪水の危険1性を軽減することが可能」と語り、自然再生こそ効率のよい治水対策であると解説
|
 |
オランダの政府高官であり、交通・公共事業・水管理省代表のスタン・力一クホフスさん.オランダのハーリングフリート河口堰は「2005年にゲートを開放することになった」と発表、河口周辺の環境に致命的なダメージを与える河口堰もすでに、建設する時代でないことはもとより、既存の堰はゲートを開放するのが当然の処置であることを強調
|
 |
ロッテルダム・エラスムス大学研究員のカースチンーシュイットさんは、自然が持つ機能の経済的価値と開発にかかる費用との関係、いりゆる「生態系費用対効果の分析」について報告。オランダのライン川周辺を例にすれば、自然の損失額は「50年間で実に286億ドルにも上る」と言う。逆にし、えば、自然が仮に正常な形で機能していたら、人々は286億ドルもの利益を得ていたことになる |
 |
リビングリバーズ代表・オーエン・ラマーズさん。ダムの寿命、それに伴う危険性について触れ、「寿命を迎えたダムに対して改修を加えるよりも、撤去したほうがコストが安い」と語るとともに、世界の潮流を例に「ダムの撤去はすでに当たり前のこと」と結んだ |
|
 |
[自然再生という公共事業の可能性] |
|
 |
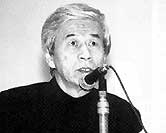 |
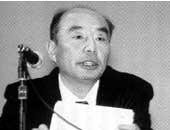 |
 |
|
鳩山由紀夫 民主党代表
|
筑紫哲也さん
|
五十嵐敬喜 法政大教授
|
天野礼子さん
|
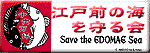 |
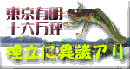 |
