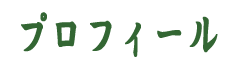
山口ゆうこと仲間たち
<自己紹介>
消費者団体、建築事務所に勤めた後、イギリスの大学院に留学。市民参加型の都市計画を学び、帰国後、1997年に「浜松地域活動ネットワークセンター」を設立。2000年にNPO法人化し、市民活動支援、自主事業、行政との協働事業、浜松市議会委員など幅広く活動しています。
N-Pocket設立の経緯
私が代表を務める「浜松NPOネットワークセンター」(以下、通称の「N-Pocket」と表記)は、浜松市とその周辺地域のNPOや市民活動を支援する「中間組織」ですが、地域のニーズを捉えた自主事業も数多く手がけている点に特色があります。 設立のきっかけは、1997年に浜松市で「情報公開条例」が成立したこと。当時、建築士としてイギリスで市民参加型の都市計画を学んできたばかりだった私は、この話を聞いてチャンスだと思い、「条例を市民参加の道具にする」ために、「情報公開条例を市民の手に」というフォーラムを開催。予想を越えた反響があり、環境問題や子育てなど、さまざまな市民グループから約80人が参加しました。 その後、この市民グループのネットワークを母体に、多くの賛同を得て「浜松地域活動ネットワークセンター」を開設。勤め先の建築事務所をやめ、代表となりました。1998年、「浜松NPOネットワークセンター」と改称。2000年にNPO法人となりました。2007年代表を交代しました。
N-Pocketの活動
N-Pocketの理念は、子ども、障害者、高齢者、在住外国人といった人びとの自立を支え、彼らの問題解決を市民と共に図り、市民参加による公共政策の新しいプロセスを開発することです。そのための方法として、行政からの委託事業に自主事業を加えることで、委託事業を自分たちの目標に引き寄せ、住民や専門家・行政職員を巻き込んでいきます。 その1例が「安間川水辺再生まちづくり事業」です。2001年度に、静岡県の「1級河川 安間川河川整備構想策定事業」を受託し、環境改善の調整役・推進役として住民による「コンセンサス会議」などを開催。同時に、自主事業として180リットル雨水枡を各戸に設置しようという「ためタル君プロジェクト」をスタート。雨水を地下水に戻して洪水を防ぐという住民が担う治水事業です。さらにサービス・ラーニング事業(小さな市民を育てるアメリカ型総合学習)も組み合わせ、安間川の水害問題や歴史を学ぶ出前講座を小学校で実施。学校と協働で5年生の1年間にわたる総合学習が実現しました。 この他にも、障害者支援、在住外国人に対する医療支援・教育支援など多くの活動があります。特に、在住外国人に対する教育支援では、若者を中心とするコミュニティ・アートを用いたイベントを開催。言葉の壁を越えて誰もが楽しみながら問題点を理解できるこの方法は、今後さまざまな事業に活かしたいといいます。この活動から第二世代の若者リーダーが育ちました。
紆余曲折の始まり
私は高知県出身。東京の女子大学で英語を学びましたが、当時は女性の職業といえば公務員か教師ぐらい。「何かやってやろう」と思っていたので、定時制の都立高校で教員をしながら、社会思想を学ぶため大学に学士入学しました。 ところが、大学紛争で授業が中断。同じ頃、医学部の学生と結婚し、2人の子どもを産みましたが、長男が内臓疾患の手術をすることになり、仕事も大学も断念することになりました。 しかし、私は諦めませんでした。子どもの病気をきっかけに環境問題の講座に通ううちに法律に興味を持ち、再度法学部に学士入学。卒業後、消費者団体に嘱託職員として就職。ところが、夫が浜松の医科大学に派遣されることが決定。2年勤めたところで浜松に引っ越すことになりました。 浜松に行ったら消費者問題に関する仕事を探そうと考えていると、ちょうど国民生活センターで消費生活問題に関するキャリア支援講座があるといいます。都の職員限定の講座でしたが、頼み込んで受験させてもらい、合格。子ども2人を育てながら、電車で1時間以上の通学は大変でしたが、「こんな大変な思いをしているのだから学んだことを自分のものにしなければ」と、毎回必ず1つは質問しました。 終了後、センターへの就職を誘われましたが、断らざるを得ません。そこへ静岡県の消費生活センターが産休要員を探しているという情報が入り、転居した翌日から、そこで嘱託職員として働くことになりました。 浜松で建築士として働く 県の消費生活センターには2年勤めました。当時急増していた欠陥住宅の問題に取り組み、そのひどさを見るうちに、日本の住宅が健全になるためには建築の分野で活躍する人が必要だと思い、建築士になろうと決意。 すでに30代。年下の若者に混じって授業を受け、勉強しました。修了後、都市計画の代表的な建築事務所の門を叩き、一度は断られたのを「事務員でもいいから」と頼み込んで入所。 やがて、都市計画の能力が認められ、主任研究員に昇格。取締役も務めるほどになりました。そんなある日、1冊の本を読んで私は「あっ」と驚きました。本の名前は、ニック・ウェイツ&チャールズ・ネヴィット著『コミュニティ・アーキテクチュア:居住環境の静かな革命』(塩崎賢明訳・都市文化社)。自分が模索してきた住民参加型の都市計画が、イギリスではすでに建築家の手で実際におこなわれ、政策的な裏づけもあるというのです。私は、イギリス留学を決意しました。
イギリスでNPOを学び、帰国
事務所は嘱託職員にしてもらい、2度の英語の試験(=IESLS、大学院進学に必要)を経て、93年からイギリスの大学院に進学。「Yukoはまるでビジネスマンのようだ」と言われるほど、都市計画に関わるさまざまな分野の市民活動を、精力的に訪ね歩きました。 イギリスのように市民の持っている情報やデータがきちんと都市計画に反映される仕組みを日本に作りたい。3年後、こうした目標を胸に、学位はとらずに、留学に区切りをつけました。 帰国後は留学の成果を仕事に活かすよう期待されましたが、既存の仕組みでは住民をエンパワーする都市計画は実現できないと思い、所長の理解を得て、16年勤めた事務所を退職。現在のNPO活動に転身しました。 私のキャリア形成のコツは、5年ほどのスパンで目標を立て、その間はその目標に集中すること。目標をクリアすると、必ず次の方向が見えてきます。物事を柔軟に捉えつつ、ここぞというときは集中する、そんな私です。