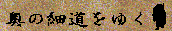
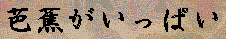
-
3ページ目、最後のページです。
 羽黒山(はぐろさん) 山形県羽黒町
羽黒山(はぐろさん) 山形県羽黒町
出羽三山のひとつ、羽黒山へ何年ぶりかで訪れると・・、あら!いらっしゃったのね、芭蕉さん。以前、冬に来たときは深い雪の中で気が付きませんでした。
山頂の神社までクルマ若しくはバスで行くこともできますが、ここは是非、杉並木の参道を歩いていってみましょう。石段の数は2446段、ふつうに歩いて約1時間かかります。修験の山なのですから、そのぐらいの苦労をしなければご利益もないと思いますよ。 (97/9)
 酒田・日和山公園(さかた・ひよりやまこうえん) 山形県酒田市
酒田・日和山公園(さかた・ひよりやまこうえん) 山形県酒田市
最上川河口に位置する酒田。かつては庄内米を積み込んだ千石船が行き交う、日本海側随一の港町であり商業都市でした。芭蕉は酒田に9泊もしていますが、上方の町人文化が流入し栄えたこの地に水が合ったのでしょう。
芭蕉以後も、隆盛を極めたこの町には数多くの文人が訪れ、港を見下ろす日和山公園にはいくつもの句碑、歌碑、文学碑が建立されています。(97/4)
 象潟・蚶満寺(きさかた・かんまんじ)秋田県象潟町
象潟・蚶満寺(きさかた・かんまんじ)秋田県象潟町
象潟は奥の細道最北の地。芭蕉はより北へとの思いもあったようですが、ここでUターンして以後は日本海沿いに南下するコースをとります。
私は、芭蕉の描写する情景のなかでも、象潟の件りが一番のお気に入り。実際象潟にも幾度か足を運んでいますが、その度に「来るべきところまで来たなあ」としみじみ思ってしまいます。
写真はここを訪れること5度目にして、やっと撮した芭蕉像。(97/4)
 出雲崎(いずもざき) 新潟県出雲崎町
出雲崎(いずもざき) 新潟県出雲崎町
芭蕉が越後路を歩いたのは、陽暦で8月中旬から下旬にかけて。「暑湿の労に、神(しん)をなやまし病おこりて、事をしるさず」と、よほど疲れていたようです。
さて、出雲崎にはスーパースター「良寛(りょうかん)さん」がいらっしゃいます。良寛さんは芭蕉よりも百年あまり後の人で、ここ出雲崎のお生まれ。禅僧で歌人で書家で、手まり遊びが好きな方だったそうですが、私はよくは存じません。
良寛さんの像は、丘の上の日本海が見渡せる、眺めの良い公園に建ってらっしゃいましたが、我らが芭蕉の像(写真)は、街道沿いの崖下の小さな公園に。やはり良寛優勢か!(96/3)
 さて、出雲崎には芭蕉さんの像がもう一基あります。風情ある昔ながらの北国街道をぶらぶら歩いて20分ほど、町並みの西のはずれから海岸側に出ると「越後出雲崎天領の里」という立派なハコモノ見学(見物?)施設が。江戸時代には日本最大級の金銀山のあった佐渡との中継地であるここ出雲崎は施政上からも重要な地で、幕府の直轄地でした。左の芭蕉さんの像はそんなハコモノ施設の脇の公園で、ひとり海を見つめています。右側にスペースがありますから、隣に座って芭蕉さんとのツーショット写真を撮るなんてのもステキかも?('11/04)
さて、出雲崎には芭蕉さんの像がもう一基あります。風情ある昔ながらの北国街道をぶらぶら歩いて20分ほど、町並みの西のはずれから海岸側に出ると「越後出雲崎天領の里」という立派なハコモノ見学(見物?)施設が。江戸時代には日本最大級の金銀山のあった佐渡との中継地であるここ出雲崎は施政上からも重要な地で、幕府の直轄地でした。左の芭蕉さんの像はそんなハコモノ施設の脇の公園で、ひとり海を見つめています。右側にスペースがありますから、隣に座って芭蕉さんとのツーショット写真を撮るなんてのもステキかも?('11/04)
 山中温泉(やまなかおんせん) 石川県山中町
山中温泉(やまなかおんせん) 石川県山中町
この付近ではなかなか芭蕉の像を発見できなかったのですが、ありました。場所は山中温泉の大木戸跡。小さいですけれど(像高は40cm位でしょうか)まぎれもなく芭蕉さんの像であります。
江戸を発って4ヶ月。ずっと芭蕉のお供をし世話をし続けてきた曽良ですが、お腹の病におかされ、遠く伊勢の長島の医者にかかるために、やむなく芭蕉と別れることになりました。
「行くものの悲しみ、残るもののうらみ」、盛り上がりの少ない『奥の細道』後半部で、とりわけみせてくれるところです。(95/12)
 天龍寺(てんりゅうじ) 福井県松岡町
天龍寺(てんりゅうじ) 福井県松岡町
福井駅からヒナびた電車に乗って15分。「松岡」という小さな町で、久しぶりに芭蕉翁とお会いできました。『奥の細道』では「丸岡」と記していますがこれはおそらくは誤り。
ひざを置き、両手を差しだしているのは北枝(ほくし)。金沢在住の芭蕉の門人で、曽良にかわって芭蕉のお供をしてきたのですが、ついにここでお別れ。「余波」は「なごり」とよみます。
奥の細道の旅もいよいよ終局に近づきました。(95/12)
 敦賀・気比神宮(つるが・けひじんぐう) 福井県敦賀市
敦賀・気比神宮(つるが・けひじんぐう) 福井県敦賀市
この写真を見て「おやっ」と思ったあなたはスルドイ。すでに、この影姿を何百も見ています。
気比神宮の芭蕉さんは、赤ずくめで、お顔もなかなかの男前。杖のしなり具合もいいですね。顔をやや上に向けて何かを見つめているようです。
それと関係あるかどうか、彼は、ここ敦賀で仲秋の名月を期待していました。しかし、前日の八月十四日は晴れわたった夜空にくっきりと月が見えたものの、当日十五日は雨。
「名月や北国日和(ほっこくびより)定めなし」は、そんな変わりやすい北陸の空模様を詠んだ句です。(95/11)
 大垣(おおがき) 岐阜県大垣市
大垣(おおがき) 岐阜県大垣市
ようやく「奥の細道」結びの地、大垣です。芭蕉は八月二十一日(陽暦10月4日)頃この地に着き、5ヶ月に及ぶ「奥の細道」の旅を終えました。
「奥の細道」結びの句は「蛤(はまぐり)のふたみに別れ行く秋ぞ」
芭蕉は大垣に約半月滞留した後、伊勢神宮に向けて再び旅立つことになりました。
写真は左が芭蕉で右は俳友の木因(ぼくいん)。2体の像は木因が芭蕉を見送る情景です。
で、どういう因縁か、300年後の現在、ビンボーな旅行者を満載した、東京発の夜行列車の終着駅はここ大垣。
芭蕉の旅は大垣からまだまだ続きます。そしてボクラの旅も。
 番外・伊賀上野(いがうえの) 三重県上野市
番外・伊賀上野(いがうえの) 三重県上野市
芭蕉の故郷は、三重県の山中に開けた盆地、伊賀上野。近鉄のなんとかという駅から、ローカルな単線電車に乗り換えて12,3分。
「伊賀」いえば忍者の里。生涯多くの旅を繰り返した芭蕉も、実は「忍者」だったと論を張る方がいらっしゃいますが、あまり根拠のある説とはうかがえません。
 芭蕉の像は「上野市」駅前に。さすがは生まれ故郷とだけあって、ひときわ高いところにそびえ立っていらっしゃいます。
芭蕉の像は「上野市」駅前に。さすがは生まれ故郷とだけあって、ひときわ高いところにそびえ立っていらっしゃいます。
左の写真の建物は「俳聖殿」。ヘンな格好ですが、芭蕉の旅姿をモチーフにしているそうです。(95/5)
ここまでご覧いただきありがとうございした。
お時間とご興味がおありでしたら「奥の細道」紀行もどうぞ。


目次へ戻る
前の頁へ


お帰りはこちら
メールはこちらへ
ご意見、ご感想、ご苦情、情報等は、メールにてどうぞ。
ホームページへ |「奥の細道」目次へ | メールはこちら
![]()
 羽黒山(はぐろさん) 山形県羽黒町
羽黒山(はぐろさん) 山形県羽黒町 酒田・日和山公園(さかた・ひよりやまこうえん) 山形県酒田市
酒田・日和山公園(さかた・ひよりやまこうえん) 山形県酒田市 象潟・蚶満寺(きさかた・かんまんじ)秋田県象潟町
象潟・蚶満寺(きさかた・かんまんじ)秋田県象潟町 出雲崎(いずもざき) 新潟県出雲崎町
出雲崎(いずもざき) 新潟県出雲崎町 さて、出雲崎には芭蕉さんの像がもう一基あります。風情ある昔ながらの北国街道をぶらぶら歩いて20分ほど、町並みの西のはずれから海岸側に出ると「越後出雲崎天領の里」という立派なハコモノ見学(見物?)施設が。江戸時代には日本最大級の金銀山のあった佐渡との中継地であるここ出雲崎は施政上からも重要な地で、幕府の直轄地でした。左の芭蕉さんの像はそんなハコモノ施設の脇の公園で、ひとり海を見つめています。右側にスペースがありますから、隣に座って芭蕉さんとのツーショット写真を撮るなんてのもステキかも?('11/04)
さて、出雲崎には芭蕉さんの像がもう一基あります。風情ある昔ながらの北国街道をぶらぶら歩いて20分ほど、町並みの西のはずれから海岸側に出ると「越後出雲崎天領の里」という立派なハコモノ見学(見物?)施設が。江戸時代には日本最大級の金銀山のあった佐渡との中継地であるここ出雲崎は施政上からも重要な地で、幕府の直轄地でした。左の芭蕉さんの像はそんなハコモノ施設の脇の公園で、ひとり海を見つめています。右側にスペースがありますから、隣に座って芭蕉さんとのツーショット写真を撮るなんてのもステキかも?('11/04)
 山中温泉(やまなかおんせん) 石川県山中町
山中温泉(やまなかおんせん) 石川県山中町 天龍寺(てんりゅうじ) 福井県松岡町
天龍寺(てんりゅうじ) 福井県松岡町 敦賀・気比神宮(つるが・けひじんぐう) 福井県敦賀市
敦賀・気比神宮(つるが・けひじんぐう) 福井県敦賀市 大垣(おおがき) 岐阜県大垣市
大垣(おおがき) 岐阜県大垣市 番外・伊賀上野(いがうえの) 三重県上野市
番外・伊賀上野(いがうえの) 三重県上野市 芭蕉の像は「上野市」駅前に。さすがは生まれ故郷とだけあって、ひときわ高いところにそびえ立っていらっしゃいます。
芭蕉の像は「上野市」駅前に。さすがは生まれ故郷とだけあって、ひときわ高いところにそびえ立っていらっしゃいます。
