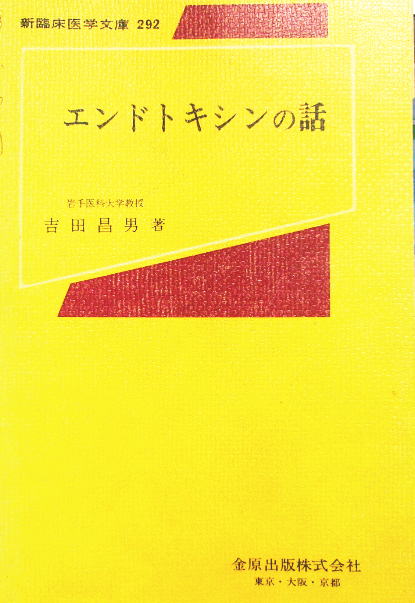 |
今回サイト名を「新エンドトキシンの話」と改題した。
恩師故吉田昌男先生は「エンドトキシンの話」(金原出版、東京、1981)を著して、当時の最新のエンドトキシン学を紹介した。先生はエンドトキシンによる骨髄反応を発見し、後に日本のエンドトキシン学の指導者の一人として活躍された。
我々は先生の教えを心の糧として、エンドトキシンの病態における役割について独自の世界を築いてきた。
”新”エンドトキシンの話を先生に捧げます。 |
エンドトキシン(内毒素、リポ多糖、LPS)はグラム陰性菌細胞壁成分であり、多彩な生物活性を持ち、敗血症性ショックにおいて最上流で作用する。
エンドトキシンの定量にはカブトガニの血球抽出液による凝固反応(リムルステスト)を用いる。サブピコグラムのエンドトキシンを定量出来る唯一の方法である。この方法は従来から敗血症の診断や、種々の病態におけるエンドトキシンの関与の研究、医薬品の製造過程におけるモニタリングに用いられてきた。
リムルステストはエンドトキシンとβグルカンの二つに反応する系があり、日本では1980年後半からエンドトキシンとグルカンの別々の定量法がそれぞれグラム陰性菌敗血症や深在性真菌症の診断法として保険適用され四半世紀が経過した。
しかし、日本以外ではもっぱら古典的(両方に反応する)リムルステストがエンドトキシンの測定法として用いられ、グラム陰性菌感染症以外でもエンドトキシンが検出されそれがエンドトキシン血症と捉えられ、結果的にエンドトキシンの病態における役割が過大評価されてきた。
2004年になってAssociates of Cape Cod(生化学工業の子会社)のグルカン特異的測定法(Fungitell) が深在性真菌症の診断法として欧米の薬局方で承認され、2012年にはエンドトキシン特異的定量法(Pyrostar
ES-F、和光純薬工業)が米国FDAの製造承認を得た。日本の方法がやっと世界標準になりつつあることを意味している。
このサイトでは、血液エンドトキンの定量法を紹介し、エンドトキシンに関する著者の考えを提示したい。
 |
エンドトキシン(LPS)の電子顕微鏡写真(陰性染色)
|
→故吉田昌男先生のホームページ
→著者プロフィール
●主な更新履歴
・1997年オープンし、2009年10月末いったん閉鎖した。アクセス数は35265だった。
・2010年2月20日 新たに『エンドトキシンの定量法;リムルステスト』を立ち上げる。アクセスカウンターをリセットする。
・2014年3月 内容を一新し、『新エンドトキシンの話』と改題した。
あなたは、 番目の訪問者です(2010年2月以降) 番目の訪問者です(2010年2月以降)
|