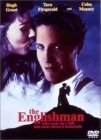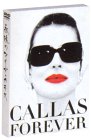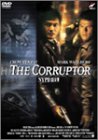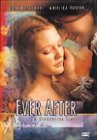| ウェディング・バンケット | ★★★★ | |||||
| 【1993年 : 台湾・アメリカ】 監督:アン・リー/音楽:メイダー 出演:ウィンストン・チャオ(ウェイトン)、 ミッチェル・リキテンシュタイン(サイモン)、 メイ・チン(ウェイウェイ)、 グア・アーレイ(母)、 ラン・シャン(父) 他 ※【現在VHS発売のみ】 |
||||||
|
台湾からアメリカに帰化した青年とアメリカ人青年のゲイカップル、そしてグリーンカードが欲しいためにその台湾人青年と偽装結婚することになった上海出身の娘が繰り広げる騒動をあたたかく描くコメディ。 ゲイのカップル二人と女が一人、という組み合わせの作品が多々ある中で、個人的には一番受け入れやすいというか、好きになれた映画です。中心にいるのはもちろんその三人なのですが、そこに主人公の両親が加わることによって、ほかの作品にはない深みや、家族をとりまく情愛が優しく漂っていたように思いました。 |
||||||
| ウェールズの山 | ★★★★ | |||||
| 【1995年 : イギリス】 監督:クリストファー・マンガー 音楽:スティーブン・エンデルマン 出演:ヒュー・グラント(レジナルド・アンソン)、 タラ・フィッツジェラルド(ベティ)、 イアン・マックニース(ジョージ・ガラード)、 コーム・ミーニー(モーガン)、 ケネス・グリフィス(ジョーンズ牧師) 他 |
||||||
|
第一次大戦後の英国ウェールズの小村を舞台に、ある丘を“山”として地図に載せるため奮闘する人々の姿を描いたコメディタッチのヒューマンストーリー。 |
||||||
| 海辺のレストラン/ガスパール&ロバンソン | ★★★★ | |||||
| 【1990年 : フランス】 監督:トニー・ガトリフ/音楽:ミシェル・ルグラン 出演:ジェラール・ダルモン(ガスパール)、 ヴァンサン・ランドン(ヴァンサン・ランドン) シュザンヌ・フロン(ジャンヌ)、 ベネディクト・ロワイアン(ローズ) 他 |
||||||
|
社会からはみ出してしまった不器用な人々が、ある家に寄り添う姿をあたたかく描いたハートフルドラマ。 |
||||||
| A.I | ★★★ | |||||
| 【2001年 : アメリカ】 監督:スティーヴン・スピルバーグ/音楽:ジョン・ウィリアムス 出演:ヘイリー・ジョエル・オズメント(デイヴィッド)、 ジュード・ロウ(ジョー) 他 |
||||||
|
愛という感情をインプットされた最初の少年型次世代ロボット・デイヴィッドの心の旅を描く作品。 |
||||||
| 永遠のマリア・カラス | ★★★☆ | |||||
| 【2002年 : 伊・仏・英・ルーマニア・スペイン】 監督:フランコ・ゼフィレッリ/音楽:アレッシオ・ヴラド 出演:ファニー・アルダン(マリア・カラス)、 ジェレミー・アイアンズ(ラリー・ケリー)、 ジョーン・プロウライト(サラ・ケリー)、 ジェイ・ローダン(マイケル)、 ガブリエル・マルコ(マルコ) 他 |
||||||
|
伝説の天才オペラ歌手、マリア・カラスの生誕80周年を記念して製作された音楽ヒューマン・ドラマ。 |
||||||
| X-メン | ★★★☆ | |||||
| 【2000年 : アメリカ】 監督:ブライアン・シンガー/音楽:マイケル・ケイメン 出演:ヒュー・ジャックマン(ローガン)、 アンナ・パキン(ローグ)、 パトリック・スチュアート(チャールズ・エグゼビア)、 イアン・マッケラン(マグニートー)、 ファムケ・ヤンセン(ジーン)、 ジェームズ・マースデン(サイクロップス)、 ハル・ベリー(ストーム) 他 |
||||||
|
社会から疎外されたミュータントたちの苦悩と闘いを描くSFアクション。 |
||||||