「こちらへくる前の話ですけど、公文式算数塾というところが似てるの
ではありません?易しい問題から入って次々解いていき、途中でつま
ずくと、また少し戻って理解して先へ進むと聞いたことがありますわ。
つまずいた所を繰り返し、出来てから前へ進むのでとっても良いと、そ
の奥さんはおっしゃっていましたわ」
と美絵夫人が日本で聞いた話を披露した。
「日本の授業のように画一的ではないんだね。個々人の能力に見合っ
た教育を受けるのが、子供にとって平等であり、幸せであると親も社会
も理解しているんだろうな。
二つの教科書があって、皆がそれぞれの能力に応じて自分なりに勉
強しているから、難しすぎていやとか、易しすぎて授業がつまんないと
馬鹿にするなどということはないだろう」
「こちらの親も子供たちも別に問題にしていないようですね。日本でし
たらPTAや教員組合が大変でしょうね。区別するのはいけないとか、
子供を叱咤激励するとか」
「それにグラマー・スクールに進学するためのイレブン・プラス(11歳
の全国テスト)を受ける子や私学受験の子が日本のように多くないか
ら、何となくのんびりしてるんだろう」
良いことかどうかわからないが、社会の階層化がはっきりしているか
ら、日本のような過熱した塾通いはない。子供たちの交友関係は穏や
かで、いじめがない。
「ダディ(お父さん)、ぼくはオレンジ・ブックでベスト・リーダーってほめ
られたよ」
ブルックランド・インファント・スクール(幼児学校)に通っている次郎君
は、イエロー・ブックを終え、次のオレンジ・ブックに進んでいた。
先生の前で一人ずつ声を出して読むのだそうだ。
「上手く読めたね」
と、異国から来た子を褒めてくださるやさしい先生に、憶良夫妻は感謝
の言葉もない。
子供たちは、ブルックランド・スクール(小学校と付属幼児学校)がすっ
かり気に入ったようだ。
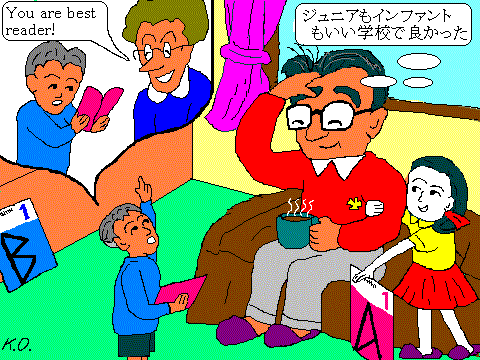
次頁へ