9
以前、鉄朗は恵里に、緑に会わせると約束した。その約束はまだ果たされていない。次第に焦れてきた恵里は、鉄朗に会わせるように迫った。鉄朗は緑にこの事を話しておらず、恵里に返事の仕様がない。
「ごめん。まだあいつの予定を訊いてないんだ。だから返事は明日でもいいかな」
「いいわよ。待ってるから」
恵里はそう言うと、自分の仕事に戻った。
鉄朗は、緑に予定がない事は知っていた。平日はバイトの後、夕食を作るので、毎日家にいる。休みの日も、鉄朗といる事がほとんどだ。鉄朗が用事でいない時は、家にいて掃除をしたり、ビデオを見たりして、あまり外には出ない。
問題は予定じゃなく、緑本人だった。
緑に、どうして会わなくてはいけないんだ、と言われると何て応えていいかわからない。まさか恵里が自分に気があり、興味本位で緑に会いたがっているなんて言えない。そんな事を言えば、緑が傷つくのはわかり切った事だ。絶対に緑を傷つけるような事はしたくなかった。
どうやって話を切り出そうか、鉄朗はそればかり考えていた。
家に帰って、緑の顔を見ても、なかなか言い出せず、時間だけが過ぎていった。最近トラブル続きで、これ以上の面倒は出来るだけ避けたかった。
しかし約束は約束である。律儀な鉄朗は、約束を破ろうとは考えなかった。
「なあ、緑…」
「ん、何?」
緑は眺めていた雑誌から目を離すと、まっすぐに鉄朗を見つめた。鉄朗は決心したように、吸いかけの煙草を灰皿に捻り消すと、一息ついてから視線を緑に戻した。
「今度の日曜、会って欲しい人がいるんだ」
「え…?」
微笑んでいた顔が、急に不安を含んだものになる。
「そんな顔するな…」
鉄朗は緑の顔を優しく包み込んで、身体ごと引き寄せた。
「会社の同僚なんだけど、俺が綺麗な男と暮らしてるって知って、会ってみたいんだってさ」
「綺麗…?」
微かに緑は苦笑し、鉄朗を見上げた。優しい瞳を見つめ、首に腕を回し、いつものように甘えた。どんなに甘えても、鉄朗は必ず受け止めてくれる。
「嫌ならいいんだ。断るだけだから。緑の考えを俺は尊重するから」
「男?それとも女?会う人って」
「女だけど…?」
「そう」
女、と聞いて、緑は少し悲しくなったが、鉄朗と付き合おうとした時に信じてみると決めた。鉄朗なら自分を傷つけるような事はしないと思った。だったらその女と会ったとしても、きっと大丈夫だろうと、結論を出した。
「いいよ。会っても」
「本当か?無理してないか?」
「してないよ。テツが一緒だったら、何があったって平気だから、俺」
「緑…」
いじらしい事を言ってくれる緑を、鉄朗は愛しそうに見つめた。付き合っていく中で培われていく信頼感を、しひしひと感じる事ができ、嬉しかった。出会った時より一段と愛しさが募り、ますます虜になっていく。
「その人に何を言われても、気にしなくていいから」
親指で口端をなぞり、そっと口付ける。
「愛してるよ」
感じる愛しさを口にし、甘い時間を過ごす。
「俺も。俺も大好きだよ、テツ。世界で一番好き」
「まーた。子供みたいに」
ぶー、と唇を尖らす緑の髪を掻き上げ、さらさらと掌から滑り落ちる髪をいつまでも見ていた。
10
「こっちだよ」
よく晴れた日曜日。鉄朗は緑と、恵里に会うため、一緒に出かけた。待ち合わせ場所にしたのは、二人のマンションから電車で五個目の駅近くにある、お洒落なレストランだった。
鉄朗には、いつまでも恵里と話している気はない。さっさと用件を済ませ、緑と買い物をしたかった。こうして二人でデートをするのも久ぶりで、朝から気分か高揚していた。
「ごめんなさい。お待たせしちゃって…」
恵里は女らしく、胸元の開いた淡いピンク色のシャツに、黒の短いスカートを履き、細く白い足を出している。
「いや…」
会社で会うときよりもセクシーな格好をしている恵里を、鉄朗は茫然と見上げた。見惚れたわけじゃない。思っていたよりも派手で、驚いたのだ。
会社ではもう少し清楚なイメージのあった彼女が、プライベートではそうでもないらしい。
見せ付けるかのように、恵里はゆるくウェーブのかかった髪を掻き上げ、鉄朗を見た。
緑はこれでも元ホストだ。たくさんの女が自分に寄って来る時、同じような仕草で誘われた。恵里が色仕掛けで鉄朗に迫っているのは、緑には一目同然だった。
(この女…)
先程までの少年らしい表情を隠し、冷たく無表情な顔を恵里に向ける。
「明智君、この子?一緒に暮らしてる子って」
「ああ」
「はじめまして、鷺宮緑です」
薄っすら笑みを浮かべ、挨拶する。そしてまたすぐに無表情に戻った。
「こちこそはじめまして。明智君の同僚の斉木恵里です。よろしくね」
極端な表情の変化に、恵里は戸惑いながらも、きっちり挨拶だけは返した。
「とりあえず何か頼もう。もう昼だし、腹が減ってきたし…」
鉄朗がそう切りだし、メニューを手に取った。鉄朗は緑と一緒にメニューを見て、何がいいか楽しそうに選んでいる。緑の表情は先程とは違い、嬉しそうに笑って、鉄朗を見つめている。
「何でも頼めよ。もちろん俺の奢りだから」
「んじゃ、パスタ」
「それだけか?もっと食わないと太らないぞ」
「太りたくないよ…」
「だーめ」
恵里はそんな二人をじっと見ていた。まったく相手にされておらず、二人は恵里の存在を忘れているような感じだった。
「変な二人ね」
「え?」
鉄朗ははっとして、恵里を見た。まるで観察しているような目つきの恵里に、嫌なものを感じた。
「まるで恋人同士みたいにいちゃついて」
棘のある言葉に、緑は冷たい目で恵里を睨んだ。
「恋人だから。緑は」
「ちょ…!!テツ!?」
鉄朗は優しい眼差しを緑に向けた。微笑んで、緑の髪を撫でる。まさかそんな事を言うとは思いもしなかった緑は、ただ鉄朗を見ていた。
「な、何言ってるの?明智さん、大丈夫?」
恵里は引き攣った笑顔を鉄朗に向け、動きを止めた。
「緑は俺の恋人だ。だからもう俺に構わないで欲しい。電話も止めて欲しい。この事を誰かに言ってもいいよ。会社でばらすのも構わない。恵里さんが俺を好きになってくれた事は、正直嬉しいよ。でも、俺には緑がいるから、付き合えない。ごめん」
真剣な顔付きで、鉄朗はすべて恵里に話した。
いくら緑が綺麗でも、所詮男同士だ。世間的には認められないかもしれない。でも鉄朗は、そんな事はどうでもよかった。この間、ホテルで緑の告白を訊き、すべてを捨てる事になっても、この手で緑を守ってやりたいと思った。誰に何を言われても、二人なら何とかなる。そう、思った。
「……っ…くっ…」
突然、嗚咽が聞こえたと思ったら、隣に座っていた緑が俯いて涙を零していた。嬉しくて仕方なかったのだ。
誰かにこの関係を打ち明ける事は、大変な決心がいる。その事は緑にもよくわかっていた。だからこそ、鉄朗が恵里に話したことが嬉しくて、自分のすべてを全身で受け止めていてくれると感じられて、涙が止まらなかった。
「何、泣いてんだ…」
しょうがない奴だな…、と苦笑して、鉄朗はハンカチで緑の涙を拭ってやった。
「明智さん…」
鉄朗の口から放たれた言葉の端々に、態度に、緑に対する愛情が十分過ぎるほど恵里には伝わった。だから出かかっていた非難の言葉を、自分の胸の中に飲み込んだ。
「ごめんなさい。明智さんの事は諦めるわ。でも。これからは友達として、仲良くしてくれる?」
失恋して傷ついた心を隠し、恵里は笑いかけた。
「ありがとう…」
そんな恵里の優しさに、鉄朗は頭を下げた。
「もちろん、誰にも言わないわ。会社にもね」
クスッと笑って、恵里は席を立ち、店を出ていった。
「ありがとう」
もう一度恵里の後姿に礼を言い、視線を緑に向けた。
「もう泣くなよ…」
「だって!嬉しかったもん……」
「かわいいね、緑」
泣いて壊れてしまっている綺麗な顔を上げさせ、素早く瞼に口づけた。
「テ、テツ!」
顔を赤く染め、恥ずかしそうに周りを見渡す緑を、優しい眼差しが見守る。
恋愛に教科書なんてない。どんな恋愛方法だって、お互いが幸せであればそれでいい。
この二人は、そういう恋愛を選んだ。
二人の心を表すように、外は綺麗に晴れ渡っていた。
|
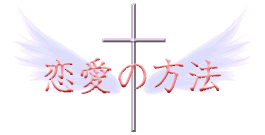
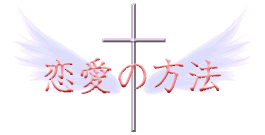
![]()