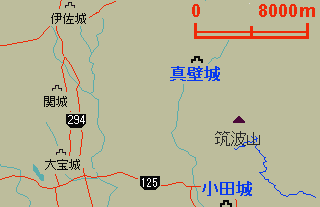
暦応元年(1338年)吉野から北畠親房一行が、南朝勢力の立直しのため海路で陸奥へと向う途中、暴風により利根川経由で霞ケ浦の東条浦(稲敷郡桜川村)に漂着します。 のち神宮寺城、阿波崎城へと入城しますがともに北朝方の佐竹軍により攻められ、筑波の小田城へと落ちました。ここで南朝方の諸侯をあつめ、常陸の南朝軍と、高師冬率いる北朝軍との攻防戦が展開されるのでした。 今回はこの小田城、同じく南朝方についた真壁氏の真壁城の紹介です。(真壁城は旧茨城西部の城から移動)
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
常陸南朝の城
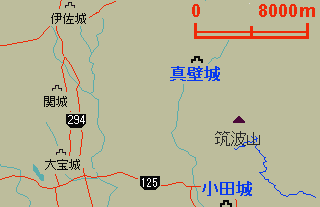
暦応元年(1338年)吉野から北畠親房一行が、南朝勢力の立直しのため海路で陸奥へと向う途中、暴風により利根川経由で霞ケ浦の東条浦(稲敷郡桜川村)に漂着します。 のち神宮寺城、阿波崎城へと入城しますがともに北朝方の佐竹軍により攻められ、筑波の小田城へと落ちました。ここで南朝方の諸侯をあつめ、常陸の南朝軍と、高師冬率いる北朝軍との攻防戦が展開されるのでした。 今回はこの小田城、同じく南朝方についた真壁氏の真壁城の紹介です。(真壁城は旧茨城西部の城から移動)
1つ前に戻る ホームへ戻る
小田城
|
所 在:茨城県 筑波郡筑波町大字小田
地図[MapFanWeb] 交 通:JR常盤線 土浦駅下車 車40分 種 別:中世 平城 撮 影:1999年 10月 小田城は12世紀末、八田知家がこの地に館を構え築城したと伝えられています。 知家は小山正光らと頼朝の決起に従い、富士川の合戦などで軍功を上げ、常陸守護に任ぜられ鎌倉幕府でも要職にありました。 4代時知から小田氏を名乗るようになり、鎌倉幕府が滅びると7代治久は北条高時の重臣として赤坂城の戦いの参加や、後醍醐天皇の隠岐島への護送役をつとめるなど、南朝とは関わり合いの深い人物で、北畠親房が小田治久を頼った経緯も自然の成り行きといえるでしょう。 暦応4年(1341年)、北朝軍の総攻撃を受けますが小田城はびくともせず、高師冬率は和平工作に転じ、治久を懐柔して城を開城させることに成功します。 親房は開城直前に小田城に見切りをつけ関城へと移動し、合戦の焦点は関城、大宝城へと移りました。 関城が落ち常陸での南北朝の騒乱後、高師冬は小田治久との開城の条件をすべて破棄し、官位、守護職の剥奪、領地の削除などで小田氏の勢威は落ちますが改易は免れたわけです。 戦国時代の小田城は結城氏や佐竹氏に激しく攻められ、15代氏治は家臣が守る土浦城に逃げ込むこと3度、そのつど小田城を奪回しますが、永禄12年(1570年)佐竹方の真壁氏との手這坂の合戦で大敗すると小田城は佐竹に占領され、その後小田氏が復活することはありませんでした。 天正6年(1578年)土浦城の氏治は子を人質に出し佐竹の軍門に降ります。 その後佐竹の家臣梶原政景が小田城代となり城を大改築します。 慶長7年(1602年)佐竹氏が秋田に転封と同時に小田城は廃城になりました。 城は広大な土地に三重の堀をめぐらした平城で、現在は本丸とその堀が比較的容易に確認できます。方形の本丸の北東、南東の角には櫓台と思われる高くなった部分があり、それぞれ碑や説明看板などありました。 上写真は北東の櫓台の最高位から南側に撮った本丸堀です。小田城では99年に障子掘が発見されたようで、堀底の青いシートはその調査関連のものと思われます。 障子掘は北条系城郭の特徴の1つですが、小田氏は北条氏康と連盟も組んだ時期もあるのでその影響か、もしくは佐竹氏城郭でも常識だったのかもしれません。 中写真は南東の櫓台を掘底から撮ったものです。写真の下にはやはり青いシートがかぶせてあり、ちょっとめくって見るとスコップなどありました。当時は障子掘の件を知らなかったのでもう少し入念に見ればよかったです。<良くない! 下写真は南西の角にあった方形の平削地で、明らかに何らかの建造物跡と思われますが詳細は不明です。 |
真壁城
|
所 在:茨城県 真壁郡真壁町古町
地図[MapFanWeb] 交 通:JR水戸線 岩瀬駅 車20分 種 別:中世 平城 撮 影:1998年 3月 最初の築城は1172年、真壁長幹により築城されたといわれています。初代の長幹は源平抗争、六代幹重は南朝に担架し落城、七代高幹が復興、12代慶幹は鎌倉公方との戦に敗れ、13代朝幹で再び復興、戦国期の17代久幹、18代氏幹と戦乱に明け暮れ、1602年に19代房幹が、佐竹氏に従い角館に移封になるまでの400年間、波乱に満ちた真壁氏による支配が続きました。 その後は浅野氏、稲葉氏と相次いで入封し、1622年に天領となっています。 遺構は本丸こそ町立体育館になっていますが、東側には田んぼの中に、二の丸、中城、外城、と展開していて、掘、館跡、櫓台?等、よく遺構が残っています。 上写真は本丸と二の丸の間にある掘の遺構で、写真右が体育館、すぐ後の山は筑波山です。 下写真は二の丸の最高位から東側を撮った写真で、中央の田んぼの中に、土塁が走っているのが分かると思います。櫓台跡のような遺構も確認できますね? 土塁の下には掘があり、さらにその向うの木が茂っているところが鹿島神社で、この裏には外堀の遺構も良く確認出来ます。 |