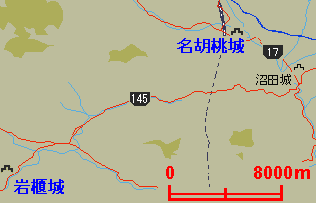
上野国の城第3弾で、真田太平記でお馴染みの岩櫃城と名胡桃城の紹介です。 岩櫃城は、岩殿城、久能城とならび武田の三堅城と称される山城で、西側から見る山の全容は切り立った岩が雄大であり、鬼でも出てきそうな容姿をしています。 名胡桃城は、沼田城から数km北にある利根川と赤谷川の合流点の断崖上にある城で、秀吉の北条討伐のきっかけを与えた城として広く知られています。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
上野の城3
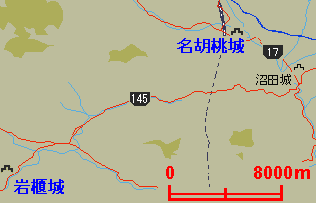
上野国の城第3弾で、真田太平記でお馴染みの岩櫃城と名胡桃城の紹介です。 岩櫃城は、岩殿城、久能城とならび武田の三堅城と称される山城で、西側から見る山の全容は切り立った岩が雄大であり、鬼でも出てきそうな容姿をしています。 名胡桃城は、沼田城から数km北にある利根川と赤谷川の合流点の断崖上にある城で、秀吉の北条討伐のきっかけを与えた城として広く知られています。
1つ前に戻る ホームへ戻る
岩櫃城
|
所 在:群馬県 吾妻郡吾妻町原町
地図[MapFanWeb] 交 通:JR吾妻線 群馬原町駅から西へ徒歩60分 種 別:中世 山城 築城は、鎌倉初期に吾妻太郎助亮によって築城された説や、南北朝初期に助亮の末裔の斎藤憲行が築城した説があります。 憲行から4代後の憲広は、大永年間(1521〜1528年)に東吾妻を制覇するものの、西吾妻には真田氏と同族の鎌原氏が武田方に通じていたため、この鎌原城の攻防が原因で、真田、武田と敵対しました。 斎藤氏の岩櫃方は上杉謙信を頼り、沼田、白井の諸侯の協力のもと、真田勢とよく戦いますが、数回の和議を経たのち真田への内応者がでたため、ついに永禄6年(1563年)に落城。 その後は真田の城代が置かれ、関ヶ原後は沼田城の支城として真田信之が支配しますが、一国一城令により廃城となりました。 標高800mの山で、最高位を含む山の北側部分は切り立った岩山で、まさに仙人が出てきそうな水墨画の世界です。 城は北側ではなく東側山腹にあり、南に望む吾妻川流域の平野を抑え、信州、上州の往来を分断できる格好の要所となっています。 城へは東側から舗装された道があり、上写真の中央の城の口と呼ばれる三叉路まで車で行く事ができ、奥への道が城の主要郭へ通じる山道で、写真左の山が城のある部分、右の山は最高位にあたる峰です。 この写真は天狗の丸から撮ったもので、この郭は城の口より少し高台になった東北に長い郭で、現在は田畑と神社がありました。ここからの眺望は最高です。 この城の口から5分ほど歩くと、右側に中城と呼ばれる平削地があり、かなりの広さを誇っていますが、全て藪の中で踏破はまず不可能でしょう。 この中城の南端から西へ、本丸に向けて登り坂があり、小さな帯郭や二の丸堀を見過ごして二の丸に至ります。 二の丸からは大型で見事な本丸堀が眼中に広がり、特に堀の西端コーナー部や、ここから山の西斜面に流れている竪堀が見所です。共に写真は晴天のため失敗しました。中写真は堀の東側にあたる所で階段を上れば本丸です。 本丸は天守台のような壇を囲むようにあり、高低差は2,3mといったところで、南側には虎口を思わせる入り組んだ遺構が見受けられます。 下写真は壇にある城址碑を撮ったものです。この壇は東西に細長く20mほどでしょうか?さほどの広さは感じませんが、ここが難攻不落を誇った岩櫃城の中枢です。 岩櫃山の全容は、西側から見る方が岩が露出している部分が雄大に見えるため、車で行かれる方は西側で一見されることをお奨めします。>作者はいつもの通り電車バスだったのだ。 |
名胡桃城
|
所 在:群馬県 利根郡月夜野町
地図[MapFanWeb] 交 通:JR上越線 後閑駅から徒歩1時間弱 種 別:中世 崖端城 16世紀始めに沼田氏の分家名胡桃氏が、沼田城の支城としてこの地に配したのが始まりで、築城は名胡桃氏によるものと、沼田城の支城として真田昌幸が築城したものがありますが、この城は秀吉に北条攻めのきっかけを与えた名胡桃城事件で広く知られています。 北条氏に上洛を促していた秀吉は、北条の要求を一部聞き入れ、利根川左岸の沼田城を北条に与え、右岸の名胡桃城は真田のものという裁断を出します。数回に渡り沼田城攻略に失敗している北条氏にとって長年の念願が果たせた訳ですが、数キロ北の対岸にある名胡桃城が真田の城であることに反発した北条方の沼田城代が、名胡桃城を攻略した事件が、真田昌幸によって秀吉に報告され、激怒した秀吉が北条攻めを決意したという話しです。 真意は不明ですが秀吉にとっては筋書きどおりの事件でしょう。 利根川の右岸にあり、背後は川の浸食による50m程度の落差のある断崖上にある城です。規模は決して大きくなく、国道17号線に分断されていますが、国道東側に主要郭の遺構がよく残っています。 上写真は国道からすぐ入った所にある角馬出しの遺構で、向こうには三の丸、二の丸が広がっています。 角馬出しの遺構は明確に残っていませんが、三の丸との間に区画の跡があること、写真左側に堀が存在していることから、三の丸から西側に開いた馬出しである事が分かります。 中写真は、三の丸と二の丸の間にある堀でこちらは明確に残っています。安易な木の橋で結ばれてる二の丸、三の丸の踏破は、容易ですが土塁などの遺構は見あたりません。 二の丸から本丸へは断崖の地形を利用した更に深い堀が存在し、こちらは土橋の雰囲気が残っています。本丸からは東へより断崖の先端に近づくため、郭は小さく周りの木々も深くなっていきます。 本丸は二の丸より格段に小さく、土肌がむき出しになった東西に長い郭で、城址碑と休憩所がありました。 本丸より堀を隔てさらに東にあるのはささ郭で、本丸よりさらに小さい空間があり、下写真は本丸側から撮ったささ郭の虎口ぽい遺構です。ささ郭からさらに西側は木々が遮っていますが、たぶん目がくらむような光景が眼下に広がっているでしょう。ここから先への立ち入りは不可能です。縄張図では更に先端に物見台跡のような平削地がありますが、数m下った位置になるでしょう。 |