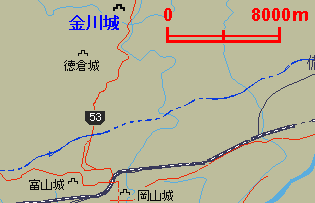
”備前の城2”は松田氏ゆかりの城です。松田氏は承久の乱後から備前を治めていた家で、戦国時代に宇喜多氏により滅ぼされました。 松田氏の本城といわれる金川城を紹介しますが、それ以外に、岡山市の富山城、御津町の徳倉城があります。富山城は、水道局の施設工事のため立ち入り禁止で、徳倉城は、辺鄙な場所になるため、電車バスでの見学は困難でしょう。金川城のみの紹介で心苦しいです。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
備前の城2
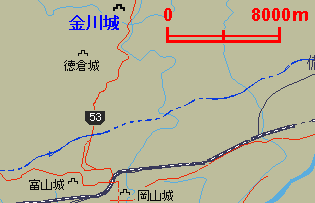
”備前の城2”は松田氏ゆかりの城です。松田氏は承久の乱後から備前を治めていた家で、戦国時代に宇喜多氏により滅ぼされました。 松田氏の本城といわれる金川城を紹介しますが、それ以外に、岡山市の富山城、御津町の徳倉城があります。富山城は、水道局の施設工事のため立ち入り禁止で、徳倉城は、辺鄙な場所になるため、電車バスでの見学は困難でしょう。金川城のみの紹介で心苦しいです。
1つ前に戻る ホームへ戻る
金川城
|
所 在:岡山県 御津郡御津町金川
地図[MapFanWeb] 交 通:JR津山線 金川駅から徒歩10分で登山口 種 別:中世 山城 築城は諸説があり定かではありませんが、承久年間(1220年頃)承久の乱の功績により相模から松田氏がこの地を与えられ築城したと言われているようです。 応仁の乱により松田元隆は、備前守護職の座を企てる赤松氏に加担し、山名氏との抗争に功績を上げ、富山城と金川城を拠点に、事実上の守護代の権力を持つに至ります。 元隆の子元就の代になると、主家の赤松氏に叛旗を翻し下剋上に及び、西備前の戦国大名として成長します。このころから東備前に君臨する三石城の浦上氏と、抗争が激しくなり一進一退を繰りかえします。 天文年間(1540年頃)、元就から3代後の元盛の代になると、浦上宗景の勢力が増し松田氏の権力が衰退し始めます。永禄11年(1566年)、南備前で台頭し始めた宇喜多直家により金川城を攻められ落城、当主元輝、子の元賢が討死にして、松田氏は滅亡します。 その後は宇喜多の家臣が入城し、小早川氏の頃にはその存在は不明です。元和の一国一城令まで存在した可能性もあるそうです。 城は、岡山平野の北限にあたる、旭川と宇甘川の合流点にある比高200mの臥龍山にあります。上写真は城の遠景で、山の南から橋を渡る直前で撮ったものです。 縄張は、本丸、大手曲輪、二の丸の連郭で構成された主要部分と、本丸から北に方向を変え郭が一直線状に展開する北の丸部分と、本丸から南に展開する道林寺丸の部分と、二の丸から東北に展開する出曲輪部分の4つで構成された複合連郭式山城ですが、確認できたのは主要部分と北の丸部分のみで、その他の現状は薮の中でしょう。 遊歩道は、城の東南の端にある出曲輪に直結しており、二の丸、大手曲輪、本丸へと至ります。大手曲輪には虎口と思われる桝形の土塁があり、崩れた石垣が散在しています。 中写真は本丸で北端の土塁に登って撮ったものです。ここも石が散在しています。本丸の北側直下には、天守の井戸と呼ばれる井戸があり、直径5m、深さ15mぐらいあるでしょうか。安易な柵がしてあるだけで非常に危険です。 本丸の北側は整備されていない北の丸の曲輪が並んでおり、途中で踏破も不可能になります。下写真は、脇の山道を歩いてみつけた堀切で、北の丸の郭列の先端にあるところです。肝心の北の丸は見つけることができませんでした。 |