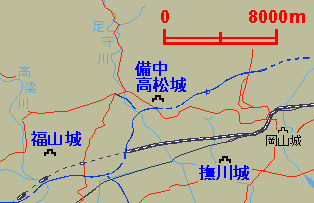
備中は岡山県西半分のことですね。戦国時代は庄氏、石川氏、三村氏らによる割拠の時代が続きますが、他国の宇喜多、毛利、尼子などによるの脅威にもさらされます。 南北朝の福山合戦や、秀吉の中国役による高松の役など、歴史のターニングポイントの舞台となったのは、備中国が山陰、山陽を含んだ中国地方の真ん中に位置する拠点であったためだと、作者は勝手に思っています。 特に吉備平野は古代から栄えたところで、国府跡や古墳など今でも堪能できます。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
備中の城
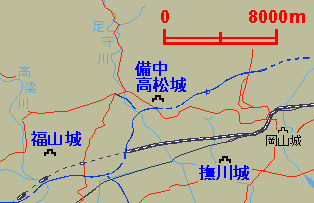
備中は岡山県西半分のことですね。戦国時代は庄氏、石川氏、三村氏らによる割拠の時代が続きますが、他国の宇喜多、毛利、尼子などによるの脅威にもさらされます。 南北朝の福山合戦や、秀吉の中国役による高松の役など、歴史のターニングポイントの舞台となったのは、備中国が山陰、山陽を含んだ中国地方の真ん中に位置する拠点であったためだと、作者は勝手に思っています。 特に吉備平野は古代から栄えたところで、国府跡や古墳など今でも堪能できます。
1つ前に戻る ホームへ戻る
備中高松城
|
所 在:岡山県 岡山市高松
地図[MapFanWeb] 交 通:JR吉備線 備中高松駅から徒歩10分 種 別:中世 平城 城郭ファンのみならず、歴史ファンなら誰しも知っている城ですね。 この地は備前との国境近くの平野部であり、東にある標高200m程度の山々が国境にあたります。毛利軍が、備前の宇喜多に備えていた境目七城の一つにも上げられ、秀吉の中国役の時にも整備強化されました。他の城が次々と攻略される中、最後に残ったのがこの高松城ということです。 天正年間(1573〜92年)に備中半国を治めていた国人石川氏による築城で、石川氏が断絶すると、清水宗治がこの城に入城します。 水攻めの経緯は割愛して、戦後は宇喜多の武将が入城し、関ヶ原後は陣屋が営まれますがまもなく廃城になりました。 かつては沼城であり、本丸と二の丸を、三の丸と家中屋敷がコ状に囲んだ簡単な縄張だったようで、現在、本丸跡は広場になっています。 上写真は本丸跡ある宗治の首塚です。 南にある旧二の丸付近も公園として整備され、東西南北に渡って秀吉軍の布陣を表わしたオブジェなどあります。 下写真は、城から東南へ2Kmほどのところにある、蛙ケ鼻の土塁で、秀吉軍が水攻めの時に築いた土塁か現存する唯一のものです。わずか数メートルが田んぼに突き出ているだけですが、立派な国指定史跡です。 |
撫川城
|
所 在:岡山県 岡山市下撫川
地図[MapFanWeb] 交 通:JR山陽本線 庭瀬駅から徒歩10分 種 別:中世 平城 近世 陣屋 築城は明らかではありませんが、備中高松城と同様に境目七城の一つにも上げられた城です。天正10年(1582年)秀吉の中国役の時には、毛利城代の村上氏、内藤氏らが死守しましたが、攻略されています。 その後は、宇喜多の家臣である戸田達安が入城します。達安は、関ヶ原直前の宇喜多家家中騒動で主家を離れますが、関ヶ原では東軍で戦功をたてたので、再びこの地に戻り、撫川城のすぐ東に庭瀬城を築城し、撫川城も古城として縄張に取り込んだようです。のちに戸田氏も改易されその後は譜代による陣屋が営まれました。 撫川城は足守川下流の旧水郷地帯にあり、現在ほとんどが埋め立てられていますが、方形の城址公園周辺は、水掘の状態が良く残っています。 上写真は堀を西側から撮ったもので、城の北西に位置する櫓跡らしき石垣が見られます。城址公園内は、陣屋から移設された城門があり、神社が鎮座しています。南東側は土塁も確認でき古城の雰囲気が良く出ています。 下写真は城から東へ200mぐらい行ったところにある庭瀬城跡です。住宅街の中に簡素な神社が残っているだけですが、わずかに残る沼が、当時は堀であったろう雰囲気を出しています。 |
福山城
|
所 在:岡山県 都窪郡清音村
地図[MapFanWeb] 交 通:JR伯備線 清音駅から徒歩30分で登山口 種 別:中世 山城 湊川合戦の前哨戦である福山合戦が行われた城で、官軍が足利軍の多勢相手に籠城した城です。国指定史跡にもなっています。 建武3年(1336年)の1月、九州の博多まで退却した尊氏に対し、官軍の新田義貞の軍勢は、備前、美作まで進み、先鋒である大井田氏経がこの城に布陣しました。 九州で軍勢を立て直した尊氏は、陸海同時に20万とも言われる大軍で京を目指し東上を開始します。 直義率いる陸軍の大軍に、城を囲まれた氏経らわずかの籠城軍は、決死の覚悟で戦に挑み、足利軍に2万余りの死傷者を出させ奮戦しますが城はついに炎上、残り百騎となった氏経らは、官軍本陣のある播磨国境近くの三石城めざして強行突破し、10回の交戦を続け三石城に逃げ去ったといわれています。 この福山合戦が行われたのは建武3年の5月で、湊川決戦の1週間前のことです。 城は、高梁川沿いの平野部の東側に位置する標高300mの山で、このあたりの山では一番高いでしょう。 上写真は城の西側の遠景で矢印が城跡になり、麓から1234段の階段が整備されています。山の頂上からは良く眺望がききます。 遺構は一の段、二の段、三の段からなり、一、二の段の間に若干ですが門跡の石垣が確認できる程度で、他は空堀、石列、井戸跡などがあるようですが、薮の中で確認は困難です。二の段には氏経を奉った神社跡があり、狛犬のみ残っています。 下写真は二の段の南側にある碑で、氏経の忠碑、福山合戦碑、城址碑の三つの石柱があります。 余談ですが、上写真の左側のコブは幸山城で、石川氏、清水氏の居城でした。こちらは戦国時代の城のようです。上記の階段の途中で北へ別れる道があり、看板表示もありましたが、私は先を急ぎました。今では後悔しています。>またか! |