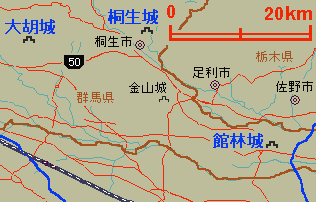
上野の城第2弾で、家から比較的近い群馬県の東部になります。群馬県の城は、現存する建築物は高崎城の乾櫓程度ですが、遺構となると利根川沿いの湿原地帯にあった城や、河岸台地上にあるもの、山城などレパートリに富んでいます。また群馬の城跡はその大半が調査され、縄張図(または推定)が日本城郭大系(新人物往来社)などにたくさん載っており、実物と合わせて見学できるのがうれしいですね。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
上野の城2
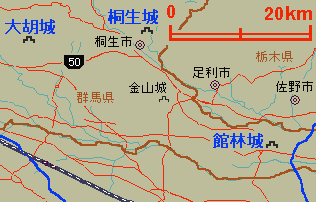
上野の城第2弾で、家から比較的近い群馬県の東部になります。群馬県の城は、現存する建築物は高崎城の乾櫓程度ですが、遺構となると利根川沿いの湿原地帯にあった城や、河岸台地上にあるもの、山城などレパートリに富んでいます。また群馬の城跡はその大半が調査され、縄張図(または推定)が日本城郭大系(新人物往来社)などにたくさん載っており、実物と合わせて見学できるのがうれしいですね。
1つ前に戻る ホームへ戻る
館林城
|
所 在:群馬県 館林市城町
地図[MapFanWeb] 交 通:東武伊勢崎線 館林駅から東へ徒歩20分 種 別:近世 平城 戦国初期に台頭した赤井氏が、城沼の南側に大袋城を築城し、当初はこちらが館林城であり、戦国中期になると赤井照康が対岸に城を移します。これが現在の館林城の原形で、白狐が尾が曳いて縄張りしたという伝説があり、別名を尾曳城といわれます。照康の息子照景は、謙信が関東に出馬した際に従わなかったため、永禄5年(1562年)に館林城を攻められ、城を追い出されています。 後には長尾氏が入城。天正12年(1584年)になると北条氏の調略により城を明け渡し、館林城は北条氏規の城代が入城します。 天正18年(1590年)石田三成率いる豊臣軍に包囲され開城となり、徳川家臣の榊原氏が十万石で入封し城下を完成させ、徳川譜代数家の入城を経て維新に至ります。 このあたりは利根川と渡良瀬川にはさまれた低地で、当時は沼や湿地がたくさんありました。縄張は城沼の西岸に三の丸、二の丸、本丸を連ねて、沼へ突き出した連郭式で、城下は沼の西側の台地に広がっていたようです。現在、城のあった部分はすっかり埋め立てれられ、市役所、図書館、公園などが隣接する公共の場となっています。 三の丸東側に土塁の一部が残っており、上写真の土橋門が最近復元されました。土塁の上に立つ真新しい塀が、アンバランスな印象を受けちゃいますね。 下写真はわずかに残る本丸土塁で、向こうにみえるドームは子供博物館の施設です。 沼の南岸にある有名なつつじケ岡公園は、館林城主榊原康政が17世紀につつじを植樹したのが始まりで、以後大名庭園として発達したものです。 |
桐生城
|
所 在:群馬県 桐生市梅田町
地図[MapFanWeb] 交 通:JR両毛線 桐生駅から車で北へ20分 種 別:中世 山城 別名を檜杓山城(読み?)といい、観応元年(1350年)桐生国綱が、麓の館から砦を構えたのが始まりです。五代あとの豊綱は佐野氏からの養子で、以後、佐野の分家の色が高まります。数代へて元亀3年(1572年)、助綱の跡を継いだ佐野家の養子親綱は、由利成繁に攻め込まれると親綱は佐野へ逃れ、桐生城は由利氏の居城となります。 成繁は山の麓に館を構え、嫡子国繁には金山城を譲りました。のち、成繁は桐生城を大改修し、今日に見られる遺構はこの時の改修によるものです。 成繁死後、天正12年(1584年)北条氏の調略により金山城を奪われた国繁は、桐生城に戻り、天正18年の小田原の役では小田原城の籠城を強制されます。戦後、母妙印尼の奔走により許された国繁は、常陸牛久に国替えとなり、桐生城は廃城となりました。 比高210mの檜杓山の山頂に西から東へ、本丸、二の丸、三の丸で”ひしゃく”の形をした縄張で、本丸が先端部分、細長い二の丸、三の丸が柄の部分のようです。上写真は、二の丸側から撮った本丸とその間にある堀切で、斜面には竪堀も確認できます。本丸は幾重かの腰郭で螺旋状になっており、現在も腰郭の存在は良く確認できます。最高位の本丸はこの城で唯一整備された曲輪で広場に碑などがありました。 三の丸と二の丸の堀切から北へ向かうと北郭があり、先端にも小さい郭の列があるようです。下写真は北郭から堀切を経て一段下がった郭を撮ったものです。このあたりは全然整備されていませんので、本当に北郭からなのかあやしいですが、遺構を見つけた時の快感はたまりません。 本丸南から大手へ通じる道は、わずかに道が確認できる程度ですので、踏破はよほどの覚悟が必要でしょう。この大手を経て南麓に館があったようです。 現在は三の丸の搦手から見学するようになってます。 |
大胡城
|
所 在:群馬県 勢多郡大胡町大胡
地図[MapFanWeb] 交 通:上毛電鉄 大胡駅 徒歩北へ30分 種 別:中世 平城 大胡氏は藤原秀郷の末裔といわれ、現在の城より西側に館を構えていたようです。天文10年(1541年)金山城の横瀬泰繁によって城を攻められ、以後大胡城は横瀬氏に属しますが、永禄8年(1565年)金山城の由利(横瀬)成繁は謙信に逆らったため、金山城攻めの前哨戦としてこの大胡城を落し、謙信は北条(きたじょう)高広に大胡城を預けます。 以後しばらくは北条高広の居城となり、本能寺の変後滝川一益が伊勢に戻ると、高広は自身厩橋城に入城し、大胡城には大胡氏の復帰で城を固めさせ、真田昌幸らと結び、北条氏(小田原)に敵対する姿勢を取り続けました。 天正12年(1584年)になると、さすがの高広も北条氏に屈服し、大胡氏もそれに従い、高広は小田原攻めの前に死去しています。 役後、徳川の家臣牧野氏が2万石で入城し、元和2年(1616年)に廃城となっています。 縄張は北から近戸郭、北城、本城(本丸、二の丸)、三の丸、南郭で構成さらた丘上にある大掛りな城です。二の丸は福祉センターみたいな設備があり、本丸と隣接する部分は大掛りな空堀が存在します。上写真は二の丸にある桝形の遺構で古そうな石垣によるものです。 本丸は周囲が土塁に囲まれあまり整備されていませんが、一応公園にはなっています。簡素な神社があり市街の眺めはよいでしょう。 下写真は本丸から北城との間にある堀を撮ったもので、写真右下にある駐車場の車と比べると堀の規模が分かると思います。北城にも最近の調査で、食い違い虎口の石垣などの遺構が確認され、生活品の出土品も豊富に出たようです。完全に保育園の敷地となっているので見学はあきらめました。 近戸郭は北城からは少し離れた郭で、現在は大胡神社となっています。大胡氏時代はこちらが本城だったようで、北条高広により本城が築かれたあとは支城として使われたようです。 南側にある三の丸、南郭は見てませんが、今は市街地なので遺構は残っていないでしょう。 |