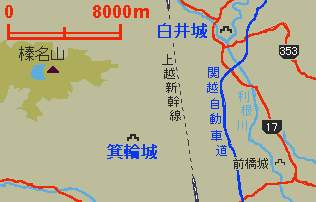
上野国は群馬県のことですね。越後、信濃、武蔵への街道が集中するこの国には、
北の上杉、西の武田、南の北条との間で、幾度も戦が繰り広げられました。城は、利根川、吾妻川、その支流沿いの台地と、関東平野の限界にあたる丘陵部に、たくさんの城があります。多分、関東では一番城が集中しているエリアでしょう。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
上野の城
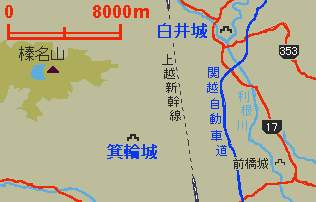
上野国は群馬県のことですね。越後、信濃、武蔵への街道が集中するこの国には、 北の上杉、西の武田、南の北条との間で、幾度も戦が繰り広げられました。城は、利根川、吾妻川、その支流沿いの台地と、関東平野の限界にあたる丘陵部に、たくさんの城があります。多分、関東では一番城が集中しているエリアでしょう。
1つ前に戻る ホームへ戻る
白井城
|
所 在:群馬県 北群馬郡 子持村白井
地図[MapFanWeb] 交 通:JR吾妻線 渋川駅から車で北へ10分 種 別:中世 崖端城 しろいじょうと呼びます。 築城は、関東管領である山内上杉家の家宰(家老のようなもの)の長尾景仲で、景仲は、白井長尾氏とも呼ばれました。孫の景春は、家宰の跡継ぎをめぐって、関東管領上杉顕定に背き、文明5年(1473年)に鉢形城を築城し、古河公方の援護のもとで、小競り合いを続けますが、永正7年(1510年)に、越後での内乱により顕定が戦死すると、景春は白井城に戻っています。 景春没後は、箕輪城の長野業政が台頭し、景春子は家臣に殺され、長野氏の息の掛かった総社長尾氏の長尾憲景が、白井城主となります。以後、関東管領の上杉謙信に恭順し、謙信亡き後は北条氏に与し、武田勢に城を取り囲まれる危機を逃れ、天正18年(1591年)豊臣軍の前田利家に城を明け渡します。徳川家康が関東に入封すると、家臣の本多氏が二万石で封ぜられますが、元和9年(1623年)に廃城になります。 非常にわかりやすい要害の地にあり、利根川と吾妻川の合流点に、切り立っている台地の先端付近にある城で、西側を吾妻川の断崖に接し、北から北郭、三の丸、二の丸、本丸と、南に展開する梯郭式の縄張りを持ちます。 上写真は二の丸から撮った三の丸掘で、底が畑になった浅い堀が、東西に200mぐらい走ってます。写真向う側にある小高い丘は、北郭の櫓台になります。 下写真は本丸から北側を撮ったもので、中央は枡形門の遺構の裏側になります。この桝形門は野面積みの石垣で構成されており、半壊の危機にさらされています。枡形門前には三日月掘の遺構もあり、全然整備されてなくわずかな水が残っている程度です。本丸は立派なキャベツ畑になっており、回りは土塁で囲まれているようです。 |
箕輪城
|
所 在:群馬県 箕輪町西明星
地図[MapFanWeb] 交 通:JR上越線 前橋駅から車で西へ40分 種 別:中世 平山城 築城は、戦国時代に西上野で名を馳せた、長野業政の父の業尚とされています。長野氏は関東管領上杉氏に従う豪族で、永享12年(1440年)の結城合戦の記録が初見のようです。天文20年(1551年)頃から長野業政は、白井、忍、安中、小幡と姻戚関係を結び、西上野の結束に努め、武田の脅威に備えますが、永禄3年(1560年)業政が死去すると、徐々に西から武田信玄に従う諸侯が出てきて、箕輪城は徐々に孤立していきます。 永禄9年(1566年)、信玄は2万の兵を従え箕輪城攻略を開始します。箕輪城主の長野氏業(業政の嫡子)は籠城の策をとりますがまもなく落城し、一族は御前曲輪で自刃します。その後は信玄の家臣の内藤氏が入封し、信玄亡きあとは北条氏、家康が関東に入国すると井伊直政が12万石で入封し、現在見られる遺構の近世城郭に大改修しますが、慶長3年(1598年)高崎城移転に伴い廃城となります。 箕輪城は榛名山東の麓の傾斜地にあり、榛名白川を西側に接した河岸台地に築かれ、南北に長い広大な城で、見所はたくさんあります。 この城は大堀切と呼ばれる大規模な掘で、城を南北に分断し、本丸などの主要曲輪は北側になり、南側は木俣、腰曲輪などで構成されています。 上写真は唯一南北をつないでいる土橋で、向う側は二の丸、手前側は郭馬出です。写真の左側が大堀切で、急速に広く、深く成長しながら西へ展開しています。写真の右側は郭馬出の掘で、こちらもなかなか大型です。 この郭馬出から南へ木俣、腰曲輪などを経由して、10分ほどなだらかに下りると、井伊時代の大手口にあたる丸戸張と呼ばれる馬出しになります。現状は民家の横の薮の中に土塁が確認できる程度です。ちなみに長野氏時代の大手は、東側にある井伊時代の搦手口で、ここから坂道をくねくね登ると二の丸へ直接通じています。 大堀切の西端にあたる登山口が白川口と呼ばれ、白川の河原へ降りる道に埋門の遺構があり、崩れた石垣が少し確認できます。白川口からは大堀切を右側にして、鍛冶曲輪、三の丸と続き、二の丸へ通じています。 中上写真は、鍛冶曲輪の石垣で、三の丸にも門跡の石垣が見られます。 二の丸と、北にある本丸の間には、本丸門馬出が東南に張り出しており、二の丸や東側直下にある搦手口からの敵を、本丸から迎え撃つ目的のようです。 中下写真は本丸で、その広大さが写真でも分かっていただけるものと思います。 本丸の北には空掘りを隔て、この城の中枢になる御前曲輪があり、大きな井戸や慰霊碑があります。長野氏一族はここで自刃しています。 さらに北に大きな空堀を隔てて、通仲曲輪、玉木曲輪、稲荷曲輪が取巻き、玉木曲輪はこの城の最高位で、東側直下には丸馬出が張り出しています。馬出の原形は崩れてしまい、今はマウンド状に少し盛り上がっている程度です。 下写真は、御前曲輪の北側の掘底から撮った稲荷曲輪の櫓跡で、高位はすぐ左横にある玉木曲輪とさほど変わらないようです。現在は簡素な神社がありました。 箕輪城は関ヶ原直前に廃城になった城でありながら、遺構がよく残った広大な城で、特にその普請の規模の大きさに、正直いって衝撃を受けてしまいました。 |