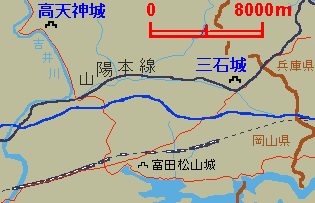
備前は、現在の岡山県南部の岡山市を含む東側の部分で、南北朝の黎明時には京を目指す足利軍と、それを死守する新政府軍との激戦が行われます。 応仁の乱で、備前の守護職である赤松氏の守護代浦上氏や松田氏、または浦上氏の被官であった宇喜多氏が台頭し、備前はこの三氏の割拠で戦国後期を迎えました。 今回はこの三氏のうち、浦上氏に関する城を紹介します。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
備前の城
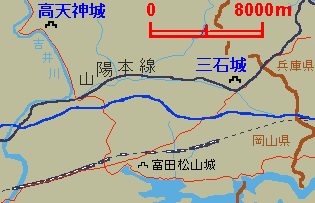
備前は、現在の岡山県南部の岡山市を含む東側の部分で、南北朝の黎明時には京を目指す足利軍と、それを死守する新政府軍との激戦が行われます。 応仁の乱で、備前の守護職である赤松氏の守護代浦上氏や松田氏、または浦上氏の被官であった宇喜多氏が台頭し、備前はこの三氏の割拠で戦国後期を迎えました。 今回はこの三氏のうち、浦上氏に関する城を紹介します。
1つ前に戻る ホームへ戻る
三石城
|
所 在:岡山県 備前市三石
地図[MapFanWeb] 交 通:JR山陽本線 三石駅から徒歩40分 種 別:中世 山城 鎌倉末期の元弘3年(1333年)、地頭の伊東氏が三石城を築城したのがはじまりです。建武3年(1336年)尊氏が九州に敗走すると、新田義貞率いる新政府軍は、足利勢の国人衆が籠城する三石城を攻撃しますが、落とすことはできず山陽道の制圧に失敗します。この敗北が新政府軍の福山合戦や湊川の敗北につながります。 応仁の乱後、三石城主の備前守護代である浦上則宗が、守護職である赤松氏を凌ぐようになります。 則宗の孫の村宗の代になると主家赤松義村と対立し、大永元年(1521年)村宗は義村を自害をさせることに成功し下剋上に至ります。 村宗の子正宗は、居城を播州国の室津城に移すと、三石城には城番が置かれ、弟の宗景、国秀が自立に動き、宗景は天神山城、国秀は富田松山城に移り、兄の正宗とは不和になります。 正宗が室津城で龍野の赤松政秀に殺されると、宗景は天神山城を居城として、美作国南部と備前国を領地とする戦国大名に成長します。これにより三石城は天神山城の支城となりますが、宗景の滅亡により廃城となります。 上写真は三石駅のホームから撮った、標高291mの三石城の遠景です。三石は、播磨と備前の国境にある船坂峠の麓であり、備前国東端の要所で、古代から駅が置かれ中世、近世は宿場町となっています。 縄張りは、山頂に円形をした本丸に、二の丸、三の丸とお玉杓子の尾状に南に展開している変形連郭式の山城です。 中写真は三石城の本丸で、御覧のとおり整備は今一つで、本丸は二段に別れて上段には館があったようです。石垣か礎石であろう石がゴロゴロ散在しており、看板に「軍用石」という表示がありますがその意味はあやふやですね。 備前焼の陶器が多数発掘されているようで、現在は発掘禁止になっているようです。 長い三の丸の西側に一段下がると帯曲輪があり、馬場とされています。この馬場を少し北上すると大手門に至ります。 下写真は大手門の石垣でこの城一番の見所でしょう。枡形でなく埋門だとされていますが、16世紀前半の山城にしては異様に早い石垣の導入とされています。さすがは西日本の中世山城ですね? |
天神山城
|
所 在:岡山県 和気郡佐伯町田土
地図[MapFanWeb] 交 通:JR山陽本線 和気駅から徒歩1時間強で登山口 種 別:中世 山城 浦上宗景は、享禄5年(1531年)浦上家の跡目を継いだ兄政宗から、一方的に独立し天神山城を築城します。その後、父兄との紛争がしばらく続きますが、天文22年(1555年)ごろには、美作から南下する尼子勢を追い払ったことや、備前守護職を奪回しようとする赤松氏を撃退したことなどで、播州を拠点とする兄正宗から、備前国の統治を認められるようになりました。 この頃が宗景の絶頂期で、美作南部と備前国の戦国大名の地位を確立します。 元亀2年(1571年)、宗景は上洛して織田信長に出仕し、領土の朱印を受けますが、このころには岡山城を拠点とする家臣の宇喜多直家が台頭し、その力関係も逆転していたようです。 天正2年(1574年)に毛利と組んだ直家は謀反を起こし、天正5年には天神山城を攻撃し、数日間の攻防のすえ、内応者を出させ落城させています。 宗景は遁走し、行き着いた場所は諸説があるようですが詳細は不明です。嫡男与次郎も直家に毒殺されています。落城後は廃城となりました。 天神山は、吉井川中流付近で、流れが東から南へ大きく曲がるところの左岸にある、標高409mの急峻な山で、主要な縄張は、そこから西北へ尾根づたいにある標高330m付近の削平地に、総長500mにわたる連郭式城郭が展開しています。 山の西北端の麓にある神社から登山口があり、そこから急峻な道を40分ほど登ると、連郭式の西北端にあたる下段の段にあたり、さらに西櫓台、三の丸と上がっていきます。さらに一段上がったところに桜の馬場(大手曲輪)があり、広さでは本丸と双璧でしょう。 上写真はその桜の馬場を北から南にむかって撮ったものです。写真左側に一段下がって腰曲輪があり大手門跡とされています。この腰郭から、桜の馬場の土手部分にある石垣の遺構が確認できます。 桜の馬場をすぎると長屋の段、二の丸、空掘を経て本丸に出ます。本丸は現在、看板のほかに”浦上遠江守宗景之城址”と書かれた碑があり、本丸の東南端に天守台?跡とされる段があるようですが、現在は天津社の祠があり雑草がひどく確認できません。 本丸をすぎると道は下りになり飛騨の丸、飛騨の丸下段、馬場の段、南櫓台、南の段と続きます。中上写真は、飛騨の丸と飛騨の丸下段の間にある石垣です。写真中央に石垣が横断しているのが分かるでしょうか? ここから先南の段までは雑草がひどくて、道すら確認できない状態が続きます。 南の段の先には堀切があり、ここから先は一転して急な上り道に入り、一気に頂上を目指すことになります。途中、亀の甲、下の石門、上の石門と呼ばれる岩場をすぎると、天神山城最高位にある太鼓の丸に出ます。 中下写真は太鼓の丸の東側にある城門の石垣で、この門は山の東側にある根小屋に対しての搦手門であったようです。 本丸からは、山の南西斜面を下る道があり、その麓に天瀬侍屋敷跡の遺構があり、広大なエリアに渡り、ところどころ石垣構築による平坦地の遺構が残っていますが、整備は今一つです。この侍屋敷跡は石垣の塀?によって囲まれている部分があり、下写真は、その石垣を撮ったものです。写真左上から右下に石垣の塀が走っているのが分かりますか? 天神山城は見所がたくさんある城ですが、山は急峻で比高もあるので、見学には覚悟が必要です。私は4時間山に入りっぱなしでしたが、生っ粋の戦国山城の遺構に触れて満足でした。(>やっぱり病気だ!) |