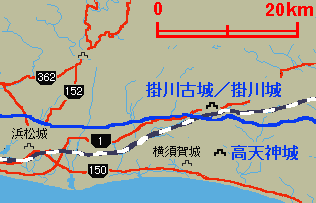
高天神城のような戦国歴史小説でよく出てくる、合戦の舞台となった城を訪れるのは非常にたのしいですね。 中央では、岐阜城、長篠城、小牧山城、といったところでしょうか? 伝承の域を越えない言い伝えの”ちょめちょめの井戸”とか”ぺけぺけの腰掛石”とか。 非常に俗っぽくて私は好きです。
高天神城にも、”ちょめちょめの抜道”、”ぺけぺけ曲輪”がありました。詳しくは本文で。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
遠江の城2
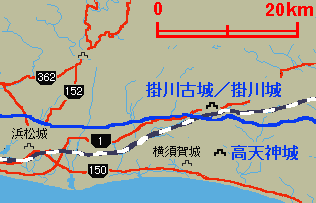
高天神城のような戦国歴史小説でよく出てくる、合戦の舞台となった城を訪れるのは非常にたのしいですね。 中央では、岐阜城、長篠城、小牧山城、といったところでしょうか? 伝承の域を越えない言い伝えの”ちょめちょめの井戸”とか”ぺけぺけの腰掛石”とか。 非常に俗っぽくて私は好きです。
高天神城にも、”ちょめちょめの抜道”、”ぺけぺけ曲輪”がありました。詳しくは本文で。
1つ前に戻る ホームへ戻る
掛川古城
|
所 在:静岡県 掛川市 城内
地図[MapFanWeb] 交 通:JR東海道線 掛川駅 徒歩10分 種 別:中世 平山城 1467年ごろ駿府館の支城として、今川義忠が重臣の朝比奈氏に命じて築城させたとあります。 1513年朝比奈氏は、斯波氏に合した信濃の小笠原氏の遠江侵攻に対抗するために、南西500m先の竜頭山に掛川新城(現在の掛川城)を築き、古城は出城的な位置づけになりました。 この古掛川城は、独立した丘陵に本丸が置かれ、南側前方の小学校のグランドあたりに、城館が置かれたようです。 上写真は本丸跡で、奥に若干ですが土塁が走っています。土塁の向う側には、台地を分割する形の深い空掘があり、掘の向こう側は二の丸になっていたようです。 写真左の小さな建造物は、大猷院殿霊廟(家光の霊廟)で、1656年掛川城主の北条氏が建造し、掛川城の守りとしました。 山内一豊が掛川城主になった時、城下を掘などで囲む総構を構築にあたり、この古城の掘を利用したようです。 下写真はその総構の掘で、上記の小学校のすぐ横にあたります。 |
高天神城
|
所 在:静岡県 小笠原郡大東町
地図[MapFanWeb] 交 通:JR東海道線 掛川駅 バス20分 徒歩20分 種 別:中世 山城 戦国期に高天神を制する者は遠江を制すといわれた有名な要害ですね。最初の築城の由来はさだかではなく、鎌倉時代に土方氏が築城した説がありますが、1500年前後に今川氏が、遠江侵攻での斯波氏との対立にそなえて、築城したのが一般的な説のようです。 今川氏没落後の1569年、徳川家康に属する小笠原長忠が城主となります。1571年に武田信玄率いる甲斐軍が遠江に侵攻し、この高天神城を取り囲みますが、守りが固く撤退しています。信玄没後の1574年、今度は勝頼が攻撃を行う一方で、穴山梅雪を通じ城主の長忠に開城を迫ります。ひと月ほど籠城しますが後詰めの援軍もなくついに開城しました。 勝頼は城番に横田氏を置きますが、翌年の1575年に長篠で大敗。家康は高天神城を囲むように小笠山砦、能ケ坂砦、火ケ峯砦、獅子ケ鼻砦、三井山砦、城山砦の六つの砦を築き兵糧攻めを行い、1581年に激しく攻めたて落城に追い込み、廃城となります。 上写真は高天神城のある鶴翁山で、標高132mのU型の切り立った孤峰でまさに要害です。 写真左側の山が本丸、三の丸がある東峰、右側の山が少し低く西の丸、二の丸のある西峰です。 中上写真は西峰の北先端に広がる堂の尾曲輪の切割あるいは堀切の遺構です。ところどころにこの切割が良く確認できます。 西嶺最高位の西の丸には神社になっており、神社手前の丹波曲輪に大きな井戸と合戦の慰霊碑がありました。(合掌) 中下写真は西峰の南西にある馬場のさらに先端にある犬戻り、猿戻りといわれる抜け道で、武田方の副将、横田甚五郎尹松がこの道をつかって甲斐まで逃げたといわれ甚五郎抜け道ともいわれます。 このような万一の脱出に利用するのは伏せの塁というそうです。 東峰は、的場曲輪、二の曲輪、本丸、三の丸と高低差のある連郭式で、的場曲輪と三の丸を結ぶ帯曲輪もあります。曲輪というより山道ですね。 北側の帯曲輪に石牢があり、徳川方の大河内正局が、家康が高天神城を奪回するまでの八年間幽閉されたといわれています。 下写真は東峰の最高位にある本丸です。写真奥に少しですが土塁も見られます。 さらに東奥の10mほど下がったところに三の丸があり、武田軍が攻めた時に小笠原与左衛門が守備したので、与左衛門曲輪とも呼ばれています。 高天神城は確かに要害ですが、山が急峻すぎて曲輪は比較的小さなものです。やや低い西峰に西の丸を置き、東峰の本丸と併用していたことがアダとなり、徳川軍は西峰から攻撃をして落城させています。 |