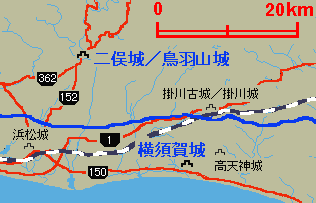
遠江の城は、今川氏、武田氏、徳川氏と戦国のビックネームが次々と登場するので、栃木に住んでいる私にはアカ抜けた印象が非常にします。まさに歴史の表舞台って感じですね。これもすべては徳川が天下を取ったからでしょう。
遠江の城の大半は平野部、あるいは平野部の台地にあるため、他県と比べ300m級の山城がすくないのも特徴です。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
遠江の城
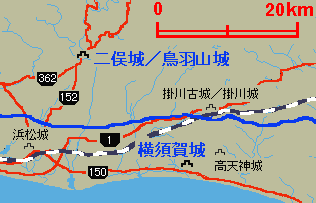
遠江の城は、今川氏、武田氏、徳川氏と戦国のビックネームが次々と登場するので、栃木に住んでいる私にはアカ抜けた印象が非常にします。まさに歴史の表舞台って感じですね。これもすべては徳川が天下を取ったからでしょう。
遠江の城の大半は平野部、あるいは平野部の台地にあるため、他県と比べ300m級の山城がすくないのも特徴です。
1つ前に戻る ホームへ戻る
二俣城
|
所 在:静岡県 天竜市 二俣町城山
地図[MapFanWeb] 交 通:天竜浜名湖鉄道 二俣本町下車 徒歩15分 種 別:中世 平山城 1500年頃に今川家臣の二俣昌長が築城したといわれています。今川氏の後は武田氏の属城となり、1568年に家康が奪回しますが、1572年の三方ケ原の前哨戦となった二俣城の攻防戦で再び武田氏のものになります。 信玄の死後、1575年に再び家康が奪回し大久保氏が城主になりますが1590年に廃城となります。 この地はすぐ後ろに天竜川の断崖が走っている要害の地です。三方ケ原は二俣と浜松のちょうど中間あたりなので、浜松を守る家康にとっては生命線だったのでしょう。 写真は本丸にある天守台で、規模の小さいものですが、時代を感じさせる野面積みで構築されています。どんな天守がたっていたのでしょうか? 本丸の虎口も良く残っています。 |
鳥羽山城
|
所 在:静岡県 天竜市 二俣町
地図[MapFanWeb] 交 通:天竜浜名湖鉄道 二俣本町下車 徒歩15分 種 別:中世 平山城 上記の1575年に家康が再び二俣城を奪回した時に本陣を置いた城で、後に館が置かれたようです。土塁などの遺構(私は見てない)も見られるようですが、それよりも有名なのは、戦国期の城館の庭園が残っていることで、全国にもまれな枯山水式の鳥羽山城庭園は貴重な遺跡であると、写真の看板にかいてありました。 私が見たところでは、良く整備されただの庭園にしか見えませんでしたので、ほとんど印象に残っていないのです。 |
横須賀城
|
所 在:静岡県 小笠郡 大須賀町
地図[MapFanWeb] 交 通:JR東海道線 袋井駅 バス30分 種 別:近世 平山城 1578年徳川家康が高天神城奪回のために、大須賀康隆に命じて築城させ、そのまま大須賀氏が城主となりました。 ここから高天神城は東へ8Kmほどで、西進する武田軍をこの城で食い止める役割もあったようです。 家康の関東移封後は、豊臣譜代の渡瀬氏、有馬氏が城主になり、関ヶ原後は、徳川譜代の数家が城主をつとめ明治に至っています。 上写真は西の丸の高台を撮ったものです。 本丸と西の丸がなんの仕切りもなく、L型をした曲輪になって最高位にあります。全て土塁によるものですが、結構規模の大きなものです。 中写真は西の丸にある館跡と勝手に思っています。(どこも記述がないので...) 本丸を含む東側は修復工事の最中で入れませんでしたが、金網からのぞくと天守台らしい遺構が確認でき、若干ですが古そうな石垣が転がっていました。石垣の修復工事のようですが、もしかしたら模擬天守をたてるのかな? 本丸の北背後には北の丸があり、建造物の遺構調査中の場所と、重機で整地している場所がありました。さらに北背後には標高20mほどの松尾山があり、頂上にはかつて貯水池があったようです。 下写真はその松尾山から撮った北の丸と本丸です。写真左に調査中の様子がうかがえますね。本丸の塁がなかなか高いのが写真の車と比較して分ると思います。 松尾山の北背後には10mほどの深さの空掘りがあり、この掘は旧二の丸(現在は幼稚園など)背後まで、浅くなりながら走っています。 本丸の東側にはさらに広大な三の丸があったようですが、現状はなにも確認できません。 かつて、横須賀城のすぐ南側に遠州灘の入江が迫っていたので、それなりに要害の地であったようです。1707年の大地震で地盤が隆起し入江は消滅したようです。 |