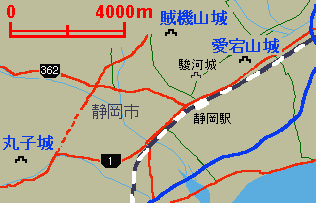
駿府といえば徳川でしょうが、家康以前の今川時代には、府中館を取り囲むように山城、出城があって、守りを強化していました。
府中館は、1411年に今川範政が館を構えてから七代に渡り、今川氏の拠点となりますが、府中館の場所や規模は、家康の駿府築城のため手がかり無しとなってます。
駿府城二の丸内で中世館の遺構が出土しており、このあたりが有力な候補となっていますが、諸説がいろいろあるようです。 1568年の武田軍による侵攻により、駿府は今川支配から離れますが、1582年には徳川が奪回しています。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |





